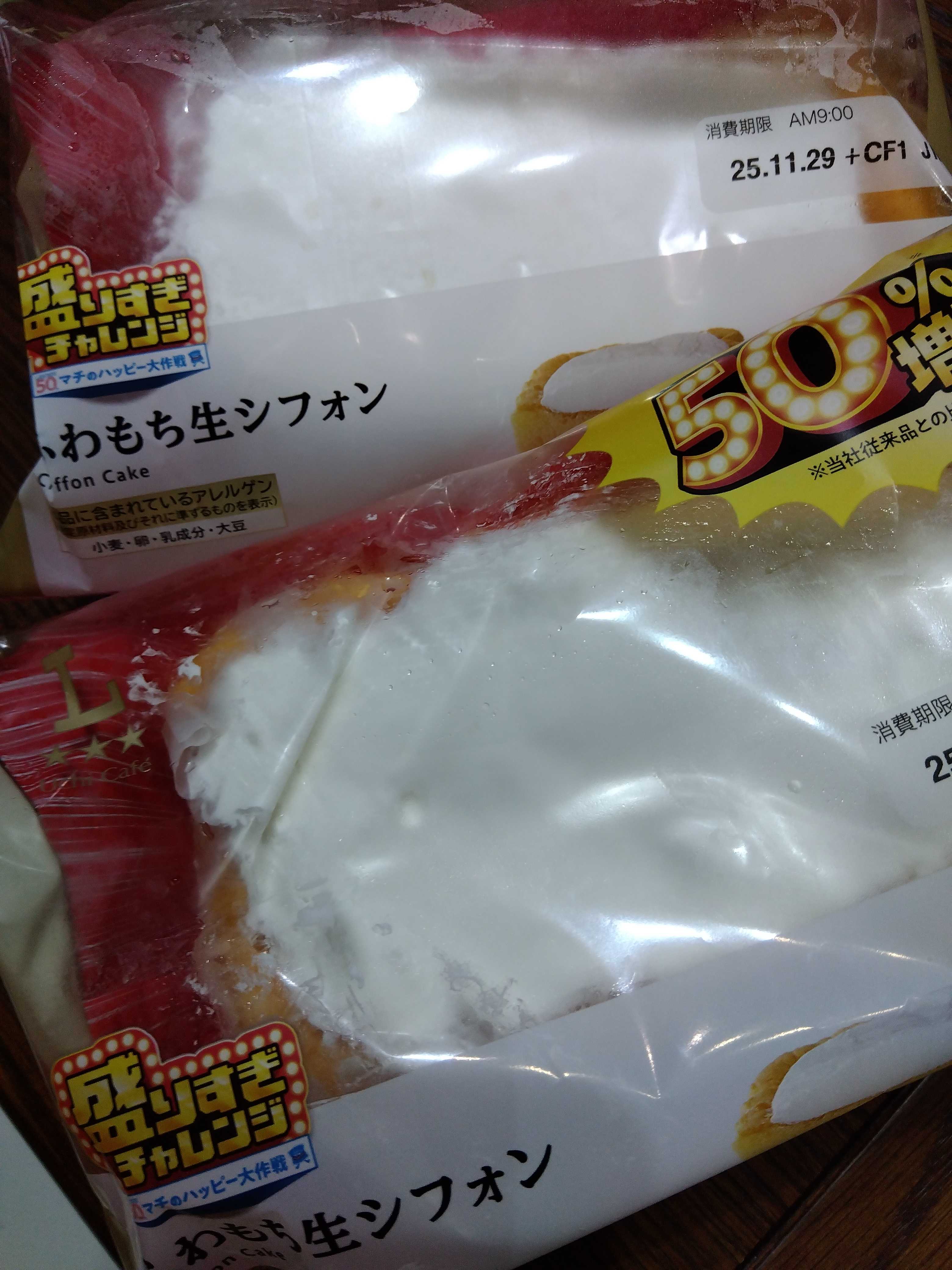2016年10月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
ハロウィーンのキャンパス
今日は・・・ハロウィーン・・・です・・・か? クリスマスなんかと違って、どうもその、昭和世代には、まだ馴染みがないと言いましょうか、子どもの頃にこの日を待ちわびたことがないので、よく分からんです。 もともとイギリス・・・というかケルトのお祭りだったものが、アメリカで変な発展の仕方をし、それがイギリスに再輸入されたものですが、それが日本にやってきてさらに変な発展をし、コスプレ祭みたいになっちゃったというね。ま、文化っていうものは、そうやって各地の土着の文化と混ざり合っておかしなことになりながら伝播するものなのだから、ある意味、昨今の日本のハロウィーン熱も、「正常進化」と言えなくはないですが。 とはいえ、一昔前まではハロウィーンのハの字も知らない人が多かった日本。我が大学の、私が所属している「国際文化コース」ですら、イギリス人とかアメリカ人の先生方がやっきになって「アメリカやイギリスにはそういうお祭りがあるんだよ」と言っても、多くの学生の目は点だったのにねえ・・・。今や、もう・・・。 今や、10月31日の大学のキャンパスってどういうことになると思います? コスプレ祭だよ! どうなってんだ、この国は? 平和ボケか? 特に今年目立ったコスプレは、「セーラー服」。女子大生たちが、二、三年前に脱ぎ捨てたはずのセーラー服を箪笥の奥から引っ張り出してご着用になり、キャンパスを練り歩くというね。 それって・・・コスプレなのか? なんかちょっと安易じゃないか? どうせなら、セーラームーン位にコスプレして来いや! (してほしいの?) さてさて、それはともかく、今日は4限のゼミの時間、OBのM君が遊びに来てくれました。大体毎年この時期辺りで、お目付け役みたいな感じで遊びにきて、後輩たちの卒論執筆のアドバイスに来てくれるのですが。 とはいえ、先輩OBのM君も、いまや卒業後20年近くになり、本当に大先輩になっちゃった。早いねえ。私の感覚では、ほんの数年前・・・とは言わないまでも、せいぜい10年位前の卒業生のような気がしているのにね。 M君も見かけは若々しいので、アレですけれども、聞けばそろそろ年齢が目に来だしたそうで。彼の勤める市役所も、ちょいとブラックっぽい灰色で、残業も月30時間ほどはあるのだとか。年齢的には40代半ばで働き盛りだから、どこに勤めていてもそうなるのかな。 ま、そろそろ無理が効かなくなるお年頃。お互い、身体に気を付けて、元気なうちに人生を楽しもうや。また、遊びにきてね~!
October 31, 2016
コメント(0)
-

明治「デイリー・リッチ」シリーズ旨し!
昨日、某スーパーで何気なく買った「明治Daily Rich」の「レンジでごちそうカレーシリーズ」の「チーズとなすの濃厚キーマカレー」を食べたのですけど、これ、いいよ。おいしい。通常のレトルト・カレーだと、お湯を沸かして温めるか、レンジでチンするにしても一度容器にあけないとダメでしょ。だけど、この「レンジでごちそうカレー」だと、パックのままレンジに入れられるので、すごく簡単。値段も、300円くらいだったかな? で、味もおいしいのよ。「チーズとなすの濃厚キーマカレー」だと、ヒヨコマメなんかもちらほら入っていたりしてかなり本格的。女子ウケもいいのではないでしょうか。これがおいしかったので、次は「コクと香りのバターチキンカレー」を試してみようかな!これこれ! ↓明治 デイリーリッチキーマカレー 中辛価格:302円(税込、送料別) (2016/10/30時点) さてさて、前にも言いましたが、我が愛車シトロエンC4が来年3月で車検を迎えるので、そろそろ次の愛車候補を考えておりまして。 で、昨日はおなじみ、外車のパラダイス「オートプラネット」に行って、あれこれ下見してきちゃった。 気になったのは3車種。 一つは「ボルボV40」。北欧の雄ボルボには一度乗ってみたいと思っておりますし、形も色もいいんだよね! ボルボだから安全性はピカイチだし。 二台目は「ベンツCLA 250 4マチック」。後部座席は狭いけど、デザインがえぐい。しかもターボで、四駆で、しかもサンルーフ付となると、私のクルマに求める夢が一度に叶うしなあ。 三台目は「ゴルフ7」。まあ、ゴルフはね、永遠のベンチマークだし。 この中で一番可能性が高いのは、もちろんゴルフ7だけど、これね、実際に運転席に座ってみると、意外に閉塞感があるんだよね・・・。サイドのショルダーラインが高くて、フロントスクリーンが狭くて、スクリーン上端が運転席の方に迫って来ていて、しかも座席が低くてやや上向きになっている。何だか体育座りをさせられて上の方を見るような感じになるわけよ。本来ならむしろ逆に、上から見下ろすように座った方が運転はし易いと思うのですが・・・。 あとさ、ゴルフ7って、ミッションが「乾式7速DSG」なんだけど、この「乾式」というのが曲者で、「湿式」と比べて壊れやすく、壊れたら数十万コースだっていうじゃん(ネット情報)。それを聞いちゃうと、ちょっとねえ・・・。 かといって、ボルボは高いし、ベンツは壊れた時の修理代が怖いし・・・。 それとも、今回は外車をやめて国産に行く? いっそ、軽の「ハスラー」辺りを中古で安く買うとか? あるいは同じスズキの「イグニス」とか? それもいいんだけど、「釈迦楽先生は外車でしょ」っていう同僚の期待が高すぎて、彼らの期待を裏切っていいものか、っていうね。(何ソレ?) 今回、クルマ選び、迷走するなあ。 まあ、それも楽しいんだけどね。 ということで、あと半年弱。この調子で迷走を続けそうなワタクシなのでありました、とさ。
October 30, 2016
コメント(0)
-

春山茂雄著『脳内革命』を読む
春山茂雄さんの書かれた1990年代の大ベストセラー、『脳内革命』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、日本の自己啓発本の歴史の中では結構、重要な地位を占めている本でございまして。 と言いますのも、この『脳内革命』の大ヒットによって「βエンドルフィン」のような脳内ホルモンの分泌を促すようにするといいよ~、みたいな話に火が付き、そこから今度は七田眞さんの『超右脳革命』が登場して、「右脳を働かせるといいよ~」みたいな話になると。なんかそういう話、どこかで聞いたことあるでしょ? で、そういう話の延長線上に茂木健一郎さんが登場して、これでまた一気に、脳をうまく使えば何とかなるっていう話がバァ~っと出てくる。 だから春山さんの『脳内革命』の大ヒットを一つの契機として、日本の自己啓発本の中に「脳科学系」というサブジャンルが建ったわけよ。だから、日本の自己啓発本の歴史を繙く上では外せない一書なのでございます。 で、じゃあ春山さんが何故に「脳内ホルモン」とか、そういうことに着目したかと申しますと、元々春山さんの家が東洋医学、つまり鍼灸とかツボとか、そういうのを家業にしていたからなんですと。だから春山さんは幼少の時から祖父からそういう東洋医学の基礎を叩きこまれていた。 で、春山さんは長じて西洋医学を学び、お医者さんになるのだけれど、東洋医学と西洋医学を両方学んだ見地から、やっぱり東洋医学には西洋医学にはない良さというものがあるな、と実感されるわけ。 例えば西洋医学では手術をする時には当然麻酔をかけるわけですけれども、東洋医学では、ここぞというツボに針を刺すことによって、西洋医学における麻酔と同じ効果を発揮させ、いわゆる麻酔なしで手術することも可能であったりする。 で、それはどうして可能なんだ? ということを調べているうちに、どうやら人間の脳には数種の化学物質、それを仮に「脳内ホルモン」と呼ぶならば、そういうホルモンを分泌することができ、それが麻酔と同等、否、それ以上の効果を発揮することができるのだ、ということが分かってくる。しかも、もともと自分自身の体内で生成しているものですから、西洋医学で用いる麻酔剤とは異なって副作用などもない。 つまり、東洋医学の鍼灸とかツボとかいうのは、結局、それをすることによって「脳内ホルモン」の分泌を促していたんだ、ということが分かってくるわけですな。ここに於いて東洋医学の原理が、西洋医学的な(=科学的な)見地から立証されたと。春山さんとしては、ここがブレークスルーだったんでしょうな。 で、以後、春山さんはこの「脳内ホルモン」の、いわば虜になっていくと。 で、調べてみると「脳内ホルモン」は、単に麻酔的な効果のみならず、人間の免疫を高めることに多大な効果があることが分かってくる。ならば、この脳内ホルモンの分泌を促すような生活をすれば、そもそも病気にならないことになるわけです。 これ、結構重要なポイントでありまして、本書の中で春山さんは何度もお書きになっているんですが、西洋医学では、医学は病気を治すものであるけれども、東洋医学の見地から言えば、それ以上に、そもそも人を病気にさせないことが重要であると。だから、東洋医学の医者は、患者が自分のところに来ると、医者がまず患者に手をついて謝るというのですな。病気にさせてしまったことは、私の不徳の致すところであるという意味でね。 だから春山さんは、医者たるもの、そもそも人を病気にさせないことに意を用いるべきであって、そのためには、この「脳内ホルモン」を活用するしかない、と考えるわけ。 で、だったら人はどういう時に、自分の体を守るような脳内ホルモンを分泌するか、と調べて行った時に、ポジティヴなことを考えたり、楽しいことを考えたりする時にこの種のホルモンがどんどん出る、ということが分かってきたと。そのことは科学的に測定することも出来るので、具体的に言えば、脳から「アルファ波」という脳波が出ている時に、いい脳内ホルモンが分泌される。逆に、ストレスを感じたり、怒ったりすると、ノルアドレナリンなどの悪い脳内ホルモンが分泌されて、これが自分の体にダメージを負わせてしまったりする。 だから、楽しいことを考えましょう、ポジティヴに生きましょう、イライラしたり、怒ったりするのを止めましょう、そうすればいい脳内ホルモンがどんどん出て、身体は健康に、長生きできますよ、と。 ここに於いて、脳内ホルモンの話が、「ポジティヴに生きよう!」という自己啓発本の主張と重なるわけですな。 でまた、食欲とか性欲とか、低次の生物的な欲望を満たしている時も脳内ホルモンは分泌されていて、それをすることが脳的に奨励されていることが分かるのですけれども、この種の欲望がある程度満たされると、今度はそれを阻害するような逆のホルモンが分泌されて、それを永遠に続けることができなくなってしまうように人間の身体はセッティングされている、ということも分かってくる。つまり、動物的な欲望の達成には限界が設けられているんですな。 だけど、「自己実現しよう」とか「それによって人の役に立とう」とか、そういう人間ならではの高次な欲望を満たそうとする時は、それを阻害するホルモンは分泌されないんですって。そういう欲望は、止めようがない。 で、春山さんは、そこにある種の神秘を感じるんですな。神さまってのが居るかどうかは分らないけれども、この宇宙の仕組みからいうと、ネガティヴな悪いことを考えている人間は、そのことによって我と我が身を滅ぼす一方、幸せになろう、人の役に立とう、世のために尽くそう、なんてことを考えている人間は、汲めども尽きぬアイディアとエネルギーが補充されるようになっていると。 つまり、脳の仕組みから言えば、神さまは人間に対して「幸せになれ! 人に尽せ!」と命じていると解釈せざるを得ないと。 自己啓発本史の見地から言いますと、この辺に「スピリチュアル系」へのゲートウェイが開いているようにも見えるけどね。 ま、もちろん春山さんご自身は、敢えてスピリチュアルな方向には行きません。むしろお医者さんとして、人の健康のことに集中していらっしゃるのであって、それゆえに本書の後半部は、むしろ脳のことより健康のことに話題が移って行く。例えば、いい脳内ホルモンの分泌を活性化するためには、食生活や運動も重要なファクターで、質の良いタンパク質を取ることを心掛けなさいよ、とかね。 あと、脂肪はなるべく取らない方がいいけれど、日々の食事の中で脂肪をゼロに近づけようとすると、それはまたそれでストレスとなって悪い脳内ホルモンを分泌してしまうから、あまり極端に無理しない方がいいとか。また運動方面のことで言えば、ウォーキングやストレッチなどの穏やかな運動はいいけれど、スポーツ選手のようにあまり必死になって運動しすぎると、それはそれで体に負担になるから止めた方がいいこと、等々、様々なアドバイスを、春山さんはこの本の中でお書きになっております。 つまり、結局この本は基本、「健康になるにはどうしたらいいか」の指南本なんですな。ただ、その中で「脳内ホルモン」に主な焦点が当たっているので、自己啓発本寄りの扱いがなされていると。 というわけで、この本、そういうものとして決して悪い本ではないと思います。少なくとも、ここに書かれているアドバイスを実行したからといって、何か悪いことが起るとも思えませんし・・・。 なんでそういう言わずもがなのことを言うかと申しますと、結構、この本に対する悪評というのがあって、やれ「インチキだ」とか「医学的にいい加減なことを言っている」とかね。そういう批判本の類も出されていたりして、世間の風当たりは強いのよ。 まあ、500万部を超すようなベストセラーになると、人の妬みを買うんでしょうな。 だけど、先ほども言ったように、それほど悪い本じゃないですよ。 実際、脳内ホルモンってものが実際どうなのかってことは別にして、何かストレスを感じるようなことがある場合、例えば明日、気の重い仕事をしなくちゃならなくて、今から憂鬱だ、なんて時、「あ、やばいやばい、今、きっと悪い脳内ホルモンが出ちゃって寿命を縮めているぞ。そうならないように、ポジティヴに考えて、いい脳内ホルモンを出そう! よーし、明日の仕事、楽しみだなあ!! 早く明日にならないかなあ! きっと大成功間違いなし、俺の評価も鰻のぼりになるぞ! ああ、早く明日の仕事したい!」って思い直すとしたら、やっぱり少しはストレス解消になるんじゃないの? そして、もしそれで少しはストレス解消になるのだったら、そのことだけでもこの本を読んだ価値はあったようなものじゃん? そういう意味で、この本、私にはそれなりに面白かったかな。【中古】 脳内革命 脳から出るホルモンが生き方を変える /サンマーク出版/春山茂雄 / 春山 茂雄 / サンマーク出版 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】価格:258円(税込、送料別) (2016/10/29時点)
October 29, 2016
コメント(0)
-
江藤淳伝絶好調
自分の原稿書きと身内の不幸が重なって今年の8月9月はめちゃくちゃな忙しさだったのですが、10月に入ってようやく少しのんびりできるようになりました。 ということで、今日は、溜まりに溜まっていた学会関連の仕事に取り組んでおりました。 で、その学会の仕事というのは、学会員から送られてくる著書のデータをきちんと記録し、礼状を書き、学会のHPに紹介文をアップする、というもの。別に大したことはないのですけれども、かなりの冊数を溜めてしまっていたこともあって、全部やるのに半日がかりよ。 だけど、今日処理した本の大半が共著もの。そして何冊かは翻訳。単著の研究書はゼロ。これが私には理解できない。 なんでみんな、単著書かないのかな。これが自分の本だ、これが自分の研究だってことを公けにして、それで毀誉褒貶をまともに喰らってナンボなんじゃないの、研究なんて。 共著だと、責任が分散するせいか、難しいことを平気で難しく書く人が多いんだよね。 だけど、単著で出そうと思ったら、やっぱり「売れる/売れない」というのが直接自分の責任になってくるじゃん? そうなると、やっぱり売れる本にしなくちゃ、という気になる。 売れる本にするには、難しいことを難しいまま書いたってダメなのよ。誰が読んでも「なるほど!」と思ってくれるように、噛み砕いた書き方にしないと。 自分ではわかっているつもりの生硬な思考を、誰が読んでも分かるような形に書き直す。これが、モノを書くってことなんじゃないのかしら? そこへ行くと、今、『新潮45』で平山周平さんが連載している江藤淳論、これはいいよ。 とにかく読んでいて面白いもんね。で、面白いのだけど、それでいて江藤淳の形成過程にギリギリと迫っている。そして、そのための調査・下調べがものすごい。 今、丁度、江藤淳が評論家としてのデビュー作となる夏目漱石論を書き出すあたりの事情が書かれているんですけど、その産婆役として山川方夫の存在が大きかったということ、そして山川方夫の方も江藤淳の存在によって小説家として成長していくという、その双方向の影響関係に迫っていてすごくスリリング。 アメリカ文学の畑でも、こういう感じの単著の研究書が出てこないかなあ・・・。 あ、私が書けばいいのか。
October 28, 2016
コメント(0)
-
大学に「キッチンカー」登場
勤務先大学で「キッチンカー」なるものを試験的に導入するってんで、今日、その第一陣が来たのだそうで。 「キッチンカー」って、和製英語? アメリカでは、よく「フードトラック」ってな言い方をしますけど、要するに食べ物を売る移動販売車ですな。 で、今日はなんと、ピザとケバブサンドを売るキッチンカーが来たんですと! 私はその情報をゲットしていなかったので、ミスってしまいましたけれども、さすがアニキことK教授はドイツ人の同様のM先生と一緒にケバブサンドの方をチョイスし、青空の下、キャンパスのベンチで食べたそうで。 ひゃー、しまった~。ケバブサンド食べたかった~! 生協の学食に飽きた学生たちも大勢、このキッチンカーに並んだそうで、企画としてはなかなか良かったのではないでしょうか。 現在は試験的な営業だそうで、これで採算がとれそうとなれば、日替わりで色々な料理を出すキッチンカーがお昼時に来学するのであれば、私も是非トライしてみたい。 ということで、うちの大学にしてはなかなか洒落た試み、いつもは辛口のワタクシも珍しく褒めてつかわしましょうかね。
October 27, 2016
コメント(0)
-

北尾トロ著『ぶらぶらヂンヂン古書の旅』を読む
私の古本道の師匠、岡崎武志さんがブログで勧めていた北尾トロさんの『ぶらぶらヂンヂン古書の旅』を読んでおります。 岡崎さんのご著書もそうだけど、「古本本」というジャンル、根強い人気がありますなあ。『古本ツアー・イン・ジャパン』の小山力也さんとか、『古本暮らし』の荻原魚雷さんとか、新しい系の古本ライターも出てきたし、倉敷で「蟲文庫」という古本屋を営む田中美穂さんの『わたしの小さな古本屋』も最近ちくま文庫で文庫化されたし。 で、北尾さんの『ぶらぶら』は、ご自身でネット古書店も営まれている北尾さんが、趣味と実益を兼ねて、地方に出張ってセドリをする、その顛末記ですな。 だから一応はお仕事なんだけど、とてもそうは見えないほど、地方の古本屋さんを1泊とか2泊とかの旅程で回る、そんな忙しない古本探索の旅をほんわか楽しんでいる様が文面から伺えて、ゆるーく楽しめる本でございます。 道すがらの風景は楽しみつつも、基本は地方都市の古本屋を巡ることが優先の古本旅。だけどそこが古本業界のゆるさというか、せっかく行ってみたのに肝腎のめざす古本屋が休みだったとか、期待していたほど収穫がなかったとか、そういうことはざら。しかし、だからといってガッカリというわけでもなく、「こんなもんだろ、それに1冊でも収穫があったからいいじゃん」的なところが窺え、古本好きとしては「そう、そうなんだよ!」と膝を打つところ。 それから、古本を買うのに資金を回すため、ビジネスホテル代をケチって、あまりにショボイ朝食にガッカリするとか、逆に収穫があった時など、買ったばかりの古本をホテルのベッドに横たわりながらパラパラやる時の至福とか、これまた古本好きならば誰もが経験していることで、「それ、あるある~」って感じですね。 要するに、そんな感じの「古本好きあるある」本であって、それだけの本なんですけど、それだけのことを語る北尾さんの語り口につい読まされちゃうニクイ本。それに、私もまた学会出張などで地方を回ることが多いので、北尾さんのこの本を読んで、そうか、そっちの方の地方都市にはそんな古本屋があるのか、よーし、今度そっちの方に行くことがあったら私も行ってみよう、っていう興味も出てきますからね。 というわけで、確かに岡崎師匠の言う通り、古本好きならたまらない北尾トロ本、私もおすすめ!と言っておきましょうかね。ぶらぶらヂンヂン古書の旅 [ 北尾トロ ]価格:637円(税込、送料無料) (2016/10/27時点)
October 26, 2016
コメント(0)
-

『クレイマー、クレイマー』は今もなお傑作だった
「アメリカ映画史入門」というタイトルの授業で、必要があって1979年の話題作『クレイマー、クレイマー』を学生に見せたんです。 そしたら、受講生の多くが号泣! 父親と別れなければならなくなったビリー少年が泣くシーンで、学生たちももらい泣き。 ふーむ。そうか。この映画は、三十数年を経ても観客の紅涙を絞る傑作だったのか・・・。 このところ、学生たちとのジェネレーション・ギャップを感じることが多かっただけに、たまにこういうことがあるとホッとしますな。一応、同じ人間の血が流れているんだ、と分かって。 だけど、この映画最後まで見ると、結局、母親(メリル・ストリープ)は親権を放棄するんだよね・・・。だからこの映画は女性バッシング映画なんだって、しばしば批判されるわけですけれども、確かに、映画の完成度という意味でも、むしろメリル・ストリープは悪役(?)に徹して、父親(ダスティン・ホフマン)からビリーを奪い取った方が感動的だったんじゃないかしら? もっともその場合、最後のシーンをどう撮るか、ちょっと難しくなるけどね。クレイマー、クレイマー コレクターズ・エディション [ ダスティン・ホフマン ]価格:1000円(税込、送料無料) (2016/10/25時点)
October 25, 2016
コメント(0)
-

『不屈の棋士』
『不屈の棋士』って本の評判がいいようですけど、買おうかな、どうしようかな。 このところ、コンピュータの将棋ソフトの実力が上っちゃって。電王戦なんかでは一流のプロ棋士が敗れることも珍しくなくなってきた・・・というより、むしろ棋士がコンピュータ・ソフトに勝つことの方が珍しくなってきた位ですけれども、そういったコンピュータ・ソフトの台頭という、きわめて今日的な問題に、今を生きる棋士たちが何を思っているのか、ということを取材した本らしいのですが。 特にこの本は、当代一の棋士である羽生さんのインタビューが載っていることでも話題で、第1回電王戦をパスした羽生さんの、コンピュータ・ソフトに対する思いが読めるのは、ちょっと興味深いところ。 大体、吹けば飛ぶような将棋の駒に人生賭けている奴が21世紀になってもいる、っていうこと自体、凄いもんね。で、コンピュータと競争して、勝つか負けるかっていうところにある、ということも考えてみれば凄い。普通、負けるでしょ。1秒間に億単位の計算する奴には。 ま、私は将棋が得意というわけではないのですが、何となく好きは好きなのよ。人間臭いからね。 世の人間同様、将棋の駒ってそれぞれ個性があって、得意不得意があって、強い奴も弱い奴もいる。それらを上手く使って、いかに戦いに勝つかっていう風になるわけだけど、時には一番弱い「歩」で王様の首を取ることだってあるわけで。そういう人間臭いところが好き。 一方、碁となると、ルールは単純だけど、なんだか雲をつかむようなゲームだから、私にはそれほど入れ込めないんだなあ。あれは人間臭いというよりは、仙人臭いよね。 でまた将棋を巡る物語ってのも、色々面白い。そう言えば今度、早世した天才棋士・村山聖についてのドキュメンタリーを元にした『聖の青春』という映画が公開されるようですが、あれも原作読んじゃったし。 もっとも、読まなくてはならない本、読もうと思って買ってあるけれども読む時間がない本が既に山ほどある中で、さらに研究とまったく関係ない本を買うというのもね、自分でもバカだなと思うんですけどね。でも、どうせ買うんだろうな。不屈の棋士 [ 大川慎太郎 ]価格:907円(税込、送料無料) (2016/10/24時点)聖の青春 [ 大崎善生 ]価格:750円(税込、送料無料) (2016/10/24時点)
October 24, 2016
コメント(0)
-

アレクシー・カレル著『ルルドへの旅』を読む
アレクシー・カレルが書いた『ルルドへの旅』っちゅー本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 ルルドって、まあ、知っている人はよく知っているでしょうけど、フランス南部にあるカトリックの聖地でありまして、19世紀後半に聖マリア様が現われ、以来、ここの泉の水を飲んだり、水浴したりすると、病気が治ってしまう奇跡が起こるというので有名なところ。今でも、医者に見放された重病患者さんなんかが訪れるところで、私の研究対象である(あった、かな?)フラナリー・オコナーというアメリカの女流作家も、紅斑性狼瘡という死病に悩み、ここを訪れたりしております。結局、39歳で死んじゃったけどね。 で、アレクシー・カレルというのは、フランスのお医者さんでありまして、それも1912年に39歳という若さでノーベル賞もらっている人。 で、カレル君は、フランス人だけに元々はカトリック信者だったのですが、科学者でもあるので、だんだん不可知論者となり、神さまがどーのこーのっていう話にはあんまり気が乗らなくなっていたんですけど、ルルドで奇跡的な治癒が数々報告されるもんで、科学者として自分の目でそれを確かめようと思ったわけ。 で、実際に行ってみたわけさ、ルルドに。 そしたら、他の医者もそう見立て、自分自身もこれは明らかに重篤な結核性腹膜炎の患者で、危篤状態にあると診断した若い女性が、たった一回、ルルドの泉を浴びただけで、なんとその日のうちに健康を取り戻してしまったのを見てしまうわけ。科学者である自分の目の前で、奇跡が起こったと。 カレルも最初は、「泉の奇跡っていうのは、多分、ヒステリーとか、その種の精神疾患に効くかも知れないけれど、器質性の病気にはさすがに効かんだろう」って、多寡をくくっていたんですけど、自分自身が「危篤」と診断した娘さんが数時間で健康になったとなると、さすがに信じないわけにはいかなくなり。 で、その顛末を、(ここが意味分らんところなんだけど)小説仕立てにしたと。小説の中では、自分の名前であるカレル(Carrel)の綴りを逆にした「レラック」なる医者を主人公にして、このレラックが上に述べたような奇跡を目の当たりにして、科学と宗教の狭間で色々思いまどうという筋書きにしてね。もっとも、書いた小説はお蔵入りにしていたらしいんですが、奥さんがカレルの死後に発表したため、世間に知られるようになったらしい。 ちなみに、なんでこんなダサい小説を私が読んだかと申しますと、この本、「あらゆる病気は、もともと単なる気の迷いなので、患者本人が治ると信じればすぐに治る」という自己啓発本の主張を裏書きするものとして有名だから。なにせ書いているのがノーベル賞受賞者ですからね。ノーベル賞取るような医者が、目の前で重篤の患者が瞬時に快癒したのを目撃しているんだから、自己啓発本の主張は間違いないでしょ、っていう根拠になっているのよ。 ま、そういうものなので、私も一応読んでみたっていうだけのことでね。 だけど、ルルドの泉の奇跡っていうのは、実際にあることはあるらしいんですな。で、当時から科学者が泉の水を分析したりするんだけど、水自体は別にどうっていうこともない普通の水なんですと。だけど、何故かこれを飲んだり浴びたりすることで、病気が治ってしまう人は実際に沢山居る。だからこそ、今なお巡礼の列が絶えないわけですが。 だから、その意味では「ルルドの泉に触れれば、私は治るんだ」という信念が、確か病気を治しちゃうっていうのは、本当なのかも知れませんな。 ところで、この本によると、著者のアレクシー・カレルっていう人も、なかなかいわくつきの人みたいです。 大体、この人は手先が器用で、血管の縫合とか、めちゃ上手かったらしいんです。出身地が縫製業で有名なところだったのでね。縫い物は上手いわけ。だからね、大怪我をした子供の血管を、その親の血管に直でつないで、ダイレクトに輸血をして命を助ける、なんていうウルトラC級の手術とかしちゃうの。すごくない? だけど、どういうわけか、途中で医学の道を放棄して、牧畜業を目指してフランスからカナダへ行く(なんで??)。 だけどカナダは田舎過ぎてどうも性に合わず、アメリカのイリノイ大学から招かれてアメリカで再び医学の道につく。で、その後シカゴ大学なんかで、臓器移植の研究をするんだけど、自分じゃ「成功した!」とか言っているものの、実際には拒絶反応があって(当たり前だ!)、彼の研究を額面通りには受け取れないらしい。 ちなみに、ここではチャールズ・ガスリーという研究者と共同研究していたのですが、共同研究なのに、発表する時はガスリーのガの字も触れないというところがあったらしく、後にノーベル賞を受賞した時も、「本当はガスリーに授与すべきだった」という説も流れたのだとか。 もっともガスリーって人もまた、ちょっとマッド・サイエンティストっぽい人だったみたいで、犬の頭を切り取って、別な犬に縫い付け、双頭の犬を作っちゃったりしたとか、「それ、ほんとに臓器移植の実験として必要だったの?」ってな実験をやっている。この双頭の犬の一件だけでも、ノーベル賞に値しない、っていう説もあるみたい。 で、その後、ロックフェラー研究所に移籍するんですが、そこでは日本の野口英世大先生なんかと同僚だったのだとか。 で、その後第一次世界大戦が勃発すると、カレルはフランスに帰ります。で、ノーベル賞の賞金で自前の研究所作ったりして楽しくやっていたみたいですけど、そこで意外なことに、かのアメリカの英雄、チャールズ・リンドバーグと懇意になる。義理の従姉妹が心臓病で亡くなったこともあり、リンドバーグはそういう系の研究をしていたカレルを応援する気になったらしいんですな。 で、驚いたことに、リンドバーグも単なる飛行機乗りというよりエンジニアなので、細胞培養に用いる機器を作ったりしてカレルをサポート、かくして二人は『器官の培養』という、まさに「STAP細胞は・・・あります」的な共著を出しているというね。マジか!! だ・け・ど。 ここからが悲劇よ。 カレルは、彼が生きた時代にはさほど珍しくなかった考え方ではありますが、優生学的な発想の持ち主だったんですな。つまり、心身とも健康な人間のみが生きるに値し、そうでない人間は早くあの世に送ってあげた方が双方のためだ、的な。 で、その考え方は、ナチス・ドイツの考え方をサポートするものと見なされるわけ。だってカレルは「ドイツ政府は、知的・身体的欠陥者、精神病者および犯罪者の増殖防止に精力的な手段を講じてきた。理想的な解決は、こうした個人が危険とわかりしだい、その各人を駆除することであろう」って書いちゃったんですから、これはもう、言い訳できない。 ということで、レジスタンス政府から「コラボラショニスト(ナチスへの協力者)」として激しい非難を浴び、公職から追放されたカレルは、1944年、失意のうちに亡くなります。 まあ、ノーベル賞受賞したっちゅーのに、ひどい後半生ですな! もちろん、身から出た錆だけど。 とまあ、アレクシー・カレルって、そんな波乱万丈(っていうのかな?)の人だったんだ、ってことが分かっただけでも、この本読んで勉強になりましたね。 ただ、この本を訳している川隅恒生さんという人の日本語が酷くてね。あと、重要なところで誤字も散見されるし。例えば、144ページ、カレルの生年を「1973年」としていたりね。そういうところは、ちょっと残念なところでございます。ルルドへの旅 [ アレキシス・カレル ]価格:799円(税込、送料無料) (2016/10/23時点)
October 23, 2016
コメント(0)
-

カルロス・カスタネダ著『ドン・ファンの教え』を読む
カルロス・カスタネダの書いた『ドン・ファンの教え』なる本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。これ、以前には『呪術師と私』というタイトルで邦訳されていたようですが、今はこっちのタイトルに代わっております。 この本が出版されたのは1968年、アメリカ・フランス、そして日本でも学生運動とか喧しかった時代。つまり既成の価値観とか、そういうものが若い世代によって拒否され、新たな価値観が模索されていた時代。そういう時に、絶妙なタイミングで出版されたこの本は、当時、相当なインパクトを社会に与えた・・・のだそうです。 ま、もちろん私は、この本が「ニューエイジ系自己啓発本」の走りとして読めるのではないかと思って読んでみたわけですけれども、読んでみて、ふーーん、って感じ。ま、面白くなくはないけど、それほどのもんか?っていうね。 結局、時代とシンクロした本なんでしょうな。だから1968年にはものすごいインパクトがあった本なのかも知れないですけど、今の時代、私は別に「新しい価値観を求めて模索」なんかしてないからさ。これ読んで、すぐに「これが答だ!」っていう風には、別に感じないわけよね。 ま、いいや。とにかくどういう内容の本かといいますとね、1960年にUCLAで文化人類学かなんかの勉強をしていたカルロス・カスタネダというブラジル系の若者が、インディアンの呪術とか、それに用いる植物の研究をしていて、当時アリゾナに住んでいた呪術師ドン・ファンに紹介されるんですな。ドン・ファンはメキシコのソノラ地方に住むヤキ・インディアンの末裔なんですが。 で、カスタネダがドン・ファンに呪術用の植物のことおせーて、おせーてってしつこく付き纏っていたら、ある時、メスカリト(=ペヨーテ)というサボテンを食わされて、それでカスタネダがすっかりラリったその様が「見込みがある!」ってんで、彼はドン・ファンの弟子にさせられると。 どうもね、呪術師(=知者)には「師弟関係」が必要なようで、ドン・ファン自身もかつて師について学んで知者となったので、その一子相伝的な智慧を、今度は弟子に伝えなければならない。それで彼はカスタネダのことを「こいつが俺の弟子になるべき人物だ!」と、運命づけちゃったわけ。もっとも、ドン・ファンがそう決意するまで1年かかったそうで、彼も自分の弟子は慎重に選んだんですな。 で、それからカスタネダが弟子を返上するまでの4年間、ドン・ファンは自身の呪術とその背景となる世界観、つまりは「智慧」を、カスタネダに伝えたと。 じゃ、そのヤキ・インディアンの知者の「智慧」とは何かと言いますと、これはね、何か固定的な知識ではどうもないようなんですな。そうじゃなくて「過程」なんです。つまり、どこか目的地に着くことが重要なのではなく、その目的地に向かうための「旅」が重要らしい。ただその際、「正しい道」を歩むことが重要なのですが、その道が正しければ、どんな道を辿ってもいいんですと。 で、人はこの智慧を巡る旅の途中で4つの敵に会う。じゃその敵とは何かと申しますと、「恐怖」「明晰さ」「力」「老年」の4つなんですと。 まず出くわすのは「恐怖」。学びを阻害する最初の壁ですな。これはもう、取り合わずにずんずん前に進むことでしか撥ね付ける方法はない。 で、「恐怖」を克服すると、次に「明晰さ」が立ちはだかる。この時期には、物事の道理が見通せちゃって、賢くなったような錯覚を覚えます。だけど、それはあくまで錯覚であって、これに満足してしまうと、もう前に進めなくなる。多分、「慢心」と言い換えてもいいものなのではないかと。 で、この「明晰さ」に騙されず、さらに智慧を求めて前に進むと、今度は「力」が手に入ってしまう。何でも出来るような気がしちゃうから、ついこの時点で人は立ちどまってしまんですけど、これまた一種の慢心でありまして、ここで止まったら単なる「横暴な人」で終ってしまい、知者にはなれないわけ。 で、「力」にも騙されず先に進むと、今度は「老年」がやってくる。旅に疲れたからこの辺で休息したいっていう気になっちゃうんでしょうな。この誘惑は非常に強い。だけど、知者への道は旅だから、休んだらそこで終り。 かくして、この4つの敵を退けた者だけが、ほんの一瞬、知者になれると。勿論、旅はその後も続くので、知者もまた前に進み続けなければならないのですが。 ところで、この知者の旅を続けるに当たって、人には幾つかの同伴者が必要らしいんです。で、その一つが「メスカリト」であると。 メスカリトによるトリップは、正しい道を歩むための「師」であり「補助者」なんですな。だけど、それはどうも二次的なものらしく、知者の旅をするには、もっと重要な「盟友(ally)」が必要であると。 で、ドン・ファンの盟友は「煙」で、これはある種のキノコを煙草のように吸うことで得られるもの。しかし、盟友は人によって異なるので、まずドン・ファンは、ドン・ファンの師の盟友であった「デビルズ・ウィード」をカスタネダに与えます。これはある植物の葉や茎、花、根、実を肌に擦り込むことで得られるのですが、ドン・ファン自身はあまり好きではない。デビルズ・ウィードは非常に女性的で、気まぐれに使用者を支配しようとするので、扱いが難しいらしいんですな。 で、デビルズ・ウィードを試したカスタネダは、ものすごいトリップを体験する。その体験は、カスタネダにとってはさほど嫌な感じはしないのですが、やはり振り回される感じはある。 で、次にいよいよドン・ファン自身の盟友である「煙」を、カスタネダも体験します。これは「飛ぶ」系のトリップを促すもので、この煙を吸うことにより、カスタネダも、モノを通過したり、空に舞い上がったりする経験をする。またこれを盟友とすると、人は何か人間以外のものになれるようで、ドン・ファンは盟友を使っていつも「カラス」に変身する。だからカスタネダもこの伝統芸を引き継いでカラスになります。 つまり、盟友を従えることにより、知者は力を持つわけね。傍から見れば、それは呪術ということになるわけですが。 とまあ、そんな感じで、カスタネダはドン・ファンから様々な教えを受けましたとさ。 ちなみに、この本の第二部は、4年間に亘ってドン・ファンの弟子をしたカスタネダが、そのドン・ファンの教えなるものを、なるべく客観的に、すなわち文化人類学的に分析・考察したものが載っているのですが、これはつまり、ヤキ・インディアンの世界観を西洋的な世界観で説明をしようと試みたもので、多くの読者から総スカンを食ったところなんですな。せっかくドン・ファンが提示した「異なる世界観」を、なんで西洋の世界観の中に無理やり位置付けようとするんだ、というわけ。この本は、この「第二部」があるおかげで、「最良の材料を扱った最悪の本」とも呼ばれております。 それからね、これはウィキペディアの情報なんだけど、カスタネダの奥さんが後に、「カルロスが色々書いてますけど、そんなのぜーんぶウソ、ウソ」とか語っていたそうで、そもそもこの本に書いてあることは全部嘘っぱちで、ドン・ファンなどという人物は、そもそも存在しないらしい、という噂も根強いのだとか。っていうか、カルロス・カスタネダ自身、謎の人物で、いつどこでどうして死んだのかすら、あまりよくは分っていないっていうね。 そう言われちゃうとねえ・・・。 だけど、まあ、とにかくこの本が、ある時期の西洋世界において非常なるインパクトを持った書物として受け入れられたという事実は変らないわけでございまして、そういう意味で、重要な本であることは確か。 ちなみに北山耕平さんの『雲のごとくリアルに』という本(これは伝説の雑誌『ワンダーランド』及び『宝島』の創刊と編集に携わった北山さんの思い出の記なんですが)によると、カスタネダについて日本で最初に言及したのは植草甚一さんだそうで、ま、アメリカの雑誌を隈なく読んでいた植草さんが、特有の鼻を効かせて、そこに掲載されていたカスタネダの記事に敏感に反応したであろうことは十分に想像できるかなと。その辺のことは、多分、植草さんの『カトマンズでLSDを一服』なんかを読めば、ひょっとして出て来るのではないかと。 だけど、これもウィキペディアに記述によれば、日本でカスタネダの『呪術師と私』に最初に反応したのは鶴見俊輔ということになっていて、あと社会学者の見田宗介(=真木悠介)とか、宗教人類学者の中沢新一あたりも言及しているらしい。それから吉本ばななとか細野晴臣とか須藤元気なんかも、カスタネダを語っている人たちらしい。 今名前を挙げた人たちって、いかにもカスタネダに反応しそうな人たちばっかりだけどね。 ま、とにかく、そんな感じ。 で、肝心な自己啓発思想史的にはどうかっていうと・・・どうなんだろうね。これ、自己啓発なのかなあ。 ま、1960年代と言いますと、アメリカではLSDなんかを使ったトリップによって、「セパレート・リアリティ」を体験することが、新たな知覚の扉として騒がれていたのであって、我々がリアルだと思っているこの世界だけがリアルなんじゃない、っていう新しい認識が言われ出した頃ですから、その流れに掉さすものではあるかなと。 で、そのセパレート・リアリティなるものが、ニューエイジ系の自己啓発本では重視されていて、現世を精一杯生きれば、来世で幸福になれるよ~的な言説があった。そういう言説の中では、セパレート・リアリティの存在は、現世での勤勉・努力の根拠になるから、その意味で、自己啓発的側面があった、とも言えるかも。 だけど、この本読んで、来世がどうのこうの、っていうのは少し飛躍しすぎかな。もっと下世話に、「俺もサボテンとか、デビルズ・ウィードとか、キノコとかキメて、トリップしてー!」っていう辺りが、この本の人気の一番の側面だったんじゃないかしら。 ま、だからといって、悪いことはないのであって。人間、好奇心を失ったらおしまいだからね。ドン・ファンの教え [ カルロス・カスタネダ ]価格:2160円(税込、送料無料) (2016/10/22時点)
October 22, 2016
コメント(0)
-
溶かして飲む風邪薬
なんか風邪流行ってないすか? このところ、急に暑くなったり寒くなったり、あるいは昼は暑いのに、朝と夜は結構寒かったり、そんな感じだからか、同僚や学生で風邪引いているのが多くて。 で、流行っているなあと思っていたら、何だか私も喉の具合が変。ありゃ、ちょっと風邪薬飲んでおいた方がいいかな? こんな時! 私にはいいものがあるんだ! るん! あのね、アメリカとかイギリスに出張がある度、現地のドラッグストアで美味しい風邪薬を買っておいて、それを日本に持ち帰っているのよ。 美味しい風邪薬というのは、ほら、昔日本でも「粉ジュース」みたいなのあったじゃん? ああいう感じで、粉状の風邪薬をお湯に溶いて飲む奴なの。これが結構おいしくて。 ま、モダンな玉子酒みたいな感じ? で、今まさに私が飲んでいるのは、「レモン・ジンジャー味」。その名の通りの味で、ちょっと甘苦くて美味しい。身体もあったまるしね。 アメリカだと、「アルカ・セルツァー」みたいに水に溶かして飲むタイプの薬って結構あるんだけど、日本にもあるのでしょうか。私は寡聞にしてあまり知らないけれども。でも、ないんだったら作ればいいのにね。小林製薬とか。好きそうじゃん、そういうの。 ま、とにかく、今日のところはこのレモン・ジンジャー味の美味しい薬を飲んで、早く休むとしましょうかね。
October 21, 2016
コメント(0)
-
素人批評の面白さ
今、巷で話題の丸亀製麺の「牛すき釜玉」、食べちゃった! めっちゃ旨い。もうさ、昼飯なんてこれで十分だよね。 それはさておきですよ。 先日、高級外車専門の中古車販売「ロペライオ」の試乗動画が面白いという話をこのブログでもご紹介しましたが、私、その後もずっとこの試乗動画を見続けておりまして、相当楽しんでおります。 で、その試乗動画に登場するのは、ロペライオの社員さんですから、もちろんある意味では専門家と言えないこともないですけれども、いわゆる「自動車ジャーナリスト」ではないわけですよ。だから、試乗インプレッションにしても、素人目線というか、普通の自動車好きの人が、自分たちが販売している高級外車に乗って「これ、いいね~!」とか、そういうレベルのインプレッションをする。 だけど、それが面白いんだなあ。 つまり、私もまた単なる自動車好きの素人だから、同じ素人の目線でインプレッションしてくれた方が、よほど納得できるわけ。逆に、ロペライオ・チャンネルを見た後で、プロの自動車ジャーナリストの試乗インプレッションとかを見ると、なんだか噓くさい・・・とまでは言いませんが、とにかく何だかあまり感じが伝わってこない、という風に感じてしまう自分がいることに気付くというね。 つまり、受容する側が批評する場合、その受容者は、あくまで素人目線でやる、というのが重要なのかなと。 一方、これまた私の好きな『漫勉』とか、あるいは『関ジャム』みたいな番組で、プロの漫画家やプロの音楽の作り手が、それぞれプロの目線で色々解説するのはすごく面白いところを見ると、製作側が批評する場合、製作者はあくまでプロ目線でやる、というのが重要なのかなと。 そうなると、文学作品の批評を面白くするためには、読者として批評するなら素人として、作家として批評するならプロとして、それぞれ批評するっていうのがいいんでしょうな。 逆に、一番良くないのは、読者サイドから批評しているのに、プロっぽくやろうとすることになりますかね。 となると、私は今、研究者として読者サイドから文学批評をしているわけですから、心得としては、やっぱりあくまで素人目線で、ということになるでしょう。 その辺、混同しないようにしないとな、なんて、ちょっと考えた私なのでした。
October 20, 2016
コメント(0)
-
研究室宛て郵便物、正しい書き方は?
学会の資料室なるものを引き受けている関係で、大学の私の研究室宛てで沢山の郵便物が届くのですが、その宛名の書き方について私には前から一つ疑問がありまして。 もちろん、学会のHPでは、会員の皆様に対し、本などを出版された場合は、その一部を資料室宛て、すなわち「○○大学 釈迦楽研究室宛て」でご恵送下さい、みたいなことを促しているわけですよ。それはそれでいい。 だけど、それをそのまま真に受けて、と言いますか、本当に「釈迦楽研究室」と郵便物の上に書いて送ってこられると、あれ? それでいいんだっけ? と思ってしまうわけ。受け取る側とすると、何だか呼び捨てにされたような気がしてね。 私だったらこういう場合、「○○研究室」とは書かず、「○○先生研究室」と書くんだなあ。 実際ね、私のところに届く郵便物の中にも、「釈迦楽先生研究室」と書かれているものもたまにあるんです。そういうのがあると、ちょっとホッとする。 だけど、ネットとかで調べても、こういう場合の正しい宛名の書き方って書いてないんですな。例えば「物理学研究室」とか、そういう例はあるんですけど、「研究室」の前に人名が来る場合の書き方が、ネット上でもなかなかない。 ひょっとすると、「人名呼び捨て+研究室」でいいのかも知れませんが、なんかね、ちょっとね、気になるんですわ。 「研究室」がついてなくて、ただ「田中宛て、ご送付ください」と書いてあった場合、「田中へ」とは書かないでしょ。「田中様」とか書くでしょ。だったら、やっぱり「○○先生研究室」と書いた方がいいんじゃないかなと。 ま、よく分かりません。どなたか、こういう時の礼儀について詳しい方、ご教示いただければ幸いです。
October 19, 2016
コメント(0)
-
納得できない機種変
なんかさあ、大学の各教室に備えつけのAVシステムがいつの間にか機種変されていたんだけど、これがまた滅法使いにくくて・・・。 前はね、上からバーッとスクリーンが降りてきて、そのスクリーンにプロジェクターで投影するようになっていたわけ。 ところが、新しい機種は、なんとスクリーンがなくて、教室のホワイトボードに直接投影するようになっているのよ。 これって、この時点で既にアホじゃね? だってさ、授業中、ホワイトボードはホワイトボードで使うわけですよ。そりゃそうでしょ。だからホワイトボードには文字が書かれているわけさ。 で、その途中で、じゃあ、参考映像を見ましょう、とかいうことになると、せっかく書いたホワイトボード上の文字を全部消さなきゃならないじゃん? でまた参考映像を見た後で、また元の説明に戻ろうと思うと、あ! さっきホワイトボードに書いたこと、全部消しちゃったよ、っていうことになる。 これさあ、めちゃくちゃ使いにくいじゃん。 それに、投影用のスクリーンに比べ、ホワイトボードは物理的に小さい(特に上下の幅が狭い)ので、映し出せる映像自体がすごく小さくなってしまったんですわ。字幕付きの映画とか見せようと思っても、教室の後ろの方の席の学生は小さい字幕の文字が見えないんだよね。 いやあ、今日、この新システムを初めて使ってみて、その使いにくさを実感。一体、前のシステム(全然、不満はなかったのに)を全廃して、この使いにくいシステムを導入した経緯って、どうなってんの? 誰が決めたの? 幾ら掛かったの? どうして機種の選定について、実際の使用者たる我々教員に相談がないの? 最近、こういう一つ一つのことが、教授会で審議されることなく、執行部が勝手にやっちゃうんですよね・・・。ホントに腹だたしいったらありゃしない。 頭きた。次の教授会で責任者つるし上げたる。クビ洗って待っとけって。
October 18, 2016
コメント(2)
-
ゼミOG会
今日のことと言うより昨夜のことですが、急遽、ゼミOG会が開催されまして。名古屋駅近くの寿司割烹みたいなところに個室をとって、3人でしっぽりと。 無論、卒業生との会合は、私にとって常に最重要イベントですので、どんなOG会も楽しみなのですが、昨夜の場合は、さらにめでたい条件が。 そう、実は昨夜集まったOGの一人が、近々、ご結婚されることになったのでありまーす! だから、いわば昨日の集まりは、その報告会的な感じに。ひゃー、そうだったの~! よかったね! まずはめでたい! そうとなれば、結婚・・・というか今はまだ婚約ですが、婚約に至るまでのなれそめとか、そういうヒュー、ヒューなネタをご馳走に、久々のゼミトーク炸裂! もちろんそれだけでなく、二人の近況全般もたっぷり聞かせてもらい、旧交を温めた次第。私は私で、今やっている研究のこととか、その他諸々、いい気分で話をさせていただきました。 で、つくづく思うのですが、ワタクシ、ひょっとして少人数の女子会好きかも(爆!)。結構女子力高いことは自負しているしね。そーいうの全然違和感ないし。 ということで、昨夜は実にいい気分で、ゼミOGとの久々の邂逅を満喫したのでした。 それにしても、卒業しても、時折、私の元に戻ってきてくれる卒業生って可愛いねえ! ほんと可愛い。「先生」と呼ばれる職業についてよかったと思うのは、こういう瞬間ですな。
October 17, 2016
コメント(0)
-

ゲイル・シーヒー著『沈黙の季節』を読む
ゲイル・シーヒーという女性ジャーナリストの書いた『沈黙の季節』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 『沈黙の季節』というタイトル、原題は『The Silent Passage』、すなわち『沈黙の通り道』という意味なんですが、この「通り道」というのが何を意味するかと言いますと・・・女性の更年期のことなのね。 そう! 何を血迷ったか、ついに私は更年期の本を読んでしまったの! 説明しよう。 自己啓発本の研究やっているでしょ。それで、アメリカでは戦後に生れたベビー・ブーマーが自己啓発本の最大読者層を構成しているわけよ。だから、自己啓発本の歴史を繙いていくと、ベビー・ブーマーの連中が、その年代、その年代に何について悩んでいたかがよく分かるわけ。 で、1980年代から90年代にかけて、つまりベビー・ブーマーの連中が40代に差し掛かり、「もう自分も若くはないな」と思い始める頃に、「若さを保つ系」の自己啓発本がどっと生み出されると。例えば、ダイエット本とか、ヨガ本とか、ワークアウト/ジョギング本とかね。あと、サプリメントがブームになるのもこの時代。ベビー・ブーマーたちは、この時代、「老いること」への恐怖を少しずつ感じ始めていたわけですな。 で、女性にとって「老いる」ことの究極の象徴が「更年期」であったと。 しかーし! アメリカ人って全般的にポジティヴだから、「努力して若さを保とう!」という掛け声には反応するわけよ。ところが逆に、「老いを受け入れよう」という方向には、心は動かない。そこが日本の自己啓発本とは違うところで。日本では、永六輔の『大往生』とかね、「死ぬ準備」みたいな本が売れるけれども、アメリカではそういう方向はもっとも忌避すべきものであって。 だから、「更年期」という言葉、英語では「menopause」だけど、この言葉は「アメリカ最後のタブー」と言われているんですな。 アメリカっていうのは、日本人が想像する以上に宗教的な縛りの強い国なので、性的なことっていうのは全般にタブーなんだけど、それでも1950年代から70年代にかけて「性革命」ってのがあって、一応、性的な事柄については若干オープンにはなってきたわけ。 しかし、「更年期」ということだけは、その後もタブーであり続けた。女性であれば、絶対に通過する「通り道」であるはずなのに、誰もそのことを言わないので、言説が積み重なっていかない。例えば年代的にそれが近づいてきた女性が、母親に向って「お母さんの時はどうだった?」と尋ねても、「その時が来れば分かるわよ」とか、そんな感じではぐらかされてしまう。明らかに、「語りたくない話題」なんですな。 だから、1990年代になろうという時期のアメリカでさえ、更年期についての情報っていうのは、まったく存在しない状態だったんですと。 これは実際、困った状態で、例えば更年期の症状、たとえ急な発汗とかのぼせとか鬱とか、そういうのに悩まされて病院に駆けこむじゃん? そうすると、医者は男であることが多く、そもそも更年期の何たるかについて知らない。だから、全然別な診断しちゃうわけよ。 あるいは、もう少し詳しい医者になると、「あー、それは更年期ですね。もう子宮要らないから、取っちゃいましょう。そうすれば子宮がんにもなりようがないし」とか言って、子宮切除手術とか卵巣切除手術を勧めてくる。 その結果、推定の数字ですが、なんと、アメリカ人女性の3人に1人は更年期を境に子宮とか卵巣を取ってしまうんですって!! ちょっと前、アンジェリーナ・ジョリーが、「将来癌になると厭だから」とか言って乳腺とったり卵巣とったりして話題になりましたけど、これと同じ感性ですよ。 だけど、その行為は、自然じゃないわけですよね。人為的だ。だから、取ったら取ったで、色々と術後のトラブルというのは生じてくる。 例えば、確かに更年期によって女性ホルモン・エストロゲンの分泌は減るけれども、ゼロになるわけじゃない。そのゼロじゃないわずかな分泌っていうのは、女性が生きていく上で必要なものなわけ。それなのに、手術で取ってしまったら、分泌はゼロですからね。当然、身体の不調というのは出てくる。 じゃあ辛い更年期への対処法としてはどうすればいいかというと、これはもう、個人個人の体質によって、方法を変えていくしかない。 例えば単純なホルモン治療では、骨粗しょう症になったり、乳癌になる可能性が高まったりするので、遺伝的な要因から調べて、ホルモン・カクテルみたいな感じでベストの選択を探っていくとか、そういうことが必要になってくる。ま、その点については大分進化してきたみたいですけれども。 だけど、それよりも何よりも、まず必要なことは、アメリカ最後のタブーとされる「更年期」を、隠したり、恥じたりすることなく、人間のナチュラルな通過点として白日の下に晒し、その上で、この時期を通過するためのベストな選択を研究する。これが重要なのではないかと。 シーヒー曰く、思春期の身体の変化だって、それに適応するためには数年を要したはずだと。だから、更年期の身体の変化だって、同じように数年かけるプロジェクトだと思って、前向きに捉えればいいのだと。 で、さらにシーヒー曰く、更年期を通過した女性には、素晴らしい未来が待っていると。 大昔、それこそ「人生50年」と言われていた時代には、女性は子供を産むことができなくなってからあまり時間を経ずに死んでいたわけよ。だけど今は違う。今は「人生80年」の時代だから、更年期を経てからまだ30年の人生が残っている。 で、この時期、女性ホルモンが低下する一方、男性ホルモンの分泌の相対的な量が増えるので、50代、60代の女性ほど、積極性が増すと。 実際、世界を見渡しても、その年代の女性がリーダーシップを発揮し始めるということはよくある事で、例えばドイツのメルケル首相しかり、イギリスのメイ首相しかり、そしてアメリカのヒラリー・クリントンしかりでしょ。考えてみれば、大国のトップ、みんなそういった年齢層の女性になりつつあるじゃん。 つまり、男性が初老期を迎え、勢いが落ちてくるのと逆に、女性はむしろその年代から生き生きと生きられるようになる。これは素晴らしいことではないかと。 「沈黙の通り道」の向こう側には、光り輝く人生の時が待っているんだから、女性達よ、更年期なんかに負けるな! ・・・というのが、ゲイル・シーヒーがこの本の中で語っているメッセージなんですな。 というわけで、この本、1990年代初頭にアメリカで大ベストセラーになりまして、だからこそ、自己啓発本の歴史の中では見落とせない一冊なんですけれども、それにしても、まさか男のワタクシが、こんな本を読む時が来るとはね。普通の意味でのアメリカ文学の研究をしていた時には想像もできなかったですが。 でもね、読んだ今では、読んで良かったと思っているのよ。だって、やっぱり分らないもんね、男には。更年期の女性の苦しみなんて。だから、せめて頭の中でもそのことを理解していればさ、少しは違うでしょ。 それに、考えてみれば、要するに私の年代じゃん、今、更年期を迎えている女性たちって。親しい同級生、親しいゼミ仲間の顔が思い浮かぶんだもの。だから猶更、女性達よ頑張れと言いたいですな。これを越せば、すごく明るい、ポジティヴな人生が30年間続くんだからねと。男からすれば、むしろ羨ましいくらいのもんですわ。【中古】 沈黙の季節 更年期をどう生きるか /ゲイルシーヒー【著】,樋口恵子【訳】 【中古】afb価格:198円(税込、送料別) (2016/10/16時点)
October 16, 2016
コメント(0)
-
ブックオフで本を売る
今日は土曜日ですが、勤務先大学で「保護者懇談会」なるものが開かれた関係で、休日出勤とあいなった次第。 しかし、転んでもタダでは起きない私は、この機を逃さず、前々から懸案のあることを決行! それは、ブックオフに本を売る、という作業だったのでありまーす。たまたま保護者懇談会にもう一人、同じ科の若手の先生が駆り出されていたのをいいことに、彼に手伝ってもらって、研究室の書棚を整理した時に出た「多分、もう読まないであろう本」を段ボール4箱分、ブックオフに売り払うことにしたわけ。 で、この4箱の段ボールをえっちらおっちらクルマに運び、大学からクルマで5分ほどのところにあるブックオフに向かったと。 で、計算してもらったところ、おいくらになったと思います? 私は1000円くらいにはなるだろうと予測、手伝ってくれたF先生は「どーせ350円くらいにしかならないんじゃないですか」とお見限り。 結果から申しますと、この賭けは私の勝ちで、全部で1450円ほどになったのでした。 持っていった本の中には値段のつかない本(洋書など)も結構ありましたが、文庫本なんかは大体1冊5円、普通の本で10円から80円といったところ。一番高い値がついたのは、比較的最近出版された、割と評判の良かった単行本本で、250円でとってもらいました。 しかし、明細をよく見るとアレだね、ブックオフでも、必ずしも一律の買い取り値段ではなく、ある程度は買い取り額に差があるのね。ごく当たり前の文庫本なんかは一律5円だけど、売れ行きの良さそうな文庫本であれば10円とか20円とか、中には80円くらいで取ってくれたのもあったし。その辺は、何か基準があるのでしょう。 ま、でも、全体として予想よりは高く買い取ってもらえたので、良かったかな。 もっともゲットした1450円は、新たに買った古本2冊と、手伝ってくれたF先生に喫茶店でコーヒーとケーキをおごったら、それでおしまいになってしまいましたけどね。ま、そんなもんでしょ。 でも、せっかくブックオフで本を売ったのに、結局またそこで本を買っちゃうんだから、いかんよね。こんな調子だから、早晩、また書棚がパンクすることになるのでしょう。 ちなみに今日、ブックオフで私が文化財保護した本は、 ○林望著『リンボウ先生の新味珍菜帖』(108円)○常盤新平著『山の上ホテル物語』(200円) の2冊。先日「もう常盤新平の本は買わない」と宣言したばかりなのに、また買ってるよ。ま、これは私が読むというよりは、父が常盤新平ファンなので、父用に買ったもの。一方のリンボウ先生の本ですが、これは私が林望先生のファンなのでね。既に相当数あるコレクションに加えようかなと。 ま、今日はそんな一日でございました。
October 15, 2016
コメント(4)
-

祝! ボブ・ディラン受賞
1993年にトニ・モリスンが受賞して以来、アメリカ人作家のノーベル文学賞受賞が途絶えていて、順番からいってそろそろアメリカ、来るだろうと思っていたんですけれども、そこへもってきて昨夜のボブ・ディラン受賞の報! いやあ、目出度い! ちなみに、今から5年前、2011年10月5日付の本ブログにおいて、私、ボブ・ディランの授賞を予想しておりました。下にその文章を引用しておきましょう: ・・・で、めぼしい候補者となると、トマス・ピンチョン、ボブ・ディラン、フィリップ・ロスあたり? あとはちょいと確率が下がってジョイス・キャロル・オーツ、コーマック・マッカーシーとか? ま、オーツとマッカーシーはないな。ボブ・ディランも、うーん、多分無理かな・・・ 「多分無理」と言っちゃってますが、これはディランが基本、文学者というよりは歌手だったからで、歌手に文学賞ってあるかな? と、そこに若干の留保があったから。一応、「取るとしたら・・・」の候補には挙げていたのよ。 それにしても、ボブ・ディランへの授賞を決定したノーベル財団、大英断だったのではないでしょうか。ひょっとしたら、各界から批判があるかも知れないけれど、私は断然、この英断を支持します。 大体さ、トーマス・マンとかゴールズワージーとか、アンドレ・ジッドとかヘルマン・ヘッセとか、フォークナーやヘミングウェイ、スタインベック、カミュ、そう言った連中が受賞していた頃と比べ、最近はどうよ。マリオ・バルガス・リョサとかドリス・レッシングあたりはまあいいとして、あとはよく知らない人ばっかりじゃん。 昨年受賞した人だって、誰だったか覚えてもいない。スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチって誰よ? 他方、ボブ・ディランだったら、この先十年、二十年経ったって「確かその辺りでボブ・ディランが受賞した」ということは覚えていられるんじゃない? やっぱり文学なんて、人に読まれ、その一節でも記憶されてなきゃ意味がない。その意味で、ボブ・ディランの歌、ボブ・ディランが書いた歌詞は、何十年に亘って、多くの人々の心に残ってきたんだからね。十分、ノーベル文学賞の受賞に値しますよ。 ということで、今日は私も、持っているボブ・ディランのCDでも聴いて、答えを風の中に捜そうかな。ザ・ベスト・オブ・ボブ・ディラン [ ボブ・ディラン ]価格:2411円(税込、送料無料) (2016/10/14時点) ところで、今回のボブ・ディランの受賞は、「詩人/小説家以外でも、文学的価値があれば、授賞対象になりうる」ということを示した意味でも、意義深いかもね。 例えば私は、長年このブログで「クロード・レヴィ・ストロースにノーベル文学賞を授与するべきだった」と言い続けてきましたが、同様の意味で、「ノーム・チョムスキーにノーベル文学賞を与えるべき」と、改めて主張しておきましょう。「人間の言語習得」という大きな謎に一つの解答(仮説)を与えたという点で、すなわち「ことば」という、人間ならではの問題に深い洞察を加えたという点で、十分、文学賞を授賞すべき理由があるのではないかと。 ま、私の意見というのは、たいてい世間様と一致しないので、チョムスキーの受賞、さすがに無理かな。
October 14, 2016
コメント(0)
-
出張先小学校で大変な事故が・・・
昨日、今日と二日連チャンで知多半島出張。今日も今日とて、教育実習生の研究授業の参観でございます。 が! 今日もまた事件が・・・。 ちょうど私がその小学校に到着した時、警察だとか消防だとかがグラウンドを占拠してたんですよ。それも、やけにものものしい雰囲気で。 で、そんな状態ですから、来客用の駐車場にクルマを止めることができず、出迎えてくれた教職員の先生に誘導されて、別な場所へ。 で、ようやくクルマを止め、校舎の方に向かって歩きながら、その教職員の方に「これは一体何事ですか?」と尋ねると、その先生曰く、「実はついさっき、業者の方が転落しまして・・・」と。 業者が? てんらく? さらに詳しく聞くと、どうも校舎の窓ガラスを清掃する業者の方が、業務中に校舎3階から転落してしまったらしいんですな。それで、気の毒なことにその方は大けがをなさり、ドクターヘリで病院に搬送されたとのこと。 道理で! さっき学校全体に霧がかかったみたいになっていたのは、ヘリコプターが舞い上げたグラウンドの砂のせいか! でまた、さらに都合の悪いことに、たまたま私が参観することになっていた授業が行われる教室の廊下の外窓が、その業者さんが転落した場所だったもので、当該の授業中ずっと、警察の連中が4、5人で現場検証をすることになっちゃって。そんな感じですから、生徒さんたちの気も散りますわなあ。 っていうか、参観している私も、気が散って散って。参観どころじゃないよ。 ということで、教育実習の総仕上げたる研究授業が、さんざんなことになってしまったのでした。 でもね、なんかさあ、私、よく経験するのよ、こういうの。こういう事件とか事故とか、招く力があるらしくて。マジで「嵐を呼ぶ男」なんだよね。 これって、新聞ネタかなあ? 明日の地方版とかに取り上げられたりして。とにかく、大けがをされたお気の毒な清掃業者さんが一日も早く回復されることをお祈りいたしております。
October 13, 2016
コメント(0)
-
知多半島出張
今日は勤務先大学の学生が教育実習をやらせていただいている小学校にお邪魔し、研究授業の参観をしてまいりました。 だ・け・ど。 もう大変だわ。小学校。とんでもないことになっとる。 学習に適応できない児童が一クラスに5人くらい居るんだもん。大変よ。授業している先生の他に、それら授業に対応できな子供たちをなだめたりすかしたりするために2人の先生が付きっきりだからね。 で、あとで聞いたら、私が担当した教育実習生も、実習中に生徒にみぞおちを蹴られて泣き出してしまったこともあったのだとか。授業中に教室中を歩き回っていた子供が、足に躓いたとかそんな理由で他の子供と掴み合いの喧嘩を始めてしまったので、それを仲裁していたら蹴られてしまったのだそうで。 また、参観が終って帰ろうと校舎の外に出たら、授業中にふらふら外に遊びに出ていた子供を教室に連れ戻すのに何人んかの先生方が四苦八苦していたし。 でまた、これも実習生から聞いた話だけど、最近の小学校2年生って、ものすごい下ネタを言って来るのだそうで、耳を疑うことが多かったのだとか。また実習生(女子)の服を脱がそうと、スカートのファスナーを降ろそうとしたり、ブラウスのボタンを外そうとする子も多く、それをとがめると逆上して蹴ってくるので、もう毎日スーツに靴跡が付いたり、ベルト通しが破れたり、ボロボロになってしまうそうで。 これ全部、小学校2年生の話ですからね・・・。 もうさ、国会議員、全員、小学校に行って、今日本がどうなっているか、見て来いって。 というわけで、惨憺たる教育現場を見て暗澹たる思いを抱かされた私。このままじゃ帰れないなと思って、ちょいと寄り道して、半田の赤レンガ建物を見に行っちゃった。 半田というのは、味噌とか醤油とか酢の醸造が盛んなところですけれども、かつてここに「カブトビール」というビール会社がありまして。札幌にあるサッポロビール、東京のヱビス、横浜のキリン、大阪のアサヒと並んで、我国の5大ビールメーカーと呼ばれていたんですな。で、その赤レンガで出来た醸造所跡が、今は半田市の所有となり、再建されて、今は市民に公開されている。 で、その赤レンガ建物、設計したのは妻木頼黄(つまき・よりなか)といい、辰野金吾、片山東熊と並ぶ明治の建築界の三巨頭の一人。この人は横浜の赤レンガ倉庫や、横浜正金銀行本店(現・神奈川県立歴史博物館〉なんかを設計した人。だから、半田の赤レンガも見事なものでございました。 だってさ、ビールの醸造には、外気温の影響を極力受けないようにすることが肝要だということで、この赤レンガ建物、外壁が煉瓦積み5層造りになっていて、その5層の間にある空気の層によって室内の気温が外気温に左右されないようになっていたりするわけ。5層だよ、5層。ちなみに、煉瓦の積み方にはイギリス式とフランドル式があって、半田の赤レンガ建物はイギリス式だ、なんてことも勉強させていただきました。 このカブトビールにしても、半田地方の醸造技術をビール造りに活かすため、ドイツから技師を呼びよせ、本格ドイツ式のビール醸造法を学んだのだとか。明治20年頃の話ですけれども、その頃から日本の企業っていうのは、野心と向上心と探求心があったんだなと。 で、私はこれらのことを学んだ後、復刻されたカブトビールを一瓶買い、帰路についたわけですけれども、21世紀の日本の教育現場の荒廃ぶりと、明治期の日本企業の先進性を比べつつ、一体、日本はどんな進歩を遂げたんだろうと、考えこまざるを得なかったのでございます。
October 12, 2016
コメント(0)
-
漫勉
浦沢直樹さんの『漫勉』という番組、現在の日本を代表する漫画家の方たちの仕事現場を丹念に撮影し、その撮影したものを見ながら、当該の漫画家さんと浦沢さんでトークする、という内容なんですが、私は最初のシーズンから見ていて、今シーズンも堪能しておりました。 それで今日は、録画しておいた今シーズンの最終回、浦沢直樹さんご本人の回を見たのですけど、やっぱり面白かった。 今回は、浦沢さんが現在連載中の作品『ビリー・バット』の最終回の制作過程を、ネーム(構成)の段階から見せるという、いわば創作のエッセンスが詰まったような、本来なら決して表に出さないようなところから見ることができた回で、見ていて唸りましたね。 漫画の創作って、ストーリーを紡ぐだけではなく、それをコマ割りして、絵に描いて・・・といった作業まで全部含まれるわけでありまして、言ってみれば、何百人ものスタッフで作り上げる映画を、たった一人で(もちろんアシスタントが入ることもありますが)作ってしまうような、しんどい作業であるはず。その修羅場を、黙々とこなしていく浦沢さんのカッコいいこと! 大事な場面だからといって、変な気合を入れたらダメで、「いつものお絵描き」のつもりで描く、という浦沢さんですが、しかしその反対に、「好きなお絵描きを職業に選んだ時点で、それは単に楽しいとか、そういうレベルを越えざるをえない」という覚悟も持っていらっしゃる。その辺のことっていうのは、もう子供の頃から何十年も漫画を描き続けている中から浦沢さんだからこそ言えることで、そういうコメントの一つ一つがものすごく重みがある。 それから、仕上げをしている段階で、アシスタントの仕事に瑕瑾を見つけ、「この仕事に手抜きなんてことはないんだからな」と、若干、怒気を含んで叱りつける浦沢さんの姿なんかも、良かったねえ。 そして、8年連載を続けた『ビリー・バット』の最終回に込める情熱。これがまたねえ、いいんだなあ。 ほんと、この番組、見せるわ~。見る度に、俺も俺の仕事の中で、日本の凄腕の漫画家さんたちに負けないだけのことをしなくちゃ、という気になるねえ。 今回のシリーズはこれでおしまいで、次のシリーズは来年の3月になるようですけれども、また面白い『漫勉』を作って、勉強させて下さいと言いたいですね。
October 11, 2016
コメント(0)
-

ロバート・キヨサキ著『金持ち父さん、貧乏父さん』を読む
ロバート・キヨサキ著『金持ち父さん、貧乏父さん』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 ベストセラーになった本ですので、とっくの昔に読まれた方も多いと思いますが、私自身は今回初めて読んで、なるほどこういう本だったのか~、と。 タイトルからして、私はこの本は寓意的な本なのかなと思っていたわけよ。オグ・マンディーノの『この世で一番の奇跡』とか、スペンサー・ジョンソンの『チーズはどこへ消えた?』的な。そしたら全然違いましたね。これ、著者が体験した実話じゃん。 著者のロバートさんはハワイで生れた日系四世で、彼の父親は高等教育を受け、ハワイ教育局の局長まで務めたインテリさん。勿論、それなりの収入を得ている人。で、ロバートさんは幼少時よりこの親父さんから「いい大学に行って、大会社に勤めて、安定した暮らしをしろよ」と教え込まれる。 一方、ロバートさんの友人のマイクの親父さんというのは、学歴はあまりないのですが、地元で手広くビジネスを展開する相当なやり手。で、彼の持論は、「学校ではお金のことをまるで教えていない。だからいくらいい大学を出て、いい就職をしても、結局、金のために働き続ける負け組にしかなれない」というもの。金の為に自分があくせく働くのではなく、自分のために金に働いてもらう、そういう人生じゃなきゃつまらん、という考え方の持主。 もちろん、ロバートさんのいう「金持ち父さん」がこの人で、ロバートさんの実父は「貧乏父さん」ですな。 で、身近に、お金に対して非常に対照的な考え方をする二人の大人を持っていたロバートさんは、実父である「貧乏父さん」に従った生き方をするか、それとも親友の父親である「金持ち父さん」のアドバイスに従って生きるか、その二者択一に悩んだ揚句、金持ち父さんの方を選ぶわけですな。で、その「金持ち父さん」から金持ちになるための「虎の穴」的なトレーニングを受け続けた結果、ロバートさん自身、長じて大金持ちになると。 だから、人々にも自分のように生きたらどうか? と提案する。それがこの本の内容であるわけ。 それにしても、この本の中に描かれる「貧乏父さん」の行き方/生き方が、あまりにも私自身の(私自身が教わってきた)行き方/生き方に等しいもので、まあ、厭になります。 私を含め、大概の(真面目に人生を生きようとしている)人というのは、学校時代にちゃんと勉強して、いい大学入って、安定した職業につくことができたらオンの字、と思っているわけですな。それなりに恥ずかしくない収入があればいいし、もしもっと収入を上げたかったら、今よりもっと一生懸命働けばいい。それで家を買って、子どもをいい大学に入れて、そしてその揚句、子どもが自分と同じような安定した職業についてくれれば、もう心配することはない、的な。 ところが、まさにこの考え方が「貧乏人の発想、負け組の人生だ」と言われちゃうんですから。 ロバートさんに言わせれば、この生き方をすると、自分が稼いだお金の相当分を税金に持っていかれるぞと。国といういじめっ子にカツアゲされているのに、唯々諾々とお金を差し出している。また、税金をガッツリ引かれた後に残ったお金で「自分の家」という資産を買ったようなつもりになっているけれども、それは「資産」ではなく「負債」であって、あくせく働いて稼いだお金も、その負債の返済のために大半が費やされてしまう。しかも、そんな状態なのに、何の不満も抱かず、そういうもんだと思っている。 一方、金持ちというのは、そういう風には行動しないと。負債ではなく、ちゃんと資産を買って、その資産にお金を生み出してもらう。だから、自分が働くのではなく、自分の代りに資産に働いてもらうのだと。しかも、税金の仕組みに通じていれば、アホみたいに税金を払うこともない。 で、この「貧乏人」になるか「金持ち」になるかの差は、ほんの少しの知識の差、ほんの少しの行動の差でしかないんだよと。お金をめぐるゲームのルールをマスターするかしないかの差であって、それは別にアインシュタイン級、ビル・ゲイツ級の頭脳なんか必要ない。だったら、金持ちの発想をするよう、ちょっとだけ努力した方がいいんじゃないの?と。 ひゃーーー。そうだったの~! で、じゃあ、つまるところ、どうすればいいの、と言う話になるわけですけれども、ロバートさんのおすすめは幾つかあって、まず「自分で会社を作れ」と。 つまりね、会社に就職するということは、その会社のオーナーを富ませるために自分の人生を捧げることを意味するんだぞと。そんな、自分から進んで奴隷になるみたいなことをするくらいなら、自分で会社を起ち上げて、自分を富ませるために、人に働かせろと。会社を興すというと、まずでっかいビルを建てなきゃならないだろうし、そんな資本は自分にはない、とか思っている奴は、まるで会社のことが分かっていない。会社ってのは、数枚の書類だけで設立できるものであって、それを作ることによって得られるメリットは計り知れないんだぞと。 ふーむ。なるほど。ま、私の親友のTは自分で会社を持っていて、時々その話を聞くのですが、確かにロバートさんの言う通りなんだよね。 とはいえ、さすがに会社を作るというのは敷居が高いというのなら、株式投資という手もある。それも、安全第一の投資信託なんかじゃなくて、見込みのある会社を自分で見つけて投資し、がっつり稼ぐというやり方。 ただ、これも普通の人は「株は怖い」っていってやらないんだけどね。 ある時、ロバートさんが友人と雑談をしていたら、その友人が「近ごろ、ガソリンの値段が上がって困る」と言い出した。で、その友人はガソリンの値段がどうして上がるか、細かいところまで状況を把握していて、その知識はロバートさんも舌を巻くほどだった。でも、だからと言って彼はそのことで何もしない。 そこでロバートさんはちょっと調べてみて、石油関係の見込みのある新興会社を見つけ、その株を買ってみた。そしたら案の定、石油価格は上昇し、その会社の株も急上昇。ロバートさんはいいところで売り抜けてひと儲けしたと。ま、情報を持っていても、「株を買う」という勇気のあるなしで、こういう差が出るわけね。 あとね、ロバートさんが勧めるのは不動産投資ね。で、ロバートさん曰く、不動産投資でも重要なのは資本ではなく、情報であると。 実際の価値はあるのだけど、価格は低い土地・建物なんてのは、実はいくらでもある。そういう掘り出し物は、不動産会社じゃなくて、裁判所が持っていたりするんですって。要するに、差し押さえ物件なんかですな。 で、そう言う物件は、えてして価値はあるのに、価格は低い。しかも、その建物の所有者は、一刻も早く処分したがっていたりする。 そこで、そういう物件を狙って、入札しちゃうわけね。で、それに適当な価格で売る。入札してから売るまで時間が掛からなければ、自分は入札のためのお金を支払うことなく、差額だけガッツリいただける。お金を稼ぐのに、元手なんていらない、といういい例ですな。 で、そこで儲かったお金をどうするかというと、次の不動産に投資する。そうすると、税金を払う必要がないから。そうやって、不動産投資で得たお金を次々に回していけば、永久に税金を支払う必要もないわけ。 あとね、不動産関連の話では、ロバートさん自身の例ではないのだけど、マクドナルドをフランチャイズ展開したレイ・クロクと言う人の話が出てきて、これがまた面白い。 レイ・クロク曰く、自分の商売は、ハンバーガーを売ることではないと。 じゃあ、マクドナルドの商売って何かというと、不動産業であると。 つまりね、マクドナルドがフランチャイズ展開をするということは、フランチャイズで店を出したがっている人からお金を受け取って、店を出すわけですよね? つまり、出店するための土地代・建物代は、フランチャイズする側が払うわけだ。 すると、マクドナルド自体がお金を出さなくても、どんどん、不動産が増えていく。しかも、マクドナルドは常に一等地に出店しますから、街の中のいい場所に、どんどん会社所有の不動産が増えていく。 だから、今やマクドナルドは、世界中の街の一等地に、とんでもない面積の不動産を持っていることになる。これがマクドナルドの資産となるわけですな。 だから、マクドナルドの本業は、ハンバーガー販売ではなく、不動産業であると。 ひょえーーー! そうだったのか! 「最近、マクドナルドのランチ戦略は迷走しているよね」とかネットで批判している連中とは別次元のビジネスが展開しているわけですな。 ま、とにかくそんな感じで、賢く立ち回ってお金を稼ぐ方法、そして資産に資産を生ませる方法を伝授しているのがこの本でございます。 もちろんね、この本読んで、それを真似したらすぐに自分もお金持ちになれました、っていうほど簡単な世界ではないとは思いますけれども、しかし、本書の至るところで指摘されている「学校では、お金を巡るゲームのことを全くおしえてくれないし、だからいい大学を出ていい就職をしたつもりでも、実は搾取されっぱなしの人生を送っていることに、大抵の人は気付きもしないんだ」ということは、まったくその通りじゃないかと思いますね。 そう言う意味で、この自己啓発本、「啓発的」であるという意味では、確かに額面通りの本ではありましたね。一度読んでみて、損はない本だと思いますよ。金持ち父さん貧乏父さん改訂版 [ ロバート・T.キヨサキ ]価格:1728円(税込、送料無料) (2016/10/10時点) ところで、不動産の話なんですけど、実は私の友人にも不動産業の男がおりまして。彼に言わせれば、「不動産業なんて簡単だよ」とのこと。 でも、資格とか、色々必要なんだろ? と私が尋ねたところ、そんなもん必要ない、俺も持ってないし、と。 彼曰く、アパートなんて買おうと思えば安いのがいくらでもある。そういうの一個買って、人に貸しちまえばいいんだと。貸すことについては、別の業者に頼めばいい。で、そうやって家賃収入を得て、その収入でまた別のアパートを買う。そういうのを繰り返せば、いいだけの話だと。 ま、そんな話を以前聞いて、ふーん、そんなもんかと思いましたけれども、今回ロバート・キヨサキのこの本を読んで、不動産投資も悪くないなと。 実は、それに関しては、一つ、いいアイディアがあるんだよね! そのうち、私もあくせくアメリカ文学なんか研究してないで、資産に資産を生ませ、自分はハワイでのんびり、なんてことになる・・・かもね!
October 10, 2016
コメント(0)
-
ヨーグルトあれこれ
最近「腸活」なんてことがよく言われるじゃないですか。「腸内フローラ」を整える、とか。 そんなこともありまして、このところ我が家では「朝、まずヨーグルトを食べる」的な習慣が根付きつつあります。 で、そんな我が家で今、流行っているのが「ヨーグルト冷製スープ」。ま、要は市販のヨーグルトにですね、フルーツ味のカルピスってあるでしょ、あれを適量ぶっ込んでグルグルと掻き混ぜ、冷たく滑らかなスープ状にして食べるというね。フルーツ・カルピスにはマンゴー味とか巨峰味とか、梨味なんてのもあるので、その時々で味を変えて楽しんでおります。 ところが! この冷製ヨーグルト・スープを作るには一つ条件がありまして。 森永の「ビヒダス」はOKなのよ。だから我が家ではこれの「脂肪ゼロ」というのを愛用しておりますが。 だけどね、明治の「ブルガリア・ヨーグルト」、これはNGなんだなあ。 なぜなら、ブルガリア・ヨーグルトにフルーツ・カルピス入れていくら掻き混ぜても、滑らかなスープ状にはならないから。どうしても固まりが残ってしまうんですな。 いやあ、ヨーグルトなんて何でも同じだろうと思ったら、ぜんぜんそうじゃなくて、メーカーによってヨーグルトの性質がまるっきり違うということ、今回初めて知りました。 もちろんね、「ブルガリア・ヨーグルト」だって、そのまま食べるんだったら美味しいのですけれども、上のような食べ方をするのだったら選ばない方がいい、ということで。別に明治乳業に恨みはないので、そこのところは悪しからず。 それはともかく、森永ビヒダスヨーグルト&フルーツ・カルピスの組合せで、しかもよーく掻き混ぜて滑らかなスープ状にして食べるというやり方、お試しあれ~。朝、最初に口に入れるものとしては、なんかすっごくヘルシーな感じで、いいですよ~!
October 9, 2016
コメント(0)
-
ブログ復活
先週、「岡山に行く」と宣言したきり、一週間ほどご無沙汰いたしておりましたが、実はこの間、近しい身内が亡くなりまして。岡山に行ったことは確かなんですが、一つ会議に出ただけでトンボ返りした次第。 この間、色々と思うこと、感じたことはあったのですが、それは自分にとっても重要な人の死に基づくものですので、ここではあれこれ書くことはしないでおこうと思っております。と、同時に、喪に服す意味もありまして、1週間ほどこのブログもお休みさせていただきました。 ということで、今日はご挨拶のみにて、明日からまた通常のお気楽日記を復活させたいと思っております。またご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。
October 8, 2016
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1