2020年12月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-

徘徊日記 2020年 12月31日 「今年も暮れてゆくわが街です。」 垂水・明石あたり
「今年も暮れてゆくわが街です。」 徘徊日記 2020年 12月31日 垂水、明石あたり 垂水の星陵台にあるアグロ・ガーデンの屋上から西を見ました。右手の給水塔のあたりの向こうが自宅です。 風は本格的に北風で雲が面白いように南に流れていきます。高速道路はとても空いていて、大晦日の様子はありませんが街は、案外にぎわっていました。 こちらは明石の「魚の棚」の年の瀬です。例年の人出はありませんが大漁旗がうれしいですね。普通なら、焼き鯛や鰤の刺身を買う所でしょうが、ぼくはハマグリと鯵を買いました。 魚の棚のすぐ近所、明石銀座にあって、いつも立ち寄る「朝霧堂」さんも、暮れの、30日、31日は本格的なお餅屋さんで、お店の前は行列でした。町の人が注文していた、お正月のお餅を次々と買い求めておられる様子はいいものですね。 とりあえず餡入りのお餅を1パック購入して、31日の夜、「焼き餅ち」でいただきましたが、まごう方なき「お餅」でした。 お店の邪魔にならないように、おおぜいの人が映らないように写真を撮ったのですが、雰囲気も全く撮れていないので、ガッカリです。 まあ、しようがないですね。この写真で2020年も撮りおさめ、徘徊おさめです。 皆さま、2021年もよろしくお願いいたします。ボタン押してね!
2020.12.31
コメント(2)
-

フランシス・フォード・コッポラ「ゴッドファーザーPARTⅢ」こたつシネマ
フランシス・フォード・コッポラ「ゴッドファーザーPARTⅢ」こたつシネマ 2020年の12月30日は「ゴッドファーザーPARTⅢ」でした。もう、なにもいう事はありませんが、アル・パチーノが日ざかりの庭で椅子から転がり落ちて映画は終わりました。 ぼくにとっては、学業も仕事も家庭もいい加減で、いろんな人に顰蹙を買っていたに違いない20代、30代に見た最後の映画で、アルパチーノがオレンジ・ジュースをすがるように飲んだシーンと、最後のシーンがすべての映画でした。 感想で書きましたが、「パートⅡ」では、たくさんの思い違いや、記憶間違いを感じたのとは好対照というか、この映画は、かなり正確に覚えていました。理由は明らかで、この映画は映画館では見たことがない作品なのです。レンタルビデオで見た映画ですが、この映画を最後にビデオも借りなくなった映画ですね。「シマクマ君、どうしたの。映画は見ないの?」「うん、映画はやめた。もう見ない。」「どうして?あんなに好きやったやないか。ザンネンやなあ。」 学生時代から親しかった友人とそんな会話をしたことを覚えていますが、ホントに30年近く映画館に行くことがほとんどありませんでした。どうして、そんなふうに思い込んで、意地を張ったのか、今思えば、よく分かるような、わからないようなことなのですが、ともかく、好きだった映画を見に行くことを30代の半ば、仕事について10年くらいのときににやめてしまいました。 それから20数年、60歳を過ぎて、仕事をやめました。で、サンデー毎日の日々が始まりましたが、本を読むことの他にすることがありません。歩いていても、海を眺めていても、過去の方ばかり眺めたがっている! そういう自分の意識に気づいて、ギョッとしました。新しい情報を入力しないとヤバイ! まあ、そこで思い浮かんだのが映画館です。それから、もう一度、映画館徘徊をはじめて3年が過ぎます。 二十代に見た映画に再会することもあります。昔見て印象に残っている作品との再会は、初めてみる映画とは違う感動というか、動揺というか、刺さってくるものがありますね。映像には、小説とかとは違う力があるのかもしれません。 今年も、新しい映画と古い映画いろいろ観ましたが、一年の終わりに偶然、いつもはほとんど見ないテレビ放映で見たアル・パチーノは、やはり、よかったですね。 昨年でしたか「アイリッシュマン」という映画で久しぶりに顔を見ましたが、愛娘ソフィアの死に叫び声をあげたシーンや、椅子から転げ落ちたマイケル・コルレオーネを演じたアル・パチーノを、アル・パチーノだと記憶してしまっている老人には、なんだか不思議な出会いでした。それは、理屈では説明できないのです。 2021年は、どんな映画と出会うのでしょうね。とりあえず、切符を予約して最初に見るのは「天井桟敷の人々」です。この映画とも、40年ぶりの再会です。たのしみですね(笑)。 それではみなさん、よいお年をお迎えください! 来年も「ゴジラブログ」よろしくお願いします。監督 フランシス・フォード・コッポラ脚本 マリオ・プーゾ フランシス・フォード・コッポラ製作総指揮 フレッド・フックス ニコラス・ゲイジ製作 フランシス・フォード・コッポラ撮影 ゴードン・ウィリス音楽 カーマイン・コッポラ編集 バリー・マルキン リサ・フラックマン ウォルター・マーチキャストアル・パチーノ(Michael_Corleone)ダイアン・キートン(Kay_Adams)タリア・シャイア(Connie_Corleone_Rizzi)アンディ・ガルシア(Vincent_Mancini)イーライ・ウォラック(Don_Altobello)ジョー・マンテーニャ(Joey_Zaza)ジョージ・ハミルトン(B._J._Harrison)ブリジット・フォンダ(Grace_Hamilton)ソフィア・コッポラ(Mary_Corleone)1990年・162分・アメリカ原題「The Godfather Part III」2020・12・30こたつシネマ
2020.12.31
コメント(0)
-

フランシス・フォード・コッポラ「ゴッドファーザーPART II」こたつシネマ
フランシス・フォード・コッポラ「ゴッドファーザーPART II」こたつシネマ 夕食を食べて、ボンヤリ、テレビ画面を見ていると映画が始まりました。いつもならテレビの人チッチキ夫人はPC相手になんかしていて、しようがないので見続けていると、どっかからアメリカにやって来た少年が入国審査を受けて、言葉ができないからでしょうか、黙っていると「ヴィトー・コルレオーネ」と名付けられて、その上、天然痘を宣告され病室に連れていかれました。 第一部でマーロン・ブランドが演じたゴッド・ファーザー、ヴィトー・コルレオーネに、彼の出身の村の名前が付けられた瞬間ですね。 フランシス・コッポラの名画、「ゴッド・ファーザーⅡ」が始まっていました。NHKの衛星放送です。ここからテレビにくぎ付けでした。久しぶりに見たのですが驚いたことが二つありました。 ひとつは、若き日の父ヴィトー・コルレオーネを演じているのが、ロバート・デニーロだということに気付かなかったことです。 ニュー・ヨークのヤクザ、ファヌッチを暗殺する、きっと有名なのでしょうね、アパートの暗い廊下の踊り場のランプが点滅する場面で、浮かび上がってきたコルレオーネの顔を見て、「あっ、デニーロだ。」と叫びそうでした。 まず、ぼくは、どちらかとういうと、遅れてきたマーロン・ブランドファンで、「波止場」とか「欲望という名の電車」は見たことがないまま、「ゴッド・ファーザー」で見て、それから、間に、たしか「ラスト・タンゴ・イン・パリ」、「ミズーリ・ブレイク」、「スーパーマン」を挟んで、「地獄の黙示録」のカーツ大佐までのマーロン・ブランドに夢中で、どの映画も封切で見た記憶があります。 今でも好きな俳優ですが、当時、どこが、そんなに好きだったのかよく覚えていません。 というわけで、今回、この映画を見ていて、声がマーロン・ブランドによく似ているのですが、この役者はいったい誰なんだと、首をかしげていたわけです。 で、彼が暗がりから浮かび上がった顔を見て、ギョッとしたわけです。この映画では最後のほうで、ヴィト―・コルレオーネがシチリア島のマフィアの親分を殺すシーンがありますが、そこで、確かにロバート・デニーロだと、もう一度気付き直して唸りました。 ぼくは、この映画も封切りで見ましたが、ロバート・デニーロは「タクシー・ドライバー」で初めて見た役者だと、今日まで思い込んでいたわけです。 蛇足ですが、「タクシー・ドライバー」という作品は、「ゴッド・ファーザーⅡ」の翌年ぐらいの封切で、見たのは後だったはずです。これは、まあ、記憶違いとかではなくて、単なる「無知」を確認したということですね。 二つ目は、記憶違いの話です。 ぼくは、アル・パチーノという、この映画の主演俳優も、ずっと好きだったのですが、この人を最初に見たのは「スケアクロウ」でジーン・ハックマンと歩いていた姿か、「狼たちの午後」でジョン・カザールと銀行強盗をしていた姿だったと思い込んでいたのですが、ちがいました。「ゴッド・ファーザー」が、最初だったのですね。 「ゴッド・ファーザー」、「スケアクロウ」、「ゴッドファーザーⅡ」、「狼たちの午後」の順に封切られていたのでした。 同じような、思い違いは映画の中にもありました。 この映画のアル・パチーノはこの写真で有名だと思うのですが、ぼくは、この写真のシーンがラストシーンだと、マイケル・コルレオーネが、ドン・コルレオーネになった、このシーンで映画は終わっていたと思い込んでいましたが、ちがいましたね。 この後、ジョン・カザールが演じる兄のフレッドの死を描く湖のシーンがあって、それは、このシリーズではとても大切な逸話なのですが、そのあとのアル・パチーノの表情が映るんですね。忘れていました。 もっとも、ぼくの記憶の中にはアル・パチーノと共演するジョン・カザールという俳優さんは、損な役まわりばかりしている印象があります。「狼たちの午後」でも、あっけなく撃ち殺されるのはジョン・カザールのほうだったと思います。でも、ジョン・カザールという早死にした俳優さんは、そんなふうにいうのは失礼な名優で、記憶に残る人なのですが、なぜかこの映画では、その死のシーンを忘れていました。 人さまから見れば、あほらしい思い出を書きましたが、今回テレビで見ていて、なぜ、こんなに面白いのか、ホントに面白かったですね。 40年以上前に封切で見て、その後も何度かビデオとかで見ていると思うのですが、今回が一番面白かったと感じました。 アル・パチーノやロバート・デニーロはもちろんですが、ダイアン・キートンやジョン・カザールをはじめ、わき役たちの、その場その場の表情が何とも言えませんね。瞬間、瞬間が記憶に残るような印象でした。「ゴッド・ファーザー」は見損ねましたが、こうなったら「ゴッド・ファザー Ⅲ」も、続けて見ないわけにはいきませんね。監督 フランシス・フォード・コッポラ製作 フランシス・フォード・コッポラ原作 マリオ・プーゾ脚本 フランシス・フォード・コッポラ マリオ・プーゾ撮影 ゴードン・ウィリス美術 ディーン・タボウラリス衣装 セオドア・バン・ランクル編集 ピーター・ツィンナー バリー・マルキン リチャード・マークス音楽 ニーノ・ロータ カーマイン・コッポラキャストアル・パチーノ(マイケル)ロバート・デュバル(義兄トム・ヘイゲン)ダイアン・キートン(妻ケイ)ロバート・デ・ニーロ(父ヴィトー・アンドリーニ・コルレオーネ)タリア・シャイア(妹コニー)ジョン・カザール(兄フレッド)1974年・202分・アメリカ原題:The Godfather: Part II2020・12・29こたつシネマno6
2020.12.31
コメント(0)
-

週刊 マンガ便 こうの史代「この世界の片隅に(上・中・下)」(双葉社)
こうの史代「この世界の片隅に(上・中・下)」(双葉社) 2020年も終わろうとしていますが、今思えば、コロナ騒ぎが最初の頂点を迎え、政治家のインチキが、あっちでもこっちでも露呈しはじめた2020年の4月ゆかいな仲間のヤサイクンのマンガ便に入っていたマンガでした。 こうの史代「この世界の片隅に」(上・中・下)(双葉社)です。 すぐに読みましたが、なかなか、思うように感想が書けないまま放っていました。 この作品は、広島で育ち、隣町の呉の北条周作のもとに嫁いだ浦野すずという主人公の、戦時下の日々の暮らしを描いた物語でした。ぼくが知らなかっただけで、アニメ映画として評判になり、単行本のマンガもよく読まれている作品であるらしいですね。誰でも知っている物語のようなので、ここでは筋書きの紹介はしませんね。 ぼくは、アニメも見ていませんし、評判になっていたらしいこのマンガも読んでいませんでした。ヤサイ君のマンガ便がなければ読むことはなかったでしょう。 ところが、最近「ペリリュー」という武田一義のマンガを読みながら、 「そういえば、あのマンガの主人公も漫画を描きたかったんだよな・・・」 と思い出したのが、このマンガの主人公すずのことでした。 彼女は戦地に出征した兵士ではありませんが、戦地で命懸けの男の人に代わり、一人でも多くの男の子を生むのが「義務」だと考えるような、純朴な女性です。にもかかわらず、子供が出来ずに悩むすずが、遊郭の女性白木リンと語り合うこんなシーンがあります。「ほいでも周作さんもみんなも楽しみしとってのに子供が出来んとわかったらがっかりしてじゃ」「周作さん?」「あ 夫です」「あんたも楽しみなんかね?」「はあ まあ・・・」「うちの母ちゃんはお産のたびに歯が減ったよ しまいにゃお産で死んだよ それでも楽しみなもんかね?」「そりゃあまあ・・・怖いこた怖いけど ほいでも世の男の人はみな戦地で命懸けじゃけえこっちもギムは果たさんと」「ギム?」「出来のええアトトリを残さんと それがヨメのギムじゃろう」「男が生まれるとは限らんが」「男が生まれるまで産むんじゃろう」「出来がええとも限らんが」「予備に何人か産むんじゃろう」 すずは、子どもができないことで、嫁ぎ先に居場所がないことを不安に思い、子どもを産めない女性が実家に帰されるということを、素直に信じる女性でもありました。 そんなすずを「売られてきた女性」白木リンはこんなふうに慰めます。 「ああ、でも子供が居ったら居ったで支えんなるよね」「ほっ ほう! ほう!! 可愛いし‼」「困りゃ売れるしね!女の方が高いけえ、アトトリが少のうても大丈夫じゃ 世の中、巧うできとるわ」「なんか悩むんがあほらしいうなってきた・・・・」「誰でも何か足らんぐらいで、この世界に居場所はそうそう無うなりゃあせんよ すずさん」「有難うリンさん」 ここに、このマンガの読みどころの一つがあると思いました。白木リンがどんな人間にもこの世界の片隅に 「生きる場所」というのはなんとかあるものだと教えるなにげないシーンですが、落ち着いて読み返すと哀切極まりないシーンなのです。 二人が、仲良しになって、悲しい会話をしたこの時にすずには、戦火の下とはいえ、まだ、大好きな絵を描く右手がありました。そして、苦界で生きる白木リンにも、永らえる「いのち」があったのでした。 やがて、ペリリュー島で田丸1等兵たちが苦労して守っていたはずの「本土攻撃」の防衛線は、肩透かしのように突破され、東洋一の軍港の町「呉」もアメリカ軍の空襲にさらされていきます。そんな戦況の中で、すずは街角の不発弾に遭遇し、手を引いて歩いていた6歳の姪、晴美ちゃんの命と、つないでいた自分の右手を一緒に失います。 「この世界の片隅に」居場所を失ったように苦しむすずは「居場所はそうそう無うなりゃあせんよ!」 と励ましてくれた、白木リンを探しますが、彼女は居場所だった遊郭ごと、「この世界の片隅」から消えていました。 敗戦の日のシーンです。 ああ、暴力で従えとったいうことか じゃけえ暴力に屈するいう事かね それがこの国の正体かね うちも知らんまま死にたかったなあ・・・ この世界に取り残されたことを、もだえ苦しむすずの頭を、天から降りてきたのでしょうか、やさしく、頭を撫でてくれる「右手」 が描かれます。 戦死した兄、要一の石ころ入りの骨壺。爆弾に吹き飛ばされた姪の晴美。やっと、友だちになれて、話ができたのに遊郭ごと消えた白木リン。1945年8月6日から行方不明の母。原爆病で起き上がれない妹のすみ。 すずの失われた「世界」 が、次々と想起される中で、幻の「右手」が彼女の居場所がまだあることを教えるかのようです。 焼け野原の呉の街で拾った戦災孤児を背負って歩いている周作とすずの後ろ姿が描かれ、マンガは、再び「この世界の片隅」のような北条家の居間に戻っていきます。 戦後社会への着地の仕方が、とてもソフトなところに好感を持ちましたが、何よりも「マンガを描きたかった!」 浦野すずという設定と、あくまでも小さな日常にこだわった筋運びに、戦後70年たって書かれている戦争マンガの新しさを感じました。 蛇足のようになりますが、宗教学者の島薗進という方が「ともに悲嘆を生きる」(朝日選書)という本の前書きで、執筆の数年前に流行った3本の映画、「シン・ゴジラ」と「君の名は」、そして「この世界の片隅に」を見たことを話題にしてこんなことをおっしゃっていました。 「シン・ゴジラ」と「君の名は」は見ごたえはたっぷりあるが、観客も涙を流すような感動はなかった。 ところが、「この世界の片隅に」は見応えがたっぷりあるとともに深く心を揺さぶられた。こうの史代の同名のコミック作品に基づく、片渕須直監督の作品だ。そこですぐ原作を買って読んだ。2006年から09年にかけて発表された作品だが、予想にたがわずため息をつきながら読みふけった。 そして、それは悲嘆が身近に感じられる21世紀の現代という時代と深い関わりがあるように感じた。 ぼくが、気になるのは、このマンガが、なぜ、今、みんなに受け入れられたのかということですが、島薗さんは、始まったばかりの「21世紀という社会」には、「悲嘆」の方向に動きやすいの空気が漂っていて、そのことと、このマンガの描く「世界」が繋がっていると論じておられますが、そうなんでしょうか。 そういえば、お葬式の作法とか、そっち方面の話が映画になったりしたのは今世紀に入ってからですね。島薗さんの御意見は、そのうち「案内」するかもしれませんが、とりあえず、そちらの本のほうで直接ご確認いただきたいと思います。追記2021・08・06 コロナの感染者数が日々新記録を刻んでいますが、大運動会の報道に夢中にみえるNHKという「公共放送(?)」は大運動会の報道に夢中で、この世界で本当に起こっていることからはかけ離れた「公共(?)」ぶりです。 そのうえ、例年、8月6日に放送していた「原爆」特集番組を、こっそり、取り止めにしたりしているようです。 なんだか。恐ろしい時代の始まりを演出して、いい気になっている夜郎自大なものを感じます。本当に気味の悪いことですね。
2020.12.30
コメント(0)
-

ワン・ビン「死霊魂」元町映画館no66
ワン・ビン「死霊魂」元町映画館 ワン・ビン、漢字で書くと王兵、1967年生まれの監督らしいですが、これまでの彼の映画を、ただの1本だって見たことはありません。今回は「死霊魂」という題名には、少し及び腰になりましたが、506分という作品の長さに惹かれて予約しました。 今までに見た長尺映画といえば、ランズマンという人の「ショアShoah」の9時間30分が最長ですが、まだ、元気だった20年ほど昔に観ました。この作品は8時間30分で、二番目の長さです。昨年観たタル・ベーラ監督の「サタン・タンゴ」は7時間とちょっとでしたから、それよりも1時間以上長いわけです。 徘徊老人シマクマ君になってからは、最長の映画です。見ないわけにはいきませんね(なんでやねん!)。 帰りの時間を考えると、駐輪場が閉まってしまうのでバスで出かけました。元町映画館は66席のミニ・シアターですが、今回は33席の上映でした。ぼくには好都合でしたが結構すいていました。 お昼の12時30分に始まった映画は、途中2回の休憩をはさんで、21時30分に無事、終了しました。 あざとい「けれんみ」もなく、声高な主張や体制批判もない、話す人の表情を淡々と撮り続ける映画でした。 想田和弘監督の「観察映画」と自称するドキュメンタリー映画の手法がぼくは好きですが、あの感じと少し似ていると思いました。 映画のチラシには「我々の時代の『ショア』だ」という宣伝文句がありましたが、あの映画とは少し違うと思いました。 たしかに中国現代史の「闇」を抉り、白日の下にさらす「怒り」と「告発」の証言集のような趣で見ることは可能ですし、そう見るように宣伝されているようですが、ぼくの印象では「ショア」のランズマンにはカメラを「武器」にして、事実で「悪」を抉るような意図を感じたのですが、この映画は、最後まで、そういう政治的、社会的な意図を感じることはありませんでした。むしろ、ある時代を「生きて」、「死んだ」人々に対して、能うかぎり「零度の映像」として8時間30分、10年以上にわたって撮り続けたフィルムに焼き付けられた「事実」を差しだそうとする「静かな意志」 を感じました。 隠された事実を掘り起こし、生きている人の証言と生活を丁寧に記録しているこの映画が、おそらく、現代中国で公開されることはないだろうという意味で、中国が「収容所国家」であるということは明らかです。加えて、映像の中で語り続けられる証言によって、証言者たちが経験した共産主義の理想の「再教育」という政策が、「共産主義」とは縁もゆかりもない、権力の都合によって意図された政治的粛清事件であったことも明らかにされています。 しかし、同じ人物の10年を越えた、二度、ひょっとすると数度にわたるインタビュー、時間の経過とともに事実に気付き始める証言者の悲嘆、名誉回復が言葉遊びで出会ったことに対する絶望、証言者の隣に座り、自らも語り始める妻や、声をかける家族を撮り続けた監督ワン・ビンのこのフィルムには、センセーショナルな告発や批判を目的にした「熱」を感じることはありませんでした。 彼が描こうとしているものは、もっと、根源的な人間の有様であったように思えたのです。 甘粛省・夾辺溝・明水という地名を聞いて、ああ、あのあたりだと見当がつく人は、多分そんなにはいないのではないでしょうか。 「一帯一路」という習近平の経済政策が話題になっています。北京から2000キロ、新しい高速道路が計画されているそうですが、あの計画にでてくる中国地図の西北の果てです。歴史好きの人なら「敦煌」というシルクロードの都市の名を上げればイメージされるでしょうか。 映画のラスト、カメラマンの動きに合わせて動くデジタルカメラが、荒涼とした明水の砂漠を映し出しています。「再教育収容所」と名付けられた施設が、1950年代の終わりに設置され、1961年に閉鎖された跡地です。 半世紀の時間が流れたはずの大きな砂の窪地のような、かつての住居跡には、風にさらされた人骨があちらこちらに転がって放置されています。 カメラは立ちどまり、次の場所でまた立ち止まり、また、次の場所へと動き、足早に歩く足音と風の音が聞こえてきます。 枯れ枝を踏み、砂を蹴る足音と風の音が「事実」の重さを、ぼくの脳裏に刻み込んでいきます。クローズ・アップされた砂漠に転がっている髑髏(シャレコウベ)たちが訴えかけてきます。「どうか、この俺たちのことを忘れないでくれ。」 この映画が、最後になって「熱」を帯びた瞬間にエンドロールが廻りはじめた、そんな印象でした。 陳腐な事実隠しにうんざりし、コロナの猖獗になすすべもない権力を目の前にした2020年でしたが、年の暮れに、途方もなく大きな「悪」と、それでも前を向いて生き続ける人間の姿にゆっくりとうちのめされる8時間30分を経験しました。傑作です。監督 ワン・ビン王兵製作 セルジュ・ラルー カミーユ・ラエムレ ルイーズ・プリンス ワン・ビン撮影 ワン・ビン2018年・506分・フランス・スイス合作原題「Dead Souls」2020・12・26元町映画館no66追記2020・12・29 盛唐の詩人李白に「子夜呉歌」という漢詩があります。高校の教科書にも出てくる有名な詩ですが、「玉門関」に派遣された兵士の妻が、夫を想う詩です。この地の果ての地名が、この映画の舞台でした。 何となく、ぼくでも知っているということで思い浮かべた詩なのでここに載せておきます。 子夜呉歌 李白長安一片月 長安一片の月萬戸擣衣聲 萬戸衣を擣(う)つの聲秋風吹不盡 秋風吹いて盡きず總是玉關情 總て是れ玉關の情何日平胡虜 何れの日にか胡虜を平らげて良人罷遠征 良人遠征を罷めん
2020.12.29
コメント(0)
-

週刊 読書案内 辻征夫「突然の別れの日に」(「辻征夫詩集」岩波文庫)
辻征夫「突然の別れの日に」(「辻征夫詩集」岩波文庫) 突然の別れの日に知らない子がうちにきて玄関にたっているははが出てきていいまごろまでどこで遊んでいたのかと叱っているおかあさんその子はぼくじゃないんだよぼくはここだよといいたいけれどこういうときは声が出ないものなんだその子はははといっしょに奥へ行く宿題は?手を洗いなさい!ごはんまだ?いろんなことばがいちどきにきこえるああ今日がその日だなんて知らなかったぼくはもうこのうちを出て思い出がみんな消える遠い場所まで歩いて行かなくちゃならないそうしてある日別の子供になってどこかよそのうちの玄関に立っているんだあの子みたいにただいまって 「辻征夫詩集」岩波文庫 谷川俊太郎が編集している、岩波文庫版の「辻征夫詩集」を読みました。高橋源一郎の小説「日本文学盛衰史」(講談社文庫)を読んでいて、「きみがむこうから」という、作中に引用されていた詩が気になりました。あれこれ探しているのですが、今のところ見つかりません。 思潮社の「現代詩文庫」の最初のシリーズの「辻征夫詩集」に入っているようですが、その詩集が見つかりません。 で、岩波文庫版や、おなじ思潮社の「続・辻征夫詩集」とかを読んでいます。目的の詩は見つかりませんが、心に残る作品には出会います。 上に引用した「突然の別れの日に」という詩も、そんな詩の一つです。2000年に61歳の若さで去った詩人が、いったいいくつの頃、この詩を書いたのだろうと思います。突然訪れた天使の余白に だれもいない(ぼくもいない)世界(世界中でそこしかいたい場所はないのに 別の場所にいなくてはならない そんな日ってあるよね)十歳くらいのときかなひとりで留守番をしていた午後そおっと押し入れにはいって戸を閉めたんだ。それからすこうし隙間を開けてのぞいてみただれもいない(ぼくもいない)部屋を!なぜだかずうっと見ていて変なはなしだけどそのままおとなになったような気がするよ。 「辻征夫詩集」岩波文庫 この詩も、引っかかりました。ぼくは66歳なのですが、「そのまま66歳になったような」気がするわけです。「おとなになった」のかどうか、仕事をやめて「大人になっていない」自分に、あらためて気づいて辟易するのですが、そういえば、我が家の子供たちは古田足日(ふるたたるひ)という人の「押入れのぼうけん」という絵本が好きでしたね。 子供が入って、部屋を覗くことができる「押し入れ」って、今でもあるのでしょうか。まあ、自分が今はいったらどうかなんて、同居人に叫ばれそうですからしませんが、いや、入ってみるのもありかもしれませんね。 今度はそのままどうなるのでしょう。 とりあえず、見つかったこの詩も挙げておきますが、岩波文庫版には入っていません。 きみがむこうから…… きみがむこうから 歩いてきて ぼくが こっちから 歩いていって やあ と言ってそのままわかれる そんなものか 出会いなんて! 田舎へ行くと いちごばたけに いちごがあり 野菜ばたけに 野菜がある 百姓の友だちが ひとりいて ぼくは 百姓の友だちの 百姓ではない友だちの ひとり なあ おれたち こうしてうろついてばかりいて きっとこのままとしとるな 二十代の次には 三十代がくる その次は たぶん 四十代だな うん とおい国には 動乱があり きのう 百人殺された 今日も 百人殺されるだろう それとも 殺すのだろうか…… 宿に帰って ひとりで 酒をのむ 腕をくむ あるいは 頭をかしげ なにもみえない 外の くらやみをみつめたり 眼を 閉じたりする これが 生きる姿勢なのだろうか 六十代になって、毎夜、コタツに向かい酒をのむ。で、静かに目を閉じたまま眠りこんだりしている。生きる姿勢といえるようなものは何もない。でも、きみがむこうからくることは心待ちにしている。追記2023・02・14 街を歩いていて、ふと、知人が乗った自動車が通り過ぎたような気がして、首をすくめた格好のまま振り返ったのですが、そこに、もう、自動車はいなくて、この詩を思い出しました。 一人で歩いていると、そんなことが時々あります。もう、この世の人ではないこともあるのですが、しようがありません。 で、記事を少し直しました。66歳の時に書いたことは直してはいませんが、もう、2年余りたったのですね。時間が勝手に通り過ぎていく日々です(笑)
2020.12.28
コメント(0)
-
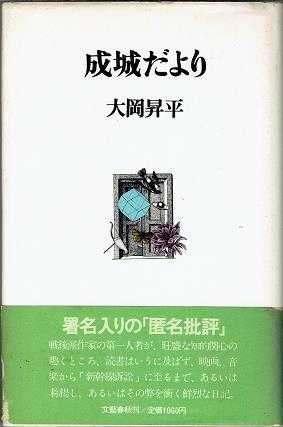
週刊 読書案内 大岡昇平「成城だより」(文藝春秋社)
100days100bookcovers no41 41日目大岡昇平「成城だより」(文藝春秋社) ERIKOさんが紹介された本の著者、出久根達郎という名前を見て、ぼくの中では、次に来るのは、もう「月島」しかありませんでした。 SODEOKAさんがお住みになっている、この「月島」という地名は、学生の頃からのあこがれの場所でした。橋という橋は何のためにあつたか?少年が欄干に手をかけ身をのりだして悲しみがあれば流すためにあつた 詩人吉本隆明の詩、「佃渡しで」の一節です。17歳か18歳の頃、この詩人の作品と出会いました。それ以来、この詩人は、彼が自分の父親と、ほぼ、同い年だと気づく二十代の半ばまで、まあ、神様でした。 というわけで、今回は吉本隆明といけばいいようなものなのですが、いや、ちょっと待てよ、戦後、達郎少年が丁稚奉公することになる古本屋の店先で本を探している、昭和十五年頃の隆明少年というのも、たしかに悪くない。しかし、その二十年ほど前に、おそらくは、俯きながら店先を通り過ぎ、渡し舟か、橋の上で涙を流した少年がいたんじゃなかったか。まずはそこからの方が面白そうだ。 「門を出ると涙が溢れて来た。私はよそ行きの行灯袴を穿いていたが、迸った涙はその末広がりの裾にさわらずに、じかに前方の地面に届いた。(私は涙もろい性質であるが、こういう泣き方をしたのは、この時と十年後弟保が死んだときだけである。)」大岡昇平「少年」 「少年」という自伝的な作品の中で、大正9年当時、10歳だった少年の姿を振り返っているのは、執筆当時64歳の作家大岡昇平です。「私はそのような卑しい母から生まれたことを情けなく思った。暮れかかる月島の町工場の並ぶ埃っぽい通りを、涙をぽたぽたたれ流しながら歩いている、小学生の帽子をかぶった自分の姿は、いま思い出しても悲しくなる。」 この時、府立1中の入試に失敗し、青山学院中学への進学が決まった10歳の少年が知ったのは、結婚するまでの母が「芸妓」であったという秘密でした。 この日、遊びに行った「月島」の伯母は国会議員の「お妾」であり、祖母は「置き屋」の女主人であったことが「少年」には描かれていますが、そのあたりに興味を感じられた方は、作品を手に取っていただくほかはありません。 ついでですが、一見、硬派に見える「大岡昇平の文学」には、この「母」の発見の悲しみを越えて、同じ人間である「母」との邂逅という主題が底流していたことを、筑摩書房版「大岡昇平全集11」に所収された批評家加藤典洋の「降りて来る光」という解説が見事に読み解いていることを付け加えておきたいと思います。 ぼくが「月島」という地名を聞いて、大岡昇平を思い浮かべたのは、その評論の幽かな記憶によるものだったと思います。 で、「少年」という作品の紹介で話は終わりそうなものですが、大作「レイテ戦記」がそうであるように「少年」という作品は読み辛いという、初読の記憶がぼくにはあります。というわけで、なんとなく紹介がためらわれます。 そこで、「そうだ!」 と思い当たったのが、最近、中公文庫で復刊された「成城だより(全3巻)」(文藝春秋社・講談社文芸文庫・中公文庫)です。 何故、今、復刊されたのかの出版事情は知りませんし、文庫版を手にとってもいないのですが、これならおススメしても大丈夫。というセレクトで落ち着きました。 1980年、今から40年前の「作家の日記」です。発表当時、署名入り「匿名批評」と呼ばれ、71歳の老作家の旺盛な好奇心、博覧強記と徹底した「ファクトチェック」ぶりが評判になりました。1980・9月18日 木曜日 曇 やや冷。やっと息を吐く。乱歩賞受賞作品『猿丸幻視行』を読む。タイム逆行剤を飲み、折口信夫先生になり替わりて、猿丸太夫=人丸説を探索す。作者の断られる如く梅原猛『水底の歌』を参看す。文章セリフ荒く、折口先生のイメージと一致せざる恨みあり。 女が男の耳をつかみて支配する場面、二度出てくる。これは「トリスタンとイズ―」の原型物語にある魔法にて、後に媚薬に変わる。作者意識しありや。(以下略)1980・9月22日 月曜日 曇 周辺映画館に味をしめ、自由が丘推理劇場に行く。ヴィスコンティ「イノセント」。上流者機影が流行、スノビズムに迎合か。退屈とエロチスムとソフィストケイトされたダイヤローグの即物的描出。悪くなし。ただし悪党だが憎めない立役のメロドラマ的自殺はいただけない。「アリア・ブラウンの結婚」の方、はるかに面白し。(以下略) まあ、こんな調子なのですが、みなさん、映画の話とか、続きが読みたいと思いませんか。 社会事象に対する辛辣で、戦争体験者の矜持にみちた発言も「読みどころ」、いや「聴きどころ」だと思います。決して、昭和の老人の繰り言ではないところがさすがです。 二十代のぼくにとって、吉本隆明と並んで、もう一人の神様だった人が最後に残していった仕事です。乞うご一読。 というわけで、YAMAMOTOさんお次をよろしく。(2020・09・21・T・SIMAKUMA)追記2022・07・22 上の投稿で話題に出した吉本隆明、大岡昇平、そして加藤典洋という3人が3人とも「戦後」という時代を生きた人でした。それぞれが、あの戦争について、戦前の国家体制について、生涯かけて考え抜いた人といっていいでしょう。吉本隆明は皇国少年としての敗戦体験、大岡昇平は飢餓の戦場の兵士として、敗戦後の俘虜としての戦争体験、加藤典洋は特高刑事の子としての葛藤、世代はずれていますし、体験もそれぞれ違うのですが、「まともな考え方」ということが、どこから生まれてくるのかを教えてくれた人たちです。 2000年あたりが転機でだったのでしょうか、彼らが書き残した「まともな考え方」に対して、軽佻浮薄さがただ事ではないと感じる政治的発言が大手を振り始め、その代表者のような人が銃で撃たれ、税金を使って葬儀をするという素っ頓狂な事態が勃発しています。開いた口が塞がらないとはこういう事態との遭遇の場合をいうのでしょうね。 まあ、詠嘆してもしようがないので、ここで取り上げた3人をはじめ、ぼくが「まともな考え方」の人だと、思う人の著作を一冊づつ案内していくほかありませんね。「まともな考え方」など、もう、誰も振り返らない時代が始まっているのかもしれませんが、老いの遠吠え(笑)ですね。さて、何冊案内できるのか、まあ、どうせヒマですしね(笑)。 追記2024・02・16 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目))いう形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2020.12.27
コメント(0)
-
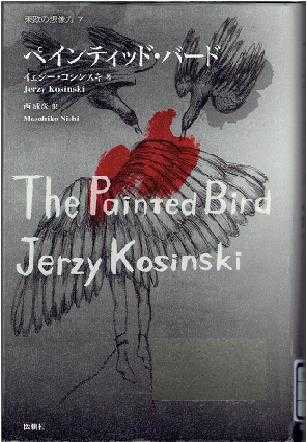
週刊 読書案内 イェジー・コジンスキ「ペインティッド・バード」(西成彦訳・松籟社)
イェジー・コジンスキ「ペインティッド・バード」(西成彦訳・松籟社) バーツラフ・マルホウル監督の「異端の鳥」という映画を見て、原作があることを知り読みました。1980年代に角川文庫版が出ていたようですが、今回は西成彦さんの新訳版です。 第二次世界大戦の後、1957年に、ポーランドからアメリカに亡命したコジンスキーという作家が1965年に書いた作品らしいですが、彼自身の少年時代の体験と重なる物語であることは間違いなさそうですが、ドキュメンタリーというわけではありません。 小説は次のような言葉で始められます。 第二次世界大戦がはじまってから数週間、1939年の秋のことだった。六歳の少年が東欧の大都市から、何千という子どもたちと同じように、両親の手によって、遠い村へと疎開させられた。 こういう事情で、東ヨーロッパの田舎の村に連れられてきた6歳の少年である「ぼく」が1939年から1945年に至る流浪の「体験」と、そこで学んだ、その時、その時、生きていくために大切だと思い知ったことを語り続ける物語でした。 作品を読めばわかりますが、作家が「ぼく」として「作中」で語らせている少年が、果たして、田舎の村を流浪しつづけていた6歳から12歳の少年そのものであったとはとても考えらません。そこで語られる「ことば」と世界に対する態度は、「大人」のものです。 ぼくはマルタの家に住み、両親が迎えに来てくれるのではないかと毎日のように待ちわびていた。泣いてどうなるものでもなかったし、めそめそしているぼくに、マルタは目もくれなかった。 これが「ぼく」が語り始めた最初の経験ですが、語っている「ぼく」は、実際の経験から何年も経って、語り始めていることは明らかだと思います。 こうして読み始めて、面白いと思ったことは、実際にこの原作で作られた映画「異端の鳥」では、ぼくの記憶では、ですが、ナレーションが入るわけではありませんから「カメラ」が映し出す映像が「語る」わけです。めそめそする少年と、そういう子どもの様子に何の関心も示さない老婆が、少し暗めのモノクロの画面に映し出されるわけで、映画の中には小説とは、また違った、「荒涼とした世界」に放りだされた少年が、次の瞬間、何が起こるのか全く予想もつかない「生」を生きているという「現在」性とでもいうニュアンスがあるわけで、そこに大きな差があると感じました。 映画に比べて小説で描かれる世界は安定しているという感じをぼくは持ちましたが、描かれるエピソードは、大筋において小説と映画は共通しています。ただ、出来事の、「ぼく」に対するインパクトの印象は、映画のほうが格段に生々しいと言えるということです。 結果的に、読後の印象は、映画を見終わった時とは少し違うものになりましたが、ある意味、当然かもしれません。 小説が描き出す「ぼく」の体験は、映画が映像として描く体験やエピソードを遥かに、詳細で悲惨なのですが、読むことに「不安」や「胸苦しさ」が絡みついてきません。 小説の「語り」の話法が微妙に時間をずらしこんでいるからでしょうか。その代わりにクローズ・アップするのが、語り手の「思想」の変化、つまり、少年の成長でした。 ぼくは自分が一人ぼっちだということにはたと気付いて、ぞっとした。しかし、二つのことを思い出した。オルガは人を頼らず生き抜くためにはその二つのことが大切だと言っていた。一つ目は、植物と動物に関する知識で、何が毒で、何が薬になるか見極めること。もうひとつは、火を、すなわち自分なりの「ながれ星」を持つということだ。 「ぼく」が最初にあずけられたマルタの死の結果、「ぼく」の扱いを衆議する村人たちから買い取ったのが、呪術師・祈祷師オルガでした。 「ぼく」が迷い込んでしまったヨーローッパの辺境の、つまりド田舎の「前時代的」、いや、「古代的」社会の実態が村人たちのオルガに対する「信仰」にも似た崇拝ぶりと、オルガの呪術の奇妙奇天烈な実態の描写で描かれていますが、「ぼく」はオルガから「生きのびるための方法」の本質を学び取りはじめます。 オルガの庇護を失い、いよいよ、一人ぼっちになってしまった「ぼく」は次々と新しい「庇護者」に拾われます。しかし、彼らは、方法こそ違いますが、ほとんど悪魔の所業というべきありさまで少年を扱います。 理不尽で、避けようのない災厄のように降りかかってくる「暴力の嵐」の苦痛を昇華する方法として、「ぼく」が自ら学んだことは「祈り」でした。そして、その年齢の少年が体験するには、あまりに苛酷な体験は、少年に「祈り」教えましたが、ついには「祈り続ける」少年から「言葉」を奪ってしまいます。失語症ですね。 5年間の流浪の末、初めて少年の前に暴力を振るわない人間として登場したのが「赤軍」兵士でした。彼らは神に祈ることが現実逃避にすぎないという驚愕の真実と、自己を振り返る自己批判の精神と、やられたらやりかえすプライドを持つことを少年に教えます。 少年は、少年に暴力をふるい続けた社会に立ち向かう方法として、「祈り」を捨て、たたかう「共産主義」にあこがれはじめます。 戦争が終わり、戦災孤児の収容施設で、「両親と新しい弟」という家族と再会しますが、「ぼく」に「ことば」が戻ってくるわけではありませんでした。 胸の内から「ことば」が溢れてくる感動のラストシーンは、是非、お読みいただいたうえで、味わっていただきたいのですが、それは少年が生まれて初めて、自分に呼びかけられる「声」との出会いの瞬間だったのかもしれません。 もう一度映画に戻りますが、映画では父親の右腕に彫られたユダヤ人収容所の収容番号の入れ墨がアップされ、一方で、一緒に乗っていたバスの曇ったガラス窓に、呼びかけられた「名前」を書く少年の姿が映し出されて映画は終わるのですが、失われていた「名前」と「ことば」、帰還した少年の悲哀と、家族を襲っていた「時代」の悲劇、突如やってくる「許し」の印象はよく似ていますが、少し違うと感じました。 読み終えて、気づいたことなのですが、「ペインティッド・バード」と題された、作家の幼い日の境遇の独白小説は、「田舎の村に紛れ込んでしまった都会のこども」、「黒い髪と黒い瞳のユダヤ人」、「家族になじめない、言葉を失った少年」、と、まさに「異端の鳥」の日々を語っていることは確かなことなのです。しかし、ポーランド人である作家コジンスキーにとっては、そんな「ぼく」だったころの苦闘の日々、ついに「救い主」のように現れ、こっそり胸ポケットに忍ばせていた、「黒い瞳と黒い口髭」の、英雄スターリンの笑顔の「偽り」に気付いた時にこそ、「ぼく」が、やっとのことで見つけた「理想社会」にも、ゆっくり羽を休める枝はなかったという、いわば、究極の「異端の鳥」の悲哀がやって来たのではないでしょうか。 そして、そこに、この作品を彼に書かせた、真のモチーフが隠されているのではないでしょうか。 この作品が「ペインティッド・バード」と名付けられた理由に対する当てずっぽうの推測なのですが、ポーランドからの亡命作家として70年代のアメリカの文学界で頂点を極めながら、58歳で自ら命を絶った「異端の鳥」の生涯を、なんだかとてつもなく傷ましいと感じたのが小説の感想でした。 時間がおありでしたら読んでみてください。
2020.12.26
コメント(0)
-

週刊 読書案内 高山羽根子「首里の馬」(新潮社)
高山羽根子「首里の馬」(新潮社) 第163回芥川賞受賞作品です。作家の名前に聞覚えはありません、SF小説を書いている人のようですが、ぼくはSFは苦手です。 書き出しのあたりはこんなふうで、好感を持ちました。 この地域には、先祖代々、ずっと長いこと絶えることなく続いている家というものがない。英祖による王統で中心の都だったとされるこの地の歴史は、現在までとぎれとぎれに歯抜けになっている。かつて廃藩置県、つまり琉球処分で区画が引き直されて、その上太平洋戦争では日本軍が那覇・首里に沖縄戦の司令部を置き、その前哨地として、ひどい激戦が続いた。ここらあたりの建物はほぼ損壊、どころか跡形もなく消え去っている。もちろん建物だけではなかった。本土から沖縄を守るためとやってきた日本軍の兵士は、前もって聞かされていたよりずっと少人数で、しかもまともに最新の兵器が扱える能力を持った者などはほとんどいなかったという。結局主力となったのは、防衛相集と称してかき集められた、取り立てて特別な訓練を受けていなかった地元の民間人だった。沖縄のあらゆる場所は成年男子なしといわれるようになったうえ、あちこちで女子学徒隊も組織された。この戦いで彼らをはじめとした住民、地域の人間の死傷者数は「不明」。この正式な記録は現在まで変わることがない。 主人公は未名子さんという女性です。二十代から三十代のはじめの方で、未婚です。彼女には二つの仕事があります。 「沖縄及島嶼資料館」という「順」さん、「より」と読みますが、たいへん高齢の女性民俗学者ですが、その順さんの資料館で、資料の整理のボランティアをしています。高齢の「順」さんを送り迎えしているのは娘の「途」さん、「みち」とよみますが、市内で歯科医を開業しています。 二人の名前も、まあ、考えてみれば、主人公の名前も意味ありげですね。どんな意味なのか分からなかったのですが。 主人公の未名子さんが、この資料館の職員のように仕事をしているのは、子どもの頃に偶然立ち寄った場所がここだったからのようです。 彼女の本業はインターネット通信のオペレーターです。 遠くにいる知らない人たちに向けて、それぞれに一対一のクイズを出題する。仕事の正式な名称は「孤独な業務従事者への定期的な通信による精神的なケアと知性の共有」。通称は問読者(トイヨミモノ)、というらしい。依頼人は個人によるものではなく。多くの場合その所属する集団で、クイズの正解数や内容により、通信相手の精神や知性の安定を確認する目的でこのサービスを利用するのだという。 カンベ主任というのが彼女の上司ですが東京(?)にいます。沖縄の事務所には未名子さん一人が勤務しています。通信の目的はクイズの出題と回答、そして、ちょっとした雑談ですが、小説中に顧客が数人登場しますが、なかなかユニークな人たちです。 ついでですから、通信の「なぞなぞ」のやり取りの場面を一つ紹介します。「問題」と未名子はいい、そうしてから自分の画面、ヴァンダからは見ることのできない場所に表示されている文章を読み上げる。「小さな男の子、太った男。そしてイワンは何に?」読み終わったあとほとんど間を置かずに、遠い距離を隔てているにもかかわらず、未名子の耳にヴァンダの明瞭な声が響く。「皇帝ツァーリ」未名子は声を出さずに表情だけで笑って、「正解」というとキーボードを打ち、アカウントに一つ、この問題に正解したという情報を入力した。 いかがでしょうか。なぜ「皇帝」が正解なのかお解りでしょうか。気になる方は本書をお読みになるしかありませんが、この作品には、こういう「小ネタ」的な面白さがちょこちょこと出てきます。 ただ、題目にもなっている首里の馬については、結局わからなかったのが、ぼくの本音です。 「馬」は、紹介した未名子さんの自宅の庭にある日突然やってくるのです。 朝になるともう風はすっかりやみ、空気は透明でさらりとしていて、強い日が差していて、この調子ではきっともう、家の前のアスファルトも乾いている。雨や雲、すべての湿度を持ったものを強い風が吹き飛ばしてしまったあとの、典型的な台風一過、今日の場合は双子台風に挟まれた、さっぱりとした晴れ間だった。でも、どうせすぐにまた大雨になるのだからと未名子は空気の入れ替えのために一階の窓を開けようと手をかける。 瞬間、小さな悲鳴を飲みこんだのは、カーテンを引き開けた目の前、未名子の家の小さな庭にいっぱいの、大きな一匹の生き物らしき毛の塊がうずくまっていたからだ。 これが「首里の馬」の登場のシーンです。 琉球諸島には宮古馬という、今では天然記念物に指定されて保護されているらしい、小型の馬がいて、かつての琉球王朝時代、王様の公用馬として活躍していたらしいのですが、その宮古馬が突如登場した場面です。 民家一軒分に積み上げられた沖縄の民俗資料。地球の果てで、一人ぼっちで生きているらしい相手に、笑いながら出題される「なぞなぞ」。嵐の翌朝に紛れ込んできた幻の宮古馬。 キーワードは「情報」らしいのですが、そういうところが、いかにもSF小説の書き手の手管という感じですが、作家高山羽根子は誰に向かって何を書こうとしているのでしょうね。 選考委員たちは、この小説のどこを評価したのでしょう。読み終わっても、実はよくわかりません。 ただ、ここの所の芥川賞作家たちの作品とは、一味違う、社会や歴史に対する「意欲」を強く感じる作品であることは間違いないと思いました。 なんだか、頼りない「案内」で申し訳ありませんね。お詫びというのもなんですが、ネット上にあった宮古馬の写真を貼っておきますね。小説の最後には、すっかり、未名子さんの愛馬になっていた馬です。 宮古島キッズネット
2020.12.25
コメント(0)
-

週刊 読書案内 古谷田奈月「神前酔狂宴」(河出書房新社)
古谷田奈月「神前酔狂宴」(河出書房新社) 現在のこの国の「民法」は、国家元首が「神」だった時代の法律を、主権者が交代したにもかかわらずそのまま引き継いだものだという話を学生時代に聞いたことがあります。 新コロちゃん騒ぎで、右往左往する権力者が下々の民草に「ほどこし」でもするかのような言動を繰り返す中で、出てきたのがマスクの配布でした。マスクを配布するという「コロナ対策」にも驚きましたが、配布に際して「世帯」という単位を思いついた「政治姿勢」にはもっと驚きました。イヤ、違和感を感じたというべきでしょうか? 個人が口に着けるマスクを「世帯」という、人間の集合をあらわす単位に二枚配るという「非現実性」がなによりの驚きでしたが、SNS上では「サザエさん家」のマンガで笑われていることに笑ってしまいました。愚の骨頂というべき政策に対する中々な風刺でした。 しかし、もう一つの疑問は「世帯」という単位の使用それ自体に対してでした。「世帯」って何だ?というわけです。現状では人口統計上の概念のように扱われています、ぼくの頭に浮かんだのは「家」でした。世帯主という言葉が家父長制を想起させ、結果、単独の国家元首を暗示させるためのパフォーマンスではないのか。 あるいは、コロナ感染という降って湧いた危機を、危機こそチャンスとばかりに、「赤子(セキシ)」という言葉を生み出した旧「民法」の「お国」思想をまき散らそうとしている演出に見えるというのがぼくの「うがち」でした。 で、思い出したのがこの小説、古谷田奈月「神前酔狂宴」(河出書房新社)です。 実に酔狂な題名がついていて「狂乱の結婚式」なんていうキャッチで、その上ご丁寧に「祝い袋」の装幀ですが、実はこの小説は、最近の小説のトレンドではないかという気がする、若い人たちの「お仕事場」小説です。芥川賞をかっさらって話題になった「コンビニ人間」とか、最近、若い作家が「お仕事場」で苦闘したり、活躍したりする姿を描くことが小説の「テーマ」として、案外流行っているのではないでしょうか。 この小説では、若い「普通の人」達が繰り広げる「神前」の「酔狂な」「宴」が描かれていました。題名を見て、とりあえず「結婚式」というセレモニーを「酔狂宴」と言い切っているところが二重丸という印象で読み始めましたが、なかなかどうして、あなどれない作品でした。 関西からほとんど出たことのない暮らしをしているぼくでも知っていることですが、東京の真ん中に、原宿というファッショナブルな街があります。 この町は「国家神道」を象徴する、ある大きな神社の門前に開けたおもむきの町です。神社はもちろん「明治神宮」ですね。その神社の周辺には明治天皇が統帥する帝国陸軍と帝国海軍という組織において、それぞれに代表的な「軍神」を祭った二つの神社があります。「東郷神社」と「乃木神社」です。 さすがに、実名は使用されていませんが、作品は「東郷神社」と思しき「高堂神社」の結婚披露宴会場でアルバイトをする二人の男性浜野君と梶君と神道系の大学を出て「乃木神社」と思しき「椚神社」で、正式に雇用された「社員」として働く女性倉地さんという「若者三人」の物語を描いています。 こう書いてみると、神社が経営する結婚式場会社なわけですから、「巫女」ではなく「社員」と書くとピタリとはまるところに、少し笑えますが、彼女は、若いながらも、信仰的にも「社員」なわけで、男性二人と少し違うというのが小説の設定です。 物語は「お金儲け」としての結婚式運営を「業務」として働く主人公浜野君に対して「信仰」に基づいた正しい結婚式を目指す女性社員倉地さん、その真ん中で、「愛」の言葉に酔うのと同じように「信仰」の言葉に魅入られてゆく梶君という三つ巴の様相を描いて行きます。 まず面白いのは「結婚披露宴会場」の業務の様子の描写です。この辺りが「お仕事場」小説とぼくが呼ぶ所以ですが、乃木希典と東郷平八郎という軍人の、それぞれの人柄の影響なのかどうか、二つの神社の従業員のふるまいの違いについて描かれているあたりは、なかなか興味深いものがありますが、小説展開上の都合のための脚色という面もありますので、鵜吞みにはできません。 描かれている人間関係は、なかなか錯綜していて、説明がつきませんが、ぼくなりに大雑把に図式化していえば、この小説で、最も面白いのは、主人公浜野君が「結婚式」という業務を、顧客の欲望の自由、個人の生き方の自由の表現形式としててってさせた結果、「同性婚」はもちろんのこと、「一人婚」という発想にまでたどり着くところなのですが、一方に「信仰」を実体化し、そこから波及してくる「正しさ」にからめとられてゆく倉地さんと梶君を配置した結果、小説全体が、現在のこの国の様相を、不気味に描き出しているのではないかという所でした。 当てずっぽうな読後感なのですが、ぼくにとっては結構リアルで、この小説を、かなり高く評価する理由です。 最近、あちらこちらの神社で、何回手を拍つとか、どこで礼をするとか、どんな根拠があるのかよくわからないことが実体化され、もっともらしく宣伝されていますが、初詣も近づいていることですし、社前で自分が何をしているのか、立ち止まって考えるのも悪くないと思わせる作品でした。
2020.12.24
コメント(0)
-

ロベール・ブレッソン「バルタザールどこへ行く」神戸アートヴィレッジ
ロベール・ブレッソン「バルタザールどこへ行く」神戸アートヴィレッジ 実は、ロベール・ブレッソンの特集で、「少女ムシェット」と週替わりのプログラムでした。で、「バルタザールどこへ行く」が前の週でしたが、「バルタザール」を見た翌週に扁桃腺をはらしてしまい、「少女ムシェット」は見損なってしまいました。というわけで、「バルタザールどこへ」の感想を、とりあえず載せることにしました。 ロバのバルタザールの誕生から、その幸せな生い立ちにもかかわらず、なんとも、不幸な一生の物語でした。 あどけない少女マリー。少女の幼馴染みなのでしょうね、農家の少年ジャック。生まれたばかりだったでしょうか、ロバのバルタザール。フィルムが廻りはじめて、すぐに気づきました。 「この映画は、30年以上前に見たことがある。主役はロバだ。」 で、そのとおりでした。 畑で犂を引くバルタザール。子どもたちを載せた馬車を引くバルタザール。粉ひきの臼を、鞭打たれながら、立ち止まり、立ち止まり引くバルタザール。再会したマリーに、頭や首すじを撫でられながら遠くを見るバルタザール。サーカスのバルタザール。酒乱の飼い主を背に載せ、主が転がり落ちたすきに、ヨタヨタと逃げ出すバルタザール。こん棒で打たれ、蹴りつけられるバルタザール。密輸の荷を積み上げられて山を登ってゆくバルタザール。流れ弾に当たり倒れているバルタザール。羊たちが草を食む草原で静かに息を引き取るバルタザール。 ロバとはいえ名優バルタザールの名演技が、少女マリーの不幸な有為転変を見事に際立たせてゆきます。 このポスターをご覧ください。ただのロバとして画面の下方で、うれしいのか悲しいのかわからない顔付きでそっぽを向いているバルタザールがいます。 右手で彼の首を抱え込み、鼻筋をなでる、美しい少女マリーの眼差しが、まず、印象に残ります。 しかし、フィルムは回り続け、ロバであるからという理由だけで、なにを考えているのかわからないと思い込んでいたぼくの前に、生きていることの哀しさをたたえたバルタザールの眼差しのクローズアップが、繰り返し突き付けられ、最後に眠るように息を引き取ってゆく姿が映し出されるに至って、名優バルタザールの存在に気付くことになったのでした。 たしかに、ポスタ―でも、このチラシでも、お気づきだと思いますが、少女マリーを演じたアンヌ・ビアゼムスキーの表情のすばらしさがこの映画の見どころであることは間違いありません。しかし、バルタザールの存在なしには、映画そのものが成り立たないのではないでしょうか。 いやはや、それにしても、すごい映画でしたね。ぼくは40年前に、いったい何を見ていたのだろうと、つくづく思いました。監督 ロベール・ブレッソン製作 マグ・ボダール脚本 ロベール・ブレッソン撮影 ギスラン・クロケ美術 ピエール・シャルボニエ編集 レイモン・ラミ音楽 シューベルト ジャン・ウィエネルキャストアンヌ・ビアゼムスキーフランソワ・ラファルジュフィリップ・アスランナタリー・ジョワイヨーバルダー・グリーンジャン=クロード・ギルベール1966年・96分・フランス・スウェーデン合作原題「Au Hasard Balthazar」配給:コピアポア・フィルム、lesfugitives日本初公開:1970年5月2020・12・05アートヴィレッジ(no13)追記2023・05・12 最近、ポーランドのイエジー・スコリモフスキ監督の「EO」というロバが主役の映画を見ました。スコリモフスキ監督がこの「バルタザールどこへ行く」にインスパイアーされて作ったと評判の映画でした。 で、昔の記事を思い出して修繕しました。で、比較してしまうのですが、この映画の「そっぽを向いているバルタザール」 が、やっぱりすごかったのだということを感じました。まあ、何故すごいのかはわからないのですが、スゴイです!
2020.12.23
コメント(0)
-

フレディ・M・ムーラー「山の焚火」元町映画館no65
フレディ・M・ムーラー「山の焚火」元町映画館 フレディ・M・ムーラーという映画監督の3本の映画を「マウンテン・トリロジー」という企画でみせてくれるシリーズを見始めて、「山の焚火」、「我ら山人たち」と、2本見たところで、体調をこわしてしまいました。 とうとう「緑の山」は見損なったまま上映が終わってしまいました。3本見たうえで、感想を描こうと思っていたのですが、仕方がありません。見ることができた2本について感想を書き残しておこうと思います。 なんといっても、1本目に観たこの映画「山の焚火」は圧倒的でした。「山」を撮っている映像の美しさ、「山」の生活のドキュメンタリーを思わせるリアリティーと、その、アルプスと思われる山の高みで繰り広げられる、神話的とでも言えばいいのでしょうか、あらゆる「閾」超えた、しかし、限りなく美しく哀しい「人間」の世界 が映し出されていました。 「叫びと沈黙」、「槌音と木霊」、「火炎と漆黒」、再び、「銃声と沈黙」。印象的な音以外、とても静かな映画でした。 チラシにあるのは、耳の聞こえない弟が、ただ一人心を許し、縋りつくようにその喉元に指先を当て、鼓動でしょうか、息の音でしょうか、歌声でしょうか、「ねえさんの音」 をさぐる美しいシーンが、焚火の炎に映し出されている光景です。映画の物語は、ここから二人の、禁断の愛のシーンへと昇華してゆきます。 母親は「いのち」 を宿して苦悩する娘をこっそり祝福します。弟は何が起こったのか理解できません。父親は銃を持ち出し、過ちを犯した「娘と息子」を撃ち殺そうと憤ります。 抗う息子との争いの中で銃は暴発し、父親の命を奪います。夫の突然の死を目の当たりにした母親は、ショックのあまりその場で息絶え、雪の降りしきる「山」に「姉と弟」の二人が残されます。そして、その夜、山がうなるのです。 映画を見ているぼくは、美しい山の風景、山で暮らす家族の「父と子」、「姉と弟」、「母と娘」、そして「家族」の生活の様に、もうそれだけで胸打たれて見ていました。 ある日、思うように動かない草刈り機を谷底に投げ込んだことが理由で、息子は父に叱られ、納得がいかない彼はもっと上の山の小屋に家出します。家出した弟を気づかい、山小屋迄荷物を運んできた姉は弟と焚火を囲み、二人の間に必然であるかのように起こって行く「事件」 に息を飲み、その結末に言葉を失ってしまいました。 この映画で起こった、どの出来事も、事実、そのようであったのではないか。どの俳優も演技などしていないのではないか。ぼくが「神話的」とはじめに言ったのはそういう印象を強く持ったからです。 映画の、ほとんど最後のシーンでした。自分の部屋のガラスの窓を外し、雪原に埋め込むように、並んで寝かせた父と母の遺体に窓をつけた弟の仕草は心のどこかに残るシーンだと思いました。 いや、それにしても、ここには、一番初めの人間の姿 が残っているのではないか、帰り道でそんなことを考えた映画でした。監督 フレディ・M・ムーラー製作 ベルナール・ラング脚本 フレディ・M・ムーラー撮影 ピオ・コラーディ美術 ベルンハウト・ザウター衣装 グレタ・ロドラー編集 ヘレーナ・ゲレバー音楽 マリオ・ベレッタキャストトーマス・ノックヨハンナ・リーアロルフ・イリックドロテア・モリッツイェルク・オーダーマットティック・ブライデンバッハ1985年・120分・スイス原題「Hohenfeuer」配給:gnome日本初公開:1986年8月2日2020・12・13元町映画館no65
2020.12.22
コメント(0)
-

週刊 読書案内 出久根達郎 『謎の女 幽蘭 -古本屋「芳雅堂」の探索帳よりー』(筑摩書房)
100days100bookcovers no40(40日目)出久根達郎 『謎の女 幽蘭 -古本屋「芳雅堂」の探索帳よりー』(筑摩書房) 前回紹介された別役実の『けものづくし』は、KOBAYASIさん曰く、――「知的」に「体系的」に、そしてブラックに、さらにアイロニカルに「デタラメ」だからおもしろい。要は、「フィクション」として読めばいいということ――なのだそう。 実は私も若い頃に読んだと思うのですが、内容を覚えていません。ひょっとするとこの記憶も捏造しているのか、あやしいですが。あの有名な別役実の作物を次のように感じたと思うのです。「けったいやなあ。難しいわと頭をひなりながら読んでるのに、いつの間にか話ずらされてて、あらら、こんなん真面目に読んでたらあほみたいやん。どう読んだらええのかわからへんわあ。」と。 でも、あれから30年以上経つと、こちらがけったいなものになったようで、素直な作物では飽き足らず、役に立たない理屈ををひねくりまわしたり、皮肉や意地悪、諧謔、ナンセンスが小気味よく思えます。(焼きが回りましたね)近いうちに彼の作品を改めて読みたくなりました。すでにSIMAKUMAさんもYAMAMOTOさんもその状態なんですね。 さあ次はどこへつなげばいいのかと思って読んでいると、KOBAYASIさんの次のくだりにビビット来ました。――読み進めていくうちに、何度か「ファクトチェック」みたいなことをやることになった。結構「事実」も含まれている。「動物園」の項に出てくる、ドゥーガル・ディクソンとその著書『アフターマン』も、何だか作ったような名前だなと思って調べたら、実在の人物であり著書だった。―― 「ファクトチェーック」!!! これ。これ。これ。そういえば、私もファクトチェックしまくりながら読んだ本がありました。250ページもない本なのに、出てくる人物、事件、事象は、本当めかしたフィクションなのかどうかが気になって、読書を中断して手元のスマホでつい検索するということを繰り返して読むのに随分時間がかかった本です。これほどスマホやウィキペディアの便利さに感謝しながら読んだのは初めてでした。好事家好みの本だとは思いますが、骨董や古書にはまる人の気持ちも少し想像できました。それは次の本です。『謎の女 幽蘭 -古本屋「芳雅堂」の探索帳よりー』出久根達郎 筑摩書房 作者 出久根達郎は「芳雅堂」(現在は閉店)という古書店主で直木賞作家だったことは有名ですが、芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されているとは知りませんでした。 恥ずかしながらこの作家の書き物を一冊まるまる読んだのはこれが初めてでした。古本屋さんがこれほど物知りだということにも驚きました。 最初のページからいきなり、「黒服に、厚紙を切り抜いて作った勲章をぶら下げて、直筆の「勅語」を新聞記者たちに売りつけていた。内閣が変るつど、「声明」を発表し、世の中の動向を「託宣」した」 「芦原(あしはら)将軍」の話題が出てきます。そこでまず検索をかけると、昭和12年に87歳で亡くなった実在の人物で、皇位僭称者、明治天皇巡行の折、「やあ、兄貴」と声をかけたこともある。などと出てきます。 私はこの人物のことは知らなかったのですが、家人に聞いたら「ああ、いたなあ。変な人。」と言うので、ご存じの方は多いのでしょうね。 また、タイトルロールの「謎の女 本荘幽蘭(ほんじょうゆうらん)」。これも検索すると、江刺昭子と安藤礼二共著の『この女を見よー本荘幽蘭と隠された近代日本』(ぷねうま舎)という書名が出てくるので、これも実在の人物らしい。 この二人に始まり、検索をかけながら読みました。ずっとこんな感じで、本が本を呼び、思わぬ発見と謎を生み、その謎がさらにあるかないのかわからない本を探し求める動機となる、「本の本」の話でした。 いささか常識にはずれた言動で世間に波風を立てるような人物を、世間は盛大にもてはやし、時に大いにけなして日ごろの鬱憤をはらして、飽きたらすっかり忘れてしまう。人の興味はそんな風に次から次へと移ってゆくけれど、古本屋は世間がほとんど忘れた頃をねらって、その人物ゆかりのものをどこからか持ち出してきて流通交換させる。値段のないものに途方もない値がつくこともある。その物を高価たらしめるのはその物の価値よりも、その物にまつわる事実の集積。そのために骨董屋や古本屋は鑑識眼はもちろんだが、膨大な事実の知識とその物証になる資料を持っているのでしょう。こういう世界の面白さにはまるとなかなか足を洗えなくなるだろうなとも思いました。 話はバブル直前の1980年ごろ。東京杉並区内の古本屋の主人が、客から聞いた「本荘幽蘭」という破天荒な人物に興味を持ち、「幽蘭の名が登場する本」を片っ端から集め続けるという大筋で、そこに古本屋仲間になる若者が家主の老女に惚れられたいざこざや、「幽蘭」に関する本を求める異母兄妹の秘められた関係や、その親戚の老舗料亭の衰退や、真贋のわからない古物の海を越えた取引などの話を絡めています。 しかし、これらの話はどうしても影が薄い。この本の主役はなんといっても本。本を浮かびあがらせるために人間が黒子として動いているように思われました。あとは古本屋の蘊蓄話も乙でした。 たとえば、「古本屋はいわゆる「本屋学問」があればよい。うわべだけの学問である。本当の学問は客がする」 とか、「古本屋の経験上、未刊といわれていた本が刊行されていた話がざらにある」 とか、「古切手は使用済(消印あり)の方が価値が高い。当時の郵便事情がわかるので」 とか。 いくつか「ファクトチェック」した事例をあげれば、・古本屋が「幽蘭」の興味を持つきっかけを与えた客、新劇俳優の松本克平(かっぺい)。芸名の由来や日本初の銀行強盗といわれる「赤色ギャング事件」で逮捕、釈放のいきさつ、特高刑事との関わり、古書業界で知らぬ者はない新劇関係書物の収集家。著書『私の古本大学 新劇人の読書彷徨』の中に「本荘幽蘭著『本荘幽蘭尼懺悔叢書』」の項目をあげて幽蘭を紹介している。「あらゆる職業を猫の眼のようにめまぐるしく渡り歩いて、常に自己宣伝を忘れなかった先端的女性であり、自ら何のこだわりもなく性の解放を実行した勇ましき女であり、さらにその自己懺悔を本に書くと宣伝して歩いた女性」と記載。同著に幽蘭の参考資料3点あげる。その一つ『女の裏おもて』青柳有美著(明治女学校で幽蘭の教師、島崎藤村の代講する)・本荘幽蘭 明治12年生まれのモガ(モダンガール)の中の最初のモガともいうべき女性。神田でミルクホールを開いたり上野に幽蘭軒という店を出し幽蘭餅を売るが、長く続かない。女落語家となり英語交じりの漫談を語る。講談師となり浪速節をうなる。女優、舞台監督、活動写真の弁士、新聞記者、救世軍、芸者、外国人のための日本語教師。尼(本荘日蘭尼と改名)。演芸通信社経営などなど、人目につきそうな職業を片っ端から舐め歩き、行動範囲も、朝鮮、満州、清、台湾、シンガポールと極めて広かったとのこと。(『らく我記』高田義一郎著) 筆者のあとがきに、 古本探しは根気仕事だが、まことにスリリングで、サスペンスがあり、この味わいを知ると、病みつきになる。さながら推理小説を読む楽しさである。-(中略)-現代はどんな「幻の本」でも、その存在はインターネットで、即座に検索できる。スリルも、ドラマもない。何の醍醐味もない。-(中略)-「バブル」は何もかも破壊した。土地だけでなく、人の心を毀した。それは書物も同様である。ただ便利というだけで、電子書籍が誕生した。実体のない電子書籍には、人間くさいドラマは生まれない。紙の本の魅力を知ってほしくて、このような小説を書いた、ともいえる。と書いている。 私が今回使いまくっているスマホも無駄が少なくありがたさを手放せなくなっているが、その代わり失ってしまったもののほうが大切なのかもしれないなと思いつつ筆をおきます。SIMAKUMAさん、おあとをよろしくお願いいたします。 追記 外にも「ファクトチェック」したくなるようなことがいくつもでてきましたが、長くなってしまいました。お忙しい方は、このあたりで。ご興味のある方はお付き合いください。・相馬黒光(新宿中村屋創業)から見た「古本探しは根気仕事だが、まことにスリリングで、サスペンスがあり、この味わいを知ると、病みつきになる。さながら推理小説を読む楽しさである。-(中略)-現代はどんな「幻の本」でも、その存在はインターネットで、即座に検索できる。スリルも、ドラマもない。何の醍醐味もない。-(中略)-「バブル」は何もかも破壊した。土地だけでなく、人の心を毀した。それは書物も同様である。ただ便利というだけで、電子書籍が誕生した。実体のない電子書籍には、人間くさいドラマは生ま幽蘭の姿を記す自伝『黙移』・宮武外骨「滑稽新聞」コレクターが多いので、その周辺からもたらされる資料からさまざまな発見があること。・夏目漱石と大町桂月の交流。大町桂月が肩入れしていた松本道別(まつもとちわき)(漱石の『野分』の中で電車事件を煽動した嫌疑で逮捕された人物で、主人公が演説会をしてその家族を援助したいという人物のモデル)という人物。服役中に健康法や呼吸法を編み出し、霊学を研究。のち、人間は人体放射能を発してして病気治癒に効果があると提唱。・松下大三郎が『国歌大観』を編集するとき女子編集委員募集の新聞広告を出したら、採用された人の中に「本荘幽蘭」という名前があった。しかし、別人だと思われる。あの『国歌大観』を編集し、松下文法と言われるほどの文法学者なのに、彼について書かれたものがほとんど見つからないのは不思議。やっと入手した『松下大三郎博士伝』の明治34年12月付記載。・秘書と言われる『医心方(いしんぼう)巻第二十八房内』が現れる。鴎外の『渋江抽斎』の中でこの書について触れられている。(私は『渋江抽斎』未読です。)隋唐期に成立した医学書百数十種を、平安時代に丹波康頼が抜粋して編述した三十巻の医書で、永観2(984)年に天皇に献上された。正親町天皇が治療の褒美に典薬頭(てんやくのかみ)半井(なからい)氏に下賜した。徳川時代になって、幕府は半井氏に献上を迫ったところ、焼失したとか、見当たらないとか言い逃れ続ける。しまいに幕府は献上の強要を諦め、写本を作るので原本を借りたいと下手に出たので、半井氏側もしかたなく、提出という顛末。ここからが『渋江抽斎』の仕事。16人で書写、校正13人、監督4人、医師2人総裁で3か月、総紙枚数1437枚、2874ページ。(石原明氏調査)木版で安政七年刊行。推定五〇〇部。幕府は半井氏に返還。しかし、その後、原本の半井家蔵本がどうなったのかは不明。明治以降、学者で原本を見た者は一人もいないという。今Wikipediaを見ると「この半井本は、1982年、同家より文化庁に買い上げがあり、1984年、国宝となっている。現在は東京国立博物館が所蔵している。2018年10月16日に、国宝「医心方」のユネスコ「世界の記憶」登録を推進する議員連盟(会長:鴨下一郎)が設立され、ユネスコ「世界の記憶」への登録を目指している。」とありました。半井家は100年以上世間からひた隠しに隠すことができたということでしょうか?? で、第二十八巻は房内篇つまり「ベッドルームでの医術」ということで、より密かに扱われ、ますます人気を呼び、ゆえに偽物も出回っており、古本屋にとってはなかなか危ないしろものらしい。今は廃刊になってしまった学燈社の雑誌「国文学 解釈と鑑賞」でも、昭和39年10月臨時増刊号と、昭和42年4月臨時増刊号でこの書を扱ったときはずいぶん読者に歓迎された。・国宝盗難事件 東大寺三月堂不空羂索(ふくうけんじゃく)観音像の宝冠の、化物(けぶつ)阿弥陀銀像が昭和12年2月に盗まれた。国内では売れない。昭和18年9月に盗難物は回収され、犯人も逮捕された。当時の朝日新聞に記事は掲載されているが、詳細にはわからない。これほど有名な物は国内で流通させることはできないので、海外に持ち出すだろうし、そうなると組織なり、流通シンジケートを読者に想像させるような蘊蓄も配されている。・日本からの盗品をヨーロッパの城を倉庫がわりにして保管し保管料を取るビジネスや、保管料を回収できないとなれば、ほとぼりのさめたころに、城や爵位のある人物が所蔵していたと言って箔をつけて闇の中から明るみ出すこともある。また密かに、あるはずのない「紅葉山文庫蔵印」というを「印章」を作って偽の写本に押して、海外旅行にやってきた日本人に高く売ることができたという。バブル期の日本人はこういうものに踊らされたのか、日本橋三越であった「古代ペルシア秘宝展」の展示物は大半が偽物とわかった。事件の真相はどうなったのか。・美術史研究の第一人者が赤っ恥をかいた「春峯庵事件」E・DEGUTI 2020・09・16 追記2024・02・16 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目))いう形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2020.12.21
コメント(0)
-
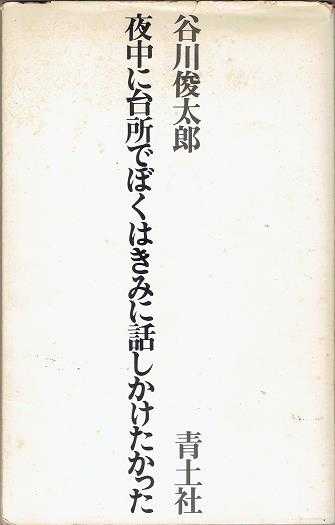
週刊 読書案内 谷川俊太郎「夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった」(青土社)
谷川俊太郎「夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった」(青土社) 1975年、ぼくは大学1年生だったか、2年生だったか?大学生協の書籍部の棚にこの詩集が並んでいたことを覚えています。 価格の900円が高かったですね。書籍部の書棚の前に立って、棚から抜き出して立ち読みしました。 芝生そして私はいつかどこかから来て不意にこの芝生の上に立っていたなすべきことはすべて私の細胞が記憶していただから私は人間の形をし幸せについて語りさえしたのだ 巻頭の、この詩を読んで、自分から、なんだか限りなく遠い人が立っているような気がしたのを覚えています。 それから45年たちました。先日、同居人の書棚にある詩集を見つけ出して、そのまま書棚の前に座り込んで初めて読む詩のように読み始めました。 2 武満徹に飲んでいるんだろうね今夜もどこかで氷がグラスにあたる音が聞こえるきみはよく喋り時にふっと黙り込むんだろぼくらの苦しみのわけはひとつなのにそれをまぎらわす方法は別々だなきみは女房をなぐるかい? 4 谷川知子にきみが怒るのも無理はないさぼくはいちばん醜いぼくを愛せと言ってるしかもしらふでにっちもさっちもいかないんだよぼくにもきっとエディプスみたいなカタルシスが必要なんだそのあとうまく生き残れさえすればねめくらにもならずに合唱隊は何て歌ってくれるだろうかきっとエディプスコンプレックスだなんて声をそろえてわめくんだろうなそれも一理あるさ解釈ってのはいつも一手おくれてるけどぼくがほんとに欲しいのは実は不合理きわまる神託のほうなんだ 谷川俊太郎も若かったんだなあ。というのがまず第一番目の感想ですね。「夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった」と題された詩篇は、全部で14あります。二つ目に「小田実に」とあるのが、なんだか不思議な感じがしましたが、どの詩も、印象は、少し陰気です。 14 金関寿夫にぼくは自分にとてもデリケートな手術しなきゃなんないって歌ったのはベリマンでしたっけ自殺したうろ覚えですが他の何もかもと同じようにさらけ出そうとするんですがさらけ出した瞬間に別物になってしまいますたいようにさらされた吸血鬼といったところ魂の中の言葉は空気にふれた言葉とは似ても似つかぬもののようですおぼえがありませんか絶句したときの身の充実できればのべつ絶句していたいでなければ単に啞然としているだけでもいい指にきれいな指環なんかはめて我を忘れて1972年五月某夜、半ば即興的に鉛筆書き、同六月二六日、パルコパロールにて音読。同八月、活字による記録および大量頒布に同意。 気にとまった作品を書きあげてみましたが、あくまでも気にとまったということです。それぞれに、刺さって来る一行があるのですね。 四歳年下の同居人が、大学生になってすぐに購入していることに、今更ながらですが、驚いています。この詩人の作品を愛していた彼女に、ぼくとの生活について問い直すことは、やはり、今でも、少し怖ろしいですね。
2020.12.20
コメント(0)
-
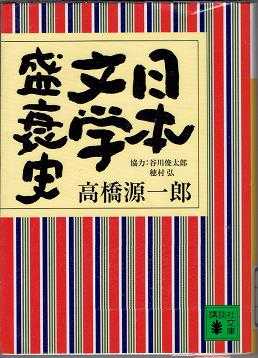
週刊 読書案内 高橋源一郎「日本文学盛衰史」(講談社文庫)
高橋源一郎「日本文学盛衰史」(講談社文庫) 高橋源一郎の代表作の一つといっていいでしょうね、「日本文学盛衰史」(講談社文庫)を読み直しました。2001年に出版された作品で、これで何度目かの通読ですが、やはり、間違いなく傑作であると思いました。何度かこの「読書案内」で取り上げようとしたのですが、どう誉めていいのかわからなかったのです。 彼は、近代文学という「物語」を、新しい「ことば」の生成とその変転として描いているのですが、近代文学のコードから限りなく遠い「文体」で描こうとしていると言えばいいのでしょうか。そこが、感想のむずかしいところだと思います。 近代日本文学の「小説言語」は、その時代の、その言葉づかいであることによって、傑作も駄作も、おなじコードを共有し、この小説に登場するあらゆる文学者たちは、そのコードをわがものにすることで、日本文学の書き手足り得たとするならば、この小説は、そのコードを棄てることで、新しい小説の可能性を生きることができるというのが高橋源一郎の目論見なのかもしれません。 文庫本で658ページの長編小説です。第1章が「死んだ男」と題されて明治42年6月2日に行われた二葉亭四迷こと長谷川辰之助の葬儀の場に集う人々の描写から始まります。 新しい日本語で、小説という新しい表現形式に最初に挑んだ二葉亭四迷の葬儀の場には、我々がその名を知る明治の文豪たちが勢ぞろいしています。お芝居の前に、役者たちがずらりと並んで挨拶している風情ですね。そういう意味で、この場面が、この作品の巻頭に置かれているのは必然なのでしょうね。 その葬儀で受付係をしていたのが、誰あろう石川啄木でした。作家は、その場に居合わせた啄木についてこんなふうに語って、この章段を締めくくっています。 すでに訪れる者も尽きた受付で、退屈しのぎに啄木は歌を作っていた。歌はいくらでも、すらすらと鼻歌でも歌うようにできた。そして、歌ができればできるほど啄木の絶望はつのるのだった。あほやねん、あほやねん、桂銀淑(ケイウンスク)がくり返すまたつらき真理をハーブティーにハーブ煮えつつ春の夜の嘘つきはどらえもんのはじまりシステムにローンに飼われこの上は明ルク生クルほか何があるぼくはただ口語のかおる部屋で待つ遅れて喩からあがってくるまで 啄木に二葉亭の葛藤はなかった。だが、二葉亭の知らない葛藤を啄木たちは味わわねばならなかったのである。 断るまでもありませんが、ここに登場する「啄木」は高橋源一郎の小説中の人物であり、引用された「短歌」は「啄木歌集」のどこを探しても見つけることはできません。 現代の歌人穂村弘の「偽作(?)」であることが、欄外で断られていますが、第2章「ローマ字日記」では、高橋自身の手による「ローマ字日記」の贋作が載せられています。穂村弘も「いくらでも、すらすらと鼻歌でも歌うようにでき」るでしょうかね。 この作品には、第1章の二葉亭四迷を皮切りに、漱石、鴎外をはじめ、北村透谷と島崎藤村、田山花袋などが主な登場人物として登場します。近代日本文学史をふりかえれば、当然の出演者と言っていいのですが、なぜが、啄木がこの小説全体の影の主役のように、折に触れて姿を見せるのです。 彼の有名な評論「時代閉塞の現状」は朝日新聞掲載のために執筆されたにもかかわらず、漱石によって握りつぶされたというスキャンダラスな推理に始まり、「WHO IS K」と題された、漱石の小説「こころ」の登場人物Kをめぐる章では、Kのモデルの可能性として石川啄木が登場するというスリリングな展開まであります。 何故、啄木なのでしょう。作家高橋源一郎が近代文学の相関図を調べ尽くす中で、文学思想上のトリック・スターとして啄木を見つけ出したことは疑いありません。にもかかわらず、いまひとつ腑に落ちなかったのですが、今回、読み返しながら、ふと思いつきました。「啄木は家族と暮らしながら、どんな言葉でしゃべっていたのだろう?」ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく 啄木の、あまりにも有名な歌ですが、この言葉遣いはどこから出てきたのでしょうね。あるいは、近代日本文学は、いったい誰の口語で書かれていたのでしょうと問うことも出来そうです。「言文一致」と高校の先生は、ぼくも嘗ては言ったのですが、作品として出来上がった「文」は、いったい誰の「言」と一致していたのでしょう。生活の言葉を棄てた架空の日本語だったのではないでしょうか。 「ふるさとの訛」を捨て、「口語短歌」に自らの文学の生きる道を見出した啄木の葛藤の正体は、どうも只者ではなさそうですね。 高橋源一郎が、そういう問いかけを持ったのかどうかはわかりません。彼が、幾重にも方法を駆使して描いている「近代日本文学」という物語の一つの切り口にすぎないのかもしれないし、単なる当てずっぽうかもしれません。しかし、何となくな納得がやって来たことは確かです。 さて、「きみがむこうから」と題された最終章は、詩人辻征夫のきみがむこうから 歩いてきてぼくが こっちから歩いていってやあと言ってそのままわかれるそんなものか 出会いなんて!(辻征夫「きみがむこうから・・・」) という、引用があり、北村透谷以下、樋口一葉、尾崎紅葉、斉藤緑雨、川上眉山、国木田独歩というふうに、当時の新聞に載った死亡広告が引用されています。 斉藤緑雨は「死亡広告」を自分で書き残し、川上眉山は自殺でした。夏目漱石の死亡広告は次のようだったそうです。夏目漱石氏逝く現代我が文壇の泰斗昨日午後七時胃潰瘍の為に大正五年十二月十日朝日新聞 こうして、二葉亭の葬儀の場で始まった、ながいながい「日本文学盛衰史」は、近代文学という物語の終焉にふさわしく、登場人物たちの「死」で幕を閉じます。 このあと、作家自身の、いわば覚悟を記したかに見える結末もありますが、そこは、まあ、読んでいただくのがよろしいんじゃないでしょうか。 何だか、最後には近代文学、戦後文学のコードに回帰していると思うのですが、高橋源一郎らしいと言えば、カレらしい結末でした。 是非にと、お薦めする一冊ですが、ブルセラショップだかの店員の石川啄木や、大人向けのビデオの監督の田山花袋も登場しますが、くれぐれも、お腹立ちなさらないようにお願いいたします。
2020.12.19
コメント(3)
-

週刊 マンガ便 奥浩哉「いぬやしき(1巻~10巻)」(講談社)
奥浩哉「いぬやしき(1巻~10巻)」(講談社) 「さよならタマちゃん」や「ペリリュー」のマンガ家武田一義さんがアシスタントとして働いていたマンガ家ということで興味を持ちました。「タマちゃん」に本人も登場します。 10巻セット1000円という価格で購入しましたが、納得のいくおもしろさでした。「納得」といっても、一冊100円程度の、ということではありません。2014年に始まって、2017年に全10巻で完結したようです。 絵柄が独特だと思います。ぼくは老人の主人公犬屋敷壱郎さんの見分けはつきましたが、獅子神晧君とそのお友達の安堂直行君の見分けが、途中からつかなくなりました。まあ、彼らの同級生の可愛らしい女子高生と犬屋敷真理ちゃんの見分けもイマイチついたとは言えません。これが、最近のマンガの「感じ」なのでしょうか。 話しの筋書きは、地球にやって来た宇宙人によって、偶然、殺された犬屋敷さんと獅子神君が「スーパー・ロボット」化されて修復され、その「スーパー」な能力を老人は「善」の方向へ、若者は「悪」の方向へ発揮するというわけで、荒唐無稽といっていいものですが、この種の荒唐無稽は映画でだって繰り返し見てきたわけですから、何の問題もありません。 先ほど「善悪」といういい方をしましたが、むしろ「自己満足」、何が「空虚な存在」であるそれぞれの「自分」や、その「こころ」を満たすのかというモチベーションが老人と高校生の二人に共通しています。 それが、この荒唐無稽な設定を支えている一つ目のポイントだと思いました。 もう一つは、ロボットの、いや宇宙人のというべきでしょうか、攻撃方法の新しさです。 現代社会の、不思議というか、理解しがたい潮流にネット社会に住み着いている「無名の悪意」のようなものがあると思いますが、それに対して一対一で報復可能なハイテクが導入されているところでした。もちろん夢の機械ではあるのですが、ぼくはこの方法が露わにしている、現代社会の特徴に対する奥浩哉というマンガのセンスはとてもすぐれていると思いました。それは、警察権力に対する戦い方にも表れていますが、スマホから直接狙撃するという発想は初めてではないでしょうか。 最終的には「家族」による「家族」、「父」や「夫」に対する「愛」の再発見、犬屋敷さんの愛犬「はな子」が最初から持っていた「愛」を、家族が共有するという結末なところが、まあ、「そうなればいいよね犬屋敷壱郎さん!」と最初からの仕込みのようなものであって、案外シンプルなところも悪くないのだろうなと感じました。 一寸穿った言い方をすれば、現代の「アトム譚」、「鉄腕アトム」の末裔の物語ともいえるわけで、このマンガのラストシーンを読みながら、太陽に向かって飛んだアトムの最後を彷彿とするのは僕だけでしょうか。 奥浩哉というマンガ家もまた。手塚治虫の末裔なのではないでしょうか、なんてことも考えさせられました。 結構な、SF活劇なのですが、案外ホームドラマなところに笑ってしまいました。ちょっと、ハリウッド映画っぽいですよね この第10巻の表紙の方は、犬屋敷さんのお嬢さんだと思うのですが、他の男の子の登場人物と、ぼくには見分けがつかないのですよね。あっちゃー!
2020.12.18
コメント(0)
-

週刊 読書案内 阿部直美「おべんとうの時間がきらいだった」(岩波書店)
阿部直美「おべんとうの時間がきらいだった」(岩波書店) このところハマっている「おべんとうの時間」のライター、阿部直美さんのエッセイですが、あちらこちらに書かれた短い文章を集めた本ではありませんでした。一冊、同じテーマで書き下ろされた(?)、いわば、私小説風、あるいは「生い立ちの記」風エッセイです。 少女時代の暮らしから始まり、高校時代のアメリカ留学体験、大学を出て働き、阿部了という写真家との出会いと結婚、子育て、そして、今や「お弁当ハンター」の異名を持つ人気ライターとしての暮らしまでがつづられています。 見ず知らず人の「お弁当」を覗いて、日本国中を旅する写真家とライターの夫婦がいます。全日空の機内誌で好評を得て、「おべんとうの時間(1~4)」(木楽舎)という単行本のシリーズも人気の仕事です。そんな仕事で、ライターを務める阿部直美さんは、実は、「おべんとうの時間」がきらいだった。 はてな、それはどいうことでしょう?というのが、人気シリーズ「おべんとうの時間」の読者が、この本を手に取る最初の動機であるという意味で、絶妙のキャッチコピーと言えるわけです。が、本当にきらいだったことが、お読みになればわかります。「ここに座れ」「まっすぐ俺の目を見ろ」 晩酌を始めた父の前に正座させられて、「貴様は最低だ」といつものパターンが始まった。その怒りを引きずった食卓で、味のしない夕飯を食べるはめになった。 この半自伝的エッセイで、最もキャラの立った人物は父マサユキさんです。彼をめぐる「恐るべき」エピソードの多さももちろんですが、上にあげた父親の描写は、実は、繰り返し登場します。 こういうタイプの父親に育てられた経験のある方なら、きっとわかると思うのですが、阿部直美さんにとって「ここに座れ」は、もう、トラウマといっていい言葉であり、それと一緒に思い出される「家族の食事」の風景は、ひいては「家族」そのものが思い出したくない「思い出」の最たるものだったに違いないのです。だから「家族」を思い起こさせる「お弁当」もまた、おなじトラウマの圏域にあったものだったに違いありません。 そんな、直美さんが「おべんとう」と、それを食べる人に興味を持って写真を撮り始めた写真家、阿部了さんの仕事を手伝うようになって変わっていきます。 それが、本書の第Ⅲ部「夫と娘」の章段の鍵ではないでしょうか。二人の間に生まれた「ヨウちゃん」の子育ての体験も苦労の連続なのですが、「家族」をつくり始めた直美さんの「おべんとう」を見る眼は変わっていきます。 最後の章段「父の弁当」で、父マサユキさんの死にさいして、父親が好きだった「おべんとう」の姿が、語られます。 その筆致にはトラウマを超えた娘の、アトピーで苦しむ娘を育てた母親の、人様の「おべんとう」の話を聞き続け、「家族」とは何かと考え続けている一人のライターの「愛」を感じるのは僕だけでしょうか。 なんだか、大げさに持ち上げましたが、「おべんとうの時間」の写真家、阿部了さんが人様のお弁当を相手に1時間も2時間もかけて写真を撮っているという、制作裏話には笑ってしまいました。 面白いう本というのは、そう簡単にできるものではないのですね。イヤ、納得しました。
2020.12.17
コメント(0)
-

徘徊日記 2020年12月8日「師走の団地」
「師走の団地」2020年12月8日 団地あたり 住んでいる棟の周りにある数本の楓が色づきました。こうしてみると、本当に紅葉といういい方に納得しますね。もう12月なのですね。朝夕の冷え込みの色でしょうか。 こちらの楓は、まだ少し緑が残っています。 銀杏の葉もそろそろ散り終わります。綺麗に散ってしまった銀杏もありました。これはこれで、すがすがしいものですね。 今年も信州から銀杏の実が届きました。近所の神社の境内で拾ってくれたそうです。いやはや、うれしい秋の便りですね。 そういえば、去年話題にしたカリンの実も大きくなっていますが、写真をとり忘れました。 今年見つけたのは夏ミカンの木です。たくさん実をつけています。酸っぱくてもいいから一つか、二つ、拝借したくなりますね。 そういいながら、いよいよ山茶花の季節です。ベランダの正面に見える、赤い山茶花は、もう満開です。 まず、赤い花から咲くのでしょうか。あちらこちらで満開です。 棟の玄関の前では、こんな赤い実がなっています。毎年この時期に実をつけるのですが、千両でしょうかね。名前がよくわかりません。 ハヤリ病が猛威を振るっている、2020年の、落ち着かない師走です。ノンビリ徘徊する気分になれません。写真を撮っていても、なかなかブログに載せる余裕がありません。なんとなく、そういう一年でした。追記2022・12・05 2年前の投稿を見ながら、今年も暮れていくのを感じている師走です。このころから続いているコロナ騒ぎは収まる気配はありませんが、収まったことにしようというムードで乗り切る世相です。この年齢になって、自分がどんな世の中に暮らしているのか見当がつかなくなるとは思いませんでしたが、うかうかしていると戦争まで起こりそうな空気さえ充満しているようで、困ったものです。それにしても、寒いような温かいような、それでいてよく雨の降る秋でしたね。ボタン押してね!
2020.12.16
コメント(0)
-

週刊 読書案内 別役実「けものづくし 真説・動物学体系」(平凡社ライブラリー)
「100days100bookcovers no39」(39日目)別役実「けものづくし 真説・動物学体系」(平凡社ライブラリー) 今回も遅くなって申し訳ないです。SODEOKAさんが前回紹介してくれたのは津原泰水の『蘆屋家の崩壊』だったが、この作家自身も名前しか知らないし、書名の元ネタのアラン・ポーもまともに読んでいないので、とりあえず今回もシンプルに考えることにする。 短編集『蘆屋家の崩壊』は、全編「動物」のモチーフ が出てくるということで、「動物」 でいくことにする。 ただ「全編、動物」というところまで考えると、そういくつも思いつくわけではない。 ということで、今回は、 別役実 『けものづくし 真説・動物学体系』 平凡社/平凡社ライブラリー を取り上げる。今年3月に亡くなった著者への追悼もかねて。 全部で239ページ(平凡社版)だったので、全編、再読してみた。 この劇作家の、この「づくし」シリーズは、結構好きで何冊か読んだ。「づくし」が付いていなくても「人体」や「病気」等の類似本も含めれば著作はかなりになるはずだ。 著者が「あとがき」でも書いているようにこの本は、シリーズの1冊目『虫づくし』(鳥書房/ハヤカワ文庫NF)に続く第2弾。 本棚にある『虫づくし』を確認したら鳥書房版だった。どこで出会ったかは例によって忘却の彼方だが、『虫づくし』が気に入ったには間違いない。 しかし『けものづくし』の「あとがき」でも触れられているように、『虫づくし』は「売れなかった」のだが、その理由として「内容がやや前衛的にすぎるきらいはあった」 と説明されている。この「前衛性」こそがこのシリーズ(類似本含む)の特徴と言っていい。 そして「前衛性」とは端的に、これも「あとがき」で言及されているが「デタラメ」 のことである。むろん、ただの「デタラメ」がおもしろいはずもない。「知的」に「体系的」に、そしてブラックに、さらにアイロニカルに「デタラメ」 だからおもしろい。要は、「フィクション」として読めばいいということだ。 ただ、出版が1982年ということもあり、読み方によっては、現代的な「ポリティカル・コレクトネス」に抵触する部分もありそうな気がする。個人的には、よく読めばさして問題はないと思うし、まして「前衛的」 であることが前提になってい本であるわけだし。 動物1種類について10ページ前後が費やされ、「いるか」から「動物園」まで全部で26項目で構成される。最後の「動物園」を除けば、すべて具体的な動物がテーマになる。 中には「猿人」や「ユニコーン」、「きりん」(「例の首の長い変種」ではない方)、「ぬえ」などという一般に「架空」 と考えられている動物も取り上げられている。むろんここでは「架空」であろうはずもない(ただ「エジプトの古い墓所に生息し死者もしくはそのたましいを常食としている」「アメンシット」については、「実在」を前提としながら、いくぶんそうでない可能性も残した表記になっている)。 たとえば「ユニコーン」は、ユニコーンの姿が、馬と雄鹿、象と猪のパーツからできていると「古い文献」に説明されているとした後、 「ここには明らかにイメージの混乱がある。ユニコーンの角は回春剤として特に修道院などでひそかに珍重されたそうであるから、もしかしたらこれは、人々からその実像をおおい隠すための『目くらまし』としての情報だったかもしれない。ありそうなことである。しかも彼らは、ユニコーンを動物学者たちの目に晒し、それに科学のメスをふるわすのを避けようとするあまり、つい近年まで、それらが実在の動物ではなく、伝説上の動物に過ぎない、とすら主張してきたのである。文献的には、紀元前数千年の昔からその存在が知られていながら、その実在が確かめられたのが、今世紀に入って1千九百三十七年だったという事実からも、彼等の陰謀のあくどさが知れようとというものである。」 と述べる。 「ぬえ」はどうだろうか。「ぬえ」が哺乳類であるか、爬虫類であるかについては議論があるし、一部には鳥類だとか両生類だとする説もないわけではないが、魚類だとする説や昆虫だする考えは支持されていないが、完全に否定されたわけではないとした後、「それにもかかわらず」と言うべきか、 「さすがに今日ではどんな素人でも、ぬえが『伝説上の動物である』とか、『架空の動物である』などの暴論を吐くことこそなくなったが、それでもまだ一部の地方には、ぬえが『動物ではなく植物である』ということを固く信じているところがある」 とする。 さらに、ぬえの「鳴き声」や翼、手、あるいは足に付いた水かきについて述べられた後、最後に「我々の知っているぬえにおける最も特徴的なことは、彼がその体に或る穴を持っている、ということである」 と言う。 その穴は我々人間も持っている生理的機能を果たす穴以外の役割を持っているようなのだが、その役割については今のところ判明していない。が、「もしかしたらぬえはそ穴によって、虚無を呼吸しているのではないか」 という説があり、 「微生物をはじめとするあらゆる生物が、その生命維持の過程で、『虚無』を呼吸する器官を養いつつあるというのが、生物学者たちの新しい主張なのである。つまり『虚無』がその生命現象を鼓舞するという作用を、重要視しはじめたのであり、ぬえにそのモデルを見ようというわけである。」さらに「もしかしたらその穴こそが、ぬえそのものではないか」「つまり。我々の言っているぬえは、単にぬえを取り巻いているものに過ぎないのであり、本来のぬえは、我々の言っているぬえによって、取りまかれているもののことでないか」 という考え方に言及する。そして、「取り囲む実体がなくとも、穴が穴であることには変わりない」(この部分に関しては個人的には納得しかねるけれど) という考え方が多方面の支持を得つつあるとし、この考え方によれば「つまりぬえというのは、それを取り囲む実体のない穴そのものなのである。それを取り囲む実体はないのであるから、それをそれとして確かめることは出来ないが、しかし、やっぱりぬえはぬえなのである」 という、結局、現状の我々の認識、つまり、ぬえの「非存在」に近い結論になっているのは「なんじゃらほい」 とは思いつつ、しかしおもしろいのは否定できない。いや、おもしろい。 「らくだ」の項に引用される、「月の砂漠」の歌詞で、「月の砂漠」が、「月夜の砂漠」か「月面上の砂漠」か、とか「銀のかめ」「金のかめ」の「かめ」が「亀」なのか「甕」(「瓶」)なのか、とかも、あほらしくて笑える。 ここでは同様の例として「猫」の項を紹介しておく。 「猫」が「化ける」のは、狐や狸と異なり(狐や狸が「化ける」のは実験段階で実証されておらず、かつ動物学者に言わせると「どことなく大衆に媚びているようなところがある」 ということもあり、著者は「俗説」とする、「それなりの必然性と、どうしようもなくそうせざるを得ないような。突きつめた純粋性」があり、それは「トロント大学のジョン・スミス博士」が、どのように飼猫「ジュスティーヌ」を「化ける」に至らしめたに表れている。 「尻尾ををつかむ」という慣用句は、何物かが「化ける」場合に尻尾だけは埒外に置かれることを暗に示しているのではないかと考えた博士は、まだ一度も化けたことのなかった飼猫ジュスティーヌが「化ける」ときのために、新案特許「尻尾固定機」を作成した。 ジュスティーヌの尻尾を固定してみると、最初ははずそうとしていたが、やがて気にしなくなった。そこにアンナ夫人が実験室の扉を開いて現れ、朝食のチーズについて博士を口汚くののしった。口論が始まり、最高潮に達したとき夫人は戸口から出ていった。 そのときジュスティーヌは化けた。アンナ夫人が出ていったにも拘らず、そこにアンナ夫人が立っていた。それも、「今の今までそうであったような全身の怒りと憎しみを奇跡のようにふるい落として、むしろ悄然と、やや淋しげにそこにたたずんでいた。」 そして博士の「あなたは、どなたですか」という問いに「アンナ・スミス夫人です」と夫人に化けたジュスティーヌは答えるのだった。そのとき、「灰色のフレヤースカートの間から、まるで小さな罪悪にように出た尻尾が、そのまま固定機につながっていた。」 ほかにも「にわとり」の項の「果たして人類に、にわとりの卵を食べる権利があるのか」 や「虎」の項の「『人食い虎』はなぜ人を喰うのか」 等、相当におもしろいが、これ以上記事を長くしても仕方ない。 というふうに大概は「デタラメ」 ではあるのだが、冒頭の「いるか」の最初の部分に登場する、SF作家ラリイ・ニーブンの「既知空域(ノウンスペース)年表」は、作家の名前も、「既知空間」という言葉も、「事実」ではある(私は作家の著作は未読だが)。さらに「いるか」というネーミングについては「古事記」の「因幡の白兎」の箇所を借用している。 だから、読み進めていくうちに、何度か「ファクトチェック」みたいなことをやることになった。結構「事実」も含まれている。「動物園」の項に出てくる、ドゥーガル・ディクソンとその著書『アフターマン』も、何だか作ったような名前だなと思って調べたら、実在の人物であり著書だった。 しかし、「猫」の項に登場するジョン・スミス博士とそのの著書『ジュスティーヌは変幻自在』は、ネットで検索してまったくそれらしいものがヒットしなかった。たぶん実在していないのだろう。 このあたりのさじ加減はさすがに別役実である。まぁ読んでいるうちに、真偽の区別はいくらかつくようにはなったけれど。 再読して改めて思ったのは、著者が、当然のようにかつ一方的に人間の立場に立つのではなく、動物の側にも立って物事ないし人間を考えようとしているということ。ときに動物心理を推測し、ときに擬人化しながら、結局、人間のことを語っている。諧謔と皮肉と辛辣さを込めて。そういうことなのだ。 だから、著者にとってみればこの手の著作も、戯曲や小説、童話等とさして変わらなかったのかもしれない。 最後に。玉川秀彦のイラストも、おもしろくて効果的。 ではDEGUTIさん、次回、お願いします。(T・KOBAYASI2020・09・10) 追記2024・02・16 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目))いう形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。
2020.12.15
コメント(0)
-

セリーヌ・シアマ「燃ゆる女の肖像」シネリーブルno76
セリーヌ・シアマ「燃ゆる女の肖像」シネリーブル 映画の始まりは、絵画教室のようです。女性ばかりの生徒に絵を教えているのはモデル役の女性のようです。生徒の一人が、彼女の作品であるらしい絵について何か言います。それがチラシにあるスカートが燃え上がっている様子の肖像画でした。見たのはセリーヌ・シアマ「燃ゆる女の肖像」でした。 そこから、その肖像画について、その画家のモノローグとして物語が始まりました。時代は18世紀のようです、小さな船に乗って女性画家マリアンヌが島につきます。 チラシによればフランスのブルターニュ地方の島で、彼女は領主である貴族の邸に呼ばれ、結婚を控えた娘の肖像画を描くためにこの島にやって来たようです。 ボートに乗っている最初の場面から、画材を海に落とした画家が服を着たまま海に飛び込むという、妙に印象的なシーが挿入されていて、屋敷に到着した彼女がずぶぬれなのですが、さて、この「水の女」の運命やいかにというわけですが、本人の回想ということですから、死んじゃったりはしないのです。 面白かったのは、画家の回想という手法の結果、「部屋」であるとか、「海辺」、「草原」、「燃え上がる炎」といった映像がとても、そしてかなり意図的な印象で、「絵画的」に美しい ことでした。自然の描写はもちろんですが、部屋の調度や壁の写し方、女性たちの衣装の写し方、映り方は「絵のよう」でした。 もう一つ、主人公が「画家」であることによって、映画において強調されていたのが、モデルを拒否する対象を盗み見ることから始まり、一方的に見つめ続ける、凝視することによる「美」の発見へと至るイメージが強調されてる映像で、「絵描き」と「モデル」という関係であればこそのリアルで、わざとらしさが、上手に回避されていました。 さて、互いが「見つめ続ける」ことによってはじまるのが、例えば、スタンダールの「恋愛論」で有名な「結晶化」です。 見つめ続けることで、そこから「美」を生み出していくのが画家マリアンヌの仕事ですが、その画家が女性であり、自らの内面に宿る「美」を形象化していく画家を見つめ続ける伯爵令嬢エロイーズもまた女性であることが、おそらく、この映画の肝心なところなのでしょうね。 残念ながら、この二人の間に生まれる「結晶化」の顛末に関しては、何となくありきたりな印象を持ちました。 とはいうものの、チラシのシーンですが、スカートに燃えうつる炎として描かれる、伯爵令嬢エロイーズの、思いがけない「愛」の発見の描写と、いったんは結ばれるのですが、結婚によって別れを余儀なくされた画家マリアンヌとの、偶然の再会の場で、マリアンヌの「眼差し」を、確かに感じながら、決してふりむくことなく、「埋火」のように燃え続ける「愛」をビバルディの音楽が強調するラストシーンのエロイーズの表情には、一種、異様な美しさが宿っていることは確かだと思いました。 「水」、「炎」、「絵画」、「音楽」、ネタは山盛りで、最初に触れた「水の女」のネタも誰かが語りそうな、凝った映画だと思いますが、ちょっと型通りだったように思いました。 偏見で言うわけではありませんが、女性しか出てこない不思議な映画で、監督も女性なのだろうと思って確かめると、やはり、そうだったことに笑ってしまいました。監督 セリーヌ・シアマ製作 ベネディクト・クーブルール脚本 セリーヌ・シアマ撮影 クレール・マトン衣装 ドロテ・ギロー編集 ジュリアン・ラシュレー音楽 ジャン=バティスト・デ・ラウビエキャストノエミ・メルラン(肖像画家マリアンヌ)アデル・エネル(伯爵家令嬢エロイーズ)ルアナ・バイラミ(召使ソフィル)バレリア・ゴリノ(伯爵夫人)2019年・122分・PG12・フランス原題「Portrait de la jeune fille en feu」2020・12・08・シネリーブルno76 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)にほんブログ村にほんブログ村
2020.12.14
コメント(0)
-

徘徊日記 2020年12月10日 「師走の街」 三宮・元町あたり
「師走の街 三宮・元町あたり」 徘徊日記2020年12月10日 三宮、元町あたり 神戸の街も12月です。今年はルミナリエが開催されませんでした。例年、この時期には見物する人はともかく、普通に帰り道を歩く人は、通行すること自体が冒険のような人出だったのですが、今年はのんびり写真を撮りながら歩くことができる大丸界隈です。 夕方の6時過ぎですが、人通りもさほどありません。電飾されたこの通りは大丸百貨店の東側、歩いていくとメリケン波止場に出ますが、ぼくは眺めるだけ眺めて、元町商店街のほうに向かいます。 天井が明るいので、すぐわかりますが、お昼過ぎに三ノ宮に向かって歩いているときの写真です。クリスマス用なのですかね、新年向けですかね、「リース」が飾られていました。 街灯にはこんなバナーも飾られています。書かれている言葉に胸打たれました。「大丈夫!ちゃんと前に進んでる。」元町商店街の4丁目と言えば「元町映画館」ですね。いつもお世話になっていますが、12月上旬の上映看板はこんな感じです。 で、2021年のお正月の特番がこれです。「天井桟敷の人々」、これは、ヤッパリ見逃せませんね。ポスターを見ているだけでも、ちょっと嬉しい気分です。 そういえば、最後に話は変わりますが、この日、阪急三宮駅のビルが完成しているのに気づきました。ずっと工事中だと思っていたのですが完成したようですね。 別に、嫌みを言う気はサラサラないのですが、こういうのは「チャンと前に進む」、いや「チャンと上に進む」らしいですね。それにしても背の高いビルができましたが、中には何があるのでしょうね。2020年、師走の三宮・元町界隈でした。ボタン押してね!
2020.12.13
コメント(0)
-

週刊 マンガ便 武田一義「さよならタマちゃん」(講談社)
武田一義「さよならタマちゃん」(講談社) このマンガは、珍しく自分で購入しました。ヤサイ君の12月のマンガ便の「ペリリュー 楽園のゲルニカ」のマンガ家武田一義さんのデビュー作だそうです。 ぼくは「ペリリュー」ですっかりファンになったのですが、この戦争マンガを読みながら、不思議に思ったことがありました。 太平洋戦争の歴史のなかでも、最も過酷な戦場であったペリリュー島の1万人の兵隊たちのなかに、作者の分身である田丸1等兵を潜り込ませた手法の卓抜さについて、第1巻の感想で書きましたが、歴史的な事実として、マンガに登場するほとんどの「戦友」たちが、必ず戦死・病死していく世界を描きながら、どうしてここまで普通の人間が生きている世界として描けるのかという疑問です。 私たちは2020年の「現実」の中で暮らしていわけで、戦場という、「死」が日常である世界を描くためには、ある「覚悟」のようなものがいると思うのですが、武田一義というマンガ家が、どうやって、その、覚悟を得たのかという疑問でした。 このマンガに、その答えがあると思いました。 このマンガは、マンガ家自身が経験した精巣腫瘍、その腫瘍の切除手術と肺への転移に対する抗癌剤治療の闘病の記録です。 主人公武田一義、35歳。マンガ家を目指すマンガ家のアシスタント。マンガ家のアシスタントとしては35歳は、決して若くないのだそうですが、がん治療の入院病棟では、ダントツの若さだそうです。 ここに載せたのは入院した武田君を迎える、同室の「戦友」たち、桜木さんや田原さんとの出会いや、武田君の最初の不安を描いたシーンです。この場面をはじめとして、第1話、第2話は「笑い」がさく裂しています。 マンガをお読みになればわかりますが、その後の展開は、決して笑ってはいられないシーンの連続です。ぼくは、ぼく自身の年齢のせいもあるかもしれませんが、何度も涙がこぼれました。 とはいうものの、武田一義さんはマンガを描いているのですから、面白く書こうとしていることは「さよならタマちゃん」という題名からもわかります。でも、それは単なる病院ギャグや、未経験者が知らない経験の「ひけらかし」ではありません。 武田さんは、普通の人が「死」を覚悟する病名を宣告された時に、それでも、今、生きていることの「明るさ」を書こうとしているように思えるのです。 先ほど、ぼくは「戦友」という言葉を使いました。武田さんは、同じ病院に入院している人たちのことを「戦友」などという言葉で表現しているわけではありません。しかし、彼の「ペリリュー」という作品を読んだ目で、この「闘病記」を読むと、彼と同室の桜木さんや田原さんの描き方は、「ペリリュー」の同じ小隊の兵士たちの描き方と同じだとぼくは思いました。 これは、無事退院できた主人公の武田君が定期検査のためにやって来た病院で、一緒に退院した田原さんの再入院を知り、彼から同室だった桜木さんの死を聞くシーンです。 このシーンを読みながら、漫画家の武田一義さんが、マンガ家として描くべき「世界」と出会った瞬間だと思いました。 この時、彼は、この作品の第1話を書いて、掲載の可否を待っている時期だったようですが、この田原さんとの再会によって、このシーンをマンガに描き、「ペリリュー」の世界へと書き継いでゆく勇気と覚悟を手に入れたのではないでしょうか。 最終話と題されたこの章が、25章にあたります。第1章、第2章で炸裂した「笑い」はやがて闘病の苦しさを描き続けることになりますが、不思議と「うっとおしさ」がないのです。主人公の武田君は、嘔吐を繰り返し、どんどん衰弱していきます。精神的にも息が詰まるような展開です。「ペリリュー」の戦場描写とよく似ています。 しかし、彼の、この二つの作品の共通点は、それでも暗くないことなのです。いったん読み始めた読み手が、辛くなって、あるいは、うんざりして投げ出すことは、ないんじゃないかと思います。 病院に入院していた武田一義さんは、生きてマンガを描く「覚悟」のようなものに出会われたのではないでしょうか。その「覚悟」から生まれた「よろこび」が「タマちゃん」から「ペリリュー」まで、たとえば田原さんというキャラクターを書くときにあらわれているのではないでしょうか。そして、それが武田さんのマンガの「明るさ」の理由ではないかというのが、ぼくの当てずっぽう推理の結論です。 裏表紙に描かれた「戦友」たちです。マンガのなかで、奥さんの早苗さんも、新人看護師の杉村さんも、同じ病気で、退院するときにはじめて口をきくことができた市川さんも、みんな戦友でした。みんな一生懸命生きている人たちでした。追記2020・12・12「ペリリュー」の感想はここをクリックしてください。
2020.12.12
コメント(0)
-

フェデリコ・フェリーニ「8 1/2」元町映画館no64
フェデリコ・フェリーニ「8 1/2」元町映画館 最近映画を見ていて、不思議に思うことがあります。最後まで見終わって、結局、何のことかわからないのに、なんだか妙に面白かったりするのは、なぜなんだろうということです。たとえば、上のシーンは、今回見たフェリーニの「8 1/2」で、マストロヤンニが帽子をかぶって風呂に入っているシーンですが、これって何なんでしょうね。 フェデリコ・フェリーニの特集ということで、2020年の10月から11月にかけて、フェリーニの映画を数本見ました。初めて見るものもありましたが、40年ほど前に見たことがあるはずの作品も数本ありました。 大学新聞の編集室にたむろしていた、まあ、後に医者になった友人が「『8 1/2』見たか?すごいぞ。」 と騒いでいたことを今でも覚えていますが、その頃、初めて見ました。 神戸で地震があったころ、ビデオで映画を見ることに凝った時期もあって、繰り返し見たものもありました。 ボクにとって、「8 1/2」という映画は、そういう映画なのですが、今回も見終わって、やっぱり、何のことかわからないままでしたが、見ていて、妙に「可笑しい」と思ったことを、今回、感じたのか、以前感じたことを思い出したのかわかりませんが、感じながら見ていました。 20代の頃どう思ったのかは忘れましたが、マストロヤンニの扮するグイドという主役の映画監督が「どうしようもないやつ」なのですが、その、自分が「どうしようもないやつ」だということが分かっているグイドの現実と、彼の頭のなかとが分け隔てなく映像化されている様子で、思いっきりハチャメチャな展開だということは記憶の通りでした。 さまざなカメラ・アングルが曲芸のように使われている印象で、そうした工夫に、ある種、フェリーニという監督の「自己言及」的な視線の、何といったらいいのかよくわかりませんが、「奇怪さ」のようなものを感じました。 最後の有名なセリフ「人生はお祭りだ」に対しても、また、そのセリフとともに繰り広げられる、あまりにも有名なダンスのシーンにも、驚きや共感というよりも、やはりうまく言えませんが、あまりにも素朴な内面凝視の「いたいたしさ」ような印象が浮かんできて、むしろ、そのことに驚いてしまいました。 こうした感想は、どうも、ぼく自身の「老化」と関係がありそうですが、この映画には、最終的に「死」への希求が描かれようとしていたのではないか、というのが帰り道で考えたことですが、それもまた、何だか辛い感想でした。 それにしてもフェリーニもマストロヤンニもとっくの昔にこの世の人ではないのですね。2020年の新作でアヌーク・エーメや、フェリーニの映画には出ていませんがカトリーヌ・ドヌーヴが新しい映画に出ているのですから、いやホント「女は強し!」なのでしょうかね(笑)。監督 フェデリコ・フェリーニ製作 アンジェロ・リッツォーリ原案 フェデリコ・フェリーニ エンニオ・フライアーノ脚本 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ エンニオ・フライアーノ ブルネッロ・ロンディ撮影 ジャンニ・ディ・ベナンツォ美術 ピエロ・ゲラルディ衣装 ピエロ・ゲラルディ音楽 ニーノ・ロータキャストマルチェロ・マストロヤンニ(グイド・アンセルミ)アヌーク・エーメ(ルイザ・アンセルミ)サンドラ・ミーロ(カルラ)クラウディア・カルディナーレ(クラウディア)1963年・140分・イタリア・フランス合作原題「Otto e Mezzo」配給:コピアポア・フィルム日本初公開:1965年9月26日2020・11・06元町映画館no64
2020.12.11
コメント(0)
-

週刊 マンガ便 武田一義「ペリリュー(1)」(白泉社)
武田一義「ペリリュー(1)」(白泉社) 12月のマンガ便に武田一義というマンガ家の「ペリリュー(1)~(8)」(白泉社)というマンガが入っていました。「ペリリューって?北のほうか?地名やろ。」「パラオって知ってるか?南洋の島や。」「戦争もん?」「ああ、おもろいで。」 表紙を開くと、現在のパラオ共和国の写真が載っています。祖父の痕跡を尋ねた青年が海岸に立っている後ろ姿があります。「ペリリュー島 昭和19年夏―」、眼鏡をかけたいかにも頼りなさそうな兵隊が行軍しています。 主人公、田丸均1等兵です。 武田一義公式ブログ 武田一義のブログに、田丸1等兵の立ち姿の写真がありました(絵ですけど)。マンガ家になりたい夢を持ちながら、徴兵され、パラオ諸島のペリリュー島守備隊に配属された青年です。 四角い眼鏡をかけて、長ズボンをはいていますが、歴史的事実に沿えば、当時は丸眼鏡しかなかったそうですがマンガの主人公として四角い眼鏡をかけさせ、半ズボンだったはずの軍装は、はかせてみると、彼の絵では子供の兵隊にしか見えないので、長ズボンをはかせたことが、あとがきでことわられています。 昭和19年のペリリュー島で何があったのか。そう聞かれても、ぼくには答えられません。そもそも、戦前、大日本帝国の信託統治領だったパラオ諸島についても、「山月記」の作家中島敦を思い出すくらいのことで、ほとんど何も知りません。しかし、地図をもう少し広げてみれば、大岡昇平が「野火」や「レイテ戦記」で描いたフィリピン諸島はすぐそこで、太平洋戦争の最も悲惨な戦場の一つであったことはぼくにも理解できます。 マンガを読み進めていくと、サンゴ礁の隆起で出来たこの島がアメリカ軍にとって、その後の戦略の鍵になる理由がわかります。それは飛行場でした。フィリピン奪還、日本本土空襲のための不沈空母、出撃基地として戦略上のかなめの島として考えられていたようです。 昭和19年9月4日、アメリカ第3艦隊、艦艇約800隻、兵員4万人が出動し、約1万人の兵隊が守備隊として配備されていたパラオ諸島ペリリューとへ向かい、マンガ「ペリリュー」が始まります。 物語の冒頭、絵をかくことのほかは肉体的も精神的にも、実戦では役に立ちそうにない主人公田丸1等兵は、小隊長の島田少尉から「功績係」として兵士の最後を記録し、遺品を収集する役目を命じられます。 このマンガが、1975年生まれのマンガ家によって、かわいらしい子供のようなキャラクターを登場させて描かれているのですが、「戦場」の悲惨さと、そこで生き、死んでいった人々の姿をリアルに読ませるための、マンガ家としての工夫が、ここにあると思いました。 マンガ家武田一義は、気弱で故郷を思い続けながら、仲間の死を一つ一つ記録してゆく田丸1等兵に潜り込むことで、新しい「戦争マンガ」を可能にしたのだと思います。 敗戦から70年以上たった「今の眼」で、主人公に潜り込んだ武田一義は戦場を見ているのです。そして、あまりに悲惨な戦場の事実に震えながら、しかし、目をつむることなく見つめる田丸1等兵を描いています。そうすることで、新しい「ゲルニカ」の可能性を夢見ているマンガ家武田一義に拍手を贈りたくなる第1巻だと思いました。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.10
コメント(0)
-

週刊 読書案内 津原泰水『蘆屋家の崩壊』(ちくま文庫)
「100days100bookcovers no38」(38日目)津原泰水『蘆屋家の崩壊』(ちくま文庫) 前回、YAMAMOTOさんが紹介された『大竹から戦争が見える』は、広島県大竹市の歴史から太平洋戦争を検証する本でした。教科書には載っていないこと、まったく知らなかった事実がまだまだたくさんあるのですね。勉強になりました。 そこで、地方発信の視点でつくられた本、というくくりでリレーを繋げないかと探してみましたが、残念ながらわたしの本棚には見つかりませんでした。ならば、終戦直後の日本を舞台にした小説、ということで2冊手に取ったのですが、どちらも何十年も前に読んだ小説で、もういちど読み直さないことには何も書けず、読み直している時間もありません。 読み直すのならば短編がいい。 それでは、ということで思いついたのが津原泰水の短編でした。津原は広島出身の作家 で、被爆二世だそうですが、彼自身はそのことを標榜しているわけではなく、幻想小説、ホラー小説の名手としてわたしの本棚を彩ってくれています。本が出たら買う作家のひとりです。 津原泰水といえば、2,3年前、百田尚樹の『日本国紀』(幻冬舎)の内容についてネットからの盗用疑惑が持ち上がり、津原がTwitterでそのことを批判するというできごとがありました。 その批判に反応した幻冬舎との間で関係が悪化し、幻冬舎から刊行予定だった津原の文庫本が刊行中止になりました。その後、社長の見城徹が、津原の著書の実売部数をtwitter上でばらしてしまい、見城が作家や編集者たちから大顰蹙を買う、という「事件」に発展しました。 文壇にも出版界の裏側にも興味はなく、『日本国紀』も読んでいないので、この事件についてはこれ以上言及しませんが、津原泰水らしいな、と思いました。「アグレッシブでしなやかな一匹狼」 というのがわたしから見た津原泰水像です。 見城がばらしたのはけっして多くはない実売部数でしたが、作品のクオリティの高さを知っている愛読者にとっては、「わたしは見つけちゃったんだもんね」 という喜びしかありません。津原の小説を刊行してくれる出版社があるならば、それが地の果てでも買いに行く自信があります。まあ、ネット書店があるので、そんなことをする可能性はほとんどないんですけど。 とまあ、長い導入になりましたが、もう少し導入は続きます。いざ津原の短編集を選ぶ段になって、『蘆屋家の崩壊』と『11 eleven』のどちらにするかで迷いに迷ってしまいます。 おそらく、今の段階で津原泰水の短編集の代表作はと訊かれたら、わたしは『11 eleven』と答えるだろう。ことに収録作の「五色の舟」と「土の枕」は名作だ。しかも『蘆屋家の崩壊』のことは、一度ブログにも書いている。けれども、エンタメを食べて生きているわたしがここで選ぶのならば、やっぱり『蘆屋家の崩壊』でないとおかしいのではないか、という結論に達したのです。 ということで、ようやく『蘆屋家の崩壊』にたどり着きました。このタイトルを音読すると、すぐに思いつく小説があるはずです。エドガー・アラン・ポーのあれです。けれども、舞台を日本に移し、換骨奪胎しただけではありません。安倍晴明のライバルだったと伝えられる陰陽師の「蘆屋道満」の子孫が現代に血統を繋いでいるというモチーフを柱に、安倍晴明を生んだとされる「葛の葉」が実は狐だったという伝説をまぶして、蘆屋家が「狐」を怖れて壊れてゆく話を紡いだ幻想小説です。 この短編集は、ほぼ全編に動物のモチーフが出てきます。タイトルだけを上げると・反曲隧道・蘆屋家の崩壊・猫背の女・カルキノス・ケルベロス・埋葬蟲・奈々村女史の犯罪・水牛群 なんとこのタイトルたちの獣っぷり。そして、全編の語り部である主人公の名前も「猿渡」です。 どの短編も、「伯爵」と呼ばれている怪奇小説家と猿渡が、好物である豆腐を食べ歩くふたり旅の途上で起こる物語という設定になっています。読みながら心に残るのは、動物の背負う「異形」だけではなく、動物に仮託された「物言わぬもの」としての佇まいです。 それを読者に伝えうるのが津原の「文体」だということになります。余計なものをそぎ落とし、練られた文体ではあるのですが、簡潔ではないのです。久生十蘭を彷彿とさせますが、十蘭より生々しい。そのあたり、津原の文体の魅力の一端を語った川崎賢子さんの解説から引いてみます。〈どれが誰の発語なのか。主語が周到に消された文章。主語をもたないのは、死者の声だからなのか。小説の言葉のなかに、生者と死者、人とけものが、ひとつに生きる。〉 そうか。この小説群に満ちているのは「声なきものの声」だったのか。声なきものの声に耳を澄ますという行為を、私たちは日常的にすっかり忘れていはしないだろうか。それが生きることの根幹にあるはずなのに。 そうそう。この川崎賢子さんの解説が、また素晴らしいのです。久生十蘭や尾崎翠の解説でよく名前をお見かけする研究者ですが、夏目漱石から中井英夫まで、日本の幻想文学史を縦断しながら津原文学の魅力が語られます。あの解説だけでも読む価値がある、というのは本末転倒ですが、それぐらいよいのです。 どの短編もイメージがひしめき合い、民俗・習俗に足を踏み入れ、豊穣に構成されて圧倒されますが、なかでも「ケルベロス」はその哀切さを、「水牛群」は内田百閒を思わせる虚実の曖昧さを、わたしは愛しています。 なお、ちくま文庫版の装幀は、俳人にはおなじみの間村俊一さんです。 やっぱり長くなってしまいました。ではKOBAYASIさん、お願い致します。 (K・SODEOKA2020・08・31) 追記2024・02・16 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目))いう形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.09
コメント(0)
-
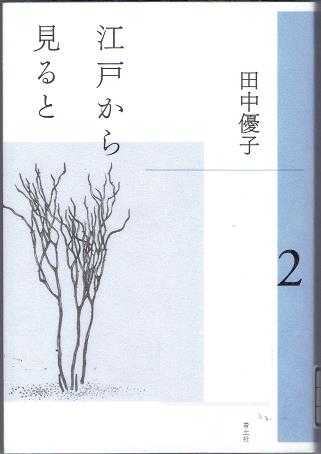
週刊 読書案内 田中優子「江戸から見ると(2)」(青土社)
週刊 読書案内田中優子「江戸から見ると(2)」(青土社) 江戸文化の、若き研究者だった田中優子さんが「江戸の想像力」(筑摩書房・ちくま学芸文庫)を引っさげて、さっそうと登場したことを、たしか1980年代の半ばだったと思いますが、つい昨日のことのように覚えています。そういえば、昨今ハヤリの、江戸の画家曽我蕭白もこの本で知ったのでした。 ほぼ、同世代の研究者であり、ぼく自身の学生時代の関心が江戸思想史だったということもあって、「江戸の音」(河出文庫)、「近世アジア漂流」(朝日文庫)と立てつづけに発表される著作に現れた関心の幅と厚みに圧倒されながらも、今でいう、フォロワーとして「カムイ伝講義」(ちくま文庫)まで読み継いでいましたが、何となくというか、自分自身の江戸に対する関心の薄れの結果でしょうか、ここ10年、その仕事に興味を失っていました。 そんな、田中優子さんですが、先日、図書館の新刊の棚で見つけたのが「江戸から見ると2」でした。 著者の来歴を見ると、いつの間にか法政大学の総長さんとかで、 「おやおや、これは、これは。」 と、いったん棚に戻しかけたのですが、内容が、新聞の連載コラムということで、 「いったいどんなことをどんなふうに語るようになっているのだろう。」 と、その場でパラパラページをくると、一つ一つの文章が短くて、日々の某所での読書にピッタリだと思い直して借り出しました。 読み始めてみると、上でも書きましたが、毎日新聞に連載されている時事コラムでした。話題は「沖縄」、「石牟礼道子」、「韓国、中国との外交」、「大学生の就職」、「中村哲」、「セクシャルハラスメント」、「老人介護」と多岐にわたりますが、論旨の根幹にある思想のゆらがなさ、思考の対象に対する関心の深さと広さ、何よりも口調のよさに一気読みでした。 論旨や思考については、まあ、今や専門家の親玉なので当然ですが、歯に衣着せぬ「啖呵」まがいの気っ風のよい口調は、この人ならではではないでしょうか。 最近、こういう「正論」をはっきり口にするコラムには、なかなか出会えないのではないでしょうか。こんなふうに言っても、よく分からないですね。 一つ例を引用します。昨年の秋評判になった「主戦場」という映画について「論争型編集で見えたもの」と題して語っている文章です。「論争型編集で見えたもの」 江戸時代、俳諧というものが盛んだった。五七五と七七を連ねていく。ある句のを前の句に続けて読んだ場合と、次の句とともに読んだ場合とでは、シーンや意味が違ってしまう。むしろその変化を楽しみ、価値を置いたのである。 遅ればせながら映画「主戦場」を見た。アメリカ人が監督した映画だ。三〇人近い人々にインタビューし、その語っている映像を論争型に編集している。編集は時に、その本人の言おうとしていることが全体の文脈から切り離され、他の要素と組み合わされることで意味が変わってしまう場合がある。私は映画を見る前、それを懸念した。「そんな発言はしていない」と訴える人でも出てくるのは、と。しかしこの映画の論争型編集の効果はむしろ逆で、ひとりひとりの本性や考えが、言葉と表情から、明確に見えるのである。 そして、背筋が寒くなった。日本がどこへ向かおうとしているか、それはなぜなのか、敗戦以後の岸信介内閣の始まりとともに走り出したその行く先に、その孫によって何がもたらされるのか?その孫を背中から支えているなんとかいう会議体。その会議体を中心にぐるぐる回っている「伝聞」で構成された言葉だけの幻想世界が見えてしまった。人の書いたものを読まないと断言する人や、自分では調べない人や、人権問題をちゃかす人々によって構成された言葉や論理に、もし国のトップや内閣が依存しているとしたら? そう、背筋が寒くなるのである。その反対に、不都合な真実であっても真剣に突き止め受け止め、そこに向き合うことを自らの生き方とする人々も見えた。私はどう生きたいか。それを問われる映画である。ちなみに私のこの文章、固有名詞も映画のテーマも書かれていない。なぜなのか。ある特定の言葉を書くと脅迫されかねない、「表現の不自由」社会になっているからだ。意味不明の方は映画を見てください。 いかがでしょうか、まあ、考え方にはいろいろあるでしょうが、ぼくは「背筋が寒くなった」と言い切っているのを読んで、胸がスッとしました。田中優子健在ですね。 今も、このコラムが新聞紙上で続いているのかどうか知りませんが、コロナ対策の迷走ぶりや、学術会議への弾圧事件に、どんなことをおっしゃっているのか、興味津々ですが、そういえば、最近、政界とかのトップに立った、見るからに金儲け主義で、強きに媚びるタイプの元苦学生(?)の政治家についての話題も、この本に所収されていますが、2019年の段階で、すでに、バッサリだったような気もします。 一度に二つ、三つ読んで、ちょっと気が晴れる読書に最適でした。追記2022・07・06 政治的なできごとに限らず、社会の動向について、そこそこの社会的ステータスを手に入れている人が批判したり、反対をコチにするという場面に出会うことが減ったと思いませんか?コンビニのような小売業に借りらず、サービス業や出版、放送を担うマスコミと呼ばれている業界で「リスク・マネージメント」がマニュアル化されて久しいのですが、「トラブったら困る」・「やり玉にあげられたらいやだ」という、リスクに対する不安が蔓延していて、社会的な発言を求められる人の社会意識をむしばんでるのが実態なのではと危惧しています。 ブラジルの高校生が、「空気オカマイナシ」で暴れている「これは君の闘争だ」という映画を観ていて思いだしましたが、田中優子さんって、そういう子供みたいなところがあって好ましいですよね。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.08
コメント(0)
-

週刊 読書案内 チャールズ・ブコウスキー「パルプPulp」(柴田元幸訳・新潮文庫)
チャールズ・ブコウスキー「パルプPulp」(柴田元幸訳・新潮文庫) アメリカの作家で、1990年代に出版されたチャールズ・ブコウスキー「パルプPulp」(柴田元幸訳・新潮文庫)を久しぶりに読み直しました。表紙の絵につられて読んだわけではありません。 翻訳家の柴田元幸と作家の高橋源一郎の二人が「小説の現在」をめぐって対談している「小説の読み方、書き方、訳し方」という河出文庫を読んでいて、こんな会話に出会ったことで、ああ、そうだブコウスキーがいたなと思いだしたのが、読み始めた直接の理由です。柴田 高橋さんが激賞される作品は、徹底的に考えないというか、壊れている方ですよね。「パルプ」もそうかもしれないし、猫田道子の「うわさのベーコン」とか。高橋 そう、フィジカルというか、体を通過してきた作品という気がします。「ニッポンの小説」のなかでも書きましたけれど、「うわさのベーコン」は、本当に頭が壊れた作者の作品だし、「パルプ」は頭が壊れたかのごとく書かれている、というか、ボディだけで書いているように見える。原理主義が破壊されずに、その本質を失わないままこの世に形を成すとしたらああいうものかな、と思っているのです。 この会話を読んで、「パルプ」という、ブコウスキーの遺作を、20年ぶりに読み直したといっても、何のことかわかりませんよね。 もう少し付け加えると、高橋源一郎は、この会話の少し前にこんなこともいっているのです。高橋 ぼくの願望ははっきりしていて、ここ何年か、いかに下手な、ダメとしか思えない形の文章で小説が書けないかと、ずっと考えています。もちろんいま「下手な」とか「ダメな」と言いましたが、美しいものについては形があります。でも、ものすごく極端なことを言うと「下手な」「ダメな」にはかたちがない、というか、それは要するにコードに則っていないものなんですね。美しいものは、だいたいコードに従っていると思うんです。 実は、この所、高橋源一郎の「日本文学盛衰史」という小説を読んでいて、とても面白いのですが、「なぜ、面白いのかわからない」という、他人さまから見れば、まあ、どうでもいいことですが、本人には「困ったこと」が起こっていて、それを解決したいというのが、「小説の読み方、書き方、訳し方」を読んだ理由です。 写真の「パルプ」は、ぼくが読んだ新潮文庫版で、2000年の発売です。高橋源一郎と柴田元幸の会話は2006年です。実はこの本も、出てすぐ読んだ記憶がありますが、それを忘れて、最近、買い直して、読み直したのです。ついでにいえば、「日本文学盛衰史」も読み直しなのですが、読み直してみて、この作品の面白さの理由がわかっていないことに気付いて、困っているのは2020年の秋のことです。要するに、三冊の本を、2020年の秋に、みんな読み直したというわけです。 余談ですが、三冊とも、それぞれの本の出版当時、購入したはずなのですが、一冊も見つからなかったという共通点もあります。 で、「おもしろさ」なのですが、高橋源一郎が口にしている「原理主義」という言葉がカギのようですね。 「文学」を「文学」足らしめている「コード」とか「規範」とか「タブー」とかを、徹底的に壊す書き方のことだというのが、高橋源一郎のほかの場所での発言から類推できますが、本当のところは、二人の会話を読んでいただくしかありません。 しかし、実は、新潮文庫の「パルプ」の解説で、ヤスケンこと安原顕という、今となっては、「伝説?」の編集者がこの本の解説で、こんなことを言っているのです。 「訳者あとがき」の中で柴田元幸氏は「パルプ」はタランティーノ監督の映画「パルプ・フィクション」同様、「無数の凡作が無節操に生産・消費された時代への賛歌と言えそうだが、安手の素材を洗練された作品に昇華させた「パルプ・フィクション」とは対照的に、こちらは安手の素材をあくまで安手のまま再現している感がある。タイトなリズムとテンポのいい会話に支えられた、さりげない反復と変奏が小気味よく織り合わされる「プルプ・フィクション」に対し、「パルプ」では、とりあえず酒場に入り、とりあえず競馬場に出かけるといったふうに、小便がたまったからトイレに行くのとさして変わらない無根拠な必然とともに、同じような行為がのんべんだらりとくり返される。タランティーノにはタランティーノの冴えがあり、ブコウスキーにはブコウスキーの凄みがある。」と書いているが、そのとおりだとぼくも思う。 おわかりでしょうか、柴田元幸は自分が訳した「パルプ」について、まともな小説の「まじめな」要素は、みんな捨てられているのだけれど、出来上がった作品には「凄み」があると言っているのです。 実際どうなのかは、もちろん読んでいただくほかはありませんが、この評言は、高橋源一郎の「日本文学盛衰史」にも、ピタリとあてはまるというのが、ぼくの納得でした。 安原顕氏は上のような引用に続けて、「パルプ」から、彼が「凄い」と判断したのでしょうね、こんな引用を延々と続けています。 宇宙人ジーニーは地球の植民地化を断念する。その理由は地球はもはや救い難いほど「ひどすぎる」からと言う。「何がひどすぎるんだ?」とのニックの問いに対しジーニーは、「地球がよ。スモッグ、殺人、大気汚染、水質汚染、食物汚染、憎しみ、無力感、何もかもよ、地球でたった一つ美しいのは動物だけど、その動物も、どんどん滅ぼされてるし、しまいにはペットのネズミと競馬の馬以外みんななくなっちゃうわ。ほんとに情けないわよ」「そうともジーニー。原爆の貯蔵量もわすれるなよ。」「・・・あんなたち、どうしようもなく深い墓穴を彫っちゃったみたいね。」「ああ。俺たちは二日後に消えてなくなるかもしれないし、あと千年もつかもしれない。どっちだかわからんから、たいていみんな、どうでもいいやって気になっちまう。」 探偵ニックの事務所にやって来た宇宙人ジニーの会話の、これは、ほんの一部ですが、これだけでは、何のことかわかりませんね。 「パルプ」にしろ「日本文学盛衰史」にしろ、作品をお読みなられることが一番ですが、読み終わって、「なんだこれは!」と投げ出される場合が無きにしも非ずなことは申し上げておきます。 なにせ、「文学的コード」は徹底的に破壊されていますからね。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.07
コメント(0)
-

フェリックス・デュフール=ラペリエール「ヴィル・ヌーヴ」神戸アートヴィレッジ
フェリックス・デュフール=ラペリエール「ヴィル・ヌーヴ」アートヴィレッジ 不思議な印象が、静かに残りました。まったく初めて見るタイプのアニメーション映画でした。たしかに「物語」を描いてはいるのですが、淡いモノクロの映像ということのせいもあると思うのですが、物語の輪郭が定めがたい印象で、どんな話だったのかを語ることが難しい作品でした。 カナダの監督らしいですが、フェリックス・デュフール=ラペリエールという人の「Ville Neuve」、「新しい町」と訳せるようですが、という、白黒のアニメーション映画でした。 海辺の一軒家を借りて住み始めた中年の男が、かつての妻だった女性に電話をかけます。彼が詩人であることはよくわかりませんが、物書きであることはわります。離婚の理由の一つは、男のアルコール中毒だったようですが、彼は、今、何度目かの「禁酒」の最中のようです。 越してきた、海辺の一軒家に「訪ねてきてほしい」というのが、男の電話の要件なのですが、それが、うまく言えないのが、この物語のだいじなところです。 妻であった女性は、何度かの電話でのやり取りの後、この海辺の家にやって来ます。二人の間にある「齟齬」が解決したわけではありませんが、その女性が、その場所、「新しい町」へやって来たことには、それなりに、女性の内面を語っていると思いました。 こう書いていると、老年にさしかかった、元夫婦の「やり直し」の話のようですね。確かにそうなのですが、この二人の関係に、カナダで実際に起こっているケベック州の独立運動の話が、鋭角に突き刺さってくるあたりから、映画そのものの「筋書」が、見ていて混沌としてくるのです。 たとえば、チラシにも映っていますが、モノクロのこんなシーンがあります。 ご覧のように、何故だか、二人の実像に対して、鏡面の絵のような、少しトーンを落とした絵が重ね合わせられています。 電話のやりとりの「遠さ」から、会話する二人の影の描写、冷たく静かな海での和解のシーンまで、アメリカの作家レイモンド・カーヴァ―にインスピレーションを得たという、チラシにある創作裏話に納得のいく、「アイデンティティの危機」の描き方なのですが、ここに、ケベック独立運動という、もう一つの、実に切実な社会的要素が重なってきて、見ているぼくは、何が何だかわからないことになりました。「白」の地に、「黒」から、様々な「灰色」を経て、再び「白」が描かれるかに見えるアニメの画面は、ある種の頼りなさを湛えながら、どこか清潔で、極彩色のアニメにはない「心象風景」を作り出していきます。 で、最後に報告しますが、そういうシーンの連続は「眠いのです」。あたかも、催眠術をかけられたかのように、「眠り」と「覚醒」の、ゆるやかな反復の80分、話の筋がよくわからない理由は、そこにもあるのでした。監督 フェリックス・デュフール=ラペリエール製作 ガリレ・マリオン=ゴバン脚本 フェリックス・デュフール=ラペリエール音楽 ジャン・ラポーロバート・ラロンドジョアンヌ=マリー・トランブレテオドール・ペルランジルドール・ロワポール・アーマラニ2018年・76分・カナダ原題「Ville Neuve」2020・12・05アートヴィレッジ(no12)にほんブログ村にほんブログ村
2020.12.06
コメント(0)
-

週刊 マンガ便 夏緑:原作・ちくやまきよし:作画「しっぽの声1~7」(協力:杉本彩 小学館)
夏緑:原作・ちくやまきよし:作画「しっぽの声1~7」(協力:杉本彩 小学館) 我が家の愉快な仲間、ヤサイクンが毎月届けてくれる、11月の「マンガ便」に入っていました。 夏緑原作、ちくやまきよし作画のマンガ「しっぽの声(1巻~7巻)」です。公益財団法人動物環境・福祉協会Eva理事長という肩書の杉本彩という人の名が、協力者として表紙にあります。ペット飼育や虐待の現実がかなり丁寧に描かれていました。 最近のヤサイクンのマンガ便には、「コウノドリ」とか「リエゾン」といった、お医者さんが主人公ではあるのですが、「子どもが生まれる」とか、「子どもたちが生きている」とかいう「現場」をまじめに描こうとしている作品が続いていると思うのですが、今度は、「動物の命」がテーマのマンガでした。 マンガを描く人もいろいろ勉強しているのですね。上の二つの作品でも感じましたが、ぼくたちの目の前にある、今の社会の姿を、「ここから見れば」という感じで、視点を少し変えることで、新しい「リアル」を発見していく描き方をしようとしているマンガ作家の、まじめな努力を感じる作品です。 「しっぽの声」という題名の通り、ペット呼ばれて人間とともに暮らしているネコや犬たちの眼から見れば、この社会がどういう姿をしているのか、ちょっと「しっぽ」のある彼らの声を聞いてみませんかというマンガでした。 アニマルシェルターの経営者で、所長さんである天原士狼くんと、アメリカ帰りの獣医師獅子神太一君の二人が、まあ、主人公ということになります。 話題はペット繁殖業、生体展示販売、飼育放棄、野良犬、ノラ猫の捕獲や殺処分と、ペットと縁のない暮らしをしているシマクマ君には、初めて知る話題満載で、面白がるというよりも、なんか、ベンキョウになるなあというマンガでした。 たとえば、第1巻には、「飼育放棄」されたワンちゃんが、空腹のあまり、自ら噛み千切って失った前足の義足の話や、密輸された蝙蝠を齧って、日本ではありえない狂犬病を発症してしまったの犬の「殺処分」の話とかが出てきますが、それぞれのワンちゃんの不幸が、「人間」の身勝手な欲望の結果としてあるのことを「しっぽの声」が問いかけていると思いました。 いつもマンガを届けてくれるヤサイクンは、二匹のネコと、飼育放棄された状態だったらしい「カルちゃん」というワンコを引き取って暮らしています。動物好きのヤサイクン一家なのですが、可哀そうなことに、子どもたちや猫たちとも仲良しの「カルちゃん」は、どうしたことか、ヤサイクンにだけ冷たいのだそうです。 現実のワンちゃんやネコ君たちというのは、なかなか、好き嫌いがはっきりしていて、「しっぽ」のない人間の声が、うまく届くとは限らないようです。 7巻まで読み終えて思いました。それにしても、街のあちらこちらで、ワンちゃんやネコ君たちが「しっぽ」をふったり、プイッと向こうをむいたり、ゴロゴロ寝そべったりしながら「ちょっと、こっちからも見てね。」と呼びかけているようです。「しっぽ」をなくした生きものたちは、もう少し、「しっぽの声」に耳を傾ける暮らしをした方が楽しそうですね。 描かれている内容は、動物好きには、かなりつらいこと、腹立たしいことが多いのですが、「しっぽ」のある「生きものたち」の「命」の扱われ方は、「しっぽ」のない「生きもの」にも、他人ごとでない「リアル」を感じさせる作品だと思いました。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.05
コメント(0)
-

週刊 読書案内 阪上史子「大竹から戦争が見える」(広島女性学研究所)
100days100bookcovers no37 (37日目) 阪上史子「大竹から戦争が見える」(広島女性学研究所) 謡曲の「井筒」で紀有常女が謡う和歌から、水原紫苑「桜は本当に美しいのか」(平凡社新書)の現代短歌へと、シマクマさんは私たちを誘ってくれました。僕は能を知らないと言いながら、縦横無尽、雄弁に語るのは、さすがです。 それにしてもこの企画「100days100bookcovers」が面白いのは、本の紹介のあとのコメントですね!私は気が利いたことをなかなか書き込みできず、もっぱら読んで楽しんでいるのですが、あっち行き、こっち行き、またそれぞれのFB友だちからの書き込みもあり…。能面が大好きなオーストラリアの友人からのコメントがあった時はびっくりしました。 さて、2日間の「青春旅行」から帰ってきたところです。バトンを受け取り、はてどうしようと…。最近は北村薫を続けて読んでいるのでそちらも気になるし、能も大好き。旅のおともに季刊俳句誌『いぶき』も持って行ったのですが、SODEOKAさんの前で俳句なんてとんでもない!会員になっているだけなんです。トホホ…。 桜についてつらつら考えながら廿日市で下車。市木が桜と…。廿日市でのお目当ては「クラフトジン桜尾」。廿日市には桜尾城というお城があるそうで、そこからジンの名前になったのかな? 次いでこの旅のメインである大竹市に足を延ばす。市内の亀居城本丸跡から瀬戸内海と桜の眺望を楽しむことができるそう。桜か…。 いや桜というより、そもそもこの大竹に来ることになったのは、先輩の先生が退職後に出された本を読んで、実際に足を運ぼうと思ったから。KOBAYASI君は市立伊丹高校卒業ですね。FBで知りました。この本の著者はKOBAYASI君の母校で長らく日本史の先生をされていた阪上史子さんです。 阪上先生とのご縁はないでしょうか?朝鮮文化研究部の顧問をされていました。…ということで、ずいぶん私的なセレクトですが、今回は旅の復習を兼ねて、この本を紹介させてください。シリーズ 広島地域近現代史―1著者:阪上 史子『大竹から戦争が見える』編集・発行:高雄きくえ 発行所:広島女性学研究所 筆者の阪上史子さんについて、本では以下のように紹介されています。 1946年、大竹市に生まれる。広島大学卒業後、兵庫県伊丹市、宝塚の公立高校で社会科(歴史)を担当。2007年退職。「神戸・南京をむすぶ会」「兵庫県在日外国人教育研究協議会」会員。現在、宝塚市在住。 私は担任した韓国人生徒との関わりをきっかけに「兵庫県在日外国人教育研究協議会」に関わり、退職した今もなぜか事務局長としてボランティアしています。先輩の先生方にはずいぶんいろんなことを教えてもらいました。阪上さんは尊敬する先輩のお一人です。 さて、大竹市はどんな町か。市のHPに次のように紹介されています。 大竹市は広島県の西端に位置し、古代には遠管郷(おかのさと)と呼ばれ、当時の都と九州・太宰府を結ぶ古代山陽道の安芸の国の終駅として、また交通の要所として栄えました。昭和29年9月1日に近隣と合併して大竹市として市制を施行し、現在に至っています。戦時中は旧日本海軍の潜水学校があり、戦後は引き揚げ港にもなった大竹港、JR山陽本線、山陽自動車道(広島岩国道路)のインターチェンジなど、交通の便が良く、小瀬川のきれいで豊かな水に恵まれた本市では、その後、パルプ、化学繊維、石油化学等の大企業を誘致し、瀬戸内地域で有数の臨海工業地区に発展しています。また、瀬戸内海では水産業が盛んで、その漁獲量、収穫量は県内有数となっています。 私の住む加古川市も海沿いで山陽道の宿場町として栄え、今は神戸製鋼などの企業を抱え、戦争中は…なんかとっても重なるんですけど…。デジャブ…。 私はずっと生まれた加古川に住んでいるけれど、大学から故郷を離れた阪上さんは、長く大竹市のことを知らないでいたわけです。 2011年、中国・海南島戦跡フィールドワークに参加し、日本兵が戦時中蹂躙した海南島に大竹が日本海軍兵士を送り出し、また敗戦時には大竹へ引き揚げるという事実を知るのです。 海南島と大竹の関係の深さや尋常ならざる大竹の戦争体験の調査や聞き取りを進めていかれます。それらの原稿を読まれた「ひろしま女性学研究所」の高雄菊枝さんのご尽力で1冊の本にまとめられ、その、上の1冊が私の手元に届いたのです。 ああ、私も広島、長崎、沖縄や南京、アウシュビッツでなく、まず足元故郷の戦争体験をちゃんと知ることで、戦争が生々しく立ち上がってくるのかもしれない…と思ったのでした。いずれにせよ、「現場主義」の私はまず大竹へ行きたいと思い、やっとこの夏決行することになりました。 本の構成は以下のとおりはじめに第一章 海南島に出会う第二章 大竹から「戦争」が見える第三章 大竹と朝鮮人おわりに 中でも第二章が中心になるのですが、歴史遺産たっぷりの大竹の中で、戦争中がすごい。軍都広島は、原爆の被害を受けたことが大きくクローズアップされるが、日清戦争時に大本営が置かれたり、呉の軍港をはじめ広島湾を囲む良港がたくさんあったりと、あたり一帯は戦争の加害とも大きく関わっています。 大竹市も大竹海兵団があり、5年未満の短期間のうちに15万人の訓練兵を輩出。城山三郎と笠原和夫は海兵団で同期、それぞれの作品から海兵団に関わる箇所を丁寧に拾っています。脚本家笠原が大竹以外の海兵団に行っていたら『仁義なき戦い』は生まれなかっただろうというエピソードも。主人公のモデルとされる元組長の美能幸三と同じ海兵団出身だとわかって通じ合うことができたとか。 また大竹は引揚港として、410,783人をフィリピン、沖縄、ベトナム、インドネシア、ニューギニア、中部太平洋、シンガポールなどから受け入れています。海南島や満州からも。映像の記録、引揚援護庁の記録などから具体的に浮き上がってくる引揚者の表情や思い。 詳細な当時の記録と比べ、最近の公文書の改ざんや非公開、そもそも公文書を作らないなどという政府はけしからんことですね。 日本中あちこちの近代インフラ整備の中で酷使された朝鮮人労働者はもちろんここにも。大林組の飯場に働く朝鮮人たちの朝鮮部落の記録や聞き取りも。原爆の被害も多い。占領時代に占領軍慰安所が一般婦女子の防波堤のためにつくられたという負の歴史もしっかり書いてあります。 慰安所設置はGHQの指示ではなく、日本政府が忖度して実施したわけです。沖縄の集団自決と同様、中国大陸で日本軍が行った残虐非道な行為を占領軍にされると信じたからなのです。当時は警察が慰安婦募集に奔走したと記録に残っているが、慰安所に従事させられた女性たちの人権は軽んじられたわけです。 また、軍隊関係地の跡地利用は国立病院や学校、民間企業に払い下げられ、駐留軍接収地が本来の所有者である企業に返還され工場誘致が進んだことで現在の大工業地帯となっていくわけです。 軍関係地が学校や企業となり、受験戦争を経て企業戦士になる。コロナ禍の今も忍従を強いられている日本はいつまでたっても集団主義から解放されないのでしょうか。目を覚さなくては! 第三章の大竹と朝鮮人では、大竹朝鮮初級学校のこと、大竹在住のおふたりの在日朝鮮人の方からの聞き取りと、阪上さんならではの温かい著述となっています。 大竹朝鮮初級学校の教員をしておられた姜周泰(カン・ジュテ)さんのお店が駅前にあるということで、阪上さんにお店の名前と電話番号を聞いて、アポなしで焼肉「照月」さんに。幸い81になられる姜周泰さんにご挨拶でき、焼き肉、ビールを美味しくいただきながらオモニといろんなお話ができました。 実際に大竹に行って炎天下に歩いて回るのは苦労するので、タクシーで要所をまわり、戦後生まれの運転手さんに話を聞くことができました。 大竹海兵団記念碑、あこがれ港広場、三菱レイヨン社宅跡地は今でもわかるけれど、潜水学校跡、大竹朝鮮学校跡地、引揚桟橋跡はずいぶん変わっていて地図と照らし合わせて確認するのみでした。最後に原爆慰霊碑を探して市民会館前へ行くと、会館内で原爆写真展と大竹戦後60年記念「大竹港引き揚げの記録」のビデオ上映が! 多くの大竹戦争体験資料も展示しており、夏ならではの催しに感謝でした。 とまあ、個人的な本の紹介にお付き合いいただいてすみません。みなさんコメントもしにくいし、バトンタッチするSODEOKAさんにも申し訳ないです。ぐっとワープしてどこか遠い所へ連れて行ってくださいませ。よろしくお願いします。 追記2024・02・16 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) 51日目~60日目いう形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.04
コメント(0)
-

ホンマタカシ「建築と時間と妹島和世」元町映画館no63
ホンマタカシ「建築と時間と妹島和世」元町映画館 建築家の名前も、映画を撮っている監督の名前も知りませんでした。もちろん建築関係者でもありません。ああ、偶然ですが、被写体であった大阪芸術大学の関係者、卒業生は、なぜか、結構たくさん知っていますが、映画とは何の関係もありません。で、どうだったかって? なぜか、退屈せずに見てきました。今考えてみて面白かったことはいくつか挙げられます。 一つは、ある時間をかけて、模型を作って、図面ができて、現場があって、また模型を作り直して、予算があって、また図面を引き直して、現場にやって来て、工事のクレーンがあって、少しずつ風景が変わって行って、まあ、変なおばさんがヘルメットをかぶってウロウロして、建物が出来上がって行って、遠くから見ると、なんだか違う風景が出来上がるという、言ってしまえば、そういうプロセスですね、それが、一寸、ワクワクしながら、見ていて面白かった。 二つ目は、数日を早回しして見せるシーンが何度かあるのですが、それが、何を意味しているのか、最初はわからないのですが、朝から夜、次の朝、昼、また寄る、というふうに工事現場が撮られていて、そのシーンを設計者の妹島和世さんが見ているシーンがあって、「おや?」と思いました。 一日とか、一週間とかのスパンで、風景は変わりますよね。で、時間のスパンによって変化の印象も違います。同じ工事現場があるのですが、ぼくのような素人の目線だと、人の位置とか、クレーンの角度とか、日の光とか闇とかにしか気付きませんが、きっと、もっと要素がたくさんあるのでしょうね。繰り返しの音楽の中で、そういう変化の「印象」を映し出している感じがして、かなり面白いと思いました。 三つ目ですが、実は、出来上がった建築物には、さほど感心しませんでした。それより、建築家として登場する妹島和世という人は、とても面白かった。 映画.com この人なのですが、ご覧の通りロンドンブーツみたいな、高下駄みたいな靴をはいていらっしゃるのですが、まず、それが「おおー、何だこの人は!」という驚きでした。ほとんど同じ年の方なのですが、このいで立ちで、工事現場に立つのですから、ちょっと、すごいなあという感じでした。 あと、この人が語る様子が映るのですが、考えていらっしゃることが、どうも言葉ではうまく言えないという、当たり前と言えば当たり前のことが、直に写っている印象で、それが、ロング・スカートと高下駄靴という形をしていそこにいて、なんだかツーカイでした。 でも、ことばと現実の狭間に「建築物」や、その「建築物」を取り巻く風景がある感じは、かなり興味を惹かれましたが、だからどうだということが、こちらに浮かぶわけではないので、「まあ、なんか、そんなふうなのかなあ?」というあやふやなことしか、やっぱり、言えないわけです。 というわけで、何にも知らないし、建物にも、格別の興味を感じるわけではない割に、むしろ、ホンマタカシという名前が気になった映画でしたが、ちょっと、現物を見てこようかなと思っている今日この頃です。監督 ホンマタカシエグゼクティブプロデューサー 内藤久幹プロデューサー 内田現アソシエイトプロデューサー 吉野裕介撮影 ホンマタカシ音楽 石若駿キャスト 妹島和世2020年・60分・日本2020・11・30元町映画館no63にほんブログ村にほんブログ村
2020.12.03
コメント(0)
-

週刊 マンガ便 石塚真一「BlueGiantExplorer 1」(小学館)
石塚真一「BlueGiant Explorer 1」(小学館) 10月のマンガ便です。「ブルー・ジャイアント・アメリカ編」が「BLUEGIANT EXPLORER(1)」(小学館)と銘打って始まりました。 表紙の宮本大君、顏が変わりましたね。彼は何年ヨーロッパにいたのでしょう。マンガ家の石塚真一は、彼に、明らかに成長した「新しい顔」を与えたようです。 「ブルー・ジャイアント・ヨーロッパ編」では130回余りのライヴ演奏をカルテット「Dai・Miyamoto NUMBAR FIVE」でやり遂げ、様々な葛藤や壁を乗り越え、有名なジャズ・フェスティヴァルでの賞賛を勝ち得る結果を手に入れました。 が、それが、たどり着いた栄光は、どこまでも前に進もうとする主人公にとっては、別れと新たな出発のときでした。で、アメリカ西海岸の街、シアトルに、またもや、一人でやって来ました。 一人でやって来て、とても超えられそうにない「山」に挑み続ける「青年」が石塚真一の描くマンガの共通した主人公のようです。まあ、だからこそ、同じ読者が読み続けるのだと思うのですが。 シアトル郊外のレーニア国立公園のキャンプ場です。この大木こそが、宮本大君が新しく出会ったアメリカの象徴ですね。 彼はこの町で、アメリカを横断するための自動車を手に入れるために、修理工場でアルバイトしますが、そこで出会ったのが、ロック・ギタリストのエディ・ドブソンでした。 エディは、みずからのギタリストとしての将来をかけて、宮本大をゲストとして舞台にあげ、リード・ギターとテナー・サックスで共演し、宮本大に最初に敗れるアメリカのミュージシャンになります。 シアトルの宮本大が、アメリカで最初に挑んだのは、ジャズのプレイヤーではなくロックのギターでした。それが、アメリカだということでしょうが、臆することなく挑んだDai・Miyamotoは、自動車修理工場のメカニックとして、今もシアトルで生活するエディ・ドブソンの心の中に生き続けます。 マンガは、宮本大がアメリカで出会い、音楽を通じて友達になった人々の回想として綴られているようです。 シアトルを出発する主人公ですが、次はどの町で、どんな出会いが待っているのでしょうね。追記2020・12・01「ブルージャイアント」(第1部)・(第2部)8巻・10巻・11巻の感想はここをクリックして、覗いてみてください。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.02
コメント(0)
-

週刊 マンガ便 石塚真一「BlueGiant Supreme 11」(小学館)
石塚真一「BlueGiant Supreme 11」(小学館) 10月のマンガ便で届きました。「ブルージャイアント ヨーロッパ編」、最終巻です。 仙台の広瀬川の堤防で、初めて手にしたテナー・サックスの練習に夢中だった、高校生宮本大くんが、ヨーロッパに渡り、そこで出会った3人のミュージシャンとマネージャーのガブで結成したカルテット「DaiMiyamoto NUMBAR FIVE」の成長の物語でした。 小柄なドイツ人女性ベーシスト、ハンナ・ペータース。神経質なポーランド人で、正確でストイックなピアニスト、ブルーノ・カミンスキー。いかにもフランス人らしく、「音楽の自由」を体現しているドラマー、ラファエル・ボヌー。そしてアジアからやって来たテナー・サキサフォン奏者宮本大が、ヨーロッパの北の果ての街、ノルウェーのモーシェーンまでやってきて、ヨーロッパ最後のライヴに挑みます。 133回目の、このライヴで、宮本大君は「サンキュー、ヨーロッパ!」の言葉をのこして、ジャズの聖地、アメリカに向けて旅立つわけです。 ここまでに、作者石塚真一の手によって描かれているのは、「DaiMiyamoto NUMBAR FIVE」カルテットが、ヨーロッパでたどり着いた、音楽のすばらしさが、国境や性別、個々の嗜好を越えて結実していくという、ビルドゥングスの物語の、ひとつの頂点だった思いました。 こういう、台詞なしの演奏シーンのすばらしさがぼくは好きですが、「オレは行くんだ。」という叫びが、ページいっぱいに響いてくるこのシーンを書いたからには、石塚真一もまた、宮本大君とともにアメリカで苦労するほかないのではないでしょうか。 すでに「BlueGiant EXPLORER 1」は発売されています。ニュー・ヨークではなく、東海岸の町シアトルに上陸した宮本大君ですが、彼に、どんな物語が待ち受けているのか、ホント、楽しみですね。追記2020・12・01「ブルージャイアント」(第1部)・(第2部)8巻・10巻の感想はここをクリックして、覗いてみてください。ボタン押してね!ボタン押してね!
2020.12.01
コメント(0)
全33件 (33件中 1-33件目)
1










