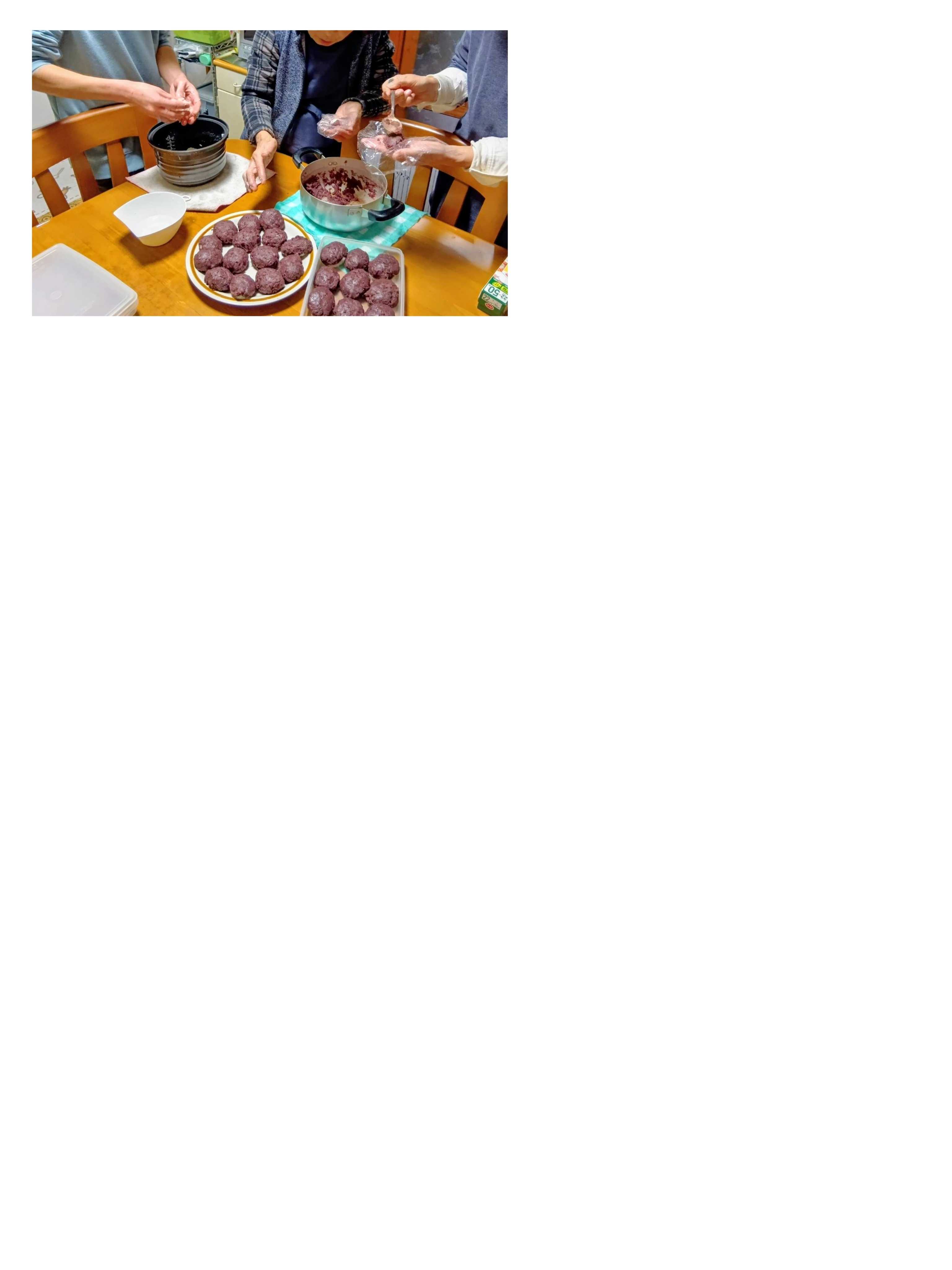2021年07月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
説教要約 1264
「十二使徒への訓戒(3)」 2021年7月25日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2019年3月28日放映「神の目と人の目」「十二使徒への訓戒(3)」 甲斐慎一郎 マタイ10章24~33節 イエスは、十二使徒への訓戒の第三回目として、彼らの「心構え」を教えられました。 イエスは、弟子たちに「もし世があなたがたを憎むなら、世はあなたがたよりもわたしを先に憎んだことを知っておきなさい」と言われました(ヨハネ15章18節)。また、彼らに、「もし人々がわたしを迫害したなら、あなたがたをも迫害します」と言われました(同15章20 これが、「弟子はその師にまさらず、しもべはその主人にまさりません」という言葉の意味です(24節)。 それでは使徒たちは、どのような心構えが必要なのでしょうか。それは、この個所に3回も記されている「恐れてはいけません」ということです(26、28、31節)。イエスは、使徒たちが恐れてはならない三つの理由を述べておられます。 一、隠されているもので、知られずに済むものはないからです(25~27節) 使徒たちが恐れることの第一は、人に正しく理解されず、中傷を受けることです。イエスは、「彼ら(人々)は家長(イエス)をベルゼブル(悪魔)と呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者(弟子たち)のことは何と呼ぶでしょう」と言われました(25節)。完全無欠な神であるイエスでさえ、悪魔と呼ばれて、中傷を受けたのですから、人に正しく理解されることを期待することはできません。 しかし「主は、やみの中に隠れた事も明るみに出し、心の中のはかりごとも明らかに」して(第一コリント4章5節)、すべてのことを正しくさばかれます(26節)。ですから使徒たちは、人に正しく理解されず、中傷を受けても、恐れてはならないのです。 二、人はからだを殺しても、たましいを殺すことはできないからです(28節) 使徒たちが恐れることの第二は、人に危害を加えられることです。人に正しく理解されず、中傷を受けるなら、最悪の結果は、これです。彼らは、むちで打たれたり、拷問にかけられたりしました。パウロは、石で打たれて殺されそうになり、ヤコブは剣で切り殺されました(使徒14章19節、12章2節)。 たとえ使徒たちが殺されたとしても、人は、彼らのたましいまで殺すことはできません。それよりも、もし使徒たちが人に危害を加えられることを恐れる余り、イエスを裏切るならば、神は、彼らの「たましいもからだも、ともにゲヘナ(地獄)で滅ぼ」されます(28節)。ですから使徒たちは、「からだを殺しても、たましいを殺せない人たちなどを恐れてはな」らないのです(28節)。 三、雀の一羽でも、神のお許しなしには地に落ちることはないからです(29~31節) 使徒たちが恐れることの第三は、神に見捨てられることです。世の人々は、使徒たちが人に正しく理解されず、中傷を受けたり、人に危害を加えられたり、果ては殉教したりするのを見るならば、彼らのことを神に見捨てられた者だと思うでしょう。 使徒たちは、決して神に見捨てられたのではありません。神は、彼らの説教やあかしの言葉、また行いや奉仕が、口先や見せかけではなく、本当で真実なものであることをあかしするため、これらの苦難が彼らの身に降りかかることをあえて許されるのです。 しかし、二羽が一アサリオン(最少単位の銅貨)で売られている、「そんな雀の一羽でも……父(神)のお許しなしには地に落ちるとはありません」(29節)。ですから「たくさんの雀よりもすぐれた者」である使徒たちは、どのような苦しみに会っても、恐れてはならないのです(31節)。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」
2021.07.25
コメント(0)
-
説教要約 1263
「十二使徒への訓戒(2)」2021年7月18日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2019年3月16日放映「三つの世界」 「十二使徒への訓戒(2)」 甲斐慎一郎 マタイ10章16~23節 イエスは、十二使徒への訓戒の第二回目として、彼らの「あるべき姿」を教えられました。使徒たちが世の人人の中に遣わされるのは、狼の中に羊が送り出されるようなもので、非常に危険なことです。ですから、彼らは、「蛇のようにさとく、鳩のようにすなおで」なければなりませんでした(16節)。 これは、世の人々の中にあっては、「賢明さ」と「純粋さ」を兼ね備えていなければならないことを教えています。なぜなら人は、賢明さだけを要求されると狡猾で不純になる傾向があり、反対に純粋さだけを求められると単純で愚かになる傾向があるからです。 しかし、なぜ使徒たちによる伝道は、狼の中に羊が送り出されるような危険なものなのでしょうか。どうして彼らは、議会(法廷)に引き渡されたり、会堂でむち打たれたり、また肉親に裏切られたり、死に渡されたりするのでしょうか(17、21節)。 キリスト教の伝道は、すばらしい福音の説教を語り、その福音によって救われたあかしをし、信じる者に与えられる聖霊によって愛の行いと奉仕をするだけでは、不十分なのでしょうか。決してそうではありません。 神は、使徒たちの語る説教やあかしの言葉、また行いや奉仕が、決して口先や見せかけではなく、真実なものであることをあかしするために、これらの苦難が彼らの身に降りかかることをあえて許されるのです。 それでは、これらの苦難の中で、彼らの持っている信仰や救いが、決して口先や見せかけではなく、本当で真実なものであることをあかしするものは、何でしょうか。イエスは、三つのことを語っておられます。 一、苦難の中における無言のふるまいによってあかしする(17、18節) 使徒たちは「キリストのゆえに投獄され」たり、法廷に引き渡されたり、会堂でむち打たれたりして、「義のために苦しむこと」があります(ピリピ一章13節、第一ペテロ3章14節)。 しかし、そのような中で使徒たちが、「悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず」、「心の中でキリストを主としてあがめ」る時、世の人々は、彼らの「神を恐れかしこむ清い生き方」と、「無言のふるまいによって、神のものとされるようになる」のです(第一ペテロ3章9、15、2、1節)。 二、苦難の中において語る言葉によってあかしする(18~20節) 使徒たちは、法廷に引き渡されたり、総督たちや王たちの前に連れて行かれたりした時、「どのように話そうか、何を話そうかと心配する」必要はありませんでした(19節)。 なぜなら、話すのは使徒たちではなく、彼らのうちにあって話される父の御霊だからです。このように「知恵と御霊によって語」る言葉は真実で力強く、だれも「それに対抗すること」はできません(使徒6章10節)。 三、家族の愛のきずなよりも強い神の愛のきずなによってあかしする(21、22節) この世において、血を分けた家族の者に理解されないばかりか、憎まれたり、恨まれたり、また迫害されたり、裏切られたりするほどつらく、悲しいことはありません。 使徒たちが家族の者に迫害されたり、裏切られたり、果ては死に渡されたりしても、神への愛のゆえに「死に至るまで忠実であ」る時(黙示録2章10節)、人々は、家族への愛よりも大切で人を動かす神への愛というものがあり、家族の愛のきずなよりも強い神の愛のきずながあることを知るようになります。 このようにして神は福音が真理であることをあかしされるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」
2021.07.18
コメント(0)
-
説教要約 1262
「十二使徒への訓戒(1)」 2021年7月11日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2019年3月7日放映「神の助けと人の助け」 「十二使徒への訓戒(1)」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、10章5~15節 イエスは、十二弟子を呼び寄せ、彼らを遣わして福音を宣べさせるために、汚れた霊どもを制する権威と訓戒を授けられました。 イエスは、十二使徒への訓戒の第一回目として、彼らの「なすべき事」を教えられました。彼らのなすべきことは、「行って、『天の御国が近づいた』と宣べ伝え……病人を直し、死人を生き返らせ……悪霊を追い出」すことです(7、8節)。 しかし、なぜイスラエルの家だけで、異邦人の道に行ってはいけないのでしょうか。どうして弟子たちを受け入れない町は、ソドムやゴモラよりも罰が重いのでしょうか。 このような疑問に対して聖書は、人に対する神のお取扱いには、次のような三つの原則があることを教えています。 一、恵みの原則――働きがなくても、ただで与えられる(8節、ローマ4章5節) イエスは、「あなたがたは、ただで受けたのだから、ただで与えなさい」と言われました(8節)。私たちに対する神のお取扱いの第一番目は、恵みの原則です。 受ける資格のない者に、価なしに与えられるものが恵みです。ですから、多く与えられていても誇ることはできず、少ししか受けていなくても、または全然なくても、不平を言うことはできません。恵みは、受ける資格のない者に与えられるものだからです。 イスラエル人が神に選ばれたのも、彼らが異邦人よりも先に様々な祝福を受けたのも、神の恵みによるのであり、彼らの行いによるのではありません(ローマ11章6節)。それでは異邦人は神に見捨てられたのでしょうか。そうではありません。イスラエルは神にそむき、「彼らの違反によって、救いが異邦人に及んだのです」(同11章11節)。 二、報いの原則――働きにふさわしい報酬が与えられる(10節、ローマ4章4節) イエスは「働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです」と言われました(10節)。私たちに対する神のお取扱いの第二番目は、報いの原則です。 受ける資格のある者に、当然の代価として与えられるものが報いです。ですから、良い働きと行いがあって、それにふさわしい人には良い報いがあり、何の働きも行いもなく、それにふさわしくない人には良い報いはありません。報いは、受ける資格のある者に与えられるものだからです。 しかし報いの原則は、一個人としては公平であっても、ほかの人との比較においては、先に恵みによって多く与えられた者のほうが、少ししか受けていない者よりも有利であり、不公平感をぬぐい去ることはできません。そのために第三番目の原則があるのです。 三、公平の原則――多く与えられた者は多く求められる(15節、ルカ12章48節) イエスは、弟子たちを受け入れない町に対して「さばきの日には、ソドムとゴモラの地でも、その町よりはまだ罰が軽いのです」と言われました(15節)。私たちに対する神のお取扱いの第三番目は、公平の原則です。 多く与えられた者と少ししか受けていない者とが、全く同じことを要求されるのは不公平です。多く与えられた者は多く、少ししか受けていない者は少し求められることこそ公平ではないでしょうか。 ですから、数々の力あるわざを行って、福音を宣べ伝えた弟子たちを受け入れない町は、このようなことが行われなかったソドムやゴモラよりも罰が重くなるのです。 私たちは、このような恵みと報いと公平という三つの原則を知る時、人に対する神のお取扱いの正しさを理解することができます。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」
2021.07.10
コメント(0)
-
説教要約 1261
「神と人との絆」 2021年7月4日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2019年2月1日放映「神のみこころと人の願い」 「神と人との絆」 甲斐慎一郎 ホセア11章4節 「わたしは、人間の綱、愛のきずなで彼らを引いた」(4節)。 「絆」という言葉には、「動物や物をつなぎとめる綱」と「切っても切れない関係」という二つの意味があります。 前者が二つのものをつないでいる「目に見える綱」であるのに対して、後者は二つのものをつないでいる「目に見えない綱」であるということができます。どちらにしても「絆」は「綱」であることがわかります。 私たち人間は、様々なものと深いつながりや絆というものがありますが、代表的なものは、次のような三つではないでしょうか。 一、自然と人との絆 人は、この世に生を受けてから、この世を去るまで、様々な自然現象の支配から一瞬たりとものがれることはできず、自然と切っても切れない関係にあります。それは、人間も自然界の一員である以上、決して気象的な変化や生物学的な作用、また物理学的な現象や化学的な反応など、自然の法則に逆らって生きていくことはできないからです。 そしてこの自然の法則は、私たちの人格や品性に関係なく働くものです。すなわち、その人の日頃の行いが良くても悪くても、高い所から落ちれば、怪我をし、熱いものに触れれば、やけどをし、有害なものを食べれば、中毒を起こすのであり、そこに例外はありません。ですから私たちが安全で健康な生活を営むためには、この自然の法則を守るほかないのです。 二、人と人との絆 しかし人間には、自然との絆だけでなく、さらに次のような切っても切れないつながりがあります。それは、家族や親族という血縁をはじめ、友人や同僚との交友の絆、知人や関係者との交際上の絆、さらに近隣や地方自治体などの地域社会の絆、そして国民としての絆に至るまで、実に複雑な人と人との絆です。 人というものは、互いに様々な絆という目に見えない綱でつながっているものです。しかもその綱は、夫婦や親子や友人の絆など、それぞれの関係にふさわしい太さ(親密度)と材質(性質)が定められています。これは、人の歩むべき道を教える倫理や道徳のことであり、正しい人間関係の基礎です。 しかし私たちがこの道を踏み外して、勝手な振る舞いをするなら、私たちにつながっている多くの人々に迷惑をかけて罪を犯すことになります。その結果、綱がもつれて身動きがとれなくなったり、正しい人間関係がこわれて、互いに憎み合う間柄や不義の関係や腐れ縁になったりするのです。 三、神と人との絆 しかし何よりも大切なのは、神と人との絆ではないでしょうか。神と人とは、どのような絆があるのでしょうか。 1.神は万物の創造者です(創世記1章1~31節)。私たちは、この神によって造られ、この神にいのちと息と万物とを与えられて、生きている者であり(使徒17章24、25節)、これほど深い絆はありません。だれが、この神のいのちを離れて生きて行くことができるでしょうか。 2.神は万事の支配者です(ユダ4節、黙示録4章8節、申命記32章39節)。自然の法則は、この神によって定められ、私たちは、その支配下にあるのであり、これほど深い絆はありません。だれが、この神の支配をのがれて生きて行くことができるでしょうか。 3.神は万人の審判者です(第二コリント5章10節、マタイ25章31~46節、黙示録20章11~15節)。私たちは、善であれ、悪であれ、すべてのことを神によってさばかれるのであり、これほど深い絆はありません。だれが、この神の審判をまぬかれて生きて行くことができるでしょうか。 神と人との絆を正しくするものは、神への信仰によって与えられる罪からの救いであり、それはまた自然と人との絆、および人と人との絆を正す秘訣なのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」
2021.07.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1