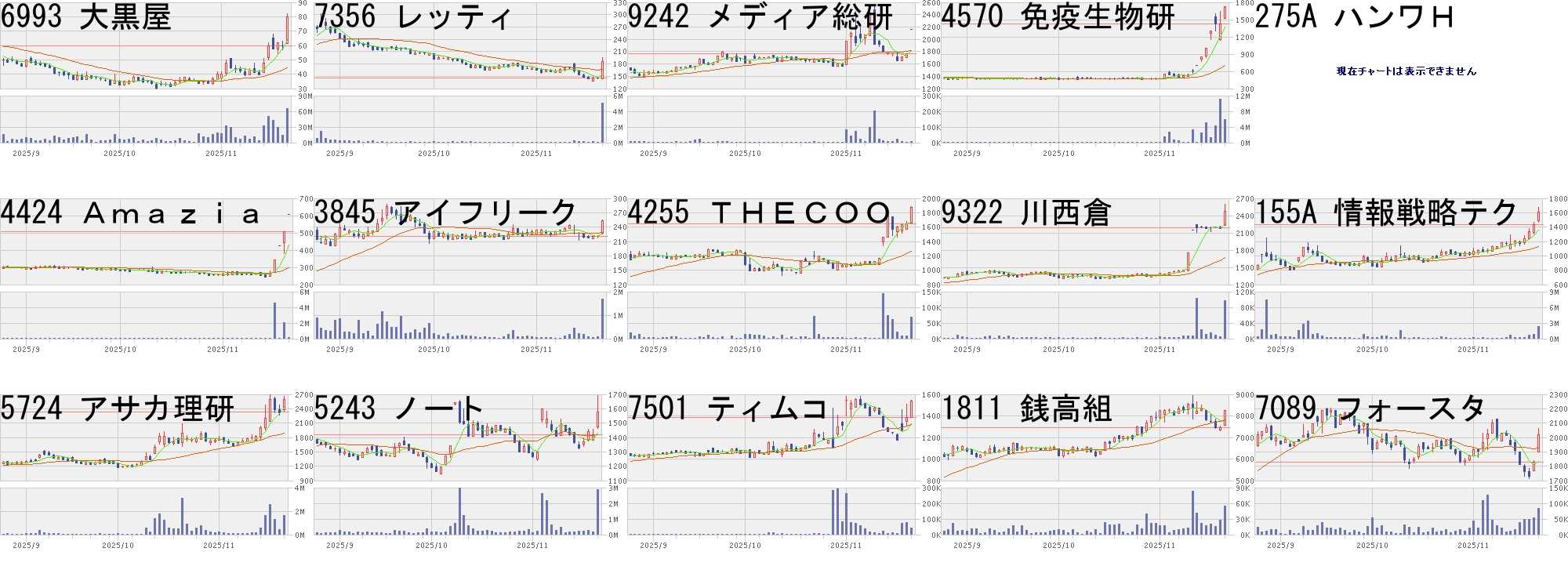2021年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
説教要約 1243
「信仰の効用(1)信仰を成長させる三要素」2021年2月28日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年5月14日放映「イエスを仰ぎ見なさい(1)」「信仰を成長させる三要素」 甲斐慎一郎 創世記、50章15節 私たちが神への信仰を持つなら、神は私たちの信仰に応えて私たちの心に働いて良い実を結ばせてくださいます。そこで信仰の効用について三回に分けて考えてみましょう。◇信仰の効用(1)――信仰を成長させる三要素◇信仰の効用(2)――信仰を形造る三要素◇信仰の効用(3)――信仰を建て上げる三要素 一、忍耐を生じさせる信仰 聖書は「信仰がためされると忍耐が生じる」と教えています(ヤコブ1章3節)。 ヨセフは、祖先から良い信仰を受け継ぎ、神を愛し、罪を憎む青年でしたが、彼の温室育ちの信仰は、嵐が吹き荒れる厳しい現実の世界で試されなければなりませんでした。 ヨセフは、兄たちに妬まれて穴に投げ込まれましたが、まず孤独に耐えなければなりませんでした。そしてエジプトに売られて奴隷になりましたが、次にしもべとして人に仕える忍耐を学ばなければなりませんでした。さらにポティファルの妻に訴えられ、無実の罪を着せられ、投獄されましたが、第三に中傷や非難を耐え忍ばなければなりませんでした。 信仰が厳しい現実の世界で生かされていくための第一の要素は忍耐です。信仰は「見えないものを確信させる」もので(ヘブル11章1節)、神の約束と保証に立って、遠くの良いことを見ることです(同11章13節)。決して霊的な近視眼ではありません。 ですから現在の一時的な孤独や苦難の中でも、つぶやかず、疑わずに、忍耐をもって黙々と神と人とに仕えていくことができます。信仰は、人を焦らせず、性急にさせずに、神のよしとされる時まで耐え忍ばせるものなのです。 二、希望を生じさせる信仰 聖書は、「信仰により……望み」を抱くと記しています(ガラテヤ5章5節)。 ヨセフは、兄たちによって穴に投げ入れられる時には理解することができずに苦しみましたが、エジプトに奴隷に売られてからは、嘆いたり、つぶやいたり、くよくよしたりせずに、喜々として働いています。また無実の罪を着せられて牢獄に入れられても、嘆いたり、つぶやいたり、くよくよしたりせずに、かえって人を慰め、励ましています。 信仰が厳しい現実の世界で生かされていくための第二の要素は希望です。「心に憂いがあれば気はふさぐ」のであり(箴言15章13節)、希望を失ったなら、気力がなくなり、自暴自棄に陥ってしまいます。 しかし信仰は私たちに希望を与えます。なぜなら信仰は、自分の周囲の様々な人間や境遇は、第二原因に過ぎず、第一原因は神であることを私たちに教えるからです。信仰者は「雀の一羽でも……父のお許しなしには地に落ちることは」ないことをよく知っています(マタイ10章29節)。信仰は、過去のいかなることにもとらわれず、くよくよせずに第一原因である神を信じて希望的観測をするのです。 三、愛を生じさせる信仰 聖書は「愛によって働く信仰」が大事であると教えています(ガラテヤ5章6節)。 ヨセフは、過去を回顧し、兄たちの嫉妬やポティファルの妻の中傷や献酌官長の忘恩など、人間の罪や失敗をも凌駕して余りある神の支配と導きを現実に見ながら、今さらのように神の愛の広さ、長さ、高さ、深さの計り知れないことを知って感激したにちがいありません。この神の愛を現実に知ったヨセフは、兄たちに対して恨みや復讐心などはみじんもなく、ただあるのは赦しと愛だけでした。 信仰が厳しい現実の世界で生かされていくための第三の要素は愛です。ヨセフは、その人の信仰の有無を問わず、周囲の人は自分の姿を写す「鏡」(箴言27章21節)、自分を磨く「砥石」(同27章17節)、神に仕えるための「相手」(マタイ25章40、45節)であることを知ったのでしょう。 しかしこれは、自尊心が強く、体面を重んじ、誇りの高い人には受け入れがたいものです。ただヨセフのように、様々な逆境や苦難を通らせられて、謙遜と自己否定を学んだ人のみ愛と感謝をもって受け入れることができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」
2021.02.27
コメント(0)
-
説教要約 1242
「御言葉への応答(3)御言葉を実行する」2021年2月21日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年5月6日放映「三つのさばき」 「御言葉への応答(3)御言葉を実行する」 甲斐慎一郎 ヤコブの手紙、1章19~25節 ヤコブは、信仰と行為とは切っても切れない不可分の関係にあり、真の信仰は、必ず行為が伴うことを私たちに教えています。 ヤコブの周囲には、律法学者やパリサイ人がいましたが、主は、「彼らは言うことは言うが、実行しないからです」(マタイ23章3節)と言われました。ヤコブは、口先だけの、行いの伴わない、浅薄な信仰をいやというほど見ていたことでしょう。 主は、山上の説教において「わたしに向かって『主よ、主よ』という者がみな天の御国に入るのではなく、天におられるわたしの父のみこころを行う者が入るのです」(マタイ7章21節)と説教されました。ヤコブは、小さい頃からそのようなことを教えられたにちがいありません。 この手紙を章毎に五つに分け、行いに表される真の信仰について学んでみましょう。 1.一章、境遇または環境の問題――御言葉を聞き、素直に受け入れることに表される信仰 この章の前半には、試練や誘惑、また貧しい境遇や富んでいる境遇について記され、後半には、御言葉を聞くことと、素直に受け入れること、そしてその結果、罪から救われて新しく生まれることと御言葉を実行することについて記されています(22、25節)。 真の信仰は、まず御言葉を聞いて、素直に受け入れ、罪から救われて新しく生まれることに表れます。その結果、すべての良い贈り物は神から下り、悪の誘惑は、自分の欲に引かれるからであることを知って、私たちは、どのような境遇や環境の中でも、すべてのことを働かせて益としてくださる神によって喜ぶことができるようになるのです。 2.二章、対人関係または隣人愛の問題――神の律法を守ることに表される信仰 この章の前半には、人をえこひいきすることについて記され(1、9節)、後半には、隣人を自分と同じように愛するという最高の律法について記されています(8、16節)。 次に真の信仰は、神の律法を守ることに表れます。対人関係の問題は、人に対して偏見を抱き、人をえこひいきして、隣人への愛がないことが、その原因だからです。 3.三章、言葉または舌禍の問題――神からの知恵を持つことに表される信仰 この章の前半には、舌の禍について記され、後半には、神からの知恵について記されています。主イエスは、「心に満ちていることを口が話すのです」(マタイ12章34節)と言われましたが、言葉は私たちの心の表現です。私たちは、舌がどんな禍を引き起こすかを知りつつも、黙っていることは許されず、神と隣人の前に正しく語ることが求められているのです(9、10節)。 真の信仰は、第三に神からの知恵を持つことに表れます。私たちは、心に神からの知恵を与えられることによってのみ、舌を制御して正しく語ることができるからです。 4.四章、世俗または自己愛の問題――神を恐れて、へりくだることに表される信仰 この章の前半には、神を無視し、神に敵対している世について記され、後半には、神を恐れて、へりくだることが記されています。神を無視し、神に敵対している世を愛することは、とりもなおさず、神を恐れず、自分で何でもできるかのように高ぶっていることです(4、15、16節)。 真の信仰は、第四に神を恐れて、へりくだることに表れます。このようにする時にのみ、私たちは、汚れた世俗を離れて、聖い生活を送ることができるからです。 5.五章、苦難または迫害の問題――忍耐と不屈の祈りに表される信仰 この章の前半には、苦難や迫害について記され、後半には、忍耐と不屈の祈りについて記されています。この世の中は、不可解な出来事や矛盾に満ち、主が来られて、すべてを正しくさばかれるまで、完全な解決はないでしょう(8、16節)。 真の信仰は、最後に忍耐と不屈の祈りに表れます。なぜなら最後まで耐え忍ぶ者のみ、救われるからです(マタイ24章13節)。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」
2021.02.20
コメント(0)
-
説教要約 1241
「御言葉への応答(2)御言葉を信じる」2021年2月14日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年4月1日放映「三つの現実」 「御言葉への応答(2)御言葉を信じる」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、4章1~13節 ヘブル人への手紙の著者は、荒野を旅したイスラエルの民および新約のキリスト者を問わず、神の言葉を聞く時に大切なことは信仰であることを次のように述べています。 「福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いたみことばも、彼らには益になりませんでした。みことばが、それを聞いた人たちに、信仰によって、結びつけられなかったからです」(2節)。 それで「信じる」ということについて、この箇所から三つのことを学んでみましょう。 一、信仰の時――今日 このヘブル人への手紙の3章と4章には、「きょう」という言葉が5回も記されていますが(3章7、13、15、4章7節に二回)、これは、どのような意味でしょうか。聖書を読んだり、説教を聞いたりしたならば、何が何でも、すぐに信じなければならないということでしょうか。そうではありません。これは、信仰というものは常に現在のものでなければならないことを私たちに教えています。 神は時空を超越された方ですから、「神にとっては過去や未来というものはなく、すべての事柄は等しく現在です」(ジョン・ウェスレー)。また人間の場合も、過去のことは、いまさらどうすることもできず、未来のことは不確かですから、確実に自分の時間として用いることができるのは、現在のみです。 神は、聖霊を通して、その古い御言葉を私たちにの心に新しく語りかけられる時が必ずありますが、その時こそ信じる時です。そしてその信仰は、常に新鮮に「きょう」という現在的なものでなければならないのです。 二、信仰の根拠――神の約束 この手紙の6章には、信仰の根拠について詳しく述べられています。6章12節から17節の間に「約束」という言葉が4回も記されています(6章12、13、15、17節)。 私たちが「信仰を持つ」とか「「信じる」という時、その信仰は何を拠り所としているでしょうか。神の存在でしょうか。神の愛とか真実さという神のご性質でしょうか。または神の言葉でしょうか。もちろん私たちは、神の存在を信じ、すばらしい神のご性質を信じ、また聖書を神の言葉であると信じなければならないことは、言うまでもありません。 しかしこれらのことを前提にしながらも、もっと中心的で大切な信仰の根拠があります。それは私たちに対する「神の約束」です。旧約聖書は、神が人と結ばれた「古い契約」であり、新約聖書は、神が人と結ばれた「新しい契約」ですが、それは同時に私たちに対する「神の約束」でもあるのです。 三、信仰の結果――安息 ヘブル人への手紙の3章と4章に、もう一つ多く出て来る言葉があります。それは、11回も記されている「安息」です(3章11、18、19節、4章1、3、5、6、8、10、11節)。 「彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであった」(3章19節)とか「信じた私たちは安息に入るのです」(4章3節)という言葉は、信じた結果は安息であることを私たちに明白に教えています。私たちは、自分がほんとうに信じたのか、信じなかったのかということは、自分の心に安息があるかどうかですぐに分かります。この安息こそ、いわゆる感動して信じる「感情的な信仰」を「真の信仰」であると錯覚している誤りから私たちを救うものです。 人々がイエスに「私たちは、神のわざを行うために、何をすべきでしょうか」と聞いた時、イエスは、「あなたがたが、神が遣わした者を信じること、それが神のわざです」と答えられました(ヨハネ6章28、29節)。 私たちは、自分のわざを終えて(10節)、神とその約束を信じるなら、この安息に入ることができます。そしてこの安息に入った者のみ、神の約束を忍耐をもって待つことができるだけでなく、その約束のものを得ることができるのです(ヘブル10章35、36節)。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」
2021.02.13
コメント(0)
-
説教要約 1240
「御言葉への応答(1)御言葉を聞く」 2021年2月7日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年3月17日放映「苦難の意味するもの(2)」 「御言葉への応答(1)御言葉を聞く」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、2章1~4節 ヤコブは、神の言葉について、「聞く」こと、「信じる」こと、「実行する」ことについて述べていますが(1章22、21節)、これこそ御言葉に対する三つの応答です。▽御言葉への応答(1)――御言葉を聞く▽御言葉への応答(2)――御言葉を信じる▽御言葉への応答(3)――御言葉を実行する 言葉を覚えるために最も必要なことは、聞くことです。人格を持ち、言葉を語る人間にとって、聞くということほど大切なことはありません。パウロが「信仰は聞くことから始まり」と述べ(ローマ10章17節)、ヤコブが「聞くには早く……しなさい」(ヤコブ1章19節)と勧めているのも、もっともなことではないでしょうか。 このヘブル人への手紙の2章から4章までの間に「聞く」という言葉が8回も記されています(2章1、3節、3章7、15、16節、4章2、7節)。 それで「聞く」ということについて、聖書の中から三つのことを学んでみましょう。 一、私たちは、なぜ聞かなければならないのでしょうか。 古今を通じて、また洋の東西を問わず、政治の世界であれ、経済の世界であれ、またどのような世界であれ、人民の声は何か、世論はどうか、世界の動向はどうなっているのか、ということに耳を傾けず、また様々な情報を適確にとらえずして、大成したり、成功したりした人はひとりもいないでしょう。 現代は情報化時代であり、人々は、この世に取り残されず、賢く生き抜くために適確な情報を得ようと汲々となっています。 しかしここに世のどんな情報よりも大切な情報があります。それは、この天地万物を造られ、この世界を支配しておられる神の声であり、神の言葉です。世の情報は私たちの地上における生活を左右します。しかしこの神よりの天の情報は、私たちの永遠の運命を決定するのです。 「神は……語られました」(ヘブル1章1、2節)。「ですから、私たちは聞いたことを、ますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません」(1節)。 二、聞くことに密接に関係のあることは、何でしょうか。 聖書は、聞くということに密接な関係にあることを5つ教えています。 1「イエスの話を聞こうとして」(ルカ15章1節)。 聞くということに密接に関係のある第一のことは、願うことであり、求めることです。 2「父から聞いて学んだ者は」(ヨハネ6章45節)。 聞くということに密接に関係のある第二のことは、知ることであり、学ぶことです。 3「羊はその声を聞き分けます」(ヨハネ10章3節)。 聞くということに密接に関係のある第三のことは、判別し、判断することです。 4「聞いたことを……しっかり心に留め」(ヘブル2章1節)。 聞くということに密接に関係のある第四のことは、信じて心に留めることです。 5「羊は、彼の声を知っているので、彼について行きます」(ヨハネ10章4節)。 聞くということに密接に関係のある第五のことは、従うことです。 三、聞くということは、私たちにとって何を意味するのでしょうか。 私たちにとって聞くか聞かないかということは、主が「聞く耳のある者は聞きなさい」(マルコ4章9、23節)と言われたように、私たちの心の問題です。 私たちは、何を聞こうとしているか、何を聞いているかによって、私たちの実質が計られ、また私たちが神の御声を聞こうとしているかどうかによって、私たちの心が神の前にどうであるかが計られます。私たちが信仰者として、また一人の人間として成長していくかどうかは、神の御声と人の声を正しく聞くか、聞かないかにかかっているのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」
2021.02.06
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1