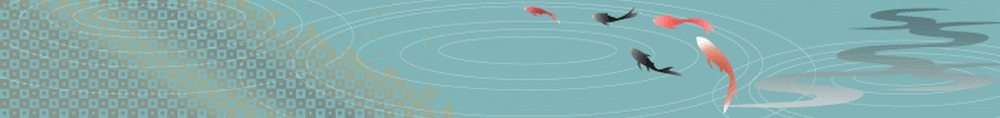2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年11月の記事
全75件 (75件中 1-50件目)
-
久しぶりに訪れる!!
今日は、2年ぶりくらいになりますが、鎌倉に行ってきました。ちょっと所要があったのですが、そこは奄太郎、寒さを気にしながら早めに切り上げましたが史跡を少し巡ってきました。 どこも何度か訪れているんですが、何度行っても史跡見学は楽しいものです。幾つか写真も撮ってきましたので、近いうちご報告したいと思っております。
2007年11月30日
コメント(0)
-
失速する親会社!!(ヤクルト球団史26)
国鉄スワローズは先述しましたように日本国有鉄道が間接的ながら親会社として運営していました。その国鉄の経営に昭和30年代後半にカゲリが見え始めたのです。 当時からモータリゼーションが少しずつ発達して輸送手段が変わってきたこと、地方の不採算な「赤字ローカル線」の存在、そして開設時よりの問題であった職員数が抜本的に多いことなどが原因です。 国鉄はそんな中、例の新幹線開通を目指し莫大な経費をつぎ込みはじめます。単独収支が赤字に転落するのは時間の問題でした。 この状況はもちろん国鉄スワローズにも飛び火します。当時の国鉄職員は「球団運営費」を給与から天引きされていましたが、職員達からはそれに不満の声を発する者もおりました。 昭和37年、国鉄はついにスワローズの経営について産経新聞・フジテレビジョンというフジサンケイグループと提携して援助を受けることになります。「国鉄スワローズ」が無くなるのも時間の問題となってしまいました。
2007年11月30日
コメント(0)
-
栄光の陰に忍び寄る・・・(ヤクルト球団史25)
国鉄スワローズのカネヤンこと金田正一は順調に勝ち星を積み上げていきました。ただ、砂押監督も浜崎監督も一年だけの指揮で更迭してしまい、首脳部は相変わらず腰が座らないという弱点がありました。 カネヤンは入団年以後、20勝以上で推移し続け、昭和30年代後半には30勝にまで達した年もありました。今の時代には考えられないことです。野球自体が当時と違っいるたとはいえ、この木記録を抜くのは非常に難しいのではないでしょうか。 私の会社の昭和20年代生まれの上司に聞いた話ですが、昭和30年代の子供の頃、川崎球場に大洋対国鉄の試合を見に行ったそうです。その時、カネヤンは試合前の練習で、ピッチャーマウンドからでなく、セカンドからキャッチャーに向かって投球練習をしたいたそうです。子供心に驚いたといっていました。 こんなカネヤンと国鉄スワローズでしたが、時代の流れに飲み込まれるように波乱の時代を迎えることとなります。 つづく
2007年11月30日
コメント(0)
-
ご意見番、現る!!(ヤクルト球団史24)
今の球界では「ご意見番」として前述した大沢親分や張本さんが有名ですが、いつの時代にもこういう人はいるもので、この浜崎監督も「球界の彦左(大久保彦左衛門)」といわれた人でした。 砂押監督時、Aクラス入りは果たしたものの、立教や日立という出身で派閥が出来てしまい、カネヤンの非協力もあって砂押監督を更迭したのち、この浜崎監督が就任しました。 浜崎監督は特異な経歴の持ち主で、慶応義塾時代に野球部の存続に尽力したり、満州国に行き(満州国の満鉄野球部はとても強かった)、満州映画で働いたり、戦後プロ野球が創設されると阪急などで活躍、なんと45歳でプレイングマネージャーになってしまったり、48歳で投手として登板したりと今の時代には考えられないことをしていました。また、背がとても小さく150センチちょっとしかなかったといわれています。 後、浜崎真二は「辛口」と評判の解説者をつとめていたのですが、国鉄の監督に招請され球団運営に乗り出しました。 早速行ったのは「天皇カネヤン」を認めないということでした。あくまで近代野球を標榜していましたので、今までの藤田、宇野、砂押監督と違い、カネヤンのご機嫌をとることは一切せず「チームは全てのもの」との持論を譲りませんでした。当時、西鉄ライオンズから豊田泰光を獲得し、「国鉄の職員チーム」から「本格的プロ野球チーム」への転換を図った点では近代スワローズの礎を築いた監督でした。 この頃からスワローズは少しずつ変わり始めます。 つづく
2007年11月30日
コメント(0)
-
はじめてのAクラス!!(ヤクルト球団史23)
ヤクルトは初代西垣監督の後、藤田監督、宇野監督と続きましたが、その後監督に就任したのがコーチだった砂押監督です。 砂押監督というと野球に詳しい方はプロ野球の監督というより「立教大学野球部の監督」のイメージが強いと思いますが国鉄スワローズがプロに招請したのです。 砂押監督は立教大時代「スパルタ」で有名でしてバットで選手の頭を叩くなど当然のように行われていました。当時の模様について監督のもとで野球をしていた大沢親分こと大沢啓二氏は著書で以下のような内容をいっています。 当時の野球部はまさに監獄だった。えらい厳しかった。大学3年のある時、一年生たちが自分の部屋にやってきた、その中には長嶋茂雄、杉浦忠といった後のプロ野球に多大な貢献をする者たちがいた。彼らは「砂押監督は厳しすぎてやっていけません。砂押監督に辞めてもらうか、そうでなければ自分たちが退部する」ので一緒に動いて欲しいというのです。大人しく卒業したかった(らしい)親分も同意、結局砂押排斥運動に発展、大学の総長まで出てきて鎮めるといった混乱ぶりでした。 後に、砂押監督は日立で監督をしていたのですが、一転国鉄スワローズ監督になり、飯田(のちスワローズ監督)、徳武(のちロッテ、中日監督代行)らとカネヤン投手陣の活躍で3位になり、はじめてAクラス入りとなりました。 ヤクルトファンで有名な三宅祐司さんが父親が国鉄職員だった関係でスワローズファンになったというのはこの時期からだそうです。 上の写真はスター長島茂雄が読売の監督になったとき談笑している砂押元監督。かつてはいがみあった関係でもお互い「野球が好きで強くなりたい」思いは一緒。後に砂押元監督は排斥運動をした立教大野球部OBが主催した「砂押監督を囲む会」に参加し楽しそうだったと大沢親分は述懐しています。 つづく
2007年11月29日
コメント(0)
-
天皇の出現!(ヤクルト球団史22)
投手金田は入団時こそ負け越したものの、次の年から勝ち越し続けます。しかも20勝ペースで投げるという今の時代では考えられません。 当時はまだスピード計測器が無い時代ですから、はっきりしたことはわかりませんが、当時打席に立った選手OBは「ほとんど150キロ後半、ときには160キロも出ていたと思う」と口をそろえます。今のプロ野球の投手の条件が「ストレートで140キロ」ですからえらい速さだったことがわかります。 また、カネヤンはこの投手の他に、投げれる変化球は大きな落ちるカーブとスライダーみたいな小さなカーブだけしかありませんでした。どれだけストレートの威力がすごかったかわかります。 こんな無敵のカネヤン、成績は国鉄スワローズをしょって立ち、性格も手伝って、発言権は当時の球団上部にまでわたりました。気に入らない監督を更迭してしますという「金田天皇」の出現となります。 国鉄スワローズはいつしか「カネヤンのチーム」になっていきました。 つづく
2007年11月29日
コメント(0)
-
いいたい放題!!(ヤクルト球団史21)
話をチーム内に戻しましょう。 国鉄スワローズに創設年の途中から入団したカネヤンは、先輩選手のバッティングピッチャーからスタートしました。 カネヤンは引退後いくつかの本を書いているのですが、その中で「金田正一のいいたい放題」という、今ではプレミアがついてしまった本があるのですが、そこでそのときのことを述べています。 カネヤンが速球を投げると、先輩選手はバットに当てることすらできません。そこで「もっと遅く投げろ」と指示がでたのですが、それを聞いたカネヤンは「なんだ、プロのバッターってこんなもんか」と早速「いいたい放題」。先輩選手のにらむ姿が目に浮かびます。しかし、プロに加入したとはいえそれほど選手層が薄かったことがわかります。 初年度、チームは最下位の広島カープのひとつ上の「7位」という散々な結果で終わります。(当時は8球団リーグ制) この「いいたい放題」の少年カネヤンは、チームが低迷するなかメキメキ頭角を現していくことになります。
2007年11月28日
コメント(0)
-
武蔵野球場の面影!!(ヤクルト球団史20)
今は跡形もなき武蔵野グリーンパークですが、かすかに地図上に痕跡を残しています。 三鷹駅の北、バスでちょっと行ったところに球場跡はありました。その跡が上の写真です。一見公団住宅が立ち並んでいるようですが、ちょっと道路の形が変わってないでしょうか?よ~くみると野球場の形をしているのがわかるでしょうか。ホームベースが北西の方にあって外野が南側になります。実際はこの野球場の形をした道路のもう一回り小さな大きさで野球場はありました。 私が武蔵野グリーンパークのことを知って、始めてこの地図を見たのは中学校の時ですが、大変感動したのを覚えています。 当時は、この楕円の球場形の南側に直線道路がありますが、そこが線路になっていて球場のまん前にホームがあり、ここまで中央線が乗り入れられるようになっていました。今の西武球場みたいですね。 ここは実際歩くと結構な大きさで当時の球場の規模を想像できます。でもここに野球場があったなんて知らなければ想像できませんね。 つづく
2007年11月28日
コメント(0)
-
夢の球場、開幕!!(ヤクルト球団史19)
慢性的な野球場不足に悩まされていた各球団はさまざまな道を模索していきます。やはり後楽園球場を何球団も使うのは不都合が生じてきていました。 そこで、当時の文化人らが中心となり、三鷹にあった中島飛行機(今の富士重工)跡に野球場の建設が始まりました。これを武蔵野グリーンパークといいます。 当時としては巨大で5万人収容の上、スコアボード完備、さらには他球場の途中経過を表示する盤まであったらしく本格的なプロ仕様の球場でした。ただ、学生野球も行われていました。 国鉄スワローズは直接的にフランチャイズにしようとしたわけではありませんが、中央線からの引込み線を造って観客動員に一役買っていました。また、この球場ではじめておこなわれた試合は、国鉄対中日でした。 後、この球場はスタンドを突貫工事で造ったため欠陥が各所に出たり、グラウンドが不良だったり、武蔵野のど真ん中にあるので砂塵が舞いやすく、たった10試合ちょっとプロで使われただけで取り壊されてしまいました。 後にここには上の写真のように公団住宅が立ち並び、今ではそこに住む人も「野球場があった」などと想像もできないようになっています。 つづく
2007年11月28日
コメント(2)
-
本拠地がなかったチーム!!(ヤクルト球団史18)
当時、国鉄スワローズには「本拠地」がありませんでした。他のチームはだいたい本拠地が確立しているのですが、国鉄はなかったのです。そこで、在京球団が早くから使用していた後楽園球場を使用することになります。 したがって後の神宮移転までの本拠地は後楽園球場でした。 国鉄スワローズはあくまで、国鉄職員の応援球団であり、ファンは全国にいるので、本拠地がそもそもなく、国鉄からサンケイ、ヤクルトと球団が変わった以降は、この「本拠地問題」は球団の大きな懸案事項となりました。 これについては、後に古田監督時の「東京ヤクルト」の球団名変更やFプロジェクトでやっと本腰を入れ始めました。手のつけ方がかなり遅いんですね。 ただ、当時としても「国鉄の本拠地」として幾つか球場が選定されていました。次回はそれについて触れたいと思います。 つづく
2007年11月28日
コメント(0)
-
なんともトレード!!
ちょっとここで、野球ネタなんですが、スワローズと関係ないのを一席。 オリックスの平野が阪神濱中、吉野らとの2対2の交換トレードで阪神に行ってしまうことになりました。守備の巧さ、シェアな打撃ともに結構好きなタイプの選手だっただけにオリックスファンとしては残念です。 上の写真は今年の千葉マリンスタジアム対千葉ロッテ戦で撮ったものです。このユニフォームもみれないんですね・・・・
2007年11月27日
コメント(2)
-
奇跡の少年、現る!!(ヤクルト球団史17)
国鉄スワローズはもともと国鉄職員の野球チームを底上げしてプロ野球に加盟したので、最初のうちはどん底に弱いものでした。プロ野球が大々的に発足したばかりなので、プロ経験者がほとんどいない状態でした。 確かに球団創設の意味は「国鉄職員のレクリエーション」的なものでしたが、勝負の世界、あまりに弱すぎれた職員たちからも見放されてしまいます。そんな時、西垣監督は「名古屋の方にすごい球を投げる投手がいる」という情報を聞きつけ、獲得に乗り出しました。 その少年こそ、ご存知「金田正一」今に残る「大投手」。金田ことカネヤンは当時享栄商の学生でして、子供のころは焼け野原で育った経緯がありました。名古屋の空襲は当時最大の国宝といわれた名古屋城の大天守閣が焼失するくらいひどかったのです。十分に野球ができなかったが、木曽川に石を投げ続け肩を作ったとか、戦後、ボロキレで作ったボールで野球をしていた中から、あの強靭な肩は出来上がったと本人が言っています。 甲子園こそエースとして行けなかったのですが、その直後西垣監督自らが名古屋の自宅を訪ねスカウトしています。当時は自由競争でスカウトという職業も満足にない球団でした。 カネヤンのお父さんは土方をしていたそうですが、喜んで受け、少年カネヤンは国鉄の特急「はと」に乗り、西垣監督、父親と3人で10時間かけて東京に出てきました。 カネヤンは移動の最中、いくらでも監督が駅弁を買ってくれるので、食べきれないほど食べたと述懐しています、当時はまだ食べ物も十分食べれなかったのですね。 東京に出てきたカネヤンは人の多さにビックリ、名古屋では少し有名だった少年カネヤンも驚きの連続だったそうで、あまりの人の多さを「お祭りをしている」と勘違いしたり、喫茶店で働く女給さんがあまりに美人なのに驚いたり、「田舎モノ」を丸出しだったと本人もいっています。 球団創設の年の途中からチームに入ったカネヤンですが、後にその頭角をメキメキと現すことになります。
2007年11月27日
コメント(0)
-
この人は誰だかわかりますか?(ヤクルト球団史16)
ちょうど国鉄スワローズが発足して2年後、プロ野球は軌道にのりはじめ、今のようにシーズン前に南でキャンプを張るようになります。 上の写真は毎日オリオンズ(今の千葉ロッテ)に早稲田大学から入団した末吉という選手をキャンプ出発前に早大生が激励に集まっているシーンです。 この握手している中央の奥に半分隠れている方が王貞治を育てたという荒川博氏、その左、マフラーした背の高い青年がいますね。この人が誰だかわかる方はなかなかの野球通でしょう。あの広岡達郎氏の学生時代の姿です。 スワローズは、この荒川博が監督をした後、広岡達郎が監督に就任してやっと念願の優勝を味わうことができることになります。球団創設から29年、この写真の広岡さんが27年後に成し遂げるのです。当時は想像もできなかったでしょう。 つづく
2007年11月27日
コメント(2)
-
多くの人の思いをのせて・・・(ヤクルト球団史15)
国鉄スワローズは昭和25年、セントラルリーグに加盟し発足しました。初代監督には西垣監督が就任しました。 上の写真はスワローズ発足時の象徴的な写真です。中央の西垣監督と硬い握手をする加賀山国鉄総裁、車窓からは新生国鉄スワローズの選手たち、それを見守る国鉄職員・・・・・ 多くの人の思いがそこにはありました。怪事件の連発と犠牲者まで出した現実、国鉄をさらに発展させたい、労使の対立をこれ以上起こしたくない・・・・・ しかし、国鉄スワローズの前途は厳しいものがありました。 つづく
2007年11月27日
コメント(2)
-
つばめ疾走する!!(ヤクルト球団史14)
特急つばめ号は当時としてはとんでもなく斬新な列車でした。電車ではなく機関車が引っ張る「客車」なのですが、一等車から三等車まで全てが連結されていて、食堂車には冷房装置までありました。 日本に鉄道が走ってからまだ100年たたない前に、ここまでの列車が走っていたことには大変驚きます。当時の国鉄が「つばめ」にどれだけ誇りを持っていたかがわかります。 この列車は後にモスグリーンに車体が塗られ、昭和30年代、まだ新幹線が走る前に今の数寄屋橋の高架を走っているモスグリーンの車体は当時の、また東京の代表的な風景でした。当時、西の田舎から上京してきた人はだれもが東京の繁栄をみた場所です。 上の写真はそのつばめ号の最後尾にある一等展望車。特等席でした。 つづく
2007年11月26日
コメント(0)
-
壊れると辛いもんで・・・
家の風呂がついに破損してしまいました。今まで何十年と問題なかったのですが・・・ 一応会社勤めなので、ないとえらい困りますね。そこでこれも何十年ぶりかに銭湯へ行きました。子供の頃はそこらじゅうに銭湯があったのですが、多くが廃業してしまって数も少なくなりました。 私が行った銭湯は未だに頑張っているのですが、鉄道模型が走っていたり、焼き芋やゆで卵を売っていたり、小さなスペースにサウナ、打たせ湯などがありかなりアイデアを出している様子。やはり衰退産業でもできることってあるんですね。 値段はずいぶんと上がりましたが、銭湯もたまにはいいもんです。
2007年11月26日
コメント(0)
-
スワローズ誕生する!!(ヤクルト球団史13)
国鉄はついにプロ球団に正式に加盟をしました。昭和25年のことです。プロ球団の創設時としては一番遅い発足でした。 ただ、国鉄は純粋な「企業」ではありませんから、直接球団経営することができず、鉄道弘済会をはじめとする外郭団体がスポンサーになる形で経営にあたることになりました。 正式名称は「国鉄スワローズ」。スワローズ、すなわち「つばめ」とは当時、東海道線を走っていた「特急つばめ」からとられました。 「特急つばめ」はもともと昭和初期に運行を開始した特急で、当時一晩かかっていた東京と大阪の間を8時間ちょっとで結ぶ「超特急」でした。当時は「つばめ」ではなく「燕」。 運行時、箱根の山を越えるのができず、御殿場経由で遠回りしていたのを、丹那トンネルができてさらにスピードアップを成功させました。まさに世界に誇れる特急列車でした。 このつばめは戦争中は中断していたのですが、ちょうどこの昭和25年に復活、国鉄の誇る特急列車の愛称が球団の名称になったのです。 つづく
2007年11月26日
コメント(0)
-
外部効果あり??
ただいま、「ヤクルト球団史」として好き勝手にブログを更新させていただいていますが、アクセスいただいた方々の履歴を見て感じました。楽天ブログの方がほとんどおられないのです。外部の、おそらく法人でない個人のアドレスの方が9割以上になっています。 もともと私のブログは、楽天ブログの方のアクセスは3割程度と少ないのですが最近は異様な感じです。 よいのか悪いのかわかりませんが、最近ブログが氾濫して「質の低下」に繋がっていると感じていましたから(私がいえる立場じゃないが)、私としては楽天ブログ以外の方が来ていただくことはうれしいことと思います。
2007年11月25日
コメント(0)
-
仲良くするチームを!!(ヤクルト球団史12)
国鉄での事件はさらに続きました。三鷹事件から一ヶ月ほど後、こんどは東北に飛び火しました。 福島県の東北本線松川駅近辺のカーブに差し掛かった蒸気機関車が突然横転、写真のように大破しました。原因は線路の枕木をおさえている犬釘が何者かの手によって抜かれていることでした。この事件では機関士方が死亡しています。この事件も犯人がわからずじまいでした。 これらの死者まで出る事件の頻発は労使間の対立が原因とは断言できませんが、国鉄首脳部はそれも理由のひとつとして考えていました。それを打開するため、労働者と使用者共に「国鉄人」として応援できるプロ野球チームを発足させることが検討されはじめました。 ちょうど昭和25年にセリーグ・パリーグに分けれた2リーグにしてプロ野球を発展させる準備がされていました。プロ野球連盟はそのスポンサーを探していたのです。そこに国鉄が名乗りをあげることになります。 つづく
2007年11月25日
コメント(0)
-
混乱の怪事件!!(ヤクルト球団史11)
下山事件からたった数日しかたっていないころ、第2の国鉄の怪事件が起こります。 今でもJRの三鷹駅には車庫がありますが、そこの車庫に停車していた無人のはずの列車が夜にいきなり動き出し大脱線、車両は商店街に突っ込み民間人の死者まで出てしまいました。 当時は、今と違って、街灯などが不十分だったので、夜の見えない中何が起こったのかわからなかったようです。朝になり現れたのは上の写真のような「地獄絵図」でした。三鷹駅のホームからは心配そうに多くの人が事故現場を見つめています。車両の状況から相当のスピードで脱線したのではないでしょうか。 国鉄職員や国民の不安は頂点に達していきます。 つづく
2007年11月25日
コメント(0)
-
連続する事件!!(ヤクルト球団史10)
労働争議が激化する中発足した国鉄ですが、その国鉄の初代総裁となった人が下山貞則という人でした。下山は大きな首切りを断行すると共に国鉄自身の発展を軌道に乗せるという難事業を請け負うこととなってしまいました。 そんな中、有名な事件が起こります。国鉄総裁に就任してから一ヶ月ちょっと後の昭和24年7月、大田区の自宅を出て国鉄本社(丸の内)に通勤していた総裁が突然行方不明になります。乗っている自動車の運転手に三越まで越させて「すぐ戻る」と言い残していなくなってしまったのです。 結局夕方になって「総裁不明」の記事が新聞に踊ることになるわけですが、総裁は見つかりませんでした。 翌日、当時はまだ東京の郊外だった常磐線の北千住と綾瀬間の線路で汽車に轢かれた死体が発見され、遺留品から下山総裁であると断定されました。 このニュースは新聞などでも全国配信され、国鉄首脳や国鉄職員はもちろん、政府関係者や一般人も衝撃を受けた事件でした。「下山事件」といいます。 下手人は、当時総裁側と対立していた労働組合やそれを指導する社会、共産主義者という見方が強かったのですが、だれも証拠不十分で事件は迷宮入りとなります。自殺か他殺かもわからず未だに様々な研究や主張がされる「怪事件」でした。 写真はその現場の当時の写真、常磐線の手前が北千住、奥が綾瀬で線路をくまなく調べている係員が写されています。 つづく
2007年11月25日
コメント(0)
-
回帰するの??
YAHOOニュースより一部抜粋 原油高で灯油などの暖房費の負担が重みを増す中、湯たんぽの売れ行きが伸びている。お湯を入れるだけの省エネ性に加え、肌が乾燥しにくいという特徴もあり、特に女性の間で人気が高まっている。百貨店でも、やや高級な湯たんぽを品ぞろえに加える店が増えている。 ちょっと今日のニュースから。 かわいい女性向けの湯たんぽがたくさん考案されているんですね。最近過去の文化で利用できるものは利用していく風潮があるんではないでしょうか。湯たんぽの場合、原油高が直接的な要因ですが、見直されているんですね。「湯たんぽなんてダサい」といった時代ではないということ。 着物も見直されればいいのですが。それには小売業者の規律から正さないといけませんがね。「湯たんぽブーム」を参考にしなければならないでしょう。
2007年11月24日
コメント(0)
-
殺人列車!!(ヤクルト球団史9)
日本の鉄道は近代輸送の中では海運と並ぶ、いやそれ以上の重要度がありました。そこで官営鉄道は大正時代に更に拡大を図るため「鉄道省」という省のもとにおかれました。今のJR線は「省線」とか「省電」といわれていた所以です。 日本は国内に鉄道を張り巡らしただけでなく、植民地である南樺太、台湾、朝鮮、満州でも様々な形で鉄道を敷設しており、それが船で結ばれていました。 しかし、太平洋戦争で戦地動員が始まると現場は男性職員の数が減り、女性が代行して運営していることが多々ありました。また、戦争末の空襲で線路はおろか、車両まで思いっきり痛手を受けることになります。 戦後、日本を占領した連合軍の総司令部は日本政府が幹線鉄道を運営するのは困難と判断し、鉄道部門を切り離して「日本国有鉄道」、すなわち国鉄が発足しました。 国鉄はただでさえ鉄道運営をすることが困難な中、戦争から復員した人々の雇用を押し付けられたりして「仕事が無いのに職員が多い」状態になり何万人規模のリストラを敢行するのですが、リストラされた側も労働組合を組織して戦い、労使ともに大混乱になります。鉄道が頼りの一般人の生活まで脅かされ、上の写真のような、今の時代じゃ考えられない電車が走っている始末でした。 戦後、ただでさえ国が混乱しているのに国鉄までが大混乱している。これが後に大きな事件に発展します。
2007年11月24日
コメント(0)
-
高額チーム!!(ヤクルト球団史8)
「高額なチーム」というと今では「高い報酬の選手が多いチーム」という感じがしますが、この新橋アスレチックスは「会費」が高いチームでした。 上の写真は発足したアスレチックスの全員写真の一部、中央右から二人目が平岡です。写真をみると日本人のほかに外国人の姿もみえます。平岡の関係から鉄道関係者も入っていたようですが、平岡独立後の実業界関係の人の姿もあったようです。当時は野球はハイカラなスポーツだったので、高い会費が払えるような人しか縁のないスポーツだったんですね。 ところで、当時は諸説ありますが、今のようにストライク3つとボール4つで決まるルールでなかったようで、ボールは何球でもよかったとか20球までOKとかだったようです。今のように投打の駆け引きが行われるのでなく、あくまで「打たしてあげる球」を投げるのが投手の務め、したがってストライクがあまりに入らないとバッターから文句が出るという状態でした。 また、「新橋のドコで野球がやれたのか」と疑問を持たれる方もいるかと思いますが、当時、新橋始発の時代、今の東京駅近辺(皇居前)は空き地が多くありました。これは明治後、商業地である新橋や銀座はそのまま繁栄していきましたが、大名屋敷のあった有楽町より北は大名屋敷がなくなってしまったので空き地だらけだったのです。大正三年に開業した東京駅のレンガビルの前(今の新丸ビル前)で野球をやっている写真が残っています。 これは今のスワローズと直接関係がないのですが、国鉄史では誇らしげに取り上げていたので一応書いてみました。 ちなみに、この平岡煕は「日本野球の父」として、今でも野球体育博物館に老後の肖像が飾られています。
2007年11月24日
コメント(0)
-
新橋でスポーツクラブ??(ヤクルト球団史7)
ヤクルトスワローズの全身は「国鉄スワローズ」だったということは、国鉄が無くなって久しい今でも知られているところです。実際、国鉄スワローズは昭和25年になって発足した新球団なんです。 しかし、「国鉄百年史」という本には国鉄の全身時代からすでに野球チームがあったことを紹介しています。これについてちょっと触れておきたいと思います。 国鉄、すなわち「日本国有鉄道」という特殊法人は戦後にできたもので、戦前までは「官営鉄道」すなわち国家が鉄道運営していましたから職員は「公務員」でした。 新橋と桜木町の間に始めて鉄道ができた時は、政府の「工部省」という省が鉄道を管轄していました。その工部省に平岡煕(ひらおかひろし)という技師がいました。上の写真の人です。 平岡は明治初期、アメリカで鉄道の研究を重ねて、帰国後役人として勤めていたのですが、当時車両はすべて輸入品に頼っていたのを国内生産するために独立し車両工場を作って成功を収めた人でした。 平岡は仕事のかたわら、アメリカ時代に野球を知って大変興味を持ち、日本に野球チームを作ろうと「新橋アスレチックス」というチームを作りました。 つづく
2007年11月24日
コメント(0)
-
泣いた泣いた!!(ヤクルト球団史6)
最後の打席、見事にヒットを打って通算安打を2097本として現役生活を終えました。「古田コール」わきあがる中、人々は寒さも忘れていました。当時の状況はこんな感じでしたし写真はスコアボードに映る古田監督。 スタンドの中は仔細に見るとそれだけで済まなくなっていました。周りで若い女の子達が泣いているのです。どうみても20代くらいで古田選手としての全盛期を知らない世代なのですが、あっちこっちで泣いている人がいました。 私は子供の頃からの阪急(オリックス)ファンでしたが、在阪球団のため東京に来ることはあまりありませんでした。そんな時よく観戦していたのがこのヤクルト戦で、神宮にも足繁く通うヤクルトファンだったんです。その時は女の子のファンなんてほとんどいなかった気がします。人気が無くって弱くって「ヤクルトが好き」というだけで馬鹿にされました。 今、ヤクルトは元に戻ったように、完全に「弱い」チームになりましたが、引退試合が満員になったり、おお泣きている女の子をみると、この古田という選手がどれだけ観衆の心をつかんでいたかを改めて感じます。「合併阻止の選手会長」だけじゃない、何か「モノ」を持っている気がします。ファンサービスも徹底してやってきたのでしょう。それと同時にヤクルトという球団が「変わったんだな~」としみじみ感じてしまいました。 そんなわけで改めて「ヤクルト球団の歴史」を見てみることにしようとしたわけです。 つづく
2007年11月23日
コメント(0)
-
最終打席まで魅せる!!(ヤクルト球団史5)
すでに引退試合を済ましていた古田監督でしたが、最後になってバッターボックスに立ちました。試合開始時には空いていた内野席も写真のように、この時期としてはかなり埋まってきていました。 「代打古田」が告げられると観客が一斉に立ち上がり、これが360度展開されました。広島の時と同じで、このような光景はなかなかみれないものです。いつの間にか球場全体が「古田コール」になっていました。 つづく
2007年11月23日
コメント(0)
-
今日がホントの引退日!!(ヤクルト球団史4)
奄太郎は東京に帰ってきた後の10月9日、横浜スタジアムのベイスターズ対スワローズの試合に行きました。 この試合はプロ野球の今シーズンペナントレースの最終試合であると同時に、すでに神宮球場での引退式を終わった古田監督の本当の最後の試合になりました。 当日は少し早めに球場に入って寝転がっていたのですが、古田監督は試合前、フェンスからサインを要求するファンひとりひとりにサインをしていました。 今年、すでに最下位が決定しているスワローズですが、野村監督以来のプレーイングマネージャーの最後の試合、とても貴重です。が平日ということもありお客さんは予想以上に少なめでした。 そんな中、試合は始まりました。 つづく
2007年11月23日
コメント(0)
-
ご注意ください!!
今日は日本海側では大雪になるところもあるそうです。東京も雪こそ降りませんが木枯らしが吹いています。 雪にみまわれる地域の方には大変な季節になりました。私が今年訪れた青森も大変なんでしょう。該当地域の方、気候にはご注意、かつご自愛ください。
2007年11月22日
コメント(0)
-
一生見れないだろう瞬間!!(ヤクルト球団史3)
カープの列が出来上がると、ブラウン監督が花束を持って古田監督を表に呼び手渡しました。球場からは拍手の嵐でした。 その後、古田監督は用意していたサインボールを敵地であるにもかかわらずカープファンに投げ込み始めたのです。カープファンからも花束が送られていました。球場一周すると今度は広島なのに「東京温度」が鳴り響いていました。私はこんな光景みるのははじめてですし、おそらく今後もないと思います。 ただの「贔屓チーム」を通り越して、やはりかつての「球界再編問題」に尽力した古田監督への感謝の気持ちがあるんでしょう。 このシーンは元広島監督である三村さんの解説付き動画にありましたので、こちらをご覧ください。
2007年11月22日
コメント(0)
-
信じられない出来事(ヤクルト球団史2)
先にお伝えしましたように、奄太郎は9月27日、広島市民球場で広島カープとヤクルトスワローズの対戦をみていました。 この試合は完全な消化試合で観客もまばらだったのですが、すでに引退、監督退任を表明しているヤクルトの古田監督には最後の広島での試合でした。 試合終盤に自らバッターボックスに立った監督は広島黒田から今期初ヒット、更にもう1本ヒットを放ち、カープファンからも大歓声を受けていました。 試合は広島に大きく負けたヤクルトでしたが、試合後なにやらカープの選手がぞろぞろベンチから出てきました。左から5番目くらいでアンダーシャツの袖が赤いのが、当日試合に出ていない前田です。「何だ?」と思ってみていると考えられないことが起こりました。 続く
2007年11月22日
コメント(0)
-
東京ヤクルトスワローズの歴史1
今日から「東京ヤクルトスワローズ」と題してあるプロ野球球団の歴史にせまってみたいと思います。上はマスコットの「つば九郎」。反転してしまっていますが気にしないでください。 途中時事問題や食べ物ネタなんかを勝手に取り上げてしまうと思いますので、通し番号を打っていきたいと思っています。 野球に興味がある方も、全くないという方も、少しでも興味を持っていただけるよう書かせていただきたいと思っていますので、どうかお読みいただきますよう、よろしくお願いいたします。
2007年11月22日
コメント(0)
-
みずみずしい・・・・・・
秋葉原に行くと俗に言う「アキバ系」と呼ばれる人々が集う場所が駅の北西にあるんですが、その通りを過ぎたところに松月庵というお蕎麦屋さんがあります。 ここは、かなり本格的なそばを食べさせてくれるお店で、様々なそばをいただいていますが、「みずみずしさ」にかけては特筆すべきものがあります。とにかく柔らかくみずみずしい。かといってコシもあるというそばで、やはりムショウに食べたくなります。 先日デジカメの修理完了のため秋葉原を訪れた時いただきました。近くにお越しの際には皆様もぜひどうぞ。
2007年11月21日
コメント(0)
-
増税に賛成します???
<政府税調>減税政策から一転、増税メニュー並ぶ 3年ぶりに消費増税を打ち出した20日の政府税制調査会の08年度答申は、成長重視で法人減税など減税政策が目立った安倍政権下の07年度答申から一転し、配偶者控除や扶養控除の廃止などサラリーマンに負担が及ぶ増税メニューが並ぶ内容となった。所得格差の拡大や増税批判をかわすためか、答申は、減税効果が及ばない低所得層に給付を行う制度の導入を提言したほか、「企業優遇」の批判も根強い法人税減税についても慎重なトーンに変わった。昨年との様変わりぶりが目立つが、いずれの提言も、与党税調との調整がつかなければ実現は不可能で、年末の議論が注目される。 (中略) 格差是正の観点からは、これまで引き下げられてきた所得税の最高税率(40%)についても、「所得再分配の観点から見直すべきだとの意見もあり、さらに検討する必要がある」とした。 その一方で、所得税については、配偶者控除や扶養控除の見直し(縮小)を明記した。見直しで得た財源を子育て支援に充てるなどと説明しているが、サラリーマンの負担増は免れそうにない。 上記 YAHOOニュースより抜粋 全体的な「絵」がわからないのでなんともいえませんし、このほかの形で増税があるなら話は別かもしれませんが、上記の「配偶者控除」や「扶養家族」の見直しという点については「賛成」します。 これらは例の「103万の壁」というもんですが、圧倒的に共働きの「ママ」に対して設定されているものです。これらは「あくまで女性は弱いもので男性より収入が低いだろう」という考えのもと作られたもの。実際これを狙って職探ししている主婦も多いと思います。 しかし、今の時代は女性の方が男性より仕事ができる、収入も高いだろうということが当たり前になってきました。税調もそこを指摘しているようです。やはり女性の社会進出を促進するためにも縮小すべきではと思います。 ただし、これには育児、介護休暇など現在労働法でうたいながら全くできていない分野をもっと明確にしてから設定するべきです。 労働基準法では「小学生以下の子供を育てる親に対して配慮すること」とか「乳児を育てる母親には授乳などの時間として1日に30分以上の休憩を2回以上あげなくてはならない」といったことが定められています。当然身重の女性を解雇することは「禁止」です。 これら育児全体の保護がされた段階で、育児に従事している女性は控除があり、逆に子供のいない女性には控除縮小をし、その分を育児従事者にまわすというのがいいのではないでしょうか? 好き勝手に書いてしまいましたがそんなことを思いました。
2007年11月21日
コメント(0)
-
アリになった気分??
松代大本営跡から出てくると、そこには案内板があります。見てみると山の中を綺麗に設計した上で掘っていたころがわかります。 ちなみにこの跡は一箇所だけでなく三箇所ほど近くに作られていましたから相当大規模なものだったようです。 この大本営跡を知る人は以外に少ないことでしょう。しかし、戦争の傷跡のように掘られた地下壕はその愚かさを今に伝えています。 地上に出ると水のきれいな長野らしい小川がのどかに流れています。今の世は平和なんだな~とつくづく感じました。
2007年11月20日
コメント(0)
-
「業務提携」という怖い現象!!
ここ数年企業の「合併」はもちろんですが、「業務提携」や「資本提携」などが新聞紙上をにぎわしています。持株会社も平気で現れるようになりました。 これらのことは、企業の「生き残り」をかけたものであると解されますが、その割には大規模な企業の名前が目立ちませんか?小売業でいえば三越と伊勢丹みたいなものです。 このブログでも好き勝手に持論を展開している私ですが、何度もいうようにこれは企業の「寡占化」の始まりです。戦後、日本の大手企業や財閥を解体させるのにGHQが必死こいていたにもかかわらず結局「政治的理由で」解体が不十分になりました。 ただ一定の成果は出て戦後経済に大きな影響を与えていたのですが、それが元に戻ろうとしています。「生き残り」に成功する企業が出たら失敗する企業も出ます。 そこで失業率上昇や就業していても賃金の大幅な格差がではじめるでしょう。もし経済的下部におかれた人間が憲法の保障する「文化的な最低限度の生活」までできなくなったとき、今の経済は崩壊するでしょう。なぜならそれらの人は他人のものを奪い取ってでも生活しようとするでしょから。
2007年11月20日
コメント(0)
-
悲しみの洞穴!!
松代大本営の中を入って15分ほど歩くと「測点跡」という看板がぶら下がっていて、更に奥の場所へは金網があり「立入禁止」になっています。 この洞穴は計画的に山の中を縦横無尽に掘られていて、ここがその計画の測量中心点であったといわれています。 この「測点跡」の周りには千羽鶴がたくさんぶら下げられています。「ここに鶴などを置かないで」と書いてあるにもかかわらずものすごい数です。 この洞穴を作成するにはたくさんの朝鮮人が無理やり駆り出されたといわれています。一般日本人でも知らなかった訳ですから、たくさんの犠牲者が出たことが想像されますが、全くの極秘でいまだにわかっていません。 そんな苦しい思いをした労働者や知られることなく犠牲になった労働者たちを慰霊する千羽鶴なんですね。
2007年11月20日
コメント(0)
-
おくやみいたします。
今日、会社から帰ると一枚のハガキが届いていました。みると私の大学時代のバイト先の友人からで、「喪中なので、年始の挨拶をしない」旨が書かれていました。どなたか身内の方が亡くなったのかとよくみてみると絶句しました。 亡くなったのは彼の愛娘(7歳)でした。 私が彼と始めてあったのは今から14ほど前、アルバイト先の先輩でした。年齢も私より2つ年上なのですが、私が入社し「よろしくお願いします」というと「こちらこそよろしくお願いします」と低姿勢で決して偉ぶらない人で、仕事も親切に教えてくれたことを覚えています。 後に年齢を超えて友人になってくれ、あまり興味がないのに野球観戦を一緒にしてくれたり、食事をともにしたりしました。 彼は後に福祉施設に就職、根がやさしいこともあってがんばって働いていました。お互い仕事をしてからは、さすがに年賀状のみの挨拶になっていましたが、娘の七五三の写真をもらったりしていました。彼の心中は察しようとしても私にはできません。 彼がこのブログを読んでいるかわかりませんが、人の死に「頑張って」とか「負けないで」という、うわっつらの言葉はかけたくないので、今度会ったとき、ゆっくり飲みながらいろいろなことを話しましょう。
2007年11月19日
コメント(0)
-
吹いちゃってるよ・・・・・・
ただいま昼前ですが、吹いちゃってますね、思いっきり木枯らしが・・・・ 仕事なんですがこりゃたまらんですね。というよりこれでたまらないなら冬越せないですが・・・・
2007年11月19日
コメント(0)
-
洞窟は奥へ続く・・・・
松代大本営の跡に入るとまず驚いたことが「涼しい」ことです。訪れたのは夏だったので、長野も汗が出る温度でしたが、中に入るといきなり10度以上も気温が低いんですね。 奥へ奥へと洞穴は続いていて奥が見えません。実際はヘルメット装着で入るのですが、私は入り口の案内係の許可をもらってヘルメットなしで入っていました。 しばらく行くと「作戦本部」の跡など部屋にあたるものがかろうじて残っています。5分も歩いていると地上にいたときの汗が完全に引き気持ちよく歩けました。 地面はところどころぬかるんでいるので気をつけて歩かないといけません。気がついたら奥の見えない洞穴に自分ひとりだけになっていました。 この奥はどうなっているのか?好奇心からかすかな明かりを頼りにして真っ暗な中を更に歩いていきました。
2007年11月19日
コメント(0)
-
ダイエット成功の思い出!!
私は、最近の食事で「肉食」を控えています。控えているといっても「止めている」わけでなく3食のうち1食のみ肉食をするという感じですかね。 以前、まったく肉を食べない生活をしてみたところ具合が悪くなり、医者にしっかり食べるよういわれたので、あくまで「量を減らした」ということです。タンパク質が摂れないと大変なことになってしまいますからね。 というわけで一週間ほど経過したのですが、早速体重が少し減少していました。 思い起こせば社会人になって一年目、暴飲暴食で体重が10キロ増えたことがありました。そこで一念発起し「昼はそばだけ」という生活を半年続けたら8キロ体重が減りました。 今回の昼食も近所のそば屋の「そば」。しかも「もりそば」。これに卵の白身だけいれて食べます。はじめのうちはものたりないですが、慣れてくるとこれで十分になってきます。 どこまで続くかわかりませんが、ちょっとそんなことにチャレンジしています。
2007年11月18日
コメント(1)
-
こんな日があってもいいね・・・・・
今日は一日中寝てしまいました。というより起きたのが今(15時)。寝たのが昨日の午後9時なので一体何時間寝ているんだ??? 寒くなってきて、だんだんこのような状態に陥る方が多いのではないでしょうか? 最近、高齢化でヒートショックなるものが流行りだしました。そうならないためにも、寒き季節はみんなで冬眠しましょう。
2007年11月18日
コメント(0)
-
洞窟に戦争の跡が!!
ここは、長野県の真ん中へんにある「松代」という城下町です。かつては上杉謙信と武田信玄の川中島の戦いがあり、江戸時代は真田家の城下町として繁栄した町で、今でのその面影をみることが出来ます。さながら「小京都」のようです。 そんな松代にはもうい一つの歴史があります。 かつて、太平洋戦争中、日本は全国的な爆撃を受け滅亡寸前の状態でした。当然東京も大空襲がありその影響を受けたのですが、東京は海に面しているため空からの防御に弱かったのですね。 そこで、日本列島の一番太くなっていて海から遠いこの松代に「大本営」という作戦本部を東京から移そうとしました。日本の総責任者は天皇ですから、天皇もここに移して最後の「アガキ」をしようとしました。 なんせ最後の砦ですから、すぐに壊れるものではいけません。そこで、松代にある「象山」という山の麓から山の中に洞窟を掘っていき、そこに本部や皇居、政治機能を移そうというわけです。 その「松代大本営」は結局使われることがなく終戦になり、荒廃していましたが、今では一部整備され中に入ることができます。 ではその中がどうなっているのか、毎日少しづつ見ていきたいと思います。
2007年11月18日
コメント(0)
-
「不如帰」を読む!!
「徳富蘆花」とは文学の好きな人なら誰でも知っているけれど、芥川龍之介とか漱石とか鴎外と比べるとポピュラーではない気がします。 明治時代を代表する作家であるのですが、文庫でもあまりたくさん出版されている所をみないですね。この間、神保町の古本屋にあるのは見たんですが・・・・ そんな蘆花の「不如帰(ホトトギス)を読んでみました。再読になりますが、何度読んでもいいですね。個人的にはあまり好きでない典型的な「純愛」文学なんですが、恋人同士がスンデのところ(山科駅と京都駅)ですれ違ってしまうところなんか、今でも東海道線で通ると思い出します。 最近、昭和初期の病床の蘆花の写真を見たのですが、蘆花がもうちょっと生きていたら、その後の世相をどう見たのかな?と思いながら見入ってしまいました。
2007年11月17日
コメント(0)
-
これからが本番!!
今日はえらい寒いですね。ついに「冬」が来たという感じです。 土日たまたま休みをいただいていたのでどこか行こうかな・・と思っていたのですが、さすがに止めました。来週の仕事が無理してストップしてしまうことを懸念してです。 今年もいろいろな所に行かせていただきましたが、さすがにこれで「出かけ納め」になるようです。
2007年11月17日
コメント(0)
-
牛飯は米沢だけじゃない!!
駅弁ネタを続けてもう一度。 「牛飯」ってありますよね。牛丼の駅弁版みたいなもので、ご飯の上にただ牛肉が乗っているというポピュラーな料理ですが、それだけに浸透していて「ご当地牛飯」が様々ありますね。やはり一番有名なのは米沢の駅弁ではないかと思います。 ただ、米沢の駅弁を見ると思うのですが、「どうも味が濃そうで・・・・」 そこで、今回ご紹介したいのは、私が長野に行った折に新幹線で食べた「信州牛飯」なるものです。 私は旅行中はあまり「駅弁」を食べません。だってあまりにたかいものですから。しかしこのとき、たまたま空腹に打ちひしがれ、つい新幹線に乗り込むとき長野駅で買ってしまいました。 ここの牛飯は写真のとおり味が薄いです。なかなかおいしいんですね。「こりゃいい」とばかりに新幹線車内で撮っておきました。
2007年11月17日
コメント(0)
-
ムショウに食べたくなる・・・・
今日、たまたま群馬横川のおぎのやの峠の釜飯が手に入りいただきました。 この釜飯、全国的に有名ですが、たまにムショウに食べたくなるんですね。年1回くらい。 実際群馬の横川までいって買ったことがあるんですが、軽井沢から行くことはもう出来ず、高崎から片道20分くらい電車に揺られていくんですね。横川はかつて軽井沢とをつなぐ交通の要所でしたが、新幹線が出来た今では、江戸時代の関所の跡と、それの回りに小さな町があるだけでえらくさびしいところになってしまいました。駅の前には「おぎのや」があり釜飯の人形が売られています。 さすがに当地にいくことは簡単ではないので、こんな形でたまに手に入るものを食べています。
2007年11月16日
コメント(0)
-
こりゃ美学か???
最近「メガマック」や「メガ牛丼」などがはやっていますね。テレビの特集でも「大盛の店」とか「特盛の店」なんていう特集がよくあります。 私が学生だったら飛びついていたでしょう。実際、私の元空手部の学生時代の友人は30過ぎた今でも飛びついていますが・・・・私は今ではさすがに躊躇しますね。 あるとき柴又帝釈天境内の名水を飲んで一枚100円もするせんべいをかじっていると、水を汲みに来たオバアチャンと話が盛り上がったときがありました。 そのときバアチャンは「人間は歳をとって来るとたくさんものを食べるより少しのいいものを食べるようになる」といっていました。 私もその境地になってきたのか、最近は「メガものの美学」にゃ飛びつかなくなりました。
2007年11月16日
コメント(0)
-
高級駐車場よみがえる!!
根城という東北の再現されたお城をめぐるのも最後になりました。 お城の中心部には上の写真のような長細い建物があります。屋根は板葺きで重石の丸石を載せているいかにも日本中世的な建物・・・・こりゃなんだ? これは当時の馬小屋です。馬は関東や東北ではいい馬が多く京都でも珍重されたくらいでした。馬は今の自動車と同じですから、さしずめ高級車が多く止まっていたことと思います。さきほどの倉庫と比較しても、当時、どれだけ馬が大事にされていたか、この馬小屋を見ても感じるものがありますね。 ちなみにこの小屋は普通の馬小屋で、発掘では主殿の近くに殿様専用と思われる馬小屋が見つかり復元されています。えらい社長さんや役人さんが一般社員と乗ってる車が違うように、やはり乗ってる「馬」も違っていたのでしょう。 今も昔も変わらんもんです。 私は根城を後にして、車を西へ飛ばし山道を縫って十和田湖へと向かっていきました。
2007年11月16日
コメント(1)
-
なんでこんなに高いのか・・・・
私は年に2度ほど歯のクリーニングのために歯石を取りにいっているのですが、少しの治療で値段が高いんですね・・・・・ もちろんケアはしているのですが、歯石は少しづつ溜まっていくもの、これからも歯肉炎にならないためにもやっとかないといけません。 私の回りの方で50代くらいの人でインプラント(人工歯根)にする人が嘆いていました。「保険適用外なんで数百万するんだよな・・・・・」 今の私にこのお金はないぞ!皆さん歯を大事にしましょう。
2007年11月15日
コメント(0)
全75件 (75件中 1-50件目)