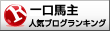2006年09月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-

恋は迷宮 5
ロッセリーニとバーグマンのコンビは53年「われら女性」 「イタリア旅行」あたりで終焉をつげる。 56年、フランスのジャン・ルノワール監督「恋多き女」に 出演、共演陣にはメル・ファーラー、ジャン・マレーらの名 前も見える。これは、ファンタジー・ミュージカルと銘うたれ たルノワールの後期の作品。 <20世紀初めのパリ。ポーランドの美しい公爵夫人エレナ (バーグマン)に惹かれる伯爵(ファーラー)と将軍(マレー) の恋の行方。> ジュリエット・グレコが特別出演、主題歌を歌っている。 ネオ・リアリズム・・・・さながら大地に生えた自然の樹木の ように、自己の環境に執着し、現実の色に染めぬかれた、 それは、なまなましく、たくましいが明晰さや普遍性に欠け ていたか。でもそれがイタリアが持つ性格でもあったろうか。 「恋多き女」は、いまや、イタリアから解放され、自由に羽 ばたくパピオンのようだった。 50年から57年まで続いたロッセリーニとの結婚生活では 一男二女があったが、58年、婚姻無効判決をうけ、同年 演劇興行主ラルス・シュミットと三度目の結婚をし、後離婚。 これに先立つ56年には「追想」でハリウッドにカムバック。 再びオスカー主演女優賞に輝いた。 『追想』 1956;アメリカ <ロシア革命の混乱時に奇跡的に生き延びたとされる ロマノフ王朝の皇女アナスタシアをめぐる陰謀と恋を 描いた名作。自称ロシア人のボーニン(ブリナー)は 記憶喪失のアンナ(バーグマン)をアナスタシアに仕 立て、ロシア皇帝が英国に預けておいた大金を詐取 しようとするが、いつしか二人の間に恋が芽生える。> 監督;アナトール・リトバク 出演;イングリッド・バーグマン ユル・ブリナー 復帰後は、年齢に応じた演技の幅を見せ、74年オール・ スター共演による、アガサ・クリスティの同名推理小説の 映画化「オリエント急行殺人事件」ではアカデミー助演女 優賞を受賞した。 『オリエント急行殺人事件』 1974;アメリカ 監督;シドニー・ルメット 出演;イングリッド・バーグマン アルバート・フィニー ローレン・バコール ショーン・コネリー アンソニー・パーキンス リチャード・ウイドマーク この映画は、第一級の優雅なエンタテイメント作品として, 世界的に大ヒットした。 クリスティ作品を長らく愛読しているエリザベス女王らが 出席した有料試写会と、その後のパーティーで、主賓の クリスティは子供のように興奮してよろこんでいたという。 そして、これが、クリスティが公の催しに出席した最後に なったのだった。 60年代に入ってからは、バーグマンは舞台出演にも積 極的で、65年の <A Month in the Country>は アメリカ、ヨーロッパで大ヒットを記録。 82年のTVM<A Woman Called Golda>でイスラ エルのゴルダ首相を演じてエミー賞を受賞。 この作品を最後に82年8月、67歳の誕生日にガンの ため死去した。 スターの座にありながら、常に自らの可能性をつづける演技 への情熱は、美しいだけの女優とは違う生命感として観客の 心を打ち続けた。 二十世紀なかごろの とある日の日曜日の午前 愛されるということは 人生最大の驚愕である かれは走る かれは走る そして皮膚の裏側のような海面のうえに かれは かれの死後に流れるであろう音楽をきく (清岡卓行 <子守唄のための太鼓>) バーグマンの墓碑銘には、生前の希望により 『生の最後まで演技した』と記されている。
2006.09.29
コメント(0)
-
恋は迷宮 4
サラマンドラは伝説の霊獣 炎を食べ 火のなかに棲み いかなる劫火にも焼かれることはなかった バーグマンのハートのなかに いつしかサラマンドラが潜んだろうか 火中の孤独と恋慕の情にもだえて サラマンドラは・・・ バーグマンがロッセリーニに熱烈な手紙を送ったことは 有名なエピソード。 37年に、バーグマンは歯科医ピーター・リンドストローム と結婚、一女ピアをもうけていた。 50年、家庭を捨てて、ロッセリーニのもとに走ったことは 当時の良識を踏み越えた振る舞いとして、アメリカの映画 界からは完全に追放された。 スキャンダルの渦中で、バーグマンはロッセリーニ監督作 「ストロンボリ」に主演した。 『 ストロンボリ/神の土地 』 1950年;イタリア映画 <第二次大戦末期、ローマの難民収容所から出るため に結婚を選んだ女性が、夫の故郷ストロンボリに行く。 島の生活になじめない彼女は、他の男と関係を重ねる。 やがて身ごもり、島の火山が爆発した日に真実の愛に 目覚める。> 続いての作品は『ヨーロッパ1951年』 技術主義の横行する現代ヨーロッパ社会のあらゆる 病患を示し、これにバーグマン演ずる女主人公の素朴 な隣人愛を対比させ、最後にバーグマンは精神病院に 反社会的な危険な存在として収容されるが、彼女の愛 を知る貧しい人々は、彼女の室の窓下に集まって、 「マ・ドンナ」と叫ぶという話。 この作品のテーマは必ずしも珍しいものでなく、全体に 宗教的な色彩が濃い。しかし技術的には、非常に洗練 されていて、ロッセリーニの最良の作品の一つであるよ うに思える。(増村保造氏) 出演;イングリッド・バーグマン ジュリエッタ・マシーナ <非常に聡明さにあふれ闊達だが、時々気むずかしく 怒りっぽくなるロッセリーニを、バーグマンはいつも かわらない平静さで見守り、演技指導のあまりうまく ないロッセリーニが、演出にあたって困惑し不機嫌に なると、バーグマンは椅子から立って、その芝居を いろいろやって見せる。その中にロッセリーニの気 に入ったのがあると忽ち機嫌をなおし、陽気に撮影 を続ける。(当時在ローマ増村保造氏)> 相思相愛の姿を彷彿させる。 しかし、このあと、二人の私生活での幸せは長くはなかった。 バーグマンの出演作は不評が続き、破産状態となって、また 一つの転機がやってくるのだった。(つづく) 、
2006.09.28
コメント(0)
-
天は二物を・・・
たわわに実るのは コシヒカリか かたわらにヒガンバナを添えて うまし瑞穂と救荒と天が二物を与える秋 (註) ひがんばなは有毒植物の一種ではあるが、 むかし、飢饉の際にはこの鱗茎をさらして 有毒成分を除いたでん粉を食用とすること もあったという。
2006.09.27
コメント(0)
-
スモーカーの近未来的パロディー
(つづき) 見えた 見えたよ 松原越しに 丸に十の字の オハラハー 帆が見えた ハ ヨイヨイ ヨイヤサ 花は霧島 たばこは国分 燃えてあがるは オハラハー 桜島 ハ ヨイヨイ ヨイヤサ (鹿児島おはら節) 葉たばこの栽培は江戸の昔からわが国の大切な産業だった。 民謡にでてくる国分は鹿児島の霧島火山地帯である。 たばこの産地として知られるところは、似たような条件の地が 多い。水利に乏しく、米がつくれなかった。畑作は実りの秋を 迎えると、鹿や猪に荒らされ、人々は貧しい生活を強いられて きた。当時の地域の知識人であった寺の和尚や神主は、常々 そのことに胸をいためていたが、修行の旅を通して情報通でも あった彼らが、たばこの種子をその地にもたらしたのは、各地 の由来記によれば、ほぼ共通して慶長のころであるという。 乾燥地でも耕作できて、利益が見込まれ、獣害のおそれがない。 さっそく種子を手に入れ、試作して領民にすすめたのだった。 それを出発点として日本のたばこ産業、たばこ文化が歴史を 重ねてきたのだった。 ・・・・ 子供のころ 隣村の丘陵地帯にたばこ畑があった 近所の女の子とお使いに行っての帰り道 「おにいちゃん あの花とってエー」 女の子がせがんだのはたばこの花 直立した茎に巨大な葉っぱが互生し 先端に淡い紅色の花が咲いている でもそれはとても背丈があって 手が届きそうにもない とれないというのも癪 『たばこはね 葉っぱ一枚だって きちんと数えてあって 盗むとすぐにわかるんだよ 花だってそうだよ』 女の子が泣きべそをかいた ほんとにたばこ畑には子供にはわからない 秘密めいた雰囲気があった 『うちにもっときれいなのがあるからあげるよ』 と女の子をなだめた うちに帰って るりやなぎの花を折って 女の子との約束を果たした るりやなぎはブラジル原産 たばこは南アメリカ原産 花の形や色は少し違うが 同じ「なす科」の植物と知ったのは 何十年も経ってからのことだった・・・・ (つづく)
2006.09.27
コメント(0)
-

金魚よ 金魚
金魚 金魚 池の金魚よ 水面を透かして ほら 見上げてごらん 薄紫にホテイアオイの花が咲いたよ
2006.09.26
コメント(0)
-
9月の読書
『御開帳綺譚』 玄侑宗久 文春文庫 芥川賞作家が記憶のなぞ「心」というミステリー に挑む。人工透析で生きる妻の願いと夫の愛 を描く「ピュア・スキャット」を併録。 脳科学者 茂木健一郎の解説は、現代文明の 有り様の一端をよく解析していて参考になる。 『日本沈没 第二部』 小松左京+谷甲州 小学館 小松左京の大ベストセラー小説「日本沈没」から 33年、第二部が谷甲州との共著として完成した。 沈没から25年後、日本海上での国家再建計画の帰趨 を中心に、最後は氷河期を迎えた地球を離れ宇宙への 移民までを描く。 読書には、逆進法というのもあっていいのではないか。 第一部を読んでいないが、映画を見、第二部を読んだ。 SF小説ではあっても、首相が「美しい国へ」を唱えるこ の国のいま、大きな示唆をふくんでいる。 また、第三部に誰かが挑戦するか興味津々でもある。 『詩とはなにか』 吉本隆明 詩の森文庫 <詩とはなにか、それは、現実の社会で口に出せば 全世界を凍らせるかもしれないほんとのことを、 かくという行為で口にだすことである。 こう答えれば、すくなくともわたしの詩の体験に とっては充分である> (本文より) いわゆる「詩論」には難解なものが多いが、本書 は、他書にはない切り口があって解り易い。
2006.09.26
コメント(0)
-
恋は迷宮 3
「助言」 ラングストン・ヒューズ <みんな、云っとくがな、 生まれるってな、つらいし 死ぬってな、みすぼらしいよ・・・ んだから、掴まえろよ ちっとばかし 愛するってのを その間にな。> (木島始 訳) 「アランブラ宮の壁の」 岸田衿子 アランブラ宮の壁の いりくんだつるくさのように わたしは迷うことが好きだ 出口から入って入り口をさがすことも イングリッド・バーグマン(Ingrid Bergman)の生い立ちは 決して幸せではなかった。 1915年スウェーデンのストックホルム生まれ。 父は写真家で画家。母はドイツ生まれ。 2歳のときに母が、12歳のときに父が亡くなり、6ヶ月後に は母代わりの叔母を失い叔父のもとで育てられた。 この孤独な環境の反動で演技に興味を抱き、ストックホルム 女学校在学中、学校劇に出演、演出も担当。 その後、ストックホルムの王立演劇学校で演技を学んだ。 34年、脇役で映画デビュー。 2年間に、スウェーデン、ドイツで11本の作品に出演したが そのうち9本は主演だった。 36年の主演作「間奏曲」がハリウッドノ名プロデューサー、 デイヴィッド・O・セルズニックの目にとまり、同作品の再 映画化「別離」の主演スターに招かれ39年に渡米した。 そして、そのみずみずしい美貌が注目され、42年には 「カサブランカ」でスターの座を獲得した。 44年「ガス燈」ではアカデミー主演女優賞を受賞し、人気 実力を兼ね備えた、ハリウッドのトップ女優として黄金時代 を迎えた。 しかし、46年の「汚名」を最後にセルズニックのもとを離れ てからは、新しい分野開拓の意欲が先に立ち、失敗作が 続く。こうしてハリウッドの仕事に満たされぬ思いを抱いてい たところへ、ネオ・リアリズムの作品群が登場したのだった。 (つづく)
2006.09.25
コメント(0)
-
恋は迷宮 2
西暦の一世紀というから、2000年前のはなし ローマにマルティアリス(M.Valerius Martialis)という 風刺詩人がいた この詩人の後援者(パトロン)は 皇帝ドミティアヌス(=51~96 在位81~96)だった そのころすでに、ローマではメセナの精神があったこと を思うと驚きである (マルティアリスの言葉より) カエサル・ドミティアヌスへ <あなたが統治なされているこのローマの街なかに、わたしは 小さな家をもっています。 ところがその家は狭い谷に面した高台に立っているので、 水は常に不足状態。 すぐ近くを通っているマルキュア水道には音を立てて多量 の水が流れているというのに、わが家の庭は一滴の水も なく砂漠も同然。これが現状ゆえ、皇帝陛下、わがあばら 家にも水を与えられんことを。もしもこれが実現したあかつ きには、わたしにとってはユビテル神が降らせる雨にも似た 恵みになるでありましょう。> <人生を愉しむのは明日からにしよう、 だって? それでは遅すぎる、ポストゥムスよ。 愉しむのは今日からであるべきだ。いや、より賢明な 生き方は、昨日からすでに人生を愉しんでいる生き方 ですよ。> <作家としての自分は、子供や処女を相手にしているの ではない、成熟した大人を相手にしているのだ。> つまり、マルティアリスの関心は、人間の「あるべき姿」 にはなく、「現にある姿」のほうにあったのである。 (塩野七生 「ローマ人の物語」より) 古代からつづく、イタリアの伝統は、二十世紀のネオ・ リアリズムの精神にも受け継がれていたようだ。 *無防備都市の梗概 『主人公のマンフレディは地下運動のリーダーでゲシュタボ に追われている。彼の同志が彼をかくまったために逮捕 され、トラックで連れ去られるところを追ったその婚約者 の子持ちの中年女性(アンナ・マニヤーニ)はナチスの 兵隊から一撃のもとに殺される。 しかし、マンフレディは麻薬患者の女に密告されて逮捕 され、地下運動に参加しているピエトロ神父も訊問を受 ける。そしてマンフレディは神父の眼の前ですさまじい 拷問を受けて絶命し、神父も翌朝、神父を慕う少年たち の見守るなかで銃殺される。』 つづいて、ロッセリーニは、これもネオ・リアリズムの傑作 のひとつにあげられる「戦火のかなた」(46)を発表。 これはロッセリーニの代表作であり、ネオ・リアリズムの ひとつの頂点をなす作品であった。 『連合軍がシシリー島に上陸したときから、ドイツ軍を撃破 しながら北上して、北部のポー川流域の湿地帯に至るまで の、各地における連合軍の将兵や従軍僧とイタリア民衆と の出会いを六つのエピソードでつづったものである。』 48年、ベルリンの廃墟を舞台に少年の短い一生を描いた 「ドイツ零年」を作り戦争三部作を完成させたのであった。 そんなロッセリーニの元に熱烈な一通の手紙が届く。 手紙にはこう書かれていた。 「もし、英語のうまいスエーデン生まれの女優が必要なら いつでも一緒に映画を作る準備があります」と。 (つづく)
2006.09.22
コメント(0)
-
恋は迷宮
私たちの人生行路のなかば頃 正しい道をふみはずした私は 一つの暗闇の森のなかにいた ああ それを話すのはなんとむずかしいことか 人手が入ったことのないひどく荒れた森のさまは 思いだすだに恐怖が胸に蘇ってくるようだ その森の難渋なことはほとんど死にも近い だが私はそこで享けた幸福を述べるため そこで見た他のことをも話すことにしよう いかにしてそこへ迷いこんだかうまくいえないが ただ正しい道を捨てたその頃の私が 深い眠りにおちいっていたことは確かである ( ダンテ「神曲」 野上素一訳より ) 映画の歴史のなかで、ネオ・リアリズム運動が澎湃として 湧き上がったのは1944年頃であった。 ローマでは、1944年6月に連合軍に解放されるまで、9ヶ月 におよぶ占領軍であるナチス・ドイツの圧制と、これに対する レジスタンスが続いた。 ファシストの残党は、ドイツ軍に協力したが、多くのイタリア人 がドイツ軍とファシスト残党に抵抗する地下組織に参加して 戦った。 この間、映画人たちはほとんど仕事はできなかったが、しかし あるいはレジスタンスに参加し、あるいはその協力者として、 解放への動きを見ながら、再び映画を作れる日に向かって 準備を重ねていた。 そして解放と同時に、沸き起こる感動を情熱のほとばしるまま にフィルムに刻みこんだ。これが第二次世界大戦終結後に 世界を驚かせたイタリア映画のネオ・リアリズムである。 特に『無防備都市』(45)はその典型的な作品であり、ネオ・ リアリズムの口火を切った傑作であった。 ロベルト・ロッセリーニ(Roberto Rossellini)は解放前から 一本のシナリオに取り組んでいた。 ドイツ軍の占領下で抵抗運動を支持し、連合軍の捕虜を逃亡 させて銃殺されたカトリック神父の実話を映画化しようとして いた。そして解放後まもなく、自分で資金を調達して映画を 撮りはじめた。撮影所は難民住宅になっていたので、使用で きず、ロケーションで撮らねばならなかったし、資金・物資の 不足から撮影用フィルムもままならず、廃棄されかかっていた 不良品など、さまざまなものを使い、照明も不十分だった。 それらの技術的な悪条件を、ロッセリーニは、まるで実際に 起こった事件の現場にカメラマンが居合わせて撮ったかの ような即興的なリアリズム演出で、強い現実性を持ったなま なましいドキュメンタリー的な効果として活用したのである。 (つづく)
2006.09.21
コメント(0)
-
スモーカーの近未来的パロディー
(つづき) 恩賜の煙草いただいて あすは死ぬぞと決めた夜は 昿野の風もなまぐさく ぐっと睨んだ敵空に 星がまたたく二つ三つ 支那事変下の昭和15年に出来た軍歌「空の勇士」 であるが、今日恩賜の煙草といっても何のことかが 解らない人の方が多いのではないだろうか。 20XX年 全面的禁煙令の施行を一ヶ月後に控えたころのこと。 各地で、宴会ならぬ「サヨナラ煙会」が催された。 カラオケも持ち込まれ、煙草がよみこまれた各時代 の名曲が数多く歌われ、歌の世界にも煙草の煙が 深く浸潤し、一つの煙草文化を形成していたことが 今更ながら思い起こされるのであった。 そして、出席者等はそれぞれの思い出を懐かしみ、 語り合い最後の煙草を手にしその一服を楽しむの であった。 いま、一時代の記憶として、そのとき歌われた名曲 の一部を列挙してみるのも、あながち無意味なこと ではないと思うのである。 古い世代に歌い継がれてきたのは先の「空の勇士」 であったが、若い世代にも世代間の好みの違いが みられたのは興味ある現象だった。 「ブルーライト・ヨコハマ」 s,43 歩いても 歩いても 小舟のように 私はゆれて ゆれてあなたの腕の中 あなたの好きな タバコの香り ヨコハマ ブルーライト・ヨコハマ 二人の世界 いつまでも (詞;橋本淳 曲;筒美京平 歌;いしだあゆみ) 「よこはま・たそがれ」 s,46 よこはま たそがれ ホテルの小部屋 くちづけ 残り香 煙草のけむり ブルース 口笛 女の涙 あの人は行って行ってしまった もう帰らない (詞;山口洋子 曲;平尾昌晃 歌;五木ひろし) 「うそ」 s,49 折れた煙草の 吸いがらで あなたの嘘が わかるのよ 誰かいい女 出来たのね 出来たのね あー 半年あまりの恋なのに あー エプロン姿がよく似合う 爪もそめずに いてくれと 女があとから 泣けるよな 哀しい嘘のつける人 (詞;山口洋子 曲;平尾昌晃 歌;中条きよし) 「想い出まくら」 s,50 こんな日は あの人のまねをして けむそうな 顔をして 煙草をすうわ そういえば いたずらに煙草をすうと やめろよと 取りあげて くれたっけ ねえ あなた ここに来て 楽しかったことなんか 話してよ 話してよ こんな日は あの人の小さな癖も ひとつずつ ひとつずつ 想い出しそう (詞・曲・歌;小坂恭子) 「北酒場」 s,57 北の酒場通りには 長い髪の女が似合う ちょっとお人よしがいい くどかれ上手の方がいい 今夜の恋は煙草の先に 火をつけてくれた人 からめた指が運命のように 心を許す 北の酒場通りには 女を酔わせる恋がある (詞;なかにし礼 曲;中村泰士 歌;細川たかし) (つづく)
2006.09.20
コメント(0)
-
高野槙のお印
* 秋篠宮の新宮様のお名前が悠仁と命名され、 お印は高野槙と決まった。これを機会にお印 について記憶に留めておきたい。 * 皇族がたは、身の回りのものに「お印」をつけ るならわしがある。身の回りの調度品や小物に ご自分の名前を書くことがはばかられたために ほかの人との区別をするしきたりがあって「お印」 がつけられた。 文字や植物の意匠が用いられるが、デザインは 特に決まっていない。 また、このお印という慣習は元来女性の間に始 まったもので、お印を決めるのは母君か、御祖母 である。たとえば、今上天皇の「栄」は御祖母の 貞明皇后がお決めになった。例外は常陸宮の 「黄心樹」で、これは昭和天皇がお決めになって いる。 * 高野槙は杉科の裸子植物。わが国特産の常緑 高木、紀伊半島から四国及び九州の山地に自生 しているが、庭園にも多く栽培されている。高さ 15メートル位になる。日本名「高野槙」は、紀州 高野山に多いという理由で名づけられた。材は 建築、器具材として有用。 学名;Sciadopitys Verticillata Sieb.et Zucc. < 天皇ご一家のお印> 天皇陛下 栄(えい) 皇后様 白樺 皇太子様 梓(あずさ) 皇太子妃雅子様 ハマナス 愛子様 ゴヨウツツジ 秋篠宮様 栂 (つが) 秋篠宮妃紀子様 檜扇菖蒲(ひおうぎあやめ) 眞子様 木香茨(もっこうばら) 佳子様 ゆうな 悠仁様 高野槙
2006.09.19
コメント(0)
-
恋と愛と恋愛と
(第一講) ガラにもなくこんなカテゴリーをつくってしまったけれど 先人の「恋愛論」はいっぱいある。あまり読んだ記憶が ない。女性にしろ男性にしろ恋愛するときには、まず 一冊の「恋愛論」に目を通すものだろうか。マニュアル として役に立つのだろうか。恋愛と一括りで表現するが はたして「恋」と「愛」は同じだろうか。違うのだろうか。 その道の達人からすれば、笑っちゃうような素朴な疑問 だろうが、当人は至って真面目なのである。 <愛と恋のイメージ> 愛はシャンソン 恋は演歌 愛は献身 恋は打算 奪われても愛 ハニートラップにかかった恋 愛は薔薇のイメージ 恋は黒百合 愛は寛容 ききわけのない恋 愛は真摯 恋は気まぐれ ひろった恋 かりそめの恋 「あなたを愛しています」 何故 素直に言えないか 愛するということは 相手を全人格的に受容すること だから女は男に どうしてもその一言を言わせたい 「わたしのすべてを受け容れてほしい」と ことばは言霊 男はいつも躊躇する
2006.09.15
コメント(0)
-
スモーカーの近未来的パロディー
(つづき) 「飲酒運転の激増は禁煙によるストレスからくる」 世の中にパチンコがあり 国営・公営のギャンブルがあり 宝籤がありTotoがあり ナンバーズにロトシックス 年賀葉書もお年玉付き 古来人類はフラストレーションのはけ口として 賭け事を必要悪として認めてきた 江戸時代でも賭場や富籤やら射的場があった それにしても ちょっと多すぎやしませんかね 「不許葷酒入山門」は禅寺の戒律だったが 一方では般若湯という言葉があり お神酒あがらぬ神がなかったように 神も仏も見て見ぬふりして酒を認めたのだろう 「酒は百薬の長」は あながち酒屋の宣伝文句でもなかった 功罪相半ばして酒は認められてきた 片や 「酒もタバコもやりません」 謹厳居士の常識では酒とタバコは同列で 「飲む打つ買う」 道楽息子のメニューにタバコはない 「朝寝 朝酒 朝湯が大好きで それで身上つぶした」オハラショウスケさんも たばこは格別問題とはしなかったようだ < なのに 何故? どおして? 煙草だけがこんなに貶しめられるの? 医者の不勉強じゃないの? もしかしたら だってそうでしょう 医学的に煙草と健康の因果関係について ハッキリ証明したひとあったかしら いろんなデータでてるけどみんな中途半端 それに あたしゃ 統計とか世論調査とかアンケートとか あんまり信用できないわぁー> というわけで 庶民にとっては 酒と煙草は兄弟分みたいなもの だって そーでしょうとも 酒屋の店先には 大概タバコの自販機があるし むかし 三公社五現業という言葉があったじゃない 国鉄・電電公社・専売公社 郵政・林野・印刷・造幣・アルコール専売 みんな国家的事業で根はいっしょだったのよ にもかかわらず この期におよんで 酒を優遇し タバコを継子扱いするのはやめてよ ・・・きっと圧力団体として セージリョクが弱かったのよ 煙草組合のさ・・・ 巷にそんな噂が流れるのも無理はなかった タバコ愛好者絶望状態の折も折 公表された某脳神経学者の見解には スモーカーはいっとき溜飲を下げたのだったが・・・ (つづく)
2006.09.14
コメント(0)
-
命名の儀
秋篠宮ご夫妻の三番目のお子様の名前が「悠仁(ひさひと)」に 決まり「命名の儀」が行われた。ご夫妻は「ゆったりとした気持ち で、長く久しく人生を歩んでいく」ことを願って命名したという。 「悠」の字の上の部分は人の背中に水をかけて滌(あら)う形で みそぎをするという意味となり、「みそぎによって心身が清められ 心がゆったりと落ち着くことを悠の字は表すという。 また、お印も「大きくまっすぐに育ってほしい」との思いから日本 固有の直立の木「高野槙」となった。名前とお印はご夫妻で話し 合い、名前については天皇、皇后両陛下にも相談し最終的には 秋篠宮さまが決められた。 命名の儀は、秋篠宮さまが毛筆で、「悠仁」、お印の「高野槙」と それぞれしたためた和紙を、ご夫妻が順に確認した後宮務官が 白木のきり箱におさめて、悠仁さまの枕元に置いた。和紙はいず れも皇室の重要行事に使われる「大高檀紙」と呼ばれる厚手の紙。 天皇が名前を決める際は通常、国文学者や漢文学者ら専門家に 検討を依頼する。日本や中国の古典をよりどころに歴代天皇の 名前との重複はないかなど調べながら複数の案を提示。天皇が 最終的に決定する。 昭和天皇の名前は「裕仁」 「雍仁」 「穆仁」の3つの案の中から 明治天皇が「裕仁」を選択。 天皇陛下の場合は、時代背景もあり、明治政府の祭政一致政策を 示した「大教宣布」から漢字をとって、昭和天皇が「明仁」と名付け た。天皇陛下の三人のお子様は 長男の皇太子さまの「徳仁」が「中庸」 二男の秋篠宮さまの「文仁」が「論語」 とそれぞれ中国の古典の文章に由来。 長女の黒田清子さんの「清子」は日本の「万葉集」が出典で いずれも昭和天皇が決めた。 皇太子の長女愛子さまの「愛」については中国の古典「孟子」 が原典となり、皇太子ご夫妻の希望を聞く形で、天皇陛下が 命名された。 天皇の子供や孫である直系に対し、天皇家から分かれた宮家での 命名は方法が異なる。漢字2文字で男子は「仁」、女子は「子」の字 を使うのは同じだが名付けるのは天皇ではなく親。古典からの引用 という慣例にも縛られない。 このたびの、「悠仁」の「悠」については、古典からの引用かどうかは 別としても、秋篠宮妃紀こさまの男子ご出産の際、紀子さまのご両親 川嶋辰彦、和代さんがその時の感懐を陶淵明の詩「帰去来の辞」に 託されたことと思いあわせると、やわり陶淵明の詩が命名の動機とし てあったのではないかと推測してみるのである。 庵を結びて人の境にあるに しかも車馬のさわがしさ無し 君に問う何ゆえによくしかするやと 心ののどかなれば地も自ずとひそまるなり 菊を東のまがきの下に採れば 悠然として南の山の見ゆ 山の気は日の夕べなるままに佳ろしく 飛ぶ鳥の相いつれだちて帰りゆく 此の中にこそ真の意(こころ)有り あげつらわんとおもいたれども已にはや言を忘れたり ( 陶淵明の連作「飲酒」の第五首 )
2006.09.13
コメント(0)
-
スモーカーの近未来的パロディー
いまや「紫煙」という言葉など死後と化してしまった 「禁酒・禁煙」読んで字のごとく たばこは酒と対をなす嗜好品だった 一服即こころを癒す人の世の必需品だった それなのに ああ それなのに たばこはこの社会から抹殺されるのか 西暦20XX年 日本政府は 天下に号令し全面的禁煙令を出したのである あわれ 煙草の末路は 燃えるゴミとして焼却処分され まさに 烽火は三月に連なり ニコチンを含んだ煙害によって 健康を害する市民が相次いだのだったが その数は 禁煙令以前の喫煙被害者の数を はるかに上回るものだったという さらに 全国の陶器・ガラス器のメーカーは 倉庫にうず高く積まれた 売れ残りの灰皿を廃棄処分した 損害の額は数億円に達したが 時代の趨勢からすれば当然の 『想定内』の措置と見做され 一円の補償もなかった ライター・メーカーも同様だった さらに さらに アッシュ・トレイやカーライター付きの 自動車は製造禁止となり 販売前の既製の新車は仕様の変更を 発表を目前にひかえた新車も設計の変更を 余儀なくされ そのコストは 自動車メーカーの損益に甚大な影響を与え 国の景気をも揺るがしかねなかったのである 一方 列島には風紀を乱す事態が蔓延していた 公務員の飲酒運転事故が激増したのである 事故が発生する度に 全国の首長は 市民や被害者を前に平身低頭陳謝するばかり 職員の綱紀粛正を約束するのだったが 事故は一向に減る気配がなかった ある首長にいたっては 「コメツキバッタ」と市民に罵倒され 辞職騒ぎにまで発展した そのころ ある高名な脳神経学者の 政府の諮問に応える発言は 世間の注目を浴びるものだった・・・ (つづく)
2006.09.12
コメント(0)
-
かまいたち
稲穂が黄金色のこうべを垂れる丁度今頃の季節 野面の風の道をつむじ風が通り過ぎて行った と 『かまいたちだぞー』 誰かが叫んでいる 散居村の屋敷林の杉木立は まだ夏の名残りの青空と雲の動きの下で じっと静もっているだけだったが 田の畦道には 脛を鮮血に染めて男が倒れていた 幼時の印象は強烈だった 「かまいたち」は鎌鼬という魔性のもの と信じていたが・・・ 串田孫一の「博物誌」にこんな鎌鼬にまつわる話がある。 (私が想像するこの動物は、全部透明であって、どうもビニール のようなもので出来ているらしい。ただその歯だけはガラス製 で、それが上顎に、帽子の庇のように大きく一枚はえている。 つまり、いつもむき出しなのだが、笑うことも出来るようである。 私はこの珍獣が、時たま思いもよらないところできらっと光る のを見ることがある。だが幸いにして、私自身どこを噛みつか れたこともない。) (これは想像でも夢でもない。私を可愛がってくれていたある女 の人が、私を抱きかかえて、崩れ倒れる家の傍を逃げていた。 まっすぐには走ることも歩くことも出来ないほどの、関東大震災 の最中だった。) (彼女の腕はあまり細くもなく、あまり白くもなく、それにぎゅっと 抱きしめられていた私は殆ど息の根が止まりかけていた。 その時、いっぱいに力の入ったその腕は、私の目の前でぱく っと口があき、血が非常な勢いで吹き出して、私の顔や胸を 真っ赤にそめた。彼女は自分の傷には少しも気がつかず、血 だらけの私を見て失神した。) ( ・・・以下略・・・ ) つむじ風などのとき、空気中に真空ができ 人体がその部分に触れると、気圧の差に よって、鎌で切ったように皮膚が裂ける。 昔はイタチのような魔物のしわざだと信じ られていた。 現象を科学的に解明してみても その怖さが和らぐ訳ではない ある日 ある時 断裂する空気の怖さは やっぱり魔物そのものである
2006.09.11
コメント(0)
-
東京駅
一 汽笛一声新橋を はや我が汽車は離れたり 愛宕の山に入リのこる 月を旅路の友として 二 右は高輪泉岳寺 四十七士の墓どころ 雪は消えても消えのこる 名は千載の後までも 三 窓より近く品川の 台場も見えて波白く 海のあなたにうすがすむ 山は上総か房州か (鉄道唱歌 東海道編は66題まである) 1872年(明治5年)、日本最初の鉄道が新橋と 横浜の間に開通した。 『鉄道唱歌』 (大和田建樹作詞 多梅稚作曲)は 鉄道沿線の風景を次々に歌ったもので、第一集の 東海道編が1900年(明治33年)出版された。続 いて山陽・九州・北陸・東北・関西の各編が発行さ れ、軽快なメロディーと興味ある内容とで全国的に 愛唱された。 その頃、東京駅はまだなかった。 明治23年、明治政府は新橋と上野間を高架線で 結び、その中央に大停車場を設ける計画を立てた。 日露戦争で計画は一時中断したが、戦後、日露 戦争の大勝を記念して巨大化することが決まった。 新しい駅舎は南北330メートルの長大な建物だ った。赤レンガに白色石材のバンドを入れた、いわ ゆる辰野式スタイルだったが、単なるレンガ建築で はなく、鉄骨を埋め込んだ鉄骨レンガ造り。そのため 関東大震災でもビクともしなかったが、昭和29年の 空襲で屋根と内部を焼失。戦後、再建の際、三階を 削って二階にし、円形のドームも簡単な形に変わって しまった。 ・・・我々の体内に、明治、大正という時代を赤レンガ というフィルターを通して眺めるという感性がある・・・ 1987年「赤レンガの東京駅を愛する市民の会」が 発足。会の代表には文化庁長官だった三浦朱門 さんと女優の高峰三枝子さんが就任した。 そして、時代の曲折を経て東京駅の復元工事が、 いよいよ来年から始まることとなった。
2006.09.08
コメント(0)
-
『賜剣の儀』
6日午後、天皇陛下が使者を通じて子供に 「守り刀」を授ける儀式『賜剣』が行われた。 刀は重要無形文化財保持者(人間国宝)の 天田昭次氏=新潟県新発田市が製作した 刃渡り約26センチの短刀で、錦織の包みに 入れた上で、桐箱に収められている。 刀は秋篠宮邸で秋篠宮さまが見た後、愛育 病院に運ばれ、守り刀として新宮さまの枕元 に届けられた。 儀式とは別に、皇后さまは枕元に置く厄よけ の天児(あまかつ)の人形や犬張子などを贈ら れたという。 * 天児(あまかつ)について 古代に、人間の身代わりとして祓(はらい)のとき これに災いを移し負わせた人形(ひとがた)をいう が、後世は、幼児にお守りとしてそば近くに置いた 人形をいうようになった。別称「おとぎぼうこ」(お伽 這子)といわれるものは、長さ30センチほどで全体 を白の練り絹で包み、黒い糸を髪として左右に分け 前にたらした様式だという。
2006.09.08
コメント(0)
-
陶淵明の詩
秋篠宮妃紀子さまのご出産によせて、ご両親の川嶋辰彦さん 和代さん夫妻は宮内庁を通じ、「誠におめでとう存じます。 『清流に臨みて詩を賦す』心に重なる感懐を覚えます。お健やか な御成長を謹んでお祈り申し上げます」との感想を文書で発表 した。 川嶋夫妻が引用したのは、古代中国の詩人陶淵明(365 ~427)の「帰去来の辞」の一節である。 東晋の抗争の渦に巻き込まれながら、反骨精神を持ち、 田園生活の自由をうたった陶淵明は、「帰去来の辞」を作し 官職を辞めて故郷の田園に引退したが、人間と社会の「真 実なもの」を追求しつづける詩精神の持ち主であった。 「帰去来の辞」 帰りなんいざ 田園将(まさ)に蕪(あ)れんとするになんぞ帰らざる 既に自ら心を以って形(からだ)の役(しもべ)と為しつつ なんぞ惆(おも)い悵(むす)ぼれつつ独り悲しむや これは、ほんの出だしの一節にすぎず、全体は 詩型に句分けすると61行にもなる長詩であるが、 引用された詩句は終りの4行中にある。 東の阜(おか)に登りて以って舒(ゆるや)かに嘯き 清き流れを臨(まえ)にしつつ詩を賦(つく)らん 聊か化に乗じて尽くるに帰し かの天命を楽しみつつ復たなにをか疑わん 引用された詩句は、晴れ晴れと澄み切った 心を表現している。それはしかし、陶淵明が 人生の幾多の山や谷を越え辿りついた末に 歌い得た境地ではなかったろうか。 * 漢詩の訓読はひとによって異なる場合がある。 本文は吉川幸次郎氏の『陶淵明伝』より引用した。
2006.09.07
コメント(0)
-
親王ご誕生に寄せて
秋篠宮家に親王誕生のニュースで今日は 日本中が慶祝ムードに沸いている。国民の 一人としても、人の子の親としても、心から 「おめでとうございます」と申し上げたいのは 私とて同様である。 ところで、皇族にお子が誕生して最初に執り 行われる儀式が『賜剣の儀』であるということ に、私は一種の感銘を受ける。これは天皇が お子に守り刀を賜るということ。その守り刀は 人間国宝級の名工が鍛えたものとされている。 皇室の伝統の重みを感じるのは当然であるが、 およそ、実用の役目からは遠くかけ離れた刀 を創ることを、現在もなりわいとする刀鍛冶の 存在そのものが稀有のことである。 歴史をはるかに遡れば「古事記」に誌された歌がある。 忍坂(おしさか)の 大室屋に 人多(さわ)に 来(き)入り居り 人多に 入り居りとも みつみつし(=枕詞) 久米の子が(久米=上古の武人) 頭椎(くぶつつい=柄頭が槌のようになっている太刀) 石椎(いしつつい)もち 撃ちてしやまむ カムヤマトイワレヒコノミコト(神武天皇)が東征のとき、その命を受 けたミチノオミノミコト、オオクメノミコトらが大和の土蜘蛛(穴居して いた異民族)を撃つべく歌った歌である。時代はまだ縄文、すでに 太刀があったのである。 記紀神話には十握剣(とつかのつるぎ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ) という宝剣が登場する。 国生みの男神イザナギノミコトが所持していたのが十握剣。 その息子であるスサノオノミコトが退治した大蛇ヤマタノオロチの尾 から取り出し、永い時を経て、英雄ヤマトタケルノミコトに受け継がれ た剣が草薙剣。草薙剣はヤタノ鏡、ヤサカニノ曲玉とともに「三種の 神器」となった。 イザナギが国生みのパートナーとして天界から伴ったイザナミノミコト は、さまざまな子神を産み、天地を満たしてくれた女神であった。しかし 最後に出産した火の神カグツチは生まれながらに全身から炎を放って いたため焼死してしまう。激怒したイザナギは十握剣を振るいカグツチ を斬ったという。 天界を乱した暴れ者として地上世界へ追放されたスサノオはかつて 父イザナギの愛刀だった十握剣を振るいい、出雲国で大蛇ヤマタノオ ロチを退治する。 スサノオから姉の太陽神アマテラスに託された草薙剣は、天孫として 降臨したニニギノミコトとともに地上世界へもたらされた。その後永らく 伊勢神宮に安置されていた剣を手にしたのがヤマトタケルであった。 十二代景行天皇の皇子でありながら、粗暴ゆえ父から疎まれ、九州 の先住民討伐を命じられたヤマトタケルは、クマソ兄弟を始めとする 強敵を倒すが休む間もなく東征を命じられる。そんな甥の境遇を哀れ んだ叔母のヤマトヒメは、斎宮として仕えていた伊勢神宮から密かに 草薙剣を持ち出し、東征の旅の護りに与えるのだった。 このときの草薙剣は「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」と呼ばれ ていた。草薙剣の異名は東国で罠に落ちたヤマトタケルが周囲の草 むらを剣で薙ぎ払い、やはりヤマトヒメから餞別に託されていた火打石 で向かい火を放って、敵を返り討ちにしたことに由来する。 ここまで来ると『賜剣の儀』の奥に秘められたロマンのようなものが ようやく垣間見えて来る。 憲法がかわっても、皇室典範がよしやかわろうとも、皇室の喜びも 苦難も、いつも国民とともにあるし、国民の喜びも苦難もまた皇室と ともにある、そんなこの国の形が続くことを願わずにはいられない。
2006.09.06
コメント(0)
-

紅萌ゆる・・・
( 京都文化博物館別館 ) この建物は1903年(明治36年)に着工され 1906年に竣工した。もともと日本銀行京都 出張所(明治44年支店に変更)として建築 された。日本銀行は昭和40年に移転、建物 は財団法人古代学協会」の所有となり、43年 平安博物館として開館。44年に国の重要文 化財に指定された。1986年(昭和61年)に 京都府に寄贈され博物館別館として公開され るようになった。 設計者辰野金吾は、日本銀行本店や東京 駅などを設計した、日本の近代を代表する 建築家であった。 赤レンガに白い花崗岩の帯を配した意匠は 辰野様式の特徴をよくあらわしている。 この建物が着工した翌年には、日露戦争 が勃発し、戦争が終わった翌年に竣工した ことを思い合わせると、この建物は日本の 近代の申し子の一つだったような気がする。 因みにこの建物が着工した翌年、明治 37年に京都第三高等学校(現京都大学) の <逍遥の歌> (紅萌ゆる岡の花)が できたのも時代の由縁でもあろうか。 一、 紅萌ゆる岡の花 早緑匂う岸の色 都の花に嘯けば 月こそかかれ吉田山 ・・・・ 三、 千載秋の水清く 銀漢空に冴ゆるとき 通える夢は崑崙の 高嶺のこなたゴビの原 (以下省略) (作詞・作曲 沢村胡夷)
2006.09.05
コメント(0)
-
猫類・猫科・ねこたち
天は猫の上に猫をつくらず 猫の下に猫をつくらなかったろうが やっぱり名前だけはつけない訳にはいかない 「オイ」 「コラ」では猫の個性を無視することになる 拾い猫・迷い猫・居候猫・貰い猫・生まれ猫・連れ子猫 いつの間にか増えに増えてしまったねこたち 一匹一匹に娘は名前をつけた 初代猫は「エレオノーラ」 白黒斑の雌猫だった エレオノーラが恋をして赤ちゃんができた 「ドラゴン」「パピヨン」「ビートル」 父は誰だかわからない よその猫も棲み付いた 「チェルノブイリ」「タイガー」「ゴンザレス」「ゴエモン」 娘は面白がっていろいろの名前をつけた そのうちエレオノーラの娘パピヨンが 思春期をむかえ恋をした 恋の相手はわからない 「バニラ」「サンダーバード」「ミルク」「レオ」「ガルーダ」 5匹の子猫に名前をつけた 毎日ねこたちの員数を確認するのも一苦労だが 娘は餌を与え世話を続け犬猫病院にもよく行った 猫の集団は本能的に適正規模を知っているのか 家出する猫・病死する猫・事故死する猫もいたりして 無制限に増えることもなかったのだが エレオノーラがまた恋をした そして生まれたのが 「ルナ」「ナーガラージャ」「サラマンダー」 「メロン」「マーブル」「ゼフィール」 猫の家系図も込み入ってぐしゃぐしゃになってきた でも娘は猫類・猫科・ねこたちの無頼を許容しながら 朔太郎でもない藤田嗣治でもない 猫とのかかわりをいまも続けているようだ
2006.09.04
コメント(0)
-
落し穴
電車のドアー・ガラスにステッカー 『←ゆびにごちゅういください』 なに? ドアーに指がついているの? いつから? どこに? どこ? へそ曲がりの俺はつい拗ねてみる もちろん 意味は解っているよ 「開閉時に指をドアーに挟まれないように 注意してください」 ということなのさ でもね この一瞬の違和感は見過ごせない 前頭前野は一瞬凍りつくのです どこから来るのか この気持ちのブレは これはきっと言葉に固有の落し穴です 言葉の用心 火の用心 ワンフレーズのキャッチ・コピーには ときにはミス・リードされることがある 『 取り敢えず注意しなくっちゃ!』
2006.09.01
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1