2006年06月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
百日草
夏の日盛りのなかで その日も百日草が咲いていた 胸を病んだ母は ずっと床についていた 高熱と衰弱とで 昏睡状態がつづいていた 少年の目にも もうこれきり 元気な母を見ることはない そんな気がしていた 『でも』と少年は思った 一度だけ母に頼んでみよう 母は黙って 頷いてくれるかも知れない その日少年の心は傷ついていた 学校での昼の食事時間のことだった 『お前の弁当箱は 女のあれみたいやないか』 ガキ大将が 教室中に聞こえるような 大声で言った 大きな丸に縦線が一本 縦線の中央に小丸を描く 悪ガキ共が トイレに落書きするあれ 少年には耐えられない屈辱だった 少年の弁当箱は兄のお古だった 蓋の対角線が溝になっていて それが箸入れだった 日の丸弁当の梅干のせいで アルミの蓋は 溝のまん中に穴があいていた 戦争も終末に近い 物資の無い頃だった 辱しさをこらえながら 『母さんにねだってみよう』 そう思い思い 急いで学校から帰って来た 『お母さん新しい弁当箱買ってね』 朦朧とした母の眼差しが その時少しだけ 微笑んでくれたと 少年は信じて来た あれから何年経ったろうか くらくらする程の夏の日盛りのなか ふと思い出す母の眼差しだけが 不思議と涼しげ そして今日も百日草が咲いている 三十代で天国へ行ってしまった母の墓標に せめて百日草の花を手向けたい 赤とピンクに黄色を添えれば しゃれた色調になる 絵心のあった母を偲んで 三色とりまぜて 百日草の花を手向けたい
2006.06.30
コメント(0)
-
流砂の記憶
果てもなく広がる砂漠・風紋 両の手でそっと砂を掬い上げても その嵩はおよそはかなくて しかもそれすら 指の隙からさらさらとこぼれ落ちる 重畳として堆積する 時間の軋轢のなか 古代シリアの文明もまた つかの間に揺曳する光 しかしいま 時の流れの 須臾のはざまにいて かいま見る古代の遺品は 私の感動を呼びおこす 永劫のうちの一瞬にきらめく マリンブルーの貴石に 金象嵌を施した耳飾り 三千年の昔 王宮の女が 渇仰したものは何だったろう また ロダンのそれとも見まがう 隆鼻白皙のトルソー 黄金の獅子頭 その眼窩に炯々として光るものは 怒り 悲しみ それとも祈りなのだろうか そしてそれらすべての きらめきを呑み込んで 眼裏をよぎる 流砂 流砂の氾濫 春まだ浅き頃 千里の海を越えて 飛来する黄砂に 大陸の地異を見たのだが 季節はいま水無月 一歩ミューゼアムを出れば 外はこぬか雨 人は酸性雨などというが 近未来の予兆か 白い淋しげな風に乗って 流砂の記憶は蘇える
2006.06.29
コメント(0)
-
おーい 鳥
おーい鳥よ どうしておまえは鳥なのだ 俺が問いかけると 鳥の感性を 持っているから だから私は鳥なのよ 鳥が答えた そして鳥は 半島の方へ あわただしく飛んで行った おーい魚よ どうしておまえは魚なのだ 俺が訊ねると 魚の知覚が具わっているから だから私は魚なのよ 魚が答えた そして魚は 遠い赤道の方に向って ひらひら泳いで行ってしまった ここは 白亜のビル街の昼下がり 雲の影が 大股で駆け抜ける ときにホモ・サピエンス ヒトの感性をみがけ ヒトの知覚を 研ぎ澄ませ そして俺は 今の この時を 急ごう
2006.06.27
コメント(0)
-
想い出・風の橋
橋の欄干を過ぎてゆく 風が涼しい夏の終章だった 間遠に聞えていたのは 祭囃子の太鼓の音だったろうか 橋下の 空間とも水面ともつかぬ 暗がりに 蛍がぼんやり光っているのを みつめていた ( あのとき 何故 もっと 話し合えなかったのだろう 何故 もっと お互いを ぶつけ合えなかったのだろう 橋を半分戻れば もう至近の距離に あなたがいるというのに 引き返す決断もなく その夜わたしは 橋に背を向け帰ってしまった ) 夏休みも終わったある日 思い定めて あなたを訪ねるべく 橋の半ばにさしかかると 対岸の斜面一杯 燃えるように 彼岸花が咲いていた その日は 橋を通る風の元素さえ とても鋭利で かすかにそよぐ 彼岸花の蕊の百千が 十指をさし伸べ 手話を話しているかのようでした 天真の原風景が わたしの心象を 癒してくれたのでしょうか わたしは 風と一緒に橋を渡り切ると まっすぐ 足早に あなたの家へと向っていました
2006.06.26
コメント(0)
-
ほたる
<ほたる> * ゆらゆらと 逃げ水顕(た)てる 朱雀門 いずこともなく 平城を 飛ぶほたる
2006.06.23
コメント(0)
-
風のオノマトペ
風のオ・ノ・マ・ト・ペ 糸が切れた凧のように 鳥がすっ飛んで行った その先の森は ものの見えない夕暮れです サティア・サイババよ ここには師が癒すほどの 淋しさがいっぱいある でも遠すぎて 目も耳もとどかない夕暮れです 木の枝が擦れ合う ざわ ざわ ざわわ しゅる しゅる しゅるる 風のオノマトペが不機嫌なのは 夕暮れ時 私のたましいの 心棒が 揺れているせいです
2006.06.22
コメント(0)
-
遺蹟のある情景
茅萱(ちがや)そよぐ丘で 遺蹟を発(あば)くのは誰 赤茶けた地肌に 眼窩さながら 鋭く穴をえぐったのは誰 そっちの穴から こっちの穴から ごっほ ごっほ 縄文人の咆哮がきこえてくる と思ったのだが 銅鑼のように 巨きな太陽は 千年 万年 真っ赤な顔して 丘を越え さっさと 海に堕ちていった
2006.06.21
コメント(0)
-
瓢箪
『 瓢箪 』 『ふるさともとめてはないちもんめ』 初夏 上弦の月を背に どこからともなく流れて来る 童唄を聞いたような・・・ 瓢箪は 思念のしずくを 一心に凝らせて 今日も 一回り大きくなった そもそも この瓢箪の出自は草莽 千成瓢箪を 旗指物に押し立てた 太閤秀吉も 尾張中村の百姓あがり とはいえ へちまでもない きゅぅりでもない そのことが瓢箪の誇りなのです 金ピカピカの 太閤の馬印を カンラカンラと響かせた それが瓢箪のご自慢なのです -瓢箪鯰などと虚仮にされてもー でもね 孔子さまのご本にも登場する この誇らしさ 『 賢哉回也。 一箪食、 一瓢飲、 在陋巷。 人不堪其憂。 回也不改其楽、 賢哉回也。』 思念のしつらえが ようように二千年を遡ったとき 上弦の月は 耿々として 瓢箪の面を 照らすのでした
2006.06.20
コメント(0)
-
夏・断章
<少年> 土手いっぱいのスカンポ野原 麦藁帽子が歩いてゆく 口笛を吹いて歩いてゆく <ギョーギョーシ ギョーギョーシ> よしきりが鳴いている 蒲の穂を 揺らすほどの 風もない 水面に釣り糸を垂れながら 老人は考えている 幸福って何だろう おとな達のいう幸福など まやかしかも知れないけれど 少年は幸福なんだろうな 海星(ヒトデ)やら やどかりを 見つけるだけで 幸福なんだよ きっと 水門のあたり 海辺の方へ 麦藁帽子が歩いてゆく ブリキのバケツをぶらさげて 口笛を吹いて歩いてゆく < 時> 霧か雲かと 見まがう なかぞら 巨大な「いとまきえい」が 音もなく 泳いでゆく -ああ 「時」がまたやってきたー かたわらの山守がいう あのものは かたときも停泊することなく いつまでも どこまでも 航行をつづけるらしい 春から夏へ 季節から零れ落ちた かすかな夢のはざまに 「いとまきえい」は 鮮烈にも現われ やがて おぼろな視界を 消えて行ったが 山々の緑は そのとき 少しずつ 翳り始めたようだった
2006.06.19
コメント(0)
-
水引草の咲くなべに
水引草の咲くなべに 山あいに湧き出す 天然の水が飲みたいという 娘は理科教師 息子は現代医学を研修中 それでも その子の母である妻は 病に効く霊水の存在を 信じているらしい 国分寺 泉涌寺 佛性寺 寺のつく地名が多いこのあたりは 昔は聖地だったのかも知れないね 泉涌寺から車で山路をたどり 木立をくぐりぬけ 佛性寺のだらだら坂を上りつめると 水汲場に出る 泉とも涌井とも言えそうな 清冽な水の一滴一滴は すでに自然の摂理として 生命を宿しているのか ああ 樹林のあわいを 夏果ての太陽光線が 幾条もの帯となって 射し込んでくる そう あの日も 病室の窓辺には 陽の光が 斜めに射し込んでいた 「これが癌病巣です」 おまえが喪失したばかりの 片方の乳房は おまえの生命を乖離し 丼一杯大の物体と化し それは 朱に染まって ゴム手袋の 外科医の手に委ねられていた ( あれから三年 あの日の いや あの日から連続する おまえの痛みや苦しみを 真実おれの痛みや苦しみともして 共有し合ったろうか ) 今は ただ 素直に信じて この水に 賦活の力を与え給えと 祈ることぐらいは出来そうだ それに このあたりの森の空気は 青葉のアルコールと 青葉のアルデヒドが 充満していて きっと 身体にいいと思うよ たやすいことだよ ポリ容器三杯の水が やがて なくなれば また 二人して 汲みに来ればいい der Brastkrebs(乳癌) こんな言葉はもう忘れよう - ああ そこらいっぱい 水引草が咲いているね ー
2006.06.17
コメント(0)
-
睡蓮
(睡蓮) スケッチの記憶はうすれていたのだが 彩色しようと思う頃には 睡蓮は忘れず花開いてくれていた
2006.06.15
コメント(0)
-
馬酔木
万葉集ゆかりの土地には、たいてい万葉植物園 がある。小さな木札に植物の名を記し、その植物 が詠みこまれた万葉の歌が表示されている。 ここは、植物園ではなく、学研都市の大通り。 さすが学研都市というべきか。ここでは木札では なく、黒御影の横長で小ぶりな石碑に、万葉の歌 が刻彫され、かたわらの木札に英訳が記載され ている。 例えば、大通りの歩道沿いに植栽された馬酔木 (あしび)の木の場合はこのようになっている。 <和文> あしび 磯の上に 生うるあしびを 手折らめど 見すべき君が ありといはなくに (大伯皇女) 巻二 一六五 <英文> (Japanese Andromeda) I would break off a branch Of the blowing staggerbush Growing on the rocky shore; But no one says he lives To whom I would show it! ( princess Oku 2-165) Andromeda(アンドロメダ)はギリシャ神話にでてくる Cassiopeia(カシオペア)の娘で、海獣の人身御供 にされようとしたのをPerceus(ペルセウス)に救わ れた。 天智天皇の皇女大伯は、斉宮として伊勢神宮に遣 わされ、弟大津皇子とともに悲劇的な生涯を終えた。 こんなことから、大伯皇女がアンドロメダになぞらえ られたのだろう。 いずれにしろ、国民的古典文学の勉強にもなるし、 英語の学習にも役立つのだが・・・・・ 市民の関心があまりないのか、行政の管理が行き 届かないのか、折角設置された石碑も英文の木札 も、雑草が覆いかくし、道ゆく人々に一顧もされない のは残念なことである。
2006.06.15
コメント(0)
-
はまなす
(はまなす) ゆるゆると 砂丘にかげろう揺れ 浜茄子の群れは 一斉に 生命の讃歌を謳いはじめた 「はまなすのこと」 はまなすはバラ科の落葉低木。寒い地方の海岸に 自生している。夏、大きな赤いかおりの高い五弁の 花が咲く。森繁久弥・詞曲 加藤登紀子が歌う「知床 旅情」が懐かしい。 知床の岬に はまなすの咲く頃 思い出しておくれ 俺たちのことを 飲んで騒いで 丘に登れば はるか国後に 白夜は明ける 因みに、皇太子妃雅子さまのお印は「ハマナス」である。
2006.06.13
コメント(0)
-
いま読みたい本
いま読みたい本 1; 『 シャガールと木の葉 』 谷川俊太郎 集英社 「歴史が決してとらえることのできないこの今 誰かがどこかで詩を書いている」(この今) 現代詩の第一人者のこの詩集は、必読の 一冊ではないだろうか。 2; 『 背負い富士 』 山本一力 文芸春秋 本邦 侠客の雄 ご存知清水次郎長伝。 山本一力の時代小説は、山本節とも言う べきテンポのよさ、ストーリー展開の意外 性等、 面白さではピカ一である。
2006.06.13
コメント(0)
-

朱雀門
(朱雀門) 春の風に乗って 海を越え その日 朱雀門にも黄砂が降っていた
2006.06.12
コメント(0)
-
愛・賛球
今日も聞けるだろうか < 六甲颪に颯爽と 蒼天翔ける日輪の 青春の覇気美わしく > 詩人佐藤惣之助作詞 「長崎の鐘」や「君の名は」を作曲した 古関裕而作曲になる<六甲颪> ! 話は十年前にタイムスリップする 阪神タイガースは1985年の優勝以来 ずっと長期低迷に喘いでいた 吉田監督以後 村山 中村 藤田と 監督は交代してもチームが浮上する ことはなかった そのころの話 『たこ焼き』 1985年秋 屋台のたこ焼きにも勢いがあった 「おっちゃん たこ焼きおくれ」 「へーい にいちゃん たこ焼き一丁!」 「おっちゃん 阪神のカワトーによう似とんな」 ぽよよんとした顔つきのおっちゃんが 相好くずして喜んだ それもその筈 阪神タイガースは破竹の勢いで セ・リーグ首位を走っていた あれは見事やったなー 開幕早々 甲子園での対巨人戦 クリーンアップの三連発 バースのスリーランに始まり 掛布 岡田 どれも バックスクリーン直撃やった 十月半ばには バース52号 掛布39号 岡田34号 ホームランの山 山 山 ライオンズ相手に とうとう日本シリーズも優勝してもうた <もう あんなこと二度とないんちゃうか> 「阪神 たこやき ストリップ」 「巨人 大鵬 卵焼き」 そんな悪口どうでもいいわい わし 華のある阪神好きやってん たこ焼きも好きやった たこ焼きには丸っこい夢があったんや それがどないや 1995年秋 「えーい カワトー出さんかい」 サントリー・モルツのコマーシャルが いくら叫んでも あわれ 川藤は 十年前の栄光だけを引きずって 巻き戻しのフィルムの中では すっかり色褪せて見えるではないか -額縁ショーやあらへんでー 「おっちゃん たこ焼きおくれ 景気どないやねん」 「さっぱりやなー」 「タイガース 今年もあかんなー」 そのころ九月になっても十月になっても 阪神タイガースは セ・リーグ最下位に低空飛行をつづけている まあ 今年もしゃあないわ 来年こそは 「ガンバリヤー」 しまいに どつくで ホンマ そして 2003年 星野監督の二年目 タイガースは18年ぶりに悲願のリーグ 制覇を果たした。さらに2005年 岡田 監督の二年目もリーグ優勝。今年こそ 日本一になって<六甲颪>の大合唱 をききたいもの。
2006.06.12
コメント(0)
-
アンモナイトの季節
ロボク・リンボク・フウインボク 大地の褶曲に 原始の植物生い茂り 海にアンモナイト 湖沼 に恐竜が跋扈する そんな季節の何万世紀を 潜り抜け いま僕の眼前に一個のアンモナイト 化石がある 硬い無機質の光沢は冷たく 太古 の海の神秘を湛え そいつが突然に僕に向か って怨嗟の一言を吐きかけた < おまえ 人間よ 俺さまの海をもとどおりに して返してくれ > 何と応えたらいいのだろう 僕はきっと仮想の 世界に迷いこんだのだ これには深い寓意が ある とつおいつ僕は考えていた そのころ 列島を紅に染めた あの桜前線は とっくに北上していた 愛でるべき花はすでに なく 慈しみ深い花守はもういなかった 酷暑 の夏を前にして 人は「美学」はいうに及ばず 「哲学」や「理念」をもすっかり喪失していたと もいうが あるいはこの国には 「美学」を語 ろうにも また「哲学」や「理念」を語ろうにも すでに範とする一冊のテキストすら 見つから なかったのやも知れぬ 人は己の内なる狂気 を 外なる狂気に仮託して 能事足れりと信じ ていたのだが 一切合財をただ紅の色に呑み 込んで 桜前線はひたすらに北上をつづけて 列島は間違いもなく 断罪のような炎天の夏 を迎えようとしていた 季節が過ぎ 例外もなく空白もない時空の極限 から しらじらとした蛍光を放ち 触手を戦かし アンモナイトの大群が この世に甦ったとしたら そんな季節には 人はもはや生存していないの だろう 輪廻転生は 演算不能の周期でやって くる 仮想のレアリテの中を 人の季節の閉塞 を突き破って
2006.06.08
コメント(0)
-
二十一世紀日乗
日記・日録・日乗・ブログ 遥かな 白神山地のブナの原生林 アカゲラは元気か それが気懸りだ 秋が深まり 落ち葉の雨が降りしきり 地上に降り積もり はらはらと降り積もり 百年 二百年降り積もり ある日 樹齢二百年のブナの巨木は 「どおー」と倒れる それは 「ばったり」というようなものではないだろう 正に 「どおー」と己の生を全うした頃 種子が次世代の新しい生命を育んでいるだろう 降り積もった落ち葉の腐葉土に 幼年のブナはすくすく育ち やがて青年から壮年へと 原生林の輪廻の時間は 清澄だ が 重い 死について考えている 例えば 北村透谷 自殺 川上眉山 自殺 生田春月 牧野信一 田中英光 原 民喜 久保 栄 芥川龍之介 自殺 自殺 自殺皆自殺 火野葦平 有島武郎 太宰 治 自殺 三島由紀夫 自決 川端康成 江藤 淳 自殺 自殺 自死はいさぎよい が 自死を否定し生を全うすること もまたいさぎよい 時代は二十一世紀 人は 日を重ねる 歳を重ねる 永井荷風は 大正六年から昭和三十四年にわたり 「断腸亭日乗」を記録した 戦時下の軍部に対する非妥協の態度を 死の直前まで貫いた 遥かな白神山地の原生林 「どおー」と倒れるブナの古木のような そのような生を全うできるか 私はささやかな決意をした 日記・日録・日乗・ブログ 形 名称はいづれにしろ 記録を続けて行こうと 私の二十一世紀として
2006.06.06
コメント(0)
-
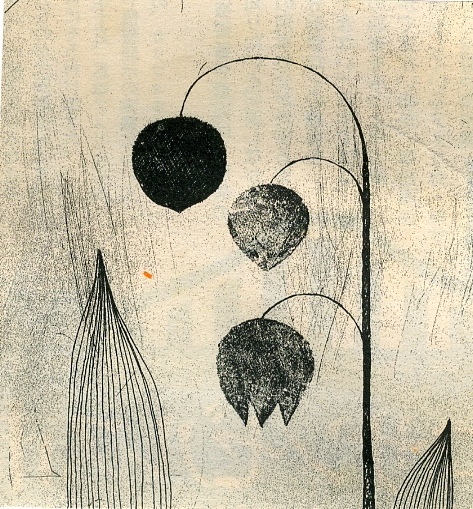
四角い旅
『四角い旅』 晴耕雨読 雨の降る日は 四角い旅に出る 四角い建物 四角い天窓 四角い書棚 四角い詩集を取り出して 四角いテーブルに 四角いページをめくる 伊東静雄を読む 伊東と戦争との関わりを読む <軍(いくさ)立ちすがしき友をみてのめば ゆたけくもはやわれら酔いにけり> 永瀬清子を読む 永瀬の女人への想い入れを読む <諸国の天女は漁夫猟人を夫として いつも忘れ得ず想っている 底なき天を翔けた日を> それから西脇順三郎を読む 西脇と一緒にギリシャへの旅をする 誰かが言った 「詩人」とは形容詞なのだと 彼女は「美人」であると言うのと同じで これは公の資格とは違うのだと 誰かが言った 詩人は「代理人」だと 政治家が私の政治的活動の「代理人」で コックは台所仕事の「代理人」であるように 詩人は私の「さびしさ」や「よろこび」 「腹立たしさ」の代理人のようだと それでも 形容詞的 代理人的詩人の 軍立ちする友への餞に共感し 天女とは諸国を遍歴し またギリシャ的抒情を味わい いっときの こころを 自由に羽ばたかせることが 出来たのだから この図書館で 四角い旅に 時を過ごした甲斐が あったというもの 晴耕雨読 雨の降る日は
2006.06.05
コメント(0)
-
厠考
『 厠(かわや)考 』 公衆便所でも ホテルのトイレでもよい 流し残しの他人様のババは きれいに流してから使いたい それは 厳然と峻別されなければならない 他人様のそれと わたしのそれは 一緒にごちゃまぜになっては困るのです わたしのペルソナの尊厳のために このことは非常に大事です もし 他人様のババが 便器の端にこびりついていたら 手に触れぬよう そっとトイレットペーパーで拭き取ります さあ これですっきりした 厠の神様にも感謝します これで ゆっくり排泄できます 厠の神様は 井戸神様や 竈(かまど)神様の兄弟で 一番偉い神様なのです 昔の武士は 馬上や 厠で 軍略やら 所領のことについて 想を練ったというではありませんか それほどに 厳粛な場所なのです ひそみに倣って わたしは わたしの ささやかな トイレ使用の セレモニーを守ります * トイレの詩で有名なのは、浜口国雄の「便所掃除」である。 浜口は、国鉄職員(1920~76)で、荷物輸送の専務車掌 を長く務めていた。「便所掃除」が書かれたのは、敗戦後の 混乱期にあたり、衣食足らず、礼節知らずで駅でも公衆便所 でもひどい汚しかただった。 ・・・・ 便所を美しくする娘は 美しい子供をうむ といった母を思い出します 僕は男です 美しい妻に会えるかも知れません この詩の終連は、「おおきなひろがりをもった男らしい 詠唱(アリア)です。」と詩人の茨木のり子が絶賛しています。
2006.06.02
コメント(0)
-
いま読みたい本
1 いま読みたい本のリスト でも6月中に読み切れるかな? 1 小池昌代 詩集『地上を渡る声』 書肆山田 2 若井敏明 『平泉澄』 ミネルヴァ書房 3 ジョン・ル・カレ 『ナイロビの蜂』 邦訳/集英社文庫 4 鍛代敏雄 『神国論の系譜』 法蔵館 5 嵐山光三郎 『悪党芭蕉』 新潮社 6 熊野純彦 『西洋哲学史』 岩波新書 7 井上宗雄 『京極為兼』 吉川弘文館 * 本屋で探すのも一苦労かも知れないが、リストアップしておけば そのうち必ず読む機会が訪れるだろう。
2006.06.02
コメント(0)
-
<愛>・農
ダラ豆を摘む なんで ダラ豆ゆうがか ようわからんが 多分 ダラほど生るからかも知れんな つる豆ゆうたり 千石豆ゆう人もおるわな 旧盆前から秋の彼岸過ぎまで 毎日毎日成るがやから 結構なこっちゃ 朝 暗いうちに起きて 鋏でチョキチョキ 籠に一杯摘んで 市場に持って行くがや 籠一杯で千円ぐらいのもんや でも 収入が目当てじゃないわ 早起きの習慣と 農の基本が大切なんや 嬶(かかあ)も死んでしもうたし 一日千円也のダラ豆摘みが いまのわしにとっては 無上の愉しみなんや そう わしの嬶はなあ 兄の嫁やったんや 昔はようあったこっちゃ 兄が南洋で戦死して 弟のわしが家継いで 兄の嫁もついでにもろうてしもたわけや そうやなあ うらなりの冬瓜みたい女やったけど そんでも 子供も三人でけたし 今となれば まあまあの所帯やったと思うとる 人はどう見とるか知らんが ダラ豆も人生も似たとこある 手抜きして莢のスジも取らんと煮たかて スジが口に残って うまいことない ダラ豆と油揚げと茄子炊いて食うてみい 高い銭出して食う料理にない なつかしそうな味がして うまいもんや 人生もダラ豆や 誠実で素朴がええ 不幸でないことが幸せやと思うてきた わしみたいな人間が これまで生きてこれたのも ダラ豆のおかげや
2006.06.01
コメント(0)
-
今日から6月
*** 6月の異称 *** 異名=水無月 異称=涼暮月(すずくれづき) =蝉羽月(せみのはづき) =鳴神月、松風月、夏越月(なごしのつき) =葵月、常夏月(とこなつづき)、風待月(かぜまちづき)等々。 われわれ日本人が古来から感じて来た、季節に対するこころの 在り様が表われている。 (おわり)
2006.06.01
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1










