2010年12月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
2011年 あけましておめでとうございます
雑煮の為に鍋のアク抜きしてたら年が変わってしまいました。おかげで今年のお雑煮は美味しく・・・皆様におかれましてもいい年になりますように。
Dec 31, 2010
コメント(6)
-
ロバート・フリップ、ステージ活動引退か?
既にご存知の方も多いでしょうが、今一度。DGM LIVE!のFripp氏の日記にプロフェッショナル・ミュージシャンとしてのラストステージを終えた旨の記述。http://www.dgmlive.com/diaries.htm?entry=18729その後、日記が更新されておりませんので、事態がどう推移するのか見守るしかないようです。「私ももう63だよ」とかボヤキつつも2008年のキング・クリムゾンの復活ステージ後の事などにも触れていますね。せっかくトニーさんが戻ったラインナップなのに。ただ全面的な引退になるとは限りませんし、ステージに立たなくとも何かしらの情報の発信が今後あると思われます。2008年のミニツアー前にも「もう長い期間ロードに出るのは無理」と言っていたので、仕方が無い部分もあります。並みの演奏能力では演奏できない演目ばかりの活動でしたからねぇ。それにフリップさんの心の支えになっていたウサギも死んでしまいましたし。演奏活動をしなくなったとしても日本にはまた遊びに着ていただきたいですね。まだフリップ先生の味わっていない和のスイーツがたくさんありますからw
Dec 30, 2010
コメント(0)
-
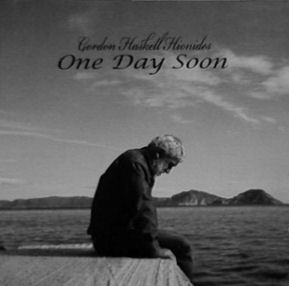
Gordon Haskell Hionides - One Day Soon (2010)
立ち退きとそれに伴う引越しやらなんやらゴタゴタで、新譜を落ち着いて聴ける見込みが無い為、ゴードン・ハスケルの新譜「ワン・デイ・スーン」を買い控えていたのだった。引っ越し先の片付けもひと段落し、ようやくいくらか落ち着いてきたのでネット購入。今回はHMVで買ったがAMAZONにしてもこちらにしても、輸入盤在庫の無い場合は毎度の事ながらだいぶ待たされる。後に注文した海外通販の方がとっくに3品届いてるのにそれから5日ほど遅れて届いたw 夏にハスケル氏の新譜が出ると紹介しておきながら、紹介した本人は購入が真冬ってどういうことやねん?とか突っ込みはご勘弁願いたい。引越しでバタバタしてる最中じゃ聞いていられないし、もしも紛失したり割った日には泣くに泣けませんからねぇ。と私的な問題はいい加減にして、作品の紹介へ。Gordon Haskell Hionides - One Day Soon (2010) 発売レーベルはFULLFILL、ユニバーサル。現在ハスケルが住んでいるギリシャの島の桟橋に腰掛けたモノクロ写真が正面を飾っている。虚飾の無い今の自分そのものと言う事だろうか?裏面には岩場で裸のまま海を眺める後姿が載せられている。全10曲、すべてがハスケルのオリジナルで占められている。メディアプレイヤーで見ると分類がフォークwケースを開けるとギターやベース、ウッドベースを抱えるハスケル、ネコと戯れるハスケル、農業を共にする愛妻と慎ましやかな生活を感じさせる写真などがコラージュされている。そう、今回の作品、ハスケルも積極的に楽器をプレイしているのだ。しかもベースはかなり弾いている。パートによっては明らかにウッドベースとか細かく使い分けてる様子もある。タイトル曲のOne Day Soonのみワルシャワでレコーディングされ現地ミュージシャンの起用でベースを弾いていないが、その他のベースはたぶん彼自身のプレイだと思う。昔から彼のソングライティングにおける特色であるジェントリーで暖かな作風の曲も確かに含まれてはいるが、シャープでタイトなリズムにのせて男の哀愁を唄うスタイルも。ここには40年前に2枚目のソロを作った時の様な、周りの成り行きにまかせて、ミックスダウンにも立ち会わなかったような人間はいない。細部まできっちり練りこんだタイトなサウンドと自信にあふれた唄いっぷりは、CDを聴く前に思い描いていた想像より遥かにカッコイイ。伊達に45年以上プロミュージシャンやっていませんなw収録曲 1. THE FOOLS OF YESTERDAY 2. SOME SINS (I SHOULD'VE KNOWN BY NOW) 3. FOREVERMORE 4. THE WAYS OF THE WORLD 5. ONE DAY SOON 6. WOUNDED TIGERS 7. GOOD MAN DOWN 8. SUNSHINE SHOES 9. HAPPY TO BE 10. THE FEAR IS GONE All songs written by Gordon Haskell Hionides.Produced by Gordon Haskell Hionides and Bob Kennedy.Gordon Haskell : bass guiter, guitar, vocals.Bob Kennedy : electric guitar, piano, drums.と、基本的に表題曲以外はボブ・ケネディとの二人で制作されている。派手さはありませんが滋味豊かな作品です。ハスケルの渋すぎるベースプレイもなかなかでおすすめですねぇ。夜のドライブのお供に是非(意味不明)Gordon Haskell Hionides / One Day Soon 輸入盤 【CD】価格:2,405円(税込、送料別)ところでHionidesってなんて読むのでせう・・・???全くわかりませーん!!どなたか教えていただけませんでしょうか?みなさま、良いお年をお迎えください。ではまた来年♪
Dec 29, 2010
コメント(1)
-

Shyster - That's a Hoe Down / Tick Tock (1967)
キングクリムゾン以前にゴードン・ハスケルのいたバンド、Les Fluer De Lys ル・フルール・ドゥ・リー(ス)(英語圏ではフラードゥリー) 。今まで何度かこのバンドの事を取り上げてきたが、今回は彼らが別名バンド(Under name)で発表した1967年シングル。激しいメンバーチェンジで丁度3人編成になったFleurs、ゴードン・ハスケル(ベース)にキース・ガスター(ドラムス)、そして前任ギタリストが抜けた為、道で拾われたブリン・ハワース(笑)。プロデューサーで事務所社長、いわゆる親分であったフランク・フェンターはバンド自身を売り出すよりも、バンドをこき使ってバックバンドやセッションワークで日銭を稼がせるほうが10倍儲かると言いながら実践し、Fleursのメンバーは夜はバンドでギグに出て、昼はレコーディングやらデモ作りなどさせられていたようです。せっかくFleurs名義で数枚シングルをだしてたのにもかかわらず、いくつかの変名でシングルを出したのは、レコード会社からフェンターが金を引き出すために使った手口だったのかもしれません。レコーディング慣れしてない新人バンドを教育して原盤製作するよりも、小器用な連中を使ってあたかも新たなバンドの様に出す方が手っ取り早く、また子飼いのバンドマンなので融通も利こうというものです。Shyster - That's a Hoe Down / Tick Tock (1967)Polydor56202作者のHammondとはアルバート・ハモンドの事で、この曲は67年当時ハモンドが楽曲提供していたオーストラリア人の歌手Lynne Randell リン・ランデルの為に書かれた曲。リン・ランデルのオリジナルヴァージョンはこちら。Lynne Randell-That's a Hoe Down 最新ヒットを早速カバーしたFleursですが、変名のShysterとはいかさま師とかいんちき弁護士とか無茶な名前。演奏もアコースティックギターとベースとドラムスのトリオ演奏でずんちゃかずんちゃか♪かなりコミカルな演奏に様変わりしております。B面のTick Tockと同じくVocal:Gordon Haskellで曲の最終バースではスキャットマンジョンの様なスキャットまで披露しています。(当然あそこまで上手くありません。というか下手w)曲の仕上がりがなんともインチキくさいのでShysterという変名にしたのではないかと思えるほどです。ただしサウンドプロダクションはかなりよく、1967年当時としてはかなり音質がよい部類と言える出来。これはB面のTick Tockにも言えます。ブリンのかなり逝ってしまった感のあるサイケなギターサウンドにしてもリズムセクションのサウンドにしてもブンブンと唸りを上げて聞こえてきます。シンプルなスリーピースのバンド編成なのでかえってレコードとCDで音の違いが出やすいようです。That's a Hoe DownがCD:Reflectionsに未収録なのは、アルバート・ハモンドの楽曲なので、版権の問題が出たのでしょうか?ブリンのアコギ、結構イイ音させているんですけどねぇ。Les Fleur De Lys音源を寄せ集めたCD:Reflectionsは、マスター起こしの音源ではなかったのか、音質がかなり厳しいですね。ただ60年代後半だったことを考えるとあの音の悪さも時代性を感じさせて趣がありましたが、実際のシングルでの音質を聞いてしまうと圧倒的な質感の違いに「やはりアナログ、それもシングルはいいなぁ」と痛感してしまいます。シャロン・タンディのリマスター音源CDも素晴らしい音でしたが、フルールドゥリーのリフレクションズもリマスターして出せたなら、きっとまた評価が変わってくるかもしれません。YoutubeにTick Tockがアップされていますが、画像がシングルの映像なのに音はCDからのモノを使用してる様でギターやドラムの抜けが悪いです。しかしどの様な曲を彼らがやっていたかご参考までに♪Les Fleur De Lys - Tick tock余談:と言うことで最近秋葉原のジャンク屋で2万円ほどで購入したNEC PC-VL300/MG2Yで録音♪2万と言っても2年前のVISTA搭載モデル、まだまだ充分使えます。ただファンがうるさかったので中身を出して、前のユーザーが溜め込んだ大量の埃を掃除機で吸引、他もクリーニング。ついでにメモリも倍増して4Gに。OSが感知しない3,2Gより後の領域はRAMDISKにして使っています。んでもってレコードを96KHz24bitで録音するのにはまっています。これは病み付きになりそうです(自爆)いやーやっぱりレコードいいっす。最高です。
Dec 25, 2010
コメント(1)
-
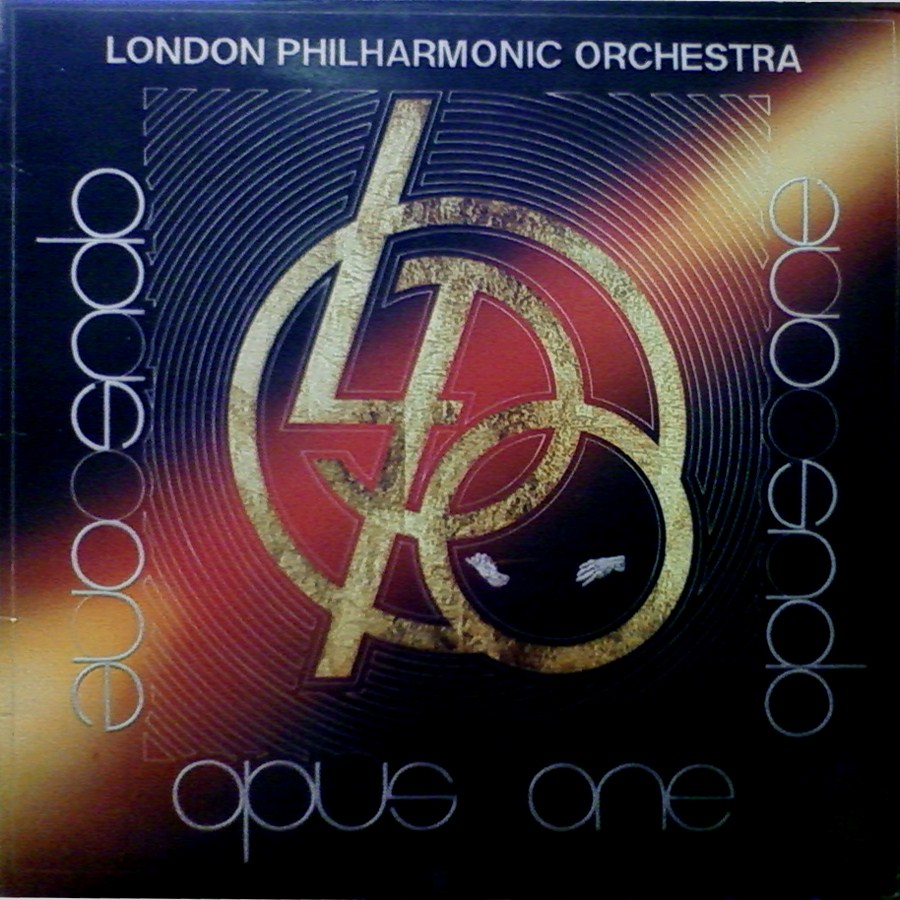
London Philharmonic Orchestra / Opus One (1980)
今回はAndrew McCulloch「最後の参加作品」と言われているアルバムです。面白いことに最後のセッションで彼と一緒に参加したのは、Greenslade グリーンスレイド時代の盟友Dave Lawson デイヴ・ロウソンとMartin Briley マーティン・ブライリー。なぜかというとグリーンスレイドでもプロデューサー/エンジニアとして深く関わっていたグレッグ・ジャックマンがプロデューサーに名を連ねているという点が関係しているのでしょうか。製作当時、世はニューウェイブ真っ只中の音楽業界。そんな時代にクラシックオーケストラとベテランロックミュージシャンの協演。日本で話題にすら上らなかったのも無理からぬことでした。曲目は以下のとおり。London Philharmonic Orchestra / Opus One (1980) PHILIPS 6308 317-SIDE ONE-Jumpin' Jack FlashWe can work it outI can see for milesBlowin' in the windAll you need is love -SIDE TWO-Good VibrationsThe House of Rising SunIf I were a carpenterこのアルバムの中心人物Andrew Pryce Jackman(2003年没)といえば、YESのTormatoやクリス・スクアイアのFish Out of WaterなどにかかわったYes人脈人物で作編曲家/キーボーディスト。製作途中から険悪な状態となったイエス「トーマト」において、彼のオーケストレーションを施したONWARDはそんな状況を感じさせない美しい名曲でしたね。日本の市場では谷村新司作品の編曲でも足跡を残しています。このアルバムでは兄弟のGregg Jackman(プロデューサー/エンジニア)とのジャックポットミュージック制作と記載されております。ジャックマン兄弟の父ビルはビートルズのアルバムSgt. Pepper's Lonely Hearts Club BandのWhen I'm Sixty-Fourにおいてクラリネット演奏をしてたそうで、他の兄弟や息子たちも指揮者や演奏家といういわゆる音楽一家だとか。アルバムの内容は、アンドリュー・ジャックマンのアレンジ・指揮によるロンドンフィルとロックミュージシャン達の競演作品で、ロック名曲のオーケストラ演奏というその昔ジョージ・マーティンが創めたスタイルをより一層推し進めた印象。発売は1980年ですが、製作時期は不明。アレンジの手間隙や、音を聞くと判るのですが参加ロックミュージシャンが、LPのA面とB面で違っているようです。というのも多くの曲が切れ目無く次の曲へと交響楽の様に数珠繋ぎになっているためです。元グリーンスレイド勢の3人は、サウンド的にB面で演奏している模様で、特徴的なアンドリュー・マカロックのドラミングが、ビーチボーイズのグッドバイブレーションとアニマルズの朝日のあたる家の2曲の盛り上がり所で弾けています。またデイヴ・ロウソンの独特なシンセソロが一緒にウニウニしているのも和みます。デイヴ・マタックスやフランク・リコッティ他の参加ミュージシャンについては下記の写真で。この作品のあと、グリーンスレイドの残党3人は各自バラバラの道へ。ロウソンはZEDやセッション活動をしながら、ジョン・ウィリアムスの映画音楽へ参加など本格的に劇伴へ活動を移していきます。ブライリーはソロシングルがスマッシュヒット、シンガーの道へ。そしてマカロックは音楽界から去り、子供時代からの経験を生かしヨットマンとしての人生をスタートさせたようです。余談ながら、ジャケット表面には金箔で作られたロゴタイプの写真がドーンと配されていますが、その中に二つの傷のようなものが見て取れると思います。実はこれ、指揮者の手なんですね。CD化はしてないアルバムですが、もしこのジャケットのまんまCDサイズにしたらなんだかごみのように見えてしまうかもしれませんね。ちなみに主役のアンドリュー・ジャックマンさん、指揮やアレンジだけではなく、ラストに歌も披露しています。
Dec 25, 2010
コメント(0)
-

おひさしぶりです、復活しました♪
引越し後回線開通に手間取り、かつネットワーク構築段階で機器トラブルが重なり難儀してましたが、やっと安定してきました。調整最後の最後でモデムの不調で回線が断続的にブツブツ切れる不具合とその原因究明にああだこうだと3日ほどかかる始末。 回線開通までの間、仕事のほかにカセットデッキのベルト交換やら、古いビデオのBDアーカイブ化とか、もちろん部屋の片付けなどやることは様々ありましたし、立ち退いた家の解体までの期間に問題が起こらぬようにちょくちょく見回りもしてたり。 とまあ個人的な話はこんなもんで。昔のステージ演奏のビデオとかも出てきたのですが、80年代前半のビデオカメラのマイク音声なので非常に音が悪い。しかもリミッターがかなり掛かって、会場ノイズも拾いまくってました。 今回引越しでその演奏をナギ先生らにやってもらったミキサーからライン録音した倍速カセットマスターからダビングした音声が一曲分だけ発見されたのです。 カセットデッキも直してみるものですねw 忘れていたこんなモノが見つかるわけですから。さすがに4半世紀前の音源なので一部傷みがありましたが、デジタル音声ソフトの力を借りて復元を試してみることに。 まず24bit/96KHzでPCに録音。その音声のテープ損傷での音量ふらつきをちまちま修正。4帯域に分けて、楽器の質感を今一度当時の会場PAの様に復元。しかし、ここでひとつ問題が!そう、ビデオの映像とカセット音源のスピードに少しずれがあるのです。ということでビデオ音源も取り込み、波形を見ながらキーポイントのタイミングをメモ。カセット音源の時間をどの程度デジタルで引き延ばすか調整しピッタリ合わせる。当然そのあとピッチを微調整、カセット音源側を21セント落とすことでほぼ解決。ビデオ音声にはライン音源に足りない一部楽器音が含まれているため、こちらも修正して両方の音を最終的にRadioLineに取り込んでバランスをミックス。 最後にビデオソフトで音声と映像をシンクロするように何度も調整し完成。古いビデオで音声も悪くてあまり見る気もしなかった映像ですが、音声が改善すると少し見やすくなったように感じます。 ちなみに私の演奏は見切れている為映像には出てきません。あしからず♪そして遅ればせながらメリークリスマス。ではまた。
Dec 24, 2010
コメント(1)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-
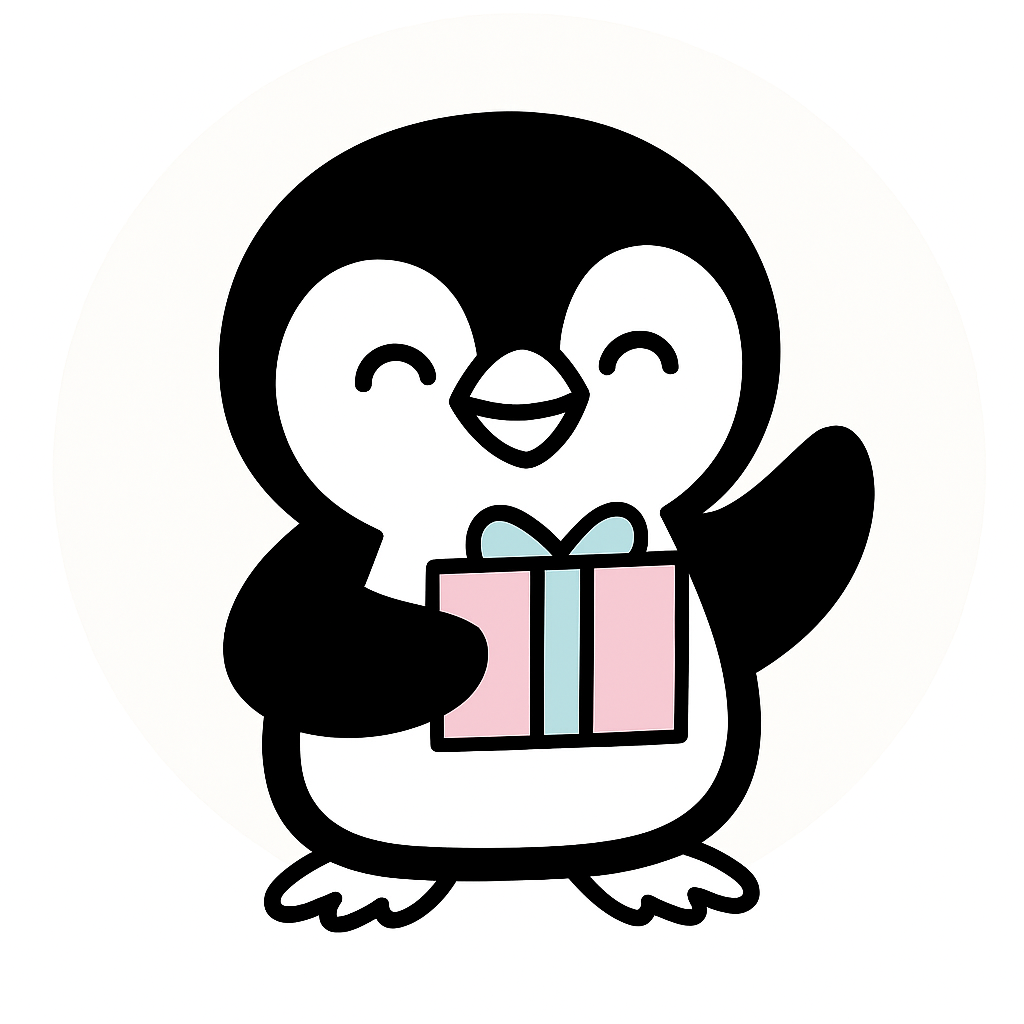
- いま嵐を語ろう♪
- 嵐コンサートツア決定! ARASHI LIVE…
- (2025-11-22 19:52:07)
-
-
-

- オーディオ機器について
- VALVOのE2dという真空管
- (2025-11-17 21:06:01)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-







