2006年11月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
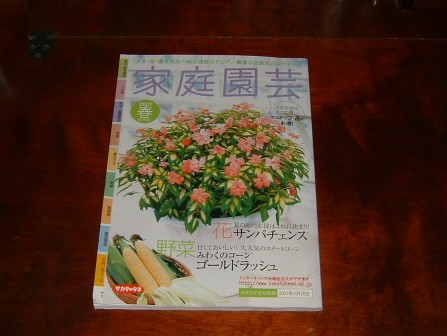
サ○タのカタログが届く。
一昨日、サ○タのタネからカタログが届いた。私は中学のころからカタログ通販を楽しんでいるが、新しいカタログを見るときのわくわくする気持ちは今も変わっていない。今ではネットで気軽に買い物が出来る時代になったが、カタログ通販の醍醐味は失われていない。他にはタ○イ、改○園、国○園のカタログを取り寄せている。 というわけで、今日の日記はこれにて終了。実は、先ほど長々と日記を書いていたのだが、いざ投稿という段階になってパソコンがエラーになってしまい、せっかくの日記がパーに・・・(泣)。ああ、新しいパソコンが買えるのはいつの日だろうか。。。
2006.11.30
コメント(8)
-

自宅の下仁田ネギ 収穫
11月22日の日記で紹介した自宅の下仁田ネギ。本当は霜が降りるまで育てておきたかったのだが、畑にもたくさん植えてあるので、自宅のものから先に収穫することにした。そしてさっそく今日の夜食のすき焼きに入れてみた。そのお味の方は・・・ウマ~~~~~イ(*^^*) なんといううまさ。長ネギみたいなスジっぽさはなくてとてもやわらかく、味の方もくせがなくてとろけるような甘さ。しかも、軟白部だけではなく葉っぱもすべて入れてみたのだが、これが今までに味わったことがないほどの美味さ。下仁田ネギの葉っぱは太くて大きく、長ネギみたいに硬いイメージがあったのだが、まったくそんなことはなく、非常に柔らかくてワカメみたいな食感。実は私は下仁田ネギは過去に1回しか食べた記憶がないのだが、こんなに美味いものだったのだと改めて知った。 自宅のあんあ悪条件でこんなに美味しい下仁田ネギが出来たぐらいなので、畑に植えてあるものはもっと美味しいのではないかと期待している。
2006.11.29
コメント(4)
-

Blc. ノーマンズ・ベイ
往年の名花、Blc. ノーマンズ・ベイ・ヘラクレス(Blc. Normans Bay Hercules FCC/RHS)が開花した。この品種は今から60年前の1946年に登録された古い品種で、カトレア交配種の歴史の中では大変有名なもの。私はそのオリジナル株を所有している。 最新の交配種に比べるとやや見劣りするのは否めないが、力いっぱい咲かせたものは今でも本当に見ごたえがある。そしてこの個体は芳香を持っており、現在私の部屋にはその甘い香りがいっぱいに漂っている。まさに天然の芳香剤と言ったところか? 今日の私は、お酒とこのカトレアの美しさとその香りにたっぷりと酔いしれている(笑)。
2006.11.28
コメント(2)
-

富士早生キャベツ 発芽
今年はダイソ○で買ったキャベツのタネを蒔き、小ぶりながらも順調に生育(10月28日の日記参照)、そして先日収穫を終えた。このキャベツ、有機栽培だっただけに非常に味が良くて、生で食べても甘くてまろやか。市販品とは全然違う。しかも「芯」までおいしくいただくことが出来た。え、キャベツってこんなに美味しかったの?と改めて思ったほど。この美味しさに文字通り味をしめて(笑)またキャベツを育てることにした。品種はア○リヤの富士早生。 11月12日にタネを蒔き、無事に発芽してくれた。収穫は来年の春の予定。実は前回のキャベツは化学肥料を隠し味程度?に使っていたのだが、今度は有機100パーセントで育てて美味しいキャベツを収穫したい。
2006.11.27
コメント(2)
-

ファビンギアナ・オオヤマザキ
カトレアの往年の名花、ファビンギアナ・オオヤマザキ(C. Fabingiana Ohyamazaki)が開花した。これは今年の6月ごろに購入してもので、まだ株がしっかり出来ていないために1輪しか咲いていないが、本来は中輪多花性の品種である。 個体名が「オオヤマザキ」なので、あの伝説の大山崎山荘で栽培されていた個体ではないかと思う。大山崎山荘とは、とある実業家がかつて所有した山荘のことで、大阪府との境界に近い京都府大山崎町にある。ここでは大正時代から昭和前半まで洋蘭の栽培育種が盛んに行われ、いわばわが国の洋蘭栽培の草分け的存在。所有者が昭和29年(1954年)に逝去された後、山荘の所有権は何度か変わり、現在はアサヒビール大山崎山荘美術館となっている。 当時はメリクロンなどの大量増殖の技術がないため、洋蘭は途方もない高値で取引されていたらしい。カトレアの名花を手に入れるために、月給の何倍もの金をはたいたという実話もあるぐらいである。そんな時代に多数の洋蘭を海外から多数取り寄せて栽培していたとは、その熱意は想像を絶するように思う。 そして今では増殖技術が発達して洋蘭は安価に園芸店に出回る時代になったのだが、その反面、夢がなくなったような気がする。かつて、洋蘭を手に入れるために愛好家たちがそれこそ血眼になって苦労した時代のことを思うと、ああ、そういう時代があったのだなあと実に感慨深い。それに引き換え、今はなんと夢のないことか。あの夢のあった時代はもう二度とやってこないかも知れない。せめて当時のロマンを身近に感じることが出来たらと思い、往年の名花を育てている今日この頃である。 ・・・今日の日記はちょっとマニアックすぎたかもしれない(笑)。
2006.11.26
コメント(3)
-

ヤーコン 収穫♪
貸農園に植えたヤーコンを前回紹介したのは9月20日のこと。あれからさらに2ヶ月が経って、今日は6株の中の1株を収穫した。 ご覧のとおりなかなかの出来栄え。今回で4回目の栽培だが一番出来がいい。ヤーコンは生で食べるとナシのようなサクサクした食感と甘さを楽しめるが、収穫後一週間以上寝かさないと甘みが出てこない。以前、収穫直後に食べたら何も味がしなかった(笑)。なお、私はヤーコンは天ぷらにして食べたこともあるが、「たくあん」のような食感とサツマイモみたいな甘さを楽しむことができた。
2006.11.25
コメント(6)
-

皇帝ダリアの根元
貸農園の畑に植えて旺盛な生育を見せた皇帝ダリア。強風に何度も倒された末にようやく開花したのはちょうど2週間前。大きな花を何輪も咲かせて、貸農園の中でもひときわ目立っている。が、今回紹介するのは花ではなく「根元」。 今年の5月に植えた小さな苗が、わずか半年あまりでペットボトルをはるかに超えるほどの太さになっている。ここまで来るとまさに「木」である。すさまじいぐらいに生育が旺盛なので、植えるときには場所を考慮しなければならない。私の皇帝ダリアは畑の肥えた土で旺盛に成育し、見事な花をたくさん付けてくれた。 ただ、せっかく豪華な花を楽しませてくれたのだが、あまりにも木が大きいために周囲の作物が日照不足になっているのが悩み。花が終わったらすぐに伐採する予定なのだが、ここまで太いとノコギリが必要になりそうだ(笑)。
2006.11.24
コメント(2)
-

ハワイアン・ウッドローズ ご臨終・・・
黄色い花が咲く朝顔 と題して8月29日の日記で紹介したハワイアン・ウッドローズ。生育はきわめて旺盛で、雑草のように蔓を伸ばしていた。が、本当に雑草と間違われたのか、大家さんに根元を刈り取られてしまった(泣)。 このハワイアン・ウッドローズは日照時間が短くならないと咲かないため、冬も暖かい地域でないとまず開花は望めない。が、とにかくこれでもかというほどよく生育してくれたので、もしかして気まぐれで一輪ぐらい咲くか、少なくとも地上部が枯れても根っこだけは越冬してくれるのではないかと期待していたのだが、これで計画がパーになった・・・(泣)。大家さんは私が園芸好きだとよく知っているはずなのだが、葉っぱがモミジ型なので雑草のヤブガラシと間違われたのかもしれない。
2006.11.23
コメント(2)
-

自宅の下仁田ネギ その後
9月29日の日記で紹介した自宅の下仁田ネギ。余った苗を軽い気持ちで自宅アパートのわずかなスペースに植えたのだが、今ではご覧のとおりの生育振り。 悪条件にもかかわらず、いかにも下仁田ネギらしい姿になっている。この電柱はアパートの敷地内にあるが、表通りとはまったく仕切られていないため、散歩中の犬にオシッ○を掛けられないかが心配。そして、ごく最近、この場所から画像の手前側のわずか2メートルしか離れていない場所に、見事に犬のウ○○が転がっていた(笑)。いや、笑い事じゃないか。こりゃ早く収穫した方がいいかも。
2006.11.22
コメント(6)
-

往年の名花 Pot. Medea AM/RHS
そろそろコートが必需品となってきた今日この頃、室内に避難させたカトレアがめでたく開花した。品種名はPot. Medea AM/RHS(メディア)。1946年に登録された往年の名花で、私が所有するものは貴重なオリジナル株。11月1日の日記で紹介した画像の右側の株がこれ。 このリップに入る大きな黄色い目がポイント。古い品種ではあるが、今でも見ごたえのある花を咲かせる。このメディアは品種として優れているだけではなく、交配親としても多くの子孫を残している。私はカトレアは原種と交配種の両方が好きだが、交配種ではこういった歴史的価値のある品種が特に好きである。まだメリクロンなどの技術の発達していなかった当時、先人たちがカトレアの育種に情熱を注いでいた時代のことを思うと胸が熱くなる。 この名花メディアをインターネットというメディアで紹介できることをうれしく思う。・・・ちょと外したか(笑)。
2006.11.21
コメント(0)
-

皇帝ダリア満開、のはずが・・・
11月12日の日記で開花報告をした皇帝ダリア。あれから1週間が経った11月18日(土)、畑に行ってみるとそこには満開になった皇帝ダリアの姿が。もちろんカメラを取り出して記念撮影。しかし・・・ 写りが悪すぎる・・・(^^;)。この日はうす曇だったのと、自分のデジカメ腕前が悪かったのとできれいに写らなかった。ああ、残念・・・。おまけに翌日の19日(日)は朝から雨だったので、畑に行けなかった。来週末まで花が持つといいが。 さて、そろそろデジカメを買い換えたいと思うのだが、その前にパソコンを買い換えなければ。私のパソコンはエラーやフリーズが多くていつもヒヤヒヤさせられる(笑)。デジカメを買うのはまだまだ先になりそう。はぁ・・・。
2006.11.20
コメント(2)
-

紫キャベツに挑戦
今年は2株のキャベツを栽培し、先日収穫を終えてさっそくお好み焼きにして食べたところ、有機栽培だっただけに非常にまろやかな味で、「芯」までおいしくいただいた。そしてこの普通のキャベツとは別に、紫キャベツの苗も1株買って植えたのが1ヶ月ぐらい前のこと。今では青々と(?)した葉を茂らせている。 キャベツなどアブラナ科の野菜にはアオムシがもれなく付いてくるが(笑)、この紫キャベツは植えた時期が遅かったせいか、今のところ無農薬でも特に被害はない。もちろんこれも有機栽培でまろやかな味を楽しみたいと思う。
2006.11.19
コメント(2)
-

スマトラオオコンニャクの成長差
11月15日の日記では、スマトラオオコンニャク1号が倒れたことを紹介したのだが、実はそれ以前に紹介したいと思って撮影していた画像がある。それがこちら。 画像の右側の小さい株が1号で左の大きい株が2号。肥料不足なのか葉の色がちょっと薄い。これは11月5日に撮影したもので、そのうち紹介するつもりでいたのだが、なんせ園芸ネタが多いもので(笑)、後回しにしているうちに1号が倒れてしまった(泣)。以前も紹介したが、去年の夏ごろの1号と2号の画像と見比べていただきたい。 この時点では1号と2号との大きさにそれほど差はなかったのだが、なぜか今年の夏の第2の成長期から大きく差が出てしまい、1号は去年と大きさが変わらず、2号は去年の倍以上に成長した。そして成長が思わしくなかった1号が倒れたのは先日お伝えしたとおり。とにかく育て方がよく分からないので手探り状態で育てているというのが現状。 さて、今までの季節は園芸ネタが多くて、毎日更新しても紹介しきれないぐらいであったが、これからの時期はネタが少なくなるのが痛いところ。しかし、毎日更新するのも大変なので、ちょっと休みたいというのが実は本音でもあったりする(笑)。
2006.11.17
コメント(4)
-

下仁田ネギに個体差
下仁田ネギの成長を前回紹介したのが10月19日のこと。収穫期が近付きますます順調に生育が進んでいる。植えた株数は記憶に間違いなければ70株ぐらい(実は正確に数えたことがない(笑))なのだが、その中でも1本だけ異様に生育がいいものがある。 この画像の中央の株だけがなぜかずんぐりむっくりして、他の株よりもひときわ太くて大きい。これはさぞかしおいしいネギが採れるだろうと期待していたのだが、来年の自家採種用に取っておくことにした。そして次代も同じ形質のものが現れるか実験してみたい。でも、本当はお鍋にして食べてみたいというのが本音なのだが(笑)。
2006.11.16
コメント(4)
-

スマトラオオコンニャクに異変が・・・
このところすっかりご無沙汰しているスマトラオオコンニャク。コンニャク類というものは、芽が出てから葉が完成するまでの1~2ヶ月ぐらいがもっとも目立った動きがある時期で、一旦葉が完成してしまうとその後はほとんど変化がない。というわけでこのブログでもしばらく紹介しなかったのだが、今日、違う意味で(笑)変化があった。実は、寒さに当ててしまったせいか、1号がバタッと倒れてしまったのある。 11月5日に、自宅で育てていたカトレアや一部の観葉植物を車で貸温室に移動したのだが、スマトラオオコンニャクは後で電車で大事に持って行くつもりであった。が、ちょっと油断してしまったのがいけなかったらしい(泣)。何とか根っこだけでも生きていればいいが・・・。ちなみに、2号の方は1号よりも葉が大きく成長し、今のところ異常はないが、寒さにやられないように注意しなければ。今度の週末に貸温室に移動しようと思う。
2006.11.15
コメント(6)
-

今日の夜食はお好み焼き
昨日の日記では自家栽培のキャベツの話を紹介したが、今日はそのキャベツでお好み焼きを作ってみた。完全無農薬とまでは行かないが、苗が小さいころのみ農薬に頼ったものの、その後は畑に行くたびに手でこまめにアオムシを取っていた。・・・はずなのだが、日曜に収穫して冷蔵庫に保存していたところ、まだ中にアオムシが1匹だけ残っていて、冷蔵庫の中で凍死していた(笑)。 さて、気を取り直して調理に取り掛かり、お好み焼きが完成。なかなか上手く出来たものだと思う。味の方も上々。特に、キャベツは有機肥料を主体に育てたので、市販品よりもおいしかった。・・・と思うのは気のせい?
2006.11.14
コメント(8)
-

割れたキャベツ
10月28日の日記で紹介したキャベツ、小さいながらも順調に育っていたのだが、11月11日(土)に雨が降ったせいか、パックマンのように(笑)ぱっくりと割れてしまった。 しばらく晴天が続いて乾燥気味だったところに雨が降ったため、キャベツが水分を吸って割れたらしい。割れたものは仕方がないので収穫することにした。かなり小ぶりではあるものの、実際に手に持ってみるとずっしりと重い。中身がギュッと詰まっていそうだ。さっそくお好み焼きにして食べようと思う(^^)。
2006.11.13
コメント(0)
-

皇帝ダリア 開花
寒さが日に日に増してゆく今日この頃、今年の5月に貸農園に植えていた皇帝ダリアがめでたく開花を迎えた。 植えた当初からある程度は予想していたが、その成長はすさまじく、現在は背丈は3メートルに達している。根元の太さは直径10センチ以上にもなって、ここまでくるともはや草ではなく「木」である(笑)。背丈が大きくなって堂々たる風格がある割には強風にはきわめて弱く、これまで何度も支柱ごと倒されてしまった。が、こうして開花を迎えてやっと苦労が報われたような気がする。 さて、皇帝ダリアは霜が下りると枯れてしまうめ、そのときになったら伐採して切り刻んで畑の肥料になってもらおうと思う(笑)。ちょっと残酷だが、とにかく背丈が高くて風に弱く、また周辺の作物が日照不足になってしまうため止むを得ない。ちなみに、隣に植えた八重咲き品種は、今になってようやくつぼみが確認できたが、霜が降りる前までに咲いてくれるかどうかがちょっと心配である。八重咲きは暖かい地域でないと長く楽しめないのが残念。
2006.11.12
コメント(8)
-

タマネギの定植
今日は神奈川では朝から雨が降っていたが、夕方に一時的に止んだので、そのわずかな合間を縫って貸農園でタマネギを定植した。品種は超極早生種のハイゴールド1号。これは自分で9月9日にタネを蒔き、9月16日の日記で紹介したもの。市販の苗を買った方が手っ取り早いが、自分で苗を育てた方が愛着が湧いて収穫の喜びも大きい。 さて、今日はタマネギの定植を済ませたわけだが、私も明後日の13日(月)に定植ならぬ定職に就くことになっている(笑)。実は事情があって前職を辞めて転職を決意。タマネギの方は無事に根付きそうだが、私の方が新しい職場に根付くのかがちょっと不安だというのが正直な気持ちである(笑)。 なお、このハイゴールド1号と1週間遅れで赤タマネギの早生湘南レッドのタネも蒔いてあるので、こちらも来週あたりには定植できると思う。
2006.11.11
コメント(4)
-

丹沢のリンドウ
昨日(11月9日)の日記では、丹沢の山登りの話を紹介。季節柄、あまり花に出会えなかったのだが、その中でも特に目を楽しませてくれたのはリンドウだった。群生することはなく、登山道に沿って点々と生えているという感じではあったが、かなりの広範囲に自生しており、その非常に可憐で美しい花に惚れ惚れした。 さて、このリンドウ、その名前の割には(?)車が通る林道では少なく(笑)、標高が高くなって大きな樹木が少なくなったあたりからよく見られる。私が見た限りでは、このあたりに自生するリンドウは背丈が20センチ以下とかなり小型で、非常に愛らしい姿であった。 余談だが、園芸店や切花店で売られている「トルコギキョウ」は、キキョウ科ではなくリンドウ科の植物で、しかも原産地はトルコではなく北米である。実にややこしい名前だ(笑)。
2006.11.10
コメント(2)
-

丹沢・塔ノ岳へ行く の巻
昨日(11月8日)は知人と3人で、神奈川県秦野市の北にある丹沢・塔ノ岳(標高1490.9メートル)へ登った。私は自然探索は好きなのだが、せいぜいバイクで林道を走って、ところどころでバイクを停めつつわき道へ少しそれて散策する程度であった。が、今回は文字通りの山歩き。私が取ったルートは、ヤビツ峠から富士見山荘を経て二ノ塔、三ノ塔へ登り、そこから尾根伝いに塔ノ岳を目指すという表尾根縦走コース。 この日は快晴にに恵まれて、眼下に広がる景色が大変素晴らしく、神奈川県全域だけではなく伊豆半島や伊豆大島、そして富士山や南アルプスがよく見えた。特に、三ノ塔から塔ノ岳に至るまでの標高1000メートル級の長い尾根伝いのルートから見る景色は見事と言うほかになく、しばし時が経つのを忘れたものだった。私の住む地域からはこの丹沢山塊がよく見えるのだが、実は今まで一度も登ったことがなく、山の上にこんな素晴らしい世界があると知ってすっかり魅了されてしまった。 なお、この一帯はシカが多いとは聞いていたが、本当に野生のシカと何度も遭遇した。それも、人間のごく至近距離にいるのにまったく逃げもせず、黙々と草を食べていた。こちらから近付いても驚きもしないし逃げもしない。やはりシカだけに我々をシカトしていたんだろうか(笑)? さて、日ごろの運動不足で体がなまっているのでそれがちょっと心配だったのだが、行きはかなり軽快に歩けた。が、下山途中でひざが痛くなり、ちょっと苦戦を強いられた(^^;)。ともかく、久しぶりに心が洗われる体験をさせてもらった。が、実は今日は筋肉痛でちょっと大変だったのだが(笑)。今回はあまり野の花に出会えなかったが、いつか花がたくさん咲く季節にまた登ってみたいと思う。
2006.11.09
コメント(4)
-

カトレア・ボーリンギアナ 開花
先日の日記で紹介していたカトレア原種、ボーリンギアナ(Cattleya bowringiana)がめでたく開花した。 画像の左がブラック・プリンス(Black Prince HCC/AOS)のオリジナル株、右が20年前に買ったセルレア(coerulea)。カトレア原種の中でも木の形が変わっていて、花はかなり小さいが、私のお気に入りの原種の一つでもある。 さて、11月5日の日記で紹介したとおり、今まで自宅庭で栽培していたランは貸温室に移動したのだが、一部のつぼみが付いた株はまだ手元に残してある。花が終わり次第、貸温室に移動させる予定。ところが、今日の強風でつぼみ付きのカトレアが一鉢倒れていて、それを見たときは心臓が凍りそうになった(笑)。風は本当に厄介だと思う。個人的には雨よりも「風」の方が嫌いである。
2006.11.07
コメント(0)
-

謎の巨大植物 ビロードモウズイカ
近年、市街地の空き地や線路脇などで、銀白色のビロード状の葉を付けた大きなロゼット型の植物を目にした方は多いのではないだろうか? あまりにも巨大であるがゆえに、近付きがたい異様な雰囲気を漂わせている。その正体はビロードモウズイカ(天鵞絨毛蕊花)。地中海原産の植物で、園芸植物として栽培されていたものが日本に帰化したもの。学名のバーバスカムという名で売られることもある。 この画像のものは神奈川県の湘南海岸で撮影したもの。左下の350mlの空き缶と比べれば、いかに大きいかがわかると思う。潮には強いようで、強風時には波しぶきをかぶりそうなところにたくさん生えていた。また、なぜか鉄道が好き?なようで、線路際にも生えているのが時々見られる。海と鉄道が好きだなんて、なんだか私に似ているような気がする。あ、関係ないか(笑)。 なお、近年は外来種が日本で帰化してしまうことが問題となっているため、ビロードモウズイカのように繁殖力が強い植物を育てる場合は、タネが実る前に花を摘み取った方がいいのではないだろうか。あと、タカサゴユリなども繁殖力が非常に強いので、野外に脱出しないよう気を付けていただきたい。
2006.11.06
コメント(2)
-

今日はランのお引越し
秋も深まって気温が下がってきたということで、今日は庭で育てていたランを貸温室に移動することにした。私は車を所有していないので、某大手レンタカー会社で車を借りた。ただ、お金をケチって最小クラスの車にしたために、1回で積みきれなくて2往復する羽目になったが(笑)。しかし、こういうこともあろうかと12時間借りていたので、今日はたっぷりとドライブを楽しませてもらった。 ところが、温室に到着したら業者からショッキングな知らせが。景気の問題や石油の価格上昇などで採算が合わないために、数年後には貸温室の規模を縮小する方向で考えているという。今はまだその心配はないが、いずれは自前で温室を買うか、あるいは株数を減らすかの選択を迫られそうだ。考えてみれば、洋蘭栽培は地球に優しくない園芸だと思う(苦笑)。
2006.11.05
コメント(4)
-

下仁田町馬山産の下仁田ネギ 発芽
今日の2つ目の日記。本当は日記を毎日書くのは大変だというのが本音なのだが(笑)、紹介したいネタが多いので今日はもう一つ日記を書こうと思う。 私は現在畑で下仁田ネギを育てているが、その種子はト○ホク種苗の香川県で生産されたもの。しかし、ネットで調べてみると、下仁田ネギ関連のサイトにはたいてい次のようなことが書かれている。・群馬の前橋ではうまく育たない(下仁田も群馬県)・長野では逆に育ちすぎて固くなる・下仁田から5~6キロ離れただけでもうまく育たない・よって「下仁田ネギは下仁田におけ」という結論に・市販の種子は他の土地でも育つように品種改良されたもので、本場産のものとは質が違う(?) しかし、他の土地で育たないと言われると余計に育ててみたくなるのが自称園芸研究家としての本能でもある(笑)。と、言うわけで、下仁田町の中でも最も本場と言われる馬山産の種子を入手。早速蒔いてみたところ、無事に発芽してくれた。 画像の奥にあるのは現在栽培中のト○ホク種苗の香川県産の種子から育てた下仁田ネギ。収穫期が近づいてだんだんとふっくらした姿になりつつある。今回入手した下仁田町馬山産の種子は、とりあえず発芽は上手くいったが、今後は育ちが悪いものを間引く予定なので、実際に収穫にこぎつける株数は少なくなると思う。ちなみに、これと平行してカ○コ種苗のトルコ産の下仁田ネギと、サ○タのタネのチリ産の雷帝下仁田の種子も蒔いた。 つまり、私はト○ホク種苗、カ○コ種苗、サ○タ、下仁田町馬山産の4系統の下仁田ネギを同時に育てていることになる。どうも私はすっかり下仁田ネギに魅了されてしまったようだ(笑)。
2006.11.04
コメント(6)
-

アンスリウム・シェルツェリアナム 品種名不詳
今年も残すところわずか2ヶ月足らずとなったが(言うのが早すぎる? ^^;)、私は観葉植物をまだすべて屋外で育てている。このところ比較的過ごしやすい陽気が続いているせいか、熱帯植物のアンスリウム・シェルツェリアナム(Anthurium scherzerianum)が今でも屋外で元気に咲いている。 これは6月ごろに購入したもので、白地に細かい赤のスポットが入るという非常にユニークなもの。7月4日の日記で紹介した「グラフィティ(Graffity)」という品種に似ているが、それよりはスポットが細かく、花や株全体が小型なので別品種である。が、品種名が分からないのが非常に残念。 観葉植物には品種名が付いていない、または誤った品種名で流通していることが多々あるが、葉や花さえ美しければ名前なんか関係ないという人が多いのだろうか? イヌやネコの血統書にこだわる人は多いのだから、植物の品種や血統にももう少し世間の関心があればいいのにと思っているのは私だけだろうか?
2006.11.04
コメント(0)
-

畑のサトウキビ
今年の5月に貸農園にサトウキビを植えた。去年も育てたのだがなかなかいい感じだったので、今年も沖縄から苗を何本か取り寄せた。しかし、サトウキビの「苗」とは言っても、長さ20~30センチぐらいの「棒切れ」が箱詰めになって届いただけだった。どうも沖縄ではそれを「苗」と呼ぶらしい。 畑に植えてから約半年。今では沖縄産と同じ太さの幹が何本も立ち上がっている。しかし、10月6日のあの強風でなぎ倒されてしまった。沖縄の台風に鍛えられて少しは風に強いのかと思いきや、意外とあっさり倒されてしまった(^^;)。 さて、このサトウキビ、このブログではどのカテゴリーに入れるか非常に迷った(笑)。野菜でもないし観葉植物と言うには無理があるし、植物学的には多年草なのだが、かと言って多年草のカテゴリーも違和感がある。で、とりあえずサトウキビは沖縄の「農作物」だということで野菜のカテゴリーに入れたが、ん・・・なんかイマイチしっくりこないな(笑)。
2006.11.02
コメント(2)
-

カトレアに続々とつぼみ
このブログを始めたのが今年の4月で、今日が11月1日なので、足掛け8ヶ月が過ぎたことになる。これまでに妙にクセのある文体(^^;)で、さまざまな植物を紹介してきたが、私の専門領域?であるはずのカトレアについて紹介する機会が少なかった。しかし、最近になってカトレアに続々とつぼみが上がってきて、いよいよ洋蘭趣味家としての楽しい季節を迎えつつある。 この画像のものは2株とも往年の名花のオリジナル株なのだが、まだ株が出来ていないためにそれぞれ1輪しかつぼみが付いていない。右側の株は例の貸温室に閉じ込めたままだったために、バックバルブが枯れてしまっている。カトレアは一旦作落ちしてしまうと元に戻すのに数年は掛かるが、今までの遅れを取り戻すべく、これからはこまめに世話をしてやりたい。品種名については開花したときに改めて紹介する予定である。
2006.11.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- 我が家のバラの開花
- 数日前草取りしたところに思ってもい…
- (2025-09-03 14:59:30)
-
-
-

- グランドカバー
- クラピアに暗雲!主要サプライヤー撤…
- (2025-11-16 05:48:58)
-
-
-

- 今日見つけた“花”は、なあ~に?
- 昨年と今年のシクラメン
- (2025-11-24 08:40:45)
-






