2006年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

平戸早生ニンニク 発芽
貸農園に植えた平戸早生ニンニクが発芽し、順調に生育している。植えた種球には大きさのばらつきがあったが、現在のところは葉の生育にあまり差はなく大きさがそろっている。 ちなみに、画像左に見えるのは、お隣の区画から境界線を越えてやって来たアシタバの葉。ここまで大胆に被さっていると園芸作業がやりにくいというのが本音。お隣さんもそろそろ気付いてくれてもいいと思うのだが。。。10月1日の日記で紹介したあのヤーコンも、一向に改善されていない。お隣さんと顔を合わせるたびに目でテレパシーを送っているのだが、やはり気付いてくれないようだ。当たり前か(苦笑)。
2006.10.31
コメント(4)
-

カトレア・ボーリンギアナにつぼみ その2
10月27日の日記では、カトレアの原種ボーリンギアナ・セルレア(C. bowringiana coerulea)を紹介したが、実はもう1株ボーリンギアナを持っている。個体名は「ブラック・プリンス」(C. bowringiana Black Prince HCC/AOS)。もちろんオリジナル株。 こちらは2000年の秋ごろに購入したもの。その直後、仕事の都合で転居し、貸温室を借りてそこに閉じ込めたままになっていたため、あまり木が大きくなっていない。しかし、ボーリンギアナは木が小さくても花を咲かせる性質があるらしい。 さて、その貸温室は現在も借りたままになっている。もうそろろそろレンタカーを借りてランを温室に移動しなければならない。本当は小型温室を買って冬の間も手元で花を楽しみたいが、予算の都合で(笑)それができないのが少々残念。 予算がまったくないわけではないが、仕事の都合で転居する可能性もあるので、温室なんか持っていたら引越しが非常に厄介になる。以前持っていた温室は、2000年秋の引越しのときに取り壊して粗大ごみに出さざるを得なかった(泣)。今後のもしものためにも貸温室はキープすることになるだろう。
2006.10.30
コメント(4)
-

畑のイチハツ
私の畑には4株のイチハツが植わっている。イチハツは中国原産のアヤメの仲間で、民家の庭先によく植えられていて、4月から5月にかけて青紫の花を咲かせる。ちなみに、私が植えているものはちょっとレアな白花品種である(^^)v。自宅の庭には斑入りも植えてある。 さて、このイチハツ、文献によれば、昔は民家の茅葺の屋根のてっぺんに植えられていたという。その理由は、イチハツが屋根に根を張って締め付けてくれるから屋根が風に強くなるという効果があったからだとか。本当に効果があったのか分からないが、かつては普通に見られた光景らしい。そういうわけで、今でも英語では「ジャパニーズ・ルーフ・アイリス(Japanese Roof Iris)」と呼ばれている。しかし、中国原産なのになぜジャパニーズなのかと突っ込みを入れたくもなる(笑)。どうも、かつて来日した外国の植物学者の見聞が、あちらで誤って伝わったらしい。まさか、向こうの人は今でも日本では屋根にイチハツを植えていると信じているのではなかろうか? 昔は屋根に植えていたという話はよく本に載っているし、ネット上で「イチハツ」で検索してもその話がよく出てくる。しかし、実際に植えられている絵や写真を見たことがただの一度もない。地方に行けばまだ茅葺の家が残っているので、もしイチハツを屋根に植えている家があればこの目で確かめ、写真に収めて記録を残しておきたい。
2006.10.29
コメント(0)
-

結球を始めたキャベツ
9月2日の日記で紹介したダ○ソーのキャベツ。定植から2ヶ月近くが過ぎ、今ではこんなに立派な姿に。 葉っぱの枚数が増え、左側の株は結球が進んでいかにもキャベツらしい姿になった。右側のものは当初から生育が遅れ気味であったが、ようやく結球が始まっている。ただ、もともとの品種の性質なのか私の栽培方法の問題なのか、普通のキャベツに比べて株自体が小ぶりではあるが、タネから育てたキャベツが育っていく姿を見るのはうれしいものである。 すでに頭の中ではこのキャベツの収穫後の利用法がもう決まっている。それはお好み焼き(笑)。本当に収穫が待ち遠しい。ちなみに関西人でもある私としては、お好み焼きには結構うるさい(笑)。なお、関西では日常的にお好み焼きが食卓に上るわけではないので、念のため。
2006.10.28
コメント(2)
-

カトレア・ボーリンギアナにつぼみ
私が育てているカトレアの中の一つ、原種のボーリンギアナ・セルレア(C. bowringiana coerulea)につぼみが上がり、間もなく開花を迎えようとしている。 私は今年の4月にブログを始めて以来さまざまな植物を紹介してきたが、何を隠そう、このボーリンギアナ・セルレアこそ、私が所有する植物の中でもっとも古株になる(^^)v。購入したのは1986年8月31日なので、今年で20年が過ぎたことになる。私の波乱万丈な?人生と共に過ごしてきたカトレアだけに、非常に愛着を持っている。たぶんこれからも手放すことはないと思う。 カトレアとしては株の姿が変わっていて、花は小さく多花性であるが、比較的丈夫で開花しやすい。本来はもっと大株になるのだが、場所の都合で小さく株分けしてしまった。もしもの時のためにバックアップ?を取っておかなければ・・・。
2006.10.27
コメント(2)
-

コロカシア・ブラック・マジック 開花
サトイモの花をご覧になったことのある方はおられるだろうか。8月28日の日記で紹介した観賞用サトイモのブラック・マジックに、現在花が咲いている。 この観賞用サトイモのフル・ネームは、コロカシア・エスクレンタ・ブラック・マジック(Colocasia esculenta cv Black Magic)といい、食用のサトイモの学名がコロカシア・エスクレンタ(Colocasia esculenta)であるから、両者は植物学的には同一種と言うことになる。 しかし、ご存知のとおり食用サトイモの花は、日本ではほとんど開花しない。そして、咲いただけでも大きな話題となり、新聞に掲載された例もある。一方、私のブラックマジックは毎年開花している(^^)v。というわけで、サトイモの花を見てみたい方にはこのブラック・マジックをお勧めしたい。
2006.10.26
コメント(2)
-

シラー・ペルヴィアナの発芽
畑に植えていたシラー・ペルヴィアナ(Scilla peruviana)の球根が発芽した。秋植え球根草花の中でも私がもっとも好きなものの一つ。10年ほど前にも育てていたことがあったが、転居の都合で置き去りにせざるを得なかった。また久しぶりに育てたいと思い、新たに球根を購入。 本種は球根草花ではあるが、どちらかと言うと宿根草の感覚で数年間植えっ放しにした方が年々大株になって増えていく。ただ、今回植えた球根はかなりサイズが小さいので、来年の春に確実に開花するかどうかは不明。 ちなみに、画像の右側が紫色の花が咲く普通種、そして左側がちょっとレアな白花種。と言ってもこの状態ではまだ分からないが(笑)。
2006.10.25
コメント(2)
-

サンセベリア・スタッキー「もどき」 葉挿し その後
5月15日の日記で紹介したサンセベリア・スタッキー「もどき」の葉挿し。あれからなんと5ヶ月もの期間を経て、ようやく新芽が顔を出してきた。 しかし、5ヶ月もかかってこの程度の成長とは・・・。もともと棒状のサンセベリアの生育はきわめて遅く、園芸店に出回っているものはおそらくほとんどが熱帯圏からの輸入物と思われる。こんな生育の遅いものを国内で生産していたのでは、商業的にはとても割に合わないと思う。 それにしても、相変わらず国内には「スタッキー」と称した別種が大量に流通している。これに限らず、品種名が間違ったまま売られているものがなんと多いことか。園芸業界は植物に詳しい人が少ないのだろうか? 私はかつてはこの業界で働くことを夢見たものだが、この歳での(あえて何歳とは言わないが ^^;)転職は無理だろうな・・・(笑)。
2006.10.24
コメント(4)
-

プリンスメロン 8個目を食す
今までに何度も紹介してきたプリンスメロン。昨日はその8個目の実を食べてみた。これは9月26日の日記で紹介したもので、収穫したのは10月7日、そして15日間もの追熟期間を経て昨日ようやく賞味することが出来た。 プリンスメロンは通常は孫蔓に着果させることになっているが、この8個目は「ひ孫蔓」に着果したという、いわゆる末成り(うらなり)のメロン。というわけで味は薄かったが、食べられなくはなかった。なお、9個目はあれ以上大きくならなかったので、廃棄処分となった。 こんなに秋も深まったのに、まさか今頃になってプリンスメロンを紹介するとは思わなかった(笑)。これで今年のプリンスメロンの紹介は最後となる。軽い気持ちで植えたプリンスメロンだったが、着果数は案外多かった。今度作るときは、質を向上させられるようにしっかり管理したい。
2006.10.23
コメント(2)
-

テラス・ブロンズの接木 その後
8月9日の日記では、観葉サツマイモのテラス・ブロンズの接木後の生育振りを紹介。台木に使ったのは食用サツマイモの定番品種「紅あずま」。これで上手く行けば地上にはテラス・ブロンズの美しい黒紫色の葉が繁り、地中には美味しい紅あずまのイモが成るはずであった。そして、1週間前の10月15日(日)、ついに収穫を迎えた。 当初の期待通り、地上部にはテラス・ブロンズが生い茂り、地下部には小さいながらも紅あずまのイモが成っている。ただ、テラス・ブロンズはもともと葉緑素が少ないためか、生育がそれほど旺盛ではなかった。黄緑色の「テラス・ライム」を使えば、地上部も地下部ももっと生育が良かったかもしれない。ほかに紅あずまを2株植えていたが、こちらは非常に生育が旺盛で、蔓を貸農園の自分の敷地に収めるのが大変だった(笑)。 さて、来年も貸農園でサツマイモを作ろうかと思っていたのだが、ちょっと考え直すことにした。とにかく蔓が縦横無尽に伸びて収拾が付かなくなるので、サツマイモは懲りたというのが本音である(笑)。
2006.10.22
コメント(2)
-

皇帝ダリアにつぼみ
貸農園にシンボルツリー?として植えている皇帝ダリアにつぼみが上がってきた。 5月ごろに畑に定植し、その後非常に旺盛な生育を見せ、強風のために2回も倒されたりしてハプニングもあったが、今日になってようやくつぼみが確認できた。 畑に植えた皇帝ダリアは一重と八重咲きの2本で、つぼみが出てきたのは一重の方。八重咲きの方はまだつぼみが出来ていないようだ。5月に植えて以来あまりにも生育が良すぎて縦にも横にも大きくなり、異様な姿を呈していた。普通の人には見慣れないためか、貸農園の周囲の方からはよく名前を尋ねられた。いちおう名前と花について説明しても、皆さん今ひとつピンとこない様子。皇帝ダリアを知らない人の目には、さぞかし得体の知れない謎の巨大植物に映っただろう(笑)。その謎のヴェール?がはがされる日ももうすぐ。開花したら周囲の人が驚くのではないかと楽しみにしている。
2006.10.21
コメント(5)
-

ドラセナ・ヴィクトリアの成長振り
7月13日の日記で紹介したドラセナ・フラグランス・ヴィクトリア(Dracaena fragrans Victoria)。あの当時は葉っぱが5、6枚の小さな株であった。 あれから3ヶ月余りたった現在はどうなったかと言うと・・・ オ~ゥ、ビューティフル(^^)。真上からはほとんど鉢が見えないほどに葉の枚数が増えてまるでリボン細工のよう。ただ、日当たりが良すぎたためか葉の所々に「しみ」が入ってしまった。 本来はもう少し日除けをすればいいのだろうが、無料で無限に供給される太陽光をわざわざお金をかけて遮ることに抵抗があるので(笑)、私は植物はなるべく葉焼け寸前になるぐらいになるべく光に当てて育てるようにしている。追記 「無料で無限に供給される太陽光を・・・」の部分、なんか前にも書いたことがあるなと思ってよくよく考えてみたら、9月19日の日記でも同じことを書いていた。ビールの飲みすぎで今日は頭の回転がおかしいのかも(笑)。
2006.10.20
コメント(4)
-

さらに「らしく」なった下仁田ネギ
9月5日の日記では、「らしく」なってきた下仁田ネギと題して下仁田ネギの成長振りを紹介。あれから1ヶ月半が経ち、よりいっそう「らしく」なってきた。 とは言っても、タネを蒔いた後の管理が不十分だったために苗の生育にばらつきがあり、それが今も影響していて株の大きさがそろっていない。しかし、この画像の真ん中にある株はひときわ生育が良く、自家採種用に取っておこうか検討中。 ちなみに、今育てている下仁田ネギのタネは、ト○ホク種苗の香川県産のもの。実は、本場の群馬県下仁田産の種子が手に入らないものかと思っていたところ、下仁田町の中でも最も品質の良いものが採れる地域の種子を本日ゲット。さっそく今度の週末に蒔こうと思う。 と言うわけで、私はト○ホク種苗の香川県産、サ○タのチリ産、そして本場下仁田産のものを同時に育てることになるわけで、それぞれどう違うか楽しみである。あるいは、案外変わらなかったりして(笑)。
2006.10.19
コメント(2)
-

ドラセナ・ドラコ Dracaena draco
ドラセナといえば観葉植物の定番で、様々な品種が園芸店の店頭に並んでいるが、今日ご紹介するのはあまりお目にかかれないドラセナ・ドラコ(Dracaena draco)の実生株。昨年の夏に種子を蒔き、1年あまり経ったもの。 ドラセナ・ドラコは大西洋に浮かぶカナリー諸島原産。ドラセナの中でも最大種で、非常に寿命が長いことで知られている。『朝日園芸百科27 観葉植物』によれば、カナリー諸島のテネリフェ島にはかつて推定樹齢6000年の個体があったが、1868年に強風で倒れたという。しかし、単子葉植物は年輪を作らないので、本当に樹齢が6000年なのかは疑問だということを何かの本で読んだ記憶があるが。 さて、このドラセナ・ドラコにはリュウケツジュ(龍血樹)という和名がある。幹を傷付けると血液のような赤い樹液が流れ、塗料や薬用などに利用されるという。いつかそれを実験してみたいと思っているのだが、このサイズで実験すると、出血多量で枯れるかも(笑)。
2006.10.18
コメント(2)
-

新ショウガの甘酢漬け
10月13日の日記で紹介した新ショウガ。実はあの日の日記で紹介したときは、すでに甘酢漬けに加工済みであった。加工したのは10月10日(火)のこと。あれから1週間が経ち、ショウガがお酢に反応して程よくピンク色に染まっている。 お寿司のガリみたいに薄く切るには、スライサーを使えばよかったのだが、どこかにしまったままになっていてそれを出してくるのも面倒だったので(笑)、包丁で切ることにした。が、結果はご覧の通りガリというよりはバナナチップみたいな分厚さ(笑)。 で、さっそく賞味してみると、美味い・・・と言いたいところだが、ショウガが分厚くて甘酢がよく染み込んでいないためか、甘酢漬けというよりはショウガそのものの味がする(笑)。食感もタケノコみたいな感じ(笑)。幸いにも薄く切ったものは甘酸っぱい甘酢漬けの味がする。これだけの量を作っておけば、一人暮らしの身にはこれから1年は持ちそうだ。
2006.10.17
コメント(2)
-

C. labiata semi alba Mrs E. Ashworth 開花
秋はカトレアの原種C. labiata(ラビアータ)の開花ラッシュを迎える季節。洋蘭関係のサイトやブログでもラビアータの開花報告でにぎわっている。そして私も10月12日に引き続いてこの秋のラビアータ開花報告第2弾。今回紹介する個体はC. labiata semi alba Mrs E. Ashworth(ラビアータ・セミ・アルバ・「ミセス・E・アシュワース」)という、カトレアの歴史において大変有名な個体。もちろんオリジナル株。 すでにこの個体は19世紀末には知られており、交配親として盛んに用いられ、今日見られるセミアルバ(白弁赤リップ)系のカトレアの交配種にはこの個体の血を引くものが多い。100年以上もの時を経て今なお健在で、私の手元でこうして力強く咲いている姿は感動ものである。こういう貴重なものは大株に仕立てて豪華に楽しみたい。 なお、これも先日の強風の時は外に出しっぱなしであったが、つぼみも株もまったくダメージはなかった。もしこれが風に飛ばされて行方不明になっていたら、とても正気ではいられなかったと思う(笑)。(10月8日の日記参照)
2006.10.16
コメント(2)
-

雷帝下仁田 発芽
10月7日(土)にタネを蒔いていた雷帝下仁田。あれから1週間が経ち、無事発芽を始めてくれた。 実はタネを蒔くときに律儀にも一粒ずつ1~2センチの間隔で蒔いたのだが、手間をかけただけあってこのようにほぼ等間隔に芽が並んでいる。これならあまり間引きの必要もないし、タネを無駄にせずに多くの苗が出来る。ここで、4月に蒔いた下仁田ネギの発芽の画像と比べてみたい。 この時は適当に蒔いたので(笑)、苗が密生しているところとそうでないところが出来てしまい、苗の生育が不ぞろいになった。これが今もずっと尾を引いていて、株の大きさにばらつきがある。野菜作りには「苗半作」という言葉があるが、下仁田ネギの場合は苗全作(?)といったところか? やっぱり横着はいけないとつくづく思った(^^;)。
2006.10.15
コメント(2)
-

風に弱い皇帝ダリア
今年5月に貸農園に植えた2本の皇帝ダリア。現在では高さが2メートル近く、根元の幹の直径がなんと10センチを越えるほどに成長。そして支柱を添えてはいたのだが、10月6日(金)の大嵐で支柱ごとあえなく倒れてしまった。その翌日に支柱を立て直したものの、1日中強風に晒された皇帝ダリアはこんな惨めな格好に・・・。 一日中同一方向からの強風が吹いていたために、風上側の葉はほぼすべてが引きちぎれ、かろうじて風下側の葉が少し残っただけ。脇芽もたくさん出ていたのだが、ことごとく折れてしまった。ちなみに画像左下に見えるのは地湧金蓮花ことチャイニーズイエローバナナ。これも葉が細切れになってヤシの木みたいになった。 皇帝ダリアは予想以上に風に弱いことが分かった。しかし、幹そのものは太く堅くしなやかで、かなりの力を入れないと折れない。もしかしてこれを物干し竿に使うと、掛け布団を干しても大丈夫かもしれない(笑)。が、一見頑丈そうに見えても根元と枝(脇芽)の付け根だけはきわめて弱く、風が吹くとあっけなく折れてしまう。とにかく、これほど見かけと中身がかけ離れている植物も珍しい(笑)。原産地は風が吹かないのだろうか? 皇帝ダリアよ、お前は故郷では一体どうやって生きているのだ?と、小一時間問い詰めたい(笑)。
2006.10.14
コメント(2)
-

新ショウガ 収穫
10月7日(土)にめでたく新ショウガを収穫したので、今日の日記でショウカいしたい(^^;)。これは今年の4月下旬に種ショウガを植え、7月16日の日記で紹介したものと同じもの。 収穫量は約750グラム。そして、驚いたことに春に植えたはずの種ショウガがそのまま原型をとどめていた。特にシワも入っていないし腐ってもいない。調べてみたところ、ショウガは種ショウガと新ショウガの両方を利用できる作物だそうな。種ショウガの数倍の新ショウガが収穫できる上に、種ショウガまで利用できるとは非常に得である。グ○コのキャラメルではないが、一粒で二度おいしいとはこういうことを言うのだろうか(笑)。 なお、この新ショウガはすでに甘酢漬けに加工済みなので、後日紹介したい。
2006.10.13
コメント(4)
-

C. labiata semi alba Gloriosa 開花
カトレア原種愛好家にとって、秋といえばカトレア・ラビアータの季節でもある。私の手元でも、ラビアータの有名個体C. labiata semi alba Gloriosa(ラビアータ・セミ・アルバ・グロリオサ)のオリジナル株が開花した。 今年の5月に株分けし、まだ株が出来上がっていないために1輪しか付いていないが、色も形もなかなかいい感じである。現在は室内に飾ってその美しさを鑑賞している。 ちなみに、これは現在は金具を使って吊り栽培しているが、10月6日(金)のあの大嵐の日もそのまま外に置いていた。あの日はあまりにもの強風のために2鉢ほど飛ばされてドブ川に落ちた(笑)というのに(10月8日の日記参照)、この個体はつぼみも株もまったくダメージがなかった。もともと原産地ではカトレアは木の高いところに着生しているので、風には案外強いらしい。
2006.10.12
コメント(0)
-

変わり果てたバナナの木
今年の春に貸農園に植えたそんなバナナことムサ・ベルチナ(Musa velutina)。畑の土が肥えていたせいか、本体はかなりの生育振り。例年ならもうそろそろ花芽が上がることだが、そこへ10月6日(金)のあの強風。一日中強風に晒されたそんなバナナはどうなったかというと・・・ 葉が切れ切れになってヤシの木みたいになってしまった(笑)。真後ろに植えてある2本の皇帝ダリアも支柱ごと倒れてしまって無残な姿・・・。ちなみに、8月23日の日記で紹介した画像を見ていただければ、いかに風が凄まじかったかがよく分かる。 日当たり、風通しが良いということで借りた当初は喜んでいたが、どうやらこの畑には背の高くなる植物を植えるのは止めた方がいいかもしれない。来年は考え直さなければ・・・。
2006.10.11
コメント(4)
-
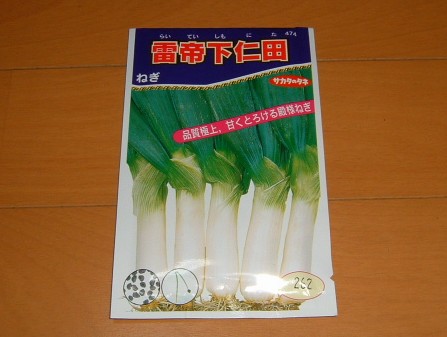
雷帝下仁田のタネを蒔く
10月7日(土)には、畑に雷帝下仁田のタネを蒔いた。これは下仁田ネギの選抜品種だということらしい。現在も畑で下仁田ネギを育てているが、こちらは特に品種名の付いていないもの。雷帝下仁田が普通の下仁田ネギに比べてどんな風に違うかが非常に楽しみ。 なお、このサ○タのタネから発売されている雷帝下仁田の種袋にはなぜか2つのヴァージョンがある。私は通販で直接購入したのだが、近所のホームセンターで売られているものはパッケージのデザインがまったく違う。タネの内容量や値段は同じらしい。私が買ったものは高級感があるので気に入っている。
2006.10.10
コメント(2)
-

二期作目のトウモロコシを収穫 しかし・・・
10月7日(土)に二期作目のトウモロコシを収穫した。この二期作目には7月23日にタネを蒔いた第一陣と、7月30日に蒔いた第二陣がある。第一陣はすでに収穫を終え、今回収穫したのは第二陣の方。 当初は生育が非常に速くて喜んでいたのだが、残念ながらアワノメイガの被害に悩まされることになった。第一陣の方は茎の被害が大きく、実があまり大きく成長しなかった。第二陣は雄花がことごとくやられてしまい、受粉が上手くいかなかったようで実の入りが悪く、また上手く実が入ったものはアワノメイガに食い荒らされてしまった。 一期作目のものはまったく被害がなかったので、完全に油断してしいた。しかし、今回の失敗にめげずに来年もスペースがあれば二期作に挑戦したい。が、アワノメイガをどう防除するかが課題。テデトールを使うかデナポン粒剤にするか、そのときになったら考えようと思う。 余談だが、「テデトール」という言葉を園芸関係のサイトで時々目にするのだが、私はその本当の意味を昨日まで知らなかった。Googleで検索して初めて意味を知った。危うく園芸店で「テデトールください」と言ってしまうところだった(笑)。危ない危ない・・・。
2006.10.09
コメント(10)
-

風と共に去りぬ!?
一昨日は神奈川県は一日中大荒れのお天気。昨日の日記でも紹介したが、自宅では鉢植えが転がり、畑の作物は強風に煽られて葉がボロボロ。しかしカトレアの場合は6月12日の日記で紹介したとおり転倒対策をしていたので、棚に固定していたものはとりあえずなんとか持ちこたえてくれた。が、吊り栽培していた鉢の中の2鉢が飛ばされてしまい、なんとすぐそばのドブ川に落ちて流されてしまった(笑)。 翌朝、さっそく行方不明になったカトレアの捜索を行なうことに。そして私が見たものは・・・Oh, my God!!! そこには割れた鉢だけが残り、中身のカトレアの姿はなかった。さらに下流に行ってみたが、すでにかなり流されてしまったようで、どこにも見当たらなかった。ただ、せめてもの救いと言ってはヘンだが、飛ばされた2鉢はあまり貴重な品種ではないのでそれほどショックはないのだが、それでも飛ばされてしまったのは非常に残念。映画のタイトルではないが、まさに「風と共に去りぬ」である(笑)。今後は気を付けなければ・・・。
2006.10.08
コメント(2)
-

貸農園が大変なことに・・・
昨日(10月6日)の神奈川県は朝から晩まで暴風雨という悪天候。仕事中も自分の植物がどうなっているか気になって仕方がない1日であった。そして夜になって帰宅すると、アパートの庭は鉢植えが転がってシッチャカメッチャカ状態。幸いにも、私の鉢植えは根張りがしっかりしているので、根鉢が崩れることがほとんどなかったのがせめてもの救い。しかし、貸農園の方が非常に気になっていた。そして今日の朝、貸農園に行ってみると・・・うぉ~何じゃこりゃ~~~!? 非常に風通しのいい場所なのである程度は予想していたのだが、畑の作物は強風に煽られて目も当てられない状態・・・。同じ農園の隣近所もかなり被害が大きかった。 (1)のサトイモと(2)のヤーコンは葉っぱが布を引き裂いたようにボロボロ。(3)はショウガだが、茎が完全に倒れてしまった。倒れたものはショウガないので(笑)収穫することにした。(4)は地湧金蓮花ことチャイニーズイエローバナナで、(5)はサトウキビ。いずれも葉っぱが細かく引き裂かれている。(6)の皇帝ダリアは葉っぱが3分の2以上ちぎれてしまった上に幹が倒れてしまった。 ここまで見事にダメージを受けると、ショックを通り越して笑えるものがある(^^;)。とりあえず今日は気を取り直してショウガ、サツマイモを収穫し、下仁田ネギのタネを蒔いた。しかし、今後のために何か対策を考えねば。今のところよりも風当たりがやや弱い他の区画に引っ越すことも検討している。
2006.10.07
コメント(6)
-

「ネトリ」の株分け
9月12日の日記では、「ネトリ」ことネオレゲリア・カロリナエ(カロライナエ)・トリカラー (Neoregelia carolinae cv. Tricolor)を紹介。私のもっとも好きなアナナスの1つ。すでに子供が大きくなっていたので、あの日の日記で紹介した後に株分けすることにした。 春からずっと直射日光に当てていたため、子株も赤く色付いて非常に美しい。購入してから半年になるが、親株もまだまだ鑑賞に堪えそうだ。もしかして親株はもう1つぐらい子供を出すかもしれない。 なお、私のブログは写真撮影日と日記を書く日が必ずしも一致しない。たいていは週末にネタを撮り貯めてそれを小出しするという形を採っている。今日は神奈川は朝から暴風雨という悪天候で、貸農園の作物が非常に気になって気もそぞろな1日であった。その農園のある場所は周囲にさえぎるものが何もなく、良くも悪くも風通しが良い。明日は天気がよければ朝早くから畑を見に行くつもりだが、いや~~~な予感がする・・・(^^;)。
2006.10.06
コメント(0)
-

平戸ニンニクの種球
今年の4月に貸農園を借りてそろそろ半年になる。私が育ててみたいと思っていた野菜の1つにニンニクがあり、「平戸」という品種の種球を買うことにした。これは暖地系早生品種で、5月ごろには収穫可能とのこと。これなら夏野菜の植付けとかろうじて重ならないということでこの品種を選んだ。 私はニンニクは大好きなのだが、めったに口にしない。というのは、やはりあの臭いが気になるからで、自分自身はそれほど気にならないのだが、周囲の人のことを考えるとうかつに食べることができない。中学生の頃、夕食のカレーにニンニクをたっぷり摩り下ろして入れたら、翌日学校に行って大騒ぎになったことがあった(笑)。 昔、テレビ番組で実験していたのだが、ニンニクを食べた後に何もしない人と、歯磨き・入浴など消臭対策をした人とでは、臭いが完全に消えるまでの時間はほとんど変わらないらしい。というのは、ニンニクの臭いは体内から体全体に発散されるわけで、歯を磨いたり入浴したりしても一時的に臭いが消えるだけで、体内のニンニク臭の元がなくなってしまうまで臭いは出続けるとのこと。栄養価と味がそのままで「完全無臭」ニン二クがあったらありがたいのだが・・・。
2006.10.05
コメント(4)
-

ドラセナ・ワーネッキー・コンパクタ 枝変わり?
10月2日の日記ではサンセベリアの枝変わりの話を紹介したが、今日はドラセナ・デレメンシス・ワーネッキー・コンパクタ(Dracaena deremensis cv. Warneckii Compacta ・・・長い^^;)の枝変わりらしきものを紹介したい。 ドラセナのワーネッキーと言えば、園芸店でよく見かけるあの観葉植物である。このワーネッキーは枝変わりを生じやすいようで、ここから様々な品種が生まれている。その中の1つにワーネッキー・コンパクタという、その名の通りワーネッキーの矮性品種がある。斑の入り方は親のワーネッキーとほぼ同じで、葉が短くて節が詰まってコンパクトな姿となる。 私がたまに出かける園芸業者の温室にそのワーネッキー・コンパクタが地植えにされているのだが、今年の5月ごろにその中から斑の入り方が異なる枝を見つけ、そこの社長さんに交渉して譲っていただいた。その画像がこちら。 葉の中央部にくっきりと白い斑が入り、コントラストがはっきりしていて観賞価値が高い。この画像のものは5月に挿し木した直後のもので、現在は根付いているものの、葉緑素が少ないためか成長は非常に遅く、大きさは当時とあまり変わっていない。なんとかこの斑を固定させたいものである。
2006.10.04
コメント(0)
-
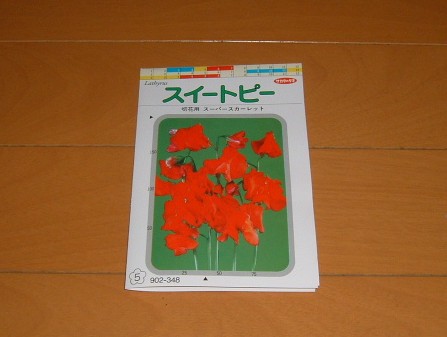
心の岸辺に咲いた・・・
♪赤い~ スイ~トピ~イ~ とまあ、冗談はさておき(笑)、聖子ちゃん世代の私としては、「赤いスイートピー」は、私の松田聖子ベスト3の一つ。ちなみに、あとの二つは「風は秋色」と「制服」。というわけで、本物の赤いスイートピーのタネを購入。私の住むアパートの南側にフェンスがあるので、そこに絡まらせてみたいと思う。花のタネは、通常はミックスと単色の両方で売られているが、いろんな色をごちゃごちゃ混ぜて植えるよりは、単色にまとめた方がかえって美しさが際立つのではないだろうか。 ただ、実際にその赤いスイートピーの写真を見ると、真っ赤に燃える情熱のイメージがあり、松田聖子の歌のイメージとはちょっと違うような気がする。もう少しピンクに近い品種の方が歌に合っていたかも。
2006.10.03
コメント(4)
-

サンセベリア・ローレンティ 枝変わり?
サンセベリア・ローレンティといえば、サンセベリアの中でももっとも流通量が多い品種で、どこの園芸店にも置いてあるし、観葉植物としてオフィスやデパートなどでも良く見かける。園芸マニアの心理としては、ありふれた品種にはあまり関心がないものである。が、今年の春ごろ、私はとある園芸店で、普通のローレンティに混じって一株だけ枝変わりと思われる株を見つけた。 その株は、斑が入っている面積が極端に広い。通常は葉っぱのふちに覆輪状に斑が入るのだが、私が見つけたものは葉っぱの総面積の半分以上の部分に斑が入っている。これは上手く固定させれば新品種が誕生するかもしれないと思い、さっそく購入して育てることに。すると、なんと葉がすべて斑入になったいわゆる白子(しらこ)の葉が出てきた。ただ、葉緑素が極端に少ないだけに、成長もすこぶる遅い。しかし、今後どうなるかが非常に楽しみである。 ちなみに某オークションでは「マイナスイオン」という言葉がサンセベリアの枕詞(笑)のように依然として使われているが、これを育てて健康になった人がいるのだろうか?
2006.10.02
コメント(2)
-

貸農園のお隣さん
貸農園にキャベツを定植したのが9月2日のこと。あれから1ヶ月が経ち、生育はまずまずと言ったところなのだが、ちょっと困った問題が発生。お隣の区画のヤーコンが境界線を越えて私の区画に覆い被さり、2株植えたキャベツのうちの1つが日照不足になってしまい、生育が遅れ気味なのである。 画像のほぼ中央に見えるロープがその境界線。お隣さんは、ヤーコンをそのロープのすぐそばに植えている。私もヤーコンを育てているが、生育のいいものでは1株でおよそ1メートル四方に広がっている。こんな生育旺盛なものを境界線ぎりぎりに植えるのはもってのほか。 しかし、お隣さんとはたまに顔を合わせるものの、こういうことはなかなか言いにくいのが現実。言ったがために気まずくなるのではないかという心配もある。あるいは、「お宅のヤーコン、よく育ってますね~」と、さりげなく褒め殺し作戦で行くとか(笑)。いや、そんなことより、こんなにはみ出してるのだからいい加減気付いてくれてもいいと思うのだが・・・。
2006.10.01
コメント(6)
全31件 (31件中 1-31件目)
1









