1998年07月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
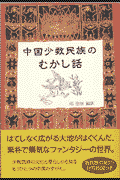
「中国少数民族のむかし話」 【邱奎福】
中国少数民族のむかし話(著者:邱奎福|出版社:求龍堂) 中国の少数民族の民話のアンソロジー。ただし、後書きによれば、もとになった中国のアンソロジーがある。 この本には三十一の昔話が紹介されているが、原書には五十七編あるという。その中から、「日本人にとってちょっと理解に苦しむと思われるものや、内容に一部の類似が見られた者などを省き」とある。ぜひ、日本人にとってちょっと理解に苦しむものも収めてもらいたかった。民族独自の考え方に触れる貴重なチャンスを失ったような気がして残念。
1998.07.17
コメント(0)
-

「目からウロコ! 日本語がとことんわかる本」 【日本社】
目からウロコ!日本語がとことんわかる本(著者:日本社|出版社:講談社+α文庫)疑問点が多いP35「牛蒡抜き」「これは、多の野菜に比べて、牛蒡は、細く真っ直ぐに伸びているので、容易に抜くことができることからいわれたことばです。」 牛蒡は抜きにくいのではないか?P68「てんやわんや」「しかし、「てんやわんや」にしろ「てんてこまい」にしろ、語源を知らなくても、なんとなく感じがわかることばです。」 「何となく感じがわかることば」の語源を明示して見せ、本来はこういう意味なんだよ、と説くのがこの本の目的なのではないか?P95「嘘」 「烏素」の話、出典は何か?P166「露骨」 「戦場で骨をさらしている姿からきていることばではないでしょうか。」 戦場とは関係なく、骨までさらけ出すほどあけすけで、全く隠すところがない、という意味だろう。P406 「生爆塩煎肉」に「ショヌバオイエヌヂエヌロウ」とルビが振ってあるが、「塩」「煎」はnでおわるからヌでもいいが、「生」はngで終わるので、「ヌ」ではいけない。 全体に、言葉に対する愛情が感じられない。何かの雑誌のコラムなどからの寄せ集めなのではないだろうか。
1998.07.16
コメント(0)
-
「『西遊記』の神話学 孫悟空の謎」 【入谷仙介】
『西遊記』の神話学 孫悟空の謎(著者:入谷仙介|出版社:中公新書) 『西遊記』が世界各地の神話と共通する内容を持っていることを明らかにし、ヨーロッパの神話の影響があるのではないかと述べているが、それは途中から混入してきたものであって、根元テーマは「死と再生」であるという。 『西遊記』は読んだが、忘れていることが多かった。 旅の途中、妖怪に襲われては撃退するということのくり返しで、エピソードの順番などいくらでも入れ替えがきくように思っていたが、次第に孫悟空の性格が変化し、三蔵を導くまでになっていくわけで、エピソードの配列にも深い意味があるように思えてきた。 しかし、孫悟空と猪八戒については深く論じているのに、沙悟浄については明確にしていない。猪八戒と表裏一体のものではあるらしいのだが、不思議な存在だ。古本で探す
1998.07.06
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1










