2000年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
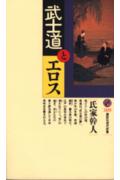
「武士道とエロス」 【氏家幹人】
武士道とエロス(著者:氏家幹人|出版社:講談社現代新書) はじめのうちは武士の逸話で、ほうほうと読んでいたら、途中から明治以降の話になり、それが続く。 看板に偽りありだ、と思ったが、考えてみると「武士とエロス」ではなく、「武士道とエロス」だ。武士道なら時代は限定されないわけだから、問題がないことになる。 主に衆道をめぐるあれこれで、知らなかったことばかりだが、よくまああれこれ文献を探ったものだ。 手当たり次第に読みあさったうちに見つけたものをまとめたのか、テーマにあった逸話を求めて、ねらいを定めて読んだのかはわからない。 著者の専攻は近世日本史だという。 時代考証のために書かれているわけではないし、江戸時代の紹介というわけでもないので、人々の暮らしに触れるというのではなく、上から見下ろしているように感じる。もちろん、それが悪いわけではない。こういう本もないと、文献に当たる必要が出たときに困る。
2000.01.26
コメント(0)
-
「旧水戸街道繁盛記(下巻)」 【山本鉱太郎】
旧水戸街道繁盛記(下)(著者:山本鉱太郎|出版社:崙書房出版) 我孫子から水戸まで。 手賀沼湖畔に住んだ白樺派の話など、『新・利根川図志』と重なるところもあるが、同じ土地を取り上げているのだからしかたがない。 『新・利根川図志』よりこちらの方が先に出版されていた。 驚くのは、著者が、1929年生まれであること。 この本の出版は1995年である。 60歳を過ぎて、日本橋から水戸まで歩き通し、自分の目で確かめて執筆しているのである。まさに精力的である。
2000.01.23
コメント(0)
-
「旧水戸街道繁盛記(上巻)」 【山本鉱太郎】
旧水戸街道繁盛記(上巻)(著者:山本鉱太郎|出版社:崙書房出版) 旧水戸街道を、東京から江戸まで自分で歩いて見て、その土地その土地の歴史、地理、伝説、現況などを記したもの。 言ってみれば、「利根川図志」のようなものを軽く読めるように書いた、というところ。 上巻は日本橋から柏まで。 この著者の本はほかにも「新・利根川図志」を読んだが、執筆態度は同じ。 文献だけで調べるよりも、つとめて土地の人に話を聞き、自分の目で確かめる。 また、現況や未来については、できるだけ明るい話題を取り上げようとしている。 「水戸街道」は正しくは「水戸佐倉街道」といい、水戸の人は「江戸街道」と呼んでいたことを初めて知った。
2000.01.20
コメント(0)
-
「秋の花」 【北村薫】
秋の花(著者:北村薫|出版社:創元推理文庫) 人の心の闇を覗く小説である。 ホラー小説よりも恐ろしい。シリーズ初の長編だが、事件が中心になっているわけではない。最初と最後、そしてところどころで触れられている、という印象が残る。 日常生活の中で、気づかずにいるだけだが、ふと振り向くとすぐ後ろに闇が存在していることがあるのだ、ということが語られている。 登場人物の中に、悪意で行動する人間は一人もいない。だからこそ怖いのだ。 このシリーズの表紙は、高野文子で、どれにも、同じ姿勢の主人公のイラストが描いてある。髪型と服が違うだけだ。そして、どれも沈んだ表情をしている。十年前に発表されたものなので、全部読んだ上で文庫版の表紙を書いたのだろうが、改めて高野文子の感性の良さに感心させられた。
2000.01.17
コメント(0)
-
「血族」 【山口瞳】
血族(著者:山口瞳|出版社:文春文庫) 自分のことをほとんど語ることなく亡くなった母。 作者は、母の死後、その母が一体どこでどんな家に生まれ、母方の親族は一体どういうつながりになっているのかを解き明かしていく。 その過程を、母の思い出などを交えて綴っている。 登場する人物は、直接関わりのない人がイニシャルになっているのをのぞけば、親族もみな実名である。 これは随筆ではないか、と思ったが、解説によれば「私小説」であるらしい。 調べながら書いたのではなく、すべてが明らかになってから書き始めてあり、後に、事実を明らかするときのための伏線も張ってある。 ミステリのようであり、読んでいるうちに引き込まれてしまった。しかし、謎解きではなく、母が生まれたあたりを歩き回り、出会った人に話を聞くことですべてが明らかになる。 それほどまでして隠さなくてはならないことか、とは思うが、当人にとっては切実な問題だったのだろう。 一カ所、読んでいて、「あっ」と思ったところがある。 工場を廻って壊れたグラインダーを集める男が登場する。 この男は、小関智弘『大森界隈職人往来』に登場する男ではないだろうか。小関智弘は、いったい何のために集めているのか分からず、同僚と首を捻っているが、この本に、その使い道が書いてある。 意外なところで意外なものとつながっているものだ。
2000.01.09
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 「困った人たち」とのつきあい方/ロ…
- (2025-11-16 04:53:29)
-








