1998年02月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
「家郷の訓」 【宮本常一】
家郷の訓(著者:宮本常一|出版社:岩波文庫) 宮本常一が、自分の育った故郷(瀬戸内の島)の暮らしを語りながら、子供の教育について述べている。 「家郷の訓」は戦争中に出されたものだが、今と同じ問題を感じているのが興味深い。「中には、子供に仕事をさせない親もあった。子供の内から荷など負うと顔をしかめるから人相が悪くなると考えた人もあった。やや生活にゆとりのあるような家にみられた現象であったが、その結果、後年親たちが顔をしかめねばならぬ場合が多かった。」(79ページ) 「近頃はこうして集まって遊ぶ風はきわめてすくなくなったという。子供達は学校での成績を争うようになってから、家のあがり口に鞄(かばん)を投げ出しておいて遊びに行く者はほとんどいなくなった。それよりは少しでもよい成績を得たいと、帰ってくれば静かに本を読む子が殖えた。」(147ページ)「われわれの子供の折りまでは、理にかなわぬこと、村の生活にそむくことをすれば、独り自分の親のみならず村人のだれでも子供をたしなめかつ叱責して怪しまなかった。親もまたこれを当然とした。しかるにいつか他家の子を叱れば、その親がかえって怒るようにまで変ってきた。子供を叱ることの許されているのは学校の先生と巡査と親だけになってきた。」(196ページ) 最後のは、今とは少し違う。今は、親は子を叱らないし、学校の先生が叱るとかえって学校にねじ込む親がいる。巡査もまた子供を叱ることはない。
1998.02.25
コメント(0)
-
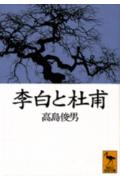
「李白と杜甫」 【高島俊男】
李白と杜甫(著者:高島俊男|出版社:講談社) 高島さんが最初に書いた本。東大の助手時代ということだが、文章はやや諧謔みが少ないだけで、ほとんど今と変わっていない。 李白と杜甫という、二人の詩人の生涯とその作品の鑑賞が主な内容だが、対照的な性格の二人がともに天才詩人として名を残してはいるものの、いずれも貧窮のうちに生涯を終えることになってしまったというのが心に残る。特に、杜甫が、親戚に預けていた妻子のもとへ尋ねていくと、末の子が餓死していたというのはあまりにも悲惨だ。 李白の就いた役職の性質など、初めて知った。わかりやすくて内容も深い。どうしてこういう書き方ができるのだろう。尊敬に値する。
1998.02.18
コメント(0)
-

「爆裂中国語」 【ジェームズ・J.ワン /もりゆみ】
爆裂中国語(著者:ジェームズ・J.ワン/もりゆみ|出版社:日経BP社) 中国語のスラング、罵倒の言葉、性に関する語などを紹介し、例文も挙げている。まず、普通の中国語の教科書には見られないようなものがほとんど。 ある程度中国語の知識がある人を対象にしているはずなのに、最後に四声の説明があるのが妙だ。また、第1章で四声を「イントネーション」と言っているが、これは「アクセント」だろう。「彼の話す標準中国語はなまりがきつくて」というのも妙だ。「標準中国語」などという言い方はあまり聞かない。「普通話」としたほうがよほどわかりやすい。原著は英語で書かれており、訳者は英文科を出た人。当然、中国語が分かる人に見てもらっているとは思うのだが、これではどういう読者を想定しているのか分からない。
1998.02.12
コメント(0)
-
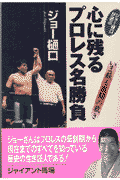
「心に残るプロレス名勝負」 【ジョー樋口】
心に残るプロレス名勝負(著者:ジョー樋口|出版社:経済界) ジョーさんが裁いた試合の中で、印象に残っているものを取り上げ、思い出を語っている。ただ思い出を語るというよりも、その試合が全日本プロレスの歴史の中で、どのような意味を持つ試合であったか、ということが語られていて、私のような日の浅いファンは知らない試合がほとんどなのだけれど、実に興味深い。 巻末は、ジョーさんとプロレスの関わりを語っていて、スキンヘッドにした理由なども書いてある。悪く取れば自慢話をするために大げさに書いているんだろうと取られてしまいそうなことでも、ジョーさんなら、「ほんとうにその通りだったんだろうな」と納得させられる。 面白いのはレスラーの呼び方。ほとんどのレスラーは呼び捨てで書いてあるが、鶴田は「ジャンボ」、馬場社長だけは「オン大」。やっぱり文章でも呼び捨てにはできないんだろうな。単なるファンにすぎない私も、田上、三沢と書くことはできても、「馬場」と書くのには抵抗を感じる。 レスラーに対する評価も冷静で、むやみにほめたりけなしたりと言うことはなく、長所も短所も書いてある。特に、川田対ハンセンの試合のところの、ハンセンに対する評価など、実にはっきり書いている。ただ、三沢だけはべた褒めに近く、ジョーさんがそこまでいうのなら、三沢って本当にすごいのかもしれないと思わせられる。田上のことはどう思っているのかなあ。 ある試合の後にテープの山を片づけていたら観客が投げ入れたらしい40センチほどのヤスリが出てきた話には驚いた。 ただ、一つだけ詳しく書いてほしかった試合もある。 ジョーさんがサブ・レフェリーをつとめたジャンボ鶴田対ニック・ボックウインクルの試合。メイン・レフェリーはテリー・ファンク。私の記憶では、テリーがスリーカウントを取った後、ジョーさんが、テリーに、ニックの肩があがっていたと抗議していたと思うのだが。レフェリーがスリーカウントを取った以上、裁定は覆らないというのが鉄則のはずなのだが、どうして抗議したんだろう。それを書いてほしかった。(私の記憶違いで、ほかの試合だったのかな) それにしてもジョーさんの本が、プロレスの本を多く出しているところからではなく、経済界というところから出るというのも不思議な話だ。
1998.02.07
コメント(0)
-

「お言葉ですが…(「それはさておき」の巻)」 【高島俊男】
お言葉ですが…(「それはさておき」の巻)(著者:高島俊男|出版社:文藝春秋) 面白い、役に立つ。「瓜田に履を納れず」を大漢和にまどわされて、「瓜畑に脚を踏み入れない」だと思っていてが、そうではなかった。 また、「アメリカ合衆国」の合衆が漢籍に基づくことなど、全く知らなかったことが多い。文章もうまいし、続きが楽しみだ。 「土人」(なんと、この言葉、ATOK11には登録されていない。慶喜や斉昭はあるのに)が明治においては差別的な意味を持たなかったことなどは、ほかの本でも読んでいたが、読んだばかりの「入門ことばの科学」にもこれが差別的意味を持つ語として出てくる。(P180)
1998.02.04
コメント(0)
-
「入門ことばの科学」 【田中春美 ほか】
入門ことばの科学(著者:田中春美|出版社:大修館書店) 平易で分かりやす文章。書き方も具体的で中身が頭に入りやすい。章ごとに「研究テーマ」が設定してあり、大学の教科書として作られたような感じ。 今は「ウラル・アルタイ語族」とは言わず、二つに分けられているというのは初めて知った。 また、日本語と朝鮮語は同系かと思っていたが、音対応する語が少ないので、同系とは見なされないというのも意外だった。
1998.02.03
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1










