テーマ: 政治について(19773)
カテゴリ: 政治
1月17日のNHK「クローズアップ現代」で、
日本の住宅が寒すぎる問題を取り上げていました。
実は危ない!ニッポンの“寒すぎる”住まい https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4739/
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4739/
住宅が寒すぎるせいで人が死んでいる。
これは暖房設備の問題ではなく、建物の断熱性の問題。
断熱性の不十分な家が原因で、
夏には暑さで、冬には寒さで、多くの人が死んでしまう。
せめて一室だけでも、
暑さや寒さをしのげる部屋があれば、
省エネにもなるし、最低限の健康を維持できるはずですが、
◇
北海道出身のわたしの友人も、
「本州の家は寒すぎる」と言っていたことがある。
実際、夏は暑すぎるし、冬は寒すぎると思います。
地方の古い日本家屋なら、
屋根裏があったり、床下があったり、縁側があったりして、
空気の層をつくって断熱性を実現していたはずだけど、
高度成長期以降に量産された日本の都市住宅は、
狭い空間をペラペラの壁で囲っただけの粗末な代物。
断熱性もなければ防音性もなく、
外観を繕っただけの、環境ホルモンにまみれた建物。
わたしも東京の賃貸アパートに住んだことがありますが、
狭くて、湿気が多くて、隣接する部屋の音がうるさくて、
暑くて、寒くて、空気が悪くて、
とてもまともな人間が生きられる環境ではありませんでした。
もともと地方の人間とは違って、
江戸時代の長屋の発想を、そのまま近代住宅に持ち込んだのでは?
とくに高度成長期以降に量産された住宅は、
見た目の効率性や機能性や、
短絡的なコスト意識にばかりとらわれて、
長く暮らし続ける人の健康や安全という観点が抜け落ちている。

ただでさえ、
高度成長期以降の日本の土建業は、
むやみに山を削り盛土をして崩れやすい土地を作り、
空気循環も無視した町をアスファルトで固めてきました。
そこに、ペラペラの壁でできた、
ハウスダストだらけで体に悪い住宅を建ててきたのです。
短期的な利益だけを求めて、
長期的な視点を度外視してきたから、
今になって、
耐用年数を過ぎた国土や住宅が壊れはじめてきている。
地震や雨によって、簡単に土地が崩れるし、
夏は暑すぎて人が死ぬし、冬は寒すぎて人が死ぬ。
そういう住環境が日本中にはびこって当たり前になってしまった。
◇
大量消費や大量廃棄を前提とした経済循環のなかで、
必要以上の電気エネルギーや石油エネルギーを要し、
短期的な建て替えを要する住宅が作られ続けてしまった。
とくに夏は、屋内が暑いせいで、
エアコンの電力を大量に消費せねばならず、
その結果、街全体がヒートアイランド化してしまい、
しかもCO2の排出によって、
地球温暖化をも助長する悪循環になっています。
口先では「省エネ」だの「CO2削減」と言いながら、
実際には国民を断熱性の低い住宅に住まわせることで、
大量のエネルギーを消費せざるをえない状況を強いている。
ひとたび停電になったら、生命すら繋げないような住宅。
◇
この種の問題を「消費者の自己責任」で済ましてはいけません。
そもそも一般の消費者には専門知識がないのだから。
行政が積極的に主導して、
国民生活の安全性を担保しなければならない。
国や不動産業界は、
建売物件や賃貸物件を、
「健康」と「安全」という観点から等級化すべきだと思う。
そうしなければ、
もはや住環境に対する信頼性を担保できないと思います。
◇
従来のように「最寄り駅が何分」などといった機能的な条件は、
コロナ禍のなかでプライオリティが下がっていますし、
そんなことよりも、
「地盤が強固である」とか、
「建物の耐震性が高い」とか、
「夏に涼しい」とか「冬に暖かい」とか、
「騒音が少ない」とか、
「ハウスダストが少ない」とか、
そういうことの方がはるかに重要性を増しています。
ことは国民の生命や健康に関することであり、
国内経済のエネルギー問題にも関わることであり、
さらには地球温暖化の問題にも関わることなのだから。



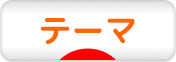
日本の住宅が寒すぎる問題を取り上げていました。
 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4739/
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4739/
住宅が寒すぎるせいで人が死んでいる。
これは暖房設備の問題ではなく、建物の断熱性の問題。
断熱性の不十分な家が原因で、
夏には暑さで、冬には寒さで、多くの人が死んでしまう。
せめて一室だけでも、
暑さや寒さをしのげる部屋があれば、
省エネにもなるし、最低限の健康を維持できるはずですが、
◇
北海道出身のわたしの友人も、
「本州の家は寒すぎる」と言っていたことがある。
実際、夏は暑すぎるし、冬は寒すぎると思います。
地方の古い日本家屋なら、
屋根裏があったり、床下があったり、縁側があったりして、
空気の層をつくって断熱性を実現していたはずだけど、
高度成長期以降に量産された日本の都市住宅は、
狭い空間をペラペラの壁で囲っただけの粗末な代物。
断熱性もなければ防音性もなく、
外観を繕っただけの、環境ホルモンにまみれた建物。
わたしも東京の賃貸アパートに住んだことがありますが、
狭くて、湿気が多くて、隣接する部屋の音がうるさくて、
暑くて、寒くて、空気が悪くて、
とてもまともな人間が生きられる環境ではありませんでした。
もともと地方の人間とは違って、
江戸時代の長屋の発想を、そのまま近代住宅に持ち込んだのでは?
とくに高度成長期以降に量産された住宅は、
見た目の効率性や機能性や、
短絡的なコスト意識にばかりとらわれて、
長く暮らし続ける人の健康や安全という観点が抜け落ちている。

ただでさえ、
高度成長期以降の日本の土建業は、
むやみに山を削り盛土をして崩れやすい土地を作り、
空気循環も無視した町をアスファルトで固めてきました。
そこに、ペラペラの壁でできた、
ハウスダストだらけで体に悪い住宅を建ててきたのです。
短期的な利益だけを求めて、
長期的な視点を度外視してきたから、
今になって、
耐用年数を過ぎた国土や住宅が壊れはじめてきている。
地震や雨によって、簡単に土地が崩れるし、
夏は暑すぎて人が死ぬし、冬は寒すぎて人が死ぬ。
そういう住環境が日本中にはびこって当たり前になってしまった。
◇
大量消費や大量廃棄を前提とした経済循環のなかで、
必要以上の電気エネルギーや石油エネルギーを要し、
短期的な建て替えを要する住宅が作られ続けてしまった。
とくに夏は、屋内が暑いせいで、
エアコンの電力を大量に消費せねばならず、
その結果、街全体がヒートアイランド化してしまい、
しかもCO2の排出によって、
地球温暖化をも助長する悪循環になっています。
口先では「省エネ」だの「CO2削減」と言いながら、
実際には国民を断熱性の低い住宅に住まわせることで、
大量のエネルギーを消費せざるをえない状況を強いている。
ひとたび停電になったら、生命すら繋げないような住宅。
◇
この種の問題を「消費者の自己責任」で済ましてはいけません。
そもそも一般の消費者には専門知識がないのだから。
行政が積極的に主導して、
国民生活の安全性を担保しなければならない。
国や不動産業界は、
建売物件や賃貸物件を、
「健康」と「安全」という観点から等級化すべきだと思う。
そうしなければ、
もはや住環境に対する信頼性を担保できないと思います。
◇
従来のように「最寄り駅が何分」などといった機能的な条件は、
コロナ禍のなかでプライオリティが下がっていますし、
そんなことよりも、
「地盤が強固である」とか、
「建物の耐震性が高い」とか、
「夏に涼しい」とか「冬に暖かい」とか、
「騒音が少ない」とか、
「ハウスダストが少ない」とか、
そういうことの方がはるかに重要性を増しています。
ことは国民の生命や健康に関することであり、
国内経済のエネルギー問題にも関わることであり、
さらには地球温暖化の問題にも関わることなのだから。


お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.02.28 02:28:01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(209)ドラマレビュー!
(291)NHKよるドラ&ドラマ10
(26)NHK大河ドラマ
(18)Re:リベンジ~ゆりあ先生~Dr.チョコレート!
(19)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(187)メディアトピック
(37)映画・音楽・アート
(71)漫画・アニメ
(18)鬼滅の刃と日本の歴史。
(27)岸辺露伴と小泉八雲。
(19)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)東宝シンデレラ
(62)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(48)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(38)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(62)トリリオン~ONE DAY!
(16)警視庁・捜査一課長 真相ネタバレ!
(12)「エルピス」の考察と分析。
(10)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(10)北斎と葛飾応為の画風。
(13)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(18)スポーツも見てる!
(29)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)家政夫ナギサさん
(6)半沢直樹!
(4)探偵ドラマ!
(7)倉光泰子
(4)パワハラ
(7)ドミトリー
(37)ゴミ税
(3)その他。
(1)夢日記
(4)© Rakuten Group, Inc.









