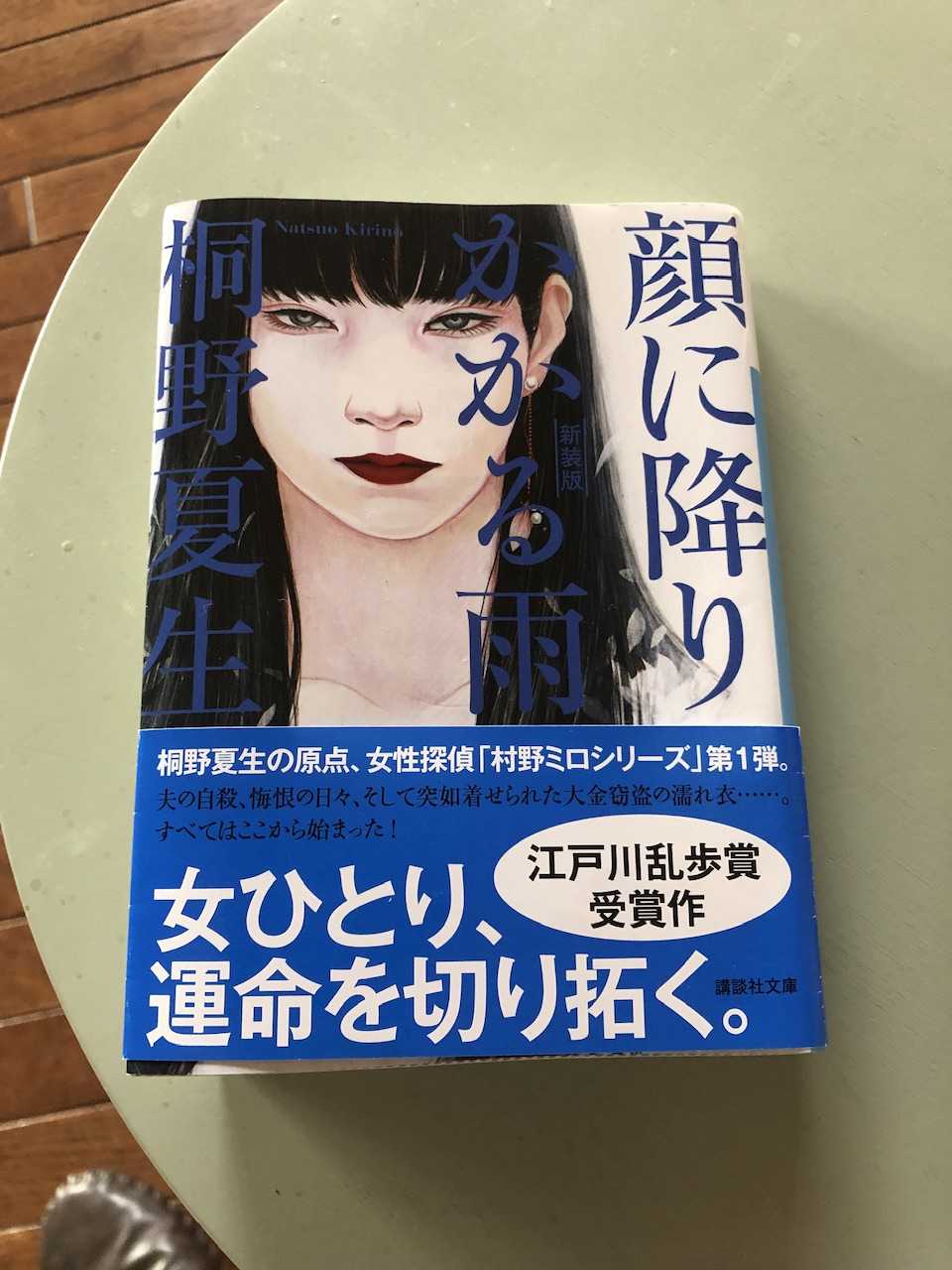2008年05月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
若菜@与謝野源氏
若菜の上巻は源氏が40歳のころのことで、少しだけ朧月夜の尚侍の君と源氏が対面する場面があり、ここもなかなか心理描写に長けた面白い表現があるのです。 朱雀院のご出家に伴い、院の尚侍でいらしった朧月夜の君もその任から離れておいでになります。そこへ源氏の君は朧月夜の君に「お逢いしたい」とお伝えになります。 すると意外にも「めっそうもないこと」と、きっぱりと断わられてしまいます。 原文では「げに人は、もり聞かぬやうありとも、心の問はんこそ、恥づかしけれ」つまり、他人に漏れ聞かれることよりも、自分自身にとって恥ずかしいこと…と、もっともなことを言います。 しかし源氏が「昔のようなあるまじき心など、40歳となった今ではございませんのに」と、平静を装って強く対面を所望なさると「いたく嘆く嘆く、ゐざり出で給」ふのです。 ここで作者は「さればよ。猶、けぢかさは(昔のままなり)と、かつ思さる」と短く書いています。「けぢかさ」には、親しみやすさ、気軽さといった意味があり「なんだかんだ(上記のようなことを)言ってもやっぱり出てくるのだから、あの性格は昔と変わらないなぁ」と、一方ではお思いになるのです・・・といったところでしょうか。この部分の現代語訳では、谷崎源氏:「さればこそ、やはり人なつっこさは変わりがないのだと、一方ではお思いになります。」瀬戸内源氏:「『やはりこうだ。靡きやすさは昔のままなのだから』と源氏の院は逢いたいと思う一方で考えていらっしゃいます。」与謝野源氏:「だからこの人は軽率なのであると、満足を感じながらも院は批評をしておいでになった。」 私は与謝野源氏をあまり好きにはなれなかったのですが、この短い文章の中で「満足を感じながらも」一方では「批評をして」と、男の自信に満ちた支配欲と身勝手さを充分に表現しているところなど、私は「すごいなぁ!」と感嘆してしまうのです。
May 30, 2008
-
「提灯」
私が中学生のころだったでしょうか。通学途中の電車通りにはたくさんの医薬品や衣料品のメーカー、大小いくつもの問屋や商店が並んでいました。そんな建物の看板の中で、いつも目にする「提灯」という漢字がありました。 私は「これはいったい、なんと読むのだろう」と、思ったのです。そうなると気になって仕方がありませんでした。漢和辞典を引けばすぐ解決したのですが、なぜかそれは私にとってもったいないような気がしたのです。 私はこの文字を長い間考え続けました。それが甘やかな秘密めいた暗号のように思えて、誰にも言わずひたすら心の中で大事に思い続けました。 毎日通るたび「ていとう、ていてい・・・、ていちょう・・・」と読むうちに、ある日突然それが「ちょうちん」であることに気がついたのです。さっそく学校の図書室に飛び込んで漢和辞典を引き、それが正しいことを確認した時の喜び、嬉しさは、長い間欲しかったものを手に入れたような、あるいは喉もとに詰まったものがすとんと落ちたような、なんともいえない満足感と爽快感でした。 求めよ、さらば与えられん。尋ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。すべて求むる者は得、たづぬる者は見いだし、門をたたくものは開かるなり。マタイ6:7~8
May 27, 2008
-
若いお客様
昨日の午後のことです。おしゃれで背の高い、若くすてきな男性が3人も来店してくださいました。 カウンターの上にある開店チラシを手に取りながら「女性専門なの?男性の精力減退に、なにかいいものない?」といいます。 私は相談机に広げていた本や辞書、パソコンを端に引き寄せながら「男性も女性も区別はありませんが・・・。」と、腎陽と腎陰が精力の源であることをお話しました。 けれど彼らはそんなことよりそのクスリがどんなものか、いくらするのかが知りたいらしく、「どれなの?」と急かします。 私はしかたなく説明を諦めて「補腎陽」の漢方薬を出すと「高いんだねー!」、「なんだ、そのときだけ飲むんじゃないんだ」、「こんなにいらないんだけど」と異口同音に言います。そのうちの一人が「目が疲れる」と言えば、もう一人は「更年期の漢方薬って、なに?」と口を挟み、「花粉症なんだけど、何かない?」と賑やかです。 結局「目が疲れる」といった男性に肝陰を補う芍薬甘草湯を一週間分売りましたが、忙しくて慌しくて、あのすてきな3人組が帰った後は、私が一人ぽつんと取り残されたような気分になりました。 そのすっきりしない気持ちの中には、もう少しゆっくり不調感を聞いてあげたかったという思いと、もっとしっかり説明したかったという不全感がありました。目の疲れだって虚実があります。私は虚を補ったのですが、加えて清熱もしたほうがよかったかもしれません。更年期というなら、杞菊地黄丸もお勧めしたいところです。それより手っ取り早く、開竅薬を売ったほうが良かったのかしら・・・。 なんだか反省点ばかりが気になってしまうのですが、それでも新しいお客様、しかも若い男性が躊躇なく来てくださったことに喜びを感じた一日でした。
May 25, 2008
-
ことばの壁
四川大地震のニュースが日々報道される中で、よく目にしながら意味の分からない簡体字の中国語が出てきます。うかんむりに火という漢字です。これはいったいどんな意味があるのだろうといつも思いながらも中日大辞典は店にあるため、なかなか引けませんでした。 じつはこれは「災」という字で、災害、災難という意味がありました。 漢字を日常語としている中国と日本では同じ意味のものもありますが、中国本土は簡体字を使いますし、その意味も日本とは微妙に異なり、まして発音はまるで違います。 成都の病院に派遣された日本の医療チームが、言葉の障壁に困難を感じながらもなんとか任務を遂行できることを祈る毎日です。
May 24, 2008
-
ミニ・ジャングル
100円ショップで観葉植物を買いました。葉がひょろひょろと伸びるクッカバラというのと、シュロチク、それにサトイモの葉のようなクワズイモの三種類で、どれも10~20センチほどの高さの小さなものです。プラスチックの窮屈そうな入れ物から素焼きの鉢に植えかけると、なかなか素朴ですてきな雰囲気になりました。 日当たりのいい窓辺において毎日水をやっていると、小さくて可憐だった葉っぱがだんだん大型に広がるようになり、クッカバラなどは葉の重みで倒れんばかりになりました。すると地面に近い茎の部分から黄緑色の根が出て下に向かって伸びていき、植物全体を支えるように土に突き刺さっていくのです。しかも葉っぱは買ったときの3倍もの大きさになり、四方八方に大きく突き出て、ダイナミックというよりなんだか下品に思えて、私はがっかりしています。おまけにシュロチクは、猫が食べてしまってぼさぼさになりました。クワズイモはクッカバラに負けじとばかり濃い緑色の葉を、「これでもか」といわんばかりに伸ばしていて、ここだけまるで小さなジャングルのようです。・・・ちいさくて細くて可憐なところが良かったのに・・・。
May 18, 2008
-
鳩時計
店にドイツ製の鳩時計を買いました。家の形をした箱の、おなじみの鳩時計です。 30分には一回だけ、正時にはぼーんと音が鳴ったあとに、白い鳩が小窓から顔を出して時間の数だけ「ぽっぽー」と、頷きながら鳴くのですが、その声と姿がとてもかわいらしいのです。 箱の下部からは錘がふたつ鎖で下がっていて、8日かけてだんだんと下まで降りてきます。 錘はひとつが1.5キロもあってしかもこれを引き上げるのですから、時計を掛ける壁の内部に柱がなくては持ちません。大工さんがその場所を確認し、大きな釘を打って掛けてもらったのですが、水平でないと振り子が左右均等に動くことができないのですぐ止まってしまいます。ちょうど内装屋さんも入っているときだったので、みんながこのかわいい時計に注目し、鳩が鳴いたときは「おお~、鳴いた、鳴いた!」と歓声があがりました。 じつはこの鳩時計、時間合わせ(つまり振り子の位置合わせ)に、かなりの時間と工夫と手間を要するのです。仕組みはうちの居間にあるホール・クロックと同じなのですが、ホール・クロックは冬になると遅れ気味で、暖かい季節になると逆に早くなるので、一年中4~5分程度の時間にずれがありそれが当たり前のようになってしまって、神経質に合わせたりしたことがありませんでした。 毎朝店に入るとまず鳩時計の時刻を合わせるのですが、振り子の位置をほんの数ミリ動かしただけで時間が早くなったり遅くなったりします。一日二日では気づかないのですが、三四日すると数分遅れてきたり、逆に進みすぎたりしてなかなかうまく合わせられません。 遅れたときは振り子をこころもち上げ、長針を動かすだけですみますが、早くなったときは振り子の動きを進んだ分だけ数分止めて、時間合わせをしなくてはなりません。その「数分」がクセモノで、つい忘れて数時間が経ってしまいます。鳩時計は短針を動かすことができないので、そこでまた脚立に乗って30分ごとに長針を指で動かして音を出し、鳩にお出ましいただき、鳴いてもらって時間調整のしなおしです。このあたりはホール・クロックも同じです(ただホール・クロックはサイレントにし、長針をぐるぐる回して調整します)。 パートナーは「デジタルじゃないところがいいんだから、多少のずれは気にしない気にしない。」と言いますが、そこをなんとかジャスト・フィットさせたくて毎日の日課にしていました。 それが苦労の甲斐あって、このごろようやくうまく時間が合うようになったのです。けれどすっかり習慣化していたせいか、なんだかとても物足りない気分になってしまいました。
May 17, 2008
-
贖罪と大惨事
成都中医薬大学の外事処によると、「成都市内の被害はそれほど大きくはなく、大学の先生方もみなご無事」とのことでした。 しかしTVの報道では、成都市内は学校のほかに「中医の病院が倒壊」とのレポートが伝えられ、私はびっくりしてしまいました。実際のところ大学とTV特派員のどちらが本当の状況報告なのかと、首を傾げてしまいます。レポーターがありもしないことを伝えるのは、考えられないことです。しかし・・・。 それにしても、こういった不幸を目にするたびに、神様は人間の罪を贖ってくださったはずなのに、どうしてこんなに惨いことをなさるのか・・・と、空しい気持ちになるのです。
May 16, 2008
-
身軽な暮らし
店のまん前が、神社です。境内の広さはよくわかりませんが、あまり大きくなさそうです。それでも不安や心配事の多い世の中だからでしょうか、その小さな神社にも毎日いくばくかの人や車の出入りがあり、手を合わせて祈る姿を見ることがあります。そのかわいい神社の短い参道に、先々週の日曜日には青空骨董市がたちました。ちょっとのぞいてみると、仏像のレプリカや立派な装飾を施した陶器の器があるかと思えば、コカ・コーラの懐かしいグラスや、サントリーの灰皿、再生硝子で作ったかき氷用の器など、まるで引越しのゴミに出したようなものにまで、ちゃんと値札がついて売られているのです。中で、木質の大きな仏頭に目が留まりました。広隆寺の弥勒菩薩と思しき、上品なお顔です。見とれていると、お店の人が自慢げに声をかけてきました。「これ、いいでしょう。仏像ばっかり集めてた人のとこから出たんですけどね。」値段を訊くと「5000円」だといいます。驚く私に「プラスチックだからね~。」と持ち上げて見せ、「でも良く出来てるでしょ。」と勧めます。ちょっと気持ちが揺らめいたのですが、やめておきました。近頃は身の回りの品物を極力少なくして、身軽に暮らそうと思っています。
May 15, 2008
-
乳香(にゅうこう)
乳香を仕入れてみました。方剤の中に配合して使おうというわけではないのですが、別名が薫陸(くんろく)香ともいうらしく、お香の材料のひとつです。それがどんな香りなのか、どんな形状をし、どんな色をしているのか知りたかったのです。カンラン科の植物の樹皮に傷をつけて採取するそうで、中国の古い医学書でもその芳香の気が記されています。肝、心、脾に帰経し、効能は血液の流れを改善し、気を巡らせ、痛みを止め、腫れを引き、皮膚の新生を促すので、古くから外科の要薬とされています。入荷したものは透明がかったオレンジ色の、ちょっとクリスタルな粒でした。もともと樹脂ですから、口に含むと体温でとけてちょっと歯に粘つきますが、多少の苦味はあってもさわやかな香りがします。本当はこれをお香に加工したいところですが、それには高価な沈香や白檀、入手困難な麝香が要ります。キリストが生まれたとき、東方の3人の博士が黄金や没薬とともに持ってきたこの「乳香」ですが、今では沈香や麝香のほうが手に入らなくなってしまいました。
May 14, 2008
全9件 (9件中 1-9件目)
1