2012年04月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
トレーナーが読むべき必読本
少し前のトレーナー・セミナー@Skypeの音声の一部をアップしました。↓クリック★トレーナーセミナーの推薦本「ミッキーマウスに頼らない本物の指導力」「部下を持ったらどんな本を読んだらいいですか?」という質問をよく受けます。その度に迷いました。それなりにためになる本はあるものの、著者の経験や所属企業があまりにも特殊過ぎてなかなか参考になる本がなかったというのが本音でした。しかしこの本が出版されてからというもの、即答できるので、プレッシャーから開放された気分です(笑)。著者である町丸義之氏とは、初めて出会って今年で20年になります。その間、町丸氏の実績と育てた部下たちと付き合ってきて、改めてそのレベルの高さと地に足がついた指導力には脱帽です。本に出てないことを言えば、町丸氏は、顧客満足と部下の指導力、それにその施設の利益を生み出す、、、この3つを両立させることができるのが大きな特徴です。単に「お客様のために」とか「部下を思う心」みたいなきれいごとではなく、ビジネスとして成り立つようにする能力がこうした本の著者の中では突出しています。(現実に)読んでみると、特に涙ぐむ感動やマインドを押し付けられることなく指導に必要なのは「冷静さと勇気」なんだということがわかります。トレーナーばかりでなく、リーダー、店長、幹部社員まで部下の育成に悩む全ての人にお勧めできる一冊です。(悩まない人はいないでしょうが、、、)
2012/04/30
コメント(0)
-
新入社員研修のカリキュラムで抜けているもの
毎年この時期は様々な企業の新入社員研修に呼ばれます。そこで、カリキュラム全体を見せてもらうと、、、たいていは似ています。(別に悪いことではないですが、、、)ただし、本当は「入れた方がいいのにな」という「抜け」カリキュラムがあるのも似ています。いくつかありますが、そのうちの一つは「退職の仕方」です。入社時に辞め方を教えるなんて、、、とムキになる人もいますが、単なる手続きのことではありません。数年のうちに辞めていく人がいるのは事実だから、正しい辞め方を教えておくべきだということです。契約を守っていればそれでよし、というレベルではなくて、例え1ヶ月前に退職届けが提出されようとも、退職に当たってギクシャクすることが多い。逆に、退職後も気持ちよく食事に行けるくらいの関係はどのくらいあるのか?これがポイントだと思います。最近では、今後の期待と本人の希望でわざわざ海外留学をさせたり、海外勤務をさせてみたら、帰国した数ヶ月すると退職届け、、、というトラブルが多発しています。(私の周辺では特に)海外でよい刺激をもらったはいいけど、それで辞められては、何のために人材投資したのか?と泣きたくなるのはどの経営者も同じでしょう。本人は海外で視野が広がったとかで、ステップアップ病にかかってしまっているので、何を話しても言うことを聞きません。こうしたことに懲りて、海外留学や海外勤務の希望を取らなくなった会社もあります。(現地採用、在日外国人採用に切り替えたわけです)最近の企業の動向をみても、そうした苦い経験の結果だと思います。(もちろん、国内の新卒者たちにとってはいい迷惑です)たかが辞め方でも、こうして企業の人事制度に大きな影響を与えていきます。同時に、次の後輩たちのチャンスが減ってしまう結果になる、、、そういうこともしっかりと教えなければならないと思います。それでも転職をしていく人はいます。その中で、本当にステップアップしている人材は、前の会社の仲間やボスたちと普通に再会できる人です。「堂々と再会できる人になってください」
2012/04/25
コメント(0)
-
インバウンドセミナー「集客に効果的なお金の使い方を教えてください」
Skypeで実施したインバウンドセミナーでチャットで寄せられた質問に応えた音声の一部です。↓クリックインバウンドセミナー「集客に効果的なお金の使い方を教えてください」
2012/04/24
コメント(0)
-
中国人観光対応セミナー:Case35をアップしました!
2011年10月3日号の週刊トラベルジャーナル「中国人客の購買パワー獲得術」Case35より。Skypeで実施したセミナーの録音の一部です。↓クリックでYoutubeへ中国人観光客対応セミナー:Case35「スキップ経済のスピード感」内容は日本からみれば何でもかんでもスキップしてしまう中国の事情。(ビデオはスキップしてDVDへ、、、など)これは旅行でも小売業の販売現場でも同様です。ついこの間まで寝巻きやジャージ、すっぴんで歩き回っていたかと思えば、ネイルしてガールズファッションが急増してます。こうしたことを理解して対応しましょう、、、などです。【お問合せはこちらをクリック】
2012/04/19
コメント(0)
-
コンサルタントになって20年、その原点は、、、
販売サービスの研修やセミナーで講演をしていると、よく聞かれるのが「斉藤さんの基本、原点はやっぱりディズニーランドですか?」という質問です。まぁ多分、そういう答えの期待があるのかもしれませんが、答えは「NO」です。なぜならディズニーランドで学んだことは「運営」であって、販売ではないからです。ディズニーやサンリオと言った世界的ブランドで働くと「凄い」と思われがちですが、こと「販売」に関してはあまり参考になりません。黙っていてもそれなりに売れるからです(笑)。すでに有名で知られている「あこがれ」の商品を販売するのは差ほど難しいことではありません。対して、日常品や無名ブランドの商品を販売する時こそ創意工夫が必要だし、大いに勉強になります。先日、久しぶりに中野区鷺宮に行きました。何を隠そう高校生時代は鷺宮の商店街の魚屋さんでアルバイトをしてました。毎日授業が終わると(または終わらなくても、、、または学校を休んだ時でも、、、:笑)夕方から魚屋さんで働きました。だいたい3hの仕事です。高校生になったらアルバイトをしたいというのが私の希望で、父は魚屋さんのアルバイトは許可してくれたからそうなっただけで、別に魚屋さんが好きだったわけではありません。そのお陰で3年間働いて「魚嫌い」がすっかり直って「魚好き」になってしまったのですから、父の思惑通りになったのでしょう。魚屋さんは夕方から約3時間くらいが勝負で、それ以外の時間帯はほとんど売れません。そして、なんと言っても生魚ですから「毎日売り切れ!」が目標です。とてもシンプルです。余ったらほとんど捨てなければならないので。最も強烈に印象の残っているのは、例えば今日はアジをたくさん仕入れたのでアジを売れ!とおやじさんから指示されます。それで私たち学生アルバイトは各自が創意工夫しながら薦めます。すると私より2倍も3倍も売る人がいました。ユウちゃんと呼ばれていて学校は違うけど同級生でした。「なぜなんだ?」と考えたところで答えは簡単でした。商品は同じ生のアジです。だけど接客が違うわけです。(魚屋さんですから特に「身だしなみ」に大きな違いなんかありません)そこでよくよく耳を澄ましてユウちゃんの会話を聞いてみると「このアジは刺身でもいけるけど、ちょっと贅沢に天ぷらでもおいしいですよ」とか話していました。そうです。ユウちゃんは、料理の提案をしていたのです。私はただただ生のアジを「新鮮ですよぉー、これ見てくださいよ、きれいでしょう」とか、オウムのように繰り返していただけでした。そこで「ユウちゃんのようになりたい」と思ってみたもののどうして良いのか?わかりません。結局、おやじさんに相談しました。聞けばユウちゃんは母子家庭でした。お母さんが夜遅くまで働いているから、小学生の時から兄弟で自炊をしていたとのこと。だから料理に詳しいので良く売れるのだ、と。そして、「お客さんは魚のコレクターじゃないぞ、料理して美味しい食事がしたいだけだ。魚はその材料なんだ」と教えてくれました。今となっては当たり前のような話ですが、高校生の私にとってそれこそ目から鱗が落ちた瞬間でした。そうは言ってもその頃の私は、目玉焼きとホットケーキくらいしか作れませんでした。お客さんに料理を説明する知識は持ち合わせてません。そう愚痴ると、翌日おやじさんが練炭を買って来てくれました。魚屋の中に置いて練炭を使って色んな料理を作ってくれました。それ以来毎日料理教わりつつ魚を売る日々が続きました。(ちなみに、それが私たち学生の食事にもなってました)そんな私たちの姿をみて、店の両隣の八百屋さん、肉屋さんのおやじさんたちが可愛がってくれるようになりました。気温が下がってくると、隣の八百屋のおやじさんが「今日は白菜が安いから鍋を薦めろ」とかアドバイスをしてくれるようになりました。そして、すぐに「今日はタラで鍋がいいですよ」とどんどんお薦めします。それでタラを買ったお客さんはそのまま隣の八百屋で白菜を買う、、、という流れです。(これがきっかけで販売サービスに興味を持ちました)そうした料理の知識が全くない私にとって、店の両隣の八百屋さんと肉屋さんのアドバイスはとても貴重でした。さらに夜7:00を回ったら、少しずつタイムセール、つまに値引きをしながら売っていきます。売上げと廃棄ロスのバランスを常に計算しなければならないので、今考えても大変高度な体験だったと思います。運営サービスのコンサルタントになって今年で20年経ちますが、原点はやはり魚屋さんだと思います。近年、書店には様々なビジネス本(セールス、店舗運営、接客、、、)が並びますが、よく見てみると別に新しい手法なんてそうあるものではありません。どれも見せ方や表現を変えているだけで基本は商店街にいくらでも転がっています。そんなわけで、今もスーパーマーケットの研修の際にはやっぱり魚売場の販売サービスに関して熱が入ってしまいます(笑)。
2012/04/19
コメント(0)
-
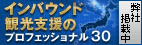
「インバウンド観光支援のプロフェッショナル30」に 選出されました。
日本最大のインバウンドのポータルサイト「やまとごころ.jp」が監修運営する、「インバウンド観光支援のプロフェッショナル30」に選出されました。私たちが提供できるサービスは、1.現地で行う中国人従業員の販売サービス研修で得た情報と2.中国人観光客を誘致・アテンド業務を通じて得た情報、3.上海インバウンド・カフェの運営を通じて得た情報、、、、の3つ「アナログ接近戦」の情報を中心に日本の観光産業の活性化(設ける方法)の支援を行うことです。今まで実施してきた主なセミナー・研修は以下の通りです。●中国人観光客の動向の実態。不平不満とは?●中国人観光客にもっと売るおもてなし術●もう一品売るための飲食店メニューの作成方法●アフター7マーケットの可能性とその対策●中国人観光客のショッピングモールでの回遊率をあげる方法●中国人観光客が納得するホテル・旅館のサービス改善方法●中国人観光客を誘致するための媒体の使い分けと活用方法●中国人スタッフの育成方法と活かし方●現場で使える簡単な中国語会話の学習方法●中国人観光客対応に必要なツールとその使い方、、、などです。その他、相談があれば上記までお問合せください。
2012/04/12
コメント(0)
-
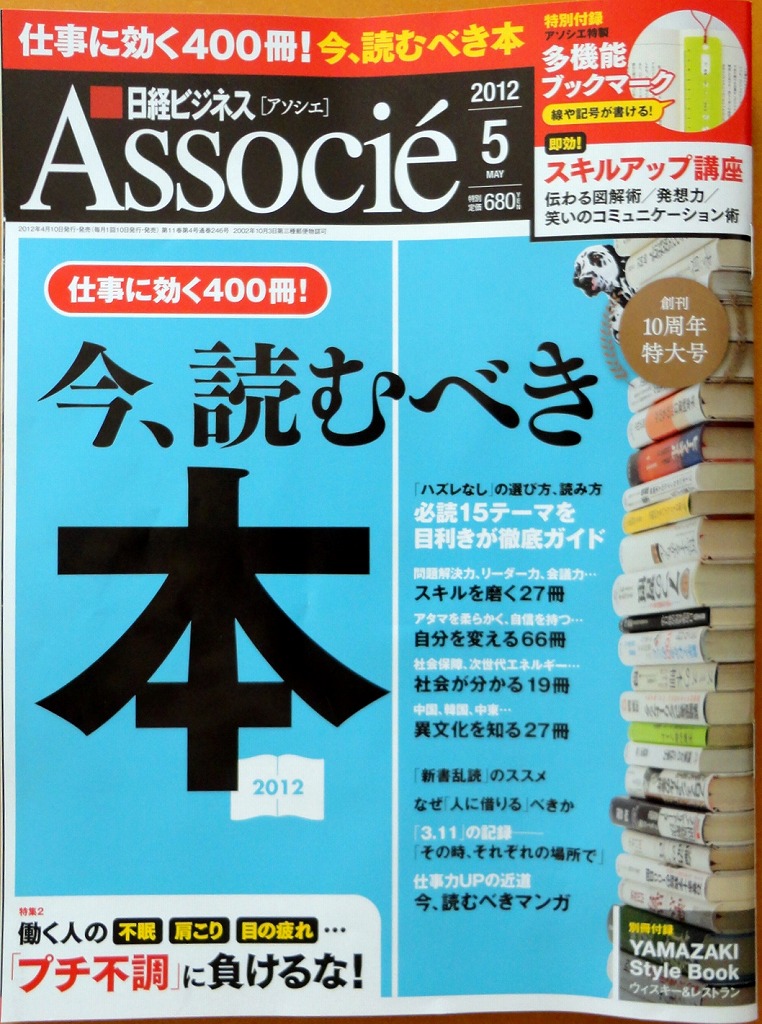
日経Associe2012年5月号で紹介されました。
日経Associeの2012年5月号はその中の「世界を知る」の項目の中で中国ビジネスのページで本が紹介されました。「超速中国語」などのe-ラーニングシステムで有名なWEIC社の内山社長が記事の中で推薦してくれました。===内山社長が「まずはこれから」と薦めているのが「島耕作」です。今や知らない人はいないほど有名になったビジネスマン漫画です。実は、私自身2000年に始めて北京のプロジェクトに参加する際に、「取締役島耕作」を読んでくるように、、、と言われて読破しました。これは大変勉強になりました。単なるビジネス書で勉強すると、淡々としていて「手に汗握る」ことがないので、なかなか身につきません。頭で理解して「知っている」レベルで終わります。しかし、漫画の場合は感情移入できて「自分の時は、、、気をつけよう」と感情の記憶としても残るので特に失敗の回避に役立ちました。===中国に進出する企業を見ていると成功と失敗の格差が凄まじい。近年特にトラブルが増加しているようです。その理由や原因は色々ありますが、大きな原因として「海外ド素人」がいきなり中国に行かされてしまう、、、というがあります。「やればなんとかなる!」とばかりに送り込まれて(または本人の希望も)、数年で見事に撃沈、、、ということが多々あります。私がお付き合いさせて頂いている日系大手企業の皆さんのほとんどが「中国で4カ国目です」のような人ばかりでした。だから冷静だし、当然、語学力も高い。または、通訳の正しい使い方も知っているわけです。ごくたまに、裸一貫で来て成功した人がクローズアップされてしまうと、それに続けとばかりにやってきますが、そういう特別な人と自分は違うんだ、という冷静な心が必要です。それは規模によっても違うでしょう。私たちのような小規模事業の場合は、そのスキルと実績があればそれを武器にすれば何とかなります。(ノウハウを盗まれないような工夫は大事)しかし、多くの中国人消費者を相手にするような規模の大きい商売の場合、やる気だけではどうにもならないのが中国です。なので、今回の特集で紹介されている本くらいは読んだ上に、その業界にいる中国ビジネス先人たちのレクチャーをしっかり受けて、避けられる失敗はしっかり避けて、少しでも効率よくビジネスをしてもらいたいと思います。
2012/04/12
コメント(2)
-
中国人観光客対応セミナー:Case39をアップしました。
週刊トラベルジャーナルで連載中の「中国人客の購買パワー獲得術」の記事を元にSkypeを使ったセミナーで話した音声の一部をアップしました。中国人観光客対応セミナー:Case39内容は、接客現場にお目見えしたipadなどのツールの活かし方。だけどツールより人が中国語を話した方が儲かりますよ、だから少しずつでも中国語を勉強しましょう、それで現場に適した勉強に仕方の紹介、などです。
2012/04/10
コメント(0)
-
日本のGDPはとっくに世界一位という考え方
上海で研修が終了した夜、あるバーで上海人の経営者とチュニジア人の経営者と飲んだ時のこと。両名とも、かつて日本にに10年間も住んでいたことがあり、会話はほとんど日本語でした。その時、チュニジア人のAさん(仮称)に指摘頂いた日本経済の見方がとてもためになったので、一部紹介します。===GDPに関して、いつまでもあれこれ議論されているが、日本の庶民は素晴らしい。他国に比べれば大騒ぎせず、淡々と暮らしているし、極端に生活のグレードも落ちてない。それに日本で暮らして大発見があった。私は少々郊外で暮らしていたので、兼業農家をやっている人とかいて、「今日はこれが採れたから、、、」と野菜をタダでくれた。(私たち外国人のアパートに届けてくれていた)そういう人がたくさんいた。こちらはお礼するものがないから、アパートで同居する外国人たちと交代で各自月に2日間ずつ、その農家の人々の作業の手伝いをした。また、ある日本人主婦たちは食事を作りに来ていた。その農家の老夫婦たち仲間は交代で近所の主婦の子供たちを預かっていた。だから主婦たちは、昼間に働きに行くことができた。こういう個人やグループ間の貸し借りが非常にうまく作用していた。これらはお互いに金銭のやり取りはない。だから、こういう活動は経済活動の指数には反映されない。しかし、現実にはこのような活動は日本全国で大小様々な形で行われている。もしも天才的な経済学者か誰ががこういう活動を経済活動のお金に換算することができたとしたら、日本のGDPはとっくに世界一でしょう。しかしながら、ビジネスモードになったらこうした活動続くのかどうなのか?わからない。現在も、上海の私たちのビジネスの企画書を日本の友人が手伝ってくれている。ここでも「善意の手伝い」だ。しかし、そのお礼に彼らが欲しい中国の情報を定期的にレポートにして提供している。人々は賢くて、経済的に不況になると「物々交換」や「手間手間交換」を始めるのだ。全てをビジネスにすればGDPがアップして幸せになれるか?と言えば、それはNOなのかもしれない。何でもかんでも契約書、見積書、請求書の「紙ビジネス」にしたいとは思わない人がいるのだ。このような「交換」のままで良いものもある。ビジネスをしたいというよりは、お互いに困っている部分を補い合って、生活しやすくしているのだ。これが少しでも成立していると、精神的な充実感とか安心感を感じることができる。これは信頼と絆があってはじめて成り立つとても高度な社会でどんな国でも真似できるものではない。こういう世界にはない素晴らしいお手本は皆足元にあって書店やビジネススクールにはない。このような活動ができる善意を再確認する教育を全国に広めていけば、高齢化も少子化もどんどん改善するはずだ。この教育に関してだけは妥協してはいけない。日本の強みがなくなるからだ。日本の家は狭いと言うけれど、こうして地域と一体化して暮らしているととても広く感じるものだ。だから、日本に滞在中の私たちは金銭的には決して裕福ではなかったが、美味しい食事をたくさん食べることができたし、人々と一緒に良く働いて多いに遊んだ。とてもハッピーな気持で暮らすことができた。私は日本の庶民が勝手に自然にやっていることが正しいと思っている。こんなことができるのはおそらく日本だけだ。日本の庶民は人から奪うとか騙すことを考えていないからだ。これは外国から見れば凄いことだ。現在私が住んでいる上海の経済活動は活発だが、その分、凄まじいストレスと付き合わなければならない。社内も社外も社会も騙しあいの壮絶なバトルが繰り広げられているからだ。全ての活動をお金に変えようとする典型的な街と言える。それが果たして幸せなのかどうか?日本人はすぐに欧米や中国、韓国と比べて、あーだ、こーだと自虐的になるが、全く違うのだから比べても仕方ない。日本人が幸せになるには、あくまでも日本流で行けば幸せになれるのに、、、といつも思っている。===などなど生活に密着した「そういう考え方もあるんだなー」というユニークな視点の数々でした。無料でコンサルを受けた気分だったのでワインをご馳走させて頂きました(笑)。
2012/04/05
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










