2012年05月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
SNSでフォロアーを増やさなければならない人たち、必要ない人たち、、、
大事な話しだなと思ったのでシェアしたいと思います。先日、ある会議後の懇親会で関係者同士で食事をしました。名刺交換をした後、IT大好き系?35歳くらいの自称青年起業家Aさんが次第に話題の主導権を取り出して、自然とSNSやブログの話しに、、、。「○○さんはFacebookやってますよね?フォロアーはどのくらいですか?」とテーブルを囲む人々に聞いていきました。「私は、、、120人くらい」とか「50人くらい」とか、そんな答えが多かったと思います。すると、「えー?皆さん少ないですねー。僕は12000人いますよ。なんでだと思います?コツを覚えれば1000人は楽勝ですよぉぉぉ!」と興奮気味に得意満面でした(笑)。「自分をマーケティングするにはノウハウがいるんですよ。これだけフォローがいればイベントの集客にも効果的で、、、友達の友達とクリック一発でつながるんですよ。そうすれば、、、」と延々と続きました。周りは大人な人たちで、およそ30分間くらい黙って聞き手になっていました。すると話しを聞いていたナイスミドルな経営者の方が口を開きました。「それは君がそれを商売にしているだけでしょう?私は自分の友達とつながりたいだけだ。故郷の同級生とか、20年会ってない従姉妹とか、、、。そして、そのなかなか会えない友人たちの近況が知れれば、私はそれで十分なんだ。そういう意味ではありがたいツールだと思う。だけど、私はそんなにたくさんの友人もいないし、別に無理して欲しいと思っていない。今いる友人知人ともっと少しでも会う機会を増やすためにやっているだけだ。だいたい仕事の関係を除いて、一年に100人もの友人には会えないしょう?人の人脈を利用するようなことが楽しいの?クリック一発で友人ができると思ったら大間違いだし、私はゴメンだ。フォロアーの人数を聞いてどうするの?人数が多いと偉い?少ないと友達の少ない人というレッテルでもあるの?自分は人気があるとか思っているの?それはマナーとしても何だか失礼だね。なんかを一発で宣伝できるからとか、イベントで集客できるとか言うけど、そういうことが必要な人たちに話しなさい。ここにいる人たちは別に無理に宣伝しなくても、必要な人たちが勝手に探してくれる人たちなんだ。そんなことをしなくても食べていける人たちはたくさんいるんだよ。今は、こうしてせっかく皆初対面で食事をしてるんだ。あなたのセミナーに参加しているわけじゃない。せっかくなんだ、人の話も聞いたらどうだろう?ネットやマスコミに出ないその道の実力者の皆さんが目の前にいるんだ。こんなチャンス滅多にあるもんじゃない。SNSもいいけど、まずは人と楽しく会食をすることを学んだ方が君の人生にきっと役に立つはずだ。二度と会えないかもしれない人もいるんだから、、、さあ、せっかくの料理がさめてしまう。食べよう、、、」のような指摘をされました。久しぶりにジーンときました。と同時に、自分も気をつけようと身が引き締まる思いがしました。考えてみれば、自分と他人の人脈が明らかになるので、それをうまいこと商売にしたり、時には悪用される場合もあるということです。(悪用の自覚はなくても)だいたい12,000人って、多分、自分の情報を発信するだけで、フォロアーの情報をいちいち見てないでしょうね。無理。まぁ熱烈な「ファン」は別として、それ以外でちゃんと「つながろう」と思っている人にはともすると失礼になっちゃうでしょうね。純粋にFacebookしたい人たちと、それでフォロアーを増やして商売に使いたい人たちが混在しているからややこしい。いつか棲み分けができるようになればいいなと思います。いくつになっても、こうして間違いを正してくれる人、それを口に出来る人の存在は大事だし、ありがたいものです。===なぜ、こんなに長い会話を再現できたのか?この参加者の皆さんの会食中も最初から最後まで、MP3で録音してたんです(笑)。滅多に聞けない話があると思っていたので、、、。そしたら、こんな副産物が、、、正解でした(笑)。
2012/05/29
コメント(0)
-
失敗しない事業計画に必要なことは「撤退ライン」を決めること
楽天が中国の検索大手「百度」との合弁を解消して撤退、というニュースがありました。その後、様々なメディアで「楽天が中国事業で挫折」の文字が躍るようになりました。また「叩きが始まったか」と思いました。事業が自らが計画したものと違ったから、一旦仕切り直すためにも撤退する、、、という決断した、ということですが、報道の仕方いかんでは悲劇的なニュースに着色されてしまいます。私の興味は違います。ニッチもサッチも行かなくなって泥まみれの失敗劇になる前に、事前に自ら線を引いて「ここまで!」と撤退できるのはなぜか?その線の引き方や、決断の仕方に興味があります。(もちろん失敗の教訓も)事業でも株でも賭け事でも、大負けしないで撤退するのが難しい。(もうすぐ風向きが変わるはず、、、とかでズルズルしてしまう)起業するのは簡単だけど、大やけどする前に辞めることができる人は少ないです。大損して身包みはがされて、、、やっと「諦める」パターンが目立ちます。(私の周囲では)起業など「始め方」を教える人や団体は多いけど、それに比べれば事業の「辞め方」を教えてくれる人は少ないでしょう。それだけ判断と決断が難しい分野なのだと思います。これは大きなものだと太平洋戦争も同様です。戦争目的が明確化されないまま始まった戦争は泥沼化します。もうニッチもサッチも行かない状態になるまで辞めることができないわけです。(原爆が落とされるまで自らで辞めることができなかった)それは戦争設計がないからでした。戦争の目的を果たしたら「ここで辞めます!」というものです。その目的を国内外にきちんと提示し続けてないからズルズルと流れてしまいました。その後、勝手な解釈をする人たちが出てきて、アジア全体に拡大していく、、、まさに最悪の典型でした。(まぁ、本来の目的は「石油」のはずでしたが、、、)そんな最悪を経験した日本が「撤退の仕方」や「辞め方」を教えない、学ばないのは、実は、まだまだ戦争に教訓を真剣に学習していないのではないか?と思います。(もちろん、戦争にならないような外交戦略はもっと大事ですが)日本は先進国の中でも起業する人が少ないということで、テレビで議論がありました。それで銀行の担保の話しやエンジェルがいない、など評論家の先生たちが書店で学べる程度の議論をしてました(笑)。その話しは間違いではないけど、撤退の仕方を教えないからだということを付け加えたいな、と思いながら聞きました。アメリカは特に起業家が多い。合わせて撤退や合併も多い。「ここまでやったら売る」とか「辞める」という線引きがハッキリしているから、辞めても皆「軽症」です。(日本に比べれば)だから、すぐに別の事業でリベンジできる。日本の企業の場合は、限界まで踏ん張る傾向があるから、失敗した時にのダメージが大きくて、ほとんどが再起できないし、そういう報道も目立ちます。そういうのを聞けば、無理して起業しようと思う人は減るでしょう。まるで起業は「命がけ」のようなイメージになってしまいます。「成功するか?失敗するか?」とても勇気がいる決断を迫られます。本当はそこに撤退方法とか辞め方のノウハウがあれば、逆に「やってみるよう!」という人が増えるはずです。街では起業塾など開催されてますが、ぜひ「被害を最小限にする撤退の仕方」の事例もカリキュラムに入れて頂きたいと思います。(もっと多くの事例を)===実は、私自身このことを学習していたお陰で中国でビジネスを続けることができました。(大失敗や泥沼化の撤退をすることなく、、、)また、日本国内では大型リゾートやテーマパークの事業計画の仕事をしていた経験と失敗教訓もいきています。大手(ゼネコン、代理店など)の下請けで事業計画を作成すると「撤退ライン」を入れないのです。(求められない)巨大な投資を必要とする施設を「造ることが目的の人たち」はそうなります。そして完成後、現実には多くの施設がその撤退のタイミング見失い、巨額の負債を抱えて倒産して、国民にも多大な迷惑をかけました。そんなこともあって、中国で活動するにあたっても多少大雑把でしたが、心の中で「ここまでライン」を決めていたからです。このラインを超えなければよい、というものです。投資する金額も1500万円まで、とか活動期間の目標は10年続くように、、、(それ以上続いたらご褒美みたいなもの)(そして、現地スタッフの社長化)、、、とか、そういうことです。この2つを決めておくだけで、妙な深追いを回避することができます。仕事の性質上、巨額の富を得るような目標ではなくて、日本で経験した運営・販売・サービスの教育が中国で受け入れられるかどうか?がテーマで、それで食べていけるようになるのかどうか?そんな程度の目標でした。だから人々からは「もっと真剣に取り組んで拡大化をするべき」というようなご指摘を良く受けました。(または、出資をするからやりなさい!など)そういうのに惑わされないのは、自分で決めた身の丈にあった「ライン」があったからです。大儲けもしてない変わりに大損もしない、、、。お金でみればその程度のことですが、代わりに「ノウハウ」は、膨大に蓄積できました。これが大きな収穫であり、これを日本に持ち帰ると、「欲しい!」という人や団体がたくさんあるのです。私たちの活動をわかりやすく言えば中国に小さな農園を持っている、つまり「農業モデル」のようなものです。サービス業の種を中国に持ち込んで、農園で育てて、そこで収穫された農産物を日本に輸出する、、、という感じです。そして、この5年くらいは「中国人観光客」の接客方法や販売方法を教えて欲しい、、、という要望が大きくなって、中国での経験がより大きな実りになってきました。これは、東北の農家出身で大手証券会社に勤務していた私の父親が(高度成長期とバブル崩壊までをまさにど真ん中で経験した人生)常々「農業のような仕事をしろ」と教えてくれたことが教訓でした。さすがに農業そのものはできませんが、種をまいて育てて収穫する、、、というモデルそのものがいつも頭に刷り込まれていたので、(ネチネチと酒を酌み交わす度に、、、:笑)自然とそういう風に活動できたのだと思います。そういう意味では大事なアドバイスでした。ついこの前までは農民がほとんどだった日本人は、やっぱり農業的なビジネスの仕方が合うのかもしれませんね。ちなみに、今後は日本と中国で本物の農園を持つことが目標です。===先日、某企業行われた「中国ビジネスの成功、失敗事例セミナー」で講演した内容の一部でした。
2012/05/26
コメント(0)
-
中国企業幹部社員が語る「悪い中国人」の見分け方
先日お会いした中国企業の幹部社員たちとの会食で教わったことです。大変ためになる話しだったのでシェアしたいと思います。===日系企業の人たちが不思議に思うことの一つに、中国の人事があると思います。それは当然でしょう。「なぜ、あの人をクビにしたんですか?いい人だったじゃないですか?」と聞かれたことは、一度や二度ではありません。また、中国の現地法人の人事をみて日本の本社も「人事考課は問題ないのになぜ?」と。日本型の人事制度だけでは中国の本当の人事は評価できないからです。中国人にとって最も大事なのが、家族と人脈です。この人脈を荒らす社員が最も悪い社員なのです。これは日本型の人事考課にはないでしょう。例えば、私が斉藤さんの部下だとすると、最初のうちは斉藤さんの仕事にアシスタントとして同行して、色んな人に人々に会います。それで知り合った中で、自分に有利な人に対して少しずつアプローチしていきます。そのうちに、斉藤さん抜きで抜きで会うようにします。そして、斉藤さんの悪口を少しずつばら撒きます。そうして、人脈を私のものにしつつ、少しずつ斉藤さんの人脈を断つわけです。気がつけば「私の人脈です!」となります(笑)。これは上司1人だけではなく、色んな上司や先輩の人脈をもらいます。すると、仕事の受注が増えたりして、出世が速くなって斉藤さんを抜くことができます。あるいは、転職、独立好きな中国人は、この人脈を使って商売を始めるわけです。だから、上司も簡単には部下に人脈を紹介しません。こういうことをする人はもう「本能的」であって、日本風の悪気はないのです。まぁ、三国志の時代からずーっと変わってない(笑)。だから中国ビジネスは歴史を勉強するのが最も重要と言われるし、その通りです。陣地を崩すには「まずは人脈から」です。これが毎日のように社内、社外で繰り広げられているのが現状です。中国企業の社内は「毎日が派閥抗争」と言われる所以ですし、事実です。こうしたことがあるから、上司や先輩は、簡単には部下や後輩に人脈を紹介しません。財産だからです。だから、自分の人脈に勝手にアプローチしただけでクビにする上司もいます。自分の人脈(財産)を守るためです。金銭的な財産を盗まれたら誰でも怒るでしょう。人脈はそれ以上に貴重なので、クビに匹敵するのです。これが俗に言う「人脈荒らし」型の人材です。もちろん、荒らさない人もいます。そういう人は大事にします。自分の人脈と、人の人脈の区別がしっかりしています。人の人脈にアプローチする際には、その人に一言許可を得るなど、面子を守ります。つまり、悪い中国人というのは「自分の面子は守るが人の面子を潰す人」です。良い中国人は「人の面子も自分の面子も大事にすることができる人」です。こういう良い中国人なら一緒に仕事をしてもOKです。(中国企業はこういう人をひたすら求めている)だから中国人を見分けるには、このように「人の人脈の接し方」を見ればすぐにわかります。悪い中国人は、「金は取らないで人脈をもらう」から、一般的な日本人にはわからないのです。日本語が話せて留学経験があったり、日本文化に詳しいというだけで採用して、、、失敗するのです。これは何も社員だけではありません。業者との付き合いでもこの点を見極めなければなりません。私たちの所にもたくさんの日本企業、団体が訪れます。その際に、提案された案件が決まる場合もあれば、決まらない場合もある。決まらないと、日本側は「値段かな?」とかビジネスライクに考え込んでしまいます。しかし、中には日本側が雇っている中国人スタッフに問題がある場合があるのです。「こいつは人脈荒らしの臭いがする」というのを私たちは決して見逃しません。だから、いつくら日本語が話せてもそういう人を雇っているうちは業績はあがらないでしょう。優秀な経営者、幹部は、人脈荒らしを決して中には入れません。人脈荒らしは、必ず客を奪ったりしてビジネスの敵になりますから。これが中国ビジネスの最大のリスクヘッジなのです。===日本人には見えない人事があるというわかりやすい話しでした。聞いてみて、今までの中国ビジネスの出来事や関わった人たちを思い出すと、「なるほど!!!そうだったのか!」と色んな事件の原因が理解できました。中国は人脈社会という言葉はよく聞きますが、それは私たち日本人が想像するよりも、とても根深いということがわかります。
2012/05/21
コメント(0)
-
大事なことがどんどん決まる会議の進めかた
これだけITツールが進化すると、誰でも容易に情報を得ることができます。その分、弊害もあって会議や打合せで「なかなかまとまらない・決まらない現象」が起きています。だからコンサルタントとしてそうした場に参加する際に、人の意見を聞きながらも注意しなければならないことがあります。ある会議でA氏から社内に対してプレゼンがあったとします。プレゼンが一通り終わると、参加者からあれこれ意見や質問が飛び交います。そのうちに喧々諤々の議論に発展します。(これ自体は別に悪いことではない)その時に、どのようにして人の意見を聞けばいいのか?どの意見を優先順位高く受け止めてるべきかなのか?、、、というのがともて大事なのです。「概要はわかったけど、俺の思うに、、、そんな成果は出ないと思うよ」「いやー私の感じだと、そんな売上げにはならないはず、、、」「だいたい女性はそんなのは好きじゃないですよ、、、」とか、「思うよ」「だいたい」「はず」という言葉が多くなります。そこで、私の場合は、自分で決めた基準を作っています。(過去に師匠に教えてもらいました)その人が体験した情報なのか?その人が「見た」情報なのか?その人の「過去の経験的勘」情報なのか?「人から聞いた」情報、「噂話」なのか?「ネットやSNSの情報なのか?最後に議論が分かれそうになったら、こうして「採点」して、優先順位を決めてその意見を優先するようにしてます。(項目はその時で多少違いますが)それをもとに、この指摘は正しいのではないか?とか、この意見は最もらしいけど、感覚的だから無視しよう、など考えます。そうしないと、せっかく提案してもは、「新しいこと」いくらでも潰せてしまいます。こうした基準を考えながら参加しないと、たいていは役職の高い人、話しがうまい人、声の大きい人、知識人っぽい人の意見に振り回されることになるからです。「自由に議論しよう」という姿勢は大事です。しかし、こうした基準を設けてないと、まとまらないどころか潰し合いになります。するといつまでも新しいモノやサービスは生まれません。そして、最後に最も重要なのは、「この人、意見と感情のどっちを言いたいのだろうか?」という視点です。多くの人は意見と感情がごちゃまぜになっていて、まるで「お子ちゃま」な意見もあります。だから会議の前に「意見と感情は分けて発言しなさい」としてスタートすると効果的です(笑)。
2012/05/18
コメント(0)
-
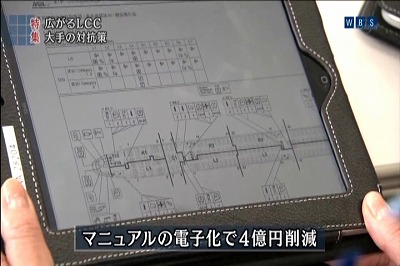
マニュアルを超えても良い条件とは、、、
全日空のキャビンアテンダントの皆さんのマニュアルが電子化されたようです。ipadなどの電子ツールの活用方法として、こういう使い方はいいですね。元々分厚くて重たいマニュアルは持ち歩くことができません。そして、変更するたびにマニュアルを更新(加筆修整)するのも一苦労です。そうした弱点を解消してくれます。おまけに紙代など経費を圧縮してくれるので、サービス業では相性がいいです。(何百冊も印刷することを考えれば紙経費は膨大です)ただし、これには大事なポイントがあって、「マニュアルは大事」ということです。相変わらず、ネットや雑誌の記事では、やれ「マニュアルを超えるサービス、、、」とか、「マニュアル以外のサービスこそ大事」とか、、、アバウトな発言が絶えません。それはなぜそういう発言があるのか?と言えば、そう話す人たちが、マニュアルが嫌いだったからです。または、マニュアルを厳守しなくても問題ない程度の仕事をしていたからです。マニュアルを超えたり、時には以外のことをするのは何となく感動的は話しになったり、イメージとしてかっこいい。だけど、こんな話しばかり広がってしまうと、その施設や店舗のサービスは必ず下がります。たまにはそういう人がいても美談になるには、絶対的な条件があります。それは、「マニュアルを厳守してくれる他のメンバーがいてこそ成り立つ」ということです。ディズニーランドも同様で、しっかりメンテして清掃して、いつ来てもいつ乗ってもいつ食べても安全や衛生を確保してくれる、、、というバックボーンがあってこそです。接客は大事ですが、サービス全体に占める割合は2-3割です。その他は、こうした準備と片付けがサービスなのです。全員がマニュアルを超えようとか言い出せば、メチャメチャなことになるのは目に見えているわけです。上記のエアラインに勤務するような人々がしょっちゅうマニュアルを超えてたら、、、飛行機は定時に飛ばない、到着しないかもしれないし、第一、安全性が減少してしまいます。だから、ipadのようなツールを使って、しっかり携帯してもらって、わからないことがあったらいつでもマニュアルで確認できるようにしてもらうのは私たち客にとってもいいことです。
2012/05/16
コメント(0)
-
ラジオで接客、接遇、販売サービスを学習する方法とは
先日、久しぶりに知人の会社のオフィスに行きました。以前の場所から晴海の日当たりの良いオフィスに引越ししてました。驚いたのは「電化製品のソーラー率」です。スタッフのデスクにある電気スタンドは、ソーラーLED照明です。まぁ部屋自体が大きな窓のお陰もあって外光が入ってとても明るいのですが。広いテラスにも大きなソーラーパネルが置いてあって、オフィス内の様々な電化製品に利用されています。彼は私と一緒でラジオ好きで、これまたソーラー充電のラジオを聴いてました。その他、携帯電話の充電器など、こまごまとありました。3.11以来、万が一を考えるようになったことと、ソーラーで動くもの使えるものは全てソーラーに換える、、、ということでした。===その場所にたまたまラジオ局の方がいました。(打ち合わせ中でした)年々リスナーが減少傾向になったけど、この数年は、盛り返しているようです。まずは3.11で、非常用に購入する人たちが増えたこと。何だかんだいっても省電力で動くので、見直されたようです。さらに、そうして「せっかく買ったんだから使おう」という流れで徐々にリスナーが増えています。(まぁ局にもよるのでしょうが)また、インターネットでも聞けるようになってきて、スマホで通勤時やオフィスで聞く人も増えつつある、、、と。また、ラジオ番組の運営とSNS(ツイッターなど)の相性がいい。リスナーの参加度が大いに増してくる、と。テレビ業界が、ハードも視聴率もCMも減少に歯止めがかからないところで、ラジオの存在がクローズアップされているようです。ラジオ局にとっては、ラジオ本体が売れなければリスナーは増えない、、、という図式が長かった。しかし、インターネットのお陰でPCがあば聴けるようになり、さらにスマホにアプリが入ることでもっと気軽に聴く事ができるようになってきました。「ラジオ」というハードに左右されない存在になりつつあるわけです。テレビとの比較では、そのリスナー数はまだまだ及ばないものの、「聴く時間数」では、圧倒的にラジオに軍配があがります。私自身、テレビはほぼ8割は「録画」で見ます。なので、番組の「気に入っている部分」しかみてません。もちろんCMは全てスキップです。対して、オフィスにいる時には基本的にはラジオはつけっ放しです。(自宅の書斎でもラジオだけです)毎日6-8時間は聴いていることになります。録音を聴くわけではないので、CMをスキップすることはできません。===ただ、私がオフィスでもラジオをつけっ放しにしているには理由があります。もちろん、ニュースなどの情報を聞くことですが、もう一つは「ラジオのCMが好き」だからです。基本的にテレビは録画でCMスキップなので見てません。(見るに耐えないCMが多いから、、、が原因ですが)ラジオのCMは「声と音」だけなので、その脚本が大変よく考えられています。日本でも中国でも販売サービスの研修やセミナーが中心ですから、ラジオCMの商品の紹介の仕方がとても勉強になるのです。声と音だけを使って構成されているので、そのヒントは全て接客に使えます。しかも、テレビCMよりも長い。30秒以上のCMもあって、じっくり聴くことができます。そして、テレビCMとの違いは、(私の実感ですが)テレビはどちらかと言えば「商品自慢」が多い。対してラジオCMは、「客目線」の内容が多いのです。(使い方やそのシーンなど)さらに見逃せないのが「声と音」だけなので、たいていの場合、主人公と恋人や親、友達、同僚、、、と必ず2人称、3人称で展開されます。それらは、普段の接客や販売サービスで欠けていることを教えてくれることがあります。(盲点に気づかせてくれる素晴らしい情報源と言えます)なので、研修やセミナーでは必ず「ラジオを聴きなさい」と言います(笑)。私の場合正真正銘の「おっさん」ですから、女性や若者の気持はわかりません。そんな時に、若者目線の使い方やそのシーンを学習できるのです。地域によっては、農園、印刷会社、美容院、スーパーマーケット、バー、、、など様々な業種がCMを流しているので、これもテレビにはない魅力です。「なるほどなぁ」とため息が出るものに出会った時のために、いつもラジオの前には「ICレコーダー」を置いてあります(笑)。
2012/05/15
コメント(0)
-
正しく日本を元気にする方法
母の日は「お母さんありがとう!」が飛び交います。その度に、母が生きているうちに親孝行ができたら、、、と思います。私が31歳の時に他界したので、まさに「これから、、、」でした。ただ、感謝はもっと伝えられたのではないか?と悔やむ時もありますね。その代わりと言ってはなんですが、社会に出てからお世話になった上司、先輩たちに恩返しをしようと(社内に限らず仕事でお世話になった方々)毎年誰かしらにお礼をするようにしてます。自分自身がキャリアを重ねれば重ねるほど、本当に色んな上司や先輩たち、師匠には相当苦労をかけたんだな、ということがわかるようになるからです。まさにお世話になりまくり、、、でした。家族や肉親、それから学校の先生ならともかく、何だかんだ言っても赤の他人の後輩に対して根気良く指導して、おまけに給与や仕事をくれて、、、というのは改めて凄いことなんだと思います。時には、自分の分を削ってまで部下に給与を支給しなければならないからです。(こういうのは、自分自身で身銭を切って初めて実感できます)ともすると人は「人にしてあげたこと」ばかり覚えていて、「人にしてもらったこと」を忘れてしまう、結構都合のいい動物です。海のモノとも山のモノともわからない人材を採用して、たいていの場合は最初は自力では「給与分も稼げない」からあれこれ指導して機会を与えながら育ててくれます。それで3年-5年くらいたつと、やっと一人前になってまさに会社の稼ぎ頭になるかな、、、と思った頃に「もっとステップアップしたい」とか「自分の実力を試したい、、、」ということで退職してしまう、、、そんな風潮がこの20年くらいで増殖していると思います。まさに「会社を学校代わりに利用する」と言われても仕方ありません。社内の恩返しが未清算のうちに辞めてしまう人が増えてきたお陰で、企業は社員採用にますます消極的になってきました。ヘタすれば辞めた後に似たような商売を始める人もいるほどです。そうなると、上司も先輩も若手社員にノウハウを教えることに消極的になって当然です。「せっかく教えても、吸収するだけしたら独立してしまうのではないか?」と。コンサルタントをしていると、各社のそうした事情(や気持)がよくわかってしまいます。かつては、村の秀才を皆で育てて、その後お金を出し合って東京の大学に行かせて、卒業したら地元で、養豚技術やら栽培技術、経理に土地の改良方法から大きなものでは村の産業振興まで持ち帰って村を豊かにする、、、という恩返しのサイクルがありました。家庭でも会社でも恩返しの循環が止まると、世の中のストレスがどんどん大きくなります。それが大きく膨らむと日本経済がますます不調になるのでしょう。そういう意味では、無理に「日本を元気にします!」とか、ヘンな大声を出す前に、常日頃、お世話になった方々への恩返しを徹底してみてはいかがでしょう?そうすれば、すぐに日本は元気になるでしょう。
2012/05/13
コメント(0)
-
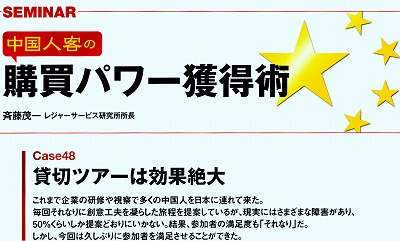
中国人観光客対応研修の講師養成講座スタート!
週刊トラベルジャーナルでの連載も3年目に突入しました。最近は、購読者の方々からメールを頂く機会が増えて来ました。そして、記事にあった事例を実践して、、、「結果はこうなりました」という話しを聞くとやはりうれしいものです。改めて思うことは、この雑誌の影響力の大きさです。観光産業に関わる人々が読むいわば業界なので、こうした情報に貪欲な方々が多いようです。私自身が利用するホテルや鉄道、空港、百貨店のような場所でも記事で問題を提示すると改善されていることがあります。そういうのを発見すると、やはりうれしいものです。(見つけたら早速、中国の友人たちに知らせています)年々増える(増やさなければならない)外国人観光客の対応はますます重要になってきます。それに合わせて全国各地でインバウンドセミナーや中国人観光客対応研修の開催の機会も増えてきています。私たちの元にも各地からお問合せを頂く機会が増えました。しかし、残念ながらスケジュールやコストの問題で、いつも全国を飛び回ることはできないのが現状で、インターネット電話のSkypeを使ったセミナーで対応させて頂くことも多くなってきました。それは裏を返せば、全国にこうしたセミナーや研修の講師がいないことが原因だと思います。中国語を話せる日本人は増えて来たものの、実際に販売サービスの経験があるとか、誘致したことがある、という人はまだまだ極少数だからです。そこで、最近始めた新たなサービスは、インバウンドセミナーや中国人観光客対応の研修を実施できる「講師養成講座」です。(現在、17名の方に指導中です)こういう人が各地方にいれば効率が良いと考えました。これを人に話したら、「何でわざわざライバルを育成するのか?」と気でも狂ったのか?と言われました(笑)。現在の対象者は、商業施設(SCや小売業、飲食業)に勤務する社内講師の育成と、現地団体の観光課の職員が対象です。なので別にライバルでもないわけで、問題なしです。別に全国制覇をしたいわけでもないし、北海道から沖縄まで、自分たちだけで対応できるわけもないし、、、。中国で実施している研修も、これと同じケースが多いです。あの広大な中国の全国チェーン店を回れるわけありません(汗)。各地で店長やトレーナーの育成の教育をして来ました。(それだけでも凄い距離で、一年間に18回も出張しました)どんな業界でもノウハウやスキルとしっかり定着させて利益を得るには、トレーナーの育成が最も重要だと思います。あの東京ディズニーリゾートも人材教育費の約4割がトレーナー育成予算だと以前新聞で読んだことがあります。本当にそう思います。
2012/05/12
コメント(0)
-
ガチャ問題から見る観光産業の課題
「コンプリート・ガチャ問題」こういう話は、それぞれの業界や立場で意見が分かれるます。どの立場で考えるか?が求められます。レジャー、観光産業の立場からみれば、こうした規制は必要となります。携帯ゲーム(スマホを含む)は、どんなに大きくなっても、そのほとんどは地元に雇用を生みません。同時に、お金も落ちません。こうしたゲームへの出費が大きくなると、地元の若者たちの財布はますます軽くなり、地元の商業が落ち込みます。収入が激増している時代はいいけど、デフレの時代には収入は上がってません。なので、上がるものがあれば落ちるものもあるわけです。携帯電話関連の出費は、家庭全体では年々大きくなっています。通話代に加えて、こうした課金モデルがあり、Wifiの契約など、一家4人で、10万円、、、なんて珍しい話ではないのです。それぞれの県や地域の政策として、観光産業(商業も)に力を入れるのなら、携帯ゲームというのは無視できない存在なのです。観光産業は、県外や外国から来てもらうから関係ないと言う人がいますが、現実は、およそ半数以上は、地元客が来てくれなければ経営は成り立ちません。かつて、全国で大型リゾートやテーマパークが建設されて、ほとんどがことごとく倒産しました。その原因は、県内客が来ても採算が合わないような大型化に取り組んだからです。県内客だけで「とんとん」、それに加えて県外客、外国人客で利益になる、、、という(今では当たり前の)モデルになってないまま突き進んだからです。その際に、人口、人口構成、世帯収入、交通などそれらしく調べて「GO!」と許可した人たちが大勢いました。でもこれは大変アバウトな調査で、現実は、「パチンコ人口」が肝心でした。人口一人当たりのパチンコユーザー数、店舗、台数、、、の検証が無視されたのです。こうした中毒性の高い娯楽は、大きな出費があります。このユーザー数や市場規模を見て、「このくらいにしておこう」と適正規模の施設を作ればよいわけです。毎月、5万円も10万円もパチンコに注ぎ込む人が多い街で、リゾートを建設しても、地元客が少ないのは当たり前です。パチンコに注ぎ込んでしまって、それ以外の娯楽のお金は残ってないからです。観光産業というのは、このように地元の出費バランスを見ながら規模を決めなければならないし、必要に応じては、産業育成の優先順位を決めて規制をしなければならないのです。そうしなければどの産業も育たない、ということになります。観光産業だけを見ている人たちが見逃す視点です。こちら側だけでみると「高速道路があれば、、、」「飛行場があれば、、、」「LCCが飛べば、、、」など、そっちに目が行ってしまいます。インフレの時はそれでも多少はOKかもしれませんが、デフレ時代は、優先順位を決めて取り組まなければなりません。幸い私たちは、レジャー産業全体を研究してきました。他の娯楽との関連性が明暗をわけるのだと考えています。
2012/05/09
コメント(0)
-
中国人社員教育に効果絶大なのは「なでしこジャパン」
最近は、日本で働く中国人の若者に対して勉強会をしています。彼らが働く日本企業側からも、もっと日本流を理解して欲しいという声もあるし、中国人社員たちも、わかりづらいという声もあり、両方にストレスがあるわけです。これは日本でも中国でも同じです。2年前に北京空港で知り合った宋くんも例外ではありませんでした。(東京で就職しました)自宅が近いこともあり、良く飲みに行って彼の悩みを聞くようになりました。すると、彼の友人も加わってくるようになり、段々と勉強会の形に発展してきました。(もちろん勉強会終了後は、やっぱり飲み会ですが:笑)今回は、サッカー好きの彼らに合わせてNHKのBS1で放映された証言ドキュメント「永遠に咲きなでしこジャパン」~女子サッカーの30年~という番組を見てくることを宿題にしました。(全員が日本語が堪能なので)そして、会うなり「もう感動して言葉がでません」が全員一致の感想でした。昨年のワールドカップの16カ国の出場チーム中、身長も体重も16位で、最も小さい彼女たちがなぜ世界一になれたのか?実はとても不思議だったそうです。いくらなんでも優勝は奇跡では無理で、やっぱりその理由が知りたいと思っていたのです。「日本人はコツコツ努力家だから、、、」という評論は中国語のブログでもかなり見かけるけど、全く具体的ではないのよくわからなかったようです。しかし、この番組(全3話)を観て、その努力とはどういうものなのか?が良くわかった、と。そして、大事なポイントは、「私たち中国人がイメージしていた努力とは違った」ということでした。特に印象的だったことは、日本人は先輩たちからのバトンを後輩がしっかりと受け継ぐこと。先輩たちも後輩のためを思って惜しみなく指導すること。歴代の監督が、その当時のチームの実力に合わせたテーマを掲げて、それを確実に実践してきたこと。そして、監督たちも歴代の実績をきちんと積み上げていること。選手たちが徹底的に話し合うこと。監督が全部決めないで、選手に話し合い納得させる機会を与える度量があること。。そして、全員が感嘆していたことは、、、「アルバイトをしながら代表選手をしてい人がいること。さらにその代表選手たちが、試合の遠征の費用を半分自腹というのもまさに信じられない。こんな選手がいたら、中国は絶対に日本には勝てない」正直な意見としては、、、「実は、中国で日本との試合があると、ブーイングしてました。だけど、本音では日本はなんてフェアプレーなんだ!と思ってました。だから日本戦を観戦する時には、いつも複雑な心境になってとても疲れました」いずれにしろ、なでしこのサッカーを通して日本式というのが理解できたようです。照らし合わせて自分たちが今いる会社でも似たような指導を受けていることがわかったという意見が何よりでした。おもしろかったのは、「みんな女子選手なのに、侍に見えた」でした(笑)。いずれにしろ、素晴らしい教材でした。これは永久保存版ですね。===この映像は中国語の字幕版があれば、現地での教育でも使えるのに、、、。
2012/05/03
コメント(0)
-
スマホで聴く音声セミナーを公開
こちらに、スマホで聴けるようにと、セミナーの音声を公開しました。(別にパソコンでも構いませんが、、、:笑)↓スマホ用セミナー音声ファイル(無料)音声セミナーの元になっているのは、Skypeです。(Skypeとはインターネットを利用した通話料無料のテレビ電話のこと)このSkypeを使用してセミナーを実施するようになった理由は、地方の方々からの要望でした。セミナーの講師として呼びたいけど、講演料+旅費交通費が重い負担になるわけです。特に田舎の観光地ほど予算もない。しかし、外国人観光客の一人でも多く受け入れたいし、売上げもあげなければ先がない。そこで、Skypeを使って、お互いに会議室からパソコンを使ってミニセミナーをやりましょう、ということになりました。私を知る人は、私が「録音魔」であることは御存知でしょう(笑)。一番の目的は、セミナーでも打合せでも、自分自身が前回何を話したのか?思い出すためです。このSkypeセミナーも一応全部録音しています。ただ、こうしたセミナーのファイルが貯まってくると、定期的に削除してましたが、どうせなら復習用にYoutubeにアップしておいて欲しいという声があり、Youtubeにアップするようになりました。すると今度は、通勤の車の中でスマホをつないで聞くので、動画仕様では重たい。音声だけにして欲しい、という要望があって、音声だけのコーナーと作った次第です。以前は、こうしたファイルは非公開にして、聴きたいと言う人に直接アドレスを送信するようにしてましたが、3.11の後、公開にするようにしました。その頃、ちょうど福島県のインバウンド政策のお手伝いをしていました。3.13日は、現地で研修を実施する予定でした。その後は、東北でも被災してない地域の観光のお手伝いができればと言うことで、現地の人々とSkypeセミナーを実施するようになりました。(私たちにできるボランティアです)別にアクセス数を競うような代物ではありません。知りたい人がアクセスできればそれでいいと思っています。===そうは言っても、お金を払ってセミナーを依頼して頂いた人のプライバシーもあるので、音声は私自身の声のみが録音されています。相手側の音声は、全てヘッドフォンで聞いてやりとりしているわけです。また、セミナー中にお見せしている、記事やPPTや写真のような画像までは公開してません。あくまでも私の音声のみ、ということで参加者の方々には了解を得ているわけです。===改めて、セミナー系の音声ファイルを調べてみると、800以上ありました(汗)。これからも、公開可能なものを選んでアップして行きたいと思います。
2012/05/02
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- Bruno マルチコンパクト炊飯器
- (2025-11-17 09:13:23)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 限定イヤープレート付🎄Disney SWEET…
- (2025-11-17 06:41:29)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 心豊かに生きる方法
- (2025-11-17 08:45:59)
-







