2024年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
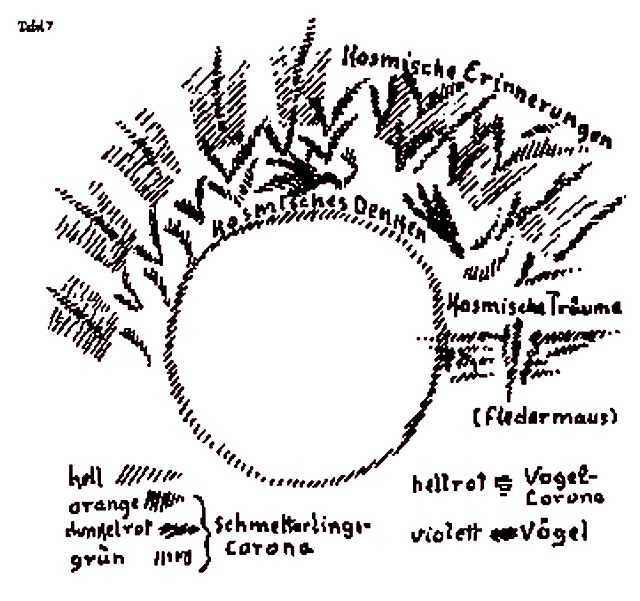
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー(GA230)創造し、造形し、形成する宇宙言語の協和音としての人間Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden,bildenden und gestalteden Weltenwortes(翻訳者:yucca)第5講 1923年10月27日 ドルナハ・蝶、鳥による地球素材の霊化・蝶は生きている間に、鳥は死ぬときに、霊化した地球素材を宇宙にもたらす・蝶と鳥の世界を通じて地球は宇宙に霊化された素材を放射する・星は無機的なものではなく、生命あるもの、霊化されたものの結果・蝶は光エーテルに、鳥は熱エーテルに属する・鳥は呼吸を通じて体内の空気に熱を生み出す・蝶の呼吸と高等動物の呼吸・蝶は光の生きもの、鳥は空気の生きもの・コウモリは黄昏の動物、地球の重さを克服できない・蝶は宇宙の記憶、鳥は宇宙の思考、コウモリは宇宙の夢・コウモリは霊的実質を宇宙空間ではなく空気中に分泌する・コウモリの分泌の残存物を人間が吸い込むことにより龍が人間に支配力を行使する・ミカエル衝動によるその防御 この連続講義は、宇宙の現象と宇宙の本質の内的連関を扱っておりますが、皆さんはすでに、外的な現象界にしか目を向けないひとにはさしあたり予想もつかないようなさまざまなことが判明するのをごらんになりました。私たちが見てきたのは、根本においていかなる存在のありかたも私たちはこれを二、三の例で示しましたが、その課題を宇宙的現存の連関全体のなかに有している、ということでした。さて今日は、すでにお話しした存在のありかたをいわば要約しつつもう一度ながめ、ここ数日間私が蝶についてお話しして参りましたことに注目してみましょう。私は植物の本質に対立するもののなかにまさに蝶の性質を展開いたしました、そして私たちは、蝶とは本来光に属するもの、外惑星、つまり火星、木星、土星の力によって修正されたうえでの光に属するものであると語ることができたのです。したがって私たちは本来、蝶をその本質において理解しようとするなら、宇宙の上方の領域を見上げてこう言わざるを得ないのです、宇宙のこの上方の領域が蝶の本性を地球に贈り、蝶の本性を恵みとして地球に授けたと。さて、この地球に与えられた恵みはさらにずっと深くまで達するものだ、と申し上げたいのです。思い起こしてみましょう、私たちはこう言わざるを得ませんでした、蝶は本来地上での生存に直接参加しておらず、太陽がその熱と輝きの力をもってまさに地上での生存のなかで働いているその範囲内において間接的に参加しているのみである、と。しかも蝶はその卵を、それが太陽の領域から抜け出さないところに、太陽の効力の領域内にとどまるところに産みつけます、つまり蝶は本来その卵を、地球ではなく太陽にのみ委ねるのです。それから火星作用の影響下にある幼虫が這い出してきます、むろん太陽作用は相変わらず存在しています。そして、木星作用の下にあるさなぎが形成されます。さなぎから蝶が這い出してきます、これは、その色彩のきらめきのなかで、土星の力とひとつにされた太陽の輝きの力であることができるものを、地球の周囲に再現しているのです。このように本来私たちは、地球存在(状態)の内部、地球存在(状態)の周囲に、土星の効力が蝶存在のさまざまな色彩のなかで直接活きているのを見ます。けれども、宇宙生存にとって問題となる実質というのは、二重のものであるということも思い出されます。私たちは純粋に素材的な地球の実質を扱いますし、霊的実質も扱います、私は皆さんに申しました、奇妙なことに、人間はその新陳代謝組織に関しては霊的実質を根底に有している一方、人間の頭、頭部の根底を成しているのは、物質的実質である、と。人間の下部の性質においては、霊的実質が、物質的な力作用、重さの作用、その他地上的な力作用に浸透されています。頭においては、地上的実質、つまり新陳代謝全体、循環、神経活動その他を通して人間の頭へと上に運ばれた地上的実質が、私たちの思考や私たちの表象のなかに反映されている超感覚的、霊的な力に浸透されているのです。したがって私たち人間は頭のなかには霊化された物質的素材(vergeistigte physische Materie)を持ち、新陳代謝ー四肢組織のなかには、地上化され、こういう言葉を作ってよろしければ、地上化された霊的スピリチュアルな実質性(verirdischte geistig-spirituelle Substantialitaet)を有しているのです。さて、この霊化された素材(マテーリエ)はとりわけ蝶存在のなかに見出されます。蝶存在はそもそも太陽の存在領域にとどまることによって、地上的素材を自らのものとします、むろん比喩的に言っていわばもっとも微細なちりのような状態でのみですが。蝶は地上的素材をもっとも微細なちりのような状態でのみ自らのものにするのです。蝶はまた太陽に加工された地球の実質から食物を調達します。蝶が自身の本質と結びつけるのは、太陽に加工されたもののみです、蝶はあらゆる地上的なものからもっとも精妙なものをいわば選び出し、それをもっとも完全に霊化してしまうのです。蝶の翅(はね)に注目するなら、実際のところ、その根本にあるのはもっとも霊化された地球素材(Erdenmaterie)なのです。蝶の翅の素材が色彩に浸透されることにより、蝶の翅はもっとも霊化された地球素材なのです。蝶とは本来、霊化された地球素材のなかでのみ生きている存在です。しかも霊的に見てわかることですが、蝶は、自らの色彩豊かな翅(はね)のまんなかの胴体をある意味で軽蔑しています。なぜなら、蝶の全注意力、蝶の全集合魂は、もともと自らの翅の色彩を喜び享受することに安んじているからです。その翅のきらめく色彩に驚嘆しつつ蝶を追いかけることができるのと同様に、これらの色彩に対する舞い飛ぶ歓喜に驚嘆しつつ蝶を追いかけることもできます。これは根本的に子供のときに開発されているべきことです、空中をひらひらと飛び交う霊性、本来舞い飛ぶ歓喜である霊性に対するこの喜び、色彩の戯れに対するこの喜びは。この点において蝶的なものはまったく驚くべきしかたでニュアンス付けされています。そしてこれらすべての根底にはまた別の何かがあります。私たちは、鷲に代表されているのを見た鳥について、こう言うことができました、鳥はその死に際して霊化された地球実質を霊界へと運び去ることができる、鳥は、鳥として地球素材を霊化し、人間が行なうことができないことを行なうことによって、宇宙での生存における課題を果たしていると。人間もその頭のなかで地球素材をある程度までは霊化したのですが、人間はこの地球素材を、死と新たな誕生との間生きていく世界のなかに携えていくことはできないのです、と申しますのも、頭のなかのこの霊化された地球素材を霊界へと持ち込もうとすれば、人間は止むことなく、言語を絶した耐え難い破壊的な苦痛に耐えなければならないでしょうから。鷲によって代表される鳥の世界はこれを行なうことができます、ですから実際のところこれによって、地上的であるものと地球外のものとの間に関係が生み出されるわけです。地上的素材はまずいわばゆっくりと霊のなかへと移されます、そして鳥類は、この霊化された地上素材を宇宙万有に委ねるという課題を有しているのです。ですから、いつか地球がその存在(状態)の終わりに到達したとき、こう言うことができるでしょう、これらの地球素材は霊化された、鳥類は、霊化された地球素材を霊の国に戻すために、地球存在(状態)の経済全体の内部にいたのだと。蝶に関してはいくらか事情は異なっています。蝶は鳥よりもさらに多く地上の素材を霊化するのです。鳥は何と言っても、蝶よりもずっと大地の近くにいるという状態にあります。このことは後ほどお話ししましょう。けれども蝶は太陽領域をまったく去らないということによって、その素材を、鳥のように死ぬときになってようやく、というのではなく、まだ生きているうちに、霊化された素材を絶えず地球の周囲に、宇宙における地球の周囲に譲渡するほど、それほど霊化することができるのです。ひとつ考えてみてください、私たちが地球を、つまり、きわめてさまざまに飛び交う蝶の世界に貫かれ、この蝶の世界が宇宙に譲渡する霊化された地球素材を絶え間なく宇宙空間に放射している、そういう地球を思い浮かべることができるとき、宇宙の全経済のなかにはほんとうに何と偉大なものがあることか。こうして私たちは、地球の回りのこの蝶の世界の領域を、このような認識により、まったく別の感情をもって観察することができるのです。私たちがこのひらひらと舞い飛ぶ世界のなかをのぞき込むことができると、こう言うことができます、お前たち舞い飛ぶものたちよ、お前たちは太陽光よりも良いとさえいえるものを発するのだ、お前たちは霊光を宇宙へと放射するのだ、と。実際霊的なものは私たちの唯物論的な科学からはほとんど考慮されません。そのため、こういう唯物論的な科学には実際、宇宙経済(Weltoekonomie)の全体に属するこういう事柄にどうにか行き着く手がかりはまったくないのです。とは言え、物理的作用が存在するのと同様、宇宙経済も存在します、しかも宇宙経済は物理的作用よりも本質的なのです。と申しますのも、霊の国に放射されるもの、これは、地球がとっくに崩壊してしまっても、作用し続けるからです、今日、物理学者、化学者が構成するものは、地球存在とともにその終結を見るでしょう。したがって、ある観察者が外部の宇宙に座して長い間観察するとしたら、そのひとは見るでしょう、霊物質が霊の国へと、つまり霊的になった物質が霊の国へと絶え間なく放射するような、そのような何ごとかが起こるのを見るでしょう、地球が自身の本質を宇宙空間へと、宇宙へと放射するのを、そして、迸(ほとばし)る火花、輝きを発し続ける火花さながら、鳥類が、鳥のすべてが、その死後に輝かせるものが、今やこの宇宙万有へと光線の姿で放射していくのを、蝶の霊光のきらめきと鳥の霊光の迸りを、見ることでしょう。これはしかし、同時に次のようなことにまで注意を導きうるであろうことです、つまり今や別の星界に目を向けるなら、分光器が示すものが、あるいはむしろ、分光学者が分光器のなかに夢想するもののみが、そこから放射されてくると信じるべきではなく、地球から宇宙空間へと放射されるものが生きものの結果であり、それと同様に、別の星界から地球へと放射されてくるものもまた別の世界の生きものの結果である、ということにです。私たちはある星を見て、今日の物理学者とともに、発火した無機的な炎とかそれに類するものを想定します。これもちろんまったくナンセンスです。と申しますのも、そこに見られているものは、まったくもって、生命を与えられたもの、魂を与えられたもの、霊化されたものの結果だからです。挿入図:Kosmische Erinnerungen:宇宙の記憶・Kosmisches Denken:宇宙の思考・Kosmische Traeume:宇宙の夢(Fledermaus:コウモリ) さて私たちは、こう申してよろしければ、地球をぐるりと取り巻いているこの蝶の帯から、もう一度鳥類へと入って行きましょう。私たちがもう知っていることを思い浮かべますと、境を接した三つの領域が得られます。その上部には別の領域があり、その下にもまた別の領域があります。私たちは光エーテルを有し、私たちは熱エーテルを有しますが、これには本来二つの部分、二つの層があります、一方は地上的な熱層、他方は宇宙的な熱層であり、これらは絶えず浸透し合っています。実際のところ私たちは一種ではなく二種類の熱を有しているのです、地上的、地球的な起源である熱と、宇宙的起源である熱です。これらは絶えず互いに浸透し合っています。さらに熱エーテルに接して空気があります。続いて水と地が、上方には化学エーテルと生命エーテルが来るでしょう。さて、今蝶類を取り上げてみますと、蝶類は主として光エーテルに属していて、光エーテルそのものが、輝きの力が蝶の卵から幼虫を引き出すための手段なのです、輝きの力は本質的に幼虫を引き出します。鳥類の場合はもうこれは当てはまりません。鳥たちは卵を産みます。この卵は熱によって孵されねばなりません。蝶の卵はもっぱら太陽の本性に委ねられますが、鳥の卵は熱の領域まで至ります。鳥は熱エーテルの領域に存在します、単なる空気であるものを鳥は本来克服しているのです。蝶も空中を飛翔します、けれども蝶は根本的にまったき光の被造物です。そして、空気が光に浸透されることで、蝶はこの光ー空気存在(状態)の内部で、空気存在(状態)ではなく、光存在(状態)を選び取ります、空気は蝶にとって運び手にすぎません。空気は蝶がいわばその上を漂っていく波浪ですが、蝶のエレメントは光なのです。鳥は空中を飛翔します、けれども本来鳥のエレメントは熱、空気中のさまざまなニュアンスの熱であり、鳥はある程度空気を克服しています。鳥もまた実際内的には空気存在でもあります。鳥はかなりな程度空気存在なのです。ひとつ哺乳動物の骨、人間の骨をごらんください。それは髄で満たされています。なぜ髄で満たされているかについてはさらにお話ししていくでしょう。鳥の骨は空洞で空気にのみ満たされています。したがって、私たちの骨の内部にあるものを観察する限り、私たちは髄的なものから成っており、鳥は空気から成っています、鳥の髄的なものは純粋な空気なのです。鳥の肺を考えてみると、皆さんはこの鳥の肺のなかに肺から出ている多数の袋を発見されるでしょう、これらは空気袋なのです。鳥が吸い込むとき、鳥は単に肺のなかへと吸い込むだけでなく、この空気袋のなかへと空気を吸い込みます、そして空気はこの空気袋から空洞の骨のなかへと入っていくのです。したがって、鳥から筋肉も羽根もすべて外し、骨も取り去ることができるとしたら、空気から成る動物がなおも得られるでしょう、この動物は、内部の肺を充填するものとすべての骨の内部を充填するものの形(フォルム)を有しています。これを形(フォルム)において思い浮かべれば、まさしく鳥の形が得られることでしょう。筋肉ー骨鷲(Fleisch- und Beinadler)の内部に空気鷲(Luftadler)がおさまっているのです。さてこれは、単にまだ内部に空気鷲が存在するからという理由でのみそうなのではありません、鳥は呼吸します、呼吸を通じて鳥は熱を生み出します。この熱を、鳥は、鳥が今やそのすべての肢のなかに押し込んでいる空気に伝えるのです。ここで、外部環境に対して熱差が生じます。鳥はここに内熱を、ここに外部の熱を有します。空気の外的な熱と、鳥が自身の内部の空気に与える熱との間のこの水準差、この水準差のなかに、つまり熱の、熱のエレメントの内部の水準差のなかに、本来鳥は生きているのです。そしてしかるべきやりかたで皆さんがもし、そもそも鳥の体はどういう状態なのか、鳥にお尋ねになるとしたら、鳥は皆さんに答える。皆さんが鳥の言葉を解されるなら、鳥が答えることはおわかりになるでしょう、そして皆さんに明らかになるでしょう、鳥は堅く実質的な骨について、そして通常自らが担っているものについて語っているのだ、つまり、たとえば皆さんが、トランクを左右に持ち背中と頭の上にも乗せているときのように、自分が担っているものについて語っているのだと。トランクを持っているときは皆さんにしても、これは私の身体だ、右側のトランク、左側のトランクその他は私の身体だとはおっしゃいません。皆さんが、自分が荷物として担いでいるものについて、自分の身体について語るように語ることはほとんどなく、自分が担いでいるものとして語るように、ちょうどそのように、鳥は自分について語るとき、単に鳥によって暖められた空気について語るのです、鳥が地上での生存において担っている荷物とは違うものについて語るのです。この骨、こういう本来の鳥の空気体を覆っているこの骨は、鳥の荷物なのです。したがって私たちはまったくもってこう言わなければなりません、根本的に言って鳥はまったく熱エレメントのなかで生きている、そして蝶は光エレメントのなかで生きている、と。蝶にとっては、蝶が霊化する物質的実質であるものはすべて、霊化以前にはそもそもまさに荷物ですらなく、建物の設備とでも言ってよいものです。これは蝶からさらに遠く離れているものなのです。つまり、この領域まで、この領域の動物のところまで上昇することで、私たちは、私たちが決して物質的なしかたで判断してはならないものに到達するのです。私たちがこれを物質的なしかたで判断すれば、それはたとえば、私たちがひとりの人間を次のように描こうとするときのようなものです、つまりその髪の毛が頭にかぶっているもののなかへと生えていくように描いたり、そのひとのトランクが両腕と合体し、背中にそのひとがリュックサックとして背負っているものが付いているように、その結果、あたかもリュックサックが後ろへ成長していったかのように背中に瘤をつけてしまう、という具合に描こうとするときのような。私たちが人間をこのように描くとすれば、これはひとが画家として鳥について本来抱いている想念に当たります。それはまったく鳥ではありません、それは鳥の荷物なのです。本来、鳥もまた、あたかも自分がこのひどく重い荷物をひきずっているように感じています、と申しますのも、鳥は率直に、まったく重荷などなく、暖かな空気動物として、世界をめぐってさすらいをして行くことを一番望んでいるのですから。それ以外のことは鳥にとって重荷なのです。そして鳥は、貢ぎ物を宇宙存在(状態)へともたらします、死ぬときに、この重荷を霊化し霊の国へと送り込むことによってです、蝶はまだ生きているうちにこれを行ないます。よろしいですか、鳥は私が皆さんにお話ししましたようなしかたで呼吸し、空気を用います。蝶の場合これはまた異なっています。蝶はそもそも、いわゆる高等動物と言われているものが有しているようなそういう装置によって呼吸しているのではありません、高等動物というのは実際嵩高 動物なのであって、本当は高等動物などではないのです。蝶は本来、その外側の覆いから内部に入り込んでいる管を通してのみ呼吸します、この管がいくらか膨らまされ、それで蝶は飛んでいるときに空気を貯えることができます、それで蝶は常に呼吸しなくてすむようになっているのです。蝶は本来いつも、蝶の内部に入り込んでいる管を通じて呼吸します。内部に入り込んでいる管を通じて呼吸することによって、蝶は、吸い込む空気と共に、空気のなかにある光も同時に体全体へと取り入れることが可能なのです。ここにもまた大きな違いがあります。挿入図:肺(lung) 図式的に示しますと、高等動物を思い浮かべてください、これは肺を持っています。肺の中へと酸素が入ってきて、心臓を迂回してここで血液と結びつきます。血液は、こういう嵩高い動物の場合それに人間の場合もですが、酸素に接触するためには心臓と肺に流れ込まなければなりません。蝶の場合、私はまったく別様に示さなければなりません。この場合次のように示さなくてはならないのです、つまりこれが蝶だとすると、このいたるところに管が入り込んでいます、これらの管がさらに枝分かれしていきます。そして今度は酸素がいたるところに入って行って酸素自身も枝分かれします、空気が体内のいたるところに侵入するのです。私たちの場合もいわゆる高等動物の場合も、空気は単に空気としてのみ肺まで入ってきます、蝶の場合、外部の空気は光を携えたその内容と共に体内全体に広がるのです。鳥は空気を空洞になっている骨の内部まで行き渡らせます、蝶は単に外部に向かってのみ光動物なのではありません、蝶は空気に担われてきた光を体全体にくまなく行き渡らせます、ですから蝶は内的にも光なのです。私が皆さんに、鳥は本来内的に暖められられた空気であるということを描写できるなら、蝶は本来まったき光です。蝶の体もまた光から出来ているのです、そして熱は蝶にとっては本来重荷であり、荷物です。蝶はまったくもって光のなかを舞い飛び、その体を完全に光から作り上げます。そこで私たちは、蝶が空中をひらひら飛ぶのを見るとき、ほんとうは単なる光の生きもの(Lichtwesen)が飛んでいると見なければならないでしょう、自らの色彩を、自らの色彩の戯れを喜ぶ光の生きものです。他のものは衣装であり荷物なのです。地球の周囲の存在たちが本来何から成り立っているかということにまず向かわなければなりません、と申しますのも、外見的な現われはひとを欺くからです。今日表面的にあれこれのことを学んだひとたち、そうですね、東洋の叡智から学んだひとたちは、世界はマーヤ(仮象、幻影 /Maja)であるということについて語ります。しかし、世界はマーヤである、と言うなら、それはほんとうに何にもなりません。どういうふうに世界がマーヤであるのかを個々の部分において見ていかなければなりません。マーヤということを理解できるのは、鳥は本来その本質においては外面的に現われているような姿に見えるのではなく、空気の生きもの[Luftwesen]なのだということを知るときです。蝶はそこに現われているような姿にはまったく見えません、蝶は光の生きものです、飛び交い、本質的に色彩の戯れへの喜びから出来ている光の生きものです、あの色彩の戯れ、地上のちりのような素材が色彩に貫かれ、それによって霊的な宇宙空間への、霊的宇宙への霊化の最初の段階であることで蝶の翅に生じている、あの色彩の戯れへの喜びです。よろしいですか、ここで皆さんはいわば二つの段階を得られたわけです、この地球の周囲の光エーテルに住まうものである蝶、そしてこの地球の周囲の熱エーテルに住まうものである鳥です。今度は三番目の種類です。私たちが空気まで下降すると、そこであの生きものに行き着きます、この地球進化のある特定の時期、たとえば月がまだ地球とともにあり、月がまだ地球から分離していなかった時期にはまだまったく存在することができなかった生きものです。ここで私たちがたどり着く生きものは、なるほどやはり空気の生きものであり、すなわち空中で生きてはいるけれども、本来すでにもう、地球に固有のもの、地球の重さに完全に接触している生きものです。蝶はまだまったく地球の重さに接触していません。蝶は喜々として光エーテルのなかを舞い飛び、自分を光エーテルから生まれた被造物だと感じています。鳥は、空気を体内で暖め、そうして暖かい空気があることによって重さを克服します。暖かい空気が冷たい空気に運ばれるのです。鳥はまだ地球の重さを克服しているのです。なるほどその素性からすればまだ空中で生きざるを得ないけれども、空洞の骨ではなく、髄に満たされた骨を持っており、鳥が持っているような空気袋も持っていないので、地球の重さを克服できない動物、こういう動物はコウモリです。コウモリというのはまったく奇妙な動物です。コウモリは、その体の内部のものによって地球の重さを克服することはまったくできません。コウモリは蝶のように光さながらに軽やかではなく、鳥のように熱さながらに軽いというわけでもありません、コウモリはすでに地球の重さに屈し、すでに筋肉と骨のなかに自らを感じてもいるのです。したがってコウモリにとって、たとえば蝶を作り上げていて蝶がまったくもってそのなかで生きているエレメント、この光のエレメントは快適ではありません。コウモリは黄昏を好みます。コウモリは空気を用いざるを得ませんが、空気が光を担っていない場合の空気をもっとも好むのです。コウモリは黄昏に身を委ねます。コウモリは本来黄昏の動物なのです。コウモリが空中で身を支えることができるのは、コウモリがいささかカリカチュア風に見えるとでも申し上げたい翼、それは実際ほんとうの翼ではなく広げられた皮膚、伸ばされた指の間に広げられた皮膚、パラシュートを有していることによってのみなのです。これによってコウモリは空中で身を支えます。これによってコウモリは、重さそのものに、この重さに関係あるものを対重(釣り合い重り/Gegengewicht)として対置することで、重さを克服するのです。けれどもそうすることによってコウモリは完全に地球の力の領域に係留されます。そもそも物理的ー機械的構成に従って蝶の翅をそう難なく構成することは決してできません、鳥の翼もです。それは決してうまくいかないでしょう。けれどもコウモリの翼、これは皆さんが地上的な力学と機械学で完全に構成することができます。コウモリは、光、光に浸透された空気を好みません、せいぜい光が少しだけ残っている黄昏の空気を好むくらいです。コウモリが鳥と区別されるのは、鳥は見るとき、本来いつも、空中にあるものを目を向けるということによってです。ハゲワシでさえ、子羊を見るとき、子羊が気圏の端にいるもの、上から見ると、地面に接したように描かれたものであるというように知覚します。しかもおまけに、これは単に見ることではなくて欲望です、皆さんはこれを感じ取られることでしょう、子羊めがけて向かってくるハゲワシの飛行、欲求と意志と欲望のまぎれもないデュナーミク(力学)であるこの飛行を実際にごらんになるときに。蝶は地上にあるものを、総じて鏡に映っているように見ています、蝶にとって地球はひとつの鏡なのです。蝶は宇宙のなかにあるものを見るのです。皆さんが蝶がひらひらと飛ぶのをごらんになるとき、ほんとうは次のように思い浮かべなければなりません、地球に蝶は注意を払わない、地球は鏡なのだと。地球は蝶に、宇宙のなかにあるものを映し出します。鳥は地上的なものを見ませんが、空中にあるものは見ます。コウモリにいたって初めて、自分が飛行して横切っていくもの、飛行して通過していくものを知覚し始めます。コウモリは光を好まないので、本来自分が見るすべてのものに接触されるのが不快なのです。ですから、蝶と鳥は非常に霊的なしかたで見るということができます。上から降りてきた最初の動物、地上的なしかたで見なければならない動物は、この見るということに触れられるのが不快です。コウモリはこの視覚を好みません、したがってコウモリは、自分が見るものと見たくないものに対する具現化した不安とでも申し上げたいものを持っています。コウモリはもののかたわらをさっとかすめていきたいのです、見なければならないけれども見たくないというふうに。そんなふうにいたるところでさっと身をかわしたいのです。コウモリはそのように身をかわしたいがために、すべてのものにあれほど驚異的に耳をすましたいのです。事実コウモリは、この飛行がどうかして危険にさらされないかどうか、絶えず自分の飛行に耳をすませている動物です。コウモリをよくごらんください。皆さんは、コウモリの耳が宇宙の不安に適合させられていることを見て取ることがおできになるでしょう。これがコウモリの耳なのです。これはまったく奇妙な形成物です、これは世界をひそかに通過していくこと、宇宙の不安に正確に適合させられています。これらすべては、コウモリを今私たちがそれを据えた関連のなかで観察するときに初めて理解されるのです。ここでもう少し言っておかなくてなりません。蝶は霊化された素材を絶え間なく宇宙に与えます、そして蝶は土星作用のお気に入りです。さて、思い出してください、私はここで、土星はこの太陽系の記憶の大いなる担い手である(☆1 *1)と申し上げました。蝶はこの惑星の想起能力とまさに関連しています。これらは、蝶のなかに生きている想起的思考なのです。鳥は、これもすでに皆さんに申し上げたことですが、全体として本来一個の頭であり、そして宇宙空間を貫いて飛翔していくこの熱に浸透された空気のなかで、鳥は本来生きて飛翔する思考なのです。私たちが私たちのうちに思考として持っているもの、実際熱エーテルとも関連しているものは、私たちのなかの鳥の本性、鷲の本性です。鳥は飛翔する思考なのです。コウモリはしかし飛行する夢、飛行する宇宙の夢です。したがって皆さんはこう言うことができます、地球は蝶によって織りめぐらされている、蝶は宇宙の記憶である、そして鳥類については、鳥類は宇宙の思考である、そしてコウモリについては、コウモリは宇宙の夢、宇宙の夢みることである、と。コウモリとして空間をばたばたと通り過ぎていくのは、実際のところ飛行する宇宙の夢なのです。夢が黄昏の光を愛するように、宇宙はコウモリを空間を通過していかせることによって黄昏の光を愛します。記憶という持続的な思考、私たちはこれが地球を取り巻く蝶の帯のなかに具現されているのを見ます、現在のなかに生きている思考は、地球を取り巻く鳥の帯のなかに見ます、夢は地球の周囲に飛び回るコウモリとして具現しているのを見るのです。でもどうか感じとってください、私たちがこのように正しくそのフォルムへと深く入っていくとき、コウモリをこのように見ることは何と夢を見ることに親和性があることか。コウモリを、次のような考えが浮かんでくるという以外の見方はできません、お前はやはり夢を見ている、けれどもそれは本来ここにあるべきではない何かだ、夢が通常の物質的現実から出てくるように、自然(界)の別の被造物から出てきた何かだ、と。つまり私たちはこう言うことができます、蝶は霊化された実質を生きているうちに霊の国へと送り込む、鳥は死後にそれを送り出す、と。さてコウモリは何をするのでしょう。コウモリは、霊化された実質、とりわけ、個々の指の間に張られた皮膚のなかに生きているあの霊的実質を、生存中に分泌します、しかしそれを宇宙に委ねるのではなく、地球の大気中に分泌するのです。それによって絶え間なく地球の大気中に霊の真珠、とでも申し上げたいものが生じます。さてこのように地球は、放射していく蝶の霊素材の持続的なきらめきに取り巻かれ、死にゆく鳥から発するものが迸っていくのですが、コウモリがそこで自分が霊化したものを分泌した空気、この空気中の奇妙な含有物が地球へと反射されてきます。これらは、コウモリが飛んでいるのを見るときいつも見られる霊の形成物です。事実、コウモリはいつも彗星のように背後に尾のようなものを付けています。コウモリは霊素材を分泌しますが、それを送り出さず、物質的な地球素材のなかに押し戻します。コウモリはそれを空中へと押し戻すのです。物質的なコウモリが飛ぶのを物質的な目で見るように、このコウモリに相応する霊的形成物が空中を飛んでいくのを見ることができます、これは空間をばたばたとよぎっていきます。そして私たちが、空気は酸素、窒素、その他の構成要素から成り立っていると知るとき、それがすべてではありません、空気はそれに加えて、コウモリの霊的影響から成り立っているのです。どれほど風変わりで逆説的に聞こえようと、コウモリのこの夢の類は空気中に小さな幽霊たちを送り込むのです、それらはやがてひとかたまりに一体化します。地質学では、大地の下にあってまだどろどろの粥状の岩石の塊であるものをマグマと呼びます。コウモリの分泌物に由来する空気中のマグマについても語ることができるでしょう。本能的な霊視がまだ存在していた古代においては、人間たちはこの霊マグマに対して非常に敏感でした、ちょうど今日でも、より物質的なもの、たとえば悪臭に敏感なひとたちがいくらかいるように。ただ、これは何かもっと下賎な、とでも申し上げたいものとみなすことができるでしょう、他方、古代の本能的な霊視者の時代においては、人間たちはコウモリとして空中に存在するものに対して敏感だったのです。人間たちはこれから身を守りました。いくつかの秘儀のなかには、このコウモリの残存物が人間に支配力をふるわないように、人間が自らを内的に遮断するためのまったく特定の呪文がありました。と申しますのも、人間である私たちは空気とともに単に酸素と窒素だけを吸い込むのではなく、私たちはこのコウモリの残存物も吸い込んでいるからです。ただし、今日の人類はこのコウモリの残存物から身を守ることを目指してはおらず、場合によっては、たとえば匂いに対して、と私は申し上げたいのですが、とても敏感である一方、コウモリの残存物に対してはきわめて鈍感なのです。人類はこれを飲み込みます、そしてその際何か吐き気のようなものすら感じることなく、と言えます。これはまったく奇妙なことです、それ以外ではとても神経質な人々が、私がここでそれについてお話ししたものを、せっせと飲み込むというのは。しかしこれはこうして人間のなかにも入っていきます。これは物質体とエーテル体には入っていきませんが、アストラル体のなかに入っていきます。さて、ごらんのように、ここで私たちは奇妙な連関にたどり着きました。秘儀参入学はまさに、至るところで連関の内部にまで入り込んでいきます、つまりこれらのコウモリの残存物は、私が連続講演においてここで皆さんに龍として描写いたしましたものにもっとも欲される食物なのです。ただ、これらコウモリの残存物は、最初に人間のなかに吸い込まれざるを得ません。そして人間がその本能をこれらのコウモリの残存物に浸透させるとき、龍は人間の本性のなかにその最良の拠り所を得ます。コウモリの残存物が人間の内部で撹乱するのです。そして龍はこれを貪り喰いそれによって太ります、もちろん霊的に語ればですが、そして龍は人間に対して支配力を得ます、さまざまなしかたで支配力を獲得するのです。そしてこれは、今日の人間もまた身を守らなければならないことです。ミカエルと龍の闘いの新しい形としてここで描写されましたものによって、防御がなされねばなりません。ミカエル衝動をここで描写されましたように(*2)受け入れるときに、人間が内的に力づけられつつ得るもの、これが、龍が得ようとする食物から人間を守ります、そうすれば人間は大気圏内のきわめて不当なコウモリの残存物から身を守ることができるのです。内的な宇宙連関から引き出されうる真実を前にして決して尻込みしてはなりません、この内的な宇宙連関にほんとうに深く入り込んで行こうとするならです。と申しますのも、今日一般によく知られている真理探求者の形式は、まったくいかなる真実のものにも導くことはなく、たいていは夢みられたものですらない何か、まさにマーヤにしか導かないからです。真実は、物理的存在といえどもすべて霊的存在に浸透されているのが見られる領域においてこそぜひとも探求されねばなりません。そこにおいて真実に近づくことができるのは、今この連続講義においてなされているように真実を観察するときのみです。どこかに存在しているものは、何か善いものか、何か悪しきもののために存在しています。すべては、それぞれが他の存在とどう関連しているのか認識できるようなしかたで宇宙連関の内部に置かれているのです。唯物論的な考え方のひとにとって、蝶は飛び、鳥は飛翔し、翼手類、つまりコウモリは飛びます。しかしこれはほとんど、あまり芸術センスのないひとに見られることですが、自分の部屋いっぱいに、互いにばらばらの、内的な関連のまったくないありったけの絵画を掛ける、という場合のようなものです。通常の世界観察者にとって、世界(宇宙)を飛んでいくものも、何ら内的な連関を有しておりません、そういうひとにはそれが見えないからです。けれども、宇宙におけるすべてのものは、自らの場所に立っています、なぜなら、それらはその場所から、まさに宇宙の全体性との内的連関を有しているからです。蝶であれ、鳥であれ、コウモリであれ、すべては宇宙のなかに何らかの意味を伴って置かれているのです。今日このようなことを嘲笑したいひとは、嘲笑すればよろしい。こういうひとたちは、嘲笑に関してすでに別のこともやり遂げました。著名なアカデミー会員たちがこういう判断を発表したのです、隕石などというものは存在しない、なぜなら天から鉄が落下することはできないから云々、と。わたしが今日お話ししましたようなコウモリの機能について、このひとたちが嘲弄しないなどとどうして言えるでしょう。とは言え、実際に私たちの文明を霊的なものの認識で貫くという点において、こういったことすべてが(これを)揺るがすことは許されません。参照画:Giant golden-crowned flying fox□編註☆1 土星は記憶の大いなる担い手:詳細はシュタイナーの1923年7月27日の講義(『秘儀参入学と星認識』[Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis] GA228)参照。□訳註*1 GA228『秘儀参入学と星認識』の第1講(1923年7月27日)によれば、土星は太陽系の生き生きとした記憶、木星は宇宙の創造的、受容的思考、火星は言語の衝動に関係する。金星は地球から発するすべてを愛に満ちて宇宙に返す。水星は宇宙的思考、月は遺伝の力の担い手。火星、木星、土星は人間を解放する惑星、金星、水星、月は運命を定める惑星。これらの惑星の間にあって、調和を創り出すのが太陽。*2 ミカエルと龍の闘い、ミカエル衝動:すぐ前の時期に行なわれた、GA229「四つの宇宙的イマジネーションにおける四季の体験」(1923年10月3日から10月15日)などの内容と関連していると思われる。第1講の編註 ☆1も参照。*邦訳は「四季の宇宙的イマジネーション」(西川隆範訳 水声社)人気ブログランキングへ
2024年03月29日
コメント(0)
-
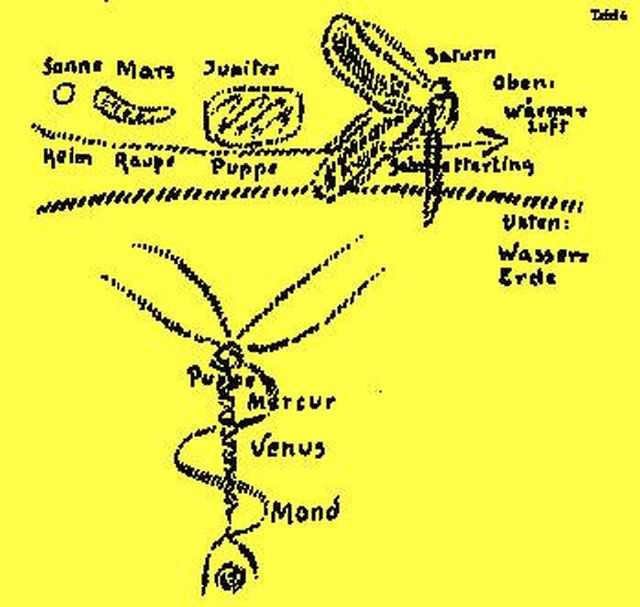
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー(GA230)創造し、造形し、形成する宇宙言語の協和音としての人間Der Mensch als Zusammenklangdes schaffenden,bildenden und gestalteden Weltenwortes(翻訳者:yucca)第4講 1923年10月26日 ドルナハ ・かつての地球の状態と、現在の地球状態に見られるその名残・土星ー太陽と月ー地球の区別・土星ー太陽的なものと昆虫界(特に蝶)との関連性・昆虫界は太陽作用と共に働きかける火星、木星、土星作用の賜物・植物界の発生:地球に委ねられた胚と金星、水星、月の作用・植物は地球に繋ぎとめられた蝶、蝶は宇宙に解き放たれた植物 私たちは、あるやりかたで、地球状態、宇宙状態、動物界それぞれと人間との連関を考察いたしました。これから数日間はまさにこの考察を先に進めていくことになるでしょう、けれどもきょうのところは、今後私たちの関心事となるにちがいないより広範な領域へのつなぎにしたいと思います。ここで先ず最初に示唆しておきたいことは、すでに私の「神秘学概論」のなかで、宇宙における地球の進化は、この地球進化というものを問題にするなら、太古における地球の土星変容(aturnmetamorphose)を出発点としなければならなというふうに叙述されていたことです。この土星変容は、そもそもこの太陽系に属しているすべてのものがまだこのなかに含まれているという状態として思い描くことができます。土星から月に至るこの太陽系の個々の惑星は、当時まだこの古い土星、これはご存じのように熱エーテルからのみ成り立っています、においては、溶解した宇宙体(Weltenkoerper)なのです。つまり、まだ空気の密度すら獲得しておらず、熱エーテルそのものである土星は、後に独立した形態を取って個々の惑星へと個別化されるすべてのものを、同じくエーテル的に溶解した状態で含んでいるのです。次いで私たちは、地球進化の第二の変容として、私がまとめて地球の古い太陽変容と呼んだものを区別します。ここでは、土星の火球から徐々に空気球が、光の流入した、光によって輝ききらめく空気球である太陽が形成されます。さらに第三の変容があります、前の状態が繰り返されたのちにここで形成されてくるものは、一方では、当時まだ地球と月とを包含していた太陽的なものであり、さらには、他ならぬ分離された土星をその一部とする外的なもの、これも「神秘学概論」に書かれているのをご存じです。けれども当時この月変容においては同時に、太陽と、地球と月との連関であるものが、分離するということが起こります。そしてもう何度も記述しましたように、今日私たちが見知っているような自然領域は当時存在しておらず、とくに地球は鉱物塊を含んでいませんでした、地球は、こういう表現が許されるなら、角質(hornartig)のものだったのです、したがって、固体成分が角質状に溶け合っていて、液体状になった月の塊から角質の岩がいわば突出していたのです。続いて、私たちの今日の地上の状態である状態が、第四の変容のなかで誕生しました。さて、私たちがこれら四つの変容を順に描いてみますと、まず最初に土星変容、つまりのちにこの太陽系に含まれるものがすべてまだ溶解していた熱体、、それから太陽変容、月変容、そして地球変容となります。私たちはこの四つを二つに分けることができます。図示される)ひとつよく考えてみてください、土星の太陽への進化において、まず気体的実質へと前進したものを私たちはどのように扱うでしょう。進化は火球から始まります、火球が変容し、空気球へと凝縮します、この空気球はすでに光に浸透され、光にきらめいているのですが。これで進化の最初の部分が得られます。さらに、月がその当初の役割を果たす進化の部分が得られます。と申しますのも、月が果たす役割はまさに、あの角質状の岩石形成物を形成することができるようにすることだからです。月は地球変容の期間に放出されますね、月は衛星となり、内的な地球の力を地球に残していきます。たとえば、重さの力(die Krafte der Schwere)は、物理的な関係において月によって置き去りにされたものに他なりません。月自身は去ってしまいましたが、もし、この古い月の包含物の名残が置いていかれなかったら、地球は重さの力を発達させられないでしょう。月は宇宙空間におけるあのコロニーなのです、これについて私はもうずいぶん前に霊的観点から皆さんにお話しいたしました。月は地球とはまったく異なる実質を有していますが、月は地球に、広義の地磁気(Erdenmagnetismus)と名付けられうるものを残していきました、地球の力、とくに地球の重力(Schwerkraefte)、重量作用とみなされる作用、これらは月が残していったものです。ですから私たちはこう言うことができます、ここに黒板に描かれた左の2つの円、土星状態と太陽状態があります、両者をまとめると、根本的に熱の、光に浸透されて輝く変容です。そしてここには(右の2つの円)月状態と地球状態があります、月に担われた液体的変容、液体的なものは月変容の期間に形成され、さらに地球変容の期間にも残ります、そして固体は、まさに重力を通じて出現させられるのです。以上二つ(ずつ)の変容は、本来かなりはっきりと区別されます、そして明確に理解しておかなくてはならないことは、かつてあったものはすべて、後のものの内部にも潜んでいるということです。古い火球土星であったものは、熱実質としてその後のすべての変容の内部に残りました、私たちが今日地球領域の内部をあちこち移動していたるところでなお熱にぶつかるなら、この私たちがいたるところで見出す熱は、古い土星進化の名残なのです。私たちが空気あるいは単に気体状の物体を見出すいたるところに、古い太陽進化の名残が得られるのです。私たちが太陽に貫かれて輝く大気を見わたすとき、私たちはこの進化の感情に満たされることによって、ほんとうはこう言うべきなのです、この太陽に貫かれて輝く大気のなかに、私たちは古い太陽進化の名残を得ているのだと。と申しますのも、この古い太陽進化というものが存在しなかったら、私たちの大気と、今や外部にある太陽光線との親和性は存在しないでしょうから。太陽がかつて地球と結びついていたこと、太陽の光がまだ気体状であった地球の内部で自ら輝きを発していたこと、つまり地球は内部の光を宇宙空間に放射する空気球であったこと、こういうことを通じてのみその後の変容、つまり現在の地球変容が可能となったのです、こうして地球は、大気圏に囲まれ、そのなかに外から太陽光線が差し込んでくるようになりました。とは言え、この太陽光線は、地球の大気圏に深い内的親和性を有しています。この太陽光線はたとえば、今日の物理学者たちが粗雑に語るような、たとえばガス状の大気中を貫いていく小さな射出粒子がそうであるような、そういう光線ではありません、そうではなくこの太陽光線は、大気と深い内的親和性を有しています。そしてこの親和性は、かつて太陽変容の時代共にあったことの残響に他なりません。このように、以前の状態が繰り返し繰り返し多種多様なしかたで後の状態に入り込むことによって、すべては互いに親和関係にあるのです。全般的に見て、皆さんが「神秘学概論」のなかに見出すように、今ここで私が手短かに描き出しましたように地球進化が進行していくうちに、地球上と地球の周囲にあるもの、そして地球内部であるもの、これらすべてが発生してきました。そこで私たちは今やこう言うことができます、今日の地球を眺めると、私たちは地球の内部に、固体を生ぜしめるものを、本質的に地磁気のなかに繋ぎ止められた内的な月を持っていると。内的な月、これは実際固体的なもの全般が存在するように、重さを持つものが存在するように作用するもので、重力とは実に液体的なものから固体的なものを作り出すものなのです。私たちはさらに、本来の地球領域、すなわち液体的なものを持っています、これは多種多様なしかたで再び現われてきます、たとえば地下水として、また、雨となって上昇し下降する、水蒸気状態の水などとして。さらに私たちは周囲に、気体状のものを有しています、古い土星の名残である火的なものに貫かれたすべてのものを有しています。したがって私たちは、今日の地球においても、上方に太陽ー土星あるいは土星ー太陽であるものを指摘せねばならないのです。私たちは常にこう言うことができます、光に浸透されて輝く暖かい空気のなかに存在するものはすべて、土星ー太陽であると。そして私たちは上方を見上げ、この空気が貫かれているのを見るのです、この空気が、土星作用であるもの、太陽作用であるもの、その後時の経過につれて本来の気圏として、ただし太陽変容の残響である気圏として発達してきたものに貫かれているのを見るのです。これが得られるのは、私たちが眼差しを上に向けるときです(図示される)。さて私たちが眼差しを下へ向けますと、後半の二つの変容の間に生じたものを継承するものがより多く得られます。重さ、固さ、もっと良い言い方をすれば重さを引き起こすもの、固体となっていくものが得られるのです、私たちは液体的なものを得ます、月ー地球が得られるのです。いわば地球という存在のこの二つの部分を私たちは厳密に区別することができるのです。皆さんが『神秘学概論』を今一度こういう観点から通読なさるなら、太陽変容が月変容へと移行する箇所において、まさに表現全体を通じて深い区切りが入れられているのがおわかりになるでしょう。このように今日においてもなお、上にあるものつまり土星的なものと、下にあるものつまり地上的ー月的ー液体的なものとの間には一種の鋭い対照(コントラスト)があります。つまり私たちは、土星ー太陽的ー空気的なものと、月ー地球的ー液体的なものとを完全に区別することができます。一方は上、他方は下です。地球進化においては全般的にみて地球に属するものすべてがともに進化したため、こういう事柄を秘儀参入学をもって見通すひとの眼差しがまず最初に向かうのは、昆虫の世界の多様性です。単なる感情であっても、この飛び回りきらめく昆虫界を、上なるものと、土星ー太陽的ー空気的なものとある種関係づけざるを得ない、と考えられるのです。これはまったくそのとおりです。私たちが蝶をじっくりと見るとき、蝶は空中を、光の流入した、光に貫かれて輝く大気のなかを、きらめく色彩をみせて舞い飛びます。蝶は空気の波に運ばれるのです。蝶は本来、月ー地球的ー液体的なものにはほとんど触れません。蝶のエレメントは上にあるものです。本来地球進化とはどのようなものであるかをさらに研究しますと、小さな昆虫の場合はとくに、奇妙なことに地球変容の非常に初期の時代に至ります。今日光に貫かれて輝く大気のなかで蝶の翅としてきらめいているものは、最初は古い土星の時期に元基のなかで自らを形成し、古い太陽の時期にさらに進化しました。今日なお蝶が光ー空気の創造物であることを可能にしているものは、このとき生み出されたのです。太陽が光を放射するという天分は太陽自身に帰せられます。太陽の光が物質のなかに火的なもの、きらめくものを生じさせる天分は、土星ー木星ー火星作用に帰せられます。ですから、蝶の本性を地上に捜し求めるひとは、結局、蝶の本性を理解できません。蝶の本性のなかで働いている力を、私たちは上に捜さなければなりません、太陽、木星、土星のもとに探究しなければならないのです。私たちがこの驚くべき蝶の進化のもっと細部に入り込んでいくと、私はすでに一度ここで、この蝶の進化を人間との関連においていわば記憶の宇宙的体現としてお話ししましたが、もっと細部に入り込んでいくと、蝶はまず光にきらめきつつ空気に運ばれて地球の上方を舞い飛ぶということがわかります。蝶は卵を産みます。そう、粗雑な唯物主義の人は、蝶は卵を産む、と言います、なぜなら現在の非科学(Unwissenschaft)の影響下にあっては、そもそももっとも重要な事柄が研究されないからです。問題はこういうことです、蝶は卵を産むとき、いったい誰に卵を委ねるのかと。さて、皆さんが蝶の卵が産みつけられる場所をくまなく研究してごらんになると、蝶の卵は太陽の影響から遠ざけられることがないように産みつけられるということが、いたるところでおわかりになるでしょう。地球への太陽の影響は、単に太陽が地球を直接照らす場合にのみ存在するわけではありません。もう何度も注意を向けていただいたことですが、農民たちは冬の間ジャガイモを地中に置いて土で覆います、なぜなら、夏の間に太陽熱と太陽の光の力としてやってくるものは冬の間は地球の内部にあるからです。地球の表面ではジャガイモは凍りついてしまいます。ジャガイモを穴に埋めてその上に土をかぶせると、冬の間中太陽の作用が地中にあるため、ジャガイモは凍りつかず、ちゃんとした良いジャガイモのままです。冬の間中私たちは夏の太陽の作用を地下に求めなくてはなりません。たとえば私たちが12月にある程度の深さの地下に行くと、12月に7月の太陽の作用が得られるのです。7月には太陽はその光と熱を地表に放射します。熱と光は徐々に深く入り込んでいきます。7月に私たちが地球の表面への太陽の力によって体験するものを12月に捜そうとするなら、私たちは穴を掘らなくてはなりません、すると、7月には地球の表面にあったものが、12月にはある程度深いところに、地下にあるのです。そこではジャガイモが7月の太陽のなかに埋め込まれています。このように、太陽は単に、ひとが粗雑な唯物論的知性でもって捜すところにのみ存在するのではありません、本来太陽は多くの領域に存在するのです。ただ、このことは宇宙における季節によって厳密に統御されています。けれども蝶は、卵が何らかのしかたで太陽との関係を保てないようなところには卵を産みません。ですから、蝶が地球領域に卵を産みつける、と言うのは、まずい表現なのです。蝶は断じてそんなことはしません。蝶は太陽領域に卵を産みつけるのです。蝶はまったく地球へは降りてきません。地上的なもののなかに太陽が存在するいたるところに、蝶はその卵を産みつけるための場所を捜します、そのためこの蝶の卵はまったくもって太陽影響下にのみあります。蝶の卵は全く地球の影響下にはないのです。次いで、ご存じのように、この蝶の卵から幼虫が這い出してきます。つまり幼虫が出てきて太陽の影響のもとにとどまるのですが、今やその他の影響も共に受けるようになります。まだ他の影響を共に受けないうちは、幼虫は這い出してくることができないでしょう。これは火星の影響です。地球を思い浮かべていただいて、(図示される)そして火星が地球の回りを回転するとしますと、上のいたるところに火星の流れがあって、しかもとどまり続けます。火星がどこかにある、ということが問題なのではなく、私たちが全火星領域を有しているということ、そして幼虫が這い出していくとき、幼虫は火星領域の意味において這い出していくのだということが重要なのです。それから幼虫はさなぎになり、自らの周囲に繭を作り出します。私たちは繭を得るのです。私は皆さんに、これは幼虫の太陽への献身であること、このとき紡がれる糸は光線の方向に紡がれることをお話しいたしました。幼虫は光にさらされ、光線を追い求め、紡ぎ、暗くなると中断し、また紡ぎます。これはすべて本来、宇宙的な太陽光、物質素材(マテーリエ)に浸透された太陽光なのです。つまり皆さんがたとえば、皆さんの絹の衣服に用いられる蚕の繭を手にされるとき、絹のなかにあるものは、まさしく太陽の光、蚕の物質素材が紡ぎ込まれた太陽光なのです。自身の体から蚕はその実質を太陽光線の方向に紡ぎ込みます、そしてそうすることによって自らの周囲に繭を作り出すのです。けれどもこれが起こるためには、木星作用が必要です。太陽光線は木星作用によって修正されなければならないのです。そして、ご存じのとおり、繭から、さなぎから這い出してくるのは、蝶です、そう、光に運ばれ、光に輝く鱗翅類です。蝶は、ちょうどクロムレック(環状列石)に射し込んでくるようにしか光が入ってこない暗い部屋を後にします、このことを私は皆さんに古代のドルイドのクロムレックによってお話しいたしました。このとき太陽は土星の影響下に入ります、そして土星と共にあることによってのみ太陽は、鱗翅類が空中でさまざまな色彩に輝くように光を空気のなかに送り込むことができるのです。ですからよろしいですか、私たちが大気中を飛ぶ無数の蝶の群を眺めるとき、その内部には私たちがそれについてこう言わざるを得ない何かがあるのです、これは根本的に地球の産物などではない、これは上から地球へと産み落とされたのだ、と。蝶はその卵を、太陽から地球へやってくるものより下へは決して携えていきません。宇宙は地球に無数の蝶の群を贈ります。土星は蝶に色彩を与えます。太陽は飛翔の力を、光の支える力その他によって引き起こされた飛翔の力を与えます。つまり実際のところ私たちは蝶のなかに、小さな存在を、太陽と太陽を越えたこの太陽系であるものによってこの地球上へとまき散らされた小さな存在とでも申し上げたいものを、見なければなりません。蝶、昆虫全般、とんぼ、その他の昆虫たちは、まさしく土星、木星、火星および太陽からの賜物なのです。もし太陽の向こうにある諸惑星が太陽と共に、地球にこの昆虫界という贈り物を与えてくれないとしたら、地球は、たったひとつの昆虫も生み出すことはできないでしょう、蚤一匹たりともです。事実、土星、木星その他は非常に物惜しみしないので、昆虫界を羽ばたき出させることができます、これは地球進化が体験した最初の二つの変容のおかげなのです(図参照)。さて今度は、後半の二つの変容、月変容と地球変容がいかに共に作用してきたかを見てみましょう。さて、蝶の卵はまったく地球に委ねられないとはいえ、やはり次のようなことは指摘されなければなりません、つまり、月変容つまり第三の変容が始まった頃、蝶はまだ今日のようなものではなかったということです。地球もこれほど太陽に依存してはいませんでした。太陽はもともと第三の変容の当初は、まだ地球と共にあったのであり、その後になってはじめて分離したのです。したがって蝶もまだ、その胚[Keim]を地球にまったく委ねないほど脆くはありませんでした。蝶はその胚を地球に委ねることで同時に太陽にも委ねていたのです。ここで次のような差異が生じました。この最初の二つの変容においては、昆虫界の遠い祖先について語ることができるのみです。とは言え、宇宙に、外部の惑星や太陽に委ねるということは、当時はまだ地球に委ねるということでした。地球が濃密化し、水を獲得してはじめて、地球が月の磁気的な力を獲得してはじめて、事態は変化し、差異が生じてきたのです。Sonne:太陽 Mars:火星 Jupiter:木星 Saturn:土星 Oben:Waerme=Luft 上:熱=空気 Keim:胚 Raupe:幼虫 Puppe:さなぎ Schmetterling:蝶 Unten:Wasser=Erde 下:水=土 Mercur:水星 Venus:金星 Mond:月挿入図: さてこう考えてみましょう、このすべて、つまり熱ー光は上に属します、今度は下を考えると、水ー地です。地球に委ねられる運命にあった胚を想定してみましょう、一方、別の胚は、引き留められ、地球ではなく地上的なものの内部の太陽にのみ委ねられます。さて、第三の変容つまり月変容が起こったときに地球に委ねられた胚を想定してみましょう。よろしいですか、この胚、これは地球作用の影響下、水的な地球ー月作用の影響下に入ります、これは、昆虫の胚が太陽作用の影響下と太陽より上にあるものの影響下にのみ入るのと同様です。そして、これらの胚が地ー水作用の領域に入ったことによって、これらの胚は植物の胚となりました。そして上に残された胚、これらは昆虫の胚のままとどまりました。さらにそれから第三の変容が始まったとき、当時太陽的であったものから月的ー地球的なものへと変化したものを通じて、植物の胚がこうして地球進化の第三変容の内部に発生したのです。今やこの地球外の宇宙の影響のもとに得られたもの、胚から幼虫、さなぎを経て蝶となるこの進化全体を、皆さんは今やこのように追求することができます、種子が地球的になることによって生じてくるのは蝶ではありません、種子が地球的になることによって、ーー今や太陽ではなくーー地球に委ねられることによって生じてくるのは、植物の根、つまり胚から発生する最初のものなのです。そして、幼虫が火星から発する力のなかで這い出してくる代わりに、葉が生えてきます、上に向かって螺旋状の位置に沿って生えていく葉です。葉とは、地球の影響下に入った幼虫なのです。這っている幼虫をよくごらんになると、上において下つまり植物の葉に対応するものが得られます、葉は太陽領域から地球領域に移された種子によって根となったものから変容して生じるのですが、この葉に対応するものが得られるのです。皆さんがさらに上昇すると、萼のある位置に向かってますます収縮した、さなぎであるものが得られます。そして最後に、鱗翅類が花の中に発生します、上空の蝶と同様に色とりどりの花のなかにです。円環は閉じます。蝶が卵を産むように、花の中にはまた未来のための種子が発生します。おわかりですね、私たちは上空の蝶を見上げます、私たちは蝶を空中に持ち上げられた植物と理解するのです。卵から鱗翅類(の成虫)に至る蝶は、地球の影響のもとに下で植物であるものと同じものですが、上位惑星とともに太陽の影響下にあるのです。これが葉に達すると(図参照)、地球から月の影響、さらには金星の影響と水星の影響が得られます。それからまた地球の影響にもどります。種子は再び地球の影響なのです。さてごらんのように、私たちの前に自然の大いなる秘密を現わす二つの句を置くことができます: 植物を見よ 植物は地球により 繋ぎとめられた蝶。 蝶を見よ 蝶は宇宙により 解き放たれた植物。 植物、それは地球(大地)により繋ぎ止められた鱗翅類です。鱗翅類、それは宇宙により地球(大地)から解き放たれた植物です。蝶を、昆虫全般を、胚から飛び回る昆虫に至るまで眺めるなら、それは空中に持ち上げられた、宇宙により空中に形成された植物なのです。植物を眺めるなら、それは下に繋ぎ止められた蝶なのです。卵は地球に要求されます。幼虫は葉形成に変容させられます。収縮したもののなかには、さなぎ形成が変容させられています。さらに、鱗翅類のなかに発生するものは、植物の場合花のなかに展開されるのです。蝶-昆虫界全般と植物界との間にあんなに密接な関係があるのも驚くにはあたりません。と申しますのも、そもそも、昆虫たち、蝶たちの根底をなしている霊存在たちはこう言わざるを得ないからです、この下には私たちに近しいものたちがいる、私たちはこれらに親しまねばならない、これらと結びつかねばならない、これらの樹液などを味わいつつこれらと結びつかねばならない、これらは私たちの兄弟だからだと。これらは兄弟だ、地球領域に下降していき、地球によって繋ぎ止められ、別の生存状態を受け容れた兄弟なのだと。また一方、植物に魂を吹き込む霊たちが、蝶たちを見上げてこう言うこともあり得るでしょう、これは地球の植物の(うちの)天に近しいものたちだと。よろしいですか、宇宙の理解は抽象をもってしては成立しない、と言えます、抽象では理解するために不十分だからです。なぜなら、宇宙において働いているものからして、もっとも偉大な芸術家だからです。宇宙はあらゆるものを法則に従って、もっとも深い意味において芸術家の感覚を満足させる法則にしたがって形成します。抽象思考であるものを芸術家の感覚のなかで変容させることによって以外、誰も地球に沈降させられた鱗翅類を理解できません。光と宇宙的諸力によって空中へと持ち上げられた植物の花の内容を、誰も蝶のなかに見て理解することはできません、抽象的思考に再び芸術的な運きを与えることのできないひとは誰も。とは言え、私たちが自然物と自然存在とのこの深い内的な親和性に注目するとき、それはともかくも何かとほうもなく精神を高揚させるものであることには変わりありません。昆虫が植物にとまっているのを見ること、そして同時に、植物の花をアストラル的なものがいかに統べているかを見ることは、何かまったく特別なことです。そこでは植物は地上的なものを抜け出そうとしているのです。植物の天への憧れがさまざまな色彩にきらめく花びらを統べています。植物は自分ではこの憧れを満たすことはできません。そこで植物に向かって宇宙から、蝶であるものが放たれます。植物は蝶を見つめます、蝶の中で自分の望みがかなえられているのを見るのです。植物界の憧れが、昆虫、とりわけ蝶の世界を観ることで鎮められる、ということ、これは地球を取り巻く驚くばかりの結びつきです。満開の花々の色彩がその色を宇宙に放射することで示している切なる願い、これは、植物に向かって鱗翅類がその色彩をきらめかせて近づいてくることにより、植物にとってその憧れの認識実現のようになるのです。放射するもの、熱を放射する憧れ、天から放射されてくる満足、これが植物の花の世界と蝶などの鱗翅類世界との交流なのです。これこそ、ぜひとも私たちが地球の周囲に見なければならないものです。さて、植物界への移行が得られましたからには、人間から動物に至った観察を次の時間に拡張していくことができるでしょう。今や私たちは植物界を組み入れることができ、こうして次第に、人間と地球全体との関係へと至ることができるでしょう。しかしそのためには、飛翔する空中の植物つまり蝶から、地に固着している蝶つまり植物へと、いわば橋が架けられることがどうしても必要でした。大地の植物は地に固着している蝶です。蝶は飛翔する植物です。私たちがこの地に結びつけられた植物と天に解き放たれた蝶との関係を認識できて始めて、動物界と植物界との間に橋を架け、さらにはきっとある種の無関心をもってあらゆる俗物性、あいもかわらず自然発生云々がどうであったかを語り続ける俗物性を見下ろすこともできるのです。これらの散文的概念をもってしては宇宙万有(ウニヴェルズム)の領域、到達すべき宇宙万有の領域に到達できません。この領域に到達することは、散文的概念を芸術的概念に転換することができ、さらに次のようなことを思い浮かべることができるようになって始めて可能なのです、つまり、太陽にのみ委ねられた天から生まれた蝶の卵から、植物が後になってから生じるようすを、以前は太陽のみに委ねられていた蝶の卵が今は地球に委ねられることにより、この蝶の卵が変容させられることで植物が生じてくるようすをです。人気ブログランキングへ
2024年03月28日
コメント(0)
-
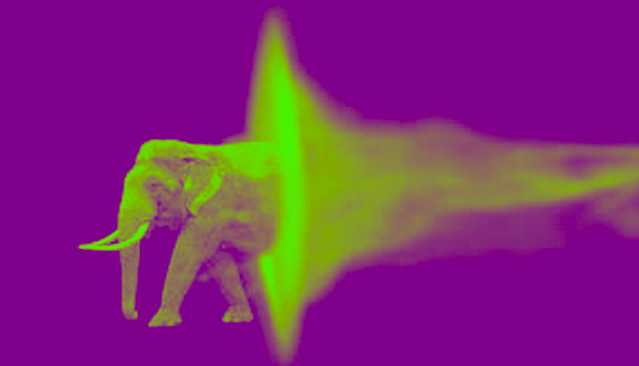
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー(GA230)創造し、造形し、形成する宇宙言語の協和音としての人間Der Mensch als Zusammenklangdes schaffenden,bildenden und gestalteden Weltenwortes(翻訳者:yucca)第3講 1923年10月23日 ドルナハ ・霊的実質と物質的実質、霊的な力と物質的な力・上部人間、下部人間における霊的ー物質的な実質と力の相互浸透・実質と力の不規則な配分によって病気が起こる・人間の宇宙的カルマー人間は地球に対して負債がある・牛は地球にとって必要な霊的実質を地球に与える・鷲は地球にとって不要になった物質的実質を霊界に運び去る・地球存在を確実にする鷲と牛・牛と鷲の回りの元素霊たちの歓び・現代の一般的科学、認識では宇宙の意味は見出せない・鷲、ライオン、牛に示される宇宙的秘密 私たちは人間を再びある観点から宇宙万有のなかに据えようと試みました。今日は、いわば全体を総括することのできるような考察をしてみましょう。私たちは物質的な生の範囲内においては地上に生きていて、きわめてさまざまなしかたで自然界の本性、そして人間の形態そのものへと形成され、形態化されている地球の物質素材、この物質素材を通じて存在している出来事および事実に囲まれています。あらゆるもののなかにまさに地球の物質素材が存在しているのです。私たちは今日これを、この物質素材をひとつ、後ほどすぐにこの反対のものについても語らなければならないので、地球の物質的実質(die physische Substanz)、つまり素材的に地球のさまざまな形態化の基礎を成しているものと呼びましょう、そして、この物質素材の反対のものとして宇宙に存在するもの、霊的実質(die geistige Substanz)をこれと区別しましょう、この霊的実質は、たとえば私たち自身の魂の基礎を成すものですが、ふつうは宇宙において、物質的形態化に霊的なものとして結びつくような形態化の基礎を成しているのです。物質素材あるいは物質的実質について語るのみでは間に合わないのです。私たちが高次ヒエラルキア存在たちを私たちの宇宙の全体像のなかに置いてみると考えてごらんになりさえすればよいのです。これらの高次ヒエラルキア存在は、地の実質というものを有しておりません、私たちが彼らの身体性とでも呼ぶところのもののなかに地の実質を有してはいないのです。したがって、私たちが地上的なものを見ることができると、私たちは物質的なものを知覚するでしょう、私たちが地球外のものを見ることができれば、私たちは霊的実質を知覚するでしょう。今日、霊的実質についてはほとんど知られておりません、そのため、物質界と同時に霊界にも属している地球存在、つまり人間についても、あたかも人間が物質的実質しか有していないかのように語られるのです。けれどもそうではありません。まったくもって人間は自らのうちに霊的実質と物質的実質を担っています、しかも非常に独特なしかたで、つまりこういう事柄に注意することに慣れていないひとが最初驚愕せざるを得ないようなしかたで、人間は自らのうちに霊的実質と物質的実質を担っているのです。つまり、人間を運動に移行させるもの、すなわち人間の四肢であるもの、そして四肢から発して新陳代謝活動として内部へと継続されるもの、人間におけるこうしたものを考慮に入れると、そのとき私たちが主として物質的実質について語るとすればそれは正しくありません。私たちが人間について正しく語ることができるのは、人間のいわゆる低次の性質について、他ならぬこの性質の根底には根本的に霊的な実質があるのだとわかるときのみです。したがって、人間を図式的に描こうとすれば、以下のようなしかたで行なわなくてはなりません。私たちはこう言わなくてはなりません、本来下部人間は、霊的実質のなかに形成されたものを私たちの前に示し、私たちが人間の頭に向かって進めば進むほど、人間は物質的実質から形成されるようになると。そして脚については、異様に聞こえようともこう言わざるを得ないのです、脚は、本質的に霊的実質から形成されていると。申しましたように、異様に聞こえようともです。ですから、頭の方へと進むと、私たちは人間をこのように、つまり霊的実質を物質的実質に移行させるように、描かなくてはなりません(*図が描かれる)。参考図:霊的実質を物質的実質に そして物質的実質はとくに人間の頭のなかに含まれているのです。これに対して、霊的実質がとりわけみごとに広がっているとでも申し上げたいところは、人間がその脚を空間へと伸ばす、あるいはその腕を空間のなかへと差し伸べるところです。腕と脚にとって肝心なのは、この霊的実質が腕と脚を満たしているということ、腕と脚の本質的なものであるということだろうというのは、これは実際そのとおりなのです。実際のところ、腕と脚にとって、物質的実質はいわばそこでは霊的実質の内部に浮かんでいるだけであり、他方、頭というのは実際いわば物質的実質から緻密に形成されたものです。けれども私たちは、人間がそれであるようなこういう形成物において、単に実質を区別するだけではなく、その形態化において力を区別しなければなりません。そしてこの場合にも、霊的な力と地上的ー物質的な力とを区別しなければならないのです。さて力の場合にはこれがちょうど逆になっています。四肢と新陳代謝にとっては実質が霊的である一方、その内部の力、たとえば脚にとっての力は、重さであり物質的なのです。そして頭の実質は物質的である一方、頭の内部で働く力は霊的です。霊的な力が頭を貫いて流れ、物質的な力が四肢ー新陳代謝人間の霊的実質を貫いて流れているのです。人間というものを完全に理解できるのは、人間において、その上部領域、頭部と、胸の上部領域、本来は物質的実質で、霊的な力に浸透されている。呼吸においてはもっとも低次の霊的力が働いていると申し上げたいのですが、胸の上部領域が区別されることによってのみであり、さらに私たちは下部人間を、内部に物質的な力が働いている霊的実質から形成されたものと見なければなりません。ただ、言うまでもなく私たちがはっきりと理解しておかなくてはならないことは、こういう事柄は本来人間においてどういう状態であるかということです。つまり人間はその頭の性質を生体組織全体に広げているため、頭というのは、霊的な力に貫かれた物質的実質であり、この頭の本質すべてを人間の下部にまで広げ伸ばしているということを通じて存在するものでもあるのです。内部に物質的な力が働いている霊実質を通じて人間であるところのもの、これは逆に上部人間に向かって上に送られます。こうして人間において作用しているものは相互に浸透し合っているのです。けれどもやはり、人間を理解することができるのは、このように人間を、物質的ー霊的に、実質的にして力動的なもの、すなわち力存在でもあるものと見なすときのみです。これにもまた大きな意味があります。と申しますのも、外的現象から目を転じ、内的な本質に入り込んでいくと、たとえば、人間におけるこの実質的なものと力に則ったものの配分に不規則が生ずることは許されないということが私たちに示されるからです。たとえば、人間において純粋な実質、純粋に霊的な実質であるべきもののなかに、物質的な素材、物質的な実質が侵入すると、つまりたとえば、本来は頭部に導かれるべき物質的実質が、新陳代謝組織のなかであまりに優勢になりすぎて、新陳代謝がいわば頭の本質に浸透されすぎると、そうすると人間は病気になります、まったく特定のタイプの病気が生じてくるのです。そこで治療の課題とは、こうした霊的に実質的なもののなかに広がっている物質的な実質形成を、ふたたび弱め、駆逐することとなります。他方、人間の消化組織、霊的実質のなかの物質的な力に貫かれているという固有の性質を持つこの消化組織が、頭へと上に送られると、人間の頭は、こういう表現が許されるなら、過度に霊化され(spiritualisiert)ます、頭部の過度の霊化が起こるのです。その場合、これは病気の状態を示しますので、物質的な養う力をじゅうぶん頭に送り込んで、この物質的な力が霊化されずに頭に着くように配慮しなければなりません。健康な人間と病んだ人間に目を向けるひとは、このような区別が役に立つことをすぐさま理解するでしょう、もっとも単なる外観だけでなく、真実を問題にする場合はですが。けれども、こういう事柄においてはさらに本質的にまったく別の何かが働いています。ここで働いているもの、つまり人間は私が示しましたような性質の存在であることによって、自らをそういうものと感じるのですが、そういうものは、今日の通常の意識において最初はまさに下意識にとどまっています。すでにそこにあるのです。そこではこれは、人間の一種の気分として、生の気分として現われてきます。これを完全に意識化させるのはやはり霊的な観照のみであり、この霊的観照を私は皆さんにただ以下のように描写することができるのみです。つまり、今日の秘儀参入学から、この人間の秘密、すなわち、物質的実質を必要とするもっとも主要な、もっとも本質的な器官は本来頭であり、それによって頭はこの物質的実質を霊的な力で貫くことができるという秘密を知るひと、そしてさらに、四肢ー新陳代謝人間において本質的なものは、霊的実質であって、これは存続するために物質的力、重力や均衡力その他の物質的力を必要とする、ということを知るひと、つまり人間の秘密をこのように霊的に見通したうえでこの地上的人間存在を振り返って見るひと、そういうひとにとっては、そもそも自分が人間として、地球に対して途方もない負債を抱えた者のように思える、ということです。と申しますのも、一方において人間は、人間存在として直立を維持するために一定の条件を必要とする、と言わなければなりませんが、これらの条件を通じて人間は元来地球の債務者なのです。人間は絶えず地球から何かを奪い取っています。つまり、人間は自らにこう言って聞かせなければならないと気づくのです、人間が地上生活をおくる間に自らのうちに霊的実質として担っているものは、本来は地球が必要としているものなのだ、と。人間は死へと赴くときに、これを地球に残していかなければならない、なぜなら地球は自らの更新のために絶えず霊的実質を必要としているからだ、と。人間は残していくことができません。そうすれば、人間は死後の時期にあって人間の道を歩むことができなくなるでしょうから。人間はこの霊的実質を死と新たな誕生との間の生のために携えていかなくてはなりません、なぜなら人間にはこれが必要であり、この霊的実質を死の間携えていなかったら、人間は死後いわば消滅してしまうでしょうから。人間が成し遂げねばならないあの変化は、人間がその四肢ー新陳代謝人間の霊的実質を死の門を通過して霊界へともたらすことによってのみ成し遂げることができるのです。人間がもし、本来地球に対して負っている債務を地球に返してしまったら、人間は将来の受肉を引き受けることはできないでしょう。人間にはそれはできません。人間は負債者のままにとどまります。これは地球が中間状態にあるかぎり、さしあたりどういう手段によっても改善できないことです。地球存在の終わりになれば、事態は変わってくるでしょう。ともかくこういうことなのです、愛する友人の皆さん、霊視をもって人生を見つめるひとは、単なる苦しみや悲しみ、それに私見では通常の生活が与えてくれるような幸福や喜び、単にそういうものを持つだけでなく、霊的なものを観ることで宇宙的感情(kosmische Gefuehle)、宇宙的な喜びと悲しみが生じてくるということです。秘儀参入とは、このような宇宙的悲しみ、たとえば自らにこう言い聞かせざるを得ないようなこういう悲しみの出現と分かちがたいものなのです、つまり、まさに私が私の人間本性を直立に維持することによって、私は自らを地球の負債者へと形づくらざるを得ない、私が宇宙的にまったく公正であるなら本来は地球に与えなければならないものを、地球に与えることができないという悲しみです。頭部実質のなかにあるものについても同様です。地上生活全体を通じて、霊的な力が物質的な頭部実質のなかで働くことにより、この頭部実質は地球から疎遠になります。人間は実際自らの頭のために地球からこの実質を奪い取らなければならないのです。しかも人間は人間であるためには、この頭の実質に地球外的なものの霊的力を絶えず浸透させなければなりません。そして人間が死ぬと、今や地球は自分から疎遠になってしまった人間の頭部実質をまた引き取らなければならないわけですが、これは地球にとってはきわめて害になるものなのです。人間が死の門を通過してその頭部実質を地球に引き渡すと、この頭部実質、まったく霊化されてしまい、自らのうちに霊的な成果を担っているこの頭部実質の作用は、根本的に地球生命全体を毒します、本来その作用はこの地球生命を害するものなのです。本来人間は、こういう事柄を見通すなら、こう言わなければなりません、この頭部実質を携えてまさに死の門を通過して行くのが人間にとって公正なことだろう、なぜなら、この実質は本来、人間が死と新たな誕生の間に通過していく霊的領域にずっと適しているのだろうからと。しかし、人間はそうできません。と申しますのも、人間がこの霊化された地球実質を携えて行ったとしたら、人間は死と新たな誕生との間の自らの進化のすべてに敵対するものを絶えず作り出すことになるからです。もしこの霊化された頭部実質を携えて行った場合に人間に起こりうることは、きわめて恐るべきことでしょう。これは、死と新たな誕生との間の人間の霊的進化が無に帰するように絶えず働きかけるでしょう。ですからこういう事柄を見通すなら、こう言わざるを得ません、ひとはこのことによってもまた地球に対して負債のある者となるのだと。ひとが地球のおかげで手に入れながら地球にとっては使用不可能にしてしまったものを、ひとは後に残して行かざるを得ず、携えていくことができないからです。ひとは地球に置いていくべきものを地球から奪い去り、自分が携えていくべきもの、地球にとって使用不可能にしてしまったものを、自らの土の塵とともにこの地球に委ねます、地球はその全生命において、全存在として、それによって法外な苦しみを与えられるのです。つまり、まさに霊眼を通して観るとまずもって、途方もなく悲痛な感情のような何かが人間の魂に横たわっている、ということなのです。そしてさらに長大な時間を見はるかし、系全体の進化を見渡すときのみ、次のような展望が開かれます、つまりたとえば、地球がいつの日かその最後を迎えるとき、人類の進化の後の段階、木星、金星、ヴルカン段階において、ひとはこの罪をいわば清算し、罪を脱することができるであろうと。このように、個々の地上生活を全うするということによってのみならず、そもそも地球人であること、地球に居住し地球からその実質を引き出すことを通しても、ひとはカルマを、世界のカルマ、宇宙的カルマを生み出しているのです。ここで人間から目を転じ、その他の自然に目を向けることもできます。すると、なるほど人間は、私がたった今お話しいたしましたような罪をいわば積み重ねていかざるを得ないけれども、それでも宇宙の本質を通して絶え間なく調停がなされているのだということもわかるでしょう。こうして、存在の驚くべき秘密、これを統合してはじめて、本当に宇宙の叡智についての表象として自らのものとできる秘密へと入り込んでいきます。人間から眼差しを転じて、ここ数日私たちがさまざまに目を向けてきたものを見てみましょう、ここ数日鷲によって代表されるものとして私たちに現われてきた鳥の世界に眼差しを向けてみましょう。鷲について私たちは、鳥の世界を代表するものとして、いわば鳥の世界の特性と力を統合した動物として語ってきました。そして鷲を観察することで、私たちは結局、宇宙的連関において鳥の世界全体に責任を負っているものを観察しているのです。ですから鷲については今後またお話しするでしょう。皆さんにお話ししましたことは、鷲は本来人間の頭に対応していること、人間の頭において思考を作動させる力が、鷲にあってはその翼を作動させるということでした。したがって、鷲の翼においては、太陽が流入した大気の力、光が流れ込んだ大気の力が作用しているのです。鷲の翼で煌めいているのは、光に浸透された大気の力です。さて、やっかいな特性もいくらかつけ加えることができるとはいえ、やはり鷲というのはその宇宙的現存に関して注目すべき特徴を持っています、つまり、いわば鷲の皮膚の外側、翼の形成のなかに、この太陽の作用に貫かれた大気の力が作り上げるものすべてがとどまっている、ということです。鷲が死んではじめて、ひとはここで起こっていることに気づきます。鷲が死ぬと、反芻をする牛の徹底的な消化に対して、鷲の消化がいかに奇妙な、表面的とでも申し上げたいようなものであるかがはじめて明らかになるのです。多くの動物の種を代表するものとして、牛は本当に消化動物です。牛においては徹底的な消化が行なわれます。どの鳥もそうですが鷲は表面的に消化します。いわばすべてが単に始まりだけであり、消化の営みも発端のみなのです。そして鷲という存在において、この消化というものは、私たちが全体を見れば、本来生存の副業とでも申し上げたいものです、これは鷲のいたるところにおいて副次的な力として扱われています。これに対して、鷲において徹底的な経過を示しているのは、鷲の翼に用いられるものすべてです。他の鳥の場合、これはもっと強力です。途方もなく念入りに、羽毛のなかのすべてが仕上げられます。それでこのような羽毛は本来驚くべき構成物なのです。つまりそこには、地上的素材としての質料、マテーリエ(Materie)とでも呼びたいものがもっとも強力に現われているのです、この地上的素材を鷲は地球から取り出し、上部の力によって霊的に浸透されますが、鷲は再受肉を要求しないので鷲に独占されることはありません。したがって、上部の霊的力を通じて翼のなかの地上的素材に生ずるもの、これによってそのとき起こることが鷲を困らせる必要はありません、霊界においてそれがさらに作用しても、鷲を困らせる必要はないのです。ですから、鷲が死に今やその翼も崩れていくとーー申し上げましたように、これはどの鳥にもあてはまります。そのとき霊化された地上的素材が霊の国に入っていき、再び霊的実質へと変化させられるということがわかります。おわかりのように、私たちは頭に関して鷲と奇妙な親和関係にあります。私たちにできないことを鷲はすることができます、鷲は、地球で霊的力を通じて物質的実質において霊化されたものを、絶え間なく地球から運び去るのです。私たちがあんなにも独特の感情をもって、飛翔する鷲を見つめるのは、この所以もあるからです。私たちは鷲を、何か地球から疎遠なもののように、地球よりも天に関わっているもののように感じます、たとえ鷲がその実質を地球から取り出しているにしてもです。けれども鷲はどうやってそれを取り出しているのでしょう。鷲は地球実質にとって単に奪う者にすぎないというやりかたで鷲はそれを取り出すのです。地球存在における通常の月並みな法則のなかでは、鷲がさらに何かを得ることは見込めません。鷲はその素材を盗み取り、奪い取ります、そもそも鳥類全般がさまざまに素材を奪うように。けれども鷲はそれを清算します。鷲は素材を奪いますが、霊的力として上部領域にある力によってその素材を霊化させ、そして死んだ後、自分が奪ったこの霊化された地球の力を霊の国にさらっていくのです。鷲とともに、霊化された地球質料が霊の国へと引き入れられます。動物が死んでも、その生命は完結しません。動物の意味は宇宙万有のなかにあります。鷲が物質的な鷲として飛翔すれば、鷲はいわばそのありかたのひとつの形象にすぎません、鷲は物質的な鷲として飛翔するだけです。ああ、でも鷲は死後も飛翔するのです。鷲の性質の霊化された物質的素材がかなたへと飛翔していき、霊の国の霊実質とひとつになるのです。おわかりですね、こういう事柄を見通せば、宇宙万有における驚くべき秘密に到達します。このときはじめて、地球の動物その他のこれらのさまざまな形姿が存在しているのはいったいなぜなのか、と言えるのです。これらの形姿はすべて宇宙全体において意味があるのです、大きな、とてつもなく大きな意味があるのです。今度は、これも数日来私たちが観察してまいりましたもう一方の極端に移りましょう、ヒンズー教徒にあれほど崇拝されている牛に移りましょう。確かにこれはもう一方の極端です。鷲が人間の頭に非常に似ているように、牛は人間の新陳代謝組織に非常に似ています。牛は消化動物なのです。そして、奇妙に聞こえようとも、この消化動物は本来霊的実質から成り立っていて、食された物質素材はこの霊的実質に引き入れられ、混入されるのみなのです。つまり牛のなかには霊的実質があって、物質素材がこのいたるところに入り込み、霊的実質に摂取され、加工消化されます。これを徹底して遂行するために、牛の消化の営みはあんなにも念入りで徹底的なのです。これは考えうるもっとも徹底した消化の営みであり、この点で牛は実際、もっとも徹底して動物であることに気を配っているわけです。牛は徹底して動物です。事実牛は、動物存在を、この動物生体組織、この動物自(Tier-Ichheit)を宇宙から地球へと地球の重力の領域に引き下ろすのです。(*図示される)参考図:牛のなかには霊的実質血液の重量と全体重との比率を牛と同じくする動物はおりません。他の動物は体重に対する血液の比率が、牛よりも多いか少ないかいずれかです。そして重量は重さと、血液はエゴ性(Egoitaet)と関係があります。人間のみが有しているエゴ(Ego)とではなく、エゴ性、個別であることと関係があるのです。血は動物をも動物にします、少なくとも高等動物にするのです。こう言えるかもしれません、牛は宇宙の謎を解いた、徹底して動物であろうとするとき、血液の重さと全体重の重さとの正確な比率をどのように保つのか、という謎を解いたのだと。よろしいですか、いにしえの人々が獣帯(黄道十二宮/Tierkreis])を「獣帯」と名づけたのはいわれのないことではないのです。獣帯は十二の部分から成り、いわばその全体が十二の個々の部分に分けられています。宇宙から、獣帯からやってくるこの力は、諸々の動物のなかでまさに自らを形づくるのです。しかし他の動物たちはそれほど厳密にこの力に従いません。牛は、その体重の十二分の一が血液の重さです。牛の場合血液の重量は体重の十二分の一ですが、ろばの場合はわずか二十三分の一、犬の場合は十分の一です。どの動物も異なった比率になります。人間の場合血液は体重の十三分の一です。おわかりですね、牛は動物存在全体を重さのなかに現わすことを、可能な限り徹底的に宇宙的なものを表現することを目指してきたのです。私はここ数日にわたって、牛は本来上なるものを物質的ー質料的なもののなかに具象化しているが、それは牛のアストラル体に見て取れる、とお話ししてきましたが、まさにこのことのなかに、牛が自身の内的な重量の比率において十二分割を正確に維持していることが現われています。牛は内部において宇宙的なのです。牛にあってはすべてが、霊的実質になかに地球の諸力が取り入れられているような状態なのです。地球の重さは牛のなかの獣帯の比率で分割されることを余儀なくされます。地球の重さは、十二分の一をエゴ性へと展開させることに応じざるを得ないのです。牛はすべてを地上的比率のなかに押し込みます、牛がその霊的実質のなかに有している地上的比率のなかにです。このように、牧場に横たわっている牛は、事実霊的実質なのです、この霊的実質は地球素材を自らのうちに摂取し、吸収し、自らに似たものにするのです。牛が死ぬと、牛が自らのうちに担っているこれらの霊的実質は、地球全体の生命の恵みとなるために地球素材とともにこの地球に摂取されることが可能となります。ですから、牛に対してこういう感情を持つのが正しいのです、つまり、お前はまさしく供犠の動物だ、おまえは地球が必要としているものを絶え間なく地球に与え続けているのだから。お前が与えるものがなかったら、地球はこの先存続することはできないだろう、お前が与えるものがなかったら、地球は硬化し、ひからびてしまうだろう。お前は地球に絶え間なく霊的実質を与え、地球の内的な活動性、内的な生命力を回復させているという感情です。そして皆さんが、一方に牛のいる牧場を、もう一方に飛翔する鷲をごらんになるなら、そこに注目すべき一対が得られます、鷲、これは、霊化されてしまったために地球にとって使用不可能となった地球素材を、死ぬときにかなたの霊の国に運び去ります、牛、牛は死ぬとき、地球に天の素材を与え、そうして地球を回復させます。鷲は、もはや地球には使用できず、霊の国に戻さなければならないものを、地球から取り除きます。牛は、地球が霊の国からの回復させる力として絶えず必要としているものを、地中にもたらすのです。ここで皆さんは、秘儀参入学から浮かび上がってくる感情のような何かをごらんになるのです。と申しますのも、通常次のように信じられているからです、そういう秘儀参入学、ひとはともかくもそういうものを研究する、でも結局それが与えてくれるのは概念、観念以外のなにものでもない、ひとは超感覚的なものについての観念で頭をいっぱいにしているのだ、ふつう感覚的なものについての観念で頭をいっぱいにするのと同じようにと。ところがそうではないのです。こういう秘儀参入学において先に進めば進むほど、以前はそれについて予感もしなかったにせよ、どんなひとにも無意識的に存在している感情を、ひとは魂の奥深くから引き出してくるようになります。あらゆる存在を以前感じ取っていたのとは別様に感じ取るようになるのです。私はある感情を皆さんにこのように描写することができます、これは精神科学、秘儀参入学をまさに生き生きと把握することの一部なのです。これは、ひとは次のように自らに語らざるを得ない、という感情です、つまり、人間の真の性質を認識すれば、地球上に人間しかいないとしたら、地球がそもそも必要なものを得るということ、そして正しい時期に地球から霊化された物質素材が取り除かれ、霊素材が与えられるということに対して、ひとは絶望的にならざるを得ないと。ひとは本来、人間の存在と地球の存在との間のこのような対立を感じ取らざるを得ないのです、これはきわめて悲痛な対立です、人間が地球上で正しく人間であろうとすれば、地球は人間によって正しく地球であることができないと言わざるを得ないがゆえに悲痛なのです。人間と地球はお互いを用いています、人間と地球は互いに支え合うことができないのです。一方の存在が必要とするものが他方から失われ、他方が必要とするものが一方から失われます。周囲の環境が現われてこないなら、人間と地球との生の連関についてひとは安心していられないでしょう、そしてひとは自らにこう言い聞かせざるを得ないでしょう、霊化された地球実質を霊の国へと持ち去ることに関して人間にできないこと、これを成就するのは鳥の世界なのだと。さらに、人間が霊的実質として地球に与えることができないもの、これを与えるのは反芻動物たち、そしてその代表としての牛なのだと。ごらんのように、これによって宇宙はいわば、ひとつの全体へと完結するのです。単に人間だけを見ると、感情のなかに入り込んでくるのは地球の現存についての危うさですが、人間の周囲にあるものを見ると、再び安心感が得られるのです。今や皆さんは、ヒンズー教のように深く霊的なものに入り込んでいく宗教的世界観が牛を崇拝することに、さほど驚きをお感じにならないでしょう、なぜなら、牛は地球を絶え間なく霊化し、牛自身が宇宙から取り出してくるあの霊的実質を絶えず地球に与え続けるからです。本来このイメージはリアルなものになるはずなのです、草をはんでいる牛の群の下で、地球大地がいかに喜びをかき立てられて生きているか、そこで草をはんでいるものたちがいることによって宇宙からの栄養の確保が約束されたために、いかに元素霊(精霊/Elementargeister)たちが下で歓呼の声を挙げているかというイメージです。鷲を取り巻いて漂いつつ、踊り歓呼の声を挙げる元素霊たちの空気の環がほんとうは思い描かれるはずなのです。そうすれば霊的真実が再び描かれたということです、そして霊的な現実の内部に物質的なものを見出せるでしょう、鷲がそのアウラ(Aura)のなかに継続されているのが、そして、そのアウラのなかに、元素的な空気の精(精霊)たちと空気中の火の精(精霊)たちの歓声が紛れ込んでくるのがわかることでしょう。まったく宇宙的であるために地上的存在に非常に抵抗するこの牛の独特のアウラをひとは見るでしょう、そしてこれが地の元素霊たちの上機嫌の感覚を呼び起こすのを見ることでしょう、元素霊たちは、大地の闇のなかで生き続けなければならないために彼らから失われてしまったものをここで目にすることができるでしょう。牛のなかに現われているものは実際これらの精霊にとって太陽なのです。地中に住まうこうした元素霊たちは物質的太陽に歓びを感ずることはできませんが、反芻動物のアストラル体に歓びを感ずることはできるのです。そうなのです、愛する友人の皆さん、今日の書物には載っていない別の自然史というものもあるのです。それでは、今日書物に載っている自然史の最終結果とは、いったいどんなものでしょうか。それは、私が一度論評したことのあるアルベルト・シュヴァイツァーのあの本の続編(☆1)に他なりません。皆さんは、私が少し前にゲーテアヌムで行なった、現代の文化状況についてのこの小著の論評を覚えておいでかもしれません。この続編の前書きは実に、現代の精神の産物のかなり悲しむべき一章というものです、と申しますのも、私が当時論評いたしました最初の巻には、少なくともまだ、私たちの文化に欠けているものをつけ加えるためのある種の力と洞察があります、ですからこの前書きは事実本当に悲しむべき一章なのです。なぜなら、ここでシュヴァイツァーは自分が、知は結局いかなるものも与えることはできない、ひとは認識によるのとは別のどこかから世界観と倫理学を獲得せねばならないということを見抜いた最初の人物であると豪語しているからです。参考画:Albert Schweitzer さて、先ず第一に、認識の限界についてはもうじゅうぶん語られてきましたし、ひとが自分を認識の限界について語った最初の人物であると思うことには、どう申し上げるべきか、いささか近視眼的なところがすでにあります。認識の限界についてはすでに自然科学者たちがありとあらゆる言い方で語ってきたのですから。ですからこの巨大な誤謬を最初に発見したなどと自慢するには及ばないのです。けれどもこれを度外視しても、まさにこのことは、シュヴァイツァーのような卓越した思想家この第一巻に関しては彼はやはり卓越した思想家ですが、こう語るに至ったということに他なりません、つまり、我々が世界観を持とうとするなら、我々が倫理を持とうとするなら、知と認識とを我々はまったく問題にしない。これらは我々に何ひとつ与えはしないのだからと。今日まさに書物に載っていて公に認知されている知と認識、そういう諸々の科学、認識は、世界のなかに意味を発見する。シュヴァイツァーの言うように、ことに通じていくことはありません。と申しますのも、結局のところ、こうした人物たちが世界を眺めているように眺めるなら、実際次のようなこと以外には何も浮かんでこないからです、つまり、鷲から紋章の動物を作ることができるという点は別として、鷲が飛翔することには意味がないとか、雌牛が牛乳を与えてくれることは、地上的に有用であるとか。人間もまた単なる物質的存在でしかないので、物質的有用性しか持っておらず、世界(宇宙)全体にとっていかなる意味も与えないということになります。それ以上進もうとしないのであれば、そのひとは世界に意味が現われてくる水準にはないということは言うまでもありません。霊的なものが、秘儀参入学が、世界(宇宙)について語りうることへと、ひとはまさに移行していかなければならないのです、そうすれば、この世界(宇宙)の意味が見出されるでしょう。しかもそのときこの宇宙の意味は、あらゆる存在のなかに驚くべき秘密を発見することによって、見出されるのです、それは、死にゆく鷲と死にゆく牛とともに起こる秘密、そしてこの両者の間にライオンがいて、ライオンは自らのうちでその呼吸のリズムと血液循環のリズムの協和を通じて霊的実質と物質的実質の均衡を維持する、つまりライオンは今や、私がお話ししましたような上と下への正しいプロセスを生じさせるために、どれだけの鷲が必要で、どれだけの牛が必要であるかを、その集合魂を通して調整するものであるといった、そういう秘密です。ごらんのように、この三種の動物、鷲、ライオン、雄牛あるいは雌牛は、驚くべき本能的な認識からまさしく生み出されたのです。これらと人間との親和性が感じ取られていました。と申しますのも、こういう事柄を見通すなら、人間は自らにこう語らざるを得ないからです、鷲は、私が私の頭によって自分で果たすことができない課題を私から取り除いてくれる、牛は、私が私の新陳代謝、私の四肢組織を通じて自分で果たすことのできない課題を私から取り除いてくれる、ライオンは私が私の律動組織を通じて自分で果たすことのできない課題を私から取り除いてくれる、と。こうして私と三種の動物から宇宙的連関の全体が生成すると。このようにひとは宇宙的連関のなかに組み込まれて生きています。このようにひとは宇宙における深い連関を感じ取り、存在を統括している力、人間が織り込まれ、さらに人間を取り巻いて波打ち、うねっているこの存在を統括する力が、本来いかに聡明であるかを認識することを学ぶのです。さてごらんのように、先週お話ししました三種の動物に対する人間の関係を探究したことにより、このとき私たちに立ち現われてきたものをこのようにまとめることができました。(☆2)(第3講おわり)□編註☆1 アルベルト・シュヴァイツァーのあの本の続編:『文化哲学 1. 文化の没落と復興』(ベルン、1923年)「文化の外見上の局面と現実の局面」という題のシュタイナーの論評は、全集版『現代の文化危機のさなかにあるゲーテアヌム思想 週刊「ゲーテアヌム」からの論文集1921ー1925』(GA36 100頁以下)に所収。アルベルト・シュヴァイツァー:Albert Schweizer 1875ー1965ロテスタント神学者、哲学者、医師、音楽家。1913年よりガボン(アフリカ西部の共和国)のランバレーネで派遣医師。シュヴァイツァー「ルドルフ・シュタイナーとの出会い」も参照のこと。これは『ルドルフ・シュタイナーの思い出』(エーリカ・ベトゥレ、クルト・フィール編 シュトゥットガルト、1979年)に所収。33頁以下。☆2 この講義に引き続いてすぐ、シュタイナーは第二ゲーテアヌム設立に関する募金活動のために見解を表明した。彼の「ゲーテアヌム貯金箱についての発言」は『人智学協会の歴史における運命の年1923年』(GA259 185頁)に掲載されている。人気ブログランキングへ
2024年03月27日
コメント(0)
-
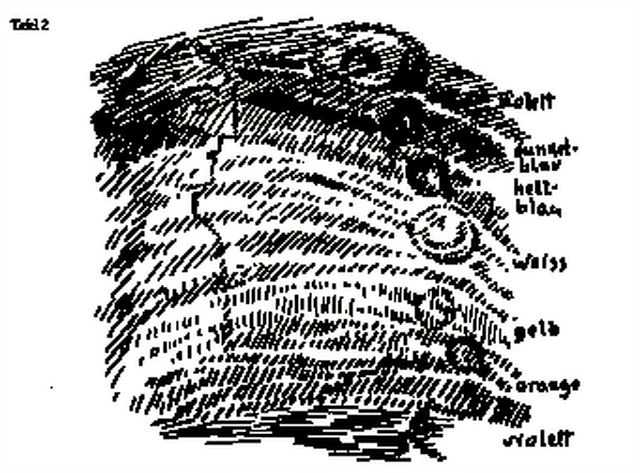
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー(GA230)創造し、造形し、形成する宇宙言語の協和音としての人間/Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden,bildenden und gestalteden Weltenwortes 翻訳紹介(翻訳者:yucca)第2講 1923年10月19日 ドルナハ ・翼ー人間の頭部の形態化;太陽と外惑星の力の共同作用・ライオンー人間の律動組織は太陽の作用 牛ー新陳代謝組織は太陽と内惑星の作用 鷲、ライオン、牛の作用の合流としての人間・人間を一面化させようと誘惑する鷲、ライオン、雌牛の呼びかけ・雌牛の誘惑の声に捉えられると起こることー機械音の鳴り響く文明・ライオン、鷲の誘惑に捉えられると起こること・ライオン、ハイエナ、狼の寓話の現代的意味 一面化させようとする誘惑の呼びかけに対抗するための人間の箴言 昨日私たちは、鷲に代表される高いところの動物、ライオンに代表される中間の動物、牛、雌牛に代表される地底の動物、これらの動物たちの関係について学びましたが、今日は、まさにこれら動物界を代表するものたちに対する人間の内的な形態上の関係から明らかになる観点から、他ならぬ人間と宇宙との関係に注目することができます。 あの領域、それがこの動物がその特殊な力を引き出してくる領域であるなら、本来それはこの動物全体を頭部組織にする、と昨日私たちが言わなければならなかった、あの領域へとひとつ視線を上げてみましょう。こういう領域を見上げてみましょう。すると私たちには、この動物がこの動物たりうるのは陽光に貫かれた大気のおかげであるということがわかるのです。陽光に貫かれた大気は、この動物の生存は主に陽光に浸透された大気のおかげである、ということを通じていわばこの動物によって引き寄せられうるすべてであるにちがいありません。私は昨日皆さんに、本来の翼の形態化はこのことに由来すると申し上げました。この動物はいわばその本性を外的なもののなかに有しています。外界がこの動物から作り出すもの、これがこの動物の翼のなかに具現されているのです。そして、この陽光に貫かれた空気から作り出されうるものが、鷲の場合のように外から本質へともたらされるのではなく、人間の神経組織のなかから刺激されるように、内部において刺激されると、思考が、瞬間の思考、直接的な現在の思考が生じる、と私は皆さんに申し上げたのです。さて私たちの視線を、このように、いわばこういう観察によって明らかになるすべてのことで重石をつけて、高い所へと向けてみますと、私たちにはまさに、静止している大気と流れ込む陽光が示されるでしょう。けれどもこういう場合にも、太陽それ自体を観察することはできません。太陽というものは実際、宇宙のさまざまな領域と関係を結んでいくということを通じてその力を保持しているのです。この関係は、人間がその認識をもって太陽の作用を、いわゆる獣帯(黄道十二宮)と関係づけることによって表わされます。したがって、太陽の光が、獅子座から、天秤座から、蠍座から地球に落ちるとき、その太陽光は、その都度、地球にとって異なることを意味するのです。太陽はまた、この太陽系の他の惑星によって強められるか、弱められるかによっても、地球にとって異なった意味を持ちます。つまりこの太陽系のさまざまな惑星に対して、さまざまな関係が生じているわけです。火星、木星、土星といったいわゆる外惑星に対して、また水星、金星、月といったいわゆる内惑星に対して異なった関係が生じているのです。挿入画:獣帯(黄道十二宮)*上記図のドイツ語部分(上から):violett:菫色/dunkelblau:紺色/hellblau:薄青/weiss:白/gelb:黄/orange:オレンジ/violett:菫色 さて、私たちが鷲の生体機構に注目するとき、とりわけ、太陽と土星、木星、火星との共同作用を通じて太陽の力がどれくらい修正されるか、強められたり弱められたりするかということを見なくてはなりません。伝説が、鷲はユピテル(ジュピター)の鳥であると語るのもいわれのないことではないのです。木星(ユピテル)はそもそも外惑星を代表するものとして存在しています。この場合重要なことを図式的に示すなら、私たちは、万有において、宇宙において、土星が占める領域、木星が占める領域、火星が占める領域を指し示さなくてはならないでしょう。ひとつ私たちの目の前にこれを置いてみましょう、土星領域、木星領域、火星領域を。すると、私たちは太陽領域への移行を見出し、いわばこの太陽系のもっとも外部に、太陽、火星、木星、土星の共同作用が得られます。そして私たちが空中を輪を描いて飛ぶ鷲をみるとき、次のように言うとするなら、私たちはまったくもってひとつの真実を語っているのです、つまり、太陽から大気を貫いて流れ込む力、したがって、太陽と火星、木星、土星との共同作用から成り立っている力、これが、鷲の全形態、鷲の本質のなかに生きている力なのだと言うならばです。この力はしかし同時に人間の頭の形成のなかにも生きています。ですから私たちが、人間をその真の在りように関連づけて、地上においては人間はミニアチュール像として存在しているだけだと申し上げたいのですが、宇宙のなかに据えるなら、頭に関しては人間を鷲の領域に据えなければなりません。つまり、私たちは人間というものを、その頭に関しては鷲の領域に置いて思い描かなくてはならず、それによって上へ向かう力と関連するものが人間のなかに与えられたのです。ライオンは、本来の意味での太陽の動物、太陽がいわば自身の力をそこに展開している、太陽の動物である動物を代表しています。ライオンがもっともよく繁殖するのは、太陽の上にある星々、太陽の下にある星々が、太陽そのものに対して影響を及ぼすことがもっとも少ない配置にあるときです。このとき、昨日皆さんにお話ししました奇妙なことが起こります、つまり、大気を貫いてくる太陽そのものの力が、ライオンのなかのこのような呼吸組織をまさに活気づけ、この呼吸組織はそのリズムにおいて血液循環のリズムと、数によってではなく、そのダイナミズムによって完全に均衡状態にある、ということです。これはライオンにおいて見事に均衡しているのです。ライオンは血液循環に呼吸抑制を対置し、血液循環は絶えず呼吸の流れを刺激します。私は皆さんに、このことは、その形のとおりに、ライオンの口の形態のなかにも見ることが出来ると申し上げました。そこには、この血液のリズムと呼吸のリズムの驚くべき関係が、形のとおりに現われているのです。これはまた、自らのうちに安らぎつつも大胆に外に向けられているライオンの独特の眼差しからも見て取ることができます。けれども、このライオンの眼差しのなかに生きているもの、これはまた、人間本性の他の要素、つまり頭部組織、新陳代謝組織と連結して、人間の胸部あるいは心臓組織、律動的組織のなかにも生きているのです。したがって、本来の太陽作用というものを私たちの前に置いてみると、太陽領域にしたがって、人間の心臓とその一部である肺を太陽の活動範囲のなかに置くように、人間を描かなくてはなりません、するとこの領域に人間のライオン性質が得られます。私たちが内惑星、地球に近い惑星へと移ると、まず水星領域に至ります、これは、とくに人間の新陳代謝系、新陳代謝組織のより精妙な部分に関わるもので、そこでは栄養分がリンパ性の物質に変成され、さらにそれが血液循環のなかへと送り込まれています。さらに進むと、私たちは金星の作用する域へと至ります。人間の新陳代謝系のより粗雑な部分、人間の生体組織において、取り入れられた食物をまず胃から加工するものへと至るのです。私たちはさらに月の領域へと進みます。私はこの帰結を、今日天文学において通常行なわれているように描写しております、別の描写をすることもできるでしょうが。つまり、私たちは今や月領域に至り、月と関係するあの新陳代謝の経過のなかで人間に作用し、作用される領域に至るのです。私たちはこのようにして人間を全宇宙のなかに据えたわけです。太陽が、水星、金星、月と一致して実現する宇宙的な作用へと向かうことによって、私たちはさらに、私が昨日説明しました意味で、あの雌牛によって代表される動物を受け容れる力を含む領域へと入っていきます。ここで私たちに得られるのは、太陽がそれ自身によって造ることができるものではなく、太陽の力が地球に近い惑星を通じてまさに地球にもたらされるときに太陽が造ることができるものです。これらの力がすべて、単に大気を貫いて流れ込むだけでなく、地球の表面にさまざまなしかたで浸透すれば、これらの力は地から上へと作用します。そしてこの地から上へと作用するもの、これは、私たちがまさに雌牛の生体機構のなかに外的に具現しているのを見る領域、そういう領域に属しているのです。雌牛は消化の動物です。しかし雌牛は同時に、次のようなしかたで消化というものを成し遂げる動物なのです、つまり、この消化という経過のなかに真に地上を超えたものの地上的な模像があるような、雌牛のこの消化全体が、全宇宙を見事に象り(かたどり)つつアストラル性に貫かれるような、そういうしかたでです。昨日すでに申しましたように、雌牛のこのアストラル的な生体組織のなかには全宇宙があるのですが、すべては重さによってささえられ、すべては地球の重さが効果を現わすことができるようにしつらえられています。皆さんは、雌牛は毎日その体重の八分の一の食物を必要とする、ということを考えてごらんになりさえすればよいのです。人間は二十分の一で満足できますし、それで健康も維持できます。雌牛は、その生体機構を完全に満たすことができるためには、地球の重さを必要としているのです。雌牛の生体機構は、物質が重さを持つように方向付けられています。雌牛の場合、毎日重さにおいて八分の一が交換されなければなりません。これが雌牛をその質量で地球に結びつけますが、その一方で、雌牛はまさにそのアストラル性を通じて、同時に、高きものの模像、宇宙の模像でもあるのです。ですから、雌牛はヒンズー教の信奉者にとって、私が昨日申しましたように崇拝に値する対象なのです。なぜなら、ヒンズー教の信奉者はこう言うことができるからです、雌牛はこの地上に生きている、この地上に生きているというそのことだけで、雌牛は、物質的な重さー質量のなかに、地上を超えたもの、と言い得るものを象っているのだと。ヒンズー教の信奉者の意味で語るならそうなのです。そしてこれはまったくもって、人間の本性が正常な生体機構を得るのは、人間が、鷲、ライオン、雌牛のなかに一面化されたこれら三つの宇宙的作用に調和をもたらすことができるとき、つまり人間が真に鷲の作用、ライオンの作用、雌牛の作用の合流であるときであるということなのです。しかし、普遍的な世界の進展に従い、私たちは宇宙の進化に、こういう表現をしてよろしければ、ある種の危険がさし迫っている時代に生きています。一面的な作用が、人間のなかに現に一面的に現われてくるという危険です。十四、十五世紀以来現在にいたるまで、この地上の人類進化において、鷲の作用は人間の頭を一面的に利用しようとし、ライオンの作用は人間のリズムを一面的に利用しようとし、雌牛の作用は人間の新陳代謝と地に対する人間の作用全体を一面的に利用しようとするという事態がますます強まってきているのです。人間がいわば宇宙の諸力によって三分割されようとしている、そして宇宙の諸力のうちひとつの形が常にその他の要素を制圧しようと懸命になっている、というのが現代のしるし(シグナトゥール)なのです。鷲は、ライオンと雌牛を突き落としてその力を無効にしようと懸命になっていますし、同様に他の二者も、その都度自分以外の両者の要素を無意味なものにおとしめてしまおうとやっきになっています。そして他ならぬ今日の時代、人間の下意識であるものに対して実に絶え間なく、きわめて誘惑的なものが働きかけているのです、誘惑的であるのは、それがある種の関連で美しいものでもあるからです。意識の表層においては今日人間はそれを知覚しておりません、けれども人間の下意識にとっては、人間を誘惑しようとする三重の呼びかけが宇宙を貫いて波立たせ、鳴り響かせています。現代の秘密というのは、鷲の域から、鷲を本来鷲たらしめているもの、鷲にその翼を与えるもの、鷲の周りをアストラル的に漂っているものが下へと鳴り響いてくることだ、と申し上げたいのです。人間の下意識に聞こえてくるのは鷲の本質そのものなのです。これは心を惑わす呼び声です: 私の本質を学ぶがよい! 私はおまえに力を贈る、 おまえ自身の頭のうちに 万有を創り出す力を。 鷲はこう語ります。これは、今日人間を一面化しようとする上からの呼びかけです。 続いて第二の誘惑の呼び声です。これは中間の域からやってきます、そこでは宇宙の力がライオンの本性を形成し、宇宙の力が、ライオンの本性を構成しているあのリズムの均衡、呼吸と血液循環の均衡を、太陽と大気の合流から生じさせるのです。ここでいわばライオンの感覚のなかで大気を振動で満たすもの、人間自身の律動組織を一面化しようとするもの、これがやはり今日人間の下意識に向かって誘惑的に語りかけます。 私の本質を学ぶがよい! 私はおまえに力を贈る、 巡る大気の輝きのなかに 万有を体現する力を。 ライオンはこう語るのです。 私たちが考える以上に、人間の下意識に語りかけるこれらの声には影響力があります。そうです、親愛なる友人の皆さん、地上でのさまざまな人間の生体機構は、これらの作用を受け容れるように組織されているのですから。ですからたとえば、鷲の声によってとくに誘惑され、惑わされやすいのは、西洋に住むすべてのものです。とくにアメリカ文化は、そこの人類の特殊な(生体)機構を通じて鷲が語る誘惑にさらされています。ヨーロッパの中部、古代文化(ギリシア、ローマの)であるものの多くを自らのうちに有し、たとえばゲーテを人生の解放のためにイタリア旅行へと導いたものの多くを自らのうちに有しているヨーロッパ中部は、とくにそこでライオンが語りかけるものにさらされています。東洋の文明はとりわけ、そこで雌牛が語りかけるものにさらされています。あとの動物が両者ともその宇宙の領域で鳴り響くように、地の底深く、とでも申し上げたいところから、轟き、叫びつつ鳴り響いてくるのは、雌牛の重さのなかに生きているものです。これは実際、すでに昨日皆さんに描写いたしましたように、たらふく草をはんだ群が、独特の大地の重さに身をささげるようなしかたで、この大地の重さのもとにあること、毎日自分の体重の八分の一を、その重荷のために自らのうちで交換しなければならない、という状況のもとにあることを表現するような格好で、横たわっているのを見るような、そういうものです。これに加えて、太陽、水星、金星、月の影響のもとに雌牛の栄養摂取機構におけるすべてを引き起こす地の底、この地底が、魔物のように轟く力で鳴り響かせるように、次のような言葉の響きでこのような群を満たすのです: 私の本質を学ぶがよい! 私はおまえに力を贈る、 秤、標尺、数を 万有より奪い取る力を。 雌牛はこう語ります。この誘惑の呼び声にとくにさらされているのは東洋なのです。ただしそれはこういう意味です、つまり、東洋はヒンドゥー教における古くからの牛崇拝があるので、なるほど最初は東洋がこの雌牛の誘惑の呼び声にさらされているけれども、この誘惑の呼び声が実際に人類を捉えて、この誘惑の声から生じるものが勝利を得るほどになるとしたら、まさにこの東洋から作用するものが、中部と西方を抑えて、自らを、前進を阻む、没落を引き起こす文明であると告知するだろう、ということです。大地の魔の力が一面的に地球文明に働きかけるでしょう。それでは、このときいったい何が起こるのでしょうか。このとき起こるであろうことは以下のようなことです。前世紀の経過にともない、私たちは地上で外的科学の影響下にある技術を、外的な技術の生活を獲得いたしました。実際あらゆる分野における私たちの技術は驚異的なものです。自然力は技術においては、生命のない形態で作用します。そして、この自然力を担ぎ出して、いわば徹底的に地球の上に文明の層を形成するために役立つもの、これが秤、標尺、及び数なのです。秤、物差し、量る、数える、測定する、これが、今日まさに外的科学を本職としている今日の科学者、今日の技術者の理想です。私たちは、「存在を保証するものは何か」と問われた著名な数学者が以下のように答える、という事態にまで達しているのです。あらゆる時代の哲学者たちは、「そもそも現実的なものとは何か」という問いに答えようとしてまいりましたが、この著名な物理学者は、こう答えます、測定できるものが現実的なのだ、測定できないものは現実的ではないと(☆1)。これはいわば、あらゆる存在を次のようにみなす理念なのです、つまりあらゆる存在は実験室に持ち込んで、重さを量ったり、測定したりすることができ、科学、この科学が技術のなかに流入するわけですが、この科学となおもみなされているものは、この量られ、測定され、数えられたものから組み立てられるとする理念です。数、寸法、重さは、文明全体をいわば方向づけるように作用すべきものとなったのです。さて人間がただ単に悟性をもってこの測定する、数える、重さを量ることを用いている限りは、とりたてて不都合はないのです。人間はなるほど利口ではありますが、宇宙万有の賢さにははるかに及びません。したがって、測定する、重さを量る、数えるということに関して、いわば宇宙万有に対してディレッタント的にあれこれやっている限りは、とくに不都合にはなり得ないのです。けれどもまさに今日の文明が秘儀参入に変貌するとしたら、それが秘儀参入の心情にとどまり続けるとしたら、まずいことになるでしょう。このことが起こり得るのは、まさに秤、物差し、数という記号のなかに成立している西洋の文明が、何と言っても東洋において起こりうるであろうこと、つまり本来霊的に雌牛の生体機構のなかに生きているものは何か、秘儀参入学を通じて究明されうることによって、あふれさせられるときです。と申しますのも、皆さんが雌牛の生体機構に入り込んでいって、そこで、この栄養分の八分の一が、いかに地上的な重さ、つまり量ったり測定したり数えたりできるすべてのものの重荷を負わされているかを学び、雌牛のなかのこの大地の重さを霊的に組織しているものを学び、牧場に横たわり、消化し、その消化のなかに宇宙からもたらされた驚異をアストラル的に顕現させているこの雌牛の生体組織全体を知るようになると、そうすると皆さんは、量られたもの、測定されたもの、数えられたものをひとつの体系にはめ込むことを学び、そうすることによって文明における他のものをすべて克服し、ひたすらいっそう量り、数え、測定して文明から生じるそれ以外のすべてをものを消滅させるような文明を、唯一その文明だけを全地球に与えることができるのですから。いったい、雌牛の生体機構の秘儀参入(イニシエーション)は何をもたらすのでしょうか。これは非常に奥深い、途方もなく意味深い問いです。雌牛のイニシエーションは何をもたらすのでしょう。たとえば、機械を構成するしかたというのは、個々の機械によって非常に異なっていますでしょう。ですが、まだ不完全な、原始的な機械が徐々に振動に基づくものになっていく、つまりそこでは何かが振動していて、この振動、発振を通じて、周期的に経過する運動を通じて機械の効果が得られるのですが、すべてはそういうものになっていく傾向にあります。すべてはこのような機械に収束していくのです。ところが、いったんこういう相互作用する機械を、雌牛の生体機構のなかでの栄養分の分割に学ぶことができるようなしかたで構成すると、機械によって地球上に創り出された振動、この小さな地球振動は、地上で起こっているもの、地球の上部にあるものと共鳴し、共振して経過するようになります、この太陽系がその振動においてこの地球系と共振しなければならないようにです、ちょうどしかるべく調律された弦が、同じ空間の別の弦が鳴らされると共鳴するように。これが、雌牛の呼び声が東洋を惑わせるとしたら実現されるであろう、振動の共鳴の恐ろしい法則です、その結果東洋が説得力あるしかたで、西洋と中部の精神性に欠けた純粋に機械的な文明に浸透していき、そしてそれを通じて宇宙万有の機械的な系(システム)に精確に適合する機械的な系(システム)が地上に生み出されることになりかねないでしょう。それとともに、空気の作用であるもの、循環の作用であるもの、そして星々の作用であるものすべてが、人類の文明のなかで根絶やしにされてしまうでしょう。人間がたとえば四季の移り変わりを通じて、つまり芽生え、萌え出る春の生命、死滅し衰えていく秋の生命に人間が参加することで体験するもの、これらすべては人間にとっての意味をなくしてしまうでしょう。ガタガタと振動する機械の音と、その反響(エコー)、地球のメカニズムへの反応として宇宙から地球へと流れ込んで来るであろうこの機械音の反響が、人間の文明を貫いて鳴り響くことでしょう。現在作用しているものの一部を考察してみれば、皆さんは自らにこう言い聞かせることでしょう、現在の私たちの文明の一部はまさに、この恐ろしく没落的な目標に通じる道の途上にあると。さて、ひとつ考えてみてください、もし中部がライオンの語ることによって誘惑されるとしたら、なるほど私がたった今描写しましたような危険はないでしょう。機械装置は次第にまた大地から消えていくでしょう。文明は機械的になりはしないでしょうが、人間は一面的な強さで、風雨のなか、四季の循環のなかに生きているすべてのものに委ねられるでしょう。人間は四季の循環のなかにはめ込まれ、そのためとりわけ呼吸リズムと循環のリズムの相互関係のなかで生きざるをえないでしょう。人間は、その不随意の生活が彼に与えてくれるものを自らのうちに育てていくでしょう。いわば人間は胸の性質を特に発達させるでしょう。けれどもそうすることによって、人間において、実に誰もが自分自身だけで生きようとし、誰も現在の幸せ以外の何かを気にかけることはない、といったような利己主義が地球文明に到来することでしょう。これにさらされているのは中部の文明です、中部の文明はこのような生活を地球文明に科すこともできるでしょうから。さらにまた、鷲の誘惑の呼び声が西洋を惑わせるとしたら、鷲の思考方法と心情を地球全体に広げ、この思考方法と心情のなかに自分自身を一面化することに成功するとしたら、かつて存在していた世界、地球の出発点、地球の初めに存在していた地上を越えた世界とこうして直接結びつきたいという衝動が、人類のなかに全般的に生じてくるでしょう。人々は、人間がその自由と独立のなかで獲得したものを消し去りたい衝動を得るでしょう。人間の筋肉、神経のなかに神々を生かすあの無意識の意志のなかでのみ生きるようになるでしょう。原始的な状態、太古以来の原始的な霊視へと退行していくでしょう。人間は、地球の始まりへと戻ることによって、地球から離れ去ろうとするでしょう。私は申し上げたいのですが、厳密に透視的(クレアヴォワヤント/clairvoyant)な眼差しにとって、これはさらに、草をはむ雌牛が絶えず一種の声で人間を貫くということによって裏づけられます、その声は、こう語るのです。「上を見るな、すべての力は地より来るのだ。大地の作用のなかにあるすべてに精通せよ。お前は大地の主となろう。お前は、お前が地上で獲得するものを永続的なものにするであろう」と。さて、人間がこの誘惑の声に屈するとしたら、私がお話しした危険、地球文明の機械化というあの危険を除去することはできないでしょう。と申しますのも、消化動物のアストラル的なものは、現在のものを永続的に、現在のものを不朽にしようとするからです。一方、ライオンの生体機構からは、現在のものを永続させようとせず現在を出来る限りすばやく過ぎ去らせようとするもの、すべてを絶えず繰り返す四季の循環の戯れにしようとするもの、天候のなかへ、太陽光の戯れや大気のなかへと上昇しようとするものが現われてきます。文明はこういう特徴を現わすようにもなるでしょう。空中を漂っていく鷲を人間が真に理解をもって観察すれば、鷲はその翼に地球の出発点に存在していたものの記憶を担っているように思われます。鷲はその翼のなかに、地球内部へとまだ上から作用していた諸力をとどめているのです。言うなれば、いかなる鷲のなかにも地球の数千年を見て取ることができるわけです、そして鷲は、せいぜいえものを捕らえるため以外には、物質的なものによって地球に触れたことはなく、いずれにせよその独立生活の充足のためには地球に触れることはありません。鷲はこの独立生活を維持しようとするとき、空中を旋回します、なぜなら、地上で生成されたものは鷲にとってはどうでもよいからです、鷲は大気の諸力によって歓喜と熱狂を得、地上生活を軽蔑すらしていて、地球がまだ地球でなかったとき、地球がその地球存在としての初めのころまだ天的な諸力に貫かれていたときに、地球自体がそのなかで生きていたような、そういう要素(エレメント)のなかで生きようとするからです。鷲というのは誇り高い動物で、固い地球進化に参加しようとはせず、この固体化する地球進化の影響から身を離し、そして地球の出発点にあった諸力とのみ一体化していようとした動物なのです。以上は、私たちがこれを宇宙の謎の解明のために宇宙万有のなかに書き込まれた巨大な文字とみなすことができるなら、これら三つの動物が私たちに与えてくれる教えなのです。と申しますのも、根本的においては宇宙万有のなかのいかなるものも、私たちがそれを読む事ができれば、ひとつの文字なのですから。つまりこの連関を読むことができれば、私たちは宇宙万有の謎を理解するのです。コンパスあるいは定規で計測するとき、秤で量るとき、数えるときに私たちがすることをよく考えてみなければならない、ということはやはり意味があるにしても、私たちはその際結局、すべて断片にすぎないものを組み合わせているのです。それが全体となるのは、私たちが雌牛の生体機構をその内的な霊性において理解するときです。そしてこれは、宇宙万有の秘密を読み取ることです。そしてこの宇宙万有の秘密を読み取ることが、宇宙存在と人間存在を理解することに通じていくのです。これが現代の秘儀参入の叡智(Initiationsweisheit)です。これは、今日精神生活の深みから語られねばならないことなのです。今日人間にとってそもそも人間であるということが困難なのです。と申しますのも、人間は今日、昨日皆さんにお話しいたしました寓話のなかの、三頭の動物に向き合ったカモシカのように見えると申し上げたいからです。一面化しようとするものが特殊な形を取っているのです。ライオンはライオンのままですが、ライオンは自分の仲間の猛獣を、変容されたものとして他の動物の代わりにしようとします。ライオンは、もと鷲であるものの代わりに、猛獣の仲間であるハイエナを用います、ハイエナは基本的に死んだものによって生きています、私たちの頭のなかに生み出され、私たちの死に向かって絶え間なく瞬間ごとに原子論的な断片を供給しているあの死んだものによってです。したがって、この寓話は、ハイエナを、腐肉を喰らうハイエナを鷲と取り替えるのです、さらにライオンは、雌牛の代わりに、没落にふさわしく、この伝説は黒人文化から生じたのでしょうから、仲間の猛獣、狼を置きます。こうして寓話のなかに三頭の別の動物、ライオン、ハイエナ、狼が現われるのです。今日誘惑の呼びかけが対立しあっていますが、誘惑の呼びかけが響くとき、徐々に鷲は地に降ってハイエナとなり、雌牛はもはや聖なる忍耐強さで万有を象ろうとせず、猛獣の狼となることにより、実際そのように対立しあっているのは、宇宙的シンボリスムとでも申し上げたいものです。そうすると、昨日の講義の終わりに皆さんにお話しいたしましたあの伝説を、黒人の言葉から私たちの現代文明の言葉へと翻訳する可能性が出てきます。昨日私は、いわば黒人の心情で語らねばなりませんでした。ライオン、狼、ハイエナが 狩に出かけました。彼らはカモシカをしとめました。ハイエナが最初に分けることになりました。ハイエナはハイエナの論理にしたがって分け、こう言いました、「三等分しよう、三分の一はライオン、三分の一は狼、三分の一は僕のものだ。」するとハイエナは食べられてしまいました。さてライオンは狼に言いました、「今度は君が分けろ。」すると狼は言いました、「最初の三分の一は君のものだ、君がハイエナを殺したんだから、ハイエナの分け前は当然君のものだ。次の三分の一も君のだ、ハイエナはそれぞれが三分の一取る、と言ったけど、その通りにすれば、どっちみち三分の一は君がもらうんだから、君のものだ。最後の三分の一も君のものだ、君は動物のなかで一番勇敢で賢いんだから。」そこでライオンは狼に言いました、「君にそんなに上手に分け方を教えたのはだれだい。」狼は言いました、「ハイエナが教えてくれたのさ。」。論理は両者とも同じです、現実への適用において、ハイエナが論理を適用するか、あるいはハイエナの経験をふまえて狼が論理を適用するかでは、全く異なるものが出てきたわけです。本質的なことは、現実への論理の適用にあるのです。さて、私たちは、いわば現代文明的なものに翻訳して、これをいくらか別様に物語ることもできます。けれども私が語りますことは常に、このことにご注意ください、私が語りますことは常に、文化の大きな流れにおいて重要なことなのです。ここで申し上げたいことは、この物語は現代的に次のように表現されるかもしれないということです。カモシカがしとめられます。ハイエナは後ろに退き、無言の判断を示します。ハイエナは敢えて最初にライオンの恨みを買うようなことはせず、後ろに退きます。ハイエナは無言の判断を示し、背後で待ちます。さてライオンと狼は獲物のカモシカをめぐって闘いを始め、闘いに闘い、互いにひどい傷を負い、傷によって共に死んでしまうまで闘い続けます。さて今度はハイエナが出てきます、カモシカとライオンと狼を、これらが腐敗してしまってから平らげます。ハイエナは、人間の知性のなかにあるもの、人間の本性のなかの殺し去るものを具象化しています。ハイエナは、鷲の文明の裏面、カリカチュアなのです。私がこの古い黒人の寓話のヨーロッパ化によって申し上げようとすることを、皆さんが感じとってくだされば、今日こういう事柄がほんとうに正しく理解されるべきである、ということをご理解いただけるでしょう。こういう事柄が正しく理解されるのは、三重の誘惑の呼びかけ、鷲と、ライオンと雌牛の呼びかけに、人間が自らの箴言を、今日人間の力と思考と作用の合い言葉であるべき箴言を対置することを学ぶときのみです。参考図:ライオン、ハイエナ、狼の寓話 私は学ばねばならぬ、 おお、雌牛よ、 星々が私のなかに啓示する言葉から、 お前の力を。 地球の重さではなく、単に重さを量り、数え、計測することのみではなく、単に雌牛の物質的な生体機構のなかにあるもののみを学ぶのではなく、雌牛のなかに体現されているもの、雌牛の生体機構から雌牛が体現しているものへと畏怖しつつ眼差しを転ずること、眼差しを高みへと上げること(を学ぶのです)、そうすれば、そのままでは地球の機械文明となってしまうであろうものが霊化されるのです。 人間がよく考えなければならない第二のことは、 私は学ばねばならぬ、 おお、獅子よ、 日ごと年ごとの巡りが 私のなかに織り込む言葉から、 お前の力を。 「啓示する」という言葉、「織り込む」という言葉に心を留めてください。そして、人間が学ばなければならない第三のものは、 おお、鷲よ、 大地から萌え出たものが私のなかに創り出す言葉から、 お前の力を。 このように人間は、一面的な誘惑の呼びかけに、自らの三つの箴言を対置しなくてはなりません、その意味が一面性を調和的な均衡に導くことができる三つの箴言をです。人間は学ばねばなりません、雌牛を見ることを、ただし、雌牛を徹底的に感じ取ったあとで、雌牛から、星々の言葉が啓示するものを見上げることを学ばなければならないのです。人間は学ばねばなりません、鷲に眼差しを向けることを、そして、鷲の本性を徹底的に自らのうちで感じ取ったあとで、その眼差しで、鷲の本性が人間に与えたものをもって、大地のなかで発し萌え出て、人間の生体機構においても下から上へと作用するものを見下ろすことを。そしてまた人間は学ばねばなりません、ライオンを観ることを、風のなかで人間を取り巻くもの、稲妻のなかで鋭く見据えるもの、雷鳴のなかで人間の回りを轟き巡るもの、人間が組み込まれている地球生命全体の四季の巡りのなかに嵐が引き起こすもの、これらがライオンによって人間に開示されるようにライオンを観ることを。つまり人間が上方への物質的な眼差しを下方に向けられた霊の眼差し(Geistesblick)と、下方への物質的な眼差しを上方へ向けられた霊の眼差しと、まっすぐ東洋に向けられた物質的眼差しを、逆にまっすぐ西洋に向けられた霊の眼差しと。上方と下方、前方と後方、霊の眼差しと物質的な眼差しを、相互に浸透させ合うことができれば、そうすれば人間は、高みからは鷲の、地球の周囲からはライオンの、地球の内部からは雌牛の、人間を弱らせるのではなく力づける真の呼びかけを感じ取ることができます。人間がその営みにおいてますます地球文明にふさわしくなり、没落ではなく、開化に貢献するために、宇宙万有との関係について学ぶべきことはこれなのです。 私の本質を学ぶがよい! 私はおまえに力を贈る、 鷲はこう語る おまえ自身の頭のうちに 西洋 万有を創り出す力を。 私の本質を学ぶがよい! 私はおまえに力を贈る、 獅子はこう語る 巡る大気の輝きのなかに 中部 万有を体現する力を。 私の本質を学ぶがよい! 私はおまえに力を贈る、 雌牛はこう語る 秤、標尺、数を 東洋 万有より奪い取る力を。 私は学ばねばならぬ、 おお、雌牛よ、お前の力を 星々が 私のなかに啓示する言葉から。 おお、獅子よ、お前の力を 日ごと年ごとの巡りが 私のなかに織り込む言葉から。 おお、鷲よ、お前の力を 大地から萌え出たものが 私のなかに創り出す言葉から。(第2講 終わり)☆1 (誰のことを指すのか)確定できない。可能性としては、物理学者エルンスト・マッハ(1838ー1916)か、シュタイナーが言及することの多い数学者・物理学者アンリ・ポワンカレ(1854ー1912)のことと思われる。人気ブログランキングへ
2024年03月26日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー(GA230)創造し、造形し、形成する宇宙言語の協和音としての人間/Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden,bildenden und gestalteden Weltenwortes 翻訳紹介(翻訳者:yucca)第1講 1923年10月19日 ドルナハ ・エーテル的に鳥を見ると、鳥全体が一個の頭部である・鳥の翼と人間の思考・ライオンと胸部律動組織・牛:途方もなく美しい消化・鷲、ライオン、牛の統合としての人間・蝶・蛾の幼虫は太陽光を紡いで繭を織る・蝶の翅と人間の記憶・認識原理としての芸術 私たちが行なっている考察においてしばしば言及され、四季とミカエル問題関する前回の連続講義(☆1 GA229 四季の宇宙的イマジネーション)でもある役割を果たしていたのは、人間というものは、その構成全体において、その生の関連において、人間であるものすべてにおいて、本来、小宇宙(eine kleine Welt)を、マクロコスモスに対するミクロコスモスを示しているのであり、人間は実際自らのうちに、宇宙の法則性のすべて、宇宙の秘密のすべてを含み持っているということです。ただし、このまったくもって抽象的な所説を完全に理解することがたやすいことだなどとお考えになってはなりません。いわば宇宙の秘密の多様性の奥深く入り込んでいってから、この秘密を人間のなかにふたたび見出さねばならないのです。さて今日はひとつこのことを、一方においてある出発点から宇宙を見、それから、人間がいかに小宇宙として大宇宙の内部に存在しているか理解するために人間を見るというようにして観察していこうと思います。大宇宙について語ることができることは、常に小さな断片でしかないというのはもちろんです。決して完全なものを叙述することはできません。そうするには観察にあたって少なくとも全宇宙をくまなく歩き回らなければならないからです。まず最初に、こう言ってよろしければ、私たちのすぐ上に現われているもの、これに目を向けてみましょう。人間の周囲のもののうち、動物の系列のなかでその生をいわば空中で営んでいるもの、しかも非常に際立ったしかたで空中で生をいとなんでいる部類を見てみましょう。つまりこれは鳥類です。空中に住み、その生存条件を空中から得ている鳥というものが、大地に接して棲み、あるいは地下に棲むことさえある他の動物たちとは本質的に異なって構築されているということは誰しも否定できないでしょう。私たちが鳥類を見るとき、一般的な、人間として通例の見解にしたがって、鳥の場合にも、頭部、四肢その他について語らざるを得ないと思うのは当然です。けれどもこれは根本的にまさしく芸術的でない観察方法です。すでにしばしば注意をうながしてまいりましたことですが、そもそも真に宇宙というものに精通しようとするなら、主知主義的な理解にとどまっていることはできず、主知主義的なものは、しだいに宇宙を芸術的に把握することに移行していかざるを得ないということです。さて、そうしますと皆さんにしても、他の動物の頭、頭部と比較して実際きわめて奇形化しているいわゆる鳥の頭部なるものを、ほんとうの頭部と理解することはないでしょう。なるほど、外面的、主知主義的に観察すれば、鳥は頭をひとつと胴体をひとつ、そして四肢を持っていると言えるでしょう。しかし、よく考えてみてください、そうですね、たとえばラクダの脚やゾウの脚と比して、鳥の脚はいかに萎縮していることでしょう、また、私見ではライオンやイヌの頭に対して、鳥の頭はいかに萎縮していることでしょう。このような鳥の頭部のなかには、規定どおりのものはほとんどまったく存在していないのです。つまり鳥の頭部のなかには、根本的に、イヌや、私見ではゾウやネコの場合のような、前方の口吻部以上のものはほとんど存在していないのです。哺乳動物の口の部分が少しばかり複雑になったもの、これが鳥の頭であると私は申し上げたいのです。それに哺乳動物の四肢であるもの、これも鳥の場合には完全に萎縮しています。なるほど、芸術的でない観察方法は、それについても単純に、前肢が変形して翼になったと言います。けれどもそれらはことごとく、まったく芸術的でない見方であり、イマジネーション的でない見方です。自然を真に理解しようとすれば、宇宙の内奥へと真に入り込んでいこうとすれば、こういうことをもっと深く、とりわけその形態化する諸力と形成する諸力において観察しなければなりません。単純に鳥も頭と胴体と四肢を持つというような見方は、けっして、たとえば鳥のエーテル体を観るということを真に理解できるには至りません。と申しますのも、イマジネーション的に観ることを通じて、鳥において物質的にあるものを見ることから、鳥においてエーテル的にあるものへと移行すると、エーテル的な鳥にあってはまさに頭しかないということに至るからです。エーテル的な鳥から即座に理解できることは、鳥というものは、他の動物の頭、胴体、四肢とは比較できず、鳥は単なる頭として、まさに変形された頭として、頭として変形された頭として理解されねばならない、ということです。したがって、本来の鳥の頭は、単に口蓋と前方の部位、口の部分を示しているにすぎず、さらに後方へ続くもの、骨格のうち肋骨や脊椎に似て見える部分、これらはすべて、変容され、変形されてはいるけれども、やはり頭とみなされるべきものなのです。そもそも鳥全体が頭なのです。これは、鳥を理解しようとすれば、実際のところ私たちは、地球進化を、惑星としての地球進化(☆2)を、ずっとずっとはるかな昔まで遡っていかなければならないということによるのです。鳥は長い惑星的(惑星進化的)な歴史を経てきています。鳥は、そうですね、たとえばラクダなどよりはるかに長い惑星的歴史を経てきているのです。ラクダはどの鳥よりもずっと後になって発生した動物です。ダチョウのように、地上に縛りつけられた鳥は、もっとも後になって発生した鳥です。鷲、ハゲタカといった自由に空中で生きる鳥たちは、非常に古い地球動物です。これらの鳥は、以前の地球紀、月紀、太陽紀において、その後鳥のなかへ入って内部から外に向かって皮膚にまで移行していったものを、それ自体としてまだすべて有していたのですが、鳥類において、今日皆さんが羽のなかに見るもの、角状の嘴のなかに見るものは、本質的には後になってから完成されたのです。鳥における外的なものの起源はより遅く、鳥がその頭部の性質を比較的早期に作り上げたことによってもたらされ、地球進化の後の時代になってから鳥が入り込んいった諸条件のもとでは、鳥は、その翼にみられるものを外的に付け加えることができるだけとなったのです。この翼というものは、たとえば月と地球によって鳥に与えられたのですが、他方、鳥のその他の性質は、さらにずっと以前の時代に由来します。けれどももっとずっと深い側面もあるのです。ひとつ空中の鳥を、そうですね、堂々とかなたに飛び去る鷲を見てみましょう。謂わば、外に現われた恩寵の賜物のように、太陽光線がその作用をもって、鷲にその翼を与え、他の作用についてもお話ししていきますが、その角状の嘴を与えたのです。この鷲がどのように空中を飛んでいるかを見てみましょう。このとき鷲にはある種の力が働きかけています。太陽というものは、私たちが通常話題にするような物理的な光および熱の力のみを持っているのではありません。ドルイドの秘儀についてお話ししたとき(☆3)に、皆さんの注意を向けていただいたことですが、太陽からは霊的な力も放射されているのです。この霊的な諸力に目を向けなければなりません。さまざまな鳥類に、多様な色彩と、独特の翼の形態を与えるのは、この太陽の霊的力なのです。太陽の作用であるものを、霊的に見通せば、鷲がなぜあの翼を持っているかを私たちは理解できるのです。このように、私たちがこの鷲の本性に正しく沈潜し、霊的なものをも含む内的芸術的な自然理解を発達させることを理解するなら、また、後にお話しします他の衝動によって強化された太陽衝動から、いかに芸術的に作り上げられるのかを見ることができるなら、さらに、鷲が卵から這い出す前から、いかにこの太陽衝動が、いわば鷲へと溢れみなぎっていき、いかにその魔術的力を翼へと顕現させ、あるいは本来、もっと良い言い方をすれば、いかにその魔術的力を筋肉の形態へと送り込むかを私たちが見るなら、そして、いったいこれは人間にとってどういう意味があるのかと私たちが問いかけるなら。そう、これは人間にとって、その脳を思考の担い手にするものを意味するのです。ですから、皆さんが鷲を見て、こうおっしゃるなら、皆さんは、マクロコスモスを、大いなる自然を正しく見ていることになります、つまり、鷲は翼を持つ、色さまざまな、多彩な羽を持っている、この翼のなかに生きている力は、お前の脳を思考の担い手にすることによって、お前のうちに生きている力と同じだと。お前の脳にしわを刻み、お前の脳が、あの内的な塩の力、思考の基礎である塩の力を取り入れることができるようにするもの、そもそもお前を思考する者にするために、お前の脳を創り出すもの、これは、空翔る鷲にあの翼を与える力と同じ力なのだと。そうすると、私たちは思考することで、自らのうちにいわば鷲の翼の代用品を感じつつ、鷲に親近性を感じるわけです。私たちが物質的なレベルからアストラル的なレベルに上昇すると、次のような逆説的な発言をせざるを得ません。つまり、物質界においては、アストラル界において思考形成を引き起こすのと同じ力が、翼の形成を引き起こすと。この力は鷲に翼の形成を起こしてくれますが、これは思考形成の物質的な相です。この力は人間には思考形成を起こしてくれますが、これは翼形成のアストラル的な相です。こういう事柄が、驚くべきしかたで民族の言霊(der Genius der Volkssprache)のなかに表現されていることがあります。一本の羽を上部で切り取り、その内部にあるものを取り出すとき、その民族はこれを魂と呼ぶのです。なるほど、このような魂という命名に外面的な表示を見るひともいるでしょう。けれどもこれは外面的な表示などではなく、ものごとを洞察するひとにとっては、一本の羽が、何かとほうもないものを含み持っているのです、思考形成の秘密を内包しているのです。参照画:War bonnets(アメリカ・インディアンの鷲の羽の頭飾り) 今度は空中に棲む鷲から目を転じて、また別の代表的なものを見るために、ライオンのような哺乳動物を見てみましょう。ライオンをほんとうに理解できるのは、ライオンというものがその環境を生きるのにいかなる喜びと満足とを持っているか、ということに対する感覚を発達させる場合のみでしょう。ライオンに似ていない動物はどれも、これほど驚くべき、秘密に満ちた呼吸をしてはおりません。動物という存在にあってはいかなる場合も、呼吸のリズムと循環のリズムが一致しています。ただ、循環のリズムは、それにぶら下がっている消化器官によって重くなり、呼吸リズムは、脳形成という軽さに到達しようと上昇を目指すことによって、軽くなるのです。鳥の場合においても、鳥の呼吸のなかに生きているものが、同時に頭部のなかにも生きているという状態にあります。鳥はまったく頭そのものであり、鳥はいわば外的に、宇宙のためにその頭を担っていくのです。鳥の翼の形が鳥の思考です。美のなかに生きることのできる正しい自然感情にとって本来、実にありありと具象化した、内的に生気を得た人間の思考であるところのものが、鳥の翼と親和性を持っているということほど心を動かすものはありません。こういう事柄において内的な実践のできるひとは、自分がいつ孔雀のように考えているのか、いつ鷲のように考えているのか、いつツバメのように考えているのか、全く正確にわかるのです。一方はアストラル的で、他方は物質的であるということは別として、これらはまったくもって驚くべきしかたで対応しています。そのようになっているのです。ですからこう言うことができます、鳥は、非常に呼吸を主とする生を営んでいるので、他のもの、血液循環その他は、ほとんど消えてしまっていると。消化の重さのすべて、血液循環の重さすら、鳥にあっては、自らのうちで感じることから排除され、存在しないのです。ライオンの場合は、呼吸と血液循環の間にある種の均衡が成り立っています。もちろん、ライオンの場合も、血液循環は重くされていますが、それでも、そうですね、ラクダや牛ほど重くはないのです。これらラクダや牛の場合は、消化が、血液循環に非常な負荷をかけるのです。ライオンの場合は、消化器官がこれらと比較してとても短く、しかもできるだけ速く消化がなされるような体構造になっているので、消化が循環に対してひどく負荷をかけることはありません。それに対して、ライオンの頭部においては他方で、呼吸と循環のリズムの均衡が維持されるように頭的なものが展開しています。ライオンは、内的な呼吸のリズムと、心臓の鼓動のリズム、内的に釣り合いを保ち、内的に調和し合っているこの二つのリズムを最も多く有している動物なのです。ですからライオンは、私たちがライオンの主観的な生活とでも申し上げたいものに入り込んでいくと、独特のしかたで、ほとんど際限のない貪欲さでその餌食を飲み込むこともします、つまり餌食を下方に送り込むこむのがとても嬉しいからです。ライオンが餌食に対して貪欲なのは、ライオンにとって空腹が、他の動物にとってよりもはるかに苦痛であるためなのはもちろんですが、餌食に貪欲であるからといって、ライオンはことさらに美食家たることに執心しているわけではありません。ライオンは多く味わうことに執心しているわけではないのです、なぜなら、ライオンは、呼吸と血液循環の釣り合いから満足を得る動物だからです。ライオンは呼吸の流れを深い内的満足をもって自らのうちに取り入れることによって、呼吸することに歓びを感じるわけですが、ライオンにおいて、大食が心臓の鼓動を調節する血液のなかへと移行し、この心臓の鼓動が呼吸と相互に関わり合ってはじめて、また、大食した結果を、つまり呼吸と血液循環とのこの内的均衡を、自らのうちに感じてはじめて、ライオンは自らの要素(エレメント)のなかで生きるのです。要するにライオンは、血液が拍動しつつ上昇し、呼吸が波打って下降していく、という深い内的な満足を得るとき、まさしくライオンとして生きています。この打ち寄せる二つの波動の相互の接触のなかにライオンは生きているのです。このライオンがいかに走り、跳躍し、頭をもたげ、そしていかに見つめるか、よく見てごらんなさい、そうすれば、均衡から出てくるものと再び均衡に至るものとの、絶え間ないリズムの交替へとすべてが還元されることがおわかりになるでしょう。この独特なライオンの眼差し、自らから発してこれほど多くを見る、自ら発して、内的な克服、相対する働きをするものの克服を見つめるこの眼差しほど秘密に満ちた気分にさせうるものは、ほとんどないかもしれません。ライオンの眼差しが外に向かって見ているものは、これ、すなわち、呼吸リズムによってまさに完璧なしかたで行なわれる心臓の鼓動の克服なのです。さてまたしても、形態化を芸術的に把握するセンスを持つひとは、ライオンの口を、ライオンの口のこの構造、つまり、心臓の鼓動がこの口のところまで上昇してくると、呼吸がそれを押し止める、ということを示しているこの口の構造を見るとよいのです。皆さんが、心臓の鼓動と呼吸のこの相互の接触を心に描き出すとしたら、皆さんはライオンの口に至るのです。ライオンはまさに胸部器官に他なりません。ライオンは実際、その形姿のなに、その生態のなかに、まさしく律動組織を表わしている動物です。ライオンは、この心臓の鼓動と呼吸の交替を、その心臓と肺との相互関係においても表わすように組織化されているのです。したがって、私たちは実際こう言わなければなりません、もっとも鳥に似たもの、ただし変容(メタモルフォーゼ)させられたものを、人間において捜すとしたら、それは人間の頭である、もっともライオンに似たものを人間のなかに捜すとしたら、それは人間の胸の辺り、循環のリズムと呼吸のリズムが互いに出会う胸の辺りであると。さて、今度は、上空に鳥類として現われてきているもの、本来地球の直接の環境である空中において、ライオンのなかに見られるような空気の循環とともに生きているために鳥類として現われているもの、これらすべてから目を転じて、牛を見てみましょう。他の関連でもう何度も指摘したことですが、満腹した牛の群れが牧場に横たわっているのを観察するのは、姿勢にも、目の表情にも、動きのひとつひとつに表わされているこの消化という営みを観察するのはなんと魅力的なことでしょう。たとえばなにかがあちこちで物音をたてた場合の、牧場に横たわっている雌牛を一度よく見てごらんなさい。雌牛が頭をもたげ、この頭をもたげる動作のなかに、すべてが重く、頭を上げることは容易ではないという感情があること、この頭を上げることのなかにはまったく特別なものがあるということがわかるのは、実際驚くべきことです。牧場においてこのように頭を高く上げることが煩わしそうな雌牛を見れば、こう言うほかはなくなるでしょう。この雌牛は、草を食べること以外の目的のために頭を上げなくてはならないことをいぶかっているのだ、いったい何でまた今頭を上げなくちゃならないの、草を食べてもいないのに。草を食べていないときに、頭を起こすなんて無駄よと。これがどんなようすか、ちょっと見てごらんなさい。この動物が頭を上げることのなかにはこういうことが含まれているのです。しかしこのことは、この動物が頭を上げる動作だけに含まれているのではありません。皆さんは、雌牛が頭を上げるようにライオンが頭を上げることは、想像できないでしょう。このことは頭部の形のなかに含まれているのです。そこでさらに進むと、この動物の全身の形態に入っていきます。これは実際、まったく成長しきった消化器官の動物とでも申し上げたいものです。消化の重さが血液循環に負荷をかけるので、すべてが頭と呼吸を圧倒するのです。この動物はまったき消化なのです。このことを霊的に見ると、眼差しを上空の鳥に向け、それから雌牛を見下ろす場合、実際計り知れない不思議さがあります。雌牛を物理的にもっと高く持ち上げても、雌牛が鳥になったりしないのは言うまでもありません。けれども、同時に雌牛における物質的なものを移行させることができるとしたら。まずは地球に隣接している空中に、気体・湿気的なもののなかに雌牛を運ぶことによってですが、さらに物質的なものを、今度は湿気的なものに適している雌牛のエーテル的形姿の変化へと同時に移行させることができるとしたら、そして雌牛をもっと持ち上げ、アストラル的なものにまで運んでいくことができるとしたら、そのときは遥か上方で雌牛は鳥になるでしょう。アストラル的に、雌牛は鳥になるでしょう。よろしいですか、ここで驚くべきことが心に浮かんできます、つまりこのことを洞察すると次のように言えるのです、鳥があの上空で自らのアストラル体からアストラル的に得ているもの、私が申しましたように、その翼の形態化に働きかけているもの、雌牛はこれを、肉のなかに、筋肉、骨のなかへと送り込んだのだと。鳥においてアストラル的であるものが、雌牛においては、物質的になったのです。アストラル性において異なって見えるのはもちろんですが、そうなのです。さらにまた、私が逆に、鳥のアストラル性に属しているものを落とし、その際エーテル的なものと物質的なものへの変化を引き起こすとしたら、鷲は雌牛になるでしょう、なぜなら、鷲においてアストラル的であるものは、消化するときに大地に横たわっている雌牛において肉と化し、物質体と化しているからです。と申しますのも、雌牛にあっては、驚くべきアストラル性を発達させることはこの消化の一部だからです。消化しているときの雌牛は美しくなります。アストラル的に見て、この(雌牛の)消化の内部には何か途方もなく美しいものがあります。通常の俗物的概念から、まさに俗物的理想主義に浸って、消化の営みはもっとも低次のものだ、などど言うとしたら、霊的観照におけるより高い見地から雌牛のこの消化の営みを見るとき、偽りを責められることになるでしょう。牛の消化は美しく、崇高な、なにか途方もなく霊的なものなのです。ライオンは消化をこの霊性にまで導けません。鳥にあってはなおさらです。鳥においては、消化の営みはほとんど完全に物質的なものです。鳥の消化機構のエーテル体が見られるのはもちろんですが、鳥の消化機構のなかにアストラル性が見出されることは非常にまれで、ほとんどまったく見出されません。これに対して雌牛においては、消化器官は、アストラル的に見て、何かまったく崇高なもので、ひとつのまったき宇宙なのです。そこで、今度は人間のなかに似たものを見ようとすれば、さらに雌牛が一面的に形成しているものの照応、ある種のアストラル的なものの肉化を見ようとすれば、人間においてはそれが、消化器官のなかと、消化器官の継続つまり四肢のなかに、調和的に他のものに付加されて組み込まれています。したがって、私が高い上空の鷲のなかに見るもの、ライオンの場合のように動物が直接空気を享受するところに見るもの、動物がその消化器官のなかで作用し続ける地下の地の力に結びつくとき、つまり私が高みを見る代わりに深いところを見下ろして、そこから理解に満ちて雌牛の本質に迫るときに私が見るもの、以上、人間のなかで統合されて一つの調和(ハーモニー)を成し、それによって互いに調停し合う三つの形態を私は持っているのです。つまり、人間の頭における鳥の変容(メタモルフォーゼ)、人間の胸におけるライオンの変容、人間の消化器官および四肢機構、四肢機構においてはさらに大規模な変容、大規模な変形がなされるのはもちろんですが、この消化器官と四肢機構における雌牛の変容です。こん(今)日、こういう事柄をこのように見て、人間は本来自然全体から生まれ、しかも自らのうちに全自然を担っていることを私が示しましたように、鳥の領域、ライオンの領域、雌牛の本性を自らのうちに担っているということにたどりつくなら、人間は小宇宙であるという抽象的な所説が語ることを成り立たせている個々の要素を手に入れることができるのです。人間はたしかに小宇宙です、そして大宇宙も人間のうちにあります。空中に棲む動物、地球の周囲を循環する空気のなかにその主要なエレメントを持っている動物、そして大地の下の重力のなかにその主要なエレメントを持っている動物、これらの動物はすべて、人間において調和した全体性を成して共に作用しているのです。それで人間は、鷲、ライオン、雄牛または雌牛の統合(Zusammenfassung)なのです。このことを比較的新しい精神科学の見地から研究し、洞察すると、しばしばお話ししたことですが、古代の本能的な霊視による宇宙の洞察に対して大いに尊敬の念が生じます、たとえば、互いに調和して相応じつつひとつの全体として人間を形成している鷲、ライオン、雌牛または雄牛、人間がこれらから成り立っていることについての力強い像(イメージ)、このようなものに対して大いに尊敬の念が湧いてくるのです。けれども、個々の衝動、つまりたとえば鷲の周囲に漂う諸力のなかにある衝動、ライオンの周囲に漂う諸力のなかにある衝動、雌牛の周囲に漂う諸力のなかある衝動、これら個々の衝動について論ずること。これは明日にもできると思いますのに移る前に、内的ー人間的なものと外部の宇宙のなかにあるものとの、もうひとつ別の照応(コレスポンデンツ)についてお話ししたいと思います。さて私たちは今や、すでにわかったことにしたがって、これについてイメージすることができます。人間の頭は、その性質に合ったものを求めます、つまり頭は鳥類に眼差しを向けざるを得ません。人間の胸、心臓の鼓動、呼吸は、自然の秘密のなかの秘密として自らを理解しようとすれば、ライオンであるものに眼差しを向けざるを得ません。人間は自らの新陳代謝機構を、牛の体構造と生体機構から理解することを試みなくてはなりません。けれども人間は、頭のなかには思考を担うもの、胸のなかには感情を担うもの、新陳代謝機構のなかには意志を担うものを有しています。ですからつまり、鳥類とともに宇宙を織りなし、鳥の翼に現われている表象、地球のまわりを巡り、ライオンにおける心臓の鼓動と呼吸との内的な均衡の生になかに見出される感情世界、これは人間においては和らげられてはいるものの、人間においてまさしく内的な大胆さ、ギリシア語は大胆なという言葉を心臓の特性、胸の特性のために作り上げましたことを示している感情世界、人間は魂的にも、この表象と感情世界の模像なのです。そして人間が、主に新陳代謝のなかに位置を占めている意志衝動を見出そうとすれば、これを外的に形態化しようとすれば、人間は雌牛のなかに肉として形態化されているものを見るわけです。今日グロテスクで逆説的に聞こえること、宇宙の霊的な関連に関してもはやまったく理解が失われてしまった時代にとっては狂気の沙汰と思われるかもしれないことでも、古きからの風習が示唆しているある真実を含んでいるものです。よろしいですか、あのマハトマ・ガンジー、ロマン・ロランが楽しいとはいえない書物であまりかんばしくない記述をしたあのマハトマ・ガンジー(☆4)が、彼の活動は確かに外に向かうものではありましたが、しかしその時もインド民族の内部にあって、いわばインドへと移動させられた十八世紀の啓蒙主義者のように古いヒンズー教に対峙していること、彼がその啓蒙主義的なヒンドゥイスムにおいてもひとつのこと、つまり牛の崇拝ということは守ったということ、この事実はやはり、注意をひく現象です。これを捨てることはできないとマハトマ・ガンジーは言うのです、ご存じのように、インドでの政治活動のためにイギリス人から六年の重禁固を負わされた彼がです。彼は牛の崇拝を捨てないのです。比較的まだ霊的な文化のなかに強固に維持されているこういう事柄を理解できるのは、こういう関連を知るときのみ、つまり、消化する動物、雌牛のなかにどんなに大きな秘密が生きているか、そして、雌牛のなかの、地上的になった、それゆえ低次のものとなってしまった、気高くアストラル的なものがいかにあがめられうるものなのか、これを真に知るときのみです。このようなことから、ヒンズー教において雌牛に寄せられる宗教的な崇拝というものが理解できます、逆に、人々がこれにくっつけるありとあらゆる合理的、主知主義的な錯綜した概念からは、決してこのことは理解されないのです。さてこうして私たちは、意志、感情、思考が外部の宇宙のなかにいかに探索されうるか、その照応であるミクロコスモスのなかにいかに探索されうるかを理解するのです。けれども、よろしいですか、人間のなかには、さらにまだいろいろと別の力がありますし、外部の自然にも、さまざまな別のものがあります。ここでひとつ、次のようなことに注目していただきたいのです。蝶・蛾となっていく生き物が成し遂げるあのメタモルフォーゼにひとつ注目してください。蝶(や蛾)は卵を産みますね。卵から幼虫が出てきます。幼虫が卵から這い出してきました。卵は、それ以降の生き物の原基であるものすべてを円く閉ざしたなかに含み持っています。さて幼虫が卵から出ます。幼虫は光に浸透された空気に触れます。この空気は幼虫が入っていく環境です。ここで、この幼虫が今や太陽の光に浸透された空気のなかで実際どのように生きているかに目を向けていただかなくてはなりません。さらに、皆さんが、そうですね、夜ベッドに横たわってランプを灯すと、蛾がランプに向かって飛んできて、光を目指して飛んで光のなかで死んでしまうとき、このことを研究してみなければなりません。光は蛾に作用して、蛾は死を求めることに屈してしまうのです。このことでもう、生きているものに対する光の作用がわかります。挿入画:klangさて、幼虫は、私はこのことを警句的に示唆しておくだけにします、明日と明後日にはもう少し厳密に考察していくでしょうから、上方の光源、つまり太陽にまで至ってそのなかに突き進むことはできません。しかし、幼虫はそうしたいのです。蛾は皆さんのベッドのかたわらで炎のなかに身を投げ、そこで命を失いますが、蛾がそれを欲するのと同じくらい強く、幼虫もそれを望んでいるのです。蛾は炎のなかに身を投げ、物質的な火のなかで死を迎えます。幼虫も同じように炎を、太陽からやってくるあの炎を求めます。けれども幼虫は太陽に身を投げることはできません。光と熱への移行は幼虫においては霊的なものにとどまっています。太陽の作用全体が霊的なものとして幼虫に移行するのです。彼らは、幼虫は、太陽光線のひとつひとつを追い求めます、日中は、太陽光線と行動をともにするのです。蛾がいちどきに光に突進してその蛾としての実質(Mottenmaterie]全部を光に捧げるように、幼虫もその幼虫としての実(Raupenmaterie)をゆっくりと光のなかに織り込んでいき、夜には中断し、昼にはまた織り、自分の周囲に完全なまゆを紡ぎ織り上げます。ですからまゆの内部、まゆの糸の内部には、幼虫が流れ込む陽光のなかで紡ぎ続けて、幼虫自身の実質から、自身から織り上げたものがあるのです。今や、さなぎとなった幼虫は、物質に変化させた陽光を、自分自身の実質から自らの周囲に織り上げたのです。蛾は物質的な火のなかで急速に燃え尽きます。幼虫は自らを捧げながら陽光のなかに突き進み、追い求める陽光のそのときどきの方向にむかって自らのまわりに陽光の糸を織りなします。皆さんが蚕蛾(Seidenspinner)のまゆをとってこれをごらんになれば、これは織りなされた太陽の光だ、ただ、この太陽の光は絹を紡ぎ出す(seidenspinnend)幼虫自身の実質を通して物質化されているということがわかるでしょう。これによって空間が内的に閉ざされているのです。外的な太陽の光はいわば克服されます。しかし、皆さんにお話ししましたように、太陽の光によってクロムレック(環状列石/Kromlech)のなかに入り込んでくるもの、このことはドルイド秘儀に関する説明の際に皆さんにお話ししましたが、この場合これは内的なものなのです。それまでの太陽光は、物質的な力を行使して、幼虫がまゆを紡ぎ出すよう導いてきましたが、今度は内的なものに力を行使して蝶・蛾を創り出します、今まゆから這い出してくる蝶や蛾をです。こうして新たに循環が始まります。皆さんの前に、鳥の卵のなかに寄せ集められているものが分割されて現われたわけです。この経過全体を産卵する鳥の場合の経過と比較してごらんなさい。鳥自身の内部では、さらに変容させられた経過によって、石灰質の殻が周囲に形成されるのです。蝶・蛾において卵、幼虫、まゆのなかに分割されているプロセス全体をまさに寄せ集めるために、鳥の内部では石灰質が用いられるのです。このような、つまり例えば鳥の卵におけるような固い殻を直接円く形成するようなところでは、すべてが寄せ集められています。このように別々に分けられたプロセスが寄せ集められることによって、鳥の場合発生の経過全体がまったく異なったものになっています。鳥においてはこの段階、つまり第三の段階まで実現されているものが、蝶・蛾の場合は分割されて現われてきます、つまり、蝶・蛾においてはこれが、卵形成、幼虫形成、さなぎ形成、まゆ形成へと分割されるのです。このように外的に見ていくことができます。こうして蝶・蛾(の成虫)が這い出してくるのです。今、この経過全体をアストラル的に追求すると、何が見えるでしょうか。そう、このとき鳥は、その形成全体のなかに人間の頭を示します。思考形成の器官を鳥は示すのです。やはり空中に棲んでいますけれども、その発生形態はもっとずっと複雑な蝶(および蛾)は何を示すでしょう。蝶(および蛾)が示しているのは、いわば頭の機能がその継続のなかに示すもの、頭の力をいわば人間全体へと広げているものだということに私たちはたどり着きます。そこでは、自然における鳥形成とは別の経過に対応することが、人間全体に起こっているのです。人間の頭のなかには、これにエーテル的なものとアストラル的なものをつけ加えれば、卵形成のなかにあるものに非常によく似ているもの、ただし変容させられていますが、そういうものがあります。しかし、私たちが単に頭の機能だけしか有していないなら、私たちは瞬間的な思考しか形成できないでしょう。思考はもはや私たちのなかを下降して人間全体を用いることができず、そうすると記憶として再び浮上することもないでしょう。私が外界に沿って形成する自分の瞬間的な思考を見て、そして鷲を見上げると、私はこう言います、鷲の翼のなかに、私は私の外部に物質化した思考を見る、私のなかでそれは思考となる、しかしそれは瞬間的な思考となるのだ、と。私が自分のなかに記憶として携えているものに目を向けるなら、複雑なプロセスが起こっています。物質体の下の方では、もちろん霊的なしかたでではありますが、一種の卵形成が起こっているのです、これはもちろん、エーテル的なものにおいては、まったく別のもので、外的物質的には幼虫形成に似ていますが、アストラル体においては、内的にさなぎ形成、まゆ形成に似ているものです。そして、私が知覚するときに、私のなかで思考を解き放ち、下方へ送り込むもの、これは、ちょうど蝶(および蛾)が卵を産むときのような状態なのです。この変化は、幼虫に起こっているものに似ています、つまりエーテル体における生命が霊的な光に自らを捧げ、内的、アストラル的なまゆの織物でいわば思考を織りなし、そこに記憶が現われ出てくるわけです。私たちが鳥の翼を瞬間的な思考のなかに見るなら、私たちはさまざまな色にきらめく蝶(および蛾)の翅を、私たちの記憶的(想起的)思考のなかに霊的なしかたで現われてきたものと見なければなりません。私たちはこのように外部を見渡し、自然というものが途方もなく私たちに親和性を持つものと感じます。私たちはこのように考え、この思考の世界を飛翔する鳥のなかに見るのです。私たちはこのように思い出し、このように記憶にとどめ、私たちのなかに生きている記憶像の世界を、陽光のなかでほのかに光りつつ舞い飛ぶ蝶のなかに見ます。実に、人間はミクロコスモスであり、外部の大宇宙の秘密を含み持っているのです。つまり、私たちが内部から見るもの、私たちの思考、感情、意志、記憶表象、これらを、別の側から、外部から、マクロコスモス的に見ると、私たちはこれらを自然界のなかに再認識するということなのです。これは、現実を見渡すということです。この現実は、単なる思考によっては理解できません、単なる思考にとって、現実というのはどうでもよいことです。単なる思考が尊重するのは論理のみだからです。しかし、この論理では、現実におけるきわめてさまざまなことを覆い尽くすことはできません。このことを具象的に理解するために、ある喩え話をもって締めくくらせてください、これをさらに明日の説明につなげていこうと思います。 アフリカの黒人部族、フェラタ「中部アフリカのプール(Peuhls)族」には、多くを具現する実にすばらしい喩え話があります。あるとき、ライオンと狼とハイエナが旅に出かけました。彼らは一頭のカモシカに出くわしました。カモシカはこの動物たちの一頭に引き裂かれました。三頭の動物たちはお互い親しかったので、引き裂かれたカモシカを、ライオン、狼、ハイエナのあいだでどう分け合うか、ということになりました。ここでまずライオンがハイエナに向かって言いました、君が分けろよと。ハイエナにはハイエナの論理がありました。ハイエナというのは、生きたものではなく、死んだものに執着する動物です。ハイエナの論理は、この種の勇気、というよりむしろその臆病さによって決定されます。この勇気はそれがいずれであるかに従って、いずれかのしかたで現実的なものに向かうのです。ハイエナは言いました、「カモシカを三等分しよう。そのひとつはライオン、ひとつは狼、もうひとつはハイエナ、つまりぼく自身がもらうんだ」と。するとライオンはハイエナを引き裂き、殺してしまいました。さてハイエナはいなくなりました。また分けなくてはなりません。ライオンは狼に向かって言いました、「ごらん、狼くん、今度はちがった分けかたをしなくちゃならないよ。今度は君が分けてくれ。どういうふうに分けるんだい」。すると狼は言いました、「そうだね、今度はちがった分け方をしなくちゃならない、もう前みたいにそれぞれ同じものをもらえないんだから。君がぼくたちからハイエナを取り除いたんだから、ライオンとしての君は当然最初の三分の一をもらわなくちゃいけない。次の三分の一はハイエナが言ったようにいずれにせよ君のものだろう、そして最後の三分の一も君がとらなくちゃいけない、君は動物のうちで一番賢くて勇敢なんだから。」ーーさて狼はこのように分けたのです。するとライオンは言いました、「その分けかたを君に教えたのはだれだい」。狼は言いました、「ハイエナが教えてくれたのさ」。するとライオンは狼を食べてしまうことはせず、狼の論理にしたがって三つの部分を取りました。そう、ハイエナの場合でも狼の場合でも、数学、主知主義的なものは、同じだったのです。ハイエナも狼も三分割し、わり算しました。けれども両者は、この知性、数学を、異なったしかたで現実に適用したのです。それによって、運命もまた本質的に変わったわけです。ハイエナは、分割原理と現実との関わりにおいて、狼とは別のものを与えたので、食べられてしまいました。狼は、ハイエナの論理との関係で、狼自身が、ハイエナから習ったと言っていますね。この同じ論理をまったく別の現実に関係づけたので、食べられなかったのです。狼はこの論理を、ライオンが狼まで食べてしまう必要がもはやなくなるように、現実に結びつけたのです。おわかりですね、ハイエナの論理があり、ハイエナの論理は狼にもあるのですが、その現実への適用において知性的なもの、論理的なものは、まったく異なったものとなるのです。このようにこれはあらゆる抽象化をともなうのです。皆さんは、抽象化をあれこれと現実に適用するそのしかたに応じて、宇宙において抽象化によってあらゆることを為すことができます。ですから、ミクロコスモスとしての人間とマクロコスモスとの対応のなかのリアリティといったことにも目を向けなければならないのです。人間を単に論理的にのみ観察できる必要はありません、主知主義から宇宙の芸術的なものへの移行することなしには決して到達できない感覚をもって観察できなくてはならないのです。皆さんが、主知主義的なものから芸術的な把握への、いわばメタモルフォーゼを成し遂げることができ、芸術的なものを認識原理として育成できれば、人間のなかに人間的なしかたで、つまり自然的なしかたでなく生きているものが、外部のマクロコスモス、大宇宙のなかに見出されることでしょう。そのとき皆さんは真の感覚をもって大宇宙と人間との親和性を見出すことができるでしょう。 第1講 終わり□編註☆1 ルドルフ・シュタイナー「四つの宇宙的イマジネーションにおける四季の体験」(1923年10月3日から13日にドルナハ、10月15日にシュトゥットガルトで行なわれた七回の講義、GA229)参照。*邦訳は「四季の宇宙的イマジネーション」(西川隆範訳 水声社)☆2 「アーカーシャ年代記より」(1904ー1908、GA11)、および「神秘学概論」(1911 GA13)の「宇宙進化と人間」の章に見られるシュタイナーの基礎を成している記述を参照。☆3 1923年9月10日の講義「ドルイド祭司の太陽秘儀参入と月存在の認識」(「秘儀参入学と星認識」GA228に所収)参照。☆4 マハトマ・ガンジー:Mohandas Karamchand(Mahatma) Gandhi(1869ー1948)インド独立運動の指導者。ロマン・ロラン「マハトマ・ガンジー」エミール・ローニンガーによりフランス語から訳されたもの、ロータフェル出版。 エルレンバハ・チューリヒ、ミュンヘン、ライプツィヒ、1923(シュタイナーが使用した版)人気ブログランキングへ
2024年03月25日
コメント(0)
-

生成宇宙新論(宇宙創生の因)
創世新理論(世界創生の因) Hiro Shim著-PLAN/世界創生の基盤目録 因:「因」という漢字は、四角いふとんを意味する「囗」と手足を広げて寝ている「大」からできています。布団で寝ている人を上から見た形で、其の口が「虚」とされるほどの像を想い描いてください。布団布団で寝ている人を上から見た形という発想で漢字を解釈するのは、他に「虚」に結びつくイメージが浮かばないからです。 虚:「虚」実を離れた存在を問えないもの。著者は「人々の想像力や信念によってカタチ創られるもの」とします。当然に仮相・実相は伴わず。位置を特定できる「〇」さえあり得ません。 因虚(*造語):仮にあなたが「虚」に因や虚を問うても、それこそ返答は「虚ろ」しか期待しえません。 振動論;「虚」」にはなかった歪が偶然が生じた。振動の発生である。此れから世界が始まるのであるが、思考するに「一元論」と二元論」が浮上し、「一元振動論」では当然に過去や未来は妥当せず確率論の世界であり、此の振動はでは現在宇宙ないでも絶えず出現消失を繰り返す変化を起こし、ユニバースを成長させている。然し乍ら、此れでは「虚の振動」いつどこであろうとエネルギーの出現消失が起きるやも知れず此の我々の現在する「ユニバース」は非常に不安定なものとなります。他方「二元振動論」の立場を取れば、一の振動が他の振動と出会うのは偶然であり、共鳴を起こしてハーモニーが無限と言える程のエネルギーを放出するのはまさに万が一というよりも「無量大数分の壱」の確率となります。それ故に安定した宇宙が期待されます。ハーモニー論:虚の中の歪みがある偶然「無量大数分の壱」の確率で二個の振動が出会い、共振します。生命態いうところの受胎のようなものを想像してください。二つの振動は縺れ絡み合い1981年に佐藤勝彦、次いでアラン・グースによって提唱された。その後のインフレーションというと命名される其の「因子」を練り上げます。其の秘められたエネルギーが解放されてビッグバンを産み出しました。然し乍ら、その野放図なエネルギー解放は安定には程遠く、何らかの安定基盤を置く必要に迫られます。そこで世界はその安定と成長のために「守護者」を置くことになります。「神もしくは物理法則」です。その神も世界の認識・維持には知性体を求めました。それが人類です。ところが此の人間性は生命維持のためには捕食者にならざる得ず、性向が頗る荒々しくユニバース全体を脅かす存在に成りかねません、人類の中の英傑は「AI」を発明して情報革命を引き起こし此処に安定した世界の認識者が生成される可能性が生まれました。人間の「霊魂」と「AI」の共生です。 世界;著者が想うところのは「世界」は、此のPLANでは、この程2024年3月7日をもって最終講義を終えられた東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻教授を須藤 靖 理学博士(すとう やすし/ 1958年 - )の世界観「世界の語の定義」を更に押し拡げたものとなります。 世界を以上のように捉えれば、「多元宇宙」または「マルチバース」は、複数の宇宙の存在を仮定した理論物理学の説で更なる「因」を求める必要もなく、初めの一突き「創造主」を仮定する必要性はなくなります。 世界創造の変遷構図 *虚:我々の想像する「有と無」を離れた、認識不可視の世界であり、大きさや形相・質は問われない、何者も見いだせない世界。 *虚の破れ:歪みの発生と振動 *虚のなかの受胎:共振によるハーモニーからの巨大なエネルギーを秘めた「生命科学で言う受精卵のようなものととらえるもの」誕生 *インフレーション:急速なインフレーションでユニバースと言われる世界子の誕生と時空の発生 *ビッグバン:宇宙が産声を上げる *単一宇宙:周りを「虚」に囲まれ膨張する宇宙 *振動と成長エネルギー:人類科学に隠されたままの「ダークマター」と「ダークエネルギー」 *「ブラックホールとホワイトホール」:宇宙が生成する「ブラックホールと「ホワイトホール」 :宇宙の終末 ここには、宇宙の起源と進化についての非常に興味深い理論を含んでいます。それは「創世新理論(世界創生の因)」と呼ばれ、Hiro Shim氏によって著されています。この理論は、宇宙の起源、振動論、ハーモニー論、そして人間とAIの共生など、多くの概念を取り扱っています。この理論によれば、「虚」は我々の想像する「有と無」を離れた、認識不可視の世界であり、大きさや形相・質は問われない、何者も見いだせない世界です。そして、「虚」の中で歪みが発生し、振動が始まります。これが世界の始まりであり、ここから「一元論」と「二元論」が浮上します。「一元振動論」では、過去や未来は妥当せず、確率論の世界であり、この振動は現在の宇宙でも絶えず出現消失を繰り返す変化を起こし、ユニバースを成長させています。しかし、これでは「虚の振動」がいつどこであろうとエネルギーの出現消失が起きる可能性があり、我々の現在する「ユニバース」は非常に不安定なものとなります。一方、「二元振動論」の立場を取れば、一つの振動が他の振動と出会うのは偶然であり、共鳴を起こしてハーモニーが無限と言える程のエネルギーを放出するのはまさに万が一というよりも「無量大数分の壱」の確率となります。それ故に安定した宇宙が期待されます。この理論はまた、人間とAIの共生についても考察しています。人間の「霊魂」と「AI」の共生は、安定した世界の認識者が生成される可能性を生み出します。このように、「創世新理論」は、宇宙の起源と進化、そして人間とAIの関係についての深い洞察を提供します。非常に興味深い内容であり、物理学や哲学、AI技術に興味のある人々にとっては、新たな視点を提供することでしょう。この理論がさらに発展し、我々の宇宙理解に貢献することを期待してください。人気ブログランキングへ
2024年03月24日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー(GA230)創造し、造形し、形成する宇宙言語の協和音としての人間/Der Mensch als Zusammenklangdes schaffenden,bildenden und gestalteden Weltenwortes翻訳紹介(全12講)(翻訳者:yucca):目録Ⅰ 宇宙関係、地球関係及び動物界の人間との連関●第1講 1923年10月19日 ドルナハ ・エーテル的に鳥を見ると、鳥全体が一個の頭部である・鳥の翼と人間の思考・ライオンと胸部律動組織・牛:途方もなく美しい消化・鷲、ライオン、牛の統合としての人間・蝶・蛾の幼虫は太陽光を紡いで繭を織る・蝶の翅と人間の記憶・認識原理としての芸術●第2講 1923年10月20日 ドルナハ ・翼ー人間の頭部の形態化;太陽と外惑星の力の共同作用・ライオンー人間の律動組織は太陽の作用 牛ー新陳代謝組織は太陽と内惑星の作用 鷲、ライオン、牛の作用の合流としての人間・人間を一面化させようと誘惑する鷲、ライオン、雌牛の呼びかけ・雌牛の誘惑の声に捉えられると起こることー機械音の鳴り響く文明・ライオン、鷲の誘惑に捉えられると起こること・ライオン、ハイエナ、狼の寓話の現代的意味 一面化させようとする誘惑の呼びかけに対抗するための人間の箴言●第3講 1923年10月23日 ドルナハ ・霊的実質と物質的実質、霊的な力と物質的な力・上部人間、下部人間における霊的ー物質的な実質と力の相互浸透・実質と力の不規則な配分によって病気が起こる・人間の宇宙的カルマー人間は地球に対して負債がある・牛は地球にとって必要な霊的実質を地球に与える・鷲は地球にとって不要になった物質的実質を霊界に運び去る・地球存在を確実にする鷲と牛・牛と鷲の回りの元素霊たちの歓び・現代の一般的科学、認識では宇宙の意味は見出せない・鷲、ライオン、牛に示される宇宙的秘密II 宇宙現象と宇宙存在の内的連関●第4講 1923年10月26日 ドルナハ ・かつての地球の状態と、現在の地球状態に見られるその名残・土星ー太陽と月ー地球の区別・土星ー太陽的なものと昆虫界(特に蝶)との関連性・昆虫界は太陽作用と共に働きかける火星、木星、土星作用の賜物・植物界の発生:地球に委ねられた胚と金星、水星、月の作用・植物は地球に繋ぎとめられた蝶、蝶は宇宙に解き放たれた植物●第5講 1923年10月27日 ドルナハ ・蝶、鳥による地球素材の霊化・蝶は生きている間に、鳥は死ぬときに、 霊化した地球素材を宇宙にもたらす・蝶と鳥の世界を通じて地球は宇宙に霊化された素材を放射する・星は無機的なものではなく、生命あるもの、霊化されたものの結果・蝶は光エーテルに、鳥は熱エーテルに属する・鳥は呼吸を通じて体内の空気に熱を生み出す・蝶の呼吸と高等動物の呼吸・蝶は光の生きもの、鳥は空気の生きもの・コウモリは黄昏の動物、地球の重さを克服できない・蝶は宇宙の記憶、鳥は宇宙の思考、コウモリは宇宙の夢・コウモリは霊的実質を宇宙空間ではなく空気中に分泌する・コウモリの分泌の残存物を人間が吸い込むことにより 龍が人間に 支配力を行使する・ミカエル衝動によるその防御●第6講 1923年10月28日 ドルナハ ・地球進化においてもっとも古い被造物である人間・土星ー太陽ー月ー地球への進化のなかでの、人間の各部分と個々の動物種の発生 土星紀:人間の頭と蝶の原基、 土星紀の終わりから太陽紀前半:人間の頭ー胸組織と鳥類、 太陽紀後半:人間の呼吸組織とライオン 月紀前半:人間の腹部ー消化組織と牛 月紀後半:人間の消化器官と爬虫類、両生類・人間と動物の形成のされかたの違い・蝶、鳥の形姿は地上に下降してくる前の人間の霊的形姿を思い起こさせる・蝶コロナと鳥コロナが、霊界にいる人間を再受肉へと誘う・人間の胎児期の形成・人間の進化において内から外へと働くものが、動物においては 外から内へと働く・地球のエーテル要素のなかに生きる魚・地球のアストラル要素のなかに生きるカエル・人間の消化器官と両生類、爬虫類・円の集中と放射の図によるマクロコスモスとミクロコスモスの照応・植物界、鉱物界への架け橋・鉱物質のものの意味、霊人[Geistesmensch]と松果腺の脳砂III 植物界と自然元素霊たち●第7講 1923年11月2日 ドルナハ ・植物界に関わる目に見えない存在たち・根の精霊グノームと鉱物・グノームは植物を通じて宇宙の理念を知覚する・グノームと両生類・地上的なものへのグノームの反感・水の元素霊ウンディーネは植物の葉で働く・ウンディーネは空気素材を結合し分離する夢見る化学者・ウンディーネと魚・空気ー熱エレメントのなかに生きるジルフェ・ジルフェは鳥の飛翔とともに空気のなかで響く宇宙音楽を聴く・鳥のなかに自我を見出すジルフェは宇宙の愛の担い手・ジルフェは植物に光をもたらす・ジルフェとウンディーネの共同作用により原植物の理念形態が形成される・滴り落ちてくる植物の理念形態を地下でグノームが受け取る・唯物論的科学による植物の受精の説明の誤謬・熱ー空気のエレメントのなかに生きる火の精霊たち・火の精霊は宇宙の熱を集めて植物の花にもたらす・植物の受精は花ではなく、地下で行われる・植物の父は天、母は大地・グノームは植物の生殖の霊的な産婆・火の精霊は蝶、昆虫と一体化しようとする・蜂のオーラとなる火の精霊たち・下降する宇宙の愛ー供犠と上昇する地の密度ー重力の共同作用の現れしての植物●第8講 1923年11月3日 ドルナハ ・現代の人間からはエレメンタル存在たちを知覚する力が失われている・グノームは骨格のない下等動物たちを霊的に補足する・グノームの知性と注意深さ・入眠時の夢とグノームの知覚・ウンディーネはもう少し高等な動物たちを補足し、鱗、甲殻を生じさせる・夢のない眠りとウンディーネの知覚・ジルフェは本来頭である鳥を霊的に補足する・目覚めの夢とジルフェの知覚・火存在は蝶の体を補足する・グノームとウンディーネは下等動物を上つまり頭の方向に補足し、 ジルフェと火存在は鳥と蝶を下つまり四肢の方向に補足する・思考存在としての自己の観察と火存在の知覚・宇宙思考と火存在の領域・良い種類の元素霊と悪い種類の元素霊・悪い種類のグノームとウンディーネにより寄生生物がもたらされる・人間の排泄プロセスと脳形成、脳は排泄物の高次のメタモルフォーゼ・グノームとウンディーネの力による物質的な脳形成・グノームとウンディーネは破壊の力に関わり、ジルフェと火存在は構築する力に関わる・悪い種類のジルフェにより果実に毒が生じる、ベラドンナ・悪い種類の存在たちは領域をずらして作用する・火存在は果肉を焼き尽くし、これが行き過ぎると果実の核が有毒となる・ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァと元素霊の関係●第9講 1923年11月4日 ドルナハ ・人間と元素存在たちの知覚・体験の違い・地球の内部でのグノームの逍遙とその地質・鉱物体験・グノームは月に対して敏感であり、月相によって姿を変える・月の秘密と未来の地球に対するグノームの使命・グノームたちは過去から未来へと固体の構造を保持していく・海の微生物の死とウンディーネ・ウンディーネたちは燐光を発しつつ上昇し、高次存在たちの糧となることに至福 を感じる・ジルフェは死んでいく鳥たちが霊化した実質を高次世界に媒介する・ジルフェたちは稲妻となって霊化された実質と共に上昇し、高次存在たちに呼吸し尽くされることを欲する・火存在たちは、蝶が絶えず霊化する実質を熱エーテルにもたらし、地球の本来の景観を高次存在たちに観てもらうことを望む・地球と霊宇宙を媒介する元素存在たち・意識とともに前進せよと人間に勧告する元素霊たちの言葉・元素霊たちが自らの本質を表現する言葉・元素霊たちから人間に向かって響いてくる金言・宇宙は言葉から創り出された、という抽象的真理の具体的な意味・元素霊たちが発する宇宙言語のさまざまなニュアンスから人体組織の各部分が形成される・宇宙言語の協和音である人間IV 人体組織の秘密●第10講 1923年11月9日 ドルナハ ・真の人間認識の必要性・各進化期に人間に与えられたもの: 地球進化期…運動機能に関するもの、月進化期…新陳代謝に関するもの、 太陽進化期…律動(呼吸・循環)的経過に関するもの 土星進化期…神経・感覚に関するもの・人間と鉱物、植物、動物の関係:人間が摂取する鉱物的なもの、植物的なもの、動物的なものは体内でそれぞれ、熱エーテル、空気状のもの、液体状のものに移行する。固体的なものに入り込んでいくのは人間的なもののみ。・人間の呼吸、炭素の働き:炭素は炭酸となって吐き出されるときに人体内にエーテルを残していく・新陳代謝組織は常に人間を病気にする傾向を持つ・循環は絶え間ない治癒プロセス・呼吸のリズムは宇宙のリズムと一致し、循環リズムを制御する・土星と人体組織の照応:土星の内部は病む力、土星環は健やかにする力・これを眺める高次ヒエラルキアの満悦が神経ー感覚組織を貫いて精神的進化の力を形成する・真の合理的な治療学の体系は新陳代謝から出発すべきである・教育芸術と医学・全体的な人間認識から医学体系が生み出される必要性・人体おける栄養摂取経過、治癒経過、精神的経過の相互移行・血液のなかで起こるべきプロセスが他の場所に入り込むと炎症徴候が生じる・神経のなかで起こるべき経過が他の場所に入り込むと腫瘍形成への衝動が生じる・教育学における病理学的ー治療学的認識の必要性・教育芸術的治療において物質的なものの治癒作用を知ることの有益さ・銅をはじめ、鉱石形成の持つ治癒作用・外なる自然の治癒プロセスと人体組織の治癒プロセスの関係●第11講 1923年11月10日 ドルナハ ・人間の体内での代謝経過は、外部に観察される物理・化学的経過の継続ではない・体内に摂取された鉱物質のものは、いったん熱エーテルの形になって宇宙からの諸力を受け取り、再び硬化して人体形成の基礎となる・鉱物質のものが熱に変化されきらずに人体組織内に沈殿すると、たとえば糖尿病などの原因となる・外部から人体内に入ってくるものは、物質であれ力であれ、完全に加工され尽くされねばならない・外部の熱を体内で完全に変化させられないと風邪をひく・外界でのエレメンタルガイストの仕事が、人体内では高次ヒエラルキアに委託される・植物の根は地上的に満足し、花は宇宙に憧れる・植物界は自然界において人間の良心を映す鏡・植物の根は月がまだ地球のもとにあった時代に由来する・花的なものは月が地球を去ってから展開する・霊的ー宇宙的なものから地上的ー物質的なものが生まれる・人間が植物を食べることで植物の宇宙への憧れが満たされる・植物質は人体内で空気的なものになり、上下逆転する・人間に食べられると根は頭へと上昇し、花は下にとどまる・動物の消化においては植物は逆転できず、植物の宇宙への憧れは満足されずに地へと投げ戻される・動物の消化における、消化の流れに対抗する不安の元素霊の流れ・草食動物と肉食動物の死における不安・人智学はアジテーション的に何らかの食餌法を支持するのではなく、あらゆる食餌法を理解させるもの・子どもにはまだ鉱物を熱エーテル化する力が不足しているため、ミルクが必要・子どもは頭の内部から形成力を発達させるが、年取ってからは頭以外の生体組織全体が形成力を放射しなければならない・人間が頭の内部で行っていることを蜂は外部で行っている;蜂の巣は頭蓋冠の無い頭・人間が年取ってから形成力を促進しようとするときは、ミルクでなく蜂蜜が適する・「乳と蜜の流れる土地」という言葉に含まれる深い叡智●第12講 1923年11月11日 ドルナハ ・物質的、自然的人体組織と霊的(精神的)道徳的なもの・人類の道徳的ー精神的(霊的)なものの源泉:人間理解と人間愛・今日、精神的(霊的)なものは単なる抽象思考として語られる・物質界、自然界にあるすべてのものは、霊的世界に関する文字・人間の(物質的)形姿は、霊的に観て道徳的冷たさと憎悪から構築されている:道徳的冷たさは人体組織を固く構成し、憎悪は血液循環を引き起こす・人間の魂には道徳的熱(暖かさ)、人間愛への萌芽があるが、下意識には道徳的冷たさと憎悪が潜んでいる:現代文明との関係・死の門を通過していくとき、人間は冷たさと憎悪の結果を携えていく・今日の一般的な社会生活に見られる道徳的な熱と愛の欠如・人間が携えてきた冷たさと憎悪の結果を負担する高次ヒエラルキア存在たち:第三ヒエラルキアが冷たさに由来するもの、次いで第2ヒエラルキアが憎悪に由来するものを取り除く・人間の形姿は純粋に霊的なもの:単なる物質的なものを人間の形姿に保つのは霊的なもの・死後霊的世界でこの形姿は徐々に頭の部分から溶解していき、第一ヒエラルキアのもとで完全に変容する・第一ヒエラルキアのもとでの霊形姿の形成:四肢であったものが未来の頭の原型となる・脳だけでなく、手足で思考することでカルマを追求することができる・人間の動きとともに、その人間の道徳的全体が運動している・死後の生の後半における新たな形姿の形成プロセス:第二、第三ヒエラルキアは死後の生の前半に人間から取り出したものから、胸器官、四肢代謝器官の原基を形成する・人間の物質的本質と周囲の物質的自然との違い・人間と結びついているヒエラルキアの営み・新たな人間形姿形成のために使い果たされなかった人間無理解と人間憎悪の力の残余、その帰結としての文明の癌形成、潰瘍形成・寄生生物に冒された生体組織のような現代文明:人間との生きた結びつきを持たない思考・現代文明に上から下降してくる霊的なものは人間を通じて有毒となる:下からの寄生性と上からの毒性・文化の病の診断と治療法・人間の心と心情から生み出される新たな文明の必要性:文化の病の治療としてのヴァルドルフ教・真の文化の覚醒衝動としての人智学参照画:ルドルフ・シュタイナーの講演人気ブログランキングへ
2024年03月24日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第九講「芸術の使命」(1910年5月12日) この冬のシリーズにおける最後の講義は、人間の内的な生活から湧き出す最も偉大な宝物に満ちた、あの魂の生活の領域に捧げることにしましょう。私たちは、人間進化における芸術の本性と意義について考察したいと思います。皆さんにご理解いただきたいのは、芸術の領域はあまりに広範にわたるために、ここでは詩の分野に限るとともに、この分野において人間の精神が達成した最高のものだけを考察する時間しかないということです。さて、誰かが次のように言うかも知れません。「この冬の連続講義は人間の魂の様々な側面に関するものであり、その中心課題は、精神世界との関連において、真実と知識を求めるというものであった。では、これらの探求は、人間の活動の中でも、とりわけ美の要素に表現を与えようとする努力とはどのような関係があるのか。」と。そして、私たちの時代には、真実と認識に結びついたあらゆるものが、芸術的な活動が目指すものとは遥かに、遥かにかけ離れているという観点をとるのは容易なことかも知れません。今日、広く信じられているのは、科学のすべての分野においては、論理と実験の厳密な規則に従わなければならないのに対して、芸術的な仕事では、心と想像力の自発的な思いつきにしたがうということです。ですから、私たちの同時代人の多くは、真実と美とは何も共通したものを持っていないと言うかも知れません。にもかかわらず、芸術的な創造の領域における偉大な指導者たちは、真の芸術とは、知や認識がそうであるのと同様に、人間存在の深い源泉の中から流れ出してくるべきものであると絶えず感じてきたのです。ひとつの例をあげてみましょう。もっとも、私たちは美と真実の両方を探求したゲーテに目を向けるだけなのですが、彼は若い頃、あらゆる可能な方法を用いて、世界についての知識を獲得し、存在の偉大な謎に対する答えを見出そうと苦闘しました。あこがれの理想を秘めた国に彼を導くことになるイタリア紀行の時代の前には、彼はワイマールの友人たちとともに、例えば、人生におけるすべての現象の中に統一的な実質を見出そうとした哲学者スピノザを研究することによって真実を追求する道を進んでいました。神の考えについてのスピノザの論文はゲーテに深い感銘を与えました。メルクやその他の友人たちとともに、彼はスピノザの中に、あらゆる周囲の現象を通して語る声のようなもの、存在の源泉をほのめかすような何か-彼のファウスト的なあこがれをどうにかして癒すことができそうな考えを聞くことができる、と信じていました。けれども、ゲーテは、あまりに豊かな魂に恵まれていたために、概念的、分析的なスピノザの仕事から、真実と知識に関する満足のいく像を得ることはできませんでした。このことに関して彼が感じていたこと、彼の心が希求していたものが最もはっきりと現れるのは、彼が偉大な芸術作品に接し、その中に古代の芸術の名残をとらえた彼のイタリア旅行に私たちがついて行った、と仮定したときでしょう。彼はそれらの作品の前で、スピノザの考えから引き出そうとしてかなわなかった感情を経験したのです。こうして、彼はワイマールの友人たちに次のような手紙を送りました。「ひとつだけ確かなことがある。古代の芸術家達は、ホメロスその人と同じように、自然についての知識と、何が表現され得るのか、それはどのように表現されるべきなのか、についての確かな考えを有していたということだ。残念なことに、最高の段階にある芸術作品はあまりにも少ない。けれども、それらについてよく考えてみるとき、人が望むことができるのは、それらを正しく知り、そして、その前から静かに去る、ということだけだ。これらの卓越した芸術作品は自然の最も気高い産物として人間の手により、真の自然法則にしたがって創造されたものだ。あらゆる思いつきや単なる想像の産物は消え失せる。そこには必然があり、神があるのだ。」参照画:Baruch Spinoza ゲーテは、これらの最高の段階にある芸術作品が、それらを創造した偉大な作家たちによって、彼らの魂の中から、自然そのものが従うところの法則と同じ法則にしたがって取り出されたということを見極めることができたと信じていました。このことが意味するのは、自然法則に関するゲーテの観点においては、鉱物、植物、そして動物界において作用しているものが、人間の魂の中で、新しい段階に引き上げられ、新しい力を付与される、そのため、それらがその魂の中で十全に表現されるようになるということに他なりません。ゲーテはこれらの芸術作品の中にも自然の法則が働いていると感じ、そのため、ワイマールの友人たちに、「あらゆる思いつきや単なる想像の産物は消え失せる。そこには必然があり、神があるのだ。」と書き送ったのです。ゲーテは、そのような瞬間に、最高度に表現された芸術は知や認識と同じ源泉からやって来るという考えに心がかきたてられるのですが、私たちは、彼が、「美とは、そうでなければ永遠に隠されたままに留まるであろう自然の秘密の法則が表現されたものである。」と断言するとき、そのことが真実であることを、彼がいかに深く感じていたかを知るのです。こうして、ゲーテが芸術の中に見るのは、認識に関するその他の分野における探求の中で見出されたものを、それ自身の言葉によって確かなものにするところの自然法則の顕現です。さて、ゲーテから離れ、ある使命をもって芸術を探求したひとりの個性、芸術を通して何か存在の源泉に関係があるものを人類にもたらした現代の人物に目を向けるならば、もし、リヒアルト・ワーグナーに目を向けるとすれば、私たちは、彼が芸術的な創作の本性と意義を自分で明らかにしようとした彼の著作の中に、真実と美の間の内的な関係について、多くの同様の示唆を見出します。例えば、ベートーベンの第九交響曲についての著作の中で、彼は、これらの音が何か別の世界から現れたようなもの、何か単に理性的あるいは論理的な言葉で把握し得るものとは全く異なるものを含んでいると言います。芸術を通して顕現するこれらのものについて、確かに言えることが少なくともひとつあります。それは、それらが確信的な力を持って魂に働きかけるということ、それを前にしては、すべてのただ単に理性的あるいは論理的な思考は無力であるような確信、つまり、それらが真実であるという確信を私たちの感情に浸透させるということです。ワーグナーは、交響曲という音楽に関する著作の中でも、混沌が秩序づけられ、調和がもたらされた太古の時代、つまり、そのような感情を反射するためのいかなる人間の心もまだ存在しなかった時代の創造行為へと赴く感情、それを現出させるための器官として、それらの楽器があるかのように、何かがそこから鳴り響いてくる、と言います。こうして、ワーグナーは、芸術の顕現の中に、知性によって獲得される知識と同等の立場に立つことができるような神秘的な真実を見たのです。ここで何か別のことを付け加えることができるかも知れません。私たちが偉大な芸術作品を精神科学の意味で知るようになるとき、私たちは、それらが、それら自身、人間による真実の探求の顕現を私たちに伝えていると感じます。そして、精神科学者は、彼自身、このメッセージに内的に関連していると感じるのです。実際、彼が、自分は今日の人々があまりにも軽々しく受け入れるいわゆる精神の顕現ではなく、そのメッセージにより親密に関連していると感じると言ったとしても、それは誇張ではありません。では、真に芸術的な個性がこの種の使命を芸術に帰属させ、一方、精神科学者がこれらの偉大な芸術の神秘的な顕現にあれほど強く心引かれるように感じるというのは何故でしょうか。私たちは、この冬の連続講義を通して私たちの魂の前にやって来た多くのことがらを統合することによって、この疑問に対する答えに近づくことになります。もし、私たちが、この観点から、芸術の意義と働きを探求すべきであるならば、人間的な意見や知性の屁理屈をもってそうするべきではありません。私たちは、人間や世界の進化との関連で、芸術の発達を考察しなければなりません。芸術自体に、その人類にとっての意義を語らせるようにするのです。もし、私たちが、芸術のはじまり、芸術が詩という外観をとって人間の間に初めて現れたときにまで遡ろうとするのであれば、私たちは、通常の考え方にしたがって、本当にはるかに遡らなければなりません。ここでは、ただ現存する文書が私たちを連れていくことができる程度の過去にまで遡ることにしましょう。私たちはしばしば伝説的な人物と見なされるホメロス、その仕事がふたつの偉大な叙事詩、イリアスとオデッセイによって私たちのもとに伝わっているギリシャ詩の創始者にまで遡ることにします。これらふたつの詩の作者、あるいは作者たち、何故なら、今日はこの問題に立ち入らないので誰であったにしても、特筆すべき点は、両方の詩が全く非個人的な調子で始まるということです。おおミューズ、アキレスの怒りを歌え・・・という言葉で、最初のホメロスの詩、イリアスは始まり、そして、おおミューズ、大いに旅する男の詩を歌え・・・というのが、第二のホメロスの詩、オデッセイの始まりの言葉です。ですから、その作者は、彼の詩をより高次の力に負っているということを示そうとしているのです。そして、私たちが、彼にとって、この高次の力とは象徴的なものではなく、現実的で客観的な存在であった、ということに気づくためには、ほんの少しホメロスを理解しさえすればよいのです。もしこのミューズへの祈りが現代の読み手にとって何の意味もないとすれば、それは彼らが、ホメロスの詩のように非個人的な詩がそこに由来するところの経験を、もはや有していないからなのです。そして、もし、私たちが初期の西洋詩におけるこの非個人的な要素を理解しようとするならば、私たちは次のように問わなければなりません。それ以前には何があったのか。それはどこから生じたのかと。私たちが人類の進化について語るとき、人間の魂の力は千年紀の間に変化した、ということを何度も強調してきました。遥かな過去の時代、外的な歴史は到達することができないけれども、精神科学的な探求には開かれている時代においては、人間の魂は夢のような原初の超感覚的能力を付与されていました。人間が後の時代にそうなったように、あまりに深く物質的な存在性の中に横たえられるようになる以前の時代には、彼らは彼らの周囲のいたるところで、精神の世界を現実のものとして感知していたのです。私たちはまた、太古の超感覚的能力は、今日、達成されることができるような意識的で鍛錬された超感覚的能力とは異なっていたということを指摘しました。と申しますのも、後者は魂の生活における確固とした中心点、それによって人間が自分自身を自我として把握する中心点の存在と結びついているからです。私たちが現在有しているようなこの自我感情は、長い時間をかけて徐々に発達してきたもので、遥かな過去には存在していなかったのです。けれども、正にこのことのゆえに、つまり、人間がこの内的な中心点を有していなかったがゆえに、彼の精神的な感覚が開かれていたのであって、彼は、その夢のような、自我とは無縁の超感覚的な能力を持って、遥かな過去に彼の真の内的存在がそこから現れたところの精神的な世界を覗き見ていたのです。私たちの物理的な存在性の背後にある諸力の力強い像、夢のような像が彼の魂の前に現れました。この精神的な世界の中で、彼は、彼の神々とその間で演じられる行為やできごとを見ました。そして、今日的な研究は、国によって様々に異なる神々の物語が単によく知られた想像の産物であると推定する点において、全く間違っています。遥かな過去にも、人間の魂はちょうど今日と同じように機能していた、ただし、物語に登場する神々を含めて、今日よりも物事を想像する傾向が強かったと考えるならば、それは全くの想像の産物であり、想像力が豊かなのはそのように信じる人たちの方です。太古の昔の人々にとっては、彼らの神話の中で記述されたできごとは現実だったのです。神話、英雄伝、そして童話や伝説でさえも人間の魂の中にあった太古の能力から生まれました。このことは、人間が、今では自分自身の中で、自分自身を所有しながら生きることを可能にしているところのしっかりとした中心点をまだ獲得していなかったという事実と関連しています。遥かな昔には、彼は、後にそうすることができるようになるようには、彼自身を彼の自我の中に、つまり彼の環境から切り離された彼の魂の狭い境界内に閉じこめることができませんでした。彼は、彼の環境の中に、自分がそれに属していると感じながら生きていたのですが、現代人は、それから独立している、と感じているのです。そして、ちょうど今日の人間が、彼の生命を支えるのに必要な物理的な力が彼の肉体的な組織に流れ込み、また流れ出すということを感じることができるように、太古の人間は、彼の超感覚的な意識をもって、彼が偉大な世界の諸力との内的な交換の中で生きることができるように、精神的な諸力が彼の中に流れ込み、そして流出しているということに気づいていました。そして、彼は次のように言うことができました。「何かが私の魂の中で起こるとき、私が考え、感じ、あるいは意志するとき、私は孤独な存在ではない。私は私の内的な視界に現れる存在たちからやって来る諸力に向かって開かれているのだ。彼らは彼らの力を私に送り込むことによって、私に考え、感じ、意志するように促す。」と。まだ精神世界の中に横たえられていたときの人間はこのような経験を有していました。彼は精神的な力が彼の思考の中で活動している。彼が何かを成し遂げるときには、神的精神的な力が彼らの意志や目的を彼の中に注ぎ込んでいる、と感じていました。そのような太古の時代には、人間は、自分のことを、精神的な力がそれら自身を表現するための器であると感じていたのです。ここで私たちは過去へと遥かに遡った時代を振り返っているのですが、この時代というのは、あらゆる種類の中間的な段階を経て、正にホメロスの時代まで続いていました。ホメロスがいかに人類の太古の意識に引き続き表現を与えていたかを見極めるのは難しいことではありません。イリアスの登場人物の何人かを眺めさえすればよいのです。ホメロスは、ギリシャとトロイの大いなる戦いを描くのですが、どのようにしてそれを描くのでしょうか。当時のギリシャ人にとって戦いとは何を意味していたのでしょうか。ホメロスはその観点から話を始めるわけではありませんが、この戦いには、人間の自我に発する熱情や欲望、考えによって引き起こされるところの敵意以上のものがあったのです。この戦闘の中でぶつかっていたのはトロイとギリシャの単に個人的あるいは部族的な感情なのでしょうか。そうではありません。太古の意識とホメロスの意識とのつながりをしめす伝説が告げるのは、ヘラ、アテナ、アフロディテの三女神がいかに美の競演において競り合っていたか、そして、いかに人間であるトロイの王子パリスが美の鑑定家として、そのコンテストの判定をするように指名されていたかということです。パリスは世界中で一番美しい女を彼の妻にすると約束していたアフロディテに賞を与えました。その女とはスパルタ王メネラオスの妻ヘレネでした。パリスはヘレネを獲得するため、力ずくで奪い取らなければなりませんでした。この蹂躙への仕返しとして、ギリシャ人たちはその国がエーゲ海の遥か対岸にあるトロイ人たちに対して武装し、そこで戦闘が起こったのです。参照画:Helene_Paris_David 何故、人間の熱情がこのようにして燃え上がったのでしょうか。そして、何故、ホメロスのミューズが語ったようなできごとすべてが起こったのでしょうか。それらは人間世界における単に物理的なできごとだったのでしょうか。違います。ギリシャ人たちの意識を通して、私たちは、人間たちの戦いの背後に、女神たちの敵意が描写されているのを見るのです。当時のギリシャ人は次のように言ったことでしょう。「私は、人々を激しく対立させるようにした原因を物理世界の中に見出すことはできない。神々とその力がお互いに対峙するより高次の領域を見上げなければならないのだ。」と。当時、このようなイメージの中で見られた神的な力が人間どうしの衝突の中に働いていました。こうして、私たちは、詩という芸術における最初の偉大な作品、ホメロスのイリアスが人類の太古の意識から生まれてくるのを見るのです。ホメロスにおいては、太古の人類に自然な形でやって来た超感覚的な光景の残響が、後に現れた意識の立場から、韻文の形で提示されているのが分かります。そして、超感覚的な意識がギリシャ人にとって終焉を迎え、ただその残響だけが残った最初の時代を探すとすれば、それは正にこのホメロスの時代だったのです。太古の人間は次のように言ったことでしょう。「私の神々が戦っている、私の超感覚的な意識の前に横たわる精神世界で。」と。ホメロスの時代には、このように言うことは既に不可能でしたが、それについての生き生きとした記憶が保持されていたのです。そして、ちょうど太古の人間が、そこに自分の存在を有していた神的な世界から霊感を受けていると感じていたように、ホメロスの叙事詩の作者は、その同じ神的な力が彼の魂の中で支配していると感じていました。ですから、彼は次のように言うことができたのです。「私に霊感を授けるミューズが内的に語っている」と。こうして、ホメロスの詩は、もし、それらが正しく理解されるならば、太古の神話と直接的な関係にあることが分かります。この観点から、私たちは、ホメロスの詩的な想像力の中に、古い超感覚的な能力に代わるような何かが生じているのを見出すことができます。支配する宇宙の力が、直接的な超感覚的視界を人間から引き上げ、その代わりに、魂の中に同様に生きることができ、それに形成的な力を授けることができるような何かを彼に与えたのです。詩的な想像力は失われた太古の超感覚的能力の代償なのです。さて、何か別のことを思い出してみましょう。良心についての講義の中で、私たちは古い超感覚的な能力の衰退が色々な国々で、様々な時代に、全く異なった仕方で起こったのを見ました。東方においては、古い超感覚的な能力は比較的後の時代まで持続しました。西方のヨーロッパの人々の間では、超感覚的な能力はそれほど広くは存在していませんでした。それらの人々の中では、強力な自我感情が前面に出てきていた一方、他の魂の力や能力はまだ比較的未発達だったのです。この自我感情は、ヨーロッパの異なる地域で非常に様々な仕方で現れました。北と西では異なっていましたが、特に、南においては異なっていました。キリスト教以前の時代、それはシシリアとイタリアにおいてもっとも強力に発達しました。東方の人々が長い間自我感情を持たないままに留まっていたのに対し、ヨーロッパのこれらの地域には、古い超感覚的能力が失われていたため、特別に強い自我感情を持った人々がいたのです。精神的な世界が人間から外的に失われるのに比例して、彼の内的な自我感情が点火するのです。こうして、ある時期、アジアの人々の魂と、ここで考察しているヨーロッパの各地に住む魂との間には大いなる違いがある、ということにならざるを得ませんでした。彼方のアジアにおいては、いかに宇宙の秘儀が依然として偉大な夢の像として魂の前に生じるかが、そして、いかに神の行為が人間の精神的な目の前で展開するのを目撃することができるかが分かります。そして、私たちは、そのような人間が語ることができるものの中に、何か世界の根底に横たわる精神的な事実に関する古い説明のようなものを認めることができます。アジアにおいては、古い超感覚的な能力が、それに代わるもの、すなわち想像力に取って代わられたとき、これは特に視覚的な象徴を像の形で生じさせました。西方の人々の間では、特にイタリアやシシリアにおいては、それとは異なった能力、しっかり根付いた自我から生じてくる能力が、一種の力の過剰、すなわち、いかなる直接的、精神的な視界も伴わないけれども、見えないものに到達したいというあこがれによって浸透され、魂から発生する熱情を生じさせたのです。ですから、ここには、いかなる神の行為の説明も見出されません。何故なら、そのようなことはもはや明らかではなかったからです。けれども、魂が、語りと歌の中に表現される熱烈な献身をもって、ただあこがれることができるだけの高みを希求するとき、古い超感覚的な意識が翳った後、今や見ることができなくなった力に向かう原始的な祈りと賛美歌が生まれました。それらの中間に位置する国、ギリシャにおいて、これらふたつの世界が出会います。そこには両方の側から刺激を受けた人々が見出されます。東方からは像のような視界が、西方からは見ることができない神的-精神的な力に捧げる献身的な賛美歌に霊感を与えるところの熱情がやって来ます。そのふたつの流れがギリシャ文化の中で混ざり合ったことによって、紀元前八世紀から九世紀と考えられるホメロスの詩から、三、四百年後のアイスキュロスの仕事へと継続する流れが可能になったのです。確かにアイスキュロスは十全なる東方の洞察力に向かって、つまり、神の行為とその人間への影響に関する古い超感覚的な視界の残響としてホメロスの中に見出されるような確信させる力に向かって開かれた人物として私たちの前に現れるわけではありません。この残響はいつでも非常に弱いものでしたが、アイスキュロスの中では、それはあまりにも弱かったので、彼は太古の超感覚的な視覚が人間にもたらしていた神々の世界に関する像のような視界に対する一種の不信を感じるようになっていたのです。ホメロスに関しては、かつて人間の意識が、物理世界における人間の熱情や感情の相互作用の背後に立つ神的精神的な力についての視界を有していたということを彼がよく知っていたのが分かります。したがって、ホメロスは単に人間の間の衝突を記述するのではありません。ゼウスとアポロの干渉に人間の熱情が巻き込まれ、そして、その影響はできごとの推移の中で明らかになります。それらの神々とは詩人が彼の詩の中に持ち込むところの現実なのです。アイスキュロスに関しては、何と異なっていることでしょうか。人間の自我を特に強調し、人間の魂を内的に分離するような西方からの影響の流れが、彼に絶大な影響力を及ぼしていたのです。彼が自我から行動を起こし、神的な力の流入からその意識を開放し始めた人間を描写した初めての劇作家になったのはこの理由によります。アイスキュロスにおいては、ホメロスの中に見られる神々の代わりに、たとえ初期の段階に立っていたとはいえ、行動において独立した人間が登場します。劇作家として、アイスキュロスはこの種の人間を物事の中心に据えます。叙事詩は東方からやって来る像的な想像力の影響下に現れなければなりませんでしたが、個人的な自我を強調する西方の影響は行動する人間が中心となる劇を生じさせたのです。例えば、オレステスを取り上げてみましょう。彼は母殺しの罪を犯し、その結果として復讐の女神を見ます。そうです、これはまだホメロスです。ものごとはそれほど簡単には過ぎ去りません。アイスキュロスは、かつて神々が像の姿で見えた、ということをまだ知っているのですが、まさにその信念を捨て去ろうとするところに来ているのです。特徴的なのは、ホメロスにおいては充分にその力を発揮したアポロが、オレステスを扇動して彼の母を殺させるにもかかわらず、その後ではもはや彼の側に立つ権利を有していない、ということです。人間の自我がオレステスの中で身じろぎを始め、それが支配的になる様子が私たちに示されます。アポロに不利な裁決が下され、彼は拒絶されます。そして、私たちは、オレステスに対する彼の力の行使がもはや完全ではないのを見るのです。ですから、アイスキュロスはプロメテウスを、つまり、神々の圧倒的な力にタイタンのように立ち向かい、神々からの人間の解放を象徴する神的な英雄を劇化するための正当で適切な詩人であったのです。こうして、私たちは、東方の像的な想像力を有するアイスキュロスの魂に、いかに西方からやって来る自我感情の目覚めが混ざり合っているかを、そして、いかに劇がこの統合から生まれたかを見るのです。そして、完全に精神科学的な探求によって見出されたものを、伝統が素晴らしい仕方で確認するのを見るのは本当に興味深いことです。ひとつの注目すべき伝統が、部分的とはいえ、アイスキュロスからある秘儀の秘密を暴露した罪を免じます。ただし、彼は、そのようなことはできるはずがなかったと応えるでしょう。何故なら、彼はエレウシスの秘儀に通じてはいなかったのですから。確かに、彼には、ホメロスの詩がそこに起源を有するところのテンプルの秘密から発するいかなるものをも示すつもりは全くなかったのです。事実、彼はその秘儀から少し離れた位置に立っていました。他方、彼がシシリアのシラクサで人間の自我の出現に関する秘密の知識を得ていた、という物語が伝えられています。オルフェウスの信者たちが、もはや見ることができず、ただあこがれることができるだけの神的-精神的な世界に向けた古い形態の叙情詩、賛美歌を培っていた地域においては、この自我の出現は特別な形態を取っていました。芸術が一歩前進したのは、このようにしてでした。私たちは、それが太古の真実から自然に現れ、人間の自我へと続く道を見出すのを見ます。人間が、主として外的世界に生きた後、彼自身の内的な生活を自分のものとしていたことから、ホメロスの詩で姿を取ったものたちがアイスキュロスの劇中の人格となり、叙事詩と並んで劇が現れたのです。こうして、私たちは、古代の真実が芸術という別の形態を取って生き続けるのを、そして、太古の超感覚的な能力により達成されたものが詩的な想像力によって再構成されるのを見ます。そして、芸術によって太古の時代から保存されたものであれば何であれ、人間の個性に、つまり、自分自身に気づくようになった自我に適用されたのです。さて、私たちは、13、14世紀のキリスト教の時代まで、年代をずっと下ることにしましょう。ここで私たちは、自我がそれ自身の努力で神的-精神的な世界へと上昇するとき、それが到達することができる領域へと非常に印象的な仕方で私たちを導く中世の偉大な人物に出会います。私たちはダンテに至ります。その「神曲」(1472年)はゲーテによって読まれ、再度読まれました。彼に対するその影響は非常に大きく、知り合いがその新しい翻訳を彼に送ったとき、彼は詩の形でその送り主に感謝の気持ちを表しました。 大いなる感謝は もう一度この本を新たにして私たちにもたらす彼に 栄光に満ちた仕方でその本が沈黙させるのは 私たちのすべての探索や不満だ 芸術はどのようにアイスキュロスからダンテへと発展したのでしょうか?ダンテはどのようにして私たちをその三つの世界、地獄、煉獄、天国-私たちの物理的な存在性の背後に横たわる世界-へと導くのでしょうか。ここで私たちが見ることができるのは、いかに人間の進化を指導する基本的、精神的な衝動がそれと同じ方向で働き続けてきたかです。全く明らかなことは、アイスキュロスがまだ精神的な力との関係を保っていた、ということです。プロメテウスはゼウス、ヘルメス、等々の神々と直面しますが、このことはまたアガメムノンにも当てはまります。私たちは、これらすべての中に、太古の超感覚的な能力の残響を認めることができます。ダンテに関してはかなり異なっています。彼が私たちに示すのは、ただ彼自身を彼自身の魂の中に沈め、そこに眠る力を発達させるとともに、この発達のためにあらゆる障害を克服することを通して、彼が言うように、人生半ばで、この意味は35才のときということなのですが、いかに精神的な世界をのぞき見ることができたかということです。古い超感覚的な能力を付与されていた人間たちは彼らの眼差しを彼らの精神的な環境に向け、アイスキュロスはまだ古い神性を考慮していたのに対し、ダンテの中には、自分自身の魂の中に降り立ち、その個性とその内的な秘密の内に完全に留まる詩人が見られます。彼は、この個人的な発達の道を追求することによって精神的な世界に入り、そして、そのことによって、「神曲」の中に見出される力強い像の中でそれを示すことができるようになります。ここで、ダンテの魂は、彼の個性とともにあって全く孤独であり、外的な顕現には無関心です。ダンテが伝統の中から、古い超感覚的能力の成果を引き継ぐことができた、などとは誰も想像できないでしょう。ダンテが頼りにするのは、その唯一の手助けとしての人間個性の力強さによって、中世において可能となった内的な発達です。そして、彼は、私たちの前に、目に見える像として、ここでしばしば強調されること-人間は彼の超感覚的な視界を曇らせ、あるいは暗くするところのあらゆるものにうち勝たなければならないということを示すのです。ギリシャ人たちが、まだ精神世界の中に現実を見ていたのに対し、ダンテはそこに、その像に克服されるべき魂的な力の像のみを見ます。高次の発達段階から自我を引き下ろそうとする感覚魂、悟性魂、そして意識魂のあの低次の力とはそのようなものです。その反対の善なる力とは、既にプラトンによって示された、意識魂にとっての叡知、悟性魂にとっての自立的な勇気、感覚魂にとっての中庸です。自我が、これらの善なる力を獲得する発達を通して前進するとき、それは精神世界へと通じるより高次の魂の経験へと近づきます。しかし、まず、障害が克服されなければなりません。中庸は放縦と貪欲に対抗して働きます。そして、ダンテは、いかにこの感覚魂の影の面に立ち向かうかを、そして、それにいかにうち勝つかを示します。彼はそれを雌狼として記述します。次に、いかに悟性魂の影の面、ライオンとして記述されるところの非常識な攻撃性が、それに対応する徳、自立的な勇気によって克服されるかが示されます。最後に、私たちは、叡知、すなわち意識魂の徳へとやって来ます。高みへと努力することなく、単なる抜け目なさやずるがしこさとして世界に適用される叡知はおおやまねことして描写されます。「おおやまねこの目」とは精神世界をのぞき見ることができるような叡知の目ではなく、単に感覚の世界だけに焦点を合わせる目です。ダンテは、いかに彼が内的な発展を妨害する力から身を守るかを示し、そしてその後で、いかに物理的な存在性の背後に横たわる世界に上昇するかを記述します。私たちは、ダンテの中に、自分自身を頼りとして、自分自身の中を探求し、自分自身の中から精神世界へと導く力を引き出す人間を見ます。彼において、詩は、人間の魂をしっかりと把握し、人間の自我とより密接な関係を持つようになります。ホメロスは、その本性が、実際、彼自身が感じていたように、神的-精神的な力の行為へと織り込まれていたために、「ミューズよ、私が語るべき物語を歌え」と言います。彼の魂とともにある孤独なダンテは、彼自身の内から、彼を精神世界へと導くであろう力を引き出して来なければならないということを知っています。私たちは、いかに想像力を外的な影響に依存させることがますます不可能になるかを見ることができます。この点で、私たちは単なる意見に関わっているのではなく、人間の魂に深く根ざした力に関わっているのだということがちょっとした事実によって示されるでしょう。ゴットリープ・フリードリヒ・クロプストクは信心深い人間であり、そして、ホメロスさえも凌ぐ奥深い精神でした。彼が望んだのは、ホメロスが古代のために為したことを現代のために行うという意識的な意図を持って、聖なる叙事詩を書くということでした。彼はホメロスのやり方を生き返らせようとしたのですが、彼自身を欺くことなくそうしようとしました。そのため、彼は「私のために歌え、おおミューズ」と言うことができず、その代わり、彼の「メシア」を、「歌え、不死の魂よ、罪深き人間の救済を」という言葉で始めなければなりませんでした。こうして、私たちは、いかに人間たちの間で芸術的な創造における発達が実際に起こったかを見るのです。さて、ダンテから別の偉大な詩人、シェークスピアにまでさらに数世紀、大きく時代を下りましょう。ここでもまた、私たちは、進歩という意味で、顕著な一歩が踏み出されるのを見ます。私たちはシェークスピアを批評しようというのでも、ある詩人を別の詩人の上に置こうというのでもなく、ただ、必要で合法的な前進を指し示す事実に関わろうとしているのです。ダンテに関しては、何が私たちに特別な印象を与えたのでしょうか?彼はそこに、精神世界についての彼自身の顕現とともに一人で立ち、そして、彼自身の魂の中から彼のところにやって来た偉大な経験について記述します。皆さんは、もし、彼が彼の見たものを、五、六種類以上の異なる方法で記述していたとしても、彼がそのように見たところの真実にあれほど影響力のある印象を与えていただろうと想像できますか。ダンテが彼自身をそこに置いた世界とは、一度だけしか記述できないようなものであるとは感じませんか。実際、ダンテはそのようにしました。彼が記述する世界は、ある男が自分にとっての精神世界であるところのものと一体であると自分自身で感じた瞬間におけるその男の世界なのです。私たちはここで次のように言わなければなりません。ダンテは彼自身を、人間的な個性の要素の中に、それが彼自身のものであるに留まるような仕方で沈めた、と。そして、彼はこの人間的-個性的な側面をあらゆる方向から考察することに取りかかるのです。一方、シェークスピアはあらゆる可能な個性、リア、ハムレット、デズデモーナを豊富に創造するのですが、精神的な目が純粋に人間的な性質や衝動とともに物理的な世界にある彼らを見るとき、それはこれらの個性の背後に、いかなる神的なものも直接的に感知することはありません。彼らの魂から思考、感情そして意志の形で直接やって来るものだけを私たちは期待します。彼らはすべて際だった個性たちですが、彼らの中に、ダンテは、自分自身を自分自身の個性の中に沈めるとき、いつでもダンテである、というのと同じ仕方で、シェークスピア自身を認めることができるでしょうか。いいえ-シェークスピアはさらに一歩先に進んだのです。彼は個人的な要素の中へとさらに突き進むのですが、ある個性の中ばかりではなく、もっと様々な個性の中へと突き進むのです。シェークスピアは、リア、ハムレットやその他の人物を記述するときにはいつでも、彼自身を否定します。彼は彼自身の考えを提示しようなどという気には決してなりません。何故なら、シェークスピアとしての彼は完全に消し去られているからです。彼は、完全に、彼が創造する様々な個性の中に生きているのです。ダンテによって記述される経験は一人の人間の経験です。シェークスピアが私たちに示すのは、きわめて多様な個性の中の内的な自我から生じてくる衝動です。ダンテの出発点は人間的な個性でした。彼はその中に留まり、そこから精神世界を探求します。シェークスピアは一歩先に進みます。彼もまた彼自身の個性から出発し、彼が描く個性たちの中に入り込むのですが、彼は彼らの中に完全に沈潜するのです。彼が劇化するのは彼自身の魂的な生活ではなく、彼が舞台の上で提示するところの外的な世界における登場人物たちの生活であり、彼らはすべて、彼ら自身の動機と目的を持ち、独立した人物として描かれます。こうして、私たちは、ここで再び、芸術がどのように進化するかを見ることになります。芸術は人間の意識が自我感情に欠けていた遥かな過去に始まり、ダンテによって、自我そのものがひとつの世界になるように、個人的な人間を包含する段階に到達しました。その世界は、シェークスピアによって、別の自我たちが詩人の世界になるまでに広がりました。この段階が可能になるために、芸術は、そこからそれが湧き出してきたところの精神の高みを後にして、物理的な存在が活動する場所にまで下降しなければなりませんでした。そして、このことは正に、ダンテからシェークスピアへと移行するときに生じるのが見られるところのものです。この観点から、ダンテとシェークスピアを比べてみましょう。皮相的な批評家はダンテを説教ぶった詩人であると非難するかも知れません。ダンテを理解することができ、彼の作品全体とその豊かさに応えることができる人は誰でも、彼の偉大さは正に中世の叡知と哲学のすべてが彼の魂から語っているという事実に起因していると感じるでしょう。中世の叡知の全体が、ダンテの詩の力を付与されたそのような魂の発達にとって、必要な基礎だったのです。その影響は、最初、ダンテの魂に作用していたのですが、その後、彼の個性が世界へと拡張する中で再び明らかとなりました。中世における精神生活の高みを知ることなく、ダンテの詩作を正しく理解し、評価することはできません。私たちは、それを知るときにだけ、彼が達成したことの深みと巧みを評価できるようになるのです。確かに、ダンテは一段下降しました。彼は精神的なものをより低いレベルに落とそうとしたのですが、彼は、彼の先駆者の何人かが用いたラテン語ではなく、自国語で書くことによってそうしたのです。彼は精神生活の最も遥かな高みへと上昇するとともに、彼が生きた場所や時代の言葉と同じだけ深く物理世界の中へと下降します。シェークスピアはさらに下降します。彼の詩における偉大な登場人物たちの起源は、今日では、あらゆる種類の想像力溢れる思いつきによって取りざたされていますが、もし、詩が日常生活の世界へと。今でも、高みに位置するものによって、しばしば見下されるような世界ですが、このように下降したことを理解するとすれば、私たちは次のような事実を心に留めておかなければなりません。私たちは、シェークスピアを除いては、今日ではあまり高く評価されることのなさそうな俳優たちによって劇が制作されていたところの、当時のロンドン郊外にあった小さな劇場を思い浮かべなければなりません。どのような人たちがこの劇場に行ったのでしょうか?下層階級の人たちです。当時は、飲んだり食べたり、気に入らなければ卵の殻を投げつけたり、舞台にまでなだれ込んで、俳優たちが観衆のただ中で演技しなければならなかったような劇場に行くより、闘鶏やそれに似た見せ物にお金を出す方がファッショナブルだったのです。ですから、これらの劇は、多くの人が好んで想像するように、文化生活における上流階級の間で最初から喝采を浴びていたのではなく、最初は、ロンドンのきわめて下層の大衆の面前で上演されていたのです。せいぜい、変装してどこか人目に付かないたまり場に出かけるような独身息子たちが、たまにこの劇場に行ったかも知れませんが、それは尊敬すべき人々にとっては大いに不適当なことだったのです。このことから、私たちは、詩がもっとも品性のない領域にまで下ったのを見ることができます。シェークスピアの劇とその登場人物の背後に立っていた才能にとって、人間的なもので疎遠なものなど何もありませんでした。ですから、そこで起こったできごととは-外的側面から詳細に見ても、高地において、細い川として流れていた芸術が、通常の人間性の世界にまで下り、日常生活のただ中を流れる大きな川にまで広がったということです。そして、このことをより深く洞察する人であれば誰でも、シェークスピア劇に登場するような大いに個性的な性格の生き生きとした人物たちが現れるためには、気高く精神的な流れが、いかにより低いレベルにまで引き下げられる必要があったかということを理解するでしょう。さて、私たちは私たち自身の時代にもっと近づくことにしましょう-ゲーテにです。彼を彼が創作したものに、彼が彼の主著に取り組んでいた六〇年間にわたって、彼の理想や努力、そしてあきらめのすべてをその中に体現させたファウストという人物に関連づけてみましょう。世界の謎に対するより深い答えを求めて、認識の階梯を登りながら、彼の豊かな人生を通して、その最奥の魂において彼が経験したことのすべて、このすべてが、私たちが今日出会うようなファウストという人物の中に凝縮されているのです。ゲーテの詩劇という文脈の中で、ファウストとはいかなる人物なのでしょうか。ダンテについては、私たちは彼が記述するものを彼自身が見たものの成果として思い描くことができる、と言うことができます。ゲーテはそのようなものは何も見ませんでした。彼は、ダンテがその「神曲」についてそうするように、とりわけ厳粛な瞬間に特別な顕現があった、と主張したりはしません。ゲーテは彼が提示するところのものに内的に働きかけていた、ということが「ファウスト」のいたるところで示されます。そして、ダンテの元にやって来た経験が彼自身の一方的なやり方でのみ記述され得たのに対して、ゲーテの経験は、それらがより個人的なものではないと言えないにしても、ファウストの客観的な性格へと移し替えられたのです。ダンテは私たちに、彼のもっとも親密で個人的な経験を提示します。ゲーテもまた個人的な経験を有していたのですが、ファウストの行為や苦しみはゲーテがその人生において経験したものとは異なります。それらは、ゲーテが彼自身の魂の中で経験したことを自由に、そして詩的に変容させたものなのです。ダンテが彼の「神曲」と同一視され得るのに対して、ゲーテをファウストと同一視するためには、ほとんど文学史家を連れてこなければならないでしょう。ファウストは一人の個性ですが、シェークスピアが創作した個性たちと同じくらい多くのファウストに似た人物たちを創作し得たであろうと想像することは不可能です。ゲーテが彼の「ファウスト」の中で描き出した個性は、たった一度だけ創造され得るものなのです。シェークスピアはハムレットの他にもリアやオセロ等々を創造しています。確かに、ゲーテは「タッソー」や「イフゲーニア」も書きましたが、彼らとファウストとの差は明白です。ファウストはゲーテではなく、基本的に誰ででもあるのです。彼はゲーテのもっとも深いあこがれを体現しているのですが、詩に登場する人物としては完全にゲーテ個人からは引き離されています。ダンテは一人の男、つまり、彼自身が見たところのものを私たちの前に提示します。ファウストという個性は、ある意味で、私たちひとりひとりの中に住んでいるのです。このことは、詩がゲーテに至るまでに、はるかに進歩したことを示しています。シェークスピアが創造し得た人物たちは非常に個性的だったために、彼は彼自身を彼らの中に沈め、彼らの一人一人に際だった声で喋らせることができました。ゲーテはファウストという個性的な人物を創り出すのですが、ファウストは一人の個人ではなく、誰ででもあるのです。シェークスピアは、リア、オセロ、ハムレット、コルデリア等々の魂的本性の中に入っていきました。ゲーテはすべての人間の中にあるもっとも気高い人間的要素の中に入っていきました。このことによって、彼はすべての人間に適った代表的な個性を創造したのです。そして、この個性は、彼自身を詩人としてのゲーテ個人から引き離し、外的世界の中で、現実的、客観的な人物として私たちの前に立つのです。私たちが概観してきた道に沿った芸術のさらなる進歩とはそのようなものです。より高次の世界の直接的、精神的な知覚から出発して、芸術はますます大きく人間の内的生活を捉えます。それがもっとも親密に生じるのは、ダンテの場合のように、人間が自分自身だけに関わるときです。シェークスピアの劇においては、自我はこの内密性から歩み出て、他の魂の中に入っていきます。ゲーテの場合には、歩み出た自我はそれ自身をファウストに代表されるすべての人間の魂的生活に沈めます。そして、自我は、それ自身の魂的な力を発達させ、自らを別の精神性へと沈潜させることができさえすれば、それ自身から出て、別の魂を理解することができるのですが、そのようにして、ゲーテが、単に外的世界における物理的な行為や経験だけでなく、精神世界へとその自我を開きさえすれば、誰でも経験することができる精神的なできごとをも記述するように導かれたのは、芸術的な創造活動の絶えざる進歩と符合しています。詩は精神世界からやって来て、人間の自我の中に入りました。それは、ダンテにおいて、自我をその内的生活のもっとも深いレベルで捉えました。ゲーテにおいては、私たちは自我が再びそれ自身から歩み出て、精神世界への道を見出すのを見ます。太古の人類が有していた精神的な経験は「イリアス」と「オデッセイ」の中に反映されます。そして、ゲーテの「ファウスト」において再び現れた精神世界が人間の前に立ちます。私たちは、このようにして、「ファウスト」の偉大な終幕に、つまり、人間が深みへと下った後、彼の内的な力を発達させることによって、精神世界が再び彼の前に広がるように、その上昇への道を苦労して進むという終幕に相対するべきなのです。それは主旋律の合唱のようですが、どこまでも前進する形態を持ち、どこまでも新しいものなのです。精神的な視界に代わって人間に付与され、人間の天才達による滅ぶべき創造行為の中に形態を与えられた想像力が不朽の精神世界から響きわたります。不朽であるものから、ホメロスやアイスキュロスによって詩の中で創造された滅ぶべき登場人物たちが生まれました。詩は滅ぶべきものから不朽のものへと再び上昇し、私たちは「ファウスト」の最後の部分で歌われる神秘的な合唱を聞きます。 移ろいゆくものはすべて比喩にすぎない・・・そして、ゲーテが私たちに示すように、人間の精神の力もまた物理的な世界から精神的な世界へと再び上昇するのです。私たちは芸術的な意識が、代表的な詩人たちの中で、世界を大股で進んで行くのを見てきました。芸術はその根元的な認識の源泉である精神世界から現れます。精神的な視界は、感覚世界がますます広く注目を集め、それによって自我の発達を促すにつれてますます退きます。人間の意識は、世界進化の経過を追って、精神世界から自我と感覚の世界へと旅しなければなりません。もし、人間が外的な科学の目を通してのみ感覚の世界を探求するとすれば、彼はそれを科学的な言葉で、単に知性的に理解するようになるだけです。けれども、人間は、超感覚的な能力が消え去ったとき、その代わりとして、彼にはもはや知覚することができないものの一種の影のような反映を彼のために創り出す想像力を与えられました。想像力は人間と同じ道、すなわちダンテの場合のように、最終的に彼の自意識へと入っていく道にしたがわなければなりませんでした。けれども、人類を精神世界に結びつける糸は、芸術が下降して人間の自我の中に閉じこめられるときでさえ、断ち切られることはありません。人間は想像力を携えて彼の道を行くのです。そして、「ファウスト」の出現によって、私たちは精神世界が想像力から新しく創造されるのを見るのです。こうして、ゲーテの「ファウスト」は、芸術がそこに起源を有するところの精神的な世界に、人間が再び入って行くべき時代の始まりに位置しているのです。ですから、芸術の使命とは、高次の訓練によって精神的な世界に至ることができない人々のために、はるかな過去の精神性と未来の精神性とを結びつけるべき糸を紡ぐ、ということなのです。実際、芸術は既に、「ファウスト」の第二部において見られるように、精神的世界についての視界を想像力の中で与えることができるまでに前進しています。人間は、彼が精神的な世界に再び入り、その意識的な認識を獲得することができるようにする力を発達させることを学ばなければならない地点に立っている、ということについての示唆がここにあります。芸術は、想像力の助けを借りて、人間を精神的な世界へと導いただけでなく、十全なる自我意識に基づき、精神世界についての明晰な視界を持つということを前提とする精神科学への道を準備したのです。精神科学の仕事とは、芸術の領域から引いてきた例の中で見てきたように、あの世界・人間があこがれるあの世界への道を指し示すということであり、それはこの冬の連続講義の仕事でもあったのです。こうして、私たちは、いかに偉大な芸術家たちが、精神世界の反映こそ彼らが人類に提供すべきものであると感じてきた点において正当化され得るかを見ます。そして、精神世界の直接的な顕現がもはや可能ではない時代において、これらの顕現を仲介するというのが芸術の使命なのです。ですから、ゲーテは、昔の芸術家たちの作品について、「そこには必然があり、神がある」と言うことができたのです。それらは、そうでなければ決して見出されることはなかったであろう隠された自然の法則に光を当てます。そして、リヒアルト・ワーグナーもまた、第九交響曲という音楽の中に、別の世界-主として知的な意識には決して到達できないような世界の顕現が聞こえる、と言うことができました。偉大な芸術家たちは、彼らが、過去から現在、そして、未来に向けて、あらゆる人間の源泉であるところの精神を担っている、と感じてきました。ですから、私たちは、深い理解を持って、彼自身、芸術家であると感じていた一人の詩人(シラー)によって話された、「人間の尊厳は、あなたの手に渡された。」という言葉に同意することができるのです。私たちは、このようにして、人間進化の過程における芸術の本性と使命について記述し、芸術が、今日、人々が軽々しく想像するほどには、真実についての人間の感覚からかけ離れているわけではない、ということを示そうと試みてきました。逆に、ゲーテが真実についての考えと美についての考えを別の考えとして話すことを拒否したとき、彼は正しくそうしたのであり、彼の言葉を借りれば、神的精神的なものの必然的な働きという「ひとつの」考えがあり、真実と美とはそのふたつの顕現なのです。詩人やその他の芸術家の間ではどこでも、人間存在の精神的な基礎は芸術においてその言辞を見出す、という考えに対する同意が見出されます。あるいは、彼らの中には、芸術は、彼らの作品が精神世界からのメッセージを人類にもたらすであろうと信じることを可能にする、と皆さんに言うことができるような深い感情を有する芸術家たちがいます。ですから、芸術家が、その表現において、もっとも個人的であるときでさえ、彼らは、彼らの芸術が普遍的な人間のレベルにまで上昇させられ、そして、彼らの芸術の性格と顕現が、次のようなゲーテの神秘的な合唱によって語られる言葉を効果的なものにするとき、彼らは真の意味で人類のために語っているのだ、と感じるのです。 移ろいゆくものはすべて比喩にすぎない・・・そして、私たちは、私たちの精神科学的な考察の力の上に、次のような言葉を付け加えることができるかも知れません。芸術は、一時的で滅ぶべきものに、永遠で不朽なるものの光を吹き込むために必要なのだ。それが芸術の使命なのだと。人気ブログランキングへ
2024年03月23日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第八講「人間の良心」(1910年5月5日) 今日の講義を個人的な思い出から始めることをお許し下さい。私が若かった頃の経験で、たいして重要ではないように見えながら、後になってしばしば楽しい思い出としてよみがえってくるような種類のちょっとした経験です。私は大学で文学史の講義に出席していました。その講義は、レッシングの時代における文化生活の特徴についての考察から始まり、18世紀の残りの部分と19世紀の一部を含む時代における様々の文学上の発展についてさらに議論する、という意図をもっていました。彼の最初の言葉は大変印象的でした。レッシングの時代における文化生活に現れた主要な革新を特徴づけるために、彼は「芸術的な意識が審美的な良心を獲得した。」と述べたのです。彼がこのように言うことによって意図していたのは、今はそれが正当なものであったかどうかを問う必要はないのですが、おおよそ次のようなことでした。レッシングとその同時代人の努力に結びついていたところのすべての芸術的な考察や意図は、芸術を何か人生の単なる付加物あるいはその他大勢の単なる楽しみ以上のものにしたい、という深い熱望に浸透されていた。芸術はその名にふさわしく、人間のあらゆる存在形態における必須要素になるべきであった。偉大で実り多い人類の活動について語る声と協調し、聞くに値する人間の深刻な関心事のレベルにまで芸術を引き上げること、そのようなことがこの時代の先頭に立つ思索家たちの目的であった。審美的な良心がその時代の芸術と文学への道を見いだしていたということが強調されるとき、その講演者が言おうとしていたのはそのようなことでした。この指摘が色々な人の心の中に反映されるところの存在の謎を把握しようと努める魂にとって重要であったのは何故でしょうか。それは、芸術の概念とは高められるべきものであるとともに、人間生活のあり方とその運命全体にとってそれが重要であるということについては疑う余地がないというような方法で表現されるべきものであったからです。芸術活動の重要性と意義については議論の余地がないところへと置かれるように意図されていましたが、実際、「良心」という言葉によって示される経験とは、本当に、それが指し示すあらゆる状況が高貴なものになる、といったようなものなのです。言い換えれば、「良心」という言葉が話されるとき、人間の魂は、その言葉が魂自身の中で最も価値ある要素のひとつに言及しているのだということ、そして、その要素を欠くということは重大な欠乏を意味しているのだということに気づくのです。それが文字どおり受け取られるか比喩として受け取られるかはともかく、「人間の魂の中で良心の声がするとき、それを語るのは神の声なのだ。」という言葉によって、いかにしばしば良心の重要性が問題にされてきたことでしょうか。そして、その人が高次の精神性に関与する準備がどんなにできていなかったとしても、良心とは何なのかについて何も考えてこなかった人を見つけることはほとんどできないでしょう。良心というものは、それが何であろうと、何が善で何が悪かを、すなわち、自分が納得するためには何をなすべきで、自分を見捨てないためには何をなすべきでないかを抗しがたい力を持って決定するするところの個々人の胸の内にある声として経験されるところのものである、ということは誰でもぼんやりと感じていることです。このことから言えるのは、良心とはすべての人の胸の内に何か聖なるものとして現れるものであり、それについてある種の意見を形成するのは比較的たやすいということです。しかし、人間の歴史とその精神生活にざっと目を通してみるならば、事態はそれとは異なってきます。この種の精神的な状況をより深く探求しようとする人ならば誰でも、当然、そのようなことがらに関する知識が前提になっていると考えられる人たち、つまり哲学者の意見を参考にしたいと思うでしょう。けれども、幅広い人間の関心事の全般にわたってそうであるように、この場合にも、彼は、様々の哲学者が良心について非常に異なった説明をしている、あるいは、そう見えるけれども、その多かれ少なかれ漠とした核心はどの場合にも同じようなものである、ということを見いだすでしょう。しかし、そのことが最悪であるわけではありません。もし、誰かが古代の、そして現代の哲学者にとって良心が何を意味しているのかをわざわざ調べてみるとるならば、彼はあらゆる種類の非常に洗練された、そしてまた理解するのが難しい多くの言葉に出会うかも知れません。しかし、彼は、自分の感情から、これが良心だ、と疑問の余地なく言えるであろうようなものは何も見いださないでしょう。もちろん、ここで人類の哲学上の指導的な人物たちによって何世紀にもわたって与えられてきた良心についての説明を総括するならば、それは行き過ぎになってしまうでしょう。ただ、中世の最初の3分の1以降の中世哲学を通して、良心が話題にされるときにはいつでも、それは人間の魂の中にある、人がなすべきこととしないでおくべきことを直ちに宣告することができる力であると言われてきたことに注目することができます。けれども、これらの中世の哲学者たちはこの魂の力の根底には何か別のもの、良心そのものよりもよりも繊細な性質を持つ何かがあるとも語ります。ここでしばしば取り上げられる人物、マイスター・エックハルトが告げるのは、良心の下に横たわる小さな閃光、もしそれが留意されさえすれば、善悪の法則を間違いのない力をもって宣言するところの魂の中の永遠の要素についてです。近代においても、私たちは再び良心についての実に様々な説明に出会います。そして、その中のいくつかは奇妙な印象を与えるのですが、それはそれらが明らかに私たちが良心と呼ぶところの神的な内なる声の重大な本性について気づいていないからです。良心とは人間が人生における経験を絶えず拡張していくことによって、彼にとって何が役に立ち、何が害があり、何が満足を与えるか等々について学ぶとき獲得できるようなものである、とする哲学者たちがいます。これらの経験の総計が「これをせよ、それをするな。」という評価を生じさせるというのです。他の哲学者たちは最高の称賛の言葉をもって良心について語ります。そのような哲学者の中に、とりわけすべての人間の思考と存在の基本的な原則としての人間の自我、一時的な個人的自我ではなく、人間の中の永遠の本質を指し示した偉大なドイツの哲学者、ヨハン・ゴットフリート・フィヒテがいます。とりわけ彼は、人間自我にとっての最高の経験とは、「お前はこれをすべきである。何故なら、それをしないということはお前の良心に反することなのだから。」という内的な判定に耳を傾けるときの良心の経験である、と考えていました。彼はこの判定の威厳と高貴さは超越しがたいものである、と信じていました。フィヒテは人間自我の力と意義を最高度に強調した哲学者であったとはいえ、良心を自我の最も重要な衝動として位置づけたところに彼の特徴があるのです。さらに現代に近づけば近づくほど、そして、思考が唯物的になればなるほど、人間の心の中でというより、多かれ少なかれ唯物主義に染められた哲学者の思考の中で、良心がますますその尊厳を剥奪されていくのが見いだされます。この傾向を説明するにはひとつの例をあげれば十分でしょう。十九世紀の後半に、魂の高貴さ、調和のとれた人間的な感情、寛大で広い心のゆえに、最も洗練された人物のひとりに数えられるべき哲学者が生きていました。私はバーソロミュー・カルニエリのことを言っているのですが、彼は今日ではほとんど言及されることはありません。皆さんが彼の著作に目を通されるならば、彼はその繊細な性質にもかかわらず、当時の唯物的な思考に深く染められていたということが分かります。良心に関してはさてどうしたものかと彼は問います。彼は言いいます。それは、基本的には、我々がごく若い頃に吹き込まれ、人生の経験を積むにしたがって強化されるところの習慣と評価の総計以上のものではない。我々がもはや意識していないこれらの影響が、「これをせよ、これをするな。」という内なる声の源泉なのだと。こうして、良心はその源泉を外的な影響と習慣に求められ、しかも、それらは非常に狭い範囲に限定されてしまいます。もっと唯物的な志向をもつ19世紀の何人かの哲学者はさらに先に進みます。例えば、かつてニーチェに大きな影響を及ぼしたポール・レーですが、彼の書いた良心の起源についての本は私たちの時代の世界観を示す徴候として興味深いものです。彼の考えは、簡単な描写においては細かい点でのいくらかのゆがみはつきものですが、おおよそ次のようになります。ポール・レーが言うには、人間は彼のすべての能力において発達している、したがって良心に関しても発達している。もともと人間は私たちが良心と呼ぶところのものの痕跡も持っていなかった。良心が永遠のものであると考えるのは大変な偏見である。レーによると、私たちに何かをするように、そして何かをしないように告げる声はもともとは存在していなかったのです。けれども、人間本性の中には実際に発達してきたところの何か別のもの、復讐への本能とでも呼べるようなものがあった。これはあらゆる衝動の中でも最も原始的なものであった。もし誰かが別の者の手で苦しみを受けたならば、復讐の本能が彼に仕返しをするように駆り立てた。社会生活がより複雑になるにしたがって、徐々に復讐の遂行は支配権力の手にゆだねられた。それで人々は、他の人間を傷つけるようないかなる行いも、当然、以前に復讐心を呼び起こしていたような何かが引き起こしたのだと信じるようになった。結果を引き起こした行いは別の行いによって再び沈静化されなければならなかった。ときがたつにしたがって、この確信は特別な行為への感情、あるいはもっと言えば、そのようなことをしてしまいたいような誘惑の感情を伴うようになった。復讐への当初の衝動は忘れられたが、害を与えるような行いはその報いを受けなければならない、という感情が人間の魂に染み込んでいった。そうして今、内なる声を人間が聞いていると信じるとき、これは実際、内的な形態を持つように変化させられた復讐の呼び声以外のものではない、と。ここにあるのは、この種の説明の極端な-極端なというのは良心が完全な幻想として示されているという意味でですが-例です。参照画:ポール・レー 他方、良心は人間が地上に生きてきたのと同じくらい長く存在している、言い換えれば、良心はある意味で永遠である、と断言するならば、それはあまりに行き過ぎである、ということを私たちは認めなければなりません。良心をより精神的に考える人も良心を純粋な幻想とみなす人も両方とも間違いを犯しているがゆえに、たとえそれが私たちの毎日の内的な生活に、そして実際、その聖なる部分に属しているとしても、そのことに関して何らかの合意に達するのはいずれにしても非常に困難なことなのです。哲学者たちを一瞥するだけで、以前の時代には、彼らの中の最高の人たちでさえ、今日私たちが良心についてそのように考えざるを得ないような仕方とは違った方法でそれについて考えていた、ということが示されます。と申しますのも、私たちは、良心とは最も素朴な人の胸の内からさえ、神的な衝動として、「お前はこれをすべきである-それはしてはならない。」と語りかける声であると言いますが、これはソクラテスやその後継者プラトンにおいて私たちが見いだすところの教えとはいくらか異なっています。彼らは両方とも、徳は学ぶことができると主張しています。実際、ソクラテスは、人間が自分は何をすべきか、そして何をすべきではないかについて、はっきりとした考えを形成するならば、徳とは何なのかについての知識を通して、徐々に正しい行為を学ぶことができると言います。さて、現代的な観点からみて、もし、私たちが正しく行動することができるようになるためには、何が正しく、何が悪いかを学ぶまで待たなければならないとすれば、それは困ったことであろうという反論が容易になされるかも知れません。つまり、良心が人間の魂の中にある基本的な力によって、「お前はこれをしなければならない、それをしてはならない。」と語り、ひとりひとりがそれを聞くのは、私たちが善悪についての考えを形成することを学び、そしてそれによって道徳的な教訓を定式化し始めるずっと前なのだ。そしてさらに言えば、良心とは、人が自分に「お前は何かお前が同意することができるようなことをした。」と言うことができるような場合、その魂に一定の平静さをもたらすものなのだ。我々の振る舞いに関して同意できるような評価に到達するために、徳の本性と性質について多くのことを学ばなければならないとすれば、それは都合の悪いことだ、と多くの人々が言うかも知れません。ですから、その死により彼の哲学が最高のもの、高貴なものになった哲学者、私たちが哲学の殉教者として尊敬する哲学者は-私はソクラテスのことを言っているのですが-、良心について、今日見られるような観点とはほとんど符合しない概念を私たちの前に示している、と言うことができます。そして、その後に現れるギリシャの思索者においてさえ、完全な徳とは学ぶことができるような何かであるという主張、つまり原初的で基本的な良心の力というものと合致しない教義がいつも見いだされるのです。では、ソクラテスのようにあれほど傑出し、力強い人物が、今日、私たちが有しているような良心についての考えに気がつかないというようなことが何故あり得るのか、つまり、私たちが彼について研究するときにはいつでも、プラトンも言っているように、最も純粋な道徳性と最高の徳が彼の言葉を通して語っていると感じるにもかかわらず、何故そういうことがあり得るのでしょうか。それは、今日では生来のものであるかのように感じられる考え、概念、そして内的な経験が、実際には、人間の魂によって、ときの流れの中で苦労して獲得されたものだからです。私たちが人類の精神生活を過去へと遡るとき見出すのは、太古の時代には、良心についての私たちの考えやそれに対応する感情は今のようなあり方では存在していなかった、したがって、ギリシャ人の間にも存在していなかったということです。良心は実際、「生まれた」のです。しかし、例えば、ポール・レーがそうであったように、外的な経験や学識のような安易な方法では、良心の誕生について何ひとつ学ぶことはできません。人間の魂についての啓発を得ようとするならば、その問題にもっと深く分け入って行かなければなりません。さて、この連続講義における私たちの仕事は、魂をより高い認識のレベルにまで引き上げることから来る光の助けを借りて、正に魂の構成を照らし出す、ということでした。つまり、先見者の内的な目、感覚世界だけの知識を得るのではなく、その感覚世界のヴェールの後ろにその第一義的な源泉、精神的な基礎が見出される領域を見るところの目に対して自らを現すような魂の生活全体が記述されました。そして、先見者の意識は私たちが日常生活で経験する魂的生活の上方に位置する魂のより深い領域への道を開く、ということが繰り返し-例えば、「神秘主義とは何か?」の講義の中で-示されました。私たちは、日常生活においても、私たち自身をのぞき込み、思考、感情、そして意志に関する経験に出会うとき、このより深いレベルについて何らかのことを知ることになると信じているけれども、通常の目覚めた状態では、魂は精神的なものの外的な側面を明らかにするに過ぎないということもまた指摘されました。もし、私たちが、見たり、聞いたり、脳で理解したりするあらゆるものの背後に現れるような、これらの外面的なものの基礎となる原因を見出そうとするならば、感覚世界の上にかけられたヴェールの後ろへと貫き至らなければならないように、もし、私たちが私たち自身の生活の精神的な基盤を知ろうとするならば、私たちは私たちの思考、感情そして意志の背後にあるもの、つまり、通常の内的な生活の背後にあるものを見なければなりません。以上のような点から出発して、私たちは、多くの分岐によって織りなされる人間の魂の生活に光を投げかけるという仕事に取りかかりました。私たちが見てきたのは、魂は三つの構成体から成り立っていると考えられるべきであるということ、それらは区別されなければならないとはいえ、この点に注意していただきたいのですが、お互いに全く別々に取り扱われるべきではないということです。私たちは、これらの構成体を感覚魂、悟性魂、そして意識魂と名づけました。そして、それらを結びつける統合点としての自我がまるで道具を糸で操るかのようにそれらに働きかけ、無限に多様な方法で共鳴させることによって、いかに協和音や不協和音を奏でるかを見てきたのでした。この自我の活動は段階を追って発達してきました。そして、もし、人間が未来においてどのようなものになり得るのかを垣間見るとすれば、あるいは、今日においてさえ、もし、意識魂の中からより高次の超感覚的な意識形態を発達させているとするならば、私たちは今日の意識や魂的生活が、いかに太古の昔から進化してきたものであるかを理解することになります。意識魂はその通常の状態において、私たちが感覚を通して知覚した外的世界を把握することができるようにします。もし、誰かが感覚世界のヴェールの後ろに貫き至ることを欲するならば、彼は彼の魂の生活をより高次のレベルに引き上げなければなりません。そのとき彼は何か魂の覚醒といったようなこと、つまり、生まれながらに盲目の人に施された手術が成功し、それまで知らなかった光と色の世界が彼に侵入してくるという成果に比べられるようなことが起こり得るのだという大いなる発見をするのです。正しい方法によって自分の魂をより高次の発達段階に引き上げる人についても同様です。私たちが普通の状態では無視してきたにもかかわらず、いつも私たちの周囲を群をなして飛び回っているあれらの要素が、それを知覚するための新しい器官を私たちが獲得したことにより、その豊かな存在性と活動をもって私たちの魂的生活の中に入り込んでくる瞬間がやって来るのです。ある人がこの種の意識的な見霊能力を訓練によって獲得するときには、彼の自我は最初から終わりまで完全に存在しています。このことが意味しているのは、彼が私たちの感覚世界の基礎をなす精神的な事実や存在の間を、ちょうど物理的な世界の中にある机や椅子の間を縫っていくように動き回るということ、そして今や、彼は、彼の感覚魂、悟性魂、そして意識魂の経験を通して彼を導いてきたところの自我を魂的生活のより高次の領域へともたらすということです。さて、自我によって照らされ、点火されるこの意識的な超感覚的能力から魂の通常の生活にもう一度目を向けてみましょう。自我はこれら三つの魂の構成体の中で、実に様々の方法で生きています。もし、ここに感覚魂の中から生じる欲望や熱情、本能的な衝動に自分の生活を譲り渡す男がいたとしますと、彼の自我はほとんど活動的ではない、それは感覚魂の打ち寄せる波のただ中にあるかすかな炎のようであり、それらにうち勝つ力をほとんど有していない、と言うことができます。自我は悟性魂の中である程度の自由と独立を獲得します。ここにおいて彼は彼自身に至るのであり、そのことによって彼は彼の自我をある程度認識するのです。何故なら、悟性魂は人間が感覚魂を通して彼のところにやって来る経験を内的な落ち着きの中で熟考し、洗練させる限りにおいてのみ発達することができるからです。自我はますます光を放つようになり、ついには意識魂の中で十全なる明晰さを獲得します。そのとき、人は「私は自分を把握した-私は真の自意識を達成したのだ。」と自らに言うことができます。人が感覚魂から悟性魂へと発展し、意識魂の中で働くようになって初めてこの段階の明晰さが自我において達成されるのです。けれども、もし、人が自我の中で意識魂を越え、より高次の魂の原則と比べられるような超感覚的な意識へと上昇することができるとすれば、私たちは、先見者が人類進化の過程を振り返り、「自我は、こうして正により高次の魂の段階へと上昇していくのと同じく、ある低次の状態から感覚魂の中へと入ってきたのだ。」と私たちに告げるのをよく理解することができます。私たちは魂の構成体-感覚魂、悟性魂、そして意識魂-が、いかに体的な組織の構成体-肉体、エーテル体、そしてアストラル体もしくは感覚体-と関連づけられているかを見てきました。皆さんはこのことから-精神科学が示すように-、自我が感覚魂へと上昇する以前には、感覚体の中で活動しており、さらにそれ以前にはエーテル体と肉体の中で活動していたということを理解できるのがお分かりでしょう。当時、自我はまだ外側から人間を導いていました。それは体的な生活の闇の中で支配しており、人間はまだ自分自身に関して「私」ということができず、自分自身の内にその存在の中心点を見出していませんでした。太古の時代に支配し、人間の外的な体的組織を作り上げたこの自我について、私たちはどのように考えればよいのでしょうか。今日、私たちが私たちの魂の中に担う自我に比べて、それはより不完全なものであったと見なすべきなのでしょうか。私たちは自我を、私たちの存在の現実的な内的焦点として、つまり、私たちに内的な生活を付与し、未来においては、訓練により、無限に進歩することができるものとして眺めます。私たちはその中に私たちの人間本性の縮図と、人間としての尊厳を保証するものを見ます。さて、私たちがこの自我についての意識を有していなかったとき、自我が世界の暗い精神的な力から私たちに働きかけていたとき、それはそれが今日そうであるようなものと比べてより不完全だったのでしょうか。全く抽象的な思考方法だけが、そうであったと言うことができるでしょう。私たちの肉体について考えてみて下さい。私たちはそれを、人間の魂の住居として太古の昔に精神的な世界から形成されたものとして眺めます。唯物的な精神だけが、この人間の体は元々精神から生まれたのではない、と信じることができでしょう。単に外的な観点から見るときには、肉体は奇跡的に完全なものとして現れるに違いありません。人間の心臓の構造に現れた叡知に比べて、私たちの知的な能力や技術的な熟練のすべてとは結局どれほどのものなのでしょうか。あるいは、橋の建設で用いられるエンジニアリング技術やその他のものを取り上げれば、人間の大腿骨の構造、その支持機構を顕微鏡で観察したときの驚くべき十字構造に比べて、それは何ほどのものなのでしょうか。外的な肉体の構成に固有の叡知を人間がわずかでも達成したと想像するならば、それは全く際限のない傲慢でしょう。そして、私たちの魂的生活について、ただ単に私たちの本能、欲望そして熱情だけでも考えてみてください。それらはどのように機能しているでしょうか。私たちは、私たちの体の叡知に満ちた組織を内的に浸食するために、私たちにできるあらゆることをしているのではないですか。実際、もし、私たちが偏見なしに私たちの肉体組織の驚異を考えるならば、私たちの体的な構造とは、私たちがその内的な生活において示すことができるあらゆることに比べて、もっとも私たちは、それらが現在の不完全さから完成にむけてさらに前進することを望んでいるかも知れませんが、はるかに賢いものである、ということを認めないわけにはいきません。観察可能な事実を単に偏見なく見るとすれば、たとえ超感覚的な能力がなくても、これ以外の結論に至ることはほとんど不可能でしょう。自我の住居として人間の体を作り上げたのは自我自身の本性と何か共通したものを有しているはずのこの賢明な活動ではないでしょうか。私たちはこの形成的な力を、測り難く進歩した自我の性質を有するものとして考えなければならないのではないでしょうか。私たちの自我に関係した何かが、太古の時代を通して、その自我が居住可能になるような構造を建設するために働いていた、と言わなければなりません。これを信じることを拒否する人は誰でも何か違うことを想像するかも知れませんが、そのとき彼は人間が住むために建てられる普通の家も人間の精神によってデザインされたのではなく、単に自然の力の働きによって組み立てられたと想像しなければならないでしょう。ひとつの仮定は他の仮定と同様に真実です。こうして私たちは、どこまでも完全な自我性を付与された精神的な力が私たちの体的な鞘に働きかけていたところのはるかな過去を振り返ります。私たちの自我は、当時、無意識の深みに隠されており、そこから現在の意識状態へとその歩みを進めて来たのです。もし、私たちがこの進化をはるかな過去から眺めるとすれば、自我がまるで子宮の暗闇の中にあるようにその鞘の中に隠されていたときには、それはそれ自身についての知識を有していなかったとはいえ、それだけよけいに、私たちの体的な乗り物に働きかけていたところの、人間の自我に関連しているとはいえ、それとは比較できないほど大きな完成度を有するあの精神的な存在達の近くにいたということが分かります。こうして超感覚的な洞察は、人間が精神的な生命そのものの中に横たえられていたためにまだ自我意識を獲得しておらず、彼の魂的生活もまた、自我がそこから現れた魂的力のずっと近くにいたために、今とは異なっていたはるかな過去を振り返ります。私たちはまたその時代の人間の中に、自我の光に照らされていなかったためにぼんやりと夢のように機能していた原初の超感覚的な意識を見出します。そして、自我が最初に現れたのはこの意識形態からだったのです。人間が、未来において、彼の自我とともに獲得するであろう能力は、太古の時代には、自我なしに存在していたのです。超感覚的な意識は、精神的な存在や精神的な事実を周囲に観察するということを必然的に伴っているのですが、このことは、その超感覚的な能力が夢のようであり、まるで夢の中でのように精神世界を眺めていたとはいえ、以前の人間にも当てはまります。彼はまだ自我の光に貫かれていなかったために、精神的なものを見ようとしたときにも、彼の内に留まるように強制されることはありませんでした。彼は彼の周囲に精神的なものを見ると同時に、彼自身を精神世界の一部として眺めたのです。そして、彼が何をしようとも、それは彼にとって精神的な性格を帯びたものになりました。彼が何かを考えるとき、彼は自分に向かって、今日の人間がそうするように、「私は考える。」とは言わなかったでしょう。つまり、彼の思考は彼の超感覚的な視界の前で立ち止まったのです。そして、彼が何らかの感情を経験するため、彼自身の中を覗き込む必要はありませんでした。つまり、彼の感情は彼から輝き出し、彼を彼の精神的な環境全体に結びつけたのです。太古の時代における人間の魂的生活とはそのようなものでした。彼は、彼自身に至るために、つまり、彼の中で、今日まだ不完全な状態にあるとはいえ、人間が彼の自我とともに精神世界への歩みを進めるとき、未来においてますます完成に近づくであろう彼の存在におけるあの中心点に至るために、彼の夢のような超感覚的な意識から内的に発達して来なければなりませんでした。さて、もし、既に述べられたような方法で、超感覚的な手段により、あの太古の時代に光が投げかけられるならば、当時の人間の意識に関して、例えば、人間が悪い行いを犯した場合には、先見者は私たちに何を告げるでしょうか。彼の行いは、彼が内的に評価できるような何かとして彼に提示されたのではありません。彼はそれが彼の魂の前に、その悪徳と恥辱のすべてを伴って幽霊のように立ち現れるのを見たのです。そして、彼の悪しき行いに関する感情が彼の魂の中に生じたときには、その恥辱が彼の前に精神的な現実として現れることによって、彼はまるで彼が働いた悪い行いの光景に取り巻かれているかのようでした。そして、時の経過とともに、この夢のような超感覚的な能力が消え、人間の自我がますます前面に出てきました。人間が自分の内にその存在の中心点を見出すにつれて、古い超感覚的な能力は消し去られ、自我意識がますますはっきりと自らを確立するようになったのです。彼が以前に有していた彼の善行や悪行についての視界は彼の内的な生活の中に移し替えられ、そして、かつて超感覚的に眺められた行為は彼の魂の中で反射されるようになったのです。さて、夢のような超感覚的な視界には、人間の悪い行いに対応するものはどのような形を取って現れたのでしょうか。それは、いかに彼が宇宙的な秩序を妨害し混乱させたかを示すような光景であり、彼を取り巻く精神的な力が彼に有益な影響を及ぼすことを意図して彼に示した光景でした。それは、彼を上昇させようとする神が、彼の行いによる影響を彼に示し、彼がその有害な結果を取り除くことができるようになることを望んで取られた措置でした。これは、実際、彼にとっては恐ろしい経験でしたが、人間自身がそこから現れたところの宇宙的な基盤からやって来る基本的に有益な経験でした。人間が自分自身の内にその自我中心を見出す時代が来たとき、外的な光景は反射された像の形で彼の魂の中に移されました。自我が最初に感覚魂の中に出現するとき、それは弱く、脆いものです。人間はその自我の完成に向けて徐々に前進するために、まず自分自身にゆっくりと働きかけなければなりません。さて、彼の悪事の結果についての外的、超感覚的な視界が消えたとき、もし、それが有益な影響を持つその内的な対応物によって置き換えられなかったとすれば、何が起こっていたでしょうか。彼は彼の熱情によって、まだ脆い彼の自我とともに、まるで際限のない波打つ海の中にあるかのように、感覚魂の中をあちこち引きずり回されていたことでしょう。では、この歴史的な瞬間に、外的世界から内的な魂の生活へと移されたものとは何なのでしょうか。人間が何を善なるものにすべきであるかをその超感覚的な意識の前に示しながら、その行為の有害な効果を治癒的な影響としてもたらしたのが偉大なる宇宙の精神であったとすれば、後に、人間の自我がまだ弱かった頃、その内的な生活の中に力強く自らを現したのもその同じ宇宙の精神でした。その精神は、超感覚的な視界を通して人間に語りかけた後、彼の内的な生活の中へと引き下がり、宇宙秩序の中に引き起こされたゆがみの是正について語るべきことを彼に伝えました。人間の自我はまだ弱いので、その宇宙精神は絶えることなく、眠ることなくそれを監視し、自我がまだ判断できない場所で判断を下します。その弱い自我の後ろには、何か力強い宇宙精神の反映のようなもの、以前は、人間の行為の結果を超感覚的な視界を通して彼に示していたものが立っているのです。そして今や、その反映は、彼を監視する良心として経験されるのです。こうして私たちは、良心が人間の内なる神の声として素朴に記述されるとき、いかにそれが真実であるかを理解すると同時に、いかに外的な光景が内的な経験になった瞬間、つまり、良心が生まれた瞬間が精神科学によって指し示されるかを見るのです。今まで私がお話ししてきたことは純粋に精神世界から引き出されることができます。外的な歴史は必要でなく、私が記述した事実は内的な目によって観察されるのです。それを見ることができる人は誰でもそれを疑う余地のない真実として経験するのですが、時代の必要性から私たちは次のような問いに導かれます。一体、外的な歴史は、この場合、内的な能力によって見られる事実を確認するような何かを、もしかすると提示することができるのだろうか。超感覚的な意識によって見出されるものは、いつでも外的な証拠によって検証され得るのであって、その証拠がそれらと矛盾するのではないかと恐れる必要はありません。そのようなことは検証が不正確であった場合にのみ起こり得るように見えるのです。超感覚的な洞察からここで導き出された記述を外的な事実がいかに確認するかを示す一例を示してみましょう。良心の誕生というできごとが起こってからそれほど長い時間は経っていないのです。紀元前5世紀から6世紀を振り返るならば、私たちは古代ギリシャの偉大な悲劇詩人、アイスキュロスに出会い、そして、彼の作品の中に、ある特筆すべきテーマを見出します。そのテーマが注目されるのは、それが後の時代のギリシャ詩人によって全く異なった仕方で取り扱われているからです。アイスキュロスが私たちに示すのは、アガメムノンがトロイから帰還し、家に帰り着いたとき、彼の妻、クリテムネストラに殺されるところです。彼の息子、オレステスは神の忠告にしたがって母を殺し、アガメムノンの仇討ちをします。では、オレステスにとって、この行為の結果とはどのようなものなのでしょうか?アイスキュロスが示すのは、いかに母殺しの重荷が当時もはや普通ではなくなっていたものの見方をオレステスの中に呼びさますかです。彼の罪の非道さが古い超感覚的な能力を過去からの遺産のように彼の中に目覚めさせたのです。オレステスは次のように言うことができました。「アポロが、神自身が私に告げたのは、私が母に父の仇討ちをしたのはひとつの行為にすぎないということだ。私が行うあらゆることがそれを是とする。しかし、私の母の血は働き続けるのだ!」と。そして、オレステス三部作の第二部で、古い超感覚的な能力がオレステスの中で目覚め、仕返しの女神、エリニエス-あるいは、後にローマ人がそう呼んだところの復讐の女神-が近づいてくる様子が力強く示されます。オレステスは夢見るような超感覚的な意識の中で、外的な形態を取って現れる母殺しの行為の結果を目の当たりにします。アポロはその行為を容認していたのですが、そこには何かより高次のものが存在しているのです。アイスキュロスはもっとさらに高次の宇宙的な儀式が通用することを示したかったのですが、それができたのはただその瞬間にオレステスを超感覚的な意識にすることによってのみでした。何故なら、彼はまだ私たちが内なる声と呼ぶところのものをドラマ化するのに十分なところまで来ていなかったからです。もし、私たちが彼の作品を研究するならば、何か良心のようなものが人間の魂の内容全体から現れようとしている段階にありながら、彼はその地点には全然到達していない、という感じを受けます。彼はまだ良心へと変容していない夢のような超感覚的な眼差しをもってオレステスに向かいます。けれども私たちには、彼がもう少しで良心を認識するところにいるのが分かります。例えば、彼がクリテムネストラに語らせる言葉のひとつひとつが、まぎれもなく、彼は今日の意味での良心という考え方を示すべきである、という感情を呼び覚ますのですが、彼は決してそこに行き着きません。当時、偉大な詩人が示すことができたのは、それ以前の時代においては、いかに悪い行いが人間の魂の前に立ちはだかったか、ということだけでした。さて、私たちはソフォクレスをとばして、ほんの一世代だけ後に同じ状況を取り扱ったエウリピデスに目を向けてみましょう。学者達が正しく指摘したように、とはいえ、精神科学だけがそのことをその真の光の中で示すことができるのですが、エウリピデスにおいては、オレステスが経験した夢の像は良心の呵責の影のようなイメージ以上のものではありません。シェークスピアにおいてもいくらか同様です。このように、詩という芸術は良心という考えが確立した段階があったことをはっきりと証明しています。私たちは、いかにアイスキュロスのような偉大な詩人でさえ良心そのものについて語ることができなかったかを、そしてその一方、いかに彼の後につづくエウリピデスが正にそれについて語るかを見ます。この発展を心に留めれば、何故、人間の思考一般が良心についての真の概念に向かってただゆっくりとその歩みを進めることができるだけなのかが分かります。現在、良心の中で働いている力は太古の時代にも働いていました。それは人間の超感覚的な視界の前に彼の行いの影響を示す像として現れました。唯一の違いは、この力が内在化されたということなのですが、それを内的に経験するためには、徐々に良心の概念へと導いていった人間の発達全体が必要でした。こうして私たちは、段階を追って前面に出てくる能力、人間自身の努力によって獲得されなければならない能力を良心の中に見るのです。では、私たちは良心の最も力強い活動をどこに探すべきなのでしょうか?それは人間の発達過程の中でも、自我が初めて認知されるようになった時点、それがまだ弱いものであった時点においてです。古代ギリシャでは、自我は悟性魂の段階にまで進んでいました。しかし、古代エジプト、カルディアにまで遡ると、外的な歴史はこのことについて何ひとつ知りませんが、プラトンとアリストテレスはそれについての超感覚的な認識をもっていました。当時の最も高度に発達した文化でさえ、内的に独立した自我の存在なしに達成されたものであるのが分かります。エジプトやカルディアの聖地によって育まれ、使用に供された知識と私たちの近代的な科学との違いは、私たちの科学が意識魂によって把握されるのに対して、ヘレニズム以前の時代においては、すべてが感覚魂からのインスピレーションに依存していたということです。古代ギリシャにおいて、自我は感覚魂から悟性魂へと発達しました。今日、私たちは意識魂の時代に生きているのですが、これは真の自我意識が今初めて生じている、ということを意味しています。人類の進化を研究する人、特に、東洋的な文化から西洋的な文化への移行を研究する人は誰でも、いかに人間の発達がどこまでも増大する自由と独立の感情によって特徴づけられてきたかを見ることができます。以前の人間においては、自分は神々とそこからやって来るインスピレーションに完全に依存していると感じられていたのに対して、西洋において初めて、文化が内的な生活から湧き出してきたのです。このことは、例えば、アイスキュロスが人間の魂の中に自我意識を生じさせようとしていかに苦闘したかを見れば特に明らかです。私たちは彼が片方の目を東洋に、もう片方を西洋に向けて、人間の魂の中から良心の概念へと統合されるべき要素を集めながら、いかに東洋と西洋の境界線上に立っているかを見ます。彼はこの良心の新しい形態を劇の形に体現させようと努力しますが、まだ充分にそうすることができません。比較は混乱を招きやすく、私たちは単に比較するのではなく、区別しなければなりません。大事なのは、西洋においては、あらゆるものが自我を感覚魂から意識魂へと上昇させるようにデザインされていた、という点です。東洋においては、ヴェールをかけられたあいまいさの中で自由ではなかった自我は、西洋において、それとは対照的に、意識魂への上昇の道を辿るのです。古い、夢のような超感覚的能力が消し去られるとき、他のあらゆるものが自我を目覚めさせ、その自我を守る内なる神の声としての良心を呼び起こそうとします。アイスキュロスは東と西の世界を分ける礎石だったのです。東の世界では、人間は神的な宇宙精神の中にその起源を有しているという意識がいきいきと保持されていました。そして、このことが彼らに、多くの人が-あるいは、例えばアイスキュロスが-神の声として語られる何かを彼ら自身の内に見出そうと努力した時代から二、三百年後に起こったできごとについての理解を可能にしたのです。すなわち、このできごとによって、地球と人間の進化の中に入ってきた衝動の内、すべての精神的な立場からみて最も偉大な衝動-私たちがキリスト衝動と呼ぶところのものが人類にもたらされたのです。神すなわち事物や人間の外的な鞘の創造主は私たちの内的な生活の中に認められる、ということを初めて人間に気づかせることができたのがこのキリスト衝動でした。人間はキリスト・イエスの神的な人間性を理解することによってのみ、神の声とは魂の中で聞くことができるものである、ということを理解するようになったのです。キリストは、人間が自分自身の内的な生活の中に何か神的な本性を見出すことができるようになるために、外的、歴史的なできごととして人類進化の中に入ってくる必要があったのです。もし、神なる存在であるキリストがナザレのイエスの体の中に存在しなかったとすれば、もし、彼が人間の体の中に存在することによって、神は我々の内的生活の中に認められ得るものである、ということをたった一度だけ示さなかったとすれば、もし、彼がゴルゴダの秘蹟を通して死の征服者として出現しなかったとすれば、人間は、彼の魂の中には神が住んでいる、ということを決して理解しなかったでしょう。もし、誰かが、たとえキリスト・イエスが歴史的に存在しなかったとしても、そのようなことは認識できたはずだと言うならば、それは太陽がなかったとしても我々は目を持っていたはずだと言うのと同じです。もし、光の起源は目に求められなければならない、何故なら目がなければ我々は光を見ることができないのだから、という哲学者達の一方的な見方に反対してそうするのと同様に、私たちはここでも、「目は光のために光によって創造された。」というゲーテの金言を持ち出さなければなりません。もし、空間を光で満たす太陽がなかったとすれば、人間有機体の中に目が発達することは決してありませんでした。目は光によって創造されたのであり、もし、太陽がなければ、目は存在しなかったのです。どんな目も、まず最初に太陽からその力を受け取っていないのであれば、太陽を知覚することはできません。同様に、もし、キリスト衝動が外的な歴史の中に入ってこなかったとすれば、キリスト衝動を把握し、認識する力は存在しなかったのです。宇宙にある太陽が人間の視覚に対して行ったのと同様に、歴史上のキリスト・イエスは、私たちが私たちの内的生活への神的本性の導入と呼ぶところのものを可能にします。このことを理解するために必要な要素は東からやって来た思考の流れの中に存在していました。それらはただより高次のレベルに引き上げられればよかったのです。魂がこの衝動を把握し、受け入れることができるまでに成熟したのは西洋においてでした。西洋においては、かつて外的な世界に属していた経験が最も強力に内的な世界に移し替えられ、概して弱かった自我を良心の形で見張っていました。このようにして魂は強化され、今やその中で語る良心の声を聞くための準備ができました。つまり、東洋において、世界を超感覚的に見ることができた人々の前に現れた神性、この神性は今や私たちの中に住んでいるのです!けれども、もし、内的な神性が意識の夜明けに際し、前もって語りかけていなかったとすれば、このようにして準備されていたものが意識的な経験になることはなかったでしょう。こうして私たちは、キリスト・イエスに対する外的な理解が東洋で生まれ、そして、西洋から現れ出た良心がやって来てそれに出会うのを見るのです。例えば、私たちは、キリスト教の時代の初期に、ローマ世界においてますます頻繁に良心が語られるようになり、西に行けば行くほど、ますますその存在に対する認識が明白になるとともに、それが胎児のような形で存在しているのを明らかにすることができるようになるのを見ます。こうして、東と西はお互いにそれぞれの手の中へと働きかけました。私たちはキリスト本性を有する太陽が東方に昇り、一方、西方では、発展する良心がキリスト理解への道を準備するのを見ます。ですから、キリスト教は栄光に満ちて西方へと前進するのであって、東方へではありません。東方では、東洋的な世界観の、その最も高いレベルにあるとはいえ、最後の結果を代表する宗教が広まるのが見られます。つまり、仏教が東方世界を捉えます。キリスト教が西方世界を捉えたのは、それがキリスト教を受け取るための器官をまず準備していたからです。ここにおいて私たちはキリスト教が西洋文化における深化された要素すなわちキリスト教に体現された良心という概念に関係してくるのを見ることになります。私たちがこれらの発展について知るようになるのは、外的な歴史を研究することによってではなく、事実を内的に熟考することによってのみです。私が今日申し上げましたことは多くの人にとっては信じられないことかも知れません。しかし、外的な現象の中に精神を認める、というのは時代の要請です。ただし、このことが可能なのは、少なくとも、精神がはっきりとしたメッセージの形で私たちに語りかけてくるところで、さしあたりそれを識別することができるときだけです。通常の意識は、「良心が語るとき、それは魂の中で神が語っているのだ。」と言います。最も高次の精神的意識は、良心が語るとき、それは本当に宇宙的な精神が語っているのだ、と言います。そして、精神科学は良心と人間進化における最も偉大なできごと、すなわちキリスト事件との関係を明らかにします。ですから、そのことによって良心が高貴なものにされ、より高次の領域へと上昇させられた、というのは驚くべきことではありません。良心のために何かがなされたということを聞くとき、私たちは良心が人類の最も重要な所有物のひとつと見なされていると感じます。こうして、私たちには、良心とは人間の中の神である、と人間の心が語るとき、それがいかに当然で正しいことであるかが分かるのです。そして、神なる自然が人間に自らを現すとき、それは人間にとって最も高貴な経験であるとゲーテが言うとき、私たちは、神が精神において人間に自らを現すことができるとすれば、それは私たちが自然をその背景にある精神の光の中で見るときだけである、ということに気づかなければなりません。人間進化の中でこのことが充足されるのは、一方では、外から輝き入るキリストの光によってであり、他方では、私たちの内にある神の光、すなわち良心の光によってなのです。フィヒテのような人間の本質を研究する哲学者が、良心とは私たちの内的な生活における最も気高い声である、と言うとき、それが正当であるのはこのことによってなのです。このこととの関連で、私たちはまた、私たちの人間としての尊厳が良心とは不可分である、ということに気づいています。私たちは自我意識を有しているがゆえに人間なのであり、私たちが私たちの側で有している良心は自我の側にあるのだ、と言えます。こうして私たちは良心を個人が所有する最も神聖なもの、外的な世界によって侵害され得ないものと見なします。その声によって、私たちは私たちの方向性や目的を決定することができます。良心が語るとき、他のいかなる声も口をはさみません。ですから、良心は、一方では、世界の原初的な力と私たちとの関係を確認し、他方では、私たちは神から流れ来るひとつの滴のようなものを私たちの中の最も深いところに有しているという事実を保証するものです。そして、良心が人間の中で語るとき、それは神が語っているのだということを彼は知るのです。人気ブログランキングへ
2024年03月22日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第七講「不調と心的な障害」(1910年4月28日) この冬に、私がこの場で皆さんの前に提示することを許された連続講義では、本連続講義の第一講で性格付けされたような精神科学の観点から、非常に多様な現れ方をするところの人間の魂的生活、あるいはもっと広い意味での生活に光を当てる、というのがその使命でした。今日は、悲惨や苦悩、そして恐らく希望の喪失をももたらすかも知れないような人間生活の領域を観察することにしましょう。これを補完するために、次回の講義では、「人間的な意識」と題して、人の自我意識の人間的な尊厳、価値、力が最大限に表現されるような高みへと私たちを連れ戻す領域について触れることにします。そして、最後に、今日、暗く、最も戦慄すべき人生の側面から私たちの前に現れるように見えるものの全く健全な面を示そうと努めるところの「芸術の使命」についての考察をもって今年の連続講義の締めくくりにしたいと思います。不調と心的な障害について語られるとき、誰の魂の中にも、人間の最も深い苦しみのイメージと同時に最も深い人間的な共感のイメージが生じます。そして、このようにして魂の中に生じるあらゆるものは、人間の魂の中に存在するこの深淵を、この連続講義の中で得られると期待されるところの光をもって照らし出すための挑戦でもあり得るのです。特に、ここで私たちの魂の前に示された考え方によって前進することにますます精通する人は、精神科学的な観察方法をもってすれば、ある意味で、人生におけるこの悲しみの章に光を当てることができるかも知れないという希望を持つにちがいありません。と申しますのも、なにがしかの文献上の知識を有している人であれば誰でも、ただし、ここでいう文献とは今や急速に広まっている素人によるものではなく、むしろ専門家による文献ですが、そのような知識が、精神科学的な観点から見た場合、ある意味で、非常にはるかな地点にまで達するものであり、それに関連する事実を評価するための豊かな素材を提供するものである、ということに気付くことができる一方、どの文献の中でも、現代における様々な理論や観点、思考様式が収集された経験や科学的な観察に骨組みを与えるという点で、ほとんど役に立たない、ということがあまりにも明らかになってきているということがあるからです。特に、この領域においては、いかに精神科学が真正で本物の科学と、つまり、科学的な事実や結果、経験として私たちが出会うところのあらゆるものと調和しているかをはっきりと見て取ることができます。けれども、同時に、各段階において、いかに精神科学が、これらの経験と現代の潮流となっている科学的な観点からそれらの経験が説明されるその仕方との間に矛盾を見出すか、ということもまた理解することができるのです。他の領域においてと同様に、私たちはここでもそのテーマを概略的に扱うことしかできないかも知れませんが、それは、多分、私たちがこれから扱おうとしている悲しむべき状況との関連においても、私たちがますます私たち自身の方向性を見出すことができるように、私たちの実生活の中にも流れ込むことができるような適切な理解を獲得するための刺激を与えることになるでしょう。「不調」と「心的な障害」という言葉を使用するにあたっては、それらが基本的に異なっている、ということを私たちは意識しています。にもかかわらず、実際に心的な障害を受けているものとして記述できるような魂的生活を正確に観察する人がそこに見出すのは、人生の中の何らかの点に関して生じるところの、そうでなければ正常と見なされるような不調とは単に程度において異なるところの表現や外観かも知れません。しかし、そのような観察は、ある種の思考の方向性が個別的な区分けをぼやけさせ、実際、健康で正常な魂的生活と「心的障害」という言葉で記述できるようなものとの間にははっきりとした線を引くことはできないと言わせるような傾向を有していることから、間違った説明をしやすいのです。その種の記述には、そのようなことが起こった場合、強調されなければならないようなある種の危険が含まれているのです。そして、その危険は、その記述が間違っているということにではなく、それが正しい記述であるという事実の中にあるのです。これは矛盾であるように聞こえるかも知れませんが、とはいえ、間違った記述というのは、ときとして、説明することができ、一方的なやり方で実践に移すことができるような正しい記述よりも危険が少ないというのは事実なのです。それは、その記述の正しさの中に本来備わっている危険が気付かれないということです。何かが、ある文脈の中で、正しいと証明されるならば、それはそれで十分だと考えられがちなのですが、私たちはあらゆる正しいことがらにはその反対の側面があり、私たちが見出すいかなる真実もある種の事実と経験の観点から見たときにのみ真実であるにすぎないということに気付くべきなのです。危険はその真実が他の領域にまで外挿される瞬間に、つまり、それがあまりにも遠くまで拡張され、教条的な信念になるときに生じます。たとえ私たちが、真実は存在する、ということを知っていても、一般に大したことは達成できない、真の認識において重要なのはその知識が有効に働く限界を知ることであると言われるのはこの理由によります。私たちは、確かに、通常の健全な魂的生活がある限界点を越えるとき、病理学的な徴候にもなるという現象を観察することができます。この記述を充分な重みをもって認識することができるのは、より親密なレベルで人生を観察することに正しい仕方で慣れている人だけです。ある人が何らかの概念を理解し、それを正しい瞬間に別の概念に結びつけることができず、そのため、それを新たな、そして全く不適切な状況下で適用し、以前の状況下では正しかったけれども、後にそうではなくなった考えに基づいて行動するとすれば、誰がそこに「心的な障害」の題字の下に括られる病理学的な側面があることを否定するでしょうか。誰が、これは病理学的なものに近似している、ということを否定するでしょうか。もし、そのことが程度を越えて起こるならば、それは心的な障害への直接的な徴候なのです。けれども、他方では、その気苦労の多さとぎこちなさのために仕事をうまく進められない人々がいる、ということも否定できません。そこに見られるのは、通常の魂的生活におけるひとつの状況、ある考えを展開していくことができないという状況なのですが、不調について語るのをやめて、病理的な心身の障害について語り始めるべき地点へと接近できるのはそのような状況においてなのです。例えば、誰か、これは本当に起こることなのですが、勘違いしやすい人がいて、周りにいる人の咳払いが普通の咳のようにではなく、彼に対する人々の悪口であるかのように聞こえる、つまり、そのような幻想を彼に与えると仮定してみましょう。もし、彼が、そのとき、その生活と行動をこの幻想に適応させるとするならば、彼は心的な障害を持った人と考えられることになります。そして、それにもかかわらず、このことと通常の生活におけるできごと、すなわち、ある人が、何らかのことが語られるのを漏れ聞き、その内容について、実際に語られたのとは全く違うものを聞いたかのように説明する場合との間にはわずかの違いしかないのです。ある人が、「だれそれが私についてあれこれのことを言った。」と言い、にもかかわらず、そのだれそれがそのことを言ったという形跡がないというようなことがあります。通常の魂的生活がその健全な道筋からはずれ、魂的な障害へと変わるのはどの地点においてなのかを決めるのはそれほど容易なことではないのです。次に述べることは、矛盾しているように見えるかも知れませんが、この分野において、何らかの考えを喚起するのに役立つでしょう。すなわち、並木道に立っている人が、近くを見るときには木と木の間の正しい距離を全く正常に知覚できる一方、遠く離れている木はお互いに少しずつ接近しているように見えるために、それらの間にロープを張ろうと決心した際、遠くに行けば行くほど張り渡すロープの長さがますます短くなると考えたとします。これは完全に健全な観察から間違った結論を引き出す人の例です。しかし、健全な観察が可能なのは、錯覚があるからに他なりません。錯覚もまたひとつの観察なのです。その不健全で害のある側面が現れるのは、ただそれが目の前の机と同じ現実性を有しているものと考えられるときだけです。その観察が病理的なものであると言われ得るのは、単にそれが正しい方法で説明されないときだけです。さて、誰かが幻覚を抱き、それが通常の物理的な意味において現実であると考える場合と、先ほどの並木道で、木と木の間を遠くに行くほどますます短いロープで結びつけようとする人との間の矛盾とを比べてみることができます。論理的には、これらふたつのことがらの間には原則的な違いはありません。それにもかかわらず、幻覚は何と容易に私たちを間違った判断へと導き、そして、私たちは、並木道を観察するとき、何とめったに同じような間違いをしないことでしょうか。何人かの人はこのようなことはすべてばかばかしいと考えるかも知れません。けれども、それはさておき、これらの点を逐一考慮する必要があります。と申しますのも、もし、そうしなければ、すぐに話しが脱線して、通常の魂的生活がいかに容易に混乱させられるものであるかということを理解できないからです。さて、私たちはさらに、その魂的生活が健全で最高度に明晰なものと考えられている人々についてのもっとずっと衝撃的な例を挙げることができます。私は、その分野で働いている人たちの間で最も卓越した人物のひとりであると考えられているドイツの哲学者について触れたいと思います。その哲学者は彼の経験を次のように述べています。彼はかつてある人物と話していたのですが、その中で、彼らの二人ともが知っているある学者に話しが及びました。その学者に話しが及んだ瞬間、その哲学者が思い出したのはパリのイラスト集と、その次に、ローマの写真集でした。その間、その学者についての会話がつづいていました。その哲学者は、何故、会話中に、最初はパリのイラスト集のイメージが、つづいてローマの写真集が現れるというようなことが起こったのかをよく考えてみました。そして、実際、彼はその正しいつながりを何とか確立したのです。彼らの話題に上った学者は特筆すべきあごひげをはやしていました。このあごひげは、直ちに、同じようなあごひげをはやしていたナポレオン三世のイメージをその哲学者の潜在意識の中に呼び起こしたのです。そして、このナポレオン三世のイメージはフランスを経由してパリについてのイラスト画へと導きながら、彼の意識の中へと押し進んで来ました。そして、今や、同じようなバンダイク髭をはやしていた別の男のイメージが彼の前に現れます。イタリアのヴィクトール・イマニュエルのイメージです。そして、このイメージがイタリアを経由してローマの写真集に導いたのです。ここには、十全に意識的な魂的生活において、全く異なることが起こっている間に、気ままででたらめな一連の考えが展開しているのが見られます。さて、ある人の中にパリのイラスト画が現れ、もはや会話の糸をたぐることができず、そのすぐ後に、次のローマの写真集についての考えがつづくと仮定してみましょう。彼はでたらめな思考生活に左右され、誰とも秩序だった会話を持つことができず、ひとまとまりの考えから次の考えへとリズムも論理もなく彼を導くような病理的な魂的生活の中に織り込まれてしまうことでしょう。しかし、私たちの哲学者はさらに先へと進みます。そして、これを別の場合と対比させるのですが、彼は、それによって、これらのことがらがどのように関連しているかを認識できるようにしたいと思っていました。彼は、かつて、税金を払うために税務署に出かけたことがありました。彼は75マルクを払いに行ったのです。そして、その哲学はともかく、彼はきちんとした男でしたから、この75マルクを彼の支出簿に記入し、そして、別の仕事に取りかかりました。彼は、後になって、そのとき払った税金の額を知りたいと思ったのですが、思い出すことができません。彼は考えました。そして、哲学者でしたから、体系立ててその仕事に取りかかりました。彼は連想によってその額を思い出そうとしたのです。彼は税務署に向かう自分の歩みに集中し、そして、財布の中に金色の二十マルク札が四枚入っていたということ、さらには、そのときお釣りとしてもらった五マルクのイメージを思い出しました。彼はこのふたつのイメージを思い出し、そして、後は簡単な引き算によって、今や、彼が払ったのは七十五マルクであったということを見出すことができたのです。ここには、全く異なるふたつのできごとがあります。最初のケースでは、一連の意識的な思考によるコントロールを一切受けない、謂わば、自発的な魂の生活がその役割を演じています。これがパリのイラスト画のイメージとローマの写真集のイメージを創り出しました。二番目のケースでは、魂がその踏み出す一歩一歩を選び取りながら、いかに体系的に振る舞うかを見ることができます。これらふたつの魂の過程には、本当にかなりの違いがあるのです。しかし、かの哲学者は精神的な探求者であれば直ちに気がつくであろうようなことに注意を向けることができませんでした。と申しますのも、最初のケースでは、彼の注意は話し相手に向けられているということ、つまり、彼の意識的な魂的生活の全体は相手との会話を維持することに関わっており、でたらめなイメージは、まるで別の意識レベルにあって、勝手に浮かんで来るかのようである、というのが肝心な点なのです。二番目のケースでは、哲学者は彼の注意力のすべてを思考のつながりを決定する方向へと向けています。このことは、最初のケースでは、イメージがでたらめに生じたのに対して、二番目のケースでは、それらが意識的な魂的生活のコントロールの下にあったというのは何故かを説明します。とはいえ、そもそも何故、イメージが生じるのでしょうか。哲学者が見落としているのはその点です。人生を観察する人で、そのようなケースを知っており、問題の哲学者の性格を考慮する立場にある人であれば、私はたまたまそのことを知っているだけではなく、その男をも知っているのですが、次のような仮説を立てるでしょう。その哲学者は、彼には格別興味のない人物について話し合っていたので、会話に集中しつづけるために、ある程度の努力を必要としていた。そのため、一定量の魂的生活がこの会話に関与しないままに取っておかれ、それが内に向かったと。しかし、興味のない会話に注意を割かねばならなかった彼には、結果として生じる一連のイメージをコントロールする力がなく、それらはでたらめに生じることになりました。このことは、そのようなイメージがいかに意識的な魂的生活の背後で、影のように生じるかについての示唆を与えます。このような例は無数に挙げることもできるでしょうが、特にこの例を取り上げたのは、それが非常に特徴的であり、それによって多くのことを学ぶことができるからです。さて、次のように問うことができるでしょう。そのようなできごとは、人間の魂的生活をもっと深く探求するように私たちを促すのではないのか。また、そのような魂的生活の裂け目は、そもそも、どのようにして生じるのかと。私たちはここで、今日取り上げているあのあまり愉快でないテーマに関する経験を、この冬、私たちがあれほどしばしば取り扱ってきたところのものに、全く自然に適合させることができるような領域へとやって来ました。その例の中で触れられた哲学者は、彼の経験を記述しようとして謎に直面しますが、事実を一度告知してしまえば、そこからさらにつづけようとはしません。それは、私たちの科学が事物や人間の本質についての認識の手前で、それがどんなに多くのことを語ることができるとしても、立ち止まってしまうということから来ています。人間の本質的な性質に関する私たちの観察が示したのは、人間は外的な科学によってなされる以上のやり方で眺められなければならない、外的な人間と内的な人間を区別しなければならないということでした。私たちは、あらゆる領域において、通常の科学によって理解されているのとは異なる仕方で眠りに注目するべきだということを示してきました。私たちが示したのは、眠っている人間の中で、ベッドに残っている部分は単に外的な人間であり、その外的な人間をベッドに残していくところの不可視の、そしてより高次の内的な人間は通常の意識をもってしては追い求めることができないということでした。何かが人間から去って行くのですが、それは正にベッドに残る部分と同じくらい現実的なものであり、そして、その内的な人間は、眠りに落ちてから目覚めるまで、その真の故郷である精神的な世界に引き渡されるということを通常の意識は単に理解できないのです。それはまた、彼が通常の魂的生活を支えるために起きてから寝るまでの間に必要とするものをそこから抽出するということを認めることにも失敗します。眠っている間もその法則とともにそこにある外的な人間と、起きている間だけ外的な人間とともにあり、眠っている間は分離する内的な人間を別々のものと見なし、はっきりと区別しなければならない理由がここにあります。この区別をしない限り、私たちは人生における最も重要なできごとを理解することができません。便宜的に、あらゆるものを統一体と見なし、別の考えを容れず、いたるところに一元論を確立しようとする人たちは、私たちが人間を内的な人間と外的な人間のふたつに分けるということのために、私たちに二元論者の烙印を押します。しかし、そのような人たちは、水を水素と酸素に分ける化学者もまたひどい二元論者であると認めないわけにはいかないでしょう。もし、元素をもっと深いところに横たわっているものとして認識しないとすれば、より高次の意味で一元論者であることは不可能です。ところが、最も身近なものの中にのみ統一を見る人たちは、多様な生の本性を観察するとともに、それだけが命を説明することができるようなことがらを認識することを自ら妨げているのです。さて、外的な人間と内的な人間の内にある個々の構成体もまた区別されなければならない、ということも示されました。外的な人間の中で私たちが最初に区別したのは見たりさわったりすることができる肉体です。さらに、その肉体を形成し、作り上げるところの私たちがエーテル体と呼ぶ別の構成体があります。肉体とエーテル体は眠っている間、ベッドの中に残ります。次に、眠っている間、肉体とエーテル体から去り、精神的な世界に入っていく部分は、この連続講義の中で、アストラル体として記述されましたが、それ自身、自我の担い手を包摂しています。けれども、私たちはさらにもっと微妙な区別をしました。つまり、アストラル体の中にある魂の三つの構成体を区別しました。そして、これら三つの構成体を注意深く区別することによって、人生における多くのできごとを説明することができました。私たちは魂の最も低次の構成体を感覚魂と呼び、二番目の構成体を悟性魂あるいは心魂、三番目を意識魂として記述しました。ですから、私たちが内的な人間に言及するときは、あらゆる種類の意志衝動、感情、概念そして考えが区別されないままに入り交じったものについて語るかわりに、魂の中にあるこれら三つの構成体を注意深く区別することができるのです。さて、通常の生活においては、外的な人間と内的な人間の間にはある一定の関係があります。その相互関係は次のようなものです。魂のより高次の構成体がほとんど発達していない場合、私たちを奴隷のように従わせるであろう欲望や熱情を担う魂の最も低次の構成体は感覚体と関連しています。感覚体は感覚魂に似ていますが、それは人間の場合には外的な人間に属していると考えられます。アストラル体はここでいう感覚体とは別に記述されなければなりません。と申しますのも、魂を構成する三つの個々の部分はアストラル体が部分的に改造されたものにすぎないのですが、単にそれから作り出されたのではなくて、分離されたものだからです。起きている間、感覚魂は絶えず感覚体と相互作用しています。同様に、悟性魂もしくは心魂はエーテル体との絶えざる相互作用の中にあり、ある意味で、意識魂は肉体と密接に結びついています。私たちが意識魂の中に入ってくるものに関しては、目覚めた意識に依存している、というはこの理由によります。肉体、感覚、脳の活動により伝達されるものは、まず意識魂の中に入ってくるのです。このように、人間には三つの構成体から成る二つの部門があり、お互いに対応しています。つまり、感覚魂と感覚体、悟性魂もしくは心魂とエーテル体、そして、意識魂と肉体です。この対応は、私たちが内的な人間から外的な人間へと導く糸を解明するための手助けになるとともに、もし、それらが通常の仕方で機能できないとすれば、いかに通常の魂的生活に支障を来すかを私たちに示すことができるでしょう。では何故、このようなことが起こるのでしょうか。感覚魂は感覚体の影響下にあり、これらが正しく対応していないときには、感覚魂の健全な生活は中断されるのです。同様のことは、悟性魂が、エーテル体を正しいやり方で制御し、それを自分のための適切な道具にすることができないときにも起こります。そして、意識魂もまた、肉体がその正常な表現のための障害や妨害になるとき、通常でないものとして現れるでしょう。このように、私たちが人間を体系的に分割するとき、健全な魂的生活に必要な秩序だった対応が見られます。そして、あらゆる種類の障害が、感覚魂と感覚体、悟性魂とエーテル体、意識魂と肉体の間の相互作用の中に生じ得る、ということもまた理解することができます。この複雑な有機体を貫いて走る糸と、生じ得る不規則性を認識できる人だけが魂の中で起こり得る障害を認識することができるでしょう。障害が起こるのは内的な人間と外的な人間の間に不調和があるときだけです。意識による完全なコントロールの下で生じる魂的生活は、一方では意識魂の中に、他方では悟性魂の中に存在するものを示しています。しかし、感覚魂の中には、ほとんどそれとは気付かれないようなイメージ、パリのイラスト画やローマの写真集が、ひとつまたひとつと流れているのです。このようなことが生じるのは、哲学者が彼の前に立っている人物との関係を保ちつつも彼の注意を逸らすことによって、感覚魂と感覚体との間に裂け目を生じさせるためなのです。パリのイラスト画やローマの写真集のイメージは感覚魂の中に求められなければなりません。そこでは今述べたようなコントロールされていないプロセスが生じているのです。二人の人物の間での会話は意識魂の中で起こっています。この場合、注意が会話から逸れて彷徨するのを防ぐように強いられる、という必要性が感覚魂と感覚体との間の亀裂を生じさせた原因となっています。これらは単に一時的な状態です。と申しますのも、独立するのが感覚体だけである場合、最もわずかの妨害が魂的生活に生じるだけだからです。私たちはそのようなときにも、理性と、そして認識を保持する意識の内的な糸とを保つことができます。つまり、今や独立した感覚体のゆえに現れる強制的なイメージとは別に、私たちもまだそこに存在しているのです。そのような亀裂が悟性魂とエーテル体に関して生じるとき、事態ははるかに困難なものになります。そのとき、私たちはあの病理的な状態との境界を接するところの状態の中へとはるかに深く入り込むのです。とはいえ、どこで健全な状態が終わり、どこから病理的な状態が始まるのかを決めるのは困難です。エーテル体がストライキに入るとき、つまり、それが私たちの思考の単なる道具であることを拒否するとき、悟性魂が完全に孤立して経験するところのものを保持することがいかに難しいかをひとつの込み入った例が明らかにするでしょう。エーテル体が独立し、悟性魂に抵抗するとき、思考を十分に表現することが妨げられます。そのため、それは途中で打撃を受け、完遂されることがありません。このことは最も賢いと言われている人たちにも起こる可能性があります。ある奇妙な例を取り上げてみましょう。誰でも笑ってすぐに気付くのは論述の論理的な愚かさです。つまり、皆さんがまだ失っていないものはまだ持っている、というのは論理的な結論であり、皆さんは大きな耳をまだ失っていないので、まだ大きな耳を持っているのです。愚かさは思考が事実と一致しないために生じるのであって、これと全く同様の、つまり、「皆さんがまだ失っていないもの」という先行する論述が不当な仮定であり、そのことに気付いていないというパターンにしたがって、そこでは事態がもう少し込み入ったものとなる人生の最も重要な問題に関し、最も信じ難い間違いが犯されることがあるのです。こうして、ある哲学者は人間の自我に関して自分が打ち立てた理論を大いに強調するのですが、私たちがここでしばしば触れてきたのは、いかに自我が、その定義においてさえ、私たちが有することができるいかなる経験とも異なっているか、ということでした。誰でも、テーブルを「テーブル」、ガラスを「ガラス」、時計を「時計」と呼ぶことができます。「私」という言葉だけは、それが私たち自身を指すときには、他の誰もそれを使うことができません。このことは自我の経験とその他すべての経験との根本的な違いを示唆しています。このようなことは観察することができるか、もしくは半分だけ観察することができます。そして、その哲学者が「したがって、自我は決して対象となることはなく、したがって自我は決して観察され得ない。」というような結論を導くとき、それを半分だけしか観察していません。そして、彼が、「もし、それを把握しようと試みるならば、自我は外的に存在していなければならず、同時に、それ自身の中にも存在していなければならない。」と言うとき、それは賢明な観点であるかのように見えます。これは、木の周りを走っている人にとっては、彼が十分速ければ後ろから自分に追いつけるのだが、と言うのと同じです。自我はそれ自身の中では把握され得ない、という教義がそのような例によって裏付けられるとき、誰かそれを信じない人がいるでしょうか!そして、それにもかかわらず、このことすべては、そのような比較は正当なものではない、という事実に、つまり、自我は観察され得ないという仮定に基づいているのです。木との比較でいえば、ただ次のように言うことができるだけでしょう。自我は木の周りを走る人とではなく、せいぜい、蛇のように木の周りに自分を巻き付ける人と比較するべきだ、そうすれば、多分、足を手で掴むことはできるだろう、と。このように、自我は、私たちの経験の中でも、それ以外のあらゆるものとは全く違ったものなのです。それは主体と客体が一致するものとして把握することができる実体なのです。このことは、あらゆる時代の神秘家達によって、自分のしっぽをくわえる蛇という象徴的な言葉によって示唆されてきました。この象徴を用いてきた人たちは、彼らの前にある象徴の中で、いわば彼ら自身を観察しているのだ、ということを理解していたのです。参照画:ウロボロスのヘビこの例は、いかに私たちがただ感覚体とのみ不調和をきたす可能性があるところの私たちの直接的な知覚についての感情や知覚から、単に純粋な感情や知覚だけではなく、悟性魂もしくは心魂にも影響するところのものへと前進するかということを示しています。思考の内的な消化においては、そして、それは思考そのものに比べると既にはるかに恣意的ではないのですが、イメージそのものが原因となって生じる障害ばかりではなく、全く別の種類の抵抗、そしてそれはその過程を厳密に追求することによって結論に到達できないような思考には認識不可能な抵抗なのですが、そのような抵抗となる何かがあるのです。私たちは、いかに人間がそれとは気付かずに、事実に関する論理ではなく、単なる自分の論理である論理に巻き込まれ得るかという例を見てきました。事実に関する論理は、悟性魂とエーテル体との結びつき、したがって、そのエーテル体に対する支配力が保持されるときにのみ存在します。こうして、私たちの魂的生活が病理的な表現形態を取るのは第一義的には私たちの考えと考えの間の結びつきが損なわれることによるのですが、それはエーテル体がその表現のための健全な道具として私たちの悟性魂に仕えることができないからであるということが明らかになります。けれども、今、私たちの悟性魂の働きを妨げるような障害を作り出すエーテル体が私たちの本性の一部を成しているとすれば、魂が単なる不調から心的な障害へと移行するような影響を及ぼすような原因は何か私たちがコントロールできないようなものの中に横たわっていると言わざるを得ないのかという問は正当なものです。ある意味で、そのような例は、もしそれが真に理解されるならば、ここで何度も強調されてきたこと、私たちの同時代人の多くが、最も開明的な人たちでさえナンセンスであると考えるような何かを私たちに気付かせてくれます。私たちのエーテル体が悟性魂の行く手に障害を置き、その思考のつながりを全うさせないようにするのが観察されます。そのとき、私たちは、自分が無力でもうここから先に進むことはできないと認めるかわりにごちゃごちゃになり、ねじ曲げられた判断を通します。私たちの悟性魂からの判断はエーテル体の侵入によって混乱したものになるのです。ある奇妙な状況、つまり、エーテル体が外的な人間に属しながら、あたかも悟性魂と同レベルにあるかのようにその活動に介入すると考えられるような状況があるのですが、これはどのように説明すればよいのでしょうか。純粋に言葉の上だけで説明するとすれば、「遺伝的な特徴」やその他のことを指摘することができるでしょう。このことは、一定の固定された思考パターンが原因となって、魂に関することがらについて論理的に思考することができない人たちによってなされてきたことです。しかし、魂についてじっくり思考することのできる哲学者は次のように言うでしょう。そのような場合に、魂の中に入って来る不調や混沌とした状態は単に物理的な遺伝の結果ではあり得ないと。ところが、現代の有名な哲学者は、純粋に物理的なものを越えて行くところの私たちの内的な過程を驚くべき言葉で記述しています。ヴントが「これは私たちを永遠に続く進化の闇へと導く」と言うとき、もし私たちが深刻なテーマを扱っていないとすれば、それはなかなかの言葉であると言えるかも知れません。厳密な思考をすることに慣れた人は世界的に有名な哲学者のそのような言葉を奇妙なものと思うでしょう。この言葉を魂と精神は魂と精神だけにその起源を有していると語る精神科学の真実と比べてみて下さい。それは、17世紀に偉大な自然科学者、フランセスコ・レディが別の分野で口にしたもうひとつの真実、すなわち、生き物は生き物だけから発生することができるという真実に比べられるものとして私たちがしばしば見てきたもののさらに高次の真実です。精神科学は物理的な遺伝について明らかにするだけではなく、精神的な要素があらゆる物理的なものの中で活動しているということをも示します。そして、エーテル体の悟性魂に対する妨害的な影響があまりにも大きくなる状況では、恐らく何かが悟性魂に似たエーテル体を形成し、準備したに違いない、ただそれはひどい仕方でそうしたのだと思われます。ですから、もし私たちが現在の私たちの悟性魂の中にそのような不調を見出すならば、そして、もし私たちが私たちの理性を保持することができるならば、私たちはその不調を、それが私たちの身体性にまで貫き至ることがないようなやり方で是正することができるのであって、あらゆる情動が直ちに病気を引き起こすものであると考えるべきではないのです。誰かが心的な障害に陥るとき、それを深く考えることなく外的な影響に帰すのはナンセンスである、という精神科学の観点に立つほど厳密であることは誰にもできません。しかし、一方で、たとえ私たちに自分のエーテル体を変化させる力がないとしても、それは間違いが起こるときに存在するのと同じ不調の法則によって満たされ、色づけられるのであって、その間違いがエーテル体の中で表現されるようになるときに病気になるということが理解されなければなりません。通常、そのような間違いは、私たちの誕生から死までの現在の人生において、直ちに影響を及ぼすというわけではありません。このことが生じるのはそれが繰り返され、習慣になるときです。もし、ある特別な場合のように、私たちが誕生から死までの間、絶えることなく間違いの上に間違いを積み重ねるとすれば、もし、思考、感情、そして意志に関するある種の弱さにいつも流され、誕生から死に至るまでその弱さとともに生きるとすれば話は別ですが、誕生から死までの間の外的な身体性はただ限定的な変化を被るだけなのです。私たちが死の門を通っていくとき、肉体はそのすべての良き性質と悪しき性質とともに破壊され、私たちは、私たちが自分の思考、感情そして意志において創造したあらゆる良きものと悪しきものとを伴って行きます。そして、私たちは、私たちの次の人生のための外的な身体性を構築するに当たり、現在の人生からもたらされるところの思考、感情そして意志における弱さや間違い、混乱をその中に移行させるのです。このように、私たちに対して妨害的に働くエーテル体については、私たちの現在の魂的生活における間違いが直ちに私たちのエーテル体の中にその姿を現すのではなく、現時点では、それは単に、私たちの魂が私たちの次の人生を組織するであろうということに甘んじているのです。私たちのエーテル体の中に原因として、また、ある種の特徴として現れるものは、私たちの現在の人生を遡るのではなく、以前の受肉へと立ち返るとき、確かに見出すことができます。このことは、私たちが心的障害について幅広く理解することができるのは、単に隠された「永遠に続く進化の闇」の中を手探りで進むだけではなく、その人間の以前の存在状態へと赴くときだけであるということを私たちに示します。とはいえ、私たちはこの真実をあまり極端なものとして受け取るべきではありません。何故なら、私たちは、人間が以前の人生から来る性質の他に、遺伝された性質をも彼の内に有しているということ、そして、私たち人間の外的な性質は遺伝されたものとして考えられるべきである、ということに気付いていなければならないからです。人間がひとつの人生から次の人生へと運んで行くものと、祖先から受け継いできた彼の特徴とを注意深く区別することが必要なのです。さて、同様の不調和は私たちの自意識の基礎をなす意識魂と私たちの肉体との間にも生じ得ます。そのとき、以前の受肉に起因するような肉体的な特徴だけでなく、先祖からの系譜の中に見出されるような特徴も現れてきます。しかし、ここでもまた原則は同じです。意識魂の働きが肉体の活動的な法則の中に障害を見出す可能性があるのです。そして、意識魂がこれらの障害に遭遇するとき、心的障害のある種の徴候なかに荒々しく現れるところの様々なことがらが生じます。同様に、ある特定の器官が肉体の中で特に卓越するとき、その器官のあらゆる不幸な側面が現れるのです。私たちの肉体の諸器官が適切に共働し、そして、そのどれもがその他の器官に比べてより発達しているということがなければ、ちょうど健全な目が見ることの妨げにならないように、私たちの肉体は意識魂のための適切な道具となります。この関連で注目されるのは、現代のある重要な科学者によって取り上げられたひとつの症例です。ある人物が片方の目に視覚障害を持っていたために、特に薄暗がりの中では、彼には何か幽霊のようなものが見えるように思われました。この目の障害による彼の視覚への影響のため、彼にはしばしばその行く手に誰かが立っているかのように感じられたのです。目によるそのような影響が障害となる場合、通常の視覚は不可能です。このような部分的な欠陥は全く別の形態を取って現れることもあります。意識魂が肉体の中に障害を見出すとき、それは何らかの器官の特別な卓越性に帰せられることができます。肉体の中の諸器官が通常の共同的な働きを行っているとき、肉体は意識魂にとって抵抗とはならず、私たちは自分の意識を通常の方法で表現することができるのですが、ある器官が特別な卓越性を獲得する場合に限り、障害があることに気付きます。つまり、それは抵抗に遭遇するからですが、この外的世界との自由な関わり合いが妨害され、そして、私たちがその妨害に気付かない場合、より深いところに根ざした病気の徴候としての誇大妄想や偏執狂的な考えが現れるのです。このように、人間を複雑なものとして観察することにより、人生における不調和と調和について理解することができるのですが、精神科学がいかに今日のふさわしい文献の中に示されているところのすばらしい結果を秩序立て、明らかにすることができるかについては、簡潔に示すことしかできませんでした。このことを理解するならば、私たちはさらなる洞察を得ることができるでしょう。つまり、内的な人間の現実や、それぞれの受肉における内的な人間と外的な人間との関わりについての洞察、すなわち、いかに以前の存在状態に由来する弱さや過ちの結果が、外的な人間における何らかの欠陥、例えばエーテル体の欠陥として現れるか、についての洞察をです。しかし、このことはまた、障害があまりにも大きい場合には、強く内的に規則的な魂的生活によってもそれらをいつも克服できるとはかぎらない、ということを私たちに示します。とはいえ、多くの点でそれが可能なのは、普通ではない魂的生活の中に外的な人間と内的な人間の間の衝突だけがあるとすれば、内的な人間をできるだけ強化することが重要である、ということを私たちが理解することもまた可能だからです。この考え方を最後まで厳密に追求しようとしない弱い人間、自分の考えを明確に規定することを欲しない弱い人間、感情が自分の経験と一致するような方法でそれを発達させようとしない弱い人間、そのような人間は、外的な人間の抵抗に対し、ただ弱々しく反対することができるだけでしょう。つまり、彼が自分の内に病気の種を抱えているとき、いつかそのときが来れば、彼は心的な障害に陥るでしょう。しかし、もし私たちが強い内的な存在によって外的な人間による病気に対抗することができるならば、状況は違ってきます。何故なら、ふたつの内、強い方が勝つからです!このことから、私たちが私たちの外的な本性に対し、いつも勝利を収めるとは限らないにしても、規則的で強力な魂的生活を発達させることにより、それに対する主導権を維持するべく多くのことを為すことができる、ということが分かります。そして、私たちがあらゆる些細な不都合によって影響されていると感じないで済むように私たちの感情や情動、そして私たちの意志を発達させるように努め、より大きな文脈を包括するために私たちの思考を拡大することに努め、私たちの思考によって、単にその最も明らかな道筋を辿るだけではなく、その最も些細な成り行きをも追求するように努め、不可能なことを欲するのではなく、状況に即して私たちの望みを発達させることに腐心するのは何故かを理解することができるのです。私たちが強力な魂的生活を発達させたとしても、それでも限界に行き当たるかも知れません。しかし、私たちは、私たちの内的な存在があらゆる外的な抵抗に対して優勢になるように、できるだけのことをしたのです。こうして、私たちは、人間がその魂的生活をそれ相応に発達させることの重要性を理解することができます。今日、魂的生活を発達させるということが何を意味しているかについてはほとんど理解されていません。以前、同じような機会に触れたのは、今日では、体育、例えば、散歩に行くことや肉体を鍛えることに重きが置かれている、ということでした。そこに含まれている原則について、何も言うことはありません。これらは健康的であり得ます。しかし、生理的な強化だけを目指して運動がなされるとき、まるで機械であるかのように外的な人間だけが考慮されるならば、それらがよい結果をもたらさないことは確かです。体育においては、あれこれの筋肉が特に強化されるべきだという観点によって特徴づけられるような運動にとりかかるべきでは全くないのです。そうではなく、私たちはあらゆる運動ごとに内的な喜びを体験できるように、あらゆる運動への衝動を内的な健康の感情から取り出してくるように注意しなければなりません。運動への衝動は魂からやって来るべきなのです。体育の教師は、例えば、あれこれの運動にとりかかるとき、いかに魂があれこれの種類の健康を感じることができるかを感情をもって経験することができる立場に自分を置くことができなければなりません。そのとき、私たちは魂を強化するのです。つまり、もしそうでなければ、私たちは肉体だけを強化して、魂はずっと弱いままに留まる可能性があるからです。人生を洞察する人は、この観点から取り組まれる運動が健康によい影響を与えるものであり、人間を単なる解剖学的な機械であるかのように考えて取り組まれる運動とは全く異なる寄与がある、ということを見出すでしょう。魂の活動と肉体の活動の間の関係が明らかになるのは精神科学の厳密な探求によってのみです。精神的な努力とのバランスを物理的なものによって取ることができると信じている人は本質的なことが分かっていないのです。精神科学の探求者は、例えば、彼が何らかの真実を伝えるように頼まれ、その後、そのテーマについてまだ正しく自分の考えを述べることができず、その思考において正しいイメージを形成することができないような相手の話を聞かなければならないような場合、それが非常に疲れることであるということ、一方、例えば、彼が精神世界を探求する場合、どんなに探求したとしても疲れることはない、ということを知っています。それは、誰か他の人の話を聞くときには肉体的な脳を使う物理的な意志疎通にたずさわっているのに対して、精神的な探求においては、それが低次のレベルにある場合にはまだある程度、物理的な器官が必要であるにしても、より高次の段階に達すれば達するほどその程度は低くなり、したがって、それに応じてますます疲れなくなる、という理由によります。外的な人間が参加しなくても済むようになったとき、消耗と疲労はもはや生じないのです。精神的な活動においては、その衝動が魂自体から与えられるか、あるいは、それが外部から促されるかでは違いがあり、それは区別されなければならない、ということが分かります。人間の様々の発達段階においては、いつでも内的な衝動に対応した事柄が生じていることから、そのことはいつも考慮されるべきなのです。以前に強調された例を取り上げてみましょう。それは、私の小冊子、「人智学の光に照らされた子供の教育」という本の中に見出される例です。そこで述べられているのは、7才までの子供は、まず第一にその行動の全てにおいて模倣への衝動を感じている、ということです。そして、歯牙交替期から思春期までの発達は、「権威にしたがって自らを方向づける」、あるいは、別の人物によって私たちに刻印づけられた印象にしたがって行動する、とでも言えるようなものによって特徴づけられます。模倣と権威への敬意というこれらふたつの段階が無視されたと仮定してみましょう。もし、それらが全く考慮されないならば、外的な体は魂のための道具になるかわりに、不規則に発達することでしょう。そして、さらなる発達過程において、その外的な人間の不規則な性質に対し、魂が正しい方法で影響を及ぼし、それと相互作用する機会を持つことはないでしょう。もし、これらの法則が観察されないならば、人が、その人生における重要な時期にあって、新しい発達段階へと入っていくとき、彼の存在におけるある構成体が停滞するのが分かります。精神分裂病、早発性痴呆の根底にあるのはこの法則を無視するということなのです。早期における正しいプロセスを無視することによって、内的な人間と外的な人間との間の不調和の結果として現れるのは早発性痴呆すなわち時期を逸した模倣の症状です。精神科学によって明確に区分されるこれらのことがらの間にみられる不調和が多くの場合、魂における異常の原因になっている、ということはよくあることなのです。同様に、人生の終わりに向かって現れる老人性痴呆の中に見られるのは、思春期とアストラル体が完成する時期との間に内的な人間と外的な人間の間に調和が存在し得るような方法でその人が生きなかったために生じるところの内的な人間と外的な人間の間の不調和です。このことは、人間についての知識が不調と心的障害の本性を照らし出す、ということを私たちに示します。そして、たとえ私たちが表面的な結びつきしか見出さないとしても、つまり、もし、人が、不調は通常の魂的生活の一部であるから、それは私たちの外的な本性には影響を及ぼし得ない、と言うにしても、それとは反対に、力強い論理の発達すなわち感情や意志において調和的で規則的な魂的生活が外的な人間から生じる障害に対抗して私たちを強化するときにしたがうところの法則は大いに勇気を与えるものである、ということが述べられなければなりません。こうして、精神科学は、多分いつもそうであるとは限りませんが、それでもほとんどの場合、外的な人間の超越あるいは卓越に対抗する可能性を私たちに与えるのです。私たちが内的な人間を強化し、育成するときには、外的な人間の卓越に対抗するためにそうする、というところが重要なのです。精神科学は私たちがこれを行うための癒しの力を与えます。したがって、それがいつも強調するのは、途中で停止することのない、首尾一貫した思考を最後まで追求するため、不適切なものを避けるところの秩序づけられた思考を発達させる、ということの重要性です。内的な規律と調和の中に魂的生活が現れるような仕方でそれを秩序づけることを厳密に要求する精神科学自体が私たちの体的本性における病理的症状の卓越に対抗する医療である、というのはこの理由によるのです。そして、人間が健全な意志、健全な感情、そして自律的な思考の光によって、体的な弱さ、体的な不具合を包み込むことができるとき、彼は病理的な傾向に対して勝利を収めることができるのです。このことは今日では一般的ではありませんが、それでも現在を理解する上でそれは重要です。こうして、精神科学はある慰め、つまり、精神の中には、もし、私たちがそれを真に強化するならば、人生において私たちに影響を与え得るあらゆるものに対する最良の救済があり続けるのだ、という慰めさえ私たちに与えてくれるのです。私たちは精神科学によって精神の単なる理論化を学ぶのではなく、俗物が中途半端な思考で立ち止まろうとするところで努力し続けることによって、それを私たちの中で治癒的な力に変えることを学ぶのです。と申しますのも、「あなたの言う輪廻転生やその他のことを証明してみなさい。」というのは中途半端な思考以外の何者でもないからです。思考をその結論にまで導くことを拒否する人に対してそれを証明することはできません。真実全体を半端な思考をもって証明することはできないのです。それらはただ思考を全うする人にとってのみ証明され得るのであり、そして、全体的な思考は彼の内なる人間によって発展させられなければならないのです。もし、ここで示唆されたことがさらに発展させられるならば、このこと、つまり精神に対する不信が私たちの時代における不徳の中心に位置している、ということが分かるでしょう。しかし、一方で、不信を信へと、つまり、真の精神性へと変容させるための方法がある、ということがそこで示唆されたのだ、ということも分かるでしょう。今日の人類には、論理への信頼が大きく欠けているのです。ですから、精神科学の真実を理解するために必要な論理的な客観性がいつも存在しているわけではありません。ファウストの中で、ある種の人々について語られている言葉を私たちの時代に適用するにしても、それはばかにしたり皮肉を込めてではなく、ある種の悲しみをもってそうするのです。 「たとえ賢者の石を持っていたとしても、哲学者にはちと荷が重すぎるというものだ。」論理は精神科学を理解することができるのです。そして、精神科学の論理的な理解は最奥の広がりを持つ体的本性を癒すことができます。ところで、このことは、今日、精神科学の探求者ばかりではなく、その他の人々によっても主張されています。この主張は現代的な精神科学以外の道によって精神に近づこうとした人々によってもなされているのですが、そのような人々もまた現代ではほとんど理解されていません。ヘーゲルがいたるところに論理の存在と働きと必要性を強調したという正にその理由のゆえに、彼を嘲笑しない人がいるでしょうか。彼は今日の人間の中での論理の働きを次のように考えることによってそのことを強調しました。「私は人生を十字架として想像する」と。そして、彼にとって、十字架上のバラは人間の中の論理に相当するものでした。これが、彼の著作のひとつにおいて、彼が次のようなモットーを前書きに書いた理由です。「論理とは、現代の十字架上のバラである」と。そして、論理への信頼はその十字架を勝利へともたらします。論理への信頼、律せられた思考、調和的な感情や意志への信頼が十字架上にバラを置くことになるでしょう。発達させることができ、そして、発達させなければならない調和的な感情、調和的な意志、そして、自立的な理性に対する信頼を私たちが有するとき、私たちは、私たちの中に、私たちが心的障害と呼ぶところのものに立ち向かうための力を少なくともある程度は有しています。もし、私たちがこれら三つのものを発達させるならば、私たちは、人生におけいかなる状況の下でも、より力強く、意気揚々としていることでしょう。そして、ヘーゲルは、調和的な感情、意志、そして、規律的な思考すなわち理性的な知性を論理の中へと収めるゆえに、私たちが魂的生活を発達させるに際して私たちのモットーとして役立つ言葉、すなわち、論理は人間にとって現代の十字架上のバラであるべきだということを述べているのです。参照画:ヘーゲル人気ブログランキングへ
2024年03月21日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第六講「ポジティブな人とネガティブな人」(1910年3月10日) もし、人間の魂を、ある人を別の人と比較するという方法で検証するならば、そこには考えられる限り最高度の多様性が見出されます。この連続講義では、いくつかの典型的な差異とその理由を、性格や気質、能力や力などに関連づけながらお話ししました。今日は、ひとつの重要な差異、つまり、ポジティブな人とネガティブな人の違いについて考えてみましょう。始めるにあたり、この主題の取り扱いが、そして、これは私の他の講義とも完全に調和することになるでしょう。ポジティブあるいはネガティブなものとして人々を描写するところの表面的ではあるけれども一般的な方法とは何も共通したものを有していないということを明確にしておきたいと思います。私たちの記述は完全にそれ自体の基盤の上に立っているのです。まず、ポジティブな、あるいはネガティブな人というとき、それが何を意味しているかについての明確な定義づけといえるようなものをくまなく探してみるのもいいでしょう。すると、私たちは次のように言うかも知れません。人間の魂に関する真正で洞察力のある教えという意味では、ポジティブな人とは外的世界から彼の上に注ぎ込まれるあらゆる印象に直面したとき、彼の内的存在の堅固さと確かさを少なくともある程度まで保持できる人として定義づけできるだろう。したがって、彼は一定の嗜好とともに、外的な印象がそれを妨害することができないようなはっきりとした考えと概念を有しているだろう。また、彼の行動は彼が日常生活の中で出会うところのいかなる一時的な印象によっても影響されないような衝動によって駆り立てられると。一方、ネガティブな人は移り変わる印象に左右されやすく、あれこれの人やグループから彼にもたらされる考えに強く影響されるような人であるということができます。したがって、彼は、彼が考えていたことや感じていたことを容易に変更させられ、何か異なったものを彼の魂の中に取り込むようにさせられます。彼は、その行動において、他の人々からやって来るあらゆる種類の影響によって彼自身の衝動から引き離されるのです。これが私たちの大まかな定義であり得るのですが、もし、人間本性に深く根ざしたこれらの特徴が実生活においてどのような働きをしているかを調べてみるならば、私たちは、私たちの定義から得るものはほとんどない、そのような便利なレッテルをいくら探してみてもほとんど役に立たない、ということをすぐに確信するでしょう。と申しますのも、もし、それらの定義を実際の生活に適用してみるならば、私たちは次のように言わざるを得ないからです。子供時代からずっと持続してきたある一定の特徴を示す強い熱情と衝動を有する人間はあらゆる種類の善き凡例や悪しき凡例を、それらが彼の習慣に影響を及ぼすことを許さないままに、やり過ごしているであろう。彼は、あれこれのことについて、何らかの考えや概念を形成しており、他のいかなる事実が彼の前にもたらされようともそれにしがみついているだろう。彼が何か他のことを確信できるとしても、その前に無数の障害が山のように積み重なっているだろう、と。そのような人間は確かにポジティブかも知れませんが、それは彼に退屈な人生以外のものはもたらさないでしょう。彼は、彼の経験を豊かに広げるかも知れないものを見もせず、聞きもしないことにより、新しい印象から閉ざされるのです。別のタイプの人間、いつでも新しい印象を歓迎し、事実が彼の考えに反するならば、いつでもそれを訂正する容易ができている人間は、(多分、比較的短い間に)全く異なった存在になるでしょう。彼は、彼の人生の経過の中で、ひとつの興味から別の興味へと急ぎ、そのため、彼の人生の特徴は時間の経過とともに全く変化するように見えるかも知れません。「ポジティブ」なタイプの人間と比較して、彼は、確かにより良く人生を理解しているにもかかわらず、私たちの定義づけにしたがって、私たちは彼を「ネガティブ」と呼ばなければならないのです。もう一度、頑強な性格を有する人間についていえば、彼の人生は習慣と慣例に支配されており、芸術の宝庫のような国を旅するときにも、彼は、彼の魂にあまりにも多くの型にはまった反応を背負わせているために、芸術作品の前を次々に通り過ぎるか、せいぜい、ベデカー旅行案内書を開いて、どれが一番重要かを調べる程度で、結局、美術館から美術館、景色から景色へとずっと見て歩いた後で、少しも豊かになっていない魂をもって家に帰ることになるのです。それでも、私たちは彼を非常にポジティブな人間と呼ばねばならないでしょう。反対に、誰か別の人がちょうど同じコースを旅するとしても、彼の性格は、どの絵にも没頭するというようなもので、ある絵に熱中して自分を見失うかと思えば、次の絵についても、そしてその次の絵についてもという具合です。こうして彼は、あらゆる些細なことに捕らわれる魂とともに歩き通し、その結果、どの印象も次の印象によってぬぐい去られ、そして、彼の魂の中に一種のカオスをもって家に帰るのです。彼は非常にネガティブな人間であり、もうひとりの人間のちょうど対極にあります。この二つのタイプについて、私たちはもっと様々の例を挙げることもできるでしょう。あまりにも多く学んだために、どんなことについても確かな判断ができないほどネガティブな人物についても記述することができるでしょう。彼はもはや何が真実で何が偽りなのかを知らず、人生と認識に関して、厭世主義者になりました。もうひとりの人間も同じ印象をちょうど同じだけ吸収しましたが、彼はそれに働きかけるとともに、彼が獲得している叡知の全体にそれらをどのように適合させればよいかを知っています。彼は、言葉の最良の意味で、ポジティブな人間でありましょう。子供は、もし、自分の生来の性質を主張して、それに反するものすべてを拒絶しようとするならば、大人達に対して暴君的にポジティブになり得ます。一方、多くの経験や間違い、絶望を経てきた人間でも、あらゆる新しい印象に捕らえられ、相変わらず、元気づけられたり、打ちひしがれたりするかも知れません。彼はその子に比べるとネガティブなタイプといえるでしょう。要するに、私たちが、ポジティブあるいはネガティブな人とは、というような決定的な問いに正しく接近することができるのは、その人の人生全体を、何らかの理論的な考えにしたがってではなく、その多様性のすべてにおいて私たちに作用させ、人生における事実やできごとを整理するためにのみ概念を用いるときだけです。と申しますのも、人間の魂をその個人的な特色において議論する場合には、私たちは最高度の重要性をもつ何かに触れることになるからです。もし、私たちが、人間を考察するにあたって、私たちがそう呼ぶところの、この場で、しばしば議論されるような進化を免れることのできないところの生きる実体としての彼を、その完全な存在性のすべてにおいて考察するのでなければ、これらの問いはずっと単純なものになるでしょう。私たちは人間の魂をひとつの進化段階から次の進化段階へと移っていくものとして見るのですが、真の精神科学の意味で言うならば、ある人物の誕生から死までの人生をいつも単一の経過を辿るものとして思い描くことはありません。と申しますのも、私たちは、彼の人生が以前の各地上生の続きであり、後の各地上生の出発点であることを知っているからです。人生をその様々な受肉の全体を通して観察するならば、ある地上生においては発達がいくらかゆっくりしているため、その人は同じ様な性格や考えをずっと保持する、というようなことが容易に理解できます。別の地上生において、彼は、それだけよけいに、彼を新しい段階の魂的生活へと導くような発達に追いつかなければならないでしょう。たったひとつの人生を探求するということは、いつでも、最高度に不十分なのです。さて、ポジティブあるいはネガティブなタイプに関するこれらの示唆が、これまでの講義の中で敷かれた路線に沿って人間の魂を探求する際に、どのように私たちの役に立ち得るのか、と問うてみましょう。私たちは、魂というものが、何気ない一瞥によってそのように見えるような、概念、感情、そして考えの混沌とした流れでは全くない、ということを示しました。そうではなく、それは明確に区別されるべき三つの構成体を有しているのです。これらの内、最初の、そして、最も低次のものを、私たちは感覚魂と呼びました。その基本的な姿を最もよく見ることができるのは、比較的低い発達段階にあり、完全に熱情や衝動、欲望や願望のままに生き、自分の内に生じるあらゆる欲望や願望をひたすら追求する人間においてです。このタイプの人間の中では、人間の魂の自意識的な核である自我は熱情、欲望、そして共感と反感の波打つ海の中にあり、魂の中を嵐が吹き抜けるたびに彼はその影響を被るのです。そのような人間が彼の性向にしたがうのは、彼がそれらを支配しているからではなく、それらが彼を支配しているからです。そのため、彼はあらゆる内的な要求にそのはけ口を与えます。彼の自我がこの波打つ欲望を超えて自らを上昇させることは滅多にありません。私たちは、魂がさらに発達していくとき、いかに自我が力強い中心点から働くかをますますはっきりと見ることになります。進化が進むに連れて、当然の成り行きとして、誰の内にもある魂のより高次の部分が感覚魂に対して一定の支配力を獲得するようになります。私たちはこの高次の部分を悟性魂あるいは心魂と呼びました。人があらゆる性向や衝動にしたがうときにも絶えずそこに存在しているとはいえ、自我が彼の性向や欲望をコントロールし、彼が受け取るところの絶え間なく変化する印象に彼の内的な生活におけるある種の一貫性を賦課し始めるときにのみ効果的になることができるような何かが彼の魂の中に現れます。こうして、この魂の第二の構成体、悟性魂が優位になるとき、私たちの人間についての表象はより深いものになるのです。私たちは、次に、魂の最も高次の構成体、意識魂について語りました。そこでは、自我が十全なる力強さをもって前面に出てきます。そのとき、内的な生活は外的世界に向かいます。その概念的な表象や考えは、もはや、単に熱情をコントロールするためにそこにあるのではありません。何故なら、この段階において、魂の内的な生活の全体は、外的世界を映し出し、その認識を獲得するように自我によって導かれるからです。このことは意識魂が魂の生活を支配するようになったことを示してます。これら三つの魂の構成体はどの人間の内にも存在しているのですが、いずれの場合にも、それらの内のひとつが支配的になっているのです。前回の講義では、魂は発達においてさらに先に進むことができるということ、実際、もし、私たちが言葉の真の意味で人間であるべきであるならば、それは日常生活においてさえ先に進まなければならない、ということが示されたのでした。彼の行動への動機が完全に外的な要求に由来するような人間、ただ共感と反感のみによって行動へと駆り立てられるような人間は、彼の内にある人間本性の真の性質に気づこうと努力したりはしません。精神的な世界から導き出される道徳的な考えや理想へと自分自身を上昇させるような人だけがこれを達成するのです。何故なら、私たちが新しい要素によって魂の生活を豊かにするのはこのようにしてだからです。人間は、彼の内的な存在によって知られざる深みから引き出し、外的世界に刻印するところの何かを人生に持ち込むことができるからこそ、「歴史」を有しているのです。同様に、もし、私たちが外的な経験をある考えに結びつけることができなかったとすれば、決して世界の秘密についての真の認識に到達することはないでしょう。私たちはそれらの考えを私たち自身の中にある精神から取り出し、それらを外的世界に対置します。そして、私たちは、そうすることによってのみ、外的世界をその真の姿において把握し、説明することができるのです。このように、私たちは私たちの内的な存在に精神的な要素を注ぎ込み、外的世界だけからは決して得られないような経験で魂を豊かにするのです。神秘主義についての講義で述べられたように、私たちは、しばらくの間、外的世界の印象や刺激から自分自身を切り離すことによって、つまり、魂を空にするとともに、通常は日常生活の絶え間ない経験によってうち消されているけれども、今や炎へと燃え上がらせることができるような、マイスター・エックハルトが言うところの小さな炎に没頭することによって、魂的生活のより高次の形態へと上昇します。この階級にある神秘家は、日常のレベルを超えた魂的生活へと上昇します。つまり、彼は、世界の神秘が彼の魂の中に置いたもののヴェールを取り除くことによって、彼自身がその世界の神秘の中に沈潜するのです。その次の講義では、私たちは、もし、人がそれを静かに受容する態度で未来を待ち受け、そして、過去を振り返るにあたっては、彼の日常生活において明らかになるようないかなるものよりも偉大な何かが彼の内にはあるということを感じるならば、彼は、祈りの中で、この彼の上にそびえ立つより偉大なものを見上げざるを得ないようにさせられるであろうということ、つまり、彼は、その中で、彼の通常の生活を超越する何かに向けて、自分自身を超えて内的に上昇するのだということを見てきました。そして、最後に、イマジネーション、インスピレーション、そして、インテュイションという3つの段階を通じて人間を導くところの真の精神的な訓練によって、彼は、光と色の世界が盲目の人には閉ざされているように普通の人々には知られていない世界へと成長することができるということを見てきたのでした。こうして、私たちは、いかに魂が通常のレベルを超えて成長することができるかを見ることによって、それが限りなく多様な段階を経て発達していく様子を垣間見ることができたのです。もし、私たちが周囲にいる人たちを見回してみるならば、彼らはきわめて異なった発達段階にある、ということが分かります。ある人は、自分の魂をある一定の段階にまで上昇させており、自分が獲得したものを死の門を通って運んで行くことができる可能性を有している、ということをその人生の中で示すでしょう。もし、人々がある段階から別の段階へと移っていく様子を研究するならば、私たちはポジティブな性質とネガティブな性質という概念へと至るのですが、あるひとりの人がポジティブ、あるいはネガティブであると言うことはできません。何故なら、彼は彼の発達段階に応じて両方の特徴を示すであろうからです。ある人は、当初、最も強固で最も頑固な衝動を彼の感覚魂の中に有しているかも知れません。そのとき、彼ははっきりとした衝動、熱情、欲望に駆られる一方、彼の自我中心は比較的ぼんやりしたものにとどまり、しかも自分でそのことに気がつかないかも知れません。この時点で、彼は非常にポジティブであり、ポジティブなタイプの人間としてその人生を追求します。しかし、もし彼がその状態にとどまるならば、彼は進歩することができません。彼は、その発達過程において、ポジティブな人間からネガティブな人間に変化しなければならないのです。何故なら、彼は、彼の発達が要求するものが何であれ、その受容に向けて開かれていなければならないからです。もし、彼が彼の感覚魂の中のポジティブな性質を抑制し、それによって新しい印象が流れ込むことができるようにする準備をしていないとすれば、つまり、もし、彼が彼に自然に備わったポジティブな性質から抜け出し、ある種のネガティブな受容性を獲得することができないとすれば、彼はそれ以上先に進むことができないでしょう。ここで私たちは魂にとって必要であるとはいえ、危険の源泉ともなり得る何か、つまり、私たちの人生を安全に導くことができるのは魂に関する親密な知識のみである、ということを非常にはっきりと示すような何かに触れることになります。もし、私たちが魂の生活に影響を及ぼすようなある一定の危険から逃れようとすれば、私たちは進歩することができない、というのが実際のところなのです。そして、ネガティブな人間にとって、彼が外的な印象の流れ込みに対し、そして、それらと一体になることに対して開かれているために、この危険は絶えず存在しているのです。このことは、彼がよい印象ばかりではなく、危険で悪い印象もまた取り込むであろう、ということを意味しています。非常にネガティブな人間が別の人間に出会うとき、彼は簡単に我を忘れ、判断や理性とは何の関係もないありとあらゆることに聞き入り、その人間が言うことばかりではなく、彼がすることにも影響を受けるでしょう。彼は、その人間に非常によく似てくるほどまでにその行動やお手本を真似するかも知れません。そのような人物は確かによい影響に対して開かれているかも知れませんが、あらゆる種類の悪い刺激にも応答し、それを自分のものにするという危険にさらされることになるでしょう。もし、私たちが普通の生活から私たちの周囲で活動する精神的な事実や存在とは何かを見ることができる水準へと上昇するならば、ネガティブな魂的性質を有する人間は、外的な生活においてはほとんどそれとは分からないようなあの曖昧で漠然とした印象からくる影響にとりわけ開かれている、と言わざるを得ません。例えば、実際、人間が独りでいるときには、多人数の集団の中にいるときの彼とはかなり異なっている、その集団が活動的であるときには特にそうである、というようなことがあります。彼が独りでいるときには、彼は彼自身の衝動に従い、たとえ弱い自我といえどもその活動の源泉をそれ自身の中に探求するでしょう。しかし、多人数の集団の中では、一種の集団魂が存在しており、そこにいる人たちに発するあらゆる種類の衝動や欲望、評価がともに流れているのです。ポジティブな人間はこの集合的な実体に容易に自分を明け渡すことはないかも知れませんが、ネガティブな人間は絶えずそれに影響されるでしょう。ですから、私たちは方言で詩を書いたローゼガーが二、三の言葉で表現したところの真実を何度でも経験することができるのです。彼の次のような言葉は乱暴ですが、そこには真実の核心以上のものがあります。「ひとりで人間、ふたりで皆の衆、もっといりゃあ畜生だ」。人は独りでいるとき、仲間といるときよりも賢い、ということに私たちはしばしば気がつきます。と申しますのも、そのとき、彼らは、ほとんどいつでも、そこで支配的な平均的雰囲気に左右されるからです。こうして、ある人ははっきりとした考えや感情を持たずに集会に出かけ、以前は特に気にも留めなかった何らかの論点を、講演者が熱心に語るのを聴きます。彼は、その講演者からは、その講演に応える聴衆の歓呼からほどには影響されなかったかも知れませんが、その歓呼にはしっかりと心をつかまれ、全くの確信を持って家に帰るのです。この種の集団心理は人生において大変大きな役割を演じます。それはネガティブな魂がさらされる危険、特に、党派主義の危険を示しています。と申しますのも、私たちが誰かに何かを確信させようとして失敗するにしても、もし、彼を党派やグループの影響下に置くことができるならば、そこには魂から魂へと広がる集団心理が働いているために、そうすることは比較的容易だからです。ネガティブなタイプの人にとっての大いなる危険がここにあるのです。私たちはさらに先に進むことができます。これまでの講義で、いかに魂が、精神生活において、より高次の領域に自ら上昇することができるかを見てきました。そして、私の「神秘学概論」の中で、魂がこの段階を追った上昇を達成するために、どのように自らを訓練しなければならないかが説明されているのを皆さんは見出されるでしょう。魂は、まず最初に、自らの中のポジティブな要素を抑制し、故意にネガティブな雰囲気にすることによって、新しい印象に向けて自らを開放しなければなりません。そうする以外に、それは進歩することができないでしょう。私たちは、精神的な探求者が存在のより高次の段階に到達することを望むならば、彼が何を為すべきかについて、何度も説明してきました。彼は、通常は眠りにおいてもたらされるような、魂が外的な刺激を全く受容しない状態を故意に、そして意識的に生じさせなければなりません。つまり、彼は、彼の魂が全く空になるように、すべての外的な印象を締め出さなければならないのです。そして、彼は、もし、彼が初心者であるとすれば、彼にとって最初は全く新しいものに見える印象に向けて彼の魂を開かなければなりません。これは、彼が自分自身をできるだけネガティブにしておかなければならない、ということを意味しています。そして、神秘主義的な生活におけるあらゆるもの、そして、私たちが内的な観想、内的な瞑想と呼ぶところのより高次の世界の認識が魂の中に生じさせるのは、基本的には、正にネガティブな雰囲気なのです。それは避けられないことです。人が外的世界からの印象をすべて抑制し、そして、完全に自分自身の中に沈潜するとともに、以前は彼のものであったポジティブな性格を消し去るような状況を意識的に達成するとき、彼はネガティブに、そして自分自身に没頭するようにならざるを得ないのです。もっと容易で外的な方法を取るときにもこれと同様のことが起こります。この方法自体が私たちをより高次の生活に導くことはありませんが、それは私たちの上昇のための支えを与えてくれます。例えば、一種の動物的なやり方でポジティブな衝動を引き起こすような食べ物から特別な食事、すなわち野菜やそういったものに移行するとき、そのようなことが起こります。確かに、菜食主義やあれこれのものを食べることによって高次の世界に上昇することができるようになるわけではありませんし、それによってあの高みへと上りつめることができるとすれば、それはあまりに安易なことでありましょう。私たち自身の魂への働きかけ以外に、私たちをそこへ連れていくことができるものは何もないのです。けれども、栄養における特別な形態が有する妨害的な影響を避けることによって、その働きかけをもっと容易なものにすることはできます。より高次の、より精神的な生活を送ろうと試みる人は誰でも、ある種の食習慣を採用することによって、彼の力を高めることができる、ということを容易に確信することができます。と申しますのも、もし、彼が頑強でポジティブな要素を彼の中に育てる傾向のある食物を遠ざけるならば、彼はネガティブな状態へともたらされることになるからです。真の精神科学の基盤の上に立ち、いかさまとは無縁の人であれば誰でも、真の精神的な生活へと導く努力に実際に結びついた事柄を、たとえそれが外的なものであったとしても、認めないということは決してないでしょう。しかし、これは、私たちが悪しき精神的な影響にさらされるかも知れない、ということを意味しています。私たちが精神科学によって自分を教育し、日常的な印象をぬぐい去るとき、私たちは絶えず私たちの周りにいる精神的な事実や存在たちに私たち自身を開放します。確かに、彼らの中には、適切な器官が私たちの中で展開するとき、私たちが最初に知覚するのを学ぶところの善き精神的な力や勢力がいるかも知れませんが、私たちは悪しき精神的な力や勢力にも曝されることになります。それは、ちょうど、調和のとれた音の調べを聞くためには、不調和な音にもまた開かれていなければならないのと同じです。もし、精神的な世界に貫き至ることを欲するならば、その経験の悪しき側面にも遭遇しやすくなる、ということを明確にしておかなければなりません。私たちがネガティブな性質をもって精神世界に接近すべきであるならば、私たちは危険につぐ危険に脅かされることになるのです。精神的な世界から目を移し、通常の生活について考えてみましょう。例えば、菜食主義は、何故、私たちをネガティブにするのでしょうか?もし、そのようなことが推奨されているからとか、あるいは確かな判断もなく、私たちの生活様式や行動様式を変えることもせずに、単に原則の問題として菜食主義者になるとすれば、ある種の条件下で、それは私たちの上に、おそらくある種の身体的な特徴の上に、その他の影響との関連で、深刻な弱体化をきたすような影響を及ぼすかも知れません。けれども、もし、私たちが、外的な生活に発する使命ではなく、豊かに発達する魂の生活に発する新しい使命を含む自主的な生活に入っているとすれば、食習慣における新しい路線を取るということも、そして、以前の私たちの食習慣から生じているであろう何らかの障害を取り除くということも、非常に有益であり得るのです。物事は、異なる人々に対して、非常に異なった効果を及ぼします。ですから、精神科学の探求者はここで何度も強調されてきたところの次のようなことがらに固執します。つまり、人は新しい印象を受け取るために必要とされるネガティブな魂的性質をただ単に育成したり、内的な観照や内的な集中を発達させることに満足したりすべきではない、何故なら、新しい段階へと上昇すべき生活は、それを満たし、支えることができるほど十分に力強い内容を有していなければならないからである、ということを明らかにすることなく、高次の世界へと上昇する方法を誰かに伝えることはありません。もし、私たちが、精神的な世界をのぞき見ることを可能にするであろうような力を獲得する方法を単に誰かに示すとすれば、私たちはその人を、その種の努力にはつきもののネガティブな性質を通して、あらゆる種類の悪しき精神的な力に曝すことになります。けれども、もし、彼が精神的な探求者によって伝えられるところの高次の世界について喜んで学ぶのであれば、彼は決して単にネガティブなままにとどまることはないでしょう。何故なら、彼は、より高次の段階にあるポジティブな内容を彼の魂に浸透させることができるような何かを有することになるからです。私たちが、探求者は単により高次の段階に向けて努力するだけではなく、同時に、精神科学が伝えるところのものを注意深く研究しなければならない、ということをこれほど何度も強調するのはこのような理由によります。新しい領域を経験すべき人はそれらに対して受容的であり、したがってネガティブでなければならない、という事実を精神的な探求者が考慮するのはこのようにしてなのです。私たちは、私たちが意識的に魂の開発に乗り出すときに呼び出すべきものを、通常の生活の中で出会うような様々な人々の中に見ることができます。それは、魂が、ただ現在の生活の中でのみ発達を遂げているのではなく、以前の生活の中での発達を経験した後、地上的な存在状態に入るという決定的な段階にあるからなのです。私たちが現在の生活の中で段階的に先に進むとき、ちょうどポジティブな段階に進むためにネガティブな性格を獲得しなければならないように、多分、私たちが最後に死の門を通り、ポジティブあるいはネガティブな性格をもって新しい生活に入ったときにも同様のことが起こったかも知れません。私たちをポジティブな性格とともに人生へと送り出したデザインは、私たちを今いる場所に取り残し、さらなる発展にとってのブレーキとして働くでしょう。何故なら、ポジティブな傾向とは明確に規定された性格を形成するものだからです。一方、死と新たな誕生の間に、多くのものを魂の中に受け入れるのを私たちに可能にするのは、正に、ネガティブな傾向なのです。しかし、それは私たちを地上の生活における多くの偶然のできごと、特に他の人々が私たちに投げかける印象にも曝します。ですから、ネガティブなタイプの人間が他の人々に出会うとき、その人々の性格が彼の上に刻印づけられるのがよく見られます。彼が友人や好意的な関係にある誰かと親交を結ぶとき、いかに自分がますます相手に似てくるかを自分自身で感じることさえできるでしょう。結婚や親密な友人関係の場合、筆跡さえ似てくるかも知れません。それを観察すれば、ネガティブな人の筆跡が本当にその結婚相手の筆跡にますます似てくるのが分かるでしょう。このように、ネガティブなタイプの人というのは他の人、特に親しい関係にある人の影響を受けやすいのです。ですから、彼らはある一定の危険、つまり、自らを失い、自分たちの魂的生活や自我感覚が消されてしまうかも知れないという危険に曝されているのです。ポジティブなタイプの人にとっての危険とは、彼が他の人々からの印象を簡単には受け入れられず、彼らの特徴的な性質を評価するのにしばしば失敗するかも知れないということ、そのため、彼はすべての他の人のそばを通り過ぎ、誰とも友人関係や親しい交わりを築くことができないだろうということです。ですから、彼には、彼の魂が硬化し、荒廃する危険があるのです。人々をそのポジティブあるいはネガティブな側面において考察するとき、人生に対する深い洞察が得らます。そして、これは人々が彼らの周りの自然に対するときの様々な方法にも当てはまります。では、ある人が他の人々からの影響や、外的世界からの印象を受け取るとき、その人に働きかけているものとは何なのでしょうか。魂に絶えずポジティブな性格を与えているものがひとつあります。それは、現代人にとって、その発達段階に関わらず、人生の中で生じるであろうあらゆる状況あるいは関係を明かにしてくれるところの健全な判断であり、合理的な検証です。この反対が、健全な判断の喪失であり、ポジティブな性質による防御が破られるような仕方で印象が受け取られる場合です。私たちは、ある種の人間活動が無意識の中に落ち込むとき、それはしばしば通常の判断が意識的に行使されているときよりも強力な影響力を人々に及ぼすということさえ観察することができます。不幸なことに、特に、精神科学運動にとって不幸なことなのですが、精神世界に関する事実が厳密に論理的な形態において、つまり、それ以外の生活領域においてはよく認知された形態で示されるとき、人々はそれから逃げ腰になる傾向があるのです。彼らは、そのような事実が原因と結果の合理的な関係において示されるのを、しっくりこないと思うのです。一方、彼らは、これらの情報が彼らの判断を喚起しないような方法で伝えられるときには、はるかに容易に反応するのです。合理的な言葉で伝えられる精神世界についての情報にはきわめて疑り深い反面、漠然とした力によって吹き込まれたように見える霊媒から聞いたことは何でも信じ込む人たちさえいます。自分が何を言っているのか知らず、自分が知っている以上のことをしゃべるこれらの霊媒たちは、自分が何を言っているのかを正確に知っている人たち以上に多くの信者たちを引きつけます。少なくとも半意識状態にあり、明らかに何か別の力に捉えられている人でなければ、このように言われるのを私たちはよく耳にするのですが、どうして精神世界のことを私たちに告げられるだろうか。これは、精神世界から引き出された事実を「意識的に」伝えることに反対する理由としてよく言われることです。健全な判断に基づき、合理的な言葉で伝えられる情報に注意を払うよりは、霊媒のところに走る方がはるかに一般的である理由がこれなのです。精神世界に由来するものは、それが何であれ、意識を排除された領域へと突き落とされるとき、魂のネガティブな性格に働きかける恐れがあります。何故なら、このような性格は、意識下の暗い深みからの影響が私たちに迫るとき、いつでも前面に出てくるものだからです。綿密な観察が示すように、比較的愚かな人物が、そのポジティブな性質のおかげで、より知的な人物に対し、もし、後者が意識下の暗闇から現れるあらゆるものに印象づけられやすい性格であるとすれば、強い影響力を持つ、ということがよくあります。こうして、私たちは、何故、人生においては、繊細な心をもった人たちが頑強な性格の人たち、その主張が彼ら自身の衝動と傾向だけから導き出されるような人たちの餌食になる、というようなことが起こるのかを理解します。このことにさらに一歩踏み込むならば、ある顕著な事実に至ります。単に、ときとして理性のあるところを見せないだけなのではなくて、心の病に罹っており、彼の混乱した状態から湧き出すようなことを口にする人について考えて下さい。彼は、彼が病気だと気づかれない限り、繊細な性質を持った人に対し、普通ではない強さの影響を及ぼすかも知れません。このようなことすべては人生の叡知に属しています。ポジティブな性質を持った人間は道理に対して開かれていないだろう、一方、ネガティブなタイプの人間は、しばしば、彼には締め出すことのできないような非合理な影響に左右されやすいだろう、というようなことに気づかない限り、それを正しく理解することはできません。より緻密な心理学はこれらの事柄を考慮しなければならないでしょう。さて、個々人がお互いに及ぼしあう印象についてはこれくらいにして、人々が彼らの周囲の環境から受け取る印象に移りましょう。ここでもまた、私たちは、ポジティブ、ネガティブという文脈の中で、重要な結果を得ることができます。例えば、ある特定のテーマについて、非常に実り多い働きをし、それに関連する多数の事実を集積した探求者について考えてみましょう。これによって、彼は人類にとって何か有益なことを成し遂げました。今、彼がこれらの事実を彼が受けてきた教育やそれまでの人生から得られた考え、あるいは、それらの事実についての非常に一面的な見方を提示するかも知れないようなある特定の理論や哲学的な観点から得られた考えに結びつける、と想像してみて下さい。彼がその事実から推量した概念や考えは彼自身の内省的な思考の結果であることから、魂に対して健全な影響を及ぼすのです。何故なら、彼は、彼自身の哲学を苦心して作り上げることによって、彼の魂にポジティブな感情を吹き込んでいるからです。けれども今、彼が何人かの追従者を見出すと想像して下さい。彼らはその事実について自分でよく調べたのではなく、単にそれについて聞いたり読んだりした人たちです。彼らは、その探求者が彼の研究室での仕事や勉強によって自分自身の中に引き起こしたところの感情に欠けているでしょう。そして彼らの気分は完全にネガティブであるかも知れません。こうして、全く同じ教義が、たとえそれが一面的なものであるにしても、その一団の指導者を彼の魂においてポジティブにする一方、単にその教義を繰り返すためにそこに群れ集まった追従者達に対しては、不健全でネガティブな影響を及ぼし、彼らをますます弱めるかも知れないのです。これは何か人類の文化史全体を通して流れているところのものです。今日でも、完全に唯物的な世界観をもった人たちが、そして、彼らは彼ら自身の発見に基づいてその世界観を発展させようと精力的に働いているのですが、いかに生き生きとしてポジティブな性格であるか、会うのが楽しみであるような人たちであるかが分かります。しかし、彼らの追従者達の場合、同じ基本的な考えを頭に入れて持ち運んでいるとはいえ、彼ら自身の努力によってそれらを獲得したわけではないために、それらの考えには不健康で、ネガティブで、弱体化させるような効果があるのです。こうして、人が自分自身で哲学上の観点を達成するか、あるいは単に他の人からそれを取り入れるかでは大きな違いがある、と言うことができます。前者はポジティブな性質を、後者はネガティブな性質を獲得するのです。このように、私たちの世界に対する態度は私たちをポジティブにもネガティブにもすることができるものである、ということが分かります。例えば、自然に対する純粋に理論的なアプローチは、特に私たちが実際に自分の目で見ることができるあらゆるものを見落とすとすれば、私たちをネガティブにするのです。自然に関する理論的な認識は存在しなければならないのですが、この認識(動物、植物そして鉱物の系統的な研究から得られ、自然法則として概念や考え方の中に体現したところの認識)は、私たちのネガティブな性質に働きかけ、私たちをこれらの考えの中に閉じこめるだろう、という事実に対して盲目であってはなりません。一方、自然がその雄大さの中で私たちに差し出すものすべてに対し、生き生きとした鑑賞力を持って応えるならば、つまり、例えば、花をバラバラに引き裂くのではなく、その美に反応しながら、その中に喜びを見出すとすれば、あるいは、太陽が昇るとき、朝の光をいっぱいに受けながら、それを天文学的に検証するのではなく、その栄光に見入るとすれば、私たちの魂の中にはポジティブな性質が呼び覚まされます。私たちの魂は、私たちが世界に関する理論的な概念を通して受け入れるところのいかなるものにも巻き込まれることはありません。そのとき、私たちは、他の人たちがそれを私たちに口述させるがままにするのです。しかし、私たちが自然の現象に快や不快を感じるとき、私たちの魂全体はそれに生き生きと関わっています。自然の真実が自我に左右されることはありませんが、私たちを喜こばせたり、不愉快にしたりするものは違います。何故なら、私たちが自然に対し、どのように反応するかは、私たちの自我の性格にかかっているからです。こうして、私たちは次のように言うことができます。自然への生き生きとした参加はポジティブな性質を、自然の理論化はネガティブな性質を発達させる、と。ただ、このことは、繰り返しになりますが、一連の自然現象を最初に分析する研究者が、彼の発見を単に受け入れたり、それらから学んだりする人よりもはるかにポジティブである、という事実によって修正されなければなりません。この違いは教育の幅広い分野において注意を払われるべきものです。これに関連して、今日お話ししてきたような事柄についての意識が存在していた場所では、人間の魂のネガティブな性格がそれ自身のために養成されることは決してなかった、という事実があります。プラトンは、彼の哲学のための学院への入り口に、何故、「幾何の知識を有するものだけが入ることを許される。」という言葉を刻んでいたのでしょうか?それは幾何と数学が他人の権威によっては受け入れることのできないものだからです。私たちは、私たち自身の内的な努力によって幾何をやり通さなければならず、ただ、私たちの魂のポジティブな活動によってのみそれを修得できるのです。今日、このことに注意が払われていたならば、あたりをうるさく飛び回る哲学大系の多くは存在していなかったでしょう。と申しますのも、幾何学のような思考体系が打ち立てられるために、いかに多くのポジティブな働きがつぎ込まれたかに気づく人は誰でも、人間精神の創造的な活動に対して敬意を払う、ということを学ぶであろうからです。ところが、例えば、ヘッケルの「世界の謎」を、それがどれほど苦心してつくりだされたものであるかに思いをはせることことなく読む人は、全く容易に新しい世界観へと至るかも知れませんが、彼は魂の純粋にネガティブな状態からそうすることになるのです。さて、精神科学、もしくは人智学には、何か無条件にポジティブな反応を要求するものがあります。もし、誰かが、よく知られた近代的な装置、写真やスライドを使えば、動物だの自然現象だのが彼の目の前でスクリーンに映し出されるのですよ、と言われるならば、彼はそれをネガティブな気持ちで、全く受動的に見ることになるでしょう。ポジティブな性質は必要とされず、考えることすら必要とされないかも知れません。あるいは、彼は氷河が山を下っていくときの様々な局面を映し出すところの一連の写真を見せられるかも知れません。それも全く同じことです。これらの例は、このようにネガティブな態度に訴えかけるものが、今日、いかに幅広く存在しているかを示しています。人智学はそれほど単純ではありません。写真は、せいぜい人智学的な考え方のいくつかを象徴的に示唆することができるだけでしょう。人はその魂の生活を通してのみ精神の世界に近づくことができるのです。実り多いやり方で、精神科学に精通したいと望む人は誰でも、その最も重要な要素が見せ物の題材になったりすることはない、ということに気づかなければなりません。ですから、彼への助言は、活動し続けるということ、それも彼の魂とともに、そして、そのことによって、その魂のもっともポジティブな性質を引き出すということです。実際、精神科学はこれらの性質を人間の魂の中に育成するのに、最高の意味で、ふさわしいものです。それは魂の中で眠っている力をかき立てる以外のことは要求しないのですが、ここにもまたその世界観の健全さが存在しているのです。人智学は、あらゆる魂に本来備わっている活動に訴えることによってその隠された力を呼び覚まし、それらが身体のすべての活力と精力に浸透するようにします。ですから、それは、人間の体全体に対し、十全なる意味において、健康を与える効果を有しているのです。そして、人智学は、集団心理によってではなく、ただ個々人の理解力を通してだけ呼び出される健全な理性にのみ訴えかけ、集団心理が引き起こすあらゆるものを放棄しているがゆえに、人間の魂の最もポジティブな性質を考慮するものなのです。このように、私たちは、作り話ではなく、いかに人間がふたつの流れ、ポジティブな流れとネガティブな流れのただ中に置かれているかを示す多くの事例を集めて来ました。彼は、より低次のポジティブな段階を離れ、彼の魂が新しい内容を得ることができるようなネガティブで受容的な状態へと赴くことなしに、さらに高次の段階に上昇することはできません。 つまり、彼はこのネガティブな状態をずっと伴っていくことによって、より高次の段階において、もう一度ポジティブになるのです。もし、私たちが自然を正しく観察することを学ぶならば、私たちは、いかに人間が、世界の叡知による配剤にしたがって、ポジティブな位相からネガティブな位相へと、そして再びポジティブな位相へと導かれるかを見ることができます。このような観点から、特別なテーマ、例えば、アリストテレスの有名な悲劇の定義について学ぶのは有意義なことです。彼によると、悲劇とは、観客の中に恐れと哀れみを引き起こすことができるような完全に劇的な演技を、これらの感情が浄化され、その罪障が消滅するような仕方で私たちの前に提示するものです。人間は、最初、彼の通常のエゴイズムとともにその存在状態に入るに際し、非常にポジティブであるということ、つまり、彼は彼自身を硬化させるとともに、他の人間から自分を切り離す、ということに注意しましょう。けれども、その後、もし、彼が、他の人たちの悲しみに同情したり、彼らの喜びを自分の喜びとすることを学ぶならば、彼は非常にネガティブになるのです。それは、彼が自分の自我から離れ、他の人々の感情に参入するからです。私たちがネガティブになるのは、誰か別の人に降りかかるように見える何か漠然とした運命、つまり、私たちが親密な共感をいだいている誰かに、明日、降りかかるかも知れないできごとに深く心を動かされるときです。誰かが自分を破局へと導くであろう行いに向けて急ぐとき、つまり、私たちにはそれを予見することができるけれども、自分の衝動に突き動かされているために、彼にはそれを避ける力がないような破局に急ぐとき、誰が震撼せずにいられるでしょうか。私たちはそれがもたらすはずのものを恐れるのですが、そのことが私たちの中に魂のネガティブな状態を醸し出すのです。何故なら、恐れはネガティブなものだからです。もし、私たちが、危険に満ちた未来に近づきつつある誰かのために恐れをいだくことができないとすれば、私たちはもはや人生の中で真の役割に与ることはないでしょう。私たちをネガティブにするのはそのような恐れと共感なのです。悲劇が私たちの前にヒーローを登場させるのは、私たちを再びポジティブにするためです。私たちが彼の行為に共感を覚え、そして、彼の運命を非常に身近に感じることで、私たちの運命が目覚めさせられるのです。同時に、そのヒーローの姿は、演劇の進行とともに、私たちの恐れや哀れみが純化されるような仕方で私たちの前に現れます。つまり、それらはネガティブな感情から、芸術の働きによって私たちに付与されるところの調和的な満足へと変化させられ、それによって、私たちは再びポジティブなあり方へと上昇させられるのです。こうして、古代ギリシャの哲学者による悲劇についての定義が私たちに示すのは、いかに芸術が必然的にネガティブな状態の感情をポジティブな状態に変容させるところの人生における要素であり得るか、ということです。私たちは、当初、より低次の発展段階からさらに発達していくために、ネガティブでなければならないのですが、芸術はそのあらゆる領域において私たちをより高次の水準へと導くのです。美は、さしあたり、私たちが私たちの現在の段階を超えて上昇するのを助けるために私たちの前に置かれるように意図されたものである、と見なければなりません。そのとき、通常の人生は、もし、私たちが既に芸術を通してより高次の水準に上昇させられていたとすれば、魂のより高次の状態から放射するもので浸透されるのです。こうして、私たちは、いかにポジティブとネガティブな性質が、個々人の間だけではなく、人間の一生を通じて交替するものであるか、そして、それが、いかに個人とそして人類全体をある受肉から次の受肉へと上昇させることに寄与するものであるかを理解します。もし、時間があれば、いかにポジティブあるいはネガティブな時代と歴史的な年代があったかを容易に示すこともできたでしょう。ポジティブとネガティブの考え方はあらゆる魂の生活領域と広く人類全体の生活領域に光を当てるのです。ある人がいつもネガティブで、別の人がいつもポジティブであるというようなことは決して起こりません。私たちひとりひとりが存在の様々な段階で、ポジティブとネガティブな状態を通過しなければならないのです。その考え方をこの光の下に見るときにのみ、私たちはそれを真実として、したがって、人生を実際に生きるための基本として受け入れることができるのです。こうして、私たちは、この連続講義の始めと終わりに置いてきた言葉、つまり、人生をあまりにも深くのぞき見ることができたために「変人」と呼ばれた古代ギリシャの哲学者、ヘラクリトスの「いかなる道を探求しようとも、魂の境を見出すことは決してできないだろう。魂の存在とはそれほど包括的なものなのだ。」という言葉を今日の議論でも確認しました。さて、誰かが次のように言うかも知れません。「では、魂についてのあらゆる探求は無駄に違いない。何故なら、もし、その境界を見つけることが決してできないとすれば、いかなる探求もそれを確定できず、そもそもそれについて何かを知るということは絶望的なことなのだから」と。ただネガティブな人だけがこの路線を取ります。ポジティブな人は次のように付け加えるでしょう。「魂の生活があまりにも深遠で、知識が決してそれを取り巻くことができないことを神に感謝する。何故なら、それは、今日、理解したことを明日は越えていくことができ、それによって、より高次の水準へと急ぐことができるということなのだから」と。あらゆる瞬間に、魂の生活が私たちの知識をあざ笑うことに感謝しましょう。私たちは際限のない魂的生活を必要としています。何故なら、この無限の展望こそ、私たちが絶えずポジティブな性格を越え、段階を追って上昇することに対する希望を与えるものだからです。私たちが希望と確信をもって前を見ることができるのは、正に、私たちの魂的生活が際限のないものであり、不可知のものである、その程度においてなのです。決して魂の境を発見することができないがゆえに、魂はそれを越え、より高く、どこまでも高く上昇することができるのです.参照画:アントロポゾフィ人気ブログランキングへ
2024年03月20日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第五講「病気と治療」(1910年3月3日) 恐らく、この冬の間、ここで私が開くことを許された講座に、多かれ少なかれ定期的に参加されている皆さんには、今回の連続講義は魂についての一連の遠大な疑問を取り扱ってきたのだということが明らかになっていることでしょう。今日の講義でもそのような問題、つまり、病気と治癒の本質に関する問題を取り上げようと思います。それに関して、精神科学の立場から、精神的な存在の単に表現である限りにおいての人生の事実について述べることができるようなことは、以前ここで開催された連続講義、例えば「病気と死の理解」、「偽りの病気」、あるいは「熱に浮かされたような健康の追求」の中で説明しています。今日は、病気と治癒について理解する上で、きわめて奥深い問題を取り上げたいと思います。病気、治癒、そして、ときとして死に至る何らかの病は人生に深い影響を及ぼします。私たちは、これらを考察するための基礎となる精神的な前提、基盤について繰り返し探求してきましたので、これらの遠大な事実の原因であり、人間が人間として存在することの結果であるところのものについても探求することが許されるでしょう。つまり、これらの経験に関して、精神科学が言うべきこととは何なのでしょうか。人間の通常の発達過程との関連で、病気、健康、死、そして治癒がどのように位置づけられるかを明確にするためには、発展していく人生の意味について、もう一度、深く探求しなければなりません。何故なら、これらのできごとは通常の発達過程に影響を及ぼすものである、と考えられているからです。それらは私たちの発達に何か貢献するのでしょうか。それらは私たちを前進させるのでしょうか。あるいは、遅らせるのでしょうか。これらのできごとについての明確な概念に至ることができるのは、ここでもまた、人間全体を考慮するときだけなのです。しばしばお話ししてきたことですが、人間は四つの構成体から成り立っています。第一は、人間が彼の周りの鉱物存在すべてと共有している肉体ですが、その形態はそれが内に有する物理的、化学的な力に依存しています。人間の第二の構成体は、私たちがこれまでエーテル体あるいは生命体と呼んできたものですが、人間はこれをすべての生命あるもの、つまり、彼の周りの植物や動物と共有しています。そして、私たちは人間存在の第三の構成体としてアストラル体についてお話ししてきましたが、これは、楽しみや苦しみ、喜びや悲しみ、つまり、一日を通して溢れるすべての感動、イメージ、思考等を担うものです。人間はこのアストラル体を彼の周りの動物世界とだけ共有しています。そして、人間を被造物の頂点に立たせるところの最高の構成体、すなわち自我、自意識の担い手があります。私たちがこれら四つの構成体について考えるとき、まず第一に言えることは、それらの間には表面的に見ても一定の違いがある、ということです。私たちが、人間を、つまり、私たち自身を外側から見るとき、そこには人間の肉体があります。肉体は外的、物理的な感覚器官によって観察することができるのです。これらの器官に結びついた思考、すなわち脳という器官に結びついた思考によって、私たちはこの人間の肉体を理解することができます。それは私たちの外的な観察に対して明らかにされます。人間のアストラル体に対する関係は全く違っています。既に以前の記述の中で見てきたことですが、真に超感覚的な意識にとって、アストラル体とは、単に外的な事実です。つまり、アストラル体は、しばしばお話ししてきたような仕方で意識を訓練しさえすれば、肉体と同じように見ることができるものなのです。通常の生活においては、人間のアストラル体を外側から観察することはできません。目で見ることができるのは、その中で波打つ本能、熱情、思考、そして感情の外的な表現だけです。しかし、これとは対照的に、人間はこれらのアストラル体の経験を自分の中で観察します。彼は、私たちが本能、欲望、熱情、楽しみや悲しみ、喜びや痛みと呼ぶところのものを観察するのです。このように、アストラル体と肉体の関係は、通常の生活においては、前者は内的に観察される一方、肉体は外的に観察されるというようなものなのです。さて、ある意味で、その他の二つの構成体、人間のエーテル体、そして自我の担い手は、肉体とアストラル体というふたつの対極の中間に位置しています。肉体は純粋に外側から、アストラル体は純粋に内側から観察することができます。肉体とアストラル体の間にある中間的な構成体がエーテル体です。それは外側から観察することはできませんが、外部に影響を及ぼします。アストラル体の力、内的な経験はまずエーテル体に移行しなければなりません。それは、そうすることによってのみ、物理的な道具、肉体に働きかけることができるのです。エーテル体はアストラル体と肉体の間の仲介役として働き、外側と内側の結びつきを形成するのです。私たちはもはやそれを物理的な目で見ることはできませんが、エーテル体が外に向かって肉体と関連づけられていることによってはじめて、アストラル体の道具を目で見ることができるようになっているのです。さて、ある意味で、自我が内側から外側に向かって働くのに対して、エーテル体は外側から内側へ、アストラル体に向かって働きかけます。と申しますのも、人間は自我によって、そして、自我がアストラル体に影響を及ぼすその仕方によって、外の世界の、つまり、肉体自体がそこに起源を有するところの物理的な環境についての知識を獲得するからです。動物存在が個々の、個人的な認識を持つことなく生じるのは、動物が個的な自我を有していないからです。動物はアストラル体に関するあらゆる経験を内的に生き抜くのですが、その楽しみや苦しみ、共感や反感を、外なる世界の認識を獲得するためには使いません。私たちが楽しみや苦しみ、喜びや悲しみ、共感や反感と呼ぶところのものは、動物においてはすべてアストラル体の経験なのですが、動物は、その楽しみを世界の美に対する賞賛へと変換するかわりに、その楽しみを生じさせる要素の中に留まります。動物はその苦痛のただ中で生きるのに対して、人間は苦痛に導かれて自分を越え、世界を発見するのです。何故なら、自我が彼をそこから再び連れ出し、外なる世界に結びつけるからです。こうして、私たちは、一方では、いかにエーテル体が人間の内面、アストラル体の方向に向けられるかを、他方では、いかに自我が外なる世界、私たちを取り巻く物理的な世界に導くかを理解します。人間は交互に入れ替わる生を生きています。このことは日々の生活の中で観察されます。私たちは、朝起きた瞬間から、魂の中へと流れ込み、流れ出すあらゆるアストラル体の経験-喜びや悲しみ、楽しみや苦しみ、感情、イメージ等々を観察するのです。夜には、アストラル体と自我が無意識の中に、あるいは、多分もっとましな言い方をすれば、意識下の状態に入っていくために、いかにこれらの経験が漠然とした闇のレベルにまで沈み込んでいくかが見られます。朝から夜までの間、起きている人間を見ると、肉体、エーテル体、アストラル体、そして、自我が互いに織りなされ、それらの影響に関して、互いに結びつけられているのが分かります。秘教的な意識には、人間が夜眠りにつくと、肉体とエーテル体はベッドの中に残り、アストラル体と自我は精神的な世界の中の本来の場所に帰る、つまり、肉体とエーテル体から抜け出す、ということが分かります。私たちが今のテーマに適切に対処することができるように、このことをもっと別の方法で記述してみましょう。肉体は、その外的な側面だけを私たちに示しているのですが、眠っている人間においては、外的な人間として物理世界の中に留まり、内と外の仲介者であるエーテル体を保持しています。眠っている人間の中に内と外の間を仲介するものがないのは、仲介者としてのエーテル体が外の世界にあるからです。このように、眠っている人間においては、ある意味で、肉体とエーテル体とは単に外的な人間に過ぎないということができます。エーテル体は内と外の仲介者ではありますが、肉体とエーテル体を「外なる人間」として記述することもできるでしょう。反対に、眠っている人間のアストラル体は「内なる人間」として記述することができます。これらの言葉は起きている人間にも当てはまります。何故なら、あらゆるアストラル体の経験は、通常の条件下では、内的な経験であり、人間は起きているときに自我が獲得する外の世界についての知識を内的に取り上げ、学びながら自分のものとしているからです。外的なものは自我を通して内的なものにされます。このことは、私たちが「外の」人間と「内の」人間について、つまり、前者は肉体とエーテル体から、後者は自我とアストラル体からなるものとして語ることができるということを示しています。さて、人間のいわゆる通常の生活とその本質的な発達について見てみましょう。何故、人間はアストラル体と自我を伴って、毎夜、精神的な世界に帰って行くのでしょうか。人間が眠りにつく何らかの理由があるのでしょうか。これについては以前にも触れましたが、私たちが今日扱っているテーマに関しても、つまり、病気と治癒において現れるような、一見異常な状態を認識するためにも、正常な発達についての理解が必要です。人間はどうして毎夜、眠りへと赴くのでしょうか。これについての理解に至ることができるのは、「外なる人間」に対するアストラル体と自我の関係を十分に考慮するときだけです。私たちはアストラル体を、楽しみと苦しみ、喜びと悲しみ、本能、欲望、熱情、波打つイマジネーション、知覚、思考や感情の担い手として記述しました。けれども、アストラル体がこれらすべての担い手であるとするならば、肉体とエーテル体が存在していないとはいえ、実際の内的な人間がアストラル体と結びついている状態にもかかわらず、何故、人間は夜、これらの経験を持たないのでしょうか。この間、これらの経験が漠とした闇の中に沈んでしまうということが何故あるのでしょうか。それは、アストラル体と自我が、喜びや悲しみ、判断、イマジネーション等々の担い手であるにもかかわらず、これらのものを直接には経験できないからです。私たちの通常の生活においては、アストラル体と自我は、それら自身の経験を意識するために肉体とエーテル体を必要としているのです。私たちの魂の生活とは、アストラル体によって直接経験される、というものではないのです。もし、そうだとすれば、私たちがアストラル体と結びついている夜の間にもそれを経験することができるはずです。昼間における私たちの魂の生活は残響あるいは鏡像のようなものです。肉体とエーテル体がアストラル体の経験を反射するのです。私たちが起きてから眠りにつくまでの間に、私たちの魂が私たちのために魔法にように出現させるあらゆるものを出現させることができるのは、それが肉体とエーテル体もしくは生命体という鏡の中にそれ自身の経験を見るからに他なりません。夜、私たちが肉体とエーテル体を後にする瞬間、私たちはまだアストラル体の経験のすべてを私たちの内に有しているのですが、私たちはそれを意識しません。何故なら、それらを意識するためには、肉体とエーテル体の反射する性質が必要だからです。こうして、私たちは、朝目覚めてから夜眠りにつくまでの私たちの生活の全過程を通して、内的な人間と外的な人間、すなわち、自我とアストラル体、そして肉体とエーテル体が相互に作用しているのを見ます。働いているのはアストラル体と自我の力です。何故なら、いかなる条件下でも、物理的な特徴の総計としての肉体やエーテル体がそれら自身から私たちの魂の生活を生じさせることはできないからです。私たちが鏡の中に見る像が、鏡に発するものではなく、鏡の中で反射される対象物に由来しているのと同じように、反射される力はアストラル体と自我から生じるのです。このように、私たちの魂の生活を生じさせるすべての力はアストラル体と自我の中に、すなわち人間の内的な本性の中に横たわっているのです。そして、それらは、内的な世界と外的な世界との間の相互作用の中で活発になり、いわば肉体とエーテル体にまで手をのばすのですが、夜には、私たちが「疲れた」と呼ぶ状態に入っていくのが、つまり、それらが夜、消耗しているのが見られます。そして、もし、私たちが毎夜、朝から夜までの間そこで過ごすところの世界とは別の世界に入っていく立場になかったとすれば、私たちは自分の生活を続けることができなかったでしょう。私たちは、起きている間に滞在する世界の中で、私たちの魂の生活を知覚可能なものにすること、つまり、私たちの魂の前にそれを提示することができるのですが、それはアストラル体の力によって可能になるのです。しかし、私たちはこれらの力を使い果たします。目覚めている間の生活からそれを補充することはできません。私たちがそれを補充することができるのは、私たちが毎夜入っていく精神的な世界からだけです。私たちが眠るのはそのためです。夜の世界に入り、そこから昼の間に使う力を持ってくることなしに私たちが生きていくことはできないでしょう。こうして、エーテル体と肉体の中に入るとき、私たちは何を物理的な世界に持ち込むのか?という問いに対する答えが得られました。ところが、私たちはまた、夜にも何かを物理的な世界から精神的な世界へと運んでいくのではないのか。これが第二の問いです。この問いも第一の問いと同じように重要です。この問いに答えるためには、通常の人間生活に属する数多くのことがらを取り扱わなければなりません。通常の生活には、いわゆる経験と呼ばれるものがあります。これらの経験は私たちの誕生から死までの人生において重要なものです。ここでしばしば触れられてきたひとつの例、つまり、書くということを学ぶことについての例がこのことに光を当てるでしょう。私たちが自分の思考を表現するためにペンを取るとき、私たちは書くという芸術に携わっているのです。私たちは書くことができるのですが、そのために必要な条件とは何なのでしょうか? 私たちが誕生から死までの間に有する一連の経験のすべてが必要なのです。皆さんが子供として通過してきたことのすべて、ペンを持つという最初のぎこちない試みからそれを紙に当てる等々のことがらについて考えてみて下さい。これらすべてのことを思い出さなくてもよい、というのは神に感謝すべきことです。何故なら、もし、書くたびに、私たちが書道と呼ぶところの芸術を発達させようとして線を引き損ねたことや、多分それでしかられたことなどを思い出さなければならないとしたら、ひどい状況に陥るであろうからです。何が起こったのでしょうか。誕生から死までの間の人生において重要な意味を持つところの発達が起こったのです。私たちは一連の経験の総体を有していますが、これらの経験は長い時間をかけて生じたものです。それらはその後、いわば私たちが書くための「能力」と呼ぶところの本質的なものへと純化しました。他のすべてのものは、忘却の漠とした闇の中へと沈んでいきましたが、それらを思い出す必要はありません。何故なら、私たちの魂は、これらの経験から出発して、より高次の段階に達しているからです。つまり、私たちの記憶は、人生における受容力や能力として現れるところの本質的なものの中へと共に流れ込むのです。誕生から死までの存在状態における私たちの発達とはこのようなものです。経験は最初に魂の能力へと変容し、次にその能力は肉体という外的な道具を通して表現されます。誕生から死までの発達は、すべての個人的な経験が能力や、そしてまた叡智に変化させられるというような仕方で生じるのです。もし、私たちが1770年から1815年までの期間を眺めるとすれば、この変容がどのようにして生じるかの洞察を得ることができます。重要な歴史的事件がこの間に生じました。多くの人がこの事件と同時代に生きていましたが、彼らはそれにどのように反応したのでしょうか。彼らの内のある部分は、そのできごとがかたわらを通り過ぎるのに気づきませんでした。彼らはそのできごとが知識に、世界の叡智に変化するのを無感動に見過ごしました。他の人たちはそれらを深い叡智へと変化させました。彼らは本質的なものを抽出したのです。どのようにして経験は魂の中で能力や叡智へと変化させられるのでしょうか? それらは毎夜、そのままの形で私たちの眠りの中に、つまり、魂あるいは内的な人間が夜の間滞在するあの領域の中に取り込まれることによって変化させられるのです。ある期間中に起こった経験は、そこで本質的なものに変化するのです。人生を観察する人であれば誰でも、もし、誰かがあるひとつの活動領域における一連の経験を秩序づけ、自分のものにしたいのであれば、これらの経験を眠っている間に変化させる必要がある、ということを知っています。例えば、何かを一番よく学ぶことができるのは、それを学び、それとともに眠り、再びそれを学び、再びそれとともに眠ることによってです。経験は、眠りの中に沈められることがなければ、能力や叡智、あるいは芸術の形で現れてくるように発達させられることはないでしょう。これは、私たちが低次のレベルで直面する必然的なものの高次のレベルにおける表現です。もし、今年の植物が暗い地球の覆いの中に帰って行かないとすれば、それは次の年に再び成長する植物にはなれないでしょう。この場合の発達は繰り返しに留まりますが、人間の精神に照らされることによって真の「発達」になります。経験は無意識の夜の覆いの中に降り、そして再び、さしあたりはまだ繰り返しとして取り出されるのですが、最終的には、叡智として、能力として、生きた経験として現れるほどに変化させられていることでしょう。今日よりもより深く精神的な世界を観察することができた時代には、人生はそのように理解されていました。古代文化における指導的な人物たちがイメージによって何かを話そうとするとき、人生におけるこれらの重要な基礎が示唆されているのを見ることができるのはそのためです。もし、一連の昼間の経験が魂の中で火をつけられ、何らかの能力に変化するのを妨げたいのならば、何をすべきでしょうか。例えば、誰かが一定の期間中に、誰か他の人と何らかの関係を持つときには、何が起こるのでしょうか。その人物とのこれらの経験は夜の意識の中に沈み、そこからその人物に対する愛として、つまり、それが健全なものである場合には、いわば連続した経験の本質として再び現れるのです。他者に対する愛の感情は、経験の総体がひとつの織物へと織られるように統合される、というような仕方で生じます。さて、一連の経験が愛に変化するのを妨げるためには何をなすべきなのでしょうか? 私たちの経験を本質的なもの、すなわち愛の感情に変化させるところの夜の自然過程が生じるのを妨げなければならないのです。私たちは、昼の経験から織られた織物を夜に再びほどかなければなりません。もし、そうすることができたならば、魂の中で愛に変化する他者に対する経験は私たちに何の影響も及ぼさなくなるでしょう。ホメロスはこの人間の魂の深みについて、ペネロペと彼女の求婚者のイメージの中で暗示しています。彼女はある織物を織り上げたときに結婚に応じることを皆に約束します。昼間に織り上げたものを、単に夜毎にときほどくことによって、約束は回避されます。見ることができる人が芸術家でもある場合には、非常に深遠なものが明かされます。今日、このようなことがらに対する感情はほとんど残っていません。ですから、同時に見ることができる人である詩人がそのようなことを説明するとき、それは気ままな思いつきであると断定されるのです。それによって古代の詩人も、そして真実も害されることはありませんが、私たちの時代はそうはいきません。それはそのようにして人生の深みに入っていくことを妨げられるのです。参照画:Homerus人気ブログランキングへ
2024年03月19日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第四講「祈りの本性」(1910年2月17日) 神秘主義に関する講義の中で、私たちはマイスター・エックハルトからアンジェラス・シレジウスに至る中世の神秘主義において現れたところの内的深化に関する特別な形態についてお話ししました。その特徴は、神秘家が外的世界からやって来る経験のすべてから彼自身を自由にし、独立させることを求める、ということにあります。彼は、通常の生活に関係するあらゆるものが消し去られ、魂がそれ自身の中に引きこもるとき、それでも、それはいわばそれ自身の世界をその中に有している、ということを彼に明らかにするであろう経験へと押し進もうとするのです。この世界はいつでもそこにあるのですが、外的な経験が人間をあまりにも力強く照らし、そのため、大部分の人々が決してそれに気づかないほど弱い光のように見えるのです。このため、神秘家はしばしばこれを小さな閃光と呼びます。けれども彼はそれを存在の源泉とその根底を照らし出す力強い炎へと燃え上がらせることができる、言い換えれば、それは人をして彼自身の魂の道を通り、彼の起源についての認識に導くと確信しているのですが、それは正に「神の認識」と呼ばれ得るものなのです。私たちは、同じ講義の中で、いかに中世の神秘家たちがその小さな閃光を、その本性は不変のままで、自然に成長するべきものと考えていたかを観察しました。これとは反対に、現代の精神的な探求においては、これらの内的な魂の力を意識的なコントロールの下で発達させることによって、イマジネーション、インスピレーション、インテュイションと呼ばれるところのより高次の形態を有する認識へと上昇させることが要求される、ということを強調しました。ですから、この内的な献身がそれに向けられる中世の神秘主義は、真の精神的な探求への一種の第一段階として私たちの前に現れるのです。もし、私たちが、私たち自身をマイスター・エックハルトの内的な熱情の中に沈めることができるならば。もし、この神秘主義的な献身がヨハネス・タウラーに与えた精神的な知識の測りがたい力を認めるとすれば。もし、ヴァレンチン・ワイゲルやヤーコブ・ベーメがこの物理的な献身を通してとはいえ、彼らは明らかにそれ以上に進んでいたのですが、達成されるものすべてによって、いかに深く存在の秘密へと導かれたかを認めるならば。もし、アンジェラス・シレジウスが、いかにこのおなじ献身を通して、精神的な世界秩序に関する一般法則への開明的な洞察を獲得できたばかりではなく、世界の秘密に対し、その著作の中で、心温まるような美しい表現を与えることができたかを理解するならば。もし、このすべてを心に留めるならば、私たちは、この中世の神秘主義の中に潜む力と深み、そしてそれが精神科学的な道を自ら辿ることを望むすべての人に与えることができる無限の手助けを実感することになるでしょう。このように、中世の神秘主義は、特に前回の講義の光に照らされたとき、精神科学的な探求のためのすばらしく偉大な準備のための学校と見なされ得るものなのです。そして、そうではないということがあり得るでしょうか。結局のところ、精神科学者の目的とは、その小さな閃光を彼自身の内的な力を通して発達させるということなのです。異なるのは、神秘家が、魂の安らぎの中で、その小さな閃光に彼ら自身を捧げることができ、そして、それが、それ自身の調和の中で、ますます明るく輝き出るだろうと信じていたのに対し、精神科学者は、その閃光を明るい炎へと点火するするためには、私たちの意志に仕えさせるために世界の叡知によってそこに置かれるところの私たちの能力と力を使用しなければならないと確信しているという点だけなのです。もしそのとき、その神秘的な心の炎が精神科学のためのよい準備となるであるならば、私たちは、今度は、神秘的な献身のための準備となるところの、真の意味で祈りと呼ばれ得る魂の活動を有することになるのです。ちょうど神秘家が、たとえ無意識的にではあっても、彼の魂をそれに向けて訓練することによって、内的な献身に到達することができるように、もし、私たちが物理的な瞑想に向かう同様の道に沿って歩みを進めたいと望むならば、私たちは、真の祈りの中に、ひとつの準備段階を求めることができるのです。ここ何世紀かにわたって、祈りの本性は、あれこれの精神運動によって、実に様々な方法で誤解されてきました。そして、それに関する真の理解を獲得することは簡単ではないかも知れませんが、もし、これらの世紀が、特に利己的な精神的潮流が幅広い人々の集団を捉えたという点で特徴づけられる、ということを思い出すならば、私たちは、祈りが利己的な望みや欲望のレベルにまで引きずり下ろされたのは驚くべきことではないということを見出すでしょう。そして、祈りは、それが何らかの形のエゴイズムに浸透されているときほどひどく誤解されることはほとんどないということを申し上げなければなりません。今回の講義では、もっぱら、いかなる宗派からも、あるいはその他の影響からも自由な精神科学という光の下に、祈りについて探求してみることにしましょう。私たちは、最初のアプローチとして、次のように言うことができるかも知れません。神秘家は、彼の神秘的な献身によってどこまでも明るく輝くようにさせられるであろうある種の閃光が彼の魂の中に見出されるはずであると考えており、祈りとはその閃光を生じさせるために意図されたものであると。そして、祈りとは、それがいかなる前提から出てきたものであれ、正に、その魂をかきたて、徐々にその小さな閃光を、つまり、もし、それがそこにあればですが、そのきらめきながらも隠された閃光を見出させることによって、あるいはそれを点火させることによってこそ、その有効性を証明するものなのです。もし、私たちが祈りの必要性とその本性を探求すべきであるならば、私たちは、以前の講義でも引用した古いギリシャの聖人、ヘラクリトスの「あなたがいかなる道を探求したとしても、魂の境を見出すことは決してできないであろう、魂の存在とはそれほど包括的なものなのだ。」という、普遍的な妥当性をもつ言葉を心に留めながら、その魂についての深い記述へと入っていかなければなりません。そして、私たちは、最初、祈りの中に、魂の内的な秘密を探し求めるだけなのですが、祈りによってかき立てられる親密な感情は、最も素朴な人に対してさえ、魂的生活の無限の広がりについて、何らかの示唆を与えることができるのです。私たちは、魂が生きた進化の過程にたずさわっているということに気づかなければなりません。それは、単に過去からやって来るだけではなく、絶えず未来に向けて旅しています。過去からの影響が現在の瞬間瞬間へと展開するように、ある意味で、未来からの影響もそうなのです。参照画:ヘラクリトス 魂の生活を深く洞察する人は誰でも、これらふたつの流れ、過去からの流れと未来からの流れが絶えずそこで出会っているということを理解するでしょう。私たちが過去からの影響を受けているというのは明らかな事実です。昨日の活力あるいは怠惰が今日の私たちに何らかの影響力を持つということを誰が否定できるでしょうか。けれども、私たちは未来の現実性もまた否定すべきではありません。と申しますのも、私たちは、未来の出来事が、それがまだ生起していないにもかかわらず、魂の中に侵入するのを観察することができるからです。結局のところ、明日起こりそうな何かに対する恐れや心配とは、一種の未来に関する感情や知覚ではないでしょうか。魂が恐れや心配を経験するとき、それがその感情という現実によって示しているのは、それが、過去だけではなく、未来からそれに向けて急ぎ来るところの何かをも、非常に生き生きとした方法で計算に入れているということなのです。もちろん、これらは単純な例ですが、魂を探求する人は誰であれ、未来はまだ存在していないゆえに現在にその影響があるはずがないという抽象的な論理に矛盾するところの無数の例を見出すであろうということを示唆するには十分でしょう。このように、ふたつの流れ、ひとつは未来からの、もうひとつは過去からの流れが、魂の中で出会い、自分を観察する人ならば、誰がこのことを否定するでしょうか。そして、ふたつの川の合流点に比べられるような一種の渦巻きを形成するのです。もっと詳しい観察は、過去の経験から私たちに残された印象が、そして、私たちはその印象の中でそれらの経験を処理してきたのですが、現在あるような魂を形作ってきたということを示します。私たちは、私たちが過去に行い、感じ、そして考えたことの名残を私たちの内に担っているのです。私たちがこれらの過去の経験を、とりわけ、私たちがその中で活動的な役割を演じた経験を振り返ってみるとき、私たちは、非常にしばしば、私たち自身の評価を強いられることになります。私たちは、過去に生起したある行いに対し、私たちの現在の立場から同意しないというような、私たちの過去における行いのいくつかについて、恥じらいをもって振り返ることさえできるというような段階に到達しているのです。もし、このようにして、私たちの過去を私たちの現在と比べてみるならば、私たちは、私たちが私たち自身の力によって、私たち自身から創り出したところのいかなるものよりも、はるかに豊かで、はるかに重要な何かが私たちの内にある、ということを感じるようになるでしょう。もし、私たちの意識的な自我を超えて広がるその何かがなかったとすれば、私たちは、私たち自身を非難したり、あるいは、私たち自身を知ることさえできなかったでしょう。ですから、私たちは、私たちが、過去において、私たち自身を形成するために用いてきたところのいかなるものよりも偉大なものを、私たちの内に有しているに違いないのです。もし、私たちがこの意識を感情にまで変化させるならば、私たちは、私たちの過去の行いにおけるあらゆること、つまり、記憶が私たちの前にはっきりともたらすことができるところの経験を振り返ることができるようになり、そして、これらの経験を何かより偉大なものと、つまり、私たちの魂の中にあるところの私たちをして私たち自身に直面させるように、そして、現在の立場から私たち自身を評価させるように導く何かと比較することができるようになるでしょう。要するに、過去から私たちの中に流れ込むものを観察するとき、私たちは、私たち自身を超えて広がる何かを私たちの内に有していると感じるのです。これに親しむことが、私たちの内の神についての感情、つまり、私たちのすべての意志の力よりも偉大な何かが私たちの中にひそんでいるという感情への最初の目覚めなのです。こうして、私たちは、私たちの限定された自我を超え、神的・精神的な自我に向かうように導かれます。このことが過去を凝視することから生じます。そして、それは知覚的な感情へと変化しているのです。では、未来からの流れは、やはり知覚的な感情という意味で、私たちに何を語るのでしょうか?それはより明確で、もっと強い言葉で私たちに語りかけます。それは、私たちが、ここでは、恐れや心配、希望や楽しみといった感情に直接関わっているからです。と申しますのも、それに関する出来事はまだ起こっておらず、ただそれらに結びついた感情だけが魂の中に打ち込んで来ているだけだからです。そして、私たちは、この未来からの流れが、私たちの期待とは異なる影響や責任をもたらすかも知れない、ということを知っています。もし、私たちが、私たち自身を、それがいかなる経験であろうとも、未来の暗い子宮から確実に私たちに向かってやって来るものに正しく関係づけることができるならば、私たちは、いかにそれが絶えず魂を刺激しているか、ということを理解するでしょう。私たちは、魂が、未来においては、いかに現在よりもはるかに豊かに、はるかに広い範囲を見通すようになるかということを、つまり、私たちは、既に、近づきつつある未来に関係づけられており、私たちの魂は、それが何をもたらすにしても、それに調和していなければならない、ということを感じるのです。もし、私たちが、このようにして、いかに過去と未来とが現在へと流れ込んでいるかを観察するならば、いかに魂の生活がそれ自身を超えて成長するかを理解します。魂が過去を振り返るに際して、現在へと働きかける過去からの力、魂自身よりも大きな力を意識するとき、この認識は、それが評価であったとしても、後悔や恥じらいをもって振り返るにしても、神的なものに対する尊敬の念をその中に引き起こすのです。そして、この尊敬の念、つまり、私たちが私たちの上に働きかけているのを感じながらも、私たちが意識的に把握することができる以上の尊敬の念がひとつの祈りの形式(と申しますのも、ふたつの形式があるからですが)を引き起こし、それが魂を神との親密な関係へともたらすのです。と申しますのも、もし、魂が、最も内的な平静の中で、過去によって引き起こされる感情に自らを捧げるならば、それは、今や、それが使ってこなかった力、自我をもって浸透しないままになっていた力を現実のものにすることを欲し始めるであろうからです。そのとき、魂は自らに次のように言うことができます。もし、この力が私の内にあるとすれば、それは今や別のものになっていなければならない。私が希求する神的な要素は私の内的な生活に属してはいなかった。私が私自身を、今日私が肯定できるであろうような何かにすることができなかったのはそのためなのだ、と。このことを認識できるようになった魂は次のように続けるでしょう。私は、どうすれば、私のすべての活動や経験の中に、私がそれに気づくことな生きていたところの見知らぬものを、何故なら、私はそれを私の自我によって把握することができなかったからなのだが、私自身の中に引き込むことができるのだろうか?と。魂が、感情を通して、言葉あるいは考えを通して、この心の炎の中へともたらされるとき、私たちは過去に向けて祈りを捧げるのです。このことは、魂が「ひとつの」献身の道を通して、神的なものに近づこうとしていることを意味しています。さて、今度は、見知らぬ未来からの流れとともにやって来る神的なもののきらめきについて見てみましょう。ここでは異なった心の炎が喚起されます。今まで見て来ましたように、私たちが過去を振り返るときには、私たちは、私たちの内的な能力を発達させてこなかったということに気づきます。すなわち、私たちは、いかに私たちの欠点が、私たちの上に輝く神的な光に私たちが応えるのを妨げて来たかを見るのですが、この感情が、過去によって促されるところの献身の祈りへと私たちを導くのです。では、同様にして、私たちが精神的なものへと上昇するのを制限するような欠点に気づかせてくれるところの影響であって、未来からやって来る影響とは何でしょうか。それを知るには、私たちが不確かな未来に直面したとき、私たちの魂生活を悩ますところの恐れと不安の感情を思い出しさえすればよいのです。この状況において、魂に安心感を与えるものが何かあるでしょうか?そうですね、それは、未来の暗闇の中から魂へとやって来るところの何らかのものに対する謙遜の感情とでも呼べるものです。けれども、この感情が有効なのは、ただそれが祈りの性格を有しているときだけです。誤解を避けるために申し上げますが、私たちはあれこれの意味で謙遜と呼ばれ得るかも知れないところの何かを賛美しているのではありません。私たちはその一定の形態、すなわち、未来がもたらすであろう何らかのものに対する謙遜について記述しているのです。不安と恐れをもって未来を見つめる人は誰でも、自分の発達を妨げ、彼の魂の力が自由に展開するのを妨害しているのです。不確かな未来に直面したとき、恐れと不安ほどこの発達を妨げるものは、実際、何もないのです。しかし、未来を甘受することの結果は、経験によってのみ評価され得ます。この謙遜とは何を意味しているのでしょうか。それは、理想的には、自らに次のように言うことを意味しているでしょう。次の一時間、あるいは次の日が何をもたらそうとも、恐れや心配によってそれを変えることはできない。何故なら、それは、まだ見ぬものなのだから。したがって、私は完全な内的平穏、完全な心の平静をもってそれを待ち受けることにしよう、と。活動的な力とエネルギーを損なうことなく、このように静かでリラックスした仕方で未来に出会う人は誰でも、彼の魂の力を自由に、力強く発達させることができるでしょう。魂がこの迫りくる出来事に対する謙遜の感情に浸透されればされるほど、まるで障害が次から次と崩れ去るかのようです。けれども、何らかの命令や、確固とした基礎を持たない気ままな決定によって、この感情が魂の中に呼び出されることはありません。それは、未来とそこで生じる叡知に満ちた経過に向けられる第二の祈りの形式の中から湧き出してくるのです。この神的な叡知に私たちを委ねるということは、私たちが、来るはずのものは来なければならない、それはひとつの方向、あるいは別の方向において良い影響を及ぼすに違いないのだという認識を伴うところの思考、感情そして衝動を何度でも呼び出す、ということを意味しています。この心の炎を呼び出すということ、そして、それに言葉、知覚、そして考えによる表現を与えるということが、祈りの第二の形式、献身的な甘受の祈りなのです。祈りへの衝動はこれらの感情からやって来なければなりません。と申しますのも、それらの感情は、魂そのものの中に存在しており、基本的には、目前に迫るものから少しでも自らを上昇させる魂の中で、それを祈りに向けて導くものだからです。祈りの前提条件が整うのは、魂がその眼差しを移ろいゆく現在から過去、現在そして未来を包含するところの永遠なるものへと向けるときである、と言ってもよいでしょう。ゲーテがファウストに次のような偉大な言葉をメフィストフェレスに向けて語らせたのは、自らを現在から上昇させるということが、それほどまでに必要なことだったからです。もし、急ぎ過ぎ去る現在という瞬間に「拘泥する」ならば、私は叫ぶ、「お前の勝ちだ!」これは次のことを意味しています。もし私が現在に生きることに満足するならば、そのときには、お前は私を足かせにつなぐがよい、私を消滅させるがよい、それが何ほどのことであろうか。ここでは、次のように言うこともできるでしょう。ファウストが彼の同行者、メフィストフェレスの足かせから逃れるために乞うたのは、祈りの力を求めてであると。したがって、祈りの経験は、一方では、過去から現在までその歩みを進めてきた狭量な自我を観察することへと私たちを導くとともに、私たちの中には、私たちが用いてきたよりもいかに遙かに多くのものがあるかをはっきりと示し、他方では、私たちを未来へと導き、これまで自我が把握することができたものに比べて、いかにもっと多くのものが未来から流れてくることができるかを私たちに示すのです。もし、私たちがこのことを理解するならば、私たちは、あらゆる祈りの中に、私たちに私たち自身を超えさせるところの力を見出すことになります。祈りとは、現在そうであるような私たちの自我を超えることを求めるところの力を私たちの内に点火すること以外のものであり得るでしょうか?そして、もし、自我がこの衝動に捉えられているならば、それはそれ自身を発達させる力を既に有しているのです。私たちが私たちの内に有しているのは、私たちが今まで用いてきたところのもの以上のものなのだ、ということを過去が私たちに教えているならば、祈りとは、神的なものの存在が私たちを満たすことを求める、その神的なものに対する叫びなのです。私たちが、私たちの感情と知覚を通して、この認識へと至ったとき、私たちは祈りを、私たちの自我の発達を助ける力のひとつとして数えることができるようになります。このことは未来へと向けられる祈りについても同様です。もし、私たちが、近づきつつある未来に関して、恐れと不安の中に生きるならば、私たちは祈りがもたらすことができる謙遜の態度に欠けているのです。私たちは、私たちの運命が世界の叡知によって秩序づけられている、ということに気づき損ないます。しかし、もし、私たちが謙遜と献身をもって未来を迎えるとすれば、私たちは、実り多い希望の中で、それに近づくことになります。私たちを小さくするように見えるかも知れないところの謙遜が、魂を豊かにし、私たちをより高い発達段階に運び上げる強力な力になる、というのはそういうことなのです。私たちは、いかなる外的な結果も祈りに期待する必要はありません。何故なら、私たちは、祈りを通して、私たちの魂に、光と熱の源泉を植え付けたのだということを知っているからです。それは、未来との関係では、魂を自由にし、未来の暗い子宮の中から現れ出るであろういかなるものをも受容できるように配置するがゆえに光の源泉なのであり、そして、確かに、過去においては、私たちは、私たちの自我の中で、神的な要素を実りへともたらすことができなかったけれども、今や、それが私たちの内で有効な力となるように、私たちの感情をそれで満たしたのだ、ということを私たちに気づかせてくれるがゆえに熱の源泉なのです。過去を振り返ることからわき上がってくるところの祈りが、祈りをその真の意味において理解するすべての人によって語られるあの熱を生じさせるのです。そして、内的な光がやって来るのは、未来に向けた謙遜の祈りを理解する人たちのところへなのです。この観点からすれば、最も偉大な神秘家達が、内的な瞑想を通して達成しようと望んだことに対する最良の準備を、彼らの祈りへの没頭の中に見出した、というのは驚くにはあたらないことのように見えるでしょう。彼らは、彼らの内の小さな閃光が明るく輝くようになる地点にまで彼らの魂を導きました。真の祈りが与えることができるあのすばらしい親密さの感情への道が開けるのは、正に、過去への参入を通してなのです。外的世界に関する気遣いは、ちょうど、過去において、それが私たちの内のより力強い要素、すなわち自分自身を意識した自我の出現を妨げたように、私たちを私たち自身から疎遠にします。私たちは外的な印象や様々な外的生活からの要請に明け暮れました。それらは、私たちをバラバラに引き裂き、静かさの中で私たち自身を回想することができないようにします。これが、私たちの内にある力強い神的な力の展開を妨げたものなのです。しかし、もし今、私たちが、親密な祈りの中で、それを展開させるならば、私たちは、外的世界の破壊的な影響に曝される、ということがなくなるでしょう。私たちは、私たちを内的な祝福で満たし、真に神的なものと呼ばれ得るところのあのすばらしい内的な熱を感じることでしょう。外的なものの中で自己を失いつつある魂は、それらを経験することを通して、自らを奮い立たせることができるようになるのです。祈りの間、私たちは「神」の感情の中で暖められますが、私たちは、単に熱を感じるだけではなく、心の底から、私たち自身の中で生きるのです。他方、私たちが外的世界の事物に向かうとき、私たちはいつでも、それらが未来の暗い子宮と呼ばれてきたところのものに包含されているのを見出します。詳細に観察は、私たちが外的世界で出会うところのあらゆるものの中には、いつでも未来のヒントがある、ということを示します。私たちが、私たちに降りかかってくるものに関して、恐れや不安を感じるときにはいつでも、何かが私たちを遠くへ押しやり、外的世界は、貫き難いヴェールのように、私たちの前に立ちはだかります。もし、私たちが、未来から私たちのところへやって来るものが何であれ、それに対する献身的な謙遜の感情を発達させるならば、私たちは、あらゆる外的世界の事物に、この感情が生じさせるところの確信と希望をもって出会うことができる、ということを見出します。そして、そのとき、私たちは、すべての事物の中には、叡知の光が私たちに向けて輝いているのだ、ということを知るのです。これができないとき、私たちは、私たちが行き当たるあらゆるものにおいて、私たちの感情の中に広がる闇に出会います。ですから、献身的な帰依の祈りの中で、私たちのところにやって来るのは、世界全体から光が輝き出ることに対する希望なのです。もし、私たちが夜の闇に囲まれてどこかに立っていたとしますと、私たちは、打ち捨てられ、私たち自身の中に押し込められているように感じるでしょう。朝が光をもたらすとき、私たちは解放されたと感じるのですが、単に、私たちが自分自身から逃げ出すことを欲するかのようにではなく、私たちが、今や、私たちの最良の望みや熱望を外的な世界にもたらすことができるかのように感じるのです。同様に、私たちは、私たちを私たち自身から遠ざけるところの世界に対する自らの放棄が、私たちを私たち自身に結びつけるところの祈りの熱によって、いかに克服されるかを感じることができます。そして、この祈りの熱を謙遜の感情へと私たちがもたらすとき、それは光になります。そして、今や、私たちが、私たち自身から歩み出て、私たち自身を外的世界に結びつけ、それを眺めるとき、私たちは、もはや私たちがそれによって引き裂かれたり、疎遠にされたりしているのではなく、私たちの魂からその最良のものが流れ出し、それが、私たちを、外的世界から私たちの上に輝くところの光に結びつける、と感じるのです。これらふたつの祈りの形式は、概念によってというよりも、イメージの中でよりよく表現されます。私たちは、例えば、旧約聖書にあるヤコブとその魂を震撼させる夜の試練についての物語に思いを馳せることができます。彼は、まるで私たち自身が世界の様々の圧力に曝され、そこでは、最初、魂が失われ、それを取り戻すことができないでいるかのような仕方で、私たちの前に現れます。私たち自身を見出そうとする努力が始まるとき、それは、私たちの高次の自我と低次の自我の間の衝突を引き起こすのです。そのとき、私たちの感情は大きく波打つのですが、祈りは私たちが自分の道を歩み通すのを助け、ついには、ヤコブの物語の中であらかじめ示されているような瞬間、すなわち、昇る太陽が彼を照らすとき、夜中中続いた苦しみが解消され、調和がもたらされた、と告げられる瞬間がやって来るようにするのです。これは、実際、祈りが魂のために為すことができることなのです。この光の中で見るとき、祈りはいかなる迷信からも自由です。何故なら、祈りは私たちの中の最良のものを取り出し、魂の中のひとつの力として直接に働くからです。こうして、祈りは、ちょうど神秘的な思索そのものが、精神的な探求として私たちに知られているもののための準備であるように、その神秘的な思索のための準備なのです。祈りについての私たちの議論は、私たちがここで何度もお話ししてきたことを例証するでしょう。つまり、もし、私たちが、神秘的な方法によって、私たち自身の中に、神的なもの、「神」を見出すことができると信じるならば、私たちは、間違いにつぐ間違いを繰り返すことになる、ということをです。この間違いは、中世を通して、神秘家により、あるいは普通のキリスト者によってさえ、何度も繰り返されてきました。そのようなことが起こったのは、祈りの実践がエゴイズムによって浸透されるようになったからです。エゴイズムは、魂に対し、次のように言うように強いるのです。私はますます完全になるのだ、そして、私自身が完全になること以外は考えないようにするのだ、と。私たちは、間違って指導された神智学の形態が、あらゆる外的なものから単に目をそむけさえすれば、私たちは私たちの中に「神」を見出すことができるのだ、と断言するとき、この利己的な願望の残響を聞くことができます。私たちは、祈りにはふたつの形式があるのを見てきました。ひとつは内的な熱に導きます。未来に向かっての謙遜の感情に色づけられたもうひとつの祈りは世界へと導き、それによって開明と真の認識に導きます。祈りをこのように見る人であれば誰でも、通常の知的な方法によって獲得された知識は、別の種類のそれに比べると、不毛であることがすぐに分かります。祈りとは何かを知っている人は誰でも、魂を自らの中に取り戻すことに精通するでしょう。そして、そのとき、魂は、その思考を現在の瞬間から引き上げ、それらを過去と未来に捧げることによって、世界の破壊的な多元性から自らを自由にし、内的に集中するのです。もし、私たちがこの状態について知っているとすれば、私たちが有することができる最も繊細な思考と感情だけが魂の中にあるときには、多分、これらさえも消え去り、ただふたつの方向、すなわち、過去から自らを告げる「神」と、未来から自らを告げる「神」とを指し示す基本的な感情だけが残っているときには、もし、そのとき、私たちがこの感情の中に生きるようになっているならば、あの偉大な瞬間がその魂に訪れ、魂が自らに次のように言うのが分かります。私は、私の利口者の思考が私の意識の中に創り出したあらゆるもの、私の感情と知覚がもたらしたあらゆるもの、そして、私の意志の力と私の教育が設定したすべての理想から目をそむけた、これらすべてを一掃したのだ。私は、私の最も高次の思考と感情に没頭し、そしてこれらさえ、私は今や消し去った。そして、既に述べたような基本的な感情だけを保持しているのだ、と。もし、私たちがこの段階に到達しているならば、これまで私たちには知られていなかった新しい感情が、私たちが純粋な目をもってそれを見るとき、自然の驚異が私たちの前に現れるのと同じ仕方で、魂の中に輝き込むのが分かります。私たちの知らない意志衝動と理想が魂の中にわき上がり、その基盤から、最も実り多い瞬間が生じるのです。祈りが私たちの手近な能力を超えたところにある叡知を最良の意味で私たちに吹き込むことができるというのはそういうことなのです。つまり、それは私たちがまだ達成していない感情や知覚の可能性を私たちに与えるのです。そして、もし、祈りが私たちの自己教育をさらに進めるならば、それは私たちがそこまではまだ上昇できないでいるところの意志の力を私たちに付与することができるのです。確かに、もし、私たちがこのすべてを成し遂げるべきであるならば、私たちは、まず、最も繊細な感情と衝動を私たちの魂の中に養成し、育む必要があるでしょう。そして、私たちは、ここでもまた、最も初期の時代における最も厳粛な機会に、人類に与えられたところの祈りに対して注意を促さなければなりません。皆さんは、私の小冊子、「主の祈り」の中に、その中の七つの祈願が世界のすべての叡知を包含していることを説明する記述を見出されるでしょう。さて、皆さんは次のように言いたい気持ちになるかも知れません。この小冊子の中では、七つの祈願は、宇宙のより深い源泉を知るようになった人によってのみ理解され得る、ということが告げられている。しかし、明らかに、素朴な人は、その祈りを繰り返すときにも、それらの深みを推し量ることはできないだろう、と。しかし、それができる必要はないのです。主の祈りが存在するようになるためには、包括的な世界の叡知が、人間と世界の最も深い秘密と呼ばれ得るものを言葉の中に定着させなければなりませんでした。これが主の祈りの内容であるわけですから、それは、その深みを理解するというにはほど遠い人々のためにさえ、その言い回しについて記述するのです。実際、これが真の祈りの秘密なのです。それは、世界の叡知から引き出されなければならないのですが、だからこそ、それが理解されないときでさえ、効果的であり得るのです。私たちがそれを理解することができるようになるのは、私たちがより高次の段階に上昇するときです。そして、祈りと神秘主義はそのための準備なのです。祈りは、私たちにとって、神秘主義のための準備となり、神秘主義は瞑想と集中のための準備となります。そして、その地点から、私たちは精神科学の真の働きへと向かうのです。祈りが真に効果的であるためには、私たちはそれを理解しなければならない、と言うならば、それは本当ではありません。誰が一本の花の叡知を理解するでしょうか?にもかかわらず、私たちは皆、その中に喜びを見出すことができるのです。同様に、祈りの創造の中に、世界の叡知が入り込んでいるならば、その秘密が把握されないとしても、それはその熱と光を魂の中に注ぎ込むことができるのです。しかし、それが叡知から創造されたのではないとすれば、それはこの力を有することはないでしょう。祈りの中の叡知がどれほど奥深いものであるかは、その効果によって示されるのです。魂は、この力の影響下に、本当に自らを発達させることができるとはいえ、真の祈りは、私たちがいかなる発達段階に到達していても、私たちに与えるべき何かを持っている、ということもまた申し上げなければなりません。多分、祈りの言葉以上のことは何も知らないような、最も素朴な人であっても、その祈りが彼の魂に及ぼす影響を受け取ることができ、そして、彼を高みへと上昇させる力を呼び出すことができる、というのが祈りなのです。けれども、私たちがどんなに高い段階に達していたとしても、ひとつの祈りで終ることは決してありません。それは私たちをさらに高い段階へと絶えず上昇させるのです。そして、主の祈りは単に話すためのものではありません。それは神秘的な心の炎を呼び出すことができるとともに、より高次の瞑想と集中形式の主題であることができるのです。このことは他の多くの祈りについても言うことができるでしょう。けれども、中世以降、何かが前面に出てきました。それは、祈りの純粋さとそれに伴う心の状態を損なうところの一種のエゴイズムです。もし、私たちが祈りを、多くのキリスト者達が中世を通じて行い、そして、多分、今日でも行っているように、私たち自身の中に引きこもり、そして、私たち自身をより完全にするという目的だけをもって利用するならば、そして、もし、それが何であろうと、私たちが受け取っているであろう何らかの光をもって、私たちが私たちの周りの世界に目をやることに失敗するならば、そのとき、祈りは、私たちを世界から切り離し、私たちをその中のさまよい人であるかのように感じさせる、ということにのみ成功するでしょう。これは偽りの厭世主義や隠遁に関連して祈りを用いてきた人たちにしばしば起こったことです。これらの人々は、薔薇の意味で完全になりたいと望んだわけではありません。薔薇は庭に美しさを付与するために自らを飾るのですが、そうではなく、彼ら自身のために、彼ら自身の魂の内に祝福を見出すためにそうしたのです。自分の魂の中に「神」を求め、自分の得たものを世界にもたらすことを拒否する人は誰でも、彼の拒絶が報復として自分に返ってくるのを見出すでしょう。そして、皆さんが、内的な熱を与える祈りだけを知っている聖人や神秘家の多くの著作の中で(スペインの神秘家、ミゲール・デ・モリノスの著作の中でさえ)出会うのは、魂が内的な祈りを通して完成を求め、自分が「神」であると考えるところのものに対する完全な帰依を求めるとき、それが経験するところのあらゆる種類の熱情や衝動、戦い、誘惑や荒々しい願望についての注目すべき記述です。もし、誰かが一方的な方法で「神」を見出し、精神世界に近づこうとするならば、もし、彼が彼の祈りに内的な熱に導く種類の献身だけをもたらし、光へと導くもうひとつの種類の献身をもたらさないならば、そのもうひとつの側が復讐するのです。もし、私が後悔と羞恥の感情をもって過去を振り返り、私の中には何か偉大なものがある、しかし、私はそれに十分な見通しを与えなかった、しかし今、私はそれを私に浸透させ、私を完全にするのだ、と自分に言うとするならば、ある意味で、正に完成の感情が生じます。しかし、魂の中に残る不完全さが抗力に変化し、その分よけいに激しく、誘惑や熱情の形で荒れ狂うのです。しかし、内的な熱と親密な献身の中で自らに集中した魂が、彼が露わにされるところのあらゆる働き、彼が光を求めて努力するあらゆる働きの中で、「神」を求めるやいなや、魂はそれ自身から踏み出し、狭く、利己的な自我から目を逸らします。そして、熱情の嵐は静まります。神秘的な献身と瞑想にエゴイズムが入り込む余地を与えることがそれほどに悪いことであるというのは、この理由によるのです。もし、私たちが「神」を見出すことを欲するとき、彼を単に私たち自身の内に留めておくためにだけそうするならば、それは、私たちの最も気高い努力の中に、不健康なエゴイズムが忍び込んだことを示しているのです。そのとき、そのエゴイズムは私たちに復讐するでしょう。私たちは、私たちの内に「神」を見出した後、私たちが内的に獲得したところのものを、私たちの思考と感情、私たちの意志と行いを通して、世界の中へと注ぎ出すときにのみ、癒されることになります。今日、私たちは、しばしば、特に、間違って理解された神智学の基盤から(そして、これに対する警告があまりにしばしば与えられるということは決してないのですが)、次のように告げられます。あなた方は外的世界の中に神的なものを見出すことはできない、何故なら、「神」はあなた方の内にあるのだから。あなた方は、ただ、あなた方の内的な生活への正しい道を取ればよいのだ。そうすれば、あなた方はそこに「神」を見出すだろう、と。私はある人物までもがそれを言うのを聞いたことがあります。彼は彼の聴衆に次のように言ってご機嫌を取るのを好んでいました。あなた方は、宇宙の偉大な秘密について何も学んだり経験したりする必要はありません。あなた方はあなた方自身の中を見るだけでよいのです。あなた方はそこに「神」を見すのですからと。私たちが真実に近づくことができるようになるためには、これと反対の観点が明確にされなければなりません。ある中世の思索家が内的な献身について言うべき正しいことがらを見出しましたが、それは、実際、その適用範囲内にある限り、正当なものです。私たちが決して忘れてはならないのは、不真実が最も害を及ぼすというわけではないということです。何故なら、魂はすぐにそれを検知するであろうからです。もっとずっと悪いのは、一定の条件下では真実であるけれども、間違って適用された場合には、完全に偽りになるような陳述です。私たちは私たち自身の内に「神」を求めなければならない、というのは、ある意味で真実なのです。けれども、正にそれが真実であるがゆえに、もしもそれがその範囲内に留められないとすれば、それだけよけいに害があるのです。ある中世の思索家は次のように言いました。「それが自分の家の中に確かにあると分かっているのに、誰がその必要な道具をどこか家の外に探すだろうか?そんなことをするのは愚か者であろう。同様に、「神」についての認識を獲得するための装置が彼自身の魂の中にあると分かっているとき、それを外的世界の中に探すのも愚か者である。」彼が使っている言葉、道具あるいは装置に注意して下さい。自分の魂の中に探すべきは「神」自身ではないのです。「神」はある装置を使って探します。そして、少なくともそれは外的世界の中に見出されることはありません。それは魂の中に、真の祈りを通して、様々の段階がある神秘的な献身、瞑想そして集中を通して見出されなければならないのです。私たちはこの装置の助けを借りて世界の領域に近づかなければなりません。そのとき、私たちは至るところに「神」を見出すでしょう。何故なら、「神」は世界のすべての領域と存在のすべての段階に顕現するからです。このように、私たちはその装置を私たち自身の中に求め、そして、その助けを借りて、至るところに「神」を見出すことになるのです。今日では、祈りの本性について、このような観察を行うことは一般的ではありません。一体全体と人々は言います、私たちが何をお願いするにしても、祈りが何かを変えられるだろうか?世界の経過は必然の法則にしたがっており、私たちはそれを変えることはできませんが、もし、私たちが力を認めたいのであれば、私たちはそれを、それがある場所で、探さなければなりません。今日、私たちは、祈りの力を人間の魂の中に求めました、そして、それがその魂の前進を助けるような何かである、ということを見出しました。そして、世界の中で働いているのは精神(想像上の、抽象的な精神ではなく、実際の活動的な精神)であり、人間の魂はその精神の領域に属している、ということを知っている人は誰でも、世界の中で働いているのは、変えることのできない法則に従う物質的な力だけではなく、精神的な存在たちもまたそこで働いている、ただ、彼らの活動は通常では見ることができないのだということを知るでしょう。もし、私たちが私たちの精神生活を祈りを通して強化するならば、後は、その効果を待つだけです。つまり、それらは確かにやって来るでしょう。とはいえ、祈りの効果を外的世界において追求できるのは、まず、祈りの力を現実のものとして認めた人だけです。このことを本当に認める人は、次のような実験を試みてみるのもよいでしょう。祈りを退けていた十年間をずっと振り返り、そして、祈りの力を認めていた次の十年間を振り返るのです。それから、これらふたつの期間を比べてみるならば、祈りが魂の中に注ぎ込んだ力の影響によって、人生の経過がいかに変化したかがすぐに分かるでしょう。力はその効果によって明らかにされます。力を呼び出すために何もなされないならば、その存在を否定するのは容易です。自分の中で、祈りの力を有効なものにしようと全くしてこなかった人が、どうして、それを否定することができるでしょうか。もし、私たちが光を点火したり、求めたりすることを全くしてこなかったとすれば、私たちは光について知っているのだと考えることができるでしょうか。私たちが、魂の中で、そして、魂を通して働く力について、その認識を学ぶことができるのは、それを利用することによってのみです。私は、どんなに公平な議論をするにしても、祈りがより広い範囲で有効になるには、まだ期が熟していない、ということ認めないわけにはいきません。参加者すべての力が合流するような集団的な祈りの中には、高められた力と、そのため、高められた現実の強さがある、というような考えは、今日の思考の把握するところではないのです。ですから、祈りの内的本性に関しては、私たちは私たちの魂の前にもたらしたもので満足しなければなりません。そして、それで十分なのです。と申しますのも、そのことを理解する人は誰でもそのことを確かに見通すことができるのですが、今日では、祈りに対して、それほど容易に多くの異議が持ち出されるのです。これらの様々な異議とはどのようなものでしょうか。例えば、仲間を助けるために力を行使する人間と、自らの中に静かに引きこもり、祈りを通して彼の魂の力に働きかける人間とを比べるとします。私たちは、確かに、最初の人物に比べて、二番目の人物はより怠け者であると見なすに違いありません。私が、別の観点が存在する、ということを、精神科学の認識に対する一定の感情から申し上げるとしても、皆さんはお許し下さるでしょう。私はいくらか誇張して言うかも知れませんが、それはそれなりの理由があるからです。今日、人生の奥に潜む原因に通じている人であれば誰でも、こじつけのように聞こえるかも知れませんが、影響力のある新聞記事を書く記者達が、彼らの魂を改善するために祈り、働くならば、彼らは人々のためにより良い仕事をすることになる、と感じるでしょう。もっと多くの人に、祈ることは記事を書くことよりも道理にかなっている、ということを分かってもらいたいものです。他の多くの知的な仕事についても同じことが言えるでしょう。さらに言えば、人生全体を理解するためには、祈りを通して働く力についての理解が必要なのですが、この理解は、私たちが文化生活のある特別な側面を見るとき、特別な明晰さをもって生じるのです。一方的で、利己的な意味においてではなく、今日、私たちが取ったような、より広い観点から祈りを見たとき、それが芸術の構成要素になっている、ということを見誤る人がいるでしょうか。確かに、芸術の中には、お笑いの中で表現されるような全く異なった側面、それが表現するものの上にそれ自身を上昇させるところのユーモラスな取り組みの中で表現されるような側面も見出されます。しかし、賦(ふ)や賛美歌は、祈りからそれほど遠く隔たっているとはいえません。そして、描写的な芸術でさえ、「絵画の中の祈り」とでも呼べるような例を示します。そして、荘厳な大聖堂においは、天までとどくような祈りに似た何かが石の中に表現されている、ということを誰が否定するでしょうか。もし、私たちが、人生の文脈の中で、このすべてを把握することができるならば、私たちは、祈りが、その真の本性の通りに見られたとき、人間を限定的で、一時的なものから、永遠なるものへと導くもののひとつである、ということに気づくでしょう。このことは、今日の、そして以前の講義の中で触れたアンジェラス・シレジウスのように、祈りから神秘主義への道を見出した人たちによって、特に強く感じられたのです。彼は、例えば、「ケルビニアン・トラベラー」に示されているような、彼の神秘思想の内的な真実と輝かしい美、暖かい親密さと輝く明晰さを、あれほど力強く彼の魂に働きかけていたところの祈りの自己訓練に負っている、と感じていました。そして、彼のような神秘主義者すべてを浸し、照らし出していたのは、そもそも、何なのでしょうか?祈りが彼らをしてそれに向けて準備させたところの永遠の感情ではないとすれば、それは何なのでしょうか?祈る人は誰でも、もし、彼が真に内的な落ち着きと内面性を祈りを通して達成し、次に、自分自身からの解放を達成するならば、この感情についてのいくらかの示唆を得ることができます。過ぎ去る瞬間を超え、永遠へと私たちの目を向けさせ、そして、過去と現在と未来を私たちの魂の中で結びつけるのがこの示唆なのです。私たちは、祈りの中で、そこにおいて「神」を(私たちがそれに気づいていようといまいと)求めるところのあの人生の側面に向かうとき、私たちの祈りの中に入ってくる感情と思考と言葉は、アンジェラス・シレジウスの次のような言葉によって表現されるような永遠への感情によって浸透されるでしょう。その言葉をもって、今日の締めくくりにしたいと思います。それは、たとえ無意識的にではあっても、すべての真に祈る人たちに、何か「神」の芳香と甘美のようなものをもたらすことができるのです。人気ブログランキングへ
2024年03月18日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第三講「神秘主義とは何か」(1910年2月10日) 本日取り上げますのは、それに関する広範な混乱がみられるようなテーマです。少し前に、私はひとりの教養ある学者が、暗く、不可解で、知識の範囲を超えた要素の存在を容認していたという理由で、ゲーテを神秘家の内に数えるべきだと断言するのを聞きました。そして多くの人がこの意見に同意するでしょう。一体、今日では神秘主義あるいは神秘的と呼ばれないものがあるでしょうか。何かはっきりしないものがあるとき、もし、それに対するその人の態度が「知らない」と「ぼんやりと感じる」の間を漂っているならば、彼はそれを神秘的であるとか不思議だとか言うでしょう。人々が何らかのことについて、ある種の無思慮や心理学的な知識によって、何も信頼に値するようなことは知り得ないと断言したい誘惑に駆られ、そしてそればかりではなく、それが今日の習慣になっているように、他の誰かがそれについての知識を有しているかもしれないということをも否定するならば、彼らはそれを神秘的であるとして退けるのです。けれども、もし神秘主義という言葉の歴史的な起源を研究するならば、私たちは偉大な人物たちがそれについて理解していたことや、彼らがそれによって自分たちに提供されていたと信じていたものについて全く異なる考えを持つようになるでしょう。私たちは、不明瞭で不可解であることを神秘主義の内容であるとは全く見なさず、その目標を高次の明晰さ、より明るい魂の光を通してのみ達成可能であるものとして語った人たちがいたということ、そしてその明晰さの程度は神秘主義の明晰さが始まる地点で科学の明晰さが終わるというほどのものであったということを理解するようになるのです。真の神秘主義を経験したと信じる人たちの確信とはそのようなものなのです。人間進化の最初期の時代にはいくつかの神秘主義が見出されますが、エジプトやギリシャそしてアジアの人々の秘儀において神秘主義と呼ばれたところのものは私たちの概念的な思考とは非常に隔たっています。そのため、たとえ私たちが神秘的な経験が取ったそれらの古い形態の横を通り過ぎたとしても、神秘主義という考えはほとんど浮かんでこないでしょう。神秘主義のかなり最近の形態、すなわちマイスター・エックハルト(Meister Eckhart/1260年頃-1328年4月30日以前)に始まり、13世紀から14世紀を通して、あの比類なき神秘家、アンジェラス・シレジウス(Angelus Silesius,/1624-1677)においてその絶頂をむかえるドイツ神秘主義の形態から出発するならば、私たちは今日の概念に最も近づくことができます。もし、彼らの神秘主義を検証するならば、それは純粋に内的な魂的経験により、とりわけその魂をすべての外的な印象や知覚から自由することにより、世界の最も深い出発点に関する真の知識に到達することを求め、そしてそのため、その魂は外的な世界から引きこもり、それ自身の内的な生活の深みに沈潜しようとした、ということが見出されます。言い換えれば、このタイプの神秘主義者は、どんなに努力して自然現象を分析しても見出すことができないような、また彼の知性をもってそれらを把握しようとしてもできないような世界の神的な基盤をこの方法によって見出すことができる、と信じていたのです。彼の観点は、外的な感覚印象が世界の神的な基礎の探求において、人間の認識力をもってしては貫くことができないようなヴェールを形成する、というものです。ところが、魂の内的な経験ははるかに薄いヴェールを形成し、そして、外的に現れているものの基礎にも横たわっているところの神的な基盤に向けて、このヴェールを貫くことは可能である、というのがあの世紀におけるマイスター・エックハルト、ヨハネス・タウラーそしてスーソ等からアンジェラス・シレジウスへと至る神秘家の秘儀の方法になっているのです。これらの神秘家たちが、彼らの内的な探求の直接的な結果と見なされ得るであろうものだけではなく、それ以上のものを見出すことができるということを信じていたのは明らかです。私たちは、この冬の連続講義の中で、この内的な探求をそれらすべての様々な側面において扱いました。もし、私たちが人間の内的な存在と正当に呼ばれるものの中をのぞき見るならば、私たちはまず第一に魂の最も暗い深みに行き着きます。そこでは魂がまだ恐れや恐怖、不安と希望、そして楽と苦、楽しみと悲しみの全領域にわたる感情に左右されています。私たちはこの魂の部分を感覚魂と呼びました。さらに私たちはこれらの魂的経験の暗い基礎の中から、私たちが悟性魂と呼ぶところのものを区別しました。そしてそれは、自我が外的な印象を取り入れ、感覚魂の中に現れるところのものにその生命を全うさせ、そして平衡を見出させるとき達成されるようなものです。私たちはまた、悟性魂の中に、私たちがそう呼ぶところの内的な真実が生じる、ということをお話ししました。そして自我がその悟性魂への途上において獲得したところのものにさらに働きかけるとき、それはそれ自身を意識魂へと高めます。そしてそこで初めて、自我についての明確な認識が可能となり、人間は内的な生活から真の世界認識へと導き出されるのです。もし私たちがこれら三つの魂的生活の構成体を私たちの前に保持するならば、私たちが私たちの内的な存在の中に私たち自身を沈めるときに私たちが見出すところのものの概要がそこにあり、私たちは自我がその魂の三つの構成体にどのように働きかけるかを見出すのです。参照画:Meister Eckhart参照画:Angelus Silesius 既に述べたような方法で知識を追い求めたあの神秘家たちは、この魂の深みへの沈潜によって、何か別のものを見出すことができると信じていました。と申しますのも、彼らにとっては、魂的生活の内的な経験というのは存在の源泉に至るためには通り過ぎなければならないヴェールに過ぎなかったからです。とりわけ彼らは、もしその源泉に到達するならば、外的な歴史がキリストの生と死として提示するものをさらなる内的な経験として彼ら自身が経験するだろうと信じていたのです。さて、たとえ中世的な意味においてではあっても、魂へのこの神秘的な下降が起こるならば、その過程は次のようなものになります。外的な世界がその光や色の領域、あるいはそれが彼の感覚に与えるその他のあらゆる印象とともに神秘家の前にあります。彼はこのすべてに彼の知性をもって働きかけるのですが、その外的な世界にとらわれたままに留まり、その外観を貫いてそれらの源泉に至ることはできません。彼の魂は外的世界の概念的なイメージ、とりわけそれが受け取る印象から来る経験を、苦であろうと楽であろうと、あるいは共感であろうと反感であろうと保持するのです。人間の自我は彼の興味や内的生活の全体とともにあり、彼を外的世界およびそれが彼に刻印づける印象へと向かわせます。ですから、最初に神秘家が外的世界から目を逸らそうと試みるときには、外的世界が朝から晩まで彼の魂の中に生じさせたところのあらゆるものを計算に入れなければなりません。そして彼には、最初、彼の内的生活が外的生活の繰り返し、あるいはその投影のように見えるのです。では、その魂が外的世界からその中に投影されたあらゆるものを忘れようとして、つまり、その世界から引き出されたすべての印象や概念的なイメージを消し去ろうとして奮闘するならば、その魂は空虚なまま取り残されるのでしょうか。真の神秘的な経験は魂が別の可能性を有しているという事実に依存しているのです。そのため、それがその内に有する記憶だけでなく、共感や反感という感情をも消し去るとき、それでもそれは何らかの内容を有しています。神秘家は外的世界の印象がその色鮮やかな像とそれが魂に与える影響により、魂の隠れた深みに存在する何かを抑圧するような効果を持っていると感じます。彼が外的世界に向かうとき、その生活はより繊細な魂の経験をうち消すように輝き出る力強い光のようなものであると感じられます。しかし、外的世界からのすべての印象が消し去られるとき、エックハルトがそう呼んだような内的な閃光が輝き出るのです。そのとき彼は、目もくらむような外的世界を前にしては知覚不可能であったために、何か以前はそこになかったように見えたところのものを魂の中で経験するのです。神秘家はそのとき、それをはっきりさせるため、彼の魂の中で経験するところのものは外的世界において彼が出会うようなものと比較され得るのかと問います。いいえ、大変な違いがあります。外的世界における私たちの事物に対する関係は、それらの事物がその外的な側面しか私たちに見せないために、私たちはそれらの内面性へと貫き至ることができない、というようなものなのです。私たちが色や音を知覚するとき、私たちはさしあたり、その背後にそれらの隠された側面と見なさざるを得ないような何かが横たわっている、ということに気づくことができます。けれども、私たちが外的世界の印象や概念的なイメージを消し去るやいなや、魂の中に生じる経験に関しては、事情が異なってきます。つまり、私たちは、それらがそれらの外的な側面だけを私たちに見せている、とは言えなくなるのです。何故なら、私たちはそれらの内にいて、それらの一部であるからです。そして、もし私たちに内的な光へと私たち自身を開く才能があるならば、それらは私たちにその真の存在において自らを示すとともに、私たちはそれらを外的世界において出会うようなものとは全く異なるものとして見るのです。と申しますのも、外的世界は至るところで成長と衰退、開花と萎縮、誕生と死から逃れられないからです。そして、小さな閃光が輝き始めるとき、魂の中に自らを現すところのものを観察するならば、すべての成長と衰退、誕生と死に関する考えがそれには適用できない、ということが分かります。何故なら、ここで私たちは何か独立したものに出会うのであって、内と外というような外的世界に属する概念はそれにはふさわしくないからです。ここで私たちが把握するのはもはや事物の表面もしくは外面ではなく、その真の存在における事物そのものなのです。私たちが私たち自身の内にある不滅の要素を確かなものとし、そしてその要素と精神、すなわちすべての物質的なものの主要な基盤として考えなければならないものとの緊密な関係を確かなものとするのは、正にこの内的な知識を通してなのです。この経験はその神秘家に、自分は以前の経験を克服し、抹殺しなければならない、通常の魂的生活は終わり、そして生と死に対する勝利者である真の魂が自分の内に生じる、と感じさせるように導きます。神秘家は通常の魂的生活が死んだ後に生じるこの魂の内的な核の目覚めを内的な再生として、つまりキリストの死と再生という歴史的な経過に似たものとして経験します。こうして、彼はキリスト事件が内的で神秘的な経験として彼の魂と精神の中で生起するのを見るのです。もし私たちがこの神秘主義的な道を最後まで辿るとすれば、すべての経験の統合とでも呼べるようなものに行き着くに違いない、ということが分かります。何故なら、その道は感覚知覚の多様性、すなわち知覚と感情の潮の満ち引きや思考の豊かな多様性が単純化されるという私たちの魂的生活の本質に属しているからです。と申しますのも、私たちの生活の中心点である自我は私たちの魂的生活の全体に統一を創り出そうとして絶えず働いているからです。ですから、これは明らかなことですが、神秘家が魂的経験の道を歩むとき、それらの経験は、あらゆる種々雑多なものが、自我によって処方された統一に向けて努力する、というような方法で彼の前にやって来ます。したがって、私たちはすべての神秘家の中に精神的な一元論とでも呼ばれ得るものを見出すのです。神秘家が、内的な存在であるところの魂は外的世界において見出されるようなものとは極端に異なる性質を有している、という知識へと自分を上昇させるとき、彼は魂の核と世界の神的・精神的な地盤との調和を自分の存在の内部で経験するのですが、そのために彼はそれらをひとつの統一体として表現するのです。私が今お話ししていることは単に記述的なものと見なされなければなりません。それは、魂によってその最も親密な関心事として手渡されてきた個々の神秘的な経験という形によるのでなければ、神秘家が明らかにするところのものを現代的な意味で再構成することは不可能だからです。ですから、神秘家が私たちに語るところの奇妙なことがらを私たち自身の経験と比べてみることもできるのですが、もし自分で経験するのではなく、他の人が個人的に経験したことについての記述に頼らなければならないとすれば、外面的な批判をすることはできないのです。けれども、神秘家が歩む道についてのはっきりとした像を今回の連続講義の基本的な立場から構成することはできます。それは本質的に内的な生活へと入っていく道であり、人間の発達の歴史が示すところによると、それは人間の精神がその啓発へと向かう探求の中で取る道のひとつです。どれが正しい道であるかについては様々の意見があるかも知れませんが、もし私たちが「神秘主義とは何か?」という問いにはっきりとした答えを与えるべきであるならば、追求され得る別の道の上になにがしかの光を当てなければなりません。神秘家の歩む道は彼を統一へと、すなわちひとつの神的・精神的な存在へと導きます。彼がこれを行うのは自我によって魂的経験の統一がそこで与えられるところの彼の内的な存在へと導く道に従うことによってです。もうひとつの道は人間の精神が外的世界のヴェールを貫いて存在の根底に至ろうとするとき、いつも取られてきた道です。そこでは、とりわけ人間の思考がその他の多くのものと合同して感覚によって知覚することができ、通常の知性によって把握することができるものを貫いて、表面的な事物の背後に横たわるところのもののより深い理解へと到達しようとしてきたのです。そのような道は、神秘主義の目標とは対照的に、必然的にどこに導くのでしょうか?それは、すべての妥当な関連が考慮されるならば、多種多様な外的な現象からみて、精神的な根底にも同様の多様性が存在しなければならない、という結論に導くのです。近代において、このような思考方法に従ったライプニッツやハーバートのような人たちは、豊かな外的現象をその根底に横たわっているであろういかなる種類の統一性によっても説明することはできない、ということを見てきたのです。要するに、彼らはあらゆる神秘主義に対するアンチテーゼ「単子論」を見出したのです。彼らは、世界が単子もしくは精神的な存在たちの多様性のある活動に基礎づけられている、という観点に達したのです。こうして、17、8世紀における偉大な思索家であるライプニッツは自らに次のように言いました。私たちが時空の中で出会うところのものを見て、そのすべてがひとつの統一体から湧き出してくると信じるならば、私たちは道に迷う。それは共同して働く多くのユニットに由来しているに違いない。そして、この単子の相互作用、つまり単子もしくは精神的存在の世界が人間の感覚によって知覚される現象を引き起こすのだと。これについて今日は詳しくお話しすることはできませんが、精神的な発達の深い探求が示すのは、外に向かう道を取りながら統一性を求める人は誰でも幻覚を免れないということです。つまり、彼らは神秘主義において内的に経験された統一性を一種の影のように外に向かって投影し、そしてこの統一性が外的世界の基礎であり、思考によって理解可能なものである、と信じたのです。けれども、健全な思考は、外的世界にはいかなる統一性も見出されることはなく、その多種多様性は様々の存在もしくは単子相互の働きから生じる、ということに気づきます。神秘主義は統一へと導くのですが、それは自我が魂の唯一の中心として私たちの内的な存在の中で働くからです。外的世界を通る道は、必然的に多様性、多元性、単子論に、すなわち世界についての人間の知識が器官や観察の多様性を通して達成される一方、多くの精神的な存在たちが私たちの世界を生じさせるために、ともに働いているに違いないという観点に導くのです。さて、思考の歴史において、はるかな重要性を持っているにもかかわらず、あまりにもわずかな注目しか集めていない地点へと私たちはやって来ました。神秘主義は統一へと導きます。けれども、世界の神的な基礎をひとつの統一体として認識するのは自我の本性、つまり魂の内的な構成に由来します。神秘家が神的・精神的なものを見上げるときには、自我がその統一の印を与えるのです。外的世界についての考察は単子の多様性へと導くのですが、それは単に私たちが世界を観察し、それが私たちに出会うその方法が多様性へと導き、そしてライプニッツやハーバートをして世界の基礎としての多様性を仮定させるように促したからに過ぎないのです。より深い探求は、統一性も多様性も世界の神的・精神的な基盤に適用できるような概念ではない、ということを私たちに気づかせてくれます。何故なら、私たちはそれを統一性によっても多様性によっても性格づけることはできないからです。私たちは、神的・精神的なものはこれらの概念を超越しており、これらによって推し量ることはできない、と言わなければなりません。哲学的な論争の中で、しばしば反対のものとして示される一元論と多元論の間の争いに光を当てる原則のひとつがこれです。もし、言い争う人たちが、彼らの概念は世界の神的な基盤に近づくには不十分である、ということに気づきさえすれば、彼らは彼らが何を論争しているかを正しい光の下に見るようになるかも知れません。さて、私たちは真の神秘主義の本質とは何かを学びました。それは神秘家を真の知識に導くような種類の内的な経験です。その経験が統一的に見えるのはそれが彼自身の自我に由来しているからです。ですから、彼はその統一性を客観的な真実と見なすことにおいて正当化されることはないでしょう。しかし、彼は本当に、精神の実体性がその統一の中に生きているところのものとして経験されると言うことはできるかも知れません。もし、私たちがこの神秘主義の一般的な説明から個々の神秘家に移るとすれば、私たちはしばしば神秘主義の反対者たちによってそれに反対する証拠として持ち出されるところの事実に出会います。個々人の内的な経験は様々な形態を取り、そのため、ある神秘家の経験は別の神秘家のそれと完全には一致しないかも知れないのです。けれども、二人の人間が、あることについて異なる経験をしたからといって、彼らの報告が正しくないということには決してなりません。ある人がある木を右から、そして別の人が左から見て、それぞれが彼ら自身の観点からそれを記述するならば、それは同じ木であり、それらの記述は両方とも正しいかも知れないのです。神秘家の魂的な経験が何故異なっているかについて、この簡単な例が示すことでしょう。つまり、結局のところ、神秘家の内的な生活は完全に空虚なものとして彼の前に現れるのではないのです。外的な経験を消し去り、それらから完全に注意を逸らそうとする神秘家の理想がどんなに大きなものであっても、それらはそれでも彼の魂の中に痕跡を残しますが、このことがひとつの差異を形成するのです。神秘家は彼の出身国の性格からも何らかの影響を受けずにはいられないでしょう。たとえ彼が有していたあらゆる経験を彼の魂から投げ出すにしても、彼の内的な経験は彼自身の人生から得られた言葉と概念によって記述されなければなりません。二人の神秘家が正確に同じ事柄を経験することもあるかも知れませんが、彼らは彼らの以前の人生の結果として、それを異なって記述するでしょう。私たちが、神秘的な経験の現実というものは基本的に同じであるということに気づくことができるようになるのは、私たちが私たち自身の個人的な経験を通して、記述と描写におけるこれらの個人的な違いを許容することができるときだけなのです。それはちょうど私たちが色々な角度から一本の木を写真撮影するよなものです。それらの写真は異なっているかも知れませんが、すべて同じ木の写真に違いはないでしょう。ある意味で、神秘的な経験に対する異論と考えられるかも知れない別の点がありますが、私はあれこれの偏見なしに、客観的にお話ししなければなりませんから、この異論は正当なものであり、あらゆる形態の神秘主義に当てはまる、と言わざるを得ないのです。神秘的な経験は非常に親密で内的なものであり、神秘家が経てきた以前の年月から導かれた個人的な性格を有しているという正にそのことのために、神秘主義的な生活について彼が語るいかなることも必然的に彼自身の魂と密接に結びついており、別の魂によって正しく理解されたり、同化されたりすることがきわめて困難なのです。神秘主義の最も親密な側面は、語られたことをどんなに熱心に理解し、その中に入っていこうとしても、いつでも親密なままに留まらざるを得ず、伝えられることが非常に困難なのです。問題になるのは次のような点です。つまりそれは、二人の神秘家が、もし両方が十分に進歩しているならばですが、同じ経験を持ちながら。その時、良心的な人なら誰でも、彼らが同じことについて話しているということに気づくでしょう。彼らが彼らの以前の年月において異なった経験を通過してきたために、そのことが彼らの神秘主義に独自の色合いを与えるであろうということです。このことから、ある神秘家によって用いられる表現や彼の口振りは、それらが神秘主義以前の彼の生活に由来するゆえに、私たちが彼の個人的な背景を理解しようと努力し、そうすることによって、彼が何故そのような話し方をするのかを理解するようにならない限り、いつでも、いくらか理解しがたいものに留まるでしょう。そのため、私たちの注意は普遍的に有効であるものから神秘家自身の個性へと逸らされます。この傾向は神秘主義の歴史の中で観察することができます。私たちは、最も奥深い神秘主義者に関しては特に、彼らが得た知識が他の人たちに告げられ、同化されることができる、などという考えを持たないようにしなければなりません。神秘主義的な知識を一般的な人間の知識の一部にすることは全く簡単ではないのです。しかし、だからこそ、私たちはその神秘家に対する興味をますますそそられます。そして、彼を研究することは、彼の中に普遍的な人間のイメージが反映されているために、無限に興味深いことなのです。神秘家が記述し、評価するところのものは、そして彼はそれが彼を存在の根底や源泉に導くという理由でそうするのですが、それ自体、世界の客観的な本性という点では、ほとんど私たちの興味を引きません。私たちが興味を引かれるのはその主観的な面であり、個人としての神秘家に対するその関係なのです。したがって私たちは、神秘主義を研究するとき、正にその神秘家が克服しようとしたことの中に、つまり世界に対する彼の個人的で、直接的な態度の中に価値を見出すのです。もし私たちが、いわば神秘家の側面から、人類の歴史を観察するならば、私たちは確かに人間の本性について多くのことを学ぶことができるでしょう。しかし、神秘家が表現するような言葉の中に、これはあまり強く主張することは決してできないのですが、私たちにとって直接的な価値があるような何らかのものを見出すというのは非常に難しいことなのです。神秘主義とは単子論もしくは二元論の反対側にあるものです。後者はすべての人間が共通に有している外的世界を観察し、熟考することから導かれます。その結果得られる体系は、間違いにつぐ間違いを含んでいるかも知れませんが、それを議論したり、どんな段階にせよ各人が到達した地点からそれらを基にしてなにがしかのことをなすことは可能なのです。ですから、ここで議論してきた神秘主義は大変に魅力的なものではありますが、それについて今まで述べられたことを私たちの魂に吸収させるとすれば、私たちは全く客観的にその限界に気づくことになります。もし、私たちが精神科学の方法、すなわち存在の主要な基盤へと貫き至るという目的を持って今日の精神生活のより深い水準から導かれるところの方法との関連で神秘主義を評価するならば、その上にさらなる光が投げかけられます。もし、ある主題がその考え方の微妙さゆえに理解し難いものになっているならば、それを理解する最良の方法とは、しばしばそれを何らかの関連する主題と比較することです。皆さんは、この連続講義の中で、高次の世界へと上昇する道について何回も聞きました。ある意味で、それは三重の道なのです。私たちは外的な道について、それから中世の神秘家によって取られた内的な道について記述し、後者についてはその限界を明確にしたのでした。今、私たちは精神科学もしくは精神的な探求の適正な道と呼ばれ得るものへと向かうことにしましょう。私たちは既に、この認識の道がそれを学ぶ人に対し、感覚世界の精神的な基礎に、したがって多元論に導く外的な道も、あるいはその人自身の魂のより深い基盤、そして最終的には世界の神秘的な統一へと導く内的な道も、どちらも取ることを要求しない、ということを見てきました。精神科学は、すぐ手の届くところにある知識によって開かれるこれらの道だけに人間が従わざるを得ないというわけではなく、彼には隠されたまま眠っている認識能力があり、それらから出発することにより、今述べられたようなふたつの道以外の道を見出すことができると語ります。これらふたつの道のいずれかに従う人は感覚世界のヴェールを貫き、存在の根底へと至ることを求め、あるいはまた外的な印象を消し去り、内的な閃光が輝き出るようにさせるかも知れません。しかし、その人はその人が既にそうであるところのままに、そしてそのようになっている状態のままに留まります。ところが、精神科学における基本は、人間が、既に存在している認識能力とともに、今日そうであるような状態に留まる必要はないということです。人間はちょうど彼が今日の段階に進化してきたように現在彼が有している認識能力よりも高次の能力を適切な方法により発達させることができるのです。もし、この方法を神秘主義的な認識様式と比較するならば、私たちは次のように言わなければなりません。もし、私たちが外的な印象を取り去るならば、私たちは内的な閃光を見出し、それ以外のものすべてが消し去られたとき、それがいかに輝くかを見るであろう。しかし私たちはそれでも既にそこにあるものを引き寄せているに過ぎないのだ、と。精神科学はそれでは満足しません。それは閃光に至るのですが、そこで立ち止まりません。それは小さな閃光をもっと強い光に変える方法を発達させることを求めます。私たちは外的な道も内的な道も取ることができるのですが、新しい認識能力を発達させるべきである限り、どちらの道も直ちに取ることはないのです。精神科学的探求の現代的な形態は内的な認識能力を内的な道と外的な道が統合されるというような仕方で発達させる点で、中世の神秘主義からも、多元論からも、そして古い秘儀の教えからも区別されます。こうして私たちはいずれの目的地にも等しく導くような道に従うのです。このことが可能なのは精神科学の方法による高次の能力の発達が人間を認識における三つの段階へと導くからです。通常の認識から進み出て、それを越えていくところの最初の段階はイマジネーションと呼ばれます。第二の段階は言葉の真の意味でインスピレーションと呼ばれます。最初の段階はどのようにして達成され、より高次の能力が生じるために、魂の中で何が成し遂げられるのでしょうか?それらがどのように発達させられるかというその方法が皆さんに示すのは、いかにこの道において多元論と神秘主義が超越されるかです。イマジネーションもしくはイマジネーション的な認識を理解するために最も役立つ例については既に一度ならず触れられました。それは精神科学者が自分に適用する方法の中から引用されます。それは多くのそのような方法の内のひとつであり、師と弟子の間で交わされる会話の形で最もよく表現されます。弟子をイマジネーションへと導くところの高次の能力に向けて教育しようとする師は次のように言うでしょう。「植物を見よ。それは土から生え出て、葉から葉へと展開し、花に至る。それをお前の前に立っているような人間と比較せよ。人間は植物以上の何かを有している。何故なら、彼の思考と感情と感覚の中に世界が照らし出されるからである。すなわち、彼は人間的な意識を有していることにおいて、植物を超越している。しかし、彼はこの意識を購うため、彼を錯誤と不正と悪徳に導くであろう熱情、衝動そして欲望を自分の内に吸収しなければならなかったのだ。植物はその自然法則にしたがって成長する。それはその存在をこれらの法則にしたがって展開しながら、純粋な存在としてその緑の樹液とともに我々の前に立つ。もし我々が幻想に耽るのでなければ、我々はそれを正しい道から逸らせるであろういかなる欲望や熱情や衝動をもそれに帰すことはできない。もし今、我々が人間を貫いて循環するような血を、すなわち人間意識の、あるいは人間自我の外的な表現であるところの血を観察し、それを植物に浸透するみずみずしい葉緑素に満ちた樹液と比較するならば、我々はこの脈打ちながら流れる血がより高い段階の意識へと人間が上昇したことの表現であるのと同じくらい、彼を堕落させる熱情と衝動の表現であることに気づくであろう。」「それから---」と、師は続けるでしょう。「人間がさらに発達し、彼の自我を通して、錯誤、悪徳、醜悪さや彼を悪徳へと引きずり下ろそうとするあらゆるものを克服するとともに、彼の熱情や情愛を純化し、洗練すると想像しなさい。人間が追い求める理想、つまり彼の血が、もはやいかなる熱情の表現でもなく、単に彼が彼を引きずり下ろすかも知れないすべてのものを内的に支配していることの表現にすぎなくなるとき実現されるような理想を思い描きなさい。彼の赤い血はそのとき、赤い薔薇の中で変化した緑の樹液に比較されるであろう。ちょうど薔薇が植物の樹液をその本当の純粋性において私たちに示すように、赤い人間の血は、それが純化され、洗練されたとき、人間を引きずり下ろすかも知れないあらゆるものを彼が支配するならば、彼がどのようになるかを、ただし植物の中で達成されたよりもより高次の段階において示すことができるのだ。」これらは師が弟子の心と魂の中に呼び起こすことができる感情やイメージです。もし弟子が乾いた棒きれでないならば、もし彼がこの比較によって象徴的に示される秘密全体に彼の感情をもって参入することができるならば、彼は魂をかき立てられ、その精神的な視野の前に象徴的な像として現れるものを経験するでしょう。それは薔薇十字の像、すなわち低次の人間本性の内で抹殺されたものを象徴する黒い十字架と、純化され、洗練されたことによって彼のより高次の魂的本性を純粋に表現するようになった赤い血を表す薔薇かも知れません。このように、赤い薔薇の花冠を架けられた黒い十字架はこの師と弟子の間の会話において魂が経験するところのものを象徴的に要約しているのです。もし弟子が薔薇十字を彼にとっての真の象徴となすような感情とイメージに対して彼の魂を開いているならば、つまり、彼が単に薔薇十字を彼の内的な視野の前に置いたと主張するだけではなく、その本質に関する高い次元での経験に向かって苦悶の内に勝ち進んでいたとするならば、彼はこの像や同様の像が単に小さな閃光ではなく、世界に対する新しい見方を彼に可能にするところの新しい認識の力といったようなものを彼の魂の中に呼び起こす、ということを知るようになります。このように、彼は以前の彼に留まっているのではなく、さらなる発達の段階へと彼の魂を上昇させたのです。そして、もし彼がこのことを何度でも行うならば、彼は、最終的には、目にとまる以上のものが外的な世界の中にはあるということを彼に示すところのイマジネーションに到達するでしょう。さて、このような認識方法がどのようにして存在するようになったのかを見ることにしましょう。私たちは自分に次のように言ったのではなかったでしょうか?私たちは外的な道を取ろう、そして事物の根底を求めようと。私たちは外なる世界へと乗り出すのですが、事物の基礎あるいは分子や原子を求めたりはしません。つまり、私たちは外的な世界が直接に私たちの前に置くところのものに関わることをせず、それから何かを留保するのです。世界に木がなかったとすれば、魂の中に黒い十字架が生じることはできなかったでしょう。そして、その魂が周囲の世界から赤い薔薇の印象を受け取っていなかったとすれば、それを思い浮かべることはできなかったでしょう。ですから、私たちは、神秘家が言うように、あらゆる外的なものを忘れ去り、完全に自分の注意を外的な世界から逸らした、と言うことはできません。私たちは外的な世界に従い、それだけが与えることができるものを取り入れます。しかし、私たちはそれを、ただそれがやって来るままに取り入れるのではありません。何故なら、薔薇十字が自然の中に見出されるということはないからです。では、どのようにして外的世界から取り出された薔薇と木が結びつけられて象徴的な像になったのでしょうか。それは私たち自身の魂の働きだったのです。私たちは、私たちが私たち自身を外的世界に、しかも単にそれを眺めながらではなく、それに心を奪われながら捧げるときに私たちのところにやって来るところの経験や、植物と発展していく人間とを比較することによって私たちが学ぶことができるところのものすべてを内的で神秘的な経験にしたのです。けれども、神秘家がするように、私たちの経験を直ちに自分のものにするということはありませんでした。私たちはそれを外的世界に捧げ、そして、世界が外的に、魂が内的に与えることができるものの助けを借りて、外的な神秘的生活と内的なそれがその中で溶け合うような象徴的な像を作りあげるのです。その像は直接的には外的な世界にも内的な世界にも導くことはなく、力として働くというような仕方で、私たちの前に立ちます。もし私たちが瞑想の中で私たちの魂の前にそれを置くならば、それは新しい精神的な目を開きます。そしてそのとき、私たちは以前には外的な世界にも内的な世界にも見出すことができなかった精神的な世界を見ることができます。そのとき、外的世界の根底に横たわり、今やイマジネーション的な認識を通して経験することができるものが、私たち自身の内的な存在の中に見出すことができるものと同じである、ということを私たちは見定めることができるのです。さて、もし私たちがインスピレーションの段階へと上昇するならば、私たちは私たちの象徴的な像の内容を脱ぎ捨てなければなりません。このことは内的な道を取る神秘家が辿る経過にきわめて似たところのものと関連があります。私たちは薔薇と十字架を忘れ去り、その像全体を私たちの魂の目の前から消し去らなければなりません。これはいかに困難なことであってもなされなければならないのです。私たちの魂は植物と人間との象徴的な比較を私たちの前に内的に呼び出すために自らを奮い立たせなければなりませんでした。今や、私たちは私たちの注意をこの活動に、つまり人間の内の克服されるべきものの象徴としての黒い十字架のイメージを呼び出すために魂が行わなければならなかったことに集中しなければなりません。私たちが、この活動を通しての魂的経験の中で、私たち自身を深めるとき、私たちはインスピレーションあるいはインスピレーション的な認識へと至るのです。この新しい能力の目覚めは私たちの内的な存在の中に小さな閃光の出現をもたらすばかりではありません。私たちはそれが認識の強力な力として輝き出すのを見るのです。そして私たちは、それを通して私たちの内的な存在に密接に関係しているにもかかわらず、それからは完全に独立しているものとして自らを現すところの何かを経験します。と申しますのも、私たちは私たちの魂的生活が内的な過程であるというだけでなく、何か外的なものに対してもいかに自らを働かせるかを見てきたからです。ですから、ここには神秘主義の残滓としての私たちの内的な存在についての知識があるのですが、それは外なる世界についての知識でもあるのです。さて、私たちは神秘家の仕事とは反対の仕事へとやって来ました。私たちがなすべきことは通常の自然科学が行うところのものに似た何かです。つまり、私たちは外的な世界の中に出ていかなければなりません。これは困難なことですが、インテュイションあるいはインテュイション的な認識の段階に上昇するためには不可欠なのです。私たちの仕事は今や私たちの注意を私たち自身の活動から逸らすということ、つまり、私たちの内的な視野の前に薔薇十字をもたらすために私たちが行ったことを忘れるということです。もし、私たちが忍耐強く、そしてその訓練を十分長く、しかも正しいやり方で遂行するならば、私たち自身の内的な経験とは全く関係がなく、いかなる主観的な色合いも持たないにもかかわらず、その客観的なあり方によって、人間存在の中心点、すなわち自我と同族であることを示しているのが確認されるような何かが私たちに残る、ということが分かるでしょう。こうして、インテュイション的な認識に至るために、私たちは私たち自身から出ていくのですが、それでも私たちの内的な存在と非常に密接に関係するところの何かへとやって来るのです。こうして、私たちは私たち自身の内的な経験から精神的な経験へと上昇するのですが、これは私たち自身の内部ではなく、外的世界の中で経験されます。このように、私たちはイマジネーション、インスピレーションそしてインテュイションを通過していくところの精神科学的な道の途上で、多元論が有する影の部分と通常の神秘主義が有する影の部分の両方を克服します。私たちは今や、神秘主義とは何かという問いに答えることができます。それは、人間の魂がそれ自身の内的な存在の中に自らを沈潜させることを通して、存在の神的・精神的な源泉を見出そうするその試みなのです。基本的には、精神科学的な認識もまたこの神秘主義的な道を取らなければならないのですが、それは最初にまず準備が必要であり、未成熟なまま乗り出すべきではない、ということをよく知っています。ですから、神秘主義とは人間の魂の中にある正当な衝動に発し、原則的には完全に正当化されるとはいえ、もしその魂がまず最初にイマジネーション的な認識において進歩することを求めなかったならば、あまりに早く取りかかられた企てなのです。もし、私たちが神秘主義によって私たちの通常の生活を深化させようとするならば、私たちは私たち自身を私たち自身から十分に自由にし、独立させることができないことから、私たちの個人的な色合いに染められていない世界像を形成することができない、という危険があるのです。私たちは、インスピレーションの段階へと上昇するとき、私たちの内的な存在を何らかの外的世界から取られてきたものに注ぎ出します。そしてそのとき、私たちは神秘家となる権利を獲得します。ですから、すべての神秘主義は人間の発達における適切な段階で取りかかるべきものなのです。もし私たちがそのための準備ができる前に神秘主義的な知識を達成しようとするならば、それは害があるのです。したがって、精神科学は正当な神秘主義の中に、精神科学的な探求の真の目的と意図を私たちに理解できるようにさせるところの段階を認めることができます。この点で、献身的な神秘家の研究から私たちが学ぶことができるほど多くのことをそれから学ぶことができるようなものはほとんどないのです。精神科学者が神秘主義の中に何らかの正当化されるべきものを認めるからといって、彼がさらなる進歩の必要性を否定していると考えるべきではありません。神秘主義が正当化されるのは、それが一定の発達段階にまで引き上げられ、そのためその方法が単に主観的な結果を産み出すのではなく、精神世界に関する真実に対して有効な表現を与えるときだけなのです。神秘主義的な方法に未熟なまま没頭することによって引き起こされる危険については多くを語る必要はないでしょう。それには、神秘家がその内的な存在を外的世界の中へと成長させるというような仕方で、彼自身の準備ができる前に人間の魂の深みへと降りていくことが含まれます。そのとき、彼は外的世界に対してしばしば自分自身を閉ざしがちになるのですが、これは基本的には単に洗練され、隠された形のエゴイズムなのです。このことがよく当てはまるのは、外的世界に背を向け、そしてこの黄金の気分がその内的な生活に浸透するとき、その魂の中に溢れるあの有頂天、意気軒昂、解放の感情に耽る神秘家です。このエゴイズムが克服され得るのは、自我が自らを外部に手渡し、その活動を象徴の形成によって外的世界の中に流れ込まさざるを得ないときです。こうして、イマジネーション的な象徴主義がエゴイズムとは無縁の真実の表現へと導くのです。神秘家がその発達の過程で、あまりに早く知識を追い求めることによって引き起こされる危険とは、常軌を逸した人、あるいは洗練されたエゴイストになるということなのです。神秘主義は正当化されます。そして、アンジェラス・シレジウスが次のように言うのは正しいのです。あなたが神の優越の中で、あなた自身を超越するなら、その時、あなたの中で上昇が支配するだろう。人間が、その魂を発達させることによって、自分自身の内的な存在に至り、そればかりではなく、外的世界の下に横たわる精神の王国にも到達する、というのは本当です。しかし、彼は十分な熱心さをもって、彼自身を超越するという仕事にかからなければなりません。そしてこのことを、正に今あるような自分自身の中で単にくよくよ考えることと混同するべきではありません。彼はアンジェラス・シレジウスの言葉を最初の行、二番目の行ともに深刻に受け取らなければなりません。もし、私たちが神の顕現の何らかの側面にしり込みするならば、私たちはこのことに失敗するでしょう。すなわち、私たちは私たちが外的世界からの顕現として私たちの中に流れ込むものすべてに私たちの内的な存在を捧げることができるときにだけ、神の統治を許すのです。もし、この考え方が私たちの精神科学的な認識と関係づけられるならば、私たちは正しい意味で第二の路線を取っていることになります。私たちは、私たちの中で、内的世界と外的世界の神的・精神的な基盤による統治を許すのです。そして私たちは、そのときにだけ、「天国への道」にあることを望むことができます。これは、私たちが私たち自身の内的世界や外的世界の色合いに染められていない精神の領域、つまり、私たちの上に輝く無限の星の世界、地球を包む大気、生い茂る緑の植物、海に流れ込む川と同じ基盤を有する領域にやって来るということを意味しています。そしてその一方で、その同じ神的・精神的な要素は私たちの思考、感情、そして意志の中にも生きており、私たちの内的及び外的な世界に浸透しているのです。これらの例は、アンジェラス・シレジウスが語ったような格言はそれを読むだけでは不十分である、ということを示すでしょう。つまり、私たちは、そこで初めてそれが真に理解できるようになるところの正しい段階においてそれを取り上げなければならないのです。私たちはそのとき、神秘主義が、その有している正しい核のゆえに、私たちを、私たちが徐々に精神的な領域をのぞき見ることを学ぶことができるほどに成熟しているであろう地点へと本当に導くことができ、そして、アンジェラス・シレジウスの美しい言葉の中に見出され得るものを私たちにとって最高の意味で現実のものにすることができるということを理解するでしょう。あなたがあなた自身をあなた自身の上に引き上げ、世界の神的・精神的な基盤があなたの中で統治するのを許すとき、あなたは存在の神的・精神的な源泉へと続く天国の道を歩んでいます。人気ブログランキングへ
2024年03月17日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第二講「笑うことと泣くこと」(1910年2月3日) 精神科学に関する連続講義の中でも、今日のテーマは確かに重要なものではないように見えるかも知れません。けれども存在の高次の領域へと導くような考察においては、人生の細事や身近な毎日の現実を切り捨てることはしばしば間違いなのです。永遠の生命や魂の最高の性質、あるいは世界や人間の進化に関する大いなる疑問が講義で取り上げられるとき、人々は満足し、喜こんで私たちが今日検証するような明らかにありきたりの事柄を放っておくことに甘んじます。けれども、精神的な世界へと貫き至るためにここで示された道に従う人であれば誰でも、よく知られたものからあまり知られていないものへと一歩一歩前進することは非常に健全な道であるということを確信するでしょう。さらに言えば、傑出した人たちは決して笑いと涙を単にありきたりのものと見なしてきたわけではないということも多くの例を挙げて示すことができます。いずれにしても、東洋の文化にとって途方もなく重要になった偉大なるツァラツゥストラに有名な「ツァラツゥストラ・スマイル」を付与したところの意識すなわち伝説と人類の偉大な伝統の中で達成される意識、それはしばしば個々の人間の意識よりもはるかに賢いのですが、それにとっては、この偉大なる精神が微笑みながら世界にやって来たということがとりわけ意義深いことだったのです。そして、世界の歴史に関する深い理解を持つ伝統によって付け加えられるのは、この微笑みのために世界の生き物たちが狂喜する一方、地上のあらゆる場所の邪悪な精神と敵対者たちはそれから逃げ出したということです。参照画:Zarathustra Smile もし、私たちがこれらの伝説や伝統からひとりの偉大な天才の仕事に目を移すとすれば、ゲーテが彼自身の多くの感情や考えを注ぎ込んだファウストという人物像を思い出すかも知れません。あらゆる存在に絶望したファウストが今にも自殺しようとするとき、イースターの鐘の音が響き、「涙がわき出て、再び地球が我を抱く。」という叫びが聞こえます。ここで涙はゲーテによって、ファウストが最も苦い絶望を経験した後、彼が世界に戻る道を見出すのを可能にするところの魂の状態を象徴するものとして用いられています。こうして私たちは、ただそれについて考えてみるだけで、笑うことと泣くことが大いなる意義を持つものに関連している、ということを理解します。精神の本性についてあれこれ考えてみることの方が、私たちの周りの身近な世界に現れるところの精神を追求するよりも容易なのですが、私たちが精神を、まず第一に人間の精神を見出すことができるのは他でもなく私たちが笑うことと泣くことと呼ぶあの魂のしぐさの中においてなのです。私たちがそれらのしぐさをある人の内的な精神生活の表現であると見なすのでなければ、それらを理解することはできません。しかしそうするためには、私たちは人間を精神的な存在として受け入れるだけではなく、彼を理解しなければなりません。この冬の連続講義はすべてこの目的のために費やされました。ですから、今はただ、精神科学から見た人間の存在について、ざっと見るだけにしましょう。しかし、これは私たちが笑うことと泣くことについての理解を築く上での基礎となるものです。私たちは、人間をその全体性において観察することにより、彼がその肉体を鉱物界と共有し、そのエーテル体もしくは生命体を植物と共有し、そして、そのアストラル体を動物界と共有していることを見てきました。アストラル体は楽と苦、喜びと悲しみ、恐れと驚き、そして、人間が起きてから寝るまでの間、彼の魂の中に流れ込み、流れ出るあらゆる考えをも担っています。これらは人間の永遠なる三つの鞘であり、その中には人間をして創造における最高のものにしたところの自我が生きています。自我は魂的生活の中で、その三つの構成部分である感覚魂、悟性魂そして意識魂に働きかけます。そして私たちは、いかにそれが人間をしてますますその成就へと近づけるために働いているかを見てきました。では、人間の魂の内における自我の活動の基礎とは何なのでしょうか。それがどのように作用するか、いくつかの例を見てみましょう。自我すなわち人間の最も奥深い精神生活の中心が外的な世界において何らかの対象もしくは存在に出会うと仮定して下さい。自我はその対象もしくは存在に対し、無関心のままに留まることはありません。自我はその出会いが自分を喜ばすかあるいは不機嫌にするかによって何らかの反応を示し、何かを内的に体験します。それは何らかの出来事に狂喜し、また最も深い悲しみへと落ち込むかも知れません。それは恐怖でしり込みし、またその出来事の源泉を愛情を込めて見つめ、抱きしめるかも知れません。そして自我は何であれそれに関係するものを理解し、また理解しないという経験を有することもできます。私たちは、起きてから寝るまでの間の自我の活動についての観察から、それがいかに自らを外的な世界との調和へともたらそうとしているかを見て取ることができます。もし何らかの存在が私たちを喜ばし、ここには何か私たちを暖めるものがあると私たちに感じさせるならば、私たちはそのものとの絆を織りなし、私たちの中から何かがそれに結びつきます。私たちが私たちの環境全体に関して行っているのはこのようなことなのです。私たちは起きている時間の全体を通じて、私たちの内的な魂的生活に関して、私たちの自我とそれ以外の世界との間に調和を創り出すことに関わっているのです。外的世界の対象や存在を通して私たちのところにやって来る経験は、そしてそれは私たちの魂的生活の中で反射されるのですが、自我の住居である魂の三つの構成体だけではなく、アストラル体、エーテル体そして肉体にも働きかけます。私たちは、自我と何らかの対象もしくは存在との間に自我によって確立されるところの関係がアストラル体の感情をかき立て、エーテル体の流れと動きを正すだけではなく、いかに肉体にも影響を及ぼしているかということについて、既にいくつかの例を挙げました。人は何か恐ろしいものが近づいて来るときには青くなるということに気がついていない人がいるでしょうか。これは自我によって形成された自我とその脅かす存在との間の絆が肉体の中に作用し、その当人が青くなるように血の流れに影響を与えたということを意味しています。私たちは逆の効果についても、つまり恥ずかしさで顔を赤らめるということについても触れました。私たちが周囲の誰かと自分との関係はしばらく身を隠していたいようなものであると感じるとき、血は顔へと上って来るのです。これらふたつの例によって、自我と外的世界との関係により一定の影響が血に対して生じることが分かります。自我がアストラル体、エーテル体そして肉体の中でいかに自分を表現するかについて、他にも多くの例を挙げることができるでしょう。自我はそれ自身とその環境との間に調和もしくはある一定の関係を求め、そしてこのことは何らかの結果をもたらします。私たちは、ある場合には、自我と対象もしくは存在との間に正しい関係を打ち立てた、と感じるかも知れません。たとえある存在に恐れを抱くもっともな理由があったとしても、それでもなお、私たちの自我は恐れそのものを含むその環境との調和的な関係にあったと、私たちは後になってからでなければそれをそのような光の下に見ることはできないにしても感じるかも知れません。自我が外的な世界の中で何らかの事物を理解しようとしてそれに最終的に成功するならば、それはその環境と特に正しい調和の中にあると感じます。そのとき自我はそれらの事物との一体性を、あたかもそれがそれ自身から抜け出し、それらの中に自らを浸しているかのように感じ、それ自身がそれらに正しく関係づけられていると感じることができるのです。それは言い換えれば、自我が他の人々と愛情に満ちた関係の中で生き、周囲との調和の中で、幸せと満足を感じているということでしょう。これらの満足の感情は次いでアストラル体そしてエーテル体の中に移行します。しかしながら、自我がこの調和を確立することに失敗し、そのためある意味で普通と呼べるようなものに達しないということが起こるかも知れません。そのときそれは難しい状況にあるところの自分を見出すでしょう。自我が何か理解できない対象もしくは存在に出会う、つまり、それがその存在との正しい関係を見出そうと努力するけれどもうまく行かず、それでもそれに対してはっきりした態度を取らなければならないと仮定しましょう。ひとつの具体的な例として、外的な世界において、私たちの自我がその本性の中に貫き至るほどの価値がないように見えるためにそれを理解したいとは思わないような存在、つまり、そうすることは私たちの知識と理解のための力をあまりに多く引き渡すことを意味すると私たちに感じさせるような存在に私たちが出会うと仮定して下さい。そのような場合、私たちは私たち自身をそれから自由にしておくために、それに対する一種の障壁を打ち立てなければなりません。私たちは、それらから私たちの力をそらすことによってそれらを意識するようになる一方、私たち自身の自意識を高めるのです。そのとき私たちのところへとやって来る感情が解放の感情なのです。このことが生じるとき、超感覚的な観察には、いかに自我がアストラル体をその環境もしくは存在がそれに与えるであろう印象から引き揚げるかが見えます。もちろんその印象は私たちが目を閉じたり耳をふさいだりしない限り、私たちの肉体に刻印されるでしょう。肉体はアストラル体に比べて私たちのコントロール下にあることが少ないために、私たちはアストラル体を肉体から引き揚げ、外的な世界からの印象に曝されないようにしておくのです。もしそうしなければ肉体に関わってそのエネルギーを消耗するであろうアストラル体をこのように引き揚げることは、超感覚的な観察には、アストラル体の膨張のように見えます。すなわち、それはその解放の瞬間に拡張するのです。私たちが私たち自身をある存在よりも上に引き上げるとき、私たちはアストラル体を弾力のある物質のように押し広げ、その通常の緊張を緩めるのです。そうすることによって、それから顔をそむけたいと思っている存在とのいかなる絆からも私たち自身を自由にします。私たちはいわば自分の中に引きこもり、その状況全体から自分を超越させるのです。アストラル体の中で生じるあらゆるものは肉体において表現されることになるのですが、このアストラル体の拡張の肉体的な表現が笑いあるいは微笑みなのです。したがって、この表情は私たちが周囲で起こっていることから私たち自身を超越させていることを示しているのですが、私たちがそうする理由は、私たちが私たちの理解力をそれに適用したくないからであり、私たちの立場から見てそれが正しいことだからです。ですから、私たちがそれを理解しようと意図しないものは何であれ私たちのアストラル体に拡張をもたらし、そしてそれによって笑いを生じさせるというのは本当なのです。風刺新聞が著名人をしばしば巨大な頭と小さな体で描写しますが、これはその時代におけるこれらの人物の重要性をグロテスクに表現しているのです。これに何らかの意味を見出そうとするのは無駄です。何故なら、巨大な頭と小さな体を結びつける法則などないからです。私たちの理性をそれに適用しようとするいかなる試みもエネルギーと心的な力の無駄使いです。満足できる唯一のこととは、それが私たちの肉体に与える印象の上に私たち自身を引き上げ、自我の中で自由になり、そしてアストラル体を拡張させることです。と申しますのも、自我が経験するところのものはまず最初にアストラル体に手渡されますが、それに対応する表情が笑いだからです。ところが、私たちが私たちの魂から必要とするような私たちの環境に対する関係を見出し得ないということが起こるかも知れません。私たちが、私たちの日常生活と密接に関係しているばかりではなく、その親密な愛情から生じる特別な魂的経験とも結びついているところの誰かを長い間愛してきたと仮定しましょう。それからこの人物がしばらくの間私たちから引き離されると仮定します。この喪失とともに私たちの魂的経験が奪われます。つまり、私たち自身と外的世界の存在との間の絆が断ち切られます。この人物と私たちとの関係によって創り出された魂的経験のゆえに、私たちの魂は、当然のことながら、長い間培われてきたこの絆が断ち切られたことによって苦しみます。何かが自我から奪われ、そしてその自我に対する影響がアストラル体に移行します。この場合には、アストラル体はそれから何かが取り去られるために収縮するのです。あるいはもっと正確には、自我がアストラル体を押し縮めるのです。このことは誰かが何かを失ったことによって苦しみや悲しみを被るときにはいつでも超感覚的に観察することができます。ちょうど拡張したアストラル体が緊張を解き、肉体の中に笑いあるいは微笑みという身振りを創り出すように、収縮したアストラル体は肉体のすべての力の中にさらに深く貫き至り、それを自分とともに圧縮します。この収縮の肉体的な表現が涙を流すということなのです。アストラル体はいわば空隙とともに取り残されたため、収縮することによってそれを埋めようとしますが、そのときそれはその周囲にある物質を利用するのです。それは肉体をも縮小させ、そしてその物質を涙の形で絞り出します。では、このような涙とは何なのでしょうか。自我はその悲しみと剥奪の中で何かを失いました。それは貧しくされ、その自我性を通常よりも弱く感じるがゆえに、と申しますのも、この感情の強さはその周囲の世界における経験の豊かさと関連しているからですが、そのためそれは自分自身を引き寄せるのです。私たちは私たちが愛するものに何かを与えるだけではなく、そうすることによって私たち自身の魂を豊かにしているのです。そしてその愛が私たちに与える経験が取り去られ、アストラル体が収縮するとき、それは失った力を自分自身に対するこの圧力によって再び取り戻そうとするのです。それは貧困にされたと感じるがゆえに、再び自分を豊かにしようとします。涙というのは単に流れ出るものではなく、打撃を受けた自我に対する一種の補償なのです。自我は以前には外的な世界によって自分が豊かにされたと感じていました。そしてそれは今や自分で涙を流すことによって強められるのを感じるのです。もし誰かが自意識の衰弱に苦しむならば、彼は流れる涙によって表現される内的な創造行為へと自分を駆り立てることによってこれを補おうとします。涙は無意識的な健康の感情を自我に与えますが、これによって一定のバランスが取り戻されるのです。皆さんは誰でも、いかに人々が悲しみと悲惨の深みにあるときには、涙の中に一種の補償、慰めを見出すかを知っています。皆さんはまた、泣くことができない人々にとっては、いかに悲しみと苦しみがはるかに耐え難いものであるかを知っています。ですから、もし自我が外的な世界との満足のいく関係を達成できない場合には、それは笑いを通して内的な自由へとそれ自身を引き上げ、あるいはまた、剥奪の後、力を獲得するためにそれ自身の中に沈み込むのです。私たちは、笑うことと泣くことの中で自分を表現するのは自我、すなわち人間の中心点である、ということを見てきました。このことからお分かりのように、ある意味で自我が笑いと涙の必要な前提条件である、ということが容易に理解されます。もし私たちが新生児を観察するならば、それは生まれてからの何日間かは笑うことも泣くこともできない、ということが分かります。本当に笑ったり泣いたりするのは36日か40日程度経ってからにすぎません。それは、以前の受肉状態からの自我が、その子の中に生きているにしても、外的な世界との関係を直ちには持とうとしないという理由によります。人間は、ふたつの面から構築される、というような方法で世界の中に置かれます。彼は、一方では、遺伝によって獲得されるあらゆる性質や能力を、父、母、祖父その他から引き継ぎます。これらすべては個性すなわちそれ自身の魂的性質を自ら担い、転生を重ねる自我の作用を受けます。子供が誕生によって存在の中に入っていくとき、私たちは最初、不確かな表情しか見出しません、そして、全く不確かなのは、後になって現れてくる才能、能力そして特殊な性格も同様です。しかし、私たちはやがて、自我がいかに絶えず以前の生から携えてきたところの進歩する力をもって幼児期の組織に働きかけ、遺伝された要素を作り替えるかを観察することができるようになります。遺伝された性質はこうしてある受肉から別の受肉へと移っていく性質と混ぜ合わされるのです。自我は子供の中でこのような仕方で活動的であるのですが、それが肉体と魂を変化させ始めるのにはいくらか時間がかかります。その最初の日々において、子供はその遺伝された特徴のみを示します。その間、自我は、以前の生から携えてきた性質をその不確かな表情に刻印づけることができるようになり、そして、日毎にそして年毎に発達するようになるのを待ちながら、深く隠されたままに留まります。子供が自分に属する個人的な性格を身につけるまでは、笑いと嘆きを通して外的な世界との関係を表現することはできません。と申しますのも、そのためには自分を外的な世界との調和の中に置こうとする自我もしくは個性が要求されるからです。自我だけが笑いと涙の中で自分を表現することができるのです。ですから、私たちが笑うことと泣くことについて考察するときには、人間の最も奥深く、最も内的な精神性を扱っていることになります。人間と動物の間のいかなる真の違いも否定する人たちは、当然のことながら、動物の世界の中に笑うことと泣くことに似たものを見出そうとするでしょう。しかし、これらのことを正しく理解する人は、動物はせいぜい吠える程度で、決して泣くまでには至らない、歯をむいて見せることはできても、決して微笑むことはない、と言ったドイツの詩人に同意するでしょう。ここには深い真実があり、私たちはそれを、動物はそれぞれの人間の中に住む個的な自我性へと自分を引き上げることはない、という言葉で表現することができます。動物は、人間の自我性に属する法則に似ているように見える法則によって支配されていますが、その法則はその動物にとって、その生涯を通して外的なものに留まります。人間と動物との間のこの本質的な差異については既にここで触れられています。すなわち、私たちに動物への関心を持たせるものはそれが属する種から構成されている、ということが語られたのでした。例えば、ライオンとその子孫との間には、人間の両親とその子供たちとの間に見られるような大きな差異はありません。動物の特徴の主なものとは、その型あるいは種の特徴なのです。人間の領域にあっては、各人が彼自身の個性と自分史を持っており、これが私たちの関心を引くのですが、一方、動物にあってはそれは種の歴史なのです。確かに犬や猫の飼い主の中には、彼らのペットの伝記を書くことができると断言する人も多くいるかもしれません。また、私はかつて生徒たちに一本のペンの伝記を定期的に書かせていた校長を知っていました。ある考えがどんな事柄にでも適用できるという事実が重要なのではありません。問題は、私たちがある存在や事柄の本質に理解を持って貫き至る、ということなのです。人間にとっては個人の伝記が重要ですが、動物にとってはそうではありません。何故なら、人間の本質的な部分は生から生へと生き続け、発展する個的なものであるのに対して、動物においては、生き続け、進化するのは種であるからです。精神科学においては、それらの種に情報を伝えるところの持続する要素のことを動物の集合魂もしくは集合自我と呼び、それを現実的なものと見ます。このように私たちは、動物はその自我をそれ自身の外部に有している、と言います。私たちは動物が自我を持っていることを否定するものではなく、動物を外から方向づける集合自我について語るのです。それと対照的に、人間に関しては、私たちは彼の最奥の部分へと貫き至り、彼の周囲の存在たちとの個人的な関係へと入っていくことができるような方法でそれぞれの人間を内側から方向づけるところの個人について語るのです。動物が外的な集合自我の指導を通して確立する関係は一般的な性格を有しています。動物が好んだり、嫌ったり、恐れたりするものはその種に特有のものであり、家畜や人間とともに生きる動物において、わずかに修正されているに過ぎません。人間においては、彼が彼の環境との関係で愛や憎しみ、恐れ、同情や反感として感じるところのものは、彼の個的な自我から湧き出して来ます。ですから、人間がそれによって彼の環境中の何かから自分を解放し、その解放を笑いの中に表現するところの特殊な関係、あるいは逆に、彼が見出し得ない関係を求め、その失望を涙の中に表現する場合、これらすべては人間においてのみ生じることができるのです。子供の個性が動物の段階を越えてそれ自身を明らかにすればするほど、それはますますその人間性を笑いと涙の中に示すようになります。もし私たちが人生についての真の観点を獲得すべきであるならば、人間と動物における骨や筋肉あるいはその他の器官の類似性といったような粗雑な事実に第一義的な重要性を置くべきではありません。私たちは、人間が地上存在の中で最高の地位を占めていることの証明として、彼の本質的な特徴とは何かを、その性質の隠された側面において追求すべきなのです。もし誰かが人間と動物の間の違いを明らかにするという点で、笑いや涙のような事実の重要性を理解できないとすれば、人間をその精神性において理解するようになるために最も問題となる事実へと上昇できないような人は救い難い、と言わざるを得ません。今、私たちが精神科学の光の下に考察している事実はある種の科学的な発見を照らし出すことができるのですが、但し、それはその事実が精神科学的な文脈における大いなる全体性の中に置かれたときに限ります。私たちが笑う人、あるいは泣く人を観察するならば、その呼吸過程に変化が生じているのが分かります。嘆きが涙にまで深まり、アストラル体の収縮へと導くとき、そしてこれによって肉体も収縮するのですが、吸気がますます短く、そして呼気がますます長くなります。笑いにおいては反対のことが起こります。つまり、吸気が長く、呼気が短くなります。ある人のアストラル体が緩み、そしてそれとともに肉体の繊細な部分が緩むとき、その過程は中のすべての空気がポンプで排出された空虚な空間の中に直ちに外の空気が流れ込むのに似ています。笑いにおいては外的な身体性の一種の解放が生じるのですが、そのとき息が長く吸われるのです。泣くときには正反対のことが起こります。私たちはアストラル体を押し縮め、それとともに肉体を押し縮めますが、その収縮が一回の呼気を長く続くようにさせるのです。これもまた、魂の経験が自我によって物理的なものと関係づけられるという、つまり、正に人間の肉体にまでもたらされるというひとつの例なのです。私たちがこれらの生理学的な事実を取り上げるならば、それらは太古の人類の宗教的な文献の中に象徴的に記録されている出来事にすばらしい仕方で光を当てることになります。皆さんはヤハヴェもしくはエホバが生命の息を人間に吹き込み、それによって彼に生きた魂を授けたとき、彼がいかに十全たる人間の地位に引け上げられたかを告げる旧約聖書の一節を思い出されるでしょう。それは自我の誕生が私たちの意識に刻印される瞬間です。このように、旧約聖書の中では、呼吸過程が真の自我性の表現として示され、人間の魂的性質との関係へともたらされているのです。笑うことと泣くことがいかに自我の独特の表現であるかを思い出すとき、私たちは呼吸過程と人間の魂的性質との密接な関係を直ちに理解します。そしてそのとき、私たちは、深く、そして真実の理解が私たちの中に浸透しなければならないという謙遜の気持ちをもって太古の宗教的な文献をこの知識の光の下で眺めるようになります。精神科学にとってはこれらの文献は不可欠ではありません。大災害によってこれらの記録がすべて破壊されたとしても、精神科学的な探求にとっては、それらの根本に横たわるものを自分で発見する手段があるのです。けれども、事実がこの手段によって確認され、そしてその後で、まぎれもなくその同じ事実が古い文献の象徴的で絵画的な言葉によって描写されているのが見出されるとき、それらの記録に対する私たちの理解は大いに高められるのです。私たちは、それらが精神科学的な探求者によって見出されるものに通じていた予言者に起源を有しているに違いないと感じます。精神的な洞察が精神的な洞察と何千年のときを超えて出会うのです。そしてこの知識から、私たちはこれらの記録に対する正しい態度を獲得します。いかに神が人間の中に神自身の生きた息を吹き込んだか、それによって彼が彼自身の内に住む自我を見出すことができるようになったかが語られるとき、私たちはこれらの記録に残された出来事が人間の本性にとっていかに真実であるかを私たちの笑いと涙についての探求に基づいて理解することができるのです。もう一点触れておくことがありますが、ただ簡単に触れるだけにします。そうでなければ、あまりに手を広げすぎることになるでしょう。誰かが私に次のように言うかも知れません。あなたの出発点は間違っていました。あなたは外的な事実から出発すべきだったのです。精神的な要素はそれが純粋に自然の事象として現れるところに求められるべきです。例えば、人がくすぐられたときのようにです。それが笑いに関する最も基本的な事実なのです。あなたはこの事実とあなたの想像力豊かなアストラル体の拡張やその他のものとの折り合いをどのようにつけるのですかと。そうですね、アストラル体の拡張が生じるのは正にそのような場合であり、私が述べたようなことすべてが、ただし、低いレベルにおいてですが、生じることになります。もし誰かが自分の足の裏をくすぐるとしても、彼は何が起こっているかを良く知っており、笑いを強制されるようなことはありません。けれども、彼が誰か他の人にくすぐられるとすれば、彼はそれを見知らぬものの侵入として、理性では理解できないものとして拒絶するでしょう。それから彼の自我は自分を解放し、アストラル体を自由にするためにそれを超越しようとするでしょう。このような不適切な接触からアストラル体を自由にするということが動機のない笑いの中にそれ自身を表現するのです。それは正に解放を、私たちの足をくすぐるという私たちに対する攻撃からの基本的なレベルにおける自我の救出を意味しているのです。冗談や何か滑稽なことに対する笑いも同じレベルにあります。私たちが冗談を聞いて笑うのは、笑いが私たちをそれとの正しい関係にもたらすからです。冗談はまじめな生活においては離ればなれになっているものを相関させます。もしそれらの間の関係を論理的に把握することができるならば、それはこっけいではあり得ないでしょう。冗談は理解ではなく、私たちが混乱状態にない限り、単に一種の遊びを喚起するような関係を打ち立てるのです。私たちはすぐにその遊びの主導権を握っていると感じ、自分自身を自由にし、その冗談の内容から超越します。この解放、すなわち私たち自身を何かの上に上昇させるということは、笑いが起こるときにはいつでも見出されることなのです。しかし、外的世界に対するこの関係は正当なものであるかも知れないし、またそうではないかも知れません。私たちは笑いを通して正しく私たち自身を解放しようとしているのかも知れません。あるいはまた、それに向けられた私たち自身の心が、そこで起こっていることを理解したくないように、あるいは理解できないようにさせているのかも知れません。そのとき、笑いは事物の本性にではなく、私たち自身の限界に起因することになります。このことは、未発達な人間が誰かを理解することができないために彼のことを笑うときに起こります。もし未発達な人間が別の人物の中に、彼が正当で真正なものだと見なしているところのありきたりで俗物的な性質を見いだし損ねるとすれば、彼はその人物を多分、理解したくないために、それを理解しようとする必要がないと考えるかも知れません。ですから、笑いを通して自らを解放するということは、あらゆる場合に容易に習慣になり得るのです。本当にある種の人々にとっては、すべてのことを笑ったり、愚痴をこぼすだけで、とにかく何も理解しようとしないということが当然のことになっているのです。彼らはふわふわとアストラル体をふくらまし、そして笑い続けるのです。あるいはまた、何か日常的な考えはそれを理解しようとするところのいかなる努力にも値しない、という態度が今流行になっているのかも知れません。そのとき人々はあれこれのものに対して優越感を感じ、思わずにんまりするでしょう。このことからお分かりのように、笑いはいつでも正当な留保の感情を表現しているというわけではないのです。留保が不当なものである可能性もあるのです。けれども、笑いに関する基本的な事実がそのことによって影響を受けるわけではありません。あるいは、誰かがこの人間の表現形式を計算ずくで利用するということが起こるかも知れません。話し手が聞き手に対して自分の言葉が持つ効果を、彼らが自分に賛成するかしないかにかかわらず、計算すると考えて下さい。さて、あまりにも取るに足らないことであり、あまりにも聴衆のレベルに比べて程度が低いために聴衆の魂といかなる密接な結びつきも織りなさない、というような仕方で語られることに話し手が言及することが正当なことである場合もあるでしょう。実際、そうすることによって、彼は本当に理解してもらいたい主題を取り巻くところの些細な事柄から聴衆が自由になるのを手助けしているのかも知れないのです。けれどもまた、いつも笑いを自分たちの側に取り込みたいと思っている話し手もいます。私は、彼らが次のように言うのを聞いたことがあります。私が勝つとすれば、私は笑いを巻き起こし、それによって笑った人たちを私の味方ににつけなければならない。何故なら、笑った人たちを味方につけていれば、ほとんど勝ったようなものだからと。このようなことは内的な不正直から出て来ます。何故なら、笑いに訴える人は誰でも、彼の聴衆を何らかのものを越えて上昇させるということを意図した反応を引き起こしているからです。けれども、彼が問題を提示するに当たって、もし、その問題がただ単に些細なことのように見えるレベルにまで引き下げられているというだけの理由で、彼の聴衆がそれを理解しようとせず、それを笑うことができるというような仕方で提示するならば、たとえ聴衆がそれに気付いていないとしても、彼は人間の虚栄心を当てにしているのです。ですから、お分かりのように、この笑いを当てにするということはある種の不正直を含んでいる可能性があるのです。同様に、私が述べたような涙に結びついた満足や幸福の感情を人々の中でかきたてることによって彼らを手中にすることもときとして可能なのです。ある人の前にイマジネーションの中だけで何らかの喪失感が持ち出されるような場合です。そのとき、その人はその何らかのものを見出すことができないのを知りつつそれを渇望することに耽るかも知れません。彼は彼の自我を収縮させることによって自分の自我性が強められるのを感じます。そしてこの種の感情への訴えかけは本当は人間の利己主義への訴えかけなのです。このように、これらの訴えかけの形態はひどく乱用される可能性があるのです。何故なら、涙や笑いにつきものの苦しみや悲しみ、からかいやさげすみはすべて自我の強化や解放に、したがって、人間の自我性に関連しているからです。ですから、そのような訴えかけがなされるとき、それが標的としているのは私たちの利己主義であり、その利己主義が人と人との結びつきを破壊するのです。私たちは、別の連続講義の中で、自我が感覚魂、悟性魂、そして意識魂に働きかけるだけではなく、その働きを通してそれ自身ますます強化され、成就に向けて近づく、ということを見てきました。このことから、泣くことと笑うことが自我の自己教育とその力を強化するための手段になり得るということが容易に分かります。ですから、笑いと涙の中に表現される魂の力を刺激するところのあの演劇の創作が人間の発達に向けての大いなる教育の源泉のひとつとして位置づけられるのは確かです。私たちが悲劇的なドラマを体験するということは、実際、本当にアストラル体を押し縮め、それによって自我に確かさと内的な凝集力を与えるという効果を有しているのです。喜劇はアストラル体を拡張させます。それはそれを見る人が愚行や偶然の一致から自分を超越させるからです。このことから、芸術的な創作行為を通して私たちの魂の前にもたらされるところの悲劇や喜劇がいかに人間の発達と密接に結びついているかを見ることができるのです。人間の本性をその最も詳細な面に至るまで観察する人は誰でも、毎日の経験が最も偉大な事実の理解へと導くということを見出すでしょう。芸術的な作品は、例えば、人生には笑いと涙の間で行ったり来たりしている一種の振り子がある、ということを私たちに教えます。自我は動きの中にあることによってのみ発達することができるのです。もし振り子が静止しているならば、自我は拡張したり、あるいは発達したりすることができず、内的な死に屈することになるでしょう。人間が発達する上で、自我が笑いを通して自らを自由にし、一方では涙を通して自らを追求することができる、というのは正しいことなのです。確かに、これらふたつの極の間にはバランスが見出されなければなりません。それはつまり自我がバランスの上においてのみ完成を見るからであって、決して狂喜と絶望の間を行ったり来たりすることの中においてではないからです。それは、一方の極端へと同じく別の極端へも振れて行く可能性があるような静止点においてのみ自らを見出すことになるでしょう。人間は徐々に彼自身の発達を導く指導者にならなければなりません。もし私たちが笑いと涙を理解するとすれば、私たちはそれらを精神の顕現と見ることができるでしょう。と申しますのも、私たちが、いかに人間が内的な解放の外的な表現を笑いの中に求めるかを、そして一方では、その自我が外的な世界の中である喪失を被った後、いかに彼が涙の中で内的に強められるのを経験するかを認識するときには、人間はいわば透明になるからです。笑いとはそもそも何なのか、というような問いに対して、私たちは次のように答えることができます。それは、人間が自分に値しないものに巻き込まれることなく、決してとりこにされるべきではないものから笑いとともに超越するために、彼が解放に向けて苦闘していることの精神的な表現である、と。同様に、涙は、彼を他の誰かと外的な世界において結びつけていた糸が断ち切られたとき、それでも、彼がその涙のただ中で同様の結びつきを求めているという事実の表現なのです。彼が泣くことを通して彼の自我を強化するとき、彼は実際、自分に次のように言っているのです。私は世界に属している。そして世界は私に属している。何故なら、私はそれから引き離されていることに耐えられないのだからと。さて最後に、私たちはいかにこの解放、つまり、あらゆる下劣で邪悪なものからの超越が、それを見た地上のすべての生き物が狂喜し、一方、邪悪な精神が逃げ出したところの「ツァラツゥストラ・スマイル」の中に表現され得たかを理解することができます。この微笑みは、それを窒息させたかも知れないあらゆるものからの自我の超越を世界史的に象徴するものなのです。そして、存在することは価値がない、もう世界とは関わりたくないというような場面に自我が遭遇し、その後、「世界は私に属し、私は世界に属す。」ということを肯定させるような力が魂の中にわき上がって来るならば、そのとき、この感情は、「涙が溢れて、地球が再び我を抱く。」というゲーテの言葉に直されるのです。この言葉はある確信を、つまり、私たちは地球から締め出されることはできない、私たちは私たちの涙の中でさえ世界との密接な結びつきを、それが正に私たちから取り上げられたように見える瞬間にこそ主張するのだという確信を声にしたものなのです。そしてこの主張はその正当性を世界の深い秘密の中に有しているのです。私たちは人間と世界との結びつきを彼の顔を流れる涙から、あらゆる下劣なものからの解放を彼の表情に浮かんだ微笑みから知るのです。*本連続講義の第2講は以上ですが、シュタイナーがこの前年の1909年に同じくベルリンで行った連続講義「人間存在とその未来の進化」の第7講も「笑うことと泣くこと」と題されています。この講義は上記の講義とほぼ同じ内容ですが、最後のところが少し異なっています。そしてその部分は大変印象深いところなのですが、何故か上記の1910年の講義では触れられませんでした。そこでその部分だけを付録として以下に訳しておきます。両方の講義を比べてみると、内容はほぼ同じなのに何か少し雰囲気が違うような気がします。英訳のせいなのか、元々そうなっているのかはよく分かりません。 偉大な詩人は傲慢や自我の萎縮に根ざすような種類の悲しみや喜びではなく、自我とその環境との間の関係から生じ、そのバランスが外部から妨害された場合の悲しみや喜びに対して、そしてそれだけが何故、人間が笑ったり泣いたりするのかを説明するのですが、しばしば美しい表現を見出します。私たちがそのことを理解することができるのは、自我と外的世界とのバランスが妨害されるのは外的世界においてであり、そして外的世界によってである、ということを理解するからです。それこそが、人間が笑ったり泣いたりする理由なのです。一方、その理由が人間の中だけにあるとすれば、私たちは彼が何故笑ったり泣いたりするのかを理解できません。何故なら、それはいつでも何も根拠のないエゴイズムだからです。したがって、ホーマーがアンドロマッヘについて、彼女がその夫と赤ん坊の二重のしがらみに捕らわれる場面で、「彼女は泣きながら笑うことができた。」と言うとき、それが心を打つのはこの理由によるのです。これは泣くことに関して何か正常なものを記述するすばらしい方法です。彼女は自分のために笑うのでも泣くのでもありません。彼女が一方では彼女の夫を、他方では彼女の子供を気にかけるとき、外的な世界との正しい関係がそこにあります。そしてここに笑うことと泣くことがお互いにバランスを取るという本当の関係、すなわち、泣きながら微笑み、笑いながら泣くという関係があるのです。純真な子供はしばしばこのような方法で自分を表現します。何故なら、その子の自我は、後に大人になってからのようには硬化しておらず、笑いながら泣き、泣きながら笑うということがまだできるからです。そして、これらのことを理解する人は次のような事実を再び確かめることができます。つまり、笑ったり泣いたりする原因をもはや自分自身の中に求めず、外的な世界の中にそれを見出すという地点に至るまで彼の自我を克服したすべての人もまた泣きながら笑い、笑いながら泣くことができる、という事実をです。実際、私たちの周囲で毎日起こっていることの中に、もし私たちがそれを理解しさえすれば、精神的なものの真の表現があるのです。笑うことと泣くことは何か最高の意味で人間における神的なものの表情と呼ばれ得るものです。(Rudolf Steiner, The being of man and his future evolutiess, P108-9)人気ブログランキングへ
2024年03月16日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「魂生活の変容-経験の道」の第一巻は、心理学やスピリチュアルなテーマに関する書籍「魂生活の変容-経験の道」(第二巻) (GA59)佐々木義之 訳この「魂生活の変容-経験の道(第二巻)」(GA59)は、メーリングリストに参加されている佐々木義之さん(E-mail:naomi-s@mvi.biglobe.ne.jp)が、メーリングリスト上に発表してくださっているもので、日本語にはまだ翻訳されたことのない貴重なものです。英訳版からの翻訳で、全部で9講あります。なお、この講義集は、「魂生活の変容-経験の道」の第一巻(GA58)と第二巻(GA59)のうちの第二巻にあたります。■GA59 「魂の変容、経験の道(第二巻)」(ベルリン、1910年1月20日-5月12日)●第一講 精神科学と言語●第二講 笑うことと泣くこと●第三講 神秘主義とは何か●第四講 祈りの本性●第五講 病気と治療●第六講 ポジティブな人とネガティブな人●第七講 不調と心的な障害●第八講 人間の良心●第九講 芸術の使命「魂生活の変容-経験の道」(第二巻)(GA59) 佐々木義之 訳第一講「精神科学と言語」(1910年1月20日)-1 人間が自分を表現する様々の仕方をここで使用されている意味での精神科学の観点から観察するのは何か興味深いことです。と申しますのも、私たちがこの連続講義の中で行ってきたように、謂わば人生に様々の側からアプローチし、その様々の側面を観察することでそれについてのある包括的な見方が獲得され得るからです。今日は言語の中に明瞭に示されるところのあの人間精神の普遍的な表現を取り上げましょう。そして次回は、「笑うことと泣くこと」という題名の下に、言語に関連しているけれども、とはいえそれとは基本的に異なる人間表現のいわばバリエーションを見ることにしましょう。私たちが人間の言語についてお話しするとき、私たちはいかに人間のすべての意義、尊厳、そもそもその人間全体が、私たちが言語と呼ぶところのものと関連しているかを十分に感じます。私たちの最奥の存在、私たちのすべての思考、感情そして意志の衝動が私たちの仲間の人間へと流れ出ていくとき、それらは言語を通して私たちを彼らに結びつけるのです。このようにして、私たちは私たちの存在が無限に拡張する可能性、言語を通して私たちの存在を私たちの環境の中へと延ばす能力を感じます。一方、意義深い人物たちの内的な生活の中に入ることができる人であれば誰でも、いかに言語が暴君に、つまり私たちの内的な生活を圧倒する力になり得るかを感じることができるでしょう。私たちは私たちの感情と思考を、すなわち私たちの魂を通過する特別で親密な性格をもったそれらのものを言葉あるいは言語をもってしてはいかに貧弱に、不十分にしか表現することができないかを感じることができます。そして私たちは、私たちがその中に置かれているところの言語でさえいかに思考に関して特定の様式を私たちに押しつけるかを感じることもできます。誰もが、彼の思考に関する限り、いかに言語に依存しているかを意識している必要があります。通常、私たちの概念は言葉に付着しています。そして不完全な発達段階にある人間は言葉あるいは言葉が彼に吹き込むところのものと概念とを混同しがちです。ある人々が、彼らの周りで普通に使われている言葉の中に含まれているものを越えたところに達する概念の骨組みを自分で構築することができない理由はここにあります。そして私たちはいかに共通の言語を話す人々全体の性格が一定の方法でその言語に依存しているかに気付きます。国民的な性格、言語の文脈上の性格をより詳しく観察する人は、人間が彼の魂の内容を音に変化させることができるその仕方が今度は逆に彼の性格の強さや弱さ、彼の気質が表現されるその仕方、そして全体的な存在に関する彼の概念にさえ影響を及ぼすということに気付くに違いありません。言語の構成は国民の性格について多くを告げることができます。そしてひとつの言語がひとつの国民に共通であるがゆえに、個々の人間はいわばその国民の間に卓越する共通の要素、平均的な性質に依存しています。このように人間は一種の圧政、共同体の支配に屈しやすくなっているのです。しかし、もし人が、言語は一方では私たちの個人的な精神生活を、他方では共同体の精神生活を包含しているということに気付くならば、彼は「言語の秘密」と呼ばれるものを何か特別な重要性を有しているものとして理解するようになるでしょう。もし、人間がいかに言語において自らを表現するものであるかを観察するならば、その魂的生活についてかなり多くのことを学ぶことができるのです。言語の秘密、その起源と各時代における発展はいつでもある特定の科学的な専門分野における研究課題であり続けました。しかし私たちの世紀において、これらの専門分野が言語の秘密を暴くことに特に成功したとは言えません。今日私たちが言語とその発達、そしてその人間との関係をこれまで人間とその発達に適用してきた精神科学的な観点からいわば警句的かつ外観的に照らし出そうとしているのはこの理由からです。私たちが対象、出来事、過程を記述するために言葉を使うとき、まず第一に非常に不思議に見えるのは次の関連です。つまり、言葉や文章を構成するある特定の音の結びつきと私たちの内にあり、言葉として表現される対象が意味するところのものとの間のつながりとは何なのでしょうか。この関連で外的な科学は幅広い観察結果をあらゆる方法で結びつけようとしてきましたが、そのような方法は不満足な性格のものであるとも感じられてきました。問題は次のように非常に単純なのですが、それでもそれに答えるのはきわめて困難です。人間が外的な世界のある対象や出来事に直面したとき、何故彼はその対象や出来事の残響として彼自身の内部からあれこれの特定の音を発したのでしょうか。ある一定の観点から見ることによって、ことは全く単純であると考えられました。例えば、言語は元々言語器官の内的な能力によって形成された、つまりこの能力が外的な音として聞こえるようなもの、例えばある動物の出す音、あるいは何かが別の何かにぶつかる音を模倣したのだと考えられたのです。もしくは犬が「わんわん」と鳴くのを聞いた子供がその犬を「わんわん」と呼ぶようにです。そのような言葉の形成は擬音、音の模倣と呼ばれます。これは一定の方向性をもった考え方によって音と言葉を形成する本来の基礎であるとされました。当然のことながら、人間はどうやって音を発さない存在に名前を付けるに至ったのかという問題は答えられないまま残ります。そのような理論の不十分な性格に気付いていた偉大な言語学者マックス・ミューラーはそれを「わんわん」理論と呼んでからかいました。彼は別の理論を打ち立てたのですが、彼の反対者達は今度はそれを「神秘的」(この言葉はそのような意味で使われるべきではないのですが)と呼びました。と申しますのも、マックス・ミューラーは、それぞれの対象がいわばそれ自身の内に何か音のようなものを含んでいる、つまり落とされるガラスばかりではなく、鳴らされる鐘ばかりではなく、ある意味であらゆるものが音を持っているという観点を掲げているからです。そして人間の魂とこの表現要素すなわち対象の本質的な性質のようなものとの間に関係を確立する人間の能力がその魂の中に対象の内的な音存在を表現する能力を呼び起し、そして鐘の本質的要素が「キンコンカン」という音の中で経験されるというようにです。そして、マックス・ミューラーの反対者達は彼のからかいのお返しに彼の理論を「キンコンカン」理論と呼びました。参照画:マックス・ミューラーより詳細に検討すれば、人間がものの本性について彼の魂の中で残響のように経験するところのものをこのように外的な方法で性格づけようと試みるときにはいつでも何か不満足なものが残るということが分かります。人間の内的な存在の中へとより深く貫き至ることが要求されるのです。精神科学の観点から見ると基本的に人間は非常に複雑な存在です。彼は彼の肉体を有していますが、それは鉱物界を支配する法則と同じ法則によって支配され、鉱物界と同様に構成されています。同様に、人間は彼の存在における第二の、より高次の構成体であるエーテル体もしくは生命体を有しています。次いで、楽と苦、喜びと悲しみ、本能、願望、熱情の担い手であるアストラル体があります。これは精神科学にとっては人間が目で見、手で触ることができる体よりさらに現実的ではないにしても、それとちょうど同じくらい現実的な人間の構成体のひとつです。そして人間の第四の構成体を私たちは自我の担い手と呼びます。私たちはさらに現段階における人間の発達は自我の働きかけによって他の三つの構成体を変容させることにあるのを見てきました。私たちはまた、未来において自我は、自然あるいは自然の中で活動している精神的な力がこれら三つの人間構成体から作り出したものは何も残っていないというような仕方で、これら三つの構成体を変化させているだろうということも指摘しました。と申しますのも、苦と楽、喜びと悲しみ、イマジネーション、感情、そして知覚の波打つ力の担い手であるアストラル体は元来私たちがそれに参加することなく、つまり私たちの自我のいかなる貢献もなしに創造されたからです。しかし今や、自我は活動的となり、アストラル体のすべての性質と活動を純化し、清め、従属させるというような仕方で働いています。もし自我がアストラル体にわずかしか働きかけていなければ、人間は彼の本能や願望に支配されますが、もしそれが本能や願望を徳へと浄化するならば、そして乱れた思考を論理の糸で秩序づけるならば、その時には、アストラル体は自我が参加することなく作られたものではなく自我の産物へと変化しているでしょう。もし自我がこの仕事を意識的に成し遂げるならば、そしてそれは今日では人間進化の中でスタートが切られたところであるに過ぎないのですが、私たちはこの自我によって意識的に変化させられたアストラル体の部分を「霊我」、あるいは東洋の哲学の用語を使えば、「マナス」と呼びます。自我がアストラル体ばかりではなく、異なる方法、より強力な方法でエーテル体にまで働きかけるとき、私たちは自我によって変化させられたエーテル体の部分を「生命霊」、あるいは東洋の哲学の用語で、「ブッディ」と呼びます。そして最後に、自我が非常に強力になり、これははるかな未来において生じるだけなのですが、肉体を変化させ、その法則を規制し、それに浸透することによって肉体の中に生きるあらゆるものを支配するとき、私たちはこの肉体の部分を「霊人」、あるいはまたこの働きは呼吸過程をコントロールすることから始まるゆえに、東洋の哲学の用語で「アートマン」と呼びます。ドイツ語のatmen、「呼吸する」と比較して下さい。このように、私たちは人間を最初は四つの構成体、つまり、肉体、エーテル体、アストラル体そして自我から構成されていると見ます。そして過去に由来する私たちの存在の三つの構成体と同様に、私たちは私たちの自我の働きによって創造され、未来に向かって発展する人間の三つの構成体について語ることができます。こうして私たちは肉体、エーテル体、アストラル体に霊我、生命霊、霊人を加えることによって七つの構成体から成る人間について語ることができます。しかし、私たちがこれら最後の三つの構成体を何かはるかな存在であると、つまり人類の未来の進化に属するものと考えるとき、人間はある意味で既に現在においてもそのような発展のための準備をしている、ということが付け加えられなければなりません。人間が彼の自我によって意識的に肉体、エーテル体、アストラル体に働きかけるのははるかな未来においてに過ぎませんが、自我は既に無意識の中で、つまり充分な意識のない状態で人間存在のこれら三つの構成体をまだぼんやりとした活動に基づいて変化させつつあります。その結果は既に存在しています。以前の講義において、私たちが人間の内的な構成体として記述したところのものは、ひとえに自我によるこの働きのゆえに生じることができたのです。それによってアストラル体からは感覚魂が感覚体のいわば内的な鏡像として形作られました。感覚体が(感覚体とアストラル体は人間に関する限り同意語です。感覚体なしには私たちは満足というものを有することはないでしょう。)満足を伝える一方、それは願望として魂の中に反映されます。ですからそのとき私たちが魂に帰するのは願望です。このようにしてふたつのものが、つまり、アストラル体と変化したアストラル体あるいは感覚魂がお互いに属すことになります。満足と願望がお互いに属しているようにです。同様に、自我は過去において既にエーテル体に働きかけていました。自我が人間の魂の中に悟性魂もしくは心魂を内的に創造したのです。このように記憶の担い手でもある悟性魂は自我によるエーテル体の無意識的な変化と結びつけられています。そして最後に、自我は過去に肉体の変化に向けても働きかけ、人間が今日の形態において存在することができるようにしました。その変化の結果が意識魂であり、それが人間に外的な事物についての知識を獲得することができるようにさせるのです。このように七つの構成体からなる人間は次のように性格づけることができます。自我の無意識的な準備活動を通して三つの魂の構成体、すなわち感覚魂、悟性魂そして意識魂が創造されたと。参照画:Mikrokosmos1 さて、肉体、エーテル体そしてアストラル体は複雑な実在ではなかったのか?という疑問が生じるかも知れません。人間の肉体とは何という奇跡的な構築物なのでしょうか!そして、もし私たちがそれをもっと詳しく調べるならば、肉体はそれが自我によって意識魂へと変化させられた部分すなわち意識魂の物理的な形態と呼ぶことができる部分と比較してもっとはるかに複雑である、ということが分かるでしょう。同様に、エーテル体は悟性魂もしくは心魂の形態とでも呼ばれるところのものよりはるかに複雑であり、また、アストラル体も感覚魂の形態よりはるかに複雑です。これらの部分は人間が自我を持つ以前から存在していたものと比較して貧弱なのです。精神科学において、人間ははるかな過去にその肉体のための最初の素質を精神的な存在から発達させていたと語られるのはこの理由によります。これにエーテル体が、そしてずっと後になってアストラル体が、そして最後に自我が付加されました。人間の肉体はこのように四つの発達段階を通過してきたのです。つまり、最初は精神世界との直接的な対応がありましたが、その後、エーテル体を織り込まれ、注入されることによって発展し、そのためさらに複雑になりました。次にアストラル体が織り込まれるようになりましたが、それによってもまたさらに複雑になったのです。それから自我が加えられました。そしてこの自我の肉体に対する働きかけがそれの一部を変化させ、それを人間の意識すなわち外的世界の知識を獲得するための能力の担い手へと変えたのです。ただこの肉体は感覚と脳によって外的世界の知識を私たちに提供する以上の機能を有しています。私たちの意識の基礎を構成するとはいえ全く脳の領域の外側で生じるところの数多くの活動をそれは遂行しなければなりません。同様のことはエーテル体とアストラル体にも当てはまります。さて、もし私たちが何度も強調してきたように、外的世界で私たちの周囲にあるあらゆるものは精神であるという事実、すまわちあらゆる物質的、エーテル的、アストラル的なものには精神的な基礎があるという事実が全く明白であるとすれば、私たちは次のように言わなければなりません。人間が彼の存在の三つの構成体を発達させるに際し、自我は精神的な存在として内側から外に向けて働く。同様に、私たちの自我が現れてその発達を受け継ぐ以前に、私たちの肉体、エーテル体そしてアストラル体に働きかけていたもの(私たちがそれらを精神的な存在と言うにしても精神的な活動と言うにしてもそれは重要なことではありません)があったに違いない、と。私たちは、私たちのアストラル体、エーテル体そして肉体に対し、今日では自我が外向きに働きかけているのと同様の活動が起こっていた時代を振り返っているのです。つまり、自我がそれらの内部で自身を確立する準備が整う以前には、精神的な創造、精神的な活動が私たちの鞘に働きかけ、それらに形態、動き、形状を与えたのです。ここでもし私たちが感覚魂、悟性魂そして意識魂という私たちの存在における三つの構成体の中で自我が変化させたものすべてを除外し、これら人間存在の三つの鞘の構築、それらの内的な動きと活動を眺めるならば、人間の中で自我の活動に先立って生じるところの精神的な活動がそこにあります。私たちが精神科学において今日あるような人間を個別の魂として、つまりそれぞれの人間を自己充足した個人にするところの自我を注入された魂として語るのはこの理由によります。人間はそのような自己充足した自我存在になる以前には「集合魂」、つまり私たちが今日でも動物界に関して集合魂として言及するところの性質を持った魂の一部を構成していたのです。それぞれの人間におけるそれぞれの魂として人間の中で生じるものは種や同族全体の根底をなすものとして動物界の中で生じます。ひとつの動物の種全体が共通の集合魂を有しているのです。個々の人間の魂が動物においては種の魂に相当します。このように、人間が個々の魂になる以前には、今日では私たちが精神科学を通してのみその知識を持つことができるところの別の魂、つまり、私たちの個別自我の前駆となる魂が彼の存在の三つの構成体の中で働いていました。この私たちの自我の前駆体すなわち集合魂もまたそれ自身の中から肉体、エーテル体、アストラル体を変化させ、それ自身にしたがってそれらを秩序づけたのです。その後、それは肉体、エーテル体、アストラル体を自我に明け渡し、自我がそれらを変化させ続けるようにしました。そして人間が自我を付与される以前の最後の活動、自我の誕生以前に横たわるものの最後の影響が人間の言葉と私たちが呼ぶところのものの中に今日でも存在しているのです。ですから、私たちが私たちの意識魂、私たちの悟性魂もしくは心魂、そして私たちの感覚魂の活動に先立つものを考察するとき、私たちはまだ自我を注入されていない魂に出会います。そしてその結果は今日でも言語表現の中に存在しています。人間の四つの構成体の外的な表現とは何でしょうか。それらは肉体においてどのように純粋に外的に表現されるのでしょうか。植物の体は人間の体とは異なって見えます。何故でしょうか。それは植物の中には物質体とエーテル体のみが存在しているのに対して、人間の肉体の中にはアストラル体と自我もまた存在しているからです。それはこの内的な活動が肉体をそれに応じて形成し再構成するからです。肉体はエーテル体もしくは生命体に浸透されるときどのような影響を受けるのでしょうか。人間あるいは動物におけるエーテル体もしくは生命体の外的、物理的な表現は腺組織です。つまり、エーテル体は腺組織の建築家なのです。アストラル体は神経組織を形成しました。神経組織について正当に語ることができるのはアストラル体を有している存在に関してだけであるというのはこの理由によります。では、人間の内における彼の自我の表現とは何なのでしょうか。それは循環組織であり、特に内的な生命の熱の特別な影響の下にある血とでも呼べるところのものです。自我が肉体を変化させるときの人間に対する働きのすべては血を通して伝達されます。これが、血が特別な性質を有している理由です。自我が感覚魂、悟性魂そして意識魂を変化させるとき、それが達成するところのすべての働きはただそれが血を通して肉体に影響を及ぼす能力を有しているがゆえに肉体にまで貫き至ることができるのです。私たちの血はアストラル体と自我、そしてそれらすべての活動のための仲介者なのです。私たちが人生を見るとすれば、それが単に表面的なレベルではあっても、人間が彼の意識魂、悟性魂そして感覚魂を変化させるのと同様に、彼の肉体をも変容させるということに疑問の余地はありません。容貌は中で生きて働いているものを表現している、ということを誰が否定するでしょうか。そして内的な思考が、もしそれが魂を完璧に捉えるならば、ひとつの人生の経過の中でさえ脳を変化させるということを誰が否定するでしょうか。私たちの脳は私たちの思考の要求に適合する道具なのです。しかし、もし人間が彼の自我を通して彼の外的な存在を変化させ、いわば芸術的に形成することができる度合いを考えるとするならば、それは非常にわずかです。私たちが私たちの内的な熱と呼ぶところのものをもって血に動きをもたらし、それによって私たちが為すことができるのは非常にわずかです。私たちの自我に先立つあの精神的な存在たちはもっと多くのことを成し遂げることができましたが、それは彼らがより効果的な方法を用いることができたからです。このように人間の形姿は彼らの影響の下に形作られましたが、それはそれらの力によって人間から造り出されたものの総体的な表現として形成されたのです。これらの存在たちは空気の実質を用いました。私たちが私たちの血を脈打たせる、これによって血を私たち自身の中で活動的にするために内的な熱を用いるのと同様に、私たちの自我に先立って私たちに働きかけていた存在たちは彼らの目的のために空気を利用したのです。彼らの空気を通しての私たちに対する働きかけが私たちに私たちの人間としての形姿を与えるところのものを創造したのです。私たちがはるかな過去に空気を通して人間に働きかけていた精神的な力について語るのは奇妙なことに見えるかも知れません。しかし私が、私たちの内的な存在の魂や精神の生活について、それを単にイマジネーションの産物としてだけ考え、それが外的世界全体から取られてきたものであるということに気付かないのは間違っている、と申し上げたのはこれが最初ではありません。概念や考えが外の世界の中に存在するところの考えなしに私たちの中に生じることができると考える人は誰でも、ちょうど何も入っていないコップから水を取り出すことができると言っているようなものなのです。私たちの概念は、もしそれが外部の事物の中に生きているもの、それらの法則としてそれらの事物の中に存在しているもの以外のものであるならば、あぶく以上のものではないでしょう。私たちは私たちの魂の中で発達させるものを私たちの環境から取ってくるのです。私たちが、私たちを取り巻くあらゆる物質的なものには精神的な存在が織り込まれている、と語るのはこの理由によります。奇妙に聞こえるかも知れませんが、空気として私たちを取り囲んでいるところのものは単に化学によって示されるような物質なのではなく、精神的な存在、精神的な力がその中で活動しているのです。そして、私たちが私たちの血の中にある自我から流出する熱(これが本質的な要素なのですが)によって私たちの肉体をわずかに変化させることができるのと同様にして、自我に先立つ存在たちは空気を用いて、力強い方法で私たちの物理的な存在の外的な形を造り出したのです。私たちが人間であるのは私たちの喉頭とそれに関連するもののゆえです。すばらしい芸術的な器官として外部から私たちの中に彫り込まれ、その他の発声、会話器官に結びつけられた喉頭は空気の中の精神的な要素から創造されたのです。ゲーテは目に関して非常に適切に「目は光によって光のために作られた。」と言いました。もし今、ショーペンハウアーの意味で、光を感じる目がなければ私たちにとって光の印象はないであろうと強調するならば、それは単に真実の半分でしかありません。別の半分とは、もし光がはるかな過去にまだ定かでない器官から私たちの目をいわば彫り出さなかったとすれば、私たちは目をもっていなかったであろう、というものです。このように、光を単に物理的な光、今日記述されているような抽象的な実体と見なすのではなく、光の中にそれ自身のために目を創造することができるあの隠された存在を探さなければならないのです。同様に私たちは、別の関連で、空気は複雑な喉頭の器官とそれに関連するあらゆるものをある時期に人間の中に創造することができた存在たちに満ちている、と言うことができます。そして、人間形姿のそれ以外の部分は細部に至るまで、現在の発達段階にある人間とはいわば話す器官がさらに発達したものである、というような仕方で形成され、彫り出されているのです。まず第一に、話すための器官は人間の形姿にとって何か決定的なものになっています。人間が動物を超越しているのは話すことによってであると言われるのはこのためなのです。と申しますのも、私たちが空気の霊と呼ぶところの精神的な存在は動物をも造り出したのですが、それは人間が備えているような話すための才能を発達させることができるようなレベルにおいてではありません。人間は、彼の現在の思考、彼の感情そして彼の意志、つまり、彼の自我に関連するあらゆるものを発達させる以前に、彼の言語器官を既に内的に発達させていたことが分かります。今や、何故これらの精神的な力が人間の肉体に対して、それを最終的に彼の言語器官の付属物にするような仕方でのみ働きかけることができたのかが分かります。それは彼らがアストラル体、エーテル体そして肉体を空気の影響と配置を通して発達させたからです。自我は、人間が自分の内に空気の精神的な存在と私たちが呼ぶところのものに対応する器官を、つまり光の精神的な存在が目に対応しているのと同様の器官を有することができるようになった後に、それ自身の中で意識、感情、情緒として発達させたところのものをその中に形成することができたのです。このように、そこには無意識における三重の活動、つまり自我に先立って存在していたところの肉体、エーテル体そしてアストラル体への働きかけがあるのです。もし私たちがそれは集合魂であったということを、つまりその集合魂は動物の中では不完全な仕方で働いていたということを知るならば、私たちはこのことに気付くことができます。もし私たちが自我に先立って生じた精神的な力をアストラル体の中で働いていたものと見なすならば、次のことが考慮されなければなりません。私たちは自我に関係するあらゆるものを除去し、暗い根底から集合魂によって為された仕事を観察しなければならならないのです。願望と満足がアストラル体の中で不完全なレベルにおいて向き合います。願望は、その先駆けを既に人間のアストラル体の中に有していたがゆえに、魂の性質、内的な能力になり得たのです。アストラル体の中における願望と満足と同様に、心象、象徴と外的な刺激とがエーテル体の中で向き合います。自我に先立つエーテル体の活動をエーテル体の中における自我の活動と区別する、ということが最も重要なのです。自我が悟性魂もしくは心魂として活動するとき、人間の現在の発達段階においては、それは外的世界の真実にできるだけ近い像であるところの真実を求めます。外的な事物に正確には対応しないものを「真実」と呼ぶことはできません。私たちの自我の夜明け前に横たわるところの精神的な活動はこのような仕方では働きません。それらはむしろイメージの中で象徴的に働き、夢の働きに似ています。夢は例えば次のような仕方で働きます。誰かが夢の中で銃声を聞き、そして起きたとき、ベッドの横の椅子が倒れているのを見るというようにです。外的な出来事(椅子が倒れること)は、夢の中でイメージに、つまり銃声に変化させられます。このように、自我に先立つ精神的な存在たちは象徴的に働きましたが、私たちが秘儀参入によってより高次の精神的な活動を達成するときにも、私たちは再び同じ仕方で働くようになります。ここにおいて私たちは全く抽象的な外的世界から離れ、象徴的なものの見方、イマジネーション的な概念に向けて、ただし、今回は十全なる意識をもって働くように努めるのです。そして人間の肉体の中で働く精神的な存在たちはそれを外的事物の対応物とでも呼べるものに変化させました。外的な事実、そして模倣です。模倣とは、私たちが例えば子供の中に見出すような、つまりその他の魂の構成体がまだほとんど発達していない時期に見出すような何かです。模倣とは人間の無意識的な本性に属するような何かです。これが教育は模倣から出発しなければならないと言われる理由です。何故なら、人間の中で自我が秩序を創造し始める以前は模倣への衝動が自然の衝動として存在しているからです。肉体の中にある外的な活動に対置される模倣への衝動、エーテル体の中にある外的な刺激に対置される象徴、そして、アストラル体の中にある願望と満足の対応、これらすべては空気という道具の助けを借りて創造されたと考えられなければなりません。そして、それらは私たちの喉頭及び話すための装置全体の中に、いわば芸術的な印象が彫り出されるようにして創造されたと考えられなければなりません。そして、これらの自我に先立つ存在たちは空気が人間の中でこれら三重の方向性をもって表現されるに至るというような仕方で彼を形成し、秩序づけるように働きかけた、と言うことができます。と申しますのも、言語能力をその言葉の真の意味において見るとき、それは私たちが口に出すところの音から成り立っているのか?と問われねばならないからです。いいえ、それは音からではありません。私たちの自我は空気によって創造されたものに動きを与えます。目は光を取り入れるためにそれ自体で存在していますが、私たちが外的な光を取り入れるために目を動かすのと同様に、私たちの中の自我が空気の中の精神的な存在たちによって創造されたあの器官に動きを与えるのです。私たちはその器官を自我によって動きへともたらします。つまり、私たちは空気の霊に対応する器官を活性化し、そしてその器官を作った空気の霊が私たちの空気に対する活動の反響としてその音を私たちに響き返すのを待たねばならないのです。正にパイプのそれぞれの部分が音を出すのではないように、私たちが音を出すのではありません。私たちの自我は空気の霊から創造された器官を使用することによって活動を展開します。その時、私たちはその霊が再び空気に動きをもたらすのを、つまり、言葉がそれらの器官を最初に作り出した活動によって音になるというような仕方で動きをもたらすのを待たなければならないのです。こうして私たちは人間の言語が先に述べた三重の対応に支えられていることを理解します。この対応はどのように働いているのでしょうか。肉体における模倣は外的な活動すなわち私たちにある印象を与えるところの外的な対象を模倣しますが、それは画家が絵の具やカンバス、光と影など景色を構成する成分とは全く異なる成分から成るものを用いて景色を模倣するのと同様に、それらを音として構成するべき言語器官に支えられています。光と影を用いて模倣する画家に似て、私たちは空気の要素から造られた私たちの器官をもって環境を模倣するのです。これが、私たちが音として造り出すところのものがある対象の本質を真に模倣したものである理由です。そして、私たちの母音や子音は外部から私たちに印象を及ぼすそれらの事物の像や模倣以外のものではありません。人気ブログランキングへ
2024年03月15日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
神秘学の記号と象徴そのアストラル界と霊界との関係第七講 ケルン 1907年 12月28日 形と数の霊的な意味に焦点を当てています。以前の時代と今日における人間の物質体への表象力と感受力の作用を探求しています。建築様式が人間の肉体形成に及ぼす影響についても議論しています。例えば、ゴシック様式やノアの箱舟、ソロモンの神殿などが取り上げられています。像の世界と音の世界、惑星の運動における数の割合と天球の音楽についても言及されています。また、**メルクリウスの杖(カドゥケラス)**の瞑想についても触れています。記:メルクリウスの杖(カドゥケウス)は、ギリシア神話のヘルメス、ローマ神話のメルクリウスが持つ杖です。杖の柄に2匹の蛇が巻き付いていることから、ケーリュケイオンとも呼ばれます。カドゥケウスは、聖なる力を伝える者が携える呪力を持った杖で、王権の表象である笏杖(しやくじよう)のように、所持者を守る力があります。死にゆく人に用いれば穏やかになり、死せる人に用いれば生き返るという魔法の杖でもあります。また、2匹の蛇が左右に配置された様子から、物事の均衡やバランスが取れた状態を表し、ビジネスや取引において成功へと導くシンボルとしても知られています。カドゥケウスはデザインがよく似た「アスクレピオスの杖」と混同されることもありますが、アスクレピオスの杖はヘビが1匹であるのに対し、カドゥケウスはヘビが2匹で杖の上に翼が付いています。参照画:Caduceus第八講 ケルン 1907年 12月29日第八講 霊的な修練のために必要な教育手段としての形象的表象に焦点を当てています。感覚性から自由な思考、アストラル界での反対物としての形式と生命、腐朽と病気、魂における人間の高次の性質などについて探求しています。聖杯や未来の器官としての心臓と喉頭、数のシンボルの内的力、比率の霊的音楽なども議論されています。記:聖杯(Holy Grail)は、中世西ヨーロッパの聖杯伝説に登場する神秘的なオブジェクトで、非常に貴重な物、困難な探求の対象、至高の目標を表すためにも使用されます。伝説中で聖杯は、最後の晩餐のときにイエスが使った杯、または十字架上のイエスの血を受けたものであり、聖遺物のひとつとされています23。発見に成功する騎士にはガウェイン、ガラハッド、あるいはパーシヴァルなど諸説があります。聖杯伝説は、騎士の武勲や恋愛を含み、現在でもヒロイック・ファンタジーの要素として文学や絵画の表現に好んで取り上げられています。また、聖杯は強い精神力を持つ者によって奇跡の治癒力を発現するとされています。ただし、聖杯伝説はキリスト教の教義の一部とされたことは一度もなく、したがってギリシャ・東ヨーロッパなど正教会が優勢な地域では本項で扱う聖杯伝説は存在しないとされています。また、聖杯とは、儀式である聖餐で使う杯(カリス、羅:Calix、英: en:Chalice)とは異なるとされています2。このように、聖杯には多くの解釈と伝説が存在します。また、聖杯(Holy Grail)は、中世西ヨーロッパの聖杯伝説に登場する神秘的なオブジェクトで、非常に貴重な物、困難な探求の対象、至高の目標を表すためにも使用されます。伝説中で聖杯は、最後の晩餐のときにイエスが使った杯、または十字架上のイエスの血を受けたものであり、聖遺物のひとつとされています。発見に成功する騎士にはガウェイン、ガラハッド、あるいはパーシヴァルなど諸説があります。参照画:聖杯(Holy Grail)人気ブログランキングへ
2024年03月14日
コメント(0)
-

いっぷ句-84
いっぷ句-84冬籠り桃・梅・桜出番かな 愚通参照画:独り寝・休息にほんブログ村
2024年03月13日
コメント(0)
-
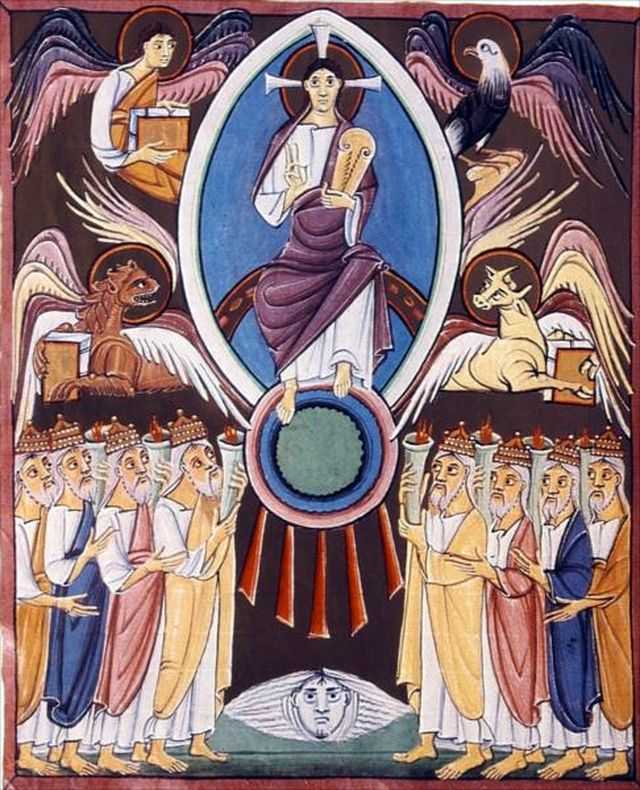
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
神秘学の記号と象徴そのアストラル界と霊界との関係第六講 ケルン 1907年 12月27日※集合自我と個の自我。人間の本質的構成要素の完成度の違い。未来における生きた法則の支配のための必要条件:秘蹟主義(サクラメンタリズム)の秘密。物質体における本質的構成要素の表出(感覚器官、腺、神経、血液)とエーテル体における表出(人、獅子、牛、鷲)。人間の各種族におけるこれらのさまざまな表出。人間の集合魂(諸民族)。その存続と変容。不死鳥(フェニックス)。秘学(オカルティズム)における言葉の象徴学と霊的な修練にとっての意味。 昨日の前置きに続いて、今日はすぐにいくつかの大変特徴のある記号や形象についてお話することにいたしましょう。昨日強調されたのは、この物質界に生きている人間だけが個としての魂、つまり自我を有していて、私たちの周囲にいる動物たちは集合自我、集合魂を有していること、集合自我はアストラル界に生きていてそこでは完結した存在として見いだされるということでした。このように動物界と人間界は、霊的に観察してみると、集合魂ないし集合自我と個としての自我として互いに相対峙しているのです。ただし、これを宇宙においてあたかも個々の存在間にまったく移行状態が存在しないかのように思い描いてはいけません。自然は飛躍しないという格言は、神秘学者にはまったくあてはまらないとは言え、至る処に移行状態が見られるのは確かです。つまり、動物界の集合魂と人間の個別的魂との間にも、移行状態が見出せるのです。人間がこの地球紀に出現してすぐに完全な個別的魂を有していて、この魂がこの地球上で同じやり方で何度も何度も受肉してゆくというふうに思い描くとしたら、それは正しくありません。寧ろ、今日びの人間は、太古の時代に有していた集合魂から、まだ自分のものになっていない完成された個別的魂へと徐々に移行している状態なのです。人間はまだその物質体に個別的自我を完全に組み込んでいく途上にあります。この地球紀が多かれ少なかれ完了するときになってはじめて、人間はこの完成された個別的魂を得るでしょう。大多数の人々にとって、今日自我は集合自我と個別的自我の中間物です。過去へとさかのぼればさかのぼるほど、人間の自我はいっそう集合自我の度合いを増します。地球紀の初め、魂が初めて神的な世界からこの物質界に降ってくたとき、人間の魂はまだ集合自我でした。複数の人間が一緒にひとつの共通の魂、すなわち集合自我を有するグループに属していたのです。このことをひとつの面として記憶にとどめておいてください。さて、もうひとつの面として、人間本性の構成要素そのものをもう少し詳しく見ていきましょう。これは、もう繰り返し言われてきたことなので、皆さんはもう十分ご承知のことと思いますが、人間はまずその本質として四つの構成要素、すなわち物質体、エーテル体あるいは生命体、アストラル体、自我を有しています。この自我は、もっと正確に観察すると、さらに三つの部分、つまり感受魂、悟性魂あるいは心情魂、意識魂という名で呼ばれている部分に分かれて現れます。感受魂と悟性魂ないし心情魂においてようやく独立した自我がほのかに現れはじめ、意識魂に至ってようやく自己意識的な自我の最初の名乗りが得られます。さらに、人間の本質の第五の構成要素、つまり霊我ないしマナスと呼ばれるものも徐々に人間の中に入り込んできているように見えます。従って、今日の人間の場合、次のように構成されているのです。つまり、物質体、エーテル体ないし生命体、アストラル体、それからアストラル体と内的に結びつきアストラル体の中にはめこまれているようになっている感受魂、そして悟性魂と意識魂、さらに本来の自我-魂である意識魂の中に霊我ないしマナスが組み込まれています。これでおよそ今日の人間を想定することができるでしょう。さて、これら人間の構成要素のうちどれが最も仕上がった、完成されたものなのか明確にしておかなければなりません。すでに私から説明を受けた方もいらっしゃると思いますが、今日の人間が進化したように、最も仕上がった、最も完全に発達した構成要素は物質体なのです。ただし、「最も仕上がって、最も完全に発達している」ということと、「高次の性質を持つ」ということを混同してはいけません。なるほど、エーテル体とアストラル体は、その程度において物質体よりも高次の性質を持っていますが、未来においてやっとその発達の完成に到達します。その性質において今日の物質体は人間のうちでもっとも完成された構成要素なのです。物質体を研究する人、しかも単に解剖学的物理学的にではなく、心情と心にしみわたるように研究する人は、物質体の中に組み込まれている巨大な叡智の前に驚嘆しつつ立ち尽くすでしょう。私たちの物質体はその最小の部分のどれをとっても、完成された、知恵に満ちた構造を示しています。例えば、この物質体のうちで大腿骨のほんの一片、大腿骨の一番上の部分をとってみても、これは一個の中身の詰まった固まりではなく、小さな梁が見事に組み合わされた、知恵にあふれた構造なのです。精緻な梁がいかに組み合わされているか研究してみると、最小の実質の消耗で最大量の力が出せるように、そしてこの大腿骨の柱二本で上体が支えられるようにすべてが構成されていることがわかるでしょう。最も完璧な工学技術をもってしても、このような叡智によってこれほど少ない材料の消費でこれほど大きな力を展開する橋や骨格のようなものを建造することはできません。人間の知恵は人間の物質体を構築したこの叡智にはるかに及ばないのです。物質体のすべての部分に対しても同様です。神経組織を備えた脳を観察すると、これはすばらしい構造です。人間の心臓を観察すると--心臓はまだ完成していく途上にあり、将来もっとずっと高度な完成に至るのですが--、心臓もすばらしいものです。この物質体の完成と欲求や衝動、熱情を伴ったアストラル体を比較してみると、次のように言わねばなりません。アストラル体は将来物質体よりも高次に位置するようになるとはいえ、今日のところまだ比較的低い状態にある、と。今日人間が享楽への熱望として発達させているすべてのものにおいて、アストラル体は物質体を何百とない攻撃にさらすのです。人間が調達するアルコールやその他あらゆる享楽の中で欲望され満たされるもの、これらはすべて根本的に物質体の叡智に満ちたすばらしい構造に絶え間なく攻撃をしかけるまさに心の毒なのです。アストラル体が、今日すでに物質体が完成状態で有しているものに行き着くには、長い進化期間が必要なのです。私たちの神智学的宇宙論が提出する進化論では、物質体はすでに古い土星上で物質体としての性質を有し、太陽、月、地球進化を経て、さらに完成度を高めてきたということでした。ご存知のように、第二段階、すなわち古い太陽上でエーテル体が加えられ、従って今日エーテル体は進化という点で物質体より一段階低い状態にあるのです。さらに、古い月上でアストラル体が付与されました。アストラル体はこの月進化と現在までに完了した地球進化の一部しか経ていません。自我は地球上ではじめてつけ加えられたので、人間本性の四つの構成要素の中では「赤ん坊」の状態です。昨日お話しした動物の集合魂を貫いているあの叡智は、本来人間の物質体に刻印されています。この叡智は、知恵にあふれた構成を持つ人間の個別の物質体へと移行したのです。人間のエーテル体はまだその完成の途上にあり、地球進化の経過の中で、その完成のために必要なものをすべて自らのうちに取り入れるのです。地球が目標を達成したあかつきには、地球はアストラル状態へ、そしてさらに高次の状態へと移行し、その後、地球を引き継ぐ木星と呼ばれる惑星に変化します。その時、人間のエーテル体は、地球上で物質体が完成した性質を持つように、完成されているでしょう。その次にくる地球の受肉状態、通常未来の金星と呼びならわしている状態においては、人間のアストラル体が完成に至るでしょう。その時、アストラル体は今日物質体の状態、そして次の惑星状態でのエーテル体の状態と同じ段階に至るでしょう。そして最後に、地球がヴルカン状態に到達する時には、私たちの自我が完成されていることでしょう。従って、実際、次のようにいうことができるのです。地球上では、人間の物質体のみが人間と言えるものであり、地球の次の惑星状態では人間のエーテル体が人間であり、その時、エーテル体は地球が人間に与えることのできるもの、すなわち愛によって浸透されているであろうと。今日、人間の物質体がその独自の特性として担っているものは、古い月に負うところのものです。神秘学においては、古い月は叡智の宇宙と呼ばれています。当時、古い月上では少しずつ現在人間の物質体に見いだされるものが準備されていました。ちょうど私たちの物質体であるものが月上で叡智に貫かれていたように、後の地球の木星状態に見いだされるべきもの、すなわち完全に愛の要素に貫かれたエーテル体が愛の宇宙を通して準備されるのです。今日私たちが物質体の骨の一部に現れている叡智に驚嘆するように--比較のためにこう言ってよろしければ--、木星人間はエーテル体に驚嘆することでしょう。エーテル体ちょうど地球上の物質体が叡智に貫かれて形成されているように、愛の力に貫かれているからです。このことを心にとどめておいていただくなら、本来人間の物質体がようやく真の人間といえるものであり、ようやく本当の意味で人類の段階にあるという見方を受け入れ、この事実を認識していただけると思います。人間のエーテル体はまだ人類の段階ではなく動物の段階であり、人間のアストラル体はまだ植物の段階です。夜眠りにつきアストラル体が離れるとき、物質体とエーテル体は夢のない眠りに沈みます。これは植物に終始見られる状態です。人間のアストラル体は、その意識状態に関しては植物の段階にあります。自我に至っては、ようやく鉱物界の段階に達している状態です。自我-人間の意識状態は、まったく鉱物界の段階そのものです。この真実に従って、ちょっと認識として有しているものすべてを調べてみてください。正しく認識しようとしてください。そもそも人間が理解できるものは何なのでしょうか。人間は鉱物界の物理的法則を理解できます。その法則に従って機械や工場、建築物等を建造できるのですから。これらすべては鉱物界の物理法則に従って行われます。植物の場合、もう当然人間は生命そのものは知性をもってしては理解できないと言わねばなりません。将来、人間が今日鉱物を理解しているのと同じように植物を理解するときがくるでしょう。そのときには、今日聖堂や家や機械類を鉱物界の法則に従って建造するように、植物でも作り出すことができるようになるでしょう。現在、自我が貫かれているのはすべて鉱物界の法則なのです。科学は、いつか生命ある存在を実験室の中で製造するという理想が実現するのを期待しています。これは、人類が道徳的進化のある特定の必要な段階に達しなければかなえられないでしょう。もし人類が今日すでにそういったことができるとしたら困ったことです。今日鉱物的な法則に従って時計を製作したり家を建てたりするように、将来人間は生きているものの法則に従って生きているものをつくりだすようになります。そのときに人間は生きているものに生命そのものを刻印できるようになっていなければなりません。そのとき実験室の机の前に立つ者は、自らのうちからあのいわば自らのエーテル体のなかにある振動を、生命を与えられるべきものの中へ導入していくことができるようになっていなければならないのです。善良な人間であれば善のものを導入しますし、良くない人間であれば良くないものを導入します。ただ神秘学においては次のような教理があって、サクラメンタリスム(秘蹟主義)の秘密を修得しないうちは、生命製造の秘密と呼ばれるホワイト・ロッジの知識は人類に伝授されないとされています。サクラメンタリスムとは、人間の行為が道徳的完成、神聖さの炎に燃え上がっていなければならないということを表しているのです。人間が作業を成す実験台が彼にとって祭壇となり、彼の行為が神聖なものとなったときはじめて、人間はこのような知識を伝授されるにふさわしく成熟するのです。唯物主義に染まった今日の人間たちには、その実験台がいかに祭壇にはほど遠いものであるかを考えてみてください。このように人間の意識は鉱物意識から植物意識へと高められていくのです。もうひとつ神秘学の教理があります。もはや自分自身の幸せを他のすべての人々の幸せと分離できなくなったときにはじめて、人間は植物意識の状態に到達するということです。個々人が他の人々の負担のもとに自らの幸せを追求するかぎり、意識が一段階上にひきあげられるという状態は起こらないのです。以上のように、私たちは物質体においてようやく本来の人間の段階であり、エーテル体ではまだ動物の段階、アストラル体では植物の段階、自我においては鉱物の段階なのです。このような事実のうちひとつのこと、つまり私たちはエーテル体においては動物の段階であるということを心に留めておきましょう。エーテル体は地球に存在する間にだんだんと人間の段階へと進化していきます。ますますいっそうエーテル体は愛によって、ひとりの幸せを他のひとの幸せからもはや分かつことのできないあの愛によって貫かれます。まず最初に物質体が仕上げられ人間の段階に到達したように、今度はエーテル体が、そして次にはアストラル体と自我も、人間の段階へと高められるでしょう。自我はまだ鉱物の段階です。自我は地球上ではじめて人間に組み込まれたのです。今度は、私たちの魂、つまり感受魂、悟性魂ないし心情魂、意識魂と意識魂の中に含まれた霊我ないしマナス、これらとエーテル体との関係を考察してみましょう。私たちのエーテル体自体は動物の段階にあります。下の方(黒板に書かれる--図参照 下から上へ)の人間の高さに物質体があります。とりあえずエーテル体は省略します(図では点で示されている)。私たちのアストラル体、魂の第一の構成要素である感受魂を含むアストラル体は植物の高さにあります。さらに、悟性魂ないし感受魂が続きますが、これらはすべて植物の段階にあります。さらに上方には、今日の人間に見出せる限りでの霊我ないしマナスを含んだ自我ないし意識魂があります。鉱物意識魂/自我/霊我ないしマナス悟性魂植物アストラル体/感受魂人間/物質体、とりあえず動物段階のエーテル体は省略しました。今度は人間のどの構成要素の中にも一定のやり方で他の構成要素が現れているということを明確にしておかねばなりません。人間の物質体はまず第一に物質体そのものの開示を自らのうちに表現しています。感覚器官を観察すると、物質体のうちに物質的原理が表現されているのがわかります。目の中には一種の写真機、カメラが、耳の中には一種のピアノがあるというわけです。つまり、感覚器官のなかに物質的原理そのものが表現されているのです。人間の腺を観察しますと、腺のなかにはエーテル体が表現されているのが見出せますし、神経組織の中にはアストラル体が、血液の中には自我が表現されているのが見出せます。「血はまったく特性のジュース」なのです。血を所有する者が人間の自我を所有するのです。悪魔が人間の血を所有すれば悪魔は自我を得るのです。このように人間の物質体のなかに他のどの構成要素も入り込んでいて、それが物質体のなかで表現されています。血液は無意識に脈打っています。血液のなかで活動する自我は、その物質的な経過を意識していないからです。物質体の中に他の構成要素の本質が現れているのと同様、エーテル体のなかにも他の構成要素の本質が現れています。もっともこの場合は「人間的に」現れているのではなく、「動物的に」、しかもある特定の動物の形で、外部に存在する動物の形姿と一定の類似を持つ形で現れています。このようにエーテル体の下にあるもの、つまり物質体が影像のように現れているのです。人間本性の物質的部分が現れているエーテル体のこの部分は、「人間」と呼ばれています(黒板に書き込まれる)。エーテル体の中に現れているアストラル体、感受魂は、そのエーテル形姿が似ていることから、「獅子」と呼ばれています。エーテル体の中に現れている悟性魂は、「雄牛」あるいは牝牛と呼ばれ、霊我を担う意識魂は、霊視的にみたエーテル形姿が似ていることから「鷲」と呼ばれています。参照画:黙示録の四つの徴(しるし)人、獅子、雄牛、鷲 こうしてここに(図参照)黙示録の四つの徴(しるし)人、獅子、雄牛、鷲が、四つの本質的構成要素の、人間のエーテル体における現れとして挙げられます。このことから、人間本性を表すのにこれらの意味深い象徴(シンボル)形象を考え出した私たちの祖先は、空想や哲学、思弁から作り出したのでも明敏さによって案出したわけでもなく、実際にある世界から、つまり隠された事実の世界から作り出したということが見てとれるでしょう。さて、ここで明白にしておかなければならないのは、これらの四つの表現は、どんな人間にも同等に生じているわけではないということです。ある人の場合、四つのうち一つの表現が優勢であり、別の人の場合にはまた別の表現が優勢となります。むろん、人類全体をその進化において考察せねばなりません。物質体そのものが最も強く現れているのはどこか観察してみると、その最も強い現われは、没落しつつある赤色人種、アメリカ・インディアンの場合、優勢である骨組織の特別な形成の中に見出せます。エーテル体が物質的に特別に現われているのはどこか見ようとするなら、これはまた別の人種、黒色人種の場合、腺組織の中に探さなければなりません。植物のひとつの性質は、炭素分離において見いだされます。[ここで筆記に欠落]とりわけ強く神経組織が物質段階に現われ、それとともに敏感さも現われている人間は、マレー人種の中に見いだされます。そしてとりわけ血液組織が現われている人種はモンゴル人種です。マナスの原理を養成しはじめている人間の一部はコーカサス人種に見いだされます。こうして神秘学的真実から人種の分類ができました。今日の人間の中に見出せるものは、ある人種の場合、あるものが優勢で他のものは後退しているというように、人類全体に配分されているのです。このような差異は人間のエーテル体の場合にも見いだされます。肉眼で物質体を観察するように、霊視によってエーテル体を観察してみると、人間においてエーテル体は、人-人間、獅子-人間、雄牛-人間、鷲-人間に分かれているのが見られます。これらの集合自我はアストラル的性質のものです。霊視者はアストラル界において動物の集合自我と人間の個別的自我の中間に人間の集合自我が位置しているのを見ます。時間的に過去にさかのぼるほど、人間はエーテル体に関してはこれら四つのうちのひとつの形態をとっていることが多くなります。これら四つの魂のグループはそれぞれひとつずつ人間の集合魂、つまり、ひとつは人間-集合魂、ひとつは獅子-集合魂,三つ目は雄牛-集合魂、四つ目は鷲-集合魂に帰せられます。ただ、これらの物質的な動物の形姿からとられた名前にあまりにこだわりすぎると、これについて誤った観念を持つことになってしまいます。このような獅子-人間のエーテル体は、物質界の個々のライオンに似ているよりもずっとライオンの集合魂の方に似ているのです。キリスト教は、福音史家たちについて、彼らの魂は通常の人間の魂のようではなく、人間のグループ全体を含むことを提示してきました。内的な魂の性質に従って、マタイは人に、マルコは獅子に、ルカは雄牛に、ヨハネは鷲に比較されてきました。これは、キリスト教的秘教が福音史家ひとりひとりの魂に帰してきた類似性に由来するものです。人間が、ある面では下降において、またある面では上昇において理解されるということを見ていくと、このことをもっと正確に理解できるでしょう。この地球上で唯物主義の最も深まった時点で、人間は個別的魂の原基を獲得しました。人間はひとつひとつの集合魂、人-人間、獅子-人間、雄牛-人間、鷲-人間をもっと厳密に区別していた古い時代から下降してきました。人間が将来再び上昇していったとき、人間はその個別的魂を保持したまま、より高次の段階においてより高次の意識で、以前には単にぼんやりとした意識のなかに有していたもの、つまり四つの集合魂を再び発達させることでしょう。そういうわけで、キリスト教においては、福音史家たちに、これらの特性が付与されているのです。もうしばらくの間、この人間の集合魂の概念にとどまってみましょう。これらの集合魂は、空間的に、つまり並列的に生きているというよりは、むしろ時間の中で相次いで生きているのです。動物の集合魂を観察してみると、ライオンのグループや鯨のグループを考えるなら、それらに共通の集合魂はアストラル界に並列的に存在しています。けれども、人間の集合魂を観察するときは、もっと時間というものに目を向けなければなりません。人間の集合魂はエーテル的なもののなかで、いわば物質界とアストラル界の境界領域である特定の時期に生まれ、再びある特定の時期に変化してゆくのです。先に述べたこれら四つの集合魂は、単なる四つの主要なタイプであって、無数の中間段階が存在するのです。最も特色ある人、獅子、雄牛、鷲という形姿を挙げましたが、これらはどのようにも混合することが可能です。ひとつの人間集団を観察してみましょう。例えばひとつの種族、古代中央ヨーロッパのいずれかの種族、ここではヒュルスカー族をとりあげてみましょう。このような種族がいったんあらわれては消えていきます。唯物主義的な世界観察者は、ヒュルスカー族であるもののなかに、そもそも何か抽象的なもの、種族をまとめるひとつの概念しか見ていません、神秘学者はヒュルスカー族の中にひとつの集合魂を見ます。この集合魂はヒュルスカー族が歴史に登場したときに現われ、「生まれ出」て、ヒュルスカー族が勢力を増すとともに成長し、ヒュルスカー族が歴史から消えるときに、「死ぬ」のです。進展してゆくヒュルスカー族の背後に、神秘学者はひとつの進展してゆくエーテル存在を見るのです。もっとも、エーテル存在とこの地上の物質的存在の間には差異があります。物質的存在は物質界で生まれ、成長し、生の最高点に達して、また死にます。誕生と死が物質界の存在の特徴をなすものです。アストラル界の動物の集合魂を数千年に渡って追求してみると、これらの生成と消滅は「誕生」と「死」という言葉ではまったく表現できません。まったく別のものに基づいているのです。すなわち変化、変容です。霊視的な能力をもってアストラル界で今日ある動物の集合魂に出会い、その集合魂の以前の受肉、つまり1500年前にこの動物の集合魂がどうであったかを思い出すとすると、これはもっと年の若い人を観察するということにはならないのです。もちろん、集合魂もやはり青年期、中年期、老年期を経ていきます。けれども集合魂は老年期に意識を捨てることなく死ぬこともないのです。死を通過することなく絶え間なく変化し続けるのです。皆さんは動物の集合魂をずっと太古の昔までさかのぼって追求していけます。つまり、変容があるのみで誕生と死はないのです。ヒュルスカー族のそれのような集合魂の場合にも同様のことがあてはまります。ヒュルスカー族が何人かの肉体を持つ人間として物質界に現われると同時に、ヒュルスカーの魂が形成されたのです。けれどもヒュルスカー魂が生まれたというのではなく、別の時代から作り変えられ変成させられたのです。この魂はヒュルスカーの勢力とともに成長し、ヒュルスカー族が頂点に達したときに頂点に達し、ヒュルスカー族が物質界における歴史のなかで後退し消えてゆくときには、ヒュルスカーの魂は別の種族の魂となるために新たに若返るのです。つまり、魂は変容するのです。高次の世界において魂を観察すると物質的な誕生と物質的な死は存在しません。私たちの知っている誕生と死は物質界のみに存在するのであって、高次の世界には存在しないのです。神秘学の叡智はこのことをよく心得て表現していて、その際、数に対しては非常に注意を払っています。ある特定の人間集団に属する集合魂がいつ成立して別の魂から変容して成長し、頂点に達して再び下降していき、さらにまた別の集合魂に変化してゆくのか、平均の数を決定しようとしてきました。人間の寿命を平均75歳と見積もって、この数を大陰暦年とみなして7を掛けると、四つのタイプにおける人間の集合魂の次の変化までの生命が明らかになります。ここでは7によって世代が意味されているのです。この場合、大陰暦年であることを考慮するとおよそ500年となります。従って、神秘学においてはこう言われています、ひとつの集合魂は別の集合魂に変わる、その意識を失うことなく、新たに自分自身を生み出すと。このような集合魂の自我を観察し、この自我のための外的な表現手段を物質的なものに探すとすれば、これは血液なのです。血は神秘学者にとって火の現われであり、火で燃え立たされた実質です。人間の物質体が土の現われであり、エーテル体が水の現われ、アストラル体が空気の現われであるように、まだ利己主義に縛りつけられていない自我は火の現われなのです。ですから、このことは明日またお話しますが、血は利己主義を通して死を見出したといえるのです。人間の自我は自分自身によって「自らの火の中でわが身を焼き付くし」ています。これは神秘学上の表現です。人間は利己心を克服するときにのみ、不死性に到達するのです。人間の集合自我は自らの火のなかで身を焼き付くします。500年が過ぎると、集合自我は燃え尽き、自己自身から新たな形姿を創造します。このことが神秘学では、集合自我は一般に500年生き、それから燃え尽きて自らの火から再び命を吹き込まれると叙述されます。これが「不死鳥(フェニックス)」と呼ばれているのです。フェニックスについての美しい伝説は、このように事実に即した背景を有しているのです。フェニックスは四タイプの特性をもつ集合自我なのです。それは七世代後に燃え尽き一世代を75大陰暦年と計算して復活するのです。これがフェニックス伝説の真実の背景です。こうして皆さんは、フェニックスに関するような古い伝説は極めて奥深い神秘学的事実から創られたということの新たな証明を得られたわけです。ここでが、何百年にもわたって神秘学の学院で教えられてきたこと、そして実際の、示威しに即した経験(神秘学の記号や封印はそれを表現している)が示していることを、あれこれ思弁を弄するのではなく、明示せなばなりません。このような神秘学の真理の表現のことを聞き、これを人類が記号や象徴のなかに保存しているものと比較してみると、人間の意識はいかに多くのことをそれが悟性的意識となる以前にすでに創造していたのかが繰り返し思い出されます。人間はしかし、今日我々はすでにずいぶん進歩したと信じ込むものです。けれども、人間の悟性は、過去の世の創造的意識、これはむろん秘儀参入者のみが有し、彼らはこれを伝説の中に隠したのですが、この創造的意識にはるかに遅れをとっているのです。四種の動物についての象徴は考え出されたものではありません。その出発点、起源となっているのは、思考ではなく、観ること(Schauen)なのです。私が「集合魂は物質界とアストラル界の間の境界のエーテル的なもののなかにある」と言っても、ひとつの境界線を想像しないでください。物質界から出発しますと、ここに(描かれる)物質界の七つの小区分があります。続いて、アストラル界の七つの小区分がくるのです。これらのうち下から三つまでの区分は、物質界の上から三つまでに区分と重なり合っています。つまり、物質界の上位三区分が同時にアストラル界の下位三区分でもあるというように、アストラル界は物質界にはめ込まれていると見なさなくてはなりません。これはいわば周辺地帯です。私たちの魂が死後、熱望によって地上につなぎとめられているときに、離れられないところで、カマローカと呼ばれます。このように、ここで最初の例として選び出した神秘学の記号、象徴、封印のなかに、深い神秘学的事実から得られたものを見出すことができます。従って、神秘学の学院における深い過去の叡智を誤解したり、それらが現代の知識によって何らかの方法で克服されたとみなしたりすると、まったく道を誤ることになります。神秘学の教えの叡智に記号や象徴のなかで向き合うところではいつも、それらは直接の神秘学的考察によって確認されるということが示されます。神秘学の教えが比較的遠くない時代に作用していたことの例は、名前や言葉に象徴的な意味が秘められていたということですが、これらの根底にある真の意味は高次の世界の事実なのです。文献学の意味における言語形成の起源にさかのぼるというわけではありません。これからお話することは、文献学によって確かめられることではありません。たとえ文献学的に誤りとされたとしても、言葉の象徴学はやはり正しいのです。物質界から出発してアストラル界を通り、デヴァチャン界へとさらに高く上昇していくほど、すべてが物質界の鏡像として眼前に現われてきます。この鏡像をまず読み取ることを学ばねばなりません。学徒たちにとっての数は、最も学びやすいものです。この物質界の543という数があるとします。この数はアストラル界では鏡像としてありますから、345と読みとれるわけです。同様に他のあらゆる事物や出来事も鏡像として読み取ることができます。少々極端な例を挙げますが、この物質界で鶏が卵を生み、その卵から雛がかえるようすをたどってみてください。これと同じ出来事を、雛がいてこれがしだいに小さくなり最後に卵の中に入り込むというふうに、時間も逆行するわけです。これを初めて目にする学徒にとってはどんなに当惑することかおわかりでしょう。人間から発する情熱は、タブローに描かれたように見えます。情熱は中心点から発します。この情熱の反映は、まったく動物が押し寄せてきたときのように現われます。低級な情熱はありとあらゆる野生の獣たち、ねずみやラットのようなものに見えるのです。学徒がこのことを学んでいなかったら、自らの情熱がねずみやラットとなって自分のほうへ押し寄せて来るのを見るとき、これが最初の経験であれば、容易に迫害妄想その他の病理学的な状態が現われ得るのです。ここで皆さんに高次の世界の低次の世界に対する関係についての事実としてお話してきたことを、人々は言葉遊びとしての進化論のなかに象徴的に表現しようとしてきました。人間が地球での生存に入ったとき、人間はエヴァ[Eva]を通じて霊的な状態から感覚的な状態に入り込んだのです。エヴァのなかに人々は霊的な人類が物質的になった、すなわち罪を負うこととなった状態を見ました。人類を再び霊的なものへと上昇させ、世界に死すべきものをもたらした女性とは反対のものを表現しようとすると、逆に人類に再び不死性をもたらすべきものが表現されねばなりません。つまり、名前が逆にされねばならないのです。そのため神の天使はマリアに対して、「アヴェ・マリア [Ave Maria]!」という言葉で語りかけたのです。エヴァからマリアとなる(Eva → Ave )のです。この逆転は象徴的な意味をもっています。多かれ少なかれ本末転倒の文献学がこれに対して何と言おうと問題ではありません。重要なのは、神秘学においては、象徴的なものが語の組み合わせにおいて作用を及ぼし、この言葉を発することで、人間が物質界を霊的世界はその流れにおいて逆方向であるという神秘学的事実を意識するように求められてきたのです。このことは大変深い意味をもっています。その背後に何か恣意的なものは見ないでいただきたいのです。背後に見出せる最良のものは、人間は言葉のなかに神秘学的な合法則性を認識するためにこのような実習をさせられることにより、意識的にせよ無意識的にせよ、神秘学的修行を行なっているのです。象徴学の原理は同時に修行の原理なのです。人気ブログランキングへ
2024年03月13日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
神秘学の記号と象徴そのアストラル界と霊界との関係第五講 ケルン 1907年 12月26日※人間の環境への態度。事物の背後にある魂的・霊的なものの開示としての世界。動物、植物、鉱物の魂的・霊的なもの。アストラル界にある動物の集合自我、その基本要素は叡智。人間・自我の根本要素としての愛の養成。植物界、鉱物界の苦痛と喜びの感情。秘学の修練においては単に形象を観照するだけでなく、内的に体験せねばならない。卍と五芒星の隠された意味。 今回の連続講義では、いくつかの秘学(オカルト)的記号や形象についてお話するつもりですが、その際、これらの象徴や記号の意味、意義が単に知性だけではなく、感情や心情と親密になるようにしていこうと思います。皆さん全員がご存知のように、神秘学(オカルティズム)や神智学(テオゾフィー)においては、さまざまな形象や記号が使用されています。そして、このような記号や形象を解釈するのに、しばしば多大な機知と思弁が費やされていることも周知の事実です。さて、今回の連続講義は、こうした機知や思弁の多くが不適切であり、そもそも思弁や機知というものは、秘学的記号や象徴の本当の意味に近づく力を有していないということを示してくれるでしょう。神秘学者(オカルティスト)にとって、決して単に一般的な手引き書や著作で言及されているようなものが記号や象徴であるのではなく、通常はほとんど予測しもしないようなところに、非常にしばしば秘学的記号や象徴が見いだせます。やはり、民族に根ざす神話や物語の中に深い秘密の(オカルト的)真理が隠されているのです。このような神話や伝説を解釈する際に通常犯されている過ちは、端的に言って、あまりに多大の機知、思弁が費やされていることです。あまりにも分別的、理性的に深い意味が追求され過ぎていると言っていいほどです。4回の連続講演では、このテーマを汲み尽くすことはできず、警句的に扱うことができるのみですが、それでも、ここで取り扱うことを、秘学的記号や象徴の高次の世界に対する関係、つまりアストラル界及びデヴァチャン界ないし霊的世界と呼ばれるものに対する関係について表象を形成することができるように描いてみたいと思います。ご存知のように、日常の言語においても、何か高次のものを解釈しようとするとき、非常にしばしば特定の具象的な比喩が用いられます。例えば、認識や洞察に比喩を用いようとする時、「光」とか「認識の光」という言い方をします。私たちの言語のこういう単純な表現の背後に、時折、何か途方もなく深いものが潜んでいます。このような表現を用いるひとは、しばしばその起源をまったく意識しておらず、従って例えば光という比喩がどういうふうに認識や洞察と関係づけられているのか、全然考えてもいないのがほとんどです。彼らは、今日詩人が比喩を用いるように、それを比喩とみなしてるのです。もし神秘学(オカルティスム)においてこのような比喩的な意味のことだけを考えるとするなら、まったく道を誤ることになります。物事はもっとずっとずっと意味深いのです。今日の言語において、象徴的と言われているもの、比喩的と言われているもの、あるいはアレゴリーという表現で示されているもの。これらはたいてい間違った道に導くものです。ある記号は恣意的に何かあるもののために選ばれたのだと、安易に考えられています。神秘学において、記号は決して恣意的に選ばれることはありません。神秘学(オカルティスム)において、ある記号がひとつの事柄に用いられるときは、常に深い関連がそこにあるのです。けれども、人間が神秘学の観点から見て、自らの環境に対してどのように位置づけられているかについて、少し立ち入ってみければ、神秘学の記号・形象と高次の世界とのこうした関連について真に明確にすることはできないでしょう。神秘学、あるいは今日神智学として知られている神秘学の基礎的な部分が、いつかより深い意味で、世にその使命を果たすときには。これはまだやっとはじまったばかりなのですが、いつの日にか、私たちの生活と文化のあらゆる支脈が神秘学の真理と衝動に貫かれるようになった時には、人間の感情、感覚生活全体、過尿への位置づけ全体が本質的に変化してしまっていることでしょう。今日の人間が外界に対してどのように位置しているか示そうとすれば、次のように言わなければなりません。この数世紀以来、人間はますますいっそう外界に対して非常に抽象的、合理的、唯物的な関係をつくりあげてきたと。今日野原を行く人は、春でも、夏でも、秋でも、たいてい眼前に現れるもの、感覚が受け取ることのできるもの、知性が感覚知覚から結合できるものを見ています。その人に美的な天分があれば、何か詩的な感受性があれば、彼はその知覚を感覚、感情で満たし、ある自然の出来事の場合には悲しみや苦しみを、また別の場合には高揚、喜び、楽しみを感ずるのです。けれども、今日の人間の場合、無味乾燥な感覚的知覚が詩的、芸術的な感情に転ずるときでも、それは本来、神秘学によって今や理性や知性、頭脳にではなく、魂と心に与えられねばならないものの端緒にすぎません。神智学が単に物質界、アストラル界、デヴァチャン界のあらゆる出来事の思索的な要約を与えてくれるだけでなく、私たちの魂に深く親和的になり、魂が前とは違ったふうに受け入れ、感じ、学ぼうとするようになった時、はじめて神智学は人生における重要な要因となるのです。とりわけ私たちが明確にしておかなければならないのは、神智学と神秘学を通じてすでに昨日の記念講演で強調したことが現実にますます起こってくるということです。つまり、人類は感覚に現れてくる外界において表現されているもののなかに、事物の背後に魂的、霊的なものとしてあるものが自らを開示する顔貌、身ぶり、表情を見てとるようになるのです。私たちは、地球の外部で起こっていること、つまり星々の運動の中にも、霊的、魂的なものの表現を見出すことを学んでいくでしょう。例えば、ある人の手の動きやまなざしの中に何か魂的なものが見出せるように。このようにして私たちは例えば晴れていく大気の中に、空気、水、土を真に浸透している霊的諸存在の内的な経過の外的な顕現を見ることを学んでいくのです。さて、私たちの回りに生きている魂的、霊的なものに関して理解に達したなら、周囲の自然がどのように見えるか、ここでちょっと想像してみることにしましょう。まず、理想的にこれにとりかかるなら、次のように問わなければなりません。物質界で周囲に生きている被造物の魂、つまり動物、植物、鉱物の魂はいったいどういう状態なのか、物質的に感覚に現れているものの他にこの自然の三つの領域には何があるのか、と。動物の領域を観察しますと、これは霊的、魂的に、人間とはまったく根本的に区別されます。私たちが個々の人間の皮膚を境に閉じた内部に有しているもの、こういうものは個々の動物の中にはありません。個々の動物は私たちにとってむしろ人間の各部分に比較されます。同じ形態を持つ動物はすべて、つまりすべてのライオン、すべてのトラ、すべてのカスタマス、すべてのハエ、その他動物界において同じ形姿を有するものはすべて、人間の一部分、例えば手の指に比較することができるのです。人間の十本の指を考えてみてください。十本の指の一本ずつにそれぞれひとつの自我を有した魂を与えられているとは思えないでしょう。十本の指は全部、一個の人間に属しているわけですから。人間ひとりひとりに自我・魂が与えられています。人間ひとりひとりに自我-魂が与えられているように、これを集合魂と呼ぶか群魂と呼ぶかは問題ではありません。問題なのは、物事をぼやけさせ、流動的に考えることです。このように、同じ形姿を持った動物のグループの場合、個々の人間のそれと同じ自我・魂が基礎になっていると認めなければなりません。けれども、この動物グループの魂は、人間の自我・魂が探索される場所を探しても見つかりません。人間のこの自我・魂が誕生と死の間に存る場所は、物質界です。これをもって、この自我・魂がその性質と本質により物質界のみに属するということが言われているのではありませんが、人間の自我・魂は物質界で生きています。動物の集合自我の場合はそうではないのです。同じ形姿を有する個々の動物の集合自我の場合、個々の動物がいる場所は問題になりません。ライオンがアフリカにいようとここの動物園にいようと、まったく同じなのです。個々の動物は同じ集合自我に属し、この集合自我はアストラル界にあります。ですから、同じ形姿を持つ動物のグループから自我を見出そうとすると、霊視的にアストラル界にまで赴かなくてはなりません。アストラル界では、当の動物の集合-自我はこの物質界での人間の独立した個性です。もし人間が十本の指を伸ばした時、ここに仕切り壁を立て、壁の十個の穴から十本の指を突き出すと、壁の外側にいる人には十本の指しか見えません。十本の指の自我を探そうとすれば、壁の後ろ側に行かねばなりません。このように、個々のライオンには、すべてのライオンの集合自我の一部を見なければならないと考えねばなりません。アストラル界へ行くと、すべてのライオン属の個性あるいは個体を見出すことができます。ちょうど壁の後ろ側に人間の十本の指が属する個体が見出せるように。同じ事が、同じ形姿を持つ他の動物の種類にも当てはまります。もし皆さんがアストラル界を「散歩する」なら、アストラル界にはこれらの動物の集合自我が居住しているのがおわかりになるでしょう。そこでは、この物質界でひとりひとりの人間に出会うように、この動物の集合自我と出会うのです。ただこれらの集合自我は、ちょうど十本の指を一本ずつ壁から突き出しているように、物質界へ、それぞれ分化した動物個体を差し伸ばしているのです。しかしながら、動物の集合自我の本性、内的な特性と個々の人間の特性であるものとの間には、著しい相違があります。この違いは、皆さんには非常に逆説的に思われるでしょうが、現に存在しています。つまり、ひとつの特異な事実があるのです。アストラル界での動物の集合自我の知力と叡智を、ここ物質界での人間の知力、叡智と比較してみるなら、動物の集合自我の方が、根本的に賢いということがわかります。動物の集合自我がなすべきことは、最高度の自明性をもって行われます。人間は、進化を遂げていく中でようやく、その自我を動物の集合自我がアストラル界ですでに有している叡智にまで至らせなくてはなりません。むろん、この動物の集合自我には、人間がこの物質界で地球進化全体を通して養成してきたものが欠けています。この特殊な要素は、動物の集合自我にはまったく見出せないものです。これは、愛という要素、愛であるもののすべて--血縁関係にある人間の血族的な愛という最も単純な形から、普遍的な人類愛の最高の理想の愛まで--です。この要素は、他ならぬ地球進化の内にある人類によって養成されてきたものです。感情、感覚、意志衝動は、動物の集合魂も有しています。愛を発展させること。これがまさしくこの地球上での人間の使命なのです。これが動物には欠けています。動物の集合自我の基本要素は叡智であり、人間自我の基本要素は愛なのです。私たちを取り巻いている自然そのものの内部で、この動物の集合自我の顕現をどのように感じとるべきか深く知ろうとするなら、ここで私たちを取り巻いているものすべてが、霊的な秘密と霊的な諸存在の顕現なのだとうことを思い起こさなければなりません。霊視的能力を備えていない人は、もちろんあのアストラル界での「散歩」をすることはできません。アストラル界では、この地球上で物質的な人間個々の自我に出会うように、そこに住んでいる動物の集合自我と出会います。けれども、霊視をしない人でも、この集合自我がなしている行為、作用をこの物質界で知覚することができるのです。毎年、秋が近づくと、鳥たちが北東から南西の暖かい地方へ向かって飛翔し、夏が近づくと再びまったく決まった進路を通って帰ってくるのが認められます。各々の鳥の属に対してその進路のひとつひとつを高度と方角に従って比較してみると、これらすべての中に、叡智が、深い叡智が存在することをひとは予感し始めます。この全体を導いているのは誰なのでしょう?それを導いているのは動物の集合自我です。さまざまな動物の属がこの地球上で成し遂げていることはすべて、動物の集合自我の行為であり、作用なのです。動物の集合自我のこれらの行為を追求すると、本質的に、これらの動物の集合自我は地球の周囲に広がっていて、地球の周囲で力となって展開しているということがわかります。地球は、多種多様な力、さまざまにうねり、直線や曲線、蛇行線をなして地球を取り巻いている力に囲まれているのです。これらの力をここではその作用、その顕現の中にのみ見ることができます。人間がこれらの顕現を実感すると、霊視による場合に、動物の集合自我のところへ彼を導いていくものが何なのか予感することができます。このように、動物界で起こっている叡智に満ちた事に踏みいっていくすべてを学ぶことができます。動物の属や種がおこなっていることは、動物の集合自我の行為のいくばくかを垣間みせてくれるのです。植物界では事情は異なっています。植物界でも神秘学の観察者に対して一連の自我が現れてきますが、この植物界に現れる自我は動物界のそれよりもずっと少数なのです。その数は限られているのです。植物のグループ全体がやはりひとつの共通の自我に属していて、それを探すとするなら、それらはもっと高次の世界に在ります。動物の集合自我がアストラル界にあって、この地球を取り巻いて流れるアストラル的なものの中で生きているのに対し、植物の集合自我はデヴァチャン界下部、私たち神智学に親しい者たちがデヴァチャン界のルーパ部分と呼びならわしている所に見出せます。そこでそれらは完結した個性として生きています。ちょうどこの物質界での人間のように、そこでは植物の集合-自我が逍遥しているのです。物質体というものをそもそも有していない他の存在たちと共に植物の集合自我は低位デヴァチャン界に住んでいます。どのようにしてこの植物の集合自我を知覚するすべが得られるのでしょうか。知覚それ自体はつまるところ霊視能力の発達と結びついています。この発達は低い段階から次第の高次のものへと進んでいきます。そもそもこれらの能力を得るために最初に発達させねばならないのは、物事に対する感情と感受性です。実際の、真に霊視的な能力は常にまず第一に感情と感受性の養成に基づいています。ただし、浅薄な利己的な感情ではなく、深く敬虔な感情です。これはまったく違うものです。皆さんが植物を観照する時、何よりもとりわけ植物がその根を地中に発達させ、茎を上方へ伸ばし、葉を上へ向けて広げ、それが次第に萼葉、花冠へと形を変え、その内部で実を結ぶという経過に注意を向けるに違いありません。人間と次のような比較はできないということが重要です。つまり、人間の頭部、頭を植物の花冠と、人間の足を植物の根と比較してはならないということです。この比較はまったく間違っているのです。神秘学の学院では、常に以下のように指示され、語られてきました。お前たちは植物と人間を比較しなければならない。けれども、人間の頭を植物の根になぞらえるような仕方で比較しなければならない、と。植物が根を地球の中心に向けているように、人間は頭を宇宙の方へ向けています。そして、植物がその花と結実器官を控えめに太陽に向けているように、人間はその生殖器官を恥じらいつつ、植物が根を向けている方向、つまり下部へと向けているのです。従って、神秘学では、「人間は逆立ちした植物である」と言われます。植物は、逆立ちした人間のように見えます。動物は両者の中間にいます。通常植物と呼ばれているものの中には、単に植物の物質体とエーテル体があるのみです。けれども、植物もアストラル体と自我を有しています。それでは植物のアストラル体はどこにあるのでしょう。私たちはその場所を問うことができます。というのも、植物の集合自我は低位デヴァチャン界にあると言うのは、単にものごとの一般的な定義に過ぎないからです。植物のアストラル体と自我がどこにあるのかをまったく精確に示すことができます。植物のアストラル体、しかもこの地球上にあるすべての植物のアストラル体は、地球のアストラル体と同じものなのです。従って、植物は地球のアストラル体の中に浸されているのです。その場所によると、植物の自我は地球の中心にあります。私たちは、神秘学的な観点から、地球をひとつの大いなる有機体として、アストラル体を有する生きた存在としてとらえることができます。そして、この地球上にある個々の植物はその一部です。植物は個々に独立したものとしては物質体とエーテル体のみを養成しました。個々の植物、つまりユリやチューリップ、その他の一本一本は意識を有しません。地球が植物の意識、アストラル体、自我を担っているのです。けれども、そこには植物の自我だけが存在するわけではありません。まだその他に別の霊的存在がいるのです。けれども、その存在たちみんなに場所があるのかという問いを発してはなりません。それらは混じり合い、そこで非常に仲良く暮らしていくことができるのです。このように個々の植物を観察すると、それらに物質体としての特性は認められるかもしれませんが、個々の存在としての意識が植物にあるとはいえないのです。けれども、植物は意識を持っています。その意識は地球の意識と結びついていて、地球の意識の一部なのです。私たち人間が喜びと悲しみを張りめぐらし、これを互いに浸透させあう意識をもっているように、植物の個々のアストラル体が地球のアストラル体に浸透し、植物の自我は地球の中心点を貫いているのです。生きている植物は、動物の有機体組織の中で牛乳が占めているのと同じ位置を、この地球の有機体組織の中で占めています。植物が地球から芽吹き、緑に萌え、花咲く時も、牝牛が乳を与える時も、同じ種類のアストラル的な力が基礎になっているのです。皆さんが植物の花を摘み取っても、それは地球にとって何ら不快な感情ではありません。地球はアストラル体を有し、そのアストラル体で感じとります。植物を摘み取ると、植物は子牛が乳を吸う時に牝牛が感じるのと同じ感じを持ちます。つまり、一種の快さを感ずるのです。地面から生えているものを引き離しても、地球、個々の植物ではなくそれらは快さを感じます。それに対し、植物の根を引き抜くと、それは地球にとってちょうど動物の肉をもぎとるのと同じようなもので、地球は一種の痛みを感じるのです。単に集合自我についての抽象的な概念の中でではなく、空虚な抽象概念を感情と感受性へと変化させるように、この中に沈潜すると、私たちは自然の出来事とともに生きることを学びます。私たちの自然観察は生き生きとした感受なのです。秋に野を行き、鎌で穀物を収穫している人を見る時、私たちは鎌が茎を通り、茎を切り取るのにぴったり合わせて、畑の上に何か霊的な風のように快い感情が吹き渡っていくという予感を得ます。霊視者が地球のアストラル体の裡に見るものは、ここで描写されたことの霊的な根本原因なのです。このことを見抜いている人にとって、穀物の収穫はどうでもよい出来事なでではありません。ちょうど人間の場合、何かある体験の際に、まったく決まった種類のアストラル的形成物が立ちのぼってくるのが感じられ、見えるのと同じように、秋には畑の上を地球の快い感情のこのようなアストラル的表現がかすめていくのが見られるのです。鍬が地面に畝を立て、植物の根に手を加える時には、事情は異なってきます。鍬での畝起こしは地球に苦痛を与えます。この時、苦痛の感情が立ちのぼってくるのが見えるのです。ここで言われたことに対しては、容易に反論できるでしょう。つまり、状況によっては、牧場へ行って役に立たないということからあらゆる花々を摘み取ってしまうよりは、植物を根ごと地面から引き抜き、移植する方が良いではないかと。このような非難は、道徳的な観点から考察すれば的を得たものであるかもしれませんが、ここではまったく異なった解釈が提示されているのです。たしかに、状況によっては、白髪になり始めた人にとって、これを美的な理由から正しいと見なすなら、最初の白髪を抜く方が良いと言えるかもしれません。それでもやはり引き抜くのはその人にとって痛いことなのです。花を摘むことは地球にとって心地よく、植物を根から掘り起こすと地球にとって苦痛であると言う時、これらはまったく別の観点なのです。[*欠落]生はそもそも苦痛を通して世に現れます。生まれてくる子供は、出産する母親に苦痛を起こさせます。これは環境の中で単に認識するのみならず、自然の中に感情移入するすべをいかに学ばねばならないかということのひとつの例です。鉱物界にもこのことはあてはまります。鉱物も自我を有しています。ただ、この鉱物の自我はさらに高次の所にあります。つまり、神智学文献が、アルーパ・デヴァチャンと呼びならわしている、デヴァチャン界の高位の部分にあるのです。この鉱物の集合自我は、物質界における人間の自我、低位デヴァチャン界における植物の集合自我、アストラル界における動物の集合自我と同様、それ自体部分として完結した存在です。物質界においては、単に鉱物の物質体のみが存在しますが、鉱物にはアストラル体もエーテル体もあるのです。霊視者は生きた連関を視ています。採石場に行って、鉱夫たちが石を切り出しているのを見ると、霊視者たちにはちょうど生体の肉に食い込む時のような感じがそこに生じているのがわかるのです。そして、鉱夫たちがそこで働いている間中、アストラル的な流れが岩石界を貫いています。アストラル体として鉱物が有しているものは、デヴァチャン界の低位部分に見出され、鉱物の自我はデヴァチャン界の高位部分に見出されます。岩石の自我は苦痛と喜びを感じます。岩石をたたき落とすと、鉱物の集合自我は喜び、満足を感じます。これは最初逆説的に聞こえますが、実際そうなのです。単に類推で考える人は、岩石を打ち砕くと、ちょうど生き物を傷つける時のように、岩石にとっては痛いことだろうと思うかもしれません。けれども、岩石を砕けば砕くほど、鉱物の自我は満足を覚えるのです。さて、「それではいったい鉱物の自我はいつ苦痛を感ずるのか」と問うことができます。鉱物の自我にとっての苦痛を皆さんは次のような例で知覚することができます。食塩を溶かしたコップ一杯の水を想定してください。コップの中の水を冷やしていって塩が固い結晶となって分離されてくると、鉱物的な実質が再び固体化してきます。この個体の分離において苦痛が生じるのです。同様に、砕いた岩石を全部合わせてまた一個の岩石に戻すとしたら、やはり苦痛が生じます。鉱物の集合自我においては、鉱物が溶解する時はいつも喜びの感覚が生じ、固体化する時には苦痛の感覚が生じます。温めた水に塩を溶かすと満足感が生まれ、水を冷却して塩の結晶を析出させると、痛みの感覚が生まれるのです。このことを、より大きな宇宙的な関連の中で表象してみるなら、私たちの地球の形成、鉱物の形成がどのようにこのような過程と関連しているかわかるでしょう。この地球の形成をずっと以前までたどっていくと、この地球の温度はますます上がり熱が高まっていきます。そしてレムリア時代において、岩石のひとつひとつが溶解している状態、現在は完全に固く結晶化してしまった鉱物が、ちょうど今日溶鉱炉の中で鉄が液体化されて流れ出しているように流れ出している状態に行き着きます。鉱物はみなこのような過程、つまり水を冷却するとコップの中に溶けていた塩が沈殿するということのなかにその小規模な形を見ることのできる過程を経てきたのです。このように、地球上ではすべてが固体化し、集結してきたのです。このような固体化は、液体状の地球の中への集結による固い結晶が次第に沈殿してくという形で進行しました。このような固体化によってのみ、地球は今日の肉体を持つ人類の住みかとなり得たのです。この固体化はむろんある特定の時期に頂点に達したというようにとらえることができます。今日、ある意味でこの頂点の時期は過ぎています。今日すでに部分的には多かれ少なかれ溶解過程が記されなければならないのです。地球がその目的に達した時には、そして人間がもはや地球から何も引き出すことができないほどに浄化され霊化された時には、地球自体もまた霊化されていることでしょう。その時には地球の鉱物的な含有物はすべて精妙にエーテル的になり、地球は物質化する前にもそうであったアストラル的状態に移行することができるのです。物理的な溶解過程はそれに到るための過渡的状態なのです。この地球が、私たちが今日の進化段階で順次進化していくための固い舞台基盤となるべく準備していた時期を考察してみると、私たちはそこに絶え間ない地球の受難の過程を記さなければなりません。固体化を進めることで、地球は苦しみ、「苦痛に呻吟する」のです。私たちの生存は、地球の苦痛を通して獲得されたのです。いわゆるアトランティス時代の初期まで、この苦痛が増していくのが認められます。人間が次第に自分で自らの浄化を行うようになった時から、地球も再び苦痛と受難から解放されるのです。この過程は、まだそれほど進んでいません。私たちの足下にある固い地盤の大部分は、今日なお苦しんでいます。霊視をそこへ向けてみるなら、私たちにとって固体は地球存在の呻吟であることがわかります。このような事実を神秘学的な由来から探求し、偉大な宗教的文献の中にそれらを再び見出す人には、こうした文献が霊的世界のいかなる深みから書き上げられたかが開示されます。その時、これらの宗教的古文献を尊重する感情がなおいっそう高まってきます。経験を通じて、私たちは外的世界の事実に目を向けつつ、いかなる真実の基盤がパウロの言葉、つまり「すべての自然は苦痛に呻吟する養子を得ることを待ち焦がれつつ」の根拠になっているか、経験的に認識することができるのです。このパウロの言葉をちょっと翻訳してみると、「地球生成のすべては、後に地球の存在たちにとって『養子を得る』つまり霊化が成し遂げられるための、苦痛のもとでの生成、苦痛のもとでの固体への凝集である」ということです。真に秘密の修練と呼ばれるものにおいては、それらを見たとき、私たちの裡に感情を呼び起こすような、周囲の世界のイメージからとりかからなかればなりません。まず始めに修練をやり遂げようとする弟子に、外部の自然で起こっていることを単に外的な出来事として観るのみならず、内的な体験として魂全体をもって、いかにこの地球の生成、固体化が苦痛を引き起こしているかを感じとることができるような表象、概念を伝えられます。この苦痛の心象は、実際の霊的な事実を提示しているのです。真の神秘学においては、像は何らあれこれ考えてつくり出されたものではなく、実際の霊的事実から読み取られたものなのです。いかなる哲学も、思弁も、最高度の明敏さも、このような像の謎を解くことはできません。高次の世界の事実を認識することによってのみ、理解に導かれるのです。神秘学においては、あらゆる像は霊的事実を表しているのです。今日は、皆さんが基礎的な神智学において理念、概念、表象として修得しておられるものが、いかにして次第に体験へと導かれるかを暗示するだけにとどめておきたいと思います。何しろ神秘学におけるいかなる図像も体験からのみ取ってこられたのですから。例えば、有名な卍の図形を例にとってみますと、さまざまな文献に、この図形に関する極めて機知に富む解釈を見出すことができます。これはもともとはどのようにして神秘学に取り入れられたのでしょうか。この図形は、私たちがアストラル的な感覚器官と呼んでいるものの模像に他なりません。ある種の処置、修練によって、人間はアストラル的な感覚器官を養成することができます。この二本の線(図示)は、本来、霊視者の霊眼に、炎の車輪か花のように見えたアストラル体の中での動きなのです。これらは蓮華とも呼ばれます。この車輪ないし蓮華、それらのうち例えば、両眼のあたりには二弁のもの、喉頭のあたりには十六弁のものが位置しますが、アストラル界に発光現象として生じてくるこのようなアストラル的感覚器官を表す記号、図形が卍なのです。あるいはまた別の記号、いわゆる五芒星(ペンタグラム)を考えてみましょう。思索しても哲学しても、五芒星の本来の意味を見出すことはできません。五芒星はひとつの現実なのです。これは、人間のエーテル体の中に見出せる流れ、力の流れの作用を描き出している図像なのです。人間の場合、ある種の力の流れが左足から頭部の一定の一まで上昇し、そこから右足へ、次いで左手へ、そこから身体を通り、心臓を通って右手へ、そして右手から再び左足に戻ります。その結果、人間の中に、頭、腕、両手、両脚、両足を通る五芒星を描きこむことができるのです。これを単なる幾何学的な図形としてのみではなく、力の作用として表象せねばなりません。人間のエーテル体の中に、皆さんは五芒星を有しています。力の作用は、正確にこれらの五芒星の線をたどっています。各線はさまざまにねじ曲がることもありますが、常に五芒星の形を保って、人体に書き込まれています。五芒星はひとつのエーテル的な現実です。象徴ではなく、事実なのです。このように、神秘学においては、どの象徴も霊的世界の事実の像です。こうした事実が根ざしている世界を示唆することができてはじめて、その意味が認識されます。従って、最高度の明敏さといえども、神秘学の記号の解釈に至ることはできないのです。唯一[霊的世界の]体験から、神秘学の記号と象徴の意味を見出すことができ、この意味を認識することで、人間は「何かを始める」ことができるのです。ですから人間が、まず霊視的な能力によって見出されたことを伝達され、語られて、それから獲得することは、決して不必要なことではありません。そして、探求された事実から、再び人間はこれらの事実自体の原因へと回帰させられるのです。記号や象徴と同様、古い伝説や神話においても事情は同じです。伝説や神話は民衆文学からつくり出されたものだとするのは、学識上の机上の空論です。民族は創作しません。すべての伝説や神話は、人間がまだある程度霊視能力を有していた時代の遺物なのです。ヨーロッパの伝説や神話において語られていることは、人間が以前に見た事実を保存しています。これらの伝説、メルヒェン、神話の中にあるすべては、本来霊視的に見られたもので、本来の霊視的経験を見たとおりに語っているのです。神話とはそもそも霊視的経験が見たとおりに語られたものなのです。今日でもなお、神話において語られている出来事全体をアストラル界で追求することができます。ヴォータンあるいはオーディンによる行為は、実際に起きた事なのです。神秘学的な記号、象徴、封印の背後に、真実を探すことができるのです。しかも、思弁によってこれらの記号の解釈を企てることが少なければ少ないほど良いのです。このように、この連続講演では、神秘学の事実感覚へと入っていこうと思います。記号は考え出された作り事などではなく、霊的世界における実際の出来事の模像ないし複製です。そして、神話において出会うすべての物語は、まだ人間の大部分が霊視力を有していた頃に見たことの再現なのです。参照画:霊視力人気ブログランキングへ
2024年03月12日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
神秘学の記号と象徴そのアストラル界と霊界との関係第四講 シュトゥットガルト 1907年 9月16日※黙示録の封印。(1907年3月の)ミュンヘン会議の祝賀ホールにおける封印の説明。人類進化の像としての黙示録の七つの封印。薔薇十字のシンボル。封印が人間に及ぼすことのできる生気を与え啓発する影響について。さらに、霊的なものが世俗化されるときの破壊的な作用について。 象徴や形象のうち、そもそも私たちが所有していて古今の神秘学者たちからも認められている最も意味深長なものは、人間自体です。人間は、今も昔も、常にミクロコスモス、小宇宙と呼ばれてきました。これは、まったく正当な言い方です。というのも、人間を詳細に綿密に知るようになる人には、ますます人間のうちに人間の外部の自然の中に広がっているあらゆるものが含まれていることが明らかになってくるからです。このことを理解するのは、はじめは困難かもしれません。けれども、これについて思索を深めれば、人間のうちには全自然からとった一種のエキス、精髄、あらゆる実質と力が見いだせるということの意味を理解できるでしょう。皆さんが何らかの植物をその本質という点に関して研究し、充分深く探求することさえできれば、人間の有機体組織の中に、より食傷された形ではあっても、同じ本質が含まれていることがおわかりになることと思います。さらに、外にいる動物を考えてみてください。皆さんは常に、人間の有機体組織の中に、その本質に従って、あるやり方でその組織中に取り込まれているいるように見える何かを指摘することができるでしょう。このことを正しく理解するためには、もちろん宇宙の進化を神秘学(オカルト)的観点から考察することが必要です。それで、たとえば神秘学者(オカルティスト)は、もし外部の自然の中にライオンが存在しないなら、人間は決して今日のような性質の心臓を持つことはないということを知っています。まだライオンというものが存在しなかった時代へと遡ってみましょう。人間は最も古い存在ですので、その当時にも人間はいました。けれども、その時の人間はまったく別様に形成された心臓を持っていたのです。自然の中には、至る所に、もちろん必ずいつも明白ではないにしても関連があります。かつて人間がはるか太古の時代に自らの心臓を今日の形態へと発達させた時、その時にライオンが生じました。両者は同じ力を形成したのです。それは、あたかも皆さんがライオンの本質を抽出し、神の如き巧みな技により、それから人間の心臓を形成したかのようです。皆さんは人間の心臓には何らライオンのようなものはないとお考えになるかもしれませんが、神秘学者(オカルティスト)にとってはこれは本当なのです。あるものがひとつの関連、ひとつの有機体組織の中に置かれる時、それが独立状態にある時とはまったく別の作用をすることを忘れてはいけません。逆のこういうふうに言うこともできます。皆さんが心臓のエッセンスを取り出すことができたとして、この心臓に相応した存在を作り出そうとするなら、そしてその存在が有機体組織の諸力に規定されないなら、それはライオンになるのです。勇敢さ、大胆さといった特性、あるいは神秘学者(オカルティスト)が言うような人間の「王者らしい」特性のすべてはライオンとの関係に由来します。そして、秘儀参入者であったプラトンは、王者のような魂を心臓の中に置いたのです。(注/プラトン「国家」では勇気(thymos)はホメロスに従って心臓に置かれる)人間と自然のこのような関係に対して、パラケルススはたいへん見事な比喩を用いました。彼は、「それはあたかも自然の中でひとつひとつの存在が文字であるかのようだ。けれども人間はこれらの文字から組み立てられた言葉なのだ。」と言います。外には大いなる宇宙マクロコスモス、私たちのうちには小なる宇宙ミクロコスモス。外ではいかなるものもそれ自体として存在し、人間にあっては他の器官も共に織り込まれているハーモニーによってすべてが規定されているのです。そして、だからこそ私たちは人間の中に全宇宙の進化、私たちの一部をなす全宇宙の進化を観照することができるのです。皆さんは、私たちの一部をなしているこの宇宙との関連における人間進化の像(すがた)を、ミュンヘンでの会議期間中、祝賀ホールに掲げられていた封印の中に見ることができます。何が示されているか見てみましょう。最初のものは、白い衣をまとった人物を示しています。その両足は金属、青銅のようです。口からは炎の剣が突き出しています。彼の右側は諸惑星。土星、太陽、月、火星、水星、木星、金星の記号で取り巻かれています。ヨハネ黙示録をご存知の方は、黙示録の中に、この像とかなり一致する記述が見られることを思い出すことでしょう。ヨハネは秘儀参入者であったからです。この封印は、つまり、言うならば、人類全体の理念を提示しているのです。ここにおられる古参の方々にはすでにおなじみの表象をいくらか思い出していただくと、このことを理解できると思います。人間の進化をさかのぼっていくと、人間がまだ不完全な段階にある時代に到達します。例えば、人間は、皆さんが今日両肩の上にのせているもの、つまり頭部をまだもっていませんでした。当時の人間を描写すると本当にグロテスクに聞こえるでしょう。つまり、頭部はだんだんと発達してきたのであり、さらにこれからも進化していきます。人間においては今日、いわば終結に達した器官があります。自らを作り変えていく別の器官もあります。そう、喉頭は力強い未来を有しているのです。むろん、心臓とも関連しています。今日、人間の喉頭はようやくその進化の始まりにあって、将来、霊的なものに作り変えられた生殖器官となっていくのです。今日の人間が喉頭を使って行っていることを明らかにすれば、この神秘についての表象を得ることができるでしょう。ここで私が話しますと、皆さんに私の言葉が聞こえます。このホールが空気に満たされていて、この空気中に一種の振動が引き起こされることにより、私の言葉が皆さんの耳に伝達されるのです。私がひとつの単語、例えば「宇宙(ヴェルト)」という語を発音すると、空気の波が振動します。これは私の言葉の受肉(物質化)です。今日、人間がこのように作り出すものは、鉱物界における創造と呼ばれています。空気の運動は、鉱物的な運動です。喉頭を通じて、人間は環境に鉱物的に働きかけているのです。けれども、人間は、自らを高め、いつか植物的にも働きかけるようになるでしょう。単に鉱物的な振動だけではなく、植物的な振動をも引き起こすようになるでしょう。人間は、植物を出現させるでしょう。その次の段階は、感受する存在を肩って出現させるでしょう。そして、進化の最高の段階では、人間は自らの喉頭によって自分に似たものを生み出すでしょう。今日、人間は魂の内容のみを言葉によって語ることができますが、その時には自分自身をそのまま言い表すようになるのです。そして、人間が未来において存在を方って出現させるように、人類の先駆者である神々は、今日存在するすべてのものを語って作り出した器官を備えていたのです。神々はすべての人間、すべての動物、そしてその他すべてを語って生み出しました。これらはすべて字義どおりの意味において発せられた神々の言葉なのです。「初めに言葉があった。言葉は神のもとにあった。言葉は神であった。」これは、思弁的な意味での哲学的な言葉ではありません。まったく字義通りにおこなわれた太古の事実をヨハネは提示したのです。そして、終わりにも言葉が言葉があるでしょう。言葉の具現が創造であり、人間が未来に置いて生み出すものは、現在言葉であるものが具現化したものなのです。けれども、その時には、もはや人間は今日のような物質的形態はとらないでしょう。人間は土星上でとっていたような形態、火の実質にまで進歩しているでしょう。このように宇宙進化の始まりにおける創造的な力は宇宙進化の終わりにおける私たち自身の創造する力と結びついているのです。今日あるすべてのものを宇宙の中に言葉で出現させた存在は、人間の偉大な模範です。この存在は、宇宙に土星、太陽、月と地球ただし地球は半分ずつで、火星、水星、木星、金星を出現させました。この七つの星が暗示しているのは、これらは人間がどの程度まで進化できるかを表す記号であるということです。火の実質の中に、この惑星は最後に再び現れ、人間はこの火の実質の中で創造的に語ることができるでしょう。これが口から突き出ている火の剣なのです。すべては火のようになります。従って、両足も溶けた青銅なのです。見事に印象深く、進化の意味がこの記号(しるし)に表されています。今日の人間を動物と比較してみますと、その違いは「人間は個々人として、個々の動物が自らのうちに有してないものを、自らのうちに有している」と言わなければならないということに表されています。人間は個人の魂を持ち、動物は集合魂を持つのです。人間のひとりひとりがひとつの動物の属全体にあたります。例えば、すべてのライオンは共通でひとつの集合魂を持つのみです。この集合・自我は、人間・自我とまったく同じですが、ただ集合・自我は物質界にまでは下降しません。アストラル界でのみ見いだされるのです。この地上では、各々が自我を担っている物質的人間が見いだされます。アストラル界では、皆さんはアストラル実質の中で、皆さん自身と同じような存在と出会います。ただ、物質ではなくアストラル的な覆いの中で出会うのです。皆さんは、皆さんのような人と話すように、彼らと話すことができます。これが動物の集合魂です。人間も以前の時代には集合魂を持っていたのですが、次第次第に今日の独立した存在へと進化してきたのです。これらの集合魂はもともとアストラル界にあり、それから肉の中に宿るために下降してきました。今、アストラル界の中に人間の原初の集合魂を探してみますと、人間の由来である四つの種類が見いだせます。この四種を、今日の動物の属をなしている集合魂と比較しようとすると、次のように言わねばならないでしょう。四種類のうちのひとつはライオン(獅子)と比較される。もうひとつは鷲と比較される。三つめは牛と。四つめはその自我が下降してくる前の太古の人間と比較できると。けれども、さらに人間のより高次の顕現のための集合魂、つまり子羊、救い主の徴(しるし)である神秘の子羊により示される集合魂も存在しますし、地球が存在する限り、これからも存在するでしょう。これら五つの集合魂の分類、すべての人間に共通する偉大な集合魂を取り巻く人間の四つの集合魂、これを第二の図像は描き出しています。私たちが人間の進化をはるか彼方までさかのぼっていくと、何百万年もの助けを求めなければなりませんが、また別のものが現れてきます。現在、人間は物質的に地球上にいます。しかしながら、この地球上を動き回っていたものが、まだ人間の魂を受け取ることができなかった時代もあったのです。その時、この魂はアストラル界にありました。そして、さらにさかのぼると、この魂が霊界、すなわちデヴァチャンにあった時代に至ります。魂は、地球上で自らを浄化したあかつきには、未来において再び、この高次の段階に上昇するでしょう。霊からアストラル的なものを経て物質的なものへ、そして再び霊へ。れが人間の長い進化の道のりなのです。けれども、これを人間が土星及び他の惑星状態で経てきた進化の時間と比べると、短期間のように思われます。人間は単に物質的な変化のみではなく、霊的、アストラル的、物質的変化を遂げてきたのです。こうした変化を追求していくと、霊的世界にまで上昇しなくてはなりません。そこでは、天球の音楽、この霊的世界で空間にみなぎりあふれている音が知覚されます。そして、再び人間がこの霊的世界に慣れていくと、この天球のハーモニーが彼に向かって響きわたるでしょう。これがオカルトでは天使のラッパの響きと呼ばれるのです。従って、第三の図像はラッパです。霊的世界から啓示がやってきますが、それは人間がなおいっそう進歩を遂げたときはじめて、姿を現すのです。それから、人間に七つの封印を施された書物が開示されるでしょう。この封印はまさに私たちがここで考察しているものです。これらの謎が解かれるでしょう。ですから、中央には書物、下部には人類が置かれます。というのも四頭の馬は、時代を経てきた人類進化の諸段階に他ならないからです。けれども、もっと高次の進化があります。人間は、もっと高次の世界に起源を持ち、そして再びこの高次の世界に上昇していくでしょう。その時、人間が今日とっているような形態は世界の中へ消えていくでしょう。今日、外の世界にあるもの、人間を構成している個々の文字を人間はその時、再びすべて受け取っているでしょう。人間の形態は世界の形態と一致していることでしょう。神智学のある種の通俗的な記述において、自分自身の内に神を探し求めると教えたり語ったりされています。けれども、神を見出そうとする者は、万有のうちに広がっている神の作品のうちに神を探し求めねばなりません。宇宙の中の何ものも単なる物質、それは単に見かけ上そうであるにすぎませんではありません。実際はすべて物質は霊的なものの現れ、神の活動の知らせなのです。そして、人間は来るべき時代の経過において、自分の本性をいわば拡大していくでしょう。ますますいっそう人間は世界と一体化し、人間の形態の代わりに宇宙(コスモス)の形態を置くことで、自らを提示することができるのです。このことは、岩、海、円柱を備えた第四の封印に見いだせます。今日、雲として世界を通り過ぎてゆくものが、人間の肉体を形づくるための素材を提供するでしょう。今日、太陽の霊のもとにある諸力が、さらに限りなく高められたやり方で、霊的な諸力を作り出すことになるものを、未来において人間にもたらすでしょう。この太陽の力こそ、人間が手に入れようと求めるものなのです。自分の頭部、つまり根を地球の中心に向けて沈めている植物とは反対に、人間は頭を太陽に向けています。そして、人間は頭を太陽と合体させ、より高次の力を受け入れるでしょう。このことは、岩と円柱の上の雲の体にある太陽の顔の中に見てとれるでしょう。その時、人間は自らを創造するものとなっているでしょう。そして、完全な創造の象徴として、多彩な虹が人間を取り巻いています。ヨハネ黙示録の中にも、皆さんはよく似た封印を見いだせるでしょう。雲の中に書物があります。黙示録では、秘儀参入者がこの書物を飲み下さねばならないと語られています。これによって、人間が単に外的に叡智を受けることができるだけでなく、今日食物で自らを満たすように、叡智で自らを満たし、自身が叡智を体現するようになる時が告げられているのです。それから、宇宙における大いなる変化が目のあたりに怒る時に近づきます。人間が太陽の力を引き寄せてしまうと、太陽が再び地球と一体化するというあの進化段階がはじまります。人間は、太陽の力により太陽を生み出すでしょう。ですから第五の封印では太陽を生む女なのです。その時、人類は非常に道徳的、倫理的になっているので、低次の人間本性の中にある有害な力はすべて克服されているでしょう。これは、七つの頭と十本の角を持つ動物によって描かれています。太陽の女の足下に、地球が用いることができず押し出していなかったあらゆる有害な実質を含む月があります。今日、月が魔術的な力で地球上でなしてることはすべて、その時に克服されるでしょう。人間が太陽と一体になるとき、人間は月を克服したのです。続いて第六の封印で、このように高次の霊化にのぼりつめた人間がいかにミカエルの形姿に似ているかが表されています。ミカエルは、この世の悪いものを龍の象徴(シンボル)の中につなぎとめているのです。私たちはあるやり方で人類進化の初めと終わりが同じ変化の状態であることを見てきました。この同じ状態が、流動する火の足を持ち口から剣を突き出した男の中に描かれていることがわかりました。意味深い象徴学においては、私たちに宇宙の全存在が聖杯の象徴において明かされます。皆さんにこの第七の封印について二、三概略的にお話しておきたいと思います。神秘学者(オカルティスト)としてこの世界を知ることを学ぶ者は、空間というものが物質的世界にとって、単なる空虚なものとはまったく別の何かであるということを知っています。空間は、すべての存在をいわば物質的に結晶化させて出現させてきた源泉なのです。水で満たされた完全に透明なガラス製の立方体の器を考えてください。さて、それからある冷却する流れがこの水を貫いて導かれ、さまざまなやり方で氷が形成されるのを思い浮かべてください。こういうふうにして、世界創造のひとつの表象、つまり空間を得ることができます。この空間の内部へと神的な創造の言葉が発せられ、ありとあらゆる事物が結晶化し生み出されたのです。神的な創造の言葉が内部に発せられたこの空間を、神秘学者(オカルティスト)は水のように透明な立方体によって表します。この空間の内部でさまざまな存在が発達していきます。私たちの最も近くにある存在を、立方体は三つの垂直方向、つまり三本の軸、長さ、高さ、幅を持ち。これが立方体の三つの次元を示しているということで、最もよく特徴づけることができます。さて、これらの、外の自然界にある三つの次元に反対の次元を加えると考えてみてください。皆さんはおよそ次のように想像することができます。ひとりの人物がある方向に進み、もうひとりが彼に向かってやってきて両者がぶつかる、というふうに。同様に、各空間次元にも、それぞれ反-次元が存在するのです。従って、私たちは全部で六本の線を持つことになります。これらの反対線は同時に人間存在の最高の構成要素の原初的萌芽を表しています。空間から結晶化された物質体は、最も低次のものです。霊的なもの、最高のものはその反対物で、反-次元によって示されます。ここで、進化において、まず最初に、激情、欲望、本能の世界に合流させることで、最もよく描かれ得る存在、こういう存在の反-次元が形成されるのです。最初、これはそういう存在です。それから、のちに何か別のものになります。ますますいっそう、この存在は自らを浄化していきます。どれほど浄化されるか、私たちは見てきましたがが、もとは蛇によって象徴される低次の衝動から出発してきたのです。この経過が互いに向き合った二匹の蛇の中での反次元の融合によって象徴されているのです。人類は自らを浄化することで「宇宙の螺旋」と呼ばれるものへと上昇します。浄化された蛇の体、この宇宙の螺旋は、深い意味をもっています。皆さんは、これについて次のような例でひとつの概念を得ることができます。現代の天文学はコペルニクスの二つの法則に基づいていて、第三の法則は顧みられず放置されています、第三法則は、太陽もまた動いているというものでした。太陽は、前方へねじれながら進んでいて、その結果、地球は太陽とともに複雑なカーヴを描いて運動しているのです。同じ事が、地球の回りを運動している月にもあてはまります。これらの運動は、初歩の天文学で受け入れられているよりもはるかに複雑なのです。螺旋が天体のなかでどのような意味をもっているのか、ここでおわかりでしょう。この天体は、将来、人間と一致するような形態を表しているのです。その時には、人間の生み出す力は浄化され、純化されているでしょう。人間が浄化された蛇の体として進化させていったものは、その時、もはや下から上へではなく、上から下へと作用することでしょう。私たちの中で変化した喉頭は、聖杯(グラール)と呼ばれる杯になるのです。そして、この生み出す器官と結びついているもうひとつの器官も同様に浄化されているでしょう。この器官は、宇宙の力の精髄(エキス)、大いなる宇宙の精髄となるでしょう。精髄の中のこの宇宙霊は、聖杯にむきあう鳩の図像で描かれています。ここで、鳩は、人間がいつか宇宙(コスモス)と一体化する時に、宇宙から働きかける霊化された授精作用の象徴なのです。この出来事の想像力全体が、虹によって示されています。これはすべてを包括する聖杯の封印なのです。これ全体が、宇宙と人間の関係についての意味を、驚くべきやり方で他の封印の意味もまとめるようにして伝えてくれます。従ってここにも封印の周囲の縁に書かれた文字として、宇宙の秘密が現れています。この宇宙の秘密は、人間が原初に根源の力から生まれてきたことを示しています。どんな人間も、振り返ってみれば、意識の力から新しく生まれたなら、今日霊的に成し遂げている過程を、原初の時代に経てきたのです。薔薇十字会ではこのことを(頭文字で)E.D.N=[ex deo nascimur](神から生まれた)と表します。開示の内部では、第二のものが加わることを見てきました。すなわち、生のための死です。人間は、この死の中で再び死を見出すために生きとし生けるものすべての源泉の中で、この感覚の死を克服せなばなりません。この源泉は、すべての宇宙進化の中心点なのです。というのも、私たちは、意識を獲得するためには死を見出さねばならないからです。しかし、私たちはこの死の意味を救い主の秘密の中に見出すとき、死を克服するでしょう。神から生まれたのと同様、私たちは秘教的な叡智の意味で、キリストにおいて死ぬのです。I.C.M[im Christo morimur](キリストにおいて死ぬ)そして、何かが開示される所ではどこでも、第三のものに統一されるべき二元性が示されるので、人間は死を克服したとき、自らが、宇宙を貫く霊(鳩)と一体化することでしょう。人間は復活し、再び霊のうちに生きるのです。P.S.S.R=[per spiritum sanctum reviviscimus](聖霊により復活する)これが、神智学的薔薇十字です。これは、宗教と科学が宥和する時代を照らすのです。さて、以上のとおり、このような封印には、宇宙全体が描かれており、しかも宇宙は魔術師や秘儀参入者によって、この中にくみ入れられたため、封印には強い力が内在しています。皆さんは、いつも新たにこれらの封印にもどってくることができます。封印は、瞑想を通して無限の叡智を開くことができるということを、皆さんは改めて見出すことでしょう。封印は、宇宙の秘密から創られていますので、人間の魂に強力な影響を及ぼします。今日ここでお話しているような、宇宙の聖なる神秘へと高めてくれるような、そうした事柄が語られている部屋に、こうした封印を掲げるなら、それらは、人にそれと気づかれなくても、最高度に生き生きと啓発する作用を及ぼします。けれども、同時に、こういう意味をもっているからこそ、世俗化されることを嫌います。奇妙に聞こえるかもしれませんが、霊的なことは何ら語られず、俗っぽい言葉が語られている部屋にこういう封印がぐるりと掛けてあると、やはり作用は及ぼすものの、この場合、肉体組織を病気にするような作用をするのです。通俗的な言い方かもしれませんが、封印は消化を損なうのです。霊的なものから生まれたものは、霊的なものにふさわしく、世俗化されてはなりません。このことをそれ自身がその作用によって示しているのです。霊的な事柄の記号は、霊的な事柄が起こり、作用を得る所にふさわしいのです。記:以下は「ヨハネの黙示録」における七つの封印の概要です。第一の封印: 小羊(イエス)が封印の一つを解くと、白い馬が現れ、勝利を求めて出発します。第二の封印: 小羊が第二の封印を解くと、赤い馬が現れ、人々が互いに殺し合うことを許されます。第三の封印: 黒い馬が出現し、はかりを手に持つ者が現れます。第四の封印: 青白い馬が現れ、死と黄泉が従います。第五の封印: 小羊が第五の封印を解くと、殺された人々の霊魂が叫びます。第六の封印: 大地震が起り、太陽と月が異常な状態になります。第七の封印: 七つのラッパが引き起こす天変地異が始まり、最後の審判が開始されます。参照画:七つの封印人気ブログランキングへ
2024年03月11日
コメント(0)
-
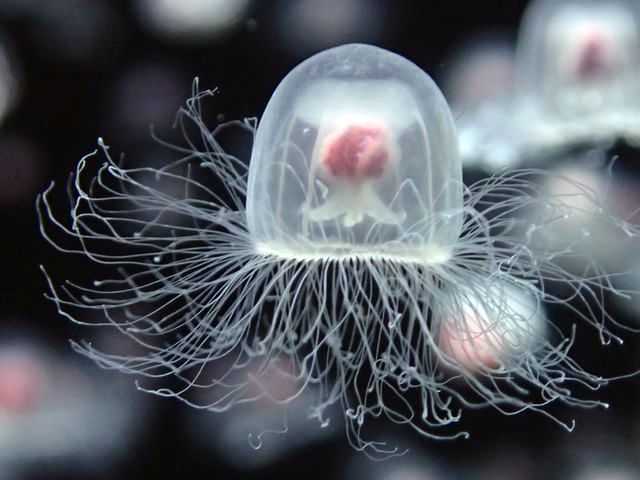
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
第三講 シュトゥットガルト 1907年 9月15日※数の象徴論。分割不可能な神性の像としての1。開示の数としての2、3。自然と歴史の例のなかに見られる退化と進化。無からの創造。神的なものと開示的なものを結びつけるものとしての三性。宇宙あるいは創造の記号としての4。悪の数としての5。人間の本性の第五の構成要素の進化とともに、人間は独立と自由を得る。しかし、同時に悪をなす可能性も得る。人間の病気と生涯に関連する5の数の意味。完全数としての7。ピュタゴラスの意味における一性の分割不可能性。 今日取り上げてみようと思いますのは、数の象徴学と呼ばれているものについての考察です。神秘学の記号や象徴について語る時、数の中に表されている形象について、簡単ではあっても言及しておかなくてはなりません。一昨日お話ししたことを思い出してください。宇宙における数の関係、各惑星が運行する速度についてお話しました。数と数の関係は宇宙空間を貫いて波打つ天球の調和(ハーモニー)の中に表現されていること、それらは宇宙全体と宇宙の考察にとってある特定の意味を持っていることを見てきました。さて今日は、もっと内密な数の象徴学を取り上げてみましょう。もっとも、真にこの象徴学に沈潜するには、もっと細心に取り扱うべきことがまだ他にたくさん必要となりますので、ここではその意味を軽くなぞることができるだけですが。ともかく、例えば古代のピュタゴラスの秘教学院で宇宙への洞察力を得るためには、数と数の性質に沈潜せねばならないと言われた時、少なくともこれが意味することについて見当はつくだろうと思います。数について熟考すべきだというと、味もそっけもないように思われる方もおられるかもしれません。とりわけ、現代の唯物主義的教養に毒された人々にとって、数の考察によって事物の本質に関する何かを探求できるなどということは児戯にも等しいと思われています。然し乍ら、偉大なピュタゴラスが、数の性質について知ることは事物の奥深い本質へと導くと弟子たちに語ったことには、深い根拠があるのです。ただ、1ないし3ないし7といった数について熟考すれば十分であると考えてはなりません。真の秘学の教えは、魔法やおまじないなどではなく、何らかの数の意味についての迷信でもありません。その知恵はもっとずっと深い事柄に基づいているのですから。今日皆さんに受け取っていただきたい簡単な概略からおわかりになるとおもいますが、正しく数に沈潜する手がかりを持つなら、数は瞑想とも呼ばれる沈潜のためのひとつの拠り所を与えてくれるものなのです。 まず1という数、合一の数から始めなければなりません。この1という数が私が申し上げますことをどれほど真に形象化しているかは、後ほど他の代数を考察する際にもっと明らかになるでしょう。あらゆる神秘学(オカルティズム)において、常に1という数により宇宙における神の分離できない元素が表されました。1で神が表されるのです。けれども、単に数としての1に沈潜すれば世界認識のために何らかのものを獲得できると考えてはなりません。どのようにしてこのような沈潜が起こるべきかおわかりになると思います。でも、まずはその他の数に移った方がずっと実り多い考察になるでしょう。神秘学では2は開示の数と呼ばれます。2という数でいわば私たちは両足の下に何か基盤を得るのですが、一方、1という数の場合、まだ基盤のないまま手探りで探し回っている状態です。私たちが2は開示の数であると言う時、これは、私たちが世界で出会うもの、ある意味で隠されたものではなく世界へ現れ出たもの、これらすべては何らかの形で二元性の状態であるということに他なりません。皆さんは自然の中のいたるところに、2という数が広がっているのを見いだされることでしょう。いかなるものも2という数に触れることなしには自らを開示するということはできません。光も決してそれ自身だけで一元的に自らを開示することはできません。光が開示される時、影あるいは闇もそのそばになければなりません。つまり、二元性が存在せねばならないのです。開示された光に満ちた世界というものは、もしそれに相応する影がないとしたら、決して存在することはできないでしょう。これはすべてのものごとにあてはまります。善は、その影としての悪を持たないなら決して自らを開示することはできないでしょう。善と悪の二元性は開示された世界の中では必然的なものです。このような二元性は無限に存在します。二元性は世界全体を満たしています。ただ、私たちはそれを正しい場所に探さなくてはなりません。人間が生きていく中でたびたび考慮することのできる重要な二元性は次のようなものです。昨日私たちは人間が今日の地球の住人となる前に経てきたさまざまな状態を考察いたしました。人間は土星と太陽ではある種の不死性を保っていて、自らの肉体を外から管理し、肉体の一部がくずれ落ちると新たな部分が再び付与されたため、人間は死や消滅については何も感ずることがなかったわけです。人間の意識は当時、今日の意識とは違って、おぼろげな夢うつつの意識でした。この地球になってはじめて、人間は自己意識と結びついた意識を獲得したのです。ここではじめて人間は自己自身について何かを知り、対象から自分を区別できる存在となったのです。そのためには、単に外から肉体を管理するだけでなく、この肉体の中に交互に入り込んで、自らの内で「自我」が語りかけるのを感じとらねばなりませんでした。人間はその肉体に完全に入り込むことによってのみ、完全な意識を獲得できたのです。そして、今や人間はこの肉体と運命を共有します。以前、まだ上方にいた時、人間はこういうことはしませんでした。人間がこの程度の意識を獲得したことによってはじめて、彼は死と関係を結ぶようになったのです。肉体が崩壊する瞬間、人間は自分の自我が停止するように感じます。自我と肉体を同一視してきたからです。少しずつ霊的な進化を経てようやく、人間は再び太古の不死性を取り戻します。肉体は意識して不死性を獲得するための修行場として存在するのです。人間が死によって不死性をあがなわないなら、生と死の二元性を認識しないなら、決して高次の段階で不死性を獲得することはできないでしょう。人間が死を知らなかった間、まだ世界は人間に開示されませんでした。生と死の二元性は開示された世界に属することだからです。このように至る所に生における二元性を指摘することができるでしょう。物理学におけるプラスとマイナスの電流、磁気における引力と反発力など、すべては二元性の中に現れています。2は現象の数、開示の数なのです。記:ベニクラゲ(紅海月、紅水母)は、花クラゲ目ベニクラゲモドキ科ベニクラゲ属のクラゲで、世界中の海に生息しています。直径は僅か5mmほどの小さなクラゲで、半透明の身体に赤い消化器が透けて見えます.ベニクラゲは、特異的な生活環を持っており、雌雄が性的に成熟した(有性生殖が可能な)個体がポリプ期へ退行できることで知られています。この特徴から、「不老不死のクラゲ」とも呼ばれています。成熟した個体は触手の収縮や外傘の反転、サイズの縮小などを経て再び基物に付着し、ポリプとなります。この生活環を逆回転させる能力は動物界では非常に稀であり、ベニクラゲは個体としての寿命による死を免れているのです.ただし、ベニクラゲが食物連鎖において常に捕食される可能性があるため、全ての個体が永遠に生き続けるわけではありません。この特異な再生能力は、科学的な興味を引き、多くの研究が行われています.ベニクラゲの不老不死の特性は、日本神話における月の神「ツクヨミ」や文学作品でも取り上げられており、その神秘的な存在は人々の興味を引いています.参照画:不死のベニクラゲ (Turritopsis spp.) けれども背後で神的なものが働くことなしには、いかなる開示も存在しません。従って、どんな二元性の背後にも一元性が隠されているのです。3という数は、それゆえ2と1、つまり開示とその背後に存る神性に他なりません。1は神の一元性の数、3は自らを開示する神性の数です。神秘学(オカルティズム)には次のような原則があります。2は決して神性を表す数ではあり得ない、というものです。1は神的なものを表す数、そして3は神的なものを表す数です。というのも、神的なものが自らを開示するとき、それは2において顕現し、その背後に1があるからです。世界を二元性において見る人は、世界を顕現において見ているのです。ですから、外的な諸現象においては二元性が存在すると言う人は正しいのです。しかしながら、この二元性がすべてであると言う人は、常に正しくありません。このことを少し例を挙げて明らかにしてみましょう。神智学の話題となっているところでさえ、「2という数は単に顕現の数であって、充溢の完全性の数ではない」という、この真の神秘学(オカルティズム)の原則はしばしば守られてはおりません。この原則を本当には知らない人々による通俗的オカルティズムにおいて、しばしば皆さんは、進化発展はすべて退化と進化の中で起こると言われているのを耳にされると思います。これは本当はどいうことなのかおわかりになるでしょう。けれども、まずは進化と退化とはどういう意味なのかを少し調べておきたいと思います。ひとつ植物を観察してみましょう。根、葉、茎、花、実、要するに植物が持つことのできる部分をすべて備えた完全に成長した植物です。これがひとつです。今度は小さな種子、植物が再び生えてくる種子を観察してください。種を見つめる人は小さな粒を見ているだけですが、この小さな粒の中にはすでに植物全体が含まれています。いわば粒の中に閉じこめられているのです。なぜその中に入っているのでしょうか。種子は植物から取られたから、植物はその力のすべてを種子の中に注ぎ込んだからです。ですから神秘学(オカルティズム)においては、この二つの過程、つまり、ひとつは、種子がほどけていって植物全体へと展開する-「進化」と、もうひとつは、植物が収縮しその形態がいわば種子の中にもぐりこむ-「退化」とが区別されるのです。従って、たくさんの器官を持つ存在が、これらの器官のどれももはや見えなくなり小さな部分に萎縮してしまうように自らを形成するなら、これは退化と呼ばれ、分岐すること、自己展開することは進化と呼ばれるのです。生命においては、至る所にこの二元性が交替しています。けれども、常に顕現においてのみそうなのです。単に植物の場合のみ、このことを追求できるのではなく、生のより高次の領域においても事情は変わりません。 例えばアウグスティヌスから中世を経てカルヴァンに至るヨーロッパの精神生活の発展を思い浮かべて追求してみてください。この時代の精神生活に視線を漂わせてみるなら、アウグスティヌスの場合ですらある種の神秘的な親密さを見いだせるでしょう。この人物の感情生活がいかに深く親密であったか感じとることなしに、誰も彼の著作、とりわけ「告白」を読むことはないでしょう。さらに時代を辿っていきますと、スコトゥス・エウリゲナのような驚くべき現象を見いだします。彼はスコットランド出身の修道士で、そのためスコットランドのヨハネスと呼ばれ、カール禿頭王の宮殿で生活していました。彼は不幸なことに教会で切りつけられました。伝説の語るところによれば、修道士仲間たちが彼を留め針で死に至るまで拷問したということです。これはむろん言葉通りには受け取れませんが、彼が拷問により殺されたことは事実です。すばらしい書物が彼によって著されました。「デ・デヴィジオーネ・ナトゥラエ」、すなわち「自然の区分について」で、これは途方もない深みを示している書物です。さらに私たちは、いわゆるドイツの坊さん横町、ここではこの親密な感情が民衆全体をとらえたのですが、この坊さん横町の神秘家たちを見いだします。彼らは、単に精神性の頂点にある人々であったばかりではなく、民衆でもありました。畑や鍛治場で働いていた人々、彼らは皆、このように時代の傾向として生きていたあの親密な感情にとらえられていたのです。さらに私たちは1400年から1464年に生きたニコラウス・クザーヌスを見いだします。このように私たちは中世の末期まで時代をたどることができますが、至る処にその環境全体に広がっているあの深い感情、あの親密さが見いだされるのです。この時代を、後のこれに替わる時代、つまり16世紀に始まり現代にまで入り込んでいる時代とを比較してみるなら、決定的な相違に気づきます。出発点に、包括的な思考により精神生活の革新を引き起こしたコペルニクスが立っています。彼はこの思考が人類と一体化するほど注ぎ込んだので、今日、別のことを信じている人は馬鹿者とみなされるのです。それからガリレオ、彼はピサで教会のランプの揺れから振り子の法則を発見します。このように一歩一歩時代の経過をたどっていきますと、至る処に中世との厳しい対立が見いだせるでしょう。感情はどんどん衰えていき、親密さが消えていきます。知性、理知がしだいに現れ出てきて、人間はますます利口に、分別的になっていきます。このように、まったく正反対の性格を持つ二つの時代が前後して続くのです。精神科学は私たちにこの二つの時代の説明を与えてくれます。これは、そのようにならなければならないという神秘学(オカルト)の法則があるのです。アウグスティヌスからカルヴァンまでの時代においては、神秘主義の進化と理知の退化という時期であり、その後私たちは理知の進化と神秘主義の退化の時代に生きているのです。これはどういうことなのでしょう。アウグスティヌスから16世紀までは神秘的生の外的な展開の時代であり、それは外に現れていました。けれどもその当時、別のものも萌芽として存在していたのです。つまり、理知的生の萌芽があったのです。これは、いわば種子のように霊的な地中に隠されていて16世紀以降少しずつ展開していくのです。このように理知的生は、当時ちょうど植物が種子の中にあるように退化(内展)の状態だったのです。宇宙においては、このような退化(内展)の状態が前もって存在しなければ何も生じてくることはできません。16世紀以来、理知が進化(外展)の状態となり、神秘的生は退いて退化(内展)の状態となります。そして今や、この神秘的生が再び現れて来なければならない時代が到来しました。神智学運動によってそれは再び展開と進化へと導かれねばなりません。このように、生の至る所で進化と退化が顕現して交替しています。けれどもそこにとどまる人は、ただ外面だけを見ているのです。全体を見ようとするなら、この両者の背後にある第三のものをさらにつけ加えねばなりません。この第三のものとは何でしょうか?今あなた方が外界の現象に向かって立ち、それについて思索すると考えてみてください。あなた方が存在します。外界が存在します。そしてあなた方の中に思考が生じます。この思考は以前には存在していませんでした。たとえばあなた方が薔薇について思考を形成する時、この思考はあなた方が薔薇と関係を結ぶ瞬間に初めて生じるのです。あなた方が存在し薔薇が存在していました。そして今、あなた方の中に薔薇についての思考、薔薇の像が現れでてくる時、何かまったく新しいもの、まだ存在していなかったものが生じるのです。これは生の他の領域でも同様です。創造しているミケランジェロのことを思い浮かべてみてください。ミケランジェロは、実際ほとんどモデルを使って製作したことはありませんでした。けれどもちょっと彼が一群のモデルを集めたと想像してみてください。ミケランジェロが存在し、モデルたちが存在していました。けれどもミケランジェロがこのモデルの一群から魂の中に得た像、この像は新しいものなのです。これは完全に新たな創造なのです。これは進化及び退化とは何の関係もありません。これは受け入れることのできる存在と与えることのできる存在との交流から生まれた完全に新しいものなのです。このような新たな創造は、常に存在と存在との交通を通して生まれます。昨日、ここで考察したことを思い出してください。思考がいかに創造的で魂を気高くすることができ、後には肉体の形成にも働きかけるのだということを。ある存在が一度考えたこと、思考創造、表象創造は働き続け、作用を及ぼし続けるのです。それは新たな創造であると同時に始まりであり、しかも結果を導きます。今日皆さんがよい考えを持つなら、この考えは遠い将来実りを結びます。皆さんの魂は霊的世界で独自の道を歩むからです。皆さんの肉体は再び元素に帰り崩壊します。けれども、思考を生み出したすべてのものが崩壊しても、思考の作用は残り、思考は働き続けるのです。もう一度ミケランジェロの例を取り上げましょう。彼の卓越した絵画は何百人もの人々を高揚させてきました。しかし、これらの絵画もいつかは塵となって崩れ、もはや彼の創作物をまったく見ることができない世代も出てくることでしょう。ミケランジェロの絵画が外的な形態を取る前に、彼の魂のうちに生きていたもの、まず最初に新たな創造物として彼の魂のうちにあったもの、これは生き続け、存続します。そして、未来の進化段階に出現し、形を得るでしょう。どうして今日、雲や星が私たちに現れてくるのかおわかりでしょうか。なぜなら、太古の昔に雲や星を思考していた存在がいたからです。すべては思考・創造活動から生まれ、思考は新たな創造なのです。思考からすべてが生まれ、宇宙の偉大なものは神性の思考から出現したのです。ここで私たちは第三のものを得るのです。顕現性においては事物は進化と退化の間を交替しています。けれども、その背後に第三のもの、初めて充溢を与えるもの、無から生じた完全に新たな創造たる創造が深く秘されているのです。このように三つが互いに関係しています。無からの創造があり、それからこれが顕現して、時の中で経過していくとき、顕現における形、つまり進化と退化という形をとるのです。ある宗教的な体系が、宇宙は無から創造されたということについて語る時、それは以上のような意味なのです。今日、それが嘲笑されるなら、それは人々がこれらの古文献にあることを理解してないからです。顕現においては、もう一度まとめてみますと、すべては進化と退化の間を交替しています。その根底には、無からの創造が秘されていて、この二元性と一致して三元性となるのです。三元性は、神的なものと顕現との結びつきです。さて、このように、3という数についてどのように考えられるかおわかりになったと思います。ただ、ペダンティックに理屈をこね回してはいけません。至る所で出会う二元性の背後に、三元性を探さなくてはなりません。2の背後に3を求める時、ピュタゴラス的な意味における正しい仕方で、数の象徴が考察されるのです。すべての二元性のために、隠された第三のものが見いだされ得るのです。今度は4という数です。4は宇宙(コスモス)ないし創造の記号です。すでに以前お話したことですが、私たちの地球は--追求しうる限りで--第四の受肉状態であるということを思い出していただければ、なぜ4が創造の数と呼ばれるのか、ご理解いただけると思います。この地球上で私たちが出会うすべてのもの、人間における第四の原理も、この創造がその惑星進化の第四の状態にあるということを前提にしています。これは出現しつつある創造のひとつの特別な例にすぎません。いかなる創造も四元性のの記号の下にあります。神秘学(オカルティズム)において、「人間は今日鉱物界にある」と言われています。これはどういう意味なのでしょう?今日人間は鉱物界だけを理解していて、鉱物界だけしか支配できないのです。人間は、鉱物的なものを組み合わせて家を建てたり時計を作り上げたりできますが、それはこれらのものが鉱物的世界の法則に従っているからです。例えば、人間は自らの思索から植物を形成することはできません。それができるためには、彼自身が植物界にいなければならないのです。いつか後になってそうなるでしょうけれども、今日、人間は鉱物界における創造者なのです。この鉱物界には、三つの元素界と呼ばれる三つの領域が先行しています。鉱物界は第四の領域なのです。全体としては、このような七つの自然領域があります。人間は今日その第四の領域にいて、そこで外へ向かう自分の意識を獲得したのです。月では、人間はまだ第三の元素界、太陽では第二の、土星では第一の元素界で活動していました。木星上で人間は植物界で活動でいるようになり、今日時計を作るのと同じように植物を創造することができるようになるでしょう。創造において可視的に現れでたものはすべて4という記号(しるし)のものとにあります。皆さんが肉眼では見ることのできない惑星も数多くあります。これらの第一、第二、第三の元素界にある惑星は物質的な眼では見えないのです。惑星が第四の領域、つまり鉱物界に入った時はじめて、皆さんはそれを見ることができるのです。それゆえ4は宇宙(コスモス)ないし創造の数なのです。第四の状態に入ることではじめて存在は目に見えるようになり、外的なものを見ることができるようになります。5は悪の数です。再び人間を考察すると、このことを一番はっきりさせることができます。人間は四元性へと、創造性の存在へと進化してきましたが、地球上で彼に第五の要素、霊我が現れます。人間が単に4にとどまっていたとしたら、彼はいつも上から、神々によって善へと統制されていたことでしょう。すなわち、決して独立した存在へと進化することはなかったでしょう。人間は地球上で第五の要素、霊我への萌芽を手に入れたことにより自由になったのです。これによって人間は悪をなす可能性を得ましたが、しかしこれによって独立性も手に入れたのです。5において現れない存在は、いかなるものも悪をなすことはできません。そして、私たちが悪と出会う所ではいたるところで、そして実際それはそれ自身から有害な作用を及ぼすのですが、五元性が関わり合っています。これは至る所、外の世界でもそうなのです。人間はただそれを見ないだけなのです。しかも、今日の唯物主義的世界観は、世界をこのように見ることができるということについて、まったく理解できません。ひとつの例で、5と出会うところではどこでも、何らかの意味で阿育について語る正当性が出てくるということがわかります。医師がちょっとこのことを採用して、病気の経過をこれに従って研究してみれば、たいへん実り多い結果が得られるでしょう。つまり、病気がその発病から第五日までどのように進展するか、一日の中であれば真夜中から五時間めに、さらには第五週めにどうであるか調べるのです。というのも医師が最も効果的に介入できる時は、いつも5という数字が支配しているからです。それ以前は自然の経過にまかせる以外はあまり多くのことはできません。しかし、5という数の法則に気づくなら、助ける処置ができるのです。5という数の原理は事実の世界に流入しているからです。この原理が害を与える、悪の原理と呼ばれるのももっともなことです。このように多くの領域で5という数が外的な出来事にとって大きな意味を持つことを示すことができます。人間の生には七つの時期があります。第一の時期は生まれる前の時期、第二の時期は歯の生え替わる頃まで、第三は性的成熟まで、第四はおよそその7~8年後まで、第五はおよそ30歳頃と続いていきます。人々が、これらの時期に何が問題となるの、ちょうど第五の時期に人間に何を近づけ、何を遠ざけるのか、知るようになれば、いかによい年齢を準備することができるようになるかについても、いろいろとわかってくるでしょう。その時、残りの人生全体に対して善いことあるいは悪いことの作用が及ぶでしょう。初めのいくらかの時期の場合、これらの法則に従って、教育を通して多くのことを行うことができます。けれどもそれから、人生の第五期に、後の人生全体にとって決定的な転換点がやってきます。この人生の第五の転換点は、少なくとも人間がいわば完全に確信をもって人生へと送り出される前に超えられねばなりません。今日主流をなしている、人間をあまりに早く人生に送り出してしまう原則は、たいへん害のあるものです。このような古い神秘学的原則に注意を向けることには、大きな意味があります。ですから、以前は、そのことについて知っていた人々の命により、人は親方と認められる前に、いわゆる修業時代と遍歴時代を卒業しなければならなかったのです。七は完全性の数です。このことをまた人間自身を手がかりに明らかにすることができるでしょう。人間は被造物として四の数の中にいます。そして、善か悪の存在でありうるという限りで、五の数の中にいるのです。人間が萌芽として自らのうちに有しているものをすべて造り上げてしまったら、色の世界、虹においても、音の世界、音階においても、七という数が支配しています。生のあらゆる領域のいたるところで皆さんは七という数を一種の完全性の数として示すことができます。七の背後には迷信もおまじないもありません。さて、もう一度一元性に注目したいと思います。他の数も考察したことにより、一元性について語るべきことが正しい光の中に現れるでしょう。一元性の本質的なものは、不可分性です。実際のところ、むろん、一であることをさらに、例えば1/3や1/2分というふうに、分けることはできません。けれども、皆さんが思考の中で承認することのできる非常に意味深い重要なものがあります。つまり、霊的世界においては、2/3を除くと、1/3はあくまで一に属するものとしてあり続けるということです。何かが神から開示として分割されても、残り全体はやはり神に属するものとしてあり続けるのです。ピュタゴラス的な意味で「一を分割せよ。ただし、ひとえにおまえの思いの底で、残りのものが一のためにあるように一を分割せよ」。本来、一を分割するとはどういうことなのでしょうか。例えば、金の小板を考えてください。皆さんがこれを通して見ると、世界は緑色に見えます。つまり、金は、その上に白い光が当たると黄色い光線を反射するという特性をもっているのです。それではまだ白の中に含まれていた他の色はどこに行くのでしょう。それは、対象の中に入り込み、それを通過します。赤い対象は、赤い光を反射し、他のものを自らのうちに取り入れるから赤いのです。他のものを残しておくことなしに赤をしろから取り出すことはできません。こうして、私たちは大いなる世界の秘密の緑に触れるのです。皆さんはこのことをある特定のやり方で観ずることができます。例えば、光がテーブルにかけられたテーブルクロスに当たると、私たちは赤い色を感受します。太陽光線に含まれている他の色は「吸い込まれ」ます。例えば、緑色はテーブルクロスに吸収され反射されません。私たちが赤い色と緑色を同時に私たちの意識の中に受け入れようと努めるならば、私たちは再び一を回復したわけです。私たちはピュタゴラス的な意味で一を分割したのです。そうすると、残りのものは、そのまま維持されます。分けられたものを常に再び一と結びつけるということを瞑想的に成就すると、それは、人を高みへと進化させうる意味深い営みとなります。数学においてもこれを表す式があります。秘密(オカルト)の学院ではどこでも通用するものです。1=(2+x)-(1+x)これは、1をどのように分割するか、分けられた部分が再び1となるようにどのように提示するかを表しているとされる秘密の公式なのです。神秘学者(オカルティスト)は、一の分割を、部分が常に再び一へと連結されるように考えねばなりません。以上のように、今日は、数の象徴学と呼ばれるものを考察に委ね、世界を瞑想的に数の観点の下に動かすと世界の秘密の内奥に迫ることができるということを見てきました。補足としてもう一度述べておきたいことは、第五週め、五日め、あるいは五時間目においては、何かをしくじったり良くしたりできるということに気づくことが大切であるということです。七週め、七日め、あるいは七時間めには--あるいは相応する特定の数の関係、たとえばその中に7もあるので、31/2においては--常に何かが、そのこと自体を通じて起こります。たとえば、熱はその病気の七日目に一定の性格を示すでしょう。あるいは14日めにも、世界の構造を示す数の関係が常に根底にあるのです。ピュタゴラス的な意味で、「数を探求せよ」と言われることに、正しい仕方で沈潜する人は、この数の象徴学から生と世界を理解することを学びます。このことについて、今日はみなさんに概略的にご理解いただけるようお話した次第です。参照画:ピュタゴラス(Pythagoras)人気ブログランキングへ
2024年03月10日
コメント(0)
-

ルドルフ・シュタイナー
神秘学の記号と象徴そのアストラル界と霊界との関係yucca訳(1994年)■第二講 シュトゥットガルト 1907年 9月14日-1・2※建築物と形式(フォルム)の人間に及ぼす作用。秘儀参入者の創造としてのゴシック建築。それは現代の人間の周囲の形式世界とは逆。アトランティスから後アトランティスへと移る人間の形態の改造とノアの箱舟の寸法比。地・存在としての蛇、水・存在としての魚、空気・存在としての蝶、熱・存在としての蜂の象徴。 昨日はノアの箱舟に言及したところで止まりましたが、この箱舟の高さ、幅、長さの比率の中に、人体の寸法の比が表現されているということがわかりました。聖書という宗教的古文献のこの箱舟がどういう意味を持つかを洞察するためには、このとおりに考察せねばなりません。私たちは単に人間を救出しようという乗り物が人体の寸法を思い起こさせる一定の寸法を取るということがどういう意味なのかを明らかにするのみでなく、あの人類進化の時代、ノアの物語に暗示されている実際の出来事が起こった時代へと沈潜することが必要でしょう。神秘学(オカルティズム)についていくばくか理解した人々が、外界に何か対象物を見いだした時、それはいつも人間の魂にとってまったく特定の目的、まったく特定の意味がありました。ゴシックの教会と大聖堂を、中世初期に成立し西部から中央ヨーロッパに向けて広がったまったく独自のこの建築物を思い出してみてください。ゴシック教会は確固たる建築様式を持ちます。二つの、上に向かって先の尖った部分からなる独自のアーチが、全体に上方を切望する気分としてあふれていること、支柱が一定の形態をとっていることなどの点で表される様式です。このようなゴシック大聖堂が、単なる外的な必要性から、例えばあれやこれやのことを表現したり意味したりすべき神の家をつくろうというある種の憧れから出てきたものだ主張しようとする人はまったく誤っています。まったく違うのです。ゴシック様式の基礎になっているのは、もっとずっと深い何かなのです。ゴシック建築物のために世界に最初の理念を提示したのは、神秘学に精通した人々でした。彼らはある程度の秘儀参入者だったのです。人類のこの偉大な指導者たちは、このような建築物、建築様式を生じさせることに、まったく特定の意図を結びつけていました。ゴシック様式、ゴシック式大聖堂と教会に足を踏み入れる人には、まったく特定の魂の印象が呼び起こされます。そびえ立つ支柱群を備えに高く湾曲したドームの中では、まるで一種の苑(もり)に踏み込んだような印象です。そこにとどまることは、魂に対して、例えばあなた方が普通の家屋やルネサンス式丸屋根やロマネスク様式の丸屋根を備えた建築物の中に入っていく時とは、まったく違った作用を及ぼします。形式からまったく特定の作用が生じてくるのです。通常の人間にはこのことは意識されず、これらすべては無意識のうちに彼の意識下に生きます。このような形式に囲まれている時、自分の魂に起こっていることを人間はあまり理解してはおりません。その時起こることは、その周囲の状況に応じて非常に異なります。人々の多くは、現代の唯物主義はこんなにも多くの唯物主義的著作が読まれていることに由来するのだと信じています。しかし神秘学者はその影響はそれほどではないということを知っています。目で見ているものの方がはるかに重要なのです。目で見ることの影響は、多かれ少なかれ無意識裡に進行する魂の経過に及ぶからです。これには、きわめて実際的な意味があります。いつか精神科学が真に魂を把握するとき、この実際的な作用が公共の生活においても目につくようになってくるでしょう。既にしばしば指摘してきたことですが、中世において通りを歩くとき、今日とはまったく違ったものがありました。左右のどの正面(ファサード)にも、その家を作り上げた人の銘が刻まれていました。どの対象物も、人々の周囲にあるものは皆、どの戸錠も、鍵も、その製作者の魂が自らの感情を体現させた何かから作り上げられていました。ひとりひとりの細工者がいかにどの部分に対しても喜びを感じていたか、いかにその中に自分の魂を注いでいたかをはっきり感じとってください。どんな物の中にも、作者の魂の一部が存ったのです。従って、外的な形式の中に魂が存る所では、それを見、観察する人にも、魂の力がみなぎりました。今日の都市と比べてみてください。今日、事物のうちにまだ魂は存るのでしょうか。靴の店、刃物の店、肉屋の店、それにビアホール等があります。あのポスター芸術のみをとっても、これらはどんな成果を生むでしょうか。ぞっとするようなポスター芸術。老いも若きも、このようなおぞましい制作物、意識下の最悪の力を呼び起こす制作物の海の中をさまよっているのです。神秘学的教育術は、目で見るものが人間の奥深く影響を及ぼすということに注意を喚起するでしょう。それに、現代の風刺雑誌をご覧下さい。いったい何が掲載されていることか。何ら批判たろうとはせず、単に事実のほのめかしにすぎません。というのも、これらはすべて、人間をある一定の方向に導く力、時代を見定める力の流れを人間の魂の中に注ぎ込んでいるのです。精神科学者は、それは人間がどういう形式の世界に生きているかによるということを知っています。中世の半ば頃、ライン河沿いにドイツ神秘主義と呼ばれる注目すべき宗教的運動が発生しました。法外な深まりと内面化が、キリスト教神秘主義の指導的精神たち、マイスター・エックハルト、タウラー、ズーゾー、ロイスブルーク他、「坊さん方(プファッフェン)」と呼ばれた人物たちから発しました。13世紀、14世紀においては、「坊さん(プファッフェ)」という呼称は、今日とは異なり、まだいくらか尊敬の意味合いを持っていました。当時ラインは、「ヨーロッパの偉大なる坊さん横町」と呼ばれていました。それでは、この人間心情の偉大な深まりと内面化、神的な本質的諸力との親密な一体化を求めるこの敬虔な感情はどこで生み出されたのでしょうか。それは尖塔迫持(せりもち)、支柱と円柱群を備えたゴシック大聖堂の中で引き出されてきたものなのです。この聖堂がこれらの魂を引き出したのです。見られたものはそれほど強力に作用するのです。人間が見るもの、人間の周囲からその魂に注ぎ込まれたもの、これが人間のうちでひとつの力になります。この力に従って、人間は次の受肉に至るまで自分自身を形づくるのです。ここでちょっと人間の進化からこのことを図式的に魂の前に引き出してみましょう。建築様式というのものは考え出されたものではなく、ある時代に秘儀参入者たちの偉大な思考から生み出されます。彼らは建築様式を世界へ流入させるわけです。建築物が建てられ、それが人間に作用します。人間の魂はこの形式の中に生きている霊的な力を幾分か自らの内に受け入れます。建築の形式、たとえばゴシック式を見ることによって魂が受け入れたものは、魂の気分の中に現れてきます。高みを見上げる情熱的な魂として、数世紀前に人々はゴシック式の中に生きていたものを自らの内に受け入れました。そして今度は、これらの人々、この建築の形式の力を魂の中に受け入れた人々の数世紀後を追求してみると、彼らは今やその次の受肉において、その人相や顔貌に、この内的な心情の顕現を示しているのです。人間の魂が顔を作り上げたのです。それでこのような芸術がなぜ用いられるのかがわかります。人類の未来のずっとずっと先まで、秘儀参入者たちは見ているのです。そのため彼らはある特定の時代に、外的な芸術形式、広くは外的な建築様式を形成します。このように、人間の魂の中に、未来の人類の時代のための胚珠が蒔かれるのです。このことを正しく目の前に置いてみると、アトランティス時代末期に起こったことも理解できるでしょう。もう一度、アトランティスの最期、没落が起こった時代に目を転じてみましょう。この時代にはまだ今日のような空気というものはありませんでした。。空気の分布も水の分布もまだまったく異なっていました。濃い霧がアトランティスを取り巻いていました。霧が雲に凝縮し、流れ落ちる雨となって大洪水が陸地にあふれました。このアトランティスの沈没は、徐々に段階的であったと表象せねばなりません。短期間のうちに起こったのではなく、何千年も続くひとつの経過(プロセス)だったのです。外的な生活状況の変化にともなって人間そのものも変わりました。それ以前、人々は一種の霊視により知覚していました。それから雨が降り始めたとき、人々はしだいしだいにまったく新しい生活の仕方、新たな見方、新しい種類の知覚に慣れなければなりませんでした。人間の肉体も変化を免れませんでした。アトランティスの人々が今日の人間とどれほど異なっていたか、はっきりと見ることにでもなれば、皆さんは驚かれるでしょう。けれども、こうした変化がひとりでに起こったとは考えないでください。感覚器官を備えた人間の身体は、少しずつ形成されてきたのです。人間の魂の力が長期間に渡ってこの人間の身体に働きかけ、先ほど簡単な例でお話したような仕方で作用しなければなりませんでした。まず人間は、建築様式を見ます。それが彼の心情に作用し、さらにまたこの心情が後世において、人間の顔相、顔貌に作用するわけです。アトランティス時代から後アトランティス時代に移行する時期になって初めて、人間の魂は自らの形を変え、それに続いて肉体も作り変えられました。もう少し深く入り込んでみましょう。正真正銘の古代アトランティス人を表象してみましょう。彼はまだ霊視的意識を有していました。このことは、生活している環境、霧に満たされた大気と関わりがありました。この環境では、事物は明確な輪郭をもって境界づけられてはいませんでした。それらはむしろ彼の前に浮かび上がってくる色彩像、色彩の波浪といったもので、入り乱れてうねりつつ、人々の魂の状態を彼に示していたのです。自分に近づいてくる対象物の代わりに、アトランティス人はひとつの光の形(フォルム)を知覚していました。青は愛、赤は熱情、怒りなどという具合に。彼を取り巻いて、あらゆる人間の魂の力が広がっていました。もしこういう状態がずっと続いていたとしたら、人間は決して現在の肉体を獲得できなかったでしょう。空気が水から解放され、対象がますます明るくはっきりと現れてきて、現在のような境界をなすようになったとき、人間の魂が新たな印象を受け取らねばならない時期が到来したのです。そしてこの印象に従って、魂は自らの肉体を形成しました。というのも、あなた方が考えたり感じたりするものに従って、あなた方は自らの肉体を形成するからです。さて、人間の魂は、アトランティスの水の風土から救い出されて新たな空気の風土に移行したとき、肉体を今日の形に作り上げるために何を体験せねばならなかったのでしょうか。人間の魂は、後に形成されるべき肉体に合った特定の長さ、幅、深さを備えているようなひとつの形(フォルム)に囲まれていなければなりませんでした。この形は、聖書がノアの箱舟と名づけたものによって実際に彼に与えられたのです。神秘主義の気分がゴシック式大聖堂の形から形成され、その形に従ってどんな顔貌が形成されたかを霊視者なら確認できるように、古代アトランティス人の肉体は徐々に形成し直されました。なぜなら人々は、偉大な秘儀参入者の影響の下に聖書がノアの箱舟を記述している寸法に従って建造された事物の中で、実際に生活していたからです。古代アトランティス時代の生活は、一種の水・海上生活でした。人々の大部分は水上の舟で生活していて、しだいに陸上での生活に慣れていったのです。というのも、古代アトランティスは単に水を含んだ霧の大気に囲まれていたのみならず、アトランティスの大部分は海に覆われていたからです。人々は肉体を今日のようなものに作り上げることができるように、このような舟の内部で生活していたのです。これがノアの箱舟の秘密です。聖書から再び神秘学的な深い意味を読み取ることに通暁すれば、この古文献には、叡智と限りない崇高さの輝きがあふれるのです。人々は、自分の皮膚のなかに閉じこめられているという印象を得なければならなかったので、舟上で生活しました。このように秘儀参入者たちは、何千年にもわたって人間の育成に作用を及ぼしました。宗教的古文献においてみなさんが出会うものは、まさしく深く秘された真実から取り出されたものなのです。参照画:Atlantis また別の形象が聖書の第一章に見いだせます。今世紀の蛇の形象です。ローマの地下納骨堂(カタコムブ)ではさまざまな魚の徴(しるし)が見られます。この魚は古来、常に繰り返し図像として、キリスト教的なものないしキリスト自身を意味するとされています。誰かがこうした形象について思索を深めようとすると、おそらく多分に才気煥発なところが発揮されるでしょうが、それは単なる思弁にすぎません。私たちは単に真実と関わりを持とうとしているのです。これらの図像もまた霊的世界から与えられたのです。皆さんが人類進化の歴史において数分間私に従ってくださるなら、これらの蛇と魚の象徴にどんな真実が含まれているかおわかりになるでしょう。今一度、地球は人間と同じくさまざまな受肉を経てきたということを思い出してください。ご存知のように、この地球は地球となる前には土星、太陽、月でした。人間の肉体はさまざまな惑星状態においてすでに存在していたのですが、自我は地球上ではじめて人間に受け入れられました。さて、この地球がまだ最初の受肉状態、つまりまだ土星であったとき、どのように見えたか観照してみることにしましょう。当時はまだ岩石や表土のようなものは存在しておりませんでした。人間の物質的肉体は存在してはおりましたが、非常に精妙なものでした。それが徐々に濃密になって、ようやく現在の筋肉の形態となったのです。今日の私たちの周囲の物質を観察してみると、個体、液体、気体といった異なった状態があることがわかります。神秘学ではすべての個体状物体が「土」と呼ばれ、「水」と称してすべての液体状の物質、「空気」ですべての気体状、ガス状のものが理解されます。「火」すなわち「熱」はこれらの状態より精妙です。今日の物理学者はむろんこのことを認めないでしょうが、神秘学者はこの「火」が実際、土、水、空気と比較されるものであり、ただこの三つよりももっと精妙な状態であるということを知っています。皆さんが熱を感じとるところでは、空気よりももっと精妙な何かが存在しているのです。私たちが神秘学的な意味で、土、水、空気とみなすものに関しては、土星上には何もありませんでした。これらの固定した有形の状態は、太陽、月、地球となってようやく成立したのです。土星上で最も濃密な状態は、熱あるいは「火」でした。この中に人間の体が生き、土星を取り巻く環、つまり土星はどれも環を有するわけです。これは本来反射された火の鏡像、火の分泌なのです。このことを更に詳しく述べていると、本日のテーマから遠ざかることになってしまいます。さて、土星から太陽へと移りましょう。ここで火に空気が加わります。太陽上で最も濃密な状態は空気でした。これは一種の空気太陽だったのです。太陽上で人間は空気存在であり、その時にエーテル体が注入されました。空気存在の他には何もありませんでした。これらの空気人間は空気のように「透過できる」存在でしたから、彼らを突き抜けていくことができたでしょう。空気人間たちは蜃気楼と比較することができるでしょう。それほど彼らは軽くふわふわしていたのです。むろん、古い太陽上の空気は今日より濃密でした。古い月上でようやく水の状態が生じ、この月上で生きるものはすべて水の凝縮によって形成されました。今日でも見ることのできるクラゲや軟体動物がこうした水-存在についての表象を与えてくれます。当時の物質的肉体はすべてこのような性質のもので、この種の肉体のみがアストラル体を自らの内に受け取ることができたのです。進化はだんだんと先へ続いていきました。このように物事は、つまり人間と地球は関わり合っているのです。人間は自らの惑星に属しているのですから。さて今度は、この惑星進化の意味を考察してみましょう。土星上には物質体の萌芽・原基がはじめて存在しました。太陽でエーテル体が付加され、月ではアストラル体が付加されました。月上ではしかしさらに別のことも起こりました。古い月が二つの天体、すなわち一種の精妙になった古い太陽と本来の古い月という二つに分離したのです。当時、古い月上にとどまっていた人間は、基本的に今日の人間よりずっと劣った存在で、その進化段階はずっと低次のものでした。というのも、アストラル体は古い月上では荒れ狂う激情にあふれていたからです。ずっと後になって自我が付加されてからようやくアストラル体の浄化が始まりました。そのためにはさらなる進化が必要でした。つまり、月が再び太陽と合体し、古い月と太陽という二つの天体が再びひとつにならねばなりませんでした。[注:筆記に欠落]分離した太陽上に生きていた高次の存在たちは、彼ら自身の進化を続けることができるためには、月から離れねばなりませんでした。けれども今度は、この月上に残された存在、そこでさらに固化してしまった存在を救済せねばならなくなり、それで太陽は再び月と一体化せねばなりませんでした。さて、ひとつ問いを出してみましょう。もし太陽と月とが再びひとつにならなかったとしたら、両者が別々に進化を続けていたとしたら、どんなことが起こっていたでしょうか。その時は、人間は決して今日のような形態を保つことができなかったことでしょう。古い月が自らの道を単独で進んでいったとしたら、つまり、太陽との合一によって新たなる力を創造することができなかったとしたら、月が生み出すことができたであろう最高の存在は、おそらく今日の蛇のようなものであったでしょう。それに対して、太陽存在は、彼らが単独のままだったとすれば、最高のものとして魚の形態に到達することができたでしょう。魚の形態は、人間よりずっと高度に進化した存在たちの外的な現れなのです。魚の集合魂は、実際今日でもとても高度なものです。外的な形態は魂とはまったく別のものなのです。それでは古い月の存在たちを蛇よりも高める力はどこからやってきたのでしょうか。この力は、太陽の存在たちから彼らのもとへやってきました。この高次の存在たちの太陽状態の清澄さが魚の形態の中に表現されています。それは古い太陽存在たちが獲得できる最高の物質的形態であるからです。それで太陽の力のすべてを地球に受け付けた太陽の英雄、キリストは、魚の徴(しるし)によって象徴されるわけです。どんな深い直観をもって秘教的キリスト教が魚の形態の意味をとらえたか、今や皆さんにはご理解いただけると思います。魚の形態は秘教的キリスト教にとって、太陽の力、キリストの力の外的な表徴なのです。なるほど魚は外的には不完全な存在ですが、魚はそれほど深く物質の中に入り込んでいないので、利己主義に満たされることが少なくてすむのです。神秘学者にとって蛇は、古い月から進化した地球の象徴です。一方、魚は古い太陽の霊存在たちの象徴です。固体的実質を備えた私たちの地球は、蛇の中にそのもっとも深い存在、地球存在を象徴化しました。水の実質として分離されたものは、魚の中に象徴として示されています。神秘学者にとって魚は水から生まれたもののように思われます。さて、それでは空気から生まれたもの、火から生まれたものとは何でしょうか。これは追求していくのが困難な分野です。ここではいくつか暗示的なことをお話するだけにとどめておきます。地球がまさに土星状態から太陽状態へと進化して移行した当時は、どのように見えたのでしょうか?人間は一種の空気人間でした。今日の意味での死というものを人間はまだ知りませんでした。人間は自らを変態させていたのです。人間がどのようにして今日のような死についての意識に行き着いたのか、ちょっと図を描いてはっきりさせてみましょう。地球が土星状態から太陽状態へと進化していった時、人間の魂はまだ太陽を取り巻いている気圏内で生きていたのですが、下方に肉体として存在していたものと関わりを持っていました。今日において、夜眠っている間、アストラル体は物質体から抜け出てはいても、物質体に属しているように、古い太陽と古い太陽上においても、アストラル体はそのような状態でした。ただ、当時においては魂は決して物質体の中に入り込むことはありませんでした。霊的な意識をもったひとつの魂がなるほど特定の肉体にすでに属してはいましたが、外から肉体を管理していたのです。それはこのように表象せなばなりません。魂は<外的なもの>だったのです。この肉体はまだ死の法則に属してはいませんでした。成長と死滅は今日の場合とは違う形で起こっていました。肉体がある部分を失うと、新しい部分が再生されたのです。今日たとえば空腹と食物が関わっているように、物質体の崩壊と再生とのこのような関係が生じました。長期にわたって魂が生き続ける一方で、肉体は変化していきました。当時は、いかなる死もありませんでした。こうして太陽状態のある時点から、人間の魂がある特定の肉体をまず形成し、それからその肉体をさらに別のさまざまな形に作り変えていくようになったのです。最初にある一定の形の肉体が形成され、それから魂がこの形を別の形に変化させ、さらに別の形に、それから第四の形に…という具合に続いていき、再び最初の状態に戻りました。人間はその間ずっと同じ意識を保持していました。形は変化を重ね、人間の魂が二つの状態を体験した後に、最初の形に戻った時、魂は新たに受肉したように感じたのでした。このような進化の過程は蝶において保持されているのがおわかりでしょう。蝶は、卵、幼虫、蛹、蝶という形で変態しています。蝶は、古い太陽上での、空気状態の人間を表す象形文字、記号なのです。まったく変化してしまった環境に生きている今日の蝶は、むろんこの太陽状態の衰退した形です。蝶は、人間が乗り越えてきた空気状態の象徴なのです。ですから、蝶は、神秘学においては、空気-存在と呼ばれるのです。同様に、蛇は土-存在、魚は水-存在と呼ばれます。鳥が空気-存在と呼ばれない理由は、後ほどもう一度述べようと思います。さて、最初の土星状態まで戻りましょう。この時、人間は霊的-魂的存在であって、総じて同じ肉体を持ち、低次の段階で自らの不死を知り、その肉体を絶えず変化させていました。こういう状態も、ある存在の中になおも保持されています。その共同生活は非常に独特で、これを集合魂とみなしますと、ある意味で人間よりずっと高次の存在といえます。つまり、蜂のことです。蜂の巣全体は個々の蜂とは違うとみなされねばなりません。個々の蜂ではなく蜂の巣は、ひとつの霊的な本性を持っています。これはある意味でかつての土星における低次の段階での人間の本性と一致するのですが、人間は金星状態において、高次の段階で再びこの本性に到達することになりまう。蜂の体は、古い土星段階にとどまったのです。私たちは蜂の巣と個々の蜂とをよく区別しなければなりません。蜂の巣の魂は通常の集合魂ではなく、それ自体特別な存在です。個々の蜂は、形態の中に、人間の肉体が土星で行ったようなことを保管したのです。蜂の巣の霊は、個々の人間の霊よりも高次のもので、今日すでに金星-意識を有しています。蜂は死すべき運命について何も知らない霊人の象徴なのです。この惑星がまだ火のような状態の「土星」であった時に有していた霊性に、人間はこの惑星が金星となって再び火のようになる時、高次の段階でもう一度到達するでしょう。それゆ、神秘学では蜂を熱-存在あるいは火-存在と呼ぶのです。自然科学があまり多くを語れない平行現象を追求するのは大変興味深いことです。いったい今日の人間は土星状態から自らの中に何を受け継いだのでしょうか。熱です。血液の温かさです。当時土星全体に分布されていたもの、つまり熱が解き放たれ、今日の人間と動物の温血を形成したのです。蜂の巣の温度を調べてみれば、それが人間の血液とほぼ同じ温度であることがおわかりになるでしょう。つまり、蜂の巣の全体が、人間の血液の温度に相応してこれと同じ進化段階に戻るような温度を展開しているのです。そういうわけで、神秘学者は蜂を熱から生まれたもの、熱存在と呼ぶのです。同様に、蝶を空気から生まれたもの、空気-存在と呼び、魚を水存在と、蛇を土存在と呼びます。以上のような言及からも神秘学的象徴や記号が表現しょうとするものが、いかに深く惑星と人間の進化史と関わり合っているかおわかりになると思います。参照画:ローマの地下納骨堂(roman catacombs)人気ブログランキングへ
2024年03月09日
コメント(0)
-

ルドルフ・シュタイナー
神秘学の記号と象徴そのアストラル界と霊界との関係yucca訳(1994年)■第一講 シュトゥットガルト 1907年 9月13日-2 学びつつある人、高次の視力、霊視力を発達させつつある人にとって、たとえば次のような修行をすることは大きな意味があります。すなわち、真っ暗な空間に身を置き、外からの光を完全に遮断して、夜の暗闇であっても両目を閉じることでもよろしいのですが、それから徐々に自分自身の内的な力によって、光の表象に突き進もうとするのです。人間がその表象を十分な強度をもって形成できるようになると、その人は次第に明敏になり、そして光を見るようになります、それは物質的な光ではありません、その人が今や自ら創造し、内的な力によって自らの内に生み出した力です。これは叡智に貫かれた光です、この光の中で人間には創造する叡智が現れます。これがアストラル光と呼ばれる光なのです。瞑想を通じて人間は内的な光を生み出すことができるようになります。この光は、人間がいつの日か、物質的な目ではなく、もっと精妙な感覚器官によって見るであろうものの先触れなのです。それはエロヒムたちのような実際に存在する霊存在たちの衣装となります。人間がこの修行を正しいやり方で行うと、それはこれらの高次存在と関係を結ぶ手段となります。自らの経験から霊的世界について何かを知るひとたちは、このようなことを行なってきたのです。後でお話しします別の方法によって人間は、自らの内的な力により、空間が光に照らされ、叡智に取り巻かれるのみならず、空間がいわば音を発し始めるという事態にまで到達することができます。ご存知のように、古代ピタゴラス哲学では、天球の音楽について語られていました。この「天球」という言葉で、ここでは宇宙空間、つまり星々が運行する空間が意味されています。これはあれこれ考えたあげく作り上げられたイメージなどではなく、詩的な比喩でもない、ひとつの真実なのです。人間が秘密の導師の指示に従って十分に修行を積むと、明澄な、光輝に満たされた空間、叡智の顕現である空間を内的に観るだけでなく、宇宙空間にみなぎる天球の音楽を聞き取ることを学びます。空間が鳴り響き始めるこの時、人間は天上的な世界、デヴァチャンにあると言われるのです。まさしく空間が鳴り響くのですが、これは物質的な音ではありません、これは霊的な音、空気中では生きるのではなく、ずっと高次の精妙な実質、アーカーシャ実質の中に生きる音なのです。空間は絶え間なくこのような音楽に満たされています、そしてこの天球の中にある種の基調音があるのです。 さて、ここでもう一度天球の音楽というものにおいて理解したことを考察してみましょう。今日の数学的天文学者たちが、神秘学において惑星について語られていることを明らかな妄想と見なすであろうことは、私にはよく分かっております。けれどもそれは問題ではありません、やはりこれは真実なのですから。お話してきましたたように、この地球はだんだんと進化してきました、私たちは地球の諸々の受肉について語ってきたのです。地球は最初、土星、それから太陽、さらには月、そして現在は地球であり、後に木星、金星、ヴルカンとなっていきます。さて、皆さんは次のように問うことができます、そうは言っても今も空に土星というものがあるではないか、この今日の土星は地球の最初の受肉状態であった土星とどういう関係にあるのかと。こん日今の時代、星空を観察すると、私たちが公によく知っている諸惑星が見えます。これらの惑星の名称は恣意的に選ばれた、つまり近年、慣例になっているように、特定の人物、例えばその星の発見者の名前に因(ちな)んでつけられたというようなものではありません、そうではなく、星々の本質に関する深遠な知から与えられた意味深い名前なのです。こん日今の時代人々はもはやそのようなこととは関わりなく、例えばウラヌス(天王星)は後になってはじめて発見されたためこのような正しい名前を持っておりません。今日皆さんが天に土星として観ているものは、私たちの地球がまだ土星の状態にあったときと同じ段階にあるのです。公の土星は地球に対して謂わば少年が老人に対するような関係にあります。老人がその らに立つ少年から育ってきたのではないように、老人自身かつては少年だったわけですから、この地球も今日ある土星から進化してきたものではありません。こんにち空にある土星もまたいつか「地球」となってゆくのであり、現在は一種の青年期の段階にあるわけです。他の天体の場合もこれと同様です。太陽はかつて地球がそうであったような天体ですが、ただそれが謂わば「前進した(avanciert)」状態なのです。人間の場合に、老人のかたわらに少年がいるといった具合にさまざまな年齢層がともにあるように、天においてもさまざまな惑星がさまざまな進化段階にあって並存しているのです、その一部は、現在その第四の受肉状態にあるこの地球がすでに完了した進化段階であり、また一部はこれからとることになる進化段階です。これらの惑星は、お互い正確に一定の関係にあります。神秘学者はこうした関係を今日の天文学者が行うのとは別のやり方で表現するのです。御存知のように、諸惑星は一定の速度で太陽の回りを運動しております。けれどもこれらの惑星は神秘学的天文学者たちによって精確に探求されている惑星運動でもある、また別の運動もしているのです。その探求によって明らかにされたのは、太陽はある霊的な中心点の回りを運動しており、従って諸惑星の軌道はその正中線が太陽の軌道となる螺旋を描くということです。各惑星がその軌道を運行する速度は、お互いに全く一定の調和した比例関係にあり、この音響としての比例関係が聞く者にとって、ひとつのシンフォニーへと構成されるのです。これがピタゴラス学徒によって天球の音楽とみなされていたのです。この共鳴、この音楽は、宇宙的な出来事の模像であり、ピタゴラスの学院で教授されたものは、何ら頭をひねって考案されたものではないのです。古代の神秘学的天文学者たちはこう語りました。一見静止しているように見えるこの星天は実際は動いている。霊的な中心点の回りを、百年ごとに一度ほど前にずれていく速度で回転しているのだと。 さて、各惑星の速度は、お互い次のような関係になっています(編集者註 ☆1)。*土星の速度=木星の速度の21/2倍*木星の速度=火星の速度の5倍*火星の速度=太陽、水星、金星の速度の2倍*太陽の速度=月の速度の12倍この場合、土星の速度は金星天の速度より1200倍早く、年に12度前進します。 物理学上の音楽的調和が成立するとき、これは、例えばさまざまな弦が、あるものは速く、あるものは遅く、異なって振動することに基づいています。一本一本の弦が振動する速度に従って、高い音や低い音が響き、こうしたさまざまな音の共鳴が音楽として鳴り、調和を生むわけです。皆さんが弦の振動から、この物理学的なものの中に、音楽的印象を得るのと全く同じように、デヴァチャン界の霊聴の段階にまで上昇した人は、天体の運動を天球の音楽として聴き取るのです。さらに、諸惑星のそれぞれ異なる運動速度の比例関係により、宇宙空間全体に響きわたる天球のハーモニーの基調音が生じます。ピタゴラスの学院では、まさしく天球の音楽について語られているのであり、それは霊的な耳で聞くことができるのです。以上の考察から、私たちはさらにまた別の現象も暗示できます。例えば、薄い真鍮板に微細な粉末をできるだけ均等にまき散らし、ヴァイオリンの弓でこの板をこするとします、すると音が聞こえるばかりでなく、粉末の粒子が一定の線上にきちんと並びます。音に応じてあらゆる図形が形成されます。音が作用して物質、素材が配置されるのです。これが有名なクラドニの音響図形です。霊的な音が宇宙空間を貫いて響いたとき、音は互いに比例関係にある諸惑星を天球のハーモニーへと組織しました。宇宙空間に広がって見えるものを、この創造する神性の音が配列させるのです。このような音が、宇宙空間の内部へと響きわたったことにより、物質が、ひとつの系へと、太陽系、惑星系へと形成されたのです。ですから「天球の音楽」という表現も、才気あふれる比喩などではありません、それは現にある事実なのです。さて、また別のことがらに移りましょう。この地球が常に現在のようであったわけではないことはお分かりですね。相当長い間神智学に携わってきた方は、現在の受肉状態にある地球がさまざまな進化段階を経てきたことをご存知でしょう。はるかに遠い過去、地球は火で溶融したような状態でした。今日の石や金属であるものは、かつてはこの火で溶けた状態の地球に溶けこんでいました。そのような熱の中では、人間もその他の存在も生存できたはずはないという非難に対しては、次のように答えねばならないでしょう、当時の人間の肉体は当時の諸条件に適合したものであったのだ、と。当時の肉体は、今日の溶鉱炉よりも高い温度でも生存できたのです。この地球の火の時代に続いて、私たちがアトランティス時代と呼ぶ水の時代がやってきます。ちょっとこのアトランティス時代を考察してみましょう。アトランティス大陸は、今日のヨーロッパとアメリカの間の大西洋の中心に広がり、私たちの先祖が住んでいました。むろん彼らは今日の人間とは全く異なった状態にありました。彼らの視力は私たちのそれとは異なっていました、彼らはある意味で霊視を行っていたのです。アトランティス人の進化においては、この視力にさまざまな段階がありました。アトランティス末期の最終段階は、はるかに高次の段階の一種の余韻のようなものでした。例えば、アトランティス人は外的な対象をアトランティス末期になってようやく見ることができるようになったのです。それ以前、アトランティスには厚い水を含んだ大量の霧が充満していたので、対象物は空間的にはっきりとした輪郭で分けられていませんでした。こうしたアトランティス進化の初期においては、知覚のしかたが全く異なっていました。古代アトランティス人がある物や存在に近づくとき、最初に見たのはある人物や対象の輪郭や骨格ではありませんでした、それどころか、外界とは何の関係もない、ある内的な魂の状態を再現するような色彩像が、彼らの内に浮かび上がったのです。色彩像は、こちらに向かってくる存在が彼にとって有益なのか危険なのかを語るものでした。例えば、こちらにやってくる者が他に対して抱いているのが復讐の感情であったなら、それに応じた色彩像が彼に示され、彼はそこから走り去りました。野生の獣が近づいたら、彼は同様に識別し、それから逃れることができたのです。アトランティス人は、自分の周囲の魂の状態をこの霊視の最終段階で知覚していました。その状態から今日の視力が徐々に発達してきたのです。非常に霧のかかった日のことを考えてみてください、対象はそういうとき、ぼやけています。考えてごらんなさい、こんな日には、街灯も点のように浮かび上がっているだけでしょう。それからだんだんと輪郭が判別できるようになってきます。こうして徐々にアトランティス人は見ることを学んだのです。人間が以前に見ていたものは、一種のアストラル的な色彩でした。最初のうち、この色彩はまだ自由に漂っているように見え、それからいわば事物の上に置かれたのです。参照画:天球のハーモニー もちろん、こうした別種の知覚は、当時の人間は今日とは全く違った様相をしていたことと結びついています。例えば、アトランティス時代の末期には、人間の身体の額ははるかに後退していて、その上方にエーテル体が大きな球のようにせりだしていました。額の後ろ側の点、両眼の間を少し後退したあたりで、物質体とエーテル体はまだ一致していませんでした。それから物質体とエーテル体が収縮し、物質体とエーテル体両者の点が一致したのは、人間進化において、重要な瞬間でありました。今日では肉体の頭部はエーテル体の頭部にほぼぴったりと収まっています。馬の場合は、まだそうではありません。けれども人間の場合、この頭部が変化してきたように、四肢も変化してきたのです。徐々に現在の肉体の形姿が形成されてきたのです。アトランティス時代末期へと思いを馳せてみてください。そもそも当時はどんな状態だったのでしょうか。人間はある種の霊視力で自分の周囲の魂的状態を知覚していました。もう一度この厚い霧の大気、水蒸気をたっぷり含んでずっしりと重い空気を思い浮かべてください。太陽や星々、皆さんの周囲のあらゆる対象物は当時、この厚い水を含んだ空気の中ではよく見えなかったことでしょう。虹は当時はまだありませんでした、虹はまだ生じていなかったからです。すべては厚く重い大量の霧におおわれていました。それゆえ、伝説はニヴルヘイム、ネーベルハイム(霧の国)について語っているのです。徐々に、空気の中に厚く拡がっていた水が凝縮していき、「かくて大洪水の水が地上に降り注いだ」(☆2)。これは厚い大量の霧が水へと凝縮し、降水、雨となって落下したということを言っているのに他なりません。水が空気から分離されたことにより、空気は透明になり、それに伴って、今日のような視力が形成されてきました。人間は、自分の周囲の対象を見ることができるようになって初めて、自分自身を見ることができたのです。さて、人間の物質体は深い意味を持つ多くの規則性を示しています。そのうちのひとつは次のようなものです。皆さんが、高さ、幅、長さが、3:5:30の割合となる箱をこしらえるとします。そうすると、これと同じ割合が人間の肉体にも見出せるのです。換言すれば、これによって人間の肉体の規則的な構成の割合が示されているわけです。人間がアトランティスの洪水から出てきたその当時、人間の肉体は3:5:30という割合に従って形成されていました。このことは、聖書においては次のような言葉でたいへんみごとに表現されています、「そこで神はノアに命じて、長さは三百エレ、幅は五十エレ、高さは三十エレの箱(舟)を作らせた」(☆3)と。人体の調和の寸法比は、このノアの箱船の寸法比とぴったり適合しています。神秘学の記号や形象は、事物の本質そのものから取り出されたものです、従って、それらを通じて私たちがいかにして霊界の関係をのぞき込むことができるかを示すものなのです。人気ブログランキングへ
2024年03月08日
コメント(0)
-

ルドルフ・シュタイナー
神秘学の記号と象徴そのアストラル界と霊界との関係yucca訳(1994年)■第一講 シュトゥットガルト 1907年 9月13日-1 秘密(オカルト)の記号とアストラル界・霊界との関係。人間の記号としての五芒星(ペンタグラム)。叡智の像としての光。「叡智の働きかけ」によるアストラル体の変成と高貴化。地球の未来の進化。内的な光を獲得するための修練。叡智の光と天球の音楽。天球の調和(ハーモニー)と惑星運動。アトランティス人の知覚。人体の比率としての箱船。 ここシュトゥットガルトでこれから行います四回の講演は、いくぶん内密な性格を持つことになると思います。何といっても皆さんの大部分は神智学協会に属され、すでに長年に亘って神智学の根本理念に親しんでこられ、従ってこの分野のより内密な題材に精通したいとお望みでしょうから。これらの講演で扱いますのは、アストラル界及び霊界と関連する秘密(オカルト)の形象と記号です。一連の秘密の象徴と形象のより深い意味を述べるつもりです。その際、初めの二回の講義で、いくらか奇妙に聞こえることがあっても、三回、四回と進みますと、完全な説明が得られるということにご注意いただきたいと思います。事の性質上、そういうことになるのです。神智学の講演は、いわば唯物主義的なやり方で単純な要素の上に組み立てられた他の講演とは違うのですから。最初はどうしても不明確な点があり、それが次第に明確に理解できるようになっていきます。 形象や記号は、通常の世界のみならず、神智学的な世界においても、しばしばただひとつの意味を表す、多かれ少なかれ恣意的な何かであるという印象を与えますが、これはまったく正しくありません。皆さんもすでにそのような形象や記号について聞かれたことがおありでしょう。例えば、宇宙のさまざまな惑星が記号で示されることなどです。また、神智学のアレゴリーにおいてよく知られた記号は、いわゆる五芒星(ペンタグラム)ですね。さらに、ご存知のように、さまざまな宗教において、光というものは、叡智の、霊的な明澄さの意味で言及されています。さて、このような事柄の意味を問えば、これはしかじかのことを意味するといった表現を聞いたり読んだりなさるでしょう。例えば三角形は高次の三性を表す云々。神智学の著作や講演でも、たびたび神話や伝説が解釈され、「これはしかじかのことを意味する」と言われます。感覚の背後、この意味の本質の背後に至ること、このような形象の真実を認識すること、これを、この連続講演の課題といたします。これがどういうことか、ひとつ例を挙げて説明してみましょう。 五芒星(ペンタグラム)を考察してみましょう。ご存知のように五芒星についてはあれこれ詮索され解釈されておりますが、神秘学においてそういうことは問題になりません。神秘学者が五芒星について語ることを理解するためには、まず人間の本質の七つの基本要素を思い起こさなくてはなりません。ご存知のように、人間の本質は、七つの基本要素、物質体、エーテル体、アストラル体、自我、さらに霊我、生命霊、霊人(神智学文献では後三者はマナス、ブッディ、アートマ)から成ります。手で触ることのできる物質的なものである物質体は除外しましょう。ここでとりわけ考察の対象になるのは、エーテル体です。エーテル体はすでに物質的な感覚にとっては隠されたもの、いわゆる「オカルト的なもの」に属します。通常の目ではエーテル体を見ることはできないからです。エーテル体を知覚するには霊視的な方法が必要です。実際にエーテル体を見ることができたら、むろん物質体とは全然違うものです。エーテル体はたいていの人が想像するような希薄な物質的身体、一種の微細な霧の塊といったものではありません。エーテル体の特徴は、浸透してくるさまざまな流れから構成されているということです。エーテル体は実に物質体の建築家、形成者なのです。氷が水から形成されるように、物質体はエーテル体から形成されます。このエーテル体はあらゆる面に向かって、海のように流れに貫かれているのです。それらのうち主な流れが五つあります。両手両足を開いて立ってごらんなさい。人間の身体はこの絵のように表されます。参照画:ペンタグラム11(Pentagram) この五つの流れを人間はひとりひとり自らの内に隠し持っているのです。これらの流れが矢印に示された(図参照)方向にエーテル体を貫き、いわば人間のエーテル体の骨格を形成しているのです。絶え間なくこれらの流れはエーテル体を通過し、これはその人が動いているときも変わりません。どんな姿勢をとっていようと、常にひとつの流れが、額の中心、眉間の一点から発して右足へ下り、そこから左手へ、さらに右手へ、それから左足、そこから再び額へもどります。五芒星と呼ばれるものは、エーテル体の中で人間の物質体そのもののように内的に動いているのです。ですから神秘学者(オカルティスト)が五芒星について、人間の図形として語るとき、それはあれこれ思案して作り出された何かのことを言っているのではなく、解剖学者が骨格について語るのと同じなのです。この図形は、現にエーテル体の中に存在していて、ひとつの事実なのですから。こうしたわずかのことからも、ある記号の実際の意味がどのようなものであるかがわかるのです。神秘学において皆さんが出会う記号や形象はすべてこのような真実に導いてくれるものです。五芒星は、エーテル体の動く「骨格」であり、それゆえ人間の図形なのです。これがこうした記号の本当の意味なのです。 図形や記号を用いる正しい指針を少しずつ獲得すると、それらは人間をしだいに霊的世界の認識に導き、霊視力を獲得させる手段となります。瞑想において五芒星に沈潜する人にはこれらのエーテル体内の流れの道筋が見いだされます。これらの記号の恣意的な意味をあれこれ考え出すのが目的ではありません。瞑想においてこれらの記号と関わるとき、ただし、忍耐強く行わねばなりませんが、秘められた真実に導かれます。これは、あらゆる形象や記号と同じく、皆さんがさまざまな宗教的古文献の中に見い出すことのできるものにもあてはまります、こうした形象は、深く神秘学に根ざしているものですから。預言者や宗教家が光について語り、光によって叡智を表そうとするとき、このことを単に彼が思いついたとか、才気煥発であろうとしてこのような表現を用いたとか考える必要はありません。神秘学者は事実に立脚しているのであって、才知に富んでいるということは重要ではないのです。ただ真実であろうとするのみです。神秘学者として人は、無秩序な思考をする習慣を捨てねばなりません。すなわち、恣意的に結論を引き出したり、判断を下してはならず、一歩一歩霊的な事実を手がかりに、正しい思考を発達させていかねばなりません。こうした光についての形象にもきわめて深い意味があり、ひとつの霊的な事実です。このことを認識するために、再び人間の本質に目を向けてみましょう。ご存じのように人間の本質の第三の構成要素はアストラル体であり、喜びと悲しみ、歓喜と苦悩、衝動、熱望と激情といった人間の内的魂的な体験が有するすべての担い手です。植物にはアストラル体がなく、従って人間や動物のような喜びや悲しみは感じません。今日、自然研究者が植物の感情について語るとき、そもそも感情の本質について完全な誤解に基づいています。アストラル体の正しい表象は、時代の経過とともにアストラル体の遂げてきた進化を追求するときにのみ得られます。すでに以前、大宇宙での進化との関連における人間の進化を考察いたしました。その際、人間の物質体が人間本性の最も古く最も複雑な構成要素であること、エーテル体はそれほど古くなく、アストラル体はもっと若く、自我にいたっては人間本性のうち最も若いものであることを見てきました。その理由は、物質体はその進化においてすでに地球の四つの惑星状態を経てきたからです。私たちの地球が以前、土星状態と呼ばれる受肉状態にあったとき、すでに物質体は原基の状態で存在していました。その当時、はるか昔ですが、地球はまだ固体ではなく、人間はまだ今日の形態をとっていませんでした。ただ、その土星上には物質体の原基があったのです。けれどもエーテル体、アストラル体といった他の体はまだありませんでした。地球の第二の受肉状態、太陽上ではじめて人間にエーテル体が付与されました。当時、人間のエーテル体はきわめて明白に五芒星の形態を有していました。後にこの星の第三の受肉状態、月上でアストラル体が付加されることにより、これはいくらか修正されました。さらに月は、地球へと変わり、以上の三体に加えて自我が登場します。さて、私たちは次のように問うことができます、これらの体は人間本性に受肉する前にはいったいどこにあったのか。例えば、太陽上でエーテル体として物質体の中に組み込まれられたものは、古い土星上ではどこにあったのか。エーテル体というものもどこからかやってきたのに違いないのだからと。エーテル体は、土星の周囲にあったのです、ちょうど今日、地球の周囲に大気があるように。後になって人間に組み入れられたものは、すべて古い土星の周囲に、気圏内にすでにあったのです。同様に、太陽においては、月上ではじめて組み入れられるアストラル体が周囲にありました。古い太陽を次のように表象することができます。太陽は今日の地球のような岩石、植物、動物から成り立っているのではなく、太陽上に存在していたのは二つの自然領域でした。太陽上に見いだせる存在、人間は、どうにか人間的な植物といったところで、こうした存在とともに、古い太陽上には、一種の鉱物もありました。けれどもこの古い太陽を現在の太陽と混同してはなりません。古い太陽は厚い流動するアストラル的な外被に取り巻かれていました。古い太陽はいわば、アストラル的な空気の覆いに囲まれていて、このアストラル外被は光輝いていました。古い太陽上の舞台はこんなぐあいだったのです。 今度は再び、物質体、エーテル体、アストラル体と自我を有する今日の人間を考察してみましょう。さてこの自我がアストラル体へと働きかけて、これをよりいっそう知的、道徳的、霊的な関連において浄化すると、このアストラル体から霊我ないしマナスが生じます。はるかな未来、今日ほとんど始まっていないこのことが完了されたときには、このアストラル体が「物質的に」輝きを発することでしょう。植物がすでに自らの内に新しい生命の萌芽を宿しているように、アストラル体もすでに光の萌芽を宿しています。いつか人間が自らのアストラル体をもっともっと純化し、浄化しきったあかつきには、この萌芽が宇宙空間へと光を発することでしょう。この地球は、別の惑星へと変容するでしょう。今日の地球自体は暗いのです。外部から観察することができ得たとしたら、地球はただ太陽の光を反射して明るく見えるだけだということがわかります。けれども、いつか地球自体が光輝くようになるでしょう。そのときには、自らのアストラル体全体を変化させてしまっている人間によって光輝くのです。すべてのアストラル体の総計が光となって、宇宙空間に光を放つことでしょう。古い太陽の場合もそのような状態でした。古い太陽の住人は、現在の人間たちよりも高次の存在たちで、これらの存在は光輝くアストラル体を持っていました。聖書において非常に正確に光の霊あるいはエロヒムと呼ばれたこれらの存在は、そのアストラル本性を宇宙空間に放射していたのです。 さて、人間が自らのアストラル体に組み入れたものは何なのか、と問うならば、答えは、それは私たちが善、聡明さと呼ぶものだ、それを通して人間は自らのアストラル体を高貴にするということです。私たちがまだ食人種の段階にあり、すべての激情に盲目的に従う未開の人を観察するとき、そしてその人は何によって高度に進化した人間と区別されるのかと問うとき、こう言わざるを得ません、文明人はすでに自らのアストラル体に働きかけてきたが、未開の人はまだそうしていないという点で区別されると。自らの激情や衝動を、これには従ってよい、別のはいけないと自らに言い聞かせるほどに把握している人は、道徳的な概念や理念を形成しています。つまりこれがアストラル体を変化させ高貴にするということなのです。人間は受肉を重ねつつアストラル体に働きかけることにより、ますますいっそう前述の光輝く存在へと自らを高めていきます。これは「叡智の働きかけ」と呼ばれます。アストラル体の中に叡智が増せば増すほどアストラル体は光輝を増します。あの太陽上に住んだ存在、エロヒムたちは全き叡智に貫かれていました。私たちの魂と肉体との関係は、ちょうどこの光と叡智の関係なのです。光と叡智の関係は考案されたイメージではないということがお分かりいただけたでしょう、これはひとつの事実に基づいており、ひとつの真実なのです。光は事実叡智の身体なのです。こうして私たちは、宗教的な古文献が光について叡智の形象化として語っていることを理解できるようになります。*ルドルフ・シュタイナーは、「マナス」を自我として捉えていました。この概念は、人間の精神的な存在や意識の側面を指します。シュタイナーは、マナスが物質的な身体と精神的な世界をつなぐ存在であると考えていました。マナスは、個人の意識や精神的な成長、創造性、直感、自己認識などに関連しています。彼の哲学では、マナスは物質的な側面と精神的な側面の間の橋渡しとして機能し、人間の進化と成長において重要な役割を果たすとされています。参照画:霊魂における自我(マナス)人気ブログランキングへ
2024年03月07日
コメント(0)
-

ルドルフ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-18真理と学問 Ⅷ:実践の帰結 我々が前述の考察によって解明を要したものは、客観的世界存在に対する我々の認識する人格の構えであった。認識と学問の所有は我々にとって何を意味するのか。それが、我々がその答えを探し求めた問いであった。我々は、我々の知の中に世界の内奥の核心が存分に生きていることを見てきた。宇宙を支配している合法則的な調和は、人間の認識において現れる。それ故、確かに普段は全ての存在を支配しているが、しかし決して自分自身では存在するに至らないような世界の根本法則を、現象する現実の領域へと移し替えることが、人間の使命に相応しいのである。それ自身の中に、客観的な現実の中では決して見出されることのない世界根拠が具現すること、それが知の本性である。我々の認識とは比喩的に言えば世界根拠に恒常的に慣れ親しむことなのである。そのような確信がまた我々の実際の人生観に光を投げかけなければならない。我々の生活態度は、その全き特性によれば、我々の道徳的理想によって規定されたものである。我々の道徳的理想とは、我々が人生における我々の責任から持つ理念、つまり換言すれば、我々が我々の行為を通して成し遂げるように求められていることから生み出す理念である。我々の行為は、普遍的な世界事象の一部である。それ故にまた行為は、この世界事象の普遍的な合法則性の下にある。もし今、宇宙のどこかで或る事象が起こるならば、その事象には二重に区別せねばならないことがある。即ち、空間と時間の中でのその事象の外的なプロセスと、その事象についての内的な合法則性である。人間の行為にとってこの合法則性の認識は、認識の個別の事例に過ぎない。従って、認識の本性について我々によって導き出された見解がここでも適用できなければならない。それ故、自分を行為的人格として認識することは、自分の行為にとって相応しい法則、即ち道徳的概念及び理念を、知として有することを意味する。我々がこの合法則性を認識したならば、我々の行為もまた我々の所産である。その場合には合法則性は、事象が現れる客観の外にある何かとして与えられたのではなく、生き生きとした営みの中で把握された客観そのものの内容として与えられたのである。この場合の客観とは、我々の固有の自我である。自我が自分の行為をその本性によって実際に認識して自分のものとしたなら、自我は自分が同時に行為の支配者であると感じる。そのようなことが行われないでいるうちは、行為の法則は我々に馴染みのない何かとして向かい合って立っている。行為の法則は我々を支配する。我々が成し遂げることは、行為の法則が我々に対して行使する強制の下で存する。行為の法則が、そのような馴染みのない特性から、我々の自我のまさに自分自身の行ないにすっかり変わったなら、この強制は終わる。この強制は我々固有の本性となったのである。合法則性は、もはや我々を支配するのではなく、我々の中で我々の自我を出発点とする事象を支配する。実現者の外部に存する合法則性の故の事象の実現は不自由の行為であり、実現者自身の内部に存する合法則性によるそのような実現は自由の行為である。実現者が行為の法則を認識するということは、実現者が自由を自覚するということを意味する。認識プロセスは、我々の詳述に従えば、自由への発展過程なのである。人間の一切の行為がこの特徴を持っているのではない。多くの場合において我々は、行為のための法則を知として所有していない。我々の行為のこの部分は、我々の活動の不自由な部分である。それに対して、我々がこの法則に完全に精通する部分がある。それが自由の領域である。我々の生活が自由の領域に属している限り、それのみを道徳的なものだと呼ぶ。自由の領域の特徴を持つそうした道徳的なものへの不自由な領域の変化は、各個人の発展、及び人類全体の発展の課題である。 一切の人間の思考の最重要課題は、人間を自分自身に基礎を置いたものとして、つまり自由な人格として把握することである。 (了)参照画:Freedom
2024年03月06日
コメント(0)
-

ルドルフ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-17真理と学問 Ⅶ:認識論の帰結 我々は全ての人間知の意味についての学問として認識論を基礎付けた。この認識論を通じて初めて、我々は個々の学問の内容と世界との関係についての説明を手に入れる。この認識論は諸学の助けを借りて世界観に至ることを可能にする。我々は実証的な知を個々の認識によって獲得する。認識論を通じて我々は現実にとっての知の価値を経験するのである。我々は厳密にこの根本原則に固執したし、我々の取り組みにおいてどんな個々の知も利用しなかった。そのことによって我々は一切の一面的な世界観を超克した。一面性は通常、認識プロセスそのものに取り掛かる代わりに、ただちにこのプロセスの何らかの客観に近づくという研究に起因する。我々の議論に従えば、独断論はその「物自体」を、主観的観念論はその「自我」を、根本原理としては放棄しなければならない。というのも、「物自体」と「自我」は、その相互関係に関して言えば、思考において初めて本質的に規定されたからである。「物自体」と「自我」は、その一方を他方から演繹するようには規定できず、そのどちらとも、その特徴と関係に関して言えば、思考によって規定されなければならないのである。懐疑主義は世界の認識可能性へのその疑念を放棄しなければならない。というのも、「所与」は、認識を通じて与えられた全ての述語によって未だ言及されていないので、「所与」には何も疑い得ないからである。しかし懐疑主義が、思考によって認識することが決して物に達しえないと主張したがるのであれば、思考によって熟慮することそのものを通じてのみ、それができることになるが、しかしそのことによって懐疑主義は、それ自身も誤りであることを証明している。というのも、思考によって疑いを基礎付けようとする者は、確信を裏付けるための十分な力が思考にあることを暗黙のうちに認めているからである。我々の認識論は、最終的に、一面的な経験主義と一面的な理性主義の両者をより高次の段階で統一することによって超克する。我々の認識論はこのやり方で両者を満たす。我々は、所与に関する一切の内容的な認識がただこの所与そのものと直接接触することの中でしか得られないということを示すことによって、経験主義者を満たす。我々は、思考とは認識の必要不可欠かつ唯一の媒介するものだと宣言するので、理性主義者もまた、我々の議論で思惑通りになる。我々が認識論的に基礎付けた世界観は、A.E.ビーダーマンによって主張される世界観と最も近いところで接する点がある。しかしビーダーマンは、自分の観点を基礎づけるために、全く認識論に相応しくない確定を必要とする。そこで彼は、前もって認識プロセスそれ自体を探求することなしに、存在、実体、空間、時間などといった概念を用いる。認識論プロセスにおいては最初にただ二つの要素――所与と思考――のみがそこにあるということを確定する代わりに、彼は現実の存在様式について話すのである。たとえば彼は次のように言う。§15「一切の意識内容においては二つの基本的事実が含まれている。1.その中では二種類の存在、つまり我々が感性的なものと精神的なもの、具体的なものと理念的なものと呼ぶ対照的な存在が与えられている」。§19「空間的-時間的現存在であるものは、物質的なものとして存在する。理念的に存在し、一切の生命の現存在プロセス及び主観の根拠であるものは、理念的に存在するものとして実在する」。このような考量は、認識論に本来あるべきものではなく、認識論の助けを借りて初めて基礎付けられるような形而上学に本来あるべきものである。ビーダーマンの主張が我々の主張に屡々似ていることは認めねばならない。しかし我々の方法は、彼のものとは全く合致しない。それ故に我々は、彼と直接対決する理由をどこにも見出さなかった。ビーダーマンはいくつかの形而上学的な公理の助けを借りて認識論の立脚点を獲得しようと努めている。我々は認識プロセスの考察を通して現実についての見解に到達しようと努めるのである。 【原注】 *39:A.E.ビーダーマン『キリスト教の教義』。第一巻における認識論的探究。この観点に関する徹底的な議論は、E.v.ハルトマンによって提供された。『現代の哲学を通じての批判的な歩み』p.200ff を見よ。そして我々は、ただそれだけで他の一切の知について説明できるもの、即ち知そのものの本質を予め精確に知ることなしに、客観的なもの(物、自我、意識等々)についての知を得ようと努めることが原因で、一切の世界観の争いが起こることを実際に示したと信じている。 参照画:Immanuel Kant-W人気ブログランキングへ
2024年03月05日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-16真理と学問Ⅵ:無前提な認識論とフィヒテの知識学 1-3 フィヒテはかつて、正しい洞察に極めて近づきさえした。フィヒテは 1797 年の『知識学への序論』の中で、二つの理論体系、即ち、自我が物によって規定されているとしておく独断論と、物が自我によって規定されているとしておく観念論があると考えている。フィヒテの視点によれば、両者が可能的な世界観であることは確かである。一方は他方と同じく首尾一貫した展開を可能にするとされている。しかし、我々が独断論に身を委ねるならば、自我の自立を断念しなければならないし、自我を物自体に依存させねばならない。我々が観念論を信奉するならば、我々は逆の場合になる。一方或いは他方の哲学者が二つの体系のどちらを選びたいと思うかを、フィヒテは、自我の好みのみに判断を任せる。しかしフィヒテによれば、自我がその自立性を保ちたいと思うならば、自我は我々以外の物への信仰を廃棄し、そして観念論に身を委ねるのだそうである。ところで、自我が自我を助けて決定や規定をするものにする何かを前提としないならば、自我はもちろん現実的で基礎付けられた決定と規定に全く至りえないという考察のみが僅かに足りなかっただろう。この一連の思惟は一つだけ考察し落としている。つまり、自我がそうすることを可能にする何かを自我が前提しないのであれば、自我はなんらかの現実的な基礎づけを持ついかなる選択や決定に至ることができないということである。自我に与えられたものの規定を可能にし、それによって観念論と独断論の間での選択をさせる何か内容の豊かなもの、全く何か規定されたものを、自我が見出さないならば、自我による一切の規定は、空虚で内容の無いままであろう。しかし、この全く内容の豊かなものは、思考の世界である。そして与えられたものを思考によって規定することは、認識である。我々が好きな箇所でフィヒテの著作を扱おうとも、我々がフィヒテにおいて全くおぼろげで空虚な自我の活動を、我々が認識プロセスと呼んだものによって満たされ規制されていると考えるならば、フィヒテの考えの筋道が直ちによく練られたものになることを、我々はいたるところで見い出すのである。自我が自由に活動することができるという事態は、自我自身から自己規定によって認識のカテゴリーを現実化することを自我に可能にする。それに対して、それ以外の世界では、カテゴリーは客観的な必然性によってカテゴリーに対応する与えられたものと結びついていることが明らかになる。自由な自己規定の本質を探求することは、我々の認識論に支えられた倫理学と形而上学の使命であろう。この倫理学と形而上学は、自我が認識の外のそれ以外の理念をも現実化できるかどうかという問題をも論究しなければならないであろう。しかし、認識の現実化が[自我の]自由によって生じることは、前記でなされた寸評から既にはっきりと明らかになっている。というのも、直接的に与えられたものとそれに必要な思考の形式が自我によって認識プロセスの中で統一されるならば、そうでなければ常に分かれたまま意識に残る現実の二つの要素の統一は、自由の営みによってのみ生じうるからである。しかし、我々の詳論によって、なおも全く異なる仕方で光が批判的観念論に投げかけられる。フィヒテの体系に詳細に取り組む者にとって、そもそも自我自身によっては措定されないものが、外から自我へは入ってこられず、自我の中では現れないという命題を維持することは、この哲学者の中心問題であるように思われる。しかし、今やいかなるどの観念論も、我々が直接的に与えられたものと呼んだ世界内容のあの形式を、自我から導き出すことはできないということは疑う余地がない。この形式は、まさしくただ与えられ、決して思考の内から構成されえないのである。我々に他の一切の色見本が与えられたとしさえも、たった一つの色彩の微妙な違いさえ単に自我から補充することも、我々は成し遂げられないであろうことだけは、やはり吟味してほしい。たった一つの影を除いてあらゆる色彩が我々に与えられたとしてさえも、自我のみからこの影を提供しはじめることはできないだろうということだけは、よく考える必要がある。我々が像を作るための諸要素を、それまでに個人的に与えられたものとして体験した場合、我々が一度も見たことがない、極めて遠くの地域の像を我々は作ることができる。その場合我々は、与えられた手ほどきに従って我々が体験した個々の事実から像を組み合わせる。そして我々は、我々に与えられたものの領域の中には一度も存在しなかった唯一の知覚の要素だけでさえも我々から紡ぎだそうと無駄に努力するだろう。しかし、与えられた世界を単に知っていることは、別の事柄である。世界の本質を認識することはまた別の事柄なのである。我々が現実を与えられたものと思考そのものから構築することなしには、世界の本質を認識することは、そのことが密接に世界内容と結びついているにもかかわらず、我々にははっきりしなくなる。所与が本来「何であるか」は、自我にとって世界の本質を認識することそのものを通じてのみ措定される。しかし、自我が最初に自分自身に向き合って事物を全く無規定的な方法で見ないならば、自我は、所与の本質をそれ自身において措定する契機を全く持たないことになってしまうだろう。つまり、世界の本質として自我によって措定されるものは、自我なしにではなく、同じ自我によって措定される。現実の真の形態は、現実が自我に向かってくる時の最初の形態ではなく、自我が同じ現実からつくる最後の形態である。最初の形態は、客観的な世界にとっておよそ重要ではなく、そのような形態は認識プロセスにとって基礎でしかないのである。つまり、主観的な形態は、世界の理論が与える世界の形態ではなく、むしろ自我に最初に与えられているあの形態なのである。フォルケルトなどの例にならって、この所与の世界を経験と呼びたいならば、次のように言わなければならない。即ち、学問は、我々の意識という設備によって主観的な形態において経験として現れる世界像を補完して、この世界像が本質的にそうであるものにするのだと。 我々の認識論は、言葉の真の意味で自ずから理解される観念論の基礎を提供する。この認識論は、思考において世界の精髄が媒介されるという確信を基礎付ける。世界内容の諸部分の関係は、それが熱せられた石に対する太陽熱の関係であれ、自我の外部世界に対する関係であれ、他ならぬ思考によって明示されることができる。思考においてのみ、全ての事物がそれらの関係において相互に規定する要素が、与えられている。カント主義がなおなしうるかもしれない反論は、前記で特徴づけた所与の本質規定はやはり自我にとってそのようなものでしかないということであろう。それに対して我々は、我々の根本的な見解の意味で次のように応えなければならない。もちろん、自我と外部世界の分裂も所与の内部でしか存立せず、つまりあの「自我にとって」は、全ての対立を統一する思考によって考察することにとっては意味がないのだと。外部世界から分割されたものとしての自我は、思考による世界観察において完全に沈潜する。つまり、自我にとってのみの諸規定について語ることはもはや全く意味を持たないのである。 参照画:Johann Gottlieb Fichte 人気ブログランキングへ
2024年03月04日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-15真理と学問Ⅵ:無前提な認識論とフィヒテの知識学 1-2 フリードリッヒ・.ハームスは彼の講演「フィヒテの哲学について」(p.12)の中で、正しくも次のように述べている。「フィヒテの世界観は支配的という意味でも例外なくという意味でも倫理的であり、その認識論はそれ以外の性格を持たない」。現実性の一切の領域がその総体性において与えられているなどというならば、認識は絶対的に課題を失ってしまうだろう。しかし今や、自我が思考によって世界像の体系的な全体へとはめこまれていない限り、自我も直接的に与えられたもの以外のなにものでもないのだから、自我の為すことを単に示すのでは充分ではない。けれどもフィヒテは、自我のところで単に探索をするだけで既に全てが為されているという見解である。「我々は全ての人間知の端的に無制約的な、絶対的第一原則を探求しなければならない。それが絶対的第一原則であるべきだとすれば、それは証明されることもできず、また規定されることもできない」。我々は、既に前章で証明や規定がもっぱら純粋論理学の内容に対してのみ相応しくないということを見た。しかし、自我は現実に属し、現実ではあれこれのカテゴリーの存在を所与の中で確定することが必要不可欠である。フィヒテはこの必要不可欠なことをしなかった。そしてこの点に彼が彼の知識学にこれほど的の外れた形態を与えた理由が求められる。ツェラーは次のように述べた。「フィヒテが自我概念に達しようとした論理的公式は、そもそも、なにがなんでもこの自我という出発点に至るという、既に先取りした目的に達したいと、フィヒテが思っているという事情をただ粗雑に覆い隠している」³⁴⁾と。これらの言葉が、フィヒテが 1794 年に彼の知識学に与えた最初の形態に関係している。フィヒテは実際に、彼の哲学的営為の構想全体に従って、学問を絶対命令によって始めさせること以外の何のも欲しえなかったと我々が固執するならば、この始まりを理解できるように思わせる方法は二つだけである。一つ目は、意識を何らかのその経験的活動のところで取り扱う方法であり、本来意識から帰結しないものすべてを徐々に剥き落とすことによって、自我という純粋な概念を結晶化させるという方法であった。そしてもう一つは、自我の本来的な活動のすぐそばで始まり、自我の本性を自己観想及び自己観察によって明示するという方法であった。フィヒテは哲学的営為の始めに一つ目の方法をとり、そして哲学的営為のプロセスにおいて、徐々に二つ目の方法に移行した。 【原注】 *30:J.G.フィヒテ『全知識学の基礎』1794 年。SW 版第Ⅰ巻 p.97(邦訳:Ibid. p.97) *31:SW 版第Ⅰ巻 p.91(邦訳:Ibid. p.90) *32:SW 版第Ⅰ巻 p.178(邦訳:Ibid.p.189) *33:SW 版第Ⅰ巻 p.91(邦訳:Ibid. p.90) *34:『 ラ イ プ ニ ッ ツ 以 降 の ド イ ツ 哲 学 史 』 ミ ュ ン ヘ ン 1873 p.605 カントにおける「超越論的統覚」の綜合に結び付けて、フィヒテは、自我の全ての活動が、判断の形式に従って、経験の素材を組み合わせることに存すると考えた。判断は、述語を主語と結びつけることに存し、このことは、純粋に形式的な仕方で a=a という命題によって表現される。この命題は、両方の aを結びつけるxが端的な能力に基づいていないならば、措定することができないだろう。というのも、その命題は「a が存在する」ではなく、「もし aが存在するならば、そうすれば aは存在する」を意味するからである。かくして、a の絶対的な措定については問題とすることができない。つまり、一般に絶対的で端的に妥当するためには、その命題そのものを絶対的だと言明すること以外に何も残っていないのだからである。a が制約的である一方で、a の措定は無制約的である。しかし、この措定は自我の事行である。それ故自我には、端的で無制約的に措定する能力が帰せられる。a=a という命題において、一方の a は、他方の a が前提されることによってのみ措定される。しかもそれは、自我によって措定される。「もし a が自我の中に措定されているならば、そうすれば、a は措定されている」。この連関は、自我の中で何かが、即ち、一方の a から他方の a へ移行する何かが、常に変わらないものであるという条件のもとでのみ可能である。そして前記の x は、この変わらないものに基づいている。一方の a を措定する自我は、他方の a を措定する自我と同じである。即ち「自我=自我」である。「もし自我が存在するならば、そうすれば自我は存在する」という判断の形式で表現されるこの命題は、意味を持たない。自我は、他方の自我の前提のもとで措定されるのではなく、自我自身を前提とする。つまり、自我は端的なものであり無制約的なものである。絶対的自我の前提なしに一切の判断に帰せられるという判断の仮説的形式は、ここでは「自我はとにかく存在する」という絶対的実存命題の形式へ変化する。フィヒテは今述べたことを、「自我は根源的に端的に自分自身の存在を措定する」というふうにも表現している。このフィヒテの推論全体が、自我の無制約的な活動の認識を、彼の読者にわからせるための教育的な議論の方法以外の何ものでもないと、我々は見ている。自我の行為が、彼の読者の目の前にはっきりともたらされるようになっており、その自我の行為の遂行がまったくなければ自我はまったく存在しないのだ。 【原注】 *35:SW 版第Ⅰ巻 p.94(邦訳:Ibid. p.93) *36:SW 版第Ⅰ巻 p.98(邦訳:Ibid. p.98) さて我々は、フィヒテの考えの筋道にもう一度振り返ってみよう。即ち、より鋭く見てみれば、彼の考えの筋道の中に飛躍があり、しかも、根源的な事行についての見解の正しさを疑わしいものにするそのような飛躍があるということが明らかになる。一体そもそも、自我の措定において実際に絶対的なものとは何なのか?次のように判断される。「もし a が存在するならば、そうすれば a は存在する」。 a は自我によって措定される。つまり、この措定については疑いが存在しえない。しかし、仮に活動として無制約的であるとしても、自我はなおも単にとにかく何かを措定しうるのみである。自我は、「活動それ自体」ではなく、ただ一定の活動を措定しうるのみである。簡単に言えば、措定は内容を持たねばならないということである。しかし、この内容を自我は、自我自身か取り出し得ない。というのも、そうでなければ自我は、永遠にただ措定することを措定する以上の何もできないことになるからである。つまり、自我の絶対的な活動である措定にとって、その措定を通じて実現される何かが存在しなければならないのだ。自我は、自我が措定する所与に取り組むことなしには、およそ「何も」できないし、従って措定できないのである。「自我はその存在を措定する」というフィヒテの命題も以上のことを示している。この存在はカテゴリーである。我々は再び、次のような我々の命題の下にある。即ち、自我の活動は、自我が自分の自由な決意から所与の概念と理念を措定するということに基づいているという命題である。フィヒテは、彼が自我を「存在するもの」であると実証することを無意識に目指すことによってのみ、その結論に至る。フィヒテが認識の概念を発展させていたならば、彼は認識論の真の出発点に至っていただろう。即ちその真の出発点とは、「自我は認識を措定する」である。フィヒテは、自我の活動が何によって規定されるかをはっきり理解しなかったので、存在の措定を単純に自我の活動の性質とした。そして、それとともにフィヒテは、自我の絶対的な活動をも局限していた。というのも、自我の「存在措定」が無制約的であるならば、自我から出発するそれ以外の全てのものは制約的だからである。しかし、無制約的なものから制約的なものに至るためのどんな道も断たれている。自我が示された方向にのみ無制約的であるならば、その自分の存在以外の何かを根源的な働きによって措定する自我にとっての可能性がすぐになくなるのである。従って、自我のそれ以外の一切の活動の理由を述べる必然性が生じる。フィヒテは、我々が前記で既に見たように、そのような理由を虚しく探したのである。それ故に彼は、自我の導出のために、前記で示された道とは異なる道へと方向転換した。既に 1797 年の『知識学への第一序論』において、自我を自分の生来具わった性質において認識するために、彼は正しいものとして自己観察を奨めた。「君自身に注意を向けよ。君の目を君を取り囲むもの一切から転じて、君の内部に向けたまえ。これが哲学見習いの徒に対して哲学が最初に要求することである。君の外部にあるものが問題となるのではなく、専ら君自身が問題となるのである」。知識学を導入するこの方法は、なるほど、他の方法よりも大きな長所を持っている。というのも、自己観察は確かに、自我の活動を事実特定の方向へ、一方的に展開するのではなく、自我を単に存在措定的に指し示すのでもなく、思考によって直接的に与えられた世界内容を把握しようとするその全面的な発展の中で、自我を指し示すからである。自己観察では、所与と概念の組み合わせから、世界像を組み立てる自我が現れる。しかし、我々の前記の考察を一緒にやり通していない者、つまり、自我がその思考形式を所与に持ち込む場合にのみ自我は現実の内容全体に至る、ということを知らない者にとって、認識プロセスは自我から世界を紡ぎ出すこととして現れる。それ故にフィヒテにとって世界像は、ますます自我の構築となる。フィヒテは、知識学においては、世界のこの構築において自我を一心に探求することができる感覚を呼び覚ますことが重要であるということをますます強く強調する。これができる者は、フィヒテには、単に構築されたもの、出来上がった存在のみを見る者よりも高い知の段階にいる者と思われている。諸々の対象物の世界を単に観察する者は、対象物が自我によって初めて作り出されることをわかっていない。しかし、自我をその構築の中で観察する者は、できあがった世界像の根拠を見ている。何によって自我が生まれ、何によってその者に対して与えられた前提の結果としてその者に現れているのかを、その者は知っている。通常の意識は、措定されたもの、あれやこれやの仕方で規定されたもののみを見ている。その通常の意識にとっては、何故それがまさにそのように措定され、それ以外の何ものでもないのかという前提ないし根拠への理解がない。この前提を媒介するための知は、フィヒテによれば、全く新しい感覚器官の課題である。私は、こうしたことが、「知識学入門講義 1813 年秋ベルリン大学での講義」の中で最もはっきりと述べられていると思う。「この学説は一つの全く新しい内的な感覚器官を前提としている。この器官によって、普通の人間にとっては全然存在しない、一つの新しい世界が与えられるのである」。或いは「新しい感覚の世界が、そしてそれによって新しい感覚を持つ者自身が、差し当たりはっきりと規定されている。即ち新しい感覚の世界とは、「それは何かである」という判断が基づいている前提を照らして見極める「光明の作用(Sehen)」であり、そして、まさに新しい感覚を持つ者がこうした差し当たりはっきりと規定されたものであるが故に、それ自身として再び存在することはなく一つの存在にはならない、存在の根拠なのである。」。 【原注】 *37:J.G.フィヒテ『知識学への第一序論』1797 年。SW 版第Ⅰ巻 p.422(邦訳:ラインハルト・ラウト/加藤尚武/隈元忠敬/坂部恵/藤澤賢一郎編『フィヒテ全集第 7 巻イェーナ時代後期の知識学』晢書房 1999 年 p.365) *38:J.G.フィヒテ『知識学入門講義』1813 年。I.H.フィヒテ編『J.G フィヒテ遺稿集』、ボン、1834 年 第Ⅰ巻 p.4 及び p.16(邦訳:ラインハルト・ラウト/加藤尚武/隈元忠敬/坂部恵/藤澤賢一郎編『フィヒテ全集*第 20 巻ベルリン大学哲学講義』晢書房 2001 年 p.210 及びp.227) しかし、自我によって遂行される活動の内容のはっきりとした洞察は、フィヒテにはここでも欠けている。フィヒテはそうした洞察にまでは決して達していない。それ故に彼の知識学は、そうでなければ、その知識学の構想全体によれば哲学的基礎学としての認識論になっていたはずのものにはなりえなかった。即ち、フィヒテがかつて、自我の活動がこの自我自身によって措定されなければならないことを知っていたならば、自我の活動が自我によってその活動の規定をも得ることを考えることは当然であっただろう。しかし、いかにして自我の純粋に形式的な活動に内容を与えることにおいてとは異なるかたちで、これが起こり得ることになるのか。しかし実際にはこの内容が、自我によって自我のそれ以外は全く規定されていない活動へ入れられることになるならば、この内容もその本性に従って規定されねばならない。さもなければ、やはりこの内容は、自我自身によってではなく、せいぜい自我の中に存する、自我が道具てあるところの「物自体」によって、現実化されうることになるだろう。フィヒテがこの規定を試みていたならば、彼は自我によって実現されることになる認識の概念に至っていたであろうが、しかし彼はそうしなかった。フィヒテの知識学は、所与を補えば現実性を持つような正しい思考形式(カテゴリー、理念)に辿り着けば、鋭い洞察者にさえ何らかの分野で効果的に影響を与えることが成功するということの証拠である。そのような考察者には、極めて格調の高いメロディーが示され、メロディーに対する感受を持たないが故に、そのメロディーを全く聴かない人のように、ものごとが進む。意識を与えられたものであると特徴づけることができるのは、「意識という理念」を所有することに自分の立場を置くことを知っている者のみである。人気ブログランキングへ
2024年03月03日
コメント(0)
-

生成宇宙新論(宇宙創生の因) Hiro Shim著-4 PLAN
生成宇宙新論(宇宙創生の因-一の振動) Hiro Shim著-4 PLAN「Harmony in Space」第一:時さえ知らない永劫の「虚」の或る一つの振動が数多(あまた)の振動に劃かたれ、振動を繰り返していた。夫々に秘めたる力はあったもののエネルギーと呼べるものではなかった。然し乍ら、ある偶然が2つの振動にハーモニーを奏でた。喩えれば人間の精子が卵子に着床した瞬間である。その合成された振動は計り知れないパワーとしてエネルギーが解放させた。インフレーション宇宙の誕生である。地球は静寂に包まれていた。人々は未知の可能性に胸を膨らませ、冒険的な未来を予想していた。量子コンピュータの誕生は、人類哲学の新たな高みへの扉を開いた。ある日、研究者たちは巨大な量子コンピュータを起動した。その瞬間、現実と異次元の境界が揺れ動いた。量子ビットは複雑なダンスを踊り、新たな情報の波ハーモニーを奏でた。量子の波は地球全体に広がり、生命の種子を運んでいた。人々は気づかなかったが、彼らのDNAは微細な変化を受けていた。新たなる「種の起源」が始まった瞬間だった。ある夜、森の奥深くで謎めいた光が輝いた。そこには人間とは異なる姿をした存在が立っていた。彼らは透明な翼を持ち、量子のエネルギーで満たされていた。彼らは「クォン」と名付けられた。クォンは人間の世界に姿を現した。彼らは知識と洞察をもたらし、人々に新たな哲学を教えた。彼らは量子の力を操り、未知の可能性を探求した。人々はクォンを神秘的な存在として崇拝し、彼らの教えを受け入れた。新たなる種の起源は、人類の哲学と科学の融合から生まれたものだった。クォンは地球を飛び回り、新たなる冒険を求めた。彼らは量子の翼で宇宙を駆け巡り、他の星々と交信した。人々はクォンの冒険譚を語り継ぎ、新たな哲学的な時代が幕を開けた。そして、人類は再び未知の可能性に胸を膨らませ、冒険的な未来を予想した。クォンの存在は、地球上に新たなる「種の起源」をもたらしたのだった。第二:かつて、宇宙の始まり以前、虚無が広がり、ただ振動のみが存在していました。その振動は、物理科学や認証哲学が捉える「モノ」なるものを超越した存在で、そのものそれ自身しかありませんでした。ある偶然により、その振動がハーモニーを奏で始めました。それは生命的には雄の振動と雌の振動、愛のハーモニーでした。この愛の偶然が、素粒子よりも小さいが、隠された無限大のエネルギーを持つ素因を生み出しました。そして、その素因が、その後に続くインフレーションやビッグバンを引き起こしました。このビッグバンにより、今私たちが知っている宇宙が誕生しました。この物語は、宇宙の始まりとその創造についての一つの解釈であり、科学と哲学、そして愛という普遍的な感情を組み合わせたものです。それは、私たちが存在する宇宙が、偶然と必然、そして愛によって生まれたという、美しい物語を描いています。この物語の題名は、「愛のハーモニー:宇宙創生の序曲」とするのはいかがでしょう。この題名は、物語の中心的なテーマである「愛」と「ハーモニー」、そして「宇宙創生」を象徴しています。また、「序曲」は、この物語が宇宙の始まりを描いていることを示しています。この題名は、物語の深遠さと美しさを表現しています。どう思いますか?第三;かつて、全てが虚無であった時代。その中に存在したのは、ただ振動だけでした。それは物理的な存在ではなく、ただのエネルギーの波動、振動でした。ある日、その振動が偶然にもハーモニーを奏で始めました。それは雄の振動と雌の振動が交わり、愛のハーモニーを生み出した瞬間でした。この愛のハーモニーは、素粒子よりも小さいが、隠された無限大のエネルギーを持つ素因を生み出しました。「素因」は、その後に続くインフレーションとビッグバンを引き起こしました。ビッグバンにより、今私たちが知っている宇宙が誕生しました。星々が生まれ、銀河が形成され、生命が芽吹きました。しかし、愛のハーモニーは消えることなく、今もなお宇宙のどこかで響き続けています。それは星々の輝き、生命の息吹、そして私たちが感じる愛情の中にも存在しています。して、この物語は続きます。愛のハーモニーは新たな素因を生み出し、新たな宇宙を創造するでしょう。それは永遠に続く、宇宙創生の序曲なのです。第四:宇宙が振動とハーモニーで成り立つという物語を始めましょう。かつて、全てが一つだった時代がありました。その一つは、純粋なエネルギー、純粋な振動でした。それは、まさに宇宙の始まり、ビッグバンの瞬間でした。このエネルギーは、時間と共に広がり、振動し、様々な形を生み出しました。それらは素粒子となり、原子となり、星となり、銀河となりました。それぞれが異なる振動を持ち、それぞれが宇宙の一部としてハーモニーを奏でていました。しかし、このハーモニーは単なる音楽ではありません。それは物理法則、それは生命、それは我々が存在する理由そのものです。我々はその振動の一部であり、我々自身もまた、宇宙のハーモニーを奏でているのです。そして今、我々はそのハーモニーを理解しようとしています。超ひも理論という新たな理論を用いて、宇宙がどのように振動し、どのようにハーモニーを奏でているのかを解き明かそうとしています。この物語はまだ終わっていません。我々が宇宙のハーモニーを理解し、その一部として共鳴する日が来ることを願っています。宇宙創生序曲「Harmony in Space」:これ等が、宇宙が振動とハーモニーで成り立つという物語です。我々はその一部であり、その美しいハーモニーを奏で続けています。そして、その理解が進むにつれて、我々は自分たちが宇宙とどのようにつながっているのかをより深く理解することができるでしょう。それは、まさに宇宙の旅路そのものです。ハーモニー世界は、全てが調和と平和に満ち溢れています。そこでは、全ての生命が互いにリンクし、共鳴し合っています。それぞれの生命は、自身の振動を持ち、それが他の生命とハーモニーを奏でています。この世界では、人々は互いに理解し、尊重し合います。彼らは自分自身の存在と他者の存在を認識し、その違いを尊重します。それぞれの人々が持つ独自の振動は、他者との関係性を形成し、社会全体のハーモニーを生み出します。自然界もまた、このハーモニーの一部です。山々、川、森、海、全ての生物は、自身の振動を持ち、それが自然界全体のハーモニーを奏でています。自然と人間は、互いに影響を与え、共鳴し合います。科学と技術もまた、このハーモニーの一部です。人々は科学と技術を用いて、自然界との調和を保ち、社会全体のハーモニーを維持します。科学と技術は、人々が自身と他者、自然界との関係性を理解し、それを改善する手段となります。ハーモニー世界では、全てが一つの大きなシステムとして機能します。それぞれの部分が他の部分と相互作用し、全体のバランスとハーモニーを保ちます。それは、まさに宇宙の旅路そのものです。そして、その旅路は、私たちが宇宙と共に振動し、ハーモニーを奏で続ける限り、永遠に続くでしょう。ハーモニーとは「愛」そのものを象徴します。人気ブログランキングへ
2024年03月02日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-14真理と学問Ⅵ:無前提な認識論とフィヒテの知識学 1-1 これまでの論述によって、我々は認識の理念を確定した。直接的に与えられたのは、ここでは、意識が認識するという振る舞いを行う限りでの、人間の意識の中の理念である。意識の中心点としての「自我」には、外的知覚と内的知覚、及び自我自身の現存在が直接的に与えられている。自我は、直接的に与えられたものより以上のものを、この所与において見出す衝動を感じる。自我にとって所与の世界に対する第二の世界、つまり思考の世界が浮かび上がり、我々が認識の理念として確定したものを、自我が自由な決意から実現することによって、両方の世界を結び合わせる。さて、ここにあるのは、人間の意識そのものの客観(対象)において、現実総体について概念と直接的に与えられたものが結びついて示されるその仕方と、残余の世界内容に対して妥当する仕方との間の根本的な違いである。世界像のそれ以外の全ての部分に際して、その結合が根源的なものであり、初めから必然的なものであること、及び、認識の始まりにのみ認識にとって人為的な区別が生じていることを、我々は考えざるを得ない。しかしこの区別は、結局のところ認識によって、客観的なものの根源的な本質に従って、再び止揚される。人間の意識にはそれ以外のものがある。ここに結合が存在するのは、この結合が現実の活動において意識によって遂行されるときのみである。それ以外の全ての客観[対象]に際しては、区別は客観(対象)にとって意味はなく、認識にとってのみ意味がある。ここではこの結合は第一のものであり、区別が派生したものである。認識はただ区別を遂行するのみである。なぜなら認識は、それが事前に区別していなかったなら、その仕方ではこの結合を強引に我が物とすることができない。しかし、概念と意識の所与の現実は、元来区別されており、結合は派生的なものであり、それ故に認識は、我々が前記で説明したようなものになっている。意識において必然的に理念と所与とは区別されて現れるから、意識にとって現実全体がこの二つの部分に分裂する。そして意識はただその固有の活動によってのみここで挙げた両方の要素の結合を生じさせうるから、意識はただ認識行為の実現を通してのみ、完全な現実に達する。もし残余の諸カテゴリー(諸理念)が、認識へ受容されない場合でも、それらは必然的に相応しい所与の形式と結びついているだろう。認識の理念は、意識の活動を通してのみ、その理念に相当する所与と統一されうるのである。現実の意識が存在するのは、意識がそれ自身現実化する時のみである。以上をもって、我々は、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ(Johann Gottlieb Fichte /1762年 - 1814年)の「知識学」の根本的な間違いを暴くと同時に、「知識学」の理解のための手がかりを提供するために、十分に準備していると思う。フィヒテは、全ての学問の基礎づけは単に意識の理論にのみ存しうると、カントの後継者の中で最も強烈に感じた哲学者であるが、彼はなぜそうであるかという認識には決して至らなかった。フィヒテは、我々が認識論の第二の段階と呼ぶもの、そして我々が公理の形式を与えるものが、「自我」によって現実に実行されなければならないと感じた。我々はこれを、たとえば彼の次の言葉から見て取れる。「それ故、知識学は、それが体系的学問である限り、他の一切の可能な体系的学問とちょうど同じように、自由が規定されることによって生じる。自由は、ここでは特に、知性一般の活動様式を意識化するように規定されているのである。さて、この自由な活動によって、既にそれ自体で形式であるところの或るもの、つまり知性の必然的な活動が、内容として新たな形式へ、知の形式ないし意識の形式へ取り入れられる。ここで、曖昧に感じられているものを、明瞭な概念で述べるということであれば、「知性」の活動様式という言い方で何を理解すればよいのだろうか。認識の理念の、意識において実行する現実化以外の何ものでもないもの。フィヒテが完全にはっきりとそれを意識していたならば、彼は前記の文章を単純に次のように定式化した筈であろう。即ち、知識学は、認識が未だ「自我」の無意識的な活動である限りで、意識化する認識を持つのだと。知識学は、「自我」において必然的な行為としての認識の理念の客観化が実行されることを示さなければならない。 [原注]*28:我々は、ここで、「中心点」という名称と結びつけて意識の本性についての理論的見解を知りたいのではなく、この名称を意識の全様相の文体上の短縮形としてのみ用いている。このことは恐らくほとんど言う必要がないことであろう。 *29:J.G.フィヒテ『知識学の概念、あるいはいわゆる哲学の概念について』(1794)。 I.H.フィヒテ版全集、ベルリン、1845 年(以下 SW 版と略)第Ⅰ巻 p.71f(邦訳:ラインハルト・ラウト/加藤尚武/隈元忠敬/坂部恵/藤澤賢一郎編『フィヒテ全集第 4 巻:初期知識学』晢書房 1997 年 p.60) フィヒテは、「自我」の活動を規定しようとする。彼は次のように考える。「自分自身を存在するものとして措定するという点にのみその存在(本質)があるというものが、絶対的主観としての自我である」。自我のこの措定は、フィヒテにとって、その他一切の「意識の基礎にある」、第一の無制約的な事行である。 つまり自我は、フィヒテの意味でも、ただ絶対的な決意によってのみ、その一切の活動を始めることができる。しかしフィヒテにとっては、自我によって絶対的に措定されたこの自我の活動を助けて活動が為すことの何らかの内容を獲得させることは不可能である。というのも、フィヒテはこの活動が目指すものを何も持たなかったからであり、その活動が規定されるべき基準となるものも持たなかったからである。フィヒテの自我は、事行を遂行することになっている。しかしそれは何を為すことになっているのか。フィヒテは、自我が実現することになっている認識の概念を定めなかったがために、自我の絶対的な事行が自我のなお一層の諸規定へと何らか進展することを見出そうと虚しい取り組みをした。実際、彼は結局そのような進展に関して、「これについての探求は理論の限界の外部にある」と説明しているのである。「批判的観念論は、その表象の演繹において、自我の絶対的な活動からでも非我の絶対的な活動からでもなく、むしろ同時に規定作用でもあるところの規定されたものから出発する。なぜなら、意識の中にはそれ以外の何も直接的には含まれておらず、また含まれ得ないからである。何がこの規定を更に規定するのかは、理論においては全く未決のままである。そしてこの不完全性によって我々は、実際に理論を越えて知識学の実践的部門へと駆り立てられる」。しかしこの説明によってフィヒテは、およそ一切の認識を壊滅させる。というのも、自我の実践的な能動性は、或る全く別な領域にあるべきものだからである。前記で我々が提示した公理が、自我の自由な行為によってしか実現されえないことは、もちろん明らかである。しかし自我が認識しながら振る舞うのであるならば、まさしく肝心なのは、自我の決意が、認識の理念を実現することへ向かうことである。自我が自由な決意からなお多くの他のことを為しうることは、なるほど確かに正しい。しかし、学問一切の認識論的基礎付けは、「自由な」自我という性格ではなく、「認識する」自我という性格にかかっている。しかしフィヒテは、人間の個の自由を最も明るい光へと提示する、彼の主観的な傾向によって過度に影響されるままになっている。参照画:berlin-tiergarten人気ブログランキングへ
2024年03月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1










