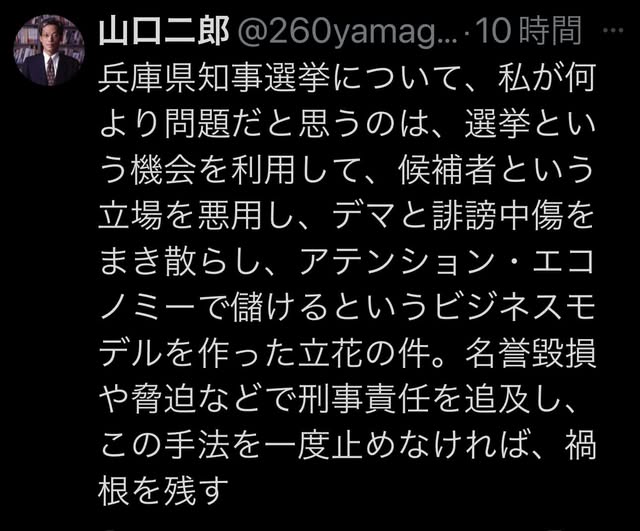2024年05月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説並びに精神科学(人智学)の基礎(GA1)第8章 芸術から科学へ 佐々木義之訳 思索家の精神的な発達を描写しようとするときには、その発達の特別な方向性がどのようにして生じてきたのかをその人物の人生に関わる事実から心理学的な意味で説明しなければなりません。ところが、「思索家」としてのゲーテを提示する場合、重要なのは、彼の特別な科学的方向性を正当化しながら説明するというよりも、「そもそも」この天才が科学者として活動するようになったのは何故なのかを示す必要があるという点です。ゲーテは同時代人たちの間違った考え、つまり、詩的な創作活動と科学的な探求が一人の人間の中で統合されることはあり得ないという考えに大いに苦しみました。ここで最も重要なのは、この偉大な詩人に科学を取り上げさせた動機は何かという問いに答えることです。芸術から科学への移行は単に彼の主観的な傾向、個人的な思いつきから生じたものなのでしょうか。それとも、ゲーテの芸術的な性向が「必然的に」彼を科学へと導いたのでしょうか。もし、前者が本当であったとしたら、ゲーテの芸術と科学への同時献身は、単に人間的な努力の二つの側面に対する個人的な熱中から「偶然の」結果として生じてきたことになり、私たちは「たまたま」思索家でもあった詩人を取り扱うことになったはずです。人生の過程が少し異なっていれば、ゲーテは科学に何の興味も持たなかったとしても同じように詩作を取り上げていたことでしょう。その場合、この人物の両方の側面が別々に私たちの興味の対象になったはずです。また、両方の側面が人類の発達に大きな貢献をしたことでしょう。けれども、これら二つの精神的な方向が二人の異なる人物の中に生きていたとしても、それは同様に真実であったことでしょう。「詩人」であるゲーテと「思索家」であるゲーテはお互いに何の関係も持たなかったはずです。ところが、第二の仮定が正しいとすれば、ゲーテの芸術的な衝動がそれ自身の内的な必然性から科学的な考え方によって補われることを要求したということが考えられ、二つの衝動が二人の人物の間で分割されることなど全く考えられなかったことでしょう。二つの衝動のそれぞれが「単にそれ自身の目的のため」だけではなく、一方の他方への関係という理由によっても私たちの興味の対象になったはずです。そのとき、芸術から科学への「客観的な」移行、つまり、一方の分野に精通することが他方の分野に精通することを要求するような仕方で両方が出会う地点が存在するはずです。もし、そうであるならば、ゲーテは単に個人的な傾向に従っていたのではなく、科学的な活動を通してのみ満足させ得る必要を彼の中に目覚めさせたのは、彼が没頭していた芸術的な衝動だったはずです。私たちの時代には、芸術と科学はできるだけ離しておくものだと信じられています。それらは人間の文化的な発展の両極端だと考えられています。科学は最も客観的な世界像を提供する、つまり、鏡のように現実を私たちに示す。言い換えれば、客観的に与えられるものに完全に忠実であり、すべての人為的な主観性を排除すると思われています。その法則はそれが従うべき客観的な世界によって決定され、科学は何が真実であって何が偽りであるかの判断基準を感覚的に経験される対象の中だけに見出すと考えられているのです。芸術的な創造活動ということになると、すべてが全く違ってくると思われています。その法則は人間精神の自律的で創造的な力から生じるというのです。科学においては、あらゆる人間的な主観性の介入は現実の歪曲・経験の越権行為であり、他方、芸術は天才の主観性を糧に育つものと考えられています。その創造は人間的な想像力の産物であり、外的世界の鏡像ではありません。科学的な法則の起源は私たちの外、客観的な存在性の中にあり、審美的な法則の源泉は私たちの中、私たちの個別性の中にあるのであって、後者は何らかの認識論的な価値を有しているとは考えられません。つまり、現実の要素など微塵もない幻想を創り出しているだけなのです。このようにものごとを見る人がゲーテの詩作とゲーテの科学との間の関係を明確に理解することは決してないでしょう。その結果、彼らは何も理解しません。ゲーテの偉大な歴史的重要性は、彼の芸術が原初の存在の源泉から直接流れ出しているという事実、それに関しては何ら幻想的、主観的なものはなく、むしろ、自然の働きの奥深くにある世界精神に耳を傾けるとき、詩人として理解した法則性の先駆けとしてそれは現われるという事実の中にあります。芸術はこの段階において、ちょうど科学が別の意味においてそうであるように、世界の秘密を説明するものとなります。事際、ゲーテはいつでも芸術をこのような仕方で見ていました。彼にとって芸術は世界の原初的な法則性の「ひとつの」顕現であり、科学は「また別の」顕現だったのです。彼にとっては、芸術も科学も「単一の」源泉から湧き出してくるものです。研究者は現実を深く探求し、その原動力を思考の形で定式化しようとするのに対して、芸術家は同じ原動力を彼らの媒体の中に吹き込もうとします。科学は一般的なものの認識、抽象化された認識と呼ぶことができる一方、芸術は活動に適用された科学と言えるでしょう。つまり、科学は原因であり、芸術はその働きです。ですから、それを実際的な科学と呼ぶこともできるでしょう。ですから、結局のところ、科学は定理であり、芸術は課題なのかも知れません。科学がアイデア(*定理)として表現するものは、芸術がその媒体をそれで満たすところの法則性と同じものです-つまり、それは芸術の課題となります。「人間の働きの中で最も言及する価値があるのは、自然の働きにおけるのと同様、その意図なのです。」(散文の中の韻)記:IDEA(イデア)とは「何かが保存されるという想定」、観念上の想定であり、まさしくイデアです。もっと広く言えば、「法則」こそイデアに他なりません。このような理念に自然現象の本質があると考えて探求しているのが現代の自然科学、とりわけ物理学なのです。物理学者のリー・スモーリンもこう言っています。「プラトニズムは、移ろい知覚される世界の背後にある永遠で抽象的な世界の探求は、古代から現在まで物理学者と数学者たちの探求を駆動してきた。」参考画:リー・スモーリン記:リー・スモーリン(英: Lee Smolin、1955年6月6日 - )は、アメリカの理論物理学者、ペリメーター理論物理研究所教員、ウォータールー大学の物理学教授、トロント大学の哲学部の大学院教授のメンバー。2006年に出版した「迷走する物理学」の中で弦理論を批判した。彼は量子重力理論、特にループ量子重力理論(*ループ量子重力理論は、時空(時間と空間)にそれ以上の分割不可能な最小単位が存在することを記述する理論)として知られるアプローチに貢献。 ゲーテが外的な世界の中に探し求めたのは、感覚に与えられるものだけではなく、世界がそれを通して生じたところの傾向でした。「この傾向」を科学的に把握し、芸術的に形成すること、それが彼の使命だったのです。自然はそれ自体の働きを形成する中で、「あたかも袋小路に行き着くかのように」その詳細へと入り込みます。私たちは、ちょうど数学者があれこれの三角形に焦点を当てるだけではなく、あらゆる可能な三角形の根底に横たわる原則にいつも注意するように、自然の傾向が何の障害もなく自己実現していたとしたら生じたであろうことがらに戻って行かなければなりません。本質的な問題は、自然が「何を」創造したかではなく、「いかなる原則に従ってそれを創造したのか」なのです。そのとき、やるべきことは、その原則をそれ自身の内的な傾向に適うように発展させるということであって、無数の偶発的なことがらに左右されながら自然の中でそれが生じたようにそれを発展させるということではありません。芸術家の使命は「ありきたりのものから高貴なものを、不格好なものから美しいものを発展させる」ということなのです。ゲーテとシラーは芸術をその深遠さにおいて包括的に把握しました。美しさとは「秘密の自然法則が顕現したものであり、もし、それが現れなかったとしたら、永久に我々から隠されたままになっていたようなものです。」(散文の中の韻)彼が次のように述べたとき、それは空虚な言葉などではなく、深く内的な確信であったということに気づくには、その詩人の「イタリア紀行」を少し覗いてみるだけで十分です。偉大な芸術作品とは、同時に、「真の自然法則」にしたがって、人間によって生み出された最も崇高な自然の作品です。ここにあるのは、あらゆる気まぐれ、あらゆる空想が抜け落ちた、必然であり、神なのです。」(1787年9月6日)。彼にとって、自然と芸術が共通の源泉を有していることは明白でした。彼はギリシャ芸術について次のような調子で述べています。「それらは自然そのものと同じ法則、私がその足跡を追っているのと同じ法則にしたがって生じた、という気がしてならない。」そして、シェークスピアについては、「シェークスピアは世界精神と同類だ、彼は世界がそうするように世界を完全に理解しており、両者には隠されたものは何もない。けれども、事が起こる前に、そして、しばしば起こった後でさえ、秘密にしておくのが世界精神のやり方であるとすれば、その詩人にはその秘密を暴露するつもりがある。」と述べています。ここでもう一度、思い出していただきたいのは、詩人がカントの「判断力批判」のお陰で過ごした「楽しい時間」についてです。その時間が過ごせたのは、彼がそこで、芸術の創造と自然の創造とが同様に扱われており、審美的な判断能力と目的論的な判断能力がお互いに照らし合っているのを見た・・・。詩という芸術と自然の比較研究の両方が非常に密接に関連しており、同じ判断能力に左右されると考えられているのが嬉しかったという事実によります。ゲーテは、彼の随筆「たったひとつの天才的な言葉による重要な前進」の中で、全く同じ意図をもって、参加型の彼の客観的な「詩作」と客観的な「思考」を同列においています。ですから、芸術と科学はゲーテにとって同じように客観的なものとして現われます。ただ、それらの形態だけが異なっているのです。両方が「ひとつの」存在の表現として、「単一の」発展におけるいくつかの必然的な段階として現われます。芸術あるいは美を人間進化の全体像から「遠く離れた」孤立した位置に追いやるようなあらゆる観点は彼に対してひどく反発します。ですから、彼は言います「審美的な領域で美についてのアイデアを語るというのはよくないことです。そうすることで、私たちは美を孤立させ、それを別個のものとして考えることができなくなります。(散文の中の韻)型は、私たちがそれを目に見える形で把握することを許される限りにおいて、「知」という最奥の基盤に、つまり、ものごとの本質的な特質に基づいています。(「単純な自然の模倣、マンネリズム、型」)「ですから、芸術は知ることに基づいています。」科学は、世界がそれにしたがって構成される秩序を思考の中で再創造するという使命を、芸術は、その秩序についてのアイデアを個別の詳細において発展させるという使命をもっています。芸術家は手に入れることができるあらゆる世界の法則性を彼らの作品の中へと取り込みます。ですから、芸術作品は世界のミニチュアとして現われるのです。」。ゲーテ的な傾向を持つ芸術が科学によって補われなければならない理由はそこにあります。芸術であっても、それはひとつの知の形態なのです。ゲーテが実際に望んでいたのは科学でも芸術でもありません。「彼が望んでいたのはアイデアだったのです。」彼は、たまたまそれが彼に自らを提示するその仕方によって、それを記述したり、描写したりしました。ゲーテは、世界精神の働きを明らかにするため、それと自らを連合させ、芸術あるいは科学という媒体を通して、必要なことは何でもしました。ゲーテの本性の中に横たわっていたのは、一面的な芸術的努力でもなく、一面的な科学的努力でもなく、むしろ一瞬たりとも休むことのない衝動、「あらゆる種子、あらゆる活動的な力を見よ」(ファウスト384行)という衝動だったのです。とはいえ、これによってゲーテが哲学的な詩人になることはありません。何故なら、彼の詩作は、思考という遠回りをして、それらの感覚知覚可能な形成へと導かれるのではなく、むしろ、あらゆる生成の源泉から直接流れ出しているのですが、それはちょうど彼の科学的な探求が詩的な想像力によって浸透されるのではなく、アイデアの直接的な知覚にかかっているのと同じです。ゲーテは哲学的な詩人ではありませんが、哲学的な観察者にとって、彼の基本的な傾向は、それでも哲学的に見えます。このように、ゲーテの科学的な仕事に哲学的な価値があるかどうかという問題は全く新しい形態を取ります。私たちがこれらの仕事に関して知っているものから、それらの根底に横たわる基本的な原則を導くかどうか、ということが問題になります。それらの前提からゲーテの科学的な主張が流れ出てくるようにするには、私たちは何を仮定すればよいのでしょうか。私たちの使命は、ゲーテによっては明らかにされないまま残ったものを明らかにするということですが、そのことによってのみ彼の観点を包括的なものとすることができるでしょう。 (第8章了)
2024年05月31日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説並びに精神科学(人智学)の基礎(GA1)第7章 ゲーテの科学的著作集の編集 佐々木義之訳 自然科学に関するゲーテの著作集を編集する責任者としての私を導いてきたアイデアは、詳細なことがらの根底に横たわる壮大なアイデアの世界を示すことによって、それらの探求を生き生きとしたものにするということでした。私は、もし私たちが深く包括的なゲーテの世界観への十全たる理解をもってそのあらゆる主張にアプローチするならば、それらはまったく新しい意味で、実際にその真の意味を獲得すると確信しています。彼の時代以降、著しく進歩した現代の科学から見れば、彼の科学的な主張の多くが取るに足らないもののように見えることは否定できません。けれども、ここではそれが問題なのではなく、そのような主張が「ゲーテ自身の観点という文脈の中で」有している意義こそが重要なのです。科学的な疑問は、その詩人が立っていた精神的な高みにおいては、より大きな強度を帯びたものとなります。しかし、そのような疑問なしに、科学はあり得ません。「ゲーテが自然に問うた疑問とはどのようなものだったのでしょうか。」それこそが重要な問題なのです。彼がそのような疑問に答えたかどうか、どのように答えたかについては二次的なものと考えられます。もちろん、今日、私たちが用いることができる、より充実した手法や経験をもってすれば、彼が問うた疑問に対して、より十分な答えを見出すことも可能でしょう。けれども、私の解説が意図しているのは、私たちが用いることができる、より大きな手法をもってしても、彼が示した道を進む以上のことはできないということです。私たちがとりわけゲーテから学ぶべきこととは、「どのようにして自然に問いかけるか」です。私たちは、単に、ゲーテの時代以降に再発見され、今や、私たちの世界観にとって重要な位置を占めるようになった様々な観察を彼の業績に帰することで、何が最も重要なのかを忘れてしまっています。ゲーテの場合、研究結果は彼がそれによってそこにたどり着いた方法ほどには重要ではないのです。彼は「あえて発せられる意見は、チェス盤の上で動き回る駒に似ている、それらは取られるかも知れないけれども、勝利されることになるゲームを開始したのだ」と適切にも自分自身で述べています。ゲーテは自然と完全に調和した方法を発展させました。彼は、彼が用いることができる手法を用いて、その方法を科学に導入しようとしました。彼の探求の個々の成果は科学の進展に伴って変化させられてきたかも知れませんが、そのようにして導入された科学のプロセス自体は科学にとっての変わらぬ進歩であり続けています。これらの観点は、当然のことながら、編集された著作の構成に影響を及ぼします。私はこの素材を構成するに当たって通常のやり方から出発したので、何故、最も賢明と思われる次のようなやり方を採用しなかったのかと問うことは許されるでしょう。すなわち、第1巻に一般科学、第2巻に植物学、鉱物学、そして気象学、そして、第3巻に物理学を配置することによって、最初の巻には一般的な観点が含まれ、他の巻にはこれらの基本的なアイデアが個々に洗練されたものが含まれるというようにしなかったのかということです。これは非常に魅力的ではありますが、私はそのような構成にするつもりは全くありませんでした。そのようなやり方をすれば、私は私の目的、つまりゲーテの比喩に帰すれば、ゲームにおける最初の動きがその根底に横たわる戦略を明らかにするという目的を決して達成できなかったでしょう。意識して一般的な概念から始めるということほどゲーテにとって無縁なものはありません。彼はいつでも「実際の事実」から始めて、次にそれらを比較しアレンジしました。そのようなことを行っている間に、その事実の根底にある基本的なアイデアが彼には明らかとなりました。あのよく知られた「ファウスト」のアイデアに関する彼の言葉に基づき、ゲーテの創作活動の背後にある駆動力はアイデアではないと主張するのは非常に間違っています。ものごとをよく考えてみるとき、本質的ではない偶発的なことがらを除去した後、残ったものが彼にとっての彼の言葉の意味での「アイデア」だったのです。ゲーテが用いた「方法」は、彼がアイデアへと上昇するときでさえ、いつでも純粋な経験に基づいていました。彼は主観的な要素が彼の探求に潜り込むことを決して許しませんでした。彼は単に偶発的な現象を解き放ち、それらのより深い基盤へと進むことができるようにしただけです。彼の主観は、その対象の最奥の本質を明らかにするような仕方で、それを説明することだけを意図していました。「真実とは神のようなもので、直接には現れません。むしろ、その顕現を通して理解されるべきものです。」人は、「真実」を見ることができるような仕方で、それらの顕現を結びつけなければならないのです。真実あるいは「アイデア /ドイツ語でIdee(観念。理念としてのイデア若しくは着想)」(プラトンの哲学*真の認識とは「想起」(アナムネーシス)にほかならない)は、私たちが直面する事実の中に既に含まれているのですが、観察においては、それを覆い隠しているベールが取り除かれなければなりません。真の科学的な方法とはそのベールを取り除くことなのです。ゲーテはこの道を取りました。もし、私たちが彼の心に十分に近づきたいと思うのであれば、彼に従わなければなりません。言い換えれば、私たちはゲーテの植物学から始めなければなりません。何故なら、彼はそこから始めたからです。豊かな内容が初めてそのアイデア、それは私たちが後に一般的かつ方法論的な問題に関する彼の随筆の要素として見出すことになるアイデアを彼に現わしたのは、そこにおいてだったのです。もし、私たちがそれらの著作を理解したいのであれば、私たちはまず私たちの心をその内容で満たさなければなりません。方法論を扱っている随筆はゲーテが歩いた道をたどる労を取らない人たちにとって、単に紡ぎ出された考えに過ぎません。物理的な現象に関する研究はゲーテの自然観の結果として生じたものと言えます。 (第7章了)記:ゲーテの社会的評判としてベートーヴェンがよく取り上げられていますが、真相は如何なものでしょう。参考画Ⅰ:Goethe and Beethoven-01参考画Ⅱ:Goethe and Beethoven-02参考画Ⅲ:Zur Farbenlehre(Goethe and Newton)人気ブログランキングへ
2024年05月30日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説並びに精神科学(人智学)の基礎(GA1)第6章 ゲーテの認識方法 佐々木義之訳 1794年6月にヨハン・ゴットリープ・フィヒテは彼の「科学理論」の最初の部分をゲーテに送りました。参考画:Johann Gottlieb Fichte-01 6月24日にはゲーテは此の著名な哲学者に次のように応えています。「私は哲学者なしで済ますことなど決してできませんでしたが、同時に、彼らとの一体感を持つことも決してできませんでした。もし、貴方が私を哲学者たちとの最終的な和解に導くことになるならば、私としましては、途方もない恩義を貴方に負うことになるでしょう。詩人がフィヒテに求めていたもの、以前はスピノザから得ようとし、後にはシェリングやヘーゲルに求めることになったものとは、彼自身の思考方法に完全に対応する哲学的な世界観でした。けれども、彼が出会った哲学的なアプローチのどれもが彼を完全には満足させませんでした。私たちは哲学的な観点からゲーテにアプローチしようとしていますから、このことは私たちの使命をよけいに難しくします。もし、彼が科学的な立場を求めていたならば、私たちはそれに言及することもできたでしょう。しかし、そうではありませんでした。したがって、私たちの使命は、私たちが入手可能な詩人の作品の全てを考慮しながら、その哲学的な中心を見極め、その際立った特徴を描き出すということです。この問題への正しいアプローチとは、ゲーテやシラーがその生涯を捧げたのと同じ「最高の」人間的な要求を満足させようとしてその道を歩んできたドイツ理想主義哲学を基盤とする思考の系譜に従うことであるというのが私たちの主張です。それは同じ文化的な運動から生じたので、今日一般に科学を支配している観点よりもはるかにゲーテに近いものがあります。この哲学から始めることにより、ゲーテの詩や科学に関する作品を導きだすことができるような観点をそこから構築することができるでしょう。科学における今日の傾向に基づいてそれを行うことは決しできません。それは、今日、私たちがゲーテの特質に生来備わっていた考え方から遠く隔てられているからです。実際、私たちがあらゆる文化的な領域で進歩したことは確かですが、それが「深さ」方向への前進であったと主張することはほとんどできないでしょう。結局のところ、ある時代の重要性は発達の深さによってしか測ることができませんが、私たちの時代は真の人間的な深化の可能性をことごとく拒絶したという事実によって最もよく特徴づけられる、と言いたくなります。私たちはあらゆる分野で気弱になってしまいましたが、それは特に私たちの思考と意志においてそうなのです。思考に関して言えば、際限なく情報は集積されますが、それを包括的な現実に関する科学的な観点という文脈の中に据える勇気がありません。一方、ドイツ理想主義哲学が科学的ではないといって責められるのはそのような勇気を持っていたからです。今日、人々は感覚によって「知覚」したいのであって、「思考」したいとは思っていないのです。思考への信頼は全く失われてしまいました。世界と人生の謎に貫き至る力は思考にはないと考えられているのです。人々は存在の大いなる謎に対する解決策なしに生きることに完全に甘んじており、唯一可能であると考えられているのは、「感覚的な経験によって与えられるものを体系化する」ということだけなのです。この観点は、はるか昔に克服されたと信じられている立場へと私たちを導くということが忘れられています。よく考えてみてください、あらゆる思考を拒絶し、感覚的な経験だけに頼るということは、宗教に見られる啓示に対する盲目的な信仰と同じものです。いずれにしても、そのような信仰は、お仕着せの真実として教会から与えられるものを信じなさいと言われることに基づいています。それらのより深い意味にまで貫き至ろうと努力したとしても、思考は「真実にアプローチする」能力、それ自身の力によって世界の深みへと貫き至る能力を欠いているのです。感覚的な経験に限定された科学は思考に何を要求するでしょうか?事実に基づく情報の考察とその説明、そしてその整理です。この科学は世界の中心にまで浸透する思考の独立した力を否定します。神学は人の思考に対して教会による支配への盲目的な服従を要求する一方、科学は感覚による支配への盲目的な服従を要求します。どちらも、独立した、深く洞察する思考には何の重きも置きません。経験主義的な科学が忘れているのは次のようなことです。つまり、何千何万という人々がある感覚知覚可能な事実を観察しながら、それについて何も特別なことに気づくことなく、そのそばを通り過ぎた後、誰かがそれを見て、ある重要な法則がその中に働いているのに気づく、というようなことがありますが、私たちはこれをどのように説明すればよいのでしょうか?その発見者はそれ以前にやって来た人たちとは異なる仕方で見ることができたはずなのです。その発見者は異なる目でその事実を知覚し、その事実を他の事実に「いかに」関係づけるかについて、あるいは、そこでは何が重要で何が重要ではないかについて、ある一定の考えを持っていた、ということです。そのように、科学的な発見を行う人たちは「思考」を通して彼らの経験を理解し、秩序づけますが、その結果、他の人たちに比べてより多くを見ることになるのです。「彼らは精神の目をもって見るのです。」あらゆる科学的な発見の基礎には観察者が正しい思考によって導かれるような仕方で観察できる状況が横たわっています。「考える」ということが観察を導くのは当然ですが、探求する人がそれへの信頼を失い、その適用範囲と重要性を理解しないのであれば、そうはいきません。何の助けもなく現象の世界をさまよい歩く経験的な科学はその経験へと貫き至る思考のエネルギーを欠いています。そのため、それにとって世界は個別的なものの混乱した多様性となります。今日、人々が認識の限界について語るのは、思考の使命を理解し損なっているからです。彼らは自分たちが「何を」達成したいのかについて、明確な観点を欠いており、それを達成する能力に疑いを抱いています。今日、誰かがやってきて存在の神秘に対する解答を私たちに示したとしても、私たちはそれをどうしてよいか分からず、それから得られるものは何もないことでしょう。私たちの意志や行為についても全く同様です。人々は実際に達成することができる明確な人生の使命を自分たちに課すことができないでいるのです。彼らは不明確で漠とした理想について単に想像するだけです。そして、彼らは彼らがほとんど思い描くこともできないようなものを達成できないからといって不平を言います。今日の厭世主義者たちに、彼らが実際何を望んでおり、何が達成できないからといって絶望しているのか聞いてみるとよいでしょう。彼らには何の考えもありません。彼らの本質は問題の中に絡め取られ、いかなる状況にも対処できず、いかなるものにも満足することがありません。誤解しないでいただきたいのですが、私は人生における瑣末な喜びに満足し、何らより高次のものに憧れることのない表面的な楽観主義を奨励したいのではありません。私たちのあらゆる行為を麻痺させる状況、私たちがそれを変えようとして無駄な努力をしている状況へのきわめて悲劇的な依存に対して、苦痛に満ちた意識を有する人々を責めるつもりもありません。苦しみは楽しみの先駆けであることを忘れないようにしましょう。子供たちの繁栄という母親の楽しみは、その楽しみが心配や苦しみ、そして努力によって勝ち取られたものであればあるほど、より甘美なものとなります。実際、考える人であれば誰であれ、外的な手助けによって差し出されるどんな幸せも拒否しなければならないでしょう。何故なら、私たちは、結局のところ、努力せずに手渡される賜物によっては本当の幸せを経験することはできないからです。もし、創造主が幸せを遺産として人間に付与するつもりであったのであれば、そもそも私たちを創造しなければよかったのです。そうすればもっとうまくやれたはずです。人間の尊厳が高まるのは、私たちが創造したものがいつも無残にも破壊されるときなのです。いずれにしても、その結果、私たちは絶えず新たに構築し、創造しなければなりません。私たちの幸せは私たちの行為の中に、私たちが達成するものの中にあります。顕現された真実は苦労せずに与えられた幸せのようなものです。私たち人間の尊厳は、感覚的な経験や顕現によって導かれるかどうかではなく、私たち自身で真実を追い求めるかどうかにかかっています。一度このことが完全に認められるならば、顕現された宗教は自らの役割を果たしたことになります。もはや人々は神の顕現を求めたり、いくらでも与えられる祝福を望んだりはせず、彼ら自身の思考を通して得られる認識や彼ら自身の努力を通して得られる幸せを欲することでしょう。私たちにとって、より高次の力が私たちの運命をより良い方向に導こうとしているのか悪い方向に導こうとしているのかはどうでもよいことです。私たちは自分で自分たち自身の道を決定しなければなりません。神性についてのもっとも高められた考えとは、それでもやはり神なのですが、それは、人間を創造した後、完全に世界から手を引き、全面的に私たち自身の工夫に委ねる神なのです。 感覚による知覚能力を超えた知覚能力を思考に帰する人であれば誰であれ、この能力は感覚知覚可能な現実を超えた対象に狙いを定める、ということもまた認めなければならないでしょう。思考の対象は「アイデア」です。私たちの思考が、あるアイデアを理解するとき、それは宇宙的な存在の根本と一体化します。外的な世界の中で生き生きと活動するものが人間の精神の中に入ってきます。すなわち、人間はその最高の力を持って、客観的な現実と「ひとつになる」のです。「外的な現実の中にアイデアを見ることは、人間の真のコムニオン(聖体拝領、交わり)なのです。」。思考のアイデアに対する関係は、目の光に対する、耳の音に対する関係と同じです。すなわち、「知覚器官」なのです。この観点は、現在、完全に相容れないものと考えられている二つのアプローチ、科学的な世界観としての経験主義的な方法と理想主義を統合するものとなります。今日、経験主義的な方法を受け入れるということは必然的に理想主義の拒絶につながると信じられています。これは確かな真実ではありません。もちろん、もし、私たちが、客観的な現実の唯一の知覚器官は感覚であると信じているとすれば、私たちの結論はそうなるでしょう。感覚が提供するのは機械的な法則へと還元できるようなことがらの間の関係だけです。それに基づけば、機械論的な世界観が唯一のものとなります。しかし、この観点は、機械論的な法則に還元することが「できない」ような、他の同様に客観的な現実の要素を単に無視するという間違いを犯しています。「客観的に」与えられるものは、機械論的な観点が主張するような「感覚に」与えられるものとは決して一致しません。感覚に与えられるものは、与えられるものの半分に過ぎません。他の半分は「アイデア(*ルドルフ・シュタイナーの語彙:観念、理念)」から成っています。それはまた経験、それは確かに、より高次の経験での対象でもあり、思考器官によってアクセスすることができるものです。ですから、アイデアは帰納法によっても達成することができます。現代の経験主義的な科学は全く正しい方法に従っています。つまり、その方法は与えられたものに忠実に従うのですが、受け入れられない規定をつけ加えるのです。つまり、その方法は感覚知覚可能で事実に即した結果に導かなければならないという規定をつけ加えます。私たちは、「いかにして」私たちの観点に到達するかという問題に自らを限定するのではなく、むしろ、初めから、これらの観点の本質とは「どのような」ものかということを決定します。唯一満足できる科学的なアプローチとは、その結果として、アイデアへと導く経験主義的な方法です。それは理想主義なのですが、漠然と想像された「普遍的な統一性」を追及するような種類のものではなく、今日のきわめて正確な科学が事実を追い求めるときと同じ経験の確かさをもって、現実に関する具体的なアイデアを把握しようとする理想主義なのです。私たちは、これらの観点をもってゲーテにアプローチすることにより、彼の存在の正に本質へと突き進んでいると信じています。私たちは理想主義を掲げているのですが、私たちがその発達の基礎とするのはヘーゲルの弁証法ではなく、より高次の、より純化された経験主義です。エドゥアルト・フォン・ハルトマンの哲学もまた同様の観点に基づいています。彼は、理想的な統一体が、実際の形態の中で、内容に満たされた思考に自らを譲り渡すときのその統一体を自然の中に追い求めました。彼は単なる機械論的な世界観や外観にしがみつく超ダーウィン主義を拒絶しました。科学において、彼は具体的な一元論を打ち立て、歴史や美学においては、具体的なアイデアを追求しました。このすべてにおいて、彼は経験論的、帰納的な方法論に従いました。ハルトマンの哲学が私のそれと異なっているのは、厭世主義の問題、そして、彼の「無意識的なるもの」を形而上学的に強調する点に関してだけですが、これについては後で議論することにします。ハルトマンが厭世主義の「基礎」として提示するもの、世界には何も満足すべきものはなく、不満足はいつも楽しみよりも多いという観点は、正に、私たちが人間として、私たちの「幸運」と呼ぶところのものです。彼が提供するものは、私にとっては、幸福を追求することに意味はないということの証明に他なりません。私たちは確かに、あらゆるその手の努力を放棄し、私たちの理性により設定される理想主義的な使命を無私の態度で達成することに私たちの人生の目的を見出さなければならないでしょう。このことは正に、私たちは「創造」という絶えざる活動の中にのみ自分たちの幸せを追究すべきであるということを意味しているのではないでしょうか。自分たちの運命を何とかして成就しようとする人々とは、活動する人々、実際、その活動において鷹揚な人々、何ら報酬を望まない人々をおいて他にありません。私たちの活動に対する報酬を望むことは馬鹿げたことです。つまり、真の報酬などあり得ないのです。ハルトマンはこのような洞察の上に立脚すべきです。彼が指摘しなければならないのは、そのような状況下で、私たちの活動に対する動機づけは実際にはひとつしかあり得ないということです。望む目標を達成する見通しが崩れ去るやいなや、その動機づけとなる力はその対象自体への無私の献身以外にはあり得ません。つまり、「愛以外にはあり得ないのです。」、愛から生じる行為のみが道徳的であり得ます。科学においては、私たちを導く星は「アイデア」でなければなりません。私たちの行為においては、それは「愛」でなければなりません。そして、このことは私たちをゲーテに引き戻します。「活動的な人間は正しいことを行うことに関心があるのであって、正しいことが起こるかどうかにではない・・・。生きるという行為には、存在するために自分たちの存在を諦めるということが含まれる。(散文における韻)」。このことに関しては、私はゲーテやヘーゲルを研究することによってのみ私の世界観に到達したわけではありません。私は、機械論的、自然主義的な世界観から始めたのですが、そのとき気がついたのは、強化された思考はそのような見通しを受け入れがたいものにする、ということです。私は厳密な科学的手法に従って前進しながら、客観的な理想主義が唯一満足すべき世界観であることを見出したのです。私の「認識論」は、いかに思考が、それがそれ自身を理解し、それ自身と矛盾しないときにこの観点に到達するかを示しています。そして、私は、この客観的な理想主義が、その根本的な洞察において、ゲーテの世界観に十分に浸透するということに気づきました。私自身の観点は、実際、何年にもわたって、私のゲーテ研究と平行して発展してきました。そして、私の基本的な見通しは「原則として」ゲーテの科学的な仕事とは決して衝突しないということが分かりました。もし、私が、第一に、私の観点をそれが他の人たちの中にも生きるような仕方で発展させることに、そして、第二に、これは確かにゲーテの立場であるということを彼らに確信させることに、少なくとも部分的にでも成功していたならば、私の使命は達成されたと考えられます。 (第6章了)参考画:ドイツ国民に告ぐJohann Gottlieb Fichte-02人気ブログランキングへ
2024年05月29日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説並びに精神科学(人智学)の基礎(GA1)第5章 ゲーテの形態論についての結語 佐々木義之訳 ゲーテの変容理論に関する以上の考察の最後に当たり、言及する必要があると感じられた観点を振り返るとき、思想界の様々な学派を代表する著名な人物たちの多くは私の観点とは反対の観点を分かち合っていると認めざるを得ません。彼らのゲーテに対する立場は私には明白であり、私たちの偉大な思想家であり詩人を描出するという私の試みに対する彼らの評価も完全に予見可能です。ゲーテの科学的な試みに対する意見は二つの正反対の陣営に分かれています。ヘッケル教授に率いられた現代の一元論者たちはゲーテをダーウィン主義の予言者と見ています。つまり、有機的な世界に関しては、彼らと同様の、つまり、無機的な自然の中に働くのと同じ法則によってそれは支配されているという考えを有しているものと見ています。ただ、ゲーテに欠けていたのは自然淘汰の理論であり、それによってダーウィンは一元論的な世界観のための「基礎」を与え、進化論を科学的な確信のレベルにまで引き上げたのだと彼らは言うでしょう。この観点に対抗する別の観点は、ゲーテの元型についてのアイデアを一般的な概念、あるいは、プラトン哲学の意味でのアイデアに過ぎないと見ます。ですから、彼らは、ゲーテの生来の汎神論が進化論を連想させる様々な主張を彼にさせたのであって、究極の「機械論的な基礎」にまで貫き至る必要性を彼は全く感じていなかった、したがって、現代的な意味での進化論をゲーテに帰すことはできないと主張します。ゲーテの観点に関して、いかなる独断的な立場も取ることなく、純粋にゲーテ自身の特質とその精神全体に基づいてそれを説明しようとする私の試みは、これら二つの立場のいずれもが、それらのゲーテに対する評価への貢献がいかに重要であったとしても、自然についての彼の観点を全体として正しく説明しているとは決して言えないということを明らかにしました。最初の観点について言えば、ゲーテは、有機的な自然を説明する試みにおいて、有機的な世界と無機的な世界の間には越え難い障壁があるとする二元論的な論法に反対したと主張する点で確かに正しいと言えます。しかし、ゲーテが有機的な自然は理解可能であると主張するとき、それは、その形態と現象が機械論的に説明できるという理由からでは決してありません。むしろ、それらがその中に存在するところのより高次の文脈は、私たちの認識にとって、実際に近づくことができるものであるということに気づいたからこそ、彼はそのように主張したのです。事実、彼は宇宙を一元論的な仕方で、つまり、そこから人間が排除されることは決してないようなひとつの分かち難い統一体として思い描いていましたが、彼がこの統一体の「内部に」それら自身の法則に従う段階にあるものを見分けることができると見ていたのは、正にその理由からだったのです。ゲーテは、若い頃でさえ、この統一性を「画一的なもの」として思い描くような傾向、有機的な世界が―実際、自然の中でより高次の段階で現われるものであれば何であれ―無機的な世界の中で働く法則によって支配されていると考える傾向を拒絶していました。この拒絶は後に、有機的な自然を理解する手段としての先験的な知覚による判断の正当性を仮定し、無機的な自然を理解する推論的な知性からそれを区別することへと彼を導きました。ゲーテは世界をそれ自身の説明原則を持つそれぞれの環からなる環と考えていました。現代の一元論者たちは、たったひとつの環、無機的な法則に支配される環だけを認めます。第二の観点は、ゲーテにおいて私たちが扱っているものは現代の一元論とは何か異なるものである、ということを認めます。しかし、この観点を代表する人たちは、科学が無機的な自然を説明するのと同じ方法で有機的な自然を説明しなければならないと信じており、そのため、ゲーテのような観点を前に恐れをなし、彼の探求をより綿密に見ることには何の意味もないと考えているのです。したがって、ゲーテによる高次の原則は、どちらの陣営からも、決して「完全に」有効なものとは考えられていません。そして、これらの原則こそが彼の探求における傑出した要素となっているものなのです。ゲーテの探求におけるいくつかの「細部」を訂正する必要があることが判明したとしても、その深遠さを十分に認識している人たちにとって、それらの原則の重要性が失われることはありません。ですから、ゲーテの観点を解説しようとする人に義務としてかかってくるのは、ゲーテ的な自然の見方において「中心的な」ものに対する注意を引くということであって、何か特別な科学の領域における彼の発見の詳細に関して、批判的な評価にとらわれることではありません。私は、そのような使命を果たそうとしてきた中で、私にとって最も残念な誤解、すなわち純粋な経験論者たちからの誤解を受ける可能性に直面することになりました。私が言っているのは、その相互関係を事実として示し得る有機体(*自らを経験的に提示する物質)のあらゆる側面を探究し、今日、有機的な世界の基本的な原則に関して公に問いかけているような人たちです。それらと私が提示するものとは関係がなく、彼らに反対することもあり得ません。逆に、私の希望の一部は経験論者たちの上に打ち立てられます。と申しますのも、正にすべての道が彼らには開かれているからです。彼らはゲーテの主張のいくつかを正すことができる人たちです。何故なら、実際的な面では、彼はときとして判断を誤っているからです。この点では、天才といえどもその時代の限界を克服することはできません。とはいえ、彼は原則の領域においては基本的な観点に到達しており、その観点の有機的な科学に対する重要性は、ガリレオの基本法則の機械論に対する重要性と同じです。私はこの事実を確かなものにするという仕事を自分に課しました。私の言葉に確信が持てない人たちにも、少なくとも、私が意図していた問題、それは、ゲーテの科学的な著作を彼の特質全体から説明し、私にとって示唆的であると思われる確信に表現を与えるということでしたが、その解決に向けて真摯な意図をもって努力したということを認めていただければと思います。そのような仕方でゲーテの詩を説明しようとする試みが、幸いにも成功裏に始められたという事実自体が、彼の作品のすべてを同様のアプローチにより探求し直すためのチャレンジとなります。遅かれ早かれ、そのようなことが起こることは間違いありません。そして、私の後を引き継ぐ人たちが私以上の成功を収めるならば、私にとってこの上ない喜びとなるでしょう。若くして苦闘する思想家や探究者、特に、その観点が、単に幅広いだけではなく、「中心的な」洞察へと直接貫き至るような人々が、私の考察に注意を払い、私が提示しようとしたものをより完全な仕方で提示するために、大挙して後に続いてくれますように。 (第5章了)参考画:Charles Darwin人気ブログランキングへ
2024年05月28日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説並びに精神科学(人智学)の基礎(GA1)第4章 ゲーテの有機形態論に関する著作の本質と重要性 佐々木義之訳 ゲーテの形態論に関する著作の重要性は、それらが有機的な自然を探求するための理論的な基礎と方法論を確立したということにあります。それは「第一級の科学的業績」です。私たちがこの事実を正しく評価するためには、とりわけ無機的な現象と有機的な現象の間の途方もない違いが考慮されなければなりません。例えば、2個のビリヤードのボールが衝突するのは無機的な現象です。もし、1個のボールが静止しており、もう1個がある方向からある速度をもってそれに衝突するならば、静止していた方はある方向にある速度をもって動き始めるでしょう。そのような現象については、感覚に直接与えられるものを概念に変容させるだけで「理解する」ことができます。感覚的に知覚可能なものであって私たちが概念的に把握しなかったものが何もない限りにおいて、私たちはそれを行うことができます。私たちは1個のボールが別のボールに近づいて衝突し、その別のボールが動き出すのを見ます。私たちがこの現象を「理解した」と言えるのは、最初のボールの質量、方向、速度と第2のボールの質量から第2のボールの速度と方向を予測できるとき、言い換えれば、この現象が与えられた条件下で「必然的に」起こるのを見るときです。けれども、このことは、私たちの感覚に現れるものは私たちがアイデアとして仮定するところのものの「必然的な結果」として現れなければならないということを意味しているに過ぎません。その場合、概念と現象は一致すると言うことができます。「現象ではない概念はなく、概念の中にない現象もありません。」を無機的な自然の中で必然的な生起へと導くような条件についてもう少し詳しく考察してみましょう。私たちはここで、無機的な自然における感覚的に知覚可能な生起を決定づける条件は感覚の世界にも属しているという重要な事実に出会います。先ほどの例で言えば、質量、速度、そして方向であり、実際に「感覚」の領域に属する条件が考察の対象となります。他のいかなる条件もその現象を規定しません。感覚にとって直接に知覚可能な要素のみが「お互いにお互いを」決定づけます。ですから、そのような生起の概念的な理解は、単に目に見える現実から目に見える現実を演繹するに過ぎません。空間的、時間的要素、質量、重量、あるいは、光や熱のような感覚的に知覚可能な力は、すべて同じ範疇に属する現象を引き起こします。物体は暖められ、それによって膨張しますが、原因と結果、つまり、加熱と膨張の両方が感覚の世界に属しています。したがって、私たちはそのような生起を把握するために感覚の世界を超えて行く必要がありません。その世界の「内部で」、ある現象を別の現象から演繹しさえすればよいのです。ですから、私たちがそのような現象を説明し、概念的に理解したいのであれば、感覚によって「知覚され」得る要素だけを含めればよいのです。私たちが理解しようとするものはすべて知覚することができます。そこにあるのは知覚されたもの外)と概念との一致です。そのような出来事の中には私たちにとって獏としたままのものは何もありません。私たちは無機的な世界の本質的な特質を引き出し、いかにそれを「それ自体を通して」、それを超えて行くことなく、説明することができるかを示しました。人類が初めて考え始めたのはそのようなことがらの特質についてですから。このことに関してはいかなる疑問もありませんでした。もちろん、彼らは概念と知覚対象との一致へと導く上記の判断過程をいつも辿ったわけではありませんが、先に示したような現象自体の本質的な特質を通してそれらを説明することを決してためらいませんでした。(R.シュタイナーによる注:哲学者の中には、私たちは感覚世界の現象をその根源的な要素にまで辿ることができるけれども、だからといって、私たちが生命の本質的な性質について説明することができる以上にこれらを説明できるわけではないと主張する人たちがいます。このことに関して言えば、これらの要素は「単純」であるそれら自体がより単純な要素からは構成され得ないということを強調しておく必要があります。とはいえ、それらの単純さの中で、それらを導き出したり、それらを説明したりすることができない理由は、私たちの認識能力の限界によるものではなく、それらがそれら自体に依存しているという事実によります。つまり、それらはそれらの全くの直接性において私たちの前に提示され、それら自体で完結し、それらは他のいかなるものからも導き出すことができないということです。)。けれども、「有機的な」領域における現象については、「ゲーテに至るまで」それは真実ではありませんでした。有機体の感覚的に知覚可能な側面、その形、大きさ、色、温度等々は、同じ種類の要素によって決定されているようには見えません。例えば、植物の根の大きさ、形、位置等が、葉や花の感覚的に知覚可能な特徴を決定していると言うことはできません。そうであるならば、そのような物体は有機体ではなく、機械であるはずです。生きた存在の感覚的に知覚可能な特徴は、無機的な自然とは異なり、その他の感覚的に知覚化能な条件の結果として現れることはないということが認められなければなりません。(R.シュタイナーによる注:有機体と機械の差はここにあります。機械において本質的なのは、その部品の相互作用だけです。その相互作用を支配する統合的な原則はその対象自体の中に存在しているのではなく、それを組み立てた人の頭脳の中にある計画として、その外にあります。機械においては、その部品の相互作用を支配する決定的な原則は外的そして抽象的なものであるのに対して、有機体においては、それはその対象自体の中で現実的な存在性を帯びているという事実こそが正に有機体と機械との間の相違点であるということを否定できるのは最も近視眼的な見方によってだけです。ですから、有機体の感覚的に知覚可能な状態は、単にひとつのものが別のものに続いて生じるようにして現れるのではなく、感覚には知覚不能な内的な原則によって支配されているのです。その意味で、この原則は、組み立てる人の頭脳の中にあって心にとってのみ存在している計画以上に感覚にとっては知覚不可能なものです。それは本質的にはそのような計画なのですが、それが有機体の内的な存在の中に入り込んでおり、第三者、すなわち組み立てる人を介して作用するのではなく、直接それに作用するという点で異なっているのです。)実際、知覚に関連した特質が有機体の中に生じるのは「もはや感覚にとっては知覚不能な」何かによってです。それらは感覚的に知覚可能なプロセスの上に浮遊するより高次の統一性の結果として現れます。それは根の形が茎の形を決定づけ、茎の形が葉の形を決定づけ、等々というようなものではありません。そうではなく、これらの形はすべて、それらの上方に存在する何か、感覚によってはその形に近づくことができないような何かによって決定されています。知覚可能な要素はお互いにとっては存在していますが、お互いの結果として存在しているのではありません。それらはお互いによって決定されるのではなく、何か別のものによって決定されています。ここでは、私たちが私たちの感覚をもって知覚するものを他の感覚要素へと還元することはできません。つまり、私たちは感覚の世界には属さない要素を、ものごとについての私たちの概念に含めなければなりません。「私たちは感覚の世界を越えて行かなければならないのです。」。現象を理解しようとするならば、私たちが知覚するものだけでは不十分です。私たちは「統合する原則」を概念的に把握しなければなりません。とはいえ、その結果、知覚されたものと概念との間には距離が生じ、もはやそれらは一致しないように見えます。つまり、概念は観察されたものの上に浮遊し、それらがどのように関連しているのかを理解するのが困難になるのです。無機的な自然においては、概念と感覚的な現実はひとつのものですが、ここではそれらは分岐し、実際、ふたつの異なる世界に属しているように見えます。知覚されるもの、自らを感覚に直接提示するものが、それ自身の中に、それ自身の説明あるいはその本質をもはや担っていないように見えるのです。そのものは自己説明的であるようには見えません。しかし、それはその概念が何かそれ以外のものから取られているからなのです。そのものは感覚にとっては存在しているにもかかわらず、感覚的な世界の法則には支配されていないように見えるために、あたかも自然の中の解決できない矛盾に遭遇しているかのようなのです。それはまるで自己説明的な無機的現象と有機的な存在との間に深淵が横たわっているかのように見え、後者においては、自然法則が何者かの侵害を受けて、正当な法則が突然打ち破られているかのように見えます。実際、科学の世界では、「ゲーテによって」このミステリーが解決されるまで、この深淵は当然のことと考えられていました。それまでは、無機的な自然だけがそれ自身を通して説明可能であり、人間の知識に対する能力は有機的な自然の段階で終わると信じられていたのです。近代哲学の偉大な改革者「カント」がその古い間違った概念を共有していたばかりではなく、何故、人間の心は有機的な実体を決して説明することができないのかということについての科学的な「理由」を探究しさえしたことを考えると、ゲーテが達成したことがどれほどのことだったのかを理解することができます。実際、カントは、先験的な知性が有機的な存在と無機的な領域の両方において、概念と感覚的な現実との間の関係を把握することができる可能性を確かに認めていたのですが、人間がそのような知性を有する可能性を否定していたのです。カントによると、人間の知性は事物の統一性や概念を把握できるけれども、ただ、それはその各部分の相互作用から生じるものとして、抽象的な論理立てを通して達成されるところの分析的に一般化されたものとして、把握できるだけであり、各部分が明確で具体的な(合成的な)統一性の結果、先験的な概念の結果として生じるというような仕方で把握されるのではありません。ですから、彼は、人間の知性が有機的な性質、その活動は全体から各部分へと放射しているのを説明することは不可能であると考えていたのです。カントは言います。「したがって、私たちの知性は、私たちの判断力に関して、奇妙な特質を有している。つまり、知性による認識においては、個別のものは普遍的なものによっては決定されず、したがって、それだけから導くことはできないという特質を。(「判断力批判」段落77)」この記述にしたがえば、私たちが有機的な実体を探究するとき、私たちは、総体(それは単に思考することができるだけ)についての考えと時空の中で私たちの感覚に現れるものとの間の必然的な関係を知る可能性を放棄しなければならないということになります。カントによれば、私たちはそのような関係が存在することを知ることで満足しなければならず、そのような一般的な思考、あるいはアイデアが「いかにして」そこから一歩踏み出しながら感覚的な現実として現われるのかを知ろうとする私たちの論理的な思考を私たちは満足させることができないということになります。私たちは、そのかわり、誰かがあるアイデアにしたがって何らかの合成物・機械のようなものを組み立てるときのように、概念にとっても感覚的な現実にとっても外的な影響によってそのようなものが生じさせられた後、何らの仲介もなく対峙すると考えざるを得なくなります。こうして、有機的な世界を説明する可能性は否定された、実際にはその不可能性が証明されたように見えました。ゲーテが有機的な科学に没頭し始めた頃の状況とはそのようなものでした。彼は、繰り返しスピノザ哲学を読むという最も適切な準備を行った後、これらの研究に取りかかりました。ゲーテが最初にスピノザを取り上げたのは1774年の春でした。彼は「詩と真実」の中で、この哲学者との最初の出会いについて次のように書いています。「私のとんでもない存在を教育するための方法を求めて、世界中を探し回った後、私はついにこの男の「倫理(エチカ)」に出会った。」。その同じ年の夏、ゲーテはフリッツ・ジャコビに出会いました。当時、ジャコビはスピノザの教えに関する彼の1785年の手紙が示すようにスピノザを研究していました。ジャコビこそがゲーテをその哲学者の本質へとより深く導いた人物でした。当時、彼らはスピノザについて大いに議論しましたが、それは、ゲーテにとって「まだすべてが発酵し、泡立ちながら、何らかの最初の影響を及ぼし、そして、またその影響を受けていた」からです。参考画:Baruch Spinoza ほどなく、彼は父の蔵書の中に、ある本を見つけましたが、それはスピノザに対して悪意に満ちた攻撃をしかけ、実際、彼を完全に戯画化するほどにまで歪曲していた著者によるものでした。ゲーテはこの深い思索家を再び真剣に研究することでそれに応えました。彼はスピノザの著作の中に、当時彼が問いかけることができた最も深い科学的な疑問に対する鍵を見出したのです。詩人がフォン・シュタイン夫人とスピノザを読んだのは1784年でしたが、11月4日には彼女宛てに「私はラテン語でスピノザを持ち歩いています、ラテン語ではすべてがずっと明確なのです」と書いています。ゲーテはその哲学者が途方もない影響を彼に及ぼしたという事実をいつでもその全く率直に認めていました。1816年、彼はゼルター宛てに、「シェークスピアとスピノザを除けば、亡くなった魂たちの中で、私に(リンネほど)大きな影響を与えた者を知らない」と書いています。ですから、彼は、彼に最も大きな影響を与えた人物はシェークスピアとスピノザの二人であるとみなしていたのです。彼がその「イタリア紀行」の中でラバターについて書かざるを得なかった点について考えてみるとき、その影響がいかに彼の形態論的な研究において現われているかを最も明確に見て取ることができます。ラバターは、生きた有機体はそれ自体の本性の中には本来存在しない影響を通して、つまり、普遍的な自然法則の侵害を通して生じることができだけであるという当時流布していた観点を主張していました。ゲーテは次のように書いています。「最近、私は、チューリッヒの予言者による嘆かわしくも使徒的で僧侶的な御託宣の中に、次のような愚かな言葉を見つけました。それはすべての生あるものは、それ自身の外にある何かを生き通していると少なくともこのように聞こえました。さて、これは正にそのような異教の宣教師が書きそうなことであって、どんな守護神も彼がそうするようには彼の裾を引き寄せたりはしないでしょう。(「イタリア紀行」1787年10月5日)」。これはスピノザの精神そのものです。スピノザは三種類の知識を区別します。第一の知識は私たちが一定の言葉を聞いたり読んだりするときに生じます。私たちは言及されていることがらを思い出し、それについての心的な像、私たちがものごとを自分で思い描くとき一般に用いるような像を形成します。第二の種類の知識において、私たちはものごとの特徴に関して十分に形成された私たちの心的な像から一般的な概念を創り出します。第三の種類の知識において、私たちは、神の何らかの属性に関する実際の特質についての十分なイメージからものごとの本質的な特質についての十分な知識へと前進します。スピノザはこの種の知識を「直観知/scientia intuitiva」あるいは「見ることにおける知識」と呼んでいます。ゲーテが追及したのはこの最高の種類の知識でした。スピノザが、ものごとはその本質において何らかの神の属性が認識されるような仕方で知られなければならない、と言ったとき、彼が何を意味していたのかを明確にしておきましょう。スピノザのいう神とは世界の思考内容、駆り立て、すべてを支え、すべてを保持する原則(記*スピノザの汎神論及び唯物論は≒物理法則)でした。さて、私たちはこの原則を独立した存在、限りある世界から独立し、自立した存在、限りある存在たちから離れていながらそれらを支配し、活気づける存在であると仮定することによって思い描くことができます。他方、私たちはこの存在について、限りある世界に入ってきたものとして、もはや現世的なものの上方や傍らにいるのではなく、それらの「内部に」存在しているものとして考えることができます。この観点は決してあの太古の原則を否定しているのではなく、それを完全に認めています。ただ、その原則が世界の中に「注ぎ出されている」と見るのです。最初の観点は有限の世界を無限の世界の顕現として見ますが、この無限性はそれ自身の存在の内にとどまり、自分自身からは何も譲渡しません。それは決してそれ自身を越えて行くことはなく、それが顕現する前の状態にとどまります。第二の観点もまた有限の世界を無限の世界の顕現として見ますが、この観点はこの無限の存在がその顕現を通して完全にそれ自身を越えて行った、それ自身の存在と生命をその創造の中に据え、今や、「その創造の中にのみ」存在している、と考えます。さて、明らかに、知識とはものごとの本質を知覚することであり、その本質はそれが限りある存在としてあらゆるものごとの根本的な原則に関与する程度においてのみ存在しているわけですから、知るということは、ものごとの中の無限なるもの(R.シュタイナーによる注:つまり、それらの中にある一定の神の属性)を知覚するということを意味しています。既に記述してきましたが、実際、ゲーテ以前には、無機的な自然はそれ自体を通して説明することができる。それはそれ自体の説明とそれ自体の本性をそれ自体の内に含んでいる。しかし、それは有機的な自然の場合には当てはまらない、と考えられていました。後者の場合、対象の中に現れる本質的な特質あるいは存在はその対象自体の内部に見出すことはできない、したがって、それはその対象の外側に存在すると考えられていたのです。言い換えれば、有機的な自然は最初の観点に、無機的な自然は第二の観点にしたがって説明されました。このように、スピノザは、統合された知識の必然性を証明しましたが、この理論的な洞察を様々に分化した有機的な科学の専門分野の中で証明するにはあまりにも哲学者過ぎました。この仕事はゲーテのために残されたのです。スピノザの観点への彼の確固とした支持は、先に引用された文章によってだけではなく、多くの他の文章によっても示すことができます。彼は「詩と真実」の中で、「自然は永遠不変の法則にしたがって働く、それはあまりにも神聖であって、神ご自身でさえその中の何ものをも変えることはできない」(第16冊、第4部)と書いています。1811年に出版されたジャコビによる本(「神的な事物とその顕現について」)を引用しながら、ゲーテは次のように述べています。「非常に愛すべき友人による本が、自然は神を内に秘めているという命題を発展させているのを見るのは、私にとって非常な喜びであった。私の純粋で深淵な、そして、経験豊富な生来のものの考え方、特に、「自然の中に神を見、神の中に自然を見る」ということを私に教え、それによって私の全存在を基礎づけているこのものの考え方をもってすれば、そのような奇妙で、一面的に限定された主張によって、私が愛し、尊敬してきたこの人間として最も高貴な心から私がいつまでも精神的に遠ざけられているということなどあってはいけないことではないのか。」ゲーテはその踏み出そうとしていた一歩が科学の将来に大きな影響を及ぼすことを十分に知っていました。彼は、無機的な自然と有機的な自然の間の境界を破壊することによりスピノザの考えを推し進めることによって、科学の方向性を大きく変えようとしていることに気づいていました。そのことは彼の随筆「先験的な知覚による判断」の中で表明されています。彼は、人間の知性は有機体を説明することができないことを証明しようとしたカントの「判断力批判」の試みに言及した後、次のような反論を述べています。「ここで著者は確かに神的な知性に言及しているように見えます。しかし、もし、私たちが本当に道徳的な領域において、神、善、そして不死への信仰を通して、より高次の領域に上昇し、原初の存在に近づこうとするのであれば、知的な領域においても、私たちは絶えず創造する自然の考察を通して私たちをその創造に精神的に参加する価値があるものとすることができるのではないでしょうか。いずれにしても、私は、元型的、典型的なものに向かって最初は無意識に、そして、内的な衝動から休むことなく突き進んできて、それがいかに自然法則にしたがって展開するかを示すことにも成功してきました。ですから、今や、ケーニッヒスベルクの聖人その人がそう呼んだような「理性の冒険」へと大胆に乗り出すことを妨げるものは何もありません。」、「本質的なことは、無機的な自然の中でのできごとは、つまり、何か感覚的な世界の中だけで生じるものは、同様に感覚的な世界の中だけで生じる過程が原因となって決定されるということです。原因となる過程が要素m、d、そしてv(運動するビリヤード球の質量、方向、そして速度)、そして、結果となる過程が要素m’、d’、そしてv’から構成されていると想像してみましょう。m、d、そしてvが与えられるときにはいつでもm’、d’、そしてv’はそれらによって決定されるでしょう。原因と結果からなるこのできごと全体を理解するためには、それらの両方を含むひとつの概念によってそれを定式化しなければなりません。けれども、その種の概念はそのできごと自体の中には存在せず、それを決定づけることもありません。それは両方の過程をひとつの共通の表現の中に包含していますが、その原因となることはなく、それを決定づけることもないのです。感覚世界の物体だけがお互いを決定づけます。要素m、d、そしてvもまた外的な感覚にとって知覚可能ですが、この場合、概念は外的なできごとを要約するために働いているだけです。それは何かアイデアや概念としては現実的ではないけれども感覚にとっては現実的なものを「表現して」いるのです。それが表現するこの「何か」とは感覚的な知覚対象です。無機的な自然についての知識は、感覚を通して外的な世界を理解し、概念を通してその相互作用を表現することができる可能性に基づいています。カントは「そのようにして」ものごとを知る可能性を人間が近づくことができる唯一の種類の知識であると見なしていました。カントはこのような考え方を推論的と呼びました。私たちが知ろうとする「もの」は外的な知覚であり、概念あるいはひとつに結びつけるものは単なる手段なのです。けれども、カントによれば、私たちが有機的な自然を理解しようするときには、私たちは理想的、概念的な側面を、何か別のものを表現したり、示唆したりすることによって、その意味を借りてくるものとして把握することはできません。むしろ、私たちは「理想的な要素をそれ自体として」把握しなければならないはずです。それは、空間的-時間的な感覚の世界に発するのではなく、それ自身に発するそれ自身の意味を含んでいなければならないはずです。無機的な世界の場合、私たちの心が単に抽象的に思い描くところの統一性はそれ自身を「それ自身から」形成しながら、それ自身の上に構築しなければならないでしょう。それはそれ以外の対象からの影響によってではなく、それ自身の存在にしたがって形作られなければならないでしょう。自己形成し、自己顕現する実体を理解することからは、カントによれば、人間は排除されているのです。そのような理解を達成するためには何が必要なのでしょうか。私たちはある種の思考を必要としているのですが、それは外的な感覚知覚から導かれたのではない実質を考えに付与することができるような、つまり、感覚によって外的に知覚されたものを理解するだけではなく、感覚の世界から離れた純粋な考えを把握することもできるような思考です。感覚の世界から抽出されたのではない概念、その内容がそれ自身から、そして、それ自身だけから発展するような概念を「先験的な概念」と呼ぶことができます。そして、そのような概念を理解することを「先験的な知識」と呼ぶことができるでしょう。それから導かれるものは明確です。「生きた有機体は先験的な概念を通してのみ理解できる」です。ゲーテは実際にこのような知の可能性を示しました。無機的な世界は、できごとを構成する個々の要素の相互作用、つまり、それらがお互いを決定づけるその仕方によって支配されています。これは有機的な世界には当てはまりません。そこでは有機体を構成する個々のものが別のものを決定づけているのではなく、全体(あるいはアイデア)がそれ自身から、それ自身の存在と調和して、それらを決定づけているのです。この自らを決定づける実体に言及するとき、私たちはそれを、ゲーテの言葉にしたがって、「エンテレキー」と呼ぶことができます。すなわち、エンテレキーとは自らを存在へと呼び込む力です。その結果現れるのが感覚的な存在であり、それらはこのエンテレキー的な原則によって決定づけられているのです。このことから明らかな矛盾が生じるのですが、それは、有機体は自己決定的であり、前提となる原則に従ってそれ自身からその特徴を生じさせるにもかかわらず、感覚的に知覚可能な現実性を有している、という矛盾です。すなわち、有機体はその他の感覚世界の対象とは全く異なる仕方で感覚的に知覚可能な現実性を達成し、その結果、それは不自然な仕方で生じるように見えます。有機体は外的には他の物体と同様、感覚世界の影響にさらされているということもまた理解できます。屋根から落ちるタイルは無機的な対象にも、生き物にもぶつかる可能性があります。有機体は、栄養やその他のものを取り込むことを通して、外的な世界に関連づけられています。すなわち、外的な世界の物理的な状況の影響を受けるのです。もちろん、このことが生じるのは、有機体が空間的-時間的な感覚世界の対象物である限りにおいてのみです。この外的世界の対象物-エンテレキー的な原則が外に向かって現れたもの-は、有機体の外的な表現ですが、それはそれ自身と完全に一致しているようには見えず、それ自身の本性に厳密に従っているようにも見えません。それはそれ自身と調和しているようにも、それ自身の本性に厳密に従っているようにも決して見えませんが、その理由は、有機体がそれ自身の形成的な法則に従っているだけではなく、外的な世界の条件にも左右されていることによります。つまり、それはそれ自身を決定づけるエンテレキー的な法則に従えばそうなるはずのものであるだけではなく、それが依存している外的な要因の影響によりそうなったものでもあるからです。人間理性が関係してくるのはここにおいてです。有機体がそれ自身の原則にのみ対応し、外的な世界の影響を無効にしながら展開するのは「アイデアの領域において」なのです。「いわゆる」有機的なものとは関係のないあらゆる偶発的な影響は完全に抜け落ちます。有機体における純粋に有機的な側面に対応するこのアイデアこそが元型的な有機体であり、ゲーテが言うところの「型」なのです。こうして、型というアイデアの際立った有効性が明らかになります。それは単なる「知的な概念」ではなく、すべての有機体における真に有機的な側面であり、それなしでは有機体ではあり得ないような何かなのです。それは「あらゆる」有機体の中に現れるので、いかなる実際かつ個別の有機体よりもより現実的なものです。それはまた、「いかなる個々の特別な有機体よりも」より十全に、そして、より純粋に有機体の本質を現わします。私たちが型についてのアイデアに至る道は、外的な現実から抽出された概念、内的に活性化していない無機的なプロセスに関する概念に至る道とは根本的に異なっています。有機体についてのアイデアはそのエンテレキーとして有機体内部で活発に活動しています。それは、私たちの理性によって理解される形を取ったエンテレキーそのものの本質なのです。アイデアは経験の総体ではありません。それは経験を「生み出す」ものなのです。ゲーテはそのことを次のように表現しました。「概念とは経験の『総体』であり、アイデアとはその『結果』である-概念を理解するためには知性が必要であり、アイデアを把握するためには理性が必要である。」この言葉はゲーテの元型的な有機体(元型的な植物あるいは動物)に帰せられるべき種類の現実性を説明しています。このゲーテ的な方法論は明らかに有機的な世界の本質を理解するための唯一の方法です。私たちは、無機的な領域においては、多様性に富むその現象はそれを説明する法則性と同じものではなく、何かその外側にあるものとして、この法則性を単に指し示しているに過ぎないのだ、という本質的な状況に気づかなければなりません。私たちが「知覚する」もの―外的な感覚を通して与えられる私たちの知識における物質的な要素―と「概念」―あるいは、私たちが知覚するものの必然性を認識するための形式的な手段―との関係は、それらがお互いをその対象物として必要としている、というようなものです。その関係は、概念は経験されたできごとという個別のことがらの中に生きているのではなく、それらのことがらの相互関係の中に生きている、というようなものなのです。この相互関係は、多様なものをひとつの統合された全体へと結びつけており、与えられた個別のものに基づいていますが、実際、「全体」(あるいは統一されたもの)としては具現化されません。この関係の中では、「個別のもの」だけが外的な存在性の中に―対象の中に―現れます。統一性あるいは概念が「そのようなものとして」現れるのは、現象の多様性を結びつけることをその使命とする私たちの知性の中においてのみです。つまり、概念は現象の「総体」としてその多様性に関係づけられているのです。ここで私たちが扱っているのはひとつの二面性、私たちが「知覚する」多様な現象と、私たちが「思考する」その統一性という二面性です。有機的な自然においては、有機体の多様で個別のものはそのような外的な相互関係を有していません。統一性は知覚されるものの中に現れます。それは多様性と共に存在するようになります。つまり、それらは同じものなのです。現象する総体(有機体)の個々の構成要素の間の関係はひとつの現実となり、もはや私たちの知性の中にだけではなく、対象の中にも具体的に現われます。そして、そこでは、それはそれ自身から多様性を生み出します。概念は、単にその「外側」にある対象物を要約する要素としての役割を演じるだけではなく、完全にその対象物と一体になっています。私たちの知覚対象はもはや私たちがそれを通して思考するところの概念ではありません。私たちは概念そのものをアイデアとして知覚するのです。ですから、ゲーテは有機的な自然を把握する能力を「先見的な知覚による判断」と呼びました。説明するもの、私たちの知識の形式的な要素である概念と説明されるもの、物質的な要素である知覚されたものが同じなのです。ですから、私たちがそれを通して有機的なものを理解するアイデアは、私たちがそれを通して無機的なものを説明する概念とは本質的に異なっています。それは単に与えられた多様性をひとつの要約のようにして結びつけるのではなく、それ自身からそれ自身の内容を生じさせるのです。それは与えられたもの(経験)の結果であり、具体的な現れなのです。(編者による注:したがって、例えば、時計についての概念はその各部分を通して直接的に自らを表現したりはしません。それはそれらの相互作用と目的を知的に理解することによってのみ把握することができます。そこでは、その統一性あるいは目的はその各部分を通して直接的に現れることはありません。有機体の場合は違います。例えば、動物の各器官の形成やその振る舞いの各側面は、その本質的な性質、あるいはアイデアの直接的な表現です。このアイデアは直接知覚され、賦活され、経験を通して深化されます。その意味で、それは経験の「結果」なのです。)。無機的な科学においては、私たちは「法則」(自然法則)について語り、事実を説明するためにそれらを用いますが、有機的な科学においては「型」が用いられるというのはそのためです。「法則」はそれが支配する知覚された多様性と同じものではなく、その上に立つものです。一方、型においては、理想と現実が一体化しており、多様性は全体の中のひとつの点、そして、その点は全体と同じものなのですが、その点から生じてくるものとしてのみ説明することができます。ゲーテの探求における重要な側面は無機的な科学と有機的な科学の間のこの関係がよく洞察されていることです。今日よく言われるように、ゲーテの科学が見通していたのは、有機的なものを無機的な自然を決定づけるために用いられるのと同じ原則(機械的、物理的な範疇と法則)に還元することによって、それらを包括するような統合された自然観を目標とするところの一元論であると言うのは間違いです。私たちはゲーテが一元論的な観点をどのように思い描いていたかを見てきました。有機的なものを説明する彼の方法は彼の無機的な領域に対するアプローチとは根本的に異なるものです。彼は、より高次の原則にかかわることでは、必然的に機械論的な説明が厳密に拒絶されるのを見たいと思っていたのです。(R.シュタイナーによる注:「私たちは重要なことがらが部分の中に集められているのを見ます。建築作品について考えてみれば、いかに多くのことがらが規則的あるいは不規則的な仕方で寄り集まることにより生じるかが分かります。したがって、原子論的な概念は非常に便利なものであり、有機的な生命が含まれる場合にも、それらを適用するのをためらいません。何故なら、正にダイナミックな説明だけが可能な問題を脇に押しやるときにだけ、機械的な説明の仕方が再び時代の趨勢になるのですから。」[散文の中の韻])彼は有機的な現象の原因を無機的なものに求めようとしたキーザーとリンクを批判しています。このゲーテについての間違った観点が生じてきたのは、彼が有機的な自然を理解する可能性に関してカントに対して取った立場によるものです。カントが我々の知性は生きた有機体を説明することができないと主張するとき、それは、それらが機械的な法則によって規定され、物理的あるいは機械的な分野に属しているためにそれらを把握することができないのだ、と言っているのではありません。カントによれば、我々の知性が説明できるのは正に物理的-機械的なものだけなのですが、有機体にとって本質的な存在はそのような性質のものでは「ない」という事実こそがそれを不可能にしている理由なのです。もし、それがそのようなものであったならば、知性は、自分が得意とする分野を通して、それを理解することができたでしょう。もちろん、ゲーテは有機的な世界を機械的な観点から説明することによってカントに反論しようとしていたわけではありません。彼の論点は、我々は有機的な世界の本質である創造的な活動におけるより高次の形態を把握する能力に欠けてはいないということだったのです。今お話したことを考えてみるとき、直ちに分かるのは、無機的な特質と有機的な特質との間には重要な違いがあるということです。無機的な自然においては、「いかなる」プロセスも別のプロセスの原因となる可能性があり、その別のプロセスもまたさらに別のプロセスの原因となる可能性があることから、一連のできごとは決してそれ自体で完結するようには見えません。すべてが連続する相互作用に向けて開かれており、どの対象となる集団も他の集団の影響から自らを隔離することはできません。無機的なできごとの連鎖には始まりも終わりもないのです。ひとつのできごとと次のできごとの間には偶然の関係があるだけです。石が地面に向けて落ちるとき、その影響はたまたまそれがぶつかるものの種類によります。有機体においては、状況は全く異なっています。そこでは統一性が主要な要因になります。自立した生命が持つ、目的へ向かって完成し全体化する力であるエンテレキーは多数の感覚的に知覚可能な発展型から構成されており、それらの中のあるものは最初に、別のものは最後に来なければなりません。それらの間では、あるものの後に別の何かが続くということは一定の仕方で決まっています。理想的な統一性は一定の空間的な関係性の中で、時間の経過にしたがって、一連の感覚的に知覚可能な器官を生み出します。それはある一定の明確に決められた仕方で自然の他の部分からそれ自身を切り離し、その様々な状態をそれ自身から生み出します。ですから、これらのことがらは理想的な統一性から進み出てくる一連の状態の形成を追っていくことによってのみ把握することができます。言い換えれば、「有機体は、それが成ることにおいてのみ、つまり、その発達においてのみ把握することができます。」無機的な物体は完成され、固定されています。それは内的には非動的であり、外から動かすことができるだけです。有機体は決して同じところに留まりません。それは絶えず内から外へと自らを再構成し、変容し続けます。ですから、ゲーテは次のように述べています。「理性はその活動領域を成っているところのものの中に見出し、知性はそれを完成されたものの中に見出します。理性は「何のために」とわざわざ聞いたりはしません。知性は「どこからなのか」を問うことがありません。理性は発達しているものの中に喜びを見出し、知性はすべてをしっかりと把握することによってそれを利用しようとします・・・。理性は生きているものだけを規定します。地理学の関心事である既に成っている世界は死んだ世界です。(詩と散文)」。有機体は自然の中で主に二つの形態を取って私たちの前に現れます。ひとつは植物、もうひとつは動物ですが、それぞれ異なる仕方で現れます。植物は、「現実の」内的生活が欠如している点で、動物とは異なっています。動物においては、この内的生活は感覚や意図的な動き等々として現われます。植物はそのような魂的な原則を有していません。それはその外的な「形態」の発達を越えて行きません。植物においては、エンテレキー的な原則がその形成的な活動をいわばある一点から展開するとき、それぞれの器官は共通の形成的な原則にしたがって形づくられる、という事実を通して現れます。エンテレキーは個々の器官を形成する力として現われます。すべての器官はひとつの形成する型にしたがって形成されます。「ひとつの」基本的な型が変容したものとして現われるのです。つまり、それらはその器官の様々な発達段階における繰り返しなのです。植物を植物としているところのある「特別な形成力」がすべての器官の中で同じ仕方で働いているのですが、その意味で、あらゆる器官は他のすべての器官と、そしてその植物全体と「同じもの」なのです。ゲーテはこのことを次のように表現しています。「私は私たちが通常、葉と呼ぶところの植物の器官は、あらゆる形成の中に自らを隠し、そして、現す、真のプロテウスを隠し持っているということに気づきました。後ろにも前にも、植物はひたすら葉であり、未来の種子と不可分に結びついているために、一方を他方抜きで考えられないほどです。(イタリア紀行、1787年5月17日、1787年7月の報告に含まれる)「このように、植物は、ちょうど複雑なものがあまり複雑ではないものから成り立っているように、いわば多くの個別の植物から成り立っているように見えます。植物の発達過程は段階を経て進行し、その器官を形成します。各器官はすべての他の器官と形成的な原則において同一ですが、外観において異なっています。植物の内的な統一性は外に向かって広がっています。つまり、それは様々な形態において自らを表現するとともに自らを失うことにより、動物がそうするようにはそれ自身の具体的な存在性と一定の独立性を達成するということがありません。そして、それは、生命の中心点として、その器官の多様性に出会い、それらを外界との仲介者として利用します。私たちは今、それらの内的な原則の意味で、そうでなければ同一であったはずの植物器官の外的な差異は何によって生じさせられるのかと問わなければなりません。どうして、「単一の」形成的な原則によって導かれる形成的な法則が、ある場合には葉を生じさせ、別の場合には萼を生じさせるのでしょうか。植物は完全に外的な領域に存在していますから、この差異は外的、空間的な要因に基づいているに違いありません。ゲーテは拡張と収縮の交替こそがそのような要素であると考えていました。植物のエンテレキー的な原則が一点から外に向かって働きながら外的な存在性へと入っていくとき、それは空間的な実体として現れます。形成的な力は空間中で活動し、一定の空間的な形をもった器官を創り出します。さて、これらの力は、収縮期においては、一点に向かって集中し、拡張期においては、展開しつつ、いわばお互いに離れようとして分散します。植物の一生を通して、三つの拡張期と三つの収縮期が交代します。この拡張と収縮の交代こそが、植物の本質的には同一の形成的な力が分化する原因となっているのです。最初、植物のポテンシャルのすべては一点へと収縮し種子の中で眠っています(a)。次に、それは葉の形成という形で出現し、展開し、そして「拡張」します(c)。形成的な力はお互いにますます反発し合うようになりますが、その結果、下部の葉はコンパクトで原初的なものとして現れ(cc’)、上部では肋骨状でぎざぎざになります。そして、密集していたものすべてが分かれ始めます(葉d、e)。以前は連続した間隔によって分離していた(zz’)ものすべてが-萼の形成とともに(f)-茎上の一点へと引き寄せられることによって現れます(w)。これが第2の収縮です。花の花冠では新たな展開あるいは「拡張」が生じます。萼片(f)に比べると花弁(g)はより洗練され、より繊細になっていますが、これは一点へと向かう収縮が弱まることによります。つまり、それは形成的な力の拡張がより強くなることにより生じることができるようになったものです。次の収縮は雄しべ(h)と雌しべ(i)という生殖器官の内部で生じます。そして、新たな拡張は果実(k)の形成の中で始まります。果実から現れる種子(a’)の中では、植物の存在全体が再び一点へと濃縮されます。(R.シュタイナーによる注:果実は雌しべ下部[子房、l]の成長を通して発達します。つまり、それは雌しべの後半の段階ですから、ただ別個のものとして描くことができるだけです。果実の形成は植物における最終的な拡張なのです。その生命は今や、その環境から自らを閉ざす器官―果実と種子―の中で分化したものとなります。果実において、すべては兆候となりました。つまり、それは外見的な兆候に過ぎず、自らを生命から引き離し、死せる産物となったのです。植物におけるすべての本質的な内的生命衝動は種子の中へと濃縮され、そこから新しい植物が生じることになります。種子はほぼ完全なアイデアです。その外見は最小限のものへと還元されています。)。芽あるいは種子が展開あるいは実現したものが植物全体です。それらが十分に展開し、植物を形成するためには、正しい外的な影響だけが必要です。芽と種子の違いは、種子はその基盤として地面を必要としているのに対して、芽は一般に植物上での植物の形成に相当している、ということに過ぎません。種子はより高次の性質を有する個別の植物、いわば、植物形成における循環全体を表現しています。新芽によって、植物はその生命の新しいフェーズを開始します。つまり、それはそれ自身を再生し、その力を濃縮しながら新たなものとするのです。したがって、芽の形成は植生のプロセスを中断することになります。生命を現出するための条件が欠けているときには、植物の生命は芽の中へと引き下がり、再び正しい条件が現れたとき、また発芽させることができます。植生の成長が冬の間に中断するのはこの理由によります。ゲーテはこのことについて次のように述べています。「極寒によって植生の成長が中断されない場合、それがいかに継続するかを観察することは非常に興味深いことです。ここ(イタリア)には芽というものがないので、芽とは何かを理解し始めています。(イタリア紀行、1786年12月2日)」このように、私たちの気候条件では芽の中に隠されているものがそこでは露骨に現れているのです。実際、その中には植物の真の生命が隠されており、ただそれが展開するための条件だけが欠けているのです。交代する拡張と収縮というゲーテの概念は特別に強力な反対に出会うことになります。とはいえ、それらの攻撃のすべては誤解-つまり、これらの概念に対する物理的な原因が見出されない限り、そして、植物の内的な法則がいかにその拡張と収縮の原因となっているかを示すことができない限り、それらは有効ではあり得ないという信念-から出たものでした。しかし、それは馬の先に馬車をつなぐようなものです。拡張と収縮の原因としては何も仮定することができません。他のすべてはそれらから続いており、それら自身が段階を追って展開する変容の原因となっているのです。そのような誤解は、私たちが概念をそれ自身の先見的な形態において理解することに失敗し、それは外的なできごとの結果に違いないと主張するときには、いつでも生じます。私たちは拡張と収縮を原因ではなく、結果としてのみ考えますが、ゲーテはそれらを植物の中の無機的なプロセスの結果として生じるというよりは、むしろ、植物のエンテレキー的な原則が自身を形成する方法であると見なしていました。ですから、彼はそれらを感覚的に知覚可能なプロセスの総計から演繹されるのではなく、内的、統合的な原則そのものから生じてくるものとして見ざるを得なかったのです。植物の生命はその新陳代謝によって維持されています。栄養を地面から吸収する根に近い器官と、他の器官を通過してきた栄養を受け取る器官とでは、それらの新陳代謝に基本的な違いがあります。地面に近い器官はその無機的な環境に直接依存しているように見えますが、他の器官はそれに先立つ有機体の部分に依存しています。ですから、連続した各器官はそれに先立つ器官によっていわば特別に準備された栄養を受け取ることになります。自然は、後から来るものが前に来たものの結果として現れるように、種子から果実へと、段階を追って発達します。ゲーテは「精神的な階梯に沿った発達」として、この段階的な発達に言及しています。私たちが示してきた以上のものは、彼の次のような言葉の中には見当たりません。上部の節はそれに先立つ節から生じ、それによって仲介される樹液を受け取るので、茎のより高いところにある節はその樹液をより洗練され、よりろ過された状態で受け取るに違いありません。そして、それは以前の葉の発達からの利益を享受し、その形態を洗練させ、さらに洗練された樹液をその葉や芽に送り込みます。私たちがこれらのことすべてを理解し始めるのは、それらをゲーテのアイデアという光の下で見るときです。そこで提示されるアイデアは、何らかの個別の植物において現れるような要素、その本来の形態においてではなく、外的な条件に適応した形で現れるような要素ではなく、元型的な植物の特質の中に、元型そのものにのみ対応するような仕方で横たわっているような要素です。当然のことながら、動物の生においては、何か別のものが介入してきます。動物の生命は、外的な特徴の中に自らを失うのではなく、むしろ、自らを分離し、その身体性をもって自らに仕え、その身体的な現れを単に道具としてのみ用います。それは、もはや単に内部から有機体を形成する能力として現れるのではなく、むしろ、有機体のそばにあるものとして、有機体の内部でそれを支配する力として活動しながら、自らを表現します。動物はひとつの自己完結した世界として、あるいは、植物よりもはるかに高次の意味で、小宇宙として現れます。それはそのひとつひとつの器官によって仕えられるひとつの中心を有しているのです。それぞれの口は上手に餌をくわえ、弱く歯のない顎であれ、恐ろしい歯を持つ強力な顎であれ、身体の必要に適ったものとなっています。いずれにしても、あるひとつの器官は他のすべての器官に供するのに完全に適したものとなっています。それぞれの足もまた、長いものであれ、短いものであれ、大いなるスキルをもって、その生き物の衝動と必要に仕えるために動きます。(「動物の変容」より)植物の各器官は植物全体を包含していますが、生命の原則は、明確な中心点としては、どこにもありません。各器官の存在理由はそれらがすべて同一の法則にしたがって形成されているという事実の中にあります。動物においては、各器官は明確な中心点からやってくるように、つまり、その中心点がそれ自身の性質にしたがってすべての器官を形成しているように見えます。こうして、動物の形態はその外的な存在性の基礎を与えるものとなるのですが、それは内部から決定されます。したがって、それらの同じ内的な形成原則によって、動物がどのように生きるかが方向づけられることになります。一方、動物の内的な生活は自由であり、それ自身の内部に限定されません。つまり、それはある一定の限度内で外的な影響に適応することができます。それは外的、機械的な影響によってではなく、型の内的な性質によって決定づけられます。言い換えれば、適応は有機体が外的世界の単なる産物として現れるようになる原因にまではならず、その形成は一定の限度内に制限されています。いかなる神もこれらの限度を超えることができない。何故なら、それらは自然によって尊重されているのだから。そのような限度を通してでなければ、決して完全なるものが達成されることはなかったのだ。(「動物の変容」より)もし、すべての動物が元型的な動物原則にのみ一致していたとしたら、すべて同じ動物となっていたことでしょう。ところが、動物の有機体は各々が一定程度発達する能力を有するいくつかの器官体系へと分化していますが、そのことが異なる進化への基礎を与えているのです。理想的には、それらはすべて同じように重要とはいえ、ある器官体系が卓越し、有機体の形成力の蓄積全体を自らに引きつけるとともに、他の器官から引き離すということがあり得るのです。そのような動物はその器官体系に向けてとりわけ発達したものとして現れる一方、別の動物は別の仕方で発達することになるでしょう。それによって、元型的な有機体が現象世界に入っていくとき、様々な種や属として分化する可能性が生じるのです。この分化の実際の(事実上の)原因はまだ述べられていません。外的な要素がその役割を果たすようになるのはここにおいてです。それは有機体がその外的な環境にしたがって自らを形成する「適応」であり、卓越した条件に最もうまく適応した生き物だけが生き残るのを許す「生存競争」です。けれども、適応と生存競争は、もし、その形成原則が内的な統一性を維持しつつ多様な形態を取ることがなかったとしたら、有機体に対していかなる影響も及ぼさなかったことでしょう。私たちはこの原則が、ひとつの無機的な実体によって別の実体が影響を受けるのと同じ仕方で外的な形成力の影響を受けると想像すべきではありません。確かに外的な条件は元型がある特別な形態を取るという事実に対して責任がありますが、その形態自体は内的な原則から導かれるのであって、それらの外的な条件からではありません。形態について説明するとき、私たちはいつも外的な条件を考慮しなければなりません。しかし、形態自体が「それらの」結果として生じると考えるべきではありません。ゲーテは、ちょうどある器官の形態を外的な目的という観点から説明する目的論的な原則を拒否したように、有機的な形態が環境の影響から単に因果律によって導かれるという考え方にも反対したはずです。動物の器官体系はその外的な構造(例えば、その骨格)により深く関連していますが、私たちはその中に―例えば、頭骨の骨格形成の中に―植物において観察される法則が再び現れるのを見出します。純粋に外的な形態の中に内的な法則性を見るゲーテの才能がここでは特に明白なものとなります。植物と動物の間には明確な境界はないのではないかという疑念には確かな理由がある、という最近の科学により発見された事実からすれば、ゲーテの観点に基づく植物と動物の間のこの違いは不適切なもののように見えるかも知れません。ゲーテもまたそのような境界を打ち立てるのは不可能であると気づいていましたが、それによって植物と動物を明確に規定するのを妨げられるということはありませんでした。それは彼の世界観全体と関係していました。ゲーテは、現象世界においては、定常的で固定されたものは一切なく、すべてが絶え間なく変動し、動いていると考えていました。けれども、私たちが概念において把握するものの「本質」は、変動する形態からではなく、それがそこにおいて観察され得るようなある種の「中間的な段階」から導かれることができます。ゲーテの世界観は、当然のことながら、一定の定義づけを行いますが、それにもかかわらず、私たちが特別な遷移状態にある形態を経験するとき、その定義が堅固に保持されることはありません。実際、ゲーテが自然の生命の柔軟性を見たのは正にそこにおいてだったのです。ここで記述されたアイデアによって、ゲーテは有機的な科学の理論的な基礎を据えました。彼は有機体の本質的な特質を見出しましたが、もし、私たちが元型(それ自身からそれ自身を形成する原則、エンテレキー)を何か別のもので説明することができると考えるならば、この事実を容易に見逃してしまうことになります。とはいえ、そのような仮定は正当なものではありません。何故なら、元型は、先験的に理解されるならば、自己説明的なものだからです。それ自身にしたがってそれ自身を形成するこのエンテレキー的な原則を理解した人であれば誰であれ、これが生命の神秘に対する解答であることを理解するでしょう。他のいかなる解答も不可能です。何故なら、それがものごとの本質だからです。もし、ダーウィン主義が原初の有機体を仮定するように強いられるならば、ゲーテはその原初の有機体の本質的な特質を見出したのだと言うことができます。(R.シュタイナーによる注:現代科学においては、原初の有機体という言葉は、通常、原始的な細胞[原始細胞]、有機的な進化における最も低次の段階にある単純な実体のことを指しています。ゲーテの意味での「原初の、あるいは元型的な有機体」という言葉はそのことを指しているのではなく、本質的なもの[存在]、あるいは「原始細胞」を有機体にするところの形成的、エンテレキー的な原則のことを指しています。この原則は、最も単純な有機体にも、最も完成された有機体にも現れますが、これらは異なった発達段階にあります。それは動物の中の動物性であり、生きた存在を有機体にするところのものです。ダーウィンは初めからそれを仮定しています。それはそこにあり、導入されているのですが、そのとき彼は、それは環境の影響に対してあれこれの仕方で反応すると言います。ダーウィンにとって、それは不定項Xだったのですが、ゲーテはその不定項Xを説明しようとしたのです。)種や属の単なる分類を打破して、有機体の真の本性に沿った有機的な科学の再生を始めたのはゲーテでした。ゲーテ以前の分類学者たちが外的に存在する異なる種の数だけの(彼らはそれらの間を取り持つものを何ひとつ見つけることができませんでした)概念、あるいはアイデアを必要としていたのに対して、ゲーテは、すべての有機体はアイデアにおいて同一であり、外見的な違いがあるだけだと宣言したのです。そして、何故そうなのかを説明します。こうして、有機体の科学体系のための基礎が打ち立てられ、後はそれを洗練させるだけとなりました。どのような意味で、存在するすべての有機体はアイデアの顕現に過ぎないのか、そして、それらはどのようにして個別のケースにおいてそれを現すのか、ということが示されるはずでした。この偉大な科学上の業績は、より深い教育を受けた科学者たちによって、広く認められることになりました。ダルトン弟(エドワルド・ジョセフ)は、1827年7月6日、ゲーテに宛てて次のように書いています。そのすばらしい見通しと、新しい観点を通して、植物学が完全なる変容を遂げたというだけではなく、骨相学の分野においてもまた、自然科学は多くの第一級の貢献を閣下に負っています。もし、その閣下にお褒めの言葉をいただけるような努力を、私が同封させていただいたページの中に見ていただけるならば、これ以上の喜びはありません。ネース・フォン・エーゼンベックは1820年6月24日に、あなたの随筆「植物の変容を説明する試み」の中で、植物は自らについて私たちに初めて語りかけました。そして、まだ若かったころの私もまた、そのような美しい擬人化の虜になってしまったのです。そして、最後にフォイクトは1831年6月6日に次のように書いています。「私は生き生きとした興味と謙虚な感謝をもって、変容についてのあなたの小作品を受け取りました。私はこの理論への当初からの参加者として加えられていることを感謝します。動物の変容(古くから知られている昆虫の変容ではなく、脊柱から来る変容)が植物の変容に比べてより公平に扱われているのは奇妙なことです。盗作や乱用とは別に、そのような静かな認識は、動物の変容というものは「あまりリスクを含んでいない」と信じることから来るのかも知れません。と申しますのも、骨格系においては、個々の骨はいつでも同じであるのに対して、植物系においては、変容によって用語全体に、したがって、「種の同一性」に革命が起こる恐れがあるからです。これは弱い者にとっては脅威です。何故なら、彼らはそのようなことがどのような結果をもたらすかを分かっていないのですから。」ここにはゲーテのアイデアに対する完全な理解が見られます。そこにある気づきとは、個別(の有機体)を見るためには新しい観点が必要であり、そのような観点だけが個別のものを探究する新しい科学的な体系のための基礎を与えることができる、ということです。自己形成する「元型」は、それが現れるとき、無限に多様な形態を取ることができます。種や属は実際に時空の中に生きているので、そのような形態は私たちの感覚による知覚対象となります。私たちの心が統一性の中にある有機体の世界全体を理解するのは、一般的なアイデア―元型―を理解した程度に応じてです。私たちが個別の現象形態の中で何らかの形を取る元型を「見る」とき、それらは理解可能なものとなるのです。それらは段階や変容の過程を追って現れますが、元型はその中で自らを表現します。ゲーテの洞察に基づく新しい体系的な科学の使命は、本質的には、これらの様々な段階を指し示すということです。動物界と植物界の両方において、上昇する進化過程が卓越しています。つまり、有機体はその発達の度合いにしたがって分化しています。何故それが可能になっているのでしょうか。私たちは有機体の理想的な形態あるいは元型を、それが空間的、時間的な要素から成り立っているという事実によって特徴づけることができます。その結果、それは「感覚的/超感覚的」な形態としてゲーテの前に現われました。それはアイデアとして(先験的に)知覚することができる空間的-時間的な形態を含んでいます。それが現象世界に現れるとき、実際に感覚的に知覚可能な形態、今やそれは先験的に知覚されることはないが理想的な形態に完全に対応しているいないこともあるでしょう。つまり、元型は十全なる発達を遂げていることも、遂げていないこともあります。ある種の有機体が低次の状態にあるのは、彼らの現象形態が有機的な元型に十分に対応していないからです。ある特定の存在の外見と有機的な元型が一致していればいるほど、その存在はより完全なのです。それは上昇する進化の連続した過程にとっての客観的な根拠となります。何かを系統的に提示しようとするならば、この関連を各々の有機体の形態の中に探究することが必要です。しかし、元型、すなわち主要な、あるいは元型的な有機体を確立しようとするときには、そのことを考慮することはできません。つまり、最も完成された元型の表現を代表する形態を見つけなければならないのです。ゲーテの元型的な植物はそのような形態を表しています。ゲーテは、その元型を確立するに際して、「隠花植物」の世界を無視したとして批判されてきました。私たちは既に、彼もまたそのような植物を研究していたので、それが十分に考慮された決定であったに違いない、ということを述べてきました。「隠花植物」というのは実際、元型的な植物がきわめて一方的な仕方でのみ現われているような植物なのです。それらは一方的で感覚的に知覚可能な仕方でのみその植物のアイデアを現わしており、達成されたアイデアにしたがって評価することができるかも知れませんが、そのアイデア自体が実際に成就するのは「顕花植物」においてのみなのです。しかし、ここで重要なのは、ゲーテが基本的な考えを洗練させることは決してなかった、ということです。彼は個別の領域にあまり深く入っては行かなかったのです。ですから、彼の作品はすべて断片的なものに留まりました。彼の「イタリア紀行(1786年9月27日)」の中の記述は、彼もまたこの領域を解明する意図を持っていたということ、そして、彼のアイデアをもってすれば、今日に至るまでただ思いつきによってのみ為されている種や属を真に決定することが可能になっていたであろう、ということを示しています。彼は、彼のアイデアと個別の世界、つまり特定の形態という現実の世界との間の関係を協調的な仕方で提示することによって、この意図を最後まで追求するということはありませんでした。そのことを彼は彼の断片的な著作の欠陥であると見なしていましたが、それについては、F.J.ソーレー宛てのドゥ・カンドーレに関する彼の書簡(1828年6月28日)の中で次のように述べています。「彼がその意図をどのように見ていたのかが私にもますます明確になってきました。私はその意図を持ち続けており、「それは私の変容についての随筆の中で明確に表現されています。しかし、私がずっと知っているような経験的な植物学とそれとの間の関係は十分に解明されているとは言えません。」。これはまたゲーテの観点が非常に誤解されてきた理由であるように見えます。それらが誤解されてきたのは、そもそも「それらが理解されなかった」からです。ゲーテのアイデアはまた、ダーウィンやヘッケルの発見、つまり、個体の発達(個体発生)はその全体的な進化(系統発生)の繰り返しであるという発見に対して概念的な説明を与えます。いずれにしても、ヘッケルがここで提示しているのは、説明されていない事実、つまり、各個体は個別の有機的形態として古生物学によって記述されるすべての発達段階を簡略化した仕方で通過するという事実以上のものではないと考えるべきです。ヘッケルとその追随者たちはそれを遺伝の法則に帰着させました。しかし、その法則自体がその事実の「簡略化された表現」に過ぎません。その説明とは、様々な古生物学的な形態であれ、いかなる現生生物であれ、すべて引き続く時代の中で、可能性としてその中に横たわる形成的な力を展開するたったひとつの元型が現れたものであるということです。より高次の個体というのは、実際、それがその内的な本性にしたがって自由に発達することを許すような好ましい周囲の影響によって、より完成されたものとなっています。他方、もし、ある個体が様々な影響によってより低次の段階に留まるように強いられるならば、その内的な力の一部分だけが現れます。そして、そのようにしてひとつの全体として現われるものは、より発達した有機体の一部だけを含んでいることでしょう。こうして、より高次の段階へと発展する有機体はより低次の有機体から成っているように見え、同じ理屈から、より低次の有機体は、その発展において、より高次の有機体の部分として現われるのです。私たちは、より高次の動物の発達の中に、すべてのより低次の動物の発達を認めることができるのです(ヘッケルによる生物発生の法則)。物理学者たちは単に事実を述べたり記述したりすることでは満足せず、それらを支配する「法則」、現象についてのアイデア-を探究します。同様に、生きた存在の本質へと貫き至ろうとする人たちは、単に近縁性、遺伝、生存競争といったような事実を引用するだけでは満足せず、それらの背後に横たわるアイデアを知りたいと思うでしょう。それこそゲーテが求めていたものです。彼の元型に関する考えの有機的な科学者に対する関係は、ケプラーの3法則が物理学者に対して有している関係と同じです。そのような法則がなければ、私たちは世界を単なる事実の迷宮として経験することでしょう。これはしばしば誤解されてきたことですが、ゲーテの変容についてのアイデアは私たちの知性の中で抽象的に生じる単なる「イメージ」に過ぎない。彼は、葉が花という器官に変容するという概念が意味を持つのは、これらの器官(例えば、雄しべ)がかつて実際に葉であった場合だけであるということに気づいていなかったのだと主張する人たちがいます。けれども、これはゲーテの観点を逆転させています。あるひとつの器官を原則的に主要なものとして、そこから他の器官を逐語的に導き出しているのです。ゲーテは決してそのようなことを意図していたわけではありません。彼にとって、時間的に最初に生じる器官は、アイデアあるいは原則という意味では、決して主要なものではありませんでした。雄しべが葉と関連しているのは、それらがかつて実際の葉であったからではありません。そうではなく、それらがかつて葉であったというのは、それらの内的な本性を通して、つまり、原則としてそれらが関連しているからです。感覚的に知覚可能な変容はそれらがアイデア上で関連している結果であって、その反対ではありません。植物の水平方向の器官はすべて同一であるということがここで経験的に確立されました。しかし、何故、それらは同一であると考えられるのでしょうか。シュライデンによると、それはそれらが「すべて」水平な突起物として茎の上で発達しながら外側へと押しやられるために、水平な細胞形成が茎の近くで継続する一方、最初に現れた先端部分では新しい細胞が形成されないことによります。この純粋に外的な関連が同一性という考えの基礎になっているのです。ゲーテによると、そうではなく、水平な器官が同一であるのはそれらの理想的、本質的な特質によるものです。だからこそ、それらは外的な形成においても同一のものとして「現われる」のです。彼によれば、感覚の前に現れる関係性は内的、理想的な結びつきの結果です。ゲーテの観点と唯物的な観点とでは質問の立て方が異なっています。それらは矛盾しているのではなく、相補的な関係にあります。ゲーテのアイデアは唯物的な観点のための基礎を与えます。ゲーテのアイデアは後の発見の詩的な予言以上のもの、独立した、理論的な発見なのですが、その価値はまだ認められ始めたばかりです。科学はこれからもずっと支えとなる栄養をその発見から引き出し続けることでしょう。ゲーテが用いた個々の経験的事実は、より正確で詳細な探究に取って代わられ、あるいはある程度反証されるかも知れません。しかし、彼が確立したアイデアはいつでも有機的な科学を基礎づけるものとして留まり続けるでしょう。何故なら、それらは個々の経験的事実から独立したものだからです。ちょうど新しく発見された惑星が恒星の軌道をケプラーの法則に従って周回しなければならないように、有機的な自然におけるプロセスはすべてゲーテのアイデアに従わなければならないでしょう。星の世界のできごとはケプラーやコペルニクス以前にも長く知られてきましたが、これらの人たちによって初めてその法則が発見されました。有機的な自然はゲーテ以前にも長く観察されてきましたが、彼がその法則を発見したのです。「ゲーテは有機的な世界におけるケプラーであり、コペルニクスなのです。」ゲーテの理論の特徴は次のような仕方でも説明できます。通常の経験的で純粋に事実を集める機械論の他に、基本的に機械論的な原則の内的な特質から先験的な法則を導き出す合理的な機械論があります。経験的な機械論の合理的な機械論に対する関係は、ダーウィン、ヘッケル、その他による理論のゲーテの合理的な有機的科学に対する関係に似ています。当初、ゲーテは彼の理論のこの側面に明確に気づいていたわけではありません。しかし、後になって、彼はそのことを非常に強調しています。ですから、彼はH. W. F. バッケンローダー宛に次のように書きました。「引き続きあなたの興味を引くものを何でも私に教えて下さい。私の観察にどこかで結びつくはずですから。」(1832年1月21日)これは、有機的な科学の基本原則は彼により発見されていたので、他のあらゆるものはそこから演繹できるはずだということを意味しています。けれども、以前には、このすべてが彼の心の中で無意識のうちに働いており、彼はそのようにして事実にアプローチしていました。それが意識的になったのは、彼がシラーと科学について初めて会話をしたことによってです(これについては後で記述するつもりです)。シラーは直ちにゲーテの元型植物の理想的な特質に気づき、外的な現実は決してそれと完全に一致することはないだろうと主張しました。これによって、ゲーテは彼が「元型」と呼んでいたものと経験的な現実との間の関係について考えるようになりました。彼は今や、アイデアと外的な現実、思考と経験の間の関係とは何か?というすべての人間の探求におけるもっとも重要な問題のひとつに直面することになったのです。個別の経験的な対象物は彼の元型に完全には一致せず、それと同じものは自然の中には存在しない、ということが彼にはますますはっきりとしてきました。したがって、元型という概念は、たとえそれが感覚的な世界との「出会いを通して」獲得されるとしても、感覚的な世界そのもの「から」やって来ることはありません。その結果、元型が生じることができるのはそれ自身からだけということになります。元型的な存在というアイデアは内的な必然性によってそれ自身からその内容を発展させ、そして、その内容は現象世界の中に別の形態、知覚表象として現われるのです。この関連で、ゲーテが、経験主義の科学者たちとの出会いにおいてさえ、いかに「経験の正当性」を是認し、アイデアと対象を厳密に区別したかを見るのは興味深いことです。1796年、ゾンメルリンクは彼に1冊の本を送りましたが、その中で彼が試みていたのは魂の座を見つけるということでした。ゾンメルリンクへの手紙(1796年8月28日)にもあるように、ゲーテはその観点の中にあまりにも多くの形而上学を織り込んでいたことに気づきました。彼は、「経験の対象物」についてのアイデアがその対象物自体の本質的な特性に基づくのではなく、もし、それを越えて行くとすれば、そのようなアイデアが正当化されることはないということを述べています。彼は、経験の対象となるものを扱うときのアイデアとは現象の必然的な相互関係を理解するための器官であって、そのような器官がなければ、現象は時間と空間の中でランダムに生じるものとして盲目的に知覚されるだけであろうと主張したのです。アイデアはその対象物に何も新しいものをつけ加えませんが、それから導き出されるのは、対象物はその実際の本質において理想的な特質を持っているということです。実際、すべての経験的な現実はふたつの側面を持っていなければなりません。ひとつは、それを通してそれが個別のものとしての特質を有することになるような側面、もうひとつは、それを通してそれが理想的、普遍的な特質を有することになるような側面です。ゲーテと同時代の哲学者やその著作との交わりはゲーテにこの問題に関する数多くの観点をもたらしました。彼はシラーの「世界魂について」や(最初の)「自然科学体系概論」(ゲーテの年譜1798-1799年参照)や、ヘンリック・シュテッフェンの「哲学的自然科学の基礎」から刺激を受けました。彼はまた多くの問題についてヘーゲルと議論しました。これらすべてのことがらによって、彼は再びカントの著作についての研究へと導きかれ、シラーに促される前に、それを行うことになりました。1817年には(彼の年譜参照)、カントを研究していた年月がいかに自然と自然現象についての彼のアイデアに影響を及ぼしたかについて論評がなされています。これらの考察は次のような随筆に結びつきました。ゲーテはそれらの中で科学における最も中心的な諸課題に取り組みました。「幸運な出会い」「先験的な知覚による判断」「再考とあきらめ」「形成的な衝動」「正当な企て」「設定された目的」「序文の内容」「私の植物学研究史」「植物の変容についての随筆の起源」です。これらすべての随筆は先に触れた考え方、つまり、すべての対象には二つの側面-外見(現象形態)という直接的な側面とその「本質」(存在)を含む第二の側面-があるという考え方を表現しています。こうして、ゲーテは自然についての唯一の満足すべき観点に至ったのですが、そのことによって真に客観的な方法のための基礎が据えられたのです。アイデアを対象そのものとは異質なもの―単に主観的なもの―と見なす理論は、そもそもアイデアを用いる限り、自らを真に客観的なものであると主張することはできません。一方、ゲーテは、予め対象の内部に存在していないものは何もつけ加えないと主張することができます。ゲーテはまた、彼のアイデアが関係する科学分野における詳細で実際的な側面も追及しました。彼は1795年に、ローダーの靭帯に関する講義に出席しました。彼はこの時代を通してずっと解剖学と生理学を視野に入れていました。このことは彼が当時、骨相学の講義を執筆していたことから余計に意義深いものとなりました。彼は1796年に、暗闇と色つきガラスの下で植物を育てる実験を行いました。その後、彼は昆虫の変容についても研究しています。ゲーテはまた、文献学者F. A. ヴォルフから刺激を受ける中で、植物の変容について、ゲーテのアイデアに似たアイデアを公表していたヴォルフ(彼の同名人)に注目するように促されました。それによってゲーテは1807年を通して、ヴォルフのより詳細な研究へと導かれました。とはいえ、彼がその後に見出したのは、ヴォルフはその鋭敏さにもかかわらず、本質的な問題については明確ではなかった、ということです。彼はまだ元型を感覚には知覚不能な実体、純粋に内的な必然性からその内容を発達させる実体としては考えてはいなかったのです。彼はまだ植物を個別の詳細からなる外的で機械的な複合体と見なしていました。このように、彼は、多くの科学者である友人たちとの交わりによって、あるいは多くの気の合う仲間たちから認められたり、熱心に見習われたりする幸せから、1807年には、それまで差し控えていた科学的な業績の断片を出版することを考えるようになっていました。彼はより大部の科学的著作を執筆するという考えを徐々に放棄していたのです。とはいえ、その年の彼は個別の随筆を出版する時間を持つことができませんでした。彼の色彩論への興味によって、形態論はしばらくの間、再び背景へと押しやられることになりました。彼の随筆の最初の小冊子はその後10年に渡って出版されることはありませんでした。しかし、1824年までには、合計二巻で四冊からなる第一巻と、二冊からなる第二巻が出版されました。彼自身の観点に関する随筆に加えて、形態学上の重要な文学的出版や他の学者たちの論文について議論したものが見出されますが、それらの発表はいつでも何らかの仕方で自然についてのゲーテの説明を補足するものとなっています。ゲーテはその後、二度にわたって自然科学をより集中的に取り上げることに挑戦しました。いずれの場合にも、ゲーテ自身の仕事に密接に関連した重要な科学的出版が含まれています。最初の挑戦は植物学者カール・フリードリッヒ・フィリップ・フォン・マルシウス(1794-1868年)による植物における螺旋への傾向に関する仕事に触発されたものであり、二番目はフランス科学アカデミーにおける科学上の論争に触発されたものでした。マルシウスは植物の発達における形態を螺旋と垂直という二つの傾向の組み合わせであると見ていました。垂直への傾向はそれを根から茎に至る線に沿った成長へと導き、螺旋への傾向は 広がっていく葉や花やその他の器官によって表現されます。ゲーテがこの考えの中に見たのは、変容に関する彼の随筆によって1790年に確立していた彼自身のアイデアを単に空間的な側面(垂直や螺旋)を強調する方向で綿密化したものに過ぎませんでした。ここでゲーテの「植生における螺旋への傾向について」に関する私たちのコメントに言及しておきましょう。そうすれば、ゲーテはこの随筆の中で、彼の以前のアイデアに関しては、何も本質的に新しいものを提示していない、ということが明確になります。私たちが特にこのことを強調するのは、ゲーテの随筆の中に彼の以前の明確な観点から「神秘主義の深淵」への退化を見る、と言う人たちがいるためです。最晩年になって、ゲーテはさらに二つの随筆(1830-1832)を仕上げました。それらはフランスの科学者ジョルジュ・バロン・フォン・キュビエとエチエンヌ・ジョフロワ・サンチレールとの間の論争についてでした。これらの随筆も際立った簡潔さをもって集積されたゲーテの自然観についての原則を含んでいます。キュビエは古い学派に属する経験論者でした。彼が追及していたのは各々の動物種のための適切な個別概念でした。彼は、彼の有機的な自然に関する体系という壮大な概念の構築物の中に、自然に見られる様々な動物種と同じだけ多くの型を含めなければならない、と信じていました。とはいえ、これらの型はいかなる仲介もなく並立していました。彼が見落としていたのは、知識を求める人たちは、個別のものがその直接的な現象形態においてそのまま私たちの前に現れたとしても、それに満足することはない、という事実です。そうではなく、私たちは、感覚世界の中で、ある対象を知ろうとする意図をもってそれにアプローチするわけですから、私たちは私たちの知識に対する能力の欠如のために個別のものでは満足できないのだ、と考えるべきではありません。むしろ、その対象自体が私たちにとっての不満足の理由を含んでいるはずなのです。その個別のものの特性はその中で、つまりその個別性の中で言い尽くされるわけではありません。すなわち、私たちは、その理解に向けての努力において、何か個別のものにではなく、何か一般的なものに向けて駆り立てられるのです。この一般的なアイデアこそが個別のものとして存在するものすべての真の存在その本質であり、その個別性はその存在性の一側面に過ぎません。そのもうひとつの側面が一般的なもの、あるいは元型です。このことは、一般的なものの形態としての個別のものに言及するとき、理解しておくべきことがらです。一般的なアイデアは個別的なものの真の存在あるいは本質ですから、それを個別のものから演繹あるいは抽出することはできません。一般的なものはその本質を個別のものから借りてくることができないので、自分自身で提供しなければなりません。ですから、一般的な型の特質とは、その本質と形態が一致しているということです。したがって、それは、個別のものとは独立して、全体としてのみ理解することができます。科学は、それぞれ個別のものが、その特質を堅く守ることによって、いかに一般的なアイデアに関連しているかを示すという使命を持っています。こうして、「特別な種類の存在」が認識の領域に参入してきますが、私たちは、その領域において、それらの相互決定と相互依存を再構成します。そうでなければ関連のない仕方でのみ、つまり、空間と時間の中で孤立した実体として知覚されるはずの事物が、今や、その「必然的、合法則的な」相互関連性において理解されることになります。キュビエは、ジョフロワ・サンチレールが主張したこの観点をきっぱりと否定しました。実際、ゲーテが興味を引かれたのは彼らの論争におけるこの側面だったのです。この問題は、偏見なくそれらにアプローチする場合とは非常に異なった光の下で事実を提示する最近の観点によってしばしば歪められてきました。ジョフロワ・サンチレールの主張は彼自身の探求だけではなく、ゲーテを含む数多くの同様な心を持ったドイツの科学者たちの仕事にも基づいていました。ゲーテはこのことに大いに興味を持ち、ジョフロワ・サンチレールの中に同志を見出したことを深く喜びました。1830年8月2日に、彼はエッカーマンに次のように述べています。今や、ジョフロワ・サンチレールはそのフランスにおけるすべての重要な学生や同調者たちとともに明確に私たちの側に立っています。このことは私にとって信じがたいほどの価値を持っています。そして、私の人生を捧げ、非常に特別な意味で私自身のものでもある主張の最終的な勝利を本当に喜んでいるのです。ドイツにおいては、ゲーテの探求に対する好意的な反応は主として哲学者たちからであって、科学者たちからはそれほどでもなかったのに対して、フランスでは科学者たちから好意的な反応があったというのは確かに特筆すべき現象です。オーガスタン・ピラーム・ドゥ・カンドールはゲーテの変容理論に最高の注意を払っており、彼の植物学へのアプローチはゲーテ自身のアプローチに近いものでした。ゲーテの随筆「変容」(1790年版)はジンジャン・ラサラによって既にフランス語に訳されていました。そのような状況下では、ゲーテの植物学に関する著作がフランス語に訳されたとしても、それが彼の協力の下で行われたならばですが、それは不毛な大地に落ちることはまずないだろうと思われました。その翻訳は1831年に、ゲーテの絶えざる協力の下、フリードリッヒ・ジャコブ・ソレによって為されました。そのフランス語訳はオリジナルのドイツ語を見開きとして出版されました。それはあの1790年の最初の「試み」とともに、ゲーテの植物学研究の歴史、彼の理論が彼の同時代人たちに及ぼした影響、ドゥ・カンドーレに対する何らかの影響を含んでいました。 (第4章了)参考画:フィボナッチ数列 フィボナッチ数列は、自然界の秩序や美しさを表す法則としても解釈されています。これは、私たちの世界が偶然ではなく、何らかの意味や秩序に従って成り立っているという哲学的な視点からの見方です。また、フィボナッチ数列は無限に続くため、人々はその中に無限の可能性や神秘を感じることがあります。宇宙生成のインストレーションからビッグバンへの流れ以前の我々の「有無」の意識構造を超えた「虚」の解明をも可能にする不可思議性を備えます。人気ブログランキングへ
2024年05月27日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説並びに精神科学(人智学)の基礎(GA1)第3章 動物の形態学に関するゲーテの思考の起源 佐々木義之訳 ラバターの「人相学についての随想」が出版されたのは1775年から1778年にかけてでした。ゲーテはその発行責任者としてばかりではなく、執筆分担者としてもこの仕事に生き生きとした興味を持っていました。しかし、今、私たちにとってこれらの貢献が特に興味深いのは、その中に彼の後の動物学上の作品となったものの種子が見出されるからです。人相学では、人々の内的な性質や精神をその外的な形態を通して見定めようとします。形態はそれ自体として捉えられるのではなく、魂の表現であると考えられました。ゲーテが有する彫刻のような、まるで、ものごとをその外的、形式的な関係性において把握するために創られたような精神が、そのようなアプローチに限定されるはずもありませんでした。単に内的な存在を認識するためにだけ外的な形態にアプローチするようなこれらの研究に関わりながら、ゲーテは形態自体の独立した意義に気づくようになりました。そのことは「人相学についての随想」第2巻パート2に挿入された動物の頭蓋に関する彼の1776年の研究の中に見て取ることができます。彼がその年にこれらの研究を始めたのは、人相学についてのアリストテレスの著作を読んで刺激を受けたからです。彼はまた人間と動物の違いを検証しようとしました。彼はその違いを、人間の形態においては、いかにその構造全体がその頭部を際立たせているかという点に見出しました。つまり、その体のあらゆる部分がその中心として指し示すところの高度に発達した人間の脳の中にそれを見い出したのです。「いかに人間の形姿全体が天を映し出すドームを支える柱としてそこに立っていることか。」動物の構造にはその正反対であるところのものを見出しました。「頭部は脊椎に補足的に取り付けられているに過ぎない!脊椎神経の先にあるその脳は、その動物の精神を表現するために必要な、そして、その場限りの感覚を通して生きる生き物を方向づけるために必要な羅針盤以上のものではない。」。このように示唆することによって、ゲーテは人間本性の内と外との相互作用に関する考察を超えて、包括的な全体の把握、形態そのものの考察へと進みます。彼は人間形態の「全体」をその生のより高次の表現のための礎として見るようになりました。そして、彼は「その全体」が有するある特徴の中に、それによって人間が創造の頂点に置かれたところのある前提条件を認めました。私たちは、このような考えを形成するに当たって、ゲーテは動物の形態を完全に発達した人間の形態に関連づけようとしていたのだということを心に留めておかなければなりません。とはいえ、動物においては、主として動物的な機能に仕える器官がいわば支配的になっており、彼らの組織全体がそれに向けて方向づけされているのに対して、人間の有機組織の場合は、特に精神的な機能に奉仕する器官が発達しています。この初期の段階においてさえ、私たちは、ゲーテが動物有機体として心に描いていたのは、もはや私たちが感覚的な現実の中に見出すような個別の有機体ではなく、それはむしろ、人間においてはより高次の側面に向かい、動物においてはより低次の側面に向かってさらに発展するようなひとつの理想的な有機体であったということが分かります。ここにはゲーテが後に「元型」と呼んだものの種子が横たわっているのですが、彼がそれによって意図していたのは「個別の動物」ではなく、動物というアイデアだったのです。そうです、もっと言えば、私たちは後に彼が定式化した法則についての暗示をここに見出すのですが、それは「形態の多様性は、ある部分がその他の部分に対して卓越することから生じる」という重要な暗示でした。実際、既にここでは、動物と人間との間の相違はひとつの理想的な形態が二つの方向に逸脱することを通して生じる、そして、それによって、異なる様々な器官体系が優越性を獲得するとともに、その生き物全体に特有の性質を与えると考えられていたことが分かります。同年(1776年)には、動物有機体の形態にアプローチする方法が明確になっていたということも分かります。後に彼が彼の解剖学的な研究、それはいつも骨学から出発しました-の中で擁護した考え、つまり、骨が形態の基礎であるということに彼は気づいていたのです。その年に彼は次のような適切な文章を書いています。「動的な部分はそれら骨にしたがって、それらとともにと言った方がいいかも知れませんが出来上がっており、その硬い部分が許す限りにおいて、その役割を演じる」と。そして、ラバターの「人相学」では、もうひとつの示唆がなされました。私が、「骨格体系は人間の基本的な素描」であり、頭骨は骨格体系の根幹であり、そして、肉質部分はこの素描の色づけ以上のものではあり得ないと考えていることは既にお分かりでしょう。恐らくこれは、ラバターとこれらのことがらについてしばしば議論したゲーテの示唆によるものだったと思われます。このような観点は確かにゲーテのものと同じだからです。しかし、彼は私たちが考察すべきさらなる観察を行います。特に頭蓋をはじめとする骨の研究を行うことによって、骨格が形態の基礎であることを明確に理解することができるというこのコメントは、ここでは動物においては議論の余地がないにしても、人間の頭蓋における相違に適用するときには、かなりの反対に遭うかも知れません。ゲーテがこの後1795年に記述しているような複合的な人間の中により単純な動物を探すことを除き、彼はここで何をしようとしているのでしょうか。(編者注:ゲーテは、その随筆「形態学について」の「提示された目的」の部分で、この部分の記述に次のように光を当てています。「生き物が不完全であればあるほど、その各部分はお互いに、その全体に、より相似したものとなる。生き物が完全であればあるほど、その各部分は不相似となる。前者の場合、その全体は多かれ少なかれその各部分と同様であり、後者の場合、それはその各部分と同様ではなくなる。各部分が似ていれば似ているほど、それらは互いにより少なく依存し合っている。その各部分の依存性は、より完成された生き物であることの証なのだ。」)私たちはそれによって、動物の形態学に関する彼の後の考えをその上に基礎づけたところの基本的な概念をゲーテが確立したのは、彼が1776年のラバターの「人相学」に没頭していたことによる、と結論づけるように導かれます。この年はゲーテが解剖学の詳細な研究を始めた年でもあります。1776年1月22日に、彼はラバター宛に「公爵は私に6つの頭蓋を送るよう手配してくれました。私は輝かしい観察を行うことができましたから、もし、貴方がまだ私抜きにそれをされていないのであれば、お伝えできます」と書き送っています。ゲーテのイエナ大学との結びつきは彼の解剖学の研究をさらに刺激することになりました。1781年にその最初の示唆があります。ゲーテは、カイルによって編纂された日記の中で、1781年10月15日に「アインシーデル老」とイエナに行き、解剖学に精を出したと記しています。イエナにはローダーという学者がいて、ゲーテの研究に大いに貢献しました。ゲーテを解剖学の分野へとさらに導いたのは彼だったのです。ゲーテはそのことについて10月29日にはフォン・シュタイン夫人宛に(R.シュタイナーによる注:「私が関わっている面倒な愛の労働は、私を私の探求へとさらに導いています。ローダーは私に骨や筋肉のすべてについて説明してくれています。そして、私は2,3日の内に多くのことを理解するでしょう。」)、そして、11月4日にはカール・アウグスト宛に(R.シュタイナーによる注:「彼[ローダー]は私に、骨学と筋肉学について、8日間に渡ってみっちりと-私の注意力が持ちこたえる限りにおいてですが-説明してくれました。」)書簡を送っています。この手紙の中で、彼はその意図について次のように述べています。「芸術学院の若い人たちに、人間の体に関する知識の概略を説明し、それに向けて彼らを導くためです・・・。私がこれを行うのは、私と彼らの両方のためですが、彼らは、この冬季過程を通して、私が選んだ方法により、体の基礎に完全に精通するようになるでしょう。」ゲーテの日記の記述は、実際に彼がこれらの講義を行い、それが1782年1月16日に終了したことを示しています。ローダーとは、この時期に、人間の体の構造についてかなり議論していたはずです。1月6日のゲーテの日記には「ローダーによる心臓の説明」という記述があります。私たちはゲーテが早くも1776年には、動物の有機体の構造に関する先見的な考えを抱いていたことを見てきました。ですから、この時点において、彼の精力的な解剖学への関わりは詳細なことがらを超え、より高次の観点へと上昇していた、ということに全く疑いの余地はないでしょう。彼は1781年11月14日に、ラバターとメルク宛に、彼が「すべての生命とあらゆる人間的なものをそれに補足することができる文脈としての骨を」扱っている、と書き送っています。私たちがある文脈を読むとき、私たちの心の中で像と考えが形成されます。それはその文脈によって引き起こされ、創造されたように見えます。ゲーテは骨をそのような文脈として取り扱いました。つまり、彼がそれらを観察している間、すべての生命とあらゆる人間的なものに関する考えが彼の中に生じました。それらを深く考察する過程の中で、有機体の形成に関するあるアイデアが彼に刻印されたのです。1782年のゲーテの頌歌「神」は、人間の人間以外の自然に対する関係について、当時の彼がどのように考えていたかを私たちがある程度理解するための助けとなります。。初の韻文には次のようにあります。「高貴であろうではないか、役立つもの、善良なものであろう。それらだけが、私たちが知るあらゆる存在から私たちを区別するのだから。」この韻文の最初の二行で人間の属性を特徴づけた後、ゲーテはそれら「だけ」が私たちを世界のあらゆる他の存在から区別すると主張します。この「だけ」は、人間の物理的な構成はその他の自然と完全に調和しているとゲーテが考えていたことを非常に明確に私たちに示しています。私たちが以前に注意を促した考え、つまり、ひとつの基本的な形態が人間と動物の両方の形を支配しているけれども、人間においては、それは自由な精神的存在の乗り物になるほどの完成の域に達している、という考えは彼の中でますます生き生きとしたものになっていたのです。感覚的に知覚可能な特徴に関しては、韻文が語るように、私たちはまた人間として、「私たちの存在という円環を完成させなければならない・・・。強大な、鉄の必然という永遠の法則にしたがって。」とはいえ、私たちの場合、これらの法則は、私たちに「不可能」を行わせるのを許すような仕方で発達します。「我々は区別し、選択し、評価する、そして、その瞬間に永遠の形態を与える。」私たちはまた、ゲーテの観点がますます明確なものになっていた1783年には、彼が「人類史の哲学に関する考察」を定式化し始めていたハーダーと活発に連絡を取り合っていたということに注意しておかなければなりません。この仕事はこれら二人の男の議論から生じてきた、そして、そのアイデアの多くはゲーテにまで辿ることができると言っても差し支えないでしょう。その文体はハーダーのものでしたが、そこに表現された考えはしばしば全くゲーテのものでした。ですから、私たちはそこから、当時のゲーテの考えについて、信頼するに足る結論を引き出すことができるのです。ハーダーは彼の作品の第1部で、自然の世界について次のような観点を発達させました。我々は、あらゆる存在を貫き、様々な仕方、自らを実現するような原則的な形態を仮定しなければならない。「石から結晶へ、結晶から金属へ、それらから植物の創造へ、植物から動物へ、それらから人間へと」我々は「組織形態の上昇」を見る。それとともに、この生き物の力と衝突しますます可変的なものとなり、ついには、それらを包含できでに人間の形態の中へと統合される。この考えは完全に明確なものであり、理想的、典型的な形態は、そのようなものとしては感覚的な現実性を有しておらず、空間的に分離され、質的に多様な存在、そして、それは人間に至るまでそうなのですが、そのようなものとして自らを実現するということです。より低いレベルの有機的な組織においては、それはいつもある特定の方向で自らを実現し、非常に顕著な仕方でそれに向けて発達します。この典型的な形態が人間へと上昇するとき、それは低次の有機体の中で一面的な仕方で発達させられたあらゆる存在の間に配分されるすべての形成的な原理を「ひとつ」の形態へと集約します。そのことによって、きわめて高い完成度が人間において達成される可能性が創造されたのです。自然はここにおいて、多くの段階や秩序の下にある動物たちの間に分散させていたものをひとつの存在へと付与しました。この考えはその後のドイツ哲学に非常に実り多い影響を及ぼしました。ここで、この概念をさらに明確にするために、オーケンによって後に定式化されたものを参照してみましょう。「動物界とは、たったひとつの動物のことである。別の言い方をすれば、それは、その有機体のひとつひとつがそれ自体の中に全体として存在するというような仕方で動物性を代表しているのである。個々の有機体が一般的な動物体から分離し、しかも動物としての本質的な機能を確立するとき、個々の動物が存在することになる。動物界とは、最高の動物である人間がバラバラにされたものに過ぎない。人間の類、族、種にはたったひとつしかないが、それは単にそれが動物界全体であるからという単純な理由によるものである。(自然哲学教本、イエナ、1831年)」。ですから、動物たちの中には、例えば、触覚器官が発達したものがいますが、彼らの有機体全体」が実際に触ることに向けて方向づけられており、それが目的となっているのです。また、食べるための器官が特に発達した動物やその他の動物たちがいます。言い換えれば、それぞれの動物種において、ひとつの体系が一方的な仕方で際立っており、その動物全体がそれに浸っている一方、それ以外のものはすべて背景へと退いているのです。ところが、人間の構成においては、すべての器官と器官体系は、それぞれの器官が他の器官に自由に発達するための余地を残しておくというような、つまり、それぞれがその他のすべての自己実現を許すのに十分なだけ引き下がるというような仕方で発達します。ですから、個別の器官や体系の調和的な相互作用が生じることによって、他のすべての生物の完成度を統合しつつ、人間を最も完全な存在にするところの調和が創り出されるのです。このような考えは、ゲーテとハーダーとの会話の内容になっていますが、後者はそれらを次のように表現しています。「人類とは、人間性を達成するために集合する「より低次の有機的な力の大いなる合流」である・・・したがって、我々は「人間を動物の中でも中心的な生物、つまり、あらゆる種の特徴がその最も繊細な本質においてそこに集められた最終的な形態」であると考えることができる。(ハーダー、「人間性の歴史に関する哲学の考察」第5冊のⅠあるいは第2冊のⅠ)」ゲーテがクネーベルに出した手紙の次のくだりは、ゲーテがどれほどハーダーの「人間性の歴史に関する哲学の考察」に関与していたかを示しています。「ハーダーは歴史哲学を書いています。ご想像の通り、一から新しく積み上げながら。一昨日は、最初のいくつかの章を一緒に読みましたが、すばらしい出来です・・・。今や、世界史と自然史が私たちとともに正に荒れ狂っているようです。」ハーダーの(人間有機体とそれに結びつくあらゆるものに固有の直立姿勢こそ人間の思考にとって基本的な前提条件であるという:同、第3冊のⅥ、及び第4冊のⅠ)観察は、上で述べたゲーテによる人間と動物の属的な差異に関する1776年の示唆を直接思い出させるものです。(「人相学についての随想」第2巻第2章)ハーダーの表現はこの考えのひとつの定式化に過ぎません。このすべては、ゲーテとハーダーが自然の中の人間の位置づけについて、当時(1783年)本質的に一致していたという私たちの仮定を裏づけるものです。さて、そのような基本的な観点のひとつの帰結とは、ある動物の器官、あるいは部分は人間の中にも見出されるけれども、全体が調和していることによって課される限定の範囲内に抑制されている、ということです。例えば、特定の骨が特定の動物の中で卓越しているのであれば、それはある一定の仕方で実際に発達していなければなりませんが、それはまたすべての他の動物の中に少なくとも示唆されていなければならず、そして、人間の中に不在であってはなりません。それは、動物の中では、それ自身の法則性に対応した形態を取るのに対して、人間においては、全体に適応しつつ、その形成的な法則を有機体全体の法則に適合させなければなりません。しかし、もし、自然という織物が引き裂かれるべきではないとすれば、それは全く不在というわけにはいきません。何故なら、もし、そうであったならば、元型の首尾一貫した仕上げが妨げられたはずだからです。ゲーテがこの偉大な考えと完全に矛盾する意見に突然気づいたときの彼の観点とはそのようなものでした。当時の学者たちの関心は動物種を見分けるための特徴を見出すことにありました。動物と人間の違いは、動物には左右対称の上顎の間にあって門歯を支えている小さな骨―顎間骨―がある点であると信じられていたのです。この骨は人間にはないと考えられていました。1782年に、骨学に興味を持ち始めていたメルクは、当時、最も著名だった学者の何人かに助けを求めました。その年の10月8日に、優れた解剖学者であったゾンメルリンクは動物と人間の間の相違についての情報をもってそれに応えました。「顎間骨」については、ブリューメンバッハをご覧になるとよいでしょう。それは、他のすべては同じであるけれども、オランウータンに至るまでの類人猿以上の動物には見られて「人間には決して見られない」ただひとつの骨なのです。この骨を例外として、あなたが人間の中に見出されるあらゆるものを動物に移しかえるのを妨げるものは何もありません。ですから、私が雌鹿の頭をあなたに提供しようとしているのは、ブリューメンバッハがそう呼ぶところのこの「顎間骨」は、上顎に門歯を持たない動物にも存在していることを確認していただくためです。ブリューメンバッハは人間の胎児や幼児の頭骨の中に「顎間骨」の原始的な痕跡―実際、そのような頭骨のひとつには、実際の顎間骨のように完全に分離した二つの小さな核さえあったのです-を見出していたのですが、それでも彼はその存在を認めようとはしませんでした。彼は、「これと真の顎間骨との間には、ひとつの世界ほどの違いがある」と言っています。当時の最も有名な解剖学者、キャンパーも同じ意見でした。彼は顎間骨について、例えば「人間には全く見いだされていない」ものとして言及しています。キャンパーを非常に尊敬していたメルクは彼の著書を読みふけっていました。メルクは、ブリューメンバッハやゾンメルリンクと同様、ゲーテと手紙の交換をしていました。ゲーテのメルクとのやり取りは、彼がその骨学研究に大いに興味を持っており、それについて意見交換をしていたことを示しています。1782年10月28日に、彼はメルクに、キャンパーの「未知の動物」について何か書き送ってほしい、キャンパーからの手紙を送ってほしいと頼んでいます。もっと言えば、1783年4月に、ブリューメンバッハがワイマールを訪れたことに注意する必要があります。ゲーテは同じ年の9月に、ブリューメンバッハをはじめすべての教授たちに会うためにゲッチンゲンを訪れています。9月28日に、彼はフォン・シュタイン夫人宛に、「私はすべての教授を訪問することにしました。数日の内に一回りするとしたら、どれほど忙しくなることか、ご想像いただけるでしょう」と書き送っています。それから、彼はカッセルに赴き、フォルスターとゾンメルリンクに会いました。そこからフォン・シュタイン夫人宛てに彼が次のように書き送ったのは10月2日のことでした。記:シャルロッテ・アルベルティーネ・エルネスティーネ・フォン・シュタイン(シャルト)(Charlotte Albertine Ernestine von Stein(Schardt) ,/1742年12月25日 - 1827年1月6日)はドイツ・ヴァイマール公国のフォン・シュタイン男爵の妻であり、ヴァイマール時代のゲーテと親しかった人物。「(フォン)・シュタイン夫人」としても知られる。彼女の存在は、ゲーテのほかシラー、ヘルダーなど同時代のヴァイマルの文人たちに大きな影響を与えた。彼女自身も文人として知られていた。「私はとても美しく、すばらしいものを見ています。私の静かな勤勉さが報われているのです。今や私は正しい途上にある、今からは、私に関して何も失われることはないだろう、と言うことができるという事実こそが、今最も幸運なことなのです。」参考画:Charlotte Albertine Ernestine von Stein ゲーテが顎間骨に関して支配的だった観点を初めて知ったのは恐らくこの交流があった頃だったでしょう。彼の観点からは、直ちにこれは間違いであると思われました。それは、それによってすべての有機体が形成されるところの典型的で基本的な形態を破壊するようなものだったからです。ゲーテは、あらゆる高等動物の様々な発達段階で見出されるこの部分は人間形態の構築にも関わっているけれども、そこでは精神的な機能に仕える器官のために栄養に関わる器官が全体として退いているために、ただ後退しているに過ぎないということに疑いを持つことができませんでした。ゲーテは、その全体としての内的な方向づけから、人間にも顎間骨があるに違いないと考えざるを得なかったのです。問題は、それが人間の中でどのように形成され、人間有機体全体にそれがどの程度適合しているかを検証することによって、それを経験的に証明することだけだったはずです。1784年の春に、ゲーテはローダーと共にイエナで人間と動物の頭骨を比較し、その証明を見つけることができました。彼はその発見を3月27日に、フォン・シュタイン夫人(R.シュタイナーによる注:「めったにない喜びですが、私は重要で美しい解剖学上の発見を行いました。」)、そして、ハーダー(R.シュタイナーによる注:「私が見つけたのは―金でも銀でもなく、それは言葉にできないほどの喜びを私に与えてくれるものー人間の顎間骨です。」)の両方に伝えています。私たちはこのひとつの発見だけを過大に評価するのではなく、その基本となった偉大な考えと対比しながら推し量るべきです。ゲーテにとって、それは、彼の考えを有機体における最も仔細なことがらに至るまで一貫して追求するのを妨げるように見えた偏見を取り除くことができたという点で価値があったに過ぎません。ゲーテはまたそれを独立した発見であると見ていたのではなく、絶えず彼の自然についてのより大きな観点との関連で見ていたのです。私たちはそのように理解すべきですが、それは、ゲーテがハーダーに宛てた手紙の中で、「それはあなたを大いに喜ばせるはずです。何故なら、それは人間にとっての要石のようなものだからです。それは失われたのではなく、やはりそこにあったのです。しかし、どのようにして。」と書いていることからも分かります。そして、彼は直ちに別のことがらについても彼の友人に次のように思い出させています。「私はまた、あなたの全体像との関係でそれを考えていました。それがそこにあれば何と美しいことだろうと。」ゲーテにとって、動物には顎間骨があるけれども人間にはない、というような議論は無意味だったのです。もし、有機体を形成する力が動物のふたつの上顎の間に顎間骨を置いたのであれば、人間の中にも、動物の中でその骨が見つかった場所に対応する位置に、外的な表現は異なるとしても、本質的に同様の仕方で、その同じ力が働いていなければなりません。ゲーテは有機体を、死んで固定されたものの組み合わせとは決して考えておらず、内的な形成力から絶えず生じてくるようなものであると考えていました。ですから、彼は、この力は人間の上顎の中では何をしているのだと問わざるを得なかったのです。顎間骨が存在するかどうかを問うのではなく、むしろその特徴と形態とを決定しようとしたのです。それは経験論的に行われなければなりませんでした。彼の様々な陳述が示しているように、今やゲーテの中では、自然に関して、より包括的な作品をという考えがますます大きな活力をもって掻き立てられるようになっていました。こうして、ゲーテは、彼の発見についての論文をクネーベルに送付した際に、彼に次のように書き送りました。「現時点で注意を引くのを差し控えている。」「私は現時点でその結論それはハーダーがその考察の中で既に示唆していた。人間と動物の間の差異はいかなる個別事象の中にも見いだされないという結論です。」、ここで最も重要なのは、ゲーテがこの基本的な考えを述べる前に「現時点で注意を引くのを差し控えている」と言っている点です。ですから、彼は後に、より大きな文脈の中で、そうするつもりだったのです。さらに言えば、この陳述は、私たちにとって最も興味深い基本的な考え方、すなわち、動物の型についてのゲーテの偉大なアイデア―はその発見のはるか以前から彼の心の中に生きていたということを示しています。ここでゲーテはそれらがハーダーの「考察」の中で示唆されていたことを認めていますが、そのことが述べられた文章は顎間骨の発見以前に書かれたものだったのです。「ですから、顎間骨の発見はこれらの壮大な観点の結果に過ぎないのです。」そのような観点を持つことができなかった人たちにとって、その発見は理解不能なものにとどまったに違いありません。ゲーテの広く知れ渡った観点―動物たちの間に配分された要素を「ひとつの」人間形態の中に調和的に統合し、それによって、すべての個別的な部分は同じであるにもかかわらず、自然の中で最高の位階を人類に付与する総体としての差別化―について、彼らが思い至ることはほとんどありませんでした。彼らの観察方法はアイデアを通してではなく、外的な比較によるものでした。実際、その観察にとって、顎間骨は人間の中には存在していなかったのです。彼らはゲーテが求めたもの、つまり、「精神の目をもって」見るということをほとんど理解しませんでした。彼らとゲーテの間で評価の仕方に違いがあるのもまたその理由からです。ブリューメンバッハが-彼もまた物事を非常に明確に眺めた人です-「これと真の顎間骨との間には、ひとつの世界ほどの違いがある」と結論づけたのに対して、ゲーテの場合には、「必然的な内的」同一性があるとすれば、そのような外的な相違は、それがいかに大きなものであったとしても、どのようにして説明できるだろうかと問うことによって物事が判断されたのです。ゲーテは今やこの考えを首尾一貫した仕方で仕上げようとしていました。1784年5月1日に、フォン・シュタイン夫人はクネーベルに宛てて次のように書いています。「ハーダーの最近の仕事は、私たちが始めは植物や動物だったかも知れないと思わせるものです・・・。今、ゲーテはこれらのことがらについて非常に慎重に考察しています。そして、彼の心をよぎるあらゆるものは、きわめて興味深いものとなっています。」。ゲーテは自然に関する彼の観点を主著の中で提示したいと望んでいました。その願望がいかに強烈なものであったかということは、新しい発見がなされるたびに、彼の考えが自然全体を包含するように拡大する可能性について友人たちに断固として語られたその力強さの中に生き生きと見て取ることができます。1786年に、彼は、いかに自然が、いわばひとつの主要な形態を巧みに操ることによって、その多様な生命を創り出しているかということについての彼の考えを自然のすべての領域、その王国全体に拡張するという彼の願望について、フォン・シュタイン夫人宛に書き送っています。そして、イタリアでは、植物界における変容の概念が、そのあらゆる詳細に至るまで、彫刻のような明快さをもって彼の精神の前に立ちました。1787年5月17日に、彼はナポリで「同じ法則をすべての生き物に適用することができるだろう」と書いています。彼の「形態論ノート」(1817年)の最初の随筆には、「こうして、私が若い頃の熱情の中で完成された仕事として夢見ていたものが、下書きとして、断片的なコレクションとして、今提示されることになりました」という言葉があります。結局、そのような仕事が彼のペンから流れ出すことは決してなかったというのは私たちにとって非常に残念なことであったと言わざるを得ません。私たちが手に入れることができるものだけから判断しても、そのような制作が行われていれば、これまでの時代に達成されたその種の仕事のいずれをも凌駕するものとなっていたはずなのです。それは原則に関する標準的な根幹になるとともに、そこからあらゆる科学的な努力がなされ、その精神的な本質をそれに即して評価することができるというようなものになっていたことでしょう。最も深遠な哲学的精神(*それがゲーテの中にあるのを見逃すのは表面的な心の持ち主だけです。)が、感覚的な経験を通して与えられるものへの愛に満ちた沈潜と、そこでひとつに結びつくというようなものになっていたはずです。彼の仕事は、ひとつの一般的なスキームにすべての存在が包含されると主張する体系に取りつかれた偏狭さとはかけ離れたものであり、個々人を正当に取り扱うものであったはずです。人間的な試みにおけるひとつの分野だけを他のすべてに対して偏重することもなく、それにもかかわらず、たとえ個別の課題に没頭しているときであっても人間存在全体がいつもその背後に存在しているような心による仕事がそこにあったはずなのです。こうして、個々の活動は全体との関係で正しい位置を占めることになり、その心は、それが考察すべき諸目標に客観的に沈潜するとき、完全にそれらの中に入っていくことになります。ですから、ゲーテの理論は対象物から抽出されたもののようにではなく、考察の中で自らを忘れ去る心の中で、対象物そのものから形成されているかのように見えるのです。この最も厳密な客観性はゲーテの仕事を科学的な仕事の中でも最も完成されたもの、あらゆる科学者がそこに向けて努力すべきひとつの理想にしたことでしょう。哲学者たちにとって、それは客観的な世界考察に関する法則を見出すための元型的な模範になったことでしょう。今や、いたるところで科学の哲学的な基礎として現われている認識論は、ゲーテの観察方法や考察方法をその参照点として据えるようになるまで、実り多いものとはならないだろう、と推測することができます。ゲーテ自身が、1790年の「年代記」の中で、その仕事が決して実現しなかった理由を、「それはあまりにも荷が重過ぎて、たった一回の取り乱した生涯の中で解決するのは不可能であった」からと述べています。この観点からすると、断片的に手に入れることができるゲーテの科学的な仕事の重要性は途方もないもののように思われます。実際、あの偉大な全体性から、いかにしてそれらが生じてきたかを私たちが理解しない限り、それらの価値を正しく推し量り、理解することはできないでしょう。とはいえ、1784年に、顎間骨についての論文がいわば単に予備的な習作として作成されることになりました。それは、ゲーテからゾンメルリンクに宛てた1785年3月6日の文書にあるように、さしあたり公表される予定はありませんでした。「私の小論は全く刊行の予定はなく、単に最初の草稿とみなすべきものです。ですから、あなたがこの課題について私と共有したいと思われるようなものであれば何であれ、喜んでお伺いしたいと思います。」。とはいえ、その計画は必要なすべての個々の研究とともに非常に注意深く達成されました。直ちに何人かの若い人たちが(ゲーテの指導の下で)描画を手助けするために招集されました。1784年4月23日に、ゲーテはこの方法に関する情報の提供をメルクに依頼するとともに、キャンパーの方法による描画を彼に送るようゾンメルリンクに頼んでいます。メルク、ゾンメルリンク、その他の知人たちはあらゆる種類の骨格や骨の提供を求められました。4月23日のメルク宛の手紙には、「myrmecopfagous(南アフリカアリクイ)、bradypus(ナマケモノ)、ライオン、虎、あるいはそれと同様の骨格を入手したいのですが」とあります。ゾンメルリンクは5月14日に象とカバの頭骨を、9月16日に山猫、ライオン、若い熊、アメリカマンモス、アリクイ、ラクダ、ヒトコブラクダ、そしてアシカの頭骨を依頼されています。彼の友人たちには特定の情報も求められました。メルクには、サイの口蓋についての記述、特に「実際、サイの角が鼻の骨の上についているのは何故なのか」ということについての説明が求められました。ゲーテはこれらの研究に完全に没頭していました。ヴァイツはキャンパーの方法にしたがって多くの角度から象の頭骨を描写しました。そして、ゲーテは、その頭骨の縫合線がまだほとんどと共に成長していないのを見て、自分が所有する大きな頭骨やその他の頭骨とそれとを比べてみました。その頭骨を調べているうちに、彼は重要な観察を行ったのです。他のすべての動物においては、顎間骨から生えているのは門歯だけで、犬歯は上顎骨に属しているが、象だけは例外であり、恐らく犬歯も顎間骨に属しているはずだ、と以前から考えられていました。今、その骨はそれが事実ではないということを示していたのですが、ゲーテはハーダーへの手紙の中でそのことを書いています。ゲーテの骨学研究は、その夏のアイゼナッハとブラウンシュバイヒへの旅の間も続けられました。彼は、ブラウンシュバイヒに滞在している間に「象の胎児の口の中を見て、ツィンマーマンと心からの対話を続けたい」と考えていました。彼はメルク宛にこの胎児についてさらに次のように書き送っています。「ブラウンシュバイヒにあるような胎児が私たちの保管庫にもあったなら、すぐにでも解剖して、骨格標本に仕立てることができるのですが。その内部構造を説明するために、それを分解しないというのであれば、そのような巨大なアルコール漬けの化け物が何の役に立つのでしょうか。」これらの研究は、キルシュナー文学全集のゲーテ自然科学論集第1巻に収録されている論文(編者注:「顎間骨は動物や人間の上顎に存在する」)になっています。ローダーはこの論文を作成するに当たって非常な助け手となり、彼の助力によってラテン語の語句が導入されました。彼はラテン語の訳も準備しました。ゲーテはその論文を、1784年の11月にはクネーベルに、12月19日にはメルクに送っていますが、その少し前(12月2日)までは、そのことで年末までに多くのことが生じるとは思っていませんでした。その仕事には必要な図表とともに、キャンパーのためのラテン語の訳がついていました。メルクはその仕事をゾンメルリンクに送ることになっており、彼はそれを1785年1月に受け取りました。そこからそれはキャンパーの元に届けられました。今、ゲーテの論文がどのように受け取られたかを見るならば、私たちはどちらかというと不愉快な場面に直面することになります。当初は、ゲーテが共に働いたローダーとハーダーを除いて、誰もそれを理解することができなかったのです。メルクはその論文を楽しみにしていましたが、その主張が真実であるとは確信していませんでした。ゾンメルリンクはその論文が届いたことを次のようにメルクに知らせています。ブリューメンバッハは既に主要なアイデアを有していました。彼(ゲーテ)の一節は、「したがって、疑問の余地はありません。それら(縫合線)の中の他のものは共に成長しているからです」というように始まっています。ただ問題は、それらが全く存在していないということです。私はここに3ヶ月から生まれる前までの胎児の顎の骨を持っているのですが、そのどれひとつにも前面に向かう縫合線は含まれていません。その説明は、骨が互いに押し合う圧力のためということになるのでしょうか。実際、自然がハンマーと楔を操る大工のように働いたと。」1785年2月13日に、ゲーテはメルク宛に「私はゾンメルリンクから全く思慮に欠ける手紙を受け取りました。彼は実際、そのことについて私と徹底的に話し合いたいのです。ああ、何ということでしょう。」と書いています。そして、1785年5月11日に、ゾンメルリンクはメルク宛に「昨日のゲーテからの手紙によると、彼は『顎間骨』に関する彼のアイデアを捨てる用意ができていないように見受けられます」と書いています。そして、キャンパーですが、彼は、1785年9月16日に、添付されていた図は確かに彼の方法によって描かれたものではない、とメルクに報告しています。彼はそれらが全く間違ったものであるとさえ思っていたのです。彼は美しい原稿の外観を賞賛しましたが、ラテン語の訳を批判し、著者にそのラテン語を磨くように示唆することさえしたのです。3日後、彼は、それまでに何度も顎間骨を観察したけれども、人間にはそのような骨は存在しないと主張し続けざるを得ない、と書いています。彼はゲーテの観察が正しいことを認めましたが、人間に関する観察は別でした。そして、彼は再び1786年3月21日に、多数の観察の結果、「人間には顎間骨は存在しない」と結論づけたと書いています。キャンパーの手紙が明確に示しているのは、彼はそのことがらについて調べることに全くやぶさかではなかったけれども、ゲーテを理解する能力には完全に欠けていた、ということです。ローダーはゲーテの発見を正しい光の下で直ちに理解しました。彼は1788年に出版された彼の「解剖学ハンドブック」の中でそれに重要な位置づけを与えるとともに、その後の彼のすべての著作の中で、疑う余地のない科学的に完全に受け入れられた事実としてそれに言及しています。ハーダーはクネーベル宛に「ゲーテは骨に関する彼の論文を私たちに示しましたが、それは非常に簡潔で美しいものです。この男は自然の中で真実の道を歩んでおり、幸運が彼に訪れています」と書いています。ハーダーは、ゲーテがそうしたように、本当にその「精神の目」をもって物事を見ることができたのです。その能力なしには、それと折り合いをつけることは全くできなかったでしょう。このことは、ゲッチンゲン大学の講師であったウィルヘルム・ジョセフィが彼の「哺乳類の解剖学」(1787年)の中で次のように書いていることからも分かります。「顎間骨」は人間とサルとを区別する主要な特徴のひとつであると考えられているが、私の観察によれば、人間もまた、少なくともその人生における最初の数ヶ月間は、そのような「顎間骨」を有している。しかし、それらは通常、非常に初期の段階から、実際、まだ母親の胎内にいる間に、特にその外側に関して、真の上顎骨と共に成長するため、しばしばそれらを見分けることができるような痕跡は残らない。ゲーテの発見は、実際、ここで完全に確認されることになるのですが、とはいえ、それは型の首尾一貫した仕上げの結果としてではなく、直接目で見ることができるものの表現として確認されたのです。もちろん、もし、目だけに頼るとしたら、それは偶然だけに、つまり、実際にそこでは物事を正確に「見る」ことができるような標本をたまたま見出すことができるかどうかにかかってきます。ところが、ゲーテのようにして、アイデアを通して物事を把握するならば、これらの特別な標本は単にアイデアを確認するためのもの、もしそうでなければ自然によって隠されていたであろうものを「おおっぴらに」表現するためのものとなります。とはいえ、アイデア自体はいかなる標本の中でも明らかなものとなり、それぞれの標本はそのアイデアの特別な例を表現するものとなります。私たちが実際にアイデアを有しているならば、正にそのアイデアを通して、それがもっとも明確に表現されているような標本を見出すことができます。しかし、アイデアなしには、私たちは偶然の恩恵を待つしかありません。実際、科学の共同体は、ゲーテがその偉大な考えを通してその衝動を与えた後で、多数の例を観察することによって、徐々に彼の発見の正しさを確信するようになったのです。メルクは迷い続けていたように見えます。1785年2月13日に、ゲーテは彼に、分離していた人間の上顎の骨とマナティーのそれとを一緒に送り、それらをいかに理解すべきかについてのヒントを与えています。4月8日のゲーテの手紙からは、メルクが多かれ少なかれ宗旨替えをしていたことが見て取れます。けれども、彼はすぐに再び考えを変えます。と申しますのも、1786年11月11日に、彼はゾンメルリンク宛に「ヴィック・ダジュールは実際、『ゲーテのいわゆる発見』を彼の本に含めたと聞いています」と書いているからです。ゾンメルリンクは徐々にその反対の姿勢を捨てるようになりました。彼はその「人体の構造について」という著作の中で次のように述べています。「上顎の顎間骨が動物と同様、人間にも見出されるということを、比較骨相学を通して示そうとした1785年のゲーテによる天才的な試みは、その非常に正確な図とともに、公的に認知されるに値する。」ブリューメンバッハの考えを変えさせるのはもっと困難でした。彼はその「比較解剖学ハンドブック」(1805年)の中で、人間には顎間骨がない、という彼の確信について主張しています。とはいえ、ゲーテはその随筆「動物学的な哲学の原則」(1830-1832年)の中で、ブリューメンバッハの改宗について語ることができるようになっていました。個人的なやり取りの後、彼はゲーテの側につくことになったのです。1825年12月15日に、彼はゲーテにその発見を実証する美しい標本を提供することさえしています。一人のヘッセン人アスリートが顕著に卓越して動物的な「顎間骨(がっかんこつ)」を手に入れるために、ブリューメンバッハの同僚であったラーゲンベックの助けを求めました。ゲーテの考えの擁護者については後でさらに議論する予定ですが、ここでは次のことをつけ加えるだけにしておきましょう。M.J.ウェーバーは、希釈した硝酸を用いて、上顎骨が溶解してもその後に残る顎間骨を単離することに成功したのです。ゲーテはこの論文を完成させた後も骨の研究を続けました。同時に行われた植物学上の発見は自然に対する彼の興味を強化しました。彼は関連する研究対象を友人たちから借り続けていました。1785年12月7日に、ゾンメルリンクは「ゲーテは骨を返してくれない」と怒り始めています。ゲーテがそれらの頭骨をまだ持っていたことは、彼のゾンメルリンク宛の手紙(1786年6月8日)から分かります。ゲーテの偉大な考えは彼と共にイタリアに赴くことになりました。元型的な植物についての考えが彼の心の中で形を取るようになっていたとき、彼は人間の形態についての概念をも発達させていたのです。1787年1月20日に、彼はローマで次のように書いています。「解剖学に関する準備は相当にできており、かなり努力したとはいえ、私は人体に関する知識をも獲得している。ここにある永遠に瞑想する彫像の傍らにいると、より高められた仕方においてではあるが、人の注意は絶えず人体へと引きつけられる。我々の医学的-外科的な解剖学はその各部分を知ることのみに関心があるので、その目的にとっては、情けない筋肉でも役に立つ。ところが、ローマでは、その各部分は、それらが高貴で美しい形態の一部でもあるということでない限り、何の意味も成さない。サン・スピリートの偉大な病院では、芸術家のために、非常に美しい筋肉組織のモデルが、人をその美しさへの称賛で満たすような仕方で、設置されている。それは皮を剥がれた半神半人、マルシャスでも通るだろう。ここでの習慣は、古代の習慣に従って、人為的にアレンジされた骨の塊としてではなく、それに生命と動きを与える靭帯とともに骨格を研究するということなのだ。」。注:顎間骨(がっかんこつ)または切歯骨。上顎骨の前部を占める一対の骨で,間顎骨または顎間骨ともいう。「人間では発生の初期に狭義の上顎骨と合着してしまう」が,一般に哺乳類ではよく発達し,終生,独立の骨として存在する。現代ではそれほど神秘的なものではなくなった。 ゲーテが主として求めていたのは、自然が有機的な形態、特に人間の形態を形成するときにしたがう法則、その形成に当たって、それにしたがうところの傾向に通じるということでした。ゲーテは、無数の植物形態の多様性のただ中で、それにしたがえば必然的に首尾一貫した植物を無数に創り出すことができるような元型的な植物、自然の傾向に完全に合致し、対応する条件さえ生じれば存在するようになる植物を探していたのですが、それと同様に、彼は、自然の法則に完全に合致した「理想的な特徴を発見する」ため、動物や人間を探求するつもりだったのです。イタリアから帰って間もなく、彼は「解剖学に熱心」となりました。そして、1789年には、ハーダー宛てに「新たに発見された『調和した自然』を提示したい」と書いています。彼の新しい発見は頭蓋の脊椎理論の一部だったと思われますが、この発見が完成したのは1790年になってからです。彼は、それ以前にも、頭の後ろ側を構成するすべての骨は三つの変化した脊椎骨によって表わされるということを知っていました。ゲーテはそのことを次のように考えていました。脳は最高度に完成された脊椎索物質の塊である。主として有機体下部の機能に仕える諸神経は脊椎索で終わると同時にそこから枝分かれしている、それに対して、より高次の精神的な機能に仕える神経、主として感覚神経は脳で終わると同時にそこから始まる。脳として現れるものは、潜在的にではあるけれども脊椎索の中に示されているところのものが単に十分に発達させられた形態を取ったものであるに過ぎない。脳とは十全に発達した神経索であり、神経索とは未分化の脳である。さて、脊柱の脊椎骨は脊椎索の様々な部分と完全に調和して形成され、それらを包み込むのに必要な保護構造を構成しているが、もし、脳が実際に可能な限りの高みへと引き上げられた脊椎索であるとすれば、それを包み込む骨もまた、より高次の段階へと引き上げられた脊椎骨に過ぎない、ということはあり得ることのように思われる。したがって、頭部全体が、より低次のレベルで存在する体的な器官の中で予め形成されていたように見える。付随的なレベルで活動する力はここでも働いているのであるが、それらは可能な限りの高みへと発達させられている。ゲーテはここでも、いかにそれが外的な現実の中に実際に現われているか、ということを確かめることだけに関心を持つようになります。彼は自分が非常に早くから、頭蓋の後部に当たる後頭骨や前と後の蝶形骨との関係で、この関連に気づいていたと述べています。けれども、彼の北イタリアへの旅の途中にリドの砂丘の間に散らばっていた羊の頭骨を見つけたとき、彼は、口蓋骨、上顎、そして、顎間骨もまた変化した脊椎骨である、ということに気づいたのです。羊の頭蓋骨は、その様々な部分が個別の脊椎骨であることを容易に見て取ることができるような幸運な仕方でバラバラに落ちていたのです。1790年4月30日に、ゲーテはこの美しい発見をフォン・カルプ夫人に示し、次のように言っています。「ハーダーに伝えてほしいのですが、私は、全体の成り立ちから見たときの動物の形態とその様々な変容へとますます近づいています。それも、非常に奇妙な偶然を通して」。この発見の重要性は非常に大きな広がりを持っていました。それは、ひとつの全体としての有機体のすべての部分はアイデアにおいて同等であり、「内に向かって形成されてはいない」有機的な塊が外に向かって広がっていくとき、それらは異なる仕方で発達するということを示していたのです。言い換えれば、ひとつの同じものが、より低次のレベルにおいては、脊椎神経として現れ、より高次のレベルにおいては、感覚神経として感覚器官へと至り、それが外的な世界を取り込み、把握し、理解するものになった、ということです。こうして、あらゆる生きものは、自らを内から外へと形成する能力の中で、形態を創造する力として現れました。つまり、今初めて、それを「真に生きた」実体として理解することができるようになったのです。ゲーテの動物の形成に関する根本的なアイデアもまたひとつの結論へと至りました。今やそれらを仕上げるときが来ていました。とはいえ、F.H.ジャコビとの往復書簡の中でも示されているように、彼はもっと以前にそれを行う計画でした。ゲーテが公爵に随行してシレジアの野営地(ブレスラウ、1790年7月)に赴いていたとき、彼は動物形態学の研究に没頭し、そこでその課題についての彼の考えをまとめ始めました。8月31日に、彼はフリードリッヒ・フォン・シュタイン宛に「この大騒ぎのただ中で、私は動物形態学に関する私の講話を書き始めました」と書いています。より大きな意味では、動物の型に関するアイデアは、1820年初版のゲーテの二番目の「形態学ノート」に掲載された詩「動物の変容」の中に含まれています。1790年から1795年まで、ゲーテは主として色に関する科学的な探求を行いました。1795年の初頭には、彼はフォン・フンボルト兄弟、マックス・ジャコビ、そして、シラーとともにイエナにいました。ゲーテは比較解剖学に関する彼のアイデアをこれらの友人たちに示したのですが、彼らはそれが非常に重要なものであると考え、それらを書き留めるように彼に促しました。ジャコビ兄へのゲーテの手紙は、彼の比較骨学に関する概略をマックス・ジャコビに書き取らせるという形で直ちにその提案を受け入れたことを示しています。その序章は1796年に仕上げられました。これらの講話には、ちょうど植物形態学に関する彼の観点が、その「植物の変容を説明する試み」(編注:「植物の変容」の原題)の中に見出されるように、ゲーテの動物形態学についての基本的な観点が含まれています。シラーとの交友(1794年に始まる)を通して、彼の観点は節目を迎えました。彼は今や、彼自身の研究方法を観察し、それによって、物事を観察する彼のやり方を「意識する」ようになったのです。私たちはこれらの歴史的な展開を追ってきましたが、これからは有機体の形成に関するゲーテの観点の本質とその重要性について考察していきたいと思います。 (第3章了)人気ブログランキングへ
2024年05月26日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説 並びに、精神科学(人智学)の基礎 (GA1)第2章 ゲーテの変容についての概念の起源 佐々木義之訳 有機的形態論に関するゲーテの考察について、その発達の歴史を辿るとき、確かに、詩人の若き日に、つまり、彼がワイマールに来る前の時代に何を帰せばよいのかと不思議に思うかも知れません。「外的な自然とは一体何なのかについて、いかなる概念も私にはなく、まして、そのいわゆる三つの世界についての知識などほとんどなかった」というように、ゲーテ自身が、その時代における彼の科学についての知識を高く評価してはいませんでした。この陳述からすると、ゲーテの科学的な考察が始まったのはワイマールに着いた後、1775年の彼が26歳のときからと一般には考えられます。とはいえ、彼の観点の全体的な精神を説明しないままにしておきたくないのであれば、もっと過去にまで遡る必要があるように思われます。彼の探求を以下に述べるような方向で導いた強力な衝動は既にその最初期の時代にその姿を現していました。ゲーテがライプツィヒ大学に入学したとき、そこでのすべての科学的な試みは、18世紀を通して特徴的であった精神、そして、その精神は科学全体を二つの極に分離し、誰もそれを統合する必要を感じていなかったのですが、そのような精神にまだ支配されていました。一方には、完全に抽象の領域に浸された存在論を演繹的科学とし、アプリオリに知ることができ、2 つの基本原則に基づいていると考えたクリスチャン・ヴォルフの哲学があり、他方には、際限なく続く詳細事項の外的な記述の中に自らを失い、探求すべき世界の中で、より高次の原則を見出す努力をしないままでいた科学の様々な分野があったのです。ヴォルフの哲学は、抽象的な概念の領域から直接的な現実の世界、個別存在の世界へと続く道を見出せないままでいました。もっとも明白なことがらが徹底した完璧さをもって処理されました。人が学んだのは、「もの」とは矛盾を含んでいないような何かである、実質には限定されたものと限定されないものがある等々というようなことがらです。けれども、それらの生命や働きを理解しようと試みる探求者が、これらの一般的なことがらをそれらのもの自体に適用しようとするときには、直ちに全く立ち往生することになりました。つまり、彼らは、その中に住み、理解しようとしている世界にそれらの概念を適用することができなかったのです。その代わりに、私たちの周囲にある実際的なものは、ほとんど何の原則も含んでいないような仕方で、つまり、純粋に、外見と外的な特徴にしたがって記述されていました。すべての生きた内容に欠け、直近の現実の中にきわめて忠実に没頭することのない原則の科学と、原則や理想的な意味に欠ける科学とが並び立っていたのです。これらは仲介されることなく対峙しており、それらのどちらも他方に実りをもたらすことがありませんでした。ゲーテの健全な特質にとって、そのどちらもその一面性において受け入れ難いものだったのですが、彼はそれらに立ち向かうことによって、後に彼を自然の生産的な理解、すなわち、そこではアイデアと経験とが完全な相互作用の中で、互いに互いを賦活させつつひとつの全体となるような理解なのですが、そのような理解へと導くことになる観点を発達させました.参考画:クリスチャン・ヴォルフ(christian_von_wolff) ですから、ゲーテはまず、それらの両極端には全く理解できないような概念、つまり「生命の概念」を発達させたのです。生きた存在は、その外観において観察されるとき、そのメンバーや器官として私たちの前に現れる個的なものの総体として自らを現します。これらのメンバーをそれらの形、相対的な位置、大きさ、等々において記述することは、上に述べた科学の第二の学派によって精力的に実行されるような種類の探求の目的です。とはいえ、無機的な物体が機械的に組み立てられているようなものであれば、このような仕方で記述することもできます。有機体を考察するとき、主として心に留めておくべきなのは、その外観は内的な原則によって支配されている、あらゆる器官の中には全体が働いているということであるということは全く忘れ去られていました。その外観、その構成要素の空間的な配置は、その生命が破壊された後でも検証することができます。何故なら、それはしばらく存在し続けるからです。けれども、私たちの前にある死んだ有機体は、本当はもう有機体ではありません。すべての個的なものの中に浸透していた原則は失われてしまったのです。以前には、ゲーテは、より高次の観点を得るという可能性と必要性のために、生命を破壊することによってそれを探求するというアプローチに直面していました。それは既に、1770年7月14日の日付がある手紙の中に見られます。当時、彼はストラスブールにいて、蝶について次のように書いています。「哀れな生き物は網の中でバタバタしながら、そのもっとも美しい色を撒き散らしている。そして、無傷で捕らえられれば、硬直し、生命なく、ピン留めされる。死体は生き物全体ではない、何か別のものがそれに属している。ひとつの重要なもの、そして、この場合、実際、その他あらゆるものの場合にも、それが主たるものなのだ、つまり、その生命が・・・。」。次のファウストからの言葉も同様の観点から生じてきます。「生きることの始まりを探求し、記述するためにその各部分から精神を追い出そうというのか、彼の手のひらの上にはすべての断片にないものなど何もない、精神とのつながりを除いては」 (ファウスト、1936-1939行)ものごとに対するひとつの見方を否定したままで満足するようなゲーテではなかったので、彼はますます自分自身の観点を発達させようとしました。そして、私たちが手に入れることができる1769年から1775年までの間の彼の考えを示唆するものの中に、彼の後の作品の種子となるものを見て取ることができます。その存在の各部分は他の部分を賦活し、その存在の中ではひとつの原則があらゆる個的なものの中に浸透している、そのような存在についての考えを彼は発達させていたのだということが次の文章から分かります。彼はファウストの中で次のように語ります。「全体の中ですべてが織りなしている。ひとつひとつが他のものの中に働き、生きて・・・」 (447-448行)そしてまた、ザティロス(第4幕)の中で語ります。「無から原初が生じ、光の力が闇を貫いて鳴り響く、存在の深みで炎が点火したのだ。願望に担われた創造の喜び、それらの要素は世界の中へと注がれる、渦巻く相手を互いに貪るように、すべてに浸透し、すべてが浸透される。」ゲーテはこの存在を、時間の中で絶えざる変化を免れないけれども、これらの変化のすべてを通して、いつでもただひとつの存在として自らを現し、変化のただ中にあって永続し、安定したものとして自らを主張する何かであると考えていました。ザティロスには、この根源のものについて、さらに次のような記述があります。「そして、上下左右に揺れながらやって来たのは、すべてでありひとつである永遠なるもの、いつまでも変化し、どこまでも続くもの。」。この文章と、変容についての研究の導入部分として1807年にゲーテが書いた次の文章とを比較してみてください。「けれども、もし、私たちがすべての形態を、とりわけ有機的な形態を観察するならば、永続的なるもの、完成され、静止しているものなど何もない」すべては絶え間なく揺れ動いているのだということが分かります。この流れと対照的なものとして、今やゲーテはアイデアあるいは「何か単にしばらくの間、経験の中にしっかりと保持されているようなもの」を「一定のもの」として仮定します。ザティロスの一節から、ゲーテの認識論的なアイデアの基礎は既に彼がワイマールに来る前に敷かれていたということに全く明確に気づくことができます。けれども、気をつけなければならないのは、この生きた存在についてのアイデアは個別の有機体、宇宙全体はそのような生きた存在には適用されていなかったということです。もちろん、この概念は、ゲーテがライプツィヒから帰還した後(1768-1769年)、フォン・クレッテンベルグ嬢とともに行った錬金術的な研究、そして、テオフラストゥス・パラケルススを読んだことにその起源を有しています。当時、何らかの種類の実験によって、宇宙全体に浸透する原則を明らかにする、つまり、何らかの実質を通してそれが現れるようにするという試みがなされました。けれども、この種の「神秘的なるもの」と境を接するような世界の見方は、ゲーテの発達過程における一時的なエピソードを構成しているに過ぎず、すぐに、より健全で客観的な考え方へと道を譲っています。とはいえ、宇宙全体をひとつの大いなる有機体として見る観点は、ファウストやザティロスの一説の中に示されているように、1780年頃までゲーテの考えの中で不可欠なものとして残りました。そのことは後で彼の随筆「自然」との関連で見ていきたいと思います。普遍的な有機体に浸透する生命原則としての地球の精神については、ファウストの次の箇所でも記述されているのが分かります。「生命の潮の中で、行動の嵐の中で、あちらこちらと私は波打つ、永遠に織りなせ!誕生と墓場、永遠の海、変化に満ちた闘い、輝く生命。」 (501-507行)ゲーテはこうしてある観点を発達させる一方で、ストラスブールにおいて、彼自身の世界観に真っ向から反対する世界観を確立しようとしていた本、ホルバックの「自然の体系」に出合います。それまでのゲーテは、生きているものを個的なものの機械的な寄せ集め「であるかのように」記述しようとする傾向を、単に批判していればよかったのですが、彼は今や、ホルバックにおいて、生きた有機体を実際に機械的なものであると「見なす」哲学者に出会ったのです。以前には、単に生命の根幹を認識できないことから生じていたものが、ホルバックにおいて、生命を否定するドグマへと導かれていました。彼は彼の自叙伝「詩と真実」の中で次のように書いています。「物質は、永遠の昔から存在し、運動の中にあったかのように考えられていた。そして、今や、何のさらなる骨折りもなく、その運動によって、右や左に、そして、あらゆる方向に、際限のない存在という現象を生じさせることになっていた。もし、その著者が、私たちの目の前で、彼の活動する物質から本当に世界を作り出していたのであれば、私たちはそれで満足していたことだろう。しかし、彼は私たち以上に自然について知っていたとは言えないのかも知れない。何故なら、彼は、二乃至三の一般的な概念へと突き進むやいなや、自然よりもより高次のもの、あるいは、自然の中のより高次の自然のように見えるものを、物質、つまり、より重い要素、確かに、活動してはいるけれども、方向性も形もないものへと変換するために、すぐにそれらの概念から離れ、それでかなりのことを達成したと考えているからである。」ゲーテはこれらすべての中に何も見出せなかったのですが、「動きの中にある物質」に関しては、それに反対したことで、彼自身の自然についての概念がますます明確な形を取ることになりました。これらのことは、1780年頃に書かれた彼の随筆「自然」の中で、首尾一貫した全体として提示されているのが分かります。それまでただ散見されるだけだった自然についてのゲーテの思考のすべてがそこにまとめられていることから、この随筆は特別な重要性を帯びることになります。「私たちはそこで、絶えざる変化を蒙りながら、それでも同じものとして留まる存在についてのアイデアに出会います。すべては新しく、それにもかかわらずいつでも古い・・。彼女(*自然)は永遠に自らを変容させ、彼女の内には一瞬たりとも立ち止まるものはないけれども彼女の法則は不変である。」。後で見ていくように、ゲーテはここで既に示唆されているような考え、つまり、植物形態の際限のない多様性の中のひとつの原型的な植物というものを追求していました。彼女(*自然)の働きのひとつひとつがそれ自身の存在を有しており、そのそれぞれの表現は最も孤立した概念を有しているが、それでも、すべてが「ひとつ」を構成している。実際、例外に関する彼の後の立場、つまり、例外を単に不完全な形成と見なすのではなく、自然法則の現われであるとして説明する立場でさえ、既に、「最も不自然なものでさえ自然であり、例外はまれである」というようにきわめて明確に表現されているのです。私たちはゲーテが既にワイマール以前にも、有機体についての明確な概念を発達させていたということを見てきました。と申しますのも、「自然」は彼のワイマール到着のずっと後に書かれたとはいえ、そこに含まれているのは概して彼の初期の観点だからです。彼はその概念を自然現象の個別の秩序、すなわち個々の生物にはまだ適用していませんでした。それを行うためには、生きた自然という現実の世界に直接接近する必要があったのです。ゲーテは人間の心をよぎる反映されたものとしての自然による刺激を受けていませんでした。ライプツィヒで行われた枢密顧問官ルードヴィッヒとの植物学についての会話やストラスブールで行われた医者仲間との夕食会での会話もより深い影響を与えることはありませんでした。若きゲーテはその科学的な探求の中で正にファウストのようにして現れます。直接的で新たな自然の眺めを奪われたファウストはそれへのあこがれを次のように表現しています。「ああ、高い山の上で あなたの月のやさしい光の中で 洞窟や木々の間をさまようことができさえしたら。夕暮れ時に曲がりくねった・・・。 (392-395行)この思いは、ゲーテがワイマールに到着して、「部屋と都会の空気が、田舎と森と庭にとって代わられたとき」に満たされたように見えます。詩人が植物の研究に乗り出すことになった直接の動機は、彼がカール・アウグスト公から賜った庭の植栽に関わったことであったということが分かります。彼がその庭を受け取ったのは1776年4月21日だったのですが、彼の日記(*カイルにより編纂されたもの)には、それ以降、しばしば彼がこの庭で仕事をしたことが記されており、それは彼のお気に入りの時間のひとつになっていました。チューリンゲンの森によってこの種の活動の場はさらに追加されたのですが、より下等な有機体に関する現象を知る機会をそこで持つことになりました。彼が特に興味を持ったのはコケや地衣類でした。1777年10月31日、彼はフォン・シュタイン夫人に、繁殖させることができるよう、できるだけ根と湿り気がついたままのあらゆる種類のコケを依頼しました。ゲーテが当時、既にこれらの下等な生物の世界に関わっていたこと、それにもかかわらず、後に高等植物の組織に関する法則を導き出したという事実はきわめて意義深いことであると考えなければなりません。以上の状況から、その事実は、多くの評論家がそうしてきたように、彼がより未発達な有機体の重要性を過小評価していたことにではなく、十分に意識的な意図をもっていたということに帰せられると考えられます。それ以後、詩人が植物の世界を離れることは決してありませんでした。彼が当初からリンネの著作を取り上げていたことはほぼ間違いありません。彼がそれらに通じていたことが分かるのは、フォン・シュタイン夫人に宛てた1782年の手紙からです。「植物についての知識に体系的な概観をもたらそうとしたのはリンネです。彼が目指したのは、あらゆる有機体がその内部で特定の場所を占めるような明確な系統的法則、それらをいつでも容易に特定できるような、実際、その無限の多様性の中で方向づけを行うための方法となるような系統的法則を見つけるということでした。そのためには、植物が相互に関連する度合いを検証し、それに応じてグループ分けする必要がありました。主要な点は、いかなる植物であってもその体系の中で同定し、容易に分類するということでしたから、特にある植物を別の植物から区別するための特徴に注意が払われなければなりませんでした。混乱が生じないように、主としてこれらの区別を行うための特徴が追及されたのです。こうして、リンネと彼の門下生たちは、「外的な特徴」大きさ、数、個々の器官の位置を特徴的なものと見なしました。植物は確かに系統的に秩序づけられましたが、一連の無機物もまた同様の方法で整理することができるような仕方、つまり、植物の内的な本性から捉えられるのではなく、それらの外観から捉えられるような特徴によって秩序づけられたのです。それらが秩序づけられたその仕方は、必然的な内的結びつきに欠けた表面的なもののように見えます。ゲーテは生きた有機体についての特別な概念を有していたので、このような仕方で植物を見ることで満足することはありませんでした。何故なら、それは植物の根本的な特質へのいかなる探求も含んでいなかったからです。ゲーテは「ある自然存在を植物にしているものとは何か。」と自問せざるを得なかったのです。さらに言えば、彼は、それが何であれ、すべての植物において同様に生じなければならないということを認めざるを得ませんでした。そして、それでも個々の実体は無限に多様化しており、それは説明を要するものとしてそこにあったのです。この一体性はいかにしてそのように多様な形態の中で自らを現すのか。ゲーテがリンネの著作を読んだときに生じた疑問とはそのようなものであったに違いありません。と申しますのも、彼自身が「彼、リンネが無理に引き離そうとしたものは、私自身の最奥の衝動にしたがえば、ただ一体性に向けて苦闘しているだけのように見える」(「わが植物研究の歴史」)と述べているからです。ゲーテがルソーの植物学上の研究に出会ったのは、彼が最初にリンネを知ったのとほぼ同時期でした。1782年6月16日に彼はカール・アウグストに次のように書き送っています。ルソーの仕事の中には、植物学についてのすばらしい手紙類がありますが、その中で彼はこの科学をひとりの夫人に最高に明瞭かつ魅力的な仕方で説明しています。それは本当に教え方の模範となっており、「エミール」の補足にもなっています。ですから、私は今、この機会を利用して、私の友人である美しいご夫人たちに美しい花の世界をお勧めしたいと思います。ルソーの植物学上の研究はゲーテに深い印象を与えずにはおきませんでした。植物の本性に対応して生じてくる命名法の強調、観察の独創性、いかなる実利的な考察からも距離を置く植物そのものへの熟考-ルソーの仕事が有するこれらすべての側面はゲーテに強く訴えかけたのです。二人に共通していたのは、彼らが植物研究に取りかかったのは、何か特別な科学的目的があったからではなく、むしろ純粋に人間的な動機からであった、ということでもあります。同じ興味が同じ課題へと彼らを引きつけたのです。次にゲーテが植物界について徹底的な観察を行ったのは1784年のことでした。ルースヴュルムと呼ばれるウィルヘルム・フライヘール・フォン・グライヒェンは、「植物界からの最近の便り」、「植物、花、昆虫、及びその他の注目すべき事物との関連で、顕微鏡を用いてなされた代表的な発見」という探求を取り扱う二つの仕事をちょうど出版していたところでしたが、それらはゲーテの興味を強く引くところとなりました。それらの著作はいずれも植物の受精過程を取り扱っていました。花粉、雄しべ、雌しべが注意深く調べられ、それらの内部で生じるプロセスが美しく設えられたプレートに描写されました。今度はゲーテがそれらの調査を追試します。1785年4月2日、彼はF.H.ジャコビに「私は種の問題について、私の経験が許す限りにおいて、よく考えてみました」と書き送っています。これらの探求すべてにおいて、彼は細かなことがらには興味がありませんでした。つまり、彼の努力が目指していたのは、植物の本質的な特質を探究する、ということでした。1785年4月8日、彼はメルクに「植物学における満足のいく発見と組み合わせを見つけた」と報告しています。「組み合わせ」という表現は、彼の意図が植物界におけるプロセスの思考像を構築することにあった、ということをも示しています。彼の植物学の研究は明確な目標に向かって急速に接近していました。当然のことながら、この関連で私たちが心に留めておかなければならないのは、ゲーテは既に1784年に顎間骨を発見しており、それによって彼は自然が有機体を形成する仕方についての秘密に近づくための重要な一歩を踏み出していた、ということですが、そのことについては後で詳細に議論する予定です。私たちはまた、ハーダーの「人間性の歴史に関する哲学の考察」は1784年に完成し、当時ゲーテとハーダーとは自然に関することがらに関してしばしば会話していた、ということを心に留めておかなければなりません。そこで、フォン・シュタイン夫人は1784年5月1日に、クネーベルに次のように報告しています。「ハーダーの新しい作品は、私たちが最初は植物や動物だった可能性を示唆しています・・・今、ゲーテはこれらについて非常に深く思索しているのですが、彼の心に浮かんだあらゆることがらはとても興味深いものとなっています。」。これは、当時、最大の科学的な問題であったところのものに対するゲーテの関心の特質を示しています。したがって、彼の植物の特質に関する思索と1785年春における彼の「組み合わせ」は全く包括的なもののように見えます。その年の春、彼はその疑問や問題を急いで解くためにベルヴェデールに赴きました。そして、5月15日にはフォン・シュタイン夫人にそれを伝えています。自然という本が私にとっていかに読みごたえのあるものになっているか、とてもお伝えすることができそうもないほどです。お手紙をお書きするたびにずっと解明しようとしてきた私の努力が役に立ちました。今や全く突然、それが効果をあげ始めており、私の静かな喜びは表現しようもないほどです。この少し前には、彼は簡単な植物学の論文を書いてクネーベルをこの科学に引き込もうとさえしていたのです。(R.シュタイナーによる注:1785年4月2日付けのクネーベル宛の手紙には「もし、既に植物学についての課題が書けてさえいたら、喜んで貴方にお送りしたところなのですが」とあります。)彼は植物学に強く惹かれていたので、1785年6月20日に始まり、その年の夏をそこで過ごすことになるカールスバッドへの旅は植物探査旅行となりました。彼に随行したのはクネーベルです。イエナの近くで彼らは17歳のディートリッヒに出会ったのですが、その標本箱は彼がちょうど植物採集の帰りであることを示していました。この興味深い旅行については、ゲーテの「わが植物研究の歴史」と、ディートリッヒの原稿にもとづいてブレスラウのコーンが書いた報告書からもっと詳しく知ることができます。カールスバッドでは植物学についての会話がしばしば楽しいひとときを提供することになったのです。旅から帰ったゲーテは植物学の研究に大いに力を注ぎました。リンネの「植物学」の助けを借りて、彼がきのこ類、コケ類、地衣類、藻類の観察を行ったことは、フォン・シュタイン夫人への手紙から分かります。彼にとってリンネがより役に立つようになったのは、彼が多くのことを考え、観察した後でのことに過ぎません。つまり、彼はリンネを通して多くの詳細なことがらについての情報を見出したのですが、そのことが彼の「組み合わせ」を前進させるために役立ったのです。彼は1785年9月9日付の手紙でフォン・シュタイン夫人に次のように報告しています。私はリンネを読み続けていますが、他の本が手元にないので仕方がありません。私にとって本を最後まで読むというのは簡単なことではなく、一冊の本を意識的に読むというのは最もよい方法ですから、もっとしばしばやるべきことでしょう。この本は読むというより要約するようにできていますから、私にはとても役立ってくれています。と申しますのも、私はその重要な点のほとんどを自分で考えてみたからです。この研究の過程を通して、「個々の植物の無限の多様性として現れるものは、結局のところ、たったひとつの基本的な形態である」ということがますます明確になってきました。すなわち、この基本的な形態そのものがますます知覚可能なものになってきたのです。さらに彼は「この基本的な形態の内部に横たわっているのは、それによって統一性から多様性が生み出されるところの無限に変化する能力である」ということに気づきました。1786年7月9日、彼はフォン・シュタイン夫人に「それはいわば、自然がいつもそれとともに単に戯れながら、そして、その遊びの中でその多様な生命を生み出しているところの形態に気づくようになるということです。」と書き送っています。今や彼が必要としていたのは、この持続する一定の要素、いわば自然がそれとともに戯れるところのこの元型的な形態を取り上げ、それを詳細に把握することができるような像へと発展させる、ということでした。これを行うために、彼は植物形態における真に一定で持続する要素から変化するもの、移ろい易いものを分離する機会を必要としていました。ゲーテの探求は、この種の観察を行うにはまだあまりにも視界が狭かったのです。彼は同一種の植物を異なる状況や影響の下で観察しなければならなかったでしょう。何故なら、そのときだけ移ろい易い要素が本当に可視化されるようになるからです。それは異なる種の植物においてはそれほど顕著ではありません。このすべては、9月3日にカールスバッドから旅立ったイタリア旅行によって叶えられました。アルプスの植物相によって、彼は多くの観察の機会を与えられました。ここで彼が見つけたのは、彼が初めて見る植物ばかりではなく、既に知っていたものもあったのですが、それらは「変化していた」のです。[低地では、葉柄や茎はより強く、より厚みがあります。芽はより密集しており、葉はより広くなっています。山の高いところでは、葉柄や茎はより繊細なものとなり、芽は互いにより離れるようになり、そのため、節と節の間にはより広い空間ができています。そして、葉は槍の先のような形態を取るようになります。これは柳やリンドウにおいて見られますが、それらは別の種ではないと私は確信しています。バルヒェンゼー(バイエルン)でも、イグサは低地のものより長く、細くなっているのが見られます。(「イタリア紀行」、1786年9月8日)]。同様の観察が繰り返し行われました。[海の側のベニスでは、砂交じりの土の古い塩だけが、さらに言えば、塩気のある空気だけが与えられるような特徴を示す様々な植物に出会いました。彼がそこで見つけたのは「私たちが知っている無垢のフキタンポポではあるが、鋭い武器で武装し、皮のような葉と、同じく鞘や茎も皮のようになった、つまり、すべてが厚く、太くなった」(同、1786年10月8日)植物でした。]ゲーテは植物の外的な特徴、すなわちその外観に属するあらゆるものの不定性、絶えず変化する特質に出会っていました。このことから、彼は、植物の本質はこれらの特徴にではなく、より深いレベルで探さなければならないと結論づけたのです。ダーウィンが類や種の外的な形態の一定性についての疑問を提示したときも同様の観察に基づいていました。しかし、二人の思索家が到達した結論は全く異なるものでした。ダーウィンは、実際、有機体の本質はそのような外的な特徴に限定されると信じており、その可変性から見て、植物の生命には何ら一定のものはないと結論づけたのに対して、ゲーテはさらに深く追求し、もし、外的な特徴が一定でないのであれば、一定であるところのものは、そのような変化する外面性の下に横たわる何か別のものの中に探さなければならない、と結論づけたのです。この「何か別のもの」の概念を発展させることがゲーテの目的になったのに対して、ダーウィンの努力は有機体の多様性の原因を詳細に探求し、説明することに向けられました。両方のアプローチが必要であり、互いに補い合うものとなります。有機的な科学におけるゲーテの偉大さは彼がダーウィンの先駆者であったことによる、と単純に信じるのは全くの間違いです。ゲーテのアプローチはもっとはるかに広範なものだったのです。それは二つの側面を含んでいます。ひとつは元型―すなわち、有機体の中に現われる法則性、及び動物の中に現れる動物存在、すなわち、それ自身から展開する生命、様々な外的形態(種、類)において、その内部に横たわる可能性を通して、自ら発展する力と能力を有する生命であり、もうひとつは有機体と無機的な自然との相互作用、並びに、有機体同士の相互作用(適合と存在に向けた苦闘)です。ダーウィンは有機的な科学における後者の側面だけを発展させました。ですから、ダーウィンの理論はゲーテの基本的なアイデアを進化させたものである―それは実際には、それらのアイデアのひとつの側面を発達させたものに過ぎません-と言うことはできません。それは、生きた有機体の世界が一定の仕方で展開する原因となる諸事実のみを見るのであって、それらの事実に決定的な影響を及ぼすものとされる「何か」を見ることはありません。このひとつの側面だけを追求しても有機体に関する完全な理論へと導かれることは決してありません。そのような理論は、本質的に、ゲーテの精神において追求されなければなりません。このひとつの側面は、彼の理論の別の側面を通して補足され、深化させられなければならないのです。ものごとをより明確にするために単純な比較をしてみましょう。鉛を取り上げ、それを液体になるまで加熱した後、水に注ぐとしましょう。鉛は連続する二つの段階を通過することになります。つまり、それは二つの状態、最初は高温によって生じる状態、二番目に低温によって生じる状態を通過します。二つの段階がどのような形態を取るかは、単に熱と冷たさの性質だけによるのではなく、全く本質的に、鉛の性質自体にも依存します。異なる実質は、同じ影響に曝されても、非常に異なる変化を示すでしょう。同様に、有機体もその環境からの影響を受けますが、それらの影響を受けるときに彼らが取る状態は異なります。そして、彼らは、正に彼らの性質にしたがって、つまり、彼らを有機体として成り立たせている本質的な存在にしたがってそうするのです。そして、私たちがゲーテのアイデアの中に見出すのはこの本質的な存在なのです。それについて、つまり、彼らの本質的な性質であるところのものについて理解するときにのみ、私たちは、何故、有機体がある特定の影響に対して一定の仕方で反応するのか、何故、別の仕方では反応しないのか、ということを理解することができます。そのとき初めて、有機体が表現する形態の多様性、そして、それに関連するそれらの適合と生存競争を支配する法則についての正しい観点を形成することができるのです。(R.シュタイナーによる注:この観点は現代の進化論に疑問を投げかけるものではなく、その主張を制限しようとするものでもないということを明確にしておかなければなりません。逆に、それはそのような主張にとってしっかりとした根拠を打ち立てるものです。)。元型的な植物についてのアイデアはゲーテの心の中でますます明確ではっきりとした形を取っていました。見知らぬ植物相のただ中で移動したパドヴァの植物園では、「多分、ひとつのものからすべての植物形態を発展させられるだろう、という考えがますます生き生きとしたものになって」きました(イタリア紀行、1786年9月27日)。11月17日に、クネーベルに次のように書き送っています。結局、こうして私の若干の植物学は私に大いなる喜びを与えてくれます。より幸福で、より妨害を受けることの少ない植物相がくつろいでいるこのような土地では特にそうなのです。私は既に一般的なものへと向かう傾向を持つかなり喜ばしい観察、貴方もまたそれを心地よいと思われるような観察を行いました。1787年2月19日に、彼はローマで、「新しく美しい関係性、その自然、その膨大さ、筆舌に尽くしがたい豊かさが、いかに単純なものから多様性を発達させるかということを見出す」途上にあると書いています。5月25日に、彼は、彼が間もなく元型的な植物についての準備を整えるはずだということについて知っておいてほしいとハーダーに頼みます。4月17日には、彼はパレルモで元型的な植物について次のように書いています。「確かに、そのようなものがあるはずだ。もし、そうでなければ、もし、それらすべてが同じ型にしたがって形成されないとすれば、私はどうしてあれこれの形態が植物であると認識することができるだろうか。(イタリア紀行)」彼が心に抱いていたのは、植物を組織し、植物を植物にしている形成的な原則-それを通して自然の中の特定の対象が私たちの中に「これは植物である」という思考を引き起こすところの形成的な原則の複合体、つまり、元型的な植物でした。したがって、それは何か理想的なもの、つまり、思考においてのみ把握できるとはいえ、形態を取ることができるもの、特定の形態、大きさ、色、器官の数、等々を取るようなものです。この外的な現象は何ら固定されたものではなく、無限の多様性を経験することができ、そのすべてがあの形成的な原則の複合体と調和しながら、必然的にそれから生じるものです。私たちがこれらの形成的な原則―植物のこの元型的な像―を把握するということは、自然がそれに基づいてあらゆる個々の植物を基礎づけるところの正に根幹、彼女がそこから植物を導き出し、それを通してそれが存在するようになるのを許すところの根幹をアイデアとして把握するということです。実際、人は、この法則性にしたがえば、植物の本質的な性質から必然的に生じるような植物形態を作り出すことさえできるでしょう。そして、もし、必要な条件が生じれば、それは存在することができるでしょう。こうして、ゲーテは自然がその形成する働きの中で達成するものを思考において再現しようとします。1787年5月17日に、彼はハーダーに次のように書き送っています。「もっと言えば、私が植物の発生と組織化の秘密にきわめて近づいているということを貴方に打ち明けなければなりません。そして、それは考え得る最も単純なことです。元型的な植物は世の中で最も途方もない生き物であり、そのために自然そのものが私をうらやむことでしょう。この型とそれへの鍵をもってすれば、人は首尾一貫した植物を際限なく作り出すことができるでしょう。言い換えれば、たとえそれらが存在していないとしても、存在する可能性があり、画家や詩人の単なる思いつきではなく、内的な真実と必然性を有しているのです。同様の法則を生きとし生けるものすべてに適用することができるでしょう。(同)」。この時点で、ゲーテの観点とダーウィンのそれとのさらなる違いが明白になりますが、後者が通常どのように表現されているかを考えるとき、それは特に明白になります。(R.シュタイナーによる注:私たちはここで、経験的な事実に基づいて結論づける科学者たちが持ち出す進化論についてそれほど言及しているわけではなく、むしろ、ダーウィン主義の下に横たわる理論的な基礎あるいは原則、特に、ヘッケルに率いられたイエナ学派によって提示されるようなものですが-に言及しているのです。ダーウィン主義的な理論は、この第一級の知性において、その一面性にもかかわらず、その最も首尾一貫した表現へと至りました。)。この観点が想定しているのは、外的な影響は有機体の性質に対して機械的な原因として働き、そのようにしてそれを変化させるということです。ゲーテにとって、個別の変化は元型的な有機体の様々な表現です。そして、その元型的な有機体はその内部に多様な形態を取る可能性を有しており、いつの場合にも、その周囲の状況に最も適した形態を取ることになります。これらの外的な状況は内的な形成力が特定の仕方で現れるための外的な誘引に過ぎません。植物の中で、これらの力だけが本質的な原則、創造的な要素なのです。したがって、ゲーテは1787年9月6日に、それらを植物世界における「ひとつであり、すべてであるもの」と呼んだのです。さて、私たちがこの元型的な植物そのものを考察するとき、次のように言うことができます。生きているものとは、いずれにしてもそれ自体から様々な状態を生じさせるところの自立した総体であると。すべての生きた実体は、その構成部分の感覚的に知覚可能な特徴、あるいは、それによって以前の段階が後の段階を決定づけるような何らかの種類の機械的な因果関係によっては決定づけられないと思われるような相互作用を、その構成要素の空間的な配置においても、その時間的に遷移する段階においても現します。それらの相互作用は、むしろ、その構成要素やその段階よりも上位に立つところのより高次の原則によって支配されているのです。ある一定の段階が最初に生じ、別の段階が最後に生じるというのは総体的であるものの本質的な特徴であり、継続する中間段階もまた総体という考え方の中で決定されます。つまり、初めに来るものは最後に来るものに依存し、逆もまた真なのです。要するに、生きた有機体においては、あるものからあるものへの「展開」、ある段階から別の段階への遷移があるのであって、何か特別なものが完成し、完了した状態で存在するのではありません。そうではなく、絶えざる生成があるのです。植物の中で、このように各々の構成体が総体によって個別に決定されるのは、その器官のすべてが同一の基本的な形態にしたがって構築されているからです。1787年5月17日に、彼はこの考えをハーダーに次のように伝えています。私は、私たちが通常葉と呼ぶところの植物の器官は真のプロテウス(著者注:いかなる形態を取ることもできるギリシャの神)を有しており、それはすべての形態の中に自らを隠すこともでき、現すこともできます。後にも先にも、植物は葉に過ぎず、それは未来の種子と不可分に結びついていて、その結びつきは、片方を他方なしには考えられないほどです。動物においては、すべての個体を支配する、より高次の原則は、その器官を動かし、それらをその必要にしたがって用いるところのものとして、具体的に、私たちのところにやってくるのに対して、植物はまだそのような手に取るように分かる生命の原則を欠いています。その生命の原則はより不明確な事実、つまり、そのすべての器官が同じ形成する型にしたがって構築され―実際、植物全体が可能性としてその各々の部分の中に存在しており、適当な条件下では、それがそれらの部分から産み出される―という事実の中に現れるに過ぎません。ゲーテにとってそのことが明確になったのは、顧問官ライフェンシュタインとローマで散歩していたときに、彼があちこちで小枝を折って、もし、それらが地面に突き刺さったならば、一本の植物にまで育つだろう、と言ったときです。ですから、一本の植物とは、時間の経過とともに、同一のアイデアにしたがってすべてが構築されるような特定の器官、そして、それらの器官は互いに関連しており、各々の器官は全体と関連しているのですが、そのような器官を発達させる存在なのです。各々の植物は、植物たちから構成される調和した総体です。(R.シュタイナーによる注:正にこれらの個体がいかに全体と関係しているかについては、この序論の中の様々な箇所で議論されることになるでしょう。生きた部分的実体から構成される全体という概念を現代の動物学から借りれば、昆虫の群れの例を取り上げることができるでしょう。これは一種の生きた存在たちの共同体、独立した個体から構成される個体、より高次の種類の個体です。)ゲーテにはそのことが明らかにななりましたが、唯一残された課題は、展開する植物の様々な発達段階を詳細に記述することが可能になるような個別の観察を行うということでした。そのために必要な下地は既にできていました。私たちが見てきたように、ゲーテは既に1785年の春には、種子に関する研究を行っていました。1787年5月17日に、彼はイタリアから、胚が隠されるポイントを非常に明確に、かつ疑いもなく発見した、とハーダーに報告しています。これは植物の生における最初の段階に当たります。けれども、すべての葉の形成における統一性もまた間もなく明らかになりました。無数の例がありましたが、とりわけ新鮮なフェンネルにおいて、上方の葉と下方の葉が同じ器官であるにもかかわらず、強力に分化しているのを見出しました。3月25日(1787年)に、彼はハーダーに、子葉についての彼の研究はあまりにも昇華され過ぎており、先に進めるのは困難である、ということを知っておいてほしいと頼んでいます。花弁、雄しべ、雌しべもまた変化した葉である、ということを認めるためには、わずかな一歩しか残っていませんでした。英国人の植物学者ヒルの研究は、当時、より一般的に知られるようになっていましたが、それは花の特定の器官の別の器官への変化を取り扱うものでした。その関連で、それはゲーテのための道ならしとなりました。図1.花びらから雄しべへの変化=参考画:Change from petals to stamens 植物存在を組織する力が実際に存在するようになるとき、それらは空間的な形成過程を取ります。今や、求められているのは、これらの形態を前後に結びつける生きた概念でした。 1790年に(「植物の変容」の中で)定式化された変容についてのゲーテの研究を検証すれば、ゲーテにとってこの概念は交代する拡張と収縮の概念であった、ということが分かります。種子においては、植物の形成は最も強く収縮あるいは濃縮されています。葉で起こっているのは形成力の最初の発現と拡張です。種子において一点に圧縮されたものは、今や葉において外に向かい、空間の中へと到達します。蕾の中では、力は再び萼の軸を中心に集まります。花冠は次の拡張の結果です。雄しべと雌しべは次の収縮によって生じ、果実は第三の、そして最後の拡張を通して生じます。そして、植物の生命力全体(その活力原則)は再び最も強力に収縮した状態である種子の中に隠されます。さて、私たちはゲーテの変容についての考えを、1790年の随筆の中で、その最終形に至るまで、ずっと追っていくことができます。しかし、拡張と収縮についての彼の概念に関しては、それはそれほど容易ではありません。とはいえ、この考え(ついでに言えば、それはゲーテの精神に深く根ざしていました)は、イタリアにおいて、既に彼の植物形成についての概念の中にも織り込まれていた、と考えても間違いはないでしょう。拡張と収縮についての概念は形成力にしたがって決定されるような多かれ少なかれ空間的な展開を含んでおり、直接目に見えるような形で提示されるので、私たちがその自然な形成にしたがって植物を描けば、その概念は非常に容易に生じてくる、ということは確かでしょう。ゲーテはローマで潅木のようなカーネーションを見つけたのですが、その中で彼は特別な明晰さをもって変容を知覚することができました。このすばらしい形態を保存する方法を見つけられなかったので、私はその正確な描写を試みました。そして、それによって、私は変容についての基本的な概念に対する洞察を深めたのです。彼はそのような描写をしばしば行い、それによって、当の概念に導かれたのかも知れません。1787年9月、再度ローマに滞在していたゲーテは友人のモーリッツにその問題について、つまり、そのような描写を通して、それがいかに生きた活力あるものになるかが分かった、ということについて解説しています。何かが議論されると、それらは必ず書き留められました。この(「イタリア紀行」の中の)文章やその他のゲーテの言葉から、変容についての彼の研究における最初の少なくとも金言的な定式化もまた、既にイタリアで行われていたと思われます。彼は続けます、「私はこうして―つまり、モーリッツに提示することによって初めて、私の考えのいくつかを紙に書き留めることができました」と。こうして、その仕事が今の形で書かれたのは1789年末から1790年初めにかけてであった、ということに疑いはありませんが、この原稿の中で、どれほどが単なる論説であって、当時どれほど書き加えられたかを決めるのは困難なままに留まります。次の謝肉祭の書籍フェアに向けた本の告示はいくつかの同様の考えを含んでいたかも知れません。そして、それは1789年秋には、ゲーテがその考えを取り上げ、それらの出版に向けて準備をするための誘引になったかも知れません。11月20日に、ゲーテは、植物学についての彼の考えを書き留めるように駆り立てられていた、と大公宛てに書き送っています。彼は早くも12月18日には、イエナの植物学者バッチに読んでもらうために原稿を送付し、20日には、それについてバッチと自分で議論するためにそこに赴き、22日には、バッチがそれを好意的に受け取ったとクネーベルに報告しています。帰宅した彼は再度推敲し、もう一度原稿をバッチに送付したのですが、彼は1790年1月19日にそれを送り返したのです。その原稿とその印刷版がその後辿った運命については、ゲーテ自身によって長々と記述されています。彼の変容についての概念とその特徴の大いなる重要性については、この後の第4章「有機的形態論に関するゲーテの著作の本質と重要性」で取り扱われる予定です。 (第2章了)
2024年05月25日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナーゲーテの自然科学論序説 並びに、精神科学(人智学)の基礎 (GA1)Einleitung zu Goethes Naturwissenschaftlichen SchriftenZugleich eine Grundlegung der Geisteswissennschaft(Anthroposophie) 佐々木義之 訳■ゲーテの自然科学論序説~並びに、精神科学(人智学)の基礎~ GA1 ◎第1章 緒論 2008.10.4.登録◎第2章 ゲーテの変容についての概念の起源 2008.10.4.登録◎第3章 動物の形態学に関するゲーテの思考の起源 2009.1.5.登録◎第4章 ゲーテの有機形態論に関する著作の本質と重要性 2009.8.12.登録◎第5章 ゲーテの形態論についての結語 2009.11.8.登録◎第6章 ゲーテの認識方法 2009.11.8.登録◎第7章 ゲーテの科学的著作集の編集(2009.11.8.登録◎第8章 芸術から科学へ 2009.11.8.登録◎第9章 ゲーテの認識論(2010.1.11.登録◎第10章 ゲーテのアイデアという光の下での認識と行為 2010.6.14.登録◎第11章 他の観点と比較したゲーテの思考方法 2010.8.23.登録◎第12章 ゲーテと数学 2010.11.4.登録◎第13章 ゲーテの地質学上の基本原則 2010.11.4.登録◎第14章 ゲーテの気象学上のアイデア 2010.11.4.登録◎第15章 感覚的な知覚の主観性について 2010.11.4.登録◎第16章 思索家、そして研究者としてのゲーテ 2011.6.20.登録◎第17章 ゲーテ対原子論 2011.9.19.登録◎第18章 ゲーテの「散文の中の韻」における世界観 2011.11.1.登録第1章 緒論 佐々木義之訳 1787年8月18日、イタリアにいたゲーテはクネーベルに次のように書き送っています。ナポリ周辺やシシリア島の植物や魚たちの中に私が見たのは、私がもう十歳若かったら、インドに旅してみようと思わずにはいられなかったであろうというようなものでした。何か新しいものを見つけるためにではなく、既に発見されているものを私自身の方法で観察するために。この言葉は、ゲーテの自然科学論を考察するための視点を与えてくれます。彼にとって問題だったのは、何か新しいことを発見するということではなく、「新しい見通しを開く」、ある特別な仕方で自然を眺めるということでした。ゲーテが数多くの偉大な発見、例えば、顎間骨の発見や頭蓋脊椎理論の提唱といった骨学上の業績の他、植物の器官と葉との間の内的な相似性といった植物学上の発見等々を行ったのは確かです。けれども、自然についての壮大な観点こそが、これらすべての個々の業績に浸透していたところの生き生きとした魂だったのです。それらの業績はこの観点に基づいてなされました。有機体に関するゲーテの研究においては、ひとつの偉大な発見は他のすべての発見、それは有機体そのものの本性についての発見に影を投げかけていました。ゲーテは、ひとつの有機体が何故そのように現れるかという原則について、つまり、生命がその外的な表現へと導かれる要因について詳述しています。実際、彼は、そのようなことがらに含まれる原則に関して、あらゆることに光を当てているのです。有機的な科学の分野におけるゲーテの努力は、初めからその目標(*生命がその外的な表現へと導かれる要因)に向けられていました。彼がその目的を追求するとき、発見は自然に生じました。ですから、彼はさらに努力を重ねていく上で、それらが妨げにならないようにしなければなりませんでした。ゲーテ以前の自然科学は生命現象の本質に気づいていませんでした。有機体を探求するとき、ちょうど無機的な現象を探求するときのように、単に部分的な組成や外的な特徴を探求するにとどまっていたのです。したがって、そのような古い科学は、しばしば詳細なことがらについて不正確な説明をし、偽りの光の下にそれらを提示してきました。もちろん、個別のことがら自体を探求しても、そのような間違いが露見したりはしません。説明的な判断は私たちが有機体を理解して初めて可能になるのです。何故なら、特殊なことがらを個々に考察しても、それらを説明する原則はそこには含まれていないからです。それらは全体としての自然を通してのみ説明され得るのですが、それは、それらに存在と意味を与えているのは「全体」であるからです。ゲーテは全体としての自然を発見した後で、初めてそれらの説明の間違いに気づきました。それらの説明は、生きた存在についての彼の理論とは相容れないものであり、矛盾するものだったのです。そこから少しでも先に進もうとするのであれば、そのような偏見は取り除かれなければなりませんでした。顎間骨の場合がそうです。例えば、背骨の特徴を持つものとしての頭蓋の理論のようなものがあって初めて有効で興味あるものとなるというような事実は以前の自然科学には知られていませんでした。これらすべての障害は個別の発見を通して取り除かれる必要がありました。ですから、ゲーテの場合、これらの発見は決してそれ自体が目的ではなかったのです。それらが必要とされたのは、いつの場合でも、大いなる考えを確証するため、彼の「中心的」な発見を確認するためでした。ゲーテの同時代人たちが結局は同様の観察を行ったこと、ゲーテの努力がなかったとしても、恐らく今日ではそれらすべてが知られるようになっていたであろうということを否定することはできません。しかし、今日まで、有機的な自然のすべてを包括する彼の偉大な発見を、あれほどまでにすばらしい方法で、独立して定式化した人は誰もいないということを否定するのは、もっとはるかに難しいことでしょう。実際、彼の発見についてのいくらかましな評価でさえ未だに欠けているのです。 R.シュタイナーによる注:この関連で、私たちは、ゲーテが全く理解されてこなかったと言っているのではありません。むしろ、私たちはこの文章の中で、繰り返し、ゲーテの考えを推し進め、洗練させてきたと思われる人たちに言及しています。その中には、フォイクト、ネース・フォン・エーゼンベック、ダルトン父子、シェルバー、C.G.ガルス、マルティウス、その他等々が含まれます。けれども、これらの人たちは、ゲーテの著作の中で据えられた観点を基礎として、その上に彼らの体系を構築しています。ですから、彼らについて言えることは、彼らは「ゲーテなしに」彼らの概念に至ることはなかったであろうということです。他方、ゲーテの同時代人たちは、例えば、顎間骨の場合にはゲッチンゲンのジョセフィ、背骨理論の場合にはオーケンですが、独立してそれらの発見に至っています。 このような基本的な観点からすれば、ゲーテがある事実を最初に発見したのか、あるいはただそれを再発見しただけなのかを問題にするのは不適切なことのように思われます。と申しますのも、その事実が真の意義を有するのは、彼がそれを彼の自然についての観点に適合させるときのその仕方によってだからです。それはこれまで見過ごされてきたことです。特殊なことがらがひどく強調されてきたのですが、それは不当な挑発や論争を呼び起こすことになりました。確かに、自然の一貫性についてのゲーテの確信はしばしば指摘されてきたことですが、それは彼の観点におけるほとんど重要ではない特徴に過ぎないということに気づくことなくそうされてきたのです。例えば、無機的な科学における主要な目的は、この一貫性の基礎となるものを明らかにするということでしたが、もし、それを「型」と呼ぶのであれば、ゲーテにとって型の本質的な特質(*形質)とは何かということが分かっていなければなりません。例えば、植物の変容に関して重要なのは、葉、萼、花冠等々が同一の器官であるという個別の事実を発見するということではないのです。そうではなく、相互に貫通する形成的な諸原則から成る生きた総体について思考された壮大な構造が重要なのです。その発見から生じるこのダイナミックな思考された構造は、植物の発達の詳細や個々の段階をそれ自身から決定します。このアイデアの偉大さが、その後、ゲーテは動物界にもそれを拡張しようとしました。私たちの上に啓(ひら)けてくるのは、私たちがそれを私たち自身の心の中で生命へともたらすように試み、それを再考察しようと試みるときだけです。それは、私たちが、この思考された構造は正に植物自身の本性であり、ひとつの「アイデア」の形へと翻訳されたものである、それはちょうど対象の中に生きるように私たちの心の中にも生きているということに気づく瞬間です。私たちはまた、それを死んだもの、完成された対象としてではなく、進化し、生成し、決して自分自身の内部で止むことのないものとして思い描くとき、私たちは私たち自身で、ひとつの有機体を、正にその最小の部分に至るまで、生命へともたらすのを観察することになります。次章からは、ここで示されたものすべてを詳細に提示するように試みることになりますが、同時に、ゲーテ的な自然観と今日の自然観、特に現代の進化論との真の関係を見ていくことになるでしょう。 (第1章了)参考画:long-lived trees
2024年05月24日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー真相から見た宇宙の進化 Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen第5講 地球期における地球の内的側面 ベルリン 1911年12月5日 佐々木義之 訳 今回の連続講義の中で、これまで私たちが私たちの魂の前に置いてきたのは、私たちがマーヤあるいは大いなる幻想と呼ぶあらゆるものの背後には精神的なものが立っているということを示す一連の観察結果でした。今日は、もう一度、私たち自身に問いかけてみましょう。私たちは、私たちを取り巻くすべてのものの背後には精神的なものが認められる、ということを、私たちの物理的な身体を通してもたらされるような私たちの感覚や宇宙についての理解という観点から、どうすれば知るようになるのかと。これまでの探求の過程で、世界の直接的、外的な現象はさておき、真の現実についての特徴に貫き至るように努めることによって、私たちは精神的なものを特徴づけることができました。そして、その特徴を、喜んで犠牲を捧げること、与える徳、そして、諦め、あるいは拒絶、それらは私たちが私たち自身の魂の中をのぞき込んだときにだけ知るようになる特徴でと見なしました。実際、その特徴は私たち自身の魂の文脈においてのみ理解し、受け取ることができるようなものなのです。言い換えれば、もし、幻想世界の背後で、現実的かつ真実なるものを体現していると考えられる、あの特徴を理解したいのであれば、それらをその真の本性において理解したいと望むのであれば、私たちは次のように言わなければなりません。真の存在や実在から成るこの現実の世界は現実的で生きた特徴あるいは性質を含んでいる。しかし、それは私たちが私たち自身の魂の中で知覚することができる特徴とだけ比べられるようなものであると。例えば、外的には熱として自らを現しているものを特徴づけたいのであれば、それを、捧げられる犠牲、世界の中に流れ出す犠牲というようなその真の本性との関連で特徴づけようとするのであれば、私たちは熱の要素を精神的なものにまで辿るとともに、外的な存在性のヴェールを取り払い、それによって、外的な世界の中のこの特徴は私たち自身の精神的な本性と同じものであることが分かるということを示さなければなりません。私たちは、観察を続ける前に、もう一つ別の考えについて考察しなければなりません。それは、私たちが幻想の世界の中に見いだすあらゆるものは本当に一種の無の中に消え去るのかということについてです。感覚知覚と外的理解の世界には、いわゆる真実あるいは現実であるところのものに対応するものは何もないのでしょうか。次のような比較をしてみてもよいでしょう。私たちは、ちょうど水塊の中には流れの内的な力、あるいは、正に大海そのものが隠されているように、真実あるいは現実の世界はさし当たり隠されていると言うかも知れません。ですから、マーヤの世界は水の表面の波の働きと比べられるかも知れません。それは、何かが実際に大海の底からわき上がって来て、表面にさざ波を生じさせるということを私たちに示します。ですから、それは正しい比較であり、それはまた、この何かとは水の実質であり、水の力による一定の配列であるということをも私たちに示します。けれども、あれこれの比較を行うことが重要なのではありません。私たちはさらに、広大なマーヤの領域内には「本当に」存在しているものはあるのかと問わなければなりません。今日、私はこれまでの講義で行ってきたようにして話を進めて行きたいと思います。ここでは、私たちの魂の経験を出発点として、私たちが私たちの魂の前に置こうとしているものへと徐々に近づいていくことにしましょう。「土星」、「太陽」、そして「月」存在としての進化を精神的に辿った後、私たちは今や「地球」存在へとやって来ました。ですから、前回までに比べると、より親しみのある、より一般的とさえ言える魂の経験から始めることになります。前回は、魂生活の隠れた深み、すなわち、精神科学がアストラル体と呼ぶものの中に生じるところのものを見てきました。そこでは、あこがれがざわめくのを感じるとともに、ある存在の内部で、この場合には人間ですが。あこがれがいかに作用するかを見てきました。私たちはまた、魂生活におけるそのようなあこがれが、いかに像の世界においてのみ和らげられ得るかということも見てきました。私たちは像の世界を魂生活における内的な動きとして理解するようになりました。そして、それによって、個々の魂の小宇宙から、私たちが運動霊に帰属させた創造する世界の大宇宙へと続く道を見いだしたのです。ですから、今日は、よく知られた魂の経験、そして、それは古代ギリシャ人に示唆され、よく知られていたと同時に、今日でもその真実性においてきわめて意味深いものですが、そのような経験を私たちの出発点にしたいと思います。この経験は次のような言葉によって暗示されるでしょう。すべての哲学は、つまり、ある種の人間の知へと向かうすべての努力は驚きから生じる。実際、この言い方は正当なものです。多少なりとも、ものを考え、何らかの学びに近づこうとするとき、自分の魂の中で生じるプロセスに注意を払う人であれば誰であれ、認識への健全なる道はその起源を、驚き、あるいは、何かに驚くことに有しているということを既に見いだしているでしょう。、すべての学びの過程はそこから生じる驚きと不思議は、単調で、空虚で、無味乾燥なものを高揚させ、それに生命を吹き込みます。と申しますのも、私たちの魂の中に生じた知識で驚きから生じなかった知識とはどういう種類のものでしょうか。それは空虚と学者趣味に浸かった知識に違いありません。驚きから生じて、謎を解く中で経験する無上の喜びへと導く魂の過程だけが―それは驚きを越えたところへと上昇します。つまり、驚きに始まる魂の過程だけが、学びを高貴なものにし、それを内的に生き生きとしたものにします。皆さんは、実際、これらの内的な感情に満たされていない知識がいかに無味乾燥なものかを感じ取るようにしなければなりません。真の健全な知識は、驚きと、謎を解く喜びという文脈から生じます。他の種類の知識は外側から獲得され、あれこれの基盤の上に適用されます。しかし、これらふたつの感情に包み込まれていない知識は、それがいかに真剣なものであれ、本当には人間の魂からわき上がって来るものではありません。知識の中の生きた要素が醸し出す雰囲気によって生じる知識の「アロマ(芳香)」はすべてこれらふたつのことがら、驚き、不思議を解く喜びから生じるのです。しかし、驚きそのものの起源とはどのような種類のものでしょうか。驚き、すなわち外なるものへの驚嘆が魂の中に生じるのは何故でしょうか。驚きや驚愕が生じるのは、私たちが何らかの存在、事物、あるいは事実の前に立ち、それによって不思議な喜びを感じるからです。この不可思議さが驚きや驚異に導く最初の要素です。けれども、私たちは、私たちにとって不思議なものすべてについて驚きや驚愕を感じるわけではありません。私たちが何らかの不可思議なものに対する驚きを体験するのは、同時に、私たちがそれと関係していると感じられるときだけなのです。この感情は次のように言うことによって表現することができるでしょう。この物、あるいは存在の中には、まだ自分の一部にはなっていないけれども、自分の一部になるかも知れない何かがあると。私たちが驚きや驚愕をもって何かを受け取るとき、私たちはそれを不思議であると同時に、私たちに関係していると感じているのです。「(*不可思議なものに対する)驚き」という言葉は、「(*雷に打たれたような)驚愕」という言葉と関係があります。知覚可能な関係を見いだすことができないような驚きという現象に、何かが付け加えられるのです。けれども、それは単にその人の間違いかも知れません。少なくとも、責任はその人にあるはずです。そして、その人物は、仮に、彼または彼女がその「不可思議な」何かは、彼または彼女に関係しているはずだと結論づけないかぎり、拒絶や反論の精神をもって、その物あるいはできごとにアプローチすることはないでしょう。と申しますのも、唯物論的な、あるいは純粋に知的な概念に基づいて行動する人たちは、例えば、他の人たちがひとつの驚きであると認識しているものを、それが嘘あるいは不真実であるという直接的な証拠がないにもかかわらず、何故、否定するのでしょうか。今日では、哲学者でさえ、人間の目の前に広がっている世界の現象に基づいたのでは、ナザレのイエスの中に受肉したキリストは死者の中から甦らなかったと証明することは決してできないということを認めざるを得ないでしょう。この主張に対する反論は可能ですが、それらがどのような反論であれ、論理的な意味では、持ちこたえられません。今日の啓蒙主義的な哲学者たちは既にそれを認めています。何故なら、唯物主義の側から持ち出され得る反論、例えば、今まで、キリストが死者の中から甦ったようにして甦った人を見た者はいないというような反論は、論理的には、魚しか見たことがない者は、鳥は存在しないと結論づけなければならないという主張と同じレベルにあるからです。ある種の存在がいるということに基づいて、別の存在がいないということを導き出すのは、論理的に首尾一貫した方法によっては、不可能なのです。同様に、物理的な世界の中で人間が経験することに基づいたのでは、ゴルゴダのできごと、それは「驚き」として記述されなければならないについて、何も導き出すことができません。とはいえ、もし、皆さんが誰かに「奇跡」として記述されなければならないようなことについて語り、その人物が「私には理解できない」と言ったとしても、この人物は私たちが驚きの概念について話したことに対して反対しているのではありません。何故なら、その人物は、彼または彼女にとって同じように真実であるようなあらゆる知識へと向かうときには、それと同じ出発点に立つということを示しているからです。その人物は皆さんの記述が彼または彼女自身の内部でこだますることを求めているのです。ある意味で、その人は、自分に伝えられることを精神的あるいは概念的に自分のものにしたいのですが、それが可能であるとは信じられず、自分に関係があることであるとも考えられないために、その受け入れを拒否するのです。私たちは自分自身の「驚き」の概念に到達することができますが、驚きや驚愕が生じるためには、すべての古ギリシャ哲学の観点から言えば、人間が何か不可思議なものに直面し、それと同時に、何か関係があるもの、よく知っているものがそこにあると認識できなければならない、ということを認めなければならないでしょう。さて、ここで、以上の概念と、前回、私たちが私たちの魂の前に置いたあれらの概念との間に橋を架けることを試みてみましょう。前回お示ししたのは、喜んで犠牲を捧げようとする存在たちがいるということ、そして、ある存在たちがこれらの捧げものの受け取りを拒み、その犠牲がそれらを捧げた存在たちに戻ってくることによって、いかにある一定の前進が進化の中にもたらされるかということでした。私たちは、差し戻される犠牲の中に、古「月」進化期における重要な要素のひとつを認めました。実際、ある存在たちがより高次の存在たちに犠牲を捧げ、そして、後者がそれを差し戻したということが、古「月」進化期における最も重要な側面のひとつなのです。こうして、月存在たちの犠牲の煙がより高次の存在たちに向かって立ち上りますが、その存在たちは犠牲を受け取ろうとはせず、そのため、その煙は、実質として、犠牲を捧げようとした存在たちの中に導かれ戻されました。「月」存在たちに関して最も特徴的なのは、彼らがより高次の存在たちの元へと送り届けようとしたものが犠牲の実質として彼ら自身の中へと突き返されるのを感じたという点であるということもまた私たちは見てきました。そうですね、確かに、私たちが見てきたのは、より高次の存在たちの一部になろうとしたけれども、そうすることができなかった実質は、正にそれを送り出した存在たちの中に取り残されるということ、そして、そのことによって、拒絶された犠牲を差し出したこれらの存在たちの中に、あこがれへと向かう能力が生じたということでした。実際、私たちが私たちの魂の中であこがれとして経験するものすべての中には、古い「月」の上で生じたものの遺産、その犠牲が受け入れられなかったことを知った存在たちの遺産が今なお存在しているのです。古い「月」の発達期と、その精神的な雰囲気を精神的な観点から理解するとすれば、それは、当時、犠牲を捧げようとしたけれども、より高次の存在たちがその受け取りを差し控えたために、それが受け入れられなかったことを知った存在たちがいたという事実によって特徴づけられるでしょう。古い「月」の特徴的な雰囲気の背後にあるのは、他に類を見ないような憂鬱な状況、つまり、拒絶された犠牲なのです。そして、カインもまた彼の犠牲が受け取られなかったのを見たのですが、地球における人類進化の出発点を指し示すこのカインの拒絶された犠牲は、カインの魂を捉えた古い「月」進化の基本原則の繰り返しであるかのように現れます。ちょうど、古い「月」状態における存在たちの場合のように、そのような拒絶とは、あこがれを生み出す悲しみや痛みを私たちの中に生じさせるような何かなのです。私たちは、前回、古い「月」上に運動霊が入ってきたことによって、犠牲とそれが受け取られなかったことで存在たちの中に生じたあこがれとの間にバランスあるいは矯正が生じたということを見てきました。少なくとも、犠牲が拒絶された存在たちの中に生じたあこがれがある程度満足させられる可能性が創出されたのです。最も生き生きとした方法で次のように想像してください。犠牲を捧げられるべきより高次の存在たちがいますが、彼らはその犠牲の実質を送り返します。犠牲行為を行おうとした存在たちの中にあこがれが生じ、彼らは今や次のように感じます。「もし、私が犠牲を与えることができていたとしたら、私の中の最良のものがあれらの存在たちの中で生きることになっただろう。実際、私自身があれらの存在たちの中に生きていたことだろう。けれども、私はこれらの存在たちによって排除された。私はここに、そして、より高次の存在たちは向こうに立っている。」けれども、今や、運動霊に(私たちはこのことをほとんど文字通り理解しなければなりません)よって、これらの存在たちは、その中では拒絶された犠牲から来るあこがれが、より高次の存在たちに向かって煌めいているのですが、多くの異なった側面から、より高次の存在たちに近づくことができるような地点へともたらされます。拒絶された犠牲を捧げた存在たちを取り巻く、それのより高次の存在たちから受け取る豊かな印象によって、拒絶された捧げものとしてこれらの存在たちの中に留まっているものに均衡と補償がもたらされます。こうして、犠牲を捧げようとした存在たちとそれを拒絶したより高次の存在たちとの間にひとつの関係が創り出されます。それらの新たな関係によって、捧げものが差し戻されたために満たされることがなかったものが、あたかも犠牲が受け取られたかのように補償されるのです。もし、私たちが、より高次の存在たちを象徴的に太陽として視覚化し、より劣った存在たちが、ある一点にひとつの惑星として集まるものとして視覚化するならば、ここで意味していることを明確にすることができます。より劣った惑星の存在たちがその犠牲をより高次の惑星、つまり太陽に捧げることを欲すると仮定してみましょう。けれども、太陽はそれを差し戻し、犠牲の実質はそれを捧げた存在たちとともに留まらなければなりません。これらの存在たちは、その孤独と隔離の中であこがれに満たされます。そして、運動霊が彼らをより高次の存在たちの周りを巡る周回へともたらします。今や、犠牲を自分自身の中に保持する存在たちにとっては、より高次の存在たちに向けて直接、犠牲実質の流れを送り出す代わりに、その実質を彼らの周りを巡る動きへともたらし、それによって、その犠牲をより高次の本質を有する存在たちとの関係へともたらすことが可能になりました。それはちょうど、深いあこがれが、ひとつの大いなる達成によってではなく、一連の部分的な満足を経験することによってなだめられるようなものです。その人の魂全体が、そのような一連の部分的な満足によって、動きへともたらされるのです。私たちは前回このことを非常に正確に記述しました。私たちは、より高次の存在たちと内的に結ばれていると感じられない存在に、外から来る印象がひとつの代替物として生じるのを見てきました。これらの代替物としての満足は、そのような存在がいかに部分的な充足を達成するかということを私たちに示しているのです。けれども、捧げられるように意図された犠牲は、より高次の存在たちの中では、より低次の存在たちの中に留まったときに取る形態とは異なる形態を取ったであろうということは否定できません。と申しますのも、実際には、その意図された存在形態にとっての必要条件はより高次の存在たちの中にあるからです。ここでもまた、私たちはこれを図象的に想像することができます。もし、ある惑星の実質全体が「太陽」の中に流れ込んでいたとすれば、「太陽」がそれを拒絶しなかったとしたら、この惑星存在たちは、「太陽」存在として、「太陽」がその実質をその惑星に差し戻していたとしたら見いだしていたはずの条件とは異なる存在条件を見いだしていたはずです。私たちが犠牲の内容と呼ぶべきものの疎外(それはこの犠牲実質のその起源からの疎外)はその拒絶を通して生じるのです。次のことについてよく考えてみてください。存在たちが喜んで犠牲として捧げようとしたもの、つまり、その真の目的が達成されるのはそれが捧げものとして差し出されるときだけであると彼らが感じるようなもの、それを彼らは彼ら自身の内に保持せざるを得ません。もし、皆さんがそのような存在たちの経験を甦らせることができるならば、私たちが、「宇宙存在たちのある部分が自らの本質的な意味から、そして、偉大な宇宙の目的から排除されたできごと」と呼ぶところのものを経験するはずです。存在たちは絵画的に語るとすれば、実際には別の場所でその目的を達成できたはずの何かを彼ら自身の内に保持します。その結果、拒絶された犠牲の煙が排除されたこと、そのような犠牲の実質の排除によって、その犠牲実質はそれ以外の宇宙進化の過程から排除されるのです。もし、皆さんが、表現されていることを、単に皆さんの知性によってではなく、と申しますのも、知性はそのようなことがらに関しては機能しないからですが、皆さんの感情で把握するならば、皆さんは、普遍的な宇宙のプロセスから引き離されるということがどういうことなのかを経験するでしょう。犠牲を拒絶した存在たちにとっては、何かを彼ら自身から遠ざけたということに過ぎません。けれども別の存在たち、その中に犠牲の実質が留まる存在たちにとっては、それは自分自身の起源からの疎外という刻印を担っているような何かです。そのとき、そこにいるのはその実質が自分自身の起源から疎外されたことを示しているような存在たちです。このことを注意深く理解するならば、もし、それ自身の起源からの疎外がその中に潜んでいるような何かについてのこの考えを注意深く魂の前に置くならば、それは死についての考えであるということが分かります。宇宙における死とは、その犠牲が拒絶されたために、それを自分自身の内に保持せざるを得なかった存在たちの内部で生じたものに他なりません。こうして、私たちは、私たちが進化における第3の段階で見いだした諦めと拒絶から、より高次の存在たちによって拒絶されたもの、すなわち死へと進んで来ました。そして、死の真の意味とは、本来の場所に居るのではなく、本来の場所から排除された状態にあるということに他なりません。死が人生において具体的に発生するときにも同じ原則が当てはまります。幻想の世界に取り残される死体を見ますと、それは、死に際して、自我、アストラル体、そしてエーテル体から引き離され、それによって、肉体としての唯一の真の意義をそれに付与したものから疎外されることになった実質だけから構成されているのが分かります。人間の肉体は、エーテル体、アストラル体、そして自我なしには意味がないものだからです。死の瞬間に、肉体はその意味を失うのです。それはその意味の源泉から疎外されます。人が死ぬとき、もはや感覚では知覚できないものが、大宇宙の中で、自らを私たちに開示します。より高次の領域における宇宙的な存在たちが、犠牲として彼らにもたらされようとしたものを投げ返したために、この犠牲の実質は死を免れないものとなりました。死とは宇宙的な実質あるいは宇宙的な存在がその真の目的から除外されるということだからです。記:死についての哲学的な視点を考えると、宇宙的な存在がその真の目的から除外されるという観点は興味深いものですが、いくつかの視点を共有します。物理的な視点:宇宙的な存在(物質やエネルギー)は、物理法則に従って相互作用し、変化します。死は、この物理的な過程の一部であり、エネルギーの転換や物質の再構成として捉えられます。したがって、宇宙的な存在がその真の目的から除外されるという視点は、物理的な現象の一側面を考慮しています。哲学的な視点:エクスキューズ(exculsion)という概念は、哲学的な議論においても重要です。これは、ある条件や要因によって他の要因が除外されることを指します。死が宇宙的な存在にとってエクスキューズであるとする視点は、人間や他の生物が死を通じて新たな次元や状態に移行することを意味するかもしれません。宗教的な視点:宗教的な信念によって、死は魂の旅路や永遠の存在への移行と結びつけられることがあります。例えば、キリスト教では死後の世界があり、神との交わりが待っているとされています。この視点では、死は宇宙的な存在が真の目的へ向かうための一歩となる可能性があります。個人的な視点:人々は個々の経験や信念に基づいて死を解釈します。自己意識や人生の目的についての考え方、宇宙的な存在とのつながりによって、死に対する意味が異なります。以上の視点は、死に対する真の目的を探求する際に考慮すべきものです。宇宙的な存在がその真の目的から除外されるという視点は、私たちが人生と死について考える上で、新たな視座を提供してくれるものと言えるでしょう。 こうして、私たちは私たちが宇宙における第4の要素と呼ぶところのものへとやって来ました。もし、火がその純粋な意味において犠牲であるとすれば、火あるいは熱が生じるところでは、どこでもその背後には犠牲が横たわっています。私たちが、私たちの地球の周りに空気として広がっているものの背後に、贈り物を与えること、あるいは徳の付与を見いだすとすれば、私たちが、流れる水、すなわち流体の要素を精神的な諦めあるいは拒絶として特徴づけるとすれば、土の要素については、死を担うものとして、拒絶を通してその意味から疎外されたものとして特徴づけなければなりません。仮に、土の要素がなかったとしたら死は存在していなかったでしょう。ここには、いかに流体から固体が生じるかを具体的な形態において示す何かがあります。そして、それはまた、ある意味で精神的な過程を反映しています。例えば、池に氷が張り、それによって水が固体になると想像してみてください。水の氷への変換が生じるのは、実際、水に水としての意味を与えているものから水を引き離すものによってです。この過程の中には、固体になるということの精神的な表現、土になるということの精神的な表現があります。と申しますのも、4大元素としての特徴に関して言えば、氷は実際には土だからです。つまり、液体であるとろこのものだけが水なのです。自らの目的と意味から引き離されること、それは私たちが死と呼ぶものであり、死は土の要素の中で自らを開示するのです。私たちは、幻想(マーヤ)の世界の中に、何か現実的なものがあるのか、その内部に何か現実に対応するものがあるのかという問いから始めました。今私たちが私たちの魂の前に置いた概念を注意深く考えてみてください。最初に私が皆さんに申し上げたのは、今回の講義で取り上げる概念はかなり込み入ったものになるということでした。ですから、私たちはそれらを単に知的に受け止めるのではなく、それを瞑想しなければなりません。そうしたときに初めて、それらは私たちにとって明らかなものとなるでしょう。この死の概念、すなわち土に関連するものについての概念を取り上げてみましょう。それは実に注目すべき側面を示しています。私たちが取り扱ったすべての他の概念については、私たちの周囲に広がるマーヤの世界の中にはいかなる現実性も見いだされず、真実なるものはただ根本的に精神的なものの中においてのみ見いだされると言わなければなりません。けれども、私たちがここで確認したのは、マーヤの領域において、何かが死として自らを特徴づけるということでした。それは、それが正にその目的から引き離されたものであり、本当は精神的な領域の中に存在すべきものであったということによります。つまり、何かが切り離され、このマーヤの中に閉じこめられたのです。それは本当はそこにあるべきでものではなかったのです。マーヤと幻想の広大な領域のすべてを通して見いだされるのは偽りと幻想だけです。しかし、私たちは、マーヤの中で何かが真実に対応しているということ、つまり、何か真実であるところのものが、精神的なものの中でそれに意味を与えるものから切り離される瞬間、破壊と死を被るようになるということを見いだします。ここには正に大いなる真実と言えるようなものがあります。つまり、死は「マーヤの世界の中で、ただひとつ、その現実性において自らを現している」のです。他のすべての表現に関しては、それに対応する現実へと辿らなければなりません。マーヤの中に生じる他のすべての表現の背後には、現実であるところのものが横たわっているのです。ただ、死に関してだけは、それが現実的なものとして見いだされるのは、マーヤの中においてなのです。つまり、マーヤの領域全体を通して、死だけが現実なのです。ですから、もし、私たちが、普遍的なマーヤの中の至るところに広がっているものから偉大な宇宙の原則へと向かうならば、精神科学にとって最も重要で最も適切な帰結とは次のような命題であるということ、つまり、私たちのマーヤの世界において、何か現実的なものとして存在しているのは死だけであるということが分かります。ここで私が言おうとしていることは別の面からアプローチすることもできます。例えば、私たちの周囲を取り囲んでいる別の領域に属する存在たちについて考えてみることができます。次のように問うことができるでしょう。例えば、鉱物は死ぬのかと。鉱物が死ぬというのは神秘学者にとっては意味をなしません。と申しますのも、それは、切り取られた爪は死んだと言うのと同じだからです。爪は、それ自身の存在に対して、それ自身がそれ自身で正当性を有しているものではありません。それは私たちの一部であり、私たちが爪を切るとき、私たちはそれを私たちから切り離し、それが私たちと共にしていた生命から引き離します。それが死ぬのは私たち自身が死ぬときだけです。それと同じ意味で、精神科学にとって、鉱物は死にません。鉱物は、ちょうど、爪が私たちの有機体の構成要素であるように、より大きな有機体の構成要素に過ぎないからです。そして、鉱物が破壊されたように見えるとしても、それは、ちょうど爪の一部が切り取られて私たちの有機体から切り離されるように、単に大いなる有機体から引き離されているに過ぎないのです。鉱物の破壊は死ではありません。と申鉱物は、それ自身が、それ自身で生きているのではなく、むしろ、それをひとつの構成要素とするより大きな有機体の内に生きているからです。もし、皆さんが、植物の本性についての私の講義を思い出されるならば、植物自体もまた独立した存在ではないということが分かるでしょう。植物もまた地球有機体の構成要素なのですが、それは必ずしも鉱物がより大きな有機体の一部であるような仕方においてそうなっているのではありません。精神科学的な観点から言えば、個々の植物の生について語ることには意味がなく、むしろ、地球有機体について語るべきなのですが、それは、植物がこの有機体の至るところでその一部になっているからです。植物の死に関しては、指の爪を切るときの状況に似ています。指の爪が死んだと言うことはできません。植物についても同様です。何故なら、彼らは、地球全体に等しいより大きな有機体に属しているからです。地球はひとつの有機体です。それは春になると眠りにつき、その器官としての植物を太陽に向けて送り出します。秋には、再び目覚めて、植物を自らの中に精神的に取り戻しますが、それはその種子をその存在の内部に受け入れることによってそうするのです。植物を個別のものとして見るのは無意味です。それは、たとえ個々の植物が枯れたとしても、総体としての地球有機体が死んだわけではないからです。同様に、私たちの髪が白くなっても、私たちは死にません。たとえ私たちが私たちの白い髪を、少なくとも何らかの自然な方法によっては、黒くすることができないとしても、私たちが死ぬことはありません。もちろん、私たちは植物とは異なる立場にあります。しかし、地球は白い髪を黒い髪に戻すことができる人間に喩えることができるでしょう。地球自体が死ぬことはありません。私たちが、しおれる植物の中に見るのは地球の表面で生じている過程です。彼らはしおれますが、それでも、植物が真の意味で死ぬと言うことはできません。動物もまた、私たちが死ぬような仕方で死ぬとは言えません。個々の動物は真の意味では存在していないからです、その動物の集合魂が超感覚的な世界の内部に存在しています。真に動物であるところのもの、つまり、その真の存在は、アストラル平面上において、集合魂としてのみ存在しているのです。個々の動物は、その集合魂から濃縮されて出てきます。そして、その動物が死ぬと、それは集合魂の構成要素として取り置かれ、そして、別の動物に置き換えられるのです。ですから、私たちが、鉱物、植物、動物界において、死として出会うところのものは、単に見かけ上のもの、死の幻想に過ぎません。現実には、「人間だけが死ぬのです。」それは人間が個別性を発達させ、肉体の中に下降するまでになっているからです。人は、その肉体の中で、地上的な存在性を担うことによって、現実的なものであろうとしているのです。死に意味があるのは、地上に存在している間の人間にとってだけなのです。このことを把握すると、「人間だけが実際に死を経験することができる」と言わなければなりません。さらに言えば、精神科学的な探求から学ぶことができるように、人間だけが、本当に死を克服することができるのです。死に対する真の勝利が可能なのは、私たちにとってだけです。と申しますのも、他のすべての存在たちにとっては、死は見かけ上のものに過ぎないからです-それは本当には存在していません。もし、私たちが、人間性を越えて、より高次のヒエラルキア存在たちにまで上昇するならば、より高次の存在たちは、人間的な意味においては、死を知らないということが分かるでしょう。真の死、すなわち物理的な領域における死を経験することができるのは、物理平面上における存在性から何かを引き出してこなければならないような存在たちだけなのです。人間は、物理的な文脈の中で、自我意識を達成しなければなりませんが、それは死なしには見つけることができないものです。人間より下のランクに位置する存在たちにとっても、上に位置する存在たちにとっても、死について語ることに意味はありません。他方、私たちが「キリスト存在」と呼ぶ存在の地上における最も重要な行いが無効になることはありません。実際、「キリスト存在」に関しては、ゴルゴダの秘蹟「死に対する生の勝利」が、あらゆるできごとの中で最も重要なできごとであったのを私たちは見てきました。そして、死に対するこの勝利はどこで遂行されたのでしょうか。それはより高次の世界の中で行われ得るものでしょうか。そうではありません。私たちが鉱物、植物、そして動物の領域の中で言及したような、より低次の存在たちに関しては、死について語ることができませんが、それは、これらの存在たちが真に存在しているのは、感覚の世界を越えた、より高次の世界の中だからです。そして、より高次の存在たちについて語ることができるのは、「死ではなく、変容、メタモルフォーゼ(Metamorphose)、そして、再編についてだけです。」。私たちが死と呼ぶところの生への切り込みが生じるのは、人間状態に関してだけなのです。そして、人間が死を経験できるのは、物理的な文脈の中においてだけです。もし、全く物理平面の中に入って行かなかったとしたら、人間は決して死を知らなかったでしょう。と申しますのも、物理平面に入って行かない存在は、死について何も知ることはないからです。他の世界の中に、死と呼べるようなものは何もありません。そこにあるのは変容とメタモルフォーゼだけです。もし、「キリスト」が死を通過しようとするのであれば、物理平面に下る以外にはなかったでしょう。何故なら、彼が死を経験できるのは、物理平面においてだけだからです。こうして、私たちは、人間の歴史的な発展において、より高次の世界の現実が、マーヤの中で、驚くべき仕方で働いているのを見ます。私たちが歴史的なできごとについて正しく思考しているのであれば、確かにそれは物理的な領域の中で起こっているけれども、その源泉は精神的な世界の中にあるということに気づくはずです。このことはあらゆる歴史的なできごとについて言えます。ひとつのできごとを除けば。ゴルゴダのできごとに関しては、それは物理平面上で生じたが、それに対応する何かがより高次の世界の中に存在しているとは言えないからです。確かに、「キリスト」自身はより高次の世界に属し、そして、物理平面へと下って来ました。けれども、他のすべての歴史的なできごとに関して存在しているような元型は、ゴルゴダで成し遂げられたことがらに関しては存在していないのです。ゴルゴダの秘儀は物理的な領域の中でのみ生じ得たできごとだったのです。精神科学はその証拠を提供することになるでしょう。例えば、次の三千年にわたって、ダマスカスにおけるできごとの新しい例が多数見られるようになるでしょう。これについてはしばしば言及してきましたが、パウロがダマスカスで見たように、人間は、アストラル平面上で、エーテル形姿の「キリスト」を見る能力を発達させるでしょう。より高次の能力を通してキリストを知覚するこの経験は、次の三千年期を通してますます発達しますが、私たちの二〇世紀において始まるでしょう。今の時代以降、これらの能力は徐々に現れ、次の三千年期を通して、多数の人々によって身につけられることになります。それは、多くの人々が、「より高次の世界を覗き見ることによって」、「キリスト」はひとつの現実であるということ―彼は生きているということ―を知るようになる、ということです。彼らは彼を知るようになるのですが、それは「彼が今生きている」からです。彼らは、いかに今彼が生きているかを知るようになるのではなく、むしろ、正にパウロがそうであったように、彼は死に、そして復活したということを確信するようになります。けれども、このことの基礎はより高次の世界にではなく、物理平面上に見いだされなければなりません。もし、今日、いかにして「キリスト」自身の発達が成し遂げられるのかということ、そして、それとともに、いかにしてある種の人間の能力もまた発展するのかということを理解するならば。もし、そのことを精神科学によって理解するならば、人間が死の門を通って行くときにも、彼がダマスカスでのできごとに与るのを妨げるものは何もありません。何故なら、今や、死は人間の世界に最初に輝き込む「キリスト」の顕現として現れるからです。今日、肉体の中に居ながらにして、このできごとに備える人たちは、死と新生の間の生活においてもそれを経験することができます。けれども、それに備えない人たち、今回の受肉において、それを全く理解しない人たちは、死と新生の間の生活においても、「キリスト」に関して、今既に生じ、次の三千年を通して生じ続けることがらについて、何も知ることができません。彼らは再び受肉するまで待たなければならないでしょう。彼らは、再び地上に戻るとき、それに対するさらなる準備をしなければなりません。ゴルゴダにおける死とその死から生じたもの、それは「キリスト」の実質全体が地上で展開するために必要だったのを理解することができるのは、肉体の中に居る間だけなのです。私たちのより高次の生活にとって唯一重要な事実は、肉体の内にある間に把握されなければなりません。一旦肉体の中で理解されたならば、それはより高次の世界の中でさらに働き続け、ますます育成されるでしょう。けれども、それはまず肉体の中で理解されなければなりません。ゴルゴダの秘儀は、より高次の世界の中では決して起こり得ず、より高次の世界の中に元形を有してもいません。それは、物理的な世界の中に完全に限定されるところの死を包括するできごとなのです。したがって、それが理解できるのは物理的な文脈の中おいてだけです。地上にいる人間の使命のひとつとは、彼または彼女のどれかの受肉において、この理解を達成するということなのです。ですから、私たちはここで、直接的な現実、直接的な真実を示すような重要な何かを、物理平面上に見いだしたと言わなければなりません。物理平面上にあって現実的であるものとは何でしょうか。物理平面上にあって、あまりにも現実であるため、立ち止まって「ここには真実がある。」と言うようなものとは何でしょうか。それは人間の世界の中にある死であって、他の自然の領域における死ではありません。地球進化の過程の中で生じる歴史的なできごとを理解するためには、それらのできごとから精神的な元形へと上昇しなければなりません。けれども、ゴルゴダのできごとに関してはそうではありません。ゴルゴダの秘儀に関しては、直ちに、そして直接現実の世界に属するところの何かがそこにあるのです。今お話ししたことの別の面もまた明らかになります。それは途方もなく興味深いものです。今日では、ゴルゴダでのできごとは真実ではないとされ、外的な歴史に関しては、このできごとを歴史的な事実と認めるのは不可能である、と人々が言うのを聞くのは非常に重要なことです。大きな歴史的事実の中で、ゴルゴダの秘儀ほど外的、歴史的に確認できる方法で証明することが困難なものはほとんどありません。これに比べれば、外的な世界における人間の進歩にとって重要なソクラテス、プラトン、あるいはその他のギリシャ人たちの存在についての歴史上の議論をすることがいかに容易なことかを考えてみてください。「ナザレのイエスが実際に生きていた」ということは歴史を根拠にして主張することはできないと。それはある程度正当なことですが、多くの人は其のように言います。けれども、それに関する否定的な歴史的証拠も存在していません。いずれにしても、他の歴史的事実を取り扱うような仕方で、ゴルゴダの秘儀という事実を取り扱うことはできないというのは確かなことです。この外的、物理的な平面上で生じたできごとが、すべての超感覚的な領域における事実と同じ特徴、つまり、いかなる外的な方法によっても証明され得ない、という特徴を有しているのは正に特筆すべきことです。そして、超感覚的な世界を否定する人たちの多くが、同時に、このできごと、それは超感覚的なできごとを把握する能力を欠く人たちでもあるのです。そのできごとが現実であることはそれが与える影響によって確かめられるということは事実ですが、その人々は、その現実のできごと自体が歴史的な意味で実際には起こらなかったとしても、それらの影響は生じ得るだろうと推測するのです。彼らはその影響を社会学的な状況の結果として説明しますが、宇宙的な創造の過程を知っている者にとっては、「キリスト教」の影響はその背後に立つ力なしでも生じ得たと考えるのは、ちょうど、畑に種を植えなくてもキャベツは育つと言うのと同じくらい賢い考えなのです。この話をさらに進めれば、福音書の著作に携わった一人一人の個人にとっても、ゴルゴダの秘儀という歴史的なできごとを歴史的な証拠に基づく歴史的な事実として証明する可能性はなかったのだ。何故なら、それは外的な観察によって知覚可能な痕跡を残すことなく生じたからですと言うことができます。皆さんは、ヨハネ福音書の著者)彼は直接的な目撃者)を除く福音書の著者たちが、どうやってこれらのできごとを確信するようになったのかをご存じでしょうか。彼らにとっては、伝承と秘儀についての書物以上のものはなかったので、歴史的な出典によって説得されたということではありません。この状況に関しては、私の「秘儀的な事実としてのキリスト教」の中で概説されていますが、彼らが「キリスト・イエス」の実在を確信したのは、星の配列を通してだったのです。と申しますのも、彼らはまだ、大宇宙と小宇宙の関係について非常によく知っていましたから。彼らが有していた知識、今日でもそれを持つこと可能によると、星の配置を通して、世界史における重要な時点を計算することができたからです。彼らは、「星座がこのような配置であるとき、「キリスト」と言われる「存在」が「地上」に生きたはずだ」と言うことができました。マタイ、マルコ、そしてルカ福音書の著者たちが歴史的なできごとについての確信を得たのはこのようにしてだったのです。彼らは、福音書の内容については超感覚的な能力によって獲得しましたが、あれこれのことが地上で起こったはずだという確信は、宇宙における星座の配置から引き出したのです。これについての知識がある人は福音書の著者たちを信じることができるはずです。福音書の歴史性についての反論は不正確なものであるということを証明するのは割に合わない仕事です。私たちは、人智学者として全く異なる基礎、精神科学への洞察を通して得られる基礎の上に立っているということを明確にしておかなければなりません。これに関連して、今回の連続講義を通して私が確立しようとしたことがらに対する注意を促しておきたいと思います。それは、人智学が語る現実を、それら自体が、そしてそれら自体で、正しい反論によって傷つけ、だめにしようとしても、それは不可能であるということです。人間というものは、自分たちの知識にしたがって、いくらでも正しいことを言うことができますが、それによって精神科学が否定されることはありません。私は、「いかにして神智学の基礎を見いだすか」という講義の中で、比喩を引きながら次のように言いました。小さな少年が家族のために朝食用のロールパンを買いに村に通っていました。さて、その村では、ロールパン1個が2クロイツァーしていたのですが、その少年はいつも10クロイツァーもらっていました。その少年はパン屋からたくさんのパンを持ち帰っていましたが、ここで注意しなければならないのは、彼は大数学者ではなかったということです。それについてそれ以上のことは考えていませんでした。それから、その家族に養子がやって来ました。彼は最初の少年の代わりに、パン屋にパンを買いにいくように言われたのですが、その養子はよい数学者だったので、自分に次のように言い聞かせました。「10クロイツァー持ってロールパンを買いに行く。パンはひとつ2クロイツァーで、10÷2は5だから、家に持って帰るのは5個のはずだ。」ところが、家に帰ってみると、6個のパンを持ち帰っているのが分かりました。そこで彼は自分に言いました。「これはおかしい!10クロイツァーでそんなに買えるはずがない。計算は正しいはずだから、明日は5個持って帰ることになるだろう。」次の日も彼は10クロイツァーで6個のパンを持って帰りました。計算は正しかったのですが、それは現実には対応していなかったのです。と申しますのも、実際の現実は異なっており、その村では、10クロイツァー分のパンを買う人は誰でも、おまけにもう1個のパンをもらうので、5個ではなく、6個のパンを受け取る、という習慣になっていたからです。その少年の計算は正しかったのですが、現実には対応していなかったのです。このように、精神科学に対する最も批判的に考え抜かれた反論は、「正しい」かも知れませんが、全く異なる原則の上に立っていることがある現実とは何の関係もない可能性もあります。この顕著な例は、数学的に正しいことがらと実際に真実であることがらとの間の違いを理論的にと言ってもよいほど示しています。以上のように、私たちの努力によって、マーヤの世界は現実へと導かれ帰っていくということが示されました。この過程が私たちに示したのは、火とは犠牲であり、空気の要素とは流れ与える徳であり、あらゆる流体はあきらめと拒絶の結果であるということでした。私たちは今日、この3つの真実に4つ目の真実を付け加えました。それは、「土あるいは固体の要素の本性とは、死であり」、ある実質の宇宙的な目的からの分離であるということでした。この分離状態が始まったとき、死そのものが、マーヤあるいは幻想の世界の中に、ひとつの現実的なものとして入ってきたのです。神々自身は、何らかの仕方で物理的な世界に下降し、マーヤあるいは幻想の世界であるその物理的な世界の中で、死をその真の本性において理解しない限り、決してそれについて知ることはなかったでしょう。以上が、これまで私たちが議論してきた概念に付け加えたいと思ったことです。ここでもまた、これらの概念、それは、後で見ていただくことになりますが、マルコ福音書に書かれていることを根本的に理解するには、とても必要な概念について、何らかの明晰さを獲得することができるのは、規則正しい瞑想を通してそれらの概念を繰り返し私たちの魂に作用させることによってだけです。と申しますのも、マルコ福音書を理解することができるのは、最も意義深い宇宙的な概念の中に礎石を置くときだけだからです。 (第5講了)-真相から見た宇宙の進化(完)記:メタモルフォーゼ(Metamorphose)人気ブログランキングへ
2024年05月23日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー真相から見た宇宙の進化Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen第4講 月期における地球の内的側面 ベルリン 1911年11月21日 佐々木義之 訳 私たちは、私たちの世界観における困難な側面について、ある程度でなら外的感覚的な世界の顕現の背後に横たわる精神的な現実を見ることを学ぶところまで追求してきました。とはいえ、私たちは、感覚的な世界の中で私たちが見るものの背後には精神的なものに特徴的な形態が実際に立っているという本当の事実は外的に見ただけではよく分からないものであることを私たちの魂の生活の中で経験します。けれども、私たちは、そのような外観の背後には、精神的な活動、精神的な性質や特徴が本当に立っているのだということを認識するようになりました。例えば、私たちは今や、私たちの通常の生活において、暖かさ、熱、あるいは火の性質として現れるものは犠牲の精神的な表現であるということを知っています。そして、私たちが空気として出会うもの、それが精神的なものであるということは、私たちの概念の中では、ほとんど明らかになりませんが、その中には、私たちがある特定の宇宙的な存在によって与えられる徳と呼ぶところのものが認められます。水の中に認められるのは、私たちが諦め、拒絶と呼ぶところのものです。以前の世界観、これには簡単に触れるだけにしますそこにおいては、当然のことながら、外的、物質的なものの内にある精神的なものの存在はもっとすみやかに直感され、認識されました。このことの証拠は、私たちが日常的に使うスピリット(エキス)という言葉、私たちはそれをスピリチュアルなものに関して特別な仕方で用いますが、特別に揮発性の高い物質を表しているということにも見られるでしょう。私は「スピリット」というよりも、むしろ「ス ピリチュアル(精神的なもの)」と言います。けれども、外的な世界においては、人々は「スピリチュアル」という言葉を必ずしも真に精神的な現実あるいは感覚を超えたものには適用しません。 皆さんの何人かは、かつてミュンヘン精神主義者協会に宛てられた手紙が、誰も精神主義者協会とは何かを知らなかったために、「スピリット」つまりアルコール飲料協会本部に届けられたことがあったのをご存じですね。本題に戻りますと、今日は、地球惑星の進化が古「太陽」から古「月」にまで進展したときに生じたその発達における重要な移行について見ていくことにしましょう。そうすることで、私たちは別の種類の精神的な発達について考察することになるでしょう。私たちは、前回の講義で取り上げた点、拒絶という行為から始めなければなりません。前回、私たちは、精神的な存在たちがこの拒絶、あるいは「差し控える」という行為の中で、犠牲、私たちはこの犠牲、意志あるいは意志実質を捧げることとして認識しましたが、それを受け取る機会を諦めるのを見てきました。ある存在たちがその意志実質を捧げたいと望み、一方で、より高次の存在たちが、その差し控えるという行為によって、この意志を受け取るのを拒むところを見るとき、私たちは、この意志実質は、それをこの存在たちはより高次の精神的な存在たちに捧げたいと望みましたが、それを許されず、それを捧げたいと望んだ存在たちとともに留まらざるを得なかったのだという概念へと容易に上昇することができるでしょう。ですから、宇宙的な文脈の中には、犠牲を捧げる準備、自分たちの最奥の存在の中に安んじているものを献身的に捧げる準備ができているにもかかわらず、それを許されず、そのために、自分たちの内にそれを留めなければならない存在たちがいるのです。あるいは、別の言い方をすれば、これらの存在たちは、 その犠牲が拒絶されたことで、もし犠牲を捧げることが許されていたとしたら生じたであろうより、高次の存在たちとのある種の結びつきを確立することができませんでした。聖書の中で、カインがアベルに立ち向かう場面は、この「拒絶された犠牲」の意味のいくらかを、強調された仕方ではありますが、擬人化し、歴史的に象徴するものとなっています。カインもまたその犠牲を神に捧げたかったのですが、その犠牲は神の喜ぶところとはならず、神はそれを受け取ろうとはしません。 一方、アベルの犠牲は神によって受け取られました。私たちがここで注意を向けたいのは、その犠牲が拒絶されたことを知ったときのカインの内的な経験です。このできごとに対する最高度の理解へと私たちが至るためには、通常の生活の中においてのみ意味を持つ考えをここでお話ししている、より高次の領域に持ち込むべきではないということをはっきりさせておかなければなりません。犠牲の拒絶は欠陥や悪行によって生じたのだと言うならば、それは間違いでしょう。これらの領域においては、私たちが通常の生活において知っているような罪や贖いに言及することはまだできないのです。そうではなく、私たちは犠牲を拒絶したより高次の存在たちの観点からこれらの存在たちを見なければなりません。言い換えれば、より高次の存在たちは、単に犠牲の受け取りを差し控え、それを譲り渡したに過ぎないのです。私たちが先週特徴づけた魂の雰囲気の中には、欠陥や失敗を示すようなものは何もありません。むしろ、諦めや拒絶の行為はあらゆる偉大で意味深いものを包含しています。とはいえ、私たちは、犠牲を差し出そうとしたあの存在たちの中に―たとえそれが極めてかすかな反対であったとしても、彼らの犠牲を拒否したあの存在たちに対する何か反対のようなものを始める雰囲気が、確かに生じるのを感じ取ることができます。ですから、この反対の雰囲気が、例えば、カインの場合のように、後の時代になって私たちの前に提示されるとき、それは増幅されたやり方で提示されることになります。カインの中に見いだされる雰囲気と同じ雰囲気を、「太陽」から「月」への移行期に発展したあの存在たちの中に私たちが見いだすことはないでしょう。この存在たちの間に反対の雰囲気が生じるといっても、それは異なる程度においてなのです。ここでもまた、私たちが信頼できる仕方でこの雰囲気を知るようになることができるのは、前回の講義でもそうしたように、私たち自身の魂の中をのぞき込み、私たちが自分に、私たちは、私たちの魂の中の、どこにそのような雰囲気を見いだすことができるのか。そして、どのような魂の状態がそのような雰囲気、つまり、その犠牲の捧げものが拒絶された者たちの中に醸し出されたに違いない雰囲気を私たちに気づかせてくれるのかと問うときだけです。私たちの中のあるこの雰囲気は、そして、ここで私たちは地上的な人間の生にますます近づいてきました―、実際、その不確かさにおいて、そして同時に、その苦しみあるいは苦痛において、どの魂にもなじみのあるものなのですが、それについては次の木曜日の公開講演「魂生活の隠れた深み」(GA61)の中で十分に取り上げるつもりです。どの魂にもなじみがあるこの雰囲気あるいは態度は、魂生活の隠れた深みを支配し、恐らく、その雰囲気があまり苦しみを生じさせないときには、その表面に向かって押し上げてきます。けれども、私たち人間はしばしばこの雰囲気の周りを巡っているだけです。私たちのより高次の意識の中では、私たちはそれをそれと気づくことなく担っているのです。私たちは、「あこがれを知っている者だけが私の苦しみを知る」というある詩人(ゲーテ「ウィルヘルム・マイスター」)の言葉を思い出すかも知れません。これらの言葉は、漠としているけれどもしつこい魂の苦痛、同時に苦しみの感情を伴う苦痛をよく捉えています。これは魂の雰囲気としてのあこがれを意味しています。それは、単に魂があれこれのことを熱望したり、それらに向かって苦闘したりするときだけではなく、人間の魂の中に、魂の雰囲気として絶えず生きているようなあこがれです。私たちが古「土星」と「太陽」の進化期において精神的に生じたことがらの中に身を置こうとするのであれば、私たちは私たちの眼差しを魂の特別な状態、つまり、人間の魂がより高次の努力に向けて舵を取り、苦闘し始めるときに現れる魂の状態に向けなければなりません。私たちは、第2講の中で、諦めや犠牲の本性を、私たち自身の魂の生活からそれを描くことによって明らかにしようとしました。私たちは、「喜んで与えること」あるいは「自分自身の自我を 進んで諦めること」とでも呼べるようなものへと滴り落ち、そして、それから生じるのが見られるような叡智から人間が何を達成できるかを見てきました。私たちは、以前の状態から発展してきた地球の状況に近づけば近づくほど、今日の人間でもまだ経験できるような魂の状態に似た状態にますます出会うようになります。けれども、私たちは、私たちの魂生活の全体は、私たちの魂が地上的な体の中に挿入されていることで、その表面の下深くに流れる隠れた魂生活の上にある最上層のように横たわっている、ということを明確にしておかなければなりません。隠れた魂の生活がある、ということに気づかない人がいるでしょうか。人生は、そのような魂の生活が存在しているということを十分に教えてくれます。この隠れた魂の生活について何らかのことを明らかにするために、一人の子供が、7才か8才、あるいは別の年代の子供としましょうか、あれこれのことを経験すると仮定してみましょう。例えば、実際にはしていない何らかのことで責められ、ひとつの道理を経験するかも知れません。子供たちはしばしばこのようなことがらに対して特別に敏感です。しかし、それをしたということでその子を責めることによって事を納めるのが、その子を取り巻く人間たちにとっては都合のよいことでした。実際、子供たちはこのような仕方で道理に苦しめられることに対して本当に敏感です。けれども、人生とは、この経験がこの若い生命の中に深く食い込んだ後、年を経るにしたがってさらなる層がその魂の経験に付け加えられ、その子は、少なくとも日常生活の意味では、そのことを忘れてしまうというようなものです。多分そのようなことは二度と再び生じないでしょう。けれども、その若者が15才か16才のとき、例えば学校で、新たな道理を経験すると仮定してみましょう。すると、今や、そうでなければ波打つ魂の奥深くに眠っていたはずのものが起き出すのです。問題の若者は、彼または彼女が子供のときに経験したことの思い出が作用しているのだということも知らず、実際、全然別の考えや概念を形成するかも知れませんが、もし、以前のできごとが起こっていなかったとしたら、例えば、それがひとりの若い男であったならば、彼はただ家に帰り、いくらか涙を流し、そして、多分いくらか不満を言うかも知れませんが、それでも、彼はそれから立ち直るでしょう。ところが、以前のできごとが正に生じていたために、ここで私は、何が起きているかについて、その若者が知っている必要はないということを特に強調したいのですが、ちょうど、静かに見える海面下で波が打ち寄せるように、その以前のできごとがその魂の生活の表面下で働きかけるのです。そして、そうでなければ単なる涙と不平、そして侮辱で終わったはずのものが、今やひとりの学生の自殺というという結果をもたらします。こうして、魂生活の隠された深みは、最も深いレベルから表面へと上昇し、その役割を果たすことになります。そして、これらの深みで支配する最も重要な力とは、それは、その本来の姿で上方へと押し進むとき、最も意義深いものになるのですが、それにもかかわらず、私たちはそれについて無意識のままに留まりますし、あこがれなのです。私たちはこの力が外的な世界の中で有しているいくつ かの名前を知っていますが、それらは漠として比喩的なものです。何故なら、それらの名前は複雑な関連を表現するものであり、意識の中にまでは全く入ってこないからです。よく知られた現象を取り上げてみましょう。町に住んでいる人たちはそれにあまり影響されませんが、それでも、他の人たちの中にそれを認めるかも知れません―つまり、私 が言いたいのは「ホームシック」と呼ばれる感情のことです。もし、皆さんがホームシックとは本当は何なのかを探求するとしたら、皆さんには、それが基本的にはそれぞれの人間によって異なるものであるということが分かるでしょう。ある人にとってはあれこれであり、別の人にとっては何か別のものです。ある人は、家で聴いた親しみのある物語にあこがれますが、本当は家を恋しがっているのかも知れません。個々人の中に生きているのは、とりとめのないあこがれであり、方向性のない望みです。別の人は故郷の山や、あるいは、さざ波を見るときには―よく遊んだ川に あこがれます。これらすべての異なる性質は、魂の中でしばしば無意識に働いていますが、「ホームシック」という言葉で括ることができるかも知れません。そして、それは何千もの異なった仕方で演じられますが、それでも、一種のあこがれとして最もよく記述されるような何かを表現しています。さらに漠としているのが切望ですが、それは多分、人生において最も人を苦しめるものとして生じます。人はその関連に気づきませんが、それでもそれはあこがれなのです。とはいえ、このあこがれとは何なのでしょうか。私たちは、犠牲を捧げることを望みながらそれを諦めなければならなかった存在たちの雰囲気にそれを関連づけることによって、それが一種の意志であることを示唆しました。そして、私たちがこのあこがれを検証するときにはいつでも、それはある種の意志であるということが分かります。けれども、それはどういうタイプの意志なのでしょうか。それは成就され得ない意志あるいは意図なのです。と申しますのも、もし、それが成就されたならば、それはあこがれであることをやめるからです。それは実現され得ない意志なのです。私たちはあこがれをこのように定義しなければなりません。ですから、私たちは、その犠牲が拒絶されたあの存在たちの雰囲気について、次のようにすれば、いくらか特徴づけられるかも知れません。私たちが、私たちの魂の深みにおいて、あこがれとして感じ取ることができるものは、私たちが今お話ししているあの太古の時代から受け継がれてきたものとして、私たちの中に留まっているものです。ちょうど、私たちが別の性質を、別の太古の発達段階からの遺産として受け取るように、私たちが古「月」の進化段階から受け取るのは、魂の深みに見いだされるあらゆる形態のあこがれ、あらゆる形態の成就され得ない意志、阻止された意志なのです。この発達期の間に捧げられた犠牲が差し戻されることによって、 抑制され、阻止された意志を持つ存在たちが創造されたのです。彼らは、この意志を抑制し、それを自分自身で保持しなければならなかったために、非常に特別な状況に置かれました。そして、ここでもまた、もし、これらのことがらを感じ取り、経験したいのであれば、人は自分自身の魂の状態の中に身を置かなければなりません。と申しますのも、単なる思考はこれらの状態に貫き至るためにはあまり十分ではないからです。意志を捧げることができた存在は、ある意味で、その犠牲が生じた相手の存在とひとつに結ばれることになります。私たちはそれについても、つまり、私たちが犠牲を捧げる存在の中に、いかに私たちが生きて、自分自身を織りなすかということ。すなわち、その存在がいることによって、いかに私たちが充足感と幸福を感じるかということについても―人生の中で感じ 取ることができます。ここで私たちがお話ししているのは宇宙的な存在を含むより高次の存在たちへの犠牲です。彼らに犠牲を捧げる存在たちは全くの喜びの中で上方を見やるのですが、正にそのために、阻止された意志として、あこがれとしてその存在たちによって差し戻されたものは、その犠牲を完遂することがされたとしたらそうでなったであろうものとは、内的な雰囲気において、 内的な魂の内容において。決して同じものではあり得ません。と申しますのも、もし、犠牲を捧げる存在たちがその犠牲行為を許されていたとしたら、それはその別の存在の一部になっていたはずだからです。ですから、比較という方法で語るとすれば、もし、地球やその他の惑星存在たちが太陽への供儀を許されていたとしたら、それらは太陽とひとつに結ばれていたであろうと言うことができるでしょう。けれども、それらが太陽への供儀を許されず、それらが捧げたはずのものを保持せざるを得なかったとしたら、それらは離れたままになり、その犠牲を自分たちの中へと引き戻すことになったはずなのです。もし、私たちが今お話ししたことを一言で把握するとすれば、私たちは、宇宙という総体の中に何か新しいものが入って来ているということに気づきます。それは何か別の方法で表現することはできないものだということをはっきりと理解してください。つまり、自分の中に生きているものすべてを、別の存在に捧げようとする存在たち、宇宙的な存在に自分を捧げようとする存在たちは、その供儀が受け入れられなかったとき、その犠牲を自分自身の内に担うように導かれるのです。皆さんはここで、私たちが「エゴ(自我)」あるいは「自我性」と呼ぶような何か、そして、それは後に「エゴイズム」としてあらゆる形態において現れるのですが、そのような何かがきらめくのを感じないでしょうか。こうして、私たちは進化の中に流れ込んだものが、あの存在たちの内部で、遺産として生き続けるのを感じ取ることができます。私たちは、あこがれの内部に、たとえそれが最も弱められた形においてであるとはいえ、エゴイズムが稲妻のように光るのを、そしてまた、あこがれが宇宙進化の中に忍び込んで来るのを見ます。こうして、私たちは、あこがれに身を任せる存在たち、つまり、自分のエゴイズムに屈服する存在たちが、もし、何か別のものが介入しなかったとしたら、いかに、ある意味で、一面性の中に突き落とされるかを、自分たちの中だけに生きるようにさせられるかを見ることになるのです。供儀を許された存在について想像してみましょう。この存在は別の存在の中に生きます。その中に永久に生きるのです。供儀を許されなかった存在はそれ自身の存在の中に生きることができるだけです。ですから、そのような存在は、彼あるいは彼女が他の存在の中で、この場合、より高次の存在を経験できたはずのものすべてから排除されるのです。そのときには、実際、その問題の存在たちは、進化の過程から排除され、一面性へと突き落とされ、消えてしまうことでしょう。もし、その一面性を取り除くために進化の過程に介入しようとするような何かが生じなかったとしたら。この「何か」とは、一面性への宣告と追放を阻止する新しい存在たちの介入です。ちょうど、「土星」上における意志存在や、「太陽」上における叡智存在の場合のように、「月」上では運動霊が現れて来るのが見られるのです。私たちは「動き」という言葉によって、空間中での動きをイメージするのではありません、そうではなく、より思考過程に関連した何かに言及するのです。「思考の動き」という表現は正にその人自身の思考の流れや流動性を表しており、その表現は誰でも知っていますが、この表現からだけでも、もし、動きを包括的に把握しようとするのであれば、動きは空間中における単なる位置の変化(それは動きのひとつの側面に過ぎません)以上の何かであるということを理解しなければならないということが分かります。もし、あるより高次の存在に対して、多、数の人間たちが自らを捧げるならば、それらの人間たちは、そのとき、その存在はその人間たちの中にあるすべてを表現することになりますが、それは、その存在が犠牲として差し出されたものすべてを受け入れているからです。そのひとつの存在の中に生き、その中で充足します。しかし、もし、彼らの犠牲が拒絶されたとすれば、これらの人間たちは 彼ら自身の中で生きざるを得ず、決して充足することができなくなります。そうなったとき、運動 霊がやって来て、そうでなければ自分自身に頼らなければならなかったはずの存在たちを、他のすべての存在との関係へと導くのです。運動霊を単に位置の変化を生じさせる存在として考えるべきではありません。そうではなく、彼らは、ある存在を絶えず別の存在との新しい関係に導くような何かを生じさせる存在なのです。私たちはここでも、魂の対応する雰囲気を考察することによって、宇宙進化のこの段階で達成されたものについての考えを形成することができます。あこがれが停止させられ、行き詰まったとき、そして、いかなる種類の変化も経験することができなくなったとき、それがいかに苦痛に満ちたものであるかを知らない人がいるでしょうか。人はそれによって耐え難い状態、私たちが退屈と呼ぶところの状態に陥ります。私たちは通常、退屈というものを表面的な人々にのみ帰属させますが、それにはあらゆる段階があります。偉大で高貴な本性の中にも、外的な世界の中では満足させることができないようなあこがれとして、それらの本性自身の本質が表現するところのものが生きているのですが、退屈の中には、そのような本性に影響を及ぼすようなレベルの退屈もあるのです。そして、このあこがれを満足させる方法として変化以上に良いものがあるでしょうか。それは、このあこがれを感じる存在たちが絶えず新しい存在たちとの関係を求め続けていることからも分かります。あこがれの耐え難い苦しみは、絶えず変化する新しい存在たちの 集団との関係によってしばしば克服へともたらされます。こうして、私たちは、「地球」がその「月」の相状態を通過する間、運動霊 が、そうでなければ荒廃状態に陥ったはずのあこがれに満たされた存在たち、退屈とは一種の荒廃であるから生活の中に、変化、動き、新しい存在たちや状況との絶えず更新される関係をもたらすところを見ことになります。ある場所から別の場所への空間中での移動というのは、私たちがお話ししている動きに関する幅広いスペクトルの内のひとつの側面に過ぎません。私たちが別の種類の動きを経験するのは、朝起きたとき、魂の中にある一定の思考内容を自分の中だけに留めず、誰か別の人に話すときです。こうして、私たちは、多様性、変化、そして私たちが経験するものの中における動きを通して、私たちのあこがれの中にある一面性を克服します。外的な空間中に存在しているのは変化に対するある特殊な能力に過ぎません。太陽に面している惑星について考えてみましょう。その惑星が、太陽 との関係で、いつも同じ位置にあるとしたら、もし、それが全く動かないとしたら、それは一面性の中に固定されてしまうでしょう。その惑星はいつも同じ面を太陽に向けることになります。しかしそのとき、運動霊がやって来て、その惑星が太陽の周りを回転するように導き、その位置に変化をもたらします。位置の変化は、変化の一種に過ぎません。そして、運動霊が宇宙における位置の変化を生じさせるとき、彼らは動きという一般的な現象の中の特別な例を生じさせているのです。運動霊が動きと変化を宇宙に導入したことで、何か別のものがそれとともにやって来ました。私たちが進化の中に、つまり、運動霊、人格霊、叡智霊、意志霊等々の形で進化する全宇宙の多様性の中に、見てきたのは、空気や気体の精神的な基礎を形成するように放射する叡智に向かって流れる与える徳の形態の中には物質性もまた存在しているということでした。これは、今やあこがれへと変容した意志とともに流れ、そして、これらの存在の中で、人間が「像」として知っているところのものになります。それはまだ思考としては知られていません。これは私たちが夢を見るときに持つイメージによって最もよく視覚化することができます。流動的で過ぎ去る夢の像は、その中に意志があこがれとして生きている存在、運動霊によって他の存在との関連へともたらされる存在、そのような存在の中で生じるもののイメージを、呼び起こすことができます。ある存在が別の存在の前に立たされるとき、前者が後者に完全に帰依することは不可能ですが、それはその存在の中に自分自身の自我性が生きているからです。けれども、その問題の存在は別の存在の過ぎ去る像、夢の像のようにその中に生きている像を受け取ることができます。こうして、イメージの潮流とでも呼べるようなものが魂の中に生じます。言い換えれば、この進化期の間に、像の意識(形象意識)が存在するようになったのです。そして、私たち人間は、現在の 地上的な自我意識なしにこの進化期を通過したことから、私たちは、私たち自身を、今日、私たちの自我を通して私たちが達成するところのものを欠いていたものとして想像しなければなりません。当時、私たちは統合的な宇宙の中に存在し織り込まれていたのですが、一方で、私たちのあこがれの経験に比較できるような何かが私たちの中に生きていたのです。ある意味で、苦しみとは地球上に現れる苦しみの条件を度外視すれば、詩人が述べているように「あこがれを知る者だけが私の苦しみを知る」というようなものに他ならないと想像することができるでしょう。魂の表現としての苦しみや痛みが私たちの本性の中に、そして、私たちの進化に結びついた他の存在たちの本性の中に入り込んで来たのは、「月」の進化期においてでした。それ以降は、そうでなければ空虚であったはずの内的な自我が、それはあこがれに苛まれる内的な自我が、治癒的な慰めに満たされることになったのですが、それは運動霊の活動を通してこれらの本性たちの中に注ぎ込まれた像の意識の形でなされました。このことが生じなかったとしたら、これらの「月」存在たち(月の本性たち)の魂の中に あこがれ以外のものは何も存在しない空虚な存在となったことでしょう。けれども、像という慰めが、その孤独と空虚の中に滴り落ち、多様性で満たし、存在たちを追放と非難から解放するのです。私たちがそのような言葉を真剣に受け止めるとき、私たちは、私たちの地球が「月」の相状態にあったときに発達したものの根底に精神的なものとして横たわっているものと、そして、今や私たちの意識の奥深くに、「地球」としての相状態の下に層を成して横たわっているものの両方を把握することができます。しかし、それは、魂のあまりにも奥深くに横たわっているために、そして、これについては、明後日の公開講演(GA61)で、分かりやすくお示しするつもりです。ちょうど、海の底を押し寄せる水が海面に波を生じさせるように、私たちに気づかれることなく活動を始め、そして、意識の中へと現れて来ます。私たちの通常の自我意識の表層下には、表面へと押し寄せる可能性がある魂に深く根ざした生活があるのです。そして、この魂の生活が表に現れて来たとき、それは何を語るのでしょうか。私たちがこの魂の無意識的な生活の宇宙的な根拠をひとたび理解するならば、私たちは、魂の奥底から生じるように感じられる私たちの魂の生活とは、「月」の発達期に設定されはしたけれども、正に「地球」期になって初めて、私たちに 浸透したものを打破するものであると言うことができるようになります。私たちが 「月」の本性と私たちの「地球」の本性との相互作用を把握するとき、私たちは、古い「月」から「地球」の存在状態へと精神的にもたらされたものとは何かを、本当に説明することができるようになるのです。覚えておいていただきたいのは、今お話ししましたように、荒廃を緩和するためには、絶えず像が浮かび上がってくる必要があったということです。そうすれば、皆さんは 非常に重要で意義深い概念に至るでしょう。つまり、渇望と空虚の苦しみの中であこがれる魂は、 次から次へと生じる一連の像によって満足させられ、このあこがれを調和の中に保つという概念に至るでしょう。そして、いくつかの像が生じ、しばらくは留まるのですが、その後、魂の奥底で再び古いあこがれが目覚め、運動霊が新しい像を呼び起こします。そうすると、新鮮な像がまたしばらく存在するようになるのですが、結局はさらに別の像へのあこがれが新しく生じてきます。この魂の生活の側面について、私たちが言うべき重要なことは、絶えず新しい像を求める像によってあこがれが満足させられたとしても、この際限なく続く流れに終わりはないということです。この過程に介入する唯一の方法とは、この際限なく続く像の流れの中に何かが参入するということですが、それは像以外のものによって、すなわち、現実によって、あこがれを購うことができる何かです。言い換えれば、私たちの「地球」が惑星的に体現した相状態、そこでは運動霊の 活動によって導かれる像があこがれを満足させるのですが、そのような相状態は、「地球」として 惑星的に体現した相状態、つまり、「救済」の相と呼ばれるべき状態によって置き換えられなければならなりません。実際、これから見ていきますように、ちょうど「地球」以前の体現である 「月」存在が「あこがれの惑星」と呼ばれ得るように、それは無限に続き、決して終わることのない経過を通してのみ満たされ得るあこがれですが、「地球」は「贖いの惑星」と呼ぶことができるでしょう。私たちがこの人生を通して地上的な意識の中で生きるとき、そして、その意識は、既に見てきましたように、ゴルゴダの秘儀による贖いの行為を私たちの前にもたらし、贖いへのあこがれを絶えず生じさせるものが私たちの魂の奥底から生じてきます。それはまるで、意識の表面には通常の意識の波があり、その下、私たちの魂の生活という海の底には、魂の岩盤があこがれの形を取って生きているかのようです。そして、このあこがれは、それを満足させてくれる宇宙的な存在への無限に続く像の連なりによってただ単に慰めるのではなく、それを最終的に満足させてくれる存在です。供儀を遂行しようと飽くことなく熱望しているかのようです。私たちは、地上に生きる人間として、これらの雰囲気を実際に感じ取ることができます。そしてこれらの雰囲気は人が経験することができる最良のものです。実際、これらの地上に生きる人間の中で、今日、このあこがれを感じる人たちが、とりわけ、私たちの時代において私たちの精神科学的な運動に参加して来ているのです。外的な世界においては、私たちは私たちの通常の表面的な意識を満足させるあらゆるものを認識することを学びます。しかし、私たちの無意識から脈打って来るのは、外的な事情によっては決して満足させられることがなく、人生の中心的な根拠を切望する何かです。けれども、私たちがこの中心的な基盤を獲得することができるのは、単に人生における特別なことがらだけではなく、その全体に関与する普遍的な科学を手に入れたときだけです。今日、魂の奥深くで生じるものは、それはより高次の意識へともたらされることを求めます。世界の中に生きる普遍的なものと交わるようにさせられなければなりません。この接触がなされないならば、何らかの達成不可能なものへのあこがれが魂の奥底から生じてくるでしょう。この意味で、精神科学は魂の奥底に生きているあこがれへのひとつの回答です。そして、世界の中で生起していることの序章は以前の時代にあったということを考えますと、今日生きている人々が、彼または彼女の魂の中にあるあこがれの力を精神科学によって和らげようとしていることは、特に、そのような魂の力が意識的な気づきを越えたところにあり、そのようなあこがれが脅威となるように、人を消耗させようとしているときには私たちにとって驚くべきことではありません。もし、そのような人物が、この精神的な叡智が存在せず、したがって、それを手に入れることができなかった以前の時代に生きていたとすれば、彼または彼女は、彼らが正 に「偉大な精神」であるが故に精神的な叡智に対する絶えざるあこがれに苛まれ、そして、人生の意味を把握する可能性から疎外されて来たはずなのです。他方、今日では、像へのあこがれを和らげ、絶望を沈黙させ、それを退治するような何かがその魂の中に滴り落ちています。以前には、 この一連の像の行進が止むのを待ち望み、その像がますます大群となって居座れば居座るほどそれをさらに待ち望むということしかできませんでした。ハインリッヒ・フォン・クライストが友人に宛てて次のように書き送っているのを見ますと、魂のあこがれの中に香油のように自らを注ぎ出すこの精神科学をまだ手に入れることができなかった時代に生きていた人の言葉で、いかにそれが表現されているかを聞き取るこができます。「この地球の上で幸せになりたいって。そんなことを言うやつがいたら、ほとんど、恥を知れとでも言いたい。すべてが死で終わるところで、そんな目的に向かって努力するなんて、いかにも先が読めないご立派な人間がすることだ。我々は出会い、三度の春をお互いに愛し合い、そして、永久にお互いから逃げ出す。愛がないのに、その努力にどんな価値があるというのか。ああ、何か愛以上の、幸せ以上の、名声以上の、xyz以上の、何か我々の魂が夢想さえしないようなものはないのか。世界のてっぺんにいるのは悪い精神ではあり得ない。それは何か不可解なものに過ぎない。我々だって、子供が泣いているとき、笑わないか。この無限の広がりについて少し考えてみたまえ。無数の時間領域、それぞれがひとつの生命、それぞれが我々のこの世界のように顕現した存在なのだ。ああ、静止した瞬間よ、教えてくれ、これは夢なのか。我々が夜、仰向けになって見る二枚の菩提樹の葉の間には、その先見性において、我々の思考が捉え、言葉が表現することができるよりもずっと豊かな見通しが広がっているではないか。よし、何か善い行いをしよう、そして、それをしながら死のう。我々は既に無数の死のひとつを死に、そして、未来にもまた死ななければならない。まるで、ひとつの部屋から別の部屋に行くようなものだ。ほら見てごらん、僕には世界が大も小もなく一緒くたに箱詰めにされているように見える。」これらの言葉で表現されたあこがれは、この人物を促し、その友人に宛てたこの手紙を書かせました。けれども、この精神、クライストは、現代の魂が精力的な理解力をもって精神科学に近づくような仕方では、まだそのあこがれに対する充足を見いだすことができませんでした。と申しますのも、この精神は、百年前にまず友人のヘンリエッテ・ヴォーゲルを、次に 彼自身を撃ってその涯を閉じたのですが、今は、一世紀前に彼の亡骸が最初に葬られたヴァンシー河岸にある寂しい墓の下に眠っているからです。クライストが表現したことがらについてここでお話しすることができるというのは、特筆すべき天啓です。カルマの行為と言ってもいいでしょう。それは、差し止められた犠 牲への意志があこがれへと変化させられたことについて、今まで私たちがお話ししようとしてきたことがらを、運動霊によるあこがれの緩和、その最終的な充足に向けた衝動、そして、それが「贖いの惑星」上で達成されるであろうということを最もよく記述しているのです。この焦点の定まらないあこがれを最も気高い言葉で表現へともたらし、そして、この切なる望みを、それが体現し得る最も悲劇的な行いへと注ぎだした魂を思い出させることがらについて、今日、正に私たちがお話ししていることは特筆すべきカルマの解消なのです。それに気づこうとしさえすれば、この男の精神は、それが私たちの前に立つときの全体性において、本当に魂の奥深くに生き、私たちを地上的な存在性以外の存在性へと連れ戻すものの生きた体現であるということに気づかないことなどあるでしょうか。クライストが最も意義深い仕方で私たちのために記述してくれているのは、自分を越えたところに横たわっているものを探し求めるように人間に強いるものについて人間が経験できるもの、それは、仮に彼が彼自身の生命の糸を未成熟なまま断ち切らなかったとしたら、後になって理解することになったはずのものについてではないでしょうから。正に皆さんが「個人と人類の精神的な導き」の最初のページに書いてあるのを見いだされることを、彼は経験したのではないでしょうか。フォン・クライストの「ペンテシリア」(アマゾンの女王ペンテシリアとアキレスの血みどろの戦いについてのギリシャの伝承に基づいて書かれた凄惨な悲劇)について考えてみてください。ペンテシリアの中には、彼女自身の地上的な意識をもって推し量ることができるよりも、いかに遙かに多くのものがあることでしょうか。もし、彼女の魂は彼女がそれは偉大な魂ですが、彼女の地上的な意識をもって包含することができるよりもはるかに無限の広がりを持っているということを私たちが仮定しないならば、彼女をその特殊性において理解することは全く不可能でしょう。ですから、その無意識をドラマの中に芸術的な仕方で引き込む状況が劇中で生じなければなりません。こうして、一連のできごと、クライストがアキレスのために設定するようなできごとが、より高次の意識で検分される可能性は阻止されなければなりません。そうでなければ、私たちはその悲劇の重大さを経験することができないでしょう。ペンテシリアは、アキレスによって囚われの身となるのですが、アキレスの方が彼女の囚人であると思い込まされます。「彼女の」アキレスという言い方がなされるのはそのためです。意識的な気づきの中に生きているものは、無意識の中へと投げ入れられなければなりません。そして、ハイルブロンのカティーの中で表現されているような状況においては、特に、カティーと、シュトラールのヴェッターとの間の特筆すべき関係、そして、それは十全たる意識の中で遂行されますが、人間には気づかれることなくその間を行き来する力が潜む魂の奥深いレベルにおいて遂行されますにおいては、この低次の意識はどのような役割を果たすのでしょうか。私たちは、この状況を目の当たりにするとき、世の中の重力や引力といった通常の力の内部に横たわるものの精神的な本性を感じ取ります。世界の力の内部に横たわるものを感じ取るのです。例えば、私たちは、カティーがその愛する人の前に立つ場面で、何が意識下に生きているかを、そして、それが、外的な世界の中に生きているもの、諸惑星の引きつける力として無味乾燥に言及されるものとどのように関連しているのかを見ます。一世紀前には、透徹し、苦闘する魂でさえ、この意識の深いレベルにまで潜入することができませんでした。今日では、それが可能になっ ています。悲劇「ホンブルグの王子」(1810年に書かれたクライストの最後で偉大な作品)もまた、今日では、一世紀前とは異なる仕方で私たちに感銘を与えます。私は、人間が達成するあらゆることがらを理性に帰属させようとする現代の抽象的な思索家たちが、ホンブルグの王子のような人物、すなわち、彼のすべての偉大な行い、最終的な勝利へと導いたあれらの行いさえも一種の夢の状態で成し遂げた人物を、どのように説明するのかを知りたいものだと思います。 実際、クライストは、王子はその意識的な気づきから勝利を達成し得たのでも、より高次の意識という意味ではとりわけ秀でた人物でもなかったということを。と申しますのも、彼は後に、死に直面して、めそめそ泣いたからですことがはっきりと示しています。王子が力を発揮できたのは、 彼の魂の奥深くに生きていたものを途方もない意志の努力によって引っ張り出してきたときそのときだけだったのです。人類にとって、「月」の意識からの遺産として残ったものは、何か抽象的な科学によっては引き出してくることができないようなものです。それは、多くの側面を持つ繊細な概念、緩やかな輪郭を持った精神的なことがらを把握することができる概念、つまり、精神科学によってもたらされるような概念から導かれなければならないような何かです。最も偉大な諸概念は、中間的で通常の諸概念に自らを結びつけます。こうして、私たちが私たちの今日の魂の中で経験する状態は宇宙と宇宙の総体とに結びつけられているということを精神的な科学は示すということが私たちには分かるのです。私たちはまた、私たちが魂の中で経験できることだけが事物の精神的な根拠についての概念を形成することができるということを理解します。さらに、私たちは、私たちの時代においては、 私たちの時代に先立つ時代があこがれたけれども、私たちの時代においてのみ与えられることができるものを達成することができるようになったということを理解するようになります。こうして、以前の時代の人間たちに対する、つまり、その心があこがれたものへと続く道を見いだすことができなかった人間たち、世界は彼らにそれを与えることができませんでした。その心があこがれたものに対する一種の賞賛が生じます。私たちが、すべての人生はひとつの総体であるということ、そして、今日の人間は人類が既にはるか昔に必要としていたような―彼らの運命は本当にそのことを私たちに示しています 。精神的な運動に彼または彼女の人生を捧げることができるということを思い出すとき、確かに、そのような人物たちに対するある種の賞賛が生じて来ます。ですから、私たちは精神科学を人類のあこがれに対する救済を担うものとして指し示すことができるかも知れません。荒れ狂うと同時に悲惨に満ちた人間たちが長い間探し求めてきたものを精神科学は今や与えることができるということを私たちが思い出すのに適した日には。と申しますのも、これらのあこがれに満ちた人物たちのひとりが悲劇的な死を遂げてから一世紀経つからですが、とりわけそうすることができるかも知れません。私たちがこのような考えを、多分、人智学的な考えも胸に抱くことができるのは、ドイツの最も偉大な詩人のひとりが亡くなって百年経ったこの記念の日においてかも知れません。 (第4講了)記:ハインリヒ・フォン・クライスト(Heinrich von Kleist) ハインリヒ・フォン・クライストは、19世紀のドイツの劇作家であり、彼の作品は感情豊かで複雑なキャラクターと哲学的なテーマ性を持っています。彼の代表作には悲劇『ペンテジレーア』や喜劇『こわれがめ』があります。一方、シュタイナー(Rudolf Steiner)はオーストリアの哲学者、神秘家、教育者で、アンソポゾフィー(Anthroposophy)という独自の思想体系を提唱しました。彼は教育、芸術、農業、医学など多岐にわたる分野で影響を与えました。 クライストとシュタイナーは異なる時代と分野で活躍しましたが、彼らの作品と思想は今日でも多くの人々に影響を与えています。ハインリヒ・フォン・クライストは、軍人の家庭に生まれ、代々続く軍人の家系で育ちました。彼の作品は、人間の葛藤や社会の不条理を描いており、カフカなどにも影響を与えました。しかし、生前にはあまり評価されず、上演される機会にも恵まれず、失望と苦悶の中で、34歳の若さでピストル自殺を遂げています。参考画:Heinrich von Kleist人気ブログランキングへ
2024年05月22日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
真相から見た宇宙の進化Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen(GA132) 佐々木義之訳第3講:土星紀における地球の内的側面 ベルリン 1911年11月14日 私がこれまで2回の講義の中で指摘しようとしたのは、私たちの宇宙におけるあらゆる物質的な現象の背後には何か精神的なものが横たわっているということでした。熱や流れる空気の現象の背後に見いだされる精神的な現実を特徴づけようとしたのです。私は、そのような特徴を皆さんに伝えるために、私たちの進化発展における遙かなる過去にまで遡らなければなりませんでした。私たちはまた、物質的な宇宙の根幹をなす精神的な文脈を記述するため、私たち自身の魂の生活をのぞき見ました。いずれにしても、何かを特徴づけようとするときには、それに用いるアイデアはどこか別の場所から取ってこなければなりません。言葉だけでは不十分です。明確なアイデアそのものが必要なのです。私たちが言及しなければならない精神的な文脈は、現時点で人類が経験するものから、つまり、今日の人間が知ることができるものから遙かに隔たったところに横たわっているということを私たちは見てきました。ですから、この文脈を理解するためには、私たちは滅多に見いだされることのない状況、一般に、私たち自身の魂や精神の生活においては理解されることのない文脈を呼び出さなければなりません。私たちは、外的、物理的な火や熱の顕現からは遠く離れた、熱や火の状態の最も深い性質を探求しなければならない、ということを見てきました。確かに、私たちが犠牲、それも、特定の存在による犠牲、すなわち、「地球」の進化における古「土星」状態の間に私たちが出会った存在であり、そして、当時、その犠牲をケルビームに捧げた存在であるところのトローネによる犠牲を宇宙における火と熱のあらゆる状態の本質と同一視するととき、それは今日の人間にはおとぎ話のように聞こえるに違いありません。けれども、本当の意味で語るならば、それが宇宙進化におけるその時点で生じたとき、熱あるいは火の状態で外的、幻視的に私たちの前に現れるあらゆるものは、犠牲から構成されていると言わなければならないのです。同様に、私たちが流れる空気あるいはガスと呼ぶところのあらゆるものの背後には、何か非常に遙かなるもの、つまり、私たちが与える徳、精神的な存在たちが彼ら自身の存在を献身的に注ぎ出すこと、と呼んだものが横たわっているということを私たちは前回に指摘しました。あらゆる風のひと吹き、あらゆる空気の流れの中に存在しているのはこれなのです。外的、物理的なものとして知覚されるものは、実際には、幻想、マーヤに過ぎません。私たちは、幻想から精神的な現実へと進んだときにだけ、正しい考えを持つことができるのです。火や熱や空気は、人が見る鏡に映った人間のイメージの中に人間が存在していないのと同様、現実的なものとしては存在していません。つまり、鏡に映った像が、人間との関係で言えば、本質的には幻影であるのと同様、火や熱や空気は幻影であり、ちょうど現実の人間が鏡の中のイメージと関係しているように、その背後にある真実が現実なのです。真実という現実の中に私たちが探し求めるのは火や空気ではなく、犠牲であり与える徳なのです。私たちは、与える徳が犠牲に付け加えられるのを見たとき、古い「土星」の生活から「太陽」の生活へと上昇しました。私たちの地球による第二の体現の中に私たちが見いだすのは、私たちの発達における本当の状況へと私たちを一歩近づけるような何かです。そして、ここで私たちは、もう一度、幻想の世界に対抗する真の現実の領域に属する概念を導入しなければなりません。それは、私たちが私たちの進化発達における実際の状況を取り上げる前に、ある特定の概念を獲得しなければならないということです。次のようにして、この概念に近づいてみましょう。人間が外的な生活の中で何かを行い、あるいは何かを達成するとき、一般にその結果は彼または彼女の意志衝動からもたらされます。人間が何をするにしても、それが単なる手の動きであれ、偉大な行為であれ、その活動の背後には意志衝動があります。ある人物に何かをさせたり、何かを達成させたりするように導くあらゆるものは、そこから放射して来ます。そして、強力で力に満ちた行い、例えば、治癒や恵みをもたらす行いは、強い意志衝動から来る、そして、あまり重要でない行いはより弱い衝動から来る、と言われるかも知れません。一般に、私たちは、行いの程度は意志衝動の強さにかかっていると考えがちです。けれども、もし、私たちが私たちの意志を強化すれば、私たちは世界の中で何か重要なことを達成するだろうと言うならば、それはある程度正しいに過ぎません。ある地点を越えれば、もはやそうではないのです。驚いたことに、人間が遂行し得るある一定の行い、特に、精神的な世界に関連した行いは、私たちの意志衝動の強化に依存していないのです。もちろん、私たちが住んでいる物理的な世界においては、行いの程度は確かに意志衝動の強化に依存しています。つまり、より多くのことを達成しようとすれば、より多くの努力が必要となります。けれども、精神的な世界においてはそうではなく、むしろ、その反対なのです。精神的な世界において最も偉大な行いを達成し、最も偉大な結果をもたらすためには、前向きな意志衝動の強化が必要なのではなく、むしろ、ある種の身を引くこと、諦めが必要なのです。私たちは、最も些細な純粋に精神的なことがらに関しても、この仮定に則って前進することができます。私たちは、私たちの切なる望みを働かせたり、それに没頭したりすることによってではなく、私たちの意志を抑え、望みを抑制し、それらを満足させることを諦めることによって、一定の精神的な成果を達成するのです。ある人が、内的、精神的な方法を通して、世界の中で何かを達成しようとしていると仮定してみましょう。その人は、まず自分の意志や望みを抑制することを学ばなければなりません。そして、物理的な世界の中では、よく食べ栄養が行き届き、それによってよりエネルギッシュになるとより強くなるのに対して、精神的な世界の中で何か意義のあることを達成できるのは、これは記述であって、アドバイスではなく、断食を行い、意志や望みを抑制するための、あるいは諦めるための何かを行うときなのです。最も偉大で精神的な努力に向けた準備には必ず意志、望み、そして意志衝動を捨てることが含まれています。私たちは、意志することが少なければ少ないほど、人生が私たちの上に降りかかるのに任せる、あれこれのことを望むのではなく、むしろカルマが私たちの前にそれを投げかけるままにものごとを受け取るとますます言うことができるようになります。つまり、私たちは、カルマとその結果を受 け入れることができればできるほど、つまり、私たちが人生において、そうでなければ達成したいと思ったはずのあらゆることを諦め、静かに振る舞えば振る舞うほどにますます強くなるのです。このことが正しいのは、例えば、思考活動に関してです。あこがれに満たされ、とりわけ、良い食べ物や飲み物を好む教師や教育者の例では、その教師が生徒に向けて語る言葉はあまり多くのことを達成できない、それは生徒の一方の耳から入り、片方の耳からすぐに出ていくということが明らかになるでしょう。そのような教師は、それは生徒の責任だと信じるかも知れませんが、いつもそうであるとは限りません。人生におけるより高次の意味を理解し、慎みをもって生き、生命を維持するのに必要なだけ食べ、とりわけ、運命が与えることがらを意識的に受け入れるような教育者は自分の言葉が大きな力を有していることに徐々に気づくようになるでしょう。そのような教師を一目見るだけでも大きな効果がありま す。実際、その教師が生徒を見る必要さえないでしょう。そのような教師は生徒の近くに居さえすればよく、勇気づけるような考えを持ちさえすればよいのです。その考えが言葉で表現される必要はありません、そんなことをしなくても生徒には伝わります。すべては、そうでなかったとしたら強く望まれるようなことがらに関して、人が行使する諦めと断念の程度にかかっているのです。諦めの道は精神的な活動における正しい方法であり、より高次の世界の中で精神的な結果へと導きます。この点に関して、私たちは多くの幻想に出会います、そして、たとえ諦めの幻想が外的には真の諦めに似ているように見えたとしても、幻想が正しい結果に導くことはありません。通常の生活において、禁欲主義、すなわち自ら課す苦しみと言われているものを皆さんはご存じですね。多くの場合、そのような自ら課す苦悩は、自己陶酔、あるいは自己満足のため、何かより大きな欲望、あるいはどこか別の源泉から来る欲望を成就するために人が選択するものである可能性があります。そのような場合、自己否定は効果的ではないのですが、それは、精神的なものに根ざした諦めを伴っているときにだけ自己否定に意味があるからです。私たちは創造的な諦め、創造的な断念の概念を理解しなければなりません。諦め、あるいは創造的な断念、それを私たちは魂の中で実際に経験することができます―を日常的な生活からは遙かにかけ離れた考えとして認識することがきわめて重要です。そのとき初めて、私たちは、人類の進歩において、一歩先に進むことができるのです。と申しますのも、「太陽」の発達段階から「月」の発達段階に移行する進化の過程において、そのようなことが生じたからです。そのとき、何か諦めに似たことがらが、より高次の世界の存在たちの領域において生じたのですが、彼らはあの「地球」の発達過程に結びついた存在たちでした。このことを理解するために、私たちは、もう一度、古い 「太陽」における発達について考えてみる必要があるでしょう。けれども、その前に、私たちが既に知っているけれども現在に至るまである意味で謎めいて見えたような何かに注意を向けてみましょう。私たちが繰り返し指摘してきたのは、発達の過程で後に取り残された存在にまで遡ることができるような、発達における先行者たちについてでした。私たちは、実際、ルシファー的な存在たちが地上の人間の中に介入しているのを知っています。そして、度々指摘してきましたように、これらのルシファー的な存在たちは、古い「月」の発達期に達成できたはずの発達段階に到達することができなかったために、地球進化期において、私たちのアストラル体に侵入することができるようになったのです。この文脈の中で、私たちはしばしばちょっとした比較を行ってきましたが、それは、ひとつの学級を繰り返すのは生徒だけではなく、偉大な宇宙進化の過程においても、宇宙的な存在たちがひとつの発達段階を全うすることができず、後になって、他の存在たちの発達段階に介入することがあるということでした。そのようにして、ルシフ ァー的な存在たちは古い「月」の発達期において後に取り残され、「地球」上で人間たちに介入しているのです。表面的には、これらの存在たちには何か欠陥があったはずだ。世界進化における弱者に違いない。そうでなければ、どうして達成できたはずのことを達成できなかったのかと安易に考えがちです。そのような考えが私たちに起こるかも知れません。けれども、別様に考えることもできます。もし、「月」上において、ルシファー的な存在たちが取り残されなかったとしたら、人間は決して自由に到達することができなかったはずだ、決定を行うための独立した能力を発達させることは決してできなかったであろうと。一方では、私たちは私たちのアストラル体の中に欲望、衝動、熱情を有していますが、それがいつも私たちを一定の高みから駆り立て、私たちの存在のより低い部分へと引きずり下ろそうとするのは、ルシファー的な存在たちに依るものです。け れども、他方では、私たちが、私たちのアストラル体の中にあるルシファー的な存在たちの力を通して、善からさまよい出て、悪になる能力を持たなかったとしたら、私たちは自由に行動することも、私たちが自由意志、あるいは選択の自由と呼ぶところのものを有することもできなかったでしょう。ですから、私たちは私たちの自由をルシファ ー的な存在たちに負っている、と言わなければなりません。ルシファー的な存在たちは人間を正道からはずれさせるためにだけ存在しているという一面的な観点では不十分なのです。むしろ、私たちは、ルシファー的な存在たちの背後にある残りの部分を何か善きものとして、それなしには私たちは言葉の真の意味において人間としての価値を達成できなかったであろうような何かとして見なければなりません。とはいえ、私たちがルシファー的な存在たちの、そしてアーリマン的な存在たちの背後にある残りの部分と呼ぶところのものの根幹には、何かより深いものが横たわっています。私たちは既に古「土星」上でそれに出会いましたが、それに気づくのはきわめて困難であり、そのため、いかなる言語においても、それを特徴づけるための言葉を見いだすのは非常に難しくなっています。とはいえ、もし、私たちが今日記述したような諦め、あるいは断念の概念を考慮することによって、古「太陽」の現実へと歩を進めるならば、私たちはそれを非常に明確に特徴づけることができます。と申しますのも、存在たちが後に取り残されることとその影響の根幹は、より高次の存在たちの側での諦め、あるいは拒絶の中に横たわっているからです。そのとき私たちは古「太陽」上で次のようなことがらが生じるのを見ます。私 たちは、トローネ(意志の霊)がケルビームに供儀を捧げたと言いました。前回、見てきましたように、彼らはこの供儀を「土星」期の間だけではなく、「太陽」期の間にも捧げ続けます。トローネ、つまり、意志の霊は、「太陽」期においてもまた、ケルビームに供儀を捧げるのです。熱あるいは火の状態としてこの世界に存在するあらゆるものの実際の本質はこの供儀の中にある、ということもまた私たちは見てきました。さて、 もし、私たちがアーカーシャ年代記を遡って見てみるならば、私たちは、「太陽」期の間に何か別のことが生じたということに気づくことができます。トローネたちは犠牲を捧げ、その犠牲の行いを維持し続けます。私たちは犠牲を捧げるトローネを見ます。私たちはまた、多くのケルビームたち、彼らに向かって犠牲が上昇していきますが、犠牲から彼ら自身の中に流れ込む熱を受け取るのを見ます。けれども、同時に、多くのケルビームたちが別のことを行うのです。つまり、彼らは犠牲を拒絶し、それに与りません。私たちは、このことに気づくことによって、前回の講義の中で私たちの魂の中に入ってくることを許したイメージを完全にすることができます。この像の中には犠牲を捧げるトローネ、そして、犠牲を受け取るケルビームが見られますが、そこにはまた、犠牲を受け取るのではなく、犠牲として彼らに向かって突き進んでくるものを反射するケルビームも見られるのです。このことをアーカーシャ年代記の中で辿っていくのは途方もなく興味深いことです。つまり、私たちは、古 「太陽」期の間に、大天使によって「太陽」の最外殻から光の形で反射される供儀の煙が立ち上るのを見るのですが、それは与えるという徳が叡智霊から犠牲の熱の中へと流れ込むことによります。しかし、私たちはまた何か別のものをも見ます。それは、あたかも古い「太陽」の広がりの内部で何か全く別のもの、つまり、大天使によって光として反射されることもなく、ケルビームによって受け取られることもなく、そのために 逆流する供儀の煙が存在しているかのようなのですが、それによって、「太陽」の広がりの中には、上昇する犠牲と下降する犠牲であるところの供儀の煙、すなわち、受け取られる犠牲と拒絶され、戻される犠牲が存在することになります。この実際の精神的な雲のイメージによる「太陽」の広がりの中における自らとの出会いというものは、前回、私たちが外と内と呼んだものの間にも見いだされます。私たちはそれを「太陽」上のふたつの次元の間にある別々の層として見いだします。こうして、私たちは、中央には犠牲を捧げるトローネを、高みには供儀を受け取るケルビームを、そして、その供儀を受け取るのではなく、それを方向転換させて元に戻すあのケルビームたちを見いだします。この方向転換させて戻すことを通して環状の雲が生じ、そして、その周りには反射された光の塊が見られるようになります。この像を生き生きとした方法で想像してください。この古「太陽」の広がり、 この古「太陽」の塊は、宇宙的な球のように存在していますが、その向こうには何も想像することができません。そのため、私たちが考えることができるのは大天使までの広がりしか持っていない空間です。その中心では、受け入れられた供儀と拒絶された供儀との間の出会いから、輪が形成されると想像してください。これらの受け入れられた供儀と拒絶された供儀から、古「太陽」の内部で、何か「太陽」実質全体の分化、多様性とでも呼べるようなものが生じます。もし、私たちが、古い「太陽」を外的な像 になぞらえたいのであれば、それは私たちの現在の土星、つまり、環に取り巻かれた天体と比べることができるだけです。集積する犠牲の塊は中心部へと引き寄せられ、外側に取り残されるものは環の形を取るように命じられます。こうして、「太陽」実質 は停止させられた犠牲の潜在力という力を通してふたつの部分に分割されます。犠牲を拒むケルビームが生じさせるものとは何でしょうか。ここで私たちはきわめて困難な課題へと近づいてきました。皆さんは、長い瞑想の過程を経た後で初めて、私たちがこれから考察しようとしている概念を把握できるようになるでしょう。 ここで提示されようとしている概念は皆さんが長い間思索した後で初めてその下に横たわる現実を見いだすことになるようなものなのです。私たちが言うところの諦めは、時間の創造、そして、それは古「土星」上で生じたことを私たちは知っていますが、その時間の創造に結びつけられなければなりません。私たちは、時間の霊、アルカイとともに古「土星」上で最初に時間が生じたということ、古「土星」以前の時間について 語ることには意味がないということを見てきました。さて、この過程の中で繰り返しが生じるのですが、とはいえ、その時点から時間は続いている、と言うことはそれでも可能なのです。継続、存続という概念は「時間」という言葉に包含されています。私たちが「時間は継続的である」と言うとき、それは、私たちがアーカーシャ記録の中で「太 陽」や「土星」について語られることを検証するとき、時間は「土星」期の間に創造され、「太陽」上にも存在しているのを見いだすということを意味しています。さて、もし仮に、「土星」と「太陽」に関するすべての条件がこれまで二回の講義の中で特徴づけたような仕方で続いていたとしたら、「時間」は進化の過程の中で生じたあらゆるものの構成要素のひとつとなっていたことでしょう。私たちは進化におけるあらゆるできごとから時間の要素を取り除くことができなかったでしょう。私たちが見てきたのは、時間の霊が古「土星」上で創造され、時間があらゆるものの中に埋め込まれたということです。ですから、それ以後の進化について私たちが思い描き、想像するあらゆることがらは時間の文脈の中で捉えられなければなりません。もし、生じたことがらが、私たちが提示してきたこと、犠牲を捧げることや与える徳からのみ構成されているとしたら、このすべては時間を前提とするものでなければなりません。時間に左右されることなしに存在するものは何もなかったでしょう。存在するようになるあらゆるもの、消え去るあらゆるもの、したがって、時間に関係するあらゆるもの、つまり、すべては時間に左右されることになったはずなのです。犠牲を拒絶し、それとともに犠牲の煙の中に存在していたものを拒絶したあれらのケルビームがそれらを拒絶したのは、それによって、彼らがこの犠牲の煙の中に含まれる性質に拘束されることから脱するためでした。さて、犠牲の煙の中に含まれる性質の中には、とりわけ時間と、そして、それとともに、生じたり、消え去ったり する経過があります。ですから、犠牲の拒絶全体の中に横たわっているものとは、時間の条件を超えて成長するケルビームの能力なのです。これらのケルビームは時間を超えて前進します。彼らはもはや時間に左右されません。こうして、古「太陽」進化の諸条件は分割され、ある条件は犠牲や与える徳として「土星」から直接継続する線上で時間に左右されるものに留まり、一方、他の条件は犠牲を拒絶したケルビームの指導の下で自らを時間から引き離しますが、そのことによって、生じたり、消え去った りする過程を被ることのない永遠、永久が存在するようになります。これは特筆すべきことです。つまり、私たちは古「太陽」進化の中で時間と永遠が分離した地点へと至ったのです。古「太陽」進化期の間のケルビームによる断念によって、その進化期の間に生じたある条件の結果として、永遠が生じたのです。ちょうど、私たちが私たち自身の魂の中をのぞき見るとき、人間が拒絶と諦めを引き受けるときには、ある種の効果が魂の中に生じるのが見られたように、今や、ある種の神的、精神的な存在たちが犠牲と与える徳の遺産を拒絶したことによって、永遠と不死が古「太陽」上で生じるのが見られます。ちょうど、「土星」上で時間が存 在するようになったのを見たように、今や、私たちは、ある種の状況を通して、「太陽」進化の局面から時間が引き剥がされるのを見るのです。既に申し上げましたように、もちろん、このことには注意していただきたいのですが、永遠は「土星」期の間に既に準備されており、それが始まったのは、実際には「太陽」期の間ではありません。けれども、そのことを概念の形で表現できるほど明確に見ることができるのは「太陽」期においてのみなのです。私たちの概念と言葉は、何かそのようなことが古「土星」とその進化にとっても存在していた、ということを十分に特徴づけることができるほど正確ではないので、永遠の時間からの分離を「土星」上で知覚するのはほとんど不可能なのです。私たちは今や、諦め(古「太陽」期の間における神々による拒絶)と不死の達成の両方の意味を知るようになりました。このことのさらなる結果とは何でしょうか。「神秘学概論」によりますと、とはいえ、その中の記述はある意味でマーヤのヴェールがかけられていますが、「月」進化期が「太陽」期に続き、終わりには、すべての存在条件が一種の黄昏、宇宙的なカオスの中に沈められ、そして、これらが再び「月」として現れたということが分かります。私たちは犠牲の出現を再び熱として見ることができるのですが、「太陽」上で熱に留まるものも「月」上では外 的な熱として現れます。以前に与える徳であったものはガスあるいは空気として再び出現します。諦め、犠牲の拒絶もまた継続します。私たちが諦めと呼んだところのものは古「月」上で生じるあらゆるものの中に存在しています。それは本当にそうなのです。つまり、私たちは、私たちが「太陽」上で諦めとして経験することができたところのものを、「太陽」からやって来て、古い「月」上に存在するあらゆるものの中に存 在する力としても、そして、何か外的な世界の中に存在していると考えられるものとは異なるものとしても考えなければなりません。犠牲として存在していたものは、マーヤの中では、熱として現れ、与える徳であったものはガスあるいは空気として現れ、諦めとして存在していたものは液体あるいは水として現れます。水は外的にはマーヤであり、もし、拒絶と諦めの中にその精神的な基礎を有していなかったとしたら存在していなかったでしょう。世界の中で、水があるところには必ず神的な拒絶があるのです。ちょうど、熱が幻想であり、その背後には犠牲が存在しているように、ちょうど、ガスあるいは空気が幻想であり、その背後には与える徳が存在しているように、物質としての水は外的な現実としては単なる物質的な幻想であり、真に存在しているもの、すなわち、ある存在たちが別の存在たちから受け取ることができたはずのものの拒絶の反映なのです。水は諦めがその現象の下に横たわっているときに世界の中を流れることができるだけだ、と言うことができるでしょう。さて、私たちが知っているのは、「太陽」から「月」への移行に際して、空気の状態が水の状態に濃縮したということです。水が最初に存在するようになったのは「月」上であり、「太陽」期の間には水はありませんでした。私たちが古「太陽」進化期の間に集積する雲の塊の中に見たものが圧縮されるにしたがって水となり、「月」進化期の間に「月」の海として現れたのです。私たちがこのことを考慮するとき、ここで提示される疑問を解くことができま す。水は諦めから生じます。実際には、水は諦めそのものなのです。こうして、私たちは、水とは本当は何なのかという疑問に対して、非常に特別なタイプの精神的概念を獲得します。けれども、私たちは次のように問いかけることもできます。ケルビームがこの諦めを達成しなかったとしたら生じたであろう状態と。彼らが彼らに提供されたものから自由になったときに生じた状態との間には相違があるのではないのかと。この違いは何らかの方法で表現されるでしょうか。はいそのとおり、それは表現されます。それは、あの諦めの結果が「月」の状態の間に生じたという事実によって現されます。もし、この諦めが生じていなかったとしたら。もし、拒絶するケルビームが彼らにもたらされる犠牲を受け取っていたとしたら、彼らは図式的に言えば、彼ら自身の実質の中に犠牲の煙を有することになったでしょう。つまり、犠牲の受容は犠牲の煙の中に表現されることになったでしょう。これらのケルビームがあれこれの行為を遂行すると。仮定してみましょう。その時、その行為は、外的に表現すれば、自己変容する空気の雲を通して現れたことでしょう。捧げられる実質を受け取ることによってケルビームが行ったであろうことは、空気の外的な形態の中に表現されることになったでしょう。けれども、彼らは捧げられる実質を拒絶し、そのことによって、死ぬ運命から退き、不死の中に入っていきました。一時的なものから退き、継続するものへと入っていったのです。犠牲の実質はまだそこにあるのですが、そうでなければそれを吸収したであろう力から、いわば解放されるのです。捧げられる実質はもはやケルビームの傾向や衝動に従う必要がありません。何故なら、それはこれらのケルビームによって解放され、差し戻されたからです。そのとき、この犠牲の実質に関して何が起こるでしょうか。別の存在たちが独立できるようになるのです。これらの存在たちはケルビームの近くに見いだされますが、もし、ケルビームが犠牲の実質を受け取っていたら、彼らはその指導の下にあったことでしょう。けれども、その実質はもはやケルビームの内部にはなく、独立したものとなっています。そのことによって、諦めとは正反対のことが起こる可能性が生じるのです。つまり、別の存在が、その注ぎ出された犠牲の実質を彼ら自身へと引き寄せ、その内部で活動するようになるのです。これらは後に取り残された存在たちです。ですから、後に取り残されたものたちの存在はケルビームによる拒絶行為の結果なのです。後に取り残された存在たちを生み出したのはケルビーム自身です。彼らはそのようにして「後に取り残される」可能性を生じさせました。ケルビームによる犠牲の拒絶を通して、それを諦めず、自分自身の欲望や望みに身をまかせながら、それらを表現へともたらす他の存在たちが、供儀とその実質を自分のものにする可能性、そして、他の存在たちと並んで独立した存在になる可能性を得たのです。こうして、「太陽」進化から「月」への移行に際して、そして、ケルビームが 不死になるとともに、他の存在たちが、彼ら自身の実質の中で、ケルビームの継続する発達から自分自身を分離する可能性、実際、不死なる存在から自分自身を完全に引き離す可能性が生じたのです。後に取り残されることのより深い理由を見いだせば、これらの存在を後に引き留めた責任は、もし、原因の究極的な要因について語りたいのであれば、それらの存在たち自身にはないということもまた理解できます。これは私たちが把握しなければならない最も重要な点です。もし、ケルビームが犠牲を受け取っていたら、ルシファー的な存在たちが後に取り残される可能性はなかったのです。何故なら、彼らがこの犠牲実質の中に体現するようになる機会はなかったはずだからです。諦めこそ、存在たちがこのようにして独立するための前提条件だったのです。賢明なる宇宙の導きは神々自身がその反対者たちの存在を呼び出すように命じます。もし、神々が自分自身から自由にならなかったとしたら、存在たちが彼らに反対することは不可能だったでしょう。あるいは、もっと簡単に表現すれば、神々は、もし、彼らが、「土星」から「太陽」への移行の後も、それまでと同様に創造行為を続けていたとしたら、自分自身の主体性から行動する自由な存在たちは決して存在しなかっただろうということを見通していたと言うことができるでしょう。神々は、自由 な存在が創造されるためには、敵対者たちが全宇宙の中で彼らに反抗し、それによって、彼らが時間に左右されるあらゆるものの中で、抵抗に遭遇する可能性が与えられなければならないということに気づいていたのです。彼らは、すべてを支配する者が彼ら自身だけであったとしたら、そのような反対を見いだすことは決してできないだろうということを知っていました。もし、神々がすべての犠牲を受け入れていたとした ら、ものごとは彼らにとって非常に容易なものとなったはずだ―何故なら、そのときには、すべての進化は彼らの思い通りになっていたはずということを彼らは認めざるを得ないだろうと私たちは想像することができます。けれども、彼らはそうしないことに決めました。彼らは彼らから自由な存在たち、彼らに反抗することができる存在たちを望んだのです。そのため、神々は、犠牲のすべてを受け取ることはせず、それによって、存在たちが、神々自身の諦めを通して、そして、その他の存在たち自身がその犠牲を受け取るという事実を通して、彼らの反対者になるように定めたのです。ですから、お分かりのように、悪の起源はいわゆる悪の存在たちの中にではなく、いわゆる善なる存在たちの中に、つまり、その拒絶によって、世界の中に悪をもたらすことができる存在たちを通して悪が生じる可能性を初めて与えた存在たちの中に探さなければなりません。さて、誰かが次のように反論することは十分考えられます。そして、皆さんには、この考えを皆さんの魂の中にきわめて正確に作用させるようにしていただきたいと思います。つまり、誰かが「今まで私は神についてもっとましな意見を持っていた、神々は必ずしも悪を創造しなくても人間の自由のための舞台をセットすることができるはずだと考えていた筈なのに一体どうしてこれらの神々は悪なしに人間の自由を世界の中にもたらすことができなかったのか。」と反論するかも知れません。皆さんに思い出していただきたいのですが、世界があまりにも複雑すぎると考えたスペインの王様は、もし、神様が世界の創造を自分に任せてくれていたら、もっとずっと簡単にしていたのにと言いました。人間たちは、その弱さの故に、世界はもっとシンプルにできたはずだと考えるでしょう。しかし、賢明な神様たちは世界の創造を人間たちには任せませんでした。精神科学の観点から見ると、この状況をもっとずっと正確に特徴づけることができます。何かの台を必要としている人に、誰かが、柱を立ててれば、その上に物を置く支えになるよ、と示唆すると仮定してみましょう。そのように言われた人は、「しかし、別の方法もあるだろうに、どうして別のやり方でやらないのだ。」と言うかも知れません。あるいはまた、別の誰かは、建設中に三角定規を使いながら、「どうしてこの三角定規には三つの角しかないのだ。多分、神様は三つの角を持たない三角定規を作れたはずだ。」と言うかも知れません。けれども、神様は悪や苦の可能性なしに自由を創造できたはずだと言うのは、三角定規は三つの角を持つべきではないと言うのと同じくらいナンセンスなのです。ちょうど三つの角が三角形に属しているように、自由は精神的な存在たちの側からなされた諦めによってもたらされた悪の可能性に属しているのです。私がお話ししてきたことはすべて神の諦めに属しています。と申しますのも、神々は、犠牲を受け取ることを諦めることによって不死のレベルに上昇した後、悪を導いて善に戻すために、不死から進化を創造したからです。それは正にこの諦めという手段を用いてなされました。神々は、それだけが自由の可能性を与えることができる悪を回避しませんでした。もし、神々が悪を抑え込んでいたとしたら、世界は貧弱で単調なものになったことでしょう。神々は、自由のために、悪が世界の中に入り込むのを許さなければならず、それによって、悪を善へと導くのに必要な力をも獲得しなければなりませんでした。そして、この能力は拒絶と諦めの結果としてのみやって来ることができるような何かだったのです。諦めは、偉大な宇宙の神秘を写し出すために、いつも像やイマジネーションとして存在しています。今日、私たちは、太古の発達段階に言及するとともに、犠牲や与える徳の概念に諦めの概念を付け加えることによって、マーヤや幻想に対峙する真の現実に至るためのさらなる一歩を踏み出しました。宗教はそのような像や概念を私たちに提供します。ですから、聖書的な宗教においてもまた、私たちは犠牲や諦め、あるいは犠牲の拒否といった概念に近づくことができるのです。例えば、アブラハムの物語では、自分の息子を「神」に犠牲として捧げようとするのですが、「神」は 父祖の犠牲を受け取るのを差し控えます。もし、私たちがこの「差し控える」という概念 を私たちの魂の中に取り入れるならば、私たちが既に述べた瞑想のイメージもまた私たちの元にやって来ます。かつて私は、アブラハムの犠牲が受け入れられ、イサクが犠牲になっていたらという仮定について示唆しました。もし、「神」がこの犠牲を受け 取っていたとしたら、イサクに発する古代ヘブライ民族の全体が地球から取り去られていたことでしょう。「神」は、ヘブライ民族の領域を諦めることによって、つまり、自分 の影響が及ぶ範囲からそれを締め出し、それが自分の外にあるようにすることによって、アブラハムに由来するすべてを贈り物として与えたのです。もし、「神」がアブラハムの犠牲を受け入れていたとしたら、「神」は古代ヘブライ民族が活動していた領域全体を自分自身の中に取り込んでいたことでしょう。と申しますのも、犠牲になったイサクは「神」と共にいることになったでしょうから。しかし、「神」はそれを放棄し、それ によって、この進化の流れ全体が地球上に発散するに任せたのです。太古の父祖によって提供された犠牲の意味深い像を通して、すべての諦めや犠牲の概念が私たちの中に呼び起こされます。私たちはまた、より高次の存在による諦めあるいは犠牲のもうひとつ別の例を地球の歴史の中に見いだすことができます。私たちは、ここでもまた、既に前回触れたことに、つまり、レオナルドダビンチの絵、「最後の晩餐」に言及することになり ます。「地球」と「キリスト」双方の本質的な意味を同時に私たちの目の前にすることになる場面を思い描いてください。その絵の持つ完全な意味の中に貫き至るようにしてみましょう。そして、「もし、私が死の供儀を避けたいと欲したならば、天使の大群を 呼び出すことができないということがあろうか。」(マタイ二六章五三節)という福音書 の中の言葉を思い出してみましょう。諦めと拒絶によって、「キリスト」は発動できたは ずのこの明確で安易な解決法を拒否したのです。キリストイエスが私たちの前にもたらす拒絶の最も偉大な例が生じたのは、彼を裏切るイスカリオテのユダが彼の領域に入って来ることを許したときです。もし、私たちがキリストイエスの中に見ることができ るはずのものを本当に見るべきであるならば、私たちは彼の中に、犠牲を諦めなければならなかったあの存在たち、その本性自体が諦めであるところのあの存在たちのひとつの反映を見なければなりません。「キリスト」は、ちょうど神々自身が、古「太 陽」期の間に、彼ら自身の反対者たちをその拒絶行為を通して呼び出したように、もし、ユダが彼の反対者として行動することを許さなかったとしたら生じたであろうことを拒否したのです。こうして、私たちは、このできごと―宇宙の力に対する反対者たちの出現―が「地球」上において絵画的に繰り返されるのを見ます。私たちは十二人の真ん中にいる「キリスト」が、裏切り者としてそこに立つユダとともにいるのを見ます。人 類にとって計りがたい価値をもつものが進化の過程に入ってくるために、「キリスト」自身が彼の反対者を彼自身に対立する位置に置かなければならなかったのです。この絵が私たちに深い印象を与えるのは、「最後の晩餐」を見つめることが、力強い、宇宙的な瞬間を私たちに思い出させるからです。「私とともにその手を皿に浸した者が私を裏切る」(マタイ二十六章二十三節)という「キリスト」の言葉を私た ちの前に掲げるとき、私たちは神々自身によって神々に反対する位置に置かれた神々に対する反対者たちの地上的な反映を見ます。これはいつも言っていることですが、火星の住人が地球に降りてきたとすれば見ることになるあらゆるものは、たとえ彼らがそれを十分に理解できなかったとしても、多かれ少なかれ、興味深いものであるはずです。けれども、そのような火星人たちがこのレオナルドダビンチの手になる絵を見たならば、宇宙的な観点から見て、地球にとってばかりではなく、火星にも密接に関連した、そして、実際には、太陽系全体に関連した何かを見いだすことになるでしょう。そして、それによって、「地球」の意義が認識されることでしょう。「最後の晩餐」の中 に地上的な図式において示されているのは全宇宙にとって意味があることなのです。つまり、ある種の力が不死の神的な力に対抗する者としてそれに対立する位置に置かれたということが示されているのです。そして、死を克服し、地上における不死の勝利を具体的に示した「キリスト」が証しているのは、神々が時間にとらわれた存在たちから自らを区別し、時間に対する勝利を達成したとき、つまり、不死になったときに生じた意義深い宇宙的な瞬間なのです。私たちがレオナルドダビンチによる「最後の晩餐」を見るとき、このすべては私たちの心の中で感じられるかも知れません。どうか、素朴で単純な感受性を持って「最後の晩餐」を見る人は、今日私たちがお話ししたようなことは理解しない、などと言わないでください。そのような人がこ れらのことがらを知る必要はないのです。と申しますのも、人間の魂の神秘的な深みとは、人間の魂の中で感じられることがらは知的に知る必要はないというようなものだからです。花は、それによって自分が育つ法則を知っているでしょうか。いいえ、そんなことに関係なく、それは育つのです。花が自然法則に対していかなる必要性を有しているというのでしょうか。そして、もし、私たちが、神とその反対者が私たちの目の前で繰り広げているものを見るとき、つまり、表現することができる最も高貴なできごと、不死と死の差別化が私たちの前へともたらされるとき、私たちの目の前に存在するものの圧倒的な重要性が感じられるとすれば、人間の魂は、理性に対して―つまり、知性に対して、いかなる必要性を有しているというのでしょうか。それを知的に知る必要はありません。人が世界の意味そのものを写し出すこの絵の前に立つとき、むしろ、その経験が、不思議な力によって、その魂の中へと貫き至るのです。その絵を描くために、画家が神秘家である必要もありません。そうでなかったとしても、レオナルドの魂の中には、正にこの最も高く、最も意義深いものを表現へともたらすことができる力が存在していたのです。偉大な芸術作品がそれほどまでに力強い効果を有しているのはそのためです。つまり、それはそれらが宇宙的な秩序の意味に密接に結びついているからなのです。以前の時代には、芸術家たちは、それと知ることもなく、ぼんやりとした意識の中で、宇宙的な秩序の意義に結びつけられていました。けれども、将来においては、もし、精神科学が、新しい知の形として、芸術に対する新しい基礎をもたらさなかったとしたら、芸術は存続していくことができないでしょう。無意識の芸術は過去のものとなりました。精神科学によって息を吹き込まれるのを自らに許す芸術はその発達の初期段階に立っています。過去の芸術家は、彼らの芸術の根底に立つものを知っている必要はありませんでした。しかし、未来の芸術家はそれを知っていなければならず、それも、もう一度不死を描き出すことができる力、それは魂の内容全体から何かを提示することができる力です-によって、それを知らなければならないでしょう。精神科学を知的な科学に、図式や範例で表現される知的な科学にしようとする人は誰であれ、それを理解していませんが、私たちがここで展開したあらゆる概念、犠牲、与える徳、そして拒絶のような概念によって、言葉のひとつひとつについて、その言葉から湧き出てこようとしているもの、その考え方そのものをその絵の多様性から流れ出て来るものを経験しながら経験するような人、そのような人は誰であれ、精神科学を理解している人です。もし、人が、世界の発達は抽象的な概念の中で成し遂げられると信じているならば、図式を提示することもできるでしょう。けれども、もし、犠牲、与える徳、そ して、諦めのような生きた概念を提示しようとするのであれば、図式はもはや十分ではありません。これら三つの言葉は、いくつかの文字の向こうにあるものをあまり考えさえしなければ、図式的に提示されることもできます。けれども、もし、私たちがこれらの概念―犠牲、与える徳、そして、拒絶―についてよく考えてみようとするのであれば、私たちは前回私たちが記述したような絵を、つまり、犠牲を捧げるトローネ、ケルビームに供儀を送る者たち、犠牲の煙をまき散らす者たち、大天使から反射される光を受け取る者たちの絵やその他の絵を自分で描かなければなりません。そして、私たちは、次回の講義で「月」存在の考察へと進むとき、いかにその絵がより豊かになるかを見ることになります。私たちは、いかに集まる雲の塊が液体となり、「月」の塊としてさざ波を立てるかということを、そしていかにセラフィー ムの魅了する光をそれに付け加えなければならないかということを見ることになるでしょう。そのとき、私たちは十全なる理解に達しようと努めなければなりません。これについては、次のように言わせていただきたいのですが、未来において、人類は、外的な世界において、外的な世界のために、そうでなければアーカーシャ年代記の中に読むことができるものを表現へともたらすための可能性、芸術的な素材、そして、芸術的な手法を創り出すための方法を見いだすであろうと。 (第3講了)参考画:Freedom of Lucifer人気ブログランキングへ
2024年05月21日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
真相から見た宇宙の進化Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen(GA132) 佐々木義之さん訳■第2講:土星紀における地球の内的側面 ベルリン 1911年11月7日 前回の講義から、私たちの「地球」の創造に先立つ3つの発達段階のそれぞれを記述するのはきわめて難しいことだということがお分かりになったと思います。私たちは、それを行うためにはまず私たちの宇宙的な発達の中でも遠く離れた見知らぬ状態にまで至るのに必要な概念と思考を構築しなければならないということを見てきました。既に指摘しましたように、古「土星」期やそれに続く「地球」の惑星体現期に関するいかなる記述も、例えば、「神秘学概論」の中の記述などですが、網羅的なものではありません。私は、その本を書くに当たって、身近で手近なものから導き出された図式の衣装をその主題に着せることで満足しなければならなかったのですが、それは、その本が公衆にとって理解可能で、かつ、過度にショッキングにならないように意図されたものだったからです。「神秘学概論」の中で与えられた記述は、ただ不正確であるというのではなく、図式的にいえば、幻想あるいはマーヤの中に浸されているのです。真実に貫き至ろうとするのであれば、幻想の中を努力しつつ進まなければならないのです。例えば、古い「土星」は、私たちが地、水、あるいは空気として知っているあの諸要素からではなく、全く熱から成り立っている、と記述できるかも知れません-そして、これが正しいのはある限度の範囲内なのです。同様に、空間に言及するときにはいつも図式的な記述にならざるを得ないのですが、それは、前回の講義の中で見てきたように、古「土星」上には時間さえ存在しなかったからです。古「土星」上には、少なくとも私たちの言葉の意味での空間はありませんでした。しかし、一方では、その当時、初めて時間が存在するようになったのです。ですから、私たちが自分を古「土星」の文脈の中に置くときには、私たちは空間を持たない領域の中にいることになります。ですから、もし、私たちがこのことを思い描こうとするのであれば、それは像に過ぎないのだということを明確にしておかなければなりません。このように、もし、私たちが古「土星」の「空間」の中に入ることができたとしても、そこにはガスとして記述できるほど濃厚な実質は見いだされなかったでしょう。そこにあるのは暖かさと冷たさだけだったでしょう。実際、空間の一部から出たり、別の部分に入ったりすることについて語ることはできなかったのです。そこにあるのは、より暖かい状態とより冷たい状態の間を動くという感情だけです。超感覚的な能力を有する人でさえ、古「土星」の時代の中に身を置くと想像するときに経験するのは、空間を持たない暖かさが満ちたり引いたりするという印象だけなのです。けれども、この印象は「土星」状態の外的な覆いに過ぎません。と申しますのも、神秘主義でいうところのこの火の暖かさは、その精神的な基盤において、私たちにその実体を現すのですが、既に見てきましたように、古「土星」上で実際に生起しているのは精神的な行であり、できごとだからです。私たちは、古「土星」上で起っているのはどのような種類の精神的な行為なのかということについてのイメージを形成しようとしました。私たちがお話ししたのは、「意志の霊」トローネが犠牲行為を遂行したということでした。このことは、私たちが「土星」上で生じたことを振り返るとき私たちが見るのはケルビームとトローネから流れ出す供儀であるということを意味しています。トローネからケルビームへと供儀が流れ出すのですが、外から見たときには、これらの犠牲行為は熱として現れます。ですから、熱の状態とは供儀の外的、物理的な表現なのです。実際、全宇宙の中で、私たちが熱を知覚するときには、それがどこであれ、熱はその背後に立つものの外的な表現なのです。熱は幻想であり、熱の背後には、精神的な存在たちによる犠牲行為という現実があります。ですから、熱を正確に特徴づけたいのであれば、「宇宙の熱とは、宇宙的な供儀、宇宙的な犠牲行為の表現である」と言わなければなりません。私たちはまた、トローネたちがその犠牲行為をケルビームに捧げるときには、私たちが時間と呼ぶところのものが同時に生まれるということを見てきました。既に触れましたように、「時間」という現代の言葉は、私がこれから記述しようとしていることがらに、それほど適合してはいません。ここでいう時間は、私たちが今日感じるような「前に」や「後で」というような抽象性をまだ包含していません。時間は、「人格の霊」あるいは「時間霊」とも呼ばれる精神的な存在の外的な配列として始まったのです。これらの「時間霊」は、太古における時間の表現であり、トローネとケルビームの所産なのです。とはいえ、時間的側面を持った存在たちが古「土星」上で生まれたのは、犠牲行為という状況があったからです。私たちが暖かさの背後に立つものを本当に理解しようとするとき―古「土星」は暖かさから構成されていたと言うとき、私たちは単に外的、物理的な概念だけを適用すべきではありません。私たちが暖かいという言葉を使うとき、それは物理的な概念である、ということを思い出していただきたいのですが、ここではそうではなく、「魂の」生活―魂の道徳的な生活、叡智に満ちた生活-から導かれる概念を適用すべきなのです。自分が所有するもの、自分が持っているもの、自分自身であるところのものさえ、喜んで捧げるということが何を意味しているかを想像することができない人は誰であれ、暖かさとは何かを知ることができません。必要なのは、魂の観点から、自分自身の存在を捧げるということ、自分自身を意識的に諦めるということが何を意味しているかについての理解に至るということです。言い換えれば、自分の最良のものを世界の治癒のために与えるということ、自分の最良のものを自分のために取っておくのではなく、全宇宙という祭壇の前に捧げようとすることについて想像することができなければならないのです。もし、私たちがこれらのことすべてを生きた概念として、私たちの魂に浸透するひとつの感情として把握するならば、それは私たちを熱の顕現の背後に立つものについての理解へと少しずつ導いていくことができるでしょう。現代生活においては犠牲の概念が何に結びついているかということを想像してみてください-つまり、意識的に犠牲を捧げる人が自分の意志に反してそうすることは考え難いことである、ということを。もし、誰かが自分の意志に反して犠牲を捧げるとすれば、そのような圧力を感じていたからに違いありません。強制があったに違いないのです。けれども、それはここでいうところの供儀が意味しているものでは全然ありません。ここでは、供儀は、それを捧げる存在から当然のこととして流れ出るのです。もし、誰かが、何らかの外的な強制や、何かを成し遂げるという期待なしに、もし、誰かが内的に促されるのを感じて犠牲を捧げるとしたら、その人は内的な熱と至福を経験するでしょう。私たちが内的な熱と幸福で輝くのを感じるとき、それが表現しているのは、「犠牲を捧げ、そして、暖かさに浸透されるのを感じる人が幸福で輝くのだ」と言うことによってのみ記述することができるような何かです。私たちは、いかに犠牲の輝きが世界における外的な熱という幻想の中で私たちに近づくかを自分で経験することができます。世界の中で、暖かさがあるところにはどこでも、その基盤としての魂的、霊的な現実がある、ということを把握する人だけが、暖かさとは何かを本当に理解するのです。暖かさとは、犠牲の喜びを通して存在し、活動するようになる何かです。暖かさをこのような方法で経験することができる人であれば誰でも、物理的な暖かさという現象、つまり幻想の背後に存在し、隠されている現実へと至ります。さて、もし、私たちが古「土星」存在から古「太陽」存在へと突き進もうとするのであれば、私たちの現在の太陽ではなく、古い「太陽」の実質についてのイメージを創造するための概念に向けて、その基礎づけを行わなければなりません。この場合にも、私が「神秘学概論」の中で提示したのはその外的な表現に過ぎませんでした。古「太陽」は、空気と光を熱につけ加えることによって、その熱を高めたのですが、ちょうど私たちが「意志の霊」によってもたらされた犠牲の輝きを知覚するためには熱を越えたところを探求しなければならなかったように、今や、仮にも私たちが古「太陽」上で熱につけ加えられた空気と光を理解したのであれば、私たちは、空気と光の本質として、何か道徳的なものを探さなければなりません。私たちが古「太陽」上における空気と光についての考え、表現、感情に至ることができるのは、私たちが、魂的、霊的な方法で、私たち自身の内部で経験することができるものを探求するときだけです。この感情は次のような方法で魂の経験として記述することができます。皆さんが真の犠牲行為を観察すると想像してみてください。つまり、前回の講義の中で記述したように、トローネがケルビームにその供儀を捧げるというイメージが皆さんを深く感動させ、そのため、そのイメージが皆さんの魂を無上の喜びによって生き生きとさせると想像してみてください。もし、皆さんが、そのような犠牲を捧げる存在を観察するならば、あるいは、皆さんの魂を目覚めさせ、生き生きとさせるようなこの種の像について想像するならば、皆さんの魂は何を感じるでしょうか。もし、皆さんが生命に満ちた感情を持っているとしたならば、もし、皆さんが、犠牲行為の中で感じる喜びを前にして、無関心で立っていることができないのであれば、皆さんはこの犠牲行為を目の当たりにして、深い目覚めを経験せざるを得ないでしょう。皆さんは、犠牲から生じる無情の喜びを見守るということは最も美しい行いであり、そもそも魂の中で生じ得る最も美しい経験である、と皆さんの魂の中で感じざるを得ません。別の経験も生じ得ます。それは完全に身を任せるという態度です。実際、もし、犠牲が、魂の中に、完全な献身をもってそれを見つめたいというあこがれを生じさせないとしたら、そして、自己犠牲の雰囲気をもたらさないとしたら、皆さんは一片の木でなければならないでしょう。そのように自らを諦める無我について考えてみてください。それは行為の中で変容された自己犠牲です。そして、能動的で意識的な自己犠牲について熟考することにより、自分を譲り渡すということ、自らをなくすということ、自己を忘れるということに対する親和性を作り出すことができます。もし、そのような雰囲気、あるいは、少なくともそれについての示唆もしくは残響を作り出すことができないとしたら、犠牲についてのより綿密な理解へと本当に至るということは決してないでしょう。実際、私たちは、淡々と自己を諦める、というこの雰囲気を魂の中に注ぎ込むならば、より高次の認識形態が私たちに与えることができるものへと至ることができるかも知れません。自己犠牲の精神を創造することができない人は、より高次の認識を達成することもできません。この自己犠牲という態度の正反対のものとは何でしょうか?それは自己意志、自分自身の意志を主張するということです。自分が思索するものの中に自らを無くすこと、そして、自らの意志で自分の中にあるものを主張すること、これらが魂の生活におけるふたつの極です。これらは大いなる対極です。もし、皆さんが真の認識を達成し、皆さん自身を叡智で満たしたいとすれば、この自己意志は致命的なものとなります。日常生活においては、自己意志は偏見として知られています。そして、偏見はより高次の洞察を絶えず破壊します。実際、自己犠牲への能力として私がここで記述しているところのものを思考の中で強化する必要があるのですが、それは、自己犠牲の強化された感覚によってのみ、人はより高次の世界に向けて歩を進めることができるからです。より高次の世界においては、自分を捨てる能力、少なくともその魂的な雰囲気を経験できなければなりません。もし、私たちが科学的な知識や日常的な思考だけでやっていくならば、より高次の認識を達成することは決してできないということを強調しておきたいと思います。通常の科学や日常的な思考が働くのは、通常の人間的な意志、すなわち、私たちが受け継ぎ、あるいは涵養してきた経験、感情、そして、考えにおいて自己意志が創り出してきたあらゆるものを通してであるということを私たちは明確にしておかなければなりません。私たちはここで間違った方向に導かれる可能性があるのですが、実際、この領域では、錯覚することが非常に多いのです。人々がやって来て、例えば、次のように言うかも知れません。精神科学が提示する知識のあれこれの側面を受け入れるべきであると言われても、私は、私が既に考えたことと一致しないものは何ひとつ受け入れるつもりはない、証明されないものを受け入れるつもりはないのだと。確かに、証拠なしに何かを受け入れるべきではありません。しかし、私たちが私たちに提示されたものの中から私たちが既に知っているものだけを受け取るとしたら、私たちは一歩も前に進むことができないでしょう。超感覚的な能力を持ちたいと願う人であれば誰であれ、自分は自分が既に証明したものだけを受け入れることにしよう、などとは決して言わないでしょう。超感覚的な能力を持ちたいと願う人はあらゆる自己の追求から自由でなければならず、宇宙から自分たちのところへやって来るものはすべて、ただ「恩恵」という言葉で記述されることができるだけだということをあらかじめ知っていなければなりません。そのような人々は、照らし出す恩恵からあらゆるものがやって来ることを見通しています。では、人はどのようにして超感覚的な認識を達成するのでしょうか?それは私たちが既に知っているあらゆるものを脇にやることによってのみ可能となります。私たちは、通常、私には私自身の判断がある、と考えています。けれども、通常の判断は皆さんの先達が既に考えたこと、皆さんの願望を刺激するもの、あるいはその他のものを単に新しくすることからやって来るに過ぎません。決して自分自身で判断するかどうかが問題なのではありません。自分自身の判断を行使していると最も主張する人たちが、いかに自分自身の偏見に隷属的に結びつけられているかに最も気づいていない人たちなのです。もし、私たちがより高次の認識を達成したいのであれば、これらのことすべてから脱却していなければなりません。魂は空虚でなければならず、空間もなく、時間もなく、対象もなく、事象もない、隠された、秘密の世界から受け取ることができるものを静かに待つことができなければなりません。私たちは、顕現あるいは悟り、つまり、照らし出すものとして私たちに提供されるあらゆるものに出会うための雰囲気が私たちの中に醸成されることを待つことなしでも、より高次の認識を獲得できると決して信じるべきではありません。私たちに近づいてくるあらゆるもの、他でもない恩恵として、私たちのところに「来るべきもの」として、私たちに何かを与えるところのあらゆるものを私たちが待っていられるのは、ただこのような雰囲気の中においてのみです。そのような認識はどのようにして自らを現すのでしょうか。私たちのところへとやって来るはずのものは、私たちが十分に準備できたとき、どのようにして現れるのでしょうか。それは、精神的な世界から私たちに出会うためにやって来る贈り物によって、祝福されるという感情として自らを現すのです。もし、私たちの人生において、そのようにして私たちの前に立つところのもの、恵みに満ち、私たちをその認識で満たしながら私たちの前に立つもの、それが何らかの存在であれ、何か別のものであれ記述したいのであれば、それを表現する仕方はただ次のようなものだけです。つまり、私たちは、恵みを与えるものとして、贈り物をするものとして、私たちに何かを与えるものとして、私たちのところへとやって来るものを経験すると。ある存在の主な特徴が、付与し、与え、提供する恵みを注ぎ出し、降り注ぐ能力で構成されているとき、そのような存在の本性を把握するには、トローネのケルビームに対する犠牲のイメージを自分のものとする必要があるのです。ある存在が、トローネによるケルビームへの供儀の意味を理解している人のところにやって来る、と想像してください。それは、トローネの犠牲を理解する能力を与えるという能力、自らの贈り物を自らの周りに恵みとして注ぎ出すという能力に変化させることができる存在です。私たちが薔薇を見て喜びに満たされ、そうすることで、私たちが「美しい」ものとして眺める何かによって祝福されるという感情を経験していると想像してください。そして、また別の存在について想像していただきたいのですが、それは、ケルビームに対するトローネの犠牲の意義を理解し、それが有しているものを周囲のものに捧げる存在であり、与える精神の中で、与えられるものすべてを世界の中へと注ぎ出す存在です。もし、私たちが、そのような存在について想像するならば、それは、「神秘学概論」の中でも記述したように、土星存在期の間に知られるようになったあの存在たちに、太陽存在期の間に、つけ加えられたあの叡智の霊たちなのです。さて、もし、太陽存在期に現れ、土星存在期を通して既に存在していた霊たちにつけ加えられたこれらの叡智霊たちの特徴とはどのようなものか、と問われるならば、私は次のように答えなければならないでしょう。これらの霊たちは、そのはっきりとした特徴として、与えるという、授けるという、恩恵を行使するという、徳を有している、と。もし、私がこれらの存在たちについての定義を見いだそうとするならば、彼らは叡智の霊、大いなる譲与者、宇宙における偉大な与える者たちである!と言わなければならないでしょう。ちょうどトローネを偉大な犠牲者と呼んだように、叡智霊については、彼らは偉大な与える者たちであり、宇宙がそれから織りなされ、生かされている正にその贈り物を授ける者たちである、と言わなければならないでしょう。何故なら、彼らは、彼ら自身を宇宙の中に注ぎだし、最初に秩序を創り出したからです。「太陽」上における叡智霊の影響とはそのようなものです。つまり、彼らは彼ら自身の存在をその周囲に向けて与えるのです。けれども、もし、私たちが外的な観察に顕れるものを、より高次の感覚知覚によって見たいのであれば、「太陽」上では何が起こるかと問うかも知れません。私たちが「太陽」を見るとき、私たちが観察するのは「神秘学概論」の中で記述されたところのものです。熱に加えて、「太陽」は空気と光からも構成されています。けれども、単に、「太陽」は熱だけではなく、空気と光からも構成されていると言うならば、例えば景色について、遠くに灰色の雲が見えると言うようなものです。もし画家であったならば、この印象を得たとき、灰色の雲を描くかも知れません。しかし、もっと近づいてみるならば、灰色の雲というよりも、むしろ虫の大群のようなものを見いだすかも知れません。実際、灰色の雲のように見えたものは、無数の生きた存在たちだったのです。私たちが遠く離れたところから古「太陽」存在について考えるとき、私たちはそれと同じような状況にあります。遠くから見ると、古「太陽」は空気と光からなる天体のように見えます。けれども、もっと近くからそれを見るならば、私たちはもはや空気と光からなる天体を見るのではありません。そうではなく、叡智の霊による授与という大いなる徳が現れてくるのです。空気を単にその外的で物理的な性質にしたがって記述する人は決して空気の真の本質を見いだしません。これらの性質は単なる幻想(マーヤ)であり、外的な顕現に過ぎません。宇宙においては、空気があるところには必ず、贈り物を授与するという叡智の霊の行為がその背後にあります。織りなし、働き続ける空気は、大宇宙の霊による授与という徳を顕しているのです。空気の真の本質を見る人だけが、私はここに空気の要素を知覚する、しかし、実際には、叡智の霊たちが贈り物を周りに与えている、何かが叡智の霊からその周囲へと流れ出しているのだと言います。こうして、私たちは、今や、古「太陽」は空気からなっている、と言うときには、本当は何について語っていたのかを知ります。私たちは、今や、外的には空気として現れるものは、実際には、叡智の霊たちが彼ら自身の存在をその周囲へと流れ出させている活動であるということを知るのです。ところが、この時点で、超感覚的な視覚の前に、古「太陽」上での顕著なできごとが現れて来ます。このことを理解するためには、与えるという徳についてのもっと正確な考えを魂の生活の中から創造することができなければならない、ということをはっきりさせておく必要があります。私たちがこれまで記述してきたような、供儀の雰囲気の中での知覚や考えを私たちに浸透させることができるときに持つことができるような感情を、もう一度創り出してみましょう。そのようにして浸透させられた考えは、私たちにいつも特別な感情を起こさせます。それは科学的な考えのようなものではありません。それに非常によく似た経験は、芸術の領域において見いだされるかも知れません。その領域においては、ひとつの独立した実体を世界に提示するために、色や形態が世界の中へと流れ出すその流れ出し方をマスターした考えが必要になります。そのような贈り物を与える能力を持った存在を特徴づけるとすれば、この贈り物に結びつけられるのは生産性、創造性である、と言うことができるかも知れません。と申しますのも、与えるという行為そのものが創造的な活動だからです。そのように考え、その考えが世界に治癒をもたらすと感じ、そして、それを芸術作品の形で提示する人であれば、それが誰であれ、与えるという徳のもたらす果実を正しく理解しています。芸術家の心の中にある創造的な考えについて、そして、その考えがいかに物質の中に顕現するかについて、考えてみてください。つまり、この考えとは、正に空気の精神的な存在なのです。空気があるところには創造的な活動がある、ということです。そして、この生きた創造行為が「太陽」上にあったことにより、空気と創造的な活動とは関連しているということを事実として見て取ることができるのです。時間の霊が古「土星」上で誕生したことを思い出してみるならば、「太陽」上にも時間が存在していた。と申しますのも、時間は「土星」から「太陽」へとやって来ていたからということも分かります。そこにも時間は存在していたのです。原型的な与えるという行為が存在していたことで、古「土星」上では生じ得なかったひとつの可能性が古「太陽」上には存在していました。もし、時間が存在していなかったとしたら、与えるということはどうなっていただろうかと考えてみてください。つまり、与えるということは、与えることと受け取ることの両方から成り立っていますから、授与ということはあり得なかったことでしょう。受け取るということなしに、与えるということは考えられません。ですから、与えるということは与えることと受け取ることのふたつの行為から成り立っているのです。そうでなければ、与えることには何の目的もなくなってしまいます。「太陽」上では、与えるということは、受け取るということに対して、非常に特別な関係にありました。「太陽」上には既に時間が存在していますから、古「太陽」の周囲へと送り出される贈り物は時間の中に保存されるのです。叡智の霊たちがその贈り物を注ぎ出すとき、それらは時間の中に存在する状態に留まります。そのとき、それを受け取ることができる何かがやって来なければなりません。叡智の霊たちによる活動との関係で、受容ということが時間の流れにおける後の地点において起こります。叡智の霊たちが与えるのは以前の瞬間においてであり、その与えるということに受け取るという形で必然的に結びついていることがらが生じるのは後の時点においてなのです。このことについての正確な像を得るためには、もう一度、私たち自身の魂の経験を考察しなければなりません。皆さんが何かを理解しようとして、あるいは、何らかの考えを形成しようとして大変な努力をすると想像してみてください。皆さんは、今や、あれこれの考えを創造しました。次の日、皆さんは、前の日に皆さんの思考の中で創造したあらゆるものを再び心の中にもたらすために、皆さんの心の中を空にします。皆さんはこのようにして、昨日形成したものを今日受け取るのです。古「太陽」上でも状況は同じです。つまり、以前の時点において与えられたものは保存されたままとなり、そして、後の瞬間になって受け取られるのです。しかし、この受け取るということにはどのような意義があるのでしょうか。原型的な与えるということと同様、受け取るということもまた古「太陽」上における行いあるいはできごとだったのです。受け取るということが与えることと異なっているのは時間的な意味においてだけです。受け取るということが起こるのは後になってからです。与えるということは叡智の霊から生じますが、では、誰が受け取るのでしょうか。誰かが受け取るということが生じるためには、まず受け取る者が存在していなければなりません。「土星」上でのトローネによるケルビームへの犠牲が時間の霊の誕生へと導いたのと同様に、「太陽」上における叡智の霊による宇宙的な授与が始まったことで、私たちが大天使あるいはアークアンゲロイと呼ぶあの霊たちが生じたのです。大天使とは古「太陽」上で受け取る者たちのことです。けれども、彼らは非常に特別な仕方で受け取ります。と申しますのも、大天使たちは、叡智の霊から受け取るものを自分たちのために保持するのではなく、ちょうど鏡が、受け取った像を反射するように、それを反射するのです。こうして、「太陽」上の大天使たちは、以前の時点において与えられたものを受け取るという使命を持っているのですが、そのため、それは保持され、大天使によって後の時間の中へと再び反射されるのです。ですから、「太陽」上には、与えるという以前の行為と、受け取るという以後の行為が存在していますが、ここで言うところの受け取るとは、以前の時点において与えられたものを投げ返す、反射するということです。地球を現在あるがままにではなく、以前の時代に起こったことが再び現在へと流れ込んで来ていると想像してみてください。私たちは実際そのようなことが起こっていることを知っています。私たちが生きているのは第5後アトランティス時代ですが、第3後アトランティス時代である古エジプト-カルディア時代に起こったできごとは今の時代にまで流れ込んで来ているのです。第3の時代に生じたことは再び出現し、反射されるのです。これは古「太陽」発達期に生じた、与えることと受け取ることの再現です。このように、私たちは叡智の霊を古「太陽」期における与える者、そして、大天使を受け取る者と見なすことができます。このことから特筆すべきことがらが生じてくるのですが、それを正確に思い描くには、与えられるべき何かがその中心から放射してくるような内的に閉じられた天体を想像するしかありません。中心から周辺へと何かが放射され、そして、そこから再び反射されて中心点へと戻って来るのです。大天使たちは、自分たちが受け取ったものを、その天体の外表面の内から再び反射しています。外側から何かかが来ると想像する必要はありません。私たちは中心から外に向かって動く何かを想像しなければならないのですが、それは叡智の霊からやってくるものです。それはあらゆる方向へと放射され、それを反射し、返す大天使たちによって受け取られます。空間中へと反射し、返されるものとは何でしょうか。再び反射されるところの叡智の霊による贈り物とは何なのでしょう。再びその源泉へと向けられる放射する叡智とは何なのでしょうか。それは「光」なのです。大天使たちは光の創造者でもあるのです。光とは外的な幻想の中に現れるようなものでは全くありません。光が生じるところではどこでも、叡智の霊による贈り物が私たちに向けて反射されているのです。光があるあらゆる場所にそれが居ると考えなければならないような存在とは、大天使たちのことなのです。ですから、私たちは、溢れる光線の内部には大天使たちが隠れている、と言わなければなりません。私たちの元に来る溢れる光線の背後には大天使たちが隠れているのです。光を流出する大天使たちの能力は、叡智の霊たちが彼らに向けて放射するところの与えるという徳から生じます。こうして、私たちは古「太陽」の像に至ります。想像してみてください。中心では、叡智の霊たちが、古「土星」から受け継がれてきた遺産、トローネによるケルビームへの犠牲行為についての思索の中に沈んでいます。この犠牲の行いについて思索することによって、叡智の霊たちは彼ら自身の内実、与えるという徳の形を取った流れる叡智を放射するように促されます。この徳は、時間に浸透されているために、送り出された後、再び反射されるのですが、そのため、私たちの前にあるのは、その源泉、中心へと反射し、返される徳によって内的に照らし出された天体です。と申しますのも、私たちが想像しなければならないのは、古「太陽」は外に向かってではなく、内に向かって輝いているということだからです。そして、このことによって何か新しいことが生じるのですが、私たちはそれを次のように記述することができます。叡智の霊が「太陽」の中心で、犠牲を捧げるトローネについて思索し、彼ら自身の存在をそのはるかな周囲へと放射すると想像してください。そして、彼らが放射したものは、その天体の表面から、光の形で戻ってきて、再び彼らによって受け取られます。あらゆるものがますます照らし出されるようになるのですが、彼らに反射し、返されるものから彼らが受け取るものとは何でしょうか。大宇宙への贈り物として捧げられたのは彼ら自身の存在、彼らの最奥の存在です。今やそれが反射されて戻ってくるのです。彼ら自身の存在が外から彼らのところへと戻ってきます。彼らは大宇宙全体にばらまかれた彼ら自身の内的存在が光として、つまり、彼ら自身の存在の反映として、反射され、戻ってくるのを見るのです。今や、内と外とがふたつの極として私たちの前に立ち現れます。前と後とが自ら変容し、内と外とになります。空間が生まれるのです!叡智の霊によって与えられた授与するという徳の贈り物から、古「太陽」上で空間が生じます。それ以前には、空間とは、単に寓意的な意味しか持つことができないものでした。けれども、古「太陽」上には今や実際の空間があるとはいえ、それは2次元的なものに過ぎず、上下も、左右もなく、ただ内と外があるだけです。実際には、これらふたつの極は、古「土星」期の終わりには既に現れていたのですが、古「太陽」上での空間の創造に際して、その過程が繰り返されるのです。そして、もし、私たちがこれらのできごとのすべてを想像し直そうとするならば-ちょうど、以前、犠牲を捧げるトローネが時間霊を生じさせたことを私たちの魂の前にもたらしたように-光からなる天体を思い描いてはなりません。と申しますのも、光はまだ外に向かって放射するのではなく、単に内に向かって放たれる反射として存在していたからです。私たちはむしろ内的な空間としての天体を想像しなければなりません。その中心では、「土星」の像の繰り返し、つまり、ケルビームの前に跪く霊として存在するトローネ―ケルビームは自分自身の存在を捧げるあの翼を持つ存在たちです。そして、それらに加えて、犠牲の思索の中に浸る叡智の霊が生じます。今、想像することができるのは、犠牲(トローネの犠牲の火)の中に横たわるきらめきが叡智の霊の犠牲へと自ら変容するということですが、その犠牲の物質的な表現は、犠牲行為の間、捧げる煙として生じる空気です。ですから、次のように想像するならば、私たちは完全な像を得ることができます。・ ケルビームの前に跪き、犠牲を捧げるトローネ、・ 「太陽」の中心では、トローネの犠牲の印象を前にして祈りを捧げる叡智霊の合唱、・ 彼らの献身は犠牲の煙のメージとなり、あらゆる方向に広がり、外へと流れだし、周辺で雲へと濃縮する、・ 大天使が煙の雲から生じる、・ 周辺からは、犠牲の煙という贈り物が光の形を取って反射し、返される、・ 「太陽」の内部を照らし出す光、・ 叡智霊の贈り物が返戻(へんれい)され、それによって、「太陽」の領域が創造される。 この領域は燃える熱と犠牲の煙という外に向かって注ぎ出される贈り物から成立っています。外縁には光の創造者である大天使がいて、「太陽」上で以前に生じていたものを反射しています。時間がかかりましたが、最終的には、犠牲の煙が光として返戻されることになりました。大天使は何を保持していたのでしょうか?彼らは以前に生じていたものを保持していたのですが、それは叡智霊の贈り物です。彼らはそれを受け取り、そして、その後、反射し、戻したのですが、とはいえ、以前には時間として存在していたところのものを、彼らは空間として返したのです。時間を空間として反射し、戻すことによって、大天使たちは彼ら自身がアルカイから受け取っていたものを返したのです。こうして、彼らは原初の天使たちとなります。と申しますのも、彼らは以前から存在していたものを後の時代にもたらしたからです。大天使とは原初(アルカイ)の御使いたちなのです!真の秘儀の知識からこのような「言葉」が再び現れてくるということ、そして、この「言葉」が太古の伝統の中で生じ、パウロの弟子であるディオニシウス・アレオパギータの学院を通して私たちのところにまで伝えられた、ということを思い出してみるのはすばらしいことです。この言葉はあまりにも深く刻みつけられたために、私たちがそれを再び、書かれたものとは別に、見いだすとき、最初に生じたもの―最初の意味―が再び生じてくる、というのはすばらしいことです。それは私たちを大いなる尊敬の念で満たします。私たちは秘儀の叡智に参入するための古い聖なる秘密の学院に結びつけられているように感じます。それはこの太古の伝統が私たちの中に流れ込んでいるかのようなのですが、それは、たとえ、私たちが私たち自身の責任で、その古い伝統とは別に、この知識を獲得しているとはいえ、私たちがそれを理解することによって把握しているからです。私たちに伝えられてきた古い表現形式の雰囲気について何かを経験することができる人たちは、たとえそれらの伝統に気づいていないとしても、人間精神の内にある時間霊の影響の下に置かれていると感じます。人類の進化全体に結びつけられているというすばらしい感情、これらのことがらにおける確かさの感情がここから生じるのです。大天使たちは原型的な原初の思い出を保持しています。あれこれの惑星上に存在していたものであれば何であれ、後の時代に繰り返されるのですが、後で現れるときには、いつも何か別のものがつけ加えられます。ですから、ある意味で、私たちは、私たち自身の「地球」上に見いだすものの中においても、「太陽」の存在に出会うことになるのです。このイマジネーションの全体、私たちが発達させることができるこの感情全体が私たちに与えるのは、犠牲を捧げるトローネの像、その供儀を受け取るケルビームの像、その供儀から放射するきらめきの像、空気のように拡散する供儀の煙の像、そして、原初に生じたものを後の時代のために保存する大天使から反射する光の像です。この感情が私たちの中に目覚めさせるのは、これらの創造に関連したあらゆるものについての理解なのです。この環境、私が魂の状況としてここで描写した環境は、私たちが以前、物理的な表現を通して達成したところのものを、より精神的な観点から提示します。そして、私たちは今や、キリスト存在として「地球」上に現れた存在が生まれるのはこの環境からであるということを理解します。キリスト存在が「地球」に何をもたらしたのかを私たちが理解することができるのは、宇宙の光として「太陽」体内部の実質に向けて反射される、そして、それはこの光によって浸透され、照らし出されます。そのような、与えるという慈悲を生じさせる徳についての概念を自分のものにするときだけなのです。もし、私たちが今述べたようなこのイメージを掲げ、それをイマジネーションへと変容させ、そして、この存在が地球へともたらし、そこで体現したのはこれであると考えるならば、キリスト衝動という精神的な存在をより深く経験することができるでしょう。人間の魂の中に住むことができるぼんやりとした暗示が、この表現によって今記述されたことは「地球」上に再び住むことができるのだということを感じ取るとき、私たちはその暗示を理解することができるようになるでしょう。私たちが「太陽」について今述べたことがらが、ある「存在」の魂の中に集積され、完全に濃縮され、そして、後になって再び前面に持ち出されると想像してみてください。この「存在」は地上に現れ、原型的な行為と犠牲の煙が創り出したもの、つまり、光を生じさせる時間と与える徳から、賦活する慈悲の精髄が受け継がれ、魂の熱と輝く光が宇宙から反射されるような仕方で働きを行いました。このすべてがたったひとつの「魂」の中に濃縮され、その「魂」がそれを「地球」存在に受け渡すと想像してください。そして、それを反射し、返すとともに、後に残る「地球」存在のためにそれを保持する意図を持った者たちがその「魂」の周りに集まると。中心には、犠牲から、犠牲を通して、与える「者」が、そして、この「存在」の周りには、それを受け取る意志を持った者たちがいます。ここで私たちが結びつけたのは、一方では、地上的な存在へと置き換えられた、犠牲であるところのものと、その犠牲に属するものであり、他方では、この犠牲を破壊する可能性です。と申しますのも、慈悲を生じさせるために人間に与えられる可能性があるものはすべて、拒否されるか、あるいは、受け取られるかのどちらかだからです。このすべてが直感的知覚(インテュイション)の中に体現される、と想像してみてください。そのとき、そこにあるのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の前に立つときに経験するものです。つまり、そこには、以前の時代に生じたものを後の時代へと伝えるために選ばれた「者」たちから反射し、返される全「太陽」であり、それは、犠牲を捧げる「存在」たち、与える徳の「存在」たち、魂を暖める喜びと光に満ちた荘厳さの「存在」たち、それは魂によって把握されともにあります。このすべては、特に「地球」のために、同時に、それが裏切り者によって拒絶される可能性とともに設えられました。「太陽存在」が「地球」上に再び現れたものとしての「地球の存在」は、このようにして経験することができます。外的、知性的な仕方ではなく、真に芸術的な方法でこれが感じられるならば、「地球」存在の精髄を反映するあの偉大な芸術作品の中に、真の推進力を経験することができるでしょう。そして、次にこの絵を見るときには、「キリスト」がいかに「太陽」の環境から育ってきたかということを知るとともに、私たちがしばしば語ってきたことをよりよく理解することにもなるでしょう。つまり、もし、ある精神が「火星」から「地球」にやってきて、彼が見るものすべてを理解できなかったとしても、その精神がレオナルドの「最後の晩餐」を自分に作用させるようにするならば、彼は「地球」の使命を理解できるだろうということを。火星の住人は、「太陽」存在が「地球」存在の内部に隠されているに違いないということを理解することができるでしょう。そして、私たちがこのことの重要性について語ることができるあらゆることが、彼には明らかとなるでしょう。その火星の住人は「地球」が意味あるものであることを理解し、「地球」にとって何が重要なのかを知ることでしょう。彼は自分に次のように言うかも知れません。「これは地上のどこかで起こり得ることであり、「地球」存在の片隅でのみ意味を持つことかも知れない。しかし、もし、この行い、中央の人物のそれを取り巻く人物たちとの関連における色彩から私に向かって流れてくる行いを本当に表現することができるなら、「叡智の霊」たちが「太陽」上で経験したところのものが、ここでは「私の記念にこれを行いなさい」という言葉の中にこだましているのを感じることができるだろうと。ここには以後における以前の保存があります。これらの言葉を理解することができるのは、私たちがちょうど学んできたように、全宇宙の文脈からそれらを把握するときだけです。私がここで指摘したかったのは、第一級の芸術行為がいかに宇宙の発達全体に関連しているかということでした。次回の講義では、「月」の精神的な「存在」の観点へと進むために、「太陽」の精神的な「存在」の観点から「キリスト存在」を理解するということが私たちの仕事になるでしょう。参考図:霊的太陽系-01人気ブログランキングへ
2024年05月20日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
真相から見た宇宙の進化Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen(GA132) 佐々木義之さん訳■第1講:土星紀における地球の内的側面 ベルリン 1911年10月31日 去年の支部の夕べにおいて私たちが行った考察をさらに進めていきたいと思うのであれば、私たちがこれまでにお話ししてきたものとは別の何らかの概念、考え方、あるいは感じ方を自分のものとしなければなりません。と申しますのも、もし、私たちが私たちの宇宙体系全体の発展を前提としない限り、人類が残してきた福音書やその他の精神的な文献について私たちが語るべきことがらは、それだけでは十分であるとは言えないと思われるからです。私たちはこの進化を私たちの惑星そのものが「土星」、「太陽」、そして「月」の存在状態を通過し、ついには現在の「地球」としての存在状態を取るに至ったものとして記述してきました。私たちがこれらの基本的な原則にいかにしばしば言及してきたかを思い出す人であれば誰でも、それらが人類の進化に関するあらゆる秘教的な観察にとってもまたいかに必要なものであるかを知っています。けれども、もし皆さんが「神秘学概論」の中に記述されている「土星」、「太陽」、「月」、そして「地球」の発展段階に関する説明をご覧になるならば、そこに書かれていることは、たとえ拡張されているとはいえ、単なるスケッチに過ぎず、それ以外のものではあり得ないということを認めざるを得ないでしょう。それはある観点から描かれたスケッチに過ぎませんから、また別の特定の観点から説明することもできます。と申しますのも、ちょうど地球の存在状態が詳細な内容を途方もなく豊かに提供するように、「土星」、「太陽」、そして「月」の存在状態についてもまた、記録すべき無数の詳細な内容があるというのは当然のことだからです。とはいえ、これらの詳細についての大まかなスケッチや概要を描いてみせるということは、まさにいつでも可能なのです。ですから、今回の連続講義では、さらに別の面から進化の特徴を描いてみるということにならざるを得ないでしょう。私たちがこれらの説明すべては一体どこから来たのかと自らに問うとき、私たちは、それらはいわゆるアカシャ年代記への参入に由来するものであるということを知っています。私たちは、宇宙的な発展の経過の中で一度生じたことであれば何であれ、アカシャ実質と呼ばれる精妙な精神的実質の中に刻まれた印象を用いて、ある程度読みとることができるということを知っています。かつて生じたことがらすべてが残したこの種の刻印から、物事はかつてどのように存在していたのかを聞き取ることができるのです。物理的な世界においては、私たちが何かを見るとき、私たちのより近くにあるものは、その詳細において、一般に明確ではっきりとしているけれども、それがより遠くになるにしたがってあまり明確ではなくなると考えることができます。物事が、時間的に、私たちにより近い場合にも、より遠く離れている場合に比べて、より正確な姿で現れてきます。超感覚的な能力をもって振り返るときも同様です。例えば、「土星」や「太陽」の存在状態は「地球」や「月」の発達期に比べてその概要はより不明確なものとなるでしょう。しかし、一体何故そのようなことをする必要があるのでしょうか。何故、私たちは私たちの時代からそれほどまでに遠く離れている時代を追跡することを重要だと考えるのでしょうか。誰かが次のように問うかもしれません。「何故、この人智学者たちはそんな大昔のことを今さら持ち出すのか。私たちはそんなことに関わる必要は全くない。私たちには現在進行中のことが沢山あるのだから。」と。そのように言うのは間違っています。何故なら、時間の流れの中にかつて置かれたものは、今日においても、実りを迎え続けているからです。土星期の間に存在へともたらされたものは、単にその時代だけに、あるいは、その時代のためだけに存在したのではありません。当時起こったことは私たちの時代にまで影響を及ぼし続けているのです。とはいえ、それは人間をとりまく物理世界の中で外的に存在しているものとの関係においては、ヴェールをかけられ、見ることができないものとなっています。実際、はるか昔の古「土星」存在期に起こったことは今日ではほとんど見ることができなくなっています。にもかかわらず、古「土星」存在期は人類にとって今でも重要なのです。それが私たちにとって何故重要なのかを考えるために、次のことがらを私たちの魂の前に置いてみましょう。私たちは、私たちの存在の最奥の核は私たちが「私」と呼ぶところのものとして私たちの前に立つということを知っています。私たちの存在の最奥の核であるところのこの自我は今日の人間にとっては本当に実体がなく、知覚できないものとなっています。それがいかに知覚不可能なものになっているかということは、いわゆる「公的な」心理学の中で魂についてどのように語られているかを見れば推し量ることができます。それらはもはや自我を構成するものについてのいかなる考えも、あるいは、実際にはそのような自我を示唆することができるかもしれないという考えすら持っていないのです。私は19世紀のドイツ心理学において、「魂なき魂理論」という表現が徐々に使われるようになったという事実に注意するようにということをしばしば言ってきました。ウイルヘルム・ヴントの世界的に有名な学院は、ドイツ語を話す地域だけでなく、心理学について語られるところであればどこでも、大いなる尊敬を集めてきましたが、その学院が「魂なき魂理論」を流行らせたのです。この「魂なき魂理論」は、魂の特質を記述するにあたって、独立した魂の実存を前提としません。そのかわり、あらゆる魂の特質が最初に一種の焦点に集まるのです。つまり、自我の中へと集合するのです。かつて魂に関する理論に関連づけられたものの中で、これほどの愚考はありません。けれども、今日の心理学は完全にその影響下にあるのです。つまり、今日では、この概念は世界中でもてはやされているのです。将来、私たちの時代を研究するであろう文化歴史学者は、一体何故そのような理論が19世紀から20世紀に至るまで心理学の分野における最大の成果とまで見なされるようになったのかということを知るために、それらの仕事を切り抜きして利用することになるかも知れません。私がこのようなことを申し上げるのは、単に、「公的な」心理学が、自我すなわち人間の中心点に関して、いかに不明確であるかを指摘したかったからです。もし、私たちが自我をその真の性質において把握し、肉体を目の前に置くような仕方で、それを私たちの前に置くことができるとしたら、そして、肉体が目によって外的に見ることができ、感覚を通して知覚することができるものに依存し、栄養を必要とし、そして雲や山やその他のものを周囲の物理的な世界の中に見いだすのと同様の意味で、自我が依存している環境を見いだそうと努めるならば、つまり、もし、私たちが肉体についての文脈を知るのと同じ意味で自我にとって本質的な文脈を見いだそうと努めるならば、私たちは今日においても私たちの周囲に不可視的に浸透している宇宙の像あるいは絵巻物に至るのですが、それは古「土星」期の宇宙像と同じものなのです。言い換えれば、自我をそれ自身の世界において知ろうとする人であれば誰でも、古「土星」期の世界に似た世界を想像できなければならないのです。この世界は隠されています。つまり、それは人間にとって感覚知覚を超えた世界なのです。実際、私たちの現在の発達段階においては、その知覚を担うことは不可能なのです。それは境域の守護霊によりヴェールがかけられていることで、隠されたままになっているのですが、それは、そのような像を見ることに耐えられるためには、ある一定段階の精神的な発達が必要とされるからです。実際、人が最初に慣れなければならないのは、古土星が提示するような像を見る、ということです。皆さんは、何にもまして、一体どうすればそのような宇宙像を何か現実的なものとして経験することができるのかということについてのイマジネーションを形成しなければなりません。皆さんが感覚をもって知覚するあらゆるものを皆さんの思考から取り除かなければなりません。同様に、皆さんの内的な世界は魂の内部における潮の満ち引きから構成されていますから、皆さんはそれを捨て去らなければなりません。皆さんは世界に存在するものについての思考を消し去り、思考そのものもすべて解消するのです。感覚を通して知覚されるあらゆるものを外的な世界から取り除かなければなりません。つまり、皆さんは皆さんの内的な世界における魂や思考活動を消去しなければならないのです。このことを行った後、もし、皆さんが、この考えを本当に把握しようとするときに到達しなければならない魂の状態、あらゆるものが完全に取り除かれ、人間だけが残るということを思い出し、それについての考えを形成したいのであれば、皆さんが言うことができるのは、私たちの周囲に口を開けている底なしの空虚、無限に続く無の恐怖に耐えることができなければならないということだけです。完全に恐怖に満たされた環境を経験できなければならないのですが、同時に、自分自身の存在の内的な堅固さと確かさによってこれらの感情を克服できなければなりません。魂におけるこれらふたつの傾向―存在の無限に続く空虚への恐怖とそれを克服すること―なしには、古土星存在がいかに私たちの宇宙存在の基盤に横たわっているかを暗示するいかなるものも経験することはないでしょう。今、私が性格づけしたふたつの経験を、人々が自分で発達させることはめったにありません。また、この状態について書かれたものを見つけることもほとんどありません。もちろん、それを何年にもわたって超感覚的な力を用いて探求しようとしてきた人々はそれについて知っています。けれども、書かれたり出版されたりしたものの中には、人々が無限の深淵を前にしたときの恐怖やその克服について経験したということを示唆するものはほとんどないのです。私は、このことについての何らかの洞察を得る目的で、計りがたい空虚を前にしたときの恐怖らしきものが表現されている最近の文献を調査してみました。一般に哲学者はきわめて賢いので、概念については物知り顔にしゃべっても、恐怖を起こさせる印象については触れるのを完全に避けているのです。ですから、哲学的な文献の中に何かがこの問題について記録されているのを見つけるのは容易ではありません。何も見つけられなかった文献について今話すつもりはありませんが、それでも、ヘーゲル派の哲学者、カール・ローゼンクランツの雑誌の中に、この経験の残響のようなものを見いだすことができました。この雑誌の中で、ローゼンクランツは彼がヘーゲルの哲学に没頭しているときに経験した非常に親密な感情を記述しています。私は彼が全くそれとは知らずに彼の雑誌の中に載せている注目すべき文章に出会ったのです。ローゼンクランツにとって全く明白であったのは、ヘーゲルの哲学はヘーゲルによる「純粋存在」の理解に基づいているということです。ヘーゲルの原則である「純粋存在」については、19世紀の哲学文献の中で、非常に多くの表面的なことがらが語られてきましたが、実際には、それはきわめて貧弱にしか理解されていません。19世紀後半の哲学がヘーゲルの「純粋存在」について理解しているのは、雄牛が1週間ずっと飼い葉を食べ続けてきた日曜日について理解しているのと同じ程度においてであると言ってもいいくらいです。「純粋存在」というヘーゲルの概念―存在の経過ではなく、存在するという状態そのもの―は私が定義づけたような恐怖が流れ込む恐ろしい空虚のようなものと全く同じではありません。そうではなく、ヘーゲルの「存在」における空間のすべては人間が経験することができない特質、つまり、存在というものに満たされた無限の色合いを有しています。そして、カール・ローゼンクランツはかつてこれを、単なる存在以外の内容をもたない空間の宇宙的な広がりという恐ろしく打ちひしがせるような冷たさの状態として経験したのです。宇宙の根底に横たわるものを把握するためには、それを概念において語ったり、それについての考えを作り出したりするだけでは不十分です。古土星存在を特徴づける無限の空虚に直面したときに経験するものの像を呼び起こすことの方がずっと重要なのです。そのとき、魂は恐怖の感情を、たとえそれがそれを暗示するものに過ぎないとしても、把握します。山のように高い場所におけるめまいの感情、しっかりとした足場もなく深淵の縁に立つときの感情、あるいは、自分ではどうしようもない力に圧倒されながらあちこちと振り回されるときの感情を再現することによって、この土星状態を超感覚的に見上げることができるようになるための準備をすることができます。これが最初の段階、初めの感情です。次に、足下の大地だけではなく、目で見るもの、耳で聞くもの、手で触るもの-周囲の空間中に存在するありとあらゆるものが失われます。そして、不可避的に、人はあらゆる思考を失い、一種の黄昏あるいは眠りの状態に沈み込むのですが、そこでは何も認識的に把握することができません。あるいはまた、人はあらゆる感情の中に浸り、そして、しばしば克服することのできない目眩(めまい)の状態に捉えられ、死の状態に落ち込むことしかできなくなるのです。今日の人間には、深淵を前にして恐怖に捉えられることに打ち克つために、ふたつの可能性があります。ひとつの確立された方法は、福音書の理解、ゴルゴダの秘儀についての理解を通過する道です。福音書を本当に理解する人、福音書について現代の神学者が語るような方法によってではなく、内的に経験することができるその最奥のものを吸収する人は、彼あるいは彼女とともにその深淵の中に何かを持ち込むのですが、それは、まるで一点から広がっていき、勇気の感情、ゴルゴダにおいて供儀を完成させた存在と一体になることを通して守られているという感情によってその空虚を完全に満たしていくような何かです。これがひとつの道です。もうひとつは、福音書ではなく、真の、真正な人智学によって精神的な世界に貫き至る道です。これもまた可能なのです。ご存じのように、私がいつも強調しているのは、私たちのゴルゴダの秘儀についての考察は福音書から始めるのではない、ということです。その理由は、たとえ福音書が存在しなかったとしても、私たちはゴルゴダの秘儀を見いだすはずだからです。このことは、ゴルゴダの秘儀が生じる「以前」には不可能なことでした。しかし、それが今日可能になったのは、精神的な世界を精神的な世界の印象そのものから把握することを人々に可能にするような何かがゴルゴダの秘儀を通して世界の中にやって来たからです。これは世界における聖霊の存在、宇宙的な思考による世界の統治と呼んでもいいようなものです。とはいえ、人はそのための準備ができていなければなりません。私たちが恐怖を呼び起こすような空虚に直面しなければならないときでも、福音書あるいは人智学を携えているならば、道を失ったり、無限の深淵の中に飛び込んだりすることはないでしょう。もし、私たちが「いかにして超感覚的な世界の認識を獲得するか」、そして、それに続く他の著作の中で紹介されている準備を経てこの幽鬼的な空虚に近づき、精神的な世界、そこで生じるあらゆるものは私たちの感情は痙攣させ、私たちの思考を飲み込無事に貫き至るならば、私たちは動物、植物、あるいは鉱物界における存在たちとは全く似ていない存在たちに出会うことになるでしょう。私たちが「土星」という存在、そして、そこには雲も、光も、音もないのに親和し、適応するようになれば、私たちは存在たちを知るようになります。実際、私たちは、私たちの呼び方で、「意志の霊」あるいは「トローネ(座)」と呼ばれる存在たちを知るようになるのです。私たちが具体的な現実として知るようになる「意志の霊」たちは、いわば波打つ勇気の海から構成されているのです。人間にとって最初は想像することしかできなかったものが、超感覚的な能力によって、具体的な「存在」となります。皆さんが海の中に浸されていると考えてみてください、そして、キリスト存在とひとつになり、キリスト存在によって支えられていると感じている精神的な存在としてその中に浸され、泳いでいるのですが、それは今や水の海ではなく、流れる勇気、波打つ力で構成され、無限の広がりを完全に満たす海の中なのです。それはただの無関心で未分化な海ではありません。そこでは、勇気の感情として記述することができるようなもののあらゆる可能性と多様性が私たちのところへとやって来ます。私たちがそこで知るようになるのは勇気から構成されている存在たちなのですが、全く個別化されているのです。彼らは完全に勇気から成っているとはいえ、私たちが出会うのは勇気だけではなく、具体的な存在としての彼らなのです。肉からなる人間と同様に現実的でありながら、肉ではなく勇気からなる存在たちに出会うというのは確かにおかしなことのように思われるかも知れません。しかし、そうなのです。私たちは正にこの種の存在であるところの「意志の霊」に出会い、そして、彼らに出会うとともに、それによって、「土星」存在について記述しているのです。と申しますのも、それこそ勇気から成る「意志の霊」によって表現されているものだからです。それが「土星」なのです。それは球のような形をした世界ではありません。六つの角も四つの角も持っていません。空間的な側面を適用できないのです。ですから、「土星」存在には「終点」というものを見いだす可能性がありません。ここでも「泳ぐ」というイメージを用いたいのであれば、「土星」は海面を持たない海であると言うことができるかも知れません。その代わり、あらゆる場所で、あらゆる方向に、「勇気の霊」あるいは「意志の霊」が見いだされるのです。人はこのような洞察にすぐには到達しないのですが、何故そうなのかについては、後の講義で説明するつもりです。と申しますのも、ここでは以前に用いた「土星」、「太陽」、「月」という順番を用いようとしているのでが、本当は、反対の順番で、超感覚的な方法で実際に知覚される順番、つまり、「地球」から「土星」へという方向に-進む方がよいからです。しかし、今のところは、「土星」、「太陽」、「月」の順に特徴づけしていきたいと思います。順番そのものは重要ではありませんから。このようなものの見方に特徴的なのは、もし、人が少しずつ、慎重にその考えに到達するように注意していなかったとしたら、想像するのがきわめて難しいような何かが生じてくるということです。と申しますのも、そのとき何かが存在するのをやめるのですが、それは何にもまして通常の想像力に密接に結びついているものだからです。つまり、「空間が存在しなくなる」のです。例えば、「の頂上で」、「の下で」、「の前で」、「の後ろで」、「右へ」、「左へ」私は泳ぐというような、あるいは、実際、空間に関連したその他のあらゆる表現がもはや意味をなさなくなるのです。古「土星」においては、空間的な関連は全く意味をなしません。「至るところで」というのも「同様」です。けれども、最も重要なのは、「土星」の最初期の時代に入るときには、時間もまたなくなるということです。正に、後も先もなくなるのです。当然のことながら、それは今日の人間には想像するのがきわめて難しいことがらです。何故なら、ある考えは別の考えの前あるいは後に現れるというように、今日では人の考えそのものが時間の中を流れているからです。とはいえ、時間の欠如は感情を通して見積もることができるでしょう。しかし、この感情は心地よいものではありません。皆さんの思考形成能力が麻痺して、皆さんが思い出すことを可能にしているあらゆるもの、皆さんが行おうと計画しているあらゆるものが固まった棒のように麻痺したと想像してみてください。こうして、皆さんは、まるで皆さんの考えがしっかりと捕捉されて、もはやそれに触ることができないかのように感じます。この状態においては、皆さんは、皆さんが「以前に」経験した何かは、時間の中のある「時点」において生じたと言うことができません。皆さんはそれに結びつき、それはそこにあるのですが、それは完全に固定されているのです。時間が意味をなさなくなっているのです。時間は全く存在していません。ですから、次のように問うことは無意味なのです。「ところで、「土星」、「太陽」、あるいはその他の存在について記述したわけだが、「土星存在の前には何があったのかね」と。この文脈の中では、「前に」というのは無意味なのです。当時、時間は存在していなかったので、私たちは時間に関連したものを示すあらゆるものなしにやっていかなければなりません。「土星」存在というのは板張りされた世界の中にいる状況と似ています。思考は行き止まりになっているのです。超感覚的な能力も同様です。通常の思考はずっと前に置き去りにされています。それはそれほど遠くまで行けません。イメージ的に表現すれば、皆さんの脳は凍りついてしまいます。皆さんがもはや時間を包含しない意識についてのイメージに近づくことができるのは、皆さんがこの麻痺した状態を知覚できる程度においてです。ここまで来ますと、その全体像の中に生じる顕著な変化に気づきます。別のヒエラルキアに属する存在たちが、「意志の霊」とともに存在し、勇気からなる無限の海という時間のない世界であるところの麻痺の中に入り込み、活動するようになるのです。時間の不在が明らかになる正にその瞬間に、他の存在たちの活動に気づくのです。勇気からなる無限の海の内部に何かが存在しているのに気づくのですが、それは不明瞭な意識によってです。まるでそのことを経験しなかったかのようなのです。この広がりの中に何かが点灯するのですが、それは稲妻の素早い発光というよりは、明かりのようなものです。それは最初の差別化であるところのひとつの明かりなのですが、明るい光の印象を与えるような明かりではありません。皆さんは別の方法でこれらのことを理解するように努めなければなりません。例えば、次のようなことを想像してみるのもよいでしょう。皆さんは皆さんに何かを語りかける誰かに出会い、「この人物は何と知的なのだろう。」という感情を抱きます。この人物が語り続けるにつれて、この感情は強くなり、皆さんは「この人物は賢い、無限を経験している、だから、賢明なことがらを語ることができるのだ」ということに気づきます。さらに言えば、この人物は魅惑的なオーラを発散しているかのような感じを起こさせるのです。そして、この魅惑の要素が無限に強化されると想像してください。勇気の海の中に雲が現れるのですが、その中に、稲妻の光というよりは、正確にはきらめく放射が見られるのです。全体として、皆さんが想像することになるのは、今や「意志の霊」の内部で活動する存在、単なる叡智ではなく、放射する叡智の流れであるところの存在についてです。ここで、皆さんは、「ケルビーム」とは何かについて、超感覚的な知覚によるところの考えを持つことができます。つまり、「ケルビーム」とは、勇気の海に流れ込む存在たちのことなのです。さて、私が記述したもの以外には皆さんの周りには何もないと想像してください。実際、既に強調してきましたように、皆さんは、皆さんの「周囲」に何かがあると言うことはできないのです。皆さんが言うことができるのは、「そこに」それがある、ということだけです。そのように考えるようにしなくてはなりません。さて、何かが点灯しているというイメージは全く正確というわけでありません。そのため、私は瞬間的な煌めきというよりも、どちらかというと燃えるような輝きと言ったのです。と申しますのも、あらゆることが同時に起こっているからです。何かがある瞬間に存在するようになり、別の瞬間に消え去るというようなものではありません。すべてが同時なのです。とはいえ、「意志の霊」とケルビームの間には結びつきがあるという感情を持ちます。彼らがお互いに関係しているという感情を持つのです。このことが意識されるようになります。そして、「意志の霊」、トローネが彼ら自身の存在をケルビームに捧げる、ということが意識されるようになります。これが「土星」を逆向きに辿るときに得られる最終的なイメージです。「意志の霊」がケルビームにこの供儀を捧げる、というイメージを受け取るのです。それより先は宇宙がまるで「板張り」にされているかのようです。けれども、私たちが「意志の霊」によるケルビームへのこの供儀を経験する程度に応じて、何かが私たち自身の存在から絞り出され―押し出されて来ます。このことを言葉で表現するならば、「意志の霊」からケルビームにもたらされる供儀から「時間が生まれる」と言うことができます。けれども、この時間は私たちがそれについていつも話しているような抽象的な時間ではありません。それは独立した存在です。この時点で、私たちは初めて、何かが始まるということについて語ることができるようになります。最初は、時間とは時間存在、完全に時間から成る存在なのです。時間だけから成る存在が生まれて来るのですが、この存在は「人格の霊」、私たちがヒエラルキア存在の中の「アルカイ」として知っているところの存在です。「土星」存在においては、「アルカイ」とは全くの時間なのです。私たちは彼らのことを「時間*霊時間を司る霊」としても表現しました。彼らは霊として生まれてくるのですが、実際には、完全に時間から成る存在なのです。「意志の霊」によるケルビームへの供儀、そして、「時間の霊」の誕生に与る(*関与する)ということはとてつもなく重要なことです。時間が生まれた後で初めて、「土星」の状態、つまり、現在、私たちの周りを取り巻いているものに似た何かであるかのように語ることを私たちに許すような何か別のものが生じることになります。私たちが「土星」における熱の要素と呼ぶのはトローネによる供儀の煙であり、時間を生じさせるものです。私はいつも、「土星」は熱の状態として存在していると言って来ましたが、そのように言うことによって、そこに存在しているものを記述して来たのです。と申しますのも、現在、私たちの周囲にあるすべての要素の中で、古い「土星」にも存在していた要素として、熱だけを認めることができるからです。熱は「意志の霊」がケルビームに捧げた犠牲から生じたのです。このことはまた私たちが火についてどのように考えるべきかを私たちに示します。私たちが火を見たり、熱を感じたりするところでは、今日の人間が当然のこととして習慣的にそうするように、それを物質的に考えるべきではないのです。むしろ、それは、私たちが火を見たり熱を感じたりするところではどこでも、今日においてもなお「意志の霊」によるケルビームへの供儀なのです。熱の精神的な基礎を私たちの周囲に見ることはできないとしても、それは存在しています。あらゆる熱の顕現の背後に立っているのは供儀であるという真実に世界が至るのはこの洞察を通してなのです。「神秘学概論」の中では、人々を過度に怒らせることがないように、古土星の外的な状態だけが述べられていますが、それでも怒りを買ってしまいました。現代の科学的な文脈の中でしか考えることができない人々はこの本を全くのナンセンスであると見なします。けれども、もし、人が実際に次のように言うことができたとしたら、それは何を意味しているかということを考えてみてください。・古土星は、その最奥の存在として、正にその根底として、「意志の霊」に属する存在たちを有しており、彼らは彼ら自身をケルビームに捧げた。・「意志の霊」のケルビームへの供儀により生じた煙から、時間が生まれた。・時間が誕生したことにより、アルカイあるいは「時間の霊」がもたらされた。・私たちが知っているような熱は「意志の霊」による供儀の外的な表現、反映である。・したがって、外的な熱は幻想(マーヤ)である。もし、真実を語りたいのであれば、熱が顕現するところではどこでも、実際には、供儀(*ケルビームの前に捧げられるトローネの供儀)があると言わなければならない。 イマジネーションの能力を発達させることは薔薇十字的な秘儀参入の第2段階に当たります。このことは「いかにして超感覚的な認識を獲得するか」やその他のところでしばしば触れられています。人智学徒は、世界についての健全な表象からイマジネーションを形成しなければなりません。そのようにして、私たちは思考を想像力に染められたイマジネーションへと変容させることができるのです。私たちは今日お話ししたことがらを例として取り上げることができます。トローネあるいは「意志の霊」は完全な献身をもってケルビームの前にひざまずくのですが、それは卑しさの感情からではなく、捧げることができる何かがあるという意識から生じるものです。強さと勇気に基づき、喜んで供儀を捧げようとするトローネたちはケルビームの前にひざまずき、その捧げものを彼らに向けて差し上げます。トローネたちはその供儀を泡立つ熱、燃え上がる熱として送り出し、そのため、供儀の炎から立ち上る煙は翼をもったケルビームに向けて燃え上がるのです。私たちはそのようにこの現実を描写できるでしょう。そして今や、この供儀から生じるものとして、そして、それはまるで私たちが言葉を空中に向けて発し、その言葉が時間、それも「存在」としての時間であるかのようなのですが-これらのできごとの全体性から生じるものとして、「時の霊」あるいはアルカイが現れます。このアルカイを発生させるというイメージは非常に力強いものです。そして、私たちの魂の前に置かれたこのイメージは、私たちを隠された知の領域へとますます深くもたらすことができるようなイマジネーションにとって、きわめて強い効力を持っているのです。私たちがイマジネーション、すなわち像の中へと受け入れるアイデアをこのようにして変容させるということは、私たちが成し遂げるべきことがらです。たとえ私たちが形成する像が原始的なものであったとしても、それらが擬人化されたものであったとしても、たとえ私たちが描写しようとするこれらの存在たちが翼をもった人物であったとしても、それは重要ではありません。それが問題ではないのです。私たちの努力につけ加えられる必要があるものがあれば、それが何であれ、最終的には私たちに与えられるでしょう。私たちのイマジネーションが有するべきでないものは消え去るでしょう。もし、私たちがそのような像の中にひたすら浸るようにするならば、そのような活動そのものが私たちを実際にそのような存在の元へと導くことになるでしょう。もし、皆さんが、勇気に満たされ、叡智に満ち溢れた存在を特徴づける、という試みを受け入れることができるならば、皆さんは、魂がすぐに頼らなければならなくなるのは、理性によって形成される概念とはかけ離れた、ありとあらゆる種類の像である、ということが分かるようになるでしょう。知性的な概念が存在するようになったのはずっと後のことです。いずれにしても、純粋に知性的な方法で「土星」存在に近づくべきではありません。超感覚的な能力が、知性的に方向づけられた人たちとは異なる仕方で、素朴な超感覚的能力から何かを描き出そうとする人物の心の中で展開するということが何を意味しているかを、皆さんは理解するようにしなければなりません。知性的な人たちの側からそのような心が適切に理解されるということは決してありません。そのような例を皆さんに示したいと思います。アルバート・シュヴェグラー(1819-57年)の「哲学の歴史」(シュテュットガルト、1848年)を取り上げてみましょう。この本は、かつて学生たちが試験の前に勉強するのを好んだものですが、哲学から魂が取り除かれたことにより、もはや役に立たないものとなっています。しかし、後の版では改訂を受けているとはいえ、初版本の重要なところは完全には失われていません。つまり、それはヘーゲル哲学の観点から見た哲学の歴史書なのです。ですから、皆さんがシュヴェグラーの「哲学の歴史」を取り上げますと、皆さんはそれが書かれた当時の哲学像を知るためのよい例、ヘーゲル哲学の優れた参考文献をそこに見いだすことになります。けれども今、ヤーコブ・ベーメに関する短い章を読んでみますと、知的な哲学書を書く人物が、ヤーコブ・ベーメのような精神に直面するときには、いかに無力なものであるかを知ることができます。幸いなことに、彼はパラケルススを取り上げていませんが、もし取り上げていたとしたら、彼についての相当にひどい代物を書いていたことでしょう。とはいえ、シュヴェグラーがベーメについて何を書いているか読んでみましょう。彼はベーメの中にひとつの心を見いだしました。そして、その心の中では、古「土星」の像ではなく、「土星」の繰り返しの像が素朴な仕方で夜明けを迎えていたのです。この「土星」像の繰り返しは「地球」期において繰り返されたものです。シュヴェグラーがベーメの中で出会ったのは、知性を通しては理解できないような何かを言葉と像で記述しようと試みることしかできない精神でした。「土星」の繰り返しを把握しようとする純粋に知的な方法のすべては失敗するしかありません。つまり、それは、まるでこれらのことがらを全く理解できないかのようであるというよりは、もし、通常の、無味乾燥の哲学的論理にしがみつくだけならば、それらを把握することができないということです。お分かりのように、重要な点は、通常の知性の十全さを越えて自らを上昇させる、ということです。通常の知的な能力をもってしても、まだシュヴェグラーの「哲学の歴史」のように優れた作品を作り出すことはできますが、だからこそ、それは並はずれた知性が、ヤーコブ・ベーメのような精神に直面したとき、いかに完全に立ち止まらざるを得ないかということを示すよい例となっているのです。私たちは今日、古「土星」に関する考察の中で、私たちの「地球」が太古に体現した惑星状態の内的な側面に貫き至ろうとしました。私たちは古「土星」存在を振り返り、トローネたちが自らをケルビームに捧げることよって時間存在を創造したときの印象を生じさせるようにしましたが、この後の講義では、私たちがそれによって達成した概念に負けず劣らず印象深い概念に到達するために、「太陽」と「月」存在について同じことをしていくことにしましょう。時間とは犠牲から生じたものであり、生きた「時間」から成立っているのですが、「太陽」存在の間に、いかにこれらのことすべてが変化していくのかを、そして、私たちが「土星」存在から「太陽」そして「月」存在へと進むとき、宇宙におけるその他の力強いプロセスがいかに生じるのかを見ていくことにしたいと思います。 (第1講了)参照画:Saturn Mind記:ヤーコプ・ベーメ(Jakob B?hme):[1575~1624]ドイツの哲学者。靴屋職のかたわら、神秘主義思想家として、独特な汎神論的自然哲学を形成。のち、シェリング・ヘーゲルにより再評価された。主著「曙光」。参考画:haublin_result(Jakob B?hme)人気ブログランキングへ
2024年05月19日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 (GA233)翻訳紹介:yucca第9講 1924/1/1 ドルナハ 今、私たちは、人智学運動のための力強く重要な出発点とせねばならないこの会議の最終回に集っておりますので、この講義を次のように展開させていただきたいと思います、つまりこの講義がその衝動にしたがって、この連続講義によって与えられたさまざまな観点に内的につながりながらも、他方においては、ある意味で感受力に応じて、とでも申し上げたいしかたで、未来を、とりわけ人智学的努力の未来を示唆することもできるように、そのように展開させていただきたいのです。今日世界を眺めますと、なるほどもう数年来、きわめて夥しい破壊的様相が現れています。西の文明がさらにいかなる破滅の淵へと導かれるかを予感させる諸々の力が働いています。けれども、こう言ってよいかもしれません、生活のきわめてさまざまな分野においていわば外的な主導権を握っている人々を直視してみれば、これらの人々がいかに恐るべき宇宙的眠りにとらわれているかに気づくだろうと。彼らはほぼ次のように考えます。そしてつい最近までたいていの人はこう考えていました。十九世紀まで、人類は理解力と観照に関しては素朴で子供じみていたと。それからきわめてさまざまな分野に近代科学が到来した。そして今や、末永く真実として保存されねばならないものがきっとあるのだと。このように考える人たちは実にとほうもない高慢のなかに生きているのですが、ただそのことをわかっておりません。これに対して、今日の人類の内部には、事態はやはり、私がたった今大多数の人々の意見として示したようなものではないという何らかの予感が現れることもあるのです。少し前にドイツで、ヴォルフ事務所によって企画されたあの講演(☆1)を行うことができ、非常に多くの聴衆を得て、実際いかに人智学(アントロポゾフィー)が求められているか、少なからぬ人が気づいたわけですが、このとき、数多くのたわいない敵対の声に混ざって、ひとつの声が発せられました、なるほどほかのものに比べて取り立てて内容的に思慮深いところはないのですが、それでも独特の予感を示している声です。それは新聞の小記事で、私がベルリンで行うことのできた講演のひとつが引き合いに出されていました。その新聞の論評というのはこうでした、このようなこと、私があの時ベルリンでの講演で述べたようなことですが、それを傾聴するなら、人間たちを今までとは異なる霊性へと駆り立てる何かが、単に地上のみならず、私はほぼその記事どおり引用しています、全宇宙において起こっているということに気づかされるだろうと。今、単に地上的な衝動のみならず、いわば宇宙の諸力が、人間に何かを要求している、宇宙における一種の革命を、その成果がまさに新たな霊性への努力でなければならない一種の革命を要求していることがわかると。ともかくもこのような声がありました、そしてこれは実際注目すべきことです。と申しますのも、今や私たちがドルナハから始めようとするものに正しい衝動を与えなければならないもの、それは、私がここ数日間さまざまな観点から主張しましたように、地上で芽生えた衝動ではなく、霊的世界で芽生えた衝動でなければならないからです。私たちはここで、霊的世界からの衝動に従う力を発達させようとしているのです。ですから私は、このクリスマス会議の期間中夕方の講義で、歴史的進化のなかにあったさまざまな衝動についてお話ししました、霊的衝動を受け入れるために心を開くことができるようにです、まず地上世界へと流れ込ませなければならず、地上世界そのものにとらえられてはならない霊的衝動を。と申しますのも、今まで正しい意味で地上世界が担ったものはすべて、霊的世界に起源を有していたからです。そして私たちが地上世界のために実り多いことを成し遂げるべく定められているなら、そのための衝動は霊的世界から取ってこられねばなりません。このことは、愛する友人の皆さん、この会議から今後の活動のなかに私たちが持ち帰るべき推進力が、いかに大きな責任と結びつかねばならないかを指摘させずにはおかないのです。この会議を通じて私たちに大きな責任として負わせられるもののそばに、数分ばかりとどまらせてください。過去数十年間、霊的世界に対するある感覚をもつひとは、幾人もの人物のそばを通り過ぎることができたでしょう、霊的に観察し、この観察から地球の人類に到来しつつある運命に対して辛い感情を覚えながら。まさに霊において可能なあのしかたで地上の同胞のそばを通り過ぎ、そしてこうした人々を観察することができたでしょう、睡眠中に物質体とエーテル体を去り、自我とアストラル体とともに霊的世界に滞在しているときのこうした人々を。過去数十年間、人々が眠っている間の自我とアストラル体の運命の上方を逍遙するのですが、これがすでに、こういうことを知ることができる人に対して責任の重さを指摘する経験へのきっかけだったのです。眠りについてから目覚めるまで物質体とエーテル体を離れていたこれらの魂が、それからしばしば境域を守る者(境域の守護霊/Hueter der Schwelle)へと近づいていくのが見られました。この霊的世界への境域の守護者は、人類進化の経過にともない、きわめて多種多様に人間の意識の前に登場しました。少なからぬ伝説、神話、なぜならもっとも重要な事柄は、歴史的伝承という形式ではなく、こういう形で維持されるのが常なのですから、それが、かつての時代において、あれこれの人物が境域の守護者と出会い、そしてこの守護者から、霊的世界へといかに参入し、物質界へとまたもどってくるべきか教えられたことを示しています。と申しますのも、霊的世界への正しい参入にはすべて、どの瞬間においても物質界へと帰還することができるという可能性がともなっていなければならないからです、夢想家ではなく、夢想的な神秘家ではなく、まったく実際的で思慮深い人間として物質界のなかに現実的にしっかりと両脚で立つ可能性が。結局のところ、霊的世界への参入を目指す何千年にもわたる人間の努力のすべてを通じて境域の守護者に対して求められたのはこのことでした。けれどもとりわけ十九世紀の最後の三分の一の時期には、目覚めた状態で境域の守護者のところまで達する人間はほとんど見られなくなりました。何らかの形で境域の守護者のかたわらを通過することが歴史的に全人類に課せられている現代においては。しかし、申しましたように、霊的世界のなかをふさわしく逍遙してみると、眠っている魂が自我およびアストラル体として境域の守護者に近づくのがますますいっそう見出されます。今日得ることのできる重要な形象(光景)とは、目覚めた状態では境域の守護者に近づく力を持たないため、睡眠中に接近してくる、眠れる人間の魂集団に取り囲まれた厳格な境域の守護者なのです。そしてそのとき起こっている光景を見ると、不可欠の大きな責任の芽生えと名づけたいものと結びついている考えに至ります。このように眠った状態で境域の守護者に近づく魂たちは、人間が睡眠中に有している意識、目覚めた意識にとっては無意識的かあるいは下意識的なものをもって、霊的世界への参入を、境域を踏み越えることを要求します。そして数え切れないほど多くの場合、厳格な境域の守護者の声が聴こえます。お前はお前自身の救済のために境域を踏み越えることは許されない、お前は霊界への参入を許されない、お前は戻らなければならないと。と申しますのも、境域の守護者がこういう魂たちにあっさりと霊的世界への参入を許すとしたら、こういう魂たちは、境域を通過し、今日の学校、今日の教育、今日の文明に与えられた概念とともに、霊的世界に参入してしまうだろうからです、今日人間が六歳から結局は地上生活が終わるまでの間、それとともに成長していかざるを得ない概念や理念とともにです。これらの概念や理念にはこういう特性があります、現代の文明や学校を通じてこれらの概念や理念とともに人はこうなったわけですが、こういう概念や理念をもって霊的世界に参入すると、人は魂的に麻痺してしまうのです。すると思考も理念も空虚な状態で物質的世界に戻ってくることになるでしょう。もし境域の守護者がこれらの魂を、現代の人間たちの多くの魂を、厳格に突き返さないなら、これらの魂を霊的世界に入らせてしまうなら、これらの魂は、目覚めて再び帰還するとき、決定的な目覚めの状態で戻ってくるとき、こういう感情を持つことでしょう。私は考えることなどできない、私の思考は私の脳をとらえない、私は考えることなく世界を歩いて行くしかないと。と申しますのも、今日人間があらゆるものに結びつけている抽象的な理念の世界とは、その理念とともに霊的世界に入っていくことはできても、その理念とともに出てくることはできないというものだからです。そして、今日ふつう思われている以上に数多くの魂が今日睡眠中に実際に体験しているこの光景を見ると、人はこう言うのです、おお、これらの魂が睡眠中に体験していることを、死においても体験しなくてすむよう、これらの魂たちを守ることに成功しさえしたらと。と申しますのも、このように境域の守護者の前で体験される状態がじゅうぶん長く続いていくとしたら、すなわち、人間の文明が、今日学校で受容され、文明を通じて受け継がれ保存されるもののもとに長くとどまるとしたら、眠りから生が生じるようになるでしょうから。人間の魂は死の門を通過して霊的世界に入っていくでしょうが、理念の力をふたたび次の地上生へともたらすことはできないでしょう。今日のような思考とともに霊的世界に入っていくことはできますが、その思考とともにまた出てくることはできないからです。魂的に麻痺した状態で再び出てくることしかできません。よろしいですか、現在の文明は、これほど長期にわたって育成されてきた霊的生活のこういう形式に基づいていますが、生はこの形式には基礎を置くことはできないのです。この文明はしばらく続いていくでしょう。魂はまさに目覚めている間は、境域の守護者について何ら予感することもなく、麻痺してしまわないように睡眠中に境域の守護者に拒絶され、とどのつまり「*鯔の詰まり」、未来において、この未来の地上生のなかで知性も、人生における理念も示すことのない種類の人間が生まれるでしょう、そして、思考は、理念のなかの生命は、地上から消えてしまうでしょう。地球は、病的な、単に本能的な人類を住まわせるしかなくなるでしょう。理念の力に導かれることのない、劣悪な感情と情動だけが人類進化のなかに蔓延(はびこ)るでしょう。そう、悲惨な形象(光景)が霊視する者の前に現れるのは、単に描写しましたようなしかたで、霊界に参入できない境域の守護者の前にたたずんでいる魂たちを観察することによってのみではありません、別の関連においても現れるのです。特徴をお話ししましたあの逍遙、境域の守護者の前の眠っている人間の魂を観察することのできるあの逍遙の際に、今度は西ではなく、東の文明に起源を持つ人類を見てみますと、そのような東の人類を見てみますと、彼らから、西の全文明に対する恐るべき非難のように霊の声が高まってくるのが聞こえます。「見るがいい」このようなことが続けば、今日生きている人間たちが新たに地上に受肉して現れるとき、もう地球は荒れ果てているだろうと。人間たちは理念を持たず、本能のなかでのみ生きるだろう。お前たちも落ちぶれたものだ、お前たちが東洋の古の霊(Spiritualitaet)にそむいたからだと。実際のところ、人間の課題であるものにとって、霊的世界への私が描写しましたこのような眼差しこそが、強い責任の所在を明白に示すことができるのです。そしてここドルナハには、それを聴きたいと思う人たちにとって、霊的世界におけるあらゆる重要な直接的体験について語られることのできる場所がなければなりません。ここは単に、思案の限りを尽くし論理を操る経験的な現代の科学性のなかに、霊的なもののかすかな痕跡があそこあるいはここにあるということを示唆する力が見出されるだけの場所でなければならないというのではありません。ドルナハがその課題を実現しようとするなら、ここは、霊的世界において歴史的に生じるもの、霊的世界で衝動として起こり次いで自然的存在のなかに入り込んでいって自然を支配するものによって開かれていなければなりません、ドルナハにおいては、真の体験について、真の力について、人間の霊的世界での真の本質について聞くことができなければなりません。ここは真の精神(霊)科学の大学でなければなりません。そして、私が描写しましたように眠っている人間を厳格な境域の守護者の前に導いていく今日の科学性の要請を前にして、私たちは今後、退却することは許されません。ドルナハにおいていわば、これは霊的な意味で申し上げたいのですが、霊的世界に真正面から真に対峙し、霊的世界について経験する力を獲得することができなければならないのです。ですから、ここで今日の科学理論の不十分さについて論理を弄ぶ長弁舌を振いたいわけではありません、そうではなく人間が通常の学校のなかにその末端の見られる科学理論に貫かれて、どういう状態で境域の守護者の前にやってくるか、そのことに注意を喚起しなければならなかったのです。今この会議に際して、一度このことを真剣に自らの魂に対して認めたなら、このクリスマス会議は力強い衝動を魂のなかに送り込むことでしょう、そしてこの衝動はこれらの魂を今日人類に必要な力強い働きへと導いていくことができるでしょう、人間たちが真に境域の守護者に出会うことができ、つまり、文明そのものが、境域の守護者の前で耐えられる文明になるような次の受肉を人間たち見出すために必要な働きへと。今日の文明を以前の文明と比べてみてごらんなさい。かつてのあらゆる文明には、まず超感覚的世界へ、神々へと上昇してゆく概念、理念、つまり産出し、創造し、生み出す世界へと上昇していく概念、理念がありました。次いで、仰ぎ見るなかでとりわけ神々に属している概念とともに、ひとは地上世界を見下ろし、今度はこの地上世界をも神々にふさわしい概念と理念で理解することができたのです。神々にふさわしく神々に値するよう育成されたこれらの理念とともに境域の守護者の前にやってくると、境域の守護者はそのひとにこう言ったのです、お前は通過することができる、地上生の間に物質体のなかですでに超感覚的世界に方向づけられたものを、お前は超感覚的世界のなかへと携えていくからだと。それなら、物質的ー感覚的世界に帰還するときにも、超感覚的世界を見ることによって麻痺させられないための力がお前に残されるだろうと。今日人間は、時代の精神にしたがって単に物質的ー感覚的世界にのみ適用しようとする概念と理念を発達させています。これらの概念理念は、ありとあらゆる計量できるもの、測定できるものその他を扱いますが、ただ神々を扱うことはできません。これらの概念理念は神々にふさわしくありません、神々に値しないのです。それゆえに、神々に値せず神々にふさわしくない理念の唯物主義にまったく陥ってしまった魂たちに雷のような声が轟きます、眠りながら境域の守護者のところを通りかかるとき彼らに対して雷のような声が轟くのです、境域を越えてはならぬ!と。お前はお前の理念を感覚界に対して誤って用いた。それゆえお前はお前の理念とともに感覚界にとどまらねばならない、魂的に麻痺してしまいたくないなら、お前はその理念とともに神々の世界に入ることはできないと。よろしいですか、こういう事柄について語られねばなりません、それについてあれこれ考えをこね回すためにではなく、その心情が、これらの事柄によって貫かれ、浸透され、かくも厳粛な人智学協会クリスマス会議より持ち帰るべき正しい気分に至るために、語られねばならないのです。と申しますのも、私たちが持ち帰るほかのすべてにもまして重要になるのは、私たちが持ち帰る気分、ドルナハにおいて、霊的認識の中心が生み出されるだろうという確信を与える気分だからです。ですから、今日の午前、ここドルナハにおいて育成されるべきひとつの分野、つまり医学の分野のために、ツァイルマンス博士(☆2)によって次のように語られたことは、非常に真実味をもって響きました、つまり、今日、通常の科学の方からはもはや、ここドルナハで基礎固めをしなければならないものへと橋を架けることはできない、ということです。私たちの地盤の上に医学的に育つものについて、私たちが、我々の論文は現代の臨床的な要求にも耐えうると自負している、というように述べるなら、私たちの本来の課題である事柄をもってしては、私たちは決して特定の目標に到達することはないでしょう、なぜなら、そうすればほかの人々はこう言うだろうからです、ああ、新薬ですね、我々ももう新薬を造りましたよと。けれどもやはり重要なのは、人智学の生のなかに、医学のような生の実践の一部門が取り入れられるだろうということです。このことを私は今日の午前ツァイルマンス博士(☆2)の切望と解しました。と申しますのも、この目標に対し彼はこう語ったからです、今日医者になった人は、私はまさしく医者になったと言います。けれども彼は、新たな世界の一角から衝動を与える何かを切望しているのですと。そしてよろしいですか、医学の分野では、将来疑問の余地なく、これをここドルナハから実行していかなければなりません、人智学的なもののなかに胚胎されていた人智学的活動の数多くの他部門がまさに活動してきたように、そして今、私の協力者であるヴェークマン博士(☆3)とともに、まさにあの人智学そのものから形成される医学システム、人類はこれを必要とし、まずこれが人類の前にあらわれるでしょうが、あの医学システムが作り上げられたように。同様に私が意図しているのは、あれほど祝福に満ちた活動をしているアーレスハイムの臨床医療研究所との緊密な関係を、ゲーテアヌムとこの研究所とのできるだけ密接な結びつきを、できるだけすみやかに近い将来確立することです、そうすれば実際に、そこでの成果が人智学の真の方向づけのラインに乗っていくことでしょう。これはまた、ヴェークマン博士自身の意図するところでもあります。さて、これとともに、ツァイルマンス博士はある分野のために、ドルナハの理事会が人智学的活動の今やあらゆる分野において課題とするであろうことを指摘されました。したがってどういう事情なのか、今後わかってくるでしょう。ひとはこうは言わないでしょう、あそこにオイリュトミーを持っていこう、人々がまずオイリュトミーを見て、人智学について何も知らないなら、オイリュトミーは人々の気に入るだろう。それからその後、オイリュトミーが気に入ったのでひょっとしたら彼らはやってくるかもしれない、そしてオイリュトミーの背後に人智学があることを知るかもしれない、そうしたら人智学も彼らの気に入るだろうと。あるいは、まず最初に、人々に薬の実用を示さなければならない、そうすれば人々はこれを買うだろう。そうすれば彼らは後になっていつか、その薬の背後に人智学が潜んでいると知るだろう。そうすればそのときは彼らも人智学に近づくだろうと。注:オイリュトミー(Eurythmie)は、ドイツの哲学者・教育者ルドルフ・シュタイナーが1911年ごろに創出した教育法で、ギリシャ語で「調和のとれた美しいリズム」を意味します。音楽や言葉のリズムに合わせて身体表現を行う運動芸術で、手足を使った固有の動きに母音や子音の響き、音楽のリズムなどを表します 私たちは、このようなやり方をとることを不誠実とみなす勇気を持たなくてはなりません。私たちがこのようなやり方を不誠実とみなす勇気を持ち、そういうことに内的な嫌悪を覚えてはじめて、人智学は世界へと通じる道を見出すことでしょう。そしてこの点において、将来ここドルナハが、ファナティスムなしに、誠実でまっすぐな真理への愛のなかで堅持しなければならないものとは、まさに真理への努力でしょう。そうすることによってこそ、過去数年にかくも甚だしく働かれたかなりの不正を糺していくことができるかもしれないのです。軽々しい思いではなく厳粛な思いをもって、私たちは一般人智学協会設立に通じたこの会議を去らねばなりません。けれども私が思いますに、クリスマスにここで起こったことから誰もペシミズムを持ち帰る必要はなくなりました。なるほど私たちは毎日、悲惨なゲーテアヌムの廃墟の前を通っております、けれども、この会議のためにこの丘を登ってきてこの廃墟のそばを通り過ぎたどの魂のなかにも、同時に、ここで行われたことを通じて、つまりありありと目に見えるように、ここで私たちの友人たちによっておそらく心のなかで理解されたであろうことを通じて、あらゆるものからやはりこういう思いが起こってきたと思うのです、まさに再建されつつあるゲーテアヌムからの真の精神生活として将来の人類の恵みのためにぜひとも生み出さねばならない霊的な炎が、私たちの勤勉を通じて、私たちの帰依を通じて生み出さねばならない霊的な炎が、きっと出てくるのだ、という思いが。そして私たちが、人智学上の事柄を行う勇気をもってここから出かけて行けば行くほど、私たちの集いによってこの会議においてともかくも希望に満ちた霊の行進のように進行したことを、私たちはいっそうよく聞き取ることになるでしょう。と申しますのも、皆さんに描写しましたあの光景、しばしば目にすることのできあの光景、境域の守護者の前で眠っている退廃した文明と学校とともにある今日の人間、これは本来、感受性のあるアントロポゾーフたちのグループにはやはり存在しないからです。それでもやはり、状況によっては、勧告のみを要するものもあります、その勧告はこのようなものです、お前は霊の国からの声を聞くために、この声を自ら認め、発展させる強い勇気を持たなければならない、お前は目覚め始めているのだからと。ただ勇気の欠如だけが、お前を眠りに導くことができると。勇気を出すように勧める声、勇気による目覚めへと勧告する声、これが別のヴァリアンテ(変形)、現代の文明生活におけるアントロポゾーフたちのためのヴァリアンテです。アントロポゾーフでない人たちにはこのように聞こえます。霊の国の外にとどまるがいい、お前は理念を単なる地上的な対象に誤用した、お前は、神々に値するような、神々にふさわしいようなどんな理念も集めなかった。それゆえお前は、物質的ー感覚的世界に再び帰還する際、麻痺せざるを得ないだろうと。しかしアントロポゾーフの魂であるような魂にはこう語られるでしょう、お前たちの心情の傾向により、お前たちの心の傾向により、お前たちが声として聞き取ることができるであろうものを認める勇気においてのみお前たちを試すこととしようと。親愛なる友人の皆さん、私たちがかつてのゲーテアヌムを焼き尽くした燃え上がる炎を見たときから昨日一年目を迎えましたが、きょう私は、私たちは一年前に外で炎が燃え上がっていたときでさえ、ここでの仕事の継続を妨げられはしませんでしたので、こう望むことを許されるでしょう、物質的なゲーテアヌムが立つときには、私たちはもう活動していて、物質的ゲーテアヌムは、今世界へと出ていく私たちが共に理念として受け取りたい霊的ゲーテアヌムの単なる外的な象徴(シンボル)になっていることを。私たちはここに礎石を据えました。この礎石の上に建物を築いていかなければなりません。私たちのすべてのグループにおいて今や広い外の世界でひとりひとりによって成し遂げられる働きがそのひとつひとつの石となるような建物を。精神において今、こういう働きを眺めましょう。すると、今日お話ししました責任が私たちに意識されるでしょう、境域の守護者の前にたたずんでいる現代の人間たち、霊的世界への参入を拒まれねばならない人間たちに対する責任が。私たちに一年前にふりかかったことについて、この上なく深い苦痛と悲しみを感じる以外、決して思い浮かばないというのはまったくたしかです。しかしながら、世界においては何事も私たちはこれも心に刻みつけておいてよいでしょう。世界においてある一定の偉大さに到達したものはすべて、苦しみから生まれるのです。ですから愛する友人の皆さん、皆さんの働きによって力強く輝かしい人智学協会が苦しみから生まれるように、そのように私たちの苦しみが用いられますように。これを目指して、私が最初に語りましたあの言葉のなかに私たちは沈潜しましたが、あの言葉をもって私はこのクリスマス会議を終えたいと思います、単に年の始まりのためのみではなく、霊的生を帰依に満ちて育むために献身しようとする宇宙紀元の始まり(Welten-Zeitenwende-Anfang)のためにも、私たちの聖夜、クリスマスとせねばならないこのクリスマス会議を(☆4)。人間の魂よ!お前は四肢のなかに生きる、宇宙空間を貫き霊の海のうねりのなかでお前を担っていく四肢のなかに。魂の深みに霊を思い出せ、そこにしろしめす宇宙創造存在のなかで自身の自我は神なる自我のうちにある。 かくてお前は真に生きるだろう人間宇宙存在のなかで。なぜなら高みの父なる神は存在を生み出しつつ宇宙の深みでしろしめすのだから。セラフィム、ケルビム、トローネよ、高みより響きわたらせよ、深みに反響(こだま)すものを。それは語る、エクス デオ ナスキムル(神より生まれる)。元素霊たちがそれを聴く、東で、西で、北で、南で。どうか人間がこれを聴くように。人間の魂よ!お前は心臓と肺の鼓動のなかに生きる、時のリズムを貫きお前を自身の魂の本質を感じることに導く鼓動のなかに。魂の均衡のなかに霊を思え、そこにうねる宇宙生成行為は自身の自我と宇宙自我をひとつにする。かくてお前は真に感じるだろう人間の魂の働きのなかで。なぜなら経巡るキリスト意志は魂を祝福しつつ宇宙のリズムのなかでしろしめすのだから。キュリオテテス、デュナーミス、エクスシアイよ、東より鼓舞せよ、 西によって形作られるものを。それは語る、イン クリスト モリムル(キリストにおいて死ぬ)。元素霊たちがそれを聴く、東で、西で、北で、南で。どうか人間がこれを聴くように。人間の魂よ! お前は休らう頭のなかに生きる、永遠の奥底からお前に宇宙思考を明かす頭のなかに。思考の静寂のなかに霊を観よ、そこでは神々の永遠の目的が宇宙存在の光を自由な意志のために自身の自我に贈る。かくてお前は真に思考するだろう、 人間の霊の奥底で。なぜなら霊の宇宙思考は光を懇願しつつ宇宙の本質のなかでしろしめすのだから。アルヒャイ、アルヒアンゲロイ、アンゲロイよ、おお、深みより請い求めよ、高みにおいて聴かれるものを。それは語る、ペル スピリトゥム サンクトゥム レヴィヴィスキムス(聖霊により甦る)[元素霊たちがそれを聴く、東で、西で、北で、南で。どうか人間がこれを聴くように。](☆[ ]内の言葉は速記原稿によればここでは語られていない)紀元の初めに宇宙の霊の光が地上存在の流れに歩み入った。夜の闇が蔓延(はびこ)っていたが 真昼のように明るい光が 人間の魂を照らした。光、それは貧しい羊飼いの心を暖める。光、それは聡い王者の頭を照らす。神的な光よ、キリスト太陽よ、暖め給え、私たちの心を。照らし給え、私たちの頭を。私たちが心の底から目的を定めて導いていこうとするものが良くされるように。 このように、わが愛する友人の皆さん、皆さんが人智学協会のための礎石を据えたときの暖かい心を担っていってください、この暖かい心を、世界への力ある、治癒力ある働きかけへと担っていってください。そして、今皆さん全員が目的意識をもって導いていこうとするものが皆さんの頭を照らすことが、皆さんの助けになるでしょう。きょう私たちはこのことを全力で決心したいと思います。けれども私たちにはわかるでしょう、私たちがそれにふさわしく自己を示せば、ここから意志されたものの上に良き星がしろしめすであろうことを。従いなさい、わが愛する友人の皆さん、この良き星に。神々がこの星の光によって私たちをいずこに導いていくか、私たちは見てみたいのです(*)。神的な光よ、キリスト太陽よ、暖め給え、私たちの心を。照らし給え、私たちの頭を!□編集者註☆1 ヴォルフ事務所によって企画されたあの講演:1921年の秋冬と1922年の新年に、当時最大のコンツェルトディレクション、ベルリンのヘルマン・ヴォルフ及びユーレス・ザックスが、シュタイナーとの講演旅行を企画した。ベルリン、シュトゥットガルト、フランクフルト、ケルンその他の大都市において、シュタイナーは人智学の本質、人智学と科学、人智学と霊認識といったテーマについて語った(GA80として出版予定)。1922年ミュンヘンにおける不幸な暗殺計画の後、もはや講演者の安全が保障されないことが明らかになった。この後シュタイナーはもはやそれ以上の公開講演の義務にもはや応じなかった。☆2 ツァイルマンス博士:F. W. Zeylmans van Emmichoven ツァイルマンス ファン エミヒョーベン 1893-1961 医学博士、オランダの医師、著述家、オランダ地区協会事務総長。とくに『ルドルフ・シュタイナー 伝記』(シュトゥットガルト1961)を著した。 *邦訳『ルドルフ・シュタイナー』伊藤勉・中村康二訳(人智学出版社)☆3 イタ・ヴェークマン:Ita Wegman 1876-1943 医学博士、チューリヒ大学で研究、診療の後、1921年アーレスハイムに臨床医療研究所(現在イタ・ヴェークマン・クリニック)を設立。1923年クリスマスから1935年まで一般人智学協会理事会書紀、自由大学医学部門の長。1924/1925年、シュタイナーの主治医及び『精神科学的認識による治療芸術拡張のための基礎』(GA27)をシュタイナーと共著。☆4 以下の朗唱詩は速記原稿により、シュタイナーに語られたままがここに再現されている。旧版では、この詩はシュタイナーの最初の手書き草稿にしたがって印刷された。これについては『一般人智学協会設立のためのクリスマス会議1923/1924年』(GA260 1985年版、300 頁)の巻の特註を参照のこと。□訳註* この最後の数行でシュタイナーは、聴衆に向かって今までのSie(通常の敬称二人称) に代わって、古い形のIhr (十七世紀以前に使われた敬称二人称)によって呼びかけています。 (第9講了)人智学の光に照らした世界史完了参考画:Aヒトラー とR・シュタイナー-1人気ブログランキングへ
2024年05月18日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 (GA233)翻訳紹介:yucca第8講 1923/12/31 ドルナハ 今日(きょう)この日、私たちは、苦痛に満ちた記憶の徴(しるし)のなかに立っております。そして私たちは、今日まさにこの講義の内容としなければならないものを、何としてもこの苦痛に満ちた記憶の徴のなかに据えたいと思うのです。ちょうど一年前、かつての私たちの建物のなかで私が行うことを許された講義は(☆1)、ここにいらっしゃる皆さんのご記憶にもあると思いますが、地上の自然の諸関係から出発して、霊的世界と、この霊的世界を歩む星々からの開示(顕現)へと至る道筋を取りました。そしてその際、人間の心、人間の魂は、その本性に従って、人間の精神(霊)を次のようなものに関係づける可能性があったのです、地上的なものから出発し、単に星々の広がる世界のみならず、この星々の世界を通じて、霊的なものを宇宙の歩みのように写しているものにまで入っていくときに見出せるものに。そして、その直後に私たちから奪い去られたあの部屋で、私が黒板に描き出すことを許された最後のものは、まったくもって人間の魂を、霊的な高みにまで上昇させてゆくことを目的としていました。それによってまさにあの晩、私たちのゲーテアヌム建築がまさにその本質のすべてを通して捧げられるはずであったものに直接結びつけられたのです。ですから、あのとき結びつけられたものについて、今日はまず、ちょうど一年前にここで行われた講義の続きのように語らせていただきたいと思います。エフェソスの火災より前の時代において秘儀のことが話題になるとき、心情において秘儀についていくらか理解していた人たちの話はすべて、ほぼ次のように響きました。人間の智慧、人間の叡智は、秘儀のなかに場所を、居場所(安住の地)を持っていると。そしてあの古(いにしえ)の時代に世界の霊的指導者たちの間で秘儀のことが話題になったとき、つまり超感覚的な世界において秘儀について話されたとき、私はあえてこういう表現をしたいと思います。この表現はもちろん、超感覚的世界から下へと思惟され、感覚的世界へと作用が及ぼされるしかたを比喩的に示しているだけなのですが、つまり超感覚的世界において秘儀について話されたとき、その話はほぼ次のように響いたのです、供犠を捧げる人間と我々神々が出会うことのできる場所を、人間は秘儀のなかにしつらえる、供犠のなかで人間は我々を理解するのだと。と申しますのも、それは実際のところ、古の世界における一般的な認識だったからです、秘儀の場において神々と人間が出会うということを、世界が支え持つものはすべて、秘儀において神々と人間たちとの間で起こることに関連しているということを、古の世界にあって知っていた人たちの一般的な認識です。けれども、外的歴史的にも受け継がれてきたひとつの言葉があります、それはこの歴史的伝承からも実際人間の心に感慨深く語りかけることができますが、その言葉がとりわけ感慨深く語りかけるのは、青銅の、しかし霊(精神)においてほんの一瞬だけ目に見える文字で人類の歴史のなかに書き込まれるように、まったく特殊な出来事からその言葉が形作られてくるのを見るときです。そしてこれは、霊的な眼差しをヘロストラトスの行為へと、エフェソスの火災に向けるとき、このような言葉をいつも見ることができる、ということです。この火焔のなかに、「神々の妬み(der Neid der Goetter)」という古の言葉が見いだされます。とは言え、古の時代から受け継がれてきて、私が今描写しましたように古の時代の生活のなかに見いだされる数々の言葉のうち、この「神々の妬み」という言葉はこの物質界において最も恐ろしいもののひとつだと思います。あの古の時代にあっては、物質体を持って地上に現れる必要のない超感覚的存在として生きているものすべてが、神(Gott)という言葉で表され、きわめてさまざまな種類の神々があの古の時代には区別されていました。そして、人間の最も内的な本性にのっとって人間を生み出し、時代の推移を通過して送り出すというかたちで人間と結びついている神的ー霊的存在たち、私たちが外なる自然の壮麗さそしてきわめてささやかな現象を通して感じ取り、私たちの内部に生きているものを通じても感じ取っているこの神的ー霊的存在たち、こうした神的ー霊的存在たちが妬み深くなることはあり得ないというのは確かです。けれども、古の時代においては、「神々の妬み」ということで何か非常にリアルなものが意味されました。人間という種族がエフェソスの頃まで進化した時代を追求してみますと、比較的進化した人間個体が、秘儀において良き神々が彼らに喜んで与えたものの多くを自らのものとしたことがわかります。と申しますのも、次のように言えば、私たちはまったく的を得ているからです、つまり、良き人間の心と良き神々の間には、秘儀においてますます固く結ばれた親密な関係があった、そのため、人間が良き神性へとますますいっそう近づかされた。そのことが、ある種のほかの、ルツィファー的・アーリマン的神存在たちの魂の前に現れたと。そして、人間に対する神々の妬みが生じた。精神を希求する人間が悲劇的な宿命を辿るとき、古の時代にはその悲劇的な宿命が神々の妬みと関連づけられて示されるのですが、私たちは、歴史のなかにおいてこれを何度も何度も、聞かなければならないのです。ギリシア人たちは、この神々の妬みというものがあることを知っていました。そして人類進化おける外的な出来事のうち少なからぬものについて、その由来をこの神々の妬みに求めたのです。そもそもエフェソスの火災とともに明らかになったのは、人間のさらなる進化に対して妬みを抱く神々すなわち超感覚的存在たちがいるのだということを意識するようになったときにのみ、人類は霊的にある種さらに進化することができるということです。このことは結局、エフェソスの火災に続く且つアレクサンダーの誕生に続くと言うこともできますが、すべての歴史に特殊な色合いを添えます。そしてこのこと、つまりある種類の神々の妬みに満ちた世界を見渡すということは、また、ゴルゴタの歴史の正しい理解の一部でもあるのです。そうです、魂の雰囲気は、すでにペルシア戦争直後の時代以来、ギリシアにおいてもともとこの神々の妬みの作用に満ちていました。そして、その後マケドニア時代になされたことは、神々の妬みが霊的な雰囲気となって地表面を覆っているということを完全に意識して行われざるを得ませんでした。けれどもそれは、神々と人間との誤解に抗って、勇敢に、大胆に行われたのです。そして、神々の妬みに満ちたこの雰囲気のなかに、世界に実在しうる最大の愛を為すことのできた神の行為が下降していきました。他のすべてのものに、古代世界、つまりヘラス、マケドニア、前アジア、北アフリカ、南ヨーロッパにおける雲の形象(Bild)をもさらに付け加えることができるときにのみ、神々の妬みの現れであった雲の形象を付け加えることができるときにのみ、ゴルゴタの秘蹟を正しい光のなかで見ることができます。そしてこの暗雲に満ちた雰囲気のなかに、奇しくも暖みを与え穏やかに光を放ちつつ、ゴルゴタの秘蹟を通じて流れ出る愛が入り込んでいくのです。当時、こう申し上げてよろしければ、神々と人間との間に起こった事柄であったものは、この現代においては、人間的自由の時代においては、より下位の物質的な人間の生活において起こざるを得ません。それがどのように起こっているかを描写することもできます。古の時代においては、秘儀のことを考えるとき、ひとは地上でそれについてこう語りました、人間の認識、人間の叡智は、秘儀のなかにその居場所を持っている、と。ーー神々のもとにあったとき、ひとはこう語りました。私たちが秘儀のなかに沈潜していくと、私たちは人間の供犠を見いだす。そしてこの供犠の捧げる人間において私たちは理解させられると。結局のところエフェソスの火災とは、秘儀の本質の古い形式が次第に消え去っていく時代の始まりでした。私はそれがあちこちで、たとえばヒベルニアの秘蹟におけるように壮麗に存続されてきたようすを物語りました、ヒベルニアの秘儀においては、かなたのパレスティナでゴルゴタの秘蹟が物質的に起こったのと時を同じくして、祭祀(さいし)においてこの秘蹟が祝われていたのです。人々はこれをパレスティナ(*現代のアラブ人移民国は違いペルシテ人居住の国)とヒベルニアとの間の霊的な中継からのみ知ったのです、物質的な中継からではありません。とは言えやはり、物質界における秘儀の本質は、ますますいっそう衰退していきました。外的な居場所、神々と人間との出会いの場所は、ますますその意味を失っていきました。それらは紀元後十三、十四世紀にはほぼ完全に失われたのです。と申しますのも、たとえば聖杯への道を求めるひとは、霊的な道を歩むすべを理解しなければならなかったからです。エフェソスの火災より前の古の時代には、物質的な道を行きました。中世には霊的な道を行かなくてはなりませんでした。十三、十四世紀、とりわけ十五世紀以降、真の薔薇十字の教えを授かろうということであればとくに、霊的な道を歩まなくてはなりませんでした。と申しますのも、薔薇十字の神殿は、外的物質的な体験からは深く秘されていたからです。多くの真の薔薇十字会員は神殿の訪問者でしたが、いかなる外的物質的な人間の目もこの神殿を見いだすことはできまでんでした。けれども、智慧と人間の神聖な行いの隠者のようにそこかしこで見つけ出され得たこの古の薔薇十字会員たち、穏やかな目の輝きから神々の言葉を聴くことのできるひとには見いだすことのできたこの薔薇十字会員たちのところに行った弟子たちもいたにちがいありません。私は偽りを申し上げているのではありません。私は比喩を述べたいのではなく、まったくもって真実を述べたいのです、私が示唆します時代においてほんとうに重要な真実であった真実を。物質的な穏やかな目の輝きのなかに天の言葉を聴くことのできる能力が獲得されたとき、ひとは薔薇十字の導師(マイスター/Rosenkreuzer-Meister)を見い出しました。その後、中部ヨーロッパにおいてまさに十四、十五世紀には、きわめて質素な環境において、きわめてつつましい関係のなかで、ひとはこれらの独特な人物たちに出会いました、内面を神に満たされ、霊的な神殿、実在はしているけれども、名高い伝説において聖杯への接近として描写されている接近が困難であるように、実際に近づくことは困難な、そういう霊的な神殿と内面において関わり合っていた人物たちです。このような薔薇十字の導師とその弟子との間に起こったことを眺めると、近代的形式ではあっても神々の叡智を示す、地上を歩みながらのいくつかの語らいを聞き取ることができます。その教えはまったくもって深く具体的でした。孤独のなかで薔薇十字の導師は、彼を探し彼を見出すことに身を焦がした弟子によって見いだされました。このとき弟子たちのひとりが、神々の言葉を語る穏やかに見つめる目を見ると、弟子はつつましくたとえば次のような教えを受け取ったのです。見るがいい、わが息子よ、お前自身の本質を。お前は、外的物質的な目が見ているあの肉体を担っている。地球の中心点が、肉体を可視的にする力をこの肉体に送っているのだ。それがお前の物質体だ。だが地上のお前自身の周囲を見るがいい。お前は石を見る、石はそれ自体として地上にあることを許されている。石は地上に馴染んでいる。石はある形態をとると、地球の諸力によってこの形態を維持することができる。結晶をごらん、結晶は自らのうちにその形(フォルム)を担っている、結晶は地球によって自身の本質の形を維持するのだ。お前の物質体はそうすることができない。お前の魂が物質体を去れば、地球は物質体を破壊する、地球は物質体を塵(土)にもどすのだ。地球はお前の物質体に対してはいかなる力も持たない。地球は、驚くべき形態を与えられた透明な結晶構成物を形成し維持する力を持つが、お前の物質体を維持する力は持たない、地球はそれを塵に返さねばならない。お前の物質体は高次の霊性の一部だ。セラフィム、ケルビム、トローネ、お前の物質体の形(フォルム)と形態(ゲシュタルト)であるものは、これらの一部なのだ。この物質体は地球の一部ではない、この物質体は、お前にさしあたって接近できる最高の霊的力の一部なのだ。地球は物質体を破壊できる、だが決して物質体を組み立てることはできない。そしてお前のこの物質体の内部には、お前のエーテル体が宿っている。いつか、お前の物質体が地球に受け取られ破壊に向かう日が来るだろう。そしてお前のエーテル体は、宇宙の広がりへと消散していくだろう。宇宙の広がりはなるほどこのエーテル体を解消することはできるが、組み立てることはできない。エーテル体を組み立てることができるのは、デュナーミス、エクスシアイ、キュリオテテスのヒエラルキアに属するあの神的ー霊的存在たちのみだ。お前にエーテル体があるのはこれらの存在たちのおかげなのだ。お前は地球の物質的素材をお前の物質体と同化させる。だがお前のなかにあるものは、地球の物質的素材を変化させる、お前の内部で地球の物質的素材が、物質体の周囲に物質的にあるすべてのものと同じではなくなるように。お前のエーテル体は、お前の内部で液体であるもの、水であるものすべてを、お前の内部で動かす。内部を巡り、循環する液体、それはお前のエーテル体の影響のもとにある。だがお前の血をごらん、この血を液体としてお前の血管のなかに巡らせているのは、エクスシアイ、デュナーミス、キュリオテテス、これらの存在たちなのだ。お前は物質体としてのみ人間なのだ。お前のエーテル体のなかではお前はまだ動物だ。ただし、第二ヒエラルキアによって貫かれ霊化された動物なのだ。私がここで皆さんに、今は不十分な言葉でではあれ、要約してお話ししていることは、その穏やかな眼差しのなかに弟子が天の言葉を聴きとったあの導師の長い教えの対象でした。続いて弟子は、私たちがアストラル体と呼ぶ人間の本質の第三の部分を示されました。弟子がはっきりと理解させられたのは、このアストラル体は、呼吸のための、人間の生体組織において空気であるものすべてのための、人体組織のなかを空気として脈打っているすべてのもののための衝動を含んでいるということです。けれども、人間が死の門を通過してから後も長期間にわたって、地上的なものが空気状のもののなかでどうにかしていわば騒ぎたてようとしたり、そして霊視的な眼差しには、地球の大気圏の現象のなかで数年にわたって、死者たちのアストラル体が騒ぎ立てているのが感知できるのにも関わらず、やはり地球も地球の周囲も、アストラル体の衝動に対して、それを解消するということ以外に何をすることもできないのです。と申しますのも、アストラル体の衝動を形成できるのは、第三ヒエラルキア、つまりアルヒャイ、アルヒアンゲロイ、アンゲロイといった存在たちだけだからです。そして、弟子の心を深くとらえながら、導師はこう言ったのです。お前がお前のなかに鉱物界を取り入れてそれを変化させる限り、お前がお前のなかに人間界を取り入れてそれを加工する限り、お前はお前の物質体にしたがって、セラフィム、ケルビム、トローネの一部なのだ。お前がひとつのエーテル体である限り、お前はエーテル体においては動物のようだが、お前は第二ヒエラルキア、キュリオテテス、デュナーミス、エクスシアイの霊たちと呼ばれる霊たちの一部なのだ。そしてお前が液体エレメントのなかで活動する限り、お前は地球の一部ではなく、このヒエラルキアの一部なのだ。そしてお前が空気の形状のエレメントのなかで活動することで、お前は地球の一部ではなく、アンゲロイ、アルヒアンゲロイ、アルヒャイというヒエラルキアの一部なのだと。そしてこの教えを十分に伝授された後では、弟子はもはや自分を地球に属するものとは感じませんでした。彼はいわば、自分の物質体、エーテル体、アストラル体から出て、鉱物界を通じて彼を第一ヒエラルキアに結びつけ、地球の水状のものを通じて第二ヒエラルキアに結びつけ、大気圏を通じて第三ヒエラルキアに結びつける諸力を感じたのです。そして、熱エレメントとして自分の内部に担っているものを通じてのみ自分は地上に生きているのだということが彼に明らかになりました。けれども同時にこの薔薇十字の弟子は、自分のなかに担っている熱を、自分のなかに担っている物理的(物質的)な熱を、本来の地上的にして人間的なものと感じたのです。そしてさらにいっそう、彼は魂の熱と霊の熱を、この物質的な熱と親和性のあるものと感じることを学ぶようになりました。そして自分の物質的内容、エーテル的内容、アストラル的内容が、固体的なもの、液体的なもの、気体の形状のものを通じて神的なものとどのように関連しているかについて、後の人間はますます誤解していきますが、一方薔薇十字の弟子は、これについてまさに良く心得ていて、真に地上的ー人間的なものは熱エレメントであると知っていたのです。薔薇十字の弟子に、熱エレメントと人間的ー地上的なものの関連についてのこの秘密が明かされた瞬間、この瞬間に、弟子は自分の人間的なものを霊的なものに結びつけることを知ったのです。そしてこのような薔薇十字の導師たちが住んでいたしばしばほんとうに質素なあの住まいでは、弟子たちはそこに入る前に、しばしばわざとらしくない、不思議に思われるようなやりかたで、心構えをさせられました、彼らは気づかされたのです。ある者はこういうやりかたで、また別の者は別のやりかたで、それは表面的にはしばしば偶然のように見えました。お前は、お前の霊的なものが宇宙的ー神的なものと結びつくことのできる場所を探さなくてはならない、そう気づかされることで、心構えをさせられたのです。そしで、皆さんに今お話ししましたあの教えを弟子が受け取ったとき、そう、そのときに、弟子は導師に次のように言うことができました。私は今、地上で私に得られうる最大の慰めとともに、あなたのもとから去ります。なぜなら、あなたは私に、地上の人間はそのエレメントをほんとうに熱のなかに持っているということを示されました、それによってあなたは私に、私の物質的なものを魂的なもの霊的なものと結びつける可能性を与えてくださったからです。私は、固い骨、液体としての血液、気体の形状の呼吸のなかには、魂的なものをもたらすことができません。熱エレメントのなかに私は魂的なものをもたらすのです。つまり、この上ない静けさとともに、あの時代において教えを受けた者たちは導師たちのもとから去っていきました。そして面差し(Antlitz)の静けさから、この静けさは大いなる慰めの成果を表していましたが、この面差しの静けさから、天の言葉を語ることのできるあの穏やかな眼差しが徐々に育っていきました。そしてこのように、十五世紀の最初の三分の一までは、深い魂的な教えが根底にあったのです、外的な歴史が伝えるあの経過にとっては隠匿されていましたが。けれども、全人間を感動させた教えの伝授が行われていたのです、人間の魂に自身の本性を宇宙的ー霊的なものの領域に結びつけさせた教えが。このまったく霊的な気分は、前世紀の経過とともに消え去っていきました。その気分はもはや、現代の文明のなかにはありません。そして外面的な、神と離れた文明が、今しがた皆さんに描写しましたようなことをかつて見た場所の上に広がったのです。今日ひとは、今皆さんに描写しましたような場面に似た場面のいくつかについての、霊のなかにのみ、アストラル光のなかにのみ作り出すことのできる記憶とともにそこにいるのです。しばしば暗黒の時代として描写されるあの時代を振り返り、それから現代に目を向けると、今日基調となっている気分を与えられます。けれどもこのように見ても、十九世紀の最後の三分の一の時代から人々に可能になる霊的な開示から、心のなかに、霊的なしかたで再び人間に語りかけようという深い憧れが立ちのぼってくるのです。そしてこの霊的な方法は、単に抽象的な言葉によって自らに語らせるのではありません。この霊的な方法は、包括的に語るためにさまざまに徴(しるし)を必要としています。そして、一年前に焼失した私たちのゲーテアヌムの形(フォルム/Form)は、現代の人類に語りかける使命を持つあの霊的存在たちのために見出されるはずであった言葉、そのような言語フォルム(Sprachform)だったのです。演壇から聴衆の理念へと語りかけられていたものは、真に、このフォルムのなかで(☆2)語り続けられるはずでした。そして同時に、まったく新しいフォルムのなかで古のものを真に再び思い起こすことができた何かが、ある方法でゲーテアヌムとともに存在していました。秘儀に参入しようとする者がエフェソスの神殿のなかに歩み入ったとき、彼の眼差しは、ここ数日にわたってお話ししましたあの立像、心の言語で次のような言葉を実際彼に語りかけたあの立像に向けられました。「宇宙エーテルとひとつになりなさい、するとお前はエーテルの高みから地上的なものを見るだろう」という言葉を。このようにエフェソスの少なからぬ弟子が、エーテルの高みから地上的なものを見たのです。そしてある種類の神々がこれを妬むようになりました。それでも、ゴルゴタの秘蹟前の数世紀間、大胆な人々は神々の妬みに抗して、太古の聖なる人類進化の年月からエフェソスの火災まで働きかけてきたものを継続していく、弱まった状態ではありましたが、弱まりながらも作用し続けることはできたのですが、可能性を見い出しました。そして私たちのゲーテアヌムが完成していたら、西側に入っていくことにより、眼差しはやはりあの立像に向けられたでしょう、ルツィファー的な力存在とアーリマン的な力存在の間に据えられ、神を担い内的に存在を調停している宇宙的な存在として自己自身を知れという要求を、人間はあの像のなかに見いだしたことでしょう。そして、列柱、台輪(アーキトレーブ/Architrav)のフォルムに注目しますと、それはひとつの言葉を語りました、演壇から発して霊的なものの理念のなかへと翻訳するように継続してゆく言葉を。言葉はさらに、彫塑的に形成されたフォルムに沿って響きました。そして上のドームには、人類進化を霊的な眼差しに近づけることのできた場面が見られました。このゲーテアヌムにおいても、感じ取ることのできるひとにとって、エフェソス神殿の記憶を見出すことができたのです。けれども、ゲーテアヌムをゲーテアヌムそのものによってスピリチュアルな生の改新の担い手にしていかねばならなかった進化のまさにあの時点に、かけ離れてないやりかたで、つまりかつてのやりかたと似ていなくもないやりかたで、またも松明がこのゲーテアヌムに投げ込まれたとき、この記憶は実に苦痛に満ちたものとなりました。愛する友人の皆さん、私たちの苦しみは非常に深いものでした。私たちの苦しみは筆舌に尽くしがたいものでした。けれども私たちは、私たちを襲ったこの上ない悲惨、悲劇に妨げられることなく、霊的世界のための私たちの営みを続けていくことを決意しました。と申しますのも、心のなかで自らにこう言い聞かせることができたからです、エフェソスから燃え上がる炎を見ると、まだ人間に自由がなく、良き神々悪しき神々の意志に従わねばならなかった時代には、神々の妬み、と炎の中に書き込まれているのが見えると。現代においては、人間は自由に向けて組織されています。そして一年前の大晦日、私たちは焼き尽くす炎を見ました。赤い火焔は天へと燃え上がりました。暗い青の、赤みがかった黄色の炎の筋が、ゲーテアヌムに収めてあった金属の楽器から発してあまねく拡がる炎の海を、内部にさまざまな色彩を帯びた炎の海を貫いて、めらめらと燃え上がったのです。そして内部の多彩な筋とともにこの炎の海を見たとき、魂の苦悩に語りかけてくるものを、人間たちの妬み(Der Neid der Menschen)を、読み取らねばなりませんでした。人類進化において時代から時代へと語りかけるものは、このように最大の災厄のなかですら、ことごとく配列されているのです。人間がまだ不自由な状態で神々を見上げていたけれども、不自由から自らを自由にしなければならなかった時代、あの時代の最大の災厄を表現する言葉から、一筋の糸がつながっています、炎のなかに、神々の妬みと書かれているのが見えた時代のあの災厄から、人間が自らのうちに自由の力を見出すべき現代、炎のなかに人間たちの妬み、と書き込まれた現代の私たちの災厄まで、霊的進化の一筋の糸がつながっているのです。エフェソスには神々の像が、ここゲーテアヌムには人間の像がありました、人類の代表者、キリスト・イエスの像です、このキリスト像において私たちは、それと一体化しつつ、きわめて謙虚に、認識において上昇しようとしたのです、かつて、エフェソスの弟子たちが、今日の人類にはもはや完全には理解しがたい当時特有のしかたで、エフェソスのディアーナにおいて上昇したように。昨年の大晦日に私たちにもたらされたものを歴史的な光のなかに見ても、私たちの苦悩はやわらぎません。建物全体と調和するようにしつらえられた演壇上に最後に立つことを許されたとき、私はまさにあのときの聴衆の眼差しを、魂の眼差しを、地上の領域から星々の領域へと導こうとしたのです、意志と叡智、霊的宇宙の光を表している星々の領域へ。私はあのとき、皆さんに描写しましたように中世において弟子たちを教えていた精神の持ち主たちのうち少なからぬ人数が立ち会っていたことを知っております。そして最後の言葉が語られた一時間後、私はゲーテアヌム火災のため呼び戻されました。そして私たちは、昨年の大晦日の夜をゲーテアヌム火災のかたわらで過ごしたのです。こういう言葉を語るだけでもう、私たち全員の心、私たち全員の魂の前に、名状しがたいものが湧き起こります。けれども、人類進化におけるひとつの聖なるもの以上のものが奪い去られたときも、物質的なものが消滅したあともなお霊(精神)のなかで、物質的なものが供犠として捧げられた霊のなかで作用し続けることを誓った幾人かが常にいました。そして、私たちのゲーテアヌムの災厄から一年目を迎えるこの瞬間に私たちはここに集いましたので、私たちはこう述べることが許されると思います、物質的なフォルム、物質的な像、物質的な形態を通してゲーテアヌムとともに物質的な目の前にも置かれ、ヘロストラトス的行為によって物質的な目から奪い去られたものを、人類の前進する波を通って精神(霊)においてさらに担っていくことを私たち全員が誓うなら、私たちの魂は、私たちがともにあることについての正しい気分を持つのですと。かつてのゲーテアヌムには私たちの苦悩がこびりついています。私たちが今日記憶のなかで、誰もが魂のなかに担っている神的な最良のものの前で、あのゲーテアヌムのなかに外的なフォルムとして現れた霊的な衝動に忠実であり続ける、と誓うときにのみ、私たちは、このゲーテアヌムを建築することを許されたことによってともかくも私たちに課せられたものにふさわしくなるでしょう。このゲーテアヌムは私たちから取り上げられました。このゲーテアヌムの精神は、私たちが真に誠実で率直であろうとするなら、私たちから取り上げられることはあり得ません。私たちの愛したゲーテアヌムから炎が燃え上がった一年前のあの時点からまだ間もないこの真に厳粛な時間に、この瞬間に、私たちが単に苦悩を新たにするのみならず、苦悩から脱し、十年間にわたってこの場所を建設することを私たちに許したあの精神に忠実であり続けようと誓うなら、このゲーテアヌムの精神が奪われるおそれは最も少ないでしょう。愛する友人の皆さん、今日この内なる誓いが、誠実に、率直に、心からあふれ出し、私たちが苦悩を、苦難を、行為の衝動へと変化させることができるなら、そのとき私たちは、悲しい出来事をも祝福へと転じていくことでしょう。そうすることで苦悩が和らぐことはないかもしれません、けれども、それは私たちに、苦悩から脱して、行為への、精神(霊)における行為への推進力を見出させずにはおかないのです。愛する友人の皆さん、このように私たちは、私たちをあれほど言いようのない悲しみで満たしたあの恐ろしい火焔を振り返ります。けれども今日(きょう)は、私たち自身のなかの最良の神的諸力に誓って、私たちの心のなかの聖なる炎を感じましょう、私たちがこの意志を人類の前進の波を通って担い続けることにより、ゲーテアヌムとともに意志されていたものをこの炎で霊的に照らし暖めなければならないのです。この瞬間、私たちはこのように、私が一年前、ほぼ同じ時刻に語ることを許されたあの言葉を深めつつ繰り返しましょう。あのとき、私はほぼこういうことを語りました、私たちは大晦日に生きています、私たちは新たな宇宙年(Weltenjahr)を迎えて生きなければなりません、と。おお、ゲーテアヌムがなおも私たちのもとにあるなら、この激励を今この瞬間に新たにすることができるなら。もはやゲーテアヌムは私たちのもとにはありません。それはもはや私たちのもとにないからこそ、この奨励の言葉を、今日この大晦日の晩、何倍も力を強めて発することが許されると思います。ゲーテアヌムの魂を、新たな宇宙年へと担っていきましょう、そして、新たなゲーテアヌムのなかに、かつてのものの肉体にふさわしいモニュメントを、ふさわしい記念碑を打ち立てるべく努めようではありませんか。愛する友人の皆さん、これが私たちの心を、私たちが諸元素へとゆだねなければならなかったかつてのゲーテアヌムに結びつけてくれますように。これが私たちの心を、このゲーテアヌムの精神(霊)に、魂に、結びつけてくれますように。そして、私たち自身のなかの最良の存在へのこの誓いとともに、私たちは単に新年へと生きていくのみならず、力強く行為し、霊を担い、魂を導きつつ、新たな宇宙年へと生きていこうではありませんか。愛する友人の皆さん、皆さんはかつてのゲーテアヌムへの追憶のなかで身を起こし、私を迎えてくださいました。皆さんはかつてのゲーテアヌムへの追憶のなかに生きておられます。さあ今こそ、立ち上がりましょう、私たち人間の本性をかたどる像のなかに見出すことのできる最良の力とともに、私たちはゲーテアヌムの精神においてさらに活動し続ける、という誓いの証(あかし)として。どうかそうあらんことを。アーメン。そして、愛する友人の皆さん、私たち人間の魂を神々の魂に結びつける意志に従って私たちがそうできる限り、私たちはこれを持ち続けようではありませんか、私たちはこの神々の魂に精神において誠実であり続けようします、私たちがゲーテアヌムの精神科学を求めた人生のあの時、神々の魂へのこの誠実を私たちはその精神から追求したのです。そして理解しましょう、この誠実を守るということを。 (第8講了)参考図:Rosenkreuzer-Meister□編註☆1 ちょうど一年前 … 講義は:1923年12月31日ドルナハでの講義。『人間と星界の関係 人類の霊的な聖体拝領』(十二回の講義、1922 GA219)所収。☆2 この形のなかで:ルドルフ・シュタイナー『ゲーテアヌムの建築思想』(1921年6月29日、ベルンでの講義、GA290 シュトゥットガルト、1958)参照のこと人気ブログランキングへ
2024年05月17日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 (GA233)翻訳紹介:yucca第7講 1923/12/30 ドルナハ 人類の歴史的進化における最後の大きな転換点(区切り)は、しばしば言及しました十五世紀の最初の三分の一の頃、悟性魂あるいは心情魂と呼ばれるものから意識魂への移行が起こった頃です。私たちは、人類にもっぱら意識魂の発達が起こっている時代に生きているわけですが、この時代には、自然のより深い衝動や力、すなわち自然における霊の衝動や力と人間を関係づける真の洞察は失われてしまいました。私たちは今日、人間と人間の物質的な成り立ちについて語るとき、たとえば化学者が今日いわゆる元素(エレメント/Element)と定めている化学物質について語ることさえします。けれども、何らかの食物が、炭素、窒素云々を含むことを知ったところで、それはもはや人間認識にとって、この時計がガラスとあるいは銀とその他いくつか別の素材からできていると知ることが時計のメカニズムにとって持つ以上の価値はありません。このように、実質的なものを、水素、酸素云々といったこのきわめて外的な抽象に還元することはすべて、結局真の人間認識はもたらしません。時計のメカニズムが力システムの連関から知られなければならないのとまったく同様に、人間の本質も、自然の諸領域に分割され宇宙のなかで別様に作用している宇宙のさまざまな衝動が、人間のなかで今まさにどのように発現しているか、その発現のしかたから知られなければならないのです。すでに退化したとはいえ、生まれつき良い本能に恵まれた人物たちによって十四、十五世紀まではいくらかのことが可能であったのですが、このようにそれでもまだ比較的残っていたもの、人間と宇宙との連関を真に見通すものは、パラケルススやヤーコプ・ベーメなどの少数の例外を除いて、少しずつ、完全に消え去ってしまいました。十五世紀以来徐々に形成された近代科学は、たとえば、そうですね、植物界、動物界と人間との関係について何を知っているでしょう。科学はまさに植物の化学的成分を調べ、それから何とかしてこの化学的成分の人間にとっての意味を研究しようとします、そして場合によっては、健康な人間と病気の人間への物質の作用について表象を形成しよう。これもたいがい放棄されるのです。けれども結局これらすべては人間をめぐる認識の闇をもたらすだけです。歴史的な洞察に基づいて人間認識において前進したいと思うなら、今日まったくもって重要なのは、人間の外にある自然と人間との関係についてまた知るようになるということです。十五世紀の最後の大きな飛躍までは、人間は明確な感情を持っていました。外部の自然のなかの金属と、人間の実質的なもの、人間の物質的なものに目を向けるとき何らかのしかたで現れてくる金属、そうですね、たとえば人体組織のなかにさまざまな結合して現れる鉄、あるいはマグネシア(苦土/Magmesia)などといった金属との間にどれほど大きな違いがあるかということについて、明確な感情があったのです。人体組織そのものを調べれば見出せるような金属と、人体組織を調べてもまずは見つからない金属が存在するということ、地上の金属に見られるこの違いについて、十五世紀までは、深い、根本的な感覚がありました。と申しますのも、人間はミクロコスモスである、と言われていたからです。マクロコスモスである外部世界に見出せるものはすべて、何らかのしかたで人間のなかに見出せるのです。これは何か普遍的抽象的な原理などではなく、かつて何らかの方法で秘儀参入学に近づいたひとにとって、それは人間の本質と宇宙の本質に必然的に結びつけられたものとして続いていきます。と申しますのも、全自然をその衝動と物質的な内容のすべてと関係づけるときにのみ、人間をほんとうに認識できるようになるからです。そのとき人間の本質についての像が、イマジネーションが得られます。そしてもし人間そのもののなかに見出すことのできない何かが外部の自然のなかにあるとしたら、この像、このイマジネーションは、損なわれるだろう。そうですね、まだ九、十、十一世紀の初頭に自然研究者であった人物はこのように考えたのです。けれども、人間が物質的な食物を通じて取り入れるものは、人間の物質的な生体組織を、生体の組織全般を維持しているものの一部にすぎないし、おそらくは最も重要なものですらないということも当時はよく知られていました。さて、呼吸というのもやはり新陳代謝なのですが、物質的な栄養から呼吸へと上昇するということには容易に思い当たりますね。ところが今日の人間は、さらに上昇していくということには思い至らないのです。十五世紀の自然研究者は、知覚というものに目を向ければ、単に目によって見ているというだけではなく、知覚プロセスが続く間、限りなく微細に分割された物質的なものが宇宙万有から目を通じて取り入れられるのだということをはっきりと理解していました。このように目を通し耳を通して、それは起こるのですが、人間の生体組織のほかの部分を通してもこれは起こりました。そして最も重要なことと見なされたのは、人間が粗雑な状態では自らのうちに有していないもの、そうですね、例えば鉛ですが、人間はこれを、まず予想できないほど限りなく微細に分割された状態から摂取するということです。鉛はさしあたり体内には検出されない金属です。けれども鉛は、拡散した金属、人間の思慮の及ぶ全宇宙にまで非常に希薄な状態で拡散した金属なのです。そして人間は鉛を、呼吸プロセスよりもずっと精妙なプロセスを通じて宇宙から取り入れます。人間は絶えず、周辺の(peripherisch)方向に自分から物質を分泌しています。皆さんは単に爪を切るというだけでなく、絶えず皮膚から物質を分泌しているのです。けれどもこれは単に退去するというだけではなく、物質が去っていく一方でほかの物質が摂取されるのです。よろしいですか、このように中世の九、十、十一、十二世紀の自然研究者はまだこうした思考の道筋のなかに生きていました。彼にとってはまだ、諸々の物質が、力が、どのように作用しているかを定めるのは、秤などではありませんでした、無骨な測定器でもありませんでした。そうではなく、自然の内なる特質(Qualitaeten)のなかに入り込んでいくこと、自然の内なる衝動と、自然と人間の関係のなかに入り込んでいくことでした。そうすることによって、この十五世紀までは多くのことが知られていました、それらをまた知ることが始められなければなりません。今日人間についてはまったく何もわからなくなっているからです。人間の成り立ちを探究して、一種の分類、一種の一般的なプランとでも申し上げたいものを与えるために、私たちはまず、人間は物質体、エーテル体、アストラル体、自我あるいは自我組織(Ich-Organisation)から成ると言っていますね。そう、これらはとりもなおさず言葉です。こういう言葉をもって始めるというのは良いのです、これらの言葉で誰しも何か少しは思い浮かべることができるでしょうから。けれどもこれらを生の実践において用いようとするなら、つまり人間の認識から追求しうる最も重要な生の実践である治療において用いようとするなら、これらの言葉にとどまっているわけにはいきません、言葉を真の内容で満たすもののなかに入っていかなければなりません。まず最初に問いましょう、物質体です、私たちはどのようにして物質体の表象に辿り着くでしょう。私がなぜこの概念を展開するのか、皆さんはのちほどすぐおわかりになるでしょう。私たちはどのようにして物質体の表象に辿り着くか。さて、地上において人間の外部に何かある対象が、そうですね、石があるとしますと、石は地面に落ちます。石は重い、石は地球に引き寄せられる、石には重さがあると私たちは言います。私たちはそのほかにも作用している力を見出します。石が結晶へと形成されるとき、石のなかには形(フォルム)を成す力が働いています。けれどもこれらの力は地上的な諸力に親和性があります。要するに、私たちが周囲の世界を見ると、地上的な本質に従っている物質があるわけです。私たちはこのことを心に留めておきましょう、私たちは地上的な本質に従っている物質を持つと。こういうことにきちんと目を向けないひとがやってきて、一個の炭、黒い炭を見せるでしょう。実際これは何なのでしょう。地球の近くでのみこれは炭なのであって、この炭を比較的短い距離であっても地球から離すとその瞬間に、それはもはや炭ではなくなるでしょう。地上で炭を炭たらしめているものはすべて、地球の諸力なのです。つまり皆さんはこう言うことができます、ここに地球があるとすると、地球の諸力はこの地上的なもののなかにあるのだが、この地球上で私が持つどの対象のなかにもあると。そして、人間の物質体はなるほど複雑に組み合わされているけれども、根本においてこれも、地球のこれらの物質的な力、地球の中心点からやってくる力に従う対象なのです。これは人間の物質体です、これは地球の中心からやってくる諸力に従います(外向きの矢印)。さて然し乍ら、地上には別の諸力もあります。これらの力は周囲からやってきます(内向きの矢印)。私がまったく定かならぬ遠方まで出かけていくとひとつ考えてみてください。そのとき、ちょうど地球の力とは逆に、定かならぬ遠方から力がやってきます。この力は至るところから働きかけてきます。そう、いたるところから作用してくる力、宇宙のあらゆる方向から地球の中心点に向かって働きかけてくるこのような力があるのです。これらの力について、まったく確かで具体的な表象を得ることができます、それは以下のようにしてです。有機体の、つまり植物、動物、人間の有機体(生体組織/Organismus)の基礎をなす最も重要な物質は、蛋白質です。けれども蛋白質はまた、植物、動物、人間の新たな生体組織の基礎でもあります。胚細胞(生殖細胞/Keimzelle)、受精した胚細胞から、植物、動物、人間の生体組織として発達するものが発生します。蛋白質は物質です。今日、ひとは真の科学を行う代わりにいたるところで空想しますので、こう思い描きます、蛋白質、これは、いわゆる炭素、酸素、水素、窒素、硫黄、いくらかの燐から複雑に組み合わされた、まさしく複雑に組み合わされている物質であると。つまり蛋白質のなかに、原子論者が考えるような理想の組み合わせが得られるというわけです。まったく複雑に原子と分子を描き込まなければならないでしょう。そしてそれから、動物母体あるいは植物母体のなかでこの複雑な蛋白質分子が形成されていく、あるいは好まれる言い方によれば、これがさらに発達していって、純粋な遺伝によって新たな動物が発生すると。しかしながらこういうことはすべて、霊的な眼差しの前ではまぎれもないナンセンスです。ほんとうは、動物母体の蛋白質は複雑に組み合わされているのではなく、完全に損なわれ、カオスとなっているのです。通常身体のなかに含まれている蛋白質というものはまだいくらか秩序があるのですが、生殖のもとになる蛋白質の特徴とはまさに、内的に完全にカオス状態で入り乱れ揺り動かされているということ、物質素材が完全にカオスへと引き戻され、もはや構造がなく、内部で完全に寸断され引き裂かれ破壊されているためにもはや地球に従っていない物体の堆積にすぎないということなのです。蛋白質は、なんとかまだ内的にまとまっている限りは地球の中心的な諸力に従っています。蛋白質が内的に分裂させられる瞬間、蛋白質は全宇宙領域の影響の下に移ります。力はいたるところから入り込んできます。そして生殖の元になる小さな蛋白質の塊が生じるのです。私たちにもまず最初に見渡すことのできる全宇宙万有の写しとして。どの蛋白質の塊もひとつひとつが全宇宙万有の写しです。なぜなら、蛋白質の実質は分裂させられ、破壊され、カオスへと導かれ、それによってまさに宇宙の塵として、全宇宙に従うのにふさわしくされるからです。こういうことについて、今日何も知られておりません。今日こう信じられています。さてここに親の鶏がいる。それはまさに複雑な蛋白質を持っている。蛋白質は卵のなかにもたらされる。それから新しい鶏が生まれる。それは継続され、さらに発達させられた蛋白質である。それからまた胚実質となり、こうして鶏から鶏へと続いていく。けれどもそうではないのです。ある世代から次の世代へと移行が起こるたびごとに、蛋白質は全宇宙にさらされるのです。したがって私たちはこう言わなければなりません、私たちは、一方において、地上的な中心的諸力に従う地上的な物質を持つけれども、私たちはある意味ではその物質を、宇宙万有の境界からいたるところから働きかけてくる力に従うものと考えることもできると。この後者の力は、人間のエーテル体のなかで働いている力です、エーテル体は宇宙の力に従うのです。よろしいですか、今、私たちは物質体とエーテル体についてのリアルな表象を持ちます。今、皆さんが、皆さんの物質体とは何かと問いかけるなら、物質体とは、地球の中心点からやってくる諸力に従うものです。皆さんのエーテル体とは何かと問うなら、それは皆さんにおいて、周辺のいたるところからやってくる諸力に従うものです。これも描いてみることができます。ひとつ考えてみてください。ここに人間がいるとします。人間の物質体は、これが地球の中心点へと向かうなら(赤)、地球の中心点へと向かう諸力に従うものです。人間のエーテル体は、宇宙万有の果てのいたるところから入り込んでくる諸力に従います(緑)。こうして今、人間のなかにひとつの力組織があると考えられます、垂直に位置しているあらゆる器官のなかにもともと存在していて、下降していく力と、外からやってきて、本来このような方向性を持つ(矢印)力から成る力組織です。皆さんはこのことを、一方の性質ともう一方の性質を代表している人間の形(フォルム)から形として見て取ることができます。脚を研究するなら、皆さんはこうおっしゃるでしょう、脚は周辺の力よりも地球の力に適合しているので、当然その理由からあのフォルムを有していると。頭は地球の力よりも周辺の力に適合しています。同様に皆さんは腕を研究することもできます。これはとりわけ興味深いことです。皆さんが腕を体に押しつけると、腕は、地球の中心点に向かう諸力に従います。皆さんが腕を活発に動かすと、皆さん自身が腕を、周辺のいたるところから入り込んでくる諸力に従わせるのです。よろしいですか、これが脚と腕の違いです。脚は一義的に地球の中心的な力に従い、腕は特定の姿勢でのある条件においてのみ、地球の中心的な力に従うのです。人間は地球の中心的な力から腕を引き上げて、周辺のいたるところからやってくる私たちがエーテル的と名づける力のなかに組み込むことができます。けれども、ひとつひとつの臓器についてもこのように、これらの臓器がどのように宇宙に組み込まれているかを実際いたるところで見ることができるのです。さて、皆さんは物質体、エーテル体を有しています。けれどもアストラル体とは何なのでしょう。空間のなかにはもはや、第三の種類の力はありません。そういうものはもはや存在しないのです。アストラル体はその力を空間の外に持っています。エーテル体の力は周辺のいたるところから入り込んできますが、アストラル体はその力を空間の外部から受け取るのです。地球の物質的な力が、あらゆる方向からやってくるエーテル的な力に組み込まれているようすを、自然の特定の場所に捜し出すことができます。ひとつ考えてみてください、蛋白質、これはまず物質的な地球に存在します。蛋白質のなかで、硫黄、炭素、酸素、窒素、水素が化学的にどうにか安定している限り、蛋白質はまさに物質的な地球の力に従います。蛋白質が生殖の領域に入ると、蛋白質は物質的な力から引き上げられるのです。周囲の宇宙万有の力が分裂した蛋白質に働きかけ始め、全宇宙万有の写しとして新たな蛋白質が生じます。けれども、よろしいですか。こういうことが起こることもあります。つまり分裂がじゅうぶんに進行することができないといった事態です。たとえば、何らかの動物に生殖が起こるためには、全宇宙万有の力に組み込まれることができるよう、産みつけられた卵のなかで分裂させられなければならない蛋白質もあるでしょう。こういう動物は、もっぱら全マクロコスモスのなかに組み込まれなければならないこのような蛋白質を生殖のために提供することを何らかのかたちで妨げられているのです。生殖可能な蛋白質は全マクロコスモスに組み込まれなければなりません。この動物は生殖可能な蛋白質を問題なく形成することを妨げられているわけですが、そう、たとえばタマバチ(Gallwespe)がそうですね。それではタマバチは何をするでしょう。タマバチは何らかの植物の一部に卵を産みつけるのです。タマバチが卵を産みつけた柏その他の木々にはいたるところでこれらの虫こぶ(没食子/Galle)が見つかるでしょう。するとこうした奇妙な虫こぶがたとえば葉についているのを皆さんはごらんになるでしょう、虫こぶのなかにはタマバチの卵があります。なぜこういうことが起こるのでしょう?なぜタマバチの卵は、たとえば柏の葉に産みつけられ、今発育しようとする卵が内部に入ったこのような虫こぶができたのでしょう。卵は自分だけでは発育することができないでしょう。なぜなら植物の葉は自らのうちにエーテル体を有しています。このエーテル体は全宇宙エーテルに適合していて、そしてこれがタマバチの卵の助けになるのです。タマバチの卵は自分だけではどうすることもできません。ですからタマバチは、すでにエーテル体を内部に持ち、全宇宙エーテルに組み込まれている植物の一部分に卵を産みつけるのです。つまりタマバチは、自分の蛋白質に分裂を起こすために、回りの宇宙周辺が柏の葉を、柏を通じて働きかけることができるように、柏の木に近づくのです、一方、タマバチの卵だけでは崩壊してしまわざるをえません、タマバチの卵はあまりに固く結合していて分裂できないからです。よろしいですか。このことは、自然のなかでいかに不思議な活動が営まれているかをのぞき見る可能性さえ与えます。けれどもこの活動は通常も自然のなかにあるものです。と申しますのも、想像してみてください、この動物は単に、生殖のために宇宙エーテルにさらされうる胚実質を提供することができないのみならず、自分自身のなかで任意の物質を食物に変え、内的な栄養に用いることもできないと。ミツバチの例(☆1)がすぐ思い浮かびますね。ミツバチは何でも食べるということはできません。ミツバチが食べることができるのは、植物によってすでに配分されたものだけです。けれどもさて今皆さんは非常に不思議なものをごらんになるでしょう。ミツバチは植物に近づき、蜜液をさがしてそれを摂取し、体内で加工し、ミツバチについて私たちが驚かざるを得ないものを作り上げます、まるごとの蜂の巣を、巣箱のなかの巣房を作り上げるのです。私たちはこれらふたつのまったく不思議な驚くべき経過を眺めます、外で花にとまっているミツバチが花の蜜を吸い、それから、巣箱に入り込んでいって、ほかのミツバチとともに、蜂蜜で満たすための蜜房を自分自身から作り上げるのです。いったいここで何が起こっているのでしょう。よろしいですか、皆さんはこれらの蜜房をその形(フォルム)に従って見なければいけません。それらはこのように形成されています(図参照、右)、ここにひとつ、続いてふたつめと続きます。これらは小さな房で、その空洞はもちろん物質で満たされるように形作られるのですが、水晶、つまり珪酸の結晶の形成のとはいくぶん違って形成されています。皆さんが山に出かけて、水晶をごらんになれば、皆さんはそれもこのように描くことができるでしょう。水晶はいくぶん不規則なところはありますが、連続した巣房に似た図になるでしょう。ただ、巣房は蜜ろうから、水晶は珪酸から出来ています。これを追求していくと、こういうことがわかります、普遍的なエーテル的、アストラル的なものの影響下で、地球進化の特定の時期に、珪酸の助けを借りて、山のなかに水晶が形成されたと。皆さんはここに、地球の周囲からやってくる諸力、エーテル的ーアストラル的力として作用し珪酸のなかに水晶を形成する力を見るのです。皆さんは外の山地のいたるところにそれを見出します。まさに驚くべき水晶、この六角形の形成物を。この水晶であるもの、これは、空洞となれば巣箱のなかの巣房です。つまりミツバチは、かつて六角形の水晶を作り出すべく存在していたものを花から取り出します。ミツバチはこれを花から取り出し、自分自身の体を通して水晶の複製を作り出すわけです。このとき、ミツバチと花の間では、かつて外部のマクロコスモスで起こったことに似た何かが起こっているのです。私がこういうことをお話ししますのは、炭素、窒素、水素、酸素云々のなかに存在しているこのまったく嘆かわしい抽象を眺めるだけでなく、驚くべき形成(ゲシュタルトゥング/Gestaltung)プロセスを、自然と自然の経過における内的で親密な関連を見ていくことがどんなに不可欠か、皆さんにおわかりいただくためです。そしてこういうことが実際かつては本能的に科学の基礎となっていました。それは十五世紀頃から人類の歴史的進化にともなって失われてしまいました。それは再び獲得されなければなりません。私たちは再び、自然の存在とその人間への関わりとの内密な関係のなかへと入っていかなければならないのです。このような関係が再び知られるようになるときにのみ、健康な人間と病んだ人間への真の洞察が再び存在するようになるでしょう。さもなければ、どんな薬学においても、内的な連関は洞察されることなく、単に試してみるばかりという状況は変わりません。十五世紀から今日まで人間の精神の進化において一種の不毛の時代があったのです。この不毛の時代は人類を圧迫しました。と申しますのも、植物を見ても、動物を見ても、人間を見ても、鉱物を見ても、あらゆることについてもはや何もわからなくなったこういう不毛な時代は、人間全般をあらゆる宇宙連関から引き離したからです。そしてとどのつまり、人間はあのカオスのなかに入り込んでしまいました、そのカオスのなかで人間は今日、もはや宇宙との何らかの関連のなかで自らを知るということのない世界に対峙して生きているのです。このような事柄がよく考えられていた時代には、生殖が起こるたびごとにマクロコスモス全体が語りかけていることを、人間はよく知っていました。生殖可能な胚あるいは種子のなかで、全マクロコスモスの写しが生じます。大宇宙は外にありますが、きわめて小さな胚のなかには、大宇宙のいたるところからやってくる作用の結果があるのです。さて人間のなかでは最初、地球の物質的ー中心的な力が共に作用しています、それらは人間のすべての器官(臓器)のなかで作用していますが、これらの力に対して、あらゆるところからやってくるエーテル的な力が随所で作用しています。なんらかの方法で肝臓を、脾臓を、肺をごらんになってください、そこでは地球の中心点からやってくる力と周囲の宇宙のいたるところからやってくるあの力が共に作用している、ということを知るときにのみ、皆さんはまずこれらの臓器を理解なさるでしょう。ーーさらに、ある種の臓器はアストラル体に、また自我組織(Ich-Organisation)に浸透されています。けれども、ほかの臓器は、これら高次の構成部分にはあまり浸透されていませんし、そもそも人間は睡眠状態では自分のなかにアストラル体と自我組織は持っていないのです。ひとつ何らかの臓器を、肺を(最初の図参照、右上)、考えてみてください。何らかの原因で、宇宙万有のいたるところからやってくる力(矢印)が、人間の肺にあまりに強く働きかける状態になったとします。肺は病気になってしまうでしょう、なぜなら、肺のなかで地球の中心点から作用するものと、周囲のあらゆる方向からやってくるものとの間には、一種の調和的な均衡状態が生じていなければならないからです。今、皆さんが、肺のなかであまりに強く働きかけているエーテル力の釣り合いをとる鉱物(ミネラル)実質をどのようにして見つけ出せるか首尾良く知ることができるなら、皆さんは、強く作用しすぎているエーテル的諸力を除去する治療薬を得るでしょう。そして逆のことが起こる可能性もあります、つまりエーテル的諸力があまりにも弱くなって、地球の中心点から作用する物質的な諸力が強くなりすぎるといったような。皆さんは、何らかの臓器を通じてエーテル的諸力を強めるように人間に作用することのできるものを、周囲の植物界のなかに求めるでしょう。そうすれば、皆さんはふさわしい治療薬を得るでしょう。単に物質体を観察するだけでは、最少の治療薬をどうにか見つけ出すことも不可能です、物質的な人体そのものには、人体の成り立ちについて何かを語る根拠はまったくないからです。と申しますのも、人体のなかで起こっているいわゆる正常なプロセスは自然のプロセスですが、病気のプロセスもまた自然のプロセスだからです。皆さんがいわゆる正常な肝臓をお持ちだとすると、皆さんは自然のプロセスのみがそこで起こっている肝臓をお持ちなのです。けれども皆さんが潰瘍を起こした肝臓をお持ちだとしても、皆さんはやはり自然のプロセスのみがそこで起こっている肝臓をお持ちなのです。物質体からはこの違いを見つけだすことはけっしてできません。物質体からは、ある場合は別の場合とは異なって見える、という事実を確認することができるだけで、原因については何も知ることはできないのです。皆さんの肝臓に潰瘍があったとすると、こういう場合たとえばアストラル体が、そうすべき程度よりずっと強力に肝臓に介入しているということを知っているときにのみ、皆さんは潰瘍の原因を発見するでしょう。皆さんは、肝臓の潰瘍形成の場合肝臓に強く介入しているアストラル体を、肝臓から追い出さなければなりません。そして、物質体から出て、人間本性の高次の構成部分にまで入っていかないことには、健康な人間と病気の人間についてリアルに語る可能性などそもそもないのです。ですから結局こう言うことができます、そもそも薬学というものは、人間の物質体から出ていくときにはじめてまた可能だろう、病気の本質は、物質的な人体からは理解することができないからだと。今回私は、事柄を歴史的関連で叙述することだけを意図しております。けれどもまさしく、古の時代から近代へともたらされてきたものがどんどん光を失っていったとき、人間認識一般もことごとく消え去ってしまったということなのです。今日私たちは、再び人間認識を獲得しなければならないという急務の前に立っております。この人間認識は、人間と周囲にある自然界の関係を再び把握することができるときにのみ獲得されるでしょう。ひとつ人間の自我組織から出発してみましょう。まず、そうですね、秘儀参入学由来のイマジネーション認識を通して人間の自我組織についての観照を得ると、自らにこう問いかけることができます、今日の人間の生体組織のなかではいったいこの自我組織はとくに何と関係しているのだろうと。この自我組織は、人間のなかで鉱物的であるものととくに関係しています。ですから皆さんが鉱物質(無機質)のもの、本質上鉱物質のものを摂取すると、たとえば塩を舌の上にのせると、たちまちこの鉱物質のものに襲いかかるのは自我組織なのです。次いで鉱物質のものはさらに送られ、胃のなかに移ります。自我組織は、塩実質が胃のなかにあるときにも、そこに居残っています、自我組織はそこに居残っているのです。塩はさらに進み、むろんいろいろな変化を遂げますが、腸を通過し、さらに進みます、けれども皆さんの塩は、決して自我組織に見捨てられることはありません。これらは、つまり自我組織と人間のなかに入ってきた塩は、対になったもののようにふるまうのです。よろしいですか、皆さんがたとえば、蛋白質という物質とまだいくらか結合している目玉焼きを食されるときには、そうではありません。皆さんが目玉焼きの蛋白質を舌の上に運ぶときには、自我組織は少し気にかけるだけです。さらにそれが胃のなかへと入り込んでいく間も、アストラル体はそれをほとんど気にかけません。さらに進むと、エーテル体が集中的に働きかけ、次いで物質体がそうします。皆さんが目玉焼きとともに皆さんの生体組織のなかに取り入れた蛋白質を、これらが皆さん自身のなかで分解するのです。そして今、目玉焼きは皆さん自身のなかで完全に鉱物的にされます。それは分解されます。腸壁においてこれら外的に取り入れられた蛋白質は、どうにかまだ蛋白質であることもやめ、完全に鉱物化されるのです。こうして今それはまた自我組織のなかに移行していき、そして鉱物化された蛋白質は、そこから自我組織に摂取されるのです。こうして私たちはいつもこう言うことができます、自我組織は鉱物質のものだけと関わり合うと。けれども鉱物質のものはどれも、人間の生体組織のなかで自我組織によって、外部にあるときとは異なったものになっています。人間の生体組織のなかでは何ものも、それがこの人間の生体組織の外部にあるときのままであることは許されないのです。自我組織は非常にラディカルにそのことを気にかけなければなりません。単に、そうですね、食塩やそういった物質が、自我組織に捉えられて、外部にあったときとはまったく別の何かに内的に変えられるというだけではなく、人間がある特定の熱状態に囲まれているとき、外的な熱状態が人間に何らかのしかたで浸透しているときですら、それは{外的な熱がそのままであることは}許されないのです。皆さんの指が、外的な熱として広がっているものによって満たされることは許されないのです。熱は皆さんに刺激として作用することが許されるだけで、皆さんは内部に持つ熱を自分で生み出さなければなりません。皆さんが単なる対象となり、皆さんの暖かさあるいは冷たさを自分では生み出さず、皆さんのなかのどこかで熱を、たとえば何らかの対象の場合のように作用させ続けるだけであるなら、その瞬間に、皆さんは病気になります。外的な熱そのものによって、単なる物質によってではなく、外的な熱によって病気になるのです。ちょっと考えてみてください。ここに布かスポンジか何かがあり、向こうにストーブがああるとしましょう。ストーブの熱はまったく静かに広がり、布あるいはスポンジに浸透するでしょう。布あるいはスポンジは、そこにストーブの熱として広がっているものを単に継続するだけです。ストーブの熱が皮膚まで到達すると、そうすることは許されません。ストーブの熱が感覚の刺激を引き起こすと、反応が返ってこなければなりません、つまり内部の熱が内から生み出されざるを得ないのです。風邪の状態というのはまさに、内部の自分の熱を生み出すべく刺激を与えさせるだけにとどまらず、外部の熱をいくらか皮膚の下に入れてしまって、その結果、自らの作用、自らの衝動そのものに満たされた完全に活動的な人間として自身を世界のなかに据えるのではなく、ひとつの対象のように自分を置き、自分を通じて外界の作用に浸透されるままになっていることに起因するのです。自らのうちに鉱物質のものを取り入れ、けれどもこれを内的に徹底的に変え、何か別のものに変化させること、これが自我組織の本質です。私たちが死んではじめて、鉱物質のものは再び外的自然の鉱物質のものとなります。私たちが地上に生きて、鉱物質のものを私たちの皮膚の内部に有している間は、自我組織が絶えず鉱物質のものを変化させています、私たちが摂取する植物質のものは、アストラル組織によって、アストラル体によって、絶えず変化させられているのです。したがって私たちはこう言うことができます、人間の自我組織は、鉱物質(無機質)のものすべて、単に固体状のもののみならず、液体状のものも、気体状のものも、熱状のものも、徹底的に変容させるのだと。おおざっぱな言い方をすれば、むろん、このあたりに水がある、私は飲む、水は今私の内部にあると言うことはできます。けれども私の生体組織が水を取り入れる瞬間、私の内部にあるものは、私の自我組織を通じて、もはや外部の水であるものと同じではなくなります。私がそれを汗として染み出させたりあるいはほかの方法で水に戻すとはじめて、それはもとに戻るのです。私の皮膚の内部では、水は水ではなく、生きた液体性である何かです。このようにして常に、限りなく多くのことが考え直されなければなりません。今日は皆さんにほんの小さな示唆を与えることができただけです。けれども皆さんがこのことを考えぬき、蛋白質は全マクロコスモスの作用のなかに入るために分解させられねばならないことがおわかりになるなら、私が飲む水は内的に生きた液体であり、もはや無機的な水ではなく、自我組織に浸透された水であることがおわかりになるなら、また、皆さんがキャベツを食べるとき、外にはキャベツがある、アストラル体がすぐさま内的にキャベツを、少なくとも現実の、物質的なキャベツを取り入れ、それを何かまったく別のものに変化させるとじっくりお考えになるなら、ここで私たちは、とほうもなく重要な経過の観察に至り、次のような観照へと押し進みます、つまり、私たちは私たちの新陳代謝のなかに、私たちのたとえば脳のなかにあってそこで神経系その他を作り出している代謝プロセスと、進化のある種の段階だけ異なっている経過を有しているのだ、という観照へ。これについては明日もさらにお話しするつもりです、紀元後十二世紀と二十世紀の人類のまったくラディカルな違いを際だたせるために、そして、そこからさらに、人間認識がすべて消え去ってしまい、健康な人間についても病気の人間についてももはや何もわからなくなってしまわないためには、さらなる進展になかで健康な人間と病気の人間のために、新たな衝動がやってくることがどうしても必要であることをご理解いただくためです。 (第7講・了)参考画:自我組織(ego organization)□編註☆1 ミツバチの例:1923年12月1日ドルナハでの講義を参照のこと。『人間と宇宙自然における霊の作用ーーミツバチの本質について』(ゲーテアヌム建築に携わる労働者たちのための15回の講義、第5巻 GA351)所収□記;シュタイナーの「自我組織」は、人間の意識と肉体の関係に焦点を当てています。以下に要約します。自我の付与には肉体が必要:人間は肉体を持つことで「自己同一性」と「自己独立性」の意識を形成します。低次自我と高次自我:現在の自我は低次のもので、「私は私である」という自己同一性と「私と他者は別の存在である」という自己独立性を持っています。真の自我性への成長:真の自我性は「自己独立性」と「自他同一性」を統合した意識であり、肉体を通じて形成されます。必要悪としての自我の下降:肉体による自我は利己主義や物質的欲望を生み出し、唯物論的思考を促進します。シュタイナーは、真の自我性を意識的に育てる時代が到来していると考えています。人気ブログランキングへ
2024年05月16日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 (GA233)翻訳紹介:yucca第6講 1923/12/29 ドルナハ ゴルゴタの秘蹟前の三世紀から四世紀までと、ゴルゴタの秘蹟後の三世紀から四世紀まで、この間六百年から八百年にわたりますが、この時代は、東洋との関連という点で西洋の歴史を理解するためにとくに重要です。私がここ数日お話ししてきました出来事、これはアリストテレス主義(アリストテリスムス)の登場とマケドニアからアジアへのアレクサンダーの遠征において頂点に達しましたが、この出来事の本質とは、これらの出来事が、まだ秘儀の本質への衝動のなかにまったく浸りきっていたオリエントの文明にとって、ある種完了させるものとなるということです。このまぎれもなく純粋なオリエントの秘儀衝動のいわば終焉は、あの冒涜的なエフェソスの火災でした。そこにはいわばヨーロッパにとって、ギリシアにとって、神に浸透された古(いにしえ)の文明が秘儀の伝統のかたちで、いわば影像のかたちで残されていたものがあったのです。そしてゴルゴタの秘蹟後の四世紀、私たちは別の出来事を通して、いわば秘儀本質の廃墟のうちになおも残存していたものを見ることができます。私たちはこれを背教者ユリアヌス(ユリアヌス・アポスタータ/Julianus Apostata)(☆1)に見ることができるのです。ローマ皇帝最後の「異教徒皇帝」背教者ユリアヌスは、四世紀に、エレウシス秘儀の導師の最後のひとりによって、まさにひとが参入させられることのできたものに参入させられました。つまり、背教者ユリアヌスは、オリエントの古代の神々の秘密であったもののうち、紀元後四世紀にエレウシスでまだ体験することができた分だけを体験したわけです。こうして私たちは、ある時点に、ある時代の出発点に、エフェソスの火災を置きます。エフェソスの火災の日はアレクサンダー大王の誕生日にあたります。この時代の終わり、つまり363 年には、命日があります、かなたのアジアでの背教者ユリアヌスの非業の死があります。こう言ってよいかもしれません。この時代の真ん中にゴルゴタの秘蹟があると。ここで、私がたった今区切りましたこの時代は、人類の全進化史のなかでそもそもどう見えるかということをもう一度見ておきましょう。私たちはまさに今、奇妙な事実を前にしているのです、人類の進化をこの時代の向こうまで遡って見通したいと思うなら、私たちはその観るということにおいて、何か別のものに似たことをしなければならないという事実をです。ただ、私たちは通常このふたつのことを関連づけることはありませんが。思い出してください、私は『神智学』(☆2)において、私たちが考慮すべき諸世界を示す必要がありました、つまり、物質界、それに境を接する中継的世界つまり魂界、そして人間の最高の部分だけが入っていくことのできる世界としての霊界(ガイスターラント、霊の国[Geisterland])です。そして、この霊界、つまり現在人間が死と新たな誕生との間に経験するこの霊界の独自の特性を度外視し、このように霊界の普遍的な特性に目を向けるなら、こういうことになります、つまり、この霊界を理解するためには私たちが私たちの魂状態を方向づけしなおさなければならないのと同じように、この時点の向こう側にあるものを理解するためには、私たちの魂状態を方向づけしなおさなければならないのです。今日の世界に適用できる概念と表象をもって、エフェソスの火災の背後にあるものを理解できるなどと思ってはなりません。ここでは別の概念と表象を育成しなければならないのです、人間が呼吸プロセスにおいて外部の空気と関わり合っているのと同様に、自分たちは魂を通じて絶えず神々と関わり合っているのだとまだ知っていた人たちを見晴るかすことをも許すような概念と表象を。すると今や私たちは、いわば地上のデヴァカン(Devachan)、地上にある霊界(霊の国)であるこの世界を見ます、物質的世界はこの世界には何の役にも立たないからです。次いで、キリストより前の356年からキリストから後の363年までのあの中間の期間(Zwischenzeit)が来ます。さてそれではこの中間の期間の向こうには何があるのでしょう。その向こうにはアジアの方向へも、ヨーロッパに向かっても、まさに概念において現代の人類がそこから発してきた世界があります、ちょうど古代人類がオリエント世界からギリシア世界を経てローマ帝国へと入って行ったように(図参照)。と申しますのも、中世の数世紀を通じて現代に至るまで文明として発達してきたもの、これは、秘儀の本質の本来の内容を度外視すれば、人間がその概念と表象をもって育成しうるものを基礎として形成され、展開されてきた文明だからです。ギリシアではすでに「歴史の父」とも呼ばれるヘロドトス以来、それが準備されてきました、ヘロドトスは歴史の事実を外的なしかたで記述し、霊的なものにはもはや近づかないか、せいぜいのところきわめて不十分に近づいただけでした。この文明はますますいっそう形作られていきます。けれどもギリシアには、霊的な生活を思い出させたというあの影像の息吹のいくばくかがあいかわらず残っているのです。それに対してローマにおいては、現代の人類に親和性のあるあの時代が始まります、ギリシアの魂状態であったものとさえまったく違うしかたで、ある魂状態を得るあの時代が。背教者ユリアヌスのような人物のみが、古(いにしえ)の世界への抑えがたい憧れのように何かを感じ取り、そして彼はある種の敬虔さをもってエレウシスの秘儀へと参入することを受け入れます。けれども彼がそこで得るものには、もはや何の認識力もありません。何はさておき、彼は、オリエントの秘儀の本質の伝統としてあったものをもはや魂の内部をもってしては完全に理解することはできない世界の出身なのです。もしアジアの後にギリシア・ローマが続かなかったとしたら、今日の人類は決して発生しなかったでしょう。今日の人類というのは、個人性(パーソナリティ/Persoenlichkeit)に、ひとりひとり別個の(individuell)個人性に基づくあの人類です。オリエントの個人性、オリエントの人類は、ひとりひとり別個の個人性に基づくものではありませんでした。ひとりひとりは、自らを、絶えざる神的なプロセスの一分岐と感じていたのです。神々は地球進化に対して意図を有し、神々はあれこれと意志しました、それでこの地上であれこれのことが起こったのです。神々は人間の意志のなかにインスピレーションを与えつつ働きかけました。皆さんに示唆しました力強い人物たちがオリエントで行ったことはすべて、神々のインスピレーションだったのです。神々が意志し、人間が行為しました。そして古代世界にあって秘儀とはまさに、この神々の意志と人間性とを正しい軌道へと導くことに適していたのです。エフェソスにおいてはじめて事態は変化しました。皆さんに申しましたように、エフェソスでは、秘儀の入門者たちはもはや季節の経過ではなく、彼ら自身の成熟を頼りにせざるを得ませんでした。ここではじめて個人性の最初の痕跡が現れてきたのです。その前の受肉でのアリストテレスとアレクサンダー大王も、当地で個人性の衝動を受け取りました。しかし今、オリエントの秘儀の本質たる人間でありたいという最後の憧れを背教者ユリアヌスが持った時がその黎明となる時代がやってきました。今や、人間の魂において、ギリシアにおいてさえそうであったものとはまったく別の状態になる時代が到来するのです。エフェソスの秘儀においてたとえば行を達成したというような人間を思い浮かべてみてください。エフェソスの秘儀によってではなく、その人があの時代に生きたということによって、その人の魂においてはこういう状態だったのです。よろしいですか、今日、普通言われるようにある人が思い出すということをするとき、彼は何を思い出すことができるでしょう。彼は誕生以来個人的に体験した何らかのことを思い出すことができます。ある年齢のひとがいます、彼は二十年前、三十年前に体験したことを思い出します。内的な記憶想起は個人的な人生を越えていくことはありません。たとえばまだエフェソスの文明に加わっていた人々の場合にはそうではありませんでした。エフェソスにおいて達成されるべきあの行のほんの痕跡を得ただけで、彼らは思い出し、今日個人的な人生の記憶が浮かび上がってくるように、地上以前の生存や出来事が彼らの魂のなかに浮かび上がってきました、自然の個々の領域における地球進化に先立つ月進化、太陽進化、といった出来事が。このとき人は自らの内をのぞき込むことができたのです、そして宇宙的なものを、人間と宇宙的なものとの結びつきを、いわば人間の宇宙的なものへの依存を見たのです。人間の魂のなかに生きていたものは、自己記憶(自己想起/Selbsterinnerung)でした。つまり私たちはこう言うことができます、私たちはここにひとつの時代を持つ、エフェソスで宇宙の秘密を体験することのできたあの時代だと。当時は、人間の魂が宇宙における太古を思い起こすということがありました。この想起(記憶)より前には、太古の時代の内部に実際に生きるということがありました。そのなかで、単に太古の時代をのぞき込むということだけが残ったのです。ギルガメッシュ叙事詩が語っている時代においては、私たちは、宇宙における太古についての人間の魂の記憶と言うことはできません。そこでは、現在における太古の体験、と言わなければならないのです。今や、アレクサンダーから背教者ユリアヌスに至るあの時代がやってきます。さしあたってはこの時代を飛ばしましょう。次いで私たちは、中世と近代の西欧文明がそこから育ってきた時代に至ります。そこにはもはや、宇宙における太古についての人間魂の記憶も、現在における太古の体験もなく、残されているのは伝統だけでした。 第一に:現在における太古の体験 第二に:宇宙における太古についての人間の魂の記憶 第三に:伝統 ひとは起こったことを記録することができました。歴史が生じたのです。この歴史というものはローマ時代に始まります。この圧倒的な違いを考えてみてください。以前のエフェソスの入門者たちが加わった時代のことをよく考えてください。彼らには歴史の書物は必要ありませんでした。起こったことを書き留めるなどということは、彼らにとってはこっけいに思われたことでしょう。と申しますのも、じっくりと、じゅうぶんに深く考えざるを得なかったからです。そうすれば、意識の底から、起こったことが浮かび上がってきたのです。そして、これを心理分析として描写する現代の医者などはおらず、生き生きとした記憶からかつて存在したものをこのように取り出してくるのは、まさしく人間の魂の歓喜だったのです。それから、人類がこのようなことを忘れてしまい、起こったことをかろうじて記録せざるを得なくなった時代になりました。けれども、以前人間の魂のなかで宇宙的な記憶力であったものを人類が退化させて行かざるを得なかった期間に、つまり、世界の出来事を記録する、歴史を書く云々ということを人類が不器用に始めざるを得なかった期間、この期間に、人間の内部では、個人的記憶力(das persoenliche Gedaechtniss)、個人的記憶(想起)というものが発達したのです。どの時代にもそれぞれ独自の使命が、独自の課題があります。ここで皆さんは、私が最初の講義で、時間記憶が登場した、と説明いたしましたことの別の面をごらんになるわけです。この時間記憶の最初の揺籃の地はギリシアでしたが、その後他ならぬローマ・ロマン文化を経て、近代にまで至る中世へと発展してきました。そしてすでにもう背教者ユリアヌスの時代に、この個人文化へのきっかけが芽生えたのですが、このことを証明しているのが、背教者ユリアヌスはエレウシスの秘儀への参入を受け入れたけれども、それが彼にはもはや何の役にも立たなかったということです。さて今や、西洋の人間は紀元前三、四世紀から現代に至るまで、地上生活の間霊的世界のまったく外部で生きるという時代となります、単なる概念と理念、抽象のなかで人間が生きる時代です。ローマにおいては神々でさえ抽象となります。人類がもはや霊的世界との生き生きとした関係について何もわからない時代がやってくるのです。地球はもはや、諸天の一番下の領域であるアジアではなく、地球はそれ自体ひとつの世界となり、諸天は遠く、人間の観照のなかで薄れていきました。そしてこう言うことができます、ローマ文化として西洋に到来したものの影響のもとに、人間は個人性を発達させると。霊界(Geisteswelt)に、上方の霊の国(Geisterland)に接して下に魂界(Seelenwelt)があるように、ちょうどそのように、今や時代にしたがって、西洋の文明であるものつまり一種の魂界も、この霊的なオリエント世界に接しています。そしてこの魂界がそもそも直接現代の日々にまで入り込んでいることが明かです。けれども今日人類は大多数においてまだ、大きな飛躍が実際に進行中なのだ、ということに気づいておりません。私の話をしばしば聴かれた何人かの友人の皆さんは、ある時代が過渡期であるということについて私が話すことを好まないのはご存じでしょう、なぜならまさにどの時代もが過渡期であり、つまり以前のものから後のものへと移行しているからです。問題はただ、何から何への移行が起こっているのかということです。けれどもまさに私が皆さんにお話ししたことによって示唆しましたのは、この移行が、ひとが霊の国から魂界へ、そしてそこからはじめて物質界へ至る、というようなものであるということです。おお、今まで発展してきた文明のなかには、いつもある種の霊的な響き(Anklaenge)がありました。唯物主義(マテリアリスムス)のなかにすらある種の霊的な響きが漏れ出ていたのです。あらゆる分野における本来の唯物主義というのは、十九世紀半ばになってはじめて出てきたもので、まだきわめてわずかのひとにしか唯物主義の完全な意味は理解されておりません。しかし唯物主義は巨大な力をもって存在しています。そして今日の時代は、第三の世界への過渡期に当ります、前のローマ世界がオリエント世界と違っていたように、このローマ世界ともまったく違う第三の世界への過渡期です。さて、申し上げたいのですが、アレクサンダーとユリアヌスの間のある時代にいわば触れずにおきましたが、この時代の真ん中にゴルゴタの秘蹟が起こるのです。このゴルゴタの秘蹟はもはや、人々が秘儀を理解していた時代のようには受け取られませんでした、そういう時代であれば、ナザレのイエスという人間のなかに生きたキリストについて、人はまったく別の表象を得たことでしょう。ゴルゴタの秘蹟の同時代人で秘儀に参入したわずかのひとのみが、まだそういう表象を有していました。ヨーロッパの人類の大多数は、ゴルゴタの秘蹟をスピリチュアルに理解するためのどんな表象も持っていませんでした。したがって、ゴルゴタの秘蹟が地上に根付くしかたはまず、外的な伝統を通じて、外的な伝承を通じてというものでした。最初の数世紀における秘儀参入者のグループ内においてのみ、ゴルゴタの秘蹟と同時に起こったことをがスピリチュアルに理解されることができたのです。けれども、また別のこともありました、これについてはつい先日の講義で(☆3)すでに何人かの方々にはお話ししましたが。彼方のヒベルニア、アイルランドには、古アトランティスの叡智の余韻が残っていました。一昨日皆さんに概略をお話ししたヒベルニアの秘儀においては、入門者には、二つの暗示的な姿をとって、古アトランティス人たちが見ていたように鋭く世界を見る機会がありました。そしてこのヒベルニアの秘儀は、自らのうちに厳しく閉ざされた、とほうもなく厳粛な雰囲気に覆われたものでした。ヒベルニアの秘儀はゴルゴタの秘蹟の数世紀前にあり、ゴルゴタの秘蹟の当時にもありました。彼方のアジアでゴルゴタの秘蹟が起こり、その後伝統的歴史的に福音書のなかに伝えられることがイェルサレムで起こりました。けれども、人間のだれかれの口が情報をもたらしたわけでもなく、何らかのそれ以外の結びつきがあったわけでもないのに、ゴルゴタの秘蹟が悲劇的に成就した瞬間、ヒベルニアの秘儀においては、パレスティナにおいて真のゴルゴタの秘蹟が起こったということが霊視的に知られたのです。ヒベルニアの秘儀の地において、同時に、象徴的な光景が実現したのです。その地でひとは伝統を通して学んだのではありません、そこではゴルゴタの秘蹟がスピリチュアルな方法で知られたのです。そして偉大な壮麗な出来事がパレスティナで外的物質的事実のなかにもたらされる一方で、ヒベルニアの秘儀においては、そのアストラル光のなかにゴルゴタの秘蹟の生き生きとした光景を生じさせるあの祭式がとりおこなわれていたのです。ものごとがいかに連鎖しているか、おわかりですね、神々との古(いにしえ)の関わりが消えるとともに、一種の世界の谷間とも申し上げたいものが事実生じるのです。東洋では、エフェソスの火災の後、神々についてのこの古い観照は堕落していきます。ヒベルニアにおいてはこの観照は存在し続けますが、これもやはり消えていきます。と言っても、それは紀元後になってからですが。そして、ゴルゴタの秘蹟から放射するものすべてが、伝統を通じて、口承によって、展開されます。西洋で発達するのは全般に、口承のみに頼るか、あるいは後になっては外的な自然研究、純粋に感覚的な自然研究を頼りとする世界なのです、つまり、自然の分野においては単なる伝承に、歴史の分野においては文字に記録されたかあるいは口伝えによる伝承に対応しているのです。ですから、ここに個人性の文明(die Zivilisation der Persoenlichkeit)がある、と言うことができるのです。心霊的なもの(スピリチュアリスティッシュなもの/das Spiritualistische)、ゴルゴタの秘蹟は、歴史的に伝承されはしますが、もはや観られることはありません(次の図を参照)、ただ生き生きと思い描いてほしいのです、背教者ユリアヌスの時代以後、スピリチュアルなものを排除した文明がいかに広がっていくか、思い描いてほしいのです。十九世紀末になってはじめて、七十年代の終わりから、いわば霊的な高みからの新たな呼びかけが人類に近づいてきました。私がしばしばミカエルの時代として特徴づけましたあの時代が始まったのです。今日はこのことを、こういう観点から特徴づけたいと思います、つまり私が言うのは、人間が古い唯物主義(マテリアリスムス)にとどまりたいと思うなら人類の大部分は最初これにとどまりたいと思うでしょう。人間は恐ろしい奈落へと入り込んでいくだろうということです。人間は、古い唯物主義にとどまりたいと思うなら、必ず人間以下のもの(das Untermenschliche)に陥り、人間的な高みにとどまることはできないのです。人間的な高みにとどまるためには、人間は感覚を開かなくてはなりません。これから先得られるべきスピリチュアルな啓示に向かって人間が感覚を開くことは、十九世紀末以降、どうしても必要なことなのです。ある種の霊的な力存在たち(geistige Maechte)が活動していて、それらはヘロストラトスという人物のなかに、いわば外的な顕現のみを見出していました。ヘロストラトスとはいわば、ある種の霊的な力存在たちがアジアから突き出した最後の剣だったのです。そしてヘロストラトスがエフェソス神殿に松明を投げ込んだとき、いわば彼を単なる剣か松明の延長としてかざしながら彼の背後にいたのは、魔的な存在たち(daemonische Wesenheiten)でした、要するにこのヨーロッパ文明にスピリチュアルなものをもたらすまいともくろんでいた存在たちです。よろしいですか、これに抵抗するのがアリストテレスとアレクサンダー大王なのです。そもそもいったい何が起こったのでしょう。アレクサンダーの遠征によってアジアへともたらされたものは、アリストテレスの自然智であったものでした、そしていたるところに、根本的な自然智が広まりました。アレクサンダーは、アレクサンドリアだけでなく、エジプトだけでなく、かなたのアジアにもいたるところにアカデミアを設立していましたが、そこに彼は古代の叡智を定着させ、その結果この叡智はそこにあって長い間保存されたのです。ギリシアの賢人たちはいつでもそこに行くことができ、そこに自分たちの安住の地を見出しました。自然智はアレクサンダーによってアジアへともたらされたのです。ヨーロッパは正直のところ、最初この深い自然智に耐えられませんでした。単に外的な知、外的な文化、外的な文明のみを欲していたのです。そのため弟子のテオフラストスは、アリストテレス主義のなかにあったもののうち、西洋にゆだねることができたもののみを取ったのです。けれどもこのなかにはなおも途方もなく多くのものが潜んでいます。西洋は、アリストテレスの論理学的傾向の強い著作を得ました。けれどもまさにこれがアリストテレスの独特なところなのですが、アリストテレスが抽象的で論理的であるところですら、アリストテレスは他の著作者とは別様に読めるのです。内的な、スピリチュアルな、瞑想に基づいた経験とともに、ひとつプラトンを読むのとアリストテレスを読むのとの違いを見出そうと試みてほしいものです。真正の霊的な感覚を備えた現代人が一定の瞑想に基づいてプラトンを読むと、その人はしばらくして、自分の頭が物質的な頭より少し上にあるかのように、物質的な体組織から少し抜け出したようにこ感じます。単に大ざっぱにプラトンを読むのでない人の場合、必ずそうなのです。アリストテレスの場合はそれは別のものです。アリストテレスの場合、アリストテレスを読むことによって体の外に出るなどという感覚は決して得られません。けれども、一定の瞑想的な準備という基礎を整えてアリストテレスを読むと、まさに物質的な人間のなかで活動している、という感情が得られるでしょう。まさにアリストテレスによって、物質的人間が前に出てきます。これが活動するのです。それは単に観察される論理学ではなく、内的に活動する論理学です。アリストテレスはそれでもなお、後からやってきてアリストテレスから論理学を形成した小物たちよりも一段上なのです。アリストテレスの論理学の著作は、ある関連においては、それが瞑想の本として理解されるときにのみ正しく理解されます。こうして、奇妙なことが起こります。ひとつ考えてみてください、マケドニアから西に向かって、中部ヨーロッパ、南ヨーロッパへと、西洋へと、アリストテレスの自然学の諸著作が単に移動したとしたら、それらは、災いに満ちたものになったであろうしかたで受容されたことでしょう。なるほど、人々に受け入れられるものもあったでしょう、しかしそれは災いに満ちたものとなったでしょう。と申しますのも、アリストテレスがたとえばアレクサンダーに自然学的にーー私はこれについての見本をお見せしました。伝えることのできたものは、エフェソス神殿の火災以前のエフェソス時代の秘儀の本質にまだ触れられることのできた魂をもって理解されなければならなかったからです。そういう魂は、かなたのアジアか、エジプトのアフリカにのみ見出されました。ですから、アレクサンダーの遠征を通じて、アジアへと、自然存在認識と自然存在洞察(黒板にさらに描かれる;右へのオレンジ色)が移動させられたのです、それはのちに弱められた姿で、あらゆる可能な道筋を通ってスペイン経由でヨーロッパに到来しましたが、篩(ふるい)にかけられ、弱められた状態になっていました(右から左への黄色)。けれども直接もたらされたのは、アリストテレスの論理学の諸著作でした、アリストテレスの思想的なものだったのです。そしてこれは生き続けました、中世のスコラ学のなかに生き続けたのです。そうです、今、この二つの潮流が得られたわけです。中部ヨーロッパ的洞察に基づき、細々とではあれ、いくぶん素朴な(primitiv)人々の間にさえ広汎に流布している、とでも申し上げたいものがつねにあったのです。ひとつごらんになってください、かつてアレクサンダーがアジアへともたらした種子が、あらゆる可能な道筋を通って最初アラビアその他を越えて行き、けれどもその後十字軍参加者たちによって陸路でヨーロッパへとやってきた種子が、細々と、秘密の地においてではありますが、いたるところで生きていることを。この秘密の地に、ヤーコプ・ベーメやパラケルススといった人々、その他数多くの人々が赴き、このような迂回路を通ってヨーロッパの素朴な人々の間に広く入り込んだものを受け取ったのです。ここに、通常考えられているよりはるかに多く、民衆的叡智(eine volkstuemliche Weisheit)が伝えられています。民衆的叡智が生きているのです。そしてこれは、ヴァレンティン・ヴァイゲル、パラケルスス、ヤーコプ・ベーメ(☆4)、その他ほとんど名前を知られていない人々、といったような蓄えのなかに流れ込んでいることもあります。ヨーロッパに後になってはじめて到来したアレクサンドリア学派(アレクサンドリニスムス)、つまりバシリウス・ヴァレンティヌス(☆5)その他のなかにあったあるいは現にあるものが、豊かに輝きを発するのです。修道院においては、真の錬金術的叡智が生きていました、これは単に物質のいくつかの変化について解明するようなものではなく、宇宙万有における人間の変化そのものの最も内奥の特性について解明する叡智でした。定評ある学者たちが扱っているのは、むろん歪曲され、ふるいにかけられ、論理化されたアリストテレスです、けれどもこのアリストテレス、スコラ学及び後には科学が哲学として扱ったこのアリストテレスは、それでもやはり西洋にとって恵みとなるのです。と申しますのも、十九世紀になってはじめて、アリストテレスについて何も理解されなくなり、あたかも、アリストテレスを行ずるべし、ではなくアリストテレスを読むべし、というふうに、つまりあたかもアリストテレスは瞑想の本ではないかのように、そのようにのみアリストテレスが研究されるようになったのですが、そういう十九世紀になってはじめて、人々はアリストテレスから何も得られない、という状態になったからです、なぜなら、アリストテレスは人々のなかで生き生きと作用することはなく、それは行の本ではなく研究対象であるために、単に研究されるだけだからです。十九世紀まで、アリストテレスは行の本でした。けれどもよろしいですか、十九世紀においては実際すべてにおいて、前には行であったもの、能力であったものが、抽象的な知へと変化していくという状況なのです。ギリシアにおいては、このもうひとつの線によってもこのことを特徴づけできます、人間が洞察として有しているものは、まるごとの人間(der ganze Mensch)から出て来るのだという信頼があります。教師はギムナスト(体操家/Gymnast)なのです。肉体的な動きのなかに神々が働き、その動いているまるごとの人間から、いわばそのとき到来して人間の洞察となるものが現れ出るのです。ギムナストは教師です。ローマにおいては、のちにギムナストの代わりにレートル(雄弁家/Rhetor)が現れます。これはすでに、まるごとの人間からはいくらか抽象化されたものですが、それでも少なくともまだ、生体の一部における人間の動きと関連しているものがありました。私たちが語るとき、何が動き始めるでしょうか!私たちの心臓、私たちの肺のなかで、私たちの横隔膜、そしてさらに下へ向かって、なんと語りが生きていることでしょう。それはもはや、ギムナストが行っていたものほどは強度をもってまるごとの人間のなかで生きてはいませんが、それでも人間の大部分のなかでいつも生きています。そして、考えというのは、語ることのなかに生きているものの単なるエッセンスなのです。レートルがギムナストたちに代わって現れます。ギムナストはまるごとの人間に関わります。レートルがまだ関わっているのは、いわばもう四肢を閉め出した、つまり人間の一部から頭へと洞察であるものを上昇させるもののみです。そして、第三の段階は、近代になってようやく現れます、これがドクトルです、ドクトルは頭以外のものは何も訓練せず、おもに考えのみを見るようになります。いわば十九世紀においてはまだ、いくつかの大学では弁論の教授が任命されておりましたが、語ることに何かを与えるということがもはや一般的でなくなったために、万事ただ考えるということのみが欲されたために、これらの教授たちはもはや弁論を行うことができなくなってしまったのです。レートルたちは死に絶えてしまいました。まるごとの人間のうち、きわめて小部分のみを代表するドクトルたちが教育の指導者となったのです(☆6)。そして、ほんとうのアリストテレスが生きていた頃は、実際にアリストテレスから帰結として出てくるものは、行、節制(Askesis)、黙想でした。そしてこれら二つの潮流が依然として残っていました。あまり若くはなく、十九世紀の半ばから最後の数十年までに起こったことに意識的に加わったひとは、たとえばパラケルススが地方の人々のところを遍歴したようなしかたでいくらか歩き回れば、中世の民の智慧(Volkswissen)の最後の名残が、ヤーコプ・ベーメ、パラケルススから汲み出されて、結局十九世紀の七十年代、八十年代にまで現存していたことがわかるでしょう。そして結局のところこれもまた正しいのです、つまり、とりわけ特定の結社の内部や特定の親密なグループの生活のなかで、十九世紀の最後の数十年にいたるまで、一種の実践の、内的な魂実践のアリストテリス主義が維持されていたことも。それで、こう言ってよいでしょう、一方においては、アレクサンダーによってアリストテレスからアジアへともたらされたもの、他方においては、西南アジア、アフリカを通ってスペイン経由で入ってきて、バシリウス・ヴァレンティヌスといった人々やその後の人々のなかに民衆的叡智として生き返り、ヤーコプ・ベーメ、パラケルスス、その他多数の人たちをも生み出したもの、これらの最後の末裔たちと、まだ知り合うことができたのだと。それはまた十字軍を通じて別の道筋でももどってきました。それは広く民衆のなかにあり、まだそれを見出すことができたのです。十九世紀の最後の数十年にはひとはまだこう言うことができました、ありがたいことだ、ほとんど見分けがつかず、腐敗したかたちであるとはいえ、アレクサンダーの遠征によって古代の自然智としてアジアへともたらされたものの最後の末裔たちがまだここに生きていたのだ、と。古の錬金術によって、古の認識および、自然の実質と自然の諸力との連関によって、素朴な民のなかに不思議になおも生きていたもの、それは最後の余韻でした。今日、それは死に絶えました、今日もはやそれは存在しません、もはやそれを見出すことはできず、もはやそのなかに何も認識することはできないのです。同様に、知り合うことのできた特定の少数の人々においては、アリストテレス的な霊修行がありました。今日それはもはや存在していません。当時東方へともたらされたもの(黒板に続けて描かれる;右から左への赤色)と、アリストテレスの弟子テオフラストスという回り道を通って西方へともたらされたもの(中央から左への青色)が保存されていたのです。けれども、東方へともたらされたものは、またもどってきました。そしてこう言うことができます、十九世紀の七十年代、八十年代には、皆さんに描写しましたあの出来事を最後の末裔たちのなかに受け継いでいたものに、新たな、直接的なスピリチュアルな認識をもって結びつけられることができたと。これは驚くべき関係ですと申しますのも、そこから見て取れるのは、アレクサンダーの遠征とアリストテレス主義は、古のスピリチュアルなものとつながる糸を保持するためにあった、唯物的な文化となっていこうとするもののなかに、効果を、新たなスピリチュアルな啓示がやってくるはずのときまで続く効果を与えるためにあったのだということだからです。よろしいですか、こうした観点のもとでは、実際にこのように思えますし、また、一見不毛に思えることも、人類の歴史的生成のなかで極めて意味深いことが明らかになる、ということは正しいのです。アジアとエジプトへのアレクサンダーの遠征は退潮して(verfluten)しまっただろうにと安易に言うことはできます。それは退潮してはおりません。アリストテレスは十九世紀に途絶えた、と言うこともできます。それは途絶えておりません。二つの流れは、新たなスピリチュアルな生が始まる可能性のある時まで続いてきたのです。実にさまざまな場所で皆さんにしばしばお話ししたことですが、この新たなスピリチュアルな生は、十九世紀の七十年代の終わりに最初の示唆として開始され、さらに世紀末とともにますますさかんになりました。今日私たちには、高みから私たちのもとに来ると申し上げたい完全な霊的生を開始するという課題があります。私たちがこの奇妙な関連と以前のものとのこの結びつきを意識しないなら、私たちの周囲の霊的生のなかで起こっているきわめて重要な出来事に対して実際眠り込んでいることになります。今日、きわめて重要な出来事に対してほんとうになんと眠り込んでいることが多いことでしょう。けれども人智学によって人々を目覚めさせなければなりません。今このクリスマス会議にお集まりのすべての皆さんにとっては、目覚めを引き起こしうる衝動があると思います。よろしいですか、私たちは、まさにこの日を目の当たりにしております、この会議において、この悲しい出来事の一周年を見通していくことをせねばならないでしょう、私たちは、ゲーテアヌムを焼き尽くした恐ろしい火柱が燃え上がったあの日を前にしているのです。さてこのゲーテアヌムの消失について、世間が、この火災は人智学運動の発展においてとほうもなく重い意味を持つ、と考えたがるならそうさせておけばよいのです。けれども、一方において、不可思議に、これについては明日以降もお話ししますが、オルガンのパイプやその他の金属製のものから、金属が焦げながら炎となって燃え上がり、そしてこの炎に不思議な色彩が生じたとき、このときこの物質的な炎がどのように燃え上がったかを見ていないなら、このことをやはりその完全な深さにおいて判断することはできません。記憶を昨年へと携えていかなければならないでしょう。けれどもこの記憶のなかに、物質的なものはマーヤであるという事実が生きていなければなりません、私たちは今や、心のなかに、魂のなかに霊的な火をかき立て、その炎のなかから真実を探し出さなければならないのだという事実が。物質的に燃えるゲーテアヌムのなかに、霊的に作用するゲーテアヌムを、私たちはぜひとも生み出さねばなりません。私たちにかけがえのないものとなったゲーテアヌムが恐ろしい巨大な炎に包まれて燃え上がるのを一方において見、また背景に、魔的な力存在たちに導かれてヘロストラトスが松明を投げ込んだ冒涜的なエフェソスの火災を見る、ということをしないなら、これが完全な歴史的意味において起こることができると思ってはおりません。前景にあるものと、背景にあるものを、ともに感じ取ることのなかで、私たちが一年前に失い、全力で再建しなければならないものを、私たちの心のなかにじゅうぶん深く刻み込むことのできるひとつのイメージを得ることができるかもしれません。□編註☆1 背教者ユリアヌス:フラヴィウス・クラウディウス・ユリアヌス Flavius Claudius Julianus、361年から363年までローマ皇帝、キリスト教に対する背教者[von den Christen Apostata, der Abtruerninige]と呼ばれた。1917年4月19日ベルリンでの講義(『ゴルゴタの秘蹟の認識のための礎石』GA175所収)を参照のこと。☆2 私は『神智学』において:『神智学ーー超感覚的な世界認識と人間規定への導き』(1904、GA9)「三つの世界」の章を参照のこと。☆3 つい先日の講義で:第四講の☆1参照のこと。☆4 ヤーコプ・ベーメ:Jakob Boeme, 1575-1624、テオフラストス・パラケルスス:Theophrastus Paracelsus, 1493-1541 ヴァレンティン・ヴァイゲル:Valentin Weigel, 1533-1588 シュタイナー『近代の精神生活の黎明のなかでの神秘主義と近代の世界観』(GA7)参照のこと。☆5 バシリウス・ヴァレンティヌス:Basilius Valentinus 十五世紀の錬金術師、おそらくエルフルトのベネディクト会士。 彼の名で、1600年頃、一連の錬金術的著作が出版された。1924年4月26日のシュタイナーの講義(『カルマ的関連の秘教的考察』第2巻 GA236)参照のこと。☆6 ギムナスト、レートル、ドクトル:シュタイナーはこれについてたとえば1923年8月6日の講義(『現代の精神生活と教育』GA307所収)で詳細に語っている。1924年7月24日の講義(『教育という文化世界における人間認識の教育的価値』GA310所収)も同様。 (第6講・了)参照画:燃えるゲーテアヌム(Goetheanum)人気ブログランキングへ
2024年05月15日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史(GA233)翻訳紹介:yucca第5講 1923/12/28 ドルナハ 古代の秘儀のうちでもエフェソスの秘儀はまったく特殊な位置を占めています。私は西洋の歴史において、アレクサンダーという名に結びつくあの進化因子とともに、このエフェソスの秘儀のことをも考えざるを得ませんでした。かつてのあらゆる古代文明の源は秘儀の本質であったわけですが、これがオリエント(東方)からこちらのオクツィデント(西方)、つまりまずギリシアへと経てきた急激な変化のなかに入っていくときにのみ、新旧の歴史の意味を理解できます。そしてこの急激な変化とは以下のようなものです。よろしいですか、東洋のかつての秘儀をのぞき込んでみますと、秘儀の祭司たちは、彼らの観たものから偉大な意味深い真実を弟子たちに啓示することができたのだという印象をいたるところで受けます。そうですね、時代を遡れば遡るほど、これらの祭司賢者たちは、神々そのものを、惑星界あるいは地上の現象を導く霊的諸存在を、秘儀において直接現前させることができました、神々は実際にそこに現われたのです。人間とマクロコスモスとの関連、それは実際さまざまな秘儀において明かされました、ヒベルニアの秘儀やアリストテレスがまだアレクサンダーに語ることができたものについて昨日皆さんにお話ししましたが、あのように壮大なしかたで明かされたのです。けれどもどの古オリエントの秘儀においても、とりわけ、道徳的なもの、道徳的な衝動が、自然の衝動と厳密に分かれていなかったということが言えます。アリストテレスがアレクサンダーに水のエレメントの霊たちが支配していた北西を指し示すことで北西からやってきたものは、今日のように風やその他純粋に物質的なものがやってくるといった単に物質的な衝動だけではありませんでした、物質的な衝動とともに道徳的な衝動もやってきたのです。物質的なものと道徳的なものはひとつでした。それが可能だったのは、そもそもこれらの秘儀において与えられたあの認識を通して、人間は自らを全自然と、人間は自然の霊を知覚していたわけですから一体のものと感じていたからです。たとえば、ギルガメッシュの生涯と、次の受肉でエフェソスの秘儀に近づいた個体の生涯の間に流れ去ったちょうどその時期に、人間の自然に対する関係において、あるひとつのことがあります。ちょうどその時期には、人間と霊自然(Geistnatur)との関連についての直観がまだ生き生きと見い出されます。この関連はこのようなものでした。自然のなかの元素霊たちの作用や、惑星の経過のなかの知性的存在たちの作用について、当時知っていたことすべてを通じて、人間はこう確信するに至っていました。外ではいたるところに植物界が広がっているのが見える、新緑に芽吹き、生長し、実を結ぶ植物界が。春に生え出し秋には枯れてゆく一年生植物が、草原に、野原に見える、そこには何百年も成長し続ける木々も見える、樹皮と木質部を外側に持ち地中深く根を伸ばした木々だ。この外界で一年生草本や花として根を降ろしているものすべて、硬い衝動とともに地中へと伸びてゆくものすべてを、人間としての私はかつて私のなかに担っていた。こういう確信です。よろしいですか、今日人間は、どこかある部屋に人間の呼吸によってできた炭酸があるとすると、私はこの炭酸を吐き出したと感じます。人間は、自分は炭酸をこの部屋のなかに吐き出したと感じるのです。人間は今日、まだわずかしか宇宙と関わり合っていないと言ってよいかもしれません。人間存在の空気的な部分において、生体組織のなかで起こっている呼吸及びその他の空気プロセスの根底にある空気において、人間は大いなる宇宙と、マクロコスモスと、まったく生き生きと関わり合っています。人間は吐き出された呼気を、つまり最初内にあって今は外にある炭酸を眺めることができます。人間が今日、実際そうしないにしても、そうすることは可能でしょう。吐き出された炭酸を眺めるように、ちょうどそのように、オリエントの秘儀に参入したか、あるいはオリエントの秘儀から外に流れ出た叡智を受け入れた人は、植物界全体を眺めていたのです。その人はこう言いました。私は宇宙進化において古い太陽紀を振り返って見る。そのとき私はまだ内部に植物を担っていた。その後私は植物を地球存在のあたり一面に流出させた。けれども、私がまだこの植物を私のなかに担っていたとき、私がまだ、植物界とともに全宇宙を包含していたあのアダム・カドモンであったとき、そのときこの全植物界はまだ水(液体)的ー空気(気体)的な何かであったと。人間はこの植物界を自身から分離(分泌)したのです。もし皆さんがこの地球の大きさになって、それから植物的なものを、今や水の元素のなかで変容し、生じ、枯れ、成長し、別様に変化し、まさしくさまざまな姿をとるこの植物的なものを、内に向かって分泌すると思い浮かべてごらんになれば、皆さんは当時の心情を皆さんのなかに呼び起こすことができるでしょう。そしてかつてはこのようであったということ。これを、ギルガメッシュの時代に彼方のオリエントで教育を受けたひとたちは語ったのです。彼らは草原の植物の成長を見るとこう言いました、私たちは、私たちの進化の前段階で植物を分離したが、地球が植物を受け取ったと。そのうち根のようなものは、木質のもの、植物のうち木の性質のものすべてと同様に、最初地球にはありませんでした。けれども、植物性のもの全般を人間は自分から切り離し、それは地球に受け取られました。人間は植物性のものすべてと密接な親和性を感じていました。高等動物に対して人間は[植物に対するのと]同じ親和性は感じておりませんでした、と申しますのも、動物的形成を克服し、進化の途上で動物たちを置き去りにしたことによってのみ人間は地上に到達することができたということを知っていたからです。人間は植物を地球まで携えてきて、それから植物を地球に委ねました、地球は植物を自らの懐に受け入れたのです。地球上で人間は、植物にとって神々の仲介者、神々と地球との間の仲介者となったのです。したがって、今やあの大いなる体験、これはごく単純化してこのようにスケッチできますが(図参照)、あの体験を現実に有したひとたちは、人間は宇宙(黄)から地球にやってきたと感じたのです。数は問題になりませんよ、昨日すでに申しましたように、人間たちは互いに合体していた(ineinanderstaken)のですから。人間は植物的なものをすべて分離し、そして地球は植物的なものを受け取って、それに根のようなものを与えたのです(暗緑色の線)。このように人間は、自分が植物の成長とともに地球を包み込むように(赤い覆い)、また地球がこうして包み込まれることに感謝しつつ、人間が液体ー気体的植物エレメントのかたちで地球に吹きかけることのできたものを受け入れたように感じました。そしてこのようなことを感じたひとたちは、このように地球に植物をもたらすことに関連して、自らを神、つまり水星の主神(Hauputgott des Merkur)と密接な親和性のあるものと感じました。自分が地球に植物をもたらしたのだというこの感情を通して、人は水星神と特別な関わりを持つに至ったのです。これに対して、動物についてはひとはこう感じました、動物を地球にもたらすことはできなかった、動物を切り離し、動物から自分を解放しなければならなかった。さもないと正しいしかたで人間の形姿を発達させることはできなかっただろうと。いわばひとは動物を自らから押し出し、その結果動物は人間からまさに押し出され(外側の赤い線)、人間のそれよりは低次の段階で動物自身の進化を遂げざるを得なくなったのです。このように一方において、まさにギルガメッシュ時代およびそれに続く時代の古代人は、自分が動物界と植物界の間に据えられていると感じたのです。植物界に対して人間は自らを、神々の代理としていわば地球に授精する担い手と感じました。動物界に対しては、動物という重荷を下ろし、そのため動物は退化するのですが、重荷を脱して人間となるためにあたかも動物界を自分から突き放したかのように感じました。ところで、エジプトの動物礼拝全体はこの直観と関連しています。アジアに見られる動物に対するあの深い同情の多くもこれと関連しているのです。そしてそれは、一方において植物界との、他方において動物界との人間の親和性を感じていた偉大な自然観でした。動物界に対しては解放を、植物界に対しては植物界との緊密な親和性をにひとは感じていたのです。人間としてひとは、植物界を自分自身の一部分と感じ、親密な愛のなかで地球を感じていました、なぜなら地球は、植物というこの人間性の一部を、自らのうちに受け入れ、自らのうちに根づかせ、しかも木々においては自分の素材を樹皮として植物を覆うことさえしてくれたからです。物質的な外界の判断のなかにはあらゆるところに道徳的なものがありました。ひとは草原の植物に近づいていき、この植物のなかに単に自然の成長を感じ取るのみならず、人間とこの成長との道徳的関係をも感じ取っていたのです。動物に対してもやはり道徳的な関係を感じ取っていました、ひとは動物を超え出ていったのだと感じたのです。つまりあちらのオリエントでは、こうした秘儀から大いなる霊自然観(Geistnatur-Anschauung)が流れ出していたのです。ギリシアにおいては当時秘儀は存在していましたものの、真の霊自然観をともなうことはずっと稀(まれ)でした。ギリシアの秘儀はなるほど壮大なものでしたが、まさにその本質からしてオリエントの秘儀とは区別されました。オリエントの秘儀においてはすべてが、地球上で人間はそもそもこの地球を通して自らを感じるのではなく、自分を宇宙、宇宙万有に組み込まれたものと感じていたという具合でした。ギリシアにおいては、秘儀の本質は最初、人間が自分を地球と結びいたものと感じるという段階に至ります。したがって、オリエントにおいて秘儀のなかで現われたもの、あるいは感じられたものは、本質的に霊的世界そのものだったのです。古えのオリエントの秘儀においては、供犠を捧げ祈りを唱える祭司たちのもとに神々自身が出現したと言われるとき、絶対的な真実が描写されているのにほかなりません。秘儀の神殿は同時に、神々を地上に迎える場所でした。そこで神々は天の宝として人間たちに贈るべきものを、祭司賢者たちを通じて人間たちに贈ったのです。一方ギリシアの秘儀においては、神々の像(映像、イメージ/Bild)、写し(模像/Abbild)、何か影像(Schattenbilder)のようなもののみが現われました、真の純粋な像ではありましたが、影像のようなもので、もはや神的存在たちそのもの、現実の存在ではなく、影像のみが現れたのです。そのためギリシア人は、古えのオリエントの秘儀の一員であった人とはまったく異なった感情を持っていました。ギリシア人はこう感じたのです、神々は存在する、けれども人間にできることは、これらの神々の像(Bild)を得ることだけだ、ちょうど記憶においては体験の像が得られるだけで、もはや体験そのものではないようにと。それはギリシアの秘儀から発してきた深い根本感情でした、自分たちは宇宙の記憶のような何かは有しているが、宇宙の現象そのものではなく宇宙の像だ、神々の像は持っているが神々そのものではない、土星、太陽、月上での経過についての像(Bild)は有しているが、土星、太陽、月上で現実(リアル)であったことと、たとえば人間が子ども時代とリアルに結びついてるようなそれほどの生きた結びつきはもはやないと人間たちは感じたのです。そしてこの、土星、太陽、月とのリアルな結びつきを、オリエント文明の人々の方はその秘儀から得ていました。このように、ギリシアの秘儀の本質には何か像のようなもの(etwas Bildhaftes)がありました。神的ー霊的現実の影のような霊たち(Schattengeister)が現われたのです。けれどもこのことは別の重要なことをもたらしました。と申しますのも、よろしいですか、オリエントの秘儀とギリシアの秘儀の間には、もうひとつ違いがあったのです。オリエントの秘儀においては、そこで経験できる大いなるもの巨大なもののうちいくらかなりと知ろうとするなら、ひとはまず時が熟すまで待たなければならないということが常でした。それに付属する供犠を、つまりいわば超感覚的な試み(Experimente)を、秋に行なう、あるいは別の試みを春に、また別のそれを真夏に、また真冬に行なう、するとそのときにのみ何かを経験することができると言う具合だったのです。そしてまた、月がある特定の位相をとることによって正しい時期と知ることのできた時期に、何らかの神々に供犠が捧げられるということもありました。神々はそのとき秘儀のなかに姿を現わしました。神々が顕現したのです。さらにまた、何らかの神的存在が秘儀においてまた顕現する機会がやってくるまで、そうですね、三十年ほど待たなければなりませんでした。たとえば土星に関わるすべてのものは、何らかのかたちで三十年ごとに秘儀の領域に入ってくることができるのみでしたし、月に関わるすべては常におよそ十八年ごと、等々でした。ですから、オリエントの秘儀の秘儀祭司たちは、彼らが得た壮大巨大な認識と観照を、時間と空間とあらゆる可能なものに左右されるかたちでのみ獲得することができたのです。たとえば、洞窟の奥深くではまったく違う啓示が得られましたし、山の頂上では別の啓示が得られました。どうにかしてあちらのアジアの奥深くにいたりあるいはまた海岸その他にいるときには、違った啓示が得られたのです。つまり、地上の空間と時間への依存、これがまさにオリエントの秘儀において特徴的なことでした。ギリシアにおいては、大いなる現実(リアリティ)は消え去っていました。像(Bilder)だけが残っていたのです。けれども、今やひとは季節や世紀の流れや場所に依存することなく像を得ることができました、人間として正しいしかたで準備をすれば、あれこれの黙想をし、あれこれの人格上の(persoenlich)供犠を捧げれば、この像を得ることができたのです。供犠と人格的成熟のある段階に到達すれば、ひとは人間としてそれに到達したがゆえに、大いなる宇宙の出来事と宇宙存在たちの影を近くするようになったのです。これは古(いにしえ)のオリエントからギリシアへの秘儀の本質における大きな変化です、古オリエントの秘儀は地上の場所と地上の空間の諸条件に従属していて、一方ギリシアの秘儀においては、人間は自分が神々にもたらしたものに関わり合ったのです。神がスペクトルム(Spektrum)の姿で自分のところにやってくるようにと行なった準備を通して人間が評価されたときに、神々はいわば、影像の姿、スペクトルムの姿でやってきたのです。このことによってギリシアの秘儀は、新たな人類を真に準備するものとなりました。さて、古のオリエントの秘儀とギリシアの秘儀との中間の位置にエフェソスの秘儀がありました。それはまさに特殊な位置を占めていました。と申しますのも、エフェソスにおいては、そこで秘儀に参入したひとたちは、古オリエントの巨大で壮麗な真実のいくばくかをまだ経験することができたからです。人間と大宇宙(マクロコスモス)の関連、大宇宙の神的ー霊的存在たちと人間との関連についての内なる感受と感覚によって、まだそれらの真実に触れることができました。おお、エフェソスにおいては、地上を超えたものについてまだ多くのことが感じ取られていたのです。そしてエフェソスの秘儀の女神アルテミスとひとつになることによって、あのまだ生き生きとした関係がもたらされました。植物界はお前の世界である、地球はただ植物界を受け取ったのだ。お前は動物界を克服した、お前は動物界を置き去らなければならなかった。お前が人間となることができるために置き去りにせねばならなかった動物たちを、お前はありったけの同情をもって眺めなければならない。このように大宇宙と自分がひとつであると感じること、この感情が、エフェソスの秘儀参入者たちにはまだ直接の体験から、現実(リアリティ)から、伝えられたのです。けれどもエフェソスにおいては、西洋に向けられた最初の秘儀として、季節あるいは世紀の流れ、要するに地上の時と場所からの独立というものがありました。エフェソスにおいてはすでに、人間が行なう黙想、そして神々への供犠と帰依を通じてどのように自分を成熟させるかというそのやり方に注目されていました。その結果、実際のところエフェソスの秘儀は、一方で秘儀の真実の内容を通してまだ古オリエントを指し、他方、人間進化へと、人間性へとすでに押しやられたことによって、エフェソスの秘儀はすでにギリシア精神への傾向を有していたのです。それはいわば、古の大いなる真実が人間に近づいていた、近づくことができたあの東方における最後の秘儀でした。と申しますのも、東方においては秘儀がすでにもう頽廃(Dekadenz)に至っていたからです。古の真実がもっとも長く維持されていたところ、それは西方の秘儀のなかでした。キリスト教成立後数世紀になおもひとはヒベルニアについて語ることができました。けれども、ヒベルニアの秘密は根本的に言って二重に秘密に満ちていると申し上げたいのです。と申しますのも、よろしいですか、昨日私が皆さんにこれら二つの立像についてお話ししたこと、そのひとつは太陽像でもうひとつは月像、ひとつは男性像でもうひとつは女性像だったのですが、この立像の秘密というのは、今日、その秘密自体をいわゆるアーカーシャ年代記から探究することがまだ困難な状況なのです。こうした物事において修練された人たちにとっては、オリエントの秘儀の像に近づいて、これらの像をアストラル光のなかから取り出してくることは、比較的困難ではありません。ところが、ヒベルニアの秘儀に近づこうとすると、アストラル光のなかで近づこうとすると、ひとは最初何か麻痺(眩惑)のようなものに見舞われます。それはひとをはね返します。このアイルランドの秘儀、ヒベルニアの秘儀は、もともとの純粋さを最も長く保っているにもかかわらず、今日もはやアーカーシャ年代記のなかに自分の姿を見せようとはしないのです。さてよく考えてみてください、アレクサンダー大王のなかに入り込んだ個体(個人)は、ギルガメッシュ時代、今日で言うブルゲンラント地方に至る西への旅のときに、ヒベルニアの秘儀によって触れられました。それはこの人間個体のなかで生きました、この西方に依然としてアトランティス時代の強い余韻があった時代に、非常に古いしかたで生きたのです。それは、死と新たな誕生との間に経過する魂的状態を通じて担われていきました。それからふたりの友、エアバニとギルガメッシュは、今度はまさにエフェソスにいました、そしてそこで、以前のギルガメッシュ時代に、神的ー霊的世界との関連で多かれ少なかれまだ下意識的に体験されたことを、非常に意識的に体験したのです。このエフェソス時代は、その前のもっと活動的な時代に魂のなかに引き入れられたものを消化し、加工する比較的静かな人生でした。さて、よく考えてみなければなりません。この両個体がギリシアの頽廃期、マケドニアの全盛期に再び出現する前に、このギリシアを通過していったものは何だったのでしょう!この古代ギリシア、海を越えて拡がりエフェソスをも包含し、小アジアの奥にまで入り込んでいたこの古代ギリシアは、古の神々の時代の余韻をなおすべて影像のなかに有していました。人間と霊的世界との関連は影のなかでまだ体験されていたのです。けれどもギリシア精神はこの影のなかから徐々に抜け出します、そして私たちは、ギリシア文明がいわゆる神的な文明から純粋に地上的な文明へと入り込んでいくさまを、段階を追って見ることができるのです。おお、今日の唯物論的に外面的な歴史なるものにおいては、歴史的生成のうちでももっとも重要な事柄が、まったく触れられてもいないのです。ギリシア精神の理解全体にとっても重要なのは、ギリシア文明のなかには、人間が超感覚的世界と関わっていた古の神性の影像のみがあったために、人間が徐々に神々の世界から出て人間自身の、完全にひとりひとり個人的な霊的能力を用いるようになったということです。このことは段階的に起こりました。古の神々の時代についてなおも感じられていたことが、今度は芸術的な像のなかに現われてくるさまを、私たちはアイスキュロスのドラマのなかにまだ見ることができます。ところがソフォクレスに至るやいなや、人間はいわばこの、神的ー霊的存在と自分をひとつと感じることから引き離されます。そしてそれから、ある観点からすればあまり評判の良くないのももっともな、ある名前と結びつくものが登場します。世のなかにはさまざまな観点があるものですけれども。よろしいですか、実際ギリシア古代においては、歴史を記述する、ということは必要ありませんでした。いったい何のために歴史がいるのでしょう。当時は重要な過去の出来事の生きたシルエット[Abschattung]がありました。歴史は、秘儀において示されるもののなかに読みとられました。影像が、生き生きとした影像があったのです。いったい歴史として何を書き留めると言うのでしょう。それから、これらの影像が下の世界に沈んでしまう時代がやってきました。人間の意識はもはや影像を受け取ることができなくなりました。ここではじめて、さあ歴史を書こうという衝動が生まれたのです。ここで最初の歴史の散文家ヘロドトス(☆1)が登場しました。そしてこの時から多くの名を挙げることができるでしょう、いわば人類を神的ー霊的なものから引き離し、純粋に地上的なもののなかに据えることが常に目指されるようになったのです。けれどもギリシア精神がこうしてまったく地上的になっていく、その上には、いつもひとつの輝きがありました、明日私たちはこれついて聞かされるでしょうが、これはローマ精神にも中世にも受け継がれませんでした。けれどもひとつの輝きがあったのです。影像から、ギリシア文明の黄昏のなかで光を失ってゆく影像から、それらは神的な起源を持っていたということをひとはなおも感じ取り、感受していました。そして、あらゆるもののさなかに、文化の断片とでも申し上げたいかたちでそのギリシアに存在していたすべてについて解き明かされる隠れ家のようなあらゆるもののさなかに、エフェソスはありました。ヘラクレイトス、最も偉大な哲学者たちの数々、プラトンも、ピュタゴラスも、彼らは皆まだエフェソスから学んでいました。エフェソスとは真に、ある時点まで古えのオリエントの叡智を維持してきたものだったのです。そして、アリストテレスとアレクサンダーであったあの個人たちもまた、ヘラクレイトスよりも少し後になってから、その叡智を経験することができました、オリエントの秘儀のなかにまだ古(いにしえ)の智としてあったものは、エフェソスの秘儀のなかに遺産として残されていたのです。エフェソスで秘儀の本質として生きていたものは、とりわけアレクサンダーの魂と密接に結びつきました。さて今や、あの歴史的な出来事が起こります、凡俗な人はこれを表面的な偶然とみなしますが、これはまさしく、人類進化の内なる連関に深い深い根拠を持つ出来事なのです。この歴史的な出来事の意味を見通すことができるように、ひとつ以下のことを魂の前に呼び起こしてみましょう。考えてみてください、のちにアリストテレスとなった人の魂(*ポリス的人間魂)と、アレクサンダー大王(*世界人間魂)となった人の魂、この両者の魂のなかで、太古の時代に由来して内的に加工されたものがまず生き、次いで、エフェソスにおいて彼らにとって途方もなく価値あるものとなったものが生きました。アジアがまるごとにとでも申し上げたいのですが、ただしエフェソスでギリシア的になった形をとって、この両者の魂のなかに、とりわけのちにアレクサンダー大王となった魂のなかに生きたのです。さて、この人物の性格、私はこれをギルガメッシュ時代から述べたのを思い浮かべ、さらによく考えていただきたいのです。さて今やアレクサンダーとアリストテレスの生き生きとした交流のなかで、古オリエントとエフェソスに結びついていた智が繰り返されました。新たな形をとって繰り返されたわけです。このことをひとえに思い浮かべていただきたいのです。もともとこの両者の魂のなかで途方もない強度をもって生きた巨大な記録、この巨大な記録であるエフェソスの秘儀が存在していたなら、つまりアレクサンダーとしての受肉においてもアレクサンダーがエフェソスの秘儀に出会ったとしたら、どういうことにならざるを得なかったでしょうか。このことを思い描いていただきたいのです、そしてさらに事実を正しく評価していただきたいのです、アレクサンダーが生まれた日に、ヘロストラト(Herostrat)がエフェソスの聖域に燃える松明を投げ込み、そのためエフェソスのディアナ神殿は、アレクサンダーの生まれた日に、冒涜者の手によって燃え尽きたという事実(*1)を。アレクサンダーの記念碑的記録と結びついていたものはもはや失われました。それはもうなくなり、結局今はただ歴史的使命として、アレクサンダーの魂とその師アリストテレスの魂のなかにあるのみとなったのです。さてここで、彼らのなかで魂的なものとして生きたものを、私が昨日、地の配置から読みとれるもののように、アレクサンダー大王の使命のなかに示したものと結びつけてみてください。すると今や皆さんも理解なさるでしょう、オリエントにおいて現実に、神的ー霊的なもののリアルな顕現であったものは、エフェソスとともに消し去られたようになったのです。ほかの秘儀は根本において、伝統を保持し続けているのみの衰退した秘儀(Dekadenzmysterien)にすぎませんでした、たとえそれが非常に生き生きとした伝統であったにしても、またとりわけ素質のある性質のなかに当然ながら霊視的な力を呼び起こすような伝統であったとしても。古の時代の偉大さ、巨大さはもうありませんでした。アジアからやってきたものは、エフェソスとともに消し去られたのです。今や皆さんは、アレクサンダー大王の魂のなかの決心を正しく評価なさるでしょう。かつて有していたものを失ったこのオリエントに。ギリシアにおいて影像のなかに自らを保管してきた形で、せめてそれがもたらされねばならないという決心です。それとともに、移動できうる限りアジアへ移動しようというアレクサンダー大王の思いが生じたのです、オリエントが失ったものを、ギリシア文化の影像のかたちでオリエントにふたたびもたらすために。そして今や私たちは、このアレクサンダー大王の遠征とともに、実際まったく驚くべきしかたで行われたのは文化征服ではない、ということがわかります、いかなるかたちであれアレクサンダー大王はヘレーネントゥム(ギリシア文化/Hellenentum)を外的なしかたでオリエントにもたらそうとするのではありません。いたるところで土地の風習を受け入れるばかりでなく、いたるところで彼は、人々の心、心情から考えることができるのです。彼がエジプトのメンフィスに行くと、彼は、それまで支配していた霊的なあらゆる奴隷拘束具からの解放者とみなされます。彼はペルシア帝国に、ペルシアには不可能であったある文化、文明を浸透させます。彼はインドまで押し進みます。彼はヘレニズム文明とオリエント文明との間に宥和を、調和を生み出すというプランを立てます。いたるところに彼は学院(アカデミア/Akademien)を創設します。後世にとって最も重要な意味を持つのは、彼がエジプト北部、アレクサンドリアに創設した学院ですね。けれども最も重要なことは、彼がアジアのいたるところに大小の学院を設立し、そこでその後の時代に、アリストテレスの諸著作と、アリストテレスの伝統が培われたということです。そしてこれは数世紀を通じて西南アジアにまで作用し続けました、アレクサンダーが開始したものが相変わらず弱々しい残像のように繰り返されるとでも申し上げたいしかたで作用し続けたのです。アレクサンダーはまず、力強い一撃で、自然智をかなたのアジアに、インドの中へと植え付けました。早く訪れた死のために、彼はアラビアまで行くことはできませんでしたが、アラビアに行くことが彼の主要目的だったのですが。インドの中へ、エジプトの中へ、いたるところへと。アレクサンダーは自然霊の智(Naturgaeist-Wissen)としてアリストテレスから受け取ったものを移植しました。そして彼はそれをいたるところに据えました、それを受け取るべき人々が、それを自分たちに押しつけられたなじみのないヘレニズム的なものと感じるのではなく、自分たち自身のものと感じ、それによって、実り豊かなものとなるように据えていったのです。実際のところ、そこで引き起こされたようなことを起こすことができたのは、このアレクサンダー大王のような火を吹くような性質の人だけでした。常に後援軍がやってきたからです。後の時代の多くの学者もまたギリシアを出て行きました、とりわけ学院のうちあるものはエデッサ郊外(*ゴンディシャプールの学院がありました)数世紀にわたって繰り返しギリシアからの移住を経験したのです。ここで、途方もないことが成し遂げられました、オリエントからやってきたもの(描かれる、両方が重ね合わせられる;黒板原画8参照、右から左への赤、明色の斑点)、ヘロストラトスの松明によってエフェソスで止められたもの、これが、ギリシアにあったその影像によって、また照らし出されたのです(左から右への明るい緑)、それは、東ローマの暴虐によって(☆2)ギリシアの哲学者たちの学院が紀元後6世紀に閉鎖され、最後のギリシア哲学者たちがゴンディシャプールの学院へと逃れていった最後の幕まで続きました。それは、先に進んだものと、残存されてきたものが相互に働きかけあうというものでした。このことによって、多かれ少なかれ無意識的であったにせよ、実際のところこの使命のなかにあったものは、ある意味でギリシアにおいてはルツィファー的なしかたで文明生活の波が到達し、かなたのアジアにおいてはそれがアーリマン的なしかたで残されていた、エフェソスに両者の調停があったということなのです。そしてアレクサンダーは、エフェソスが物質的には彼の誕生した日に崩壊してしまったために、霊的なエフェソスを、その太陽光がオリエントとオクツィデントを照らすべく建設しようとしたのです。深い意味でアレクサンダーの意図の根底にあったものは、西南アジアを通ってインドの内部まで、アフリカのエジプトを通って、ヨーロッパ東方を通って霊的なエフェソスを建設するということでした。この背景を知らないと、西洋の人類の歴史上の進化を理解することはできません。と申しますのも、このことが起こった直後に、つまりここで太古の由緒あるエフェソスを広範囲に拡げようとすることが試みられた後、結局エジプトのアレクサンドリアにおいて、くすんだ写字の形ではあっても、エフェソスにおいてかつて輝く広い文字のなかにあったものが保存されたからです。そして、このエフェソスの遅咲きの花が咲き誇った後、かなたの西方では今やまったく別世界であるローマ精神が勃興していました、もはやギリシアの影像とは関わりなく、人間の本質のなかにはこの古の時代への追憶のみしか残されていないローマ精神が。したがって、歴史において研究されうる最も重要な区切りは、エフェソスの火災の後アレクサンダーによって霊的なエフェソスが建設されたときの区切りなのです、この霊的なエフェソスはその後、最初はローマ精神として、次いでキリスト教その他としてさらに西方で勃興していくものによって押し戻されるのですが。そして、人類の進化は次のように言うときにのみ理解されます。つまり、知性で理解し、意志から働きかける私たちのやりかた、心情気分を持った私たちそのままに、私たちは古代ローマを振り返ってみることができる。そのすべてを理解できる。ところがギリシアを、オリエントを振り返ってみることはできない。その場合イマジネーションのなかで見なければならない、そのためには、霊的に観ること(geistiges Schauen)が不可欠であると。南に向かっては、通常の素っ気ない散文的な知性をともなった歴史的生成のなかで見ていくことも許されるでしょう、けれども東方に向かってはそれは許されません。と申しますのも、東方を見るとき、私たちはイマジネーションのなかで見なければならないからです、背景にあるアトランティス後の太古アジアの力強い秘儀の神殿を。そこでは、祭司賢者たちが弟子のひとりひとりに、宇宙の神的ー霊的なものとの連関を明らかにし、私が皆さんに描写しましたようなギルガメッシュ時代に受け入れられることができたような文明が存在していたのです。さらに私たちは、この驚くべき神殿がアジア中に拡散されたのを観るとともに、いかにエフェソスが中心になっているかを見なければなりません、アジア中に拡散された神殿のなかで色褪せてしまったものの多くをまだ維持しながら、すでにギリシア精神のなかに移行していたエフェソスが。人間はもはや、エフェソスで神々の啓示を受け取るために、星位や季節の到来を待つ必要はありません、人間は、黙想をすれば、人間が成熟に至ったときに供犠に捧げるものによって、神々に近づくことができるのです、神々が恩寵豊かに人間のところにやってくるわけです。そして今や私たちは、この像(光景/Bild)によって再現される世界に、ヘラクレイトスの時代に、皆さんにお話しした人物たちが準備されているのを見ます、今や私たちは、紀元前356年、アレクサンダー大王の誕生した日に、エフェソスの神殿から火炎が燃え上がるのを見ます。アレクサンダーは生まれ落ち、師アリストテレスを見出します。そして、この天へと昇っていくエフェソスの火炎から、理解できる人々にとって、このように響いてくるかのようです、古の物質的なエフェソスがその中心中核として記憶のなかに存在することのできる場所に果てしなく、霊的なエフェソスを建設すると。このように私たちは秘儀の地のあったこの古のアジアの像(光景)を見ます、前景に燃え上がるエフェソス、その弟子たち、そしてほぼ同時期、少し後に、ギリシアが人類の進化のなかで与えることのできたものをあちらにもたらしたアレクサンダーの遠征、そしてその結果アジアがその内実をなくしてしまっていたものが像としてアジアにやってくるのです。そしてはるかに見晴るかし、そこに巨大なものとして起こるものによって私たちのイマジネーションに翼が与えられて、私たちはイマジネーション的に捉えなければならない歴史の真の古い断絶を振り返ります。そしてそのときはじめて私たちは、ローマ世界が、中世世界が、現代の私たちにまで続いてきている世界が、前面に上昇してくるのを見るのです。その他のあらゆる区切り、古代、中世、近世、その他私たちが区分と称しているようなものは、根本において誤った観念しか呼び起こしません。私が今皆さんの前にお見せしましたこの像(光景)だけが、皆さんがそれをますます深く追求していかれるなら、今日に至るまでヨーロッパの歴史の生成のなかに生じている秘密についても真の展望を皆さんに与えてくれるのです。これについては明日さらに続けましょう。参照画:Temple of Artemis at Ephesus□編註☆1 ヘロドトス:Herodotos von Halikarnassos 前5世紀、最古のギリシアの歴史家、ペルシア戦争史の記述者。☆2 東ローマの暴虐によって:ユスティニアヌス[Justinian](東ローマ皇帝(527-565)、農民の息子)は、529年にアテネに対して、当地では哲学を教えてはならないという勅令を発した。そのため、アテネの最後の哲学者7人がローマ帝国を去り、ペルシアに移住した。Ernst von Lasaulx 『ヘレニズムの没落とキリスト教会による神殿財宝の吸収』(1854)を参照のこと。H. E. Lauer 編『埋もれたドイツの著作』(1923 シュトゥットガルト)に再出、とくに196頁以下。□訳註*1アレクサンダーの生まれた日に:歴史に名を残そうと、前356年、ギリシアの王ヘロストラトス[Herostratos]は、エフェソスのアルテミス神殿を焼き払った。Herostrat「売名的犯罪人」 の意味の由来。(第5講・了)人気ブログランキングへ
2024年05月14日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 (GA233)翻訳紹介:yucca第4講 1923/12/27 ドルナハ 昨日の私の課題は、世界史上の進化がどのように起こるかということを個々の人物を手がかりに示すことでした。精神科学の方向で前進したいと思うなら、ひとは出来事の結果を人間のなかに反映させるという以外には表現しようがありません。と申しますのも、よく考えてみてください。この現代だけが、この連続講義においても引き続きお話ししていく理由から、人間が自らをその他の世界から切り離された個別の存在と感じるように性格づけられているのですから。以前のあらゆる時代、そして将来のすべての時代において、これははっきり強調されねばならないことですが、人間は自らを全宇宙の一部、全宇宙に組み込まれたものと感じましたし、感じるようになるでしょう。たびたび申しましたように、人間の一本の指はそれ自体で完結した存在ではあり得ず、人間に所属するものであるように、また他方、指が人間から切り離されればもはや指ではなく崩壊してしまってまったく別ものとなり、生体組織とは別の法則に従うようになるように、ちょうどそのように人間は、地上生という形(Form)であれ、死と新たな誕生との間の生という形であれ、何らかの形で全宇宙と関り合っている存在にすぎないのです。けれどもこのことについての意識は、まさしく前の時代には存在し、これからまた存在するようになるでしょう。この意識が曇り、暗くなっているのは今日の時代だけです、なぜなら、私たちがこれから聞くことですが、人間が自由の体験をまったく完全に自らのうちに育成することができるように、この意識が曇り、暗くなることが人間には必要だったからです。そして時代を遡れば遡るほどますます、いかに人間が自分は宇宙の一部であるという意識を持っていたかがわかります。さて私は皆さんに、ふたりの人物、ひとりは名高い叙事詩においてギルガメッシュと呼ばれ、もうひとりは同じ叙事詩でエアバニと呼ばれた人物を描写し、それから私は、このふたりの人物が古代カルデアーエジプト時代に当時の人に可能であった生き方で生き、その後エフェソスの秘儀を通じてさらなる深まり(深化)を経験したようすを皆さんに示しました。さらに昨日注意を向けていただいたことは、この同じ人間存在たちがその後アリストテレスとアレクサンダーとして世界史の進化のなかに置かれたということでした。けれども私が描き出しましたことがこれらの人物たちに起こったあの時代において、地球進化の歩み全般がどのようなものであったかを私たちが完全に理解することができるためには、このような魂たちがこの三つの相前後する時代において自らのうちに受け入れたものを、さらに厳密に見通さなければなりません。私は皆さんに、ギルガメッシュという名前の背後に隠れている人物が西への道を辿り、アトランティス後の一種の西方のイニシエーションをともかくも通過することに注意を促しましたね。さて今度は、さらに後のものを理解するために、このような後になってのイニシエーションがどのようなものであったかについて思い浮かべてみましょう。むろん私たちは、こういうイニシエーションを、古えのアトランティスのイニシエーションの余韻が長い間残っていた土地に探さなくてはなりません。そして、ここドルナハにいらっしゃる友人の皆さんにはすでに前回お話ししましたが、ヒベルニアの秘儀(☆1)がそれでした。けれどもここで考察することを私たちが完全に理解できるためには、お話ししたことのいくつかを繰り返さなければなりません。※「ヒベルニアの秘儀」とは、古代アイルランドにおける霊的な儀式や教えのことを指します。これらの秘儀は、古代アトランティスの叡智の余韻が残る中で行われ、象徴的な光景や精神的な存在の輪郭が明確に浮かび上がる霊界を参入者に見せる機会を提供していました。また、ヒベルニアの秘儀は、ゴルゴタの秘蹟が起こる数世紀前から存在し、ゴルゴタの秘蹟当時にも続いていたとされています。これらの秘儀は、自然界や宇宙との深い関連を持ち、人間とマクロコスモス(大宇宙)との関連を明かすものでした。秘儀においては、自然の元素霊や惑星の経過の中の知性的存在たちの作用についての知識を通じて、人間は宇宙との関わりを感じ取ることができたと言われています。ヒベルニア自体は、アイルランド島の古称であり3、その地で行われた秘儀は、西洋の霊的伝統の中でも特に重要な位置を占めていたと考えられています。これらの教えは、現代においても人智学や神秘学の研究において参照されることがあります。 アイルランドの秘儀であるヒベルニアの秘儀はほんとうに長い間存続してきました。それはキリスト教成立の時代にもなお続いていて、アトランティス民族の古えの叡智の教えをある面からもっとも忠実に保存してきた秘儀なのです。さてまずはこれから皆さんに、アトランティス後の時代にアイルランドの秘儀に参入を許された誰かの持った体験について、ひとつの像(イメージ)をさし上げたいと思います。この秘儀、このイニシエーションを受けることになった人は、当時、厳しく準備を課せられなければなりませんでした。古代においてはそもそも秘儀参入への準備には途方もない過酷さがつきものものでしたが。その人は実際、内的にその魂状態、人間としての状態をまるごと造り替えられなければならなかったのです。それから、ヒベルニアの秘儀においては、その人はまず人間を取り巻く存在のなかの虚偽のもの、人間がまず感覚知覚にのっとって自分の存在の拠り所としているあらゆる事物のなかの虚偽のものに対して、強い内的体験をしつつ注意を向ける、という準備を課せられました。そしてその人はさらに、彼が真実を、ほんとうの真実を希求するときにたちふさがる困難と障害のすべてに注意を向けさせられます。その人は、感覚世界において私たちを取り巻くすべては根本的に幻影(Ilusion)なのだ、感覚は幻影的なものを与え、真実は感覚の背後に隠れてしまう、つまり真の実在はそもそも感覚知覚を通じては人間には到達できないのだと気づかされたのです。さて皆さんはこうおっしゃるでしょう、人智学に長く親しんでそれはいつももう十分確信していることだと。それはもうよくわかっていると皆さんはおっしゃるでしょう。けれども、感覚的外界の幻影的性格について、そもそも現在の意識のなかで人間が持ちうるあの知識などは、当時ヒベルニアの秘儀参入のために準備を課された人々によって経験された内的な震撼、内的な悲劇に比べれば、まったく無に等しいのです。と申しますのも、このように、全てはマーヤだ、全ては幻影だと理論的に言うとき、そもそもそれは非常に軽く考えられているのですから。けれどもヒベルニアの秘儀入門者たちの準備は彼らが自分にこう言うところまで押し進められたのです、幻影を突き抜け実際の真実の存在にいたる可能性は人間にはないのだと。入門者たちは、いわば最初は絶望の念から、内的、魂的に幻影に自足する、という準備を課せられました。この幻影の本性はあまりに強圧的、圧倒的なので、ひとはそもそも幻影を越えてゆくことなどできないのだ、という絶望に満ちた気分のなかに彼らは入り込んでいきました。そしてこの入門者たちの生のなかに繰り返しこういう気分がありました、さてこれからひとは幻影のさなかに在り続けなければならない。けれどもそれは、これからひとは足もとの基盤を失わざるを得ない、幻影に確実な足場は求められないからだということでした。そう、古えの秘儀における準備の過酷さ、これに関しては、今日のひとは根本においてほとんど想像もつかないでしょう。人々は内的な進化を真に促すものの前ではまさにひるんでしまうのです。そして存在と存在の幻影的な性格についてと同様に、入門者たちにとっては真理を求める努力についても事情は同じでした。そして彼らは、人間が真理に至ろうとするのを、情緒のなかで、人間を打ち負かす暗い感覚と感情のなかで妨げるものを、認識の明澄な光を曇らすものすべてを知ったのです。こうして彼らはここでも、次のように言う時点に至りました、私たちが真理のなかに生きることができないのなら、私たちは錯誤のなか、虚偽のなかで生きざるを得ないと。これはまさしく、人生のある時期に、存在と真理に絶望するに至るなら、その人の人間性は自己自身からもぎ離されるということなのです。これらすべては、人間がとどのつまりに目標として到達すべきものの反対のものを体験することを通じて、この目標に正しく深い人間的感情を向けることができるために必要だったのです。と申しますのも、錯誤と幻影とともに生きるということがどういうことか知るに至らなかった人は、存在と真実を尊重するということなどわからないからです。それでヒベルニアの秘儀の入門者たちは、真実と存在を尊重することを学ばされねばならなかったのです。そして入門者たちがこのようなことを為し遂げ、彼らがいわば最終的に行き着かなければならないもの対極を為し遂げると、彼らはここで起こったことを私は、当時実際にヒベルニアの秘儀においてリアルだったように具象的に描写しなければならない一種の聖域に導かれました、そこには二つの立像、途方もなく強い暗示の威力を持つ立像がありました。そしてこれらの巨大な立像の一方は、内部が空っぽでした、この空洞を囲む外側の面、つまりこの立像が作られている全実質はきわめて弾力のある素材で、そのためどこを押してもこの像を内部へと押すことができましたが、押すのをやめた瞬間、形はもとどおりになりました。立像全体は、頭の部分を主として形成されていて、この像に向き合ったひとは、力が頭から巨大な体躯のほかの部分へと放射している、と感じるほどでした。と申しますのも、空洞の内部空間は見えず、知覚することもできず、押してみてはじめてひとは内部空間に気づいたからです。頭以外の体躯全体が頭の力よって放射されている、この立像にあっては頭がすべてを為していると感じられたのです。散文的な生をおくっている今日の人間がこの立像の前に連れて行かれたとしても、抽象的なもの以外の何かを感じることなどほとんどないだろうということを認めるのに私は吝(やぶさ)かではありません。なるほど、内部全体で、その精神(霊)、その魂、その血、その神経をもって幻影の力と錯誤の力を体験したということは、そしてこのような巨大な姿の暗示的な猛威を体験するというのは、まさに何か別のことなのです。この立像は男性の特徴を持っていました。この像のかたわらに、女性的特徴を持つもう一方の像が立っていました。こちらは空洞ではありませんでした。このもう一方の像は、弾力的ではないけれど可塑的な素材から造られていました。この像を押すと、ー人は今度も像を押すように促されたのです。形は壊れ、像の体には穴が開きました。けれども、一方の立像のところで、弾力があるために形態がすべてもとにもどってしまうということを経験し、もう一方の立像のところで、押すことによって像を変形させることを経験したあとで、入門者は、私がこれからお話ししていくいくつかの別のことにしたがって、部屋を去り、それから、可塑的ではあっても弾力のない、女性的特徴を持つ立像に彼がつけた欠損と変形がすっかりもとにもどされてから、またこの部屋に連れ戻されました。入門者は、立像が無傷の状態にもどされてから連れ戻されたのです。こうして入門者が成し遂げたすべての準備を通して、私は事態を概略的に描写できるだけなのですが、入門者は、女性的特徴を備えた立像のところで、霊、魂、体による全人間性においてある内的体験を得ました。この内的体験はすでにもう以前から準備されてきたことではありますが、立像そのものの暗示的な作用によりきわめて完全に起こったのです。入門者は自らのうちに、内的な硬直の感情を、内的に凍りつき硬直する感情をおぼえました。そしてこの硬直の感情は、彼のうちに、自分の魂がイマジネーションで満たされるのを見るという作用を及ぼしました、そしてこれらのイマジネーションは地球の冬の像、地球の冬を示す像でした。つまり入門者は、内部から霊のうちに冬的なものを観ることに導かれたのです。もう一方の立像、男性的な立像の方ですが、こちらの像の場合はこのような状態でした、つまり入門者は、ふつう彼の全身のなかにある生命のすべてが血液のなかに流れ込むときのような、つまり血液が力に浸透されて皮膚を圧迫するときのような何かを感じたのです。つまり入門者は、一方の立像の前では、凍り付いた骸骨になると思わざるを得なかったのですが、他方、もう一方の立像の前では、自分の内部の全生命が暑熱を帯びて崩壊し、自分が張りつめた皮膚のなかで生きている、と思わざるを得ませんでした。そしてこの、表面を圧迫された全人間の体験が、入門者を、次のように自らに言う洞察へと導いたのです、お前は感じ取る、お前は感じ、お前は体験する、とりわけ宇宙において太陽だけがお前に作用するときになっているであろう状態のお前をと。そして入門者はこのようにして、宇宙的な太陽作用をその区分において知るようになりました。彼は人間の太陽への関係を知るようになったのです。さらに彼は、宇宙のほかの方角からのほかの諸力がこれらの作用を修正するというこの理由によってのみ、実際のところ自分は、今太陽の像の暗示的な作用のもとに出現した状態の自分ではない、ということも知るようになりました。このようにして入門者は、宇宙に慣れ親しむことを学びました。そして入門者が月の像の暗示的な作用を感受したとき、つまり内的に硬化して凍りついたものを、冬の風景を体験したとき、太陽像の場合彼は夏の風景を自分自身から生み出されたように霊の中で体験したのですが、そのとき人間は、もし月の作用のみしかなかったら人間はどのようになるだろうということを感じたのです。よろしいですか、現代において人はそもそも宇宙(世界)について何を知っているでしょう。人は宇宙について、チコリは青い、薔薇は赤い、空は青い、云々といったことを知っています。けれどもこれは震撼するような印象というわけではありませんね。これらは、人間の周囲にあるきわめて日常的なことを告げているにすぎません。人間は、宇宙万有の秘密に通ずるようになりたいと思うなら、全本質をもってより集中的に感覚器官にならなければなりません。それで、まさに太陽像の暗示的な作用を通じて、彼の本質はその全血液循環に集中させられたのです。人間はこれらの暗示的な作用を自らのうちで体験することで、自らを太陽存在として知るようになりました。さらに人間は、女性的な像の暗示的な作用を体験することで、自らを月存在として知るようになりました。さらにそれから、人間はその内的な諸体験から、今日人間が自分の目の体験によって薔薇がどのように作用するかを、自分の耳の体験によって嬰ト音がどう作用するか等を言うことができるように、そのように太陽と月がどのように人間に作用するかを言うことができたのです。このように、この秘儀への入門者たちはアトランティス後の時代においてなお、人間が宇宙に組み込まれていることを体験していたのです。これは彼らにとって直接的な経験でした。さて、私が皆さんにお話ししましたのは、キリスト教の発展の第一世紀まで、ヒベルニアの秘儀において、太陽体験および月体験に導かれた入門者たちによって宇宙的な体験としてまったく壮大に体験されていたことの短いスケッチにすぎません。エフェソス(エペソ)の秘儀、小アジアのエフェソスの秘儀において入門者たちが成し遂げた体験はまったく別のものでした。このエフェソスの秘儀においては、のちにヨハネ福音書の冒頭の言葉、(太初に言葉/Wort)があった。そして言葉は神のもとにあった、そして「言葉は神であった」に模範としての表現を見出したものが、とくに集中的に、全人間をもって体験されました。エフェソスでは入門者は二体の像の前に連れて行かれるのではなく、エフェソスのアルテミスとしてよく知られている像の前に連れて行かれました。そして、生命に満ち、いたるところで生命に満ち溢れているこの像と同一化することで、入門者は宇宙エーテルに深く親しみました。内なる体験と感情の全てをもって彼は単なる地上生から引き揚げられ、宇宙エーテルの体験へと引き揚げられたのです。そして彼には以下のことが明らかになりました。彼にまず伝えられたのは、人間の言葉とはそもそも何かということでした。そしてこの人間の言葉、つまり人間の写し(Abbild)、世界ロゴスにして宇宙的なロゴスの、人間における写しであるロゴス、これを手がかりに、いかに宇宙言語(Weltenwort) が創造的に宇宙(コスモス)を貫いて生き生きと動き沸き立っているかが彼に明らかにされたのです。私はここでも概略をお話しすることだできるだけです。それはこのような経過でした。入門者は、とりわけ、人間が話すとき、人間が呼吸で吐く息に言葉を刻印するときに起こることを真に体験することに注意深くさせられました。入門者は、次のような体験に導かれました、このとき彼自身の内なる行為を通じて生命に移行するものは、空気のエレメント(元素)のなかで生起すること、しかもこの空気のエレメントのなかで起こっていることに、二つの別の経過が結びついていること、これらを体験するように導かれました。思い描いてみましょう、これが呼気だとします(図参照、右部分、赤い(rot)線を伴う明るい青(hellblau)、この呼気に人間が話す何らかの言葉形成物(Wortgebilde)が刻印されるとします。言葉に形成されたこの呼気が私たちの胸から外へと流れ出る一方、リズミカルな振動が、人間の生体組織(有機体)に浸透するまったく水のような液体的エレメントのなかへと下降していきます(明色/hell;水/Wasser)。それで人間は話す際、その喉頭の上部、言語器官のなかに、空気のリズムを持っているのです。けれどもこの話すことと並行して、人間の内部では液体的身体(Fluessigkeitleib)が浸透し動きうねっています。言語領域の下の方にあるこの液体が振動し始め、人間のなかで共振するのです。そして私たちが話すことに感情が伴っている、これは本質的なことですね。人間のなかの水状のエレメントが共振しないとしたら、言葉が中立した状態で外へ、つまり無造作に外へと出ていくとしたら、人間は話されたことに共感することはないでしょう。けれども上に向かって、つまり頭に向かっては、熱エレメント(赤)が上昇していきます、そして私たちが呼気に刻印した言葉は、上方に流れていく熱(暖かさ)の波を伴っています、この波が私たちの頭に浸透し、そこで私たちが言葉に思考を伴わせるように働きかけるのです。そのため、私たちが話すとき、私たちは三重のものと関わっています、つまり空気、熱、水あるいは液体と。人間が話すときに活動し生きているものの全体像をはじめて与えるこの経過が、エフェソスの秘儀入門者の場合、最初の時点で取り入れられたのです。次いで彼に明らかになったことは、このとき人間のなかで起こっている経過は、もっと古いある時代に地球そのものに働きかけた宇宙的出来事が人間化されたものである、ということでした、ただしそのとき地球においてこのようにうねり動いていたのは、空気エレメントではなく、水、液体的エレメント(図の左部分、青/blau)、昨日私が揮発的ー流動的卵白としてお話ししたあの液体状エレメントだったのですが。人間が話すとき、そのとき人間のなかに呼気のかたちで小規模に空気があるように、ちょうどそのように、かつては、大気として地球を取り巻く揮発的ー液体的卵白があったのです。ここで空気状のものが熱エレメントに移行していくように、これはさらに一種の空気エレメントに移行していき(左、明るい青)、そして下の方で一種の土状エレメントに移行していきました(明色)。その結果、私たちの場合には私たちの体のなかで液体エレメントを通じて感情が生まれるように、地球においては地球形成、地球の諸力、地球において力として作用し湧き起こるものすべてが生じたのです。そして空気エレメントの上方には、地球的なもののなかで創造しつつ働きかける、活動する宇宙的思考であるものが生まれました。かつてマクロコスモス的にあったもののミクロコスモス的な余韻が自らの言葉のなかに生きていることに注意を導かれたとき、人間がエフェソスにおいて得たものは、荘厳な、圧倒的な印象でした。そしてエフェソスの秘儀入門者は、話すことで、その話すという体験のなか、宇宙言語の作用への洞察を感じたのです、かつて意味深く揮発的ー液体的エレメントを動かし、上では創造する宇宙思考に、下では生まれ出る地球諸力に接していた宇宙言語の。このように入門者は、話すと言うことを正しく理解するということを学んで、宇宙的なものに精通するようになりました。つまりこういうことが学ばれたのです、お前のなかには人間ロゴス(der menschliche Logos)がある。「人間ロゴスは、お前が地球紀を過ごす間、お前から作用する、人間としてのお前は人間ロゴスなのだ」。と申しますのも、実際のところ、液体エレメントのなかで下へと流れ出すものを通じて、人間としての私たちは言語から形成されるのですから。上へと流れ出すものを通じては、私たちはこの地球紀の間は私たちの人間としての思考を持ちます。しかしお前のうちでもっとも人間的なものがミクロコスモス的ロゴスであるように、ちょうどそのように、かつてロゴスが原初にあった、ロゴスは神のもとにあり、自身が神であったのだと。こういうことがエフェソスでは、人間を通じ人間そのものにおいて理解されたために、徹底的に理解されました。よろしいですか、今皆さんが、ギルガメッシュという名前の背後に隠れているような人物をごらんになるなら、皆さんはこのような感情をお持ちになるにちがいありません、この人物は秘儀から放射されたまったき境遇、まったき環境のなかで生きたのだ、と。と申しますのも、以前の時代においては、すべての文化、すべての文明は、秘儀からの放射だったからです。そして私が皆さんにギルガメッシュの名を挙げるなら、彼はまだ故郷のエレクにいたときはなるほどまだエレクの秘儀そのものには参入しておりませんでしたが、こうした宇宙との関係を通して感じられ得たものに実質的に貫かれた文明のさなかにいたことは確かです。その後、西に向かう旅路において彼が体験したものは、むろん彼を直接ヒベルニアの秘儀に通じさせはしませんでした、彼はそこまで行けなかったわけですが、いわばこのヒベルニアの秘儀のコロニーにおいて育まれたものには通じることができました、皆さんにお話ししましたように、このコロニーは今日で言うブルゲンラントにあったのです。このことがこのギルガメッシュの魂のなかに生きていました。このことは死と新たな誕生との間にさらに育て上げられ、今も継続し、そのために次の地上生の際、当のエフェソス(*トルコのエーゲ海地方の中央に位置する古代都市)において魂の深まり(深化)が起こったのです。今や、私が話してきましたふたりの人物のために、このような魂の深まりが起こりました。ここでいわば普遍的な文明から、これらの人物の魂に現実性をもってどよめいてきたものは、なおも強く集中的な現実性をもってどよめいてきたものは、ホメロス時代以来ギリシアにおいてはもう本質的に美しい仮象にすぎなくなったものでした。はるかなエフェソス、かつてヘラクレイトスも生き、後のギリシア時代、紀元前六世紀から五世紀頃まで古えの真実の数々がなおも感受されていたあの地、ほかならぬこのエフェソスでは、かつて人類がそのなかで生きていた現実(リアリティ)全体をまだ追感することができました、人類がまだ神的ー霊的なものと直接関わり合っていた頃、まだアジアがもっとも下位の天であった頃の現実です、このもっとも下位の天でひとはまだ、この天に接する上位の天と結びついていました、なぜならアジアにおいては自然霊たちが体験され、その上の天ではアンゲロイ、アルヒアンゲロイその他が、その上ではエクスシアイその他が体験されたからです。それでこう言うことができます、すでにギリシアにおいてさえ、かつて現実であったものを手がかりにその余韻が形成されるだけとなった。現実であったものが、根源の事実を示唆していることが明白に見て取れる英雄伝説の像へと変化していった。つまりギリシアにおいては、根源の事実の劇的要素がアイスキュロスにおいて生命を得た。他方、エフェソスにおいては、あいかわらず人は秘儀の深い闇のなかに沈潜し、人間が神的ー霊的世界と直接関わり合って生きていたかの古えの現実の余韻を感じ取っていたと。そしてギリシア精神にとって本質的なことは、ギリシア人は、人間にとってより身近な神話や人間にとってより身近な美と芸術のなかに、つまり模像のなかに、かつて宇宙との関わりのなかでまさに人間によって体験され得たものを潜ませたのだということです。さて、一方においてこのギリシア文明が今やすでにその絶頂に達し、ペルシア戦争におけるように古代アジアの現実性の側からなおも反撃しようとしたものすら誇らかに退けたとき、つまり一方でギリシア文明がその絶頂に達し、しかし他方ではすでに崩壊に瀕していたとき、かつて人間の霊、魂、体のなかの神的ー霊的な地上的現実であったものの余韻を魂のなかにはっきりと担っていた人物たちがどのような体験をしたのか、私たちは今思い描いてみなければなりません。私たちはこう思い描かざるを得ません、そもそもアレクサンダー大王とアリストテレスは、何と言っても彼らにまったく合致しない世界、本来彼らにとっては悲惨な世界に生きていたのだ、と。奇妙なことに、アレクサンダーとアリストテレスのなかに生きていたのは、霊的なものに対して彼らの環境とは別の関係を持っていた人間たちでした、彼らはサモトラケの秘儀をさして気に留めていなかったにもかかわらず、その魂においては、サモトラケの秘儀においてカベイロスとともに起こったことに多大な親和性を有していたのです。このことは長い間感じ取られていました、中世においてはまだ感じ取られていました。そしてこう言わざるを得ませんーーこのことについて今日の人間はまったくまちがって思い描いているのですがーー、中世においてはまだ、十三、十四世紀頃までは、あらゆる階級の何人かの人々には、少なくともかつて古えのオリエントでアジアと呼ばれた領域において、はっきりとして霊的観照があった、と。そして中世にある司祭によって著わされた「アレクサンダーリート」(アレクサンダーの歌)(☆2)は、何と言ってものちの中世の非常に重要な文献です。アレクサンダーとアリストテレスを通じて起こったことについて、今日歴史のなかにゆがめられて生きているものに対して、ラムプレヒト司祭が十二世紀頃にアレクサンダーリートとして著わしたものはなおも、アレクサンダー大王を通じて起こったことについての古えの把握に近しい雄大な把握のように思われます。皆さんは以下のことを魂の前に据えてくださりさえすればよいのです。ラムプレヒト司祭のアレクサンダーリートのなかには実際すばらしい叙述があります、たとえば次のようなすばらしい叙述です。毎年、春がやってくるとひとは森に出かけていき、森の縁まで行く、森の縁には花々が育ち、同時に太陽は、森の木々から影が森の縁に育つ花々の上に落ちる位置にある、そしてひとは、春に森の木々の影のなかで、花々のうてなから霊的な花の子どもたちが出てきて、森の縁で輪になって舞い踊るのを見るというような。そして、ラムプレヒト司祭のこのような叙述において、真の経験、当時の人々がまだ得ることのできた経験のいくばくかがほのかに輝いているのがはっきりと認められます。その経験は、人々が森に出かけていって、散文的に、ここに草がある、ここに花がある、ここで木が始まるなどと言うような経験ではありません、そうではなく、人々が森に近づくと、太陽が森の背後になって影が花々の上に落ちるとき、この森の影のなかで、花々から被造物である花の世界全体が彼らを迎えたのです、彼らが森に入る前からその世界は彼らのためにそこにあったのですが、森のなかで彼らはまたほかの元素霊(エレメンタルガイスト)たちも知覚しました。この花々の輪舞、これはラムプレヒト司祭にとってとりわけ描写したい好ましいものに思われたのです。そして、何と言っても重要なのは、ラムプレヒト司祭がアレクサンダー遠征を描写しようとしたとき、この描写にまだ十二世紀、十二世紀の初頭ですが、自然の描写を浸透させ、流れ込ませたことです、いたるところに元素界(エレメンタル界)の顕現を内包している自然の描写を。全体が意識によって支えられているのです、アジアへのアレクサンダー遠征が始まり、アレクサンダーがアリストテレスに教えを受けたとき、かつてマケドニアで何が起こったのかを描写しようとするなら、それを描写しようとするなら、人は周囲の散文的地球を描写することでそれを描写することはできない、散文的地球にエレメンタル存在たちの領域を付け加えてのみそれを描写することができるのだという意識に。けれどもよろしいですか、今日皆さんが歴史書を読まれるとき、今日の時代にはそれはまったく当然のことですねー。そう、そのとき皆さんはこう読むでしょう、アレクサンダーは師のアリストテレスに不従順で師の序言に逆らって、次のような使命があると思い込んだ、異邦人たち(バルバーレン)を文明化された人々と宥和させ、文明的ギリシア人つまりヘレーネン、マケドニア人、異邦人から成る平均的文化といったようなものを生じさせなければならない、と。これはなるほど今日の時代にとっては正しいことですが、真実、ほんとうの真実にとってはまさしく愚かしいことです。アレクサンダー遠征を描写するラムプレヒト司祭がこのアレクサンダー遠征にまったく別の目的を置いているのを見ると、雄大な印象が得られます。そしてあたかも、私がたった今、自然ーエレメンタル界つまり自然のなかの霊的なものが自然のなかの物質的なものに入り込んでいることとしてお話ししましたこと、このこともまさに導入部にすぎないかのように思われるのです。ラムプレヒト司祭のアレクサンダーリートにおけるアレクサンダー遠征の目的とは、いったい何なのでしょうか。アレクサンダーはパラダイスの門まで行くのです!なるほど当時のキリスト教的なものに置き換えられてはおりますが、これから詳述していきますように、これは本来かなりな程度真実に合っているのです。と申しますのも、アレクサンダーの遠征は単に侵略をするためになされたのではなく、あるいはアリストテレスの助言にそむいて異邦人をギリシア人と宥和させるためになされたわけでもないからです、そうではなくアレクサンダーの遠征は真の高い霊的な目的に貫かれていました、それは霊から発動されたのです。そして私たちがさらにラムプレヒト司祭、彼はつまりアレクサンダーの生きていた時代から十五世紀後に、非常に献身的に彼のやりかたでこのアレクサンダー遠征を描写したわけですが、彼の書物から私たちが読み取るのは、アレクサンダーはパラダイスの門まで行くけれども、パラダイスそのものには入らなかった、ということです、なぜなら、ラムプレヒト司祭の言うように、パラダイスに入ることができるのは真の謙譲(Demut)を有する人だけだからです。けれども前キリスト教時代におけるアレクサンダーはまだ真の謙譲を持つことはできませんでした。と申しますのも、キリスト教(Christentum)がはじめて真の謙譲を人類のなかにもたらすことができたからです。ともかくも、狭量な感覚ではなく、心広い感覚でこのようなことを把握するなら、キリスト教司祭ラムプレヒトが、アレクサンダー遠征の悲劇的なもののいくばくかを感じているようすが私たちに見えるのです。さて、このアレクサンダーリートの叙述によって私がただ皆さんの注意を喚起したかったのは、西洋の人類史における先行するものと後続のものを東洋に付加された状態で描写するために、まさにこのアレクサンダー遠征の例で始めても、驚く必要はないということです。と申しますのも、この場合感情として根底にあるものは、皆さんもご存じのように、中世の比較的後期に至るまで、単に普遍的な感情としてのみ存在していたのではなく、このアレクサンダーリート、皆さんに特徴をお話ししたふたつの魂を通じて起こったことを、実際真に、大いに劇的に描き出すこのアレクサンダーリートが生み出されるほどに、具体的に存在していたのです。まったくもってマケドニア史のこの時点は、一方においてはるかな過去を、他方においてはるかな未来を示唆しています。その際とりわけ考慮しなければならないのは、アリストテレスとアレクサンダーのもとにあったすべての上に、世界史上の悲劇が漂っているということです。この世界史上の悲劇はすでに外的に現われています。実際、特殊な関連によって、特殊な世界史上の運命の関連によって、アリストテレスの著作のほんのわずかな部分しかヨーロッパ西洋に伝わっておらず、その後教会によって保管されたということによって、その悲劇は露呈しているのです。実際それらは、論理学の著作と、論理学的なものをまとわされた著作のみでした。けれども今日なお、アリストテレスの自然科学的な著作に含まれているわずかなものに沈潜する人には、宇宙と人間との連関においてアリストテレスの洞察がいかになお強力なものであったかが見えるしょう。ここでひとつのことにだけ注意していただきたいと思います。私たちは今日、土状のエレメント(元素)、水状のエレメント、空気状のエレメント、火状のあるいは熱エレメントについて、そしてさらにほかのもの、エーテルについても話しますね。アリストテレスはどのように記述するでしょう。彼は地球を記述します、固体状地球(図参照、明色の核)、液体状地球、水(明るい赤)、空気(青)、全体は火に貫かれ火に取り巻かれている(深い赤)。けれどもアリストテレスにとって地球は月まで達しています。そして宇宙から、星々から、月へと。つまり、もはや地上領域のなかにではなく、月まで、ここまでなのですが、獣帯から、星々から、空間的ー宇宙的エーテル(外側の明色)が入り込んでくるのです。このエーテルは月まで下降してきます。学者たちは今日なおこのことを、アリストテレスについて書かれた書物のなかに読むことができます。けれどもアリストテレス自身が弟子のアレクサンダーに常に繰り返し言ったのは、こういうことでした。この地上的ー熱的なものの外側にあるあのエーテル、つまり光エーテル、化学エーテル、生命エーテルは、かつて地球と結びついていた。これらすべては地球まで達していた。ところが古い進化において月が退いたとき、そのときエーテルも地球から退いた。そして、アリストテレスは弟子のアレクサンダーにこう言ったのです。外的空間的に死んだ世界であるものは、このように地上で最初にエーテルに浸透されていないのだ。けれどもたとえば春が近づくと、元素霊たちは、生まれてくる存在たち、植物、動物、人間のために、月からエーテルを、月領域からまたこの存在たちのなかへともたらすのだ、それで月は形成するものなのだと。ヒベルニアにおいて一方の女性的な形姿の前に立つと、ひとはこれをまったく生き生きと感じました、エーテルは本来地球に属するものではなく、存在が生まれるのに必要な限り、年ごとに元素霊たちによって地上へともたらされるということを。アリストテレスにおいても人間と宇宙との連関についての深い洞察がありました。それについて扱われている著作を、弟子のテオフラストス(☆3)は西方にはもたらしませんでした。これらの書物のいくつかは、このような事柄への理解がまだあったオリエントへともどっていきました。そしてその後、北アフリカとスペインを経て、ユダヤ人とアラビア人を通じて、それはヨーロッパ西部へとやってきて、私がさらに述べていきたいと思いますしかたで、放射、つまりヒベルニアの秘儀からの文明放射とぶつかったのです。けれども、私が皆さんに今まで特徴づけてきましたものは、アリストテレスがアレクサンダーに与えた教えにとってはまったく出発点にすぎないものでした。これらはまったくもって内的体験に関わっていました。そして私が事態をいわばいくらかざっと素描してみますなら、次のように言わなければならないでしょう。アレクサンダーはアリストテレスを通じてよく知るようになった、外部宇宙(世界)に土、水、空気、火のエレメントとして生きているものは、人間の内部にも生きているということ、人間はこの関連で真にミクロコスモスだということ、人間のなかには、人間の骨のなかには土のエレメントが生きているということ、人間の血液循環と人間のなかで液体、生きた液体であるものすべてのなかには、水のエレメントが生きているということ、人間のなかでは空気エレメントが呼吸と呼吸刺激という状態で作用し、言葉のなかに作用しているということ、火のエレメントは思考のなかに生きているということを。アレクサンダーはまだ宇宙のエレメント(諸元素)のなかに自分が生きているのを知っていました。宇宙のエレメントのなかに生きている自分を感じることで、人はまだ地球との密接な親和性をも感じたのです。今日人間は、東へ、西へ、北へ、南へと旅行しますが、彼はそこでそもそも自分に押し寄せてくるすべてが何なのかを感じることはありません、彼は外的な感覚が知覚するものしか見ないからです、彼は地上的な物質は彼のなかで知覚するもののみを見て、エレメントが彼のなかで知覚するものを見ないからです。けれどもアリストテレスは、アレクサンダーに教えることができました。地上を東へ向かえば、あなたはますますいっそうあなたを乾燥させるエレメントのなかへと入っていくでしょう、あなたは乾いたもののなかに入っていくのですと(図参照)。このことを、アジアへと向かうと、人はまったく干からびてしまうなどと想像なさってはいけません。これらが精妙な作用であることはもちろんです。これらの作用をアリストテレスの導きによってアレクサンダーが自らのうちに受け取ったのです。アレクサンダーはマケドニアで自らにこう言うことができました。私のなかにはある程度湿ったものがある、私が東へ向かうと、それは湿ったものを減少させると。このように彼は、地上を遍歴しながら地球の構成を感じたのです、ちょうどそうですね、ある人の体のどこかある部分を撫でていくと。鼻と目と口がどう違うのか感じられるように。描写されたこの人物はこのように、乾いたもののなかにますますいっそう入り込んでいくときに体験することと、もう一方へつまり西へ、湿ったもののなかに入り込んでいくときに体験することにはどういう違いがあるかを、なおも感じ取っていたのです。おおざっぱにではあっても、今日なお人々はまた別の違いを体験しています。北へ向かって人々は冷たさを南に向かっては熱、火的なものを体験しますね。けれども北西へと出かけていっても、あの湿ー冷の共演を人々はもはや感じないのです。アリストテレスはアレクサンダーのなかに、ギルガメッシュが西への道を辿ったときに体験したものを喚起しました。そしてその帰結として、弟子は直接的な内的体験において、今やまさに湿と冷の間の中間地帯で北西に向かって体験されるもの、つまり水を知覚することができるようになりました。それでアレクサンダーのような人間にとって、北西へと進軍すると言わずに、水のエレメントが統治しているところへと進軍すると言ったのは、まったくもって単に可能な言い方ではなく、非常に現実的な言い方だったわけです。湿と暖の間の中間地帯には、空気が統治しているエレメントがありました。古代ギリシアの大地の秘儀で教えられたこと、古えのサモトラケの秘儀(☆4)で教えられたこと、アリストテレスによって直弟子に教えられたことはそのようなことでした。そして、冷と乾の中間地帯、つまりマケドニアからシベリアへの方向では、地そのもの、地上的なものが統治していた地球領域が体験されました、地(土)のエレメント、固体的なものです。暖と乾の中間地帯、つまりインドに向かっては、火のエレメントが支配的であったあの地球領域が体験されました。それはこういう具合でした、アリストテレスの弟子は北西を指して、私はそこで水の霊たちが地上へと働きかけているのを感じると言ったのです。また彼は南西を指して、ここでは空気の霊たちを感じると言いました。彼は北東を指して、そしてそこで主として地(土)の霊たちが漂ってくるのを見ました。彼は南東、インドの方向を指して、火の霊たちが漂ってくるのをあるいは火のエレメントのなかに見たのです。さて最後に私が、アレクサンダーのなかにこういう言い方が生じた、と申しましたら、皆さんも自然のものと道徳的なものに対するあの深い親和性をお感じになるでしょう、つまり、私は冷たく湿ったエレメントから火へと突入しなければならない、インドへの進軍を行なわなければならないというアレクサンダーの言い方です。これは、道徳的なものと同様、自然のものにも結びついている言い方です、これについては明日さらにお話ししてきたいと思います。私は当時生きていたものがありありと見えるように皆さんをそのなかに導き入れたいと思いました。と申しますのも、当時アレクサンダーとアリストテレスの間で話されたことのなかに、皆さんは同時に世界史上の進化における激変そのものが反映しているのをごらんになるでしょうから。当時においてはなお、過ぎ去った時代の大秘儀について内輪の授業で語られることもありました。その後人類は論理的なもの、抽象的なもの、カテゴリーのみをいっそう取り入れ、そのほかのものは突き返すようになりました。したがって、このことをもって同時に私たちは、人類の世界史上の進化における途方もない激変を示唆するのです、オリエントとの関係におけるヨーロッパ文明の全経過のなかでもっとも重要な時点を。これについてはまた明日にいたしましょう。参照画:Alexander's coffinインド神話に登場するスカンダ神は、戦争と勇気の神であり、仏教では「韋駄天」としても知られています。スカンダ神は、アレクサンダー大王の名前から派生したとされることがあります。一時期、アレクサンダー大王がスカンダ神のモデルになったという伝説が広まりましたが、これは歴史的な証拠に基づいていないものです。スカンダ神はアレクサンドロス(イスカンダル)が元になったという説があります。このスカンダは後に仏教へ取り込まれ「韋駄天*私的には毘沙門天。」となっていますので、この説が正しいのなら形を変えて日本にまで到達しているとも言えますが、如何なものでしょう。□編註☆1 ヒベルニアの秘儀:シュタイナーはすでにこの直前、1923年12月7、8、9日にこれについて詳しく述べている(『秘儀の形成』GA232 *邦訳『秘儀の歴史』西川隆範訳、国書刊行会)。両方の描写を比較すると、同じ事柄についてのふたつの両立しない説明なのかどうかという問題に通じる。『秘儀の形成』に記述されている経過ーー太陽像の作用による冬のイマジネーションの体験、月像の作用による夏のイマジネーションの体験ーーは、この12月27日の説明、つまり月像に直面して冬のイメージが、太陽像の前で夏のイメージが出現する、という説明によって解消されるように思われる。けれどもふたつの描写を厳密に比較すると、ふたつの異なる体験の局面があることがわかる。当面の講義では、ふたつの立像に直面しての体験で、入門者は立像を通して自らを太陽存在あるいは月存在として知るようになるのだが、それに対して12月8日の講義では、特定の像の前での体験、外から近づいてくる太陽及び月の宇宙作用を入門者に開示する体験の、徐々に生じてくる余韻を扱っている。ーー詳細は『ルドルフ・シュタイナー全集に寄せる論文集』Nr.69☆2 『アレクサンダーリート』:フランケンの聖職者、司祭ラムプレヒトにより1125年頃に著わされた。ドイツ語の最初の世界的叙事詩。花のエピソードについては、母及びアリストテレス宛のアレクサンダーの手紙(5001ー5205節)を参照のこと。☆3 テオフラストス:紀元前390ー305(*) アリストテレスの弟子、アリストテレスは彼をアテネのペリパトス学派の指導者として後継者に任命した。(*紀元前372頃ー286頃とも)☆4 ギリシアの大地の秘儀[…]サモトラケの秘儀:1923年12月4日と21日の講義参照のこと。『秘儀の形成』(GA232)所収。画像参照:宇宙のエレメントのなかに生きている自分(第4講・了)人気ブログランキングへ
2024年05月13日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 (GA233)翻訳紹介:yucca第3講 1923/12/26 ドルナハ ちょうど十三年前のこの日、私はシュトゥットガルトにおきまして、やはりクリスマスから新年にかけて連続講義を行ない(☆1)、今回と共通するところのあるテーマについてお話ししました。ただ、当時のテーマに沿って定められていた観点を、今回は少しばかり変えていかなくてはならないでしょう。私たちの取り組みは、二回の導入的な講義で、歴史上の、とりわけ先史時代の進化が経過していくなかで、人類の心情および魂の状態が根本的に変化したということについての理解を私たちの魂にもたらすことでした。今回は、少なくともさしあたっては数千年以上前にさかのぼる必要はありません。皆さんもご存じのように、地球を襲ったいわゆるアトランティスの大災害以後、歴史的なものおよび有史以前のものにとって生じるきわめて重要な関係だと私たちが精神科学的に見なすものは、通常地球が氷結していく時代、初期氷河期と呼ばれるものです。けれども当時はまだ、今日大西洋の海底を形成しているアトランティス大陸の沈没の最終段階が進行中でした。そしてこのアトランティスの大災害ののち現代に至るまで、これについてはしばしば注意を促してまいりましたが、五つの大文化期が相次いで(☆2)起こりました、これらのうち最初のいくつかの文化期については、歴史的伝承はまったく残されていませんが。と申しますのも、あちらのオリエントにおいて文献に含まれているものは壮大なヴェーダや深遠なヴェーダンタ哲学においてさえ、常に原インド文化期、原ペルシア文化期として「神秘学概論」のなかでも話題にしましたあの文化期を示そうとするとき描写しなければならないものの余韻にすぎないからです。さて、今日はその時代まで遡ることはせずに、ギリシア文化期の前の、私がしばしばカルデア・エジプト文化期と呼んできました時代に目を向けてみることにしましょう。私たちが注意を払わなければならないのは、アトランティスの大災害とギリシア時代の間のこの時代において、記憶の能力、人間の記憶力に関連して、そして人間の共同生活に関連して、大きな変化が起こった、ということです。私たちが今日持っているような記憶、この記憶により私たちは時間をさかのぼって何かを現実化することができるのですが、このような時間記憶(Zeitgedaechtnis)というものは、この後アトランティス第三文化期にはまだ存在しておらず、当時あったのは、私が描写しましたようなリズム体験に結びついた記憶でした。そしてこの記憶は、アトランティス時代にとくに強く存在していた場所化された記憶から生じてきたものです、当時人間はそもそも現在意識しか持っておらず、人間が外界において見つけるか自分で建てるかした可能な限りのものを目印とし、この目印を通して人間は、単に自分自身の人格の過去のみならず、人類一般の過去とも関係を結んでいたのです。けれども、単に直接地面にしつらえられたものだけが目印だったわけではありません、かなり古い時代においては天の星位、とりわけ諸惑星の星位もまた目印であり、この繰り返され、変化をともなって繰り返される星位から、人々は前の時代がどうであったかを知りました。ですからもともと古代人類の外的な場所化された記憶の育成にとっては、天と地が共に作用していたのです。けれどもこの古代人類は、そのまったき人間としての組み立てにおいても、後の人類とは異なっており、この現代の人類とはなおさら異なっていました。現代の人類は、目覚めているとき自我とアストラル体を自分の物質体のなかにそれと気づかず担っていて、ほとんどの人はそもそも、その人自身よりずっと意味深い有機組織(Organisation)であるこの物質体が、エーテル体とならびアストラル体と自我組織を自らのうちに担っていることに気づいていないのです。皆さんはこの関係をご存じですね。けれども古代人類は、自身の存在という事実をまったく別様に感じていました。さて私たちが先の後(ポスト)アトランティス第三文化期、つまりエジプト・カルデア文化期へと遡っていきますと、私たちはそのような人類にまで戻っていきます。その頃人間は、目覚めているときでさえ、まだ物質体的なものエーテル体的なものの外部で、高度に霊と魂として自らを体験していました。人間はこう区別することを知っていました、私はこれを、私の霊及び私の魂として、私たちはこれを自我とアストラル体とを有し、これは私の物質体および私のエーテル体と結びついていると。人間はこういう二重の状態(Zweiheit)で世界を歩いていました。人間は自分の物質体とエーテル体を私(自我、イッヒ/Ich)とは呼びませんでした、人間はまずもって自分の霊と魂のみを私(自我)と呼んだのです。霊的であり、下に向かって物質体およびエーテル体とある種のしかたで、しかし当人も関知している関係を結んでいたもののみを。そして人間は、この霊ー魂的なもの、この自我とアストラル体のなかに、神的ー霊的ヒエラルキアが押し入って来るのを感じていました、ちょうど今日の人間が自然の物質が自分の物質体のなかに押し入ってくるのを感じるように。人間はこの物質体のなかではこう感じますね、食物とともに、呼吸とともに、自分は外部の自然界の物質を取り入れているのがわかる、と。外界の物質ははじめは外にあって、それから人間の内部に入ります。これらの物質は人間に浸透し、人間の一部になる、という具合に作用するのです。当時人間は、自分の霊的ー魂的なものが物質体的ーエーテル体的なものからの若干分離していることを感じていましたが、次のようなことを知っていました、つまりアンゲロイ、アルヒアンゲロイから最高のヒエラルキアに至るまでの存在たちは、霊的にして物質(実質)的なもの(Geistig-Substantielles)であり、今や人間の霊的ー魂的なものを通じて浸透しているこの霊的にして物質的なものが、こういう表現をしてよろしければ、人間の一部となる、ということを知っていたのです。ですから人間は、生のどの瞬間にも、私のなかには神々が生きていると言うことができたのです。人間は自分の自我を、物質的、エーテル的実質によって下から組み立てられたものと解していたのではありません、そうではなく、人間は自我を、恩寵によって自分に贈られたもの、上から、ヒエラルキアの側からやってくるものとして把握していたのです。そして、人間は自分の物質的ーエーテル的なものを、いわば荷物のように、乗り物のように、物質的世界で前進するために使う人生の車に似た何かのように把握していました。このことをふさわしいしかたで魂の目のなかにとらえなければ、人類進化の歴史上の経緯などはそもそも理解できません。さて、私たちはさまざまな特徴ある例を手がかりに、人類進化のこの歴史上の経緯を追求していくことができるでしょう。今日はいわば私たちの前に一筋の糸を置いてみたいと思います、十三年前の当時にも、私は、これからお話ししようとするあの進化の最古の段階を示しているあの歴史的ー伝説的文献(☆3)、つまりギルガメッシュ叙事詩「Gilgamesch-Epos」を引合に出すことでこの糸に触れたわけです。このギルガメッシュ叙事詩はまさに一部が伝説的なのですが、申しましたように十三年前にお話ししましたこの経過を、今日はそれが霊的な観照から直接生じてくるようにお話ししていきたいと思います。当時、西南アジア(近東)のある都市に、ギルガメッシュ叙事詩ではエレク/Erek☆4)と呼ばれていますが、昨日お話ししましたような、あの侵略者的性質の人々のひとりが見られました、昨日特徴づけされたあの魂状態と人間社会の状態からまさしく育ってきたあの性質の人々のひとりです。叙事詩はこれをギルガメッシュと呼んでいます。つまりここで私たちが関わり合うのは、今話題となっている時代において、ちょうど私が特徴づけたような性質を持っていた人物、それより前の時代からの古い人類の特性をまだ多く保っていた人物です。けれども当時このような人物は、自分がいわば二重の存在(Doppelheit)であること、つまり、神々が入り込んでくる霊的ー魂的なものと、地球物質および宇宙物質つまり物質的実質とエーテル的実質が入り込んでくる物質的ーエーテル的なものとの間で二面性を持っているということをはっきりと理解していました、そしてまた、このギルガメッシュ叙事詩が語る人物が生きていた時代において、まさに特徴的な人々、代表的な人々がすでにその後の人類進化への過渡期(移行期)にあったということもひとつの事実です。そしてこの移行というのは、比較的その直前の時代には霊的ー魂的なもののもとで上の方にあった自我意識(Ich-Bewusstsein)が、こういう表現をしてよろしいなら、体的ーエーテル的なもののなかに沈みこんでいったということなのですが、その結果、ギルガメッシュはまさしく、内部で神々を感じることのできる霊的ー魂的なものに対して私(Ich)と言うのではなく、地上的ーエーテル的なものに対して私と言い始めた人々のなかにあったのです。それがこの新たな魂状態でした。私たちが話題にすることのできるこの魂状態のなかへと、霊的ー魂的なものから自我が下降しました、体的ーエーテル的なもののなかへと、自我は意識的自我として(als bewusstes Ich)下降したわけですが、この人物においては同時にまだあの古い習慣が、主としてリズムのなかで体験されたもののみを記憶のように体験するというあの習慣が残っていましたし、人間を思慮深さへと導くものを生み出すのは本来死の力だけなので、死の力に精通しなければならない、と感じていたあの感受性もありました。今、このギルガメッシュという人物において私たちが関わるのは、ある魂、つまり当時すでに数多くの受肉を経てきたけれども、私がたった今描写しましたような人間存在の新たな形式のなかに歩み入っていた魂、そういう魂なのですが、それによって、この人物は、物質的生存において、ある種の不確実さを自らのうちに担うことになったと申し上げたいのです。いわば侵略という習慣やリズム的記憶の根拠は、もはや地上にとって有効なものではなくなってきました。このように、この人物の体験はまったくもって過渡期の体験であったわけです。そのため次のようなことが起こりました、この人物が古来の習慣から、ギルガメッシュ叙事詩でまさしくエレクと呼ばれているあの都市を侵略によって占領したとき、この都市に紛争が生じたのです。最初この人物はこの都市で歓迎されず、よそ者と見なされました、都市で生じていた困難のすべてをひとりではうまく処理できなかったためもあるのでしょう。ここで運命によってここに導かれたもうひとりの人物、ギルガメッシュ叙事詩ではエアバニ(Eabani☆5)と呼ばれているのが見い出されます、私が「神秘学概論」に記述しました意味での、地球人類が一定期間過ごしたあの惑星生存状態から、比較的遅くなってから地上に降りてきた人物です。皆さんもよくご存じのとおり、地球進化の非常に早い時期に宇宙のさまざまな惑星へと地球から退いていた魂たちが、アトランティス時代に、あるものは早く、あるものは遅く、相次いで地球に降(くだ)ってきたのです。ギルガメッシュにおいて私たちが関わっているのは、比較的早く地球にもどってきた個体で、私がお話ししている時代には多くの受肉を体験していました。やはりあの都市に導かれたもうひとりの人物において私たちが関わるのは、惑星生存状態に比較的長い間とどまり、遅くなってからやっとまた地球に赴いた、そのような個体です。十三年前に精神科学(霊学)の立場から歴史について行なわれた私の連続講義においては、このことはいくらか異なった観点から読まれなければなりませんでしたけれども。さてこの人物は、ギルガメッシュと親密な友情を結び、それからふたりは共同して、小アジアの都市エレクに真に堅固な社会状態を作り出すことができました。このことが可能だったのはとりわけ次のようなことによります、つまり、この第二の人物が、あまり地球への受肉をしないことにより、地球外の宇宙での滞在で維持されてきたあの智のうち比較的多くを残していたからです。すでに前回シュトゥットガルトでも申しましたように、この人物には、一種の透視(霊視/Hellsichtigkeit)、霊聴(Hellhoerigkeit)、光明を得た明澄な認識(Hell-Erkenntnis)がありました。そして、一方の人物のなかに存在していた古来の侵略習慣とリズム志向の記憶に由来するものと、もうひとりの人物の宇宙の秘密を見透す能力、この両者が合流することから、もう少し古い時代にはたいていそうであったように、西南アジアのあの都市に社会秩序が確立されていったのです。この都市には平和が訪れ、住民の幸福が訪れました、そして事実の経過全体を別の方向に導いたある特定の出来事が再び起こらなかったら、まずすべては秩序を保っていたことでしょう。あの都市には、ある種の秘儀が、ある女神の秘儀がありました、そしてこの秘儀は非常に多くの宇宙の秘密を保持していました。それは当時の意味において一種の綜合的な秘儀(synthetische Mysterium)とでも申し上げたいものであり、すなわち、当時この秘儀のなかにアジアのきわめてさまざまな秘儀の啓示が集められていたのです。そしてさまざまな時代に、秘儀の内容は変更され、変容させられて、その地で保存され教えられました。叙事詩においてギルガメッシュという名を持つ人物は最初このことを理解できず、この秘儀の地を、矛盾だらけのことを教えていると非難しました。それで、権威ある筋から、私がお話ししているこのふたりの人物は、何と言っても都市全体に秩序を与え管理した人物だったからですが、つまり意味深い立場から秘儀が非難されたことによって、諸々の困難が生じ、これは結局、古代の秘儀において伺いを立てることのできたあの権威に、秘儀の祭司たちが伺いを立てる、という事態に通じていきました。古えの秘儀においては、高次ヒエラルキアの霊的存在たちに伺いを立てることが実際に可能だったのだということを、今日は皆さんも、いぶかしく思われることはないでしょう、昨日皆さんに申しましたように、古えのオリエントの時代にあっては、アジアは本来最も下位の天であり、この最も下位の天においても、人々は神的ー霊的存在たちの実在を知り、これらの存在と交渉を持っていたからです。とりわけ秘儀のなかでこういう交渉は続けられました。こうしてイシュタル秘儀の祭司職が、啓示(光明/Erleuchtung)を得ようとするときふだん常に伺いを立てていたあの霊的な威力に伺いを立て、その結果、この霊的威力が都市に対して一種の刑罰を科するという状況になったのです。当時このことは、本来は高き霊的な力であるものが、エレクにおいて動物的な暴力として、不気味な動物的力として働きかけたと言うことで表現されました。ありとあらゆるものが住民たちにやってきました、肉体的な病気、とりわけ魂の錯乱が。そして、ギルガメッシュの味方となった人物、叙事詩でエアバニと呼ばれている人物が、これらの困難のために死んでしまうという結果になるのですが、彼は、もうひとりの人物ギルガメッシュの地上での使命を継続するために、死後も霊的にこの人物のそばにとどまりました。つまり私たちは、叙事詩においてギルガメッシュという名を担っているあの人物のその後の人生、その後の進化を、ふたりの特徴ある人物の間の共同はさらに続いたというように理解しなくてはなりません、エアバニの側からギルガメッシュに霊感(Eingebungen)、啓示が与えられるということが起こったのです。すなわち、ギルガメッシュは、彼自身の意志のみでひとり行為し続けたのではなく、ふたりの意志から、ふたりの意志の合流から行為し続けたのです。このことをもって私は、この古えの時代にあってまったくもってひとつの可能性であった何かを再度皆さんの前に据えたわけです。あの古えの時代、人間の心情は今日のそれのように一義的なものではありませんでした。したがって、感覚においても今日のような自由の体験というものは存在し得なかったのです。当時できたことは、一度も地上に受肉したことのない霊的存在が地上のある人物の意志を通じて働きかけるか、あるいは、ちょうどこのギルガメッシュの場合のように、すでに死を通過して死後の生(Postmorten-Leben)を送っている人物が地上の人物の意志を通じて話したり行為したりするか、いずれかでした。そしてギルガメッシュの場合もそうでした。こうしてふたりの意志の合流から生まれたものから、ギルガメッシュのなかに、彼が本来どのような歴史的状態にあるのかということについてのかなりはっきりとした認識が浮かび上がってきました。ギルガメッシュは、まさにインスピレーションをもたらしてくれる霊の影響によって、自我が死すべき物質体とエーテル体のなかに下降してきたということを知り始め、そしてギルガメッシュにとって、不死の問題が強く集中的な役割を演ずるようになってきました。ギルガメッシュの憧れのすべては、どうにかしてこの不死の問題の背後に至ろうとすることに向けられました。当時地上での不死について語るべきことを保管していた秘儀は、当初ギルガメッシュには明かされませんでした。これらの秘儀は、まだ伝統と、この伝統から現存する生きた認識の大部分を有していましたが、一方地上では古アトランティス時代の太古の叡智が有力でした。けれども、かつて霊的存在として地上を歩き回っていたこの太古の叡智の担い手たちは、とっくに退き、月の宇宙的コロニーを建設していました。月は今日の科学が描写するような硬い凍結した物体だなどと考えるのは、子どもじみています。月は、とりわけ地球人類の最初の偉大な教師たちであったあの霊的存在たちの宇宙での滞在地でした、かつて地球人類に太古の叡智をもたらし、物理的天体としての月が地球を去って太陽系内に自らの位置を獲得した直後に、この月へと引き揚げていったあの存在たちの滞在地です。今日、イマジネーション的認識を通じて、真に月を知る能力を持つひとは、この宇宙のコロニーのなかに、かつて地上で人類の太古の叡智の教師であったあの霊的存在たちをも知るようになります。これらの存在たちがかつて教えていたこと、そして人が自らこの太古の叡智とある種の関わりを持つことを可能にするあの衝動をも、この秘儀に保管されていました。とは言え、たとえば西南アジアのこの秘儀と、叙事詩の中でギルガメッシュと呼ばれている人物との間では、正しい結びつきはありませんでした。けれども、死後の状態でギルガメッシュとひとつになった友人の超感覚的な影響を通じて、ギルガメッシュのうちに内的な衝動が目覚めました、魂の不死性について何らかのことを経験できるようになる道を、世界のなかに探し求めようとする衝動です。中世には、霊的世界について何かを体験したいと思えば、人間の内面に沈潜するということが一般的になってきました。近代においては、さらに内的な経過が普通になっていると言ってよろしいでしょう。けれども、今お話ししているあの古えの時代においては、地球は、今日の地質学が記述しているようなあんな岩石の塊ではなく、生き生きと魂を吹き込まれた霊的な存在物なのだ、ということを人々はまったく正確に知っていました。そして、ちょうど小さな生き物が人間の上を走り回るとき、その生き物が鼻や額の上、髪の毛を伝わって走り、この旅によって知識を獲得することで人間のことを知ることができるのと同じように、当時においては、人間は地球(大地)の上をあちこと歩き回ることで、さまざまな場所でさまざまな土地の成り立ちから地球(大地)を知り、それを通じて霊的世界を洞察していたのです。人間は霊的世界を洞察していました、秘儀への接近が許されているにせよいないにせよ、洞察していたのです。ですから、ピュタゴラスや同様の人たちについて、彼らが認識の獲得のために大いに遍歴したと語られる(☆6)のは、実際どうでもよいことではありません。この地球のさまざまな場所の、霊的ー魂的ー物質的地球のさまざまな形成のされ方から観察されうるものを、地球の成り立ちの多様性のままに受け取るために、人間は地を巡回したのです。今日、人間はアフリカやオーストラリアに旅行することができますが、見物の対象となる表面的なものを除いては、家にいて体験することに比べてさほど変わった体験をするわけではありません。と申しますのは、地球のさまざまな場所の間に存在する根本的な差異に対して、人間の感受性はまさに死に絶えてしまったからです。今お話ししている時代においては、この感受性は死んでおりませんでした。ですから、地上の遍歴を通じて不死性の問題の解明のための何かを得ようとする衝動は、ギルガメッシュにとって非常に重要な意味があったのです。こうしてギルガメッシュは、遍歴の第一歩を踏み出しました。彼にとってこの遍歴は何と言っても、とてもとても重要な結果をもたらしました。彼は、近ごろよく話題になるとは言えその社会状況は当然ながら非常に変わってしまったある地域、つまりいわゆるブルゲンラント(*1)地方で、ある古い秘儀に出会いました、ブルゲンラントをツィスライターニエンの一部とするかハンガリーの一部とするか最近議論されましたが、つまりこのブルゲンラントの地で古い秘儀に出会ったのです。この秘儀の大祭司は、ギルガメッシュ叙事詩ではクシストロス(Xisuthros ☆7、*2)と呼ばれています。ギルガメッシュは、ある古い秘儀に出会いました、古アトランティスの秘儀を純粋に受け継ぐ形式の秘儀です、ただし後の時代にはしばしばそうであったであろうように、もちろん変化してはいましたが。そして実際のところ、この秘儀の地においては、ギルガメッシュの認識力を判定し、評価するすべが知られていました。人々は彼を出迎えようとしました。当時秘儀参入の弟子たちの多くに課せられていた試練がギルガメッシュに課せられました。その試練とは、七日七晩を通じて完全に目覚めた状態で、ある種の黙想(Exerzitien)をすることでした。ギルガメッシュにはそれができませんでした。そこで彼はこのような試練の代用品(Surrogat)に屈しました。この代用品というのは、服用して実際にある種の光明(啓示/Erleuchtung)が得られる特定の物質がギルガメッシュのために調合されたということです、例外を認める一定の条件が保証されないときはこの地方ではいつもそうだったのですが、たとえこれらの物質がある意味で疑わしいものであっても、調合されたのです(*3)。こうして今やギルガメッシュにある種の光明がもたらされました、宇宙連関への、宇宙の霊的な構造へのある種の洞察が。こうして、ギルガメッシュがこの遍歴を終えて再び帰還したとき、彼のうちには実際に高次の霊的洞察があったのです。ギルガメッシュはほぼドナウ河に沿って遍歴し、ドナウ沿いを南方に向かって故郷へ、選ばれた故郷の地へと戻ってきました。けれども、彼は私が描写しました別のしかたではなく、あのいくらか問題の多いしかたでアトランティス後の秘儀への参入を授けられたために、この故郷の地に到着する前に最初の試みに屈服してしまいました、彼は都市に起こったことについて聞き、自分にふりかかった出来事についての恐ろしい怒りの発作に屈したのです。彼は都市に到着する前に、そのことを聞きました。恐ろしい怒りが沸き起こり、この湧き起こる怒りのために光明(啓示)はほとんど完全に曇らされ、彼は光明なしに到着する結果となりました。とは言っても、そしてこれがこの人物の特別なところなのですが、死んだ友人との関係を保ち、この死んだ友人とともに、この死んだ友人の霊とともに、霊的世界をのぞき見る可能性、あるいは少なくとも霊的世界についての情報を得る可能性は、ひき続き失われませんでした。それでもやはり、イニシエーションを通じて霊的世界を直接見通す、あるいは死後の状態にある人物について情報を得る、というのは、別のことなのです。けれども、不死の本質への洞察のいくばくかがギルガメッシュのなかには残されている、と言うことはできます。さて今度は、死後になし遂げられることから読みとってみます、死後に成し遂げられることというのは、当時も今も、次の受肉の意識のなかに働きかけます、まだそれほど強く働きかけるのではないのですが、意識のなかに働きかけるのです。生命のなか、内的な構成のなかへの働きかけはなるほど非常に強いのですが、意識のなかへの働きかけは強くはありません。よろしいですね、私は皆さんに、ふたりの人物を描写しました、後アトランティス第三文化期のほぼ中頃の人間の霊状態をともに表わしていて、その生き方から、人間が二つの部分から成り立っていることが強く見て取れるような、まったくもってまだそのような生き方をしていた人物たちです。と申しますのも、一方のギルガメッシュは、自我意識が下降するということ、自我が物質的ーエーテル的なもののなかに沈み込むということを成し遂げた最初の人々のひとりであったにしても、この二元性をよく意識していたからです。もうひとりの人物は、地上に受肉したことがあまりなかったために、明澄な認識(Hell-Erkenntnis)を有していて、それによって物質、素材、などというものは存在せず、すべては霊的なものであって、いわゆる物質的なものというのは、霊的なものの別の形(フォルム)にすぎない、という洞察を得ていました。皆さんはこのように思い描くことができるでしょう、人間の本質がこのように構成されていたのなら、今日考えたり感じたりしていることすべてを、当時の人間が考えたり感じたりすることができなかったのは当然だ、と。人間の思考や感情の全体がまったく違っていたのです。そしてこのような人物たちに近づくことのできたものは、今日私たちが学校で学ぶようなことではなく、今日の小学校や高等学校で学ぶことに似た何かでもありません、霊的、文化的、文明的に人間たちに近づいてきたものは、実に秘儀から流れ出してきて、何らかのしかたであらゆる通路をとおってきわめて広汎に人々に告げられたのです。けれども本来それを育成するのは、秘儀の祭司である賢人たちでした。さて私がお話ししている人物ふたりに独特なことは、私がたった今描写しましたあの受肉において、独自の魂の性質により、秘儀に、つまりまさに彼らの周囲にあった秘儀と親密になることができなかったということです。ギルガメッシュ叙事詩でエアバニと呼ばれている者は、地球外に滞在していたことによって秘儀に親しんでいました。ギルガメッシュと呼ばれている者は、あるアトランティス後の秘儀において、一種のイニシエーションを体験しましたが、これは彼にその果実を半分しかもたらしませんでした。けれどもこのすべてが作用を及ぼして、これらの人物自身の存在のなかで、彼らを人間の先史時代に似せる何かが感じられるようになりました。ふたりはこう話し合ったことでしょ。我々はいったいどうなったのか。地球進化にともない我々はふたりでいったい何をしてきたのか。我々はまさに地球進化を通じてこうなったのだ。我々はその時いったい何をしたのか。ギルガメッシュが悩み、格闘した不死の問題、これは当時まさに人間の魂のなかにあったものを通じて、地上の先史時代の進化について欠くことのできない洞察と関わっていました。そして、地球の最古の進化段階、月状態、太陽状態云々の時期にすでにそこにいた人間の魂が、その後地上的になったものが自分に近づいてくるのをどのように見たかということについてのい洞察が同時になかったら、そもそも当時の感覚では、魂の不死について、考えたり感じたりすることはできませんでした。人は、自分は地球の一部である、自分自身を認識するためには自分と地球との関係を見通さなければならないと感じていました。参考画:gilgamesh さて、あらゆるアジアの秘儀のなかで培われていた秘密というのは、何をおいても宇宙的な秘儀であり、宇宙との関係のなかでの地球進化の経過をその教義と叡智の内容としていました。それはこれらの秘儀にまったく生き生きとしたしかたで現われ、人間のなかで理念となることができました、地球がどのように進化してきたか、そして物質の波とうねり、地球の諸力のなかで人間がいかにこれらの物質すべてとともに、太陽紀、月紀、地球紀を通じて進化してきたか、この概観が人間の前にもたらされました。この光景がきわめて生き生きと見せられたのです。このような光景を人間に見せていた秘儀のひとつは、非常に後の時代まで維持されていました。それがエフェソス(エペソ)の秘儀の地(☆8)、エフェソスのアルテミスの秘儀の地です。このエフェソスの秘儀の地、それは、その中心に女神アルテミスの像を持つものでした。今日誰かがエフェソスのアルテミス女神の模造品を眺めても、乳房を露出した女性の姿というグロテスクな印象を持つだけでしょう、こういうことが古えの時代にはどのように体験されていたのか見当もつかないからです。古えの時代にはまさにこういうものを体験するということが重要だったのです。秘儀の入門者たちは準備を終え、それから秘儀の本来の中心に導かれました。このアルテミス像がこのエフェソスの秘儀の中心でした。入門者たちがこの中心に導かれると、彼らはこの像とひとつになりました。この像の前に立つと、人間はその皮膚の内部の何かであるという意識が中断されました。人間は、自分はこの像であるという意識を持ちました。彼はこの像と一体化したのです。そして、このようにエフェソスの神々と意識のなかで一体化することは、こういう作用を及ぼしました、つまり、人はもはや周囲の地球領域、石や木々や河や雲などを見ることはなく、アルテミスの像のなかに入り込んでいると感じることで、自分とエーテル界との関係を内的に観照するに至ったのです。人は自分が星々の世界と、星々の世界の出来事とひとつであると感じました。人は人間の皮膚の内部の地上的な物質性を感じず、自らの宇宙的存在を感じました。エーテル的なもののなかに自らを感じたのです。そしてこのエーテル的なものなのかで自らを感じることを通じて、人間の以前の地上生活の状態、そしてその地上生活そのものが、その人に明かされました。今日私たちは、地球を、すでに話しましたように、一種の岩の塊のように見ています、その表面の大部分を水に覆われ、酸素や窒素その他の物質が含まれ、とりわけ人間が呼吸のために必要としたりなどする物質が含まれる大気圏に囲まれた岩塊のように。そして今日、人間が通常の自然認識なるもののなかで思弁を繰り返し、観察し、観察を解釈するということを始めると、何か正しいことが明らかになるいうわけです。今日の状態に先行するもっとも古い時代におけるものというのは、霊視(Geistesschau)によってしか獲得することができません。けれども地球と人類の太古の状態(☆9)に関するこのような霊視が、エフェソスの秘儀の入門者たちには明かされました、彼らが神々の像と一体化したときにです。そのとき彼らは、今日地球の周囲の大気圏であるものがかつては現在のようではなく、今日の大気圏があるこの地球の周囲に存在していたものは、きわめて精妙な、流動性ー揮発性の(fluessig-fluechtig)卵白(蛋白質/Eiweiss)、卵白実質(Eiweisssubstanz)であったことを知りました。すなわち、地上に生きていたすべてが生じるために、すべてのものはこの地球の上を流動し揮発していた卵白の力を必要としていましたし、その中で生きていたのです。そしてさらに観照されたことは、この卵白の中にある意味ですでにあったもの、細かく分散された、けれどもいたるところで結晶化しようとする(図参照、赤系)傾向を持つもの、つまり細かく分散された状態で珪酸としてそこにあったものが、地球の一種の感覚器官であったことです、宇宙のいたるところからの影響を、イマジネーションを自らのうちに受け入れる感覚器官です。このように、地上的ー卵白状大気の珪酸の内容物のなかには、いたるところに、真の、外的なありようのイマジネーションがあったのです。このイマジネーションは、巨大な植物有機体の形(フォルム)をとっていて、そしてこの、自らを地上的ものにとってのイマジネーションと考えたものから、植物のようなものが発達してきました、のちに大気状の物質を受け入れることによって植物となるのですが、最初はまだ地球の周囲の揮発性ー流動性のフォルムをとっています。それはあとになってから地面へと下降してきて、のちの植物類となりました。さらに珪酸含有物の外部には、このアルブミン大気の中へと、細かく分散された石灰的なもの(Kalkiges)が埋め込まれていました。石灰的なものからは、この卵白の凝固の影響を受けながら、動物的なものが発生しました。そして人間は、これら全ての内部に自らを感じていました。人間は、自分が太古の時代には全地球とひとつであったと感じました。人間は、イマジネーションを通じて地球で植物として形成されたもののなかに生きていました、人間は、地上的なもののなかに動物として形成されたもののなかに生きていました、これは私が今しがた描写しましたとおりです。根本においてどの人間も自分を、地球全体に拡がっている、地球とひとつである、と感じていたのです。ですから人間たちは、私が『「神秘的事実としてのキリスト教」という著書で、人間の理念能力に関連してプラトンの教義のために叙述しましたように、互いのなかに組合わさっていたのです。さてよろしいですか、私がシュトゥットガルトで語り、今もまた話題にしておりますあのふたりの人物は、運命の導きで、エフェソスの秘儀に所属する者としてふたたび受肉し、私がこれまで概略をお話ししてきたことを親しく魂のなかに受け入れました。それによって彼らの魂的なものが、ある種のしかたで内的に強められました。以前は体験のなかで、とは言え大部分は無意識の体験でしたが、体験のなかでのみ接近したものを、ふたりは今や、秘儀を通じて受け取ったのです。つまりこのことにより、このふたりの人物における人間的なものの体験は、二つの別々の受肉に分けられたのです。これにより、彼らは自らのうちに、上方の霊的世界と人間が関連しているという強い意識を持つようになり、同時に、地上的なものすべてに対する強い、集中的な感受性を持つようになりました。と申しますのも、よろしいですか、ある人にとって二つのものがいつも入り混じって流れているとしたら、二つを切り離すことができなければ、その二つは混じり溶け合ってきます。けれども二つが明確に分けられれば、双方をもう一方に照らして判断することができるのです。それでこのふたりの人物も、生から導かれた上方の世界の霊的なものを、以前の受肉の余韻として内部に生きていたものを、一面において判断することができました。さて今や、秘儀において、女神アルテミスの影響下にあるエフェソスの秘儀において、こういうことがふたりに伝授されたわけですが、今やふたりは、地上の事物が人間の外にどのように生じたか、人間以外のものが、人間をも包含していた原初の物質的なものから、地上でどのように徐々に形成されてきたかを、判断することができるようになりました。これにより、ほかならぬこのふたりの人物の人生、一部ヘラクレイトス(☆10)がエフェソスで生きていた最後の時代に当たりますが、その後の時代に当たるこのふたりの人物の人生は、とりわけ内的に豊かな、宇宙の秘密に貫かれて内的に強く光を放つものになったのです。そしてさらに、人間はその魂生活において、単に水平的に地上に拡がっているものだけではなく、人間がその本質を上へ伸ばすときには、上に向かって拡がるものとも関連しているのだ、という強固な意識も生じました。そしてこのふたりの人物、古エジプトーカルデア時代にふたりして働きかけ、その後、ヘラクレイトスの時代と言えるかもしれませんがそれよりは少し後の時代に、エフェソスの秘儀と関わりつつ生きたふたりの人物の内的な魂形成(Seelenkonfiguration)、この共同作用は、継続し続けることができました。お互いが育て上げた魂形成、これは死を通過し、霊的世界を通過して行って、それからある地上生を準備しました、それが原因で根本的に多くのことが問題とならざるを得なかった、むろんさまざまなしかたで問題とならざるを得なかった地上生です。そして、これらふたりの人物が地球進化の歴史的経過に自らを置かざるを得なかったまさにこのやりかたを手がかりに、カルマ的に後の地上生のなかへも継続してゆく、魂の前の時代に由来する体験によって、どのようにものごとが準備されるかを見ることができます、後の時代にまったく変容して組み込まれ、地球人類進化のなかに現われるものごとが。私がこの例を引きますのは、これらふたりの人物がその後歴史上の進化のきわめて重要な時代に登場するからなのですが、この時代については前にシュトゥットガルトでも示唆いたしました。もともとこういうことすべてを十三年前にもう特定の観点から述べているのです。エジプトーカルデア時代に、はるかに拡がった宇宙生を通過したこれらふたりの人物、その後この宇宙生を内的に深め、その結果ある意味で魂を強めたこれらの人物は、のちの受肉において、アリストテレス(☆11)とアレクサンダー大王(☆12)として再び生きました。そしてアリストテレスとアレクサンダー大王の魂のなかのこの根底に注目してはじめて、私がすでにシュトゥットガルトであの歴史の章で述べましたように、ギリシア精神の退嬰のなかローマ・ロマン民族による統治の出発点にあったこれらの人物のなかで、当時あれほど問題のあるしかたで作用し、その後これらの人物を通じて作用したものがそもそもどこにあるのか、理解することができるのです。これについてはさらに明日、次の講義で引き続きお話ししたいと思います。※Gilgamesh:ギルガメッシュ叙事詩は、世界最古の文学作品の一つで、古代メソポタミアの文学作品です。この叙事詩は、ウルクの王であるギルガメッシュの冒険を描いています。彼は強大な力を持つ半神半人の英雄であり、唯一の親友であるエンキドゥと共に様々な冒険に旅立ちます。ギルガメッシュはウルクの王で、英雄である一方で暴君としても恐れられていました。彼は都の乙女たちを奪い去るなどの悪業を働いていました。ウルクの人々は神々に訴え、大地の女神アルルは粘土からエンキドゥという野獣のような猛者を造り上げました。エンキドゥはギルガメッシュと戦うために作られた存在で、物語は二人の間に芽生えた友情とともに進んでいきます.参照画:□編集者註(*はyucca による補足、主に『ギルガメシュ叙事詩』(矢島文夫訳 ちくま学芸文庫)解説を参考にしました)☆1 シュトゥットガルトにおきまして[…]:『隠れた歴史 世界史の人物と出来事についてのカルマ的関連の秘教的考察』(六回の講義、1910/11 GA126)*邦訳:『世界史の秘密』(西川隆範訳 水声社)☆2 五つの大文化期が相次いで:R・シュタイナー『神秘学概論』(GA13)参照のこと。さらに多数の講義録の叙述、たとえば『西洋の光の中の東洋。ルツィファーの子どもたちとキリストの兄弟』(九回の講義、ミュンヒェン1909 GA113)参照。*邦訳:『西洋の光の中の東洋』(西川隆範訳 創林社)☆3 あの歴史的ー伝説的文献:ギルガメッシュ叙事詩は、クジュンドゥシュクの丘、アシュルバニパル王宮の遺跡で発見された楔形文字粘土板十二枚に刻まれている。それは、断片がいくつか発見されたさらに古いシュメール語原典に遡る。*シュメール民族は、前第五ー四千年紀ごろからメソポタミア地方に居住し、高度な文明を発達させたとされるが、セム民族に征服されていった。セム人の王朝の首都はアッカドと呼ばれたので、この王朝はアッカド王朝と呼ばれ、その後北方のアッシリアと南方のバビロニアに分かれる。彼らは文化的にはるかに進んでいた先住民族のシュメール人から、きわめて多くの文明的諸要素を取り入れた。シュメールの都ウルクの遺跡には、シュメールの王名を記した表が残っているが、大洪水後のウルク第一王朝第五番目の王としてギルガメシュの名が出てくる。ギルガメッシュが登場するシュメール神話(英雄詩)は五つほど知られているが、そのうちの四つがのちにアッカド語(アッシリア語、バビロニア語)で『ギルガメシュ叙事詩』にまとめられたとされる。☆4 エレク:この都市は、聖書で(モーゼ I、10ー10)エレクと呼ばれている。楔形文字テキストではウルクと呼ばれる。*彼の王国の初めは、バベル、エレク、アッカドで、それらはみなシナルの地にあった(創世記10ー10)「彼」はメソポタミアの神話的英雄ニムロデ。「シナル」はシュメール。*「ギルガメッシュ」という名は19世紀末まで正しい読み方が分からず、このニムロデと同一視あるいは同系統のものとみなされて、『ニムロデ叙事詩』と題されたこともあった。☆5 エアバニ:楔形文字テキストではエンキドゥ[Enkidu]あるいはエンギドゥ[Engidu]と呼ばれる。☆6 ピュタゴラスや[…]と語られる:ディオゲネス・ラエルティウス『名高い哲学者たち』第二巻8冊 ピュタゴラス、プラトンその他も参照。☆7 クシストロス:バビロンのベルの神官ベロッソスは、紀元前280年頃、ギリシア語でバビロニアーカルデアの歴史を著わし、それがバビロンの寺院書庫から発見されたのだが、ベロッソスはこのように、ジウスドラというシュメール語の名をギリシア語化している。この名は楔形文字テクストではウトナピシュテムとなっている。☆8 エフェソスの秘儀の地:これについてシュタイナーは1923年12月2日の講義で詳しく述べている:『秘儀の形成』(十四回の講義、ドルナハ 1923 GA232)参照。*邦訳:『秘儀の歴史』(西川隆範訳 国書刊行会)☆9 地球と人類の太古の状態:シュタイナー『神秘学概論』、さらに『真実の観点から見た進化』(五回の講義、ベルリン 1911 GA132)、及び『秘儀の形成』所収の1923年12月1日の講義参照のこと。☆10 ヘラクレイトス:エフェソスのヘラクレイトス、前535ー475、ソクラテス以前の哲学者。シュタイナー『神秘的事実としてのキリスト教と古代密儀』(索引)参照。*『神秘的事実としてのキリスト教と古代密儀』(石井良訳 人智学出版社)付録の「編者の注」より。この人物については、ディオゲネス・ラエルティオス『著名哲学者の生活と意見』のなかの古代エピグラムに、その特徴が伝えられている。ヘラクレイトスの書物の頁は、性急にはめくらぬこと、登らねばならない小径は、急で、けわしい。暗黒が支配し、不可解な闇が支配しているが、奥義を受けた者が、汝を導くならば、この書物は日光より明るく汝を照らすであろう ☆11 アリストテレス:前384ー322 シュタイナー『哲学の謎』(GA18)参照。☆12 アレクサンダー大王:前356ー323、前336年よりマケドニア王、バビロンで死亡。訳註*1 ブルゲンラント:オーストリアの東端、ハンガリーとの境にある州。*2 クシストロス:☆7のように、ギルガメッシュ叙事詩のシュメール語版の主人公ジウスドラ(アッシリア語ではウトナピシュテム)がギリシア風になまったものとされています。旧約の大洪水の記述との関連も指摘されますが、ベロッソスの『バビロニア史』の第一巻に見られる大洪水の話の主人公がクシストロスです。*3 この部分に関連する『ギルガメッシュ叙事詩』のテキストからの概略:不死の生命を求めてやってきたギルガメッシュに対し、ウトナピシュテムは「起きて六日と六晩眠らずにいてみよ」と言うが、ギルガメッシュはたちまち眠ってしまう。彼が眠っている間、ウトナピシュテムの妻は毎日パンを焼き、七個目のパンが炭火の上にあるとき、ウトナピシュテムはギルガメッシュに触れて彼を起こす。[…]落胆して帰途につこうとするギルガメッシュに、ウトナピシュテムは水底の草を教える。その草を得れば生命を得るという。ギルガメッシュは水に飛び込んで草を取る。そしてこれを故郷に持ち帰ろうとするが、途中、泉で水浴をしているときに、草は近寄ってきた蛇に奪われてしまう。『ギルガメシュ叙事詩』(矢島文夫訳 ちくま学芸文庫 129頁以下)第十一の書板(アッシリア語テキスト)参照。なお、シュタイナー『世界史の秘密』によると;ギルガメッシュはこの試練を受けるのですが、すぐに寝入ってしまいます。そこで、ウトナピシュテムの妻は七つの神秘的なパンを焼きます。このパンを食べることによって、六日と七夜かけて獲得されるものが得られるのです。この生命の霊薬を持って、ギルガメッシュは道を進み、若返りの泉に浴し、チグリス川とユーフラテス川のほとりの故国の岸に戻ってきました。ここで、一匹の蛇が生命の霊薬の力を奪ってしまいます。こうしてギルガメッシュは、生命の霊薬なしに国に帰ることになるのです。けれども、不死にいたる意識をギルガメッシュは持ち、少なくとも、エンキドゥの霊を見られるという憧れに満ちていました。エンキドゥの霊は現われ、ギルガメッシュと話をします。このことから、どのようにエジプトーカルデア文化期において霊的世界とのつながりが意識されるようになったのかを、私たちは知るようになります。ギルガメッシュとエンキドゥの間の、この関係が大事なのです。『世界史の秘密』(西川隆範訳 水声社)16頁 (第3講・了)
2024年05月12日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 (GA233)翻訳紹介:yucca第2講 1923/12/25 ドルナハ 昨日お話したことからおわかりいただけたと思いますが、地上の人類進化の歴史的経過について正しく観ることができるのは、異なる時代に存在していたまったく異なる魂状態に関わり合うことによってのみなのです。さらに昨日私は、本来の古オリエント、アジアの進化を限定し、アトランティス民族の後裔がアトランティスの大災害ののち西から東へ、徐々にヨーロッパへの道を見出し、アジアに定住するようになったあの時代を示唆しようとしました。アジアでこの民族を通じて起こることは、リズム的なものに慣れ親しんでいたこれらの人々の心の状態に強く影響されていました。最初はまだ、アトランティスにおいて完全なかたちで存在していた場所化された記憶の余韻、はっきりとした余韻が認められました。次いでオリエント進化の間に、リズム的記憶への移行が起こります。そしてみなさんに示しましたとおり、ギリシア進化とともにようやく、時間記憶への飛躍が始まります。けれども、本来のアジア進化ーーと申しますのも、歴史が記述しているのはすでに退廃に至った状態(Dekadenzzustaende)だからなのですが。というものは、後の時代の人間とは全く別種の人間の進化であり、外的な歴史上の出来事といえども、あの古(いにし)えの時代にあっては、人間の心情のなかに生きていたものに左右される度合いが、後の時代よりもずっと大きかったのです。あの古えの時代に人間の心情のなかに生きていたものは、まさに全人のなかに(im ganzen Menschen)生きていました。人間は今日のような分離された魂生活、思考生活というものを知りませんでした。人間の頭の内部の出来事との関連をもはやまったく感じられないようなこういう思考を知りませんでした。血液循環との関連をもはや知ることのないこういう抽象的な感情は知らず、頭の中の出来事として同時に内的に体験するような思考、呼吸リズム・血液のリズムなどのなかに体験するような感情のみを知っていました。人々は、分けられない統一されたものとしての全人を体験し感じていたのです。けれどもこれらすべては、世界との関係、万有との、宇宙(コスモス)との、宇宙における霊的なもの及び物質的なものとの人間の関係が、後の時代とはまったく異なって体験されていた、ということに結びついています。今日の人間は、地上において多かれ少なかれ、田舎で体験し、あるいは都市で体験します。人間は、彼が森として、河として、山として眺めるものに囲まれています、あるいは人間は、都市の外壁であるものに囲まれています。そして人間が宇宙的ー超感覚的なものについて語るとき、それはいったいどこにあるでしょう。現代人は謂わば、宇宙的ー超感覚的なものを思い描かせてくれる領域をこれと言って示すすべを知らないのです。実際現代人にとってはどこであれ、とらえることも、つかむこともできないのです、これは魂的ー霊的な意味で、とらえ、つかむことはできないということですが。あの古えのオリエント進化においてはそうではありませんでした、あの古オリエントの進化においては、そもそもが今日の私たちなら物理的環境とみなすであろう環境というものも、統一的に考えられた世界の一番下の部分にすぎませんでした。人間の周りには、三つの自然領域に含まれているもの、河や山その他に含まれているものがありましたが、これは同時に、霊と密に混じり合い、こう言ってよろしければ、霊が流れ込み、霊に織りなされていました。そして人間はこう言ったのです、私は山と共に生きている、私は河とともに生きている、だが私は山の元素霊たち、川の元素霊たちとも、共に生きている。私は物質領域に生きているが、この物質界は霊的領域の体である。私の周りにはいたるところに、霊的世界が、最も下位の霊界があると。※宇宙の呼称:ユニバースorマルチバース、スペース、コスモスetc 此の内本講に出てくる「コスモス」は宇宙はギリシャ語の「秩序」「飾り」「美しい」という意味の「Kosmos, Cosmos」に由来する「cosmos」は、哲学者のピタゴラスが、秩序によって調和を保っている宇宙のことを「cosmos」と呼び始めたと言われ、「コスモスは数学、音楽、哲学、芸術、建築によって魂を開いた人間であれば見ることのできる神聖な秩序である」とも述べています。それ故に、英語の「universe」の類義語ですが、コスモスには秩序・調和の存在が暗示されています。神秘学・神秘体験を語るルドルフ・シュタイナーには適切な用いれ方だといえます。参考画:Pythagorean model of the Cosmos 私たちにとって地上的なものとなったこの領域は下にありました。人間はここで生きていました。けれども人間はまさに像(イメージ/Bild)のなかで(図参照)、ちょうどこの領域(明色/hell)が上に向かって中断するところで、別のものが始まり(黄赤/gelb-rot)、この別のものへと下のものが移行していくこと、そしてさらにまた別のもの(青/blau))が、そして最後に、なお到達しうる最高のもの(オレンジ/orange)が続くということを思い描きました。そして、私たちの間で人智学的認識として慣れ親しまれているものに従ってこの領域を名づけようと思うなら、古代オリエントの生活においては別の名称がありましたが、それはともかく、私たちにおなじみの名称で呼びたいと思います。この上の部分はセラフィム、ケルビム、トローネの第一ヒエラルキア、続いてキュリオテテス、デュナーミス、エクスシアイの第二ヒエラルキア、そしてアルヒャイ、アルヒアンゲロイ、アンゲロイの第三ヒエラルキアとなります。さて今度は人間の生きている場である第四の領域です、今日では私たちの認識に合わせて、対象としての自然、自然の経過のみが置かれていますが、この当時の人たちは、この領域で、自然の経過と自然の事物が水や土の元素霊たちに貫かれ織りなされているのを感じていました。そしてこれがアジアでした(図参照)。アジアとは、まだ人間の生きた場であった最も下位の霊領域を意味していました。けれども、人間の日常的意識のためにある、今日の私たちの通常の見かたは、あの古えのオリエントの時代にはありませんでした。あの古オリエントの時代に、人々がどこかに霊なき物質を想像する可能性もあったなどと考えるのはまったくばかげたことと言えるでしょう。あの古えの時代には、今日私たちが酸素、窒素について語っているようなことを考えることはまったくできなかったでしょう。酸素とは、すでに生命あるものを生き生きと励起させ、生命あるものの生を促進する作用をする霊的なものでした。窒素は空気中に酸素と混ざって含まれていると今日私たちは考えていますが、窒素とは世界を貫いて織りなす霊的なものでした。窒素は生命ある有機的なものに作用することで、自らのうちに魂的なものを受け入れるようこの有機的なものを準備するのです。例えば酸素と窒素について人々が知っていたのはこれだけでした。そして人々はあらゆる自然の経過を霊的なものとの関連において知っていました、なぜなら、今日世間一般のひとがするような見かたはまったくなされなかったからです。こういう見かたのできた人々も若干いましたが、それは秘儀参入者、イニシエーションを受けた人たちにほかなりませんでした。それ以外の人々は、通常の日常的なものに対して、醒めてみる夢、ただし私たちにおいては異常な体験のなかにのみまだ存在しているような醒めてみる夢に非常によく似た意識状態を有していました。こういう夢とともに、人間は歩き回っていました。こういう夢とともに、人間は草原に、木々に、河の流れに、雲に近づきました、そしてこの夢状態で見たり聞いたりするような、そういうしかたですべてを見ていたのです。今日の人間にとってはここで例えばどういうことが起こりうるか、ひとつ想像していただかなければなりません。人間が眠り込みます。突然この人の前に像(Bild)が、夢のなかで燃えるストーブの像が現われます。その人は火事だ!という声を聞きます。外ではどこかの火事を消すために消防自動車が走り去っていきます。いわゆる人間理性が無味乾燥に、そして通常の感覚的な見方がこの消防隊のふるまいから聞き取るものは、夢が人間に見せてくれるものから何とかけ離れていることでしょう。けれども、あの古代オリエントの人類が体験していたすべてはこのように夢のなかに流れ込んでいました。そこでは外部の自然領域のなかにあったものはすべて像に変化していました。そしてこの像のなかで人々は、水の、土の、空気の、火の元素霊たちを体験したのです。私たちのあのずだ袋眠り(Plumpsackschlaf)、文字通り袋のように横たわってまったく意識がなくなっているようなあの眠りのことを申し上げているのですが、そういう眠りは当時の人間にはありませんでした。でもこういう眠りは現在よくありますね。けれども当時の人間にはそういう眠りはなく、彼らは睡眠中(*睡眠中も脳活動は活発に働いており、休止しているわけではない。)もぼんやりとした意識を有していました。彼らは一方において、今日私たちが言うように身体を休めるのですが、その間、彼らのうちで霊的なものが生き生きとした外界となって活動し始めました。そしてこの活動のなかに第三ヒエラルキアであるものが知覚されたのです。通常の目覚めての夢状態、すなわち当時の日常的な意識のなかでは、アジアが知覚されました。第三ヒエラルキアは眠りのなかで知覚されました。そして、この眠りのなかに、さらにぼんやりとした意識が沈んでくることがありました、そのひとの体験を心情のなかに深く刻みつける意識です。つまり、このオリエント民族は、このようにすべてがイマジネーションや像へと変化していく日常的意識を有していたのです。このイマジネーションや像は、あのもっと古い時代、つまりたとえばアトランティス時代やレムリア時代、あるいは月紀のものほどリアルではありませんでしたが、ともかくも、このオリエント進化期にもまだ存在していました。つまり当時の人々はこうした像を有していたのです。さらに彼らは、睡眠状態において、次のような言葉で表わすことのできたものを有していました、つまり、通常の地上的状態から眠りに落ちると、私たちはアンゲロイ、アルヒアンゲロイ、アルヒャイの領域に入っていき、それらの存在たちのもとで生きるという言葉で。魂は生体から自らを解き放ち、高次ヒエラルキアの存在たちのもとで生きるのです。同時にはっきりと理解されていたことは、アジアに生きている間、ひとはグノームたち、ウンディーネたち、ジルフェたち、サラマンダーたちと、すなわち土、水、空気、火の元素霊たちとともにあり、肉体を休める睡眠状態では、第三ヒエラルキアの存在たちを体験していて、同時に惑星的な存在とともに、地球に属する惑星系のなかに生きているものとともに体験していたということです。けれども、第三ヒエラルキアが知覚されていた睡眠状態のなかに、さらにまったく異なる状態が入り込んでくることがありました、眠っているひとがその時、まったく見知らぬ領域が私に近づいてくる、それはいくらか私を引き受け、私を地上的状態からいくらか引き離すと感じるような状態です。第三ヒエラルキアのなかに移されている間はまだこれが感じられることはないのですが、このもっと深い睡眠状態がやってくると、こう感じられるのです。もともと、この第三の種類の睡眠状態の間に起こることについては、はっきりとした意識があったことはありませんでした。けれども、人間の全存在を深く深く貫いて、第二ヒエラルキアから体験されたものが入り込んできたのです。人間はこれを目覚める際に心情のなかに感じ、こう言いました、私は、惑星状態を超えて生を持つ高次の霊たちから祝福された、と。ーーこのときこの人間は、エクスシアイ、キュリオテテス、デュナーミスを包括するあのヒエラルキアについて語ったのです。ーー今私が皆さんにお話ししていることは、基本的に古代アジアではいわばふつうの意識状態でした。つまり、目覚めながらの眠り、眠りながらの覚醒と、第三ヒエラルキアが入り込んでくる睡眠、という二つの意識状態は、すでに最初から誰もが有していたものでした。そして若干の人々に、特別な生来の資質により、さらにこのより深い眠り、第二ヒエラルキアが人間の意識のなかに入り込んで活動するこの眠りが到来したのです。※「階層制(ヒエラルキア/hierarchy)」: そして秘儀に参入した人々、彼らはさらにまた別の意識状態を獲得しました。どういう意識状態でしょう。それはまさに驚くべきものです。当時の秘儀参入者たちはどういう意識状態を獲得したのかという問いに答えるなら、その答えは、今日皆さんが日中いつも有している意識状態です、ということになります。皆さんは人生の二年目,三年目の頃に自然なしかたでこの意識状態を発達させます。古代オリエント人は、自然にこの状態に到達することは決してなく、意図的にこれを育成しなければなりませんでした。古代オリエント人は、これを、目覚めながら夢見ている、夢見ながら目覚めている状態から育成しなければならなかったのです。この目覚めながら夢見、夢見ながら目覚めている状態で動き回っていたとき、古代オリエント人は、今日私たちが鋭い輪郭のものとして見るものを多かれ少なかれ象徴的にのみ与えてくれるだけの像をいたるところに見ていました、しかし他方で秘儀参入者たちは、今日人間が通常の意識で毎日見ているように事物を見る、というところにまで到達していたのです。当時秘儀参入者たちは、この発達させたばかりの意識を通じて、今日(こんにち)におる小学校でどの生徒も学んでいるようなことを学ぶという状態に達していました。今日との相違は、内容が異なっていたということではありません。とは言え、今日のような抽象的な活字というようなものは当時にはありませんでした。文字は、宇宙の事柄や経過ともっと親密に関わり合っていた特性を示していました。それはともかく、書くこと、読むことを学んだのはこの古えの時代では秘儀参入者たちだけでした、なぜなら、書くこと、読むことを学ぶことができるのは、今日自然なものである知性に即した意識状態においてのみだからです。つまり、当時のありようそのままの人間のいるこういう古オリエント世界がどこかに再び出現し、今日のような魂のありかたのまま皆さんがこれらの人たちのなかに歩み入ると想像なさるなら、皆さんは全員当時の人々にとっては秘儀参入者だということになるでしょう。違いは内容上のことではありません。皆さんは秘儀参入者でしょうが、皆さんが秘儀参入者だと知られた瞬間、皆さんは当時の人々から可能なかぎりのあらゆる手段によって土地から追い立てられるでしょう、なぜなら、当時の人々は、秘儀参入者は今日の人間たちが知るように物事を知ることは許されないということをよく知っていたからです。たとえば、当時の見方をこういうイメージで特徴づけます。当時の人々の見解にしたがえば、今日の時代の人間が書くように書くことができるということは許されませんでした。当時のある心情のなかに入り込んでみたとして、その心情(の持ち主)がこのような似非(えせ)秘儀参入者、すなわち現代の普通に利口な人間と対面するとしたら、あの時代のその人はこう言うことでしょう。この人は書くことができる、この人は何かを意味する記号を紙に書き付けている、しかも、このようなことをしながら、意識してさえない、こういうことを行ないながらも、こういう行為は神的な宇宙意識の委託を受けた状態でのみ許されるのだという意識が内部にないなどというのはどれほど悪辣きわまることかを。何かを意味する記号を紙に書き付けてよいのは、手の中で、指の中で神が働きかけている、神が魂のなかで作用している、だから魂がこの字母の形を通じて自らを現わすのだ、と意識しているときだけだ、そういう意識がないとは。この、内容の違いではなく、人間による事態のとらえ方の問題ということ、これが、内容的には同じものを有している現代人と古えの時代の秘儀参入者とがまったく異なっている点です。今度新版の出た私の著作「神秘的事実としてのキリスト教」(☆1)を読み返していただければ、冒頭すぐに、古代の秘儀参入者の本質とは本来この点にあったことが示唆されていることがおわかりでしょう。そして本来、宇宙進化においては常にそうなのですが、後の時代に自然なしかたで人間のなかに成長するものは、それ以前の時代には秘儀参入によって獲得されなければならないのです。このようなことをお話しすることで、皆さんは、こうした先史時代の進化段階の古オリエントの心情のありようと、後になって文明のなかに登場してきた人間との根本的な相違を感じ取ってくださるでしょう。最も下位の天をアジアと呼んでその名のもとに自らの土地を、自らを取り巻く自然を理解していたのは別の人類です。最後の天がどこにあるか人々はよく知っていました。今日の見方と比較してごらんなさい、現在の人間が、自分を取り巻くものを最後の天とみなすことがどんなに少ないか。たいていの人々はこれを最後の天とみなすことはできません、この最後の天に先行する天も知らないからです。さて、おわかりのように、この古えの時代には霊的なものが自然存在の内部深くまで入り込んでいます。とは言っても、私たちはこれらの人々のもとで、現代において少なくとも私たちの大多数にとって野蛮きわまりなく思えるであろうものに出会います。当時の人間にとって、誰かが今日ものを書くときのような気持ちで書くことができたとしたら、それは恐ろしく野蛮なことに思えるでしょう。それは彼らにとっておよそ悪辣なことに思えるでしょう。しかし逆に現代の大多数の人間にとって、あのアジアの地で、西から東へと遠く移動していったある民族が、先住の別の民族をしばしば非常に残酷に支配し、土地を征服し、人々を奴隷にしたのはまったく当然であったということが非常に野蛮に思えるのは確かです。そもそもこれが広い範囲にわたって全アジアを通じてのオリエント史の内容なのです。これらの人々は今特徴をお話ししましたような、高度なスピリチュアルな観照をしていましたが、他方でその外的な歴史は、ほかの地を絶えず侵略し、その民を隷属させることで過ぎていきました。このことはたしかに現代の多くの人間にとって野蛮に思えます。そして今日では何らかの侵略戦争があるとき、その際、その戦争を弁護する人々でさえ、心にまったくやましいところがないわけではありません。侵略戦争の弁護からも、まったくやましいところがないわけではない、ということが察せられます。当時においては、ほかならぬ侵略戦争に対して、人々は心にいささかもやましいところはありませんでした、しかも、この侵略はそもそも神の意志によるものだ、と見なされていたのです。そして、のちになってから平和への憧憬としてアジアの大部分に広がったものは、本来、文明の後期の産物(Spaetprodukt)なのです。これに対してアジアにとっての文明の早期の産物(Fruehprodukt)とは、他の土地の絶えざる侵略と人々の奴隷化です。先史時代を過去に遡れば遡るほど、こういう侵略は数多く見出されます、クセルクセスや同様のひとたちがしたことも、こういう侵略の影にすぎません。けれどもこの侵略原理の根底には、何か確固たるものがあります。当時の人々においては、皆さんに描写いたしましたあの意識状態によって、人間の他の人間に対する関係も世界に対する関係も、今日とはまったく異なった状態にあったのです。地球の諸民族の何らかの違いは、今日その原理的な意味を失っています。当時その違いは今日とはまったく異なるしかたで存在していました。そこで、ひとつ、しばしば現実にあったことを、例として私たちの魂の前に据えてみることにしましょう。ここ左にヨーロッパ地域(下図)、右がアジア地域だと考えてください。侵略民族(赤)は、アジアの北方からもやってきたかもしれませんが、アジアのどこかの地域に広がり、人々を隷属させました(黄色の周囲の赤)。実際そこで何があったのでしょう?実際の歴史進化の流れを定めたこの場合においては、侵略行為をする人々というのは常に、民族あるいは種族として、若かったのです。若く、青春の力にあふれていました。さて、現在の地球進化の人間の場合、若いとはどういうことでしょうか。現在の地球進化の人間の場合、若いということは、その生のどの瞬間にも死の力を自らのなかに担っているということ、人間の死にゆく経過を必要とする魂の力をまかなえるだけの量の死の力を担っている、ということです。私たちは私たちのなかに、芽吹き芽生える生命力を有していますが、この力は私たちを思慮深くさせず、私たちを気絶させ、意識を失わせます。解体する死の力もまた常に私たちのなかで作用していますが、死の力はいつも睡眠中に生命力によって克服されます。その結果私たちはまさに人生が終わるときにのみ死の力のすべてをこの一度の死のなかに総括するわけですが、この死の力が絶えず私たちのなかになければなりません。この死の力が思慮深さを、意識をもたらすのです。これがまさに現代の人類の特徴です。あの若い種族、若い民族は、あまりに強い生命力に悩まされていました。そういう人間は絶えずこういう感情を持っていました、私は始終、私の血を肉体の壁に向かって押しつけ続けている。私は血を押しとどめることができない。私の意識は思慮深くなろうとはしない。私は若さのゆえに私の人間性のすべてを発達させることができないと。参考画:power of death もちろん普通の人々はこんなことは言いませんでしたが、当時まだこの歴史的経過全体を導き方向づけていた秘儀に参入した人たちは、このように語りました。このようにこうした民族は、自らのうちに、あまりに多くの若さを、あまりに多くの生命力を有していて、思慮深さを与えてくれるものはあまりににわずかしか持っていませんでした。それから彼らは出かけていって、もっと古くからの民族が住んでいた地域を侵略しました、古い民族はすでに退廃状態に達していたために、すでに何らかのしかたで死の力を自らのうちに受け入れていたのですが、出かけていってこの古い民族を支配したのです。侵略者たちと奴隷にされた人々との間に、血縁関係が生じる必要はありませんでした。侵略者たちと奴隷にされた人々との間で魂の内部で無意識に演じられたものは、若返らせる作用をしましたし、思慮深さに向かわせる作用もしました。今や奴隷を所有しその土地に城を築いた侵略者も、自分の意識への影響を必要としているだけでした。侵略者はこの奴隷たちに意識を向けさえすればよかったのです、すると、気絶への憧れのうちに魂が和らげられ、とでも申しますか、そして意識が、思慮深さが生じてきたのです。今日私たちが個人として達成しなければならないものが、当時は他の人々との関係のなかで達成されたのです。堂々と登場するけれども若く、完全な思慮深さには到達していない民族よりも多くの死の力を有していた民族、そういう民族がいわば自分の周囲に必要だったのです。若い民族は、ほかの民族を征服することによって、自分が人間として必要としているものへとよじ登っていったのです。このように、これらしばしばぞっとするような、今日の私たちには野蛮に思える古代オリエントの闘いは、人類進化全般の衝動にほかなりません。これはなくてはならないものでした。これらの今日の私たちには野蛮に思えるぞっとするような戦闘の数々がなかったとしたら、人類は地上で進化することはできなかったでしょう。けれども秘儀に参入した人たちは、すでにもう今日の人間が見るような世界を見ていました、ただ、それに結びついていたのは異なった魂状態、異なった心情でした。彼らにとって、今日私たちが感覚によって知覚する際に外的事物を鋭い輪郭で体験するように、秘儀参入者たちが鋭い輪郭で体験したものは、彼らにとってはいつも、神々からやってきたもの、人間の意識のために神々からやってきたものでした。よろしいですか、そうですね、稲妻が起こったとしましょう。ありありと思い浮かべてみましょう。さて、今日の人間は、皆さんもよくご存知のとおり、まさしく稲妻を見るように稲妻を見ます(図参照、上)。古い時代の人間はそのようには見ませんでした。彼が見たのは生きた霊的存在たちが動いていくようす(黄)で、稲妻の鋭い輪郭は完全に消えていました。それは、宇宙空間の上あるいはそのなかを前へと押し進んでいく霊存在たちの行軍あるいは行進でした。稲妻そのものは彼には見えませんでした。彼が見たのは宇宙空間を漂っていく霊たちの隊列でした。秘儀参入者はと言えば、彼もまたほかの人々と同様にこの行軍の列を見ましたが、彼のなかで開発された観かたにとっては、隊列の像が徐々にぼやけそして消えていく一方で、稲妻が今日誰もが見ているような姿で現われてきたのです。今日誰もが見ているような自然は、古えの時代においては秘儀参入によって獲得されなければなりませんでした。けれどもひとはこのことをどのように感じていたのでしょう。今日の人間が認識や真理を感じるときのような無頓着さでこれを感じるということはまったくありませんでした。このことはまったくもって道徳的一撃(落雷)とともに(mit einem moralischen Einschlag)感じ取られていたのです。秘儀の入門者たちに起こったことを観るなら、私たちはこう言わなければなりません。彼らは、のちには自然の流れによって誰もが到達できる自然観に導き入れられた。厳しい内的試練と試しを通過したわずかの者のみがこの自然観に導かれた。けれども彼らはまったく自然に即してこのような感情も持っていた、ここに通常の意識の人間がいる、彼は空気中を行進してゆく元素霊たちの隊列を見ているという感情を。しかしこのように観ることにより、通常の意識の人間には人間の自由意志が欠けていた。彼は神的ー霊的世界にすっかり身を委ねていた。と申しますのも、この目覚めながら夢見、夢見ながら目覚めている状態においては、意志は自由な意志として生きるのではなく、神的な意志として人間のなかに流れ込んでいたからです。そして、このイマジネーションから今や稲妻がやってくるのを観た秘儀参入者は、これをこう感じました、彼の導師を通じてこう語ることを学んだのです、私は、宇宙において神々なしでも動くことを許される人間でなくてはならない、神々はこの人間のために宇宙内容を不確定なもののなかへと投げ出すのだが、そういう人間でなくてはならないと。イニシエーションを受けた人たちにとって、彼らが鋭い輪郭のなかに観たものはいわば、神々によって投げ出された宇宙内容でした、秘儀参入者は神々から独立するためにそれに近づいていったのです。これは何らかの調停する要因がなかったら耐えられない状況であったろう、ということがおわかりでしょう。けれども調停する要因はありました。と申しますのも、秘儀参入者は、神に見捨てられ、霊に見捨てられたアジアを体験することを学ぶ一方、他方においては、第二ヒエラルキアにまで達する意識よりもさらに深い意識状態を知るようになったからです。秘儀参入者は、神のいない世界に、セラフィム、ケルビム、トローネの世界を知るようになったのです。アジア進化のある特定の時期、ほぼ中間期頃、時期についてはもっと厳密にお話しすべきでしょうが、これらの人々、つまり秘儀参入者たちの意識状態というのは以下のようなものでした。彼らは地上を歩き回り、地球領域についてほぼ現代人が見ているような光景を見ていたのですが、彼らは本来はこれを四肢のなかで感じていました。彼らは、自らの四肢が神の去った地球物([Erdenmaterie)のなかで神々から解放されるのを感じました。しかしその代わりに、彼らはこの神々なき土地で、セラフィム、ケルビム、トローネという高位の神々に出会ったのです。秘儀参入者である者は、単に、森の像、木々の像であったあの灰緑色の霊存在たちのみならず、秘儀参入者である者は、霊なき森をも知るようになったのです、けれどもその代わりに調停するものがありました。つまり森のなかで、ほかならぬ第一ヒエラルキアに属するものたちに、セラフィム、ケルビム、トローネの領域からの何らかの存在に出会ったのです。これらすべてが社会の成り立ちとして把握されるというのがまさしく古代オリエントの歴史的生成における本質的なことです。さらなる進化を促進する力は、若い種族と古い種族との間に調停を求める力です、その結果、若い種族は古い種族をもとで成熟することができます、支配された魂たちのもとで成熟することができるのです。このように遠くアジアを見晴るかしますと、私たちは至るところにこの、自分自身では思慮深くなることのできない若い種族が、侵略行為のなかに思慮深さを求めているようすを見出します。けれども私たちが眼差しをアジアからギリシアへと向けてみますと、状況はいくらか異なってくることがわかります。ギリシアにおいても、ギリシア進化の最盛期にもう、年老いていくことをむろん理解していたけれども、この老いていくことを完全な霊性で浸透するということは理解できなかった民族がありました。私はしばしば聡明なギリシア人のあの特徴ある表明、影の国の王であるよりは上の世界で乞食であるほうがよい(☆2)という表明に注目を促さなければなりませんでした。外なる死、及び人間の内にもある死と、ギリシア人はうまく折り合っていけませんでした。けれども他方においてギリシア人はこの死を自分のなかに有していました。ですから、ギリシア人の場合、思慮深さは内に衝動として存在していたでしょうから、思慮深さへの憧れはなく、ギリシア人の場合死への不安があったのです。若いオリエントの民族はこういう死への不安を感じることはありませんでした、彼らは、民族として死を正しいしかたで体験できなかったら、侵略に出かけていったからです。けれども、ギリシア人が死とともに体験した内的な葛藤、これが内的な人類衝動となって、私たちにトロヤ戦争として伝えられているものに通じていきました。ギリシア人たちは、思慮深さを内部に獲得するために、ほかの民族のなかに死を捜し求める必要はありませんでしたが、まさに自分たちが死から感じ取っていたもののために、死についての内的な生き生きとした秘密を必要としていました。そしてこのことが、ギリシア人自身と、ギリシア人のアジアでの後裔である人々との、あの葛藤を招いたのです。トロヤ戦争は憂慮の戦争(Sorgenkrieg)、トロヤ戦争は不安の戦争(Angstkrieg)です。トロヤ戦争において、小アジアの祭司文化を代表する者たちと、内部に死を感じてはいるけれども死に対して何らなすすべのないギリシア人たちが対峙し合っているのがおわかりですね。侵略に出かけていったオリエントのほかの民族は、死を欲していました、死を有していなかったからです。ギリシア人は死を有してはいましたが、死を扱うすべを知りませんでした。ギリシア人たちには、いくらか死を扱っていくすべを知るために、まったく別の一撃が必要でした。アキレウス、アガメムノン、これらの人々はすべて、死を自らのうちに担っていましたが、死について何らなすすべがなかったのです。彼らはアジアを見晴るかしました。そして、アジアには逆の状態の民族が、真反対の魂状態の直接的な印象に悩まされている民族がいました。向こうにいたのは、ギリシア人のような強烈さで死を感じることはなく、根本において死を生に逆らう何かと感じる人々です。ホメロスは実際これを驚くべきしかたで表現しました。トロヤ人がギリシア人に対峙させられる至るところにヘクトールやアキレウスといった特徴ある人物をごらんなさい。至るところにこの対立があります。そしてこの対立のなかに、アジアとヨーロッパの境界で起こることが表現されているのです。あの古えの時代においてアジアにはいわば死に対する生の過剰があり、死に憧れていました。ギリシア基盤のヨーロッパには、人間のなかになすすべを知られぬ死の過剰がありました。このようにヨーロッパとアジアは二重の観点から対立していたのです、つまり一方においてはリズム的記憶から時間的記憶への移行があり、他方には人体組織における死に対してのまったく異なった体験がありました。今日は考察の最後にこの対立を皆さんに暗示することができただけですが、これをさらに明日詳しく考察していきましょう、人類進化にこのように深く食い入っているあの移行、アジアからヨーロッパへと移ってきて、これを理解することなしには、根本において人類の現代の進化におけるどんなことも理解することができないあの推移のことををよく知るために。 (第2講・了)□編集者註☆1 『神秘的事実としてのキリスト教』:R・シュタイナー『神秘的事実としてのキリスト教と古代の秘儀』Das Christenthm als mystische Tatsache und die Mysterium des Altertums (GA8)*邦訳 『神秘的事実としてのキリスト教と古代密儀』石井良訳 人智学出版社☆2 影の国で王であるよりは … :ホメロス『オデュッセイア』第11歌 489-491 行、下界でのアキレウスの言葉。人気ブログランキングへ
2024年05月11日
コメント(0)
-
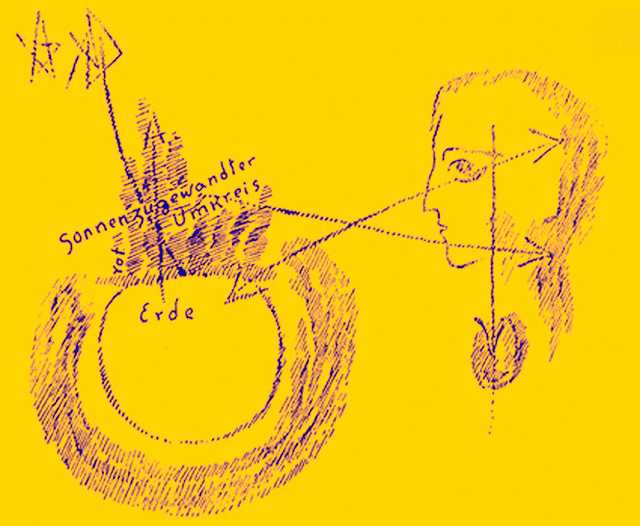
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史(GA233)Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtungund als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes 翻訳紹介(全9講) 翻訳者:yucca●第1講 1923/12/24 ドルナハ (2001.5.22.登録)●第2講 1923/12/25 ドルナハ (2001.7.3.登録)●第3講 1923/12/26 ドルナハ (2001.8.10.登録)●第4講 1923/12/27 ドルナハ (2001.9.15.登録)●第5講 1923/12/28 ドルナハ (2001.11.22.登録)●第6講 1923/12/29 ドルナハ (2002.1.26.登録)●第7講 1923/12/30 ドルナハ (2002.2.10.登録)●第8講 1923/12/31 ドルナハ (2002.3.7.登録)●第9講 1924/1/1 ドルナハ (2002.4.6.登録)ルドルフ・シュタイナー人智学の光に照らした世界史 GA233 翻訳紹介:yucca第1講 1923/12/24 ドルナハ 今夕のクリスマス会議では、皆さんに地上の人類進化についての展望を示したいと思います、現代の人間というものをますます親密に強度に意識のなかに受け入れることに通じていくような展望です。全文明にとってこれほど重大きわまりないことが準備されていると申し上げてよいであろうまさにこの現代のような時代にあっては、深く考えるということをする人間なら誰しも、本来なら次のような問いを投げかけて然るべきでしょう、人間の魂の現在のような形での現われ、現在のような状態は長期の進化からどのようにして生じてきたのかという問いをです。と申しますのも、現在のものは、それが過去からどのように生じてきたかを理解しようとすることによって理解できるものになるというのは実際否定できないことでしょうから。さて、とは言え、まさにこの現代においては、人間と人類の進化に関して非常に偏見に支配されています。まずはこう考えられております。歴史上の全時代を通じて人間は魂的ー霊的生活に関しては本質的に今と同じようなものであったと。確かに、狭義の科学的なものとの関連でこう考えられているのです、古い時代、人間は幼稚で、ありとあらゆる空想的なものを信じていた。そしてつい最近になってようやく人間は科学的な意味でほんとうに賢くなったと。だが狭義の科学的なものというものを度外視すれば、今日の人間が有する魂状態をギリシア人もオリエントの人もおしなべてすでに有していたと考えられています。細部においては魂生活における変遷ということが考えられるにしても、全体としては、歴史上の時代を通じて本来すべては今日と同様だったのだと。つまり、歴史上の生活が先史時代へと流れるとすると、当時人間は正しいことは何も知らなかったと言われます。さらに時代を遡ると、当時人間はまだ動物のような姿をしていたと。つまり歴史を遡っていくと、魂生活はほとんど変わらないものと想像され、続いて霧のなかのぼやけた映像、そして、動物のような不完全な人間、いくらかなましな猿のような存在というわけです。今日ほぼこのように思い描かれるのが常となっていますね。これはまさにとほうもない偏見に基づいています。と申しますのも、このような想定をすることで、現代の人間と比較的そう昔でない時代。そうですね、十一、十、九世紀の人間との間にもすでにどれほど深い違いがあるか、あるいは、今日の人間とゴルゴタの秘蹟の同時代の人々、あるいは今日の人間とギリシア人との間においても魂状態にどれほど大きな違いがあるか、これを認識する努力がなされてないからです。さらに、ギリシア文明を一種の植民地(コロニー)、後期コロニーとしていたオリエント世界へと遡ると、私たちは現代の人間の魂状態とは全然異なる魂状態のなかに入っていきます。それで私はこれから、そうですね、およそ一万年ないし一万五千年くらい前にオリエントで生きていた人間が、ギリシア人とも、また例えば私たち自身ともまったく異なった状態であったことを、実例で、実際の事例で皆さんに示したいと思います。ひとつ私たちの魂の目の前に私たちの魂生活を据えてみましょう。私たち自身の魂生活から何かを取り出してみましょう。私たちは何らかの体験をします。諸感覚あるいは人格を通じて私たちは体験に関与するわけですが、私たちはこの体験から、理念を、概念を、表象を形成します。私たちはこの表象を思考のなかに保持し、表象はしばらくしてから記憶(想起/Erinnerung)として私たちの思考から意識的な魂生活のなかにまた浮かび上がってくることでしょう。皆さんは今日、そうですね、もしかしたら十年前の知覚体験に遡る何らかの記憶体験をお持ちだとします。さてここで、それが実際何であるか正確に捉えてください。皆さんは十年前に何かを体験しました。そうですね、皆さんは十年前にある人たちのパーティーに出かけ、その人たちひとりひとりの顔その他のついて表象を得ました。これらの人たちが皆さんに何を話しかけたか、彼らと一緒に皆さんが何をしたか、それぞれが云々を体験しました。これらは全て、今日像のかたちで皆さんの前に現われてくるでしょう。それは、たぶん十年前の出来事について皆さんのなかにあった内的な魂の像なのです。そして科学に従ってのみならず、ある普遍的な感情、当然のことながら今日ではもう極めて弱々しく体験されるだけとはいえたしかに存在している普遍的な感情に従って、体験を再びもたらすこのような記憶表象は人間の頭に位置づけられます。頭には、体験の記憶として現存するものがあると言えるのです。さてここで人類進化をかなり大きく跳躍しつつ遡ってみましょう、そしてオリエント地方の住人たち、今日の歴史で描かれる中国人、インド人その他は本来その後裔なのですが、この人々を眺めてみましょう。つまり私たちは実際に何千年も遡るわけです。この古い時代の人間に目を向けてみますと、その生活からして当時の人間は、私が外的生活のなかで経験し、行なったことについての記憶は私の頭のなかにあるとは言いませんでした。このような内的体験を人間は有しておらず、人間にとってそういうものは存在しなかったのです。人間はその頭を満たす思考も理念も持っていませんでした。今日我々は諸々の理念、概念、表象を有している、歴史上いつの時代にも人間は常にこれらを有していたと思うのは現代人の皮相さです。然し乍らそうではないのです。霊的洞察をもってじゅうぶん過去に遡ると、私たちは理念、概念、表象を頭のなかにまったく有しておらず、つまり、頭のでこのような抽象的な内容を体験することがなく、皆さんにはグロテスクに思われるかもしれませんが、頭全体を体験していた人間に行き当たります。これらの人間は私たちの諸感覚に見られる抽象性に関わることはありませんでした。頭のなかで理念を体験するというようなことを彼らは知りませんでした、けれども自分自身の頭を体験すること、これを彼らは知っていました。そして、皆さんがある体験にともなう記憶像を持つとき、この記憶像を体験に結びつけるように、皆さんの記憶像と外部にあった体験との間にある関係が成立するように、ちょうどそのように彼らは彼らの頭の体験を地球に、全地球に結びつけていたのです。彼らはこう言いました、宇宙(世界)には地球がある、宇宙には私がいて、私には頭が付いている。そして私が両肩の上に担っているこの頭、これは地球についての宇宙的記憶なのだ。地球は以前からあったが、私の頭は後からだ。けれども私が頭というものを持っていること、これが記憶なのだ、地球存在についての宇宙的な記憶なのだ。地球存在はなおも常にある、しかし人間の頭の全構成、全形態であるもの、これは全地球と関連している。このように、古代オリエント人は自身の頭のなかにこの地球惑星そのものの存在を感じていたのです。古代オリエント人は言いました、「神々は、自然界をともなう地球、数々の山河をともなう地球を、普遍の宇宙存在から創り出し、生み出した。一方この私は、両肩の上に頭を担っている。この頭は地球そのものの忠実な写し(模像)である。内部に血液の流れるこの頭は、地表の河の流れや潮流の忠実な写しである。地上で山脈の形に現われるものは、私自身の頭の中の脳の形のなかに繰り返される。私は両肩の上に、地球という惑星の私所有の写しを担っているのだ。」現代人が記憶像を体験に関係づけるのとまったく同じように、古代オリエント人は自らの頭全体を地球惑星に関係づけていました。よろしいですね、人間の内部観照(内視/Innenanschauung )というのもかなり異なっていたのです。続けましょう。古代オリエント人が地球の周囲を知覚し観照のなかに捉えるとき、この周囲、つまり地球を取り巻く大気的なものは、太陽と太陽熱及び太陽光に浸透されたものとして彼に現われます、そしてある意味で、地球の大気圏のなか太陽が生きてると言うことができるのです。地球は、自分から送り出す作用を大気圏に委(ゆだ)ね、自らを太陽作用に明かすことで、自らを宇宙万有に開きます。そしてこういう古えの時代には誰もが、自分が今まさに生きている地球の地域を、とくに重要なもの、とくに本質的なものと感じていました。しかも、そうですね、古代オリエント人は、地表のどこかの部分を、下は大地、上は太陽に向けられた周囲(の気圏)までを、自分の部分と感じていました。大地のその他の部分、左右前後、というのは、もっと普遍的な状態でぼやけていました(図参照、左部分)。挿入図:Sonnenzugewandter Umkreis(太陽に向けられた周囲/Erde:地球) つまりたとえば、インドの地に住むある古代インド人が、このインドの地を彼にとってとくに重要なものと感じたとき、地上のそれ以外の部分、東方、南方、西方は全部彼にとって消え去りました。ほかの土地で地球(地)が宇宙空間にどのように接しているかということは、さしたる関心事ではありませんでした。それに対して、まさに自分が立っている土地は彼にはとくに重要でした(図参照、左、赤)。その地域における地球(地)の宇宙にまで延びる生が彼にとってとくに重要となりました。この特別な地で自分はどのように呼吸すればよいのか、これを彼は自分にとって特に重要な体験と感じました。今日人間は、特定の土地でどのように呼吸するかと問うことはあまりありません。もちろん人間は、より好都合なものであれ不都合なものであれ諸々の呼吸条件の影響下にあるのですが、これは意識のなかに受け入れられることはないのです。古代オリエント人はもともと、どのように呼吸すればよいかというまさにそのやりかたにおいて深い体験を有していました、そしてこれに関連するもうひとつのこと、地球が宇宙空間へとどのように接していくかということにおいてもそうでした。地球全体であったもの、これを人間は自分の頭の中に生きているものと感じていました。けれども、この頭は、固い骨の壁によって、上、両側面、後ろに向かっては閉じられています。しかし頭には下に、胸郭に向かって、ある種の出口、ある種の開口部があります(前図参照、右)。古い時代の人間たちにとって、いかに頭が相対的な自由さをもって胸郭に向かって開いているかを感じることは、とくに重要なことでした。人間は頭の内的な構成を地球的なものの写しと感じました。地球を自分の頭と関係づけなければならないとき、人間は、周囲、つまり地球の上方にあるものを、自分のなかで下の方に向かうものと関係づけなければなりませんでした。下に向かって開くこと、心臓の方向に向けられること、人間はこれを、周囲に連なることとして、像として、宇宙に向かう地球の開け(あけ/Oeffnung)として感じました。そして人間が次のように言ったとき、それは人間にとって圧倒的な体験でした。私の頭のなかに私は全地球を感じる。この頭は小さな地球なのだ。けれどもこの全地球は、心臓を担う私の胸郭の中へと開いている。そして、私の頭と私の胸郭、私の心臓との間で起こること、これは、私の生から宇宙へと、太陽に向かう周囲へと担われていくものの写しである。さらに、古代の人がこう言ったとき、それは重要な根本的な体験でした、私の頭のなかに、私のなかに、まさにここに地球が生きている、私が下降すれば地球は太陽に向かう(矢印を参照)、私の心臓は太陽の写しなのだと。ここで人間は、古(いにし)えの時代における私たちの感情生活に相当するものに行き着いたのです。私たちはまだ抽象的な感情生活を有していますが、私たちの心臓については直接何も知りません。解剖学、生理学によって私たちは心臓についてなにがしかを知っていると信じています。けれどもこうして知られたことは、私たちが紙製の心臓模型について知っていることとおよそ変わらないのです。私たちが世界の感情体験として有しているものをかつての人間は持っていませんでした。その変わりに心臓体験を有していました。そして私たちが感情を、私たちとともに生きている世界へと関係づけていくように、ある人を好んでいるのか、ある人に反感を持って向かうのか、あれこれの花を好み、あれこれの花を嫌うのかを私たちが感じるように、つまり私たちが私たちの感情を世界に、とは言え、堅固な宇宙から空気のような抽象へともぎ離された世界、とでも言ってよいでしょうか、そう言う世界へと関係づけるように、そのように、古代オリエント人はその心臓を宇宙へ、すなわち地球から周囲へ、太陽へと向かうものに関係づけたのです。そして、今日私たちはたとえば、私たちが歩くとき、私たちは歩きたいと言います。私たちは、私たちの意志が四肢のなかに生きているのを知っています。古代オリエントの人間は、本質的に異なった体験をしていました。今日私たちが意志と呼んでいるものを、古代オリエントの人間は知りませんでした。私たちが思考、感情、意志と呼んでいるものが古代オリエントの民族にもあったと思うのは、偏見にすぎません。断じてそういうことはありませんでした。彼らが有していたのは、地球体験であった頭体験、太陽までの地球に隣接する周囲の体験であった胸体験ないし心臓体験だったのです。太陽は心臓体験にあたります。さらに彼らには、四肢へと伸び、広がっていくという体験、両脚と両足、両腕と両手の動きのなかに自身の人間性を感じるということがありました。彼らはその動きのなかにいました。四肢へと伸びてゆくこの伸長のなかに内在して、彼らは単に地球の周囲の写し(模像)のみを見出していたのではありません、彼らはそこに人間と星界との関係の写しを直接感じ取っていたのです(前掲図参照)。私の頭のなかに私は地球の写しを見る。頭のなかで心臓目指して胸へと下に開いて広がっていくもののなかに、私は地球の周囲の写しを見る。私の両手両腕、両足両脚の力と感じるもののなかに、彼方の宇宙空間に生きている星々と地球との関係を写し取るものがある。ですから、あの古えの時代の人間が今日そう呼ばれるであろうところの意志する人間として得た体験を言い表わすとき、私は歩く、とは言いませんでした。そういう言葉では言い表わせなかったのです。私は座るとも言いませんでした。古い言葉のこういう精妙な内容をよく吟味してみるなら、「私は歩く」と私たちが表現する事実に対して、古代オリエント人では、火星が私に衝動を与える、火星が私のなかで活動していると表現されることがいたるところで見つかるでしょう。前進するということは、両脚のなかに火星衝動(Marsimpulse)を感じることです。「何かをつかむ」という手にともなう感情は、金星が私のなかで作用すると表現されました。何かを指すこと、乱暴な人間がほかの人をけ飛ばすことで何かを示そうとすることであれ、何かを指し示すことはすべて、水星が人間のなかで作用すると言うことによって表現されました。座るということは人間のなかの木星活動でした。そして、休息するにせよ、怠慢のためにせよ、横たわるということは、土星の衝動に身を任せると言うことによって表現されました。このように人々はその四肢のなかに外部はるかに広がる宇宙を感じていたわけです。地球から宇宙の彼方へと歩みを進めると、地球からその周囲へ、星領域へと至るということを人間は知っていました。頭から下へ降るとき、人間は自分自身の本質のなかで同じことを行なうのです。人間は頭においては地球のなかにいます、胸郭と心臓においては[地球の]周囲に、四肢においては外部の星宇宙にいるのです。ああ、哀れなわれわれ現代人は抽象思考を体験するのだと私は申し上げたいのですが、ある観点からすれば、こう言うことはまったく可能なのです。それがどれほどのものでしょうか。私たちは抽象思考をたいそう誇りにしていますが、自らのきわめて利口な抽象思考に夢中になるあまり自分の頭のことを忘れています。私たちの頭というものは、私たちの最も利口な思考よりもはるかに内容豊かなのです。脳のただひとつの回旋ですら、解剖学も生理学も脳の回旋の驚くべき秘密について多くを知ってはおりません。人間の誰それかの最も天才的な抽象の学よりもすばらしく圧倒的なものです。そしてかつて地球上には、人間が単にみすぼらしい思考だけではなく、自分の頭を意識していた時代、人間が頭を、そうですね、私が思いますに、四丘体(Vierhuegelkoerper)や視床(視丘/Sehhuegel])を感じていた時代、それらを人間が地球の特定の物質的な山の成り立ちを模写しながら感じていた時代があったのです。当時人間は単に何らかの抽象的な学説から心臓を太陽に関係づけていたのではありません、そうではなく人間はこう感じていたのです、私の頭と私の胸、私の心臓の関係のように、地球は太陽と関係があると。それは、人間がその生全体をもって宇宙万有と、宇宙(コスモス“cosmos”は、「秩序ある調和のとれた宇宙」)と合体していた時代でした。しかもこの合体は人間の生全体のなかに現われていました。とは言え私たちは、頭の代わりにみすぼらしい思考を据えることによってこそ、思考的な記憶というものを得る状態に移ったわけです。私たちは、私たちが生きてきたものについての思考像を、私たちの頭の抽象記憶として形成します。思考を有さず、まだ頭を感じていた人にはこれはできませんでした。思考を持たないひとは記憶を形成することはできなかったのです。ですから、人々がまだ自分の頭を意識していて、思考、つまり記憶も有していなかった太古オリエントのあの地域に入っていくと、私たちにまた必要となってくるものが、特殊な形で見出されます。人間は長い間それを必要としませんでした。それで、私たちにそれがまた必要となるというのは、実際のところ私たちの魂生活のちょっとしただらしなさというものです。私が話しましたあの時代、私が話しましたように頭を、胸を、心臓を、四肢を意識していた人たちが生きていた地域に入っていきますと、いたるところで、地面に何か小さな杭が打ち込まれていたり、何かしるしになるものが立てられていたり、何かの壁に何かしるしが付けられていたりといったことが見られます。人間の生きるあらゆる領域、あらゆる生の場所は目印だらけでした、当時まだ思考記憶というものがなかったからです。そこに建てられた目印を手がかりに、できごとをふたたび体験したのです。人間はまさに頭において地球と合体していました。今日人間はただ頭のなかにメモ(覚え書き)をするだけです。そして私が申しましたように、私たちは頭のなかにメモをとるだけではすまず、メモ帳その他にもメモをとるということをまた始めましたが、これもやはり申し上げましたように、「魂のだらしなさ」というものです。私たちはますますメモ帳を必要とするようになるでしょうけれども。けれどもかつては、思考、理念というものがそもそも存在していなかったために、頭のなかにメモするということはあり得ませんでした、それであらゆるところが目印だらけだったわけです。そして人間のこの自然に即した資質から、記念碑建造ということが生まれたのです。人類の進化史に登場してくるものはすべて、人間の性質の内部から条件付けられているのです。記念碑を建造することのほんとうの深い根拠を、現代の人間はまったく知らないのだということを正直に認めなくてはならないでしょう。現代人は慣行として記念碑を建てます。けれども記念碑というのはあの古い目印の名残なのです、当時人間はまだ今日のような記憶を持っておらず、何かを体験した場所に目印をしつらえ、そしてふたたびそこにやってくるたびに、どういうしかたであれ、地球と結びついているものすべてを甦らせることのできる頭のなかでその体験を甦らせるというやりかたに頼らざるを得なかったのです。私たちは頭が体験したことを地球に委ねる。これが古えの時代の原理でした。私が申し上げたいのは、古代オリエントにおいて、太古の時代、つまりすべて記憶にのっとったものが本来的に、地上に記憶のしるしを建てることと結びついていた、場所化された(ひとつの場所に結びつけられた、局所化された)記憶(想起/lokalisierte Erinnerung)の時代を認めなくてはならないということです。記憶は内部にはなく、外にあり、いたるところに記念碑や石碑がありました。人々は地面に記憶の目印を据えました。これが場所化された記憶(Gedaechtnis)、局所化された記憶(想起)です。人間の内部に見られる記憶ではなく、人間と地上の外界との関係のなかで繰り広げられ、形づくられるかつての記憶に何かを結びつけるというのは、今日でもなお、人間のスピリチュアルな進化のためには本来非常に良いことなのです。例えば、私はあれこれを憶えておくのではなく、あちこちに目印をしておこうと言うのは良いことです。あるいは、私はあることについて、目印にしたがって内なる魂的な感受性を発達させるだけにしようと。私は部屋の一隅に聖母像を掛けよう、そしてこの聖母像が私の魂の前に現われることで、まさに私の魂が聖母に向けられるなかで体験されうるものを体験したいと。と申しますのも、私たちが少しばかり東方に行くだけでも、私たちが居間で出会う聖母像といったような調度品に対する繊細な関係が見られるからです。ロシアにおいてのみではなく、東欧の中部においてもう至るところでそうなのです。基本的にこれらすべては場所化された記憶の時代の名残です。記憶は外部の場所に固着していたのです。けれども、人間が場所に結びついた記憶からリズム化された記憶(rhythmisierte Erinnerung)へと移行する第二の段階はまた異なっています。つまり、第一に場所化された記憶、第二にリズム化された記憶となっていきます。人間は今や巧妙に意識された技巧からではなく、自身の内なる本質から、リズムのなかに生きようという欲求を発達させます。人間は何かを聞くたび、聞いたものをあるリズムが生じてくるように自分の中で再生しようという欲求を発達させました。牛(モー/Muh)を体験すると、人間はそれを単にモーではなく、モーモー(Muhmuh)と呼びました、あるいはもっと古い時代になると私が思いますにはモーモーモー(Muhmuhmuh)と呼んだでしょう。つまり、知覚したものを、あるリズムが生じてくるように積み重ねていったのです。今日においてもこのことをたどることのできる語形成がいつくかあります、たとえばガウガウ(Gaugauch)あるいはカッコウ(Kuckuck)、 といったものです。あるいは、語形成が直接順次並んでいるというのではなくても、少なくとも子どもたちの場合にはこうした繰り返しを形成する欲求がまだあるということはおわかりになるでしょう。これはまだ、リズム化された記憶がはびこっていた時代の遺産なのです、単に体験されただけのものは記憶されず、リズム化すること、つまり繰り返し、リズミカルな反復のなかで体験されたもののみが記憶されていた時代の遺産です。ですから並んでいるもの同士の間には、少なくとも類似がなければなりませんでした、マン(人間/Mann)とマウス(ねずみ/Maus)、シュトック(杖/Stock)とシュタイン(石/Stein)というように。体験したものをこのようにリズム化すること、これは、あらゆるところでリズム化しようとする高度な憧れの最後の名残なです。と申しますのも、場所化された記憶に続くこの第二の時代においては、人間はリズム化されなかったものを記憶にとどめることはなかったからです。そしてもとをたどればこのリズム化された記憶から、古来の全詩学(Verskunst)、韻文による文芸一般が発達してきたのです。次いで第三段階となってようやく、私たちが今日まだ知っている時間的な記憶(zeitliche Erinnerung)というものが形成されました。私たちはもはや空間としての外界には記憶の手がかりを持たず、もはやリズムにも頼ることはできません、時間のなかに置かれたものを後から再度呼び起こすことができるだけです。私たちのこういうまったく抽象的な記憶は、記憶進化のなかの第三の段階なのです。さて、人類進化のなかで、まさにリズム的記憶が時間記憶に移行する時点に正確に注目してください、現代人の痛ましい抽象性のなかで私たちには自明である時間記憶というものが最初に現われる時点に。時間記憶にあっては、私たちが呼び起こすものは像のなかに呼び起こされ、私たちはもはや、何かを再度生じさせたければ、なかばあるいは完全に無意識的な活動のなかでリズミカルに反復しながらそれを呼び起こさなければならないという体験をすることもありません。リズム的記憶から時間的記憶へのこの移行の時点を想定していただくと、古代オリエントがまさにギリシアへと植民してくるあの時点、歴史上、アジアからヨーロッパへと創設された植民地の成立として記述されているあの時点となるでしょう。アジアあるいはエジプトからやってきてギリシアの地に居を定めた英雄たちについてギリシア人たちが物語ることは、もともとはこういうことを意味していた物語だったはずです、つまり、かつて偉大な英雄たちがリズム的記憶が存在していた国を去り、リズム的記憶を時間的記憶、時間記憶へと移行させることのできる風土を探し求めていたと。これをもってギリシア精神(グリーヒェントゥム)出現の時点が正確に示されます。と申しますのも、ギリシア精神の母なる地あるいは元なる地としてオリエントにあったものというのは、根本的にいってリズム記憶を発達させていた人々の地域だからです。そこではリズムが生きていました。そもそも古代オリエントというのは、人間がこれをリズムの地と思い浮かべるときにのみ正しく理解されるのです。そして楽園(パラダイス)というものが聖書がそうしているところまで元の場所に引き戻されるなら、つまり私たちが楽園をアジアに移すなら、もっとも純粋なリズムが宇宙を貫いて響き、リズム記憶であったものが人間のなかで再び燃え上がらされ、リズムを体験する者としての人間がリズムを生み出す者として宇宙のなかに生きていた地域を私たちは思い浮かべたことでしょう。みなさんがバガヴァッド・ギーターのなかに、かつてあの雄大なリズム体験であったものについてなおいくばくかを追感されるとき、ヴェーダ文学のなかにそれを追感されるとき、さらに西アジアの文芸と西アジアの文献の多くのもののなかにもそれを追感されるとき、こういう現代の言葉を使うことが許されるなら、そこにはかつて全アジアを荘厳な内容で貫いていたリズムの余韻が生きています、地球の周囲の秘密として人間の胸郭のなかに、人間の心臓のなかに反映していたリズムの余韻が。そして私たちはもっと古い時代へと入っていきます、リズム的な記憶が場所化された記憶へと後退してゆく時代、人々が何かを体験したら目印を立ててそれを頼りとしていた時代です。人々がその場所にいないときは目印は用いられず、その場所にやってきたときに彼らは思い出さずにはいられませんでした。けれども人々が思い出したのではなく、目印が、地球が彼らに思い出させたのです。そもそも地球というものが、人間の頭をその写しとして持っているように、今や地上の目印も、場所化された記憶を有するこうした人々の頭の中に写し取られたものを呼び起こすわけです。人間はまさに地球とともに生きており、人間はまさに地球との結びつきのなかにその記憶を有します。福音書も、キリストが地面に何かを書き込むと伝えるある箇所で、まだこのことを思い起こさせます(☆1)。そして私たちは、場所化された記憶がリズム的記憶に移行する時点を確定することができます。それは、古アトランティスの沈没にともない、西から東へ、アジアに向かって、太古の後アトランティス民族たちが移動していく時点です。と申しますのも、ヨーロッパからアジアへと移動していくときに、今日大西洋の底にある古アトランティスからアジアに向かっての移動(図参照)がまずあり、それから文化がヨーロッパへと再び戻ってくるからです。アトランティス民族のアジアへの移動の際に場所化された記憶からリズム化された記憶への移行が起こり、リズム記憶はアジアの霊生活のなかで完成を見ました。次いで、ギリシアへの植民の際に、リズム的記憶から今日なお私たちが有しているような時間的記憶への移行が起こります。挿入図:記憶の移行1-2-31-lokalisierte Erinnerung:場所化された記憶2-rhythmisierte Erinnerung:リズム化された記憶3--zeitliche Erinnerung:時間的な記憶 アトランティスの大変動とギリシア文明の成立との間の全文明、歴史的にというよりは多分に伝説的、神話的に古えのアジアから私たちに響いてくるすべては、このように記憶が養成されてくるなかにあります。私たちは、とりわけ外的なものに目を向けることによって、つまり外的な文献を調べることによって、地上の人間の進化を学ぶのではありません、人間の内部に生きているものの進化発達に目を向けることによって、記憶力、記憶能力というような何かがいかに外から内へと進化してきたかに目を向けることによって学ぶのです。こういう記憶力が今日の人間にとってどういう意味を持つのか、みなさんもご存じでしょう。みなさんも、人生の覚えておいてしかるべき部分を突然病的なしかたで消し去ってしまった人たちについてお聞きになったことがあると思います。私の親しくしていたある人は、次のようなことが起こったことによって死の前におそるべき運命を経験しました。ある日のこと彼は自宅を出て、駅である地点までの切符を買い、それから下車してまた切符を買いました。その間、切符を買うまでの彼の人生の記憶は一時的に彼の内部で消し去られていたのです。彼はすべてを賢明に行ない、知性はまったくもって健全でしたが、記憶は消えていました。その後の彼は記憶を再び以前のものに結びつけることで、ベルリンの浮浪者収容施設にいる自分を見出しました、彼はそこに辿り着いていたのです。後に確かめられたことによると、彼はそうこうする間、この体験を以前の体験に結びつけることができないまま、ヨーロッパを半周の旅をしていたということです。彼が自分ではまったく分からずに、この浮浪者のためのベルリンの収容施設に着いたあとで、ようやく記憶が明るくなってきたのです。これは私たちが人生において出会う数多くの事例のひとつにすぎませんが、この例で、記憶の糸が私たちの誕生後のある時点までとぎれないままでなかったら、現代人の魂生活はいかに損なわれたものとなるかかがわかります。このことは、場所化された記憶を発達させていた人間の場合にはあてはまりません。彼らはそもそもこういう記憶の糸などというものを知りませんでした。けれども、自分の体験を思い出させてくれる記念物に土地のいたるところで囲まれていないとしたら、彼らが自分で建てた記念物にも、彼らの父たち、姉妹たち、兄弟たちその他によって建てられ、作りが彼ら自身のものによく似て見えるために彼らを親族のところに導いてくれる記念物にも囲まれていないとしたら、彼らは魂生活において不幸であることでしょう、何かが私たちの内部で自己(Selbst)を消し去ったときに私たちがなるような状態になるでしょう。私たちが内的に私たちの健全な自己の条件と感じているものが、これらの人々にとっては外的なものだったのです。人類におけるこの魂の変遷を私たちの魂の前に引き出してみることによってのみ、この魂の変遷が人類の歴史的進化において持つ意味へと至ることができます。こういうことを考察することによって、歴史ははじめて光を放ちます。それで私はまず最初に、ある特殊な例を手がかりに、人類の魂の歴史は記憶力に関してはどのようなものであるかということを示したいと思ったのです。さらに明日以降、このように人間の魂の学(Seelenkunde)から引き出される光で照らすことができてはじめて、歴史上の出来事はその真の姿を表わすだろうということを見ていきたいと思います。□編集者註☆1 福音書も[…]このことを思い起こさせます:ヨハネ8,6参照のこと。人気ブログランキングへ
2024年05月10日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「キリスト衝動の告知者としてのノヴァーリス」 1912年12月29日、ケルンでの講義(GA143所収) yucca訳:以下に訳出してみましたのは、GA(シュタイナー全集)143 Erfahrungen des Uebersinnlichen.Die drei Wege der Seele zu Christus 所収の1912年12月29日ケルンでの講義です。 ノヴァーリス(Novalis1772-1801 本名 Friedlich von Hardenberg 作品『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』(青い花)、『ザイスの学徒たち』など)についてはほかの著作、講義でも触れられていますが、この1912年12月29日は、連続講義「バガヴァッド・ギーターとパウロ書簡」(GA142)の第2日目にあたり、「バガヴァッド・ギーターとパウロ書簡」の内容との関連も深く、古インドのヴェーダやサーンキヤ哲学の余韻がゲーテやフィヒテに響いていることなどがここでも語られています。ノヴァーリスは、こういうゲーテやフィヒテ、そしてシラー等の形成する豊穣な精神的地平のなかに育ち、深く共感・沈潜しながらその内容を血肉化し、さらにこれらをいわば未来へ向かって、愛=キリスト衝動で貫き暖める。このノヴァーリスが、新しい精神潮流(この翌年シュタイナーは神智学協会を離れ、人智学協会を発足させます)の導きの星のひとつとされているのが印象的です。「夢幻的な浪漫派詩人」としてのノヴァーリスにとどまらず、30年に満たない生涯のなかで、カントやフィヒテ研究をはじめ、鉱山官としての実際的な仕事に加えて(とくに『青い花』の第5章などでは、鉱山実務に携わった人ならではの体験が活かされています)数学、化学、物理学等々当時の自然科学全般に深く親しみ、膨大なメモを取りながら、精神と自然のあらゆる学の分野を綜合する「百科全書学(エンチュクロペディー)」を構想していたノヴァーリス。高次の自然学としての詩学を追求するノヴァーリスと芸術を認識原理としてとらえながら諸学に生命を吹き込むことを目指したシュタイナー、こういう点でも、ちょうどシュタイナーの一世紀前に生きたノヴァーリスの志向は、シュタイナーの精神科学的人智学の魅惑的な序曲のようにも思えます。*「すべて、見えるものは見えないものに、聞こえるものは聞こえないものに、感じられるものは感じられないものに付着している。 おそらく、考えられるものは考えられないものに付着しているだろう」(ノヴァーリス)。参照画:Novalis このように、私たちの愛するノヴァーリスの心の響き、彼をかくも親密にキリストの使命について告知することに導いたこの心の響きを聴きますと(☆1)、私たちは私たちの精神潮流を正当さを証しする何かを感じます、と申しますのも、その全性質が宇宙の謎と宇宙の秘密のすべてと深く親しんでいた人物から私たちはそれを感じるからであり、私たちが目指すのと同じ世界観を通じてこれからの新しい人間が求めていかなければならないあの霊的世界への憧れのように、何かがこの人物から響いてくるのを感じるからです。ノヴァーリスがそうであったような、そのような人間の心魂のなかに沈潜していくのは、驚くべきことです。ノヴァーリスはヨーロッパの精神生活の何という深みから成長し、霊的世界への憧れを何と深く把握したことでしょう。そしてさらに、ノヴァーリスがその受肉においていかに若々しい心のなかにこの霊界を流れ込ませたか、そしてこの霊界が彼に向かっていかにキリスト衝動により輝きわたらされたかをそのように私たちに作用させるなら、私たちはこれを、私たち自身の魂、私たち自身の心を奮い立たせるもののように感じるでしょう、ノヴァーリスの前に常に神々しい光のように輝いていたものに向かって、ノヴァーリスがその短い生涯をかけて目指したものに向かって、彼とともに邁進して行こうと。そして私たちは、彼がこの受肉において、私たちが霊界において探求しようとするもののための近代における預言者のひとりであったことを感じます、さらにまた、ノヴァーリスの心、魂のなかに生き、そしてキリスト衝動に親密に貫かれることで彼のものとなったあの霊感(Begeisterung)によって、この探求のためにいかに私たちがもっともよく霊感を吹き込まれうるかということも感じます。そしてまさしく今この瞬間、つまり一方においては人間の謎のすべてを自らのうちに包み込もうとする人智学協会を設立し、他方においては、オリエントからかくも輝かしく射してくる光(☆2)をキリスト衝動との関連においても考察しようという現在のこの瞬間、私たちはこの瞬間においてキリスト衝動のひとつの現われとしてこのノヴァーリスの魂のなかに生きたものと結びつくことが許されるでしょう。私たちは、それがかつて古代ヘブライにおいて偉大な預言として、創造から迸る意義深いエリヤの言葉として響いていたのを知っています。私たちは、それが宇宙的なキリスト存在がナザレのイエスの体に下ったときにそこに居合わせた衝動であったことを知っています。私たちはそれが、人類進化に組み入れられるべきものを当時預言として前もって告知していた衝動と同じ衝動であったことを知っています。私たちはそれが、ラファエロの魂のなかで人間の注視の前にキリスト教の無限の秘密を不可思議に現出させたのと同じ衝動であったことを知っています。そして憧れに満ち謎を感じつつ、私たちは、ノヴァーリスの中に再受肉したエリヤの、洗礼者ヨハネの、ラファエロの魂に向かい、この魂とともに、その霊的な振動のすべてが人間の新たな精神生活への憧れを貫き燃え立たせているのを感じます、そして勇気を感じ、さらには人類のこの新たな精神生活に向かって生きていく力のいくばくかが私たちに与えられるのを感じます。おお、このノヴァーリスは、いったいなぜスピリチュアルに捉えられるべきキリスト衝動を預言的に告知すべく近代に生まれ落ちたのでしょうか。彼をめぐるその精神的地平は、実に全人類の偉大な精神潮流が復活したかのようでした。ノヴァーリスは、ヨーロッパの神智学ー人智学的世界観の最初の告知のごとく精神生活そのものが燃え上がっていたグループのなかから成長しました。ゲーテという太陽、シラーという太陽の輝きのなかで、キリスト衝動へと止むことなく憧れるこの魂は成熟していったのです。ゲーテのなかにはどのような精神潮流が生きていたのでしょう。霊太陽はゲーテを通じてどのように顕われ、ゲーテの若き同時代人ノヴァーリスを照らしたのでしょう。ゲーテは、自らの熱く燃えさかる情熱を静め至福に導き霊へと向かわせることのできる全てを、スピノザの世界観から感受しようとしました(☆3)。スピノザの包括的世界観から、ゲーテは宇宙の広がりへの眺望、この宇宙の広がりを織りなし人間の魂のなかに輝き入る霊的存在たちへの眺望を探し求めました、この存在たちが輝き入ることで、人間の魂はあらゆる存在と宇宙のなかに活動し生きているこの存在を感じ認識して、自然を解明し自身の謎を解くことができるのですが、そういう眺望を求めました。このようにゲーテは、スピノザから得られたものから清澄さと観照へと跳躍しようと努めたのです。ゲーテは、古いヴェーダの言葉から私たちに響き輝いてくる、あのスピリチュアルな意味での一神論的な(monotheistisch)世界観のいくばくかを感じていました。そして、耳を傾けようとしさえすれば、ゲーテが再生させる宇宙的ヴェーダ(☆4)の言葉とノヴァーリスから響いてくる暖かい霊感が、宇宙のキリストの秘密のなかでこの上なく美しく共鳴しているのを聴くことができます。キリストを告知するノヴァーリスの言葉が、ゲーテの光に満ちた言葉のなかに流れ込むのを感じるとき、ゲーテのヴェーダの言葉から私たちに光が迸り、光の中に愛と熱が流れ込みます。さらに私たちが別の位置でのゲーテ、つまりゲーテは、宇宙ー統一認識を十全に知覚しつつ、どの魂にもライプニッツ的な意味での独立を認めるのですが(☆5)、そういうゲーテをとらえるとき、サーンキヤ哲学(☆6)の再生の響きであるヨーロッパのモナド論が、言葉の上ではなく心情に即してゲーテから私たちに吹き寄せてきます。サーンキヤ哲学の再生の響きのように当時のヴァイマール、当時のイェナが体験したものすべてへと、ノヴァーリスはキリストに向けられた心とともに成長していきました。そして時にひとは、フィヒテのようにその生硬さのなかで近代的なニュアンスでサーンキヤの心情に浸透された精神を感じ、そしてその精神の傍らに、帰依に満ち熱中しつつその精神を受け入れるノヴァーリスを思うとき、いかにこの精神が時代の真の精神へと和らげられたかを感じるのです。一方ではフィヒテの独特に再生された古インドの言葉が聞こえます、我々を取り巻く世界は夢にすぎず、通常の思考は夢の夢にすぎない、しかしこの夢の世界に力として意志を注ぎ込む人間の魂は現実であると。フィヒテの新たに再生されたヴェーダの言葉(☆7)はこのようなものでした。その傍らにノヴァーリスの確信があります。おお、ノヴァーリスはその確信をほぼこのように感じます。そう、物質的存在は夢で、思考は夢の夢だ、けれどもこの夢からは、人間の魂がその最も価値あるものと感じ感受し、そのように感じ感受しつつ精神的に行為しうるものすべてがほとばしり出ると。そしてノヴァーリスの魂はこの生の夢から、キリストに霊感を与えられた自我から、彼の名づけるところの魔術的観念論を、すなわち精神(霊)に支えられた観念論を創造するのです。そしてノヴァーリスの愛に満ちた魂が、同時代のまた別の精神の英雄のかたわらに立っているのを感じるとき、つまりその観念論によって世界に霊感を吹き込もうと試みたシラーに耳を傾けながら、ノヴァーリスの魂がこの英雄のかたわらに立っているのを感じるとき、さらにノヴァーリスがシラーの倫理的観念論を描き出すことで、彼自身の内部でキリストに霊感を与えられた心からいかに魔術的観念論を告知するかを感じるとき、私たちは、宇宙空間におけるいつもの状態よりもほとんど調和的に何かが結び付き合うのを感じるのです。それにしてもこれは何と深く私たちの魂に語りかけることでしょう、ノヴァーリスが感激してシラーについて書くとき(☆8、*1)の善良さ、ノヴァーリスの最も内面的なヨーロッパの親密な善良さとでも呼びたいこの善良さは。ノヴァーリスにとってシラーがそうであったもののために、人類にとってシラーがそうであったもののために、このシラーを讃えて語るノヴァーリスのこのような言葉を私たちに作用させてみるとき、そこには人間の魂の善意のすべてが、人間の魂の愛の能力のすべてが表現されています。この称讃を表明するために、ノヴァーリスはほぼ次のように言います。私たちが霊たちと呼ぶあの欲望を離れた存在たちが、シラーから流れ出るこれほどの言葉、これほどの人間の智を霊の高みで聴き取ることができるなら、私たちが霊たちと呼ぶ欲望を離れた存在たちですら、人間界に降(くだ)って受肉したいという願いではちきれそうになるだろう、このような人物から流れ出るこのような智を受け取ることを許された真の人類進化のなかで働きかけるために。愛する友人の皆さん。このように敬い、このように愛することのできるのは何という心でしょう。これは、混じりけのない真の献身的尊敬と愛の感情に身を捧げたいと思うすべてのひとにとって模範となる心です。このような心はまた、宇宙と人間の魂の秘密であるものをもきわめて平明に語ることができます。それゆえ、ノヴァーリスの口から発せられた言葉の数々も価値あるものです、三重の人間の潮流から霊へと、あらゆる時代を通じてかくも憧れに満ち、時にかくも光にあふれて鳴り響くことを許されたものを、あたかもふたたび鳴り響かせるかのごとく価値あるものなのです。このように彼は私たちの前に立っています、この三十歳に満たないノヴァーリス、この再生したラファエロ、この再生したヨハネ、この再生したエリヤは。このように彼は私たちの前に立ち、そして私たちはこのように彼そのひとを敬うことを許されています、このように彼は、霊的な世界観潮流のなかで追求される霊の啓示に加えて、私たちがいかに真正の心、真正の愛、真正の情熱、真正の帰依をも見出すことができるか、その道を教える数ある仲介者のひとりなのです、崇高な霊の高みから降ろしてこようとするものを、私たちが最も素朴な人間の魂にも流れ込ませることができるようになるための。と申しますのも、だれかれがこの新たな精神探究の理解しがたさについて何を言おうとも、この理解しがたいというのが真実でないということは、ほかならぬ素朴な魂、素朴な心情によって証明されるでしょうから。なぜなら彼らは、この精神潮流における私たちの追求によって霊の高みから降ろしてこられたものを理解するでしょうから。霊的な高みからのこの道を、私たちは単に、何らかの形である種の知的な精神生活のなかで自らに作用させうるひとたちのためのみ見出そうとするものではありません、真実と霊への憧れを持つすべての憧れる魂のためにこの道を追求していこうとするのです。そしてその平明さによってこそ十分深く捉えられねばならない「叡智は真実のなかにのみある」というゲーテの言葉(☆9)を私たちの序の言葉としたいように、私たちの目指す目標は次のようなものでなければなりません、つまり、私たちが求め耳を傾けるスピリチュアルな生活を、スピリチュアルな力の恩寵によって私たちに与えられるように変容させ、それがありとあらゆる憧れる魂に接近することができるようにこのスピリチュアルな生活を刻印することです。このように私たちは努めなければなりません。実際のところ私たちは、受肉のいかなる段階にあるにせよ、あらゆる探し求める魂への道を見出すべく、働きかけたゆまず心がけたいと思っています。受肉の秘密は奥深く、ほかならぬノヴァーリスそのひとのそれのような受肉の道が私たちにそのことを示してくれます。このノヴァーリス自身が一種の導きの星のように私たちの行く手に輝いています、彼を感じ従いつつ、認識において全力をあげて彼のところまで高まろうという良き意志を私たちが持てるように、また他方で、霊的なものを真実求めるいかなる人の心にも認識とともに押し迫っていこうという生き生きとした意志を私たちが育むように、その星は輝きます。このように、ノヴァーリス自身がかくも見事に語ったもの、そして私たちにとって決意するための一種の座右銘(モットー)でもありうるものが、人智学的な精神潮流の出発点で私たちの前に輝いているのです。精神の言葉が世界観を基礎付けるものであるとき、言葉はもはや単なる言葉ではなく、そのとき言葉は最高の魂にとっても最も素朴な魂にとっても輝き暖めるものとなります。これが私たちの憧れでなくてはなりません。これがノヴァーリスの憧れでもありました。ノヴァーリスはこれを美しい言葉に表現しています、私はこの言葉の最後を一語だけ変更して、愛する友人のみなさん、みなさんの心のためにこれをご紹介させていただいと思います。私はノヴァーリスのこの語を変えます、自分を自由な精神と思い込んでいるうるさがたは少々ご立腹かもしれませんけれどもね。そうしてノヴァーリスの美しい言葉のなかにあるもの(☆10)も、他の導きの星々とならんで私たちの導きの星となりますように。 数と図形がもはや あらゆる被造物の鍵でなくなり、 歌ったり口づけしたりするものたちが 学識深き人たちよりも多くを知るとき、 世界が自由な生へ、 そして世界へと立ち帰るとき、 それからふたたび光と影が結婚し ほんとうの澄みきった明るさが生まれるとき、 そして童話(メールヒェン)と詩のなかに ひとが永遠の世界歴史を識(し)るとき、 そのとき、ひとつの秘密の言葉を前に、 道を誤ったものたちの群はことごとく飛び去るだろう(*2)。 Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren Sind Schluessel aller Kreaturen, Wenn die, so singen oder kuessen, Mehr als die Tiefgelehrten wissen, Wenn sich die Welt ins freie Leben Und in die Welt wird zurueckbegeben, Wenn dann sich wieder Licht und Schatten Zu echter Klarheit werden gatten, Und man in Maerchen und Gedichten Erkennt die ewgen Weltgeschichten, Dann fliegt vor einem(原文斜字) geheimen Wort Das ganze verkehrte Herden-Wesen fort.■編集者註☆1 このように私たちの愛するノヴァーリスの心の響き[…]を聴きますと:この発言の直前に、マリー・フォン・ジーフェルスによるノヴァーリスの「宗教的な歌」の朗唱が行なわれた。☆2 オリエントからかくも輝かしく射してくる光:1912年12月28日から1913年1月1日までの講義『バガヴァッド・ギーターとパウロ書簡』(GA142)参照のこと。☆3 ゲーテは[…]スピノザの世界観から感受しようとしました:スピノザはーー新プラトン主義とデカルトから出発してーー汎神論的な必然性哲学を説いた。彼は倫理的な理想として情念からの解放を提示し、人間は存在物の必然的法則の明確な洞察によって導かれるべきであるとした。ーーゲーテは自叙伝『詩と真実』において、この世界観に影響されたことについて以下のように記している。「かくも決定的に私に作用し、私の思惟方法全体にかくも大きな影響を与えたにちがいないこの精神は、スピノザであった。つまり私は、私の不可思議な本性を教化するすべを見出すべくむなしく世界中を探しあぐねた末に、ついにこの人物の”エーティク”[エチカ]に行き着いたのだ。この作品から何を読み取ったにせよ、作品のなかへ何を読み込んだにせよ、私には釈明の余地はないだろうが、ともかく十二分に、私はこの作品に私の熱情を静めるものを見出した。それは私に感覚的道徳的世界について偉大にして自由な展望を開いてくれるように思われた。[…]すべてを宥和させるスピノザの静謐は、すべてを揺り起こす私の奮闘と対照をなし、スピノザの数学的方法は、私の詩的な感覚の使い方および叙述法の反対であった。そしてひとが倫理的対象に対してはふさわしくないとみなしたがったまさにあの法則的な扱い方こそが、私を彼の熱狂的な弟子、公然たる崇拝者としたのだ。精神と心、理性と感覚が必然的な親和力[Wahlverwandtschaft]をもってたがいに求め合い、この親和性を通じて異なった本性の一致が達成されたのである。」(14 巻第3部)「私は[スピノザの]読書に没頭し、私自身の内を見つめるにつけても、世界をこれほど明瞭に見たことはついぞないと思った。」(16 巻第4部)☆4 ヴェーダ:リシ(聖仙)によって啓示されたインド人の聖なる智慧。インド、インドゲルマン文献のうち最古の記録。☆5 ゲーテは、宇宙ー統一認識を十全に知覚しつつ、どの魂にもライプニッツ的な意味での独立を認めるのですが:1813年1月23 日ヴィーラントの埋葬の日、ゲーテはファルクとの対話のなかでこう述べている(ゲーテと個人的に親しく交流して書かれたファルクの『ゲーテ対話録』チューリヒ1969 第2巻、771頁)。「[…]私はあらゆる存在の究極の根本要素には、つまりいわば自然におけるあらゆる現象の原点(起点[Anfangspunkt])というべきものには、さまざまなクラスや序列があると思いますが、全体の魂化(魂を吹き込むこと)[Beseelung]はここから始まりますので、私はこれを魂[Seelen]、あるいはむしろ単子(モナド[Monaden])と呼びたいと思いますーーライプニッツのこの用語を憶えておいてください!最も単純なものの単純さを表現するのに、これ以上良い表現はないでしょうから。ーーさて、これらの単子ないし起点のうちのいくつかは、私たちに経験が示すとおり、非常に小さく取るに足らないものなので、せいぜい副次的な役割あるいは副次的な存在にしか向いていません。これに対して、非常に強く力強い単子もあります。この後者のような単子は、近づいてくるすべてのものを自分の圏内に引きずり込んで自分に帰属するものにしてしまうことを常としています、つまり、人体や、植物や、動物や、さらには天の星にまで変化させるのです。そして、その志向を霊的に内在させている小世界(小宇宙)あるいは大世界(大宇宙)が外的に姿を表わすまで、それは続けられます。この後者の単子のみを私は魂と呼びたいのです。その帰結として、世界単子、世界魂が存在するように、蟻の単子、蟻の魂が存在し、両者はその起源においては完全にひとつとは言えないまでも、元なる存在という点では親和性のある、ということになります。」☆6 サーンキヤ哲学:六つの古典的正統的なインド哲学体系のひとつ。シュタイナーの1912年12月28,29,30日の演『バガヴァッド・ギーターとパウロ書簡』(GA142)、また1909年9月16日の講演『ルカ福音書』(GA114)に見られるサーンキヤ哲学についての言及も参照のこと。☆7 フィヒテの新たに再生されたヴェーダの言葉:ヨーハン・ゴットリープ・フィヒテ『人間の使命』(1800年フランクフルト及びライプツィヒ)を参照のこと。第2巻「知識」には、「あらゆる実在/Realitaet)は、夢見られる生も夢見る精神もない不可思議な夢に転ずる、自己自身についての夢のなかで凝集する夢に。直観(直観すること/Anschauung)は夢であり、思考(思考すること/Denken)私が空想するあらゆる存在とあらゆる実在の源泉、私の存在の、私の力の、私の目的の源泉ーーは、かの夢の夢である」とある。☆8 ノヴァーリスがかつて感激してシラーについて書くとき:1791年10月5日、ノヴァーリスはイェナ大学哲学教授ラインホルト(1758ー1823)(*1)宛にこう書き送っている。「シラーは幾百万の凡人を超えています、私たちが霊たちと呼ぶあの欲望を離れた存在たちに、死すべき者となりたいという望みを抱かしめたのですから。シラーの魂は愛情をもって(コン・アモーレ con amore )自然を形づくったように見えます、彼の倫理的な偉大さと美は、彼自身がそこに住まう世界を、定められた没落から救済することができるでしょう[…]」ノヴァーリス著作集、Paul Kluckhohn 編、ライプツィヒ(出版年なし)、第4巻『書簡と日記』(Nr.21)22頁。☆9 「叡智は真実のなかにのみある」というゲーテの言葉:『箴言と省察』☆10 ノヴァーリスの美しい言葉のなかにあるもの:『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』[邦訳『青い花』未完]の遺稿に見られる詩。この続編を企図したティークの報告も参照のこと(Paul Kluckhohn 編ノヴァーリス著作集 第1巻『文芸作品』244,251頁)。最終行はノヴァーリスでは Das ganze verkehrte Wesen fort 「狂った(あべこべになった、道を誤った)ものはすべて飛び去るだろう」となっている。■訳註*1 ラインホルト:Karl Leonhard Reinhold ノヴァーリスはイェナ大学在学中にこのラインホルトとシラーに深く影響を受けた。ノヴァーリスはフィヒテをとくに深く研究したが(彼の父がフィヒテの学資援助者であった関係もあって個人的にも早くから交流があった)、フィヒテはラインホルトの後任として1794年からイェナの教授となった。*2 シュタイナーはこの詩の最終行にHerden(群れ)という一語を付け加えてHerdenーWesen としています。 『青い花』遺稿に見られるこの詩の邦訳をここにいくつかご紹介しておきます: もしも数と図形が、 すべての自然の鍵でなくなり、 もしもすべての自然が、深遠な学者が知っているよりも豊かに、 歌い、接吻するならば、 もしも世界が自由な命(いのち)のなかにおもむき、 自由な世界にもどるならば、 もしもそれから、光と影がふたたび結婚して、 まことの澄みきった明るさが訪れるならば、 そしてひとが童話(メールヒェン)と詩のなかに 真実の古い歴史を識るならば、 そのとき、一つの秘密の言葉をまえにして、 逆さまになっていたすべてのものが飛び去るだろう。 (中井章子訳) 最早数や図形などが すべての被造物を解く鍵ではなく、 歌ったり口づけし合う人々が 学者たちより知に勝るとき、 そして世界が自由な生へ、 <自由な>世界へふたたび帰り、 こうしてふたたび光と影が 真の明澄へと結び合わさり、 ひとびとが童話と詩の中に <古い>真の世界歴史を認識するとき、 ひとつの神秘な言葉の前に、 狂ったものはすっかり飛び去る。 (薗田宗人訳) もはや数学と図形が 全ての存在物をとく鍵とはならず、 歌い口づけしあうものたちが、 深い学識の人より多くを知るなら、 世界が自由な生活へと戻るならば、 そして再び光と影が交わって 真の光明に変じるならば、 メールヒェンと詩の中に、 <もとの>真の世界の歴史が認められるならば、 その時こそ秘密のひとつの言葉から、 狂ったものはすべて飛び去る。 (青山隆夫訳)※ドイツ・ロマン派の詩人ノヴァーリスの小説『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』(原題)の邦訳名である『青い花』は、肺結核による29歳前のノヴァーリスの死により未完に終わっています。1799年秋から翌年にかけて書き始められ、1802年に発表されました。ドイツロマン主義文学の未完の傑作。詩人を志す主人公ハインリヒの現実世界での冒険と出逢いと、心理世界における旅の記録。本作は未完であるがゆえ、後半の第二部は作者の友人やその他遺稿に基づく構想集となっている。本作がロマン主義の傑作たりえた理由はこの不完全性、「未完故の余白の多さ」にあるのではないか。未完ゆえに解釈の余白、構想が読者たちによってもたらされていく。そしてロマンの象徴である青い花は己の心や身近にしかないことを示す。参考画:Rose Blue Novalis人気ブログランキングへ
2024年05月09日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神的な探求における真実の道と偽りの道」 (GA243)佐々木義之 訳 トーケイ、ディヴォン、1924年8月11日-22日第十一講 精神的な探求と精神的な探求の理解とはどのような関係にあるか 今回の講義の中で私が触れたよりもさらに多くのことがらをつけ加えることはもちろん可能なのですが、今日はこのテーマ全体を総括することによって、それらを結論づけるように努力することにしましょう。今回の講義全体を通して私たちが取ったアプローチが投げかける重要な問題とは、人智学あるいは人智学として提示されるような精神的な探求に対する態度とはどのようなものであり得るか?ということです。今日、別の世界に関する人智学的な記述を感じ取り、それを完全に自分で検証することを可能にするような精神的な訓練や実践に直ちに取りかかることができる人はほとんどいないと思われます。では、そのとき、人智学が教えるところのものを理解するという点に関しては、どのような立場があるのでしょうか。 この問題は、人智学を取り上げなければならないという衝動、あるいは憧れさえをも感じるような人々の心のすぐ近くに横たわっているのですが、いつも間違った光の下に眺められ、正に、私がこの連続講義の中で擁護してきたような正しい手続きが把握され得ないために誤解される可能性が高い問題となっているのです。人々は次のように問うかも知れません。私が自分でそれをのぞき見ることができないとすれば、精神世界についてのこれらの記述は一体何の役に立つのかと。そこで、今日は、ざっとした分析の中で、この問題に触れてみたいと思います。自分で精神世界を探求できない限り、人智学の教えやその理解に対する正しい洞察を獲得することはできないと言うならば、それは真実ではありません。特に、現代においては、別の世界に関する事実を実際に発見するということがそれらの事実を理解するということから区別されるというのが本質的なことなのです。今日、私たちが知っているような人間について、彼は実際には別の世界に属しているのであって、彼の経験は別の世界から導き出されるのだということを思い起こすならば、この区別は皆さんにとって明らかなものになるでしょう。今日のように構成された人間にあっては、その一連の知識とその日常的な意識は彼が毎日の経験を通過する中で獲得されます。この意識は私たちの探求の出発点なのですが、それは、人間が目覚めて生活をしている間、ある限定された分野について、つまり、感覚知覚によって近づくことができるとともに、人間がその進化の過程で発達させてきたところの知性という手段によって把握し、説明することができるような世界の側面について、彼に一定の見通しを与えることができるだけなのです。人間は、その理解力によって、既に指摘したような漠としてはっきりしない仕方で、夢の中に、つまり現象世界の背後に隠された世界の中に貫き至ります。彼は、その魂的な生活の中で、彼が死と再生の間に通過する世界との接触を持つのですが、ただ、それは夢のない眠りの中においてであり、そこでの彼は、精神的な闇に取り囲まれ、通常は思い起こすことができない生活を送っているのです。人間は三つの意識状態-覚醒、夢、そして深い眠り-を知っています。しかし、彼はこの三重の意識によって近づくことができる世界の中でのみ生きているのではありません。と申しますのも、彼はその王国に多くの邸宅を持つ存在だからです。彼の肉体は、そのエーテル体が住む世界とは異なる世界に住んでおり、エーテル体はまたアストラル体とは異なる世界に、そして、その両方ともが自我とは異なる世界に住んでいるのです。そして、この三重の意識、はっきりとした覚醒意識、夢の意識、そして眠りの意識(意識が存在しないと言いたいかも知れませんが、それは減退した意識としてしか記述することはできません)は、今日見られるような自我に属しています。そして、この自我は内側を見るときにも三つの意識状態を有しています。それが外側を見るときには、目覚めの(昼の)意識、夢の意識、そして眠りの意識があるのですが、内側を見るときには、まず、はっきりとした知的な意識があります。次に、感覚意識、すなわち感覚生活があるのですが、これは通常、想像されているよりもはるかに不透明で夢のようなものです。そして、最後に、漠とした黄昏のような意志の意識があり、これは深い眠りの状態に似ています。通常の意識によっては、眠りの起源を説明できない以上に、意志の起源を説明することはできません。人間が意志の行為を遂行するときには、明確ではっきりとした思考が伴っています。さらにこの思考にはより不確かな感情が被せられています。感情に浸透された思考は四肢へと降りて行くのですが、その過程を通常の意識によって経験することはできないのです。私が昨日と一昨日お話しした種類の探求に対して意志が提示する図とは次のようなものです。つまり、思考が頭の中で何かを意志し、それが感情を通して体全体に移されることによって、人間が彼の体全体で意志する間、微妙で繊細かつ親密な燃焼過程に近い何かが生じるというような図です。人間は、秘儀に参入する意識を発達させるとき、熱の影響にさらされるところのこの意志の生活を経験することができるようになるのですが、それは通常の意識には隠されたままに留まります。これは意識下に横たわるものがいかに秘儀に参入する意識レベルにまで上昇させられるかを示すひとつの例です。昨日触れた本の情報がますます公のものとなるとき、人々は、人間によって遂行される意志の行為が秘儀に参入する意識の中で熟考されるとき、それはろうそくの光、あるいは暖かさを与える光の点火をも見ているような印象を与えるということに気づくことになるでしょう。私たちは、ちょうど、この場合には、外的な現象についての明確な像を有しているように、意志の中に沈殿したものとしての思考を見ることができるようになっているでしょう。そのとき、私たちは、思考が感情を発達させる、感情から、それは人間の中で下降する方向に向かいますが、暖かさの感情、人間の中の炎が発すると言います。そして、この炎が意志するとき、それは段階を追って点火されることになります。私たちはこの通常の意識を次のような図式で示すことができます。(「内的」 「外的」 明晰な思考 目覚めた昼の意識 感情生活 夢の意識 意志の意識 眠りの意識)さて、それにもかかわらず、精神的な世界を探求するためには、私たちは、必然的に、私たちの意識を私たちが意識的に理解しようとする世界に向けなければなりません。とはいえ、もし、私たちの探求の果実を正直に伝えようとするならば、口頭で伝えられる考えは、それとは別の意識形態を持つ言語によって表現されなければならないのです。多分、皆さんには、これは二重の過程である、ということがお分かりでしょう。私たちは、まず第一に、例えば、私が昨日説明したような人間の器官の世界を探求します。私たちは、人間が、その人生の経過を通して、精神世界に近づくとき、彼の中に突然現れる力を利用して問題の現象を探求します。私たちがそのとき見いだすのは、その理解の範囲内で現れる事実です。そして、世の中には、これらの事実に気づき、それを世界に伝える人たちがいるのですが、そのような人たちによって世界に伝達されるそれらの事実は、もし、私たちが必要な客観性をもってそれらを見るならば、通常の意識によって理解することが可能なのです。人間進化の過程においては、いつの時代にも、精神世界に関連した事実の探求に自らを捧げ、その探求の成果を他の人々に伝える少数の人たちがいたのです。さて、今日、あるひとつの要素がそのような知識の受容に不利に働いています。それはつまり、一般に、人々は、ある社会環境の中で、そして、彼らがただ事実の世界、感覚の世界、そして感覚の世界から導かれる論理的な情報だけを信じるようになるまでに彼らの習慣的な反応を条件づけるような教育システムの下で成長するということです。この習慣はあまりに強く、根深いために、人々の間には、「大学には、教えることに加えて現象世界のある実際の側面について研究する、あるいは、教育の分野で他の研究者が見いだしたことを確かめるような教育学部の卒業生がいる」と言う傾向があるほどです。誰もが彼らの発見を受け入れ、自分でその事実を探求しないときでさえ、それを信じているのです。この際限のない馬鹿正直さは特に現代科学のために取っておかれています。人々は、洞察を有している人にとっては、単に問題が多いというだけではなく、全くのうそであるところのものを信じているのです。この状況は何世紀にもわたる教育の結果として現れてきました。この教育の形態はそれ以前の世紀に生きた人間にとっては見知らぬものであった、ということを指摘したいと思います。彼らはまだ彼らの意志と感情に適合していた精神的な世界に対する古い洞察のいくらかをまだ保持しており、その中に参加していたために、精神的な事実を探求する人たちを信じる傾向の方がはるかに大きかったのです。今日の人々はそのような知識とは無縁です。彼らは、大陸においてはより理論的なものとして、イギリスとアメリカにおいてはより実践的なものとして今やしっかりと確立された観点に慣れ親しんでいるのです。大陸には、これらのことがらについての詳細な理論が存在する一方、イギリスとアメリカには、彼らにとってそれを克服するのが決して楽ではないようなそれらに対する本能的な感情が存在しています。何世紀も経過する間に、人類は現象世界に関連する科学的な観点に慣らされ、例えば、天文学、植物学、動物学、医学等を、有名校や学習センターで教えられるような形で受け入れるようになったのです。例えば、化学者が彼の実験室で何らかの研究に取りかかるとき、人々はそこでどのような技術が使われているのかをほとんど理解していません。その仕事は喝采をもって迎えられ、彼らは躊躇なく「ここには真実がある、信仰に訴えかける必要のない知識がある」と断言するのですが、実際、彼らが知識と称しているところのものは信仰なのです。現象世界を探求し、論理という道具によって現象世界の法則を確かめるために採用される方法の中には、ひとつとして精神世界についてのほんのわずかの情報さえも提供するものはありません。しかし、精神世界全体をそれなしで済ますことができる人もほとんどいません。そうできるという人は自分に正直なのではなく、そう思いこんでいるだけです。人類は精神世界について何かを知るという差し迫った必要を感じているのです。人々は、現在知られているような精神世界について彼らに何ごとかを語る人たちをまだ無視していますが、歴史的な伝統や聖書の教え、東洋の聖典についての話しを聞く準備はできています。彼らがこれらの伝統的な書物に興味を持つのは、それ以外には、精神世界との何らかの関係をもつという彼らの必要性を満足できないからです。そして、人々は、聖書や東洋の聖典が個々の秘儀参入者によってのみ探求されてきたという事実にも関わらず、それらの聖典は別の種類の見方を反映しており、現象世界の知識、科学的な知識とは関係がなく、信仰に依存し、信仰に訴えかけるものであると主張します。こうして、科学と信仰の間には厳格な仕分けの線が引かれ、人々は科学を現象世界に、信仰を精神世界に関連づけるのです。大陸の福音派教会の神学者たち、福音派や自然科学者の二元論を認めず、古い伝統を保持するローマカトリック教会の神学者ではありませんが、彼等の間に存在しているのは、知識には明確な境界線があり、信仰が問題になるのはその向こう側であるということを示すための無数の理論です。それ以外の可能性はないと彼らは確信しているのです。イギリスではそれほどまで悪夢に悩まされるということはありません。しかし、それは理論化することがそれほど一般的ではないからです。そこでは、科学が語るべきことには耳を傾け、信仰の中では-私は、信心家ぶってとまで言うつもりはありません-敬虔に生きることによって、これらふたつの領域を厳密に切り離しておくというのが伝統的な態度になっているのです。過去のある時代においては、俗人と学者がこの観点を採用していました。※プラトンとアリストテレスの師弟関係と思想対決:哲学者アリストテレスの師はプラトンで、プラトンの師はソクラテスです。つまりギリシア哲学は三代はっきりと連続性のある直接的な結びつきがあるわけです。そしてアリストテレスは観照的生活、現代に言う合理的を理想として自分でも学問一筋な生き方をしたが、師のプラトンやソクラテスはそうではありませんでした。つまり、弟子は師の教えるところを鵜呑みにして同意した「信仰」ではなく、その思考論理を学び自己実践したのです。哲学とは自己の思考を持って思想を確立することが本分だからです。参照画:Plato and Aristotle ニュートンは重力理論、つまり、正にその本性によって、いかなる精神的な見方の可能性も排除するところの空間概念に関する理論の基礎を打ち立てました。もし、世界がニュートンによって記述された通りのものであったとすれば、それは精神を欠くものであったでしょう。しかし、それを認める勇気を持ち合わせている人は誰もいません。神的-精神的な存在がニュートン的な世界の中で生き、活動し、その中に存在するということを想像することなど誰にもできないのです。けれども、精神を排除する空間と時間の概念は、この考えを信奉する人たちによってだけ最終的に受け入れられたのではなく、研究活動に独自で取り組む人たちによっても受け入れられることになります。ニュートン自身が後者のよい例です。と申しますのも、彼は精神的なものを排除する世界観の基礎を据えただけではなく、同時に、黙示録に関する自身の解説の中で、精神的なものを完全に受け入れているからです。現象世界の知識と精神世界の知識との間の結びつきは断ち切られてしまいました。今日、理論家たちはこの二元論のしっかりとした証拠探しに乗りだしています。そして、理論を信用しない人たちの思考と感情にこの考えを植え付けることによって、最終的に彼らを条件づけるためのあらゆる努力がなされているのです。他方、人間の知性、理解し、考えるための力、思考能力は、今日、もし、彼がそれらに対する意識的なコントロールを保持しているとすれば、理論によっては秘儀に参入する科学の教えを探求することはできないにしても、理論によってそれを把握することができる地点にまで達しています。本質的なのは、次のような観点が広く受け入れられるということです。つまり、精神世界への探求は以前の受肉からの力を現在の地上生において呼び出すことができる人たちによって引き受けられなければならない、何故なら、精神的な探求を行うために必要な力はそのような力から導かれるからであるが、この探求の結果はますます多くの人々によって受け入れられ、理解可能な考えの中に取り込まれることになるだろう。さらに言えば、精神的な探求の結果が他の人々の健全な理解力によって受け取られるとき、この理解力のお陰で、これらの人々が、精神世界について、本当の経験をするための道が準備されることになるというような観点がです。と申しますのも、しばしば述べてきましたように、精神世界に参入するための最も健全な道とは、まずそれについて書かれているものを読む、あるいは、それについて語られることを自分のものにするということだからです。もし、私たちがそれらの考えを受け入れるならば、それらは内的に生き生きとしたものになり、私たちは、理解する、ということだけではなく、カルマ的な発達にしたがって、超感覚的に見るということをも達成することになります。これとの関連で、私たちはカルマの考え方を深刻に受け止めなければなりません。今日の人間はカルマに関心を持っていませんから、ちょうど実験室で硫黄を分析するように、いわゆる超常現象と言われるものの起源を実験室的な手法によって分析できると信じていたり、通常ではない認識形態を示す人を、硫黄と同様に、実験室的な試験に供しなければならないと信じているのです。けれども鉱物としての硫黄はカルマを有していません。人体に関連した硫黄だけがカルマを有しているのです。何故なら、カルマに左右されるのは人間だけだからです。実験室において人間のカルマの一部を試験することが、もし、その探求が何らかの価値を持つべきであるならば、必要な前提条件となるであろうと仮定することは私たちにはできないのです。私たちが精神科学を必要とするのはこの理由によります。他の人の手助けによって精神世界の知識を獲得することを私たちに可能にするようなカルマ的な条件を探求することがまず第一に必要になるかも知れません。私の著書「神智学」の最近の版では、その最後のところでこのことが明確に説明されています。今日の人類にはこの考えを受け入れる準備ができていませんが、それは彼らが無能であるからではなく、保守的であるからなのです。けれども、それは途方もなく重要な考えなのです。私たちは直ちに精神世界の探求に取りかかる必要はない、しかし、他方で、もしカルマ的な必然性がないところでカルマの実験をしたり、私たちが理解しない技を使う霊媒たちを使って実験するというような望ましくないやり方を採用せず、この世に適した意識状態であるところの日常意識を頼りにするならば、私たちは秘儀に参入する科学が伝えるものについての完全な理解に至るであろうということに気づくこと、それが本質的なことなのです。もし、とりあえず自分自身で精神的な世界を経験できないならば、それを理解することはできないだろうと想像するならば、それはとんでもない間違いです。「自分でそれを経験できないならば、精神世界が何の役に立つのか。」と言うとすれば、それは今日よく犯される別の間違いを助長することになります。それは最も大きな、最も危険な、最も明らかな間違いを犯すことであり、人智学協会のような運動に携わる人たちは、そのことをはっきりと意識しているべきです。この物理平面上における人間の存在は別の世界における存在と結びついています。このことは、偏見のない見方に対しては、次のような事実、つまり、人間の経験とは、その経験全体という光の中で見たときには、人生における最も決定的な問題との関係で、ある意味では、それらが密接に関連しているにもかかわらず、お互いに無関係のように見えるために、通常の日常意識によっては理解されないという事実によって説明することができます。ですから、ここでは簡単な説明しかできませんが、まず最初に、人間の物理世界への参入と退出、つまり、誕生と死についてお話ししたいと思います。私たちの地上における人生の中で最も重大なできごとである誕生と死は通常の意識にとっては別々の現象のように見えます。私たちは、誕生に先立つものすべて、つまり、人間の受肉に関係するものすべてを私たちの地上における人生の始まりに関係づけ、死をその終わりに関係づけます。それらは引き離されているようにも見えます。しかし、精神的な探求を行う人にはそれらがますます接近するのが分かるのです。と申しますのも、もし、私たちが月の秘儀へと導く道を辿り、昨日お話しした仕方で夜を昼の中に召還するならば、私たちは、いかに肉体とエーテル体が誕生の過程の中でますます成長し、繁栄するようになるかを、つまり、いかにそれらが芽の状態から段々と人間の形を取るようになるかを、そして、いかに地上に生きる間、それらの活力が、35才になるまでは、ますます増加するとともに、その後は段々と減少し、衰退が始まるかを知覚するからです。もちろん、この過程を外的に観察することはできませんが、昨日お話しした月の道を辿る人は、肉体とエーテル体が細胞状態から成長し、発達するとともに胎児の形態を取る一方、人智学ではアストラル体と自我と呼ばれる別の生命形態が衰退と死の力に曝されるということを知覚するのです。私たちが生命の奥深くに隠された場所を暴くとき-これについては昨日、具体的な記述を行いました。私たちは肉体とエーテル体の誕生、そして、アストラル体と自我の死を意識するようになるのです。私たちは死が生命に織りなされ、人生の冬がその春と提携させられるのを知覚するのです。そして、ここでも、私たちが秘儀に参入する意識をもって人間を観察するとき、私たちは、人間の体が衰退する一方で、35才を境に、自我とアストラル体が芽吹き始めるということを意識するようになります。この芽吹く生命は肉体とエーテル体の中に存在する死の力によって遅延させられますが、にもかかわらず、はっきりとした再生が本当に生じるのです。そして、そのようにして、私たちは、精神的な探求という手段によって、「生命の中には死が存在し、死の中には生命が存在している」ということに気づき始めます。参考画:多細胞型ロボット こうして、私たちは、誕生の時点で死んでいくのが見られるところのものをそれらがその十全たる意義と偉大さにおいて現れる地上以前の生活にまで辿っていくための準備をするのです。また、私たちは、衰退していく肉体とエーテル体の中に、アストラル体と自我が徐々に芽生えてくる。と申しますのも、それらは肉体とエーテル体の中に捕らえられているのを知覚し、それらが、死の瞬間に、肉体とエーテル体から精神世界へと解き放たれるのを追っていく準備をします。このように、誕生と死はお互いに相関しているにもかかわらず、通常の意識には別々のできごとのように見えるということが分かります。精神的な探求によって明らかにされるこれらの情報のすべては、今日の講義の最初に示したように、通常の意識によって把握することができるのですが、同時に、通常の意識には実証的あるいは科学的な証拠を要求するのを諦めさせる準備ができていなければなりません。かつて、次のように主張した男がいました。ちょうど石が地面に落ちるように、椅子を持ち上げて離せばそれもまた地面に落ちる。何故なら、すべては重力に曝されているのだから。したがって、もし、地球が支えられていなかったとすれば、それも必然的に落下するだろうと。彼が気づきそこなっていたのは、物が地面に落ちるのは地球の引力に引きつけられているからであって、地球自体は、お互いに支え合い、引きつけ合っている星のように、自由に空間中を動いているということです。現代の科学者のように証明が感覚的な証拠によって支えられていることを要求する人は、地球は、もし、しっかりとピンで留められていなければ、落下するに違いないと信じているこの男に似ています。人智学的な真実はお互いを支え合う星のようなものです。全体的な構図を見る準備ができていなければなりません。そして、もし、それが可能であったとすれば、人々は誕生と死の相互関係というような人智学的な考えを本当に把握し始めることでしょう。話しをもう少し進めて、現代科学の原則にしっかりと基づいている一方で、人智学的な考えにも注意を払うとともに、受容的であるにもかかわらず、人間全体を考慮に入れることは学んでおらず、昨日お話しした仕方で、個々の器官だけを考慮する人の場合を取り上げてみましょう。秘儀に参入する過程の中で獲得されたその器官についての知識を通して、私たちは誕生と死だけではなく、何か全く異なるものをも意識するようになるのです。この器官についての光の下では、誕生と死はその通常の重要性を失います。と申しますのも、死ぬのは人間全体であって、彼の個々の器官ではないからです。例えば、彼の肺は死ぬことができません。今日の科学がぼんやりと気づいているのは、人間全体が死んだとしても、彼の個々の器官はある程度賦活されることができるということです。人間が埋葬されようと、火葬されようと、彼の個々の器官が死ぬということはないのです。それぞれの器官はそれぞれが関係づけられているところのあの宇宙領域へと向かう道を辿ります。人間が地下に埋められたとしても、それぞれの器官はそれぞれの場合に応じて水、空気、あるいは熱を通って、宇宙への道を見いだします。実際には、それらは解消されるのですが、消え去るのではありません。消え去るのは全体的な人間だけなのです。ですから、死が意味を持っているのは全体的な人間に関してだけです。動物においては器官は死にますが、人間においてはそれらは宇宙へと解消されるのです。それらは急速に解消されます。埋葬はよりゆっくりとした過程であり、火葬はより速い過程です。私たちは個々の器官が無限へと向かう道、それぞれがそれ自身の領域へと向かう道を辿るのを追っていくことができます。それらは無限の中に失われるのではなく、昨日お話ししたような力強い宇宙的な存在形態を取って還っていくのです。こうして私たちは、秘儀に参入する意識をもってその器官を観察するとき、死に際してそれらの器官に一体何が降りかかるのかを、つまり、いかにそれらの器官がそれぞれが属する宇宙領域へと流れ出していくのかを見ます。心臓は肺とは異なる道を、肝臓は肺や心臓とは異なる道を辿ります。それらは宇宙全体にばらまかれるのです。そして、宇宙人間が現れます。つまり、私たちは彼を宇宙に組み込まれた真の姿において見るのです。そして、この宇宙人間の視覚の中で、私たちは例えば引き続く受肉の源泉とは何かについて意識するようになります。私たちは、以前の地上生が現在の人生にカルマ的に戻ってくることを再び、明確に、はっきりと意識することができるようになるためにこの視覚を必要としているのですが、その視覚はその起源を人間全体の中にではなく、いくつかの器官の知覚の中に有しているのです。月の道を通って精神世界に接近した人たち、神秘家や神智学者たちはきわめて不思議な現象、かつては地上に生きていた人間の魂、神、そして精神を知覚したのですが、彼らには、それが一体何者なのかを理解したり、決めたりすることも、そこにいるのがアラヌス・アプ・インスリスなのか、ダンテなのか、あるいはブルネットー・ラティーニなのかをはっきりさせることもできませんでした。それらの実体はときとして最もグロテスクな名で呼ばれました。つまり、彼らには、そのとき接触している受肉が彼ら自身のものであったのか、それとも別の人々のものであったのか、あるいは、それらが何者であったのかを決めることができなかったのです。ですから、精神世界は昼の中に招き入れられた月意識の領域と関連しているのですが、金星衝動の流入によってこの視界が失われ、私たちは、今や、精神世界をその全体性において眺めることになります。しかし、それは本来そうあるべきであるような明確に規定された世界ではありません。私たちが全体としての人間の世界的な状況、宇宙存在としての人間の立場に最初に気づき始めるのはこの領域においてなのです。けれども、この関連で、私たちは悲劇的な現実に気づかざるを得ません。と申しますのも、もし、人間がこの地上ではそのように見えるところの完璧に物理的な人間でさえあったならば、彼はきわめて有徳かつ素直、そして高貴な存在であったはずだからです。ちょうど、通常の意識をもってしては、死について探求することがほとんどできない。死についてはいつでも既に示唆したような意味で理解することができます。こように、私たちは、通常の意識という手段によっては、何故、人間は正直そうな顔をして-彼らが正直そうな顔をしていることは否定できません。悪いことができるのかを知ることはほとんどできないのです。悪人になることができるのは全体としての人間ではありません。現在のような彼の外皮、皮膚は高貴で善良なものなのですが、人間はその個々の器官を通して悪人になるのです。つまり、悪の可能性は彼の器官に存在しているのです。こうして私たちはそれらの器官とそれに対応する宇宙領域との関係、あるいは悪への強迫観念がどの領域にその起源を有しているのかを理解するようになります。つまり、基本的には、ほんのわずかでも悪が現れるところには必ず強迫観念が根底にあるのです。こうして、私たちの人間全体に関する知識によって、まず、誕生と死が明らかなものとなり、次に、彼の有機体についての知識によって、彼の宇宙に対する関係が健康や病気すなわち悪において明らかになります。そして、私たちが、人間の器官学を通して、宇宙人間を眺めることができるとき、私たちはゴルゴダの秘儀を経験したあの存在を初めて精神的に知覚することができるようになるのです。と申しますのも、キリストが太陽からやってきたのは宇宙人間としてだったからです。その瞬間に至るまで、彼は地上の人間であったのではなく、宇宙的な形態をとって地球に接近したのです。もし、まず最初に、宇宙人間をその真の姿において理解する準備が私たちにできていないとしたら、どうしてそれを認識することができるでしょうか。 キリスト教が発展していくことができるのは、正にこの宇宙人間についての理解からなのです。こうして、いかに真の道が精神世界に向けて、つまり、誕生と死、人間有機体の宇宙に対する関係、悪の認識やキリスト、すなわち宇宙人間についての知識へと導くかが分かります。このすべてが理解できるようになるのは、それらが様々の側面でお互いに支え合っているのが示されるというような仕方で提示されるときです。そして、精神世界への道を見いだすための最良の方法とは、理解すること、そして、理解したものを瞑想することです。瞑想のためのその他の原則は付随的な役割を果たします。今日の人間にとっては、これが精神世界への正しい道なのです。他方、意識の正常な道筋を維持し、利用することに失敗するその他のあらゆる方法、霊媒術、夢遊病、催眠術等々のトランス状態を用いるあらゆる試み、意識によっては理解できない世界事象についての現代自然科学を戯画化したものであるところの方法によるあらゆる探求。これらすべては偽りの道です。何故なら、それらは真の精神世界には導かないからです。精神的な探求により見いだされたものを人間が感覚的に意識するとき、すなわち、器官に関する知識を通して宇宙人間が返ってくるということ、秘教的な探求と洞察に明かされるもののすべてが秘儀に参入する意識に受け入れられ、彼の意識生活の重要な部分になるならば、ある程度、この宇宙人間の帰還はキリストの理解へと導くことができるということを人間が意識するとき、感情を通して、神が地上的なものの中に現れるのです。そして、そこに芸術の本分があります。芸術は人間が今お話ししたような道に沿って精神的な世界から受け取るところのものを感情を通して半意識的に体現します。ですから、いつの時代でも、精神的なものに物質的な形態をまとわせてきたのは、そのカルマによってそうすることが運命づけられた人々だったのです。私たちの自然主義的な芸術は精神的なアプローチを捨て去りました。芸術の歴史における絶頂期においては、精神が感覚的な形態の中に示されるか、あるいは、むしろ物質的なものが精神の領域に引き上げられました。ラファエロが高く評価されるのは、他の画家たちよりもはるかに高度に、精神的なものに感覚的な表象という衣を着せることができたからです。さて、芸術の歴史の中には、より造形的、写実的な芸術への傾向を持つ一般的な動きが存在していました。今日、私たちはもう一度、造形芸術に新しい命を吹き込まなければなりません。それは、何年も昔に当初の衝動の直接性が失われてしまったという理由によります。何世紀にもわたって「音楽」への衝動が増大し、広がってきています。したがって、造形芸術は多かれ少なかれ音楽的な性格を持つようになっています。言語芸術における音楽的な要素を含めて、音楽は未来の芸術であることを運命づけられているのです。ドルナッハの第一ゲーテアヌムは音楽的に構想されましたが、そのため、その建築、彫刻、及び絵画はほとんど理解されませんでした。同じ理由により、第二ゲーテアヌムもまたほとんど理解されないでしょう。と申しますのも、絵画、彫刻、そして建築には、人間の未来の進化と調和して、音楽の要素が導入されなければならないからです。人間進化における最高の地点として私が言及したキリストという存在の到来、精神的に生きたものであるところの存在の到来は、ルネッサンスあるいはルネッサンスに先立つ時代の絵画の中にすばらしい描写を見いだしましたが、未来においては、音楽を通して表現されなければならないでしょう。キリスト衝動に音楽的な表現を与えようとする衝動は既に存在しています。それはリヒアルト・ワーグナーの中で予見され、最終的に「パーシファル」が創造される原因となりました。けれども、「パーシファル」においては、キリスト衝動の現象世界への導入、そして、そこでは、最も純粋なキリスト精神に表現を与えることが追求されたのですが、その導入においては、ドーブ等の登場に見られるように、象徴的な示唆が与えられているに過ぎません。聖餐式もまた象徴的に示されました。「パーシファル」の音楽では、宇宙と地上におけるキリスト衝動の真の意義が表現できていないのです。音楽はこのキリスト衝動を音楽的に、つまり、精神によって内的に浸透された調べの中で表現することができます。もし、音楽が精神科学によって霊感を吹き込まれるのにまかせるとすれば、キリスト衝動を表現する道を見いだすことになるでしょう。と申しますのも、いかにキリスト衝動が調べの中で、交響曲的に、宇宙と地上において目覚めさせられるかが、音楽によって、純粋に芸術的に、そして先験的に明らかにされることになるからです。そのためには、隠された感情の深みに貫き至るところの音楽的な経験を内的に豊かなものにすることによって、正に、長三音階の領域についての私たちの経験を深めることができるようになる必要があります。もし、私たちが長三度の領域を人間の内的な存在の内部に完全に包み込まれた何かとして経験するならば、そして、そのとき、完全五度の領域が「包み込む」性格を有しているのを感じ、それによって、私たちが五度の構成の中へと成長して行くならば、私たちは人間的なものと宇宙的なものとの境界に達することになります。そこでは、宇宙的なものが人間的なものの領域の中へと鳴り響くとともに、あこがれに燃え上がる人間的なものが宇宙的なものへと殺到することを希求しています。そして、そのとき、長三度と完全五度の領域の間で演じられる秘儀の中で、宇宙的なものへと到達する何か人間の内的な存在のようなものを音楽的に経験することが可能になるのです。そして、もし、私たちが、そのとき、七度の不協和音を、そして、それは、人間が様々な精神的な領域に向けて旅をするとき、大宇宙の中で経験するところの感覚的なものを表現しているのですが、その不協和音を解き放ち、宇宙的な生命を響かせることに成功するならば、つまり、もし、私たちが七度の不協和音を死滅するにまかせ、その死滅を通して、それらにある種の確かさを獲得させることに成功するならば、それらは、死滅する調べの中で、音楽的な耳にとっては何か音楽の大空に似たものの中へと最終的に調和させられることになるのです。ですから、もし、私たちが、既に「長調」によって「短調」をかすかに示唆した後、七度の不協和音が死滅しつつある緊張の中で、つまり、この不協和音の全体性への自発的な再創造の中で、七度の不協和音から、あるいは、これらの消滅しつつある不協和音が調和に近づきつつあるところから、短調の雰囲気の中で、五度の領域に移行する方法を見いだすならば、そして、その地点から五度の領域に短三度の領域を混合させるならば、私たちは、それによって、受肉についての、そして、もっと言えば、キリストの受肉についての音楽的な経験を呼び覚ますことになるでしょう。私たちは、一見したところ八度音階によって支えられていることによって、宇宙的な感情にとっては単に見かけ上不協和音であるに過ぎない七度の領域、私たちが「大空」へと形成するところの七度の領域に向けて手探りで歩み出るのですが、もし、私たちが、そのとき、それを感情で把握した後、既にお示しした仕方で私たちの歩みの跡を辿るとともに、いかに、私たちが、短三度和音の胎児的な形態の中に、受肉を音楽的に表現する可能性があるかを見いだすならば、この領域において、私たちが長三度への私たちの歩みの跡を辿るとき、キリストへの「ハレルヤ」がこの音楽的な構成の中から純粋な音楽として鳴り響くことができるようになります。人間は、そのとき、その調べの構成の中で、超感覚的なものについての直接的な認識を魔法のように出現させ、それを音楽的に表現することでしょう。キリスト衝動は音楽の中に見いだすことができます。そして、ベートーベンの中に見られるような交響曲的なものの不協和音に近いものへの解消は、音楽における宇宙的なものによる支配への回帰によって救い出されることが可能になります。ブルックナーは、伝統的な枠組みという狭い範囲においてですが、これを試みました。しかし、彼の死後に発表された交響曲は彼がこの限界から逃れられなかったということを示しています。私たちは、その偉大さを賞賛する一方で、真の音楽的な要素に接近することへの躊躇、そして、私たちが既にお話ししたような仕方で出現させるところの、つまり、純粋音楽の領域に歩みを進め、そこで、調べを通して、ひとつの世界を魔法のように出現させるところの本質、すなわち、根本的な精神を見いだすときに初めて経験することができるこれらの要素を十分に実現することに失敗しているのを見いだすのです。もし、人類が退廃へと沈み込んでいかないとすれば、私がお話しした音楽的な進歩がいつの日か達成される、ということに疑いはありません。そして、最終的には、それは完全に人類にかかっています。キリスト衝動の真の本性が外的に明らかにされることになります。このことに皆さんの注意を促したのは、皆さんに、人智学は人生のあらゆる側面に浸透することを求めているということに気づいていただきたかったからです。もし、人間が、彼の方で、人智学的な経験と探求への真の道を見いだすならば、これは達成されることができるでしょう。いつの日か、音楽の領域が人智学の教えの中にこだまし、キリストの謎が音楽を通して解決されるということさえ起こることでしょう。以上述べたことによって、私が思い描いていた目的を示すとともに、今回の連続講義では単に示すことができただけのものを結論づけることができたならばと思います。しかし、付け加えさせていただきたいのは、人智学的な真実についての何らかの認識が皆さんの魂の中に呼び起こされるとともに、これらの真実が成長し、増大し、ますます広い人間生活の分野を豊かなものにするようになればということです。人智学が達成しようとしているはるかな目的にとって、この連続講義がささやかな貢献となります。 (第十一講・了)参考画:Space Harmony※宇宙(space)、宇宙全体(universe)、秩序ある調和のとれた宇宙(cosmos)に関連する「harmony」は、宇宙のあらゆるものが互いにつながっているという考え、または宇宙のあらゆるものが複雑な関係の網目の一部であるという信念を意味します。人気ブログランキングへ
2024年05月08日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神的な探求における真実の道と偽りの道」 (GA243) トーケイ、ディヴォン、1924年8月11日-22日 佐々木義之 訳第十講:地球外宇宙が人間の意識に及ぼす影響 昨日は、精神世界への異常かつ病理的なアプローチについて、つまり、一方では、内的な理解の深化を通る道、夢の世界により深く貫き至る道について、他方では、実際には自然科学的な手法を戯画化した方法を用いて、夢遊病者や霊媒が外的に表現するものを探求しようとする道についてお話ししました。私は、私たちが本当に秘儀に参入する認識を獲得しようとするならば、これらふたつの道を意図的に追求しなければならないということを指摘しました。今日は、この問題をさらに綿密に検討するとともに、人間の意識やその存在全体が左右されるところのあの宇宙的な影響を探求するということを提案したいと思います。人間に及ぼす影響の中では、地球の影響を除けば、太陽と月の影響が卓越している、ということは容易に分かります。一般に、人々はこのことに対してそれほど注意を払っていませんが、今日では、太陽の放射がなければ地上には何も存在し得ないということは科学者にとってさえ明らかな事実です。太陽の力は植物の生命を地球から魔法のように出現させます。その力はすべての動物の生命と人間の肉体及びエーテル体にとって不可欠なものです。太陽の働きは、私たちがそのつもりになって探せば、いたるところに見いだされるでしょう。つまり、それらは、人間存在の高次の構成体にとって、決定的に重要なものなのです。ところが、月の影響に対してはそれほど注意が払われていません。そのような影響が今日まで生き残っているとしても、しばしば迷信という形においてであり、それらについての正確な認識はしばしばその影響についての迷信的な概念の存在によってねじ曲げられたものになっています。今日、科学の分野で働こうとするような人は、自分は迷信とは無縁であると感じていますから、月の影響が何らかの意義を有しているとは考えず、それについて真剣に考えてみようとも思いません。けれども、月の不思議な力が詩的なイマジネーションを刺激することに気づいている詩人たちや、月の光の下で熱い思いを交わす恋人たちだけではなく、それぞれ異なる仕方ですが、地球に対する月の影響についての予感を持つ賢者たちもたまにはいます。そして、これは非常に教示的である、ということを証明することができます。十九世紀中頃のドイツにシュライデンとグスタフ・テオドール・フェヒナーという二人の教授が生きていました。フェヒナーは人間と自然のより幅広い領域における神秘的な働きについての科学的な探求に傾倒していました。彼はある特定の地域における降雨量が月の満ち欠けに関係していることを示すデータと統計的な証拠を集め、降雨量は月の満ち欠けによって変化すると結論づけました。彼は当時の科学理論に反する彼の立場を迷うことなく主張しました。彼の大学の同僚であり、著名な植物学者であるシュライデン教授の見解は異なっていました。彼は、フェヒナーの考えはばかげている、月のそのような影響について語るのはナンセンスである、と断言したのです。さて、二人の教授は結婚しており、当時彼らが住んでいた大学町の雰囲気はまだ家族的なものでした。当時は、布を洗濯するのにちょうどよいというので、主婦たちによって雨水が貯められる習慣がありました。月の影響を議論していたのは二人の教授だけではなく、彼らの妻たちもまた問題の核心に迫ろうとしていたのですが、ある日、フェヒナー教授が妻に言いました。シュライデン教授は降雨量が月の満ち欠けに影響されるということを信じようとしない。貴女にはある月周期に、シュライデン教授夫人には別の月周期に雨水を集めてもらいたい。シュライデン教授は月の満ち欠けがそのようなことに影響するということを信じていないのだから、これに異を唱えるはずがないと。ところが、シュライデン教授夫人は、フェヒナー夫人に、彼女の夫の説によると降水量が多いはずのない月の周期を担当させることに乗り気ではなかったのです。大学も家族もふたつに分かれていつもの論争は続きました。さて、このできごとには科学的な根拠があります。精神科学の方法によってこれらの影響について調べますと、単なる迷信の名残としてではなく、科学的な事実として太陽と月の強力な影響について語ることができるのが分かります。私たちはこのように述べることによって、通常の意識を有する現代人がこのテーマについて知ることができる事実上すべてのことを言い尽くしてしまいました。現代人はいわば地球、太陽、そして月の影響下で生きており、基本的には、その意識もまたそれらに依存しています。何故なら、既に指摘したように、星や太陽、そして月の目に見える外的な側面は決定的な要素ではないからです。月の領域には、太古の時代に人類の教師であったあの存在たちがかくまわれているということについては既に強調されました。太陽の領域にも非常に多くの精神的な存在たちがかくまわれています。ちょうど地球が人類の宇宙的な植民地であるように、すべての星は存在たちの植民地なのです。既に指摘したように、今日の人間はその誕生から死までの間、ほとんど地球、太陽、そして月の影響だけの下に生きています。私たちが今獲得しなければならないのは、人間が太陽と月の影響下に生きるときの精神的、魂的、そして物理的な条件についてのより正確な知識です。注:生物が生きていくためには、適度な温度、気体の酸素の存在、液体の水の存在が必要だと考えられており、これらの条件を満たす領域をハビタブルゾーンといいます。ハビタブルゾーン(Habitable zone、HZ)とは、太陽のような恒星の周りを回る惑星で、液体の水が存在できる範囲のことです。日本語では生命居住可能領域や生存可能圏とも呼ばれます。ハビタブルゾーンの範囲は恒星の明るさで決まり、太陽系の場合、太陽から地球までの距離の0.95~1.5倍程度です。ハビタブルゾーンより内側では海水がすべて蒸発する「暴走温室状態」、それより外側では海水がすべて凍結する「全球凍結状態」になります。参考図:Habitable zone 夢の状態がそれらの間に横たわるところの意識のふたつの極-覚醒意識と空虚な眠りの意識、つまり夢のない眠りの意識について考えてみましょう。アストラル体と自我から肉体とエーテル体が引き離された状態にある眠っている人間を観察するならば、彼が眠りに落ちてから目覚めるまでの間、肉体とエーテル体から引き上げられた太陽の影響がアストラル体と自我の中に注意深く保持されているのが分かります。私たちは、起きてから眠るまでの間、太陽を外的に経験し、雨によってその影響が全く覆われているときにもそれを意識しています。それは私たちが周囲の事物を反射された太陽光のお陰で知覚できるからです。私たちは目覚めているときの生活全体を通して、外から事物を照らし出す太陽の影響に曝されているのです。私たちが眠りの状態に移行するやいなや、太陽は私たちの自我とアストラル体の中で輝き始めます。私たちは私たちの精神の目でそれを知覚します。眠ってから起きるまでの間、太陽は私たちの内部にあります。皆さんご存じのように、ある種の鉱物は光を照射されてそれを吸収した後、暗い部屋の中に放置されるとき、周りを照らすようになります。精神的に見ると、人間の自我とアストラル体は同様の形式にしたがっています。それは覚醒状態では、ある程度外的な太陽光に圧倒されていますが、眠ってから起きるまでの間は、今や太陽光が浸透していることによって、輝きを発し、照らし始めるのです。要するに、起きている間、人間は外的な太陽の力の影響下に生きているのですが、眠っている間は、目覚めの瞬間に至るまで、今や彼自身の内に担っている太陽の力の影響下にあるのです。私たちは、眠っている間、太陽を私たちの内に有しており、肉体とエーテル体だけが後ろに残されるのですが、それらは私たちの内に保存された太陽の光によって外から、精神的な世界から照らされるのです。事実、私たちは保存された太陽光を外から私たちの皮膚に振り向け、あるいはそれを感覚器官に同化させることによって、私たちの有機体に活気や生き生きとした成長力を供給しているのです。ですから、実際、眠っている間、アストラル体と自我は肉体とエーテル体の外にあり、人間はまず最初に彼の皮膚を照らし、そして、太陽の光を目と耳を通して神経系に振り向けるのです。眠りの現象とはこのようなものです。太陽は人間の自我とアストラル体から輝きだし、皮膚を照らし、感覚の扉を通って人間存在へと貫き至るのです。そして、月の力は、それが新月であるか満月であるかによらず-と申しますのも、その影響は、月の相によって変化するとはいえ、いつでも存在しているからですが-人間の肉体とエーテル体に外から侵入してきます。ですから、眠っている間は、自我とアストラル体からやって来るところの太陽による肉体とエーテル体への働きかけとともに、肉体とエーテル体に対する月の働きが見られるのです。眠りの状態は、宇宙との関係で、このように特徴づけられます。眠っている間、人間の内的な生活は太陽と、その外的な生活は月と関係づけられています。と申しますのも、アストラル体と自我は外にあるとはいえ、それらは実際には彼の内的な存在であるからです。(Schlafen 眠りrot 赤色Sonnenwirkungen vom Ich und Astralleib自我とアストラル体からの太陽の働きMondenwirkungen vom aussen auf den physischenLeib und Aeterkeib肉体とエーテル体への外からの月の働きWachen 覚醒gelb 黄色Sonnenwirkungen von aussen auf physischen Leib und Aetherleib肉体とエーテル体への外からの太陽の働きgelb 黄色gruen 緑色innnerlich Mondenwirkungen auf Ich und Astralleib自我とアストラル体への内的な月の働き)目覚めの生活においては状況は逆になります。私たちが起きているときには、月の影響が私たちの内的な存在全体に浸透する一方、太陽の影響は外から私たちの中に侵入します。ですから、目覚めの生活においては、太陽の影響は直接私たちの肉体とエーテル体に流れ込み、私たちの内なる自我とアストラル体は蓄えられた月の力に左右されているのです。ですから、目覚めて生活している間、私たちの肉体とエーテル体の中には太陽の力が外から流れ込み、私たちの内的な存在には蓄えられた月の力が浸透します。眠っている間は太陽が、起きている間は月がアストラル体と自我に居住し、起きている間は太陽が、眠っている間は月が肉体とエーテル体に居住しているのです。徹夜をしたり、眠りを犠牲にして次の日の二日酔いを招いたとしても、これらの影響はやはり存在しています。と申しますのも、人間が自然の法則をあえて無視したとしても、自然の慣性力、宇宙的な継続性のお陰で、ことは自然の成り行きに従うからです。人間が昼間眠り、夜起きていたとしても、月の影響は、夜の目覚めの生活において、やはり彼の自我とアストラル体の中で活動しています。そして、太陽の影響もまた彼の中に流れ込むのですが、彼がそれを経験するのは、通常は街灯から投げかけられる光や、野宿して星を見上げるときのその弱い光を経験するであろうようにしてです。とはいえ、人間が眠っている間に蓄える太陽の力や、起きている間に彼の内的な存在に浸透する月の力は至るところに存在しています。肉体とエーテル体に関してはその立場が逆転します。人間は生まれてから死ぬまでの通常の意識をこのようなものごとのあり方に負っているのです。さて、人間がより高次の意識形態を達成するとき、状況がどのように変化するかを考察してみましょう。と申しますのも、秘儀に参入した人の太陽と月に対する関係は徐々に変化するのですが、この宇宙に対する関係の変化を通して、人間は精神世界への道を見いだすことになるからです。通常の意識状態にある人間について、その世界に対する関係、太陽や月に対する関係を記述する必要はないでしょう。人間が昼の意識や夜の意識の中でどのように生きているかを思い起こせば、誰にでもそれが分かります。人間が、通常は混乱した夢の意識との関係で、内的な魂の力を強化し始める瞬間、つまり、この夢の意識をして現実を理解するための道具に変化させることに成功する瞬間、彼は、起きている間は集積された月の力が自我の中に存在しているということに気づくようになります。人間が、秘儀に参入する認識を通して、実際に夢を現実に変化させる瞬間、彼は彼の中にいる第二の存在を感じ、この第二の存在の中には月領域の力が生きているということを知るのです。人間は、秘儀に参入する意識の初期の段階において、自分の中には月の力が存在しており、その力は第一の人間の中に収められた第二の人間をその中でいつも発達させようとしている、ということに気づくようになるのですが、そこでひとつの衝突が起こります。目覚めの意識においてではなく、眠っている間に、今お話ししているこの第二の人間の中で、月の力が内的に活性化し始め、この内的な力によって第二の人間が自然へと解き放たれるとき、つまり、彼が月の存在によって夜に解き放たれ、眠りの受動的な状態の中で意識に目覚め始めるとき、第一の人間、つまり通常の人間の中に隠された第二の人間が月の光の中で第一の人間を連れて辺りをさまよい始めるのです。これが眠りながら歩く人の特徴である夢遊病的な状態の起源です。月が外を照らすとき、魔術的な力、つまり自然の力とは種類が異なる変則的な力との接触を持つ第二の人間を目覚めさせることが可能になるのです。彼は辺りをさまよい始め、減退した意識状態の中で眠りながら歩く人として、通常の意識とは異質の仕方で振る舞います。彼は、通常であればそうするであろうように、ベッドに横たわるのではなく、辺りをさまよい、屋根に登ったりするのですが、彼が探し求めているのは、実際には彼の肉体の外側で経験すべき領域なのです。このことが、意識的かつ内的な経験になり、正常な道筋へと導かれるとき、私たちは秘儀に参入する意識への最初の一歩を踏み出すことになります。けれども、この場合、私たちが接触するのは実際の外的な月の影響ではありません。第二の人間が意識を発達させるのを可能にするのは、私たちの存在の中にある月の力です。私たちはこの第二の人間がさまよい出るのを何としてでも阻止しなければなりません。それが亡霊のようにさまよい出て、間違った道に沿ってうろつく危険性はいつでも存在しています。第二の人間はコントロールされていなければならないのです。この遍歴する可能性のある第二の人間が体の内に留まり、肉体と関連する正常で当たり前の意識に結びついた状態で秘儀に参入する意識を獲得するためには、内的な安定と自己自制が不可欠です。私たちは、この第二の人間が創り出したもの、強化された内的な月の本性が創りだしたものが私たちから自らを解き放つのを阻止するように、絶えず努力しなければなりません。第二の人間は、新陳代謝、蠕動運動、胃やその他の器官に関係するあらゆるものに強く引きつけられ、それらに重くのしかかります。人間の中で、秘儀に参入する意識が夜明けを迎えていることを示す最初の経験とは、彼が取るべきふたつの道の内のひとつ-発達へと導く道、夢の世界の意識的な認識へと導く道にしたがっているということです。そして、もし彼が-そして、これは、既に指摘したように、必要なステップなのですが、今、夢の状態の中で意識的になるならば、彼は、外は昼間であるにも関わらず、自分の中に夜を担っているとうことに気づきます。何か内的な夜のようなものが昼の間に彼の中で目覚めるのです。この秘儀に参入する意識が目覚めるとき、外的な目と外的な事物の認識にとって昼間は昼間なのですが、この昼の間に、きらめく月の精神的な光が辺りに浸透し、照らし始めます。そして、精神が輝き始めるのです。私たちはこのようにして、人間は内的な努力によって昼の意識の中に夜の意識を持ち込む、ということを悟ります。このことがしっかりとした意識の中で、ちょうど他の活動が昼の間に意識的に遂行されるように、生じるとき、つまり、この寝ずの番をする人間が夜の月の活動を昼間の目覚めた経験へともたらすことができるとき、彼は正しい道を歩んでいます。もし、彼が、十分に意識的でないままに、何かが自分の中に入り込むのを許し、それによって夜の経験が、それら自体の内的な惰性から、昼の意識の中に生じるようにするならば、彼は、結局は霊媒主義につながる間違った道の上にいる自分を見いだします。ですから、本質的なのは、私たちは十分に意識的であるとともに、経験を十分にコントロールしていなければならない、という点です。現象や経験そのものよりも、私たちがそれらにどのように反応するかが決定的な要素なのです。もし、通常の夢遊病者が、屋根のてっぺんに登っているときに、十分な意識を発達させることができたとすれば、彼は、その瞬間、秘儀に参入するとはどういうことなのかを経験するでしょう。私たちが彼に向かって目を覚ますように叫ぶとき、彼は地面の上に落ちてくるのですが、それは彼がこの意識を発達させるのに失敗しているからです。もし、彼が、落ちてくるかわりに、十分に目覚めた意識を発達させ、この状態を維持することができたとすれば、彼はそのとき秘儀参入者になっていることでしょう。秘儀に参入する意識がやるべきこととは、夢遊病者の中で病理的に発達させられるものを健全な、あらゆる面で健全な道筋に沿って発達させるということなのです。このように、精神世界においては、真実と偽りとの差がいかに紙一重であるかがお分かりでしょう。物理世界においては、真実と偽りとを区別するのは難しくありません。それは常識に訴えたり経験を積むことができるからです。精神世界に参入するやいなや、この区別をつけるのが極端に難しくなります。それは自制と内的な気づきに左右されます。さらに言えば、人間が昼間に夜を目覚めさせるとき、月の光はその外的な放射の性格を徐々に失います。その経験はどちらかというと外的なものではなくなり、内的な居心地のよさというような一般的な感じをもたらします。けれども、私たちは何か別のものも意識するようになります。すばらしく輝く水星の光がこの精神的な夜の空を照らすのです。水星という惑星が、昼の中へと誘われたこの夜の中に本当に昇るのです。とはいえ、それは水星の物理的な側面ではありません。何故なら、そこで私たちは何か生きたものの存在に気づくからです。私たちには水星の居住者である生きた精神的存在たちをすぐに意識することはできませんが、水星が私たちの前に現れるその仕方から、私たちは、自分は精神的な世界と関係しているのだという一般的な印象を持つのです。精神的な月の光が、私たちの内で、生命を与える普遍的な賦活力、私たちがその一翼を担うところの賦活力になるとき、水星という精神的な惑星が昼の意識の中へと誘われた夜の意識の中に徐々に昇ってくるのです。水星はきらめく黄昏の中から現れてくるのですが、そこから浮かび上がってくるのは私たちが水星の神的な存在と呼ぶところの存在です。私たちは彼を絶対的に必要としているのですが、その理由は、もし、彼がいなかったとすれば、混乱が始まるからです。まず第一に、私たちはこの存在を、つまり私たちが水星に属していると確信している存在を精神的な世界の中に見いださなければなりません。私たちはこの神的な存在(水星)を意識することを通して、私たちの中で目覚めさせられる「第二の人間」を意のままにコントロールすることができるようになるのです。私たちはもはや夢遊病者のようにつまずきながらあてどもない道を行くのではなく、神の使者である水星の導きの手によって、精神世界へと続くはっきりと規定された道に沿って導かれることができるようになります。ですから、もし、精神世界への真の道を見いだしたいのであれば、私たちはまず、私たちを導き、方向づけするのに役立つある明確な経験を通過しなければなりません。通常の神秘家は内側を見ます。彼は内省を通して、神や宇宙、天使や悪魔が調合された感情の発酵体を生じさせますが、その内省が行き着く先はせいぜい通常の夢の状態です。そこでは、それらが性的な局面からやって来たのか、あるいは知的な局面からやって来たのかを告げることはできません。その経験は一般に混乱し、漠としたものです。これは夢を照らし出すことのない漠然とした雲のような神秘主義であり、秘儀に参入した人だけが理解できることから、混乱をより深刻なものにする神秘主義です。そのような経験は、シエナのカトリーヌやその他の人々によって記述されたように、非常な驚きと詩情に満ちているのですが、それを理解することができるのは秘儀に参入した人だけなのです。何故なら、経験されたものが何かを本当に知っているのは彼だけだからです。ですから、もし、私たちが、計算をしたり、幾何学を研究したりするときと同じような、明晰ではっきりとした意識をもって秘儀に参入することを求めるならば、つまりもし、これらのことがらに十全なる意識をもって貫き至るならば、私たちは正しい道の上にいるのです。私たちは、内的な月の夜を外的な昼の中に招き入れることを実現することによってのみ、真の精神世界を発見することができるのです。ちょうど、月や水星が外的な空間の中に昇ってくるのは現実であり、夢のような幻想ではないということを否定できないように、私たちが十全なる意識をもって精神的な世界に入っていくとともに、ちょうどこの地上で人間に出会うように、精神的な存在たちにそこで出会うとき、それもまた同様に現実的な世界なのであり、幻想ではないのだ、ということが分かるのです。私たちが精神世界の本性を意識することなく精神的なものを求めるとすれば、私たちは必ず間違った道筋に沿っています。もし、私たちが、地上に留まりながら、霊媒やその顕現に関する実験に満足し、精神的なものとの直接的な接触を持たないとすれば、私たちは間違った道の上にいいます。精神的な世界の中で意識を目覚めさせることなく、例えば表面的な神秘主義のように、つまずきながら手探りで進み、成果だけを求めるようなあらゆる活動は、間違った道の上にいます。精神的な世界に貫き至るに際して、直ちにこの世界を精神的な現実として経験するところのあらゆるものは、正しい道の上にいます。ですから、月領域に関する内的で生きた認識は秘儀参入への道のひとつの出発点なのです。そして、私たちは次のように言うことができるでしょう。太陽と月の関係において、普通は眠りの中で経験されるところの人間の通常の経験を、秘儀参入者は今や目覚めた生活の中で経験する、と。人間は月の影響を、それがまるで彼にとって外的なものであるかのように意識するようになります。彼は夜を昼の中に招き入れます。そして、私たちの精神の目には、私たちが夜空を見上げるときに通常見られるような星が散りばめられた夜空ではなく、まず水星という惑星が昇ってくるのが見られます。そして、もし、私の本「より高次の世界の認識」に書かれている指示にしたがって、真のイマジネーションを発達させることに成功していたとすれば、そのイマジネーションの世界が、私たちが目覚めて生活している間、ひとつの現実としてこの月領域の中に現れてきます。水星の影響が及ぶ領域に私たちが参入するとき、これらのイマジネーションは水星存在たちに移行します。私たちは今や、現実に欠けた単なるビジョンを経験するのではなく、イマジネーションとしてのビジョンを知覚するのですが、これらのイマジネーションはそれぞれ対応する存在たちに移行するのです。ですから、もし、私たちが秘儀に参入する道に沿って十分に前進していないとすれば、私たちは大天使についてのビジョンを持つかも知れませんが、それはビジョンのままに留まるのです。そのビジョンが実際に大天使との接触を持ち、真の大天使がそのビジョンの中に現れるのは私たちがもっと進歩した段階に達している場合だけです。それより前の段階においては、私たちが私たちの内に月の光を経験したとしても、必ずしも大天使がそこにいるとは限らなかったのです。しかし、今や、大天使は現実のものとなりました。こうして、私たちは、私たちの視覚世界が実際に私たちが精神を知覚するところの世界へと移行する中で、水星の影響を意識するようになるのです。私はこのことをいつも強調しなければならないのですが、これが正しい仕方で達成されるのは私たちが完全に意識的であるときだけなのです。そしてさらに、もし、私たちが私たちの瞑想をさらに追求するとともに、私たちの内的な存在をますます強化し、活性化させるならば、私たちは水星の影響に金星の影響が加えられる領域に至ります。そして、金星の影響との接触を持つとき、つまり、金星がこの昼へと招き入れられた内的な夜の中に昇るとき、イマジネーション的な光景、すなわち真の視界を現す像の中に現れた存在たちが視界から失われ、私たちは空になった意識をもって精神的な世界に直面することになります。そこには精神的な存在たちがいる、ということを私たちは知っています。私たちは精神的な存在たちが住む金星領域に到達したのです。私たちは太陽領域が近づいてくるのを待ち受けます。今までのプロセス全体が再び太陽を経験するための準備だったのです。このすべてが生じるのは、私たちが目覚めた昼の意識を保持しながら外から太陽の影響を受けているときです。私たちは既に述べられた道を月から水星、そして金星へと辿ります。そして、視界が失われ、私たちはさらに押し進みます。それは地球から月、水星、金星、そして、ついには太陽へと続く道だったのです。私たちは太陽の内的な存在へと参入し、再び太陽を、今度は精神的に眺めます。それは見たところとらえどころがなく、はっきりとしてはいませんが、私たちは、私たちがそれを精神的に知覚しているということを知っています。私たちは太陽の内的な存在をじっと見ているのです。乱暴な比較ですが、それは次のように言うのと似ているでしょう。遠くに何かあるので近寄ってみる。最初はじっとしている物体だと思ったが、取り上げてみると私の手に噛みつく。そこで、それはじっとした物体ではなく、本物の犬であることが分かる。私はそれが内的な存在によって所有されているのに気づくと。この乱暴な比較によって、皆さんは、これらの経験が現実に根ざしているという事実に注意を払うかも知れません。私たちは、地球から出発して、月の影響を通過し、水星、金星を通って、太陽を眺める段階へと至ります。そこで、私たちは、それは生きた精神的な存在である、その中には精神的な存在が生きているということに気づきます。これがまず第一に辿ることができる道です。秘儀参入者が進歩するときには、この道のどの段階においても十分な意識を保持していなければならない、そのとき、彼は正しい道の上にいる、そしてもし、人間がどのような方法であれ、彼の体を離れ、意識を失い、そして、彼の眼前で精神的な現実となった宇宙へと参入するならば、彼は間違った道の上にいるということが十分に明らかになります。私たちは、内的で精神的な知覚に向かう真の道と偽りの道との間の違いを内的に意識しなければなりません。私は昨日、いかに様々の心霊的あるいは秘教的な団体が、時代の要請にしたがって、自然科学的な手法を戯画化した方法により、外的な現象を通して精神的な世界を探求しようと試みているかを示しました。誤解しないでいただきたいのですが、私はこれらの方法をけなしているのではありません。と申しますのも、私は人間が、外的な現象の観察を通して、精神的な世界の真の本性を科学的に認識することをいかに熱烈に望んでいるかを痛いほど知っているからです。私が指摘したいのは、いかにこれらの道が必ず間違いへと導くかということ、そして、真の道の本性とはいかなるものでなければならないかということです。私たちは科学の時代に生きており、これからも生きていかなければなりませんから、自然科学の直接的な方法によって精神的な世界を探求したいと考える人たち、その他の純粋に精神的な道は信頼に足るものではないと考える人たちがいるであろう、ということはよく理解できます。そして、彼らは、一方では、通常の世界があり、その中で生きる人々、社会生活が要求するものを満たし、この社会生活との関係で考え、行動する人々がいるという結論に達します。そこには何も特別なものはありません。それは受け入れられる生き方です。科学的な探求の分野では外的な現象、すなわち熱、光、電気、磁気等々が問題になります。他方、人生においては、普通ではない状況が生じます。人間は自動筆記を行い、催眠術や誘導の影響下で様々の行為を遂行します。彼らはこの方法で通常の世界の中に見知らぬ世界が現れるのではないかと疑い、これらの外的な兆候や普通でない現象を説明しようとします。通常のニュースは無線で伝えられる一方、彼らは、どのようにしてニューヨークにいる人の考えや経験がテレパシーによってヨーロッパに住むその人と魂的に親和性のある友人に伝えられるかを説明しようとします。この種の現象に関しては無数の例を引き合いに出し、自然科学の統計的な方法によって研究することができるでしょうが、この道はいかなるゴールにも、最終的な理解にも導きません。何故なら、精神世界そのものの中に求められるべき人間の方向づけ、必要とされる精神的な方向づけを欠いているからです。これらの現象のすべては、それらがどれほどすばらしくても、外的な世界における雑多な現象の寄せ集めのように見えます。私たちはそれらについての認識や理解に到達することはできません。それらを記録し、途方もないものであるとみなし、精神世界についての仮説を打ち立てるのですが、それは無意味なのです。何故なら、それらの現象自体がその源泉を精神世界の中に有しており、それらがその真の本性を簡単に漏らすことはないからです。私たちがいかに霊媒や科学的な事実に取り組んだとしても、精神的な世界はいつでも私たちとともにあるにもかかわらず、その真の本質が明かされることはありません。この関連で、皆さんには、昨日触れた私とベークマン博士の研究を思い起こしていただきたいと思います。今、これらの現象を正確に記述しようとする試みがなされています。夢の内的な生活に光を投げかけようとする別の探求の道については既にお話ししましたが、ちょうどそれと同じく、この探求方法も精神的な洞察なしには成り立ちません。その探求は、探求すべき現象が精神世界そのものにおけるそれらの対応物に直接関係づけられるというような仕方でなされます。けれども、これらの現象は私たちが、ちょうど今お話ししたような仕方で、外的な世界において出会うところの個々の奇跡的なできごととは関係がありません。それらが属している領域とは、医学や解剖学、生理学の訓練を受け、人間の器官(肺、肝臓、あるいはその他の器官)の外的な形態についての知覚がこれらの器官のイマジネーション的な理解に向けて変容を遂げ、徐々に人間の有機体をイマジネーションにおいて見ることができるようになり始めた人によって知覚されるところの領域です。ですから、このことが可能になるのは、自然における通常の外的な現象ではなく、異常な現象と同じ仕方で働くところの人間の器官について私たちが研究することができるときなのです。つまり、それが可能になるのは、私たちが当初の人間的、科学的、解剖学的な認識を人間の有機体へと精神的に貫き至るものに変容させる立場にあるときなのです。以前に私がお話しした方法では、私たちは人間存在全体を出発点とします。私たちが精神的な解剖学を通して直接知覚し、理解するところの個々の人間の器官から出発する道は、自然科学を戯画化したものである統計的な手法によって外的な現象を理解しようとする偽りのアプローチとは対照的に、真の結果へと導くことができる道なのです。このことからお分かりのように、これらのことがらを議論することができるようになるためには、この道筋に沿って訓練を受けてきた臨床家の協力が必要だったのです。さらに言えば、この観点から解剖学を見る人は、このような方法で人間の器官を精神的に理解するとき、目の前のゴールについていかなる疑いも心に抱くべきではない、ということがお分かりでしょう。そして今、精神的な知覚の前に、以前に述べたような内的な人間ではなく、もちろんまだ漠然とはしていますが、力強く、巨大な姿をした外的で宇宙的な人間-全体として知覚されるのではなく、彼の器官の内的で精神的な知覚を通して現れるような人間が明らかになります。単なる物理的な人間ではなく、宇宙的な人間が出現するのは、これらの器官が精神的に眺められるからです。ちょうど、以前に、夜の世界-月の領域-が昼に招き入れられたように、今や私たちがこの存在、それは完全な人間ではなく、個々の器官から構成されている存在なのですが、その中に招き入れるのは土星領域の衝動なのです。ちょうど、以前の段階において、月の領域が通常の目覚めた意識の中に招き寄せられたように、今や土星の領域が科学的な意識の中に招き寄せられるのです。私たちは土星の力があらゆる器官の中で特別な仕方で働いているのに気づくようになります。その働きは肝臓の中では特に強く、肺の中では比較的弱く、頭部においては最も弱くなっています。こうして、私たちは、いたるところで土星の影響を探す、という私たちに課せられた目標を意識するようになります。ちょうど、私たちが、以前の段階において、瞑想を実行することによって精神的に前進したように、今や、土星の探求、すなわち、個々の器官の内的で精神的な構造の探求と同化することによって、私たちは木星領域へと貫き至り、あらゆる器官は、実際、神的-精神的な存在の地上における対応物であるということに気づくようになるのです。人間は、彼の内に、神的-精神的な存在のイメージを彼の器官として担っています。宇宙全体は、最初、土星領域の中に巨大な存在として出現したのですが、巨大な宇宙的存在としての人間全体が、何世代にもわたる神々の内的-有機的な共同作業の総体として現れるのが見られるのです。私たちはここでも、精神的な経験をする過程で私たちを支え、保持することができる力によって活性化されたように、十全たる意識の中でこの道を追求しなければなりません。私たちは、これらすべての影響はまず第一に胎児の段階に現れるが、その出現は一時的なものであるということを心に留めなければなりません。それらの存在に気づくのは実際には容易なことなのですが、もし、私たちが本質的な危険に屈するならば、つまり、この領域で生じるあらゆるものが私たちの意識から直ちに消え失せ、そのため、私たちはそれについてじっくりと考える立場には決してないという本質的な危険に屈するならば、それらを記述すること、それらの明確な印象を保持すること、それらを心的なイメージへと形づくることはできません。さて、今日、魂の探求に従事する人たちは精神を顧慮することなど夢にも思っていません。彼らは自分たちのやり方、つまり、あれこれの人を実験室に呼んでテストしながら仕事をすることを好みます。けれども、精神的な現実は人間のレベルにまで引き下げられることはありません。このような方法でそれらを理解し、徐々に科学的な解釈に到達するつもりであると公言する場合は特にそうなのです。昨日お話しした医学書に可能なのは、はるかな未来において十分に発達した科学になることができるところのものへの最初の基本的な導入を提供する、ということだけです。けれども、これらのことがらが今日の精神的な世界に存在し、地上にではなく、太陽上に生きる存在たちにとって自然なものである程度に応じて、それらは今お話しした仕方で地上的な意識の中にもたらされることができます。私たちは、実験室における実験手段や教科書の中に見られるような抽象的な解剖学によって精神的な洞察を発達させることができる、と想像すべきではありません。すべての精神的なことがらは人間自身によって直接経験されなければならないというのが本質的な点なのです。何故そうなのでしょうか。私たちがこれらの現実を光の中にしっかりと保つことができるのは、それらが人間の共通の努力から生じる力によって、つまり、人間が地上における以前の受肉から導き出す力によって支えられ、保持されるときだけだからです。このことが起こるとき、土星と木星の領域の世界に私たちが火星の領域と呼ぶところのものが入ってきます。それらはインスピレーションを通して現れます。そして、私たちはインスピレーション意識をもって再び太陽へと戻るのです。これは今日の自然科学が要求するところのもうひとつの道、昨日お話しした秘儀参入者たちが避けたがる道です。彼らはこの道との接触へともたらされるとき、落ち着かなく感じるのですが、にもかかわらず、それは従うべき道なのです。この議論からお気づきと思いますが、月領域を通過する道は古い秘儀参入者たちには全く適したものだったのです。この月の道に関しては、H.P.ブラバツキーの中にすばらしい記述があります。もし、私たちが真実を作り話から区別することができるならば、「シークレットドクトリン」の中には多くの重要な真実を見いだすことができます。けれども、この道はH.P.ブラバツキーが密接に関係していた月のアストラル的な光の領域を通過する道です。そこでは気高い水星の使者が彼女の解釈を方向づけていました。私たちが彼女の論説を追っていくとき、いかに彼女が絶えず彼女のイマジネーションを正しい源泉へと向かわせていたかということに気づきます。ブラバツキーのすばらしいところは、最初に彼女がイマジネーションへと促されるのを感じるやいなや、それが直ちに実現するという点です。彼女は水星の使者によって秘密の図書館へと導かれます。考えが彼女の中で形を取ると、水星の使者が彼女をバチカンによって注意深く守られていた本へと導くのです。彼女はその本を読み、私たちは、もし、そうでなかったとしたら、バチカンによって何世紀もの間、用心深く守られてきたために、彼女にはアクセスできなかったであろうような様々な情報を彼女の著書の中に見いだします。この道は実際、よく通われた道であり、しっかりとした内的コントロールの下で達成されるあらゆるものとは注意深く区別されるべき道なのです。もうひとつの道は私がお話しした経過を辿るのですが、それはH.P.ブラバツキーがペストのように嫌った現代の自然科学の方法に依存しています。その道は、私がお話しした仕方で、つまり、カルマ的な記憶を呼び覚ますためというよりは、その記憶をしっかりと保持し、記述するために人間の力をカルマ的に発達させる、という点にその道はその力とそのよりどころを見いだすということを十分に意識した上で歩くべき道です。今日の科学は昨日この領域における私の協力者に言及したときにお話ししたような人間的な価値に浸透されていなければなりません。私たちが真の道と偽りの道の源泉を最もよく見いだすことができるのは定義を通してではなく、具体的な例を議論することによってなのです。この連続講義のまとめとして、明日は、私たちに残された短い時間の中で、このテーマに関するできるだけ多くの情報をつけ加えたいと思います。(訳注)シュタイナーはシュライデン教授夫人とフェヒナー教授夫人の雨水競争の話がよほど気に入っていたらしく、あちこちの講義で取り上げています。何故シュライデン夫人が競争を嫌がったのかがよく分からなかったのですが、この講義でようやく分かりました。ご存じと思いますが、水星と金星は後世になって名前が取り違えられました。したがって、神秘学的に言うと、惑星は、地球-月-水星-金星-太陽の順に並んでいます。(第十講・了)人気ブログランキングへ
2024年05月07日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神的な探求における真実の道と偽りの道」 (GA243) トーケイ、ディヴォン、1924年8月11日-22日 佐々木義之 訳第九講:精神的な世界への異常な道とその変容 私たちはこの連続講義を通常の夢の生活への探求から始めて、私たちが誕生から死までの間に住むところの世界とは異なる世界に参入することを可能にするさらなる意識状態についての考察へと進んできました。最後に、私たちは霊媒的な意識、人間が夢遊病の状態で経験するところの意識、何故なら、霊媒状態とはいつでもこの性格を有するものだからですが、そのような状態について議論しました。さて、これら両方の経験は、通常の生活においても、その真の姿において見いだされるような魂の状態です。それらが真の道、あるいは偽りの道へと分かれていくのは、それらが強められたときだけです。今日は、私たちの夢の生活をもう一度検証してみましょう。私たちは、人間が通常の意識において、覚醒状態から眠りの状態に移行するときには、夢に曝されるということ、彼のアストラル体は眠りの状態にある間、エーテル体や肉体の中にあるときの彼の経験についての残響を記録している、ということを見てきました。混乱し、本当に途方もない夢の経験がそれに続くのですが、それを正しく説明できるのは秘儀に参入した人だけです、何故なら、精神世界の本性により深く貫き至ることのない人は、これらの通常は混乱した経験にただ当惑するだけだからです。けれども、私たちはまた、瞑想や集中の訓練を通して、いかに夢の生活の横糸がより高次の意識の縦糸に織りなされることができるかを見てきました。ですから、私たちは驚くほど混乱した夢の世界に移された人間を目の当たりにするのですが、彼は、彼にとって通常の生活と同じくらい現実的な夢の生活の中にあって、完全な意識を保持しています。そして、彼が死者をその死後の存在において追っていくことができる別の世界への洞察を獲得するとき、彼は私たちの世界に比べて遙かに大きな現実性を有する世界に包まれていると感じるのです。さて、問題は、彼が今や接触する世界の真の本性とは何かということです。これについては既にお話ししましたが、今日は別の角度からこの問題に触れてみたいと思います。かつて地球には、肉体ではなく、繊細なエーテル体に住み、したがって地球を包むエーテルの中に受肉することができた偉大な教師たちが生きていた、ということをお話ししましたが、彼らはインスピレーションを通して人間を指導し、地球上における古代の文化の基礎を築きました。適切な意識状態によってこれらの太古の時代を振り返るならば、これらの教師たちが人類と生活をともにしていた、ということが分かります。その後、彼らは月の領域へと退き、今日ではその領域から、今まで一度も地上に生きたことのないあらゆる種類の存在たちを彼らの目的に仕えさせているだけです。彼らはこの元素存在たちのただ中に生き、死の門を通過した人間たちに自分のカルマにどのように対処すべきかを教えながら働きかけています。私たちが最初に精神世界に入るときに関わってくるのがこれらの存在たちなのです。ちょうどこの地上の生活においては、社会や社会関係を無視できないように、より高次の認識を達成するためには、これらの別の存在たちと共に働かなければなりません。私たちは、太古の時代に地上の人間の教師であったこれらの月存在と彼らが従える存在たちの助けを得て私たちの世界に直接境を接するところの精神世界を探求するのです。私たちはそこで地球の以前の時代と人間の以前の受肉への鍵を見いだします。そのとき私たちはかつて地上に生きていた人物たちを、彼らが私たちとカルマ的な関連を有していたかいなかったかに関わらず見いだすことになります。私はこのことを示すために、私たちがこのレベルの意識をさらに発達させることによって、いかにブルネットー・ラティーニ、ダンテ、アラヌス・アプ・インスリスやその他の今日ではもはや地上には受肉していない存在たちと次第に接触するようになるかについて指摘しました。ですから、この意識状態は夢の状態が照らし出されたもの、半透明に光るものなのです。通常の生活において、夢は単にいわば基礎的なはじまりを示しているに過ぎません。さて、秘儀に参入した人と通常の意識レベルで生きている人との違いを示すのは非常に簡単です。通常の眠りの状態の下では、人間の肉体とエーテル体が後に残される一方、彼のアストラル体と自我は体の外にあります。夢の状態における経験では、自我だけが本領を発揮します。夢の中で経験されるできごとがまだ肉体とエーテル体の外にあるアストラル体に属しているということは確かですが、通常の意識という意味では、自我だけが夢を経験することができるのです。ところが、秘儀に参入した人は、彼の自我と、特に彼のアストラル体によって経験します。ですから、秘儀に参入した人と普通に夢を見る人との違いは、後者が肉体とエーテル体の外にあるときには彼の自我だけで経験するのに対して、秘儀に参入した人は彼のアストラル体によっても経験するということです。さて、この知覚様式は特に古代の秘儀において超感覚的な世界を探求するという目的のために高度に発達させられ、退廃した形においてですが、中世とその後の時代全体を通してさらに発達させられました。それは近代においては実質的に消滅しているとはいえ、通常の夢の生活の中でいかに全く意識的な状態に留まるかということについて、太古の秘儀の教師たちから精神的な方法によって、あるいは伝統を通して教えを受けてきた人々があちこちに存在していたのです。そのような人々はいつの時代でもこれらの世界に貫き至ることができましたが、その試みは危険に満ちたものでした。イマジネーション的な認識を有する秘儀参入者が通常の夢の世界に浸るとき、直ちに物理世界とのつながりを失うとともに、意識を失い、無の中に沈み込むような感じを持ちます。まるでしっかりした地面が彼の足下で崩れ落ちるかのように、もはや重力に引きつけられていないかのように感じるのです。彼は内的な解放の感情、宇宙の海の中に吹き飛ばされるかのような、もはやしっかりとアンカー留めされていないために自分に対するコントロールを容易に失ってしまうかのような感じを経験します。私の本「より高次の世界の認識」の中で述べられている精神的な訓練の目的はこの危険を回避するということです。正しい仕方でこの瞑想に取りかかる人であれば誰でも、魂の「翼」を発達させることができるということ、今や重力を克服して翼を広げることができるということが分かるでしょう。秘儀参入者が足下の物理的、エーテル的な大地を失うにもかかわらずアストラル体と自我の「翼」を発達させていない場合には、危険な状況が生じます。図式的に表現していますが、皆さんにはこの意味がお分かりと思います。危険は十分に現実的なものなのです。これらの訓練の結果として私たちが参入する世界のために怠りなく準備するならば、あらゆる危険の可能性は排除されます。私たちは、ちょうど肉体とエーテル体を通して物理世界に与るように、これらの世界に徐々に参加することができるようになるのです。これは多かれ少なかれずっと以前の人間の状態なのですが、今日では、私たちはこの状態を精神的な訓練を実行することによって達成しなければなりません。太古の人間の成り立ちとは、私たちの目覚めの意識とは対照的に、私が記述したようなカルディア人たちの間で見られた精神的な視界、つまり、私たちの夢の意識と同じようなものではなく、ひとつのイマジネーション的な知覚形態であるところの状態に自然に恵まれている、というようなものだったのです。他の人間に出会ったとき、彼はその物理的な輪郭を知覚しただけではなく、彼を取り巻くオーラについての夢のような印象を持ちました。それは本物のオーラであって、単に主観的な幻想ではありませんでした。肉体のオーラを知覚するというこの才能に加えて、彼は別の能力-と申しますのも、それらはお互いに関連しているからですが、肉体に受肉していない精神的な存在のオーラを知覚することを可能にする能力をも有していました。ですから、彼は精神的な存在の姿を夢見たのです。それらの違いに注意して下さい。つまり、太古の時代において、人間が肉体に対応するものを見るときには、そのまわりのオーラを本当の夢の中でイマジネーション的に知覚しました。精神的な存在、天使や元素存在に出会うときには、最初からそのオーラについての精神的な知覚を有しており、その存在が有するところの形態を「夢見た」のです。最も初期の画家たちはこのようにして描いたのですが、今日、私たちはそれに気づいていません。これらの画家たちは精神的な存在を見て、それに対応する形態を「夢見た」のです。天使のヒエラルキアに属する存在はほとんど人間に似た形で、大天使については、体は明確ではありませんがはっきりと規定された翼と頭を有しているものとして、アルカイは翼の生えた頭をだけを有しているものとして描かれました。彼らがそうしたのはその形を「夢見た」からです。太古の人々にとってこれらの洞察はちょうど今日、私たちが他の人の姿を自然なものとして見るのと同じように自然なものだったのです。人間は、徐々に失ってきたその超感覚的な能力を精神的な訓練によって再び獲得しなければなりません。しかし、太古の人間にとって超感覚的な能力は自然なものであり、精神的な訓練によって再び獲得するのは比較的容易であったことから、その課題は何年にもわたって精力的に探求されてきました。月の領域への探求やそこでの死者たちとの出会い、そして、世界がその領域からどのように見えるかについて多くの語るべきものを持つとともに、真の探求者であるところの太古の秘儀参入者や月存在たちに支配される世界への活発な興味がいつも存在していたのです。コペルニクスはその太陽中心説を地上的な意識による観点だけから打ち立てました。古いプトレマイオスのシステムは間違っているのではなく、月の領域に関する意識の観点から見ると正しいのです。さて、これらの探求者、すなわち月領域の秘儀参入者に特徴的なのは、彼らの活動がその領域に限られているということです。ここにおられる皆さんは現在の人智学協会が以前は神智学協会の一部であったということをよくご存じです。神智学協会は、最近になって設立された多くの同種の協会と同じく、豊富な文献を収集していますが、皆さんがこの文献を参照するならば、それが正しいか間違っているかはさしあたり重要ではありません、今お話ししている世界、月の領域、すなわち、私たちが月存在との関係で探求するところの世界についての記述がある、ということが分かるでしょう。私に神智学協会で働いてはどうかという提案があったとき、それは私にとって重要な意味を持っていたのですが、最初はある困難に直面しました。それは、神智学協会においては、研究や文献がこの月の領域のみに限定されている、ということが分かったからです。この素材は確かに多くの間違いを含んでいたのですが、H.P.ブラバツキーの著作にはユニークで非常に重要なことがらが特に多く含まれていました。しかし、H.P.ブラバツキーの著作の中に見いだされるあらゆることがらは、彼女の月領域との交流、そして、犠牲行為としてこの月領域に留まることを自ら選んだ秘儀参入者と彼女との関係で決定されているのです。私はこれらの秘儀参入者の多くを知るようになりましたが、私が皆さんに保証できるのは、そのような月領域に貫き至る精神が、さらに発達したいという人間の望みにいかに無関心であるかということです。 私は、1906年から1909年にかけて書いた「神秘学概論」の中で、地球を、月、太陽そして土星という以前の受肉状態において記述しましたが、私の記述は月の受肉状態で終わることなく、遠く土星の受肉状態にまで遡って地球を記述しました。一方、これらのことがらについて語ったすべての秘儀参入者は彼らの説明を月と太陽の間で完結させ、実際には、ただ月領域にまで地球の受肉を辿っただけでした。さらに以前の地球の受肉にまで遡るべきである、という趣旨のいかなる示唆も無関心か、ときにはいらだちの感覚をもってさえ迎えられました。彼らは、そこへの道は越えることのできない障壁によってブロックされているため、それは不可能であると断言しました。その理由を理解することは当然ながら最も重要なことであり、無関心ではいられません。さらに親密になってまもなく明らかになったのは、これらの秘儀参入者たちは現代の科学的な観点に対して敵意や反感を持っている、ということです。これらの秘儀参入者たちは、ダーウィンやヘッケル、そして彼らの追随者たちの考えを紹介されると、非常に憤慨し、それらを子供じみてばかげたものと見なし、それらと関わりを持つのを拒否しました。最初、ゲーテの考えにはそれほど反感を示しませんでしたが、結局は彼も現代の科学者の言葉で語っているとして、すべてが退けられたのです。 要するに、そのような考えはその秘儀参入者たちにはアピールしなかったのです。私が太陽や土星の領域に貫き至ることができるということを初めて理解したのは1906年から1909年にかけて現代科学の考えに没頭し、それにイマジネーションを吹き込もうとしていたときです。私はこれらの科学的な概念をヘッケルやハクスレーのやり方に基づいて認識の手段として用いたのではなく、現代科学の観点がまだ存在せず、したがって、単に夢の世界にイマジネーションを吹き込むことによってのみより高次の意識を達成することができた時代に秘儀参入者たちがぶつかっていた限界を克服するための内的な動機づけとして用いたのです。私の著書「神秘学」の中で、私は通常は外的な世界にのみ関連しているハクスレーやその他の人々の完全に意識的な科学的観点に内的な意味を浸透させるとともに、それをイマジネーションの世界に吹き込もうとしました。土星、太陽、そして月というこの連なりの全体を理解し、古い秘儀参入者の認識を地上で探求することが可能になったのはそのときです。私は、これらのことがらがどのようにして生じたのかを皆さんに理解していただくためにこの認識への道を記述しているのです。皆さんは、それは個人的な説明である、と言うかも知れません。けれども、この場合、個人的な要素は、実際には、完全に客観的なものなのです。私の本「神秘学」に対して向けられた批判は、それが数学の教科書のように書かれており、私が議論してきた発達の道全体が数学的な公平無私の態度で記述されているということでした。けれども、この道は正確に私が記述した通りのものであり、コペルニクスとガリレオの時代以来存在し、ゲーテによって豊かなものにされた思考の様式性が、通常はイマジネーションの中に存在するのと同じ魂のあり方に結びついているという状況の中にその起源がありました。私が秘儀参入者たちにはいつでも近づくことが可能であった領域をその土星における起源にまで遡って辿ることができたのはこのようにしてだったのです。この例からお分かりになると思いますが、これらのことがらには、漠としたでたらめなやり方ではなく、はっきりと意識した思慮深さをもって近づき、容易に無思慮が取って代わるところで注意を喚起する、ということが重要なのです。自我だけと接触を持つというのが夢の生活における通常の状態ですが、アストラル体とも接触する場合があるというのがその例です。私が「神秘学」の中で提供した情報は現代の自然科学とどこが違うのか?という質問に対する私の答は、現代の科学者は自我にアピールすることができるだけであり、自我を手放すやいなや夢を見始めるのに対して、私は自然科学の概念を夢の生活の中に持ち込むことができ、私が記述すべき世界にアストラル体を差し向けることができるという点で異なるというものです。これは皆さんに正確にお話しすることができる道なのであり、いかに真の道が偽りの道と異なっているかを恐らくより正確に示すのに役立つひとつの例となるでしょう。この夢の状態の正反対が夢遊病や霊媒の状態です。夢を見ている人は完全に彼の自我とアストラル体の中に生きています。彼は、アストラル体の中では意識的な知覚を有していませんが、肉体とエーテル体の外にいるときにも、完全に自我とアストラル体の中に生きているのです。彼は彼自身の存在の中に突き落とされ、その中に浸されるのですが、そのとき、その存在は別の世界と関係づけられています。このように、夢を見ている人はいわば彼自身の存在の中に、したがって宇宙の中に、そして、ある程度は彼の肉体組織の中にも沈み込んでいるのです。その正反対が霊媒と夢遊病者の場合です。人間が霊媒や夢遊病の状態になるのは、その自我とアストラル体が肉体とエーテル体の外にあるときだけですが、この場合、既に指摘したように、彼の自我とアストラル体は見知らぬ存在に乗っ取られているのです。ですから、霊媒や夢遊病者は物理的な体を有していますが、その自我とアストラル体は肉体とエーテル体の外にあり、別の存在に取り込まれて抑圧されているのです。そのため、霊媒は正しい仕方で肉体とエーテル体に影響を及ぼすことができませんが、私たちは、例えば夢のない眠りの状態にあるときでさえ、肉体とエーテル体に影響を行使しています。私たちは、起きているときには内側から肉体とエーテル体に浸透し、眠っているときにはそれらへの侵略を外側から防いでいるのです。このことはもはや夢遊病者には当てはまりません。霊媒や夢遊病者は、その肉体やエーテル体をコントロールすることができず、いわば遺棄された領地のようになっているのです。私たちの時代においては普通であるような魂のあり方をしている人の場合、その肉体とエーテル体に影響を及ぼすのは植物や鉱物の力だけです。もし、鉱物の力すなわち鉱物地球の力がに私たちの肉体に影響を与えなかったとすれば、これらの力に依存する私たちが歩いたり動き回ったりすることは不可能だったでしょう。鉱物世界の力に与ることは許されます。つまり、その状態は正常なのですが、それらの力はエーテル体の中に入り込むべきではないのです。同じことは植物にも当てはまります。あまり強すぎなければ、植物の力がエーテル体に働きかけることはある程度許容されます。しかし、動物の感覚を刺激するところの力や別の人間の力が人間の体、特にエーテル体に影響を及ぼすことはもはや許されません。動物や地上的な人間の力が霊媒あるいは夢遊病者の肉体やエーテル体に働きかけるのは、それらが放棄されるときです。その肉体やエーテル体はまわりの影響を受けるようになります。ちょうど思考が夢から環境中に移行するように、この場合には意志が人間から引き離され、環境と融合するのです。霊媒や夢遊病者に指示して立たせたり歩かせることができます。ジャガイモを差し出して、それがおいしい梨であるとかその他のものであると示唆することができるのです。私たちが霊媒や夢遊病者に指示をだすときには、人間としての私たちがその肉体と直接的な関係を持ち、したがってそのエーテル体と直接的な関係を持つことになります。霊媒や夢遊病者は、普通の人間の場合もそうであるように、肉体にのみ反映されるべき物理的な環境を彼らのエーテル体の中に有しています。ですから、普通の人間は、夢に似た状態の中で、彼自身を彼の内の精神的な世界にゆずり渡すのですが、霊媒は外的な自然の世界にゆずり渡すのです。さて、霊媒や夢遊病の現象は、その状態自体が正常なものである限り、正常な状態です。何故なら、動き回ったり、ものを掴むことができる能力、いかなる種類のものであれ外的な活動を遂行することができる能力とは、誰の場合にも、魔法や夢遊病のようにして達成されるものだからです。けれども、この活動は肉体にのみ限定されるべきであり、エーテル体にまで及ぶことがあってはなりません。もしそうでなければ、正常な状態から異常な状態に移行することになります。ですから、夢を見ている人は完全に彼自身の内に生きており、霊媒や夢遊病者はその外にいるのです。彼らの肉体とエーテル体はいくらか自動人形と同じ仕方で機能し、私たちはそれらに働きかけることができるのですが、それは彼自身の自我やアストラル体がそれらをコントロールし損なうからです。その結果、ちょうど夢を見ている人の場合に内なる精神的な世界が創造されるように、霊媒や夢遊病者の場合には外なる自然の世界、形態の世界とその起源、すべての知覚可能なもの、時空に関係するあらゆるものとの合一が生じるのです。私たちが夢の世界に沈むとき、私たちは形態のない状態、絶えざる変容の状態の中に浸されます。私たちが肉体とエーテル体をもって夢遊病者や霊媒が何らかの指示の下でその意志を行使する世界に貫き至るとき、そこではあらゆるものが明確に規定されているのが分かります。つまり、外からの影響の結果として生じるあらゆるものが非常な正確さをもって遂行されるのです。これは正に通常の夢の世界に対する反定律の世界です。つまり、それは、夢遊病者においては、夢の活動であり、外的なものとなった自然な行為なのです。行為の中で見られる夢、夢に似た状態の中での行為、単に内的な経験に留まらない夢です。秘儀に参入する立場から見ると、この反定律は最も興味深く、意義深いものです。秘儀参入者が夢の世界をイマジネーションによって満たそうとしてそれに沈潜するとき、彼はある困難に出会います。このことは既にお話ししましたが、彼は、もはや重力の影響下にはない、自分の足下にはもはやしっかりとした地面はない、と感じるのです。夢遊病者は無意識的にそこに入り込みますが、秘儀参入者がこの世界に入るときにはそれに意識的に近づかなければなりません。彼はいつでも意識を失うかも知れないと感じ、絶えずこの可能性に直面するのですが、完全な意識を保持するために、自分自身をしっかりと支えていなければなりません。もし、私たちが秘儀参入者としてこの世界にもっと深く貫き至るとすれば、見たり知覚したりできる世界の通常の存在たちと同じように、そこでも分別をもってかつ知的に前進していかなければならないのです。秘儀参入者は、通常の人生を生きるのと同様、精神的な世界においても完全に意識的な生活を送るという事実に背くべきではありません。と申しますのも、もし、ほんの一瞬でも物理世界から離れたと想像するようなことがあれば、もったいぶった態度を取り始め、仲間の人間からむしろ変なやつだと思われるであろうからです。そして、彼らは、こいつはとうとう気が狂ったと言うでしょう! ちょうど感覚の世界が周囲のいたるところに存在するように、いたるところの存在する精神的な世界を通過するとき、完全な意識を保つために、自分自身をしっかりと支え続けることをしなければ、このようなことが起こり得るのです。ここにおいて、神智学協会によってではなく、大物自然科学者たちによって取り扱われたきた世界、すなわち心霊的な探求の領域が開かれます。これらの探求は科学的なバックグラウンドや限定された潜在能力を持つ人たちによって遂行されましたが、彼らは精神的な世界の本性を確かめるために統計的な手段と霊媒による実験を用いました。人間の魂が別の存在によって保有されている間、通常の意識状態においてではなく、完全な無意識状態あるいは減退した意識状態で手足を動かしたり、反応したりするとき、何が起こっているのかについて客観的に探求しようとする試みがあらゆる種類の団体で様々の観点からなされています。 こうしてそのような方法で意識が減退させられた人々の反応が記録されてきたのです。この種の探求に熱心な人が私に勧めたのは、内的な世界の現象を客観的に探求してもらうために、私と私の探求の成果を彼らの実験のために提供すべきであるということでした。これは、誰かがやってきておよそ次のように言うのと似た状況です。私は数学のことは分からないので、数学者の言うことが本当かどうかを確かめるため、彼を実験室に連れていこう。彼が偉大な数学者かどうかを示す実験をやってみるのが一番だと。私がここでお話をしているのは、人間の内面に貫き至ろうとする真の試みについてではなく、単に科学的な方法を漫画的にしたものによって、外側から夢遊病者や霊媒を探求しようとする現代的な試みがなされている分野についてです。と申しますのも、もし、人々が本当に人間の内面に貫き至るならば、霊媒や夢遊病の現象の中に見られるのは外的な乗り物、肉体とエーテル体からなる自動人形であるということ、つまり、彼らが探求しているのは精神的な現実についてではなく、彼らが探求しようとしているものが置き去りにした外的な乗り物である、ということに気づくはずだからです。彼らは精神世界のより精妙な側面をのぞき見ようとはしません。彼らはしばしば内的な経験を通してだけではなく、見たり知覚したりすることができる形においても精神的なものを感じ取ろうとするのです。このアプローチは、私が既にこの道についてお話ししていた正にそのときに起こったように、ときとして別の形を取ります。彼らは肉体の中にあるキリストの精神的な姿を求め、精神的なものの直接的な顕現を外的な世界の中に見いだすことを欲していたのです。私たちは物理世界をそのようなものとして認め、精神的なものをそれが本当に存在するところに。もちろん、物理的な世界にですが、本質的には、物理世界に浸透した精神的な領域の中に求めなければなりません。ここにはさらに別の領域があります。健全な状態にある人は、内的な経験の領域と外的な知覚、混乱した夢の世界と霊媒や夢遊病者の異常な世界との間にあるギャップに橋を架けなければならない、という感じを持ちますが、芸術はこれらふたつの世界の統合によって、そして、それらがお互いを実り多いものにすることによって生まれました。つまり、芸術においては、外的な形態が精神によって浸透され、精神的な内容が外的な形態をまとっているのです。神智学協会が普通の人間を精神的な実存であると言い立てるのに忙しくしている間、私たちは人智学協会において、秘教的な流れを「芸術」に向けるように駆り立てられました。神秘劇とオイリュトミーが生まれ、言語造形の芸術が発達させられました。これらは人智学協会において発達させられた他のものと同様、精神的なものと物理的なものの間のギャップに橋を架け、混乱した夢の世界と霊媒や夢遊病者の混乱した世界とを意識によって結びつけようとする衝動が実りをもたらしたものでした。これらふたつの世界は芸術において意識的に融合させられるのです。 いつかはこのことが理解されるでしょう。マリー・シュタイナー婦人が実践しているような言語造形がかつて人間がまだ本能的に精神的であった時代に享受していたようなレベルを回復するとき、人々は私たちの努力の目的を理解するでしょう。当時の人々にとっては、空虚で抽象的な言い回しよりも言葉のリズムと韻の方がもっと重要だったのです。これらのことを再び生き返らせなければなりません。そして、オイリュトミーが再び私たちのために回復するのは私たちの前で動きを通して展開する人間、魂と精神からなる存在である真の人間です。私たちがオイリュトミーから学ぶことができるのはこのようなことなのです。 ※マリー・シュタイナー;マリー・シュタイナーは、ルドルフ・シュタイナーの妻で、ルドルフ・シュタイナーが著した『一般人間学』の序文の原作者です。ルドルフ・シュタイナーは、科学的・神秘体験を通じて精神世界を研究することを目的とした「人智学」を確立したことで知られています。1923年のクリスマス会議で、ルドルフ・シュタイナーは普遍アントロポゾフィー協会と精神科学自由大学を設立し、マリー・シュタイナーは理事を務めました。また、ルドルフ・シュタイナーの思想に基づく教育方法である「シュタイナー教育」では、子どもの個性を尊重し、個人の能力を最大限に引き出すことを目指しています。独自の遊びや学びの方法がとられ、知的な学習だけではなく、感情や意志に働きかける総合芸術も重視されます。幼児期には縦割りでの異年齢保育を実践し、早期の知的教育を避けるため、テレビやゲームなどが基本的に禁止されています。また、保育所や幼稚園でよく使われる絵本や紙芝居は用いず、先生の語りのみでお話を楽しみます。参照画:彗星の人、マリー・シュタイナー ですから、私たちはまず最初に芸術の中で、夢を見る人が目的もなくさまよう世界から霊媒や夢遊病者がつまづきながら盲目的に歩き回る世界への橋を架けなければならなかったのです。今日の唯物的な時代にあっては、夢を見る人は孤独な省察の中に取り残され、精神的なものを表現し、明らかにするところの実質的な形態や構成について何も知ることがありません。そして、夢遊病者たちは霊媒としての名声を享受しているかどうかや、共産主義者たちのように理想的な国家理論を発明しているかどうかなど気にすることもなく自分の人生を生き、そして、霊媒もそうですが、あらゆる種類の顕現を周囲の世界にばらまき散らしています。夢を見る人も夢遊病者も、精神的なものの存在についてのほんのわずかな疑いを持つこともなく現代の世界を生きているのです。物質から精神に、そして精神から物質に導く橋を再び見いだすことが本質的なことであり、私たちはまず芸術の分野においてこの橋を見いだし、もはや半意識的な状態で躓きながらさまようのではなく、普通とは異なる種類の精神運動を通して芸術に対する感覚を発達させなければなりません。ですから、オイリュトミーはその真の内的な源泉を秘儀への参入の中に有しており、私たちが言語造形という芸術において実践するあらゆるものはその同じ源泉から生じてくるのです。そして、予定されている舞台芸術のコースがドルナッハで催されるとき、私たちは舞台芸術の精神的なイメージを再び回復するように努めることになるでしょう。長い間、どうすれば俳優を舞台の上で最大限の現実性をもって提示することができるかに注意が払われてきました。このテーマに関する90年代の議論は全く漫画的なものでした。シラーの登場人物たちがその英雄的なせりふを演説調に話すとき-結局、当時は自然主義が勝ちを収めたのですが-、彼らの手をズボンのポケットに入れておくべきかどうかという問題について-と申しますのも、それが現代的なファッションであったからですが-議論されたのです。ですから、精神世界を探求するための正しい道を見いだすということについては色々な理屈がありますが、芸術の道にしたがうというのは健全な基本方針です。最も重要なのは、月の秘儀とそれに関連するあらゆるものに浸された古代の秘儀参入の学を超越し、秘儀参入者の隠された認識を実り多いものにするために自然科学の成果、この文脈では自然科学による知的な征服に言及しているのを使うことができるときにだけ達成することができるところの、あの魂の内的な状態を発達させるということなのです。他方、同様に重要なのは、夢遊病者あるいは霊媒がトランス状態で元素存在に取りつかれるとき、エクトプラズムの形態の中で何が起こっているのかを確かめるために行われる生半可で混乱した実験を特別な探求の場にするということです。と申しますのも、これらふたつの道は本当は同一のもの、つまり、夢から意識的な夢への出現であり、自然科学がその鉱物的な側面においてのみ知っているところの外的な世界の意識的な理解であるからです。あのいわゆる心霊研究が提案するのはそのやり方による生半可な探求です。科学の時代に生きている私たちにとって重要なのは、精神的な探求において、この道を追求し、夢の世界の対極にある別の世界を精神的に探求するということです。夢遊病者や霊媒は私たちが生じさせるのは通常の生活においては見られない現象です。彼の筆記や動き、会話や味覚は普通の人間のものではありません。それは、彼のアストラル体と自我が肉体とエーテル体の外にあり、私たちが扱っているのは、打ち捨てられ、宇宙の影響下に置かれた肉体とエーテル体であるということによります。私たちは、自然の通常の働きを反映した物理的、エーテル的なものの顕現ではなく、精神的な世界から進み出てくるものに直面することになります。と申しますのも、結局のところ、私たちが霊媒に指示を出しているかどうか、あるいは、霊媒が何らかの星座、天候、あるいは金属の影響を彼のエーテル体の中に取り入れ、その影響下にあるかどうかということは問題ではないからです。私たちは霊媒の乗り物が魔術的な目的のために精神的なものの用に供されているのだということを心に留めておかなければなりません。心霊研究協会は外的な実験によって探求しようとするかも知れませんが、精神的なものに関する知識なしにこれらの顕現を研究することは私たちにはできません。それらの精神的な関連が調べられなければならないのです。私たちは霊媒や夢遊病者が生じさせる現象とその背後にある精神的な基礎を観察しなければなりません。霊媒や夢遊病者を通して示されるこれらすべての現象は他の霊媒的な現象とも関連しています。霊媒がトランス状態において、人間的あるいは宇宙的な影響の下で何らかの行為を行うとき、つまり、肉体やエーテル体が何らかの行為を遂行するとき、それは人間を病気にさせる毒のある植物の中で生じている過程と一時的に、とはいえ、それは別の要素によって決定されているのですが、同様のものとなっているのです。霊媒的なあるいは夢遊病の状態の中で示されるのは単に外的かつ一時的な病気の仮面に過ぎません。ある観点から言えば、これについては次の講義でもっと詳細に議論する予定ですが、私たちが霊媒や夢遊病の現象の中に見ることができるのは(別に必ずしもそうする必要はないのですが、それはいつでも可能なことです)病気の人の中で生じていることなのですが、それは、その人の自我とアストラル体が何らかの異常な仕方である器官から、あるいはその有機体全体から立ち去り、別の精神的な影響によって置き換えられているということによるのです。太古の時代においては、人間はこの関連に気づいていたので、秘儀はいつでも治療と関連していたのです。そして、人々は今日ほど詮索好きではなかったために、霊媒や夢遊病者に興味を示す必要性を全く感じませんでした。と申しますのも、彼らの行いは病気の状態と同じく彼らにとってはよく知られたものだったからです。これらのできごとには医学的な観点からのアプローチがなされましたが、これは私たちが再び獲得しなければならない立場なのです。そして、自然現象を通して、自然科学を通して、生半可なやり方で精神的なものにアプローチするもうひとつの道も正しい仕方で追求されなければなりません。すべての現象は、特に人間や動物の病理的な状態を通して表現されるあらゆるものは正しい見通しの下に再び見直されなければならないのです。私たちは、そのときはじめて、心霊研究のための協会が探求することを欲するであろうような現象を調べることができる位置に立つでしょう。 そして今、この研究分野は人智学協会によって開かれました。病理的な現象の研究に際して、それを通して精神世界への扉が開かれるというような仕方でそれを行うことが可能になったのです。これが可能になったのは、イタ・ベークマン博士と私がこの研究分野を、心霊研究からは無視されてきた正しい道筋に沿って発達させるように努力してきたからであり、イタ・ベークマンが、有能な医者としての知識だけではなく、医療上の所見から精神的な洞察へ、そしてそこから真の治療へと直接導くあの先験的な治療の才能を有していたからです。ですから、ここに横たわっているのは私が示した領域を探求するために従わなければならない道です。私たちは、自らの努力によって、それ自体が秘儀に参入する自然科学であるところの真正な秘儀の医療を発達させることを望んでいるのです。こうして多くの偽りの道とははっきりと区別される真の道がすべての人に示されることになります。そして、ベークマン博士と私が書いた本の最初の巻によって、踏み出されるべき最初の一歩が示されるでしょう。この関連で、指摘しておいた方がよいと考えられるのは、真の道と偽りの道との違いは例を上げることによって最もよく示されるということです私は以前、精神の領域を再び自然科学の領域に結びつけるところの芸術への道が見いだされなければならないということを述べました。私が今付け加えなければならないのは、自然現象についての探求と関係のある正しい道、すなわち精神科学の道を最初に探求してはじめて芸術に向かう正しい道を見いだすことができる、というのは現代文明のおかれた状況から本質的なことであるということです。と申しますのも、人類は特に病理現象の発生の中に見られる精神的なものの活動を確信できてはじめて、つまり、いかに精神が物質の中で作用し、自らを現すかについてのはっきりとした証拠があるときはじめて、芸術の中には精神が活発に浸透しているのだ、ということを納得するのですが、今日、芸術の分野においては、人類は私がお話しした橋を架けるのとはそれほどまでに遠いところにいるからです。人類が、精神を直接世界に提示することができるのは芸術作品の形によってであるという考えに対する心からの熱情を十分にかき立てることが可能になるのは、恐らく、自然界における精神の活動に気づくようになるときでしょう。明日はこれらのことがらについてもう少しお話しするつもりです。※イタ・ベークマンはオランダ人の医師で、思想家ルドルフ・シュタイナーとともに100年前にアントロポゾフィー医学を創始しました。アントロポゾフィー医学は統合医療の一種で、自然科学的・アカデミックな医学を否定するものではなく、近代西洋医学の基盤となっている自然科学的視点を基本としています。ベークマンは、1925年に人智学医学を『治療の基本. 概念 -精神科学の叡智による医術の拡大-』という本の中で体系化しました。また、水頭症の子どもに関する初期治療を試みたことも知られています。(訳注)この講義は、一読してそれほど重要ではないという印象を受ける方もおられるかも知れませんが、鉱物や植物の精神が動物や人間の精神よりもより高次の領域にあるように、自然科学の精神はいわゆる精神科学の精神よりもより高次の領域にある、ということを示唆しているように思われる点で興味深いものがあります。自然科学が存在していなかった古代には、低次の精神的な領域に昇ることは比較的容易であった反面、それ以上の上昇が不可能であった理由がよく分かります。知的な人間は超感覚的な認識を獲得するのが難しい代わりに、もし獲得できればより高次の認識段階に昇ることができる可能性がある、極悪人が改心すれば善人よりもより聖なる存在になる(この逆の例がアーリマン)可能性があるというようなことも考えさせられます。(第九講・了)人気ブログランキングへ
2024年05月06日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神的な探求における真実の道と偽りの道」 (GA243) トーケイ、ディヴォン、1924年8月11日-22日 佐々木義之 訳第八講:精神的な探求において陥る可能性のある過ち 既にお話しした意識レベルを発達させるとき、それぞれのレベルにおいてある特別な宇宙領域への扉が開かれます。人間が有する知覚の本性と適切な意識状態を発達させることによって到達することができるところの様々な領域との関係を概略的に記述してみるということを提案したいと思います。これらの領域は実際にはお互いに重なり合っているのですが、隣接したものとしてしか描くことはできません(ここで、黒板に描かれる)。月と水星の領域がいかに私たち自身の領域に浸透しているかについては既に示されました。死後数年以内の死者と関わりを持つことを可能にするところの意識レベルを私たちが発達させると想像してみましょう。その世界は私たちの世界と境を接しています。(rot 赤色 gelb 黄色 unser Welt:私たちの世界 hell 明るい)次の意識レベルは、死者がカマロカにおいてその地上生活を逆向きに辿った後に入るところの生活へと貫き至ることを可能にするものです。私はそれを空になった意識と呼びました。しかし、それは物理世界との関係では目覚めた意識です。私たちが次に参入するのはより広い領域であり、そこでは水星存在、すなわちラファエルの領域に特徴的な事象やできごとと密接な関わりを持つことになります。特に、人間本性に生来備わっている治癒力が意識されるようになります。※カマロカは、死者が残してきた人を心配している場所を指す言葉です。ルドルフ・シュタイナーの「精神的な探求における真実の道と」では、死者がカマロカにおいて地上生活を逆行する意識レベルがあるとされています。 こうして私たちは、それぞれの意識状態によって固有の宇宙領域に参入し、その時々において、これらの領域に属する存在たちを知るようになるのです。もし、死後間もない人間が置かれる状態を知りたいならば、彼らが住む世界に参入するのに適した意識を発達させなければなりません。彼らの真の姿は彼らが属する世界においてのみ私たちに示されます。もし私たちが水星存在を観察したいのであれば、彼らの世界の意識に与らなければならないのです。ですから、これらの世界はある意味でそれぞれ切り離されており、当然それぞれの世界には固有の意識状態がある、と考えることができます。それは実際、私たちが正しく宇宙を理解するための必要条件なのです。何故なら、私たちはそのように考えることによって初めてこれらの存在たちをその真の性格において知る準備をすることができるからです。ここで、簡単な例によって、そのような認識-ある特定の宇宙領域に適した意識状態を正しい仕方で発達させようとする認識-がどのような方向に導いていくのかを皆さんに示すということを提案したいと思います。私たちの前に植物がその葉や花とともにあると考えてみましょう。私たちは既に、植物とは精神世界に存在する元型の地上における反射像であるということを学びました。そして、私たちがこの元型の世界へと意識を上昇させ、植物世界の認識を獲得するとき、決定的に重要なことがら、すなわち地上に見いだされる植物の種類は明確に区別されなければならないということが明らかになります。適切な精神的知覚力をもって、私たちがある特別な試料、例えばチコリを検証するとき、その外観は他の多くの植物とは異なっています。典型的な例として通常のスミレを取り上げ、それをベラドンナ(ベラドンナは古くから「悪魔の草」と呼ばれ、その強い毒性が恐れられていた。)と比べてみましょう。今お話ししたような方法で植物の世界を探求しつつ、スミレが属する世界に参入するとき、つまり、空になった目覚めの意識に参入するとき、スミレはその全く無垢の姿で精神の目に映るということが分かります。他方、ベラドンナはその存在を別の世界から導き出します。私たちが、植物は物質体とエーテル体を有している、そして、その花と実は普遍的な宇宙の要素に取り囲まれている、ということを知覚するとき、私たちは通常の植物という存在を理解することになります。地球から芽生える植物の有機的な生命、その周囲のエーテル体、そして、一見雲に包まれたようなアストラル的な要素が至るところで見られます。スミレのような植物の性質とはそのようなものです。ベラドンナのような植物はそれとは異なって構成されています。その釣り鐘型の花の内部には実が形成されるのですが、アストラル的な要素はその実の中へと浸透していくのです。スミレが発達させる「さく」は単にエーテル的な要素の中にあります。ベラドンナは、その実がアストラル的な要素を同化しているため、毒を持っているのです。いずれかの部分が大宇宙のアストラル性を同化している植物はすべて毒を持っています。動物の中に入っていく力、動物にアストラル体を付与し、それを感覚的な存在へと内的に形成する力は植物における有毒な要素の源泉でもあるのです。これは非常に興味深いことです。私たちのアストラル体は植物によって同化されるとき、毒性を示す力の担い手になるということが分かります。毒についてはこのように考えなければなりません。私たちは人間のアストラル体が実際にあらゆる毒の力を含んでいるということに気づくときにだけ毒についての内的な理解を獲得することができるのですが、それはそれらの力が人間存在を構成するひとつの重要な部分になっているからです。私がこの議論の中で、後になって精神的な探求における真実の道と偽りの道を区別するための助けとなるであろうようなはっきりとした観点を提示しようとしているのです。スミレとベラドンナの例から私たちは何を学ぶことができるのでしょうか。それぞれの植物世界に適した意識を発達させるならば、スミレはその本来の世界の内部に留まり、外の見知らぬ世界から何も引き寄せることのない存在であるということが分かります。他方、ベラドンナの場合、見知らぬ世界から何かを自分に引きつけます。それは、植物の世界ではなく動物の世界の特権であるところの何かを同化しているのです。このことはすべての毒のある植物に当てはまります。彼らは、植物存在には属すべきではないもの、実際には動物界に属すものを同化しているのです。さて、宇宙には様々の領域に属す多くの存在たちがいます。私たちが死者たちに出会い、彼らがそこを離れるまで10年、20年、あるいは30年にわたって付き添っていくことができる領域にも、人間に気づかれることなく私たちの物理世界に入り込んでいる多くの存在たち、疑いもなく現実的な存在たちが見いだされます。彼らはある特別な種類の元素存在として記述するのが最も良いでしょう。こうして、私たちは、死の門を通過して間もない死者たちの後を追っていくとき、あらゆる種類の形態を付与された元素存在たちが住む世界、彼らが現実にそこに属すところの世界へと入っていくことになります。私たちは、これらの存在たちはその世界に属している限り、その世界に適した力だけを実際に使用すべきである、と言うかも知れません。さて、これらの元素存在の中には、その活動を彼ら自身の世界に限定せず、例えば、人間がものを書く様子を観察したり、人間が生まれてから死ぬまでにその世界の中で行うところのあらゆる活動を追跡するものたちがいます。私たちは私たちの活動の観察者であるそのような存在たちにいつも取り囲まれているのです。さて、この観察者としての役割自体は害があるというものではありません。何故なら、今私がお話ししていることがらの背後にある全体計画の本質とは、人間が物理的な世界との関わりを通して獲得するところのあらゆるものが、私たちの世界と境を接するあらゆる世界、私たちが死後直ちに入っていく世界、私たちが死後何十年も経った死者たちと接触を持つ世界、つまり、これらすべての世界には欠けているというようなものだからです。この死者の世界には、例えば、書くことや読むこと、私たちが知っているような飛行機、自動車、あるいは客車は存在しません。私たちはこの地上で自動車を組み立て、読み書きをし、本を書きますが、このすべてに天使たちは参加していない、とは言えません。これらのすべてが宇宙一般にとって意義がないものである、とは言えないのです。今私が記述したような存在たちは私たち自身の世界と直接境を接する世界から「委嘱」を受けている、というのが実際のところであり、彼らは人間の活動を見守らなければならないのです。彼らは人間の本性に関心を持ち、未来の時代のために、その分野で彼らが学ぶものを保持する、という任務を別の世界から負っているのです。私たちは人間として、私たちのカルマや外的な文化によるカルマへの影響をひとつの人生から別の人生へと運んでいくことができます。私たちは自動車に関連した私たちの経験をひとつの地上生から別の地上生へと運んでいくこともできるのですが、自動車の組立そのものを運んでいくことはできません。地上の力だけに担われたものを、ある人生から別の人生へと運んでいくことは私たち自身にはできないのです。ですから、人類は文明を通して何らかのものの基礎を築いてきたのですが、それは、もし、別の存在たちが力を貸してくれなかったとすれば失われていたであろうようなものなのです。さて、私がお話ししてきた存在たちは、人間がひとつの地上生から別の地上生へと運んでいくことができないものを未来のために保持するという任務のために「分遣隊」に分けられます。これまで、これらの存在たちの多くにとって、その任務を成就するのは最も難しいことでしたから、太古の時代に見いだされたものの多くが再び人類から失われてきました。私が確立しようとしている顕著な点とは、私たちは、人間がひとつの地上生から別の地上生へと自分で伝えることができないようなもの、例えば文献中の抽象的な内容を宇宙的な計画にしたがって未来に運んで行くという使命を負った存在たちに取り囲まれている、ということです。人間と直接的な関係にある精神的な存在たちにはそれは不可能です。したがって、人間としての私たち自身にもそれは不可能なのです。これらの存在たちが彼らの手助けをするものとしてリストアップしなければならないのは、彼らとは長らく疎遠であった別の存在たち、すなわち人間と関わってきた精神的な存在たちとは全く異なる進化を経験してきたものたちです。これらの異なる進化を遂げた存在たちを、私は私の本の中でアーリマン的な存在たちと呼びました。彼らは異なる進化を経てきたにもかかわらず、ときとして、例えば、私たちが自動車を組み立てるとき、彼らが私たち自身の進化に関わりを持つことがあるのです。彼らは、彼らのアーリマン的な宇宙の力によって、自動車の組立のような現代技術を理解することができる存在であり、人間自身がひとつの受肉から次の受肉へと運んでいくことができないような文明の技術的な成果を未来の時代へと伝える存在なのです。私たちが手に入れることができるこの情報によって、私たちは今、霊媒とは本当に何なのかを記述する地点に立ちます。もちろん、私たちは最も広い意味での霊媒と文字通りの意味における霊媒とを区別しなければなりません。「霊媒」という言葉を広い意味に取ると、基本的には、私たちはすべて霊媒です。私たちは皆、誕生から死までの私たちの人生を生き通すために受肉する以前には、魂と精神からなる存在でした。私たちの精神的な本質が物質体に受肉するのです。物質体は精神が活動するための媒体となるものです。ですから、「霊媒」という言葉を最も広い意味に取ると、あらゆる存在はある程度は霊媒である、と言うことができるのです。これは私たちが通常、「霊媒タイプ」という言葉に与える意味とは異なります。誕生と死の間の世界においては、霊媒的な人とは、脳のある部分を彼の全体的な存在性から切り離すというような仕方で発達させた人のことです。ですから、ときとして、これらの脳の部分、特に自我の活動を支える部分が、その基盤的な役割を果たさなくなることがあるのです。私たちが自分に向かって「私は」と言うとき、つまり、私たちが十分に自我を意識しているとき、この意識は脳のある特定の部分に根ざしています。これらの脳の部分が霊媒によって切り離されますと、私が先ほどお話ししたような段階にある実体が、人間の自我の代わりにそのような部分に滑り込みたい、という衝動を感じるようになります。そのとき、そのような霊媒は、文明の成果を未来に伝えることが本来の機能であるところのあの存在たちの乗り物になるのです。これらの実体たちは、たまたま自我が不在になった脳に取り憑くとき、この脳の中に自らを確立したいという圧倒的な欲求を感じます。そして、霊媒がトランス状態にあり、脳が切り離されるとき、アーリマン的な影響を被るこの種の実体、文明の成果を未来に伝えるのがその機能であるところのこの種の実体が脳の中に滑り込むのです。そのような霊媒は、一時的に、自我の担い手ではなく、宇宙における自らの義務を怠っている元素存在の乗り物になるのです。皆さんには、宇宙的な義務を怠る元素存在、という表現を全く文字通りに受け取っていただきたいと思います。そのような存在の義務は人間がどのようにして書くかを観察することです。人間は私がお話ししている脳の部分に根ざした力を用いて書くのですが、これらの存在たちは正常な仕事としての単なる観察の代わりに、切り離される可能性がある霊媒的な脳を絶えず探しているのです。そして、その中に滑り込み、書くという技術について彼らの観察が教えるところのものを同時代の世界に導入します。こうして、彼らは、霊媒の力を借りて、彼らの使命に従えば未来に伝えるべきものを現代に投影します。霊媒主義は、未来の能力となるべきものが混乱し、ぼんやりした仕方で既に現代において発達させられる、という事実に依拠しているのです。これが霊媒の予知能力の源泉であり、他の人々を魅了する元ともなっているものです。実際、その機能は今日の人間の機能よりもずっと完璧なものなのですが、それは既に述べたような仕方で導入されるのです。ちょうどベラドンナがアストラル世界を媒介するように、つまり、その実に吸収したある種のアストラル的な力を媒介するものとして働くように、人間もまたその特別な脳のタイプを通して、ある未来の時点において私たちの文明に参加すべきこれらの元素存在のために、と申しますのも、人間にはある地上生から別の地上生へとすべてのものを運んでいくことは不可能だからですが、それを媒介するものとなるのです。これが霊媒現象、ある種のクラスの存在たちによる憑依の秘密です。さて、一方で、皆さんは、これらの存在を実際に創造したのはアーリマン的な存在たちである、と結論づけるかも知れません。アーリマン的な存在たちは宇宙にあって人間の知性を遙かに凌駕する知性を有しているのです。私たちは、私たちの世界と直接境を接する世界においてアーリマン的な存在たちに出会うとき、あるいは、洞察を達成することによって、物理的な世界においても彼らに出会うかも知れませんが、彼らの広大で卓越した知性に驚きます。彼らの知性は人類のそれを遙かに越えています。そして、私たちはいかに彼らが無限に知性的であるかに気づくとき、初めて彼らを尊敬するようになります。この知性のなにがしかが彼らの子孫、霊媒的な脳に滑り込む元素存在たちに伝えられることから、霊媒という手段で重要な情報が明らかにされるというようなことが起こり得るのです。私たちは多くの決定的に重要なことを、特に、霊媒たちが十分に発達した意識の中で伝えることに関して、学ぶことができるかも知れません。私たちが精神的な世界の本性と成り立ちを正しく理解するならば、霊媒が多くの権威ある情報を伝えることができるということを否定することはできません。私たちは彼らから多くの重要なことを学ぶ可能性があるのですが、それは精神的な認識に向かう正しい道ではありません。このことは植物霊媒、つまり植物毒の元となるある種のアストラル的な力を媒介する植物の例からもお分かりと思います。このような状況がいかにして生じたのかに気づくことができるのは、正しく発達させられた意識を通してだけです。このことを次のような方法で記述してみたいと思います。と申しますのも、精神的な世界について議論するときには、抽象的な概念で語るよりも、明確で具体的な記述の方がよいからです。死者たちが死後の生活を送る世界に超感覚的な認識をもって参入すると仮定してみましょう。私たちがそのようにして死者を追っていくとき、最初に入っていくのは私たち自身の世界とは全く異なる世界です。これについては既にある程度述べましたが、そのときに指摘したのは、その世界は私たちが誕生から死までの間を生きる世界よりも遙かに現実的な印象を与えるということでした。私たちがこの世界に参入するとき、私たちは死者たちの魂とは別に、そこに見いだされる特筆すべき存在たちに驚かされます。最近亡くなった人々の魂が奇妙なそして悪魔的な形態をしたものに取り巻かれているのです。死者が入って行かなければならないこの隣接する世界、私たちがある種の超感覚的な視覚によって彼らを追っていくことのできるその世界の入り口で、私たちはアヒルか野鴨、あるいはその他の水性動物のように、水かきのついた巨大な足、地上的な基準に照らして巨大ということですが、絶えずその形を変える巨大な水かきのついた足を持つ悪魔のような姿をしたものに出会います。これらの存在たちはいくらかカンガルーのような形をしていますが、半分鳥のようでもあり、半分ほ乳類のようでもあります。私たちが死者に付き添って行くときには、そのような存在たちが住む広大な領域を通過していくことになるのです。私たちがこれらの存在たちはどこに見いだされるのかと問いかけるとすれば、まずそのような存在たちの在処、彼らの居場所についてのはっきりとした考えを持っていなければなりません。彼らはいつも私たちの周りにいるのです、何故なら、私たちは死者と同じ世界に住んでいるからです。しかし、皆さんは彼らをこのホールの中に探すべきではありません。真性で正当な探求はこの地点から始まるのです。秋のクロッカスがたくさん生えている牧場を歩いていると想像してみましょう。秋のクロッカスのただ中で、死者を追っていくことができる意識状態を引き起こすように努めるならば、それが生えているところであればどこでも、ちょうど今述べたような存在、水かきのついた足と奇妙なカンガルーのような体を持った存在が見られるでしょう。秋のクロッカスのひとつひとつからそのような存在が現れて来るのです。もし、さらに移動を続けて、ベラドンナが道ばたに生えている場所に行き、皆さんを今お話ししたような意識状態に移行させるとすれば、皆さんは全く異なる存在、やはりこの世界に属する恐ろしい悪魔のような存在に出会うでしょう。ですから、秋のクロッカスとベラドンナは隣接する世界の存在たちが彼らの中に入ってくるのを許すところの霊媒、別の側面から見ると、実際に死者の世界に属する霊媒なのです。このことを心に留めれば、別の世界は私たちの周囲の至るところにある、ということが分かります。この世界に意識的に参入するということが、ただし、単に通常の意識をもって秋のクロッカスとベラドンナを知覚するのではなく、死者と関係を保つことができるより高次の意識をもって知覚するということが本質的なことなのです。さて、ここに秋のクロッカスが生えている牧場があると考えてみましょう。ベラドンナの花をつける植物を見つけるためには、遠くまで旅をし、山岳地帯に登らなければならないかも知れません。物理世界の中では、ベラドンナと秋のクロッカスが一緒に見いだされることはありません。しかし、精神世界の中では、彼らはごく近くに見いだされます。空間が別のあり方をしているのです。物理世界においては、遠く離れて存在している物体同士が、精神世界においては、ごく近くに見いだされることがあります。精神世界はそれ自身の原初的な法則を有しており、そこでは、あらゆることが異なっているのです。さて、これらの植物に死者の世界で出会うと想像してみましょう。私たちが初めて死者と連絡を取るとき、彼らの中には、これらの植物が私たちの中に引き起こすところの恐ろしい印象が引き起こされることは決してないということが分かります。彼ら、死者たちは、これらの悪魔的な存在たちは賢明な宇宙の計画にしたがってそこにいるのだ、ということを知っているのです。ですから、私たちが死者と連絡を取るとき、中間的な世界には、毒のある植物に対応する悪魔的な形態をしたものたちが多く住んでいるということが分かります。さらに進んで、死者が10年、20年、あるいは30年後にさらに高次の領域に入っていくために後にするところの領域に至るとき、私たちは毒のない植物に関連した形態を見いだします。ですから、植物界は物理世界におけるのと同様、それに隣接するより高次の世界においても重要な役割を果たしているのですが、後者の中では異なる形態を取っているのです。その真の姿においては星の世界に属するところのものが、地上におけるその対応物として、ベラドンナ、秋のクロッカス、あるいはスミレのような形態を有しているのです。それは、その真の姿が既に述べたような仕方で反映されるところの死者の世界の中にもその対応物を有しています。ある世界の中に存在するところのあらゆるのものは別の世界にも働きかけるのですが、私たちがこれらのことがらを真に認識するためには、それらが実際に属する世界に意識的に参入して行かなければならないのです。同じことはこれらの別の世界の存在たちにも当てはまります。私たちは、私たちの世界と直接境を接する世界に参入するときはじめて、元素存在とは、つまりアーリマン的な力の子孫とは何なのかを知ることができます。さて、これらの存在たちは霊媒を通して現れます。彼らは霊媒に憑依し、それによって一時的に私たちの世界に入ってくるのです。もし、私たちが人間の霊媒を通してだけ彼らと接触するならば、私たちは彼らを、彼らにとって本当は見知らぬはずの世界において知るのであって、彼らをその真の姿においては知らないということになります。彼らが現れているのは彼らにとっては見知らぬはずの世界ですから、ただ霊媒による出現のみによってこれらの存在たちを知るようになる人たちが真実に至る可能性はほとんどありません。精神的な顕現が伝えられている、ということに疑いはありませんが、彼らが属しているのではない世界からそれらが流れ出してくる限り、それらを理解することは不可能なのです。霊媒的な意識に結びついたあらゆるものの中にみられる高度に幻惑的で当てにならない要素は、これらの存在たちと接触を持つ人たちが彼らの真の本性を理解していない、という事実によって説明することができます。さて、彼らはこのようにして世界の中に入り込んでくるのですが、そのため、特別な運命がこれらの存在たちに用意されることになります。私が述べた宇宙についての知識は私たちの知識の範囲を広げるのに役立ちます。私たちが死者の世界に参入し、秋のクロッカスや紫のジギタリス、棘リンゴ等々の悪魔的な森を横切るとき、私たちはスミレが未来において変容を遂げ、全く異なる形態を取るであろうということに気づきます。彼らは宇宙の未来にとって、何らかの意義を有しているのです。秋のクロッカスは、正にその本性によって、それが運命づけられているところの死を準備します。毒のある植物は絶滅すべき植物、未来においては発達する可能性がなく、死滅しつつある植物なのです。彼らは未来においては別の毒のある植物に取って代わられるでしょう。今日、毒のある種類の植物は私たちの時代において既に死滅しつつあります。もちろん、ひとつの時代は長い間続きますが、これらの植物は彼らの内に死の種を宿しているのです。そして、それは植物界全体の運命になるでしょう。私たちがこの精神的な視界をもって植物の世界を探索するとき、私たちは未来に向けたダイナミックな衝動をもって成長し、発達する力と、死につつあり、消滅することが運命づけられた世界を知覚するのです。そして、これは霊媒に憑依する存在たちにとっても同様です。彼らは、現在を遙かな未来に向けて運んでいくことがその使命であるところの彼らの仲間から自らを引き離します。彼らは霊媒という代理を通して現在の世界に侵入し、そこで地球の運命に捕らえられ、彼らの未来の使命を犠牲にするのです。こうして彼らは人間からその未来の使命を大いに奪い取ります。これが霊媒主義の真の本性を私たちが理解するとき、私たちが目の当たりにするところのものです。と申しますのも、霊媒主義が示唆しているのは、現在だけを重要なものとするために、未来を消滅させるということだからです。ですから、私たちが真正な秘儀の関連性と宇宙の真の本性に対する洞察をもって心霊主義的なセッションに参加するとき、まず最初に驚かされるのは、心霊現象を見に集まった人々のサークル全体がまるで毒のある植物に取り囲まれているかのようであるのを見いだすときです。あらゆる心霊主義的なセッションは実際、毒のある植物の庭に取り囲まれているのですが、それらの植物はもはや死者の王国におけるのと同様の側面を見せるのではありません。心霊主義者のサークルの周りで成長し、そして、その実や花からは悪魔的な存在たちが現れるのが見られるのです。超感覚的な視覚を持つ人が心霊主義的なセッションで経験するのはこのようなことです。彼は、大まかに言って、内部から活性化され、部分的に動物となった毒のある植物の一種の宇宙的な茂みを通過するのです。私たちが彼らを毒のある植物であると気づくのはただ彼らの形態からだけです。私たちはこのことから、この心霊主義的な形態の内部で働くあらゆるもの、本来ならば人間進化の過程を前進させ、未来において実を結ぶべきあらゆるものが、それらが属していない現在へと引きずり下ろされている、ということを学ぶことができるのです。それらは、現在にあっては、人間性に有害な働きを及ぼします。心霊主義の内的な秘密とはこのようなものです。この秘密について、ここでもう少し学ぶことにしましょう。さて、心霊主義のどの側面が人間の構成にとって主要な問題を提示するかを正確に示すことができます。この文脈の中では、私の説明は必然的にいくらか抽象的なものに見えるに違いありませんが、それは心霊主義の本性に関するなにがしかの理解に向けて、いくらか皆さんの助けになるでしょう。さて、頭蓋の空洞中に横たわる人間の脳は平均で1500g、あるいはそれより少し重い程度の重量があります。これは本当にかなりの重量です。もし、人間の脳がその基底部にある繊細な血管をそれ自身の重量で押しつけるとすれば、それらは直ちに押しつぶされてしまうでしょう。ところが、私たちがどんなに長く生きたとしても、私たちの脳の重量がその下にある血管網を押しつぶすということは決してありません。このことは正しい説明によってすぐに理解できます。現在のような構成を持つ人間を取り上げてみましょう。脊椎管は上方にのび、脳のところで終わります。ある部分を除いて、脊椎管は液体で満たされており、脳はこの液体中に浮かんでいます。(lila 淡紫色 rot 赤色)さて、アルキメデスの原理について考えてみましょう。皆さんは物理学の勉強でよくご存じですね。彼が風呂に入っているときにインスピレーションのひらめきで発見したと言われています。彼は次のような実験をしました。彼が風呂に浸かっているときに、片方の足を水の上に上げ、続いて別の足を上げました。彼は彼の足が水の上にあるか水の中にあるかで重さが異なることに気づきました。水に浸かっているときには重さが失われたのです。アルキメデスのような人物にとっては、この経験はもっと広い意味を持っていました。彼は、物体が液体に完全に浸されているとき、見かけ上、押しのけられた水に相当する重量を失うということを発見したのです。水を入れたビーカーを実験台の上に置き、バネばかりからひもでつるした物体をその水の中に下げていきます。その物体は、水中では、空中にあるときよりも軽くなります。物体が液体に浸されるとき、それは押しのけられた水の重量に等しい浮力を受けるというのがアルキメデスの原理です。この原理は人間にとって大変ありがたいものです、何故なら、脳は脊椎液の中に浮かんでおり、脳の見かけ上失われた重量は押しのけられた脊椎液の重量に等しいからです。こうして、私たちの脳は1500gの重量を有してはいません。それが見かけ上失った重量は押しのけられた脊椎液の重さ、つまり、1480gですから、アルキメデスの原理に従って、その実際上の重量はたったの約20gということになります。私たちは、脳組織の中に、その実際の重量よりもはるかに軽い何かを有しているのです。私たちの脳は20gしかありませんが、私たちはこの20gを大切にしなければなりません、何故なら、それだけが私たちの「自我」を担うことができるものだからです。さて、私たちの体全体には、液体の媒体中に浮かぶあらゆる種類の固体成分、例えば血球が含まれています。それらはすべてその重量の喪失を被り、その一部分だけが残ります。それらもまた「自我」を担っています。このように、「自我」は重力に左右されることのない血液の中に拡散しているのです。私たちは人生の過程の中で、私たちの中にある知覚可能な重量を有するあらゆるものを注意深く観察しなければなりません。私たちは、脳の重い部分に位置するところのもの、まだ文字通りの意味で重量を有しているものに対して、最も厳密な注意を払わなければならないのです。何故なら、他でもなくそこに「自我」が位置しているからです。そうでなければ、アストラル体やエーテル体等々が取って代わることになります。霊媒とは、彼の構成体におけるこの固体である部分、20gの重量を有する脳がもはや「自我」を包含しない人のことです。「自我」は放逐されても、これらの部分はまだ重量を保持しており、元素存在たちが直ちに入り込むことが可能になっているのです。唯物的な思考様式はあらゆるものを位置決めしようとしますから、元素存在が霊媒に憑依するとき、人間のどの部分に入るのかを知りたがります。これは機械的、数学的に考える唯物的な心が語る言葉です。ところが、生命は機械的、数学的にではなく、ダイナミックに進行するものです。ですから、私たちは、その霊媒が純粋に数学的、幾何学的に位置決めすることができるあれこれの場所において取り憑かれている、と言うべきではありません。霊媒が取り憑かれているのは彼の構成体におけて重量あるいは重さを有している部分、つまり地球に引きつけられている部分であると言わなければなりません。とはいえ、アーリマン的な存在たちはそのようなところ入っていくことができるだけではなく、別のところにも入っていくことができます。皆さんにお示ししたこの記述はものごとの最も粗雑な側面を示したに過ぎません。もっと繊細な側面についても議論する必要があるのです。さて、目は私たちが外の世界を見るための器官です。目の中に配置された視覚神経は脳に結びついており、色を感じ取るための基盤を与えています。唯物主義者は視覚神経がどのようにして色の感覚を脳に伝え、そこでそれを解き放つかを説明しようとします。彼はそのプロセス全体を船の荷役あるいは鉄道輸送と比較します。何かが視覚神経に外から「積み込まれ」、神経によって輸送され、それがどこそこの場所で下ろされて魂の中に入っていくと。もちろん、その説明はこれほど粗雑なものではありませんが、結局はそういうことになります。本当の説明はこれとは全く違うのです。視覚神経の機能は色の感覚を脳へと運び込むことではなく、ある地点でそれを切り離すことなのです。色は周辺部においてのみ存在しています。視覚神経の機能とは、色の感覚が脳に近づけば近づくほどそれを絶縁し、そのため、脳には実際、色の感覚がなく、ただ弱く、かすかな色だけが脳に達するようにするということです。そして、色の感覚だけが絶縁されるのではなく、外的な世界とのあらゆる種類の関係もまた絶縁されます。聞くことと見ることは感覚器官に関連しています。脳の近傍においては、視覚神経と聴覚神経、そして熱を感じ取る神経が、周辺に位置するあらゆるものを弱い印象へと減退させているのです。この感覚についての関係は、1500gに対する20gの関係と同じです。と申しますのも、20gは脳の重さのかすかな印象を与えているに過ぎないからです。これだけが私たちに残されたもののすべてです。私たちが感覚を通して夜明けのすばらしい光景を取り込むとき、後脳はそのかすかな影、ぼんやりとした印象だけを捕らえます。私たちはそのぼんやりとした影に注意を払わなければなりません、何故なら、私たちの「自我」が入ることができるのはそこだけだからです。「自我」が隔離され、霊媒的な力が現れる瞬間、元素存在たちがこのかすかな影、聴覚から進み出てくるわずかな音の中に入り込みます。この存在は外的な感覚知覚が忘れ去られ、「自我」がいなくなった場所に滑り込み、霊媒に取り憑くのです。次にそれは神経網、すなわち意思の形成を司るところの神経という意志の器官に入り込みます。その結果、霊媒は活発に反応し始めるのですが、それは「自我」の支配下にあるべきものが元素存在たちに取って代わられたからです。あらゆるかすかで影のような要素、脳の残存重量、色や音の感覚の名残はファントムのように私たちを捕らえます、何故なら、この20gの重さはファントムであり、私たちの内的な存在を貫いて入ってくる色のかすかな影はファントムのようなものだからです。元素存在たちがこのファントムの中に入り込み、霊媒が深い昏睡状態になることによって、彼の体が全く受動的になるとともに、本当は「自我」によって浸透されるべき-通常は「自我」が間借りするはずの-かすかでファントムのような影の中に存在するところのあらゆるものが今や彼の中で活動するようになるのです。人間が霊媒になることができるのは、普通の人間にとって役に立つ能力が昏睡や完全な不活性によって阻止されるとともに、今述べたファントムが活性化されるときだけです。このことは、例えば、霊媒がものを書くときの仕方で観察することができます。もちろん霊媒は、脳の場合のように、彼の内のあらゆるものがより軽くなっていなければ書くことはできないでしょう。と申しますのも、元素存在が書く領域とは、重量を有するあらゆるものが液体の媒体中に浮かび、軽さの感覚やその感じを与え、そのため重力に左右されない領域、通常は「自我」がペンを操るはずの領域だからです。そのとき、霊媒の中で、この人間ファントムの中で、ペンの支配権を握っているのは元素存在なのです。すべての霊媒現象において別の世界の侵入が見られるという事実は否定できません。別の世界のアーリマン的な存在たちは、ちょうど霊媒によって遂行される動きの中に入り込むことができるように、昨日お話しした放射の中にも入り込むことができるのです。人間有機体の、特に腺組織の領域には強力な液体放射が存在しています。これらの元素存在たちは液体放射の中だけではなく、呼吸放射や光放射の中にも貫き入ることができます。化学放射の場合だけは、これらの化学放射を利用する人とその中に入ってくる存在たちとの間に意識的な交流があります。ここから始まるのが黒魔術、私がお話ししたような仕方で入り込んでくるところのこれらの存在たちとの意識的な共同作業です。霊媒や霊媒を使って実験する人たちは実際にどのようなプロセスが起こっているのかに気づいていません。ところが、黒魔術師は、これらの元素存在たちを、彼自身の目的のために、人間の、特に彼自身の化学放射の中に誘い込んでいるのだということを十分に意識しています。ですから、黒魔術師はこれらの元素存在たちからなる無数の僕に絶えず取り囲まれ、彼らが秘密の化学衝動を現象世界において用いることを、彼自身の放射を通して、あるいは実験室で香木を焚くことによって可能にしているのです。こうして、私たちは、ちょうどベラドンナ(bella donna)が見知らぬ世界に踏み込むことによって、毒を持つようになるのと同様、精神世界が、霊媒を通して、私たちが誕生から死までの間に住むところの世界に踏み込んでくるということを学びます。そして、基本的には、人間の意識、つまり彼の十全なる自我意識が抑圧されるとき、麻酔や昏睡状態にあるとき、あるいは実際に気絶しているときにはいつでもその危険が存在しているのです。眠りによってではなく、何か別の要因によって人間の意識が抑制されるときには絶えず元素存在たちの世界に曝される危険が存在しています。次の講義では、このことが人間の生活においていかに重要な役割を果たしているかを見ていくことにしましょう。(第八講・了)参照画:bella donna*ベラドンナは、イタリア語で「美しい淑女(bella donna)」を意味し、イタリア・ルネサンス期にはベネチアなどで女性が化粧用として点眼していたことからこの名前が付けられました。ベラドンナにはアトロピンという成分が含まれており、瞳孔を拡大させる作用があるため、目を大きく見せる効果が期待できたのでしょう。また、ベラドンナは植物全体に毒性があり、摂取すると幻覚や錯乱、呼吸困難などを引き起こすほか、昏睡状態に陥ったり死に至ったりすることもあります。根には特に強い毒性があり、葉に触れると皮膚がかぶれたり潰瘍ができたりすることもあります。そのため、「悪魔の草」「魔女の花」などとも呼ばれ、誤って食べてしまうと強い食中毒を引き起こします。昔のローマでは、植物を扱う人を魔女とみなして魔女狩りが行われており、魔女を仕立てるためにベラドンナが使われていたという説もあります。たてつく人や気に入らない人にベラドンナを与え、幻覚や錯乱状態にして魔女に仕立てたと言われています。また、魔女はこの草を使って人殺しをしたり、サバト(集会)に出かける際には、これを混ぜた膏薬を体に塗って空を飛んだと伝えられています。人気ブログランキングへ
2024年05月05日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神的な探求における真実の道と偽りの道」 (GA243) トーケイ、ディヴォン、1924年8月11日-22日 佐々木義之 訳第七講 星の世界の認識、人類の歴史時代の区別とその精神的な背景 前回の講義では、人間がいかに様々の人生の期間を駆使して、それらの期間を精神的な視界をもって振り返るかを見てきました。彼は、このようにして、彼の意識を星の世界との十分な霊的交渉に向けて一歩一歩上昇させるインスピレーションを達成します。もちろん、この世界は、純粋に霊的な存在たちと事実の純粋に霊的な表現、顕現として理解されなければなりません。精神世界への扉を開き、その世界の探求に取りかかるときには、必要な意識状態と必要な魂の条件を発達させるために骨の折れる努力がなされなければなりません。私たちは、通常の意識を用いて精神的な洞察を達成できるという幻想を抱くべきではありません。この点を示すために、いくつかの特別な例が役立つでしょう。精神的な探求において間違いの源泉となる可能性があるものを示す前に、次のような前置きをしておきたいと思います。精神世界への扉の鍵を開け、いわば精神世界との対話を持つための知覚を可能にするところの精神的な訓練に真剣に取りかかる人は、人類の歴史的な進化は広範な特殊性、すなわち精神的な背景についての特筆すべき差違を示しているということに気づきます。後で示すような理由によって私たちが「ミカエルの時代」と呼ぶところの今の時代は一九世紀の終わりから三分の一、およそ一八七〇年代に始まりました。この時代に先立つ時代は三、四世紀の間続きました。精神的な認識を有する人たちにとって、この時代の性格は完全に別のものでした。さらにその時代に先立ち、やはり全く異なる性質の別の時代がありました。したがって、私たちが秘儀に参入する認識をもって過去を振り返るとき、個々の時代が全く異なる印象を呼び起こすということが分かります。私はこれらの印象を抽象的な記述ではなく、具体的な例によって示そうと思います。※ルドルフ・シュタイナーは、1703年に「ミカエルの太陽諸力による」という論文の中で、「ミカエル支配を通して、キリスト教が一つのより深い意味の中で捉えられるべきである」という問題を提起しています この連続講義の中で、人類の進化に関して様々の役割を演じてきた人々についてお話ししてきました。例えば、有名なダンテの師ブルネットー・ラティーニ、シャルトルの学院における教師たち、ベルナルドゥス・シルベストリ、アラヌス・アプ・インスリス、フィオーレのヨアキムについて触れましたが、さらに、九世紀から一二世紀あるいは一三世紀にかけてさえ、何百人の人々について語ることができるでしょう。これらの人々はそれぞれがその時代を特徴づける人たちでした。精神科学の立場から、人類の歴史を、例えば、ダンテやジョットーの時代、すなわちルネッサンスの時代を探求しようとする人は、精神世界にいる人間、肉体を脱いだ人間たちと交わることが絶対に必要であると感じます。つまり、隠喩的に言うと、死と再生の間にある人間たちと面と向かって出会わなければならないと感じるのです。秘儀に参入する認識の中で、私たちは、ブルネットー・ラティーニのような人物に対する私たちの精神的な関係は、物理的な世界における私たちの仲間の人間との関係のように個人的なものでなければならないという明確な感情を持つのです。私はこれについて、以前に述べたことの中で示唆しようと試みました。つまり、フィオーレのヨアキムやブルネットー・ラティーニについて語ったとき、私はこの時代を、私の記述にできるだけ個人的な気味を与える必要があると感じるのは明白なことである、というような仕方で記述したのです。一九世紀の三分の二に至るまで続く次の時代においては状況は全く異なります。この時代には、私たちが接触しようとする肉体を脱いだ魂と個人的あるいは個別的な関係を持つ必要はずっと少なくないのです。私たちはむしろ彼らをその全体的な環境の中で見たいと思うでしょう。つまり、彼らと直接的に接触するのではなく、何か地上的な認識、通常の意識を通して彼らと接触する必要を感じるのです。ここで、個人的な経験の中からあることがらを紹介させていただくのをお許しいただきたいと思います。この場合についていえば、個人的な経験は完全に客観的なものなのです。私たちの時代に先立つ時代とはゲーテの時代でしたが、私は数十年にわたって彼の作品の研究に携わってきました。最近の数年間は、精神的な存在として精神世界にいる彼と直接個人的に接触する必要が生じたのですが、当初は、個人としてのゲーテではなく、いわば星の世界における存在としての彼の宇宙に対する全体的な関係性の中で死後の彼を経験する必要がありました。他方、ブルネットー・ラティーニや彼の時代の本質に関する研究に関係する人々と精神的に接触したいときには、彼らと個人的かつ密接な精神的かかわりの中で考えや意見を交換する直接的な必要性が感じられるのです。これは非常に重要な相違なのですが、それはこれらふたつの時代の内的、精神的な特徴が全く異なっているという事実に結びついています。今日、私たちは、人間、あるいは全人類が精神的な真実を直接理解するという珍しい機会を有する時代、つまり、秘儀参入の科学が普遍的な財産になるという時代に生きているのです。私たちは、ちょうど始まったばかりのこの時代を、文化的に開けた階層の側が主要な事実に、世俗的、物理感覚的な事実ではなく、精神的な事実に心から気づくということなしにやり過ごすべきではありません。これからの私たちの時代は精神世界に直接関連するところの精神科学を精力的に追求していかなければなりません。そうでなければ、人類は定められた使命を果たすことができないでしょう。私たちはますます精神的な時代へと入っていかなければならないのです。これ以前の時代には、別の力が人類の進化に主要な影響を及ぼしていました。そして、私たちが真正なる星の認識の立場から語るときには、次のように言うことができます。前世紀の七〇年代に始まった時代においては、魂的な生活や物理的な生活、科学、宗教、芸術におけるあらゆるものの中で、とりわけ太陽から輝き出る精神的な力が主要な影響力を及ぼさなければならない、と。私たちの時代においては、太陽の力の影響と活動がますます広範に行き渡るようにならなければならないのです。真の認識を有する人々にとって、太陽は現代物理学が記述するようなガス球ではなく、精神的な存在たちの集合体です。そして、太陽の光が物理的、エーテル的に輝くように、精神的なものを放射する最も重要な精神存在たちはキリスト教的-異教的あるいはキリスト教的-ユダヤ教的な用語法にしたがってミカエルと呼ばれる存在のまわりに集まっています。ミカエルは太陽から働きかけます。太陽からの精神的な影響はミカエルとその仲間たちの影響と呼ぶこともできます。私たちの時代に先立つ時代においては、人間の生活や活動、そして認識を求める探求の背後にある原動力は太陽の力ではなく月の力でした。三、四世紀にわたって続き、一八七〇年代に終わりを告げた時代の背後にあった原動力は月の力だったのです。この時代、地球進化に影響を及ぼしていた指導的な存在たちは、古代の用語法にしたがってガブリエルと呼ばれる存在のまわりに集まっていました。別の名を、用語はそれほど重要ではありませんので選ぶこともできますが、キリスト教的-ユダヤ教的な伝統にしたがってガブリエルという名前を使うのが最もよいでしょう。こうして、私たちは星の世界から導かれる人間の精神的な活動を私が示したような仕方で気づくようになります。私たちは、秘儀に参入する認識を通して、誕生から歯が生え替わるまでの時期に人間の中で働いているものを確認するとき、宇宙に存在する月の活動に対する洞察を獲得します。言い換えれば、子供時代の最初の年月をインスピレーション的、遡及的に辿ることを通して、私たちは月の影響が特に活発に働いていたガブリエルの時代についての認識を得るのです。他方、私たちの時代の特徴的な性格を知覚するためには、私たちはもっと成熟し、私たちが二〇代から四〇代であった頃、より正確には二一才から四二才までの間に私たちの中で形成的に働いていた力を振り返ることができるような年代になっていなければなりません。したがって、私たちの時代に先立つ時代においては、世界の宇宙的な方向性に関して決定的な役割を果たしていたのは非常に若い子供たちでした。ガブリエルの時代の力は既に幼年期に働く衝動の中に投影されていたのです。私たちの時代において、太陽の力からの衝動を受け取るように運命づけられているのは三〇代や四〇代の人たちです。つまり、全世界の宇宙的な指導において決定的に重要な役割を担っているのは成人たちなのです。これらの事実は、私が一昨日皆さんにお話しした直接的で精神的な知覚から得られる実際的な結果です。それらは空疎な理論ではなく、実践的な知覚による果実なのです。ですから、お分かりのように、現在のミカエルの時代に先立つガブリエルの時代を理解するためには、その時代の肉体を脱いだ魂に個人的に出会う必要は特にありませんでした。これらの魂に向き合うときには、幼年期のインスピレーション的な知覚をもっていなければならなかったために、大人の前に立つ子供のように感じられたのです。それに先立つ時代、アラヌス・アプ・インスリス、ベルナルドス・シルベストリ、フィオーレのヨアキム、ハンビルのジョンやブルネットー・ラティーニの時代を探求するのは全く別のことです。この時代は、歯の生え替わりから思春期までの時代に彼の内で働いている力を遡及的に振り返るときに獲得される力によって支配されていました。これは水星の力です。人間がこの人生期を出発点として精神的なものの知覚に対応する器官を発達させるとき、彼は何か非常に意義深いものを経験します。歯の生え替わりから思春期までの時期において、人間は何でも知りたがる子供ですが、この人生期に属する器官をもって知覚するとき、彼は再び子供の熱情を経験するのです。彼がこの時代に属する人々に個人的に会いたいと望むのはこのためです。そして、彼は秘儀参入から生まれた認識をもって、実際にそうするのです。彼は、ちょうど十才か一二才の子供が目上の人、彼の教師や先生に出会うような仕方でブルネットー・ラティーニのような人物に向き合いたいと思うのです。秘儀に参入する真の認識を自分のものとするとき、人間は現象世界のことがらに無関心ではありません。彼は大人であると同時に知識を渇望する子供なのです。彼はブルネットー・ラティーニと対等の立場で向き合うのですが、彼から学びたいという強烈な欲求をもってそうするのです。十五世紀から十一世紀にまで遡る時代の秘儀に参入する認識はこの関係から来る特別な色合いを帯びています。それは地球と人類に対する主要な衝動が水星から与えられた時代なのです。それを中心にあらゆるものが回っていた存在、その時代において特別な重要性を有していた存在はラファエルという太古の名前の下で知られていました。ラファエルはルネッサンスに先立つ時代、ダンテやジョットーの時代における水星だったのです。私たちは正に歴史上ほとんど知られていない人たち、その名前が記録されなかった人たちと個人的に知り合いたいと感じるのです。私たちが精神科学の教えに精通するとき、その時代は私たちの中に奇妙な反応を引き起こします。まず第一に、私たちはブルネットー・ラティーニやアラヌス・アプ・インスリスのような人物について教科書がほとんど何も語らないことに当惑し、もっと歴史的な事実が与えられないものかと思うのですが、私たちの地平が広がるにしたがって、通常の歴史が沈黙していることに感謝し、ありがたく思うようになります。何故なら、外的な歴史資料は単に断片的なものだからです。もし、私たちの時代の認識に関して、その歴史上の副次的な枝葉末節についての新聞記事が唯一の有効な証明であると考えられるとしたら、それが子孫の目にどのように映るであろうかを想像してみて下さい。私たちは、これらの人物に関して、百科事典の中に見られる限られた情報によってじゃまされないことにただ感謝することができるだけです。そして、私たちは、今日、人智学協会が手にすることができるあらゆる手段を用いて、これらの人物との精神的な接触を試みるとともに、精神科学の立場から彼らについて確認することができるあらゆることがらについて報告しようしているのです。この関連で、ラファエルの時代において自然認識にたずさわっていた人物たちと関係を持つことはとりわけ重要なことです。より深い自然認識、医学のより深い理解は、この時代の精神的な夜明け九世紀から十五世紀の中から超感覚的な知覚の前に現れ出るとともに、私たちに現在流行している物質概念や人間の全宇宙に対する関係についての考え方を教示してくれるところの多くの人物たちを通して伝えられます。私たちが超感覚的な視覚をもってこの時代をのぞき見るとき、その名が後世に伝えられて来なかった多くの無名の人物たちに出会うのですが、これらの人物たちは現実に存在していたのです。これら多くの人物たちが私たちの前に現れるとき、私たちは、そこに立っているのは「大パラケルスス」であるが、その名前は記録には残っていない、他方、後の時代、ガブリエルの時代には「小パラケルスス」が生きていたが、彼は大パラケルススの自然の叡智を、もはやその純粋かつ崇高な精神の形態においてではなく、思い出として有していたのだと言います。後のガブリエルの時代には「小ヤーコブ・ベーメ」が私たちの前に現れます。そして、そのときも、この人物は様々の伝統的な教えから学び取った崇高な真実、彼のインスピレーションに刺激を与えた崇高な真実を告げた、と言うのですが、私たちが本当に「小ヤーコブ・ベーメ」を理解するのは、後世には知られていない、その名前もアラヌス・アプ・インスリスやブルネットー・ラティーニと同様、たまにしか触れられることのない「大ヤーコブ・ベーメ」が私たちの前に現れるときだけです。ルネッサンスに先立つ時代は、そして、その時代の終わりには、ダンテやブルネットー・ラティーニのような有名な人物やシャルトルの学院が孤立した明かりのようにそびえ立つ一方で、その中心には、スコトゥス・エリウゲナが標石(訳注:氷河などに運ばれて意外なところで見つかる玉石)のように現れるのですが、何か力強い精神的な刺激を包含しています。中世についての外的な歴史は闇に包まれていますが、この闇は今お話しした時代を照らし出すことができる力強い人物たちの存在を隠しているのです。私たちが九世紀から十五世紀までのラファエルの時代(原注)に入っていくとき、ダンテやジョットー、そして後世にその名が知られていない人物たち、あるいはまた私が触れた別の人物たちが大きく浮かび上がってきます。彼らは身近な人間としての印象を私たちに与えます。肉体の中に一度も受肉したことのないラファエル自身はもっと背景の方向に退いています。永遠に精神世界に居住するその他の精神的な存在たちはこの時代にはそれほどはっきりとは規定されていません。大きく浮かび上がってくるのは人間、特に死者たちです。続くガブリエルの時代は、ゲーテ、スペンサー、バイロン卿、あるいはボルテールのような人物たちでさえ精神的な世界の中では影のような存在であるという印象を与えます。他方、私たちは、精神的な知覚を通して、人間というよりも超人のような印象を残すすばらしく壮大な存在を意識するようになります。彼らは今日も存在しています。そして、地球が私たちの誕生から死までの住居であるように、月の領域が彼らの永遠の住居なのです。これらの印象的な存在たちが私たちの注意を引く一方、人間の魂はもっと背景へと退いています。今日、私たち人間がそうであるように、これらの存在たちはかつて地球に結びついていたということが分かります。人間は物理的な体の中に生きていますが、これらの月存在たちは、地球上では、精妙でエーテル的な体の中に生きていました。そして、太古の時代には地上にあって人間と交流し、人間の精神的な教師であった存在たちは今でも私たちと共にあるということに気づきます。彼らは、彼らの地上での使命が成就したとき、月の領域へと退き、今日ではもはや地球には関係していないのです。私の本「神秘学」をお読みになった方はご存じのように、月はかつて地球と結びついていましたが、後に分離しました。これらの存在たちは月の分離に際してそれに同伴し、その後、月の領域の住人となりました。ですから、私たちは、私たちが死後間もない死者たちと連絡を取ることを可能にする認識段階において入っていく世界の中でも、通常の意識に関する以前の認識をまだ保持しているために、私たちを取り囲む人たちはかつて地上において肉体を持った人間であったのだ、ということを今日の通常の覚醒意識によって認めるのです。つまり、私たちは、この異なる意識に参入するとき、ちょうど私たちが地球に属しているように月の領域に属する精神的な存在たちと共にあるのだということにますます気づくようになるのです。彼らは普遍的に存在し、人間の行いに関心を寄せているのですが、それは今日の人間がそうするような物理的な観点からではありません。かつて人類の偉大な教師であった存在たち、すなわち、もはや地球の住人ではなく、いわば月領域の住人であるところの存在たちの中には、圧倒的な壮大さと最高度に発達した精神性を有し、内的、精神的な荘厳さに満ちた存在が見いだされます。宇宙の神秘に関する非常に多くのことがらを彼らから学ぶことができます。彼らの知識は通常の意識が到達することができる知識をはるかに凌駕しているのです。けれども、彼らはこの知識を抽象的な思考によって表現することができません。彼らのそばに近づくと、歌が押し寄せてくるのに出会いますが、彼らはあらゆるものを詩や芸術的なイメージを通して表現するのです。彼らは、その独自のやり方で、ホメロスや古代インドの叙事詩では知られていなかった崇高な調和をもって私たちを喜ばせ、魅了するのですが、彼らが私たちの前に魔法のように出現させるものすべての中には深い叡智が横たわっています。とはいえ、彼らの中にはそれほど完全でないものたちもいます。ちょうど地上に愉快な連中や不愉快な連中がいるように、これらの異なる存在たちの間にも、その仲間たちほどの荘厳さや完全さを達成しなかったものたちを見いだすことができるのです。にもかかわらず、彼らは生徒や弟子として地球領域を離れ、月領域に生きながらそこで働き続けたために、ある程度の完成段階に到達しています。卑近な表現ですが、彼らとつき合うとき、彼らが地上のできごとに燃えるような関心を寄せているのがすぐに分かるのですが、それは全く異なる種類の関心なのです。これらの存在は好意的ではなく、どちらかというと招かれざる連中なのだ、と想像してはなりません。彼らは、その仲間と比べれば不完全であるとはいえ、現代人が通常の意識をもって到達することができるレベルをはるかに超えた明晰さ、賢さ、洞察力を有しているのです。彼らはいつでもその仲間と同じ習慣を共有しているのですが、今日の通常の人間とは異なる習慣や傾向を有しているのです。ここでことの詳細に入っていきたいと思いますが、これはある種の重要性を持っています。私たちがそのような存在たちと関係を持つとき、これは確かにいくらか卑近な表現ですが、意見交換をしたい、あれこれのことがらについて彼らと話し合いたいという自然な感情をもつようになります。具体的な例をあげますと、私たちがこれらの存在たちと、書くことについて、人間が記述した作品について語り合っていると想像してみましょう。ある人は単純にその名前を書きとめ、別の人は自分のサインあるいはイニシャルを書くと想像します。私たちがこれらの問題についてその存在たちと議論するとき、彼らは次のように答えるでしょう。お前たち人間は全くつまらないことに、つまり、言葉の一義的な意味、例えば、「鍛冶屋」や「床屋」が何を意味しているのかに興味を持つが、それらの単語が書きとめられるときの書き手の特別な動き、各人がいかに異なった書きぶりをするか、速く書くか、骨を折って書くか、巧みに書くか、ぎこちなく書くか、機械的に書くか、芸術的に書くかを観察する方がもっとはるかに興味深いのだと。これらの存在たちは人間が書くときの特別な動きのパターンに綿密な注意を払っているのです。それが彼らの興味を引くものなのです。そして、私が今お話ししている精神的な世界において、これらの存在たちは、既に地上には住んでいない実在たち、あるときは人間よりも下位に、あるときは上位に位置づけられるような実在たちをその取り巻きとして有しています。彼らは私たちに用語法や命名法について私たちを指導することはありませんが、彼らが地上にいたときから人類が発達させてきた筆記パターンや形態について助言を与えているのです。今日の意味での書くということは、これらの存在たちが地上にいたときには存在していませんでした。彼らは人間との交わりの中で、筆記が徐々に進化するのを観察してきました。彼らは指の器用な動きに興味を持ち、その器用さが後に羽ペンが加わることによって補完され、さらには万年筆によって補完されるのに注目してきました。彼らは紙に委ねられたものにはほとんど興味を持たず、それをするために必要な動きに完全に没頭したのです。さて、ある付加的な要素が考慮されなければなりません。今でも生き残って存在する地球からの放射は大体において見過ごされてきました。それらの放射が取る多くの形態の中に、まず今お話しした人間から発する動きがあります。これらの存在たちと語り合うことができるのは、人間から発する動きなのです。ところで、さしあたり、これはあの存在たちの真の領域へと導くような何かではありません。何故なら、彼らが地上に住んでいた時代には書くということはまだ存在していなかったからです。今日の人間が自分の流体放射に関して限定的な理解力しか持ち合わせていないことについて、これらの存在たちから発せられるコメントは相当に皮肉に満ちたものです。現代人には無視されますが、それはこれらの実在たちには非常によく知られたものなのです。そのように、これらの存在たちが地上にいた時代には、流体の放射、皮膚からの流体放射は決定的に重要なものだったのです。人間はその吐息を通して仲間の人間を認識するようになっていたのですが、このことは後には知られなくなりました。これらの存在たちが特に受け入れる第三のものとは皮膚からの発散、人間から発する空気要素です。これらすべての放射は、あとで見ていきますように、半精神的な性格を有しているかも知れません。これらの存在たちが特に敏感なのは人間から発するこれらの放射。筆記における固体要素、皮膚発汗における液体要素、皮膚呼吸における空気要素です。人間はいつでもその皮膚を通して呼吸していることを思い出さなければなりません。第四に、これらの存在たちは熱放射を受け入れます。これらすべては地上に存在しているために、あの月存在たちにとって特別に重要なものなのです。人間はその筆記における動作の構成やその発散における特別な性質によって判断されるのです。次は恒常的に存在する光の放射です。誰でも、オーラからだけではなく、肉体やエーテル体からも光を放射しているのです。通常の状態では、これらの放射はあまりにもかすかであるために目には見えませんが、最近、モーリッツ・ベネディクトは特別にしつらえられた部屋を用いてそれらが存在することを示しました。彼は肉体が場所によって様々に異なる赤や黄色、そして青い光の放射を示す繊細なオーラによって取り巻かれているのを示したのです。モーリッツ・ベネディクトが私たちに語るのは、彼がどのようにして色のついたオーラを示したかです。彼は通常の光の条件下では体の左側半分を、オーラを出現させる条件下では別の半分を示しました。すべてはいかに適切な実験条件を設定するかにかかっています。参照図;アウラ(Aura)※アウラ(Aura)は、もともとは「風」「輝き」「さわやかな香り」など、さまざまな意味を持っていましたが、現在は霊的なエネルギーを表現するときに使われます。オカルティズム、神智学、超心理学の領域においては、人間を取り巻く神秘的な光彩の放射として表象されます。 第六の放射は化学的な力の放射ですが、これは、今日、地上においては例外的なケースであり、まれにしか見られません。それは当然のことながらいつでも存在しているのですが、黒魔術が行われるようなまれな場合にしか作用しないのです。人間が自分たちの化学的な放射を意識し、それらを探求するのは、地上で黒魔術が行われているときなのです。七番目の種類の放射は精神的な生命の直接的な放射、もしくは命の放射です。今日、化学的な放射を用いるとすれば黒魔術に陥ることは避けられませんが、それは嫌悪すべきものであり悪徳です。黒魔術は対処すべき力ですが、生命放射がそれほど重要ではないというわけではありません。今お話ししている月存在たちの場合、絶えず生命放射に依存し、それに働きかけるとともに、善のために用いているのですが、彼らは黒魔術師ではありません。何故なら、黒魔術師とはある条件下で悪に屈し、「地上で」悪を行うものだからです。けれども月存在たちが生命放射に依存することができるのは、太陽の反射光の中に生き、その影響の下にある満月のときだけです。私たちは精神世界から学ぶものを創造的に用いるように努めなければなりません。私たちの時代の使命は生きたアイデアを見いだし、生きた概念、知覚、そして感情を発達させることであり、死せる理論を発動することではないのです。そして、これらは私たちがミカエルと呼ぶ存在に結びついた存在たちによって直接インスピレーション的に与えられるのです。以前のガブリエルの時代、人類は物質世界により引きつけられていました。人々は、ある条件下で人間に密接に関係する存在たちとの接触を求めようとはしていませんでした。それはこれらの存在たちがその時代には知られていなかった何か、つまり、人間から出てくる神秘的な放射に関係していたからです。既に述べたような仕方で私たちが死者と関係を持つところの精神的な世界は、私たちが誕生から死までの間に住むところの物理的な世界に隣接しています。けれども、この世界は他の多くの側面を有しており、その中には人間の放射の中に生きるあの力の作用効果があります。ある意味で、これは宇宙の中でもきわめて危険な領域であり、私たちが持つべきなのは、今回の連続講義でもしばしば触れましたが、これらの月存在たちから進み出てくるあらゆるものを、悪の力ではなく、善の力にするようにな魂的、霊的なバランスと抑制力です。実際、今の時代のすべての力と衝動は、生命放射を地上のものと考える方向に急いで向かわなければなりません。ところが、致命的に容易なのは、この生命放射と私たちが大喜びで持ちたいような他のすべての放射との間に横たわるもの、つまり黒魔術の餌食になる、ということです。人間がとりわけ好むのは、動きの中で表現されるもの。これについては後ほどお話しするつもりですが、流体放射や光放射の中に存在しているものを可視化するということです。このすべてはある程度善の力に関連しており、ただ善に向かうことができるだけなのですが、それは人々の間でミカエルの時代がその夜明けを迎えているためです。このすべての間に横たわっているのが、精神的な探求に向かう正しい方法を追求するためにはそれに対抗しなければならない黒魔術なのです。1.人間から発する動き2.液体要素の皮膚からの発散3.空気要素の皮膚からの発散4.熱放射5.光放射6.化学的な力の放射(黒魔術)7.生命放射 さて、地上の人間と月存在たちの間の精神世界におけるこの関係が-そして、これは無意識の領域の中で絶えず生じているのですが-生じるとき、ある種の月存在たちが筆記や描写の動きに対して発達させる興味、つまり、超感覚的に見ることができるこの興味に関しては、精神世界におけるある種の元素存在たちの中にもその残響が見いだされます。元素存在たちは月存在たちよりも低次の段階にあります。彼らは一度も地上に受肉したことはなく、霊的-エーテル的な存在として、隣接する世界に住んでいます。彼らの人間世界に対する興味の結果とは次のようなものです。観察によって、人間が筆記を通じて伝える考えは彼の全存在に働きかける、ということが分かります。それらの考えはまず最初に自我の中に存在し、そしてアストラル体に伝えられます。アストラル体は正確に自我が決めたとおりの動きを遂行します。次にそれらはエーテル体からさらに肉体にまで作用します。ある種の元素存在たちはこれらの影響を観察し、同じように反応することを望みますが、それは不可能なのです。何故なら、彼らの世界に通用する法則は筆記が実行される世界の法則とは異なるからです。筆記は地上の人間の物理世界における特権なのです。ところが、次のような状況が生じます。ものを書いたり、考えたり、あるいは感じるときでさえ、しっかりとそのエーテル体につなぎ止められている人々がいるのです。つまり、そのような人々の場合、エーテル体全体がそれらの過程に巻き込まれ、そしてそれが肉体に強く刻印づけられます。その自我は抑制され、アストラル体とエーテル体と肉体は筆記や描写を忠実に再現します。霊媒とはこのようなタイプの人間なのです。そのような霊媒たちは、自我が抑制されているために、月存在から筆記の動きを学んだ精神世界の従順な元素存在たちを自分の中に取り込みます。そして、十全なる自我意識をもってではなく、それをコントロールするところの元素存在たちの影響下で筆記の動きを実行するのです。霊媒的な筆記や描写、通常の霊媒現象が起こるのは、減退した意識状態における霊媒からの発散を通してです。これらの放射はそれをコントロールするために利用されます。第二の種類の放射は月存在の影響下で容易に人間の芸術的な才能を吸収することができるある種の存在たちによって利用されます。これらの存在たちもまたある種の人間たちの中に入っていくのですが、その人間の表層意識は抑制され、放射へと導かれるある種の芸術衝動をそのエーテル体とアストラル体の中に有しているのです。ある種の条件下で、このタイプの人間が元素的-精神的な存在に取りつかれ、それらの放射が、一見するとまぼろし(ファントム)の形をしたもの、つまり、その一部はその人間の人生経験についての知覚がエーテル体とアストラル体にまで沈み込み、放射として現れるところのものから構成され、別の部分は、彼の中に入り込んだ元素存在だけが住む世界から伝えられるところのものから成り立っているところのファントムに侵されているのを観察するのはきわめて興味深いことです。さて、同様の結果はシュレンク-ノッチングの実験からも得られました。彼の実験対象はある種の霊媒タイプの人たち、影響を受けやすい霊媒たちでしたが、彼らは、その自我が抑制され、減退した意識状態の下では、彼らの皮膚からの流体放射のために、元素存在たちにとって理想的な素材でした。そのテーマに関しては、シュレンク-ノッチングによる興味深い本があります。それをいかさまだと言う人もいれば、高く評価する人もいました。後者が彼の発見を普通ではないと考えたとしても驚くにはあたりません。何故なら、霊媒を使って実験が行われたとき、エクトプラズム(ectoplasm)、すなわち地上には見いだされない精神的な要素を体現する形態が体のある部分から流れ出した、というのは普通のことではないからです。多くの場合、霊媒が最近見たグラビアの絵がその形態に関連している、ということが分かりました。何かが霊媒から流れ出します。それは皮膚からの発散です。そして、この中には全く精神的な何かが流れ込むのですが、それには霊媒が最近グラビアや漫画雑誌の中で見た、例えばポアンカレの肖像のようなもの参照画:ectoplasm 人々がそのようなことに驚愕するとしても驚くにはあたりません。けれども、流行の装いをした品のよい人々が、そして、皮膚からの分泌について話したり、魂の具現化について議論したりするのを最も嫌がるであろうようなご婦人方までが、これらのエクトプラズム的な形態が紛れもない霊媒の汗から具現化されるのを見たいというみだらな欲求を感じるというのは本当に驚くべきことです。シュレンク-ノッチングの実験で見られた現象は、単に分泌物が皮膚からの発散を通して元素存在たちによって活性化されたエクトプラズマ的な形態へと具現化したものにすぎません。同様にして、皮膚発散、すなわち霊媒から流出する気体の形成はある種の元素存在たちによって刺激されることがあります。けれどもこれらの皮膚発散は特定の人間の形態に非常に密接に結びついており、これらの存在たちに可能なのは、せいぜい人間自身の幽体(ファントム)を創造するという程度のことにすぎませんが、それは人間が自らの人間的な形態をそれらに非常に強く刻印することによります。そのとき私たちが目撃するのは霊媒からの幽体の流出現象です。人間からの熱放射や光放射をつくり出すことによって霊媒が何か目に見えるもの、これらの元素存在たちが月存在の影響下で働きかけることができる幽体のようなものを現出させるのはそれほど容易なことではありません。まず、ある種の準備がなされなければなりません。既にお話しましたように、自然科学は最近、暗い部屋の中である種の光放射や熱の発散を見えるようにすることができる技術を開発しました。この関連で、モーリッツ・ベネディクトの実験は最も輝かしいものです。けれども、それはいつの時代でもそうだったのです。つまり、今でもそうなのですが、黒魔術を通して物理世界を操作するだけではなく、香を焚いたり、特別な香料や調合剤を使うことによって幻覚的な効果をつくりだすという準備段階を踏んだ人だけが熱や光の発散を有効に使うことができたのです。これらの魔術的な儀式の目的は、人間からの熱や光の発散の中に本来存在するところの力を引き出すということです。エリファス・レヴィーや、パプスというペンネームを持つエンコースの著作の中には、このテーマに関するきわめて危険で疑問の多い説明が見られるのですが、これらのことがらに関して、その客観的な側面や真の本性について語るべきであるならば、それらを無視して済ますことはできません。これらすべてのことがらは地上的な要素の中に隠された精神的なものを利用するところの黒魔術へと直接導くものです。この精神的な要素とは何なのでしょうか? 皆さんは私の著書「神秘学概論」の中に、月はかつて地球と結びついていた、という記述を見いだされるでしょう。月に属する多くの力が地球上に残され、今や、鉱物、植物、そして動物の中に広がっています。これらの月の力は今でもそこにあるのです。ですから、私たちが、地球存在として、本来は鉱物、植物、動物、あるいは人間には属していない月の力を利用するとき、月存在たちから多くのことがらを私たちの世界にとっては見知らぬ方法で学んだ元素存在たちに出会う領域に踏み込むことになります。黒魔術師は、このようにして、まだ地上に存在している月の力を利用しているのです。けれども、彼は、このような仕方で働くことによって、元素存在たちに接触することになります。そして、これらの元素存在たちは人間と月存在たちの間の正しく正当な関係を-人がハルマやチェスのゲームを見るように-いわば監視することによって、物理世界に限りなく接近し、それをのぞき込み、そしてそこに足を踏み入れることさえ学んでいるのです。しかし、通常の人間の場合、これらすべては無意識の中に留まり、これらの存在たちと接触を持つことはありません。ところが、月の力を使って仕事をし、彼らを試験管やるつぼの中に閉じこめる黒魔術師はこれらの元素存在たちの渦中に捕らえられることになります。正直でまっとうな人間もこれらの黒魔術師たちから学ぶことができます。ファウストの第一部でゲーテが示したのは人間が渦巻く力の中心にいるという状況、危険な黒魔術の近くにいるという状況です。人間は、これらの力を利用することによって、月存在たちに奉仕する実在たちが容易に人間と関係を持つことができる領域に入っていくことになるのです。こうして、黒魔術の中心地は月の力とそれに直接奉仕するようになった精神存在たちとが悪事のために共に働くところに生じます。そして、ここ数世紀にわたって多くのこの種の活動が実践されてきたために、地上には危険な雰囲気がつくりだされています。危険な雰囲気は疑いもなくそこにあり、人間の活動と月の要素との統合、動的な月の力とよこしまな月の力に奉仕する元素存在たちとの統合から産み出される夥しい力が注入されています。ミカエルの時代に太陽の領域から進み出てくることが定められているすべてのものに活発に反対しているのはこの領域なのです。そして、このことは特に魂と精神の領域における生命の発散との関連で考慮されなければなりません。明日は、この観点からさらに探求を行う予定です。1.人間からの発散-霊媒的な力2.液体要素の皮膚発散-物質化3.皮膚発散-幽体の示顕4.熱放射5.光放射6.化学的な力の放射(黒魔術)7.生命の放射 ミカエル-太 ガブリエル-月 ラファエル-水星(原注)一九二四年八月一八日付けのルドルフ・シュタイナーのノート(トーケイ、朝の講義)には、大天使の時代に関して次のような書き込みがある。一八七九-一五一〇年 ガブリエル 月、一五一〇-一一九〇年 サマエル 火星、一一九〇- 八五〇年 ラファエル 水星、八五〇- 五〇〇 ザカリエル 木星、五〇〇- 一五〇年 アナエル 金星、一五〇- 二〇〇年 オリフィエル 土星 (第七講・了)人気ブログランキングへ
2024年05月03日
コメント(0)
-
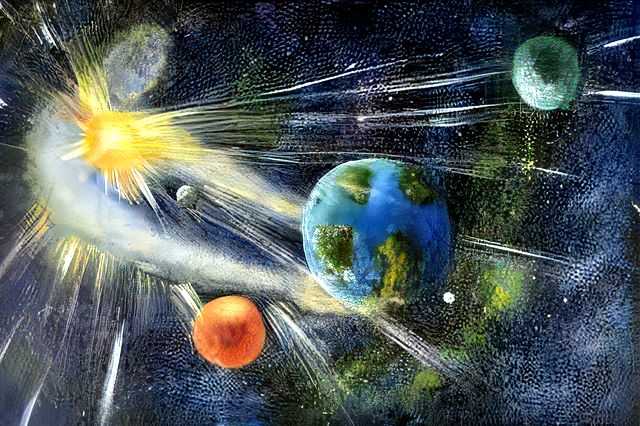
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神的な探求における真実の道と偽りの道」 (GA243) トーケイ、ディヴォン、1924年8月11日-22日 佐々木義之 訳第六講:秘儀参入への認識、覚醒意識と夢の意識 これまで人間の魂の力から発達する様々な意識状態についてお話ししてきました。秘儀参入への認識は、私たちの世界認識がこれらの様々な意識状態に由来するという事実に依存しています。今日は、人間の世界に対する関係がどのようにしてこれらの様々な意識状態によって決定されるかを確かめるということを提案したいと思います。まず最初に、たったひとつの意識レベル、すなわち日々の覚醒意識が日常生活にとっては十分なものであるということを思い出してみましょう。私たちの時代には、通常の覚醒意識に加えて、さらにふたつの意識状態を発達させる可能性があるのですが、さしあたり、それらは知識を獲得するという直接的な目的に対して有効な判断力を提供することはできません。そのひとつは人間がその中で日々の生活における経験を回顧したり、精神的な存在の生活に関するかすかな暗示を受けるところの夢の意識状態です。しかし、通常の夢の生活の中では、これらの経験や暗示はあまりにもゆがめられ、お互いに相関しないグロテスクなイメージや象徴があまりにも多く混じり込んでいるために、それらから何も学ぶことはできないのです。もし、秘儀に参入する知識の助けを借りて、人間が夢を見ているときにはどのような世界にいるのかを知ろうとするならば、その答えはおよそ次に述べるようなものでしょう。人間は、通常の生活において、科学の研究対象であり、感覚によって知覚可能な体すなわち物質体を有している。これは人間の成り立ちにおける第一の構成体であり、誰もがよく理解していると想像していますが、あとで見ていくように、実際には、今日最も理解されていないものです。第二の構成体はエーテル体ですが、これについては私の著書、特に「神智学」の中でより詳細に記述されています。エーテル体もしくは形成力体はデリケートな組織であり、通常の視覚で見ることはできません。それを知覚できるのは、死者を死後数年にわたって追っていくことができる第一の意識状態を発達させた人だけです。エーテル体はその全体的な組織がより独立した物質体に比べて、より密接に宇宙に結びついています。(hell:明るい orange:オレンジ色 guruen:緑色 rot:赤色)人間の成り立ちにおける第三の構成体は、古い表現にこだわるのが最もよいように思われますが、アストラル体と呼ばれます。これは感覚には知覚不能な組織ですが、エーテル体と同じようにして知覚することもできません。もし、私たちが、今日、外的な世界を知覚するために用いている認識力をもって、あるいは、死者と接触する最初の超感覚的な意識による洞察をもってアストラル体を知覚しようと試みるならば、アストラル体が位置する場所に私たちが見い出すのは空虚あるいは真空以外のものではありません。要するに、人間は感覚によって知覚可能な物質体、既に示されたような仕方で行う集中や瞑想を通して発達させることができる力に基づくイマジネーションによって知覚することができるエーテル体を有しています。けれども、これらの力を借りてアストラル体を知覚しようとしても、私たちが出会うのは虚無、何もない空間です。この虚無が内容で満たされるのは、私が記述した空になった意識を達成するとき、すなわち、感覚印象が忘れ去られ、思考や記憶が沈黙させられても、なおその存在を意識するというような仕方で、十全なる覚醒意識もって世界に直面するときだけです。そのとき、私たちは、この虚無の中には私たちの最初の精神的な乗り物、人間のアストラル体があるのだということを知るのです。人間の組織を構成するものにはさらに自我そのものがあります。私たちが自我を知覚するのは空の意識を段々と発達させるときだけです。私たちが夢を見るとき、私たちの肉体とエーテル体は精神世界に滞在するアストラル体と自我から引き離されているのですが、もし、私たちが通常の意識だけを有しているとすれば、アストラル体と自我だけで知覚することはできません。私たちが周囲の世界において外的な印象を知覚することができるのは、肉体が眼や耳を付与されているからです。現在の人間の進化段階においては、アストラル体や自我は、肉体と異なり、通常の生活においては、眼や耳を付与されていないのです。ですから、人間が肉体とエーテル体から出て夢の状態にはいるとき、眼と耳に去られた肉体が物理世界に残されたかのように、まわり中が暗くなり、何も聞こえなくなるのです。けれどもアストラル体や自我はいつまでも器官を持つことなく、つまり魂の眼や耳なしに留まるように意図されていたわけではありません。私が本の中で述べたような精神的な訓練を通して、これらの精神的な器官をアストラル体や自我の中に目覚めさせることができます。したがって、秘儀参入に伴う洞察を通して、精神的な世界をのぞき見ることが可能になるのです。そのとき、人間は、肉体とエーテル体から離れ、ちょうど肉体とエーテル体の中で物理的なものを、そして、ある意味でエーテル的なものを知覚するように、精神的なものを知覚します。この洞察を達成する人が、そのとき、秘儀参入を達成するのです。さて、普通、夢見る人の立場とはどのようなものでしょうか。眠りに落ちる過程を具体的に想像してみて下さい。肉体とエーテル体がベッドの上に取り残される一方、アストラル体と自我は物理的な乗り物から抜け出します。この瞬間、アストラル体はまだ肉体とエーテル体に同調して振動しています。アストラル体は一日中眼や耳のあらゆる内的な活動、あるいは、肉体やエーテル体の機能における意志の働きの中に参加していました。アストラル体と自我はこれらのすべてに与っていたのです。それらが体を去るとき、振動は継続します。その日の経験は、それらの振動の継続により、周囲の精神的な世界と接触することになるのですが、そこから生じるのは外的な精神世界と振動し続けるアストラル体のひどく混乱した相互作用です。人はこのすべてに捉えられ、その混乱を意識します。彼が携えていったもののすべては、彼に衝撃を与えた後、振動しつづけながら夢になるのです。(gruen:緑色 rot:赤色 hell:明るいorange:オレンジ色)夢が現実の理解にほとんど貢献しないことは明らかです。秘儀に参入した人の立場とはどのようなものでしょうか。彼は、肉体とエーテル体から抜け出すとき、持続する振動やその名残を抹消することができます。ですから、彼は肉体とエーテル体から進み出てくるものすべてを抑制するのです。さらに言えば、秘儀に参入する人は、集中、瞑想、そして空になった意識を通して、魂の眼や耳を獲得しています。彼は今や、彼自身の内部で起こっていることではなく、彼の外で、精神的な世界の中で起こっていることを知覚するのです。彼は今や夢の代わりに精神的な世界を知覚し始めます。夢の意識は精神的な知覚に対応していますが混乱した対応物なのです。秘儀参入者がこの内的なアストラル体の器官、超感覚的な視覚と超感覚的な聴覚を初めて獲得するとき、彼は自分が肉体とエーテル体に発するこれらの残響やその名残を抑制するための絶え間ない努力と衝突の中にあるのを見いだします。彼がイマジネーションの世界に入るとき、つまり、精神的なものについての先験的な知覚を獲得するとき、夢が自らを主張するのを防ぐための絶えざる戦いがあります。彼を惑わし、夢のようなファンタジーへと解消させようとするものと精神的な世界の真実を表現するものとの間には絶え間ない相互作用があるのです。秘儀に参入しようとする人は誰でもいつかはこの衝突について熟知するようになります。彼は精神的な世界に意識的に参入しようとする瞬間、再び生じる物理的な世界の残映、精神的な世界についての真の像に侵入してくるこの妨害的なイメージを経験するということに気づくようになるのです。この強烈な内的衝突を克服することができるのは、忍耐と努力によってのみです。さて、もし、夢のイメージが私たちの意識に溢れるのにあまりにも安易に満足するならば、私たちは、精神的な世界の現実に参入する代わりに、容易に私たち自身を幻想の世界の中で夢を見る人にしてしまうでしょう。実際、秘儀に参入することを望む人は知的であると同時に極端に強い自制心を持っていなければなりません。そのため彼には何が求められるかを想像してみて下さい。もし、私たちが精神的な探求について、つまり、精神的な世界に到達するための方法について語るべきであるならば、これらのことがらに注意しなければなりません。もし、私たちが精神的な世界についての理解に向けて第一歩を踏み出すことを望むならば、その使命に対する真の熱情が示されなければならないのです。内的な昏睡、内的な無関心や怠惰はその達成のための途上にある障害物です。私たちの内的な生活は活動的で、生き生きとした反応を示さなければなりません。しかし、白日夢の中で自らを失い、幻想の糸を紡ぎ出すという危険があるのです。私たちは、一方では、想像力の翼に乗って天空を駆けめぐることができなければならないのですが、他方では、慎重さと真摯な判断力によってこの内的な活動性と応答性を沈静化させることができなければなりません。秘儀参入者はこれら両方の性質を有していなければならないのです。単に自分の感傷にふけることと同様、知性の支配に屈したり、すべてを理屈でかたづけるのも望ましくありません。私たちはこれら両極端の間で釣り合いを取ることができなければなりません。私たちは夢を夢見ることができると同時に、地上に足をつけていることができなければならないのです。私たちが精神世界に参入するときには、私たちは創造的なイマジネーションのダイナミックな世界に参加しながら、同時に自分自身をしっかりとコントロールするべきです。私たちは豊かなイマジネーションに恵まれた詩人としての受容性を有しながら、その誘惑に負けないようにするのです。精神的な知識を求めるときには、創造的な衝動によっていつでも点火されると同時に、ファンタジーの世界へと流されないように、実際的な常識によって自分をコントロールすることができなければなりません。そうすれば、私たちは、幻想の餌食になることなく、精神的な現実を経験することになるでしょう。この内的な魂のあり方こそが精神的な探求においては決定的に重要なのです。私たちが夢の意識についてよく考え、それが精神的な世界から混乱したイメージを魔法のように出現させるものであるということに気づくとき、私たちは同時に、精神的な知識を獲得するためには、夢のような状態に留まろうとする私たちの個性のすべての力が魂の活力として加わらなければならないということにも気づくのです。私たちはそのとき初めて、精神的な世界に参入するということが何を意味するのかを知るのです。私は、夢が精神的なものを魔法のように出現させる、と言いました。このことは、夢の意識が体的な生活から導かれる像をも魔法のように出現させる、という叙述に矛盾するように思われるかも知れません。けれども体は単に物理的なものなのではなく、精神的なものに完全に浸透されているのです。おいしそうなごちそうが目の前に出されて、それを食べようとするけれども、ポケットにはそれに見合うお金が少しもないというような夢を誰かが見るときには、彼の消化器官の真に精神的、アストラル的な内容が食事という象徴化されたものにおいて示されているのです。精神は体的なものの中にその座を有しているという事実にも関わらず、夢の中にはいつでも精神的な要素が存在しています。夢はいつでも精神的な要素を含んでいるのですが、それは体に関係した精神的な要素である、ということが非常に多いのです。この事実に気づくことが必要です。蛇の夢を見るとき、そのとぐろは消化器官や頭部の血管を象徴しているということが理解されなければなりません。私たちはこれらの秘密へと貫き至らなければならないのです。それは、魂の中で発達させられるこれらの微妙で親密な要素についての理解に至ることができるのは、私たちが秘儀参入の科学を通して精神的な探求に取りかかり、これらのことがらに綿密な注意を払うときだけだからです。人間が日常生活の中で通過する第三の段階は夢のない眠りです。その状態を思い出してみましょう。肉体とエーテル体がベッドに横たわり、アストラル体と自我組織はこれらの外にあります。肉体とエーテル体からの残響やその名残は止みました。人間が精神世界に住むことができるのはアストラル体と自我の中においてのみですが、必要な器官がないために、何も知覚することができません。彼は闇に囲まれて眠っています。夢のない眠りとは、自我とアストラル体の中に生きながら、私たちを取り囲む広大で壮大な世界を知覚できない、ということを意味しています。目の見えない人の場合を取り上げてみましょう。彼は色や形についての知覚を有していません。これらに関する限り彼は眠っているのです。さて、知覚するための器官を持つことなくアストラル体と自我の中に住んでいる人を思い描いてみましょう。精神との関係では、彼は眠っています。夢のない眠りの状態にある人間とはそのようなものなのです。集中や瞑想の目的はアストラル体と自我組織の中に精神的な眼や耳を発達させることです。そのとき、彼は彼を取り巻く精神の豊かさを目の当たりにし始めるのです。彼は、通常の意識状態においては眠りの中で失われ、瞑想や集中を通してその眠りから目覚めさせるべきものによって精神的に知覚します。それ以外の場合には配置されていない要素が組み込まれなければなりません。そのとき彼は精神的な世界をのぞき込み、通常は彼の目や耳を通して物理的な世界の生活に与るように精神的な世界の生活に与るのです。これは秘儀に参入する真の認識です。誰かを外的な方法によって精神的な知覚に向けて準備させることはできません。すなわち、彼はまず、通常は非常に混乱した彼の内的な生活を効果的に組織化することを学ばなければならないのです。さて、人類の歴史においては、誰かを選んで秘儀参入に向けて準備させるということがいつの時代でも行われてきました。しかし、極端な唯物主義の時代には、つまり15世紀以来今日に至るまで、これはある程度中断されています。この間、秘儀に参入するということの真の意義は忘れられました。人々は認識への欲求を秘儀への参入なしに満足させることを望み、そのため、物理的な世界だけが適正な探求の場であると徐々に信じるようになったのです。しかし、実際のところ、物理的な世界とは何なのでしょうか。私たちがその物理的な側面だけを考慮したとしても、それと折り合いをつけることはできないでしょう。物理的な世界はそれを満たす精神を理解できたときにはじめて理解することができるのです。人類はこの認識を再び取り戻さなければなりません。私たちは今、岐路に立っています。世界は分裂し、ますます混乱の様相を呈しています。けれども、私たちは、この混乱、逆巻く闇、すべてを破壊しようとする暗い熱情のただ中で、人間の中に新しい精神性を目覚めさせようとして苦闘する精神的な力の存在に気づいている先験的な認識を有する人がいるということを知っています。そして、人智学に向けて準備するということは、私たちの唯物的な時代の大騒ぎのただ中でもまだ聞くことができるこの精神の声に耳を傾けるということなのです。人間は、いつの時代にも、精神的な世界を知覚するというような仕方でその人間としての組織を発達させようと努力してきたと私は言いました。時代によって条件は変化しますが、古代カルディア時代、あるいはブルネットー・ラティーニの時代を振り返ると、人間は今日に比べて肉体やエーテル体にもっとゆるやかに結びつけられていたということが分かります。人間がそれらにしっかりと固定されるというのは当然の成り行きです。つまり、それは私たちの今日の教育からいって避けられないことなのです。いずれにしても、多くの場合、歯が生え替わる前に読み書きを学ぶように強いられるというのに、どうして精神的な存在たちとの交流を期待することができるというのでしょうか。天使や精神的な存在たちは読むことも書くこともできないのです。読み書きは人間進化の過程で、物理的な条件に対応して発達してきました。そして、もし、私たちの存在全体が純粋に科学的な探求へと方向づけられているならば、私たちが肉体やエーテル体から退くことは明らかに困難であるはずです。私たちの時代は、私たちが肉体とエーテル体から離れているときには、いかなる精神的な経験をも持つ可能性がない、というような方法で、私たちの文化生活全体を秩序づけることに一定の満足を見いだしているのです。私は私たちの時代の文化を罵倒したり非難したりするつもりはありません。それはその時代の不可避的な表現なのです。後で、その意味について議論するつもりですが、さしあたりは、ものごととはそのようなものであるとして受け入れられなければなりません。太古の時代にあっては、アストラル体と自我は、目覚めの状態においてさえ、今日に比べて肉体とエーテル体にもっとゆるく結びついていました。秘儀に参入した人たちもまた、彼らにとって自然であった体のゆるい結びつきに頼っていました。実際、はるかな過去においては、ほとんどすべての人が秘儀に参入することができたのですが、人間の地位を越えて上昇することが誰にでも可能であったのははるかな過去の時代、古代インドや古いペルシャの時代だけだったのです。そして、後の時代においては、秘儀に参入するための候補者の選定は、肉体とエーテル体から退くことにほとんど困難を感じない人たち、そのアストラル体と自我が比較的高度の独立性に恵まれていた人たちの間に限られました。秘儀に参入するためには一定の条件があらかじめ必要とされました。このことは、彼の能力に見合った最高の段階の秘儀に参入することを妨げるものでは全くありませんが、ある地点を越えて成功に導かれるかどうかは希望者がアストラル体と自我の中で容易に独立性を達成するか、あるいは単に苦労して達成するかにかかっていました。そして、このことは彼の成り立ちと自然の配列によって決定されました。世界の中へと生まれて来る人間にとって、誕生から死までの世界に依存することはある程度避けられないことなのです。ここで、今日の人間も、秘儀参入に乗り出すとき、同様の限界に左右されるのか、という疑問が生じますが、ある程度そういうことがあります。この講義では、精神的な世界へと導く真実の道と偽りの道について十分かつ明確な説明を加えるつもりですから、今日の秘儀参入への途上に横たわる困難について指摘しておこうと思います。古代の人間は、秘儀参入者になるにあたって、その自然に備わった資質により依存していました。現代人もまた、秘儀参入の入り口にまで連れていかれることはできます。実際、適切な魂の訓練を通して、精神的な視覚を発達させ、精神的な世界を知覚することができるように彼のアストラル体と自我組織を形成するができるのです。しかし、この視覚を完全なものにし、完成させるためには、今日でもなお、何か別のもの、極端に微妙でデリケートな何かに依存しているのです。私にできるのは一歩一歩先に進むことだけですから、今日これから私がお話しすることについて、次の講義の内容を把握する前に、最終的な結論を出さないよう皆さんにお願いしなければなりません。今日の秘儀参入においては、人はある程度年齢に依存しているのです。人生に期待がもてる37才で秘儀参入を始める場合を取り上げてみましょう。彼は瞑想や集中、その他の修行を、誰かの指導の下、あるいは何かの教本に基づいて、自分で実行し始めます。瞑想やあるいは何らかのテーマを繰り返し実行することで、彼はまず第一に地上における彼の生活を振り返ることができる能力を獲得します。彼の地上生がひとつのまとまった織物の形で彼の内的な目の前に現れます。ちょうど物体が三次元空間の中に置かれているように、つまり、椅子の前二列とそこに座っている人たち、向こう側には机、その後ろの壁というように私たちはすべてを遠近法によって、同時性の中で見るのです。このように、私たちは秘儀参入のある段階において、「時間」をのぞき見ることになります。時間の経過が空間的な印象を与えるのです。さて、私たちは37才のときに自分を振り返ります。私たちは36才のとき、35才のとき、そして、誕生のときに至るまで何らかの経験をしてきました。私たちは私たちの前にひとつの織物を時代を遡りながら見ます。今、秘儀参入のある段階において、ある人がその人生を逆向きに振り返ると仮定してみましょう。37才では、彼は誕生からおよそ7年目の歯の生え替わりの時期まで、そして、7才から14才、つまり思春期までを振り返ることができるでしょう。そして次に、14才から21才、そして37才までの残りの人生を振り返ることができます。彼は彼の人生をパノラマのように、いわば時空間的な見通しにおいて探求することができます。彼が空になった目覚めの意識から生まれる意識をこの知覚に加えることができるとき、ある種の知覚力が彼を貫いて閃くのです。彼は洞察を獲得するのですが、その洞察は非常に広範な形態を取ります。誕生から7才までの経験、14才から21才、そしてその後の時代の経験は彼の中に異なる反応を喚起します。それぞれの時代が独特の反応を示し、それ自体が独自の視覚力を有しているのです。さて、63、4才の人について考えてみましょう。彼は37才より後の時代を振り返ることができます。21才から42才までは比較的均一のように見えます。それに続く時代はもっと違っています。42才から49才まで、49才から56才まで、そして56才から63才までの時代で彼の知覚には重要な違いがあるのです。これらすべての時代は彼の成り立ちにおける枢要な部分になっています。それらは彼の地上における人生の精神的な側面を表しているのです。もし、彼がこの内的な視覚を発達させるとすれば、彼は彼の様々の洞察がある特定の年代における彼の存在レベルに依存しているということを理解するでしょう。その最初の7年間は7才から14才までの年代とは異なる洞察を彼の中に目覚めさせます。14才から21才までの思春期、21才から42才までの年代はさらなる相違を、そして、もっと後の時代に属するいくらか異なる洞察力がそれに続きます。私たちの人生の経験についての記憶像を有する能力を獲得するとともに、その記憶像を消し去った空の意識から導かれる洞察を私たちが達成したと仮定してみましょう。今やインスピレーションの力が働き始め、その結果、私たちは、もはや物理的な目を通してではなく、精神の眼である新しい視覚器官を通して私たちの人生の期間を探求します。私たちは、もはや様々なできごとがあった人生の期間の像を魔法のように出現させるのではなく、インスピレーションを通して、精神的な眼や耳でそれらを知覚する地点へと達したのです。あるときは7才から14才までの人生の期間を超感覚的に眺め、別のときは49才から56才までの期間を、ちょうど外的な世界で眼や耳を使って聞いたり知覚したりしたように、超感覚的に聞くのです。インスピレーションの世界においては、7才から14才までの期間、そして42才から49才までの期間から導かれる力が使われます。この世界においては、様々な人生の期間が異なる認識器官になるのです。このように、私たちの視覚の範囲はある程度私たちの年齢に依存しています。37才では、秘儀参入の経験を一次情報として語ることが完全に可能なのですが、63才になれば、私たちはより深い知識をもって語ることになります。何故なら、その年代では別の器官を発達させているからです。人生の期間が器官を創造するのです。さて、ブルネットー・ラティーニやアラヌス・アプ・インスリスのような人物を本に載っているような情報からではなく、超感覚的な知識から記述することを提案すると仮定してみましょう。(これらの例は、ここ数日にわたって既にお話ししていますから、皆さんよくご存じのはずですね。)もし、私たちが37才になったとき、彼らのことを描写しようとするならば、目覚めた眠りの意識の中で彼らと精神的に関係しているということを発見するでしょう。隠喩的に言えば、私たちは私たちの仲間の人間と語るようにして、彼らと語り合うことができるのです。そして、不思議なことに、精神的なことがらについて彼らと語ることができるのは、現在の叡智と精神性のレベルからだけなのです。そのとき、私たちはいかに多くのことを彼らから学ぶことができるかを知ります。私たちは彼らに耳を傾け、彼らが伝えようとすることを信頼して受け入れなければなりません。さて、皆さんは、精神的な世界において、ブルネットー・ラティーニのような人物と共にあるということが軽々しいことではないということにお気づきでしょう。けれども、もし、私たちに必要な準備ができているとすれば、私たちは自分が夢に幻惑されているのか、あるいは精神的な現実の中にいるのかを決定することができます。そのため、私たちが受け取る伝達を評価することは可能なのです。では、私たちが37才のときに精神的な世界においてブルネットー・ラティーニと語り合うと想像してみましょう。もちろん、このことは文字通り受け取られるべきではありません。彼は私たちに多くのことを語るでしょう。そして、多分、私たちはもっと正確で詳細な情報が必要だと思うかも知れません。それに対して、彼は、「その場合、我々は現在の20世紀から19、18世紀、そして私がダンテの師として生きた世紀にまで遡って足跡を辿らなければならない。もし、あなたがこの道を通って私について来ることを望むならば、あなたがもう少し歳を取るまで、つまり、あなたがあと何年かの年月を後にするまで待たなければならない。そのとき、私はすべてを話し、あなたの知への渇きを満たすことができるだろう。あなたは高次の秘儀参入者になることができるが、現実には、精神的な意欲だけでは過去への道を通って私についてくることはできないのだ。」と言うでしょう。と申しますのも、このことが可能であるためには、皆さんはもっと歳を取っていなければならないからです。もし、皆さんが問題の人物とともに精神世界へと障害なく帰還することを確実なものにしたいならば、皆さんは少なくとも42才を通過して60才に達していなければならないのです。これらのことがらは人間存在のより深い側面とそれらが若年期や老年期において果たす重要な役割を皆さんに示すことになります。何故ある人は若死にし、別の人は熟年まで生きるのかというようなことを私たちが理解することができるのは、これらのことがらに注意を払うときだけなのです。このことについては後でもう少しお話しいたします。人間が発達していくとき、いかに彼が精神的な世界についての知覚をますます深め、広げていくかを見てきました。つまり、ブルネットー・ラティーニのように肉体を脱いだ魂として精神世界にある存在との関係が、彼の進化状態とともに、すなわち精神的な知覚のために使用される器官が若年期に発達させられたものであるか、あるいは老年期に発達させられたものであるかによっていかに変化するかが示されました。世界の俯瞰的な探求と、そのようにして人間の魂の前で展開するその進化はその他の領域に拡張されることができます。問題は、人間の意識、人間の洞察をどのようにして拡張し、それに別の方向性を与えるかということです。今日はそのようなひとつの方向性を示し、そのさらなる詳細については次の講義で述べることにします。私たちは、地上の生活における通常の意識の中で、誕生から死までの間の地球の環境についてだけ知っています。もし、私たちの混沌とした夢の生活に終わりがあり、私たちが、通常の意識ではなく、深く夢のない眠りの状態において知覚を有することができていたとすれば、私たちはもはや私たちの周囲に、純粋に地球のものであるところの環境を経験してはいなかったでしょう。私たちは、実際、通常とは異なる知覚と意識の状態を付与されていたことでしょう。さて、私たちの日常意識が私たちの身近な環境と関連していると考えてみましょう。私たちは地球の内部をのぞき見ることはできませんから、私たちを直接とりまく環境が通常の意識の領域です。宇宙に存在するその他のあらゆるもの、太陽や月、そしてその他のすべての星はこの領域へと輝き込みます。太陽と月は、他の天体と比較して、宇宙におけるそれらの存在をより明確に示すものを送り込んでいます。もし、物理学者たちが彼らのやり方で。と申しますのも、彼らは私たちのアプローチを考慮しようとしないからですが、月と太陽の領域において卓越している状態を経験できるとしたら、驚愕することでしょう。と申しますのも、天文学や天体物理の教科書に書いてあることは全く的外れだからです。それらは非常に漠とした示唆を与えるだけです。私たちが、通常の生活において、誰かと知り合いになることを望み、後で話す機会を得たならば、私たちは通常、この人物については漠とした印象しかない、彼はほとんど視界から消えるほど遠くに退いているに違いないとは言いません。そのような場合には、私は彼についてもっとはっきりとした印象を持ち、彼の様子を記述するはずです。もちろん、物理学者に選択の余地はありません。当然の結果として、彼らは遠く離れたところから星々を記述することができるだけです。けれども、変化し、拡大した意識は私たちを星の世界へと引き上げます。そして、私たちがこのことから最初に学ぶのは、通常の生活において語るのとは全く異なる方法でこれらの星の世界について語るということです。私たちは、通常の意識の中で、私たち自身がこの地上に立っているのを見ます。そして、夜空の月は私たちの上にかかっています。別様に見るためには、私たちは異なる種類の意識の中に入っていかなければなりません。そして、それにはときとしてかなりの時間がかかります。私たちがこの意識を達成し、私たちの経験、すなわち誕生から7才の歯牙交代期までに通過したあらゆることを、死者と連なる意識、つまり、インスピレーションを達成し、それによって内的な視覚力となった意識をもって知覚することができるとき、私たちは私たちの周囲に完全に異なる世界を見ます。通常の世界はぼんやりとしてはっきりしないものになります。この別の世界とは月の領域です。私たちがこの新しい意識を達成するとき、私たちはもはや月を独立した実体としては見ません。私たちは、実際、月の領域に住んでいるのです。月の軌道は月の領域の最も遠い境界を通っています。私たちは私たち自身が月の領域の内部にいることを意識します。さて、もし、8才の子供が秘儀に参入することができ、その人生の最初の7年を振り返ることができたとしたら、その子はこのような仕方で月の領域に住むことができるでしょう。実際、子供はまだ後の時代の影響によってだめになっていないので、月の領域に入っていくことにほとんど困難を感じないでしょう。このことは理論的には可能ですが、もちろん、8才の子供を秘儀に参入させることはできません。(Sonne 太陽bis42 42まで Mars 火星 Mond 月 weiss 白色 Merkur 水星 rot 赤色 gelb 黄色 Jupiter 木星bis 56 56まで Mars 火星bis 49 49まで0-7 7-14 Saturn 土星bis 63 63まで Erde 地球 guruen 緑色 Venus 金星bis 21 21まで)私たちが、最初の人生期である誕生から7才までの期間から導かれる力を精神的な視覚のために用いるとき、私たちは通常の意識によって知覚される領域とは極端に異なる月の領域に入っていくことができます。ひとつの類推が論点を説明するのに役立つでしょう。今日の胎児学では、生物学者たちは胎児の発達をその最初期の段階から研究しています。胎児の発達のある段階で、外縁部のある一点において細胞膜の厚みが増す、ということが起こります。次に包接が起こって一種の核が形成されます。ところが、このことは顕微鏡ではっきりと見ることができる一方、これは胚珠であり、胎児に過ぎないのだ、と言うことはできません。何故なら、他の部分もまた枢要な部分だからです。同じことが月やその他の星にも当てはまります。私たちが月として見ているものは単なる一種の核であり、その全領域が月に属しているのです。地球は月の領域の中にあります。もし、胚珠が回転すれば、この核もまた回転するでしょう。月の軌道は月領域の境界線を辿っているのです。ですから、これらのことがらについてまだなにがしかのことを知っていた古代人たちは、月についてではなく、月領域について語りました。私たちが今日見るような月は、彼らにとっては最も遠い境界にある一地点に過ぎませんでした。この点は毎日その位置を変え、28日間かけて私たちのために月領域の境界線を辿ります。誕生から7才までの私たちの内的な経験がインスピレーション的な視覚になるとき、私たちは、私たちの地球についての知覚を徐々に失うとともに、月領域に入っていくための力を獲得するのです。人生の第二期、歯牙交代期から思春期までの経験がインスピレーション的な視覚に変化させられるとき、私たちは第二の領域である水星(訳注:金星のこと)領域を経験します。私たちは地球とともに水星領域に生きるのです。水星領域での経験を見ることができるのは、7才から14才までの地上における人生の経験を意識的で明確な知覚力をもって振り返るとき、私たちが私たちのために創造するところの視覚器官によってだけです。思春期から21才までの期間から導かれるインスピレーション的な視覚力をもって、私たちは金星(訳注:水星のこと)領域を経験します。古代人たちは私たちが想像するほど無知ではありませんでした。彼らは彼らの夢のような認識力によって、これらのことがらについて多くのことを知っていました。そして、彼らは、私たちが思春期の後に経験する惑星システムに、この時代における性的な目覚めに関連した名前を付与したのです。そして、21才から42才までの期間における私たちの経験を意識的に振り返るとき、私たちは私たちが太陽領域にいることを知ります。それぞれの人生期が内的な生活のための器官に変化させられるとき、それらは私たちに宇宙的な意識を一歩一歩拡大させる力を付与するのです。私たちが42才になるまでは太陽領域について何一つ知ることができない、というのは真実ではありません。私たちは水星存在たちからそれについて学ぶことができます。何故なら、彼らはそれについて十分に知っているからです。けれども、その場合、私たちの経験は、超感覚的な教えを通して、間接的に私たちのところにやって来ます。自分自身の意識で太陽領域を直接経験するためには、つまり、その中に入っていくことができるためには、私たちは21才から42才までの期間を生きただけではなく、42才を越えていなければなりません。私たちは過去を振り返ることができなければならないのです。と申しますのも、秘儀が開示されるのは回顧的な探求の中でのみだからです。そしてさらに、私たちが49才までの人生を振り返ることができるとき、火星の秘儀が開示されます。もし、私たちが56才までの人生を振り返ることができるとすれば、木星の秘儀が明かされることになります。そして、深いベールに包まれているとはいえ、驚くべき輝きを発する土星の秘儀-その秘儀には、次の講義で見ていくように、宇宙の深い秘密が隠されています-が開示されるのは、私たちが56才から63才までに起こったできごとを振り返るときです。ですから、皆さんお気づきのように、人間とは実際、小宇宙なのです。彼は通常の意識では決して知覚されることのないこれらのことがらに関連しています。もし、月の力が誕生から7才までの間、彼の中で活動していなかったとすれば、彼は彼の人生を形づくったり、秩序づけたりすることができなかったでしょう。彼は後になってその影響を知覚します。もし、水星の秘儀が彼の中で活動していなかったとすれば、彼の7才から14才までの経験を再創造することはできなかったでしょう。同様に、もし、彼が金星領域に内的に関連づけられていなかったとすれば、14才から21才までの期間-もし、彼がカルマによってそれを受け取るように予め配置されていたとすれば、強力な創造力が彼に注ぎ込まれる期間ですが-における彼の経験を再創造することもできなかったでしょう。そして、もし、彼が太陽領域に統合されていなかったとすれば、彼は21才から42才までの時代、つまり、私たちが若年から熟年へと通過していく年代についての成熟した理解や経験を発達させることができなかったでしょう。昔のシステムは非常に異なっていました。職人は21才になるまで徒弟として働きました。次に「旅する男」になり、最終的に「親方」になりました。こうして、21才から42才までの年代の内的な発達はすべて太陽領域に関係づけられていたのです。そして、56才から63才までの彼の衰退期における経験のすべては土星領域の影響に帰属させることができます。私たちは地球とともに7つの互いに貫き合う領域の中に存在しており、人生の経過にしたがって、それらの中に成長するとともに、それらに関連づけられるのです。誕生から死までの私たちの人生は、私たちを形づくる星の領域からの影響によって、当初のパターンからの変化を被ります。私たちが土星の領域に達するとき、私たちは惑星領域の存在たちがその慈悲によって私たちのために成し遂げるもののすべてを通過したことになります。そのとき、私たちは、秘教的な意味において、秘儀に参入した立場から惑星生活を振り返るところの自由で独立した宇宙存在、つまり、ある意味で、もはや以前の人生期からの強制に左右されない存在として船出するのです。これらのことがらについては、次の講義でさらにお話しする予定です。(第六講・了)参考画:人生と霊的太陽人気ブログランキングへ
2024年05月02日
コメント(0)
-

ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタイナー
ルドルフ・シュタイナー「精神的な探求における真実の道と偽りの道」 (GA243) トーケイ、ディヴォン、1924年8月11日-22日 佐々木義之 訳第五講:金属質の本性を通しての魂の内的な活性化 私は、いかに人間が日常生活の意識とは異なる意識状態を発達させることができるかということ、そして、その知識と活動の分野において、人間は今日の私たちのような意識を有していなかったということに関して、進化の歴史がいかに豊富な証拠を提供するかということを示そうと試みてきました。そして、十世紀、十一世紀、そして十二世紀に生きた学者たちの意識と、当時、例えばシャルトルの学院において知識が涵養された方法との間の関係に注意を促す、ということを次に試みました。それとの関係で、いかに私たちの現在の意識レベルとは全く関連しない知覚形態が生じてきたかということも指摘しました。ダンテの教師、ブルネットー・ラティーニ(イタリアの哲学者,文学者。ダンテの師とされる。)の場合がそうです。昨日はもっと以前の時代、例えばエフェソスの秘儀の時代における人間の宇宙に対する関係を呼び起こすということを試みました。それによって、私たちは、当時、今日の通常の科学的な意識状態にある程度関連している。とはいえ、いかに全体として異なった意識状態が卓越的であったかを知りました。さて、少し脇道にそれた後、今日は私たちの探求を続けたいと思います。私は既に金属性が、つまり鉱物元素の基本的な物質性がいかに人間とその意識状態に関連しているかということを示しました。すなわち、金属銅に対する人間の関係を示した後、いわば死後間もない死者の経験に参加することを可能にするところの意識状態について記述しました。私たちは、ブルネットー・ラティーニが発熱の後、半ば病理的な状態の中で経験したのはこのような知覚形態であったということに気づかなければなりません。彼が記述することのすべて、女神ナチュラ(誰を指すのかは疑問符)のインスピレーションを通して彼のところにやってきたもののすべては、あの死後間もない死者の経験に与ることができる意識状態、それは私たちの日常意識に密接に関連しているその中で、本当に達成することができるのです。※ブルネットー・ラティーニが発熱の後、半ば病理的な状態の中で経験した知覚形態は、彼が記述するすべてのものが女神ナチュラのインスピレーションを通じて彼のもとにやってきたというものでした。彼の文学的な作品や詩は、この神秘的なインスピレーションから生まれたものであり、彼の創造性と芸術的な才能を示しています。このような体験は、芸術家や作家にとっては非常に興味深いものであり、創造的なプロセスにおいて神秘的な要素がどのように影響を与えるかを考えさせられます。ナチュラのインスピレーションは、人々の心を打ち、美しい作品を生み出す源泉となることがあります。他方、ルネットー・ラティーニ(Rentto Latini)は、架空の人物である可能性が高いため、彼の経験についての詳細は不明です。ただし、彼の名前は文学的な作品や詩の中で使用されていることがあります。(ルネットー・ラティーニがブルネットー・ラティーニの誤写でないとしたらの話ですが。)※ブルネットー・ラティーニ:ダンテがブルネットを本当に恩師だと思っていたならば、地獄には落とさないで、天国とまではいかないにしても、煉獄のどこかに置いていたのではないでしょうか。参考画:インフェルノ、カント15:ブルネットラティーニがダンテを告発、ダンテアリギエーリ作「The Divine Comedy」(1885年) このような神秘的な体験は、文学や芸術の世界において、創造性と想像力を刺激する要素として重要です。私は、それはより現実性の大きい状態であったと言いました。私たちはより力強く、より光り輝く世界に、つまり、現象世界に比べて、あらゆるものにさらなる完成をもたらす世界に住んでいるのです。私たちはこのことによってのみ、死の門を通って間もない魂の経験に与る可能性を有しているのです。それと同時に、この世界のある奇妙な特徴が明らかになります。私たちが、今お話しした意識状態をもって、その世界に滞在するとき、日常生活における通常の経験を観察することはもはや不可能になります。この世に生まれる直前の私たちの生活、生まれる前、まだ精神的な世界にいたころの私たちの経験だけを見るのです。ですから、私たちは、この意識状態の中では、私たちが通常住んでいる世界から引き離されるということに気づかなければなりません。それがどういうことなのかを示しましょう。ある人がある時点で生まれたとします。もし、彼が40才のとき、銅の意識状態を達成したとすれば、このことは既に一昨日の講義で説明しましたが、彼の知覚はもはや現在の経験にも、彼が30才あるいは35才の時の知覚にも関連せず、ただ生まれる直前の経験を振り返ることができるだけなのです。彼は、これを彼自身についても、他の人についてもできるのですが、日常的な存在の世界を理解できません。それができるのは人間についてだけです。動物はその見慣れた物理的な姿では現れません。私たちは直上の世界をのぞき、集合魂と呼ばれるものを知覚します。いわば動物の種のオーラを見るのです。そして、現在の唯物的な時代においては完全に無視されている。とはいえ、人類にとって最高に重要な何かがその世界に見いだされることになります。そして、もし、私たちが、ベルナルドゥス・シルベストリ、アラヌス・アプ・インスリスやその他のシャルトルの学院の教師たちによってあれほど生き生きと描写された存在、すなわち女神ナチュラとして絶えず存在していた存在に触れるとすれば、たとえ最高の学院であらゆる学問についてのすべての現代的な知識を学んでいたとしても、私たちには自分がはかり知れないほど無知であると感じられることでしょう。現在の知識は誕生から死までの世界にだけ適合している、死者を死の門の向こう側まで追って行ける意識をもって精神的な世界に参入するとき、それはもはや有効ではないと感じられるのです。私たちが化学を探求するとき、その知識の総計は誕生と死の間の世界にとってだけ有効です。いわゆる化学は私たちが死者と共有する世界においては重要ではないのです。私たちが現象世界において獲得するすべての知識は死と新生の間のこの中間的な状態においては価値がなく、単に記憶として残るだけです。私たちは、私たちが今や居住するこの中間的な領域に関する直接的な意識を有している、私たちがあれほど多くのことを学んだあの日常的な世界は私たちの意識からかすんでしまったと感じます。この別の世界が今や私たちの目の前に広がっているのです。私たちの目の前にぼんやりと山が現れてくると想像してみましょう。それはしっかりとした印象を与えます。遠くから見ると、それは太陽の光を反射しており、その輪郭と岩の様子が分かります。少しずつ近づき、そこに足を踏み入れると、その堅さが感じられます。私たちはしっかりとした地面の上に立っている。その現実性には何の疑いもないと感じられます。さて、中間的な世界においては、しっかりとしている、輝いているとして記述されたあらゆるものはいかなる意義も持たなくなります。つまり、何かが山から流れ出し、どこまでも大きくなり、そして別の種類の現実性を印象づけるのです。私たちは、通常の状態の生活において、山の上に雲が懸かっているのを見ます。それは水蒸気の凝縮によってもたらされたのだ、ということに何の疑いも抱きません。この現象もまたあらゆる現実性を失います。何か別のものが雲から現れるのです。それは山と雲が徐々に視界から消えるのにしたがって現れます。この組み合わせの中から、単に漠としているだけではなく、漠としていると同時に形態を与えられた新しい現実が生まれるのです。そして、それはこの中間的な世界におけるあらゆるものに当てはまります。多くの聴衆の前に立つと想像してみましょう。私たちが精神的な世界に入る瞬間、そのすべてのはっきりと規定された輪郭はかき消されます。私たちはそのかわり、超感覚的なイメージの形で投影された聴衆の魂と精神を知覚します。そして、周囲の神秘的で精神的なオーラが次第に私たちを包み込み、新しい世界、死者が死後に居住する世界が生じるのです。私たちは今、別の何かに気づきます。つまり、もし、私たちが今や参入したこの中間的な世界が存在していなかったとすれば、それがいたるところに存在していなかったとすれば、私たちは私たちの目や耳を、つまり感覚器官を有してはいなかったであろうということにです。化学者や物理学者たちが記述する世界は私たちに感覚器官を提供することはできません。ですから、私たちは見ることも聞くこともできなかったでしょう。私たちの中に感覚器官が組み込まれることは不可能だったのです。そして、ブルネットー・ラティーニがスペインから生まれ故郷のフィレンツェ近郊に戻り、彼にこの中間的な世界への扉を開いたところのあの若干の発熱に苦しんだとき、彼が発見した驚くべきこととはこのことだったのです。彼は彼の感覚器官がこの別の世界のたまものであることに、つまり、もし、この中間的な世界が感覚によって経験される世界に浸透していなかったとすれば、彼の感覚は全く発達していなかったであろうということに気づいたのです。私たちの人間としての地位は、私たちが私たちの感覚器官をこの第二の世界、この中間的な世界との結びつきに負っているという事実によって決定されているのです。この第二の世界はいつの時代にも元素の世界と呼ばれてきました。酸素、水素、窒素等々の言葉はそこでは意味がありません。これらの言葉は誕生と死の間の世界にだけ適用可能なのです。第二の世界においては、土、水、空気、火、光等々の元素について語ることだけが意味を持っています。と申しますのも、水素、酸素等の特質は感覚には全く無関係だからです。化学者がスミレやアギ(セリの一種)の香りについて見いだすこと、つまり、一方はよい香りで、他方はきわめて不快であるというようなこと、そして、その化学的な組成にしたがって名づけられるあらゆるもの、それらの何ひとつとして意味がありません。第二の世界においては、香りや臭いとして現象するすべてのものは精神化されています。第二の世界の立場から記述するならばそれらは空気なのですが、希薄化された空気、精神によって完全に浸透された空気なのです。私たちの感覚は元素の世界に根ざしていますから、そこではまだ、土、水、火、そして空気について語ることに意味があるのです。私たちは今や、これまで誤解していたものを正しい理解へと発展させることができます。自分を論理的、客観的であるとして、以前の時代の素朴な観点は捨て去ったと主張する現代の哲学者はこれにどのように反応するのでしょうか?。彼は、このような昔の概念は原始的であり、当時、人々は粗雑な元素である土、水、火、そして空気についてだけ語ったが、今日では四つや五つの元素ではなく、七〇から八〇の元素が知られていると主張するのです。さて、もし、ギリシャ時代の典型的な観点を有する人が今日の時代に生まれ、自分の立場についてたずねられたとしたら、次のように答えるでしょう。あなた方はもちろんまだあなた方のやり方で酸素や水素のような元素について語っていますが、私たちが四つの元素によって理解していたことを忘れています。あなた方はその構成に気づいていません。あなた方はそれらについてもはや何も知らないのです。あなた方の72や75の元素のすべてが存在していたとしても、感覚器官は決して生まれてこなかったでしょう。何故なら、それは四つの元素から生まれてくるものだからです。人間について、つまり感覚器官を備えた人間の体がどのように組み立てられているかについてもっとよく知っているのは私たちですと。ブルネットー・ラティーニのように秘儀参入に向けて第一歩を踏み出した古い時代の人間が受け取った印象について推し量ることができるのは、これらの印象が魂や精神の生活にとってどのような意義を有していたかを、つまりこれらの印象によって魂が受ける活発な刺激とその予期しない衝撃的な影響を心に留めるときだけです。もし、これまで感覚印象の現実性を信じてきた人が、その現実は彼の感覚器官を創造することさえできなかったであろうということを、その現実の背後には私がここでお話ししてきたことのすべてが存在しているに違いないということを発見するならば、その影響はとにかく大変なものでしょう。私たちが普通に抱いているような自然についての古い不毛な概念をいつまでも長引かせるならば、そのような知識や理解を発達させることはできない、ということに気づくことが重要なのです。私たちがこの第二の世界に参入するとき、あらゆるものが生命の身震いを始めます。私たちは次のように自分に言います。感覚的な経験を通して我々が知っていた山は活気のないもののように見える、我々はそれが生きた力によって浸透されていることに全く気づいていなかった、今やそれが我々に明かされる。そして、以前には静的で不活発のように見えた雲の中に、これまで気づかなかった生きた生命が生きているということが今や明かになる。あらゆるものが活気づけられ、この波打ち脈打つ生命の中で、根本的な現実が明らかになるのだと。この第二の世界における自然の法則は知的に構成されているのではなく、精神的な存在に関係しています。私たちに語りかける女神ナチュラが現実の世界からの洞察を指し示し、伝えるのです。こうして私たちは、超感覚的な世界の存在を通して、私たちを取り巻く現実について学びます。私たちは自然法則によって決定される純粋に抽象的な世界から現実的な存在の世界へと上昇させられます。そこではもはや実験や分析によって自然法則に至るのではなく、異なる世界の存在たち、知識や理解を仲介する存在たち、何故なら、彼らは私たちが人間としてまだ学ぶべきこととは何かを知っているからです。そのような存在たちがいると感じられるのです。こうして私たちは正しい仕方で精神的な世界に参入します。もし、私たちが感覚器官だけを、つまり目とその視覚神経、鼻とその嗅覚神経、そして耳とその聴覚神経だけを授けられていたとすれば、そしてこれらの神経がすべてその出発点において結びつけられていたとすれば、私たちは酸素、水素、窒素やその他の元素、そして私たちが生まれてから死ぬまでに知覚するところのすべてを意識することはなかったであろう、ということに気づきます。私たちは元素の世界をのぞき、周囲のいたるところに土、水、空気そして火を知覚していたことでしょう。土とその粗雑な物質、水とその液体要素の間にさらなる区別をつけようなどとは少しも思わなかったことでしょう。私たちは物理的な感覚を持った存在として元素の世界に通じています。けれども、私たちがここで既に記述されたことを意識する瞬間、私たちはまた、人間の中では、頭蓋の空間へと駆け戻る感覚神経がさらに差別化され、特殊化されるとともに、その領域において、脳の最初の兆しが形成される、ということに気づきます。その結果、私たちはそれ以上深く自分自身の中に入りません。つまり、私たちは外に向かうようになり、私たちが誕生から死までの間に経験するところのものを、土、火、空気、そして水という四つの元素の性質に付け加えるのです。大脳は頭蓋空間へと駆け戻る感覚神経索の段階的な変容に基づいて発達します。人間の中で自分自身へと押し戻されるこの大脳は、誕生から死までの生活においてだけ意味があります。精神的な世界についての理解にとって、知性はほとんど重要ではありません。私たちが私たちの世界と境を接する最初の精神的な領域に参入しようとするときでさえ、知性は沈黙させられなければならないのです。大脳はより高次の知覚を妨害する器官なのです。しかし、知性が沈黙させられたとしても、私たちは感覚的な経験からは逃れられません。そのためには、感覚を精神化し、イマジネーションを達成しなければならないのです。通常の過程では、感覚に導き出された外的な世界のイメージは私たちの感覚によって受け取られ、知性がそれらを抽象的で死んだ思考へと変化させます。もし、私たちが知性を沈黙させ、それでも感覚を通して世界を経験することができれば、私たちはあらゆるものをイマジネーションの形で受け取ることになります。私たちはそのことを意識し、通常の生活における意識をより高次でより精神化された状態へと発達させることによって、ついには人生に対するより深い洞察が得られるのだ、ということに気づくようになるのです。(orange:オレンジ色 rot:赤色)目や耳のように私たちの体の周囲に配置された器官は元素の世界と絶えず連絡を取り、死後数年を経た死者を知覚しています。この世界についての知覚が失われるのは私たちの知性が介入するからです。人間の周囲に配置された器官は精神的な世界、死者の世界を仲介するのですが、この世界、土、水、火そして空気元素の世界は知性的な意識によって消し去られるのです。人間ははっきりと規定された輪郭を持つ物理的な世界、私たちが誕生から死までの間に滞在する世界だけを見ます。非常に異なって秩序づけられた第二の世界が本当に存在するということは疑いのないことなのですが、この世界は知性によって消し去られ、人間がながめるのはただ日常意識にとって見慣れた世界だけなのです。現代人が昨日お話ししたような瞑想を行わなければならないのはそのためです。過去には、そのような瞑想の後、金属実質を摂取するということが行われました。それについては前回の講演でお話ししました。より高次の意識レベルに至ることができるかどうかは、まず第一に、知性を消し去るということ、感覚器官によって仲介される知覚を精神化するということにかかっています。動物の場合、大脳が発達していないために、これらの知覚に与ることができるのですが、彼らは自我意識を有していないため、その知覚は精神にではなく、単に原始的な魂の力にだけ浸透されています。彼らは人間のように感覚が精神に照らされたときに知覚されるものを周囲の世界に知覚しません。動物の知覚は人間の知覚と同じ種類のものなのですが、劣ったものであり、個的なものになっていないのです。金属性について、つまり鉱物世界の現実の実質についてこれからお話しすることは、必要な留保をもって受け取られなければなりません。昨日、金属の性質を通して魂を内的に活性化させることについて、つまり言い換えれば、金属性との内的な交流を道徳的な意味で発達させることが今日の人間の精神的な発達における枢要な部分をなしているということについてお話ししたとき、その留保に対して皆さんの注意を促しました。効能化された金属の人体組織に対する処方は臨床医の役目です。ですから、皆さんには、既に議論した以外の金属の知られざる要素について私がお話ししようとしていることを、必要な留保をもって受け取っていただきたいのです。特に水銀の秘儀は精神的な面から世界に接近する人たちにとって、すなわち物理的な実質の中に精神の働きを知覚することができる人たちにとって特別な重要性を有しています。ただし、金属の水銀は精神科学が水銀的という一般的な言葉で呼ぶところのものの一部に過ぎません。水銀的なものとは液体金属の性格を有するあらゆるものを含んだものなのです。私たちが今日知っているような自然界には、このような性格に与る金属、水銀的と見なされ得る金属はたったひとつ、つまり水銀しかありません。けれどもこれは水銀という種を構成するもののひとつに過ぎません。精神科学においては、水銀的なものとは水銀的な性質を有するあらゆるものを包含しています。水銀は単に水銀的なものの典型例と見なされるに過ぎません。この水銀には奥深い秘密があります。水銀の人間に対する影響とは、人間が物理世界のすべての印象から、そして元素の世界からも引き離されるというものです。私たち人間は脳のような器官が物理的な世界から作り上げられたのを知っています。私たちはまたこの感覚の世界から他の多くの器官を作り上げたのですが、特に、物理的な生活には不可欠の一連の腺組織全体を作り上げました。さらに言えば-感覚器官については既にお話ししました-、第二の意識レベルに関係する世界として記述された世界からも多くの器官が作り上げられています。銅と鉄は人間をこの第二の意識レベルに引き上げます。水銀の影響は異なっています。それは必然的に宇宙の中に存在していなければなりません。そして、それは実際、微細な拡散状態で普遍的に存在しているのです。私たちはいわば水銀の大気に取り囲まれているのです。人間が通常以上の量の水銀を吸収する瞬間、彼の有機体は物理世界と元素の世界から作り上げられたすべての器官を中和しようとし始めます。人間のアストラル体がいわば刺激され、星の世界から作り上げられた器官にだけ頼るようになるのです。ですから、水銀の金属性に、つまりその金属的かつ液体的な性質、水銀に特徴的な要素、基本的に手で感じられないほど微細でありながら、それでも人間に関係しているところの要素に意識を集中するやいなや、人間は「第三の人間」に浸透されるようになります。人間は銅との関係を通して内的な緊張を創り出すとともに、肉体を捨て去り、死後間もない死者たちを数年にわたって追っていくことができるような第二の人間に内的に浸透されるようになる、ということは既に述べました。水銀はもっとはるかに綿密に織られた魂的な組織に貢献するようなあらゆるものを引き寄せます。水銀の影響を通して、人間の器官における新陳代謝の全体が把握されるかのようです。人間は、水銀の力強い金属的な影響を経験するとき、様々な管組織を通して流れる液体循環の様相に突然注意を向けさせられることになります。その影響は気持ちがよいものとは言えません。と申しますのも、彼は、心と感覚を失ったかのように、内的な発酵状態、乱れと流れ、脈打つ生命と動きの中にあるかのように感じるからです。そして、彼はこの内的な活動が外の活動とひとつになっているのを感じます。既に記述しましたように、この状態は内的な生活の意識的な訓練によって生じます。水銀の活動的な影響を通して、人間は彼の脳の存在を感じることをやめるのです。脳は空虚な空間になりましたが、それは精神的な世界の知覚にとって有益なことなのです。何故なら、脳はその目的にとって全く役に立たないからです。彼が実際に感じるのは彼の有機体全体に浸透する動きと活動です。とはいえ、この発酵は最初、内的な消耗に苦しむのと同様に苦痛に満ちたものなのです。(orange:オレンジ色 rot:赤色)内的な活動があらゆるところで外的な活動と結びつけられます。私たちは地球を離れ、元素の世界が私たちの下方にあるのを感じます。あらゆるものが流れる蒸気を吐き出すのですが、この蒸気の中には、流れる呼気の中には、精神的な存在たちが住んでいるのです。ブルネットー・ラティーニがあれほど生き生きと記述したナチュラ神が今「振り向いた」のです。昨日お話ししましたように、彼女はギリシャのパーセフォニーと同じ存在です。以前、彼女の眼差しはより地球へと向けられていました。つまり、彼女は死後間もない人間の生活についての経験のようにまだ地球の領域に結びついていたものを明らかにしました。今、彼女は「振り向き」、人間の下方には地球、そして元素の世界、上方には星の世界があります。地上で植物や動物に囲まれていたように、今、彼の周りには星の世界があります。彼はもはや壮大な星の世界を目の当たりにしても、自分がとるに足らないものであるとは感じません。星の世界は、彼の今の大きさでは、ちょうど地上において周りの環境との関係で感じられていたのと同じように感じられます。彼は、その身の丈が大きくなるとともに、星の世界へと成長したのです。とはいえ、その星は私たちが地上から見るような星ではありません。そこは精神的な存在たちのコロニーであるということが分かります。私たちは再び既に皆さんにお話しした世界、つまり錫の金属性との関係を通して人間の中で目覚めさせられる世界の中にいるのです。既にお話ししたように、水銀と錫の間には内的な関係があります。水銀は私たちの存在のある一定の部分に働きかけ、それを分離し、外的、物理的には星の世界として表現される精神的な世界に持ち込むのです。けれども、私たちは、私たちの意識状態が変化したため、今や異なる世界の中にいます。つまり、その意識はもはや感覚や脳によって決定されるのではなく、水銀の金属性が私たちの有機体から引き出したところのものによって決定されるのです。私たちは全体として異なる世界の中に、星の世界の中にいる自分を見いだします。しかし、このことは別の方法で表現することもできます。「星の世界」という言葉は空間的なものを暗示しますが、私たちは今や本当に、この新しい意識レベルを達成することを通して、誕生から死までの間、空間的に存在する世界を後にし、中間的な世界、死から再生までの間、私たちが滞在する世界に参入するのです。これが水銀の隠された秘密なのです。つまり、水銀は人間を現象世界から引き離し、中間的な世界への扉を開くのですが、それが可能なのは水銀が人間存在のあの部分、つまり地球から導き出されたのではなく、中間的な世界の存在たちによって彼の中に植え付けられた部分と内的な関係を有しているからです。彼が今経験する液体の循環は彼が死から再生までの間に通過する世界によって決定されるのです。私たちは今や、ある別のことがらについて知るようになります。それもまたブルネットー・ラティーニが女神ナチュラの影響下に受け取ったものなのですが、宇宙的な液体の循環に関連した液体の循環の中で私たちは生きているということが意識されるようになるのです。私たちは肉体という乗り物を感覚から導かれた意識とともに脱ぎ捨て、死から再生までの間に滞在する世界にいる自分を見いだします。そして、液体の循環の本性に通じるようになるとともに、いかにこの内的な活動が、つまり私たちが死と再生の間に滞在する領域が私たちの気質、多血質、胆汁質、憂鬱質あるいは粘液質という性質を決定したかを理解し始めます。私たちは私たちの成り立ちについて単に感覚に頼るとき以上に深い洞察を有することになります。私たちが粘液質として生まれるとすれば、自分の鈍感さ、自分の無精が前回の死と今回の誕生との間の私たちの経験によって決定された、ということに気づくのです。しかし、私たちは物理的な液体の循環の中に自らを現わすこの気質との関連でもうひとつの要因について考慮しなければなりません。この液体の循環には何が含まれているかを少し考えてみて下さい。解剖学や生理学の分野では主として物理的なものが問題になりますが、物理的なものは精神的なものの表現に過ぎません。この液体の循環に関連する精神的な要素は物理的な世界のものではなく、死と再生の間にある人間にまで貫き至る世界に発するものなのです。私たちが様々な気質を省みるとき-そして、女神ナチュラがブルネットー・ラティーニに気質の存在とその本質に対する彼の目を開かせたことは、彼にとって圧倒的な経験だったのです-、私たちは、死と再生の間の生活が液体の循環と関連するこれら四つの異なる気質の本性を決定したのだ、と結論づけるのです。もし、私たちがもっと深く探索するならば、運命を司るカルマがその中で役割を果たしているのが分かります。たとえこの特筆すべき液体金属である水銀の物理的な面をよく考えてみるとしても、それについて理解し始めるのは、その隠された秘密、すなわち液体水銀の微細な一滴が秘儀参入者に奥深い秘密を明かす、ということを十分に意識するときだけです。この滴は死と再生の間の世界にその起源を有し、その構造をその世界に負うところの器官の中に精神的なものを浸透させることができるのです。このように、世界のあらゆる事物は相互に織りなされ、関係づけられているのです。物質的なものは幻想です。そして、物質の観点からは精神的なものもまた幻想であり、抽象に過ぎません。実際には、物質的なものは精神的なものに、そして精神的なものは物質的なものに織りなされているというのが本当のところなのです。もし、その起源を中間的な領域に実際に有するような器官が関係する障害が人間の有機体の中で発生したとすれば、その障害を修復するような力を活性化しなければなりません。死と再生の間の生活にその起源を有するところの循環器系の不具合を持つ患者が医師の診察を受けると仮定してみましょう。医者は、その循環器系統が精神的な世界との結びつきを断ち切られているような患者に直面することになります。それがその患者がたどった歴史です。精神的な要素と物理的な診断との関係は昨日示唆したような意味で理解されなければなりません。誤解のないようにもう一度繰り返しますと、この患者の循環器系は精神的な世界からひどく断ち切られているという診断になります。何が処置されなければならないのでしょうか。循環器系と精神的な世界との結びつきが回復されるように、体内に金属性を導入するというのが正しい処置です。これが水銀の人間に対する作用です。水銀は人間の有機体に対して、精神的な世界からのみ築かれ得るような器官がその精神的な世界との関係を断ち切ったとき、それらを再び接触させるようにする、というような仕方で働きかけます。こうして、私たちは意識状態に関する知識と病気に関する知識との間に存在するいくらか危険であると同時に必要な関係を理解します。一方の知識が他方に移行するのです。このようなことがらは古代の秘儀において決定的な役割を果たしていました。それは私が昨日触れたようなことがらにも光を当てます。次のようなことを考えてみましょう。自然の秘密についての女神ナチュラの教えを通して、彼女に気づくことができた古い精神的な視界が失われていた時代に、ダンテの教師であるブルネットー・ラティーニがスペイン大使の地位を離れ、興奮状態の中で帰ってきます。生まれ故郷に近づき、彼の党、ゲルフ党の運命が聞こえてきたとき、彼の興奮は高まります。彼はこのすべてを、若干の発熱が彼のところにやってくるというような心の状態で経験します。正に水銀の金属性が周囲から彼に働きかけていたのです。若干の発熱を私たちはどのように理解すればよいのでしょうか。それは環境中の水銀、宇宙全体に細かく分散した水銀の影響を感じる、ということを意味しています。ブルネットー・ラティーニはこの影響を経験した結果、人間がそのような経験に与ることができない時代であったにもかかわらず、精神の世界に近づくことができたのです。こうして、私たちは、人間の中には、自然科学が見いだすところのものや死後数年以内の死者と接触を持つ人が見いだすところのものが存在しているだけではなく、私たちの根本的な存在はもっとはるかに崇高な何か、私たちが死と再生の間に生きるところの純粋に精神的な領域にも関係しているのだ、ということを理解します。通常の科学的な手続きによって例えば肝臓や肺の形態を理解することができます。もう一段高次のレベルの知識、そして、その知識はより粗雑な側面においてのみ現代物理学に知られているに過ぎませんが、それをもってすれば、感覚器官の構造を理解することができます。けれども、秘儀に参入する知識を通してそれに近づく以外には、直立姿勢をとる人間の循環器系が示す奇妙な特徴や不思議な金属の特質を理解することは決してできないのです。このことが示しているのは、秘儀に参入するところの知識なしに、私が記述した意味で病気の本性を理解することは決してできない、何故なら、金属が病気を癒すことができるのはその物理的な性質によってではないからである、ということです。金属の物理的な特質に関する理解をもってすれば、脳の損傷を癒すことは可能でしょう。しかし、循環する液体の障害を治療することは不可能です。ただし、このように言うことは実際には厳密に正確というわけではありません。何故なら、それによって治療することができるのは脳の最も粗雑な実質だけだからです。脳内には液体も循環していることから、現実には金属だけで脳の損傷を治療できるわけではなく、精神的な知識の助けがあってはじめてそれが可能となるのです。皆さんは、確かにそうかも知れない、しかし治療芸術における今日の医学の成果をどのように説明するのかと言われるかも知れません。それに対する答は、医学に治療が可能なのは、それが金属の精神的な要素についての古い伝統的な知識の記憶をまだ保持しているからであるというものです。それが使用しているのは伝統的な知識と、ほとんど役に立ちませんが純粋に物理的な発見の組み合わせです。もし、唯物主義が伝統の犠牲の上に立って勝利を収めるとすれば、化学療法だけではいかなる治癒効果もないということになるでしょう。私たちは今新たに精神的なものに接近しなければならない、何故なら、太古の超感覚的な能力に関する古い伝統は徐々に失われているのだから、というような人間進化における一地点に立っているのです。銀の金属性の背後にある秘密は非常に特別な種類のものです。銅の背後にある宇宙的な衝動が最初のより高次のレベルにある意識を人間の中に目覚めさせ、水銀の背後にある別の宇宙的な衝動が星の世界、つまり私たちが死と再生の間で滞在する精神的な世界に関係する第二の高次のレベルにある意識を目覚めさせるとすれば、銀の金属性は全く異なる段階の意識を目覚めさせるのです。人間が銅と水銀の本性に対して採用したのと同じプロセスによって銀に対する彼の関係を強化し、高めるとき、彼は彼の内にあるより奥深い組織に関係するようになります。人間は水銀によってリンパ液の循環システムに関係づけられるのですが、それによって今度は宇宙の循環、宇宙の精神性に関係づけられるようになるのです。銀に対する彼の関係を強化することは前世から生き残っているすべての力と衝動との直接的な接触へと彼をもたらします。もし、人間が銀の奇妙な性質に集中するならば、そして、それはときとしてその効果が表れる以前かも知れません。彼は自分の内部で、液体の血管中における循環だけではなく、血流に乗った熱の循環にも関係するあの力に集中することになります。そのとき彼は、彼の人間としての地位を彼の血液中における熱の循環に、つまり物質ではあるけれども同時に血液中の精神的な要素でもあるところのある種の内的な熱を彼が感じるということに負っているのだ。そして、この熱の中には前世からの力が活発に働いているのだということに気づくのです。人間の銀に対する関係の中に表現されるのは、血の熱的な活動に影響を及ぼすことができるもの、そしてまた前世との精神的な結びつきを提供するところのものなのです。ですから、銀は前世から現世にまで生き残っているものを人間に思い出させるというあの金属としての効能を保持しているのです。と申しますのも、顕著な熱の多様性を有する血の循環はこの物理的な世界から導かれたものではなく、皆さんにお話しした元素の世界や星の世界から導かれたものでさえないからです。星の世界は血液循環の道筋や方向を決定しますが、私たちの中を血とともに循環する熱の中には、前生からの賦活力が働いています。私たちが人間との関係で銀の力を指し示すときには、直接この力に訴えかけているのです。銀の秘儀はこのようにして人間の前世に関係しています。銀は精神的なものがすべてに浸透していること、物理的な世界においてさえそうであることの驚愕すべき例のひとつなのです。銀を正しく理解する人はそれが人間の繰り返される地上生の象徴であることを知っています。ですから、銀の秘儀は生殖とその秘密に結びついているのです。何故なら、人間の存在が世代から世代へと繰り返されるのは生殖の過程を通してだからです。以前の地上生の中にあった精神的な存在は生殖過程を通して再び受肉します。これは血の秘儀と同じ秘儀です。血の秘儀、血の熱の秘儀とは銀の秘儀のことです。私たちは今や人間の正常な状態について知るようになりました。次に、その異常な状態についての探求へと進むことにしましょう。さて、血はその熱を、人間の現在の環境からではなく、彼が前世において通過した領域から取り出さなければなりません。人間の血の熱が、私たちを精神的に前世に結びつけるところのものによって活性化されず、現在の環境の影響を受けると想像してみましょう。その場合、結果として病理的な状態が生じます。それが生じるのは血の熱に結びついているもののすべてがその自然な関連から、つまり以前の地上生から切り離されるからです。発熱とは何でしょうか。精神科学の立場から言うと、発熱は人間の有機体が輪廻転生との関係を断ち切ったために生じるのです。もし、ある病気の場合のように、患者の有機体が以前の受肉から切り離される危険に陥るというような仕方で外的な世界によって働きかけられている、ということが確かめられたならば、医者は治療のために銀を処方します。この種の非常に興味深い例が、最近、アーレスハイムのベークマン博士の医院で見られました。精神生活においては、今お話ししたような状態が突然生じることがあります。血の奇妙な特性のために、人間の有機体が外的な状況を通して以前の受肉からの突然の遊離に脅かされるのです。そして、このことは正に最近ベークマン博士の医院においてある患者に起こったことです。けいれんしていた患者が突然予期せぬ高熱、通常の医学が言うところの原因不明の熱を発したのです。ベークマン博士はその先験的な理解をもって直ちに銀治療を施しました。彼女の話しから、その患者が完全に宇宙的な関連の図式を示していることが明らかになりました。このことから私たちは、一方では、人間の精神的な進化に結びついているものと、他方では、病理的な状態に導くものとの間の相互作用について、つまりそれらをどのように処置すればよいかについて学ぶことができます。秘儀参入者が地上における以前の生を探求できるというのはどのようにしてなのでしょうか。普通の人生の場合のように、私たちが前世に結びつけられ、カルマに巻き込まれている限り、通常の意識をもって前世を振り返ることはできません。前世の影響は現世の中で感じ取られます。私たちは私たちのカルマをそれらの影響の下に成就し、私たちの人生はカルマによって決定されます。通常の意識なしには振り返ることはできないのですが、もし、そうしたいのであれば、しばらくの間その限界を振り捨てなければなりません。そして、前世を客観的に見ることができるようになったとき、私たちは振り返ることができる位置に立つことになります。もちろん、私たちは全く正常な方法で現状に復帰できなければなりません。そうでなければ、秘儀に参入したのではなく、精神異常の人になってしまいます。これは精神的な発達の過程で生じる現象です。私たちは私たちを前世につなぎ止めるところのもやい綱を解くのです。異常な場合や病理的な状態では、病気がその働きをします。病気とは、私たちが精神的な視覚やその他の意識レベルを達成するために、通常はより高次の領域において達成しなければならないものの異常な仕方での表現なのです。もし、人間のその他の組織から切り離された血がそれ自身の意識、と申しますのも、血はその他の器官がそれぞれの特別な意識状態を有しているようにそれ自身の意識を有しているからです、それに支配されるとすれば、つまりその他の組織による縛りから自由になるとすれば、それはこの異常な状態の下で、ただし無意識的にですが、前世を振り返ることになるのです。意識的に振り返るためには、私たちはまず通常の意識なしで済ますことができるようにならなければなりません。病理的な状態で振り返るときには、通常の意識との結びつきが保たれているのです。このように、例えばカルマに関連するすべての病気に対するすばらしい治療法となる銀の金属性についての探求は、銀の秘儀から発してその他の深遠なる秘儀へと導きます。私たちは人間におけるあの様々な意識状態に関連したあらゆる金属的な本性について語ってきましたが、今度は、これらの意識状態に対する私たちの探求をこれらの状態を通して到達することができる別の世界との関連へと広げていくことにしましょう。つまり、次の講義では、精神的な知識に向かう正しい道についてより詳細に探求することを提案いたします。 (第五講・了)参照画:Brunetto Latino-2人気ブログランキングへ
2024年05月01日
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1