-
1

GASSHOW 訳してみました
Break Time(一休み)GASSHOW 訳してみましたGASSHOW 歌詞全文GASSHOW 歌詞と訳illion(野田洋次郎)氏の「GASSHOW」と言う曲に感銘いたしました。曲も歌詞も素晴らしいのです。恥ずかしながら、YouTubeで別件の動画から私も最近知ったばかりなのです。まず曲に耳が止まり、何て言う曲? と思っていたら12年も前の曲だった。そして調べて驚いた。「GASSHOW」と言う曲は東日本大震災(2011年3月11日14時46分に発生)の被災地支援のために作られた曲だったそうです。歌詞が古い言い回しをしているので、みなさんすぐに震災の歌とは気付かないかと思います。私もそうですが、震災の歌と言われて聞けばなるほどなのですが・・。タイトルの「GASSHOW」は「合掌(がっしょう)」の意で、文字通り手を合わせて拝むと言う意味内容にになっています。つまり、「GASSHOW」は東日本大震災のレクイエム(Requiem)だったのです。※ レクイエム(Requiem)はラテン語。本来はキリスト教や正教会での死者への追悼のミサから生じた語。死者への祈りから日本では「鎮魂歌(ちんこんか)」と訳された。被災者支援の曲ですから、実は内容も非常に重い。言われて気付く。無意識に心にひっかかったのに納得しました。メロディーも歌詞も非常に趣きのある素晴らしいもの。なぜ今まで知らなかったのか? iTunesで購入してここの所ずっと聴いている次第です。※ YouTubeでカバーで出している方も、ここの所なぜか? かなり増えました。先にも説明しましたが、歌詞は古い言い回しが使用され、抽象的な表現がされてもいるので若い方には解釈がちょっと難しい。※ 全体には古語が使われた韻文の形式で書かれている。「意味を教えてください。」と言う要望が多い理由です。わたし自身、意味を解説しているサイトを見たりしましたが、それらはワードの解説であって、完全に作詞家の意図を解説しきっている人はいない。解らなくて? 濁されている部分もみなさん多々ありました。私も何回も歌詞を見て理解を試みました。わたし自身完全に解釈するのは難しいかとも思いましたが、GASSHOW 訳してみました。これは私の解釈。作詞家の意図するところとは少し違うかもしれませんが、ストーリーは通るよう訳してみました。解りやすくする為に、英語の翻訳で言う所の超訳(ちょうやく)と言う手法で訳させていただきました。つまり歌詞を直訳した訳ではなく、歌の本意を解説的に訳したものです。もし、この歌を知らない方。ぜひ聞いてみてね。illionofficial さんがGASSHOWをYouTubeにもあげられています。リンク GASSHOW (illionofficial)先ず、歌詞全文をのせさせていただきます。次に歌詞と訳を挟む形でのせさせていただきます。GASSHOW 唄・作詞・作曲:illion(野田洋次郎)※ 野田洋次郎 (1985年~ )「illion」はソロ活動の名前で、ロックバンド(RADWIMPS)のボーカルでシンガーソングライター。GASSHOW 歌詞全文猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えとその裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)と引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよはじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはGASSHOW 歌詞と訳猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)突然起きた地震。そして起きた大津波。海が荒れ狂い。轟(とどろき)と共に海は地の上を這って迫り来る。容赦なく押し寄せる水は私たちが無垢に生活していた家々にまで届き、人を襲い海の底に引き込んだ。荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていったのだ。海が飲み込んだのは人の命だけではない。その人の想いと生きることへの渇望(かつぼう)も・・。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えと犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。八百万の神々様、どうか彼らの魂を救ってください。どうかお願いします。(( -.-人 その裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう突然の津波。そもそも何が起きたか解らずに海に襲われた人ばかりだったろう。「神様、助けて。」「誰か、助けて。」そんな絶叫もむなしく、海は容赦なく、彼らを飲み込んで行ったのだ。そして今も彼らの「叫び」は海に閉じ込められたまま、波間を漂い、ずっと木霊(こだま)のように、さまよっている事だろう。君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所君の匂いのする所に帰りたい。貴方が私の帰る場所だった。今、君はいない。私は(どこかに)進まなければならない。それは僅かに、指先に見える心もとない細い道でしかないけれど。万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない一生懸命生きて、働いて積み上げて得た幸せ。それらが一瞬にして壊され、まるでウソだったかのように現実から消えて無くなるのなら、真実さえ、受け入れたくはない。怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者もう、怒る気持ちも、涙も流さない。希望も夢も無く、私は現実の世界で淡々と生きている。残された者の現実は皆辛い。生きるのは苦しい。悲しみや痛みに捕らわれ続けているからだ。猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていった。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。幾年も積み上げて来られた人生をたった一瞬で葬り去られた無常に・・。果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く海に荒らされ荒廃した大地。私たちはどうしたら再び光を取り戻す事ができるのだろう。今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして今、できる事は祈りを込めて、海に飲み込まれた彼らの魂が戻る道しるべとなるよう街を復興させなければならない。出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ貴方と出あえたから今の自分がいる。虚無感でいっぱいだけどそれ(自分自身)は大事にするよ。運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)ともともと運命だったのか? 神の采配だったのか? 一瞬にして消えてしまったあなたの魂。引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよ貴方の命と引き換えのように残ったわが身。これも貴方の形見だから大事にするよ。はじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはもうこの世にいない貴方。貴方の遺物(遺骸の一部)さえ見つかっていない。貴方の体も魂もどこにあるか解らない。(拝むべき、墓も無い。)それでも、頼むから、この祈りの気持ちが貴方に届いてほしいと、初めて思った。切に願っているよ。東日本大震災で被災され、家族を失われた方々の気持ちを考えながら訳させていただきました。亡くなられた方々へ、深く哀悼の意を表させていただきます。自然災害とは言え、突然命を奪われた方々の無念さは言葉では言い表せない思いがあるでしょう。その気持ちは歌のように今も波間を漂っているかもしれない。魂はもしかしたら、まだ成仏されていないかもしれない。残された家族がそう思い悩まれているかもしれない事も想像に難くない。この「GASSHOW」と言う曲は残された者たちの苦悩の歌でもあるのだと、訳していて改めて感じました。逝った者も辛い。残された者はもっと辛い。せめて彼らの魂が全員救われてくれるなら・・。少しは心が晴れる。日本を統べる八百万の神々なら、彼らの魂を救いあげる事ができるかもしれない。私もそう願っています。m(_ _)million(野田洋次郎) 氏は短い言葉で非常に多くの事を語っていたのです。そして端的に被災された方々の気持ちを吸い上げて言葉にしている。作家ではなく、ミュージシャンなのに凄い方だな。と思いました。( ̄人 ̄)
2025年04月19日
閲覧総数 18115
-
2

ルーヴル美術館 8 (天井の装飾)
ルーヴル美術館 8 (天井の装飾) フランス(France)パリ(paris)セーヌ川右岸1区ルーヴル美術館(Musée du Louvre) Part 7ルーヴル宮殿室内装飾ルーヴル宮殿の室内・・と言っても下は作品の展示になっているので、天井ばかりですが、あまりに素晴らしかったので写真にとっていたものから少し紹介します。宮殿内の様式や時代もまばら、撮影場所も定かではないですが主にバロックです。最後に変わり種もありますが・・。さすがフランス王家の宮殿です。やっぱりゴージャスです1650年代to欧州では建築、絵画、彫刻、演劇、音楽と、文化の潮流がバロック芸術へと移行。ルイ14世の改修はそんな中で行われています。ルイ14世の宰相マザランはイタリア出身であった為に1640年代からイタリア・バロックが導入。特に建築家フランソワ・マンサールは、古典的なバロック建築を好んだようで1667年~74年)のそれは、フランス古典主義建築の最も完成された姿、ルイ14世様式とも呼ばれるようです。部屋のコーナーを飾るこうした彫像は単体でも貴重な美術品です。ローマに留学していた画家ル・ブランは、ベルサイユの内装をローマ・バロック様式で手掛けていますが、天井装飾は、スタッコ装飾またはトロンプ・ルイユ(だまし絵)の技法による額縁に縁取られた天井画を描いています。それに対してここにトロンプ・ルイユ(だまし絵)の技法はありません。すべてリアル彫像になっています。ところで、ルイ14世は、ルーヴル宮殿の改修に巨費を投じながらも、1660年宰相であったマザランが死去すると、忌まわしい思い出のパリを捨て父王の好んだベルサイユに王宮を移してしまいます。(1678年ルーヴルの工事も中止)ニコラ・フーケのヴォー・ル・ヴィコント城のせいだけではありません。僅か4歳で即位したルイ14世にとってパリは内乱の多い恐ろしい街だったようです。一説には潜在的な民主嫌悪症があって、ルーヴルがパリの民衆に取り囲まれているのが不安だった・・と言われています。昨年6月の「ベルサイユ宮殿 1」と3で紹介。本当に、「威厳」と言うものを感じる装飾です。ベルサイユよりこちらの室内装飾の方がお金がかかっていると思います。6月「ベルサイユ宮殿 3 (ベルサイユ宮殿とパロック芸術)」でフランス・バロック様式について少し紹介しています。ベルサイユは当代唯一の芸術家の御三家(美術家、建築家ル・ボー、画家ル・ブラン、造園家ル・ノートル)が造りあげたトータル芸術で、傑作ではありますが、ルーヴルはベルサイユの装飾より私好みかもしれないかなり傾向の違うこの部屋は新古典様式の影響ありつつ・・の帝政様式なのかもしれません。帝政様式(Style Empire)建築での帝政様式はあまり見かけませんが、基本はデザインの様式です。ナポレオンのフランス第一帝政時代に始まりフランスの地位を理想化することを意図したもの・・だそうで、分類としては第2次新古典様式と見なされる場合も・・・。帝政・・Empire のフランス語発音からアンピール様式、英語読みでエンパイア・スタイルとの呼び方もあります。(私はナポレオン様式と呼んでますが・・家具では赤色に金彩色のテキスタイルが特徴かもしれません。足や肘掛けがエジプトを思わせる派手な彫刻がある場合も。本当にどこもかしこも、「凄い」に尽きます。絵画だけ見て帰るのはもったいない。おそらくナポレオン3世の時代か? より新古典様式でも帝政様式の色濃く出た装飾の部屋。なかなか見られない装飾です。例えるならギュスターブ・モローの絵画のようです。絵画部門、最近写真撮影ができるようになったので若干あるのですが。気がついたら連休に突入・・・明日からちょっとお出かけですパソコン持って行くので更新なるべくするようにしますが、休日バージョンで行きますルーブル美術感一応終わりです。back numberリンク ルーヴル美術館 1 (ニケ、ヴィーナス他、彫刻)リンク ルーヴル美術館 2 (ギリシャ彫刻)リンク ルーヴル美術館 3 ( ミケランジェロの奴隷像)リンク ルーヴル美術館 4 ( オリエント美術)リンク ルーヴル美術館 5 (オリエント史)リンク ルーヴル美術館 6 (エトルリアの棺)リンク ルーヴル美術館 7 (宮殿小史)ルーヴル美術館 8 (天井の装飾)
2010年04月30日
閲覧総数 2080
-
3

アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人
ラストにback number入れました。すっかり忘れていました。今回は、大航海時代を支えた船の事を入れたいと思います。写真は南アフリカ、ケープ半島の喜望峰です。いわゆる船の始まりはガレー船(galley)である。動力はオールのみのガレー船(galley)と帆とオールによる動力で船を動かすタイプのガレー帆船が存在する。※ 紀元前の戦闘においてすでに利用されていた船。そのオールを動かす行為は人力であるから長時間航行には限界があった。寄港地を多く必要としたので割と陸の近くを航行した船である。ガレー船にも小なり大なりの船があり小型のガレー船でマストが1~2本。オールの数はその用途でも変わった。ただの運搬船の場合は積荷の重量を優先して漕ぎ手は少くない。つまりオールは少ない。※ 小型のガレー船フスタ(fusta)は漕ぐよりも帆走をメインとしていた。マストは1本。が、軍用船の場合、速度が重視されるから漕ぎ手は増える。昔は戦士がそのまま漕ぎ手となっていた。後に大砲など銃器も積むようになると重量も増しオールの漕ぎ手の数も増える。※ 兵士50人~150人程度?当然、船自体が大型化する。食糧や水などの供給の為に長時間航行には限界があり、補給と休息の為の寄港地も増える。※ ガレー船については、以前「海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦」の中「ガレー船(galley)の変遷」のところで紹介しています。リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦上に紹介したガレー船は地中海の比較的穏やかな海で誕生したものだ。ジブラルタル海峡を出て外洋に出ると、海にはただならぬ風と海流が存在し、海も荒れた。安全な寄港地だってあるかわからない。外洋航海を目指した彼らは外洋に耐えられる船造りの必要性に迫られる。特に水面(喫水)から上甲板までの距離(乾舷・Freeboard)は重要である。外洋は波も高くなるので船の乾舷を大きく(高く)しないと沈没しやすい。ポルトガルのエンリケ王子は未知への航海に踏み出し海図を少しずつ書き足した。同時に船の開発もしたとされる。彼がエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)と呼ばれるのは、彼の元にそれら研究が推し進められていたからだ。彼らは遠洋航海に適した大型の船の開発と、未知の探検に適した船の開発を成功させた?※ ポルトガル南部のサン・ヴィセンテ岬(Cape San Vicent)に王子のヴィラがありそこに研究施設と学校があったとされる。大航海時代、当初、世界の植民地化においてポルトガルとスペインの独壇場となったのは、外洋に出て行ける船を持っていた両国だけだったからだ。ところで船の写真はほぼウィキメディアから借りました。船の本探しましたが無いのです。あっても近年の帆船の本ばかり。中世の帆船を詳しく順序立てて解説している本が欲しかった。アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人嵐の岬から喜望峰に名称変更大航海時代の船Georg Braunの鳥瞰図キャラベル船(Caravel)キャラック船(Carrack)ガレオン船(Galleon)ケープ・ポイントと希望の岬ジェノバの商人(The Merchant of Genoa)ポルトガルとの関係ジェノバの商人の見返りは何か?スペインとの関係ジェノバ人の報酬帆船の風フォールス湾シール島自然保護区(False Bay Seal Island Reserve)嵐の岬から喜望峰に名称変更ケープ・ポイント(Cape Point)からの喜望峰(Cape of Good Hope)少し時化(しけ)た時の喜望峰(Cape of Good Hope)少しの時化でも沿岸は岩場が多いせいか波が立ってますね。ケープ半島(Cape Peninsula)の南端に喜望峰(Cape of Good Hope)はあるが、実際はケープ・ポイント(Cape Point)の方が少し南。もっと言えばアフリカ大陸の最南端は喜望峰ではない。ケープ半島南端は岩礁がすごくて海底が渦巻いているのかも。バルトロメウ・ディアス (Bartolomeu Dias)は実際、アフリカの最南端であるアガラス岬(Cape Agulhas)まで進み船をターンさせた。実は喜望峰(Cape of Good Hope)を発見するのはその後なのである。彼はアフリカ大陸の南の海で嵐に遭って13日間漂流。気付いたらアガラス岬まで来ていたのである。アガラス岬はアフリカ大陸の最南端と言うだけではない。実はここはインド洋(Indian Ocean)と大西洋(Atlantic ocean)の分かれ目なのである。それは海流(Agulhas Current)により明確に分断されている。だから彼はそこより先に進め無かったのだろう。遭難してさんざんな目にあい彼はやむなくターンしてケープ半島(Cape Peninsula)の南端まで戻る。彼はそこを嵐の岬(Cabo das Tormentas)と報告したそうだ。※ 帰りはベンゲラ海流(Benguela Current)に乗るので早い。希望の岬(Cape of Good Hope)と名を変えさせたのはジョアン2世(João II)(1455年~1495年)。東方への道が開けた「希望」が込められた名前らしい。日本ではなぜか「喜望」が用いられているが・・。大航海時代の船ポルトガルが喜望峰に到達するのは1488年。喜望峰に到達したバルトロメウ・ディアス (Bartolomeu Dias)(1450年頃~1500年)はキャラベル船(Caravel)2隻と補給船1隻でリスボンを出港。一方スペインからクリストファー・コロンブス(Christopher Columbus)(1451年頃~1506年)が大西洋横断するのは1492年の事。コロンブスはキャラック船(Carrack)のサンタ・マリア号(La Santa María)を旗艦としてピンタ号とニーナ号と言う少し小型のキャラベル船(Caravel)の3隻でパロス(Palos)港から出港。コロンブスの船は何れも中古船だったそうだ。それにしても二人はほぼ同級生だったのね。大航海時代を迎えるにあたり、まず造られた船は外洋に出られる船だ。高波にも沈まない安定した船体の船。すでにベースはあったと思われる。遠洋航海が始まると食糧など物資がたくさん詰める船倉も必要になる。交易品を積む上でも必要だ。そのうち到達した未開地の探索の為の船も必要となる。入江や川を遡上しての探検に適した小廻りがきき機動力のある船も必要とされた。植民の為の侵略が始まると、現地との争いも起こる。相手を威嚇する為に砲台の数も増えて行く。植民地との運送船には護衛する船が併走するようになる。護衛船は砲台の数を増やし戦列艦と呼ばれる砲撃戦用の完全なる軍船に進化もみせる。また砲台は減らして速度を重視したフリゲート(Frigate)も生まれている。つまり大航海時代に生まれたガレオン船(Galleon)は、戦える船として輸送と兼務した活躍をみせる。Georg Braunの鳥瞰図1572年のポルトガル、テージョ川(Tagus river)河口のリスボン港ドイツの地形地理学者 ゲオルク・ブラウン(Georg Braun)(1541年~1622年)が編集長として世界で最も重要な都市? として編纂した本「Civitates Orbis Terrarum」Volume 1、1572 からの出展? ウィキメディアから借りましたが、これの原本はハイデルベルク大学図書館のデジタル・アーカイブらしい。ゲオルク・ブラウン(Georg Braun)は546の都市の展望、鳥瞰図や地図を編纂。1572年から始まり1617年にVolume 6(第6巻)まで刊行している。当時も役に立ち、且つ後世の重要な歴史的資料にもなってます。ポルトガルではキャラベルは2本マストの三角帆が好まれたと言う。新機種 大型のガレオン(Galleon)ここにはかつてのガレー(Galley)と小型ガレーのフスタ(Fusta)もいます。キャラック(Carrack) とキャラベル(Caravel)はなんとなく分けたので間違っているかも・・。大航海時代初期に利用されたキャラック船(Carrack)もキャラベル船(Caravel)も共にポルトガルが開発した? と考えられいる。外洋航海の為に開発された安定性と容積の大きいキャラック船(Carrack)。未知の土地での探検に適した小廻りのきくキャラベル船(Caravel)確かに探検用のキャラベル船(Caravel)の完成型はポルトガルであったとは思うが、外洋航海用のキャラック船(Carrack)はポルトガルではなくジェノバの造船所が開発したものだった? 可能性もある。何しろジェノバは1312年の段階ですでにカナリア諸島まで到達していたし・・。実際、ジェノバは船も売ってたからね。海洋共和国ジェノバの事は「アジアと欧州を結ぶ交易路 12~14 海洋共和国」編の中で書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)※ 海洋共和国ジェノバ(Genoa)と交易先,十字軍遠征に対するジェノバの功績、海洋共和国ジェノバ(Genoa)の快進リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)※ キリスト教国の逆襲、十字軍(crusade)の中、十字軍効果の経済リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊※ ヴェネツィアvsジェノヴァの交易キャラベル船(Caravel)1450年頃、ポルトガルの国家管理の下で開発された探検船と言われている。それは確かに、エンリケ王子(1394年~1460年)のチームが、必然により開発した船だったかもしれない。先に紹介したよう1488年、バルトロメウ・ディアス(Bartolomeu Dias)(1450年頃~1500年)が喜望峰に到達した時に利用していた船である。しかもキャラベルは浅い沿岸海域で上流に航行する事が可能。まさに西アフリカの川を遡上しての探検の為に開発されたような船だ。50〜160トン、マストは1〜3本。3.5対1、狭い楕円体フレームを持つ。初期のキャラベル船の平均の長さは12〜18 m 39〜59トン。また、初期のキャラベル船は2つまたは3つのマストを搭載。後に4本のマストも。サイズで用途も変わるからマストの数は船のサイズによるだろうし、当然用途で異なる。また帆の形などで機能性はかなり変化する。帆の操作次第で風上に向かって航行する事も可能。小型ゆえ積載量は限られるが、その操作性と機敏さから非常に高速での移動も可能だったらしい。三角帆のキャラベル船 ウィキメディアから借りました。パリの国立海軍博物館のコレクションからのポルトガルのキャラベル船のモデル。3本のマストを持つ小型の帆船で、小廻りもきくし高い操舵性を有していた。当時ポルトガルは西アフリカ沿岸から川を遡っての未開地での調査と同時に植民地や鉱物資源を探していた。探検家たちは機動力を求めてラテンセイルを備えたキャラベルや100トン前後の軽キャラックなど小型帆船を求めたのだろう。特にポルトガルでは三角帆のラテンセイル(lateen sail)が好まれたらしい。四角帆のキャラベル船 ウィキメディアから借りました。ヨット (yacht)の語はオランダ語の 「jacht」から由来するらしいが、ヨットのルーツ自体はポルトガルのキャラベル船(Caravel)だったのではないか? と思った。ところでコロンブスの旗艦のサンタマリア号はキャラック船(Carrack)であるが、ピンタ号とニーナ号はキャラベル船とされている。小さいピンタ号やニーナ号の方が動きも迅速なのでコロンブスは旗艦のサンタマリア号よりも好んだと言う。ニーナ号(La Niña)の復元船横帆を帆装に持つキャラベル船 写真はウィキメディアから借りました。ニーナ号のマストの数は現在も論議中。2~4本?排水量およそ60トンで船団の中で一番小型だったと言うが、これを見る限りではほぼ漁船。ピンタ号(La Pinta)の復元船横帆を帆装に持つキャラベル船 写真はウィキメディアから借りました。スペインのパロス(Palos)港のドッグに繫留されているピンタ号(La Pinta)の復元船。約60〜75トンの約15〜20mの小さなキャラベル船ピンタ号とニーナ号はキャラベル船とされているがポルトガルのキャラベル船とはちょっと違う気がする。キャラック船(Carrack)ポルトガルではナウ(Nau)、スペインではナオ(Nao)と呼ばれた。キャラベル船(Caravel)よりも大型のキャラック船(Carrack)も、14~15世紀にポルトガルで開発されたとされている。全長は30mから60m。3本~4本のマスト。丸みを帯びた船体は全長と全幅の比は3:1。特徴的な複層式の船首楼、船尾楼を有する。船の安定性は高く、外洋航路での貿易船として都合が良く、貨物と物資の積載能力も高かった。ポルトガルのキャラック船は、当時は非常に大型の船であり、多くの場合1000トンを超えていたと言う。コロンブスの旗艦であるサンタマリア(Santa Maria)。レプリカのキャラック船(Carrack)の写真をウィキメディアから借りました。キャラック船(Carrack)コロンブスによるアメリカ大陸到達500周年(1992年)記念のイベントとしてサンタ・マリア号、ピンタ号、ニーニャ号の船団三隻が復元。製作は1986年に開始され、復元された船体は1992年にスペインで開催されたセビリア万博で展示。下は船体部分のみカットしたものです。キャラック船(Carrack)のシンプル図。(ウィキメディアの図を借りました。)冒頭も紹介したが、それまで地中海で使用されていたガレー船は沿岸航行が主流。外洋航海ではより強い風と海流に絶えうる転覆しない安定した船の開発は必須。高波にも安定する船体を持つキャラック船(Carrack)に近い船はすでにジェノバやポルトガルでは利用されていたと思われる。先にも触れたが、ジェノバも早くから地中海からジブルラルタル海峡を出て大西洋を北上。北海への航路を持っていたから当然、大西洋の高波にも絶えうると同時に積荷を汚さず、濡らさず運ぶ為の広い船倉を有した船の開発はポルトガルより先だったと思われる。ハンザ同盟で栄えるブルージュの羊毛製品をポルトガルが独占的に取引するのは1430年以降である。ブルージュの羊毛のタペストリーの御得意様はローマ教皇庁であり、その運搬をジェノバが担っていたと考えられるからだ。※ ジェノバとローマ教皇庁の関係は十字軍以前に遡る。前に「アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル」の中、「海洋王国ポルトガルの誕生」ですでに書いているが、リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃。第6代ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時である。以降、ジェノバの商人をリクルートして船や航海、交易のノウハウをポルトガルは獲得していく。第10代ジョアン1世(João I)(1357年~1433年)(在位:1385年~1433年)の時代にはポルト港に400~500隻の船が出入りするほどの立派な海洋王国に成長を見せていた。そのジョアン1世(João I)の娘イザベル・ド・ポルテュガル(Isabelle de Portugal)(1397年~1471年)が1430年1月、ブルゴーニュ公フィリップ善良公に嫁いだ。結婚の縁きっかけでポルトガルと北海方面の通商が始まったと思われる。※ イザベルとエンリケ王子は同母兄妹である。※ 仕入れた羊毛タペストリーは北アフリカでイスラムの商人とも取引されていた。取引自体はポルトガルではなくジェノバの商会が行っていたと思われる。造船に関しては、そもそもジェノバの方が歴史は深い。ジェノバの造船造りのノウハウを得てまた人材を引き抜いてポルトガルが開発した可能性もある。何れにしても、この外洋の高波や海流に絶えうる安定の大型輸送船キャラック船(Carrack)は、ガレオン船(Galleon)が登場するまで大西洋航路で主流の大型船であった。※ ガレオン船は16世紀半ば頃登場。下はポルトガルが軍船として開発したキャラック船(Carrack)サンタ・カタリナ・ド・モンテ・シナイ(Santa Catarina do Monte Sina)部分を拡大一見ガレオン船(Galleon)だと思っていたが・・。船底は広く安定してますね。もしかして?ポルトガルは軍船もキャラックから発展しているのでガレオン船は造っていなかったかもしれない。1547年、ポルトガルはキャラック船(Carrack)で種子島に到達。ガレオン船(Galleon)は16世紀半ばにはすでに開発されていたが、日本に来たポルトガルの交易船は最後(1638年)までキャラックのままだった?※ 数々の屏風絵に彼らと船が描き残されている。すべてキャラックだ。下は神戸市立博物館所蔵のコレクションから狩野内膳作「南蛮人渡来図」屏風絵からウィキメディアで借りました。上は部分。下が全景。狩野 内膳(1570年~1616年)安土桃山時代から江戸時代初期の狩野派の絵師制作年 1570年~1616年因みに1637年の暮れに勃発した島原の乱が決定打? となって日本政府はポルトガルを排除し、交易相手をプロテスタントのオランダ国に乗り換えたのである。詳しくは以下に書いています。リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)ガレオン船(Galleon)ガレオン船(Galleon)はキャラックから発展したとされる遠洋航海用の船。16世紀半ば〜18世紀頃主流の帆船。キャラックより小さめの船首楼と大きい1〜2層の船尾楼を持ち、4〜5本のマストを備え、1列~2列の砲台を備えて敵の襲来を防ぐ事も可能。大航海の時代には武器も必須。護衛船として有用な船だった。ガレオン船の全幅の比は1:4。(キャラック船は1:3 )キャラックよりも幅に対しての全長が長くスリムな船。形状だけでキャラックより速度が出ただろう事は解る。積載量も大きいが、喫水も浅く速度は出る反面、船体のスリムさ。重心は上に行くので安定性に欠ける。いざと言う時に転覆しやすい船であったそうだ。ガレオン船(Galleon)のシンプル図。 (ウィキメディアの図を借りました。)海上輸送で利用されると同時に大量の砲台を配備できる船は戦闘に特化した戦列艦へと発展もしている。スペインのガレオン船(Galleon)の軍船 (絵画部分)スペイン船(上図)とオランダ船(下図)では砲台の数が違う。スペインのガレオン船は、3本マストを搭載。船体は500〜600トン砲台の数が多く豪華で派手。見た目重視? 見た者を圧倒させる目的があったのだろう。先にガレオン船は吃水が浅い為に速度も出ると紹介したが、この船に関しては性能は悪くスピードも出なかったらしい。ただ、並んだ砲台により一斉砲撃戦術が確立された戦列艦となっている。植民地間を行く商船兼護送軍船でもあったので特にスペインでは大型化される傾向にあったらしい。スペインでは新大陸の護衛艦として活躍。オランダのガレオン船(Galleon)の軍船 (絵画部分)原画 米国ワシントンD.C.の国立美術館(The National Gallery of Art) 出展(ウィキメディアから)タイトル オランダとスペイン軍艦の遭遇(A Naval Encounter between Dutch and Spanish Warships) 1618〜1620年画家 Cornelis Verbeeck (1585or1591年~1637年頃)オランダ黄金期の海専(うみせん)の画家スペインとの80年に渡る戦い(1568年~(休戦1609年~1621年)~1648年)を経てオランダは独立。※ オランダを導いた中心人物がオラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)つまりこの絵はオランダvsスペインの80年戦争の最中の絵なのである。但し、描かれた年代は1618〜1620年とされている。だとすると休戦期間(1609年~1621年)ただ中になってしまうが・・。ケープ・ポイントと希望の岬下図は南アフリカのケープタウン界隈です。喜望峰はケープ半島の最南に位置しています。大西洋側からの喜望峰(Cape of Good Hope)フォールス湾(False Bay)側からの喜望峰喜望峰の手前 ダイス海岸(Diaz Beach)新ケープ・ポイント(Cape Point)からの喜望峰(Cape of Good Hope)ここまで上るのは至難です。途中からフニクラ(Funicular)があります。Flying Dutchman Funicularのレール目指すは新ケープ・ポイントの灯台(New Cape Point Lighthouse)New Cape Point Lighthouseまでラストは階段です。下の灯台はウィキメディアから借りてきました。大西洋側の旧? ケープ・ポイント 喜望峰(Cape of Good Hope)の看板このあたりはケープポイント自然保護区(Cape Point Nature Reserve)なっている。マクレア海岸(Maclear Beach)ジェノバの商人(The Merchant of Genoa)大航海時代の主役は確かにポルトガルとスペインであるが、細かく見て見ると、何れの国も海洋共和国ジェノバ(Genoa)との関わりが深い。深い・・と言うよりは何れの国も全面的に金銭をジェノバ(Genoa)に頼っている・・と言う関係だった。ポルトガルとの関係ポルトガルが海洋国家になる為にジェノバの商人を国家がリクルートしたと言う事はすでに「アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル」の所で触れているが、海運事業を立ち上げ、国際交易に参加する為のノウハウもすべてジェノバ商人の指導を受けている。※ ポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃、第6代ポルトガル王ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時商船を持ち運営するのは、ただ船があって船員を雇えば良いと言うだけのものではない。交易をするとなれば、それは技術だけではなく商売をする上で金融のノウハウも必要になる。当然、運営の資金の調達から契約の仕方、経理、法律など事務的な事のノウハウも必要となる。また、ポルトガルは100年後には自国での造船も行っている。それらの全てをジェノバの商人らがお金も貸し付け指導もしていたのである。ではジェノバの商人の見返りは何か?実はこの頃(1312年)にはジェノバの航海士がカナリア諸島にすでに到達していた。ジェノバはアフリカ大陸からもたらされる金にすでに目をつけ、西アフリカ方面に関心を寄せていたらしいのだ。ポルトガル高官の中にはリクルートされたジェノバ人も入っていた。ジェノバの商人はポルトガルに海運のノウハウを教えると共に自分達の通商に有利に計らえるよう契約? 特権? があったのだろう。1415年、ポルトガルは北アフリカのセウタに侵攻した。この時も当然バックにはジェノバがいた。※ 北アフリカの金の取引の市場は他に移転してしまい予定が外れた。しかもセウタからは何も得られなかったが・・。ポルトガルによる外洋航海にジェノバは当然力を貸している。セウタは失敗したが、もしかしたらエンリケ王子をそそのかして海洋に興味を持たせ、ポルトガルを外洋航海に向かわせたのは彼らだったのかもしれない。1425年にはポルトガルによるマデイラ諸島(Madeira Islands)への植民が始まっていた。ここにはジェノバ人によりサトウキビが持ち込まれ15世紀中には黒人奴隷を使用してのサトウキビ畑の一大プランテーシヨン(plantation)ができあがり欧州へ輸出された。ジェノバのサン・ジョルジョ商会が出資。マデイラ諸島は欧州の砂糖の主要な供給地となっていた。また、マデイラ諸島はブドウの一大産地でもありポートワイン(Port Wine)と同じく酒精強化ワインのマデイラ・ワイン(Madeira wine)の産地である。※ フォーティファイド・ワイン(fortified wine)について書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス1427年にエンリケ王子が派遣した船長によりアゾレス諸島(Azores Islands)が発見される。ここは小麦粉とブドウと藍(あい)色の染料となる大青(たいせい)の産地に育てられた。1440年、セネガル川河口で金の交易が始まる。※ 金はセネガル川上流のサハラ地区? で採掘されそれ以前は北アフリカのイスラム商人の隊商によって北アフリカの港に運ばれていた? らしい。1450年、大西洋中央に位置するカーボベルデ (Cabo Verde)で奴隷を使用してのサトウキビのプランテーションがジェノバ資本で始まった。後にポルトガルが南米ブラジルを植民地化すると、そこにもジェノバ資本のサトウキビのプランテーションができあがる。つまり表看板はポルトガル国であるが、大西洋上、マカロネシア(Macaronesia)でのプランテーションや西アフリカでの交易にはジェノバ商人の資本とサポートが多大に入っていたと言う事実だ。それにしても15世紀以降の欧州の砂糖の市場はジェノバの商人が独占していたのかな?マカロネシア(Macaronesia)アフリカ西の大西洋上の島々、マカロネシア(Macaronesia)に属するマデイラ諸島、アゾレス諸島、カナリア諸島、ベルデ岬諸島の大半にジェノバの資本が入り、15世紀にはすでに欧州への食料庫として大量生産のシステムで開発が進められていた。※ プランテーション (plantation)・・ 大農園による生産システム驚きなのはそれだけではない。ジェノバの商人はすでに新天地にもかかわっていた大西洋上のマカロネシアでのプランテーションが確立される頃、1453年5月、コンスタンチノポリスが陥落している。すでに(1381年)トリノ講和条約にてジェノバは東方交易の利権を全て失っていたが、かつては黒海周辺に植民都市をたくさん持っていたジェノバである。さらなる影響もあった? いや、逆に商機を得た?ジェノバは窮地に落ちたと思っていたが・・。地中海を捨て、大西洋に、南米に。ジェノバの商人根性、先見の明。ヴェネツィアと違った意味で凄いと思った。スペインとの関係スペインが大航海時代の覇者となるきっかけを作ったのがコロンブスによる新大陸の発見。その新大陸発見はコロンブスによる持ち込み企画で、当初はポルトガル王もスペイン王も断った非現実の冒険企画だった。でも、その夢の企画に乗って現実に近づけてくれたのが、コロンブスと同国人のジェノバの商人だった。実はジェノバ人は12世紀にはすでにスペイン国内で商業金融を営んでいたと言う。つまり12世紀にはジェノバの資本がスペイン(カステーリャ、アラゴン、レオン)に入っていたと言うことだ。しかも、彼らはスペインから免税や徴税権などたくさんの特権を受けていた。それもこれも実はスペインの王室も貴族も財政的に苦しく、王や貴族は自分らが持っていた諸々の特権を借金の代わりにジェノバ人に譲渡していたからなのだ。今回大きいのはジェノバの持っていた徴税権である。教会、騎士団、警察組織などの徴税権を持っていたジェノバはそれらの中から融通の利く税収入を一部コロンブスの航海の為に捻出している。コロンブス自身も個人でジェノバの銀行から借金もしている。実際問題として、大航海の為に一番必要なのは資金である。その資金を捻出できたのは、国王ではなく、ジェノバの商人だったと言う事実なのだ。だからコロンブスがジェノバの商人を味方につけた事は間違いなくこのプロジェクトの成功の鍵となった。※ コロンブスはジェノバ出身者。同国人だったと言うのが大きかったかも・・。つまり、コロンブス探検隊による「インディアスの事業」は表向き、カステーリャの王室が行った事業であったが、実際ジェノバ商人らによる経済力で実行し、成功できた。そして成功した暁には、ジェノバの商人は使ったお金以上の回収を望んでいたからコロンブスはそれに応える成果が何より先に欲しかった。コロンブスとスペイン帝国の名誉は後の話だ。それにしても商人らは本気で期待していたのか? 最初からギャンブルと思っていたのか?ちょっと気になる。ジェノバ人の報酬コロンブスが到達したのは、アジアでは無かった。そこは、インドでもなくジパング島でもなかったが、金鉱が見付けられたのはまさにラッキーだった。スペイン帝国は南米から産出された金をジェノバへの返済金? 報酬? にしている。ヴェネツィア駐在のスペイン大使の報告(1595年)1530年以後、8000万ドゥカード(ducato)の金銀がスペイン船によりアメリカ大陸から欧州に運ばれた。※ ドゥカート金貨はヴェネツィア共和国の当時の冶金技術で精製できる最高峰の純度を誇る金3.545gで純度99.47%の金貨。(8000万ドゥカートで金283.6トン?)しかし、全てがスペインのもうけになったわけではない。1530年から1595年までの間にその30% (2400万ドゥカード)がジェノバ人のものになっていたと伝えている。金鉱が見つかった時の取り分30%? それは最初の契約にあったのかも知れない。地中海交易でヴェネツィアと争って負けたジェノバは東洋の物産を諦めはしたがスペインやポルトガルの航海に投資していたので大航海時代に双方の交易に係わり利益を得ていたのだ。実際、スペインが南米に開いた植民地、また鉱山開発に初期投資し、アメリカ大陸との貿易に大きく組入っていたジェノバの商人。ヴェネツィアの商人よりも柔軟でやり手だったかもしれない。帆船の風地球を吹く風は大きく2種に分けられる。一年中ほぼ同じ方向に吹く恒常風(constant wind)と、夏と冬で風向が変動する季節風(モンスーン・monsoon)である。恒常風は大気大循環に伴い緯度帯ごとの循環で3種に分けられる。極東風(Polar easterlies)、偏西風(Westerlies)、貿易風(Trade wind)※ 北半球、南半球共に3つの帯がある。季節風(monsoon)は地域で異なる。日本では、冬季には陸から海へ北西風が、夏季には海から陸へ南東風が吹く。帆船の航海には風が重要なので、昔は船乗りの経験による勘(かん)で風を読んでいたのだろうが、外洋に出た大航海では地球規模の風の影響を受ける。恒常風と季節風を読めなければ外洋の航海は成しえなかった。まさに貿易風(赤道前後30度)はこの風を利用して帆船が海を渡ったことに由来するらしい。そもそもそれら風は地球の自転に起因する。だから北半球と南半球では、極東風、偏西風、貿易風の風向は反転している。下の図はオリジナルです。図を補足するのが下です。北極・・・・極渦(きょくうず・polar vortex)極高圧帯ーーーーーー極東風(北東風)・・・・高緯度地域や極地で東側から吹く 極高圧帯から亜寒帯低圧帯に向かって吹く東風亜寒帯低圧帯偏西風(南西風)・・・・30度から65度の中緯度地域で西側から吹く 亜熱帯高圧帯から亜寒帯低圧帯に向かって吹く西風亜熱帯高圧帯ーーーーー貿易風(北東風)・・30度以下の低緯度地域で吹く 亜熱帯高圧帯から熱帯収束帯に向けて吹く風熱帯収束帯赤道ーーーーーーーーー熱帯収束帯貿易風(南東風)亜熱帯高圧帯ーーーーー偏西風(北西風)亜寒帯低圧帯極東風(南東風)極高圧帯ーーーーーーー南極・・・・極渦(きょくうず・polar vortex)地球が丸い事も自転している事も知らなかったのに、経験則から風を読み、潮の流れを読み、広い海洋に繰り出し遙かかなたの大陸まで辿り付いて世界を広げた彼ら、凄すぎる。最後におまけフォールス湾シール島自然保護区(False Bay Seal Island Reserve)先に紹介したケープ半島が囲むフォールス湾(False Bay)から写真を数枚。湾に浮かぶ大きな石? 島? はケープオットセイ(Cape fur seals)のコロニーとなっている。面積は5エーカー(2ha)。64,000頭のケープオットセイが生息していてるらしい。フォールス湾の近いビーチからでも5.7 km。船で向かい遠くから撮影。接近して撮影できていないのと、デジカメの解像度が低かった時代の写真なので拡大ができません。前回、「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」の中、「エンリケ王子の資金源」で石鹸の製造販売権の独占と言うのを紹介した。彼は王国内での石鹸の製造と販売の独占権を持っていたのだが、その材料がオリーブ油とアザラシ油脂だったと言う。アザラシとオットセイは似ているからね。まさかここから調達? ボウルダーズ・ビーチ(Boulders Beach)は枚数が増えそうで今回入れられなかった。「アジアと欧州を結ぶ交易路」まだつづくBack numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史 アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン
2022年04月18日
閲覧総数 1175
-
4
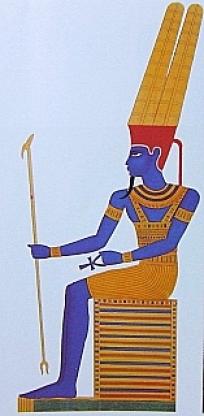
エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)
神殿紹介のつもりがやっぱり横道にそれて行ってます。(気になる事があると調べたくなるのです。)で、それたネタをなんとか盛り込もうと長くなって行くわけです・・・困ったね・・・。エジプト 14 (中王国とカルナック神殿)エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ルクソール(Luxor)中王国ら第1中間期中王国( BC2040年頃~BC1782年頃アメン神信仰カルナック神殿(Temple of Karnak)エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)エジプト中王国第11王朝時代(BC2133年頃)には都は下エジプト(ナイル下流)から上エジプト(ナイル上流)に移ります。その王朝の出身が上エジプトだからです。古王国から第1中間期下エジプトで栄えていた統一王朝である古王国は、第6王朝頃には衰退し、エジプトは紛乱期に入ります。(かろうじて第8王朝までは統一王朝を維持)ヘラクレオポリス侯のケティ1世が王を名乗り第9王朝の時に都は上エジプトに移動。歴史区分的には統一王朝ではない(第7 第8 第9 第10王朝)を第1中間期と呼びエジプト王国としてはあつかっていません。「諸侯分裂して王を名乗った」戦国時代の国盗り合戦に近い時期だったのかも・。中王国( BC2040年頃~BC1782年頃)第11王朝は古王国時代には取るに足らない一村落だったテーベ侯が王を名乗り、第10王朝とほぼ同時期に王朝を開いたようです。その中で勝ち残り、エジプトを再統一したのがメンチュヘテプ2世で第11王朝の5代目?で都は上エジプトのテーベでした。続く、第12王朝は継続した王朝なので第11、第12王朝はエジプト中王国と位置づけされています。アメン神信仰アメン神はもともとテーベ土着の大気の守護神or豊饒神だったと言われています。テーベを中心とする統一王朝を築いた事でアメン神の信仰は、太陽神のラー神と一体化して「アメン・ラー」としてエジプトの主神となって誕生します。このアメン神信仰は、末期王朝(第30王朝)までの1700年にわたり信仰されるのです。アメン(Amen)神 2枚の羽を冠した人物像として表現or牡羊として表現。「アメン・ラー」としてエジプトの主神となったので、歴代のファラオの名によくつけられています。これから紹介するカルナック神殿内に大神殿があり、アブシンベル神殿内の至聖所にも座す像があります。カルナック神殿、全図カルナック・アメン大神殿は写真上の中央に位置しています。(入り口は左)ナイル川の位置は、左側で神殿に平行するように流れています。カルナック神殿は主にアメン神を中心にして幾つかの神殿の集まった複合型の神殿で、エジプト最大の規模の神殿となるそうです。カルナック・アメン大神殿の立体想像図神殿へのアクセスは写真左上の第1塔門から入ります。古代ナイル川の船着き場から続いていたスフィンクスの並ぶ長い参道と第1塔門左の部分アメン神の聖獣雄羊の頭を持つスフィンクス・・・これだけでアメン神の神殿とわかりますね。頭の下には頭布をかぶる王の小像が彫られている。第1塔門は意外に新しくプトレマイオス朝時代のものらしい。アメン神殿より1500年以上後に造られたと言う事???幅113m高さ43m・・・実は塔門は未完成で、先程の立体想像図の門は完成予定図だったようです。第1塔門から神殿の奥をのぞむ第1塔門内第1塔門内中庭には神殿奥に向かって両サイドに列柱があり、その前にアメン神のスフィンクスがズラッと並んでいる。左が塔門側でセテイ2世の小さな神殿が見えている。パネジェムの巨像あまり詳しく神殿をする予定はないですが、長くなったので次回につづくリンク エジプト15 (カルナック・アメン大神殿)
2010年01月24日
閲覧総数 408
-
5
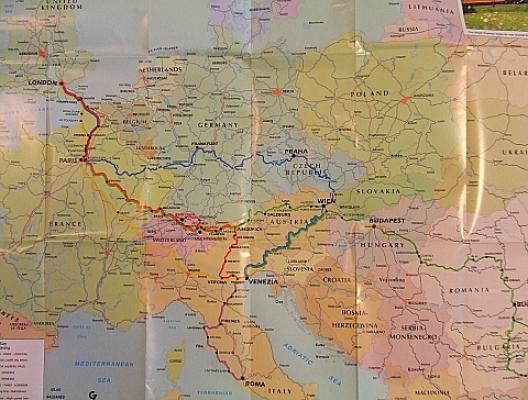
オリエント急行 1 (廃止に???)
こんなニュースで驚いたので・・シリヤライン(バルト海クルーズ) 3 は次回に繰り越しです。オリエント急行 1 (廃止に???)オリエント急行とは「オリエント急行」を名乗る会社Venice Simplon Orient Express【ロンドン時事】22日付の英紙インディペンデントによると、アガサ・クリスティの推理小説でも知られる夜行列車「オリエント急行」の運行が、今年12月に廃止される。戦争による停止や路線変更など曲折を経ながらも欧州鉄道史に輝かしい足跡を残してきたが、夜行のコスト高もあり126年の歴史に幕を下ろすことになった。オリエント急行は1883年に運行開始。1930年代の最盛時には仏パリとトルコのイスタンブールを結んでいたが、第2次世界大戦後は自動車や飛行機の発達で縮小の一途をたどり、2001年にはパリ~ウィーン間に、07年には仏ストラスブール~ウィーン間に短縮された。12月12日午前8時59分ストラスブール着の列車を最後に、時刻表から完全に姿を消す。この記事は国際夜行列車ユーロナイトの一列車としてストラスブール - ウィーン間を走行していた元祖オリエント急行が、2009年12月に廃止される事をさしています。オリエント急行とは元祖オリエント急行は、もともと国際寝台車会社であった「ワゴン・リ社」が発明した高級寝台列車がルーツです。運行は1883年。豪華な寝台車や食堂車を中心とした国際列車の中の一つで、主にパリ~コンスタンティノープル(イスタンブル)間を走行していた高級列車です。今回のニュースでは、その元祖、オリエント急行の国際寝台車会社(ワゴン・リ社)によるオリエント急行が廃止になるとの事。しかし、心配はいりません。他の会社のオリエント急行を名乗る会社の列車は存続しているので、これから乗りたい方でもオリエント急行にのれるので何も問題ありません。そもそも国際寝台車会社(ワゴン・リ社)は元祖オリエント急行と言っても、もはや路線も内容もオリエント急行とはほど遠く客足が遠のくのも当然、経営のまずさが事態を招いたような気がします。1934年に発表されたアガサ・クリスティの長編推理小説「オリエント急行殺人事件」はイスタンブール発カレー行きのオリエント急行を舞台にしたエルキュール・ポワロのシリーズの作品。このセレブ列車の豪華さもあり映画も大ヒットし、一躍有名になったのです。映画にもなりましたが、その頃がオリエント急行の全盛時代であったようです。もちろん私も子供の頃に小説を読んで、オリエント急行にあこがれた一人です。だから本家がなくなるのは微妙な気分ですけど・・。「オリエント急行」を名乗る会社もともとオリエント急行は、機関車は持たず、列車の車両(豪華寝台や豪華食堂車)のみ運行していたので、その列車を買った会社や復元した会社により、オリエント急行の車両が走ればオリエント急行になるわけです。つまりオリエント・エクスプレスは車輌の名前なのです。欧州では今も機関車による牽引の運行が多く、客車と機関車は一体ではないのです。※ 当時は蒸気機関です。オリエント急行を名乗る会社は他にもいろいろあるようです。(下は一部)ベニス・シンプロン・オリエント急行(Venice Simplon Orient Express)ノスタルジー・イスタンブール・オリエント急行(NIOE)ブルマン・オリエント急行(POE)日本人のツアーで主に使われるのが、ベニス・シンプロン・オリエント急行のLondon → Venezia (Simplon Pass)のコースです。Venice Simplon Orient Express Map of The Journeyベニス・シンプロン・オリエント急行の欧州路線マップです。ラインの色のコースがあります。青 Venzia → Praha → Palis → London赤 London → Venezia (Alberg Pass)黄 London → Venezia (Simplon Pass)緑 Palis → Istanbul → Venezia紫 Venezia → Roma → Venezia橙 Venzia → Luzern → Palis → Londonイタリアのベニス駅ベニス・シンプロン・オリエント急行の食堂車のようです。レストラン・カー(食堂車)は3両連結していて、これはグリーン・シートのレストラン。もちろんドレス・コード(服装の規定)があります。男性はタキシードかブラック・スーツです。女性はそれなりに・・。乗車時もジャケットくらい着ないと駄目です。鉄オタ・ルックでは駄目です。ブルー・シートのレストラン・カー。他にレッド・シートのレストラン・カーがあり列車の乗客は、そもそもお金持ちばかりです。朝食は部屋にコンチネンタル・ブレックファースト。おやつにケーキも来ると言うサービスも良い代わりに当然チップは必要。※ 日本と異なり、欧米ではほとんどの国でチップが必要です。それも彼らの給与の一部としてカウントされていたりするからです。キャビン・スチュアードへのチップも1人、1日40~50ユーロ。2人部屋なら100ユーロくらい払わないといけません。下は、サロン・カーです。ワゴン・リ社の設立当時、ヨーロッパの鉄道の整備は国ごとにばらばらに行なわれており長距離を想定した列車はなかったそうです。アメリカ旅行で、全て寝台車からなる長距離列車から着想を得、欧州に戻るとヨーロッパ人の好みに合うコンパートメント式の寝台車を考案採用。また独自の路線を持たず、他の鉄道会社の線路・機関車を使用し寝台車の運行のみを行なうという事業方式も考案し成功したわけです。ワゴン・リ社とプルマン社はライバル社として激しい競争を繰り広げたようですが、オリエント急行の成功によりワゴン・リ社の優位が決定的となると1886年、プルマン社は車両と列車の運行権をワゴン・リ社に売却し、ワゴン・リ社はヨーロッパの寝台列車事業をほぼ独占することに成功。このオリエント急行の成功により、ワゴン・リ社の急行列車網はさらに広がり、路線網はヨーロッパ全域からトルコ・北アフリカにおよび、またシベリア鉄道を経てウラジオストクにまで達していく。鉄道連絡船を介して日本へ乗り入れる構想もあったと言いますから驚きです。それなのに路線も小さくなって、フェード・アウトしていった所が寂しいですね・・・。つづくリンク オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)
2009年08月23日
閲覧総数 1424
-
6

カブリ島の登山鉄道(フニクラーレ)
洞窟は終わりましたが、カプリ島にはまだ見所があります。もちろん全部行ったわけではないし、ガイドブックを全てモーラしているような写真もないので、ちょっと視点を変えて少しだけ島を紹介します。この島は、小さいですが、乗り物が案外多いのです。しかも、一般的でない・・珍しい・・物が・・。そんな乗り物有りきのツアーです。登山鉄道カプリ島のフニクラーレ(FUNICOLARE)思い返してもらえば、カプリ島旅行では、すでに船だけで3種類乗っています。ナポリからの水中翼船に始まり、青の洞窟に至るクルーザー、そして、青の洞窟の手こぎボート。カプリ島の日帰りツアーの場合は、洞窟を見て、Uターンしてマリーナ・グランデに戻ったらすぐにナポリorソレント行きの船で帰るのが常なので、これだけですが、カプリ島に宿泊する人or 洞窟見学ができなかった可哀想な人達の別なコース(島内コース)です。マリーナ・グランデ到着に戻ります。水中翼船を降りたら、すぐ近くの桟橋に青の洞窟行きの船乗り場があります。もし、クローズしていたら、コースは陸に・・。写真下の真ん中、入口にアーチを持つ建物があります。玄関と言うより、ただのビルの入口にしか見えませんが、実はこれが、カプリの街に接続するフニクラーレの駅なのです。「フニクリ・・フニクラ・・」。フニクラーレは、登山鉄道です。前に紹介したように、この島の住人は海賊からの防衛の為に街を高台に作りました。カブリの街は海抜138mですから、マリーナ・グランデからカプリの街の中心であるウンベルト広場まで一気に650mを5分で登ってくれます。(この近くにミニバス乗り場があり、島内観光をここからバスで始める事もできます。)またまた小型のおもちゃみたいです。残念ながら映像はどれも正面のみで同じだったのでこれしかありません。1907年から設置されているので、案外古いですね。このフニクラーレはどうやらスイス製のようです。恐らく同じ造りと思われるスイスのピラトス鉄道の登山電車(スイスではフニクラーレとは言わない)を参考に紹介しておきます。(これはアルプナッハシュタットからピラトス行きの世界最大急勾配の鉄道です。)中は、電車の構造上傾斜があるので、段差により、5つの扉と(運転席を除く)5つのコンパートメントにステップが分けられています。1つのコンパートメントは3人座れて(車両の幅で3人分)、8人くらいが立って乗れるようです。カプリ島の登山電車は2両編成です。(すごく幅が狭いように思えますが3人座れているのが不思議です。)ところで、「フニクリ、フニクラ(Funiculì funicula)」のフレーズ、ご存知の方は多いと思いますが、これはナポリ語で書かれたイタリアのカンツォーネ(ナポリ民謡)です。1880年にトーマス・クック社(旅行会社)によって、ヴェスヴィオ火山山頂までの登山鉄道「フニクラーレ(ケーブルカー)」が敷設されると、その宣伝の為にルイージ・デンツァが宣伝用に作曲を依頼されます。「フニクリ、フニクラ」の歌は、世界最古のコマーシャルソングなのだそうです。歌詞の内容は、フニクラーレに乗った男性が、思いを寄せる女性に、告るかどうか(告白するかどうか)、行くか行くまいか、悩みまくっていると言う歌だそうです。ヴェスヴィオ火山のケーブルカーは、1944年の火山噴火で被害(破壊)にあい中止され、1990年に復活。因みに、現存する世界最古のケーブルカーは、1873年施設されたサンフランシスコのケーブルカーだそうです。下は、パンフレットより参考にデジ撮りしました。画像が悪いです。登っている映像がほしかったので・・。中央の海、マリーナ・グランデから登ってきたフニクラーレです。下は、実際に見た車外の映像です。ナポリ湾が美しいです。フニクラーレはこの後、カプリの街の中心地であるウンベルト1世広場に到着します。つづく
2009年07月02日
閲覧総数 3069
-
7

奈良散策 2 (興福寺と国宝と条坊制の都)
簡単に行こうと思ったのに迷走してしまったちょっと盛りだくさんかも・・・。前回の答えから・・・奈良県奈良、興福寺の東金堂と五重の塔でした奈良県奈良、興福寺国宝神仏分離令条坊制(じょうぼうせい)興福寺(こうふくじ)奈良・・・と言う時に紹介されるのが大仏と興福寺が上げられます五重の塔は奈良名物でもありますが、それだけではなく、興福寺は、藤原氏の氏寺であり、実は平城京への遷都の時に、飛鳥藤原京から移築された寺なのだそうです。創建は藤原鎌足(614年~669年)遷都と共に興福寺となりましたが、飛鳥から数えると推定1350年ほどの歴史を持つ寺なのです。奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一に数えられ、特に藤原氏の氏寺の為に手厚く保護され、長い歴史に数々の災厄に見舞われつつも、何度も再建され、今に残る仏像彫刻の名品(国宝)も藤原氏の勢力の賜のようです。その名品が焼失を免れて、奇跡的に今も多く残っているのです。当然、「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されてます。前回の答え・・宝物は・・たくさんありますが、特に八部衆の阿修羅像が有名です(参考)国宝館は撮影できないので本より興福寺、西金堂の仏(西金堂は現在はありません) 阿修羅像 実物 高さ153.4cm一部奈良時代、734年(天平6年) 国宝古代インドの魔神アスラは、仏に帰依して八部衆の一人、仏教の守護神となっています。興福寺、南円堂の主尊 不空羂索観音菩薩 座像 336cm鎌倉時代 1189年(文治5年) 運慶作 国宝写真左の手に羂索(金具の付いた捕縛縄)を持ち全ての衆生を救うのだそうです。運慶( ~1224年)・・興福寺を拠点に活動していた奈良仏師康慶の子で仏師。運慶の作品は現在、国宝か重要文化財である。興福寺、旧食堂の主尊(現在の国宝館の位置) 千手観音菩薩 立像 520.5cm鎌倉時代 1129年(寛喜元年)頃 国宝11面の顔と千本の手に、それぞれ一眼をもつと言われるらしいが、顔は必ずしも11面ではないらしいし、手も実際千本は無いようです。とにかく全ての衆生を漏らさず救う観音菩薩。興福寺の再興造像・・京都仏師と奈良仏師先にも触れましたが、元はかなり沢山の堂を持つ寺のようですが、1180年(治承4年)に平家の兵火により、奈良の東大寺やこの興福寺も焼亡。興福寺の再興造像は中央造仏界での勢力にしたがい京都仏師、円派、院派のほうが金堂、講堂のような主要堂塔の造像を担当奈良仏師では康慶、運慶が南円堂の本尊を担当し、本家筋にあたる成朝は食堂の本尊を担当現在残っているのは建物など鎌倉期に昔復元されたものが多いようですが、かろうじて残っている仏像のほとんども国宝で、国宝館にて展示されている仏像は圧巻です。興福寺、東金堂726年(神亀3年) 聖武天皇が叔母の病気回復を願っての建立主尊は薬師如来で、脇持に文殊菩薩と維摩居士、日光と月光菩薩の五尊で建ち、さらに十二神将と四天王、が固めた東方の浄瑠璃光世界を表現した寺なのだそうです。寺の建立にテーマがあったなんて初めて知りました・・・本格派の寺は凄い興福寺、五重の塔 国宝 高さ 50.1m室町時代 1426年(応永33年)再建、本瓦葺最初は光明皇后の祈願により730年(天平2年)に創建。現在のは6代目とか?興福寺の悲劇1868年(明治元年)に出された神仏分離令は、もともと神道と仏教の分離だけが目的で、仏教排斥を意図したものではなかったと言われていますが・・・。結果的に廃仏毀釈運動(廃仏運動)を引き起こし、春日社と一体の信仰が行われていた興福寺は直接影響を受けて、子院はすべて廃止、寺領は没収。僧は春日社の神職となって廃寺同然に追い込まれ、五重塔、三重塔さえ売りに出たと言います。1881年(明治14年)廃仏政策が反省された時、ようやく興福寺の再興が許可されたそうです。1897年(明治30年)から修復が少しずつ行われ始めていますが、神仏分離令の廃仏運動の時に、境内は塀が取り払われ、樹木が植えられて、奈良公園の一部となった姿は今もそのままで、この点がこの寺の違和感のようです。遷都1300年祭ところで、すでにご存じとは思いますが、2010年は、710年(和銅3年)に藤原京から平城京に都が遷都されて1300年目にあたる為に今、奈良では県をあげての祭りの最中なのです。王城都市プラン・・・条坊制(じょうぼうせい)平城京以前の藤原京は、実は日本史上最初で最大の都城と言われています。しかも、「碁盤の目」とも形容される「条坊制(じょうぼうせい)」による都市プランで建設された最初の計画王都なのだそうです。「条坊制(じょうぼうせい)」は、儒教の教典「周礼(しゅらい)」の説く王城の作り方に寄っていて、藤原京はこれに従って建設。これは多少変化しながらも以降平城京や平安京の建設に用いられています。京都が、「碁盤の目」になっているのは平安京の条坊制跡だからです。平城京の条坊奈良の条坊は、京都ほど残っていないようです。奈良市のメインは現在右に飛び出した一角にあります。この地図によれば東大寺は都から飛び出していて、むしろ興福寺の鬼門封じをしているように見えますね。因みに平城宮跡には現在JR奈良駅から無料のバスが出ていました近鉄奈良線が平城宮跡の中を突っ切っています。最寄り駅は近鉄の駅ですが・・。さて奈良の締めくくりは猿沢の池からの眺めです。猿沢の池と五重の塔現在は奈良公園の一部になっているようですが、昔はここも興福寺の一角だったようです。もともと捕獲した魚や鳥獣を野に放し、殺生を戒める宗教儀式(放生会・ほうじょうえ)の為の放生池として749年(天平21年)に興福寺によって造られた人工の池だそうです。周囲360mの思っていたより小さな池でした。柳でなくて松ですが・・・。この眺めは、奈良八景の一つなのだそうです。この位置からしかこれは撮影できません。なぜなら写真の右に写したくない建物が並んでいるのです。奈良も終わりです。次回またクイズ?
2010年05月13日
閲覧総数 1230
-
8
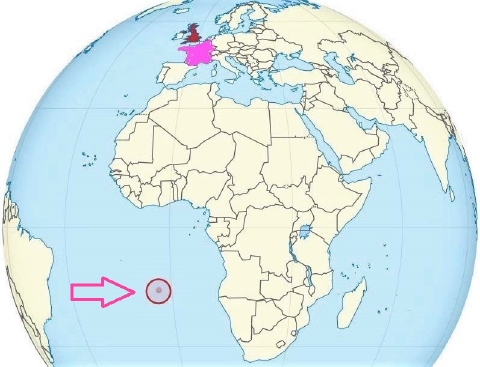
ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還
ワーテルローの戦い(The Battle of Waterloo)(1815年6月)後のナポレオンについては案外知られていないのではないかと思い、セント・ヘレナ島(Saint Helena)で亡くなりパリに帰るまでのナポレオンをちょっと紹介しておく事にしました。実はナポレオンと共にセントヘレナ島に渡った者は結構いるのです。特にナポレオンの側近として島に渡った者の中には、記録係もいるし、後に回想録を書く気満々だった人もいて、実際後に回想録が出されたりしているので島でのナポレオンの事は案外伝えられているようです。参考の為にウィキメディアコモンズからパブリックドメインの写真を借りてきていますが、オリジナル写真はパリの写真くらいです。パリの象徴とも言えるエトワールの凱旋門はアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦勝記念にナポレオンが造らせた記念碑なのです。彼は生きて完成を見る事はできませんでしたが、遺骸が祖国に戻った葬送の時に立ち寄っています。※ 凱旋門 (Arc de triomphe )の直訳は「勝利のアーチ」振り返れば、三帝会戦となったこのアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦闘こそがワーテルローの戦いの因縁になった闘いです。何しろオーストリアのハプスブルグ家を屈服させ、1000年近く続いた神聖ローマ帝国を解体。欧州の政治バランスを崩し覇権をフランスがかっさらった闘いだったからです。そしてそれはどう見ても勝利不可能な闘いでした。ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還セントヘレナ(Saint Helena)島当初のナポレオンの随行員ナポレオン最後の家最悪の医者ナポレオンの死因消えたナポレオンの本物のデスマスク遺体の返還請求Retour des cendres(灰の帰還)ナポレオンが造らせた凱旋門ナポレオンの眠るアンヴァリッド(Les Invalides)下にセントヘレナ(Saint Helena)島の位置を示しました。えらく遠くに追いやられてしまったのだと改めて思います実際、アフリカ海岸沿いに南下しギニア湾に入り西に進路をとりセントヘレナに向かった。※ セントヘレナはアフリカの海岸から1900km。ブラジルから3500kmの離島。当時は帆船。風が凪(な)いで航行できず、セントヘレナ沖に到着したのは出帆(8月9日)から67日目(10月14日)。上陸は1815年10月15日。ナポレオンの最初の感想は「気持ちの良い場所ではない。これならエジプトに残っていた方がましだった。」※ 遠征先のエジプトを密かに脱出し、フランスに戻りクーデターを起こしてナポレオンは皇帝になっている。ノーサンバーランド(Northumberland)号での航海の途中大砲に寄りかかるナポレオンNewcastle University のUniversity Library Special Collections から見つけました。※ この絵の複製は大量に販売されているようです。画家デヴッドにより大分美化された絵で宣伝されていたナポレオンですが、実際は170cmない小柄。しかも晩年は小太りしてずんぐりむっくり。一番リアル画像かもしれませんね。それにしても、哀愁(あいしゅう)感がハンパ無いセントヘレナ(Saint Helena)島島の発見は1502年。ポルトガル人によって発見され、島はヨーロッパとアジアを往復する船舶の寄港地として使われていたらしいが、本格的に入植するのはイギリスの東インド会社が補給基地としてかららしい。1660年の王政復古後、王(チャールズ2世)からの特許状を持って東インド会社は島の要塞化と植民地化を進めていた。※ 1658年建設された砦が現在のジェームズタウンそんな経緯があったから、当時の住民のほぼ半分はアフリカからの黒人奴隷だったそうです。ナポレオンが来る頃は広東貿易の寄港地として活用。当時の島の住人は5800人くらい。つまりセントヘレナ島はイギリス東インド会社が所有する大西洋上の船舶寄港地であった。下の写真は1790年の東インド会社支配下のセントヘレナ島とジェームズタウンの港を描いたエッチングです。ウィキメデイアからかりてきましたセントヘレナ島には砂浜の海岸が無い。1815年、この島にノーサンバーランド(Northumberland)号を旗艦として12隻の艦隊でナポレオンは来航する。ナポレオンを警備する名目で島には海陸の将校2181名が増えたらしい。とんでもない数である。捨て置かれた身のナポレオンにここまで経費を費やすか? とさえ思ったがやはりそれだけ大物だったと言う事なのだろう実際、英国政府はナポレオン派を警戒して島には部隊が駐屯したほか、海軍の艦船が島の周辺を警戒。また、隣の島であるアセンション島やトリスタンダクーニャ島にも英軍が派遣され警備。3000人の監視がついたとも言われている。※ナポレオンの死後、彼ら数千人の滞在者は島を去った。セントヘレナ島でのナポレオン (ウィキメディアからナポレオン救出の為に急襲されるのを恐れてか? 島には常に5隻の艦船がいたし、島の15カ所にナポレオンの状況を監視する信号所が設けられていた。散歩中、睡眠中などいちいち報告されていたようです。当初のナポレオンの随行員英国政府の計らいで、ナポレオンは3人の随行武官を選任する事ができた。武官の家族も一緒に同行。ベルトラン伯(42)・・皇帝の副官でエルバ島にも同行していた。妻ファニー。グールゴー男爵(32)・・砲兵科出身の将軍。ナポレオンを崇拝。モントロン将軍(32)・・1809年からの侍従。ナポレオンがエルバ等に流された時はルイ王朝に走り、戻ってくると再びナポレオンの元に。妻アルビーヌ。島で妊娠して出産。ナポレオンの子ではないかと考えられていたが、その子も亡くなってしまった。娘の名はジョセフィーヌ。ラス・カーズ(49)・・書記兼通訳として特別に追加。ナポレオン帝政下で枢密顧問。ナポレオンの回想録を書く気で参加。父子で参加。オマーラ(33)・・英国の海軍外科医召し使い10人・・オマーラ,ルイ・マルシャン,アリ・サン・ドニ,ノヴェラス,サンチーニら。※ 祖国フランスに残った将校らは軍法会議にかけられて処刑、投獄、流刑されている。セントヘレナでのナポレオンの住まいだったロングウッド・ハウス(Longwood House)ウィキメディアでパブリックドメインになっていた写真です。部屋室は36室。ナポレオンの住居には5つの部屋があったらしい。現在のロングウッド・ハウスはフランスがイギリスより買い取りして博物館になっているらしい。ナポレオン最後の家当初は副総督の別荘だった所を改築、ナポレオンに侍従してきた3将軍やその家族、召し使い10人、侍医、通訳などナポレオンを取り巻く人たちの家は増設され、それなりの屋敷にはなっていたようです。私たちの認識では今まで捕虜的な過酷な暮らしかと思っていましたが、行動範囲が恐ろしく限られていた事などを除けばフォンテーヌブロー宮殿の延長的な暮らしぶりだったようです。コックも居るし、ワインなども欧州や南アから美味しいのを取り寄せていたようです。何しろ貿易の寄港地なのだから結構いろんな物が得られたかもしれないですね。上の写真では清々しい感じですが、セントヘレナは気温的には悪くないようですが一年を通して曇天が多く、カビの繁殖はひどく夏には耐えられない蒸し暑さとなったようです。※ 天気の引用資料をミスりました。引用を隣の島から持ってきてました m(_ _)m当初降雨が多いとしましたが、実際は降雨は少ないけれど、一年を通して曇天が多く、湿度が高く蒸す日が多かったようです。日記にカビになやまされたとあったので露点は高くカビが繁殖したようです。セントヘレナは南半球です。夏のピークは3月ナポレオンは5月5日に亡くなったので、夏の終わり湿度は高い時期のようです。故遺体の腐敗は早く進み2日後にデスマスクをとろうとした時にはすでに困難な状況にあったようです病床のナポレオン これもウィキメディアからですが、ポピュラーな絵ですナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年8月15日~1821年5月5日)最悪の医者島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)(1769年~1844年)は、ナポレオンが逃げたら自分の責任。さらに殺されでもしたら一大事。その為に必要以上にナポレオンの行動に口を出し、ナポレオンを悩ませる元凶になった男。何より、サー・ハドソン・ローの罪はナボレオンの主治医を島から追い出した事。そして具合の悪くなったナポレオンの為に適切な医師を用意しなかった事。真の医者がいなくなり、ナポレオンの健康状態は悪化。困ったナポレオンは母に頼みコルシカ島から医者を呼んだ。それがナポレオンの最後を看取った医者アントンマルキ(Antommarchi)でありデスマスクの制作者である。が、ナポレオン自身は彼をヤブ医者と呼んでいたそうだ。※ François Carlo Antommarchi(1780年~1838年)※ アントンマルキも後に本を出している。ナポレオンはアントンマルキが無理に飲ませた当時の催吐薬(さいとやく)である吐酒石(としゅせき)により胃を余計に悪くしてしまう。飲んですぐに粘液を吐き出すほどに悪くなったのにさらに医師は吐酒石(としゅせき)を飲ませている。そして一日に何度も嘔吐を続ける状態に陥ったようだ。※ 吐酒石(としゅせき)・・・酒石酸アンチモニルカリウムの別称(K2Sb2(C4H2O6)2)「ナポレオンは殺された」よりすでに胃が食を受け付けなくなり弱り切った時に今度はイギリス人軍医により便秘の薬と言う理由で甘汞(かんこう)を飲まされる。その量は通常の10倍。甘汞(かんこう)は塩化水銀( Hg2Cl)。ナポレオンがいつも飲んでいたビターアーモンドの入った麦糖液と作用してシアン化合物が生成。2日(5月3日と4日)にわたり飲まされたナポレオンはタールのような物を排出したそうだ(上から出たのか下から出たのかは不明)そして5月5日に息を引き取った。これだけ見れば今で言う医療事故が引き金といえる。でもそもそもは体調の悪い何かがあってのこれら薬である。Death mask of Napoleon(ナポレオンのデスマスク) ウィキメディアから借りてきました。パリの軍事博物館に展示されているこのマスクはアントンマルキ(Antommarchi)の子孫の寄贈のマスクらしいです。ナポレオンの死因公式にはナポレオンの死因は胃がんと公表されている。それは先に紹介した島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)が、半ば強制的に胃がんで処理したかったからだ。万が一にも毒殺であればローの失態。責任問題である。持病でケリをつけて早く埋葬して隠したかったと言う事情があった。何しろナポレオンの体調が悪いので早く本国の医師に診てもらいたいと言う希望をローが退けてきた経緯がある。まさか本当に病気だったのか? あるいは毒殺だったら?・・と彼はおののいたのだろう。実際、ナポレオンの死の原因は何か? は非常に大きな問題である。今の科学で検査すればすぐにわかる事なのだろうが、フランス政府は遺骸の再調査の許可を出していない。その理由についてはまた色々ある。遺骸はナポレオン本人ではないかもしれないと言う不安もあるだろうが「胃がん死」が一番無難なのだろう。何にせよナポレオンの解剖はことのほか早く(24時間以内)に始まった。解剖医はアントンマルキ含む英国軍医の7人。胃の幽門あたりに潰瘍はあったらしいが、ガンが原因でない事だけはすぐにわかったらしい。問題は肝臓の肥大。しかし、これはローによって削除させられ本国には隠された。ところで ナポレオン胃がん説は、ナポレオンの父と妹が胃がんであった事から出た話であり、ナポレオン自身は生前これは胃ではないと否定しているし、「死んだら必ず解剖してくまなく調べて欲しい」と口癖のように言っていたそうだ。ナポレオン自身が不可解な体調不良に不審を感じていたのは間違いない。因みにこの時、ナポレオンの遺言で心臓が取り出され銀の容器に移されてからマリー・ルイーズに送られるはずであった。以前ハブスブルグ家の分割埋葬のところで心臓の事を紹介しているが、マリー・ルイーズがナポレオンの心臓を自分の棺に入れて眠ってくれるだろうと信じていたのかもしれない。ちょっと哀れだマリー・ルイーズは浮気して相手の子を身ごもり、ナポレオンとの間に生まれた皇子さえ捨てて、もはや完全にナポレオンの事なんか忘れていただろうに・・。※ 2018年6月「ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓」で心臓の保存について書いています。リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓消えたナポレオンの本物のデスマスクマスク造りを主導したのは英軍の六十六連隊外科医であったフランシス・バートン博士(Dr. Francis Burton)だったようだ。一応主治医であったアントンマルキであるが、彼は途中から補佐に入っただけ。バートン博士はデスマスクと胸像を作ろうとして、石膏が足りず、結局、顔面と頭頂部と頭の後ろの3つの部位の型を造り、後はパリで良質の石膏を手に入れてから作り直す予定だったと言う。ところが乾燥させている最中に肝心の顔面だけが持ち去られてしまった。理由は、すでに腐敗を初めていたナポレオンから型取りした顔ではあまりに醜く関係者には不満だったらしい。つまり当初制作したバートン博士のナポレオン像の型は消え、後にアントンマルキが別の若々しいナポレオンのデスマスクを造るに至ったようだ。そもそも、本当にアントンマルキが造ったかはわからない。造形師がいたかも・・。※ アントンマルキの新しい型からは6つのマスクが制作されたとされる。バートン博士は当然、自分に返還するよう抗議したようだが、所有権は注文主にあると主張され、最終的には英国政府もさじをなげたようだ。それ故、今出回っているナポレオンのデスマスクは、死後の顔ではなく、かなり美化された美しいナポレオンの顔なのだとされている。そもそも、ナポレオンの肖像画家であったダヴィットの描くナポレオンもかなり美化されて描かれている事は周知の事実。関係者はナポレオンの名誉を守った? と言う事なのだろう。それにしても亡くなったのが5月5日の夜。6日解剖。7日にデスマスクを採る。そして8日(4日目)には錫(すず)の棺に納められて溶接され、さらにマホガニーの棺に入れられて早い埋葬がされている。わずか2日ほどでナポレオンの体はかなり腐敗。すでにデスマスクを採るには無理があったとされているが、腐敗が進んだ理由の一つは解剖して開いたからだろう。そしてセントヘレナの暑さと湿気も進行を早めたのだろう。だからそれ故、20年後に掘りおこしたナポレオンの遺骸が、ことの外、保存状態が良かった・・と言うのが腑に落ちない。他にも理由はあるがそこに遺骸の取り替え説が浮上し、アンヴアリットに眠るナポレオンは本物か? 説が生まれたらしい。遺体の返還請求当初ナポレオンはセントヘレナのジェラニウム渓谷に埋葬された。本人の希望ではセーヌ川のほとりに埋葬してほしかったらしいが・・。ナポレオンが亡くなったのは1821年5月5日であるが、イタリアに亡命していたナポレオンの母后に知らせが届くのは7月23日。セントヘレナは遠い。ナポレオン自身が67日かけて島まで航行しているのだから・・。8月に息子ナポレオンの亡骸を返して欲しいと言う母の手紙がすくざま英国に送られた。それに対して、英国側は、フランス政府から正式な要請があれば返還の意志ありと伝えたとされるが、王政復古でブルボン王朝に返り咲いているこの時期にナポレオンがフランスに戻ることは不可能だったらしい。事情が変わるのは1840年のフランス7月革命で再びブルボン王朝が打倒されてからだ。ルイ・フィリップが王位に就くとにわかにボナバルト派の中でナポレオンの遺体を取り戻す動きが始まる。フランス政府も再び国民の中で起きているナポレオン人気にあやかるべく、公式に英国政府に働きかけることになった。ナポレオンは革命と自由の象徴として人気が復活していたからだ。英国のヴィクトリア女王も好意的であったらしいが、当時英国とフランスはアフリカ大陸の利権問題で微妙な問題もあった。それ故、この件で両国の平和維持が損なわれる問題になっては困る。お互いに譲歩しなければならない問題も含んでいた。英国としても、棺の中に本当にナポレオンが入っているか? は大きな不安材料だったようだ。確認の為に元の側近、ベルトランらが派遣されるも、万が一偽物であった場合も、英国に怒りを爆発させてはいけないと言い含められたようだし・・。Retour des cendres(灰の帰還)セントヘレナ島から船に積み込まれる棺 ウィキペディアから借りてきました。1840年7月7日、ナポレオンを連れ戻すべく船はル・アーブル港を出港。10月8日セントヘレナ島に到着。10月15日ジェラニウム渓谷の墓地で地下埋葬所の発掘が始まる。発掘作業は英国側が、しかも真夜中である。限られた関係者のみが墓に集まり、他の者は船から下りる事も禁じられ全てが秘密裏に行われた。棺の中を見ることが許されたのも数人のみ。この厳戒態勢がより皆の不審をかったらしい。さらに疑問の元になったのは1821年の埋葬時と1840年の発掘時の棺の状況の微妙な違い。加えて、英国のジョージ4世がナポレオン信奉者で1820年~25年あたりにナポレオンのミイラとなった遺骸を本国に運びウエストミンスターに置いたと言うまことしやかな話しがある。ここに英国がナポレオンの遺骸をすでに本国に運んでいたので別人でナポレオンの棺を造ったと言う説が生まれたのだろう。1840年12月14日にクールブヴォア(Courbevoie)に到着したナポレオンの棺 ウィキペディアから借りてきました棺を乗せた船はル・アーブル港からセーヌ河を遡ってパリまで到着。パリではナポレオンは葬列車に乗って市内を移動し凱旋門の下を通過。そしてアンヴァリッドへ。ウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。ナポレオンが造らせた凱旋門1806年、ナポレオン・ボナパルトの命によって建設が始まった凱旋門の完成は1836年。最初に紹介したように遺骸が祖国に戻った葬送の時に下をくぐり抜けてパレードしていますが、ナポレオンが最初に構想してから王政に移行し、再び共和制に政権が変わっているので、時の事情は建築デザインなどにも影響を及ぼしたようです。その為なのか?新古典様式とうたっている割には微妙。当初は帝政様式でデザインされてもっと装飾も多かったのではないか? と思うのです。ところで、現在は真下が無名戦士の墓碑になっているので車両の通行はできません。凱旋門は他にもありますが、放射状に道の集まるエトワールの凱旋門はナポレオンの葬送で遣われ、後にヴィクトルユゴーの遺体が安置され、第一次世界大戦の同盟国の勝利のパレード等国家的なイベントに利用される場となって行ったようです。無名戦士の墓(シャンゼリゼ方面こちらもウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。葬列はアンヴァリッドにもうすぐ到着。ナポレオンの眠るアンヴァリット(Les Invalides)オリジナル写真は外観だけですが、ナポレオンの墓地となっているパリのアンヴァリッドを紹介。これも古い写真ですが、外観は変わらないので・・正式にはオテル・デ・ザンヴァリッド( L'hôtel des Invalides)1671年にルイ14世が傷病兵を看護する施設として造った軍病院に始まり、廃兵院でもある。現在は一部軍事博物館となっているそうだ。付属の礼拝堂ドーム教会は、もともと聖ルイ(ルイ9世)の遺体安置のために建設された堂。そこに地下墓所が設けられ、ナポレオン・ボナパルト(フランス皇帝ナポレオン1世)の柩が中央に安置され、囲むようにナポレオンの親族や武将の廟が置かれている。Tombeau de Napoléon(ナポレオンの墓)私自身は中に入っていないので、ナポレオンの棺の写真を上下共に、ウィキペディアから借りてきました。建築家ルイ・ヴィスコンティによって設計されたこの墓は1861年に完成。思う以上に立派な葬列をもって葬儀が行われていたようです。ナポレオンがヒ素に犯されていたと言う問題は次回にその根拠を紹介したいと思います。Back numberリンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子 ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還リンク ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Greenナポレオン関連リンク ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠リンク ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式
2019年02月22日
閲覧総数 5747
-
9

ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓
パリのノトールダム大聖堂は、サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼の重要な起点の一つ。かつては隣接して巡礼者の宿泊所もあったらしい。※ スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela)はエルサレム、バチカンと並ぶキリスト教三大巡礼地の一つであり、そこに至る巡礼路は決まっているのである。それは四国巡礼のお遍路さんの旅に近いかも。2011年5月から「サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 」を書いています。ショートで1~14回です。事情があり、中断して中、別の物をはさみながら書いていますので6か月かかってしまいました。リンク先は3つだけのせます。リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 1(巡礼)リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 13 (聖ヤコブの棺、聖なる門)」リンク サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼 14 (ボタフメイロ・プロビデンスの眼)最初、南と北のバラ窓の写真の区別が付かなくて苦労しましたが、ちょっとした法則が解ってからはサクサク分類、一見同じに見えていたステンドグラスですが、新旧の差か? 技法の違いか? 作家の違いか? かなり異なります。写真の枚数を増やして細部を紹介したので今回も入りきりませんでした尚、写真は昔のを拾い集めているので季節も一緒くたです。一番近々に行った時はノートルダムに寄らなかったので残念な事をしました。良いカメラで撮影できていないのです。だから細部の拡大に限界があります。最もブログ用は解像度をかなり低くしているのでなおさらですが・・。ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓ノートルダム大聖堂(Notre-Dame de Paris)南の翼 側聖堂裏 側 後陣北の翼 側北翼のゲート(クロワートルのポルタイユ)ル・シュヴァリエのステンドグラス北のバラ窓前回、西の聖堂正面の紹介をしたので今回は南側面、聖堂裏、北側面とまずは外側の紹介から入ります。写真を選定する為に細部を見ていて気づいた事が幾つかありました。それはノートルダム大聖堂の一番の見所が北側とその翼にあったと言う事です。ノートルダム大聖堂ができた当初からのデザインがほぼそのまま残っている箇所が北の翼なのです。特に北のバラ窓は貴重です。(南は1841年以降の改修でできたようです。)そして今回の火災写真と照合して、南のバラ窓の上の小窓は枠ごと破壊されていて、下は恐らく無事。また北のバラ窓も恐らく無事。ただしこちらも上の小窓は枠(トレサリー)は残っているけど火災の衝撃でガラスは破損。そんな風に見受けられました。南の翼 側南の方は、前回1841年の修復問題で、ヴィオレ・ル・デュク( Viollet-le-Duc)(1814年~1879年)の勝手なデザイン変更の事に触れましたが、まさに南のバラ窓は北とは大きくデザインが異なっているのです。誰かがヴィオレ・ル・デュクのデザインは偽ゴシックだと言ってますが、確かに南のバラ窓の枠はゴシックの意匠ではありません。内部のステンドグラスからだけだと解りかねますが・・。こちらはゴシック(Gothic)ではなく、例えるならレース編み(Lace knitting)のデザインのバラ窓の枠(トレサリー)です。残念ながらこちら南の翼のポルタイユは至近撮影できませんでしたが、聖ステパノに捧げられたポルタイユ(Portail du St. Etienne)がある。大聖堂建設前からここが聖ステファノ(St Stephen)に捧げられた聖域だったそうだ。聖ステファノはキリスト教、最初の殉教者である。確認していないが、ポルタイユのティンパヌム(tympanum)だけは13世紀の物らしいが、その周りやトリュモーの像などは19世紀の作品。尖塔の拡大写真がなくて残念でした。尖塔は意外にも鉛でてきていたそうです。火災で焼け落ちたのも道理。そしてその為に鉛害が発生しているらしい。(ステンドグラスも鉛で留められているけどね。)また、屋根の上、尖塔基部を囲むように1841年以降の修復で12使徒らの像が付加されていた。問題は、その聖人のモデルに自分を含む仲間達がモデルとなっていた事だ。屋根の上にいる12使徒の1人、聖トマス(Thomas the Apostle)のモデルはヴィオレ・ル・デュク自身らしい。聖トマスは建築の守護聖人だから自らを重ねたのかもしれないが、同時に聖トマスは変わり者でもあった。聖画では、イエスが刺された脇腹に本当か? と手を突っ込んで確かめたと言うエピソードがあり、疑い深い人でもあったようだ南側のバラ窓も前回紹介した1841年以降の修復でヴィオレ・ル・デュク( Viollet-le-Duc)(1814年~1879年)により新たに造られた火災後の写真で確認できる限りだが、上の小窓のステンドグラスは枠も破壊されていた。後で比較を載せるがヴィオレ・ル・デュクはなぜ北と違うデザインのバラ窓にしたのだろう。13世紀当初に復元するのが元の計画だったのに・・。聖堂裏側 後陣聖堂裏にあるジャン(ヨハネス)Jean-XXIII(23世)公園から撮影手前にあるのは1844年に建てられた聖母の噴水(Fontaine de la Vierge)かつては、この位置に大司教館が建ち並んでいたが、1789年の革命時に教会の全財産は没収。1831年、反王党派の者らにより破壊された。ノートルダム大聖堂はフランス革命のあおりで、一度滅亡していたのである。それにしても、昔からパリ市民はかなり気が荒く、暴力的だったらしい。かつて王の居城は同じくシテ島にあったが、暴動で王の寝室まで乗り込んだパリ市民により目の前で侍従が惨殺。王はショックのあまりシテ島の王宮を捨てている。北の翼 側ノートルダム創建の初期の姿が最も残っている部分。ポルタイユのゴシック装飾の切妻型のデザインなど正面ファサードの簡素さとは違って見事である。直径13mのバラ窓は正面ファサードのバラ窓よりも大きい。その下の長い窓と合わせると採光部は18mに達する。それは1248年、先にできた王宮に付随するサント・シャベルの経験が生かされ、より袖廊より採光が取り入れられるよう研究された結果らしい。※ サント・シャベルは、2017年2月「フランス王の宮殿 1~2 (Palais du Justice)」で書いています。リンク フランス王の宮殿 1 (palais de la Cité)リンク フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)北翼のゲート(クロワートルのポルタイユ)昔、教会北側(入口からは左手側)に高位聖職者の宿舎(舘)が建っていた事から北翼の入り口はクロワートルのポルタイユ( Portal du ]Cloître)と名前が残っている。クロワートルのポルタイユ( Portail du Cloître)とは直訳すれば回廊の門である。察するに、高位聖職者の舘は隣接していて、回廊でノートルダム寺院の北翼のゲートまで続いていたと思われる。※ 古い大きな教会ではよくある造り。※ ノートルダム回廊通り(rue du Cloitre Notre Dame)と前の通りに名前も残っている。このクロワートルのポルタイユは古く1250年、ジャン・ド・シェル(Jean de Chelles)の製作。ジャン・ド・シェル(working 1258年~1265年)は、ノートルダム寺院の建設に携わった複数のマスターメイソン(master mason)の1人で彫刻家。彼はいろんな大聖堂建設で指揮をとっている。※ マスターメイソン(master mason)は石工、フリーメイソンを束ねる親方。フリーメイソンの階位は上から、グランド・マスター、マスター(親方)、フェロー・クラフト(職人)、エンタード・アプレンティス(徒弟)となっている。※ 中世の本物のフリーメイソンと現在のフリーメイソンは全くの別団体。何カ所かで説明しています。リンク 神眼・・・プロビデンスの眼リンク 2013.9 クイズこのロゴは何? 解答編 秘密結社? フリーメイソントリュモーにあるマリア像は元は聖母子像だったそうだ。革命で幼子イエスの部分が失われたらしい。マリアの繊細な微笑みと気品。13世紀の最高傑作らしい。ル・シュヴァリエのステンドグラスステンドグラスは、やはり定期的に大きく換えられているようだ。資料でわかる範囲では、18世紀に、中世の物に変わって百合の花をあしらった白ガラス方式。(百合はブルボン王家の紋章)19世紀にグリザイユ方式。1965年、現在のステンドグラスは、ル・シュバリエ(Le chevalier)の手により中世の製作法と色彩が復活されている。※ ジャック・ル・シュヴァリエ(Jacques Le Chevallier)(1896年~1987年)は美術学校で学んだアーティスト。彫刻家であり、国立美術学校のステンドグラス・コースの教鞭もとっていたステンドグラスの第一人者。Union of Modern Artists設立メンバーでもあり、本来はモダン・アート専門だったのかもしれないが、ステンドグラスアーティストとして、また、デコレーターとして彼は多くの国内外の聖堂のステンドグラスを手がけている。しかし、修復は壊れたところが優先される。実際ル・シュヴァリエがどの部分を修復したか解らない。聖堂バックヤード、上方のステンドグラスステンドグラスに関しては解像度を少し上げました。ちょうど中心にキリストと聖母マリアのようです。素敵な絵です。火事後の写真で見るからに、これらは生き残ったようです。このあたりはル・シュヴァリエ作品かもしれない。北側袖廊北側のバラ窓13世紀のスタイルがほぼ残っているようです。それゆえ、採光は弱い北側ですが、見どころは本来こちらのバラ窓です。南のステンドグラスと異なり、トレサリーなどもちゃんとしたゴシックのバラ窓です。中心には聖母子、その周りには16人の聖人が描かれている。16人? 12人じゃないので誰が選ばれているのか不明。こちらはかなり古いステンドグラスかもしれません。マリア様がちょっと険しい顔してます。バラ窓の下に並ぶ縦長のステンドグラス。合わせて窓の開口部が非常に広く、建築的にも難しい部分。それなのにずっと破壊から守られてきた北側翼です。北のバラ窓下のランセット窓 (Lancet window) 並ぶのは18人。でも聖人ではないようです王冠を被り、ユリの王笏(おうじゃく)を持っているので、おそらくフランス王です。カロリング朝、カペー朝と続く歴代の王が描かれているのかも・・。前に書きましたが、パリ・ノートルダムの建設費は王室もかなり出している。それ故、王室につながっている部分も大きく、フランス革命の時には市民に目の敵にされたのかもしれません。行った事が無い方も行った気になるよう写真を多く載せる事にしました。その為にまた押し出されました。次回、南のバラ窓とキリストの冠について触れて終わる予定です。結局、全4回ですね。f^^*) ポリポリ Back numberリンク ノートルダム大聖堂の悲劇 1 奇跡のピエタリンク ノートルダム大聖堂の悲劇 2 1841年の改修問題 ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 4 南翼のバラ窓と茨(いばら)の冠
2019年05月18日
閲覧総数 2149
-
10

アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル
ラストにBack numberを追加しました。やっと大航海時代に突入です。当初、ここが2回目くらいの予定でしたなんだかんだと深く掘りおこし過ぎた感もありますが、歴史は繋がっているので過去から段階的にやってきて良かったかも知れません。私達が習ってきた世界史はポイントだけ。繋ぎの歴史が無いからいきなり展開? いきなりその部分だけをクローズアップしても本当の意味は解らないと言う事がよく解ったからね。さて、大航海の時代に入る前に過去ログを少しおさらいしつつ、大航海時代の道筋を簡略に説明。「アジアと欧州を結ぶ交易路 」リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦ローマ帝国が衰退し、パレスチナや北アフリカがイスラムの勢力に塗りつぶされて行くと、もはやローマ帝国時代の地中海を中心とした華やかな交易は消滅していた。しかも穏やかであった地中海もイスラムの海賊の狩り場となり地中海の島々ばかりか、フランスやイタリア南岸のキリスト教徒らの街は襲われ、人はさらわれ奴隷にされた。激しく治安が悪くなった時代が数世紀。「暗黒の中世」と呼ばれる時代が到来する。8世紀頃になると、自国の商船を守りながら護衛をして地中海交易に乗り出す港湾都市がイタリア半島から複数誕生する。それが「海洋共和国(Marine Republics)」である。海洋共和国は11世紀に始まった十字軍遠征の恩恵を受けてどこも最盛期を迎える。聖地やパレスチナの十字軍国家に物資を運ぶと共に巡礼者を運んだからだ。だが、十字軍特需による恩恵は聖地が再びイスラムの元に包囲されると一気に失われた。彼らは時にイスラム商人とも取引したし、パレスチナや黒海の向こうから来る東洋の物産を仕入れては欧州に運んだ。そんな海洋共和国の中でも長きに渡り生き残ったのがジェノバとヴェネツィアである。特に両者の海運力は抜きん出ていた。以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)」でも書いているが、リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)1453年、東ローマ(ビザンツ)帝国の帝都コンスタンティノポリスがオスマン帝国により陥落すると西側の交易事情は大きく変わった。ボスフォラス海峡がイスラム支配圏になると以前のように通れなくなり黒海に入れ無いと言う事はシルクロードで運ばれる東洋の物産も手に入らなくなる・・と言う事だからだ。※ シルクロードで運ばれた荷は黒海南岸の街で船に乗った。西側諸国にとってコンスタンティノポリスを経由しない新たなルート開拓が急務となった。もちろんイスラムと取引した海洋共和国はあったが、結果論として、東洋を繋ぐ唯一のルートが閉ざされた事は大航海時代を迎える要因の一つとなったのは間違いない。同時にアドリア海の交易不振は急速に進んだのだろうと思われる。その頃はパレスチナから北アフリカは完全にイスラム支配下にあり、地中海でさえ、イスラムの海賊が闊歩して安心して航海できない現実があったからだ。ただ、海洋共和国ヴェネツィアだけはイスラムと取引。かつジェノバを負かし、東地中海交易を独占する事になる。※ レパントの海戦ではイスラムと戦ったヴェネツィアであるが海戦後(1573年)に再びイスラムと取引して交易を続けた。リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦ヴェネツィアの船は最後まで東地中海交易に特化。1380年、キオッジャの戦い(Battaglia di Chioggia)に負けたジェノバは1381年のトリノ講和会議で完全に利権を失ったから、結果、東洋貿易においては、最終的に黒海の制海権を全てヴェネツィアが独占する。他方、ジェノバは生き残りをかけて新たな道を模索せざるおえなくなった。そもそもヴェネツィアは交易による関税が主な収益であったから貿易一筋的な所があった。対してジェノバは当初からローマ教皇の為に働き、見返りに利権を受けたり植民都市を得て利益をあげていた。※ イスラムの勢力拡大と共にたくさんあったジェノバの植民都市も次々失われていた。地中海での交易の限界? 負けたジェノバは地中海交易に見切りを付け新たな商機を求め外洋に絶えられる船を造作して北海への航路を開拓。ジェノバはジブラルタル海峡(Strait of Gibraltar)を越えて北にルートを取りハンザ同盟で栄えていたフランドルのブルージュへ定期航路を持つ。売れ筋の高額商品であるフランドルのタペストリーはポルトガル王女の嫁ぎ先の品だ。ポルトガルはそれらを独占して仕入れていたのでポルトガルとジェノバの関係は深くなる。多くのイタリア人がポルトガルの港に移住してきたそうだ。以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中でヴェネツィアに地中海交易を取られた後のジェノバを紹介している。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊そこでは西への商路拡大と共に神聖ローマ皇帝カール5世(1500年~1558年)のガレー船を請け負ったり、スペインと同盟を結んだ事など紹介しているが、それ以前の14世紀以来、ジェノバはポルトガルの海洋進出にも力を貸していたのである。つまり、ジェノバは海運国としてのノウハウを輸出。また資金の貸し付け業もしていた。海運国なので当然造船技術はある。ヴェネツィアもたくさん船を造って売っていたが、ジェノバは造船だけでなく、航海士の育成の為の学校もあり、船も人(航海士)も航海技術も、また精度の高い海図なども早くから輸出していた。1317年にはポルトガル王はジェノバの商人をリクルートして商売や海運を学ぶと、その100年後には有数の海運国にのし上げている。ポルトガルが海洋国家になる一歩は間違いなくジェノバのおかげであった。今回写真はポルトガル関連、セウタ(Ceuta)が多めです。かつてポルトガルのエンリケ王子が侵攻して得た北アフリカのセウタは、ある意味大航海時代を迎える要因の一つになったのではないか? セウタ侵攻の意味も含めてエンリケ王子の紹介をします。ところで、セウタは現在スペインの所領になっています。アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル大航海の前章発見のモニュメント(Padrão dos Descobrimentos) ベレンの塔(Tower of Belém)ジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jerónimos)バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の石棺インド航路発見のの探検隊イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)海洋王国ポルトガルの誕生長子制度と3つの騎士団ポルトガルの海外進出、セウタ(Ceuta)征服モンテハチョの要塞(The Fortress of Mount Hacho)セウタの王室城壁(The Royal Walls of Ceuta)セウタ十字軍? サンフェリペ壕(Moat of San Felipe)大西洋上の船舶寄港地と植民地大航海の前章地中海を出て大海洋へ乗り出した大航海の時代、表の主役は一気に変わる。海図を書き換え地球が丸かった事を証明したのはジェノバでもベネツィアでもなくポルトガルとスペインなのである。新たな海洋国家の出現による海洋交易の主役の変更はイベリア半島で起きていたレコンキスタ(Reconquista)に大きく関係していた。(後で詳しく紹介)ポルトガルは先に紹介したよう1400年初頭にはすでに海運国となっていたが、これもレコンキスタと無縁ではない。アラゴン・カステーリャ連合(後のスペイン帝国)はイベリアに残っていた最後のイスラムの国(グラナダ王国)を陥落した。その1492年以降、本格的に海事に参戦する事になる。コロンブスにGo sign を出したのはカスティーリャの女王イサベル1世(Isabel I de Castilla)だったのである。コロンブスおかげでスペイン帝国(カステーリャ王国)は新たな海洋国として仲間入りする。※ イサベル1世の夫はアラゴン王でありカスティーリャ王でもある。※ 世界史では、1492年のグラナダ王国陥落以降をスペイン帝国と呼ぶ。スペイン帝国は西に航路をとり大西洋を横断した。コロンブスの功績でスペインは新地を発見し、スペイン帝国は多くの植民地と富を手にする事になる。「太陽の沈まない国」と形容されるほどに・・。但し、スペイン帝国と言えど、海運はカステーリャ王国が独占したし、資金は借りていたので全ての利益を手にしたわけではなかった事も判明。(後で詳しく紹介)ポルトガルは中東の市場の豊かさを知り、アフリカを南下するルートからインド洋を目指した。イスラム商人を介さず、何とか直接仕入れができないか? 北アフリカの探検隊も出している。当然、船も変った。海洋を越える長距離の航行できる船体の開発が必要不可欠だったからだ。とりわけエンリケ航海王子の貢献は大きい。ポルトガル南部のザグレスに航海学校を設立。そこでは船の造作、航路の開拓から海図の作成もしたし、天文台を置いて星の観測も余念なくした。実際に船を出して、少しずつ航海図を書き足して道を開いたボルトガル。エンリケ王子が求めなければできなかった事だ。エンリケ王子がなぜ海洋越えをめざしたのか?そこにも複数の理由が存在するが、大きくはポルトガルと言う国の立地からの領有地の拡大と収益問題につきるだろう。それは1415年、セウタ(Ceuta)攻略の根底にもある。北アフリカを押さえ、インドとの交易につなげる事が最大の目的であった。セウタ侵攻には北アフリカのレコンキスタと言う側面も確かにあった。だが、セウタ侵攻に経費がかかった上にそれ以上広げられなかったし、維持費もかかった。諸侯に与える報酬も無しではすまされない。そして、1434年、ポルトガルがボジャドール岬(Cape Bojador)を越えた時、道は開けた。カナリア諸島ついでにマデーラ諸島とアソーレス諸島を発見しポルトガルは植民地を得た。※ カナリア諸島の利権は当初は個人。後にスペインが参入。(1479年最終決着)ポルトガルは海を越えて領地を求め続けたのである。むろん、そこには未知に対する多大な好奇心もあったであろう。伝説ではボジャドール岬より先に世界は無いはずであったから、船乗りにとって越えられない壁であった。ボジャドール岬越えの衝撃は、大航海時代の本格的スタートとなる。※ ボジャドール岬はカナリア諸島南東240km現在の西サハラ海岸にある。それまで、地球が球体で在ることを皆知らなかった。ボジャドール岬を越えた船はどこまでも進み新地を見付けた。※ ポルトガルは1488年にはアフリカ大陸南端の喜望峰まで到達する。1494年、トルデシリャス条約が締結される。これから獲得するであろう西の領土をスペインが、東の領土をポルトガルが得る事を教皇が認めた裁定だ。地球が丸い事が解ると、裏側にも協定線ができた。(サラゴサ条約)先住民がそこにいようと、世界の未発見の土地は、先に見付けた国が権利を有するとローマ教皇が裁定したから、我先にと大航海の競争が始まったのである。ポルトガル、リスボン、ベレン地区発見のモニュメント(Padrão dos Descobrimentos) 東側キャラベル船の船首をモチーフにした大航海時代を記念したモニュメントで1940年にポルトガルで開催された国際博覧会の為に制作された。高さ52m。その後1960年にエンリケ航海王子没後500年の記念の時にコンクリートで造り直しされている。モニュメントの東側先端に立つのがエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)。手には大航海の為に制作されたカラベル船(Caravel)の模型を持っている。※ カラベル船はポルトガルとスペインの探検家らに愛用された船。次がアルフォンソ5世(Afonso V)(1432年~1481年)その次がヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)騎士がいて、その次にブラジル発見者、その次がマゼランらしい。モニュメント西側探検家、芸術家、科学者、地図制作者、宣教師などモニュメントは西側と東側合わせて30人。左から兄ペドロ(Pedro de Portugal)(1392年~1449年)エンリケの母でジョアン1世の妃フィリパ(Philippa of Lancaste)(1359年~1415年)右の巻物を持っているのがルイス・ヴァス・デ・カモンイス(Luís Vaz de Camões)(1524年頃~1580年)。作家で航海に同行して「ウズ・ルジアダス(Os Lusiadas)」を執筆。それはポルトガルの大航海における栄光の記録を叙事詩で壮大に描いた作品らしい。発見のモニュメントは後ろから見ると十字になっていて、さらに十字架がデザインされている。これは騎士団の意味があるらしい。そう言えばエンリケ王子はキリスト教騎士団(前身はテンプル騎士団)のマスターであった。モニュメントの手前、モザイクで描かれた方位図中心の世界地図に各地の発見年号が記されている。上空からの撮影なのでウィキメディアから借りました。ベレンの塔(Tower of Belém)サン・ヴィセンテ(San Vicente)が正式名称で、リスボンの守護神の名前らしい。もともとエンリケの時代には川の中にあったと言うサン・ヴィセンテ(San Vicente)要塞。テージョ川を航行する船の検問を行っていた。1515年~1521年にかけてヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)のインド航路発見(1498年)を記念してポルトガル王マヌエル1世(Manuel )(1469年~1521年)により再建されたものである。※ ヴァスコ・ダ・ガマは、ここから航海に出た。とは言え、当時リスボンの港には海賊が多発していて、リスボン防衛とテージョ川に出入りする船の監視が目的での再建であったから、全てのコーナーに守備の塔や砲台が備えられている。五層式の建物で、3~5階は王族の居室。東洋からの帰国船の謁見にも使われた。塔の下は塩の満ち引きを利用した水牢(すいろう)になっていたと言う。1983年に「リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔」合わせてユネスコの世界文化遺産に登録されている。共にマヌエル様式(Manueline style)と言われる装飾の用いられた特徴的建築故と思われる。ポルトガルでの後期ゴシックに入るようだが、航海事業の拡大による文化の影響か? 非常に多文化の要素が組み込まれた特殊性はマヌエル王の時代の特徴らしい。レコンキスタ後のスペインやポルトガルでは残留イスラム教徒(ムデハル)らの職人によるイスラム的な建築様式が生まれている。それにさらに複数の要素が組み込まれたもの?ジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jerónimos)ポルトガルの大航海時代の最盛期の王マヌエル1世(Manuel I)(1469年~1521年)によって着工(1502年)された。こちらはエンリケ航海王子の偉業を称えての建立らしいが、こちらも建築資金もまたバスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)が道を開いたインド航路によりもたらされた富が活用されている。発見のモニュメントの所から撮影した写真。全景を入れるのは遠くないと無理。中央から左が修道院の回廊で、現在は国立考古学博物館になっている。塔は教会の尖塔で、そこから右が修道院付属? のサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)である。下の写真はウィキメディァからかりました。手前が教会。ジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)こちらもマヌエル様式と呼ばれる特徴的な装飾が見所。大部分は1511年にできていてたものの王の逝去など時世もあり、最終的に完成するまで300年かかったと言う。不思議なゴシック。独特な柱。正確にはジェロニモス修道院に隣接するサンタマリア・デ・ベレン教会(Igreja de Santa Maria de Belém)です。バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の石棺ここにはバスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)の石棺が置かれている。石棺は棺を納めるサルコファガス(sarcophagus)。つまり外容器。彼はインドで亡くなり、ポルトガルに戻りヴィディゲイラ(Vidigueira)で一度埋葬され、後にジェロニモス修道院に移動されたと言う。写りの良い方の石棺の写真にオーブ(orb)が現れていたのでこちらにしました。王族や貴族にしか与えられないドン(Dom)の称号と年金を与えられた。つまりポルトガル貴族の仲間入りである。ポルトガル領インドの副王及び、航海士ヴァスコ・ダ・ガマの肖像ウィキメディアより借りてきました。第一回航海の後、シネスの土地(town of Sines)を王より与えられたが、これには問題が起きた。ヴァスコ・ダ・ガマはサンティアゴ騎士団の1人であったが、シネス(Sines)がサンティアゴ騎士団の領地であった事からもめたらしい。その為にキリスト騎士団に移籍? 1519年にはヴィディゲイラとフラデスの町が与えられ、今度はヴィディゲイラ伯爵の称号を与えられた。1497年、リスボン港からヴァスコ・ダ・ガマ、インドへ出発 の絵画 ウィキメディアから借りました。画家 Roque Gameiro(1864年~1935年) 1900年画リスボンのまさにベレンの塔の辺りから乗船し、出発した。すでにジョアン2世は亡くなりりマヌエル王が次代を継いでいた。反対派も多い中、インド航路開拓のGo Signをマヌエル王(1469年~1521年)は決断。これは国が立案しての計画。ヴァスコ・ダ・ガマ(1460年頃~1524年)には4隻の船と170名の乗員が与えられた。ヴァスコ・ダ・ガマのサン・ガブリエル(San Gabriel) 船は178tのキャラック(Carrack)船。全長27 m、幅8.5 m、喫水2.3 m、帆372 m新造されたキャラック船(Carrack)2隻にはヴァスコ・ダ・ガマと彼の兄が乗り、少し小さいキャラベル船(Caravel)と補給船の4隻。(帰還したのは2隻55名)小国ポルトガルには分不相応の大冒険を国家が特に王が推進しての出航であった。ところで、経験豊富な航海士候補が複数いる中で、なぜヴァスコ・ダ・ガマ兄弟に決定したのか? は不明。ヴァスコ・ダ・ガマ第1回航路ウィキメディアより借りてきました。(Indiaは足しました)喜望峰に到達するまでに、ヴァスコ・ダ・ガマは大西洋のセントヘレナ島まで流されている。無駄に航行しているのでその距離は赤道の距離(40,075km)より長かったそうだ。※ 南アフリカのモッセルベイ(Mossel Bay)で補給船? が沈没している。インド航路発見の為の探検隊ところで、中東からもたらされる香油や、アジア方面からもたらされる香辛料の生産地を西側の人間は知らなかった。それはアラブ人が秘密にしていたからだ。いわゆる東洋貿易がヴェネツィアの独占となり、アラブ人から仕入れるにしても値段は非常に高かったから、産地が解れば直接出向いて取引したいと思うのは最もな話し。ポルトガル王ジョアン2世(João II)(1455年~1495年)は中東に探りの探検隊を出していた。地中海からロードス島経由でアレクサンドリアへ、コビリャン(Covilhã)(1450年頃~1525年頃)とアフォンソ・デ・パイパの2つの隊。目的はアラブ人が仕入れているインドの香辛料の市場の特定? そして当時話題になっていた異国のどこかにいるキリスト教徒の王(プレスター・ジョン・ Prester John)を捜す事。また、船でアフリカ大陸を南下して進むコースの探検にはバルトロメウ・ディアス(Bartolomeu Dias de Novais)(1450年頃~1500年)を向かわせた。彼は1488年、ヨーロッパ人として初めて喜望峰に到達。これもまたインド航路開拓の1つとなった。因みにディアスは遭難して偶然発見した経緯から「嵐の岬」 と報告したらしい。喜望峰と命名されたのは、これから先に可能性が秘められていると言う希望?とか喜びかららしい。1488年、コビリャン(Covilhã)(1450年頃~1525年頃)は船でさらにインドのカナールへ。パイパはエチオピア方面に向かうが、途中で客死。コビリャンはインド南のマラバール海岸(Malabar Coast)でムスリムの動向を1年程観察。彼らは2月にモンスーンを利用してペルシャ湾や紅海に船を出している事を知る。またアフリカからインドへ渡る航路があるかを調査し、報告書を送っている。コビリャンのこうした調査がインド航路の発見、すなわち航行可能な海図が描かれ、バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)の実際のインド航路発見に繋がるのである。因みにコビリャンは紅海からカイロに戻った所でパイパの死亡を聞く。パイパの代わりか? 彼もまたエチオピアへ向かう。それはジョアン2世からの指令で今度はプレスター・ジョンを捜す事にあった。コビリャンはムスリムに変装して旅を続け、エチオピアでコプト教会を発見。そこが伝説のキリストの王の国か?コビリャンはそこの王に気に入られ? 帰国を許されず30年そこで過ごし亡くなった。イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)ポルトガルやスぺイン帝国が海洋の先に目を向けたのはイベリア半島内でのレコンキスタが完了し、イスラムとの戦いが終結した事に起因する。レコンキスタ(Reconquista)とは何か? の解説を入れましたイベリア半島を西ゴート王国(Regnum Visigothorum)(415年~711年)が支配していた時代、レカレド1世(RecaredoⅠ)(559年頃?~ 601年)(在位:586年~601年)王の時にキリスト教国となった。(589年)が、711年にイスラムのウマイヤ朝がイベリア半島を侵略し、西ゴート王国は滅亡する。この時、イベリア半島はイスラムの勢力下に置かれた。以降、イベリア半島をキリスト教の地に取り戻すべく戦いが始まる。キリスト教徒による再征服活動(戦い) がレコンキスタ(Reconquista)である。北に逃れた西ゴート王国の貴族Pelayoがイベリア半島北部にアストゥリアス王国(Reinu d'Asturie)(718年~910年)を建国して抵抗をみせた。キリスト教徒による奪還の為の抵抗戦、レコンキスタ(Reconquista)はこの時を開始とするらしい。※ アストゥリアス王国は、後に国名をレオン王国(Reino de León)(910年~1252年)に改名。終わりは? 再征服するまでを指すので、それはグラナダ(Granada)王国陥落。ナスル朝の滅亡1492年までのスパンが該当とされる。イベリア半島をオセロに例えてみよう。キリスト教徒を白、イスラム教徒を黒とする。キリスト教国、西ゴート王国の滅亡した時点で9割は黒になった。そこから再征服活動は開始。グラナダ陥落は最後の黒のピースを白に変えた戦いである。イベリア半島を完全に白(キリスト教)の国に戻してレコンキスタは完了する。但し、このキリスト教国は1国ではない。グラナダ攻略でスペインはポルトガルの介入を許さなかった。だからポルトガルはジブラルタル海峡を押さえる意味もあり北アフリカのセウタを攻略した。※ 北アフリカはまだイスラム教徒の世界。レコンキスタを北アフリカに広げたと解釈もできる。因みに、レコンキスタの過程では、フランク王国のカール大帝も参戦している。フランク軍は地中海側からも侵攻し801年にはバルセロナを攻略。865年、フランクはバルセロナ伯を置いて、カタルーニャを統治。欧州の中からイスラムを追い出す事はキリスト教徒全員の願いであった。以前ブルゴスの所でカスティーリャ 王国の騎士でレコンキスタの英勇エル・シド(El Cid)(1045年?~1099年)を紹介した事があるが、キリスト教徒軍が本格的に巻き返しを始めるのは10世紀頃ではないか? と思う。リンク ブルゴス(Burgos)番外編 エル・シドちょうど十字軍が始まった頃で、欧州全体がイスラムに反撃を開始した頃、イベリア半島内部で再編が起き11世紀には複数の所領? 王国が確認できる。13世紀半ばにはグラナダを残すのみとなっていたが、難攻不落のグラナダは最終的に1492年にやっと陥落。そのグラナダを陥落させたのはカスティーリャ王国(Reino de Castilla)(1035年~1715年)で、女王イサベル1世(Isabel I de Castilla)(1451年~1504年)(在位:1474年~1504年)の時。戦場に出たのはアラゴン王の夫である。因みに、コロンブスは自身の計画のスポンサーになってくれるようグラナダ陥落で気を良くした女王イサベル1世に願い出る。コロンブスは、インディアスを求め大西洋を越える航海に旅立つ許可をカステーリャ(スペイン帝国)で得たのである。※ コロンブスの話しは次回改めて入れます。海洋王国ポルトガルの誕生「アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊」の中、「アルセナーレ(Arsenale)造船所と4th Crusade」の所でダンテの時代にはヴェネツィアのアルセナーレ造船所はすでにヨーロッパで最も重要な造船所となっていたと紹介したが、同じ頃、海洋共和国ジェノバも自国造船していた。しかもジェノバには航海士育成の学校もあったのだ。そしてそれら技術は早くからポルトガルの海事発展の為に貢献?ポルトガルが海洋王国を目指したのは1317年頃、第6代ポルトガル王ディニス1世(Dinis I)(1261年~1325年)(在位:1279年~1325年)の時である。ディニス1世は経歴をみるとなかなか有能な人物だ。王権強化の為、土地台帳を細かく作り貴族の領主裁判権を制限、逆に相続法を改定して貴族の、また聖職者の権力抑制した上で様々な事業も立ち上げ、大学も創設。ポルトガルと言う国の基礎を造っている。何より海運の発展に力を注いだ事は功績だ。ディニス1世はジェノバの商人を役職に就け、海運事業の発展に貢献させている。当初は有能な船長や航海士を引き抜いて、王室所用の帆船を指揮させ運営した。ジェノバとの関係はかなり密でジェノバからの移住者には金融業者など銀行家もいた。海運事業が発展すれば商機は増えるからイタリア中の商家がポルトガルを目指した。フィレンツェからは地中海貿易の商家バルディ家がポルトガル領内でも営業をした。そうなると信用制度や為替手形などの金融システムなどもポルトガルに持ち込まれる。要するにジェノバを中心としたイタリア人らの力によりポルトガルは急速に発展して行く事になる。そもそもBackにはポルトガル王がいるのだ。王が商人を率いて事業を率先して行っているのだから商売は円滑に成功して行ったに違いない。※ ポルトガルも領内に割と早く自国の造船所を持った。カスティーリャ王ペドロ1世の庶子? 第10代ポルトガル王ジョアン1世(João I)(1357年~1433年)(在位:1385年~1433年)の時代にはポルトガルの港に400~500隻の船が出入りするほどの海洋王国になっていたと言う。地中海交易の中心は西に移動しつつあった。ポルトガルの商船は北はノルウェー、南はジブラルタル海峡を越えて北アフリカの港に及んでいた。オリエントやアフリカから香辛料、貴石、真珠、オリーブ、ワイン、ナツメヤシの実などを輸入し、北ヨーロッパに転売。※ この頃、穀類不足も起きていたと言うのでパンやヘーゼルナッツ、果物も売った。逆にイスラムにはフランドルのタペストリー(毛織物)、欧州産の馬、チーズ、バター、漁獲物、武器、木材、鋼(はがね)などを売ってもうけた。※ マデーラ諸島とアソーレス諸島が植民地となると小麦、ワイン、染料など生産。それは西アフリカにも売った。ところで、ジョアン1世はエンリケ航海王子の父でもある。以前「金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)」の所で紹介しているが、ジョアン1世とイングランドから嫁いできた王妃の元で子供達は男女に関係なく、外国語、数学、科学を学び、政治学まで学んでいる。あらゆる分野の高い教養が与えられたのだ。つまり、このジョアン1世の子息、子女はかなり賢い王子、王女なのである。ポルトガルはジョアン1世の息子エンリケ航海王子の元で大航海時代の先陣を切る。また、娘は当時欧州一の盛況をほこるブルゴーニュのフィリップ善良公(Philippe le Bon)に嫁いだイザベル・ド・ポルテュガル(Isabelle de Portugal)(1397年~1471年)である。彼女は英仏100年戦争の終結にも力を貸している。※ フィリップ善良公(Philippe le Bon)・・フィリップ3世(Philippe III)(1396年~1467年)欧州で人気の商品「フランドルの羊毛タペストリー」は娘のルートから仕入れられたと思われる。※ リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)※ リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)ポルトガル王家の勤勉さがポルトガル海運を育て、神聖ローマ皇帝の一翼であるスペイン帝国に対抗する海洋国家にまでのし上げたのだろう。長子制度と3つの騎士団ジョアン1世から始まるアヴィス王家(Avis royal family, Portugal)から、諸々、イングランド式が採用されている。貴族制度もそうであるが、長子相続制度も息子のドゥアルテ1世の時には法律で制定されている。※ 長子相続では、全ての財産を長子が総取りする。つまり次男以下に、財産はない。アヴィス王家では、子供達の位置と役割が子供の頃から分けられていたのだろう。兄弟は兄を助け、長兄の死にあたり、次男と三男で長子の子供の摂政を務めている。(他王家では兄弟で争うのはザラだ。ここも争いが少なからずあったが収まっている。)しかし、ジョアン1世は長兄以外の子供らにも、それぞれ後に獲得した領地を分配し爵位を与え、そうでない場合は騎士のトップにしている。長男 ドゥアルテ(Duarte I)(1391年~1438年) ポルトガル王。次男 ペドロ(Pedro)(1392年~1449年) コインブラ(Coimbra)公爵位。三男 エンリケ(Henrique)(1394年~1460年) ヴイセウ(Viseu)公爵位とキリスト騎士団長(Military Order of Christ)マスター四男 ジョアン(João)(1400年~1442年) サンティアゴ騎士団(Military Order of Santiago)マスター五男 フェエルナンド(Fernando)(1402年~1443年) アヴィス騎士団(Military Order of Avis)マスター驚くなかれ、アヴィス王家には3つの騎士団のマスターが存在した。通常1国で一つあれば良いところ。それが3つの騎士団を有する王国なのである。騎士団はローマ教皇により認められた正式なもの。つまり騎士団直属の所領もあるし年貢もある。それらは実質マスターの財産に近い。特にエンリケが拝命した「キリスト教騎士団」は、かつての「テンプル騎士団」を継承したもの。以前テンプル騎士団の悲劇の最後について書いているが、ポルトガルでは、解散したはずのテンプルの財産も、騎士も領地もそのまま「キリスト教騎士団」が受け継ぐ許可をローマ教皇から取り付け、ほぼまるごと相続していたのである。テンプルの領地がポルトガル領内にどれだけあったか? は不明だが、相当な財産を有していただろう事は間違いない。また今後の年貢も約束された。※ テンプル騎士修道会に触れたカ所のリンク先です。テンプルの末路は「騎士修道会 2」です。リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)こうした財産もあったのでエンリケは当初の海洋航海船の研究費や調査試験航海、また北アフリカ探険など資金が出せたのである。また、エンリケ王子はセウタ最高責任者の任務と同時に海洋航海の調査船も指揮していた事になる。ポルトガルの海外進出、セウタ(Ceuta)征服なぜ? エンリケ(Henrique)(1394年~1460年)王子が外洋に船を進めたのか?結果論から見れば、それは新天地の獲得であった事は間違いない。が、最初の一歩は何だったのだろう?研究施設まで持って、海図を造りながら、さらに船まで造ると言う並々ならない研究をしての外洋進出である。当初は利益よりも支出の方が多かったはずだ。お金と時間的余裕のできたエンリケ王子。彼の自身の知的好奇心が推進力だった? 西アフリカ沿岸の探検航海では得る物もあった。では次は? 世界の果て? と言われたボジャドール岬の先に何があるのか? 好奇心は増幅されて行った? のかもしれない。明確な答えは無いが、ポルトガルによる北アフリカのセウタ(Ceuta)侵攻が少なからずきっかけになったと考えられる。ポルトガルはカステーリャと和平を結んだ。もう国教でのいざこざも無い。また、カステーリャはグラナダ攻略の戦いにポルトガル介入させなかった事もありポルトガルには平和が訪れていた。※ 平和となったがお金は無い。ジョアン1世の3人の王子らの成人のイベントとして、1415年、セウタ(Ceuta)侵攻を思いついたらしい。それは王子らの騎士デビューの大々的なイベントとなったし、また諸侯らへの景気づけもあったのかもしれない。※ 戦が無いと困る人達もいるのだ。北アフリカのイスラムの世界に殴り込みをかけるのである。征服のあかつきには土地が得られる。略奪できる品もあるだろうし、キリスト教の布教と言うプロパガンダ(propaganda)がある。また、セウタの確保は地中海への入り口、ジブラルタル(Gibraltar)海峡の確保でもありモロッコへの足がかりでもある。その意義は大きい。実際の所、地理的にポルトガルが広げられる領土は北アフリカ方面しかなかったので、多大な借金をして下準備をタップリしてからセウタ(Ceuta)攻撃が行われている。スペインからのフェリー船上からのセウタ(Ceuta)あいにく天気が悪くかなり明るくしてもこれです。近づいてやっと見える感じ。現在のセウタはスペイン領になっているのでモロッコ入リの時はセウタに着岸してからバスでモロッコの国教を越える。高いツアーの時はセウタのバラドールに宿泊。下はセウタの突き出た部分モンテハチョ山(Mount Hacho)モンテハチョの要塞(The Fortress of Mount Hacho)標高190mのモンテハチョは市内どこからでも見える。城壁の高さは26m。一周1550mの城壁には5つの堡塁(ほうるい)が置かれている。元はビザンチン時代に造られた要塞であるが、ポルトガルが1415年にセウタを征服した時点では半壊していて使用できなかったと言う。ポルトガルとスペインの支配の間に、万が一セウタがイスラム教徒によって攻撃された場合の最後の防御的な砦として再建している。州立アーカイブ図書館からセウタの王室城壁(The Royal Walls of Ceuta)セウタの見所はモンテハチョ要塞ではなく、市内に残る王室城壁(royal walls)とサンフェリペ壕(Moat of San Felipe)である。海上からの攻撃から都市を守るための防衛設備である。半島を横断するように掘り(サンフェリペ壕)があり城塞が控えている。城壁の上から後方、右が半島の突端であり、左のみぎれている山がモンテハチョ山(Mount Hacho)上が朝で下が夜要塞の向こう側サイドにハーバーがある、見える山はモンテハチョ山(Mount Hacho)。セウタ十字軍? 1411年にポルトガル王はローマ教皇より、セウタ攻略を十字軍として公認してもらっている。つまり、セウタ攻略の部隊は十字軍として扱われる事になった。そして1415年8月、ポルトガルによるセウタ侵攻にはドゥアルテ、ペドロ、エンリケの3人の王子が戦闘に加わった。戦いは一日で勝敗が決まったらしい。彼らはこの戦いでめでたく騎士となり、信仰心が熱くこの計画に乗り気だったと言うエンリケ王子が1416年にセウタの防衛と補給の最高責任者に任命される。彼は1450年までその地位にあった。セウタの総守備は2500人を数え、エンリケ王子はセウタ総督として船団も持った。だが、先の「大航海の前章」ですでに書いた通り、セウタからは思った通りの収益が見込めないばかりか、維持費に逆にお金がかかったのだ。当初見込んでいたスーダンの金の取引も、ポルトガルの侵攻により、市場が移動してしまった。何より、セウタの守備は外に出られないほど囲まれて完全孤立。所領の拡大どころか、食糧も本国からの輸入による調達しかできなかった。セウタの軍は周辺の集落を襲って食糧調達したり、海賊行為もしたらしい。セウタ維持の騎士集めにも苦労する。ポルトガル王らは収入ゼロの上に兵器や人件費にお金のかかるセウタを実際のところお荷物に感じていた。ただ信仰心に熱いエンリケ王子(総督)は「経済は二の次、神への奉仕が絶対」と、セウタの保持にこだわったらしい。ただ、このこだわりの為に後に末弟のフェエルナンド(Fernando)王子(1402年~1443年)を死に追いやる事になる。(1437年、西のタンジール(Tangier)を得る戦いで敗戦し人質に取られ獄中で赤痢で亡くなった。)セウタにこだわったのはローマ教皇も・・。1418年にローマ教皇は、セウタで戦う騎士に7年の免罪を公布した。翌年には10年足して17年の免罪を公布。さらに数ヶ月後には8年を加え25年の免罪にしている。「セウタはアフリカ大陸で唯一のキリスト教徒の地」ローマ教皇も必死にセウタをフォローしたらしい。エンリケ(Henrique)(1394年~1460年)王子は1420年、キリスト騎士団長(Military Order of Christ)のマスターに任命された事から、その人材と財産がセウタの為に使用できるようになった。ローマ教皇もまた1456年にはポルトガルに所在する4つの騎士団に1/3の人材をセウタに派遣するよう指示し、支援している。何しろセウタ死守は正式な十字軍の任務に認定されているからね。ところで、タンジール(Tangier)での敗戦で人質を決める時にエンリケは自分が行く事を最初に申し出たが、総司令官の彼を出すわけにはいかないと、フェエルナンド(1402年~1443年)が人質になり結果、獄死した。エンリケのセウタ執着が弟を死に追いやった? もはやエンリケだけのせいではないが・・。※ 当時のイスラムの人質の扱いは、例え王族であっても特別はなかったようで、衛生状態の悪い牢獄での環境が死期を早めたと言える。父王はセウタを手放す事を進めていたらしいが、エンリケは反対した? ローマ教皇の手前、手放す事はできなかったのかもしれない。エンリケは相当に後悔したのではないか? と思える。ところで、セウタ侵攻からすぐにエンリケは海洋航海の実証実験を始めている。1434年にはボジャドール岬を越えいたし、もっと以前の1427年にはアゾレス諸島(Azores Islands)も発見している。ポルトガルは捕まえた人間を奴隷として市場で売買する事も始めていた。フェエルナンドが獄中にいる1438年にはアゾレス諸島(Azores Islands)の植民地化を本格的に開始している。タンジール(Tangier)の敗戦以降ポルトガルは北アフリカの植民から完全に手をひいているのだ。スペインとポルトガルの併合により1580年、セウタはスペイン領となる。サンフェリペ壕(Moat of San Felipe)メイン広場(Plaza de Armas)ライティングされている所に砲台が置かれた。ローマ時代にはすでに城壁が存在していたらしい。ポルトガル軍はその古代遺跡を利用して1541年から1549年の間に要塞、航行可能な堀、跳ね橋などの王室の城壁を建設することで防御を強化。現在の壁を築き上げたと言うが・・。ポルトガルがセウタに侵攻したのは1415年。エンリケ王子の時代にはここまでの城塞はなかったようだ。そして16世紀に再建。18世紀にはその隣に要塞化した兵舎が増設された。それにしても半島の右岸から左岸への船での移動ができる意義は大きい。半島を分割する運河は1540年代に本当に作ったのか? 古代、フェニキア人が地中海交易していた時代にすでに存在していたのではないか? と言う気がする。大西洋上の船舶寄港地と植民地エンリケ王子が星を観測したり、海洋調査をしながら海図を書き進めている過程で、大西洋上の諸島群を発見している。中でもカナリア諸島(Canarias Island)の発見は早く1312年、ジェノバ航海士がたどりついた時はすでに北アフリカのベルベル人が住んでいたと言う。おそらく、ジェノバの船が北上する時に偶然たどりついたのだろうと思われる。エンリケ王子が調査隊を出す以前、1341年にもポルトガル人とジェノバ人の遠征隊がすでにカナリア諸島に行っているが、カナリア諸島より先に船を向ける者はいなかったかった。それは潮流と風向の問題で、そこから先の海域では、通常コースでの帰路ができなくなるからだ。ボジャドール岬(Cape Bojador)より先は、船が戻れずほぼ遭難する事が確定されていた。この問題の理由と攻略ができた事が大航海を制する事につながったと言える。カナリア諸島(Canarias Island)マデイラ諸島(Madeira Islands)アゾレス諸島(Azores Islands)カナリア諸島(Canarias Island)カナリア諸島はすでに古代に発見され、北アフリカのベルベル人がすでに移民していたらしい。それによりここは奴隷の供給地にもなった。1312年、ジェノバ航海士が再発見。1341年、ポルトガル人とジェノバ人の遠征隊をカナリア諸島に派遣している。1402年、ノルマン人の征服にあうが個人レベルのもので征服者と先住民が共存。コロンブスが新大陸を発見するとカナリア諸島はどうしても必要な場所。カステーリャの介入が始まる。1496年、カナリア諸島の利権はカステーリャの勝利で終了する。カステーリャは大西洋を南下する時の寄港地として、またこれから始まる南米進出の際の船舶寄港地として利用した。ボジャドール岬(Cape Bojador)問題カナリア諸島はアフリカ大陸西海岸まで約115kmのサハラ沖に位置。北緯27度37分~29度24分。西経13度20分~18度10分。7つの島からなる。地理的にカナリア諸島の緯度は偏西風(北)と貿易風(南)が分岐する位置にある。北大西洋環流のコースは沿岸を南下しているのでカナリア諸島を越えると帆船の時代の船は来たコースをそのまま戻る事はできなかった。世界の果てと思われていたボジャドール岬(Cape Bojador)問題はそうした理由により船が戻れず遭難したものと思われる。エンリケ王子の指示で1434年、ジル・エアネス(Gil Eanes)はボジャドール岬を越えた。彼はもう少しアフリカ沿岸を南下し、潮流を逃れて沖にでて偏西風に乗ると言う帰路のコースを発見したのである。この時、現地の人間を連れ帰り、それが後の奴隷売買に発展する。マデイラ諸島(Madeira Islands)1419年、ポルトガル船がポルト・サント島に漂着し植民が始まる。黒人奴隷を使用してのサトウキビ栽培が行われた。現在もポルトガル領である。アゾレス諸島(Azores Islands)1427年、エンリケ王子の配下の船長によって発見。1439までに7島。以降植民地化。本国への食糧の生産が目的だったが小麦粉の栽培には50年かかったらしい。また、染料の藍(あい)色の原材料である大青(たいせい)の栽培をしている。大西洋上の船舶寄港地であり、捕鯨および遠洋漁業の基地として使われた。スペインが横取りしようとポルトガルともめた場所。コロンブスもここに寄港している。現在自治国となっているが公用語はポルトガル語。下にエンリケ航海王子の調査隊により発見された航路図を入れました。今回はこんな所で終わります。次回はスペイン編です。とりあえず載せて、誤字チェックは後からするのでご了承お願いします。今回は、諸事情でかなり遅れてのUPとなりました。本を取り寄せたりと出だしも遅かったのですが、新しい所に入る時は内容も、組みたても、写真も、いろいろ考え無ければならないから特に頭を使います。夜中の作業が中心なので昼閒疲れると睡魔には勝てません。待ってくれていた方ゴメンナサイ。m(_ _;)mBack numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン
2022年02月26日
閲覧総数 644
-
11
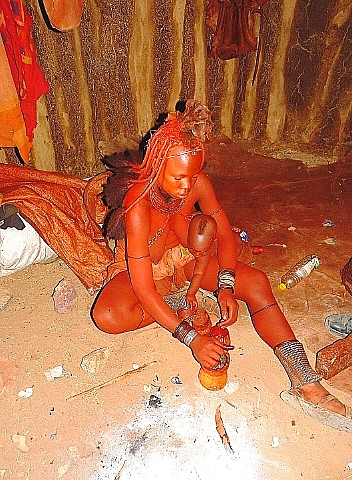
ナミビア先住民・ヒンバ族 2 (ヒンバ流オシャレ)
前回に引き続きヒンバ族です。女性は昼間、子守をしながらも、せっせとオシャレに精を出していますが・・・。ナミビア共和国(Republic of Namibia) ヒンバ(Himba)族化粧ヒンバ族の肌はその大地と同じように赤褐色をしています。でも、それは地肌の色のせいだけではありません。美しく手入れされた肌には、「オカ」と呼ばれる赤い泥粉と牛の脂肪を混ぜたものを全身に塗っているのです。ボディー・ペインティングとはちょっと意味が違うようです。この泥粉には日焼け予防と、虫除けの効果があり、さらに寒さや乾燥から肌を守る役割があるのだそうです。男性もおそらく塗っていると思われますが、村には昼間留守なので写真がありません。ベビーが胸に吸い付いていますが、気にせず、もくもくと作業を続けているようです。ところで、気づかれましたか? 入浴で落ちるのでは?実は彼女達、いえヒンバ族はお風呂に入る習慣が無い民族なのだそうです。お風呂どころか水浴びもしないといいます。唯一入浴するのは、嫁ぐ時に1回と病気になって入院するような事態が生じた時、だけなのだそうです。(病院のシーツを汚すから、らしいです。)下の女性はどうやら香木(こうぼく)を炊く準備をしているようです。入浴の習慣がなくても匂いには気を遣っているようで、1日に3度程、香木を炊いては、香りをたきしめているようです。男性は解りませんが、女性はお風呂に入っていなくても、臭いという事はないようで、むしろ匂いを感じる事もなかった? とにかく女性は、昼間、ヒンバ族なりの身繕いをせっせとしています。ヒンバ族は女性も男性もベルト、ブレスレット等のアクセサリーをたくさん身に付けているようです。女性のアクセサリーは総重量、数kg。それじたいで、既婚、未婚、子供の数までも表現しているのだそうです。その他ヤギや牛の皮で下半身をスカートのように覆っています。ベビーもとってもキュートです地面の色と同化してますが・・・。つづく
2009年09月09日
閲覧総数 1489
-
12

アントニ・ガウディ カサ・ミラ 3 (屋上1)
最新の「アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 」シリーズのリンク先をラストに載せました。さて今回はカサ・ミラ屋上の紹介です。写真の選択にちょっと時間がかかってしまった事と流れから2つに分割しました。アントニ・ガウディ カサ・ミラ 3 (屋上1)最初の構想カサ・ミラに使用された石は同じカタルーニャ州のアルト・ペネデスのビラフランカ(Vilafranca)産の石だそうです。比重が大きく重量感があるのが特徴で、その石をわざと荒削りにしてダイナミックさを出しているそうです。最初の構想最初の構想では各フロアが400m2以上の3階か4階建ての建築を考えていたようです。2つのパティオを持つ所は今も同じですが、構想では大きなパティオの周囲を馬車で各フロアまで乗り付けられるような二重螺旋の道を建設し、それぞれのフロアの住宅まで馬車で乗り付け、かつそこに駐車場をも併設したかったようです。しかし、2000m2以上の土地の確保が不可能だったので実際はパティオをとりまく螺旋階段は3階住居までで終わり、自動車と馬車の駐車場は地下になり、その為地下に至る傾斜道を建築しています。カサ・ミラ(Casa Milà)の模型 (1回目に紹介した模型の裏側断面)写真右がグラシア通り側実際のカサ・ミラは地下1階(当初駐車場)、居住フロアは地上6階。それに屋上の下の屋根裏が現在展示フロアとして使われています。1859年「バルセロナ近郊の再生と拡張の為の計画案」にのって始まったバルセロナの開発ですが、1800年代末にはまだこのグラシア通りには馬車鉄道が走っていた時代です。(それが電化され路面電車となったのが1899年)新旧革命が起きている中にあって造り上げられたカサ・ミラは当時の建築設計も工法も革新的なものでした。それが今見ても遜色(そんしょく)なく見えるのが凄いです。カサ・ミラ(Casa Milà)屋上の図面前回の図面同様に左がグラシア通り側。2つのパティオ(中庭)の他に屋上に6個の円が見られますが、それが屋上に至る螺旋階段と通風口になっていて、それぞれがオブジェのような小屋になっています。現在は屋上に落下防止のフェンスが取り付けられていますが、建築当初それはありませんでした。めったに来る所ではなかったからでしょうが、屋上は今や見学コースの目玉の1つです。甲冑のオブジェのようにデザインされた煙突が屋上を飾り、うねった床はやはり山の頂をイメージしているのかもしれません。全体として非常にシュールなデザインです。中庭を見下ろす。屋上すぐ下に小窓がたくさん開いているのが見えますが、それがいわゆる子屋根の下の屋根裏で、現在は展示場になっています。屋上つづくリンク リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 4 (屋上2)Back numberリンク アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 1 高級住宅リンク アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 コロニア・グエル教会とカテナリー曲線リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 1 (外観)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 2 (パティオ) アントニ・ガウディ カサ・ミラ 3 (屋上1)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 4 (屋上2)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 5 (屋根裏の梁)リンク ガウディ博物館 1 (グエル公園)リンク ガウディ博物館 2 (ラ・トーレ・ローザ・la Torre Rosa)リンク ガウディ博物館 3 (ガウディ家の人々)リンク ガウディ博物館 4 (ガウディの病気)リンク グエル公園(Parc Guell) 1 (2つのパビリオン)リンク グエル公園(Parc Guell) 2 (ファサードのサラマンダー)リンク グエル公園(Parc Guell) 3 (大階段のタイル)リンク グエル公園(Parc Guell) 4 (列柱ホール)リンク グエル公園(Parc Guell) 5 (ギリシャ劇場)リンク グエル公園(Parc Guell) 6 (擁壁と柱廊)リンク グエル公園(Parc Guell) 7 (テクスチャーにこだわった柱廊と陸橋)関連リンク コミーリャス(Comillas)エル・カプリーチョ(El Capricho)リンク ガウディの椅子リンク モンセラート(Montserrat)
2012年05月10日
閲覧総数 486
-
13

オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)
前回のオリエント急行でこぼれた写真をやはり紹介しておきます。オリエント急行 2 (ベニス・シンプロン・オリエント急行)オリエント急行史ベニス・シンプロン・オリエント急行(Venice Simplon Orient Express)オリエント急行史1883年10月4日、パリとコンスタンチノープルを鉄道で結ぶと言う当時は活気的な長距離列車が考案された。前代未聞の列車は40名の著名人を乗せ、パリのストラスブルグ(東駅)からルーマニア経由(フェリーを一部利用)でコンスタンチノープルへ出発。それがオリエント急行の一番列車だそうです。その後1889年にパリ~コンスタンチノープル間が全線開通。2都市間が67時間も凄かったのは距離の問題だけでなく、列車とは思えない豪勢な列車の仕様である。ジョルジュ・ナヘルマッカー(ベルギー人)の夢のような計画だったオリエント急行は豪華なタペストリー、ビロードのカーテン、素晴らしいガラス器、一流のシェフによる食事など、至れり尽くせりの豪華な設備とサービス。それらがヨーロッパ社交界の話題を独占し、数多くの人々に愛されたそうです。また著者であるアガサ・クリスティーも楽しみに乗車したらしい。それだけの栄華を誇ったオリエント急行も下火に?1977年5月 全面的にオリエント急行は打ち切り。1977年10月 オリオント・エキスプレス・ホテルズ社会長のジェームス・B・シャーウッドがモンテカルロのオークションで売りに出された2両のワゴン・リー車を購入。以降ヨーロッパ各地に散在していたブルマン車やワゴン・リー車を買い集め、5年の歳月と30億円かけて復元、改造。1982年5月25日 オリエント急行のかつての運行ルートLondon → Venezia (Simplon Pass)を復活させたのがベニス・シンプロン・オリエント急行なのです。※ 列車は豪華ではありますが、古い車輌のリメイクなのでクーラーなどの施設は当然付いていません。お世話係りスタッフキャビン・スチュワード(Cabin Steward)各車両に一名ずつ乗務し、ベットメーキング、ルームサービス、朝食を届けたり荷物の運び出し等のお世話係をしてくれます。キャビンの呼び鈴(ボタン)呼び出しです。メートル・ドテル(Maitre d'Hotel)食事のサービスの責任者。ダイニング・カー(食堂車)でのお食事時間や座席のオーダーを受けてくれます。トレイン・マネージャー(Train Manager)列車の最高責任者。緊急時の対応等列車内のすべてを統括。用命の際は担当のスチュワードを通して・・。列車内のバー・カウンター(飲み物リストも各部屋にメニューがあります。)狭くて写真がとれないのでこれはオリエント急行の雑誌から撮影。部屋は狭いので、スーツケースなどの荷物は荷物専用車両に預け、コンパクトな荷物だけ室内に・・。でも、ドレスコードもあるので衣装が・・・。キャビンには絵葉書やレター・セットが付いています。列車内でこれら郵便を投函すれば、料金は無料で郵送してくれます。日本でもタダです。(一部制限あり。)これらはお土産にもなります。列車内に売店があり、貴金属も売っています。まるで通販パンフレットのようなカタログがあり、列車内で使われているロゴ入りのグラスやお皿などもお土産として売っています。基本、客室、食堂車、ブルマン車、バー・サロン車等に用いられている内装品は全て、オリエント急行コレクションとして販売していると言う事です。(かってに持ち帰るな・・と)写真左端が灰皿でその上がカフス。下が乗車チケット。オリエント急行には東南アジアを除いてエア・コンが付いていません。ロゴ入りの扇風機のみです。当然暑くて快適とはいえません。窓の開閉は、ヨーロッパ便のみできるようになっていると言うことですが・・。「走る蒸し風呂」と形容する人もいます。ベニス・シンプロン・オリエント急行のようにグッズを売ったり、セールスがうまければ、元祖、国際寝台車会社(ワゴン・リ社)のオリエント急行も生き延びられたかもしれないのに・・。と思ったりしました。前回のリンク オリエント急行 1 (廃止に???)
2009年08月24日
閲覧総数 1005
-
14

海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦
カテゴリーを変更しました。さて、今回は海洋共和国編で度々登場したガレー船(galley)を取り扱ってみました。船に興味があったわけではないのですが、本スジの「アジアと欧州を結ぶ交易路」を考えた時に、その輸送手段は重要事項です。現代では、物流と言えば航空輸送や陸上輸送の車も対象になりますが、太古の物流は主に船でした。できるだけ船で運ぶ。時に運河も構築した。そして必要最小限が人なり馬などの動物を利用した輸送です。5000年前にはすでにガレー船(galley)が登場し、地中海交易での物流を担っていた。大航海時代に太洋を越える物流では帆船(はんせん Sailing ship)が優位に立ったが、小廻りの効くガレー船はエーゲ海や、バルト海、カリブ海などの諸島群の輸送では近年まで主力であったのだ。そしてそれは物流を担う商船と共に軍船として進化を遂げてきた。ガレー船は、その動力に蒸気機関が発明される19世紀初頭まで活躍していたのである。※ 蒸気船の事も最後に載せました。ガレー船(galley)の事に始まり、赤ヒゲ海賊の事、オスマン帝国との海戦でレパントの海戦 (Battle of Lepanto)も成り行きでいれました。写真はサンマルコ寺院の内部を紹介。最初にガレー船時代の美しい海の怪物の話しを入れました。付け足しして書いていたから、またまた長くなりました。海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦ガレー船(galley)とセイレーン(Siren)ガレー船(galley)の変遷一段櫂船(single-banked galleys)ペルシャ戦争の三段櫂船(Trireme)アレクサンドロス王とフェニキア人(Phoenician)ポエニ戦争の五段櫂船(Quinquereme)ガレー船の漕ぎ手問題ヴェネツィアとジェノバのガレー船の事情官民一体のヴェネツィア船団小型ガレー船フスタ(fusta)元海賊、オスマン帝国の海軍提督バルバロス海賊との海戦からオスマン帝国との海戦に聖エルモ城塞(Fort st.Elmo)レパントの海戦 (Battle of Lepanto)ガレー船の衰退蒸気汽船の発明サン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)内部写真ガレー船(galley)とセイレーン(Siren)まずは、私の好きな19世紀、ヴィクトリア朝の画家の作品から。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(John William Waterhouse )(1849年~1917年)写真はウィキメディアから借りました。1891年製作。絵のテーマは、古代ギリシアの吟遊詩人ホメロス(Homeros)の叙事詩「オデュッセイア(Odysseia)」から セイレーンの居る海域を通過するオデュッセウス(Odysseus)の話しである。※ 二大英雄叙事詩「イーリアス」と「オデュッセイア」の執筆者として信じられているが、実在かはハッキリしていないらしい。オデュッセウス(Odysseus)はギリシャ神話の英勇。トロイア戦争の勇者であるが、彼の船は帰路すんなり帰国できず地中海をさまよう。辛い放浪の中で幾多の怪物にも遭遇。セイレーン(Siren)は、ギリシア神話に登場するかぎ爪を持つ半身が鳥の海の怪物。彼女らの歌声を聞くと海に飛び込んでしまい、あげく、食われてしまうそうだ。ウォーターハウスは、セオリー通りに半鳥の怪物として描いている。逆説的に考えると、航海の危険地帯を諭す意味でセイレーン(Siren)を利用した?座礁を起こしやすい、慎重に船の舵を取るべき海域にセイレーンは存在したのだろう。特にガレー船は岸に近い所を航行するのが常。岸に寄ったら危険・・と言う海域の警告?最も、昔のたいていの人は、船が遭難したり難破するのは全てセイレーンの仕業。彼女らの美しい歌声を聞いて惑わされたから。と信じていたのかもしれないが・・。下はフェニキア人が描いたモザイク画のオデュッセウス(Odysseus)。紀元前の作品です。かつてのカルタゴ(現チュニジア)のバルドー国立博物館(Bardo National Museum)のモザイク画から以前一度紹介していますが。こちらもホメロス(Homeros)の叙事詩「オデュッセイア」を描いたもので中央で立って縛られているのがオデュッセウス(Odysseus)です。このガレー船の絵は有名ですが、この右隣のセイレーンの絵はあまり紹介されていない。こちらのセイレーンもセオリー通りの足がカギ爪のは半人半鳥の怪物となっている。ところで、中世になると怪物は人や人魚に代わったりしている。「船乗りを惑わすのはさぞ美しい魔物に違いない。」と考えたのでしょうか? 下は上と同テーマのホメロス(Homeros)の「オデュッセイア」1867年製作。 怪物に注目。何と怪物セイレーンは絶性の美女群で描かれている。ハーレム状態。こんな誘われ方したらね写真はウィキメディアから借りました。フランスの風景画家レオン・ベリー(Léon Belly)(1827年~1877年) 彼はフランスの中東の調査探検に記録画家として1850年~1851年参加。ギリシャ、シリア、黒海を回り、帰国後、プライベートでエジプト、ナイル川を遡上するなど中東にとりつかれた?パリのサロンでデビューし、レジオンドヌール勲章ももらっている。この絵の女性はルーベンスを思わせる肉感がある。まあ、神話だからね。が、彼の他の絵はもっと現実志向で写実的。現実の今を写真のように切り取った彼の絵は人々に中東への興味を与えただろう。恐らく流行ったのも勲章をもらったのも、当時のフランスの中東政策にはまったからかも。それにしてもイギリスではヴィクトリア朝にこのテーマを扱った画家は多いし、フランスもしかり。ロマン主義的なテーマが好まれた時代ではあるが、裸婦を描く為の方便? 確実に魔物は普通の美女に代わっているからね。※ ヴィクトリア朝(Victorian era)はヴィクトリア(Victoria)女王(1819年~1901年)が大英帝国を統治(在位)していた期間(1837年~1901年)を指す。1877年~1901年までは初代インド皇帝としても君臨している。巨大な植民地を持っていた大英帝国の経済は絶好調。比例して国力が最もあった古き良き時代でした。ガレー船(galley)の変遷ガレー船(galley)の歴史は古くBC3000年に遡るらしい。先にも触れたが、地中海周辺の船乗りの間で貿易船として、軍船として、あるいは海賊船として19世紀初頭まで使用されていた。古代のフェニキア人(Phoenician)が地中海交易で使用している。それはオールを左右に複数備えた手こぎ(人力)の船で、さらに帆も着いたガレー帆船である。※ フェニキア人は、オールが少なく、主に帆に頼る輸送船を使用していたらしい。古代エジプトのハトシェプスト(Hatshepsut)女王の治世(在位:BC1479年頃 ~BC1458年頃)に紅海の向こうから贅沢品を持ち帰るガレーのような船が記録されているそうだ。因みに贅沢品はミルラ(Myrrh)やフランキンセンス(frankincense)であったと思われる。※ 殺菌と鎮静の薬として、またミイラを作る時の防腐剤に利用されたミルラ(Myrrh)。儀式で神にささげられる貴重な香油フランキンセンス(frankincense)。以下で書いてます。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史下は古代でなく、中世にエジプトからローマにガレー船で運ばれて来たオベリスクです。ヴァチカン美術館で見付けた絵画を撮影していたものです。オベリスクを運ぶ為に特別仕様に造られたガレー船です。左右の舷(げん)で沢山の人達がオールを漕いでいるのが解ります。後方の帆船からそれは中世である事はわかりますが、ローマにオベリスクは13本あり、どのオベリスクが新たに運ばれた物かまで今回は特定していません。ローマ帝国時代に運ばれたオベリスクを再利用して広場に設置したりしているからです。※ 確証はないけどベルニーニが1667年にミネルバ広場の為にデザインした時の物かな?世界に現存しているオベリスクは30本。古代のローマ帝国の強さと、中世以降のローマ教皇庁の威信がイタリアに16本(ローマに13本と他3本)も集めたのでしょう。因みに、ヴァチカンのサンピエトロ広場にあるオベリスクはネロ帝の競技場跡に建っていたものを1586年に移転させたものです。※ 過去に「オベリスクの切り出し(アスワン)」を載せています。リンク オベリスクの切り出し(アスワン)リンク エジプト 17 (オベリスクとベンベン)下はアッシリアの壁画(大英博物館)から BC700年、アッシリアの軍艦写真はウィキメディアから借りました。オールを見ると2段式櫂船(かいせん)のようです。下はノルウェーの復元されたヴァイキング船の写真です。時代は中世初期ですが、ガレー船としてはシンプルな初期型(一段櫂船)。見本に載せました。こちらは一応ヴァイキング船なので戦闘船です。円形の楯(たて)の収納場所も付いている。一段櫂船(single-banked galleys)古代のガレー船は、漕ぎ手座は1段(single-banked) で、1人が1本の櫂(one row of oars)を担当。また漕ぎ手の列(lines of rowers)に基づいて名前が付けられていた。初期のギリシャの一段櫂船(single-banked galleys)は、オールの数で呼ばれていたようだ。30オール・・トリアコンター(triakontoroi) 左右1列づつの 2×15人50オール・・ペンテコンター(pentēkontoroi) 左右1列づつの 2×25人初期のガレー船は甲板がない漕ぎ手座だけの船。よって積荷はほとんど積めないので水や食事の補給、休息や睡眠の為に度々着岸する必要があった。あくまで近海用である。また人件費と言う意味で帆走よりコストがかかった。海賊に人件費はいらないが・・。※ 帆走(はんそう)は帆(ほ)に風を受けて航行するヨットのような船。当時の帆船には大きな正方形の帆マストが1つしかなかったらしい。ただ風に頼らず、行きたい方向に進める小廻りの効くガレー船は近海警備や戦闘用に向いていたので古代から中世までは軍船として発展して行く。ところで、当初、軍船と商船の明確な区別は無かったらしいがBC8世紀頃からスタイルの違いが出てきているらしい。多人数でオールを漕げぱ早い走行は可能。それ故、ガレー軍船は戦士をどんどん増やし大型化して行くが、逆にフェニキアの商船の場合は積荷スペースを多くする為に漕ぎ手を減らしている。ギリシャでは馬を輸送するガレー船も存在している事から用途によってガレー船のスタイルもいろいろ考案されていたのだろう。ペルシャ戦争の三段櫂船(Trireme)漕ぎ手座は3段(three banks of oars)・・・三段櫂船 トリレム(Trireme)BC6世紀中頃~BC4世紀末は三段櫂船トリレム(Trireme)が地中海における標準的な軍船となる。BC5世紀、アケメネス朝ペルシア帝国VSギリシアの間で行われたペルシャ戦争(BC492年~BC449年)でもギリシャは三段の櫂(かい)船を使用した。三段櫂船(さんだんかいせん)は漕ぎ手60名~170名を上下3段に配置される。基本は船体衝突と白兵戦である。漕ぎ手が戦士でもあった。下はGreeceJapan.comの記事「三段櫂船のオリンピアス(Olympias)号、ギリシャで試験航海を実施」からリンク 三段櫂船のオリンピアス号、ギリシャで試験航海を実施ギリシャ海軍が復元した古代ギリシャの三段式のガレー帆船の走行実験をしている写真をお借りしました。photo: Hellenic Navy全長36.9m、全幅5.5m、全喫水1.25m、35トン 乗員170人。 このオリンピアス号は漕ぎ手座は2段であるが、重装歩兵や軍馬の輸送を担う船もあり、三段櫂船のレイアウトにはいくつかのバリエーションがあったらしい。船首に付いている金属の尖った口ばしのような衝角は、敵船に体当たりして穴を開けると言うよりは敵のオールを主に破壊し、航行不能にする武器だったらしい。ガレー船は中継点を近場に必要とする船と言う特性からエーゲ海のような諸島郡では非常に適していたのだろう。中世以降もカリブ海やバルト海など小島が点在する海域で残ったのもそうした理由だろう。このペルシャ時代の三段櫂船(Trireme)の技術は4世紀のローマ帝国の動乱期に廃(すた)れてしまったらしい。つまり複数のオールで漕ぐ所は一致しているが、動乱後の6世紀以降に海洋共和国が新たに造船したガレー帆船と古代のガレー船とは設計において全く別物の船らしい。アレクサンドロス王とフェニキア人(Phoenician)ところで、全く余談であるが、ふと思ったので・・。BC324年、ペルシャ帝国を征服し、バビロンに戻ったアレクサンドロス王(Alexander the Great)(BC356年~BC323年)はフェニキアで建造した船を解体し、ユーフラテス川沿いに建設した港に船を運ぶと、同時に何千と言う水夫やこぎ手を集めてペルシャ湾岸からアラビア海湾岸を沿ってアラビア半島南端(イエメン共和国の港湾都市アデン(Aden)を経由して紅海に入る海のルートを模索している。すでにインダス川まで到達していたアレクサンドロス王は船でインドから地中海への交易路を探っていたのだ。私が着目したのはアレクサンドロス王が使用したのがフェニキアで建造した船だったと言う点。地中海交易にたけたフェニキア人は自力で船を建造していたばかりでなく、輸出もしていたのかもしれない。アレクサンドロス王は、フェニキア人の船の凄さを認めていた?因みに素材はレバノン杉。それもまた彼らフェニキアの本拠テュロス(Tyros)の特産品である。しかし、皮肉にも海の民フェニキア人の本拠地、東地中海のパレスティナ沿岸にあったテュロス(Tyros)は、アレクサンドロス王のペルシャ遠征の時に壊滅され歴史から消えた。(一部がカルタゴへ逃げた。)アレクサンドロス王はいろんな事象において、テュロス(Tyros)を壊滅させた事を後悔したのではないか? 実際、直後の欧州に大きな経済の停滞を起こしたであろう事は間違いない。何しろテュロス(Tyros)は当時の地中海貿易の中心となる都だったからだ。フェニキア人は古からの総合商社であり、運送業者でもあった。必要な品を必要な所に運ぶ。古代から存在したテュロス(Tyros)の街は、その港からあらゆる商品を地中海の港に運んでいた。当然、代替えの効かないオリジナル商品もたくさん扱っていたはずで、テュロスに依存していた国は多かっただろう。※ 現代で言えば、例えば中国が壊滅して中国からの商品の供給が全て止まったらアメリカや日本の経済もヤバイ。と言うのに近かったと思う。また、アレクサンドロス王は帝都ペルセポリス(Persepolis)を燃やして壊滅させた事も後悔していた。ペルセポリスはオリエント1の国際都市であったからだ。こちらはまさか、火事程度で壊滅するとは思っていなかったのだろうが、実際、再建できない程のダメージを受けて消滅した。知性と教養があり、すぐれた指導者であるのは確かだが、怒りの琴線に触(ふ)れると後先考えずにまず、突っ走る性格だったのかもしれない。若かったからかもしれないが、ちょっと思慮に欠けていた? 割と浅はかだったな・・と思う。彼はフェニキア人を滅ぼすべきではなかった。そもそも滅ぼされる理由は彼らには無かったし・・。彼は巨大帝国の王位に就いた時に初めて経済を顧みたのではないか?新たな交易ルートの開拓は素晴らしい事ではあるが、結果論として、現行の経済を破壊しただけで終わってしまったからだ。それ故、アレクサンドロス王を考える時、その2点は大失態だっと思う。もっとも早世(そうせい)していなかったら、彼が新しい交易のスタンダードを造り経済を再生させていたのかも知れないが・・。※ アレクサンドロス王については以下で触れています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィンリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスポエニ戦争の五段櫂船(Quinquereme)漕ぎ手座は5段(five banks of oars)・・五段櫂船 クインクレーメ(Quinquereme)ポエニ戦争ではカルタゴ海軍の主力軍船として五段櫂船(ごだんかいせん)(ペンテーレス pentērēs)が使われた。実際に櫂(かい oars)が五段になっている訳ではなく、3本の櫂を5人(上段2人、中段2人、下段1人)で漕ぐ形になっていたと解説があったが、下のカルタゴ船の図は五段になっている。スタイルは色々とあったのだろう。以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権」の所で一度紹介していますが、リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権当時のローマ船とカルタゴ(フェニキア人)の船の図です。アレクサンドロス王にテュロス(Tyros)が滅ぼされた後、逃れた一部フェニキア人は北アフリカのカルタゴ(現チュニス)に本拠を移し、カルタゴ(Carthage)の目先にあり地中海の中心でもあるシチリア島(Sicilia)を寄港地に展開する。※ カルタゴは、もともとはフェニキア人が地中海交易の中継点(船舶寄港地?)として建設していた街。が、今度はローマ軍との3度に渡るポエニ戦争で敗戦。シチリア島もカルタゴも失い、フェニキア人は都市国家ローマに完全に滅ぼされてしまう。BC146年、フェニキア人の都市カルタゴ(Carthage)は植民都市としてローマに併合されフェニキア人の歴史はここで完全に途絶えた。※ 「フェニキア人から地中海の覇権を奪ったポエニ戦争」について書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権力を付けてきた都市国家ローマは共和制ローマとなりカルタゴ(Carthage)をローマの属州(植民都市)とし、以降地中海域の王者として君臨する事になる。が、そもそもフェニキア人の技術は他が追随できないレベチな域にあった。かつてのカルタゴ(Carthage)の街も実に未来的であったが、カルタゴ(Carthage)が滅んだ事で消えた技術もたくさんあったであろう。実際、五段櫂船(ごだんかいせん)の開発は難しかったはずだ。ローマも実は第一次ポエニ戦争(BC264年~BC241年)の後、フェニキアからぶんどった船を研究して自国の船を建造している。ローマ帝国の海への進出はフェニキアの模倣から始まるのだ。古代に、すでに高度な文明を持っていたフェニキア人は何者だったのか?そして彼らのガレー船は、多少形を変えながらも動力が人力から蒸気エンジンになるまでの間、およそ2000年は続くのである。ガレー船の漕ぎ手問題当時軍船は人力でオールを漕ぐ ガレー船(galley)である。風力を利用する帆船と比べると持続力は乏しく長距離の航行には向かないが、小回りは効くし機動性はある。その為には狭い船内で、漕ぎ手の一矢乱れぬ技術が必要だったらしいが・・。とは言え人力なので漕ぎ手が全力を出せるのは30分程度が限界だったらしい。太洋に比べれば内海の為に地中海は風が緩く帆船よりはガレー船は適していたらしい。だからガレー船は地中海では長く使用された。初期の漕ぎ手座は1段(single-banked)で甲板はなかったので漕ぎ手がそのまま戦士となったから奴隷は利用できなかったが、やがて漕ぎ手座が2段になり、次いで漕ぎ手座3段(three banks of oars)の三段櫂船へと発展すると事情は変わる。※ 古代ギリシアの復元船、三段櫂船のオリンピアス(Olympias)号は漕ぎ手座が2段(Two banks of oars)だが漕ぎ手のtotalが3列。アレクサンドロ王以降は漕ぎ手座が2~3段(two or three rows of oars)はほぼ変わらず、ラインの漕ぎ手(lines of rowers)の数が増えた船が出現する。つまりオールの最大バンク(maximum banks of oars)は3段が術的にもほぼマックスで、後は1本のオールを何人で漕ぐかで人数が変わったようだ。なぜ人員が増えたかの理由は明確になっていないらしいが、投石機(カタパルト catapults)のような兵器が船に搭載されるようになった事などで人員が必要になったのが要因? 最も、無駄に増えただけで意味のなさいない船もあったらしいから自然と必要条件のそろう人員に収まったのだろう。オールを上げている時は停泊時 or 帆を上げて風待ちをしている図船によってサイズや人数は異なるだろうが、およそ長さ45m。幅9m。左右に26ずつの腰掛けがあり、一つの腰掛けに5人の漕ぎ手が座る。(横幅9mの船に横一列で10人。)450人ほどが乗船していた船もある。劣悪で、過酷以外の何物でもない。※ 囚人の場合は鎖で繋がれていた。誰が船を漕いだのか? 各国の漕ぎ手だけでもその国の事情が解る。かつてのローマ帝国海軍の場合は無産市民(プロレタリア)が漕ぎ手となっていた。ガレー船の乗り組み員は自分達の事を船員(sailors)ではなく、兵士(soldiers)と呼んでいたそうだ。それ故、労働に見合う給与なり報酬が必要であった。つまり、囚人は使用しなかったらしい。中世の海洋共和国や西側諸国の場合は国で様々。まれに囚人も使われたが、大方で漕ぎ手はやはり人件費を掛けて自由人が集められている。スペイン船では、宗教裁判で異端とされた罪人が使われたと言うが、イタリアにはそんな罪人はほとんといなかったらしい。ヴェネツィアの場合、かつて服属させたアドリア海の東岸の人々を漕ぎ手に雇用すると言うシステムが昔からできあがっていたらしい。しかもヴェネツィアは高額な給与を支払っていたので当初は人気はあったそうだ。アマルフィ、ピサ、ジェノバの海洋共和国では特に人集めが大変だったようだがやはり自由人を給与を払って募集した。イスラムの場合、拉致してきたキリスト教徒が奴隷として漕がされる事がほとんど。それ故、奴隷の反乱が起きると困るので、多人数のキリスト教徒を一度に乗船させる事はできなかった。また造船技術は西方よりは遅れていたので当初は小型のフスタ船が主に使用されていた。イスラムの乗員は50人程度。だからイスラム側は自国の軍船を出すよりは海賊を都合よく利用した。海賊は船も船員も持ち込み。軍功を上げれば正規軍として雇用されオスマン帝国の将軍にすると言われて飛びついたのだ。つまり地位と名誉が報酬で、海賊がキリスト教徒との戦闘に加わったのである。ヴェネツィアとジェノバのガレー船の事情ところで、ヴェネツィアとジェノバのガレー船は商用船でもあったので、40m級の大型が多く、漕ぎ手も一隻で200人は必要。当然1航海における人件費は高くなり一隻の航海における諸費用のほとんどは人件費で消える。だからヴェネツィアはガレー船にはペイできる高額品を積んで航行したそうだ。また、ヴェネツィアの船長の条件は厳しかったが、船数が増えると条件は緩められた。だが、航海術よりも商売に詳しい船長を採用する傾向があったそうだ。ヴェニスの商人。徹底していましたねまた、ヴェネツィアの商船は常に共和国の海軍の護衛の元に航行していたので、財力のあるヴェネツィアは傭兵隊長を別に雇って海軍維持にも努めたそうだ。一方、1381年のトリノ講和条約、以降、東方貿易での利権を失ったジェノバでは高額品の取り扱いができない。だから、地中海交易では人件費のほとんどいらない小型帆船のフスタ船にシフトしたらしい。とは言え、ジェノバはイベリア回りでフランドルに定期航路を持った。フランドルの毛織り物はそれ自体が宝石に匹敵する高額商品として取り扱われ、東方へも輸出されて行く。どこにでも商機はあるものだ 官民一体のヴェネツィア船団共和国の軍船は、当初20隻くらいであったらしいが、15世紀になるとオスマンの海賊対策の為にガレー船の数は増えて行く。前回触れたが、1502年に結成されたローマ教皇(法王)による連合軍に参戦した時は、その時だけでもヴェネツィア共和国から50隻の艦船が参戦している。それだけオスマン帝国側の海賊船の数が増えて脅威になってきたからだろう。それにしても、ヴェネツィア共和国の官民一体の協力体制はすごかった。ヴェネツィア商船は軍用のガレー船と共に船団を組んで航海に出る。つまり護衛艦に守られての航海なので途中襲われても安心して航海が可能だったのである。経済の維持に国が協力を惜しまなかったからだ。実際、交易品に掛けられる税収がヴェネツィア共和国の財源であったから・・。しかし、逆に国が民に求める事もある。いざ大きな戦闘態勢になって船が必要な時は民間の商用船も軍船に転じたと言う。。積荷は最寄りの港に預けられ商用船も戦闘に参加した。これは義務であった。因みに商船が沈没して荷物の回収ができなくなった時は、ヴェネツィア共和国が責任を持って積荷を回収し荷主に届けられたと言う。その非常に合理的な制度、さすがヴェネツィアである。 それに比べてジェノバの方はトップが4つに割れて争っていたからヴェネツィアのようなまとまりは無かった。強いて言えばジェノバはローマ教皇庁の為によく協力をしていたのでその見返りは大きかったのだと言う。第一次十字軍(The First Crusade)1096年~1099年で大きく貢献した事は「アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)」ですでに紹介しているが、ローマ教皇庁に大きく恩を売った。そして東ローマ(ビザンツ)帝国ともつながり植民地領をたくさん得る。またカール5世以降、神聖ローマ帝国とつながり、オーストリアのハプスブルグ家、スペインのハプスブルグ家とも懇意になっていく。造船や金融など利権の獲得に成功している。小型ガレー船フスタ(fusta)フスタ(fusta)は帆走をメインにした小型のガレー船である。下の絵ではマストが横倒しになっているが・・大三角帆用の1本マストがあり2人用の漕ぎ手用ベンチが並ぶ。戦闘用だと両舷に12人から18人程度の人員が漕ぐのだろうが、小型のフスタは商用だと乗員を制限して帆に頼る航行をメインにしていた。因みに、四角帆だと逆風では行きたい方向に進めないが三角帆だとジグザグに前進する事が可能。下は以前紹介したジェノバ港の絵ですが、フスタ部分をクローズアップしました。大型ガレー船よりはるかに数が多い。むしろ一般的な実用船のようです。元海賊、オスマン帝国の海軍提督バルバロスバルバロッサ(Barbarossa)とは、イタリア語で赤ヒゲを意味する。映画などでよく怖い海賊の代名詞に使われる赤ひげの海賊であるが、実は彼はオスマン帝国の海軍の提督であった。※ ハイレディン・バルバロッサ (Hayreddin Barbarossa)(1475年~1546年) 上半身のみウィキメディアから借りました。16世紀のバルバロス・ハイレディン・パシャの肖像(Portrait of Barbaros Hayreddin Pasha ) 作者不明Louvre Museumd 所蔵15世紀のオスマン帝国は、海賊を使い地中海を荒らしキリスト教徒からの略奪を繰り返していた。その中でもキリスト教徒相手に成果を上げた海賊をオスマン帝国の正規軍に迎え入れると公言し、実際大きな成果を上げたバルバロッサ(Barbarossa)は提督に抜擢された。元海賊と言う異例の経歴を持つ提督だ。 下もウィキメディアから借りました。Istanbul Naval Museumの模型ですが、原本の解像度が悪い? 船を見やすくする為にバックを修正しました1543年、バルバロッサはこの船で当時オスマン帝国の同盟国であったフランスを支援するために210隻の艦隊でマルセイユに向かった。バルバロッサは国賓としてフランスに招かれたのである。※ これらガレー船を漕いでいたのは拉致され奴隷とされたキリスト教徒であった。彼はギリシャのレスボス島(Lesbos)出身者。つまり元はカトリック教徒でもあった。しかし、当時レスボス島の周囲は完全にオスマン帝国に包囲された環境だ。イスラム側は略奪品の一部を上納すれば海賊業を認めてくれたので、好意的に解釈すれば、生きて行く為に海賊となったと思われる。裏切り者と言われようと、相手がカトリック教徒だろうが関係なかったのだろう。実際、イスラムに征服された土地の住人、また誘拐されて来た者らはイスラム教に改宗しなければ、ほぼ奴隷扱いされたのでカトリックを棄てた者は多かったと言う。※ かつて海賊と言えば、アラブ人、ベルベル人、ムーア人が主であったが、時代は変わりギリシャ人、ユダヤ人、イタリア人、スペイン人など人材も多様化。また、以前はイスラムの土地になっていたイベリア半島がレコンキスタ(Reconquista)されキリスト教徒の土地に戻ると、そこを追われたイスラムの者が海賊となり、イベリア半島を襲うと言うよう、西地中海も海賊の標的になって行く。オスマン帝国は彼ら海賊をバックアップしたので海賊の数は増え、また有能な人材も増えたらしい。※ イベリア半島は、西ゴート王国が滅亡した8世紀初頭から1492年のイスラムのナスル朝(グラナダ王国)が陥落するまでイスラムの土地になっていた。※ 土地にいたイスラム教徒も残りたい者はカトリックに改宗して多くが残留している。バルバロッサ時代のオスマン帝国販図バルバロッサ(Barbarossa)は北アフリカを襲い、チュニジアとアルジェリアをスルタン・スレイマンに献上する事で北アフリカのイスラム化にも協力していた。これはバルバロッサの先行投資であった。実際、これら功績により、バルバロッサは「トルコ帝国海軍の最も武勇にすぐれた海将」として迎えられ、スルタンよりアミール(amīr)の称号を与えられた。同時にたくさんの艦船を与えられている。※ アミール(amīr)とは、ムスリム集団の長の称号であり、アラビア語で「司令官or総督」を意味する。何より特筆するのはこの時期のオスマン帝国の第10代皇帝(在位:1520年~1566年)がスレイマン1世(Kanuni Sultan Süleyman I)(1494年~1566年)だった事。海賊登庸など大胆な彼の政策により? スレイマン1世はオスマン帝国の最盛期を造り上げたスルタンとして評価されている。因みに、聖ヨハネ騎士団からロードス島を奪った(1522年)のもスレイマン1世なのである。※ 聖ヨハネ騎士団は1530年にマルタ島を与えられ移るが、それまでは教皇庁海軍基地などに居候。スレイマン1世は、オスマン帝国の海軍提督となった赤ヒゲ、バルバロッサを地中海制覇に向けて公式に送り出したのである。1538年9月、教皇庁連合軍とのプレヴェザの海戦 (Battle of Preveza)ではバルバロッサがオスマン帝国を率いて勝利。これによりクレタ島、マルタ島を除く地中海域の制海権をオスマン帝国がほぼ掌握する事になる。海賊との海戦からオスマン帝国との海戦にスレイマン1世がスルタンになると軍船の数も半端なく増えている。また、戦いはどちらが先の一手を打つか? その為に事前の情報収集と根回しが必要。戦いは情報戦の時代となりスパイも暗躍しているようだ。闇雲(やみくも)に戦う時代ではなくなったらしい。ヴェネツィア共和国は13世紀頃から各国に大使や領事を派遣し、常駐させてきた唯一の国。ヴェネツィア共和国には諜報機関があったから情報収集もハンパ無かったのだろう。コンスタンティノポリスの軍船の移動もすぐさま伝達された。教皇庁連合結成もヴェネツィアの呼びかけであるし、レパント戦のスペイン参戦もヴェネツィアがローマ教皇ピウス5世に働きかけた結果である。総司令官をヴェネツィアがとるか、スペインがとるかでもめたらしいが・・。※ 初期のイスラムの海賊については「アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊」の中、「イスラム教徒の海賊に荒らされる地中海」と「サラセン(Saracen)の海賊」で書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊聖エルモ城塞(Fort st.Elmo)ヴァチカン美術館で撮影した写真に面白い地図を見付けた説明を撮って居なかったのでこれが何か最初は解らなかったが、本の図解でこの形がまさに・・と気付いたのだ。絵は攻防以前の城塞だと思う。1565年、マルタ島の攻防戦のメインとなったマルタ島の聖エルモ城塞を中心にした陣であった。オスマンと海賊の大軍に襲われ、危ぶまれたマルタ島であるが、当時、マルタ島には聖ヨハネ騎士団がいた。以前いたロードスがオスマン帝国に奪われ苦渋をなめていた。今回は負けられない。オスマン側の残虐な手法にも精神力で負けなかった。5月に始まった戦いは夏のシロッコや暑さに助けられた。4ヶ月に及ぶ攻防でオスマン側には疫病も流行った。キリスト軍援軍の知らせでオスマン軍は撤退し、勝利したが、エルモ城塞は壊滅。キリスト軍の7割の兵士が戦死。戦闘の中でも悲惨な戦闘の一つではないか?ヴァチカン美術館が敢えて記録として? 残している事からも、そうなのかもしれない。レパントの海戦 (Battle of Lepanto)それにしても絵画に描かれている海戦のスタイルを見て驚く。陣形が出来ている。海戦も進化した。まさに戦争だレパントの海戦 (Battle of Lepanto)(1571年10月)ローマ教皇の連合艦隊 vs オスマン帝国艦隊前回、「法王庁海軍結成と共和国連合艦隊」については説明済ですが、オスマン帝国との戦いにはローマ教皇(法王)庁先導で共和国が連合が結成された。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊レパント決戦の前にシチリア島のメッシーナに艦隊は集結。ヴェネツィア 110隻(6隻のガレアス船を含む)スペイン 72隻教皇(法王)庁 12隻マルタ騎士団 3隻サヴォイア公国 3隻その他 3隻ガレー船の総計 203隻フスタ 50隻大型帆船 30隻人員 漕ぎ手43500人 総計8万人を越えたらしい。バチカン美術館の地図ホールのフレスコ画らしい。写真は上下共にウキメディアから借りて、上は部分カットしています。艦船の数に驚く。海賊対策の教皇庁連合軍はオスマン帝国との戦争に突入。ガレーを主力とする海戦としては最後らしい。最初、防衛側にいたヴェネツィアが残虐なやり方で皆殺しにされるとそれまで対立していたスペインとヴェネツィアの対立は消え、復讐に燃え結束はかたまったらしい。戦闘は5時間ほど? 結果的にレパントの海戦は教皇(法王)庁連合の圧勝であったが、戦死者7500人。負傷者8000人。敵のイスラム側も戦死者8000人。オスマン宮廷の高官や指揮官はほぼ全滅。この戦死者のうちヴェネッアだけで半数以上の4836人出している。艦長クラスの18人全員がヴェネツィアの名家出身者がしめたと言う。料理人から技師までが、一丸となって戦っている。どこよりもヴェネッアが健闘した証しである。人数が正確に出ているのもヴェネッアだけ。管理や統計にも抜かりがなかったのだろう。教皇庁連合軍はこの海戦に勝利し、地中海の制海権を取り戻す。※ 1538年9月プレヴェザの海戦で敗戦して以来の地中海の制海権の奪還となる。勝った。負けた。は一言で終わるが、中身は知れば知るほど壮絶である。ロンドンのNational Maritime Museum 16世紀後半 下もレパントの海戦です。レパントの海戦 (Battle of Lepanto)の勝利はスペインの参戦にもある。スペインはアンドレア・ドーリア(Andrea Doria)(1466年~1560年)の元で力を付けてきた。最も彼は1560年に亡くなっているのでレパント戦にはいないが・・。ローマ教皇ピウス5世 の呼びかけにやっと応じての参戦だが、艦船が少ない。スペインがどこまで本気だったか? はちょっと疑問だ・・。ヴェネツィアが新たに開発投入したガレアス船(galleass)も勝利に貢献している。レパント戦では、ガレアス船(galleass)が6隻投入された。ガレーと帆船を合体させたガレアス船(galleass)は漕ぎ手の頭上に砲列甲板があり、13~16門の砲台を積んだ。これは今までのガレー船の2~3倍近い砲台らしい。海上で一周しながら敵に砲撃できるので敵の陣営を崩す事ができると言う新兵器だったらしい。因みに、ガレアス船(galleass)は外洋航行に向かずコストも維持費も高かい。ヴェネツィアやオスマン帝国では軍船として17世紀後半以降も使用したと言う。このレパントの海戦でオスマン帝国の海軍は壊滅したに等しい。それでもヴェネツィアは危機を唱えていたが、その勝利に酔った教皇庁の連合軍は1572年に解散。ヴェネツィアは今後のオスマン帝国の復讐戦を恐れたのだろう。1573年3月、ヴェネツィアはキプロス島を手放す条件でオスマン帝国と正式調印し和解した。ヴェネツィアはキリスト教国から裏切り者とされるが、レパントの海戦での犠牲を最も受け、オスマン帝国との戦闘を避ける事を教訓としたのだろう。ガレー船の衰退長距離航海の大航海時代(16世紀~18世紀)にガレー船は当然向いていない。ガレー船から帆船への移行は15世紀には始まっている。キャラック(Carrack)船は遠洋航海を見据えて開発された。※ 1492年、クリストファー・コロンブスが新大陸に到達した際に乗船していたサンタ・マリア号もキャラック船(Carrack)であった。16世紀から18世紀は大航海の時代に突入。ガレオン船(Galleon)の時代になるとさらに荷が多く積載できる。ガレオン船はキャラックに比べて幅と全長の比が長くスマート、また吃水が浅く沈没しやすい反面速度は出たらしい。帆船の話しは次回ですかね。本当はイントロとして使う予定だったのですが・・。蒸気汽船の発明世界初の蒸気エンジンの開発に成功したのは、実はフランス人の造船エンジニアであったクロード・フランソワ・ドロテ・ジュフロワ(Claude Francois Dorothee Jouffroy) 侯爵(1751年~1832年)だったそうだ。彼はエンジンが回転ブレードを備えたオールを動かすと言う13mの船(Palmipède)を造り1776年6月と7月にフランス、ブルゴーニュ (Bourgogne)のドゥー(Doubs)川で実験、そして1783年にはリヨン(Lyon)のソーヌ(Saône)川で、今度は外輪船(Pyroscaphe)を造り実証実験に成功している。国立パリ海兵隊博物館のコレクションから Pyroscaphe-MnM 23 MG1の縮尺モデル写真はウィキメディアから借りました。しかし、当時のフランス・アカデミーからは認められず、しかも1789年に勃発したフランス革命の不幸も重なり認められる前にパリの廃兵院アンヴァリッドでコレラにかかり亡くなっている。その後の蒸気船の開発に現れたのがアメリカ人エンジニア、ロバート・フルトン(Robert Fulton)(1765年~1815年)で、1801年に一度完成し実験に成功するも1803年のパリ、セーヌ(Seine)川での実証実験で成功はしたが沈没。フルトンはイギリスに移動しイギリス海軍が使用する武器の製造を依頼され魚雷の開発もしている。魚雷の完成度は微妙だったらしい。因みに、ロバート・フルトンは1800年に世界初の手動式潜水艦ノーティラス(Nautilus)号を設計している。最もその動力は 手動手回しのスクリュープロペラだったが、ナポレオンの要請による開発だったらしい。1805年、対仏、トラファルガーの海戦(Battle of Trafalgar)でイギリスが勝利するとロバート・フルトンの需要は減り彼は母国アメリカに戻っている。そしてそこで、富裕な投資家であり政治家のロバート・リビングストン(Robert Livingston)(1746年~1813年)の協力を得て、すでにパリで実用実験していた外輪の付いた蒸気汽船を完成させ、ハドソン(Hudson)川を遡上(そじょう)する蒸気船としてし1806年に「クラーモント(Clermont)」号の運行に成功している。※ 32時間で150マイル(240 km)走行。商業用実用化に成功したこの蒸気船はノースリバー蒸気船と呼ばれ、ニューヨーク市とニューヨーク州アルバニー(Albany)間のハドソン川を運行した。下もウィキメディアからです。1909年に運行していたクレルモン(Clermont)号。別名ノースリバー蒸気汽船(North River Steamboat)。当初のオリジナルではありません。要するに、蒸気エンジンが発明されるまで、船の動力はもっぱら風力か人力しかなかったのである。蒸気エンジンによる艦船が現れるのはナポレオン戦争(トラファルガーの海戦)以降と言う事になる。そして船体のボディーも木造から鉄製に代わって行く。船が人類史に現れて5000年? やっと造船は次の世代に入ったのである。それ以降の変革はすさまじいが・・。さらに余談ですが、1811年に開始されるナチェズ(Natchez)とニューオーリンズ(New Orleans)間のミシシッピ川(Mississippi)を走行する蒸気汽船もまたフルトンとリビングストンにより建造されている。作家マーク・トウェイン(Mark Twain)(1835年~1910年)がトム・ソーヤーの冒険 (The Adventures of Tom Sawyer )で「あこがれの蒸気船」として執筆したのがこれである。サン・マルコ寺院 (Basilica di San Marco)内部写真聖エルモ城塞やレパント戦まで入れる予定ではなかったのですが、追加が増えて力尽きましたとりあえず写真は載せましたが、サン・マルコ寺院の解説は無しで終わります。(*_ _)人ゴメンナサイ。(_△_;) ツカレタ・・何を書いて良いか迷って2週間。とりあえずガレー船について書き出しても見え無くて・・。この数日で全く別物になりました。とりあえず載せますが、誤字チェックなどはまた後で追々させていただきます。m(_ _*)mBack numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン
2021年10月22日
閲覧総数 2053
-
15

ミケランジェロ(Michelangelo) 3 (最後の審判)
敢えて違う角度からめったに取り上げられないものを選んで紹介しています。ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni)(1475年~1564年)下は、バチカンのサン・ピエトロ寺院の正面部分です。建築設計競技によって ドナト・ブラマンテが主任建築家に任命され、1506年に起工。1514年にブラマンテが死ぬと、大聖堂の主任建築家はラファエロとなったそうです。1546年にはミケランジェロも主任建築家となっています。かつてドナト・ブラマンテとはライバルでした。教皇達は、自分の栄光の為にミケランジェロを働かせる事を望んだと言われています。サン・ビエトロ・イン・ヴィンコリ聖堂の壁面墓碑1513年、教皇ユリウス2世が、ミケランジェロに自分の墓碑を依頼したまま他界。1505年より約束されていた大がかりな墓碑の建築をミケランジェロは手がけるに手がけられず40年引きずり、悩ませられたそうです。1547年に完成された教皇ユリウス2世の廟堂は縮小されてサン・ピエトロの中に制作。ミケランジェロの作で「モーセ」像は有名です。下は、サン・ビエトロ・イン・ヴィンコリ聖堂の壁面墓碑の一部のモーセ像です。当初40体の彫刻を作るはずが、忙しすぎて自分で3体しか制作できなかったようです。メディチ家礼拝堂新廟メディチ家出身のレオ10世(ロレンツォの次男で駄目ピエロの弟)が教皇に即位。彼により、ミケランジェロはフィレンツェに戻り、サン・ロレンッオ教会の外観の設計など、メディチ家の仕事をするように言われます。図書館やメディチ家礼拝堂の新聖器室などを建設。1520~1533年に作られたメディチ家礼拝堂の新廟には、ロレンツォ2世の「暁と黄昏」とジュリアーノの「昼と夜」のすばらしいミケランジェロ制作のの墓碑があります。下は、ウルビーノ公ロレンツォ2世の墓碑の部分。(以前とりあげています。)石を彫ったとは思えない素晴らしい作品です。電動ドリルもない時代にミケランジェロはどうしてこうも細やかに、まるで粘土でも彫るかのようにできるのか? 天才以上に本当に神の業です。一体彫るのにどれだけかかるのか・・。法王レオ10世の下で枢機卿として有能な手腕を発揮していたクレメンス7世が、教皇に即位した頃は不安定な国際情勢の中で、イタリアを巡るフランスと神聖ローマ帝国との戦闘の最中でした。マルティン・ルターによる宗教改革運動もあってクレメンスはサンタンジェロ城に幽閉、市内では殺戮、破壊、略奪、等の惨劇が繰り広げられていたそうです。ミケランジェロもそんな時代に翻弄され、フイレンツェの共和制を守って奮戦した為、メディチ家による処刑は免がれず、市内に隠れて不明(1975年にサン・ロレンッオ教会が隠れ場所だった事が判明)でしたが、墓所の建設と引き換えに赦免され、メディチ家礼拝堂の完成がなされます。ミケランジェロは、同士を裏切った罪にさいなまれ、また、彼の熱愛した「共和制の祖国フィレンツェ」の崩壊に絶望しローマに移ってから2度とフィレンツェに戻る事はなかったといいます。システィナ礼拝堂の祭壇壁画、「最後の審判」ローマに戻ると教皇クレメンス7世からシステイナ礼拝堂の祭壇壁画を依頼され、続く教皇パウルス3世もこの仕事の継続を望んだ為、(1536年~1541年)完成させます。巨大なフレスコ画による祭壇画は、ミケランジェロ自身が精神的な苦悩をした恐ろしいビジョンで描かれていると言われています。助手の手を借りずに一人で仕上げたと言われる壁画は、足場から落ちて大怪我したときも医師の手助けさえ拒否した程だったそうです。下の正面がシスティナ礼拝堂のフレスコ画、「最後の審判」です。、(1536年~1541年)ラテン語、賛美歌「ディエス・イラエ(神の怒り)と、ミケランジェロが暗記したダンテの「地獄編(小説)から大きなインスピレーションを得たとされ、畏敬の念を起こさせる大画面の構成になっています。1981年から1994年までに修復作業が行われ、ススで汚れていた壁画・天井画は洗浄され製作当時の鮮やかな色彩が蘇りました。(驚く程鮮やかで意外にポップな色で驚きました。古い美術書の写真は殆ど洗浄前の薄暗いものです。)最後の審判の紹介は別にやります。目的があるので・・。1544年と1545年の2度に渡って死を覚悟するほどの病気にかかります。明らかに教皇たちの過大な製作依頼が彼の体力を弱めていったようです。教皇パウルス3世はミケランジェロをサン・ピエトロ大聖堂の主任建築家にし、その後3人の教皇のもと生涯続くことになり、存命中には完成しなかったそうです。1564年2月18日88才で亡くなります。ミケランジェロは敬虔なるカトリック教徒だったそうです。しかし、隠遁者で、内向的で憂鬱質であり、情緒的に激情する事もあったと言うので、恐らくうつ病の気があったのではないかと思います。節度ある生活を送っていたとされますが、召使が長く続く事がなかったそうです。また、彼は他の芸術家とは比べられないほど男性の裸体に興味を示し、夢中になっていたとまで言われ、ホモ・セクシャルだったとされていました。確かに、システィナ礼拝堂の巫女のモデルは、女性ではなく男性であったとされていて「そうなのかな?」と思う部分もありますが、彼は己のもつ芸術性にこだわりのある芸術家ですから、必要であれば男性の裸像に興味を示すこと自体は別に不思議ではないのでは? と私は思います。(筋肉フェチだったかも?)彼は単におく手で女性に接触がない職業だけに不器用だったのではないか? (顔のコンプレックスもあるし・・)彼の人生の後半に現れたペスカラ侯爵未亡人のヴィットリア・コロンナとの精神的な友情? は老いて静かに神と人生を語り合う相手として大切な存在だったのだと思います。もし、彼が10年若ければ結婚もあったのではないか? (出会いは61才)13才より好きで芸術の道に入り、自由に発想し、自分のこだわりが発揮できた時が彼の一番の幸せな時? と考えると大好きな祖国フィレンツェのダビデの像を制作していた時だったのでは? と思います。喜んで、奮発して特大サイズでダビデを彫ったのかな? と思ったりします。ミケランジェロは終わります・・・。でも・・やはり・・一枚紹介しておきます。先に「最後の審判」番外編です。右の脱皮した後のような皮がミケランジェロです。何を表して描いたのか? 「すでに気持ちはここにない? 」 or「自分は救われるべき人間ではない? 皮くらいで? 」
2009年07月11日
閲覧総数 1592
-
16

グエル公園(Parc Guell) 4 (列柱ホール)
最新の「アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 」シリーズのリンク先をラストに載せました。グエル公園(Parc Guell) 4 (列柱ホール)ドーリス式列柱ホールガウディと職人今回写真は正面ファサードに見えるギリシャ風のドーリス式列柱の並ぶホール内部から・・。もともとここはグエル公園住宅が完成したあかつきには入居者達の買い物市場となる場所でした。(市場と言っても農家などが野菜を持って来て露天販売をする・・と言うスペースです。)因みに現在は自称ミュージシャンが生ライブしてCDを売ったりしています。実はここは3層構造になっています。1層目の屋上部分が眺望の良い集会広場(通称・・ギリシャ広場)2層目が市場予定だったユーティリティースペース3層目が公園で使用する為の雨水集積所となる地下貯水槽列柱の図面前回書いた「円や弧を使ったコンパス造形」と言うのがこれです。見本に色をつけた所がドーリス式の柱の部分大きな円は下の写真に見えるくぼみです。下からは凹んでいますが、上から見ればドーム型に突出しています。屋上にあたる上の広場のうち、列柱部分は広場の半分くらいを占める。面積は40×40m。(広場は40m×86m)83本の円柱で屋上広場の人工地盤をささえている。柱の高さはおよそ6m。勾配により場所で多少異なる。太さは上端直径1m。下端1.3m。ギリシャの神殿のように外周の柱は内転びしている。・・などガウディはわざと柱の太さに変化を付けたり、曲線を加えたり・・と、ギリシャの神殿建築で用いられた視覚的錯覚を計算した技法を取り入れているようです。ガウディ友の会が出している本より・・・等角投影図法(ラモンボッシュによる)柱の中央は穴が開いていて、人工地盤に降った雨などが溜まって地下に落ちやすい構造になっている。柱の空洞部はレンガ造り、円柱表面はプレキャスト・コンクリート製あらかじめ工場で運搬可能な大きさに制作して分割して運び設置されたと言う事です。天井部分も場所によりタイルがより細かく破砕したものがはめ込まれている。とかくガウディの設計は細かい。柱の数は83本・・のはず。(86本と書いている本もありますが・・。)計算ではその本数になるのかもしれませんが、柱の何本かは抜かれています。モザイクの・・トレンカディスで装飾されたメダイヨン(medaillon)メダイヨン(medaillon)・・・・大型メダル。建築では円形の浮き彫り装飾など。抜かれた柱の天井にはメダイヨンが取り付けられています。メダイヨンがとりつけられているのはファサードに近い前方部分。3ヶ所に空間をもうける為に柱が抜かれたようです。正確には数えてないので不明ですが、大1-2-1個の計4個? 大小で14個くらい。ガラスの破片をあしらった美しいトレンカディスこのトレンカディス装飾はジョゼップ・マリア・ジュジョール(Josep Maria Jujol)(1879年~1949年)の作品です。トレンカディス(Trencadis)とジョゼップ・マリア・ジュジョール(Josep Maria Jujol)については「アントニオ・ガウディ カサ・ミラ 1と4 」(2012年05月)で紹介しているから見てね。メダイヨンは色柄こそ異なるが、刻まれている文様は全て同じようだ。左右対称の文様である。何だろう? 柱の傾きが解る写真です。(外の柱が内転び)列柱が山側の壁に接した部分・・の装飾とにかく細部のデザインも手を抜いていない・・。雨どいにライオンのガーゴイル(gargoyle)がデザインされている。ガーゴイルと言うと魔除けの怪物の彫刻・・と言うイメージが強いが、本来ギリシャの神殿では大理石のライオンの口などが付いていたと言う。・・・こちらが正統なのだろう。ガウディと職人グエル公園の建設現場では、毎日午後3時にガウディと14人の左官とのミーティングがおこなわれていたようで、前日の予定通りに作業が進まないと、ガウディが怒り出す・・と言う場面もあったそうでかなり仕事に厳しい人だった事が伺えます。(職人の方も当然グチが多かった事でしょう。)実は労働者の権利が特にうるさく言われたこの時代です。カサ・ミラの工事が完了した1909年にガウディは左官など職人100人以上を連れて慰安旅行に出かけています。場所はモンセラート。9世紀に創建されたベネディクト会の修道院であるモンセラート修道院があります。(モンセラートは2012年05月06日に山だけ紹介)ガウディが汽車賃とミサ代(おそらくモンセラート修道院の)を払い、ミラ氏がワイン付きのお弁当代を出したそうです。出かけたのは聖アントニオの日とありますから、おそらく6月13日の聖人である聖アントニオ(パドバ)司祭教会博士 (1195年~1231年)の日。1909年と言えばここグエル公園でもドーリア式神殿列柱の前部と鉄骨構造のコーニス部の建築が進められていた頃です。もしかしたらカサ・ミラの職人はそのままグエル公園に来ていたかもしれません。つづくリンク グエル公園(Parc Guell) 5 (ギリシャ劇場)Back numberリンク アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 1 高級住宅リンク アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 コロニア・グエル教会とカテナリー曲線リンク グエル公園(Parc Guell) 1 (2つのパビリオン)リンク グエル公園(Parc Guell) 2 (ファサードのサラマンダー)リンク グエル公園(Parc Guell) 3 (大階段のタイル) グエル公園(Parc Guell) 4 (列柱ホール)リンク グエル公園(Parc Guell) 5 (ギリシャ劇場)リンク グエル公園(Parc Guell) 6 (擁壁と柱廊)リンク グエル公園(Parc Guell) 7 (テクスチャーにこだわった柱廊と陸橋)リンク ガウディ博物館 1 (グエル公園)リンク ガウディ博物館 2 (ラ・トーレ・ローザ・la Torre Rosa)リンク ガウディ博物館 3 (ガウディ家の人々)リンク ガウディ博物館 4 (ガウディの病気)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 1 (外観)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 2 (パティオ)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 3 (屋上1)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 4 (屋上2)リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 5 (屋根裏の梁)関連リンク コミーリャス(Comillas)エル・カプリーチョ(El Capricho)リンク ガウディの椅子リンク モンセラート(Montserrat)
2012年06月20日
閲覧総数 619
-
17

ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザー
前回の「ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)」で紹介したようにノイシュヴァンシュタイン城は、ドイツ、オーバーバイエルンの美術品や図書などの集積所としてナチス支配下で使われていた時代があった。確かに城塞型で近辺が一望できるこの城の存在はナチスにとっても好都合な場所だったのだろう。リンク ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)ルードビッヒ2世の理想の城はニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg)のような平城(ひらじろ)の居城ではなくどちらかと言えば中世の防衛型城塞が意識された山岳の城なので・・。そこに父の影響もあったのかもしれない。ルードビッヒ2世が青年時代に過ごした彼の父(マクシミリアン2世)が建てたホーエンシュヴァンガウ(Hohenschwangau)城も城塞型であった※ どちらも古い城跡の上に再建されている。しかし、城の内部は城塞とは遠く、どちらも当事流行のロマン主義が色濃く出た装飾がされている。マクシミリアン2世のホーエンシュヴァンガウ城は中世の騎士や英雄伝説の絵画や壁画で飾られている。共に中世を意識する所は同じであるが、ルードビッヒ2世のノイシュヴァンシュタイン城は同じ中世でも、ほぼワーグナーのオペラの内容に特化している。つまり創作性が高いのだ。当然その装飾の仕様も今までの一般的な城のインテリアとは全く違う。どこにも無いタイプなのだ。各部屋にテーマもあるが、それら装飾は例えるなら舞台装置の様相である。実際、ノイシュヴァンシュタイン城内のデザインをしたのは城郭の専門家ではなく、舞台装置画家(クリスティアーン・ヤンク)だったというのだから納得だ。※ ホーエンシュヴァンガウ城とワーグナーについては、2018年2月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)」で少し紹介。リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザー城の建築で受けた地元の恩恵未完の城歌人の広間とタンホイザーとパルジファルルードビッヒ2世の寝室、トリスタンとイゾルデルードビッヒ2世の執務室 タンホイザールードビッヒ2世の個人礼拝堂 聖王ルイ9世城の建築費城部門でも、観光全般でも上位に入るのがノイシュヴァンシュタイン城である。毎年約140万人が訪れると言う。(夏期は、1日平均6000人以上の訪問者があるらしい。)それ故、見学も一応予約制になっている。だいたい40~50人くらいのグループでまとめられて移動。城内をかってに見学する事はできない。初夏のノイシュバンシュタイン城城には常時30人が勤務して管理。王が城に滞在している時はその倍の職員が居て王に対応したらしい。写真中心部分のテラスがルードビッヒ2世の寝室のテラス1869年9月5日城の礎石が置かれる。※ 岩山を8m程 爆破して低くし、給水と道路を確保した上で礎石は置かれた。※ 設計は王室建築局の監督、エドゥアルド・リーデル(Eduard Riedel)(1812年~1885年)。1869年~1873年に城門館が建築。1873年~本丸の王館に着手1883年には1,2,4,5階が仕上る。1884年春には4階の王の住居部は完成。1884年5月27日~6月8日 ルートヴィヒ2世(Ludwig II))(1845年~1886年)城に初滞在。1886年6月13日に亡くなるまでのおよそ2年間に城に滞在したのは172日間であった。※ ルードビッヒ2世(Ludwig II)(1845年8月25日~1886年6月13日)城の正面、見えるのは城門館城の建築で受けた地元の恩恵ノイシュバンシュタイン城の建設には19世紀と言う時代の割にしっかりした建設計画や労働組合が存在していたと言うのだから驚く。前回、膨大な資材が投入された事に触れたが、例えば資材を運び上げる滑車は蒸気機関のクレーンを使用。資材はさらにトロッコで各所に運ばれていた。そんな建築機器の安全性と機能の検査を行う検査協会が当事すでにあり安全の確保が計られていたと言うのだ。前に紹介した琵琶湖疏水工事の環境を考えると日本とは比べものにならない文化レベルの高さである。※ 琵琶湖疎水は1885年(明治18年)~1890年(明治23年)(第1期)ほぼ同時期に建設されている。※ 2017年6月「琵琶湖疏水 2 (蹴上インクライン)」で書いています。リンク 琵琶湖疏水 2 (蹴上インクライン)また、この時代としては革新的だったのが1870年4月「ノイシュバンシュタイン城建設に従事する職人協会」と言う社会制度ができていた事だ。1ヶ月0.70マルクの会費に国王が多額の補助金を援助し、建設従事者が病気や傷害で休んでも最長15週間の資金支払いを保証すると言うもの。工事には何百人と言う職人を必要とし、多数の商人との取引が行われている。1880年には209人の石工、左官、大工、臨時工が直接建築に従事し、運送人、農民、商人、納入業者、さらに飲食業も建築に間接的に関わって来る。この地方全体の人が城建設に関わったと言って過言ではない。つまりこの地方全体が王が亡くなって工事が中断される1886年6月まで城から受けた恩恵は非常に大きかったと言う事だ。城門門に入ってすぐに見えるのは、後方の王の居室がある本丸。本当ならこの手前に礼拝室と巨大な塔ができるはずであった。入り口正面の突出したテラス部分は、塔ができる予定だった基礎の部分。本来は下のような90mの天守閣と下には宮殿礼拝堂が建築されるはずであった。建築はルードビッヒ2世の死と共に中断され未完となってしまったが、もしこれが完成されていたなら、もう少し城はカッコ良かったかもしれない。ちょっと中途半端なのはその為なのだ。城門館の内側城の見取り図上の二つがメインの王館となる部分ルードビッヒ2世の居室は中、ブルー系の所。メインの王館となる建物が正面テラスより上が「歌人の広間」と呼ばれるホール部分。その下の階がルードビッヒ2世の居室のある階。たぶん見える窓は左がクローゼット。壁画はニーベリングの指輪四部作の3つ目、ジークフリート(Siegfried)からジークフリートの大蛇退治。部屋の装飾はワーグナーのオペラからテーマが選ばれている。城内の撮影は禁止されているので直接の写真は無いが、参考までに城で買ったテキストから写真を拝借。そもそも印刷が悪いので写りも悪いですが・・。歌人の広間普通の城であるなら、ここは舞踏会場となる広間であるが、ノイシュバンシュタイン城では歌人の広間と呼ばれている。歌人の広間とは、文字通りここが歌合戦の会場を意味している。歌人の広間とタンホイザーとパルジファル欧州では10世紀頃より吟遊詩人らによる散文詩の歌が歌われ流行している。ドイツではヴァルトブルク城の歌合戦が有名で、ワーグナーはそれに着想してオペラ、タンホイザー(Tannhäuser)を書き上げている。※ タンホイザーの正式名称はタンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦(Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)である王はどうしても歌人の間が欲しくて、この広間を中心にノイシュバンシュタイン城を建てたと言われているほどこだわった場所だ。広間はヴァルトブルグ(Wartburg)城の祝祭会場と歌人の広間を参考にしていると言うが・・。とは言え、このアラブの意匠の入った不思議な装飾はワーグナーがルードビッヒ2世に捧げたとされるオペラ「パルジファル(Parsifal)」に由来している?※ 舞台装置画家クリスティアーン・ヤンクはエドゥアルド・リーデルの設計を書き換えて王の好むスタイルに変えていた。絵画はアンフォルタス王とパルジファル白いドレスの女性が持って要るのが聖杯。女性はもしかしたら妖女クンドリーか?パルジファル(Parsifal)聖杯と聖槍とそれらを守護する騎士団が登場。アラビアの異教徒クリングゾルは魔法と妖女クンドリーを使ってアルフォンタス王を誘惑。王は聖槍を奪われたばかりか重傷を負う。王を救えるのは清らかな愚者。そこに現れた青年パルジファル(Parsifal)。でも彼は事情が飲み込めていない。二幕ではクリングゾルはパルジファルを誘惑するが失敗して聖槍をパルジファルにとられてしまう。三幕ではパルジファルが聖槍を持ってアルフォンタス王の前に進み傷を治すと聖杯の騎士に列するる事を誓う。パルジファル(Parsifal)はルードビッヒ2世に求められて書かれたらしい。第一草稿は1865年に完成して国王に贈呈するが全草稿が完成するのは1877年。それから作曲が始まり初演は1882年、バイロイト祝祭歌劇場である。聖杯伝説も乗っかったいかにもルードビッヒ2世が好みそうなストーリーである。苦悩する新王はルードビッヒ2世の事なのか?あるいは聖杯の騎士こそが王なのか?残念ながら王の存命中にこの広間が使用される事はなかったと言う。1933年~1939年までワーグナー没後50年で祝祭コンサートが開かれたのが最初らしい。ルードビッヒ2世の寝室、トリスタンとイゾルデ(Tristan und Isolde)後期ゴシック、樫の木がふんだんに使われた木彫のゴージャスベッドの天蓋、洗面台、読書椅子など、製作はミュンヘンのペッセンバッハー・エーレングート社製。既製品ではないだろうが、家具会社に発注したもののようですね王の身長は191cm。思ったより大きいベッドである。眠りと死は同一? キリストの復活が描かれていると言うが、このベット、祭壇とか廟(びょう)にしか見えませんね トリスタンとイゾルデ(Tristan und Isolde)を読む婦人寝室のテーマはトリスタンとイゾルデ(Tristan und Isolde)。それはケルト伝承の散文が後に欧州に広まった物語。簡単に言えば悲恋の物語である。いかにも女性が食いつきそうなお話である。それを寝室のテーマに使った王は乙女か? ※ トリスタンはアーサー王伝説の円卓の騎士に連なる騎士。でも「トリスタンとイゾルデ」は別の話。ルードビッヒ2世の執務室 タンホイザーテーマは先ほど広間で触れたタンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦(Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)である。壁絵はJ・アイグナー(J Aigner)ヴェーヌス山のタンホイザータンホイザー(Tannhäuser)舞台は13世紀吟遊詩人タンホイザーは恋人がいるにもかかわらず、ヴェーヌス山で愛欲に溺れる。やがてその生活に飽きると、その世界は消え現実に帰還。地上ではヴァルトブルク城で歌合戦が行われる。お題は「愛の本質」。そこで恋人エリザーベトとも再開。しかしここでタンホイザーは過ちをおかす。非現実の世界で愛欲に溺れていたタンホイザーの「愛の本質」は(精神的な)純潔な愛ではなく、(肉欲的な)快楽の向こうにある愛。皆の非難を受け、法王に許しを請う為にローマに巡礼する事になった。が、結局許してもらえず自暴自棄になったタンホイザーは再びヴェーヌス山に逃げようとしていた。一方、タンホイザーを想う恋人エリザーベトは自分の命を差し出して彼の贖罪を願っていた。エリザーベトの葬列を見て全てを理解したタンホイザーは狂気から覚めるが彼が真に贖罪されたと同時に彼も息絶える。あらすじはこんな所であるが、これをどう演出するかでオペラの内容も面白さも大きく変わる。ダンス音楽を奏でるタンホイザールードビッヒ2世の個人礼拝堂 聖王ルイ9世ルイ9世で飾ったこの祭壇はミュンヘンのJ・ホフマン設計。ルイ(Louis)は、ドイツ語でルードビッヒ(Ludwig)。ルードビッヒ2世の名は聖人となったフランス王、ルイ9世からもらっている。※ ルイ9世(Louis IX)(1214年~1270年)※ 聖王ルイ9世については2017年2月に以下書いています。「フランス王の宮殿 1 (palais de la Cité)」「フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)」リンク フランス王の宮殿 1 (palais de la Cité)リンク フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)公開されている部屋はまだあるが、実際写真は撮影できないので紹介はこんなところで・・。春のノイシュバンシュタイン城ワーグナー(Wagner)に捧げげたとも思える城ではあるが、この城が寝泊まりできるようになる1年前(1883年)にワーグナーは亡くなっている。※ ヴイルヘルム・リヒャルト・ワーグナー(Wilhelm Richard Wagner)(1813年~1883年)城の建築費ところで城の建築費であるが、王は国税を直接使ったわけではない。王の私財と王室費(国家君主の給料)から城の建設費を支出している。とは言え、その資金だけでは十分ではなく、ルードビッヒ2世は多額の借金をしてまかなっていた。※ 官僚が度々王に支出削減を進言していたのはこの借金の事らしい。ヴィッテルスバッハ家の古文書による王室会計の帳簿によれば、1886年の建築終了までに建築に要した費用は6,180,047金マルクだとか。(現在のお金で200億くらいらしい。)しかし、王の借金は、王の死後に家族から返済されているそうだ。だから王の贅沢で国を破綻させたと言うのは誤りらしい。若き王は政治に絶望し、人に裏切られ、個人攻撃され、すっかり人間嫌悪に陥って行ったようだ。なぜ城を造ったのか? と言う答えは明確になされていないが、王侯なら、城の一つや二つ造るのは自然な事だったらしい。そもそもドイツやオーストリア圏では冬の住まい(宮殿)と夏の住まい(宮殿)は別である。それぞれに立派な宮殿を持っているのが常識。ただ、ルードビッヒ2世が王位について、1866年、内戦が起き、バイエルンはボロ負け。バイエルンの被害はとても大きいものだった。その上、プロイセンに主権放棄と3000万グルデン(5400万金マルク)と言う賠償金を払わなければならなかった事なども国庫を苦しいものにしていたのだろう。王の造った城の中でもこのノイシュバンシュタイン城はまさしく彼が夢の中に逃避するのにピッタリの城であったのは間違いない。が、せっかく造った城なのに172日間しかいられなかったなんて気の毒過ぎもっと居て、城を完成したかったろうに・・。そう考えると、何だか今も王の魂はこの城にありそうな気がしてきたゾ さて、これでノイシュバンシュタイン城おわりますが、ルードビッヒ2世に関するバックナンバーがこれで一応完成しました。2018年02月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)」2018年03月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 2 ノイシュヴァンシュタイン城 1 冬」2018年03月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザー」2015年07月「ルードビッヒ2世(Ludwig II)の墓所 (聖ミヒャエル教会)」リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 2 ノイシュヴァンシュタイン城 1 冬リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザーリンク ルードビッヒ2世(Ludwig II)の墓所 (聖ミヒャエル教会)ルードビッヒ2世が生まれた離宮と彼の乗り物2015年08月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 1 (宮殿と庭)」2015年08月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 2 (美人画ギャラリー)」2015年09月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 4 (馬車博物館 馬車)」2015年09月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 5 (馬車博物館 馬ソリ)」リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 1 (宮殿と庭)リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 2 (美人画ギャラリー)リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 4 (馬車博物館 馬車)リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 5 (馬車博物館 馬ソリ)
2018年03月29日
閲覧総数 4978
-
18

新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とロココの意匠)
写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました。どこかの記事かブログで、ベルサイユ宮殿は一般庶民にも開放されていて観光客で賑わっていた風な事が書かれていた。が、これはちょっと違う。「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)」のところでチラっと触れた「王権神授説(おうけんしんじゅせつ)」に関係した事象なのである。王権神授説では「王は、神から選ばれて王権を与えられた人」として存在している。それ故、負うのは神のみで、それ以外の例えばローマ教皇や神聖ローマ皇帝でさえも、何ら逆らえるものではない。との立場をとっている。つまり王は神に次いで特別な存在だと解釈しているのである。さらに中世には、カリスマ性のアピールもあり、王には霊験(れいげん)が宿っていると言う拡大解釈がされていたのである。もはや「王はただの人間ではなく、奇跡を起こす聖人となって庶民の病気を治していた」と言う事実がブルボン家にはあった。ルイ14世に継いでルイ15世もならい「王が病人に手を触れて病を治す奇蹟の儀式」が存在していたのである。これは国王の神聖性と権威の象徴として欠かせない行事でもあった。件(くだん)の庶民が宮殿に集まる様はまさに王に病気を直してもらうための参詣(さんけい)であったと思われる。これはルイ15世が儀式を止めてしまう1739年まで続いた行為である。フルーリー枢機卿はむろん反対したであろうが、まさに啓蒙思想が勃興(ぼっこう)してきている世の中にあって、さすがにルイ15世も続けられないと思ったのかもしれない。しかし、これは王権を存続させると言う意味においては大変意義のある行為であった。以降、王と市民の直接の関係性は無くなるのだから・・。さて、今回はルイ15世の公妾(こうしょう)(Royal Mistress)であったポンパドゥール夫人を中心にした話しになりますが、私が採用した夫人の経歴は英語版のウィキペディアがベースです。実はデュックドゥ・カストルの「ポンパドゥール夫人」と言う本も手に入れました。非常に権威のある作家らしいが、夫人の経歴からしても驚くほど中身が他と異なる。並べて比較もできないほど離れすぎ。何より今見てきたかのような、今本人が言っているような書き方。伝記とは言いがたい創作性を感じずにはいられなかった。しかもやたらと登場人物など情報は細かい。しかし、要所となるポイントは全く信用できない。使える所は使おうかとも思ったが、結論からすると無い方がマシと言う判断になった。私が求めるのは確実な史実の部分。特に年代は大事。それらを集めて再構築した方が新しい事が解るから。今回は幾つかの発見があった。また絵画に関しては、大方の所でウィキペディアから借りてきました。敢えてパステル画を集めたのです。ロココのちょっとぼやけた絵画はpastel paintingで描かれた物が多かったのです。当時パステル(pastel)画はパリで流行で、それもまたロココの印象を形作った要素の一つです。でも本来のロココはデザインの意匠です。装飾美術の本から少し持ってきました。今回も記録更新的に長くなりました。f^^*) ポリポリ 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)王の妾(めかけ)となるべく育てられた少女結婚とサロン・デビュー初期サロンの友人ルイ15世との出合い公妾(こうしょう)(Royal Mistress)正室(せいしつ)と公妾(こうしょう)ポンパドゥール夫人とルイ15世の関係ロココ時代に流行したパステル画ルイ15世(Louis XV)ベルヴュ城 (Château de Bellevue) パヴィヨン・フランセ(Pavillon français)ロココの意匠 ロカイユ(rocaille)エセ啓蒙専制君主フリードリヒ2世の討伐王の妾(めかけ)となるべく育てられた少女ジャンヌ・アントワネット・ポワソン(1721年~1764年)は1721年12月パリで誕生する。彼女の実の父親が誰かははっきりしていない。ただ、1725年に父の借金で国を離れる事になった時、チャールズ・フランソワ・ポール・ル・ノルマン・ド・トルネヘムと言う徴税請負人が彼女の法定後見人になっている事など、彼の可能性は高い。彼女の転換点となったのは、1730年。9歳で帰国した時「いつか王の心を支配する娘になる。」と占い師に予言された事。喜んだのは母である。その時から、ルイ15世の愛人になるべく、彼女には貴族の子女が受ける以上の高い教育が施され、育てられる事になった。(弟も良い教育を受けている)母は自宅に最高の講師を呼んだ。ダンスはもちろん絵画、彫刻、演劇、芸術全般の知識。絵画ではデッサンも学んだようだし、演劇については全て暗記するよう求められたらしい。つまりポンパドゥール夫人は、王の愛人になるべく、それにふさわしい教養を英才教育されていたのである。狩りをするダイアナ(Diana)に扮したポンパドゥール夫人 1746年(25歳) ウィキメディアから借りてきました。 画家 Jean-Marc Nattier (1685年~1766年) 宮中の肖像画家まさにルイ15世が射止められた仮面舞踏会の時の夫人の姿。出合の翌年に描かれた作品。結婚とサロン・デビュー1740年12月彼女は19歳でシャルル・ギヨーム・ル・ノルマンデティオール(Charles Guillaume Le Normant d'Étiolles)(1717年~ 1799年)と結婚する。相手は彼女の後見人ポール・ル・ノルマン・ド・トルネヘムの甥である。※ この結婚で2児をもうけるが、1歳と9歳で二人とも早世している。なぜ結婚したのかの疑問はある。が、この結婚の真意は、実は本当の娘? ジャンヌ・アントワネットへの合法的相続の為? との説がある。実際、この結婚で彼女はエティオル(パリの南28 km)の土地を相続する。そこは王室の狩猟場セナールの森(la forest de senart)の端に位置していて、後にそこでルイ15世と出合うのである。結婚後、彼女はパリのサロンへ出入りするにようになり、また自身でサロンも開いている。これらサロンで、時の重要人物である啓蒙思想家(けいもうしそうか)の第一人者らと知り合いになっている。※ なんとなくですが、啓蒙思想につては以下で紹介。サロンの事もこちらの前に是非一読お願いしたいです。その為に作った章です。リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)初期サロンの友人ヴォルテール(Voltaire)(1694年~1778年)本名フランソワ=マリー・アルエ(François-Marie Arouet)※ 啓蒙主義を代表する哲学者。作家、詩人。ヴォルテールの名称はペンネームみたいなもの。チャールズ ピノ デュクロ(Charles Pinot Duclos) (1704 年~1772年)※ フランスの作家シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー(Charles-Louis de Montesquieu)(1689年~1755年)※ フランスの哲学者。モンテスキュー (Montesquieu) の男爵 でもある。クロード=アドリアン・エルヴェシウス(Claude-Adrien Helvétius)(1715年~1771年)※ フランスの哲学者、啓蒙思想家。ベルナール・ル・ボヴィエ・ド・フォントネル(Bernard le Bovier de Fontenelle)(1657年~1757年)※ フランスの著述家。アカデミー・フランセーズの会員。彼女自身のサロンにも多くの文化的エリートが出入りしていた。彼女の人脈はこの時からすでに造られていたと考えられる。もっとも、啓蒙思想家はフランスのような絶対王政下では敵となるのであったが・・。彼女のサロンの客ヴォルテールモンテスキュークレビヨンフィル(Crébillon fils,)(1707 年~1777年)※ フランスの作家フランソワ=ジョアシャン・ド・ピエール・ド・ベルニ(François-Joachim de Pierre de Bernis)(1715年~1794年) ベルニス枢機卿(the Cardinal de Bernis)※ フランスの枢機卿であり外交官。ルイ15世との出合いジャンヌ・アントワネット・ポワソンは、結婚しても王の妾(めかけ)になる事を諦めてはいなかった? らしい。母の執念もあったのかも・・。※ 実際、王の愛人はたいてい人妻から始まっている。一方、ルイ15世の方は1742年にはすでに彼女の評判を聞いていた。彼女は自分の領地エティオル(セナートの森の隣)で狩猟の指揮をしながら王に会わないかと網を張っていたのである。チャンスは1744年にきた。(ジャンヌ・アントワネット23歳)王の前を一度はブルーのドレスを着てピンクのフェートン(phaeton)に乗り横切る。二度目はピンクのドレスを着てブルーのフェートンに乗って横切り印象づけた。これは成功し、この時王から彼女に鹿肉が贈られたと言う。※ フェートン(phaeton)でのアピールは他でも書かれている。下はヴェルサイユのプチトリアノン近くで撮影したフェートン(phaeton)ガラス越なので光の反射を少しカットして修正しています。フェートン(phaeton)は2頭だての小ぶりの四輪馬車。太陽の戦車を駆って天に上ろうと暴走しゼウスに打ち落とされたパエトーンから派生している。フランスではこの頃、古典的な物が流行っていたようだ。女性の1人乗り用と思われるが資料が全くなく、座って自ら御していたのか? よく解らない。写真これが唯一かも。たまたまこの年、ルイ15世の愛人(Royal Mistress)であったシャトールー公爵夫人(Madame de Châteauroux)(1717年~1744年)が1744年12月に亡くなり公妾(こうしょう)の席も空席になった。※ 彼女は問題児。暗殺説がある。翌1745年2月ヴェルサイユ宮殿で開催された王太子の婚礼祝賀の仮面舞踏会に出席するよう正式な招待状が王から届く。ジャンヌ・アントワネットはこの時、狩猟の女神ダイアナに扮して現れる。王は、7人の廷臣と一緒にイチイの木に変装。ルイ15世は彼女の美しさに即、彼女への愛を公に宣言して公妾(こうしょう)として受け入れる決心をしたらしい。※ 本命視されていたネール公爵家の4女がいたが、宮廷にコネの無い彼女が選ばれた。王の強い押しらしい。このあたりは諸説あるが、この舞踏会が決め手になったのは間違いない。公妾(こうしょう)(Royal Mistress)とは、ただの愛人ではない。実質の妻である。それは正室が国の都合で政略的に選ばれ、決められた結婚であったからだ。正室とは別に、王自身が自ら好きになり選んだ相手を公的に認めたパートナーなのである。だから愛人なのに・・と言うのはちょっと誤なのである。もっともルイ15世の場合、妻との仲も非常よかったようだが・・。恋愛結婚して仲睦まじいオーストリアのマリア・テレジアにしたら納得できなかったのだろう。女帝はフランス王室の愛人制度を良く思っていなかったようで、それがマリー・アントワネットにも伝えられていた。1745年3月、ジャンヌ・アントワネットは翌月にはすぐにベルサイユに引越をする。彼女としては、夢が叶ったのであるから問題はない。しかし夫は? 納得できなかったが相手は国王。ルイ15世は彼を遠ざけたくて、夫シャルル=ギヨームにオスマン帝国の大使館のポストを用意したが彼は拒否したそうだ。1745年、5月二人は公式に別居。娘はジャンヌ・アントワネットが引き取ったが9歳で夭折(ようせつ)。1745年6月、ルイ15世はポンパドゥールの侯爵(Marquess)位を購入。所有権と紋章付きの土地をジャンヌアントワネットに与え彼女を侯爵夫人(Marquisate)にした。マダムポンパドール(Madame Pompador)の誕生である。※ 彼女の最終の爵位は公爵(Duke)。公爵の妻なら公爵夫人(Duchess)である。ジャンヌ・アントワネット24歳。この時後見人であったポール・ル・ノルマン・ド・トルネヘムも侯爵(marquis)の称号と王室造営物総監の任をもらう。それは後にジャンヌ・アントワネットの弟アベル=フランソワ・ポワソン・ド・ヴァンディエール(Abel-François Poisson de Vandières, marquis de Marigny)(1727年~1781年)が相続すると言う条件が付いていた。1745年9月、王家に入る正式な手続きを終えると同時に正室である王妃マリー・レクザンスカ(Marie Leszczyńska)(1703年~1768年)への敬意と忠誠を誓う。ジャンヌ・アントワネットは以降ポンパドゥール夫人(Madame Pompador)として1745年から1751年まで正式にルイ15世の公妾(こうしょう)(Royal Mistress)となるのである。正室(せいしつ)と公妾(こうしょう)ところで、ルイ15世の愛人問題を正室ががどう思っていたか? であるが・・。その前にルイ15世と正室の関係性を紹介する。当初ルイ15世の結婚相手はスペインとの和睦の為に選ばれた8歳下のスペイン王女マリアナ・ビクトリア(Mariana Victoria)(1718年~1781年)であった。が、1725年に婚約は急遽解消され、今度は7歳年上の22歳になる元ポーランド王の娘、マリー・レクザンスカ(Marie Leszczyńska)(1703年~1768年)に白羽の矢が立った。この結婚は世継ぎ欲しさに非常に急がれた結婚であった為、領地拡張とか、政治取引とか、すべての政治的理由は外されて選考されていた。ルイ15世に何かあっては一大事とフランス王家は早い跡継ぎを望みすぐにでも子供の産める妃にチェンジしたのである。かくして1725年9月ルイ15世とマリー・レクザンスカは結婚する。15歳のルイ15世は年上の綺麗なお姉さんであるマリーにすぐに夢中になった。そして期待通りマリー・レクザンスカは1727年から1738年の間に2男8女を出産。ドクターストップがかかるまで、ほぼ毎年妊娠させられていたのである。母体の負担もあるが1737年頃からマリーはついに扉を閉めてルイ15世を部屋に入れない抵抗を見せたと言う。そもそもルイ15世が公妾(こうしょう)を持つに至ったの1734年頃。王妃の妊娠続きが発端らしい。それ故、ルイ15世の公妾(こうしょう)に対して、マリー・レクザンスカは嫌悪よりもむしろ喜んでいたのではないか? 実際、ポンパドゥール夫人はマリー・レクザンスカに優しく声をかけられ感激している。彼女の妃への崇敬は本物であったと思う。以降二人がどのように係わるのかは定かで無いが、少なくとも、公妾退任後の二人の仲はかなり良かったのではないかと私は推察する。共にお互いの気遣いができる二人であったと思うからだ。それにポンパドゥール夫人は1756年には女性としては最高位の王妃付きの女官(lady-in-waiting)に昇進している。ポンパドゥール夫人とルイ15世の関係正式な公妾(こうしょう)期間は1745年から1751年。1751年から夫人が亡くなる1764年までは公式に政務もまかされていたし、最後まで王のサポートをしていたと考えられる。最も病弱になり王に看病される事も。最後は喀血もあり42歳で結核の為亡くなった。ルイ15世は非常に悲しみ途方に暮れたと伝えられている。ポンパドゥール夫人は、宮中に来て3度妊娠し流産している。その処置が悪かったのか? 原因不明の帯下(こしけ)の異常が続いて悩んでいたらしい。トリコモナス腟炎など細菌感染や子宮内膜炎なども考えられる。もはやその気になれないほど酷かったらしく1750年には王との性的関係の継続はできなくなっていたようだ。だからこそ1751年には正式にルイ15世の公妾(こうしょう)(Royal Mistress)の役を降りているのである。※ しかしこれは当時でも一部の人間しか知らなかった事。最近だからこそ公的な資料が出てきているのかも・・。もはや肉体関係はあきらめざる終えなかったが、ルイ15世には十分未練があたのだろう。何より王が彼女から学んだ事は多い。狩りしか知らなかった王が彼女の勧めで園芸の楽しみ、美術の鑑賞、セーブル陶器の製造に興味を持ったり、文学や建築についても学んだ。彼女の発案で画家ブーシェや思想家ヴォルテールが宮中に出入りし、王の見識もかなり広がったと思われる。彼女は王に女性関係以外の新たな知的な楽しみを与え、王の世界を広げたと言っても過言でないだろう。彼女は王のスケジュール管理など秘書のような仕事もしていたらしい。信頼していた王はその後も彼女を側に置き続けた。それ故、世間は関係が続いていると思っていたのだろう。実は彼女の手腕を買って? 正式に仕事までまかせていたのに・・・。世間の間違いは、彼女が亡くなるまで妾が継続されていたと思っている点だ。だから妾が政治に口を挟み国家を動かしていた・・などと非難されてきた。しかし実際は妾から転職して権限を正式に与えられてフランス国家の為に働いていたのである。文化の育成、保護もその中の一環であるし、大きな政治的勝負もしている。オーストリアと和睦し、次期王とマリーアントワネットとの縁談を結んだ事。これは大きな彼女の業績である。※ もし彼女が王を手玉にして政治に口を出していたのだとしたらシャトールー公爵夫人のように早くに殺されていただろう・・と思う。ロココ時代に流行したパステル画ルイ15世 (10歳) 1720年 パステル画画家 ロザルバ・カッリエーラ(Rosalba Carriera)(1675年~1757年)1720年にパリに呼ばれフランスの王室から36点の肖像画の注文を受けた。ルイ15世の肖像画もその一つ。カッリエーラのパステル画による新しい肖像画のスタイルはパリで大きな成功を収める。しかし、妹たちに手伝わせてさっさと仕事を終えると翌1721年にはヴェネツィアに戻ってしまった。※ 後にマリア・テレジアに絵の指導もしている。甲冑を付けたルイ15世 (38歳) 1748年 パステル画画家 モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール(Maurice Quentin de La Tour)(1704年~1788年)1746年に王立絵画彫刻アカデミーの会員となりにフランスの宮廷肖像画家として1773年まで働いている。彼の技法はpastel painting パステル(pastel)を使った肖像画家として有名なロココを代表する画家の1人。代表作は1755年に描いたポンパドゥール夫人(34歳)の肖像。 パステル画ルーブル美術館所蔵 画家 モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール(上に紹介)パステル画と(pastel painting)言うと印象派の画家ミレーやドガなどの絵で知られるが、1662年にはすでにフランスに登場していたらしい。先に紹介したヴェネツィアの画家ロザルバ・カッリエーラにより1720年頃からパリでの流行が始まった。モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール自体は1727年頃からパステル画に取り組み始めたらしい。ロザルバ・カッリエーラ作品よりも格段に精密になりこんな写真や遠目に見たら一見油絵(Oil painting)にしか見えない完璧さである。これを見ると印象派の作品など素人作品に見える。自分もパステルに挑戦した事があるが、パステルは細部を描くのが難しい。こうした写実的な絵は本来パステルには向かないと思っていた。それにしてもこの時代にこのカラーバリエーション。パステル(pastel)スティックは完成されていた? パステル画はロココを代表する物? 油絵よりも早く描け完成できるのが利点です。ルイ15世(Louis XV)ルイ15世(Louis XV)(1710年~1774年) (在位:1715年9月~1774年5月)「ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)」の所ですでに紹介しているが、先王ルイ14世が亡くなり、彼はわずか5歳で即位した。リンク ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)摂政にはルイ14世の甥オルレアン公フィリップ2世が付いた。摂政による政治(摂政時代)は9年。(1715年~1723年)「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)」で彼の摂政(Regent)時代をレジェンス様式(Régence)として紹介している。リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)実はルイ14世の遺言では、享楽的なこの甥を気に入らなくて遺言では外されていた。しかし、パリ高等法院は王の遺言を棄却しオルレアン公フィリップ2世を「制限無しの全権摂政」に決めたのである。※ 法院との闇取引があったらしい。彼の政治政策は結論から言えば大失敗である。彼の治世末に経済政策の失敗でパリの株価を大暴落させるミシシッピー・ショックを引き起こした。これは後のフランス革命の要因の一つとなったからだ。※ 1720年財務総監にスコットランドの経済学者で銀行家のジョン・ロー(John Law)(1671年~1729年)を呼んだ。全ては彼の革新的経済政策の失敗が原因であった。※ 「ミシシッピー・ショック」はリーマン・ショックになぞって私が作った造語です。一方10歳になったルイ15世は摂政顧問会議に出席するようになり、帝王学を学ぶようになる。何しろ家庭教師はアンドレ=エルキュール・ド・フルーリー (André Hercule de Fleur)(1653年~1743年)。後のフルーリー枢機卿である。※ フルーリー枢機卿は (1653年~1743年)1726年から枢機卿が亡くなる1743年にまで実質の宰相を務めた。王が最も信頼した人物である。王はラテン語、イタリア語、歴史、地理、天文学、数学と描画、地図作成の指導を受けている。 ロシア訪問ではロシアの地理を良く勉強していてロシア皇帝が感激したと伝えられているし、 晩年、王の科学と地理への情熱が学術研究機関コレージュ・ド・フランス(Collège de France)の前身であるコレージュ・ロワイヤル(Collège Royal)内に1769年物理学と1773年力学の部門を創設している。但し王の学業の能力については語られていない。必ず伝えられるのは乗馬と狩猟のスキルである。そして狩猟の為の馬や犬の調教には熱心だったらしい。少年ルイ15世が何より熱中したのが狩猟であり、1722年、ベルサイユに再び宮殿を戻したのも実は狩猟が目的であったらしい。1723年、王は13歳となり成人した。これにより王の新政が始まるのだが、国の政治に対してルイ15世は意欲的ではなかった。宮廷の儀礼も嫌々。それ故、宰相(さいしょう)を置いている。1726年にはブルボン公を排除する為に宰相を廃止したが、以降王は自ら政治する事もなくほぼ「爺や」であるフルーリー枢機卿に丸投げだったらしい。フルーリー枢機卿は、本来イエズス会系の聖職者。政治家としてもすぐれた政策を打ち出し実質の宰相をしていた。※ フルーリーが代打していた時のみ収支が均衡を保ったと言われている。※ フルーリー枢機卿についても「ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)」の中で紹介しています。リンク ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)とにかく宮中内で徹底的な節約をした事は特筆される。また、何より平和主義者? 平和であればお金は使わないからと平和外交を勧めていた。(ルイ14世の造った財政赤字が要因である)にもかかわらず、ルイ15世が独断で妻の父親の為にポーランド継承戦争に参入した事は近隣諸国との関係を崩し大問題となった。ルイ15世が女好きになったのは超イケメンであったが為に宮中の女性が王をほっておかなかった事も確かにあるが、わずか15歳で結婚して世継ぎを残す為にはげんだ事。そのゆがんだ少年時代に形成されたのは間違いない。当時の彼の頭の中には、女、狩り、乗馬、馬,犬くらいしかワードが無かったのではないか?政務の方は今まで通りまかせっきり。もちろん時には政務にも出席してはいたが信頼のおける爺やがいつも見守り、代わって政治をしてくれていた。少年から青年になっても同じ。心配は何もなかったのだろうが、問題はにフルーリー枢機卿が亡くなった1743年以降である。この頃、最もしたたかだった女性にふりまわされている。ネール侯爵家の5女マリー・アンヌ・ド・マイイ=ネール(Marie-Anne de Mailly-Nesle)はシャトールー公爵夫人(Madame de Châteauroux)(1717年~1744年)である。ポンパドゥール夫人の一つ前の公妾であった女性だ。姉らも王の愛人であったようだが、その姉らを追い出し爵位、領地、邸宅や宝石などの財産を贈与だけでなく王との間に生まれた子供を嫡出子にする約束などを取り付けて地位を固めるしたたかさ。また政治や宮廷の人事にも口を出している。王がゾッコンなのを良い事に戦場にまで押しかけてやりたい放題。さすがに回りの重鎮らからは別れるよう言われる程。そして一度は王は別れたものの寄りを戻そうとしている時に彼女は急死した。シャトールー公爵夫人のこうした態度がポンパドゥール夫人と混同されているのではないか? と思う。ベルヴュ城 (Château de Bellevue) ウィキメディアでパブリックドメインになっていた図です。セーヌ川を東に見下ろす斜面の上、ムードンの広い高原にルイ15世は土地を購入し夫人にプレゼント。そこにポンパドゥール夫人は小さな城を建設した。ベルヴュ城 (Château de Bellevue)である。建物は800人かがりでり1749年開始され1750年に完成。王は度々立ち会いに来ていたようだ。建築家 Jean Cailleteau庭園家 Jean-Charles Garnierd'Is室内装飾 フランソワ・ブーシェ(François Boucher)に絵を依頼。城の建設はポンパドゥール夫人の公妾(こうしょう)引退に合わせて建設されたと考えられる。ベルサイユに一室を持っていても、大抵の貴族は別に屋敷を持っている。新たな人生の住まいとして王が夫人に贈ったもの? で間違いないだろう。ヴィーナスの化粧 1751年 油彩 ベルヴュ城の為にブーシェが描いたものの一つ。現在はニューヨーク、メトロポリタン美術館所蔵。フランソワ・ブーシェ(François Boucher)(1703年~1770年)ベルヴュ城 (Château de Bellevue)はフランス革命の後(1791年)、城主は不在となり1823年に取り壊されている。もし革命も無く、残っていたならロココ(Rococo)の様式美は、もっとはっきり解ったのかもしれない。城は夫人自身が創作した傑作であったろうから・・。ポンパドゥール夫人は、1747年から1764年に亡くなるまでブーシェのパトロンであったと伝えるものと、ブーシェはルイ15世の愛人の為に描いた。と両極の伝え方がされている。果たしてブーシェにとってはどちらだったのか?実物はすでに無いので、以下に夫人の城をイメージで捜してみました。ミュンヘン・レジデンツ(Residenz)博物館から持って来ました。ロココ様式の天井です。化粧室と思われる鏡貼りの部屋からこちらのシャンデリアもロココの意匠のデザインです。おそらくベネチアングラスで間違い無いでしょう。レジデンツも、ニンフェンブルク宮もヴィテルスバッハ家の宮殿です。ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) アマリエンブルク(Amalienburg)から鏡とガラス窓の中央ホールリンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 3 (狩猟用宮殿アマリエンブルク)パヴィヨン・フランセ(Pavillon français) 建設は1750年、こちらはルイ15世の為にポンパドゥール夫人がトリアノン宮殿の改築の指揮をとった中の一つ。トリアノンのフランス式庭園の中央に小さなパビリオンが建設された。建築家はアンジュ=ジャック・ガブリエル(Ange-Jacques Gabriel)(1698年~1782年)時期はフランスが参戦していたオーストリア継承戦争が終決した後だ。※ 1748年4月アーヘン講和会議にて終決。この戦争では無理して得たネーデルランドを返却しなければならず、結果的にフランスは一文にもならなかったどころか戦費による財政悪化を招く。新税の導入もあるし王の国民からの信頼はがた落ち。気にしていた?ポンパドゥール夫人はルイ15世を慰める為に音楽やボードゲーム、会話を楽しむ為のラウンジを持つガーデンファクトリーを建設。鶏(トリ)、牛、羊も飼っていて、王は乳製品を好んで食していたらしい。王は宮廷での汲々(きゅうきゅう)とした政務から逃れ、ここでのんびりブルジョワ風の生活をして気をまぎらわせたのだろう。下の写真はウィキメディアから借りた写真で、宮殿部分のみアップに切り取ったものです。※ 自分のはボケ気味だったので。これは4面のうちの一辺です。ベルサイユ宮殿とその別棟に歴史的建造物としてリスト。2008年に完全復元されているらしいが、内装はポンパドゥール夫人の頃のものではなさそうです。建設は1749年の春に始まり1750年の春に作業が完了。その秋に室内装飾が完了。(・_ ・。)? 先に紹介したベルヴュ城 の開始と落成期もこちらとほぼ一緒。こちらは夫人が王の為に建設。ベルヴュ城は王が度々視察して建設されている。偶然ではないだろう。もしかしたらお互いにプレゼントし合った企画だったのかもしれない。もしそうなら二人の間には消えぬ愛があった。2人の関係を愛(いと)しく感じてしまう。建物はちょっと変わった形をしている。この形を利用して、マリーアントワネットはポールを立ててテントを張ってパーティーをしている。ナポレオン妃マリールイーズもしかり。小さいけれど魅惑的な建物のようだ。下もウィキメディアから借りたパヴィヨン・フランセの図面です。真ん中に八角形のホール。十字の先に4つの小部屋。それらはボードゲームをしたりと小さなサロンになっている。設計図から見るに床は色大理石でそれぞれデザインが異なるよう。※ その後の使用者の関係もあり、現在の修復は当初の物と違うようです。※ Google の地図に場所の記載が無かったので書き込みしたら礼状が来ました女庭師姿のポンパドゥール夫人の肖像 1754年~1756(33歳~35歳) ウィキメディアから画家 Charles André Van Loo(1705年~1765年)ムクミが出ていて体調が悪そうです。下の方がむしろ若い。ブーシェとの付き合いは長いから昔の夫人を描いたのかもしれない。フランソワ・ブーシェによるポンパドゥール夫人の肖像 1758年(37歳)頬紅(ほおべに・チーク)をさしているポンパドゥール夫人ロココの意匠 ロカイユ(rocaille)今回も夫人の話しが多くなりロココの詳しい解説までできなくなりました。本当は古典古代から解説を入れたいのですが、それだけで1回になりそうです。別に改めて書くか? あるいは保留にして、今回はザックリ解説で濁(にご)したいと思います。m(_ _;)m1480年頃、地中から古代ローマのネロ帝の屋敷の一部が発見された。※ Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus(37年~68年)(在位:54年~68年)帝政ローマの5代目皇帝。洞窟のような地下に一部しか残っていなかったものの、それはネロ帝の黄金宮殿ドムス・アウレア(Domus Aurea)だったのだ。芸術に造形の深かったネロ帝の屋敷であるこれは世間が大騒ぎとなる一大ニュース。多くの芸術家がそこを訪れ、学び、ラファエロもバチカンにそれらを応用しているが、これこそがルネッサンスの元になる古典古代礼讃の序章となる大発見であった。このドムス・アウレアの壁画の様式はラファエロがバチカンで見せた壁面装飾にも現れている。マニエリスム時代に壁面を造形したスタッコ(stucco)の元もここからだ。しかし、ラファエロもマネしたグロテスク文様はロココや新古典様式の壁面装飾でも取り上げられ、三度び現れたのである。※ 地下の洞窟や墓地から発した「グロッタ(grotta)」はイタリア語であるが、それが語源となりグロテスク(grotesque)と言う造形や文様を生んだ。実はロココの様式はこの時発見された貝柄で造られたニンフのオブジェ装飾など、過剰に装飾されたこの宮殿の装飾から元を発している。※ ドムス・アウレア(Domus Aurea)は海辺のヴィラのような造りであったそうだ。このドムス・アウレアを模した? グロッテンホフ(Grottenhof)がミュンヘンのレジデンツ(Residenz)内にある。それを見ると本当にグロイと思う。以前グロッテンホフ(Grottenhof)は紹介している。リンク ミュンヘン(München) 9 (レジデンツ博物館 2 グロッテンホフ)それがロココにつながるには、以前「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)」でちょっと触れたジル・マリー・オップノール(Gilles-Marie Oppenordt)(1672年~1742年)のようなデザイナーがいたからだ。彼はロカイユのボーダーとシェルの装飾をグロテスクから着想したらしい。今回グロテスクの壁は無いが、これがロココの意匠と言うデザインを持ってきました。ロカイユ(rocaille)上下ともにすべて銀細工師ピエール・ジェルマン(Pierre Germain)(1645年~1684年)の作巻貝から着想.を得た? 曲線の装飾文様。まさしくこれが本来のロカイユ(rocaille)を指すもの。本来はロココは文様から始まっているわけで、様式でもないし、時代でもないのだが、拡大解釈でいろいろ広げられてしまったのである。そもそもバロックやロココと言うワードは、少しバカにして名づけられたものらしい。夫人の誕生は1721年なので、夫人の前後60年間には確かに入るが、夫人誕生以前からロカイユ(rocaille)の意匠は現れていたと言う事がわかる。ピエール・ジェルマンには息子がいて、Thomas Germain (1673年~1748年) もまた銀細工師。彼が父の意匠を継いだかは定かではないが、彼も当時ロココを代表する職人となり大成している。ジル・マリー・オップノール(Gilles-Marie Oppenordt)(1672年~1742年)キャビネットの脚などに見られる人頭象。これも元はネロ帝の黄金宮殿ドムス・アウレアから来ていると思われる。先にリンク先載せましたが、レジデンツ博物館のグロッテンホフの貝でできた人頭のニンフ像。たぶん同じものがドムス・アウレアにあった? それがルーツだろう。ドムス・アウレアは発見当時から崩落がひどくかなり危険な状況だったらしい。カーブしたこの脚は猫足。ガブリエル(Gabriel)。俗にルイ15世様式と呼ばれる脚である。建築、絵画、彫刻、彫金、あらゆる芸術はやはりイタリアが先端。皆がイタリア留学を目指し古典古代から学ぶので古代の意匠は忘れられる事無く継承され、時に繰り返し現れてくる。ルネッサンスの時はドムス・アウレアの発見がきっさかけであったが、18世紀にはヴェスビオ(Vesuvio)山の噴火で滅んだ古代ローマの都市ポンペイの遺跡が発見されネオ・クラッシズム(Neoclassicism)新古典様式のブームが巻きおこった。つまりどちらも考古学的発見が古典古代を蘇みがえらせブームを作ったのである。※ ヘルクラネウム(Herculāneum)はローマ支配以前のポンペイの旧名。1738年、継いで1748年にポンペイの遺跡が発見。(ポンペイの遺跡は非常に広域なのである。)※ ポンペイ以外でも18世紀から19世紀と欧州では古代遺跡の発掘ラッシが起こり同時に古代礼讃のブームが巻き起こっている。今よりもレベルが高かったのではないか? とさえ思う高度な文化と思想を持っていた古代ギリシャ人や古代ローマ人。彼らの遺跡は同時に古代人の叡智(えいち)をも示してくれる。絶えず憧れの対象である事は良くわかる。それにしても流行とは、やはり何かしらのきっかけから始まっている。ジュスト・オレール・メッソニエ(Juste-Aurèle Meissonier )(1695年~ 1750年) 時計金細工職人、彫刻家、画家、建築家、家具デザイナー下はロココ様式の燭台(しょくだい) パリのクリニャンクール(Clignancourt)の店舗で昔購入したきたもの。素材は真鍮(しんちゅう)? ぽいです。最初28万円とか言われて、最終的にオマケでもらったのでお値段わからず。何倍にふっかけて言われているか? さぐりさぐり値段交渉をするのが難しい。クリニャンクールは蚤(のみ)の市で有名ですが、良いものはちゃんと店を構えているところで買った方が良い。後々、クレームも入れられる。これと新古典様式の時計と燭台のセットをこの時購入。店のおじさんが突然すべてのシャッターを閉めだしてちょっと怖かった。ミュンヘン・アルテピナコテーク美術館からフランソワ・ブーシェによるポンパドゥール夫人の肖像 1756年(35歳)年代からも完成したばかりのベルヴュ城 (Château de Bellevue)で描かれた絵かもしれない。下の写真はウィキメディアから借りた写真の部分のみカットしました。解像度が良いので、でもカラーは実物より派手目です。3枚のペチコート作戦を決行していた当時の夫人の姿。キャビネットから羽根ペンと封書が見えます。おそらく夫人はオーストリアの女帝マリア・テレジアとロシアの女帝エリザヴェータに直接手紙を書き送り計画の詳細を伝えていたと思われます。その方が間違いないし、偽りの無い思いも伝えられる。3人の女性は同じ気持ちで打倒フリードリヒ2世の討伐に軍隊を動かしたのだと推測。「打倒フリードリヒ2世」のこの計画、叶わなかった事が個人的にも残念です。さて、今回一番私が書きたかった事。それは公妾を退任した後のポンパドゥール夫人が政治に関わった部分です。上に触れた「3枚のペチコート作戦」と言われるプロイセンのフリードリッヒ2世包囲網の真意を考えてみた。エセ啓蒙専制君主フリードリヒ2世の討伐前回の「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想) 」の中ですでにフリードリヒ2世の著書の事について紹介していますが・・。プロイセン王フリードリヒ2世(Friedrich II)(1712年~1786年)は1739年から1740年の時期に「反マキャヴェリ論(Anti-Machiavel )」を書き上げヴォルテールに推敲(すいこう)を送った。1740年(5月)は、父王が崩御しフリードリヒ2世として即位した年なので、これからの君主としてあるべき自分の理想の姿像を描いたはずであったと思う。ヴォルテールはフリードリヒのこの原稿をオランダで密かに出版する。フランス語からドイツ語など数ヶ国語に翻訳され、かなりのベストセラーになったようだ。実際、諸国の若手の皇太子らへの受けは絶大でかなりの信奉者が生まれている。フリードリヒ2世(Friedrich II)の肖像 1745年 (32歳)フリードリヒ2世(Friedrich II)(1712年~1786年)ヴォルテール(Voltaire)(1694年~1778年)モンテスキュー( Montesquieu)(1689年~1755年)ジャンヌ・アントワネット・ポワソン(1721年~1764年)フリードリッヒとヴォルテールは長らくの文通相手であったと言う。啓蒙思想家のヴォルテールは、この著書を褒めたし、モンテスキューもこれを高く評価したと言う。ところで、この1740年と言う年はジャンヌ・アントワネット(後のポンパドゥール夫人)が結婚した年でもある。以降彼女はサロンにデビューし前出のヴォルテールやモンテスキューとはサロン友達になるのである。当然その話題にフリードリヒ2世と著書「反マキャヴェリ論(Anti-Machiavel )」はあったであろう。もしかしたら、彼女もこれからの君主として理想の王になると期待したかもしれない。それなのに、同じその年の10月、オーストリアのカール6世の逝去に伴う皇位継承であらかじめカール6世が諸侯に承認を受けていたにもかかわらず、それを無効としてフリードリッヒ2世はオーストリア領のシュレーゼン(Schlesische)を奇襲して奪った。警告無しのいきなりの奇襲と言うそのやり口も非常に汚いが、フリードリッヒ2世はカール6世に恩があったはずだ。何よりカール6世の取りなしが無ければプロイセンから追い出されて今頃はただの人であったのに・・だ。さらに1713年の国事詔書により長女マリア・テレジアへのハプスブルグ家の継承を認めていたにもかかわらず、カール6世が亡くなると手のひら返して約束を反故(ほご)にし、女性の継承を認めないとした。出版したばかりの「反マキャヴェリ論(Anti-Machiavel )」は何だったのだ? と言う話しである。これからの理想の君主にるあるまじきおこないにヴォルテールも、言っている事と行動が違うと強く非難したと言う。ハプスブルグ家のオーストリア及びボヘミアとハンガリー継承は、男性であればそのまま継承できていた話しでもある。この腹立たしさは私にも解る。ジャンヌ・アントワネット(後のポンパドゥール夫人)も非常に怒ったのではないか? と推察する。当事者であるマリア・テレジアの怒りは怒髪天である。このオーストリア継承戦争(1740年~748年)は8年続いた。マリアテレジアの味方は当初イギリスだけ。1748年にロシアが参戦してくれた。乳飲み子を抱えた若い女王の苦労は計りしれなかったろう。しかも結果的に1741年4月、オーストリア軍はモルヴィッツでプロイセン軍に敗北し富めるシュレーゼン(Schlesische)はフリードリッヒ2世に取られてしまったままだ。この怒りはシュレーゼンを取り返すだけではすまされない。打倒プロイセンがオーストリアの目標となった。その為に敵はプロイセンのみ。フランスとの和睦は願ってもない案であったと思う。私がもう一つ怒るのはフリードリッヒ2世は一時はマリア・テレジアの婚約者候補になった男ではないか。マリア・テレジアがフランツを選び振られた腹いせなのか? 自分が結婚していたらハプスブルグ家の領土は全て自分の物になっていたのに・・と言う嫌がらせなのか?最低な男だ 紳士に非ず。1756年、ベルサイユでポンパドゥール夫人が動いた。今はそれなりの地位がある。フランスは長年の宿敵であったオーストリアと和睦し、打倒プロイセンで手を組んだのである。これは信じられ無いほどの転換外交である。外交革命と後に呼ばれるほど・・。※ 七年戦争(1756年~1763年)と言うとイギリスとフランスの間の紛争の方がメインになるのかもしれないが、今回は欧州内での女傑のタッグにのみを焦点にしています。また7年戦争は世界初の大戦に数えられる戦いです。フランスとオーストリアの和睦。これを協力的に支援したのがポンパドゥール夫人と言われている。が、協力支援と言うよりは、そもそもポンパドゥール夫人が持ちかけた話だったのではないか? とさえ思う。目的はもちろん打倒フリードリッヒ2世である。嘘つき啓蒙思想家の退治だ。さらにロシアの女帝エリザヴェータも個人的にフリードリッヒ2世を嫌悪していたので、欧州を誇る女傑が手を組んでフリードリッヒ2世を包囲して駆逐する作戦に打って出たのである。※ 3人の女傑 が手を組んだ事から「3枚のペチコート作戦」と呼ばれるそうだが、英語版にもフランス語版にもそんな言葉見当たらない。誰が名付けたのだ? 3枚のドレスならともかくペチコート(スカート下の下着)とは何だ? これ名付けた人は女性蔑視の人か? あきらかにバカにしている。この「7年戦争」には例のシュレーゼンの帰属がかけられていたので「第3次シュレーゼン戦争」とも呼ばれる。フランスはオーストリアのシュレーゼン奪還に協力を惜しまなかった。帝国のほとんどの国がオーストリア側に付き、一時はフリードリヒ2世を自殺に追い込むほどに優勢であった。しかし1761年ロシアの女帝エリザヴェータが急死して情勢が変わる。フリードリヒ2世を信奉していたピョートル3世が皇位継承をしたからだ。もう少しでプロイセンを破る直前。新帝ピョートル3世は勝利目前にしてプロイセンとの単独講和へ持ち込んだ。国益を損ねた愚か者以外の何者でもない。※ その半年後には妻(後の女帝エカテリーナ2世)と近衛部隊によるクーデターで新帝ピョートル3世は玉座を追われ暗殺されるが・・。すでに取り返しの付かない事をやらかした後だ。ロシアの戦線離脱を受け情勢は一転。オーストリア側はシュレーゼン奪回を諦め1763年プロイセンとの間で講和条約を結ぶ事になる。敗北だ翌、1764年、ポンパドゥール夫人も亡くなった。この試みは失敗したが、結果的にフランスとオーストリアは長い戦いに終止符を打ち和睦に成功。マリーアントワネットが後にルイ16世となる王太子に嫁ぐ事になったのである。2人の結婚は平和の象徴でもあったのだ。これはまぎれもなくポンパドゥール夫人の功績の賜(たまもの)であったと思う。それにしてもピョートル3世は愚か者であるが、マリア・テレジアの息子ヨーゼフ2世(Joseph II)も同じく愚か者だ。皆フリードリヒ2世の著書「反マキャヴェリ論(Anti-Machiavel )」にだまされたのだ。本は立派でも、理想論だけで、それほどの器の男では無かった。3人の女傑はこの嘘つき男が許せなかったのだろう。と結論した。ポンパドゥール夫人はサロンで友人のヴォルテール(Voltaire)からフリードリッヒ2世の真実を聞いていたに違いない。フランソワ・ブーシェによるポンパドゥール夫人の肖像 1759年(38歳)ウィキペディアから借りてきました。相変わらずお美しい。汚れない乙女のようです。今までの王の愛人は貴族の令嬢が多かった中で、ポンパドゥール夫人はブルジョア層出身。教養に関してはどんな女にも負けなかっただろうし、男性もしかり、そこら辺の臣下よりも知識も豊富で賢かったと想像できる。それはおそらくいつもの会話からも感じられたであろう。政治学さえも学んで来た彼女にはあらゆる方面への見識がありマルチにその能力を発揮きできる素養があった。ポンパドゥール夫人に対して「公妾のくせに政治にかかわらせて・・」と非難する声が大きいが、実際、彼女に政治手腕はあったと思うし、それをルイ15世は良く知っていたと言う事だ。※ 君主たるもの、己が直に政治をしなくても、良い人材を登庸(とうよう)し、動かせる能力があれば良いのだ。加えて言うと先にも触れたが、ポンパドゥール夫人が政治に関わるのは公妾を止めてからである。病気故に、彼女はルイ15世との関係継続が出来なくなったからだ。※ 本来は、公妾を退任したなら、彼女はすみやかにベルサイユ宮殿から退居しなければならなかった。王は彼女を愛するが故に最後まで手放したく無かったのだろう。また能力も評価し、多大な信頼もしていたのだろう。オーストリアやロシアとの交渉は正式に彼女にまかせていたと推察できる。彼女を友人として? ブレーンとして? 宮中に残す為に当初は「公妾は引退」と正式に発表できなかったのかもしれない。※ 後に役職が正式についている。先に書いたが1756年には王妃付きの女官(lady-in-waiting)にまで昇進している。以降、二人は友人になれたのか?エピソードから見えるのはルイ15世は男女の関係が終わっても、ずっと愛していたのだろうな・・と言う事。信頼か絆か? 彼女の存在が消える(亡くなる)まで諦(あきら)められなかったのだろう。世間とは全く違う見方となりました。次回、旧ベルサイユはマリーアントワネットの村里の予定。リンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想) 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃
2020年12月06日
閲覧総数 1643
-
19

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)
そこそこ写真もあるのでピサ(Pisa)とダ・ヴィンチでも紹介しようか? 私が尊敬する芸術家の一人として真っ先にあげたいのがレオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)だから・・。万能な彼はもはや神。°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°で、ダ・ヴィンチを探ぐっていたら、ミラノに行き着きました。今回ミラノの写真が多いです。そしてラストにどうしてもサルバトール・ムンディ(Salvator Mundi)を入れたかったのですが、想定外の事がおきていて、ちょっと時間を食いました。尚、絵画の写真はほぼウィキメディアから借りています。レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)両親幼少期のエピソードヴェロッキオ(Verrocchio)工房ヴェロッキオ工房でのエピソードミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ像プラトン・アカデミー(Platonic Academy)ミラノとの関わりミラノで手がけた仕事岩窟の聖母(Virgin of the Rocks) ウィトルウィウス的人体図(Vitruvian Man)ウィトルウィウス(Vitruvius)の建築論最後の晩餐(L'Ultima Cena)ミラノ公居城スフォルツェスコ城サラ・デッレ・アッセ(Sala delle Asse)ミラノ公とのミラノでの仕事レオナルドの兵器フィレンツェ時代小悪魔・サライ(Salaì)と洗礼者ヨハネ像サルバトール・ムンディ(Salvator Mundi)真作としての発見1516年~1519年フランス、ローワール時代両親彼の実父はフィレンツェの裕福な公証人であったが、小作人の娘であったレオナルドの母(Caterina)とは身段違いの為に結婚はしなかった。故に彼は未婚の母の元にヴィンチ村で生まれ、そこで育ったと考えられていた。※ 生誕はフィレンツェの父の家と言う可能性も出ている。本人 レオナルド・ディ・セル・ピエーロ・ダ・ヴィンチ(Leonardo di ser Piero da Vinci) (1452年4月15日~1519年5月2日)父 Ser Piero da Vinci d'Antonio di ser Piero di ser Guido(1426年~1504年)母 Caterina di Meo Lippi (1434年~1494年)※ 通称として出身地が付くらしい。ヴィンチ(Vinci)村のレオナルドだからレオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)であり、父にも同じくda Vinciが付いている。また、レオナルドには、父の名(セル・ピエーロ)も付されている事から私生児ではなく、ちゃんと公認された親子関係はあったと認識できるし、実際父に喜んで向かい入れられたと伝えられている。レオナルドが生まれた翌年、実父セル・ピエーロも実母カテリーナも別々の人と結婚している。実父セル・ピエーロに関しては、幾度かの結婚をし、最終的にレオナルドの異母兄弟は16人となっている。レオナルドはしばらく母の元で育てられたのかもしれないが、1457年(5歳)には彼は父方の祖父アントニオ・ダ・ヴィンチの家に住んでいた事が納税記録により証明されているそうだ。幼少期の事は不明と言われるが、彼は義母やダ・ヴィンチ家の家族に育てられたのは間違いない。思っている以上に「彼は不遇ではなかった」のだと思われる。それにしても、富裕な家にも関わらず、教育は非公式なものしか受けていないらしい。父(Ser Piero da Vinci)は仕事で忙しく、叔父(Francesco da Vinci)と親しかった事は解っているので叔父からいろいろ広い世界を学んだのかもしれない。なぜなら、画業だけにとどまらずかかわったあらゆる世界。また、後年彼が考案するに至る飛行機械、装甲車両、投石機などの開発につながる素養はある程度小さい頃からの興味に起因するからね。幼少期のエピソード美術史家ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari)(1511年~1574年)が伝えている事によれば、レオナルドの絵が上手な事を知った農民が丸い盾に絵を描いて欲しいと依頼した所、あまりに絵が怖すぎて父がそれを売り、別の盾を購入して農民に贈ったと言うもの。ここで引っかかるのが「絵が怖すぎて父が売った。」と言う点。絵は高く売れ、最終的にミラノ公の元に渡ったらしい。最初から解説すると、当時、農民は農閑期には戦争などにかり出されるので、樽(たる)の蓋(ふた)等を利用した自身の盾(たて)を自ら制作したのであろう。その盾に農民は気の利いた絵を描いて欲しいと軽い気持ちで頼んだのかもしれない。しかし、レオナルドが描いたのは、一介の農民が持つには過ぎるできだったのだろう。おそらく、盾に描かれた絵はメドゥーサの首(顔)だったと思われる。「ペルセウスとメドゥーサ」の神話で、アテナイの命でメドゥーサを退治したペルセウスは見ると石になると言うメドゥーサの首をアテナイに贈った。アテナイはその首を自分の盾(アイギス)にはめ込み最強の盾(たて)としたのである。最強の盾(たて)と言えば、これに勝るものは無い。何しろメドゥーサの髪一本一本はヘビでできているから、それ自体が怖いし不気味。伝統的にもメドゥーサの首は最強の絵図なのである。完璧すぎたのだろう。父は農民にそれを渡さず、フィレンツェの美術商に100ダカット(ducats)で売却している。父がレオナルドの才能を確信した瞬間かもしれない。※ 余談ですが、メドウーサの首について過去に書いています。メドウーサを知りたい方はどうぞ。リンク ルーベンス作メドゥーサ(Medousa)の首ヴェロッキオ(Verrocchio)工房レオナルドはヴェロッキオ(Verrocchio)の工房に14歳(1466年)で弟子入り。※ アンドレア・デル・ヴェロッキオ(Andrea del Verrocchio)(1435年頃~1488年)彼には早くから芸術の才能があった事がわかっているのでダ・ヴィンチ家では当初からそちらの才能を伸ばす事に方針を決めたらしい。父はレオナルドを当時フィレンツェで最高の工房に入れた。そもそも、ヴェロッキオは父の友人であったとも言われている。レオナルドの作品を見せられたヴェロッキオは非常に感心し、入門を許可したらしい。7年、レオナルドは20歳(1472年)になるまでに親方ギルドの資格を取得し、聖ルカ(Guild of Saint Luke)の正会員になっている。父はレオナルドがルカの会員になると彼の工房を設立しているが、レオナルド自身はその後もしばらくはヴェロッキオ工房に寝泊まりして仕事を手伝っていたらしい。レオナルドは確かに、最初に画家として名声を得たが、実は発明など彼の功績は幅が広い。製図、化学、冶金、金属加工、石膏鋳造、皮革加工、機械学などの幅広い技術力。木工品や、デッサン、絵画、彫刻などの芸術的スキル。本当にマルチな才能を発揮している人なのだ。だから芸術家として彼を扱って良いのか? 肩書きは迷う所でもある。ミラノのレオナルド・ダ・ヴィンチ像ミラノ、スカラザ前に設置されているレオナルド・ダ・ヴィンチ像。レオナルドの評価は特にミラノが高い。1858 年に彫刻家ピエトロ マーニ(Pietro Magni)(1817年~1877年)によって制作。政情による資金難で遅れ1872 年に除幕に至った。レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)(1452年4月15日~1519年5月2日)写真左側がミラノ・スカラ座。その対面側がガレリア。トップにレオナルド・ダ・ヴィンチ像台座には弟子の像4体が設置。1.Giovanni Antonio Boltraffio(1466 or 1467年~1516年)※ Salvator Mundiは長らく彼の作品と思われていた。2.Marco d'Oggiono(1470年~1549年)3.Cesare da Sesto(1477年~1523年)4.Gian Giacomo Caprotti (1480年~1524年) ※ under the name Andrea Salaino サライである。さらに台座にはエピソードのレリーフが4面。1.Giovanni Antonio Boltraffio(1466 or 1467年~1516年)最後に解説入れますが、世紀の大発見と言われたサルバトール・ムンディ(Salvator Mundi)は2011年まで彼の作品と思われていたらしい。4.Gian Giacomo Caprotti Andrea Salaino(1480年~1524年) ※ 撮影時の像が汚れていて見栄えが悪かったのでサライの写真はウィキメディアから借りています。洗礼者ヨハネのモデルであり、レオナルドの側に最後までいて、モナリザを所有していた人物。ヴェロッキオ工房でのエピソードこちらも美術史家ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari)が伝えている事であり、あまりに有名な話ではあるが・・。どうも偽りの話だったらしい。ヴェロッキオは弟子レオナルドに自身の作品「キリストの洗礼(Baptism of Christ)」の中の天使(左)を描かせた。1475年頃 キリストの洗礼(The Baptism of Christ)画家 アンドレア・デル・ヴェロッキオ(Andrea del Verrocchio)所蔵 ウフィッツィ美術館(Uffizi Gallery)Leonardo da Vinciの部分レオナルドの天使を見て、ヴェロッキオは筆を置いたと言われる。確かに目を引くのは美しい天使。特に色使いが自分よりもすぐれていると思ったらしいのだ。ヴェロッキオの芸術に対する審美眼が高かったのは確からしい。ヴェロッキオはその後「彫刻の方を専門とした」とも聞いた。実際、ヴェロッキオは彫像の方が有名だ。若い弟子時代の話のように語られているが・・。1475年頃と言う制作年代を見るとヴェロッキオ40歳。レオナルド23歳頃で、すでに聖ルカの会員になり、自身の工房を持っていた頃でもある。レオナルドは行かなくてもいいのにヴェロッキオの所に通っていた年代である。もしかしたら任せられる人材がいなくてレオナルドに頼んだのか? 仕事が無いレオナルドに仕事を与えたのか?親方になったって、仕事が無い人は無いからね。フェルメールのように・・。そもそも工房作品であるなら、どこもほぼほぼ弟子が描いている。親方がどの程度手を入れるか? はどこからの依頼か? あるいは金額による違いがあったのではないか? と思う。そう考えると、有能な弟子を持っているか? は重要だ。マンガ家のアシスタントみたいな感じかな?レオナルドはモデルも努めている。同じくヴェロッキオの所で弟子をしていたフランチェスコ・ボッティチーニ(Francesco Botticini)(1446年~1498年)はレオナルドより6歳上の兄弟子。1470年 トビアスと3人の大天使(I tre Arcangeli e Tobias)画家 フランチェスコ・ボッティチーニ(Francesco Botticini)所蔵 ウフィッツィ美術館(Uffizi Gallery)大天使ミカエル(Michael)のモデルは18歳当時のレオナルドではないか? 似ている。と言われている。日付がはっきりしているレオナルド作品で最も古い絵。1473 年 アルノ渓谷の眺望(Landscape of the Arno Valley)画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ウフィッツィ美術館(Uffizi Gallery)フィレンツェ市内を流れるアルノ川は河口の街ピサを通りリグリア海に注いでいる。物流の為にアルノ川を航行できる川にするよう最初に進言したのはレオナルドだそうだ。レオナルドへの正式な依頼はこの頃から1478年、ヴェッキオ宮殿(Palazzo Vecchio)の聖バーナード礼拝堂(Chapel of Saint Bernard)の祭壇画の依頼。1481年3月、彼はスコペト(Scopeto)のサン・ドナート(San Donato)の修道士から「東方三博士の礼拝」の依頼。しかし、急遽? ミラノに立つことになったようで「東方三博士の礼拝」は未完に終わっている。プラトン・アカデミー(Platonic Academy)ところで、レオナルドは1480年にメディチ家に居たと言う話がある。どうやらプラトン・アカデミー(Platonic Academy)に出入りしていたらしいのだ。メディチ家が主催するプラトン・アカデミー(Platonic Academy)は、後生の人が付けた名前だ。そもそも学校ではなく、高尚(こうしょう)なサロンだったと思われる。先代のコジモが古代ギリシア哲学、プラトンの思想に関心を持っていた事から?メディチ家別邸にマルシリオ・フィチーノ(Marsilio Ficino)(1433年~1499年)を(1462年頃)住まわせ、プラトン全集やヘルメス文書などをラテン語に翻訳させていたらしい。※ ルネサンス期の人文主義者、哲学者、神学者。1439年のフィレンツェ公会議がきっかけならコジモ・デ・メディチ(Cosimo de' Medici)(1389年~1464年)が最初にプラトンに傾倒したのかもしれない。が、コジモは1464年に亡くなっている。次代を継いだのがまだ若いロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)(Lorenzo de' Medici detto il Magnifico)(1449年~1492年)。彼は20歳にしてメディチ家(本家)の当主となるとメディチ家の黄金時代を作り上げた人物だ。そして彼も多くの学者や芸術家を援助した事で知られる。いずれにせよ、マルシリオ・フィチーノ(Marsilio Ficino)が居るメディチ家には人文主義者らが集ってきた。メディチ家はいわゆるサロンとなり人文学者のみならず芸術家、詩人、哲学者らも集う場所となったのだろう。そこでは皆、有益な情報を得られるから、アカデミーのような毎回勉強会の場であったのだろうと推察できる。また、メディチ家はそんな彼らへの支援を惜しまなかったから、有能な人材が多く輩出された。以前「コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)のところで触れているが、1480年頃はメディチ家全盛期で、ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)気にいられたサンドロ・ボッティチェッリ(Sandro Botticelli)(1445年~1510年)がメディチ家の為にいろいろ描いていた頃だ。1482年、「プリマヴェーラ 春の寓意(La Primavera) 」1485年、「ヴィーナスの誕生 (Nascita di Venere)(Birth of Venus)」これらは今、現在 ウフィッツィ美術館(Uffizi Gallery)を代表する絵画となっている。※ メディチ家とメディチ銀行の事かなり詳しく書いています。リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)このサンドロ・ボッティチェッリはアンドレア・デル・ヴェロッキオ(Andrea del Verrocchio)(1435年頃~1488年)の弟子だったと言われている。同じ師匠の弟子であったレオナルドが兄弟子と居ても不思議ではない。あるいはフィレンツェで成功していた公証人の父からのつてかもしれない。 博識なレオナルドはこのサロンで造られたのかもしれない? 少なくとも、より広い世界の扉を開いたのかもしれない。ミラノとの関わり先にレオナルドの評価はミラノが高いと紹介したがミラノ公に気にいられ、彼の元で働いていた期間が長いからだ。1482年から1499年まで、確かにレオナルドはミラノで活動していた。1482年、ロレンツォ・デ・メディチの命でレオナルドはミラノに向かった。先のプラトン・アカデミーの話を裏付けるエピソードだ。当時のミラノ公は、ルドヴィコ・マリーア・スフォルツァ(Ludovico Maria Sforza)(1452年~1508年)(在位;1479年~1499年)が就任したばかり。※ ムーア人のような色黒だった事から通称ルドヴィコ・イル・モーロと呼ばれていた。想像の域であるが、ミラノ公となったルドヴィコ・スフォルツァがロレンツォに「誰が人材がいたら回してほしい」と頼んだのではないか? その白羽の矢が立ったのがレオナルドだったのだと考えられる。レオナルドはミラノ公に自分が何ができるかの手紙を書いている。それによれば「工学と兵器設計の分野で自分ができる事、また絵を描くこともできる。」としているので、画家だけでなく何事もこなせる人材をミラノ公は欲していた。実際レオナルドは武器開発含めてスフォルツアの多くのプロジェクトで活躍する事になる。先に触れたが、レオナルドのミラノ滞在は1482年から1499年。ミラノ公がフランス軍の侵攻によりに捉えられる1499年までレオナルドはミラノ公の下で働いていた。ミラノ公は神聖ローマ帝国側についたのでミラノはフランスと敵対し、フランス軍の侵攻を受けた(イタリア戦争)。ミラノが占領されるとレオナルドは助手のサライと友人の数学者ルカ・パチョーリと共にミラノを脱出してヴェネツィアへ避難している。ミラノで手がけた仕事岩窟の聖母(Virgin of the Rocks) 無原罪懐胎協会(Confraternity of the Immaculate Conception) からの依頼で「岩窟の聖母(the Virgin of the Rocks)」。ほぼ同じ構図、構成で描かれた高さが約 2 m の2点の作品が存在する。左、1483年にミラノで制作依頼を受けて描かれた最初の作品がルーヴル・ヴァージョンではないか? と考えられている。この作品はレオナルドが1人で描いたとされぼかし技法スフマートが使われている。1483年~1486年 岩窟の聖母(Virgin of the Rocks) ルーブル・ヴァージョン画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ルーブル美術館(Louvre Museum)何らかの理由でレオナルドは2枚目のナショナル・ギャラリー ヴァージョンを新たに描き、納品したのではないか? と考えられている。では1枚目はどこに?制作年代で類推すると、一番考えられるのは、最初の作品がフランス占領下で略奪されたから後に新しい作品を描いて送った? と言うのが現実的かも。実際、最初の作品はルーブルに収まっているからね。1495年~1508年 岩窟の聖母(Virgin of the Rocks) ナショナル・ギャラリー バージョン画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ナショナル・ギャラリー (National Gallery)ウィトルウィウス的人体図(Vitruvian Man)あまりに有名な絵図であるが、これが何を意味しているか知っている人は少ないだろう。この絵図は古代ローマの建築家ウィトルウィウス(Vitruvius)(BC80~70年~ BC15年)の著した建築論内で人の比率について述べられていた人体の理論図を具現化したものなのである。第3巻、第1章で、ウィトルウィウスは人間の比率について述べている。へそは本来人間の体の中心。仰向けに寝て、手足を伸ばし、へそを中心にして円を描くと、それは彼の指と足の指に触れることになる。しかし、人体は円だけで囲まれているわけでは無い。今度は人体を正方形の中に配置。足から頭頂部までを測定し、腕を完全に伸ばした状態で測定すると、後者の寸法が前者の寸法と等しいことが解る。1492年 ウィトルウィウス的人体図(Vitruvian Man) 円と正方形に内接する人体の図所蔵 アカデミア美術館(Gallerie dell'Accademia)※ 常に公開されている作品ではない。この画像はウィキメディアから借りました。今まで多くの人が描いているが、レオナルドの作品が最も美しい完璧な図。ウィトルウィウス(Vitruvius)の建築論古代ローマの建築家ウィトルウィウス(Vitruvius)(BC80~70年~ BC15年)は建築論、十書を著して初代ローマ皇帝アウグストゥス(Augustus)(BC63年~BC14年)(在位:BC27年~AD14年)に捧げた。それは最古の建築論の書である。この著は長らく失われていたが、フィレンツェの人文主義者ポッジョ・ブラッチョリーニによってスイスのザンクト・ガレ修道院(the Abbey of St. Galle)の図書館で1414年に発見されたのだ。※ ベネディクト会では古来の良書を写本して残すのも修道士の仕事であった。1450年頃、レオン・バッティスタ・アルベルティ(Leon Battista Alberti)が「De re aedificatoria(建物について)」で紹介。当然、ローマ時代の建築論はプラトン・アカデミーでの話題になっただろう。ブラマンテ(Bramante)、ミケランジェロ(Michelangelo)、パッラーディオ(Palladio)、ヴィニョーラVignola)など、多くの建築家がウィトルウィウスの作品を研究したことが知られている。彼の建築論によれば、建築は「firmitas(強さ・安定性)」、「utilitas(実用性)」、「venustas(美・魅力)」の3つの要素が必要であるとしている。以降、ローマの建築物には、この原則は適用されている。今に残るローマのパンテオン(Pantheon)もその一つ。ウィトルウィウスによれば、建築は自然の模倣。鳥やミツバチのように、人間も自然素材で巣(家)を作る。ウィトルウィウスは住宅建築に関連した気候や都市の場所の選び方についても書いているらしいが、この建築技術を完成させる際に重要なのは比率としている。ギリシャ人はドリス式、イオニア式、コリント式という建築オーダーを発明。美の完成には比率こそが大事な要因としているのだ。また、彼は「建築家は図面、幾何学、光学(照明)、歴史、哲学、音楽、演劇、医学、法律に精通している必要がある」と述べている。それは建築が他の多くの科学から生じた科学であるからで、それはまた多様な学習によって装飾されるものとしているからだ。さらに、彼は理論的であると同時に実践的である事を推奨している。以前、「ローマでは服飾のデザイナーでも建築を学ぶ。」と言うのを聞いて不思議だったのだが、ウィトルウィウス(Vitruvius)の建築論がローマでもルネッサンス以降、脈々と受け継がれているからなのかと納得した。ローマだけではない、欧州で、画家らが古典古代を学ぶ為に、みなイタリアに留学していたのもそうした理由なのだろう。最後の晩餐(L'Ultima Cena)サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会(Chiesa di Santa Maria delle Grazie)の修道院食堂の壁画。1495年~1498年 最後の晩餐(L'Ultima Cena)(The Last Supper)撮影禁止なのでウィキメディアからかりました。詳しい事は「修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復」で書いています。リンク先はまとめてます。サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会(Chiesa di Santa Maria delle Grazie) 本体の堂13世紀にすでにこの場に教会はあったらしい。ドミニコ会派の修道会として礎石されたのは1463年9月。度重なるペストなどで信者も減少。その存続さえ難しい時にドミニコ会修道会自体の再建をかけた改革が行われている。その中での建築である。清貧、勤労を重んじるドミニコ会が望んだのは簡素な建物。しかし、後援となったVimercate伯爵は違った。教会ともめたが、結局教会の建築家はクリストフォロ・ソラーリ(Cristoforo Solari) (1460年~1527年)に決まった。ソラーリはすでに評判のトスカーナの建築家。堂はルネッサンス様式を意識しているものの、基本的にはロマネスク様式に近い建築となっているが技術的には高価なできだ。質素どころではない。教会と修道院の建設は長い年月がかかる。ミラノ公、ルドヴィコ・マリーア・スフォルツァ(Ludovico Maria Sforza)(1452年~1508年)(在位;1479年~1499年)が引き継ぐと後陣はスフォルツァ家の霊廟としてブラマンテに造りかえさせた。ブラマンテはソラーリが完成したばかりの後陣を取り壊し、現在のような後陣を完成。結局、フランスの侵略があり、霊廟にならなかったが・・。僧院回廊はドナト・ブラマンテ(Donato Bramante)(1444年頃~1514年)今見てもオシャレです。リンク 修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復リンク ミラノ(Milano) 1 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 1)リンク ミラノ(Milano) 2 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 2 聖堂内部)リンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-1 (会員登録と仮予約)リンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-2 (仮予約と支払い)ミラノ公居城スフォルツェスコ城ミラノ公に呼ばれたレオナルドもこの城の中で暮らしていたと思われる。1450年にミラノ公爵フランチェスコ・スフォルツァがヴィスコンティ家の居城を改築して城塞化。16~17世紀にかけて増改築された居城は欧州でも有数の規模の城塞となっていた。図は城に置かれていた看板に少し着色しました。六芒星(ろくぼうせい)の形に城壁と堀を配置した鉄壁の守りをとった要塞です。今は堀は無く、一部形跡は残っていますが、正面には噴水広場が造られている。現在残っている城は少し形が違う? 1891年~1905年にかけて、建築家ルカ・ベルトラミらによって修復されているからかも。現存しているのは1/4程度。現在、内部は市立博物館(Musei del Castello Sforzesco)となっていて、近年復元作業のすすめられているレオナルドの天井壁画がある。サラ・デッレ・アッセ(Sala delle Asse)1498年、レオナルドとその助手たちはミラノ公からスフォルツェスコ城(Castello Sforzesco)のサラ・デッレ・アッセ(Sala delle Asse)(アッセの間)の絵を描くよう依頼されたという。その証拠はレオナルドがミラノ公(ルドヴィコ・スフォルツァ)に「9月までに完成させると約束している」と書かれた1498 年4月21日付け書簡により判明。レオナルドは石膏にテンペラでアッセの間に木から茂る植物(桑の木?)を描いた。まるで屋外のパーゴラの下に居るようなだまし絵である。しかし、この手紙の直後、1499年にミラノはルイ12世率いるフランス軍に進軍されスフォルツェスコ城は陥落。アッセの間の絵は未完となった。未完の絵は後年塗りつぶされていた事が判明。1498年 サラ・デッレ・アッセ(Sala delle Asse)2013年以降修復作業が続けられた。上の写真は修復前のもの。下はウィキメディアから。ミラノ陥落後、城は何世紀も他国の要塞として軍事利用されてきた。その過程で部屋の絵は白く塗りつぶされ失われていた。1861年、イタリアが統一された時、城は完全にボロボロ。取り壊しか? 修復か?建築史家ルカ・ベルトラミ(Luca Beltrami)(1854年~1933年) がその修復に携わると1893年、部屋を覆う白い表面の下、元の塗装の痕跡がいくつか検出されたと言う。現存数が少ないレオナルドの作品としてサラ・デッレ・アッセ(Sala delle Asse)は貴重なのである。ミラノ公とのミラノでの仕事レオナルドのミラノでの功績は先に紹介したスカラザ前のレオナルド像にレリーフで刻まれている。実はレリーフの説明がどこにも無くて困っていた。意外な所(Ludovico Maria Sforza)から出てきたのだ。20年間ほぼ公国に専念したミラノ公ルドヴィコ・マリーア・スフォルツァ(Ludovico Maria Sforza)(1452年~1508年)(在位;1479年~1499年)の評判はすこぶる良い。エレガントでハンサムな容姿(詩人たちは彼のそのかっこよさを賞賛した)、教養があり、現地語とラテン語を操る。優れた作家であり、機知に富み、愉快な雄弁家でもある。楽しい会話や音楽を好み絵画の愛好家でもあると言う寛大な存在感を持っていたと言う。魅力的な完璧なルネッサンス期の紳士だったらしい。※ 実弟が対照的に悪かったらしい。レオナルドとはかなり息が合ったのではないか? と推察できる。もし、ミラノがフランスの侵攻を受けなければ、ルドヴィコ・スフォルツァが捉えられなければ、二人はずっとタッグを組んでたくさんの作品や仕事を残してくれただろうに・・。レオナルドはミラノ公ルドヴィコ・スフォルツァに「前任者フランチェスコ・スフォルツァの巨大なブロンズの騎馬記念碑」の依頼を受けていた。原型の石膏像を見せている所?このブロンズは戦争の為にブロンズが供出されたので完成できなかった。レオナルドはルドヴィコ公爵とベアトリス公爵に運河の水門を見せている。ミラノ公ルドヴィコ・スフォルツァは「最後の晩餐」の進捗を見に来たので説明している。レオナルドはモロ? の要塞の計画を示している図。イーモラ(Imola)防衛の事? ミラノとは関係なくなるが・・。ヴェネツィアでは、レオナルドは軍事建築家および技術者として雇用され、海軍の攻撃から都市を守る方法を考案。レオナルドの兵器1502 年、レオナルドは教皇アレクサンドル 6 世の息子チェーザレ・ボルジア(Cesare Borgia)(1475年~1507年)に仕え、主任軍事技師兼建築家として採用されている。レオナルドはチェーザレ・ボルジアと共にイタリアを周り、軍事建築家および技術者として活動している期間が8ヶ月ほどあるのだ。チェーザレはレオナルドに、彼の領土内で進行中および計画されているすべての建設を検査および監督するための無制限の許可を与えている。またロマーニャ(Romagna)滞在中、レオナルドはチェゼーナからチェゼナーティコ港(Porto Cesenatico)までの運河を建設。またレオナルドは新兵器のデッサンやイーモラ地図を残している。※ 図面などはミラノで見学しているのですが、暗い部屋で撮影も禁止でしたレオナルド・ダ・ヴィンチによる発明品、戦車、巨大投石機(カタパルト)、飛行機など、ロワール地方にあるクロ・リュセ城の庭園で実物大の立体展示がされているらしい。図面を探がしたけど見つからず、フランス観光局のサイトから写真を借りました。リンク Explore Franceクロ・リュセ城に展示されたレオナルド・ダ・ヴィンチの発明品サイトには他の写真もあります。連接グライダー(Flying Machine)空圧ネジ(Aerial Screw crop)戦車(Armored Tank crop)走行距離計(Odometer crop)話をチェーザレ・ボルジアに戻すと。実はチェーザレ・ボルジアはスペイン・アラゴン系のボルジア家の一員。先のイタリア戦争(神聖ローマ帝国vsフランス)ではフランス王ルイ12世のコンドッティエーレ(condottiere)(傭兵隊長)を務め、先のイタリア戦争ではミラノとナポリを占領している。要するにフランスの傭兵としてミラノを攻めていたのである。以前、スイスの傭兵の事を書いたが、イタリア内でも同じような状況があった。経済基盤を持たない地方都市は、傭兵として出稼ぎに出ていた。ヴェネツィアやジェノバのような金持ちの海洋共和国は別であるが逆にそうした所は妬みをかい、常に野心の対象とされていたそうだ。だから彼らは傭兵を雇う側。ただ、イタリアの傭兵はスイス兵とはかなり異なる。負け戦はなるべくかかわるのを避け、全滅するまで戦うような事はなかったと言う。勝つ見込みがあるまで戦い。負けそうになれば撤退。だから、かつてヴァチカンが襲われた時にイタリアの傭兵は逃げた。最後まで戦ってくれたのはスイス兵だけ。これが現在に至りヴァチカンがスイス兵しか信用せず雇わない理由だ。※ 以前、スイス人の傭兵の事書いています。リンク バチカンのスイスガード(衛兵)違いは他にも・・。イタリアの傭兵トップは洗練され教養ある事を尊いとした。チェーザレ・ボルジアはローマで暮らし、ピサやペルージャの大学で法律等を学んでいる学識者。しかし狩猟や武芸にも励んだ強者。そんな男が教会の重責もになっていたのだから中世は不思議だ。1492年 バレンシア大司教1493年 バレンシア枢機卿また、君主論の中でマキャヴェリは君主となる者はチェーザレを見習うべき人物としてあげている。彼はチェーザレの印象を「容姿はことのほか美しく堂々とし、武器を取れば勇猛果敢であった」とも書いているそうだ。32歳と若死にしているのが残念ですね。ところでレオナルドは1503年初めにはフィレンツェに戻り、10月に聖ルカ(ギルド)の会員に復帰している。それはつまり、また絵を描くと言う事。フィレンツェ時代1503年頃~1519年 聖母子と聖アンナ(The Virgin and Child with Saint Anne)画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ルーブル美術館(Louvre Museum)聖母マリアと幼児キリスト、そしてマリアの母聖アンナが油彩で描かれた板絵。ベースはポプラの木。スフマート(Sfumato)技法で描かれている。スフマートとは、いわゆるボカシ技法。レオナルド自身が煙のようなと形容しているが、境界をはっきり出さない描き方。1499 年、フランス王ルイ12世の一人娘クロードの誕生を祝う為に依頼されたと考えられている。が、この絵はルイ12世に届けられず、1517年時点でもまだレオナルドの工房にあったと言う。※ ウィキアートからどうもこの絵には諸説あるらしいが、1499年はフランスがミラノに侵攻し、ミラノ公が捉えられた年。先にふれたが、レオナルドは弟子らと共にヴェネツィアに逃げていたはず。どう依頼を受けたかも疑問。1506年~1508年 La Scapigliata (ほつれ髪の女)所蔵 パルマ国立美術館(Galleria Nazionale di Parma)1503年~1519年 モナ・リザ(Mona Lisa)(La Gioconda)画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ルーブル美術館(Louvre Museum)美術史家ジョルジョ・ヴァザーリの著書「芸出家列伝」によれば「レオナルドは、フランチェスコ・デル・ジョコンダから妻モナ・リザの肖像画制作の依頼を受けた」と書いている事から「La Gioconda」とも呼ばれる。※ 「ma donna」はイタリア語で「私の貴婦人」を意味。その短縮形が「mona」。モナ・リザ(Mona Lisa)とは、「貴婦人リザ」と言うことになる。ジョルジョ・ヴァザーリの話は「当てにならない」のが最近の考えだが、1477年に出版されたキケロ全集の余白部分にラテン語の落書きがあり、「レオナルドがリザ・デル・ジョコンダの肖像画を制作している最中である」事が1503年10月という日付と共にに記されていた事が判明したそうだ。落書きしたのは、アゴスティーノ・ヴェスプッチ (Agostino Vespucci) と言うフィレンツェの役人。2004年、科学的検証(赤外線分析)から、絵の制作開始年が、ジョコンダが次男を出産した1503年頃だと言う事も判明したそうだ。それ故、この作品は、デル・ジョコンダ家の新居引越しと次男アドレアの出産祝いだったのでは? と考えられるそうだ。小悪魔・サライ(Salaì)と洗礼者ヨハネ像1513年~1516年 洗礼者ヨハネ(Saint John the Baptist)画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ルーブル美術館(Louvre Museum)イエス・キリストに洗礼を行った洗礼者ヨハネを描いた作品。左手に葦の十字架を持ち、右手は天国を指している。モデルは弟子のサライ(Salaì)と考えられている。明暗を駆使した「陰影法(いんえいほう)」。暗闇から浮かび上がるように描かれており、不敵な微笑みを浮かべている。「モナ・リザ」や「聖アンナと聖母子」と共にともに最後まで手元に残した作品と言われる。サライ自身がモデルだからか?先にミラノの銅像で弟子の一人として写真をUPしている弟子のサライ。人生のほとんどをレオナルド・ダ・ヴィンチと共に過ごした愛弟子であるが、終生悪ガキだった?※ ジャン・ジャコモ・カプロッティ(Gian Giacomo Caprotti)(1480年~1524年) 画家として名乗る時 アンドレア・サライノ(Andrea Salaino)美術史家ジョルジョ・ヴァザーリによれば「優雅で美しい若者で、レオナルドは(サライの)巻き毛を非常に好んでいた」と記している。が、名前の小悪魔(サライ)が示すよう、サライには手を焼いたのだろう。レオナルドの金銭や貴重品を何度も盗み、また嘘つきで強情で10歳でレオナルドに入門してからどれだけレオナルドを困らせた事か?絵の才能はあったらしいから、彼は見捨てずに育てた? 彼はレオナルドが亡くなる直前までずっと側に居た。「洗礼者聖ヨハネ(St. John the Baptist)」と「バッカス (Bacchus)」はサライがモデルとなったと考えられている。問題はヨハネが美しすぎる事。だと私は思う。荒野の修道士である洗礼者ヨハネはたいてい薄汚れたおじさんで描かれてきた。こんな美しい、色気のある洗礼者ヨハネは他に見た事がない。次に紹介する絵はバッカス (Bacchus)と言う表題とされているが実は洗礼者ヨハネだったかもしれない作品として揺れているのである。制作年代で言えば、バッカス (Bacchus)の方が先に描かれている?1510年~1515年 バッカス (Bacchus)? 洗礼者ヨハネ(Saint John the Baptist)?画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ルーブル美術館(Louvre Museum)ブドウの葉の冠を頭に戴き、ヒョウ皮の腰巻きを付け、左手に杖をつかんでいる。これはほぼバッカス (Bacchus)の象徴である。バッカスであるなら杖はテュルソス(thyrsos)だと思われる。※ バッカス (Bacchus)ローマ神話の酒の神。ギリシア神話のディオニューソス(Dionȳsos)。※ ウイキョウの茎に蔦があしらった杖がテュルソス(thyrsos)。気になるのは右手で右方面を指さしている事。これはレオナルドお気に入りのポーズと思われるが、バッカスならワイングラスを持たせてもよかったのだ。この不思議、どうもレオナルド本人は洗礼者ヨハネを描いたらしいのだ。しかし、1683年から1693年の間にローマ神話のバッカス(ギリシア神話の酒神ディオニューソス)に書き換え変更されているらしい。つまり、誰かが絵の主題の変更をおこなっているのだ。何故に変更されたのかははっきりしていない。考えうるのは、美しく、若々しく、両性具有的な雰囲気を漂わせる色気をかもす洗礼者ヨハネの姿は、セオリーから遠い。なまめかしい洗礼者ヨハネに教会からクレームでも入ったのか?その可能性は高いと思われる。逆に、レオナルドは今までに無い美しくさえある聖人を描いたのだ。そこに彼が意図した事を読み解く方が面白い。この絵はフランソワ1世(François I)(1494年~1547年)の治世にフランスの王室コレクションに入り、ルーブルに収まったと考えられている。ロワールのアンボワーズにレオナルドが居た時に本人から受け取っているのかも?サルバトール・ムンディ(Salvator Mundi)「世界の救世主」の意を持つサルバトール・ムンディ(Salvator Mundi)とはイエス・キリストの肖像である。1500年 Salvator Mundi(世界の救世主)画家 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)所蔵 ルーブル アブダビ(Louvre Abu Dhabi)? ではないようです。写真はウィキメディアから借りました。真作としての発見この絵には不思議な来歴がある。レオナルド・ダ・ヴィンチの真作として歴史の表に出たのはほんの近年の事。ミラノを侵略したヴァロワ朝のフランス王ルイ12世(Louis XII)(1462年~1515年)の為に描かれたと言うキリストの絵。チェーザレ・ボルジア(Cesare Borgia)経由で依頼されたのかもしれない。が、英国のチャールズ1世(Charles I)(1600年~1649年)の手に渡って1763年以降行方知れずとなっていた。1900年に英国の収集家フランシス・クックが、ロンドンのリッチモンドにあるダウティ・ハウスのコレクションの為にJ・C・ロビンソンから購入した絵画(Salvator Mundi)は当初、レオナルドの弟子ジョヴァンニ・アントニオ・ボルトラッフィオの作品と信じられていた。※ 前出、ミラノの弟子の銅像で紹介。1958 年のオークションで 45ポンドで売却。 2011 年まで彼の作とされ続けていたのだ。それは、過去の修復の問題であった。2005年サルバトール・ムンディが、ニューオーリンズのセント チャールズ ギャラリー オークション ハウス(St. Charles Gallery auction house)でオークションに出品された時点では、絵は模写に似ているほどにかなり塗り重ねられていたと言う。アートディーラーのコンソーシアム(consortium)は 1175ドルで購入したが、そもそもこのひどい状態の絵画が、長らく行方不明だったレオナルドのオリジナルである可能性を信じていたらしい。だからしかるべき所に修復を依頼。※ ニューヨーク大学のダイアン・ドワイヤー・モデスティニ(Dianne Dwyer Modestini)に依頼。そもそもパネルの虫食いはひどく、修復過程で絵画が7つの断片に割れている。修復プロセスの開始時に上絵をアセトンで除去し始めた時、コピーではあり得ない事実を発見(指の位置に修正が加えられていた事)された。コンソーシアム(consortium)は 2005年、1175ドルで入手した作品は修復の結果ダ・ヴィンチの真筆と報道した。2008年、ロンドンのナショナル・ギャラリーが世界中の権威5人に鑑定依頼。結果は賛成1、保留3,反対1。弟子の作か? 工房の2級品か? 結局わからないまま?2011年、ロンドンのナショナル・ギャラリーで展示。期待値は高まり値段は高騰。2013年、サザビーズ (Sotheby's)のオークションでスイス人美術商イヴ・ブーヴィエ(Yves Bouvier)に8000万ドル(約90億円)で落札。後、ロシア人富豪ドミトリー・リボロフレフ(Dmitry Rybolovlev)が1億2750万ドル(約140億円)で購入。※ 画商と購入者間の手数料問題で訴訟トラブルが起きている。またリボレロフ氏はサザビーズも訴えた。2017年11月15日にクリスティーズ(Christie's)のオークションで4億5031万2500ドル(当時のレートで約508億円。手数料を含む)で落札された。※ 2015年に落札されたパブロ・ピカソの「アルジェの女たち バージョン0」の1億7940万ドル(約200億円)を抜き史上最高額。香港やロンドン、そしてニューヨークでのプレビューに訪れた人数だけでもクリスティーズ史上最高の2万7000人。それだけ感心が高かったと言う事。真贋、分かれながらも、本物として値段は高騰して行った。この時点で落札者は不明だった。2017年11月8日、ルーヴル美術館の姉妹館としてフランスのマクロン大統領とアラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム副大統領とムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン皇太子によってアブダビ市街に隣接するサディヤット島の文化地区にルーヴル・アブダビ(Louvre Abu Dhabi)開館。600点の所蔵作品に加え、パリのルーヴル美術館をはじめとするフランス国内13の美術館・博物館から貸し出された300点が展示ルーブル・パリとの契約金は30年で5億2500万米ドル。このルーヴル・アブダビ(Louvre Abu Dhabi)の目玉として、サルバトール・ムンディ(Salvator Mundi)が公開される事が2017年12月6日に発表された。サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン(Prince Mohammed bin Salman)皇太子が個人で、代理人を通じて購入していたらしい。ルーヴル・アブダビでサルバトール・ムンディ(Salvator Mundi)が公開される事。当時、私もテレビの特番で知った。誰か女優さんがUAEに行って作品を直接見せてもらっている画像もあった。UAEに行けば見られるのかと思っていた。ところが、その後、UAEでのサルバトール・ムンディの公開は中止となっていた。2018年9月、ルーヴル・アブダビで予定されていたこの絵画の展覧会が無期限延期されることが発表。また、2019年10月に予定されていたパリでのヴィンチ展でも公開されるはずであった。これに関しては、どこに飾るか? でサウジ側と意見が合わず中止になった模様。では絵画はどこに?2020年末までムハンマド・ビン・サルマン皇太子のヨット(Serene)の船内に飾られていたらしい。潮風に当たったらまずいのでは?結局、未だ公にはほとんど公開されぬままの状態。2024年に完成予定のサウジアラビアのWadi AlFannに新しい美術館がオープンするので、そこで公開される予定はあるらしい。1516年~1519年フランス、ローワール時代フランソワ1世(François I)(1494年~1547年)は1516年、ロワールのアンボワーズにレオナルドを招聘(しょうへい)した。アンボワーズ城(Château d'Amboise)自身の城は歴代ヴァロワ朝の国王が過ごしたアンボワーズ城(Château d'Amboise)。※ シャルル7世、ルイ11世、シャルル8世、フランソワ1世。アンボワーズ城近くに自分が幼少期に暮らしたクロ・リュセ城(Château du Clos Lucé)があり、そこにレオナルドを住まわせた。レオナルドは亡くなるまでそこに居た。クロ・リュセ城(Château du Clos Lucé)模型の置かれたクロ・リュセ城(Château du Clos Lucé)は、晩年のレオナルドの住まい。ウィキメディアから借りました。The chamber of Leonardo da Vinciレオナルド・ダ・ヴィンチの部屋1482年から1499年まで、レオナルドはミラノで活動していた。本当は、そんなに長く居るはずではなかったのかもしれない。おそらく事情が変わったのはメディチ家の没落である。以前、「コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)」の中でメディチ家銀行の事、ロレンツォ・デ・メディチ(イル・マニフィコ)(Lorenzo de' Medici detto il Magnifico)(1449年~1492年)の事を書いているが、メディチ銀行は最終的に1494年に破綻し、全ての支部の解散宣言が出て1499年に閉鎖している。リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)芸術家を支援し、フィレンツェを一流の都市に押し上げていたメディチ家の没落が社会に与えた影響は大きい。レオナルドもパトロンを失い、戻るに戻れず、ミラノでお世話になっていたのだろうと想われる。ところが、そのミラノでも頼りにしていたミラノ公は、ルドヴィコ・マリーア・スフォルツァ(Ludovico Maria Sforza)(1452年~1508年)はイタリア戦争のおりに捕らわれ、身代金を払って解放される時に暗殺されてしまった。レオナルドは当時有数の海洋共和国であったヴェネツィアにとりあえず渡ったのもうなずける。でも、ヴェネツィアはヴェネツィア派と呼ばれるジャンルがあるくらい画家も多い。きっと新たなパトロンを見つけられず? フィレンッエに戻っている。仕方なく? チェーザレ・ボルジア(Cesare Borgia)(1475年~1507年)の元に何でもすると売り込みに? 行ったのかもしれない。実際、レオナルドは1502年~1503年、イタリア諸都市の要塞を見学してまわっている。若いチェーザレ・ボルジアは頼りにしていたかもしれない。しかし、レオナルドは8ヶ月でフィレンッエに戻っている。結局ボルジアも7年後には亡くなっているので居ても二の舞だったが・・。1503年、フィレンツェに戻ったレオナルドはルカの会員に戻り、普通の親方絵師として個人の依頼をこなしている。もはや仕事は選んでいる場合ではなかったのだろう。しかし、持ち前の実験好き。それはトラブルの元になって行く。報酬の返還要請や描き直し、修復の依頼など多発。レオナルドは全て無視したらしい。もはやフィレンツェに居られず?ロレンツォ・デ・メディチの息子がレオ10世として教皇となっていたのでローマにも行ったらしい。だが、期待に反してレオ10世には相手にされなかった。ローマでは、レオナルドはもはや過去の人になっていたらしい。好奇心の強いレオナルドが普通に依頼の絵を描いているだけの事に満足するはずが無い。好きに絵を描いたり、彫刻を造ったり、研究をしたりするにはやはり大物のパトロンが必要。1516年、ミラノと敵対していたルイ12世の後継者であるフランス王フランソワ1世が声をかけてくれた。脳卒中ですでに手にマヒも出ていたレオナルドだが、フランソワ1世はレオナルドを非常に尊敬していたらしい。ロワール渓谷のアンボワーズで、穏やかに隠遁生活を送れるよう、自分が育った居城をレオナルドの為に提供もしてくれた。そこで手稿をしたためたり、好きな事をして、お気に入りの弟子と共に最後の3年を過ごし亡くなった。レオナルドの最後はフランソワ1世に抱きかかえられながら息を引き取ったとも伝えられる。絵画でそんな絵がある。本当かはわからないが、フランソワ1世に大事にされていただろう事は伝わる。享年67歳。(1452年4月15日~1519年5月2日)最後が幸せで良かったと想う。完がんばったげど、8月中に載せられなくて残念
2023年09月01日
閲覧総数 719
-
20
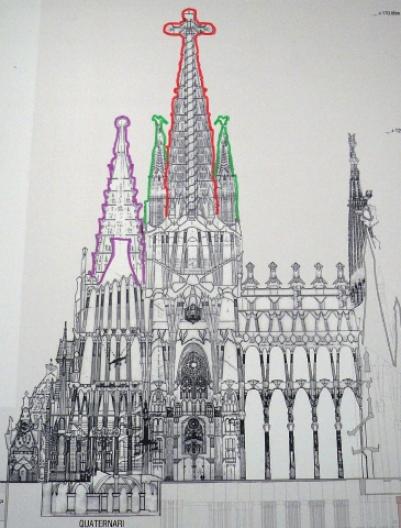
サグラダ・ファミリア 10 (教会建設)
最近弟や従兄弟が拾い犬をしてきてそのまま飼い主になっていますもちろん警察には届けたそうですが、ペットは生き物なのに拾得物になるようで・・しかし、実際倉庫に置ける物ではないので、落とし主が見つかるまで拾った人間が世話を頼まれるようです。しかも「期限に持ち主が見つからない場合は保健所に送る・・でいいですね? 」と聞かれるので結果見つからない場合は情も移るので拾った人が飼うパターンになるようです。さて、従兄弟のワンコですが、拾った・・と言うよりむしろ犬に選ばれた人のようです。ずっと彼の後ろをついてきた犬は糖尿病持ちで、おそらくその為に前のご主人に捨てられたのかもしれません。毎日のインスリン注射代金がとてもかかるのだそうです。それでも、ワンコはたまたま孫のいない伯父に気に入られ、家の中でみんなに可愛がられながら今は暮らしています。人を見る目があった犬だな・・と思ったのでしたサグラダ・ファミリア 10 (教会建設)サグラダ・ファミリア(Sagrada Familia) Part 10今も建築がつづく教会の屋上と聖堂の天井と照明サグラダ・ファミリア完成予定図の・・教会断面図左が聖所側で、赤、緑、紫は現在はまだ建築されていない塔ですが、特にこの教会のシンボルとなる170mの高さを持つ重要な塔です。教会の塔赤・・・聖堂中央ドームの上にそびえる予定のイエスに捧げられる塔。紫・・・聖堂後陣の上にそびえる予定のマリアにささげられる塔。緑・・・聖堂中央ドームの下にあった4本の柱の上 ・・4福音書記者(マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネ)に捧げられる塔。後の鐘楼は前に紹介したように東の南、西に各4本で12本が12使徒に捧げられる塔です。東(降誕のファサード)・・マテア、ユダ、シモン、バルナバ南(栄光のファサード)・・アンデレ、ペトロ、パウロ、大ヤコブ西(受難のファサード)・・小ヤコブ、バルトロマイ、トマス、ピリポ東の塔からの撮影なので、あちらに見えるのが西側の塔だと思います。つまり小ヤコブ、バルトロマイ、トマス、ピリポの塔のようです。よくみれば中の芯に鉄筋が使われていますね。素人なので工事はわかりませんが、セメントを使っているようにはみえません。外壁はパーツの貼り合わせのようです。写真右の人達はその場で石を加工して積み上げているようです。驚くのはコンクリートに貼り付けるのではなく、鉄筋のまわりに組んでいる・・と言う事です。反面鏡のような形をしているそれは何なのか?おそらく考えられるのはこれが中央ドームの上、イエスの塔の内部になるのでは? と考えられます。なぜそんな形をしているのかはガウディに聞いて下さいしかし、内部に光りを取り込むような設計になっているのは間違いないと思います。そして、こちらの奥に見える原子炉のような形の物は?おそらく後陣に建つマリアの塔の内部になるのでは? と考えられます。双方場所的に判断しています。たぶん上の内部断面の図面からも間違いないと思いますが・・とても不思議な形ですところでここで、参考に本からの写真を載せました。この工事は聖堂の内部の天井の上の葉の裏側? の部分てす。すでに聖堂内部が完成しているので、今はこの工事は終っていますが、かなり緻密に作られているのが解る写真なので載せてみました。この富士壺のようなものが、後から紹介する天井の穴一つ一つになるようです。聖堂の明かり以前紹介していますが、聖堂内部の写真を再び写真左・・・聖堂内、中央ドームの聖堂の天井写真左・・・明るいの天窓が後陣、マリアのドームの聖堂の天井ガウディは光の効果を利用して教会の神秘性を高める設計を心がけたようです。大窓、丸天井、その他あらゆる採光の要素は、森の木々の葉から光が差し込むような照明を実現する為に設計されている・・と言う事は前にも紹介しましたが・・。それは外からは光を取り込むような形状に作られ、中においては光があらゆる方向に拡散するような散光の形状に設計されているようです。建設中の双方のドームの内部構造の秘密・・が写真にはあるのかもしれませんが、建設関係者ではないので残念ながらわかりません。まだ本においても天井や塔については詳しく紹介されたものもないようです。しかし、特に以前紹介したように天井の変わったデザインは、殉教のシンボルであるシュロの葉があわさったデザインをイメージして作られています。そのデザインそのものが木漏れ日のように光を拡散させる効果を持っている・・という点は納得です。以前も聖堂内部の時に紹介した天井の写真と、夕刻の聖堂内の写真を載せますので比べてみて下さい。高さ45mにあるボールトに開く双曲面状の採光窓が身廊天井にはたくさんちりばめられています。因みに写真左右の側廊部の天井は白いコンクリート製だそうです。外からの明かり以外に人工の照明も組み込まれていますが、自然光のようなやわらかさの光は区別がつきにくいです。あの紋章入りの明かりの穴が上で紹介した富士壺型の一つ一つになっているわけです。拡大紋章のマークは聖人たちの紋章であったり、キリストやマリアを示すアナグラムのようです。さらに拡大実際下から肉眼では識別もできませんが、先ほどの富士壺型の穴(天井のボールト)にはめこまれているのは所謂提灯(ちょうちん)のようなガラスの装飾です。これも参考の為に本から載せました。こんなガラスの飾りが一つ一つに組み込まれているようです。これ一つとってもりっぱなオブジェですね。身廊側面のファサードのピナクルにはフルーツ盛り等の装飾がトッピングされています。巨大なサグラダ・ファミリアは装飾だらけの教会です。その装飾一つ一つが芸術作品として丁寧にコツコツ手作りされているのですから恐れいる工程です。近代的な工法や機械を導入してもボランティアによる手作りの工事でサグラダ・ファミリアは建設されているのです。写真は柿とイチジク最後に・・教会の着工は1882年3月19日。聖ヨセフの日に礎石。内部の礼拝堂が昨年(2010年)11月7日、ローマ教皇ベネディクト16世の来訪に併せて完成。教会の完全な完成予定はガウディの没後100年の2026年。今回はこんなところでサグラダ・ファミリアは終わりたいと思います。またいつが続編があるかもしれません。Back numberリンク サグラダ・ファミリア 1 (未完の世界遺産)リンク サグラダ・ファミリア 2 (降誕のファサード)リンク サグラダ・ファミリア 3 (生命の木)リンク サグラダ・ファミリア 4 (未完の理由 と主祭壇)リンク サグラダ・ファミリア 5 (天井と福音書記者の柱)リンク サグラダ・ファミリア 6 (天井の立体幾何学模様)リンク サグラダ・ファミリア 7 (ステンドグラス)リンク サグラダ・ファミリア 8 (受難のファサード)リンク サグラダ・ファミリア 9 (鐘楼のバルコニーから)サグラダ・ファミリア 10 (教会建設)
2011年01月31日
閲覧総数 1110
-
21

古代ローマの下水道と水洗トイレ
写真など入れ替え改定しました皆さんが古代ローマの水道の話を忘れてしまう前にどうしても下水道に触れておきたいです。古代ローマの下水道と水洗トイレ古代ローマの下水道工事エフェソスの公共トイレ(水洗式)水洗トイレの起源古代ローマの下水道工事BC753年に初代ローマ王ロムルスが現イタリア、ローマのテレヴェ川域の七つの丘の上に街を築いた時、丘に囲まれた盆地は(後のフォロ・ロマーノ)排水性の悪い沼地でした。当時、人は丘の上に住み、丘の下は死者を葬る以外使えない土地。丘の上の居住が手狭になると、人々は沼地に降りて市場や集会所としてそこを使うようになる。そこで、この沼地の排水工事が必要になったようです。工事をしたのは、エトルリア出身の第5代王タルクィニウス・プリスクス(在位BC615年~BC579年)。異邦人にもかかわらず市民権を得、先王の死後立候補して王になった異色の王です。彼は、平和な時に兵士を使って王の故郷エトルリアから導入した技術で水道を建設したり下水工事をしたようです。湿地であった土地に水はけ用の水路を造り、集まった水を川に流す為の大下水溝クロアーカ・マクシマ(掘割式)を完成させ。(BC575年頃)排水機構を整備します。この排水溝はBC2世紀頃まで露天でしたがローマの富と力が増大すると、下水溝は石造りのアーチ(ヴォールト)で覆われBC33年クロアーカ・マクシマはリメイクされました。驚くべき事にクロアーカ・マクシマは2500年以上たった今でも立派に排水溝として使われているようです。パラティーノ橋近くのテヴェレ川に石造りアーチの直径4メートルくらいの排水溝が出ているのがそれらしいです。※ 一部、紅山雪夫さんの著を参考にさせてもらいました。下水に関しての詳しい資料が拾えないので、判っている事から推察すると、古代に栄えていたエトルリアから上下水道は伝わり、古代ローマではほぼ同時に上下水道が完備されたのではないかと考えられます。エフェソスの公共トイレ(水洗式)下は下水道あっての古代の水洗トイレです。写真は前に紹介したトルコのエフェソス遺跡(古代ローマ水道 4)からです。エフェソスの最初の起源はBC10世紀頃イオニア人の入植により始まったとされますが、ローマの属州時代がこの都の最盛期です。下のトイレはローマ時代のものかギリシャ時代からあったのかはちょっと解りませんが、見た所、ギリシャの古代遺跡で見たトイレと全く同じタイプだと思います。奥に見えるのが図書館です。公共のトイレは図書館の近くにあったのです。見てわかるように座るタイプです。便座前に貯水槽があり、そこに海綿が置かれ、それで拭いた? とか掃除した? とか?ガイドの説明がありましたが・・。ここはかなり広い(30畳以上?)スクエアになっていて。回りをぐるりとトイレが並んでいます。数えた人の話では40以上席があったとか・・。一枚石版に3人分。たいした道具も無い時代によくこんなに綺麗にできたものです。床に足を置いてへこんだ跡が見えるのがリアルです。下は水が常に流れる水洗式で、汚水は下水道で川まで運ばれたようです。水洗トイレの起源水洗トイレはローマが始まりではありません。今から4000年以上前のメソポタミアのシュメールのエシュヌンナ遺跡からアッカド王朝時代(BC2200年頃)の宮殿に残る世界最古のトイレが発見されているそうです。煉瓦で椅子形に積み上げた腰掛け式の水洗式トイレで、廃水は壁に沿って造られた地下管に流れ込んでいた。管は地下に掘って埋められ、その上にアーチの蓋が掛けられた。その中は上部に通路があって掃除のために歩けるようになっていたらしい。同じくオリエントではBC2100年頃、一般住宅にも同様のトイレがあったようです。下を水が流れ、汚水は焼き物で造られた配水管を通って下水道からティグリス川の支流へと流れる水洗式トイレであったとされています。(ウキペディアより)また地中海に浮かぶ島、クレタ島でもBC2000年頃から発祥したクレタの遺跡からも水洗トイレは見つかっているそうです。(こちらは木製の便座)近年まで水洗トイレを知らなかった日本人からしたら驚きのトイレ史ですね。水洗トイレの発祥元がどこだったのか? たまたま同じ原理にたどり着いたのか? まだ謎です。ところで、ローマの水洗トイレはギリシャ由来なのは間違いありません。なぜならローマの下水道及びこうしたトイレの文化はギリシャの文化を吸収したエトルリア人からもたらされたものだからです。
2009年06月05日
閲覧総数 8664
-
22

二度と行きたくないカタコンベ
何度も訪れたい国や都市があり、ハワイのように毎年バカンスをおくりたい場所がある一方、私には二度と足を踏み入れたくない場所もあります。一つはローマ市の城壁の外、旧アッピア街道沿いにあるカタコンベです。二度と行きたくないカタコンベアッピア街道(Via Appia)カタコンベ(Catacomb)アッピア街道(Via Appia)はローマ街道の中でも古くからある街道の一つです。古代ローマの繁栄時代「すべての道はローマに通ず」と言われ主要都市とローマは幾つもの街道で結ばれていました。その中でもアッピア街道は軍隊の迅速な移動を目的とした舗装された街道一号だそうです。(馬車が通れるように大きな敷石が敷き詰められています。)紀元前71年、約6000人の奴隷が反乱を起こしマルクス・リキニウス・クラッスス(カエサルと共に三頭政治をした人)によってこの反乱が鎮圧されると、「逮捕された反乱者たちは街道沿いに十字架にかけられた。」と言うエピソードもある街道です。カタコンベ(Catacomb)カタコンベ(Catacomb)は地下の墓所の事で、死者を葬る為に使われた洞窟、岩屋や地下の洞穴のことを指します。(何層にも深く掘られている。)古代には城壁内に墓所を作る事が禁じられていた為、墓所は城壁外の街道沿い作られたのです。カタコンベ(Catacomb)は最初、単なる墓地にすぎず、ここでキリスト教徒たちは葬儀を行ったり、殉教者や死者を記念する祭儀を行っていたようです。キリスト教徒迫害時代にはここに隠れ住んだとも言われていましたが、実際はそのような事はなく、ただ殉教者が葬られた為に巡礼の聖地となったと考えられているようです。アッピア街道沿いにはこのようなカタコンベがたくさん点在していて、有料で見学させています。私が入ったカタコンベは名前も覚えていませんが、当時発見されて間もなかったのか、教会も建てられていなかったと思います。当時ローマのカメオ屋さんで働いていたF氏に連れられて何も解らないままにここに来て、中に入れられました。10人単位くらいでまとまって一列に(通路が狭くて一人しか通れない)闇の中に下って行くと、両サイドは何メーターかある高い壁になっており、そこにはいくつもの穴が開いて(横に広く)縦には三段くらいで、石の蓋のついたままのもありました。怖かったです。深く進めば進む程背筋の凍るような恐怖で、見ず知らずの前の外人の背中をつかまえて、気がつけば数珠つなぎ、芋虫のように全員が繋がっていました。途中で一人が恐怖で狂って走って逃げて行きましたが、かえって危険な行為です。たまに迷子になって死ぬ人もいるようです。普通に立って歩く事が出来ません。頭の上が怖いのです。(両サイドも怖いけど・・)皆頭を下げて前の人の背中に押しつけるようにこごんで歩いていました。私は見えないけれど、比較的敏感な方の性質なので、半端ない恐怖体験でした。怨念が強い霊が多すぎだったのでしょう。まだきちんとお祓いもされていない墓地だったのだと思いますが、凄かった・・・。知ってたら絶対入らなかったのに・・。その翌日だったか、バチカンのサン・ビエトロ寺院に行き、地下に眠る歴代法王の墓が一般公開されていたので入りました(懲りもせず・・)でも、そこは清らかでした。清められているのが解りました。さすがバチカンだと感心しましたね。 アッピア街道もカタコンペも写真はありません。下はバチカンのサンピエトロ寺院。ローマ・カトリックの総本山です。バチカンやローマも追々紹介していきます。もう一つは次の機会に・・。同じく幽霊がらみですが、こっちは後が怖かった・・。
2009年05月05日
閲覧総数 32407
-
23

ノートル・ダム寺院 7 (東聖堂側とゴシック建築の特徴)
今回は建築の話になってしまいました。ノートル・ダム寺院(Cathédrale Notre-Dame )ジャン(ヨハネス)23世小広場(Square Jean-23)聖堂後陣のある東側をジャン(ヨハネス)23世小広場より撮影。A19世紀初頭までは礼拝堂や大司教館が建てられていてノートルダム寺院の聖堂後陣側が望めることはなかったと言います。1831年、反王党派の暴動の際に建物全体が完全に破壊され撤去。B1844年に、小広場とネオ・ゴシックの噴水が出来て見晴らしよくなったようです。盛期ゴシックを代表する建築の特徴が伺える聖堂の建築がよく見えます。Cゴシック建築の特徴1. 正面入口の両側に高い2本の塔と入口の上にはバラ窓。2. 身廊にはリブ付きの高い交差ヴォールトの天井。3. さらに天井まで一杯に広げられた先尖りアーチの窓にもステンドグラス。4. 内陣の背後の壁も身廊と同じ高い窓になり、ステンドグラスが入り、聖堂全体が驚くほど広く、明るく出来ている。5. 高く持ち上げられた側壁は、外側からフライング・バットレスで支えられている。ゴシック建築は12世紀半ばから15世紀まで続き、3期に分けられます。12世紀半~13世紀初頭 初期ゴシック (ノワイヨン、ラン等) ~13世紀中半 盛期ゴシック (ノートルダム・ド・パリ、シャルトル、ブールジュ、ランス、 アミアン、ソールズベリ、リンカーン等) ~15世紀 後期ゴシツク (ルーアン、ケルン、ストラスブール、ヨーク・ミンスター、 グロスター等)後陣の屋根の上から内陣の壁を支えるフライング・バットレスDフライング・バットレス(Flyng Buttress)ロマネスク時代に側廊屋根裏に隠されていたアーチを屋根(身廊天井)を高くする為に外に出して、側廊から空中アーチで高い身廊の外壁を押さえる為に架けた飛梁です。バットレスは、もともと建築物の外壁の補強のための、屋外の張り出しを言います。簡単に言うと、積んだ石壁が、上からの重みで壁が外に押し出され、湾曲しようとする推力を押さえる為の押さえです。側廊屋根よりも高い位置に設置される為に身廊上部が塞がれる事もなく、大きな窓をとることができるようになり、ステンドグラスがたくさん入れられるようになったわけです。後陣と側廊の屋根の上から内陣の壁を支えるフライング・バットレスE聖堂内陣上部のステンドグラス。写真Dの窓の内側Fフライング・バットレスのおかげで、内陣の礼拝所の上に窓ができて聖堂内の昼は明るくなった。フライング・バットレスは後陣の屋根の上にあるので、その下の後陣には区切られた小さな礼拝室が並んでいます。つづく
2009年10月15日
閲覧総数 794
-
24

新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情
マリーアントワネット関連back numberのリンク先をラストにさらに追加しました。フランソワ・ブーシェ(François Boucher)の作品の中から衝撃の絵を発見しました。これで全ての説明が付きました。客人は持参のオマル? の下に写真追加。写真を入れ替え、増やして編集し直しました。全面改訂です。「マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情」初期も初期に書いた、つぶやきに近い物が、毎日一番多いアクセスをいただき恐縮です。長らく避けてきましたが、写真だけでも入れ替えをと見たら、中身もとてもはずかしい内容で。 (* v v)。ハズカシイ やはり直したくて仕方無くなりました。前作では、ベルサイユ宮殿は入場料を取る上にトイレも有料と言う事を書きました。トイレ代金はトイレ管理のおばさんへのチップとして徴収されていたのですが、おばさんがチップの金額をごまかすのを防止する為に領収書を発行していたのです。それが2018年くらいに新たな無料の大きなトイレが王の前庭の地下に造られ、渋滞の大幅改善がされたようです。入り口はガブリエル翼と旧翼の両方からアクセスできると言うので、個人入場口と団体入場口の両方から入れるトイレらしい。とにかくベルサイユのトイレは評判が悪かったのです。最も、このトイレも庭だけ見学の人は対象外らしく、城への入場料を支払った人のみと言う事らしい。新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情トイレ事情の悪いフランスベルサイユ宮殿のトイレ事情マリーアントワネットのトイレシオン城のトイレ客人は持参のオマル?ルイ14世は「最高の香気を匂わす国王1778年マリーアントワネット22歳の肖像画マリーアントワネットが王妃になるのは1774年。18歳で王妃にこちらの写真はウイーンの美術史美術館から持ってきました。実家に送られたマリーアントワネットの肖像画で、ルイ16世と対になっています。ベルサイユにも同じ物があるようですが、こちらは大きい作品です。本物であるのは間違いないです。トイレ事情の悪いフランスそもそも、フランスと言う国自体、公共のトイレが今現在でも非常に少ない国です。地下鉄駅にトイレは存在しないし、フランス国鉄の大きな駅でさえ、個室が僅かの有料トイレが一つある程度です。※ ルーブル美術館の駅だけ外に個室の多い有料トイレがありました。デパートもそうです。各階にトイレは無く、1階おき。男性はさらに数が少なかったと記憶しています。また、必らずと言って良いほど壊れて使用できないトイレが複数存在するのでフランスでトイレはどこも行列です。そう言えば、シャルル・ドゴール空港でも、真ん中あたりの地下に一つとそこまで行くのに大変でした。※ 一つと言う事はないでしょうが、トイレまでの距離がありすぎるし、必ず待つ事になるので時間がね。パリの街は今でこそ下水道がしっかり完備されましたが昔は汚水を窓からバケツで投げ捨てていたらしい。2階の窓から棄てる輩もいたから汚物がはねてドレスが汚れる事も・・と読んだ記憶があります。近年まで下水道の整備が遅れていたのかもしれません。私が初めてパリに行った時、街は犬のフンの悪臭だらけでした。今はフンの清掃が年中来るし、下水溝の間口が広くされ、いっきに洗い流すようにされてパリの街においては、臭い事は無くなっています。が、問題は他にも。この国はトイレが少なく、しかも有料が基本の国なので必然的にトイレでしない人が多いのです。同じフランス語圏のベルギーもそうでした。街や特に地下鉄などの地下道が臭いのです。掃除が行き届いていない事もありますが・・。これではペストも流行るよね・・と思うわけです。そんな訳でフランス旅行はトイレ・ポイントを考えながらプランを作る事をお勧めします。因みに、団体旅行でトイレ付きのバスと言うのがありますが、これもあてにできません。運転手がトイレ掃除が嫌でトイレを使用させない事が多々あるそうです。王の前庭からの王宮この地下に2018年頃、大きなトイレができたらしい。入城者は無料。下の写真のみウィキメディアから借りてきました。ベルサイユ宮殿のトイレ事情「ベルサイユ宮殿にはトイレが無かったので臭くて汚かった。」と言うのは、大方の所では当っていると思います。王や妃の場合は自室の領域に便座トイレの個室があるのを私も見た記憶があります。だから全くなかったと言うわけではないのですが、汚水を処理する下水の観点から見ると、やはり無かったと言えると思います。そもそも近年でも来客用のトイレが宮殿内に設置できなかったのは、そう言う場所が無かったと言う事を意味しているのでは無いでしょうか?ルイ14世時代には、ルイ13世の小城館とル・ボーの新城館の中庭に面した場所に「キャビネ・ドゥ・シェーズ」(椅子の間?)と呼ばれる小さな小部屋があり、シューズ・ペルセ(便座椅子)が置かれていて、ルイ14世の専用トイレだったと言われています。ルイ15世の時は寝室の隣に上げ蓋式の便器を備えた部屋があったそうです。これは城見学に行くとよくあるパターンで、私も見た記憶があります。(捜したが写真が無い)ルイ16世の時は? 「水洗式のトイレを使用していた。」などと言う説もありますが、文献がないのでわかりません。本当に水洗であるなら、下水道が無ければならない。そのような施設がどこにあったのか? どこに汚物を流したのか? と考えると不自然な気がします。ベルサイユは庭の噴水の為に遠く川から水を引き上げていました。水道の方は説明できなくは無いですが・・。ローマ水道の時に紹介したように、水洗トイレは上下水道が完備された時に初めて機能するものだから。プチトリアノン(le Petit Trianon)にある王妃の部屋の中にマリーアントワネットも使用した木製便座のトイレがあります。ガラス張りで中までのぞけませんが、水洗には見えません。横の小さな穴の方が気になります。そこから水でもそそいだのでしょうか?トイレは王妃の部屋に付随している。ベッド類も再現物のようです。また。テキスタイルもちょっと現代風でいただけない貼り方です。ついでにプチトリアノン(le Petit Trianon)のロビー吹き抜けです。ルイ15世がポンバドゥール夫人の為に建設したものの、間に合わなかった建物です。でもロココでなく、新古典様式の建物です。最初に使用したのは次の公妾(こうしょう)デュ・バリー夫人(Madame du Barry)。ルイ15世が病気で倒れるとデュ・バリー夫人は宮廷から追い出された。その後、1774年から1789年までマリー・アントワネットが使用。シオン城のトイレさて、一般のトイレですが、何百人も集まるパーティーなどにおいて、客人が使用するトイレは下水の観点からも無かったと言えます。ただ、使用人達が使用していたであろうトイレはあったはずです。写真を捜しましたが、無くてしかた無く中世のスイスの城から持ってきました。木製になっているだけで古代の石のトイレと似てますね。ただ、あちらは水洗でしたが・・。スイスのモントルー(Montreux) のレマン湖畔にあるシヨン城(Château de Chillon)の兵隊達が使用したトイレです。トイレと言った個室ではなく、煖炉もある広い部屋の一画にあり穴の下は下界です。シオン城の写真はウィキメディアから借りてきました。自分の写真は全景が入っていなかったので・・。前の湖はレマン湖です。客人は持参のオマル?基本的にトイレは椅子型の場合も、オマル型、あるいはし尿ビン型にしても一時的に受けるもので、中身はどこかに棄てなければならないものでした。また、用を足す部屋があったか? 無かったか? と言うなら、客人用には無かったようです。「274の便座椅子がある」と書いてあった本がありましたが、全くもって確証がとれません。招待を受けた紳士淑女たちは、香をたいた携帯のMy便器を持参したと言われています。でも、その中身は従者が庭に捨てていたから、ある廊下のはずれは「汚物で沈んでいた。」とまで書かれていました。一晩のパーテイーに100人来たとして、その従者などいれたら400人以上。確かに一晩で汚物まみれになりそうです。故に、ベルサイユ宮殿が汚物にまみれて汚く悪臭を放っていたのは本当なのでしょう。だから宮殿南の翼にオレンジの果樹園を置いて空気を浄化しようとした。とも言われています。フランソワ・ブーシェ(François Boucher)(1703年~1770年) 写真はウィキメディアから英語版で見つけました。1760年頃の作品。今はプライベート・コレクションとなっています。載せて良い画像か少し悩みましたが、これは当時の風俗が解る貴重な資料と思い掲載しました。何より驚くのは、これをブーシェが描いていたと言う事実。ヽ(・_・;)ノ ドッヒャー 衝撃でした。何でこんな絵を描いたのか? また描かせたのか? この女性の羞恥心は? (;^_^Aそれにしても女性の場合はこんな感じだったのですね。取ってが付いたスープ皿のような受け皿ですね。 ドレスが汚れそうです。これの中身を従者が庭に棄てに行っていたと言う事なのでしょう。住居している人の汚水処理のタンクはあったのかもしれませんが、ベルサイユにそれらを棄てる場所が公式にはなかった。また、汚水はおそらく畑にまかれるとか、遠くセーヌ川まで運ばれて棄てられていたのではないかと結論できそうです。下は、ベルサイユ宮殿内にあるゴブラン織りの衝立です。フランス王立織物工場で宮殿用に制作されたもので、とても精巧な素晴らしい物ですが・・。こうした衝立(ついたて)の物影でスカートの中にオマル入れたのですかね。それくらいの羞恥心は欲しいところです。フランドル産に比べたらたいした事ないと思ってしまう。ルイ14世は「最高の香気を匂わす国王と呼ばれていた。それは、糞便の悪臭をごまかす為に大量の香水をつけていたからだと言われています。その理由は、下絶えず下痢状態で1日14~18回もトイレに行っていたかららしい。また、間に合わないこともしばしばで、便座トイレに座ったままで会議をした事もあったとか。ルイ14世は主治医によって抜歯されていた為に歯が無かった。咀嚼(そしゃく)ができないから消化を助ける為に下剤を飲まされていたからだと伝えられている。香水が最も発達したのはこの頃なのだと言うのも納得ですね。フランス人は昔からトイレに対して、前向きな取り組みをした事がないように思えます。「取り立てて考える必要の無いどうでも良い事象 ? 」当時のエピソードを聞くと、もよおした所がどこかにかまわず、そこをトイレとしていたようです。羞恥心の生まれた18世紀からは「しないような努力と我慢の歴史」となったらしいが・・。最後にマリーアントワネットが使用していたであろう食器を紹介しておきます。今後で使用する事もなさそうなので・・。セーブル焼きの磁器?ティーカップでなくてエッグスタンドにも見えますが・・。まだ完成されていないと言うか手作り感が凄く見えますね。ドイツやイタリアに比べると磁器造りもおくれているようです。磁器の元となるカオリンはベルサイユの近郊であるセーヴルで見つかったそうです。でも当初は技術が追いつかなかったとか・・。トイレ、あるいはオマルの写真がまた見つかりましたら追加しますが、城など行っても、なかなかトイレまで修復していないので無いのが現状です。おわりマリーアントワネット関連back numberリンク マリー・アントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃back numberリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 1
2009年06月19日
閲覧総数 97947
-
25

Break Time 空からの大阪城
Break Time(一休み)一休みどころではないですが・・・ f^^*) ポリポリ大型台風が近づき、日本中ソワソワしているのではないでしょうか?どうかこれ以上災害被害が出ない事を祈るばかりです。実はまた4日から大坂行きです。台風が予定どおり通過してくれないと困るのです空からの大阪城さて、大坂と言えば、今回は私のお気に入りを紹介。実は大坂伊丹空港着陸直前にちょこっと見える空からの景色が好きなのです。飛行機からの撮影なので、窓ガラスが2重でしかも汚れているので、あまり綺麗に撮影できません。多少修正をほどこしてハッキリ見えるようにしていいるのでご了承願いますさて、あれは何でしょう。古墳ではありませんよこれはJAL機内より撮影した大坂市内です。大阪城と大阪城公園、そしてお堀の空撮です。(北外堀側からの大阪城です)下の楕円系のドームは大阪城ホールです。羽田より、JAL機で伊丹空港に飛ぶ時は、必ず左の席を確保季節や天気によって良く見えるかはかなり違います。シャッターチャンスもおよそ5秒程度で撮影の条件は悪いです。かなりボケボケで申し訳けありませんでもお堀がどうなっているか良く見えてなかなか楽しい景色ですところで全日空の場合はコースが違い、大阪城は見えなかった気がします。JALと全日空では、同じ羽田、大坂間でも飛行するコースが異なっているからです。でも、全日空の場合は大坂行きでは右に座ると富士山がかなり間近に見えてそれもステキですよ。流れで・・・空撮。 飛行機は大坂中心街上空を通過。かなり低空になっています。なぜなら、地上から見てもかなり高度が低いのがわかるからです。写真上の上部(翼の下)が大阪駅、梅田のビル群です。飛行機は淀川を越えて大坂市外(豊中市)の伊丹空港へ、あと数秒で着陸です。余談ですが、伊丹空港は大阪府と兵庫県にまたがって所在しています。面積では兵庫の方が多いそうですが、幾つかにまたがる場合には、所在は運営会社(大阪国際空港ターミナル株式会社)の事務所が置かれた地点の住所になる為に正式な伊丹空港の住所は大阪府豊中市となるようです。地上からの大阪城の写真をおまけにつけました。しかし、なかなか城の形の良いポジションが見つかりません。こちらは一般的、桜門から入った正面の城です。これは天気の日の夏に撮影。城の前ではこの位置しか撮影が出来ないのです。右の小屋はチケット売り場で、天守閣への入館料は大人600円、中学生以下は無料。15人以上の団体になると、微妙な割引があるようです。実は・・正面左側から撮影すると景色が悪くなるのです。残念障害者用のエレベーターの塔が城に張り付いているからです。せっかくの城の景色が台無しです。もっともこの城は観光用に再建されたような城なので仕方ないのですが・・。大阪城復興80年の歴史より大阪城の天守閣の再建は昭和3年(1928)に決定。昭和6年(1931年)、歴史上3代目の大阪城天守閣が竣工されたそうです。昭和20年(1945年)の空襲、昭和25年(1950年)ジェーン台風と少なからぬ被害を受け、さらに老朽化もあり平成7年~9年(1995年~1997年)にかけて大規模な改修工事が行われ現在の姿になったようです。天守閣は展望台になっています。よく見ると造りがかなりチャチっぽいのが問題で、近景の撮影には向かないのです。改修工事では腐食、雨漏り、耐久性、などが考慮され、いろいろなハイテク技術でそれらをカバーしたようですが、結果、戦国時代の城とはかなりかけはなれた城もどきになったようです。中は完全にビルの内部で、エレベーターが天守閣まで登っています。(帰りは階段ですが・・。)北外堀と内堀の間にある極楽橋からの本丸です。環状線の大阪城公園駅から歩いて大阪城に向かう時の内堀北側の橋からです。カメラが高性能になればなるほど細部が見えて城がチャッチク見えるのでやはり遠くからながめる大阪城の方が素敵なようです。今日は簡単に終わります。
2011年09月01日
閲覧総数 1213
-
26

バッキンガム宮殿 3 (宮殿と女王の近衛兵)
初期のブログなので書き直したり写真入れ替えたい部分はありますが・・。リンク先ラストに加えました。バッキンガム宮殿(Buckingham Palace) Part 3バッキンガム宮殿 3 (宮殿と女王の近衛兵)女王のライフガード 5つの近衛歩兵連隊18世紀にこの宮殿が売りにだされた時に、大英博物館も建物の購入を検討したそうです。結局30000ポンドは高額過ぎたので、10000ポンドで現在の建物である元モンタギュー公の宮殿を買い取ったのだそうです。A王室所有の宮殿は、いくつかあります。バッキンガム宮殿(女王の公式のロンドンの宮殿)セント・ジェームズ宮殿(ヴィクトリア女王が戴冠する前の住居で、この近所にある。)ケジントン宮殿ロンドン城(ロンドン塔には英国王家の秘宝が保管されています。)ウインザー城(女王が現在週末に過ごす館)王室旗がはためいています。今日のパレードは少し特別です。B女王のライフガード 5つの近衛歩兵連隊宮殿は、女王の近衛兵とホースガードによって警備されています。ほぼ毎日のようにおこなわれる衛兵交代は特に有名ですが、彼らは国王の個人的な衛兵なのだそうです。写真Aを拡大した所ですが、もうすぐ交代式があるための準備かも・・・。拡大写真によれば、この隊はアイルランド近衛連隊のようです。冬のコートを着用C帽子の羽根飾りがブルーになっているので・・。5つの近衛歩兵連隊コールドストリーム近衛連隊 ・・・1650年に創設した部隊であり、継続して任務に就いている部隊としては 世界最古。 赤い羽根、上着のボタンは2個ずつ4組で計8個アイルランド近衛連隊 ・・・1900年にヴィクトリア女王により創設。 青い羽根、上着のボタンは4個ずつ2組で計8個スコットランド近衛連隊 ・・・1642年3月にチャールズ1世の命令により創設され、1651年連隊は解散。 王制復古後の1661年、チャールズ2世によって連隊は復興。 羽根無し、上着のボタンは3個ずつ3組で計9個ウェールズ近衛連隊 ・・・1915年ジョージ5世により創立。 緑と城の羽根、上着のボタンは5個ずつ2組で計10個グレナディア近衛連隊(近衛歩兵第一連隊) ・・・起源はピューリタン革命で亡命中の皇太子(チャールズ2世)の護衛隊。 1656年にブルッヘで創設。私的衛兵の伝統を受け継ぐ。 ワーテルローの戦いで勇敢にフランスと戦った事から、 1815年に近衛第一歩兵連隊に改名。 白い羽根、上着のボタンは等間隔に8個この5つの連隊はバッキンガム宮殿、セント・ジェームズ宮殿、ロンドン塔の警護、祝日の警護、儀式で活躍します。近衛歩兵第一連隊かな? 羽根が見えないけど・・。かぶっている帽子は熊の毛です。持っているライフルは・・・。アサルトライフルL85。イギリス軍のSA80ファミリーのうちの一つだそうです。ライフルとは付いていますが、小型・軽量の自動小銃です。さらにそれに銃剣も装着しているようです。伝統的な衣装に近代的なL85小銃を抱えた姿も結構イケテルかも・・・。カバーしてるけど、命中精度を高める為の取り外し可能なスコープサイトを備えています。スチールを多用しているので現在重量は4980g(弾倉に30発フル装填して・・) かつぐのもわかりますね・・。イギリスの近衛歩兵連隊のライフルの歴史は軍隊の中でも早いようで、ワーテルローの戦いでフランスと戦った時には、すでにライフルを保持していたそうです。ライフルでも近代的な装備のものになると、街中でそんなものを使うのかな? と思ってしまいますが・・・。イギリス軍に配備されている銃のようです。言いようによっては女王陛下を守る銃なのです。話がずれてしましましたが、次回、衛兵パレードです。Back number バッキンガム宮殿 3 (宮殿と女王の近衛兵)リンク バッキンガム宮殿 4 (女王近衛騎兵連隊)リンク バッキンガム宮殿 5 (近衛隊の交替式流れ解説)リンク バッキンガム宮殿 6 (軍楽隊)
2009年10月22日
閲覧総数 1931
-
27

新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)
写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました今回はバロックを追求しなおしました。そして、これがバロック(baroque)であると言う写真をたくさん入れました。新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)バロックの語源バロック(baroque)とは?バロックの教会(ウイーンのカールス教会)フランス・バロック様式の誕生ヴォー・ル・ヴィコント城の因縁バロックの語源バロック(baroque)という語はポルトガル語の「いびつな真珠(barocco)」が由来とされ18世紀に登場したワードらしい。一般に17世紀から18世紀に流行った様式についてのワードであり、建築、美術、音楽など芸術全般で使用される。が、当初のポルトガル語の「barocco」はまさしく「いびつな真珠」その物をさした言葉だったはずだ。16世紀の大航海時代に、ポルトガルはオリエントから真珠を欧州に持ち込んだ。真円のパールだけでなく、変形した真珠が多かったのかもしれない。その後スペインが新大陸で真珠貝の産地を見つけ運ぶと欧州に真珠の一大ブームが至来したと言われている。バロック(baroque)とは?さて、バロック(baroque)の意味はわかったが、バロック(baroque)を言葉でうまく形容するのはかなり難しい。音楽に関してはなおさらである。かなり理論に無理があり、無理くりジャンルが造られた感があるからだ。一言で例えるなら「ゴージャスで派手な成金趣味」。それは王侯貴族のステータスであったからだ。上下共にベルサイユ宮殿鏡の間建築建築においては彫刻をふんだん使った華美が目立つ。(そうでない物もある。)※ 今回のベルサイユ宮殿は最高にしてそれを越える物が無いバロックの極みだろう。教会建築におけるバロックの意義は皆が度肝を抜く荘厳なる天国世界としてある。バロック式の教会のキンキラの美しさはまさに天国世界を表現したものなのである。教会建築のバロックが一番見て解り易いかもしれない。絵画絵画においては? 当然であるが、そのゴージャスの中にあってもひけをとらない華美がある事だ。バロック絵画の巨匠として名高いのはルーベンスである。※ ピーテル・パウル・ルーベンス (Peter Paul Rubens)(1577年~1640年)ルーベンスの作品は神話や寓意の壮大なスペクタクル絵画なのである。しかも大きいのが多い。まさに華美な室内に劣るよりも勝る美しさと色彩を持つのである。ヨーロッパ中の貴族階級を顧客に持ち外交官としても活躍。当然、ルーベンス作品を所有する事自体がステータスであった。ベルサイユの王の間のあるファサード上の写真一枚に関しては、デジカメになる前のアナログ写真をスキャナーで読み込んで起こした写真です。当時はまだ金の柵が無くて、みなさん正面から撮影ができたのです。正面中央の2階は王の寝室。外壁までここまで立派な宮殿は他には無い。テラスの向こうが王の寝室。下は戦争の間見て解るゴージャスさ下はヘラクレスの間ここでは当然家具や調度品も部屋に合わせて豪華。下はマリーアントワネットのベッドの天蓋。当然、額縁も豪奢(ごうしゃ)になる。教会のバロック見本はウイーンのカールス教会(Karlskirche)からしかし外装はそうでもない。だから外観だけでこれがバロックか? と言う矛盾がある。バロックの教会(ウイーンのカールス教会)1713年、マリア・テレジアの父、神聖ローマ皇帝カール6世 (Karl VI)(1685年~1740年)が、ペスト撲滅を祈願して建立を指示。建築はフィシャー・フォン・エルラッハ親子。「ペスト退散の守護聖人」、カール・ポロメーウス(カルロ・ボロメオ)に献堂されている。※ ミラノ大聖堂に聖カルロの霊廟がある。リンク ミラノ(Milano) 7 (ミラノ大聖堂 5 聖カルロ)下は天井クーポラ(cupola) 天国世界の絵図中身がバロックでも外装は必ずしもそうではない。内装だけ変えている場合もあるあるし、増築して様式が多伎にわたる建物もあるからだ。ルーブルもその一つだ。モダンなゲートまで造られて、元は王宮の一つだったとは思えないが・・。フランス・バロック様式の誕生1650年代、欧州では建築、絵画、彫刻、演劇、音楽と、文化の潮流がいわゆるバロックへと移行?※ もともとバロック(baroque)は後世付けられたネーミング。要するに変革の過渡期(かとき)。一般には、まだ石造りの恒久建築の世界では、まだルネッサンス様式が主流。バロック様式発祥? イタリアでは(1590年頃)導入していた? すでにローマ・バロック建築を代表する二人の芸術家(ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ、フランチェスコ・ボッロミーニ)がいた。フランスでもイタリア出身の宰相マザランにより、1640年代からイタリア・バロックの導入が計られたと言うが当時の建築家フランソワ・マンサールは、古典的なバロック建築を好んだ為にパロックと言うよりはルネッサンス的だったようです。17世紀から18世紀に流行った様式、バロック様式は、ルネサンス様式からマニエリスムを経て発展した様式とされているが・・。フランスではフランソワ1世(François I)(1494年~1547年)が16世紀にはルネサンス様式からマニエリスム取り入れフォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)の改築をしていた。フランソワ1世の回廊(Galerie de François)はまさにバロックの前章と言える作品である。フフォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)フランソワ1世の回廊フレスコ(fresco)画とスタッコ(stucco)による壁絵と天井画下は回廊の天井ではありません。イタリアより招いたマニエリスムの芸術家や職人により完成されたフォンテーヌブローの宮殿装飾(フランス・ルネッサンス?)が第一期フォンテーヌブロー派と呼ばれているが、これはルネッサンスよりもバロックに近い。イタリアよりも早いのではないか?1664年ルーブル宮殿の改築工事の為に、最も偉大な芸術家としてベルニーニをイタリアから呼び、ルーヴル宮殿の東ファサードの設計を依頼しますが、ルイ14世がベルサイユ宮殿に関心を向けたため、ルーヴル宮殿の計画は縮小され最終的にフランス人建築家のルイ・ル・ヴォー、クロード・ペローらによって代案が考えられ、ベルニーニ案からのモティーフを借りつつ彼のデザインとは全く印象が異なる東面ファサードが建設。(1667年~74年)それは、フランス古典主義建築の最も完成された姿とされ、ルイ14世様式と評されたようです。下は、現在美術館となっているルーブル宮殿シュリー翼外観は増改築やデザイン変更があるのでわかりにくい。新古典様式とも言えるが、下はバロックのファサード ルネッサンスの意匠が感じられるデザインです。ルーブルはかなりチャンポンなのである。だからガラスのピラミッドも造れたのかも。中の廊下にはバロックの豪奢な天井画や装飾もある。元は宮殿であったのだからルイ14世が1681年に王宮をヴェルサイユに遷すまではルーブルが王宮であった。ローマ・バロック建築の影響をもっとも受けたのが建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)で、ニコラ・フーケの居城ヴォー・ル・ヴィコント城は限りなくローマ・バロックの様式を盛り込まれてているそうだ。庭園を中央に置き、入り口は楕円の吹き抜けの広間を持ち、入り口は三角破風(ペディメント)を戴いた4本のドリス式円柱で飾るなど、ローマのベルベリーニ宮に着想を得たローマ・バロック特有の意匠を好んで取り入れたようです。下は参考の為にウィキメディアより借りてきました。ヴォー・ル・ヴィコント城(Château de Vaux-le-Vicomte)の北のファサード建物自体にそんなにバロック感はないが、三角破風がローマなのだろう。庭園は完全にバロック。庭は造園家アンドレ・ル・ノートル(André Le Nôtre)の作品ヴォー・ル・ヴィコント城の因縁ルイ14世の宰相マザランの側近で法律家にして財務官でもあり大蔵卿にまで登りつめたニコラ・フーケ(Nicolas Fouquet)(1615年~1680年)。彼が若き芸術家を結集させてヴォー・ル・ヴィコント城(Château de Vaux-le-Vicomte)を建設。建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)(1612年~1670年)画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)造園家アンドレ・ル・ノートル(André Le Nôtre)(1613年~1700年)買い占めた土地に自分の身分にあった広大なバロックの城館であった。そこまでは良かったが王を招いて自慢。王(ルイ14世)さえ持っていない城館のあまりの豪華さに王は嫉妬と怒りでニコラ・フーケを失脚させ(国費の私的流用の罪)財産没収と投獄監禁の刑にしたと言う。この3人の芸術家が後のベルサイユ建設のプロジェクト・チームのメイン・メンバーになるのです。ローマに留学していた画家ルイ・ル・ブランは内装を担当。彼もまたローマ・バロック様式を取り入れ、天井装飾は、スタッコ装飾またはトロンプ・ルイユ(だまし絵)の技法による額縁に縁取られた天井画が描いているそうだ。トロンプ・ルイユを駆使した立体彫刻に見えるだまし絵、時には空が描かれ天を舞うミューズや天使がいたり、神話の世界観が展開されていたりと官能的な美しい空間を演出。実際に見ていないが、ルイ・ル・ブランの仕事はフォンテーヌブロー宮殿のスタッコ(stucco)とフレスコを使用したフォンテーヌブロー派に似ている気がする。しかし第1期フォンテーヌブロー派は100年も早くバロックに近づいている。建物には技術的な事が関係してくるが、内装などデザインは、そこそこ流行に左右されたのではないかと思う。建物と内装の様式は必ずしも一致していない事は解った。また派手になるバロックも、経済事情や好みで相当に違いがあったと思う。ベルサイユに見るバロックは、まさにフランスの国力と王の力を対外に示すゴージャスさが必要であったの確か。外装にまで金をふんだんに使用したベルサイユは最初に言った通り本当にバロック様式は「ゴージャスで派手な成金趣味」そのものでしたね。今回は全面改装になってしまいました。「ベルサイユ宮殿 4」につづくリンク ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城) ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃
2009年06月10日
閲覧総数 1962
-
28

カプリ島、ソラーロ山頂とセイレーンの岩礁
ちょっと長すぎたので切ってしまいました。ついでに構成も変えました。ソラーロ山(Monte Solaro)とチェア・リフト(chairlift)とセイレーンの岩礁SEGGIA MONTE SOLARO下はチェア・リフトの終点駅からの撮影です。方位的には、島の北西方面です。眼下に見えるのはアナカプリの街です。下は、ソラーロ山(Monte Solaro)の山頂からの眺望です。カプリ島の東側で下に見えるのがカプリの街です。マリーナ・グランデは左側(北)で見えません。右の海がマリーナ・ピッコラです。左奥に見えるのはソレント半島です。ファラリオーニ(Faraglioni)カプリ島の南東、トラガラ岬のはずれに、ファラリオーニ(断崖)と呼ばれる岩礁があります。地元ではセイレーンの岩礁と呼ばれているそうです。セイレーン(Seirenpe)ギリシア神話に登場する伝説上の生き物で、ラテン語でシーレーン。イタリア語ではシレーナと呼ばれています。上半身が女性で下半身が鳥の姿を持つと言われ、海の怪物として知られています。海の航路上の岩礁にいて、美しい歌声で航行中の船人を幻惑して死に追いやる妖鳥です。「歌声に気を取られていて、船を岩礁に乗り上げさせて難破」 or 「舵が効かなくなり座礁」させて死んだ船員達の骨で彼女らの島は山をなしている。とされ、ホメロース以降は、怪物視されています。セイレーンは海と空に居て、冥界の女神に仕えていたと言う説があり、彼女たちは死者の魂を迎え、美しい音楽と歌声で死の苦痛を和らげ、安らかで心地よい死を導く役目を持っていた。 とするものです。セイレーンも、トルコのメドゥーサ信仰と同じようにギリシャ支配以前からの土着信仰があったようです。「死の女神に仕える者」 or 「死を司る巫女」の役割があったのではないか? と思われますが、もう少し調べなければいけませんね・・。ホメロースの叙事詩「オデュッセイア」の主人公オデュッセウスが冒険の帰途セイレーンの歌声に幻惑されますが、彼以外の船員に耳栓をさせていたので船は無事に通過してオデュッセウは無事でした。ギリシャ神話では、イアソン率いる「アルゴー船の探検」の話で、セイレーンに歌合戦を挑み勝ったのが、竪琴の名手オルペウス(オルフェウス)です。因みにオルペウスと言えば亡くなった妻を取り戻そうと冥界まで行ったあのオルペウスです。セイレーンの住む岩礁は、いくつか名乗る所があるようです。ここカプリ島もその一つですが、古代ギリシャ人が移民して住んでいた島ですから、そんな伝説がまことしやかに伝えられたのかもしれません。下はソラーロ山からカプリ島の南東を撮影したものです。島の岩肌は絶壁です。眼下の岩山の向こうの海は、マリーナ・ピッコラで、トラガラ岬に連なる岩礁が前出のセイレーンの岩、ファラリオーニ(断崖)と呼ばれる岩礁です。1晩目の岩(111m)が星or地球の断崖・・島と陸続き2番目の岩(81m)中の断崖・・下に通路がある。3番目の岩(105m)外orスコポロの断崖・・海のように青い青トカゲが生息するようです。下は、アウグストゥス庭園から撮影したファラリオーニです。アウグストゥス庭園からだとトラガラ岬は写らないですね。美しい景観です。
2009年07月03日
閲覧総数 632
-
29
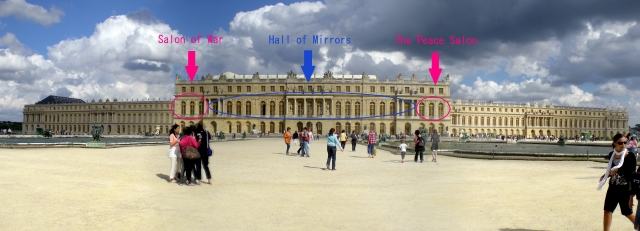
新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)
写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れましたベルサイユ宮殿は改築につぐ改築が行われているので、建物以外、内装などは全くの別物になっている。実際、近年の観光でも行くたびにあちこち変化が見られる。例えば王の内庭にできた金の柵も2005年にはまだできていない。中にあったルイ14世の騎馬像も移動されている。全くもってそれは近年の観光用にしつられえられたものなのである。実際、フランスの場合1789年、フランス革命が起きた為に当然王宮や王侯貴族の家屋敷までが破壊され略奪うけている。ハプスブルグ家が歴代のコレクションを残しているのと違い、フランスの場合はほとんど何も残されてはいないのだ。フォンテーヌブローの所でも触れたが、ナポレオンが皇帝になった時に宮殿は修復されそれなりに直されたが、歴史的な復元がされた訳ではない。最近になってルイ14世時代の王宮がもっと壮大なものであった事が解ってきたが、そう考えると、今のベルサイユはいったいどの時代に合わされているのか? と、疑問に思う。日本人の人気スポットはマリー・アントワネットの寝室であるが、それも「王妃の寝室」とタイトルされている。歴代の王妃が使用する部屋の場所は確かにそこだが、内装はそれぞれであったはず。妃の部屋のテキスタイルは一応ルイ16世時代に寄せているのだろうが、写真なんかあるわけではないからベルサイユの場合、完全に当時を想像した復元と言う事になるのだろう。つまりベルサイユ宮殿の場合、実物でなくセット物感は否めない。さて、そんな前振りしましたが、今回は「鏡の回廊」の前後に位置する二つの角(かど)部屋の紹介です。新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)戦争の間(The Salon of War)画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)平和の間(The Peace Salon)ルイ15世のメダリオン(medallion)下は位置確認です。ウィキメディアのパノラマ写真を借りてきました。中に書き込みしています。庭からの宮殿。右側ピンク 平和の間(The Peace Salon)中のブルー 鏡の回廊(Hall of Mirrors)左側ピンク 戦争の間(The Salon of War)地図も位置を確認して下さい。下の図は宮殿正面側からです。鏡の間の向かって右端が戦争の間で、左の端が平和の間と呼ばれています。戦争の間の側(右翼)が王様の寝所などの領域で、左の平和の間の側(左翼)が王妃の寝所などの領域に分けられています。鏡の間の向こう側が、広大なベルサイユの庭園がある側です。※ 団体の観光ルートでは正面右のガブリエル棟から入り、王の間の領域を抜けて、鏡の間に入り、王妃の間の領域を見学するコースになっていますが、個人の入口は反対の旧棟かららしいです。因みに2018年頃に王の内庭の地下に大きなトイレが設置され混雑緩和になったようです。戦争の間(The Salon of War)1678年マンサールがこの部屋の建設に着手し、装飾は画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)1679年2月頃から造営。天井はクーポラ仕立て壁には大理石が貼られ、その上に金箔青銅の武具装飾と、武器類が流れるようなデザイン飾りとしてとり付けられ、天井にはル・ブランにより、勝利の女神に取り巻かれる戦勝国フランスの姿が描かれている。主題は、「ニメーグ和平における軍隊の勝利」そもそも「鏡の間」自体がルイ14世の戦争の勝利など功績が描かれ、栄誉をたたえる構成図案になっている。人が多いので全体の写真を撮影するのは個人では不可能です。下の写真のみ画像は悪いですが、参考に本からです。ベルサイユで発行している公式の写真集からであるが、この写真ではレリーフ下のブロンズはそのまま。近年、金箔を貼ったようです。敵を踏みつけにしているルイ14世。上に金箔の貼られた二人の噂の女神ペーメ。楕円形の化粧漆喰朝浮き彫りで表現されています。コワズヴォクスの傑作です。花鎖につながれた捕らわれの人とその下に歴史書を書いたいるクリオー天井四隅にはフランスの紋章がレリーフされている。画家シャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)シャルル・ル・ブランはイタリアのバロック絵画をフランスに伝えた当時のバロック第一人者シモン・ヴーエ(Simon Vouet)(1590年~1649年)の工房で学び、1642~1646年までイタリアに留学。ニコラ・プッサンにも師事もしているらしい。帰国後、絵画アカデミーの設立に参加し、ルイ14世の首席宮廷画家として、ベルサイユ宮殿の装飾事業の指揮をとる事になる。つまりルイ14世のバロックはほぼシャルル・ル・ブランの作品と言う事になる。傍ら王立ゴブラン織りの製作所の長として宮殿に飾るタペストリーを制作したり、家具、銀器などの工芸品制作の監督にもあたっている。フランス美術界に君臨した画家なのである。※ フランスのゴブラン織りについては、サンカントネール美術館2の中「フランドルのタペストリーとフランスのゴブラン織り」で触れています。リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)平和の間(The Peace Salon)戦争の間と対になっているこの部屋は、装飾も大理石と鏡と金箔青銅と言う所では一致しています。テーマは平和。欧州に平和をもたらすルイ15世のメダリオン(medallion)がメインになった部屋です。鏡の間を出て、王妃の宮殿側に入る最初のこの部屋は、1680年に完成したものですが、1710年から王妃の宮殿の一部として、娯楽室として使われた。何しろ隣は王妃のベッドルームなので・・。後世の妃によってこの部屋の為の装飾が足されたりしているそうです。下の写真のみ本からの出典です。画像は悪いですが、参考に・・。大理石の暖炉の上には楕円のルモワンヌの絵(1729年制作)が飾られている。建物の構成だけでなく、内装までシンメトリー(左右対称主義)に作られている。ルイ15世のメダリオン(medallion)欧州に平和をもたらすルイ15世の図は、19才の王がヨーロッパにオリーブを差し出し、その王の上には慈愛の女神と多産の女神が舞う。また生まれたばかりの王の双子の王女も描かれ、王家の繁栄もほのめかしている。天井画も、シャルル・ル・ブラン。平和の女神が先導し、四羽のキジバトに引かせた馬車に乗って空中を渡るフランス。そのフランスに不滅の輪を冠せているのが栄光の女神。また、フランスには婚姻の神が添っている。平和条約を締結した事を王家同士の結婚に例えて表現しているらしい。ベルサイユの写真だけで数千枚。それを部屋毎に分類せざるおえなくなりました。写真は一度の撮影ではないからです。前の時も大変でしたが、あれからさらに写真が増えています。途中、カーテンの色が変わっている事にも気づきました。内装の壁のテキスタイルも微妙に変わっていそうですし、調度品や絵画は大きく入れ替わりしています。何しろ昔はナポレオンの部屋など無かったような・・。最もベルサイユで飾られている額絵に関しては、ほぼレプリカです。本物はルーブル美術館のみならず、ウイーン美術史美術館所蔵の物もありました。つづくリンク ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂) 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃
2009年06月12日
閲覧総数 6728
-
30

ヴァイキング 5 (奴隷と宗教とスターヴ教会)
実はこのスターヴ教会の写真選択をしていてヤバイ写真を見つけてしまいました。真っ黒な写真を明るく編集していたら、墓の中に光る玉が現れた。ヽヽ(≧▽≦)// キャー 恐くなって削除しました。ヴァイキング 5 (奴隷と宗教とスターヴ教会)ヴァイキング(Viking)ノルウェー(Norway)奴隷交易のルートキリスト教への改修スターヴ教会(Stavkirke)スカンディナビアの人々は、自国の資源や毛皮を売るだけでなく奴隷の売買も大きな交易だった・・・と言う話を前回しましたが・・。この時代、スペインから中東に至る地中海全域に住んでいたアラブ人の間に、奴隷の需要が非常にあったと言われています。当初は西部と中部ヨーロッパの囚人、債務者、犯罪者をアラブ人に売却することによって、彼らは奴隷をまかなっていたようですが、この地域がキリスト教化されると西側の教会はこの交易を廃止しようと動いたそうです。しかし、それは人道的な意味ではなく、キリスト教徒がイスラム教徒の奴隷にされる事が許し難かったから・・と考えられています。そこで奴隷不足に目を付けたヴァイキングはバルト海周辺やロシアに向かい、攻撃して異教徒であるスラブ人を捕らえてアラブ人に奴隷として売ると言う交易を考えたようです。(教会は、彼らが異教徒なので、キリスト教徒の土地を経由しても、何も言わなかったようです。)奴隷交易のルートロシアのヴォルガ川からカスピ海やドナウ川から黒海に至る・・・等の東ルートがメインと思われ、またフランク人とユダヤ人の協力を経てヘデビューを通過して旧奴隷ルートをマルセイユに南下すると言うコースもあったようです。東方ルートは奴隷交易の為にスウェーデン人(祖)のヴァイキングに開拓されたのかもしれません。デンマークとノルウェーのヴァイキングは主に西ヨーロッパ、特にアイルランドを攻撃して奴隷を捕らえたようですが、キリスト教徒の奴隷売買は出来なかったので、主に自家用の召使い奴隷として売られたようです。キリスト教への改修ヴァイキングの信仰した神の主な神様は今も神話の中に生きています。オーディン・・北欧神話の主神。知恵と戦いの神。魔術の達人。トール・・・・・オーディンの子。雷、天候、農耕などを司る勇ましい神。フレイ・・・・・フレイヤの双子の兄。 繁栄と豊穣の神で゛最も麗しい神。彼らの改宗については詳しく調べられた本が見つかりませんが・・野蛮とされた彼らの襲撃を避けたいが為にキリスト教徒は必死に彼らに宣教活動を行ったのは事実のようです。遠征した先で新しい文化と信仰を知り、比較的容易に受け入れられた・・・と言うのは微妙ですが、ある種妥協をしながらも同化して行ったようです。特に建国して王となった者は諸々の事情から改宗し、それについて周りも改宗せざる終えなくなる場合も多かったようです。彼らの特殊なキリスト教会・・・スターヴ教会スターヴ(Stav)はノルウェー語で「丸太」とか「木の支柱」を意味するそうです。ヴァイキング達がキリスト教に改宗して、ヴァイキング時代がさった当初(100年後)建てられた教会は、不思議なキリスト教会なのです。ノルウェー(Norway) ゴル・スターヴ教会(Gol Stavkirke)1994年に復元。今までの土着の宗教とが入り交じって何とも変わった教会は昔ノルウェーには1000件以上あったようです。(現在は30箇所)教会入り口も十字はあるけど・・なにやらドラゴンが・・・。竜とヘビを現した入り口。竜は魔除け。ヘビはミズガルドの大蛇か? 古来ヘビは悪の化身のようです。やはり東洋? チャイナにも見えるけど、ヴァイキングは何を見てこれを建築したのか・・。竜頭(ドラゴン・ヘッド)はヴァイキング船の船首飾りにあったものとほぼ同じ。日本のシャチホコにも見えるけど・・・聖堂側から撮影 何教かわからないチャンポン建築。建物は地面からの湿気を防ぐ為に高く敷石をした石の上に木で組まれている。金属は使用せずホゾとホゾ穴で接合。教会の写真がまだあるので次回につづくリンク ヴァイキング 6 (ロム・スターヴ教会)
2010年02月07日
閲覧総数 3385
-
31
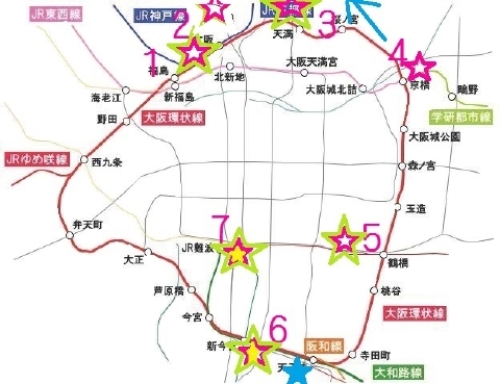
大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 2 (千日墓所と法善寺&大阪七墓)
最後に他のリンク、先追加しました。前回、秀吉による大阪城建設とそれに伴う大阪城下の区画整理(町割)が大阪の発展の始まりだと書きましたが・・。リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)もともと堺の商人の貿易力は戦国の時代から信長も認めていた事。秀吉の時代を経て江戸の城下がはるか遠くなっても、大阪は戦略的にも、経済的にも重要な拠点。徳川家康がそれをほっておくわけはなかった。大阪夏の陣後、家康の特命により摂津大阪藩10万石の藩主となったのは、家康の外孫であり養子でもある松平忠明(まつだいらただあきら)(1583年~1644年)(在職 1615年~1619年)である。そもそも彼は秀吉との休戦協定中、大阪城外堀と内堀の埋め立てを担当した奉行でもあった。※ 徳川方 勝利の一因は、この埋め立ての早さにもあった。つまり、家康の肝いりで藩主となり大阪城下の戦災復興担当に任命されたのも彼なのである。在職期間に大阪の町の区画整理をし、人を大阪に移住させたり、市街地の拡大を積極的に行い、堀の開削を進め物流を確保したり、町の強化も図っている。(少なくとも藩主時代の5年で街の骨子は造られた。)在職は5年であるから、城下中心部が主であるが、それはどれもこれも素晴らしく計算されたものである。頭の切れる人だったに違いない。松平忠明(まつだいらただあきら)は「大阪都市計画史上特筆すべき業績を残した人物」と、讃えられている。因みに、1619年、摂津大阪藩は幕府の直轄地となり大阪町奉行が置かれる事になった。つまりこの時、摂津大阪藩10万石は無くなったのである。そして1620年、松平忠明 転封(てんぽう)後に大阪城の再建が始まる。1624年には大阪城下の町組、大阪三郷(おおさかさんごう)(北組、南組、天満組)ができている。大阪城の再建は、都は江戸に行ってしまったが、大阪と言う街の活気を取り戻す事に寄与したのだそうだ。さて、今回は前回に引き続きミナミの繁華街にある法善寺の紹介ですが、その前に面白い事を発見したので先に紹介です 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 2 (千日墓所と法善寺&大阪七墓)摂津大阪藩主 松平 忠明大阪七墓と七墓めぐり千日墓地と法善寺法善寺と法善寺横丁水掛不動(みずかけふどう)大阪七墓と七墓めぐり摂津大阪藩10万石の藩主となった松平忠明が行った仕事の中に、寺および墓地の移転がある。街の拡張を行うにあたり寺は小橋村と高津村、天満村に集められた。そして、じゃまになった墓地をまとめ、また火葬場や刑場を市外に移転させたのである。(もともとそこにあった墓地もあるが・・)それでできたのが江戸(時代)の「大阪七墓」である。梅田村、濱村(南浜)、葭原(よしわら)、蒲生(がもう)、小橋(おばせ)、飛田(とびた)、千日(せんにち)※ 江戸から明治にかけて大阪市内には七つの墓所と二つの処刑場(No6.No7)があった。下の地図は現在の環状線の駅に乗せてみました。便宜的(べんぎてき)に数字を当てました。(大阪環状線を右回りに梅田を1番にしました。)1.梅田墓所・・・・・・・・JR梅田貨物駅のあった北ヤード。火葬場もあった。 1684年大阪三郷の墓地を集めた曾根崎の墓所が梅田に移動したもの。さらに長柄墓地に移転。 近年の再開発の為、平成22年8月に地蔵尊は四天王寺の地蔵堂、供養塔と後から出た墓石は川西市の稱名寺、遺骨は天王寺の一心寺に改葬。2.濱村(南浜)墓所・・・・・北区豊崎。 開所747年。 行基(668年~749年)によって開所されたと言われ、日本最古の墓所とか・・。現存。3.葭原(よしわら)墓所・・北区天神橋6丁目。沖向地蔵尊の堂宇のみ現存。堂はポケストップになっている。 墓所は北市民館建設の為、長柄墓地に移転。天六地下鉄工事爆発事故の現場界隈だった。現在は無い。4.蒲生(がもう)墓所・・・・都島区東野田町。京橋駅の外側近く。現存。5.小橋(おばせ)墓所・・・天王寺区東高津公園。真田丸の南方に位置する。現在は無い。 冬の陣、真田丸攻防の時の戦士の墓だったとも・・。1914年、北の十萬寺に移転。無縁仏は大圓寺へ。6.飛田(とびた)墓所・・・・西成区JR新今宮駅の南側。処刑場があった。 1874年新設された阿倍野墓地に移転。近年まで墓地跡に太子地蔵尊があったらしいがそれも現在は無い。7.千日(せんにち)墓所・・中央区千日前。火葬場と処刑場があった。(大塩平八郎ら20名の処刑) もともと江戸初期に集められた場所のようだが、千日寺と呼ばれた法善寺、竹林寺(天王寺区に移転)の南に刑場と聖六坊、斎場、焼場、灰山、墓地などがあった。大坂三郷、最大の墓所だったらしい。 刑場は明治3年(1870年)に廃止。千日墓地の焼き場と墓地は阿倍野墓地へ移転(1872年の地図には既に記録が無い)大阪冬の陣に続き夏の陣の戦没者は相当数いたようで、墓地は共同墓地的な要素が強かったのかも。もちろん普通の寺にも檀家の墓所はあった。まだ墓所に入れてもらえた人はともかく、堀に落ちて、そのまま埋められてしまった方々もかなりいたようだ。建設工事の時に未だに人骨もよく出るらしい。400年もたっているのにね 七墓めぐり江戸時代中頃から、明治の初期まで、大阪には「七墓めぐり」と言う風習(流行?)があったそうだ。盂蘭盆会(うらぼんえ)(7月13日~16日)の間に、諸霊供養の為、木魚、持鈴、摺すり鉦などを持って徹夜で大坂七墓を巡り無縁の卒塔婆を回向すると言うもの。※ 祖先の供養と同時に、自身が極楽浄土へ行けるようにと言う願をかけたと言う話もある。千日墓地と法善寺「千日前」とか、「千日前通り」と言う地名は今も残っているが、これは先に紹介したように千日(せんにち)墓所に由来している。明治の初期に移転をよぎなくされたが、かつて、そこには千日(せんにち)墓所があり、刑場があり、火葬場(火屋)があり、幾多の寺が寄り、地蔵が置かれた土地であった。もちろんそれができたのは江戸の初期。冒頭紹介した松平忠明(まつだいらただあきら)の町造りの中で置かれたものだ。順序としては、墓所が決められ、寺が寄ってきた。法善寺が移転してきたのは1637年。竹林寺(前身は浄業院)が移転してきたのは1649年。いずれも墓所より後。また江戸後期地図にある蓮登山自安寺(日蓮宗の門跡)が来たのは1742年。※墓所は、松平忠明の着任中(1615年~1619年)には決まっていたはず。夏の陣の戦没者などがいたはずだから・・。千日寺(せんにちでら)とはそのネーミング、一般的に周知されているのは、法善寺と竹林寺が千日回向(せんにちえこう)を行う寺だった事。通称「千日寺」とよばれ、その門前は千日寺前と呼ばれたと言うもの。千日回向とは?回向(えこう)とは、1)死者の成仏を願って(主家)供養をする。とか、2)僧が念仏で自分の修めた功徳 (くどく) を他の人に分け与える。とか、その念仏により、3)阿弥陀如来が人々を救済し、浄土に迎えくれると言う(他力回向)。など。※ 千日回向とは、詳しくわからなかったが、千日毎に行われる特別な回向があったものと思われる。そもそもは、1)の意味で「大坂の陣での戦死者を含めた死者の供養の為、千日回向が始められた」と考えられる。が、江戸も中頃以降? 目的は2)や3)に変わって行ったようだ。 一度の参詣が千日分の御利益が得られると騒がれ浄土宗の法善寺や竹林寺は千日回向に来る人でかなり賑わったらしい。確かに千日ごとでは3年弱になるからね。寺が年中賑わっていたのなら、回向は年中行われて、いつでも御利益がもらえたと考えた方が正しいのかも。下は道頓堀近くの看板の一部「道頓堀周辺図(幕末頃)」 ※ 見づらかったので手を加えました。図の難波新地は1765年に開発され、茶屋が集まりやがて大阪有数の歓楽地となる。千日(法善寺)の人気が出て、知名度が上がった理由千日の周辺は、娯楽所が寄り合っていた場所。後に難波新地もできる。本当は千日寺近辺に遊びに来るのが目的だが、体裁的に、千日参詣を口実に利用した可能性が・・。何しろ墓地のすぐ北には幕府に公認(1653年)された芝居名代5棟が立ち並んでいた。※ 芝居小屋の方が法善寺より早く1626年(寛永3年)に移動してきたらしい。(看板に書いてあった。)下は大坂歴史博物館のジオラマからこうした芝居小屋は道頓堀の前に建ち並んでいたらしい。現在、かに道楽やくいだおれ太郎の店が並ぶ道頓堀通りだ。また、芝居小屋だけでなく、法善寺の開帳時には見世物小屋が開かれ、軽業や見世物興業、勧進相などが行われたようだ。※ 実話の心中(しんじゅう)話を舞台や浄瑠璃(じょうるり)にして演じて客を呼ぶ(興業)など話題も造った。日本橋(道頓堀東)の方面には宿屋があり、新町に女郎屋が存在していたかは定かでないが、夜鷹(よたか)(辻の売春婦)は確実にいただろう。1627年、新町に吉原遊郭 誕生していた。まあ、何にしても、千日寺と共に界隈は有名になり、旅人(観光客)も立ち寄り大いに繁昌したようだ。大坂歴史博物館のパネルより現在の地図にだいたいの場所を載せてみました。黄色が現在の戎橋筋商店街、ピンク1~5は芝居小屋の位置(今の道頓堀通り)紫は現在の法善寺の場所。緑の四角内に千日墓所(東墓地と西墓地、中に刑場、火屋(火葬場)、灰山が築かれていた。※ 今回、はっきり特定するのを避けましたが、詳しく調べて載せている方はいます。※ 千日前デパートの火災事故による大きな被害は、その場所がらの因縁がもたれる由縁です。先に書いたように、刑場は明治3年(1870年)に廃止。千日墓地の焼き場と墓地は阿倍野墓地へ移転している。この元墓地の場所は繁華街となり、地価が高騰。近年の開発で千日前通りに面していた竹林寺も2008年になって天王寺区勝山へ移転している。一方、現在も残り、且つ水掛不動尊で繁盛している法善寺は。昭和の時代も平成になってからもずっと人気で、ミナミの顔となっている。法善寺と法善寺横丁どちらかと言えば、現在の法善寺は道頓堀からのが近い。ここが寺か? と思える路地を入った一角にある。正直、どこからどこまでが寺なのかもよくわからない。普通の寺なら本殿があり、そこで拝むのが当たり前。しかし、ここにはそう言うかんじではない。写真左に金比羅堂(こんぴらどう)。写真正面の唐破風の向こうに水掛不動尊(みずかけふどうそん)上は水掛の順番待ちの列。水掛不動の正体は不動明王(ふどうみょうおう)様です。乾く時間もなく、常に水を掛けられているので水苔でフワフワ、モサモサのお不動様。見て、正直ちょっと驚いた こんなになっちゃって・・・水掛不動(みずかけふどう)実際、水を掛ける根拠は何もないそうだ。そもそも不動明王(ふどうみょうおう)は大日如来の使者とされ、憤怒の相で自ら火生(かしょう)。身から火炎を放出してその火で悪魔や煩悩(ぼんのう)を焼き尽くすと言う明王である。だから本来の御利益は、厄払いです。逆境(ぎゃっきょう)を乗り越えたい人にお勧めですが、物は考えよう。学業、仕事、勝負事などなんでも行き詰まった事に厄払い。ある意味オールマイティーなのかも。因みにここでは水を掛ける事から水商売系にも良いらしい。戦前には、普通にお水を供えしていただけだったそうだ。ところがどこかの女性が願を掛けながら水を掛けたらしい。それを見た次の人が真似をした?今に至るまで、みんなが水をかけ続けていて、こんな姿になってしまったらしい。正直、石仏に水をかけ続けていつかヒビが入り壊れるのではないか? と心配である。上手い具合に火炎の所にコケは無い。それは意外に位置が高いから水がそこまで届かないのである。柄杓(ひしゃく)でかけても私には顔さえ届かない。中にはバケツでかける人もいるようだが、見ていて、さすがにお不動様に失礼な気がした。中央に不動明王(ふどうみょうおう)、脇侍は矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制多迦童子(せいたかどうじ) どっちがどっちか解りません。水掛不動の堂を横から見た所。水掛不動様は割と薄い?金比良堂江戸時代には金比良信仰でも賑わったと言う。でもこちらは神道なんですね。神仏習合の見本みたいなものです。金比良さんは漁師、船員など海事関係者の守り神として崇敬され、信仰されているそうだ。この堂の右の路地にたくさんの地蔵が・・。慈悲地蔵尊。奉納料、一体2万円なり。法善寺横丁道の両脇には和洋の飲み屋さんが並ぶ。そもそも法善寺の境内の露店から発展したのがこの横丁のルーツらしい。明治から昭和の初期にかけては寄席の紅梅亭と金沢亭が全盛で、落語を楽しむ人々で賑ったそうだ。これら夜のお店の繁盛のおかげで、逆に水掛不動尊は夜も水を掛けられているのだろう。看板の文字は西が藤山寛美さん、東は3代目桂春団治さんらしい。多分、法善寺正面の看板が西で、こちらが東。さて、道頓堀通りの看板の写真が今回載せられませんでした。大阪七墓が長くなって・・面白ハデ看板の写真だけ番外で近日アップします。今週日曜から再び大阪入りです。天気だったら良いのにな (* ̄- ̄)人Back numberリンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)他 一部リンク先リンク 世界の看板 2 大坂ミナミ(道頓堀通りの巨大看板)リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)
2017年10月31日
閲覧総数 3699
-
32

旧 仁徳天皇陵(大仙陵古墳)の謎
大阪関連のBack numberも加えました。昨年6月に大阪の堺市にある古墳を見に出かけた。そこには世界最大級の墳墓がある。私が学生の頃は仁徳天皇陵(にんとくてんのうりょう)と紹介されていた前方後円墳である。※ 今は大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)と呼ばれている。実は堺市には古墳がたくさんある。それらを総称して百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)と呼ばれているのだが、とりわけ大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)は規模が大きい。大きすぎて近くだとただの小山にしか見えない。しかもそこは天皇陵である為に宮内庁が直轄しているので中に入るどころか、遠くから小山の一部を眺める事しかできないのであった。ガッカリε~(;@_@)堺市は百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)を世界遺産にと望んでいるようだが、肝心の墳墓の発掘調査が宮内庁の壁に阻まれて、実は全然できていないから、今を持ってもほとんど解明されていないのが実情。特に最大の目玉である大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)には近づく事もできない。 御陵(天皇、皇后、皇太后の墓地)と御墓(皇族の墓地)を合わせた陵墓は宮内庁により管理。全国には896の陵墓が存在するそうだ。発掘許可がなかなか下りない事が考古学研究が遅れる要因の一つらしい。堺市は何とか観光の目玉にしたくて、上から一望できるように展望タワーの建設まで計画した事もあるそうだ。ところが実際建設のコスト計算したら観光客が入場でペイする金額と織りあわないどころか、建設費の返済に100年以上かかると算出されたらしく断念したらしい。実は昨年10月に宮内庁と堺市が共同で大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)の発掘調査を進める事が発表された。宮内庁がなぜ重い腰をあげて堺市に声をかけ、外部の者を受け入れる事にしたのかも謎ではあるが・・。そんなわけで今回は堺市博物館の資料と共に旧 仁徳天皇陵(大仙陵古墳)の謎を考えてみました。旧 仁徳天皇陵(大仙陵古墳)の謎大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)古墳のサイズと古墳ランキングから都の変遷JR阪和線 百舌鳥駅(もずえき)天王寺駅から11駅目。堺から2駅目。※ JR阪和線は大阪と紀州を結ぶ線である。下は駅近の公用地図ピンクの円で囲ったところが堺市博物館。百舌鳥駅が一番最寄り駅となる。初めての人はどこに向かったらいいかわからないと思う。何しろ近くに行っても対象物が見えないのだから・・。大仙陵古墳の陪塚(ばいづか)の一つ収塚(おさめづか)古墳大型の古墳の周りに造られた小型の古墳は、大型古墳の被葬者の親族、臣下の埋葬や、副葬品を埋納する為の塚であり、大型古墳をメインとする古墳群を形成している。墳丘長53m。帆立貝型前方後円墳。埴輪や高杯や器台など須恵器が出土しているらしい。大仙陵古墳の周囲にはこうした小さな古墳が今は13基数えられるが、本来はもっとあったはず。あるべき所に無い空があるので・・。旧 仁徳天皇陵(大仙陵古墳)は周囲を三重の壕で囲われている。下は一番外側の一つ目の濠(ほり)。墳墓が見えるの正面のみ。駅の前の道をひたすら歩くと右手に少し開けた拝所が見えてくる。最も堀の手前から墳墓が見られる程度の狭い拝所である。下が二つ目の濠の橋。一般人は入れ無い。鳥居の向こうに三つ目の濠があるはず。ウィキペディアから借りてきた2005年空撮写真(国土交通省国土画像情報より)下図は堺市文化観光局が出している「百舌鳥古墳群」の中の墳丘測量図から白黒なので解り易いように多少色つけました。ピンクの矢印が鳥居のある拝所の位置。墳丘長486m(実際は500mを超える)壕を含む全長840m三重濠の範囲464123.98㎡ (大正15年測量図による)周囲には大小の陪塚(ばいづか)※ 陪塚(ばいづか)・・大型の古墳の埋葬者のための関係者や副葬品を埋納する小さな古墳。古墳の周囲は2.85kmの周遊路があり散策できるようになっているそうだ。※ 先ほど紹介した収塚(おさめづか)古墳は右下の小円です。大山の名は、山に見えるほど大きいと言う江戸時代に読まれた句に由来。内堀の水面から後円部の高さは35.8m。※ レーザー測量による現標高は51.5m拝所の手前に250分の1スケールの石の模型がある。看板には大仙陵古墳が造られた5世紀の技術で一日あたりピーク時で延べ2000人。15年8ヶ月で述べ680万7000人が動員されたと試算。古墳の原型は意外にも幾何学的構成で積み上がるように形成されているのだな・・と言うことがわかる。現実には木が生い茂ってわからなくなっているからね。下は古墳時代の堺市全図今でこそ埋め立てがすすみ市街地が広がっているが、古墳時代、古墳のすぐ脇は海であった。江戸時代の文献では御廟は北峰にあり。石の唐櫃あり。石の蓋の長さ一丈五寸(318cm)幅五尺五寸(167cm)厚凡八寸(24cm)1872年(明治5年)前方部中段正面に竪穴式石室が発見され、中には石棺と副葬品が納められていた事が記録の絵図からわかったらしい。そしてそれら出土の絵図から、古墳の建造年代は5世紀中頃と考えられているらしい。先にも触れたが、宮内庁の管轄御陵の中でも調査許可の出ている所もある。にも関わらず、日本最大の大仙陵古墳が全く調査させてもらえなかったと言うのがそもそも不思議。もしかしたら天皇陵ではないのでは? と言う仮説もある。だから調査をされては困るのでは? との憶測も飛ぶ。何より今まで仁徳天皇陵(にんとくてんのうりょう)と記憶させられていた物が、いつのまにかシレッと大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)に名称変更されてるし・・。実際、仁徳天皇陵と伝えられてきた根拠は「日本書紀」や「古事記」の記述のみによる。日本に文字がもたらされ、編纂された最古の正史が日本書紀である。制作は720年(養老4年)。つまり古墳ができた時代にまだ日本には文字がなかったので、日本書紀に書かれた時点で、その存在は伝承意外の何物でもなかったと言うことだ。今後の発掘調査で別人の名が出るかもしれない。ところで、確証は何もないが、以前秦氏のところでチラッと触れたが、もしかしたら前方後円墳は秦氏ら渡来系の氏族により伝えられ、彼らの長の墳墓として最初造られたのではないか? と推察。理由は、前方後円墳など山系の古墳の造作はともかく、大仙陵古墳に見られる周囲を取り巻く濠(ほり)を造る灌漑(かんがい)技術は日本には無かったからだ。以前紹介しているが、灌漑(かんがい)技術を日本にもたらしたのは秦氏一族なのである。※ 2017年8月「倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい)」「秦氏の功績」で紹介。リンク 倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい玄室を支える巨石の切り出し。そして搬出も特別な技術が必要であったはず。巨大墳墓が天皇の墓であったにせよ、それは誰が造ったか? と言う謎の方に意義を感じるのは私だけだろうか?古墳のサイズと古墳ランキングから大阪府堺市の百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)と大阪府羽曳野市・藤井寺市にある古市古墳群(ふるいちこふんぐん)は、近い上に緯度も同じ。大きな古墳が点在している場所です。堺市博物館の資料にちょい足ししました。古墳の大きさランキングの上位がそろい踏みしています。※ 資料は2018年5月「古墳大きさランキング(日本全国版)」文化観光局博物館学芸課堺市博物館1位 仁徳天皇陵古墳(大仙陵古墳)墳丘長486m2位 応神天皇陵古墳(誉田御廟山古墳)墳丘長425m3位 履中天皇陵古墳(石津ヶ丘古墳)墳丘長365m7位 ニサンザイ古墳 墳丘長300m以上以前古墳時代の終わりについて紹介したがある。2017年8月「倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ」の中「古墳はどうして消えたか?」リンク 倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ646年(大化2年)に出された「薄葬令」と言う詔(みことのり)により巨大墳墓は少なくとも関西では消えた。そこそこの墳墓は地方ではまだ造られていたようだが・・。文化庁が4年に一度出していると思われる埋蔵文化財関係統計資料と言うのがある。平成28年版の「古墳と横穴墳墓の数」の統計を読み取ると1位 兵庫県 18851基 (H24年18841基)2位 鳥取県 13486基 (H24年13459基)3位 京都府 13016基 (H24年13089基)4位 千葉県 12765基 (H24年12750基)※ 最もこの統計だけではも古墳と横穴墳墓の比率がわからないし、建設年代も不明だ。意外にも関東の千葉県が上位にきていたのには驚いたが、大阪は3427基と案外少ないのにも驚いた。H24とH28の数字を比べて見るとどこも数に変動がある。増えているのは新たな発見かもしれない。減っているのは? 自然倒壊というのもあるようだ。そう言う変動を見て気づいたのは、大阪の場合、後生、古墳が取り壊されて消えている確率が非常に高いようだ。史実として平安以降、かなりつぶされているらしいし、近年もしかり・・。近年こそ遺跡を残す事に意義が見いだされているが、昭和の初期までは地主が勝手に解体して土地の切り売りが行われていたのだ。昭和30年代でも調査の後に大概がつぶされて宅地開発されている事もわかっている。百舌鳥古墳群に今あるのは104基。かつては1000以上存在していたらしいので、大阪はもしかしたら日本一古墳が建造された土地だった可能生も見える。実際、古墳数では少なくても、墳丘長が200mを超える巨大古墳が大阪には多い。巨大古墳は全国に40基近くあり、そのうち11基が百舌鳥・古市古墳群にあると言う。おそらく大阪では小さい古墳は古墳時代以降に潰されてしまったに違いない。残念下は堺市博物館から仁徳天皇陵から出土した馬型埴輪(はにわ) 5世紀中頃 複製品仁徳天皇陵から出土した鹿型埴輪(はにわ) 5世紀中頃 複製品仁徳天皇陵から出土した甲冑小札鋲留眉庇付冑(こざねびょうどめまびさしつきかぶと) 5世紀中頃 複製品横矧板鋲留短甲(よこはぎいたびょうどめたんこう) 5世紀中頃 複製品浅香山遺跡から出土した左1つ目、3つ目と4つ目(手前)は須恵器(すえき) 5世紀中期から後期左2つ目 土師器(はじき) 5世紀後半百舌鳥陵南遺跡出土左手前一つのみ須恵器(すえき) 無蓋高杯(むがいたかつき) 5世紀後半 他、土師器(はじき) 5世紀前半※ 土師器(はじき)弥生土器の流れを汲む素焼きの土器※ 須恵器(すえき)は陶質土器(炻器)。同時期の土師器(はじき)とは色と質で区別。須恵器(すえき)は青灰色で硬く土師器より上質。南瓦町遺跡出土 5世紀中頃の須恵器まるて陶芸作品のよう。お茶の器みたい 都の変遷巨大古墳を造れるのは当然富と力のある豪族。大阪に宮殿があった事は近年の発掘でわかっているが、古墳時代の大阪に、力のある豪族がいたと言う歴史的な裏付けはまだ出ていない。ただ、大阪は奈良の都から瀬戸内海につながる出口であった。逆を返せば朝鮮半島から福岡を通り、瀬戸内海を通過して奈良に向かう入り口でもあった。大切なイベント(遣隋使派遣など)では、奈良から天皇が自ら出立の見送りに難波の宮殿に来ていたと思われる。そこで盛大な見送りをしたり出迎えをしていた。そう言う事を踏まえると大阪は日本と言う国の門であったと思われる。飛鳥時代の畿内の地図に藤原京以降の都を重ねた地図(大阪市歴史博物館から)。さらに古墳群(百舌鳥,古市,長原)の位置を重ねてみました。飛鳥以前の都は藤原京より下の方ですが、全体に都は時代と共に北上しています。この図の中では、百舌鳥古墳群と古市古墳群と長原古墳群はこの中のどの都よりも古い。しかし、肝心のこれら古墳時代の都の場所の特定ができていない。地図を見ていると、河の位置や地形、古墳の建造年から見て、ひょっとしたら大和川沿いの古市古墳群(ふるいちこふんぐん)のあたりに都があったとしてもてもおかしくない気がした。河内湖に注ぐ旧大和川が近くに流れる長原古墳群と古市古墳群。都の条件に水運交通は絶対条件である。長原と古市を比べれば、河口に近い長原。安全なのは古市の方。長原古墳群は河内湖からの侵略者よけ、そして百舌鳥古墳群の方は、瀬戸内海から畿内に入ろうとする侵略者からの防衛場所に適している。古墳時代の土地を戦略的に見るなら、古市のあたりにメインの都。古市を守る防衛に長原、百舌鳥。これはベストな案だと思う。古墳はそこを守る豪族の長の墓とも考えられるからね。.河内湖は巨大な湖だった。堆積物により縮小され、後に埋め立てされて消えてしまうが、太古は大阪湾に出るには、この河内湖を経由しなければならなかった。いつしか川の方も砂が堆積して航行不能になり、都は移動せざる終えない状況になる。あるいは流行病の蔓延や、水害、干ばつなどの理由もあったかもしれない。代替わりのタイミングで、利便を兼ね備えた良い土地に遷都。都はそんな理由もあり遷都を繰り返して行ったと思われる。空白の4世紀。古墳時代初期の都はどこにあったのだろう? .昨年、難波宮の遺構も見てきた。大阪歴史博物館の地下にあるのだ。仁徳天皇が難波に皇室を持っていたとウィキペディアには出ているが、これはどうだろう。前期難波宮は第36代孝徳天皇(こうとくてんのう)(596年(推古天皇4年)~654年)が造営とされている。第16代仁徳天皇(にんとくてんのう)では時代が合わない。そもそも仁徳天皇の年齢も定かでない。以前紹介しているが、仁徳天皇の治世は87年に及んでいる。生まれたのが神功皇后摂政57年(257年)で亡くなったのが仁徳天皇87年(399年)。142歳まで生きた事になる。これでは実在したのかも怪しいかもしれない。大阪歴史博物館 難波宮を模した宮中フィギュアいったい誰の墳墓なのか? 宮内庁と堺市の発掘調査が楽しみですね。Back numberリンク 大坂の陣 古戦場 1 茶臼山と真田幸村リンク 大坂の陣 古戦場 2 安居神社(真田氏終焉の地)大阪については以下も書いています。リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 2 (千日墓所と法善寺&大坂七墓)リンク 世界の看板 2 大坂ミナミ(道頓堀通りの巨大看板)リンク 大阪 造幣局 桜の通り抜けリンク 四天王寺庚申堂
2019年01月23日
閲覧総数 7310
-
33

アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)
重大お知らせ「アジアと欧州を結ぶ交易路 24 オランダ東インド会社(東アジア)」を2つに分離させてもらいました。余りにも長すぎ、自身の扱いにも困ったので・・。そもそも長すぎたのは掲載写真が少なかった事で、写真に合わせたからなのです。24回目はそのものを固定して 2-1回と 2-2回で分けました。よってタイトルも以下に変更しました。アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)この回が前編扱いです。「オランダ東インド会社が運んだ品」以下からを中編にしました。※ 後編は「アジアと欧州を結ぶ交易路 25」でタイトルします。尚、双方に若干の写真追加などしております。さて、「アジアと欧州を結ぶ交易路 22」では世界の覇者となったスペイン帝国の「太陽の沈まぬ国の攻防」の話をしました。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防そのラストでネーデルランド(オランダ)によるモルッカ諸島(Moluccas)への進出はすでに触れていましたが今回はそのネーデルランド(オランダ)がいかにアジアに入りこんで行ったのか? の話が中心になります。そのネーデルランド(オランダ)のアジア進出は、ポルトガルやスペインとは異なる形態での参戦なのです。まずは復習から。アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)ネーデルランド(オランダ)のアジア参戦理由商船 アムステルダム号東インド会社とは何か?ネーデルランドのアジア参戦オランダ東インド会社(VOC)の進撃イングランドのアジア参戦各国の東インド会社(East India Company)東インド会社は勅許会社(ちょっきょがいしゃ)与えられた特殊な権利アムステルダム銀行の設立が支えた経済VOCコインネーデルランドの衰退、東インド会社の衰退、アムステルダム銀行の衰退ポルトガルでは、国家が大航海時代そのものの道を開きアジア進出に臨んでいる。※ 当初の船は国が開発し、用意。※ 商取引きじたいはジェノバの商人がかかわっていたと思われる。スペインの場合は、国家が冒険者たちを見受けする形で参戦。当初はポルトガルと話し合いの上、住分けしていたが、後にポルトガルの相続問題からスペイン国がポルトガルを併合した形で全てを掌握する時代が到来。(ほぼスペインの天下時代)※ 船は航海者が自前で調達。後に国力が上がるとスペイン海軍の軍船が協力。今回紹介する、ネーデルランド(オランダ)の場合は、トップが交易の許可を与えただけ。実はその頃、ネーデルランド(オランダ)は独立戦争中。(80年戦争の終結が1648年。)アジア初到達の時点(1596年6月)で、まだ国家はなかったのです。アジア進出は民間が独自に会社を設立(東インド会社)し、船も自前。それら費用をまかなう為に株式制度を導入しての参戦となったのです。もしかしたら、国家として正式参戦できなかったから株式会社と言う特殊な参戦になったのかもしれない。※ 商船のみならず、護衛の軍船も会社組織の中に保持。ネーデルランド(オランダ)のアジア参戦理由独立戦争の中、なぜネーデルランド(オランダ)商人がアジアを目指したのか?そこには、市場におけるオランダ商人の排除? が要因にあったのでは? と考えられる。事の始まりは やはり80戦争?それ以前、北海に面するアントワープ(Antwerp)にネーデルランドは大きな貿易港(マーケット)を持っていた。しかしポルトガルは北部のハンブルク(Hamburg)に卸しの拠点を変更したらしい。それはハプスブルグ家が懇意にするドイツ系の金融家であるフッガー家(Fugger family)やウェルザー家(Welser family)のシンジケートに流通を変更したからだと言う。ハンブルク(Hamburg)と言う時点でハンザ(Hanse)の流通を有利に戻したとも考えられる。そもそもアントワープの存在はハンザ衰退の要因にもなっていたし、当然、スペイン側も戦争中の相手国の港を回避した。という理由もあろう。ポルトガル王も交戦中のスペイン王(ハプスブルグ家のフェリペ2世)が兼任しているのだから・・。また、以前はポルトガルのリスボンで胡椒など仕入れていたネーデルランド(オランダ)商人が、これもまた80年戦争の影響でイベリア半島の港街への出禁となった。これらにより、ネーデルランド商人によるスパイス・ハーブの取引は、より困難が伴っていくのだが、この頃、ポルトガルが内密にしていた東アジアへの航海情報が外部に洩れつつあり、ネーデルランド商人はインドネシア諸島への直接買い付けに動いたのだと思われる。そして1596年、ネーデルランド(オランダ)のフレデリック・デ・ハウトマン(Frederick de Houtman)(1571年頃~1627年)率いる探検船4 隻がついにジャワの胡椒の主要港であるジャワ島バンテンに到達成功。※ 産地のモルッカ諸島(マルク諸島)までは行ってない。※ マルク諸島(Kepulauan Maluku)はインドネシア語。この初遠征では現地でトラブルがあり乗組員の半数が失われたが、彼らが持ち帰ったハーブ・スパイスだけでかなりの利益をあげた。それが、決め手となりネーデルランド商人らのアジア直接買い付けに道が開けたのである。もっとも、ネーデルランドによる現インドネシアの支配はVOC時代を含めて300年以上に及ぶので、当初スパイス・ハーブの独占で利益を上げていたが時代と共に需要は変化。取り扱いの商品も変わって行く。加えて、彼らが築いたアジアの拠点バタヴィア(Batavia)は、中国や日本の産物を取引する中継貿易の拠点としても発展し利益を上げる存在となって行く。スパイス・ハーブのマーケットから省(はぶ)かれて、それでもスパイス・ハーブを求めたネーデルランド(商人)達は(株式)会社を立ち上げ、自分たちで資金を調達(資本家集め)。外洋航海できる船も自前で調達してアジアに乗り込んだ。※ 1603年の初航海では艦船12隻で出陣。結果、彼らの行動は国に大きく貢献。会社も国も金持ちとなり、優秀な人間も集まり、オランダ黄金時代(Gouden Eeuw)をもたらすのである。※ 欧州で最も富裕な国で、貿易、学問、芸術の最先端国家となる。今回はそんなネーデルランド(オランダ)の「株式会社 東インド会社(VOC)」の話ですが、彼らの闇が凄い。そんな闇にもせまります。東インド遠征隊のアムステルダム帰還 1599年7月画家 Hendrick Cornelisz Vroom (1562/1563年~1640年)所蔵 アムステルダム国立美術館ヤコブ・ファン・ネック(Jacob Corneliszoon van Neck)(1564年~1638年) の指揮による第2次東インド遠征隊アジア遠征からの帰還(1599年)の図である。4隻の艦船、モーリシャス(Mauritius)、ホランディア(Hollandia)、オーファーアイセル(Overijssel)、フリースラント(Vriesland)が、スパイス・ハーブをゲットして東アジアより母国に帰還。多数の小型船と満載の手漕ぎボートに迎えられている。まさに凱旋と言った光景。ヤコブ・ファン・ネックはスパイス・ハーブの産地であるモルッカ諸島(Moluccas)に最初に到達したネーデルランド(オランダ)人となった。商船 アムステルダム号18世紀のオランダ東インド会社の商船 アムステルダム号 (レプリカ)アムステルダム国立海洋博物館に係留されているレプリカ船。1748年、アムステルダム号建造。貿易品を積んでニューヨークへ処女航海?1749年、処女航海からほどなく (ほぼ英仏海峡対岸)イングランド・イーストサセックス州にあるヘイスティングス(Hastings)沖で嵐に遭遇。崖? 岩? に激突して難破。※船と積荷は失われたが、乗組員のほとんどは助かったらしい。1969年、「アムステルダム号」発見?船体は状態も良く、海底保存されていたのでダイバーや海事史愛好家のスポットとなっていたらしい。近くの町、イーストボーン船舶博物館で、アムステルダムの展示品や破片を見ることができる。と紹介されているので、本体のサルベージ(Salvage)はされていないみたいですね。それらを基に復元したレプリカがアムステルダム港に係留されているこの船です甲板は真っ赤だったと記憶しています。かなり昔に乗船。血で汚れても解りにくい。と言う配慮だったと聞いた記憶が・・。彫刻がちょっとチープだけど、持ち物からそれぞれギリシャ神話由来の神を守り神としているのがわかる。共にオリュンポス十二神の一柱。右、トリアイナ(τρίαινα)と呼ばれる三叉の矛(ほこ)を持つポセイドーン(Poseidōn)神。海洋の全てを支配する神。地震の神。トリアイナによって大波、津波、嵐を起こすとされる。皮肉にも、船は嵐による被害で沈没してしまったが・・。左、ケーリュケイオン(kērukeion)または、カードゥーケウス(cādūceus)(伝令使の杖)を持つヘルメース(Hermēs)神。神々の伝令使であり、旅人、商人などの守護神。また、蛇がからむ杖が象徴するのは平和・医術・医学。また発明・錬金術などの神ともされる。赤い盾に✖3つは聖アンデレ(andere)の十字でアムステルダムの市章である。フラグの中央には東インド会社(Verenigde Oost-Indische Compagnie)(VOC)のロゴ入り。東インド会社とは何か?そもそも東インド会社とは何か?簡単に言えばアジア方面の交易を主軸にする会社の総称です。組織形態や会社形態などは異なるが、総じて欧州勢による「インドや東南アジア方面での商取引を専門とする部門」の事を指す。また、どこもバックに国が付いて強力に支援している。と言う点が特徴である。※ 商取引きのみならず、彼らによる植民地下のプランテーションなども含まれる。要するに「東方貿易専門の商社」が東インド会社なのである。ただし、江戸期に日本にも来ていたオランダ東インド会社は、アジアに拠点を置いた交易や植民地活動で知られて居ると思うが、実はアジアだけではない。彼らは東方貿易の道すがら、船舶の補給基地として南アフリカにも拠点を持った。オランダ東インド会社はケープ植民地(Cape Colony)として南アフリカにも植民地展開していたのである。ポルトガルやスペインが香料諸島のある東南アジア方面に進出した時には無かった名称である。ネーデルランドのアジア参戦先にすでにふれてますが、詳しく・・。1602年、「Verenigde Oost-Indische Compagnie(VOC)」「東インド諸島連合の会社」と言う会社がネーデルランド(オランダ)で設立された。これはネーデルランド(オランダ)の商人らが一体となって、寄り合い、東アジアへの商売に共同で参入する為に造った世界初の株式会社でした。彼らは株券を買ってもらう事で資本を大きく集めたのです。先にも触れましたが、スパイス・ハーブを求めたネーデルランドの商人たちですが、ネーデルランド内でも当初は複数の商社が競いあい奪いあっていたらしい。しかし、競争となれば商品の値段も跳ね上がる。そこにイングランドも参戦すれば市場は争奪戦となり、共倒れになるのは必至(ひっし)。そんな現状を鑑(かんが)み、1社に統合して共に戦うようアドヴァィスしたネーデルランドの政治家がいた。ヨハン・ファン・オルデンバルネフェルト(Johan van Oldenbarnevelt)(1547年~1619年)である。オルデンバルネフェルトの提言でネーデルランド商社連合による「オランダ東インド会社」が1602年に誕生する事になった。また、これは世界初の株式会社となり、同時に1602年、アムステルダム証券取引所も開設された。※ アムステルダム証券取引所(Amsterdam Stock Exchange )(Dutch: Amsterdamse effectenbeurs)余談であるが、1619年、VOCの創設者とも言えるヨハン・ファン・オルデンバルネフェルト(Johan van Oldenbarnevelt)をネーデルランド(オランダ)政府は処刑している。彼はオラニエ公ウィレム1世の元で戦い、ネーデルランドを独立に導いた重要な政治家の一人でもあるのにだ。※ オラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)(オラニエ公在位:1544年~1584年)処刑理由は前回「アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭」の中、「フーゴー・グローティウス亡命の件」で紹介した1618年「ドルトレヒト(Dordrecht)教会会議」の神学論争にレモンストラント派が負けたからだ。国はカルバン主義をとった、反対派の重鎮は処刑か投獄。意見を異にしただけの事で国際法の父と呼ばれるフーゴー・グローティウスは投獄され脱獄してフランスに亡命。しかしヨハン・ファン・オルデンバルネフェルトはハーグのビネンホフで公開斬首された。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭カルバン派の温情もない残虐さはこの頃から見える。VOCの根深い闇はカルバン派の思想が根底にあるからなのか・・。ヨハン・ファン・オルデンバルネフェルト(Johan van Oldenbarnevelt)に敬意を表して肖像をのせさせてもらいました。Portrait of Johan van Oldenbarnevelt ウィキメディアからかりました。1616年から1641年の間の肖像画画家 Workshop of Michiel Jansz. van Mierevelt (1566年~1641年) 所蔵 Rijksmuseum(アムステルダム国立美術館)良識ある知識人は反カルバン主義であった。ハーグのビネンホフでカルバン主義者らによって処刑されるヨハン・ファン・オルデンバルネフェルトリッデルザール(Ridderzaal)(騎士の館)前の広場。ハーグのビネンホフの写真があったので紹介しますデン・ハーグ(Den Haag)はネーデルランドの政治の中枢で、ビネンホフ(Binnenhof)は旧議事堂です。リンク デン・ハーグ(Den Haag) 2 ビネンホフ(Binnenhof)話を東インド会社に戻して・・。VOCの取引項目では特にスパイス・ハーブでも、ペッパー(Pepper・コショウ・胡椒)、クローブ(Clove・チョウジ・丁子)、ナツメグ(Nutmeg)の輸入金額だけで全体の70%~75%に上っていたらしい。特に希少なこれら産地限定のスパイスで欧州の市場の独占を図った。ただ、それを求める為に彼らがした行為はほめられたものではなかった。オランダ東インド会社では、スパイス・ハーブ以外では、生糸とシルクの反物、綿織物、砂糖、金、銀、銅、コーヒー、茶葉が主要な輸入品となっていく。オランダ東インド会社(VOC)の進撃もともとインドネシア諸島はポルトガルが開拓した場所。後追いで1596年に到達したネーデルランド(オランダ)は、次々ポルトガルの港を奪って行く。実際、オランダ東インド会社が設立されて公式の最初の航海が1603年12月のアムステルダム出航である。艦船12隻。そもそもこの航海では、モザンビーク、ゴアなどのポルトガルの拠点を攻撃し、ポルトガルを追い落とす事が目的だったと伝えられている。そもそも普通の商船ではなかったのです。あとでまた触れますが、東インド会社は海軍も供えた一団だったからです。以下はネーデルランドが占拠してい行った順に示している。正式な会社設立前からすでに先陣がアジア入りはしている。尚、最初の2つは公式に現地バンテン王国(Sultanate of Banten)から許可をもらい建設している。1602年、香料諸島南方のバンダ(Banda)1603年、ジャワ島のバンタム(Bantam)1603年、マレー半島のジョホール(Johore)1605年、香料諸島南方のアンボイナ(Amboina)1612年、香料諸島南方のティモール(Timor)1619年、ジャワ島のバタヴィア(Batavia) アジアにおけるオランダ東インド会社の貿易ネットワークの中心地となった。1635年、ボルネオ島のバンジェルマシン(Banjermasin)1641年、マレー半島のマラッカ(MalAcca) マラッカ征服後、マラッカのポルトガル語話者は捕虜になった。1659年、スマトラ島のパレンバン(Palembang)1664年、スマトラ島のパダン(Padang)上は一度「アジアと欧州を結ぶ交易路 22」のラストで紹介しています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防イングランドのアジア参戦欧州市場ではネーデルランド(オランダ)による輸入が増えて、スパイス・ハーブなどが彼らによって価格操作され始めていた。それに脅威を感じたイングランドが香料諸島の商事に参戦。慌てて東インド会社なる物を設立したと言われている。※ こちらは一つの会社ではなく複合組織の総称である。が、イングランドの場合は自国の毛織物の輸出振興と言う側面もあったらしい。ネーデルランドは買い付け目的が主であったが、基本、貿易は「売り込み」、「市場の開拓」。イングランドは、当時毛織り物産業が不振であった為に、自国の毛織り物を売り込むのが最大の目的であった。だが、それらは東南アジアでも、インドでも全く売れなかたと言う。(温かい国にウールは必要なかった?)最も、毛織り物に限らず、欧州の品はどれもほぼ売れなかったらしく、途中から金地金を送って珍しい逸品を買いあさる方向に転換したらしい。確か、日本も交易で欲しいのは中国や韓国からもたらされる生糸、名陶や茶葉、香の原料などであり、欧州の品はいらなかった。(オランダ東インド会社が日本に運んでいた品は欧州産ではなかったらしい。)各国の東インド会社(East India Company)1600年 イングランドによる 東インド会社 設立? 一つの会社と言える組織ではない。 ドレイクの時から続く、航海ごとに資金を募る(出資する)形態から後に株式配当のようなシステムにイングランドも移行する。 ※ 1623年のアンボイナ虐殺事件を受けて、市場を東南アジア諸島からインドに移行した。1602年 ネーデルランドによる東インド会社 正式設立。 正式名 東インド諸島連合の会社(Verenigde Oost-Indische Compagnie)(VOC)(株)。 ※ 資本金650万ギルダー イギリス東インド会社の10倍以上。出資は10年固定。 ※ 1799年解散。1604年 フランスによる 東インド会社 設立。 フランスの場合は、商業利権の参入だけでなく、植民地l経営の参入も大きな目的。 ※ 1664年国営会社。1612年 デンマークによる 東インド会社 設立。 クリスチャン4世の特許条で設立。1731年 スウェーデンによる 東インド会社 設立。 中国(清国)の広東との貿易が主。※ イングランドの東インド会社発足は1600年とされているが、実はアジアへの参入はネーデルランド(オランダ)のが早い。ネーデルランド(オランダ)の船団が、東南アジア(ジャワ島バンテン)に初到達したのは1596年6月。それからアジアとの取引が開始され1602年の統合設立までに14の会社が参入していた。株式会社として正式に登録されたのが1602年であっただけ。The Home Fleet Saluting the State Barge (国営船に敬礼する本国艦隊)制作 1650年。画家 ヤン・ファン・デ・カッペル(HJan van de Capel, H.)所蔵 アムステルダム国立美術館(Rijksmuseum Amsterdam)2隻のヨットが、手前、国営船で漕ぎ進む役人(検閲)たちに敬礼をしている図らしい。1602 年~ 1796 年にかけて100 万人近くの欧州人がVOCのアジア交易に従事。VOC の船は 4785 隻に及ぶ。一方、ライバルのイングランドは2690隻で上げた利益はVOCの5分の1。VOCの効率が良かったと言うよりはVOCの商売のやり方? いや、かなりあこぎな事をした結果だろう。ポルトガルが船と積み荷を返せと訴訟を起こしているし・・。東インド会社は勅許会社(ちょっきょがいしゃ)(Chartered company)東インド会社(East India Company)。オランダ語から訳すと、「Verenigde Oost-Indische Compagnie」「東インド諸島連合の会社」。略して「VOC」。ネーデルランド(オランダ)は同国の商人により結成され「オランダ東インド会社(株式会社)」として東アジア交易に参戦。そのビジネスモデルは成功を収めた。先に紹介したオルデンバルネフェルトはそれを指導しただけでなく、複数の株主による共同持ち株と言う事業形態をも発案した人物と言われる。本当に功労者だったのに・・そしてこの会社の株券はアムステルダム証券取引所で売買されネーデルランドの国民は誰でも購入が可能であった。アムステルダム証券取引所も同年、1602年に設立されている。※ アムステルダム証券所は2000年の統合により現在はユーロネクストが運営。与えられた特殊な権利ところで、この株式会社は交易だけに従事していたわけではなく、交易先を植民地化して行くのである。その為には現住民との交戦もやむなし。すでに商館を持っているポルトガルからは奪い取る事も目的であった。※ アンボイナ虐殺事件もその一つと言える。(この時の相手はイングランドであった。)そんな強硬な態度でアジア参入できたのは、この会社が国からの特別許可状が与えられた勅許会社(ちょっきょがいしゃ・Chartered company)として存在していたからでもある。彼らには普通の商社ではありえない特権が与えられていた。兵士の雇用権、アジアでの要塞建設の許可権、現地総督の任命権、現地での条約の締結権、囚人の投獄及び処刑の権利、独自貨幣の鋳造許可etc。オランダ東インド会社は、ただの商社では無く、政府機関で無いにもかかわらず、軍隊を付随させて侵略的進行(戦争)を行い自ら現地総督を任命して要塞建設及び植民地活動を行こなう。パワー系の企業。VOCKの提督(ていとく)は現地有力者と条約交渉から締結(ていけつ)までも許可されたていた。そんな特権を与えられた特殊な商社? 会社だったのである。※ 設立から先、21年間のアジア交易の独占権も付されていたと言う。The Harbour in Amsterdam (1630) showing the Port of Amsterdamアムステルダムの港の眺め 1630年制作画家 Hendrick Cornelisz Vroom (1562/1563年~1640年)所蔵 アルテ・ピナコテーク(ミュンヘン)アムステルダム銀行の設立が支えた経済東インド会社と言う株式会社が設立(1602年)され、アムステルダムに証券取引所が開設(1602年)されたすぐ後、同じくアムステルダムには公立の振替銀行が設立(1609年)された。1609年、アムステルダム銀行(Amsterdamse Wisselbank)設立。この銀行はあらゆる種類の貨幣を預金として受け入れ、法定換金率で換算した銀行通貨グルデン(gulden)で払い戻しを行った。※ 預金の単位グルデンは,銀行グルデンと呼ばれ,実際の鋳貨に数%のプレミアムのついた独自の銀行の通貨単位となった。※ グルデン(gulden)(英:ギルダー・guilder)。これは非常に活気的な事なのである。なぜなら、国ごとに純度も異なる貨幣を一律に扱う事は、本来難しい事。内外の雑多な鋳貨(悪貨もある)の流通による混乱を防ぐ意味でもセビリアやヴェネツィアのような銀行の設立が求められていた中での事。北ヨーロッパでは初。16世紀のアントワープでは、公的には預金・振替業務が禁止されていたので公立の振替銀行は存在せず、振替業務はカシール(cashier)と呼ばれる民間の金融業者等が担っていたそうだ。しかし彼らの振替えはズルいもの。世間では、多種多様な鋳貨が流通していた事は確かだが、それを理由に為替手形の支払において現金での払い戻しを嫌い、現金払いには1%から10%のプレミアムを要求。しかも、法定重量を満たさない悪貨を債権者に渡して不当な利益をあげていたと言う。※ アムステルダム銀行が設立されると民間金融業者の振替業務は禁止された。アムステルダム銀行による振替えでアムステルダムの通貨は安定。欧州各地の商人が口座を開き世界貿易の中心地となって行く。当然、アムステルダム銀行の存在はオランダ東インド会社(VOC)の商取引に拍車をかけたはず。それにしても多種多様な鋳貨が市場にある事は問題だった。例えば、金貨でも純度で価値は当然変わる。換算も面倒である。さらに法廷基準の純度に満たない悪貨も出回っているのだからすんなり信用もできない。こういう時に一度銀行に入れて銀行グルデンに振替えれば良いわけだ・・。※ 南ネーデルランドの悪貨にはアムステルダム銀行も困り、自ら鋳造して対処している。しかし、もっと簡単な方法がある。信用のおける共通通貨で商取引すれば事はスムーズに運ぶ。VOCコインの発行はそう言う事かな?VOCコインアジアでの支払いを独自コインの発行でカバーしたのか? 植民地内での生活コインか?資料があまり無いのです。私の持ってる貨幣の本では取り扱われていなかった。貨幣として公式には認められていないのかな? 確かに、国が発行した貨幣ではないからね。ネーデルランド政府は株式会社のVOCにコインを製造する許可も与えていた。1793年 オランダ東インド会社がアジア用に発行 シルバー(銀)のVOCコイン。'Rider' ducaton 「ライダー」デュカートンウィキメディアから借りました。Silver rider(銀の騎手)重さ32.779グラム、銀0.941騎士の下の盾は鋳造州を示すらしい。 これはユトレヒト(Utrecht)を示している。1659年、騎馬騎士を描いた「銀の騎手(Silver rider)」デュカートン(ducaton)の鋳造開始。1726 年~ 1751 年にかけて、オランダ東インド会社のモノグラムが刻まれたデュカートンが鋳造。1798年までライダー デュカートンは鋳造されていたらしい。1799年、オランダ東インド会社(VOC) 解散。ギリギリまで鋳造されていたようですね。最も現地は解散になるとは思ってもいなかったろうが・・。その後の支配者はしばらくネーデルランド(オランダ)国ではなくなります。1815年に再びネーデルランド国による直接支配でアジアの植民地は復活しますが、もはや株式会社VOCは無いのです。1735年 オランダ東インド会社がアジアで発行 ブロンズ(銅)のVOCコイン。ウィキメディアから借りました。表面には VOC モノグラムと製造年が、裏面にはネーデルランド(オランダ)の紋章。摩滅具合から相当使いこまれたブロンズコイン。安いコインは絵柄もシンプルですね。gold(金)、silver(銀)、bronze (青銅)に加えて、pewter(主成分はスズ)の貨幣が発行されている。※ コインは本国の地方造幣局で鋳造。ネーデルランドの衰退、東インド会社の衰退、アムステルダム銀行の衰退アムステルダム銀行に戻ると、オランダ東インド会社(VOC)の隆盛は本国の経済を潤した。ここにアムステルダム銀行の存在と役割は大きく、オランダ黄金期を迎えるのに貢献しいる。しかし、この銀行は当初、当座貸越しを厳禁し、国や市への貸付けもほとんど見られなかったのに、1683年から市の法令により抵当貸付ができるようになった。(金貨0.5%、銀貨0.25%の低利)商人は金銀を預け、(預金)証書を受け取る。気付くと、オランダ東インド会社(VOC)への貸し付けが増加していたらしい。英蘭戦争以降にネーデルランドの経済は下降を始める。第一次英蘭戦争(1652年~1654年)第二次英蘭戦争(1665年~1667年)第三次英蘭戦争(1672年~1674年)1732年頃から東インド会社への貸付額の累積赤字が膨らみ経営状況は悪化していく。東インド会社の業績が落ちて来た? 1763年 信用危機。1780年 第四次英蘭戦争でさらに打撃。1795年 フランス軍の侵攻と占領で預金者が引き上げ。(大量の預金がハンブルクへ逃げた。)1799年 オランダ東インド会社(VOC) 解散。1815年 ウイーン議定書でVOC植民地の返還が決定。 オランダによるインドネシア植民地支配が再開されるが・・。1819年 アムステルダム銀行 倒産。銀行の資産がすべて東インド会社に貸し出されていたらしい。東インド会社と共に隆盛した銀行と言えなくもないが、度重なる国の戦争が招いた経済の打撃も大きい。オランダ黄金期を造った銀行も最後は倒産してしまった。最初に紹介しましたよう。以下を移動しました。アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編) オランダ東インド会社が運んだ品東インド会社の輸入したスパイス・ハーブイングランドとのスパイス・ハーブの協定オランダ東インド会社植民都市 バタヴィア(Batavia)VOC提督 Jan Pieterszoon Coenバンダ虐殺(Banda massacre)アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)カルバン派の国と提督日本とVOCの関係VOCとの取引開始とリーフデ号ポルトガルの排除Back numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編) アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク 焼物史 土器から青磁までリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン
2025年02月15日
閲覧総数 215
-
34

ヴァイキング 3 (竜頭柱とヴァルハラ宮殿)
ヴァイキング 3 (竜頭柱とヴァルハラ宮殿)ヴァイキング(Viking)ノルウェー(Norway)オスロ(Oslo)ヴァイキング博物館(Vikingskipshuset)モンスタ-・ヘッド(竜頭柱)船首飾り戦士とヴァルハラ宮殿船首には竜や蛇のような動物の彫り物がなされ、船と乗組員を守る守魔除けとして付けられていた。竜頭柱の一部にはとっての付いた物もあり、船首のみでなく祭儀ように何か利用されたと伺える物もあるらしい。実際、オーセバルク船(Oseberg)の塚からは5つの竜頭柱が出土しているようです。材質はかえでの木。モンスタ-・ヘッド 竜頭柱ヴァイキング独特の木彫技術がすばらしい。透かし彫りになった精密な柄は実にヴァイキング的な図柄。年代は解りませんが恐らく時代が進むにつれて細密な物に変わっていると思われる。下の竜の透かし彫りは、まるでカリフラワーのように巧みな重なり具合で表現された彫り物。彫りによっては細かく何かの動物が彫り込まれている物もある。前回紹介した物ですが、細部を紹介するために・・。拡大すると透かし彫りに装飾の施された金属の鋲(びょう)が打たれている。鋲自体の装飾も、とてもこった造りです。この装飾方法は、いろんな物の装飾に取り入れられている。これも流行か?下は、竜頭柱でも先に述べたような下方に取っ手のついたもの。彫りは透かし彫りではありますが、比較的シンプル単純な文様。上のものと同じ物顔は意外にシンプル・・時代の古い物かも・・・。副葬品のそりにもモンスター飾りが付いている。このソリが結構贅沢な造りで金属も細かく使われている。船首飾り3~4世紀のヴァイキング船の船首にもモンスタ-・ヘッドが浸けられていたのが確認されています。もっとも古代ギリシアやローマ世界や地中海貿易で活躍したフェニキアなどの貿易船も船首に飾りを取り付けていたと言うので、それらは宗教的な意味において必要であったのかもしれない。安全を祈願して船を守るものとして女神などが取り付けられていたらしいので・・。もし、ヴァイキング船が古代ローマの技術に由来していたなら、そうした飾りも伝わった可能性はありそう。ただ彼らの船首飾りは美しい女神ではなくおどろおどろしいモンスターで造られているから、そこには同じ守りでも魔除け的な意味合いがあったのだろうと推察出来ます。北欧神話では大地は丸くその周りを海が囲む。そして、その向こうにミズガルドの大蛇がとぐろを巻いている。とされている。その大地の中心ミッドガルド(Midgard)(中つ国)は美しい土地で、そこに人が住んでいると考えられていたのだ。ヴァイキングの信仰の源はキリスト教に改宗する前は北欧神話の神々でした。ヴァイキング達は北欧神話に出てくる恐ろしい海の怪獣を避けていたと言われている。もしかしたら、ミズガルドの大蛇を避ける為の魔除けのドラゴンだったかも? 戦士とヴァルハラ宮殿また、北欧神話ではミッドガルドの上方の天地に、アスガルドに神々や、万物の神オーディンがいると考えられ、天界には戦死者の館、ヴァルハラ宮殿がある。戦士の父でもあるオーデインは、部下ワルキューレに命じて戦死者をこの宮殿に運ばせる。ヴァルハラ宮殿では毎日宴が催されていたのだ。運ばれた彼らはここで楽しい時を過ごす。だからヴァイキング達の時代、戦士はヴァルハラ宮殿に迎えられる事を願って勇敢に戦ったと言う。逆に勇敢でなかった者は飢えと悲しみのヘルに運ばれると言う不名誉が待っていた。だから残る多くの石碑にヴァルハラ宮殿に迎えられる戦士の図が描かれているのだろう。一度彼らが戦えば、怖い者知らずの一団と恐れられたのは、こうした彼らの信仰故だったのかも・・・。つづくリンク ヴァイキング 4 (副葬品)
2010年02月04日
閲覧総数 999
-
35

ちょっと贅沢な「スパム(SPAM)むすび」の作り方
Break Time(一休み)今回は料理ネタです 最近は日本国内のスーパーでも売られ始めているので、知っている人も多いアメリカのホーメル・フーズ(Hormel Foods Corporation)が販売するランチョンミート「スパム(SPAM)」を使った、少し贅沢なスパムむすびを紹介します。お年寄りにも大受けの和テイストの上品な仕上がりです (^~^)~^)~^)^~^)゛ちょっと贅沢な「スパム(SPAM)むすび」の作り方1937年に誕生したスパム(SPAM)はホーメル食品(Hormel Foods Corporation)が商標登録したランチョンミートです。スパム(SPAM)缶詰12oz(340g)とスパムむすびメーカー(Musubi Maker)アメリカ産と言う事もあり、昔から在日米軍基地周辺では比較的有名な缶詰食品です。そんなわけで基地の多い沖縄でのスパム(SPAM)の定着度はハワイなみです。内地(本州)より値段が安い事も流通が多い理由でしょう。ゴーヤ・チャンブルにも豚肉ではなくスパム(SPAM)を使用する所も多いそうです。ただ、ちょっと塩分と油分が強いので高血圧の方は25%Less Sodium(減塩)の缶詰がおすすめです。通常サイズ(340g)なら一缶8枚切りくらいが調度良い厚さ。切ったら水分を抜きましょう。このまま使う人は少ないでしょうが、焼くにしてもちょっと生臭いです。スパム(SPAM)の素材ランチョンミートとは、ソーセージの一種で、香辛料を加えた挽肉を固めてオーブンで加熱したもの。本家のホームページによれば原材料は主に「豚肉、砂糖、塩、水、少量のポテトスターチ(でんぷん)に、発色剤として(亜硝酸Na)が入っている」・・と言う事ですが、Less Sodium(減塩)のスパムにはチキンも入っているようです。豚肉は、豚モモ肉を加工した「ハム」と、その他の部位の豚肉をミンチ状にした「ポーク」が使われている・・との事。ホーメルフーズジャパン株式会社 のホームページからのレシピコーナーです。リンク レシピまずはフライパンで焼き目がつくまで・・。かなりの油が出るので油切りをお勧めします。このまま食べても美味しいのがスパムです。Less Sodium(減塩)のスパムでもかなり塩分が強いのでご飯がすすむ このままスパム・メーカーでにぎる人もいるのかもしれませんが、一手間二手間加えるととてもおいしくなります。スパム(SPAM)に少し甘めの味付けをします。材料はきび糖、ハチミツ、醤油、日本酒 より美味しく、上品な味に仕上がります ご飯を用意します。適したお米は日本型のお米、アメリカならカリフォルニア米を使用すると良いでしょう。タイ米を使用してバラパラになり失敗した人がいます。ところで、普通ならただの白飯が一般的ですが、ここでもご飯に一手間加えます 今回はちりめん山椒(さんしょ)を混ぜ込みました。残っていたひじきのふりかけも入れたようです・・。とにかく山椒のピリリ・・が良く合います スパムむすびメーカー(Musubi Maker)に入れるご飯の量はちようどお茶碗1杯分です。入れたらくずれない程度に型押ししてください。(あまり押しつぶさないように・・。)海苔を用意します。贅沢に半切り1枚使用。ぐるりと巻き込むのがおいしさの秘密です。ご飯の上に味のバランスで伽羅蕗(きゃらぶき)の佃煮やたくあん漬けなど少し入れるのも良いでしょう。微妙なさじ加減に味のセンスが出ますね 今回の贅沢な「スパム(SPAM)むすび」で、何の単価が高いか? と言えば海苔が一番高価です。実際、市販の物はちょびっと海苔で帯しただけの物がほとんどです。高級な海苔ほど風味が良いので時間がたっても美味しいです。あるなら、贅沢に良い海苔で巻いてみてください 軽くつつみ込むように巻き付けてください。かなり大きいのでラップにくるんで半分にカットすると食べやすいです。ちりめん山椒(さんしょ)と伽羅蕗(きゃらぶき)の佃煮入りの贅沢スパム(SPAM)むすびの完成です。下は別の日のカリカリ梅とひじきのふりかけがご飯に入った贅沢スパム(SPAM)おにぎりスパム(SPAM)に若干甘めの味付けを施しているので、カリカリ梅なども非常に良くあいます。食感も出るし・・。野沢菜などのまぶしご飯なんかもいけるかもしれませんし、たくあんを細かく刻んでご飯に入れるのも合うかもしれません。(中に入れる物の塩加減には気をつけてくださいね。)今までのスパム(SPAM)むすびとはかなり違う「和テイスト」の品のある高級むすび。発案はワイキキ在住の日系一世Kyokoさんです。名付けてKyoko Special SPAM Musubi 油と塩分を控えて、食材の生きる組み合わせにしているので、スパムを食べた事のないお年寄りにもいけるはずですよ。Kyokoさんはよく作って売れば・・と言われるそうですが、単価をはじき出したら高すぎて売れない・・と嘆いています 自分用だからこそできる贅沢スパム(SPAM)むすびなのです。ところで、この「スパム(SPAM)むすび」はいつ頃からあるのか?義理の兄によれば、スパム(SPAM)むすびは、ハワイのカウアイ島の発祥だそうです。ハワイ在住の日系アメリカ人によって第二次世界大戦後に考案されたそうで、40年以上前からすでにハワイではポピュラーになっていたそうです。それなのに今まで「スパム(SPAM)むすび」に関しては全く進化していなかったようです。不思議ですね。食にこだわりの強いKyokoさんが自分の為に編み出した「贅沢スパム(SPAM)むすび」是非お試しあれ
2013年11月13日
閲覧総数 2131
-
36

ブルージュ(Brugge) 7 (ブルグ広場 3 聖血礼拝堂と聖遺物の話)
12世紀頃は中世世界の転換期にあたるようだ。建築はロマネスク様式からゴシック様式に変わる。威厳あるゴシックの建物は人々を驚かせたに違いない。天に向かって高くそびえる教会の尖塔、きらびやかに光輝くステンドグラスは、驚きと共に、そこにいる者を神の栄光に近づけさせる効果があったろう。同様にゴシックの建築で建てられた立派な鐘楼や市庁舎の威厳に満ちた存在感は、来訪者に市民の自治の象徴として知らしめ、大聖堂同様に市民の誇りであったに違いない。中世ブルージュ(Brugge)にはこの両者があった。それはまさしく市民の力で築いた成功した中世地方都市の輝く栄光。しかしそれだけではない、ブルージュにはもっと凄い物が存在した。それは神そのものの化身・・とも言えるイエス・キリストにまつわる聖遺物。今回はその聖遺物を持つ教会と聖遺物にまつわる話を紹介 ブルージュ(Brugge) 7 (ブルグ広場 3 聖血礼拝堂と聖遺物の話)聖血礼拝堂(Heiling BloedBasiliek)アルザスのティエリー(Thierry of Alsace)(Dietrich)聖血の祭り聖遺物(聖遺物収集、聖遺物産業、聖遺物の略奪)聖血礼拝堂(Heiling BloedBasiliek)Heiling BloedBasiliek(オランダ語) Basilica of the Holy Blood(英語)ブルグ(Burg)広場の片隅にバシリカ(Basilica)がある。(円で囲った部分)バシリカ(Basilica)は(構造だけでなく)一般の教会堂より位の高い教会だそうだ。もともとはフランドル伯(Comte de Flandre)家の個人礼拝堂として城に隣接して建てられた(1134年~1149年)とされている事から後にバシリカに格上げされた礼拝堂のようだ。※ 2013年1月「真実の口 (Bocca della Verita)」の回、「バシリカ(basilica)様式の教会」を紹介しています。リンク 真実の口 (Bocca della Verita)礼拝堂は2層式になっていて、当初は西フランドルのロマネスク様式で建築。15世紀末にゴシック様式で改築。19世紀にはゴシックリバイバル様式で改修されているので内部はいろんな様式がミックスされている。(1階から2階に上がるエスカルゴのような螺旋階段にロマネスクの名残が見られる。)修復中のせいもあるが、一見地味なこの礼拝堂に人が参拝するのはここが聖遺物の中でもスペシャルな聖遺物を祀っているバシリカだからである。宝(聖遺物)を持ち帰ったのは戸口に飾られている黄金の像左の黄金の像・・Thierry of Alsace(Dietrich)・・アルザスのティエリー(後のフランドル伯)戸口の右の黄金の像・・Philip of Alsace・・・アルザスのフィリップ(ティエリーの息子で後のフランドル伯)アルザスのティエリー(Thierry of Alsace)(Dietrich)アルザスのティエリーこと、ディートリック(Thierry of Alsace)(Dietrich)(1099年~1168年)アルザスの領主ティエリーは、もともとフランドル祖家ロベール1世(1071年~1093年)の孫だそうだ。1128年~1168年彼はフランドル伯(Comte de Flandre)の爵位を継承。(フランドル伯家はティエリーから3代アルザス家が継ぐ。)アルザスのティエリーは第2次十字軍遠征(1147年~1148年)に参加し、聖地よりイエス・キリストの血の遺物を持ち帰りこのバシリカに奉納した・・とされている。・・・と言うのが一般に人気の伝承である。聖遺物にまつわる新説最近の検証では、第4次十字軍(1202年~1204年)の時、十字軍が陥落させたコンスタンティノープルから持ち込まれた(略奪?)のではないか? と言う説があるようだ。理由の一つはコンスタンティノープル陥落後にラテン帝国を建国したのがフランドル伯ボードゥアン9世(1172年~ 1205年)だった事。他には、聖血の祭りの開始時期など史実をさぐっても13世紀以前には該当しないらしいのだ・・。ここに疑惑がおきた。 (・_・?)はて?ではなぜ「第4次十字軍の時にフランドル伯ボードゥアン9世が・・」と、しなかったのか?あくまで憶測であるが、考えられるのは、出時期含めて、聖遺物そのものが略奪、もしくは怪しいルートから街にもたらされた物であったからなのでは? 中世、聖遺物産業と言うのが存在したのだ。(その話は後の「聖遺物」のコーナーで紹介します。)聖血の祭り聖なる血の行進(Procession of the Holy Blood)1303年に制定? されたと言う中世以来のお祭りは、毎年5月、復活祭から40日目のキリスト昇天祭(毎年変動。今年は5月29日らしい)に行われる時代祭りのパレードである。メインはブルージュの宝であるキリストの血とされる聖遺物。聖櫃(せいひつ)に収められた聖遺物は礼拝堂の外に出され、市中を行進する。それはあたかもブルージュに聖血がもたらされた時のように・・。2階にある礼拝堂この礼拝堂は歴代のフランドル伯だけでなく、金羊毛騎士団の祈りの場でもあったそうだ。金羊毛騎士団はブルゴーニュ公フィリップがこのブルージュで結婚式をあげた時に造った騎士の爵位である。(これについては長くなるので別の機会に・・。)リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)バシリカ自体の見学は10:00~12:00 昼休みはさみ14:00~17:00まで。写真右の球形の鍋のような物は、実は「講壇」である。(非常にめずらしい形です。)この礼拝堂の右にバシリカ(列柱)があり、その奧の部屋で毎日決められた時間にちょこっと「聖血の遺物」が開帳されます。(バシリカへの入場は無料だった気がしますが聖遺物を見せて頂いた時は別途、多少のお布施をお願いします。)撮影は禁止されています。当然聖遺物もこっそり撮る事はできないのですが、特別許可の写真でしょうか? ウィキペディア・コモンズで公開されていたので借りてきました。黄金の装飾のついたガラスの筒に入っているのはキリストが流したとされる血のついた羊の革らしい。伝承ではゴルゴダで十字の貼り付けより降ろされたイエス・キリストの体をアリマタヤのヨセフが拭き取って保存していた品だとされている。まだ割と生々しく赤いのだ。血は固まって黒ずむ(酸化する)はずなので、あきらかに怪しいのは言うまでもない。何しろ2000年前の血液ですよ 聖遺物(聖遺物収集、聖遺物産業、聖遺物の略奪)聖遺物と言うのは、宗教上の崇拝する主にまつわる遺物の事だ。少し前にケルン大聖堂に祀られている「マギの聖骨」について触れたばかりであるが、今回もキリスト教関連の聖遺物である。しかもキリスト自身の血液とされているので、聖遺物の中でも最上位のランクだ。キリスト教の聖遺物と言えば、イエス・キリストを筆頭に聖母マリア、12使徒、キリストに関係した人々、他にバチカンで公認された聖人列伝に叙せられた諸々の聖人に関する遺物は全て聖遺物である。内容もいろいろである。着衣の破片や、遺骨もあるし、分割されすぎて指1本・・と言う場合も・・。イエス・キリストが磔刑にされた十字架の木片は家が建つほどあるらしいし、打ち付けた釘は数十本になるとか・・。聖遺物収集そもそも聖遺物収拾は古代ローマ帝国でキリスト教が公認された時から始まった。その筆頭が前に聖墳墓教会の所で紹介したコンスタンティヌス帝の母ヘレナである。今風に言えばヘレナは聖遺物収集のマニアであった。何しろその為にエルサレムまで詣でたのだから・・。実際彼女の探してきた聖遺物はどれもレベルが高い。(信憑性は別として・・。)そう言う意味で言えば、ヘレナ同様、十字軍の参加者の中には聖遺物収拾を目的に出かけた者も多かったはずだ。聖遺物には霊力が宿っているとされた。そして聖遺物を所有する者は聖遺物に選ばれた人となり、自身にも神の栄光が降り霊験を得られると考えられた。信仰心だけではない、貴重な聖遺物を所有するという事は名誉であり、社会的地位を確固たる者にした。欧州の王侯貴族や、聖職者などは財力を駆使して聖遺物を手に入れようとした事実は計り知れる話だ。聖遺物産業需用があれば品が欲しい。聖遺物は高値で取引できる商品になった。聖遺物の偽物が大量に出回ったのがまさに十字軍遠征中の欧州である。しかも製造の本拠はコンスタンティノープルだったと言う。確かにコンスタンティノープルで手に入れた品なら信憑性も高くなろう・・。十字軍の参加者は観光土産のようにそれらを手にして国に帰ったわけである。聖遺物の略奪特に酷かったのは第4次十字軍遠征の時だ。聖地エルサレムでなく、進路を東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルに向け同じキリスト教徒の同胞を征服し、軍隊は略奪の限りを尽くした。聖遺物は本物も、偽物も略奪され、欧州に売られて行ったのだ。聖血礼拝堂の「聖血」は本当はどこから来たのか?第二次十字軍に参加したアルザスのティエリー(フランドル伯)が持ち帰った・・は、その信憑性を高める為のフィクションかもしれない。本物か? 偽物か? それでも「聖血」が街に人を呼んでいる。観光客は沢山のお金を落として行くではないか。「聖血」は真に霊験あらたかな聖遺物になってしまったのかもしれない。ブルグ広場終わりますが、ブルージュはつづくリンク ブルージュ(Brugge) 8 (Rozenhoedkaai)※ 聖遺物についてはあちこちで書いています。リンク デルフト(Delft) 4 (新教会 ・聖遺物の話)リンク ミュンヘン(München) 10 (レジデンツ博物館 3 聖遺物箱)リンク 聖槍(Heilige Lanze)(Holy Lance)
2014年04月09日
閲覧総数 2931
-
37

ボツワナの動物 3 ( ケープハゲワシ)
ある意味Break Timeです。ゾウの写真をPIC UPしていたら、あまりに紹介したい写真の量が多すぎて絞れません。ゾウは生態も紹介したいので、何部作かになると思います。で、編集中の為、今回は哺乳類ではなく鳥で行きたいと思います。ジャングルに欠かせない鳥と言えば・・・ハゲタカですハゲタカは、サバンナの掃除屋とも呼ばれている嫌われ者?・・・・な鳥です。でも、考えようによっては環境にやさしい鳥なのかも・・。所謂「エコ・鳥」か?ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物ケープ・ハゲワシ(Cape griffon)シブリー・アールキスト鳥類分類鳥綱 Aves コウノトリ目 Ciconiiformes コウノトリ亜目 Ciconii ハヤブサ下目 Falconides タカ小目 Accipitrida タカ科 Accipitridae タカ亜科 Accipitrinae シロエリハゲワシ属 Cape Griffon Vulture Gyps ケープハゲワシ種 Cape Griffon G. coprotheres分布 ジンバブエ南部、スワジランド、ナミビアの一部、ボツワナ南東部、南アフリカ共和国、モザンビーク南西部のサバンナやステップなどに生息。ケープハゲワシは、他のハゲワシより、案外カワイイ顔です。全長100~120cm。翼開張260cm。体重7~11kg。食性食性が腐肉食と言う事で、大型動物の死骸を食します。彼らはは生態的上位の者が摂食中の死体を狙い、隙を見て横取りしたり、残り物を得たりする習性があります。スカベンジャー・腐肉食動物(scavenger)動物の死体(動物遺体)を主に食する性質を持つ動物を腐肉食動物or屍肉食動物と言うそうです。環境中にある死体を探し当てて食物とする彼らは、ある意味生態系の食物連鎖に重要な役割をしているとてらえる事も出来ます。屍肉食いの代表のように考えられ代名詞化までしているハイエナは、実は自分で狩りをする事も多く、むしろ獲物を奪われる側なのだそうです。その獲物を横取りしたりするのがジャッカルやハゲワシのようです。肉は確かに腐りかけが(熟成した方が)美味しいのは確かです。案外グルメなのかな?高い木の上から360°獲物を探しているようです。不思議と枯れ木に止まっているような・・・よく見えるからか?倒れたら、死んだかと思われて、食われそうで怖い気がしますが・・・・。1回に1個の卵を産み、雌雄交代で抱卵。営巣場所が限られるため同じ営巣場所が数世代に渡って用いられることもあり、数百ペアからなる大規模な集団繁殖地(コロニー)を形成する事もあるのだそうです。 肉食動物の減少や家畜の死骸処分(焼却や埋葬)により獲物が減少。また、、薬用の捕獲、交通事故、送電線による感電死、人間の侵入による繁殖地の減少で生息数は減少しているようです。
2009年11月16日
閲覧総数 589
-
38

ストックホルム市庁舎 1
ノーベル賞の晩餐会が開かれるスウェーデン、ストックホルムの市庁舎は、ナショナル・ロマンティシズム(ナショナル・ロマン様式)の傑作と言われている。スウェーデン建築家、ラグナル・エストベリの設計で、1909-1923年にかけて建設された。建物はロマネスクやゴシック様式の要素が入りつつ、ヴェネチアのドゥカーレ宮殿(元首宮)を意識しているようなルネッサンス様式の要素が入りつつ、室内はビザンティン様式のきらびやかなモザイクがありつつ、北欧独特の伝統技法も盛り込まれていて、民族主義もかいま見られる。(民族的ロマン主義とか、国民的ロマン主義)ヨーロッパ各地の名建築からインスピレーションを受けた折衷的なネオ・デザイン? である。でもそれが、ある意味「北欧的だな。」と私は思った。下はストツクホルム市庁舎の外装で、メーラレン湖側の庭からの撮影(全景は二つ前のプログにあり。)下は中庭の階段モダンなルネッサンス様式といった感じである。下は内部ブルーホール。ノーベル賞のディナーの部屋?中世イタリアの広場を思わせる広間であるが、もはや何時代かわからない様式のパラレルワールド。下は、ストックホルム市議会の議事場。近く固まっていて、マイクなしでも声が届く議事場ですね。厳粛な作りではありますが・・あの天外は何 ? なぜ ?下は会議室天井。この天井が、ヴァイキング・ルネッサンス様式とか言う、この建物のナショナルの部分(北欧的な部分)の一つです。ここは必見です。ロマンティシズム(Romanticism)は、ヨーロッパの18.9世紀に流行した芸術運動の根幹にある思想? である。文学、美術や音楽、建築など広範囲の芸術領域に波及した。(簡単に言えば、古代ギリシャ・ローマがベースにあるが、幻想的な夢やおとぎ話等のロマンチックなものを好む考え方。)それに対して、ナショナル・ロマンティシズム(National Romanticism)は、ヨーロッパ主体のロマンティシズムではなく、民族や文化、国家をも含むアイデンティティを主張したロマン主義である。(簡単に言うとヨーロッパ芸術の根幹は借りているが、これはウチの国のオリジナルだ! 的主張。)だから、ヨーロッパ文化の中心をなす国よりも、北欧・東欧・南欧などの周辺地域の国にに多いらしい。唯我独尊的なヨーロッパ人(イギリス・フランス・イタリア等)に対抗して自国のアイデンティティを主張するあたりは、日本人も真似をするべきだと思うが・・。次に晩餐の黄金の間を紹介。
2009年05月15日
閲覧総数 485
-
39

オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)
ミラノ大聖堂はまだ聖堂内部の紹介が残っているのですが、ちょっと飽きてきたので気分転換に久しぶりの鉄道ネタです。昨年はロンドンからユーロスター(Eurostar)でベルギー、インターシティー(InterCity)でオランダへと列車移動しましたが、今年はオーストリアの国際特急列車レールジェット(railjet)でザルツブルク、ミュンヘンへと移動。昨年の列車は汚くて凄く嫌な気分でしたがレールジェット(railjet)は素晴らしく綺麗でサービスが良く快適な列車でした全2回の予定。オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)固定編成を採用プッシュプル方式客車のグレードと車イス専用車両オーストリアは、欧州のほぼ中心。その地理的な要因でいろいろな国の国際列車が走っていますが2008年12月から運行が始まったオーストリア連邦鉄道(QBB)のレールジェット(railjet)は従来の国際列車より快適で早い。最高速度275 km/h。(実車時の最高速は245km/h。速度表示が出ます。)車内サービスも飛行機なみにグレードアップした特急列車です。ウイーン西駅(Wien West bahnhof)・・・始発駅何よりうれしいのは窓ガラスが綺麗で窓越しに風景が撮影できた事です。昨年のユーロスター(Eurostar)はロンドン発だったにもかかわらずこ汚くてキズだらけでカメラ向ける気にもなれない窓ガラスでした。(外側が汚いからどうしようもない。)下の車両は機関車ではなく、運転席付き制御客車です。下の車両は機関車機関車に客室はなく運転席と動力のみ。制御車には制御用の運転席と客車がついているので窓があるかないかで違いがわかる。固定編成を採用車両前後は新幹線のように客車と機関車で統一したデザインが採用されています。これは固定編成の概念を導入したからです。(これは欧州では画期的考え)日本では一体型は当たり前の事ですが動力集中方式を採用している欧州では従来進行方向が変わると列車の動力源である機関車の部分を前後付け替える必要がありました。だからユーロスター(Eurostar)やインターシティー(InterCity)にしても、機関車はまちまちで、まして客車とは何の統一性も無かったのです。何しろかつては国により電荷も違ったので国境で機関車をチェンジする必要もあった・・と言うのも動力集中方式が採用されてきた理由の1つです。因みに、日本の新幹線などは動力分散方式を採っているので前後どちららにも動く(ペンデルツーク方式)が早くから採用されています。要するに動力を前後に持っている・・言う事です。(日本の場合は動力車両にも客車が付いている)日本は曲線や勾配が多い事、地盤が弱い・・など、動力集中方式が難しかったようです。プッシュプル方式機関車を付け替える事なく、列車を前後に動かす。普通なら日本と同じ動力分散方式(機関車-客車-機関車)になりそうなものですが、レールジェット(railjet)では動力集中方式のままで前後に動く事を可能にしています。それがプッシュプル方式で行きは客車を牽引、折り返しのバック走行の時は機関車が客車を押す形(プッシュプル方式)で走行する・・と言うもの。つまりレールジェット(railjet)は(機関車-客車-運転席付き制御客車)と言う結合になっているのです。下のような連結は途中切り離して別方向に進む事が考えられる。(ザルツブルグ駅)下は、これから発車する列車の編成を表示したデジタル画像の一部です。(ウイーン西駅)解りやすくする為に機関車をピンクに制御車を赤く囲いました。黄色・・1等車、ビジネス、 緑色・・2等車、赤色・・ダイニング・カーおよび車イス専用車両これによりレールジェット(railjet)の気付かなかったサービスもわかりました。First Class (1等客室 )(横3席)椅子は半分で向きが異なり日本のように変える事はできない。しかし、この列車ではインターネットが自由に使える。各椅子にはコンセントが付いていて、パソコンの電源も確保できるのだ。Economy Class (2等客室)(横4席)新幹線の普通席クラスかな? 悪く無いです。客車のグレードと車イス専用車両レールジェット(railjet)ではBusiness(ビジネス)、First Class (1等客室 )、Economy Class (2等客室)と3つのグレードがあります。しかし、列車の編成によれば必ずビジネスの車両がついている訳ではないようです。ビジネスは残念ながら見落として写真を撮ってきていないのですが、1等客車の中で一部コンパートメントになっているカ所がビジネス扱いのようで数は少ないです。また、編成表によれば、子供のプレイ車両や、ベビー用の車両をそなえている場合もあるようですし、たいていの列車にはDining Car(食堂車)が付いていて、その客車に付随して車イス専用のFirst Class (1等客室 )も付いています。※ QBBの場合、自転車積み込み専用車両があったりするのだが、レールジェット(railjet)の編成では見あたらなかった。車イス専用車両車イス専用車両は席数が少ないが、隣がDining Car(食堂車)と反対隣が広い車イス用のトイレとなっている。但し、欧州の列車の問題点は乗車時にバリアフリーではなく段差がある事。一応First Class 扱いで、4人がけテーブル1組と2人がけテーブル3組が設置されている。車イス2台は楽勝。大型の荷物を置く場所はない。たまたま予約していた場所がその客室だったのだが通常人は来ないようだ。車イスの人がそのまま入れるトイレ。トイレはEconomy Class でもそこそこ広い。(日本のは狭すぎる)尚、このトイレの後ろに列車内インフォメーションがあった。車掌さんが通常待機している場所のようだ。チケット確認に来た車掌さんガラス扉の奥がDining Car(食堂車)チケットは今やほとんどインターネットのプリントアウトである。だから必ず確認されるのは、チケット購入時のクレジットカードの提示である。人のチケットでかってに乗り込む人がいるからなのだろう。次回列車内の豪華メニューを紹介リンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)ザルツブルグの所でQBBの発券機を紹介しています。ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)
2014年08月22日
閲覧総数 2818
-
40

デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)
ウイーンと言えば可愛らしい洋菓子で知られています。今回は200年以上の歴史を持つウィーンの王宮御用達の老舗デーメル(DEMEL) を紹介します。とはいえオーストリアは共和制となり、現在王室はありません。最後のオーストリア=ハンガリー帝国の皇帝は、ハプスブルグ・ロートリンゲン家のカール1世(Karl I)(1887年~1922年)の代で終わっています。デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)デーメル(DEMEL) ウイーン王宮御用達菓子店ハプスブルク家の紋章(双頭の鷲)がブランドマークのデーメルはウィーンの歴史、ハプスブルク家の歴史と共に歩んだ歴史を持つ洋菓子店です1786年「デーメル」の歴史は、スタートします。当時、貴重だった砂糖を使ったお菓子を皇帝やその家族、王侯貴族らのために作る「ツッカーベッカー」と呼ばれる菓子職人がいたのだそうです。ハプスブルク家の女帝(マリア・テレジア)の長子ヨーゼフ2世の統治時代に、ツッカーベッカーの一人、ルートヴィッヒ・デーネが、王宮劇場の舞台側入り口の前に、ロココ様式の店を開いたのが、現在の「デーメル」の原型となったそうです。そして初代ルードヴィッヒが亡くなった1799年、店はウィーン王宮御用達菓子司と看板を得て、その後、王宮劇場に寄り添うように200年以上の歴史ある老舗です。王宮劇場と店とは地下道でつながれ、劇場での催し物があるたびに地下道を使ってお菓子を運んでいたと言われています。1888年、店舗も王宮劇場の移転に伴い、現在の場所である王宮そばのコールマルクト14番地にデーメルの本店はあります。今回は最近ザルツブルク旧市街のモーツアルト広場近くに新装開店したお店から紹介。店内の写真です。表はありません。店内はモダンなつくり。1階がケーキ売り場と喫煙可能な喫茶店2階が禁煙喫茶店とトイレ。ショーケースの中のケーキ 一部デイー・ルームでケーキや凝ったドリンクもいただけます。カフェラテホットなのにガラスの容器なのですね。持ち手は後ろ側に。枝付きのグラスの濃いコーヒーに多量の生クリームでフタをしたもの。。ウインナ・コーヒーは本場ウイーンでは、アインシュペナー(一人乗りの馬車?)とか言うそうです。馬車に乗った御者が揺れにこぼさずにコーヒーを飲むために考えられたとか・・。ガイドさんが言ってました。海外店舗1号店が原宿店だそうで、本家に支店がほとんどないのに日本に15店舗もあるのに驚きです。日本のオンラインではザッハトルテを通販しているようです。ザッハトルテは次回につづく。リンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)関連先リンク カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)リンク 元祖ザッハ・トルテのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)
2009年11月27日
閲覧総数 184
-
41

世界で最も醜い植物 第4位 1
2018年05月31日「新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)」を公開しました。内容はかなりくわしいものになっての改訂です。下をクリックすると直接飛びますスマホも同じです。リンク 新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)1859年オーストリアの探検家フリードリッヒ・ヴェルヴィッチュによってアンゴラの砂漠で発見された多肉植物は「世界で最も醜い植物 第4位」に選ばれた植物なのだそうです。(1~3位は何?)一生知る事も、ましてお目にかかる事も無い希少な植物を2回に分けて紹介します。世界で最も醜い植物 第4位 1.ウェルウィッチア(Welwitschia Mirabilis)和名 サバクオモト(砂漠万年青) 奇想天外の園芸上の名を持つ。一属一種の裸子植物で、アンゴラ、ナミブ砂漠に群生する多肉植物。界・・・・・・・・・・・植物界 門・・・・・・・・・・裸子植物 綱・・・・・・・・・グネツム網 目・・・・・・・・グネツム目 科・・・・・・・ウェルウィッチア科 属・・・・・・ウェルウィッチア属 種・・・・・ウェルウィッチアナミブ砂漠とウェルウィッチア一見ゴミが落ちているように見える・・・。何だ? これは????砂漠の暑さの中地面にへばりついて生えている。葉先から枯れて分解しているようです。葉は裂けやすく、一見何枚もあるように見える(裂けてる)が、短い茎から、生涯2枚だけの葉を伸ばし続けるそうです。(この2枚の葉は、最大4mくらいになるらしい・・。)葉の基部に分裂組織があり(基部で成長)、どんどん伸び続けるようですが、永続的に成長する葉は陸上植物界の中でもまれなのだそうです。そもそも、褐藻類のコンブ類の成長のように葉の基部で成長を続けるタイプは、陸上植物界では他に例がないのだそうです。茎の先端から細かい枝を出し、花序をつける。雌雄異株。ゴキブリでも張り付いているのかと思った・・。雌花は他の裸子植物の雌花の多くにも見られる松かさ状。だからこの株は雌のようです。葉の気孔から大気中の湿気を吸収し、長さ3m~10mにも達する根によって地下水を吸い上げているそうです。こんなに大きくなります。どうも大きいのは雄株らしいです。寿命は数百年から2000年。次回巨大なウェルウィッチアを紹介。
2009年08月22日
閲覧総数 679
-
42
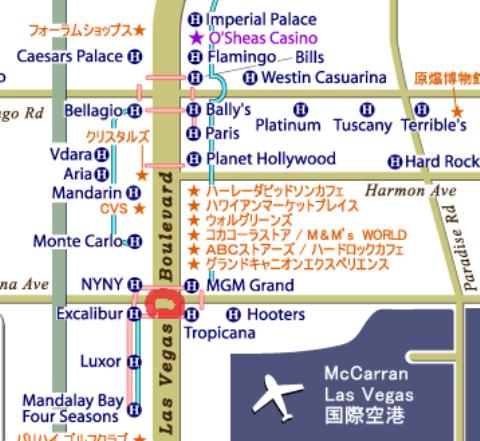
ラスベガス・ストリップ南のホテル 2 (MGMグランド)
昨日はインフルエンザの注射をしてきました注射は毎年先生に出張して打ってもらっていたのですが、いつしかそれは夕食後? のおまけになり・・・昨日は前菜? 毎年、レストランの駐車場でコソコソと打ってもらうのが恒例となりました。もしその姿を人に見られていたら・・かなり怪しい人達ですさて、ラスベガスも今回で最後にする予定です。ネバダ州(Nevada)ラスベガス(Las Vegas)ラスベガス・ストリップ南のホテル Part 2ニューフォーコーナーのMGMミラージュ系ホテルMGMグランド(MGM Grand)ニューヨーク・ニューヨーク(New York New York)一応ラスベガスの地図です。今回の場所の確認赤い印の交差点の所です。水色の線がモノレールの線です。前回紹介したマンダレイ・ベイからエクスカリバーの他にMGMグランドから北上する別のモノレールもあります。(そちらは有料です。)有料のモノレールMGMグランドからストリップに沿うようにサハラホテルまでを15分で結ぶラスベガスモノレール公社が運営する公共のモノレール。路線距離 6.3kmもとはMGMグランドホテルとバリーズホテル間を結んだ無料モノレールだったようです。南の空港と北のダウンタウンへの延伸がのぞまれているようですが、いつになるか・・。MGMの乗り場が(広大なカジノの中を抜けるので)解りにくく、ストリップ沿いといってもどこもホテルの裏手に着く(離れている)ので利便性は悪いのです。ラスベガスのバス(ACE GOLD)バスは何社か運行しているようで、バス停はストリップ沿いの最寄りのホテル近くにあります。ホテル移動ならモノレールより絶対便利。ラスベガスのタクシー日本のように歩いていて捕まえるのは難しいかも・・・。どこかホテルに行けば別ですが・・。さて、前回紹介したエクスカリバーのある交差点は歩道橋が四隅を結んでいます。そのせいか? 地図では「ニューフォーコーナー」と書かれています。因みにハラーズ系のベラッジオ、シーザースパレス、フラミンゴ、バリーズのある交差点は「フォーコーナー」です。エクスカリバーの斜め前はMGMミラージュ系ホテルでも、ラスベガスにおいても客室数最大(5044室)のMGMグランドがあります。MGMグランド・ラスベガス(MGM Grand Las Vegas)ホテル棟は30階。そのカジノ敷地面積は15793 m²。野球場が4つ入るほどの面積で、それは客室数だけでなく、カジノとしても世界で3番目の面積なのだそうです。最初のMGMは現在のバリーズの場所にあったようです。金のライオンの像はこのホテルの象徴重量は約45t、高さ13m、台座部分を入れる総高は約20mとか・・。この像もまた全米で最も大きい銅像なのだそうです。カジノの中にはガラス張りのライオンの檻ががあり、時間で餌付けをするが見学できます。暗すぎて写真に写りませんでした。ニューフォーコーナー、エクスカリバーの北隣はニューヨーク・ニューヨーク手前はエクスカリバーニューヨーク・ニューヨーク(New York New York)1930年から1940年のマンハッタンの街がテーマなのだそうです。残念ながら中には入っていませんが、カジノ・フロアはセントラル・パークやブルックリンなどの地名があり、フード・コートはダウン・タウンがテーマになっているそうです。ジェット・コースター・・・マンハッタン・エクスプレス時速100km以上でビルの谷間を走行。近くを歩いていたら悲鳴が聞こえます。新ホテル群このニューヨーク・ニューヨーク北隣のモンテカルロとベラッジオの間は長らく空き地でしたが、最近複数のホテルが完成。何やらガラス張りでオフィスっぽい建物です。写真だけ紹介です。グッチやプラダ、ルイ・ヴィトンなどの高級ブランドの店舗も密集しているようです。地図によれば3件のホテルが建っているようです。テーマのあったラスベガスのホテルとはちょっと異質な感じのするホテル群ですね。私としては昔懐かしいラスベガスの方が親しみ安い気がする・・と思うのですが・・。古いのかな?おまけ写真・・・ハードロック・カフェラスベガスおわり
2010年11月16日
閲覧総数 1142
-
43

世界で最も醜い植物 第4位 2 (ジャイアント・ウェルウィッチア)
2018年05月31日「新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)」を公開しました。内容はかなりくわしいものになっての改訂です。下をクリックすると直接飛びますスマホも同じです。リンク 新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)昨日に引き続きウェルウィッチアPart 2です。生態と長老を紹介します。世界で最も醜い植物 第4位 2 (ジャイアント・ウェルウィッチア)ウェルウィッチア(Welwitschia Mirabilis)1科1属1種の裸子植物である超珍稀植物。日本名が奇想天外。アンゴラ、ナミブ砂漠に群生する多肉植物とは書かれていますが、実は本当に多肉植物の定義に入るか? と言うと実はあやふやなのだそうです。多肉植物関係の人が係わったので多肉植物園芸の分野に落着く事になった? (実は行き場がない植物分類? )らしい。前回紹介した松かさのようなものからはがれたタネ。タネがひらひら飛んで、着床して芽が出たウェルウィッチアです。雄株のような気がします。まだ、葉は這いつくばっていませんが2枚葉が良くわかります。砂漠以外に着床したブッシュのウェルウィッチアは、地面を這わずに普通に天に伸びるので、環境適応は遺伝性ではないのかも・・。ブッシュの中で普通に生えているウェルウィッチアは、一見本当に万年青(おもと)です。ウェルウィッチアに非ずと言いたい別物ですね。(写真の容量の都合で載せません。)水分補給それにしても、砂漠で運良く着床できたウェルウィッチアも根が水源にたどり着く前に枯れてしまうので、なかなか生きていけないようです。前回も紹介しましたが、葉の気孔から大気中の湿気を吸収するか、長さ3m~10mにも達する根によって地下水を吸い上げていると言われています。ナミブ砂漠は年間の雨量が20ミリ程度で、大変暑く、砂漠の表面と空気は40~70℃に達する事もあり地表の水分も蒸発が激しく、植物にはとても過酷なのだそうです。が、海岸近くには年間100日ほどの霧の発生があり、年間50ミリ降雨量に匹敵する水分を得られるのだそうです。また、ウェルウィッチアの自生はナミブ砂漠の北に集中しているそうで、おそらく霧の発生にも関係しているのでしょう。絶滅しそうでガンバッテいるウェルウィッチア、自然の中に生きる物は強くたくましいです。下は砂漠の写真ですが、良く見るとウェルウィッチアが点在しています。ちょっと見づらいかもしれませんが、ウェルウィッチアは砂漠に一定の幅で一直線に生えています。Why?ウェルウィッチアは砂漠の下に走る水脈の上にきっちり着床して水を得ているのです。ウェルウィッチアの生ている所に「水脈あり」なのです。人間はウェルウィッチアを見る為に砂漠を走ります。おのずと道も水源に沿って走っていたわけです。実に面白い・・。ジャイアント・ウェルウィッチア(Giant Welwitschia)寿命は数百年から2000年と言われ、希少植物であることから、ナミビアでは厳重に管理されています。写真Bも実は石で囲われています。下、柵で囲われて保護されているのは樹齢1500年以上の雄の木だそうです。このあたりの最高齢の長老です。グランド・マザー・プラント? グランド・ファーザー・プラントですね。柵の横にやぐらがあり、上から見学するようです。アバウトですが、直径2.5mくらいで高さは1.2mくらい? の大きさがあるそうです。思った以上に大きいのです。でも、葉っぱは2枚なのだそうです。信じられないけど・・・。未知の国には神秘がいっぱい・・。
2009年08月23日
閲覧総数 14421
-
44

ボツワナの動物 2 (アフリカン・バッファロー)
以前「ハンサムな動物とブサイクな動物」ですでにバッファローは紹介済みですが、ビッグ・ファイブ(Big 5)なのでまたまたきちんと紹介。今回は群れの写真もあります。ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物アフリカン・バッファロー(African Water Buffalo)チョベ川の湿地で草を食べているアフリカン・バッファローの群。アフリカスカン・バッファロー(African Water Buffalo)綱 哺乳綱 Mammalia目 ウシ目(偶蹄目)Artiodactyla亜目 ウシ亜目 Ruminantia科 ウシ科 Bovidae亜科 ウシ亜科 Bovinae属 アフリカスイギュウ属 Syncerus種 アフリカスイギュウ Syncerus caffer本種のみでアフリカスイギュウ属を形成。アジアスイギュウ、インドスイギュウは属からスイギュウ属として分かれる。チョベ川で草を食べている。食性は植物食で、草、木の葉など。生態水場から数10km以内に限って生息。昼間は水場で水を飲んだり泥浴びを行う。泥浴びは熱さや乾燥や寄生虫、吸血性の昆虫類等から体を保護する為と考えられているそうです。彼らの体の上には鳥がたいてい乗っている? くっついている。鳥と仲良しに見える行為は、それも寄生虫を食べてもらうという相利共生(互いに利益を得ることができる共生)関係のようです。体長240~340cm。肩高140~180cm。体重オス425~870kg。メス400~600kg。全身は黒や褐色の粗い毛に覆われ、群れでも異なるようですが、未成獣は褐色が強いそうです。壮年期になると鼻筋とその両側に白髪が生えてくると言う事で、上のバッファローは年寄りなのかも・・。寿命は25年程らしいです。目が・・・怖いヤクザの人みたいににらんでいます。親分ぽい顔してますね。性格は気が強く、やられたら、執拗にやり返す性格らしく、ハンターの死傷率が一番高いのが、バッファローなのだそうです。角オス、メス共に頭頂部を覆う湾曲した角を有しているがそれ以外はやはり、牛である。角は、オスが長さ、厚み、幅ともにメスをはるかに上回って大きいとされる。幼獣の角は左右に離れて生え、成長と共に根元は中央に寄ってくるので、年を取ると根元が密着。めずらしく、優しそうな顔のバッファローです。鳥と戯れていました。100頭以上の群れを形成して生活。多いときには1000~2000頭にもなる大規模な群れを形成すると言います。下の写真には写りきらないグループが幾つか密集。100は越える。茶褐色の群れは、若いバッファローの群れのようですね。本当に怖い顔してますが、牛と思えば動作は牛です。天敵はほぼライオンだそうです。牛肉だから美味しいのかも・・・。サァファリー・カーとガイドさん。
2009年11月15日
閲覧総数 5108
-
45

カッパドキア 9 ( 奇岩のできかた)
トルコ共和国(Republic of Turkey)中部アナトリア地方カッパドキアギョレメ地方(Goreme)パシャバー地区(Pasabag)修道士の谷奇岩のできかた図の左が2000万年前に起きたカッパドキアの3つの山、(エルジイェス、ハサン、ギュルル)火山の噴火によって火山灰(凝灰岩)が降り積もり形成されたカッパドキアの台地図の右が長い年月かけて水に溶解しやすい石灰岩などの岩石のみ溶けて、台地がけずれるように浸食される図。特異なカルスト地形の帽子をのせたような奇岩はこうして生まれたようです。写真左右、崖からもうすぐ生み出されてくる「きのこ岩」左は綺麗な三角錐の帽子がすでに乗っています。写真中央の岩からも、もう少しで誕生。左下のような丸まった帽子を持つキノコ岩もありますし、写真右の岩は、また造りが違いますね。写真右の岩は浸食されたしシメジ茸型の上に溶岩でも塗布されたような感じですね。粘質の火山灰が厚みをもって降り積もった跡かも知れません。修道士の谷の山側は、ここも浸食の度合いで微妙な谷がいくつも出来ています。上の写真の右側のパノラマ。次回ゼルベのラクダ岩につづく
2009年12月04日
閲覧総数 2039
-
46

お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)
お金シリーズのBack numberをラストに追加しました。Break Time (一休み)今回はユーロ(Euro)の紹介です。お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)ユーロ(Euro) €ユーロは欧州の経済通貨同盟国で現在使用されている通貨です。但し、全てのヨーロッパの国が経済通貨同盟に加入しているわけではないので、加盟していない国は相変わらず、その国の通貨に両替する必要があります。2002年1月1日に現金の流通が11カ国で開始されてから、現在経済統合により導入しているのは16カ国に過ぎません。しかし、後発のユーロですが、今やドルに次いで、基軸通貨(国際間の取引に使われる通貨)になりつつあるお金です。オーストリア、ベルギー、ドイツ、フィンランド、 フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペインギリシャ、キプロス、マルタ、スロバキア、スロベニア※ その他、通貨同盟などによって、相手国と同じくユーロを法定通貨とした小国などもあります。(アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン)ユーロの導入について導入していない国の中にはイギリスなどの大国も入っています。導入しているかしていないか・・については、その国の経済理由があるからなのです。ユーロの導入は、「その国の財務状況、物価の安定性、為替相場の変動幅、長期金利などについて、決められたマースリヒト基準をクリアしていなければならない。」と言う条件があります。つまり、加入したくても入れない国が存在するわけです。また、クリアできても、国民投票で否決される場合もあるのです。今回問題になったギリシャについては、そもそもそれら基準をクリアしていないのに、インチキして達成している振りをして加入に漕ぎ付けた経緯が指摘されています。ユーロ紙幣さて、今回、ユーロを紹介するに当たって、手持ちのお金では高額紙幣の持ち合わせがありませんでしたもっとも200ユーロ札や500ユーロ札に関しては、高額故にほとんど市場に流通していません。しかし、今回奥の手を使って紹介します。ユーロ表側 5、10、20、50、100、200、500ユーロ札の7種類。ユーロの紙幣のデザインはすべての国で共通。ユーロ裏側???? 実は、これは見本紙幣なのです。この紙幣は、2002年1月1日に現金の流通が始まる前に、パリの某デパートが事前の訓練用に使用していた、限りなく本物に似せた偽物なのです。突然の導入ではお店が混乱します。従業員に、事前に紙幣を覚えさせて間違えないように練習していた時のお札ですが、どうもデパート用ではなく、公式の練習用のお札のようです。実際のお札とどう違うか? 上の段が偽物です。偽物の方が、わずかに小さく出来ていますが、柄は一緒で比べると色が微妙に異なるのと、ホログラムが本物には付いている事が違う程度です。5ユーロ紙幣・・・本物1ユーロ・・東京三菱BKの昨日の買いのレートはCASH 114.37円。5ユーロ・・・571.85円。10ユーロ紙幣紙幣・・・本物 10ユーロ・・・・1143.7円100ユーロ・・・11437円200ユーロ・・・22874円・・・高額過ぎて市場にはない500ユーロ・・・57185円・・・同20ユーロ紙幣紙幣・・・本物50ユーロ紙幣・・・本物ユーロのコインコイン、上段は全て練習用の偽物。下段は本物。左から2ユーロ、1ユーロ50セント、20セント、10セント、5セント、2セント、1セントお札の柄は全ての国で共通ですが、コインに関しては、裏側は加盟国が各々自由な柄で印刷しているのです。肖像もあれば、国を代表するような建物。イタリアはレオナルド・ダビンチの人体図などのせています。1ユーロと2ユーロの柄が同じ国もあれば異なる場合もありました。2ユーロの重さは500円玉と同じでした。お金シリーズ Back numberリンク お札シリーズ 1 (アメリカ合衆国ドル・・ドルの札束) お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)リンク お札シリーズ 3 (ユーロ札束)リンク ドル・トラベラーズ・チェック(T/C) の高額券リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話
2010年07月22日
閲覧総数 8778
-
47

モンマルトル 5 (ユトリロ 1 恋多きユトリロの母)
ユトリロの紹介をする前振りのつもりで書いていたらやけに長くなってしまい、ユトリロと独立させる事にしました。モンマルトル 5 (ユトリロ 1 恋多きユトリロの母)フランス(France)、パリ(paris)セーヌ川右岸18区 モンマルトル(Montmartre)モーリス・ユトリロ(Maurice Utrillo) Part 1 シュザンヌ・ヴァラドン(Suzanne Valadon)(1865年~1938年)恋多き母シュザンヌ・ヴァラドン「パリ派」を指すエコールド・パリの1人であるモーリス・ユトリロは、海外からモンマルトルやモンパルナスに集まったボヘミアンな画学生とは違って、このモンマルトルで生まれて育ち、画家となった人である。私たちが知るその絵は、このモンマルトルを描いた作品が多い。さて、彼を紹介する為には、まず彼の母の紹介からしなければならないのだ・・。恋多き母シュザンヌ・ヴァラドンシュザンヌ・ヴァラドン(Suzanne Valadon)(1865年~1938年)本名マリー・クレマチーヌ・ヴァラドンは、最終的に画家であるが、ユトリロの母として知られている。彼女自身私生児で、母と共に5歳の時にパリに出るが、貧困の中で10代始めから様々な仕事に就き、一時はサーカスのブランコ乗りにもなっている。(おそらく母に売られたのだろう)しかし、良く知られているのはルノワールやロートレック、ドガらのモデルを努めた事と同時に彼らの愛人でもあった事である。ルノワールがアリーヌと結婚した翌年41歳の時にシュザンヌに会っている。シュザンヌ16歳の時でそれからしばらくルノワールの愛人になるが、公然と浮気をして、ユトリロを身籠もる事になる。下の「都会のダンス」部分はシュザンヌがモデルでこの時彼女は18歳でお腹にユトリロがいたらしい。もちろんユトリロも私生児しとて生まれるのである。ブランコで腰を痛めて、サーカスを出なければならず、生きる為にモデルになったようですが、美しい彼女にとってそれは天職でした。この都会のダンスの少し前に彼女はラパン・アジルで19歳のロートレックに出会うのである。恋をしたのはロートレックで、彼は「君をシュザンヌで呼びたい」と言う。本名マリーはルノワールが彼女の名を呼ぶ時に使用する。ロートレックはそれが嫌だったらしい。そして、シュザンヌはそれを受け入れルノワールと別れてシュザンヌ・ヴァラドンになり、ロートレックの愛人になるのである。シュザンヌはその後出産すると母を呼び寄せてユトリロを母預けにしてしまうのである。出産してすぐロートレックのアパートで同棲が始まる。その頃ロートレックが彼女を描いた絵「酒を飲む女または宿酔い」が下である。 まだ十代なのに随分やさぐれてしまった感がある絵である。2人の関係は長くはなかった。理由は、ロートレックが敬愛していた画家、エドガー・ドガに彼女を紹介し、結果的にドガが彼女を弟子にしたいと申し出たからだそうだ。彼女に絵の才能があったのは事実であるが、弟子とは愛人になる事と同じだったらしい。ドガ52歳の時であるが、シュザンヌの方が積極的だったらしい。言うまでもなく、ロートレックが傷つき、ドガにも彼女にも2度と会わなかったようだ。シュザンヌとモーリス・ユトリロ親子シュザンヌは28歳の時に作曲家の、エリック・サティと交際。彼はシュザンヌに彼女に300通を超える手紙を書いたらしいが半年で破局。しかし、ドガとの師弟関係は続いていたようだ。画家としてサロン出典もしている。青い部屋ロートレロックの影響が見られると言われる作品・・美術書から31歳で資産家のポール・ムージスと結婚するも44歳の時に息子より3歳年下の画家志望の青年アンドレ・ユッテル(23歳)を恋人にして離婚。49歳でユッテルと正式に結婚。画家としては、彼女の主要作品がフランス政府によって買い上げられ、後にパリ国立近代美術館に所蔵されるまでになるのだが、余りに恋の遍歴がすさまじく、そちらの印象の方が強いのである。1896年~ユトリロと母(シュザンヌ・ヴァラドン)が住んでいたアパート(現在モンマルトル博物館)ラパン・アジルのすぐ近所である。今回は正面の写真がありません。ユトリロにつづくリンク モンマルトル 6 (ユトリロ 2 モンマルトルを描いた画家)
2010年04月14日
閲覧総数 2653
-
48

キクラデス文明と彫刻
ちょっと触れようと思っただけだったんですが・・。せっかくだから写真を載せたら長くなって、ミコノス島は今回カット。次回につづきます。謎のエーゲ海文明キクラデス文明(Cycladic civilization)新石器時代から青銅器時代初期(BC3000年~BC2000年頃)にエーゲ海のキクラデス諸島に栄えたとされる文明でクレタ島のミノア文明よりも古い文明です。以前「サントリーニ島4(ロバと街)」の所でそのキクラデス文明に少し触れましたが、アトランティス大陸か? とも思われる高度な文化を持った文明だったようです。この頃の人々の様子が、ある土器から推察できたそうです。シロス島のハランドリアニ遺跡からたくさん出土しているそのフライパンのような形をした土器は、背面に長くオールを30も持つ船の絵が描かれ、大型の船をあやつっての交易らしき文化のあった事がわかるそうです。ただ、その土器そのものの用途が未だ謎だとされています。下が、形から「フライパン」と呼ばれる謎の土器。アテネ国立考古学博物館所蔵キクラデス諸島には大きな特徴があり、それぞれの島から産出される天然資源が不均一に異なるのだそうです。例えば、黒曜石(石器の材料)の産出はミロス島のみ。銀や銅等の鉱石の産出ははシフノス島とギリシャ本土のアッティカ東南のラヴリオン一帯のみ。BC2000年頃まで栄えたキクラデス文化の遺跡にはすでに黒曜石の石器のみならず、青銅製の短剣や槍先、金や銀のブレスレットなどが出土しているので、島々相互の特産を交換しての海上交易が早くから行われていた事がわかるのだそうです。この交易は、キクラデス諸島内にとどまらず、トルコのアナトリアにまで広がるものだったようで、アイソトープ検査で出土品の履歴が今は特定できるのだそうです。キクラデスの大理石彫刻キクラデス文明の遺跡からの出土品に白亜の大理石を様々な形に加工した容器や、精巧な大理石製の石偶が出土しています。大理石はエーゲ海地域に広く産出し、神殿建設や彫刻には欠かせない素材ですが、どこからでも産出されるものではなく、とりわけ光沢のある美しい上質の鉱脈を求めてキクラデス文明期から探し求められていたようです。(パロス島に採掘抗の跡が残るそうです。)下は、ケロス島から出土した石偶「アウロスを吹く人」 アテネ国立考古学博物館所蔵。対に「ハープを吹く人」がある。優美な一対として、ある音楽を奏でる石偶である。これらキクラデスの石偶は後のギリシャ彫刻に見る精巧な大理石の彫刻とは異なりますが、現代のモダン・アートを思わせる水準の高い造形です。(決して稚拙ではないです。)キクラデスの彫刻作品を見たときに驚きました・・モディリアーニが頭に浮かんで・・。下も、おそらくデロス島からの出土品? アテネ国立考古学博物館所蔵。アメデオ・クレメンテ・モディリアーニ(1884年~1920年)がキラクデスの彫刻を知っていたとは思えませんが、彼の彫刻作品は確かに民族美術に影響を受けた模倣にも近い作品だったのは確かなのです・・。(彼の作品はアフリカ系が多いですが、デッサンはギリシャ彫刻も結構ありました。)やはり(モダンだと)そう思ったのは私だけではなかったようです。20世紀半ばにコレクター達がその現代風な彫刻(ジャン・アルプやコンスタンティン・ブランクーシを想わせる)を奪い合うようになったことで再び注目された。(ウキペディア)残念な事にその為に遺跡が掘り荒らされてキクラデス彫刻は散逸して文明の脈絡が解らなくなってしまったようです。(作品が少ないと思いました。偽物も盛んに取引されたと言います。)文明は一線的に発展するものでは決してないそうです。ギリシャも初期青銅器時代から現代までに繁栄と衰退を繰り返し、時には自然現象で文明は絶え、時には侵略者により塗り替えられて来ています。キクラデス文明とクレタのミノア文明は、場所柄が近いにもかかわらず似て非なる文明なのだそうです。何故キクラデス文明が衰退したのか? 何故クレタ島の力が増したのか? 是非とも、そのきっかけを知りたいものです。これから博物館を廻る時は、キクラデス文明期の彫刻に注意してみなければ・・・。とは言え、実はギリシャ彫刻ではアルカイック期の作品が結構好きです。精神的に受ける何かインスピレーションを感じるんですよね・・。そう考えて見ると、ギリシャ彫刻は美しいだけでなく、奥が深ーいのかもしれないです。
2009年07月27日
閲覧総数 2981
-
49

ザルツブルクのモーツァルトクーゲル
前回紹介したように、モーツァルトはザルツブルクを捨ててウィーンに定住し、そこで亡くなっていますが、没後しばらくして、彼の名声が高まると、思い出したかのようにザルツブルクではモーツアルトを奉り始めます。いわゆる村おこしに近い発想で始まったのでしょう・・・。国際モーツァルテウム財団(1880年9月20日発足)ザルツブルクの街では、1840年に、モーツァルトの銅像が街の広場に建てられ、モーツァルト広場に名を変えています。1880年にはモーツァルトの音楽を奨励し、保護し、モーツアルトを讃える事を主目的に「国際モーツァルテウム財団」が発足。通称「モーツァルテウム」と言うモーツァルト会館には、財団事務局、音楽学校、モーツァルト資料図書館、コンサート・ホールが備えられ今や、モーツァルト関連の国際窓口の一つとなっています。前回紹介したモーツァルトの生家は、1880年に財団が買収。タンツ・マイスター・ハウスは1938年に財団が買収。それぞれ展示場になっています。他にも有名なのが、毎年夏に行われるザルツブルク・フェスティバル(音楽祭)です。これも、モーツァルトを記念した音楽祭となっています。前振りが長くなりましたが、今回紹介するのは、お菓子のモーツァルトですオーストリア共和国(Republic of Austria)ザルツブルク(Salzburg)の菓子店フュルスト(Furst)のモーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)モーツァルトと名の付いたチョコレート菓子は、今や世界に出回っていて、知っている方も多いと思います。ちょっと見は同じなのですが、実は多種のメーカーから発売されているのです。今回紹介するのは、もちろん本家のモーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)ですが、歴史は1890年と、国際モーツァルテウム財団に近いくらい古いのです。本家のはモーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)の包装は他と少し違います。包装紙にはモーツァルトの横顔。包装紙だけではなく、ここの品は手作りなのです。(他の偽物は全て工場生産品)本家はもともと1884年創業のカフェ、フュルスト(Furst)。・・アイアン・ワークが美しい。菓子職人パウル・フュルスト (Paul Fuerst) が試行錯誤の末に考案し、1890年に完成させたのが、モーツァルトクーゲル(Mozartkugeln)です。新しいチョコレート菓子はザルツブルクの人気商品となり、1905年のパリ菓子博覧会で金賞、受賞。ところが特許をとっていなかたようで、包装までマネする会社がボコボコ現れたようです。そういう意味で言えば、他は全て模造品なのです。スーパーで安く売られている大量生産品のミラベル社(Mirabell)と比較してみました。左側が本家フュルスト(Furst)・・・一見2層構造だけど3層構造。ソフトな仕上がり。右側がミラベル社(Mirabell)・・・・4層構造。香料にくせを感じます。値段は本家が1個0.9ユーロくらい(手作り)ミラベル社のはスーパーで0.32ユーロくらい。材料(下、2枚の写真は、本家のドイツ版ホームページから画像を拝借。)ピスタチオを練り込んだマジパンを芯に、ヘーゼルナッツ入りのチョコクリームを巻き付けチョコボールを作成。そのチョコボールにスティックを刺して、をさらにチョコレート・コーティング。完全なる家内制手工業ですね。本家のが高い訳です。工場の生産品とは別物です。最近流行しているスティック付きのチョコレート・ドリンクに見た目似てますが、乾燥させてから、スティックを外し、その空いた穴にもチョコレートをつめて・・・(ヘソになっています。)完成です。昔と変わらない製法で味を守り続けています。本家の手作り品は、製造個数が限られ、販売場所も系列店だけとか・・。カフェ、フュルスト(Furst)は菓子店なので、モーツァルトクーゲルだけを売っているわけではありません。店の奥がカフェ。ザルツブルクに行ったら自分用には本家のものをお奨めです。会社には安いので・・・。
2009年12月12日
閲覧総数 3659
-
50

サグラダ・ファミリア 3 (生命の木)
サグラダ・ファミリア 3 (生命の木)サグラダ・ファミリア(Sagrada Familia) Part 3生命の木・・・糸杉天からの使い(聖霊)としての白鳩果実今回は建物に表現されているキリスト教の象徴から紹介。その前に、前回降誕のファサードの3つの入り口について左の門がヨセフ、中の門がキリスト、右の門が母マリアを象徴する・・と紹介しましたが、門にはそれぞれ名前がついていました。左の門「信仰の門」中央の門「慈悲の門」右の門「希望の門」左の門「信仰の門」と中央の門「慈悲の門」入り口降誕のファサード、上部4本の鐘塔と中央「慈悲の門」の上部にある糸杉のオブジェ拡大してみると鐘楼となる塔の壁には「sanctus」と、文字が刻まれている。sanctus・・・意味は「聖なる」 という形容詞他にsanctusが示すのは1.三聖唱「聖なるかな,聖なるかな,聖なるかな・・・」で始まる賛美歌。2.ミサの最高潮の時にならす鈴または鐘。3.鐘楼そのもの。ガウディはこのサグラダ・ファミリアの外壁のあちらこちらにこうした文字も刻んでいます。生命の木・・・糸杉ヒノキ科イトスギ属、西洋檜(せいようひのき)サイプレス(Cypress)とも呼ばれます。糸杉は、ローマ時代には棺桶の素材でもあり、今も墓場に糸杉、あるいは死のイメージがつきまとった樹木です。聖書の各所には糸杉の記述があり、それによりいつしか「生命の木」の解釈がされるようになったようです。特に13世紀のビザンティン美術の中で十字架が生きた樹木として表現される時に糸杉が用いられるようになったと言われています。天に向かってまっすぐ伸びる事、常緑樹である事から墓場の糸杉は死後の生命の不滅・・と解釈され、キリストの復活と永遠の命のシンボルとなったようです。因みにキリスト磔刑(たっけい)の十字架はこの木から作られた・・との伝説もあるようです。白い鳩はアラバスターで彫られているらしい。天からの使い(聖霊)としての白鳩鳩は旧約聖書の「ノアの箱船」の中ですでに言伝の使者として登場しています。また「モーセの律法」の中でも「汚れていない物」として山羊や羊の代わりに神への捧げ物の動物とされていたようです。キリスト教では白鳩は三位一体、神の第三位格である聖霊としてのイメージで使われています。キリスト教美術において白鳩が現れた時、それは聖霊の啓示を受けた事を現しています。他にも外壁にはいろんな箇所に文字が刻まれている。ガウディは彫刻だけでなく、文字や石の壁の形にもこだわって、最高の聖堂を作ろうとしていたようです。聖堂そのものが、聖なるメッセージとなるように・・。告知する天使の像天使の頭の上の柱にも文様のような文字が浮かぶ。降誕のファサード左側身廊の側壁上部フルーツの盛り合わせらしい。果実は豊穣と知恵のシンボルそして、ここでは果実は聖霊の12の果実を暗示する為、愛、喜び、平和、忍耐、寛容、親切、誠実、善意、柔和、信仰、節制、純潔のシンボルになるようです。拡大してみるとモザイクになっているようです。Back numberリンク サグラダ・ファミリア 1 (未完の世界遺産)リンク サグラダ・ファミリア 2 (降誕のファサード)サグラダ・ファミリア 3 (生命の木)リンク サグラダ・ファミリア 4 (未完の理由 と主祭壇)リンク サグラダ・ファミリア 5 (天井と福音書記者の柱)リンク サグラダ・ファミリア 6 (天井の立体幾何学模様)リンク サグラダ・ファミリア 7 (ステンドグラス)リンク サグラダ・ファミリア 8 (受難のファサード)リンク サグラダ・ファミリア 9 (鐘楼のバルコニーから)リンク サグラダ・ファミリア 10 (教会建設)
2010年12月08日
閲覧総数 2117










