2008年11月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
新刊購入~佐藤彰一『中世世界とは何か』
近所の書店に並ぶのが待ちきれないのは分かっていたので、今回はアマゾンさんで、タイトルにも書きました次の本を購入しました。佐藤彰一『中世世界とは何か』岩波書店、2008年 こちらは、池上俊一・河原温両先生の編によるシリーズ「ヨーロッパの中世」の第1巻になります。 なお、このシリーズは全8巻、毎月刊行予定で、全体の構成は次のとおりです。1.佐藤彰一『中世世界とは何か』2.河原温『都市の創造力』3.小澤実/薩摩秀登/林邦夫『辺境のダイナミズム』4.関哲行『旅する人びと』5.堀越宏一『ものと技術の弁証法』6.大黒俊二『声と文字』7.原野昇/木俣元一『芸術のトポス』8.池上俊一『儀礼と象徴の中世』→第2回配本、来月刊行予定 なお、『中世世界とは何か』をぱらっと見てみたのですが、註はないようです。参考文献は割合充実しています。 この手のシリーズものを集めたことはないですが、ヨーロッパ中世に焦点をあてたシリーズだけに、今回は8巻全て揃えたいと思います。次回配本の池上先生の著作も面白そうですが、日本でぶいぶい中世西欧の説教研究を進めておられる大黒先生が担当される第6巻も楽しみです。もちろん、その他の巻も楽しみです。 『修道院文化史事典』も読了したので、次の読書はこの『中世世界とは何か』にしたいと思います。
2008.11.29
コメント(5)
-

P・ディンツェルバッハー/J・L・ホッグ編『修道院文化史事典』
P・ディンツェルバッハー/J・L・ホッグ編(朝倉文市監訳)『修道院文化史事典』(Peter Dinzelbacher und James Lester Hog (Hg.), Kulturgeschichte der Christlichen Orden in Einzeldarstellungen, Alfred Kroner Verlag Stuttgart, 1997)~八坂書房、2008年~ ヨーロッパの主要な修道会の歴史を概観するのにうってつけの1冊。これはすごいです。 まず、本書の構成を掲げておきます。ーーーまえがき(シュトゥットガルド アフルレッド・クレーナー出版社)序章 修道制と文化 I.中世(ペーター・ディンツェルバッハー;朝倉文市訳) II.近世以降(ジェイムズ・レスター・ホッグ;小川宏枝訳)第1章 ベネディクト会(ウルリヒ・ファウスト;石山穂澄/朝倉文市訳)第2章 シトー会(ペーター・ディンツェルバッハー;平伊佐雄訳)第3章 カルトゥジア会(ジェイムズ・レスター・ホッグ;梅津教孝訳)第4章 アウグスチノ修道参事会(フーベルト・ショプフ;谷隆一郎訳)第5章 プレモントレ会(ルトガー・ホルストケッター;富田裕/朝倉文市訳)第6章 病院修道会(ユルゲン・ザルノフスキー;梅津教孝訳)第7章 騎士修道会(ユルゲン・ザルノフスキー;岡地稔訳)第8章 フランシスコ会とクララ会(レオンハルト・レーマン;伊能哲大訳)第9章 ドミニコ会(マイノルフ・ロールム;山本耕平訳)第10章 カルメル会(ゲルダ・フォン・ブロックフーゼン;山崎裕子訳)第11章 アウグスチノ隠修士会(ヴィリギス・エッカーマン;谷隆一郎訳)第12章 イエズス会(アンドレアス・ファルクナー;富田裕訳)第13章 東方正教会の修道制(ヴォルフガング・ヘラー;谷隆一郎訳)参考文献主要修道会の体系的分類表主要修道会略号表索引(修道会名/人名)監訳者あとがきーーー それぞれの章について、歴史的展開、会則・組織・服装、霊性は基本的な共通項目として書かれていて、その他にも文学、音楽、社会科学、経済活動などなどの項目があり、それぞれの修道会の成果が紹介されています。そして各章の末尾には、それぞれの修道会に関する参考文献目録もあり(日本語文献の紹介も豊富)、概観をつかめるだけでなく、さらに研究を深める上でもとても便利な1冊です。 序章など、I節II節あわせて50頁弱ですが、それだけで修道制のはじまりから今日の状況までが(もちろん簡単ではありますがポイントはしっかり押さえた上で)概観できて、読み始めからわくわくしました。 また、原書には一切註はないそうですが、邦訳版では適宜註も挿入されています。特に、それぞれの修道会が日本にいつ入ってきたかとか、どの会派が入ってきたとか、日本との関わりについて補足されて、こちらも興味深いです。 内容自体についてはつっこんだことは書けませんが、メモ程度に思ったことや興味深いことをつらつらと書いておきます。 まず、普段から感じていたことですが、フランシスコ会を紹介する日本語文献は割合数があるのに、ドミニコ会のそれはあんまりないなぁ、ということ。本書の8章と9章の参考文献目録を見てもそれは明らかです。いずれも同じ時期に生まれ、当初は説教活動に力を入れていたという共通点はあるのですが(一方、創始者の性格はずいぶん違うようにも思いますが)。 意外な有名人の名前や業績も知ることができて、楽しかったです。たとえば、避雷針は、アメリカのフランクリンとは無関係に、プレモントレ会修道士ポロコープ・デヴィシュが発明、使用していたとか。「メンデルの法則」で有名なグレゴール・メンデルはアウグスチノ隠修士会、現在のブルノの修道院長であったとか。これは完全に自分のメモですが、聖人伝の史料集『アクタ・サンクトールム』 (Acta Sanctorum)はイエズス会で編纂されているとか。 こんな感じで、上に書いたようなそれぞれの項目について、その会に所属する修道士たちの業績がいろいろと紹介されていて、興味深いです。 イエズス会は日本でもなじみ深いですが、この会について特に興味深かったことも書いておきます。それは、そのイエズス会にとって演劇が非常に大きな重要性をもった、ということです。学校劇も行われたそうです。このことに関して著者は、「イエズス会学院の生徒たちは、教室で学び取った内容を、魅力的で人を引きつけるような方法で大勢の観衆のまえで表現することが出来るようにならなければならなかった」(470頁)といいます。なるほど、まさに彼らはどんどん海外に出て宣教活動をするのが重要な使命だったと、合点がいきました。 第10章のカルメル会は、ミシェル・パストゥロー『悪魔の布』の第1章で紹介されています。というのも、パレスチナ起源のカルメル会は、もともと縞模様の服を着ていました。ところが西欧では、縞模様は軽蔑された図柄だったため、彼らが縞模様の服をきてやってきたことは大きなスキャンダルだったというのですね。 本書には図版も豊富に含まれているのですが、カルメル会修道士が縞模様の服を着ている絵も何枚か紹介されていて、興味深かったです。 図版に関連して、いくつかの修道会の修道院については見取り図が紹介されていて勉強になります。修道院の外観の写真もきれいですし(裏表紙にはモン・サン・ミシェル修道院の回廊の写真がありますが、かなり魅力的です)、図書室の写真もかっこよいです。修道院の書架から大型の本を取り出してぱらぱらと眺める… 素敵でしょうね…。(2008/11/27読了)
2008.11.29
コメント(2)
-

坂木司『先生と僕』
坂木司『先生と僕』~双葉社、2007年~ 坂木司さんの短編集です。5編の短編が収録されています。 本作では、大学生の「僕」、伊藤二葉さんと、その「先生」、中学生の瀬川隼人さんが活躍します。 それでは、簡単にそれぞれの内容紹介と感想を。ーーー「一話 先生と僕」恐がりで、殺人の起こる本なんて読みたくもない僕は、大学入学後最初の友人に推理小説研究会に誘われた。その日、公園で少年に声をかけられた。これが、「先生」との出会いだった。 勉強もできる「先生」―隼人は、親の目をごまかすためのアリバイ的な家庭教師になってほしいという。そして僕は、彼からミステリについて教えてもらうことになっていく。 そんなある日。二人は駅ビルの本屋で、ギャル向け雑誌に不審な付箋が貼られていることに気付く。はたして、その目的は…。「二話 消えた歌声」友人にカラオケに誘われた僕。ところが、ある知人に出会ったり、ボヤ騒ぎが起こったりと、なんとも踏んだりけったりな一日に。ところが、知人が、「カラオケにいたはずの人たちがいない」と言ったことが、隼人の好奇心に火をつける。「三話 逃げ水のいるプール」友人に誘われ、僕は隼人とともに区営プールに遊びに行く。ところが、そこの職員がどうも不審で…。僕はその男が、まるで暗号のようなものを書き留めているのに気付く。はたして、その意味は。「四話 額縁の裏」穏やかな無料のギャラリーで、穏やかな女性といろいろ話をするのが楽しくなってきた僕。その前に、隼人から詐欺の見分け方についても注意するよう言われていたし、しっかり用心もしていた。それでも隼人は、そんな僕をやけに心配する。「五話 見えない盗品」隼人がハムスターを飼い始めた。ハムスター用のヒーターを買おうと調べごとをしていると、ある種の犯罪が行われているのを確認する。その犯行を未然に防ごうと、次に狙われるはずの店で待機してみるものの、犯人らしい人物は現れない。それでいて、犯行は行われているようなのだった。ーーー 僕の、見たものを写真のように瞬時に記憶する能力が、隼人さんの推理を調査を補っていくという、なかなか面白い設定でした。そしてこの作品、タイトルで、少年が「僕」で大学生が「先生」として、謎に挑んでいくのだろうと想像していたのですが、それが逆だったというのも楽しかったです。 作中、おそらくそれぞれの事件と関連もするような、殺人が起きないミステリが中心に紹介されます。ここで紹介されている作品はほとんど読んだことがないですが、ちょっとした本の案内みたいな性格もあって、良いですね。 坂木さんの今までの作品では、不快になるようなこともしばしばでしたが、今回はあんまり不快な気持ちにならずに読みました。行われる事件としては卑劣で不快きわまりないものもあるのですが…。私の気の持ち方も変わってきたのかもしれませんが、穏やかに読みました。(2008/11/24読了)
2008.11.26
コメント(0)
-
ミシェル・パストゥロー『紋章学概論』より「中世社会全体による紋章の採用」
ミシェル・パストゥロー『紋章学概論』第1巻第2章「中世社会全体による紋章の採用(1180頃-1320頃)」(Michel Pastoureau, Traite d'heraldique, pp. 37-58 : Livre I, chapitre II"L'adoption des armoiries par l'ensemble de la societe medieval (vers 1180-vers 1320)") 今回は、ミシェル・パストゥロー『紋章学概論』より、その第1巻第2章「中世社会全体による紋章の採用(1180頃-1320頃)」を紹介します。 まず、本章の構成は次のとおりです。ーーーI.貴族全体への紋章の使用の拡大(1180頃-1230頃) 1.原因 a)防具の変形 b)トーナメントの流行 2.過程II.全ての社会階層への紋章の使用の拡大(1230頃-1330頃) 1.女性の紋章 2.聖職者の紋章 3.「ブルジョワ」と職業人の紋章 4.農民の紋章 5.都市的・宗教的共同体の紋章III.西洋紋章学の成立ーーー 以上の流れに沿って簡単に内容紹介をして、若干のコメントを付け加えたいと思います。I.貴族全体への紋章の使用の拡大(1180頃-1230頃) Iでは、騎士たちの防具の変形が、紋章の流行の原因となることが指摘されます。第1巻第1章では盾が大きくなることが指摘されますが、ここでは、兜と鎖帷子が体を覆う面積が広くなることから、識別のしるしとして図柄で飾られる必要が出てきたことが示されます。 トーナメントについては、後には切れ味の鈍い剣や木製の武器を使うようになりますが、13世紀半ばまでは実際の戦場での装備とかわらない装備で行われていたということが指摘されます。ちなみに、トーナメントでは死者も出ますが、教会はそうした死者を教会の墓地に埋葬することを拒んでいました。 2の「過程」の中でいちばん面白かったのは、「同一紋章集団」(groupes d'armoiries. これは試訳ですが、なにか定訳があるかもしれません)の存在です。従来、家臣や陪臣(家臣の家臣)は、自分の領主と同じ紋章を使っていました。13世紀頃には、自分の紋章をもつようになりますが、それも、領主の紋章をちょっと変えたくらいのものも多いそうです。そのため、ある地域の中で、親族関係にない(ように思われる)いくつかの家系がそっくりの紋章を持つようになる、というのです。これが「同一紋章集団」です。…むむ、厳密には微妙な違いもあるわけですから、訳語に「同一」を加えるのは不適切かもしれませんね…。はてさて…。II.全ての社会階層への紋章の使用の拡大(1230頃-1330頃) 本章の中でこの節をいちばん興味深く読みました。騎士たち以外に紋章が広まる大きな要因は、印章の使用です。 1では女性の紋章とありますが、もちろん貴族階層の女性のことです。もっとも、14世紀以降には庶民の女性も紋章をもつようになるそうです。 なお、女性の紋章は、おおまかにいって4つに分類されます。(1)夫と同じ紋章。(2)父(稀には母)の紋章。(3)それらの組み合わせ。(4)夫のとも父のとも異なる新しい紋章。以上の4つです。 少し飛ばして、農民の紋章は、描かれた図柄の一覧表も示されていて興味深かったです。動物が多く描かれる伝統的な紋章とは違って、農民の紋章描かれた図柄は、圧倒的に植物が多く、その他、日常生活や仕事で用いる道具も多いようです。なお、ここでパストゥロー氏は興味深い問題提起をします。というのは、こうした農民の紋章の特徴は、農民たち自身の嗜好によるのか、それとも、それらの印章を作った職人さんが農民に対してもっていたイメージを反映しているのか、という問題です。III.西洋紋章学の成立 ここでは、本章で扱った時代―特に13世紀に、厳格な紋章規則がほぼ完成することが論じられます。氏は、その厳格な規則のため、貴族の紋章と農民の紋章は、見た目には違いがない、ということを強調しています。たとえば、誰の紋章か分からない紋章があるとして、その持ち主が貴族なのか農民なのか、判別することはできない、というのですね。 また、この時期には、伝説の人物にも紋章が付与されたり、次男以下が長男が引き継ぐ紋章とちょっと違った特徴を付け加えた紋章を使うという差異化brisureも見られるようになったりします。 もう一つ、Iの2で、家臣たちが領主のと同じ紋章を使っていたと書きましたが、やがてそういう習慣も消えていくそうです。そうした中で、それぞれの嗜好や集団的な心性が果たした役割を氏は強調するのですが、これについてはまた別の章で論じるとのことです。 * * * ひとまずこの章も全訳を作ってみましたが、註を見ていると、イタリア語からスペイン語(?)の文献まであって、研究者の博識ぶりに圧倒されるばかりです。 そして、農民の紋章のところでも少しふれましたが、パストゥロー氏の論考を読んでいると、つねに問題提起があり、ますますその研究分野に興味をひきつけられます。本書は、かなりの大著で、ミシェル・パストゥロー氏の研究の一つの集大成と思うのですが(研究生活の割合早い時期に出された集大成的な書物という意味で、私はジャック・ル・ゴフ『中世西欧文明』と本書が近い位置づけにあると思っています)、それでいて、さらなる研究をうながす視点をつねにもっています。わくわくする読書体験です。
2008.11.25
コメント(2)
-

高田崇史『カンナ 飛鳥の光臨』
高田崇史『カンナ 飛鳥の光臨』~講談社ノベルス、2008年~ QEDシリーズでおなじみ、高田崇史さんの新シリーズ開幕、第一弾です。 今回の主人公は、伊賀・出賀茂神社を継ぐことになっている青年、鴨志田甲斐さんです。といって、そのご両親、神社の職員で甲斐さんのお祖父さんみたいな存在の加藤丹波さん、その孫娘で博識、現役東大生にして巫女のアルバイトをしている貴湖さんと、まわりの人物もみなさんキャラが強く、みなさん活躍されます。 そして鴨志田家は忍者の末裔…。すごい設定ですが、QEDシリーズよりもユーモアも強い感じで、楽しい一冊です。 と、ほとんど総評みたいなことを書いてしまいましたが、あらためて内容紹介と感想を。ーーー 地方出版社「月刊歴史探究」で、殺人事件が発生した。鍵のかかった会議室に入ってみると、男性職員が死んでいた。その男性のもとには応接室の鍵が落ちていた。そして応接室には、女性職員が死んでいた…。 * 同じ頃、出賀茂神社に泥棒が入った。泥棒は、その社伝を盗んだという。その社伝は、滅ぼされた蘇我氏による歴史書であるという…。 また、飛鳥でも、聖徳太子に関する記録をねらった盗難事件が相次いでいた。 * そしてまた、同じ頃。甲斐の知人、早乙女志乃芙から、相談事を持ちかけられていた。甲斐自身もお世話になっていた彼女の夫、諒司が、行方不明になったという。 さらに聖徳太子の謎も考えながら、甲斐と貴湖は事件に巻き込まれていく…。ーーー QEDシリーズと同じく、物語の中の殺人事件と歴史上の謎をリンクしています。本書の謎は、聖徳太子は存在したのか。聖徳太子として伝えられているのは、誰だったのか。 丹波さんが、甲斐さんに聖徳太子とその関連する事項(人物)について簡単に説明するところがあるのですが、三つの問題提起にわくわくしました。聖徳太子も推古天皇も大化の改新も否定されるのですから…。 本書で提示される説(日本史は苦手ですが、ものすごくわくわくしながら読みました)の真偽はともかく、いわゆる正史はあくまで権力者の視点で書かれているということを、あらためて認識しなければいけないと思いました。いかに、学校で教えられている歴史が作られた歴史か…。 ところで、本書の中で、貴湖さんが、歴史を人物中心に見ることを強調するシーンがありました。天皇125人+5人を覚えるだけで、日本史が鳥瞰できる…。あ、たしかにそれはその通りだと思いました。 けれども私自身は、いわゆる歴史の表舞台に出てくる人たちの抗争なんかよりも、そのような時代に、「普通の人々」がいかに生きたか、という点に関心を持っています。なんというか、彼らも生きていたんだ、ということを感じたいと思います。もっとも、貴湖さん自身が、こうした歴史を軽視しているというわけでもないと思いますし、歴史を鳥瞰する方法として代表的な人物を中心に見ていくのが便利なのはたしかですが…。いろいろ考えさせられました。 なお、本書は、森博嗣さんのGシリーズやXシリーズのように、一般の講談社ノベルスとは違って、一段組になっています。なので割合すらすらと読めました。 いやはや、こちらも面白いシリーズになりそうです。(2008/11/22読了)
2008.11.24
コメント(0)
-

『中世西欧の下層民―その用語、知覚、現実』
Pierre Boglioni, Robert Delort, Claude Gauvard ed., Le petit peuple dans l'Occident medieval. Terminologies, perceptions, realites (Actes du Congres international tenu a l'Universite de Montreal, 18-23 octobre 1999), Paris, 2003 ロベール・ドロールほか編『中世西欧の下層民―その用語、知覚、現実』の構成を紹介します。 中世の「下層民」(petit peuple)に関して行われた国際会議の成果をまとめた論文集です。 本書の構成は以下の通りです。 (*できる限りタイトルは試訳で示しましたが、どうにも訳せないのは原文で記しています) (*論文の前の通し番号は、本書にはありませんが、便宜的に付しました) (*基本的に仏語論文ですが、何本か英語論文もあります。タイトル試訳の後に(英語)と書いています) (*全ては読めないと思いますが、読んだ論文については記事を書いて、その都度ここからリンクをはろうと思います)ーーー0.序文1.ロベール・フォシエ「中世の下層民―アプローチと諸問題」第1部 「下層民」の知覚―分析、分類、判断2.ニコル・ベリウ「13世紀の『身分別説教集』における下層民」3.ジャック・ベルリオズ/マリ=アンヌ・ポロ・ド・ボーリュー「公の場と日常生活の間で―13-15世紀の「例話集」における下層民」4.ピエール・ボリオーニ「トマス・アクィナスによるPopulus, vulgus、その他の用語」5.ゲルハルト・ヤリツGerhard Jaritz「後期中世中欧における下層民の良い見本、悪い見本、あるいはその利用」(英語)6.マッシモ・モンタナーリ「農民のイメージと食行動の規範」7.Vincent Pollina「トゥルバドゥール・マルカブリュと農民」8.Maria Bendinelli Predelli「薪と飢餓―フランコ=ヴェネツィア騎士道文学における貧困の痕跡」9.Tania van Hemelryck「動乱の中の民衆―ある定義のもとでの中世の平和的文学におけるモチーフ」10.Alessandro Stella「『チョンピ…最も地位が低く…不潔でぼろを着た人々』―描写、賤民化、排斥」11.Joseph Morsel「中世末期高地ドイツにおける<貧者>(arme Laute)―あるいは、<下層民>の歴史に意味はあるか?」第2部 「下層民」への経済的・社会的アプローチ―水準、カテゴリー、ヒエラルキー12.Walter Prevenier「13-14世紀低地地方におけるコミューンの人々による社会的状況の自覚と知覚」13.Jean-Pierre Sosson「都市の<下層民>―不可欠な尺度か不可能な尺度か?南部低地地方の若干の声(13-15世紀)」14.Sandrine Thonon「笑劇の中の人々―中世末期の都市民の活動への文学的アプローチの道しるべ」15.Francois Menant「<下層民>の始まり―コミューンの時代におけるロンバルドの農民(12-13世紀)」16.Francoise Michaud-Frejaville「中世末期における農村のブルジョワ、バロンの奴隷、ベリー公の下層民」17.John Drendle「プロヴァンスの農村における結婚戦略―トレト地方、1292-1350」18.Andree Courtemanche「移住民―中世末期におけるマノスクへの移住に関する予備的分析」19.Michel Hebert「13-14世紀プロヴァンスの伝達使」20.Bruno Paradis「国家の下層にある奉仕者―14世紀プロヴァンスの死刑執行人」21.Beatrice Leroy「中世末期ナヴァール王国における下層民」22.Serge Lusignan「パリ大学の貧乏学生」23.Armand Jamme, "Les compagnies d'aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes paralleles au milieu du XIV siecle"24.Raoudha Guemara「1425-1502のヴェローナにおける<下層民>たる羊毛業者―不可欠の職人、課税台帳に記載された『市民』(cives)、勤労の貧者」25.ロベール・ドロール「中世末期トスカナにおける奴隷という下層民」26.Francine Michaud「14世紀マルセイユの奴隷と使用人」27.Jean-Marie Yante「雇用の場place d'embauche(13-15世紀)―社会的職業か雇用主の戦略か? フランスを例に」28.Philippe Bernardi「若者、貧者、よそ者…―管理する多様な方法」29.Sharon Fermer「若者、男性、障害者」(英語)30.Julie Mayade-Claustre「生活難の下層民―中世末期パリにおけるprison pour dette」31.Pierre Monnet「下層民と上流層―中世末期ドイツの自伝的証言における家柄に関する議論」第3部 下層民の文化―システム、行動、価値32.クリスティーヌ・クラピシュ=ズュベール「15世紀ボローニャのある石工の日常生活と彼らの衝突」33.ポーラ・クラーク「15世紀のある古着商の心性」(英語)34.Paolo Golinelli「聖人の民衆―聖人伝史料から見る後期中世パダノ地方のいくつかの都市における一般民衆」35.Bernadette Filotas「初期中世司牧文学における民間宗教」(英語)36.Edina Bozoky「聖遺物の捏造[inventions]における下層民の役割」37.Franco Cardini「第一回十字軍における<petits>」38.Danielle Laurendeau「熟慮された宗教的手続き―パミエの異端審問の寄託者による証言における懐疑」39.Madleine Jeay「マリー・ロビーヌとコンスタンス・ド・ラバスタン―人々の中の慎ましき女性、君主と教皇の導き手」40.Marina Montesano「厳格派フランシスコ会士による説教活動における下層民―文化的層、『無益な迷信からの』(ex vana superstitione)信仰、儀礼的魔術」41.Mary R. O'Neil「日常生活の技術―14-17世紀モデナの異端審問における魔術的慣行」42.Virgina Nixon「民衆のための生産―絵画作品を読み解く過程に関する後期中世の様相」(英語)43.Elisabeth Schulza-Busacker「12-13世紀、俗人のために用いられた教化的文学」44.Kouky Fianu「中世末期における下層民のアルファベット順配列と定義―パリの図書館の事例」45.Marilyn Nicoud「<下層民>の衛生、病理学、医療の普及―中世末期の医学的議論と実践」46.Alessandro Vitale Brovarone「中世の冒涜と悪態―語源の社会史に関する覚え書き」47.Gherardo Ortalli「下層民も楽しむにちがいない」48.Claude Gauvard「中世の下層民―結論」ーーー 初めてお名前を拝見した研究者がほとんどなので、無理にカタカナ表記はせず、原綴りのままにしておいたことをお断りしておきます。タイトルの試訳も、中身を読まないままにつけているので、あるいは不適切な訳もあるかもしれません気付いたときには訂正しようと思います。 さて、ここでは、序文で述べられている本書のプランについて書き留めておきます。 まず、本書(会議)のテーマは、(書名からも明らかですが)従来の歴史研究ではあまり注意を払われていなかった「下層民」「庶民」に光を当てることです。 そのために、大きく二つのテーマが設けられます。一つは、「下層民」petit peupleが社会でどのように知覚されていたかという点について、主に語彙やレトリックの面から見ていくこと。もう一つは、現実に生きていた彼らの具体的な生活を明らかにすることです。 現実に生きた彼らの生活にせまるには、大きく3つの水準が考えられます。第一に、経済的水準。第二に、政治・社会的水準。第三に、文化・宗教的水準。厳密に分けるのは難しいと思いますが、主に第一・第二水準について第二部で、第三水準について第三部で扱うようですね。順番は前後しますが、第一部では、上にあげた語彙やレトリックの面に関する議論が主に行われます。 全部は読めないと思いますが、興味がある論文だけでも、ぼちぼち読んでいきたいと思います。
2008.11.23
コメント(0)
-

北森鴻『写楽・考―蓮丈那智フィールドファイル3』
北森鴻『写楽・考―蓮丈那智フィールドファイル3』~新潮文庫、2008年~「異端の民俗学者」蓮丈那智先生が活躍するシリーズ第3弾です。4編の短編が収録されています(第4話の表題作は、中編と呼んでも良いくらいボリュームがあります)。 では、それぞれについて簡単に内容紹介を書いて、感想を。ーーー「憑代忌」蓮丈研究室の助手・内藤三國の写真が学内に広まっていった。彼の写真を犠牲とすることで、蓮丈の厳しい評価もくぐりぬけ、無事に卒業できるという噂ができたらしい。ちょうどその頃、那智は内藤と新しい助手・佐江由美子を調査に向かわせる。そして、調査先の邸宅の家宝である人形をめぐり、事件が起こる。「湖底祀」鳥居に関するレポートを下読みした内藤は、そのまま那智エマージェンシーコールにより、出張をよぎなくされる。そこには、円形でもないのに円湖と呼ばれる湖の底に、神社跡があるのではないかという説を唱えた民間研究者がおり、湖の調査が進められていた。そして、鳥居をめぐって事件が起こる。「棄神祭」学生時代に、那智と狐目の男が遭遇した殺人事件の起こった旧家へ、ふたたび那智たちは訪れた。3年に一度神像を燃やすという独特の儀式がちょうど開かれることもあり。そして、祭りにまつわる謎とともに、殺人事件の真相が暴かれる。「写楽・考」「仮想民俗学」を提唱する「式直男」という謎の人物に興味を引かれる三國と由美子。そして、高知で那智が巻き込まれた失踪事件の、まさに失踪した人物こそが式直男という。式直男はなぜ消えてしまったのか。そして式家に伝わるカラクリ箱と、「べるみー」という画家の正体は…。ーーー 最初の3編がだいたい60ページずつくらいなのですが、表題作は130ページと、読み応えある作品となっています。 佐江由美子さんがメンバーに加わったことも覚えていないまま、読み進めましたが、いやはや、面白いです。北森さんの他のシリーズは読んだことがないのですが、こちらは民俗学を題材にしていることもあり、興味深く、楽しく読み進められます。…しかしまぁあらためて考えると、私が民俗学をしていたとして、蓮丈先生にC判定以上をつけてもらえるのかと、不安になってきますね…。考える力と発想力の乏しさが恨めしいです…。 それはともあれ、どの作品も楽しく読みました。けれど特に、表題作はぞくぞくしながら読みました。 北森さんも、いろんなシリーズをリンクさせておられるようですが、とりあえずは他のシリーズまでは手をのばせなさそうです(いずれ余力ができればあるいは…)。でも、このシリーズはこれからも追っていきたいです。(2008/11/19読了)
2008.11.22
コメント(2)
-

ジャン=クロード・シュミット『中世の迷信』
ジャン=クロード・シュミット(松村剛訳)『中世の迷信』(Jean-Claude Schmitt, "Les ≪Superstitions≫", dans Jacques Le Goff et Rene Remond dir., Histoire de la France religieuse, tome 1, Des dieux de la Gaule a la papaute d'Avignon (des origines au XIVe siecle), Paris, Seuil, 1988, pp. 417-551)~白水社、1998年~ 原著情報が長くなりましたが、本書は、ある一冊の本の邦訳ではなく、大部の本『宗教的フランス史』第1巻の一章分の邦訳です。原著の現物は一部コピーするためにちょっと見たことがあるだけなのですが、きれいな装丁の本です。第1巻は、ここに邦訳されたシュミットの論考も含め、4つの章からなっています。 この『中世の迷信』は、他の国でも訳が出ていて、かなり人気の(有名な)著作のようです。 なお、著者ジャン=クロード・シュミットの簡単な紹介については、その論文「中世の自殺」の記事をご参照ください。すでに記事を書いたその他の著作としては、『中世歴史人類学試論―身体・祭儀・夢幻・時間』があります。 今回、枕元の友にして、数年ぶりに通読しました。 さて、前書きが長くなりましたが、本書の構成は以下の通りです。ーーー日本語版に寄せて序文第一章 ローマとラテン教父における<迷信>概念の基礎第二章 異境から<迷信>へ 異教徒の改宗―ひとつの模範 <迷信>―キリスト教化の副産物第三章 中世初期の魔術師と占い師 自然の災難―人間・動物・収穫 死者たち 時間と占い 夢と悪魔第四章 村の<迷信> 中世文化の新しい軸 <老女たちの信心> 公式的な儀式の濫用 同化不可能な<残滓>―死者の軍勢とアボンド夫人第五章 中世末期の魔女のサバトとシャリバリ訳者あとがき参考文献索引ーーー まず、シュミットは、<迷信superstition(s)>という言葉をカッコ付きで使うことを強調します。現代の<迷信>と、中世において<迷信>という言葉がもった意味は異なるため、中世の意味で<迷信>という言葉を用いるために、ということです。なお、『中世歴史人類学試論』所収の論考「中世宗教史は成立可能か」でも、漠然と言葉を使うことによる時代錯誤の危険性を説き、カッコを使うよう強調しています。 さて、後は、興味をもったところ、面白いところについて、いろいろと書いておきたいと思います。 初期中世において、聖人たちは<異教>の神殿・信仰の対象物を破壊するという役割を持っていました。面白い記述を引いておきます。「聖マルティヌスは神殿を燃やすのに熱心だったあまり、周辺の家屋への延焼を防ぐために奇蹟を起こさねばならないほどであった!」(46頁) しかし同時に、キリスト教はうまく土着の信仰と妥協していこうともします。パリでドラゴンと戦った聖マルセルが、ドラゴンを殺すのではなく服従させたということを、この観点から説明していて、興味深かったです(ル・ゴフも聖マルセルとドラゴンについて論文[『もうひとつの中世のために』所収]を書いていますが、あんまり考えずに読んでいたので印象に残っていません…)。 次は、興味深かった記述を。「教会が与える罰とは…罪の軽重と教会内での罪人の社会的地位に応じて異なっていた。聖職者の方が非聖職者よりも厳しく罰せられた」(62頁)。 この方面についてはほとんど勉強していないので、さっぱりなのですが、ふと、日本をしょって立っている(はずの)国会議員さんたちは、なぜか非国会議員たる一般国民よりもそうとう優遇されているなぁ、と思いました。国会議員は、国会期間中は、基本的に逮捕されないという特権がありますが、しかしそもそも国会議員が逮捕されるようなことをすることがおかしいのであって、変な制度だなぁと思います。上の引用を見習っていただきたいですね。 第三章の、「時間と占い」の節が、今回読んだなかでは一番興味深く読みました。時間のキリスト教化について論じる部分です。 たとえば、曜日の話。ルーナ(lundi,月曜日)、マルス(mardi,火曜日)、メルクリウス(mercredi,水曜日)、ユピテル(jeudi)、ウェヌス(vendredi,金曜日)、サトゥルヌス(samedi,Saturday,土曜日)と、それぞれ曜日には神々あるいは神格化された天体の名前がつけられています。しかも、木曜日にはユピテルのために休むという、聖職者には許せない慣行もあったとか(アルルのカエサリウスの説教)。これに対して教会は、神が6日働き、七日目に休んだということで、<神の日>(dies domini)こそが特別なのだと説きます。 たしか最初に本書を読んだ頃でしょうか、そういえば現代フランス語では日曜日はdimancheといって、英語のSundayと違い太陽のイメージがないように感じるのですが、これはなぜかと考えたことがあります。考えただけで調べてないので、いまだに答えは知らないのですが…。あえて上で曜日を列挙したときは現代フランス語を例として付記したのですが、日曜日dimancheだけは「~di」のかたちになっていませんし、やっぱり気になります。私はイタリア語が分からないのですが、あるいはラテン語圏では日曜日だけ特殊な言い方なのでしょうか。 曜日の話が長くなりましたが、あるいは一月一日の話。一月(英January)の名前のもとになっているヤヌスは前と後ろに顔があるので、これが年から年への移行を意味していたため、ローマでは一月一日に重要性がありました。ところが、この日はキリスト教にとってはべつだん大した意味はないのですね。そこで、一月一日に行われる祭事を告発することとなります。また、1564年にフランス王シャルル9世が1月1日を一年のはじまりとして決定するあたりの話も書かれていて、面白かったです。 第四章はいろいろな<迷信>の話が紹介されていて面白いです。他のジャン=クロード・シュミットの研究もいくつか読んできたなかでの再読なので、あらためて理解が深まる部分もあり、良かったです。 魔女の話は、中世西洋史に関心をもち始めていたころは興味をもっていましたが、莫大な先行研究もあるでしょうし、チャレンジするのがためらわれる領域ですね…。 ある共同体の女性がほかの共同体の男や寡夫と結婚すると、その共同体の若者たちがお付き合いできるはずだった女性の数が必然的に一人減ってしまうという事情もあり、そういった新婚夫婦のもとで若者たちが大騒ぎするというシャリヴァリの話は、もう少し関連文献を読んでみたいと思っています。こちらも思いながら、なかなか手をつけていませんが…。 …と、まとまりにない紹介になりましたが、このあたりで。(2008/11/17読了)
2008.11.20
コメント(2)
-

横溝正史『金田一耕助の冒険2』
横溝正史『金田一耕助の冒険2』~角川文庫、1981年5版(1979年初版)~ 角川文庫『金田一耕助の冒険』(1976年初版)を2分冊にした第2巻です。第1巻の感想はこちら。第2巻には、後半の5編の短編が収録されています。 では、今回もそれぞれについて簡単に内容紹介を書いて、感想を。ーーー「夢の中の女」金田一耕助は、夢見る夢子さん…とあだ名される女から、3年前に姉が殺害された事件についての調査の依頼を受けていた。ところが、その女が殺害された。彼女には、金田一耕助の名を騙った手紙が届いていた…。「泥の中の女」探偵作家の仕事場に雨宿りを頼んだヤス子に、そこにいた女は留守番を頼んだ。妹が風邪を引いたので、医者に行ってくるというのだが、ヤス子がその「妹」の様子を見ると、女が殺されていた…。あわてて警察に行き、戻ってきたときにはしかし、探偵作家とその友人が歓談しており、殺人の痕跡は残っていなかった。「棺の中の女」彫刻家・古垣氏の落選作品・「壺を持つ女」を取りに来た運送業者の男。ところが、作品を運ぶ途中、ちょっとした事故を起こしてしまい、その作品の中に殺された女が塗り込められていることが判明した。女は古垣氏の元妻で、彼女が古垣氏と別れた後に向かった彫刻家は行方不明になっていた…。「鞄の中の女」ある日の夕方、金田一耕助に一本の電話があった。前日に報道された、トランクから女の足が覗いていたという事件 …報道では人形の足だったというが、人殺しがあったのではないかという。その後、女の夫という男がかわりに金田一耕助のもとを訪れ、妻の非を詫びるが、そこに妻から電話が。件の車を運転していた男のアトリエに、女の死体があるという連絡だった。「赤の中の女」金田一耕助が静養に訪れた浜辺で起こった寸劇。新婚夫婦の、夫には知人の女が、妻には知人の男がそれぞれ偶然に(?)出会い、白い服を着た別の男は妻の知人らしい男をにらみつけていた…。その夜、夫婦はケンカし、夫には何者かから手紙が届き驚愕する。翌日には、新妻の遺体が発見された。ーーー この中で特に面白いと思ったのは、「泥の中の女」でしょうか。最初はキツネにつままれたような雰囲気の事件ですが、サスペンスの要素もあり、良かったです。「棺の中の女」も、凝っていて良かったです。 全11話の「女シリーズ」、まとまった時期に書かれていたということもあり、シリーズとしてのまとまりもあると同時に、バリエーションも豊かになっています。あまりインパクトのある作品はありませんが、楽しく読めるシリーズでした。(2008/11/14読了)
2008.11.18
コメント(0)
-
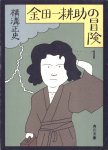
横溝正史『金田一耕助の冒険1』
横溝正史『金田一耕助の冒険1』~角川文庫、1983年12版(1979年初版)~ 角川文庫『金田一耕助の冒険』(1976年初版)を2分冊にした第一巻。映画「金田一耕助の冒険」封切りを目前に控え、2分冊にしたのだそうです(映画のタイトルは先日読んだ『横溝正史読本』で確認したのですが、こんなタイトルの映画もあったのですね)。本巻には6編の短編が収録されています。 なお、『金田一耕助の冒険』は、横溝正史さんの角川文庫表紙画でおなじみ、杉本一文による表紙なのですが、ちょっと金田一さんがリアルすぎて…。その点、分冊版の方は和田誠さんの絵で、かわいらしい感じになっています。 というんで、今回は分冊の方で読みました。電車の友にも、厚さがちょうど良いので…。 前置きが長くなりましたが、まずはそれぞれについて簡単な内容紹介を書いて感想を。ーーー「霧の中の女」霧の深い夜、宝石店に現れた一人の女。アクセサリを盗んだ女を店員は追うが、殺されてしまう…。後日、また別の男が殺害される。現場には、宝石店の事件で盗まれていたアクセサリが盗まれていた。そして奇妙なことに、被害者の衣服が持ち去られていた…。「洞の中の女」しばらく空き家だった家に住み始めた作家夫婦。その庭にある一本の木の洞を塗り込めたセメントから、女の髪がのぞいていた…。「鏡の中の女」金田一耕助が信頼をおく、読唇術のできる先生と金田一耕助がカフェで話をしているとき、先生はふいに鏡の中の女の唇を読んで言葉をメモしはじめた。まるで殺人の計画を練っているような言葉に不安がよぎるが、その後、その話の通りに殺人事件が起こった。ところが被害者は、殺人計画を練っていたはずの女だった…。「傘の中の女」目立つビーチパラソルの中から聞こえてくる男女の甘い声を、近くに陣取っていた金田一耕助は聴くはめになってしまった。やがて泳ぎに出た男が帰ってくると、砂に埋もれて待っていたはずの女は殺されていた…。そして金田一耕助は、その犯人を目撃していたのかもしれないのだった。「瞳の中の女」事件に巻き込まれて、記憶を失った一人の男。男にはしかし、瞳にやきついた女の顔があった…。入院中に火事を経験したことをきっかけに記憶を取り戻した男は、事件の起こった場所に何かを探しに行く。「檻の中の女」川を流れてきた一艘のボートには、犬の檻が乗っており、その中には女が縛られて閉じこめられていた…。そして、大きな汚職と関係していたこの事件の関係者は、失踪を遂げていた。ーーー 最近はなかなか読了後すぐに感想を書けなくなっているので、どんどん記憶が薄れていきます…。 さて、『金田一耕助の冒険』のタイトルで収録された全11の短編(本書は分冊なので前半の6編のみ)は、すべて「~の中の女」というタイトルで統一されています。なので別名「女シリーズ」ですね。 金田一さんが緑ヶ丘荘に引っ越してきて間もない頃の事件だそうです。そしてこのシリーズのラストでは、シリーズの記録者に金田一さんが事件について語るというスタイルをとっています。 本書の中でいちばん面白かったのは、「瞳の中の女」です。金田一耕助シリーズとしては異例の結末ですが、本書の主人公は金田一さんというよりも、記憶を失っていた男だと思います。記憶を失った彼のひとみに焼き付いている謎の女…。「瞳の中の女」とはそういう意味かと納得すると同時に、なんとかっこいいタイトルかとも思います。 第二巻も読了したので、また記事を書いてアップします。*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。(2008/11/12読了)
2008.11.15
コメント(2)
-
ブログ開設4周年
早いもので、ブログを開設して、4年が経ちました。 あらためて、ご訪問くださっている方々へ、感謝いたします。みなさまからのコメントやTBが、本当に励みになっています。ありがとうございます。 さて、先日、就職の試験に無事合格しました。来年度からは正規雇用のかたちでがんばっていくことになります。 その合格記念に、西洋史関連の本をいろいろ注文しました。高いのもあるので、こういう記念にかこつけてじゃないと、なかなか買えないですね…。とまれ、届くのが楽しみです。 今月から、岩波書店さんの「シリーズ ヨーロッパの中世」全8巻の刊行が始まりますし、来月にはミシェル・パストゥロー『黒の歴史』(未邦訳)の英訳が出るので、楽しみがどんどん増えますね。 これからも、無理せずぼちぼち続けていこうと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。
2008.11.14
コメント(8)
-

浦賀和宏『生まれ来る子供たちのために』
浦賀和宏『生まれ来る子供たちのために』~講談社ノベルス、2008年~ 松浦純菜&八木剛士シリーズ最終刊です。 …ほとんど感想は書けないですね。最後に、ああ、と思いました。そこから全てがはじまって、こんなことになってしまったのか、と。 全9巻。第1作『松浦純菜の静かな世界』、第2作『火事と密室と、雨男の物語』では、わりあい普通の(?)ミステリとして読んできましたが、第3作あたりから方向がどんどんミステリから離れていき、やがて八木剛士の復讐物語になり、崩壊へ…。 なんともいえないシリーズでした。 安藤直樹シリーズは『透明人間』以来ストップしていますが、また再開するのでしょうか。(2008/11/08読了)
2008.11.11
コメント(2)
-

ジョルジュ・デュビィ『三身分―封建性の想像界―』
George Duby (Trans. by Arthur Goldhammer)The Three Orders. Feudal Society ImaginedThe University of Chicago Press, 1982 (Paperback edition)(Les trois ordres ou l'imaginaire du feodalisme, 1978, Gallimard) ジョルジュ・デュビィ(Georges Duby, 1919-1996)はコレージュ・ド・フランス教授、アカデミー・フランセーズの会員でした。邦訳書も多く刊行されています。私が所有している本の中から二冊、例を挙げます。ジョルジュ・デュビー(篠田勝英訳)『中世の結婚―騎士・女性・司祭―』新評論、1984年デュビィ(池田健二/杉崎泰一郎訳)『ヨーロッパの中世 芸術と社会』藤原書店、1995年 今回紹介する『三身分』は、祈る者、戦う者、働く者という三機能論が、中世においてどのような意味をもち、どのように各々の言葉の含む意味が変遷したのか、ということを論じた、身分論研究の上では重要な一冊です。 私は英訳で読み、しかも電車の友にしたので辞書も引かず流し読みの部分も多くあり、十分な整理はできていませんが、とにもかくにも通読することができました。(なお、副題の訳は仏語原著のタイトルを優先し、松村剛さんがジョルジュ・デュビー『歴史は続く』であてておられる訳を参考にしました) 構成は以下の通りです。ーーー前書き(Thomas N. Bisson)謝辞研究の領域第1部 啓示 1.最初の定式化 2.ジェラール・ド・カンブレと平和 3.ランのアダルベロンと王の使命 4.体系第2部 創始 5.階層 6.一致 7.諸身分(諸秩序) 8.諸機能―祈ることと戦うこと 9.三元法ternarity 10.天の模範第3部 状況 11.政治的危機 12.競合体系 13.封建革命第4部 失墜 14.修道士の時代 15.フルーリ 16.クリュニー 17.新しい時代 18.修道主義の最後の栄光 19.学校にて 20.君主への奉仕のなかで第5部 復活 21.真の出発 22.騎士道 23.パリでの抵抗 24.封建主義の矛盾 25.採用エピローグ略号一覧註索引ーーー 先日紹介したフランドロワ編『「アナール」とは何か』の中では、多くの研究者がデュビィを名文家・美文家と評しています。本書の構成を見ても(日本語訳が不適切な部分もあるかもしれませんが)、がちがちの研究書というよりも、どこか物語の目次のような雰囲気があります。 さて、本書には二人の主人公がいます。第2章と第3章で詳述される、カンブレ司教ジェラールと、ラン司教アダルベロンです。二人が、祈る者、戦う者、働く者という三身分論を定式化した最初期の人物だからです(11世紀初頭)。以後、本書では、他の人物による定式化や言葉の意味を見るときも、たいていこの二人の意見が参考として示されることになります。 なにしろ整理が不十分なのでいろいろ書くのもためらわれますが、漠然と整理をしておきます。 社会の人々を三区分するその分け方には、次のようにいくつかがあります。・祈る者/戦う者/働く者・聖職者/修道士/俗人・処女/寡婦/既婚者 聖職者と修道士は、「祈る者」の中に含まれて考えられたり、別個に考えられたりします。 そして、時代背景と著作家自身の境遇から、それらの中のどこに重点が置かれるかが異なってきます。ジェラールとアダルベロンの頃は聖職者の重要性を説きます(なお、この頃は王の権威も強調しますが、しかし聖職者はその助言者として位置づけられることになります)。 修道士たちの中には、修道士を司教などの在俗聖職者よりも上に位置づける人物がいます。 本書の第5部―特に21章、22章あたりでは、戦う者として、王よりも騎士たちの存在が強調する思想が紹介されます。 私が個人的に興味深かったのは、24章で取り上げられるthe White Capeです。以前読んでいたアシル・リュシェール『フランス中世の社会』(まだ通読していないので、記事は書いていません)のなかで、「白頭巾講」というのが紹介されていました。手元にあるその他の概説書をざーっと見る限り、この運動はふれられていないので、ずっと気になっていたのですが、今回出てきたthe White Capeがまさにそのことなのかと、すっきりした気分になりました。しかし『フランス中世の社会』は訳語が独特なので、「白頭巾講」以外になにか訳語がないのか、気になるところです…。 本書自体の読み込みは不十分ですが、その他、関連する文献を挙げておきます。 ジョルジュ・デュメジル(松村一男訳)『神々の構造―印欧語族三区分イデオロギー』は、タイトルのとおり、祈る者/戦う者/働く者という三区分が、印欧語族特有の思想だということを論じます。インドの『ヴェーダ』からはじまり、ギリシャ・ローマの神話などなどを分析、その他の文化圏にはこの三区分は見られないということも強調します。(こちらは通読しているのですが、記事を書きそびれています…) もう一つ、Giles Constable, Three Studies in Mediecal Religious and Social Thought (ジル・コンスタブル『中世の宗教的・社会的思想に関する三つの研究』)の第三部「社会の諸身分」は、中世に見られる多様な身分の三区分法や身分観を、通史的に整理しています。デュビィの文章は(今回は英訳ですが、邦訳を読んでいても)私にはなんとなく読みにくくて苦手なのですが、コンスタブルの文章はすっきりしていて読みやすいように思います。こちらも、第一部「マリアとマルタの解釈」、第二部「キリストの模倣という理想」は未読なので、本の紹介は(できるとしても)相当先になると思います。(2008/11/08読了)
2008.11.10
コメント(0)
-

横溝正史(小林信彦編)『横溝正史読本』
横溝正史(小林信彦編)『横溝正史読本』~角川文庫、2008年改版初版~ きわめて入手困難となっていた(そうな)文庫の復刊です。不意の嬉しいニュースでした。 なお、本書の背表紙の著者名のところには小林信彦編とありますが、番号は(よ5-200)となっているので、この記事の著者名には横溝正史さんの名前も掲げておきました。 本書の構成は次のとおりです。ーーー序にかえて(横溝正史)横溝正史の秘密(横溝正史/小林信彦) 第一部 「新青年」編集長時代から喀血まで 第二部 自作を語る 第三部 同時代作家の回想 第四部 クリスティーの死と英米の作家たち資料1 探偵茶話<エッセイ>資料2 作品評 『本陣殺人事件』を評す(江戸川乱歩) 『蝶々殺人事件』について(「推理小説論」)(坂口安吾) 『獄門島』について(高木彬光)年譜(島崎博/浜田和明)あとがきにかえて(小林信彦)解説(権田萬治)ーーー 順番に、簡単にコメントをしていきます。「横溝正史の世界」は、横溝さんと小林さんの対談です。横溝さんの奥様も参加しておられて、ほのぼのしながら読みました。 この中で特に興味深かったのは、第三部と第四部です。第三部では、森下雨森さんから鮎川哲也さんまで、横溝さんが活躍した前後の作家たちについて語られます。読んだことがない作家さんも多いのですが、詳しい方がこのあたりを読むとより興味深く読めるのでは、と思います。私は、ここで紹介されている作家さんたちにあらためて興味をもちました(なかなか試せないと思いますが…)。 第四部は、ちょうどアガサ・クリスティーが亡くなられた翌日に行われた対談ということで、クリスティーに関する話題が多いです。私はクリスティーは1冊も読んだことがないのですが、横溝さんは彼女の作風に近いそうですね。また、クリスティーが高齢になっても長編を書き続けていたことにならって、横溝さんも闘志を燃やしておられるところなど、他のエッセイでも読んだことがありましたが、あらためて横溝さんが素敵だなぁと思いました。 そして、『Xの悲劇』などを書いたバーナビー・ロスが、実はエラリー・クイーンだったということ。いまはもう悲劇三部作も『…最後の事件』もエラリー・クイーン名義で書店にならんでいたかどうか、とにかく二人が同一人物ということは有名(というか、ロスの名前もほとんど覚えていませんでした)ですが、覆面作家としてロスが出てきて、実はクイーンと同一人物だと知ったときは驚きだったでしょう。こう考えると、先入観や予備知識なしで新しくなにかを知ることがどれだけわくわくすることかということがよく分かります。 ふっと思ったのですが、たとえば『我が輩は猫である』なんか、教科書で読むのではなくていろんな小説を読んでからはじめてふれると、なんと猫の一人称かと、かなり衝撃的なのではないか、と考えたり…。先人の偉業が当たり前のようになってくるのは、どこか寂しいような気もした次第です(このニュアンスがうまく伝わりますかどうか…)。 話は前後しますが、もちろん第一部・第二部も面白いです。『獄門島』の犯人について、奥様の一言が大きな役割を果たしたエピソードなど、こちらもどこかで読んだか聞いたかした覚えがありましたが、奥様もまじえての対談ということで、あらためて楽しく読みました。 さて、これらの対談は1975年、1976年に行われていますが、資料1として紹介されるエッセイは、1947年に執筆されています。 こちらのエッセイもとても面白いです。探偵小説の内容から離れますが、最初の「困ったこと」というエッセイのなかでものすごくプラス思考をされているのが楽しかったです。がんばって畑仕事をしたのに失敗したということで、三度豆の種が土の中で腐ってしまったり、ということが書かれています。でもこんなことも健康なら違ったように考えられるのではないか、ということで、たとえば、「三度豆が半分腐ったおかげで、忘れていたささげの播き場所が出来て却って好都合であった」(200頁)とあります。横溝さんのユーモアあふれる人柄が伝わってきて素敵でした。私も最近、たとえばはじめて出かける場所に向かう途中で道に迷ったり、あるいは日常の中で起こりそうな残念なことを予想しては、そんなことがあっても広い心でいようと考えたり、なにかあってもプラス思考にもっていこうとするようになってきているので、このエッセイはとても参考にもなりました。 それから、クリスティーの名作が『みんないなくなったとさ』というタイトルで書かれているのですが、昔はこんな邦題で出ていたのか、横溝さんの試訳か…。なんだか良かったです。 対談の方でも書かれていますが、横溝さんは戦前・戦時中と、ばりばり外国の探偵小説を原著で読んでおられます。あこがれます。 資料2の作品評は、私が大好きな『本陣殺人事件』を坂口安吾さんがぼろくそに言っていたり、江戸川さんもその良さを認めながらいろいろ難点を挙げたりと、ちょっと悔しく思いながら読みました。論理的に書いているようで、結局は好みですから、この手の批評は難しいなぁと思った次第です。私もブログで好き勝手書いていますが…(良いところを紹介するように心がけてはいます)。 なお、本書の中では、エラリー・クイーンやクリスティーのいくつかの作品について、割と重要なネタが割られてしまっています。私は数年(数ヶ月!?)で忘れられるでしょうし、すぐに海外の古典ミステリを読む予定もないので大丈夫(?)ですが、いままさに海外の古典ミステリをばりばり読んでいこうとされている方は、ご注意ください。 冒頭にも書きましたとおり、本書はきわめて入手困難な状態にありました(ようです)が、このたび改版ということで、年譜が2008年の記事まで補足されていて、こちらも興味深いと思います(しっかりとは見ていないですが…)。 横溝さんの対談を読むことができて、幸せな読書体験でした。(2008/11/06読了)
2008.11.09
コメント(2)
-
本購入~浦賀和宏、島田荘司、高田崇史、坂木司
今日は一つ作業にきりをつけたので、講談社ノベルスなどの新刊を買いに出かけました。というんで、新刊は次の三冊を購入。浦賀和宏『生まれ来る子供たちのために』高田崇史『カンナ 飛鳥の光臨』(以上2冊、講談社ノベルス)島田荘司『Classical Fantasy Within 第五話 アル・ヴァジャイヴ戦記 ヒュッレム姫の救出』(講談社BOX)浦賀さんのは、ついに松浦純菜シリーズ最終作です。どうなるのか…。今夜は読みふけりたいと思います。高田さんのは新シリーズ始動ですね。こちらはしばらく先になるかもしれません。島田さんのも、第二部が完結したら第四話から一気に通して読みたいと思います。そして、古本屋で次の一冊を購入。坂木司『先生と僕』こちらも楽しみです。
2008.11.08
コメント(2)
-

杉崎泰一郎『欧州百鬼夜行抄』
杉崎泰一郎『欧州百鬼夜行抄―「幻想」と「理性」のはざまの中世ヨーロッパ』~原書房、2002年~ 杉崎先生は中央大学文学部教授で、主に中世における修道院の研究を進めておられます。私が所有しているもう一つの著作は、杉崎泰一郎『12世紀の修道院と社会』原書房、1999年 記事も書いていますが、また再読して書き直したいですね…。 さて、本書の構成は次のとおりです。ーーーはじめに第一章 怪人たち 1 異境の怪人たち 2 土着の民間信仰―巨人と小人 3 社会の周縁に住む者―野人、狼人 4 教会と怪人たち第二章 怪獣たち 1 教会に刻まれたもの 2 文書に書かれたもの 3 自然物や自然現象第三章 ドラゴンと蛇 1 動物神話の中のドラゴン(龍)と蛇 2 聖人とドラゴン 3 蛇女の伝説 4 神話、英雄伝説第四章 幽霊たち 1 キリスト教布教の時代 2 中世の死者祈祷と幽霊 3 幽霊を科学する―ゴシックの時代 4 幽霊の土俗化―中世末期 5 幽霊の姿形おわりにーーー 本書も数年ぶりの再読ですが、この手のテーマを読むのもずいぶん懐かしいように思います。枕元の友にして、寝る前に少しずつ読み進めました。 なお、第四章に関して、杉崎先生は次の論文を発表しています。杉崎泰一郎「中世修道院の亡霊譚-死者が語る生者への教訓-」『西洋史学』183、1996年、19-34頁 全体がですます体で書かれていて読みやすく、構成からもうかがえるとおり、読み物としてとても面白いです。ただそれだけでなくて、もちろん研究文献や一次史料が下敷きになっていて、深みもあります。普段は意識していませんでしたが、そういえばそうかと思った指摘を引いておきます。「また教会も民衆の慣習を弾圧する一方であったとは考えられません。中世の聖職者や修道士は妻帯しませんので、みな俗世で生まれ育ってから出家するわけですから、巷の価値観に無縁ではなかったはずです」(230頁) もう一点、怪物について興味深かった指摘を挙げておきます。それは、中世にはじめて登場する怪物の中には、写字生が字を写し間違えたり、間違えて翻訳したりしたことによって、普通の動物が怪物として書かれてしまった可能性があるという、ある研究者の指摘です。なかなか怪物の研究までは手がまわりませんが、こういう話を読むと興味深いですね。 どの章も面白いのですが、特に興味深く読んだのは第三章です。その冒頭で、日本、中国、その他の文化圏の蛇に関する神話・伝承にふれているのですが、読みながらミシェル・パストゥロー氏による牛の象徴史に関する論考の冒頭を思い出しました。どの研究にもいえると思いますが、こうした比較研究―とまではいわなくても、中心に論じる地域とは異なる文化圏に目を配るのは重要ですね。 また、その他の章についても、日本(史)との比較をする記述があり、興味深いです。 次の枕元の友は、兼岩正夫『西洋中世の歴史家』にしようと思っていたのですが、これはノートをとりながら読むべきと考えたので、ジャン=クロード・シュミット『中世の迷信』を枕元の友にして久々に再読したいと思います。(2008/11/02読了)*訂正とお詫び本書のメインタイトルは『欧州百鬼夜行抄』です。最初に記事をアップした際には、「抄」の字を書き忘れていました。タイトルを間違えるなんて…。帰宅後気付いてすぐに訂正しました。失礼いたしました。
2008.11.06
コメント(4)
-

辻村深月『ロードムービー』
辻村深月『ロードムービー』~講談社、2008年~ 辻村深月さんの初の短編集です。デビュー作『冷たい校舎の時は止まる』のサイドストーリー集。 まずは、それぞれの内容紹介を簡単にしてから、感想を書きたいと思います。ーーー「ロードムービー」クラスで人気のあったトシは、いじめられていたワタルに好感を抱き、親しくなった。それから、いじめの標的はトシに移ってしまう。二学期にはいじめの中心的立場であるアカリが学級委員となり、トシは低学年の頃からの夢だった児童会長への思いもくじけそうになってしまう。 * 6年に進級する前の春休み。トシはワタルとともに、家出を決行する。「道の先」塾の講師のアルバイトをしている俺は、一人の中学生に好意を寄せられる。気に入らない講師を次々と辞めさせたという、大宮千晶である。なにかを抱えて苦しんでいる彼女に、俺は自分自身も救われた言葉をかける。「雪の降る道」親友が死んでから、ずっと熱を出して寝込んでいるヒロのところに、みーちゃんはいつもおみやげを持ってきてくれる。ヒロがいじわるを言って泣いてしまっても、彼女は翌日にはきっとおみやげを持ってきてくれた。しかしある日、ヒロがひどい言葉を言ってしまい、みーちゃんがいなくなってしまう。ヒロは必死に、死んでしまった親友に助けを求めながら、みーちゃんを探しに行く。ーーー 苦しくもあり、温かい救いのある物語たち。『冷たい校舎の時は止まる』以来ずっと読んできていますが、辻村さんの作品は素敵だと思います。『冷たい校舎の…』の内容を忘れてもいるので、本書の背景も分からない部分はありましたが、もちろんデビュー作を読んでいなくても楽しめると思います。「ロードムービー」の演説シーンはとても素敵でした。「道の先」は、素敵な言葉に出会えて良かったです。そして「雪の降る道」は、本書の中ではいちばん泣いたように思います。 なお、本書には「辻村深月の本」という小さなリーフレットが挟み込まれています。こちらも素敵でした。なおその中で辻村さんは、『名前探しの放課後』について、第一期の総決算というようなことを書かれています。今回の短編集は、一つの折り返し地点、あるいは新しい出発点といったところでしょうか。また新しい物語に出会えるときを楽しみにしています。(2008/11/02読了)
2008.11.05
コメント(0)
-
新刊購入~小林信彦編『横溝正史読本』
今日は大きな用事が終わったこともあり、帰り道にある本屋さんで次の本を購入しました。小林信彦編『横溝正史読本』既に絶版となっていて、古本でも高額な値段がつけられているそうな角川文庫旧版の、改版です。いままで読んだことのない横溝さんの作品(しかも対談やエッセイ)が読めると思うとそれだけで涙腺がゆるんでしまいました…。最近は、月末の用事のために電車の友は洋書にしていますが、今日また別の大きな用事も終わったことですし、まずは『横溝正史読本』を電車の友にすることにします。***テーマとは関係のない雑記ですが…。今朝新聞で知ったニュースは残念でした。私はtrf大好きで、その後はglobeも大好きで聞いているものですから…。globeについては、しばらくの活動休止状態の後に出た『globe2 pop/rock』、『maniac』『new deal』というアルバムも大好きで、最近は作業中などに流しているのです。今月来月にはglobeの新しいシングルも出る予定だったのに(カップリングのバージョン違うのを2種類出すというあのテの売り方のようだったですが、なんなら両バージョンとも買おうというくらいの気持ちでした)、残念です…。あの方の女性関係のあり方はあんまりだと思っていましたが、globeは好きですので…。
2008.11.04
コメント(2)
-

筒井康隆『富豪刑事』
筒井康隆『富豪刑事』~新潮文庫、2006年39刷(1984年)~ 大資産家の息子、神部大助刑事が活躍する4編の短編ミステリ集です。筒井さんの楽しい表現もいっぱいあって、面白い1冊です。 いつものようにそれぞれの…とも思うのですが、今回は、それぞれの作品がどんな題材のミステリか(密室など…)だけを書いて、つらつらと感想を書こうと思います。読了から日が経ってしまったので、あまり書けないと思いますが…。「富豪刑事の囮」…時効が迫った5億円強奪事件。「密室の富豪刑事」…密室状況での不審な火災と焼死体。「富豪刑事のスティング」…誘拐事件。「ホテルの富豪刑事」…暴力団対策。 ミステリとしても面白いのですが、筒井さんの作品を読むときに感じる楽しさの方を強く感じながら読みました。迷宮入りという言葉に過敏で、言った人を射殺したいと思う警部さん(かなり印象に残っています)に、事件解決後にとつぜん現れる署長さん。大富豪の息子で刑事の神部大助さんが主人公ですが、そのお父さんは泣き上戸(?)でやたら発作を起こしたり…。楽しいです。 解説にも書かれていることですが、「富豪刑事の囮」では行を空けることもなく(場合によっては改行すらもなく)場面転換があったり、「富豪刑事のスティング」では時系列の提示法に工夫があったりと、実験性も感じました。 たぶん、筒井さんの他の作品を読む前に、ミステリを読む一環として本書を読んでいれば、ミステリとしてとても楽しめたと思うのですが、筒井さんの他の作品も多く読んでいるいまとなっては、筒井さんの多彩な作品の一つとして楽しんだという感が強いです。「ホテルの富豪刑事」では、他の刑事さんたちの活躍譚も面白いけれど、ここでは省略しなければいけないのが残念という記述がたくさんでてきて、それはそれで楽しいですが、他の刑事さんの活躍を想像するのも面白いです。(2008/10/24読了)
2008.11.02
コメント(2)
-
本購入~辻村美月、筒井康隆、横溝正史、岩崎つばさ
今日は8年ぶりくらいにプリンタを買いに行ったのですが(コピーやスキャナまでついていてわくわくしています(笑))、久々の休日ということもあって、本もいろいろと買ってきました。 まず、新刊は次の一冊。辻村深月『ロードムービー』 辻村さん初の短編集ということで、楽しみです。 古本のマンガを1冊。岩崎つばさ『突撃!第二やまぶき寮』 岩崎さんは日立オール電化生活のイメージキャラクター、湯神リリコさんが活躍するマンガ『30GIRL.com』の作者なのですが、『30GIRL…』が好きなので、こちらも試してみることにしました。 そして、古本は次の5冊。筒井康隆『筒井順慶』筒井康隆『旅のラゴス』横溝正史『金田一耕助の冒険1』横溝正史『金田一耕助の冒険2』横溝正史『七つの仮面』 筒井さんのは所有冊数が多くなってきて、買ったもののまだ読んでいない作品もあるものですから、新しく買うときはかぶってしまわないかが心配になってきます…。今回のは大丈夫でした(笑) 12月の電車の友になるでしょうか。 横溝さんのは、どれも同内容のものは持っているのですが、『金田一耕助の冒険』を分冊化した2冊と、「金田一耕助ファイル」に収録された作品の旧版を買いました。どれも解説が気になるのもあり…。横溝さんの作品についてはコレクションという意味合いも強いです。
2008.11.01
コメント(3)
-
「2008年10月の読書記録・小説部門」
今回は、2008年10月に記事を書いた本のリストです。番号は、今年記事を書いた順番で、印象に残った本には☆マークをつけています。83.筒井康隆『アフリカの爆弾』84.横溝正史『刺青された男』85.森博嗣『銀河不動産の超越』86.若竹七海『スクランブル』 ☆87.横溝正史『ペルシャ猫を抱く女』88.筒井康隆『アルファルファ作戦』 ☆~総評~ 9月には6冊の感想を書きました。小説はまとまった時間に読むようになっているのですが、最近はなかなか小説用の時間がとれず…。むしろ少しずつ読み進めた西洋史関連の本の紹介の方ができたように思います。11月も月末にイベントがあり、その準備の本を読んだりしているので、11月もあまり小説は読めないかもしれません…。 とまれ、この中では、『スクランブル』と『アルファルファ作戦』に☆マークをつけました。 若竹七海さんの『スクランブル』は、高校が舞台ということもあり、あの頃独特のほろ苦さを感じさせられます。殺人事件の解明も面白いですし、いわゆる「日常の謎」の解決も面白い、充実した一冊です。 筒井康隆さんの『アルファルファ作戦』は、完全に私の好みですが、収録作品の「慶安大変記」と「色眼鏡の狂詩曲」が面白かったので…。「慶安大変記」は登場人物の会話がかなり面白くて大好きな作品です。 トップページに、以下の文章を追加いたしました。なにか良いアドバイスがあればお願いいたします。☆お知らせ☆ ある方のページで知り、迷惑コメント&迷惑TB対策として、禁止ワードに「http://」を追加しました。この設定のため、いつも見に来てくださっている方からTBが届かなかったことがあり、その点はきわめて残念ではあります。けれど、ブログの確認をするたびに不快な迷惑コメント&迷惑TBが届いているのを知り、消していくのがなんとも空しくなるので、あらためて上記の設定にいたしました。 他になにか良い迷惑コメント&迷惑TB対策があれば、ご教示いただければ幸いです。
2008.11.01
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月2日分)
- (2025-11-16 01:19:06)
-
-
-

- 楽天ブックス
- [楽天市場]「カレンダー」 検索結…
- (2025-11-15 21:30:44)
-
-
-

- ジャンプの感想
- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3
- (2025-11-14 13:43:41)
-







