2008年07月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
古本購入~ジャック・ル・ゴフ『歴史と記憶』
今日はのんびりと出かけていたのですが、古書店で、タイトルにも書きました次の本を購入しました。ジャック・ル・ゴフ(立川孝一訳)『歴史と記憶』法政大学出版局、1999年 ル・ゴフによる歴史理論、歴史哲学的な話はほとんど読んだことがないので、興味を持っていました。…が、はたして頭がついていけるかどうか…。 2008年7月現在で、ル・ゴフの邦訳で私が持っていない著作は『絵解きヨーロッパ中世の夢』だけになりました。またいつか買って読みたいですが、しかしこの邦題はなんとかならなかったのかといささか残念です…。 今日買った『歴史と記憶』もそうすぐには読めないと思いますが、読めるときにはじっくり読みたいと思います。
2008.07.27
コメント(4)
-
ミシェル・パストゥロー「アーサー王物語の紋章」
Michel Pastoureau, "L'heraldique arthurienne : Une heraldique normande?" dans Michel Pastoureau, Figures et Couleurs : Etude sur la symbolique et la sensibilite medievales, Paris, 1986, pp. 183-191. 今回は、ミシェル・パストゥローの初期論文集『図柄と色彩―中世の象徴と感性に関する研究』所収の論文「アーサー王物語の紋章―ノルマンディ地方の紋章か?」を読んでみました。 短い論文ですし、記事も簡単にまとめておきます。 アーサー王物語の作者は、登場人物に紋章を割り当てるにあたり、三通りの紋章を使いました。1.他の作品で既に使われている紋章。 これは特に、アーサーやランスロットなど主要な人物に割り当てられ、時代を経ても変わらないという性格があるそうです。2.オリジナルで、象徴的な意味をもつ紋章。 これは突然登場する人物に割り当てられ、彼らの意図・性格や、その後のエピソードを暗示するとか。3.現実の紋章の採用。 これは、物語の中ではほとんど役割を果たさない人物、あるいは一度しか言及されないような人物に割り当てられたといいます。影響力をもった家系へのお世辞の意味もあったかもしれません。 以下、この論文では、物語に現れた紋章と現実の紋章を付き合わせるという調査の結果報告が行われます。結論的にいえば、はっきりしたことを言うのは難しい、ということになります。 物語に現れる紋章と同じ紋章を、いくつもの家系が使っている場合。物語で言及される紋章はしばしば簡略化されてしまっていて、具体的な像が分かりにくいこと。などなど、こうした研究を行う上での難しさが指摘されます。 一方、ノルマンディ地方の紋章に多く見られる特徴(色の組み合わせや図柄)から、アーサー王物語の紋章は、同地方の「影響」を受けている、と指摘します。物語上の紋章と現実の紋章の正確な対応が見いだせないため、現実の「複写」があったとはいえないものの、現実の紋章が模倣された、ということになります。ーーー 私はいまだにアーサー王物語をちゃんと読んだことがないので、なんともぴんとこない話でしたが、物語を読むことがあれば、紋章の側面にも注目することになると思います。 最後に、ミシェル・パストゥローの経歴や主要な著作については、こちらを御覧下さい。(2008/07/26読了)
2008.07.27
コメント(2)
-
島田荘司『嘘でもいいから誘拐事件』
島田荘司『嘘でもいいから誘拐事件』~集英社文庫、1994年~ 『嘘でもいいから殺人事件』に続く、シリーズ第二弾です。今回は、二編の中編が収録されています。それでは、それぞれについて内容紹介と感想を。ーーー「嘘でもいいから誘拐事件」 1981年8月。 「こんばんワン」と鳴く犬を撮りに行こう!また「やらせの三太郎」の変な企画が立ち上がった。舞台は、宮城県鳴子町鬼首。ゴンドラで上がったところにあるペンションにその犬はいるというが、ゴンドラで事件が起こる。ボク―タックと、ターボの次に乗ったはずの、タレントが消えてしまったのだ。心配しながらもペンションで過ごすボクたちの前には、赤い顔の鬼が現れて…!? 鳴子町鬼首、懐かしいです。仙台にいた頃、年に何度か県北に行ったことがあるのですが、その中で行ったことがあります。私が、三太郎さん同様に「鬼首」の地名にテンション上がっていたことはいうまでもありません…。 さて、本作。あんまり深くは言えませんが、ある意味では前作がミスディレクションになり(私が勝手にある思いこみをしただけですが)、私の予想は外れてしまいました。…事件はともかく、今回もかなり笑えました。「嘘でもいいから温泉ツアー」 1987年夏。 三太郎はプロデューサーに昇進したもののまったく変わらず(むしろ、タイアップしまくるという新たな技?も獲得)、ボク―タックはディレクター、ターボはアシスタント・ディレクターとなったものの、結局3人は相変わらずの関係だった。無口なミキシング・エンジニアに、喋りまくりの小朝田サードADと、新たなメンバーも加わって、軽石組が向かうのは五色温泉。温泉の色が急に変わるなど、やっぱり三太郎のやらせはとどまることを知らないが…。 今回の旅も大雨におそわれ、パトカーがスピンして転落する現場に居合わせたり、そして宿では恐ろしい事件が待ち受けていた。 今回もまた、テンション高いです。謎は小振りですが、とにかく勢いがあって楽しくて、どんどん読み進めました。ーーー 前作はミステリとしての謎もなかなかに魅力的でしたが、今回は謎自体は前作ほどでないにしても、その分ユーモアが押し出されているようにも思います。 本作以降このシリーズは出ていませんが、果たしてタックたちはどうしているのでしょうか。(2008/07/23読了)
2008.07.25
コメント(2)
-

清水義範『私は作中の人物である』
清水義範『私は作中の人物である』~講談社文庫、1996年~ 清水義範さんの短編集です。10の作品が収録されています。 では、それぞれについてコメントを。「私は作中の人物である」。良いです。「私は踏みつぶされてぺしゃんこになったミミズです」。なぜ読者の皆様は「私」=「ミミズ」と信じるのですか?というところから始まります。小説の人称の問題は高校生のときにも気にかかっていましたが(その後目をそらせました)、面白い問題ですよね。「魚の名前」方言では、普段使っている言葉が別の言葉で使われることがあるよね、という話。この物語は、なんだか不安な気持ちにさせられました…。ちなみに、岡山弁で「えらい」には、「しんどい」という意味がありますが、仙台では通じませんでしたね… (どこまで通じるのでしょう?)。「どえりゃあ婿さ」歴史物です。私は日本史は苦手ですが、こういうのは割と好きです。「全国まずいものマップ」旅先にでて美味しいものを求めるなんて甘い!美味しいものなんてどこででも食べられるのだから、まずいものこそ探すべき!というルポ(フィクション)です。それぞれの小見出しが素敵です。「悪夢に近い旅館の夕食」などなど…。笑えます。「重箱の隅」日本でどれだけの人が知っているのか、というマイナーな問題を出すクイズ番組です。今回は、「畦倉商事株式会社鴨居市水田町寮クイズ」です。こういうの大好きです。「保毛田岩の由来」ある地方に伝わる岩についての伝説を、科学的に解明しようという論文(フィクション)です。これも好きです。「文字化けの悦楽」戒律の厳しい宗教の国で、官能小説家が仕事をします。…が、その国で買ったフロッピーのせいか、肝心の作品部分はひどい文字化けで…。これもすごいですね。「とねちり」落語風のむちゃくちゃ話です。繰り返しになりますが、こういうの大好きです。「船が州を上へ行く」ジェイムズ・ジョイス(柳瀬尚紀訳)『フィネガンズ・ウェイク』のパロディ(?)です。その柳瀬さんは、解説でこの作品を「挑戦」と言っておられます。『フィネガンズ・ウェイク』は、図書館でぱらっと見てみて、すごいと思いつつ挫折したのですが、本作もすごいです。「観戦記」これはなんというのでしょう…夫婦が将棋(囲碁?そんな感じのゲーム)で勝負するのですが、一手ごとが、「ガスレンジが油でこてこてじゃないか」みたいな意味をもつのです。その解説が楽しくて、案外わくわくしながら読みました。「全国まずいものマップ」といい、「重箱の隅」といい、よくこんなの思いつくなぁという作品で、楽しいです。ーーー これはほとんどハズレのない、面白い作品集でした。(2008/07/22読了)
2008.07.24
コメント(2)
-
島田荘司『嘘でもいいから殺人事件』
島田荘司『嘘でもいいから殺人事件』~集英社文庫、1987年~ 隈能美堂巧(くまのみどたくみ。通称タック)さんが主人公のユーモア・ミステリです。本書の内容を思い返してみると、音楽を演奏するシーンはともかく、全体的に島田荘司さんらしくない、という印象があります。不可解な謎は、これぞ島田さん!というくらいわくわくするのですが…。それだけ作風が広いということですね。 ではでは、内容紹介と感想を。ーーー 1980年夏。やらせがひどいことで有名なディレクター、軽石三太郎があまりにひどいやらせ番組を流したことから、彼の首はついにとびかかっていた。軽石のもとでサードADとして働くタックは、首をつなぐための企画を考えさせられることになった。そんな中、タックの友人(華族の家柄)の田村が猿島という無人島に幽霊屋敷とも呼ばれる別荘を相続することになったという話を聞く。これだ!ということで、軽石ら一行は、猿島へ向かうことになった。 番組制作の方は、結局はそこでも無茶苦茶なやらせだったが、一行には大きな問題がふりかかる。台風のため、島から出られなくなったのだった。 屋敷には、田村とその婚約者、そして公認会計士の向井がいた。撮影一行は、軽石にタック、タックとバンドを組むターボ、西村カメラマンにビデオ・エンジニアの篠塚。一行は、予定以上に屋敷に泊まらせてもらうことになる。 屋敷には、戦時中の申年に、密室状況から男が消えたという話が伝わっているという。そして、申年の人間に対する殺人予告ともいえる紙が現れ、彼らを驚かせることになる。その予告の実現か、西村エンジニアが密室状況の中消えてしまう。 なんとか伝わった電話でやってきた警察関係者は、どうも頼りない人間ばかり。そんな中、向井氏の部屋で、首を切断された西村カメラマンの死体が発見されたのだった。ーーー 軽石三太郎の言動に腹が立って腹が立って、こてこての憎まれキャラです。先に記事を書いた筒井康隆さんの「乱調人間大研究」(『暗黒世界のオデッセイ』所収)でいえば、その第二章の典型といったところでしょうか。 一方、警察関係者の三人もとても面白かったです。やっぱり、中でも毒島さんでしょう。彼の悲惨な過去と残念な服装もすごいですが、女性嫌いの彼を女性たちがよってたかってからかうのがすごかったです。…いやはや…。 軽石の下で働くタックとターボの苦労もなかなか壮絶ですが、タックが彼に逆らえないのには若干自業自得の面も…?それにしても、ブタに金粉塗ったり、猛暑の中ゴリラの着ぐるみで走り回ったりと、ドタバタぶりはとても楽しいです。 …と、事件とは関係ないところで大盛り上がりの本書ですが、事件の謎も魅力的です。そして解決編も。 上にも書きましたが、島田荘司さんの幅広い作風の一つにふれられる、楽しい一編でした。*なお、隈能美堂巧さんは、御手洗潔シリーズの短編「疾走する死者」(『御手洗潔の挨拶』所収)(2008/07/21読了)
2008.07.23
コメント(4)
-
筒井康隆『暗黒世界のオデッセイ』
筒井康隆『暗黒世界のオデッセイ』~新潮文庫、1982年~ 解説の文章を引用すると、「本書は、小説家としての筒井さんの作品集ではなくて、漫画家、エッセイストとしての筒井さんの作品集」です。簡単な構成は以下の通りです。ーーー「二〇〇一年暗黒世界のオデッセイ」「レオナルド・ダ・ヴィンチの半狂乱の生涯」「星新一論」「筒井康隆全漫画」 …17編の漫画を収録「乱調人間大研究」 第一章 正気と狂気の間 第二章 天上天下唯我独尊 第三章 アンコール万歳 第四章 デマ・デマ・デマ 第五章 ヒストリー大行進 第六章 もうひとりのあなた 第七章 気ちがいと紙一重 第八章 乱調傾向分類表ーーー 章立てまで書きましたが、「乱調人間大研究」がすごく良かったです。…が、まずは順番に、簡単にコメントを。「二〇〇一年暗黒世界のオデッセイ」は、昭和49年(1974年)時点での未来予想…それも暗黒の未来予想です。幸い、2001年段階ではこの作品ほどの世界になっていませんが、「分娩地獄」の話はどきっとします。もっとも、この作品上では、人口爆発のせいで、産科が足りなくなっているという想定ではありますが…。「筒井康隆全漫画」…絵がむつごいですが、面白かったです。短編を漫画化した作品もオリジナルの作品もあります。 原作を読んだことがある作品では、「傷ついたのは誰の心」(『笑うな』所収)、「客」(『笑うな』所収)あたりが良かったです。「客」は、『笑うな』の記事では感想を書きませんでしたが、あらためて読むと深いですね…。オリジナルでは、「カンニバリズム・フェスティバル」が、かなりブラックユーモアで面白かったです。「冠婚葬祭(葬儀編)」はブラックがすぎていますね。…くすっとなりましたけれど。 さて、先にも書きましたように、「乱調人間大研究」が良かったです。 第一章は、自殺志願の症例を専門書などから多く引用しています。 第二章は、(行きすぎた)権力志向について。面白いところをいくつか引用しておきます。「当然のことだが、権力欲の非常に強い人間は、人に使われたり指示されたりすることを非常に嫌う。どの職場にも、ひとりやふたり必ずいるが、仕事ができないくせにやたらに反抗的なやつがそれである。仕事がうまくできない劣等感の補償として威張り、反抗するわけである」(223頁)「下に対して威張り散らす人間ほど、上からの圧力に弱く、自分以上の権力にはぺこぺこするという定説もある。[…]特に会社などのように、階級がはっきり定められているところでは、こういう人間は相手が自分の上役か下役かで驚くべき態度の急変を見せるから面白い」(227-228頁) このあたりは、島田荘司さんが書いているいくつかの文章を連想しながら読みました。 第三章は、アルコール依存について。個人的にはお酒が嫌いなので、無理強いする人間は嫌悪しているのですが、しかしここでも指摘されているように、「日本では特に、酔っぱらいの狂態を黙認して咎めない習慣があり、それに甘えている酒飲みも多い。だからたまに批判されると、心外だから怒るわけだ」(233-234頁)。さらに、筒井さんはこう続けます。「どうやらアルコールに関して日本は、正気の人間よりも乱調度の高い人間の法が住みやすい国らしい」。 個人的にはタバコは吸いません。吸う人が他人に迷惑かけずに吸う分には構いませんが、ぽいぽい捨てられているタバコを見ると、この人たちが職場や家庭でどんな方なのか知らないけれど、残念な人間なんだなぁと思っています。そんな昨今、タバコを1000円にしてみようという意見も出てきていて(禁煙者の私は賛成ですが)、とかく喫煙者には厳しい世の中になっています。 …が、どうも飲酒の方は規制されていないような…?(私の無知ならすみません)。第二章とも関連しますが、えてして自分の下役に偉そうな人が下役にお酒を無理強いするのではないかと想像するのですが、部下はなかなか上司には反論しづらく、苦しむ、ということになるでしょう。酩酊による暴力事件や器物損壊事件などもあるでしょう。といって、タバコのように酒税もどかっと上げて、醜悪な酔っぱらいを減らそう、という風にはあまり動かないように思います。 なおお酒にしても、自分の好みでたしなむ分にはまったく良いとは思っています。友人たちと楽しく飲む、素敵なことです。タバコにも通じますが、一部の残念な人間のせいで全てを否定する、というわけにもいきません。が、どうも腑に落ちない部分もありますね…。 第四章の、デマが広まっていく過程や言い間違いについての話も面白かったです。 ちょっと飛ばしまして、第七章では天才についての話です。歴史的に天才と認められる人たちには、みな異常なところがある、という話。いろんな天才たち(ドストエフスキー、ニーチェ、モーパッサンなどなど)のいろんなエピソードが紹介されます。同時に、現代は、こういう天才は生まれにくい(認められない)という指摘もあり、興味深かったです。 ただ、こちらのエッセイ(?)は、いろんな研究者の名前を挙げながら事例を紹介してくれていますが、そうした参考文献も掲載してもらっていると良かったのかな、と思いました。「二〇〇一年暗黒世界のオデッセイ」では、参考文献が紹介されているのですが。 この中で、「乱調人間」は、「一般社会に棲息している「少しおかしい」人間」という意味で使われています。が、どの章も、自分(あるいは、多かれ少なかれ誰にでも)にあてはまる部分がありそうです。 とまれ、興味深い一冊でした。(2008/07/21読了)
2008.07.22
コメント(2)
-

ジャン・クロード・シュミット『中世歴史人類学試論』
ジャン・クロード・シュミット(渡邊昌美訳)『中世歴史人類学試論―身体・祭儀・夢幻・時間―』(Jean-Claude Schmitt, Le Corps, les Rites, les Reves, le Temps. Essais d'anthropologie medievale, Paris, Editions Gallimard, 2001)~刀水書房、2008年~ ジャン=クロード・シュミットの邦訳書としては、三冊目になります。本書以前には、次の2冊があります。(松村剛訳)『中世の身ぶり』みすず書房、1996年(松村剛訳)『中世の迷信』白水社、1998年 また、訳者の渡邊昌美先生はカタリ派研究の大御所です(『異端カタリ派の研究』は、私は未読なのですが…)。私が所有し、読んでいる渡邊先生の本は、次の3冊です(邦訳書含む)。フェルナン・ニール(渡邊昌美訳)『異端カタリ派』白水社文庫クセジュ、1979年渡邊昌美『中世の奇蹟と幻想』岩波新書、1989年→読みやすい、面白い、オススメの一冊です。エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ(井上幸治/渡邊昌美/波木居純一訳)『モンタイユー ピレネーの村1294-1324』(上・下)刀水書房、1990-1991年→こちらも面白いです。 さて、本書の構成は以下の通りです。ーーー まえがき第一部 信仰と祭儀 第一章 中世宗教史は成立可能か 第二章 聖の観念と中世キリスト教への適用 第三章 西欧中世における神話の問題 第四章 中世の信仰 第五章 信経の良き効用第二部 民俗伝統と知的文化 第六章 中世文化における民俗伝統 第七章 「若衆」と木馬の舞踏 第八章 取り込まれた言葉(採用と変形) 第九章 仮面、悪魔、死者第三部 主体とその夢 第十章 「個人の発見」は歴史のフィクションか? 第十一章 ギベール・ド・ノジャンの夢 第十二章 夢の主体第四部 身体と時間 第十三章 病む体、憑かれた体 第十四章 キリスト教における身体 第十五章 十二世紀における時間、民俗、政治 第十六章 待望から彷徨へ 第十七章 未来の観念訳者あとがき原注人名索引ーーー 最初に、訳書としてちょっと残念だったところを指摘した後に、内容についてのコメントを。・表記の不統一…レヴィ・ストラウス、レヴィ・ストロース・表記ミス?…ジャン・デリュモー(106頁)→ジャン・ドリュモーが一般的・注について(1)…2章注16に、「本書第3章…pp.54-77を参照」とありますが、訳書では第3章は40-58頁です。見れば分かるから良いのですが、せっかくなのだから訳書の該当ページも書いてあった方が良いと思いました。・注について(2)…研究者名が、カタカナ表記してあったり、原綴のままだったり(書誌情報とは別の部分で)、統一してあればより良いように思います。それにしても外国人研究者名をカタカナ表記するのは難しいですね…。・注について(3)…邦訳のある文献もけっこう引かれているので、邦訳書の該当ページまでとはいいませんが、邦訳書のタイトルも示してもらっていればなぁ、と思いました。こちらはないものねだりですが…。 なお、ジャック・ル・ゴフ(加納修訳)『もうひとつの中世のために』は、注に引かれた文献の邦訳書の情報もしっかり書いてくれていて、とても親切な一冊です。 では、内容の方の紹介を(まとまりはない文章になりますが…) 第一章だけは原書で読んでいたのですが、よく分かっていませんでした。「迷信」「宗教」など、中世と現在で概念が違っている言葉はかっこをつけて表記しよう、という部分は印象に残っていたのですが…邦訳でも、やっぱりよく分かりませんでした。本書の中には抽象的・観念的な話が多く、なかなか難しかったです。 そんな中、第四章、第六~九章(=第二部)、第十三章あたりは話も具体的で、興味深く読みました。 第四章では、私が数年研究したジャック・ド・ヴィトリの説教史料も多く引用されていて、興味深かったです。 これは本書とは話がずれますが、ジャックの『俗人向け説教集』は、聴衆の社会的身分に応じた説教集なのですが、全体の校訂版が出版されていないので、読める部分は限られているのが現状です。Jean Longereがその全体の校訂版を準備しているとのことですが(1)、果たして出版はいつになるのでしょう…。 第七章は、若者の「木馬の舞踏」を扱った例話を手掛かりに、その民俗的性格と、聖職者がそれをどのように例話として使ったのかを分析しています。 第八章も同じく、悪魔としての猫が登場する例話を手掛かりに、猫の性格や、その例話と関連する一連の話の中で、内容がどのように変わってきているかと分析します。なお、ラテン語で猫はmurilegus[ハツカネズミを狩るもの](2)と言われていましたが、13世紀頃から catusと言われるようになります。ジャック・ド・ヴィトリの例話を読んでいると、その両方が書かれていることがあり、はてなと思っていたのですが、本書で、12-13世紀からcatusがmurilegusにとってかわることになり、ジャックの史料はその過渡期を示すとの指摘があり、なるほど!と勉強になりました。 * 本書ではしばしばカロライン・W・バイナムCarolyne Walker Bynumの研究が引用されていて、バイナムの研究も読んでおいた方が良いかとあらためて思いました。あらためて調べていると、かなり著作の多い研究者で、しかもどの著作も面白そうです。邦訳が出ないものでしょうか…。 * 近年(といっても、もう20年ほど前から)ジャン=クロード・シュミットは図像学的な研究にも取り組んでいますが、本書でもそのアプローチが試みられるところがあり、図像も割合載っていて、興味深いです。 なお、図像に関する著作(Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris, 2002)が、本書と同じ刀水書房から邦訳される予定があるそうです(3)。 内容についてのコメントがほとんどないですが、このあたりで。ーーー(1)Carolyn Muessig, "Audience and Preacher : Ad Status Sermon and Social Classification", in idem, Preacher, Sermon, and Audience in the Middle Ages, Brill, 2002, pp. 255-276 (p. 255, n. 4)(2)cf. ロベール・ドロール(桃木暁子訳)『動物の歴史』みすず書房、1998年、378頁。(3)小池寿子「歴史図像学」高山博/池上俊一編『西洋中世学入門』東京大学出版会、2005年、155-179頁(178頁)。なお、この本は、そのタイトル通り、西洋中世史の研究を志す方々の必読書となるでしょう。はじめて書店に並んでいるのを見たときは衝撃が走りました(即座に買いました)。(2008/07/20読了)
2008.07.21
コメント(6)
-

西尾維新『きみとぼくが壊した世界』
きみとぼくが壊した世界西尾維新『きみとぼくが壊した世界』~講談社ノベルス、2008年~ 世界シリーズ第3弾です。 むー、今回の内容紹介とコメントは、文字色を反転させておきます。ネタを割らざるをえない部分があるので、未読の方はご注意ください。ーーー というのも、今回は作中作という形式。第一章を病院坂黒猫が書き、第二章を櫃内様刻が書き…という構造で、いわゆる「メタ」的作品。竹本健治さんの『ウロボロスの偽書』や、比較的最近読んだところでは、舞城王太郎さんの『九十九十九』が連想されます。 読んだら人が死んでしまうという「呪いの小説」を書いた英国の作家から黒猫の親族に相談があり、急遽その代理として作家のもとを訪れることになった黒猫さんが、櫃内さんを誘ってイギリスへ。作家の相談はそれはそれとして、まずは観光を楽しもう…という気持ちではあるものの、事件に巻き込まれたり、作家の周辺に起きていた怪事件を解決していく、というのが大きな流れです。 第一章では、究極の密室ともいうべき飛行機内で、様刻の隣(窓際)の席に座っていた男性が、胸にナイフを刺して死んでいた。 第二章では、作家の妻が湯船に顔だけ入れて死亡していた謎を解く…といった感じです。 それぞれの章ごとにちょっとした短編ミステリとして読めば良いかもしれませんが、読むにつれて謎解きへの関心が薄れていくのもまた事実。一方、解決になかなか斬新な視点が持ち込まれているのが面白くもあり…(その意味で第三章が特に良かったです)。とまれ、二人の主人公の掛け合いも楽しくて、良かったです。 第一章でわくわくしながら読んだものですから、入れ子構造について読む前から知っていたら興ざめと思い、今回は文字色を反転にしたのでした。ーーー(2008/07/19読了)
2008.07.20
コメント(0)
-

浦賀和宏『地球人類最後の事件』
浦賀和宏『地球人類最後の事件』~講談社ノベルス、2008年~ 八木剛士&松浦純菜シリーズ最新作です。同シリーズとしては8冊目になります。 女に罠にはめられ、殺人等の容疑で逮捕されることになった八木剛士。紆余曲折を経て、ついにスナイパーとの戦いにまで話は進みます。そして…。 終盤、最悪の気分を味わわされました。「地球人類最後の事件」というほどの話ではないと思いますが、それでもこれは酷い。読んでいるときはただでさえ吐き気がしていたのに、余計に気分が悪くなるような話でした。 次回がシリーズ最終話とのことですが、いったいどういう方向に行くのか、まったく見当が付きません。(2008/07/14)…楽天の表現検閲の在り方に疑問を感じ始めています。私はニュースに関する記事はまず書きませんが、これではある種の事件についての記事も書けなければ、それこそ歴史関連の記事も書くことができなくなります(高田崇史さんのQEDシリーズの歴史分野に関するコメントなどもできづらいでしょうね)。文脈を無視した単語だけの規制はどうかと思いますが…。フリーページが便利ですし、慣れもあって楽天ブログは使い勝手が良いのですけれど、ときどき考えざるをえなくなりますね…。
2008.07.18
コメント(3)
-

清水義範『永遠のジャック&ベティ』
清水義範『永遠のジャック&ベティ』~講談社文庫、1991年~ 清水義範さんの短編集です。 まずは収録作品を掲げた上で、印象に残った話についてコメントを。ーーー「永遠のジャック&ベティ」「ワープロ爺さん」「冴子」「インパクトの瞬間」「四畳半調理の拘泥」「ナサニエルとフローレッタ」「大江戸花見侍」「栄光の一日」ーーー まず表題作「永遠のジャック&ベティ」はやってくれました。中学校の英語教科書のように喋る二人の男女が主人公です。そう、それはこんな会話。「これはソファですか」「いいえ。これはソファではありません。これは椅子です」 …懐かしいですね。 ところが、このお話で、ジャックとベディは三十数年ぶりに再会したのですが、その間、二人はいろんな人生を経験してきています。それがやたら重くて、上のような会話とのミスマッチがまた面白くもありました。「インパクトの瞬間」もすごいです。本書の中で一番笑ったし、楽しめたように思います。論文調なのですが、内容は意味不明というか、無茶苦茶というか。第二節のジンクピリチオン効果は、ドコサヘキサエン酸なども発揮しているように思い、懐かしくもなりました。第三節の遠赤外線の話もぐっときます。「ナサニエルとフローレッタ」も、ユーモアにあふれていて面白い作品です。こちらは映画の解説をモチーフにした話なのですが、映画の解説や紹介と、映画の筋が、違ってはいないですけれど、その印象がかけ離れているのが面白いです。 時代劇風の「大江戸花見侍」も、パロディもあるのですが、さわやかな感じで良かったです。(2008/07/14読了)
2008.07.17
コメント(1)
-
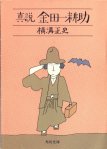
横溝正史『真説 金田一耕助』
横溝正史『真説 金田一耕助』~角川文庫、1979年~ 横溝さんの随筆集です。こちらは、昭和51年(1976年)から翌年まで、毎日新聞で連載されていたそうです。 最近紹介しました『横溝正史自伝的随筆集』よりも、軽快な感じです。和田誠さんによるイラストも素敵です。 映画「犬神家の一族」に出演されたときの思い出から、とつぜんのブームに驚いておられる様子、作品にまつわる思い出など、いろんなエピソードの紹介があって面白いです。そう、金田一シリーズの自選ベスト10なんかにもふれられていますよ。 本書を読んでいて思うのは、横溝さんはとてもサービス精神が旺盛な方だったんだなぁ、ということ。文章からも、ファンへの感謝の気持ちや優しさが伝わってきます。 印象に残って付箋をはったのは、勲章(勲三等瑞宝章)をもらったときのエピソード。芥川龍之介は「勲章を胸にぶらさげて歩く人間の気がしれぬ」という意味の言葉をいったそうですが、その言葉をひきながら、次のように続けます。「ところで私の文庫本を支持してくれる読者の大半は、ヤングといわれる年齢層だときいている。私のところへくるファン・レターも大部分は高校生である。しれみれば、ヤングが勲章をくれたのも同じではないか」「そうなのだ。私だって苦しみの連続だった。たとえいかがわしいと自分で極めつけている作品にしろ。そういう作品群が、若い人たちのいくらかでも憩いになっているとすれば、誇りをもって勲章をもらってよいではないかと、私は納得した。 ちかくごく内輪のひとたちで、私の叙勲祝いをやろうではないかという議がもちあがっている。私は胸に勲章ぶらさげて、その席に臨むつもりである。たとえ芥川龍之介が生きていて後ろ指を指そうとも」(52-53頁) なんというか、素敵な方だなぁとあらためて思います。ーーー ところで、この土曜日に出かけたときにかけていたラジオで、たまたま横溝さんの話題になっていました。どうもご親戚の方が言うには、横溝さんは気むずかしい方だったとか…。そんなエピソードも興味深いですね。(2008/07/14読了)*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2008.07.16
コメント(0)
-
ジャン=クロード・シュミット「中世の自殺」
Jean-Claude Schmitt, "Le suicide au Moyen Age"Annales. Economies, Societes, Civilisations, 31-1, 1976, pp. 3-28. 久々に外国語論文の紹介を。 著者のジャン=クロード・シュミットは、古文書学校卒業後、高等実習研究院(1975以降、社会科学高等研究院)で教鞭をとり、「中世西欧歴史人類学研究グループ」(Groupe d'anthropologie historique de l'Occident Medieval, 略称GAHOM)では例話研究や図像学の研究を進めています。なお、GAHOMのHPでは、所属研究者の業績が(おそらくほぼ)網羅されているので、興味がある方は見てみてください(著書だけでなく、論文も発表年順にリストアップされているので便利です)。 シュミットは、次の3作が邦訳書となっています。(松村剛訳)『中世の身ぶり』みすず書房、1996年(松村剛訳)『中世の迷信』白水社、1998年(渡邊昌美訳)『中世歴史人類学試論―身体・祭儀・夢幻・時間』刀水書房、2008年 さて、ここで紹介する論文「中世の自殺」の構成は次の通りです。ーーー[序]1.悪魔の側面について2.自殺の約50の事例3.自殺と社会集団4.狂人の自殺5.「ある目的」をもった自殺6.自殺の時と場所7.社会的行動8.教会による理解と予防9.文学証言のいわゆる独自性[結]ーーー この論文では、13~16世紀の裁判記録や赦免の書簡などから、約50の自殺の事例を取り上げ、分析します。 中世では、「自殺suicide」という語はなく、「自身を殺す」というような表現が使われたそうです。自殺は悪の力の勝利で、悪の誘惑が「希望」の欠如した魂に入り込みます。なお、自殺者にとっては悪魔は物理的に存在していて、たとえば悪魔が井戸に自殺者を押したりする、と考えられたとか。 第2節以下では、自殺の事例の男女比、自殺の方法(首つり、溺死など)、自殺者の社会的身分(都市の職人が多いです)、自殺を行うのは何月、何曜日、一日の中でもどの時間帯が多いか、自殺の場所はどこか(家の中が最も多いです)、などが分析されます。それぞれ表になっていて興味深いですね。なお、シュミット自身言っているように、リストに上がらないような貧しい者たちなど、ずっと多くの人たちが自殺していたに違いない、ということです。 第7節は、自殺者の財産・身体はどう扱われたか、ということが論じられていて興味深いです。 まず、その財産は押収されます。その身体は、公的に「処刑」され、キリスト教徒の墓地に埋葬することは禁じられます。また、窮屈なたるに入れて川に流すという事例も紹介されています。 第8節では、どの感情(あるいは悪徳)が自殺につながっていくかが、チャート的に示されます。直接的な引き金は「絶望desperatio」で、「落胆accidia」、「悲哀tristitia」が「絶望」につながっていく主な要因です。 あるいは、聖人伝や「例話」などで、聖母マリアや聖人たちが自殺志願者の前に現れて彼らを救うという事例が紹介されますが、ここで興味深いのは、その聖人には女性が多いことです。 第9節は、宮廷文学における自殺(企図)の事例を分析します。自殺企図は、「社会からの離脱desintegration」の長い過程だ、ということで、ある登場人物が、ほとんど飲食せず、体も洗わず、人よりも野獣のようになっていく様を紹介します。ところがそうした人物は、友人や隠修士に救われる、とのこと。 最後に、結びの部分から、自殺者の「社会への再統合reintegration」を促す三つの主体をみておきます。 まず、教会。絶望者を社会に再統合するにあたり、モデルとしたのは宗教文学における聖人たちの奇跡的介入です。 同じく教会に関して、現実的側面でいえば、聴罪司祭が彼らを救おうとします。 最後に、宮廷文学のモデルでは、隠修士や友人が自殺企図者を救います。 教会は、自殺者は永遠の地獄落ちの運命にあると説きました。世俗的な面では、遺産の没収や遺体への厳しい「処刑」が待っています。にもかかわらず、それらは自殺を防ぐことはできませんでした。それでも、教会も世俗も、文学的表現に見られるように、自殺を防ごうとしていた…と、こういう図式が説かれています。 最後に、ちょっと所感を。 サンプルが少ないから仕方ない部分もありますが、年代ごとにいつごろの自殺者が多いか、ということが分かれば、その歴史的背景との関連も論じることができて興味深いのでは、と思いました。 それにしても、昨今の日本の状況には不安になります…。 なお、この論文は3年ほど前に読み始めたのですが、あと数ページのところでずっと読んでいませんでした。今回、一通り最後まで読めて良かったです。(2008/07/12読了)
2008.07.15
コメント(2)
-
映画「西の魔女が死んだ」
今日は、映画「西の魔女が死んだ」を観てきました。 原作の、梨木香歩さんによる小説『西の魔女が死んだ』が大好きなので、観てきたのですが、映画もとても良かったです。原作にとても忠実で…。 なので、あらすじは上にリンクをはりました原作の方にゆずるとして、ここでは映画について。 まず、配役が素敵です。私は映画もテレビもめったに観ないので、タレントさんには全く疎いのですが、みなさん素敵でした。特に、西の魔女役のサチ・パーカーさんはとても良かったです。 話の流れの上で、とても良かった登場人物は郵便屋さんです。この方の明るさが、映画に華を添える感じです(おじさんなのですが…)。 大好きな言葉も原作通りに聞くことができましたし、ラストでは分かっていても涙があふれました。というか、冒頭から泣きそうになり、2時間ずっとハンカチは手放せませんでした。 本当に素敵な映画でした。原作もぜひお試し下さい。
2008.07.13
コメント(0)
-
本購入~新刊(浦賀和宏、西尾維新)、古本(筒井康隆、梨木香歩)
今日は久々にのんびりと図書館で作業したり買い物したりの一日でした。さて、まずは今月の講談社ノベルスのうち、浦賀和宏さんの『地球人類最後の事件』と西尾維新さんの『きみとぼくが壊した世界』を購入。浦賀さんの八木剛士&松浦純菜シリーズも、あと一作で終結とか。本書も楽しみです。古本では、筒井康隆さんの『暗黒世界のオデッセイ』、梨木香歩さんの『家守綺譚』を購入。筒井さんのは、マンガもあったり、かなりバリエーションに富んだ一冊のようです。梨木さんは、新潮文庫で読んできている作家さんです。大好きな作品『西の魔女が死んだ』は映画化されていて、明日観に行く予定です。明日もなにか本を買うかもですが…。ーーーところで、講談社ノベルスは来月もかなり熱いですね。島田さんの『帝都衛星軌道』はもちろん、大好きな石崎幸二さんのミリア&ユリシリーズの新刊も出るようですし、深水黎一郎さんの新刊も出るようで…。来月と9月は、また若干読書ペースが落ちるかもしれませんが、講談社ノベルスが楽しみです。
2008.07.12
コメント(2)
-

横溝正史『悪魔の家』
横溝正史『悪魔の家』~角川文庫、1991年21版(1978年初版)~ 横溝さんの短編集です。1938~1940年に発表された7編の短編が収録されています。では、それぞれの内容紹介と感想を。ーーー「広告面の女」新聞の広告欄に、次第に現れてきた女の顔。最初は輪郭だけ、やがて少しずつ顔のパーツがそろっていき…。そしてその女を発見した者には、莫大な賞金を出すという発表が出される。アパートのそばに邸宅を構える子爵のもとにその女の姿を認めた蜂屋三四郎は、やがて意外な真相にたどり着く。「悪魔の家」霧の深い夜、新聞記者・三津木俊助は、一人の女とでくわした。何かに怯えているような女を家まで送る途中、とつじょ、暗闇の中に不気味な首が浮かび上がり、女はそれを悪魔と呼んだ…。 翌日。三津木の職場に、女が訪れてきた。義兄の身に危険が迫っていること、幼い姪が悪魔に怯えていることなどを明かし、彼女は、家を調べて欲しいと依頼する。「一週間」特ダネは創ってこい―上司に言われた新聞記者が特ダネを探しているところ、かっこうの人物に出会う。過去に心中に失敗したその男は、今度は悪名高い元女優と心中したいという。そこで記者は、偽の殺人事件を起こせば、二人とも死なずして有名になれると助言するが…。「薔薇王」結婚式の日、花婿が失踪した。花婿は唐木子爵を名乗っていたが、唐木家はすでに途絶えているはずだった…。 作家の甲野朱美はその偽子爵を車で拾うが、警察の尋問にひっかかったとき、男は姿を変えていた。朱美は男に興味を抱き、その周辺を探っていくが、花嫁の側も動き出すことになる。「黒衣の人」旅先で出会った「黒衣の人」に憧れていた由希子のもとへ、「黒衣の人」から手紙が届いた。由希子の兄は、殺人の濡れ衣を着せられたまま死亡してしまったが、その人は、事件について知っているという。手紙を読み、由希子は一つの冒険に挑む。「嵐の道化師」嵐の夜、心中を企てた男女のもとに、犬が人の指をくわえてきた。被害者は、男の父親。そして加害者は、女の父親の道化師らしかった。 新聞記者の三津木と男女は、道化師が被害者を乗せて船を出す場に居合わせたが、加害者も被害者も見つからない。出張に行っていた由利先生が帰ってきたとき、事件は急展開する。「湖畔」呼吸器を患い、S湖畔で休養の日々を送っていた私は、一人の紳士に出会う。あるときは温厚で、あるときは気むずかしいその紳士は、やがて大きな事件を起こすことになる。ある朝、私が散歩していると、紳士を見つけた。公園のベンチに座り微動だにしないその紳士は、既に死亡していたのだった…。ーーー 久々の再読です。 主に金田一シリーズを中心に紹介してきていますが、本書に登場する新聞記者・三津木俊助と、白髪の探偵・由利先生は、横溝さんの戦前の作品で探偵役を果たしていた人物です。等々力警部はこのときから登場していますが、年齢についてはふれないことにしましょう…。(横溝さんご自身も、『真説 金田一耕助』の中で、等々力警部の年齢についてふれています)。 ちょっとびっくりしたのは、三津木さんが等々力警部とため口で話していること。金田一さんは冗談を言ったり憎まれ口をたたきながらも基本穏やかなので、なんだか新鮮でした。 さて、いくつかの短編についてコメントを。まず、「広告面の女」は、出だしから引き込まれました。主人公の蜂屋さんとともに、事件(?)の様相がよく分からなくなっていき、そして反転、真相が明かされる流れにはわくわくします。 表題作は、どろどろした中に優しさもある物語なのですが、最後の一文がなかったらなお良かったかな、などと私は思いました。「薔薇王」は本書の中で最も長い作品で、スリルも溢れていて良かったです。同じく「黒衣の人」も、スリルもあり、物語としてもわくわくします。 最後に収録されている「湖畔」は、静謐な雰囲気が印象的な一編。話の真相の一つにはうすうす気付いたのですが、その雰囲気が味わい深いです。この作品を最後においているという、その配列も良いですね。 金田一耕助シリーズ以外にも再読してない作品がまだまだありますし、そして未読の作品もちらほら、まだ持っていない作品もあるのですから、今後も横溝作品を読んでいくのが楽しみです。(2008/07/10読了)*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2008.07.12
コメント(2)
-

横溝正史『横溝正史自伝的随筆集』
横溝正史『横溝正史自伝的随筆集』~角川書店、2002年~ 横溝さんが発表していた随筆を、新保博久さんが編集した本です。発売当時買っていたにもかかわらず、6年も経ってから読むことになってしまいました。 本書に入る前に、なぜいま本書を読んだのか、そのあたりから書いておきましょう。個人的にはNHKはあまり好きではないものの、そのNHK教育で、横溝さんを特集した番組が4回放映されました。これがどの回も面白く、あらためて、横溝さんの生涯に関心をもったことが一つ。 もう一つは、去年の今頃から横溝作品を再読しはじめて、あらためて横溝さんの作品に魅了されたことです。おどろおどろしい雰囲気、残酷な殺人事件、旧家にひそむどろどろした怨恨…その一方で、金田一さんは飄々として温かい人柄ですし、横溝作品の多くには優しさも溢れています。トリックも謎解きも秀逸ですし、とにかく素敵です。『真説 金田一耕助』など、横溝さんのエッセイは何冊か読んでいますが、本書はずいぶん貴重な一冊だと感じました。 幼年期の思い出、生母の死、継母や腹違いの兄を迎えての生活などなど、横溝さんの少年時代が分かるのももちろんなのですが、横溝さんが初めて日本にエラリー・クイーンを紹介したこと、原著でディクソン・カーの本を読みあさり、どんどんカーの作風に傾倒していくなどの叙述にはわくわくしました。 では、付箋をつけたところを中心に、面白かったところについてもう少し書いておきましょう。 まずは、横溝さんの作品に影響を与えたエピソードや人物について知ることができます。『悪魔の手毬唄』の手毬唄は、(全部は紹介されていないですが)本当にあったこと、『八つ墓村』に登場する小竹さん・小梅さんにはモデルの双子の女の子がいたことなどなど、わくわくします。「片隅の楽園」という一文には、先に横溝さんがはじめてエラリー・クイーンを日本に紹介したことにふれましたが、その他、横溝さんが海外の探偵小説にどんな評価を下していたか、どれだけわくわくしながらそれらの作品を読んでいたかが記されていて、とても興味深いです。 一応文字色を反転して、一文を引用します。「伴大矩氏の持ち込んできたもの[エラリー・クイーン『オランダ靴の謎』]はもちろん原書であった。その目次をひらいてみて、各章の見出しの頭文字のつづりがザ・ダッチ・シューズ・ミステリーとなっていたり、また作者がエラリー・クイーンで、しかも、三人称で書かれている主人公が同名だったり、さらにまた、読者にたいするチャレンジがあったり、どうやら大凝りに凝っているらしいところが、趣向好きのわたしの好みに大いに合致したのである」(238-239頁) 私は、エラリー・クイーンの作品を(まだ2、3冊しか読んでいませんが)読む前から、読者への挑戦のことや作者と探偵が同名のことなどは知ってしまっていましたので(善し悪しはともかく)、この一文を読んで、なんだかとてもうらやましいような気持ちになりました。同時に、ぱっとした探偵小説がなかなか読めなかった時代に、エラリー・クイーンの本にふれたときの横溝さんの気持ちがありありと伝わってきて、なんだかこちらまでわくわくしてしまいました。 本書の最後の部では、江戸川乱歩さんが横溝さんに送った手紙が紹介されています。その中で、乱歩さんは、仏経と自らの作品の類似性について考察しているのですが、この考察もとても興味深く読みました。「正史もまた永遠にして不滅である」という新保博久さんの一文の中に、素敵なフレーズがあったので、こちらも文字色をかえて引用しておきます。「[横溝正史は]最初にして最後の探偵小説家であったのだ」(301頁)ーーー 上で少しふれたNHK教育の番組で、横溝さんのインタビューの映像も見ることができました。その中で横溝さんは、自分たちの時代には推理小説という言葉はなかったから、やっぱり自分の作品は探偵小説と呼んで欲しい、というようなことをおっしゃっていました。それを見て以来、私は記事のタグにも「探偵小説」と表記するようにしました。なんというか、言葉は大切ですよね。 横溝作品の大ファンを自認していますが(まだまだ知識は足りないので、マニアとまでは言えないですが…。そして私は、マニアという言葉は否定的には使いません)、横溝さん自身のファンになっているのを感じています。本書で明らかにされるような波瀾万丈の人生を送りながらも、多くの文章に溢れる優しさ。 本書も面白かったです。良い読書体験でした。(2008/07/10読了)
2008.07.11
コメント(4)
-
筒井康隆『文学部唯野教授の女性問答』
筒井康隆『文学部唯野教授の女性問答』~中公文庫、1997年~ 『婦人公論』1991年1月号~12月号に連載されていた作品です。読者からの疑問に唯野教授が答えます。 印象に残った問答について、ちょっと書いておくことにします。「進歩的文化人とされる男性は概して似非フェミニストなのですか?」で紹介される、ルソー、トルストイ、イプセンなどの実生活はなかなか勉強になりました。イプセンの『人形の家』は割合面白く読んだ覚えがあるのですが、一面彼はこんなだったのか…と。「ノストラダムスの「世界破滅」の予言におびえています」も興味深かったです。結局何事もなく過ぎましたが、あの頃、わりあい特番が組まれていたのを思い出しますね。 とまれ、ここでは、筒井さんがいろんな作品で紹介しているハイデッガー哲学も引き合いにだされていて、興味深かったです。以前読んだ、笠井潔さんの『哲学者の密室』もハイデッガー哲学を下敷きにした作品でしたが、ものすごく簡単に自分になりに掴んだことをいえば、それは、やがて確実にくる(それは数十年の後かもしれませんし、明日かも、あるいはちょっと散歩に出る数時間後のことかもしれません)死を意識することにより、自己を見つめ、自分のすべきことを理解する、ということです。 そういえばここ最近は考えませんでしたが、『哲学者の密室』を読んでしばらくは、けっこうそうしたことを考えました。そうすると、たとえば私はかなりひきずりやすい人間ですが、たとえば、恨みや憎しみに襲われ続けるのは馬鹿らしいなぁと思えてくるので、結果的に、前向きに考えられるようになります。 私はハイデッガーを読んだことはありませんし、『哲学者の密室』や筒井さんのいくつかの作品で得た上の理解も誤解かもしれませんが、困ったときの良い道しるべになったと思うと、上のように考えられるきっかけを得られたことは良かったです。「『仮定の質問』にはどう答えるのが正しいでしょうか」も面白かったです。そうですよね、そんな質問に対する答えはフィクションにしかなりえないですよね…。 …などなど、興味深かったです。唯野教授の語り口が良いですね。(2008/07/07読了)
2008.07.09
コメント(0)
-

横溝正史『悪魔の寵児(金田一耕助ファイル15)』
横溝正史『悪魔の寵児(金田一耕助ファイル15)』~角川文庫、1996年改版初版~ 金田一耕助シリーズの長編です。 まずは、内容紹介と感想を。ーーー 雨の降る昭和33年(1958年)6月18日、本屋にレイン・コートの男が入ってきたことが、事件の発端だった。 男が店員に作らせたハガキが、バー・カステロのマダムら、3人の女たちに届く。彼女たちは、戦後巨富を築いた風間欣吾の愛人であった。黒枠の塗られたハガキの文面を読むと、欣吾の妻、美樹子と、カステロの店員早苗の兄、石川宏が心中を遂げるメッセージのようだった…。 カステロに集まった三人は、早苗とともに石川家に赴く。そこでは、裸で抱き合ったまま昏睡した宏と、絶命している美樹子が横たわっていた。 早苗に好意を寄せる新聞記者、水上三太がその場にかけつけ、医者を呼ぼうとしたところに現れたのが風間欣吾。風間は、水上に取引をもちかけ、いったん妻の亡骸を家に持って帰るが、その夜、妻の亡骸が消えてしまっていたという。 宏は何者かに注射で薬を打たれたらしく、美樹子の帯紐もなかったことから、二人は心中のように見せかけられたのではないかという疑いもあるなか、美樹子の失踪により、実は彼女はまだ生きていたのではないかという可能性も出てきた。 こうした中、悪魔の寵児は恐ろしい事件を演出する。風間の愛人の一人の新店オープンのパーティの中に届けられた箱。その箱の中では、その愛人の遺体と、風間の人形が抱き合っていたのだった…。 風間が雇った私立探偵、金田一耕助も事件を調査していくが、水上もまた彼にライバル心を燃やし、いくつもの冒険に挑んでいく。ーーー 10年ほどぶりの再読ですが、内容をすっかり忘れていたので、新鮮な気持ちで読みました。 …読了後は、なんとえげつない事件かと、しばらくひきずってしまいました。 ちょうど1年ほど前から、横溝作品を再読してきていますが、このえげつなさはなかなかないと思います。横溝さんの作品には、しばしばタイトルに「悪魔」という言葉が付けられていますが、この事件の犯人の形容にはそう言わざるをえないですね。 そして、内容紹介を書くにあたってあらためて物語のことを考えると、今度はその巧さにうなりました。雨の日にふらりと現れる雨男に、怪しい蝋人形館。主に水上さんが繰り広げる手に汗握る冒険…。 面白いです。…が、やっぱりかなりえげつないです…。(2008年7月6日読了)*表紙画像は横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2008.07.08
コメント(2)
-

小路幸也『スタンド・バイ・ミー 東京バンドワゴン』
小路幸也『スタンド・バイ・ミー 東京バンドワゴン』~集英社、2008年~ 下町の古本屋さんを舞台にした、東京バンドワゴンシリーズ第三弾です。新しい家族も加わり、ますます賑やかに堀田家ですが、今回もいろんな事件が舞い込みます。 それでは、それぞれについて簡単に内容紹介と感想を。*なお、続き物ですので、前二作もふまえての紹介になります。以前の話で明かされたことを紹介の中で書かざるをえない場合もありますので、ご注意ください。ーーー「秋 あなたのおなまえなんてぇの」 ある日、<東京バンドワゴン>を訪れた若い女性が売っていった一冊の本。その本には、「ほったこん ひとごろし」と、子どもの字で書き込みがあった。 紺に、何があったのか。本を売りに来た女性について調べるうちに、悲しい過去の事件が浮かび上がる。 また一方、<東京バンドワゴン>にやってくる別の客は、本の位置を勝手に並べ替えているようで。なんのためにそんなことをするのか、そしてその客は誰なのか。 また一つ、二つと、堀田家の知人の輪は広がっていく。「冬 冬に稲妻春遠からじ」 クリスマスの近づいてきた頃、アメリカから<東京バンドワゴン>に大量の洋書が届く。送り主は、堀田家とつながりのある人物だった。 同じ頃、堀田家の周囲にはまた二つの事件がもちあがる。 一つは、小料理居酒屋<はる>の真奈美さんとコウさんの結婚の話。コウさんには事情があるらしく、結婚は断るつもりのようで…。 一方、堀田家のまわりに不審な人物が現れる。彼らの目的は、一体何なのか。「春 研人とメリーちゃんの羊が笑う」 クリスマス頃から、研人とますます仲良くなったメリーちゃんは、毎日のように堀田家に来ては、一緒に小学校へ行き、帰ってくるときも<東京バンドワゴン>に寄って本を読むようになった。そんな中、彼女の母が堀田家を訪れ、娘が変なことを言ってないかという。メリーちゃんは、羊が追ってくる、堀田家に行けば羊がいなくなる、と話しているらしい。 不審者が着いてきているのかと考えた研人は、ある日デジカメを持って登校した。その日、研人は、衝撃的なものをカメラに収めたのだった。「夏 スタンド・バイ・ミー」 子どもたちは海に遊びに行き、楽しい季節。ところが、またしても問題が浮上する。 我南人と、大女優・池沢百合枝の周辺をかぎまわっている人物がいるらしい。青との関係を知られると、我南人はともかく、池沢にとってはスキャンダルとなる。ところが、事態は最悪の方向へ動いていく…。ーーー なんというか、冒頭から温かい物語で、読んでいて安心します。私はこんな大家族の中で育った経験はないのですが、なぜだか懐かしくなります。それこそ、「刷り込み」かもしれませんが、日本人なんだなぁとしみじみと思います。 いつものように、それぞれの物語の冒頭には一家の朝食の風景。何人もの言葉が入り乱れているのですが、研人くんの台詞と相手の台詞は拾っていくようにしています(笑) そして、勘一さんの調味料の使い方(と、それへのツッコミ)には毎回笑ってしまいました。 上の紹介では書きませんでしたが、「春」の回ですずみさんと青さんが京都に行きます。そこでのすずみさんのかっこよいこと!印象的な場面の一つです。あぁ、羊も…(笑) ともあれ、温かい物語です。(2008/07/05読了)
2008.07.06
コメント(0)
-
筒井康隆『幻想の未来』
筒井康隆『幻想の未来』~角川文庫、1987年36版(1971年初版)~ 筒井さんの短編集です。140頁をこえる表題作の他、9編の短編(ショート・ショート)が収録されています。まずは収録作を掲げた上で、印象に残った作品についてコメントを。ーーー「幻想の未来」「ふたりの印度人」「アフリカの血」「姉弟」「ラッパを吹く弟」「衛星一号」「ミスター・サンドマン」「時の女神」「模倣空間」「白き異邦人」ーーー なんといっても、表題作「幻想の未来」はすごい作品です。 放射能で、地下にもぐった人々。何世代も地下で暮らしていた彼らの中には、地上に上がる者もいましたが、決して地下に帰ってくる人はいませんでした。やがてときは経ち、最後の人間が子どもを産みます。その子どもは、環境に適応し、植物に近い存在となっていました…。 さらに時は経ち、「前意識紀」「分意識紀」など、いくつもの時代が過ぎていきます。その特徴は、意識が空間に存在している、ということです。過去の記憶、意識は、有機生命体の意識に働きかけ、彼(彼女)を導いたり、他の星からの訪問者に意思疎通を図ったりします。 ありふれた言葉でいえば、人間(生物)が生きる意味、生きた意味を描く作品といえるのでしょうが、そのスケールは圧倒的です。 最初の、ホモ・サピエンスが絶滅していく過程の描写は恐ろしくもありました。ところが、終盤、あるいはラストでは、優しさや救いも感じました。 あらためて、これはすごい作品です。 なお、この中の一部を独立させた「血と肉の愛情」という短編があります。こちらは、『ベトナム観光公社』に収録されています。 その後の収録作品は短めの作品が多く、表題作よりは軽めの気持ちで読めます。これは面白い、と思ったのは「アフリカの血」。主人公にときどき現れる「顔」の正体が明かされてから、わくわくしながら読み進めました。 「姉妹」はユーモラスな雰囲気ももつ一編。昼食のあとにすぐに横になったら牛になるよ、と私も言われて育ちましたが(いまでは、私自身が冗談で言うことがありますが)、本編では、本当に弟が牛になってしまいます。お姉さんの、「およしなさいよ。どうして牛になんか……」という言葉がぐっときました。 最後に収録されている「白き異邦人」は、どこか悲しくもあるのですが、救いもあるというか、読み終えた後に感慨深くなる作品でした。 表題作だけでも読む価値ありです。良い読書体験でした。(2008/07/04読了)
2008.07.05
コメント(0)
-
筒井康隆『48億の妄想』
筒井康隆『48億の妄想』~文春文庫、1976年~ 筒井康隆さんの最初の長編です。いやはや、小説を読む時間がとれるようになり、2冊目に読みましたが、こちらもものすごく面白かったです。読んでいて何度か感動で震えましたが、久々に読書ができて物語がもつ面白さに感動しているのもあると思いますが、本書のすごさも大きいと思います。 まずは、簡単に内容紹介を。ーーー「情報化社会」に入った日本では、マスコミが絶大な力を握っていた。日本各地には小型のテレビカメラ(アイ)があからさまに、あるいは密かに設置され、局の方で面白い映像を確認すると即座にそれを流す、という社会。日本中の(そして、これは世界中にあてはまるのですが)ほぼ全員がテレビに出たがり、アイを意識して行動する。有名人のバロメーターは、その家に設置されたアイの数で。国民はとにかく分かりやすく、派手で、面白い番組を期待し、ニュースにもそれを求める。国民の意見でマスコミもどんどん報道を派手にし、大事故の模様をセットで再現するほどの世界。 銀河テレビのディレクター、折口も、どんどん派手なニュース番組を制作していた。ところが、日韓対立の大問題の解決に悩まされていた外相の死後、彼の在り方は変わるようになる。外相の葬式を大々的に報道する中、外相の一人娘だけは、決してテレビカメラを意識した行動をとらなかったのだ。 彼女と出会い、折口は変わっていく。そんな中、ついに、日韓のマスコミ同士で示し合わせ、両国は「喧嘩」として、海戦を行うことになる。ーーー まず、平岡篤頼さんによる解説の一文を引用します。「[…]彼の小説はカフカの場合と同様、前提だけが非現実的だが、後はきわめて論理的に、必然的に展開される」 なるほど!と、うならされました。本作を読み進める中で、そのリアリズムが引き起こす恐怖感に何度もぞくぞくしたのですが、この解説の言葉ですっきりしました。アイが日本中に設置され、ほぼあらゆる人がテレビを意識し、テレビに出たがる社会… というのは「非現実的」な前提なのですが、登場人物たちの思考は、その前提をふまえた上でとても現実的なのです。個人的には、最近はほとんどテレビを見ませんが、しかし本作のレベルほどでなくても、同様のことはいまも行われているのではないかと思います。 たとえば、某報道番組では、職場を退いた方のインタビューの際、その方に元の職場の制服を着せていたことがありましたし、某教養番組では、事実の改変が行われていました。個人的には、前者は放送局がバカだな、で済むのですが、後者は、放送に分かりやすさ・面白さを求め、テレビ番組の言うことにすぐに飛びつく消費者の方にも問題があり、放送局が増長した部分もあるのではないかと想像しています。 ということをふまえて読むと、余計に怖くなる物語でした。 また、第一部終盤のクライマックスではどきどきしました。 なんとも語彙がないのがもどかしいのが、とにもかくにも面白いです。良い読書体験でした。(2008/07/01読了)
2008.07.02
コメント(2)
-

高田崇史『毒草師~QED Another Story~』
高田崇史『毒草師~QED Another Story~』~講談社ノベルス、2008年~ さて、やっと個人的に大きな仕事(?)も終わり一段落ついたので、さっそく久々に小説を読んでみたのですが…びっくりするほど面白かったです。 作業したり、西洋史関連の文献を読むことに時間をかけてきていたので、小説への情熱が薄れているのではないか、読んでもすぐに飽きるかも…と、そんな心配もしていたのですが、杞憂に終わりました。やっぱり小説面白いです。というより、それだけ本書が面白かったということもあります。 と、前書きが長くなりましたが、本書は、QEDシリーズの重要人物の一人となっている「毒草師」御名形史紋が探偵役をつとめるミステリです。では、簡単な内容紹介と感想を。ーーー 鬼田山家は、呪われているのか―。そこでは、奇妙な事件が相次いでいた。 先々代の俊春は子どもの頃、一つ目の山羊に遭遇し、無我夢中で山羊を打ち倒した。その後、彼と妻の間に最初にできた子どもは死産。そしてその子どもは、一つ目だった…。 先代の壮治郎は、ある突然屋敷の離れにこもってしまう。窓も扉も内側から閉ざされたその離れに異変を感じ、家族が扉を破って中に入ったとき、壮治郎は消えてしまっていたという。一ヶ月後、彼の遺体が、隅田川から揚がった。 壮治郎の先妻の死後、その二人の娘が相次いで失踪。長女は、一つ目の鬼を見たと、壮治郎と同じく離れにこもり、消えてしまった。その数日後、妹も失踪した。 そして今年(平成10年[1998年])。今度は、壮治郎の後妻、久乃が、離れにとじこもり、消えたのだった。 * 医業界向けの書籍や雑誌を発行する「ファーマ・メディカ」に勤めるぼく―西田真規は、鬼田山家の関係者と懇意にしていることもあり、鬼田山家の事件を独自に調査することになった。フリー編集者の朝美と事件について語りながら、先に進めないぼくは、奇妙な隣人―御名形史紋にも事件の話をした。すると御名形は、『伊勢物語』、キュプクロスという言葉を、ぼくに示唆したのだった。 朝美の協力をえながら、『伊勢物語』、在原業平について調べていくうちに、ぼくは、この事件との類似性に次第に気付いていくことになる。ーーー 歴史上の謎と、現在進行形の殺人事件の謎を並行して解明していくという、QEDシリーズおなじみのパターンですが、今回はどちらの解決も見事で、本当に面白く読みました。 いまさらながら、ギリシャ神話のキュプクロスが鍛冶神だということを知り、日本と一緒なんだなぁと感心しました。日本でのそれも、QEDシリーズで学んだわけですが…。 今回は、主に西田さんの一人称で物語が進むのですが、彼が楽しい方なので、読んでいるこちらも楽しくなりました。地の文での御名形さんへのツッコミはもちろん、とつぜん熱く語り出したり、話の中で例を挙げるときの、その例も面白く…。毒草師のシリーズは第二作も出版されていますが、西田さんがまた登場しているのか、ちょっと楽しみです(講談社ノベルスになるようならそちらを買いたいので、しばらく我慢ですが)。 ところで本書では(でも、というべきでしょうか)、いくつかの「差別語」が扱われます。筒井康隆さん、島田荘司さんのエッセイなどでも「差別語」の問題(「差別語」を使うことではなく、ある言葉を「差別語」とする社会の問題)にふれていますが、本書でも的確な指摘があったので、文字色を変えて引用します。「それらの人間に対して、悪意を吹き込んだのはまた別の人間じゃないか。言葉自身には、何の罪もない。というよりむしろ、連綿と続く歴史をぼくらに教えてくれているわけだ。本当に問題なのは言葉ではなくて、それが差別用語になってしまったというその過程にあるんじゃないか」(118-119頁) ミステリとしても面白く、『伊勢物語』などの歴史上の問題の解明も面白く(浅学ながら、「詠み人知らず」の意味を今回はじめて知ったように思います)、とても素敵な読書体験でした。(2008/06/29読了)
2008.07.01
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1










