2005年08月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
在庫の逆数の高値が続いている.
1978年からの長期系列で見ると,在庫の逆数の高値すなわち在庫不足が2002年7月頃から続いている.その値は1989年以前の日本が強気一辺倒であった時期と同じレベル.かつ生産指数も高値を持続.出荷ー在庫バランス(対前年比)は底へ.黄色の日経平均を人口,為替,GDPで割った数の推移は1978年から2002年までは鉱工業生産指数とレベル的に同じように見えるが,その後日経が鉱工業生産指数を下回ったまま.成長株から資産株へと評価を落とした日本の姿そのものともいえる.要するにPERではなくPBRで買われている?もっとも個人金融資産が1400兆円,国債および地方公共団体の借金あわせて1000兆円と株主資本比率は低い国ではあるが.鉱工業生産指数をみると,チャート上はここが天井とも見えるが,今後の上昇予測,日銀,竹中さんの踊り場脱出宣言が正しければ,日経との差がさらに生じることになる.円高か株価上昇によって,黄色の線が上昇し,日経月足volume ratio100に上昇するまでキープが正解?今月はvolume ratio(5)が80.33
Aug 31, 2005
コメント(0)
-
アルメディオ
少し前まで持っていた銘柄です.今日の鉱工業生産をみると,DVDビデオは対前年比で生産 -27.8出荷 -24.8在庫 -2季節調整済みの前月比でも生産-3.5,在庫+2.5最近じり安の状況ですが,まだ底とはいえない状況.今日の鉱工業生産対前年比は生産-2.2,出荷,-2.3,在庫+5.0,在庫率+7.5と弱い数字でしたが,電子デバイス部品の8月予想は+8.1,9月予想+8.0と強い数字で,メガチップスについては期待してもよいのかな?昨日のMacronix社の月次データは日本の電子デバイス部品の生産推移と傾向が非常に似ていますね.原数値でみると両者とも去年の10月からマイナスに転じ,4月,5月くらいを底に7月は改善.経済の勉強を始めて1年ほど経過し,少しずつですが,細かい数字を見れるようになっている感じです.今日は卒業試験問題作り.
Aug 31, 2005
コメント(0)
-
明日の鉱工業生産
UFJでは前月比-0.8%,前年比-1.9%の予想.生産指数は2004年1月に100を超えてから,ずっと100前後を保っていますが,同じような状況は平成バブルの15ヶ月連続100越え以来ですね.竹中さんの踊り場脱出宣言が正しいなら,このままの状況をキープしながら,次の景気上昇に移行するということになりますが,,,,在庫のほうは前年比-1.9%以上減少すればいいんですけど.Manufacturers' Shipments, Inventories, & Orders (M3)で7月の在庫をみると上昇しているので期待できないか、、Inventories of manufactured durable goods in July, up seventeen of the last eighteen months, increased $1.6 billion or 0.6 percent to $282.2 billion. This followed a 0.4 percent June decreasehttp://www.census.gov/indicator/www/m3/index.htmlメガチップスと今年5月から提携をしているMacronixの月次データ2005 Monthly Net Sales Revenue*Month 2005 2004 Y o Y % Change July 1,509,192 2,370,145 -36.32% June 1,272,606 2,346,642 -45.77% May 1,286,645 2,255,025 -42.94% April 1,316,322 2,099,948 -37.32% March 1,204,542 1,780,272 -32.34% February 1,174,993 1,629,627 -27.90% January 1,245,801 1,394,192 -10.64% 4,5月,6月の対前年比が-37%から-46%と下落,7月は-36%と5,6月よりは改善.このまま改善進行を期待.ちなみに2004年は対前年比+27%ですが,2004年10月から対前年比はマイナスに転じています.そろそろ浮上しても,,,http://www.macronix.com/QuickPlace/hq/PageLibrary48256F56003383AE.nsf/h_Toc/86F31EC6EFA0FC0F48256F5600343747/?OpenDocument
Aug 30, 2005
コメント(0)
-
「やな」に鮎を食べに行く
昨日は読書のあと,車で30分ほどにある「やな」に鮎を食べに行く.ここに来るのは一年ぶり,川面の風が涼しく気持ちが良い.近くの温泉を入ってから自宅に戻る.先週は通常の診療に加え,講演,特別講義などがあったが無事に終える.今年は忙しくて夏休みがほとんどとれず,もう学生たちも戻っており,昨日は久々の休日といった感じでした.昨日も書きましたが「デフレの終わりと経済再生」を読んだことで,来るべき日本の姿が少し見えてきた気がします.知識がつきました.先行き楽観はできませんが,知識が私に安心を与えてくれたようです.秋は松茸狩りに行きたいですね.老いた父が元気なうちに,,,
Aug 29, 2005
コメント(0)
-
最近の読書
「デフレの終わりと経済再生」米山秀隆著過去の不況、デフレ、過剰発行国債(政府の借金=国民の借金)について歴史が知りたかったので最適の本だった。良書。日英米の過去のデフレとその後の回復がわかりやすく述べられている。また8つの国が国債過剰からどのように立ち上がっていったかについても、丁寧な説明がなされている。著者はみずから片寄った意見などを述べることもなく、事実に基づいた記述に好感が持てた。結局、政府借金は何らかの形で国民が返すことになるのだろうが、その返済方法は程度の差こそあれインフレと経済復興に頼るしかないようである。過去の歴史を振り返れば、通貨危機によってそれが一気に促されることもあれば、ゆっくりと解消しうる場合もある。労働人口の低下が不可避な日本だが、産業が力を取り戻し、企業利益率を上げることが出来なければ、通貨不安による強制的解消(一気に円安=プラザ合意の逆?とインフレ)となる可能性がある。今の日本の企業経常益はバブル時を上回っているし、2007年に団塊の世代が大量引退を始めれば、企業の若返りが進行すると思う。そのときに技術継承により競争力を維持しえれば、まだまだ大丈夫ということか?中国の経済関係の本を読んでみると、中国も水供給がボトルネックとなり経済の天井はそれほど高くないという指摘もある。少し前に少々のお金を元に替えておいたけど、今のところ株式は購入していない。「相場で儲ける方法」ラリーウイリアムズ著前に[Right Time at the Right Stock](原著の方が安かったし、大学に置いても何の本か秘書さんにばれない)を読んで面白かったので購入。デイトレ用の本だが、内容は参考になる。ファンダメンタルで購入しても、売るときはなんとなく適当だったけど、すこしテクニカルも考えて売ってみよう。テクニカル本としては「投資苑」が良かったと思っているが、これもなかなか良かった。ただデイトレは実行不可能。月足のテクニカルというのは成立しないのだろうか、少し不安。いまは個別のファンダメンタル分析、景気分析(為替や鉱工業生産など)、月足のvolume ratioの3つを用いて行こうと思っています。日本と米国の企業利益比較 1985年以降プラザ合意以前(1ドル240円くらい)の日本の利益をドル換算し、現在の利益もドル換算すると、日本の企業利益は20年ほどで6倍になる。一方、米国の企業利益も同期間で6倍になる。今の日経平均12000円は調度1985年頃と同じレベル。一方、当時は双子の赤字に苦しんでいた米国の株価は、当時の10倍になっている。20年でいったいどうしてこんなに差が出てしまったのか、経済学者のうちでこのような事態が予想できた人はいたのだろうか?http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/data/p025.pdf
Aug 28, 2005
コメント(0)
-
まじめ外務員さん J Coffeeさん
愛読してきたまじめ外務員さんとJ CoffeeさんのWebが相次いで更新を停止されました。何度も訪問し、いろんなことを学ばせていただきました。残念なことですが、なにか一つの時代が終わったような気がします。
Aug 19, 2005
コメント(0)
-
メガチップス
今年1月以来、久々に株式購入。メガチップス1230-1232円で400株。この日経の高さで購入するのは躊躇していたのだが、景気サイクル的には今年の10-12月が底と思うので。少しづつ買ってみることに。中期計画では2008年に営業利益60億。現在の時価総額は約300億。株主資本率は80%超。流動資産140億、流動負債25億、投資その他資産32億、有利子負債0、配当15円/株、優待30円/株もし中期計画が達成できなくても、配当と優待を考慮するだけで、100株づつ家族で分散すれば利回り3.6%なら割に合うと考えた。チャートは鉱工業生産の生産指数、在庫率、在庫指数、出荷ー在庫循環モメンタム日経volume ratioが30以下になり,その後6ヶ月から1年ころに購入すればあまり損はしない.また景気サイクルを考慮に入れておけば(ただしこれが全てではない)よいだろう.ところで日経平均の最近の推移だが,日経平均を為替(円ドル),GDPで割った値とFRB発表のIP値(半導体除く)の推移と非常に似ていることに気がついた.次は数ヶ月程度の短期的マクロと株価の関連を少し勉強してみよう.
Aug 16, 2005
コメント(0)
-
今の日本の株価は高いのか安いのかわからない。
日本の優良企業株式の外国人占有率がけっこう高いように思うのだが、、、、日本はそんなに貧乏になってしまったのだろうか?今の日本の株価は歴史的に見て高いのか、安いのかまったく見当がつかない。平成バブルがはじけたのは40歳代人口が減少したためだと論じられている。ならば日経平均をその年の40歳人口で割れば平坦になるだろうと考えてチャート作ってみた。たしかに1989年から2000年までの株価はそれで説明がついたが、2002年以降の株価の下落はそれでは説明できない。そこでさらに日本のGDPの推移をドルベースで考え、それでさらに割ってみた。つまり、円、ドルの為替相場とGDPで除した。これを対数軸で示した。同時に鉱工業生産の生産指数、出荷ー在庫の対前年比(循環モメンタム)および米国の産業サイクル(30ヶ月=半導体をexclude)、TOPIXvolume ratio5ヶ月を同時に表示した。これで明らかになったことはけっこう大きいかもしれない。1)コンドラチェフのピーク(1982年)以降1987年までのデフレ下経済成長期に日経平均はドルベースで一気呵成に上昇している。2)2000年のITバブルまでは、ピーク、ボトムとも一定である。これがクズネックサイクルなのだろうか??3)2000年以降これまでの底を割って低下している。これは何を意味するのだろう?4)今の日本の株価は1982年以前のレベルにもどる過程のたんなんる踊り場なのか?それとも1987年から2000年までのレベルにもどるほうが正しい姿なのか?5)株価の底を見つけるには、米国サイクルを目安にして、底に近い部分をはさんで前後1年間に2度TOPIXのvolume ratioが30以下になる時期がある。概ね最初のvolume ratioの底から6ヶ月以上経過してから、2度目の底が来るまでが株価の底のようである。こう考えておくとあまり損はしないかもしれない。
Aug 15, 2005
コメント(0)
-
米国景気と日経平均の長期系列
米国景気と日経平均の長期系列を検討してみた素材に選んだのは以下の5つ1)日本鉱工業生産の出荷と在庫バランス2)日経平均3)FRBのdiffusion index http://www.federalreserve.gov/releases/G17/diffusion.htm4)FRBのIP、対前月比、3ヶ月移動平均, 計算式 =FRB!C7*30-50Capacity, and Utilization: Manufacturing excluding Selected High-Technology Industrieshttp://www.federalreserve.gov/Releases/G17/Current/table15.htm5)TOPIX volume ration 5monthsほかに半導体を除いた米国の産業短期サイクルは30ヶ月といわれているらしいのでそれをマークした。推論:経時的には30ヶ月サイクルの底付近でIP-60,DI50以下が底か?ただし日本鉱工業生産の出荷と在庫バランスでみると平成バブル以来の大きな山にいることがわかる。また日本鉱工業生産の出荷と在庫バランスがプラス5%を上回っているのは1978年以降では初めての事態である。要するに在庫不足がこれほどのレベルで生じているのは過去30年来初めての状況。これはいったい何を意味するのだろう?IP-60以下,DI50以下,TOPIX volume ratio40以下が次の買い場と想定しておこう。
Aug 5, 2005
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…
- (2025-11-14 19:41:15)
-
-
-

- 楽天市場
- 【最短0.25秒間隔*の高速照射で時短…
- (2025-11-14 19:58:21)
-
-
-
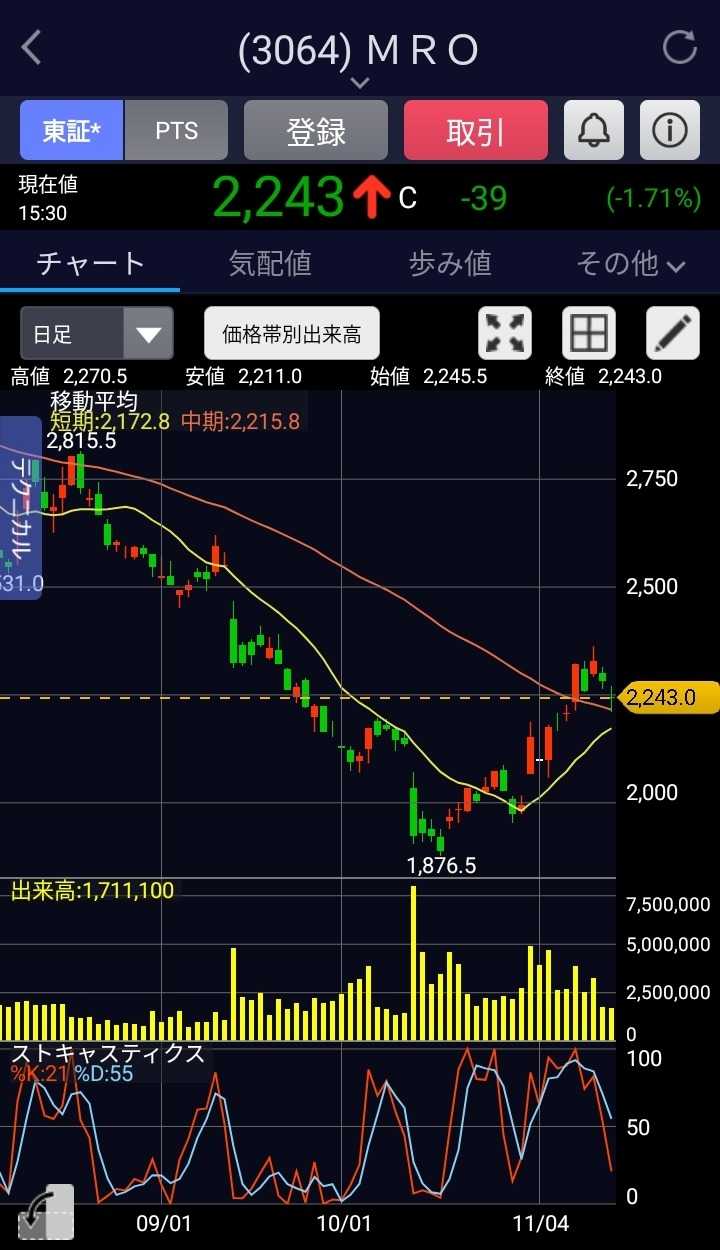
- 株式投資日記
- 株式資産は減少、精神的な不安定回復…
- (2025-11-14 17:07:04)
-







