2022年01月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

29日に採集した貝殻の写真を撮った。
釣りに出掛けて2漁港を股にかけても不漁で、フグを15匹釣っただけで早々に帰宅した。 余った時間を潰すのに、先日採取してきた貝殻の写真を撮った。名前の分からない貝も数個あった。
Jan 31, 2022
コメント(0)
-

土日とも徘徊する。もう少し晴れたならと悔やまれる。
土曜日は糸島方面へ、日曜日は今津近辺へブラブラ出掛けた。良い場面もあったが空模様が曇天傾向の上に、相変わらずのピンボケ病でチャンスを逃す。視力の低下と望遠レンズの絞り機能が壊れていて開放でしか撮れないので、ピントが合う範囲が狭くなっているのが原因だ。 29日。今津湾から糸島加布里へ。カンムリカイツブリ。下水処理場の排水口に群がるオオバン。汚物を食っているらしい。ミヤマガラス。電波塔の上にハヤブサがいた。1時間半付き合うことになるとは。一度飛び立ってすぐに戻って来た。セグロカモメ若鳥。カラス2羽がやって来て、ハヤブサを追い出そうとちょっかいを出すと、ハヤブサは飛び出してカラスを追いかけて攻撃して追い払った。さすがハヤブサ。その動きは隙が無かった。ドバトが時々近くを飛んでもハヤブサはじっとしていた。なにゆえ長時間時っと止まっているのか。見始めて1時間ほど経過した時に突然飛び出した。加布里湾の方向へ水平飛行する。200mぐらい先であっという間にドバトを捕まえていた。ハヤブサの狩りは上空から急降下して捕まえる場面が多いが、水平飛行で易々と狩る場面はあまりにも見事だった。このハヤブサの技が優れているのだろう。以前に室見川で夕方コウモリを狩る場面がやはり水平飛行だった。ハヤブサはドバトの羽毛をむしって時間をかけて食っている。ドバトの羽毛が風で流れてゆっくり落ちてくる。食うものと喰われるものの現実は常にある。ドバトは橋の橋脚をねぐらにしている模様で、ハヤブサとの攻防は日常的なもので、はやぶさは鉄塔が網代になっている。カラスなどに渡せないはずだ。 1時間半も見てから、現場を離れて海岸へ向かった。加布里湾名物のハマグリをとっている人々。もちろん一般の人は採ることは出来ない。海へ向かう途中の電柱にチョウゲンボウの雌が止まっていた。久し振りに見た。ノスリもいた。糸島の海岸。ウスバハギの死骸。時間が経っているのか皮と骨だけになっている。この時期に海水温が低下すると、暖海性のこの魚は死んでしまうことがある。サクラガイ。ツメタガイに襲われて貝殻に穴が開いている。この貝も穴が開いている。ウスバハギがもう1匹。午後になってやっと晴れ間が出た。 30日。海岸近くの水溜りに卵塊があった。卵が見えるし、孵化したらしいものもある。孵化した子供。以前霞サンショウウオが産卵に来ていたのでそれか。周りの木々を伐採されたのに生き延びていたのかも知れない。海を眺めていると、ウスバハギが漂流していた。余りにも小さい獲物のボラ。水上の太陽。水を飲むツクシガモ。泥の中の餌を食っている。
Jan 30, 2022
コメント(2)
-

唐泊、西浦2港を股にかけ、一度は当たり、もう一度は失敗。
天気はすっきりしない日々が続いているが、そう寒くも無く風はあまり強くないので海は凪いで釣り易い。潮も次第に良くなって行く。 27日は朝8時から10時まで唐泊でフグを釣ってから、西浦へ移動して2時間釣った。 唐泊ではもうフグしか釣れない。それも際限なく釣れるわけではなく、15匹ぐらいで終わる。その後西浦へ場所を変えテトラで釣る。 テトラでグレ釣りなどする人は殆どいないので、延べ竿で餌包みで釣れば撒き餌はあまり使わないで済む。グレはぼつぼつ釣れ、3匹の足裏サイズが釣れた。 西浦での収穫。アジゴが2匹釣れ、これが次の日の災いとなる。海面で休むカツオドリ。3羽のカツオドリがいたのでカメラを取りに行ったが1羽しか残っていなかった。飛び立つカツオドリ。カツオドリは海面から飛び立つときは両足で水面を蹴るように助走する。ウも同じ動きで、ハクチョウやガンは足を交互に動かして水面を走るように助走する。帰り道で能古島を見れば、霞がかかり視程が悪い。ツワブキの種。同じキク科のタンポポに似ている。今津四所神社のツバキを見て帰る。 28日は日の出を見られる時間に出掛けた。しかし東の低高度には雲が懸り見られなかった。27日にも増して空気が濁っていた。視程は3㎞ぐらいしかなかった。8時前になってやっと雲の上に冴えない朝日が出た。西浦から見た朝日。 28日は唐泊へは曲がらず、先に西浦へ向かった。西浦へ着いてみれば前日まで多かった港内でのアジゴ釣り人が激減し、釣り場はより先端へ移動していた。 いつものように外側テトラで8時半頃からグレ兼フグを釣り始めた。すると、すぐに当たりが有り、アジゴが食い付いた。すぐに悪い予感がして、釣っても釣っても15cm位のアジゴばかりで、どうやら長く港内にいたアジゴの群れが港外に出てしまったらしい。 もう釣りにならなかったが、アジゴを待っている人もいるので辛抱して35匹釣って止めた。そのまま帰れば良かったのに、前日とは逆に唐泊でフグを釣ることにした。 フグを釣ってみると一向に釣れず、1時間で3匹に終わった。逆また真なりとはいかなかった。 お気に入りの山でパンを齧った。しばらく遠くを眺めながらぼんやりしていると、どこかに沈殿していた澱の様な感情がふわりふわりと浮き上がって来る。 歌の文句で言えば、若い頃にどこか遠くへ行きたいと思い、思えば遠くへ来たもんだとなり、もう捨ててしまった故郷をいまだ忘れ難きとつぶやいてしまう。何で福岡に長々といるんだろうか。偶然ながら福岡は自分にはいい所ではあったとは思いつつも。 山道を下った小田でこの日のツバキを見た。ミヤマホウジロ。 夕方に日の入りを見るために小戸公園へ行った。夕日も雲に隠れて見られそうになかった。福岡ではこんなケースが多い。辛うじて夕日らしきものが見える。 28日はサンライズ、サンセット、フィッシング何れも不調の一日だった。
Jan 29, 2022
コメント(0)
-

フグ釣りが本命になってしまった。
26日午後は年2回受けている過去のアスベスト吸引の肺への影響観察検診日で、それでも朝の内だけ唐泊へ釣りに出掛けた。唐泊で釣るのは2週間ぶり位で、初めからフグを釣る積りだった。唐泊は博多湾口に位置しているのでやや内湾的で、冬季は海水温が西浦より下がり1月から3月までは釣りのシーズンオフとなる。 それでもフグは最後まで釣れる魚だから、どんな具合か試験操業してみたかった。朝は弱い気圧の谷が通過中で曇っていた。 唐泊に7時半に着いてみれば、釣り人は数人しかおらず、アジゴ釣りでごった返している西浦とは対照的だった。200mぐらいある長いテトラは貸し切り状態だった。 小潮で潮が引いた状態で、何時ものように延べ竿で釣り始めると、30分はなにも釣れなかったのが突然フグが釣れだした。狙いが当たったと喜んだのもつかの間、30分ぐらいで釣れなくなった。干潮に近いのが災いしたのかも知れない。 フグと言えば釣りの餌取の邪魔者で、ハリスを切られる嫌われ者の最右翼だろう。それでいつでも食い付く印象があるが、フグを本命で釣ってみれば、フグにもれっきとした時合があることが分かる。 2時間ばかりフグ釣りをしてナシフグ、ショウサイフグ主体で14匹釣って止めた。唐泊漁港の入り口の離岸堤を延伸するのか台船が石を投入していた。大して意味も無さそうだが、工事業者を保護するためには公共事業は欠かせないのだろう。バイクのシートの上でくつろぐ猫。 25日は朝に貝の写真を写した後、北東の風も収まったのでゆっくりめに西浦へ釣りに出た。釣り場へは何時もとは逆に道草しながら向かった。アワビのかけら。背振山系にかかる笠雲。ボラを捕まえて自ら飛び上がったミサゴが身震いをして水を振り落としている。同じカラス科のカササギとハシボソガラス。同じ所に7羽もいるのは珍しい。あちこちに散らばったカササギ。 さんざん道草をして西浦へ着いたのが10時過ぎで、港内のアジゴ釣りの多さに驚いた。40人ぐらいはいただろう。 やっと干潮を過ぎた10時半頃からテトラで釣り始めた。この日も食いは悪く、1時間までは小型のウミタナゴやグレしか釣れなかった。それでも30cm位のグレが2匹釣れた。この時期に延べ竿で釣れたことは記憶にない。船溜まりに浮かぶプラゴミ。世界の啓発をあざ笑う光景。そう言う我が身もなにもしてはいないが、せめて漁協あたりが回収したらよいのに。全部が釣り人由来でもないし、サザエやナマコを獲る情熱の一部を割いて、海に生きるものとして回収すればと思う。その姿を見れば、釣り人もごみを捨てなくなるのではないか。海を愛する偽善的釣り人の独り言。つぼみが膨らみつつあるハクモクレン。季節を忘れたコスモス。
Jan 26, 2022
コメント(0)
-

釣りに出掛けるも天候回復せず、終日北東風強し。
小潮になり朝の潮が悪い上に、北斗の風が8~10m吹いてどうせ釣りにはならないとは思いつつ、波を見る積りで釣りの準備もして8時過ぎに出た。海に近づくにつれて風が強くなり、曇っていて時々小雨が降る。急いで行くことも無いのでウメなど見ながらブラブラ走る。今津湾は潮が引いている。 9時頃に西浦へ着いてみれば、北東風が相当強く、テトラではとても竿を振れそうになかった。それならと西へ走って波見物をすることにした。 二見ガ浦の波は2mぐらいで波形も余り良くないので、さらに西の野北へ行ってみた。ここの波も見るべきものは無かったが浜に下りて歩いていると、多種多様な貝殻が打ち上げられていて、あれこれ拾うのが楽しかった。 タカラガイの小さいのを見つけて、福岡では初めてだったので感激した。60年前に郷里の海であれこれタカラガイを拾って、文字通り宝のように集めていた。 昼が近くなったので、引き返し二見ガを通りかかると、朝は少なかったサーファーが多くなっていたのでそれをしばらく眺めた。サップで波乗りしている。 西浦へ戻ってみると、風は少し凪いでいるようだったのでせっかくだから、ちょっとだけ竿を出してみることにした。弱ったとはいえまだ結構風が吹いていたので釣り辛かった。延べ竿で釣ってみたが、全く釣れず、時々小さいウミタナゴが釣れるだけで、やがて何度かフグにハリスを切られ、漁獲は無くもう止めようかと思いながら、もうちょっとと未練げに釣っていてやっとコモンフグが1匹釣れ、その10分後にいきなり大物がつれて、7.2mの延べ竿が大きく曲がりボラかと思いつつ何とか凌いで、姿が見えるとチヌだった。網は無かったので水際まで引き上げて鰓に指を突っ込んで引き上げた。 チヌは思わぬ外道だったがリリースもせずに、これで釣りは止めることにした。43cmのチヌはよく肥えている。味は良くないが姿は良いチヌ。ツバキの葉が部分的に葉脈だけになっている。
Jan 24, 2022
コメント(0)
-

下り坂の空はきれいな雲に満ち溢れている。
土曜日ながら釣り道具を持参で出かけた。日の出頃なら朝日か雲が見られるので釣りは二の次で良かった。日の出頃に東の地平近くには雲があって、残念ながら日の出は見ることが出来なかった。 先に進んで宮之浦手前の小浜でバイクを止めて、太陽が雲の層から出るのを待った。空一面に高積雲が広がった。西の空には高積雲の波状雲が見られた。月齢20の下弦の月が西に傾いている。雲の海の下をドバトの群れが飛んでいる。西浦漁港へ着いたのは8時を過ぎていた。 土曜日とあって港内ではアジゴ釣りの人が驚くほど多かった。幸いテトラには釣り人が少なく、思うところで釣ることが出来た。海はすっかり凪いではいたが、大潮も終わり潮具合は良くない。 いつものように延べ竿で釣る。リール竿も持って来てはいても、どうしても延べ竿で釣りたがる。9時頃でも潮が引いていて食いが悪く、フグさえ釣れない時間が続いた。12時まで釣ってはみたが、鳴かず飛ばずで2匹だけ足裏サイズのグレが釣れた。相変わらずフグ主体の漁獲。25cm位のコモンフグが4匹釣れた。小田観音から見た柑子岳。 21日は海が濁り余り釣れなかった。28cmと26cmのコモンフグ。産卵前で卵巣が大きい。肝臓と精巣、卵巣、皮膚には猛毒のテトロドトキシンがあるとされている。皮にも毒があり筋肉は弱毒とされているが、どこまで調べられているのか疑わしい。
Jan 22, 2022
コメント(2)
-

19日は珍しくグレが釣れた。
20日の午後は雪になり切れなかった小さい氷雨が降っている。大陸の高気圧がやや東にあって、等圧線が東に傾いてこれまでの北西の風から北北東になって、朝鮮半島の東を回り込む風に変わり、その分朝鮮半島に遮られずに日本海を渡った風が水蒸気を含んで雨になった。寒気がもう少し強ければ雪になっただろうか。 釣りには行かずに午前中、志摩の四季でサゴシでも買ってから少し徘徊する積りで出かけた。開店10分後に着くと、客はいつものように多くは無く、もう魚の争奪戦は終わったか、初めから魚も客も少なかったのか冷蔵ケースにはほとんど魚は無かった。50cm位のボラがずらりと並んでいたのが目に付いて、1尾500円の値札が付いていた。 少ない魚の中からサゴシ1匹、サバ1匹、千葉産の大場マイワシ3匹を買った。サゴシとサバは酢締めにしてバッテラにしようと思っている。 その後どちら方面へ行こうか思案して見上げた空に、ハイタカが飛んで来た。開けた場所ではあまり見ないので、しばらく眺めた。数分後にハイタカは南へ飛び去ったので、北の海方向へは行かず、南の泉川方向へ行くことにした。比較的低く飛ぶ雄のハイタカ。潮が満ち始めた泉川(雷山川)でミサゴがボラを捕まえた。 ハマボウの土手を加布里湾方向へとろとろ走っていると、ハイイロチュウヒの雌が低高度でいきなり飛んで来た。西から東へ飛んで行き、すぐにカラスの襲撃に合い見えなくなってしまった。引き返して後を追ってみても見つけることは出来なかった。低空を飛ぶチュウヒに上からカラスが襲い掛かる。 10時頃に北東の空が怪しい空模様になって来たので早々に帰途に就いた。 19日は7時前に釣りに出た。今津湾の月と大原海岸で日の出が見えるはずだった。海へ向かうカワウ。少し先へ進むと丁度毘沙門山に太陽が架かる、ダイヤモンド毘沙門になる。さらに進んで北崎中学校あたりで朝日を浴びる波を見た。2mぐらいのうねりがある。気温が今冬一番冷えて、崩れた波濤から湯気が出る。 唐泊漁港へ行って海を見ればうねりの為か濁りがあるし、うねりがあるので断念し西浦へ向かった。 西浦漁港の港内にはアジゴのサビキ釣り人が多数竿を出していた。アジゴには用事が無いので外側のテトラで釣ることにする。テトラには釣り人は殆どいないので、何時もの場所で延べ竿で釣ることにする。 フグでも釣れれば良いと思っているので気軽に釣りが出来る。浮き下2mの餌包みで釣り、上からの撒き餌はしない。そもそも柄杓は持っていないし、撒き餌をするときは手柄杓でする。 1時間ぐらいはコモンフグ主体のフグが多かったのが、コッパグレやウミタナゴが釣れ始め、潮が満ちるにつれてグレはサイズアップした。足裏サイズも混じって、3時間半釣って25~28までの足裏サイズを6匹釣ることが出来た。この時期としては上々だった。 昼にパンでも食って道草しながら帰った。ハイタカを見た。穂が開いたガマの群落。
Jan 20, 2022
コメント(0)
-

フグ釣りばかりで意欲は低下するばかり。
2022年度の1回目の満月の17、18日の二日とも朝に沈む月を写そうと二見ガ浦へ出掛けた。冬型の天気が続いているので雲が多く、海に沈む月が見られるかどうかは微妙だった。 16日。海に没する15分前に雲に隠れてしまい最後まで見ることは出来なかった。その後唐泊へ移動した。東の空も雲が多く、少し朝焼けが見られたが日の出は見られなかった。 唐泊で釣り始めると次第に雲が少なくなり太陽が姿を見せた。太陽から離れた左右に幻日が現れた。3時間延べ竿で釣って、20cm足らずのショウサイフグ、ナシフグを釣ったがグレは0だった。太陽の周りの雲が彩雲となった。 18日の朝。7時15分頃の二見ガ浦には月は無かった。水平線付近には雲は無く、期待しつつ待った。雲間から満月が出た。烏帽子灯台に灯がともる。背後の島影は壱岐。水平線上の島は恐らく下対馬。月は沈むにつれて影が薄くなって行く。大気の透明度がイマイチ良くない。月の下が水平線に接したはずでもほとんど見えなくなった。下対馬の高い山が浮島になっている。ミサゴが餌を探す。 8時頃に西浦のテトラで釣り始める。北北西の風が強い。いつものように延べ竿で釣るも、釣れども釣れどもコモンフグ主体のフグばかりで、それも大きくない。3時間釣ってやっと30cmのグレを1匹が釣れた。 フグは食材としても、加工の材料としても悪くはない。内臓にはテトロドトキシンという毒があるので自己責任で自分だけ喰うしかない厄介なものでもある。過去30年で数千匹食って生きているので肉だけ喰う分には何の問題も無い。味醂干しは特に美味く、他の魚の追随を許さない。 そんなフグも釣魚としては小型のフグでは当たりは小さく、針掛しても対して引かないし、ときどきハリスを切られるし、面白味はほとんど無い。 それならば冬の休漁に入れば済むことだが、釣りをしないで日々を過ごすことが出来ないのでフグでも釣って凌ぐしかない。釣り人に嫌われるフグを駆除していると言い訳しつつ明日もフグを釣る。カメリアは乗客を乗せぬまま釜山へ向かい、きずなは壱岐対馬から博多港へ向かう。この冬もヒメウが来た。生の松原に以前から生えているバショウかバナナ。寒さに耐えて増えている。帰りの途中に道から見えるツバキが綺麗だったので、バイクを止めて松原を歩いて見に行った。
Jan 18, 2022
コメント(0)
-

15日土曜日に西浦へ釣りに行って、釣り人の多さに驚いた。
16日は朝は小雨が降っていた。風は無く日曜日でなければ釣りに行っただろうに、15日の西浦の釣り人の多さを目の当たりにしただけに、とても釣に行く気にならなかった。午後に市民会館で市民オーケストラのニュ-イヤーコンサートがあったので生の音楽を聴くことが出来た。 コロナ感染の急拡大下で、危うい開催だったにもかかわらず盛況で、楽団員の方たちも力が入ったことだろう。 15日は続いていた冬型の天気が緩んで季節風が収まったので、久々に西浦へ釣りに出た。7時半頃に着いて驚いた。釣り場には多数の車が駐車していて、港内の至る所にアジゴ釣りの釣り人が竿を出している。 自分が釣るのは外側テトラだからどうかと思いつつ堤防に登ってみれば、港内ほどではないがやはり釣り人が多い。所定の場所は先客がいたので別の場所で釣ることにした。 フグが釣れれば良いと延べ竿で釣り始めると、初めは小型のフグばかりでどうにもならなかったが、やがて20cm前後が釣れて、まずまずの結果だった。外道がないというのはまことに結構なことだ。 フグに5本釣り針を切られながら3時間釣って止めた。流れて来たソウシハギ。何者かに目玉は食われていたが、全長40cmほどあって未成魚と思われ、寒波で海水温が急激に低下して死んだものと思われる。ウスバハギがこの時期に瀕死の状態で見つかることは珍しいが、より南方系のソウシハギが冬にいたのは初めてのこと。夏に幼魚を見ることは結構ある。夏場西浦で見ることがあるソウシハギの20cm位の幼魚。逆さまの姿勢でいることが多い。 このところよく見かけるノスリ。こちらに警戒して飛び立つ前には必ず脱糞する。 漁港で釣りをする人が特に増えたのは2年前からのコロナ流行が影響している。それに伴ってマナーの悪化も目に付き、漁船のロープに仕掛けを引っ掛けて切れたり、餌やゴミの始末も悪い。いずれ釣り禁止になる懸念もある。
Jan 16, 2022
コメント(0)
-

寒風吹きすさび波止釣はもう終わりか、代わりに波を見るのみ。
頻繁に現れる冬型の天気で北西の寒風が強く吹いて釣りにならない日が増えた。それでも全天候型釣り人はフグでも良いと波止釣りを試みるが、風と波でフグさえ1匹も食い付かない。 13日もアジゴでも釣れないかと唐泊へ出掛けた。西浦では長くアジゴが釣れ続けていたが、魚体が痩せていて加工しても味が悪く、唐泊の方が質が良い。しかし長くアジゴ釣りをしてないし、アジ釣り人もいないので釣れるかどうかは分からない。テトラで釣りが出来ない状況なので、港内での苦肉の策だった。 かじかむ指で餌を付け延べ竿で7時過ぎから港内で釣り始めた。向かい風が強く釣り辛く、軽い仕掛けが凧のように空を舞って捕まえるのに手こずり、釣りのリズムが出来ない。それでもやがて浮きが沈んでアジゴが釣れた。何匹か釣れてこれは良いぞと思ったのもつかの間、40分ぐらいで突然終わってしまった。 わずか11匹に終わったが、0で無かったのは良かった。 8時半には帰途に就き、北崎で波を少し見た。釣りが駄目でも波があるという感じで、楽しんでいる。 10日は瑞梅寺ダム方面へ行ってみた。まず今津湾岸へ行ってみた。カワセミの雄を見ることが出来た。 産の宮から南へ向かい一気に瑞梅寺ダムへ行った。ダムの向こうに井原山がある。ダムから少し上に小さい藤原神社があり、この神社には直径80cmもあるツバキの木がある。オオイヌノフグリ。糸島市の井原周辺には遺跡が多い。これは前方後円墳。背後は高祖山。溜池にはカモ類の姿は無かった。可也山が霞んでいる。小川にクレソンが茂り、少し採取した。 11日。2羽のツクシガモは大きさがかなり違う。どちらが雄なのか。この頃は何処でもノスリを見かける。10日に行った井原山は雪が積もっていた。 12日は唐泊、西浦テトラで少し釣りをしてみたがフグどころか餌さえ無くならなかった。海釣り公園には数人がいる。遠くの油山は雪が降っている。今津の東海岸でミサゴが20羽も餌の魚を狙って集まっていた。同じ場所でこれほど飛んでいるのを見たのは初めて。月はいつの間にか半月を過ぎている。冷え込むと陽炎が出来る。
Jan 13, 2022
コメント(0)
-

部屋に籠って越年の写真を整理する。
去年のことは去年の内に片付けておく積りが、12月分の写真が未整理のまま残ってしまった。放置すればするほど今年の分が重なって、にっちもさっちもいかなくなるのは目に見えていたので、連休で釣りはしないし天気も雲で出かける気もしないので、日曜日は写真の分類整理をすることにした。 デジカメになってからはやたらに写真の枚数が増える。フィルムの時は爪の先に灯をともすように写していたことを思い出す。多く写しても納得できるものは少ない。連写などもってのほかで、一度も連写したことも無く、オートで撮ることも無い。ピンボケ病がひどくなって消去する写真が増えても、飽きもせずに写し続けている。 9日は姪浜で日の出だけ見た。 6日。 平日ながら釣りは休んだ。散歩がてらに小戸公園には出掛けた。グレ釣り用の浮きを3本作る。小戸公園に三毛の野良猫がいた。小戸の妙見神社から西の可也山を見る。アオジ。仕上げた浮き3本。 7日は西浦でグレ、フグ釣り。潮が悪く、凪で澄み過ぎているのでフグでさえ食いが悪い。潮が満ちてくるまで辛抱して釣ると、10時頃から少し釣れて、1匹だけ30cmオーバーだった。 8日は糸島まで足を延ばした。二毛作の麦が伸びる冬。カラスに追われるチョウゲンボウ。しぶとく食い下がるカラスに逃げる一方のチョウゲンボウ。タカ類やハヤブサ類を目の敵にするカラス、特に獰猛なハシブトガラスは数の多さといい、大きさといい絶対的な脅威になっている。若いキンクロハジロの雄。圧倒的の多いカルガモ。マガモ雄。ヨシ原で漁をするカワセミ。下水処理場の排水に集まるオオバン。オオバンは増え続けて水草を食いつくす。干潟で餌を探すミヤマガラス。本来は穀物を食っているが、雑食性でもある。加布里のクロツラヘラサギは1羽しか見られなかった。スギの花粉はもう飛ぶ日も近い状態になっている。凪で烏帽子灯台付近では漁船が多く操業していた。火山のパラグライダー。 明日も祝日で釣りは休み。どう過ごすか思案中。 このところ新型コロナのオミクロン株による感染拡大が起こりつつある。これまでの株より症状は軽いようで重症化しにくいらし反面、感染力が強い。 各国ではコロナと共存するウイズコロナを受け入れている。しかし今回の変異株はむしろ新型コロナウイルスの戦略、ウイズヒュウマンと言えそうで、症状を軽く、感染力を強くして人間に対してダメージを少なくして、広く深く長く生き延びる戦略に見える。 アフリカのエボラウイルスが余りにも致死性が高いがゆえに、広く蔓延しなかったのとは対照的だ。 新型コロナウイルスが更に今後どのような変異を続けるのかは分からないが、ワクチンなどを製造する製薬会社が巨額の利益を上げ続けるのは間違いない。コロナは福の神に違いない。
Jan 9, 2022
コメント(0)
-

驚くべきフグの攻勢に耐えた先に釣れたものは。
正月休みも終わり各分野の仕事は5日が実質的な始まりだろう。ということで西浦へフグ兼グレ釣りに出掛けた。そう早く行く必要もないので大原あたりで日の出を見られる時間に出た。 下り坂の天気とあって、雲が多い空で日の出はみられるかどうか微妙だった。朝焼けは結局見られなかった。 日の出を諦めて西浦へ向かう途中に、ちょっとだけ太陽が見えてすぐに雲に隠れた。西浦のテトラには釣り人は殆どいなかった。8時前頃からテトラから延べ竿で釣り始めた。浮き下2mの餌包みで上からの撒き餌はせずに釣ると、1投目からフグが食い付いて来た。 釣っても釣っても15cm位のショウサイフグ、コモンフグ、ナシフグ、ヒガンフグの順番で攻め立ててくる。時々釣り針を切られ、作った針の在庫がどんどん減って行く。 加工に出来る大きさのフグはクーラーボックスに入れて小さいものは逃がすので、一般のようにフグばかりで最悪というわけではないが面白みがない。 やがて潮がかなり満ちて来た9時頃から、フグの合間に20cmオーバーのグレが少し釣れ始めた。そして10時頃に波止では大物のグレが食い付き、7.2mの延べ竿が大きく曲がって十分楽しめた。掬い網は無いので糸を掴んで31cmのグレを引き上げた。ハリスは1.7号だから切れることは無い。続いてもう1匹釣れた後はもう喰わなかった。 11時には釣りは止めて曇天の下を帰った。ヒガンフグの口腔から出た寄生虫。15mmもありさぞ摂餌し難かっただろう。この寄生虫はタイノエと呼ばれる甲殻類。帰る途中に立ち寄った溜池で見たカモ。キンクロハジロの番。ホシハジロ。尾羽が短い。 3日は家族で熊本城見物に行った。年に1度か2度のことで珍しい。 熊本地震による被害の修復が終わっていない櫓。本丸はすっかり修復されていた。急こう配で美しいカーブを描く石垣。色が違うのは過去の修復跡か。さすが肥後の石工の本場だけのことがある。天守閣の割には地味なしゃちほこ。壊れたままの石垣。大賑わにの加藤清正神社。 熊本城を後にして西へ向かい、金峰山へ登って駐車場の車の中で持参した弁当を食った。時間が足りず山頂への登山はしなかったのが心残り。 西へ下り河内町へ出た。山の斜面は石垣が築かれミカン栽培が盛ん。熊本は畑でさえ見事な石垣が積まれている。広大な有明海の干拓地の水門。玉名市の菊池川。江戸時代には米などの運搬船が行き来して大いに賑わったという。九州道は南関から鳥栖付近が渋滞して、福岡に入る頃は夕方になっていた。 高知の皿鉢料理を思い浮かべて作った。 4日の徘徊。梅一輪。田んぼで米を食っているオナガガモ。ハシビロガモの雌。コガモ。雄1羽でハーレム状態。ヘラサギ。
Jan 5, 2022
コメント(0)
-

新春第一弾は太陽がいっぱい。
2022年1月1日の朝日が何も特別な太陽でもないのに、それを見ることが幸福なことだと人々は思うのだろう。初日の出を見ようと多くの人たちが唐泊周辺に日の出前に繰り出した。 いつも日の出を見ているのにそういう私ものこのこ出かけた。どうせ行くなら初釣りをしようと延べ竿を持参した。冷え込んではいたが、雲は無く申し分ない上天気で、一番日の出を見易い場所にバイクを止めた。糸くずのような細い月が明るくなりかけた東の空に出ていた。空気が澄んでいるので早々に光度が増した。冷えた大気が揺らめいて太陽は楕円になり周縁がいびつになっている。朝日に赤く染まる波しぶき。高く昇るにつれて丸くなる太陽。海面に少し霧が出来ている。 日が昇ってしまうと初日の出見物の人々は潮が引くようにさっさといなくなった。しんばらく波を見てから西浦へ向かった。1月1日でも若い人を中心に何人も釣り人はいた。 冬型はすっかり緩んで風も収まって釣るのに何の支障は無く、テトラで延べ竿での釣りを始めた。釣れるのは予想通り各種のフグばかりで15cm以上は獲物となる。外道でなくなればフグでもそう嫌がることも無い。3時間釣ってグレはわずか3匹だけに終わった。その1匹は29cmの良型だった。 カラスに追われるノスリ。 天気は終日晴れで、夕日も見られそうだったので、朝日だけでは片手落ちだと思ったので、晩飯前に小戸公園へ久し振りに出かけた。午後4時半には太陽は西に傾いていて、地平近くに雲が少しありその他はよく晴れていた。 こんな時は幻日がよく現われる。今津の毘沙門山。朝はこの山の向こう側から朝日を見た。太陽と現実は相当離れている。日が沈むにつれて幻日も下がり、これまで見たことが無い大きい幻日になった。太陽は雲に隠れて日没は見ることは出来なかった。太陽が沈んだ後、東の空には地平近くに黒い帯が見られた。地球影ヴィーナスの帯という現象。 2022年1月1日はこの時期に珍しい好天に恵まれて、太陽がいっぱいでスタートした。
Jan 1, 2022
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- フライフィッシング【flyfishing】
- オトコのロマンを追い掛けよう ~20…
- (2025-11-28 19:30:21)
-
-
-
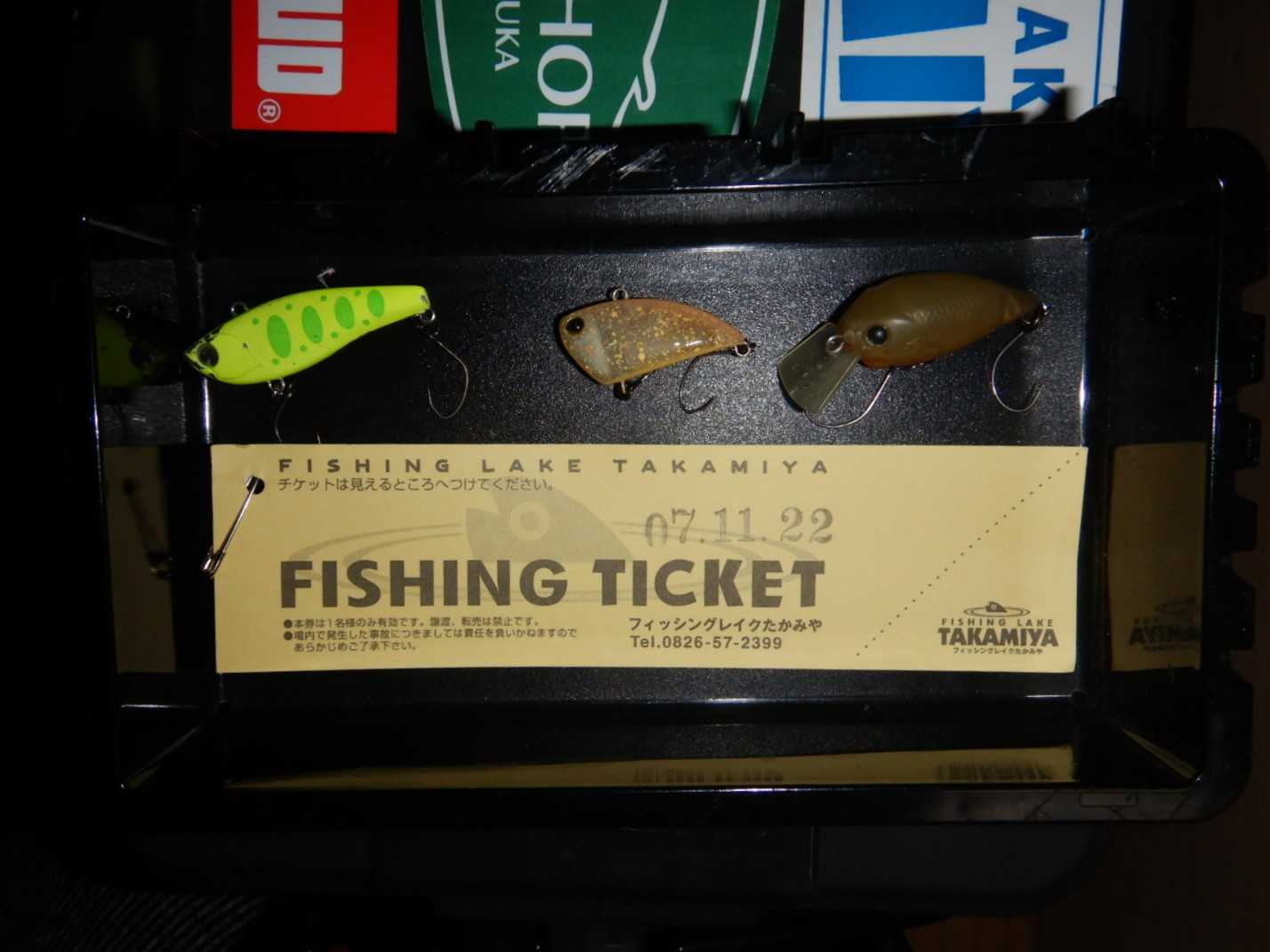
- 管理釣り場のルアーフィッシング
- かなり厳しかった
- (2025-11-26 18:30:07)
-
-
-

- ★自然の中で感じること★
- 今日は暖か
- (2025-11-28 17:00:05)
-







