まるで炎上商法かと見まがうタイミングで文春の記事が出たので、
長女の水嶋凜について検索する人も多いかと思います。
◇
水嶋凜は、
テレ朝「泥濘の食卓」やNHK「大奥」にも出てますが、
おりしも、つい先日、
来年の舞台「エウリディケ」への出演が発表されました。
シンデレラの次はエウリディケ。
日本版の演出は白井晃。
月9で福本莉子と共演中の栗原英雄も出演。
…2人とも三谷組ですね。
音楽を担当するのは林正樹&藤本一馬。
去年の出演作「シンデレラストーリー」。
林正樹&藤本一馬のライブ動画。
今回の戯曲「エウリディケ」のオリジナルは、
米国の女性作家サラ・ルールの2003年作品で、
マシュー・オーコインのオペラにもなっている。
オペラ版「エウリディーチェ」
https://www.shochiku.co.jp/met/program/3768/
https://www.shochiku.co.jp/met/news/4261/
一般に、
ギリシア神話の 「オルペウス&エウリディケ」 は、
イタリア語なら 「オルフェオ&エウリディーチェ」
フランス語なら 「オルフェ&ユリディス」 との日本語表記になります。
それから 「オルフェウス」 ってのはラテン語らしい。
以下は公式サイト (https://eurydice-stage.com)
愛し合う二人の切なくも美しいラブ・ストーリー…。その根底に描かれる「父と娘の愛」。
音楽家であるオルフェは、エウリディケと愛し合い結婚を約束する。結婚式当日、危険でおもしろい男に見初められてしまったエウリディケは、亡くなった父からの手紙を渡してもらえるという言葉につられ、彼が住むとても高い場所の部屋に行ってしまう。手紙を取り戻し彼の誘惑から逃れたエウリディケだったが、はずみで階段から足を踏みはずし、転び落ちて死んでしまう。死者の国で父親と再会したエウリディケは、父親からの愛によって「忘却の川」で消し去られた様々な記憶やオルフェと愛し合った日々の記憶を取り戻す。
一方、オルフェはエウリディケを探し続け、とうとう地獄の門までたどり着く。自らの歌によってエウリディケを取り戻せる可能性を掴んだオルフェだったが、地下の国の王から「振り返って決して彼女を見てはいけない」という約束をさせられる。そして…
たとえばオペラの歴史は、
ペーリやカッチーニの『エウリディーチェ』 (1600) や、
モンテヴェルディの『オルフェオ』 (1607) にはじまってる。
その後も、
グルックの『オルフェオとエウリディーチェ』 (1762) や、
オッフェンバックの『地獄のオルフェ (天国と地獄) 』 (1858) があります。
そこから考えても、
このギリシャ神話は、ヨーロッパ演劇にとって古典中の古典。
…
由貴ちゃんなら、
コクトーの映画『オルフェ』 (1950) を観てるかもしれない。
わたしが観てるのは、
ブラジルを舞台にした『黒いオルフェ』 (1959) だけですが。
◇
◇
由貴ちゃんが今回のドラマ「すき花」で演じたのは、
例によって依存型の毒親でしたが、
思ったより物分かりのよい毒親でした(笑)。
今後の由貴ちゃんがどうするのか分からないけど、
すでに下の娘も成人してるわけだし、
もう親は親、子は子の選択をすればいいんじゃないかな。
すくなくとも由貴ちゃん自身は、
長女に対する依存などはないだろうし、
凜は凜で自分の仕事を着実にやってくれればいいと思います。
◇
なお、
オルペウス神話とイザナギ神話の類似性のことは前にも書いたけど、
https://plaza.rakuten.co.jp/maika888/diary/202209140000/
これはもちろん松江の黄泉比良坂にもかかわる話だから、
https://plaza.rakuten.co.jp/maika888/diary/202310070000/
わたしの最近の出雲ネタにもつながる!(笑)
そして、
エロス&プシュケーの話に似てるところも。
https://plaza.rakuten.co.jp/maika888/diary/202303300000/
◇
一方、
わたしが観た『黒いオルフェ』は、
ヴィニシウス・ヂ・モライスの戯曲を、
フランス人のマルセル・カミュが映画化したもので、
カンヌのパルムドールと米アカデミー外国映画賞をW受賞し、
それがブラジルのサンバカーニバルや、
ジョビンのボサノバを世界中へ知らしめることになった。



ヴィニシウスは、
外交官でフランス文化にも精通してたから、
彼が1956年に戯曲『Orfeu da Conceição』を書いたのは、
きっとコクトーの映画の影響もあったと思うけど、
もうひとつ、わたしが気になってるのは、
サルトルが1948年に 「黒いオルフェ」 という文章を書いたことなのよね。
このサルトルの文章は、
黒人文学への賛辞であると同時に、
当時のネグリチュード運動に対する批評でもありました。
https://www.nhk.or.jp/meicho/famousbook/106_fanon/index.html
http://homepage1.canvas.ne.jp/sogets-syobo/rinri-7.html
http://www.kiss.c.u-tokyo.ac.jp/eng/docs/kss/vol17/vol1702nakamura.pdf
『リオデジャネイロから降る雪』の福嶋伸洋さんの新刊『オルフェウ・ダ・コンセイサォン』(松籟社)、映画『黒いオルフェ』原案の戯曲です。ボサノヴァの詩人、ヴィニシウス・ヂ・モライス著。カッコいい装丁! 訳者あとがきにはサルトルとボーヴォワールのブラジル滞在時の興味深いエピソードが。 pic.twitter.com/0KnKtccBKi
— tomoka watanabe (@scentofmatin) September 27, 2016
カエターノ・ヴェローゾなどは、
マルセル・カミュの作った映画について、
「黒人社会の実態を描いてない!」
「ヴィニシウスの作品とは似て非なるもの!」
みたいに批判してたけど、
それがサルトルの批評と繋がるかどうかは分からない。
かたや、
マーティン・バナールの 『黒いアテナ』 (1987) なんかは、
もともとギリシャの神々はアフロ・アジアの黒人だったのだ!
…みたいに主張しました。
実際のところ、
ギリシャ文明にせよ、ヘブライズムにせよ、
それは西欧文明の起源というより、
本来はオリエンタルな異文化だったはずです。
◇
◇
最後に、
9月に発表された凜の曲のことも書いておきます。
3rdシングル「涙、かくれん坊」は
武部聡志&一青窈によるオリエンタル路線でした。
おのずから由貴ちゃんや一青窈の楽曲の雰囲気に似てくる。
もともと武部は凜の歌声を「エアリー」と評してたけど、
これを聴くと彼女が 「n」 の鼻音を出せる歌手だとわかります。
かくれん坊の「ん」の音だけでなく、
「ぜんぶ」「つつんで」「ゆけるんだ」「なれるんだ」など…
重要な箇所で「ん」をしっかり歌えなきゃいけないからですが、
あえて、そういう楽曲にしたんでしょうね。
それこそカエターノ・ヴェローゾなどは、
こういう鼻音を得意としているわけですが、
日本人には、そういう歌手は少ないかもしれません。
そこが凜の歌手としての特性なのだろうな。
姪でなければ許されないイジり物まねw
— まいか (@JQVVpD7nO55fWIT) October 25, 2023
かなり失礼ww #斉藤由貴 #芹澤優 #セリコソロ pic.twitter.com/o4oBLBjG5C
泥濘の食卓&大奥。
#水嶋凜 https://t.co/TUn45Mi9oq pic.twitter.com/XY9j9BdkGu
— まいか (@JQVVpD7nO55fWIT) October 30, 2023
由貴ちゃんのときと同じ企画w
— まいか (@JQVVpD7nO55fWIT) October 31, 2023
安里麻里は『氷菓』の監督。 #斉藤由貴 #水嶋凜 #キョコロヒー #泥濘の食卓 #ヒコロヒー #齊藤京子 https://t.co/dvUsqLKckX pic.twitter.com/unyUGQdjZN
◸ news ◿
— 舞台『エウリディケ』 (@eurydice_stage) November 3, 2023
舞台 #エウリディケ
メインビジュアル公開☁️🫧
愛し合うエウリディケ( #水嶋凜 )とオルフェ( #和田雅成 )。
ふたりを待つのは青空か、それとも…
▼2024年2月4日 - 25日...東京・大阪にて上演 https://t.co/NwHp9heonJ
◎他出演者 #栗原英雄 #崎山つばさ #櫻井章喜 #有川マコト #斉藤悠 pic.twitter.com/YBFXF6hCZS
舞台「 #エウリディケ 」に #水嶋凜 さん #和田雅成 さん #崎山つばさ さん #栗原英雄 さんの出演が決定✨
— フジテレビュー!! (@fujitvview) October 24, 2023
演出を #白井晃 さんが担当します🎤
水嶋さんは「感じたことのない悲しみや喜びを経験するのが楽しみ」とコメント😊
2024年2月に上演🎭 @eurydice_stage
▶️記事 https://t.co/RQYtmF4eEJ pic.twitter.com/SZCcTLfHlg
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurydice_(Ruhl_play)


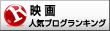

-
當真あみが「青春という名のラーメン」で… 2024.10.08
-
黒島結菜版「時かけ」&萌音・萌歌・紘菜… 2024.10.02
-
斉藤由貴×武部聡志「水響曲~夏」&高見沢… 2024.07.28
PR
キーワードサーチ
カテゴリ









