2012年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

タヒチスイカ 収穫
8月15日に紹介したタヒチスイカ。あれから順調な生育を続け、ついに収穫の時を迎えたのでここに紹介したい。今回、正常に収穫できたものは4個。ただ、さすがに一人で平らげるのは無理があるので(笑)、そのうち3個は職場に持って行くことにした。もともと職場では私がスイカを栽培していることを話しており、収穫できたら職場に持って行くと公言していたのだが、約束通りに持って行くことができたわけだ。 こちらが収穫1個目。市販品よりやや小さめだが、中身はしっかり赤くなっていて、自分でおいしくいただいた。 こちらは1個目を収穫した翌日の畑の様子。カラスよけにネットを張ってある。普通の縞々模様のスイカはカラスに狙われやすく、神奈川時代に私も1個やられたことがある。黒皮のスイカはカラスにはスイカだと認識されにくいと言われるが、やはりカラスは頭がいいようで、最近では黒皮スイカが被害に遭った事例が出ている。 こちらが2個目。市販品と比べても遜色のない大きさ。これは職場に持って行って一部部署で非公式におすそ分けしたところ、非常に好評だったので、これなら全職場の人に自信を持ってお出しできると確信した。 というわけで、最後まで残しておいた自信作の3個目と4個目を収穫。特に画像の右側のものは、大きさと言い見栄えと言い、今まで私が作ったスイカの中では最高の出来だ。 そして、会社の昼食の時間に満を持してお披露目。これがかなり大好評で、私は鼻高々だったのは言うまでもない(笑)。食感、糖度ともに満足のいくもので、収穫のタイミングがぴったり合ったようだ。職場の人には、私がスイカを育てたということが信じられない人もいて、いろいろと質問されてちょっとご満悦状態(笑)。 ところで、今回は実は失敗作もある。正常に収穫できた4個のほかに、あと5個も結実していたのだが、うち1つは収穫時期が遅すぎてツルが枯れてしまい、それに気付かなかったために収穫が遅れ、中身が腐り始めていた(泣)。その果実の大きさは1個目と同じぐらいで、中身はしっかり赤くなっていただけに、惜しいことした・・・。あとの4個は大きさはハンドボール大なのだが、すでに株全体の老化が始まってツルが枯れかかっているために、収穫時期を迎える前にツルが枯れてしまうはずだ。本来は、このような結実時期が遅かったものは摘果した方がもっと品質の良いスイカが収穫できたはずなのだが、とにかくツルの勢いがすごく、どの果実がどの株に成っているのかが判別できなかったのと、たくさん結実したことに気を良くして(笑)摘果しそびれてしまった。それでもしっかり4個収穫できたのだから良しとしよう。 あと残っているのは例の種無しスイカだ。こちらはこの日記執筆の時点ですでに2個収穫しているのだが、実に面白い結果になったので後日紹介したい。
2012.08.27
コメント(0)
-
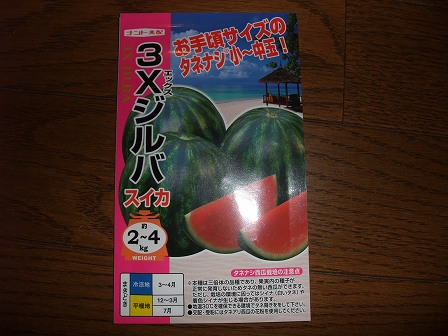
種無しスイカ 3Xジルバ 結実中
昨日のタヒチスイカに続いて今年のスイカ栽培報告第2弾。今回はぬゎんと「種無しスイカ」なのだ。私が中学3年生の時に、種無しスイカができるからくりを生物の参考書で知って以来、ぜひとも挑戦してみたいと思っていたのだが、このたびめでたく実現することに。実は、正確には3年前にも一度挑戦したのだが、種子が3倍体のためか種皮が分厚く、それが原因なのかどうかわからないが発芽率が悪く、せっかく発芽した個体もうまく育たず、あえなく失敗に終わった。が、今年は別の品種を入手して再挑戦することにした。 というわけで入手したのがナント交配の「3Xジルバ」である。小玉の種無し品種で、皮は虎模様になる。ちなみに、ナント種苗ではほかに何種類か種無しスイカの種子を扱っている。ちなみにこの種子のお値段はいくらかというと、ナント(笑)千円なのだ。もはや失敗は許されない。 植えた苗は2本。こちらも下仁田ネギのコンパニオンプランツ付き。この品種は3倍体のせいか、葉が普通のスイカに比べて若干大きい。タヒチスイカと同様、こちらも無数のツルを茂らせている。 ところで、実は種無しスイカを育てるには絶対に忘れてはならない作業がある。それは、普通の2倍体のスイカの花粉を交配すること。これをしないと3倍体の品種は結実しないのだ。つまり、種無しスイカを栽培するためには、普通のスイカも同時に栽培しなければならないのだ。花粉親にする品種は種有りスイカなら何でもよい。私が「授粉樹」として使ったのはもちろん例のタヒチスイカ。で、7月下旬ごろ、3Xジルバに雌花がたくさんついたころ、早起きして出勤前にせっせと人工授粉をしておいた。が、化成肥料をやりすぎてツルぼけしてしまったのか、現在のところ確実に結実が確認できているのはたったの2個。 それでもその2個は両方とも品種本来の大きさに育っている。というわけで、ここにサカタのタネとナント種苗のコラボレーションが実を結んだというわけだ(笑)。まあとにかくツルがすごい勢いで繁茂しているために、畝の中央部までは結実しているかどうかが確かめられない。あと1~2個ぐらいは着果していてほしいものだが。さて、生まれて初めて食べる種無しスイカがどんな食感なのかが楽しみだ。
2012.08.16
コメント(0)
-
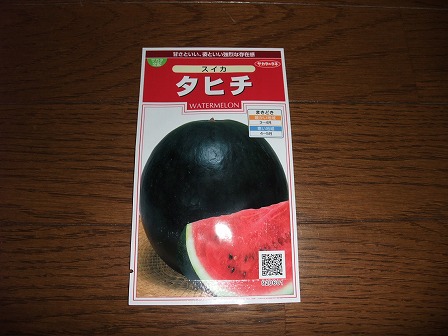
タヒチスイカ 結実
私は2007年以来、毎年スイカを作ってきた。もともとは、2006年にタイに旅行に行き、屋台で食べたスイカがおいしかったので、成田空港の検疫を通して種子を持ち帰り、毎年自家採取を繰り返していたもの。2007年8月には最高の味のものが収穫できたのだが、やはりあのスイカはF1だったようで、毎年形質が劣化していき、2010年夏には他の品種と交雑したようで、昨年の2011年には果実の形が変わってしまった。というわけで、今年は市販種子を買って「正攻法」で行くことにした。 とはいっても、普通のスイカでは物足りないので、黒皮スイカとして近年人気が出ている「タヒチ」を育てることに。前々から気になっていたのは、その品種名の由来。ネットで検索しても、リゾート地で有名なタヒチ島でスイカが栽培されているという情報が見当たらない。こういう場合は発売元に直接聞いた方が早い。サカタのタネの話では、この品種は「夏」や「日焼け」をイメージして「タヒチ」と命名したとのこと。それを聞いて納得した。 種子を蒔いた日は正確には記録していないが、上の種子の写真を撮ったのが5月20日なので、確かその日に蒔いたと記憶している。スイカの蒔き時期としてはやや遅めだが、成田市の砂質土壌と相性がいいのか、かつて神奈川県在住時には見たこともないほどの勢いでツルが繁茂している。ちなみに成田のお隣の富里市はスイカの産地として有名である。アフリカの砂漠生まれのスイカには、やはり砂質土壌が合うらしい。 現在、市販品に近い大きさのものが4個、やや小ぶりのものが4個の計8個の着果が確認できている。植えた苗の数は、1ポット2本植え×2ポットで、当初は生育の悪い方を間引いて最終的には計2本にするつもりだったのだが、仕事が忙しくて手入れに行けない間に4本ともすごい勢いで生育してしまい、間引くのがもったいなくて(笑)結局4本とも育てることになった。 本来、品質の良いスイカを収穫するためには、正しく整枝したり、子ヅルの何節目に着果させるとか、1株当たりの着果数は何個がいいとか、追肥はいつがいいとか、いろいろと伝統的に培われた栽培技術というものがある。しかし、ここまで無数のツルが茂ってしまうと、もはやどの果実がどの株に成っているのかを判別するのがほぼ不可能(笑)。まあ、少なくとも、人様に堂々とお見せできるものが4個成っているということで良しとしよう。 余談だが、現在ではスイカは病気に強いカンピョウやカボチャなどに接ぎ木して栽培されるのが主流となっている。園芸店やホームセンターに売られるスイカの苗も、100パーセントが接ぎ木苗だ。私が中学生のころは近所の種苗店で自根苗が1ポット50円で売られていたが、少なくともここ10数年、スイカの自根苗が売られているのを見たことがない。味に関しては何と言っても自根栽培のものが最高だ。やはり「他の野菜」の根を借りて育ったものはどうしても味が落ちてしまうのは否めない。私のスイカはもちろん自根栽培なので8月下旬の収穫時期を楽しみにしている。なお、種子を蒔くときにツル割れ病防止のコンパニオンプランツとして下仁田ネギを一緒に植えてある。ネギがスイカのツル割れ病防止に効果があると言われ、すでに混植が常識になっている産地もあるという。というわけで自根栽培に挑戦される方は、ネギと一緒に植えることをお勧めしたい。 ちなみに、2枚目画像の右上端に見えるのは別品種の「種無しスイカ」である。これについては後日紹介したい。
2012.08.15
コメント(0)
-

C. dowiana aurea 開花
カトレア原種のC. ドウィアナ・オーレア(Cattleya dowiana aurea)が開花した。3年ぐらい前に買った小さな実生苗を育ててきたもので、今回が初開花となる。 ご覧の通り、大変色鮮やかな花を咲かせるのが本種の特徴で、カトレア原種収集家の間でも人気が高い。芳香も素晴らしく、カトレア原種の中では特に強い香りを放つ。個人的にも、カトレア原種の中では私の一番のお気に入りである。洋蘭栽培を本格的に始めた高校生の頃に初めて本で見た写真に、この世にこんな美しい花があるのかと大きな衝撃を受けたものだ。過去に、ドウィアナ・オーレアの選抜個体を大株にして豪華に咲かせたことがあったが、その後、欲張って小さく株分けしたがために、全滅してしまうという痛い思いをしている(泣)。今回は実生の初花ということで花がきれいに開いていないが、来年はもっと豪華に咲かせてみたい。
2012.08.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 花や風景の写真をアップしましょ
- 東京の今朝の天気、神代植物公園の秋…
- (2025-11-25 06:59:58)
-
-
-

- 花のある暮らし・・・
- グラス植物の株分け後の様子や植え込…
- (2025-11-25 00:00:09)
-
-
-

- 今日見つけた“花”は、なあ~に?
- 昨年と今年のシクラメン
- (2025-11-24 08:40:45)
-






