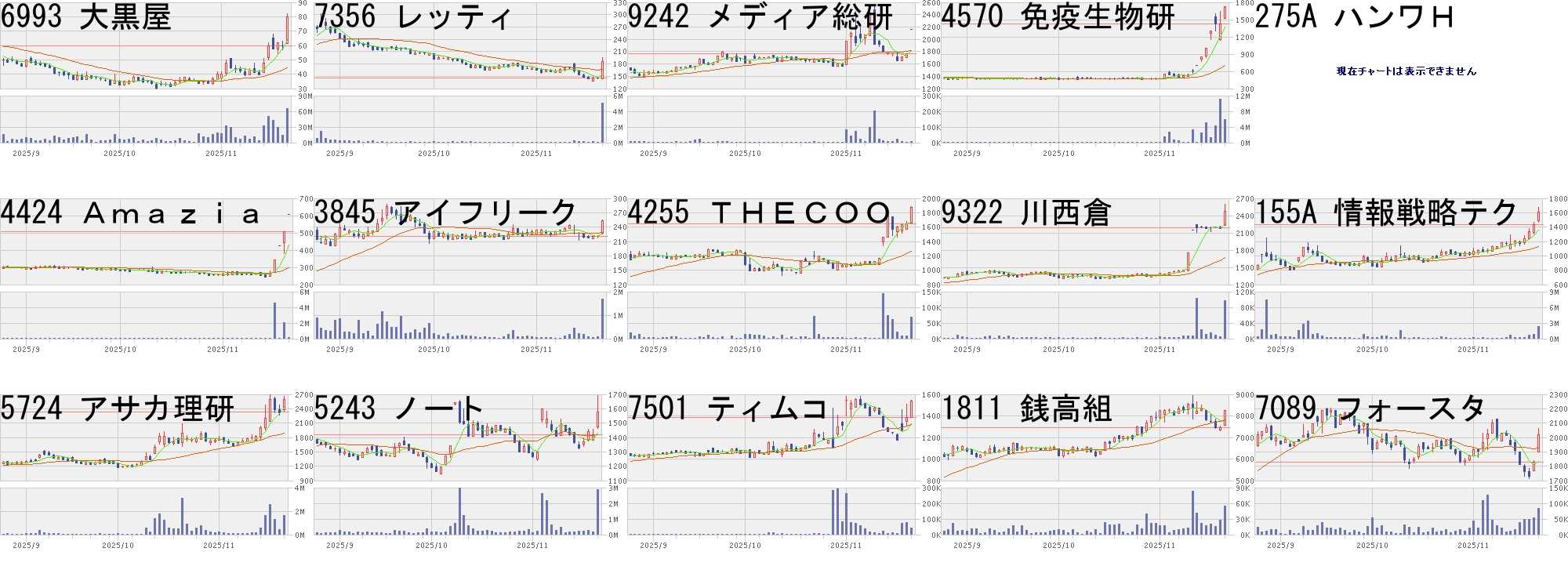2023年04月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

スクーターで山に行って鳥の写真を撮って笛も吹いてきた
奥多摩の三頭山に行ってきました。何度も登っている手軽な山ですが、今回は初めてスクーターで登山口まで行ってみました。ある程度朝早く出発したのですが、結局着いたのは9時半頃でした。山登りとしてはごく手軽な山ですが、着く前に疲れていたり。これも東京都です。東京の本土唯一の村※である東京都檜原村に属しています。※伊豆諸島は大島町と八丈町以外はすべて村ですが。一挙にムシカリ峠へ。標高約1400m。峠から山頂までの間で1500mの標識。山頂に到着。1524m(実際には、これは西峰であり、中央峰が1531mで本当の最高峰なのですが、何度も登っている山なので、今回は中央峰はパスしました)ややかすんでいますが、富士山が見えます。東京都の最高峰雲取山です。鷹ノ巣山石尾根の山々。実は今回、14年ぶりに新しい登山靴を買ってしまいました。今回はその履き慣らしも兼ねています。ツツジがあちこちに咲いていました。これは、検索した限りではトウゴクミツバツツジではないかと思います。今月は4月2日の鳥写真を間違って3月分てして公開してしまったので、4月の鳥写真は今回だけになります。ミソサザイ。あちこちでさえずっていました。ミソサザイ。尾羽を上に立てる独特の姿勢でさえずっていました。笛練習1か所目笛練習2か所目。2か所目の笛練習場所(展望台)からの眺め。ところで、都民の森は奥多摩周遊道路の途中にあります。奥多摩周遊道路はバイクツーリングの人気スポットで、多くのバイクが走っています。うねうね道をバイクがいっぱい走っていくわけです。往路(登り)はともかく、帰路(下り)はカーブでスピード出すのはなかなか怖くて、直線はともかく、カーブに来ると、どうしても40km/hくらいまで減速しないと曲がれません。って、そもそも制限速度が40km/hですけど(爆)。ミッションバイクにはずいぶん抜かれました。事故らないように気を付けて帰りました。(でも、うねうね道を走るのって、確かにちょっと楽しいです)山としては超入門編の手軽な山ですが、復路のスクーターがへとへとに疲れました。これまでなら帰りのバスでグーグー寝ているところですからね。
2023.04.29
コメント(3)
-
もう元には戻らないだろう
日本の将来推計人口、50年間で3割減 1割は外国人に厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は26日、2070年まで50年間の将来推計人口を公表した。20年に1億2615万人だった総人口(外国人含)は、56年に1億人を下回り、70年には8700万人で現在より3割減少する。前回推計(17年)より平均寿命の伸びと外国人の増加で減少ペースはわずかに鈍化した。だが、40年代以降は高齢化率が4割近くに高止まりし、超高齢化の進行に歯止めはかかっていない。中位推計では、推計の前提となる70年の合計特殊出生率を1.36と見込み、前回推計の1.44(65年)から下方修正した。同様に70年の平均寿命は男性85.89歳、女性を91.94歳とし、一定の伸びを想定した。外国人は国勢調査の前年までに入国超過数が急増したことを反映し、40年まで年間16.4万人増とした。70年には10人に1人が外国人となる計算だ。70年の出生率は、20年実績の1.33からは微増を見込む。ただ、日本人女性の生率は上がらず、微増は外国人女性の出産による影響という。出産世代の人口減少に伴い、日本人の出生は38年に70万人、48年に60万人を下回り、59年に50万人割れとなる。65歳以上の人口は43年に3953万人でピークとなるが、その後も高齢化率は緩やかに上昇し続ける。20年の28.6%が、70年には38.7%まで上昇。その一方で現役世代に当たる15~64歳は同期間に59.5%から52.1%まで減る。20年に現役世代2・1人で1人の高齢者を支えている構造は、38年に1.7人に1人、70年には1.3人と「肩車型」になる。同研究所は今後100年間の長期参考推計も公表。2120年の総人口は4973万人で、5000万人を割り込むとした。---2070年といえば、私は100歳を越えるので、まず生きてはいないでしょう。しかし、うちの子は60代なので、多分生きているでしょう。その時代の人口予測が8700万人ですか。日本の人口は2008年に1億2808万人だったのをピークに、15年続けて減少しています。引用記事では2020年に1億2615万人とありますが、最新データでは、2022年11月現在で1億2491万人なので、すでにピークから300万人以上減少しています。そして、引用記事の指摘を待つまでもなく、人口が再び増加に転じる可能性はありません。少子化対策を頑張れば、人口減のスピードを緩めることは可能ですが、人口増に転じることはとうてい不可能です。唯一可能性があるのは大幅な外国人移民の受け入れですが、いくつかの点から可能性は低く、かつ効果は限定的でしょう。可能性が低い理由はいくつかあります。排外主義的な連中が外国人の大量受け入れは拒もうとするでしょう。いや、排外主義的な連中だけではないかもしれません。私ですら、日本の人口の4割5割あるいはそれ以上が外国人(出身者)になることを、ものすごく好ましいかと言われれば、腹の底から「そのとおり」とは言えないのが正直なところです。それに、人口減少とともに日本がさらに貧しくなっていけば、外国人にとっても魅力に乏しい国となり、多くの移民が押し寄せる、ということはなくなるでしょう。更に、少子化は東アジアの中国、韓国、台湾に共通した問題で、特に中国は今年人口減に転じたことが報じられています。つまり、移民すら各国で「取り合い」になる可能性があるわけです。そこに本は勝てるでしょうか。効果が限定的であるのは、外国人の出生率が高いのは、移民第一世代だけだからです。体感的に考えて、子沢山の在日フィリピン人、ブラジル人などは見ても、その子どもの世代で子沢山という実例は見たことがありません。また、米国の例を見ても同じことが言えます。米国は1970年代以降ヒスパニック系が急増し、今ではスペイン語話者数がメキシコ、スペインに次いで世界第三位というスペイン語国でもあります。そのヒスパニック系の出生率は白人などに比べて大変高いと言われてきました。しかし、統計を見ると、1990年代には2.9前後もあったヒスパニック系の合計特殊出生率は2008年頃から急落し、2017年には2ぎりぎりです。それでも白人(非ヒスパニック系)より若干高いものの、もはや大差ではなくなっています。これらの点から考えても、外国人大量受け入れという手段が、少子化の完全な解決策になるとは言えません。ただ、それ以外に効果の大きい解決策があるかというと、なかなか難しいもがありますが。選択的夫婦別姓制の導入、非嫡出子差別の撤廃、保育園の増設などは、結婚や子育てへの障害の除去という意味で重要と思いますが、それだけで劇的に出生率が上がる、とは想定しがたいものがあります。少子化の流れは先進国から今では一部中進国にまで及んでいるので、全世界的な現象ではありますが、中でも日本の状況が特に深刻なのは、やはり長く続く経済不振による、若年層に不安定雇用が多いためでしょう。特に団塊ジュニア世代(わたしも、世代という意味では概ねその端くれに位置しますが)の就職時期に不況は特に厳しく、結婚も出産もできず、という人が大量に生じたことは大きかったでしょう。今となっては、経済不振だから人口が減る、人口が減るから経済も回復しない、と負のスパイラルに入っているような気もします。結局、多分人口減を根本的に止める手段はなく、ただかろうじてその減少幅を緩めつつ、人口減を前提に、それに適応した社会のあり方に変えていくことで破滅的な事態を回避するしかないのでしょうね。回避できるかどうかも分かりませんけど。
2023.04.27
コメント(6)
-
泉代表じゃダメでしょう
立憲「補選全敗でも責任取りません」執行部に不満噴出、「枝野さん」トレンド入りで再登板望む人も4月23日に投開票された衆参5補選で、立憲民主党は、公認候補を出した千葉5区、山口4区、大分選挙区で敗北。山口2区では、無所属で出馬した平岡秀夫氏を菅直人元首相ら有志グループが支援したものの、党本部は及び腰で敗北。和歌山1区では候補者を擁立せず、日本維新の会に議席を奪われることとなった。同時におこなわれた市議選で獲得議席数を大きく増やしたこともあり、立憲の執行部で責任論が出てくる様子はない。岡田克也幹事長は、24日未明、「特に足らなかったところは思い当たらない。非常にいい戦いができていた。あとは自力の問題かもしれない」と述べた。党執行部の責任について、「この補選で責任を取るとかそういう話ではない。私も代表から言われない限りは幹事長を続けることで、次の総選挙で結果をしっかり出したい」と記者団に語った。(以下略)---共産党に絶望したにもかかわらず、結局また共産党に入れてしまった理由の一つには、泉代表の立憲民主党じゃ、支持する気にならない、という側面もあります。個々に議員を見れば、支持できる人もいますけど。以前にも書いたことですが、「愛国リベラル」「愛国左派」と自称して泉代表が乃木神社に参拝したことには、私は心底がっかりしました。もちろん、理論的に言えば泉がどこの神社を参拝しようが、それは泉の自由です。だから、「乃木神社に行ったことがけしからん」と批判はしません。ただ、投票しない自由を行使するだけです、ということに尽きます。そもそも、「愛国」を自称して乃木神社に行くという行為は政治的に愚策です。要するに、左翼、リベラル票は無視しても右翼層の票を取り込もうとしたわけです。ところが、実際には右翼層はほとんど固定観念的に、立憲民主党という名前を聞いただけで「大嫌い」となる。そこにいくら媚を売ったところで、振り向いてはくれないのです。媚を売っても支持してくれるはずのない人たちに媚を売り、そのために元々の支持層を切り捨てるのでは、どっちを向いて支持を訴えているんだ、と言わざるを得ません。しかし、岡田幹事長は「特に足らなかったところは思い当たらない。」のだそうです。たりないところがなけれは補選全敗(策に旧社会党の牙城だった大分)なんてことにはなっていないと思うんですけどね。なお、引用記事にある市議選で議席数を大きく伸ばしたというのは、おそらく前半戦の道府県議選と同じではないでしょうか。道府県議選では、前回統一地方選後より当選者が増えましたが、これは前回統一地方選以降に旧国民民主党の大半の議員が立憲民主党に合流した(泉代表もその一人)ためです。旧国民民主党合流前より当選者数は増えましたが、合流以降の議席数からは減っています。だから、議席数が増えたにもかかわらず不振と報じられました。市議選も、おそらくこれと同様で、議席数が増えても勝ったわけではない、というところではないでしょうか。
2023.04.25
コメント(0)
-
有言不実行の男
本日は例によって朝6時過ぎから夜9時近くまで仕事でして、疲れているのでごく簡単な記事のみ。先日、期日前投票に行きましたが、あれだけ「二度と共産党には投票しない」と言っておきながら、まあいろいろ思うところがあって、結局は共産党の候補に票を投じてしまいました。我ながら、有言不実行ですね。松竹氏の除名に対する私の意見は変わりませんが、消去法的にやむなく入れた、というところです。ただし、若干失敗したのは、期日前投票にギリギリの時間に行ってしまったため、各候補の選挙公報をよく読まずに票を投じてしまったことです。しかし、改めて選挙公報を見直してみると、共産党以外にも、少なくとも1人、「この人なら投票してもいい」と思える候補がいました。事前にそれに気づいていても共産党に入れたかどうかは、自分でも分かりません。もちろん、だらと言って共産党の候補に投票したことを間違ったとは思っていませんが。明日も仕事だ。今も疲労は多少ありますが、過去の経験則から言って、明日朝はもっとヘロヘロになってます。もう風呂に入って寝よう。補足「二度と共産党には投票しない」と言っておきながら前言撤回した理由は、消去法的にやむなく入れたのですが(詳細を書いていくと、共産党以外のX党が候補者を出している/出していない、Y党は候補者を出している/いないの組み合わせから、私の住んでいる自治体が、特定はされないけれどある程度絞れてしまうため、これ上は書きません)、それ以外にもう一つ無視できない理由があります。別記事のコメント欄にも書きましたが、松竹氏除名について公然と異を唱えている地方議員、公然とではないけれど異論をほのめかせている議員が何人かいることは以前から認識していました。しかし、改めて松竹氏のFacebookを見てみると、「赤旗」が松竹氏非難の記事を連日繰り返した後の現在でもなお、国会議員を含む議員、元議員、かなり熱心に活動している党員や支持者が、数多く「友達」登録を維持しています。このことは、最近まで気が付いていませんでした。(ちなみに、私は友達申請したのですが、承認されていません。いろんな人からの反応が増えて、それどころではないのだろうと思います)党中央が「敵」認定しても、敵とは考えない党員も議員も案外多い、やはりそれなりに規模の大きい政党だけに、幅は決して狭くはないなと思いました。正直言って、投票した人自身がこの問題にどういう意見を持っているかまでは調べ切っていません。ただ、党中央が「除名」と言えば前議員が一斉に「除名賛成」となっているわけではない、という事実を踏まえて、とりあえず地方選に関しては前言撤回することにしました。国政選挙については…今後の展開も見て、またその時に考えます。
2023.04.23
コメント(0)
-
確かにそれはよくないが
着物イベントの「左前」ポスターが物議 「死に装束」指摘も...制作元は修正否定「ファッションに決まりない」東京・銀座で開かれる予定の着物イベントのポスターについて、イラストの着物が左前になっていると、ネット上で疑問が相次いでいる。左を手前にして着る左前は、「死に装束」とされていることが理由だ。イベントの運営会社は、「着物は、もっと自由でいいと思っています。ポスターはイメージで、深い意味はありません」と取材に説明している。ポスターでは、花を背景に、黒髪の少女がピンクに近い色の着物を着ている上半身のイラストが描かれている。イベントは、「銀座今昔きもの大市」と題して、2023年5月12~14日に開かれる予定だ。公式ツイッターでは、4月17日にポスター画像を載せてイベントをPRした。ところが、この画像に対し、リプライ欄で突っ込みが相次いだ。「それ死装束じゃ......?」「左前は駄目でしょ」「これでよくGOサイン出したな」さらに、着物の中にシャツらしきものが見える、などと違和感を訴える声も次々に寄せられた。(以下略)---洋服だと、男物と女物で左右逆ですが、和服だと男だろうが女だろうが必ず右前で、左前はダメ、というのは、知らない人にとっては若干分かりにくい部分もありそうです。多分、男性より女性の方が間違える危険がありそうに思います。男性なら洋服でも和服でも重ね方は同じですが、女性は洋服と和服で逆になるからです。ともかく、こういうことは表現の自由とか、自由にコーディネイトしていいなんて言っても仕方のないことです。死に装束を生きている人間がするのは、驚いたり悲しんだり不快に思うことがいっぱいいるのですから。という、実に当たり前のことを、こういう話だとたいていの人が当たり前に理解し納得するものです。ところが、これが性的なイラストに対しての批判になると、途端に「表現の自由だ」「フェミナチだ」「リベラルの奴らがポリコレを押し付ける」などと叫び始める輩が現れるのです。不思議なことです。性的なイラストを公の場に掲示する表現の自由があるなら、左前の着物の女の子のイラストを掲示する表現の自由だってあるはずですよね。左前の着物のイラストが批判の対象になるのに、スカートの中が透けて見えるようなイラストは批判の対象にしてはいけないと、どうしてそんなふうに思えるんでしょうかね。どちらの場合も、自由な表現としてのイラストではなく、あくまでも商業的イベントの宣伝と手段としてのイラスト、つまり広告です。ならば、購買層に不快感を抱かせたら目的を果たしていない、失格ということになります。その意味で、どちらも失格だと思うのですがね。
2023.04.21
コメント(4)
-
安全保障問題はやっかいだが逃げられない
松竹伸幸氏と鈴木元氏除名の件で共産党に対しては心底絶望している私ですが、共産党系(と世間一般には言われている)団体の末端の末端の、そのまた末端の役員をしていることもあり、党員、熱心な支持者、何人かの地方議員の知り合いもいます。(さすがに、国会議員の知り合いはいません)そんなわけで、共産党に対する批判は自分自身にもすごく痛みを伴うものです。そのため、長年票の半分を投じてきた政党を批判することには、わたしなりにかなり葛藤があり、私の主観としてはかなり批判のボルテージも抑制しているのですが、それでも許せない、という方から猛批判をいただきました。ブログで主義主張を前面に出している以上、その主張に対する批判があるのは当然のことですが、味方、あるいはそう思っていた人と争うのは心楽しくないものです。いや、先方はとっくに、味方とも何とも思っていないのだろうということは承知していますけど。さて、前置きが長くなりましたが、私が共産党に対して絶望したのは、松竹氏を除名した点についてのみ(鈴木氏もですが)です。共産党の主義主張に絶望したわけでは、必ずしもありません。多分共産党中央、あるいは熱心な支持者は、松竹氏と共産党中央の主張は全面的に相いれないと考えているから除名した(あるいは除名に賛成)のでしょう。しかし、他党の例を考えれば、辻元清美と泉健太と松原仁が同じ党にいるのが立憲民主党です。あるいは、かつて三木武夫や宇都宮徳馬と石原慎太郎などが同居していたのが自民党です。共産党中央と松竹氏の主張の隔たりが、それらの党より大きいとは、私には思えません。そしてもちろん、松竹氏の主張がすべて正しく、共産党中央の主張がすべて間違っている、ということもないと私は考えています。逆(党中央の言い分がすべて正しく、松竹氏の言い分がすべて誤っている)もないと思っていますけど。というより、どちらが正しくどちらが間違っている、という問題てはないでしょう。何に力点を置くべきか、何を重視するか、というのはかなりの程度主観、価値判断の問題であり、正解も不正解もありません。で、私は以前にも書いたように、松竹氏の主張を共産党が政策に採用しないこと自体は仕方がない面もあると思うわけです。しかし、そのことと、党から除名という形で追い出すことは、イコールではありません。その程度の意見の多様性を許容できない党が、社会の様々な場面で多様性を守ることができるのか、と危惧しますし、より多様な意見の持ち主からできるだけ多くの支持を集めるという方向性とは、まるで逆行します。さて、松竹氏と共産党中央の主張は全面的に相いれないわけではないはず、と書きました。共産党は、現在でも天皇制の廃止、日米安保破棄、自衛隊の解散などを綱領に掲げています。が、それらの政策が実現できるとは、共産党自身も思ってはいないでしょう。実際、政権を取ってもそれらの綱領を強行などしないことは野党共闘路線以前から明言しています。とりわけ、2015年に野党共闘路線にかじを切って以降、党固有のこれらの政策は野党共闘政権には持ち込まない、と言っています。言い換えれば政権を取るに際してはこれらの主張は凍結、あるいは棚上げするということです。日米安保容認が右翼分子なら、日米安保容認の立憲民主党も右翼分子だし、共産党が全力で支援している沖縄県の玉城知事も、前任の故翁長知事も右翼分子、ということになってしまいます(玉城知事翁長知事とも、日米安保については容認を明言していた)。ということは、立憲民主党やオール沖縄と共闘して、政権獲得の暁には日米安保破棄の政策も凍結すると言っている共産党自体も右翼分子になるのではないか、という疑問は当然湧きます。党固有の政策(主張)自体を変えることと、主張は変えないけれど棚上げすることの違いは、共産党中央やその熱烈支持者には大きいのかもしれませんが、外部からは大した違いには見えません。その程度の差で異論の持ち主を除名するのでは、むしろ「野党共闘に党固有の政策は持ち込まない」という言い分自体に疑念を抱かれることにもなりかねません。共産党が宮本体制以来の、他党すべてを敵視する「確かな野党路線」から野党共闘に路線を変え、主要な共闘相手を安保容認の旧民主党系に定め、しかも政権を目指すと言い始めた時から、党固有の主張と政権の政策の二律背反は常について回り、今後もついて回る問題です。野党共闘路線を捨てて、かつての一党孤立路線に戻るのであれば、その二律背反は解消します。玉城知事も安保破棄を目指せ、拒否するならオール沖縄からは脱退だと言えば、その時には、確かに松竹路線と党中央の路線は「相容れない」くらいの違いとなるでしょう。しかし、その先に待っている未来は、絶望しかないのではないかと私は思います。政権を目指す(政権の一角に参加するだけだとしても)と決めた以上は、現実と理想の折り合いをどうつけるか、という問題から逃げることはできません。どんなに理想的な政策を並べても、政権に就いた途端に、それを一つも実現できなかったとなれば、支持はあっという間に失望に変わります。2009年にあれだけ大勝した旧民主党は、別に日米安保破棄とか自衛隊解体なんて革命的な政策を掲げていたわけではありませんが、「普天間基地の県外移設」という、実に控えめで穏健な主張すら実現することができず、それだけが理由ではないにしても、決して小さくはない要因となって、政権が崩れていきました。さて、私は当ブログで以前より何度も書いてきたように、憲法第9条は日本にとって必要な規定である一方、自衛隊も日本にとって、少なくとも現在の国際情勢下において必要な存在であり、したがって自衛隊は合憲である、と考えています。私も、10代のころは単純に自衛隊は憲法違反だから解散すべき、と考えていたこともあるのですが、少なくとも20世紀の終わりころ以降はずっと、上記のように考え、主張もしてきました。一方で、私は日米安保体制は脱却して非同盟中立の日本を目指すべき、とも考えています。決して、非武装中立ではなく、非同盟・軽武装中立です。これもそのころからの一貫した考えであり、そこが松竹氏の主張に近いので、非常に魅かれたわけです。共産党にもこんな意見の人がいるんだな、というのも新鮮な驚きだったし、そういう意見の持ち主が党員でいる共産党の懐の深さ、幅の広さも魅力を感じました。もっとも、後者の中立ということに関して言えば、この1年のロシアのウクライナ侵攻をみて、かなり動揺したことは事実です。もちろん、日本はウクライナと違ってロシアとの間には海というものがあります。ロシアの海軍力はかなり弱いので、ウクライナに対して行ったような陸路大軍を送り込むことは不可能です。「ある日北海道にロシア軍が」などというのは妄想の類にすぎないわけですが、陸軍が大挙上陸してくるだけが戦争の形ではありません。航空攻撃もミサイル攻撃も戦争の形だし、潜水艦による海上交通破壊も戦争の形です。それでも、自衛隊に一定の防空能力と対潜水艦戦能力があれば排除できるとは思いますが、いずれにしてもロシアと(ほかの国でも同じですが)戦争になったら、経済へのダメージは極めて深刻なものが予想されます。日米安保体制からの脱却を目指すべきという私の考えはそれでも変わりませんが、それに対する賛同が極めて少ない、ロシアの蛮行によって更に少なくなったことをひしひしと感じることもまた事実です。前述のとおり、松竹氏は元々自衛隊は必要だが日米安保は脱却すべき、という主張の持ち主です。しかし、現在日米安保についても、容認に主張を変更しています。そこは、私も残念ですが、理由は分かります。松竹氏もロシアのウクライナ侵攻を見て考えるところは多々あったものと思います。今日米安保破棄を言っても、とうてい実現など見込めない。ならば、核抑止抜きの日米安保容認という、日米安保のかなりの部分を骨抜きにしつつ名目的には維持する策を考えたのでしょう。それだって、毎日新聞の山田孝男特別編集委員(確かそうだったと思います)が「それも実現性はない」と書いていたくらいです。もし実現して日米安保が核抑止抜きの通常兵器だけの安全保障条約に変わったら、日本をめぐる国際関係には相当大きな変化が生じるくらいの大変なことです。それが「右翼分子」なら、世の中のほとんどのことは右翼分子だし、右翼分子ではない政策など、ほとんど実現不可能と言わざるを得ないことになります。ヨーロッパを見れば、長く中立政策を取ってきたスウェーデンとフィンランドが、中立を捨ててNATO加盟を申請しました。周知のとおり、スウェーデンの加盟は、スウェーデンに亡命するクルド人独立派組織との関係でトルコが加盟に反対しているため、現時点では実現していませんが、フィンランドの加盟は実現しました。そうなったのは残念なことですが、その事態を招いたのはあくまでもプーチンの蛮行である以上、両国が中立を捨てたことは残念ではあるけれどやむを得ないものです。で、NATO加盟を申請した政権はスウェーデンの社会民主労働党とフィンランドの社会民主党です。そして、両国の共産党の後身政党であるスウェーデンの左翼党、フィンランドの左翼同盟はNATO加盟に反対はしましたが、徹底的な反対はしていません。というのはスウェーデン左翼党は閣外協力、フィンランドの左翼同盟は連立政権の一員ですが、NATO加盟を決めた政権への支持を撤回したり、閣僚を引き上げて政権離脱はしていないからです。フィンランドは今月に入って総選挙で社民党が敗北したために下野することが決まりましたが。松竹氏の主張が右翼分子だとすると、両国そして両国の社民党政権もまた右翼分子ということななりそうですが、本当にそうなのでしょうか。もちろん、米国もまた、決して公平な平和の守護者などではありません。この国が過去の歴史でどれだけラテンアメリカ諸国、特に中米カリブの独立と経済的自立を奪ってきたかは、言うまでもありません。しかしロシア(旧ソ連)が東欧諸国に対してに対してやってきたことでも同じです。独善的な大国は、自国のシマと見做した近隣諸国を収奪します。それが米国にとってのラテンアメリカ、ロシアにとっての東欧です。だから、ラテンアメリカ諸国では反米感情が強いし、東欧諸国でも反露感情が強い。そして、近くの敵に対抗するために、遠くの大国に助けを求めるのも通例です。だから東欧諸国はロシアの圧迫に対抗するために米国の庇護を求めてNATOに加盟し、逆に米国の長い圧迫に苦しんだキューバは旧ソ連の友好国となって生き残りを図ったわけです。その生き残り策を批判できるものではない、と私は思います。ただし、ここまで書いたことはすべて、「現下の国際情勢の元では」という注釈付きです。現下の国際情勢は永久不変ではありません。米国が永久に大国であり続けるとも、永久に日本の友好国であり続けるとも限りません。日米安保の必要性重要性は永久不変ではありません。だから、現下の国際情勢の下での政策転換の可能性を探っても実現不可能なことばっかりだから、国際情勢が激変した時に対応して新しい国の姿を目指す、という考え方もあり得るとは思います。もっとも、そのような場合でも自衛隊の必要性がなくなることは考えにくいのですが。人間とは、実に業の深い存在です。殺し合いの道具をたがいに備えて「安全」を保障するのが現実的な政策だ、というのは、冷静に考えればある種の集団狂気としか思えません。かつては非武装中立が理想だと考えていた、今も心の奥にはその理想のかけらは存在する人間としては、「自衛隊は必要」などということには忸怩たる思いはあります。でも、人間の本質が変えられないものであるなら、その範囲内で準備を整えることは、悲しいけれど仕方がないのです。理想を守って滅ぼされるわけにもいかないですから。ただ、それは異常なことだという視点だけは忘れるべきではないと思いますが。
2023.04.19
コメント(18)
-
新聞の衰退
産経新聞 120人希望退職を労組に提示「48歳以上対象」19年にも180人募集…止まらぬ不況"日本から新聞が消える"立法、行政、司法に次ぐ「第4の権力」と言われてきたマスメディアの衰退が止まらない。ネット動画を見る人々の増加で、テレビ業界は視聴時間や広告売り上げの減少に苦しんでいるが、とりわけ危機にあるのは新聞業界だ。部数減から優秀な人材が離れ、質の低下につながるという「負のスパイラル」に陥っている。リストラで窮地を脱しようとする新聞社が相次ぐ中、はたして10年後、20年後も生き残ることはできるのか。「ついに朝日も……」。4月5日、朝日新聞社は、愛知、岐阜、三重の3県で5月1日から夕刊を廃止すると発表した。同社は「朝刊だけの購読希望が増えている」ことを理由としている。ネットメディアの台頭で無料記事を好きな時間に読むことができる時代、その日の昼頃までのニュースを夕方になって読みたい人は少ないだろう。だが、3県での夕刊廃止は、読者ニーズに沿ったというよりも、苦境にある企業の “延命策” と見るべきだ。朝日新聞は1990年代に発行部数が800万部を超えていたが、2022年は400万部を下回った。この約30年間に半減した計算になる。~読売新聞は、直近の平均販売部数が約660万部だ。かつて1000万部の大台を超えていたことを考えれば、その勢いには陰りが見える。2010年に電子版を創刊し、デジタルファーストに転換した日本経済新聞は、電子版の有料購読数を含めれば約247万に達している。逆に産経新聞は2000年には200万部を超えていたが、直近は100万部を下回り、約20年間で大幅に減った。2019年に180人の希望退職を募ったが、更に社経営陣は労働組合に対して、48歳以上の社員を対象に120人の希望退職を募る案を提示したという。保守系の新聞としてファンもいるとはいえ、ネット時代におけるビジネスモデルの転換に失敗している感は否めない。日本新聞協会が発表している新聞の総発行部数によれば、20年ほど前は5000万部近くもあった。だが、2022年の一般紙は2869万部で、前年から200万部近くも減っている。インターネットやスマホの普及とともに、主要各社の売り上げは下降しており、このままのペースで悪化すれば、あと15年弱で日本から新聞が消える計算になる。小手先の人員削減策では対応できないレベルといえ、その前に倒産したり、買収されたりする新聞社が出てくるのは想像に難くない。(以下略)---ネトウヨ諸氏は朝日新聞が「反日」だから衰退していると信じているようですが、現実には、ネトウヨの機関紙たる産経は、朝日新聞と同様に部数は半減です。読売も、2/3以下に減っているので、これも大同小異と言えるでしょう。我が家は結婚した当初から、ずっと毎日新聞を購読していますが、子どもは新聞を読みません。子どもは、就職したら一人暮らしをすると言っているので、そのときにはおそらく新聞はとらないでしょう。デジタル化の進行による紙の新聞の衰退は否定しようがありません。引用記事の後段(引用外の部分)でニューヨーク・タイムズのCEOが「20年後も印刷されていたら驚くだろう」と2020年に発言しているという話は有名ですし、実際にそうなるでしょう。というわけで、紙の新聞が衰退していくことはやむを得ないのですが、問題は、電子版も含めた新聞社(あるいはネットメディアも含めた報道機関)が生き残れるがどうかです。「無料記事を好きなだけ読める」というのは、実際には持続可能な状況ではありません。なぜなら、その無料記事を掲載しているのは、たいていの場合は新聞やテレビ局など既存の報道機関だからです。新聞紙面の一部、報道番組の一部をネット上で広告付きで掲載することで、多少の収入にはなるでしょうが、それだけで採算が取れるレベルではないでしょう。ネット上だけにニュースを流すネットメディア(BuzzFeedとか、J-CASTニュースとか)もありますが、現状ではその取材能力、ネットワークは既存のメディアすべてを置き換えられるほどのものではありません。つまり、もし新聞社やテレビ局がつぶれたら、ネット上の無料記事の配信も大半が消滅してしまうということになります。ツイッターで世の中で起こっていることはみんな分かる、という意見もあるでしょうが、実際にはそうはいかないものです。そうなった場合、紙面を「編集する」という行為が消滅します。百人死んだり、内閣総理大臣が襲撃された事件は大きく報じ、小さな事件は小さく報じる、といった取捨選択は読み手にゆだねられます。読み手が自由に選択する、と言えば聞こえはいいですが、無数にある雑記事の中から重要と考える記事をもれなく探し出すのは案外難しいことです。また、「報じてほしい」ニュースは頼まれなくても提供されるでしょうが、「隠したい」ニュースは隠ぺいされるでしょう。それを系統的に調べて報じるのは、かなり困難でしょう。フェイクニュースをはじくことも難しいでしょう。外国の出来事を日本語に翻訳するのも、それなりに手がかかることです。これらのいずれも、短期的、単発的になら報道機関でなくてもできるでしょうが、長期的継続的にとなると、なかなか難しいものがあります。結局、無料で何でも提供できるものではない、ということに尽きます。というわけで、報道機関というものが社会にとって必要である理由はいくらでもあり、なくなってしまったら社会の健全性を保つのは困難と思うのですが、「必要である=存続できる」となるとは限らないのが難しいところです。その必要性を理解して何らかの形でお金を払う人や組織が一定数以上いなければ、どんなに必要でも存続はできないわけですから。新聞という報道機関の一形態に限定した話ではなく、報道機関全般に、ぜひ消滅するようなことがないようにと願うばかりです。
2023.04.17
コメント(0)
-
このままオリンピック招致は中止で
30年札幌五輪招致 秋元市長「現状のまま進めていくのは厳しい」札幌市が招致を目指す2030年冬季五輪・パラリンピックについて、IOC側が札幌開催は「困難な情勢」と日本の招致関係者に伝えたことに関し、札幌市の秋元克広市長は15日、「現状のまま進めていくのは厳しい状況」との認識を示した。招致を目指す大会については「30年を34年にするとか、そういう結論を持って進めているところではない」と述べた。札幌市内で記者団に答えた。秋元氏は東京五輪を巡る汚職・談合事件で五輪不信が高まっていることを踏まえ「(30年大会招致への)支持率が落ちており、今の状況のままでは招致活動を進められない」と言及。そうした情勢についてはJOCとも「同じ意識でいる」との認識を示した。五輪の運営方法の改善策を示し、今後も市民の理解を得ていく考えも強調した。---私は東京都民なので札幌オリンピックに賛成か反対か、ということをあまり大声で主張しても仕方がない部分はあります。でも2021年の東京オリンピックで、コロナ禍の中一般国民には行動制限を求める一方でオリンピックだけは「特別扱い」にしたこと、巨額の赤字を残し、今後も施設維持の出費が続くこと、そしてオリンピック終了後に表面化した汚職など、まさに汚れ切ったオリンピックになったことについては、きわめて腹立たしいものがあります。東京オリンピックでは、最終的な経費1兆4千億円余とされていますが、会計検査院はこれ以外に、国立競技場の建設に伴う調査費や周辺施設の移転費用、大会施設の改修補助金、日本代表選手の強化費用や開会式の航空自衛隊「ブルーインパルス」によるカラースモークの実施費用なども経費に含めるべきと指摘しており、その合計が3000億円近くあります。なので、実際に経費は1兆7千億円以上となります。それに対して、収入は6400億円しかありません。残りはすべて東京都と国が負担しています。東京都が6000億円弱、国が1900億円弱ですが、そこに会計検査院が指摘した「隠れ経費」を加えれば約4700億円になります。これだけの費用を、結局は都民、国民が負担しています。これほどの赤字を残しながら、同種のスポーツイベントをまたやりたいと考える神経は、私には理解不能です。ただ、さすがに北海道でもオリンピックに対する世論はかなり厳しいようです。世論調査の結果は時期と調査主体によってかなりバラバラですが北海道新聞1月8日札幌オリンピック、札幌市民反対52%+どちらかと言えば反対15%、北海道全体反対42%+どちらかと言えば反対19%でいずれも反対が6割超読売新聞3月7日札幌オリンピックに全国では645賛成も北海道では反対が5割超朝日新聞3月20日全国では「賛成」が60%、「反対」が33%と賛成の方が多かった。地元の北海道も「賛成」が「反対」をやや上回った。というわけで、朝日の調査を除くと、北海道では反対多数、特に札幌では反対多数であり、朝日の調査でも賛成が圧倒的ではなく、「やや上回った」程度にすぎません。開催するのはあくまでも札幌市なので、全国で賛成多数というのはあまり意味はありません。北海道、札幌という実施主体となる自治体の住民に反対の声が大きいということは、実質的にはオリンピックの招致は無理だ、ということです。で、住民は2030年の札幌オリンピックの招致には反対だけど2034年の招致なら賛成するのでしょうか?聞いてみたわけじゃないけれど、そうは考え難いですよね。日本の財政状況も(北海道、札幌市もおそらく大同小異でしょう)、先になればなるほど厳しくなることが容易に予想できるので、2030年に困難なものが、2034年ならやりやすい、という可能性も乏しいように思います。というわけで、姑息に2030年はあきらめて2034年に、などというのではなく、ここはきっぱりとオリンピック招致は白紙に戻すことが必要でしょう。
2023.04.16
コメント(0)
-

新しいヘルメットを買って1か月半で・・・・・(涙)
小型二輪の免許を取る前、当然ヘルメットを購入したのですが(一昨年の秋に購入したはずです)、高いヘルメットを買って免許を取れなかったらもったいないと思って、値段は失念しましたが、5000円か6000円くらいのヘルメットを買いました。これを教習でも、その後免許を取ってからも使っていたのですが、シールドの取り付け部がガタついてきました。安物なので、シールドを交換できるようにはなっていないようです。その他にも、頭よりやや大きめで、どうもフィットはしないことも気にかかっていました。それで、もう1か月半くらい前ですが、新しいヘルメットを購入しました。左の黒いヘルメットがこれまで使っていたもので、右の白いヘルメットが新たに購入したものです。乗っているスクーターはホンダだけどヘルメットはヤマハ製(笑)ヤマハのヘルメットは1万3千円のものと2万1千円円のものがあったですが、かぶってみるとどう考えても2万1千円の方がかぶりやすかったので、奮発して高い方を選択。でも、アライとかショウエイのヘルメットは4~5万円するから、それよりはずっと安いですですが。今までのヘルメットに比べて、圧倒的に頭にフィットする感じです。で、このヘルメットを使っていたのですが、先日、ちょっとした不注意でやらかしてしまいました。事故りました。いえ、嘘です。ヘルメットをシートの上にのせてリアケースの荷物を取り出していたら、なんの衝撃か、ヘルメットがコロコロっと転がり落ちてしまい、シールドがアスファルトの上で傷だらけになってしまいました。落ちた面がシールドだったようで、シールド以外のところに傷はつきませんでしたが。でも、かぶってみたら眼前が明らかに傷だらけ。これじゃ、シールドを上げて走らないと前がよく見えないかも。幸いにして、このヘルメットはシールドは交換可能です。早速アマゾンで購入したのですが、4000円もしました。最初に買った安物のヘルメットより高い、ということはさすがにないものの、ほとんどそれに近い値段がシールド一枚で飛んで行ってしまいました。ああ、次からは落とさないように気を付けなくては。でも、ある意味では、転がったのがヘルメットでよかったですけどね。スクーター本体や自分の体が転がったら、目も当てられませんから。
2023.04.14
コメント(0)
-
本音と建前の乖離
「努力義務」の自転車ヘルメット、「かぶるべき」7割弱 朝日調査朝日新聞社が8、9両日に実施した全国世論調査(電話)で、「努力義務」となった自転車のヘルメットについて、「大人でもヘルメットをかぶるべきか」と聞いたところ、「かぶるべきだ」が68%で、「そうは思わない」が28%だった。自転車のヘルメットは、いままでは、13歳未満の子どもへの「努力義務」だったが、道路交通法が改正され、1日から自転車に乗る人すべてに対しての「努力義務」となった。年代別に見ると、40代以下では、「かぶるべきだ」は5~6割だが、50代以上では7~8割と、年代が上がるにつれ、「かぶるべきだ」が増える傾向にある。---記事は途中までしか掲載されていないので、ひょっとしたら「かぶるべきか否か」だけでなく「かぶっているか否か」も聞いているのかもしれませんが、それは掲載されていません。ただ、「かぶるべき」が7割とはずいぶん高い数字だなと思います。それなら、きっと実際に自転車にヘルメットをかぶって乗っている人の人数も相当多いだろうと思いたくなるところですが、周知のとおり、現状は自転車ヘルメットの着用率は非常に低いです。かなり高速が出るロードバイクなどのスポーツ用自転車は、もともと生活の足というより趣味で乗る側面が強いせいか、従前からヘルメットの着用率はかなり高いと感じますが、それ以外の、生活の足として使われる、いわゆるママチャリなど普通の自転車でのヘルメット着用率は非常に低いです。たまたま、一昨日子どもと二人で隣の駅まで出かけた際に自転車のヘルメット着用義務についての話題になって、歩きながら観察していたのですが、ちゃんとヘルメットをかぶっていたのが1台と、幼児を載せた二人乗りで子どもだけにヘルメットをかぶせていたのが2台でした。それ以外は数十台の自転車すべてノーヘルでした。着用率は1割かそれ以下だったのではないでしょうか。着実にヘルメットをかぶっているのは警官の乗る自転車くらい、というのが現実です。というわけで、皆さんアンケートには「大人でもヘルメットをかぶるべき」と回答するけど、自分が自転車に乗るときはかぶらない、というのが現実、ということになります。矛盾しているけれど、法律で「努力義務」(罰則はないけれど)が定められたものを「必要はない」とはアンケートでも公言しにくい、というところなのでしょうか。多分、この現象を大規模にしたのが、2016年の米大統領選で各調査機関の世論調査がヒラリー優勢と予測したけれど、実際にはトランプが当選した現象なのだろうと思います。もっとも、米大統領選は単純多数ではなく州ごとの選挙人総取りという極めて特殊な選挙制度であり、総得票数では実際にヒラリー48%対トランプ46%だったので、「世論」調査としては間違っていなかった(「選挙予測」調査としては間違っていた)のですが。本題に戻りますと、オートバイの場合は、1965年に高速道路でのヘルメット着用義務(罰則なし)が始まり、1975年には51cc以上で罰則導入、1978年にはすべての道路に対象が拡大され、1986年には50cc以下でも着用義務化となっています。私が生まれる前には、バイクで高速を走ってもヘルメットの着用義務がなかったとは驚きですが、この流れから考えると、自転車も10年後にはヘルメットが罰則付きで着用義務になるのでしょうか。法律というのは、なかなかきめ細かく状況ごとに義務を課したり課さなかったりというのは難しい側面がありますが、正直なところ、40km/hとか50km/hで走るロードバイクならともかく、買い物で使う自転車に、立ち漕ぎではなくサドルに着座して走っている状態で、ヘルメットがなけれゃ危険かと言われると、私はそうは思いません。それを危険と言い出してしまうと、自分の足で走ることにも「ヘルメット着用が」という話になってしまいかねません。走っているときに転んだり人にぶつかったりすれば、それなりにけがをしたり追わせたりする可能性はありますから。実際、街中で歩いていて(多分その瞬間は走ったのでしょう)、転倒して、頭ではありませんが骨折という知人の事例を知っています。そういう意味で、自転車にヘルメットという話も、罰則なしの努力義務くらいだったらいいですが、罰則付きとすることには反対です。と言っても、現時点では罰則付きにする動きもまだないでしょうけど。
2023.04.12
コメント(5)
-
そりゃ、必然的にそうなる
統一地方選「ひとり負け」の共産党、除名騒動が影響か 次期衆院選に「大ダメージ」の可能性2023年4月9日に投開票された統一地方選の前半戦では、41道府県議選の改選定数2260議席のうち自民党が1153議席を確保した。前回19年の1158議席は下回ったものの、過半数は維持した。日本維新の会が大幅に議席を伸ばす一方で、立憲、公明は微増。そんな中で「ひとり負け」の様相を呈しているのが共産党だ。議席の4分の1近くを失い、所属議員がいない「空白県」も多数生まれた。共産党では2月から3月にかけて、党首公選制を書籍で主張したベテラン党員2人が「分派」活動を行ったとして、党規約で最も重い除名処分を相次いで受けている。この対応には批判も多く、統一地方選に影響するとの見方が出ていた。共産党は41道府県議会で99議席を持っていたが、改選後は75議席に。およそ4分の1を失った。41道府県の内訳をみると、千葉や愛知など8県で議席を増やした。愛知は県議会に共産党議員がいない唯一の「空白県」だったが、解消された。ただ、19道府県で議席を減らした。このうち、新潟、福井、静岡、福岡、熊本の5県からは1人も当選することができず、空白県に転落した。最も多い12人がいた京都は9人の当選にとどまった。除名された松竹伸幸氏と鈴木元氏が所属していた「震源地」でもある。残る14県では横ばいだった。(以下略)---私は東京在住なので、統一地方選前半戦は選挙がありませんでした(都知事選も都議選も、過去に任期途中の辞職、解散があったため、統一地方選から外れています)。その統一地方選前半戦の結果は、あらゆる意味で極めて残念なものでした。比率で見た場合、壊滅的に議席が減ったのは社会民主党で、前回22議席から3議席へという転落ぶりです。ただ、元々すでに極小勢力となっていた状況でもあります。立憲民主党は前回からは議席を伸ばしているものの、前回統一地方選後に国民民主党の主要部分と合流しているため、改選前から見れば減っています。れいわ新選組は議席を取れませんでした。そして共産党は前回99議席から75議席へと1/4を減らしました。他の党のことはともかく、共産党の敗北には、松竹伸幸氏の除名が大きく影響していることは間違いなかろうと思います。むしろ、あれでよく1/4程度の議席減で済んだな、とも思いますが。熱烈な支持者ではなく「うっすら支持者」に過ぎないとはいえ、永年にわたって約半分の票を投じてきた政党が、あのような行動をとったことへの幻滅は非常に大きい一方、それでもあのような主張を掲げる左派政党は必要であるという強い信念は変わらないので、共産党の議席が減ったことには非常に複雑な心境です。残念な思いもあるけれど、しかしあれで議席が減らなかったら、党内の異論排除という蛮行に対する反省も生まれないでしょうから、多分あれでよかったのだと思います。もっとも、その代わりに議席を伸ばしたのが維新ではね、まったく絶望的な気分にさせられます。後半戦には市区議会の選挙がありますけど、まあ残念ながら共産党には入れないでしょう。いや、もしSNS等で、松竹除名への異論を公言している候補者がいるなら、その人には投票してもいいかな、とは思いますが。(全国の地方議員にはこの除名について党中央への異論を書いている方が少なくとも何人かはおられますが、私の住んでいる自治体の議員、候補者にいるかどうかは未確認です)「貧すれば鈍す」と言いますが、全体的に党勢が伸び悩んでいるときに、あのような行動で、多くの「うっすら支持者」に愛想をつかさせるのは、正気の沙汰とも思えません。選挙での勝利より、党勢の拡大より、気に入らない党内の異論を排除するのが大事だとしたら「終わっている」としか思えません。こんなことを書かなきゃならないこと自体、残念で仕方がないのですが、そんな方向性の先に、選挙の勝利だの党勢の拡大だのがあるとは到底思えないし、私も期待を寄せる気にはなれません。
2023.04.10
コメント(18)
-
富士山噴火?
もういつ噴火が起こっても全然不思議ではない――研究の第一人者に聞く、「富士山リスク」への向き合い方静岡県と山梨県にまたがってそびえ立つ日本最高峰の山、富士山。過去に何度も噴火を繰り返し、人々に恐れられた火山だ。火山噴火予知連絡会の元会長で、現山梨県富士山科学研究所の藤井敏嗣所長に、富士山噴火の可能性や想定される被害について話を聞いた。富士山が最後に噴火したのは1707年のこと。富士山の南東斜面に新たな火口を開けた「宝永噴火」、山麓の村々はもちろん、当時の江戸にまで火山灰を降らせた激しいものだった。これ以降、現在に至るまで富士山は表向き静穏な状態を保ち続けている。―― 300年以上も噴火を起こしていないので、富士山が活火山であるというイメージを持つのはなかなか難しい。「この300年は、富士山にとっては非常に特殊な状況。5600年前まで調べたところ、平均30年に1回ぐらいのペースで富士山は噴火している。なぜ今、300年以上期間が空いているのか、よくわからない。今までの富士山の歴史の中では、非常に長い期間休んでいる状態」―― もういつ噴火が起こっても全然不思議ではない。「それがわれわれの理解。全く死に絶えた火山ならば、300年前の噴火を最後にもう何もない可能性もあるが、2000年~2001年に富士山の下で深部低周波地震と呼ばれる地震が頻発したことがある。この地震は、富士山の下でマグマ等が動いているときに起きると考えられる。つまり、富士山の深いところにマグマが存在している。300年前で全て終わったと考えることはできない」―― 過去には30年に1回噴火していた火山が長い間噴火していない。それだけ噴火のエネルギーをため込んでいるという見方も可能か。「米スミソニアン自然史博物館が、世界中の火山が噴火の前にどれくらい休んでいるのか調べている。巨大噴火は、その前にほとんどが100年以上休んでいる。場合によっては1000年以上休んでいた火山が大きな噴火を起こしている。このことから、長く休むとたくさんマグマがたまるので、いざ噴火が起きると大きな噴火になりやすいことがわかる。もちろん必ずではないが」―― もし噴火するとして、それは事前にわかるものか。「富士山のマグマがどの程度溜まっているかがわからない。たとえば桜島は深さ約10km、伊豆大島や三宅島も深さ約8~10kmにマグマが溜まっている場所があり、人工衛星で山の膨らみを測ることで変化がわかる。しかし、富士山は、20kmより深いところにマグマがあるので、測ることができない。本当に浅いところにマグマが上がってくるまでわからない」―― 多くの人が「富士山が噴火する前にわかる」と思っているかもしれないけれどそれは誤りで、不意打ちで噴火することもあるということか。「そう。不意打ちの意味にもよりますが、何週間も前から分かるとは思えない。ただ、いつとははっきり言えないとしても、数時間から数日前には噴火しそうだということは分かるだろう。(要旨・以下略)---東日本大震災の同じ日の晩(日付は12日になっていたかも)、富士山直下を震源とする大きな地震が観測されました。あのとき、多くの防災関係者がヒヤッとしました。宝永地震のすぐ後の放映大噴火の例を見れば一目瞭然ですが、大きな地震と火山の噴火は連動して起こることが非常に多いからです。あのとき、地震に引き続いて富士山の噴火も起こっていた場合、その噴火の規模にもよりますが、3.11と合わせて、災害の被害はさらに巨大なものになっていた可能性もあります。不幸中の幸いというか、富士山は噴火しないで済みましたが。3.11のあと2~3年は「富士山が遠からず噴火するかも」という危惧は、ある程度世間一般に共有されていたように思います。私自身、それまで一度も登ったことがなく、あまり登りたいとも思っていなかった富士山に、「ひょっとして噴火なんか始まったら、もう登れなくなるかもしれないし、高さ3776mではなくなってしまうかもしれないかも」と考えて登ったのが2012年9月でした。しかし、のど元過ぎれば熱さ忘れる、ではないですが、それが10年経ったら、富士山噴火の可能性は世間一般にはほとんど忘れ去られてしまっているのが現状です。でも、人間社会が覚えていようが忘れていようが、リスクの存在は変わりません。そして、いつかは富士山が必ず噴火するのは確かなことです。引用記事の次のページに書かれていますが、富士山は「噴火のデパート」とも言われ、噴火のたびにタイプの異なった様々な噴火が起こっています。300年前の宝永噴火を参考に、それと同じタイプの噴火に対する備えをしておけばよい、というわけにはいきません。宝永噴火の場合は、宝永地震の1か月半ほど後に噴火が起こっていますが、地震翌日には富士山でも地震が発生、更に噴火の約2週間前からは山麓での地鳴りがあったことが記録に残っています。そのようなタイプの噴火であればかなり以前から予知が可能でしょう。しかし、それ以前の噴火については、時代が古く、また平安時代以前は畿内から見れば辺境であった富士山の噴火についての記録は少なく、噴火以前にどの程度の前兆があったのかは分かりません。有名なのは864年の貞観大噴火です。この噴火によって、当時存在した剗の海と呼ばれる湖が溶岩に埋め尽くされ、その一部が西湖と精進湖となって残りました。また、青木ヶ原を溶岩で埋め尽くして、後の富士の樹海を生んでいます。この噴火の規模(噴出物の総量)は宝永噴火の2倍にも達します。引用記事が書くように、「おそらく」噴火の数日か数時間前には噴火の予兆が顕在化する可能性が高いと思いますが、問題は人間社会の側がその予兆を「噴火の予兆」と正しく認識できるかどうか、というところになろうかと思います。その貞観大噴火の規模は、噴出物総量が1.2立方km(マグマ換算)と推定されています。(気象庁のサイトより)この噴火規模は、実は桜島の大正噴火より小さなものです(気象庁のサイトによれば、1914年桜島の大正噴火の噴出物総量はマグマ換算で1.58立方km)。そして、その桜島大正噴火も、桜島(を含む姶良カルデラ)の有史以前の超巨大噴火に比べれば、規模はごく小さなものです。富士山は日本一高い山ですが、過去の噴火の規模においては、日本のほかの山々に比べれば、実はかなり小規模なものです。関東近辺でも、箱根山の方が過去にずっと巨大な噴火を繰り返しています。ただし、あくまでも「過去においては」です。過去において超巨大噴火を起こした山は、前述の箱根山と桜島(を含む姶良カルデラ)のほか、阿蘇山、霧島山を含む加久藤カルデラ、開聞岳を含む阿多カルデラ、鬼界カルデラ、十和田湖、洞爺カルデラ(洞爺湖)などがあります。それらの火山の山容を見れば一目瞭然ですが、富士山のようなきれいな成層火山は一つもありません。いずれもカルデラつまり巨大なくぼ地になっています。阿蘇山や箱根山のように、そのくぼ地の中央に小規模な火山ができている(中央火口丘)場合もありますが。端的に、莫大な量のマグマが噴出することで、底が抜けて陥没するわけです。富士山はまだそのような超巨大噴火を経験していないからこそ、あのようなきれいな成層火山の形状を保っているわけです。が、そのまま永久にきれいな形状の成層火山の姿を保ち続けられるわけではありません。すでに、富士山は2200年前から、山頂の噴火口からの噴火は止まっています。つまり、現在の山頂が、今後成層火山の姿をさらに発達させることはもうありません。2200年前以降は、山腹の色々な場所から噴火が起こっています。宝永噴火は言うまでもなく南西斜面6合目付近(宝永噴火口)からの噴火でした。ということは、富士山がこれから超巨大噴火を起こし、成層火山の姿が吹っ飛んでカルデラになる、という可能性もあり得ないわけではありません。その場合、東京は壊滅し、日本全体も壊滅するでしょう。300年も噴火が止まっているだけに、噴火が再開した時には過去に例のない規模の大きな噴火、という事態に至る可能性は決して低くはないでしょう。まあ、それが今年や来年起こる可能性は極めて低いでしょうけど。
2023.04.09
コメント(0)
-
陰謀論もいい加減にすべき
陸自ヘリ不明「中国に撃墜された」は根拠不明 防衛省幹部も否定【ファクトチェック】陸上自衛隊幹部ら10人が搭乗していたUH60JA多用途ヘリコプター1機が6日、沖縄県の宮古島周辺で行方不明になった事故を受け、インターネット上で「外国の攻撃」だとの言説が広がっている。ファクトチェックすると、どれも推測の域を出ず、「根拠不明」だ。 SNSやヤフーコメントでは「中国に撃墜されただろ」「一瞬で航空機の機能を失うほどの爆発が起きたのだろう」などの投稿が拡散されている。「中国軍ヘリを撃墜する必要がある」などという主張もある。防衛省統合幕僚監部によると、中国海軍の情報収集艦1隻が6日、沖縄本島と宮古島の間を通過して南下した。7日の衆院安全保障委員会では玄葉光一郎氏(立民)がこの点に触れ、「関連性は絶対にないということでいいか」と質問。浜田靖一防衛相が「そういったことは今のところ入っていない。確たるものをお話しすることは差し控えたい」と述べた。独自取材をせずにネット上の情報を掲載する「まとめサイト」では、このやりとりも事故原因と関係があるかのように扱われている。しかし、中国軍の情報収集艦について、統合幕僚監部は沖縄タイムスの取材に「特異な動きは確認されていない」と回答した。陸自トップの森下泰臣陸上幕僚長も6日の記者会見で、「宮古北西海域でこれまで発見された機材らしきものの状況から総合的に判断し、航空事故と概定(おおむね判断)した」と述べた。攻撃をうかがわせる物証も目撃証言もなく、「外国の攻撃」論は7日時点で根拠がない。---陸上自衛隊第8師団の師団長、幕僚長ら幹部を含む10人が搭乗したUH60ヘリが墜落しました。まだ死亡が確認されたわけではありませんが、発見された機体の損壊状況と、海上に墜落してすでに24時間以上経過している事実から考えて、生存は絶望というしかありません。残念なことです。事故原因は判然としませんが、前述のとおり発見された残骸はバラバラで部品が散乱している状態のようです。ということは、空中でバラバラになったか、または高速で海面に突っ込んだか、そのいずれかということになりそうです。陸上自衛隊は早々に事故と判断していますが、またも例によって、一部の勇ましすぎる人たちが、「中国が撃墜したに違いない」と吹き上がっているようです。いやはや、何とかは死んでも治らない、と言いますが、どうしようもないなと思います。引用記事にある中国軍の情報収集艦がどのあたりを航行したのかは分かりませんが、日本の領海に入ったという報道はありませんので、陸地にかなり近い場所で墜落したこのヘリと、最低限12カイリ(約22km)以上離れていたことは間違いありません。「接続海域を通過した」という報道もないので、実際にはもっとはるかに遠方を通過しているはずです。その情報収集艦の映像はニュースなどで流れていますが、戦闘艦艇ではないので武装はほとんどありません。艦首に機関砲らしき砲塔があるようにも思えますが、そうだとしても、射程はせいぜい数kmで、到底20kmも先には届きません。そんな遠距離の航空機を撃墜できるとしたら対空ミサイルしかありませんが、ミサイルランチャーもVLS(垂直発射装置)も見当たりません。また、問題の情報収集艦には海上自衛隊の哨戒機が張り付いていたはずですから、武器を使用すれば即座に分かります。当然宮古島基地の対空レーダーにも捉えられます。そのような痕跡が一切ない時点で、中国官邸による攻撃など「あり得ない」ことは歴然としているのです。もっとも、名無しの権兵衛のSNSやヤフーコメントがデタラメなことを書き散らかすのは、いつものことかもしれません。しかし、さらに驚くべきはこちらです。浜田防衛相、事故の機体「大変安定」 中国軍艦との関連「情報ない」コメント2557件山田吉彦 海洋問題研究者/東海大学海洋学部海洋理工学科教授行方不明の坂本雄一陸将は、情勢分析に優れたバランス感覚ある指揮官であり、これからの日本の平和維持、防衛に必要不可欠な自衛官である。他の乗員も東シナ海に臨む島嶼防衛の要を任された精鋭である。不明者の無事を祈る。陸地が近いエリアで、ヘリコプターが突然消息を断った。救難信号を発する余裕すらなかった。一瞬で航空機の機能を失うほどの事態がおきたのだろう。例えば爆発のような。無線を麻痺させ、また、コンピュータ制御機能を麻痺させる電磁戦のような電磁波異常についても検証すべきだ。(以下略)---いやはや、口あんぐり、ですよ。「無線を麻痺させ、また、コンピュータ制御機能を麻痺させる電磁戦のような電磁波異常についても検証すべき」とはね。だって、航空自衛隊 宮古島分屯基地にはレーダーがあるわけです。さらに宮古島空港には15~16時台には1時間に発着それぞれ3~4便あり、宮古島と橋でつながった下地島(今回の墜落海域から10kmと離れていない)も旅客機の発着があります。それら各空港の管制塔にも、そして発着する旅客機にもレーダーはありますし、無線でやり取りしています。これら各基地、空港、近隣を飛行中の旅客機のレーダーや無線、あるいはその他の電子機器に異常が生じたという情報は一切ありません。そもそも墜落現場は宮古島、池間島、伊良部島と下地島に囲まれた海域であり、それらの島には多くの住民(観光客も)がいるのに、テレビ、ラジオや携帯電話網や電子機器の異常の情報もありません。周りの島のレーダー、テレビ、ラジオ、通信網に一切影響を与えずに、このヘリだけを狙い撃ちする「電磁戦のような電磁波異常」(それが人為的であれ自然現象であれ)って、いったい何ですか?そんなトンデモを「大学教授」という肩書の人が恬然として書くのかと。いや、まあ大学教授ったっていろんな人がいますけどね。かの武田邦彦なんてトンデモ屋も一応大学教授なわけですし。ともかく、最低限の知識と論理的思考、推理力があれば、「そんなことはあり得ない」と容易に理解できることを理解しない人たちが、大学教授なんて肩書の人まで含めて大勢居るわけです。人は事実ではなく、自分が見たいと思うものを見る生き物なんですね、残念ながら。
2023.04.07
コメント(3)
-

5月5日にお台場で演奏します
2023年5月3日(水祝)~ ラテンアメリカへの道フェスティバル @ お台場昨年も出ましたが、5月の連休に東京・お台場で開催される「ラテンアメリカへの道・フェスティバル」で演奏します。イベント自体は5月3日から5日までの3日間開催され、各日様々なグループの演奏と踊りがありますが、私の出番(キラ・ウィルカ)は5月5日(祝)昼12時半~1時までの30分間となっています。今年は日秘外交樹立150周年だそうで、テーマはペルーです。普段キラ・ウィルカはほとんどボリビアの曲ばかり演奏していますが、今回は柄にもなく(笑)ほぼ全曲ペルーの曲を演奏します。そのため、半分以上が新曲という大胆な取り組みです。さて、どうなることやら。キラ・ウィルカ(昨年のラテンアメリカへの道フェスティバルより)(今回この曲は演奏しません)
2023.04.05
コメント(0)
-

「教授」が亡くなってしまった
坂本龍一さん死去 がん闘病 「ラストエンペラー」アカデミー作曲賞「イエロー・マジック・オーケストラ」(YMO)で活動し、映画「ラストエンペラー」で米アカデミー賞作曲賞を受賞するなど、世界的人気を誇る音楽家の坂本龍一さんが、3月28日、死去した。71歳だった。がんとの闘病を明らかにしていた。葬儀は近親者で営んだ。東京都出身。東京芸大で作曲を学んだ。ドビュッシーやベートーベンなどのクラシックを土台にしながらも、大学入学以降は電子音楽、民族音楽に傾倒する。同大大学院を修了後、1978年にアルバム「千のナイフ」でデビューした。同年、細野晴臣さん、高橋幸宏さんとYMOを結成。「ライディーン」「東風」「ビハインド・ザ・マスク」など、シンセサイザーとコンピューターを駆使したサウンドで、「テクノポップ」という新たな領域を開き、世界的な人気を獲得した。映画音楽では、自身も俳優として出演し、音楽を担当した83年の「戦場のメリークリスマス」が英国アカデミー賞作曲賞を受賞。87年の映画「ラストエンペラー」で日本人初の米国アカデミー賞作曲賞を受賞した。92年にバルセロナ五輪開会式の曲もつくった。社会問題にも強い関心を寄せた。2006年には青森県六ケ所村の核燃料再処理工場の危険性を訴える「ストップ・ロッカショ」プロジェクトを始動。東日本大震災以降はさらに反原発運動に注力し、首相官邸前デモにも参加した。14年に中咽頭がんが判明。克服後の20年にも直腸がんが見つかり、療養していた。昨年3月に復帰し、12月には事前録画した無観客コンサートを配信。今年1月には新作アルバムをリリースするなど、病と闘いながら活動を続けた。---がんで闘病中であることは周知ではあったものの、訃報に接すると衝撃を受けます。3.11以降反原発集会に参加しておられる姿は、超遠方から、あるいはスピーカーから声だけ拝見、拝聴したことがあります。一部の連中からは「たかが電気」というフレーズを批判されましたが、私はまったくそのとおりだと思いました。これが2012年7月なので、もう約11年前か、と思うと時の流れの速さに愕然とします。この当時はまだ坂本龍一はがん発症前でした。そして、つい先日はこんこんな報道もありました。亡くなった坂本龍一さん「音楽制作が難しい」体調の中で反対した神宮外苑再開発 「深呼吸し、スマホのカメラを向けることも多々あった」この記事を、私は毎日新聞の紙面で読んだのですが、「音楽制作が難しい体調」という言葉に、その日が近いのだな」と思わざるをえませんでした。後から考えると、この記事が出た時にはもう亡くなっていたのですが。最後の気力を振り絞って発言したのでしょうね。さて、しかし社会的活動もさることながら、音楽の方面で言うと、坂本作品で一番聞く機会が多かったのは、やはり戦場のメリークリスマスでしょう。多分、誰でも一度は聞いたことがある曲だと思います。私も大好きでした。ちなみに、YMO時代のこの曲も大好きなのですが、これは坂本作品ではなく1月に亡くなった高橋幸宏の作曲です。ライディーンそして、ご本人は製作者とトラブルになってその音楽に携わったことは「黒歴史」化してしまい、名前を口にすらしなくなってしまったようですが、個人的にはこの作品も強い印象が残っています。「王立宇宙軍オネアミスの翼」ご本人には不本意かもしれませんが、私はこの作品も大好きでした。1月に高橋幸宏が亡くなり、今回坂本龍一。あっという間にYMOは細野晴臣一人を残すだけになってしまいました。ご冥福をお祈りします。
2023.04.03
コメント(2)
-

2023年3月の鳥 その2
3月の鳥2回目です。3月20日秋ヶ瀬公園秋ヶ瀬公園は駅から遠く、バスも20分に1本なので、以前は行くに気合が入りしたが、スクーターに乗るようになって、簡単に行けるようになりました。もっとも、所要時間は公共交通機関で言っていたころより特に短くはなっていないのですが。アオゲラこの日もヒレンジャクを目当てに行ったら、フラれました。ついでに、コホオアカというかなり珍しい鳥が来ているという話もあったのですが、こちらも見られませんでした。アオゲラ。見てわかるように、キツツキの仲間です。モズベニマシコ・メス。オスは名前のとおり真っ赤なのですが、メスは地味な感じです。オスもいたのですが、枝の陰に隠れてすぐ飛んでしまい、撮影できませんでした。ベニマシコ・メス3月21日葛西臨海公園ジョウビタキ・オス。ジョウビタキとルリビタキはいつもメスばかり遭遇します。逆にキビタキとオオルリはオスばかり遭遇します。なんでだろー。でも、この時はジョウビタキのオスに遭遇できました。ジョウビタキ・オス。ツグミオオジュリンオオジュリン4月1日 秋ヶ瀬公園ルリビタキ・オス。前述のとおり、ルリビタキはメスの遭遇率が高いのですが、今回はオスを撮影できました。ただ、暗くてボケっとした写真です。関東の平地では冬鳥ですが、まだいましたね。アオジのオス。これも東京では冬鳥です。あ!鳥だ!・・・・・・アトリです。これも冬鳥。カワラヒワ。これは東京に通年いる鳥です。ガビチョウ。中国と東南アジア原産の外来種です。最近各地で増加しています。秋ヶ瀬公園でもよく声は聴きます。外来種なのですごく積極的に撮影を試みたことがないうえに、暗い林床、藪に多いので、こんなふうにきれいに撮影できたのは初めてです。ベニマシコ・オス。前回メスしか取れなかったので、リターンマッチでオスを探したらいました。カメラマンも多かったですが。ベニマシコ・オス。4~5羽いました。メスもいたのですが、メスは早々に飛んでしまい、今回はオスしか撮影できませんでした。ベニマシコ・オス。これも冬鳥なんですけど(北海道と青森県の下北半島では夏鳥)、いつまで秋ヶ瀬公園にいてくれるんでしょうか。
2023.04.01
コメント(4)
全16件 (16件中 1-16件目)
1