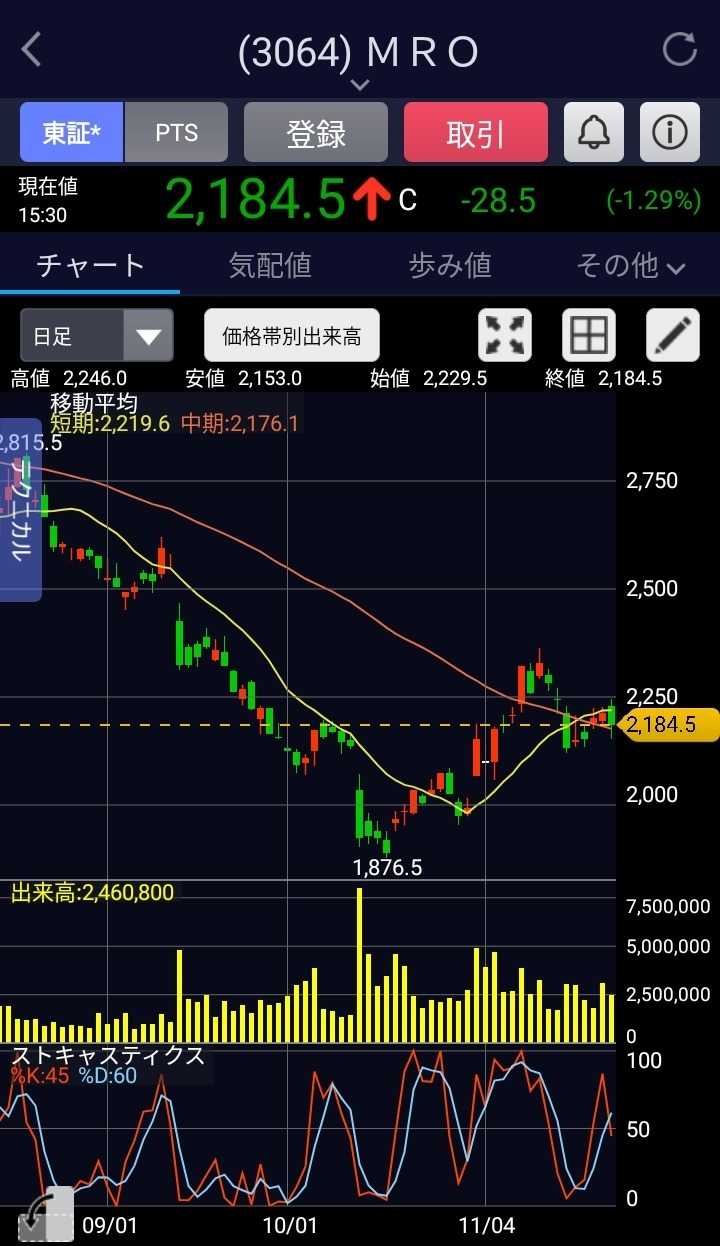2011年03月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
説教要約 717
「トマス」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、20章24~29節 「トマス」というのはヘブル語で、それをギリシャ語に訳すなら「デドモ」になり、「双子」という意味です。トマスの特徴を一言で述べるなら、「疑う人」です。彼は「証拠を見るまでは信じないパレスチナの住民」というあだ名をつけられました。どうしてこのような人がキリスト教の礎を築いた十二使徒のひとりに選ばれたのでしょうか。 一、ユダヤに行くと言われたイエスに反対した弟子の仲間に決死の覚悟で主について行くと言い出したトマス(11章1~16節) トマスは、ガリラヤの出身で、漁師であったようです(21章2、3節)。 トマスの言動が最初に記されているのは、愛するラザロが重い病気で病んでいることを聞いたイエスが「ユダヤに行こう」と言われた時です(11章7節)。そのころイエスは、二回も石で打ち殺されそうになりました(8章59節、10章31節)。それで弟子たちは、イエスがユダヤのベタニヤに行こうと言われた時、身の危険を感じて反対しました(11章8節)。 しかしトマスは、弟子の仲間に「私たちも行って、主といっしょに死のうではないか」と言いました(11章16節)。これを聞いた弟子たちは驚いたことでしょう。なぜなら彼は、証拠を見るまでは信じない慎重な人で、決して軽挙妄動する軽率な人間ではないことをよく知っていたからです。そのトマスが決死の覚悟で主について行こうと言ったのですから、彼の中に死に至るまで忠実な主に対する真実な愛を見たのではないでしょうか。 ほかの弟子たちは、トマスの勇気と愛に力づけられて、ベタニヤに行きました。彼らは、ベタニヤに行ったことで、ラザロの復活という奇しいわざを見ることができたのです。 二、イエスが去って行かれることを知らされ、当惑してどこへいらっしゃるのかを主に尋ねたトマス(14章1~7節) 次にトマスが登場するのは、イエスが十字架につけられる前の日に弟子たちに「訣別の説教」をされた時です。弟子たちは、イエスが自分たちを残して去って行かれることを聞くと、心が騒ぎ、不安に襲われ、恐れを抱いていました(14章1、27節)。しかしイエスがどこへ行こうとしておられるかを尋ねようとする弟子はだれもいませんでした。 このような重苦しい雰囲気に包まれた中で、ただひとりトマスが勇気を出して、「主よ。どこへいらっしゃるのか、私たちにはわかりません」と言いました(14章5節)。この質問は、ピリポと同じように長い間、イエスとともにいたのに、イエスのことを知らない無知と恥をさらけ出すことである反面、神と真理を探求する求道心の表れでもありました。 私たちは、恥をさらすことも恐れないトマスの求道心によって、イエスが「道であり、真理であり、いのち」であるという永遠の真理を知ることができたのです(14章6節)。 三、よみがえられたイエスに手の釘の跡とわき腹の傷跡という動かぬ証拠をつきつけられて主を信じたトマス(20章24~29節) 使徒ヨハネがトマスの最後のことばを記している出来事は、イエスが復活されてから数えて八日後に起きました。トマスは、一週間前によみがえられたイエスが十弟子に現れたことを聞いても、確かな証拠を見なければ決して信じないと言い放ちました。イエスは、トマスに現れ、ご自分の手の釘の跡とわき腹の傷跡を見せてくださいました(27節)。 トマスは、イエスに動かぬ証拠をつきつけられると、「私の主。私の神」と言いました(28節)。これは自らの不信仰を心から恥じた悔い改めの叫びであるとともに、心の底から主を信じた信仰告白です。証拠を見るまでは決して信じないトマスが、このような信仰告白をしたことは、キリスト教というものが作り話や架空の話に基づいた偽りの宗教ではなく、実際に起きた歴史的な出来事を目撃した者が、そのとおりに伝えた正確な事実に基づいた真の宗教であることを教えています。 トマスは、インドにまで福音を宣べ伝え、その地で殉教したと言われています。拙著「使徒ヨハネの生涯」26「トマス」より転載東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2011.03.31
コメント(0)
-
説教要約 716
「マタイ」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、5章27~32節 取税人のマタイは、収税所にすわっていた時はレビと呼ばれていますが(27節、マルコ2章14節)、十二使徒の名簿ではマタイと記されています(6章15節、マルコ3章18節)。おそらく初めの名はレビで、弟子になってからマタイ(神の賜物)という名が与えられたのでしょう。 一、イエスの弟子として召され、何もかも捨ててイエスに従ったマタイ(27、28節) レビの職業は取税人です。取税人は、ローマ帝国に納める税金をユダヤ人から取り立てる人で、売国奴とののしられ、税金を必要以上に徴収して私腹を肥やしている守銭奴でした。それで彼らは、遊女や犯罪者とともに罪人呼ばわりされ、神殿で礼拝することもはばまれ、社会からのけ者にされて、一般の民衆と交際することも許されていませんでした。取税人レビは、金持ちでしたが、心はすさむいっぽうだったにちがいありません。 レビは、キリストと呼ばれるメシヤのうわさを聞いていましたが、自分のような罪人は相手にしてくれないと思っていたことでしょう。ところがイエスは、このような取税人レビのところに来られただけでなく、目を留めて、「わたしについて来なさい」と言われました(27節)。レビは、息も止まるばかりに驚き、狂喜したのではないでしょうか。少しのためらいもなく、「何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った」のです(28節)。 二、取税人の仲間たちを集めて、イエスのために大ぶるまいをしたマタイ(29~32節) そこでレビは、取税人たちや大ぜいの罪人どもを集めて、「自分の家でイエスのために大ぶるまいをし」ました(29節)。それは、自分のような取税人を弟子として召してくださったイエスへの感謝を表すためであり、また今までの罪深い生活との訣別を示すためであり、そしてイエスの弟子になったということを彼らにあかしするためでした。 ところがパリサイ人たちは、イエスの弟子たちが取税人や罪人どもといっしょに飲み食いするのを見て、彼らを非難しました(30節)。神の前にも人の前にも称賛に値するマタイの行為も、パリサイ人たちにとっては批判の対象でしかありませんでした(30節)。 そこでイエスは、「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です」という当時のことわざを引用し(31節)、「救い主を必要とするのは正しい人ではなく、罪人です」という真理を示して、ご自分の弁明をするとともに弟子たちを弁護されました。レビは、このイエスのことばを聞くと、からだの震えるような感動を覚えたのではないでしょうか。 三、十二使徒のひとりに選ばれ、ほかの使徒たちと行動をともにしたマタイ(6章15節) それからイエスは「弟子たちを呼び寄せ、その中から」(6章13節)、「ご自身のお望みになる者たち」(マルコ3章13節)、「十二人を選び、彼らに使徒という名をつけられ」ました(6章13節)。イエスが十二人の名を呼ばれた時、マタイもその中に加えられていました。マタイは、思わず耳を疑ったことでしょう。しかしそれは紛れもない事実でした。イエスの弟子として召されただけでなく、十二使徒のひとりに選ばれたので、感激で胸がいっぱいになったにちがいありません。ますますイエスに従う決意をかためたことでしょう。 その後、マタイは、五旬節の日に聖霊に満たされ、ほかの使徒たちと行動をともにしています(使徒1章13節、2章1~4節、6章2節、8章1節)。しかし新約聖書は、その後のマタイの言動については何も記していません。ただ私たちは、マタイがユダヤ人を対象にして「王であるキリスト」を描いた「マタイの福音書」--王の系図をダビデそしてアブラハムまでさかのぼるキリストの系図で始まり、山上の説教をはじめ数々のすぐれた説教を載せ、新約聖書の冒頭にふさわしいキリストの生涯--を書き記したことを知っています。 マタイは、伝説によれば、ユダヤで伝道した後、エチオピヤ、マケドニヤ、シリヤ、ペルシャに福音を伝え、火刑と石責めによって殉教したと言われています。拙著「使徒ヨハネの生涯」25「マタイ」より転載東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2011.03.24
コメント(0)
-
説教要約 715
「バルトロマイ」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、1章45~51節 バルトロマイは、共観福音書にある十二使徒の名簿の中では、ピリポの次に名を連ねていますが、「ヨハネの福音書」では、ピリポの友人としてナタナエルの名が記されています(45、46節)。それでバルトロマイとナタナエルは同一人物であると思われます。 一、ナザレの人イエスがメシヤであると言ったピリポのあかしを旧約聖書に基づいて否定したナタナエル(45、46節) ナタナエルは、ガリラヤのカナの出身で、漁師であったようです(21章2、3節) ピリポがイエスの弟子になり、ナタナエルを見つけて、ナザレの人イエスがメシヤであることをあかしする時、「私たちは、モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました」(45節)と、回りくどい言い方をしていますが、これは、ナタナエルがモーセの律法や預言書をよく学び、旧約聖書に精通していたからなのでしょう。 聖書に通じていたナタナエルは、メシヤはエルサレムかベツレヘムから出ると思っていました。それでナザレの人イエスがメシヤであるというピリポのあかしを聞いた時、「ナザレから何の良いものが出るだろう」(46節)と言って、彼のあかしを否定したのです。 二、イエスが自分のことを知っておられたので、イエスを信じたナタナエル(46~49節) 聖書に精通していたナタナエルは、ピリポのあかしは取るに足りないと、否定したものの、ピリポから「来て、そして、見なさい」(46節)と、真実で熱心な誘いのことばをかけられた時、心に感じるものがあったのでしょう。イエスに会うために出かけました(47節)。 いちじくの木の下は、イスラエル人にとっては、旧約聖書を調べて研究したり、黙想したり、祈ったりする非常に大切な場所でした。ナタナエルは、よくいちじくの木の下にいました(48節)。それは、真剣に聖書を学んで、深く思い巡らし、熱心に祈っていたことを教えているのではないでしょうか。またそれによって「きよい心と正しい良心と偽りのない信仰」(第一テモテ1章5節)を持つ人格が形造られたにちがいありません。 イエスは、ナタナエルこそ神が望んでおられるほんとうのイスラエル人で、彼のうちに偽りがないことを見ておられました(47節)。ナタナエルは、イエスが自分の心を見抜いておられることを知って、自らの無知を深く恥じたことでしょう(48節)。そしていちじくの木の下にいたことまで見ておられることを知って、「あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です」と言って、この方こそメシヤであると確信したのです(49節)。 三、ご自分は天に届くはしごであるというイエスの証言を聞いたナタナエル(49~51節) ナタナエルは、ナザレの人イエスが神の子であり、イスラエルの王であることを信じました。しかしそれは、地上における栄光のメシヤを信じたことを意味しています。それでイエスは、さらに大きなこと、すなわち「天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを、あなたがたはいまに見ます」と言われました(51節)。 聖書に通じていたナタナエルは、このことばを聞いた時、ヤコブがベテルにおいて見た夢--頂が天に届くはしごを神の御使いたちが上り下りしている夢--を思い起こしたことでしょう(創世記28章12節)。これは、イエスこそ天と地の間にかけられたはしごであることを教えています。しかしそのためにイエスは、受難のメシヤとして十字架の上で贖いのわざを成し遂げなければなりませんでした。この時のナタナエルは、そこまで理解することはできませんでしたが、五旬節の日に聖霊に満たされた時、このことのほんとうの意味がわかったことでしょう(16章13節)。 その後、ナタナエルは、ほかの使徒たちと行動をともにしています(使徒6章2節、8章1節)。伝説によれば、小アジヤ、ペルシャ、そしてインドにまで福音を伝え、最後は、異邦の地で捕らえられ、逆さはりつけにされて、壮絶な殉教の死を遂げたということです。拙著「使徒ヨハネの生涯」24「バルトロマイ」より転載東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2011.03.18
コメント(0)
-
説教要約 714
「ピリポ」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、1章43~46節 ピリポは、マタイ、マルコ、ルカという共観福音書と「使徒の働き」にある十二使徒の名簿の中に名を連ねていますが、その言動は「ヨハネの福音書」にしか記されていません。 一、イエスの弟子になり、ナタナエルをイエスのもとに連れて来たピリポ(43~46) ピリポは、ベツサイダで生まれ育った漁師で(44節、21章21節)、バプテスマのヨハネの弟子であったようです。アンデレとヨハネは、自分たちのほうからイエスについて行きましたが(37節)、ピリポの場合は、イエスのほうからピリポを見つけ、「わたしに従って来なさい」と言われたので(43節)、その声に従い、イエスの弟子になりました。 ピリポは、イエスが自分を見つけて声をかけてくださったことがうれしくてしかたなかったのでしょう。友人のナタナエルを見つけ、ナザレの人イエスこそ旧約聖書が預言しているメシヤであることをあかししました(45節)。しかし聖書の知識ではナタナエルにかなわないと思ったのでしょうか。議論せず、彼をイエスのもとに連れて来たのです(46節) 二、イエスに信仰をためされたが、常識的な答えしかできなかったピリポ(6章5~7節) その後、イエスがピリポに声をかけられたのは、大ぜいの人の群れが寂しい所で、食べる物がなく、空腹を覚えていた時でした。イエスは、「どこからパンを買って来て、この人々に食べさせようか」と言って、ピリポをためされました(6章5、6節)。 このイエスの質問に対してピリポは、「めいめいが少しずつ取るにしても、二百デナリのパンでは足りません」と答えました(7節)。この答えは、ピリポが論理的な頭脳の持ち主で、物事を正確に分析し、合理的に考える現実的な人であることを教えています。 ピリポは、イエスがカペナウムやエルサレムにおいて行われた数々の奇蹟を見てきましたが、その同じイエスがこのようなへんぴな所においても奇しいわざを行うことができるということを信じる信仰がありませんでした。イエスが少しのパンと魚を増やし、五千人の男の人が満腹したのを見て、自らの不信仰を深く恥じたことでしょう。 三 イエスに会いたいというギリシャ人の頼みを聞くと、アンデレに相談し、彼とともにイエスに取り次いだピリポ(12章20~22節) 祭りの時、礼拝のために上って来た幾人かのギリシャ人は、イエスに会おうとしました。その時、イエスに取り次いでくれるように声をかけて頼んだのはピリポでした(21節)。どうして彼に頼んだのかよくわかりませんが、またしても声をかけられたのです。 ピリポは、友人であるアンデレに話し、ふたりでギリシャ人のことをイエスに伝えました(22節)。おそらく彼らが異邦人なので、ユダヤ教の偏見にとらわれ、ためらっていたのでしょう。このようなところに何事にも慎重で、友人に相談するという長所がある反面、自分ひとりでは判断することができず、決断力に乏しいという短所があることがわかります。ピリポは、アンデレの偏見を抱かない心の広さと決断力を学んだことでしょう。 四、長い間イエスとともにいたのに、心が鈍くてイエスのことがわからず、父を見せてくださいと求めたピリポ(14章8、9節) その後、ピリポは「イエスの訣別の説教」を聞いた時、「主よ。私たちに父を見せてください」と言いました(14章8節)。この質問は、長い間イエスとともにいたのに、イエスのことがわからず(14章9節)、心が鈍いことの表れである反面、どこまでも神と真理を探求する熱心な求道心を表しています。ピリポは、「わたしを見た者は、父を見たのです」(14章9節)と言われたイエスのことばを忘れることができなかったことでしょう。その後、五旬節の日に聖霊に満たされ、すべての真理がわかったにちがいありません(16章13節)。 ピリポは、ギリシャとアジヤ地方に福音を伝え、ヒエラポリスに葬られました。伝説は、ヒエラポリスで捕らえられ、頭を下に逆さ吊りにされて殉教の死を遂げたと伝えています。拙著「使徒ヨハネの生涯」23「ピリポ」より転載東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2011.03.12
コメント(0)
-
説教要約 713
「ゼベダイの子ヤコブ」 甲斐慎一郎 マルコの福音書、1章16~20節 ゼベダイの子ヤコブは、最初にイエスの弟子になった弟のヨハネに導かれて主の弟子になった人です。十二使徒の中にヤコブという名の人がふたりいます。ひとりはゼベダイの子ヤコブ、もうひとりはアルパヨの子ヤコブです。前者は大ヤコブ、後者は小ヤコブと呼ばれています。ヤコブの生涯は「四福音書」と「使徒の働き」に記されています。 一 人間をとる漁師として召され、何もかも捨ててイエスに従ったヤコブ(19、20節) 四福音書は、ヤコブがイエスの弟子になってから人間をとる漁師として召されるまでの経緯について何も記していません。しかし弟のヨハネとともにイエスのお供をし、イエスの行われたことと語られたことを見聞きしているうちに、イエスが真のメシヤであることを確信し、この方に自分の生涯をささげて行こうと心にかたく決めていたのでしょう。イエスは、「わたしについて来なさい」とヤコブをお呼びになりました。すると彼は、「父ゼベダイを雇い人たちといっしょに舟に残して、イエスについて行った」のです(20節)。 二 十二使徒のひとりに選ばれ、三人の側近のひとりに選ばれたヤコブ(3章17節、5章37節) イエスは、大ぜいの弟子の中から「ご自身のお望みになる者たち」十二人を選んで(3章13節)、彼らに使徒という名をつけられました。この十二使徒の中に二組の兄弟、すなわちペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネの四人が含まれています。しかもこの四人のうちアンデレを除いた三人は、イエスのそば近く仕える側近にも選ばれました。 主は、この三人をエルサレム教会の柱として初代教会を建て上げる指導者とするために訓練されました。この三人の側近だけがヤイロの娘がよみがえった家に、またイエスの変貌された山に、そしてゲッセマネの園に連れて行かれたのです(5章37節、9章2節、14章33節)。 三 主を受け入れなかったサマリヤ人を焼き滅ぼそうとしたヤコブ(ルカ9章51~56節) イエスが十二使徒を選ばれた時、ヤコブとヨハネの「ふたりにはボアネルゲ、すなわち、雷の子という名をつけられ」ました(17節)。ふたりは、サマリヤ人がイエスを受け入れなかったのを見ると、義憤に駆られ、雷の子の本性を現し、熱心のあまりとはいえ、「彼らを焼き滅ぼしましょうか」とイエスに進言したのです(ルカ9章54節)。彼らは、自分の思い通りにならないと、すぐに怒りを爆発させてしまう気性の激しい人でした。ペテロとヨハネが初めから指導者としてふさわしい人物ではなかったようにヤコブとて同じでした。 四 栄光の座でイエスの右と左にすわることを求めたヤコブ(マタイ20章20~28節) ヤコブは、側近のひとりであるペテロがイエスから天の御国のかぎを受けたことを知ると(マタイ16章18、19節)、嫉妬にかられたのでしょうか。母サロメと弟ヨハネとともに栄光の座でイエスの右と左にすわることを求めたのです(同20章20、21節)。彼らが、このようなことを求めること自体が、それにふさわしくないことを表しています。ヤコブは、奉仕においては有能でしたが、人間としても信仰の指導者としてもまだまだ未熟でした。 五 ヘロデ王によって殺され、最初の殉教者になったヤコブ(使徒12章1、2節) ヤコブは、四福音書においてはペテロやヨハネの陰に隠れ、三人の側近の中で最も目立たない存在でした。しかし彼の生涯の晩年、いや最期は決してそうではありません。アンテオケを中心とする異邦人への伝道の働きが広がっていった後、ヤコブはヘロデ王によって殺され、十二使徒の中で最初の殉教者になったのです(使徒12章1、2節)。 なぜヤコブが最初に殺されたのでしょうか。それは、五旬節の日に聖霊によって雷の子としての怒りの火が燃える愛の火に変えられ、だれよりも熱心に伝道し、影響力が最も大きい卓越した人物になっていたからでしょう。こうしてヤコブは、イエスの飲む杯を飲み、イエスの受けるべきバプテスマを受けて(マルコ10章39節)、天の御国に凱旋したのです。拙著「使徒ヨハネの生涯」22「ゼベダイの子ヤコブ」より転載東京フリーメソジスト昭島キリスト教会
2011.03.04
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1