2013年02月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

華麗な花が待ち遠しい
5年ほど前にRUMIXさんからエンジェル・フェザーというランの花(シンビジューム)を頂いた。どんな手入れをしてよいかも知らず何もしないで来たが、まだ生きていてくれる。昨年はエアコンを常時使う部屋に置いて失敗。花芽が着かなかった。甘やかしすぎたのだ。今年はエアコンは使うが花はカーテンで仕切って暖房があまり来ない出窓に置いた。これが大成功。今日見ると見事なつぼみが沢山ついた枝が3本出ている。やったあ!今年の春はあの華麗なエンジェル・フェザーが咲く!!とても気持ちが明るくなり、希望の灯火がともった。 余談だが、最近はエンジェルフェザーと言うとランの花ではなくエンジェルフェザーバンガードなるカードゲームのほうが有名らしい。
2013年02月28日
コメント(6)
-

栄養学に一生を捧げた香川綾さん
2月27日朝から雨が降り、空は灰色。とても寒い。本来なら西上州方面にアイスクライミングに行く予定で準備完了していたが、この天気で中止。こたつに入って香川 綾~栄養学と私の半世紀~という本を読んだ。香川綾さんは5年ほど前、香川式食事法(4群点数法)でダイエットした関わりで、栄養学に生涯を捧げた女性だという程度の知識はあった。この自伝を読んで綾さんの栄養学にかける並外れた情熱に打たれた。戦争中に学校そのものを疎開させてまで学生を教育する。生きていくことだけに精一杯な戦時中に普通そんなことしないだろう。また計量スプーンや計量カップなど私が物心ついたときには既に世の中に存在していて、家庭科の授業でよく使用していた。それが綾さんの発案によるものとはついぞ知らなかった。料理カードもよくお世話になって田舎で洋風料理を作ることができたが、それも綾さんの誰にでも正確な料理ができるようにという意図で作られたものだったのだ。夫亡きあとも子育てしながら栄養学を広め国民の健康を願って専門学校、短大、四大の設置に腐心する。すごい人だ。明治時代の気骨ある女性の典型だ。 ちなみに彼女が英知と工夫を重ねて確立した4群点数法という食事法は無理なく減量でき、健康を損なわずリバウンドもないという優れた食事法である。私は自分が実践した経験から明言できる。
2013年02月27日
コメント(2)
-

城ヶ崎でトムボーイの攻略
2月25日伊豆城ヶ崎にクライミングに出かけた。久しぶりに新幹線に乗った。熱海近辺でくっきりと白銀に輝く大きな富士山を見た。いつ見ても心が洗われる。これまで温かかった城ヶ崎も今日ばかりは冷たい風が吹いてどんよりしていた。今日の参加者は5名、全員が女性でその内4名が60歳代。平日のクライミングらしい年代層である。懸垂下降してシーサイドへ降り立ち、名探偵登場、ハジノラインでウオーミングアップし、海賊フックとトムボーイのあるエリアに移動した。城ヶ崎も今日で3回目。海賊フック(10.b)から取り付く。例のつるつるの一枚岩のトラバースでリーチ不足。少しは岩に慣れて上部は前回より見通しがよかったが、まだまだ難しい。 笑顔でスタートしているように見えるが、内心はヒヤヒヤ あと2センチが届かない!!次に前回手も足も出なくて悔しさ極まったトムボーイ(10.d)にトライ。出だしからもう困難続き。ここの岩は丸まっこくてホールドが甘くなかなか確信が持てない。自分の握力や筋力も不足している。何とか左に回り込んで中間部に行くが、次に待ち受けるのが前回の敗退箇所。何度もトライするが今日もできない。でも2回目なので上がどうなってるのか見たいと思い、ヌンチャクを使って強引にズリ上がり、上の岩場に出る。ここからも一筋縄にはいかなかった。しかしリーチが絶対的に不足している箇所は1カ所であとはルートに慣れムーブを工夫すればできそうだった。つまり中間部が昇れればあとは何とか昇れるという見通しができた。全体を把握できて安心した。 トムボーイ シンデレラボーイすぐ近くに有名かつ高難度のシンデレラ・ボーイ(5.13)というルートがある。いつも若者が取り付いて「ワォー」とか雄叫びを上げながら練習している。今日も取り付いていたが、核心部を切り抜けてレッド・ポイントなりそうな状況になっていた。みんなでそれを見て「ガンバ」とか声をかけ、成功した時は拍手したり「おめでとう」「やったね」とか声を出して大いに盛り上がった。見ず知らずの青年の健闘と成功をみんなで喜び讃えてクライマー同士ならではのいい雰囲気だった。
2013年02月26日
コメント(2)
-

筆あとの魅力ー点・線・面
筆あとの魅力~点・線・面~印象派から抽象絵画までと銘打った展覧会に行った。ブリジストン美術館のコレクション展である。ここはJR東京駅八重洲中央口から直進、徒歩5分で行けるため、私のような方向音痴の田舎者にはとても有り難く、昨秋「ドビュシーーその音楽と美術」展をみて以来、川村美術館につぐお気に入り美術館になっている。平日だったがそこそこの訪問者がいた。ほとんどが私のような立場すなわち退職者風である。第1室から第10室まであり、広すぎない部屋にテーマ毎に作品がまとまっていた。メインは第2室の「筆あとの魅力」The Power of Brush である。ゴーガン、シニャック、クレー、ミロ、カンジンスキー、佐伯祐三、岡 鹿之助、青木 繁などの作品が展示されていた。点・線・面に特化した解説が付けられていたので真面目に読んでしまって、後で後悔した。知的理解から入ると感性はしぼんでしまう。 エントランスのポスター ブールデル 風の中のベートーベンパウル・クレーの絵がすごく今の自分の心情にぴったりだった。 ルノワール『すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」
2013年02月25日
コメント(0)
-
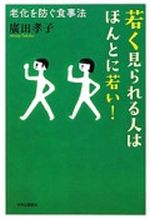
糖質ゼロか糖質制限か~食とダイエットに関する4冊の本
図書館に行くとどうしても食生活・ダイエット・アンチエイジングなどの本が目についてしまう。今回もタイトルに惑わされて思わず3冊を借り出してきた。☆廣田 孝子 老化を防ぐ食事法 若く見られる人はほんとに若い☆釜池 豊秋 食べても太らない! 糖質ゼロ健康法☆伊達 友美 食べてやせる! 魔法のダイエット ☆桐山 秀樹 おやじダイエット部の奇跡のレシピ (買って自宅で使用しているが同じテーマなので載せる) 最先端は「糖質ゼロ健康法」である。最近、書店に行くと糖質制限食に関する本がものすごく出版されている。その理論的基礎は釜池豊秋さんと江部康二さんの両雄だろう。その釜池さんは私の故郷愛媛県宇和島市在住の医師なのでとても親近感を抱いた。釜池さんは糖質ゼロ、江部さんは糖質制限を提唱しているが似たようなものだと思っていた。しかし今回本を読んでインスリンの放出に関する根本的考えが全く違っていることがわかった。糖質ゼロの食生活は1食糖質5グラム以下、制限食は1食糖質20グラム以下としている。糖質ゼロは相当難しい。既に糖尿病などに罹患して困っている人が大決心して実践するものだと思う。健康増進をめざす程度なら制限食の方が一般人向きだろう。「奇跡のレシピ」は糖質制限食の具体的レシピがたくさん載っていてとても参考になり、毎日の献立つくりに役立つ。このレシピで知った納豆オムレツとか豆腐カレーとかアボガド豆腐とかいろいろ作って息子に喜ばれた。男性の視点によるレシピなので極力手間を省いてあるため、調理時間は最短30秒、平均でも4分と超簡単。昔ながらの手順を踏んだ調理をしてきた私の目からは鱗が落ちた。「若く見られる人はほんとに若い」が最もオーソドックスである。若い女性に人気のある伊達さんの説は単なる減量ではなく、ボディラインと肌を美しく変身させることを目標にした独自の食事法が展開されていて、参考になった。
2013年02月24日
コメント(4)
-

尾白川ガンガノ沢シークレット大滝クライミング
翌日21日は尾白川流域 ガンガノ沢アイスクライミングに出かけた。朝6時出発、白州市から日向山に向かう雪道を詰める。これが積雪の後の氷結状態で道路が超恐かった。ここが本日の核心と言える程だった。駐車場までやっとのことで到着し、錦滝まで50分ほど歩く。天気は上々だが甲斐駒ヶ岳には雲がかかり、山の団十郎と言われる勇姿がみられない。錦滝は大きく見栄えがする。これを昇るんだと思ってワクワクしたら結氷状態が悪いのでスルーとのこと。錦滝の迂回ルートのトラバースがスリルがあった。ガンガノ沢をつめてF2を肩慣らしに軽く登攀。さらに沢を詰めてシークレット大滝と呼ばれている滝に到着。ここでも雪道の急坂に辟易。腰痛を懸念してゆるい生活をしている内に、体力も根性も失っている。ヤバイ!いや、ヤバすぎる。 きれいな滑滝が3本揃っている。手前2本は緩斜面で易しすぎるため右側を昇る。積雪が谷を埋めてしまい、氷瀑が3メートルほど短くなってるらしい。 氷瀑をクライミングするのはほとんど問題なかったが、一番ストレスになったのが手袋である。手の大きさは身長に比例するので私の手はとても短く小さい。当然丁度合う手袋がないため、自ずと指先1センチ位が余る大きな手袋になる。その手袋でカラビナその他のギア類を扱いロープワークをしなければならないのだが、手袋の余った指先がカラビナに挟まってしまう。その都度やり直しで手間暇がかかり、ついには業を煮やして素手になる。そうすると手が冷えるというので必ず注意される。もうイヤになるし、気持ちが晴れない。でも仕方がない。やるしかない。 また、昇るのは楽しいのだが、氷瀑の数カ所にカラビナをかけたアイススクリューが打ち込んである。それを回収するのに大きい手袋でまたまた時間がかかる。本当にどうして私はこんなに身体的不利が多すぎるスポーツが好きなのか?などど考えながら昇った。F2が核心でバーチカルだったが、凹角を使って昇れた。最終ピッチは短く楽だった。終了点から懸垂下降を繰り返して取り付きまで戻り、再び雪道を下って錦滝まで帰り着いた。数人の男性たちが昇っているのが見えた。2日間のアイスクライミングで身体が滝に大分慣れて、こつを掴めたような気がした。 スケールの大きい錦滝
2013年02月23日
コメント(4)
-

唐沢の滝アイスクライミング
2月20日小川山山麓の唐沢の滝にアイスクライミングに行った。いつもロッククライミングで近くを通るのでその名は知っていたが、実際に滝に行ったのは初めて。雪道を歩き、途中からけっこうな急坂を詰めておよそ2時間のアプローチ。しばらくぶりに雪道を歩き、げんなりした。唐沢の滝は2段になっていて見事に氷結していてかなりボリュームがあった。でも2ピッチしかないので少し慣れた頃にもう終わってしまった。あっけなく早く終了してしまったが、たまにはこんな余裕がありすぎる日程も高齢者には丁度良い。 唐沢の滝 全景 前段を昇る
2013年02月22日
コメント(4)
-

疲れを知らない孫の子守りに疲れて
娘の体調が悪いのでまた葵ちゃんの子守りに行った。初めのうちはおとなしくしているのだが、その内慣れてきてエネルギー全開、可愛い声を出して遊び続ける。こちらが疲れても全く平気。シクラメンのかほりという歌の中に~♪♪疲れを知らない子どものように~♪ という歌詩があるが本当に疲れを知らないで遊ぶ。最近は車が好きになり「ブーブー」と言いながら部屋中を歩く。何にでも興味があるから油断できない。つまみとかボタンとか取っ手などちょっと手がかりのあるものには何にでも触りたがるので要注意。 アオイ、ママと同じハンバーグも食べれるの ワタチ、左利きかもね食欲も旺盛で味噌汁、ハンバーグ、イチゴ、ヨーグルトと次々に平らげる。疲れて一休み中の私と娘が横になっている側で1人であれこれ言いながら遊んでいたが、いつのまにか寝ていた。あどけないものだ。
2013年02月21日
コメント(6)
-

モロッコ土産
真面目な友人が数年ぶりに海外旅行した。アルジェリア事件の近く、モロッコを訪ねてきたのである。帰国報告でお茶すると、久し振りの異国体験がとても刺激的だったようで、話が止まらない。4時間ほどファミレスで長居して話を聞いた。お土産ももらった。ドライフルーツの白イチジクとアルガンオイルである。イチジクはちょっと乾燥しいたけのような形をしているが、甘みが凝縮していてとってもおいしい。クライミングの行動食にぴったりだ。アルガンオイルは、モロッコにのみ生育するアルガンの樹の実から採油された希少な オイルで、「モロッコの黄金」と呼ばれて美や健康に役立てられているらしい。貴重なものを頂いた。アルガンオイルをサラダにかけ、顔にも塗り、ドライイチジクを食べて元気で遊ぼう。 アルガンオイル ドライイチジクもろ
2013年02月20日
コメント(4)
-

都市部には数十メートルのユーカリやパイン類がたくさん
高山地帯では南極ブナ類がたくさん見られましたが、都市部ではまた少し違った樹木類を見ることができました。クイーンズタウンではユーカリの大木やさまざまな針葉樹が見事でした。 巨大なユーカリが街のあちこちにありました パインなどの針葉樹も巨大、実もたわわ 右の巨大な木はクイーンズタウンの街中に保存されている記念樹 ブナや針葉樹は数十メートルの高さに生長するので山岳地方でその実を見ることはなかなか難しいのですが、公園で間近に見ました。右はブナの実。 日本でもよく見かけるようになったスモークツリーも見事でした長く続いたニュージーランドシリーズ、アップする私自身がもう辛くなっていましたが、何とか終わりまでこぎ着けました。ああ、ほっとした!!
2013年02月19日
コメント(2)
-

NZテアナウとクイーンズランドで見た花~その2
都市部テアナウとクイーンズタウンで見た花の2回目です。 この紫の花は日本でもよく見ます。 赤いアヤメ 園芸種のフクシァ 見事なケシ B&B前の花壇 今を盛りと咲き乱れるラベンダー 芝桜 花と言えばこれこうして低地に咲く色彩豊かな花を見ると確かに美しいのですが、高山に咲いていた花たちを思い出すとエネルギーや芯の強さ、たくましさに欠けるような気がしてしまいます。山岳地方と都市部両方の花を満喫できてとても心が潤いました。
2013年02月18日
コメント(4)
-

NZテアナウとクイーンズランドで見た花
山岳地方では白と黄色の花しかなくて少し色彩に欠けましたが、都市部は夏期の始まりで正に百花繚乱でした。日本でよく見る花もあり花の国際性を感じました。一方見たことのない花もあり、変化に富んでいました。ここで紹介する花はテアナウとクイーンズタウンで見たものです。花名はあまりわかりません。 かんざしのようなピンクの花と緑色の葉の対照が美しい 白いマーガレット ピンクのカーネーション 右のこのピンクの花は日本でもよく見ますよね。 色とりどりの花で溢れる街角の花壇 一般家庭の庭に咲く赤とピンクのしゃくなげ
2013年02月17日
コメント(2)
-

白と黄色の花しかないNZ山岳地方の不思議
これまでNZ山岳地方の花をごらんになって気づかれたことがあると思います。花の色が白と黄色しかない!!でもテアナウやクイーンズタウンなど都市部では赤・ブルー・ピンク・黄色など豊かな色彩の花が溢れている!!始めの頃、ほとんどの花の色が白でたまに黄色しかなくて、これは一体どういうことだろうと不思議に思っていました。ガイドの説明によるとNZには花粉を媒介して受粉する蝶やミツバチが極端に少ない。そこで実際に受粉しているのは蛾で、蛾は夜しか仕事をしないので夜に見える色というと白になるので、NZの花は白が中心になるという。 サウスアイランドマウンテンフォックスグラブ NZブルーベル ホリド スパニアド と呼ばれるいかにも痛そうな植物。葉が鋭く尖って触ると痛い。花にもトゲがある。嘘かホントかわからないが、当時スペインと仲が悪かったのでホリド(酷い・野蛮な)スパニアド(スペイン人)と名付けられたとか。 右はブッシュ・フラックス NZフラックス 刀の様な葉は約2m、そこから更に1mほどの大きな花が咲く。マオリ人はこの葉を編んで篭や服、ひもなどを造り、イギリスへ輸出していました。 カマヒ サザンラータ 海辺でよく見ました マウントクック地方に多いピンクと珍しい白のジキタリス オダマキ
2013年02月16日
コメント(2)
-

身の丈にあったムーブを探して
2月14日先週に続いて幕岩にクライミングに行った。今日の受講生は私1人だった。アリババの岩場でじっくり取り組めた。アリスでアップし、アリス右ルート、アン、アニー、アリババ、シャワーコロンと何しろ1人しかいないのでどんどん進んだ。ご存じの通り私は身長が139センチしかない。標準身長160センチ前後の人たちと同じホールドを取ることはかなり困難でいつも自分の身の丈に合った独自の昇り方を模索してきた。受講生の多い普段はできないが、今日は1人なので私の身長にあった昇り方を指導して頂いた。まずアニー(10.b),昇ると動きが止まる場所がある。ホールドが取れない、標準のリーチなら使わなくてすむけど小さい私には必要な中継ぎの手・足を見つけられないなどが原因である。勿論大元には筋力の無さが常にある。何とか1度目を昇り、2度目にトライ。しかし同じ場所でスムーズに行かなかった。次はアリババ(10.b),1回目は先生のアドバイスでこれまでで最もうまく昇れた。力を使わずほとんど疲れなかった。忘れないうちにと計3回アリババにトライしたが、同じ場所でつまずき、反復学習の成果がでない。うーん、難しい!!でもこれまでこういう風にスムーズに昇れない箇所を何度も昇って自分の身長にあった無理のない昇り方を模索することはほとんど無かったので、とても勉強になった。根気よくこの地味なくり返しを続ければ自分のスタイルを確立していくことができる気がした。岩の形状を見つめ直して自分に使える溝や出っ張りやふくらみを発見し、そこをどう使ってどんなムーブにすれば無理なく昇れるのか、正にクリエイティブクライミングである。単にトップアウトするより遙かに奥が深い。最後にシャワーコロンを2回昇って終了した。10本ほど昇った。 アニー アリババ
2013年02月15日
コメント(2)
-

極上の一粒
下の娘からバレンタインチョコをもらった。Decadence du Chocolat(デカダンス ドュ ショコラ)社製のボンボンショコラシリーズという品らしい。「チョコレートとフルーツ、スパイス、日本ならではの素材を組み合わせた、ステファン・ヴュー シェフの、極上の一粒です。宝石箱のようなチョコレートボックスをお楽しみ下さい」と書いてある。 いやあ、恐れいった。こんな高価なチョコをもらうのも食べるのも産まれて始めてだ。ボンボンだけでなく箱も食べられるという。もったいなくてちょっと手が出ないが、一粒食べたら余りの美味しさに欲望が止まらなくなる気もする。「デカダンス ドュ ショコラ」は、料理を芸術の世界へと極める2つの偉大なる国、日本と フランスの融合を、小さくてデリケートなチョコレートの中に、鮮やかに表現しているんだそうだ。チョコ専門店でそこにはエグゼクティブ パティシエ ステファン・ヴューというチョコ専門家がいるらしい。彼はフランスの伝統を 慈しみながらも日本らしいテイストをも感じさせるスパイスとチョコレートの独創的なチョコを作り出しているという。有り難く頂くそのルージュクールという赤いハート形の一粒を口にしてみたら、今まで味わったことのない複雑微妙な味がする。正にシェフが工夫して作り出した極上の一粒だった。息子と夫にも食べさせようとまた箱にしまった。というよりこれを自分1人で食べたら一体何百キロカロリー?とか些末なことを考えてしまったというのが本心だ。
2013年02月14日
コメント(2)
-

壮麗な宝登山神社
正直に言うと長瀞アルプスも宝登山も蝋梅も物足りなかった。たったあれだけの短く展望も無い山道をアルプスとする命名にも違和感があったし、ろうばい園は小さく、観光化がすすんでいるのも頂けなかった。それに反して何の期待もせず道すがら立ち寄った宝登山神社は素晴らしかった。 宝登山神社本殿全景創建は西暦110年、今からおよそ1900年前、第12代景行天皇の御代というから歴史も伝統もすごい。本殿は権現造りという様式で造られ、壮麗で見応えがあった。彩色も華麗で見事な彫り物が本殿の四面に張り巡らされ、その細部に渡たる細かなデザインが美しく、全く手抜きがない。こういう仕事をする日本人の美意識に心から誇りを感じる。 本殿正面の彫り物 右側柱の立体的柱の彫り物目を惹いたのが神楽殿正面の「神人和楽」という文字である。神様と人が和して楽を奏し舞を舞う、何といい言葉だろう。字も素晴らしい。中をのぞき込んだら能の面や楽器などの額絵が天井にはってあり、とても興味を惹かれた。神楽や能を奉納する日があるのだろうか。 神楽殿 日本武尊社また、奥社の狛犬を一目見てすごく惹きつけられた。後で見た神社の狛犬はよく見かける大きな姿だが、奥社のはかなり異形でこれまで見たことのない気迫が伝わってくる。調べたらこれこそが日本武尊の受難を助けた犬で眷属とされている霊獣らしい。すごい!!犬の気迫に思わずたじろいだ。 奥社の狛犬と宝登山神社の狛犬 奥社の狛犬のパワーに比べれば神社のは形こそ大きいものの可愛いし、愛嬌すらある。
2013年02月13日
コメント(2)
-

長瀞アルプスと宝登山のロウバイ
2月11日急に思い立って長瀞アルプスを歩いて宝登山の蝋梅を見ようと思い、早朝出発した。休日お出かけパスを使って熊谷までJRを乗り継ぎ、熊谷から秩父鉄道である。ルートは秩父鉄道野上駅→萬福寺→天狗山分岐→野上峠→本山根線林道→宝登山登山口→宝登山頂・奥宮→宝登山神社→長瀞駅である。野上という小さな駅で下車、駅からすぐハイキングできる。 萬福寺の脇を通り抜けるとすぐ登山道になる。緩やかな起伏が続き、雑木林がほとんどなので日差しが入って山が明るいのが嬉しい。2時間ほど歩くともう宝登山直下、200段の階段をゆっくり登ると山頂である。蝋梅園は黄色のろうばいがたくさん咲いて春めいている。ロープウエイで来ることもできるので、たくさんの人で賑わっていた。 秩父鉄道 野上駅 登山道の取り付き 山頂からは奥武蔵の山がしっかり見え、両神山のギザギザの稜線もよく見えた。 宝登山頂 両神山ろうばいを心ゆくまで見ていたが、だんだんものすごく冷たい風が吹き付け、風花も舞うようになり、寒くて我慢できなくなった。またしても帽子に覆面で歩いた。反対方向から来る人たちの視線を浴びたが格好より実質だった。登山道というには恥ずかしいような広い道を下って宝登山神社に行った。
2013年02月12日
コメント(8)
-

自分のおむつは自分で
育児サポートで娘の家に行った。葵ちゃんを保育所に迎えに行き、夕食を食べさせ、一緒に遊んだ。しばらく見ない間にまた生長していて、足が強くなり、全く危げなく歩いている。始めのうちは他人を見るようなよそよそしい表情だったが、婆を思い出したのか、だんだん興奮気味になり、可愛い声を出してパワー全開で遊んだ。翌日、保育園へ預けに行く時間調整でテレビを観ていた。ふと、気づくと両手に新しいおむつを持っている!!うんちかおしっこかが出て、幼心にもおむつが必要と考えたのだろうか、自分で紙おむつ置き場に行って持ってきたのだ。何て面白い子なんだ!!おかしくも感心してしまった。この様子ならトイレトレーニングは順調に行きそうだと思ったのだった。 両手に自分のおむつを持ってテレビを観る葵、汚れたおむつが気持ち悪いのだろう、足の形も微妙だ。頭の形とふくらんだほっぺが誰か(?)にそっくり。
2013年02月11日
コメント(8)
-

湯河原のつるし雛と湯河原の花
幕岩のある湯河原に行く時、通常は全線JRでジパング割引で行く。今回初めて新宿から小田急線に乗り継ぎ、小田原でJR乗り換えて湯河原に行ってみた。小田急は旅費が安い。割引無しでもジパングとほぼ同じ旅費だった。小田原駅構内で雅なつるし雛を見た。伊豆稲取が発祥の地だが、和布とつるす立体性や流動性が新鮮でとても素敵だった。 小田原駅構内のつるし雛幕山は梅祭りの準備が行われていた。やはり暖かいので、水仙、さざんか、紅梅、白梅が咲いて一足早い春を告げていた。 小田原駅構内には小田原城をデザインしたプレートがホームの床に貼られていて地元の誇りを感じた。
2013年02月10日
コメント(2)
-

強風にめげず幕岩でクライミング
2月7日神奈川県湯河原の幕岩にクライミングに行った。ゲレンデは桃源郷エリアのアリババ。標高は低いが岩山のてっぺんで遮るものがなく、強風が直に吹き付けてロープもしなうほどだった。寒くてたまらず、もうなりふり構わず帽子に覆面をして昇った。 シャワーコロン(5.9)でアップしアリババ(5.10b)、アン(5.9+)、アニー(5.10b)、アラジン(5.10c/d)などを昇り、最後はアリス(5.9)を気持ちよく昇ってクールダウンした。平日でクライマーが少なく、落ち着いてじっくり昇ることができたし、同行は息子より若い男性1人で気心があい、楽しい1日になった。若い人がぐんぐん伸びていく姿を見るのはなかなか楽しいものだ。
2013年02月09日
コメント(2)
-

様々なデージーが咲き乱れるNZ
ミルフォードやルートバーンのトレイルを歩いて実感したことはNZはデージーの宝庫だということである。デージー科は50種類もあるという。正確な判別でないのですが、見たものをアップしました。まずは一番大きいラージマウンテンデージーです。葉が銀色がかっていて厚みがあり、南島の標高の高い所(例えばマッキンノン峠周辺)にしか咲きません。 ハーストデージー 一株から何本も枝分かれします ラージフラワードマットデージー 海抜900m~2000mの岩場に咲きますホワイトクッションデージー 1m位の幅で密集し、茎はなく葉の中から咲きますエバーラスティングデージー NZの北から南まで標高の高い所に15mm位の小さな花が密集して長い期間咲くのでエバーラスティング(永遠の)という名がついています。日当たりのよいどこにでも広がっています。 ロッククッション 標高の高い地域に石や岩を覆うように生えています。触ると弾力があり、クッションのようなのでこの名がある。約6000万年前からNZに生息しているらしい。ベジタブルシープ 変わった形をしているが、デージー科の一種。羊が密集しているように見えることからこの名がついている。標高の高い山岳地帯に育ち、厳しい寒さや暑さにも耐えられるように葉が毛のようなもので覆われている。 ? マオリオニオン プラテァ
2013年02月08日
コメント(0)
-

NZの華~その1
苔類・樹木類が終わってやっと花の部類まできました。NZで見た花は膨大にあって、花名も確定できないのですが、変わった姿の花、綺麗な花を中心にご紹介します。 NZで最も有名な花、マウントクック・リリーです。葉の形がスイレン(ウォーターリリー)に似ているのでリリーと命名されていますが、キンポウゲ(バターカップ)科です。世界一大きなキンポウゲなので正式にはジャイアントバターカップと呼ばれています。南島の草原の中に真っ白い大きな花が1本の茎からたくさんの花が咲きます。次に貴重だと思ったのはこのサウスアイランド・エーデルワイスです。とっても小さくな花の中央は黄色で15枚ほどの花びらが密生しています。海抜1600mまでの岩場に見られます。しかし実際にはなかなか無くて、ルートバーントラックで2カ所見ただけでした。 アイブライト 標高の高い湿った場所に低く這って広がっています。 シルキーイエローバターカップいわゆるキンポウゲで、普通のものより花が大きくシルクのように艶やかでしっとりしています。 ハースト・キャロット 要は人参の花です イエロー・マーガレット サンデュー グリーンフーデッドオーキッド(頭巾ラン)サンデューは食虫植物の毛氈ゴケです。標高の高い沼地に生えて、虫を捕まえて窒素を吸収して生きています。とっても小さくてしゃがみ込んで見ました。頭巾ランは珍しいラン類です。受粉の仕組みが変わっていて、花の入り口にある舌のような部分に虫が止まると、奥の柱頭に向けてはじき飛ばします。その虫が持ってきた花粉で受粉し、虫が出ていくとき、真ん中にあるヤクに触ってその花の花粉をつけていくようになっています。何ともユニークで自然の知恵に満ちています。
2013年02月07日
コメント(0)
-

トゲで入れ墨をする木~NZの樹木その2
南半球だけあって日本では見ない樹木類が沢山あり、なかなか名前を確定できず覚えられませんでしたが、自分の好みの木はいくつか覚えました。針葉樹はこれでスクラブされるとほっぺたが傷つきそうにとがっていました。 ターペンチンスクラブ ゴブパイン どこにでもありそうでない クロミコ キャベツ ツリー どうしてこれがキャベツ?と頭を捻ったキャベツ・ツリーは海辺や湖の近くでよく見た高木で白い花が咲いていました これはマタゴーリと言う低潅木でトゲだらけです。マオリ族もこのトゲには難儀したらしいですが、この鋭いトゲを使って入れ墨をしたと聞きました。現地ガイドの男性も入れ墨をしていた人がいて、日本と同じく入れ墨文化がありました。 マタゴーリマスキーツリーデージーデージーが木質化したものです。 ブッシュ・スノーベリー ブロードリーフブッシュ・スノーベリーはその時期になると可愛い赤い実がなります。日本の苔桃にちょっと似た感じです。 野生のバラ私は野バラから作ったローズヒップティーが好きなのですが、原料となるローズヒップはチリやNZ産がほとんどでその花も実も見たことがありませんでした。ガイドの説明によるとNZではこの野生のバラが沢山自生していてこの実をローズヒップティーにしているのだと聞いてとても親しみが湧きました。花も自然のままの素朴なバラで愛しかったです。 ラーンツ・ウッド ツリー・グランゼルラーンツ・ウッドは大変ユニークな木です。写真は若いときの姿で尖った葉が下を向き、鳥に食べられないような葉形をしていますが、生長して大きくなると鳥も届かないのでもっと幅の広い葉に変貌します。ツリー・グランゼルは白く大きな花をつけ見栄えがします。
2013年02月06日
コメント(1)
-
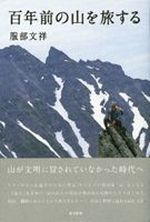
百年前の山を旅する
以前から、文明社会の利器を持たずに山中で食料を調達しながら山を登るサバイバル登山家の服部文詳さんに関心を持っていた。その彼の「百年前の山を旅する」という本をアイスクライミングにいく電車の中で読んだ。 100年前の装備で山に入るとか日本最初の沢登りとか火を持たないで入山するとか、非情に興味深い章で構成されていて、どれも面白かった。まず感じたことはこの人は何という探求心の旺盛な人なんだろうということだ。更に資料を細かく読み込んだり古い装備のことを詳しく調べる能力にも驚いた。失礼な話だがサバイバル登山家で蛇や蛙やイノシシを殺して食べる人が資料を渉猟するというイメージに繋がらなかった。今回は古い資料や古い地図がふんだんに引用されてさまざまな考察もなされている。そして単に詳しく情報を探り出しただけではなく、調査で知った昔の登山や冒険の意味を服部本人の視点で捉え直し、意味づけしている。根底には便利になった現在の登山や文明のあり方に懐疑的な視点を投げかけていて、いつも「山に登るとはどういうことか」という自己への問いかけがある。日本最初の縦走という登山形式を実行した木暮理太郎と田部重治が現在で言う奥高尾縦走・笹尾根縦走を日本登山の黎明期1909年明治42年に行った記録がある。その時と同じスタイルで服部は出かける。和服・鳥打ち帽・股ひきに脚絆・わらじ・着ござ、鍋とシャツという奇妙な出で立ちで、その写真を見るとこれは芝居の一場面かと思ってしまった。国定忠治が出てきそうな雰囲気だった。とにかくユニークすぎる人だ。平出さんや竹内さんのような登山家とは運が良ければ登山用品店で会うチャンスがあるが、彼の登山スタイルは現代の便利な登山スタイルを拒否しているので、そのチャンスはないだろう。情熱大陸という番組に出たときは相当な変人ぶりを発揮したらしい。一度、生のご本人と会ってみたいものである。
2013年02月05日
コメント(0)
-

ドライウォールにチャレンジ!!
翌日2月3日も風もなく温かくて絶好のアイスクライミング日和に恵まれた。今日の目標を限定ルートとドライウォールを入れて最低でも10本は昇ることと自分なりに決めた。他の参加者も昨日にもまして意欲的で、女性グループの皆さんも朝からガンガン昇っていたが、私は腰と肩に配慮して休憩を勘案しながらじっくりと昇った。初めてドライウォールにチャレンジした。どういう風にして昇るのかルールも全く知らなかったので教えてもらい、試しに直線部分だけでもと体験してみたら何とハングを越えて終了点までたどり着けた。ドライというので異次元のようにおそれていたが、異次元ではなくウォールクライミングとアイスクライミングの中間のような感触で、アイスクライミング専用のクランポンの爪で木質のウォールを突き刺す感覚がとても快感だった。アイスを何本か昇って2度目のドライルートに取り付いた。中間部がハングしていて、腕の力が要る。無い力を振り絞ってワンステップづつ身体をあげていく。正対だと駄目なので身体を斜めにねじって上のホールドにバイルを引っかけようとトライ。何とかハングを越えて終了点まで到着。ああ、面白かった!!、でも腕の力を目一杯使ってしまった!! 取り付き ハング部分 どうにかハングを越えて やったあ、終了点だ!! ドライウォールチャレンジに成功してすっかり気分がよくなり、その後アイスも連続して昇った。目標は楽々達成。カナダ人のガイドと、昨秋のアルゴンキンを訪ねた時の話題で盛り上がり、親しくなるというおまけもあった。
2013年02月04日
コメント(5)
-

岩根アイスツリーでアイスクライミング
2月2日信州川上村にある人工氷瀑岩根アイスツリーでアイスクライミングの練習をした。スポーツメーカーのミレー主催のイベントである。最近の若い人たちの間でアイスクライミングは人気があるようで、若い男女の参加者が圧倒的に多くて、いつもは靜かな岩根山荘も活気に満ちていた。 午後1時頃から練習開始。私は熟年女性7名のグループで練習した。温かくて有り難かった。1年ぶりの岩根アイスツリーだったが「がんばるぞ」という気持ちがあまり起きず、無意識でやったのが返って良かったのか力が抜けていて、全く身体に負担なくできて、よかった。軽く4本登って初日は終了した。夜はアルコールの1滴も飲まず9時半に寝た。 温かいせいで氷の締まりが緩く、アックスの刺さりが良くて楽でした
2013年02月03日
コメント(0)
-

NZで見た樹木類~その1
南半球にあるNZの樹木類は日本では見られないものが多く、大変珍しかった。南極ブナのような大木は主に幹しか見られなかったが、低潅木は花が咲くものが多く覚えやすかった。名前はすべて英語とマオリ語の二通りの表示があり、マオリ語はその植物を感覚的に表現していて面白かった。 シルバービーチの葉 大木の葉にしては小さく可愛い シルバービーチとシダ類 シルバービーチとコケ類シルバービーチが大木になり、コケ類やシダ類を寄生させて無尽蔵に生物を養っている姿を見て、自然は生きている、自然は共生していると思うと深い感動を覚えた。 森の中のブナの高木 王者の風格 ティーツリー白い小さな花を無数に着けるこの小潅木はマオリ名ではマヌカと言い、これから取った蜂蜜はビタミンを多量に含み、医療効果もあるらしく、マヌカハニーとして高額で販売されていた。 ラージ・フラワード・ヒービー海抜800mから1600mの多雨地帯に生育し、真っ白な花が群生するのですぐわかる親しみやすい潅木です。幾つか種類があり、これは花の大きい種類です。 ツリー・フューシャ 園芸品種の フクシアツリー・フューシャは ミルフォードトラックで何度も見たピンク色の可憐な花が咲く蕎木です。樹林の中を歩くと道にこの花が落ちているので不思議に思って上を見てその存在に気がつきました。園芸品種のフクシアとよく似ていてとても親しみがありました。パイナップル スクラブ 葉がパイナップルの葉に似ていて、標高1400m程度の日当たりのよい場所にたくさん生えていました。
2013年02月02日
コメント(4)
-

NZの苔とキノコ
NZで1200枚ほど写真を撮ってきた。珍しい植物が多かったので手当たり次第に撮ったが、いざアップするとなるときちんと分類するのが私の能力を超えている。大まかに樹木類、コケ類、シダ類、花類程度の枠組みで紹介します。正確では無いことをご了承下さい。 南極ブナにぶら下がるゴブリンモス 日本のサルオガセ風です こちらもゴブリンモスの様な形ですが白くて異次元の世界を感じさせますレッドキャップス (地衣類) 岩などに生え、根はそこから栄養を取り、茎で光合成する。赤いキャップのような先端部分に胞子が入っている。一見真っ白い苔の大群落です。 クラブモス 彩度の高い緑色がグランドカバーのように地面を覆っている 左 ブラケット・ファンガイ(猿の腰掛け) 腐った木の幹などに直角に生える。上の部分は黒く、下は白い。癌の治療に効果があると言われている。右 ビーチ・ストロベリー キノコの一種でシルバービーチに寄生する癒しの旅だと考えてろくに事前学習もせず、遊び半分でNZを訪ねた。おかげで新発見ばっかりだった。ここはコケ類・シダ類・地衣類の宝庫でこの方面に興味がある人にとっては垂涎の的のような地域だった。あまり興味がない私でも珍しくて関心をかき立てられた。
2013年02月01日
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1










