2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年03月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
ゆりかもめ
あしたも送別会があるので、今週まっすぐ家に帰れるのは今日だけ。疲れたときには甘いものかも・・・ということで、地下鉄の乗り換え駅で、いつも元気に売り込みをしているシュークリーム屋さんの声に負けてしまい、冬季限定のホワイトチョコレート味とチョコレート味と、2種類も買ってしまいました。今日は会社の近くにまで伸び、今週月曜から開業しているゆりかもめに一駅だけ乗りました。工事のはじめのころ、高速道路と勘違いしたこともあり、それからものすごくできるまで時間がかかっていたところを知っているので、やった実を結んでよかったと思いました。車窓から東京タワーや晴海トリトンその他の高層ビルをながめて、ちょっと気分がよかったです。そのうち東京魚市場が築地からこの沿線に移転してくるので、もっとお客様も増えることでしょう。東京駅から4Kmほどしか離れていないのに、昔はタクシーで行ってもらえなかったようなところだったそうですが、そんな街も大きくかわりそうです。大きな造船場の跡地は、一大再開発プロジェクトとなり、しばし、変わり行くところを見届けたいところです。新橋方面へはときどき出かける用事があるのですが、バスで行く経路と、ゆりかもめで行く経路と2経路選べることになりそうです。ゆりかもめは、お台場をとおり新橋行きです。ずいぶん遠回りになり、時間もかかりそうですが、レインボーブリッジあたりで夕焼けをながめ、ノスタルジックになりたいときは、この経路を選びます。途中にあるテレビ局へも友人がいるので、何度か中にも入ったりしたことがあるのですが、また用事をつくってきれいな食堂でご飯を食べたいものです。BGM:モーツァルト トルコ行進曲 このあいだ買ったBEST CINEMA CLASSICSから トゥルーマン・ショーという映画に挿入されているそうです。 私がいちばんはじめに聞いたクラシックの曲はたぶんこれです。 幼稚園のころ、雨がふったら教室にはいりましょう・・・という 音楽がこれでして、この曲が好きだと言ったかどうか定かでありませんが 親がドーナツ盤(45回転)のレコードを買ってくれました。 表が「トルコ行進曲」で、裏が「子犬のワルツ」 今も実家にあるのでしょうか? 表が「ドナウ川のさざなみ」で、裏が「スケーターズワルツ」というのも 確か家にありました。 同じ頃、「帰ってきたよっぱらい」とか「ブルーライトヨコハマ」とかの ドーナツ盤も家にありました。 昭和40年代半ばのことのおはなしです。オルガン教室にも行っていました。いろんなことを思い出してしまいました。
March 30, 2006
コメント(6)
-
ルガーノ
昨日は今年度組織の納会、言ってみれば打上げ。今日も、同じくちょっと身内の納会、打上げ。いろいろありながらも、こういう会をもって楽しく会話ができるのはまだありがたいことだと思っています。昨日と今日と似たような一日だったので、似たようなキーワードで聴きたい音楽を探しました。BGM:ベートーヴェン ピアノソナタ第12番 op.26「葬送」 ピアノ:ミケランジェリ 1981年ルガーノ音楽祭でのライブレコーディング昨日聴いていたアルゲリッチのCDに「ルガーノ」というキーワードが目に付きました。スイスにあってイタリア語圏の小さな街で4-5月に音楽祭があることもさっき知りました。ベートーヴェンの前半のソナタが聴いてみたい気分だったのと、ちょっといろいろあって「葬送」ということをイメージしたかったこともありました。***ピアノの発表会や長い目の曲を決めるとき、ニ社択一になることが何回かありました。ショパンのバラード2番/3番で、結局2番を選び、シューベルトのD935-2の即興曲、D946-2の3つの小品では、3つの小品(2番)を選び、ベートーヴェン11番(op.22)/12番(op.26)では11番を選らんだりしています。ということで12番ソナタは楽譜を見ただけなのですが、お気に入りのひとつであることはいうまでもありません。時間があれば、どちらもやればいいのですが、そのときの雰囲気とちょっとした決めてがあって選んでいるみたいです。op.26の変奏曲は、ソナタ形式のソナタから何か変化をのぞんでいるようで、私から見れば意欲的な作品の1つなのかもしれません。気分がなごむ曲のひとつであったりします。はなしがもどって、ルガーノ音楽祭、アルゲリッチが続けて弾いているみたいなので、どこかのブログには別府に似た街なのでは???と書いていましたが実際はどんなところなのでしょう。散策してみたくなりました。
March 29, 2006
コメント(3)
-
21時前の書店めぐり
会社の帰り、閉店間際の八重洲ブックセンターへ行き、仕事関係の本を買ったあと、講演会である先生から前から是非読んでくださいと薦められていた藤原正彦さんの「国家の品格」という本が、レジの前にも並んでいたので、手にとって読み始めています。日本人の持つ国柄、情緒、教養、武士道などを取り戻してほしい点、欧米の論理と合理に身を売りすぎている点を指摘しています。2-3ヶ月前にも書きましたが、外国人のビルトッテンという著者も同じようなことを指摘していて、アメリカ人の真似をするような社会風土に一石を投じていたりしていて、この論調の本に共感することが多いです。***小学校で英語教育をするのは悪いことではないけれど、日本語をもっと力入れたほうがいいのでは、私も同感です。高校の現代国語に芥川龍之介や森鴎外がなくなるとか、聴いたことありますが、いったい文部科学省はどんな発想なのだろうと、疑問におもったりもしています。本の背表紙に、重要なのは、「文学」「芸術」「数学」とありますが、自分自身も少しはあやかりたいです。BGM:ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第4番 B-Dur op.11 「街の歌」 ピアノ:マルタ・アルゲリッチ クラリネット:マレク・デネマルク チェロ:マーク・ドロビンスキー 2002年 ルガーノ・フェスティヴァルでのライブ CDのライナーノーツには、 弟子のチェルニーによると、ベートーヴェンがあるクラリネット奏者の 依頼により書いた作品とのこと。 「街の歌」というCDが必ずおいてあるだろうとおもって 渋谷HMVへ行きましたが、その甲斐はありました。
March 28, 2006
コメント(2)
-
ジャズ組曲2番だったとは・・・。
ピアノの発表会がおわってまもないのですが、次の曲はあれがいいとかこれがいいとか、よく話題に上ったりするのはよくあることです。CDとか楽譜とかそれなりに持っていることはだんだん知られてきて問い合わせもあったりします。今日の夕方は、私自身ここ3-4年、まったく見もしなかったハイドンのソナタの楽譜を、古くからの音楽仲間に貸すことにしました。それから、ブッフビンダーとブレンデルのCDと一緒に。ハイドンのソナタは、番号が出版社やCDによってまちまちで、結局ホーボーケン番号(Hob)が、世間共通の番号なのだといろいろ会話をしてみてわかりました。発表会でもあまりおめにかからないハイドンのソナタ、最近きいたのは、Hob.XVI-48のC-DurとHob.XVI-52のEs-Dur(こっちのほうが有名かも)なので、これはAさんが弾いたもの、これはBさんが弾いたものとお伝えし、ついでに唯一自分が大人になってからさらったHob.XVI-34 e-mollも弾いていて楽しかったのをお伝えしました。この3楽章は、また弾きたくなってしまいました。帰りに渋谷で下車し、23時まであいているCDショップへ行きました。このあいだから言っていたベートーヴェンのCDも見つけました。それ以上に、たまたまいたときになっていた音楽が、今の自分の心情にぴったりな感じがし、家でも聴きたくなって衝動買いしました。お店でかかっているCDはときどき買ってしまうのですが、店員さんはしてやったりなのでしょうか・・・。映画音楽ばかりあつめたクラシックのCD1-2年前にみた三谷作品のエンディングで聴いたような記憶があります。BGM:ショスタコーヴィッチ ジャズ組曲第2番より ワルツ第2番 マリス・ヤンソンス指揮 フィラデルフィア管弦楽団 (BEST CINEMA CLASSICS 100より) この曲、ショスタコの曲だというのはさっき知りました。 日本人にはものすごく受けそうなメロディのように感じます。 大正デモクラシィの時代のようにかかっていた当時のモダニズム みたいな風景が浮かびます。 さっきからこればっかり聴いています。 今日はあまりなにも考えたくなく、頭をからっぽにしたい気分です。
March 27, 2006
コメント(2)
-
もぬけの殻から脱出
発表会がおわってもぬけのからの状態で、夕方までほとんどなにもしない日でありました。CDで音楽を聴きたいとも思いませんでした。こちらでは、多くの書き込みをいただき、いつもより多いアクセス数もあり、気にしていただいた方がたくさんいらしたことに改めて気付きました。心から御礼申し上げます。たった10分間舞台に出るだけのこんなのですから、毎週のように演奏活動されている方や、AプログラムとBプログラムがあるような方とか、全国を駆け巡る演奏家が、どれだけの体力と精神力があるのかとか感じてしまい、尊敬してしまいます。そうおもって、いろんな演奏会を聴かせていただくのもまたいいかもしれません。夕方、気分転換にヘアーサロンへ行き、髪を切りに行きました。普通はピアノの発表会へ出る前に整えるものでしょうが、そんな余裕はみじんもありませんでした。某ホテルの地下にあるのですが、15分のクイックマッサージも受けました。熱い蒸しタオルも首の後ろをおさえ、ちょっとストレッチするとたいへんリラックスできました。そのあと、今日は食材を少し買い求めに商店街を散歩していました。見上げると、桜が三分咲きくらい、下を向いてあるかずに、上を向いて歩くほうが今日はよかったです。BGM:メンデルスゾーン 交響曲第3番「スコットランド」 クリーヴランド管弦楽団 指揮:ドホナーニ この交響曲のCD,商店街を散歩しているときに急に聴きたくなり、 家に帰ってから探しました。パズルを探すような感じなので来週は CDの整理でもしないと。 スコットランドの4楽章、ほのぼのとして、元気がでてきます。
March 26, 2006
コメント(6)
-
病み上がりの発表会
昨日はあまりにも体調が悪すぎて、いろいろ書いてしまいました。毎週土曜日は、「風のハルカ」を1週間まとめてみて、そのあと流れで「俳句王国」という番組がテレビで流れるのですが、いつもと同じように、寝床で見ていました。氷まくらをしていて、少し楽になりました。3月の土曜・日曜は、時間のないなか、それなりに練習したとおもうので、とにかく平常心になろうとおもって、1時間ほど家でピアノを弾いたあと、虎ノ門にあるホールへ行きました。事前に2-3分さわれるので、気になる箇所を弾いていました。発表会では、シューマンの謝肉祭op.9から、パンタロンとコロンビーヌ、ドイツ風ワルツ、パガニーニ、告白、プロムナード、休憩、ペリシテ人と闘うダヴィッド同盟の行進と、自分では久々に長い目のプログラムでした。おかげさまで、熱がようやく下がったところで出ることができました。9ヶ月という準備期間が長いか短いか、意見はわかれるところですが、それなりに時間をかけただけのことはありました。譜読みすら満足にできない曲(パガニーニ)とか、本当に弾けるのかと、昨夏は疑心暗鬼となりましたが、3月にはいって、やっとそれなりになった感じがしてきました。演奏の方は、直すところはいろいろあるものの、今の自分の力量だったら、これでいっぱいいっぱいだっただろうと思います。最後の「ペリシテ人と闘う・・・」は、少し走ってしまった感がありますが、やっているときは、夢中でよくわかりませんでした。集中力を維持することを考える意味でも自分ではいい選曲でした。毎年ピアノを聴いてくださる方が、去年と比べて和音の音色が格段によくなったと言ってくださったのは、ありがたかったです。(昨年はブラームスのop.118-3、op.118-5と比較して)3月に入って、グランドピアノのある場所でたくさん弾けたこと、いろんな人に聴いていただける環境で弾いたことはプラスになったと思っています。ありがとうございます。打上げは、いつものメンバーと六本木ヒルズへ行き、いろいろ談笑しました。(他の人はバラード3番、別れの曲、献呈、喜びの島、ベートーヴェンの悲愴ソナタ、シューベルト即興曲D935-1,ベルガマスクのパスピエなど)みんないい演奏で、楽しい発表会となりました。3月月末の土曜日は、毎年同じようなことをして、7年になり、有意義なことも多いということも実感しています。先のことは何も考えられない状態ですが、落ち着いたらまたピアノを引き続けるようになりたいです。5月の連休にいろいろお誘いを受けているので、そのときもまたいい演奏できるようにしていきたいです。ブログを書き始めて興味をもってくださって、発表会のたびに応援していただき、たいへん感謝申し上げます。ありがとうございます。
March 25, 2006
コメント(18)
-
熱さましor氷まくら
ピアノの発表会はあと16時間後。体調がよくないときの方が、邪念もとれ、すこしはいい演奏ができるかもと、言ってくださる人もいますが、実際そうなることを祈っています。確かに変なところへはあまり力がはいらない、というより入れられません。早寝して、あしたが少しでもいい日であることを祈ることにします。前の日はいつも、まったく眠れなかったりするのですが、今日はそういう心配は、特になさそうです。立ち上がりがよくないのと、おしまいにスタミナ切れしないのと、そう書いてしまえば、高校野球のピッチャーのようですが、10分は普通からみれば長い方、せめて小さな曲ののタイトルたちが、弾いているときに、はっきりイメージできるようにしたいです。神様が風邪と熱をもたらしたのであれば、それはいい神様だと信じることにします。
March 24, 2006
コメント(11)
-
街が歌につつまれたらいいですね
風邪をひいて、一緒に落ち込みたいとき、シューベルトの冬の旅をよく聴きます。風邪のピークを超えて、いっきにテンションがあがるときは、リストの超絶技巧だったりします。マゼッパだったり10番だったり。ようやく精神的に安定したころ、メンデルスゾーンの無言歌集を聴いています。自分で意識しているわけでないのに、ここ何年かかってにそうなってしまって、今ではすっかりバロメータになっていたりします。ちょっと元気になりたいとき、前向きになりたいとき、ベートーヴェンの初期の作品を聴くこともよくあります。op.22という11番のソナタを何年か前ピアノの発表会のために弾いていたこともあるのですが、この年は一度も風邪を引かずに元気なままで冬を越したりなんかしました。自分で弾いた音を聴いているだけでも、元気になったりするので不思議です。晩年は耳の病気とかで作風も当然変化しますが、もって生まれた明るさがあるような気もしています。ご縁あって、op.11の「街の歌」という素敵なピアノトリオの演奏を仕事の合間に聴きました。2週間くらい風邪気味ですごしているので、こういう楽しい音楽を聴くということがぴったりでした。室内楽のCD,ピアノトリオ、ピアノカルテットのものを持っているかといえば、あまりありません。「大公」は友人が発表会で弾いたときにはまったことがあるのですが、せいぜいその程度。年に数えるほどしか聴きません。それでもいろいろ探して、初期のピアノカルテットが見つかったので、そのCDを聴いています。ライブで聴いた曲にいちばん近い曲を探して、今日は妥協しました。 BGM:ベートーヴェン ピアノ・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロのための四重奏曲 op.16 演奏:パドヴァ・トリオとヴィオラ奏者 (ほかのCDではピアノと管弦楽のための五重奏曲となっています) この曲の3楽章のロンドが好きで、一時期目覚めの音楽にしていました。週末、発表会がおわったら、久々にCDを買いにいこうと思います。いろんな音楽を聴いていると世界が広がっていくようです。
March 23, 2006
コメント(6)
-
予言の鳥
今日も明日も宴会が続きそうです。火曜日が祝日だったのでよかったとおもっています。あいかわらず、ヘモグロビンA1Cの値が高く、産業医の先生は困りはててしまいましたが、来週以降は、八百屋さんへも行き、ヘルシーな食材も買い揃えようと思っています。一時期、コンビニ弁当ばかりで、身体をこわしてしまい、自らコンビニ禁止令を出したりしましたが、最近は、お惣菜とかが充実したりするので、家の近くにある5件ほどある、コンビニエンスなストアにお世話になること多いです。今日も、終電車だったし、平日はしょうがないのかもしれません。明日早起きして、おきてすぐに暗譜でピアノが弾けるかやってみようか、でも疲れているので二度寝してしまうかもしれません。明日の朝は、大切な打ち合わせもあるので、変なところで言いくるめられたり妥協したくないことにもなりそうですので、リフレッシュしないといけません。朝にペリシテ人と闘う・・・・を弾いたら、リフレッシュできたり、テンションがあがったりするのでしょうか?変に期待したら、まったく弾けずに落ち込んでテンションが下がってしまうかもしれません。謝肉祭を弾く発表会がおわったら、謝肉祭は弾き続けながら、モーツァルトのソナタやシューマンの小品を夏の終わりごろまで弾くことにしようと思っています。弾きたい曲を言い出すときりがないくらいあるので、あわてずゆっくり練習できるように。3月やこの前の11月のようなテンションで保つのは年に2回くらいが充分なんでしょうね。お酒がはいっているので、今日は(も?)文章がまとまっていないかもしれません。BGM:シューマン 森の情景 op.82 (pf)ピリス 今日は「予言の鳥」という曲が急に聴きたくなりました。
March 22, 2006
コメント(4)
-
森の入り口
自分自身、統計的にみて、火曜日に会社を休むことが多いです。単に体調が悪いというときもありますが、それだけが理由でないときも時にはあります。火曜日が祝日となって、ほっとひといきの一日になりました。ピアノの発表会まであと4日。ピアノは3時間近くさわっていましたが、たぶん今くらいというか今以上にはもう発表会では弾けませんが、その日になにをするのか、同じことをやってみようと思いました。曲を通して弾くのはもう当日まで多くて3回くらい。細かいところをさらって、楽譜を見直すようにしたほうがいいようにも思えてきました。いろいろやっていると森の中をさまよっている感じになり、きりがなくなってしまいそうになって、適当なところで今日は弾くのをやめることにしました。発表会がおわって、5月の始め頃、弾く機会もありそうなので、根を詰めすぎず、マイペースでやっていきたいです。とはいってもテンションの低い演奏ではぜんぜんつまらないので、当日の10分間、ものすごく集中できるように、どうすればいいのか考えてみることにします。静かな曲を急に聴いてみたくなりました。BGM:シューマン 森の情景 op.82 ピアノ:マリア・ジョアン・ピリス 森の入り口にはじまって、別れという曲まで9曲、 今やっている曲の反動か、こういった曲にあこがれてしまったりします。今年はモーツァルトとシューマンにかなりこだわるかもしれません。
March 21, 2006
コメント(6)
-
ものづくり寄席
ブログをはじめるきっかけになったのは、仕事の延長線上から、情報共有→ソーシャルネットワーキングという勉強会に参加したのがきっかけだったりします。その流れでいろいろメーリングをとっています。毎週、講演会の案内があって、興味のあるときにときどきうかがいます。経済学の先生も話がかたくならないように、「ものづくり寄席」ということで、受付の方も落語の寄席の格好をしたりして、嗜好を凝らしています。そんなわけで、今日は夕方、丸の内の三菱ビルというところで聴いてきました。<テーマ>3月20日(月)高橋 伸夫東京大学大学院経済学研究科教授「育てる経営と学習曲線」 「日本型年功制」は明らかに年功序列ではなかった。「育てる経営」という思想を実践してきた企業が、長い時間をかけて、「日本型年功制」というシステムを体現するようになったのだ。今こそ原点に立ち返り、従業員の生活を守り、従業員の働きに対しては次の仕事の内容と面白さで報いるようなシステム「日本型年功制」をより洗練された形で再構築すべきである。今回は、できれば学習曲線にまつわるトピックスも交えてお話したい。***成果主義ということばに疑問をもちはじめたころ、高橋先生の日本企業のよさを見直す本に琴線に触れ、感銘をうけたのは1年ほど前。実際にライブで先生のお話を聴ける機会を楽しみにしていました。日本人は不況になれば、成果主義のようなものをもちだして、ものごとをこわそうとする。バブル前の円高不況のころは能力主義といっていたが、やっていることは同じ。普通の評価のサラリーマンの人をA/B/Cとか、無理に評価しても徒労におわるだけでほとんど意味をなさないということを得々と説明されました。日本のいいところは、給与とか役職でなく、興味のある面白い仕事をアサインメントして報いることで、それが人事システムとして機能していたはず、主観的に評価していた意義をもう一度思い起こすべき。・・・と、感銘を受けました。<成果主義の違和感>として -大多数の人には差をつけること自体に徒労。 -点数を換算せざるをえなくなって不満増大。 -好き嫌いで点数・給与を反映させる不条理感。 -明らかになった客観的無責任 >>本当の評価とは、「また君と一緒に仕事がしたい・・」では? >>何のための評価??? 日本企業は客観評価より主観評価の方が正しいことに気づきだした。 (とくにすごく仕事ができる人とそうでない人の評価が客観評価だとものすごくぶれる結果になる) *** 日経新聞にも1ヶ月ほど前出ていましたが、住友商事とか大手商社が もとの職能管理制度に戻す動きがあるとか。 たぶんそういう方向に世の中がまた向かっていくとおもいます。 いろんなことをやってみて、また日本企業も自分も成長したのであれば、 このふりまわされた2-3年間は、無駄にならないでしょう。
March 20, 2006
コメント(4)
-
メトロノーム
今日は風が強いことが一日家にいてもわかりました。無理をしない何もしない日にしようと思っていました。昼からテレビ三昧、スポーツ三昧、WBCはすばらしい投手戦のなか、6-0は見ていてすかっとしました。雨が降ってたいへんでしたが、ダイヤモンドをかこう大きなシートをみて、ウィンブルドンテニスの雨の様子を思い出しました。阪神大章典、ディープインパクトは格が違いすぎました。個々の競馬場の桜並木はきれいなので、いつかまた立ち寄りたいと思い出しました。栃東と魁皇が勝ってほっとしました。魁皇は負け越せば引退とか。5月場所はまた1日くらい両国へ行ってみたいとおもっているので、がんばってほしいです。内容のいい相撲が多かったのでこれも満足です。****合間をぬってピアノの練習。BGM:ベートーヴェン 交響曲第8番 ヘ長調 NHK交響楽団のテレビ 指揮:ネヴィル・マリナー 第2楽章は、メトロノームをイメージして作曲しているとの 池辺先生の解説。まったく知りませんでした。 ベートーヴェン自身がそんな手紙も書いているのが残っているそうです。 8番の交響曲は、好きな曲のひとつです。 こういう力のぬけたときのベートーヴェンを聴くと旅行したくなります。 ****メトロノームをつかってピアノを弾くのがどちらかといえばというより相当苦手です。ロマン派の作品でテンポは一定にしなくてもいいものであっても、やはり基準となるようなことも必要。弾いているとだんだん速くなるのはほどほどにしないと。シューマンのペリシテ人・・・はアッチェの指示がところどころありますが、それを見て安心してしまうと、とんでもないことが起こってしまいそうということで、最後までテンションを保つ方法を模索しています。
March 19, 2006
コメント(200)
-
ピアノの発表会の下見・・・
ピアノの発表会1週間前。私の通っている音楽教室はピアノ以外にも弦楽器、声楽もあり、かわったところでファゴットやチェンバロの先生もいます。そんなわけで発表会となると、3月の土日をほとんど使っておこなわれます。他の部の演奏も聴きたいということもあって、来週ピアノを弾く発表会の会場へ行きました。20人くらいの演奏を聴いたのですが、仕事をしながらレッスンに通っている人ばかりなので、共感するものも多いです。おしまいのほうのプログラムは、ブラームスop.116-4、ラフマニノフop.23-4、バッハ/イタリア協奏曲、リスト/ため息ベートーヴェンop109の3楽章、ブラームスop.118-2・3リスト/メフィストワルツ。みなさん、さすがでした。去年自分が弾いた曲もあり、他の人の演奏を聴いて勉強になりました。メフィストはめったに聴けない迫力ものでした。人となりも知っている人も多いので、多くのピアノ仲間が集まってきて、1年ぶりに会う人も多かったです。この場にいれば、誰かに会えそうと期待できる不思議な日でもありました。「来週の発表会聴きにいきますから・・・」とわざわざ声をかけてくださる方もいて、ありがたかったです。また今日のすばらしい演奏を聴いて、自分なりにがんばろうとおもいました。夜9時からピアノレッスン。佳境にはいっているだけあって、深く掘り下げてかつ、1週間で修正できるものになり、この時期のレッスンはいつも忘れられないものになったりします。アッチェランドの神様は今日もいるようで、だんだん速くなりすぎて収集がつかないということにならないよう、ときどきクールダウンして、知的な演奏を目指したいです。BGM:シューマン シンフォニックエチュード op.13 ピアノ:伊藤恵
March 18, 2006
コメント(2)
-
ザ・グレイト/第197回 東京シティフィル定期
東京シティフィルハーモニック管弦楽団第197回定期演奏会を聴いてまいりました。(東京オペラシティ・コンサート・ホール)ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58 (ピアノ:三輪郁)シューベルト 交響曲第8番 ハ長調 「ザ・グレイト」 D944 指揮:飯森泰次郎/東京シティフィルやっぱりライブのコンサートはいいです。大好きなプログラムだったこともあって、昨日から楽しみにしていました。その日の仕事しだいでお伺いできるかわからないと、ピアニストにはあいまいな返事しかしていなかったのですが、聴くことができて本当によかったです。今年は寒い冬が長かったせいか、やっと春が見えてきましたという感じで、明るい曲調とさわやかなピアノとオケの演奏に魅了されました。ブラウンのドレスもなかなかよかったです。シューベルトの「ザ・グレイト」「飯森泰次郎のザ・グレイト」とパンフレットにありましたが、圧巻でした。「人間の声が束になっている。全部の楽器がだよ。」とシューマンが言ったそうですが、長い絵巻物のような歌がつづきました。第4楽章、長い長い坂道をあがって、感激するかのように、自分自身も聴きながら、どこかを駆け上がっているかのようでした。オペラシティ・ホールでオーケストラ聴くのはいいですね。飯森さんの指揮もまた見てみたいです。終わって2時間くらい今たっていますが、まだ音楽があたまのなかを駆け巡っています。
March 17, 2006
コメント(4)
-
パウゼ
ちょっと風邪気味だったため、会社の診療所で薬をもらって、飲み続けているのですが、すぐ眠くなるみたいです。会社でエクセル表で集計していても、今日はやめておいたほうがいいかもと、悟ってしまうくらいでした。ついこのあいだまで不眠症気味だと騒いでいたのが、信じられないくらい熟睡できます。今日は夜7時半には家に帰り、2時間ほど「休息」したあと、ピアノの練習。シューマンの謝肉祭の「休息」をせっかくなのでさらっていました。中途半端に暗譜をした後遺症が残っていまして、長丁場のこの曲のなかでも、なかなか納得がいかない箇所が多いです。ミスをすると、たいへんめだってしまう曲なのですが、思い切り良く弾きたい曲でもありますし、流れに乗って、次の曲につなげたいですし、落ち着いてよく考えてみることにします。曲を通して思いっきり弾く体力はあまり使わず、来週にできるだけとっておきたいところです。明日、仕事が早くおわればコンサートに行きたいです。BGM:ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 op.58 ピアノ:内田光子 王立アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 指揮:クルト・ザンテルリンク ベートーヴェンのピアノ協奏曲はみんな好きですが、冒頭のいきなりピアノで始まる部分から聴き入ってしまうこの曲は特にお気に入りです。1808年12月、運命と田園と一緒にウィーンで初演されたそうです。東京シティフィルのホームページに、同じ頃の日本の歴史が書かれていて、1806年に喜多川歌麿没、1808年に間宮林蔵樺太探検とありました。日本史は好きでしたが、もうひとつピンと来ませんでした。ショパンとシューマンは1810年に生まれているので、やっぱり音楽のことで考えたほうがピンときそうです。
March 16, 2006
コメント(6)
-
桜前線・私鉄沿線
東京の桜は3月22日に開花するとか、今年は寒い日が多かったので、こういうニュースもほっとさせられます。気象庁と民間気象会社の見解の違いは、どのような決着を迎えるのでしょう。切磋琢磨するのも悪くないと思い、東京メトロや山手線での桜並木を楽しみにしています。***ピアノの発表会はいつも五分咲きの桜の頃だったりして、それにあわせて曲をイメージしたこともあります。今回で大人になって今のピアノ教室で7回目の発表会になり、弾いた作曲家もショパン→シューベルト→ベートーヴェン→ベートーヴェン→シューベルト→ブラームスで、今回はシューマン。ショパンは初めて発表会に出たときに弾いてから、それ以来6年もレッスンでみてもらったのは1曲もなし、シューベルトは3-4年周期でこれからも弾きそう、ベートーヴェンのソナタも2年間はまった時期がありますが、ときどき戻ってきそうです。去年テンペストを他で弾いたりしたのと、まだまだ弾きたいととっておきたい作品もあります。ブラームスはop.118以外にもop.117とop.119は取り上げてみたいです。そういう年にもなったのかもしれません。発表会の近くになると、この先どうしようかと考えたりすることもあるのですが、今年はモーツァルトとシューマンの年でもあるので、自分が納得するまで弾いてみるのもいいかもと思っております。他の方がよく弾く作曲家も、ほとんど手をつけたことがないというのもずいぶんありますが、マイペースで細々とでもつづけていきたいですね。今日は1時間ほどピアノが弾けました。暗譜するのをやめ、細かく譜を読み直すことに今週は専念します。いろいろ助言してくださってありがとうございます。BGM:モーツァルト 2台のためのピアノソナタ K.448 ピアノ:アリシア・デ・ラローチャ アンドレ・プレヴィン 弾く相手が見つかれば弾きたいとおもい、 楽譜が数年そのままになっている曲、 ずっと前ですが、頭がよくなる曲と紹介されたのがこの曲です。 頭がよくなりたいです。
March 15, 2006
コメント(8)
-
ホワイト
ピアノの発表会まであと10日と14時間くらい。風邪を弾かないように、包丁を持つときは気をつけるように、なるべく早寝早起きするように、深酒はしないように・・・心配性で小心者なのでいろいろ書き出すときりがありません。頭の中が真っ白にならないような精神力もつけたいです。3月20日の週は打上げやら送別会のオンパレード、ビール1杯以外はお茶に切り替えることができるかどうか、というよりも、21日に祝日以外はほとんどピアノが弾けないかもしれないと、カレンダーを見ながら不安なことも考えてしまいました。二日酔いの翌日、真っ白にならずに弾けるか暗譜で弾くことにします。無理をしてでもどこかでスタジオを借りるとか、午前中会社を休んで練習するとか、強引なことも考えてみることになるかもしれません。白い鍵盤をイメージしつづけることにします。昨日は土日の疲れからか熱っぽくなってしまって、会社から帰ると寝込んでしまいましたが、ようやく収まってきたので、pppでさっきまでピアノを弾いていました。先週末、暗譜で人前で4回弾いたので、あやふやなところはさすがにはっきりしきました。いい加減学習能力がないといけないとおもい、本をみて、ゆっくり弾いていました。体力がないので、通して弾くのは、2-3日に1回だけで、細かく見ることにするとおもいます。BGM:シューマン ウィーンの謝肉祭の道化 op.26 ピアノ:アリシア・デ・ラローチャ 謝肉祭op.9とアレグロop.8とセットで入っているCDは、 特に最近のお気に入りです。 op.26-4の間奏曲は、いつか弾けるようになりたいです。 こういうピアノの小品には憧れます。ホワイトデーなので、お礼のメールを打たなければ・・・・
March 14, 2006
コメント(6)
-
オーケストラ・ニッポニカ
オーケストラ・ニッポニカは、作曲家芥川也寸志(1925-1989)が提唱していた「日本人の作曲していた交響作品を蘇させる」ことを活動のひとつとしているそうです。そんなコンサートへ行ってきました。(3/12:紀尾井ホール)オーケストラニッポニカ第9回演奏会昭和9年の交響曲シリーズ(第2回)大澤寿人作曲(1907-1953) 交響曲2番(1934)***「さくらの声」ソプラノとオーケストラのための(1935)ピアノ協奏曲第2番(1935)管弦楽:オーケストラ・ニッポニカ 指揮:本名徹次ソプラノ:腰越満美 ピアノ:三輪郁****ラヴェルとガーシュインがまざったような曲と、どこかにも紹介されていましたが、その当時の日本人が作曲したとは思えないような、洗練された音楽でありました。当時日本公演をおこなっても、たぶんお客がこの曲についていけなかったのかもしれません。昭和10年代のことです。その後戦時中になり、だんだん忘れられていく・・・と時代の波に消されていったようでもありました。楽譜が数年前に見つかったこともあり、最近復活演奏が何度かされたそうです。プログラムのなかでは、実際に演奏されたピアニスト野平一郎氏、迫昭嘉氏、指揮者の飯森泰次郎氏も絶賛しています。だれかがきっかけにして、再評価し、また演奏される機会があることはすごいことでもあります。***私が知っている限りでは、メンデルスゾーンが、バッハを評価して、広めようとしなければ、完全に忘れられた作曲家になっていましたし、ヴィヴァルディの「四季」という曲もレコードが普及しだしたころ、表・裏にちょうど入る曲をさがしていたころ発掘されて、今ではだれでも知っている曲になったそうですし、ほとんど演奏される機会がなかったハイドンやシューベルトのソナタも、ブレンデルがとりあげたことで、相当メジャーなものに押し上げられたとか。何かそんなきっかけになればと感じました。最後に、芥川也寸志氏が述べられたことばがプログラムにあります。感銘を受けましたので紹介します。「感動と言うのは精神の風車を廻すことである。たとえば、私たち音楽を愛する者が田っ気の技術は拙くとも練習に練習を重ねて、僕等の拙い精神の風車を廻す練習をし、ある作品を舞台で演奏すると、その廻る風車の風は吹かれて客席のみなさんの精神の風車も徐々に廻り始める。さび付いた風車も、普段から手入れの行き届いた風車も勢い良く廻り始める。これが感動と言うものだと思う。だから自分の風車をまず廻そう・・・」
March 13, 2006
コメント(4)
-
八宝菜のような一日
ピアノの発表会2週間前金曜日から日曜日にかけて、自分でリハーサルとおもって人に聴いていただいたのが4回。ようやく週末を終えようとしていますが、はっきりいってふらふらです。これほど体力がいる曲を弾いているのだということを思い知らされました。それなりに集中力を持続させるにしても、集中させられる限界もあることもわかりました。土曜日は昼間に家で練習して、昼間は弾き会で弾いて、夜はレッスンで弾いて、23時を過ぎてもまだ練習していました。でもこれ以上やったところで・・・という感じになり引き上げました。 10分程度のシューマン謝肉祭の後半は、山あり谷ありですが、結構課題がはっきりと見えてきたのは収穫でした。いつ弾いてもいつもおかしいところと、よほど集中していないと弾けないところと、楽譜を見直して丁寧にもういちどさらったほうがいいところとという感じです。パンタロンとコロンビーヌは、弾く前に充分準備しないと、すべってしまいそうです。1日に数時間以上練習をずっと続けているピアニストの方がたがものすごく体力のある方に見えてしょうがありませんでした。土曜日も日曜日もスタインウェイのピアノにさわる機会をもち、幅のある音でおもいっきりピアノをならせる環境がいかにありがたいか、弾いていて気分よかったですし、感謝の気持ちでいっぱいです。***いろんな雰囲気の曲をまとめて弾く感じとなりましたが、そんなこともあって夕飯は八宝菜を食べたくがなりました。 白菜があればすぐできる広東風八宝菜 白菜1/4とタレつきのお惣菜・・・・ これくらいだったら自力でできそうです。
March 12, 2006
コメント(10)
-
ピクニック・コンサート
ベルリンフィルのピクニックコンサート、毎年のように、テレビでお目にかかっているかもしれません。今回は、フレンチコレクション2台ピアノでカティア&マリエルのラベック姉妹コンサートを聴いたのは10年以上前なので、演奏を聴くのもそれ以来なので、すごくうれしくなりました。衣装もかっこいいけど、ベルリンフィルとの競演は華があっていいです。プーランクの曲のあと、サンサーンスの「動物の謝肉祭」を聞いています。サイモン・ラトルの指揮でこんな感じで2台ピアノとアンサンブルで演奏されるのは、楽しそうで何よりでした。動物の謝肉祭の3曲目「らば」のところの2台ピアノはすごくかっこよかったです。観客から思わず拍手が出たのもなんだかわかるような気がします。ベルリンのピクニックコンサート、東京でもこんなのがあればいいなあといつもおもっています。敷居が高くなく、気軽に音楽を楽しんでいる風景がいつもたまりません。
March 11, 2006
コメント(4)
-
春雨はここちよく感じたい
三寒四温、雨降りも多い最近ですが、その後暖かい日があり、コートも脱ぎたくなる日もあるので、雨の日でも暗くならずにすんでいます。3月に入ってあまりピアノを触れていない状態ですが、週末は、土曜日も日曜日もスタインウェイのピアノにさわることができそうで、否が応でもモチベーションはあがりそうです。ピアノが鳴るホールだったり、和音が気分よかったりすると、自然と盛り上がったりするので、まずは楽しんで演奏することからだと思っています。今回はやってもやってもきりがないくらい問題となる箇所が浮上しますが、それだけの曲を弾こうとしているのだからという、ある種の割り切りも必要になってきそうです。BGM:シューマン 謝肉祭 op.9 シンフォニックエチュード op.13 クラウス・シルデ(pf) 仲道郁代さんの先生だったり、東京芸大の客員教授だったりで、 リサイタルも聴きに行ったことあります。 なんと気品の高い演奏かと、あらためて聴き入っています。 なにも走って急いで弾く必要がないのだと、 戒めるかのような演奏でもあり、今日聴いてよかったように感じます。
March 10, 2006
コメント(0)
-
TIME IS LIFE!!
今週の平均帰宅時間が23時台とあっては、もう笑うしかない状況です。pppでピアノを練習する気力を振り絞って30-40分、とりあえずピアノの前に座る、朝、寝起きのまま、頭がまわっていない最悪のコンディションで暗譜で弾いてみてどの程度ひどいものであるか悟る、せいぜい今週の平日は、こんなときかもしれません。3月は飲み会も多く、歓送迎会も多く、打上げも多く、おまけに新年度に向けての大幅な組織変更が充分予想もでき、時間とのたたかいのような仕事もあったりで、そういう日常がカーニバルだと思うようになれればいいと、変なところで開き直っています。BGM:リスト ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 クラウディオ・アバド指揮 ロンドン交響楽団 (この曲、気を使わなくていい感じで気に入ってしまいました。) *****<コンサートのご案内> オーケストラ ニッポニカ 3月12日(日)紀尾井ホール 14:30- 昭和9年の交響曲シリーズ 大澤壽人作曲 交響曲第2番 ピアノ協奏曲第2番(pf:三輪郁)ほか 本日(3/10)17時までに連絡(メール)くだされば チケットフィーは2Kになります・・・。 昭和初期の日本の作曲家に光をあてようという企画とのこと、 どんな曲なのか、まったく想像できませんが、三輪さんからは、 プロコフィエフに似ているといわれています。 私はとりあえず出かけてみる予定です。 そういえば、紀尾井ホールでオケの演奏はほとんど聴いたことありません。
March 9, 2006
コメント(0)
-
北ウイング
3月8日は自分自身で記念日扱いにしています。今から11年前、95年3月8日に海外赴任した日でありました。次の年の4月30日まで、外から日本を眺めていました。当時、1月には神戸の大震災、赴任直後の3月中旬サリン事件があり、日本の世の中は大荒れでした。北京の住居ではCNNネットワークや香港スカイテレビが入っていたのですが、焼け野原の神戸や地下鉄の大惨事の風景ばかり写されていました。1ドル80円という超円高で、北京の両替所のボードは桁あふれをおこし、両替レートがわからないくらい高騰しました。日本がこんな状況だったので、ポジティブで、個人の主張がはっきりしている中国人社員は新鮮でした。と同時にチームワークを大切にする日本も捨てたものではないと、そのときカルチャーのちがいやカルチャーを大切にしていなければと痛感しました。この年はやはり自分にとっては財産になっています。3月は寒暖の差が激しく、最高気温20度、最低気温0度くらいで、何を着ていけばいいのかさっぱりわかりませんでした。歓迎会が1週間くらいつづき、乾杯は「杯を乾す(ほす)」のが乾杯で、45度のお酒をあいてに夜は厳しい戦いがつづきました。45分くらいしか正気でいないことはたいていで、それでも誘われればお付き合いしました。駐在員仲間ができるのはいいことですが、どうしても日本人で固まってしまう傾向があり、なんとか脱却しようと試みました。いつまでたっても言葉を覚えられないというジレンマもあり、単独行動をして、カラオケの小姐(しゃおじぇ)ととにかく世間話をしたり、これは何、あれは何と、恥も何もあったものではなく、そんなことをしながら生活をしていました。「北ウイング」は、そのときによく歌っていました。それから松田聖子さんの歌が向こうの人は大好きなようで、教えて欲しいとせがまれては、メドレーでしょっちゅう歌うことになりました。(帰国後は「天使のウインク」以外は歌っていません。)クラシックのコンサートは、なかなかチャンスがなく、日本は本当に恵まれていると思いました。そうこう思っていて、英字のコンサート情報とかは、細かくチェックしていました。それでも、思いは通じるものかもしれず、北京音楽庁というところでアシュケナージ(ショパンのスケルツォ他)と人民大会堂でアルゲリッチ(リストのピアコン)を3000円くらいで聴くことができたのはラッキーでした。人民大会堂は広すぎて、席の区画に番地がふってあるくらいのところでした。ここはやっぱり共産党大会の場所なのかと思いました。帰国後、2年たって、北京を案内してほしいと友人から依頼があり、トゥーランドットのオペラを見るというツアーコンダクター兼旅行というおまけがつきました。このときは北京飯店に宿を取り、その気になれば歩いてでも紫禁城(野外オペラ会場)へいけることにしたり、自分なりに考えました。 ***相当時間がたってしまって語学力はまったくといってありません。おととい、中華料理屋さんで中国人に「ヘンハオチー(おいしい)」ととっさにいって、喜んでいただいたり、となりの人を驚かせたりしましたが、せいぜい片言くらいしかいえないのがちょっと哀しいです。BGM:リストのピアノ協奏曲が聴きたくなりました。 アルゲリッチ(pf)アバド指揮のCD、 どういうわけか、 このCDは、シンガボールのオーチャードロードで買ったもので、 まだシンガポールドルの値札がついています。
March 8, 2006
コメント(11)
-
バラバラ
家にあるCDで、とりわけショパンのCDでいちばんよく聴いたものを今日は聴いています。BGM:ショパン バラード2番 ピアノ:クリスチャン・ツィメルマンこのCDにはバラード4曲と舟歌・幻想曲が入っています。聴きすぎたせいか、他のCDを聴いても戻ってきてしまうようで、自分自身基準になっているようです。バラ2は、7年前、今通っているピアノの発表会にはじめて出たときの曲であります。ちょうどこの頃、コンサートでクライスレリアーナのあとにバラード2番を弾くピアニストがいて、それも偶然2人つづいたのでした。ショパンとシューマンが曲の献呈しあっていたこととかで、ますます興味をもち、はまってしまったのでありました。発表会には当時8ヶ月準備期間をかけて弾きました。習いたてのころだったので、選曲をして曲が通して弾けるようになるまでどれだけかかるのかも、まったく想像できず、プレスト・コンフーコの途中から速くなるところは、たった2段の楽譜で音がそろうようになるまで3ヶ月、たぶん今だったらそんなことをしないとおもいますが、結局はいろんなことがわかってよかったのでしょう。仕事をしながらピアノを弾いていて、どの程度練習すれば本番はどの程度のものになるのか、思い知らされたこともありましたが、今では無駄になっていないと納得しています。ショパンは好きな作曲家できらいというわけでもないのですが、それ以来、一度もショパンのピアノのレッスンというのを受けていません。今年もモーツァルトとかシューマンに順番がまわってきているので、またそれ以降になりそうです。弾いても弾いても音がそろわず、バラード2番=バラ2=バラバラとkyon2(きょんきょん)のようにこの曲のことを自分で言ってました。***今も弾いても弾いても、なかなか和音がそろわず、たいへんなのですが、時間がまだあるので、もう少し何とかしたいと思っています。
March 7, 2006
コメント(4)
-
GWは音楽三昧
熱狂の日2006でGWはモーツァルトのコンサートがたくさんありますが、eplusで申し込んでいたチケットたちがようやく自宅に届きました。あんまり来なかったので、検索画面をみたりして少し心配していたのですが、ほっとしました。5月3日・4日・6日は、有楽町の東京国際フォーラムへふらっと出かけて、気軽にモーツァルトを楽しみたいです。いろいろプログラムはありますが、小菅優さんのモーツァルト初期ソナタ、児玉桃さん姉妹の2台ピアノのソナタ、小山実雅恵さんのp協27番は、時間帯も記憶しており、そのなかの朝10時からのコンサートもがんばって早起きしようと楽しみにしています。前後の日曜日と間の祝日は、いろいろお誘いもあり、自分がどこかしらでピアノを弾いている感じで、何年かぶりに東京から遠出せずという風になりそうです。桜のことや先のことばかり書いていますが、それだけ春が来るのが待ち遠しいのが自分自身の心境なんでしょう。BGM:ベートーヴェン ピアノソナタ第32番 第1楽章 ピアノ:マウリツィオ・ポリーニ アート・オブ・ポリーニという、バラバラの選曲でも結構聴きごたえのあるものを聴いています。 この2曲先のシューマン・アラベスクが急に聴きたくなったのですが、ボタンを押しまちがえて、ここちよいのでそうしています。
March 6, 2006
コメント(4)
-
水の精で桜吹雪を連想しました。
ピエール・ロラン・エマールさんのピアノの演奏を聴いています。テレビでいまやっているもの。ラヴェルの水の精を聴いていて心があらわれました。こんな音楽をBGMに4月にお花見行きたいとふと思いました。ここ最近、さくらSPOTの記事が目に付いたので紹介します。日経新聞3月4日 NIKKEIプラス1桜が似合うおすすめの城 1位 弘前城 2位 姫路城 3位 高遠城(長野県)4位 会津若松城 5位 彦根城 6位 津山城(岡山県) 7位 岡城(大分県) 8位 五稜郭 9位 大阪城 10位 高田城(新潟県)東京メトロガイド 4月 1位 千鳥が淵 2位 上野恩賜公園 3位 飛鳥山公演(王子) 4位 新宿御苑 5位 石神井川沿い 6位 外堀公園 7位 井の頭公園 8位 隅田公園 9位 六義園 10位 目黒川沿い日本にもまだ知らないところがたくさんあります。お城めぐりは、大阪城と姫路城くらいで、まだまだ修行がたりません。去年の千鳥が淵はお見事でした。六義園も初夏のころ散策しました。東京も捨てたものではありません。頭が休息日でなにも思いつかないので、きょうは静かにしています。BGM ラヴェル 夜のガスパール ピアノ:ピエール・ロラン・エマール 最近フランスものから遠ざかっていたので新鮮です。 こんど来日されることがあったら是非聴きに行きたいです。追:曲がシューマンのシンフォニックエチュードにかわりました。 これはとても楽しみです。
March 5, 2006
コメント(8)
-
150%備えるとは・・・
ピアノの発表会3週間前。昼はピアノの調律、気分よくピアノの練習ができるようにと、自分なりに工夫しています。いつも調律風景をぼおっと見ているのですが、音がだんだんクリアになっていく過程がわかったりして、うれしくなったりします。昨日見たテレビでアルゲリッチが語っていたことば。「150%を備えないと60%を得ることができない」私にはたいへん響きました。暗譜でレッスンで弾いてみても、150%どころか、70%もとても備えていないと反省、あぶなっかしいところだらけでした。3月の土日は、ピアノのレッスンやリハーサル以外は、あまり人に会わない、出歩かない・・・、春篭りをしようと決めています。これは去年もその前の年も同じだったかもしれません。あしたは素敵な1日になりますように。BGM:シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 ピアノ:マルタ:アルゲリッチ ワルシャワ国立管弦楽団 アルゲリッチのライブを初めて聴いたのはこの曲でした。 大阪フェスティバルホール、ドイツのバンベルグ交響楽団、 チケットを会社を抜け出して電話したり、そんなパワーもありました。 たたみかけるような第1楽章のカデンツァ部分大好きです。
March 4, 2006
コメント(8)
-
ザルツブルクゾリステン
ザルツブルクゾリステンモーツァルト生誕250年特別演奏会協奏曲の夕べ~弦楽五重奏版による~というものに行ってきました。場所:国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟大ホールディヴェルティメント ニ長調 K.136ピアノ協奏曲第13番 ハ長調 K.415ヴァイオリン協奏曲第2番 ニ長調 K.211ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K.414****勤務先のとなりの部長のお嬢さんが、ザルツブルクのモーツァルテウムに留学されていて、今回の演奏会に出られることになったとか。ピアノをやっていることをどこかで聴かれて、是非・・・ということで招待していただきました。クラシックとは無縁の同じ部署の社員と大勢でツアーを組んですてきな音楽を堪能しました。年度末のともすれば殺伐とする時期に、清涼剤となり、一緒に楽しめたことはなによりでした。となりの部長さんはたいへんお喜びでした。いろいろ準備されたり、お嬢さんが留学されたりで、いろんな面でたいへんだろうなあと、思ったりもしました。****弦楽五重奏のピアノ協奏曲。(ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ、コントラバス 各1)ピアノ協奏曲もこじんまりとしたアンサンブルになった感もありますが、それぞれの音がはっきり聴こえてきて何よりでした。チェロ・コントラバスのベースの楽器がしっかり音楽を支えているのがよくわかりました。楽器と人員の構成上、本来のピアノ協奏曲ではオケの前にピアノがあるのですが、弦楽器のアンサンブルのメンバーが前、ピアノが後ろということになり、ピアノは音を大きめに出さないと、アンサンブルに負けてしまうのかなあと、ちょっと思ったりもしました。**今年はモーツァルト生誕250年だけのことはあって、時折楽しい企画に誘っていただいたり楽しめるのはありがたいです。
March 3, 2006
コメント(2)
-
ほろ酔いで摩天楼のBGM
今週は宴会WEEKになってしまっています。月曜・火曜・木曜・金曜(予定)まったくちがうカテゴリーの人と飲み会、それも比較的継続している人とのなかで、深刻な内容のものは何もなく、結構楽しい1週間になりそうです。すこしずつ理想のコミュニティの世界が見えてきたかもしれません。飽きっぽい性格なのですが、ピアノも大人になって8年目にはいり、コンサートに通いだして20年目にはいり、やっぱり好きなことはつづいているように思えます。ビールと焼酎のお湯割りをたくさん飲んでしまったので、今日もピアノの練習はできず、というか、たぶんやっても意味がない日かもしれません。土曜日はピアノの調律をするので、そのときに固めて練習をしようと自分に言い聞かせています。リハーサルで弾くイメージをはやくつくっていきたいです。それから修正修正で積上げていきたいです。ピアノの発表会では、ちょっと緊張するだけで、自分がイメージしているとおりの演奏がなんとかできるようしたいです。でも、そのためには、舞い上がることのないように弾きこまなければ。3月・4月・5月・・・と、発表会に加えていろいろな人に誘われたりで、人前でピアノを何回か弾かせていただけるのはうれしいことです。ちょっとずつモチベーションがあがってきたのは自分にとってはいい傾向、トンネルの先の明かりが見えてきたのかもしれません。BGM:ガーシュイン ピアノ協奏曲 へ調 カティア&マリエル・ラベック(2台ピアノ) きのうのつづきです。 1980年の録音です。 今週はこういうのりのいい音楽を聴きたい気分です。 自分がCDショップの陳列を担当されたら、 クラシックのコーナーにもジャズのコーナーにも、 アメリカンのコーナーにも、置いてあげたいです。
March 2, 2006
コメント(2)
-
ラプソディ・イン・ブルー
雨降りの一日でしたが、夕方6時ごろ、会社の社員食堂の窓から見える夕暮れ時のブルーは、ちょっと幻想的でした。ぼんやりとしばらく眺めていました。わざわざ、ガラス越しに見とれている人もいたくらいです。だんだん日が長くなってきて、ちょっと喜んでいますが、晴れた日の夕焼けとはちがって、またこんな日もいいですね。最近夜に聴く音楽は、イージーな選択になることも多いのですが、シンプルイズベストということばも好きなので、それでもいいかと。BGM ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー カティア&マリエル・ラベック ラベック姉妹のコンサートは2度ばかり行きましたが、 2台ピアノというジャンルがこれほど楽しいものかと、 すっかり堪能してしまったことあります。 ラプソディ・イン・ブルーは、いつもアンコールで盛り上がりました。 モーツァルトのK488の2台ピアノのソナタ、 ラヴェルのボレロ・・・そのときのことは10年以上たっても はっきり覚えています。
March 1, 2006
コメント(6)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-
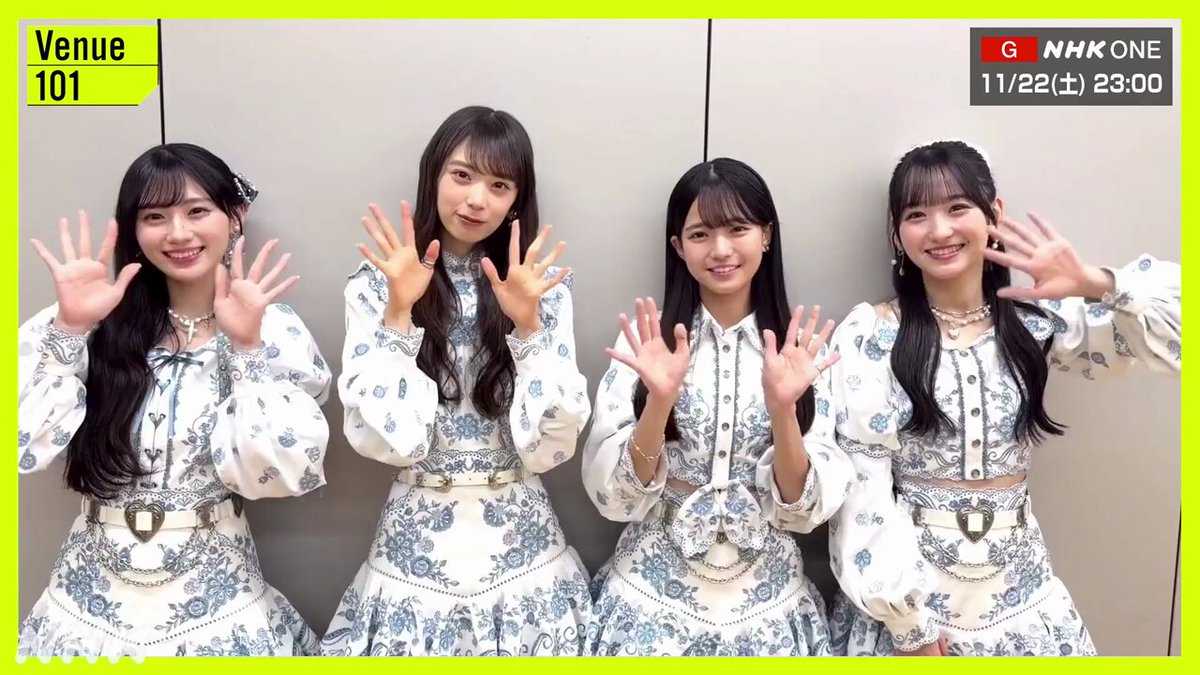
- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪本日『Venue 101』に出演…
- (2025-11-22 13:40:45)
-
-
-
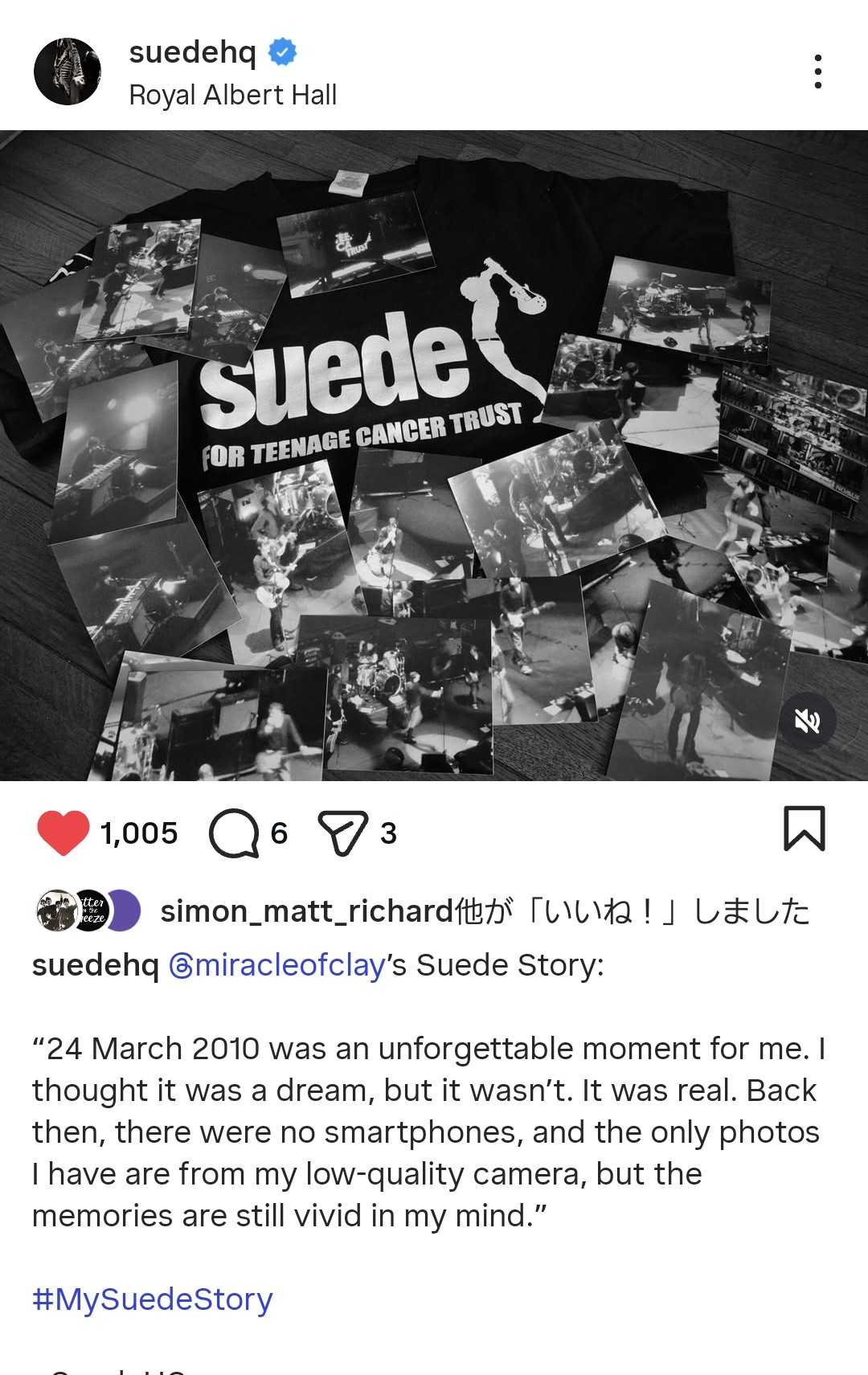
- 洋楽
- My Suede Story
- (2025-11-22 20:12:16)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-







