2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年06月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
文化の創造者
文芸春秋8月臨時増刊号より。<代表的日本人100人を選ぶ>という特集。いろんなカテゴリーで歴史上の人物が並べられています。内村鑑三が「代表的日本人」という書物を1908年に出され、それから100年たったということでのこの企画。生き方に影響を与えた人、英雄、宗教者、改革者、経済人・・・などいろいろな名前があがっています。ここでは、興味のあった文化の創造者のカテゴリー興味深い人選された名前を書きます。柿本人麻呂、聖武天皇、菅原道真、紀貫之、清少納言、紫式部、後白河方法、藤原定家、運慶、吉田兼好、世阿弥、井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉、与謝蕪村、本居宣長、葛飾北斎、森鴎外、夏目漱石、正岡子規、西田幾太郎、斉藤茂吉、折口信夫、谷崎純一郎、小津安二郎、黒澤明、三島由紀夫、手塚治虫、武満徹文化人の対談から出てきたもののようですが、ゆっくりその過程は後日として。。。結構興味深いものを感じました。作曲家がだれもいないとおもっていたら、最後に名前があがっていてほっとしました。外国では、ドイツマルクがあったころ、クララシューマンは100マルクだったし、フランスフランがあったころ、ドビュッシーは20フランだったので、きっとたくさん名前があがるのでしょうね。BGM:スカルラッティ ソナタL352、L413、L483、L449 ベートーヴェン ピアノソナタ3番 op.2-3 シューマン ウィーンの謝肉祭の道化 op.26 ピアノ:ミケランジェリ 1955年ワルシャワ・リサイタル 昨日見つけた掘り出し物CD、べー3番、かろやかで楽しく聴けました。 ミケランジェリ、リヒテルとかは見たことないCDを見ると、 ついつい聴いてみたくなります。ライブ録音でコンサート形式名物多く、 ときどき変わった選曲にうならされます。
June 30, 2006
コメント(2)
-
CDの交換/ブラームスp協2番
昨日の夕方、偶然会社で近くに帰っている先輩(たぶん7-8年年上)と、会社を出る時間が一緒になったので、たまにはどうですか・・・ということで、下町の中華料理屋さんで、老酒と餃子・シュウマイといった話で最初はサッカーW杯のよくあるお話をしていました。ひょんなことから、サッカーから歴史の話になり、歴史の話から学生時代の話になり、そこで、よくそのとき聴いたレコードやCDの話になりました。世代が微妙にずれていると、やはりおもしろいもので、たいして知らないとその方はいいながら、好きでよく聴いていらっしゃたりします。「ブラームスは交響曲も4曲、ピアノ協奏曲も2曲、少ないけど、みんなよく聴きました・・・」ということで、思わぬところから盛り上がりました。ピアノ協奏曲は2つとも、好きなフレーズを私もほろよい気分で、口づさんだりすると、そうそう、それそれ・・・という感じで、同じ部署の人とそこまでの話をほとんどしたことがなかったので、なんだかうれしくなりました。1番の協奏曲の3楽章は、朝気合を入れるときによく聴いたりするとか、2番の協奏曲は、1991年ザルツブルグ音楽祭でベルリンフィルのアバド/ブレンデルのコンサートはいまだに忘れられず、その後出たCDもすぐ買って、年末にレコード芸術の読者アンケートのようなものに正直に書いたら、名前まで載ってしまいました・・・とか、あまり会社の人に言ったことがなかったおはなしをしてしまいました。ブレンデルのCDもよく聴くのですが、最近ブッフビンダーという人の1番/2番のCDがかっこよくていいですよ。ということでブラームスピアノ協奏曲1番・2番 ブッフビンダー(ピアノ)アーノンクール指揮のCDを翌朝もって行きました。ホロビッツの歯切れのいいピアノ協奏曲がお好きなようで、私はモーツァルトのものしか知らないからということで、チャイコフスキーピアノ協奏曲1番/ブラームスピアノ協奏曲2番ホロビッツ(ピアノ)、トスカニーニ指揮 1940年カーネギーホール録音というCDを翌朝持ってきてくださいました。いろいろありましたが、ちょっとうれしい一日になりました。BGM:ブラームス ピアノ協奏曲第2番 ウラーディミル・ホロヴィッツ(ピアノ) アルトゥーロ・トスカニーニ(指揮)NBC交響楽団 無骨で時代を感じる演奏ですが、昨日のような会話がなければ、聴くことがなかった演奏、 ここまで若いときのホロヴィッツの演奏、初めて聴くかもしれません。 週末に何度も聴きなおしそうな予感がします。****p.s.1ブッフビンダー氏は7月28日ザルツブルグ祝祭大劇場(ザルツブルグ音楽祭)で出演、今年は、ポリーニ、ブレンデル、シフ、ブッフビンダーがモーツァルトイヤーのこの音楽祭でそれぞれのモーツァルトプログラムを演奏する模様です。p.s.2昨日のブログの追記、ベートーヴェンソナタの買い足しの件、結局、野平一郎さんの4番・8番ソナタ、 ブッフビンダーさんの1番・8番・10番・11番ソナタを追加することにしました。
June 29, 2006
コメント(2)
-
CDプレゼントの巻き(2006年夏編)
従姉のお嬢さんが中学生になったばかりなのですが、ピアノが好きなことから、ときどき「今どんな曲をやっているのか」とか、20年以上は軽く離れているのに共通のテーマがあるので、ときどきメールをしたりしています。私自身、小学生のときまでしか習っていなかったので、とにかく好きなものであればつづけてほしいと、言い続けてきまして、せっかくの機会なのでということで、夏と冬にCDをプレゼントすることにしています。記憶力がわるく、過去のブログで何を送ったか、さっきまで探し回っていました。2005年12月は、ブログに明細があり、2005年6月は、その頃行ったコンサートのピアニストを中心に渡したはずということを思い出しました。2005年夏は、モーツァルトのK331の1楽章を弾いていて、2005年冬は、ドビュッシーのアラベスクを弾いているという情報をもとに適当に見繕ったのを思い出しました。<2005夏CDプレゼント>ベートーヴェン ソナタ16・17「テンペスト」・18 (pf:仲道郁代)モーツァルト ソナタK.331ほか(pf:内田光子)ショパン プレリュード (pf:小菅優)ブラームス 間奏曲117-119(pf:グリモー)シューベルト 即興曲集 (pf:ブレンデル)<2005冬CDプレゼント>ショパン ワルツ集 (pf:ルービンシュタイン)シューマン 子どもの情景、謝肉祭、パピヨン、アラベスク (pf:アシュケナージ)バッハ インベンションとシンフォニア (pf:ピーターゼルキン)モーツァルト 100曲モーツァルト 10枚組ドビュッシー 子どもの領分・ベルガマスク組曲・2つのアラベスク・喜びの島・レントより遅く (pf:児玉桃)<番外編>2006 5月「熱狂の日2006のおみやげ」 「勉強がはかどるモーツァルト」1年前のブログを読んでいると、小菅さんとグリモーのコンサートでサインをもらったと大騒ぎをしている自分がいました。それとテンペストを譜読みはじめたことで、そういう選び方をしていたのだと納得しました。半年前は、モーツァルトイヤーに向けてと、シューマンの謝肉祭がはいっていて将来シューマンのレッスンになったときに選曲されそうな曲(パピヨン、アラベスク、子どもの情景)がはいっているCDをあえて選んだり、ドビュッシーで気に入っているCDを加えたり、かなりひねっている感じもしました。現在、べートーヴェンの8番ソナタ「悲愴」の3楽章を弾いているらしいです。(たぶん毎日ピアノの練習しているので、私よりは弾けるのでしょう・・・)そこで、8番のソナタが入っているCDで、いろんな組み合わせで、遊んでみることにしました。-アシュケナージの2枚組で 14「月光」・26「告別」・17「テンペスト」・ 8「悲愴」・23「熱情」・15「田園」・21「ワルトシュタイン」と題名のあるものばかり、(これははっきりいっておいしい)-ブレンデルのCDで、 8・9・10・11番この2つは、このあいだ話題にしたWポイントのお店で買い揃えました。もうひとひねりするため、あと2-3日考えようと思っています。明日お店へいって足そうとおもっているのは、-野平一郎さんの4・8番・・・自分も聴いてみたくなりました。いろいろ考えていて楽しくなってきました。
June 28, 2006
コメント(6)
-
メッツァ・ヴォーチェ
CDの解説書を忘れた頃に読み返すことがときどきあります。新聞紙を整理するときに、はっとする文面を見つけたりするのですが、何年もまったく見過ごしていたものに、耳の痛いお話もあったせいか、何度か読み直してしまいました。通訳の仕事を長くしている人が、CDの解説をしているのもめずらしいものでもありますが、日本人発言者の話のメリハリのなさ、発音の悪さに悩んだことがあるそうです。最後にどんなに内容がよくても、プレゼンテーションが悪ければ、聞き手を飽きさせてしまうのは当然で、欧米の人のように、子供のころからディペートの訓練をしていると声のトーンもちがうのだそうです。岡本和子さんという方の文章を引用します。「まず、冒頭、凛とした声で「序奏」に入り、その後展開していく内容の「さわり」をちらつかせて、相手の興味を引く。声はあくまでメッツァ・ヴォーチェ(柔らげた声で)テンポはアダージョ・マ・ノン・トロッポ(緩やかに、だが緩やかすぎずに)、続く展開部では、声のトーンをやや上げて、重要な言葉にはアクセントをつけて、多少テンポを落とし、「どうでもいい言葉」には目いっぱい装飾音をつける。小刻みにテンポを変えて、変拍子を駆使するのもいい。そして最後は、徐々にクレシェンドをかけて一気にフィナーレへと持っていく。」「スピーチの上手な人は、音楽的センスがあるのだ。歯切れが良く、効いていて非常に気持ちがいいし、内容がいい加減でも何とかさまになる、極端な話だが、内容が聞き取れなくても、スピーチは「音」だけで観衆を魅了することができるのだ。」 「重要な音はアクセントをつけて、多少テンポを落として弾いたほうがいい」と 何人もの人から言われたこともありますし、 楽器を弾いて音を伝えるのであっても、 言葉を発して物事を人に伝えるのであっても、 本質的なところは同じということなのでしょう。プレゼンテーションはあいかわらず苦手ですが、メッツァ・ヴォーチェ、日本語でいえば「柔らげた声」でお話することは、とりあえずできるので、そこから先は今後の課題にしようと思いました。シューマンやブラームスの曲を聴いて、静かな曲であっても、途中の展開部でたたみかけるように思いを伝えるようなところは大変好きでして、そんな伝え方が音でも言葉でも伝えられるようになりたいものです。BGM:オーストリアのキャロル 「静かに、静かに」 Musica Sacra(ムジカ・サクラ)
June 27, 2006
コメント(4)
-
一心値万宝
心には力ありてゆえに一途なれば想い必ずや通ずと。その不思議山の如しとも海の如しとも専ら心づくし・・・・赤坂の和菓子屋さんの進物のなかに書いてありました。実直な方がきっとおつくりになっているのだなあと、頂いて感じました。おかきも、英語表記はライスクラッカーになるのか・・・と、包み紙の和英両方の包み紙を見て感じました。少しゆとりを感じる1週間にしたくなりました。***テレビのスポーツ番組を見ていると日本チームの反省会ばかり。そんななかで、テレビ東京が呼んだフィリップ・トルシエ氏、少ししか見ていませんが、通訳を交えたコメント面白かったです。プロ野球の結果のあいだも、席でじっとしていて、ほほえましいものがありました。「ドイツが優勝候補で、ドイツのように目立たない選手が多いなか、パスをつなげてチームプレイで勝ち上がっていくところを見習えば日本チームはもっと強くなる」とか。外国人特有の前向きなご意見はなかなかよかったです。BGM ハイドン 弦楽四重奏曲第77番「皇帝」第2楽章 アルバン・ベルグ弦楽四重奏団 ハイドンが神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世に捧げた歌曲 「神よ、皇帝フランツを守り給え」、 現在はドイツ国家として知られるメロディ、 弦楽四重奏のさまざまな変奏曲形式になっていて、 静かに耳をかたむけようとおもっています。
June 26, 2006
コメント(4)
-
女神<ミューズ>との出逢い/小菅優ピアノ・リサイタル
田園都市線青葉台駅前にフィリアホールというこじんまりとしたホールがあります。このホールの恒例となっている<<女神との出逢い>>というシリーズは、今日で154回目だそうです。小菅優さんのリサイタルに出かけました。先月「熱狂の日」というイベントがあったとき、5月6日朝10時という早い時間にモーツァルトのソナタ3つを聴いたばかりなのですがまったく違うプログラムで、プログラムの妙のようなものも感じ、モーツァルトのコンサートの直後気がつけば申し込んでいたものでした。2ヶ月つづいて同じピアニストのリサイタルに行くことは、そんなにありません。<小菅優ピアノ・リサイタル>モーツァルト 幻想曲 ニ短調 K.397ベートーヴェン 幻想曲 op.77バッハ=ブゾーニ シャコンヌ***武満徹 雨の樹 素描シューマン ダーヴィッド同盟舞曲集(第1部) 第1曲 元気よく 「F・E」 第2曲 心から 「E」 第3曲 ユーモアをもって 「F」 第4曲 辛抱しきれず 「F」 第5曲 単純に 「E」 第6曲 きわめて速く 「F」 第7曲 速くなく 「E」 第8曲 生き生きと「F」 第9曲 元気よく (第2部) 第10曲 バラード風に、きわめて速く 「F」 第11曲 単純に 「E」 第12曲 ユーモアをもって 「F」 第13曲 荒々しく、そしてほがらかに「F・E」 第14曲 優しく歌いながら 「E」 第15曲 生き生きと 「F・E」 第16曲 快いユーモアをもって 第17曲 遠くからのように 「F・E(第16曲に引続き) 第18曲 速くなく***(アンコール)ラフマニノフ 幻想的小品モーツァルト ピアノソナタ第10番 K.330 第2楽章モーツァルト ピアノソナタ第11番 K.331 第3楽章「トルコ行進曲」幻想曲というものを今年は課題とされているらしく、そこから選曲をしたこと、そこからひとひねりし、シューマンはop.6を選んだようでした。op.9謝肉祭、op.16クライスレリアーナに比べて演奏される機会が極端に少なく、私自身はじめてリサイタルで聴くものでもありました。シューマンのプログラムには、曲のうしろにE・Fと表記がありました。シューマンが自分のパーソナリティを2つに分け、曲ごとにイニシャルでサインしているそうです。フロレスタン(F)は、自発的でワイルド、活発で行動的。オイセビウス(E)は、内面的でおとなしい、物静かで瞑想的。この曲は、はっきりとしていて、小菅さん自身も狂ったところ、心の底から吹き出るような美しいところ、皮肉なところ、シューマンの多色な面を表現したいとプログラムの案内に書かれていました。どの曲にいたっても、fの音の激しさと情熱的な表現をされますが、その分、オイセビウスのイメージの曲、「こころから」「単純に」などの曲のように、やわらかく、なにかに包まれるような暖かい音がものすごく映えてきます。極端に意識的に弾いた感じもありますが、アンコールも含めて、めりはりの効いた演奏にはうならされてしまいました。***9歳からドイツへ渡り、現在はザルツブルグ在住。2006年モーツァルトイヤーのザルツブルグ音楽祭では今年デビュー、魔笛の小屋のあるモーツァルテウムのホールでどんな演奏になるのか、また楽しみです。BGM:モーツァルト ピアノ協奏曲第21番 ピアノ:小菅優 ローレンス・フォスター指揮 北ドイツ放送交響楽団 さっき第1楽章のカデンツァを聴いて、いつも聴くものとちがっていたので、 ちょっとわくわくしてしまいました。
June 25, 2006
コメント(0)
-
ワールド・サッカー・クラシックス
ブラジル戦は1-4で、後半はほとんどパスも通らないような試合でしたが、単なるAマッチや親善試合でなく、ワールドカップでブラジルと試合をしてみてわかったことも多かったようにも思います。この先決して無駄にならないようにも感じます。日本チームの皆様お疲れ様でした。前半のおわりの方に期待できる時間が少しあっただけでも、早起きした甲斐ありました。夕方は、しばらく行っていなかったHMV池袋店へ行きました。日本チームとイギリスチームのあった日の翌日(たぶん現地時間でカウントしています)はWポイントデーになるとのこと。せっかくなので恩恵を被ろうと散策していました。この時期だからというCDも見つけました。ワールド・サッカー・クラシックス(3月にやっていた野球のタイトルをもじっている感じ)アイーダの凱旋行進曲、威風堂々、「ナブッコ」より、「行け、わが思いよ、黄金の翼に乗って」など、日本、イングランド、イタリアなど、サポーターがスタジアムで歌う曲の原曲を集めたもの。3大テノールがかつてワールドカップの前に歌ったものとかもの(1990イタリア大会)も含まれます。「誰も寝てはならぬ」←(これは荒川静香さんで有名にもなりましたが・・・。ぴんぽんぱんという3人の中国人も登場するトゥーランドットより)知っている曲ばかりかといえば、そうでもないのでありがたいです。BGM:ヘンデル 「戴冠式アンセム」より、「司祭サドク」 ガーディナー指揮 モンテヴェルディ管弦楽団&合唱団http://www.wmg.jp/classic/
June 24, 2006
コメント(4)
-
ドルトムント
エッセン・ドルトムント=ルール工業地帯とか、中学校のときの地理のノートには書いていたでしょう。石炭工業がさかんだったドルトムントは、今では半導体の街、そしてワールドカップの開催都市。日本xブラジルは、前半をおわって1-1。1-0と書きたかったところですが、ロスタイムにブラジルのヘディングシュートが決まり1-1、なんとかがんばってほしいとおもっています。***昨日はちょっと早い目にというか自然に睡魔がおそい、目覚まし時計もなしに、目覚めたのが午前4時。確かに学生時代は馬術部で朝の練習だったため、朝4:40に起きる生活が3年半つづきましたが、今は年に1回あるかどうかのこと。子どもの頃、ミュンヘンオリンピックのバレーボールの決勝戦、男子も女子も当時は強く、両親が早朝からテレビをつけてみていました。女子バレーボールはソ連にフルセットで11-15で負けて銀メダル、男子バレーボールは東ドイツに第4セットで勝負を決め金メダル、私は小学生でしたが、はっきり覚えています。やっぱりそういう血をわたしもひいているのでしょうか。**2点差以上ということばを、この1週間何度も聴きました。FW2人はいい動きをしていると思います。このまま後半も応援します。2度寝をすると、起きれないときが多いのですが、その後会社へ行きます。
June 22, 2006
コメント(2)
-
派手な響きと軟弱な甘ったるさは・・・
きのうは手が痛くなったときのことを思い出しました。そうそう、この本(楽譜)をよく見ていたときのことだと、2me BALLAD a Robert SCHUMANN Op.38 1838という表題を、手にとって眺めています。シューマンとありますが、献呈した相手がシューマンでショパンの曲であります。コルトー版の楽譜には解説がぎっしり、速いパッセージも分解して部分練習の方法まで書かれていて、準備練習として2-3行書かれているものをよくやっていましたが、当時はハードルも高すぎて、腕がいたくなってしまいました。いまだったらどうなのでしょうか。「ショパンは非常に派手な響きを軟弱な甘ったるさと同じように嫌った。」という解説は、私のこころに大変響くものでした。今は日本語でたくさん、この楽譜は出回っていますが、たった20年前になると、フランス語でしか書かれたものしかなかったらしく、辞書を引きながら・・・という苦労話を何人かの人からうかがったことあります。***ショパンはこの曲でさんざんこりまして、その後、6年と少したちますが、遊びで「雨だれ」や「太田胃酸??」のプレリュードを弾く程度、レッスンには1曲も持っていかず、いまだに封印中。ただ昨年秋のショパンコンクールの1次予選でブレハッチが弾いた曲でぐらっときてしまったのも事実。これがきっかけになるのかもしれません。BGM サン・サーンス ピアノ協奏曲第4番 ハ長調 Op.44 ピアノ:アルフレッド・コルトー 指揮:シャルル・ミュンシュ 1935年の録音
June 21, 2006
コメント(7)
-
腱鞘炎を防ぐ予防法
「ケータイ族に広がる腱鞘炎」という日経夕刊6/20の記事より、親指が痛くなるという症状のことから、いろいろ書かれていました。<腱鞘炎の主な症状> 指の付け根が痛くなる 手や指がだるくなる 指の動きが鈍くなる 手が腫れてくる 指を曲げ伸ばしするとカクカク動く<腱鞘炎を防ぐ主な予防法> 指を長時間使った後は10分間休ませる。 指を曲げ伸ばししてストレッチする 炎症などがある場合は氷で冷やす 指を酷使しないピアノの再開して2年目のこと、ショパンのアレグロ・コンフーコのところを意識しすぎていると、パソコンのマウスがもてないくらい、親指の付け根がいたくなったことあります。それ以来、自分なりに気をつけているつもりで、ここ最近は大丈夫なのですが、和音の多い曲、指を開くのが多い曲をするときは、やはり気になります。お風呂場であれ、(退屈な?!)会議中であれ、指を伸ばしてストレッチをすることがよくありますが、最近それは癖になってしまいました。携帯電話のおかげで、380万人くらい腱鞘炎の人がいると記事にはありましたが、ちょっとびっくりな人数でした。なにごとにもほどほどがいいのでしょうか、何とかマイペースの毎日を過ごしたいです。記事の最後のほうに「腱鞘炎は、糖尿病やリウマチの合併症でも発症する」とあり・・・やはり油断もすきもないようであったりします。BGM:シューベルト 高雅なワルツ (ドホナーニ編) ラヴェル 高雅で感傷的なワルツ ピアノ:青柳いづみこ 楽しく時には爆笑をさそうエッセイをきっかけに青柳さんのCDを聴くことに なったのは数年前。 読んでから観る映画はいくつかありましたが、 読んでから聴いたピアニスト、私にとってはこの方しかいません。 このCDは、ワルツばかり並べていますが ショパン、シューベルト、ラヴェル、サティ、リスト、ドビュッシーと 変化に富む選曲で、センスのよさも抜群です。
June 20, 2006
コメント(6)
-
プレミアム10とシチリアーノ
たくさんモーツァルトの曲をテレビ番組で聴いたので、今は余韻に浸ることにしています。「たけしの誰でもピカソ」、「世界一受けたい授業」でもモーツァルトの特集番組ありましたが、今回はNHK「プレミアム10」。(この手の番組、結構見ています・・・)詳しくない人でもわかりやすいようにということでいろんな角度から、モーツァルトをアプローチしていて、時折深い内容があったりして楽しんでいました。ジュピター交響曲での男女の会話の様子を指揮者の飯守さんがピアノで説明したところ、(1楽章、2楽章でそれぞれの説明)わかりやすかったです。ピアノを習っていて、登場人物が2人いるような曲でも、指摘されてようやく気づくこともありますが、ときどきこのように客観的に知ることは刺激になりました。子どもの頃の作品が、晩年のオペラ「魔笛」の旋律と類似しているところ、興味深いお話でした。無意識のうちにそうしているのでしょうか。***ピアノを弾く人はいつあらわれるのかと、ずっと待っていましたが、10:40ごろ、トルコ行進曲を聴くことができました。快活な曲へのアプローチは、やはり元気にさせてくれます。(そういえば、小学校5年生のときのピアノの発表会で弾いて以来、ちゃんと弾いていないのでまじめにもういちど練習してみようかと思っています。)ピアノ協奏曲23番、27曲あるなかで、最も好きな曲です。明るい1・3楽章にかこまれて2楽章を聴くのと、2楽章だけ聴くのとでは、また印象もかわるものと、テレビでバレエをバックに流れているときも感じました。かつて2番のソナタの2楽章を練習しているころ、シチリアーノのリズムの対比で23番の2楽章のさわりを比較していただいたことがあるのですが、そのときのことをおもいだしました。たしかに良く似ています。番組ではちょっと短いバージョンでしたが、映像の演出もあってかしっとりとした雰囲気で聴いていました。モーツァルトと世界史はほとんど関連付けたことがなかったのですが、フランス革命(1789年)が、生活に打撃を与えたことを改めて感じました。この時代が10年でもずれていたらと、感じてしまいますが、K.600番代の晩年の名曲もまたこういう時期に生きていたからこそできた作品なのかと、あらためて感じました。***この番組中、数分間ピアノを演奏するだけでも、朝から晩まで収録中にはいなければいけなかったとか、後日談としてうかがいました。集中力を保つのにどうすればいいのか、またいろいろとうかがってみようかと思います。
June 19, 2006
コメント(13)
-
ニュルンベルグ
ニュルンベルグという試合がおこなわれる場所を聞いて、ワーグナーの指輪やマイスタージンガーを連想してしまいました。この地名はそういうわけで知っていました。ニュルンベルグは人口50万、ドイツ東側、ミュンヘンとライプチヒの間あたりにあります。中世と現代が共存する街、中世職人広場という場所があるらしく、行ってみたくなりました。http://www.socceringermany.info/soccer/jp/2__Staedte__und__Stadien/Nuernberg.html対戦相手のクロアチアという国が旧ユーゴスラビアくらいしか知らなかったのでいろいろ検索してみました。外務省のページにかなり真面目なデータがあったのでさっきまで見ていました。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/croatia/data.html(最近クロアチアに訪れた政府関係者、ちょっと興味もちました。)1995.4-5 河野外務大臣 1999.7 谷垣大蔵政務次官 2000.2 有馬政府代表 2002.10 清子内親王殿下 BGM:ヴェルディ:歌劇「ナブッコ」より 『行け、わが思いよ、黄金の翼に乗って』 なにか景気づけるタイトルの曲はないものかと、思案していたのですが、 急に聴きたくなりました。 ヴェルディの出世作といわれるオペラの後半で全員で歌われるもの、 イタリア第2の国歌ともいわれています。 (ワーグナーのCDが出てこなかったので今日はこれを聴きます。) なんとか日本チームは勢いづいてほしいものです。
June 18, 2006
コメント(6)
-
世界の国歌
ワールドカップを見ていて、試合が始まる前におたがいの国歌が流れてやはりいいものだなあと感じます。スタジアムで何万人の合唱で、一体感が生まれます。オリンピックの表彰式、ボクシングのタイトルマッチの前のときと同じく緊張感も漂います。お国柄があらわれ、名曲もかなりあるように感じます。確か国歌ばかりのCDが家にあったはずと、探していたらやっぱり出てきました。BGM:長野オリンピック公式ライセンス商品小澤征爾conducts 世界の国歌新日本フィルハーモニー交響楽団2枚組CDで、71カ国あります。部分的に聴くといいのですが、通して聴くとさすがに疲れます・・・。モチベーションがあがりっぱなしではやはり無理があるということでしょうか。長野オリンピックのときは、リュージュと閉会式に見に行きましたが、そのときにお土産に買って帰ったものでしょうか。なんでこんなものが家にあるのか、小澤さんのCDを集めていたころだったからか、ちょっと思い出せません。あらためて解説書を読むと、ずいぶん興味のあることもありました。曲の由来とか、メモ代わりに書かせていただきます。●日本 曲名:君が代 1893年 歌詞は「古今集」の賀歌からとったというのが定説。 作曲は林広守を中心とする宮内省のチームによるもの。 日本古曲から取材されたものであり、和声はドイツ人エッケルト氏による。 ●ドイツ 1922年「世界に冠たるドイツ」として制定された後、 1950年3番の詩を正式なものとして定めた。 1990年ベルリンの壁崩壊後、旧東ドイツ連邦が加入したが国家は変わっていない。 ハイドンの弦楽四重奏曲ハ長調op.76-3「皇帝」のメロディである。●フランス 曲名:ラ・マルセイエーズ 1795年 1789年のフランス革命後、共和制と帝政を繰り返しているが、 1792年リール中尉がフランス陸軍部隊のために「ライン陸軍行進曲」を作詞作曲したが これがマルセイユ市民に熱狂的に歌われたためにこの名前がつくようになった。●イギリス 曲名:われらが女王 God Save the Queen 作詞作曲者不詳 18世紀に国歌として制定 国歌の草分け的存在。リヒテンシュタインの国歌もこの曲を採用。●イタリア 曲名:マメリの賛歌 1946年 もともと詩人マメリの「イタリアの歌」と呼ばれていた詩にナバロ作曲したものが 歌われていたが、1848年ヴェルディが作曲したものを、 1946年共和国設定の機に国歌として制定した。●アメリカ 曲名:星条旗 1931年 1814年米英戦争のとき、アメリカの弁護士キイが星条旗をみて感動し、 イギリスの古い旋律(スミスが作曲した「天国のアナクシオン」という説あり)にあわせて 作詞した。 1931年大統領が国歌として正式に選定した。 ●チェコ (←さっき試合前だったのでテレビで流れました。) 曲名:我が家いずこや 1919年 1918年チェコスロバキアとして独立、このとき劇作家テイルが作詞したものが 国歌として制定された。 1993年にスロバキアと分離した後もそのまま使用している。
June 17, 2006
コメント(7)
-
プレミアム10(モーツァルト特番のお知らせ)6/19 10PM-
6月19日(月)夜10時からNHK総合テレビでモーツァルトの特番があります。少し番宣をさせていただきます。プレミアム10 「もっと暮らしにモーツァルト」 「聴いてトクする?名曲セレクション~生誕250年~」 午後10・00~11・30 この番組のロケがあったのは、3月31日で、4月のはじめごろ、こんな番組があるので・・・ということをうかがっていました。5月10日以降の月曜日のどこかで放送されるはず・・・ということで、5月になってからコンビニでテレビガイドを見ていましたが、5月10日(月)夜10時~、NHK総合は「プラネットアース 乾きの大地を生き抜く」で5月17日(月)は「小泉純一郎の5年間という特集だったりで、???とおもっていましたが、ようやくふさわしい日がめぐってきました。6/18の日本xクロアチア戦の翌日ということもあり、どんな気分でモーツァルトを聴けばいいのか、軽いディスカッションを出演者の方としてしまいました。演奏予定といわれているトルコ行進曲とピアノ協奏曲23番の2楽章の3分バージョン(らしい)を楽しみにしています。指揮者の飯森範親さんと、ためしてガッテンの小野文惠アナウンサーが進行役、それ以外はどんな曲が飛び出してくるでしょうか。 よかったらご覧になってください。***今日は、モーツァルトから離れてぜんぜんちがう曲を聴いています。BGM ドビュッシー パンの笛 (フルート:ジャン・ピエール・ランパル)
June 16, 2006
コメント(6)
-
灰色の雲
どんよりと曇った空と、しとしとと雨。天候不順でありましたが、比較的平和な1週間だったようにも思えます。水曜日の午前中はスーツを着る寸前までいったのですけど、思い切って午前中会社を休んだりもしました。夜中はサッカーの中継をやっているので、そんな言い訳をしてもそれなりには通用するはずですが、無理に言う必要もありませんでした。最近では血糖値が高いことまでピアノを弾くことと同じ程度に知られるようになり、心配してくださる人も増えました。昔の上司にばったりあうと、「(ヘモグロビン)A1Cの値はいくつだ?」と「グリミクロンは何錠飲んでいるのだ?」とか、変な仲間意識があるのか、挨拶代わりに聞かれることだってあります。笑って済ませられる間はまだいいのですが、ずっと笑って済ませるようにしていたいものです。心配していただけるのはありがたいですが、なんとかいい状態にしていきたいものです。灰色といえば、やっぱり灰色ですが、チャコールグレーのスーツは私は大好きで、紺色より、なんか知的なふりができるので気に入っています。BGM:リスト 灰色の雲 スヴャトスラフ・リヒテル この曲は、もう何年も前、ポリーニが現代曲ばかりのコンサートの日に、 最初につけたしのようにプログラムにいれたことで、存在を知ることになりました。 今日みたいな日に聴いてみるのもとおもいましたが、軽く聞き流してしまいました。 それよりもこのCDの前後にあるポロネーズ2番、コンソレーション6番、 ハンガリー狂詩曲17番、メフィスト・ポルカと、 久しぶりに聴くリストのめずらしいものシリーズのCDに耳を傾けています。 そのあと、超絶技巧が1・2・3・5・7・8・11・10となぜか最後の順序が 逆、マゼッパと雪かきがないのがちょっと残念ですが、面白いCDです。
June 15, 2006
コメント(4)
-
タランテラ
ぐずついた天気のなか、サッカーを見て夜更かしをしてという生活がつづいています。少しでも頭が冴えてくればいいのでしょうけど、すこしでも工夫しないとと感じています。午前中会社をお休みにして、あえて午後から会社に行ってみたり、今日はそんなことをしていました。 若い社員の子が幹事をしている飲み会には参加してあげないとかわいそうだし、とかいいながら、銀座で5000円のコースが60%OFFのお得な企画にのらないのもおもしろくないしといいながら夜は談笑していました。最近は、ピアノを習っていることに興味を持ってくださる方も増えてきて、次の会社での演奏会はいつなのだ・・・と(9月下旬なのですが)部長から言われてしまい、ありがたいやらなにやらという雰囲気になりました。今日のメンバーの20名弱が、大挙として聴きにこられるのであれば、ありがたいかもしれませんが、ちょっとしたプレッシャーになるかもしれません。アマチュアの身分でいつも150人前後のお客様の前でピアノを弾ける機会はそんなにないとおもっています。真面目に曲を決めて、準備をしないとたいへんなことになるので、地道に練習しようと思っています。いままでピアノを弾いたなかでいちばん恐ろしい思いをしたのは、過去この演奏会に出たなかで、ゲスト出演のヴァイオリニストの川畠成道さんがご家族と伴奏ピアニストと一緒に最前列に座って聴かれたときでした。本当に真っ白になってしまいました。あまりにもひどい演奏だったのですが、「練習時間もないなかよく弾かれましたね」というメッセージをいただいたり、そんなことがきっかけで、親しくなるきっかけにはなったのはケガの功名みたいなものですが、長くつづけているといろんなことがあったりします。BGM:リスト 巡礼の年 第2年補遺 「ヴェネツィアとナポリ」 ゴンドラを漕ぐ女/カンツォーネ/タランテラ ピアノ:小菅優 この曲集、リストのなかでも好きなほうで、頭をすっきりさせたいとき、 不思議とよく聴いています。 タランテラ、かっこいい演奏を聴くとあこがれてしまいます。 こういう曲にかかわれるようになるといいですね。一生聴き手におわるとおもいますが。 ヴェネツィアとナポリ、 偶然ですが、どちらも訪れたことあります。 きらきらとした運河や海岸線・・・いろいろなこと思い出してしまいます。
June 14, 2006
コメント(8)
-
Relaxing
昨日は、サッカーの試合を見終わった後、たいへん沈んでしまいました。カイザースラウテルンという街の名前、ずっと覚えておこうと、思ってはいますが、ドーハというしばらく忘れていた街の名前まで昨日は思い出してしまいました。昔、旅行先で見かけた、ベルリン、オイローパーセンター付近のカイザー・ヴィルフェルム教会という名前も、銀河英雄伝説(でしたっけ)、カイザーラインハルトという将軍の名前も、一緒に思い出しましたが、まだそっちのほうがいいのかもしれません。あまりテンションのあがりすぎる曲を聴くのはやめようと、Relaxing(リラクシング)という3年前の秋頃によくお店に並んでいたCDを聴くことにしました。知らなかった名曲と出会うとき、思わぬ曲にはっとさせられるときは、案外こういう小品のCDを聴くときかもしれません。クラシック、映画音楽、日本の歌、ちょっとユニークな22曲です。BGM:ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 ピアノ:べラ・ダヴィドヴィッチでもサッカーの試合は、やっぱり見続けています。トーゴの選手がレッドカード退場のあと、韓国チームが得点をいれ、韓国1-1トーゴ となりました。(後半10分)テレビの表示が前半となっていて、おもわず突っ込みをいれたくなります。p.s.生涯指揮者・岩城宏之の挑戦というテレビ番組のブログを4月14日書きましたが、お亡くなりになりました。たいへん残念です。ご冥福お祈りいたします。「振るマラソン」のベートーヴェンチクルス聴きたかったのですが・・・http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200604140000/
June 13, 2006
コメント(5)
-
カイザースラウテルン
ワールドカップの試合まもなくはじまります。私自身、ドイツは、過去4回訪れたことあります。降りたことのある空港・駅フランクフルト・ミュンヘン・バーデンバーデン・ベルリン・ライプチヒ・ドレスデンでも、カイザースラウテルンという地名は、今日はじめて知りました。まったく知識がないので、試合が始まるまでにネットを散策して遊んでいます。FIFAの案内カイザースラウテルン文京区は、カイザースラウテルンの姉妹都市、さっきニュースで知りました。ドイツの西側、フランスの国境まで40Km、ミシンの生産で有名。東50Kmにマンハイムという都市が近く・・・・この地名を聞いて、またモーツァルトが聴きたくなりました。サムライブルーの日本チーム、オーストラリアに勝てるといいですね。
June 12, 2006
コメント(8)
-
共感
昨日から今日にかけて、いろんな方が来て下さいましてありがとうございます。楽天日記でピアノがキーワードでリンクをはっている方、ミクシィ経由で来てくださっている方、ちょっとした出来事で書き込みしていただくことたいへんうれしく感じます。たいへんありがとうございます。***もともと、仕事がら半分ネットワークコミュニケーションとか首をつっこんでいたこともありますが、自分でいろいろ体験していることが財産になっています。****最近、言葉の定義をすることが多く、改めて整理してみました。Blog=WebLOGの略称、時系列に書かれた簡単なツールを使って維持する個人ないし企業のオンラインのウェブページ。mixiはmix(交流する)とi(人)を組み合わせた造語。リアルの友人間でこれまでの友情をさらに深められ、友人の友人、または共通の興味を持つコミュニティなどから新しい友人関係を深めることのできるサービスを目指している。2004年3月3日オープン。(私がここに入ったときは2005年3月末でidは53万台、 いまは450万を超えているらしいです。)月に1度はブログを閲覧する人(政府の調査)2005年3月 1651万 2007年 3455万人 ****ちょっと前、ドッグイヤー(1年が7年分の速さで進む世の中のこと)といわれていましたが、マウス・イヤー(1年が18年の速さで進む世の中のこと)ということばを先日、講演で聴いたりしました。言葉の定義では、杓子定規な感じもしますが、去年の後半あたりから、ひとつの音楽会や世間で興味のあることをネットでいろいろお話することが増えてきてきました。今だからできることもずいぶんあるような感じもしています。なによりうれしいことは、いろいろな人と「共感」できたこと。ツィメルマンのピアノのコンサート、九州・関西・東京近郊で、聴かれた方とここ2-3週間でお話できました。曲目も少しずつ違って、雰囲気もいろいろだったことも知ることができました。九州では半分くらいの客の入りだったこと、東京のサントリーH2回目のときは、ツィメルマンがメッセージを読み上げイラク戦争に関するコメントまで発表されたこと、ショパンの葬送ソナタを弾いた日にはアンコールがなかったこと。いろいろありますね。7月上旬には香港でコンサートがあることも知りました。美しい音や響きだけでは良い演奏ではない 社会のなかでの音楽を意識という毎日新聞のツィメルマンのコメントも知ることとなりました。鋭い意見には感銘をうけました。http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/music/news/20060516dde018200055000c.htmlBGM:バッハ パルティータ1番 変ロ長調 BMV825 ピアノ:マリア・ジョアン・ピリス きのう、出だしだけツィメルマンが弾いたのが、妙に耳に残っています。 つづきはいつか聴きたいものです。
June 11, 2006
コメント(2)
-
ツィメルマン・横浜公演
半年前から楽しみにしていたコンサート、横浜みなとみらいホールへ行ってきました。ツィメルマンは今年で50歳、白髪になり、ますます貫禄を感じています。よくプロフィールには年間のコンサート回数は50回程度にしていると書かれていますが、本当にそうなのかと思うくらい精力的な印象持ちます。5月7日盛岡からはじまった日本ツアーは18公演、横浜公演は17公演目6月に入ってからはほぼ毎日で、2日(東京/サントリーH)、3日(京都)、4日(栃木県壬生町)6日(富山)、7日(東京/浜離宮H)、9日(武蔵野)、10日(横浜)、11日(所沢)。オーバーワークかもと懸念もしましたが、懸念するという文字は辞書にはなかったように思えました。プログラムは、場所によって少しずつ違うのですが、横浜公演はプログラム1モーツァルト ピアノソナタ第10番 ハ長調 K.330ベートーヴェン ピアノソナタ第8番 ハ短調 op.13「悲愴」**ショパン バラード第4番 ヘ短調 op.52ラヴェル 高雅で感傷的なワルツ(全8曲)グラジナ・パツェヴィッチ ピアノソナタ第2番(アンコール)バッハ パルティータ第1番より プレリュードガーシュイン 3つのプレリュードより第1曲よく耳にする曲から、まったく知らない曲まで、ジャンルはオールラウンド、かなりこだわったプログラムだったようです。音符が少ない、前半の古典のソナタ2つ、私にとりましては大変興味深い演奏で、感動しました。モーツァルトはとても愛らしい音色で、ほどほどにペダルも使用され、メロディが映えました。繰り返しは、けっして1回目と同じには弾かず、強弱でちがいを見せるか、少し楽譜からはなれて変奏してみるとか、遊び心も結構あり、楽しめました。第1楽章からアタッカのように、間髪いれずにはじまった第2楽章は、まさにカンタービレ、歌心たっぷりの演奏に聴き入っていました。(たぶん地方公演とかで拍手が入ってしまい、そうしたくなかったから続けて弾いたのかなあ)ベートーヴェンの「悲愴」、数多くいままで聴いてきましたが、今日のが1番かも。圧巻でした。第1楽章は、テンションも高く、アパショナータ(熱情)ソナタを聴いているかのような錯覚するくらいでした。その分第2楽章の静けさが対比され、ソナタ全般としての構成はたいへん緻密なものでした。第3楽章、2楽章のつづきのように静かにはじまり、だんだん盛り上げていくかの演奏には惹き込まれてしまいました。この2つのソナタ、左手の音の強弱について、印象に残るところ多々ありました。伴奏として分散和音を静かに奏でている箇所、ベースの音として、はっきりと鳴らして、右手のメロディをさらに浮かびあがらせているようなところもあり、主張もはっきりしてわかりやすい演奏でもありました。(楽譜も見たことのなり知っている曲だけに、いろいろ思うところありました。)後半は、曲をそこまで知らないので、あまり書くことはできません。ただ、ラヴェルのワルツが、日本ツアーでのメインテーマだったような印象、ラヴァルスというオーケストラの曲が好きなのですが、それを彷彿させるような楽しい曲でした。たいへんな完成度の高さに圧倒されました。その前に弾いたバラ4がかすんでしまうくらいにも感じました。(もちろんバラ4もいい演奏で、念願かなってやっと聴けてうれしかったです。)バツェヴィッチの超絶技巧ソナタのあと、静かなバッハのパルティータは、やわらかな音色に引き込まれまして、少ししか弾かなかったわりには印象に残りました。ツィメルマンが楽しそうにピアノを弾いている感じがしてそれがうれしかったです。また来日することもあるでしょうし、今後もいろんな演奏を楽しみたいです。
June 10, 2006
コメント(20)
-
Klaviersutcke/6 Piano Pieces Op.118
ふとしたきっかけで、お元気ですか?とメールをいただくことがときどきあってうれしいです。朝の連ドラのなか、マルセイユという喫茶店を舞台に流れていたブラームスの間奏曲op.118-2、蓄音機がまわっていたのは、なんとも優雅でした。私自身、3年前の今頃、ちょうどこの曲を習っていて、仕事から帰ってきてふらっと弾いてみるのが楽しみでしたが、朝ドラのピアノのBGMで思い出したように、連絡をいただいたりすると、やはりうれしいものです。ちょっとしたきっかけに感謝したくなります。BGM:ブラームス 6つの小品 op.118 ピアノ:ラドゥ・ルプー 2曲目の間奏曲、3曲目のバラード、5曲目のロマンスと これまでレッスンを受けたり、人前で弾いたりしましたが、 ちょっと地味だったり派手だったりする、1曲目・4曲目・6曲目も いつか弾けるようになりたいです。 シューベルトの楽興の時やこの曲集のように、ところどころかじった曲たちは、 パズルを埋めるように、これからの楽しみにしたいところです。 ブラームスop.117-op.119は、不惑の年頃になれば弾こうと 思っていますが、今日もピアノを聴いていてなんだか楽しくなってきました。 よい週末をお迎えください。サッカー三昧の2週間になるかもしれませんね。
June 9, 2006
コメント(4)
-
銀座・京橋・八重洲
町の名前がいつから・・・というのに興味を持つことあります。ドイツのベルリンという街は熊(BEAR)が出没するからという由来だったり、オーストリアのザルツブルグは、塩(SALT)がとれるところだからとか、いろいろ聴いたことあります。遠いところの話ばかりもとおもうので、東京の身近なところから書くことにします。ちょうど区のお知らせのような新聞にかいてあったことが興味深く、備忘録代わりになってしまうようです。銀座:銀座ということばは銀貨鋳造所のことで、江戸時代の初期の1612年(慶長17年)駿府(静岡)から、今の銀座2丁目あたりに移ってきたのがはじまり。京橋:東海道の起点となる日本橋から京へ上る最初の橋だったので、京橋と名が生まれ、町名になったそうです。八重洲:江戸時代初期、オランダ人通訳ヤン・ヨーステンが内堀沿いに邸地を拝領したことから、「やよす海岸」と呼ばれ、後に八重洲町となりました。現在の八重洲になったのは昭和29年。このあたりは、雨降りでなければ、この時期お散歩するのもいいかも。「うさぎや」さんか「とらや」さんで和菓子をいただきたくなりました。この二つのお店の区別がつかなかったころ、下町の初級者といわれ、修行が足りませんと、言われたことあります。BGM:モーツァルト ピアノソナタ K.533+K.494 ピアノ:アルフレッド・ブレンデル 楽譜の番号どおり15番のソナタという人もいれば、 ただのヘ長調ソナタとなっていたり、身の置き所が・・・のソナタ。 寄せ集めで別作品だった3楽章のロンドをくっつけて ひとつのソナタにしてしまう、 ちゃっかりとしたモーツァルトさんに興味をそそられます。 第3楽章、一見なんでもなさそうな軽いロンドのようですが、 最後のフーガがまったく・・・で、 たいへんな指使いで、困ってしまいました。 頭の体操にはずいぶんなったような気がしています。
June 8, 2006
コメント(8)
-
ソネット
数年以上前、6月6日に、すごく面白くないことがあって、ちょっと落ち込んで家に帰ってきました。かなり呆然としていたときのことでした。自宅にパソコンを買い、ソネットのメールアドレスでメールをはじめてちょうど2ヶ月たったころでした。何の気になしに、インターネットの検索画面で「ぴあの」と入力し、画面を表示してみると、ピアニストの画面、ピアノ教室のHP、ちょっとしたピアノサークルのメーリングが結構でてきました。6月7日に日がかわり、朝方までいろいろ拝見していました。あまりに新鮮で、ひとつひとつ見ていたのが私自身の転機となる日にもなりました。いろいろあったあと、メーリングに登録したり、HPの掲示板に書き込みしたり、今のブログやミクシィのひと世代前の楽しみを人並みにするようになりました。その1ヶ月後にピアノを習うことになったのもこれ日がきっかけ。8年たってもそのときのことをはっきりとおぼえており、初心にかえりたくなります。いまだにときどき連絡をとったりお話できる方がたには、感謝のおもいでいっぱいです。BGM:リスト 巡礼の年第2年「イタリア」 サルヴァトーレ・ローザのカンツォーネッタ ペトラルカのソネット第47番・第104番・第123番 ピアノ:野原みどり 頭をすっきりさせたいとき、なぜか聴きたくなるのがこの曲集。お気に入りのひとつです。 ソネットついでに、 ペトラルカのソネット第104番の歌詞大意を紹介いたします。ちょっとこわいのですが・・・ (ソネットとは、14行詩のことです。) 第104番 平和は見つからず、さりとて戦うこともできない。 恐れつつ望み、燃えては氷り、高く飛んでは横たわる。 私を牢に入れ、開放もせず閉じ込めもせず、 愛の神は私を殺しもせず、自由にもしてくれない。 私は詩を望みつつ、助けを願う、 自分を憎み、他人を愛する。 泣きながら笑い、死も生もいとわしい、 私をこんなにしてしまったのは、女よ、貴女です。
June 7, 2006
コメント(4)
-
♪6月6日の参観日・・・・
雨ざあざあ降ってきて・・・・いったん家に帰りピアノのレッスンへ行こうと思ったら雨がざあざあ降ってきて、傘をとりにかえりました。心の中まで雨ざあざあでは、困るので、今日はヴァイオリンの曲でも聴いて癒されることにします。BGM ブラームス ヴァイオリンソナタ第1番 「雨の歌」 ヴァイオリン: オーギュスタン・デュメイ ピアノ:マリア・ジョアン・ピリス詩も好きなので紹介します。数年前、会社の庶務担当の女性が月が替わるとエッセイを書いたり詩を書いたりメールで送ってくださる方がいたのですが、そのときに紹介してくださって知るようになりました。**雨の歌 作品59の3 (グロート 詩) 雨よ滴をしたたらせて ぼくのあの夢をまた呼び戻せ。 雨水が砂地に泡立った時 幼い日に見たあの夢を! けだるい夏の蒸し暑さがものうげに 爽やかな涼しさと競い つやつやした木の葉は露に濡れ 田畠の緑が色濃くなった時。 何と楽しいことだったことか 川の中に素足で立ったり 草に軽く手で触れたり 両手で泡をすくったりしたことは! あるいはほてった頬に 冷たい雨の滴をあてたり 新たに立ち昇る香気を吸って 幼い胸をふくらませたりしたことは! 露に濡れたうてなのように また恵みの露にひたり 香気に酔いしれた花のように 幼な心も息づいて開いていた。 ときめく胸の奥深くまで どの雨の滴もぞくぞくするほど冷やして 創造の神々しい営みは 秘められた生命の中まで浸透した。 雨よ、滴をしたたらせて ぼくの昔の歌を呼び覚ませ 雨足が戸外で音を立てた時 部屋の中でぼくらが歌った歌を! あの雨の音に快い、しっとりした 雨垂れの音に再び耳をすまし あどけない幼な心のおののきで ぼくの魂を静かに潤したいものだが。詩: クラウス・グロート
June 6, 2006
コメント(4)
-
ああ、ママにいうわ
時代の寵児とかということばがありますが、今年はそのことばをよく聞いたりします。マスメディアが同じ方向へ向き、もちあげたかと思えば、何かの拍子にが逆のことになったりもします。時代の寵児といわれた方の悪さかげんからしてみれば、それも当然かもしれませんが。多くの新聞雑誌は売れればいいわけで、総括なんてとてもできませんと、テレビによく出る評論家の講演会で開き直られたこともあります。正論なのかもしれませんが、そのときはちょっと哀しくなりました。*「皮相の動きにとらわれず真摯に物事に取り組んでください」とピアノが弾くことが趣味ということで知り合いになったある代議士の先生から言っていただいたことがありますが、なんか表面だけで物事をとらえたくないと思った1日でありました。***そんなこんなで、頭をクリアにしたくなりました。ニュースも記者会見もそれなりに見たので、テレビは今日はもういいとおもい、さっきからモーツァルトの静かに聴く事にしています。BGM:モーツァルト きらきら星変奏曲 ピアノソナタ10番 デュポールの主題による9つの変奏曲 ピアノソナタ2番 ピアノ:クララ・ハスキル クララ・ハスキルのモーツァルトのCD,いろいろ持っているはずなのですが、 ソナタはこの2つ以外に録音があるのかどうかも知りません。 ピアノ協奏曲やヴァイオリンソナタのピアノ伴奏は結構あるのに、 やっぱり録音していないのかもしれません。想像するしかないのでしょう。 ほかの演奏で聞流していた2番のソナタはこのCDで弾きたくなりました。 変奏曲はどちらも、次の待ち遠しくなるぐらい楽しいです。 クララ・ハスキルのベートーヴェンのソナタも17番のテンペストと18番しか たぶん録音はありません。よっぽどいろんなことにこだわる人なのでしょうか。 もう遠い過去のピアニストですが、ときどき聴くことを楽しみにしています。 子どもの頃、ロンドニ長調やソナチネにあったK.545とかを弾いていたときのように 純粋な気持ちで接してみたいですね。 秋にきらきら星を人前で弾くつもりで眠っていた楽譜をたたき起こして、 練習はじめることにしました。
June 5, 2006
コメント(4)
-
スペイン舞曲(モシュコフスキー)
連弾のコンサートを聴いてきました。 モーツァルト アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク 第1楽章 4手のためのソナタ K.357 唱歌の12ヶ月(青島広志編) 1月/富士山 2月/雪 3月/春よ来い 4月/春の小川 5月/鯉のぼり 6月/雨 7月/七夕さま 8月/海 9月/村祭り 10月/もみじ 11月/菊の花 12月/冬の夜 *** A列車でいこう/愛を感じて/星に願いを/ストップタイム・ラグ モシュコフスキー スペイン舞曲集 op.12 第1番~第5番 *** ブラームス ハンガリー舞曲1番 モーツァルト トルコ行進曲モーツァルトから、ポピュラーな曲まで、いろいろ紹介していただきました。連弾ならではの、1人ではありえない重厚な和音が響いたときは、とても気分よくさせられます。モシュコフスキー スペイン舞曲、何年かぶりに聴きました。この3番がとても好きで思い出しました。ピアノを習いだした頃、同じクラスの人がちょうど連弾していて、譜めくりを頼まれたことがあるのですが、あまりにきれいなメロディに感動し、譜めくりすることをすっかり忘れてしまい、弾き終わってから、お叱りをうけたことあります。それくらい気になった曲でもありますが、いつかそういう機会があればと思っています。連弾の曲は、自分で意識しないと、あまり何があるかもわからなかったりするのですが、いい機会になりました。頭の中ではスペイン舞曲がなっています。ピアノ教室の先生どおしでの企画でしたが、楽しそうに演奏されていることがとてもうれしかったです。
June 4, 2006
コメント(6)
-
バレンボイムは夢の中で
金曜日の夜は、結構夜中に音楽番組を見ることが多いです。週末の夜もそうするはずでした・・・・12時半くらいにインターネットで番組表をあけていたのがこれ。クラシック・ロイヤルシート ベルリン・フィルのヨーロッパ・コンサート2006 チャンネル :BS2 放送日 :2006年 6月 2日(金) 放送時間 :翌日午前0:40~翌日午前2:19(99分) ジャンル :音楽>クラシック・オペラ 番組HP: http://www.nhk.or.jp/bsclassic/ -------------------------------------------------------------------------------- 「交響曲 第35番 “ハフナー” K.385」 「ピアノ協奏曲 第22番 K.482」 「ホルン協奏曲 ニ長調 K.412/514」 (ホルン)ラデク・バボラク 「交響曲 第36番 “リンツ” K.425」 モーツァルト作曲 (ピアノ)ダニエル・バレンボイム (管弦楽)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (指揮)ダニエル・バレンボイム ~チェコ・プラハ エステート劇場で録画~ とってもいいプログラム。バレンボイムの弾きふり・・・・見てみたいものだと、ちょっと横になって10分くらいうたた寝しようとおもっていたのに、目が覚めたら、朝になっていました。 テレビをつけたら「純情きらり」がはじまっていました。残念・・・こういう日もあるかと、再放送を楽しみにしています。それにしても週末になると不眠症が解消されてしまうのはなぜでしょう。バレンボイム・・・ベートーヴェンのソナタ全集はお気に入りでときどき聴きます。ずっと前、教会でベートーヴェンのソナタを弾いている番組をみて感動させられましたが、それを聴いていたとき、「ごはんができた」と親に呼ばれた時代だったので、やっぱりそうとう前なのでしょう・・・。
June 3, 2006
コメント(8)
-
トランスクリプション
昨日のつづきで、よく眠れないときに聴いていたCDをひっぱりだしてきて、聴くことにしました。BGM:ENCOREというCD Pf;田部京子 16曲入りのCDですが、適当なところから聴くことが多いです。 メンデルスゾーン=リスト 歌の翼に ワーグナー=リスト タンホイザーより「夕星の歌」 シューベルト=リスト ウィーンの夜会第6番 リストの編曲物は、このCDで、興味を持つようになったことは いうまでもありません。 まだひとつも弾いたことがないのですが、いつかはと思っているものだったりします。*** その後、ダン・タイ・ソンやキーシンの演奏で、 シューベルト=リストの「水の上に歌う」といったような歌曲のCDに 出会ったりしました。 ブーニンのCDで、シューマン=リスト 「献呈」といったものに出会いました。 ブーニンのCDは、たまたまコンサートでアンコールで弾いたこの曲が あまりにすばらしく、次の日にCDを探したような記憶があります。** BGMのはなしに戻します。 バラキレフ トッカータ リャードフ バルカローレ モシュコフスキー 火花 たぶんこのCD聴いてなかったら、今も知らない曲だったかもしれません。 よく知っている曲がたくさん入っているCDは、よく見かけますが、 このCDは、ピアニストが、いろいろこんなすばらしい曲もありますよと、 たくさん紹介してくださったという思いが強く、感謝しているCDのひとつです。 このCDにも97年1月19日のサインがあります。 田部さんがシューマンのシンフォニックエチュードのCDを録音しようとしていた のですが、途中で交通事故にあわれて、しばらくしてから、ある集まりで紹介していただいた ときのことでした。
June 2, 2006
コメント(4)
-
Music&Sience ツィメルマン演奏会&講演会
東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター分子病態医科学部門発足記念行事ということで、以下のような催しがあるそうです。詳細は以下のURLで。http://www.cdbim.m.u-tokyo.ac.jp/news/index.html少し内容を引用させていただきます。*****式次第(第一部):Zimerman氏によるピアノコンサート(曲目)Mozart Piano Sonate C-dur K.330 Chopin Ballade No. 4 f-mol op.52 ほか(第二部):討論会 “Music and Science”音楽と科学におけるインスピレーション/ 音楽と科学における絶対的な真理とその探求/ 美の探究へのストラテジー(戦略)/ 専門家になるべきか、広範な興味を持つべきか?/ 演奏家あるいは科学者の個人的な興味と聴衆あるいは社会のデマンド(要求)の差とその解決について/ ほか日時および場所平成18年6月16日(金曜日)午後6時より東京大学安田講堂にて参加費一般:5000円、学生:3000円****最近コラボレーションの企画をよくお見かけしますが、いったいどんなおはなしになるのでしょうか。ちょっと楽しみです。非常に微妙な時間帯なので、私自身はなんとも・・・ですが、もしご興味のある方、東大安田講堂に足を踏み入れたい方、是非お話聴いてきてください。まだ受付をしているようです。
June 1, 2006
コメント(9)
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- KING of IDOL 踊るパワースポット!
- (2025-10-05 15:16:43)
-
-
-
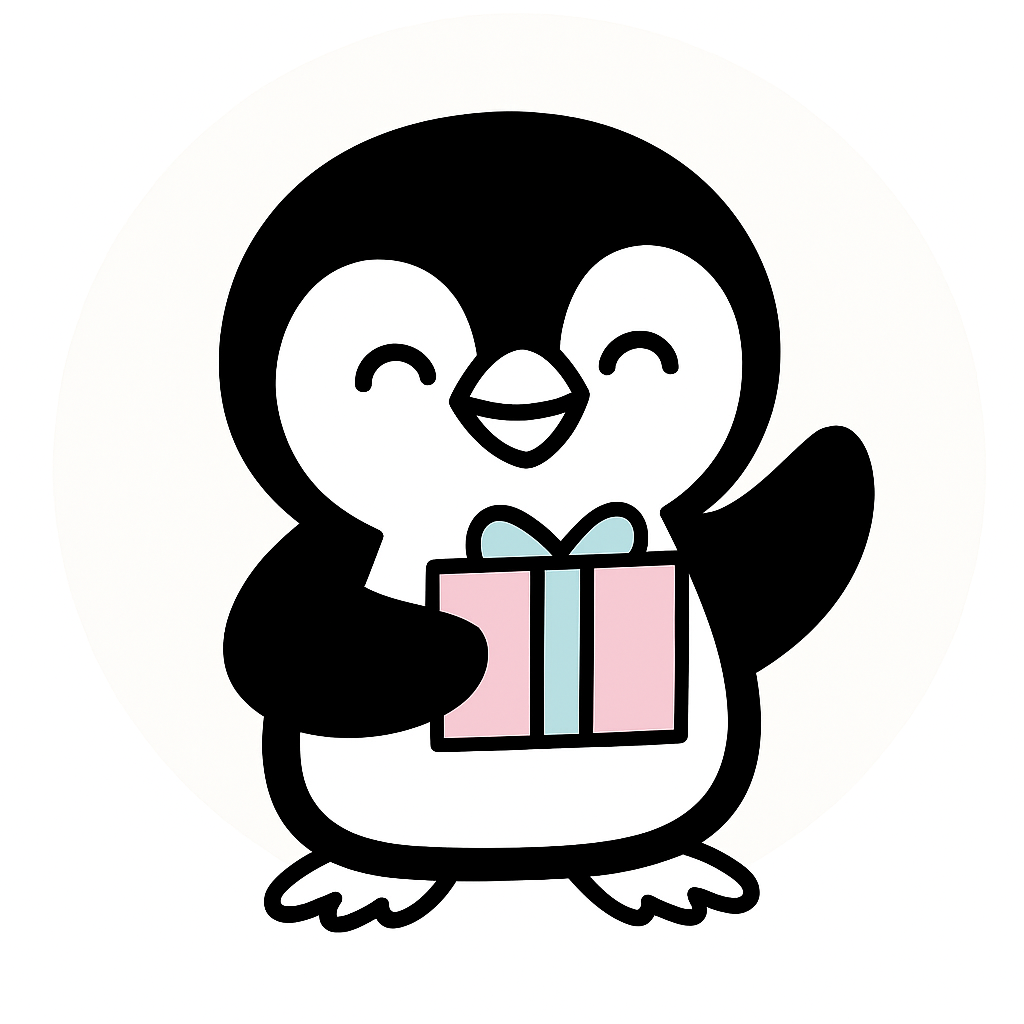
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-







