2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
トマトタンメン PART3
トマトタンメンというおいしい料理を頂くのは今年3回目となりました。その前後で、お店にあるベーゼンドルファーのグランドピアノで素敵な演奏を聴くことができたり、ピアノを触らせてもらったり、いくたびに不思議な発見がある西新宿のお店です。今日うかがえば、店内のさまざまなデザイン、モーツァルトの「魔笛」がモチーフになっているとか。ますます気に入ってしまいました。ミクシィでのクラシックピアノオフ会。ふたをあけてみないと・・・というのもありますが、多彩な顔ぶれと素敵な演奏、ベーゼンのピアノの音色の多面性、こういうときでしか、味わえないというすばらしい空間に感謝し、感激しております。関係者のみなさまへは心からお礼申し上げます。***モーツァルトの2番ソナタ2楽章、シューマンの謝肉祭から、 パンタロンとコロンビーヌ、ドイツ風ワルツ、パガニーニ、 告白、プロムナード、ペリシテ人と闘うダヴィッド同盟の行進弾きました。2次会では、ブルグミュラー25の練習曲を、みんなで弾くことになり、 23番目の「帰途」という曲を弾きました。皆さん、ブルグミュラーのご自身の楽譜を持ってきておられて、レッスン日付や、「あんぷ」といった書き込みや、丸印やシールや、それぞれの足跡を知ることになりました。今は550円くらいの楽譜らしいですが、130円という人のもいらっしゃいました。大阪の実家から取り寄せたくなったくらいです。それ以外、 モーツァルトのK.533+K.494のロンド、 K.330の第2楽章 を弾きました。 昨年の夏にかなりよく弾いていたブラームスのop.118-5のロマンスは 半年ぶりに弾いていて、まったく弾けないことがわかり、途中で弾くのをやめました。 つくづく維持させることの難しさを感じました。*** 思えば冬のものすごく寒い日、問い合わせをしたお店の方からお誘いをうけて、 うかがったのがきっかけその1で、ある掲示板の書き込みがきっかけその2。 一期一会だとつくづく感じております。BGM:書き終わったら聴くことにします。まったくちがう分野の2曲 ベートーヴェンの3番のソナタ(pf;グルダ) ドビュッシーの水の反映(pf:ルービンシュタイン) いろいろ人の演奏を聴いて刺激をうけるのはいいことです。
April 30, 2006
コメント(22)
-
キーシン/横浜みなとみらいH
キーシンのコンサート、2006年日本ツアーの最終日、横浜みなとみらいホールまで足をはこびました。GW初日ということもあってか、親子連れのお客様も多く見かけ、大勢のお客様と共に楽しみました。<プログラム>ベートーヴェン ピアノソナタ第3番 ハ長調 op2-3 ピアノソナタ第26番 変ホ長調 op.81a「告別」---ショパン スケルツォ第1番 ロ短調 op.20 スケルツォ第2番 変ロ単調 op.31 スケルツォ第3番 嬰ハ短調 op.39 スケルツォ第4番 ホ長調 op.54ベートーヴェンは、特に3番ソナタ冒頭の3度の和音の歯切れのよさ、告別のソナタ第3楽章の同じメロディが何度も登場するなかでの表情豊かな歌があり、それが左手になっても右手になってもはっきりと聴こえてきて心地よかったこと印象に残りました。緻密な構成力のもと、それほど感情的ではなく冷静な演奏であったようにおもいます。ショパンになると、音色も微妙に変化を感じました。スケルツォ1番の冒頭の高音フォルテで鳴るところから、今日は来てよかったと感じるもので、曲調自体が情熱的なものですが、それを多く感じました。テンションの高い中、4曲まとめて疾走するかの演奏は爽快でもありました。今日聴いたなかでは、2番・3番が印象に残りました。個人的にはベートーヴェンよりショパンの方がもっと聴きたいというイメージ持ちました。それにしても、プログラム全体の構成が見事だと思います。2年半ほど前、シューベルトの21番ソナタを前半に、後半の冒頭でシューベルト=リストでシューベルトの歌曲(トランスクリプション)を数曲演奏したのち、ペトラルカのソネット、メフィストワルツで締めくくったときも、うならされましたが、今回もショパンのスケルツォにマッチするベートーヴェンソナタを選曲していたようでした。(プログラムのインタビューの記事に書いていました。)<アンコール>キーシンのアンコールは多く演奏され、長いということはずいぶん知られるようになりました。2月におこなわれたパリのシャンゼリゼ劇場では4曲、2週間ほど前のサントリーホールではそれ以上だったようです。今日の横浜公演では、もっとそれ以上でした。アンコールは第3部のようでして、次の10曲が演奏され、盛り上がりました。1シマノフスキー/エチュードop.4-32ショパン/エチュードop.10-43リスト/ハンガリー狂詩曲10番4モーツァルト/トルコ行進曲5.ブラームス/ワルツop.39-156.ショパン/子犬のワルツ7.ベートーヴェン/コントルダンス8.ショパン/ワルツ7番9.ベートーヴェン/エコセーズ変ホ長調10.チャイコフスキー/ナタワルツ超絶技巧あり、ふつうにピアノを習っている人でも弾く曲もありました。アンコールお決まりの曲もあれば、思いつきで弾いた感のある曲もあり、最後の4曲くらいはスタンディングオベーションのお客様多数でした。私は、トルコ行進曲、ブラームスのワルツ、エコセーズ。自分でも弾いたことのある曲、特に興味持ちました。右手のメロディよりも、左手のベースの音がしっかり土台になっていて、バランスがものすごくいいのです。たいへん感動もいたしましたが、アンコールのときの音のイメージ忘れたくないです。そんなこんなで、拍手がようやく鳴り止みお開きになったのは、22時25分。横浜みなとみらいホールからまっすぐ家に帰っても終電2本前でした。聴く側も体力がいりましたが、とても楽しいひとときを過ごすことができました。 ***公演プログラムには、キーシンが初来日してちょうど20年ということで、いろんなエピソードも書かれていました。初来日の頃は、ロシアはまだソビエト連邦という国で、14歳だったキーシンを日本へ連れて行きたい一心だったジャパンアーツの中藤会長も、「資本主義国へ子どもを連れて行くわけにいかない。」とソ連の大臣に反対され、必死で説得し、オーケストラの楽団の保護者付きということでようやく認められたとか。まだまったくの無名だったゲルギエフという指揮者も初期の頃はかかわっていたらしいです。そういうプロモータのご苦労の積上げであることも忘れてはならないと感じています。
April 29, 2006
コメント(18)
-
ブルグミュラー生誕200年だそうです。
先週と今週はテレビのドラマでピアノの曲の挿入されているもの、いくつか聴きました。朝ドラの「純情きらり」では、東京音楽学校の課題曲として、ベートーヴェンのピアノソナタ18番の第1楽章、そして今週は、蓄音機にいもりが乗っかって、結局レコードが割れてしまいましたが、ショパンのノクターン2番、今日は、喫茶店での会話のBGMとして、ブラームスのop.118-2。昭和12年の背景なのですが、脚本家の方もいろいろ考えておられるみたいです。それ以外のピアノのシーンはハノンばっかりなので、ちょっと???なのですが、よけいに曲が流れるとほっとします。8時22分過ぎに家を出なければいけないので、途中でテレビを消すのですが、思わず聴いてしまったこともあります。木曜日の「医龍」というドラマの最後のほうで、いきなりシューベルトの即興曲op.90-2が流れてちょっとびっくりしましたが、アッチェがかかっている曲の最後のほうだったので、次週へつづくために、盛り上げたかったのでしょうか。緊迫感があって、気に入っているドラマのひとつです。***PTNAのメーリングをとっているのですが、モーツァルト生誕250年だけでなく、シューマン没後150年武満徹没後10年、ショスタコービッチ生誕100年、ブルグミュラー生誕200年・・・とありました。ブルグミュラーとあって、さすがにピアノのメーリングだと感じました。ブルグミュラー25の練習曲、小学校のときずいぶんお世話になりました。楽譜は手元になく、大阪の実家にあります。たしか150円の薄い楽譜だったと記憶しています。ぜんぶややりませんでしたが、かなりの曲は、当時のレッスンでみてもらいました。アラベスク、やさしい花、バラード、帰途、貴婦人の乗馬この5曲だったら、いまでもたぶん弾けそうです。いまはタイトル名が変わっているものもあるそうですが、25曲のなかでは、23番目の帰途という曲がいちばんお気に入りです。昔ピアノを習った人で、だれもが通る道であったりして、共通の話題になるだけ愛着もあり、ある意味偉大さを感じます。***さて、明日は、YOKOHAMA。キーシンは何曲アンコールで弾いて、家路に着くのは何時ごろでしょうか。去年の暮れに予約したチケットの日がようやくやってきました。バラードではなくスケルツォ4曲まとめてどんな風になるのか楽しみです。
April 28, 2006
コメント(12)
-
今年初めて聴くアパショナータ
サンプルCDが置いてあるお店で毎月少しずつかわっていく様子を知ることになり、ときどきハッとさせられることがあります。お店でかかっている音楽もよく考えられていたりして、その影響をうけることも多いです。CDショップにとっては、都合のいいお客なのかもしれませんが、楽しい関係が続けばいいかと思います。CDという媒体が世の中に認められて20数年、売り上げが減っているとかよく言われますが、閉店間際のお店にはずいぶんお客がいたりします。そんな様子を長く見ていることもわるくありません。ベートーヴェンのピアノソナタ、よほどのことがなければ、家にこれ以上増やすことは、もうないようにも思っていましたが、お店で聴いた個性的な演奏の割りに妙に気に入ってしまい、その結果家でも聴く事になりました。BGM:ベートーヴェン ピアノソナタ第23番 ヘ短調 Op.57「熱情」 ピアノ:ファジル・サイ 実は、ベートーヴェンのハ短調、ヘ短調の曲はどちらかといえば苦手な部類です。 32曲あるソナタのなかで、熱情ソナタは、聴かない順に並べたほうが 上に来るようなのが最近の自分自身の感性なのですが、 クールでスカッとするようなこのピアニストの演奏、すっかりはまっています。 ときどき想定外の解釈もありますが、それもまた楽しからずやです。 クラシックでは最近のレーベルでエイベックス。 「演奏という『行為』を超えた作品・作者との『神秘的合一』を思わせる」 とCDの背になる部分に長い能書きが書かれています。 熱情・ワルトシュタイン・テンペスト と順番に聴くこととします。 1970年トルコ生まれのピアニスト、シューマン音楽院、ベルリン音楽院に 10年近く学んでいたそうです。
April 27, 2006
コメント(6)
-
さしすせそ
「さとう」「しお」「す」・・・と、調味料のことで、「さしすせそ」というのは、私も知っていますが、コミュニケーションのことで、「さしすせそ」のことが書いてありました。ピアノレッスン前の、本屋さんでの立ち読みでの出来事。「さすが」「知らなかった」「すごい」「そうなんだ」・・・という合いの手をはさむことで、会話の潤滑油になるとか。今週号AERAの確か40ページあたりにありました。もし、そんなことばかり言っていたら、マニュアルどおりの人と、お察しくださいませ。22時にピアノのレッスンがおわり、練習室で引続きピアノを弾いていました。1回だけシューマンの謝肉祭を弾こうかとおもっていたのですが、最初の10分で、真っ青になりました。発表会がおわって、1ヶ月しかたっていないのに、ぜんぜん弾けません。ご縁があって、来週の日曜日も、そのまた次の日曜日もベーゼンドルファーのピアノで弾かせていただける機会があるのに、これでは・・・とおもい、1時間と少し、23時過ぎまで、練習することにしました。納得したかといえば、どうだかという感じですが、気づいてよかったというのが正直なところです。少しでもいい状態になればと思っています。いずれにしても楽しみが増え、音楽三昧のGWに期待しております。***ご案内です。木之下晃写真展のお知らせDear Maestros ~写真と自筆が語る世界の音楽家たち~5/2から5/9まで 銀座4丁目角の和光ホールでおこなわれます。トーク&サイン会は5/6 PM3:00から指揮者やピアニストとか写真をずっと取り続けておられて、音楽の友とか、各音楽雑誌などで連載されているのでご存知の方多いかと思います。木之下さんとは、3年ほど前から、ちょっとしたきっかけで親しくさせていただいていて、今回案内状をいただきました。(リッカルド・ムーティが指揮している絵葉書で)ご興味ありましたら、ご来場お願い申し上げます。BGM:バッハ コラール「心より われ こがれ望む」 BWV727 オルガン:マリー=クレール・アラン
April 26, 2006
コメント(12)
-
嘆き、または美女と夜うぐいす
ちょっと今日は早い目に会社を退社して、(といっても18時過ぎですが)気晴らしにCDショップと本屋さんをはしごしていました。銀座のCDショップでは3Fと5Fがよく行くところ、毎月定期的に行って、ある意味、定点観測しているのかもしれませんが、新譜が出たり、季節が変わってもずっと置き続けてあるCDがあったり、お店が押しているCDを眺めたり、来日記念のCDを見たり、いつものように「ぶらあぼ」というフリーペーパーをキープしたり、サンプルCDを聴いたりといった感じです。数日前に聴いていたムター(vn)の新譜があり、モーツァルトイヤーにあわせて室内楽のCDが目に留まりました。去年の秋のコンサートで感動した庄司紗矢香さん(vn)のメン・チャイのヴァイオリン協奏曲と、今年の秋のコンサートのチケットがとれれば聴きたい、内田光子さん(pf)のベートーヴェンの後期ソナタも気になりましたが、夏にまとまったお金がはいったときにしようと見るだけにしました。ムターのモーツァルトのピアノ三重奏は、旦那さんのプレヴィンがピアノを弾いているので、モーツァルトが聴ける状態になったら聴こうと思い、このCDと、先週グラナドス作品のCDを聴いて、家にないものはまだまだあるので、ラローチャ(pf)が演奏しているCDと、この日はこの2枚にしました。本屋さんは、7月2日の試験用の問題集を探しました。銀座4丁目の本屋さんは、資格用のコーナーが???だったので、結局、銀座線を一駅のり、京橋から徒歩5分、八重洲の本屋さんへ。1Fにある二宮金次郎の銅像は今日も光っていました。肩こりが激しく、頭も重かったので、近くのクアハウスでのんびり過ごして帰宅しました。せっかくなので垢すりもしてもらい、リフレッシュしました。BGM:グラナドス ピアノ組曲「ゴイェスカス」より 第1部 IV: 嘆き、または美女と夜うぐいす ピアノ:アリシア・デ・ラローチャ しばらくはこういう静かな曲を聴いているほうがいいのかもしれません。 こんなタイトルでエッセイが書きたいものですが、 タイトルだけ借用することにします。 ラローチャの演奏2回聴きにいったことあるのですが、 ショパンの幻想ポロネーズと舟歌のイメージが強く、 もっとスペインものを知って聴きたかったです。 引退されてしまいましたが、お元気でいつづけていただきたいです。
April 25, 2006
コメント(4)
-
f-moll
あと4日会社へ行けばと、気分的なもので、そう考えてしまいます。今月は新しく立ち上がった部署にいるため、やたらと決め事も多く、去年の引継ぎ業務と平行してやっていたりするので、ちょっとたいへんだったりします。それよりも今までやっていなかった領域の仕事をすることになったので、疑心暗鬼、なんとかマスターしなければということもあって、結構神経を使ったりしています。明日は本屋さんへ行って7月上旬の試験問題のテキストを買いに行こうとか、思っています。まじめに法律の勉強とか民法の一部分を解釈できるようにならなければ。今年はやはりターニングポイントになる年になりそうです。今日はきのうまで聴いていたモーツァルトがうけつけられない。無事に今週が過ごせて、早く音楽三昧の来週にならないかと楽しみにしています。BGM:シューベルト 即興曲 D935-4 f-moll ピアノ:エリソ・ヴィルサラーゼ このCDには、さすらい人幻想曲もはいっているのですが、聴いていません。 今日はこの曲が、やたらと聴きたい感じです。 19番のソナタかどっちかというような状態でしたが、この曲が繰り返しで 聴いている状態です。 ときどきこういう日が来るのですが、そういう日もときにはあるものです。 1年くらい前に、ブログとかミクシィで知り合った音楽関係の人に 教えていただいたCDです。 あとでわかった話しですが、ショパンコンクールの1次予選までいった 生徒を指導していた方ですので、不思議な世の中に感謝しなければいけません。 F-Durは、平和で暖かく包み込むような曲調をイメージしますが、 f-mollは、静かに孤独になりたいときは、この調なのでしょうか。 なんとなくそんな感じがしています。
April 24, 2006
コメント(4)
-
ヴァイオリンソナタ
どんよりと曇った1日、あんまり外へ行く感じにもなれず、ほとんど家にいました。昼間、なんとなくテレビをつけていると、明石屋さんまの番組のエンディングモーツァルトの2台ピアノのソナタだったりして、ちょっとうれしくなったりします。カレンダーをみて、来週人前ピアノを弾くことが、1回、2回、3回・・・。ということが間近にせまっていることも実感して、さすがに練習しなければという気になりました。3月末、ピアノの発表会にだした曲をもう1-2度弾ける場があることはありがたいです。弾ける曲を維持させるのはたいへんなことですが、せめて1ヶ月でも引っ張れるということは、こういうことでもないとむずかしいでしょうね。ピアノの練習以外に、1ヶ月半ほどたまった日経新聞の整理をしていました。読み飛ばしているものもずいぶんあるもので、読書タイムにもなりました。2月25日の記事で、世界の人口が65億人になっていたことも知りました。1位中国13億 2位インド11億 3位アメリカ2.9億4位インドネシア2.2億 5位ブラジル1.8億 6位パキスタン1.5億7位ロシア1.4億 8位バングラディッシュ1.3億 9位ナイジェリア1.3億10億日本1.2億私が地理の授業で習ったころは日本は7位でした。記憶が正しければ、ロシアはソ連から国が分かれたため2億だった人口が減り、日本はバングラディッシュ、ナイジェリアに抜かれました。これ以上順位があがることはどうやらなさそうです。4月の「私の履歴書」というコーナーは宮沢喜一元首相で面白かったので読んでいました。ほとんど昭和史と戦後史の勉強になりました。昭和26年サンフランシスコ講和会議で日本は再び独立するのですが、このときにサンフランシスコに行ったなかで、宮沢さんだけが現在での生き残りだそうです。(現在86歳)、特に戦中戦後のつらい時期での語り口は説得力がありました。この特集は4月末まで続きますので楽しみにしています。BGM:モーツァルト ピアノとヴァイオリンのためのソナタ集 ソナタ33番 ヘ長調 K.377 ソナタ27番 ハ長調 K.303 ソナタ28番 ホ短調 K.304 ソナタ42番 イ長調 K.526 ピアノ:内田光子 ヴァイオリン:マーク・スタインバーグ とにかく今日はここちよくなりたいです。 金曜日のテレビ番組の影響か、脳がおだやかになるといっていた音楽聴いています。 内田さんのピアノ、主張がはっきりしているのですが、音が優しく聴こえます。 このCDはたぶん1日中繰り返して聴いていても大丈夫です。 9月に日本公演があるので、16日のモーツァルトプロか18日のベートーヴェンプロの どちらかには聴きたいところです。その1週間前のサイトウキネンオーケストラの競演も 楽しみです。いずれも5月下旬のチケット争奪戦の日に忘れていなければ、ということが 前提になります。
April 23, 2006
コメント(2)
-
♭♭♭♭♭♭ と <sf
ハワイ・グアム・バンコク・ソウル・バリ島・セブ島・パリ・香港・・・。今年のGWの人気渡航先トップ8だそうです。(H.I.S)この時期らしいアンケートの回答ですが、パリの人気はあらためて高いようです。リゾート地はほとんど私自身旅行したことがなく、上記のなかでは、バンコク・ソウル・パリへいったことがありますが、夏か冬のどちらかです。5月のGW,一度だけヨーロッパ(ベルリン)へいったことがありますが、その前後はたいへんなものがありました。仕事の調整をつけるのがたいへんで、最近はもっぱら国内のどこかでのんびりしています。**限定された期間、休みの並びがいい今年なのですが、月初の5/2にせいぜい休みにしたいと思っているくらいです。それから東京国際フォーラムでの熱狂の日のコンサートが5/3-6まであり、チケットをキープした1月中旬に、はやばやと東京のあたりにいることを決めてしまいました。いずれにしてもモーツァルト三昧になるでしょう。5月6日の朝10時と夜9時半のコンサートが特に楽しみです。中途半端に間があきすぎるのですが、そのあいだなにしようか、ショートトリップしてみるのもいいかもしれません。BGM:シューマン 3つのロマンス op.28 ピアノ:マリア・ジョアン・ピリス 同じCDには、森の情景(op.82)、アラベスク(op.18) ウィーンの謝肉祭の道化(op.26)がありますが、お気に入りです。 op.26の4曲目の間奏曲を最近練習しています。 たった2分半の曲ですが、この時期にはあっているように感じます。 内声の細かいテンポのなかで、メロディが浮かび上がればいいのですが むずかしいです。 <sf、いきなりクレシェンドでスフォルツアンド、 5-5と小指で、これを表現するのは、かなり練習しないといけません。 ♭が6つで、転調もそこそこあるので楽しめますが、譜読みも苦労します。
April 22, 2006
コメント(6)
-
トルコ風
「たけしの誰でもピカソ」という番組でモーツァルトを紹介していました。ピアニストが管弦楽奏者がオペラ歌手がそれぞれのジャンルから5分で説明していたのは、おもしろかったです。ピアノでの5分の説明では、「きらきらぼし変奏曲」のヴァリエーションの組み立てのすばらしさにますます興味を持ちました。右手が和音、左手が和音、追いかけっこをする、序曲になる、暗くなる、超絶技巧になる・・・など、テンポのいい説明でした。セレナーデ11番、交響曲40番、クラリネット協奏曲、フィガロの結婚からのアリア、ピアノ協奏曲21番、番組の構成がしっかりしているのと、音楽がここちいいのと、今週はちょっと疲れ気味でしたが、ほっとさせられました。脳の動きが聴いていて安定するのはト長調のヴァイオリンソナタ、だそうです。今日はやっぱり疲れているので、ヴァイオリンの音で楽しみます。BGM:モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」イ長調 K.219 ヴァイオリン:アンネ・ゾフィ=ムター 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 年がほとんど同じのこのヴァイオリニストは、やっぱり好きでして、 過去3度ばかりコンサートにも行ったことあります。 冴えわたったクロイツェルソナタに、雨の歌に、感激しきったこと忘れません。 CDではこのモーツァルトとブラームスのヴァイオリンコンチェルトは特によく聴きます。 8年ぶりに東京に来るそうですが、チケットが倍近くになっていて驚きました。 それくらいのステータスになられたのだろうと、思うことにしておきます。
April 21, 2006
コメント(4)
-
ガレージセールからのたからもの
毎年4月に部署移動があったのち、フロアが変わったり、引越し作業があるのですが、そのとき、書架を移動しなければならないとき、本のガレージセールがあったりします。物持ちがいい人が担当だったりすると、派手にはしないのですが、行き先のフロアのスペースが小さくなったりすると、強引にでもものを捨てていかないとおさまりがつかないこともあります。今回はそんなこともあり、書架にある本を期日までに持って帰るようにとかいわれました。これという本は、会社の経費で買った本かもしれないものもいただいて帰りました。さっき斜め読みをしているのですが、感銘をうけた箇所があるので紹介します。「上司の哲学」江口克彦著 PHP文庫より・・・熱意なきところに成功なし の項「成功を収めていくには、何段階かのプロセスがある。まず最初は願望から始まる。何がしたいという願望からすべては始まるのである。次にその願望を、単なる願望から目標に変える。そしてその目標を達成しようと決意するわけである決意したら今度は行動へ移す。そして実行したらそれを継続していく。これが夢の実現へのプロセスなのである。そしてこのプロセスに絶対に必要なのが熱意だ夢をなんとしても実現したいという願望が、願望を目標や決意へと変えていく。熱意があるからこそ実行へ移し、継続していくことができる。夢を夢で終わらせるのか、夢を現実の成功へと導いていくのか、その差はただ一つ、熱意を持っているかどうかのである。」著者の江口氏は松下幸之助の晩年の22年間薫陶を受けられた人です。書いてあることは当たり前のことのようでも深いものが多いです。この本の最初に、「すべての人を自分より偉いと思って仕事をすれば必ずうまくいくし、とてつもなく大きな仕事ができるものだ」 ---松下幸之助とありました。今日は少し前向きになれそうな日でもあります。BGM:グラナドス スペイン舞曲集 「アストゥリアーナ」 「アラベスカ」 詩的なワルツ集 ピアノ:アリシア・デ・ラローチャ すごく気に入ってしまいまして、今日も聴いています。 燦々と照らす太陽のもと、歩いてみたくなりました。
April 20, 2006
コメント(0)
-
オリエンタル
東京メトロガイド5月号のフリーペーパーより、「展覧会で知的に過ごす」ゴールデンウィークをアカデミックに過ごせる・・・という文字面にぐらっときてしまいました。藤田嗣治展(東京国立近代美術館) 上野 生誕120年を記念した展示会プラド美術館展(東京都美術館) 竹橋 スペインの誇り、巨匠たちの殿堂東京-ベルリン ベルリン-東京展(森美術館)六本木 19世紀末からの日本とドイツの文化交流変遷備忘録のように書いてしまいました。去年も確かGWのさなか、テレビでゴッホの特集を朝みて、夕方にゴッホ展に行き、「夜のカフェテラス」に感動しましたが、あいかわらずの行動パターンなのかもしれません。いかに混まない時間帯にいくのか、また考えてみることにします。あわてず、はしごせずに、ゆっくり出かけたいです。BGM:グラナドス スペイン舞曲集より オリエンタル・アンダルーサほか。 今日は違った気分です。 ピアノ:アリシア・デ・ラローチャ スペインは行きたい国なのですが、まだ旅行していません。 以前迷ったあげく、ポルトガルのリスボアへは立ち寄りました。 会社の近くにスペインクラブという料理屋さんがあり、 せいぜいお茶を濁しているという感じです。 スペインもののピアノ曲、ひとつも弾いたことありませんが、 今の路線から少しかえてみるなら、このあたりも・・・という感じです。
April 19, 2006
コメント(12)
-
純情きらり
NHKの朝の連ドラ。最近は時計代わりに見ています。土曜日にまとめて見ていたときもありますが、たぶん今年は最後まで楽しみにしているでしょう。ピアノとか音楽がテーマなのでなおさらです。朝からチェロの音色もいいです。音楽の道をすすみたいとあれくらい勇気を持っていうことは今の時代も何倍もたいへんだったことでしょう。滝廉太郎の「花」、私は毎朝、春のうららの隅田川を横目にみて、会社へ行っているので、ジャズバージョンだったりの演奏も楽しいものでした。今はハノンの練習が多い週ですが、せめてクレメンティのソナチネが聴きたいです。***朝ドラ/10年間さかのぼってみると・・・2006 純情きらり2005 ファイト/風のハルカ2004 天花/わかば2003 こころ/てるてる家族2002 さくら/まんてん2001 ちゅらさん/ほんまもん2000 私の青空/オードリー1999 すずらん/あすか1998 天うらら/やんちゃくれ1997 あぐり/甘辛しゃん1996 ひまわり/ふたりっ子昭和のはじめを背景にしているのは、あぐり、すずらん、それ以来になりますね。ちょっといろいろ振り返りたくなりました。テーマ音楽のCDを唯一もっているのはあぐりです。戦時中を通り越しての舞台、脚本ではパーマ屋さんで最後はひとりだけでできるお店をつくった主人公のあぐりは、生き方に共感しました。実在する人だけに説得力を感じました。すずらん、「あしもい」という駅の駅長さん役のお父さん役がかっこよかったです。炭鉱現場のドラマとか、もう今は作れない作品のように感じます。ふたりっ子は、徹夜明けに、お客様のコンピュータ室のとなりのテレビで見るのが楽しみでした。この頃は苦戦つづきの仕事のなか、将棋の盤とにらめっこしていました。オーロラ輝子さんもよかったですが、ずいぶん励まされたドラマでした。私の青空、シングルマザーの子育てと伊藤四郎さんのおじいさん役との掛け合いに涙ぐんだことあります。 内館牧子さんの脚本、お見事でした。オードリー 大竹しのぶさんの、椿屋旅館、「今日は全館満室です。」という言葉、いまでも耳に残っています。こころ、浅草を舞台にした花火を見るのが楽しみでした。スチュワーデスから実家の食堂を手伝う主人公はファンでした。お母さん役のキャンディーズ伊藤欄さん、離れて暮らしたお父さん役の寺尾聡、キャスティングの妙が冴えていたようでした。てるてる家族、途中からはまりました。フィギュアスケート、のちの石田あゆみさん、のお姐さん2人を育てたパワフルなお母さんに元気をいただきましたが、ほのぼのとした冬子役の人柄に共感しました。ファイト、主題曲がピアノ協奏曲になっていてピアノが主人公をあらわしているときき、この音楽が大好きでした。馬のおはなしでもあり、サイゴージョンコという馬を一緒に応援していました。風のハルカ、湯布院、温泉の背景のすばらしさと、ばらばらになった家族でもひとつになれるというテーマは、今の時代に一石を投じたようにも感じました去年の2つのドラマはどちらとも見ごたえあってよかったです。***朝の連続ドラマは、1964年からはじまり、1966年の3作目の「おはなはん」というドラマでブームになったといわれています。まったく記憶がないのですが、私が小さいとき、おもちゃのピアノで、この主題歌を聴きまねで弾いていたのに、親がおどろいて、4歳のとき、私をオルガン教室に連れて行くきっかけになったと、ずいぶんあとになって聴かされました。今年の朝ドラをみていて、そんなときのことを思い出してしまいました。
April 18, 2006
コメント(9)
-
アマデウスと与謝野晶子
モーツァルトと与謝野晶子、与謝野鉄幹をテーマをした新聞記事がありました。日本経済新聞4月17日夕刊文化欄、「こころの玉手箱」より、与謝野馨(かおる)経済財政・金融担当大臣の映画アマデウスの感想と、それにまつわる祖父母のおはなし。映画「アマデウス」で比較の対象となるモーツァルトとサリエリ、天才といわゆる普通の人との対比、一日30首の短歌を楽々詠むことができた晶子と、一首詠むこことがやっとだった鉄幹を重ね合わせています。与謝野晶子は、家事・子育て・家計のすべてを担って、天才的な芸術の才能を振る舞いますが、与謝野鉄幹には、巨大な才能に向き合える人間としての魅力と、人と人を結びつける周旋に長けたとか。政治家を長くつづけられた与謝野大臣は祖父に近いものと感じられているかのようです。「人間の才能の発露は複数形であること、釣りあわない才能が反発しあったり引かれあったり不思議なものこそが人間の本質」と。***22時からはテレビ東京で、トヨタ自動車の張副会長と、村上龍との対談番組に興味をひきました。終戦当時、創業8年目でお金も設備もなにもないところで、欧米と立ち向かわなければいけなかった自動車メーカーの当時のお話は迫力ありました。そういうところを基盤にいまのカルチャーがあることに感動しました。成果主義に否定的で適材適所な人材配置することで、マネジメントの問題を指摘するあたりはうならされました。人には必ず長所があるはずで、そういうところを探すようなことをしていきたいものです。いろいろ考えさせられました。与謝野鉄幹の新聞記事をもう一度見直して、また考えさせられました。BGM:メンデルスゾーン 2台のピアノの協奏曲 ホ長調 カティア&マリエル・ラベック フィルハーモニア管弦楽団 指揮:セミヨン・ビシュコフ ほとんど家にうもれていたCDで、いつ買ったのかも覚えていません。 メンデルスゾーンも好みが分かれる作曲家ですが、 歌のあるやわらかい旋律は癒されること多いです。
April 17, 2006
コメント(2)
-
ピクニックコンサートを聴きながら。
ベルリン・フィルのピクニックコンサート、先日もBS2で見ましたが、フレンチプログラムはたいへん楽しいもので、今晩も聴いています。BGM:プーランク 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 サンサーンス 動物の謝肉祭 (ピアノ:ラベック姉妹) ラヴェル ボレロ 指揮:サイモン・ラトル ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団***今週末は、ピアノを弾く時間が少しとれましたので、いろいろ譜読みをしたり、3月までの弾いていた曲を練習しなおしたりしていました。いずれにしてもモーツァルトとシューマンにかなり偏っていますが、この組み合わせは結構気に入っています。2ページから4ページまでの曲を組み合わせて、夏ごろまでは、このペースですすめていくのでしょう。****一日家にはいないで散歩したかったのと、地下鉄のポスターで気になっている展示会があったので、葛西にある地下鉄博物館で、家の近くを走っている路線の移り変わりを知ることになりました。(日比谷線と東西線がテーマ)やはり自分が生まれたころの昭和40年代の展示、たいへん興味を持ちました。銀座線と丸の内線は、パンタグラフがなく、日比谷線、東西線、千代田線は、郊外からの私鉄との乗り入れを計画時に念頭をおいたもので、パンタグラフがある電車をという、日ごろ気づかないこともありました。昭和41年当時の路線図。こんなかわいらしいものだったのかという印象です。大手町には、まだ丸の内線しか駅がなく、表参道は神宮前という駅だったり、東西線が開通したことで、「陸の孤島」と呼ばれていた江東区に初めて地下鉄が通るという大きな新聞の見出しもありました。このころの基盤があっての今の東京なのだと、あらためて実感しました。****いろんな国を旅行して、地下鉄もずいぶん乗りました。パリのメトロはオシャレで洗練されていて、ドイツでのミュンヘン・ベルリンでは、何本もの路線が中心部の6駅くらい全部とおるような設計になっていること、ロンドン・ウィーンは駅がきれいだったこと印象に残っています。(ベルリンフィルの演奏を聴きながらなので・・・)ベルリンは、1993年に旅行したとき、西と東の地下鉄がようやくつながったと街の人に紹介してもらいました。ブランデンブルグ門を境に街の雰囲気がぜんぜん違い、まだ一つの国が一緒になったとはいえ、しっくりいっていないのかという強い印象もちました。その近くに森鴎外が住んでいたところとかがあり、「舞姫」の舞台になっているところの展示とか印象に残っています。
April 16, 2006
コメント(2)
-
トマト
知り合いの知り合い、友達の友達・・・ここ1年と少し、ブログとかミクシィのようなネットワークにかかわっていて、今だからできるような人のかかわり方に実感しています。楽天日記とかでは、ミクシィのように知り合いの知り合いという感じで表示されていませんが、相手方のブログのリンク先をたどって、他のブログへ行き、知り合いになった人もそれなりにいたりします。飛行機でトランジットするとき、ハブとなる空港があるといわれますが、そんなイメージのページやブログもあったりして、お世話になる方にただただ感謝するばかりです。そんなこともあってか、もう何年もあっていない人からメールがくるようになったり、集まりがあるとき、思わぬところから共通の知り合いの人がいることがわかったり、世の中が狭いのか、視野が広くなったのか、不思議なことがあったりします。昨日は「トマトたんめん」というものを食べる会にうかがいました。西新宿にあるこのレストランにはベーゼンドルファーのグランドピアノがあって、主催される方とかマスターは存じ上げていましたが、共通の知り合いで、私が学生時代馬術というスポーツをやっていたとき、となりの大学の2年先輩だった方に20年ぶりくらいにお会いできました。20年前にタイムスリップした感じで、今はいつなのかと談笑のなかで感じました。ピアノを弾いてほしいといわれたので、シューマンの謝肉祭op.9から、「告白」「プロムナード」という曲を演奏しました。マスターが演奏する「月光ソナタ」の1楽章、深夜のレストランでの音の響きは、すばらしかったです。オンラインとオフラインのコミュニティ、今後どうなっていくのかという気もしますが、自分自身かつて仕事でやっていたテーマでもあったりするので、誠実にかかわっていきたいです。トマトたんめん、自分でつくれませんが、今日もトマトをいただきたくなりました。
April 15, 2006
コメント(4)
-
振るマラソン
生涯指揮者・岩城宏之の挑戦というテレビ番組をさっきまで見ていまして感銘を受けました。子どものころ「オーケストラがやってきた」という番組を日曜日に見ていて、よく登場される指揮者のひとりでしたが、いまや73歳となりました。1日でベートーヴェンの交響曲9曲を全部演奏する、「振るマラソン」と称しているそうですが、曲にまつわる印象、インタビューなど楽しいものでした。NHK交響楽団が1960年に世界一周で演奏会をしたときに27歳で指揮者に抜擢され、ほとんどの演奏会で指揮されたとか、いまではほとんどありえない話ですが、運というかめぐり合わせのよさを感じたりしました。そのあと、カラヤンという指揮者に師事されていますが、今日のインタビューでは、カラヤンから「(指揮は)ドライブでない、キャリーだ」といわれたお話、世の中のいろんなことに通じるものだと共感しました。いずれも馬に乗ってたずなを持っている人のたとえ話ですが、ドライブというのは、たずなを強く握り締めて、馬へあっちへ行けこっちへ行けと命令して、馬を誘導する、馬は面白くもなんともないかもしれないがとりあえずついていくということ、キャリーというのは、たずなを伸ばした状態で、馬が好きなような方向へ行って興味のもつようなことを好きにやらせるが、実際は乗り手が、うまく操縦していくこと、ざっとそんなお話でした。かつて私も馬術というスポーツにかかわったことがあるのですが、障害物を鞭をたたいて飛ばそうとするのではなく、喜んで楽しんで馬が障害物を飛ぶように誘導しなさいと、指導していただいたことありますが、共通しているようにも思えます。単に指揮者とオーケストラの関係にとどまらず、企業社会のなかでも、一般家庭のなかでも、そうあるべきなのかもしれません。マクレガーのX理論とかY理論とか、社会心理学とかモチベーション理論とか、本を読んだことがありますが、カラヤンがいうドライブがX理論で、キャリーがY理論なのでしょうか。かなり当を得たおはなしにも聴こえました。さて、岩城宏之さんのベートーヴェンの交響曲、8番がいちばん好きというのも、なんだかいいなあという印象もちました。そのことばだけで演奏聴きに行きたいという衝動にかられました。なんだか波長があいそうです。8番の交響曲、構えず気軽に聞ける曲でして、ほのぼのとした面がたくさん現れていますから。毎年年末に池袋の東京芸術劇場で催されているようです。詳しくは知らないのですが、一日でまとめて交響曲9曲生演奏を聴くのも楽しそうです。BGM:マーラー 交響曲第7番「夜の歌」 指揮:クラウディオ・アバド ルツェルン祝祭管弦楽団 2005年ルツェルン音楽祭 (テレビを見ています。)
April 14, 2006
コメント(0)
-
ヴァリエーション
紹興酒を今日はたくさん頂いて、新しい部署の発足式というかキックオフの宴会がありました。中華料理はおいしいです。チームワークのよさそうな組織に今年は恵まれればと感じております。以前、中国に駐在していたとか、思い出したように言ってくださる人も何人かいますが、お店の人とは片言の中国語しか思い出せずに、10年も遠ざかってしまうと、記憶力は途方もなく限られたものになることを思い知らされました。なにかのきっかけではじめたことも、細々とでも続けなければと、もうちょっとでピアノを再開して8年たつことも思い起こしました。ここまで生活のなかに入り込むとは思いもしませんでした。いろんな変化の中で好みもちがってきたり、年相応の音楽が聴きたくなったりです。「自然体」というある人から助言されたことばを好きで、意識することが多いのですが、そういう振る舞いができればと感じます。モーツァルトを今年は好んでよく聴きますが、聴けているときは、精神状態が比較的安定しているということも、長く聴いていてわかっているのでそれはいいことだと感じております。以前それほど興味をもたなかったものにも、新たに発見があったり、譜読みも少しは早くなったりで、ちょっと弾いたり、楽譜を見たり、楽しみも多いです。変わり身の多い、ヴァリエーション(変奏曲)とかロンド形式の曲は、もとから好きなのですが、今日はそういう音楽を聴いています。BGM:モーツァルト フランスの歌「美しいフランソワーズ」による12の変奏曲 変ホ長調 K.353 デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲 ニ長調 K.573 ピアノ:ワルター・ギーゼギング
April 13, 2006
コメント(4)
-
祐天寺と大奥
「その時歴史が動いた」という番組は、丁重なアナウンサーの語り口と共に、知っていそうで知らない切り口で、歴史を掘り下げることで、うならされることもしばしば。家にいれば見るという感じでしたが22時台に変更になったようで、うれしい限りです。モーツァルトのソナタをpppで弾きながら、お話を聴いたり、ちょっとピアノの手を止めてテレビを見たり、そんな小一時間でありました。今日のテーマは、大奥。少し前にやっていたフジテレビの大奥というドラマも好きでしたが、六代将軍のあたりかたのお話、秩序が乱れたところを立て直す六代将軍の正室の天英院、八代将軍吉宗を次期将軍に指名することとは、知りませんでした。七代将軍は4歳で将軍になったあとの立ち振る舞い、こんなお話を高校の日本史で聴いていたら、もっともっと興味をもったかもしれません。せいぜい新井白石が政治の表舞台にいたことくらいしか、この時代は、授業でもお話を聴けていないような感じがします。八代将軍吉宗が将軍に指名されたときが、1716年だとか。これが今日のその時のようでした。「モーツァルトの生まれた40年前か」と、またこの大作曲家を基準に物事を見てしまいました。このころのゆかりのあるお寺として、目黒の祐天寺が紹介されました。桜が満開の頃、こういうところへもふらっと出かけてみたいです。http://meguroku-net.com/meisyo/yuutenji/yuutenji-Top.htmあと3週間ほどで、東京に住民票の登録して、ちょうど10年になりますが、まだまだ行ってみたいところはたくさんあります。BGM:モーツァルト メヌエット K.365 ピアノ:ワルター・ギーゼギング (これからこれは聴く予定。 さっき上記番組のあとに、荒井由実さんの「魔法の鏡」、 ♪これがさいしょでさいごの・・・というフレーズ聴き入ってしまいました。)
April 12, 2006
コメント(2)
-
メヌエット
きのうのコヴァセヴィッチさんがアンコールで弾いたモーツァルトの初期ソナタの緩徐楽章、はまってしまいました。今日はそのソナタを聴いています。BGM:モーツァルト ピアノソナタ第4番 K.282 ピアノ:フリードリッヒ・グルダモーツァルトのソナタは、それなりにひととおり聴いていますが、なんだか改めて曲のよさに発見するときがときどきあります。昨日聴いた緩徐楽章のメヌエットは自分の今の感性にフィットしていたのかもしれません。15年ほど前コンサートのアンコールで聴いたヘ長調K330の緩徐楽章も今日みたいな気分になったし、(←このときは内田光子さん)10年ほど前池袋のCDショップでニ長調のK.311の緩徐楽章を聴いたときもこれはだれが弾いているのだろう(←このときはピリス)という感じで聴き入ってしまいました。2ヶ月ほど前に聴いたモーツァルトのコンサートでもK.533+494のロンドがものすごく気に入ってしまいました。(←このときは三輪郁さん)曲全体というより、この楽章という感じで急に気に入ってしまったりします。何がきっかけで急にこの曲弾いてみたいということになったりするのかわからないときがありますが、足をはこんですばらしい演奏に出会えることを楽しみ続けたいです。5月初旬、東京国際フォーラムで催される「熱狂の日」でもK.282は行くコンサートの中のプログラムに入っていて、ますます楽しみになってきました。
April 11, 2006
コメント(4)
-
コヴァセヴィッチ ピアノ・リサイタル
静かなる巨匠。比類ない境地に達したベートーヴェン、シューベルト案内のちらしにはこのように書かれていました。スティーヴン・コヴァセヴィッチ ピアノ・リサイタル (東京オペラシティコンサートホール)ベルグ ピアノ・ソナタベートーヴェン 6つのバガテル op.126より 第1番・第2番・第5番・第6番ベートーヴェン ピアノソナタ第28番 イ長調 op.101***シューベルト ピアノソナタ第21番 変ロ長調 D960(アンコール)シューベルトの小品(曲名わかりません)モーツァルト ピアノソナタ第4番 変ロ長調 K.282より 第2楽章 メヌエット******はじめて聴くピアニストでした。力強い演奏とクリアで明るい音色が印象的でした。重厚というより、ちょっと軽い感じにも聴こえました。シューベルトのソナタ、第1・第2楽章、もう少し陰影のある音を聴きなれているせいか、よく聴くCDとか違った雰囲気、その分3楽章・4楽章は軽やかで心地よかったです。メインで演奏された大きなソナタより、6つのバガデル、アンコールの2曲のほうが印象に残りました。バガテルは、全曲演奏をできたら聴きたかったです。op.126-4のプレストは自分自身好きな曲なので、省略されて残念でした。ホールのなかで若いときに録音したバガデルのCDが売られていました。きっと好きでずっと弾かれているレパートリーなのでしょう。モーツァルトは心配りのあるチャーミングな演奏で、軽やかなメヌエットには心があらわれました。ちょっと重めの曲のあと、なかなかの選曲だったように思います。帰り道は、モーツァルトのメヌエットの演奏が頭のなかをぐるぐるまわっていまして、 「楽譜を見てみたくなりますね」と帰り道ご一緒した方とお話したとおり、家に帰ってすぐ楽譜を見てしまいました。**コヴァセヴィッチさん、東京のこのコンサートのあと、九州へ行かれ、別府と大分で催されるアルゲリッチ音楽祭に出演されるようです。BGM: ベートーヴェン 6つのバカテル op.126 ピアノ:スティーヴン・コヴァセヴィッチ
April 10, 2006
コメント(4)
-
シンプルイズベスト
楽天日記ブログの入力方法がかわりましたが、シンプルイズベストがいいとおもっているので、単純な機能のエディタの方を選択することにしました。自分のおもった以上に改行されたり、ワードのように、勝手に数字をふられたりするのは、たいへん苦手で自分の思考にあっていませんので。それと変わることをあまり最近は好まなくなってきています。明日のオペラシティのピアノコンサートのチケットが取れたと思いきや、今日紀尾井ホールで聴くはずのアマチュアオケのコンサートを失念してしまいました。四ツ谷の土手を散歩したかったのですが、また紫陽花の季節にでも歩いてみたいです。また1週間がはじまります。いろいろ決め事の多い4月、しばらくは忙しいのかそうでないのかよくわからない感じがつづきそうです。明日は早い目に仕事をきりあげて、ベートーヴェンのバガテルとシューベルトのソナタを堪能できるようにしたいです。BGM:ショパン ノクターン 遺作 嬰ハ短調 ピアノ:小菅優
April 9, 2006
コメント(6)
-
5月になるまでの前奏曲
まったりとした週末で、ちょっと曇りの午後にピアノを弾くという普段どおりの日常に戻ってきました。カレンダーをみると、あと3週間もすれば、5月の連休。気が早いですが、先のことをつい考えてしまいます。今年はピアノウィークになりそうです。演奏会を聴きにいくか、どこかで自分でピアノを弾いている日かのどちらか。いつもは東京を離れているのですが、まったく風変わりになりそうです。「熱狂の日」というモーツァルトのイベントがあるおかげで、自然とそうなってしまったのかもしれません。コンサートは4月末のキーシンのショパンスケルツォ4曲、5月の熱狂の日は、朝10時からのコンサートで小菅優さんのモーツァルト初期ソナタ、午後3時ごろで、児玉桃さんのモーツァルト2台ピアノソナタ、夜9時半からの小山実雅恵さんのモーツァルトp協27番、変則的な開始時間もありますが、書いているだけで楽しくなります。いろんな方から情報をいただいたりしたおかげで、チケットをキープできてよかったと感謝しております。たくさん刺激をうけそうです。BGM: ショパン プレリュード op.28 ピアノ:小菅優 昨年コンサートにいくつか行って感動したもののひとつ。 サイン入りのCDはお宝です。 CDを聴きながら楽譜も一緒に見たくなります。 そんなことをしつつ、弾きたい曲が、自分の引き出しにたまることがあります。
April 8, 2006
コメント(2)
-
早くもカーネーション・・・
「英語でしゃべらナイト」が金曜日にやっている。・・・ということで、曜日の感覚がおかしくなってしまいそうであります。でもそれだけ気になる番組がいくつか残っていることは、立派だと思うのと、ますます発展していただきたいものです。キャスティングのすばらしさとよく練られた番組構成はさすがです。チャングムは金曜日から土曜日に変わっていることにも気付きました。以前、土曜日の深夜にBS2でクラシックの放送があり、中村絋子さんがN響アワーをやっていたころは、土曜日の9時だったのですが、今は、金曜日の深夜がBS2のクラシック放送で、日曜9時がN響アワー。週末の予定がすっかりかわってしまったことがあります。***母の日のカーネーションのプレゼント用のダイレクトメールが届きました。ようやくコートを脱ぐ季節になった感じですが、いろいろ季節感を感じるできごとが多くてありがたいです。数年前、サントリーホールでペライアのコンサートがあって、メンデルスゾーンの無言歌集とかヘンデルの調子のよい鍛冶屋を聴いた後、休憩時間にとなりにある全日空ホテルのお花屋さんで母の日のプレゼントを宅配便で贈ったことあります。開演前に衝動買いしそうになり、休憩時間にやっぱり気になってそうしました。4月といえば、ピアノのレッスン曲がかわる月でもあったりします。下の曲も気になるのですが、しばらくモーツァルトとかシューマンの静かな曲を弾きたい気分です。夏が過ぎれば気が変わりそうな予感です。BGM:バッハ=ブゾーニ 「主イエスキリストよ、われ汝に呼ばれる」BWV639 メンデルスゾーン 無言歌集 ピアノ:マレイ・ペライア
April 7, 2006
コメント(10)
-
小心者と花吹雪後のスケジュール
4月にコンサートへチケットをあらかじめ買っていくことがそういえば少ないです。今年になって4月のおわりに聴きに行く予定にしているキーシンのコンサートも、もっと行くことができる可能性が高い、4月29日土曜日、横浜みなとみらいの日を選びました。3月中旬から下旬よりも、予定が立てづらいときもあったりします。プロジェクトの発足式、新しい部署の顔合わせ会と称した飲み会、昨年度のインセンティブの表彰式・・・突然日程が決まり、唖然としたこともあります。かつて、4月の中旬に、どうしても行きたかったコンサートで1万円以上のチケット代を無駄にしてしまったことあります。もう10年以上前ですが、モントリオール交響楽団、指揮シャルル・デュトワ、このときは50人くらいの新しくできた部の発足式と重なってしまい、欠席する人がほとんどいないくらい結束が固くて、コンサートへいける状態ではありませんでして、本当にくやしい思いをしたことあります。実は結構小心者で、そういうことときどきありました。余裕もなく、pianoを習おうという発想すらありませんでした。コンサートを行きだした頃は、風邪で早く帰りますといって、アシュケナージのコンサートへ走っていったり(フェスティバルホールまで会社から走って3分)、歯が痛いので歯医者の予約をしているといって諏訪内晶子さんのヴァイオリンを聴きに行ったり、結構いろいろありました。旅行代理店の方からも4月の芸術週間のときに、ザルツブルグでいいプログラムありますよと、お誘いをうけたことがありますが、よほどのことがないかぎり、申し訳ないけどうかがえないんですと、会社のお仕事や日本の年度始めとは・・とか、事情をとくとくと説明してしまったことあります。来週は何もなければ、ふらっとピアノを聴きに行ったりしたいですね。BGM:フォーレ 夜想曲第6番 変ニ長調 op.63 ピアノ:フィリップ・アントルモン
April 6, 2006
コメント(0)
-
ストロベリー
今日は会社で大掃除というか大整理をしていました。最近は、セキュリティも厳しくなり、そういうことに関して会社ではお手本のようなことをしている部署でもあったためか、徹底していることも多いです。紙の書類はほとんどシュレッダーで、この機械は大活躍でした。それでは間に合わないくらい廃棄書類が多く、廃棄書類としてダンボールにいれ、廃棄業者に依頼することになっていて明日が、4月前半の該当日だったりしたので、今日はそんな資料整理しました。マル秘扱いの資料も多くかかえていて、こんなときでないとなかなかできず、それと、5年間事業部で仕事をしたなかで、今回は徹底して捨てようということで、段ボール10箱分くらいになりました。重要な契約書とかは、3年保存とか法で決まっていたりするのですが、逆算して、バサバサと捨てました。こんなとき何気なくやってきた業務でも、いろんな人がかかわって、いろいろな取り決めをして、プロジェクトを立ち上げて、採算計算をして・・・と、サインや印鑑や照査する部署の多さをみて、企業での営みの重みを思い知ったりします。BGM:モーツァルト クラリネット協奏曲 K.622 第2楽章 そんなわけで、ちょっとしみじみとした音楽が聴きたくなりました。 今日はモーツァルトが自分にはフィットするようです。 木管楽器は癒されます。 今週末が第1回目のオフィスのフロア移動(引越し) 来週末が第2回目のフロア移動。 29階建のオフィスビルにいるのですが、玉突きのように 例年移動します。だんだん昨年度のメンバーの人とは離れ離れに なり、ちょっと淋しくなったりするのもこのころ、 他の会社とは雰囲気がちがったりするかもしれません。 買い置きのいちごを頂きたくなりました。 今週はなんだか気疲れしているのか長く感じます。 ストロベリーのBGMにクラリネットはぴったりです。
April 5, 2006
コメント(4)
-
アンダンテ
4月のカレンダーJALのカレンダーはインドからスペインのアンダルシアへグラモフォンのカレンダーはマイスキーからヒラリーハーンへ4月になってしばらくたってからカレンダーをめくりました。3月の余韻が多かったということでしょう。2月3月が飛ぶような速さだったのですが、4月に入ってまだ火曜日か・・・というような感じです。これがいいことなのかそうでないのかもよくわかりませんが、通常モードに戻ったと思えば少しは気が楽になるのでしょう。歩くような速さで1日が過ぎればそれでいいです。年度が替わって、新しい部署になったり、仕事の内容が少しずつかわったり、毎年悲喜こもごもだったりということもありますが、今年も桜をながめながらいろいろ考えることも多いです。「いつまでも机があると思うな・・・」とか、きびしいことを言う方もいまして、今年はやはり転機の年になるのだろうと感じております。世の中そう甘くはありません。いろいろ勉強していないといけない1年にきっとなるでしょう。BGM;シューベルト さすらい人幻想曲 D.760 第2楽章 ピアノ:リヒテル さっき、ぱらぱらとCDをみていて、急に聴きたくなりました。 この曲に、ふらっと帰ってきたくなる不思議なところがあります。 もっとピアノが上手になったら弾きたい曲のひとつであったりします。 4ヶ月前に探してないないとさわいでいたポリーニのさすらい人は この前出てきました。 この曲もシューマン謝肉祭同様、 片手以上のピアニストのCDがあるようで、またいろいろ聞き比べたいです。
April 4, 2006
コメント(7)
-
アクセント・オン
和音の多い曲を弾いていた反動か、妙にシンプルな音楽を聴きたくなることもあります。昨日のお花見、九段下(千鳥が淵)か汐留(浜離宮)か、迷ったのですが、17時から、銀座7丁目の楽器店でピアノを聴きたくなったこともあったので、浜離宮の菜の花畑になりました。菜の花のあとは、浜離宮→銀座7丁目のお散歩つきでした。ギロックという作曲家を紹介するというテーマで、ウララ・ササキさんというピアニストの演奏を聴いていました。どれもこれも1分くらいの曲なのですが、童心に返れる感じがするのと、音符が少ないこともありますが、すぐ弾いてみたくなりそうな曲の数々でした。すっかり気に入ってしまい、発売されて間もないCDも買いました。この作曲家、名前くらいしか知らず、子どもの発表会で最近登場するので、気にはしていたのですが、結構いいですね。おとぎの国へ行っている感じです。BGM:ギロック アクセント・オン1(pf:ウララ・ササキ) (長調)ワルツを踊ろう/ピクシーズ(妖精たち)/ スケートをする子どもたち/陽気なスペイン 静かな湖で/ドラムとトランペット (長調と短調)サイドウォーク・ワルツ/風/お庭でダンス/ 古い時代の舞曲/キャリヨン(鐘)/風に舞う木の葉/ ほろ馬車/マズルカ/夏のきまぐれ/妖精のいたずら/ オリエンタル・ウインド・チャイム/紺碧の海/ スイスのオルゴール/ファラオ王の国 (黒鍵)ジェットコースター/スコットランドのバラード/ 陽気のワルツ/淋しい海/ブルースのスタイルで/ ショパンにささぐ/シャンゼリゼにて/バザール/ 黒鍵のエチュード/秋のワルツ 日本ギロック教会のご案内というちらしには、「ギロック(1917-1993)、メロディの美しさから、音楽教育界のシューベルトとまで称えられました」とあります。ウララさんは、子どもはもとより、大人でピアノを再開した人、子どものときピアノを弾きたかった人とか、接してほしい作品だと、インタビューに答えられていました。ピアノのレッスンに通う人以外、普通に音楽を聴く人に、もっと知られていい作品のような気がし、CDになってよかったとも思いました。3ヶ月前にバッハ=ブゾーニのシャコンヌのリサイタルされていたピアニストの引き出しの多さにも感銘をうけてしましました。
April 3, 2006
コメント(8)
-

菜の花さくら at浜離宮
今日4月2日の午後4時ごろの浜離宮恩賜庭園大雨になる2時間前、小雨模様での風景、上半分が桜、下半分が菜の花。 1/2の神話???この庭園の中へは初めて入りました。もちろん桜も見事でしたが、30万本といわれている菜の花畑。魅了されました。この庭園、もとは徳川将軍家の鷹狩場だったのものを、埋め立てて浜屋敷なる別邸を建てたのがはじまり。六代将軍の頃に、将軍家のものに「浜御殿」と呼ばれるようになり、十一代将軍のころ、現代の姿の庭園になったそうです。(バッハが生まれる少しまえが鷹狩場のころで、ショパンが活躍していたころが、たぶん十一代将軍のころ??なのでしょう。)浜離宮は、近くにコンサートホールがあったりしてよく通るところなのですが、また散策してみたいです。秋はコスモスでいっぱいになるらしいです。それにしても汐留地区の高層ビルのとなりにこんな静かな空間があるとは。BGM:シューマン 間奏曲 op.26-4 菜の花とか雨ふりのときの桜を見ていると、頭のなかになっていました。
April 2, 2006
コメント(8)
-
Since1986
勤続20年。昨日でついにこの日を迎えてしまいました。昔はそういうものに表彰制度があったり、記念品の時計をもらったりと、いろいろイベントもあったようですが、今はリフレッシュ休暇の権利がもらえたりしますが、せいぜいその程度です。20年前、おのぼりさん気分も半分ありましたが、上京したころ、東京の街のスケールに圧倒され、永田町駅の長いエスカレータに面食らい、あるいていると駅が赤坂見附に変わっているということにまたびっくりしたり、そんなことから始まりました。そのころ買った東京の地図、いまだに持っています。地下鉄の路線図(当時は営団地下鉄、今は東京メトロ)を見るのが好きなのですが、大阪や名古屋と違い、碁盤の目のようになっていない不思議さを感じますが、背景を知ると、納得してしまうこともありました。半蔵門線は、渋谷-半蔵門どまりで、今のように、東武動物公園までつながるとは、ちょっとどころかまったく想像できませんでした。有楽町線は、新富町が終点でしたし、晴海へはそこからバスへ乗っていました。地下鉄には空調設備のないものもまだあり、「窓開け」に協力してくださいという案内がありました。渋谷のハチ公前の改札口では切符きりのおじさんがまだいました。切符のきった紙くずが山のようになっていました。自動改札はそのころは大阪の方がすすんでいたのですが、当時のことを思うと、今はやはり信じられません。パスネットもJRのSUICAカードもすばらしい文明の利器だと感じます。アークヒルズができ、サントリーホールができたのもこの頃でした。そこからあまり離れていない、溜池の赤坂ツインタワーが仮配属の場所でしたが、溜池山王という駅ができるのは、つい最近のことで、最寄り駅は、赤坂、国会議事堂前、虎ノ門、六本木、どこから歩いても徒歩15分くらいで、交通の便はいいようで、結構歩かされました。3月末は、やたらと打上げや歓送迎会が多かったのと、そんななかでピアノの発表会があったりちょっとたいへんでしたが、節目の時期はやはり必要かと、多くの方と会話をするなかで感慨深いものもありました。お花見でもしながら、転機となりそうなこれからのことも考えて見ます。自宅近くの隅田川テラスの桜も見ごろです。BGM:ヴィヴァルディ マンドリン協奏曲 第1楽章 映画、クレイマークレイマーのテーマなので、 たぶん多くの方が知っている曲です。
April 1, 2006
コメント(12)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…
- (2025-10-26 11:00:38)
-
-
-
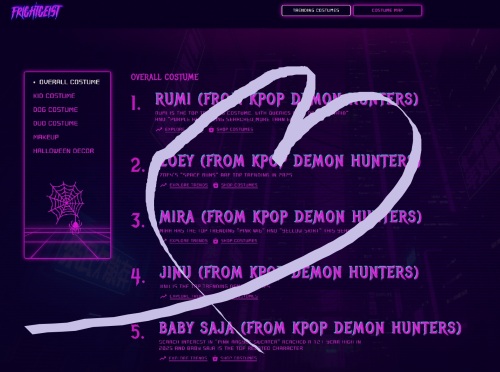
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …
- まんだらけの優待のまんだらけZEM…
- (2023-06-24 23:18:46)
-







