2010年09月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
こんな映画を観た~不知火検校
蠍座の企画「日本異端映画暗黒史」第1章の6作品に選ばれた1作。森一生監督の1960年作品。こういうのをピカレスク時代劇というのだろうか。悪人はこのところすっかり珍しくなくなってしまったが、ただ悪人というだけでなく、師匠夫婦まで手にかけて立身出世しようとするその上昇志向がすごい。そしてそのすごさを演じることができるのは、勝新太郎をおいてほかにはいなかっただろう。その意味で、この映画は稀代の名優である勝新太郎のすごさに舌を巻くためにあると言っても過言ではない。たとえば、病に苦しむ旅人を、治療めかして殺し、金を奪うシーンがある。善意と殺意の見分けがつかない、あるいは旅人が金を持っていると知り善意が一瞬で殺意に変わるあたりの演技は天下一品。善人なのか悪人なのか識別しがたい悪人ぶりはこのあとも次々と出てくるが、ある種ストイックなまでの悪人ぶりは芸術の域に達している。可憐な容姿と声で、若い中村玉緒が出演している。脇役もふくめてしっかりした俳優が揃っているが、やはりどうしてもこの二人に目が行ってしまう。こういうピカレスクもの、しかも救いのない悪人を描いた映画を人格形成期に観るのは大切だ。こういう映画を観たことがないと、オウムの麻原のような人間に簡単に騙される人間になる。
September 30, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~くノ一忍法
蠍座の企画「日本異端映画暗黒史」第1章の6作品に選ばれた1作。中島貞夫監督の1964年作品。倉本聰が脚本を担当したこの映画は、若干の映像美に見るべきものがある点以外、駄作だった。5人の女忍者と男忍者の対決という話だが、5人の女忍者が、魅力的ではあってもさっぱりエロティックではないのだ。演出がありきたりで、女性のセミヌードを見せればそれがエロティックだとかんちがいしている志の低さがその原因。女優たちの演技も一本調子で、むしろ男優たちの芸達者ぶりの方が目立つ。学歴で人を判断したくはないが、東大出が二人そろうとこういう映画になってしまうのかとうがった見方をしてしまう。とはいえ、この1作で判断せず「温泉こんにゃく芸者」など評価の高い中島作品はいつか観てみたい。
September 29, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~黒蜥蜴
蠍座の企画「日本異端映画暗黒史」第1章の6作品に選ばれた1作。深作欣二監督の1968年作品。この映画はソフト化されていない。江戸川乱歩原作で脚本は三島由紀夫。三島本人も蝋人形の死体役で出演している。丸山(現美輪)明宏の「美女」ぶりに圧倒される作品。古今東西、「彼女」ほど女性らしい女性、そして魅力的な女性がいるだろうかと思わず自問してしまうほど。マリア・カラスやブリジット・バルドーでさえ、彼女に比べたらいくぶんか「男」であると感じてしまう。叶姉妹など小娘にしか見えない。女賊である黒蜥蜴と名探偵明智小五郎が対決し、黒蜥蜴の明智に対する矛盾した恋愛感情が錯綜する文学の香り高い作品になっている。いささかゴシック趣味といえるグロテスクな映像美も見もので、これはやはり大画面で味わうべき映画だと思う。美点・欠点をあげろと言われれば数多くあげられるが、丸山明宏の魅力の前にはすべてがかすむ。女性らしさを身につけたいと思う世の「女性」たちはこの映画から学ぶべきだ。丸山明宏の10分の1も「女」っぽくはなれないだろうが。
September 28, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~猟人日記
蠍座の企画「日本異端映画暗黒史第1章」に選ばれた6作品のうちの1作。中平康監督の1964年作品。女性をモノにしてはそれを日記に書いているエリートビジネスマンの男。しかし、関係した女たちが次々に殺され殺人犯に仕立てられていく・・・というサスペンス映画。力作である。弁護士が真実を追っていくのをまどろっこしい思いをしたり、ハラハラしながら見守っていくことになるが、サスペンス映画の常套でドンデン返しがある。それが、思いもよらない犯人でありその動機が異常なため、単なるサスペンス映画が深い文学映画のおもむきになっていくのがおもしろい。主人公の好色漢を演じる仲谷昇のイケメンぶりと、弁護士役の北村和夫の味のある演技が印象的。1960年代前半の日本の風景も興味深く、室内のそれも含めて飽きることのない123分だった。
September 27, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~すべて彼女のために
原題はPOUR ELLE(彼女のために)。2008年のフランス映画。タイトルは恋愛映画ふうだが、犯罪映画。それもケチな犯罪ではなく、国家と言って悪ければ体制そのものに挑んだ犯罪。「悪法は法ならず」「悪法といえど法なり」という昔からの議論があるが、この映画は「悪法は法ならず」の立場、それも個人の立場に立ちきっていてすがすがしい。「犯罪」の成功を祈るような気持ちで最後まで集中して観させられる。冤罪のため収監された妻を脱獄させようと、国語教師である夫は決意する。情報を集め、資金を入手し、刻一刻とそのときは近づいてくる・・・冤罪であることは最初から明らかにされているので、どんな方法で脱獄させ逃亡するのかが興味の中心になる。こうするにちがいない、という予測が裏切られ、最後まで観るとなるほどとすべての伏線に納得する。たくさん映画を観てきたが、ドンデン返しを期待する観客の想像力を逆手にとって映画に引き込んでいく、こんな手法は初めてだ。ストーリーとはあまり関係ないのところで感動的なのは、折り合いの悪い父との関係。父は息子の計画を偶然に知ってしまうのだが、それについては何も語らず、無言のまま息子を送り出す。たくさん映画を観てきたが、息子の犯罪を「無言」という行為で支えるこの部分ほど感動的なシーンを見つけるのは簡単ではない。小さな欠点を二つあげれば、ひとつは平凡な教師という設定の夫(ヴァンサン・ランドン)が最初からタフネスを感じさせる風貌である点。弱々しい男がしだいに野性的になり風貌も変わってくる、というよくあるハリウッド映画の手法を採用してもよかった。もうひとつはラストの解放感がいまひとつである点。実話ではないのだから、もう少し話を作り込んでもよかった。女看守や警察官といった「悪役」がステレオタイプなのも欠点といえるかもしれない。マヌケでノロマな警官より、俊敏で賢明な刑事を出しぬく方がクライマックスの法悦感が増したと思う。それにしてもフランス映画について、あらゆる人にとって一見の価値のある映画であると述べることができるのは、忘れるほど過去のような気がする。
September 26, 2010
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~クラリネット・アンサンブル・エボニー第18回演奏会
結成16年になる、クラリネット奏者5人のアンサンブルを聴いてきた(19日、ザ・ルーテルホール)。立ち見の出る満席。プログラムのほとんどはアレンジもので、バッハのイタリア協奏曲第1楽章、モーツァルトのセレナード第11番第5楽章、5つのディベルティメントを前半におき、ガーシュイン(アイ・ガット・リズム変奏曲)、ピアソラ(革命家)、石川洋光(インプレッションズ)、ラヴェル(マ・メール・ロア)を後半というプログラム。アンコールで演奏されたモーツァルトの「二台のピアノのためのソナタ」第1楽章が、もしかすると最も興味深かったかもしれない。ピアノだとひとつひとつの音が小粒。しかしクラリネットは音の粒が大きいため、原曲よりも音のぶつかりあいやせめぎ合いが目に見えるようにわかる。おもしろい曲だとは思っていたが、こんなにおもしろかったとは、と瞠目させられた。その他でもやはりモーツァルト作品がクラリネットという楽器との相性のよさを感じた。演奏者では、いささかマジメな演奏スタイルの奏者たち中で、ジャジーな感覚に閃きを見せた斎藤雄一という人が印象に残った。このアンサンブルは元札響クラリネット奏者の渡部大三郎氏の門下生らしい。メンバーのひとり三瓶佳紀は現在札響首席奏者だが、全体として力量の差はあまりなく、日曜の夜を過ごすひとときとしては楽しめる音楽会だった。
September 20, 2010
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~札幌交響楽団第531回定期演奏会
札響としては1991年11月定期以来のマーラー「交響曲第3番」。マイケル・ティルソン・トーマスがPMFオーケストラを指揮して演奏したこともあったから、この曲が札幌で演奏されるのはこの20年で3度目。一日目の演奏を聴いて思ったのは、この20年の札響の演奏技術の進歩。この大曲は管楽器、特にホルンを筆頭とする金管楽器が大活躍する。1991年の演奏は、1930年代のベルリン・フィルより技術的に劣っていた。しかし2010年の札響の演奏は、たとえばホルンセクションに限っていえば、1970年代のベルリン・フィルを凌駕している。音楽的にも、20年前はこの曲を知っている楽員などほとんどいなかっただろうと思われるくらい、手探りの演奏だった。それがいまでは、ほとんど全員が「マーラーはこういう音楽」という確信を持って積極的に演奏しているのがわかる。ではそれが音楽的な感動に結びついたかというと、それはまた別の話だ。1991年のときの指揮は十束尚宏で、清新なマーラーだった。手探りではあったが、初々しい楽想が初々しく演奏され、スタミナ切れは見られたものの開放的な音楽が聞かれた。しかしこの日の演奏は白熱し集中していたものの、音楽的感動の点では今ひとつだった。それはたぶん指揮の尾高忠明の解釈のせいだ。尾高忠明はBBCウェールズ響時代、マーラーの交響曲第5番で圧倒的名演を聞かせたことがある。だから彼のマーラーには期待していたのだが、期待とはちがった方向に進んでいるようだ。テンポ設定が全体に速めで、インテンポが基調。したがって終楽章など緩徐楽章は格調高くなるが、マーラーの音楽のドラマは聞こえてこない。マーラーの音楽で最もアイブズ的な第一楽章も整然と聞こえ、分裂症的なマーラーの音楽の特質は後景に退いてしまう。いささか下品なところのある音楽は、その下品さを際立ててこそ全体が生きると思うのだが、開放に向かうべきところが集中してしまう。陰の部分も明るく、何だかゲオルク・ショルティのマーラーをヘタなオーケストラで聴いているような気がしてしまう。女声合唱や児童合唱もアクセントのインパクトが弱く、声量も不足に聞こえたのは、実際にそれらが不足していたというより、指揮者の解釈がマーラーの音楽からユダヤ的なものを排した、淡白なものだったからかもしれない。とはいえ、骨格はしっかりしていたし、筋肉質の聴き応えのあるマーラーであったことはたしかで、今では欧米でもこれだけのマーラーは珍しくなったかもしれない。あんなにたくさんいたマーラー指揮者も、気がついてみるとほとんどいなくなってしまった。インバル、ギーレン、ブーレーズ、みな高齢でマイケル・ティルソン・トーマスも60代後半に差しかかっている。かつて「マーラー・レース」の先頭集団にいた尾高忠明が返り咲く日は来るのだろうか?独唱の手嶋眞佐子(メゾ・ソプラノ)は歌い出しが強すぎて全体の印象を損なってしまった。聴衆も最低。最近はヨーロッパでも似た傾向があるようだが、余韻が消えるまで拍手を待てない人間が増えている。音楽を聞いているのではなく、イベントに参加している自分に自己陶酔しているのであり、マナーの問題ではない。
September 18, 2010
コメント(0)
-
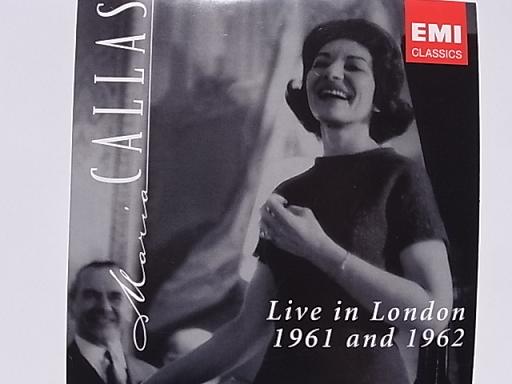
いつかの日、暗い海の底へ~マルガリータのアリア(ボーイトのオペラ「メフィストフェーレ」より)のマリア・カラス録音についての短い注
9月16日はマリア・カラスが世を去って33年目。カラスより3歳年長の叔母がまだ元気でいることを思うたび、早すぎる死に不条理を感じる。ゼフィレッリによれば、最晩年のカラスは日本、それも京都への移住を考えていたという。もし実現していたなら、演奏活動はともかく、もう少し長生きして、いろいろないい仕事をしていただろうと思う。日本及び京都はカラス・ファンにとっての聖地となっただろう。先進国の政治家はほぼ例外なくオペラ愛好家なので、日本に対する評価は何段階も上がったにちがいない。去年のきょうはプッチーニの「トスカ」第二幕のアリア「歌に生き、愛に生き」を取り上げた。この曲の1953年スタジオ録音、映像でも残されているコベント・ガーデンでの演奏のすばらしさに異を唱える人はいないだろうが、あまり知られていないカラスの名唄というか絶唱がある。ボーイトのオペラ「メフィストフェーレ」第3幕でマルガリータが歌うアリア「暗い海の底へ」である。カラス研究者で著書もある永竹由幸は1959年のテレビ向けコンサートのロンドン録音を絶賛している。しかし、このときがカラスがこの曲を歌った初めての機会だという彼の解説は間違っている。カラスはすでに1954年にロンドンでこの曲をスタジオ録音しているからだ。カラスはこのオペラを舞台では歌ったことがない。カラスは自分が主役となるオペラしか出演を承諾しなかった。これは当然のことだと思うが、それでは数々の名作オペラの傑作アリアを歌う機会を逃がしてしまう。カラスは舞台で歌ったことのないアリアも積極的にコンサートや放送で歌っていた。そうしたアリアの中でも、この歌におけるマリア・カラスの歌唱のすごさは際立っている。凄絶とかすばらしいとか陳腐なほめ言葉は、この歌唱にはかえって失礼なくらいだ。ほかの歌手など児戯のようなものであり比較は狂気の沙汰だ。それくらい他を圧倒し隔絶している。たった36小節の曲だが、カラスのこの曲の演奏のどこがどうすばらしいのかを書くだけで一冊の本になるだろう。少なくとも、ひとつの音につき数百字は書くことがある。36小節の音の数はたぶん200くらいだろうから、即座に数万字の評論を書くことができる。この曲のカラスの録音はいま三つ手元にある。セラフィン指揮フィルハーモニア管弦楽団とのスタジオ録音(1954年9月)、マルコム・サージェント指揮BBC交響楽団とのコンサート録音(1959年10月3日)、マルコム・サージェントのピアノ伴奏によるコンサート録音(たぶん隠し録り、1961年5月30日)の3つである。録音は新しいものほど悪い。カラスの歌をクリアに聴ける点では1954年の録音がベストだ。1959年の録音は音のよさで定評のあるBBCのくせにひどい。カラスの声は比較的大きな音像で録音されているが、弦楽器などダンゴになるし、フォルティッシモでは音が割れてしまう。1961年のピアノ伴奏によるコンサート録音はさらにひどい。ピアノの音はかろうじて音楽として聞こえるという程度で、これは客席からの隠し録り、いわゆる私家録音だろう。永竹由幸は1959年の演奏について、「このころカラスはオナシスの子どもを身ごもっていた。だから不義の子をはらんだマルガリータのアリアが自分の気持ちにぴったりだったのだ」と解説しているが、片腹痛い。かんちがいもはなはだしいのだ。音楽家の表現に実人生の体験が反映することはたしかにあるが、それは直截的なものではなく、もっと熟成というか長い年月のうちに獲得されるものである。それに、1954年、30代はじめでカラスはほぼ完成した表現を手に入れている。セラフィン、サージェント、いずれも大指揮者だが、サージェントの大音楽家ぶりは指揮とピアノの両方からうかがえる。オーケストラ前奏部分はこの指揮者がただの職人音楽家ではないことをはっきりと物語っているし、ピアノ伴奏ではオーケストラ的な広がりを感じさせる。この曲はニ短調だが、5小節目にはニ長調になったり、短調と長調の間を揺れ動く。クライマックスはニ長調の主和音の下降音型なのに、終結部分はニ短調といった具合だ。こうした不安定な調性移行を、カラスは完全に掌握している。ただメロディをきれいに歌っているのとは訳がちがう。音楽の構造全体を把握し、音楽の構造の中でのその音の意味、作曲家がそこにその音を持ってきた意味を完全に理解して歌っているのである。これほどすごい音楽的知性に出会うことはそうない。しかもその上に、不義の子をはらんだ女性の気持ちというか情念のようなものを感じさせるのだ。たった4分ほどの曲だが、オペラ一曲分くらいの密度がある。オペラとは何かと聞かれたら、この曲のことだと言いたくなる衝動は抑えがたい。まず歌い出しがすばらしい。マリア・カラスのインタビューはかなりのこされているが、構えることなく、質問に対してすっと話し始める、あのスムーズなカラスの会話が思い出される。これは歌い始めに、すでにこの役柄に完全になりきっているからできることであり、ここではマリア・カラスはマルガリータなのだ。すっと歌い出すだけでなく、やや暗い声で歌い始めている。この音色の選択の適切なことといったらほとんど神技といっていい。始まって二つめの、付点音符の短い音をはっきり発音している。歌ではあるが、言葉を語っているのだ。そのあと音階を3つ登り、Fの長い音に到達したあとAの短い音に下がる。音階を3つ登るとき、カラスはわずかにクレッシェンドするがあくまで暗い音色を保つ。いわゆる美しい声で歌うこともできただろうが、音楽の要求する音色を守っている。3つ(4つ)の音符の長さは正確に守り、いわゆるインテンポで清潔に歌っている。これが抑制された表現に聞こえ、のちのクライマックスのドラマを圧倒的に高めることになるのだが、ラシドと上がっていくドの音の前でほんのわずか、たぶん1000分の1秒くらい区切るのがわかるだろう。このことで、なめらかに上がっていくのではなく、何かを躊躇する女の気持ちが、歌詞がわからなくても伝わるのだ。Fの音まで上がったメロディーはいったんAという中間地点に着地し、さらにF、E♭、F、Dと下がる。E♭はニ短調の中にはない音であり、変ホ長調かハ短調に転調したのかと思わせる。すぐにニ短調に着地するのだが、このE♭の音は音楽的に非常に重要だ。この音の前のFから、カラスは発声を変え、胸声を使っている。そしてそのことでE♭の二つめの「BO」という音にものすごい深みと暗さを与えている。このE♭からF、そしてDの音にはそれぞれスフォルツァンド記号(その音だけ強く)が付けられている。作曲者はここで音の強さではなく、重さを要求しているのだ。だがただ同じように重く歌うと音楽的ではなく、流れは止まってしまう。カラスはわずかにおのおのの音の重さを変えている。E♭二つめの音を長く保ち、次のF3つのうち、3つめに重点を置いている。後半で同じメロディが繰り返されるとき、このF3つのうちの2つめをカラスは爆発的に歌うのだが、ここでは少しおとなしく表現することによって、後半のこの部分の灼熱のような表現とうまく対比させているのだ。ここまでで最初の4小節について述べた。イタリア語の発音についてや次の4小節で同じメロディがやや音程を変えながらニ長調になる部分との対比がどういう効果を生んでいるかなど、書きたいことの半分も書いていないが、このブログは5000字が制限なので書ききれない。次の4小節についてはまた来年の命日にでも書くことにしよう。10年ぐらいのうちには、36小節全体について書ききることができるかもしれない。
September 16, 2010
コメント(0)
-

こんな山に行った~当麻岳から北鎮岳・中岳
登山ガイドはルポルタージュであるべきだ。山の状況は日々変わる。徹底的に個人的な観察や印象や体験こそが重要なのに、コースタイムにしてもどういう人のものかわからなければ参考にならない。腰椎椎間板ヘルニアの心配があったが、運試しのつもりで日本で最も早い紅葉ポイントとして知られる大雪山に行ってきた。これは2010年9月15日の記録である。このコースは15年ぶり。15年前の9月15日はもう寒く、すっかり紅葉していたが今年は遅い。あと数日はかかりそうだ。このあたりは標高1600メートルで森林限界に近い。ここから上のナナカマドの紅葉が最も美しいのだが、その紅葉を見るためのポイントまでは2時間ほど歩く。駅を出ると正面に旭岳が姿を見せる。北海道最高峰のこの山は秀麗な山容で、いつまで見ても飽きない。今年は火山活動が活発だ。噴煙の勢いが強く範囲も広い。噴煙が小さいときは近くまで行って眺めたりしたものだが、そういうことをする気にならないほど。6時の始発に乗り遅れ6時30分のロープウェイに乗る。歩き始めたのは6時40分だった。この30分の遅れは致命傷になりかねない。日没の早い秋の登山は早発ちが鉄則である。遅くても17時、山によっては16時には下山していなければならない。この山は運行時刻に縛られるので6時以前には動けないが、日の出には行動を開始するのが鉄則だ。花は終わっているがリンドウが少し残っていた。年によっては雪融けが遅く花と紅葉と初雪が、つまり四季が同時にやってくることがある。この20年で2回あった。そういうときは万難を排してでも行く価値がある。裾合平分岐まではかなりのアップダウンがある。8時10分に分岐着。2時間弱かかるところ90分で着いたのは朝なので涼しく休憩の必要がなかったからだ。この分岐から当麻乗越という小ピークまでは小一時間。当麻乗越こそ、180度以上の広がりで紅葉と点在する湖沼の見られる絶景ポイントだ。ここまでなら、健康でさえあれば70代の人でも来られる。分岐から当麻乗越まではいったんピウケナイという沢に降りる。ところが、簡単に渡れるはずが、増水していて渡る場所を見つけられない。諦めかけたころ、やや下流の方で渡っている人を見つけた。あわててそちらに走っていくと、その人は向こう岸からどの石がいいか教えてくれた。少し濡れたが渡ることができた。あの人がいなかったら諦めていた。この沢をこの方向で渡ったのはこの日は4人、反対から渡ったのはひとりだった。いかにひと気のない静かな山行かわかると思う。実は、久しぶりの本格登山でもあるし、このあたりのどこかで引き返そうと思っていた。しかし、もう一度あの沢を渡ると思うと恐怖心がわいた。上部の雪渓がどんどん融けているのだから水は増えているかもしれない。川に落ちるとかなり悲惨なことになる。子どものころ川で泳いだことがあり水の流れの抗いがたい強さはよく知っている。しかしこの先、長い登りをやるのも気が滅入る。待っている尾根歩きは楽しいが、危険な場所があるのも知っていた。戻るのも進むのも恐怖。水の恐怖と断崖の恐怖を比べて、水への恐怖が勝った。前へ進むことにした。15年前に来たときは、69歳の母も一緒だった。そのときは母の荷物も背負ったので、今回より荷物は重かったと思うが、荷物が重く感じられてしかたがない。気温のせいだ。だんだん気温が上がってきて、ゆっくり登ってもぐっしょり汗をかいてしまう。この当麻岳への登りはひたすら急な坂を登り、登るほどに傾斜がきつく岩が多くなってくる。ここを登るのは7回目だと思うが、いちばんきつく感じる。こんなきつい山はもう二度とごめんだと思いながら、1時間程度で稜線に出ることはわかっていたので何とか耐えられた。1990年の9月19日には85分かかったが、今回は70分。ロープウェイの最終に遅れてはたいへんと急ぐ意識があったためだ。当麻乗越から当麻岳の稜線、それから稜線に出てから何と言っても慰められるのはウラシマツツジの真紅と言っていい草紅葉。場所によっては真っ赤な絨毯の中を歩いているようだ。こんな贅沢な経験は、この稜線以外ではできないのではと思う。しかも旭岳や裾合平の大パノラマを見ながらの天上散歩。ついさっきまでの苦しい登りを忘れてしまうほどだ。左右が崖、という稜線を危険を感じながらも行くと広がりのある尾根になる。2200メートルの安足間岳への登りで、当麻岳の尾根のとりつきが1800メートルだから400メートルの標高差。400メートルというとかなりの落差だ。写真を撮ったりしているうちに時間を食い、安足間岳には11時15分に着いた。当麻岳からはちょうど一時間かかった。ここまでは、どちらかというと日本画のような風景。ハイマツの緑の中に紅葉が点在する深い色合いで、奇岩や湿性植物やハイマツがおりなす風景は日本庭園に通じるおもむきがある。しかし安足間岳を過ぎると風景は一変する。草木のまったくない、地肌むきだしの崖で、ちょうど噴煙こそ上がっていないものの地獄谷のような風景が広がる。休まずに安足間岳を出発。この地獄谷の尾根部分を20分歩いて比布岳に着いたのは11時35分だったが、この20分は緊張した。というのは、稜線のすぐ下をトラバースするのだが、以前はしっかりとあった登山道が風化し、崖のしみのようになってしまっているのである。斜面をただ歩くという感じに近い。左側は大覗きと呼ばれる絶壁、すぐ足元から右は、絶壁というほどではないにしても滑落したら骨折程度では済まないという斜面である。今回、はじめて登山用のストックを持っていったが、これが役に立った。これより危険な斜面を歩いたことは何度もあるが、なぜか今回は緊張した。加齢のせいでバランスが悪くなっているのかもしれないし、体重が減ると重心が高くなるので、よけいにバランスがとれないのかもしれない。こういう場所はあんがい女性は強い。母もここは2回通ったがスラスラ歩いた。冷や汗をかくほど緊張して着いた比布岳には大岩がある。ふと見るとリスがいる。近くの人にリスがいると教えると写真を撮り始めた。少し話すと、この先一時間くらいは同じ道を行くことがわかったので同行することにした。60代なかばくらいの写真趣味の女性である。気温が高いせいかガスが出ては晴れる、その繰り返しで、山岳美を誇る愛別岳は見えなかったが、一日でいちばん気温の高くなる時間帯に暑い思いをしないで済んだ。歩くときは汗ばんでも止まるとセーターやウィンドブレーカーがいる、そんな季節だが、薄着でも歩いていれば寒くもなく暑くもない、そんな状態で北海道第2の高峰、北鎮岳を目指した。この女性は少し太っていて少し歩くのが遅い。おかげで疲れずに歩くことができた。比布岳から北鎮岳までの標高差は50メートルだが、一度下るので登り返しがけっこうある。感覚としては標高差200メートルくらいと感じる。それでも、比布岳発12時で北鎮岳着12時55分なので、低山ひとつ分くらいの登山である。特筆すべきは当麻岳からこの北鎮岳に至るまでの、わずかな「地獄谷」部分を除いての広大なお花畑。チングルマの紅葉がピークだったが、何度も来ているところなのに、こんなところにこんなに大きなお花畑がと驚かされた。一度だけ、このお花畑を見に6月下旬に来たことがあるが、ついさっきまでの苦しい登りや恐怖のトラバースを忘れ、次は花の時期に来てみようとさえ思ってしまった。実は、地図をクルマに忘れてしまったので、地図なしの山行だった。ただ、何度も来ているので地図はなくても大丈夫という自信があった。 しかし北鎮岳から先のルートははっきりしない。記憶では、ただ下り、標識に従えばいいと思っていた。もう登りはないので何の心配もいらないとさえ思った。しかし、目の前の雄大な景色を見ていると不安になった。晴れてはいるが、ときどきガスが出て視界がなくなることもある。そんな変な天候では、標識を見落としたりしてルートを間違うかもしれない。比布岳から同行した女性がこちらのルートもよく知っていたのであらためて教えてもらい、確信を持てた。彼女は北鎮岳から下ったすぐのところの分岐から左に折れて黒岳へ向かう。丁重に礼を言って別れた。わたしはそのまま直進し、中岳の小さなピークを越えて下り、分岐から右に折れて中岳温泉へ向かった。完全にひとりだったら景色を楽しむ余裕もなく、不安にかられて先を急いだだけで終わってしまったかもしれない。北鎮岳12時55分、中岳分岐13時55分。記憶ではすぐと思っていたが1時間かかった。このように記憶とはあいまいなものなので、地図やそれに類するもの、過去の登山記録などは重要だ。この時間になるとすでに夕方の気配が漂う。お鉢平の紅葉はピーク。ただいちばん大きな紅葉は日陰になっている。これを見るには午前中に、反対側(黒岳側)から見た方がいい。このお鉢平を見るのは15年ぶりだ。あまりに雄大で、絵にならないというか、写真に撮る気さえ起こらない。このお鉢平は一周したことがあるのでだいたいの距離感はあるが、それでも自分がここを一周したことが信じられないほど広大だ。「大雪山に登って山の大きさを語れ」と大町桂月は言ったらしいが、こんなに雄大な景色は大雪山国立公園全体でも屈指だろうと思う。ガスが晴れ、ルートを教えてもらえたので、日本ではここでしか見られない、お鉢平の雄大な景色をゆっくり楽しみながら、中岳を越え中岳分岐に向かうことができた。分岐からはひたすら下る。30分ほどで中岳温泉に。先客3人が足湯を終えたところで、ひとりになったので、少し砂や石をかきだして入浴。もう少しゆっくりしたかったが、17時30分がロープウェイの最終。温泉からロープウェイ駅までは約2時間。15時には出発しなければならない。だから入浴は10分で切り上げ、14時50分に出発。朝の30分の遅れが悔やまれた。あとは迷う心配のない下りがメーンの道である。緊張感から解放されたためか、逆に強い疲れを感じる。それでも夕暮れの太陽の光線に照らされる旭岳や秋の気配が深まる景色を見ながら、ほぼコースタイムで駅に着いた。16時35分に着き、16時45分のロープウェイで下山。さらにふもとには大雪山の湧水を汲める場所があり、そこへ向かった。この湧水は硬度が高いが柔らかい味のおいしい水で、特に珈琲に使ったりパスタをゆでたりするのに使うのに向く。今回は左回りに回ったが、右回りの方が2割くらい楽なようだ。数年に一度はこのルートの右回りをやって自分の体力の確認をする基準にしようかと考えている。
September 15, 2010
コメント(0)
-
裏札幌案内あらためヒミツのサッポロ-8-楽味
ゴルフや乗馬のために、わざわざ北海道に来る人がいる。それらの料金が安いので、旅費・滞在費をかけてもその方が割安なのだという。イタリアンやフレンチも高級店なら東京の半額以下だ。2~3回通うと旅費の元がとれてしまう。しかしこの店ほど「割安」な店は珍しいだろう。京料理をうたっているわけではないが、基本的には京料理を独自にアレンジしたものが多い。そして同じレベルの料理を京都で食べようと思ったら、少なくても5倍、場合によっては10倍ほどするにちがいない。値段を予想しながら料理を注文するテレビ番組があるが、もし一品ずつ客に値段をつけさせたら、最低でも実際の値段の倍にはなるだろうと思う。この店にはメニューがない。お酒も瓶ビールと日本酒と焼酎が一種類ずつあるだけ。おまかせのコース4000円のみで、これは20年ほど前に初めて来たときと同じだ。「楽味」という店名は作家の小檜山博の命名。この店はしばらく行方不明だった。名前を変えて移転、そして店主の病気で2年ほど休業していたという。元の名前で現在の場所にオープンして4年。ネット検索でやっと探し当てたが、そうでなければ見つけられなかった。店は「あの店のこれが食べたい」という動機で決めることが多い。しかし、この店にはそうした「この一品」はない。何が出てくるかは行くまでわからないし、まったく知らない食材が使われていることも多い。常連客が山でとってきたキノコや山菜が並ぶこともあるし、珍しい食材を手に入れる独自のルートをもっているようだ。だからこの店は「好き嫌いのある人」「食べたことのないものが苦手な人」には向かない。逆に、好き嫌いがなく珍しい食べ物に興味がある人なら破顔してしまうような料理が続く。品数が多いだけでなく量自体かなり多め。女性ならもてあましてしまうかもしれない。また、以前と比べると料理の出てくるテンポが速くなったので、ゆっくり食べたい人はその旨言っておいた方がいいかもしれない。タバコを吸っている人を見かけたことはないが、灰皿があり禁煙ではないのでその点は注意が必要だ。落ち着いた雰囲気の清潔な店内は、高級鮨店のような格式ばった雰囲気はなくくつろげる。女性同士ならともかく、男性同士で訪れるようなヤボは避けたい。また、こういう料理のすごさは自分で料理をしない人にはほんとうのところはわからないものなので、食べ歩くだけのグルメや知的好奇心のない人に教えてはならない。店主は料理については何でも詳しく教えてくれるので、その会話を楽しめないような人は客としては失格だ。また店主は陶芸や陶芸家にも詳しく、繊細すぎず大仰すぎない器も楽しみのひとつ。年に270日通った人がいるというほど、毎日ちがう料理が出てくる。いったい店主のアタマの中はどうなっているのかと思うほどで、歩く食材事典&レシピといったところだ。珍しい材料の手のこんだ料理ばかりでなく、お刺身のようなものでさえ発見がある。最近訪れたときには、カツオの刺身が大きなぶつ切りで供されたが、生のカツオは薄く切るのではなくぶつ切りがおいしいのだという。なるほどその通りだった。最近、食べログに二つめの紹介が投稿された。ラ・サンテという有名なフレンチの名店が円山にあるが、その店が目印になる。ラ・サンテから50メートルほど東にある建物の2階。営業は月~土の18時から。カウンターのみ8席なので予約は必須(当日可)。
September 12, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~永遠のマリア・カラス
レンタル落ちDVDを購入しての観賞。DVDにはマリア・カラスと親交のあったゼフィレッリ監督のインタビューが収録されていて映画の理解を助ける。2002年の作品だから1923年生まれのゼフィレッリ79歳の作品ということになる。最近、ゼフィレッリの自伝を読んだが、これがどんな冒険小説よりもスリリングでおもしろかった。ゼフィレッリは、映画監督としてもオペラ演出家としても酷評されることが多いが、なかなかどうして、さすが反ファシストの元パルチザンの気骨と知性を感じる。いわく、ハリウッドはカラスのスキャンダルをセンセーショナルに描いた映画を要求したが、カラスほどそれから遠い人間はいない。この映画で完璧を求め努力を惜しまない芸術家の真の姿を描きたかったのだと。それを若い世代に伝えたかったという。引退したマリア・カラスを主役にしたオペラ映画を作る。実際には舞台で演じたことのないカルメンに、昔の録音をかぶせて映画化しようというのだ。カラスは承諾し映画は製作されるが、カラスの心変わりによって結局はお蔵入りになる・・・というお話。ゼフィレッリの映画作りは、さすがにベテランの味がある。基本的な映画文法にのっとり、テンポも適切。映画とはこう作るものだという見本を見せてもらっているようだ。しかし、何と言ってもすごいのはカラスを演じたファニー・アルダン。容姿が似ているだけでなく、身振りにしても話し方にしても、まるでカラスの魂・内面がのりうつったかのような迫真の演技であり、何年もかけての役作り、勉強や研究の跡を感じる。この映画はアルダンなくしては駄作になっただろうし、ゼフィレッリはアルダンを発見したことでこの作品を着想したのかもしれないとさえ思う。完璧主義者カラスは、観る人によっては気難しい芸術家としか感じないかもしれないが、カルメンの制作に打ち込む部分などでは、カラスはほんとうにこういう人だったのだろうというリアリティがある。芸術というのは途方もない努力の末に生まれるというのはゼフィレッリの信念でもあるだろうが、そういう舞台裏を見るような迫力がある。ゲイのプロデューサー役はゼフィレッリ自身におきかえて見ることができる。二人の間には、こんな会話が交わされたことがきっとあるだろうと思うと感慨もひとしおだ。ゼフィレッリの恩人で友人でもあるココ・シャネルの衣装が全編に渡って使われていて、これがまたすばらしい。シャネルもまたただの「洋服デザイナー」ではなく、真摯な芸術家だったことがわかる。こういう映画は手元において、年に1度は繰り返し観たい。DVDを買ったのは正解だった。毎年12月にはこの映画を観て、カラスの生誕を祝おう。
September 10, 2010
コメント(0)
-
旅の記憶-2-
旅のノウハウで最も大事なもののひとつは、初めての国、初めての街にはできるだけ明るい時間に着くようにすることだ。多少高くついてもその方がリスクが少なくメリットが大きい。暗くなってからのホテル探しは辛いものだし、足もとを見られて変なホテルを高値づかみしたりする。空港や鉄道駅やバスターミナルは、地理に不案内な旅行者をねらう連中のいちばん多い場所だ。そういう場所からはさっさと立ち去るべきであり、暗くなってから到着してうろうろすることほど危険なことはない。ところが飛行機はいろいろな理由でよく遅れる。このときは3時間以上遅れたため、晩秋のパリはもう暗くなり始めていた。空港からはバスで地下鉄駅に行き、地下鉄で鉄道駅まで行けばいいということだけはわかっていたが、いったいどのバスに乗ったらいいかわからない。番号だけで行き先表示がないのだ。フランス語はシルブプレとメルシー、パルドンしか知らないのだから、フランス人に尋ねることもできない。同じ飛行機の乗客たちは慣れた足取りでさっさといなくなってしまった。しかたがないので、インフォメーションへ行き、無料のガイドマップをもらうことにした。英語が通じるかもしれないという期待もあった。さすがに安い飛行機会社だけあって、着いたのはシャルル・ドゴール空港ではなくオルリー空港だったが、このインフォメーションが最悪だった。フランス美人が二人いたが、おしゃべりに熱中してこっちを見ない。何度か「マップ、シルブプレ」を繰り返したところ、まるで汚いもので見るような目でこっちを振り返りつつ、マップを放ってよこしたのだった。そのあとはまたおしゃべりに夢中で、英語で話しかけても返事もない。それでも不思議とイヤな気がしなかったのは相手が美人だったからではなく、おしゃべりを中断された相手の気持ちも理解できたからだ。思ったこと感じたことを隠さずストレートに表す、その態度にも親近感をおぼえた。心にもないことを口にしたり、贈り物をするとき「つまらないものですが」と謙遜する日本の文化にずっと違和感を抱いてきた僕は、大げさに言えば故郷に帰ってきたような気さえした。 そうか僕はヨーロッパ人だったのだと、そのとき思った。日本社会に適応できなかったのは、僕のせいではなく、社会の側に原因があったのだ。無愛想なフランス女との出会いは僕には大きな救いになった。父がよく言っていたことを思い出す。父は水産関係の研究者をしていたため、漁師や漁協と関係が深く、また農協にも招かれることがあった。両方の大会は、全く雰囲気がちがうのだという。農協の大会は、和気あいあいとした雰囲気で異論もなくすすむのに対し、漁協の大会は、罵詈雑言と怒号が飛び交い、ケンカ腰。しかし大会のあとは、あれだけ罵りあってもそのあとはさっぱりしているのに対し、農民の方は、あとから批判めいたことをうじうじ言うのだという。土地から離れられない農民がどうしても本音と建て前を使い分けるようになるのはしかたのないことだろう。争いを避け形式的にでも和を尊ぶ気質は、たぶん洋の東西を問わず農民には強いのだろう。しかし、日本はとっくに農業国ではなくなっているのに、同質なものを求め、自己主張をしないことが美徳という風潮が強い。ストレートな表現より婉曲な言い回しを好むのは特に京都あたりに強く存在する文化だが、僕はこうした文化が苦手だ。贈り物をするとき「つまらないものですが」と謙遜する文化は、理解できなくはないが僕には異質だ。プレゼントは、それがどんなに珍しく貴重で有用か、それを説明しながら渡すべきだとさえ思っている。ミュンヘンの彼女(以後K)からの手紙には、ドイツ人の学生は、自分の意見をはっきりと言い、どんな相手とでも堂々と論争するとあった。そのくせ、どんなに意見や思想が異なっても、それはそれとして仲が悪くなることはない、遊びの場面では一緒に楽しむ、それが日本人とちがっていて驚いたとあった。自分の意見を持ち、それをはっきり言い、イヤなことはイヤ、嬉しいことは嬉しいと感情をストレートに表すことを好ましいと思う感性は、なぜできたのだろうかと思うことがある。当時は日本だったとはいえ台湾出身の父と、東北出身ながらソウルの師範学校を出て職業を持っていた母の影響は大きかったのかもしれない。そういう性格は、学生時代は面白がられたり人気の素になったりしたが、社会ではそうはいかない。いまとちがって、若者が自分の意見を持ち自己主張することなどは職場の年長者がゆるさない、そんな雰囲気が強かった。インフォメーション前に取り残されていた日本からの乗客がもうひとりいた。僕と同年代のその男に話しかけると、やはり地下鉄駅行きのバスがわからないという。二人で外に出てバスをひとつずつあたると、おそらくこれだろうというバスを見つけた。その男は僕以上に外国語のできない男で、バスの運転手に日本語で聞いていて笑えた。運転手はまったく相手にしないどころか、あっちへ行けと手を振り、愛想のないことはインフォメーションの美女と同じだ。しかしそのとき、バスのすぐ近くで、障害者の乗った車イスが道路のすきまにはまって動けなくなった。そうしたら、この無愛想な運転手が脱兎のごとく運転席から飛び出し、助けに行ったのである。フランスでは危機に遭遇している他人を見過ごすと刑事罰の対象になるということをかなりあとで知ったが、その運転手の行動、というか条件反射的行動には、その直前に無愛想な対応をされただけに深く感じるものがあった。警察が、被害者がストーカーに殺されるまで動かない国から来た人間としては、表面的には愛想がなく冷たいが弱者に優しいフランス人の国民性がすばらしいものに思えたのである。空港でもたついている間にすっかり夜になってしまったが、何とかバスで地下鉄駅まで来た。僕はフランクフルト経由でミュンヘン、空港で知り合った男はベルリンに。ヨーロッパの大きな街では、行き先というか方面によって駅がちがうことがよくあるので気をつけなければならない。僕はパリ西駅、男はパリ北駅が出発駅になる。どこへ行くのか地下鉄の中で話したが、彼は聞いたことのない地名を繰り返す。 コーロンに行く、コーロン経由でベルリンに行く、と言うのである。はて、と思って地図を見せてもらうと、そこにはケルンと書いてあった。スペル通り読むとコーロンだが、ケルンのことだ。彼は気分を害したと思うが、思わず笑ってしまった。もしかすると数分間、笑い続けていたかもしれない。ケルンも知らない、ケルンと読めないような人間でも平気で旅ができるものなのか、それがおもしろくておかしくてしかたがなかった。この一事で、初めての海外旅行という緊張が、一気にとけるのを感じた。その安心感というか、なんだそんなものなのかという安堵感から、張りつめていた気持ちがゆるんで笑いが止まらなくなってしまったのだった。旅の最初に、ケルンをコーロンと呼ぶ男に出会ったのは何とも幸運だった。宮城県の雑貨屋の二代目で、年に1~2度、一週間程度の日程でヨーロッパの主な街をまわっていると言っていた。外国をひとり旅というとたいへんなことと思う人はいまでも多いかもしれない。しかしアルファベットと数字が読めれば、たいていのことは何とかなる。日本人であればかなりの数の英語を知らず知らずのうちに身につけている。ケルンをコーロンと読む男でも、何とかできてしまうのが海外ひとり旅なのだ。
September 9, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~カックン超特急
3週に渡って上映されている蠍座の企画「昭和の名男優・喜劇な人びと」に選ばれた6作のうちの1作。歌手として有名だった近江俊郎監督の1959年作品。カックンという流行語はこの映画から生まれたのか、それとも流行語を元にこの映画が作られたのか。それはわからないが、今でも「あてがはずれた」「がっかり」のような意味で使われることもある「カックン」をタイトルに付けていることからもわかるように、ドジでヘマばかりのトラック便運転手ふたりのロード・ムービーである。初めて命じられた東京までの特急トラック便の運転。しかし人助けなどしている間に到着は遅れ、帰りには手配中の強盗団にトラックを盗まれてしまう。しかし運よく通りかかった車で追跡して強盗団も捕まえ、災い転じて福となった、というお話。おもしろいのは、主演の由利徹が(ちょい役で出る大空真弓も)ひとり二役になっている構成。映画の撮影所に荷物を届けたところ、出演者の由利徹にそっくりのトラック運転手が本人と間違われて出演してしまうという設定になっていて、ありえない話だが笑える。古きよき時代の撮影所にはこんなのどかでのんきな空気が流れていたのかもと思わせる。運転手の助手役には南利明、映画監督役には藤村有広など一流どころを配していて、この程度の映画(失礼!)にしては豪華な出演者が並ぶ。中には高島忠夫や江木俊夫もいる。高島忠夫の若さにも驚くが、江木俊夫など子役なのだから、このころの日本は若かった。運転手の助手役で主人公とギャグのかけ合いをやっていく南利明がひときわ懐かしい。そして喜劇役者としてはもしかすると伴淳三郎や由利徹を上回る超一流なのではないかという気がした。「ハヤシもあるでよ」のCMのインパクトが強烈だったが、名古屋弁を全国区にした「てなもんや三度笠」の出演者の中でも最も強く印象に残っている。南利明こそ日本一の喜劇俳優だったのかもしれない。
September 8, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~アジャパー天国
3週に渡って上映されている蠍座の企画「昭和の名男優・喜劇な人びと」に選ばれた6作のうちの1作。喜劇の神様としてサイレント時代から活躍した斎藤寅次郎監督の1953年作品。今回の6作のうちでは最もテンポの速い、そして唯一のドタバタで終わる喜劇。ラブレター代筆を副業にしているキャバレーのボーイ役が伴淳三郎。彼が住む同じ長屋式アパートの住人たちが身分ちがいの恋を成就させるため協力して金持ちの娘をかくまう。親が依頼した捜索人を裏で操るのはその親が投資しているキャバレーの経営者。娘を連れ戻したはずが誘拐され、今度はその彼女を取り戻すためギャング一味と大立ち回り・・・というお話。出演している俳優の数が多い。1960年以前に生まれた人ならテレビなどでよく見た懐かしい顔が次々と現れる。古川緑波、高島忠夫、清川虹子、打田典子、田中春男、内海突破、花岡菊子、田端義夫、花菱アチャコ、初音礼子、木戸新太郎、星美智子、南寿美子、柳家金語楼、堺駿二、泉友子、トニー谷、益田喜頓・・・この人はあまり見たことがない、誰だろうと思って調べたら堺正章の父の堺駿二だった。堺正章はグループサウンズのボーカルには似合わない風貌だと思っていたが、やはり血は争えないということか。ドタバタ喜劇だが、やはり復興まもない日本の姿が、映像にもストーリーにも刻まれている。他人の不幸を見ていられない人情深さ、恋愛に対するナイーブさ、犯罪者が心を入れかえるなど、21世紀の日本では化石化したものが、この映画でもたっぷりと観ることができる。このころからすでにおばさん的雰囲気全開の清川虹子が、イケメン夫の戦地からの生還を信じて待つ健気な妻役をやっていたりするリアリティのなさはご愛敬。益田喜頓は1909年生まれだからこの映画のころ40代はじめ。全盛期というところだろうか。知性を感じさせる独特の柔らかい演技は主役を食うほど強く印象に残る。
September 7, 2010
コメント(0)
-
旅の記憶-1-
僕が初めて外国の地を踏んだのはフランスだった。1992年のことである。35歳のその年まで外国に行くということがなかったのは、外国、特にヨーロッパはお金もちしか行けないところと思いこんでいたからだ。10代の終わり、1970年代の半ば、ドイツかフランスに留学したいと思ったことがあった。地方から東京の大学に行くのなら、外国に留学してもさほど費用は変わらないという話を聞いたことがあったからだ。特にドイツの大学は授業料がタダという。それで調べてみたが、今のように情報は少なく手がかりはほとんどなかった。調べても出てくるのはネガティブな情報ばかり。何せ外貨の持ち出し制限があった時代である。それに、大卒初任給が10万円に満たない時代に片道30万円の飛行機代は留学の夢を打ち砕くのにじゅうぶんすぎる金額だった。それでも、どうしても留学したいという強い執念があったらまた別だったかもしれないが、親に大きな負担をかけて留学したとして、その先で自分が成功する自信はなかった。だからあっさり諦めてしまった。それ以来、外国など夢のまた夢と思ってしまい、自分には無縁のものと思いこんでいたのである。僕から上の世代の人は、ほとんどの人が同じように思っていたと思う。調べてみると、1964年までは海外への観光旅行そのものが解禁されていなかった。高校の地理教師は無銭旅行で世界一周をしたことがあり、年に数回、授業をつぶしてその話をしてくれた。あちこちで皿洗いなどのアルバイトをしながらのその旅行の話は、手に汗をにぎるほど熱中して聴いたものだったが、1960年代までは無銭旅行の方がむしろ一般的だったろう。1985年から始まる円高が急激に海外旅行を一般化したが、それでもアメリカのビザが免除になったのは1988年だし、ヨーロッパに行くのに旧ソ連上空を飛ばなければならなかったり危険や制約が大きかった。急激な円高は1995年まで続くが、1990年を前後する時期は東西冷戦が終わり、湾岸戦争などはあったものの、世界が平和と繁栄へ向けて過去をリセットして再スタートしたかのようだった。僕が初めて外国に行ったのはこのような時期にあたる。1989年11月のベルリンの壁崩壊からちょうど3年がたっていた。外国に行くことなど夢のまた夢と思いこんでいた、そんな僕がなぜ外国に、それもヨーロッパに行こうと思ったかというと、この年の春に大学を卒業した10歳年下の恋人がドイツに留学したからだ。その彼女と知り合ったのは彼女が渡独する半年ほど前のこと。強い恋愛感情があったわけではない。僕が果たせなかった留学をしようとしていた彼女を手助けしたいと思っただけだが、ふとしたことからついセックスしてしまった。彼女はドイツで新しい恋人を作ればいいし作るだろう。半年だけ恋人として支えよう。 彼女の出発の日が彼女との別れの日。付き合い初めから、そう決めていた。移り住んだミュンヘンから、彼女はひんぱんに手紙をくれた。その内容は、外国というものに一度も行ったことのなかった僕には驚くことばかり。にわかに外国というものに興味がわいた。意外と旅費がかからないことも知った。彼女の手紙の調子がおかしくなってきたのは、留学して3か月たった9月ごろだっただろうか。あまりにひんぱんに、しかもおかしな内容の手紙が来る。あるときなど、僕がドイツに移住しないのはおかしいとまで言い出した。外国に移住してしばらくすると精神に変調を来す人は珍しくないらしい。彼女もそうした、一種のノイローゼだったのかもしれない。どうしたものか悩んだが、フェイドアウトするのではなく彼女にきちんと別れを告げ、将来に対する変な期待を持たせない方がいいと考えた。そこでドイツに行くことにした。ミュンヘン直行便はないし、ドイツ行きの飛行機は高額だった。雑誌で調べると、AOMフランス航空という航空会社がいちばん安かったので、パリからミュンヘンに行くことにした。ユーレイルパスも買い、ヨーロッパを東回りに一周する大まかなプランを立てた。ユーレイルパスは加盟国の鉄道が乗り放題になるパスで、日本でだけ買える。夜7時すぎに乗車すると日付をまたいでも1日分の利用としてしかカウントされないので、夜行で移動し、電車の中で寝て昼間は観光という旅行を繰り返す強者がいたりする。ヨーロッパの電車、急行や特急は座席が6人一室のコンパートメントになっているので、よほど混雑していない限り、二人分、三人分の座席を利用して横になって眠ることができる。寝台を使わなくても、さほど苦にならない。この旅のときは、21泊のうち、彼女の部屋に滞在した日も多かったので、ホテルなどに泊まったのは6泊だけだった。こう書いてくるときれい事に見えるが、そこには決してもう若くはない、それなりに人生経験を積んだ35歳の男の計算高さはあった。初めての外国旅行で、滞在先に知人がいるのは有利だ。ミュンヘンはちょうどヨーロッパの真ん中にある。どこへ行くにも交通のアクセスがいい。「別れを告げに行く」のに矛盾しているようだが、彼女に未練もあった。ただし彼女の心にではなく、カラダにである。25歳の彼女はやせているのにGカップで、もう少しあの巨乳を楽しみたいという未練があった。だが、それより強い未練は、付き合った半年の間にじゅうぶん彼女の性感を開発できなかったことだ。彼女は、大学の教授や講師など、かなり年の離れた妻帯者とばかり交際していた。彼女の言を信じるなら、自分本位のしかもヘタなセックスしかできない連中のようだった。セックスのヘタな男にいろいろといじられた女というのは、経験がない女よりも感じにくい体になってしまうものである。初めてセックスしたとき、これはかなり手強いと感じた。3週間のヨーロッパ旅行のうちの1週間を彼女にさくとして、僕と別れたあと出会うであろう新しい恋人と気持ちのいいセックスができるように性感を開発してあげようと考えたのである。気分はあくまでボランティアだ。彼女との円満な別れと性感開発。そんなことが両立するわけがない。結局、どちらも失敗し、それも最悪の経過をたどった。初めての外国旅行の目的はこの二つだったから、このときの旅行は失敗だったといえる。あれからもう20年近くがたつ。「ロミオとジュリエットの街」として知られるイタリアのヴェローナで別れたきり、彼女とは会っていない。しかし、彼女との出会いがなければ、いまでも海外旅行には関心がなかっただろうと思う。仮に行ったとしても、このときのひとり旅がなければ、薄っぺらな観光旅行としてしか外国を訪れることはなかっただろう。だから、彼女にではなく、彼女との出会いには感謝している。外国に行ってみなければわからないことというのはたくさんある。外国そのものではなく、自分の国のこと、さらにいえば自分自身のことだって、外国を旅して初めてわかったことというのは多い。出発前にいちばん困ったのは、お金をどうすればいいかということだった。当時はまだユーロは発足していなかった。パリの空港に着いてから少額とはいえ交通費がかかる。銀行の開いている時間に着くとは限らないので、いくらかの現地通貨はいる。それをどこでどう調達したらいいかわからないのが不安だった。父がJTBまで行って聞いてくれたが、自分の店にはヨーロッパを個人旅行する客はいままでひとりもいなかったのでわからないということだった。そのときのお金をどう用意したかはおぼえていない。たぶん、成田空港の両替所で、不利なレートで1万円分くらいのフランを用意したのだと思う。通貨の異なる国を旅するにはコツがある。つまり、前の国で余った通貨を次の国で両替する、というようなことをいっさいしないことだ。両替を繰り返すほどに手数料のためにどんどん元本が減り損をする。余った通貨は出国する国でまとめて両替する。できれば残らないようにするのがベストだ。こうして1992年11月13日、6万4千円で買った航空券と7万円で買ったユーレイルパス、円建てのトラベラーズチェックとクレジットカードを、母が作ってくれたネックポーチに入れて、ほんとにこいつはヨーロッパまで飛べるのだろうかと思わせる古びた小さな飛行機に乗り込んだ。乗り込む前に隣にいたカップルの女が「山形行きの飛行機にそっくりね」と語っていたのが不安をかきたてたがここまで来たら諦めて乗るしかない。なぜ11月13日に出発したかというと、この日を境に飛行機代ががくんと下がるからだ。いわゆるローシーズンの初日。安いだけあって若い客でほぼ満席。予想より機体が重くなったためか、13時間で到着するはずが途中モスクワで給油することになり、16時間かかった。パリに着いたときは夕方になってしまっていた。
September 6, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~フローズン・リバー
原題は同じ。2008年のアメリカ映画だが、無名監督のデビュー作だという。地味な映画なので日本公開が危ぶまれたが、東京の勇気ある映画館の働きかけによってやっと日本公開が実現したらしい。予告編から、サスペンス映画だとばかり思っていた。もう年齢的に謎解きやドキドキハラハラの映画は遠慮したい。そのためサスペンスを観る機会は減ったが、蠍座で上映するならいい映画にちがいないと思って観たところ、これが心に残る秀作だった。カナダとアメリカの国境の町で暮らす白人家族がいる。ギャンブル依存症の夫が家を出て行ったあと、二人の子どもを抱えた母は生活に困窮し、先住民の女と組んで不法移民の密入国で金を稼ぐようになる。その女も夫を事故で亡くし、子どもを義母に奪われていた。氷が割れそうな、凍った川を車で渡り不法移民を運ぶシーンだけでなく、いたるところで緊張感のある、というかいったい何が起きるのかと思わせる場面が続いて一瞬も飽きさせない。二人の女の家庭の事情も、あえて説明的なシーンは少なく、観客が読みとって理解していくように作られている。そのため、どのシーンが重要かは最後まで観ないとわからないため、集中して観てしまう、というか画面に引きつけられる。しかしこれはサスペンス映画ではなく、子を持つ母の友情のドラマだった。そのことは最後になって明らかになるが、子を持つ女性なら、男であるわたしよりもはるかに強く胸を打たれたにちがいないと感じるラストだった。最後の最後でどんでん返しというのはサスペンスの常套だが、この映画ではそれが人間の魂の変化によってもたらされ感動的なのだ。たった97分の映画で、言いたいことをすべて鮮烈に表現した監督の腕前は見事というほかない。この監督は34歳の女性でコロンビア大学で映画を教えているというが、アメリカ映画界の底力には圧倒される。
September 5, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~にっぽん泥棒物語
3週に渡って上映されている蠍座の企画「昭和の名男優・喜劇な人びと」に選ばれた6作のうちの1作。社会派として知られる山本薩夫監督の1965年作品。同時に観た1964年の「馬鹿まるだし」がカラーなのに対し、この映画はモノクロ。この時期、日本映画はモノクロとカラーが混在していた。山本薩夫監督の映画は、社会派でありながら娯楽性にも不足せず、どこかハリウッド映画に共通する大衆性を感じさせると思ってきたが、この映画も同じ印象。いっときの娯楽を求める人々と、映画に何かしら社会的なメッセージを求める人々の両方を満足させる作品になっている。1965年の映画だが、時代設定は終戦まもない1948年。ハイパーインフレで貨幣価値がなくなりアナーキーな雰囲気が満ち、鉄道謀略が相次いだ不安な時代を背景としている。土蔵破りに失敗して逃げる途中、不気味な集団を目撃する前科3犯の男。その直後に列車転覆事故が起きる。相棒のドジで4度目の刑務所入り。しかしそこで出会った列車転覆事件の犯人とされる人たちが無実であることを知る彼は、そのことに口をつぐみもぐりの歯医者として成功し人並みの幸福を手に入れていた。元々、根からの悪党ではなく、人間らしい心を持つ彼は、えん罪を晴らそうと説得に訪れる弁護士たち、刑務所で共に過ごし出所した被告の父子に出会い、とうとう自分の幸福を犠牲にして法廷で証言することを決意していく・・・というお話。貧しさゆえに歯医者への道を断たれ、しかも家族を養うために名人芸的な泥棒になった主人公の生きざまと、松川事件に取材したと思われる社会問題をうまく絡ませていて見ごたえがある。しかし何と言ってもすごいのは、主人公の浮沈激しい泥棒・もぐりの歯医者を演じる三國連太郎の演技である。歯医者のときには知性を、土蔵破りのときには大胆不敵な悪党ぶりを、結婚してからは小市民さを、クライマックスといえる法廷での証言シーンでは、いかにも東北人らしい純情素朴さを、ごく自然に感じさせるからすごい。特にこの証言シーンでの演技は彼以外では不可能だったと思われる。名優というか怪優、いや快優と言うべきだろう。刑事役の怪優・伊藤雄之助のとぼけた味わいもこの映画ならではだが、伊藤雄之助の怪優ぶりを食うほどの迫力と存在感には、大俳優の称号が贈られてしかるべきだろう。そこで思うのは、私生児として生まれ、養父は被差別部落民、中学を中退して中国に密航し、釜山で弁当売りをしたり、徴兵を逃れるために脱走し逮捕され、戦争からは命からがら生き延びて帰国したといった三國連太郎の実人生・実体験があったからこそ、これだけの演技ができたのではないだろうかということだ。もちろん生まれつきの才能や俳優としての勉強の蓄積もあるだろうが、野太く生き、しかし純情もあわせもつ人間を演じることは、渥美清のテキ屋体験などと同じで、実体験なくては不可能だったと思うのだ。最後の法廷のシーンは日本映画史に残る名シーンだ。このシーンを母語で味わうことのできない外国人はなんて不運なのかとさえ思う。抱腹絶倒のあと、裁判闘争の勝利を確信させるように映画は終わるが、やはりここでも戦後日本の初心、屈託ない健気な明るさが印象に残る。狡猾で陰湿な体制側の人間とは対称的に、貧しくても健気で、民主主義と明るい未来を信じて生きていた人々の素朴な善良さには素直に感動させられる。上映最終日に観たのが失敗だった。日をおかずもう一度映画館で観たいと思った久しぶりの映画。
September 3, 2010
コメント(0)
-
こんな映画を観た~馬鹿まるだし
3週に渡って上映されている蠍座の企画「昭和の名男優・喜劇な人びと」に選ばれた6作のうちの1作。山田洋次監督は「男はつらいよ」以前にハナ肇を主演とする6本の喜劇映画を作っていたらしいが、そのうちの1本。ここで選ばれているくらいだから代表作なのだろう。はっきり言って、山田洋次監督の映画はほとんど評価できない。「男はつらいよ」シリーズを除けばこれといった作品が見当たらないと思ってきた。「男はつらいよ」だって、かなり欠点が目につく。車寅次郎という独創的な人間を創造することには成功しているが、それだけ、という気もする。「おとうと」とか「母べえ」とか、蠍座では間違っても上映することはないだろう。蠍座で上映されるかどうかが映画のスタンダードだとすると、山田洋次の映画はそのスタンダードに満たないと考えている。しかしその蠍座で山田洋次の映画が上映されるという。もしかするといい映画なのかもしれない。そんなふうに半信半疑で出かけたが、田中次郎支配人の慧眼は相変わらず光っていた。1964年に作られたハナ肇主演ものシリーズ第1作は、もしかすると山田洋次の最高傑作ではないかと思うくらいの作品に仕上がっていた。瀬戸内の小さな町。シベリア帰りの安五郎(ハナ肇)は淨念寺に転がり込む。夫が戦地から帰ってこない住職の娘、夏子を尊敬し好意を寄せるようになる。そんな彼は町で起こるさまざまなトラブルを解決するなど大活躍し人々からも尊敬されるようになる。しかし、町長が替わり、いくつかの失敗によって人々の目は冷たくなっていき、淨念寺にも出入り禁止となってしまう。そんな折に誘拐事件が起こる。名誉挽回のチャンスと誘拐犯たちと絶体絶命の対決をしていく・・・というお話。人助けを頼まれたらイヤと言えない、単純だが情に厚い素朴な流れ者。車寅次郎とも共通するキャラクターだが、天涯孤独の流れ者である点がちがう。こういうよるべなき人たちは、戦後のある時期までは珍しくなかったにちがいないが、野生動物のように野にたくましく生きる人間を、骨太な造型で描き出すことに成功していて、その点がすばらしい。いささか劇画的な誇張もなくはないのだが、戦後のある時期まではほんとうにこういう人間がいたにちがいないと思わせる。こうした人間を演じるのにハナ肇はうってつけで、巡査役の長門勇や夏子役の桑野みゆきにしても、絶妙なキャスティングが光っている。クレイジーキャッツの面々も重要な役で要所を固めている。渥美清が1シーンだけ登場するが、そのときは会場から驚きの声があがった。わたしも驚いて、細部まで見逃すまいと集中してそのシーンを見た。ハナ肇とほとんど二人だけのシーンなのだが、やきもち焼きで酒乱の人夫役を、実に迫力ある見事な演技で演じていた。主役を食ってしまうほどの存在感と演技力であり、あらためて渥美清の俳優としてのすごさに舌を巻いた。終わり近く、安五郎が誘拐犯の放ったダイナマイトで殺されそうになるシーンがあるが、安五郎が底抜けの、ほとんど痴呆のような人の好い笑顔で立ちつくす姿は、人間の中にある神性・あるいは仏性を感動的に表現した名シーンだった。
September 1, 2010
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1






