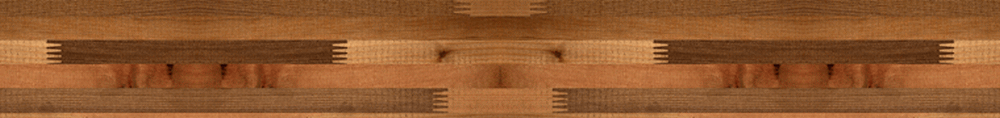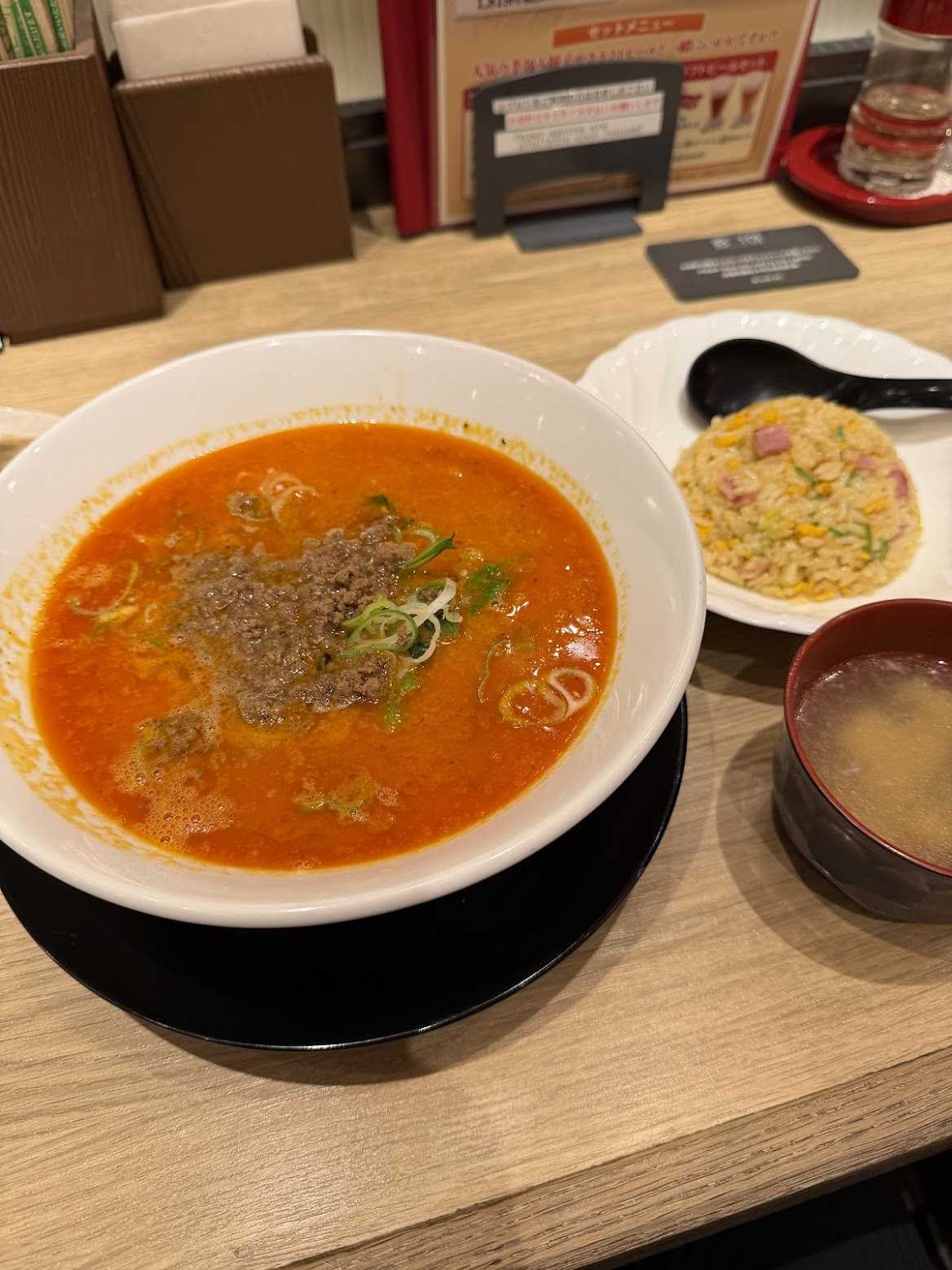2014年07月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
夏の基礎トレ その15
こんにちはenoです。選手の身体を第一に考える …(4) 酷暑が続く近年の夏。 何よりもまず身体の安全・健康を最優先にして練習に取り組もう。 時間があるからといって、長すぎる練習はかえってマイナスになります。 そして何より、 練習中の水分補給と休憩時間の設定を慎重に行う必要があります。 私は試合時間の「40分間」の練習に集中し、継続して行えることを 目標としてきました。それでも選手の特性に即した、練習時間の設定が やはり欠かせないところです。 各選手の状態をうかがいながら、 練習を慎重に進めていくよう心掛けてください。 約1ヵ月間の夏休みを有意義に過ごせるかどうかで、 チームは大きく変わってくるというのは事実だと、経験的に実感しています。 この夏、みなさんが良い夏の過ごし方をすることができ、素晴らしいチーム、 素晴らしい選手を育てていかれることを、心より願っています。
2014年07月28日
コメント(0)
-
夏の基礎トレ その14
こんにちはenoです。選手の身体を第一に考える …(3) チーム事情によって、いろいろな考え方があるのは承知しています。 否定するつもりは、まったくありません。 そうした前提に立ち、私はクリニックなどでよくこう言います。 「あまりにも過激なトレーニングは控えるように心がけましょう」と。 何より選手の身体を第一に考えなければならないからです。 暑い夏は特に、細心の注意を払うべき季節だということを忘れてはなりません。 例えば、私は一度の練習を「3時間以内」と決めていました。 指導する側の集中力が続かないという事情もそこには含まれているのですが、 体育館に空調設備がついていないのなら、なおさら長時間の練習を避けるのが 賢明でしょう。 そういう意味では、昼間の最も暑い時間帯、12時頃から14時頃からまでの 間に練習することもお勧めできません。 その間に十分な休養を取れるのであれば、午前・午後の「2部練」を行うことも 決して間違いではないと思います。
2014年07月25日
コメント(0)
-
夏の基礎トレ その13
こんにちはenoです。選手の身体を第一に考える …(2) 指導者の立場から言えば、自身が考えていることを選手に伝え、 選手が考えていることをしっかりと把握する場が必要なはずです。 練習中の言葉というのは、どうしても厳しくなってしまうもの。 選手への言葉のかけ方も、指導者としての手腕が発揮されるところでしょう。 チーム作りを開始した時期というのは、選手はミスを連発するもの。 それを逐一すべてに対して怒声を向けていたら、選手は萎縮してしまいます。 したがって、その選手がまず意識するべきことを指摘させてあげる。 それがクリアできたら、別の課題を与えていくという具合にしていくと、 選手も自信を持って練習や試合に臨むようになるものです。 監督に言われたことを、ただこなすことだけでなく、 自分でしっかりと物事を考えられるような自立した選手を育てる。 それもまた、チームの土台を作る時期の過ごし方に関わっているように 感じられます。
2014年07月23日
コメント(0)
-
夏の基礎トレ その12
こんにちはenoです。選手の身体を第一に考える …(1) 監督と選手がコミュニケーションを図る上でも、 夏休みの期間を逃すわけにはいきません。 特に学校の教員という立場の方々は、普段、校務に追われ、 チームの選手とゆっくり話しあう時間を持てないのではないでしょうか? そこで、夏休みの間だけでもミィーティングの時間を作り、 選手と向き合ってみてはどうでしょうか。 私が高校生の頃は、約10日間の合宿が行われ、 必ず夜にはミィーティングの時間が設けられていたものです。 今でも尊敬してやまない、素晴らしい監督でしたが、 当時は練習で疲れていたこともあり、ミィーティングは正直億劫でした。 それでも指導者の立場から言えば、自身が考えていることを選手に伝え、 選手が考えていることをしっかりと把握する場が必要なはずです。 練習中の言葉というのは、どうしても厳しくなってしまうもの。 ですから、理論的な話を選手とともに積み上げていくという意味でも、 ミィーティングが欠かせないのです。
2014年07月21日
コメント(0)
-
夏の基礎トレ その11
こんにちはenoです。「 夏休み 」という時期を活かす …(6) 部員数が少なくて5対5が出来ないチームもあるでしょう。 その時は3対3の練習を通じて選手達を見ていくこともできます。 先述したように、5対5になるとボールを持つ時間に偏りが出てくる場合も よくあります。それだけに、3対3の練習なども大事にしたいところです。 チームの方向性に加えて、自分の役割を理解する。 その上で基本練習に取り組み、その必要性を5対5の練習を通じて実感する。 そうした段階を踏むと、スターティング・メンバー、および6番手で出場 するべき選手が自然と浮かび上がるように感じることが今までにもありました。 それは指導者の独断で決めたメンバーというより、 名実ともにチーム全体に選ばれたメンバーだということです。 このようにしてチームの土台を築き上げていくことによって、 指導者だけでなく選手も納得のいく布陣で戦うことができる。 そして監督と選手間の信頼関係があってこそ、 選手は前向きに基本練習にも取り組むようになるのだと思います。 まさしくこうした姿勢こそが、 秋以降のチーム作りをスムーズに進めさせてくれるのです。
2014年07月16日
コメント(0)
-
夏の基礎トレ その10
こんにちはenoです。「 夏休み 」という時期を活かす …(5) オールコートを使える限られた時間、期間を有効に活かす方法に関しては、 一考の余地があるはずですが、もちろん、5対5の練習をメインに、という 極端な考えを持っているわけではありません。 5対5の中でどれだけ個々の力が発揮されるかという問題も、当然あります。 新チームに切り替わる前から試合に出ていた選手にばかりボールが集まり、 他の選手の特長や課題をつかめないまま練習時間が経過してしまうことも あるかもしれません。そのような事態は避けたいところです。 そこで、コミュニケーションをより図っておきたいのが、 各チームのポイントガードの選手です。 どの選手が良い動きをしていたのか。逆に戸惑っていて精彩を欠いた選手は 誰だったのか。もしくは、サボっているような選手が見受けられたか。 そうしたことを各チームのポイントガードから聞き出すと、 選手を把握する上で有益な情報を得られることがよくあります。
2014年07月14日
コメント(0)
-
夏の基礎トレ その9
こんにちはenoです。「 夏休み 」という時期を活かす …(4) 夏休みの最後1週間の練習では、身長やポジションのバランスを考えながら 5対5で競い合わせて、基本プレーの確認や、攻防に慣れることを狙います。 次の日にはポイントガードを入れ変えます。 そしてまた次の日には、2番ポジション、すなわちシューティングガードを 入れ変えます。さらにその翌日にはセンターを全て入れ替えて、5対5を 繰り返していくわけです。 ちなみに、3番、4番ポジションのフォワード陣に関しては、 特にチームを動かさなくても、ある程度は把握できるものと思っています。 チーム事情によっては、5対5をいきなり取り入れることに違和感を 覚えられるかもしれませんが、私としては様々な面でお勧めの方法だと 考えています。 いずれにしても、オールコートを使える限られた時間、期間を有効に活かす 方法に関しては、一考の余地があるはずです。
2014年07月11日
コメント(0)
-
夏の基礎トレ その8
こんにちはenoです。「 夏休み 」という時期を活かす …(3) 夏休みの最後の1週間の練習では、5対5で競い合わせるのも手です。 夏休みの間に意識してきた基本プレーがどれだけ自分のものになっているか 確認を得るため、また、全員が5対5の攻防に「慣れる」という意味でも 必要なことです。 例えば、部員が20人ならば、身長やポジションのバランスを考えながら 4チームに分けます。 そうして試合を重ねていく中で、自信を獲得する選手がいれば、逆に課題に 直面する選手も出てくるでしょう。 それが狙いであるわけですが、まだ続きがあります。 次の日には、それぞれのチームのポイントガードをすべて入れ替えて行います。 他の選手との相性を見ながら、コンビネーションの可能性や、 メンバーチェンジの可能性をそこで探ることが主な目的です。 ポイントガードが変わっただけで見違えるような力を発揮する選手、チームが 出てくることも決して珍しくないのです。
2014年07月09日
コメント(0)
-

夏の基礎トレ その7
こんにちはenoです。「 夏休み 」という時期を活かす …(2) 全体像の構想と照らし合わせながら、オールコートもしくはハーフコートで 5対5を展開していき、最初はディフェンスをつけない「空動き」で、形を先に 理解させる。 次にディフェンスを立たせて、ウォークスルーでやってみる。 さらにディフェンスのプレッシャーを強めて、ゲームへと近づけていきます。 こうした練習を通じて、チームが目指すスタイルの中で自らに必要とされる 基本プレーが意識しやすくなるに違いありません。 他にも、5対5の練習を夏休みから取り入れるメリットはあります。 夏休み期間中くらいしか、体育館を十分に確保できないというチームも 少なくないはずです。 そういうチームこそ余計、コートを広く使って、普段はできないことを 夏休みの間に行っておくべきかもしれません。ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年07月07日
コメント(0)
-

夏の基礎トレ その6
こんにちはenoです。「 夏休み 」という時期を活かす …(1) 監督がチームの指針を表明する。 選手が自分の当面の役割を認識する。 それをより理解しやすくさせるためには、全体像をつかめるような練習が 欠かせないと思っています。 つまり、5対5の練習を早期に取り入れるということです。 高さを武器にできそうなのか、速攻を武器できそうなのか、 そこからスタートして、どういうシステムをチームのベースにしていくのか。 センターを1人立たせる4アウト1インなのか、それとも2人立たせる 3アウト2インなのか。はたまた5人全員がアウトサイドから仕掛ける 5アウトなのか。 そうした構想と照らし合わせながら、オールコートもしくはハーフコートで 5対5を展開していきます。ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年07月04日
コメント(0)
-

夏の基礎トレ その5
こんにちはenoです。指導者と選手との考え方を合わせていく …(3) 確かに、ポジションにこだわらず、全ての基本を覚えることが大事です。 しかしながら、チームを強くさせていくことを個々のレベルアップへと繋げて いくのなら、ポジションや役割を意識させる必要がきっとあるはずです。 ただし、指導者の考えていることを選手に押しつけるというスタンスより、 両者が相談しながらチーム構想に基づく役割を浮かび上がらせていくという やり方が理想でしょう。 そうやって、指導者と選手、双方のベクトルを同じ方向に合わせていくことが チームとしての土台を築く上で必要不可欠だと強く感じるわけです。 チーム作りを開始した時期はまず、こうした練習への取り組み方を してみてはどうでしょうか。ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年07月02日
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1