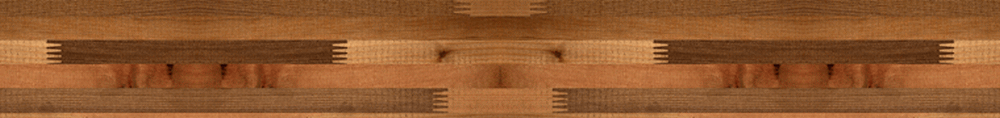2014年02月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

「からだ ”いじめ”」は社会の迷惑です その4
こんにちはenoです。 ◆ 痛みの原因スポーツ外傷とスポーツ障害の違い … ケガをすれば痛みが出るわけですが、特に覚えのあるようなケガをしたわけでもないのに、少しずつ痛く(悪く)なっていく場合があります。 これは「スポーツ障害」と呼ばれ、「使い過ぎ」による無理が重なって生じる 痛みです。それとは別に、捻挫や打撲、骨折などの突発的に起きるケガは、 「スポーツ外傷」と言います。 スポーツ外傷にしろ、スポーツ障害にしろ、痛みという「危険信号」に どの様に対処するかが大切なのですが、そのまま放置されたり、対処が 遅れたりしやすいのが、スポーツ障害です。 「痛いけど、何とか練習はできる」ような痛みが続き、どうしたらいいか モヤモヤしているうちに悪化してしまうのです。 痛み始めた最初のところで治療を受けていれば治りが早かったのに、 痛みを我慢して無理したために、障害がひどくなって、なかなか治らない 状態にまで進んでしまうことがあります。 次の項目で説明するのは、そういうスポーツ障害の代表的なものです。 (スポーツ外傷による痛みについても適切な対処が必要ですが、これについては 先に、足首の捻挫を例に説明したので参照してください)■ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月28日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ” 」は社会の迷惑です その3
こ んにちはenoです。 ◆痛みという「からだの声」を無視しないこと … この連載の3回目でも述べましたが、からだとの付き合い方でまず気をつけて もらいたいのが、痛みに対してです。 痛みを我慢することが当たり前になっている「習慣」が、 どれほど日本のスポーツを弱くしていることか! 痛みは、からだが発する「危険信号」と言えます。その信号を無視し続ければ、やがては取り返しのつかない「大事故」につながります。 バスケットボールをするのに、目や耳の判断、指先の感覚などが大切なように、 からだを出来るだけ良いコンディションに保つために、痛みという感覚は大切なのです。 痛みという「危険信号」がなければ、私達はそれこそ、からだが壊れて動かなく なるまで(そして、全く取り返しがつかなくなるまで)無理を重ねてしまうの だと思います。 痛みというのは、言わば、からだから送られてくるボールです。 そのボールを良く見ること、そしてきちんとキャッチすること、さらにそのボールをどのように投げ返せばいいかを考えることです。 ボールをよく見て状況判断をしなければ、良いプレイはできません。 からだとの付き合い方も、バスケットボールの基本と同じです■ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月26日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ” 」は社会の迷惑です その2
こんにちはenoです。 ◆ 健康管理もバスケットボールのための大切なテクニック …(2) 「体いじめ」は、やがては自分のからだ自身から「復習」されるということを 心してください。 4月。新チーム。新人も上級生も新たなスタート。 その第一歩として考えてもらいたいのが、自分自身の健康管理です。 バスケットボールのテクニックを身につけていくことはもちろん大切ですが、 自分の体とのうまい付き合い方、ベスト・コンディションを作るテクニックを 身につけることも、また大切です。 体という、 しっかりした「土台」があってこそ、素晴らしいプレイが出来るのです。 この他にも気をつけるべきことはありますが、まず体の状態をいつも意識して 体との付き合い方を覚えていくことが大切です。 以下に上げるのは、 選手に知っておいてもらいたい、健康管理に関する身近な知識です。 ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月19日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ”」は社会の迷惑です その1
こんにちはenoです。 ◆ 健康管理もバスケットボールのための大切なテクニック ...(1)ちょっと古いけども、「かぜは社会の迷惑です」というCFがありました。(CFとは、コマーシャルフィルム。つまり一般的にはテレビCMです。それ以外にも、映画館で上映前に映るものや、街頭のオーロラビジョンに映っているものもそうです)それになぞらえて言えば「体いじめは社会(チーム)に迷惑です」と言いたい。体を大切にするかどうかは、監督・コーチの指導にもかかわることですが、何よりもそれは選手自身の自覚が決定的に重要と言えます。「自分による、自分のための健康管理」をやるかどうかです。この連載でこれまで述べてきたように、体の状態が良くないのに、無理をして具合を悪化させることは、結局は自分のためにも、チームのためにもならないのです。体や心を鍛えること(トレーニングをすること)と、体をいじめることを混同しないことです。ハード・トレーニングは必要ですが、それは体をいじめることになります。いじめと痛めつけることは違います。 ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月17日
コメント(0)
-

身の回りの”ベスト・コンディション”を忘れるな その11
こんにちはenoです。 ◆ シューズの選び方 ...足の "ベスト・コンディション" を作るうえで、足に合ったシューズを選ぶことはとても大切です。シューズを選ぶ際のポイントは、自分のサイズ(何センチか)にとらわれず、履いてみてやや余裕のあるくらいのものが良いでしょう。一般に0.5センチくらい余裕のあるものが良いと言われています。靴下は普段練習で履いているもので試してみること ...。利き足の方がやや大きいことがあるので、両足とも履いてみて、大きいほうの足に余裕のあるものを、また、シューズのソールの形はメーカーによって違うので、色々なメーカーのものを試してみるのも大切です。シューズは足に余裕がなくギューギューだとマメ(水泡)ができやすいし、余裕がありすぎると、これもマメができやすい。余裕があり過ぎる場合は、靴下を2枚履くと良いでしょう。また、できれば1足だけをずっと履くのではなく、2足以上を交互に履くようにした方が、足にとってもメンテナンス上も良いと思います。 ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月14日
コメント(0)
-

身の回りの”ベスト・コンディション”を忘れるな その10
こんにちはenoです。 ◆ 足の手入れ ...(2)練習後の手入れとして、夏は特に、すぐに靴下を脱いで、足を石鹸で洗うようにしていました。水や血がたまったマメ(水泡)は、運動中に破れる可能性があるので、滅菌した針などで皮膚の外装を刺して、内部のたまりを出すようにしていました。ただし、内側(深部)の皮膚層が硬くなるまでは、皮を切らずにそのままにしておきます。そして、消毒を十分に行います。選手の人達が自分でタコやマメの処置をするときは、バイ菌が入らないよう、消毒にはくれぐれも注意してください。自分で処置するのが不安な時、または傷口が悪化しているようであれば、すぐに専門医に診てもらうべきです。足に爪の手入れも、出来るだけこまめに行うことが大切です。爪が長いままシューズで圧迫していると、爪が肉質に食い込んでくる「陥入爪」と言う障害が起きやすくなります。陥入爪(かんにゅうそう)とは、爪の角がトゲのように軟部組織(爪内部の肉)に刺さって 炎症を起こした状態をいいます。巻き爪と混同されがちだが、巻き爪とは横方向に爪が巻いた ようになる現象のことを指し陥入爪とは異なります。 ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月12日
コメント(0)
-

身の回りの”ベスト・コンディション”を忘れるな その9
こんにちはenoです。 ◆ 足の手入れバスケットボールの動きは、コートと接している「足」から生まれます。 その足のコンディションにも、私達はもっと気を配っても良いと思います。例えば、マメ(水泡)やタコなどは誰でも一度ぐらいは経験があると思いますが病院へ行くほどではないと思いながら、痛みを長く抱えるということが珍しくありません。特にマメ(水泡)は、放置しておくと何重にも重なってきたり、場合によっては内部が膿んでしまったりして、練習が出来なくなることさえあります。日立戸塚時代では、タコのある選手は、練習前にそれを削っておくようにします。 私達は「タコ削り」と呼んで、T字型のカミソリを使っていました。 ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月10日
コメント(0)
-

身の回りの”ベスト・コンディション”を忘れるな その8
こんにちはenoです。 ◆ 寒い時のウェア ...今年は、例年になく寒暖差が激しく、まだまだ寒い時期が続きます。寒さを我慢して、そこに精神力を使うよりも、練習や試合のプレイそのものに全エネルギーを集中できるようにした方が賢明です。小さなことですが、寒さに対して、"ベスト・コンディション"で臨む工夫も大切です。日立戸塚時代では、寒い季節には、Tシャツ、短パンの上にスウェットの上下(ジャージー、ハーフ・パンツなど)、さらにその上に保温効果のあるウィンド・ブレーカーの上下を着ていました。そして、選手個々の体の暖まり具合によって、それぞれが別々に脱いでいきます。また、手袋やリスト・バンド、レッグ・ウォーマーなどの小物も、選手によっては使っていました。手、手首、足首などは、体の中でも暖まりにくいところですし、逆に言えば熱が逃げていきやすいところだからです。一度脱いだスウェットなども、体が冷えてきたらまた着るなど、体のコンディションに合わせて、柔軟な対応を考えてみても良いのではないでしょうか。これは寒い時に限らず言えることです。 ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月05日
コメント(0)
-

身の回りの”ベスト・コンディション”を忘れるな その7
こんにちはenoです。 ◆ 汗をかいた後のウェア ...本当は不快なはずなのに、意外に無頓着にすまされているのが、汗をかいた後のウェアや下着です。体の「メンテナンス」を、出来るだけ良好にしておきましょう。濡れた衣服をそのまま着ていると不快なだけでなく、体が冷えて風邪をひいたり、体調をこわしたりしやすくなります。当然のことなのですが、日本では練習中や練習後に、汗をかいたウェアや下着を変える習慣が一般的でないため、多くの選手達が汗をかいたままにしています。汗をかいたら、自分で用意したタオルで拭く。そして、Tシャツがびしょびしょになって不快だったら、練習中でも着替えられるようにしたいものです。練習後も、濡れた下着をそのまま着て帰る選手が多いようですが、出来ればそれも着替えた方が衛生的です。こうしたことはチームで一律に決めて行うと言うより、やはり選手個々のコンディショニングの意識の問題の方が大きいと思います。"ベスト・コンディション"は、単にトレーニングの問題だけではなく、身の回りの「メンテナンス」の問題でもあるわけです。不快な状態を我慢するのではなく、出来るだけ気持ちよくスポーツするために努力することが大切です。 ■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年02月03日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…
- ホークスを日本一に導いた小久保監督…
- (2025-11-13 22:51:08)
-
-
-

- スキーのコト、雪のコト、はなしまし…
- ★南月山に雪★
- (2025-10-29 17:07:47)
-
-
-

- テニス
- 今年最後の三連休中日 ~当方には関…
- (2025-11-24 00:10:05)
-