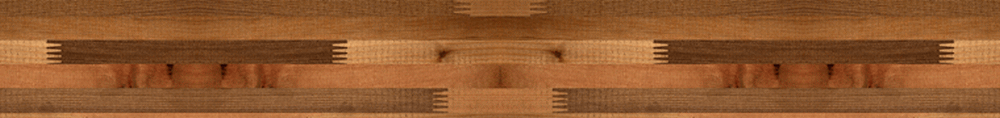2014年03月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
からだに、自信ありますか? その4
こんにちはenoです。 痛みをパーセンテージで書いてみる …(2) 「健康日報」は、練習前に選手各自が記入して、 ネージャー(トレーナー)がチェックする。 また、毎日の「健康日報」は個人ごとにファイルして、 練習の時はコートサイドに置いておく。 ≪ 健康日報記入の注意事項 ≫ ※ 痛みのパーセンテージと練習への影響 1)痛みの% 2)痛みの感覚 3)練習への影響 1)9%以下 2)ほとんど気にならない程度 3)練習するうえで影響はない(正常に練習ができる状態) 1)10~19% 2)何かの時にフッと痛みを感じる 3)同上 1)20~29% 2)明らかに特別な動作で痛みを感じる(走る、ストップ、ジャンプ) 3)同上 1)30~39% 2)じっとしていても痛みを感じたり、気になったりする 3)同上 1)40~49% 2)練習中に意識の中に痛みを感じることが多い 3)練習中に気なることがある 1)50~59% 2)特定の動作について痛みを感じる 3)練習はできるが特定のメニューについてはできないものがある 1)60~69% 2)特定の動作のみならず痛みを感じることが多い 3)練習は何とかできるが自分の動作をセーブしなくてはならない (練習種目を限定して行う) 1)70~70% 2)日常生活のうえでも支障が多く、スムーズな動作に欠ける 3)ストレッチ、支障のある部分以外のトレーニングのみ行う 1)80~100% 2)常に痛みが伴う3)完全休養
2014年03月31日
コメント(0)
-

からだに、自信ありますか? その3
こんにちはenoです。 痛みをパーセンテージで書いてみる …(1) 「健康管理」の最大の特徴は、選手に自分のからだの痛みを、パーセンテージで書いてもらうことにあります。 選手は痛みがあっても、ついつい無理しがちなものです。 少しくらいの痛みは、我慢するのが当たり前になっている日本の現状では、 監督やコーチに痛みを伝えるのはなかなか難しいことです。 コーチの側も、選手の痛みが分からないので、知らず知らず無理させてしまう。 この大問題を解決するために考えたのが、選手に「自己申告」してもらう ことだったのです。 以下に、「健康管理」の特徴や使い方の要点を挙げておきましょう。 各チームの健康対策の参考になればと思います。 また、選手の人達に分かってもらいたいのは、自分自身の健康状態を把握する ことの大切さです。 そして、こうした日報がチームになくても、痛みや体調を監督やコーチ (またはトレーナーやマネージャーなど)に伝えることの大切さです。 勇気を出して、痛みを伝えてください。 ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月29日
コメント(0)
-

からだに、自信ありますか? その2
こんにちはenoです。”健康“ に対する疑問 …(2) 「元気ハツラツ」「健康的」というスポーツのイメージは、 スポーツ選手にとって逆に「落とし穴」になっていると思います。 過激に体を使う選手こそ、からだをいたわらないといけない。 スポーツをやっていない人よりも、さらに健康には気をつかうべきです。 「健康管理」と言うと、例えば中高年の病気予防という感じで、 スポーツ選手にはピンとこないかもしれませんが、 これはコンディショニングの「土台」を成すものです。 この連載でこれまで述べてきたことも、健康管理にかかわることが 多いのですが、今回はチームでの健康管理の一例(一方法)として、 日立戸塚時代で行ってきた「健康管理」を紹介します。 ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月26日
コメント(0)
-

からだに、自信ありますか? その1
こんにちはenoです。 ”健康“に対する疑問 …(1) スポーツ選手と言えば「頑丈で健康」というイメージがありますが、 本当にそうでしょうか。 確かに、筋力や心肺能力などの体力が、スポーツを行なっていない人に比べて、 一般的に高いとは言えるでしょう。 しかし、競技は能力に必要な体力が高くても、それは健康だということでは ありません。いくら体力があっても、病気もすれば、ケガもします。 むしろケガはスポーツをしない人よりもずっと多いし、 痛みに耐えている「不健康」な選手は少なくないはずです。 競技スポーツというのは、日常生活では行わない過激な運動を行います。 だからこそ、その苛酷さは「健康のための適度な運動」とは異なるのです。 また、その過激さゆえに、スポーツ外傷や障害も生じるのです。 ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月21日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ”」は社会の迷惑です その9
こんにちはenoです。 スポーツ障害の起きやすい代表的な例 …(腰:2) 腰の痛みの原因は、大きく分けると3つあると言われています。 (筋、筋膜性の痛み) いわゆる「ギックリ腰」のように突発的に起きることもあるが、スポーツ選手は 「使い過ぎ」による痛みが、腰痛全体の中でもかなりの部分を占める。 (腰椎【脊髄】分離症) 腰椎の一部が、激しい運動による繰り返しの負担で「疲労骨折」を起こす 障害と考えられている。 小・中学生に多く見られる。腰を反ったり、捻ったりすると痛む。 (椎間板が原因の痛み) 脊髄と脊椎の間の椎間板がはみ出したり、変形したりすることで起こる痛みで、 椎間板ヘルニアはこれに含まれる。 椎間板ヘルニアは、腰からお尻、脚の方まで痛みやしびれがあるのが特徴。 これらのいずれの場合にしても、痛みが出たら、まずは病院で診てもらうこと。 また、腰痛の予防の意味からも、腹筋の強化と腰部のストレッチングを日頃から 行なっておくことが大切。 今回はスポーツ障害への対処を中心に、選手自身が行うべき健康管理について 述べましたが、次回は貧血や女子選手の生理、その他の健康管理について取り 上げる予定です。 ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月19日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ”」は社会の迷惑です その8
こんにちはenoです。スポーツ障害の起きやすい代表的な例 …(腰) 腰の痛みを経験したことのあるスポーツ選手は、とても多いと思います。 スポーツ選手でない人でも、腰痛に悩む人は非常に多く見られます。 なぜそんなに腰痛が多いかと言うと、原因の一つは腰の構造そのものに 由来します。もともと四足歩行だった人間が、直立して歩き始めた時から、 腰の部分に負担がかかりやすくなったと言われています。 スポーツではその上に、ジャンプやストップ、ターンなどのたびに腰に 負担がかかるので、「使い過ぎ」によるスポーツ障害は、腰に起きやすいわけです。 腰という漢字は、月(にくづき。肉、身体の意味)と、要(かなめ)という 字からできていて、つまり、からだの大切なだと言うことを表しています。 からだの要となるところに痛みが出やすいわけですから、腰を良い状態に するために細心の注意を払っても良いと思います。 腰の痛みの原因は、大きく分けると3つあると言われています。 ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月14日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ”」は社会の迷惑です その7
こんにちはenoです。 スポーツ障害の起きやすい代表的な例 …(足首の内側や足の甲) 捻挫や打撲などをした覚えもないのに、足首の内側や足の甲に痛みが続く場合も 「疲労骨折」の疑いがあります。 この他、大腿部(太もも)の骨にも「疲労骨折」が起きることがあります。 「疲労骨折」に限らず、痛みが長引く場合には、スポーツ障害を起こしている 疑いが高いので、ウヤムヤのまま我慢せずに、できるだけ早期に病院で診てもらう ことを心掛けるべきです。 スポーツ障害の起きやすい代表的な例 …(膝) 膝のおさらの下の部分に、骨が少し出っ張っているところがあります。 ランニングやジャンプの繰り返しによって、おさらとこの骨の部分が痛んで くるのが「ジャンパーズ・ニー」と呼ばれる膝蓋腱炎(しつがいけんえん) と呼ばれるスポーツ障害です。 これは骨の障害ではなく、膝のおさらとその下の出っ張り(スネ骨の上端)とを 結ぶ靭帯が、ランニングやジャンプの繰り返しによって炎症を起こすものです。 痛みはやはり徐々に強くなってきて、練習にも支障が出てくるようになります。 痛みが出始めたら、できるだけ早く病院での診断と治療を受けること。 そして、再発予防のために、どのように対処すれば良いのかのアドバイスをも、 できるだけ詳しくしてもらうことです。ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月12日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ”」は社会の迷惑です その6
こんにちはenoです。 スポーツ障害の起きやすい代表的な例 …(スネ) ランニングやジャンプを繰り返すことの多い競技で起きやすいのが、「疲労骨折」です。 「疲労骨折」と言うのは、突発的なケガ(スポーツ外傷)でポキッと折れる 骨折ではなくて、無理な力が繰り返しかかることで、骨に微細な損傷が生じ、 小さなヒビが入った状態になる障害のことを言います。 「疲労骨折」は色々な部位に起きるのですが、特に多く見られるのがスネです。 (スネの「疲労骨折」とほとんど同じ症状で「シン・スプリント」と呼ばれる傷害もあります) 最初は運動している間だけ痛いのですが、徐々に練習以外の時も痛むようになり 練習もできないほどの痛みに発展していきます。 スネの内側(筋肉のついていない側)に起きるのが多いのですが、スネの外側 (筋肉のついている側)にも起きます。 特に打撲などをした覚えもないのにスネに痛みがあり、 それが長引いているようならまずは病院で診てもらうこと。 ただし「疲労骨折」の場合、痛み始めて1週間くらいはレントゲンに骨の ヒビが写らないことがあるので「疲労骨折」が見透かされることがあります。 いつからどのように痛むかなど、痛みが出てきた状況を医師にキチンと 伝えることが大事です。■ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月07日
コメント(0)
-

「からだ ”いじめ”」は社会の迷惑です その5
こんにちはenoです。膝、スネ、足、腰などの痛み … 中学や高校の段階では特に、新入生と上級生の体力差は歴然です。 また、同じ学年でも選手によって体力差はあります。 さらに言えば、からだの構造や技能などの違いも個人差があります。 つまり、チームで同じ練習しても、からだにとってどれくらい負担になるかは 選手一人一人で違うのです。 コーチがいくら気をつけても、選手一人一人の体力や技能に応じた練習を 組むことは不可能と言えるので、やはり選手自身が自分のからだにいつも 気を配っておく必要がある。 スポーツ障害と言うのは、からだに無理な運動を繰り返していく中で生じる ものなので、体力のない選手に起きやすいと言えます。 ただし、体力のある上級生でも、要はからだにとって無理な力を繰り返し、 欠けていればスポーツ障害は起きるので、選手はいずれにしても注意が必要です。 スポーツ障害を予防するには、からだに無理な運動を繰り返させないように することですが、毎日の練習で何をどれだけすれば無理になるかということを 判断するのは難しいので、実質的な対応策としては、痛みを「手がかり」として 痛みが出たらできるだけ早めに治療や、練習の軽減(練習を休んだり、痛みの ある部位を安静にする)などを図るということです。 以下にあげるからだの部位は、スポーツ障害の起きやすい代表的な箇所です。■ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2014年03月05日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1