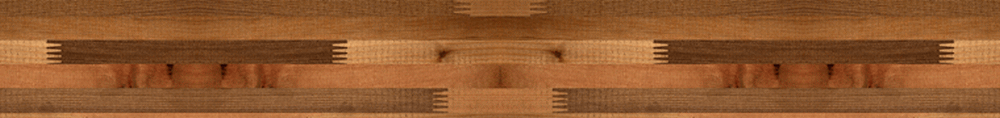2014年11月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
この時期、体調は万全ですか? その4
「からだとの対話」スポーツ外傷と障害について …(1) 秋から冬にかけての試合を迎えるにあたって、 今回は、よりよい「からだとの会話」のあり方について大切なところを、 さらに考えてみたいと思います。 以前で説明したように、一般にスポーツのケガと言われているものの中には、 「スポーツ外傷」と「スポーツ障害」と呼ばれるものがあります。 簡単に言うと、スポーツ外傷というのは、捻挫や打撲、骨折などのように、 突発的な事故によって起きるものです。 スポーツ障害というのは、 からだに無理な運動を繰り返し行う中で生じるものです。 「からだとの対話」という観点から、 スポーツ外傷やスポーツ障害について考えてみましょう。 例えば、足首の捻挫をした場合、軽くても痛みはあります。 この軽い痛みが案外、無視されていることが多いのではないでしょうか。 少しくらいの痛みは我慢して練習しようとする。 しかし、その「少しくらい」が問題なのです。 そのために、治りが遅くなったり、ケガの程度をかばいながら 無理して動こうとするために、膝や腰などにまで余計な負担をかけ、 さらに痛めてしまうことがあります。
2014年11月26日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その3
自分のからだと上手く対話できるのがいいプレーヤー …(3) 「痛み」という、最も受け取りやすいパス(聞き取りやすい声)すら無視 するような人は、その他にからだが語っている様々な声、小さなささやきも、 恐らく耳に入らないに違いありません。 もったいない話です。せっかくのからだの「声」に耳を傾けようとしないばかりに 自らチャンスをつぶしていくわけですから…。 さて、皆さんはからだとの「対話」をきちんと行っているでしょうか。 4月の新チームの編成から半年以上が経ち、練習と試合を重ねる中で「痛み」、 「無理」も重ねてきているのではないでしょうか。 からだに故障があって、痛みがあるのに、それを我慢すること。 練習に出ないと後ろめたい気持ちがして、無理に出ようとすること。 それらが自分自身にとっても、またチームにとっても、 よい結果を生まないことは、以前でお話ししたとおりです。 欧米の小・中・高校などでは、こんな日本的な無理の仕方は、 まず考えられないということも付け加えておきます。 痛みを我慢したり、無理して練習するのが当たり前になっている日本の状況は 欧米人から見ると、以上に映るということです。
2014年11月19日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その2
自分のからだと上手く対話できるのがいいプレーヤー …(2) 言葉のやりとり(つまり会話)でお互いを十分に理解し合うためには、 話をよく聞いて、そして相手が受けとめやすいような(つまり理解しやすい) 言葉のパスを送る。 同じことは、自分自身のからだに対しても言えます。 からだが発している声にきちんと耳を傾け、聞くところから、 より良いコミュニケーションは始まります。 痛みというのは、まさにからだが発している「声」です。 このままでは危険だということを知らせているわけです。 その大切な声を無視することが、コミュニケーションのあり方として、 最悪の状態であることは言うまでもありません。 バスケットボールのボールのやりとりで言えば、試合の最も大切な場面で、 味方のパスを無視してしまうようなものです。 まさか大切なパスを意識的に無視するような選手はいないでしょうが、 「からだとのパスのやりとり」に関しては、無視に近い状態の人が、 かなりいるのではないでしょうか。
2014年11月14日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その1
こんにちはenoです。自分のからだと上手く対話できるのがいいプレーヤー …(1) 痛みという「からだの声」をきちんと聞きながら、コンディション作りを 行なっているでしょうか。 ついつい無理を重ねて、「からだいじめ」を行っていないでしょうか。 以前にも述べたように、バスケットボールというのは、状況判断が大切な競技です。 敵や味方の動きを見て、即座に反応する。展開を読む。 それはいわば、1個のボールのやりとりを巡っての「対話」です。 人と人が言葉で話をするのと同じように、ボールのやりとりを通して、 話をするわけです。 言葉のやりとり(つまり会話)でお互いを十分に理解し合うためには、 まずは相手の言葉をうまくキャッチする必要があります。 話をよく聞くことです。 そして相手が受けとめやすいような(つまり理解しやすい)言葉のパスを送る。 それが、より良いコミュニケーションをしていくための原則的なことです。
2014年11月12日
コメント(0)
-
食べて勝つ!”食事で作るベストコンディション” その31
こんにちはenoです。貧血への対策も気をつけておきたい …(5) この連載で何度も言っていることですが、技術を高めることだけが バスケットボール選手としての能力を高めるわけでなくて、体そのものの 能力を高めることです。 ベスト・コンディションを作るために日常生活のレベルから努力することも パフォーマンス向上にとても大切なことです。 バスケットボールは、 敵や味方の選手の動きをよく見て状況判断することが大切です。 それと同じように、自分の体の状態をよく見て、 どうすればいい状態を作れるかの状況判断ができることが大切です。 外側ばかり見ていて、内側(自分自身)をよく見ていないと プレイは必ずつまずくし、より良いパフォーマンスは生まれません。 より良いパフォーマンスは、常に意識しながらそれぞれの食事対策について、 じっくりと取り組むことです。
2014年11月10日
コメント(0)
-
食べて勝つ!”食事で作るベストコンディション” その30
こんにちはenoです。貧血への対策も気をつけておきたい …(4) 貧血対策の食事を、なぜ夕食中心に考えるかというと、 先にも少し触れたように、たんぱく質と一緒に摂るのが効果的です。 もう一つの理由は、貧血への対策を筋肉作りとセットで考えると、 さらに効果的だからです。 筋肉の中のミオグロビン(筋肉中にあって、酸素分子を代謝に必要な時まで 貯蔵する色素タンパク質)の数も増えて、酸素の貯蔵を作る能力も大きく なります。それが、貧血の改善につながるわけです。 ですから筋肉作りのためのウェイト・トレーニングを行って、 夕食でタンパク質を十分に摂る(そして睡眠中に筋肉作りが行われる) ことが、貧血への対策としても役立つということになります。 しかし、こうした貧血対策の食事を毎日行うことは簡単ではありません。 簡単ではありませんが、考えてみれば、貧血のためにせっかく努力している 練習の効果が上がらず、能力の足を引っ張っているとしたら、少しばかり 面倒でも食事対策をきちんと行うことは気にならないはずです。
2014年11月07日
コメント(0)
-
食べて勝つ!”食事で作るベストコンディション” その29
こんにちはenoです。貧血への対策も気をつけておきたい …(3) 紅茶、コーヒー、緑茶など、タンニンの含まれる飲み物も、 鉄の吸収を阻害するので、夕食ではなるべく摂らないようにします。 貧血の人は、これらの飲み物を朝食や、昼食で飲むようにして、 夕食では摂らないように決めておくと、夕食での鉄の吸収が効果的です。 ビタミンCと、クエン酸は、鉄の吸収を促進するので、 レモン、オレンジなどの柑橘類を、夕食のデザートとして食べるのも、 あわせて考えておきたい工夫です。 オレンジジュースもビタミンCやクエン酸を含んでいるので、 吸収促進の効果があります。 貧血対策の食事を、なぜ夕食中心に考えるかというと、 先にも少し触れたように、たんぱく質と一緒に摂るのが 効果的だからです。
2014年11月05日
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1