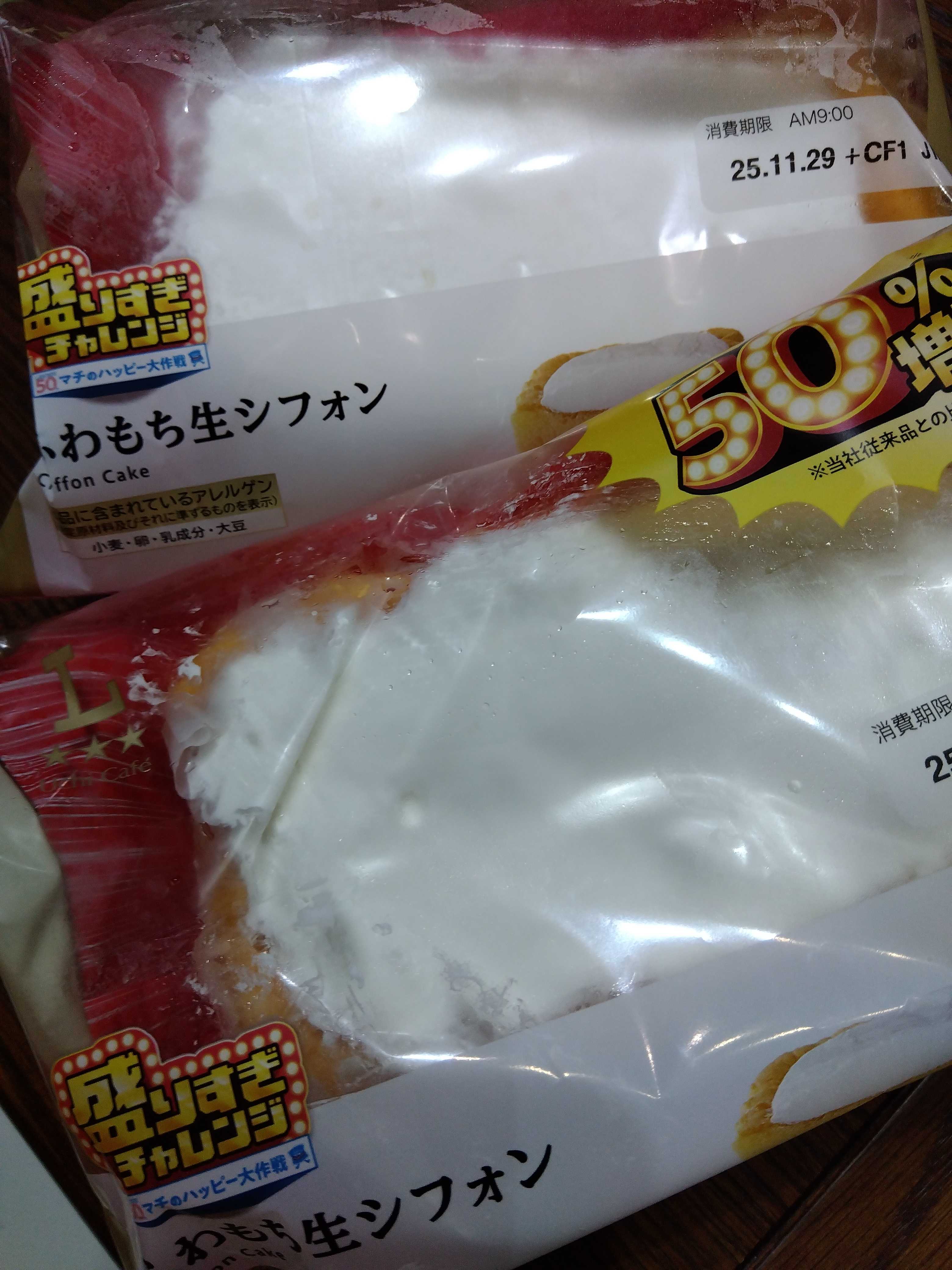2020年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
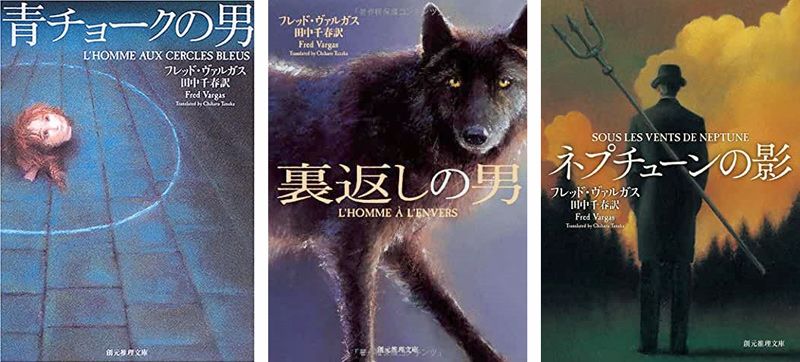
ヨーロッパのミステリー小説
コロナウィルス感染対策のStayHomeのおかげで、読書の時間がたっぷりとれた人は多いだろう。が、私の場合はふだんとあまり変わらない生活で、読書時間も変わらない。 最近の読書傾向としては、一時スウェーデンのミステリー小説にはまっていたが、最近はフランス物に凝っている。 若いころはアメリカのハードボイルド物をよく読んだが、老境に到り好みが変わってきた。 フランス物としては、最初にピエール・ルメートル の「その女アレックス」の特異なストリーに引き込まれ、続けてその後続作品3冊を読み漁った。 次に読み始めたのは、フランス・ミステリ界の女王ヴァルガスの警察小説でアダムスベルグ署長の物語を続けて3冊読んだ。さすが女王と呼ばれるだけあって面白かった。最後に読んだ「裏返しの男」は、前半はアルプスの狼の話が延々と続き、後半過ぎてやっとアダムスベルグ警視が出てくるが、昔振られた女性に未練たらたらに言い寄るあたり、フランス小説躍如たるものがある。また「ネプチューンの影」もカナダまで行って女性とトラブルを起こす。このアダムスベルグ署長の物語、もっと読みたいが現状では3冊しか出版されてない。 現在読んでいるのは、ジャン=クリストフ・グランジェの「狼の帝国」で15年前の出版だが、ほんとうの狼は出てこない。この作家の有名なミステリー「クリムゾン・リバー」は、昔読んだことがあり、20年前に映画も見た。 スウェーデンのミステリーでは人気の「ミレニアム」の連続物を何年も前から読んでおり、4作目で作家が亡くなったが、新しい作家に引き継がれ、5作目を読み終え、現在、最終章と思われる6作目を図書館での順番待ちの状態だ。 イギリス物にはイギリスの、スウェーデ物にはスウェーデのスタイルがあるように思えるが、最近のフランス物にはサスペンスにしても警察物語にしても、破天荒な筋書きがあり、予測のつかない筋書きが私を飽きさせない。フランスと言えば怪盗ルパンがあまりにも有名で出版数も多いが、今の私には興味がない。 さて驚くなかれ、フランスには「パリ警視庁賞」が1946年からあり、新人ミステリー作家を育てている。審査委員長は司法警察長官が務め、その他の警察・司法関係者が審査委員を務めているそうだ。フランスというお国柄がわかるような気がする。 アダムスベルグ署長の3冊
2020年06月21日
コメント(0)
-
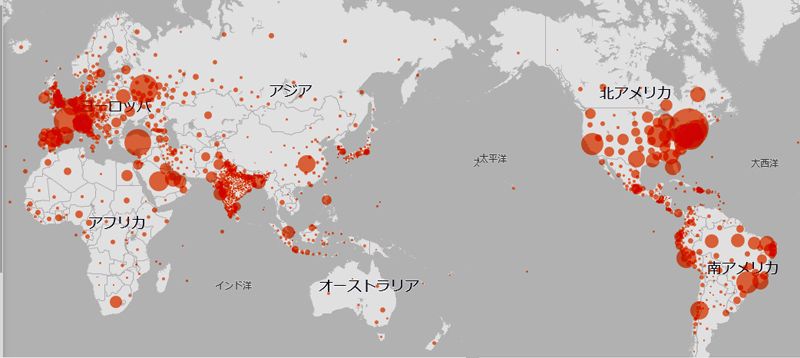
特別定額給付金
10万円の特別定額給付金がもうすぐ入るからと、スニーカーや推理小説やショルダーバッグを買ってしまった。本当はこの給付金でスマホを買い替える予定だったのだが、Xperia5ⅱの仕様未定、販売未定なのに諦め、物欲に負け生活に変化を求め、低額品を探してぽつぽつと買ってしまった。 そこで思ったのだが、安倍首相はなぜ国民全員に10万円を給付することにしたのか。公明党から言われたので、の話は置いといて、なぜ全員に給付するのか、なぜ生活に困らない者にも給付するのか、と考えている。 今回のコロナの影響がほとんどない人たち、例えば国会議員や地方議員、公務員、年金生活者、高所得サラリーマン、などは10万円なんてどうでもいいだろう。但し地方議員と年金生活者は多様で一概には言えないけど、高額受給者がいることは確かだ。その分を生活困窮者に廻した方がいいのではと誰でも思うのではないだろうか。最初に予算化された生活支援臨時給付金30万円の趣旨はそうだったはずだ。 そこで10万円全員支給という理念だが、政府の公式言い分はこうだ。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策であり、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うのが目的とある。即ち、早く給付するには選別の手間をかけられないから一律にしたと言っているが、全然迅速に配布されてない。 リーマンショック時には、大人全員一律配布完了までに3か月要したそうだが、12年後の現在でも同じような体たらくだ。マイナンバーカード制度も取り入れたが、郵送よりオンライン申請の方が遅くなるとはいやはや、10万円全員にした政府言い分が虚しい。ドイツがオンラインで早期給付が可能だったのは、リーマンショック後に不況時の雇用対策を図りシステム化を推進してきたからだという。特に芸術家支援が最優先だったのに文化の差を感じる。そして如何に日本が政治にも情報システム化にも立ち遅れているか、よくわかった。 結局30万円特定給付の方がよかったのではないかと思いながら、安倍首相の言う経済活性化の一助となる買物をしている、なんて言い訳をしている。 5月31日の世界感染状況 Microsoft Newsより
2020年06月15日
コメント(0)
-

東京アラート
小池知事の造語東京アラートが宣言され、都庁とレインボーブリッジが赤く染められた。しかし、この警報は効果を疑問視され、あまり評判がよくない。事実東京の感染者数は20から10人の間で昇降を繰り返している。赤のインスタ映えも評判はもう一つだ。 高齢者では、この東京アラートからフランク永井の「東京カチート」を思い出す人も多いのではないだろうか。メディアでも東京アラートに牽かれ「東京カチート」が出回っていた。この「東京カチート」が発表されたのは1960年、日本は神武景気を経て高度成長期に入っており、東京オリンピックの1964年開催へと、競技施設の建設、首都高速道路、東海道新幹線の開設と大きく変貌を遂げ始めていた。1960年にはTVのカラー放送が開始されていた。 そんな時代に、東京の夜を幻想的に捕らえた「東京カチート」だが、歌詞にはタウン、カチート、カクテル・グラス、ミッド・ナイト、 カーニバルと横文字のカタカナが沢山出てきた。 小池知事は「東京アラート」でそんな時代の「カチート」に想いを馳せただろうか。当時小池知事は8歳とのことだ。 因みに、この歌詞の中で、一つだけ英語ではないカタカナが「カチート」だった。「カチート」はスペイン語で「Cachito」。男性名詞で「可愛い坊や」という意味になるそうだ。 二つのレストランの駐車場
2020年06月09日
コメント(0)
-

アメリカ東部旅行-USA雑感
古い話になるが、25年前にアメリカで感じたことを記したものを見つけたので取り上げてみた。 先ず、アメリカ旅行で気付いた、アメリカ人の「気配り」について書いておきたい。 ドアを通った時は必ず後ろに注意し、人が居ればドアを支えて待っていてあげる。 ハイウエイのサービス・エリアで私の前に出た白髪の老婦人が、後ろの壮年の私のためにドアを支えて待っていてくれたのに感激したのを初めとし、混雑した店や町なかで体が触れたときに自然に出てくる「イクスキューズミィ」の一言。行く先々でこれらの気配りに会い、私も自然にそれができるようになった。そして、そうされた方は当然礼を言う。 帰国後、ドアを支えて待っている私の前を悠然かつ無言で通り過ぎる老若男女。私も昔はこうだったのだろうか。 日本では多くが自動ドアになったからその必要がないんだ、なんてぬかす御仁もいたが、その問題意識の低さに嘆く。 更に、写真を撮ろうとしていると歩みを止めて待ってくれるし、私たち二人を撮ってあげようかと気楽に声をかけてくれる。 電車やバスの乗り降りに慌てない。 シートに争って座らない。連れの一人が立っていると空いた席に自分が移り、席をゆずってくれる。 等々、他人に対する気配り、思いやりが実にこまやかだと感じた。 人間本来の優しとつくづく感じたのは、今の日本ではあまり遭遇することがなくなったせいか。 物質文明の先駆者アメリカに今なお宿る人間性に触れ、何故にこの日米の差が出てきたのか。 これはキリスト教から来るものではないだろうか、はたまた日本人の無宗教化のゆえではないだろうか、 なんて考えさせられた。 そして付け加えたいことは、遭遇したこれらの出来事はほとんど白人、しかも中年からあるていどお年を召した白人女性たちだった。それでは男性は、黒人はとなると、そのような機会がなかったようだ。当時の私の偏見かも知れない。 さて、この若い国家アメリカは今が最盛期であり、歴史の必然性として、これからローマ帝国のごとく斜陽を迎えて行くのだろうか、 とも心配する。 以上が25年前に感じたアメリカだが、現在のアメリカは、人情面ではわからないが、政治に目を向けると大国の驕り、自国第一主義があまりにも露骨で目を引き。また内政的にも貧富の差の激化、白人と黒人の軋轢が増え、私が心配したようにアメリカは混沌とした社会から崩壊へと進んでいるのだろうか。 煙に包まれるホワイトハウスと警察組織を糾弾する若者
2020年06月05日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1