テーマ: 今日聴いた音楽(75727)
カテゴリ: 音楽・映画・アート
さほど坂本龍一を熱心に聴いてきたわけでもないのに、
これで第4弾ですw
…前回からだいぶ時間が空きましたが。
◇
…というのも、
例の松尾潔の日刊ゲンダイの記事に、
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/325603/4
またも「炭鉱のカナリア」なんて表現が出てきたからです。
まあ、松尾潔は、
そもそも音楽家ごときが「カナリア」であるはずがない!
ミュージシャンに、そんな能力はありませんw
なぜか晩年の坂本龍一が、
そんなことを口にしはじめたせいで、
湯川れい子までがそれに同調したりしてるのですが、
坂本龍一ともあろうものが、
そんな下らない幻想を本気で信じていたとしたら、
あまりに愚かじゃないの?と思っていたわけです。
◇
一般的にいっても、
「音楽家が時代のカナリアだ」という考えは、
一部の馬鹿なミュージシャンが、
自分で勝手にそう錯覚しているだけの話。
歴史的に見れば、
社会の変化にもっとも敏感なのは文学者 であって、
けっして音楽家ではありません。
音楽は、芸術の諸分野のなかで、
社会の変化に対する反応がもっとも遅い。
これには必然性があります。
◇
たとえば「文学のロマン派」は、
フランス革命が起こる前から存在していましたが、
「音楽のロマン派」が登場するのは、フランス革命の後です。
つまり、
文学者ははやくから革命の時代を予兆していたけれど、
音楽家たちは、
モーツァルトにせよ、ベートーヴェンにせよ、
革命が起こるまでロマン派の時代の到来に気づかなかった。
※ウィーンが辺鄙だったからってのもあるけど。
それと同じことは、
印象派やシュルレアリスムにも言えます。
音楽の印象派は、
美術の印象派よりも遅いし、
サイケデリック音楽も、
美術のシュルレアリスムに比べて、だいぶ遅い。
◇
同じことはロックにも言えます。
アウトロー/アウトサイダーの表現は、
米国でいうなら1940年代の、
ビート文学やハリウッド映画の中に予兆されているし、
ヨーロッパの退廃主義や実存主義は19世紀から存在しています。
しかし、
音楽の世界でロックンロールが登場するのは、
せいぜい50年代の半ば。ここでも音楽がいちばん遅い!
日本でも、
無頼派の文学や東映・日活映画などが、
アウトローの表現を終戦直後から先取りしてましたが、
日本の学生たちが、
アウトロー気取りでフォークやロックをはじめたのは、
ようやく60年代も後半になってからのことです。
それにもかかわらず、
自分たちが「時代の先端」のように勘違いしていたのなら、
たんに滑稽というほかありませんw
◇
文学者が時代の変化に敏感なのは必然です。
それは、人間の精神や感性そのものが、
時代の言語や観念に規定されているからです。
そのことに自覚的な文学者ほど、
社会の変化を必然的に予兆することになる。
それに対して、
音楽家というのは、往々にして、
自分自身の感性の構造に無自覚なのです。
だから、
「インスピレーションは空から降ってくる」だの、
「感性こそが言語に先立つ」だのと、
ファンタジックな勘違いをしてしまう。
つまり、無邪気な音楽家ほど、
自分の感性が時代の観念に規定されていることを、
なかなか自覚できないのです。
そのくせ「空からのインスピレーション」があれば、
自分たちこそが時代を先取りできると思い込む。
…
坂本龍一は、日本の音楽家の中では、
かなり「文学的」なほうだったと思うのですが、
それにもかかわらず、
《音楽の予知力》なんぞを本気で信じていたとしたら、
意外に迂闊だったんじゃないか、と思います。
◇
◇
ちなみに、
ジョン・レノンの「イマジン」という有名な曲があって、
なぜか、
日本の頭の悪いロック愛好家ほど、
この曲を「ジョンの妄想」だと言って馬鹿にするのだけど、
そもそも、
あの曲の内容はジョンの独創ではありません。
あれは、
いわば文学思想の翻案であって、一種のパクリです。
そのことが分かっていれば、
あの歌詞の内容を一概に「妄想」だとはいわない。
◇
ジョンの「イマジン」の思想は、
おそらくカント哲学を根っこにしていて、
国連やEUや戦後の日本憲法の理念としても受け継がれてきた、
一種の文学的な予言なのです。
それが、
被爆国出身のオノ・ヨーコを介して、
ジョンのポップソングの形に翻案されたってこと。
その予言は、すくなくとも、
国連やEUの形で暫時的に実現してきているのだから、
たんにミュージシャンの気まぐれな「妄想」ではありません。
◇
実際、
クラシックの分野であれ、ポピュラーの分野であれ、
欧米の優れた音楽家というのは、
けっこう文学に対する造詣があって、
作品の基礎を文学に置いている場合が多いと思います。
ジョン・レノンの場合も、
(ビートルズのやんちゃ時代はともかく)
ボブ・ディランやオノ・ヨーコの影響を受けて以降は、
それなりに文学的になっていったわけですよね。
それに対して、
日本のミュージシャンの多くは、
「感性こそが言語に先立つ!」と思い込んで、
本も読まずに、空からの啓示ばかりを後生大事にしている。
こうした点は、もっと欧米を見習うべきで、
根拠のない幻想に酔っている暇があったら、
もっと多くのことを文学から学ぶべきです。


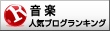

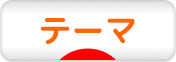
これで第4弾ですw
…前回からだいぶ時間が空きましたが。
◇
…というのも、
例の松尾潔の日刊ゲンダイの記事に、
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/325603/4
またも「炭鉱のカナリア」なんて表現が出てきたからです。
まあ、松尾潔は、
そもそも音楽家ごときが「カナリア」であるはずがない!
ミュージシャンに、そんな能力はありませんw
なぜか晩年の坂本龍一が、
そんなことを口にしはじめたせいで、
湯川れい子までがそれに同調したりしてるのですが、
坂本龍一ともあろうものが、
そんな下らない幻想を本気で信じていたとしたら、
あまりに愚かじゃないの?と思っていたわけです。
◇
一般的にいっても、
「音楽家が時代のカナリアだ」という考えは、
一部の馬鹿なミュージシャンが、
自分で勝手にそう錯覚しているだけの話。
歴史的に見れば、
社会の変化にもっとも敏感なのは文学者 であって、
けっして音楽家ではありません。
音楽は、芸術の諸分野のなかで、
社会の変化に対する反応がもっとも遅い。
これには必然性があります。
◇
たとえば「文学のロマン派」は、
フランス革命が起こる前から存在していましたが、
「音楽のロマン派」が登場するのは、フランス革命の後です。
つまり、
文学者ははやくから革命の時代を予兆していたけれど、
音楽家たちは、
モーツァルトにせよ、ベートーヴェンにせよ、
革命が起こるまでロマン派の時代の到来に気づかなかった。
※ウィーンが辺鄙だったからってのもあるけど。
それと同じことは、
印象派やシュルレアリスムにも言えます。
音楽の印象派は、
美術の印象派よりも遅いし、
サイケデリック音楽も、
美術のシュルレアリスムに比べて、だいぶ遅い。
◇
同じことはロックにも言えます。
アウトロー/アウトサイダーの表現は、
米国でいうなら1940年代の、
ビート文学やハリウッド映画の中に予兆されているし、
ヨーロッパの退廃主義や実存主義は19世紀から存在しています。
しかし、
音楽の世界でロックンロールが登場するのは、
せいぜい50年代の半ば。ここでも音楽がいちばん遅い!
日本でも、
無頼派の文学や東映・日活映画などが、
アウトローの表現を終戦直後から先取りしてましたが、
日本の学生たちが、
アウトロー気取りでフォークやロックをはじめたのは、
ようやく60年代も後半になってからのことです。
それにもかかわらず、
自分たちが「時代の先端」のように勘違いしていたのなら、
たんに滑稽というほかありませんw
◇
文学者が時代の変化に敏感なのは必然です。
それは、人間の精神や感性そのものが、
時代の言語や観念に規定されているからです。
そのことに自覚的な文学者ほど、
社会の変化を必然的に予兆することになる。
それに対して、
音楽家というのは、往々にして、
自分自身の感性の構造に無自覚なのです。
だから、
「インスピレーションは空から降ってくる」だの、
「感性こそが言語に先立つ」だのと、
ファンタジックな勘違いをしてしまう。
つまり、無邪気な音楽家ほど、
自分の感性が時代の観念に規定されていることを、
なかなか自覚できないのです。
そのくせ「空からのインスピレーション」があれば、
自分たちこそが時代を先取りできると思い込む。
…
坂本龍一は、日本の音楽家の中では、
かなり「文学的」なほうだったと思うのですが、
それにもかかわらず、
《音楽の予知力》なんぞを本気で信じていたとしたら、
意外に迂闊だったんじゃないか、と思います。
◇
◇
ちなみに、
ジョン・レノンの「イマジン」という有名な曲があって、
なぜか、
日本の頭の悪いロック愛好家ほど、
この曲を「ジョンの妄想」だと言って馬鹿にするのだけど、
そもそも、
あの曲の内容はジョンの独創ではありません。
あれは、
いわば文学思想の翻案であって、一種のパクリです。
そのことが分かっていれば、
あの歌詞の内容を一概に「妄想」だとはいわない。
◇
ジョンの「イマジン」の思想は、
おそらくカント哲学を根っこにしていて、
国連やEUや戦後の日本憲法の理念としても受け継がれてきた、
一種の文学的な予言なのです。
それが、
被爆国出身のオノ・ヨーコを介して、
ジョンのポップソングの形に翻案されたってこと。
その予言は、すくなくとも、
国連やEUの形で暫時的に実現してきているのだから、
たんにミュージシャンの気まぐれな「妄想」ではありません。
◇
実際、
クラシックの分野であれ、ポピュラーの分野であれ、
欧米の優れた音楽家というのは、
けっこう文学に対する造詣があって、
作品の基礎を文学に置いている場合が多いと思います。
ジョン・レノンの場合も、
(ビートルズのやんちゃ時代はともかく)
ボブ・ディランやオノ・ヨーコの影響を受けて以降は、
それなりに文学的になっていったわけですよね。
それに対して、
日本のミュージシャンの多くは、
「感性こそが言語に先立つ!」と思い込んで、
本も読まずに、空からの啓示ばかりを後生大事にしている。
こうした点は、もっと欧米を見習うべきで、
根拠のない幻想に酔っている暇があったら、
もっと多くのことを文学から学ぶべきです。

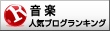

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.07.08 04:18:09
[音楽・映画・アート] カテゴリの最新記事
-
NHK「おやすみタローマン」はノスタルジッ… 2024.11.03
-
山崎貴「ゴジラ」新作とビオランテと浜辺… 2024.11.02
-
セルジオ・メンデスを「歌手」だと言って… 2024.09.09
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(220)ドラマレビュー!
(287)NHK大河ドラマ
(38)NHK朝ドラ
(31)NHKよるドラ&ドラマ10
(32)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(207)メディア問題。
(39)音楽・映画・アート
(79)漫画・アニメ
(24)鬼滅の刃と日本の歴史。
(32)岸辺露伴と小泉八雲。
(22)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)東宝シンデレラ
(67)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(48)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(38)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(64)汝の名~三千円~舞いあがれ!
(16)トリリオン~ONE DAY!
(16)Dr.チョコレート~ゆりあ先生!
(15)警視庁・捜査一課長 真相ネタバレ!
(32)「エルピス」の考察と分析。
(11)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(12)北斎と葛飾応為の画風。
(17)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(18)スポーツも見てる!
(41)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)半沢直樹!
(5)探偵ドラマ!
(12)パワハラ
(7)ドミトリー&ゴミ税
(40)夢日記&その他
(5)© Rakuten Group, Inc.









