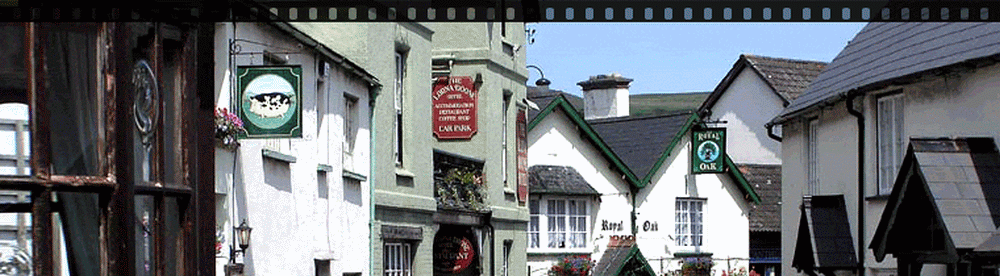2017年08月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-

花火
8月も終わりですね。夏の風物詩の花火、我が家からは2カ所の花火大会を観る事ができました。そして、庭先でも何度か花火を楽しみました。派手な花火もいいけれど、縁側が似合う花火。「線香花火」の可憐さが好き。 如何に火の玉を落とさずに最後まで粘れるか。 頑張ってみましたが、すぐに落ちてしまう。何かコツがないか探ってみました。火薬の上の部分をねじって硬くし、鉛筆のように45度に傾ける。こよりと火の玉の接着面積が大きくなって落ちにくくなる。∴線香花火は斜め45度が最も長持ちする。 という結果らしい。ついでに、線香花火には4パターンの表情があるらしい。「今すぐマスター!線香花火を長持ちさせる秘訣」より1.火をつけてからおおきな火の玉ができるまでを「牡丹(ぼたん)」2.大きく火花が飛び出しているところを「松葉(まつば)」3.少し弱まり火花がたれさがったところを「柳(やなぎ)」4.そして最後に火花がパチパチして消える直前を「散菊(ちりぎく)」知らんかった。3パターンだと思ってました。写真は左が牡丹で右が松葉でかな?で、これが柳の始まりか、散菊かもしれない。 なんとも奥深い。そして、西日本と東日本の線香花火にも違いがありました。 東日本は「長手牡丹」、西日本は「すぼ手牡丹」、と言うそうです。確かに、花火を買う時に「こんなんやったっけ??」と妙な違和感があった。画像を見ると、そうそう大阪では藁だった。と思い出しました。しかも、西日本のは300年変わらない線香花火の原形だそうで・・・。関西人やのに藁が当たり前すぎて知らんかった~!! <筒井時正玩具花火製造所より>
2017年08月31日
コメント(0)
-

千円札の富士山
帰路途中、本栖湖に立ち寄る。以前、本栖湖に行った際に千円札と同じ景色が撮れなくてリベンジ。まずは「みのぶ観光案内所」のある展望エリアから。 すっかり夕暮れですが、富士山のシルエットはしっかり写っています。そして、以前「本栖湖ダイビング」でお世話になった「浩庵」前から。 説明書き看板と同じ風景を。 そして、五千円札の裏と聞いていたのですが確認すると千円札の裏ですね。昔は五千円札の裏の真ん中に、ここから見る富士山が写っていたようです。もう、すっかり覚えていません。今は千円札に変わり、看板の説明書きも五千円札の五が消されていました。 冬ではありませんが、富士山の手前の山々もしっかり写っています。高台から見ると、富士山が湖に写っているのが見えるのかもしれないですね。それなりに満足~。
2017年08月24日
コメント(0)
-

湧水巡り「忍野八海」
【忍野八海(おしのはっかい)】世界遺産富士山の構成資産の一部、全国名水百選、県富岳百景選定地山梨県の南東部、富士北麓に位置する忍野村にある、富士山の伏流水に水源を発する湧水池、天然記念物の池。 構成資産19・七番霊場『鏡池(カガミイケ)』 ニャンコが魚を狙っている・・・。水面に富士山を映す池だったみたいで、ニャンコを撮っている場合ではなかったようです。というか、富士山が写っていること自体、気づきませんでした。メイン広場的湧水 中国人観光客が沢山来日されていました。私達が行った時間は夕方に近い時間だったため、まだ空いていた方です。道中、何台もの観光バスとすれ違ったので、早い時間だとごった返していたかも!?早朝もしくは売店が閉まっている時間帯が狙い目かもしれません。「鯉の池」水がどんどん湧き出ている為、すごい透明度。 観ていると吸い込まれそうです。「中池」(個人所有の人工池) 湧水口:水深8m人工池なのですが、いつしか湧水の通り道を作り湧き出しているようです。確かに湧き出しているのでしょう、透明度が素晴らしい。お金投げ入れ:罰金1000円人工池だけあってお土産屋さんの中を通らないと見れない湧水。その商法が嫌らしさを感じる。店内にある 名水:富士山の湧水は自由に飲んでもよいようです。 ペットボトルを持ってない人は横に空のペットボトルが100円で売られていました。がめつさが目について仕方ない。側に流れる川にはイワナ?が泳いでいました。岩魚ではなくニジマスだそうです。 構成資産17・五番霊場『湧池(ワクイケ)』八海一の湧水量と景観を誇る池 「名水百選」にも選ばれています。構成資産18・六番霊場『濁池(ニゴリイケ)』一杯の水を断り濁ったといわれる池湧池に隣接し、阿原川と合流しています。水は濁っていません。水車小屋の側に流れる川には鴨の親子が休んでいました。 小鴨はまだ完全に毛が抜けきっていない状態で痒いのでしょうか、自分の体をつついていました。「湧き出る 富士山の雪どけ水 日本の名水」 皆、体感していますね。構成資産15・三番霊場『底抜池(ソコナシイケ)』ここは「はんの木林資料館」の敷地内にある為、入館料が必要なのでスルーしました。個人所有の池でもないのに、ムリヤリに施設を作って見学させるとは!自然の物にお金を取る事に疑問です。構成資産16・四番霊場『銚子池(チョウシイケ)』 縁結びの池と伝えられている。らしいのですが、川沿い脇の草地の中にひっそりとあるため、ほとんどの人が通り過ぎて行きます。(^-^ここの池は浅いのか、湧いている様子が見られました。(写真真ん中辺り)清らかな流れの川沿いを散策しつつ八海を巡れ、自然を満喫できるのがいいですね。 構成資産14・二番霊場『お釜池(オカマイケ)』八海の中で最も小さな池です。 光でよく見えませんが澄み具合はよくわかりますね。構成資産13・一番霊場『出口池(デグチイケ)』八海の中で最も大きな霊水の池富士講信者が建てた石碑の脇、欅の木の下が湧水地らしいのですが、 よくわからなかった。(^-^; 「出口稲荷大明神」 密集している池とは少し離れた「出口池」。一番見応えがありました。密集地から歩約15分、案内がわかりにくく、地元の方に教えていただきました。住宅もあることだし、ワイワイガヤガヤされると、静かに過ごしたい住民にとっては迷惑甚だしいし仕方ないとは思うのですが・・・ 曲がる場所に案内板欲しいなぁ~。出口池付近から山近々山焼きをするのでしょうか、「中」「上」という文字が見られます。blog掲載上での写真ではかろうじて「上」という文字が判る。(真ん中よりやや左上)忍野村のマンホール 構成資産20・八番霊場『菖蒲池(ショウブイケ)』菖蒲にまつわる美しい伝説が残る池立ち寄っていません。(^-^;周っている内に、何個巡ったか分からなくなってきます。人工池もある事だし・・・。今日は午後からの歩数であまり歩いていないにもかかわらず暑さでバテ気味。8/24の総歩数:10,056歩山梨県産白桃果汁60%使用の白桃ソフトクリームで涼を得る。さっぱりで美味しかった~(^^ 濁りのない湧水、本当に綺麗でした。
2017年08月24日
コメント(2)
-

ほうとう と 滝
山梨の湧水巡りに行こうと昼頃出発し、ランチは以前おすすめされた「ほうとう小作」に立ち寄りました。 昼のピークを過ぎた時間なのに、すごい人で駐車場に車を停めるだけでも一苦労。名前を書いて待っている間にも、後から後からどんどん来店客が!実は前回「ほうとう小作 甲府駅前店」に立ち寄った事があるのですが、県庁すぐ近くのオフィス街という事もあり、混み具合は全く違う上、一人客がほとんど。今回行ったのは「ほうとう小作 河口湖店」で、6人前後のグループ客が多く、しかも外国人客が多い気がした。前回と同じメニュー「かぼちゃほうとう」を頼んだのだがお店により味が違う気がする。 左が河口湖店のかぼちゃほうとう、右が甲府駅前店のかぼちゃほうとう。 比較すると、見た目的にも煮込み具合の違いが判る気がする。半端じゃなく煮込まれており、スープに溶け込んだ野菜の出汁が混ざり、個人的には 河口湖店 のが美味しく感じた。また、別に味付けされたごぼうが美味しくって、それがいいアクセントになっている。めっちゃ美味しかった~。湧水巡りへ行く道中で「ふじさんミュージアム」へ立ち寄る。文化財が立ち並ぶ「東海自然歩道」を歩きながら建物を堪能しつつ 富士吉田市指定文化財「旧武藤家住宅」 、山梨県指定文化財「旧宮下家住宅」 江戸末期築と推定される。 、江戸中期(宝永4年(1707年))築そして、向かうのは「ふじさんミュージアム」の向かい側、国道138号線からすぐの滝【鐘山の滝】です。 落差:10m山中湖で湧いた水が忍野を通って、富士吉田市に流れ込んでいます。その途中の、富士見公園内にある鐘山の滝。相模川に繋がっていく川で、富士五胡地域では桂川と呼ばれています。 アクセスがよくて気軽に歩いて行けるのがいいです。「富士の国やまなし観光ネット」では、「駐車場はふじさんミュージアムの無料駐車場を利用ください。」と記載されているが、現地に行くと「ふじさんミュージアム」利用者以外駐車禁止と記載されていた。が、気にせず停めさせていただきました。満腹過ぎたお腹とカロリー消費には軽くほど良い運動でした。次は本来の目的地である湧水巡りへ続きます。
2017年08月24日
コメント(0)
-

掛川 倉真の観音と滝
帰路途中で見つけた看板【百観音】(掛川市倉真) 気になったので行ってみました。看板から突き当りまで行くと水路トンネルがある。奥は真っ暗です。 この横手から400m。竹林の中をどんどん登っていく。 日清戦争の頃、皆の気持ちを救いために、遠州一円をたくはつして歩き、このお金でお山に観音様をきざんでいったのが始まりです。途中、不安になりながら本当に400m?ってぐらい、てくてく登ります。到着しました。ホッとした。 山の中で鹿を見かけたが、一瞬の出来事だったので、ただ見送るばかり。日清、日露、太平洋戦争ですっかり敗けてお観音様も忘れ去られてしまっていた。倉地に嫁いできた俗名:染葉洋子氏が、山で埋もれて居た明治27年建立の百体の観音様を掘り起こし、村おこしとしてお祭りを行う。 その後、愛犬ウィンキーと共にメディアに紹介し観音様を全国に広めた。後で知ったのですが、ルートは違いますが車でも行けたようです。百観音を堪能し、道中の【松葉の滝】の看板の案内で行ってみる。そこそこ広い駐車場があるにもかかわらず、一本道だからか案内地図がない。松葉の滝は雌滝と雄滝があるらしいのですが、これかな?って思う滝を。 足元の悪い斜面の木の間から撮ったのですが、後で調べたら雌滝だった。落差:8m雄滝はもっと山を登らないといけなかったようです。あれまぁ~残念。しかし、水量も多く見応えありでした。しっかり駐車場があるぐらいなんだから案内図置いてほしい~ と思うのでした。ゲリラ豪雨だったにも係わらず、雨に遭わずにあちこち巡れて良かったです。
2017年08月18日
コメント(0)
-

遠州三山風鈴まつり
以前、浜松で持ち帰り餃子専門店で餃子を買い、何回かに分けて食べる為に一部冷凍にしていたものが無くなってしまったので、お盆も過ぎたし持ち帰り餃子専門店の別の場所を教えていただいたので、行ってみるとロングバケーションのようで、ほぼ8月いっぱいはお休みだった。ホームページがないので調べられなかったというのもあるが、このまますごすご帰るのも嫌だったので、前回行ったお店に電話をかけて営業しているかどうか確認。営業してはいたが、予約分は終了し、持ち帰り分はもうすぐ終了。という状態だったので、やはり9月に入ってから出直す事にし、近くでお昼をとる事に。道の駅っぽい施設「採れたて元気村」というのが近くに見えたので立ち寄ってみた。同敷地内に隣接する「はしもと」でお食事。季節限定「鮎フライ定食」1500円~1800円 鮎のサイズにより値段が異なる。鮎は天竜の鮎なので地元産です。 大きい 1700円サイズだったようです。ちょうど食事時にゲリラ豪雨がやってきて、台風か?という程の暴風と激しい雨、雷が。食事時で室内にいて良かった~。ゲリラ豪雨は一時的で雲が去ったら雨があがったので帰る方向「袋井市」へ。「袋井市」で開催されている【遠州三山風鈴まつり】のお寺巡りに。 お寺では邪気除けの意味でお堂や塔の軒の四方に「風鐸(ふうたく)」と呼ばれるものが吊り下げられております。この風鐸が風鈴の由来とも伝えられ、風鐸の音が聞こえる範囲は災いが起こらないと考えられております。【可睡斎(かすいさい)】徳川家康公深きゆかりの禅寺 応永8年(1401年)如仲天ぎん禅師により開創された曹洞宗屈指の名刹。11代住職の和尚が、幼い家康を戦乱から救ったことがあり、後に家康が浜松城主となった折、報恩の為に城に招かれた席で居眠りを始めた和尚。家康「睡(ねむ)る可(べ)し」(御前にて睡っても無礼ではないとの意)といい『可睡和尚』と愛称せられ、寺号も東陽軒から可睡斎と改め、拾万石の待遇と徳川幕府最初の僧録司(そうろくす)という職を与えられました。「東陽軒」可睡斎の始まりの寺 可睡斎「山門」 山門を入ると風鈴の音が耳に優しく、癒されます。 風鈴は、歴史ある『江戸風鈴』を可睡斎オリジナルで色付けしている手作り。 蓮の実?ができてました。「出世六の字穴」(権現洞) 先に「幼い家康を戦乱から救った」と記載しましたが、家康は武田信玄との戦い時、武田勢に追われ、この寺のほら穴に隠れて命拾いしました。境内入口近くのお土産屋さんでは紙で作った風鈴で「赤富士」が飾られていました。 「秋葉総本山三尺坊様御真殿」 可睡斎は、明治時代以降日本唯一の「火防(ひぶせ)パワースポット」、日本唯一の御真躰をお祀する火防霊場。とても判りにくいのですが、両方に天狗が立っております。内部も天狗の仮面が沢山。 御真殿の階段下には天狗のゲタに火箸?とスコップも。 デカイです。三尺坊大権現様は信州戸隠村岸本家に生まれ新潟蔵王権現堂の第一道場たる三尺坊たる戸隠山西窟道場において御修行成就され観音大士の化身として信仰されています。化身とは天狗ということなのでしょうか・・・。【油山寺(ゆさんじ)】目の霊山 「山門」(元掛川城大手二の門) 重要文化財 二層片潜付城門は全国的にもめずらしく静岡県唯一の城郭文化財「礼拝門」 雨上がりですね、門の壁に小さな来客がいました。「世界一願いの叶う大念珠」 この大数珠の縁の下に風鈴が吊るされていたのですが、少しだったので風鈴まつりだという事も忘れてしまうほど。 現に忘れて、写真を撮ってません。(^-^「天狗谷の自然林」の中を歩いて行きます。 るりの滝へ到着。 この建造物の天井絵「白龍の画」が素晴らしいです。 「るりの滝」 スポットライトのように太陽の光がるりの滝を照らしていて何か神々しい。しかし、食事時に降ったゲリラ豪雨の影響で、水が濁っています。このまま少し自然林の山を登っていくと(階段になっています。)「三重塔」重要文化財 滋賀県の長命寺と京都府の宝積寺、静岡の油山寺の三重塔は桃山時代の三名塔のひとつです。「本堂」静岡県指定文化財 建久元年源頼朝公が眼病全快のお礼として寄進、遠江国守護職工藤祐経がご普請奉行にあたられた建物。元文3年(1738年)時の山主幸恵法印が8代将軍吉宗公に拝謁の砌(みぎり)病気平癒のお礼に再建寄進されたもの。目の霊山だけあって、奉納されたこの額はとても判りやすいです。 本堂内には薬師如来坐像を安置した「厨子」があるのですが、網がかかっていて判りにくいです。が、重要文化財です。 灯籠と青紅葉が雰囲気があっていい。 油山寺は、大宝元年に行基大士が万民和楽、無病息災を祈念し本尊薬師如来を奉安、開山された真言宗の古刹。遠州三山風鈴まつりの最後の寺【法多山】は帰る方向とは真逆だったので今回はスルーさせていただきました。 が、「法多山」は厄除観音のお寺だったので行くべきだったかなぁ~。・・・(^-^;特に災難事はないのですが・・・。またの機会に。遠州三山風鈴まつりで風鈴の音色を聞いてから、風鈴が欲しくなりました。影響されやすいですね。(笑) でも近所迷惑かなぁ~。
2017年08月18日
コメント(0)
-

この世界の片隅に
2016年11月12日よりロングラン上映している『この世界の片隅に』をようやく観ました。 第二次世界大戦中の内容なのだが、張り詰めた、あわただしい、ピリッとするようなよくある戦争映画ではなく、のんびりした性格の主人公:すず の普通の日々の普通の生活を描いているのだが、飽きる事なく、時にはすずに、時には第三者の目で見守って観ている私がいて、色んな人との触れ合いの中ですずが自分の居場所を見つけていく。とても まったりした内容だったが、実は日々の生活の中に人々の本音が見え隠れしている様子がうかがい知れました。特に、毎日の空襲警報の中でのセリフ「警報もう飽きた~」毎日何度も何度もだとそうなるよな~。行ったり来たり大変だし、私ならいっそのこと防空壕で生活したくなる気持ちが起こるかも。私もたぶん「また~!?」って言うかもしれない。そのうち、慣れてきたりするのかもしれない。あまりにも映画がまったりした作りだったのもあり、緊張感を感じられず、ついそう思ってしまう。主人公すず が8/6に呉市から広島市へ帰る。と言い出した時は、観ている方がハラハラした。心の中で「帰ったらあかん!」って叫び続けている私。そして、呉は9つの峰に守られているから呉という。ってこと初めて知りました。おそらく呉の方も知らない人多いんじゃないかな。最後までほのぼのしており、戦時中の生活を描いたとは思えない程でしたが、何か心にじーんときます。海外でも続々公開されているのだが、ちゃんと受け止めてくれてるのかなぁ~。ほのぼのし過ぎで違った風に受け止められるのは嫌だな・・・と思わずにいられません。海外展開情報:http://archive.is/wPh6O「この世界の片隅に」北米配給が決定!今夏、劇場公開へ(2017年2月1日 映画.com)http://archive.is/mxMOl「この世界の片隅に」がアメリカで公開に。(2017年8月12日 Yahoo! ニュース)http://archive.is/ygoiD最後に、主人公すず が子供の頃に出会った座敷童に映画の途中で出会い、正体がわかります。そして、最終テロップで彼女(白木リンという)の生涯が描かれいるおまけ付き。凝ってますね。声の出演:のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美詞、小野大輔、潘めぐみ、岩井七世、 牛山茂、新谷真弓、澁谷天外(特別出演)
2017年08月14日
コメント(0)
-

田谷の洞窟、城ヶ島
千葉巡りを堪能し、旅行最終日は帰路方面に向かいつつ最初に立ち寄ったのは神奈川県は横浜市栄区にある【定泉寺】。横浜とはいえ、鎌倉のすぐ上です。 ここには【田谷山瑜伽洞(田谷の洞窟)】たやざんゆがどう と読み、手掘りの洞窟があるのです。 御洞拝観の受付をすまし、パンフレットとロウソクをいただく。パンフレットの内容をよく読んでから洞内へ入ります。 ロウソクは洞内へ入ってからつけます。洞内は撮影禁止なので、写真を撮る事ができませんが、洞内の壁面には多数の羅漢や梵字?などが行者により無数に刻まれており雰囲気も良く、素晴らしかったです。鎌倉時代初期開創から江戸時代に至るまで適時拡張され、幾度かの大地震にも耐えている。粘板岩の強大な一枚岩なので強いのでしょうね。見学も早々に終わり、次に向かうのは神奈川県の中でもまだ一度も行った事のない三浦市は「三崎」。「三崎水産物地方卸売市場」を見学。 お昼時なので、ほとんどの作業が終わっていた。8時からが見頃のようです。卸売市場内にある「卸売市場食堂」で食事予定のはずだったのだが、定休日。 ショック~仕方なく、近隣をぶらっと食事処を探していると、しらす直売店 横ではしらすを干していました。 近くのまぐろ食堂でお食事。 特選三崎まぐろの大トロ・中トロ・赤身の3種に加え、生エビ・旬の地魚4種・しらすの入った「まぐろ海鮮丼」鮪は本当に美味しかった~。さすが、鮪の水揚げ場だけあります。調べると、冷凍鮪の水揚げ量は1位:焼津、2位:三崎だった。生鮪は別の所でした。静岡に居るので次は焼津に行ってみよう!って思いました。食後は【城ヶ島】で奇岩などを見学。(城ヶ島へ渡るには、渡橋料が必要。)城ヶ島内の県立駐車場はワンデーパス(450円)で何カ所かある駐車場を何度も利用できるのがいいです。(県立に限りです。個人の駐車場は対象外。)【城ヶ島灯台】 明治3年(1870年)日本で5番目の西洋式灯台として設置点灯(設計者:ヴェルニー)関東大震災により倒壊し、大正15年(1926年)改築(現在に至る。)神奈川県ではヴェルニーさんがよく活躍されてますね。横須賀のヴェルニー公横の「ヴェルニー記念館」にも彼の作品があったり昨日立ち寄った野島崎灯台などもヴェルニーさんの設計です。【城ヶ島公園】展望台から見た安房崎。 この園内に砲台跡があるのですが、たぶんこれかな? 磯に降りて灯台へむかいます。 波打つ岩肌がすごいですね。【安房崎燈台】 設置された年月や初灯日について、何の情報もありませんでした。そして、城ヶ島公園での最大の目的地へ向かいます。 三浦半島八景の一つ【城ヶ島の落雁】(ウミウ生息地) ウミウではなく沢山のトンビが舞っていました。 そして、最大の目的地【馬の背洞門】(めぐりの洞門、眼鏡の洞門) 上から 下から 洞内から 晴れててよかったな。って思った瞬間でもありました。 高さ8m、横6m、厚さ2m長い年月をかけてつくられた海食洞欠。 土質は凝灰質砂礫岩という軟らかい岩質。私達がおばあちゃんになる頃には上部が崩れ落ちてるんだろうなぁ~。
2017年08月09日
コメント(0)
-

養老渓谷
【養老渓谷】養老川の上流に【2段重ねトンネル(共栄隧道・向山隧道)】があります。実はここ、養老渓谷の場所を確認するために地図を見た時に史跡の地図記号で見つけ、誰かの写真を見て、絶対行きたい!!と思った場所でもあります。トンネルが2段重なっているので、それぞれの入口の名前が違います。「共栄トンネル」「向山トンネル」 ここのトンネル、一見して真ん中部分が抜け落ちた感じに見えます。 トンネル構造は以下の図のようになっています。とても判りやすいです。埋めなかったからとても幻想的な風景になっています。雨の日は隧道内に水が流れこむだろうから大変かも・・・。トンネルの中に掘られた3つの防空壕のうちの一つが確認できます。 写真右上の黒い部分不思議な“2階建て”トンネル:http://archive.is/wQnab「産経フォト」の説明書きが大変解りやすいです。そして、プロの撮影でもトンネル内の色が緑に写るんだな。と認識しました。向山トンネルから入り、共栄トンネルを抜けた先の赤い橋を渡った右手から「中瀬遊歩道」が始まり、養老川の下流へと向かう。 川の中のコンクリートの橋を渡り目的地へと向かう。 川の中程の浅瀬には石が積まれていますよ。 【弘文洞跡】 約140年前、耕地を開拓するため、養老川の支流、蕪来川を川まわしして造った隧道。大多喜町公式ホームページ:http://archive.is/UvF8F崩壊前の弘文洞の写真が掲載されており、その大きさがうかがい知れます。川廻しといえば、「濃溝の滝、濃溝の洞窟」を思い出します。千葉県では同じような方法で耕地をふやし、水田利用していたんですね。そして下流にある養老渓谷滝巡りへ。大きな看板のほんの一画部分の地図で巡ります。 この入口より川へ降りて行きます。 【粟又の滝】 全長100mの房総一の名瀑(県内最大)。落差:約30m階段状に傾斜した岩盤の上 約100mにわたり清流が滑り落ちます。「粟又の滝自然遊歩道」をてくてく歩きます。緑が目に優しい。 昨夜は台風の影響で雨だったと思うのだが、川の水は思ったより少ないです。「千代の滝」はどこにあるのかわからなかった。【万代の滝】 落差10mの分岐瀑粟又の滝の水量が少なかったからか、粟又の滝より立派に感じます。地図に記載されている「昇竜の滝」「深沢の滝」はよく判らなかったが地図に乗ってない滝(立て看板あり)を見つけた。【見返りの滝】 落差はあまりないようですね。そうこうしているうちに折り返し地点にやってきてしまった。(^-^; これからしばらく登りが続き、道中「幻の滝」があったのですが、自然の物なのに有料だったのでスルーしました。養老乃滝展望台より「粟又の滝」を望む。 blogを書いていて気付いたが、滝の上流にも行ける道があったようです。人がいて気付きました。ここはかなりの健脚コースで、昨日の疲れがまだ残っているからか足が棒です。(笑)千葉県巡りはここまでにし、明日は帰路へ向かいながら他を巡ります。千葉からみたアクアライン上の「海ほたる」 初めて見た時は「道路の真中に船があるんやけど、何?」って聞いたのを思い出すなぁ~。(笑)8/8の総歩数:17,720歩
2017年08月08日
コメント(0)
-

鴨川から勝浦 海沿い巡り
千葉県唯一の 有人離島、千葉県指定の名勝で、新日本百景の地【仁右衛門島】 この島には平野仁右衛門さん一戸だけ住んでいた事から「仁右衛門島(にえもんじま)」と呼ばれています。個人所有です。ここへ行くには手漕ぎの渡し船で渡らなければいけません。 しかしながら、台風の影響で風がキツイせいでしょうか[欠航]の文字。 ムリかもしれないな~とは思っていたが、やっぱりか。まぁ、晴れてただけでも良しとしないとな。渡し船乗場前に神社があったので行ってみました。 めっちゃ急な階段を上ります。「津嶋神社」 神様はこれなんですが・・・ 貝殻らしきものが置かれているので海の神様には違いないのでしょうが・・・。気を取り直し、鴨川市から勝浦方面へ移動し目指すは海岸沿いにある海蝕洞窟。【渡島(わたしま)】 年に数回の干潮時には、砂浜と渡島がつながる自然現象をみることができるそうです。守谷洞窟方面へ行く途中、鷲?トンビ?が居た。 近隣の方が声をかけてこられたので、鷲が居る!って伝えるといつもここの木にいるらしく、飛べないとおっしゃってた。(@_@;)【守谷(もりや)洞窟】 峰須賀公が落城の途次、ここに隠れ難をのがれたといわれます。入口の高さ6m、幅8m、奥行30m なぜこの像が置かれているのかは不明です。このすぐ横にも海食洞あり。 ここの海岸の岩肌がとても綺麗です。 そして、海がとっても荒れてます。 戻って海岸手前にある神社?に行ってみます。 場所的に海の神様に間違いない。とは思うものの・・・ 恵比寿さんが大変な事になっています。早く応急処置をしてあげないと堪能したので、次は太平洋の荒波に侵食された2kmにおよぶ海岸線リアス式海岸の【鵜原理想郷】です。駐車場前の洞窟が気になって、先に洞窟を覗きます。 トンネル?? それとも防空壕?? ある方のblogでは「震洋の格納壕」と記されています。こんな所にも!? 海に近いし、そっか・・・。まぁ気にせず早々に「鵜原理想郷」ハイキングコースへと向かう。トンネルを抜け山へとひたすら登り続ける。途中の開けた場所から海が見え、「鵜原理想郷」の看板も見えたのでもうすぐか・・・(^-^; この岩の削れ具合が面白い。 ようやくそれっぽい所に到着するも、超強風(暴風?)で自分が飛ばされそうで、崖っぷちギリギリの所まで怖くて行けません。(>_<)しかし絶景なんです。 リアス式海岸の美しさを紹介できないのが残念です。「天真地蔵」 理想郷の中でも眺望がすばらしい手弱女平(たおやめだいら)という所です。鐘があったのでつきましたが、暴風なので誰もいなくとも勝手に鐘が鳴っています。 実はここ、草地ではなく砂地の方が大部分。鵜原理想郷は1周 約2300mのハイキングコースで沢山の岬へも行けるのだが暴風で砂はバチバチ当たるし、飛ばされそうだし、早々に戻る事にしました。少しだけでも青い海と青い空に囲まれた造形美が観れて満足です。お昼時、勝浦名物といえば「勝浦タンタンメン」らしい。鵜原理想郷に近い精肉店経営のお店に行きたかったのですが、長蛇の列だったので次の場所へ向かう途中で見つけることに。とりあえず見つけたお店「てっぱつ屋」 千葉最強 ご当地グルメ 一番人の 勝浦タンタンメン醤油味を。 ひき肉たっぷりのよくある担々麺とは違い、ひき肉よりも玉ねぎが多い?そして、ひたすら辛い。ヒー!! むせながら完食しました。(^-^;腹ごしらえも済み、次は【養老渓谷】へ向かいます。
2017年08月08日
コメント(0)
-

千葉県 白浜エリア
日本列島総なめと言われている台風で、今日は全国的に雨。の予報だったのだが風こそ強いがめっちゃ晴れ。 晴れ女冥利に尽きます。3日目の今日は 南房総市最南端の【白浜野島崎園地】駐車場からてくてく最南端へ向かい、遊歩道を歩きます。 「南総里見八犬伝」で有名な戦国大名:里見義実公が結城の合戦に敗れ、三浦半島から白浜野島崎へ上陸したのが1141年(1145年説あり)といわれています。とにかく上陸したのは間違いなさそうですね。ここに【伝説の岩屋】がありました。 1180年源頼朝公がこの地で武運再輿を願掛けている時、突然の時雨に近くの岩屋に身を寄せ雨をしのいだこの岩屋を「頼朝公の隠れ岩」と称し、深海に棲む創造の大蛸の海神を祀った。お賽銭が中央の大鮑の殻の中に入れば開運間違いなし!との事。 口元のこれですね。何も乗ってないという事は難しいんですね。【房総半島最南端の地】 最南端の地であるとともに、朝日と夕暮れの見える絶景ポイントらしい。台風で海は大荒れ。冬の日本海のような「波の花」ができてました。 写真では判りづらいですが、泡が飛んでいました。場所、季節に関係なくできるものなんですね。泡の正体はプランクトンや海藻類の粘液とのこと。そう考えるとどこでも出来るのかも。【野島崎灯台と霧笛舎】 「野島崎灯台」明治2年(1869年)12月18日竣工、初点灯。日本の洋式灯台としては観音崎灯台に次いで2番目のもの。当初は煉瓦造り(ヴェルニー設計)だったが、関東大震災に寄り倒壊。大正14年に現在の灯台へ改築されました。「霧笛舎」海側に立っているし、最初は海軍系の何かかも?と思い、階段もあることだし行ってみたら廃墟だった。 背が届かず、中を覗き見る事ができないので、手を伸ばして隙間からカメラのシャッターを押すと中はこんな感じ。 何だかさっぱりわからないが家に帰ってから調べると「霧笛舎」とのこと。霧や吹雪などで視界が悪いときに船舶に対し音で信号所の概位・方向を知らせるもの。霧笛はいまや船舶レーダーやGPSなど技術の進歩、灯台の無人化で使用されていません。なので、写っている機械って貴重な物なのではないのでしょうか。サビが目立ちますが、ぜひ博物館で展示すべきだと思う。「嚴島神社」 ここに武田石翁(幕末の優れた石工)の七福神があり、六体は野ざらしで 弁財天のみ社殿内に祀られているそうです。19歳の時の作品だそうです。才のある方は違いますね。「平和の愛鍵」 上手いこと言いますね。現地看板の片隅に描かれた「野島崎散策絵図」が大変わかりやすいです。 岩礁の名前まで記載されています。次に移動し、白浜エリアにある滝と鍾乳洞へ。「涼源寺」という所なので、てっきりお寺がある近くにそれらがあると思っていた私。近隣住民の方が畑仕事をしていたので、お寺の場所を聞いてみた。すると、昔この辺りにお寺はあったようだが、山津波にのみ込まれ今は無く、「涼源寺(りょうげんじ)」という名前だけ地名として残った、ということでした。せっかく来たので滝と鍾乳洞の場所もお聞きし、行ってみました。 【涼源寺の滝】と【白浜の鍾乳洞】 「涼源寺の滝」滝は普段ほとんど水量がないそうだが、昨夜の雨のおかげで今日はそれなりに。 「白浜の鍾乳洞」千葉県指定天然記念物 地元の方によると、昔は鍾乳石やらあったそうだが、子供らが出入りして遊んだり他から来る方が折って帰るので鍾乳洞とは名ばかりで、今は大したことない穴よ。と言われたのだが、千葉県唯一の鍾乳洞で県指定天然記念物。奥の方をズームしてみると、不動明王像が祀られていました。(ボケてますが・・・。) 乳の神として効があると言われて信仰されています。左上の鍾乳石っぽいのが乳のような形だからそう言われているのかもしれないですね。次は千葉県の離島へ向かいます。
2017年08月08日
コメント(0)
-

館山「沖ノ島」と2つの「ナタキリ神社」
不思議な事に、あんなに疲れていた足でしたが、戦跡を巡っている頃にはすっかり回復。まだまだ余裕で歩けそうなので館山市の館山湾にある陸続きの島三房総国定公園【沖ノ島公園】へ。 時間的にスノーケリングや磯遊び、スイミングを楽しんで帰る人達が戻っている中、反対に私達は公園へと向かう。ここに来た理由は、園内に洞窟がある。という情報を得たから。園内mapをいただいたが、洞窟の場所は書かれていない。当然、看板にも。 情報によると、休憩所を過ぎて案内のない左に入る道を行けば洞窟へ行ける。という事だけ。とりあえずは「宇賀明神」へお参り。 嘉保3年(1096年)倉稲魂(うかのみたま)の神を勧請し鷹ノ島の弁財天と共に建立。稲作の神、農業神、漁業神、商業神、福神として平安時代以降、絶えること無く人々の厚い信仰を受けてきた、あらゆる産業の神様です。「御神木」 左へ入る脇道を色々行ってみましたが、洞窟へとたどり着けずようやく見つけた浜辺に近いこの左側の脇道。 ここを入る。 一見して洞窟はなさそうに見えるが、右手にぽっかり穴が開いていた。 当然、入ります。 左右に横穴が空いており、左側の穴の空き方がトーチカっぽい。 ここから見える風景。 島への侵入者が見渡せる。間違いなくトーチカだと勝手に断定。本筋へ戻り、海へ出る。 海から洞窟を見るとこんな感じ。 発見って嬉しいですね。それにこの縞模様。 公園での目的はこれだけなのに、かなりの充実度。後で知ったが、看板の園内図に誰かが手書きで「どうくつ」と書いてくれてました。 もう消えかかっていて、見えにくいのですが・・・。浜辺に出ると穴が開いているので、興味のある方は入るんだし、書いておいてほしいです。千葉県館山市の沖ノ島について:http://archive.is/zuE1E洞窟は戦争遺跡でした。東京湾の入口に位置する為、見張り場所として使われていたようです。次は2つの「ナタキリ神社」へ。「船越鉈切神社」と「海難刀切神社」鉈切、刀切どちらもナタキリと読みます。【船越鉈切神社】 実はここには千葉県指定文化財の「鉈切洞穴」があるんです。 しかも海食洞欠。調査によると、縄文時代後期に属する土器等の遺物が出土したそうです。開口部から最奥部までの距離:36.8mここが入口です。 勝手に開けて入れるのかと思ったら鍵がかかっていて入れません。(>_<)隙間から覗き見ます。 本殿は県の指定文化財になっている鉈切り洞穴の中。 ↑これです。奥行きがなさそうにみえるが説明書きによると約36mもあるので相当奥深い。入れなくて残念。鉈を砥いだ石「鉈砥ぎ石」 浜田洞穴に大蛇が棲み村人を苦しめており、神様が大蛇退治の為鉈を砥ぎ、試し切りをしたところ、真っ二つに割れたという伝説の鉈砥ぎ石。次に斜め向かいの【海難刀切神社】 本殿横裏には奇岩群があり、 その中に名前の由来にもなっいる刀で切ったような岩の裂け目があります。 かつて両社は、ひとつの神社として信仰されていました。山側の浜田にある船越神社を上ノ宮、海側の見物にある刀切神社を下ノ宮と呼んでいたようです。 本日はここまで。台風の影響で小雨が降ってきました。明日は雨かもしれないなぁ~。と思いつつ宿へ向かう。友人が見つけた宿泊先「ペンションSunday Beach」が可愛くて乙女心満載。 どこかのリゾート地に来たような宿です。宿泊料金もリーズナブル。床の軋みが気になりましたが、居心地のいいお宿でした。。とっても気に入りました。今日はよく歩いたのでゆっくり足をほぐして休みます。 8/7の総歩数:21,565歩明日は南房総市へ向かいます。晴れるといいなぁ~。
2017年08月07日
コメント(0)
-

館山市の戦跡「赤山」周辺
いよいよ、かねてから行きたかった【赤山地下壕】です。入壕時間 9:30~16:00というは調べていたので余裕。と思ってたら、受付は15:30までで、数分前でギリギリセーフ危なかった。ここに行けなかったらかなり凹んだであろうが、良かった。入壕前に「豊津ホール」で受付をし、ヘルメットと懐中電灯を借ります。懐中電灯は自分達が持っているものの方が性能がいいのでヘルメットのみ借りる。【館山海軍航空隊 赤山地下壕跡】館山市指定史跡赤山地下壕は、戦時中 館山海軍航空隊の防空壕として使われていました。壕の中では館山海軍航空隊の事務を行ったり、病院施設があったなどの証言があります。 合計した長さは約1.6kmと全国的にみても大きな地下壕。見学できるのは、壕の一部。地図上の黄色い部分です。壕内には科(職種)ごとの居住区があったそうで、戦争末期図面では、「工作科格納庫」「応急治療所」「自家発電所」が記されてたようです。天井が高い壕は、格納庫として使われたのかもしれません。いざ入壕。 「自家発電所跡」この一角だけ壁面がコンクリートで補強され、土台や鉄筋が残っています。 4気筒200馬力のディーゼルエンジンが2台、発電機2台、変圧器9個あったそうです。この部屋の地層が綺麗です。 赤山という名前だけに、岩肌が赤いのかと思い込んでいましたが違うんですね。 このコーナーは色々ぶつけた跡がありますね。長い物でも運んだのでしょうか。ここは電球色の黄色がかった光が当てられているので壁の色が違って見えますが実際の色はどうなんだろう? ライトによって左右される岩肌の色 地層が綺麗です。 ここの地層はずれてますね。正断層かな? この部屋の地層の真中上部に妙なクボミがありますね。 何の役目でしょうか。最初の部屋の地層に似た部屋。ここはよく代表写真で使用されてますね。 しかし、壕内に入った時から全体的に霞がかかっててクリアに撮影できないのが難点。 所々にクボミがあるのだが、要所要所で用途が違い、発電所近くのクボミは、変電所電気員の待機所であったり、他の場所では電話番が腰かけて勤務していた場所だったり、桶をおいたトイレだったり。終戦後の昭和30年前後より温度が年中一定していることから、キノコ栽培に使用されていました。 この風呂やボイラー、コンクリートブロックなどはその時に設置されたものです。「ガンルーム」 少尉クラスの士官達の部屋だったようです。四角い部分は御真影を安置した奉安殿で桧の板張りだったそうです。人数が多かったからとはいえ、見学コースだけでも慣れないと絶対迷いますね。当時は自分の部屋の地層の柄で覚えたりとか、そこに居る人で判断したのか・・・。何とか営業時間内までに見学終了できました。赤山周辺には忘れてはいけない戦争の名残が沢山あります。赤山をぐるりと周るだけでも外側の坑口や出口が確認できます。そして、敵機から戦闘機を守るための格納庫【宮城掩体壕(えんたいごう)】 赤山周辺にはかつて10基余りあった掩体壕ですが、現存するのは1基のみ。ここにゼロ戦が隠されていたんですね。確かに上部からは草むらになってて判りにくいです。 中に入ってみて驚きました。零機って以外に小さかったんだ~!と。これでも大きめに造られたそうです。館山海軍航空隊には、97式艦上攻撃機を中心に124機の飛行機がありました。終戦の時には、零戦、紫電など41機の飛行機しか残っていませんでした。 近くの家と比べると家3軒分かなぁ~?? セスナよりも小さい??2人乗りだし当たり前か~・・・。いつか浜松にある航空自衛隊へ勉強しに見学に行かないとって思いました。掩体壕については中高生向けの「戦争遺跡~遺跡を通して学ぶ平和学習~」がよく解ります。http://bunka-isan.awa.jp/About/item/000/050/ul1223081656.pdf
2017年08月07日
コメント(5)
-

崖観音
早朝からの健脚に加え、午後からの広い公園歩きでそろそろ足がお疲れモード。しかし、まだ時間も早いのでもう少し頑張ります。ようやく館山市に入ってきました。【崖観音】館山市船形崖観音で知られるこの寺は、『普門院 船形山 大福寺』と称し、真言宗智山派に属する寺院です。 山の岩肌には無数の穴。 当然、入ってみます。 防空壕かもしれない。 一部お墓もあり。 本堂へ登って行きます。 今日は登ってばかりだなぁ~ ご本尊はこの中です。天井絵が鮮やかです。 ご本尊は、養老元年(717年)に行基が山の岩肌に磨崖十一面観音立像を彫刻したと言われています。 足元しか判りません。灯りが下から照らされていたら判ったかも??しかし、説明書きには摩耗が激しく目鼻口などが失われているらしい。「おんまかきゃろにきゃそわか」と唱えるようです。今でこそ、歩きやすいように道があるが当時はどうだったのだろう?? 岩肌に彫刻って考えただけでも大変そうです。崖観音に隣接して神社があるのですが、かつての石切場でしょうか。 岩肌に2種の刻印が見られます。 それぞれの縄張りの印でしょうか・・・。意外な発見が面白いです。次はかねてから行きたかった「赤山地下壕」を巡ります。
2017年08月07日
コメント(0)
-

大房岬公園戦跡巡り
南房総国定公園の中にある「大房岬自然公園」は、キャンプ場や運動広場、芝生園地、磯遊び、ビジターセンター、自然の家、等 家族連れや子供達がのびのびと自然体験できる場として提供されています。 ここには知る人ぞ知る?隠れた名所?そう、戦争遺跡があるのです。予め家から印刷していた地図を手に公園内を周ります。まずは展望塔を目指す。 地図によると展望塔下に「弾薬庫跡」があり、それはすぐに見つかった。 中に入ると真ん中部分が水浸し。 反対側から周ってみる。が、やはり水浸し。 靴が水に浸らないよう、木などが敷かれている上を歩く。横に見えた部屋はこんな感じ。 隣の部屋も同じかな、と思いここを後にし「砲塔砲台跡」へ。 この近くの要塞跡地「弾薬庫跡」へ。 ここは水がないのですんなり入れたが、先ほどと同じ。 庫内の天井にはコウモリが住んでいた。 暗いのでボケてます。(^-^;反対側は立入禁止のようだ。 というか、ここに来る方がかなり厳しい道のりなのだが・・・。ここで日立のCMで有名な「この木なんの木きになる木」っぽい大きな木を見ながら 先ほど立ち寄った道の駅で買った千葉限定販売「房総サイダー びわ風味」を飲みながら一休み。 小振りの缶な上、それほど炭酸がきつくないので一気飲み。びわサイダーと思い込み買ったが、びわ風味。確かにびわの味でした。(笑)地図に記載されている「観測所跡」が見つからず、スルーし「掩灯所跡」へ これも何かの施設の一部だと思われる。 現在は倉庫として使用されているようです。ここにきて、初めての道案内「要塞跡地」の看板発見。他にももっと看板で知らせてくれると見つけられなかった施設も観れたのに。 大房岬要塞は、旧日本陸軍が昭和3年(1928年)から4年を費やし構築したもの。昭和20年(1945年)の終戦まで横須賀重砲連隊の兵士が守った。「大房岬の要塞群」は歴史を知る意味から南房総市指定文化財に指定され、戦争遺跡としては千葉県の市町村で第一号に、全国でも8番目の遺跡指定。「照明所(探照灯)跡」 この向い側にも要塞が見えるので、行ってみる。 トンネルの中を歩いているようだ。 先へ到着し、見えたのはこれ。ここが探照灯跡で向い側の要塞は兵士の待機所かもしれない。 見上げるとこんな穴 他の機具類があればどんな感じで利用していたかが解りやすいのだが、どのように、どうやって光を照らしていたのかも、想像すらつかない。(^-^;「要塞跡地発電所施設」 両側に穴が開いているようだが、埋められているようだ。危険の為、入口コンクリートで封鎖しました。と看板に記載されている。ここで戦跡とは関係のない「大房不動滝と行者の窟」へ。 滝は竜の口から流れ出ていおり、初代の石造りのは欠け落ちてしまい2代目だそうです。1441年 結城の戦いに敗れて安房の国へ逃れてきた里見義実が、この滝で身を清め不動尊に武運を祈願したそうです。行者の窟について 701年、伊豆の大島に島流しとなった役の小角は、毎夜、大房岬へ飛んできては窟を掘り、不動明王の像をまつったと伝えられています。大島から大房岬まで毎夜、船をこいでやって来たのでしょうか・・・。大房岬公園、最後の戦跡「南けい船場」海軍秘密特殊部隊(S特)[山岡部隊]訓練基地跡(人間魚雷「回天10型」特攻基地跡) ここはどうしても見ておきたかったのだが、どこだかよく判らなかった。 他の方がUPされているYoutubeを見つけたので貼っておきます。 ここの公園は大変広く、早朝からの歩きに加え、そろそろ疲れがでてきました。いやぁ~。よく歩きました。(^-^;大房岬戦争遺跡maphttp://bunka-isan.awa.jp/About/item/000/054/ul0814194848.pdf小学生向けの地図が大変解りやすく巡りやすかったです。
2017年08月07日
コメント(0)
-

ヒカリモ と ビワの産地
移動途中に見つけた「天然記念物 光藻発生地 黄金井戸」の看板。 洞窟っぽい!という事で立ち寄ってみました。【黄金井戸】富津市竹岡 この奥の洞窟っぽいところにヒカリモはあるようです。 ここに光藻があるらしいのですが・・・。 夜しか光らないのか?? 説明書きを読み直しに行くと、「ヒカリモ」は黄金藻類に属する単細胞の藻。 洞穴内に入ってくる光を反射させます。特に菜の花の咲く頃、水面に多数浮遊するため水が黄金色に輝いて見えます。水面には何も浮いて無いようです。 説明から、特によく見られる時期は春先のようなので、今は少ない若しくは無いのかな?早々に後にし、海沿いを移動。立ち寄ったのは南房総市にある「道の駅 とみうら 枇杷倶楽部」 ここはどうやら枇杷(ビワ)が有名なようです。 道の駅グランプリ2000 最優秀賞受賞駅 らしい。 右のはビワのモニュメント。しかし、時期的にびわが不足しているようで、ビワソフトに付いてくる枇杷が1つ少ない為、通常価格から-50円 と掲げられていた。 良心的ですね。びわの季節:5月~6月私達は東京湾観音で食したばかりだったので、ここではスルーしランチに。富浦漁港直送 お食事処「魚々工房(ととこうぼう)」で房州地魚漬け丼セットをいただく。 色んな種類の地魚の漬けが入っており、普通に美味しかったです。次は大房岬公園へ戦跡巡りに向かいます。
2017年08月07日
コメント(0)
-

東京湾観音
鋸山を堪能した後は、昨日 時間的に行きそびれた場所【東京湾観音】へ。 自販機横に人が居るが判りにくいが、自販機の大きさで判断していただければその大きさが判るのではないかと思う。身丈:56mほぼ正面から 優しいお顔の観音様です。真後ろから ちょうど太陽が頭に隠れ、後光が輝っているようです。真下から 観音様の胎内を巡ります。 20Fまで全て階段です。314段が、1F当りのの高さが低いのか、あっという間に上層部に到達します。まずは腕の部分から東京湾を望む。 写っている手は右手の指です。階段途中には十二支の守り本尊と七福神を参拝できます。全て木彫りです。 17F辺りから急な階段はしご。 ここは鼻の穴の部分。 白毫(びゃくごう)部分(額の真中についている丸い部分) 耳の穴 言われないと何だかわからないですね。(笑)耳の部分から外が眺められます。 20F 冠部分 頂上到達です。 鋸山で鍛えられたか、全くしんどさを感じませんでした。慣れってこわい!降りる時は急な階段はしごは危ないので螺旋階段を利用します。 狭い螺旋階段は目が回るので、広い場所に出た時にふらつきました。(^-^;胎内の七福神を全部巡ると、こんな感じになります。 パンフの裏にスタンプを押せるようになっています。(写真は現在のパンフとは少し違います。)帰りにお箸と箸置きがセットになったお土産をいただきました。 拝観料を割引いていただいた上にお土産までいただき、ありがたや~。東京湾観音は、宇佐美政衛氏が昭和36年当時120,000,000円(1億2千万円)の私財を投じ建立されました。生家は貧しく、丁稚奉公に行き、山林に治山治水の造林事業に一生をつくされた宇佐美氏、どうやってこんな大金を貯めたんだろう。そこ、とっても知りたい部分です。東京湾観音入口で売られているビワソフトが美味しかったです。 台風が来てるというのに、晴れてて良かった~。晴れ女冥利につきます。東京湾観音 公式サイト:http://archive.is/CqjvS公式ページ内に拝観料割引券(3割引)、おみやげ1割引あり。
2017年08月07日
コメント(3)
-

鋸山日本寺
2日目の千葉県観光のメインは【鋸山(のこぎりやま)】朝の8時OPENと同時に鋸山登山自動車道(有料道路)のゲート前に到着するも、早くも2台の先着車がゲート開放に待機していた。皆さん気合入ってます。<鋸山 山頂羅漢エリア>まずは「山頂エリア」の展望台【地獄のぞき】を目指し、ひたすら登る。ようやく展望台が見えてきた。 用意と歩く速度の違いか、地獄のぞきに到着したのは1番のりでした。 右手に飛び出た岩が「地獄のぞき」の山頂展望台です。1番のりはいいのですが、逆に人が居ないので大きさが判りにくいのが難点。(笑)先端からの景色です。 この切り立った断崖、これはかつての石切場跡のようです。説明書きには名勝鋸山は山中の地質、動植物等「天然の大博物館」と記載あり。ここから後で訪ねる「百尺観音」の場所が望めます。 左上に人が居るのが判るでしょうか。いかにこの岩山が大きいかが判ります。【百尺観音】百尺観音へ続く道が早朝で朝霧に包まれて何か神秘的。 観音側から振り返るとこんな感じ。 何かジブリの世界感あり。「百尺観音」(右)と「地獄のぞき」(左の飛び出た岩) 正面からの百尺観音 端から百尺観音 観音様の真下から仰ぎ見る。 本当にデカいです。左横の立て看板のてっぺんで大体2m位だと思う。ここ、かなり気に入っています。いつまでも居てたいほど、何か違う空気感なんです。たぶん、かなりのパワースポットだと思う。発願の趣旨は一つは世界戦争死病没殉難者供養のため、一つは東京湾周辺の航海、航空、陸上交通犠牲者供養のため。6年の歳月をかけて昭和41年にかつての石切場跡に彫刻完成。これは作成された方々のサインでしょうか・・・? 鋸山はとても広いので、いつまでもここに居る訳にもいかず、羅漢エリアへ移動します。<鋸山 羅漢エリア>五百羅漢とはよく耳に目にしますが、ここのは千五百羅漢です。通常の3倍。(^-^; この羅漢様の表情が好き。 談笑している羅漢に、それを聞いてか聞かずか笑ってる羅漢、居眠り羅漢。いい表情です。「通天関」 大阪出身の私は通天閣と読み間違え、友人に指摘されて気付く。(笑) 閣ではなく関です。この洞門?の左右には仁王像?が安置されています。この羅漢様の表情は何だか宇宙人っぽいと感じるのは私だけ?? そして、めっちゃ修行に励んでる羅漢様。 通路脇全体に羅漢様が安置されているので本当にキリがない程。 「奥の院無漏窟(むろうくつ)」 「不動滝」水量があまりありません。 滝といえば不動明王。誰かがお供えしています。 こういうのって、ほのぼのしてて何かいいなぁ~。羅漢エリアを制覇したので山頂駐車場に戻り、大仏口の駐車場に移動します。有料道路内なので、駐車場を行き来でき、一度拝観料を払うと何度も再入場できる点がいい。<鋸山 大仏広場>日本最大の大仏様が安置されています。正式名称:薬師瑠璃光如来 天明3年(1783年)3年を費やして彫刻完成したものです。宇宙全体が蓮華蔵世界たる浄土であることを現わしたもの。台座を含めた高さ:31.05m「お願い地蔵尊」 足元、周りに沢山の小さなお地蔵様。 私達もお願い地蔵を買って祈願しました。<鋸山 中腹エリア>このエリアは建造物がメインのようです。主な建造物のみ紹介しておきます。「大黒堂」 「薬師本殿 医王殿」 日本寺のご本尊、薬師瑠璃光如来を祀る。鎌倉時代の禅宗様式。昭和14年に火災により焼失し、平成19年に再建。焼失前の仏殿は、源頼朝による医王殿の扁額が掲げられていたそうです。「乾坤稲荷(けんこんいなり)」 「通天窟」 中の岩の地層模様が自然である事の証明ですね。 他に表参道エリアもあるのですが、さすがに歩き疲れてる上、炎天下の中を大汗かいて戻る事を考えるとスルーしてしまいました。めっちゃ歩きました。無料駐車場に停めて散策される方は普段から登山をしなれている方でないとキツそうです。この後他にも巡る場合は有料道路を利用し、駐車場を移動した方が体力温存できるでしょう。鋸山日本寺公式サイト:http://archive.is/bIbk3案内図に駐車場の場所が記載されているのでわかりやすいですよ。
2017年08月07日
コメント(0)
-

富津市 チーバくんの太もも界隈2
今回の旅行は、行きたかった所に加え、私の好きな登録有形文化財(建造物)チェックと友人のB級スポット、そしてGoogle map上での史跡・名勝・天然記念物の地図記号をメインに計画した。その地図記号で見つけた場所をクリックすると、色んな方が写真を投稿しているのでとても参考になり、これは行ってみたい!と思ったのが【燈籠坂大師の切通しトンネル】手掘りの燈籠坂大師入口トンネル 斜め模様の地層が綺麗です。ここを抜けると、思わず「おぉ~」と声をあげてしまう程の圧巻トンネルが右手に見える。 このトンネルを抜けると 燈籠坂大師への道へと続きます。 燈籠坂大師 燈籠坂大師は弘法大師が行脚中にそこで腰を休めたという口碑をもつ、東善寺の飛地境内地。燈籠坂大師(東善寺)の住職の話によると、切り通しトンネルは城山(造海城)の尾根の関係で上り下りが急であったため、昭和初期に地元において切下げ工事を行い、現在の形になった。とのことです。夏にはさわやかな涼風が吹き抜ける隠れた名所です。(富津市役所建設経済部商工観光課)本当に涼しい上、空気が違い、パワースポットといえる場所のような気がしました。 このトンネル、高さ約15m近く。しかも手掘り!!人がいないので高さ具合が判りにくいかもしれないがこの高さがとっても爽快感。上部を仰ぎ見、写真を撮ってみました。 何かいいなぁ~。ここは富津市竹岡。地元の方の生活道路でもあります。最後に【道の駅 保田小学校】へ立ち寄りました。 廃校となった保田小学校を道の駅に変身させ、再利用されています。入っているお店のネーミングもユニーク。 「中華料理 3年B組」 「cafe 金次郎」しかも、ここの道の駅は宿泊もできます。(受付:16時まで)本日は満室、そして受付時間もとっくに過ぎた最終営業時間18時すぎ。中を覗けませんでした。が、童心に戻って「こどもひろば」で跳び箱を楽しみました。 さすがに3段は縦からも横からも飛ぶことができましたよ。まだ老化はきてないな。と、確認と共にちょっと一安心。(笑)時間があれば昼間にまた寄ってみたいと思いました。ちなみに、保田は「ほた」と読みます。知らない人は濁って読んでしまいますよね。<参考URL>富津市役所建設経済部商工観光課:http://archive.is/Fgc5F東京湾観光情報局:https://web.archive.org/web/20170812040924/http://tokyo-bay.biz/pref-chiba/city-futtsu/ch0265/保田小学校:http://archive.is/sJuKN
2017年08月06日
コメント(0)
-
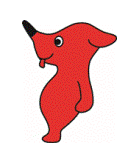
富津市 チーバくんの太もも界隈
富津公園から移動し、次は「東京湾観音」に行く予定だったが、拝観受付時間:4時まで。到着時間がどう考えても過ぎてしまうので見学は明日にし、時間にしばられない見学施設へ移動。 チーバくんの太もも界隈を巡ります。B級スポット好きの友人が行きたがっていたお寺。【圓鏡寺】富津市八幡 室町時代後期制作の市指定有形文化財の彫刻、木造阿弥陀如来坐像があるようですが、観る事ができませんでした。上総の七福神:恵比寿尊も有名のようです。 その恵比寿尊はこちら。言われて気付いた恵比寿尊の帽子・・・。 遠くから見ると・・・(^-^ 正面から写すと・・・(@_@ 恵比寿尊横の裸婦はご住職の若き頃の妻という噂が・・・。参拝者に見られても平気なのだろうか・・・そして、建物の横にはご住職夫妻。 夫婦円満には違いないのだが、ご利益あるのだろうか・・・ 失礼しました。m(_ _)m富津市数馬区にある奈良時代の高僧:行基による一夜の作と云い伝えられている【岩谷堂】正式名称:数馬村大悲山岩谷堂清源寺 本尊は十一面観世音菩薩岩山にいくつもの石洞が彫られ、洞壁に数多くの仏像が浮き彫りにされています。 古くは横穴式の古墳と思われますが鎌倉時代の「やぐら」形式の岩洞もあり。全部で14窟あるらしいです。 数えてません。 お寺周りの洞窟も入ってぐるりと半周できます。 永い間、村人の祈りや集いの場所として有り続けた村の博物館。ということです。 ここが集いの場所ですね。 一応、ランプは置かれていましたが電池?が切れてました。蚊取り線香と虫よけスプレーは必須です。涼しいので地元の方が飲み物を持ち寄って、まったりするには良さそうです。個人的には石碑の上にちょこんと乗っているこの仏像?が可愛くてお気に入り。 おそらく首がとれて、後から素人が手作りで作った気がする。顔が難しかったんですね。とりあえず顔とわかる様に作ったのがうかがい知れます。(笑)岩谷堂、気に入りました。今日はあともう一件ぐらい周れるかなぁ~
2017年08月06日
コメント(0)
-

富津公園と明治百年記念展望塔
富津。ここに来ることがなければ「ふっつ」とは なかなか読めない地名。【富津公園】 富津公園一帯は明治14年、政府により砲台と海堡が築かれました。園内に幅20~30mの外濠を掘り、一画を「中の島」とし、元洲砲台として明治14年から3年の歳月をかけて築造。 地図で見ると島になっているのがよく判ります。濠内の水は海水です。「行幸橋」 この橋を渡ると「中の島」「中の島展望塔」 ここからは海でカイトボード(カイトサーフィン)を楽しんでいる風景が見られます。 「観測壕」 展望塔を中心に左右、確認できました。「砲台の台座?」にしては小さすぎる。「方位盤」ではないかという説有り。 階段を降りると「弾薬庫?」 上部の穴は「伝声管」らしい。埋められていますが・・・。「弾薬庫の通気口?」 公園全体が戦跡なのだが、どうやら施設を埋めて公園にしているようです。一部レンガ造りの建物の一画が見えた。時季的に草がぼうぼうで埋もれてる。 ここ元洲砲台には明治28年、東京湾要塞司令部が発足し、歩兵中隊446名が守備についた。幸い、富津の砲台は一弾も発射されませんでした。詳しい園地マップでもあるといいのですが、下調べもなく全くの手探り状態でこれだけ見つけられただけでもいい方かな・・・(^-^;富津岬の先端に移動し【明治百年記念展望塔】へ。 昭和46年築。最上階の高さ21.8m。五葉松をかたどっっているそうです。建造物としては なかなか面白いデザインです。 設計:池原謙一郎ここからは第二海堡(左)、第一海堡(右)が望めます。 岬から富津市街を望む。 富津市 戦跡観光、堪能しました。
2017年08月06日
コメント(0)
-

ぶらり木更津まち歩き
江川海岸の後は恒例、登録有形文化財と西洋建築、他をちょこっと巡り。町の片側が海だったことから「片町」と呼ばれ、その真ん中に位置していた昔の木更津の町並みが残る地区「仲片町」を中心にちょこっと巡ります。当時は魚屋を中心に拓さんのお店が軒を連ねた「さかんだな(魚店)」と呼ばれた仲片町の本通り。 【安室薬局】仲片町の南境の目印になっている 昭和4年(1929年)築。東京銀座にあった文具店をモデルに建てられた建物。 【ヤマニ綱島商店】登録有形文化財 慶応2年(1866年)創業と伝わる乾物屋。【旧山崎医院】南町大通り 白辨天【嚴島神社】弁天通り 境内の池には沢山の亀。そして手水舎には亀と雀。 初代伊八(通称:波の伊八)作「日の出に鶴」「松に山鵲(さんじゃく)」の社殿彫刻が市指定文化財なのだが窓から覗いて見るしかなく・・・ 拡大してみます。 毎年10/15の祭礼時に一般公開されるそうです。【八剱八幡神社(やつるぎはちまんじんじゃ)】 源頼朝鎌倉幕府開幕に当たり、神領を寄進して社殿を造営。私の時代は1192年(建久3年)と歴史の時間に習ったが、現在ではそれ以前から政治が存続しているので1185年頃という新説がでております。拝殿内には色々と文化財があるようですが、奥まで入る事ができないので、覗き見る事ができません。 拝殿外にも「関東一の大神輿」があるようですが、これまた蔵に納められ見れません。昼間はガラス越し、夜は外の門を閉める。という方法なら観光客も楽しめるのに・・・。木更津観光協会の「ぶらり木更津まち歩き」の地図が役立ちました。木更津のシンボル。日本一高い歩道橋【中の島大橋】 ここを渡ると中の島公園へ行け、季節によっては潮干狩りが楽しめるようです。木更津 堪能しました。
2017年08月06日
コメント(0)
-

江川海岸 と ホンビノス貝
夏休みを利用し、千葉県に観光へ行こう!という話になり計画を立てました。アクアラインを渡って一番最初に訪問するのは木更津市にある【江川海岸】 ここは千葉県に住む友人がCMで有名と教えてくれた所。そのCMを見た事なかったのですが、むぎ焼酎二階堂のCMらしいです。熊本県にも同じような「長部田海床路」があるようですね。江川海岸は潮干狩りで有名な場所。海上の電信柱は、江川海岸の貝の密猟が横行していた時の対策として監視台が作られ、そこに送電するために建てられた「海原電線」夕暮れ時には満潮になってくるので「ウユニ塩湖」っぽい景色が観られるそうですが現在は立入禁止になっており、海には降りられません。しかし、夕暮れ時は海の向こうの工場地帯がライトアップし、幻想的だろうなぁ~。ちなみに、3月中旬からGW辺りは潮干狩りシーズンなので人でごった返すそうです。ランチはこの近くの「三協食堂」でいただきました。 なぜここかというと、千葉に行ったらホンビノス貝を食すべし!と取引先の方に教えていただいたから。看板に焼きホンビノス1個¥100の文字で即決です。 あさりめし(あさり汁つき)¥800 本当は丼なのだが、お昼のピークを過ぎた時間だったのでお弁当に詰替えてしまった。との事で、サービスにあさりめしのお弁当+1個とのりの佃煮をおまけしてくれた。 のりの佃煮はここで作られたもので、巷で売られているものとは雲泥の差。めっちゃ美味しい~ これが本来の「のり」なんだ~と感慨にひたる。で、待望の焼ホンビノス貝(本美之主貝)。 ホンビノス貝とアサリの大きさを比べてみました。ハマグリに近い大きさです。本当に美味しかった~。ホンビノスは本来、外来種ではあるが在来種とは生息環境が異なるので千葉県や東京湾海域での水産資源となっているようです。ここの食堂気に入りました。
2017年08月06日
コメント(0)
-

ご当地グルメ「つけナポ」
富士市のご当地メニューである「つけナポ」こと【つけナポリタン】を初食す。「つけナポ」発祥レストラン『アドニス』 店舗前にはふなっしー似のつけナポ公式キャラクター「ナポリン」が。 11:30pm~の提供で、なくなり次第終了らしいのですが、流行り始めた訳でもないい、混んで待つのも嫌なので、一般的にランチの終わる時間14:00頃に行ってみました。 つけナポは一度に6食しか料理できず、注文殺到時は1時間以上待つらしい。店内の雰囲気もいい感じで。取材が多いのか色紙が沢山貼られていました。 「つけナポ」はナポリタンのつけ麺。「つけ富士リタン」とも言う。トマトのスープスパゲティーを考えると有りですよね。富士宮市の「富士宮焼きそば」のようなご当地グルメを作りたい!と「プロジェクトチーム」を結成し、出来上がったご当地グルメなんだそうですよ。 濃厚トマトスープの中には味玉、蒸し鶏、チンゲン菜、チーズ。スパゲティの麺はソフト麺。桜えびが乗っています。【つけナポ流儀】その一、よくつけて食すべしそのニ、チーズをからめて食すべしその三、半分食べたらレモンを麺にかけるべしこの通りに食べると飽きずに、最後まで美味しく完食できました。すでにお腹は満腹を越えています。見た目よりボリューミーです。が、大食の方は麺大盛や替え玉メニューもありです。つけナポを提供しているお店はここ「アドニス」以外にも10店舗以上あるので他のお店のも食してみたいと思いました。美味しかった
2017年08月04日
コメント(0)
-
8月のほしぞら情報
8月の夜空のお知らせです。8/8 早朝、部分月食(月は最大で直径の4分の1ほどが欠けます。)時間:欠け始め:2時22分~ 最も欠ける時間:3時21分 元に戻る時間:4時19分方角:南西の空(∴日本の南西方面の方は長く観察できるという事ですね。)8/13 4時頃、ペルセウス座流星群が極大(8月12日の夜が特に見頃と予想される。22時以降~)時 間:夜半から未明(明け方)(空が明るくなり始める前に最も多くの流星が出現します。)放 射 点:北東方面の空から段々高度が高くなってきます。(空の広い範囲が見渡せる場所なら、どこを向いて観察しても良い。)流星の数:1時間に35個程度条 件:月が明るいため条件は悪い(8/8 は満月です)観察期間:2017年8月7日(月曜日)夜頃~15日(火曜日)朝方ペルセウス座はカシオペヤ座のやや下のほうです。カシオペヤ座を起点にして空全体を見渡せる場所がいいですね。防虫対策は万全に
2017年08月01日
コメント(0)
全25件 (25件中 1-25件目)
1