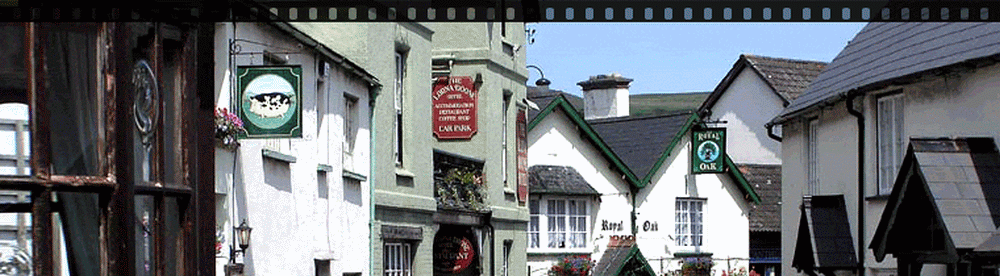2017年01月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

ロマネスコ
ロマネスコという野菜をいただいた。カリフラワーの一種です。 ネーミングにふさわしい、このらせん状の形がとても芸術的。何とも言えない美しさ。ついつい見惚れてしまいます。 この野菜と始めて出会ったのは10年ほど前のフラワーアレンジメントで。お花屋さんで。その時知った名前は「ヤリガイクン」何で、この名前??と思いましたが日本では「カリッコリー」「カリブロ」「やりがい君」「ドラゴンスパイラル」などネーミングも様々で販売されているようです。その時は食べれるって知らなかったのですが、程なくレストランでも目にするようになってきました。この形を崩したくないな~。裏を見ても小株分けできそうにないが・・・ 思い切って小株分けし、ブロッコリー同様に湯がきます。 小さならせん状が固まって一つのらせん状になっている様がよくわかりその様相にこれまた魅入られる。 自然の神秘。この後、美味しくいただきました。
2017年01月27日
コメント(0)
-

三島スカイウォーク
2015年(平成27年)の12月14日に静岡県三島市に開業した『三島スカイウォーク』正式名称:「箱根西麓・三島大吊橋」に行ってきました。 橋長400mの人道吊橋。歩行者専用としては日本最長です。入場入口で入場料¥1000のチケットを買います。 渡るだけでこの金額は高いとは思うものの、総工費を考えるとこの値段設定でないと料金回収できないか・・・と何気に思う。 橋は渡ると揺れるタイプの吊り橋ではなく、しっかりした普通の橋タイプ。オープングレーチングといって、風が通り抜けやすいような構造で安全性はバッチリ。あえて風による変形や振動を抑える耐風索を設けています。しかも 大人が2100人乗っても大丈夫らしい。吊り橋の両下部(写真では右側だけ)に耐風索の基礎部分が見られます。高さは一番深い谷から70.6m 下を覗くと、川が流れていました。遠くには富士山、その反対側には駿河湾が望めます。 向こう側に渡ると、吊り橋のメインケーブルを支えるアンカレイジが見られます。ケーブルがアンカレイジを引っ張る力は一基当り最大約800t。 アンカレイジ部分の上から撮ったスカイウォークがいい感じです。 引っ張られてます。って感じです。開業1周年イベント《風車モザイクアート》 「ふうしゃ」ではなく「かざぐるま」です。主塔 展望台から この時期、はっきりいって風が強くて寒いです。風を通さないコートに、耳あて、ニット帽子(強風でも脱げないもの)、手袋、の4点セットは必需品です。私の場合、この4点セットに加えカイロも持参しました。足元は山でも行けるブーツだったので、バッチリ。(^-^)v身体はほこほこで無敵でしたが、顔だけは無防備状態。ほっぺがカジカんで、話がしづらい上、麻痺して食べ物の味が全くわかりません。マスクは必需品ですスカイガーデンでお土産ではなく花を堪能し、(ちょっとした「なばなの里」風です) 箱根西麓三島農園「831JUICE」で有機栽培コーヒーをクーポン利用でいただく。(印刷要) 温まりました~!!ちなみに「831」は多分「やさい」と読むと思います。以前、学内にサブウェイの「831 LAB(やさいラボ)」があったので・・・今ではグランフロント大阪に入っています。橋を渡るだけですが、堪能しました。
2017年01月23日
コメント(0)
-

史跡日本百名城「山中城跡」
三島市の山手に位置する、1号線沿いにある昨年できた話題の某施設に行く前にその先にある(車で約3分)にある【山中城跡】に行ってみました。 永禄年間(1560年代) 北条氏が小田原防備のために創築したもの。天正17年(1589年) 豊臣秀吉の小田原征伐に備え、増築が始まり 翌年3月 豊臣軍に包囲され、わずか半日で落城した悲劇の山城 城跡内の敷地の一部、北条方の守将:松田康長、副将:間宮康俊の墓が「三の丸跡」のここ【宗閑寺】境内に苔むしています。 【山中城跡】は、堀や土塁の構築法、曲輪(くるわ)の造成法、橋の配置、飲料水の確保、石を使わない山城の最後の姿をとどめている点等、学術的に貴重な史跡です。堀や土塁 土塁とは・・・土製の堤防状の壁のこと。畝堀(うねぼり)や障子堀(しょうじぼり) これは必見です思わず「おぉ~!!」と歓声を上げてしまいました。(笑)曲輪(くるわ) 城郭の核となる本丸の周囲に、補佐的な二の丸、三の丸を効果的に縦深配置すること。下から見ると段々になっているのが良く判ります。橋の配置 本丸へ敵が攻めてきたら、橋を破壊し敵兵が堀を渡れなくすることが可能。少し上にある天守台から本丸を望む。 向こう側に駿河湾の海が見えます。飲料水の確保の一つ「池」 午前中だったので、まだ池が凍っていた。土も一部凍っていて、シャリっという音がします。1号線は幸い、交通量が多いせいか道路は凍結していなかったので良かった。鞍馬神社から貴船神社への山道「木の根道」っぽい雰囲気。 近くには石畳の「箱根旧街道」もあり、これまた良い雰囲気。 春になると、谷がツツジで色づき、見どころらしいです。 この丸々したツツジがピンクに色づいたのを想像すると確かに見所ですね。山手なので、富士山の眺めも絶景です。が、今日は少し雲がかかっています。 いやぁ~。広大なエリアですが、堪能しました。この城跡でロケもされていたので、TVで紹介されるかもしれませんね。
2017年01月23日
コメント(0)
-

裾野市 公園(滝)巡り
茨城県の水戸市ではなく、富士山の裾、裾野市の公園。『偕楽園』駐車場横には天明五 乙己年と刻まれた古い石仏と寺? ここから園地へ降りて行きます。 いきなり滝現わる。って音は聞こえてるんですけどね。(笑)『不動の滝』落差:10m余り お天気がいいので、水しぶきで虹がかかっています。 滝の脇に不動尊を祀った堂があるのでその名が付けられた。とのことですが、お堂に気付きませんでした。(^-^;その上、温かいからか、もう桜がちらほら。 温かい上に桜が咲いているのを見ると、やはりテンション上がるのか一層元気になります。満開になったら滝と共に絶景なんでしょうね。 『中央公園』黄瀬川と佐野川の合流点にある公園で、園内に川が流れている為、吊り橋や架け橋がかかっており いい雰囲気です。 ここでは、梅が咲き乱れて降りました。お弁当を持って、お花見に来ている親子や網をもって川で遊ぶ親子などここは既に春。かつて、明治・大正時代にこの吊り橋を渡った先に「東海道佐野瀑園 佐野ホテル [五竜館]」が建っており、新田次郎、若山牧水や皇族方も来訪された名勝地でした。今は建物はありません。この公園内にも滝があります。「五竜の滝」落差:12m 三島溶岩流の間から流れ出る滝が見事です。大きな三条の滝を雄滝、左から雪解、富士見、月見、東側にも木々に隠れて2本滝が流れています。 小支流にかかる小さな二条の滝を雌滝といいます。左から銚子、狭衣 という名がつけられ、五竜の滝の名の語源となっています。裾野市の汚水マンホールも五竜の滝(三条の滝)がモチーフです。 吊橋を下から望む。 園内入口には「旧植松家住宅」重文 内部 裾野市石脇 にあった江戸期の農家住宅を公園内に移築。今日の富士山は見る位置が違うので、表情が違います。宝永火口が真正面です。 左右で雪の量が違うのが判るでしょうか。富士市(左)側は温かいだけあって雪が少ないですね。やはり北からの寒波を富士山が遮ってくれていたんだなぁ~としみじみ。相も変わらず、ぽかぽか陽気。(最高気温:14℃)地元の方の話では、富士市は冬は降らない。と聞いているのも納得。
2017年01月21日
コメント(0)
-

「EMぼかし」で環境対策
小さな庭で家庭菜園中の我が家。毎日、野菜の皮や白菜やキャベツの芯や外葉など、捨てている部分や茶葉、コーヒーかす等がいちごのパック2杯強 でます。パックが一杯になったら、庭の土に埋めてたい肥にして土を増やしているのですが、土に居る微生物が少ないのか寒いから活動が遅いのか、そろそろ埋めるのも限界。市役所の廃棄物対策課で、堆肥を作る為のバケツを無料で配布しているのを知り、貰いに行ってきました。しっかりフタができるバケツに野菜かすを毎日入れ、「EMぼかし」という糠のような香りのチップを撒いて置いてておくだけで堆肥が簡単にできるようです。 「バケツは一つで十分です!」と伝えたのですが、堆肥を作るのに1ヶ月程かかり、一杯になった時に入れるバケツが無くなるので、1人2個づつ配布しているそうです。太っ腹~しかも、しっかりフタができるので、臭いもシャットアウトしそう。当然、猫や鳥からもイタズラされません。EMぼかしは1袋300グラム100円で売っているにもかかわらず、今回、2個もプレゼントして下さった。わ~い。早速、今日から使用します。(^^ゞその前に準備。バケツの真中部分を高くし、穴を開けたゴミ袋をセット。 野菜から出る水分を切る為の工夫。 今回、プラスチックのヨーグルト容器を使用しました。ここに、生ごみ+EMぼかし、生ごみ+EMぼかし、と毎日積み重ねていくだけ。 生ごみ100:EMぼかし1の割合なので、「EMぼかし」は少なくていいみたい。野菜は出来れば細かくした方が良いとアドバイスを受け、一応ざく切りにしました。EMにはハーゲンダッツのスプーンが調度いい感じかな?市としても生ごみリサイクルの活動にもなるし、出るごみも少なくなる。しかも土に埋めるという作業よりも簡単なのがいい。ゴミが減れば職員の処理作業も少なくすむし、双方ともに一石二鳥。都会では土の要らない人ばかりなので、このアイデアは無用ですが、畑の多い富士市ならではの環境対策の一環ですね。ありがたいです。せっかく市役所に行ったので、屋上の「ふじさんてらすMierula」で富士山撮影。 今日は雲がちで、あまりハッキリしないのですが、富士山は変わらず美しいです。
2017年01月19日
コメント(0)
-

蒲原宿 神社巡り
江戸時代、徳川家康公の蒲原御殿の後ろにあることから名付けられた御殿山、桜で有名な御殿山、その南麓にご鎮座する神社『八坂神社』 創建年月日不詳。元禄年間(1688~1703年)の蒲原宿明細書上帳に社司が記載されている。 元禄12年(1699年) 大津波元禄16年(1703年) この地に移転設立 と考えられる。当初は宿民の疫病からの守護を祈願したものを考えられ宿中央に建造。『和歌宮神社(若宮神社)』神社に関しては由緒等が記載されたものが一切ない(気付かなかった)ので詳しい事は不明です。 拝殿には「若宮神社」と掲げられているが、 裏の脇には「和歌宮神社」の額がたてかけられていた。 額の古さから、本来は「和歌宮神社」なのではないかと思う。拝殿から本殿への階段。むっちゃ急です。 下から(左)と上から(右)の両方撮ってみた。急すぎて先が見えない・・・階段途中で振り向くと、真っ青な駿河湾の海が見え、春の陽気でもうすぐ夏が来るかと錯覚する程でした。御本殿 社寺には象の彫り物。海外では神の使いですが、日本でも?? 2つの鳥居 ゆったりとした時間が流れていて、のんびりぽかぽか。春になって桜の咲くころに、八坂神社のある桜の名所である御殿山に再訪しようと思う。帰りに富士川沿いを通り、富士山を望みながら帰路に。 頂上が雲で隠れてて残念ですが、新幹線が撮れました。
2017年01月17日
コメント(0)
-

東海道五十三次 宿場「蒲原宿」
徳川家康が開いた東海道、江戸から37里(148km)。品川宿から数えて15番目の宿場町「蒲原宿(かんばらじゅく)」へ行ってみました。 東木戸(東の入口)~西木戸(西の入口)まで約1.15Km。天保3年(1832年)4月 歌川広重(安藤広重)が描いた最高傑作の地です。 絵の場所は不明ですが、当時はどこもこんな感じだったんでしょうね。商家が続く町並みの雰囲気が素敵です。 左:「佐野屋」という商家(佐藤家)、右:「僊菓堂」という和菓子商家(吉田家)「志田邸」ヤマロクという屋号の味噌や醤油醸造の商家(登録有形文化財 第22-0074号) 「本陣跡」(大名宿・本亭ともいわれる) 勅使、大名、公家などの貴人が宿泊した大旅籠。一般の旅籠との違いは、門、玄関、上段の間がある点。 個人的には江戸時代の建物と明治の頃の建物でしょうか、複合している点がとてもいい感じ。この江戸時代からある通りに大正時代の洋館があります。「旧五十嵐歯科醫院」(登録有形文化財 第22-0070号)(地域景観資源指定 第2号)町屋を洋風に増改築した擬洋風建築。 当時は電話番号を表に掲げていたんですね。 電話はTV等でよく見られる手で回すタイプのもの。そして、和室の部屋には金庫が。 庫内には桐のタンスが当初からコンクリートで固めた状態で入っています。歯医者さんなので、金歯に使う金を入れておく為のもの。他にも沢山レトロなものがあり、紹介しきれません。2Fに上がる急な階段の横にある板。 開くと奥の部屋(離れ)に行くための廊下に早変わり。ナイスアイデア 今は古くて乗るのは危険なので、市から通行禁止と言われている簡易廊下。奥の部屋は特に何もない部屋ですが、今では特別注文しないとない擦りガラスが残っているようです。 間近でみないと判り難いですが、それぞれの窓が微妙にデザインが違います。2Fの和室 富士山の欄間に鶴の襖。この襖の鶴が移動するかのような欄間が続いています。 富士山の欄間を裏から見ると、鶴の襖の裏は松と鷹 一富士、二鷹・・・の縁起担ぎでしょうか・・・。肝心の歯医者さんは2F部分で、和室が連なる隣にリノリウム床の窓が沢山ある明るい部屋が診察室となっています。 当時のままの診察椅子。 一枚扉を開けると階段部分と向こうの部屋が見え、夏には風通しをよくする為の工夫が見られます。狭い通路には洗面。配電盤も剥き出し状態。東京歯科大学出の歯医者さん、東京方面から来られる患者さんも多く、庭の続き蔵の奥の赤い屋根の家は患者さんの宿泊施設となっていました。 今の様に頻繁に行き来できないので、宿泊施設はありがたいですね。全部紹介しきれないので、主要部分だけ紹介しました。また、蒲原の町には耐火煉瓦でできた蔵をよく目にしました。 江戸時代のとは違い、これまたいい雰囲気。江戸~明治~大正~昭和初期 の時代の物を一度に堪能できる町、蒲原。ここから先、西方面へと「〇〇宿」と宿場町が続きますが、それはまた次回。次は蒲原宿にある神社をちょろっと巡ります。
2017年01月17日
コメント(0)
-

天子の七滝
昨日に続き、本日も小春日和。昨日も暑かったし道路凍結は大丈夫そうなので1日3本しかない宮バスのバス終点駅(バス停)上稲子落合にある『天子の七滝』巡りに行ってきました。バス停横には炭窯があり、炭焼きの説明が・・・。 ここで昭和20年代まで年間約2000俵、30tの炭を焼いていたそうです。「静岡県のみずべ100選」のひとつの稲子川の源流域。平成23年9月20日に発生した台風15号による被害は甚大と富士宮市のHPに平成25年12月03日掲載以降、更新されていないが、他の方のblogで平成27年に行った情報もあり、大丈夫かな。と判断。実際、立入禁止もなく普通に行けた。なぜHPを更新しないんだろう・・・。そして滝の案内板もなく、とりあえず遊歩道の矢印通りてくてく。 とりあえずルートは間違っていなかった。「清涼の滝」 「観音の滝」 「丸渕の滝」 「しずくの滝」 「瀬戸の滝」 増水時は行けない「魚止めの滝」、今日は行けそうに見える川の水量。「魚止めの滝」入口 まで行くと、入口から約40分の表示。 途中、陽が当たらない部分が一部凍っていたり、 何かの骨が落ちててビックリ。(◎_◎;) 犬?猪??何??? そして、ここから先はムリ。 魚止めの滝入口に戻ると、実は道を間違えていました。(~_~;)実はこの林の中が本当の通路。 今迄がちゃんとした遊歩道だっただけに騙された~!!途中まで行ったが、ここから道がよく判りません。随分、間違えて歩いたので疲れしまい、諦めて帰りました。戻ってきて再度案内看板がないか探してみた。駐車場にあがってみたら、看板あった! 先に見たかった~!! 最初に駐車場に寄れば良かった・・・(T_T)ちなみに、他に「不動の滝」があるのですが、別のルートでしか行けないようです。 戻ると本日の最終バスがちょうどやってきた所でした。 バス時刻表 運行は月~土曜日です。日曜ハイキングをお考えの方はお気を付けください。車の方は大丈夫ですね。週末が大寒波だなんて、考えられないぐらいの陽気で、暑すぎず寒すぎず、ハイキング日和でした。
2017年01月12日
コメント(2)
-

滝川神社とコッペパン
富士南麓の下方五社の一つが比奈地区の公園巡りの中にあり、その下方五社「滝川神社」に行きました。 創建は、第七代孝霊天皇の御代に起きた富士山大噴火の際、「浅間大神」を祀り、山霊を鎮められたのが始まり。 源頼朝が治承4年(1180年)の富士川の合戦の戦勝祈願をし、建久4年(1193年)富士の巻狩りの際に直径約5寸の黄金の玉を奉納したそうです。また境内は「赫夜妃(かぐや姫)」誕生の地であると東泉院に伝来した永禄3年(1560年)の奥書「富士山大縁起」に記されていたようです。下方五社(日吉浅間神社、富知六所浅間神社、滝川神社、入山瀬浅間神社、今宮浅間神社)全社巡る予定です。あと2社だなぁ~。帰りににコッペパンを買いに「日東ベーカリー」へ再訪。今回も以前とほぼ同じ時間帯に行ったのにもかかわらず、コッペパンが一つも見当たりません。(@_@、)ウゥゥ 私 「今日はコッペパンが無いんですね。」ご主人「そう。今日はもう無いね。」「・・・」 「ラッキーな事に1つだけ、小倉クリームならあるよ。」 私 「下さい!!」という事で、とりあえずコッペパン1つはGETできました。 家に帰ってから「メニューにない品」という事に気付きました。 もしかしたら、ご主人さんの賄いだったのかも・・・感謝です。そして、以前質問があったマーガリンの件についてすっかり忘れており、聞かずじまい。(^-^;また次回覚えていたら。ですね。(笑)
2017年01月11日
コメント(0)
-

比奈地区の公園巡り
以前、blogでも紹介しましたが、延暦年中(782~805年)の伝説(富士郡比奈村皇国地誌編輯)が残っているのと、この周辺の地名、「竹採姫」と刻まれた自然石の塚 等があることからかぐや姫との深い関係がある富士市。時間もたっぷりあるので、富士かぐや姫伝説に基づいた場所や公園、他を巡ります。富士かぐや姫伝説に基づいた場所:[竹採公園] まだ門松が飾られており、お正月らしさが残っています。この公園には実際にある「みかえり坂」を模したものや「竹採塚」などがあり、雰囲気の良い公園です。 「竹採塚」 何か刻まれているのは判りますが、「竹採姫」とは読めませんでした。(^-^;水仙の花が全盛期で、とてもいい香りでした。 癒されます。(*^▽^*) 大好きな水琴窟の音にも癒されました公園の近くには、他にも色々と見所のある場所があり、伝説の人物「小栗判官(おぐりはんがん)」の妻:照手姫(てるてひめ)が夫の帰参を待って過ごした『妙善寺 観音堂』 この中に富士市指定有形文化財の木造十一面千手観音座像と木造多聞天・広目天像があるのですが、隠されていてみれませんでした。 照手姫が、いつでも夫を迎えられるように毎日身だしなみを整えるために水鏡にした『鏡石』判り難いですが、水の中に入っている黒い大きな石がそうです。昔よりも水量が減ったそうです。鏡石は「かがみ石公園」という所にあるのですが、公園自体が「六田川水源域」になっていて、水が綺麗でした。 公園内にバナナの木があり、花が咲いていました。 花の根元には既に小さなバナナができています。夏には収穫できそうです。温かい証拠ですね。(*^▽^*)ポカポカ陽気でお散歩に持って来いの温かさ。これも富士山が北風をシャットアウトしてくれてるおかげでしょうか。過ごしやすいです。
2017年01月11日
コメント(0)
-

須津川渓谷 再訪 とドラえもん寺?
小春日和の今日は上着が要らない程の温かさ。昨年9月【須津川渓谷】に行った際、ものすごい霧だったので、再度行ってみよう!という事になり、再訪。「須津渓谷橋」へ。晴れてると見晴らしが違います。 当たり前ですが、橋の向こう側が見えてます。(笑)橋から「大棚の滝」もハッキリ見える。 そして、前回は霧で気付かなかった大棚の滝への階段道。 滝まで80m。ひたすら降りる。あっという間に滝。近っ!! 水がむっちゃ綺麗です。下から橋を望む。 晴れてる上に、凍結してなくて良かった~ついでに同じ須津方面にドラえもん寺があるようなので、寄ってみる事に。バス停前にドラえもんが。 そして、階段入口にピカチュウ。 ここは「曹洞宗 福聚禅院」 奥には「あしたか観音」 ここにはドラえもんファミリーは居ませんでしたが、ドラちゃんが嫌いなネズミさん達、他が沢山居ました。 お寺の駐車場途中に「浅間古墳」の案内板を見つけたので寄ってみました。 お茶畑の間にあるようです。【浅間古墳】は未発掘の富士県内最大級の大型古墳(前方後方墳)。国指定史跡です。 古墳の上に神社が建っています。 丘陵地になっているので、見晴らしがすごく良かったです。 お散歩日和なので、次は富士かぐや姫伝説に基づいた場所を探訪します。
2017年01月11日
コメント(0)
-

ドラえもん神社(富知六所浅間神社)
普段は、関西では十日戎の話題がひっきりなしなのに、こちらでは十日戎という慣わしがないようです。富士山南麓の下方五社(※5つの浅間神社)の一つ、【富知六所浅間神社(フジロクショセンゲンジンジャ)】(通称:ドラえもん神社)に行ってきました。タイミングよく郵便局員さんが・・・(笑)ドラえもん神社と言われる所以は、鳥居横に花道の様にドラえもんファミリーが出迎えてくれているからです。手水舎横にはドラミちゃん風キャラ。 のび太君としずかちゃん風の2体 どちらも似てないが、特にのび太君は目が4つと噂が絶えません。もう薄くなっていて薄気味悪さはなくなっていますが、石彫りの眼鏡と目の上から手書きでズレて書かれているからなんです。(右側のアップで確認)ジャイアンとスネ夫風の2体は向かい合わせに。 スネ夫に関してはスネ夫ヘアーの立体感が話題。そして、ドラえもんファミリーの他にピカチュウが居るとの話題もあり、出会えなかった友人から「探して来て!」との依頼を受け、見つけたのがこれ。 浅間神社の事業計画が書かれた案内板の上。金網でできたピカチュウ。まだまだお正月の雰囲気が残ってます。そして奥に富士山。 狛犬の1匹が藁を食んでいました。 本殿 説明通り、老朽化に伴い御造営。木が新しくピカピカに輝いています。奥には県指定天然記念物の御神木「大樟」 推定樹齢 1200余年 めっちゃ太くて(目通り13m)凄い!! この木、好きだなぁ~。裏に回ると大きな空洞。なのに青々と元気に育っています。そうそう、肝心のドラえもん。 御神木の近くにひっそりと隠れたように置かれていました。メインキャラやのに・・・(笑)ピカチュウ風がもう1体。守り番?? 何か物足りないのは尻尾が無いせい?鼻も大きくてずんぐりむっくり体形。お正月、成人式も終え、もう空いているかと思ったら、ぱらぱらではあるが、引っ切り無しに参拝に来られていました。創建:第五代 孝昭天皇の時代 と、すごく由緒ある神社なのにどこかの国みたいに真似キャラを置いているので、妙に胡散臭さ満載なのが残念です。※5つの浅間神社(現:富知六所浅間神社、日吉浅間神社、滝川神社、今宮浅間神社、入山瀬浅間神社)とりあえず、ピカチュウを見つけるというmissionはcompleteしました。
2017年01月10日
コメント(0)
-

チーズケーキ色々
前回10月に初訪問したチーズケーキと焼き菓子の店「PoliPoli」が11月に移転し、新しい場所になって初めての再訪。 色んなお店が入ったお洒落な感じの商業施設の一画。その1F店舗に。ほぼOPEN時間に行ったので、完全に商品がそろっていて嬉しい。前回はあまり種類が無かったので、今回は選び放題。PoliPoli はレアチーズが美味しいと評判のお店。左上から時計回りに旬の「いちごのショートケーキ」純生クリーム使用白かびチーズに少々ゴルゴンゾーラ入りの「ブリ・ド・モーのレアチーズ」季節限定「いちごのレアチーズ」ラム酒が香る「チーズスティック」を買ってみた。個人的にはラム酒がほどよく香るチーズスティックが気に入った。レアチーズは可もなく不可もなく、普通に美味しい。次は「ラムレーズンのレアチーズ」(いつの季節だろうか??)と夏限定の「ゆずのレアチーズ」が 食べて見たいなぁ~
2017年01月06日
コメント(0)
-

日吉浅間神社と東泉院跡地
所用で出かけた際、早く出過ぎて時間つぶしに立ち寄った富士市にある浅間神社の一つ『日吉浅間神社』へ。 崇神天皇5年と伝えるが、記録がなく創建不明。文保年中(1317~8)渡来僧妙行により創建されたとも伝えられている。天文6年2月 北条氏綱が五社別當に任じられ、日吉神社は下方五社の一つに数えられるようになりました。この神社横に『東泉院跡地』があり、綺麗な公園となって整備されていました。 東泉院は密教寺院で、今川義元より下方五社と呼ばれる富士山南麓の5つの浅間神社(現:富知六所浅間神社、日吉浅間神社、滝川神社、今宮浅間神社、入山瀬浅間神社)に認められ寺院としての活動を続けていた。また、豊臣秀吉により現在の富士市の中部から北部にかけて村々の領地としておさめることを認められています。東泉院の境内にあった「宝蔵(ほうぞう)」 安政の大地震で被害を受け、安政4年(1857年)に再建。 蔵の中には、富士山の成り立ちや神仏のことなどを記した貴重な資料6点が残されていたそうです。かぐや姫が富士山の洞穴に入り神様になったという伝承も残されていたようです。「門・塀」 東泉院は「富士山」という山号をもち、その額2枚が残されており門や本堂に掲げられていたようです。 「富士山の文字は」明和7年(1770年)右大臣:花山院常雅という公家の筆。どこもかしかも浅間神社って・・・と、思っていたのですが、説明を読むと、本当にすごい所でした。下方五社(五社浅間)の神社、全て回ってみたくなりました。順番に制覇して行こうと心に誓いました。(笑)
2017年01月05日
コメント(0)
-

富士山本宮浅間大社 と 富士山本宮選麺大社
今年の初詣は『富士山本宮浅間神社』へ。道中で見つけた道標。関西から来た私は西から。 HP上に「毎年三が日は約34万人とすごい人数の参拝者」と記載されていたので絶対混んでいる元旦、正月2日を避けて3日に決行。晴れな上に、3月の陽気で暖かくて良かった~。 すごい人。という概念があったからか、思ったより少なく感じる。ここから富士山が綺麗に見える。少し雲がかかってるかな。「二之鳥居」 「楼門」 「拝殿」 「本殿」(重文) 慶長5年(1600年)関ケ原の戦で勝利を得た徳川家康が奉賽の為に慶長9年(1604年)社殿の大造営を行った。「水屋神社」の通りは、水汲み場になっている。 飲用は煮沸してから。となっているが、柄杓が置かれてるんですが・・・「湧玉池(わくたまいけ)」国指定特別天然記念物 富士の雪解け水が溶岩の間から湧き出ている。水温:13℃、湧水量:3.6KL/秒昔からこの池で身を清めて六根清浄を唱えながら登山する慣わしになっているそうです。水の澄み方が半端なく綺麗。 柿田川湧水公園の水よりも澄んでいます。今日はお詣りだけ。次回、空いている時にもっとじっくり神社を巡ろうと早々に帰る。帰りに、富士山本宮浅間大社まえのお宮横丁へ。 「富士宮やきそば学会」直営のアンテナショップがあり、その前に焼そば大明神を祀る【富士山本宮選麺大社】があります。 麺むすび、麺運向上、厄災麺除にきくとされます。お賽銭箱には開運ならぬ「開麺」と記されており、絵馬は「麺馬」となっています。(笑)焼きそば大明神の前には、当然 小さな「富士宮やきそば」が・・・ 本物かな 食品サンプルだろうか・・・ローカル列車「身延線」に乗ってすぐなので近くて良かった身延線はローカルすぎてワンマン電車だし、無人駅とかあるのにビックリしましたが、また利用しようっと。
2017年01月03日
コメント(0)
-
2017年1月の星空情報
2017年 最初の星空情報です。〔しぶんぎ座流星群が極大〕1/3~1/4 23時頃~1/4 深夜(早朝)1時間に35個程度。 月明かりの影響がなく、比較的条件がよいです。北東の空 北斗七星(ひしゃくの形)の取っ手部分よりやや斜め下方辺り流星群はピーク時だけでなく、その前後日も見られます。この時期はお休みの企業が多いので、空気も澄んでいます。日本海側の地域はお天気があまりよくないようですが、太平洋側の地域では晴れる所が多いので、機会があれば ぜひ夜空を眺めてみてくださいね。防寒対策は万全に
2017年01月02日
コメント(0)
-

2017年元旦
2017年は丁酉(ひのととり) 酉は鶏ですが、「ひのととり」だけみると火の鳥みたいですね。何か、縁起が良さそう。<酉の由来>酉はもともとは酒つぼを意味し、収穫した果実から(実る)酒を作るという行為に由来したという説があります。商売などでは「とりこむ」と言われ、縁起の良い干支です。酉は 鶏=時告げ鳥 です。 太陽を迎えてくれる「神聖な存在」等々、諸説あるようです。また、酉年生まれの守り本尊は『不動明王』。 滝に行け!ということかっ!? まぁ、私は酉年ではないのですが・・・(笑)滝に行くと不動明王がいるのは、滝業などの仏教修行者のためにその修行をたすけ、修行の邪魔をする『魔』から護ってくれるそうです。2017年の皆さんの抱負はいかがでしょうか。 私はせっかく富士市にご縁があって来たので、富士山登頂にチャレンジするかもなので、まずは体力作りにあちこちを軽くトレッキングしつつ滝を拝み(とりあえず酉年だけに、上記理由で滝を入れ込んでみました。)(笑)夏頃までに健脚力を高めていきたいと思っています。自然の景観写真も共にお届けしますのでお楽しみくださいね。本年も変らずよろしくお願いいたします。
2017年01月01日
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- モミジの回廊
- (2025-11-25 10:06:52)
-
-
-

- アメリカ ミシガン州の生活
- いよいよ日本へ本帰国
- (2025-01-11 13:13:28)
-
-
-

- ディズニーリゾート大好っき!
- (自分用記録) ~「ディズニー・ク…
- (2025-11-23 19:05:02)
-