2011年12月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

Ferrari B.B Berlinetta Boxer
フェラーリBB。スーパーカー西の横綱。今年の最後にふさわしいかと思いまして。かつてフェラーリBBには、365GT4BBと512BB、512BBiと3種類のモデルがありましたけれども、365は365cc×12気筒、512は5リッター12気筒、iはインジェクションで、”Ferrari B.B Berlinetta Boxer”なんていうモデルはありません。写真はいわゆるプロトタイプで、1971年のトリノ・モーターショウに展示されたそのもの。私が生まれる前の話だから、文献等によるのですが、ピニンファリーナのブースで発表されたとか。DEAセンターと言われた、当時最新鋭の風洞実験設備で空力性能を設計されたプロトタイプは、現在もピニンファリーナにあります。ピニンファリーナは、トリノ・カンビアーノに本社があり、本社内にはコレッツィオーニ・ピニンファリーナなるプライヴェート・コレクションがあります。フェラーリがヴィーナスになり、スーパーカーが女王になるその秘密がこのプライヴェート・コレクションにあることは、誰でも容易に見つけられることでしょう。その容易に見つけられることは、しかしながら、その印象とは裏腹に非常に厳しい山とか壁を越えたところにありました。ピニンファリーナのWEBサイトを覗くと、このコレクションも掲載されていて誰でも見ることができ、また連絡先も書かれていて俄かに期待が高まります。http://www.pininfarina.it/index/collezionisti/collezionePininfarinaされど、これを見て何度も連絡を入れましたがまったく無しのつぶて。モンツァの時期に合わせてトリノにも出向きたいと、半年以上前からメールを送りますが、こちらからのメールが届いているのかいないのか、もしや日本語のメールは迷惑フォルダにでもフィルタリングされているのではないかというくらい、まったく音沙汰がありませんでした。その後時間が経過して夏になり、出発直前になって再度連絡しても同様で、やはりピニンは自動車メーカが相手の事業だから、まったく関係もコネも何もない一個人ではダメなのかと失望しつつ、ホテルを予約して日程もフィックスしたのでした。スパでオー・ルージュを見て、パリからTGVでフランスを縦断すると、ジャン・アレージの故郷アヴィニョンに着く頃にはもう今週にはトリノに入ってしまうという日程です。スコールの降るプロヴァンスのホテルで休息を取る1日でも、カンビアーノが気がかりでゆっくり休めません。そうして、もう一度。最後の悪あがきダメ元で連絡してみると、奇跡的にOKの返事がきました。もうベッドの上で狂喜乱舞です。週明けに判明したことには、事務所の留守電に「Mr. Inomata,Visiting cambiano torino~」とコンファームの連絡が入っていたそうです。こちらは、もちろんすぐにリコンファームをしてフィックスし、ようやくスーパーカー・ブーム以来といいますか、物心ついた時以来の念願が成就してヴィーナスとの対面です。365も512も知っていますが、何かが違う特別な一つに初めて触れる感覚。これを夢の実現といわずして何をいうのでしょう。しかし息を呑むような美しいものを目前にすると、どうやら理性も感性も両方とも高ぶり過ぎてメーターを振り切ってしまうのか、声も手も出ません。自動車メーカご一行のように仔細を検分するわけではなく、デザイン学校の修学旅行のようにディスカッションするわけでもなく、ただただ一人で存分にコレクションを独り占めしていいと言われると、手も声もでなくなるんです。何をどうしたらいいのか分からず、何から見ればいいのか分からず、許された時間のなかで忘却を許してはならないところにばかり意識が働いて、シャッターを切ったのでした。それでは、皆さま、どうぞよいお年を。感謝!
2011年12月26日
コメント(0)
-

Pinin Farina
-Italiano: Stile italiano significa senso della proporzione,semplicit? e armonia di linee, sicch? quando ? trascorso untempo considerevole si puo ancora notare qualcosa che risultapiu vivo del ricordo della bellezza.-English: Italian style means sense of proportion, simplicityand harmony of line, such that after a considerable timethere is still something which is more alive than just amemory of beauty.-日本語:イタリアンスタイルというのは、プロポーションであり、シンプルさとラインの調和である。それは、長い時間が経過した後でも、記憶のなかの美しさよりもずっと生き生きしてみえるものだ。フェラーリ・ストラダーレの秘密がここにあります。そのボディをヴィーナスに仕立てることで有名なカロッツェリア・ピニンファリーナは、現在「ピニンファリーナ」と呼ばれていますが、これは創業者バティスタの愛称が公式な名前になったもの。上記の有名な一節と共に記されているシグネチャはPinin Farinaとあります。ブログではその筆記を表現できないのが至極残念なのですが、彼の生み出した「作品」と、言葉を記す「文字」との間に、共通する「線の美しさ」または「生きる調和」が息づいていることに、現代のルネサンスを感じます。Felice bellezza amare, La F eterna.感謝!
2011年12月22日
コメント(0)
-

512BBの木型
カンビアーノで発見しました。512の5は5リットル、12は12気筒、BBはベルリネッタ・ボクサーの意であることは有名ですね。以前、どこかの雑誌でスカリエッティ工場の傍らに放置されているという写真を見た記憶がありますが、現在はマラネッロではなく、カンビアーノにあります。がしかし、512BBはiも含めて1936台も生産されたので、一つの木型で最後まで賄うことが出来たのかどうか、いささか疑問に思うところも残りますから、例えば最初のものがこちらで、スカリエッティのものは最終生産時のもの、なんて可能性もあるかもしれません。シャシーやエンジンには生産番号がつきますが、木型にはそれらしきものはありませんでした(笑)。この木型を観察して感じることは、型の上に金属板を当て板金でボディパネルを作るなら、フェンダーフレアの角はどうしても丸くなるだろうということ。と、加えてこういう細かい部位は何度も叩くことになるはずだから木型のうちでも傷みやすい部位に当たるということから、一つの木型で2000台近くも賄えたのかという冒頭の素朴な疑問に回帰します。 木型とスカリエッティといえば、木型を治具にボディを生産したのはBBや328が最後で、古い良きクルマ生産の最後の遺産です。その生産工場の当主だったセルジオ・スカリエッティ氏は、先月91才の天寿を全うされました。これも2011年の記憶になります。感謝!
2011年12月21日
コメント(0)
-

Lancia Aurelia B24 Spider
ランチア・ランチで見掛けたのはコンヴァーチブル。こちらは正真正銘のスパイダー。両方ともピニン製。よく似ていますが、ラウンドしたフロントスクリーンが特徴です。▲Lancia Aurelia B24 Spider▲Lancia Aurelia Convertible傍らに立つ案内板には、以下のようにあります。-In italiano: Versione definitiva dello spider Lancia B24destinato soprattutto all'esportazione negli Stati Uniti. Protagonista del film "Il sorpasso" di Dino Risi con Vittorio Gassman, la vettura fu construita in serie in 761esemplari (240 spider e 521 convertibili).Motore anteriore,2451cc, 117CV, trazione posteriore.-In english: Final version of the Lancia B24 Spider mainlydestined to the U.S. market. Protagonist of the movie"Il Sorpasso" by Dino Risi, with Vittorio Gassman, the carwas manufactured in 761 units (240 spiders and 521convertibles). Front engine, 2451cc, 117HP, rear-wheel drive.日本語:最終版のランチアB24スパイダーは、主に米国に輸出するためのものでした。ヴィットリオ・ギャスマンとディーノ・リージの映画"イージーライフ"の主人公は、761台(スパイダー240台、コンバーチブル521台)製造されました。フロントエンジン、2451cc、117馬力、後輪駆動。要するに、スペックに細かい人は違うクルマだと仰いますけれども、「どちらの仕様でウィンドウを組んだか」程度の違いしか違わない双子車というのが正解でしょう。日本にはほとんど存在しないため幻になっている、地球の反対側の秘密がひとつ解けました。カンビアーノにて。感謝!
2011年12月20日
コメント(0)
-

カンビアーノ・サンテーナ
イタリア・トリノの中心駅トリノ・リンゴットから、近郊路線に乗り換えて3つめ、約15分ほどにあるコムーネがカンビアーノ。駅の名前はカンビアーノ・サンテーナ。線路を挟んで北側がカンビアーノ、南側がサンテーナというわけで、日本で駅名をつけるときと似てますね。1時間に1本あるかどうかというダイヤの近郊線ですから、駅は無人で駅舎には鍵が掛けられていました。こういう場合、駅できっぷを買うことが出来ないため車掌から買うのも日本と一緒。もう慣れたものです。日本と違うのは、列車の到着が近づくと案内放送が流れるのではなく電動ベルが鳴ることで、ジリジリジリというベルが数分間に亘って人影わずかなホームに鳴り響きます。すると、どこかで聞いていたかのように乗客がバラバラと集まりだし、列車の到着に無駄なくホームにたどり着くのは、時刻表どおりに運行されることの少ないイタリアで、人々が持つ天才的な才能なのではないかと不思議に思っています。2007年のチェファルー、2009年のノートに引き続き、今年も日本人と出会うことのないイタリアを覗いてきました。感謝!
2011年12月19日
コメント(0)
-

Leone d'oro
「黄金のライオン」という最高の名前が付けられたスプマンテを頂きました。頂いたというのはダブルミーニングで、11月のランチアランチに参加した際に、くじ引きで貰ったものでもあります。くじ引きの景品として出品してくださったのはガレーヂ伊太利屋さんだとか。ガレーヂ伊太利屋さんはクルマやアパレルで有名ですが、こういった物品も取り扱っているんですね。イタリアとのパイプが出来ていると考えれば当然ですけれども、違う業界の商品というのは違うノウハウが求められるのがプロの世界ですから、それだけノウハウをお持ちだということの証左と、なにより良いモノを選択されているという目が利くという点で素晴らしいことだと思います。そういう内容を含むからというわけではありませんが、とても肌理が細かくて葡萄のテイストをストレートに伝えてくれる”思わず美味しいとつぶやいてしまう”美味しいワインです(微発泡)。一般的な流通ルートに乗ると、フルーティとか飲みやすいという形容で受け入れられていくのでしょうけれども、そういう安易な取引ではなくて、人生の楽しみを知る価値が分かる人に飲んでもらいたいと、戸棚の片隅で選ばれるのを待っているような一本です。イタリア料理を食べるなら本国よりも日本のほうが良い。されど、ワインだけは何とかならないか、というようなグルマンディーズな紳士と淑女の、週末の夜にどうぞ♪感謝!
2011年12月16日
コメント(0)
-

GLEN MHOR 1978
1983年に閉鎖されてしまったグレン・モールのカスクボトルをとあるバーで見付けました。これまた幸か不幸か、ここのバーはバーボンが専門とのことで、数少ないモルトウィスキーのボトルの陰に忘れられたかのように残って(そう、残って)いたものです。そういうお店だからかマスターも特別なご関心はお持ちでないご様子でした。このボトルは瓶詰め年の記載がなかったので、熟成年数は不明です。しかし蒸溜年のプリントがあるヴィンテージボトルという性格を考えると少なくとも20年前後でしょう。私個人的には若さと熟成のバランスが最高だと考える最適年数ですので、迷うことなくお願いしました。テイストは典型的なグレン・モールです。程よくナッティーでフルーティ。アーモンドのスライスを載せたフルーツ・タルトのよう、というと上手く表現できるような気持ちにもなりますが、一方でアルコール度数が63.2度もあるのでアルコール辛く、マイルドな甘さの後で稲妻が走る好みのタイプでした♪そういえば、グレン・モール蒸溜所はインヴァネスにあったそうで、以前訪れたことのある知っている町にあったという親近感もプラスの評価を加点したいくらいです。そういうことで大変申し訳ないですが、前回までご紹介したものはぜひ何方でもご一緒させていただきたいウィスキー。今回のグレン・モールは私一人の秘密にさせてください(笑)。感謝!
2011年12月15日
コメント(0)
-

Isle of JURA 10 yo
アイラ島の東隣にあるジュラ島。隣りというのは本当に隣りで、カリラ蒸溜所やブナハーブン蒸溜所からは川の対岸のように見えます。▲カリラ蒸溜所からジュラ島をみる。泳いで渡れそう。そのジュラ島には、その名もジュラという島唯一の蒸溜所があるのですが、目と鼻の先まで行っておきながら終にジュラ島には渡らず飛行機で戻ってきてしまいました。ウィスキーのジュラにはそういう思い出があります。そんなご縁ということが理由なのか、今までジュラを飲んだことはなく、あちらこちらで読むテイスティングノートはアイラと正反対と書かれていて、それで選択肢に登らなかったのかもしれません。ようやく初体験でした。アイルオブ ジュラ 10年幸か不幸か、はたまた何かの悪戯か、その日も強いウィスキーを飲みたい気分の日で、一杯目がラガヴーリンから始まるような具合でしたので、ジュラを飲んだときには味がなくなってしまったかのような舌の変化に狐に摘まれた気分になりました。しかしながらよく観察してみると、とてもスムーズでなめらかな舌触りをもっていて、これは確かにアイラ島では見かけない種類の味であり、あえて言えばローランドのローズバンクのようと形容するのが近いのでしょうが、されど3回蒸溜の丸い味ではなくむしろウルトラスムーズなハイランドに近い感覚です。仕込みはどうやらバーボン樽らしく、とうもろこし甘いメロウな味がころころと転がり、フィニッシュはサスティーンが長く続く爽やかな一本。一見(一舐)なんてことはないウィスキーのようですが、その実は他のどこにもない個性であり、ハイランドほどアルコール辛くなく、ローランドほどメロウでなく、アイラほど臭くなく、スペイサイドほど樽香が強くない、されど無個性ではなく味わいのあるウィスキーが飲みたい。そういう本物が欲しくなったときに最適なウィスキーです。今までご縁がなかった不徳を恥じつつ、これからは密かな常備薬としてラインナップしたい(もちろんオールドボトルを!)ウィスキーです。感謝!
2011年12月14日
コメント(0)
-

A. D. Rattray BOWMORE 14yo
前日のバーテンダー氏に、ちょっと変わったものある?と聞いて出てきたのが、こちらのボウモア14年でした。デュワラトレー ボウモア14年[1997]アイラ島で最古の蒸溜所として有名なボウモア蒸溜所系列の瓶詰業者であるデュワラトレーがボトリングしたもので、日本のメジャー酒販業者である信濃屋さんが樽買いされたのだそうです。ラベルの一番下に「for Shinanoya」と入っていました。ボウモアは、今やサントリー社傘下の蒸留所としてウィスキーを製造していますけれども、このボトルは従来蒸留所を経営していたモリソン・ボウモア社のスタッフがカスクを選んだとのことで、昔懐かしいボウモア本来の美味しさが残っている貴重な一本です。テイストは幸か不幸かシェリー樽仕込みだったようで、ミディアムにピートを焚いたモルトのピート香とモルトの甘み、シェリーの風味、ヨード香が次々と姿を現すように顔をみせ、大きな味の流れのなかにグレープフルーツのような柑橘系のヘザー・テイストが光るウィスキー。フロアモルティングで製麦したのか、複雑なボディが口のなかに広がります。もちろん、ボウモアであることを頑として主張するように黒コショウとオイリーなテイストが芯を貫いているので、ちょっと変わったボウモアとしてだけでなく、昔懐かしい本物のボウモアを味わいたい御仁にも最適です。ここまでくると、本当のボウモアを日本にもってきた酒販業者を誇りに思うべきか、ボウモアを日本の酒造メーカが所有していることを誇りに思うべきか、非常に悩ましい事態となります。かつてボウモアで蒸留長をしていたジム・マッキューワン氏は、山崎蒸留所などを経て独立、ブルックラディ蒸溜所のオーナーになりました。ウィスキー製造の世界では、蒸留長が一番強いのが通り相場だそうですが、伝統がよいのか商売がよいのかは製品のみが知るということなのでしょうか。ウイスキーがお好きでしょ(作詞:田口俊 作曲:杉真理)ウイスキーがお好きでしょもう少ししゃべりましょありふれた 話でしょそれで いいの 今は気まぐれな 星占いがふたりを めぐり逢わせ消えた 恋 とじこめた瓶を あけさせたのウイスキーがお好きでしょこの店が 似合うでしょあなたは 忘れたでしょ愛し合った事も感謝!
2011年12月13日
コメント(0)
-

LOCH LOMOND Triple distillery
『ロッホ・ローモンド』と読むのだそうです。初めて見聞きしたモルトウィスキー。バーテンダー氏はスペイサイドだと仰いました。LOCH LOMOND 18YO私はEU法によってウィスキーが40度になってしまってからというもの、あまりスペイサイドを好んで飲まなくなりました。それは43度から40度へ3度分加水することによって、その特徴の大きな割合を占めるナッツ風味が毀損してしまったことによります。シングルモルトだといって、スペイサイドを飲んでも他の地域を飲んでも差が小さくなってしまったと言い換えてもよいかもしれません。でも、このロッホ・ローモンドを選んだ理由は、40度ではなく、スペイサイドだからでもなく、3回蒸留だと聞いたからです。ウィスキーは、一般的に蒸留2回で樽詰めし熟成に回されますが、グラスゴーやエディンバラに近いローランドと呼ばれる地域では今でも3回蒸留をしています。日本ではサントリー社のおかげでオーヘントッシャンが比較的容易に入手可能でおなじみですね。しかし他の地域で3回蒸留の製法を耳にしたのは始めてで、3回蒸留するということは、2回に比べてアルコール純度が高くなり、熟成樽の成分が溶け込みやすく、熟成年数が短くて済むという特徴が、EU法のデメリットを上回ってくれると期待して頼んでみたのです。試した結果は成功で、9年熟成のボトルでしたが十二分に熟成が進み、スペイサイドらしいナッティーなテイストが(2回蒸留物に比べて)マイルドなアルコールの上でダンスしているような味わい。他のスペイサイドとは明確に違い、ローランドとも異なる、完全にユニークな個性のウィスキーが出来上がっているのですから、このチャレンジは大いに称えられるべきものでしょう。モルトウィスキーには、まだフロンティアが残されていることを高らかに宣言する素晴らしい美酒です。まだ誰も知らないうちに、あなたもぜひどうぞ♪(笑)感謝!
2011年12月12日
コメント(0)
-
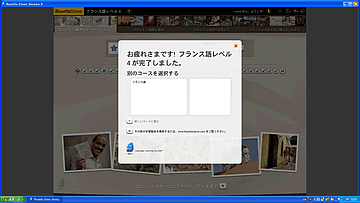
J'ai fini de etudier le 4eme pierre de rosette.
今や話題のロゼッタストーン(フランス語)の5巻セットのうち、第4巻が終わりました。第3巻終了の時には、調子に乗ってフランス語で感想を書いてみたりいたしましたが、第4巻終了時に日本語になっているということは、つまりはそういうことであります(笑)。いやはや、当たり前といえば当たり前ですが、ディスクを追う毎にフロアを上がるように難易度が上がっておりまして、前に「これはどういう意味なんだろう?」「これはどういうことを指すのだろう?」という疑問を持ったまま先に進むと、見事なくらいに分からない点が山積していってDazed an' Confusedでございます。これにはお恥ずかしながら若干の言い訳もありまして、第3巻までは渡仏前の緊張感で多少は脳の吸収率もよかったと思われるのですが、帰国後の学習というはどうしても意欲が高まり切らないのか、以前とはちょっと見える風景が違っているような気さえいたします。それはそうと、私の友人の話では「このおじさんロゼッタ人」というのは横浜・保土ヶ谷あたりの商店街にいるそうですよ(笑)。Bon week-end!感謝!
2011年12月09日
コメント(0)
-

寒い夜には中華そばで♪
今年の秋は暖かく、12月に入っても銀杏が黄色い葉を付けたまま一週間が過ぎましたが、本日は冷たい雨が降って名実共に暮れの風情となりました。お陰さまで今年も忘年会を梯子する昨今ですけれども、これまでは忘年会といっても初秋のようで雰囲気がいまいち出なかったところ、これからは本格的に師走の景色になるのでしょうか。そんな風の冷たい師走の夜には、ぜひとも熱い醤油ラーメンで締めたいものです(なにを?もちろん夜を、笑)。というところで、ぜひともおすすめなのが懐かしい中華そば。こちらは、一昨年まで「中国料理」という看板を掲げた昭和の定食屋さんがあったところに開店した、やる気溢れる兄ちゃんが仕切るラーメン店ですが、心身ともに充実しているところが味にも反映されていて、上品かつしっかりした味が嬉しい文字通りの逸品です。丼のなかは見ての通り醤油味のラーメンですけれども、煮干と昆布でじっくり時間を掛けた出汁に、なつかしい少し塩味のする醤油がスープとなっており、自家製麺だという平打ちの麺もコシが強く食い力強く、しっかりしたスープに負けず劣らず丁度良いバランスを構築していて非常にレベルの高い味。本当に美味しいとか、本当の美味しさとはこういうものかと再認識させてくれます。とかく商売が第一になると、とにかく特徴を出すために何かを極端に濃くする手法を手っ取り早く採用する例が多くなるのですが、素人だましの増量ではなく一つ一つ丁寧に仕上げていって構築される作りこまれる美味しさというものを、やる気溢れる兄ちゃんが毎日丹精込めて作っているというのが素晴らしいじゃないですか。ちょっと内緒にしたくなる極上ラーメン。食べたい人はぜひ一緒に行きましょう(笑)感謝!
2011年12月08日
コメント(0)
-

汽罐車の夢
現代では「きかんんしゃ」を「機関車」と書くことになっていますが、昔は「汽罐車」と書いたそうです。蒸気機関車は石炭を燃やして水蒸気を作り、蒸気の力で走りますから、長々しく「蒸気機関車」と書かなくても、「汽罐車」で表現できていたわけです。そういう汽罐車も、昨今は鉄道会社の体のいい話題作りと売上確保の商品という性格が強くなってすっかりSLなどと呼ばれて由とする雰囲気がありますけれども、人の移動という鉄道の原点に立つとき、その手段としての原理を後世に伝えるという役目は博物館に展示されている展示物とは、その効果において雲泥の差があるでしょう。それが証拠に、蒸気機関車牽引の列車に乗車すると乗客は楽しそう、駅員の方も充実したご様子、線路際にはカメラマンが砲列をなし、孫を肩車した好々爺が小さな手をとって振り、機関士は誇らしく汽笛で答えて機関助士はそれを眺めて微笑む。こんなに愛される機械は他にあるだろうかと思ってしまいます。いまや北海道から九州まで全国各地でこのような風景が見られるわけですから、いっそ鉄道会社各位はただのイベントや技術確保に留まらないで、文化やその伝承といったものに価値を高めるよう意識を上げてみてはいかがでしょうか。その一つの例として、同形式での重連運転というアイディアが考えられます。現在、C11形が北海道に2両、栃木に1両、静岡に2両の合計5両あります。C56形は静岡に1両、山口に1両の合計2両あります。C57形は新潟に1両、山口に1両の合計2両あります。C61形が群馬に1両、京都に1両あります。D51形が新潟に1両、京都に1両あります。これらの重連運転はできないだろうか。もちろん車両の状態はまちまちでしょうし、保有する鉄道会社の都合から保安装置の仕様違いなどもあるでしょう。なかには復元作業に近い本格的な整備が必要なものもあります。でも、現在ある資産を有効に活用しつつ、かつ比較的容易に実現できる種類の企画です。歴史的に、新しい事実を実現するという意義もあり、もちろん今行われているイベント列車という企画をヴァージョンアップできるという商品としての整合性もあります。現在行われている北海道での企画は大成功だし、栃木や静岡、山口で行われている異形式の企画だって話題になるのですから、単なるイベントを越える新しい歴史が刻まれるでしょうし、鉄道会社間を越えた技術交流として意義あるものになるでしょう。鉄道会社にとっても人材育成面でのメリットは他に替えがたいものがあるはずです。そういう過去の一線を越えた試みを見てみたい。C57-1とC57-180の重連が見てみたい。C62-2とC62-3が叶わなくても、C61-2とC61-20は見たい、そういう方はきっと日本全国におられる。もし何なら、D51-200とD51-498を九州の山線で走らせてみてはどうでしょうか?感謝!
2011年12月07日
コメント(0)
-

C6120
国境のトンネルを手前で降りると、そこはみぞれ混じりの雨だった。ニセコのC623以来のハドソン復活というのは通り相場ですが、私自身はハドソンやらパシフィックやらに余り関心はなく、地上から枕木とレールと動輪を積み上げれば自分の身長を越える高さになり見上げる巨大さと力強さが魅力の大部分を占めます。片や「復活」で山田洋次監督がお話されたように、言葉にするのが難しい要素も確かにあり、鉄道ファンの皆さまに対する鉄ではなく物質(Iron)としての鉄の魅力なのか、勢いよく噴出す水蒸気のエネルギーなのか熱気なのか白と車体の黒とのコントラストなのか、はたまた前進する姿が汗をかきながら走る長距離ランナーのように擬人化して共感するのか、なんとも言えません。言えないから特別なんだ、一生懸命感じるしかないんだとも。C61という形式の蒸気機関車は、これまであまり日の目を浴びてこなかったように思います。それはC57のように貴婦人と呼ばれる訳ではなく、D51のような最大製造台数やC62のような日本国内最大といった仕様で記録される訳ではなく、C11のように全国で姿がみられた訳でもないからでしょう。復元にあたっての検討段階で、既に稼動しているD51とボイラが共通、C57と駆動系が共通だという技術上の利点があったとしても、こうして本線上で運用に復帰したC6120を眺めてみれば、キセを載せてもバランスよい大きさのボイラと、俊足を連想させる1750mmの動輪、2軸ずつある先輪と従輪による長身が、トータルバランスの高い凛とした佇まいに繋がっているように思います。また他の復元蒸機が、使用される用途目的のために過度に装飾され、動物園の飼育動物のように使われているのに比べて、本機は余計な装飾が一切なく、現役時そのものの姿で現代にあることを美徳としたいところです。苗穂にあるC623を思い出しました。今春復元作業が終了したときには完全な艶消し黒だった塗装も、その後の度重なる洗浄を経てか、にわかに黒光りするようになってきていましたが、それでも欠かさず給油されて油光る足回りと、煤にまみれて走るボイラーとで、微妙なコントラストがあることも一級の価値を看て取れます。国境の駅で火床整理と注水を受ける姿を眺めましたが、投炭と同時に黒煙が登るボイラと、各種チェックを経ると同時に動くコンプレッサの作動音を聞く限り、本機は「絶好調」という言葉が一番しっくりくるコンディションでしょう。メカニカル・ストーカとストーカー・エンジンは撤去されていましたけれども、レールを蹴る力は十二分で少々勇みよく加減弁を引くとすぐに空転するくらいです。願わくば末永く現役であってほしいと思います。感謝!
2011年12月06日
コメント(1)
-

給水温め器の真実
あれは確か今年の夏、駅で見かけたSLキャンペーンポスターを見かけたときだったと思う。30年来の認識を覆された衝撃的な出来事でした。JR東日本群馬ディスティネーションキャンペーンの主役となった新人C6120と共に掲載されていたのはベテランD51498ですが、その正面からの写真にはボイラ上の給水温め器がオフセットして設置されていたのです。お恥ずかしいことに、子どもの時分からの思い込みで給水温め器は左右対称だと思い、その込み入った最前部形状から「蒸機のなかの蒸機」というスタイルだと思い込んでいたのですが、その後訪れた秩父のC58でも、改めて確認のために訪れた1119号機でも同じで、現役当時からの仕様だったのだと認識しました。そんなことどうだっていいじゃないか。おそらく99.9%の方は仰るでしょう。蒸機の世界には、走らせるために直接関わった方から熱心に保存される方、ベストショットを求めて日夜日本列島を駆け巡っている方まで、はるかに素晴らしい情熱をお持ちの方が大勢おられます。それに比べれば、私の拘りなんてないも同然といっていいくらいのところですけれども、三つ子の魂のようなものでどうにもはいそうですかと簡単にいかないのは、いつもどこか片隅にその力強さの象徴として脈を保っていたからではないかと思います。しかるに、C61がD51のボイラを利用して製造されるとき、同様にC62がD52のボイラを活用して製造されるときに、給水温め器もそのまま前照灯後ろ煙突前に設置されていたらと思い、それと同時にそうでなかったから、多くのタンク型蒸気機関車が全国で復活しても冷静でいられたとも思います。人生のバランスは、ほんの少しのことが将来に大きく影響していると改めて感じた出来事でした。感謝!
2011年12月05日
コメント(0)
-

PCのDVDドライヴ交換
事務所で使っているPC(といっても、私は仕事でしかPCを使いませんけれども、笑)のDVDドライヴが動かなくなってしましました。動かないってドライブ自体は動くのですが、メディアを出し入れするトレーがどこかに引っ掛かって手前に出てこないトラブルです。こういうトラブルは一番困るパターンで、ある日突然お気に入りのCDやDVDが取り出せなくなってしまうではないですか!ドライブ自体が動くので、どうにかして直せないかと思うのですが、それはともかく使えないのは困るので、ドライブを買ってきて交換修理と相成りました。買ってきたのはhpの正規品。いまさらDVDドライヴという感じもしますが、そろそろ年季の入ったマシンですので、時々使う程度のDVDドライヴは標準的なスペックさえあれば信頼性が一番の選択基準になります。正規品なのに¥1,980でした。安いですね。PCもHDD交換やらメモリ増設などを繰り返していますので、DVDドライヴの交換は朝飯前。さらに加えて事務所から徒歩3分でヤマダ電機さんやらソフマップさんやらパーツが手に入る環境なので、都合30分ほどで交換できるスピードが昨今の時代には嬉しいです。さて、ドライヴは無事交換が終了して良かったのですが、壊れた方古いドライヴの故障原因は一体どうしてなのでしょう?ちょっと検索してみると、この手のトラブルはよくあることのようですが、そんなによくあるなら、とっくにトラブルシュートが終わって過去の問題になっているのではないのかという疑問が沸いてきます。どなたか壊れない方法とか、壊れたときの修理法とか、ご存知でしたらぜひ教えてください!みんなでPCを上手に使う方法をシェアしましょう。よろしくお願いします(笑)感謝!
2011年12月02日
コメント(0)
-

Live Management Book 2012年度版にヴァージョンアップ
私が普段使っているオリジナル手帳「Live Management Book」を来年に向けてヴァージョンアップしました。今年中のマイナーヴァージョンアップも含めると4回目の進歩です。2012年版に向けてのヴァージョンアップは「今日は何の日」仕様の追加と、PDCAのCにあたるところを定量化したことです。今日は何の日を追加するのに色々と調べものをしましたが、驚いたことに、昨今では365日必ず毎日が「何かの日」になっているんです!面白いところでは12月31日は「シンデレラデー」。なんとなく意味は分かりますよね。でも1月5日に「シンデレラの日」というのもあったりします(笑)。こういう調子ならば、自分の誕生日くらい「今日は私の日」と言ってもいいんじゃないかというくらいですから、2012年からは皆自分の誕生日は自分の日にしてしまいましょう。もうひとつ、Cの改善についてはビジネス上の専門用語なのですが、言葉にすればCHECKのCです。プロの仕事というのはPLAN(計画)してDO(実行)し、CHECK(確認)してACTION(改善)するよう、行動をパッケージにして全体で繰り返すわけですが、次によりよい仕事をするためには今回の実行が計画を達成できたかどうか、また質的視点からみてどうかということをチェックすることによって初めて具体的改善に繋がります。日本では、マネジメントというととかく文系の世界の話で、言葉があれば分かったような気分になりがちですけれども、その言葉を定量的に輪郭付けすることによって次の輪郭が大きくできます。これが事業成長のメカニズムですから、お陰さまで来年からは定量的に成長をマネジメントする体制ができました。とはいっても、もう今日から使い始めていますよ(笑)感謝!
2011年12月01日
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- みそ汁のシジミ 食べますか?
- (2025-11-22 19:37:16)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 11/24発売あり♪バニラビーンズ 切れ…
- (2025-11-22 16:40:55)
-








