2008年12月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
大晦日
電車で車内吊り広告を見ていたら、佐野厄除け大師の広告がありました。ふーーーーん、と思っていたら、来年、42歳の厄年は1968年生まれだそうで。おやおや、ビンゴ!ではないですか。来年私は満41歳なんですけれどね、厄年の計算は数え年でするんですね。なるほど、厄年か、確かにそうかもしれない、と思ってしまいました。(しかし、佐野厄除け大師の計算はどういう仕組みか、年によっては満年齢で計算する厄年もあるようです。それに、前厄・本厄・後厄・方位除けと、全部真に受けていたら何だか厄でない年の方が少なくなってしまいそうな気も)この1年、社会的にも個人的にもいろいろなことがありました。個人的な話はちょっと措くとして、社会的に最大の問題は、やはり急激に訪れた不況でしょうか。冷静に考えれば、米国のサブ・プライムローン問題が表面化した昨年夏以降、いつかは景気が悪化することは見えていたのかも知れないけれど、こんなに突然、劇的なほど急激に恐慌状態となることが予測できた人は、おそらく少ないでしょう。私だって、こんなに突然大不況になるとは思いませんでした。でも、今はまだ不況の入り口です。特に雇用問題は来年一層深刻化しそうな気がします。どうも、来る年はあまりいい年になりそうな気がしません。それでも、来年が全ての人々にとってよい年であることを願っております。このブログは、8月に開設したので、まだ5ヶ月ほどしか経っていませんが、この間お世話になりました。そして、来年もよろしくお願いします。
2008.12.31
コメント(2)
-
冬山遭難相次ぐ
私は何事もなく帰ってきましたが、冬山の遭難が続いているようです。※いずれの記事も、氏名・所属等は省略して転載しましたhttp://www.asahi.com/national/update/1229/NGY200812290007.html北アルプスの西穂・槍、遭難続く 岐阜県警計5人救出北アルプスの西穂高岳や槍ケ岳で登山者の遭難が相次ぎ、岐阜県警のヘリコプターが29日、計5人を救助した。同日午前10時半ごろ、槍ケ岳(3180メートル)に登っていた6人のパーティーから「男性1人が約300メートル滑落した」と岐阜県警に救助要請があった。県警のヘリが午前11時すぎ、槍ケ岳の西側にある中崎尾根の標高2560メートル付近で男性を救出した。男性は左足に軽いけが。(中略)同日午後0時半ごろには西穂高岳の独標(どっぴょう、2701メートル)付近を下山していた女性が約200メートル滑落。同行者とともに自力で西穂山荘までたどり着いたが、背中を負傷し、体力の消耗も激しいため、山荘を通じて同県警にヘリの出動を要請。午後3時すぎ、ふもとのヘリポートまで運ばれ、救急車で病院へ搬送された。一方、西穂高岳(2909メートル)山頂近くの岩場で28日に約300メートル滑落し、救助を待っていた女性は29日午前7時20分ごろ、岐阜県警のヘリで救助され、同県高山市内の病院へ運ばれた。女性は救出時、ピッケルが左太ももの後ろに刺さった状態で、衰弱はしていたが、意識はあり、救助隊員が「大丈夫か」と声をかけると、「大丈夫です」と答えたという。また、西穂高岳を登っていた7人のパーティーからは、28日午後8時45分ごろ、「2人が凍傷になり、助けてほしい」と通報があった。岐阜県警のヘリが29日午前8時5分、山頂から南西へ約200メートル下がった付近で2人を救助した。 --------------------------------http://www.asahi.com/national/update/1229/NGY200812290010.html北アルプス・雪崩 不明の2人、2日目も見つからず岐阜県の北アルプス・抜戸(ぬけど)岳(2813メートル)で雪崩に巻き込まれ、行方が分からない2人の捜索は29日、早朝から再開されたが、2人は見つからなかった。岐阜県警などは30日も捜索を続ける。29日は、県警山岳警備隊のほか、仲間の山岳会員ら計26人で捜索。対象範囲の約9割で捜索を終え、十数カ所を掘り起こしたが、手がかりはなかった。前日は悪天候のため飛べなかった県警ヘリコプターによる捜索では、雪崩が発生地点から約800メートルにわたっていることがわかった。--------------------------------http://www.asahi.com/national/update/1229/TKY200812290090.html中央アルプスの滑落男性は死亡 同行の女性は無事長野県の中央アルプス・檜尾(ひのきお)岳(2728メートル)で行方不明になった男性は29日午前、尾根の下約300メートルの南側斜面に滑落しているのを、県警ヘリコプターに発見された。頭を強く打っており、搬送先の病院で死亡が確認された。一緒に登り、事故を通報した千葉県の女性は、避難小屋の近くで風雪をしのぎ無事だった。駒ケ根署によると、2人は27日午後5時ごろ、檜尾岳山頂から小屋に向かって尾根を歩いていて、男性が滑落したという。--------------------------------http://www.asahi.com/national/update/1229/TKY200812280236.html山形・大朝日岳 法務省職員が滑落、行方不明28日午後10時40分ごろ、山形県朝日町の大朝日岳を登山をしていた男性が沢から滑落して行方不明になったと、所属する山岳会から山形県警に連絡があった。県警は29日の天候を見てから捜索するかどうか判断する。寒河江署によると、男性は28日午後4時ごろ、強風にあおられて、大朝日岳の「ガンガラ沢」から滑落した。27日から4人で登山しており、メンバーから携帯電話のメールで事故の連絡が同会に入ったという。残りの3人は現場付近でビバークしている。パーティーは1月1日に下山する予定だった。--------------------------------見たところ、八ヶ岳の硫黄岳ほど簡単な山での遭難はないようです。西穂独標は、3月にピーク直前まで行ったことがあります。雪がなければどうということのない山ですが、積雪期は、山頂直前の十数メートルの岩場がちょっと怖くて、引き返してしまいました。転落したとすればあの場所か、あるいは西穂本峰から下山してくる途中だとすれば、もう少し先かも知れません。独標より先は、どこで落ちても不思議はない岩場の連続ですから。この時期に西穂本峰や槍ヶ岳を目指そうという人は、ベテラン登山者に間違いありませんが、それでもこういうことになるんですね。私は、無雪期に独標の一つ先のピークまでしか行ったことがありませんけれど、あんなところで転落して、よくもまあ怪我だけで済んだなと(しかも2人別々の場所で)思います。抜戸岳の雪崩は、笠新道でしょうか。別の記事によると、雪崩現場は標高わずか1480mとのことなので、小池新道から別れてすぐ、まだほんの麓の場所のようです。そんなところで雪崩に遭うとは思っていなかったかも知れません。ただ、雪崩危険地帯ではあるんですね。実は、今回八ヶ岳に行くか、西穂独標に行くか、少し迷ったのです。硫黄岳は過去何回も登っているけど、西穂独標は積雪期は山頂目前で引き返しているし(10月に登ったことはあるけど)。新穂高ロープウェーでピューッと登ればいきなり海抜2100mまで行けて楽だし、今回は西穂独標にしようかな~~~、と思ったのですが、やっぱり積雪量が八ヶ岳よりは格段に多いし、26日頃に大きな寒波が来るを知って、「こりゃ日本海寄りの山は滅茶苦茶な天気かも」と思って、八ヶ岳に決めたのです。しかし、結果的には北アルプス南部もその間、そんなに悪い天気ではなかったようですが。これから先、31日1日と更に多くの人が入山するでしょうが、これ以上遭難が起こらなければいいのですが。
2008.12.30
コメント(0)
-
八ヶ岳に行って来ました
一昨日飲み会があったにもかかわらず、昨日から一泊二日で八ヶ岳へ。美濃戸口から南沢-行者小屋-中山乗越-赤岳鉱泉と歩いたのですが、案の定前日のお酒のせいで午前中は絶不調。かなりへろへろ。飲んだ量は大したことがない(ビールのジョッキ2杯とワインをグラス1杯)のですが、どうしたかとか。アルコールそのものより、ビールの炭酸が胃腸によろしくない、という気がします。でも、午後になるとさすがに調子回復、それに昨日は一日中非常に天気が良くて、眼前の阿弥陀岳-赤岳-横岳-硫黄岳の大展望が素晴らしかった。ところが、赤岳鉱泉の山小屋について、受付でボールペンを握ったらびっくり。右手人差し指の爪がバッキリと割れている。いったいいつ、どこで??まったく思い当たる節がありません。(手袋をつけて歩いていたし)とにかく、これではしばらくギターが弾けそうにありません(T_T)さて、昨日は1日晴天だったのに、今日は朝から悪天候になってしまいました。それでも当初予定の硫黄岳を目指しました。赤岳鉱泉の気温は、昨日夕方5時頃にマイナス14度、今朝は少し上がってマイナス10度でした。樹林帯の中の雪道を登っていくと、時々ドーンと風の音がします。これはかなり風が強そう。1時間ほどの登りで、森林限界を超えて、稜線に出ました。案の定すごい風と吹雪です。(雪が降っているのではなく、積もった雪が飛ばされているだけのようですが)2年前に来たときは、ここで引き返してしまったのですが、今日は体調絶好調なので、この烈風の中、山頂を目指しました。正直、風に殺意を感じましたけど、コース的には南八ヶ岳でもっとも簡単なルートですから、危険な場所は特にありません。ただ、視界ほとんどゼロ。トレース(というか、かすかなアイゼンの痕跡)をたよりに登っていって、山頂に着いたら、無人。うーーーん。頑張って写真を一枚とりましたが、1分と手袋を外していられません。赤岳鉱泉の気温がマイナス10度ということは、ここはマイナス20度以下は確実。風邪を引いてはいなかったのですが、寒さのせいか鼻水が出る、その鼻水が即凍る。鼻毛も凍る、鼻バキバキ。数分にして、直ちに下山にかかりました。しかし困った、前が見えません^^眼鏡族はこういうときに辛いものがあります。吐く息でめがねが曇って、その一瞬後にはバキバキに凍り付いて、前が全然見えないのです。そのため、足下のトレースが見えない。登りは、足下の地面との距離が近いので、トレースは見えたのですが。それに、風は上り下りとも横風だったのですが、登りはやや後寄りから、下りはやや前よりからの風で、めがねの凍り方が一層激しい。途中でハンカチで氷を拭き取ってみたけど、10秒後にはもう凍っている、おまけに、涙が出たらしく、睫毛まで凍ってきた。あとはひたすら、足元を凝視しながらトレースを探しながら、樹林帯まで戻ってくると、そこはまるで別世界のような静けさ。樹木は偉大だなと痛感しました。赤岳鉱泉まで戻ってくると、信じられないくらいの暖かさ。温度計を見ると、朝方と同じ気温マイナス10度でした。マイナス10度がこんなに暖かいものとは思わなかった。手袋を外しても、5分や10分なら冷たくないし。で、赤岳鉱泉から北沢を下山していくと、先ほどまでの悪天候が嘘のように晴れてきました。うーーーん、残念。でも、昨日晴天だったから、まあいいか。それに硫黄岳は晴れても烈風が吹き荒れていることは確実です。実は今までに何回か冬の硫黄岳に行っていますけれど、だいたいいつでも今日と同じくらいの風が吹き荒れていました。一度だけ、まったくの無風だったことがありましたが。しかし、こんなにめがねが曇ってしまったのは初めてです。
2008.12.28
コメント(0)
-
スカボロ・フェアその他
マイ・サウンドにて7曲公開中です。Scarborough Fair(スカボロ・フェア)http://players.music-eclub.com/?action=user_song_detail&song_id=221353Encuentros(出会い)http://players.music-eclub.com/?action=user_song_detail&song_id=221766El condor pasa(コンドルは飛んでいく)http://players.music-eclub.com/?action=user_song_detail&song_id=220860Perfume de carnaval(カーニバルの香り)(MySoundからは削除したのでYouTubeにリンクします)http://jp.youtube.com/watch?v=FfGWYdp2Vi0&fmt=18いつも何度でも(千と千尋の神隠し)http://players.music-eclub.com/?action=user_song_detail&song_id=233255La Telecita(ラ・テレシータ)http://players.music-eclub.com/?action=user_song_detail&song_id=220620Mallku cunturi(王者コンドル)(削除してしまいました)
2008.12.26
コメント(0)
-
日本橋の某デパート
昨日、12月24日のことです。休みを取って、家族共々日本橋の某老舗デパートに行きました。ウクライナのナターシャ・グジーさんのバンドゥーラ弾き語りの演奏がある、というので行ったのです。この老舗デパートに足を踏み入れるのは、初めてではありませんが、かなり久しぶりです。少なくとも過去10年以上は入ったことがありません。さて、演奏は、吹き抜けの階段の踊り場付近のステージ(パイプオルガンが据え付けてあるんですね)で行われたので、我々は2階から見下ろすようにして演奏を聴いていました。2階から見下ろしているので、1階の売り場がよく見えます。そのあたりは貴金属や宝石の売り場のようでした。それで、ふと気が付きました。演奏を見るために集まっている聴衆(当然、階段の周囲に固まっています)以外に、お客さんがただの1人もいないのです。1階の売り場全部が見えているわけではありませんが、見える範囲内には、客が1人もいません。ひたすら店員ばっかりです。私は昔スーパーマーケットに勤めていたことがありますが、百貨店のことは何も知りません。しかし、当然平日よりは土日の方が客は入るでしょうし、貴金属の売り場なんてお客さんが大勢群がって、商品が飛ぶように売れるなんてことは、普段でもないのだろうとは思います。でも、昨日はクリスマス・イブです。平日とはいえ、その種の商品(貴金属や宝石)はかきいれ時ではなかろうか。地下の食品売り場に行ってみたら、そこにはお客さんがいました。特に、12月24日だけに、ケーキのコーナーは長蛇の列でした。だから店内にまったくお客さんがいないわけではないのですが、高額商品のところには人がいない。普段の客の入りの状況を知らないので、いつもそんなものなのか、昨日は特別に客が少なかったのか、比較はできないのですが、何となく不況のせいかなという気がしてしまいました。実際のところはどうなのでしょう。それはともかく、ナターシャ・グジーの歌とバンドゥーラは素晴らしかった。また聞きたいものです。
2008.12.25
コメント(0)
-
自衛隊イラク派遣:「強者に追従」だけなのか その2
18日の日記に自衛隊イラク派遣:「強者に追従」だけなのかという記事を書いたところ、ネッド。さんという方から長いコメントをいただきました。コメント欄では字数制限があるため、改めて今日の日記にコメントを受けての意見を書きます。> 戦争を起こさない為に持っているのであって、持っている事に意義があるんです。> 核があれば迂闊に戦争を仕掛けられる事もないし、強気にも出られるわけです。北朝鮮やアメリカが良い例でしょう。「核があれば迂闊に戦争を仕掛けられる事もないし」←それ、ウソですから。非核保有国が核保有国に対して戦争を仕掛けた例を書いたはずですよ。非核保有国であるアラブ諸国が核保有国イスラエル(公表はしていないが、当時核保有が確実視されていた)に戦争を仕掛けた第4次中東戦争と、非核保有国アルゼンチンが核保有国イギリスに戦争を仕掛けたマルビナス紛争。それ以外にも、核保有国対非核保有国の戦争はいくつか例がありますが、核が怖いから非核保有国が早々に降伏した、なんて例はありません。つまり、核は核に対する抑止力にはなるけれど、通常兵器に対する抑止力にはならない、ということです。> 当時、その確証が出来てた国はありません。証拠も無いのにデタラメだ、支持できない、等とは同盟国との関係では絶対に言えません。話はあべこべなのです。国連安保理が送り込んだ査察団が、「大量破壊兵器は発見できない」と公式にそう発表しているのです。米国こそが、「証拠もないのにデタラメに」大量破壊兵器はあると言い募ったのです。同盟国と言えば、フランス・ドイツ・カナダはNATO加盟国です。メキシコも、軍事同盟は結んでいませんが2000年以来親米政権が続き、経済的には米国抜きでは成り立たない国です。しかし、これらの国々はイラク戦争に反対しました。「同盟国との関係で絶対できない」なんてウソ。> で、アメリカを支持した国で自国が悪かったと反省してる国を具体的に挙げてください。>「騙された」なら自国も悪かった、となるのはおかしくないですか?非常に話がかみ合っていない気がするのですが、私は、あんな馬鹿馬鹿しい「疑惑」を真に受けて、イラク戦争を支持してしまったことについて、「有権者に対して、『誤っていた』と認めなくてはならない」と言っているのです。「自国が」では、必ずしもない。「小泉首相が」「小泉政権が」です。時の政権が政策を誤ったからと言って、必ずしも外国に対して謝罪しなければならないわけではないです。まして、「騙されたこと」を外国に対して謝罪する必要などない。しかし、国民に対しては謝罪しなければならないでしょう。「騙されたから政策誤りました、故意じゃないから国民に対して責任はありません」なんて馬鹿な話はないの。というわけで、「自国」が誤っていたと(外国に対して)表明した国は知りませんが、「自分」が誤っていたと(国民に対して)表明した政治指導者はおりますね。イギリスのブレア首相。戦争を推進したこと自体についてではありませんが、デタラメ大量破壊兵器「疑惑」については、誤っていたとして、労働党大会にて謝罪しています。イタリアとスペインは、首相が誤りを認める前に選挙に負けて退陣してしまいましたからね。後継政権は、自国の軍を撤退させるという事実によって、前政権の政策が誤りだったと認めたわけです。> ではここをどうぞ。> http://www21.tok2.com/home/tokorozawa/faq/faq01b05.html #mass-destruction-weaponsイラクに大量破壊兵器はなかったことは、ブッシュも認めている歴然たる事実です。今更、スコット・リッターの悪口やブリクス委員長の悪口を並べてみたところで、彼らの判断の方が正しかったことははっきりしています。>> いずれにしても、ブッシュ政権に忠実に尻尾を振れ続けた結果、日本はいったい何が得られたのでしょう。特に、これから先、日本政府がブッシュの忠実な僕だったことが、オバマ政権との良好な関係につながるでしょうか。そう考えれば、その時々の政権のやることに、忠実に賛同してみせることが、長い目で見て良好な日米関係につながる、というものではないと思うのですが。> 日本が得られたのは自衛隊派遣の経験、米国との同盟強化、イラクでの日本のイメージアップ、でしょうかね。自衛隊は、すでに海外派遣が繰り返されているので、今更イラクへの派遣の経験が不可欠なものではありません。それに、ブッシュ政権との同盟を強化したことが、オバマ政権との良好な関係につながるのですか?と聞いているのです。報じられているところによると、日本政府の対米政策は、共和党偏重で、民主党とのパイプは全然ないそうです。ブッシュの「一の子分」であったことは、オバマ政権との関係で言えばマイナスでしかないでしょう。国と国との友好関係というのは、その時々の政権の政策に全部賛同する、ということではないはずです。> 何度も言ってますが、日本を「普通の国」にしないとダメです。> 中国や韓国にすらへえへえ言ってるんですから、アメリカに逆らえるわけがない。世界有数の強力な航空自衛隊と海上自衛隊を持っていて、何が今更「普通の国にしないと」ですか。
2008.12.21
コメント(34)
-
ヤマハのマイ・サウンズ
ヤマハが主催するマイ・サウンズという音楽SNSがあります。最近、会員になりました。過去にこのブログで紹介した演奏のいくつかをこちらに引っ越しました。http://players.music-eclub.com/?action=user_detail&user_id=179165
2008.12.20
コメント(0)
-
自衛隊イラク派遣:「強者に追従」だけなのか
私は毎日新聞を購読しています。今日の朝刊の記事はとてもよかった。http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081218ddm001010028000c.html自衛隊イラク派遣:「強者に追従」だけなのか=編集局次長・小松浩 日米同盟の証しと米国に感謝され、一人の戦死者も出さず、無事任務を完了した自衛隊イラク派遣。隊員たちの規律と献身があったればこそだが、これを日本の「成功体験」と呼ぶことには、あえて異を唱えたい。「強い者(米国)につくのが国益」という損得勘定のほかに、私たちはイラク戦争とのかかわりを語る言葉を持たぬまま、今日まできてしまったからだ。乱暴な理屈がまかり通った5年間だった。航空自衛隊の空輸活動を「憲法違反」と断じた名古屋高裁判決を、当時の田母神俊雄・航空幕僚長は「そんなの関係ねえ」と笑い飛ばした。司法を軽蔑(けいべつ)する制服組トップ、それを傍観する政治、イラクやアフガニスタンを政局の道具立てとしか考えない国会。安全保障論議がこれほど軽く扱われた時代は、かつてなかった。「何を言っても許される」。そんな空気がまん延し、社会のタガが外れた。サマワやバグダッドで汗を流す自衛隊員たちを、どれだけの人が心にとめていただろうか。幾万もの死者を出したイラク軍事介入を正当化できるものは果たしてあるか、という真摯(しんし)な議論も、大量破壊兵器情報の誤りに対する悔恨や反省も、日本の政治指導者の口から語られることはなかった。「強い者」への追従を決めた後、多くの日本人にとって、イラクは「人ごと」になってしまった。イラク健忘症である。だがこの5年、世界はテロの拡散に加え、欧米社会とイスラム社会の共存をいかに図るか、というイラク戦争の「負の遺産」克服に苦悩してきた。その原因をつくった米国も、軍事力だけで問題は解決しないことをイラク戦争で学んだ。中国やインド、ロシア、欧州連合(EU)などを含む多極化時代が訪れ、新しい世界秩序の模索が始まった。米国との半世紀に及ぶ同盟は、日本外交の貴重な資産である。しかし、米国というプリズムを通してしか外を知ろうとしない過度の対米依存は、世界で何が起きているかをしばしば見えなくする。金融やエネルギー、地球環境、食糧。あらゆる危機はもはや、日米同盟というモノサシだけでは、立ち位置すら決められない。次はアフガン支援のあり方が、日本外交に問われるだろう。「新しい同盟」「同盟の再構築」を旗印にするオバマ次期米政権は、日本がどんな構想を持っているか、まずは聞き役に回るに違いない。地域の平和に日本は何ができるか、自分たちの頭で考えることから始めよう。「強い者」につく、という狭い国益論で思考停止に陥る愚だけは、繰り返してはならない。-------------------------------------まったくこの記事のとおり、と思います。実際には、イラクが大量破壊兵器を持っているというブッシュ政権の主張を、イラク戦争以前の時点でも、よほど盲目的な対米従属派以外は、信用した人は少ないでしょう。そして、案の定ブッシュ政権の主張は誤っていた。おそらく、いくら小泉といえども、腹の中では大量破壊兵器「疑惑」など本当にあるとは思っていなかっただろうと思います。しかし自民党はそんな、明らかなデタラメを真に受けるポーズを示してまでも、対米従属の道を選んだ。そして、デタラメがデタラメと明らかになった後でも、小泉、あるいは後継の歴代首相も誤りを認めなかったのです。その誤りによって、イラク人が何万人、ひょっとすると何十万人も殺されたにもかかわらず。当のブッシュは、大量破壊兵器の情報が誤りだったことを「最大の痛恨事はイラクの情報の誤りだった」と認めています(まあ、その責任はとっていないけど)。しかし、自民党の政治家は誤りすら認めていない。まさに、「強い者への追従」以外の何の論理もないということでしょう。
2008.12.18
コメント(10)
-
ブッシュに靴投げつけ事件 続報
http://mainichi.jp/select/world/archive/news/2008/12/17/20081217ddm007030081000c.htmlより「機会があれば、ブッシュに靴を投げつけてやりたい」。14日、バグダッドでの記者会見で、ブッシュ米大統領に靴を投げつけ拘束されたイラク独立系テレビ「バグダディヤ」のザイディ記者(29)は、同僚らにそう語っていた。アフガニスタンとイラクへ侵攻したブッシュ大統領の任期終了間際に起きた事件は、アラブ社会の根深い反米、反ブッシュ意識を改めて浮き彫りにし、オバマ次期政権に「米国への信頼回復」という重い課題を突きつける。同僚の一人はAFP通信に「彼は米国を、米兵を、ブッシュを忌み嫌っていた」と証言した。イラクからの報道によると、ザイディ記者はイスラム教シーア派対米強硬派のサドル師派が牙城とするサドルシティー出身。しかし政治的には共産党を支持し左翼系思想の持ち主とみられる。自室にはアルゼンチン生まれのマルクス主義革命家、チェ・ゲバラのポスターが張られ、兄弟の一人はAP通信に「米国による物質的占領とイランによる精神的占領を憎んでいた」と語った。同記者は昨年11月に武装組織に誘拐され、今年1月には米軍にも拘束された。また、米軍とサドル師派の民兵組織マフディ軍の衝突の現場も取材。米軍の爆撃によるイラク人の被害をつぶさに見てきたことで、「占領」に対する憎悪を深めてきたとみられる。-----------------とのことです。シーア派地域出身の共産党支持者、シーア派も共産党も、フセイン政権からもっとも激しく弾圧された勢力です。でもやっぱりフセインよりブッシュの方が憎むべき相手ということですね。
2008.12.17
コメント(0)
-
ストライクコースには飛んだが・・・・・・
http://jp.youtube.com/watch?v=ksnJRDor10w&eurl=http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1023809990&owner_id=4697166ブッシュがイラク電撃訪問の際の記者会見中に、地元のテレビ局記者から靴を投げつけられたそうです。映像はいや、当たらなくて残念、とは言ってはいけないですよね、一応。しかし、ブッシュの行ったイラク戦争がどれだけの犠牲をもたらしたかを考えれば、飛んできたのが靴だけで済んでよかったねとしか言えません。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081215-00000004-mai-intによると、「一般的にイスラム教徒の間では靴を投げつけたり犬呼ばわりすることは、最大級の侮辱にあたる。」のだそうです。(ま、日本語でも「犬」呼ばわりは十分に侮蔑ですが)こんな記者会見に出られるのは、身元がしっかりした、選ばれた記者たちばかりに違いありません。そのことを考えれば、ブッシュに対するイラク人の怒りがいかに大きいかが分かります。
2008.12.15
コメント(2)
-
野中広務の講演を聞いてきました
昨日の日記で告知した、「南京事件71周年 12・13集会」に行って来ました。集会の目玉は、なんと言っても、自民党幹事長、官房長官などを歴任した、あの野中広務の講演です。83歳という年齢にもかかわらず、1時間以上(かなり予定をオーバーした模様です)の講演に、一度も椅子に座らないのです。立ちっぱなし。声もよく通るのは、さすがに引退したといえども政治家です。そして、話も面白かった。自民党出身者だけに、全ての話に全面的に賛同、というわけではないのですが、大筋として、非常にもっともな話が多かったし、平和への思い、日中の友好関係への思いには感銘を受けました。彼自身は、戦争体験者ではありますが、南京大虐殺を直接体験しているわけではありません。しかし1971年、京都府議時代に後援会関係者200人とともに上海、蘇州、南京をめぐる旅をしたときに、思いがけない体験をしたのだそうです。後援会員の1人が、南京市街にはいると急にガタガタと震えだして、とうとう倒れてしまったのだそうです。後で回復した彼は野中氏に、「私は戦争の時、京都の福知山20連隊の一員として南京攻略に参加し、まさにここにいたのです。いま南京に来て、当時を思い起こし、地の底に足を引きずり込まれるような状態になり、体が震えてきたのです」と語ったそうです。その彼の体験とは、南京城内に入ったとき、便衣兵(軍服を捨てた敗残兵)狩りのためあちこちの家を調べているうちに、女性と子どもばかりが逃げ込んでいる家を発見したのだそうです。それで「ここは女、子どもばかりです」と言って扉を閉めようとすると、上官が「何を言っているのだ、その中に便衣兵がいるのだ、例外なしに殺せ、容赦するな」と命じ、その家ごと焼き払って皆殺しにしてしまった、というものです。そして、小泉政治に反対する確固たる信念。こういう人が自民党の有力者になったのですから、やはり自民党という政党の懐の深さは、侮りがたいものがあります。もっとも、最近は自民党からこういう人がずいぶん減ってしまったように思います。小泉チルドレンなんて、言っては悪いけれど、良くも悪くも目立たない、個性が感じられません。本当に将棋の駒としての議員に過ぎない感じ。ま、その中である意味目立っている(悪い意味で)のが、かの稲田朋美大先生かな。一応、写真撮影係というスタッフだったので、コルチャック先生から借りたデジカメで写真を撮りまくりました。でも、カメラは返してしまったので、手元に写真はありません。自分の一眼レフも持っていったので、何枚かは撮りましたが、フィルムカメラなので現像するのはまだ先かな。それに、室内だったので50mmの単焦点レンズしか持っていかなかったのですが、やはり50mmでは演台が遠い・・・・・・。
2008.12.13
コメント(2)
-
南京事件71周年 12・13集会
南京事件71周年 12・13集会12月13日(土) 開場:午後1時半、2時~4時半南京事件70周年国際シンポジウムから1年…過去と向き合い、東アジアの和解と平和を講演:野中広務氏(元官房長官、元自民党幹事長) 「戦争体験と歴史和解」(仮題)対談:笠原十九司氏(歴史学者)・能川元一氏(哲学者)「かつて百人斬りが賞賛された時代があった」提案:尾山 宏氏(弁護士) 「和解と平和のためのこれからの課題」会場:明治大学リバティータワー3階 1032教室(JR・地下鉄お茶の水駅・新お茶の水駅・神保町駅より徒歩5分程度)http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html資料代:1000円(学生500円) 告知が今日の今日になってしまいました。私も参加する予定です。
2008.12.13
コメント(0)
-
多重録音シリーズ マリュク・クントゥリ
http://homepage3.nifty.com/ryo-folklore/Mallku.MP3(都合により削除してしまいました)前回の多重録音は、あまりうまく演奏できたとは言い難いので、もっと単純な曲にしてみました。クラルケン・オロスコ作曲のマリュク・クントゥリ(王者コンドル)です。サンポーニャが中心の曲です。単純なメロデイーとはいえ、サンポーニャは結構きついです。ギター(ストローク)+ギター(ソロ)+チャランゴ+サンポーニャ(マルタ)+サンポーニャ(サンカ)の五重録音になっています。
2008.12.11
コメント(0)
-
なんで18歳成人ではいけないの?
http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200812090327.html成人年齢18歳「反対」56% 朝日新聞世論調査民法上の成人年齢を20歳から18歳に引き下げることに反対の人が56%にのぼり、賛成は37%にとどまることが、朝日新聞社が6、7の両日実施した全国世論調査(電話)で明らかになった。国政選挙などの選挙権を18歳からとすることについても、反対が賛成を大きく上回った。民法では、20歳未満は親の同意なしには結婚や契約ができない、と定められている。この成人年齢の引き下げは、特に女性で反対60%、賛成31%と、男性(反対51%、賛成44%)以上に否定的意見が目立つ。反対の理由は「判断力が十分でない」(43%)、「経済的に自立していない人が多い」(41%)が多い。一方、賛成の理由では6割が「大人の自覚を持たせられる」を選んだ。また、公職選挙法で決められている選挙権年齢の引き下げについては、反対が57%、賛成は38%。30代で賛否が相半ばするが、年代が上がるにつれて賛成が減る。憲法改正の手続きを定めた国民投票法で、国民投票ができる年齢が18歳とされたことをきっかけに始まった成人年齢などを巡る論議だが、国民の間では引き下げに慎重な意見が根強いようだ。一方、20歳未満を「少年」と定めて保護の対象としている少年法では、対象年齢を「18歳未満に引き下げたほうがよい」が81%で、「20歳未満のままでよい」の14%を圧倒。成人年齢引き下げに反対の人のなかでも約7割が、少年法については「引き下げたほうがよい」としている。 -----------------------------成人年齢引き下げには反対の人が多いようですね。私はどちらかと言えば賛成ですけれどね。(あくまでも「どちらかと言えば」であり、それほど熱意があるわけではないですけれど)少なくとも、反対すべき理由は何もないと思っています。「経済的に自立していない人が多い」って、今の時代20歳だって経済的に自立している人なんてかなり少数でしょう。毎年成人の日になると大勢の新成人※が晴れ着で着飾っているけれど、あの何割が自分で稼いだお金で買った晴れ着ですか?1割もいないんじゃないでしょうか。では成人年齢を引き上げるべきなのでしょうか。「判断力が十分でない」というのも、それとまったく同様です。が、まあ私も「どちらかと言えば」引き下げ賛成という程度なので、成人年齢は引き下げないというならそれでもいいでしょう。しかし、少年法の適用年齢は8割以上が18歳に引き下げるべきだと回答しているのはどういうことでしょう。成人ではないから少年、少年ではないから成人でしょう。成人が20歳以上なら少年は20歳未満でなければならないし、少年を18歳未満とするなら成人は18歳以上にすべきだと私は思うのですが。成人が20歳以上なのに少年は18歳未満というのは、あり得ない選択肢としか私には思えません。
2008.12.10
コメント(0)
-
たかが漢字の読み方、か・・・・・
麻生首相の支持率急降下の一因になっているのかどうかは定かではありませんが、漢字の読み間違いがかなり目に余るようです。未曾有を「みぞうゆう」と読んだとか、踏襲を「ふしゅう」と読んだとか。まあ、漢字が読めなくとも大した問題ではない、という意見もあるでしょう。直接的にはそのとおりです。漢字が読めないと政権運営に失敗する、というものでもないでしょう。しかし、政治家にとって言葉は最大の商売道具のはずです。米国のオバマ新大統領の演説ぶりなどを見ても、言葉の力がいかに大きいか分かります。その商売道具を、これほどぞんざいに扱う人が、政治家としていい仕事が出来るのかというと、否定的に考えざるを得ません。大工のかんなが錆びていたり鋸が刃こぼれしていたからと言って、建てる家が欠陥住宅になるとは限りませんが、しかしそんな大工に仕事を任せたいとは思えません。もう一つ重要なことは、麻生の失言の大半は、国会での答弁など、基本的に原稿を読み上げる場面で起こっている、ということです。国会の答弁なんて、麻生が自分で書いている原稿ではないでしょう。官僚が原稿を書いているはずです。仮に自分で書いたとしても、官僚と打ち合わせをしているはずです。麻生が漢字を読めないのは、何も首相になってから急にそうなったのではなく、以前からそうだったはずです。つまり、関係者の間では以前から周知の事実だったに違いありません。周囲の誰も、漢字の読み方について注意を促さないのでしょうか。それとも、注意を促されても聞く耳を持たないのでしょうか。どちらにしても、信頼できる補佐役が、麻生の周囲にはいない、ということでしょう。そのために、おそらく内部のチェック機能が機能していない。だから、漢字の読み間違いも素通りしてしまうのでしょう。そんな人間に行政のトップを任せたくはないです。
2008.12.09
コメント(2)
-
断末魔の麻生政権
朝日新聞の調査 支持22%、不支持64%読売新聞の調査 支持20.9%、不支持66.7%毎日新聞の調査 支持21%、不支持58%まだ成立して2ヶ月ちょっとなのに、はやくも政権末期状態です。支持率急降下の早さは安倍内閣、福田内閣も上回るんじゃないでしょうか。私が思うに、短命内閣が二代続いて、麻生は支持率の取れる「最後の切り札」だったのだと思います。それが、蓋を開けたらこのザマ。もう、このあとに人気のある首相候補は自民党にはいません。というより、根拠不明確な蜃気楼のごとき「人気」にすがろうとするから、そういうことになるのでしょう。麻生に人気なんて、私は何かたちの悪い冗談だと思っていましたから。好き嫌いで言えば小泉は大嫌いな政治家ですが、人気があるというのは確かに納得できる部分がありました。言葉に、人々を引きつける力があったことは認めざるを得ません。それに比べれば、麻生なんて話にならない。小泉みたいな怖さ(こいつに人気を取られるぞ、という)を感じません。だから、「人気」なるものは遅かれ早かれ崩れるだろうと思っていたけれど、ただ2ヶ月でここまで崩れるとまでは想像していませんでした。私は、個人的には、田母神問題では石破茂農水相、国籍法改正問題では河野太郎代議士を結構見直しました。(もともと、河野太郎の父親、河野洋平は自民党の中ではもっとも尊敬にたる政治家だと思っていますが)しかし、彼らは党内の地盤があまり強固ではないので、首相という目は当面なさそうです。正直言って、私は民主党も好きな政党というわけではないのですが(小沢は何しろ元々は自民党のタカ派中のタカ派ですから)、比較の問題として、自民党よりはまだましと思っています。
2008.12.08
コメント(0)
-
国籍法改正問題に関連して
高校生のとき、同級生から、突然「俺、実は外国籍なんだよ」と言われたことがあります。それほど親しかったわけではなく、何で突然そんなことを私に言ったのかは分かりませんけれど、それで原付の免許証を見せてくれたのです。詳細な表現は忘れましたが、本籍地の欄だったでしょうか、確かに外国籍であることを示す表示がありました。名前(本名)はごく普通の日本人の名前でした。どういうことかというと、彼の母親は日本人、父親は外国人だったらしいのです。(確かフィリピン国籍と言っていたように記憶しています)当時国籍法の規定は父系血統主義で、父親が日本人なら日本国籍が取れましたが、母親だけが日本人では日本国籍が取れなかったのです。(父親が日本人でも、母親が外国人で婚外子の場合は現在と同様の制約がありました)それで、彼は日本国籍にならなかった。調べると、国籍法が父母両血統主義に改められ、母親だけが日本人でも日本国籍が取れるように改正されたのが、1984年5月のことでした。私が高校2年生の時です。おそらく、その時彼も日本国籍が取れるようになったのだろうと思います。私は当時そんなことは知りもしませんでしたが、彼にとってはおそらく重大な関心事だったに違いありません。父親が日本人なら日本国籍を与えるけど母親が日本人でも日本国籍は与えません、というのは、実にあからさまな男女差別ですが、それが戦後39年も経った1984年まで放置され続けてきたのです。しかし、その後も婚外子に対する差別は部分的に残っていました。今回やっとそれが改められたわけです。小さな一歩とは言え、一つの前進には違いない。今回の国籍法改正については、反対派がネット上でずいぶん騒いでいましたが、国会が(自民党の大部分も含めて)正しい判断を下したことに、まずはほっとしています。しかし、今回の件で驚いたのは新党日本の田中康夫議員と、無所属の川田龍平議員が反対票を投じたこと。田中議員は、長野県知事時代には大いに支持していた(長野県民ではないから投票したことはないけれど)し、川田議員には、前回の参議院選で投票しようかなと思っていた(結局別の人に投票したけれど)のです。何というか、ちょっとがっかり。訂正・追記旧国籍法について(父親が日本人でも、母親が外国人で婚外子の場合は現在と同様の制約がありました)と書きましたが、これ不正確でした。制約は現在と同様ではなく、現在以上。旧国籍法には現在の第3条1項の規定がなかった。つまり胎児認知とか、生後認知+父母の結婚では国籍が取れなかった。父親が日本人でも婚外子には一切国籍が付与されなかったようです。
2008.12.07
コメント(2)
-
多重録音シリーズ Sobreviviendo(生き残る)
http://homepage3.nifty.com/ryo-folklore/Sobreviviendo.MP3(あまりに下手だったので、その後削除しました)アルゼンチンのビクトル・エレディアの曲ですが、ボリビアのハイメ・フナーロのアレンジをもとにしています。本当は歌詞がいいのですが、歌なしのインスト版です。後半、かなりリズムが乱れ気味ですが、もう録り直す気力がありません。8月15日の日記で取り上げた曲ですが、再度歌詞をご紹介しておきます。------------------Sobreviviendo(生き残る)私は自問する、どうやって生きてきたのかと。生き残ってきた、と私は言う。生き残ってきた、と。私は、千回以上も書かれた詩をもっている。その詩は繰り返されてきた。この大地の上で誰かが死のうとしている間に、そして戦争のための兵器が製造されている間に。私は、生き残ってこの大地を踏みしめる。危険に直面する全ての者が、生き残っている。悲しく、放浪する男たちは、生き残っている。月日が流れ、以前のような笑いが消えた、かつて、私は、ヒワのように笑っていたのに。私を傷つける確かな記憶がある、どうして広島を忘れることができようかこの地上で、どれほど多くの惨劇が今日、私は笑いたいけれど、もうできないもはや、わたしには、ヒワのような微笑みも、1月の松のような平和もない。生き残って、この世界のために歩く。私は、たった1人の生き残りにはなりたくない。私は、自分の死ぬ日を選びたい。若者よ、私は平穏と赤い血と、よい歯並びと精子をもっている。私の主義に沿った生き方がしたい。私は、動物たちの世界に対して平和の宣言を行う日など見たくない。そんな、狂った日など、笑ってしまうだろう。彼らは、命のために宣言するのだそして、我々はほとんど生き残ることが出来ない。------------------
2008.12.06
コメント(0)
-
背景画像を変更しました
まだ東京は紅葉真っ盛りですが、12月なので背景写真を変えてみました。八ヶ岳の硫黄岳手前から横岳方面を撮影したものです。ついでなので、冬山の写真をいくつか。2003年3月八方尾根より白馬三山2006年2月新穂高ロープウェー終点より西穂高岳2002年12月天狗岳(八ヶ岳)2006年12月硫黄岳(八ヶ岳)の樹氷2006年12月当ブログの背景写真のオリジナルです。
2008.12.05
コメント(0)
-
地球温暖化問題 続編3 過去から将来を予測する
では、将来の地球の気候はどう変動していくのでしょうか。まず長期の変動である氷河時代。これは、あと百万万の単位の期間続くでしょう。我々人類が滅亡するときより、今の氷河時代が終わるときの方が、おそらく先です。中期の変動である氷期と間氷期はどうでしょう。現在の間氷期はあとどれくらい続き、次の氷期はいつ来るのでしょう。氷期と間氷期のサイクルは、ミランコビッチ・サイクルと強い関連があることは、さきの日記で触れました。ところが、このミランコビッチ・サイクルは地球の軌道の揺らぎ、自転軸の首振り運動、自転軸の傾き角度の変動という3つの要素が複合しており、将来予測が極めて困難です。結局、過去の間氷期と現在の間氷期を比較して、類推するしかありません。前回の間氷期(リス-ウルム間氷期)は、従来の説では約13万年前頃から7万年前頃までの6~7万年続いたと考えられていましたが、氷床コアの分析からは、その期間の大部分はそれほど温暖ではなく、現在と同程度以上に温暖化した期間は、最初の1万年ほどに過ぎなかったことが分かっています。(その変わり、もっとも温暖な時期は現在よりもっと暖かかったらしい)もし、現在の間氷期が前回の間氷期と同程度しか続かないとすれば、もうそろそろ間氷期は終わりに近づき、次の氷期が目前に迫っていることになります。そのことを根拠に、次の氷期はもう目前に迫っている、という意見もありました。しかし、両者を比較すると、温暖化の引き金となった日射量の変化が異なっており、条件が異なっているのではないかと考えられています。その前の間氷期(ミンデル-リス間氷期)は、それほど温暖にならなかったことが知られています。そのため、米国ではミンデル氷期とリス氷期の間の温暖期を認めず、両者を併せて「イリノイ氷期」と称しています。これも現在の間氷期とは様相が異なっています。それ以前になると、従来の説と氷床コアの解析結果の乖離が大きくなってきます。従来のギュンツ-ミンデル間氷期は、実は間に氷期を挟んだ二つの間氷期であったことが氷床コアの解析から読み止めます。その後半の間氷期(32~3万年前頃)は、温暖化の程度はかなり大きかったようですが、期間はごく短期間だったようです。そして、ギュンツ-ミンデル間氷期の前半(約40万年前)が、ミランコビッチ・サイクルの条件が現在に近かったのではないか、と考えられています。この間氷期はおよそ2万年続きました。ということは、現在の間氷期も2万年くらい続く可能性が高い、ということです。現在の間氷期はすでに1万年経過していますから、残りはあと1万年です。短いとも言えますし、長いとも言えます。人類が道を踏み外していなければ、その時まだ我々の子孫は生きているでしょうが、しかし今と同じ文明がその延長線上で続いているかというと、それはまず難しいだろうと思います。石油の埋蔵量があとどれだけあるかは定かではありませんが、どう考えてもあと1万年今と同様に使い続けられるだけの量はないでしょう。さて、ではもっと短期の変動はどうでしょうか。これは、中期の変動よりもっと予測困難です。しかし、やはり未来の気候を予測するカギは過去にある。前回の日記で、最終氷期末期、ヤンガードリアス期の急激な「寒の戻り」とその原因について書きました。実は、ほとんど同じような構図による気候変動が、その後でもう一回起こっています。最終氷期が終わり、後氷期に入ってからの最近1万年は、非常に安定した気候が続いていますが、その間に一度だけ、今から8200年前に、小さな寒冷化がありました。小さな寒冷化というのは、最終氷期の激しい気候変動に比べれば、という意味です。後氷期の安定した気候の中では最大級の気候変動であり、もちろん「中世の温暖期」や「近世の小氷期」より遙かに規模の大きな変動でした。もっとも寒冷化した時期は100年にも満たない期間だったようですが、気候が完全に元に戻るまでは400年ほどもかかった見られています。この寒冷化は何故起きたのか。最近の研究では、原因はヤンガードリアス期とほぼ同じと見られています。カナダの大陸氷河が溶融していく過程で、ヤンガードリアス期は氷河の南側にたまった巨大な氷河湖が決壊して、冷たい淡水が五大湖、セントローレンス川を経由して大西洋になだれ込んだことが寒冷化の原因でしたが、8200年前の寒冷化は、今度は氷河の雪解け水がハドソン湾に流れ込んだことが原因と考えられています。つまり、このときもまた「温暖化が寒冷化を招いた」のです。ただ、ヤンガードリアス期に比べると、温暖化が進んでカナダの氷河はすでにかなり縮小していたため、おそらく流れ込んだ雪解け水の量はずっと少なかったのでしょう。寒冷化の程度が比較的小規模だったのも、おそらくそれが原因でしょう。それでも、北大西洋海流と、それにつながる深層海流への沈み込みを妨げ、熱塩循環を止めるか、ある程度弱めるには充分な威力を発揮したのです。問題は、二回の寒冷化の原因となったのが、いずれも北大西洋に冷たい雪解け水の淡水が流れ込んだことだというです。その海域が、表装の海流(北大西洋海流)と深層海流のつながる接点であることがカギになっています。そして、この海域のすぐ近くには、現在もグリーンランドの大陸氷河が現存します。このまま地球温暖化が進んでグリーンランドの氷河が大量に溶けたらどうなるでしょう。やはり、雪解け水の淡水が北大西洋海流と、深層海流につながる海水の沈み込みを攪乱して深層海流の動きを妨げる可能性は多いにあります。まさに、2004年に公開された映画「デイ・アフター・トゥモロー」の世界です。もっとも、かつてのカナダのローレンタイド氷床より、今のグリーンランド氷床の方が規模が遙かに小さいので、それが一斉に溶融しても、ヤンガードリアス期並の激しい寒冷化にはならないかもしれません。「デイ・アフター・トゥモロー」は劇映画だけに、いささか表現がオーバーなところが目立ちます。(マイナス100度の低気圧とか)しかし、8200年前の寒冷化くらいの小規模な変動なら、可能性があります。小規模と言ったって、現代人の体験したことのない激しい寒冷化です。農業は世界的に(少なくとも北半球では)壊滅的な打撃を受けます。現代社会は、その打撃に耐えられるでしょうか。おそらく、耐えられず大混乱に陥るでしょう。温暖化問題の、隠れた懸念は、このように温暖化が一転して寒冷化を招く可能性があるということなのです。(おわり)
2008.12.04
コメント(0)
-
うっかりしていました
実は、昨日地デジ問題について日記を書いたのですが、以前にも同じテーマで日記を書いたことがあるはずなので改めて過去ログを探ってみました。そうしたら、2ヶ月前に書いていました。改めて読み比べて、我ながら中身がほとんどおなじだということに気が付きました。何故そんなことになったのかというと、元ネタの記事が同内容だからです。2ヶ月前の日記のソースは朝日新聞10月15日の記事、昨日の日記のソースは読売新聞12月1日の記事です。読み比べれば一目瞭然ですが、両者とも同じ調査に基づいた記事です。ところが、朝日は調査が発表されたと同時に記事にし、読売は2ヶ月近くも経ってから記事にしている。いや、読売だけではありません。産経もそうです。何で今更そんな以前の調査結果を報じたのかは分かりませんけれど。地デジ普及の危機意識をもり立てるため?それはともかくとして、朝日新聞の記事によると、----------------------------地デジ受信機支給、260万世帯に拡大 政府・与党方針政府・与党は2日、2011年7月に始まる予定の地上デジタル放送で、受信に必要なチューナーの無償支給対象をNHK受信料の全額免除世帯(約260万世帯)に広げる方針を固めた。当初は生活保護受給世帯(約120万世帯)に限る方針だったが、景気の悪化が深刻になり、低所得者を広く支援する必要があると判断した。自民、公明両党の地上デジタル放送推進ワーキングチーム(座長・川崎二郎元厚労相)が3日にまとめる予定だ。新たに無償チューナーの支給対象となるのは、市町村民税非課税の障害者世帯(120万世帯)と福祉施設などの入所者(20万世帯)。地上デジタル放送に対応したテレビなどを購入済みの世帯を除き、希望者に支給する。総務省は当初、09年度からの2年間で計400億円を投じる予定だった。支給対象の拡大に伴い、必要な経費は600億円程度に膨らむ見通し。財源には携帯電話事業者や放送局が納めている電波利用料をあてる。チューナーの無償支給には「ばらまき」との批判もあるが、与党内では「生活保護は受けていないが、所得が少ない高齢者・障害者世帯への対策が必要」との意見が出ていた。----------------------------だそうです。これは悪くない政策だとは思います。ただし、昨日の日記にも書いたように、定額給付金などという馬鹿げた政策をやるくらいなら、そのお金で全世帯に地デジチューナーを配布すべきだと思います。定額給付金などという騒動がなければ、「全世帯に」とまでは言わないんですけれどね。だって、1人に1万2000円の給付金(老人と子どもは8000円上乗せらしい)をばらまくよりは、まだ1世帯に1台の地デジチューナー(1万円から1万5千円くらい?)をばらまく方が安上がりだし、意味があるからです。国民全員に給付金を配れば、対象者は1億2千万人ですが、1世帯に1台の地デジチューナーなら、対象者は約2600万世帯程度です(残りの約2400万世帯はすでに地デジ対応テレビを持っているので)。生保受給者や低所得者以外は、タダでとは言いません。1台1000円くらいの格安地デジチューナー購入券はどうでしょう。なぜそんなことを主張するのかというと、視聴者は、「テレビを見るため」というただそれだけのために出費を迫られているからです。視聴者が「もっときれいな画面でテレビを見たいから」テレビに買い換えたいというなら、それは視聴者本人の責任です。しかし今のテレビで満足している人であっても、テレビを見続けるには、壊れてもいないテレビを買い換えるか、外付けチューナーわなければならない。国が一方的な都合でそう決めたのです。新しいテレビ(地デジ対応の)を買えば、本人がそれを望むかどうかはともかくとして、「きれいな画面」というメリットが付随してきます。しかし、外付けチューナーには何のメリットもありません。放送自体が高画質だとしても、出力先がアナログテレビならば、現実的に見る画質は従来のままだからです。双方向通信やマルチ編成(1つの放送で同時に2つの番組を放送できる)も、大半の視聴者にとってはどうでもいい機能です。というより、安価な地デジチューナーはそういった機能を省略しているようです。国の都合で、そんなものを買わないとテレビも見られないようにするというなら、振り回される国民(視聴者)に対するアフターケアは国の責務でしょう。そもそも、問題はデジタル放送の開始(2003年)からわずか8年(2011年)でアナログを停波してしまうことです。しかも、実質的にはデジタル放送開始後も、つい2~3年前までは地デジが受信できない地域も多かったし、市場でもアナログ対応のテレビの方が売れていました。2011年の時点では、アナログテレビの多くが、まだまだ使える状態であることは確実です。それらのテレビが、アナログ停波でゴミになるわけです。アナログとデジタルの移行期間をどうしてもっと長期間(15~20年くらい)にしなかったのでしょう。
2008.12.03
コメント(0)
-
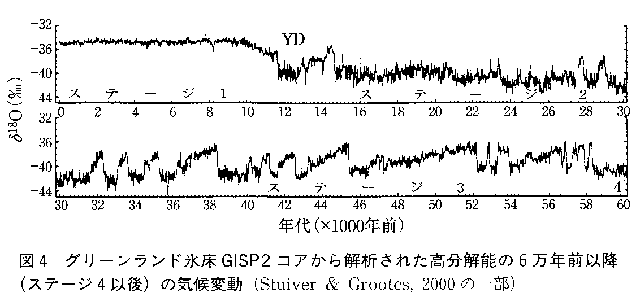
地球温暖化問題 続編2 ヤンガードリアス期
「環境・自然」のカテゴリを選択すると、地球温暖化問題の一連の投稿をまとめて表示できます。----------------------最終氷期の末期、地球の気温がいったん急激に温暖化たあと、急激な「寒の戻り」の時期があったことを前回の日記に書きました。「ヤンガードリアス期(新ドリアス期)」です。ドリアスとは、日本語でチョウノスケソウと呼ばれる高山植物のことです。チョウノスケソウ↓http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%BD%E3%82%A6寒冷期にはこの高山植物が北半球の各地で勢力を伸ばしたことから、寒冷期=チョウノスケソウ(ドリアス)が勢力を伸ばした時期、という意味で「ドリアス期」の名があります。急激な温暖化は今から14700年前、そのあとの再寒冷化は12800年前のことです。この寒冷期は約1200年ほど続き、11700年前頃、再び地球は温暖化して、最終氷期は完全に終わりを迎えたのです。この間の寒暖の変動は極めて急激なもので、特に、14700年前の最初の温暖化は、わずか3年間のうちに約10度という、とてつもない変動だったようです。ヤンガードリアス期の再寒冷化は、世界中の地層に記録が残っており、日本でも同時期に北方系の植物が分布を拡大したことが、花粉化石の分析から分かっています。一方、南極の氷床コアの解析からは、この時期の再寒冷化の痕跡はあるものの、その規模はグリーンランドよりも遙かに小さいことが分かっています。つまり、ヤンガードリアス期の再寒冷化は、北半球で激しく、南半球ではそれほどでもなかったらしいのです。ヤンガードリアス期の終了後、急激な温暖化が収まって以降も、地球の気温はゆるやかに上昇し続けましたが、約1万年前に温暖化のピークに達すると、それ以降は非常に変動の少ない、安定した気候が現在まで続いています。現在までの1万年間が、それ以前と比べていかに天候が安定しているかは、前回紹介したグラフを見れば一目瞭然です。おおむね1万年前頃に農耕が始まり、それ以来人類の文明が急速に発展してきたことは、この間の気候の安定性とおそらく関係があるはずです。それでも、この安定した気候の1万年でさえ、わずかな気候の変化によって人類の文明は大きな影響を受けてきました。この1万年の中で唯一、グリーンランドの氷床コアに明確な痕跡が刻まれている変動は8200年前の寒冷期です。最終氷期の激しい気候変動に比べれば、このときの気候変動はささやかなものですが、それでもヨーロッパの黎明期の文明には壊滅的な打撃を与えたと見られています。それ以降、これに匹敵するほどの気候変動はありません。西暦900年頃から1350年頃までを「中世の温暖期」、1350年頃から1850年頃までを「近世の小氷期」と呼ぶことがあります。しかし、グリーンランドの氷床コアからその痕跡はほとんど読みとることはできません。上記グラフの上段左端をよく見れば、確かに左端付近に、それらしき痕跡があると言われればあるなか、という程度です。この時期の地球の平均気温は、20世紀中頃に比べて、0.5度程度高かったのではないかと推定されています。わずかそれだけの気温の上昇ですが、ヨーロッパでは温暖化の恩恵によって豊作が続いた一方で、北米西部は数百年にも及ぶ長期の干ばつに襲われ、メキシコ南部では繁栄を誇っていたマヤ文明が忽然と滅亡しています。マヤ文明滅亡の真相は明白ではないものの、やはり干ばつが大きく影響しているのではないかと指摘されています。南アメリカでもボリビアのティワナク文明がこの時期に滅亡している。やはり降水量がこの時期に激減していることが分かっています。一方、近世の小氷期の影響は言うまでもないでしょう。江戸時代の大飢饉はいずれも、この寒冷期における出来事です。氷床コアにほとんど記録が残らないわずかな気候変動ですらも、人類社会に与える影響はそれほど大きかったのです。まして、最終氷期に見られるような激しく頻繁な気候変動の影響は、想像するに余りあります。おそらく、人類社会は致命的な打撃を受けるでしょう。さて、ではこのような気候の変動は何が原因で起こるのでしょう。原因が全て解明されているわけではありません。原因は単一ではなく、複数の要素が複雑に絡み合っているからです。前回書いたように、地球の気候変動には、長期の波、中期の波、短期の波があります。およそ200万年前に始まった第四紀という地質年代は、全体として「氷河時代」と呼ばれます。ただいま現在も、立派に氷河時代です。これが長期の波です。そして、200万年間氷河時代のなかに、数万年から十数万年程度の周期で、比較的暖かい間氷期と、特に寒冷な氷期という中期の波があります。現在は、最終氷期が終わったあと、次の氷期が来るまでの間の間氷期に位置していると考えられます。そして、氷期・間氷期にも激しい気候変動があり、長くても1万年、短ければ数百年の幅で、氷期でもやや暖かい時期と特に寒冷な時期、間氷期でもやや寒冷な時期と特に温暖な時期があります。これを「亜氷期」「亜間氷期」と呼びます。これが、短期の変動です。現在は、亜間氷期に当たります。そして、長期・中期・短期の変動では、それぞれ原因が異なっていることが推測できます。長期の気候変動の原因についてはここでは触れません。氷期-間氷期という中期の変動は、ミランコビッチ・サイクルと呼ばれる地球の気道や自転軸の「ゆらぎ」による日射量の変動に主因があるのではないかと考えられています。しかし、より短期の変動はミランコビッチ・サイクルだけでは説明が付きません。ミランコビッチ・サイクルは数万年から十万年程度のゆったりした変動だからです。そこには、他の要因も関係しているはずです。謎を解くカギはいくつかあります。例えば、氷床コアの解析からは、氷期の大気中には比較的塵が多かったことが分かっています。塵によって太陽光が遮られれば、気温が下がります。では、塵の発生源は何でしょう。まず、火山の噴火が考えられます。人類の歴史の中でも、巨大火山の噴火によって、世界的な規模で気温低下が引き起こされた事例があります。もう一つ、氷期には世界的に見て、寒冷化と乾燥化によって森林面積が減少した地域が多かったのではないかと推定されています。植生の乏しい裸地が増えた結果、土壌が空気中に舞い上がったのかもしれません。そして、もう一つ、短期的な気候変動の原因の一つになっているのではないかと考えられているのは、海流の変動です。ヤンガードリアス期の急激な「寒の戻り」は、この海流の変動に主因があったのではないかと考えられています。最終氷期の最寒冷期には、南極とグリーンランドの他、北欧のスカンジナビアと、アラスカ南部からカナダにかけての地域にも巨大な氷床がありました。これが、ヤンガードリアス期直前の温暖化によって、急激に溶けていきました。北アメリカでは、氷床の南側、現在の五大湖より西に、アガシー湖とい氷河湖を形成したのです。その名残が、現在のウィニペグ湖です。氷河の溶融が進に連れてアガシー湖はどんどん巨大化し、現在の五大湖よりもはるかに広い湖になりました。そして、あるところで湖岸が決壊し、水が五大湖になだれ込みました。その水が、さらにセントローレンス川を伝って、北大西洋に大量に流れ出したのです。さて、海の上には海流が流れています。例えば、日本の近海には黒潮と親潮、対馬海流などがありますし、北大西洋には、北大西洋海流が流れています。これは、海水の表層の水の流れです。それとは別に、実は深海でももう一つの海水の流れがあります。この深海流を「熱塩循環」と呼びます。低緯度の海水は温かいが塩分濃度が比較的薄い、高緯度の海水は冷たいが塩分濃度が比較的濃い(海氷が多いため)、その温度と塩分濃度の差を埋めようとする動きかが深海流の動力源と推定されているからです。深海流は、しかし所々で表層の海流と連結しています。そのうちの一つが、北大西洋なのです。大西洋には、メキシコ湾流~北大西洋海流と呼ばれる海流が流れています。メキシコ湾岸の温かな海水をスカンジナビア半島の沖まで運ぶ巨大な暖流です。これが、北大西洋で急激に冷やされて、深海へと沈み込んでいき、深層海流へとつながっているのです。ところが、そこに、アガシー湖が決壊したことで大量の冷たい淡水が流れ込んできました。この淡水が、北大西洋海流の温暖な海水をせき止め、さらには深海への沈み込みをストップさせたと推測されています。北大西洋海流がせき止められれば、その北側(グリーンランドやヨーロッパ、カナダ)では温かい海水がストップするので寒冷化します。さらに深層海流がストップすることで、世界的規模で、高緯度海域への暖かい水の供給がストップします。これが、ヤンガードリアス期の急激な「寒の戻り」の原因と推定されています。急激な温暖化が、一転して寒冷化の原因となったのです。前回の日記に、ヴァイツゼッカーの「過去に目を閉ざすものは未来に対しても盲目である」というという一節を引用しました。ヤンガードリアス期の急激な寒の戻りという「過去」に目を閉ざすものは、ひょっとすると未来に対しても盲目であるかも知れません。以下、更に次回に続きます。
2008.12.02
コメント(0)
-
地デジ世帯普及率5割に届かず
氷河時代の話の続きは後回しにして・・・・・・http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20081201-OYT1T00422.htm地デジ低調、現状で世帯普及率50%超ならず今年9月時点の普及世帯は約2350万世帯で、政府などが目標としていた2600万世帯に比べ250万世帯少ない。普及対象の全5000万世帯に対しては約47%にとどまる。景気悪化の影響で年末のテレビ商戦も期待薄となっており、政府や関連業界は普及に向けた体制や計画の見直しを迫られる可能性がある(以下略)--------------------我が家はこの夏にテレビが壊れてしまったから買い換えたけれど、そうでなければ壊れるまで使い続けたでしょう。世帯普及率47%というのは、一家に一台以上地デジが入った割合といういみであって、テレビの47%が地デジに置きかわったという意味ではないです。今は一家に2台近くのテレビがあるから、総数では日本中に1億台前後のテレビがある。その全体から見れば、おそらく1/3かせいぜい4割が置きかわったくらいではないでしょうか。そして、残りの数千万台がアナログ停波の3年後までに全部デジタルに置きかわるのはかなり難しいでしょうし、そうなったらなったで大量のテレビがゴミになる。なんという壮大な無駄でしょう。麻生内閣は、2兆円ものバラマキをやるなら、せめてその財源で地デジ外付けチューナーをつくって、希望者に配布するくらいやればいいのに。そうすれば、ただのバラマキよりはまだ多少は意味がある。
2008.12.02
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
-

- 今日のこと★☆
- 11月26日のツキアップ
- (2025-11-26 08:25:12)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンで損したくないあな…
- (2025-11-25 20:30:05)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-







