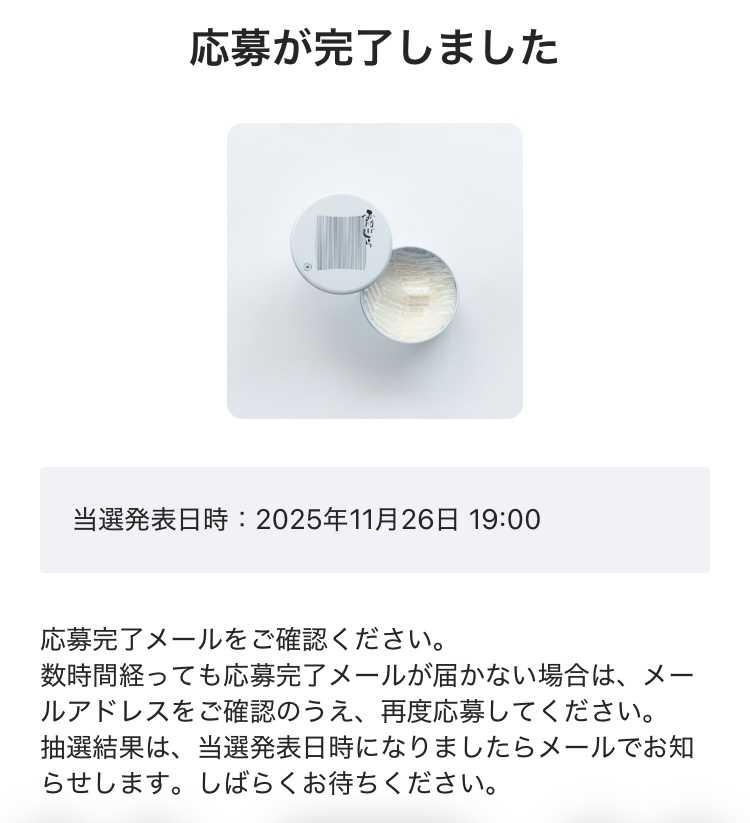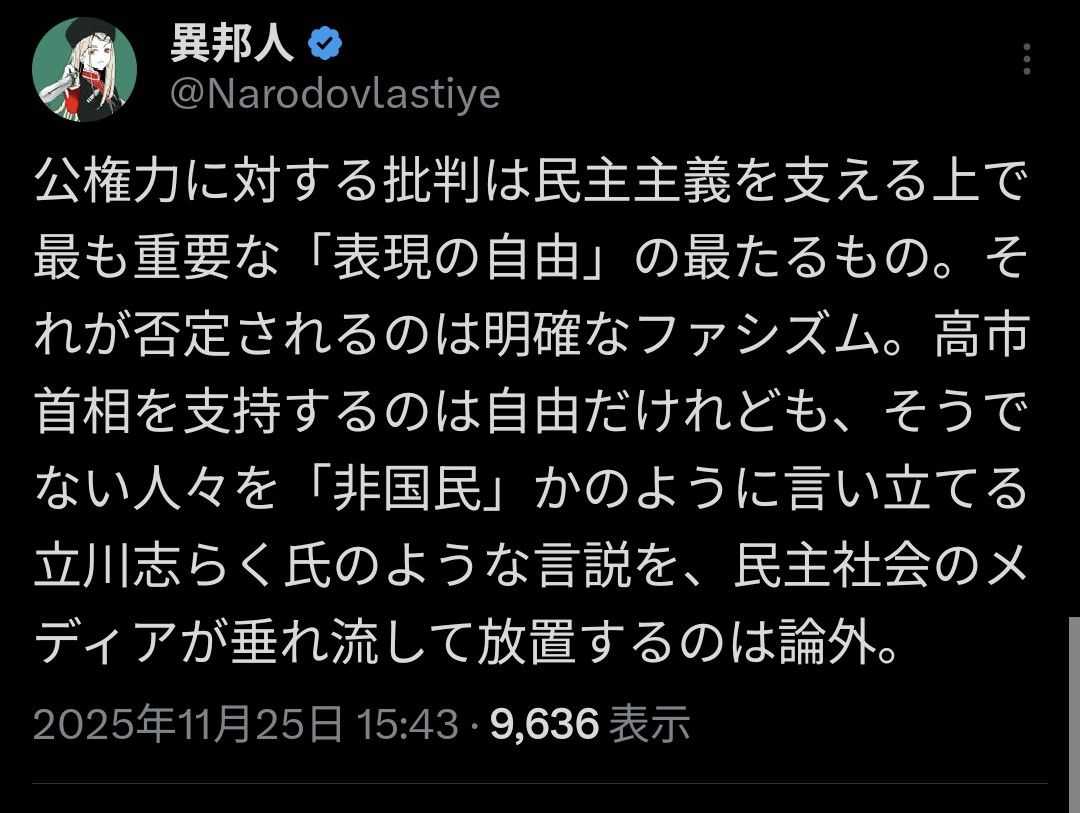2019年07月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

7月の鳥写真
7月は前半に雨が続き、ほとんど鳥を見に行っていません。野鳥観察は葛西臨海公園に1度きりで、あとは登山、旅行のついでの撮影だけです。しかも北岳では鳥の写真は1枚も撮りませんでした。が、それにもかかわらず、初めて撮影する鳥、久しぶりに見る鳥何種かに遭遇しました。まず7月20日葛西臨海公園ヨシゴイです。子どものころ見た記憶がありますが、撮影は初めてです。残念ながら、池の対岸で近くには来ず、しかもサギの仲間の中ではかなり小型の部類(はとより少し大きい程度)なので、小さくしか写せません。少なくとも2羽いました。実際にはもっといるようです。そして、27日から昨日までの富士見高原と編笠山です。まず27日、子どもと一緒に宿から登山口まで散歩している間に遭遇したのはモズ「ホーホケケョ」と囀っていましたので、ウグイスです。同じくウグイス。そして、翌28日、編笠山への登山中おそらく、メボソムシクイ。ただ、声を聞かなかったので、確実ではありません。センダイムシクイも、鳴き声は違いますが姿はよく似ています。同じく、多分メボソムシクイです。撮影場所は標高1700-1800m付近。低山帯の落葉広葉樹林と亜高山帯針葉樹林の境界付近(まだ広葉樹主体の森)。メボソムシクイは亜高山帯で繁殖し、センダイムシクイは落葉広葉樹林で繁殖するので、その意味でも微妙です。センダイムシクイかもしれないなー。2019.9.30修正 キビタキのメスか、サメビタキ、コサメビタキのいずれか、おそらくサメビタキと、記事アップ当時書いたのですが、改めて写真を検討してみると、ルリビタキのメスである可能性がもっとも高いように思えます。2019.9.30修正 くちばしの根元が黄色いことから、多分キビタキ(メス)ではなさそう、くちばしの下部から喉にかけて、暗色部が多いので、多分コサメビタキではなくサメビタキ、というのが私の見立て、とアップ時には書いたのですが、わきの下に黄色い部分がある。これはルリビタキの特徴ですね。そう考えなかったのは、ルリビタキはメスでも尾羽は青いのですが、この写真の尾羽は青くないからです。しかし、改めてネット上でルリビタキの様々な写真を検索したところ、ルリビタキの尾羽が青いのは表側だけで、も裏側は青くないようです。ホシガラス。高山の代表的な鳥です。編笠山からの下山時、ちょうど森林限界線のところにいました。ホシガラス。昨年北海道の阿寒湖付近で初めて撮影しましたが、そのときはかなりピンぼけ写真でした。今回もピントは甘いですが、まだちゃんと写っています。同じくホシガラス。そして最終日、29日朝です。クロツグミ。ピンぼけ写真です。実は、ツグミ大の鳥が2羽、飛んできたので、何だか分からないけどとりあえず撮った、双眼鏡で確認する前に飛んでいってしまった、というわけで後で写真を確認して初めてクロツグミと分かりました。分かっていれば、もう少し粘って、もうちょっとマシな写真を狙ったのですが。初めて撮影する鳥です。同じくクロツグミ。実はファインダーの中でどこにいるかはっきり分からないまま撮ったので、ファインダーの測距点に捉えていなかったのです、だからピンぼけになりました。もっとも、ちゃんととらえてもピンぼけになることがあります。鳥撮影用の100-400mmレンズは、重くてとても山や家族旅行に持っていけないので、18-300mmの高倍率ズームで撮っています。画質もそうですが、暗い場所でもピントの精度に限界があります。アカゲラ。逆光で真っ黒ですが、頭が赤いのがかすかに分かります。コゲラ。これは、東京でもって公園などでよく見かける小型のキツツキです。ホオジロ。アップは1枚だけですが、あちこちにおり、非常に数の多い鳥でした。
2019.07.31
コメント(2)
-

八ヶ岳・編笠山 その2
前回の続きです。ガレ場の登り一直線です。このあたりが一番ペースは落ちたかもしれません。そして山頂に到着です。時間は12時27分、したがって、2000m地点から標高差520mあまりを1時間54分、宿から1300m弱を3時間45分か50分かかった計算です。520mを1時間54分は遅すぎですが、2000m地点標識が実際にはもっと低い標高だったとすれば、つじつまは合います。トータルでは1時間で340m前後くらいのペースで登った計算です。やっぱり以前より足は遅くなりました。目の前に権現岳の雄姿が。権現岳。八ヶ岳の主要な山で未登なのは、この権現岳と最北端の蓼科山だけです。権現岳はよく見えるのですが、その先の赤岳、阿弥陀岳、中岳、横岳、硫黄岳などは残念ながらすべてガスの中に隠れてしまいました。西岳。編笠の山頂からだと、はっきりと低いことが分かります。標高2398mなので、編笠より120mあまり低いだけですが。南アルプスもガスに阻まれて見えません。でも、下界は見えます。なかなか雄大な景色で、非常に気持ちが良いです。山頂には30分ほど滞在し、昼食を食べ、12時57分下山開始しました。西岳を回って下山するか、まっすぐ下山するか迷いましたが、午後は大気の状態が不安定で、雷雨がありそうという予報だったので、まっすぐ下山しました。ガレ場を下って行きます。見上げると、結構な急斜面です。下りは一気に、と言いたいところですが、転倒したらイヤなので慎重に下ります。それでも、バランスを崩しそうななる場面が一度だけありましたが。7月下旬の日曜日でしたが、台風直後だったせいで、(もともとそんなに登山者が多いコースでもないけれど)往路すれ違った登山者は2組3人、登りで私を追い抜いていった方が1人、山頂にはその方と私と、他に2人(おそらく観音平に下山したと思われます)、登山中に出会った人はその6人だけでした。1人が私の前を下山しているのが見えます。森林限界付近まで降りてきました。森林限界線付近が一番の急登です。ここを下るときにアブにたかられたらかなわないと思っていたのですが、幸いにしてアブはまつたく姿を消していました、このときは。それ以降も、登りとは打って変わって、アブはまったくいない、快適な下山路を1900m地点の標識まで下ってきました。が、そこで休憩して水を飲んでおやつを食べたら、またも現れたのです、アブの大群が。ひょっとしておやつの臭いが呼び寄せたのでしょうか?そこからは登山口付近まで、往路と同様、ずーーーーっとアブにたかられっぱなし。ただ、もうキツイ場所は過ぎたところでのアブの再襲撃だったことは不幸中の幸いでした。緩い下り坂の何箇所か、小走りで下ってみたのですが、人間が走るスピードではアブは振り切れないんですね。というか、一時的に「振り切ったかな」という瞬間は何回かあったのですが、登山道の折返し、濡れた木の根が続く場所、足場が悪い場所など、走っては危険な場所が頻繁に出てくるので、どうしても足が止まる(体力も続かないですし)、そうすると、しばらくするとアブの集団が追いついてくるのです。ほんと、かないません。下山中遠方で雷鳴が聞こえ、何度か雨がパラつきました。予報どおりだったのですが、さいわいにも本降りにならないうちに登山口まで下ってきました。ただ、登山口から宿までの途中で、自販機で炭酸飲料を買って飲んでいたら、本降りの雨が降り始めてしまいました。結局、宿に帰るまでの最後の10分ほどで雨に濡れてしまいました。もっとも、宿に着いた数分後から土砂降りになったので、その前に着けたのはラッキーでしたが。登山中、およびその前後に撮影した鳥の写真を次回アップします。
2019.07.30
コメント(2)
-

八ヶ岳・編笠山 その1
実は、過去何回か登っている山ですが、家族旅行で富士見高原のペンションに泊ったので、また登ってきました。土曜から今日まで2泊3日の旅でしたが、初日夜、まさかの台風直撃。これは山は中止かと思いきや、日曜の明け方なでには台風は抜けてしまったので、予定どおり登ることにしました。早朝、5時過ぎに起きて、鳥の写真と笛練習のため散歩中、富士山が見えました。宿が朝食8時からなので、散歩の後いったん宿に戻り、朝食後の8時40分頃、出発しました。登山道は途中林道と何回か交差するのですが、その最初の交差でいきなりこんな案内が。土石流で通飛行止めだって。迂回ルートを登っていくと・・・・・・土石流というのはこのあたりでしょうか。対岸を登っていた登山道がここで途切れて、河原?土石流跡?を渡って登山道はこちら側に移ります。同じ場所です。そして2本目の林道との交差3本目、最後の林道との交差。(西岳への登山道は更に上、標高1700m付近でもう1本林道と交差します)やっと2000m地点。宿が標高1230mくらい、8時40分頃に出発して、1510m地点が9時26分、2000mが10時33分。ということは、最初標高差280mを46分、続いて標高差490mを1時間7分で登った計算になるのですが今の私が1時間で440mのペースの脚力があるとは思えないので、多分標高表示が間違えているのだろうと。ひとつだけ厄介だったのがアブの大群。登りは1500m辺りから森林限界(2400m付近)まで、下りは1900m付近から下、登山口近くまでずっと、とにかくアブの大群にたかられっぱなし。ここは腐海の森か、状態。数十回噛まれました。痛い痛い、こやつらは服の上、ズボンの上からでも噛むのです。背中とザックの間に入り込んだ輩が、何度も噛むのは閉口しました。ただ、毒はないから痛いだけで腫れたりはしないいけど。一カ所だけわずかに出血。下りは、最初は全然いなかったので、ああ、退散したんだ、よかったよかった、と思っていたら、1900mまで下ったところで水を飲んでおやつを食べたら、チョコの匂いに惹かれたのか、そこからずっとアブの大群。おやつ食べなきゃよかったか。アブにまとわりつかれたことも噛まれたことも、何回もあるけど、こんな長い距離ずっと、こんな大群にまとわりつかれ続けたのは初めてです。次から、この時期雨の直後の登山は虫除けスプレー必須です。なお、この写真は下山時に撮影したものです。森林限界の到着。森林限界を超えたところで、視界が一気に開けます。ここが標高2400m弱。視界は開けたけど、この先ひたすらガレ場の登り。山頂までまだ標高差100m以上あります。西岳。標高2398m、ほとんど同じ高さかわずかに低いくらいに見えます。ガレ場を登り続けます。森林限界を超えたところで、登りはアブの大群は姿を消しました。(下りで再び遭遇することになりましたが)以下、次回に続きます。
2019.07.29
コメント(0)
-
類は友を呼ぶ
N国党首、丸山穂高衆院議員に入党要請=「5人集め番組出演」参院選で議席を得たNHKから国民を守る党の立花孝志代表は25日、国会内で丸山穂高衆院議員と面会し、同党入りを要請した。この後、丸山氏は「NHK改革という点では非常に分かり合える。持ち帰って近々判断したい」と記者団に述べた。両氏は29日に再会談する予定だ。丸山氏は、北方領土を戦争で奪還する趣旨の発言をするなどして日本維新の会を除名された。---ひとことで言って、呆れました。いや、「NHKから国民を守る党」なんて、最初からロクなもんじゃないとしか思っていないので、「失望」はまったくありません、たんに「やっぱり」というだけですが。よりによって、北方領土を戦争で取り戻せ、だけではなく、明らかに酒乱で道を踏み外してしまった議員に、「数は力だから」と入党を呼びかける、つまり、丸山穂高と「NHKから国民を守る党」は同類、という理解でよろしいわけですね。まさしく類は友を呼ぶ、という話です。もっとも、所詮はうたかたの同盟でしょうけど。永続的にうまくやれるとは思えないし、そもそも丸山が次の選挙で当選できるとは思えないですから。
2019.07.27
コメント(0)
-
英国のトランプ
ジョンソン氏、英首相に就任…10月末離脱明言英国の与党・保守党の党首に選ばれたボリス・ジョンソン氏が24日午後、首相に就任した。首相として初の演説で、「10月31日にEUから離脱する」と明言した。今後は、与野党の反対派やEUとどう折り合いをつけるかが最大の課題となる。メイ首相が24日にロンドンのバッキンガム宮殿でエリザベス女王に辞意を伝えた後、女王がジョンソン氏を新首相に任命した。その後、ジョンソン氏は首相官邸前で演説を行い、「EU離脱は英国民の決定であり、尊重しなければならない。そして、欧州の友人たちと、可能な限り密接な協力関係を結んでいく」と述べた。ジョンソン氏は組閣に着手する。また、25日には下院でEU離脱の方針を説明する予定だ。その後、下院は夏の休会に入るため、新政権と議会の攻防は9月に本格化する。ジョンソン氏は、英国とEU諸国に社会混乱を招く「合意なき離脱」も辞さない強硬姿勢を示している。---「英国のトランプ」という評もあるボリス・ジョンソンが首相になりました。しかし、この人物は、イギリスのEU離脱是非を問う国民投票の際、離脱推進を主導したにもかかわらず、いざそれが可決して、当時のキャメロン首相(EU離脱に賛成ではなかった)が辞任に追い込まれると、その後任首相には名乗りを上げようとせず、早々に逃亡してしまいました。ある意味で貧乏くじを引かされたのが、メイ首相です。もっとも、メイ首相は退任に当たって、野党労働党党首コーヒンの党利党略を批判したそうですが、野党が与党の政策に反対するのはある意味当然で、同じ与党保守党内の全員の賛同を得られなかったこと(提案が悪かったのか、賛同しない強硬離脱派が悪かったのかはともかく)をどう考えるのかな、と思わざるをえませんでしたが。この経緯から考えると、ボリス・ジョンソン自身が、実はEU離脱が多数になるとは思っておらず、いざそれが実現した場合の準備をしていなかった、と考えざるを得ません。しかし、EU離脱に関してどっちつかずのメイ首相な舵取りでは二進も三進も行かなくなると、とうとう「本命」として姿を現したわけです。でも、ボリス・ジョンソンならうまく舵取りができるか、というと、そうは思えません。その自信があれば、最初から首相の座に名乗りを上げていたはずです。これまで、離脱についてのEUとの合意案について、あの手この手の妥協図られたものの、議会の承認は得られませんでした。ジョンソンなら妥協案がまとめられる、はずがありませんし、そもそもそのような合意形成型の政治家ではなさそうです。だから英国のトランプなどと言われるわけで。ということは、今後イギリスも欧州も、本音では避けたかった「合意なき離脱」に至る可能性が、限りなく高くなった、ということなのでしょう。あるいは、完全な合意なき離脱でなくても、完全な手切れ必要最小限度の合意だけによる離脱、ということもあるかもしれません。その結果どうなるかは、神のみぞ知る、というところでしょうが、少なくともイギリス経済によい影響はないでしょう。悪影響が、わずかなものに踏みとどまるのか、深刻な状態に至るのか、それ次第で今後のヨーロッパの動きも大きく左右されるのかもしれません。
2019.07.25
コメント(7)
-
2019年参院選雑感
参院選が終わりました。結果云々以前に、投票率が5割を切り、史上2番目に低さだったことにがっくりです。国民の多くが政治に無関心、という感情は私にも何となく理解できないことはありません。こんな政治的首長を前面に出したブログを運営しているにもかかわらず、私にも政治に対する無力感、醒めた思いが少なからずあります。しかし、期待を持とうが絶望感を持とうが、そもそも関心がなかろうが、政治は否応なく我々の生活を左右する大きな問題です。政治に何かを期待しても、物事はちっとも良い方向には変わらないけれど、悪い方向には実に簡単に変わっていく、なんとも厄介なものです。だから、私は政治にはもはやほとんど期待を持っていないにもかかわらず、棄権だけはしないことにしています。というわけで、今回も期日前で投票をしたわけですが、ズバリ私は今回、選挙区(東京)では共産党の吉良よし子に、比例区ではれいわ新選組に票を投じました。「山本太郎」にするか党名での投票にするかは若干迷いましたが、党名で投票しました。結果として、今回私の票は2票とも死票にはならずに済みました。衆院選や地方選は違いますが、参院選は、この数回、ずっと選挙区は共産党、比例区は社民党に票を投じてきました。今回も、もし票が3票あるなら共産党と社民党とれいわ新選組に票を入れましたが、残念ながら選挙区と比例区の2票しかない。話題性に乏しい今回の参院選の中で、唯一多少なりとも期待をいだけるのがれいわ新選組だったこともあって、今回とうとう社民党を見限ってしまいました。正直言って、今回社民党は議席を失うかな、と予想もしましたが、かろうじて議席を維持しました。自分が票を投じなかったのにこんなことを書くのも変ですが、議席を維持できたことは素直に嬉しいです。もはや土俵際に追い詰められた状態で、かろうじて踏みとどまった状態ではありますけど。さて、そういうわけで、話題性に乏しかった今回の参院選の中で唯一、掛け値なしに「勝利した」と言えるのが、れいわ新選組でしょう。山本太郎はなんと96万票も取ったにもかかわらず落選者になりました。この得票は、今回の比例区の個人名の得票では圧倒的最多得票ですが、れいわ新選組が2名の候補者を優先枠にしたため、いわば「山本太郎」の得票によって2人を当選させることで彼自身は当選を譲ったかたちになりました。実に「男を上げた」と思います。おそらく、山本自身も、3議席も取れるとは考えておらず、自身の落選は織り込み済みでしょう。もっとも、今回、これだけの低投票率でもれいわ新選組が2議席取ったということは、投票率が上がれば、更に議席数が伸びたでしょうから、そうなっていたら山本太郎も当選していたはずです。ただ、山本太郎はあのくらいの知名度があれば、議員の椅子にしがみつく必要性はない、ということと、もうひとつは衆院選に転進のための複線でしょう。実際、いまの勢いを維持できれば、次の衆院選で、少なくとも比例区では山本太郎の当選は堅い、と思います。それにしても、れいわ新選組が4億円もの寄付金を集めたことには驚きました(わたしは、票は投じましたが寄付まではしませんでした)。しかも、おそらくその大半は企業団体献金ではなく個人からの寄付でしょう。それでも、自民党などが集める政治資金に比べれば、桁が一つか二つ小さいはずですが、これだけあれば、知名度があったり、あるいは知名度はなくても各分野で問題提起ができる候補者を10人あつめて、全国で選挙運動を展開し、2名の当選者を出すことができるわけです。もちろん、そこには山本太郎の組織力、あるいは突破力とでも言うべきものがあることは言うまでもありません。加えて、政界の常識に捕らわれない発想力。今後もしばらくはれいわ新選組の勢力拡大は続くのではないでしょうか。ただ、そうなると、山本太郎の一人政党というわけには行かなくなります。政界の常識を踏まえつつ、山本太郎にタガをはめるのではなくその発想力を生かす、そんな参謀役が必要になってくるだろうと思います。それ以外の野党は総じて停滞気味ですが、これだけ「野党の不人気」が宣伝されている中ではよく踏みとどまったとも言えます。立憲民主党と国民民主党の合計得票は前回民進党の得票とほぼ変わらず、低投票率のため得票率では伸びているようです。共産党は6年前の大躍進時の8議席の改選で、1議席減で踏みとどまったのは、充分に善戦です。1人区で前回野党が11勝だったのに、一つ減って10勝だったことは残念ですが、現状野党が分裂して戦えば明らかに全敗なので、これ以外の選択肢はありません。野党共闘は右派、自民党系から基本政策の不一致を攻撃されることが多々あります。私見では、政権を取りに行く、ということであるなら、共産党は自衛隊の容認に舵を切るべきと思います。その一方で、日米安保体制に関してはどうでしょうか。国内では、日米安保解消を叫ぶ政治勢力は一貫して野党であり、しかもその勢力は時代とともに減ってきています。政権中枢では、戦後常に日米安保体制護持が金科玉条のように続き、今やそれ以外の選択肢などないかのようになっています。ところが、では日米安保体制は安泰なのかと言えば、明らかに違います。トランプは、少なくとも本音では日米安保などまったく重要とは思っておらず、破棄してしまいたいと考えているようです。トランプ個人の考えでそのまま実際に日米安保が破棄される可能性は、少なくとも近い将来はないでしょうが、米側は日米安保のコストを、年々吊り上げ、日本側に多くのものを要求し続けるでしょう。それをいつまで甘受するのか。全野党が日米安保破棄でまとまれ、とは言いませんが、日米安保が維持できなくなった場合の安全保障策を問題提起していく役割は、野党にこそ求められると私は思います。さて、近い将来のことで言えば、改憲に賛成する党派の議席数は3分の2を割り込んだと報じられています。しかし、安倍は相変わらず改憲発議を叫んでいます。それが口先だけか本気かは分かりませんが、本気とすれば野党側のいずれかの党を切り崩す、ということになるわけで、それは衆目の一致するところは国民民主党でしょう。今後しばらく、国民民主党q、あるいはその所属議員がどのような行動を取るか、注視していく必要がありそうです。
2019.07.23
コメント(33)
-
選挙に行こう!
今回の参院選は、盛り上がりが今ひとつだという評もあるようです。真偽のほどは知りませんが、盛り上がりがあるにしろないにしろ、今後の日本の進む道を左右する大事な選挙です。私自身は本日仕事のため、すでに期日前投票済みですが、みなさまも、貴重なら選挙権を無駄にすることなく、是非投票をお願いします。
2019.07.21
コメント(0)
-
これはもう典型的な・・・・・・
壁に穴、PCは粉々…京アニ放火容疑者、各地でトラブル「京都アニメーション」のスタジオが放火され、34人が死亡した事件。容疑者の男は、過去にたびたび近隣トラブルを起こしていた。重篤な状態が続く容疑者は、茨城や埼玉で住居を転々とし、各地でトラブルを重ねていた。身柄を確保された直後、「小説を盗まれたから放火した」という趣旨の説明をしたというが、同社の社長は「何を言っているのか分からない」と話しており、遠く京都へ向かった理由ははっきりしない。容疑者は2010年ごろ、ハローワークのあっせんで茨城県常総市の築約30年の集合住宅に単身で住んでいた。管理人によると、月約4万円の家賃はほとんど滞納していたという。家賃徴収に部屋を訪ねても無言でドアを閉められ、「ぶぜんとした様子だった」と当時を振り返る。遅くとも12年春ごろには、毎週のように近隣住民と騒音トラブルがあったという。深夜の決まった時間に目覚まし用のベルが鳴り響き、壁をたたく音や、わめく声が聞こえることもあったという。---なんというか、いろいろな意味でドキッとする話です。犯人は自身の犯行で大やけどを負って現在意識不明と報じられていますが、意識を回復して取調べを行ったとしても、おそらく常人が理解可能な「犯行理由」など何も出てこないだろうと思います。昨日の記事へのコメントでこの犯人の精神疾患の有無が話題になりました。どう考えたって、明らかに精神疾患はあります。ただし、問題は、精神疾患によって責任能力が否定されるかどうか、です。この種のトンデモな人格、行動の凶悪犯人といえば、池田小事件の犯人がいます。彼は、あの事件を起こす前にも何度も事件を起こしており、また暴力や異常な行動の数々で周囲に迷惑を掛け続けてきましたが、事件後精神疾患を装ったものの、精神鑑定でそれを見抜かれています。しかし、精神鑑定は、これに精神的な疾患がない、とはしていません。「情性欠如、妄想性人格障害などはあるが、統合失調症ではなく責任能力ありと判断され」たのだといいます。つまり、言い換えるなら、情性欠如、妄想性人格(パーソナリティ)障害などがあっても、それは責任能力を否定するものではない、ということです。そして、別報道には、こんな話があります。アニメ会社放火 確保の男 ゲームのような音楽で騒音トラブル容疑者の隣の部屋に住む男性は「去年の夏、明け方に男の部屋からゲームかアニメのような音楽が大きな音で繰り返し流れる騒音トラブルがあった。」と話していました。反対側の隣の部屋に住む男性は「数日前、ドアや部屋の壁をたたかれたので注意しに行くと、胸倉をつかまれて『お前には関係ない。こっちは余裕がないんだよ』と言われた。~以前から日常的にゲームの音楽がうるさかったので、警察に何度か通報したことがある」と話していました。隣の部屋に住む男性によりますと、~隣の部屋をノックしたところ、出てきて、いきなり胸倉をつかまれ、「お前殺すぞ」「うるせーよ」「黙れ」「こっちは余裕ないから」「失うものはないから」ということばだけを繰り返し、会話にならなかったということです。隣に住む男性は「平日の夜12時以降、スピーカーの振動音がおよそ1時間聞こえ、土日の昼ごろはゲームのようなサウンドがずっと繰り返されていた。これまでも警察を呼んで注意してもらっていたが、恐怖を感じて、ちょうど引っ越しを考えていた」と話していました。関係者によりますと、容疑者は以前茨城県内に住んでいて、7年前にはコンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして懲役3年6か月の実刑判決を受けていました。刑務所を出所したあと、一時的に出所者を受け入れる施設で生活し、その後、現在のアパートに引っ越したとみられています。関係者によりますと、容疑者は生活保護を受けていて、精神的な疾患があるため訪問看護を受けることもあったということです。---なんとなく、そうではないかと思っていましたが、犯人が生活保護を受けていた、という報道が天下のNHKから出てきてしまいました。福祉事務所関係の知人に色々聞いて見ました。彼によると、受給者が犯罪を犯した場合、逮捕されると保護停止、起訴が確認されると保護廃止となるそうです。今回のような大事件の場合は起訴されたことの確認は報道等で簡単にできるでしょうが、世の多くの小さな犯罪ではそうはいかず、それどころか逮捕の事実を把握できないことすらあるそうです。そのような例、あるいは逆に受刑者が釈放されてその足で保護申請に来た、というような例は福祉事務所では特に珍しいことではなく、よくあることだといいます。しかし、こんな凄まじい人格の受給者がいったいどれだけいるかというと、実は珍しくはないのだといいます。このレベルの、破壊的に攻撃性のある人格の持ち主は、ひとつの係に1人や2人は必ずいる、いや、もっとと多いかもしれない、のだそうです。典型的な「最悪の境界性パーソナリティ障害」(あるいは類似の障害)のパターンだそうです。そうすると、この事件の標的が何故か京都アニメだったけれど、何かの歯車がひとつ違えば、標的が福祉事務所になっていてもまったく不思議ではなかった、ということになります。むしろ、福祉事務所は受給者の収入を握る存在だから、普通ならそちらの方が遥かに可能性が高いところでしょう。あるいは、引用記事の取材対象である近隣住民やその他の関係先も同様です。そう考えると、ちょっと恐ろしい、と知人は言っておりました。いや、私も恐ろしいです。模倣犯が出てこないことを祈るばかりです。
2019.07.20
コメント(2)
-
世の中には理不尽過ぎることが多い
京アニ火災、死者33人に 身柄確保された男は意識不明18日午前、京都市のアニメ制作会社「京都アニメーション」の第1スタジオから出火し、鉄筋コンクリート造り3階建ての建物の大半が焼け、33人の死亡が確認された。このほか36人が病院に運ばれ、うち17人は入院中で意識不明の人もいる。京都府警は、ガソリンのような液体をまいて火をつけたとみられる関東在住の男の身柄を確保した。男は上半身などをやけどして病院に運ばれ、意識不明の重体。搬送される際、駆けつけた警察官に「1階で液体をまいて火をつけた」と話したという。出火当時、建物内には従業員67人と社外の6人の計73人がいたとみられる。遺体が見つかったのは、1階で2人、2階で11人、2階と3階をつなぐ階段で1人、3階から屋上に上がる階段で19人という。上階に炎と煙が広がり、多くの人が屋上に逃げようとして死亡したとみられる。確保された男と似た人物がこの日、容量20Lの携行缶二つを持って近くのガソリンスタンドを訪れ、ガソリンを買っていたという。現場近くに携行缶二つと台車のほか、包丁数本とハンマーが入った手提げかばんとリュックサックが残されていた。複数のスタジオ関係者は、男が「死ね」と叫びながらビルに入り、1階の入り口付近でバケツに入ったガソリンとみられる液体をまいた後、すぐに火を放ったのを目撃。府警は、購入したガソリンを台車で運び、現場近くで携行缶からバケツに移し替えてまいたとみている。---わたしは、高校生くらいまでは熱狂的アニメファンでしたが、現在はジブリアニメと、高校生当時までに好きだった作品以外はアニメはほとんど見ておらず、京都アニメーションという名前も実は知りませんでした。なので、有名アニメ制作会社、という点は考慮の外として、なんとも暗澹たる事件と言わざるを得ません。20Lのガソリン缶2つ、40Lものガソリンをぶちまけて火を放たれたのでは、どんな防火対策も意味をなさないでしょう。当時建物内にいたと思われる73人のうち33名が死亡という割合の高さが火の勢いの強さを物語っています。屋上に上がる階段で19名が亡くなっていた、とのことですが、別報道によると、消防隊が屋上から室内に入った際には、屋上に出る扉は閉まっていた、とのことです。この扉は、「鍵はかかっていなかった」というので、何故明けられなかったのかは分かりませんが、ともかくここから類推すると、屋上に向かって逃げた人は誰も助からなかった、ということのようです。施錠されていなかった、という上記報道が事実とすると、何故逃げられなかったのか。内開きの扉だと、人が殺到して開けられなくなる可能性がありますが、空撮動画で確認すると外開きの扉です。ただ、扉を破った形跡があります。可能性としては、鍵はかかっていなかったというのが誤りか、または扉が熱で変形して動かなくなった、ということでしょうか。あるいは、開く開かない以前に扉までたどり着けずに亡くなった、という可能性もあります。いずれにしても、火災の煙は上に向かって登っていくので、火事の際、上階に向かって逃げるのはリスクがあります。2000年11月にオーストリアでケーブルカーがトンネル内で火災を起こした事故では、たまたま乗客に消防士がいて、上に逃げるのは危険と判断し、炎を突破して下に逃げるようにほかの乗客に伝え、彼に従って下に逃げた十数人だけが助かった。斜面の上側に逃げた百数十人は誰も助からなかった、といいます。もっとも遠方まで逃げたのは日本人の少年で、それでも142m先で亡くなった、それどころか、ずっと先の山頂駅ですら、取り残されてなくなっている人がいるというのです。一酸化炭素中毒です。そうは言っても、あっという間に爆発的に火が燃え広がったら、分かっていたとしてもどうしようもありません。煙もくもく火がぼうぼうの状況で、火元を突っ切って脱出するなんて、できることではないでしょう。結局窓から助けを求めるしかなさそうです。2階なら飛び降りらるけど、3階から飛び降りるのは、相当の勇気と大怪我を伴います。追い詰められれば3階からでも飛び降りるかな。一部報道によると、犯人は、2012年に茨城県でコンビに強盗を起こして、出所後更生保護施設に入所中だった、らしいのですが、(しかし、別報道によればさいたま市のアパートに暮らしていて、周囲とトラブルを起こしていた、とこ報じられています、どちらが正解かは不明ですが)事実とすれば、いったいどこで何をこじらせて、わざわざ京都まで行って放火したのか、意味が分かりません。いや、意味が分かったところで納得も理解もできるわけはないけど。それにしても、川崎の通り魔事件といい、まるで意味不明のこの種の犯罪が続きます。実に理不尽なことです。日本では、米国などのように銃器を使った大量殺人は、銃規制が厳しいのでほとんどありません。刃物では殺傷力に限界がありますが(それでも、条件によっては二桁の犠牲者を出した事例は散見されます)、人の多い閉鎖空間で可燃物を撒いて火を放つ、というやり方は、銃の乱射に匹敵する、場合によってはそれを上回る殺傷力を発揮してしまうのですね。今回の事件も、広い意味では川崎の事件や、さらに言えば秋葉原の事件などの無差別殺人の模倣犯と見ることができますが、さらにこの事件の模倣犯が現れないことを祈るばかりです。私だって、どちらかというとトラブルの発生が多い部署に、この3月までいましたから、いろいろな意味で他人事ではない、と思ってしまいます。
2019.07.19
コメント(3)
-
自らの首を絞める行為としか思えない
JASRACは何と戦っているのだろうか~ジャスラックは、この30年ほどの間に、著作権使用料の請求先を、演奏家、歌手、レコードCDの制作者、放送、雑誌、新聞、書籍のような商業的なマスの媒体から、有線放送、飲食店の店内音楽、ダンス教室、商店街のBGMに至るまで、ありとあらゆる個人に拡大してきている。加えて、音楽ファイルが記録され得る媒体に、音楽が乗せられることを想定して、CD-RやDVD-R、ハードディスク、果てはスマホやパソコン本体にあらかじめ補償金を徴収するシステムの確立を画策していると言われる。~さて、このたびジャスラックは、音楽教室に職員を潜入させることで教室内での音楽の扱われ方を調査する手段を採用した。《JASRAC側が東京地裁へ提出した陳述書によると、職員は2017年5月に東京・銀座のヤマハの教室を見学。その後、入会の手続きを取った。職業は「主婦」と伝え、翌月から19年2月まで、バイオリンの上級者向けコースで月に数回のレッスンを受け、成果を披露する発表会にも参加した。》いったいいつの時代のゲシュタポのやりざまだろうか。これほどまでにあからさまなスパイ活動を堂々と敢行して恥じない組織が、自分たちの主張に耳を傾けてもらえると信じている姿を、いまはじめて見た気がしている。ジャスラックが潜入職員を立ててまで立証せんとしていたのは、ヤマハの音楽教室では、「音楽」がまるでコンサート会場でそうされているように、生徒によって「鑑賞」され、「享受」され、金銭を媒介する手段として「流通している」、ということなのだろう。というのも、ジャスラックとヤマハの間で争われている訴訟では、現在、教室内で演奏される音楽が、演奏技術を伝えるためのものなのか、それとも「鑑賞目的」なのかという点と、もう一つは、教室に通っている生徒が、営利目的で演奏を聴かせる対象としての「公衆」に当たるのかであるからだ。ジャスラックは、レッスン時に試奏されている音楽が、「事実上コンサートの音楽として」流通し、生徒たちも「有料入場者たる聴衆に近い聴き方で」その音楽に向き合っていると主張しているわけだ。さてしかし、音楽教室の側の立場からすれば、講師が全力を尽くして最高の演奏を披露しようとするのは、教育者として当然の姿勢だ。というよりも、どんな分野であれ、他人に何かを教える人間が、全身全霊でその任に力を尽くすのは、「教育」の大前提だ。(要旨・以下略) ---JASRACのこの行動は、さすがに各所にて驚きと怒りをもって迎えられているようです。ただ、JASRACのこれまでのやり口を見ると、最初は客を装って来店して営業状況を観察し、しかる後に音楽著作権使用料を請求してくる、というのは、ある種の定型パターンのようです。今回のやり口も、だから特に真新しいものではなく、これまでやってきたことの延長線上にすぎないとも言えます。だからといって、そのようなやり口を許容する気には、とうていなれませんけどね。当ブログでは、これまで音楽著作権使用料をめぐる問題を度々取り上げてきており、音楽教室からの徴収の話についても、過去に記事を書いたことがあります。その中で私が何度も指摘しているのは、著作権使用料が正当な権利者にきちんと支払われるものなら、払うことにやぶさかではない、ということです。ところが、現実には「包括契約」という丼勘定の契約では、具体的が楽曲名を一切把握しないのだから、正当な著作権者に使用料が支払われるはずがないのです。そもそも、音楽教室の場合、すでに著作権の保護期間が切れている古いクラシック曲が教材に使われる割合が、世間一般の音楽需要に比べてかなり高いと思われます。ましてや、CD-Rなど記憶媒体に対する一律補償金は、言わずもがなです。そのように集められ、正当な著作権者に支払われなかった使用料はどうなっているのか、結局JASRACが恣意的に配分を決めている、もしくはJASRAC自身の利益となっている、そのいずれかでしょう。もっとも、JASRACがこのようになりふり構わず取り立てに走る背景には、音楽産業全体のパイの縮小(従って著作権使用料の現象)があるのでしょう。音楽CDの売上減少が言われるようになって随分になります。代わりにオンライン配信が伸びているものの、金額的にはCDなど物理的メディアより安価ですから、当然著作権使用料も減ってきているのでしょう。その事情は分からないことはありませんが、だからと言って理屈の通らない、理不尽な請求が容認されてよい、というものではありません。だいたい、音楽教室は音楽産業、音楽文化の重要な担い手です。音楽著作権は、基本的には作詞作曲者が持っていることが多いですが、作詞作曲者だけでは音楽を流通させることはできません。演奏者がいて、初めて音楽は音として視聴者の耳に届きます。その演奏者は、大半が「レッスンプロ」でもあります。実際の収入は演奏活動よりレッスンの謝礼の方が多い、という演奏家の方が多数派かもしれません。ヤマハのような大企業が、JASRACに著作権使用料を払ったからといって倒産することはないでしょうが、費用負担の増は、結局謝礼の値上げか講師の待遇を落とすか、で吸収するしかなくなります。どちらにしても、音楽家(実演家)にとって、かなり死活的な影響を与えるはずです。JASRACは、その事業の目的として音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与することと自称しています。しかし、音楽教室からの著作権使用料徴収は、音楽文化の普及発展どころか、その重要な担い手であるはずの演奏家には、悪影響しか及ぼしません。それのどこが「音楽文化の普及発展に寄与」なのか、私にはまったく理解できません。むしろ、音楽著作権ビジネスの収益確保のためには、音楽文化の発展なんてどうだっていい、そのような意図すら感じてしまうのです。それは、結局巡り巡って、音楽文化の衰退と産業としてのパイの縮小しかもたらさない、長い目で見ればJASRAC自身の首も絞める行為としか思えません。
2019.07.17
コメント(0)
-

南アルプス北岳
金曜の夜行で、高校時代の同期など3人で南アルプス北岳に行って来ました。当初予定では白峰三山縦走の予定だったのですが、この3連休、初日以外は天気があまりよくない予報だったため、急遽予定変更して、行き先は北岳のみとしました。実は、初日に撮った写真は、とある事情でほとんど撮影に失敗、あとで画像補正で何とか復元したものの、あまりよい写真はありません。2日目はちゃんと撮れていますが、残念ながら2日目は悪天候、というわけで、今回は良い写真がほとんどありません。初日の午前中はよい天気でした。大樺沢から右俣に入って少し行ったところから大樺沢を撮影。しかし、天気は上々だったのですが、私はどうも最近の運動不足のせいで歩くスピードが伸びず、もう1人もあまりスピードが出ず、小屋泊まりにも関わらず、かなりゆっくりペース。眼前に鳳凰三山の薬師岳と観音岳。ハクサンイチゲツガザクラと思いましたが、葉の形状からコメバツガザクラのようです、と書いたのですが、更に調べると、どうやらイワウメのようです。訂正します。仙丈岳。北岳へのこのコース中で一番の難所はここでしょうか。特段困難というわけではありません。翌日、悪天候時にここを下るのは、往路よりは大変でしたが。ハクサンイチゲの群落があちこちにありました。後述するシナノキンバイに次ぐ勢力、という感じです。タカネシオガマ肩の小屋に1時過ぎ到着。広河原を7時過ぎ頃出発したので、6時間かかったことになります。昼食、一休みの間に雨が降り出してしまいましたが、せっかくここまで来たので北岳山頂へ向かいました。私自身は、1993年に始めて登って以来、北岳は実に7回目(間ノ岳3回、農鳥岳2回)なのですが、1人は30年ぶり2回目、もう一人は初めてなのでした。雨といっても、このときはそんなに大降りだったわけではありません。山頂には大勢の登山者がいました。山頂着。このあと、夕方くらいまでは時々雨が降る程度でそんなに激しい雨ではありませんでしたが、深夜になると台風直撃か?と思うような凄まじい雨。明日、こんな雨のままだったら下山できるのか、などと不安がよぎります。ちなみに、この日の北岳肩の小屋は、夕飯が4回、各回48人ずつ(8人がけ座卓6つ)最後の回だけは若干少なかったので、食事付宿泊者が160~170人くらい、他に素泊まりがおそらく20~30人はいたはずですし、テントも30張り程度ありましたから、合計では200人を超える人がこの場所に宿泊したことになります。山頂向こう側の北岳山荘の方が小屋の規模は大きいし、テン場も広いので、そちらの方が確実に宿泊者は多いはずなので、この日北岳に泊まった登山者は500人を超えていたはずです。しかし、あの激しい雨の中のテントはきつかっただろうなあ。(私も、何回か風雨の中のテントは経験していますが、どう転んでも快適ではありません)しかし翌朝、雨は相変わらずですが、深夜の激しい降りは収まり、6時半頃小屋を出発した時点では、小雨程度になっていました。もっとも、その後雨は降ったり止んだり、一時的にはちょっと激しい振りもありました。この日は写真はまともに撮れましたけど、そんな天気なので風景写真はほとんどありません。ハクサンイチゲミヤマキンバイ同じくミヤマキンバイ。バラ科キジムシロ属だそうです。キバナシャクナゲ。キバナと言っても、かなりはっきり黄色いものからほとんど白いものまで個体差があります。この花は、雨に濡れているせいもあって、ほとんど黄色くありません。右隣はイワウメのようです。(当初コメバツガザクラと書きましたが訂正します)シナノキンバイ。先ほどのミヤマキンバイと、名前は同じ「キンバイ」とつきますが、黄色い花ということだけが共通点で、分類上はかなり違う仲間です。こちらはキンポウゲ科だそうです。初日にもずいぶん撮ったのですが、黄色い花は画像補正がうまく行かず、まともに撮れたのは2日目に撮ったこの写真だけでした。ひたすらシナノキンバイの大群落。悪天候でも、これは見ごたえがありました。登山道の両側にシナノキンバイの群落。右俣と草すべりの合流点より少し上部です。往路は大樺沢から右俣に入りましたが、復路は草すべりから白根御池経由で下山しました。10年使ったゴアテックスの雨具が、透湿性がもうほとんどなくなってしまったようで、着ていても中がびしょ濡れ状態です。この花は現時点で名前が分かりません。草すべりのダケカンバ帯に咲いていました。この写真だとハクサンイチゲにも似ていますが、実際には花びらがハクサンイチゲのように先端がとがっておらず、平たい形状になっています。白根御池。この後、雨の中をひたすら下山、10時半過ぎに広河原に到着しました。バスで甲府に出て、甲府駅から徒歩10分あまりの公衆浴場(でも、天然温泉)で一風呂浴びて、生き返って帰宅しました。それにしても、脚力がかなり落ちてしまいました。ちょっと鍛えなおさないとなあ。
2019.07.15
コメント(6)
-
不正なんてありません
期日前投票 X 不正選挙いやはや・・・・・・。「投票所に備え付けの鉛筆で候補者名を書くと、消しゴムで消して書き換えられるからマジックで書く」みたいなことを大真面目に言う人がいて、以前の選挙の際にそのことを取り上げたことがあります。都合の悪い選挙結果を「不正だ」と叫ぶ困った人たち買収や投票所入場券を譲渡されての二重投票といった不正の余地は、なくはありません。しかし、投票所で投票した後の投票用紙が摩り替えられるとか消えるなどという無謀きわまる不正が、今の日本の選挙制度の下で可能か、机上の空論であれこれ考えるなら、開票所で一度見学してみればいいのに、と思います。また、仮にそんなことができたとして、5票や10票すりかえて、選挙の結果を左右できるのか、と考えてみれば、およそ「バカバカしい」としか言いようのない話です。ところが、今度は新手の「不正の手口」として、「期日前投票は不正の温床だ、夜間に投票用紙がすりかえられる」という話が出てきています(私が気付かなかっただけで、以前からそういう主張はあったようですが)。なんともコメントしようがありません。投票箱には鍵がかけられていますし、投票箱の保管場所だって、施錠されているに決まっているじゃないですか。そもそも、投票用紙の印刷枚数、手交した枚数、残数、投票総数(投票箱に投じられた票の合計数)は、厳密に管理されています。通常は、印刷した投票用紙の枚数-手交した枚数=残数、となり、なおかつ手交した枚数=投票総数、となります。ただし、実際には手交した枚数より投票総数の方が少ないことは珍しくありません。受け取った投票用紙を投票箱に入れず、持ち帰ってしまう人がいるからです。しかし逆に、手交した枚数より投票総数のほうが多いことは理論上ありえないはずです。が、現実にはそういうことが稀に発生してしまうことがあります。誤って選挙人名簿に投票済チェックを入れ忘れたまま投票用紙を手交してしまう、などの原因が考えられます。いずれにしても、何らかのミスであることは間違いないので、1票でもそういうことが起こればマスコミに報道されます。「票をすりかえる」というのは、言い換えれば投票用紙が一部行方不明になる、ということです。投票者に渡していないのに投票用紙が減っているのですから、つじつまが合わなくなります。1票での不整合があればマスコミに報道されるのに、100票も200票も数が合わなかったら、ただで済むはずがないのです。もちろん報道されないでは済まないし、負けた候補が承服しないことは確実ですから、訴えれば選挙無効になるでしょう。投票所と開票所は違う場所だから移動中に票がすりかえられる、なんて主張もあるようです。もしそれを心配するにら、期日前投票も当日投票も変わらないじゃないですか。だって、当日投票だって投票所と開票所は違う場所なんですから。というわけで、この種の陰謀論を真に受けてはいけません。こんなことを言い出したら、「不正を避ける唯一確実な策は棄権することだ」ということになりかねません。私自身は最近10年、いや、もっと前からかも知れませんが、当日に投票したことはありません。全部期日前投票です。何の問題もないし、遊びの用事であっても使える制度なので、投票日当日に何か用事がある人は、気軽に期日前投票を行うことをお勧めします。
2019.07.13
コメント(11)
-
これからどんどん進んでいくのだろう
人口43万人減、過去最大 少子化進み10年連続総務省が10日発表した住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、今年1月1日時点の国内の日本人は1億2477万6364人で、前年から過去最大の43万3239人減少した。マイナスは10年連続。昨年1年間の出生数が最少だったのが大きく影響した。都道府県別で伸びたのは東京圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)と沖縄のみ。外国人は16万9543人増の266万7199人だった。人口が減る中、居住地が東京圏に偏る構図で、少子化対策と一極集中の是正が求められる。名古屋圏(岐阜、愛知、三重)と関西圏(京都、大阪、兵庫、奈良)の落ち込みが大きかった。---日本の人口が初めて減少したのは2005年のことですが、このときの人口減少は一時的なもので、翌年から2年ほどは、ギリギリの人口増が続きました。しかし、2008年に再び人口減に陥って以降は、人口増に転じることはなく、減少幅も次第に拡大しながら現在に至っています。合計特殊出生率は、2005年の1.26を底としてそれ以下にはならず、近年は1.4を少し越える程度の「低値安定」が続いていますが、分母となる出産可能年齢の女性が減っているので、出生数は減っています。そして、現在の社会の仕組みが大きく変わるようなことがなければ、この状況が突然大きく変わることは、現在のところなさそうです。少子化は日本に止まらず、世界の多くの国で共通の現象となっています。日本韓国中国(台湾・香港も)のみならず、タイや北朝鮮すら、合計特殊出生率は2を割っています。ということは、誠に残念ながら、外国のこんな制度を導入すれば出生率は上がるだろう、とは言えないのです。もちろん、出生率を上げるための試行錯誤は必要です。子どもを育てることへの様々な障害は、少ない方がよいに決まっているのです。それで状況が劇的に改善することはなくても、多少の効果はあるでしょうから。しかし、それとともに、高齢化、人口減を前提として社会の仕組みを考えざるを得ないでしょう。国立社会保障・人口問題研究所の一昨年の推計によると、今から34年後の2053年に日本の総人口は1億人を割り、44年後の2063年には9000万人を割る、ということです。そのときの高齢化率(65歳以上の割合)は41%と推計されています。年金を巡る2000万円騒動がありましたが、年金が自分の積み立てた年金保険料を受け取るものではなく、世代間扶養、つまり今現役世代の払う年金保険料は現在の年金生活者のため、今の現役世代が将来受けとる年金はそのときの現役世代の払う年金保険料でまかなう、という建前を維持するなら(もちろん、莫大な額の年金積立金があるから、ことはそう単純ではないけれど)、高齢者が増えて現役世代が減少すれば、最終的には年金給付額を下げるか、受給開始年齢を上げるかしかなくなります。とは言え、年金生活に入るに際して2000万円必要、なんて言われても、そんな用意のある人はさほど多くはないでしょうから、結局は働ける間は働くしかない、ということになります。少なくとも私個人としては、「こうあるべき」という論は論として、そうするしかないな、と思っています。これからしばらくは、子どもの学費が大きくかかる時期ですが、それが済めば、給料が大きく下がっても問題ないですし。ところで、現在でこそ日本では少子化が深刻な問題になっていますが、数十年前には、歯止めなき人口増加が問題となっていました。戦前や、戦後すぐの出生率がその後もずっと続いていたら、日本は今とは逆に増加する人口による様々な問題に悩まされていたはずです。おそらく、そちらの方が深刻な事態に至っていただろうと思います。幸いにして、そうはならずに子どもの数は急減しました。1947年の合計特殊出生率は4.5もありましたが、わずか10年後の1957年には半減以下の2.04になっています。しかし、合計特殊出生率がほぼ2前後で推移していた期間はごく短いのです。1975年には2を割り、77年には1.8も割っていますから、現代社会にとって都合がよい、と考えられる程度の出生率だった時代はわずか20年程度です。これは、諸外国でも同じでしょう。中国はかつて厳しい一人っ子政策で人口増を抑制していましたが、それがなかったら、とても現在のような経済成長はできなかったでしょう。しかし人口抑制が効きすぎて、一人っ子政策を撤廃しても、子どもの数が増えないのが現在の中国です。何故都合よく行かないのでしょうか。私の無根拠な推測になりますが、そもそも現代文明は、人間にとっては不自然なものであり、長期間安定的に維持することが、そもそもできないのではないか、ということです。人類の歴史(旧石器時代から)のほとんどは多産多死の時代です。おそらく、平均的には女性は生涯に2人より遥かに多くの子どもを産んでいたはずです。現代文明の都合上は、子どもの数は2人前後がよいわけですが、生物としての人間は、そんな都合よく出生率をコントロールはできない、ということなのかもしれません。加えて、そもそも人類の出生率なんて、そんなに安定したものではなかったのかもしれません。有史以前、いや有史以降だって、その時々の食糧事情や天変地異の発生などによって、生き残る子どもの数は大差が生じたはずです。食糧事情が安定して、疫病や災害もない時代が続けば、乳幼児死亡率は低く、人口はあっという間に増える、しかし、気象の変化や人口の増えすぎが原因で食料が不足、あるいは疫病の流行や災害などが起こると人がバタバタ死に、人口はあっという間に急減し、その結果食糧事情は再び改善し・・・・・・といったサイクルが繰り返されてきたはずです。だとすれば、出生率(または生き残る子どもの割合)など、そもそも乱高下を繰り返してきたものであって、一定の割合で安定させること自体が不可能事なのかもしれません。いずれにしても、現代社会がいろいろな意味で曲がり角に来ている、ということの反映なのだろうと私は思います。
2019.07.11
コメント(8)
-
狭い、狭すぎる
「安倍礼賛者」にされた左派の論客 リベラルは共闘下手参院選で、少数野党は巨大与党に共闘で対抗しようと必死だ。一方で、大きな争点の消費税ひとつとっても政権を批判する知識人の意見はまとまらず、「身内」どうしで反発し合っている。左派、リベラルが一枚岩になれないのは、なぜなのか。立命館大学の松尾匡教授(理論経済学)は、安倍政権への厳しい批判で知られる左派の論客で人気も高い。しかし、ツイッターやブログで厳しくたたかれることが、まれではない。「自民党や維新の党の協力者と同じ主張を取り続けた」など、鋭い言葉を浴びせられる。これらの批判は、政権支持派からではない。味方。リベラル、左派と呼ばれる人たちからの舌鋒だ。松尾さんに直接聞くと、苦笑しながら、批判はかなり気になる様子だった。---まことに遺憾ながら、私も左翼、いや、もはや自分では左翼崩れだと思っていますが、その端くれとして、左翼陣営の一部に、極度に「狭い」人がいるということは認めざるを得ないと思います。かつては共産党がそういう「狭さ」の代表格だった時代がありました。自民党を非難攻撃するのと変わらないトーン、下手をするとそれ以上の激しさで他の野党も攻撃していたものです。当然、国政選挙では、沖縄を除いて他党との選挙協力は皆無でした。自らは常に正しい、他党はすべて間違っている(もちろん、政党たるもの、ある程度までは「わが党がもっとも正しい」という意識を持っていて当然ですが、程度というものは必要でしょう)という態度は、しばしば「唯我独尊」などと揶揄されたものです。もっとも、共産党だけに全面的に非があったとは言い切れません。野党の中でも最左派であった共産党を敵視するほかの野党も少なくなかったし、国会の外では、逆に共産党より左側にいる、新左翼からのの激しい敵意にもさらされていました。そういった状況が大きく変わったのは、2015年、安保法制の強行採決を契機として、共産党が他党との共闘路線に全面的に路線変更したことによります。それ以降、共産党の側は、ホンネでは色々不満はあるに違いありませんが、よくそれを押さえて、野党共闘を優先しているなと感じます。ところが、そういう大政党の動向が大きく変わった一方で、左派陣営の一部には、以前とまるで変わらない「狭さ」を持ち続けている人がいます。共産党を唯我独尊だったと書きましたが、政党間の協力関係はともかく、有権者との関係では、唯我独尊だったわけではありません。もちろん、それは他の党も同じですが(少なくとも中選挙区時代は。現在はかなり怪しくなってきました)。党の公式見解と少しでも意見が違ったら反党分子だ!などという態度を、有権者に対して示したら当選なんかできるわけがないのだから当たり前です。しかし、選挙で洗礼を受ける必要がない「熱心な運動家」の中には、ごく一部ながら首を傾げたくなるような人がいることは、残念ながら否定しようのない事実です。自分の意見と寸分でも違うと全面否定して敵認定する人、過去の遺恨を延々と根に持ち続け、しかもそれを第三者にまで共有を求める人。リベラルとは寛容の精神に基づく主張のはずなのに、欠片ほどの寛容じゃないじゃん、と思うことは、正直言ってあります。もちろん、ごく一部です、人数的には。しかし、そういう人に限って声が大きかったりするので、影響度(悪影響度)では必ずしもごく一部とは言えなかったりします。見たところそれはネトウヨ陣営も同じですけどね、ただネトウヨ陣営と同レベルのことをやっていたのでは勝てないだろうと思うのです。そういうわけで、引用記事の後半部分がどんな内容か分かりませんが、前半部分を読んだ限りは、「そのとおおり」と言わざるを得ません。そういう人が、「味方」であるはずの人物の、ちょっとした不一致点、気にくわない点を見て「安倍の手先」などと叫ぶのでしょう。自分と半歩でも主張が異なれば不倶戴天の敵、というのでは、あまりに狭すぎます。そのような政治的純血主義で、本人の自尊心は満たされるかもしれないけれど、支持を広げたり、目標を実現することは不可能と言わざるをえないなと私は思います。敵を味方にしていかなければならないのに、味方を敵にすることしかできないようでは、先細り以外の結末はありません。
2019.07.09
コメント(4)
-

バンドネオン
昨日、先週の演奏をアップしたところですが、その中で新しい楽器が加わっているのにお気づきでしょうか。バンドネオンです。バンドネオンというと、単語のイメージが強いですが、タンゴのために作られた楽器というわけではありません。というより、バンドネオンはドイツで発明された楽器で、アルゼンチンでは製造すらほとんどされていません。楽器もみんな輸入されたものです。アルフレド・アルノルドというメーカーの製品がプロには好まれているようです。で、当然のことながら、アルゼンチンではフォルクローレの演奏にもバンドネオンが使われることは多々あります。現在のタンゴ楽団の典型的なスタイルには、ギター(クラシックギター)は入っていませんが、フォルクローレはギターが基本なので、フォルクローレの場合はギターとバンドネオンとボンボ(太鼓、上記の動画には入っていませんが)、それに場合によってはバイオリンやフルートというのが標準的な編成になります。ケーナやサンポーニャは?実は、アルゼンチンではこれらの、いわゆるアンデス系の楽器はかなり異端です。しかし、生まれ故郷であるドイツでは、第二次大戦以降演奏人口が激減し、製造するメーカーもなくなって、ほとんど絶滅状態です。現在では、新品のバンドネオンはごくわずかのメーカーで受注生産するだけ。しかも、プロは音色などの問題から、新品のバンドネオンは好まず、前述のアルフレド・アルノルドのバンドネオンの中古(いずれも製造から80年以上経っている)を使っているそうです。というわけで、バンドネオンはその存在自体が骨董品、というわけです。アルゼンチンで使われるバンドネオンは、同じキーを押さえていても、蛇腹を引くときと押すときで音が違うタイプです。しかも、キーの配列はまったく規則性がないのだそうです。これは、キーが少しずつ増設されるる(つまり音域が広がる)度に、元のキー配列から場当たり的に新しい音域のキーを継ぎ足していったことに原因があるようです。そのため、「世界一難しい楽器」という評もあるとか。で、この楽器と一緒に演奏するなら、前述のとおり、ケーナやサンポーニャよりは、こちらの楽器の方が合うわけです。うん、なんだか普段演奏するボリビアのフォルクローレとは、思いっきり雰囲気が違いますが。ところで、このバンドネオンの祖先に当たるのが、コンサーティーナという楽器です。見た目からも明らかなように、アコーディオンとも近い楽器ですが、アコーディオンからコンサーティーナが派生し、それを更に改良したのがバンドネオン、という流れになります。正直なところ、バンドネオンを自分で演奏したいと思ったことはありませんが、コンサーティーナ(南米ではコンセルティーナと呼ばれるほうが多いかな)は欲しいと思ったことがあります。ボリビアの、古いスタイルのフォルクローレに使われることがあるからです。動画中でコンサーティーナを弾いているのは、ロランド・エンシーナス、現在のボリビアでナンバーワンのケーナ奏者であり、かつ、おそらくコンサーティーナの第一人者(演奏者が少ないから、ですけど)でもあります。コンサーティーナは、バンドネオンよりずっと小型で持ち運びも容易です。多分、弾き方もバンドネオンほど難しくはない、だろうと思います。ただ、ケーナ、サンポーニャ、ギター、フルート、チャランゴ、マンドリン、これ以上演奏する楽器を増やしても、練習時間が取れないので(上記のうち、チャランゴとマンドリンはほぼ楽器に触っていないし、最近はギターすら怪しくなってきました)断念しましたけど。
2019.07.07
コメント(4)
-

6月23日演奏の御報告
だいぶ遅れてしまいましたが、6月23日に中野区哲学堂公園で演奏した際の動画をアップしました。同じ曲目で午前と午後の2回演奏しましたが、小さな会場で立ち見の出る盛況でした。案内看板「あなたのサンバ」、アルゼンチンのアリエル・ラミレス作曲によるサンバです。(サンバといっても、ブラジルのSambaとは別物のZamba argentina)昨年からバンドネオンがグループに加わっておりますが、こういう曲は、バンドネオンがあると最高にいいです。(自画自賛)「トリニダーから」この曲は4月にも演奏しています。そのときより私自身の笛は調子がよいかな。♪トリニダー(ボリビア東部低地の街の名前)から荷馬車に乗ってやってきた、時間もかかるしお腹もすくけど、命を落とす危険はないよ、というような内容の歌です。一見牧歌的な歌ですが、実は、断崖絶壁を通過する「ユンガスの道」の危険を歌った歌です。この場所では、今後も演奏の予定があります。
2019.07.06
コメント(0)
-
れいわ新撰組は日本のPodemosになれるか
れいわ山本太郎氏、比例区で出馬 特定枠にALS患者ら政治団体「れいわ新選組」の山本太郎代表は3日、東京都内で記者会見し、参院選で比例区から立候補することを表明した。前回参院選では東京選挙区から立候補して当選した。山本氏は「6年前と同じ1議席でいいのか、私は納得がいかない。1議席をより増やせるという市民の力を示していく必要がある。目標議席は5。政党要件をクリアしたい」と述べた。また山本氏は、比例区で個人の得票に関係なく優先的に当選できる「特定枠」を活用することも表明。1位に筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の舩後靖彦氏、2位に重度障害のある木村英子氏を充てる。--山本太郎の比例転出の観測はあったので、それ自体に驚きはありませんでしたが、特定枠(その制度自体、実は恥ずかしながら一週間くらい前に知ったばかりなのですが)を自分以外の候補者2名に利用する、というのは驚きでした。だって、れいわ新撰組が比例区で3議席以上取れないと、自身は再選できない、という意味ですから。絶対の自信があるのか、捨て身の作戦かは分かりませんが、山本自身に議員の座に強い執着はなさそうです。多くの議員は「落選すればただの人」ですが、山本太郎はすでに抜群の知名度を持っているので、落選しても自らの活動に支障はないからかもしれません。れいわ新撰組がどの程度票を取れるかは現時点では判断が付きませんが、山本太郎が東京選挙区から出馬していた場合、再選は有力、という見方が多かったようですし、主に敵対陣営(具体的には池田信夫など)から、勢力伸張への強い警戒感が示されているので、勢力が拡大傾向にあるとは見られているようです。確かに、短期間の間に2億円という寄付金が集まったのは、尋常ではありません。その山本太郎は、6年前は反原発を主張して当選しましました。現在でも脱原発は山本の主要な主張の一つではありますが、それよりも格差問題、反緊縮という主張により重きを置くようになってきているようです。その選択は、おそらく正しい。加えて、山本は旧来の野党、左派、リベラル層支持者の票を取る(言い換えれば他の野党の票を奪う)ことではなく、自公支持層の票を取ることを念頭においているようです。もちろん、その見込み通りになるかどうかは分かりませんけど。れいわ新撰組という党名(元号と「新撰組」という名前)自体、旧来の左派層から支持を得ようと思ったら、まず考えない名前でしょうから。東京選挙区に創価学会員を擁立、ということも、実際の効果はともかく、公明党票を奪いたいという意図は感じます。これらの策が狙いどおりに行くかどうかは分かりません。ただ、うまく行くことを大いに期待しています。うまく行けば、ギリシャのツィプラス首相率いる急進左派連合、スペインのパブロ・イグレシアスのPODEMOSのように、既成の左派政党を凌駕する存在になれるかもしれません。もっとも、現状では強固な組織があるわけではなくすべて風任せとならざるを得ない点が弱点ですが(日本においては、それはれいわ新撰組に限らず、公明党と共産党を除くすべての党が構造的に抱える欠陥でもありますが)。私のおぼろげな記憶では、前回山本太郎が東京選挙区で当選した際、ポスター掲示板にポスターが貼られる早さは、主要候補の中では山本太郎がもっとも遅かったです。有力候補と言われる人たちは、基本的に立候補届け出をしたらその日の午前中にはポスター貼りを終えていますが、山本太郎はそうではありませんでした。それでも当選できたのは、それだけ強い風が吹いたということですが、全国規模で選挙を戦うなら、それでは厳しいだろうと思います。でも、とにかく期待しています。
2019.07.04
コメント(36)
-
勝手にバックアップ
先週、gmailが受信しなくなっていて、なんとなく気になりつつも、ニフティのメールは受信しているのでそのままにしておきました(ニフティメールからgmailに転送しています)。先週末、とあるグループの練習の際メールをまったく受信していないので、やっと思い腰を上げて調べたら、何とグーグルアカウント15GBを使い切っている、というのです。そのせいでメールが受信できなくなったようです。だけど、そんなに大量のメールをやり取りはしていないのに何で???と驚いて更に調べると、gmailは1GBちょっとしか使っておらず、グーグルフォトが大量の容量を喰っていることが判明。写真をアップロードした覚えなんかないのに、と思って調べたら、グーグルフォトって、初期状態で、勝手にタブレットで撮った写真をグーグルアカウントにバックアップする仕組みなのね。まったく気が付いていませんでした(気付くの遅すぎですが)。タブレットを買い換えたときから、タブレットで撮った写真、更にデジタル一眼レフで撮った写真もSDカードをタブレットに移し替えた際に、どんどんクラウドにバックアップされていたのね。どうりで最近通信容量が無茶苦茶喰うようになったな、と思っていたのですよ。そういうことだったのか。まったく余計なことをしてくれるよ、グーグルは。そんなことで通信容量を喰うことも、写真を知らない間に無差別に全部(私一人しか見られないアカウントとは言え)ネットにアップすることも私には許容できない。ところが、グーグルフォトの同期をさせない設定が分からないのです。タブレットでの写真の閲覧は「ギャラリー」を使っていて、グーグルフォトは、2-3回立ち上げたことがある、という程度で、ほぼ使っていませんでしたから。なので、面倒くさいのでタブレットからグーグルフォトをアンインストールした。なくて困ることはなさそうなので。こうやって勝手にデータをクラウド上にバックアップするアプリは、他にもあるのかなあ。勘弁してほしいです。
2019.07.02
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1