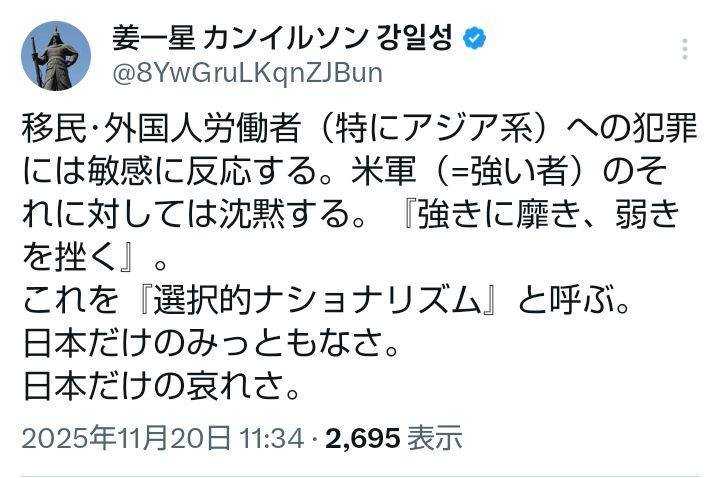2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2012年07月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
2つのカレンダー
販売促進には、大きく3つの原則があります。1は、最終到達点として販促しなくても売れる状態の構築。 その理想としてそのためになにを今為すか、という戦略的側面。2に、変化しないものと変化するものを、きちんと押さえ区分して対応する側面、3に、限りなく個別対応する。その個別対応こそ、周囲に喜んでもらうことで企業が支えて頂く、という企業の願望が成就するためのおそらく唯一の途だと考えています。 この3つの戦略の具現そのための一つのツール(戦術))として、販促カレンダーを提案したいと思います。 これには大きく分けて2つあります。まず人・企業別のカレンダーです。レディズショップ「よしだ」さんがやられている「誕生日カレンダー」、お米屋さんの「米びつカレンダー」など。最高のモデルは、はお医者さんのカルテだと思います。 もう一つは地域カレンダーです。バレンタイデーとかお正月などのカレンダーではなく、自分たちの居住する地域行事や集落のイベント、たとえば会合、お祭り、市町村選挙、運動会、結婚式などを押さえ、それに対応するためのカレンダーです。地域で運動会やお葬式があれば売れる物も売上げも変わるのですから。
2012.07.30
コメント(0)
-
うまくいくコツ
おはようございます。 今年は、天候が不順で、春が短かったのか、梅雨が長かったのか、そして梅雨明け後の、この暑さ、とここまで書きながら、またもふと思いました。人は自分の感覚に合わないと、「異常だ」と言っていますが、言われている気候からみたら、「どうして人間どもの基準や都合に、おいらが合わさねばならないのかえ?」と言いたいところでしょう。 人は、人間社会という枠の中で、人間を中心に、しかも人間以外を擬人化して見、考えている。さらにです。まずは他人ではなく、この自分を中心に、自分を基準として、人そして、世の中のあらゆることを計ります。人が、自分の基準で、自分では計るのですから当然、自分に甘く、自分以外に辛くあるいは、売れないのは「景気のせい」、「天気のせい」と、自分は正義の味方、月光仮面、怪傑ハリマオ、水戸黄門・・・と置いた上で、他者、自然すらもときには擬人化、悪者として、そちらへ責任転嫁するきらい、癖があります。 しかし、いかにそうしたことに長けていても、「変化するもの」を「不変のもの」に変えることはできない。 だから、意識して、ここに意識を置き、ものをきちんと押さえ、さらに変化を読んで、対応することが、生きることでの大原則と、私は考えています。当然、販売促進(正確には購買促進)も、それに則することが、うまくいくコツです。
2012.07.29
コメント(0)
-
迷うなかれ、同族会社
事業はゴーングコーサンである。つまり、一時的な成果のみをよしとしない。当然ゴーングコーサンな企業創造、構築が本来経営者に与えられた命題の一つになる。だから一過性的な業績を見て、成功といえるものではない。それが最近は今の為に先を犠牲にするサラリーマン経営者が多いが、それは大企業の経営者が自分の在任期間の業績をにらんだ戦略に倣うもので、おろかな考えと言わざるを得ない。彼らには長期戦略思考が欠けている点、経営者としてとうてい範にできない輩であるからだ。もとより同族会社は、孫、ひ孫まで睨んだゴーングコーサン的な体質と機運を持っているのである。胸を張れ、同族会社社長そして迷うなかれ、.ヒイヒイ孫以降も栄え続ける超長期戦略を掲げ、邁進せよ!
2012.07.28
コメント(0)
-
繁盛企業になるには、
1.未来永劫の繁栄・繁盛企業を構築したい。2 地域から尊敬され、支えられる企業を創りたい。 そうした想いを理念に、具現の方向を戦略に、組織に染み渡らせるどう考え、どう動けば消費者が支持いただけるのかを、各自が実践できるようにする 経営理念と戦略がないか希薄な企業。理念と戦略を共有している企業。これが盛衰の分岐です。 ・理念と戦略が全員に浸透することで知恵とエネルギーが一元化し、巨大なエネルギーになります。 ・理念と戦略がないと、いくら人材がいて努力をしても知恵とエネルギーが分散し、働きになりません。・理念と戦略が浸透している企業の喜び現象・1、お客がお客を招く。 必要な情報が集まる。2、状勢変化への対応が的確になり、3、お店が年々進化し 進歩発展してゆきます。4、そして未来永劫の繁栄・繁盛が約束されます。 ・理念と戦略がないか、希薄な企業の嘆き現象・1、やらなくてよいことで忙しい、 金と努力が無駄になり疲れる。2、不平と愚痴が増え、仕事が楽しくない、3、だから、お客が背を向け始めます。4、今衰退している企業は、 そうしたモデルと見て良いと思います。では、理念とは何でしょうか、戦略とは何なのでしょう。それは簡単に言うと・・・。理念は経営者の強い想い、情念。戦略はその想いに方向と勢いを与える、いわば風。想いを、見える形に為す。これを仕事といいます。 1-まず、やりたいこと、伝えたいことを書き出しましょう。 2-その中からもっとも重要なものを、わかりやすい表現でコピー化をします。 3-それらを1-5ぐらい経営理念として音読しながら清書して仕上げます。 4-次にそれを実現するための戦略をそれぞれいくつか考え練り上げます。 理念と戦略で貴企業の進む道が明快になります。スタッフはそれを具現するために各自方策を考え、働くことになります。 繁盛企業では、アルバイトに至るまで理念や戦略を受けて、自分がどういうことをなしたか実にうれしそうに語ってくれます。まるで自分が経営者という感じで話してくれます。理念と戦略は、組織全員が喜びと楽しさと成果とを共有するために必須なものだと私は思います。
2012.07.27
コメント(0)
-
ハウツー経営者の行く末
ハウツーは、ツールに分類されるものである。だから本に、ハウツーものと,そうでないものがあるのは当然である。 時代や時流、用途によりツールが変わる。変えなければ役に立たない。それに対して後者は変わらないもの、変えてはならないものである。世のすべてのものはこの不変のものと可変のものとで成り立っている。 当然、経営も然りである。とりわけ最近の経営者は、ころころと考えや言うことが変わること。 あたかも新しいおもちゃを欲しがる幼児のごとく、経営ツールを次々と取り替えることである。それも雨も降らないのに傘を指す、手の傷に風邪薬の類である。 私の周囲での最近の噴飯事例では、 ○ある大手経営者A氏が主宰していた会の熱心会員が、A氏の会社の業績が悪くなったら、一番にとびだし、別の経営者の主宰する会に入ったこと。 ○一生の師だ、と公言しつつここ数年で3人も師匠を取り替えているB氏、など枚挙に暇がない。 最近の経営者の際立つ傾向を1つだけあげるとするなら、 ハウツー経営者が多いこと、であろう。 信念も戦略もなく、あっても著名経営者の借り物、 さらに理念、戦略とは無関係に、やたらと美味しそうな戦術(ハウツー、ツール)をかき集めて、どうするのだろう。 師や本に、ハウツーを求めるお手経営者の先は、見えている。
2012.07.26
コメント(0)
-
こんなチラシもあるんだ!!
一種のミニ情報誌だから、お客に便利と喜ばれ、さらに仲間の店から喜ばれる。そして、クチコミとなり、拡がる。実はこうした反響がこのチラシの狙い、目的だったのです。 高度の接遇・サービスと地域とのコミュニケーションづくりといったものの媒体としての、このチラシのおかげで、他店が安売り攻勢しているにも拘わらず、この店は、価格競争に巻き込まれず安定した収益を上げ続けている。地域の消費者および仲間の商店との和とコミュニケーションに主眼をおき、かつ業績も上げているといったチラシは珍しいのではなかろうか。 価格訴求型の売らんかなチラシでは次第に働く者の心は荒む。だが、このようなチラシは、店と地域と消費者ともに和みを生む。
2012.07.25
コメント(0)
-
あるチラシの効果。
あるSS店への提案した、チラシのことをもとに、書いている。昨日触れたように、具体的内容としては自店の周囲のグルメ店紹介とか地域催事、たとえばお祭り、花火大会の紹介等のチラシなどなど・・・・。ところでチラシは配布しなければならない。これも一ひねり。新聞折り込みは使わず、もっぱら手配りと個別訪問、それに請求書等の書簡に同封するやり方。入庫した車客に自店のチラシを手渡しするのは当然のことだが、興味深いのはその折、近所のビジネスホテルとか米屋、カレー店、といった他店のチラシやパンフレットも一緒に配布していることである。皆、本心は自店を売り込みたい。それでいててらいがある。だから他の店と一緒の方が楽、と実施した店長の感想である。では効果は如何。一種のミニ情報誌だから、お客に便利と喜ばれ、さらに仲間の店から喜ばれ、しかも持続性がある。時にはわざわざ貰いに立ち寄るお客や、字や地図が小さいから見にくいとアドバイスするお客もいるという。で。実はこうした反響が・・・・・続く
2012.07.24
コメント(0)
-
「螺旋的効果の持続」のチラシ
多くの皆さんは、チラシの出来映えに関心がある。本来は、そうしたことはどうでも良く、狙いは「螺旋的効果の持続」にと考えている。とすれば販売促進の方針は、次の3点。 1-自らを自ら売り込まない。他社、他者を売り込む。 2-地域のお店の経営者から喜んで戴けることを掲載する。 3-地域のお客に役立ち、喜んで戴ける情報提供に徹する。これは、「自分が暖かくなりたかったら、自分の周囲を暖かくすればいい」という私の考えを、ある経営者が販促方針にアレンジしたものである。「地域社会に貢献」、「顧客満足優先」などといった立派な理念を、企業内での朝礼唱和に終わらず戦略化し、これを戦術に下ろし、行動をなし外の人間に見える形になしてこそ、理念のありがたみ、戦略の効用、戦術の効果が得られるということ。そして、その得られた効果こそが外の人の評価の集積されたもの、ということである。チラシすら企業の外のおびただしい人々の応援をいただける形を取ると、これまでの弧線奮闘のチラシなどより遙かに持続的パワーを生むのである。具体的内容としては自店の周囲のグルメ店紹介とか地域催事、たとえばお祭り、花火大会の紹介等のチラシなどなど・・・・。ところでチラシは配布しなければならない。これも一ひねり。以下明日
2012.07.23
コメント(0)
-
そうは、問屋が・・・。
Tシャツを10枚仕入れるつもりが、問屋からまとめて1000枚仕入れると、原価が安くなる、運送費をおまけする、と言われ、余計に仕入れる。 とすれば、1000-10=990 すなわち990枚には、買うお客の見込みがないのであるから、当然のこる。 これは、「見込み違い」ともいわない。残ったら、暖冬異変や不景気や、大型店のせいにして、バーゲンで数字を繕う。毎年、この繰り返し、というのが私の見てきた実態だ。 一例として,記した。こうしたことは、何気ない日常の風景の中で随所に見かけること。 売れるということは、買ってくださるお客様がいる、という当たり前のことすら検証しない謙虚さを忘れた、独りよがりな商人の姿が見られる。 こうしたことを意識に乗せ,日常の所作をほんの少しでも改めれば,ずいぶんと業績は上がるのだが、というのが私の思いである
2012.07.22
コメント(0)
-
よどみに着眼
在庫を絞るといった量の調整といった対策ではなく、流れを早くするところに、力点を置いて工程(流れ)を見てみると、よどんでいるところがわかる。よどみをなくす,フ動脈瘤を発生させない、そこを改善する、そういったお話をしてみたい。 「恐れ入りますが、今社長は会議中なのですが」。自分から時間指定しておきながら、こうである。なにごとも社内事情を優先し、その付けを外部に吐き出す。 その一方で「お客様第一主義」、「人にやさしい経営」これが我が社の経営理念、と鼻を動かしている。 経営理念、スローガン、パーフォーマンスは立派である。 「いゃあ、申し訳ないです。会議が長引きましてね」。 全然わかっていない。こんな調子で、多くの人たちに接してたらどうだろう。些細なことだからこそ口でとがめられないし態度に表せない。 だから鬱積が蓄積され、そうした不満・不評をクチコミしたり、掲示板にカキコしたりしているのである。 うそと思われたら、そこらの会社、あなたのお店でもいい。検索エンジンにかけてみたらいい。 そもそも事業の本質がわかっていない。事業はお客に役に立って何ぼであって、企業内のスケジュールをよどみなくこなすことではない。事業や自分の都合、段取り、事情、ルールに消費者をはめ込んで、言動しているのでは、成立基盤を否定することになる。
2012.07.17
コメント(0)
-
私がチラシを創ると・・・・。
いつも、小理屈ばかり書いていると、空理空論者に見られる。私は実務家である。店舗や企業の事務所のレイアウト変更や、POP、ショウカード作成といった手と足を自分で動かし、やる仕事が大好きだ。 そうした現場での実務、実技といったとこころから、自分なりの理論、原則を考え、展開しているのだが、ここで力んで申し上げても、逆効果だと思うので、本稿は、静岡の大須賀町での「街の瓦版づくり会」でお話したことを記し、実務と理論の結びつけ方を示してみたい。 これまでチラシは、激安価格の目玉商品をちりばめ、それで集客をし、他の商品も買ってもらうことを狙いとしたものが殆ど。 また、その日の売上確保を主とする媒体であるから、即効性はあるが、継続性はない。 しかも、これは売り手側の見方で、それを受け取る消費者にしたら、こうした売上稼ぎや店や商品の売り込みは、辟易。繰り返されるうちに(つまり持続的効果として)押し付けになり、プレッシャーになり、やがて刺激そのものも感じなくなる。こうなると見向きもされない。 ではどうしたチラシが、消費者から歓迎され、その効果が継続されるか。このことについて、これまでたくさんのお店や企業経営者のご協力を得て、試行錯誤を繰り返してきた。以下。その一つ。 静岡県のA市、ガソリンスタンドの丸角商事(仮名)の事例。以前、商業界に紹介されたので、ごらんなったかも知れないが、各店不統一、手書き手作り、単色でなんの変哲のない、むしろやぼったくダサイチラシ、手配りチラシである。 ポイントは、肝心な自店の売り込みは、ない。「発行者 丸角 弥次郎(仮名)」のしたに8つの支店名と分析者として( )書きで店長名が記されているだけである。チラシの殆どの部分は、市内、各支店の近辺の商店や病院等の紹介記事である。 講演で、このチラシを皆さんに見てもらうと、期待が大きかっただけに、「なんだ、これは」と失笑される方が少なくない。続く
2012.07.14
コメント(0)
-
ここです。重要なことは。
何度も繰り返しますが、人は戦略を共有したとき、協力しようという気になり、動くのです。 ここなのですね。組織の本質は。企業が、「地域一番目指すぞ」いや「オンリーワンだべ」、「2兆円企業にチャレンジ」、「勝つぞライバル」、といった内輪の願望を経営計画に折り込んでも、消費者が、... 「すったら、いっちょう、おらが協力するべー」という気になるわけなく、絵に描いた餅の方になる。美味い本当の餅すら消費者はあまり食べなくなっているこの時代に、なんで絵に描いた餅を食べようと消費に奔るでしょうか。もう一度言います。 「ここですよ。重要なところは」。 経営計画、販促計画などなど、自分の願望やきれいなスローガン、テクニックを並べる前に、戦略設定が不可欠なのです。 つまり「消費者が積極的に支持、協力をなすにはどうしたらいいか」、販促なら、お客さんが競って買いに来てくださる、他のお客をクチコミしてくださるには何を為したらいいのか。このことに苦心する。 加えて、このために、このことを組織の皆さんと、どうしたら共有できるか。ここの所が重要なのです。 このやりかたも、とっくに完成しており、ご縁ある経営者にはお伝えしています。
2012.07.13
コメント(0)
-
最低10年は止まっている政治
2004/8/21発信のメルマガに、私は、こんなことを書いていました。。今朝のニュースで、民主党主の岡田代表が、小泉政権に代わって政党を民主党が目指す」といった報道がありました。 ああ、「戦略」がわかっていない。これではダメと思いました。戦略は、目的のために人をどう動かすか、という要素が不可欠な要件です。「打倒、小泉政権」で、国民が、民主に協力してひとつその方向で動こうか。」となりましようか。否です。国民の大半は、政党はどっちでもいいのです。国と自分たちの生活がより良くなれば。 だから彼、民主党の戦略は、自民小泉政権を上回る国民の支持を得られる"こと"でなければならないのです。それを「打倒」。これは民主党・岡田さん自身の願望と党内向けへのスローガンであって、戦略ではないのです。10年前に書いたこと。岡田さん、あるいは小沢さんに置き換えてもそっくりそのまま当てはまる。ここに私達は,着眼し,驚金場ならないのでは、と今私は驚いています。10年、政治家はまったく替わっていないこと。これすなわち,政治は,この今に最低でも10年は遅れていると。10年の遅れ,止まっている政治、政治家が,国をリードしている。それがどんないおそろしいことか。これが現状の日本であること。
2012.07.12
コメント(0)
-
誤解でなく正解
内心の怒りは事実、ある。それ押さえて、「口にも顔にも出さない」から、相手は気づかない。気づかないから、当然対応できない。対応できないから、それは継続される。高じて、私の方、彼の相手方が、対応することになる。その対応の方向は、彼を避ける。敬遠する。背を向ける。それで、その人が、何で自分と疎遠になったのか、冷たくなったのか。商談を断ったのか、気がつかないのである。それどころか、「こんな商談を断るなど、冗談じゃない」」と言うことになる。経営は人が成すものである。経営は学問の一つである。だから、前者、人間のどろどろした側面そして、後者、アカデミックな側面とで構成されている、これが経営だ、と私は思っている。後者は、表向き、仮面、建前、バーチャルであり、前者こそ、内面、実態、人の心である。すべからく実態で動く。つまり、私が、「それは誤解だ」と強調しようがしまいが、それがその通りであろうが、なかろうが、相手にとっては、相手の心で感じたものが、彼にとっての正解なのである。また前者、実態と後者、バーチャルの葛藤で、最後に勝つのは、常に前者、実態である。うまくいかない裏面、側面、来店客が減じた理由には、そうしたことがそんざいし、もろにじわじわ企業の盛衰に多大な影響を及ぼしている。
2012.07.10
コメント(0)
-
我未だ,未熟なり。
20数年前、落語家の文珍さんの、落語ではなく講演を聴きに行ったとき、はっと気づいたことがある。文珍さんの話がおもしろくて、途中トイレに行きたいのに結局我慢してしまったのである。席を立つのは観客。立たないのも観客。その意思決定は彼ら。そしてその判断基準は・・・・。これは自分の話がおもしろくない。これは自分の話が役に立たない。そのせいだ、と。これは、講演をやるからには、話家としてプロを目指している私のプライドに支えられ、話のやり方などを学び、精進した。 文鎮さんの話だけではなく、夢中で小説を読んでいるとき、観ている映画に釘付けされているとき。それは生理現象、ネーチャーコールズミーの時ですらそれを拒否する、その魅力。 普段、面談したり、訪問したり、といった折、私が話している最中、再三席を外す人などに対して、私の心中は消して穏やかなどではではない。以前ほど口にも顔にも出さなくはなつたが、「ナンジャイ。俺を軽く見ている」といった気持ちがわく。そういえば、この人は、かねがねから人を待たせている。懇親会、接待など、遅刻、中抜け、早退・・・・。おれとの面談を部下に代理させたこともある。忙しい人だし、そういう習慣を持っている人だと、寛容になろうと努めても、内心の怒りは事実、あるのである。これは私の人間としての度量なさなのだが、それだけではなく、「我が話術、まだ未熟」の証なのだ。
2012.07.09
コメント(0)
-
自尊心と手づから
女将が手づからやり、それをお客が認識したとき、「ああ、私たちはおもてなしをうけている」と感じ、感激する。それは女将に感激しているように思えるが、その実、「おれは高く評価されている」といった自己充足感に、自身が浸り、感激しているのである。その逆。たとえば、人を呼んでおいて、待たす。あるいは、従業員に対応させ本人は出てこない。そう。商談中、5回も6回も、ケイタイが鳴り、その度、席を立たれる。こうしたとき、どう思うか。招かれた、という自尊心からの喜びが、「ああ、私は軽視されているのでは」と気持ちが、ぐらつくのではないか。こうしたことで日常的に、同じお招きをしても人を感激させ舞い上がらせる人もいれば、逆にがっかりさせ、人を侮蔑し、相手の人から恨みを買い、結果として敵を作っていることもある。 同じことをしても人を感激させ舞い上がらせる場合もあれば、逆に、人を落胆、侮蔑し、恨みを買う場合もある。講演の最中に、席を立たれることが時にある。昔は、結構気にして席を立つ人の背中をにらみつけたり、声を大きくしたりして、暗に不快感をぶっつけていた。だが、ここで胸を叩いて言うのだが、それは以前の話。 続く
2012.07.08
コメント(0)
-
手づから
ささやか、ほそぼそだが無料経営相談を続けている。経営と言うけれど、私にしたら100%人間学。経営を一生懸命やっているが、空回りしうまくいかない。どうも、人から疎遠されている気がする。なんでだろ。頑張っているのにどうしてだろう。経営がうまくいかない.経営者としての自分の資質を疑う。ほとんどがこの?(たぐい))の相談ごとのだ。今日は、こうしたことから経営の本質やおもてなし等について話してみたい。六次産業化プランナーの仕事に関連した調べ事があり、江戸下町を舞台にした小説を読んでいて、「てずから 【手ずから】」という語が目にとまった。「自ら」はよく使うが、なぜここで「手ずから」なんだろう?なんで?自ら」とは、どうちがうのだろう、と気になって、辞書で引いてみた。「自分の手で。直接、手を下して、自分自身で、みずから」、とある。わかった。「自ら」とは、微妙に違う。「女将が手ずから」とはいうが、「下女が手ずから」といった言い方はしない。「女将手ずから」といった言い方は、普段女将は滅多に、そうした行動をしない。それをわざわざ、(私に)といったことになる。通常、従業員がやっているようなことを、女将が手づからやり、それをお客が認識したとき、「ああ、私たちはおもてなしをうけている」と感じ、大袈裟に言えば、「感激する」。 続く
2012.07.07
コメント(0)
-
感動も対の関係
私が、企業や人物を見るときの、ものさし以前の「ものさし」は、これです。 もうすぐ、庭のひまわりが、咲き乱れの態になることでしょう。小さな庭が、あのひまわりの花々で埋め尽くされる、それは、それは美しい。豪華ともいえましょう。 毎夏のことですが、通りがかりの人が、「まあ、きれい!」と、声を上げて下さるのです。そのときの対象は、妻では、もちろんありません。 一輪の花でも、無いはずです。花々全体を、「きれい」と褒めて頂いている。 花が喜んでいるか、花の気持ちわかりませんが、明らかなのは、妻がいかにも嬉しそうな至福の顔を示すことです。 物干し竿の私のパンツをみて、「きれい」と褒めて頂いたことはありません。 幸せも、良い気分も、喜ぶにも、それにふさわしい客体の選択が不可欠。 その客体は、主体が選択して決まる。存在していても、見なければその客体は存在しない。 存在して認知したとしても、そこに感動がなかったら幸せとか、良い気分だとか、喜ぶとか、美しいとか感じる、動きがない。つまり無感動、無表情ということになります。 こう考えてみれば、主体だけでは感動は生まれない。客体だけでも感動は生まれない。主体と客体の対(つい)の関係に区々、いろんな要素が関わって、感動が生まれる、ということが、実感できるのではないでしょうか。
2012.07.06
コメント(0)
-
太陽、動く
「私」と私以外の人たち「作り手」とそれ以外の人たち「売り手」とそれ以外の人たち は、対(つい)の関係だ。協力関係なのです。 けして対立の「対」ではない。そう申し上げたいのです。 以前書きましたが、一人一人の人間の脳力はもの凄い。それも天井知らず。ですが一人の脳がものすごいのであれば、たくさんの脳を組織的に活用したら、もっと凄いことになる。そしてその脳力は、有機的システムの中にあればこそ発揮できるものである、ということ。これが、私の確信なのです。 どんなに凄くても、一人より他の多くの脳を活用する方が凄いことになる。また人それぞれが違い、得意不得意があるからこそ、相互に活かしあい、シナジー効果を発揮できる。 だからこそ、その違いを持ち味、得意として社会システムや組織の中で存在し得るし、貢献していけると思うのです。 そうした方へ、方向性を向けて生きていくことこそ、ヘーゲルの弁証法でいう螺旋状の発展の法則、脳力開発でいう進歩発展志向の生き方ではないか。この 螺旋状の発展、進歩発展志向は、人にも企業にも例外なく通用する普遍の原理、といってよいのではと思います。
2012.07.05
コメント(0)
-
花より団子。団子より花。
経営者の意志決定の問題。少なくともそうしたとらえ方が、不幸な事件を少なくできるのではないか、と思うのである。 道徳や倫理の話にしてしまうから曖昧になり、繰り返されるのである。人には,後悔や反省があるが、人ではない企業にはそれらがあろうはずがないからである。談合事件などまさにその典型的事例であろう。ばれなければ、得。ばれるリスクをマイナス計算すれば、やつた方がが得、と考えるから、やっている。これは花より団子の論理である。この倫理では解けないことは明らかなのである。だから、ここはなぜそうした企業存亡の危機を賭してまで消費者を裏切り、背を向けさせる言動をとるのか、さらにその結果、企業の業績は落ちるしあなたの地位も危なくなる。どうしてそんな損と不幸を招く決断をするのか、と、突き詰めることである。私なら、さらにくどくどと追い打ちを掛けて、「企業の命取りになる馬鹿なことをして、どうするの?」。「大切な自分の人生を反故にしたのでは間尺に合わないではないか」と、企業の論理、採算の論理で、冷厳に考えてみて欲しいと、紙と電卓、鉛筆を与えて、計算させ、はなから、問う。「花と団子、どっちが得になりましたか」。まともな経営者なら、いや人間なら、自らの破滅、所属する企業の破滅を、自ら招くことこそ、自分たちの信条としている「採算の合わない投資は見合わせる」という企業の論理に合わないことはわかるはずである。まっとうなら損することを決断するはずがないのである。かねがね思っていること為していることが違うことだから、誰が考えても論理矛盾、自己矛盾には気づいているはずである。結局、そうした人たちは、まともな判断が出来ない人か、あるいは経営のイロハ、企業論理を知らない人、といった方が正解ではないのだろうか。だから、倫理の勉強ではなく、判断学、戦略論、人間学の基本の勉強をぜひとも勧めたいのである。
2012.07.04
コメント(0)
-
それ、企業がやったこと?
正直なところ、企業が不祥事を起して、私ども経営陣も迷惑、当惑しているのでございます。といった論理ではないか。おかしくてしょうがない。この論理だと、車による交通事故での責任は車だということになる。ピストル強盗の犯人は、ピストルであり、そのピストルは殺人鬼だったということになる。実のところ人間と違い、頭も手足も口も耳も、心も感情も、血も涙もない企業が、そうした事件など起こしようがない。起こしていないものに責任も原因もあろうはずがない。企業に倫理感をいうのは、食器に清潔感を教えることと同じだ。くだらないことを,といわないで欲しい。言いたいことは、すべからく人間が判断し行ったことということ。自分が行ったことを企業に責任転嫁かと、揶揄して言っているのである。経営者、あるいはその組織に所属する人が為したことである。そうした人たちの倫理観が欠如していた、というべきであるそれならわかる。わかるが、私はそれを倫理観の問題ではなく、企業としてそうしたことを為すといった選択が、世のため、人のため、企業のため、自分のために、長い目で見て、得だろうか、喜ばしいことだろうか、といった意志決定の問題であると、考えている。続く
2012.07.03
コメント(0)
-
{選択ということ」
太陽は、動く。いや、正しくはこちらの地球が動いているのですから、日の当たる場所が東から西に変わる。花もひまわりのように顔の向きを、太陽に対応して変えてはいますが、我妻のごとく、場を移動させる、といった動きはしません。 変化に対応のこと。例で縷々書いてきました。 対応する、対応しない。ちょっとした対応、ちゃんとした対応、いろいろあり、いろいろあるから「選択の余地」がある。選択がいろいろあるから、得られる結果にも違いがでる。 「選択によって違いが出るということ」。このことに力を入れたくて、くどくどと遠回りしてきました。 要は、私の、この文章を読んでくださった方が、良い選択の一つであったと喜んでいただく、という結果を生み出すこと。これが書いている楽しみで、書く目的であれば、私は良い気持ちになれる、ということ。 そこから、この長話が始まったのです。 つまり、私が良い気持ちになる、その結果を創って下さったのは、大勢の方の選択の結果に違いない。これを言いたかった。 そして、売上は、大勢の消費者の選択の結果というのは、「ここ」に起因していると。続く
2012.07.01
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1