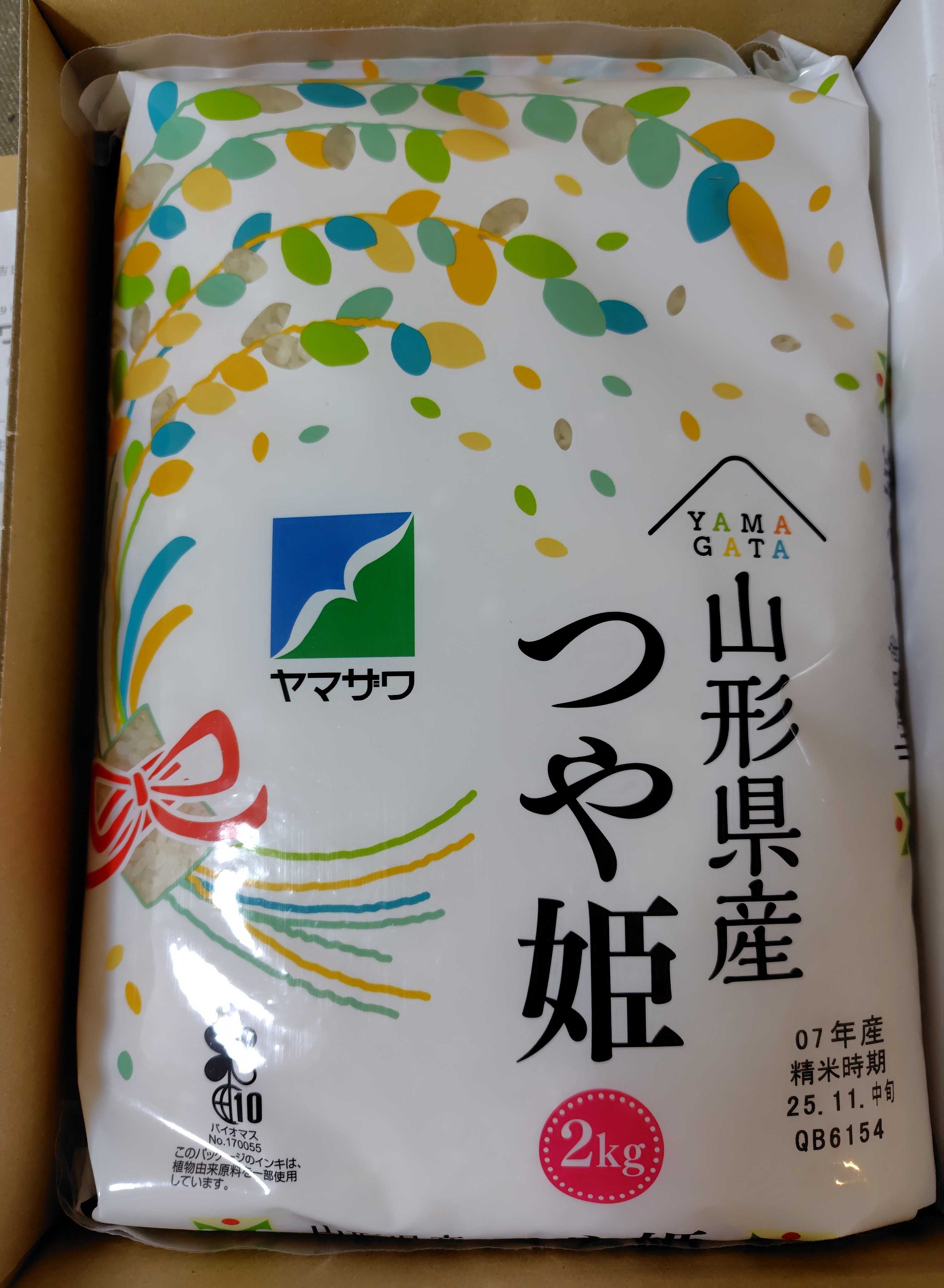2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2012年02月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
根本が抜けている!
諸行無常の世。 人智ではいかんともしがたい情勢の起伏・上下の波がある。 だが、それは当然のこと。だから戦略の範疇内、想定内として、先取り、取り込んで対応することで、その影響をマイナス面は最小に押さえ、プラス面は最大限に活用する、といった柔軟性としぶとさ、これが経営であり、これを考えるのが経営者である。 それを「雨続きで売れませんわ」といっている経営者がいる。 天気は、こちらの都合通りにならない。そんなわかりきったことですら、売れない、不振の理由にするそうした人は、まさに経営者失格なのである。 ましてや、人の心は動かせるのである。ここで念押ししておくが、確かに人が人を動かすことは、難しい。だが、人が人を動かすには、その人が自らの意志でもって、動くように、働きかけることになる。 晴れたら売れ、雨が降ったら、これまた売れる。そのためには、晴れたら下駄、雨が降ったら傘を前面にだしてといった工夫で、消費者の意思決定が購入になるようにを持って行く。 こうしたあれこれ練る、試行錯誤する、といったことが不可欠になる。 言えることは、それらはどうにもならない天候への対処ではなく、心を持ち、心を揺さぶれる人間への対応ということ。人への対応に転換してこそ、可能になるのである。 人の動きへの対応、これまさに経営戦略の根本と考えるが、この根本が経営計画、マニュアルから欠損、あるいは希薄であることが私には理解できないことである。
2012.02.29
コメント(0)
-
誰にとっての強み
繰り返すが、購買決定権は消費者にある。だから比較購買行動を起こす主役、消費者にとっての優位性こそ「強み」でなければならない。 消費者は自分の金を出し購買するのだから、購買決定までにいろいろ比較する。いろいろということは、評価が相対的なものであることを意味する。 では売る側にとっては、「相対的であること」とは、どういうことを意味するのか。 たとえば値段が安いという強みは、よそでより安い店があれば瞬時に高い、という弱みに変わり選ばれない。 品質的に劣っているものであれば安くても、他者がいわゆる「いい商品」を出したら、選ばれる機会が減少する。 この選ばれないという内容には、買い手の行動として2つに分けられよう。 1つは他社商品を購買し当社商品を買わなかったとこと。2に、購買そのものを断念。たとえば時計を買う予定を断念。旅行に振り替えた、といったことも含んで考えたいが、この2つある。 前者の1には、神経をピリピリさせ対応策を講じてはいるが、2の後者にはほとんど関心を示さず、放置状況である。 ここにシェア論の怖さがある。 事業の強みが、1の対ライバル問題である以上、常に事業は不安と不安定さを余儀なくされる。さらに2の後者に対しては、無頓着、無策・無抵抗の状況になる。これが、強みは消費者に対してのものであるべきだ、それに絶対的でなければならない、と申し上げている理由である。
2012.02.28
コメント(0)
-
多くに共通する2つの問題
長く企業活動を診てきて、総じて、あるいは共通する課題が2つあることに気がついた。 1つは戦略に関わる問題である。 企業の戦略は、個々の消費者が自社・自店を選択する意志決定と行動をなさしめるシクミを構築し、それにもとづき実践する、といったことである。 ここで「シクミ」とは、自社・自店を選択する意志決定と行動を起こさせるという戦略に基づく、あれこれの戦術が有機的に結合されたシステム概念であり、一つ一つの戦術のことではない。 ところが現実は、この点で大きく3つの問題が指摘されるのである。(1)戦略がないか、上に挙げた戦略とはことなる戦略を採っている。(2)戦略がないか、あってもそれを無視、あるいはそれに先行し、戦術がどんどん出てきて論議されているといったこと。(3)戦略にも基づく戦術がバラバラである。 ということである。以上3つの問題があるために、時間経過とともに方針がコロコロと変り、そのためこれまでのやってきたこと(戦術)が無駄になるといったことが起き、結局小田原評定の末路に至る、ということ。 2つに、強みに関わる問題である。通常、経営者たちが「自社の強みは、第一に○△、第二に×◎」といった言い方をしているが、それらは同業他社に対しての相対的優位点に過ぎない。これがなぜ問題かというと、これらは必ずしも消費者に対する絶対優位点とは一致しないし、逆に消費者の利益に反することすらあるからである。以降、このことを考えてみたい。
2012.02.27
コメント(0)
-
相手の意志を変えるということ
売上は、売上=客数×売価で示される。 この場合、売価は一部の再販価格指定商品、そしてITの世界でのオークションなどに見られるお客の裁量で決まる、といったことはあるにしても、概ね経営者の裁量で決めることができる。 だが客数の方は、個々客、買い手の意思決定の集合体、買い手の領域のことであり、経営者が決めることはできない。 だから、放置し手いる限り、売上が作り手・売り手の経営者の思う通りいくことは決してない。 その虚数に単価をかけて算出する売上も虚数になる。当たり前である。 しかし経費は、固定経費と変動費と分けられるが、限度限界、そして対外的制約があるものの、ある程度は内輪でコントロールできる。 だが、とりわけ前者の固定経費は、おおむね計画に基づき費消されるし、後者の変動には、売上に正比例し費消される、ということで減益になる。これまた必然である。 売上という言葉の云々の問題ではない。消費者の意思決定により購買が決まっている。そのことを強く意識して欲しいのだ。 すなわち消費者の購買に関わる意思決定を、当方、あるいは自社製品を、選択してもらうためにはどうしたらいいか、というアプローチが経営思考から希薄になっていることを憂いているのである。 だから消費者の意思決定が、自分の企業を選択し購入、という行動に結びつくための条件を考え、それを彼らに見える形で示す、こうしたことが経営にとっての最大関心、そして販売戦略の要諦でなければならない。必死でやっている、頑張っているという声もあろうがそれはたぶんに、「いかに売上を上げるか」ということであって、私の考える本来のものとは異なることを、ここで再度で念押ししておきたい。
2012.02.26
コメント(0)
-
黄昏と夕日
ところで、唐突。ここは、あるひなびた海岸通りの街。夕食までにと、全く人通りのない街を歩いている。寂れ、うらびれた街並みの、どのお店からだろう。ちあきなおみさんの「喝采」が流れてくる。これは朝には、似合わない歌である。黄昏にぴったしの唄だ。この唄は、かって晴れやかな喝采を浴びた歌手が人生の盛りが過ぎ、どさまわりに転じている日々。あるいは華やかなスポットを浴びる舞台でのダンサーの寂しげな姿・・・・・・そうした人生、人の持つ光と影、黄昏、悲哀といったものを見事に映し出している。私は、名歌の一つと思う。唄は刹那的。そして彼女が消えて久しいが、今も私の耳に残るのは、余韻。この唄が、自分の人生と重なるからであろうか。ところで、今歩いているこの街。この街の高度化・近代化事業が完成し、華々しい喝采を受けてテープカットの風景が、TVで放映されたのは18年前の今の時期。借り入れ返済終了まで6年を残して、今この街は、まさに黄昏どき。やがて、明けることのない闇に入る。人生も、事物も、黄昏となれば哀しいものだ、寂しいものだ。東シナ海の遠くの海に、日が落ちる。
2012.02.24
コメント(0)
-
花の命は短くて
戦略には始点がある。いな、先に帰結点があってこそ始点がある、といった方が正しい。始点と帰結点の空間は、時間軸。とすれば、人生の課題は、この始点と帰結点の空間、長さと厚みの二次元の空間をいかに長く、ふくよかにするか、というになろうか。これは経営とて同じこと。要は、経営者の戦略思考の時間軸が、短いか長いかである。またその二次元の空間に、何をなすか、ということでふくよかさを打ち出す。この何をなすかの「何」は大きく2つに分けられる。1つは、自利のため。もう一つは、いわゆる世のため、人のため。択一の、答えは決まっている。自利だけを求めていると、ジリ貧になる。企業が長く豊かに存続し続けるためには、1に経営者の思考は、長く俯瞰的である。2に、世のため、人のためこの2つの条件が充足されてこそ、ゴーイングコーンサーンなのであるから。しかし、目立ち、注目されるのは、短く刹那的な方である。表向きと実際は違うのかも知れないがとかく人は太く、短い人生を華とみて憧れる。花の生涯、花の命は短くて、といったように花にたとえるのは、その心情の表れである。 逆説的、皮相的な言い回しだが、目立たないこと、華やかでないこともゴーイングコンサーンの秘訣の1つになるのかも。
2012.02.23
コメント(0)
-
選択に迷うということ
消費者接点を減じることは、消費者の表情、すなわち顔なりに表れる情の形が、読み取れないということだ。その結果、対応力は弱くなる。しかも企業の対応が企業サイド寄りで、消費者に疎になることも必然的だ。またこのことが消費者にとって、選択肢が増えすぎて、しかも違いが大同小異。個々の違いが判別できず、選択ができず、の状態を生んだということだ。自分の欲しいものが、わからない、見つからないぐらい事実、「もの」はあふれている。が、その中から自分の必要としているものを、見つけることは難しい。これは実際に買物をしてみたらわかること。魚沼産の米俵のなかに、鹿児島産のさつまひかりを一握りいれて、分別せよといった命題を消費者は突きつけられているが如し。消費の現場は、理論に即して動いているのではない。今や、欲しいものがあるかどうか、それすらわからない、まさに「もの溢れの時代」と言える。こうした過剰な選択肢は、迷いを生じさせ、低価格になっても、消費の低迷を生み出した、と言えるのではないか、と私は思っている。
2012.02.22
コメント(0)
-
その日が、この今!
消費者接点が少なくなると、個々の消費者の表情、すなわち表れる情が読み取れなくなる。人は、美味い物を食べたら、頬が緩む。苦い物を口にしたら、苦い顔をする。そうしたことを、直接みることなく、人は美味い物を食べたら頬が緩む、であろう。苦い物を口にしたら苦い顔をする、であろう。といった仮説のまま、検証されることなくものが作られ、販売されることになる。「だろう」のごくわずかの乖離が、やがて大きな乖離となる・・・・。そしてその教養限度を超えた・・。その日が、この今。現象面では倒産、ということではなかろうか。
2012.02.21
コメント(0)
-
賞味祈願がこの今
ある温泉街での仕事。暦上では春なのだが、真冬の冷え込み。それでもかねがねからの報道とは違い観光客が結構いる。私は、例の通りブルゾンだからすぐ風景に溶け込めるが観光客の服装の中で、同行の職員たちのスーツ姿は、この地では、違和感があり、風景を壊している。こんなご時世、こんな時期にしては随分と観光客がいる、と私は思うのだが、宿の女将達は、「とんでもない」と口をとがらせ、「最近の不景気で、風評被害でさっぱりです」と一様に化粧で固めた額に皺を寄せ、マスコミをなぞる。「想い、夢は実現する」という法則が正しいとしたら、彼女達は、「盛況とさっぱりどちらを夢みているのだろう?と皮肉屋の私はからかいたくもなった。潮流として長い時間軸で、事業の盛衰を追ってみると、事業は消費者接点を増やし続けることで大きくなった。そして、事業は消費者接点を減らし続けることで合理化を図かり続けて、利益を増やしてきた。あるいは消費者との距離を遠く、疎にすることでシェアを拡げてきた。旅館の部屋で出される茶菓は、売店のお土産品で今日賞味期限が切れる茶菓。。合理化、省力化とは、総じてそういうことだ。たとえば、人件費を削減しセルフ方式にする。ここでのコスト削減は、直接的には消費者にプラスしない。企業にとっては短期的にはプラスだが、長い目ではどうか。その長期の先が、この今だとすれば、これが、大手セルフスーパー、大手量販店の業態寿命が、この「今」ではないか。同様、このホテルも、あるいはこの温泉地も・・・・。賞味期限がこの今。 続く
2012.02.20
コメント(0)
-
知的財産を奪うもの
うまくいく、うまくいかない。勝つ、負けるその繰り返し中から普遍性の高いものを集約して常勝のノウハウをルール化していく。こうしたものが、学びの本質。ことをなし、うまくいく、行かないを繰り返す、といった体験の繰り返し、積み重ね、そこから学び、創造することが本来。そしてそれらをお互い共有しあうことで、組織、社会の学びとなり、普遍性高いものはルール化され、蓄積される。こうして人は学び、学び合い、成長する。ともに組織、社会も学び、進歩発展していく。さらにそうした社会、組織から個々人は学ぶ。こうした相互の交流の繰り返しで、知恵、文明、経済といったものが、螺旋状に進歩発展していく。そして、その過程で、人、個々が学んだことは知的個人財産から脱し、組織、社会の共同財産化され、蓄積、あるいは消費される。互い学び合い、互恵しあう関係をイメージし、それを広げていくと、そんな風に私には思える。こうしたことを裏返しし、強く言えば、厳密にみて純粋に自分だけで学び得たものが、いったい存在するのであろうか、とも思う。一方、自分で体験せず、学ぶ、といったことを省き、出来合いの教えを外に求める、他人に求める、神仏に求める、といった傾向、ここで繰り返し触れてきたが、このように知的財産の創造には関知せず、ただひたすら、他者の知的財産の取り崩しに勤しむ姿勢はいかがなことか、と思うのである。
2012.02.19
コメント(0)
-
常勝の2要件
たとえば、気象予報士は、先の天気を予測し、伝えたから尊大になることはない。当たったことをことさら誇ることもあるまい。それが仕事であるから、当然である。だが、教師はどうか。親は子供に対してはどうか。占い師はどうか。自分自身が一生懸命に考えているとき、先に答えをいわれ、がっかりした経験はなかろうか。話しをている人の誇らしげな顔をみて、不快に感じた、そうした思いが頭に浮かばないか。教え込むのでなく、それぞれの人に自由に個々のやり方で実践してもらい、個々に自ら「やる」ことで、うまくいくもいかないも体験する。とりわけ、成功体験を欲し、狙い、失敗を厭い嫌う、といった傾向が強い。その結果、どうしても失敗の体験が少なくなる。だからこそ、失敗体験をあえて数多く体験させることだ。以前の話だが柔道の山下泰裕さんから、小さな頃から強いといわれてきた子供ほど、受け身の練習をいやがる傾向がある、と案じておられた話を伺ったことがある。さもありなんとおもう。勝つ練習はしても、負ける練習はしないでは、本当に強くなれないのだ。なぜなら、勝負とは、「勝つこと+負けること」そして、その勝負から、価値を得るには、「勝つこと+負けないこと」この2つの要件を充足する必要があるのだから。続く
2012.02.18
コメント(0)
-
なんでだろう?
大きな黒板に白いチョークで先生が、数式を書いている。生徒が見ているのは、黒板だろうか。それとも数式? こんなことからも、私は、経営にとってすごく大切なことを沢山教わってきた。 大きい黒板より、t小さい方の数式を見ている。なんでだろ? 数式、文字でも良いのですが、これが生徒に、見えるのはなんでだろう?お陰様、つてのは、影のお陰で、日当たりが見える、ってことなんですね。黒板があり、黒いから、お陰様で白い数式、文字が生徒に見える。お日様は実に謙虚ではありませんか。黒板は、縁の下の力もちではありませんか。ホワイトボードに、白いマーカーでは目立たない。ならばなぜ皆、横並び、画一化をめざすのだろう?お日様の謙虚さを見習いなさい、といいたくなりませんか。先生が、一生懸命話ししているのに、上の空、あるいは窓外を見ている生徒がいるのは何でだろう?などなど。
2012.02.17
コメント(0)
-
倒産と言うこと
ところで、倒産には、消費者からみたらもうこれ以上は支えないよ、通さないよ、といった側面があります。これが1つ。 倒産しない企業から見たら、お陰様で俺んちが生き残れるよ、といった側面があります。 この2つの側面虫、前者については既に触れました。で、後者について。 Aというお米屋が倒産したから、今晩からお米が食べられないといったことはありませんから消費者は困ることはない。冷たいようですが、それが現実です。。 問題は、この冷厳な事実が、国などの統制により機能しなくなるといったことがあれば、それは、それは不幸なこととなります。このことは「落ち、こぼれる」の原理のところで触れましたので、ここでは割愛です。 倒産がある。だから倒産しないよう工夫する。工夫を競ってくれるお陰で、消費者は選択の楽しみと、より便宜性を味わえる。 それがまたマクロの消費を増やす。こうしたサイクルこそ、「種」、そして社会、国家、企業の永続的発展の礎にある。 そうしたことを、私は経営支援上の経験から、直観的に、これって自然の摂理かな、と思ったりしているのです。
2012.02.16
コメント(0)
-
終りあれば、憂いなし
恐竜が滅亡した理由三葉虫が絶えた理由を考えてみる。 その場合、 ここで、「良い加減」、あるいは分限、到達点、ゴールといった言葉を、頭に置いて欲しい。それも、始まりあれば終りあり、ではないのだ。 終りを決めておいて、スタートする。いや、終りがあるからスタートするのだ。終りを決めてスタートする。 恐竜は、自分がどれぐらいまで大きくなれば、終りにすると、先に決めていなかった。 そごうは、自分がどれぐらいまで大型にすればそれが限界と、さきに決めていなかった。 三葉虫は、自分たちの種がどれだけふえたら、やばいことになる、さきにと決めていなかった。 ダイエーは、自分たちの支店が種がどれだけふえたら、死点になる、とさきにと決めていなかった 倒産は、上の2つのいずれかを決めていない場合に起きる。 いい加減にしなさいよ、と叱られてから、のではなく、最初に設定しておいて、はいスタート! これが重要なことなのです。終りあれば憂いなし。終り設定していれば、倒産無し。
2012.02.15
コメント(0)
-
分限とつながり
表は裏を削った。裏も、表を削った。その結果は双方にとって恨めしい結果になった。表は、これで憎き裏がいなくなった、と思った瞬間、自分の存在が無く舞ったことを知る。否、知るまもなく消えてしまった。 裏は、これで憎き表がいなくなった、と思った瞬間、自分の存在が無く舞ったことを知る。否、知るまもなく消えてしまった。 排他の論理はここに行き着くことを知らねばならない。否、共存の論理のもとに、繁栄の構図を描かねばならない。地球レベル、自然界という視点で考え、言えば、天敵を失う、あるいは自然の系から離脱することで、天下無敵の世界その種にとってはこの世を制覇した思いに浸れるであろう。 しかし彼らは、上の私の作り話、表裏と同じ運命を迎えることになるのだ。 創造主のすごさは、こうしたことを想定し、ある種が一方的に増えて、この地球が滅びることがないように天敵と系を創ったという、そのことである。 ならば、この今の自分に置き換えて、生き方、経営のあり方を、見てみる必要あり、と、私は、私自身に警告したいのだ。 私は、天敵は、戦略限界点、分限を知ると置き換えている。系はリンク。つながりと置き換えている。 置き換えた上で、もう一度恐竜が滅亡した理由三葉虫が絶えた理由を考えてみる。
2012.02.13
コメント(0)
-
三葉虫消滅の因
消費者が、「自分たちに、貢献していない」、「なくても困らない」、といった判定をくだした結果。「落ち、こぼれる」、「倒産する」 これが調整機能だ。 自分たちの会社では、供給過剰になれば,工場の操業調整をしているではないか。人員過剰とかいってレイオフしているではないか残業カットもそう。 ところが、これがマクロの企業になると、国が嘗ての社会主義国家並ではないにしても、保護政策を採っている産業がある。 こうしたことで調整弁が働くことがない産業、あるいは企業は、三葉虫と同じ運命で、やがて消滅するのでは、と案じているのである。 おそらく、三葉虫には、増え続けることが種の繁栄、という方針しかなく、そうしたことが想定されておらずもともと調整機能がなかったのか、あるいは・・・種ぐるみで、取り外しの令、「それ無視せよ」、の通達を出し徹底させたのか 「俺たち三葉虫族が、天下を取ろうぞ」 「おう、おう!」。 ここに、表裏一体という話がある。 表裏という珍しい木片があって、人々は表を見ては、感服し、裏を見ても感服した。 表は、裏さえなかったらおれだけが褒められる。裏は、表さえなかったらおれだけが褒められる。 それで、表は裏を削った。裏も、表を削った。 私の作り話であるが、その結果は・・・・・・。
2012.02.12
コメント(0)
-
落ち、こぼれるということ
先の三葉虫はその数の増大化により、たとえば彼らの食する食料の需給バランスが崩れたこのこともひとつ、と考えたら、これは経済の「需給と供給の原則」。 先の恐竜は、その巨大化により、その身体組織の、たとえば情報伝達力の鈍化現象が起きたこともその理由のひとつ。 さて、ここで反論があろう。前者。需給と供給の原則とは、コップがあって、コップの要領以上の水を注いだとしても、落ち、こぼれる。 この「落ち、こぼれる」ことによって、コップの中の水は安定する。それで,落ちこぼれる三葉虫が出ることによって、大多数の三葉虫は種を保てるはずだ、と。 ならば、三葉虫には、その原則が機能しなかったのか。考えているが、これ以上は、ダーウインの本すら読んでいない私には答えようがない。 そこで、経営の例で考えてみる。 倒産ということは、消費者がこれ以上は、そういうありかたは通用しない。もう通さんぞ、といった意思表明の選択が多数ということ。 消費者が、「うちらに貢献してへん」、といった判定をくだした結果だと考えたらどうだろう。
2012.02.11
コメント(0)
-
コップの水はなぜこぼれるか
先の三葉虫はその数の増大化により、たとえば彼らの食する食料の需給バランスが崩れたこともひとつ、 と考えたら、これは経済の、需給と供給の原則。 先の恐竜は、その巨大化により、その身体組織の、たとえば情報伝達力の鈍化現象が起きたこともその理由のひとつ。 さて、ここで反論があろう。前者。需給と供給の原則とは、コップがあって、コップの要領以上の水を注いだとしても、落ち、こぼれる。 この「落ち、こぼれる」ことによって、コップの中の水は安定する。それでこぼれる三葉虫が出ることによって、大多数の三葉虫は種を保てるはずだ、と。 これ以上は、ダーウインの本でも読んでみなければ、私には答えようがない。そこで、経営の例で考えてみる。 倒産ということは、消費者がこれ以上は、そういうありかたは通用しない。もう通さんぞ、といった意思表明の選択が多数ということ。 消費者がうちらに貢献してへん、といった判定をくだした結果だと考えたらどうだろう。 ミクロでは供給過剰になれば,時として、工場の操業調整をしているではないか。
2012.02.10
コメント(0)
-
三葉虫と恐竜
三葉虫が、地球を制覇していたに時代があった。そのおびただしい数が、他の種を圧倒していた。それが消えた。 恐竜が、この地球を我が物顔で闊歩していた時代があった。あの巨大さが、他の種を圧倒していたという。それが壊滅した。 このように、ある種が栄華を極め、そして消えていた。なぜか。 前者の消滅の理由は、その繁栄にある。数が増えすぎたことにある、というのが定説。 後者の消滅の理由は、その巨大化にある。大きくなりすぎたためというのが定説。 ミクロでいえば、少なくとも生き物には、ライフサイクルがある。たとえば人は小さく生まれて、徐々に成長し大きくなり、やがて死を迎える。 これは、あらゆる例外のない普遍の原則である。 マクロが、ミクロを総和した集合体ということであるならば、人類は人の総和、集合体ということになり、ミクロの人の持つミクロの原則に支配されることになる。 マクロが、ミクロの総和ではない異なるものと仮定しても、このミクロの原則が、適用されないということにはならない。こうしたことを自然の摂理だ、と断定するには、私の知識は乏しく幼稚的であるのだが。 だが、自然の摂理ではないか、とここで仮説をしたのは、そうした原則が、生き物ではない経済に置き換えられる、と,私は考えているからである。続く
2012.02.09
コメント(0)
-
つながり創り
そう。人も国も、一人では寂しいのだ。気持ちはわかるが、彼らの寂しさを癒すために戦いすら厭わないのだ。その戦いにすら、相手がいる。相手という存在がなければ,その寂しさを紛らわす戦いが出来ないということに、彼らは思いを馳せることはないのであろう。 自分の寂しさを紛らわせるために戦いを仕向け、血が流れることは、絶対に許されないことだ。 つながりが、命、生きていくことの本来。それを無視しては生きていけない。 だからといって、そのつながりを「戦い」に求めることは許されない。 事実そう国家、企業、個々人が生き続けていける歴史を,私は知らない。 つながりは、不可欠。このつながりは,「良い」と「悪い」の2つに分けられる。 ということは、進歩発展、企業の繁栄は、このつながりは、その良し悪しと緊密度、と云ったことに左右されることになる。 人はわかっていても、やらない。わかっちゃいるけれどやめられない。そうした側面は、誰にもある。 だからこそ、意識して、つながりすなわち、良い関係作りを構築し、より緊密度を高めていこう、といった姿勢が求められることになる。 そし、肝心ことは、上の「良い」の解を、誤解しないことである。 「良い」ということは、相手にとって良し。それがひいては自分にとっても良し、という意味だ。 さらに念押ししておきたいことは、その「相手」を、できるだけ広く、深く、俯瞰度を高くして、とらえることである。 例えば、自分の庭を、草花、小動物をなどを含めての自然界といったように・・・・。
2012.02.08
コメント(0)
-
繋がっていない、ということ
一人ではいかに優秀でも、つながり、連携には勝てない。孤軍奮闘という言葉があるが、私は、これを「1人でがんばったが、やはり大勢には勝てそうもないや、あるいは、負けちゃった、といったイメージをもっている。 いかに優れたハード商品であろうと、その関連機器、ソフトの広がりがないと、やはり孤立型、自滅型として萎える。 古くはソニーのビデオ、やや最近では東芝のVD・・・。やがて、グーグルの開放性と比較されているあの企業も・・・・・。 開放性、といったイメージを、あれこれ置き換えてみる。過去の歴史でも良い。あるいは今、目の前で見えるものも。悉くが、繋がっている。繋がっているということは、閉鎖的ではなく,開放性を是としている証である。 としたら、つながり、開放性といったことは、普遍性ある生き方の思想そのものであることが理解できよう。 ならば、ここで自問自答してみようではないか。 俺が、俺が、我が社、我が社、と自慢話をする俺は、気分が良かろうが、それを聞いているみんなはどうだろう。俺の一人勝ちでの有頂天、負けた連中はどうだろう あの国は、どうなのだろうか。北の国、あるいはアラブのあの国など。世界から、そして国内でも孤立しているあの国の首脳者は、戦いを挑む、といった形で、やはり、他とのつながりを求めてくる。 同情して云うのではないが、悲しい、寂しい国ではないか。国民と繋がっていない寂しい独裁者。そしてそのことがどんなに国民にとって悲惨なことなのか、悲惨な場なのか。
2012.02.07
コメント(0)
-
今の潮流を読む
今潮流は?本来のあり方は? と問われたら、私は明解に答える。 「オープンソース」、と。 元来、時代の潮流は、「オープンソース」の方へ流れている。国でみると、その閉ざされた国の一つが、今騒がしい。 すべからく、急速に情報開示・公開の流れに転化、集約され初めている。 アンチオープンは、胡散臭い、透明性に欠く、だから信頼できない、薄気味悪い、といった消費者側の情報は、閉ざされたところや輩には入らない。情報もまた、交換、つながりなのだ。 だから、単に情報が入らない、脱さない、といった消極的な理由以外に、孤立型は、孤立しているが故に恒に、永遠的に孤独であり、多勢に無勢の関係で、外部におびえて存在しなければならないのだ。融合系、協力系ないしはシステム系に、単独で太刀打ちできないからである。 だからこそ、以前は、個である自企業を大きくすることで孤立故のマイナス、寂しさからの脱却をもくろみ大きいことはいいことだ、を推進してきた。 だが今、多くの企業は、自分、自社の「系」を大きくすることを、生存の「決め手(売り)」とする潮流へ、大きくギヤチェンジしている、といってよい。 その流れが本流か?次にそのことを検証してみる。
2012.02.06
コメント(0)
-
設計図なくて柱あり
これから何をやるのか。何をやろうとしているのか、 という,私の質問には、 頑張ります,一生懸命やります。増収増益を目指します。雇用は確保しつつ、合理化を図ります。 というどこでもきく言葉の繰り返ししか帰ってこないのである。 応えられないのである。 提出書類はもっとひどい。過去の記録と、グーグル検索で集めたデーター、写真の切り貼り。聴いたような文章のつなぎ合わせ。時には,網走の地名が、そのまま出てきたりして苦笑させられる。 地産地消、この地方の特産品をつかって、 従来にないものを提供したい、 そうしたことをしきりにプレゼンテーションするのだが、 ではなにを。どうしたものをこの地域の新たな特産品として創るのかは考えてもいないのだ。 よくぞ、 作る料理を決めずに、思いつく限りの食材を取りそろえるな。 設計図なしに、この壁、この柱を使います。ふすまはこれにします。よくいえるな。 今回に限らずだが、呆れてしまう。 プレゼンテーションのツールが、昔のエクセルからパワーポイントや、マインドマップに変わろうと「戦略なきところに戦術なし」の普遍の原理が変わるわけはないのだ。
2012.02.05
コメント(0)
-
あるプレゼンテ-ション
過日の話。指名管理者の選定会議での。企業のプレゼンテーションのこと。 発表の1社20分の持ち時間、その後審査委員の質疑10分。 こうした場合のプレだが、なぜもかくにワンパターン化するか。 各社とも共通して、自社のこれまで実績、あれこれ。それに技法をあれこれ中にはパワーポイントでまた,自画自賛のてんてこ盛り。 過去ではない。これからこの事業をどんな形に、というのが私達の知りたいことなのだ。 受託した場合、この事業をどんな形にもって行くのか、 そのイメージは殆ど語られない。 知りたいのは先の夢、そしてそのために、どうするのか 1に、何をやってきたかとかあれができる、これができます、 ではなく、まず受託した事業をどんな形にもって行くのか、 この事業のあるべき姿のイメージと戦略を話していただけますか。 2に、あれできる、これできるではなく、 1の具現のために 御社としてまず何から着手したいのか。 1つだけでいいので挙げて戴けませんか。 これが私の質問である。 これまで能弁だったスピーカーがまったく沈黙。うつむく。 応えられないのである。
2012.02.04
コメント(0)
-
後ろ見ていれば前見えない
値下げという対処は、薄れた魅力、劣化した価値への対策、改善にはならない。値下げによる対処は、単に実勢価格への調整に過ぎないからである。 その誤りの対処をなすことで、本当の対策が講じられないということで、手遅れ、事態をさらに悪化させることだ。 そしてさらに何より恐いことは、誤診の結果、値下げという処方箋が出されたことで、問題の本質的要因が隠れたままで、その解明が、先送りされるというこのことである。 過去のおびただしい「倒産」という現実の中に、結果として誤診からきた,誤れりその対処、問題の本質的な解明の先送りといったことを、私たちは、見ているのである。見ているのではあるが、見えていないのである。 利益を得つつ価格を低減すること。これには必ず限界がある。 またこの路線は、価格競争に敗退した夥しい企業の屍を見ることと、「次は俺の番かも」,といった恐怖を前提に成立するのである。 しかもそれらは,概ね規模の論理で優劣が決まる。だから中小企業の勝算は立ち難い。では、低価格路線に変わるあり方は?と言うことだが、それは現在採っている低価格路線を止めなければ見えてこないのである。そのことは上に述べている。 その証に,私はこのブログに,何度も話をあれこれ変えてその答えをかき立てているのである。後ろを見ている限り前は見えない。
2012.02.03
コメント(0)
-
[風邪ひいて、早く治れと,痔の薬」
「下り坂、アクセル踏めば、地獄道」といったことを堂々と勧めている。 そうした話しを聴講した人達が,実行に移さないから救われているが、実践したら大変なことになる 勾配の程度にもよろうが、そうした低価格戦争で生き残るのは、せいぜい2-3社であろう。その彼らが限られた席に腰掛けるまでの過程で、ことごとく企業は消えていく。 言うまでもないことだが,売価を下げるということは、仕入価格を下げねばならない。卸屋にしたら,その分をメーカーの原価低減に依存。メーカーは、その分をコストダウンで吸収する。 これが模範的図式だろう。しかしこの図式はまったく機能しないことは現場経験があれば誰しもわかっていることだ。畢竟、負担,負荷は,弱い所に集中し、かかる。これが現実で,その結果が倒産である。 話をもとに戻す。値下げによる対処は、単に実勢価格への調整に過ぎないというのが私の見解である。 従来の価格では売れなくなったということは、消費者が,そこを選ばずそこの商品を購買しなかったということの結果だが、その理由が、商品・サービス、あるいは店舗に関する何か魅力が薄れた、といったことであったとしたらどうだろう。まさに、「風邪ひいて,早く治れと、痔の薬」である。
2012.02.02
コメント(0)
-
下り坂、アクセル踏み込めば
「うちの値下げ攻勢で、そのうち競合店が脱落するから」ということだろうが、その願望は相手も持っているから泥仕合になる。そもそも願望的要素を戦略に組み込むこと自体重大な誤りである。 それにこの値引き対策の結果、客層ががらりと変わってしまう。このことは当たり前のことなのだが、案外に見過ごされ,そして、後々の危惧要因になっているのだ。 混ぜなら、客層が変われば、企業の戦略、コンセプト、方針等々との整合性にブレや齟齬(そご)が出る。時には、企業の根幹を再構築する必要すら想定される。 ところが、これだけ値下げ戦略が話題になる中で、そうした問題が論議、検討されるという話は聞かない。 ということはほとんどの企業が、値下げ戦争は、他が脱落するまでの臨機体制、一過性的とみてよい。 最近、ある経営評論家が、デフレ時代においては、皆さんの会社も例外なく低価格旋風に巻き込まれ,好むとこも先ずとも関わりなく低価格戦争に泣き込まれます。ですから、早めに低価格戦略に転換しないと生き残れません、 と言っていたが、私から見たら,無責任きわまる発言と考えている。だってそうではないか。お金の価値は変動する。その変動に連動して「ものの価値=物価」が上下する。それで上がるのがインフレ、下がるのがデフレ。今、間違いなくそのインフレ時代だ。 だから、低価格商品を作ったら、作ったその商品の価格が価値が下がるのである。それは、下り坂、アクセルを踏み込み,加速せよ」といっていることに他ならない。・・・・・
2012.02.01
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1