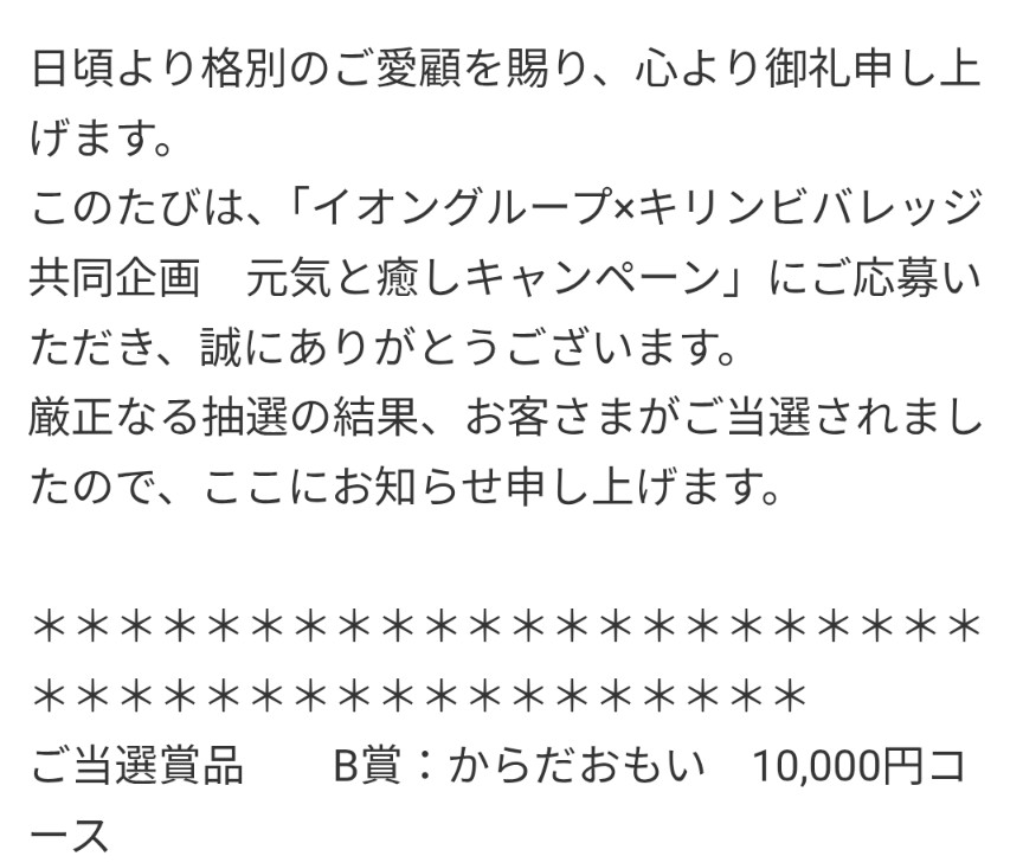2009年09月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

人口減少社会
生物学的にみれば少子は少死の結果で人類という種の宿命であり、すでにヨーロッパが経験しているように、生存の基礎条件さえしっかりしていれば社会の高齢化を恐れることはない、と言います。 ”ウェルカム・人口減少社会”(2000年10月 文藝春秋刊 藤正 巌/古川俊之著)を読みました。 藤正 巖さんは医用工学者で、東京大学名誉教授、政策研究大学院大学名誉教授、古川俊之さんは医学統計学者で、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター名誉院長です。 これから30年以内に先進諸国のどこの国でも人口減少が必然的に起こるといいます。 常識の範囲内で幾ら出産奨励をしても、人口減少は食いとめられません。 平均寿命が伸びたために、すべての年齢階層の人の死亡率が落ちています。 社会が高齢の社会になって、人口のうちに高齢者が占める割合が確実に増加してきました。 人間は寿命があり無限に生きられないから、年をとると死ぬ人が多くなります。 出生数より死亡数が多くなったら、人口は減るのは当たり前です。 そして、人口の減少の数年前から社会構造の変化に伴う社会システムの変化が始まり、人口増加に依存した社会内の既得権が崩壊します。 成熟社会で何がどう変わるか、尊敬される国の基礎作りはどうあるべきかを示し、少子化は問題だという考え方に対してそのおかしさを指摘し、人口減少社会はウェルカムだとしています。第1章 人口減少社会へのキーワード第2章 生物寿命モデルと少子化問題第3章 日本の将来の社会構造はどう変わるか第4章 子供はなぜ生まれなくなったか第5章 世界最初の人口減少社会・日本の将来第6章 日本の社会変革を妨げていた既得権第7章 成熟社会への羅針盤終章 「尊敬される国」への選択
2009.09.29
コメント(1)
-
他人と深く関わらずに生きる・・・
濃厚なつき合いはしない、社会的ルールは信用しない、心を込めないで働く、ボランティアはしない、病院には行かない。それも1つの生き方でしょう。 ”他人と深く関わらずに生きるには”(2002年11月 新潮社刊 池田 清彦著)を読みました。 他人とウマくやる完全個人主義のススメです。 著者は1947年東京都足立区生まれ、1971年東京教育大学理学部卒、1976年東京都立高等学校教諭、1977年東京都立大学大学院理学研究科博士課程単位取得満期退学、1979年山梨大学教育学部講師、助教授、教授、2004年早稲田大学国際教養学部教授。 構造主義生物学の論客として知られ進化論を激しく批判していますが、研究者が皆知っていることを都合が悪く無視されているとか定説を覆すものであるかのごとく扱うなどして、生物学としての学問的評価は低いという批判もあるようです。 しかし、本書の中で、人間は社会的な動物であり、ひとりでは生きられない、とよく言われるが、それは現在の社会システムが強い分業体制になっているからであって、人は本来生きようと思えばひとりで生きていける、という考え方には共感できるところもあります。 他力を頼まず自力で生きて、力が尽きたら死ぬのが最も上品な生き方だと言う孤高な生き方は究極的な上品であり、他人とのつきあいに悩んで死ぬよりそもそも深くはつきあわないで果てる生き方もいいじゃないかと考えさせられます。1他人と深く関わらずに生きたい濃厚なつき合いはなるべくしない女(男)とどうつき合うか車もこないのに赤信号で待っている人はバカである病院にはなるべく行かない心を込めないで働くボランティアはしない方がカッコいい他人を当てにしないで生きるおせっかいはなるべく焼かない退屈こそ人生最大の楽しみ自力で生きて野垂れ死のう2他人と深く関わらずに生きるためのシステム究極の不況対策国家は道具である構造改革とは何か文部科学省は必要ない働きたい人には職を原則平等と結果平等自己決定と情報公開個人情報の保護と差別
2009.09.22
コメント(0)
-
政権交代
政権交代は、選挙を経て、それまで政権を担っていた与党が、野党に取って代わることであす。 長期間一つの政党が政権の座に就き続けると、その政党や議員を支援する人々の既得権が固定化してしまいます。 政治的な既得権をなくしていくのは改革することですが、政権交代が改革の一番の早道です。 政権交代が行なわれることで、政治腐敗の温床となりやすい政・官・業の癒着構造を断ち切ることができ、合理的な判断で政策を決定し、実行できるようになります。 議院内閣制をとる日本では、通常、衆議院の多数党が入れ替わることで政権交代が起こります。 政権交代は二党制ではしばしば行われます。 日本でも、2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙で与野党が逆転し、1955年以降一時期の例外を除いて続いていた自民党の一党優位が終焉しました。 過去には、総選挙を経た政権交代と経ない政権交代があっりました。 総選挙を経た政権交代は、1947年の第1次吉田内閣(自由党)から片山内閣(日本社会党・民主党・国民協同党連立)への交代、1993年の宮澤内閣(自由民主党)から細川内閣(日本新党などの連立政権)への交代がありました。 総選挙を経ない政権交代には、1948年の芦田内閣(民主党・日本社会党・国民協同党連立)から第2次吉田内閣(民主自由党)への交代、1954年の第5次吉田内閣(自由党・改進党閣外協力)から鳩山内閣(日本民主党)への交代、1994年の羽田内閣(新生党などの連立政権)から村山内閣(日本社会党などの連立政権)への交代がありました。 そして2009年、麻生内閣(自由民主党)から民主党中心の内閣への総選挙を経た政権交代になる予定です。 楽しみでもあり、恐ろしくもあり。
2009.09.15
コメント(3)
-
智積院
智積院は山号を五百佛山、寺号を根来寺といい、本尊は金剛界大日如来、創建は1598年、開基は玄宥です。 智山派の大本山には、千葉県成田市の成田山新勝寺、神奈川県川崎市の川崎大師平間寺、東京都八王子市の高尾山薬王院があります。 ”智積院”(1998年6月 淡交社刊 近藤隆敬/水野克比古著)を読みました。 京都市東山区にある真言宗智山派総本山の智積院の四季を写真と文章で紹介しています。 近藤隆敬さんは智積院化主第六十七世で、1912年東京都に生まれ、1922年得度、1932年東京都長福寺住職、1997年10月真言宗智山派管長、総本山智積院化主第六十七世に推戴され、現在に至ります。 水野克比古さんは、1941年京都市上京区に生まれ、1964年同志社大学文学部卒業、1969年からフリーランス・フォトグラフアーとして、日本の伝統文化を深く見つめ、京都の風物を題材とした撮影に取り組んできました。 智積院は、紀州にあった大伝法院と、豊臣秀吉が、3歳で死去した愛児鶴松のために建てた祥雲寺という2つの寺が関係しています。 智積院は、もともと紀州根来山大伝法院の塔頭でした。 大伝法院は真言宗の僧覚鑁が1130年に高野山に創建した寺院ですが、教義上の対立から覚鑁は高野山を去り、1140年大伝法院を根来山に移して新義真言宗を打ち立てました。 智積院は南北朝時代、この大伝法院の塔頭として、真憲坊長盛という僧が建立したもので、根来山内の学問所でした。 近世に入って、根来山大伝法院は豊臣秀吉と対立し、1585年の根来攻めで全山炎上しました 当時の根来山には2,000もの堂舎があったといいます。 当時、智積院の住職であった玄宥は、根来攻めの始まる前に弟子たちを引きつれて寺を出、高野山に逃れました。 玄宥は、新義真言宗の法灯を守るため智積院の再興を志しましたが、念願がかなわないまま十数年が過ぎました。 関ヶ原の戦いで徳川家康方が勝利した翌年の1601年、家康は東山の豊国神社の付属寺院の土地建物を玄宥に与え、智積院はようやく復興しました。 さらに、三代目住職日誉の代、1615年に豊臣氏が滅び、隣接地にあった豊臣家ゆかりの禅寺・祥雲寺の寺地を与えられてさらに規模を拡大し、復興後の智積院の寺号を根来寺、山号を現在も根来に名を残す五百佛山としました。
2009.09.08
コメント(0)
-
失業率
失業率とは、就業意欲があるのに仕事につけない人の割合です。 算定は総務庁が毎月末の一週間に4万世帯(10万人)を対象に標本調査をします。 内容は「月末一週間に少しでも働いたか」とか「職を探しているか」とかの質問です。 この調査に基づいて、15歳以上の人を分類して、これに基づいて完全失業率を算出します。 完全失業率は労働力人口に占める完全失業者の割合です。 現在、働くことができる人の人数の中で、働く意欲があるにも関わらず就職できない人の割合です。 バブル崩壊後、2002年8月と2003年1月には完全失業率が5.5%と最悪になりましたが、その後は低下傾向を見せていました。 しかし、総務省が発表した労働力調査速報によると、2009年7月の完全失業率は、6月より0.3ポイント悪化して5.7%となり、現在の方法で調査を始めた1953年4月以来、最悪となりました。 生産や輸出などの指標に持ち直す動きがありますが、雇用情勢については依然とし悪化傾向に歯止めがかからない状況です。 年齢別では若年層で高い傾向にあり、製造業は1年前に比べ106万人減りました。 昨秋以降の派遣切りの増加などが影響しているようです。
2009.09.01
コメント(1)
全5件 (5件中 1-5件目)
1