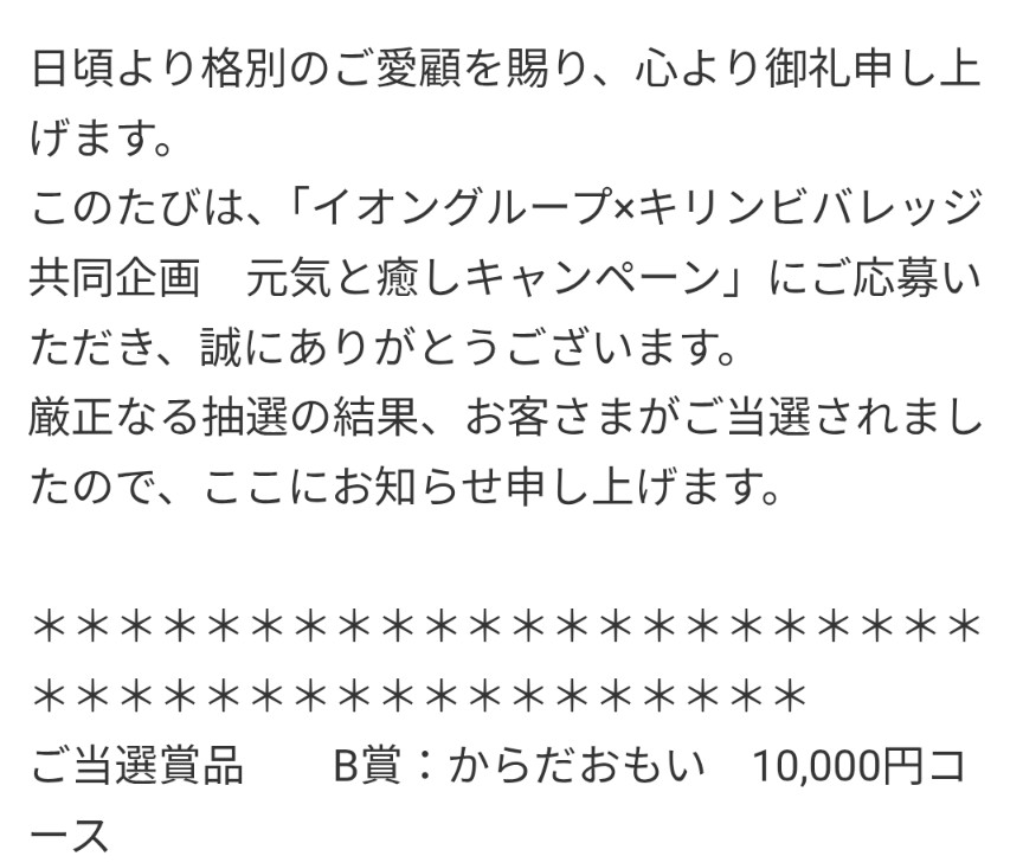2011年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
隠元
隠元は(1592-1673)は中国明末清初の禅宗の僧で、福建省福州福清県の生まれ俗姓は林で、中国福建省福州府福清県の黄檗山萬福寺=古黄檗の住持でした。 特諡として大光普照国師、仏慈広鑑国師、径山首出国師、覚性円明国師、勅賜として真空大師、華光大師と言われます。 日本からの度重なる招請に応じて、1654年に63歳の時に弟子20人他を伴って来日しました。 のちに妙心寺住持の龍渓禅師、後水尾法皇、徳川幕府の崇敬を得て、宇治大和田に約9万坪の寺地を賜り、1661年に禅寺を創建しました。 ”人物叢書 隠元”(1989年3月 吉川弘文館刊 平久保 章著)を読みました。 中国明代末期の臨済宗を代表する費隠通容禅師の法を受け継ぎ臨済正伝32世となった隠元禅師の生涯を詳しく紹介しています。 平久保章さんは、1909年生まれ、1935年東京帝国大学文学部国史学科卒業、元都立戸山高校教諭でした。 隠元は、福建省福州府福清県万安郷霊得里東林に生まれ、俗名は林曽炳と言い、10歳で仏教に発心しましたが、出家修道は母に許されませんでした。 21歳の時に消息不明の父を浙江に捜したが果たせませんでした。 23歳の時に普陀山の潮音洞主のもとに参じ、在俗信者でありながら一年ほど茶頭として奉仕しました。 29歳で生地である福清の古刹で黄檗希運も住した黄檗山萬福寺の鑑源興寿の下で得度しました。 33歳の時に金粟山広慧寺で密雲円悟に参禅し、密雲が萬福寺に晋山するに際して随行しました。 35歳で大悟しました。 38歳の時に密雲は弟子の費隠通容に萬福寺を継席して退山しましたが、隠元はそのまま萬福寺に残り45歳で費隠に嗣法しました。 その後萬福寺を出て獅子巌で修行していましたが、費隠が退席した後の黄檗山の住持に招請されることとなり、1637年に晋山しました。 その後に退席しましたが、明末清初の動乱が福建省にも及ぶ中で1646年に再度晋山しました。 江戸初期に長崎の唐人寺であった崇福寺の住持に空席が生じたことから、先に渡日していた興福寺住持の逸然性融が隠元を日本に招請がありました。 当初は隠元は弟子の也嬾性圭を派遣しましたが、途中船が座礁して客死してしまいます。 やむなく3年間の約束でこれに応じて、1654年に隠元自ら20人ほどの弟子を率いて、鄭成功が仕立てた船に乗りました。 長崎来港は7月5日夜で、月洲筆の普照国師来朝之図にこのときの模様が残されています。 興福寺、福済寺、崇福寺の唐三か寺は、幕府の鎖国政策で長崎に集まった華僑の檀那寺で、隠元はただちに興福寺、ついで崇福寺に住しました。 隠元が入った興福寺には、明禅の新風と隠元の高徳を慕う具眼の僧や学者たちが雲集し、僧俗数千とも謂われる活況を呈しました。 1655年に妙心寺元住持の龍渓性潜の懇請により摂津嶋上の普門寺に晋山しますが、隠元の影響力を恐れた幕府によって寺外に出る事を禁じられ、また寺内の会衆も200人以内に制限されました。 隠元の渡日は当初3年間の約束で、本国からの再三の帰国要請もあって帰国を決意しますが、龍渓らが引き止め工作に奔走し、1658年に将軍徳川家綱との会見に成功しました。 1660年に山城国宇治郡大和田に寺地を賜り翌年に新寺を開創し、旧を忘れないという意味を込め故郷の中国福清と同名の黄檗山萬福寺と名付けました。 1663年に完成したばかりの法堂で祝国開堂を行い、民衆に対して日本で初めての授戒である黄檗三壇戒会を厳修しました。 以後、中国福清の黄檗山萬福寺は古黄檗と呼ばれます。 隠元には後水尾法皇を始めとする皇族、幕府要人を始めとする各地の大名、多くの商人たちが競って帰依しました。 萬福寺の住職の地位にあったのは3年間で、1664年に後席は弟子の木庵に移譲し松隠堂に退きました。 松隠堂に退隠後の82歳になった1673年の正月に死を予知して身辺を整理し始め、3月になり体調がますます衰え、4月2日には後水尾法皇から大光普照国師号が特諡されました。 翌3日に遺偈を認めて82歳で示寂しました。 隠元は念仏と密教的要素を取り込んだ明末の禅風をもたらし、万福寺は、行事、建築、明代の仏師笵道生の仏像など万事が明朝風で、以後の歴住も中国僧が続きました。 隠元の書は幕閣・諸大名などに珍重され、膨大な語録である詩偈集はその精力的な活動を伝えています。
2011.02.22
コメント(0)
-
いっしょに暮らす(感想)
いまはとても生き難い時代です。 働いて自立する、自分らしく生きる、他人を愛し分かり合う。 人間が人間らしく生きるための、そんな基本が揺らいでいます。 人々は幸福をどのように捉え、それを得るためにどんな努力を重ねてきたのでしょうか。 ”いっしょに暮らす”(2005年4月 筑摩書房刊 長山 靖生著)を読みました。 親子の絆が揺らぎ、結婚しない人が増え、人間関係が苦手な若者も急増中の現在、他者との間にたちはだかる厚くて高い壁を越えるため何が必要なのかを考えさせる内容です。 長山靖生さんは、1962年生まれ、評論家、歯学博士で、鶴見大学歯学部卒業語、歯科医のかたわら、文芸評論、社会時評などを通して、近代日本について考察する仕事を手がけています。 恋愛、結婚、親子、友人、これらはいずれも誰にとっても身近な多くの人が経験する人間関係です。 しかしそうしたありきたりの関係を獲得し、良好に維持するのはけっこう難しいです。 時代と共に、ますます難しくなってきた感があります。 昔に比べて、今の日本では人間関係が希薄になったといわれています。 学校や会社での個人に対する抑圧は少なくなっているかも知れませんが、知性と忍耐力があれば場の空気を読み適当に調了を合わせて波風が立たないように過ごすなり、自分の意見は意見として胸中に密かに持して沈黙を守ることは不可能ではないはずです。 しかし、親友とか恋人とかのより緊密な関係を求める際にはそうはいきません。 当たり障りのない態度や沈黙して不満を押し隠す態度は、そのまま関係不全の結果であるだけでなく原因ともなります。 こういう場合、ふつうは本当の自分を正直にさらすのがいいかも知れませんが、世の中には正直に自分をさらすのが不得手な人間もいます。 現代の若者を見ていると、どうもこの手の不器用な人間が増えているように思われます。 そうした不器用な人間たちは、どうしたら他人といっしよに暮らせるのでしょうか。 根底に横たわるのは愛情や経済だけでなく、もっと具体的な技術なのではないでしょうか。 気待ちはあっても、コミュニケーションスキルをはじめ、基礎的な生活技術が必要です。 人間関係がうっとうしいくらい密だったかつての日本社会では、他人と生活する技術、いっしょに暮らす技術は、成長する過程でわざわざ努力などしなくとも自然に身に付いたのでしょう。 しかし現代の生涯未婚率の驚異的な増加の背景には、相互に愛情があり経済的にどうにかなっても、いっしょに暮らすことを逡巡させる要素が生まているように思われてなりません。 現代では、愛情と経済の問題以上に大きな難問として、他人と心を通わすこと自体の困難、いっしよに暮らす生活それ自体の不可能感が横たわっているのではないでしょうか。 もしかすると現代の家族が抱えている様々な問題が横たわっているのではないでしょうか。 現代でも、ふつうに成長すれば異性への関心や自立への意思は生まれるでしょう。 現代の男女が、過去に比べて出会いのチャンスが少ないとは思えません。 むしろ少くなったのは、数十年前にはごく当たり前の常識といわれていた、他人と暮らせるだけの生活技術のようなも言なのではないでしょうか。 これからの日本では、結婚して子供を持つという選択は当たり前のものでもふつうのことでもなくなってしまうかもしれません。 それでも人は、ずっとひとりで生きていけるものではありません。 結婚に付随する煩わしさから逃れた人でも、他人との同居は重要な課題にならざるをえません。 社会で家族や恋人を偕む他者と自分とのあいだに、どのような亀裂が生じているのでしょうか。 かつて存在した、あるいは現在も見られる他人と暮らす生活の実態を概観し、われわれに欠けているのは何か、あるいは新しい生活を作っていくためにどうしたらいいのかを、具体的に考えようとしています。
2011.02.15
コメント(0)
-
イスタンブール・トルコで暮らす(感想)
イスタンブールは、トルコ共和国西部に位置する都市で、古代にはビュザンティオン、コンスタンティノポリスと呼ばれました。 ボスポラス海峡をはさんでアジア側とヨーロッパ側の両方に拡がって、2大陸にまたがる大都市です。 ”イスタンブール・トルコで暮らす”(1999年3月 中央経済社刊 松谷浩尚/松谷 稔著)を読みました。 輝かしい栄光の歴史をもち伝統的に世界でも有数の親日国であるトルコの歴史・風俗から快適生活のアドバイスまでの実践的情報を紹介しています。 イスタンブール県の県都で、首都アンカラを上回る都市で、文化・経済の中心となっています。 人口は約880万人で、イスタンブール県全体では1000万人を越えています。 その歴史は長く、かつてのローマ帝国、東ローマ帝国、ラテン帝国、オスマン帝国の首都が置かれていました。 正式名称がイスタンブールに改められ、国際的にもコンスタンティノープルではなくイスタンブールと呼ばれるようになるのは、トルコ革命後の1930年のことです。 松谷浩尚さんは、1944年三重県生まれ、慶応大学卒業後、外務省入省、アンカラ日本大使館、イスタンブール日本総領事館などに勤務。 松谷 稔さんは、1973年イスタンブール生まれ、桜美林大学卒業後、時事通信社入社。 トルコは共和国で、公用語はトルコ語、首都はアンカラで、最大の都市はイスタンブールです。 面積は約78万km2、人口は7481万人で、西アジアのアナトリア半島と東ヨーロッパのバルカン半島東端の東トラキア地方を領有しています。 アジアとヨーロッパの2つの大州にまたがる共和国です。 北は黒海、南は地中海に面し、西でブルガリア、ギリシャと、東でグルジア、アルメニア、イラン、イラク、シリアと接しています。 国土の大半の部分はアナトリア半島にあたり、国民の約99%がイスラム教、宗派はスンナ派が多数です。 地理的・歴史的には西アジアに属しますが、共和国成立後は西洋化を進めています。 初代大統領のケマル・アタテュルクは、11世紀に、トルコ系のイスラム王朝、セルジューク朝の一派がアナトリアに立てたルーム・セルジューク朝の支配下で、ムスリムのトルコ人が流入するようになり、土着の諸民族とが対立・混交しつつ次第に定着していきました。 彼らが打ち立てた群小トルコ系君侯国のひとつから発展したオスマン朝は、15世紀にビザンツ帝国を滅ぼしてイスタンブールを都とし、東はアゼルバイジャンから西はモロッコまで、北はウクライナから南はイエメンまで支配する大帝国を打ち立てました。 19世紀に、衰退を示し始めたオスマン帝国の各地でナショナリズムが勃興して諸民族が次々と独立してゆき、帝国は第一次世界大戦の敗北により完全に解体されました。 1923年、アンカラ政権は共和制を宣言、1924年にオスマン王家のカリフをイスタンブールから追放して、西洋化による近代化を目指すイスラム世界初の世俗主義国家トルコ共和国を建国しました。 エーゲ海・地中海沿岸地方は温暖でケッペンの気候区分では地中海性気候に属し夏は乾燥していて暑く、冬は温暖な気候で保養地となっています。 黒海沿岸地方は温暖湿潤気候に属し、年間を通じてトルコで最も降水量が多い場所で深い緑に覆われています。 国土の大半を占める内陸部は大陸性気候で寒暖の差が激しく乾燥していて、アンカラなどの中部アナトリア地方はステップ気候に属し、夏は乾燥していて非常に暑くなりますが、冬季は積雪も多く気温が零下20度以下になることも珍しくありません。 東部アナトリア地方は亜寒帯に属し、冬は非常に寒さが厳しいです。 バルカン半島やアナトリア半島は、古来より多くの民族が頻繁に往来した要衝の地で、複雑で重層的な混血と混住の歴史を繰り返してきました。 現在のトルコ共和国成立の過程にも、これらの地域事情が色濃く反映されています。 トルコの国土は、ヒッタイト、古代ギリシア、帝国、イスラームなどさまざまな文明が栄えた地で、諸文化の混交がトルコ文化の基層となっています。 これらの人々が残した数多くの文化遺産、遺跡、歴史的建築が残っています。1章 魅惑する歴史の都イスタンブール2章 トルコ共和国の昨日と今日―重層たる歴史と日本との関係3章 日常のトルコの人たち4章 世界3大料理の1つ?―トルコの豊かな食べ物5章 トルコで暮らす6章 トルコの生活を楽しむ7章 トルコを歩く8章 トルコへの入出国手続きその他
2011.02.08
コメント(0)
-
良源
良源は912年生まれ、近江国浅井郡虎姫に地元の豪族、木津氏の子として生まれ、幼名は観音丸または日吉丸と言い、諡号は慈恵大師であり、一般には通称の元三大師の名で知られます。 ”人物叢書 良源”(1987年11 吉川弘文館刊 平林 盛得著)はを読みました。 平安中期の天台宗の僧で、比叡山中興の祖としてその繁栄をもたらした良源の生涯を詳しく紹介しています。 平林盛得さんは、1934年東京生まれ、1956年東京教育大学文学部日本史科卒業し、宮内庁書陵部の図書調査官を勤めました。 良源は12歳のとき比叡山に上り仏門に入ったといわれます。 比叡山西塔理仙の弟子となり、928年座主尊意から受戒しました。 938年に興福寺維摩会の番論議で名声をあげて藤原忠平に認められ、忠平没後はその子師輔、さらに兼家の政治的、経済的後援を得ていきました。 楞厳三昧院をはじめ、堂塔の整備と藤原氏など権門の寄進した荘園などによる経済的基盤の確立を行いました。 最澄の直系の弟子ではなく身分も高くはありませんでしたが、963年の清涼殿での宗論でも名声をあげ、異例の昇進で966年に第18代天台座主になりました。 延暦寺は935年の大規模火災で根本中堂を初め多くの堂塔を失い荒廃していて、966年にも火災がありましたが、良源は村上天皇の外戚である藤原師輔の後援を得て焼失した堂塔を再建しました。 また、最澄の創建当初は小規模な堂だった根本中堂を壮大な堂として再建し、比叡山の伽藍の基礎を造りました。 970年に寺内の規律を定めた二十六ヶ条起請を公布し、僧兵の乱暴を抑えることにも意を配りました。 981年には史上第2番目の大僧正になりました。 984年暮れに横川から坂本弘法寺に下り、翌年没しました。 母方は物部氏で、母への孝行は有名で出家後は比叡山に登れない老母のために苗鹿に山荘を作って尽くしたと言います。 弟子の性空や増賀は良源を批判して師のもとを去りましたが、源信、覚運、覚超、尋禅は四哲とされました。 比叡山の伽藍の復興、天台教学の興隆、山内の規律の維持などの様々な功績から、延暦寺中興の祖として尊ばれています。 朝廷から贈られた正式の諡号は慈恵大師ですが、命日が正月の3日であることから、元三大師の通称で親しまれています。 比叡山横川にあった良源の住房、定心房跡に四季講堂が建ち良源像を祀ることから、元三大師堂とも呼ばれています。 良源には、角大師、豆大師、厄除け大師など様々な別称があり、広い信仰を集めており、全国の社寺に見られるおみくじの創始者は良源だと言われています。
2011.02.01
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1