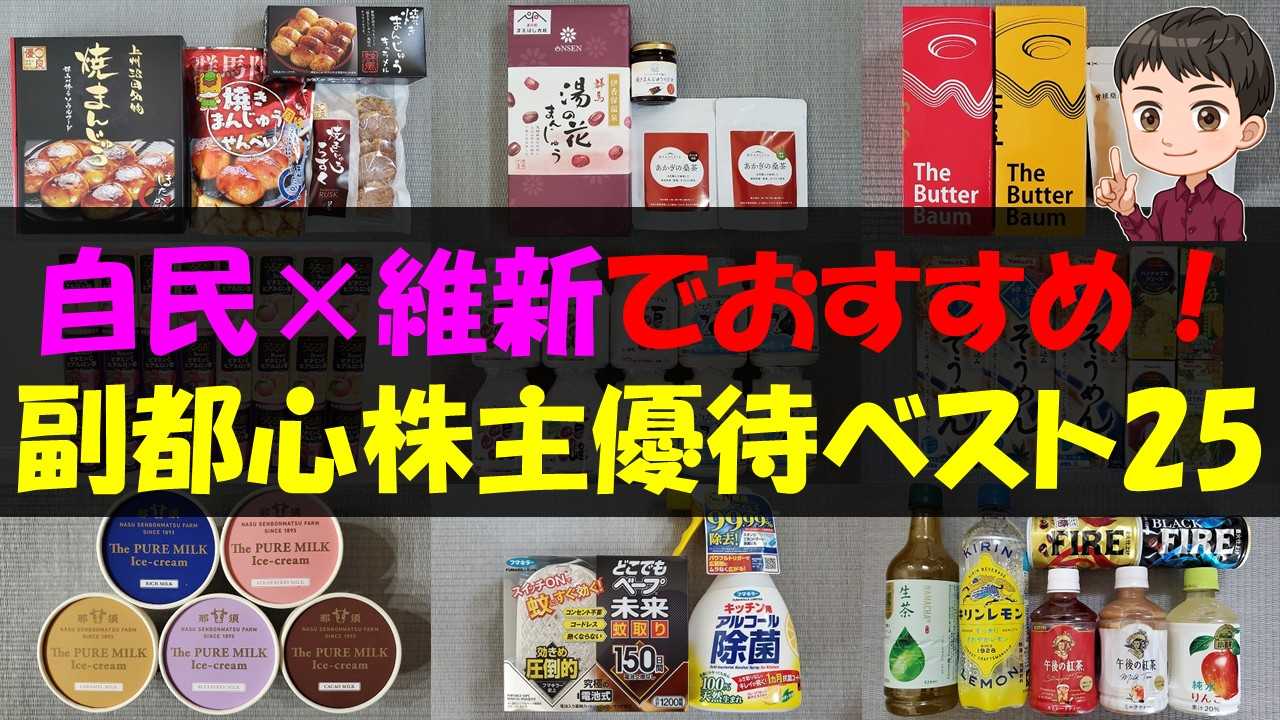2011年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
シーボルト日本植物誌(感想)
フィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルトは、1796年南ドイツ・ヴュルツブルクの医学界の名門の子孫として生まれ、父が1歳1ヶ月のとき亡くなり母方の叔父に育てられました。 1815年にヴュルツブルク大学に入学し、医学をはじめ、動物、植物、地理などを学びました。 1820年に卒業し、国家試験を受けてハイディングスフェルトで開業しましたが、東洋研究を志して1822年にオランダのハーグへ赴き、国王の侍医から斡旋を受け、オランダ領東インド陸軍病院の外科少佐となりました。 9月にロッテルダムから出航し、喜望峰を経由して1823年4月にはジャワ島へ至り、6月に来日、鎖国時代の日本の対外貿易窓であった長崎の出島のオランダ商館医となりました。 ”シーボルト日本植物誌 ”(2007年12月 筑摩書房刊 大場 秀章監修・解説)を読みました。 日本の文明のために記念すべき博物書中の大著述の一つで、日本に関する博物書としてはいまなお権威のある名著です。 ジャワ島から、「小生は新たに抜擢された駐在官の侍医、かつ自然研究者として日本へまいります。小生の望んだものはうまくゆきました。小生を待つものは死か、それとも幸せな栄誉ある生活か」と故国の伯父宛に手紙を送っています。 大場秀章さんは、1943年東京生まれ、理学博士で東京大学総合研究博物館教授、専門は植物分類学、生物地理学です。 シーボルトは出島内において開業の後、1824年に出島外に鳴滝塾を開設し、西洋医学教育を行いました。 日本各地から集まってきた多くの医者や学者に講義しました。 塾生は、後に医者や学者として活躍しています。 シーボルトは、日本と文化を探索・研究しました。 1823年4月には162回目にあたるオランダ商館長カピタンの江戸参府に随行し、道中を利用して日本の自然を研究することに没頭しました。 1826年に将軍徳川家斉に謁見し、江戸において学者らと交友しました。 その間に日本女性の楠本滝との間に娘・楠本イネをもうけました。 1828年に帰国する際、収集品の中に幕府禁制の日本地図があったことから問題になり、国外追放処分となりました。 1830年にオランダに帰着し、翌年には蘭領東印度陸軍参謀部付となり、日本関係の事務を嘱託されています。 オランダ政府の後援で日本研究をまとめ、集大成として全7巻の『日本』(日本、日本とその隣国及び保護国蝦夷南千島樺太、朝鮮琉球諸島記述記録集)『ファウナ・ヤポニカ』『フロラ・ヤポニカ』の3部作を随時刊行しました。 『フロラ・ヤポニカ』、つまり日本植物誌は、シーボルトが日々折々のあらゆる機会に書き留めた日本植物についての総決算です。 出版された植物の種数は150に満たないですが、未発表のまま残されたメモやノートは相当の量にのぼるといいます。 その後、1853年に来日するマシュー・ペリーに日本資料を提供し、1854年に日本は開国し、1858年には日蘭通商条約が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除されました。 1859年、オランダ貿易会社顧問として再来日し、1861年には対外交渉のための幕府顧問となりました。 1862年に官職を辞して帰国し、1863年にオランダの官職も辞して故郷のヴュルツブルクに帰り、1866年ミュンヘンで70歳で死去しました。 2005年にライデンでシーボルトが住んでいた家が資料館としてシーボルトの事跡や日蘭関係史を公開されています。 生物標本、またはそれに付随した絵図は、当時ほとんど知られていなかった日本の生物について重要な研究資料となり、模式標本となったものも多いそうです。 これらの多くはライデン王立自然史博物館に保管されています。 植物の押し葉標本が12,000点あり、それを基にヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニと共著で刊行されました。 その中で記載した種は2300種になり、彼らが命名し現在も名前が使われている種もあるそうです。 シーボルトはどうずれば鎖国下にある日本から最大限の資料と情報を入手できるかを周到に考え、それを実行に移したと考えられます。 日本の植物をヨーロッパに移入し、庭園を豊かなものとし林業の活性を図ろうとし、緯度がオランダやドイツにより近い本州東北部や北海道の植物に強い関心を寄せていたそうです。 シーボルトには、園芸的価値のある野生植物が少なかったヨーロッパに、日本の植物を導入してヨーロッパの園芸を豊かなものにする衝動があったといいます。 日本や中国の植物を導入するため園芸振興協会を設立し、さらに営利目的のシーボルト商会を設立したのはそのためと考えられるといいます。 鳴滝塾に集い来た塾生たちは情報収集に多大の貢献をしました。 標本を集めるだけでなく、シーボルトが投げた課題についての報告をシーボルトに提出しています。 シーボルトは居ながらにして、日本の各地の植物に関わる情報を集めることができたといいます。
2011.06.28
コメント(0)
-
ニッポン不公正社会(感想)
日本は、スタート時点から機会が全く不平等になっていて、イギリスとまではいかなくてもネオ階級社会として固定、不平等が再生産されているといいます。 ”ニッポン不公正社会 ”(2006年3月 平凡社刊 斎藤 貴男/林 信吾著)を読みました。 ジャーナリストと作家との対談集です。 ジャーナリストは斎藤貴男さん、作家は林 信吾さんです。 斎藤貴男さんは、1958年東京池袋生まれ、早稲田大学商学部卒業、英バーミンガム大学大学院修了(国際学MA)、日本工業新聞記者、週刊文春記者などを経てフリーのジャーナリストになりました。 林 信吾さんは、1958年東京板橋生まれ、神奈川大学中退、1983年から10年間在英して英国のニュースダイジェスト記者、欧州ジャーナル編集長などを務め、帰国後フリーで執筆活動を行っています。 結果の不平等、格差ならまだ仕方がないが、いまの日本社会は自由競争の名のもとに、世代を超えて格差が温存される不公正社会にされようとしているといいます。 イギリスは階級社会であり、親から継続した身分の下層社会の若者たちがいます。 負け組から生まれた人間は、勝ち組にのし上がれない仕組みになっているそうです。 サッチャーは自分の階級である上層社会のために学校制度を変えましたが、いまイギリスでは見直され否定されつつあるといいます。 日本にしのびよるネオ階級社会は、教育機会均等の崩壊から始まったそうです。 正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトというネオ階級が背景にあります。 そして、平成不況の中で正社員が減少し、大学を卒業しても正社員になれる人は一部だけの時代に入りました。 また、ニートとして社会的保障も与えられず、親の年金生活におぶさっている不幸な青年たちの数が最近急激に増えています。 大学を出た男性にとっては、卒業したとき正社員になれないと、20年経っても30年経っても正社員になれない人が大部分の社会になりました。 彼らの多くは年収200万円以下の収入で、年齢を重ねるにしたがって不安定な現在の職場すら雇用が危うくなってきており、子育てにお金を掛ける余裕もなく、世代を超えて格差が温存されます。 一方、大学を出た女性にとっては、卒業したときになかなか正社員になれなくても、キャリアを積んでノウハウを身につけ、アイデアをビジネスモデル化できれば、独立起業して経営者となり、成功すれば株式公開するチャンスも容易になりました。 しかし、男女の格差や年齢格差は縮小したものの、同じ年齢で所得格差が拡大しつつあるそうです。 かつての年功序列賃金で、歳を取れば経済的にも社会的にも楽になると期待できた30代から40代の男性社員にとって、いまや能力がアップしない限り、所得がアップする保証も雇用が継続する保証もない時代になりました。 かつてマルクスが描いたドラスティックな結末は来ず、資本主義の下では可変資本である労働者への給与支払比率は減少しており、そのしわ寄せが若者の頭上に集中しています。 このような資本主義の矛盾は避けられないものであり、若者はもっと現実社会の矛盾を学ぶべきだといいます。
2011.06.21
コメント(0)
-
私の中の東京(感想)
後に都電三号線になった外濠線沿いを手始めに 銀座、小石川、本郷、上野、浅草、吉原、芝浦、麻布、神楽坂、早稲田などを、明治末年生まれの野口 富士男さんが、記憶の残像と幾多の文学作品を手がかりに、戦前から戦後へと変貌を遂げた街の奥行きを探索しています。 ”私の中の東京 ”(2007年6月 岩波書店刊 野口 富士男著)を読みました。 愛情溢れる追想と実感に満ちた東京の文学散策です。 野口冨士男さんは、1911年東京生まれ、慶應義塾大学文学部を中退して文化学院に入学した頃から旺盛に小説を執筆し、1933年に文化学院を卒業しました。 卒業後、紀伊国屋出版部で編集の仕事に従事しましたが、1935年に紀伊国屋出版部の倒産に伴って都新聞社に入社し、1936年から1937年まで河出書房に勤務しました。 第二次世界大戦末期に海軍の下級水兵として召集され、復員語、1950年ごろから創作上の行き詰まりを感じ、徳田秋声の研究に専念し、約10年を費やして秋声の年譜を修正しました。 このころ東京戸塚の自宅の一部を改造して学生下宿を営みました。 1965年に毎日芸術賞、1975年に読売文学賞、1980年に川端康成文学賞、1982年に日本芸術院賞、1986年に菊池寛賞を受賞し、1987年に芸術院会員、1984年から日本文藝家協会理事長を務め、1993年に呼吸器不全のため自宅で死去しました。---------- ひとくちに東京といっても、あまり広大すぎてとらえようがない。 東京ほど広い都会もないが、東京の人間ほど東京を知らぬ者もすくなくないのではなかろうか。 私達が知っているような気になっている東京とは、東京のきわめて一小部分の、そのまたほんの一小部分にしか過ぎない。 たまたまなんらかの機会をあたえられて、幾つかの町を知る。 その知っているだけの町を幾つかつなぎ合せたものが、私達の頭の中で一つの東京になっている。---------- 大正7年に入学した慶応義塾の幼稚舎は、当時はまだ三田の大学の山の下にあって、飯田橋から市ヶ谷、四谷、赤坂、虎ノ門を経て、札の辻に至る系統の市電、のちに都電3号線となった外濠線を毎日往復しました。 その沿線を軸として、気ままに道草を食いながら書き始めています。 東京の町を哀惜をもって描く文学の主流は、永井荷風に始まり、野口富士男に受け継がれたようです。 野口富士男には膨大な日記が残されているといいます。 まだ紹介されていないものもあるようです。 古き良き時代の東京の姿を、文学の語り部にもっと聞いてみたいものです。
2011.06.14
コメント(0)
-
学ぶよろこび(感想)
学ぶことのおもしろさと夢を実現する生き方、法然からトヨタ創業者まで、各界の成功者の苦楽の道に自身の人生を重ねながら、創造と発見の道を歩む学ぶよろこびを説いています。 ”学ぶよろこび ”(2011年3月 朝日出版社刊 梅原 猛著)を読みました。 学問のおもしろさと創造の夢を語るエッセイ集です。 梅原 猛さんは、1925年宮城県生まれ、立命館大学文学部教授、京都市立芸術大学学長、国際日本文化研究センター所長、日本ペンクラブ会長などを歴任しました。 生まれてすぐに愛知県知多半島の内海の名士で、梅原一族の頭領である伯父夫婦の養子となり、京都大学入学まで海と山に囲まれて過ごし、哲学から仏教の研究に入り、その間に、1972年に毎日出版文化賞、1973年に大佛次郎賞、1992年に文化功労賞、1999年に文化勲章を受章しました。 少年の夢、生い立ちの記、創造への道、「発見」についての覚え書き、老木に花という構成で、ニーチェの言葉を踏まえて、忍耐期のラクダの時代、勇気と闘争のライオンの時代、創造の小児の時代について触れています。 西田哲学の超克、ニヒリズムの死への誘惑から、生の哲学への転回、笑いの研究、日本文学・思想への独自の展開という歩みが語られています。 生い立ちの記では、当時東北大学の学生だった実父の梅原半二、実母、石川千代、ともに学生だった実父母の結婚を梅原家、石川家が認めなかったため、私生児として誕生し、乳児期に実母を亡くし、生後1年9ヶ月で伯父夫婦の梅原半兵衛、俊に引き取られ養子となり、愛知一中の入試の失敗、私立東海中学に辛うじて入学、実家から2時間半をかけて通学し、1942年、広島高等師範学校に入学するが2ヶ月で退学、翌年第八高等学校に入学し、青年期には西田幾多郎・田辺元の哲学に強く惹かれ、京都帝国大学文学部哲学科に入学するも、父親は哲学科への進学を歓迎しなかったが、梅原の熱意が強いため許可したことなどに触れています。 実父は工学博士で、トヨタ・コロナを設計し、トヨタ自動車常務取締役や豊田中央研究所代表取締役所長を務めました。 小説家の小栗風葉は養母の俊さんの兄に当たるそうです。 大器晩成型で、40歳過ぎまで単著はなかったとのこと。 その後日本仏教の研究を行い、釈迦からインド仏教・中国仏教を経て鎌倉新仏教までを述べる長編の仏教史を著し、古代史に関する研究的評論の連載を始めました。 大胆な仮説により、梅原古代学、梅原日本学、怨霊史観といわれる独特の歴史研究書を多数著しています。 老木に花では、85歳まで生かしてもらって、新しい哲学を創造しようと思っていると決意を表明しています。
2011.06.07
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1