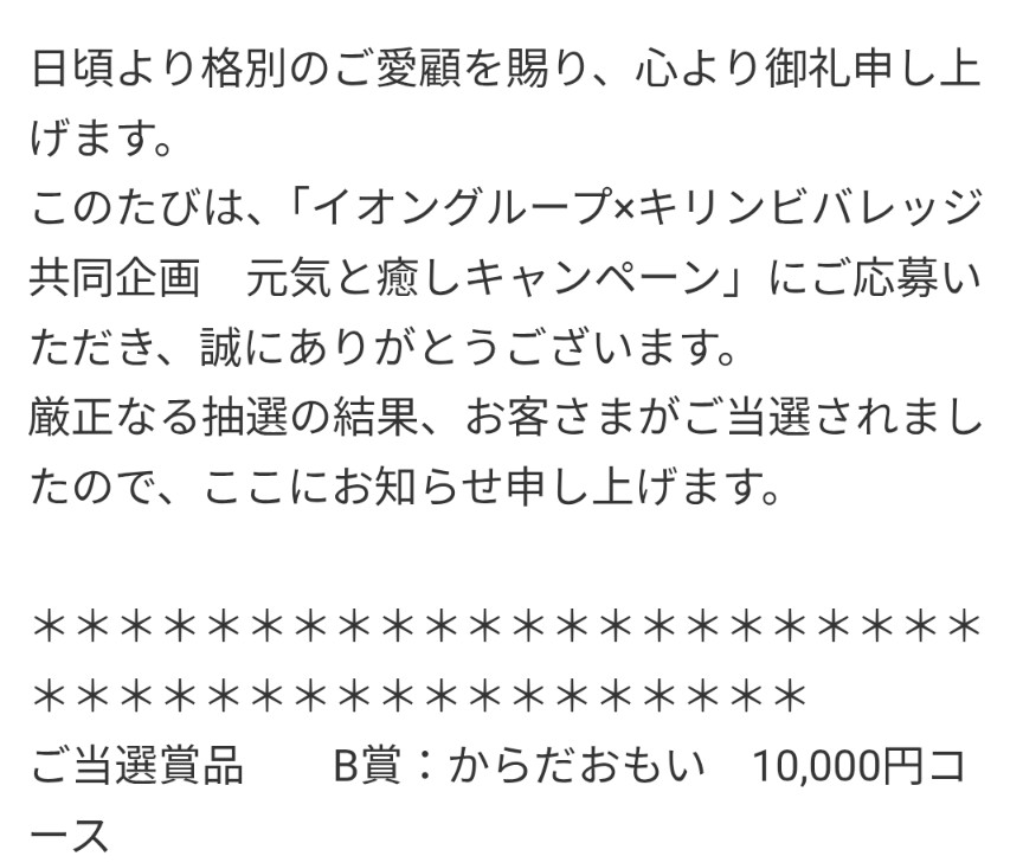2014年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
若き日の思い出(感想)
誰にも若かりし日の思い出があります。 ”若き日の思い出”(2005年6月 岩波書店刊 彌永 昌吉著)を読みました。 執筆当時、数えで100歳になる、日本の数学界の基礎を築いた数学者による半生記です。 1906年に東京府で生れてからの半生について、両親のこと、物心のつくころ、数学との出会い、東京府立四中への入学、一高での生活、数学者への道、三年間の滞欧、そして帰国後のことが瑞々しく綴られています。 それぞれの項目の最初に、赤ちゃん時代から近影まで、それぞれの思い出の写真が掲載されています。 弥永昌吉さんは、東京大学理学部数学科を卒業し、若くして欧州に留学し、そこで得た第一線の数学者との交流や研究・教育の多大な業績で数学界の隆盛に大きく貢献しました。 専門は整数論で、単項化や分岐理論など類体論の発展に多大な寄与をしました。 この本の執筆の動機は、2001年1月1日に奥様の澄子さんが亡くなり、そのとき、自伝の執筆をすすめられたことでした。 本籍地は東京都港区高輪で、ここに1923年から1945年まで両親と一緒に住んでいました。 父親は福岡県八女郡八幡村の出身で、一高を経て東大法学部を卒業し日本銀行に勤めていました。 母親は島根県松江市出身で、当時、叔父が東大を出て日銀に勤めていた関係で知り合い結婚した、といいます。 著者は1906年4月2日に本郷の東大病院の産科病室で生まれ、弥生町の小さな借家で暮らし、翌年、父親の転任に伴って広島に移って、翌年、海外に派遣となったときは母親の祖父母の住む須磨に家を借りて暮らしました。 帰国してからは本店勤務となり、牛込弁天町の家を借りて暮らしました。 1912年に愛日小学校に入学しましたが、その後も、父親が大阪、松本などに勤務したため、小学校時代も各地で過ごしました。 その後、東京府立第四中学校に入学し、のち東大応用数学科教授となる犬井鉄郎らと親しくしていました。 四年修了での旧制第一高等学校受験にうっかりミスで失敗し、四中卒業後に一高入学となりました。 その間、秋山龍や森外三郎らの訳書である代数や幾何などの一般数学書や、ポアンカレの著書などに親しんだそうです。 東京帝國大学理学部数学科では、高木貞治に師事して主に類体論について学び、1929年卒業しました。 その後、ドイツとフランスに留学しました。 1936年に東京大学理学博士となり、1942年から1967年まで東大理学部教授を、1977年まで学習院大学教授を務めました。 1970年フィールズ賞選考委員となり、1976年勲二等旭日重光章を1980年レジオンドヌール勲章を受章しました。 1978年に、学士院会員に選出されました。 主な弟子に、義弟でもあるフィールズ賞受賞者の小平邦彦、第一回ガウス賞受賞者の伊藤清、岩澤理論の岩澤健吉、佐藤の超関数で知られる佐藤幹夫などがいます。 幾何や解析など、自分の専門外の分野でも優れた弟子を数多く育てました。 2006年6月1日、老衰のため満100歳にて死去しました。 最晩年に至るまで、著書や論文を著しました。 最後に、著者による“あとがき”、三男による“あとがきのあとがき”があるほか、付録として“類体論と私”が掲載されています。
2014.02.23
コメント(0)
-
ソチオリンピック
今年の日本の冬は、各地で観測史上最大という積雪量が記録されています。 そのような中で、2014年冬季オリンピックが、黒海に面したソチ・オリンピックパークと西カフカース山脈のソチ国立公園内で、2014年2月8日より開催されています。 近代オリンピックは、国際オリンピック委員会が開催する世界的なスポーツ大会で、夏季大会と冬季大会の各大会が4年に1度、2年ずらして開催されています。 夏季リンピック第1回は、1896年にアテネで開催され、世界大戦による中断を挟みながら継続されています。 冬季オリンピックの第1回は、1924年にシャモニー・モンブランで開催されました。 1994年以降は、西暦が4で割り切れる年に夏季オリンピックが、4で割って2が余る年に冬季オリンピックが開催されています。 冬季オリンピックが始まった当初は、夏季オリンピックの開催国の都市に優先的に開催権が与えられてきましたが、降雪量の少ない国での開催に無理が生じることから、1940年代前半に規約が改正され、同一開催の原則が廃止されました。 そして、1994年のリレハンメル大会より、夏季大会と冬季大会が2年おきに交互開催するようになりました。 ソチは、ロシア連邦内のクラスノダール地方にあり、市域は3,502平方キロ、人口は445,209人です。 ロシア随一の保養地であり、黒海に面し、アブハジアとの国境に近いです。 6世紀から11世紀にかけて、グルジアのコルキス王国やアブハジアでラジカ王国から独立したアブハジア王国に属し、アドレル岬などに多くの教会が作られ、11世紀から15世紀はグルジア王国に属しました。 キリスト教徒の入植地はハザールなどテュルク系遊牧民に何度も打ち壊されてきました。 15世紀からはオスマン帝国に領有されました。 その後、カフカース戦争と露土戦争の結果、海岸線地帯は1829年にロシアに割譲されました。 ロシア革命期には白軍、ボリシェヴィキ、グルジア民主共和国の3勢力で激しい争奪戦の舞台となりました。 スターリン政権時代はソ連最大のリゾート都市に成長し、多くのスターリン様式の豪華建造物が建てられました。 ニキータ・フルシチョフ政権時代にクリミア半島がロシア・ソビエト連邦社会主義共和国からウクライナ・ソビエト社会主義共和国に移されると、ソチはさらに隆盛しました。 ウラジーミル・プーチン政権下でさらなる投資が行われました。 2007年にシウダ・デ・グアテマラで開催されたIOC総会で、2014年冬季オリンピックの開催都市に決定しました。 ロシアでの冬季オリンピックは、ロシア帝国・ソビエト連邦時代も含めて史上初です。 日本選手団は、カーリング女子の小笠原歩が旗手として先頭を行進しました。 選手団は248人と、冬季五輪の海外派遣で過去最多となりました。 選手は男子48人、女子65人の計113人で、冬季では初めて女子が上回りました。 チーム最年長は、ノルディックスキー・ジャンプ男子で冬季五輪史上最多7度目の出場となる41歳の葛西紀明、最年少はスノーボード男子ハーフパイプで15歳の平野歩夢です。 日本人選手の大いなる活躍が期待されます。 なお、1988年、ソウル大会より以降、パラリンピックとの連動が強化され、オリンピック終了後、同一国での開催が、おこなわれています。
2014.02.16
コメント(0)
-
「分かち合い」の経済学(感想)
経済危機が世界を覆い不況にあえぐ日本でも失業者が増大しています。 危機の時代を克服するにはどうしたらよいのでしょうか。 ”「分かち合い」の経済学”(2010年4月 岩波書店刊 神野 直彦著)を読みました。 他者の痛みを社会全体で分かち合う新しい経済システムの構築が急務だといいます。 日本の産業構造や社会保障のあり方を検証し、誰もが人間らしく働き生活できる社会を具体的に提案しようとしています。 神野直彦さんは、1946年埼玉県生まれ、1981年東京大学大学院経済学研究科博士課程修了、大阪市立大学助教授、東京大学教授、関西学院大学教授などを経て、東京大学名誉教授、地方財政審議会会長を歴任しています。 スウェーデン語に”オムソーリ”という言葉があり、社会サービスを意味していますが、その原義は”悲しみの分かち合い”です。 オムソーリは、”悲しみを分かち合い””優しさを与え合い”ながら生きている、スウェーデン社会の秘密を説き明かす言葉だといってもいいすぎではありません。 スウェーデンを旅すると、豊かな自然に抱かれ心優しき人間の絆の温もりに包まれ心安らかに生きることのできた、幼き頃の日本社会に出会うことができます。 スウェーデン人もヨーロッパの日本人といわれることを誇りとしているとのことで、このオムソーリという言葉を導き星に日本社会のヴィジョンを描こうとしています。 このことは、失われた時を求めた古き良き時代への回帰というノスタルジアではありません。 危機という歴史の画期に生を受けた者は、危機の時代における歴史的責任を果たさなければならないのです。 危機の時代の歴史的責任を果たそうとすれば、危機から出口へと向かうヴィジョンを描くことが必要です。 危機の迷宮から脱出するために、アリアドネの女神が授けた糸玉は、分かち合いだということができます。 アリアドネの女神は、クレーテー王ミーノースと妃パーシパエーの間の娘で、テーセウスがクレーテーの迷宮より脱出する手助けをしたことで知られています。 そこで、未来へのチャートを描き歴史的責任を果すためにアリアドネの女神から糸玉を求めようとすれば、過去の歴史の教訓に学ぶしかないのです。 現在の危機と同様の危機を歴史の高みから見出すと、1929年の世界恐慌が見えてきます。 この世界恐慌からの回復過程をみれば、生き残りをかけた競争が煽られ、結局は世界大戦という破局を招いたのでした。 しかし、この世界恐慌という絶望の海に浮かぶ希望の島と讃えられたスウェーデンは、破局の圏外にありました。 その秘密は、国民の家という分かち合いのヴィジョンにあったのです。 競争は絶望を分かち合いは希望をもたらす、といってもいいすぎではありません。 分かち合いは能動的な希望であり、孤立した人間が行動しなければ可能とはなりません。 しかも、分かち合いは指導者によって創り出されるものではなく、社会のすべての構成員の行動を必要とします。 危機を乗り越え人間の歴史的責任を果す鍵は、分かち合いにあります。 構造改革を推進させてきた日本では、社会保障も大幅に削られ、自己責任の名のもとに、格差や貧困が広がっています。 しかも、競争による成長を目指して構造改革を進めてきたはずなのに、経済も大幅に低迷し他国との競争力も著しく衰退させています。 そうした日本において、他者の痛みを社会で引き受け、一人の幸せを社会の幸せとして分かち合う発想がいまこそ必要だと言います。 日本の閉塞状況の要因を探り、分かち合いによる新しい経済システムを具体的に提案しています。第1章 なぜ、いま「分かち合い」なのか 第2章 「危機の時代」が意味すること―歴史の教訓に学ぶ 第3章 失われる人間らしい暮らし―格差・貧困に苦悩する日本 第4章 「分かち合い」という発想―新しい社会をどう構想するか 第5章 いま財政の使命を問う 第6章 人間として、人間のために働くこと 第7章 新しき「分かち合い」の時代へ―知識社会へ向けて
2014.02.10
コメント(0)
-
ライフログ入門(感想)
GPS機能のついたスマートフォンや携帯電話の普及により、場所と時間、距離などの簡単な記録が可能になりました。 また、音楽をパソコンやスマートフォンで再生している場合、再生した曲の嗜好や回数などは自動的に記録される場合があります。 これらをクラウドのライフログサービスを活用することによって人生を記録し、整理・検索し、活用するライフログを利用すれば、生活は便利になり、生産性も上がるといいます。 ”ライフログ入門”(2011年1月 東洋経済新報社刊 美崎 薫著)を読みました。 クラウド技術の進展とともに新たなキーワードとして注目されるライフログを、初歩から解説しています。 美崎薫さんは、未来生活デザイナーにして、世界が注目する記憶する住宅プロデューサーで、現実化した未来住宅を超え、記憶に近づくためのツールを作り出し、過去と未来の統合をめざしています。 必要なものは作ることをモットーに、住宅、書斎、机を始め、多数のハードウェア、ソフトウェアの開発をプロデュースしています。 ライフログとは、人間の生活を長期間に渡りデジタルデータとして記録すること、またその記録自体を指しています。 広義には、個人の起床時間や睡眠時間、移動場所や移動距離、食事のデータ、読書経歴や音楽再生の記録なども含まれています。 ユーザが自分で操作して記録する手動記録と,外部デバイスにより自動的に記録する自動記録があります。 手動記録は、詳細で自由度の高い記録が可能であり、ブログやメモなどのように記録にユーザの主観的意見を含めることができますが、ユーザ操作を伴うため記録負担が大きいです。 主なライフログサービスには、Life-X、FoodLog、読書ログ、食べログ、地図ログ、ブクログ、ねむログ、gooからだログ、ゲームメーター、profile passport、読書メーターなどがあります。 自動記録は、ウェアラブルデバイスを装着して、画像・動画・音声・位置情報といったデータを常時記録するというものです。 ユーザの記録負担は小さいですが、取得されるデータが限定されており、客観的なデータしか取得することができません。 これらのライフログにより、凡庸な記録の山をヴィンテージにかえることができ、ログが予測し人が考える作業をサポートするようになるといいます。 本書は、ライフログを実践するためのツールを紹介するとともに、人生をデジタルに記録することによってどんなメリットがあり、それが社会をどのように変えていくのかを解説しています。 誰にとっても人生はたった一度きりですが、自分が見たこと、聞いたこと、食べたことなどの個別の体験を積極的に記録している人はまだ少数です。 しかし、ライフログを残していれば、大切な思い出や、自分だけの気づきを風化させることなく、後から人生を再体験することが可能です。 自分だけの感動と発見を積み上げることは、自分を深く知ることにもつながり、成長のエンジンを生み出すということです。Chapter1 イントロダクションChapter2 ライフログの可能性Chapter3 ライフログのある生活Chapter4 さまざまなライフログシステムChapter5 ライフログで人生は変わる
2014.02.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1